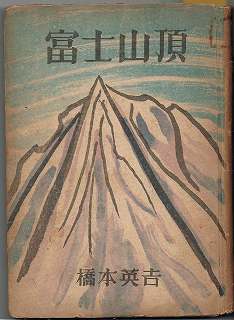| ー橋本英吉文学の世界ー お山の力、「富士山頂」を読んで 作成2013・6・13 はじめに 昔、越後の八海山の女人堂まで登ったことがありました。記憶は薄れていますが泊まったのは宿坊のようなところで、「八海山」の酒を飲み、満足な山岳登山の格好もないまま山を歩きました。ある程度まで登ると雪を踏むようになり、前夜の飲みすぎた酒で心臓がバクバク云っているのを感じながら、また、だんだんと変わってゆく山の景色の変化に私は次第と心細くなっていきました。人っ子ひとりいない静寂で孤独な世界の中にありました。 ザクザクの雪道をなおも進んで、なんとか避難小屋の女人堂まで辿り着くことができました。余りの静寂さに驚きながら、「もう、俺のようなものが来るところではない。」そう思いながら、私は山から逃げるようにして麓まで引き帰しました。 あれから、40年の歳月が過ぎ、山への興味は少しはありましたが、また山に登ろうと云う気持にはなりませんでした。そう云う私がこれから山のことを書こうというのですから、なんと気ままなことかと不思議なものです。 ある日、私は古本市で「富士山頂」と云うご本に出会いました。「富士山頂」と云うご本には、これまで新田次郎と橋本英吉の書かれた作品がありました。前者は富士山頂にレーダーを取り付けた気象観測所をテーマに、後者は日本の高層気象観測への道を切りひらかれた野中到夫妻をテーマにした2作品があります。どちらの作品も映画化され多くの人々に感動を与えました。また、前者は第1回のNHKプロジェクトXでも放送され大反響を呼んだことは記憶の新しいところです。
橋本英吉は小説の最後のページに「作者記」を書き添え、その作品の有様を「この作品は伝記ではなく、小説でありますから、事実の取捨選択は小説らしく、かなり自由にしました。なほ、雑誌発表後、野中至氏に面会の機会に恵まれましたので、構成にさしつかへない程度の訂正を加へたうへ、二十節以下は全く新しく書き加へました。野中到氏は今年(昭和二十二年)八十一歳の高齢ですが、まだ往年の意気おとろへず、逗子町の海岸、浪子不動堂上の高台に隠栖をつづけて自適の生活をされながら、まだまだ何事か為すところがあるらしく、研究と企画に没頭されてゐる様子です。氏の健康の愈(いよ)いよ盛んなることを祈る次第です。」と記しました。 二・ 富士山頂 (原文のまま) ひとつ想像してもらいたひ。氷山にのって漂流してゐる男女の二人を。氷山をくりぬいた洞窟、まはりは一歩も出ることのできない荒海である。浪が白い牙をむいてよせて来る。ガスと風が無慈悲な伴奏者である。洞窟とまはり数尺の地が彼等の天地にすぎない。明けても暮れてもガスと風と氷である。これらの自然現象の暴壓とたたかふよりも避け、巧みにこの破壊力からのがれながら、一方で自然現象の秘密をかぎださうと、不断の努力をつづける二人をー (略) 至は隙間からさしてくる暁の色をみたとき、一種の精気が体中にみなぎっているのを感じた。風も雲もなく、満天に星のかがやいてゐるのを、彼はすぐ知った。すると千代子がまだ御来光ををがんだことのないことを思ひだした。 「起きるんだよ。そして着物をうんと着て外に出なさい。すばらしい御来光が拝めるよ。きっと。」 「御来光! いっしょにをがみましょう。でも外に出られるかしら。」 彼女がきてから天気がわるくて、まだ一度も御来光ををがむ機会がなかったのである。 「出られるよ。僕が先に窓からでて氷を割るから、お前はうちから戸を押してみてくれ。たいがい大丈夫だ。今朝はいくらか暖かいよ。」 と云っても零下三度六分であったが。出入口は吹きたまった雪が、敷居の溝から上まで凍りついてゐたから、彼はいつも窓から出入りしてゐた。凍った雪を取りのけてもすぐ凍りついたし、そのままにしておけば、かへって隙間風を防いでくれるのである。 彼か金槌をもってきて、小屋の外から雪をたたきわってゐると、金槌の柄が手袋にしみついた。氷は厚くてコンクリートのやうにかたい。二人は気合をかけて内と外からこじあけた。 風力計をすゑた囘光台には、登りやすいやうに麻縄をまへから垂らしてあった。それは棒のやうに凍ってゐた。十字型の風杯についた霧氷は、風の方向に飛行機の尾翼に似た十字盤をつくってゐた。岩といふ岩は氷柱をつけ、それが牙のやうに、またトンネルのやうになってゐた。 「そら、また! 震へるからすべるのだよ。両脚にしっかり力をいれ、綱につかまるのだよ。」 至は千代子のうしろから押してやる。空はいくらか明るくなってゐたが、頭のうへではまだ星がきらめいてゐた。 「あああ・・・・・」風力計の軸にやっと取りついた千代子は、微かにうめき声をあげた。そして横にしゃがんだ至の肩に手をかけた。眼前にひらけはじめてみる暁の風景が、彼女の鬱血した心を、熱湯をかけたやうに溶かしてしまった。二人は電線にとまった寒雀のやうに、羽がひを一つに寄せ丸くなってゐる。 東の空には、はや一條の薄明かりが、サーチライトのやうに横にひろがってゐた。地上はかへって夜中よりも暗黒にとざされてゐる。ことに奮噴火口は、そこだけ地球の一角をゑぐりとったやうに、底しれぬ闇をたたへてゐた。その絶壁にかかってゐる巨大な氷柱は、懸崖を支へる無数の柱のやうだ。成就ヶ岳が馬の背なかのやうになだらかに起伏してゐる。その曲線の彼方に、箱根、丹沢の連峰が、青にをおびた黒い塊を浮かせてゐた。これらの連山は、なべて波濤から首だけを持ちあげた島のやうに、ひとつひとつ孤立してゐた。 あちこちの渓谷から湧きあがる白雲の團塊は、除々にひろがり、やがて峰々だけを残して、大地を蔽(おお)うて行く。富士自身もこの白雲の層にかこまれて、大きな白い首巻をまいたやうに、頭部だけを宙天に浮かべた。 東の空のサーチライトは次第に幅をひろげる。それにしたがって雲の形、山の色どりが刻々と変化する。彼方、甲斐、赤石の山やまも白い團雲に裾を没して、甲斐駒、赤石嶽の主峰だけが、尖った頂を雲表に持ちあげてゐた。みてゐる間に、富士川を境にして、白い層雲がわれてきた。その裂け目は千メートルに近い断層をなし、正しく垂直にたれた切口は、すだれのやうに美しく雲が細分されて、その盡(つ)きるあたりを、富士川が銀色に流れてゐるのだった。
太陽が地平線をはなれる刹那に、眞紅は頂点に達する。空も雲海も峰みねも、限りない屈折の方向にしたがって、万化の色彩を放ち、茫洋とした織物の上に佇ずんでゐる眩惑を感ずる。相模湾のうへにはレンズ形の雲がある。それは雲海とは別個に、悠々と浮かんでゐる。レンズの周辺は眞紅にかがやいてゐるが、中ほどは黄色、真中は暗い紫色に染まり、横になびく幟のやうに、ゆっくりと北に移動してゆく。虎岩の四五メートルもありさうな氷柱、あちこちの岩から軒のやうに垂れてゐる氷塊、それらもいっせいに輝きはじめるのだった。 剣ヶ峰の岩頭にうづくまってゐる彼等も紅色に映える。彼等は岩にやどった二滴の露のやうに小さく見えるのだった。初めて御来光のまへに立った彼女の眼は紅色にうるんでゐた。そして一方の手は、至の手をかたく握ってゐた。彼女は手をにぎってゐることも忘れてゐた。いやそばにゐる夫も、頬にあふれる涙も感じなかった。御来光は、光線が斜めに水蒸気や塵埃の層を通過するときに、屈折を受けておこす現象であることを、彼女は知ってゐた。けれどこのしごく単純な原理によっておこる複雑微妙な美は驚異であった。それはまた至が、水銀の自然現象に対する複雑微妙な反応におどろき、自然に対する愛着をつよめたのと似かよふ心持とも云へる。驚異することは、また自然現象の観察者にとって必要な資格でもあった。冷静な観察や緻密(ちみつ)な数学的な計画だけが、自然科学者の条件ではないのである。美を愛し驚き疑ふことが、つまり人間的であることも、機械的である以上に必要な条件であった。 二人はよりそひ助けあひながら、岩頭からおりて行った。そして狭い洞窟に座をしめたとき初めてほっとし、深い溜息をつくのだった。
「誰でも一応は卑下するがいいのだよ。自然にうちのめされてみなければ、ほんとに人間らしくないからね。僕などは本当のことを云ふと、名誉慾やそれにつきものの、権威とか栄耀とかを望んだこともあったが、しばらくここにゐるうちに、そんなことは忘れてしまった。いや忘れてしまったと云へば云ひすぎだが、自分の欲望がだんだん鈍化されるやうな気がしてきたよ。」 至はくせになった手の摩擦をつづけながら述懐するのだった。 −橋本英吉 「富士山頂」による− まとめ この区画内に記された文章には、観測所のことなどについての記載は一つもありませんでした。このひと区切りの中の文章は野中夫妻が初めて見た御来光、それと時間と共に変化して行く空と山々の景観だけです。そして、そのひと区切りの文章の最後は二人の会話で終わります。お山の偉大な力でしょうか。存在の確かさ、そして、尊さ、己の姿を見つめている光景。どこか、マラソンランナーにもサイクリングにも、また、旅人の姿のようにも似ていないか。 さあ、またどこかへ行こう。漂泊の旅でもいい、その行方の先は分からない。一遍、西行、日蓮、親鸞も空海それから最澄だって大宇宙のなかの微細な旅を求めたではないか。此れを一口に宗教と呼んでもかまわないのではないか。山岳は古今を問わず人生修行の場なのですね。 「富士山頂」、朝の日の情景を、どなたが区切っただろう、その一文を読みながらそんなふうなことを感じました。 ー富士山が世界文化遺産に登録されたことを記念してー 2013・6・27 成就ヶ岳・虎岩・剣ヶ峰 参考資料 富士山頂 橋本英吉 鎌倉文庫 発行 昭和23年3月 欅の芽立 橋本英吉 三和書房 発行 昭和14年2月 富士 橋本英吉 甲鳥書林 発行 昭和16年9月 日本の「私」を索とめて 佐伯彰一 河出書房新社 発行 1974年9月 峠と人生 直良信夫 NHKブックス 発行 昭和51年5月 霊山と日本人 宮家準 NHKブックス 発行 2004年2月 旅のなかの宗教 真野俊和 NHKブックス 発行 昭和55年3月 修験の山々 柞木田龍善 法蔵館 発行 昭和55年7月 六根清浄 お山は晴天・北相模の富士信仰 戻る |