| 西暦 |
和年号 |
年齢 |
主な出来事 |
加藤武雄 |
事項 |
| 1872 |
明治5年 |
1 |
1月22日、田山花袋、邑楽郡館山町1462番地、次男として生まれる。
3月25日、長野県西筑摩郡神坂村字馬籠、島崎正樹(43才)の四男として生まれる。母縫子(36才)、春樹と名づく。
|
|
| 1873 |
6年 |
2 |
1 |
|
| 1874 |
7年 |
3 |
1 |
|
| 1875 |
8年 |
4 |
1 |
|
| 1876 |
9年 |
5 |
1 |
|
| 1877 |
10年 |
6 |
1 |
|
| 1878 |
11年 |
7 |
神坂村小学校入学。
|
|
| 1879 |
12年 |
8 |
1 |
|
| 1880 |
13年 |
9 |
|
|
| 1881 |
14年 |
10 |
4月、長兄秀雄、友弥と共に連れられ上京。京橋槍屋町の長姉園子の嫁ぎ先高瀬薫方に寄寓し、泰明小学校に転入。
|
|
| 1882 |
15年 |
11 |
高瀬家帰郷のため、高瀬の縁者力丸元長方に寄寓。
|
|
| 1883 |
16年 |
12 |
高瀬と同郷の士族、代言人(弁護士)の吉村忠道(ただみち)方へ寄寓。銀座四丁目
|
|
| 1884 |
17年 |
13 |
海軍省官吏、石井其吉に英語を学ぶ。
|
|
| 1885 |
18年 |
14 |
1 |
|
| 1886 |
19年 |
15 |
漢学者武居用拙に「詩経」「左傳」を、英学者島田奚疑に英語を学ぶ。三田英学校(後の錦城中学校)入学。
11月29日、父郷里の座敷牢内にて狂死。
|
|
| 1887 |
20年 |
16 |
吉村氏日本橋浜町に移転。神田の共立学校に転学、木村熊二の教えを受ける。
9月明治学院に入学、戸川秋骨、馬場孤蝶らとクラスを同じにする。
|
|
| 1888 |
21年 |
17 |
6月17日、先師木村熊二の手により、高輪台町教会でキリスト教の洗礼を受ける。
|
1 |
1 |
| 1889 |
22年 |
18 |
1 |
2 |
1 |
| 1890 |
23年 |
19 |
1 |
3 |
1 |
| 1891 |
24年 |
20 |
明治学院卒業。吉村氏横浜に雑貨店「まからずや」を開き、しばらく手伝いに行く。
11月24日、祖母桂子死去。長兄秀雄に代わり葬儀のため帰郷。木村熊二の知人巌本善治主宰「女学雑誌」に翻訳を乗せることになる。
|
4 |
1 |
| 1892 |
25年 |
21 |
1月、「女学雑誌」第298号発行「無名氏」(匿名)の署名で「人生に寄す」を掲載、しばらく同誌に翻訳等の仕事をする。
10月、明治女学校教師となり牛込に下宿、教え子に佐藤輔子がいた。星野天知、北村透谷、平田禿木を知る。
|
5 |
「春」の時代 |
| 1893 |
26年 |
22 |
1月、「文学界」創刊、同人となり以後終刊まで同誌に作品を寄稿。同月下旬、突然、教職を辞し一番町教会の籍も脱し、2月1日、創刊された「文学界」を手にして関西へ旅立ち放浪する(約9ヶ月の長旅)。鎌倉円覚寺帰源院にも滞在。秋は東北一の関へ行く。
10月、帰京長兄秀雄の下宿に身を投じ再び吉村家へ戻る。
11月、母及び秀雄の家族が上京、下谷三輪に住む。
|
6 |
「春」の時代 |
| 1894 |
27年 |
23 |
4月、再び明治女学校教師となる。輔子は高等科を卒業。
5月16日、北村透谷自殺。
5月末、秀雄は水道鉄管にからむ私文書偽造で収監される。次兄は朝鮮に行き、三兄友弥は京橋の木綿問屋の奉公生活に失敗して秀雄の家に寄寓していたため、結局藤村が一家をささえることになり三輪町に居を移す。学校でも気力がなく、「燃えガラ」とあだなされる。
6月、花袋、透谷の死を悼み、短歌を「文学界」に送ったことから同人との交友が始まる。
8月、はじめて樋口一葉と会う。
10月、「透谷集」を編む。
|
7 |
「春」の時代 |
| 1895 |
28年 |
24 |
母とともに一家を本郷新花町に移る。8月13日、札幌農学校講師鹿討(ししうち)豊太郎に嫁した佐藤輔子が札幌にて病死。同月教職を辞す。9月25日郷里大火舊宅焼失。
12月、房州に旅行。
|
8 |
「春」の時代 |
| 1896 |
29年 |
25 |
4月、秦フユ明治女学校本科を卒業。この頃、上田敏、田山花袋、柳田国男を知る。
9月、仙台の東北学院教師となり赴任、留守家族を本郷森川町に移転。
10月25日、母ぬいがコレラで死去したため帰京、遺骨を郷里に葬り11月7日、帰りに小諸の木村熊二を訪ね15円を借用し 仙台へ帰る。
|
9 |
「春」の時代 |
| 1897 |
30年 |
26 |
7月、教職を辞し帰京。夏中、吉村樹(しげる)と房州小久保におもむき小説「うたたね」を執筆。秋、長兄秀雄一家と本湯島新花町に移転。
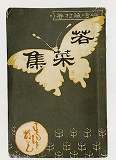
8月第1詩集「若菜集」を春陽堂より刊行。11月「新小説」に「うたたね」を発表。
|
10 |
1 |
| 1898 |
31年 |
27 |
1月、「文学界」終刊。4月、東京音楽学校選科入学、ピアノ科助教授橘糸重を知る。
6月、第2詩集「一葉舟」を春陽堂から刊行。
7月、吉村樹を連れ木曽福島の姉の家高瀬氏を訪ね、詩集「夏草」を書く。9月、伊良湖岬に柳田国男を訪ねた花袋は木曽福島の藤村を訪ねる。帰途小諸に木村熊二を訪う。斉藤緑雨、高安月郊、蒲原有明を知る。
12月、第3詩集「夏草」を春陽堂から刊行。 |
11 |
1 |
| 1899 |
32年 |
28 |
4月5日、木村熊二に英語と国語の招かれ小諸義塾教師として赴任、熊二の家に暫く下宿。
5月6日、明治女学校校長巌本善治の媒酌で秦冬子(明治女学校卒業生、函館の網問屋の次女)と結婚。
小諸馬場裏に住む。月給30余円(のち同校の経営悪化のため25円) |
12 |
小諸時代 |
| 1900 |
33年 |
29 |
5月3日、長女緑生れる。
8月、散文「雲」を発表。「千曲川スケッチ」(45年刊行)に着手す。 |
13 |
小諸時代 |
| 1901 |
34年 |
30 |
4月、女子学習舎が開校式をあげる。この頃、塩川べんに夜枕草子や作文を教える。妻フユも学習舎の教員として習字や裁縫を教える。
8月「落梅集」を春陽堂刊行。この頃から散文に移りはじめる。
11月12日、柳田国男来訪。
|
14 |
小諸時代 |
| 1902 |
35年 |
31 |
3月31日、 次女孝子生まれる。
7月29日、恩人吉村忠道死去、遺族困窮のため以後1年間、毎月7円50銭を送金。
6月、原題「炉辺雑興」を「太陽」臨時増刊「海の日本」に発表する。
|
「炉辺」 の散文詩は後、大田水穂と島木赤彦による合著「山上湖上(さんじょうこじょう)」の序として掲載、二人の門出を祝福した。 |
11月「藁草履」を「明星」に発表。 |
15 |
小諸時代 |
| 1903 |
36年 |
32 |
8月25日 神津猛、小諸義塾参観、初めて藤村に会う。
橘糸重、有島生馬、小山内薫、青木繁、久保猪之吉、等がこの頃来訪。★「太陽」6月号に「老嬢」を発表。 |
16 |
小諸時代 |
| 1904 |
37年 |
33 |
1月5日、田山花袋来訪1泊。夜遅くまでこれからの文学を語り合う。
1月13日、「破戒」の構想に着手。白檮山(かしやま)いそじと三村きのを同行、雪の飯山真宗寺(破戒の蓮華寺)を訪ねる。翌日対岸に出てそりを体験する。
4月9日、三女、縫子生れる。
7月下旬、自費出版費用相談のため妻の父を函館に訪ねる。
12月17日、神津猛来訪。「破戒」の草稿を示し、それを自費出版する計画を語る。
★「水彩書家」を「新小説」1月号に発表。「椰子の葉陰」を「明星」3月号に発表。
9月、「藤村詩集」を「春陽堂」刊行。「津軽海峡」を「新小説」12月号に発表。
この年、長兄秀雄が再び入獄する。 |
17 |
小諸時代 |
| 1905 |
38年 |
34 |
3月、太田水穂と島木赤彦による合著「山上湖上(さんじょうこじょう)」が刊行される。
|
藤村は後年、刊行した「早春」のなかで明治39年に「(序文は)東京より上州磯部温泉に身を養いに行った時の作。」と誤って記述。 |
10月星野天知と共編「透谷全集」を文武堂より刊行。11月「新小説」に「旧主人」を発表、発禁となる。
3月4日、志賀村神津猛を訪ね「破戒」完成までの生活費借用を頼もうとして口に出せず。一泊。
猛の乞いにより、愛用の机を贈ることを約束。翌日、手紙で事情を訴えて400円の借用を乞う。
3月20日、猛から150円届く。
4月29日、小諸義塾を辞し上京、西大久保405番地に借家。
5月6日、三女縫子ハシカから脳膜炎を起こして死去近くの長光寺へ葬る。
7月、猛から60円借りる。
10月20日長男楠雄生れる。
前年度より引続き「破戒」執筆11月27日、脱稿原稿用紙535枚。★国木田独歩を知る。
|
18 |
小諸時代
西大久保時代
|
| 1906 |
39年 |
35 |
1月、「朝食」を「芸苑」1月号に発表。
3月25日、「破戒」を「緑陰叢書」自費出版刊行。1500部。好評で4月に再版。7月4版なる。
4月7日、次女孝子、急性腸カタルで死去。
6月 「文章世界」を「博文館」より発行。
6月12日長女緑、ハシカから脳膜炎になり死去、長光寺へ葬る。
|
資料 「芽生」より
「芽生は枯れた、親木も一緒に枯れかかって来た……」 こう私は思うように成った。
その晩、私は急に旅行を思い立った。磯部の三景楼というは、碓氷川の水声を聞くことも出来て、信州に居る時分よく遊びに行った温泉宿だ。あそこは山の下だ、あそこまで行けば、山へ帰ったも同じようなものだ、と考えて、そこそこに旅の仕度を始めた。
「なんだか俺は気でも狂いそうに成って来た。一寸磯部まで行って来る」 こう家のものに言った。翌朝早く私は新宿の停車場を発った。 |
10月2日浅草新片町に移転。この頃次の長編を「春」と決め準備にかかる。
|
19 |
西大久保時代
新片町時代
|
| 1907 |
40年 |
36 |
1月第一短編集、「緑葉集」を「春陽堂」が刊行。
9月8日次男鶏二生れる。
6月、「黄昏」を「文章世界 6月号」に発表する。
9月、花袋、「蒲団」を「新小説」に発表し、文壇に確固たる地位を築く。
10月、「並木」を「文芸倶楽部臨時増刊」、「壁」を「早稲田文学」、「収穫」を「文章世界」に発表する。
11月、「散歩」を「明星11月号」に発表する。
|
20 |
新片町時代 |
| 1908 |
41年 |
37 |
花袋「生」を4月13日から「読売新聞」に連載。
「春」を4月7日より8月19日迄「東京朝日新聞」に連載(長谷川二葉亭が推薦、135回で終了)。
10月、神津猛に100円借金を依頼する。同月、単行本「緑陰叢書第二編 春」を自費出版として刊行。
12月17日三男蓊助生れる。
|
21 |
新片町時代 |
| 1909 |
42年 |
38 |
1月「中央公論」に「一夜」。「伯爵夫人」を「趣味」。「苦しき人々」を「文章世界」に発表する。
2月下旬田山花袋、蒲原有明、武林夢想庵とともに伊豆地方を旅行する。
2月、「群」を「女子文壇」に発表する。
4月、「旅」を「太陽」に発表する。
5月「青年」を「無名通信」に発表する。
6月、「弟子」を「早稲田文学」、「死」を「読売新聞」に発表する。
7月、「土産」を「帝国文学」。「雑貨店」を「新潮」に発表する。
8月「河岸の家」を「趣味」、「奉公人」を「女子文壇」に発表する。
同月、長兄、秀雄の長女いさ子が西丸亮の息子啓三に嫁す。
9月22日『新片町より』を佐久良書房より刊行(「長谷川二葉亭氏を悼む」「山国の新平民」「北村透谷君」等を収録)。
10月「芽生」を「中央公論」。同月、「家」の準備のため、約一週間木曽路を旅する。14年ぶりの帰郷。
12月「浅草にて」を「早稲田文学」。第二短編集「藤村集」を「博文館」から刊行。
|
22 |
新片町時代 |
| 1910 |
43年 |
39 |
1月1日より5月4日まで「家」を112回にわたって「読売新聞」に連載する(正宗白鳥の厚意)。
6月9日、高瀬慎夫(ちかお)死去。8月6日妻冬子、四女柳子を分娩後、出血のため三十三才にて死去、長光寺へ葬る。楠雄、鶏二を手許におき蓊助を木曽福島の姉高瀬そのに、柳子は姪西丸いさ子の世話で茨城県大津の漁家鈴木家に預ける。次兄広助の長女ひさ、次女こま子が家事手伝いのため来訪する。
高瀬その宛書簡の概要 9月4日付から 六歳をかしらに四人の子供を控えいかにこの母なき子供らを処置すべきやということは私にとって一通りならぬ苦心であった藤村は、姉そのに四人の子供を預かってほしい旨申しいれた。しかし鶏二を蒲原有明に預けたところ、数日を経ずして帰ってきたので、思い直して長男楠雄と次男鶏二は手元におき、三男蓊助のみを預かってほしいとその旨を申し入れた。そして、二歳たらずの蓊助を長姉そのに預ける。藤村が再び蓊助と会ったのはフランスから帰朝した時で、高瀬家を2人の子供と共に訪ねた時だった。
|
23 |
新片町時代 |
| 1911 |
44年 |
40 |
3月12日、三兄友弥死去(43才)。
1月号および4月号に「犠牲」を「中央公論」に発表する。
6月「母」を「文章世界」に発表する。
6月23日、「家」の出版費として300円借用を高瀬家に依頼。
6月〜9月「千曲川スケッチ」を「中学世界」。
8月「平和の日」を「太陽」に発表する。
9月「孤独」を「中央公論」に発表。
11月3日「家」を「緑蔭叢書第三編 上・下」を自費出版。
|
24 |
新片町時代 |
| 1912 |
45年 |
41 |
1月、平塚に静養中の神津猛を訪ねる。
5月〜大正2年4月まで「ある婦人に与ふる手紙」のち「幼き日」、「生ひ立ちの記」に改題「婦人公論」に連載する。
6月初め、次兄広助の長女久子、藤村の世話で外交官田中文一郎に嫁す。こま子は残って家事の手伝いを続ける。
11月、馬籠に頌徳碑が建立されたのを記念して、父島崎正樹の遺稿集「松か枝」を自費出版する。
12月、「芭蕉の一生」を「文章世界」に発表。同月20日、「千曲川スケッチ」を「佐久良書房」から刊行。
|
25 |
新片町時代 |
| 1913 |
大正2年 |
42 |
1月、台湾から帰ってきた義兄高瀬薫を木曽福島に送り届ける。(薫は奇応丸本舗高瀬家十代で、木曽谷一の秀才とうたわれたが、不身持でいろいろな事業に手を出したが失敗を重ねた。大正3年死去。)
|
資料 新生 十三号より こま子が藤村に妊娠を告げる
ある夕方、節子は岸本に近く来た。突然彼女は思い屈したような調子で言出した。
「私の様子は、叔父さんには最早(もう)よくお解(わか)りでしょう」
新しい正月がめぐって来ていて、節子は二十一という歳(とし)を迎えたばかりの時であった。丁度二人の子供は揃(そろ)って向いの家へ遊びに行き、婆やもその迎えがてら話し込みに行っていた。階下(した)には外に誰も居なかった。節子は極く小さな声で、彼女が母になったことを岸本に告げた。
避けよう避けようとしたある瞬間が到頭やって来たように、思わず岸本はそれを聞いて震えた。思い余って途方に暮れてしまって言わずにいられなくなって出て来たようなその声は極く小さかったけれども、実に恐ろしい力で岸本の耳の底に徹(こた)えた。それを聞くと、岸本は悄(しお)れた姪(めい)の側にも居られなかった。彼は節子を言い宥(なだ)めて置いて、彼女の側を離れたが、胸の震えは如何(いかん)ともすることが出来なかった。すごすごと暗い楼梯(はしごだん)を上って、自分の部屋へ行ってから両手で頭を押えて見た。
|
2月、「眼鏡」を「実業の日本社」が刊行。
3月、芝二本榎西町3番地(次兄広助の家)に移転。
4月、新潮社、島崎藤村著作集「緑蔭叢書」の改刷刊行、4編の著作権を藤村の要求額2千円で購入。
|
参考 「島崎藤村論」正宗白鳥 昭和29年9月発行 文藝 臨時増刊号 島崎藤村読本より
(前略)「新生」事件で煩悶苦悩のあまり、三十六計逃ぐるに如かずの決心をしたのも、中沢臨川の醉餘の扇動言に依るのであって、臨川が煽(おだ)てなかったら、洋行を思ひついたであらうか。「新生」にも書いてあるが、臨川も、駟も、舌に及ばずで、うっかり口に出した事を無視する訳には行かなくなって、幾分の援助はした。しかし臨川の出した五百円くらいではどうにもならないので、藤村は、自分のすべての著作権を売却する覚悟を極めた。けれども「破戒」「春」「家」その他短編集小品集感想録など、一切合財集めても、二千円以上で買い取らうとする書店はなかった。やうやく新潮社が採算を無視して二千五百円を支拂ふことになって、旅費がどうにかまかなはれることになった。(後略)
 |
4月13日神戸発フランス船、エルネスト・シモン号にてフランスに渡り、マルセイユ、リオンを経てパリに入る。
(途中、香港より手紙でこま子の父親だけに告白、後の事をたのむと。そして、ふたたび故郷の土は踏まないという
覚悟の旅であった。)
|
資料 新生 五十一号より こま子の父親・広助に宛てた手紙の内容
彼は波に揺られていることも忘れて書いた。この手紙は上海を去って香港への航海中にある仏蘭西船で認(したた)めると書いた。神戸を去る時に書こうとしても書けず、余儀なく上海から送るつもりでそれも出来なかった手紙であると書いた。自分が新橋を出発する時も、神戸を去る時も、思いがけない見送りなどを受けたのであるが、それにも関(かかわ)らず自分は悄然(しょうぜん)として別れを告げて来たものであると書いた。何故に自分が母親のない子供等を残してこうした旅に上って来たか、その自分の心事は誰にも言わずにあるが、大兄だけにはそれを告げて行かねば成らないと書いた。多くの友人も既にこの世を去り、甥(おい)も妻も去った中で、自分のようなものが生き残って今また大兄にまで嘆きをかける自分の愚かしい性質を悲しむと書いた。自分は弟の身として、大兄の前にこんなことの言えた訳ではないが、忍び難いのを忍ぶ必要に迫られたと書いた。自分が責任をもって大兄から預かった節子は今はただならぬ身(からだ)であると書いた。それが自分の不徳の致すところであると書いた。自分の旧(ふる)い住居(すまい)の周囲は大兄の知らるるごとくであって、種々な交遊の関係から自然と自分も酒席に出入したことはあるが、そのために身を過(あやま)つようなことは無かったと書いた。その自分がこうした恥の多い手紙を書かなければ成らないと書いた。今から思えば、自分が大兄の娘を預かって、すこしでも世話をしたいと思ったのが過りであると書いた。実に自分は親戚(しんせき)にも友人にも相談の出来ないような罪の深いことを仕出来(しでか)し、無垢(むく)な処女(おとめ)の一生を過り、そのために自分も曾(かつ)て経験したことの無いような深刻な思を経験したと書いた。節子は罪の無いものであると書いた。彼女を許して欲しいと書いた。彼女を救って欲しいと書いた。家を移し、姉上の上京を乞(こ)い、比較的に安全な位置に彼女を置いて来たというのも、それは皆彼女のために計ったことであると書いた。この手紙を受取られた時の大兄の驚きと悲しみとは想像するにも余りあることであると書いた。とても自分は大兄に合せ得る顔を有(も)つものでは無いと書いた。書くべき言葉を有つものでも無いと書いた。唯(ただ)、節子のためにこの無礼な手紙を残して行くと書いた。自分は遠い異郷に去って、激しい自分の運命を哭(こく)したいと思うと書いた。義雄大兄、捨吉拝と書いた。
|
4月18日、「微風」を「緑陰叢書第四編」として新潮社が刊行。
4月25日「後の新片町より」を「新潮社」が刊行。(「北村透谷の短き一生」「芭蕉の一生」などを収録)
7月 新潮社、牛込区矢来町中ノ丸五十八号に家屋を購入、佐藤義亮上京19年目で初めて自家を持つ。
8月、こま子男子出産。
8月より4年8月までフランスからの紀行文その他を「東京朝日新聞」に送り「仏蘭西だより」を掲載。
|
26 |
仏蘭西時代 |
| 1914 |
3年 |
43 |
8月欧州大戦勃発、リモオジュに避難。正宗得三郎(長兄は白鳥)同行。
11月パリに帰る。帰途フランス西部旅行。★「桜の実の熟する時」を「文章世界」の5月、8月、翌4年1月、2月、4月号に発表。
|
27 |
仏蘭西時代 |
| 1915 |
4年 |
44 |
1月「平和の巴里」を「佐久良書房」が刊行。
6月頃、神津猛に帰国費200円の借用を依頼。10月頃帰国する予定だったが、藤村後援会「藤村会」が帰国のカンパする計画を聞き延期。
12月「戦争の巴里」を「新潮社」が刊行。
|
28 |
仏蘭西時代 |
| 1916 |
5年 |
45 |
4月、「水彩書家」を「春陽堂」が刊行。
4月29日、「藤村会」の送金を得てパリをたちロンドン、喜望峰を経由にて帰国。
7月4日神戸着。
東京芝二本榎西町三番地(次兄広助の家)に假寓。秀雄(広助?)の家計が窮迫し、経済的援助を強いられる。
8月、加藤武雄、小林愛川の名で「文章倶楽部8月号」に「文壇立志篇 島崎藤村氏」を発表する。
8月、「藤村文集」を「春陽堂」が刊行。
|
29 |
仏蘭西時代 |
| 1917 |
6年 |
46 |
2月、精神病院に姉そのを入院させる。
4月、広助の援助等のため、高瀬兼喜(養子・奇応丸店主)に300円借入れ依頼。童話集「幼きものに」刊行。
6月、芝西久保桜川町の高等下宿風柳館に移る。姪こま子との関係が復活する。
11月より大正7年6月まで「桜の実の熟する時」の後編を「文章世界」に発表。
|
30 |
1 |
| 1918 |
7年 |
47 |
4月5日、次兄広助妻あさ死去46才。「新生」第1部(5月1日より10月5日まで)「東京朝日新聞」に第1部135回を連載、広助と義絶した。
7月、こま子が台湾の長兄秀雄のもとに去った。
10月、麻布飯倉片町に転居。
|
31 |
1 |
| 1919 |
8年 |
48 |
4月、「新生」第2部(4月から10月まで)「東京朝日新聞」に連載
12月、こま子が秀雄とともに台湾から帰京、羽仁もと子(西丸哲三方か検討要)宅に住み込んだ。
|
32 |
1 |
| 1920 |
9年 |
49 |
3月、長姉そのが根岸病院で死去。6月「ふるさと」を「実業の日本社」から刊行。 |
33 |
1 |
| 1921 |
10年 |
50 |
3月、加藤静子が始めて訪れた。同月、蓊助(13才)を引き取りに木曽高瀬家へ行く。
7月、「ある女の生涯」を「新潮」に発表。 |
34 |
1 |
| 1922 |
11年 |
51 |
1月、「藤村全集 全12巻」が同刊行会から出版され始める。
4月、「藤村全集 全12巻」の収益によって婦人雑誌「処女地」を創刊、加藤静子らを編集助手に依頼する。
8月、長男楠雄を明治学院中等部から退学させ、馬籠に帰農させる。また、妻子の遺骨を木曽永昌寺の墓地に改葬する。
9月5日 「アルス社」より『飯倉だより』を刊行(「芭蕉」、「北村透谷二十七回忌に」などを収録)
|
35 |
1 |
| 1923 |
12年 |
52 |
1月、柳子と「羽根つき」をしていて軽い脳溢血で倒れる。
10月、朝日新聞に「震災記(子に送る手紙)」を連載する。
|
36 |
1 |
| 1924 |
13年 |
53 |
1月、長兄秀雄、大塚製氷問屋に招かれ再び台北に渡り、2月に病死。
2月、馬籠旧本陣跡下隣りの土地を購入、過去の復活を祝った。病気のため、国語調査委員会を辞す。
4月、加藤静子に求婚。
7月、西丸家が秀雄の埋骨のため馬籠に行く。鶏二、蓊助が同行。
8月、「汎信州会」が発足。
10月、「信濃協会」が発足する。
|
37 |
1 |
| 1925 |
14年 |
54 |
1月、鷹野弥三郎により、「汎信州会」の機関紙、「汎信州」が第1号として発刊される。
1月、「伸び支度」を「新潮」に発表。
3月、「アルス社」から「感想集 春を待ちつゝ」を刊行。
「浅瀬を奔り流るゝ水のごとく」、「透谷君の三十回忌に」、「芭蕉のこと」など
5月 文章倶楽部5月号に「千曲川旅情の唄」として始めて詩碑が掲載される。 拡大図
6月 「「若菜集」時代 寝ごと (詩碑に就いて)」を「日本詩人」に発表。
|
(上略)先月の「文章倶楽部」に文壇の漫画が出ていて、その中に、何か斯う、芝居の書割りのような田舎の景色を描いたところがありました。向こうの方には、道中記にでも見るような石碑が立って、それには「千曲川旅情の歌」としてあるし、その中には、私として一生の望みがそれで叶ったといふやうなことが書いてありました。もし若い時分に詩に志したものが、年をとって自分の古作を石か銅にでも刻されるのを見て、自分に一生の望みがそれで叶ったでも思ふとしたら、これほどの滑稽はありませんからね。ああいふところがカリカチュウルかとも思ひました。自分はさういふ積もりで居るものではありませんと、漫画の弁解でもしようものなら、益々自分は漫画中の人になってしまひますからね。
|
8月頃から加藤静子と「藤村読本」の編集に着手。全六巻を大正15年2月に刊行。
|
38 |
1 |
| 1926 |
15年 |
55 |
4月、柳子とともに、楠雄がいる馬籠の緑屋を訪れる。
5月、鶏二に半農半画の生活をすすめて、楠雄のもとに送る。
9月、「嵐」を「改造」に発表。
10月、馬籠を再訪、「夜明け前」の準備を始める。
|
39 |
1 |
| 1927 |
昭和2年 |
56 |
この夏、取材のため次男鶏二(20才)を伴い山陰地方を旅する。
5月16日、雑誌「郷土」へ「消息(私の詩碑について)」を発表する。
|
「もともと、あれは信濃協会と旧小諸義塾同窓会の発起であった。鷹野弥三郎君は信濃協会を代表し、武重薫君は旧小諸義塾同窓会を代表し、東京と小諸の間の連絡を取って万事の交渉に当てられた。そのことは信濃協会の機関紙で鷹野君の編輯してをられた「汎信州」に精しい。鷹野君は最初の発起者でもあり、東京に居住せられる関係から、よく碑の話を持って私のところへ見へた」
|
7月24日、「千曲川旅情のうた」詩碑の除幕式に欠席、長男楠雄(22才)と蓊助(19才)が参加。
製作は高村豊周(光太郎の弟)
7月30日、「山陰土産」を「大阪朝日新聞」に連載。50回
|
40 |
1 |
| 1928 |
3年 |
57 |
4月より5月初にかけて「夜明け前」準備のため信州飯田方面より山を越え木曽路に入る。
10月25日、次兄広助死去。
11月3日、加藤静子(当時33才)と結婚、三崎方面に旅行。
|
41 |
1 |
| 1929 |
4年 |
58 |
4月〜7年1月にかけ「夜明け前」第一部を「中央公論」に連載する。
5月13日、長兄秀雄の妻、松江死去(根岸の松江姉さん)。70歳
6月13日、静子夫人と共に、こっそり詩碑を見に来たが、小諸駅にて「東信新報」の記者に発見され翌日、大きく新聞に掲載される。
9月、三男蓊助、ドイツ留学に出発。 |
42 |
1 |
| 1930 |
5年 |
59 |
5月13日、田山花袋が没する。 高樹院晴誉残雪花袋居士
10月、「市井にありて」 芥川龍之介君のこと
この年、経済不況により、信濃銀行、支払猶予となる。常務取締役神津猛ら苦境に陥る。藤村は見舞金として300円送る。
|
43 |
1 |
| 1931 |
6年 |
60 |
楠雄が結婚。
|
44 |
1 |
| 1932 |
7年 |
61 |
「夜明け前」執筆に専念。
9月、神津猛、自宅を除く全財産を信濃銀行債権者に提供して上京、藤村宅に近い麻布に住む。猛の四男康雄ら、しばしば借金の依頼等に訪れる。「この頃の先生は然しもう余り有名になっていて、敗残の父の心の支えとなっていただくには、少し忙しすぎたようである」(「後凋」あとがき、神津康雄) |
45 |
1 |
| 1933 |
8年 |
62 |
2月、蓊助帰国。父の帰国命令に従わず、送金も断っていたので、神戸で鶏二から謹慎を命ぜられ、1年余り父に会えず。
6月、小田原の北村透谷碑の除幕式に出席。
|
46 |
1 |
| 1934 |
9年 |
63 |
1 |
47 |
1 |
| 1935 |
10年 |
64 |
9月、柳子が井出五郎と結婚、佐久臼田町に赴く。
|
48 |
1 |
| 1936 |
11年 |
65 |
4月、「早春」、定本版「藤村文庫」第三編を「新潮社」が刊行。
6月、「岩波書店」より「感想集 桃の雫」を刊行。
7月、鶏二の結婚を認め、蓊助の謹慎を解く。
7月、19年間住みなれた飯倉の家をたたみ、第14回国際ペンクラブ大会出席のため静子夫人同伴、有島生馬と共に南米ブエノスアイレスへ。
|
49 |
1 |
| 1937 |
12年 |
66 |
3月6日、東京日々新聞にこま子が養育院に収容された記事が掲載される。
5月、こま子が「悲劇の自伝」を「中央公論」に発表。
6月、帝国芸術院創設、会員に推されたが辞退。
10月16日、萎縮腎に倒れ、病臥。心労のためか。この年、神津猛一家、志賀の旧宅に帰る。
|
50 |
1 |
| 1938 |
13年 |
67 |
1 |
51 |
1 |
| 1939 |
14年 |
68 |
1 |
52 |
1 |
| 1940 |
15年 |
69 |
11月、「力餅」を「研究社」から刊行。
|
(略)東京に修行に出たのは十歳少年の頃でしたが、中仙道にはまだ汽車のない時分で、子供の足にも峠を三つも四つも越したことを覚えています。祖母が亡くななりました折にも葬式のため郷里に帰りまして、その帰り道に和田峠といふところを歩いて越し、下諏訪の方へ出たこともありました。
(略)それからずっと後になって、今度は自動車で和田峠を越したこともありましたが、あの峠の上まで行くと、西餅屋といふのが一軒残って、そこで昔ながらの力餅を売っていました。(略) 「力餅」 はしがきより
|
|
53 |
1 |
| 1941 |
16年 |
70 |
12月、真珠湾攻撃、太平洋戦争始まる。
|
54 |
1 |
| 1942 |
17年 |
71 |
1 |
55 |
1 |
| 1943 |
18年 |
72 |
3月、掛川俊夫ラバウルからニューギニアに向かう途中で戦死。
8月21日 島崎藤村、永眠 「文樹院静屋藤村居士」
|
56 |
1 |
| 1944 |
19年 |
1 |
10月、鶏二がボルネオのタラカン島沿岸で飛行機事故により死亡。
|
57 |
1 |
| 1945 |
20年 |
1 |
1 |
58 |
1 |
| 1946 |
21年 |
1 |
10月、掛川俊夫(の兄)、「農村文化協会長野県支部」から「島崎藤村論」を発表。
|
59 |
1 |
| 1947 |
22年 |
1 |
2月17日、「ふるさと友の会」の発会式が馬籠本陣跡にて行われる。
8月、平野謙、「筑摩書房」から「島崎藤村」を発表。
11月15日、藤村記念堂が完成する。
|
村の青年や女子達は、昼の生業を終えて、夜の山坂道を沢から材木を運び上げた。遠くの窯場から、一枚の瓦を縄で背負った子供たちの列が蟻のようにも続いた。/藤村を慕う村の人々の意地と情熱が、若きすぐれた建築家の心を動かし戦後荒廃の、しかも峠の一山村に、ついに美しい藤村記念堂が完成した。
菊池重三郎著「木曽馬籠」 発行 昭和52年 帯文(表)より |
|
60 |
1 |
| 1948 |
23年 |
1 |
1 |
61 |
1 |
| 1949 |
24年 |
1 |
1 |
62 |
1 |
| 1950 |
25年 |
1 |
6月、中村光夫、「河出書房」から「風俗小説論」を発表。
|
63 |
1 |
| 1951 |
26年 |
1 |
1 |
64 |
1 |
| 1952 |
27年 |
1 |
1 |
65 |
1 |
| 1953 |
28年 |
1 |
1 |
66 |
1 |
| 1954 |
29年 |
1 |
1 |
67 |
1 |
| 1955 |
30年 |
1 |
1 |
68 |
1 |
| 1956 |
31年 |
1 |
9月1日 加藤武雄、逝去 戒名は浄智院久遠冬海居士、墓は多磨霊園。 |
69 |
1 |
| 1957 |
32年 |
1 |
1 |
1 |
1 |