| 回数 |
開催月日 |
「たつご教室」での開催内容 |
語り部 |
原稿〆切日 |
| 1 |
2024年
4月27日 |
第1回 加藤武雄が編集した「日本総合文化財図鑑」とその背景について
|
江戸時代から明治時代、そして、太平洋戦争の終結から民主主義の時代へと、大きな変革の時代がありました。微細な日本人の心の変化を過去の事象から考えて見ることも決して無駄ではないような気がいたします。大衆作家として一世を風靡した地元の加藤武雄は「日本文化財図鑑」を編集しこの世を去りました。でも、この図鑑が実際に世に出たのは亡くなられた一ケ月後のことでした。生前、加藤武雄がどのようなことを考えながら推敲していたか。当時、多くの人々に受け入れられていた坂口安吾著
|
|
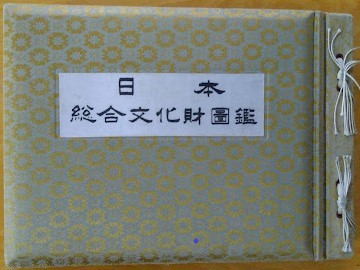
日本総合文化財圖鑑(表紙) |
|
「堕落論」等も参考にしながら考証を深めて行きたいと思います。 |
|
保坂健次 |
3月15日 |
| 2 |
5月25日 |
第2回 久保沢観音堂内の百体観音について
|
久保沢観音堂の堂内には、相模原市登録有形民俗文化財に指定されている百体観音が祀られています。
また、観音堂は津久井観音霊場第五番の札所にもなっています。
その観音像の作者は北原七兵衛と云い、他にも大正寺の百体地蔵を始め川尻八幡宮や大島諏訪明神の石灯籠、向原山王社の石鳥居等、多くの作品を残しています。
今回は長年に亘り、石仏研究も進めておられる村田公男さんに語り部になって頂き貴重なお話を伺います。どうぞお楽しみに。
|
|

イトヒバが聳える久保沢観音堂 |
|
村田公男 |
4月12日 |
| 3 |
6月22日 |
第3回 川尻八幡宮の境内で発見された錫杖頭について
|
昨年、の11月2日、広田小学校6年生による地域学習の中で大発見がありました。
その錫杖頭は高さが10㎝ほどの小さなものですが、そこには、2匹の龍やその下方に、蓮の花弁の彫金が施されていました。 これは神仏習合時代の名残か、はてまた・・・
|
|

発見された錫杖頭 |
|
保坂健次 |
5月 日 |
| 4 |
7月27日 |
・ |
・ |
6月 日 |
| 5 |
8月24日 |
・ |
・ |
7月 日 |
| 6 |
9月28日 |
・ |
・ |
8月 日 |
| 7 |
10月26日 |
茶の花忌 |
・ |
9月 日 |
| 8 |
11月23日 |
勤労感謝の日 |
・ |
10月 日 |
| 9 |
12月28日 |
お休み |
・ |
11月 日 |
| 10 |
1月日 |
・ |
・ |
12月 日 |
| 11 |
2月日 |
・ |
・ |
1月 日 |
| 12 |
3月日 |
・ |
・ |
2月 日 |
 「たつご教室」にようこそ tatugokyousitu.html
「たつご教室」にようこそ tatugokyousitu.html 「たつご教室」にようこそ tatugokyousitu.html
「たつご教室」にようこそ tatugokyousitu.html