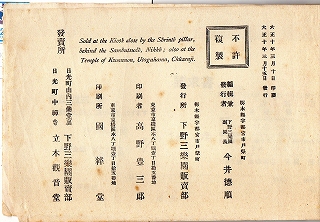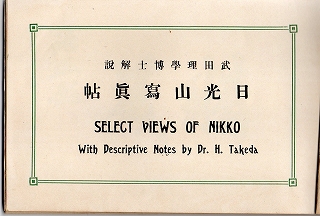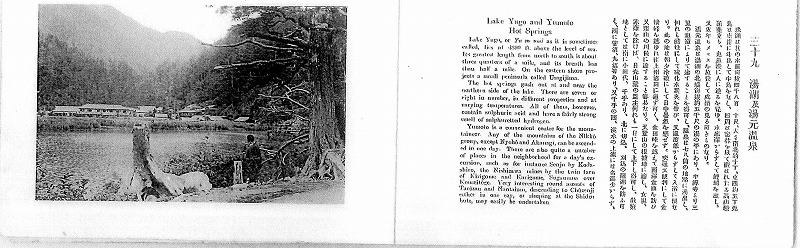�Q�W
�i�Łj
|
�@�吳�ܔN�̋㌎���{�A���N�Ԃ�œ����֍s�����T�Ȃ����B�������璆�{�K�֏\�N�ڂŏ���Č����B���|���҂�Ɠ����֍s���Č������Ȃ�A�����ď\��N�ڂœ��{�Ő������āA�������������āA��B�����S�̊ۏ��܂ʼn��������B�R�炵���R�ɂ͓o��Ȃ������B��Z��l�Ăƒ�����T�������̒��オ�����̒B�����ō��y�ł���A���Ȃ��݂̏������֓��ɝДO�����B
�@�������v���Ԃ�ŗ��Č���Ƒ啪�̂������Ƃ��ڂɂ��A��ԏ���傻�����h�ɂȂ����A���d���d�������̋������𑖂��ċ���A�o���邱�ƂȂ��J��ւ��������ւȂ�A���͎R���ւȂ�V�����������A�����֓d�d��ʂ��ĊтЂ����Ǝv�����B
�@�R���i�T���i�C�j����w�悭�Ȃ����B���H�����邫�悭�Ȃ�A���X�ɓ�����ׂ��o���āA�s�ē��Ȑl�ł��n�����ē��L�ʂ����Ăɂ��Ĉ�l�ł��邯��̂͗L��A����ʂɐ����ɂȂ����͉̂����S�n�悢�A�R���ɂ͐�p�̓d�����N���āA�_�ИŊt�X�H�����߁A���@�Z��ɔV��p��A�m������E�����̂͌��\�Ȃ��Ƃł���B�������L��̂������Ȃ����̂́A�։����̏O�k�Ȃ��������]�߂̐l�X�������H�ȑт��Ȃ��A���ʎᓒ�ȂǁT�]�ӉB���p���ɋy�Ȃ��Ȃ������ƂŁA���̕������R�Ȃ̂ł͂��炤���A���i�������j�ɘł����l�Ԃɋ߂��Ȃ�����暝��ł���B
�@���Ƌ{���r�R�_�Ђ̛�����������āA�����قƉ]�ӓ��ʂȌ����̒��֒邱�Ƃɂ����̂͂�邢�l�ł͂���܂��A�������y���ŏ����o���ċ��鏰�̏��f���┒���܂̂܁T���邩������̂ɂ͍��i�������j����������Ȃ��B�����Ă��T���ӓ���̌�����ʂȂ�A�ދ���ȏ��Ŏ�̂��͂�
|
���d���d��
���R���i�T���i�C�j�F�Ȗ،������s�R���ɂ���n���ŁA�����R���Ƃ͓������Ƌ{�E�����R�։����E������r�R�_�ЁE�ƌ��_��Q�@(�Ȃǂ̂����т�����
�������]�߁i���傤�����j�F�u�~���v�͔������āA�ۂ߂����̂��ƂŁA�]�߂́@�P
�n���߂̂�����B�����B�Q�@�m��
�����H�ȑсF�o�ƏC�s�҂�����H���C�Ȃ��߂Ƃ邱�ƁB
���ʎᓒ�F�m�ƂŁA���̂��ƁB
��暝��i���傤���j�F
|
|
�Q�X
�i�Łj
|
�ɁA����ɒʂ����ē��l��u���āA���J�ɐ���������悳�����Ȃ��̂��A�ނ��ē��L���̂��ċ���̂�����A��������߂Ă悭���j�ƈ�����ׂČ�����o���锤�Ȃ̂ł��炤���A�����ʓ|�Ȏd����������ɒZ���ԂɌ��I�炤�Ɖ]�Ӑl�X��ਂ߂ɂ͕s�K�c�ł���A������S���l�I�����y����s�Г�ƂȂ�A�i���Ɉ�X�ڂ���������������悳�����Ȃ��̂��A���݂̔��j�D�ƁA���Ăցu���āv�Ɖ]�ӂ킩�肫�����D��������A���X�ɊȒP�Ȑ����ɍs���������ł͔@���ɂ��s�e�ł���A��ւΓ��������i�����͂��j�̎��̈ꕔ�������l�`�̐����Ȃǂ́A���т̉����邩��m���ċ���l�ɂ͂悢�����Ȃ��Δ[�����ɂ������炤�B�l�`�̐���҂̖��Ȃǂ͂Ȃ������Ȃ��B�����c���҂͏�ɐl����ق߂��Ă̂��āA�ꌾ��悷��l�ɏo���͂Ȃ��ׂ߂���ł悢���Ǝv���ċ���̂ŁA�������ӂ������Ă��̗l�Ȃ��������ċ���̂ł͂Ȃ��̂��炤���A���ǂ��P�n�͏[���ɂ���Ǝv�͂��B
�@�����������i����j���̕��͕����ň�t�ł������B������������|�����ŏ[�����ċ��āA��������U���ɂł��o��Ƃ�邢���Ƃ����Ȃ��̂ɂЂǂ�������B�c�ɏ����̕Ȃő��X�����Ȍ�熂�M������A���R���Ȃ��̂ɐl�����������肷��Ύ��������炭�Ȃ���̂ƐS���Ă��A���ɂ͉��\�ȋ������֖ڂɂ����Ƃ�����A���T���Ӕy�i�₩��j�͏[���ɌP�����ď����̐E�̉����邩�����ցA����ł��킩��ʓz�i��j�͖ƐE�ɂł����Č���Ȃ���A���l�������f���邱�ƈ�ʂ�ł͂Ȃ��A�e�p���{�̏����͐l����ی삷�邱�Ƃ������ɑ��В���̂�{�E�Ƃł��S����̂��A����݂���s���邱�Ƃ̂ݍl�ւċ���ɂ͍��������̂ł���B
�@�����̒��͉E�̗l��桂ŁA�U��������i���j�o�����A������K�͂�ɂ��e�p�ɒʍs�~�߂̖��Ɉ��ӂ̂ŁA������ਂ߂ɗ���l�̝ɂ͜n���ď����A�J����������{�K�ɓo���Ċ������T���Ɏ��R�̋��ċz���������܂��ł���B
�@�����ł͑�ւ��s�����R�ɂ��o�炸�A���܂����v���Ă���ł��r�N�i���j���̂ŁA��m���Ɩ{�{�Ƃ�K
|
�������сi�����͂��j�̎��F
�y�i�₩��j�F�P �i���j�������̐l�X�B��ƈ��B�ő��B�ꑰ�B������B�@2�@���ނ̎҂����B���ԁB�A���B�Ƃ�����B���ɁA�悭�Ȃ��A���B
|
|
�R�O
�i�Łj
|
�˂��ɂ����Ȃ������B�����͋��ɓ�r�R�_�Ђ̕ʋ{�ł��邪�A�ߘ҂͎Ж����ŏ������C�U�Ɉӂ����T���Ȃ��ׂɁA����e���Ȃ��L�l�ł���B��m���ɐ̂��炠���������쓃���قɈڂ��āu�����v�ȂǁT�]�ӂ����߂����D�������Ă��邪�A���ꂪ�������ċ��������F�Ȃǂ͍r�ꎟ��A���͗������͌X���Ɖ]�ӎ���ŗ܂̍Â����ւ����Ȃ��B
�@�A���������Ŋ��i�قƂ����́j�@�ؐ��i������j�Ɏʂ����̂ň�x�͐���s���Č������Ǝv���ċ������A������ʍs�~�߂ƂȂ鋰�ꂪ����ƁA����l���璉������Ă����̂ŁA�J�V�̓���I��ł�������ƌ����ɍs�����B���]�����`���͌����v�X���ŁA�����R�A���ߋ����ꂽ�A�������j铎R��ɃJ�E�V���T�E�ƃ��V�g���X�~���Ƃ𑽗ʂ�ᢌ������ƌ��͂ꂽ������粂ł��邩��x���g�������������̂��A�����̌��ɂ��ƒj铂̃c�K�U�N���͍��͈�{���Ȃ������ŁA�������̃n�q�}�c���������̂͐△�ɂȂ��������ł����B
�@�̂͒��{�K�֍s���Ƃ����Ă͒��X�����Ȃ��̂ł��������A���͓d�ԂŔn�Ԃ܂ōs�����l�ɂȂ����̂ŁA�ꐡ���ʂ��ŗV�тɍs�����̂͂��Ă��֗��Ȑ��̒��ł���B�����O�\�ܔN���l�\�N�ƈ��U���^���������āA��J��։��ӂ��V���̑啔�����j�ꂽਂ߁A���͒ʘH���d�ԘH���T�����p���𑖂邱�ƂɂȂ��ċ���A�]���ė����֍s���ɂ�����֍s���ɂ��֗��ɂȂ��čD�s���ł���B�d�Ԃ̏I�y���p�̔n�Ԃ̈�����ŁA�����ɝɌ��̒��X���o�āA�������l�X���Ăэ��ނɖZ�����B
�@�d�ԂŔn�Ԃɒ����������́A�ו����u�����v�ɑ����Ĕn�ŗ��X�܂ő��点�邱�ƁT���A�k�����{�K�Ɍ������B����粂������傻���悭�Ȃ��āA�����Ԃ�ʂ���v�`���ւ��邳���ł��邪�A�������^�тɎ���Ȃ��̂͑�����c�ꂹ����Ȃ��A�����̐l�Ԃ������畨���I�ɂȂ����ƂāA���{�K�֎����Ԃ�ʂ���ƌv�`����ȂǛ��ɈȂĂ̊O�Ȃ͂Ȃ��ł���A��s�킪�֗�������Ƃāi���{�ł͖������X�����͍s���܂����j�����̎�֑������͂Ђ��đ啗�ɏ悶�Ĕ��Ō���l�Ȃ��̂��A���̒��ɂ͔n���Ȑl�Ԃ��ɑ����邪�A���{�K�֏捇�����Ԃ�ʂ���l�ȍl���N���z�́A�S�{��ւł���э���Ŏ���
|
�����F�i�ǂ��]���j�F���̌��B���̌����B
���]�����`�F�����A��������̎�C�B���U��ʂ��ČܕS�镶�ƂƊւ�肪�[���B���˔ˎm�̏o�g�B�����C�O�Ƃ͉����ɂ�����B
���c���i�������j�F��яj�����ƁB�j��B
|
|
�R�P
�i�Łj
|
�������܂��И���ਂ߂ɂȂ邾�炤�B
�@�n�Ԃ��o�ĝɒ��s���āA�O��r�̕����̉������肩��A�H�͈ꐡ��J��̉E�݂�ʂ邱�ƂɂȂ�A�]���đ��Ɉ��ӈ���̂��Ԃ��ɂʂ�銳���Ȃ��A�X�ɍ��݂ɂ���A�[�V�i�݂��́j�������Đ[�V�̒����ɒ����A����͑�铑�̘̂H�̂����ɂȂ���������ŁA�����͂��̕����������B��粂̊R�ɋH�i�V�������i�M�̎Ⴂ����O�{����̂����������̂͂��ꂵ�������B
�@�[�V����o����y�ɂȂ����A�؉A�ŗ������̂ɁA�����������ɔ䂵�Ă͋}�ɏ��̂ŗL��B�n�������ɂ��������l�������z���ꂽ�̂����ꂵ�������B�₪�ĕ����ʎ�̓��̌����钃���ɒ����A�����ĉE�̏����Ȃ̂������A���̑�Ȃ̂��ʎ�Ɠ����R�u�ɂ͏o�ċ��邪�A���ݕ��y��\�ݕ��̒n�����ɂ͋t�ɏo�ċ���A�ǂ��炪�������̂������͝В肷�邱�Ƃ��o���Ȃ��B
�@�������������قȂ��̂��A���m�������̋������Z���̂ō��̐܂��ʓ��Ɍ䏬�x�Ɖ]�ӂ��ƂɂȂ�B���m�����͍��n�Ԃ́u�����v���S�c���ċ���̂ŁA���T�ɂ̓g���L�`������ᢌ��҂Ȃ�_�R�Ћg������A�̂悭�R�֘A��čs�������Ƃ�����̂Őq�˂Č������A��������Ĉ��͂��ɂ��܂����͎̂c�O�ł������B
�@���m�������烂�[��Ƒ��i�����ЂƂ����j�o��Ɖ��Ƃ��]�Ӓ���������A�s�v�ȏ��Ȃ̂ł����x���Ƃ��Ȃ��A���ꂩ��͂��ő啽�i���ق��Ђ�j�̓����ɏo��B�ߔN���T�̘H�̍��̏��������ɒ��X���o���āA�����̒����Ɩ��ł��Ă���A���X�͑����ɂ����͂����Ɍ������̂悢���ŁA����o���Č���K�v������A���]�͈ꐡ�O�R��̂���Ɏ��ċ���B�i�O�R�ɂ��Ă͖{�����N����j�ɂ���~�V�{�m�̋L�����Q�Ƃ��ꂽ���j�B�n�Ԃ��獟�|�܂ŎO�l�\���ŒB���邱�Ƃ��o����B�������̒n���͓�r�R�_�Ђɑ����ċ���̂ŁA���Ђœ��������Ă��Ƃ͒n��܂���D�ő݂��̂ŁA�؞҂��Ƃ����āT���̂��ċ���̂��Ɖ]�ӂ��Ƃł���B
|
�����l���i�ɂ�ɂ�ǂ��j�F�����̎Q�w���ւ������@�ŁC���ɏ����̂��߂ɓ��݂������ɁB�����͂����ŏC�s�Ȃǂ�����B |
|
�R�Q
�i�Łj
|
�啽�̓�������E�̕��̎R���ɓ���H�����ɂ��ċ���̂�F�߂��B���͒n���̏��������̑�̐����̕��ւł����铹���Ƃ��v�������A�����V���������߂�@���Ȃ������B�啽�̖{�c�̖���m���Ɨ~����l�́A�j铂֊�������̖ؗ��̒��֓���K�v������A���ɐ[�тƉ]�ӂ��Ƃ������邱�Ƃ��o����A�����ɒ������ē��H�ɏo��Β��ɐg�������l�̊Ԃɂ���Ɖ]�ӏ��̛��Ƃ��ʔ����B
�@���{�K�͋ߔN�Ă��Ă��痷�X���R���̕��������͉̂q���㌋�\�Ȃ��Ƃł���B�ȑO�ΐ��ɂ������T���ĉƂ����������͐�Ђ��̂ɂ��ϕ��ɂ��ΐ��̐���p��̂ŁA�����̗l�Ȑ_�S���̎҂͒��{�K�ł͉����H�ӗE�����Ȃ��������̂��B���ł͏Ă��c�����Ƃ̊O�͊F�R���ɂ��邾���ł��S�����悢�A��K�O�K���̗��h�ȗ��X�������Ȃ�ׂĂ��邪�A���������܂Ō����������l�ȉ��������Ȃ̂ŁA�����Ɏz�l�ȏ��ɐ������韆�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�|���K���i���߁j�����̂��l�ɍs�����Ōΐ��̑�K���������̒n�ɂ��錳�̃��V�A�̑�g�̕ʑ��Ѝ���ŁA����𑽏��������ė��X���c��ŋ���̂ŁA��ʂ�͏��Ȃ��ՐÂŎ��������炵�̂悢���|���傢�ɟ��ɓ������A�ډ��V�z�̎O�K�����������đ����̋q�̏h���ɂ��֗��ƂȂ����B�㌎�̏��߂̂��ƂŒ��x�q���������ċ��Ȃ����Ȃ̂ŁA��̂��Ĉ�����ԂɈ��Q���ɗp��āA���i���j�؍݂��o�����͍̂D�s���ł������A����ɓ����ƈ���������Âɒʍs�~���Ȃ������ł������̂сi���j����A�����̊�����Ȃ������ł��S�����悢�B
�@�ĉ��̓�K�ɏo�Ē��߂�ƁA���ʂɂ͔����R�����������A�E�ɂ͌ΐ�����ʂ��o�����ƌ��ւ�܂ŁA���R����O�p�`�̍��ؗ��̒j铎R�����т��ċ���B�����̍��ɂ͑��O�֎R�̂U���̎��i���U�j���ԂƍX�ɑ��̓�ɂ̓Y�b�g�Ⴂ�h���V�R��������B���钩�̂��ƁA�O�钅�����q�̈�l�����̌i�����Ĕԓ����Ă�Ŏ�X�̎����ᢂ��ċ������A�������̔���̍��ՂɂЂǂ������āA���낵���ЁU�̓����Ă���R���Ȃ��ƒQ���ċ���ƁA�n�C���l�Ńn�C�A�ƒ��q��������ԓ��̐،�����ӂ���ċ����A�ЁU�����T�Ђǂ������Ă͈ꐡ���Ȃ͂Ȃ��B
|
�����l�i��������j�F�P �����̖����ȂǂɂƂ���Ă���l�B�����������Ȃ����{�̒Ⴂ�l�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q �m�ɑ��āA���Ԉ�ʂ̐l�B�����̐l�B
�����Ái�ނ�݁j�F�P ���ʂ␥����l���Ȃ��ŁA�������ɕ��������邱�ƁB�܂��A���̂��܁B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q �����̏�Ԃ��x���Đr���������܁B�Ђǂ��B
�������i����j�F�R�Ȃǂ��������т������ƁB
|
|
�R�R
�i�Łj
|
�ΐ��ł͖������b�g���ɐǏo�Ă����̂܂Ɂi���j����p�͔������B�a�D�ŏo������q�����X����A���������j���āA���{�K���̃��_�ɏo�ė��̊ω���q���A���ꂩ�甪���o�������Ď�����ɏ��A���S��t�̑n���ɌW��Ɖ]�Ӗ�t���Ɍw�ŁA�������쓈�ɓ����Ēj铎R��q���ğd��̂ł���B���T���̖����͖�����݂̂łȂ��A���i����j��A�Ԋ�����߁A��������i����j���̕��ɂ͎�X��������̂�����B�M���~���Č𓌐��ɏc������̂��ʔ����A����̐��ɞ��V�Ɖ]�ӂ�����A����͐����D�T��̎����V�𗧂Ă��ÐՂł��邳���Ȃ��A���ݕ��̒n���ɂ͞����ƋL���Ă���A���������R���ɂ͍O�@��t���������y�������炾�Ɖ]�ӂ̂œ�����������Əo�ċ���B�U�Ɖ]�ӂ͕̂U�̗l�Ȍ`�̐ŁA�̂͑单�V�𑴏�Ɉ��u�������������A���͉����Ȃ��B�Ԋ�Ɖ]�ӂ͉̂ΎR��炵���ԐF�̊₪�I�o���ċ���|�ŁA�������g�t�̖����Ƃ��o���ċ���A���̊ω����͐��̓��̓���Ɉʂ��ꐡ���`�̒n�ł���A���̑��Ɋω������Ɖ]�Ӑ������N�o���ċ���B�ꐡ������̗l�ɂȂ��ė���o��̂����A�ɋߏ�����N�o��̂ł���A���̍����Ɖ]�ӂ̂͊ω����̉��̊�i�Ήp����H�j��������������̂ŁA�k�݂̉ΎR��Ƒ�Ɏ���قɂ���|����l�̒��ӂ���|�ƂȂ����̂ł���B���̖k���Ɋ��Ɖ]�ӂ̂�����A����͎O�p�`�̏������ۂɂ�����̂ő債�Ėڂɗ����̂��̂ł��Ȃ��B
�@���̓���ɂ́A���V�A�O�R�i�Ƃ�܁j�V���̏����O�l�����āA�ΐ��ɒ����ŋ���B�O�R�V�̗����ɎR�t�ɖ��������������ďZ�ЁA�ߖT���J�����ă\�o�A�_�C�R������X�̂��̂�����Ă��邪�A���т͉Ȃ�ǂ��Ƃ��A�ꐡ�����Ƃ���o�������悢�l�ł���B��������粂͍����ł���̂��A�J�����ƂƂ��ċ���҂��ق��ę_�O�N�O���̔@�����n�ɂ����̂��Ƃ��A���J�����Ƃ̎҂͑��v�w�A��̋��҂��Ɖ]�Ӓ��q�ŁA�v�͏d���傫�Ȑ悪�����܂ꂽ�A�c�`�̌L��ŐU�č��̍�����ڈʂ̐[���ɖx��N���ƁA�Ȃ�������ӂ�Е����č���������A���i�����܂��j�ɂ��ĜA��Ȗʐς��J�����ďI��̂��Ɖ]�ӂ��Ƃ����A�������̗����͋ɂ߂ė��Ȃ��̂ŁA��؏\�K�ʂƂ͋��������l�ł���A����ň���Z�\���J�����I
|
���D�T��̎����V�𗧂Ă��ÐՂł��邳���ȁF
�������R���F
������i�����j�F������p�̂����ŁC���w�ω����N�����ɁC�C���ω��ɂ��c�����k�␅�̓����Ȃǂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����I�ȗ͂ɂ���Ċ���j�ӂ��錻�ۂ������D���݂��̌�͎g�p����Ă��Ȃ��B�@���@�ϊ��s�\�@���i�J�{���@�����j |
|
�R�S
�i�Łj
|
��Ƃ͑������̂ł���B
�@���̓��肩�珮���֓���Ɛ�胖���Ɖ]�ӏ����n������A����粂�������H���Ƃ��]�ӂ����ł���A��������i��Œ��R�i�Ȃ���܁j�̈��֏o��Ɛ��i�����j�m���i���j�Ɖ]�ӏ�������A�l粎R�ň͂܂�����Hℂ̋��ł���B�̈�����������̒n�������ăX�Q�̗ނ�C�g�L���p�E�Q�Ȃǂ������ċ���B���͐������ɂ̓A�J�n����}�X���������Ă��邳�������A�M�͂Ȃ������܂͂��ėV�Ԃ��Ƃ̏o���Ȃ��̂͂��̂���Ȃ���������B�̐��͖��V�ƂȂ��Ē��T���ɒ����̂ł��邪�A��������Ώ��������ꂸ�A�S�R�u�����ꂽ�����i�݂����܁j��ƂȂ藹����̂ł���A�����đ�x�̕����痬��o�Ė��V�ɍ������V�������S���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邪�A����ł����V�̗����ɂ͉Ȃ葽�ʂɐ�������A�܂�n���𐅂����U�������ĈӊO�ș|�ŗN�o���Đ�ƂȂ��Čΐ��i���T���j�ɒ������ƁR�Ȃ�̂ł���B���m�݂̊̈ꕔ�ɂ͋͋���A�V�������ċ���O���Ƃ͍������������ċ���A�I�z�Y�~�̑��V���a������A����粂ɂ̓j���̑�����[�R�I�z�i���Ɍ����Đ����ċ��邪�A�k�C���ɂ���j���Ƃ͎}�Ԃ肪�啪�ق��Ă����ċ��Ȃ��B���̊Ԃɂ̓S�}�i���V�R�炢�ċ����B
�@�O�R�V�ɉ��ӂė��h�ȗѓ����o���ċ��āA�Ă����n���A�~�͐����p��ĊO�R�V�̉�����ޖ��o���ċ���A�n���Ƃ͂܂�n��ɗp�����̂ŁA�ѓ��Ɉ��ڒu�ɂ��낪���Ă���ۖ̏�����ׂ��ē������̂ŁA�ނ̓I�W�������̔@����v�Ȃ��̂�p��A�����ʂ����`�m����h���Ċ�������₤�ɂ��ėp���̂ł���A���m�ɍs���ɂ́A���̗ѓ��ɂ��ĝɒ��i�݁A�₪�ĊO�R�V�ɑ傫�ȃi���̈�{���̂���|���炱��ƕʂ�āA�ނ̋���n��ђ��������ɐi�ނ̂ŁA�����s���ƍ�����҂ĉE�ɍs���ꏬ�l�����邪����͖��V����҂���̂Ƃ��ł���A����ɂ��܂͂������ɍs���Έꌬ�̕S���Ƃ�����̂��߂��āA���V�̏㗬����A���ђ��������s���ƍ��Ɍΐ�������̂ł���A�ډ��͊O�R�V����Ҋ����_�ɏo�闧�h�ȓ����o���ċ��邩��i�����͍��̓��͒ʉ߂��Ȃ������A�����ꕔ��]�������̂�
|
���H���i�����݂�����j�F
���H℁i�䂤�����j�F�i�F�Ȃǂ����[���Â��Ȃ��ƁB�܂��A���̂��܁B
�������i���ザ��j�F�y�n���Ⴍ�Đ��͂��������A�������߂��߂��Ă��邱�ƁB�܂��A���̓y�n�B
���n���i����j�F
���`�m���F�`(��)���܂̖��B�×���茚�z�p�Ɏg���銣�����B�؍ނ̕\�ʂɖ����͂�̂Ŗh�����ʂ�����B
痂�
|
|
�R�T
�i�Łj
|
�ł���j����ɂ���Ē��{�K����S�R���H�ɂ���Đ��m�ɒB���邱�Ƃ��o����B���͏Ҋ����_����M��݂��čs���̂��悢�B�Ҋ����_�̉�����͑��Y�R�������Či�F���悢�B
�@���T���ɏM�ׂČ��ē��Ɋ�����̂́A���l���̎R�ɐ����ċ��閧�т̔������ł���B�����̎�������Ƃ��ăn�R�l�_�P�̐�����R�Ŗڂɂ����̐X�т��Ȃ��͈̂��m�̙J�l�������邱�ƈ�ƒʃ��łȂ��A����Ɣ����ɒ��T���̎l���̎R�̖��ю�ɏ�Ύ��́A�i�ɂǂꂾ���̕��v��Y�ӂ�ł��炤���A���̖��т���ď��߂Ē��T���͐�����̂ł���B���̏�Ύ�������Q���Ղ�₽��Ƃ��ċ���B���������琁����ŕ��͓�݂̎R�̒�����i���Łj�ɖV��ɂ��Ă��܂����A���������̏�ȂƂ͎�ɔߎS�ł���A���R�A�����x�̕��ʂ͎R�����������ɁA�ŕ��̒B����ʂ������̂��A�͖̝ɂ���T�������A����ł�����Ŗ��Ɍ͖�m���̎���������B���̂܁T�Ői�߂���\�N�����璆�T���̓�݂͈���̉e���ɂȂ��Ȃ�ł��炤�A�����Ēj铂̉������ǂł͍��̓Ŗ��ŕ���ਂɓ���Ƃ�Ԃ��̂��ʐԗ��ɂ���Ă��܂ӂ̂��B�����ɂ͐��땍�߂̎R�͖��_�����̌��݂̏�ԂƑI�ԏ����Ȃ��Ȃ�A�����R�����̔��y�͉��|�ɋ��߂邱�Ƃ��o����l�ɂȂ邾�炤���B���Q�͉v�X�N��A�R�͂��Â�A�l�Ƃ͗���M�d���Ƃ����Ӑl���͈ꖕ�̐��A�Ƌ��ɂ�����̂ł���A�����ɂȂ��Đl�̎q�͎�����A��߂�ਂ߂ɖS����T�̂��A�����Ċ��Ő��ł���̂��炤�B���̔@�����R���s�i�������j���Ă���|������i�����܂��j������Ƃ���҂��A�����Ɠ������A�������`�ԛ{�ォ��A�l�ނƂ��Ď戵�͂�A�Љ�⚠�Ƃ��Ȃ����q�ł���̂��Ǝv�ӂƁA�����ꍏ�������l�Ԃ���߂Ă��܂Ђ����A�����Đ���Ă锒�_�ƂĂ��Ȃ������k�E�Ȑl�ނ̖ʏ�ɓV�����������Ă�肽���B
�@���{�K���߂ŊO�ɗV�тɍs�����͋߂��ł͉̃m�_�̊ω��A������A�������ȂǂŁA���r�Ȑl�͒j铎R�֓o��̂��悩�炤�B�ΐ���x�i�߂��j���Ĉ������֍s���H�́A�̃m�_��ʉ߂�����̂ŁA�̃m�_����悫�͍לl���͌ɓ��舽�͊R�ɏ��Ȃǂ��āA���Ăɂ̓c�o���I���g�̔��Ԃ��ӂ݁A���H�ɂ̓��}�g���J
|
���������琁����ŕ��͓�݂̎R�̒���߁i���Łj�ɖV��ɂ��Ă��܂����B�F
��痁i�����܂��j���F �����܂�������
���k�E�i����ɂ�j�F�����łނ����C�c�E�ł���
�����i�˂ނ�j���āF�@�S�g�̊������ꎞ�I�ɋx�~���A�ڂ��Ƃ��Ė��ӎ��̏�ԂɂȂ�B�˂�B
�A ���ʁB�܂��A����Ŗ�������Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�i�\�́E���l�Ȃǂ��j���p����Ȃ���Ԃł���B �C��������߂ĐÂ��ł���B
�D�ڂ��ނ�B�ڂ����B |
|
�R�U
�i�Łj
|
�u�g�̎��Ԃɓ�����čs���A�̂Ȃ���̎R�������ƂȂ��Ȃ������B������͒ʗ�M�ŖK�ӏ��ł��邪�A���H�����čs����ʂł��Ȃ��B�A���H�炵���H���Ȃ��̂ŁA���X�Β��̊���̂�z�����薔�����t�Z�i�������j�������킯�čs�����v�����Ȃ��B�j铎R�ւ͒��{�K���璼��O�����j����A���N�p��������莵���܂ł����W����i�ւāA���݂����Ύ҂����߂ŎR�ւ����o��̂ŁA�o�R���͈�l���O�\�ܑK������B����ō������Ȃ�����\�ܑK�͏��v�ƂȂ�̂ŁA��r�R�_�Ђ͗D�ɝɐ皢�̛���������桂ł��邪�A����ł����������ێЂ͐\���ɋy���A�����A���Y���̎R���̎Ђ͍r�p�ɂ܂����Ă���̂ŁA�����P���č���ʂ������ȁB
�@�����ɍs���ɂ͏M�ŏҊ����_�܂ōs�����A���͑S�R�k���ɂ�邩�A���͈ꕔ�Ȃ�S���Ȃ�l�͎Ԃ�����邩�ł��邪�A�����͎l�l��̛��Ɍ����ڂ炵���A�ǂ����̑|���߂���ł��E���ė����l�Ȕn�Ԃ����{�ɉ�������A��Ԓ��͈�l�Г��l�\�ܑK�Ƃ��\�K�Ƃ����������A�z�l�ȏ���̂𗘗p���₤�Ɖ]�Ӌ��u�Ƃ����邩�Ǝv�ӂƁA���Ԃ͜A�����̂��Ɗ�����B
�@�̖k�݂ɉ��ӂďҊ����_�ɏo��ɓk���ꎞ�ԋ���v����A���̂炸�S���̂悢�H�ŁA�Ђǂ��������Ȃ��؉A���s���͖̂����ł��邪�A���V���R�s�̔n�����ɒʂ�̂őe��Ȕn�q�ɏo���ӂ̂͌����ėL����Ƃł͂Ȃ��A�������M�s�͐��V�ɂ͉Ȃ菋�����Ƃ��S�傹�˂Ȃ�܂��B
�@�Ҋ����_�ɂ͒鎺�і�Ǘ��ǂ̗{���ł�����A�ނŔq�ς��������A���ӂɌ���Ɖ]�ӌW���̌䌾�t�Ȃ̂ŋɏ]���Đ��ӂɌ��邱�Ƃɂ����A�r���V�R�o���ċ��āA�n���V��������Ă��鐴�����n�I����ċ���Ԃ��A�召���S�̃}�X���j���ŋ���̂������ł���B���O�ɂ͐��V���R�ŗp���d����ᢓd��������A�߁X�V�����āA���R�܂� ���d����ʂ��ĉݕ��̉^�����J�n����̂��Ƃ��A���ɂ̍H�v�͓��荞��Ő�ꃖ���̎O�{����粂ɂ͉��Ƃ������̏o�����Ȃǂ��֏o���āA�������q�Ƃ��������ӑR���炵�߂ċ���B
|
���t�Z�i�������j�F�t��(�������傭�j�@�P �C�o���ȂǁA�Ƃ��̂���Ⴂ�B�܂��A���������̐����Ă���r�ꂽ�y�n�B
�@�@�@�@�@�Q ��Q�ɂȂ���́B����܂ɂȂ���́B����̑������Ƃ��B�@�@�R
�l���Q���悤�Ƃ���S�B���S�B�@���@�i���j�ϊ��s�\�@�����{�h�̍���
���W��i���傤�j�F�P�@���_������ΏۂɏW�������C�@���I�Ȑ��_��Ԃɓ��邱�ƁB�܂��C���̐��_��ԁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�x�m�R�E���R�E���R�Ȃǂ̗�R�ɓo��C�s�҂��C�s���邱�ƁB�@�R�@ �R�̒���B�Ⓒ�B
���Ύ��i��������j�F�_�ЁE���t�ɂ��Q�肷��l�B�ΎҁB
�������i�܂�����j�F1.�{�Ђɕt�������_�ЁB2.�����������B
���ێ��i��������j�F�{�Ђɕt�����A���̍Ր_�Ɖ��̐[���_���Ղ�����(�₵��)�B�i���͖��Ђ���ʁB
���d���i�Ă������j�F�S�̑����j������荇�킹���j�B�܂��A�P�[�u�� �J�[
���ӑR�i����j�F��낱�ԗl�q�B��낱��ŁB |
|
�R�V
�i�Łj
|
�@�Ҋ����_����O�l�����s���ƒn�����V�ɏo��A���h�ȋ����o���ĕ��̂Ɠ��T�ċ���B�n���̒����̌����ӂɃ`���C�Ɠo��ƒ����Ȃ��݂̗����̑�ŁA�������o���ċ��Ċϋq�̋x�ނɕ֗��ł���B�����̑�ɂ��č�H�����ƕ��ꒃ�����p�ՂƂ��i�������̂�����A�ꎞ�����̑�ȂǁT�j���ċq���Ă��̂����A���͜E��Ă��܂����B
�@���ꂩ�璩�Ȃ����w�����ď�������o��̂��A�̂͂���粂����ꃖ���̓����܂ň�тɃI�z�i�����̗тł������̂��炤���A���͖��c�ȐՂ��~�߂ċ���ɂ����Ȃ��B
�@�������ň�Ԏ����̂���ЂȂ̂͂��̗�����̏�̓o��ł���B�i�̂悢��ꃖ�������V�ɂ͓��A�͂Ȃ��A����ɍH�v�A�y���A�n�q�A���q�̌Q�ɏo���ӂ̂��@���ɂ���ɂȂ̂ŁA�ʘH���l�ւċ����̂����A�t�g�������Ƃ���q�c���i��������j�̌����S�ē����ɏo��H��ᢌ������̂ŁA��������ɏЉ�邱�Ƃɂ���B�������̗����̑�̒��X���班�����Ɠ��̒����ɓ�O�\�ؒ��̕��n�������āA�����������|�ł����Ė�҂����炵�����Ƃ�����A���T���獶�̕��ɍלl���ʂ��ċ���A�R�i���j�ďҊ�������ᢓd���֓��삩�琅���Ă̂��Ǝv�͂�T��̎c�[������A���̌����ĉE�ɂ���לl��i�߂悢�̂ł���B������̏㗬���������i�݁j�čs���ƐF�X�Ȍ`��������̊Ԃ𐅂�����T�̏�͜��i�������j�Ɉꗗ�̙J�l������A��͈��͋��܂舽�͜A���Ȃ邪�A�ɒ����s���ƁA���݂��Q�����߂����ċ����Ȃ��Ƃ��y�Ɋ₩���ւƂшڂ��Ĕފ݂ɒB�����T��������A�����ł͗��h�ȑe�S�����˂��Ă��邩��n���֎��R�ɒB������ł���A���T�Ő��n�炸�ɍs���ΐ�ꃖ���̓����̒����̏��ɏo�邪�A�H�̂͝�����Ȃ��炵���B���n���čs���Έꐡ�����ł܂��Ⴂ�J���}�c�Ȃǂ������ċ���A�Q���i�ނƊԂ��Ȃ��I�z�i���̖��тɓ���A�I�z�i���Ɍ����ĕS�ڒ��X����J���}�c���������邪�A�����ċ���ȃI�z�i���ŁA���т��i���Ă��悢�A�n�͊T���ĕ��R�ŋ͂ɏ㉺����݂̂ł���A�ђ����͓����ʂ����A���s���̂ʼn��V�����P���قł���B���̃I�z�i���̏��т͐�ꃖ���̐��ɘA���āA�₪�Ă͓��{�̓���̉����
|
�������|�i���₪���j�F�����������邱�ƁB���ɁA�ŋ��〈�����̂��߂̏��������邱�ƁB�܂��A���̏����B
|
|
�R�W
�i�Łj
|
�̒n�ɋy�сA�������ꃖ���̎l����㔂��ċ���̂����A��粂͑��Ŕ��Ȃ���̂ŋH�Ɍ���|�̂��̂ł��邩��A�X�т̎��L����l��C�{���s�̍ۂȂǂɂ͓��ɗ��Ĉꗗ�������̂Ǝv�ӁA��������N���ɂ܂��l�̎q�̎�ɂ��T���Ĕ��̂���T�����m��Ȃ��B
�@�т̒����T���Đ��k�w���čs���Ə\�ɒ��ŁA�ꐡ�k�Ɍ����Đi�ނƏ����ȍ�H����邱�ƂɂȂ�A�H����{���邪������s���Ă����ɍ����邩��S�z����ɋy�Ȃ��A���������Ă���i���j�ƉE��ɉ���ƁA���T�ŏ��߂ĘH�����A���̂�����ĎR�̐��ɂ��ĕ����k���琼�̕��ւ���i���j�~��ɐi�ނƓ�l���ŁA�̊Ԃ��珬�c��m����������A�т��o����ăp�b�Ɩ����Ȃ��Č������ڂ̑O�ɊJ�W�����A�O�ʂɂ͑O������㔂��̎R����i�킾���j�܂��č��̕��Ɏ����x�̈�p�������B�����s���ƘH�����A���̂��s���ƒ��ɕ���ɕ����A�����̂������ɍs���ď��c��m�r�ɓ����Ă��܂ӂ̂Ő��������ċ���ɂ���˂Βʍs�͏o����A���̂��̂͒r�̂ӂ��������đ����݂ɋ߂����ŊO�R�V����̓��ɍ�����A�r�̐��͑���������̂ŁA�r��x��H�͎��ɒr���ɕ���T���Ƃ�����B����Ŏ��ɂ͍����̏�������������̒��ɓ���|�������āA�m��ɂ������ʉ߂ɂ͍������鍢��͂Ȃ��B��ɒr�ȂɃ~�d�S�P�Ȃǂő�����i���Ƃ����j���l�ȏ��͊F���ł��邩��S�z�͂���Ȃ��B���c��m��͌��ݕ��̒n���ɂ͒r�炵���L���ĂȂ����A��J�̌�ɏ������̗���ʂȏ��𗧔h�Ȓr�̗l�ɈĂ����y�����i��j�l�ւĂ��A���̒r�̓��`�c�g�r�炵���戵���Ė�Ђ������̂��B�O�R�V����̘H�ɍ����Ďb���͑��ɕ��i������j�ꂽ��טH�����ǂ�̂����A�₪�ė��h�ȓ��H�ƂȂ��āA�R�̐���ʂ��ē��k�ɑ���̂ł���B��ɗ��߂��đO�q�̎O�{�̓��̉E�̜l�͂ǂ����Ɖ]�ӂƁA����͏��c��m���̓��̉��𗪖k���ɐ��ɑ����āA�т̒[�̑��̒��ɒʂ��A�₪�ď\�����ŊO�R�V����̘H�ɍ�����̂ł���B���Ԃ��P�T�̂Ȃ��ꍇ���͒r���߂���̂�����Ȏ��ɂ��̘H���s�������͑�ɒZ�k����桂ł���B��粂͋ߔN�䗿�ǂŃJ���}�c�̐A�т�����ċ���̂ŁA��җ��h�ȗт��o���邾�炤�B��������ਂߍ�N�����悭����
|
�R�X
�i�Łj
|
�Ɖ]�Әb�ł���B
�@���ꂩ��ĂуI�z�i���̗тɓ����Ă���i���j����ɓ��k�w���čs���A�ɒ���������i���Â݂��ǁj�ɏo��A����͘H�̉E���̊R���ɂ����Đ������₦���N�o���ċ���A���p�ɍ��x�͂Ȃ��l�Ɍ������R����~��Ɉꐡ�����ł���B���|����E�ɐ�ꃖ���̈ꕔ���f�˂̌����������B�����߂��A����i���j�Ɖ����Ĉꐡ��������n�蕜�ɕ�����ăI�z�i���̗тɓ��荶�ɂ܂����ď����~�肬�݂ɂȂ��Đi�ނƁA�Ԃ��Ȃ������n�鋴�ɏo��A�_�݂͋��؎}�������͐Âɗ���A�i����邢�Ƃ͌����Đ\����B���ꂩ���ɂ��č��ɏ����s���ď�������ƑS�ʂ͊J���āA���T�ɂ��X�ј����̎S�����ċ���B�ꌬ�̕S�����̑O�������čs���ƁA���͉����Ȃ��Ƃ����A����G�̔ɂ��������s���Ɠ�O���œ��{���Ɠ��듹�ƕʂ�T���֏o��
�s�������@���������@�����������@�����@�x�����������@���������������@�x�����������@�v�����������������@�Ɖ]�ӊ�ȓ�����ׂ��������Ȏ��ŏ������Ă���B
�@���|���瓒���ɍs�����͕ʒi�\���ɂ��y�Ȃ��A���̂��猩��ƃT�����K�Z���������������̂��ڂɂ��B
�@�����ɂ͌�����ȗ��X���܌�����A�{�����N����j�Ō�Љ�Ēu�����ԓ��̋����R�c�����P���ȑO�ɂԂ�A�ߔN�g����������������Ɉ�����Ă���A���Ƃ͓�ԁA�ĉ��A�����A�n粗��قŁA�P�͎O���ȉ��̂��̓�O�ɂ����Ȃ��B���V��]�ސl�͓�Ԃ��悩�炤�A���Ȃ��Δ��͋��S�̂悢�ƂŎ������������l�ł���A��铓������͒m��ʂ����T���ł������ł��A�M�B�̐z�K�Ȃǂɔ�r����Ɨy���Ɉ��l�Ŏ����戵���悭�����Ȃǂł��킩�肪�悢�A�ނ��z�K�Ⓑ��̗l�ȏ��͐M�B�ӊO�ɂ͂���Ƃ���܂��B
�@�������߂ɂ͎U���ɍs�������Ȃ��Ƌ������Ӑl������l�����A�o���Ȃ����爫�i���j���̂ŁA�����܂߂Ȑl�Ȃ�J�V�ŁU���Ȃ��Αދ����邱�Ƃ͂���܂��B���ɏM���ׂ���悵�A�����K�ӂ��ʔ������A��
|
�����r�i�����݂�ǂ����j�́A��ꃖ���̖k���[�ɂ���r���B
���f�ˁi�ʂ��Â��j�́A��ꃖ���̂قڒ������ɂ���u�B���͂ɂ͍��w�����̐A����������B |
|
�S�O
�i�Łj
|
�傠����͎U��ɂ͒��x�悢�����ł���A���͌É�J�i������j��������i���키�Ƃ��j������֍s�����悩�炤���A���H�����Ƃ͂ʐl�͐��V���R�ւ��s����A�R�H������ʐl�����m�A�؍��A������K�ЁA���͔����A���Y�ɓo��A���͋������������Ċۏ������薘�s�����ʔ����炤�B���ɑ���O�̂��́T�����U�b�g�Љ��B
�@�����̖k�����ݓ��̌��̖T��ʂ��čלl�����A���ߏ����}�ŏ���ƎR�������ɍs���B�����Ȃ���ċ��邪�債�ĕ����ɂ��T���Ȃ��A�����ō����ɐ���������A�לl�����ǂ��Ă���ɉ�������m�̈�[�ɏo��A���������ě��݂ɏo�邱�Ƃ��o����B���������͎l���R�ŁA��܂��ꂽ�R���̈ꏬ���n�ŁA�ېl�͍��n���^�e�ƌĂ�ŋ���A�͎R��藎�鐅�̗��������̂ŗ������Ȃ����������Ƃ��Ȃ��A�~�͌��X�ɕ���Ă��܂ӂ̂ł���B���ނƂ��Ă͑����̃}�X�������Ă���݂̂ł���A���̉��ɂ̓^�f�m�E�~�m�R�������T�E������A�����X�Q�̗ނȂǂ������ċ���B
�@���m�̃^�f�͓������т̋�ɂ����邪�A����͉ʂ��ă^�f�̎�ނł��邩���͑S�R�z�l�Ȃ��̂͂Ȃ��̂����m��Ȃ��A������ɂ����Ԕ��̓��K�Ȃ���̂͂ǂ������ۂɂ��炤�Ƃ��v�ւʁA�����������T���̖ؓ����~�̺�Ёi�c�N�o�q�̂��Ɓj���������邱�Ƃ���v�ӂƁA���đz����痂����Ĉ��̓N�������L�t�f�̔@�����̂ł��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������o���Ȃ��ł��Ȃ��B�܂�ʂ��Ƃ��������̎������f�Ёi�����H�j���₤�Ǝ���l�̂��鐢�̒��́A���̈ʂȂ��Ƃɝɍs���P�����Ă��ҏS�����疕�E����T�l�Ȃ��Ƃ�����܂��B
�@���m�����p�H�ɗ������ǂ��āA���O�i����Ƃ₪�Ĉꐡ���Ƃ��]�Ђ����ȏ��ɏo��A�V������Ƃ�⌴��Ƃł��������l�ȕ��n���V���c���ɍr�ꋶ�������ɏo��A��粂��얔�͑�샖���ȂǁT�i����B���̌��̓����Ƃ��]�Ӊ����̓��̍����Ɉꏬ�r������A�r�Œ��ɂ̓~�N���̈�킪��ʂɐ����ċ���]�������Ȃ����̂ł��邩��V�Ƀ~�N���m�r�Ɖ]���i�Ă��o�ӂ邱�Ƃɂ����B���ݕ��̒n���ɂP�V�O�V�@�ƋL���Ă��邠����ł���B
|
�S�P
�i�Łj
|
�@��쌴���c�ɑ����Ċ����ɒ����傫���V���n���ɋL���Ă��邪�A���V�͕���͖����ł���B���͖ؗ��̒������͍��̒��𑽏��㉺���čs�����Ɲɒ��ŋ}���V�ɉ����Ă�������Ђ��邱�ƂɂȂ�A��粂͋��陿�ܔN�̑�\���J�ɍr�ꂽ�|�ŁA���ł��c����������ȏ�Ԃ��v�Џo�ł��T�B�n���ɂ͗��h�ɋ����O�����L���Ă��邪���ۂ͈�c���Ȃ��A�����̎O�c�ڂ̋��̂������V��n�肩�ւ��ĕ��ؗ��̂����Â������b���s���Ɛ؍��̈�[���ڂɓ���B�؍��A�����̓�͂��܂����m�̑�Ȃ�l�Ȃ��̂ŗ����̂Ȃ��ł���A�����ē�ׂ͍������łȂ����ċ��āA��̐��ʂ͓��������ł���A���ݕ���̒n���ɂ͑�Ȃ���ʂ���Öڂɓ�����̂������Ƃ�����؍��Ƃ��Ă��邪�A��������p�Ŕ����ł͂Ȃ��̂��Ǝv�͂�T�^������A�ډ��V���]�X����ɏ[���̍ޗ��������ʂ�����^�𑶂���������̎m�̋�����ӂ��邱�ƁT����B�i�����Ђ����݂Ă����E�͒v���܂���ł����̂ɁB�ҏS���j
�@�ɂ��ď����s���Ə��k�̍����҂�Čɂ��T�����̂����������\�Ԏ��т��s���čX���V�����̎R���炨���������|�ɏo��A����k�͐����₦�ʗl�ł��邪�A�n���ɂ͈���ɋL���ĂȂ��B���̍r��o�����V��������ƒ��X�̜E�䂪����A�D�y���l粂ɔ�юU���āA�^���c���̔@���ɔߎS�ł������������ɑ���̂ł���B
�@�n���̏����؍������ւ͗ђ��H�Ȃ�������̌ɂ��ĒH��ΒB���邱�Ƃ��o����A�͋��ɐ[�����Ńt�i���������鑼���͂Ȃ��Ɖ]�ӁB
�@������߂��ď����Έꔪ���O�Ă̋��c�i���˂��j���ɏo��B����̒��]���d�����ʂ̎R�x���֒�R�܂Ō����邳�������A�����͐��V�ɍ���ɗ��������Ƃ��Ȃ��̂Ŕ@���Ƃ��\����B�����z���ΐ��V���R�ւ��A���͌I�R�̐얓�ւ��o����̂ŁA���R���炳���͌����͓��H���悵�ʍs���݂��Ɖ]�ӂ��Ƃł���A�����c���̘H�͋��N�͈�x�������������������A���N�͑��ؔɖɂ܂����Ă���̂ł�T�������������Ȃ��B
|
������i���������j�F
���p�i���Ⴍ�j�F ���肼���E�������ā@1.���肼����B�����������B���Ȃ��B�~�]����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2.���ւ�����B���肼���B�Ђ��B
������̎m�i�͂����j�F�w��E�Z�|�ɍL���ʂ��A�������킫�܂��Ă��邱�ƁB
�����Ёi��������j�F�����͂��������߂邱�ƁB�����ɂ�锻�f�B
|
|
�S�Q
�i�Łj
|
�����o�R�Ɋւ��Ă͌��Ӗ����Ȃ����N�̏n�m�����T�|�ł��邪�A�]���̓o�R�q�͑����V������đO�����ɏo�錎���݂̓����㉺����ɂ����Ȃ��B���{����o��Ƃ���ΐ�Ë�������o�葴���ォ�獶�ɐ܂�Ĕ����B�ЂɑO�����̈�p�ɏo�邱�Ƃ��o����A�A�r��������̏������̂���ł��ƌ��ӂ�������[���p�ӂ��čs���ΐ�ɕs�\�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���B�������̒��ォ��唚������o�ď�B�ɉ���͕̂K���������邱�ƁT�v�ӂ��A�����͖����V�����s����@���̂Ȃ��̂��⊶�Ɏv�ӁB���H�ɂ���ĉ��R����Βn�}�ɏ����������Ƃ��锒���̈�̒����̙|�ɉ���̂ŁA�H���@���r��ċ��邱�ƁT�v�ӂ��A��̒�������͈�m�P�ɏo���p���i���݂��j�𐴐��i���݂Áj�ɖ߂�A�݈�s����ꂽ�炱�T��Ɉꔑ���邩�A���Ȃ��Α����ɌܐF���̕��߂ɖ�c���ē���|�ł��Ώ[���ł���B
�@���ēˈȏ�̓��ŋ��������̗��h�ȓ��̂��ċ���̂͑������ʙ|�ł���B���݂ł͋�ڕ��̐��փS���S�����ċ��Ȃ����Ɋy�ȓ��ł���B�������o�Ĉꎞ�ԋ���ŋ����_�ЂɒB����A�Ђ͓|�ɂ����Ԃ���Ĉ���ȗL�l�ł��邪�A����ł���K���݈�ƌܑK����������Ă������̂͌䗘�v�ɕς��̂Ȃ�暝��i���傤���j�ł��炤���B�Ђ��璸��܂Ŕ����ԂƂ͂��T��ʂ��A�x�e���Ԃ����đS铂ňꎞ�Ԕ��ƌ��ς�Γ�������������̒��㖘�B���邱�Ƃ��o����B���̏�B���͊����ɐ��Q��ւ�Ȃ��̂Ő̂Ȃ���̘H�ł���A�O�\���T���i�Ȃ����j�O�\�ܕ��Ő����ɒ����A���|�͐����m���̓����̒[���c��|�ŁA�O�ɂ��������i���傶��j�Ȓn�����邵�A�����������Đ��w�Ȑ����ɂ��T���ŋ���B�i�������͂Ȃ����珬�e�n�Ƃ��Ă͓K�c�ł���B
�@�̂͌��ݕ��̒n�}�ɐ��y���ȂĎ����Ă���H�ɂ���Ĉ�m�P�܂Ŗ��l�̋����s�������̂����A�ߔN�疾�����ۏ��ŗ{�������߂ĐV�����Ĉȗ����h�ȘH���J����Ēʍs�ɂ͋ɂ߂ĕ֗��ł���B���|�����ւ������Ⴍ�ɉ��ӂē��������̂Ȃ�X�ɂ悢���炤�Ǝv�͂��B
�@�V���ɂ���Đi�ނƏ\�P���ŏ��̖k�����̊Ԃ��猩�҂ɓ���B���|�ňꐡ���̖��i�ɂ��Ĉ�
|
������
�������i���傶��j�F�y�n���Ⴍ�Đ��͂��������A�������߂��߂��Ă��邱�ƁB�܂��A���̓y�n�B |
|
�S�R
�i�Łj
|
������B�͉̂��ƌĂ�ŋ����̂��m��R���Ȃ����A�Éi��N�ň팩�L���Y����������{���n�n�}�ɂ́A���|�Ɉ���L���ă^�E�����Ƃ��Ă�ł���̂����ڂ낰�Ɍ�����B���ꂪ�O�̉�����c��▔�S���̑��i�ɂ�s���ł���̂ŁA�V���l暂̎����Ƃ͂Ȃ���A�����ɋߔNᢍs�̂��̂ł͗��n���ʕ��̓�\�݂̒n�}�ɋ����ƋL���Ă��邪�A���݂̂ɂ͐����Ƃ���A�����Ȃ閼�͐k�И��h��������\���j�ɂ��o�ċ���A�ߔN��ʍ������ȂČĂԂ��y�l�͈ˑR�Ƃ��Đ����m�����i���ċ���A�����R�͑O�L�̓����̓��ɐ�������������̂ō��|�𐴐��Ƃł��Ăт��ꂩ�琴���m���Ɖ]�ӂɎ������̂ł͂Ȃ����Ɖ]�Ӊ��������邪�����͔ۂƓ��ւ���v�����Ȃ��A���͌��ݕ��̒n�}�ɂČ���@���x���`���Ȃ��ċ���̂ő��̓����Ɍ��Әr�𓌖����i���k���̘r��k���Ɖ]�ӁA���k���Ȃ閼�͉Ȃ�Â����̂ňꔪ���O�N�o�ł́@�g���������������@�������@�i���������@���łɂ��A�ڂ��ċ���A���������n�X���i�Ώ��̋`�j�Ƃ��ĂԂ��̂����邪�P��A���s�͂�Ă͋���ʂ炵���A����Ȃ閼�͋����ɂ��Ȃ�Ŗ��������̂��Ɖ]�Ӑ������邪�A�����̂��͍̂�����p��A�Ⴕ���ꂪ��B�̖����Ƃ���Ƌ���̌����ʕ��ʂ̐l�Ԃ����̔@��������͈̂ꐡ�o���ɂ����B�����P�i�Ȃفj�n���������̒n�}���Q�Ƃ���K�v�����邪�A�����i�����ɂ��j�茳�ɂȂ����瑼���@���܂ł��Â���Ƃ���B
�@�k���̏��������Ă�����Ȃ��E�ɓ���לl������A����ɂ��čs���Ə��������ČΔȂɏo��A���|�ɏ��ɂ��������������C�W�i�Ȃǁj���z�i����j�����ċ���|����l���ւ�Ƒ؍݂ɂ�����㞂��Ȃ��炵���B���T���班������̎R���ɓ��荶����҂�לl�ɍ����ĉE�ɋȂ�ƕ��ΔȂɏo�āA���ꂩ�琅�ۂ�B���Čΐ��̗����ɏo��A�����̌Γ�����l�\�ܕ����͂��T����B���|�Ő����m���̐��͎O�S�ē˂������Ċۏ��ɒ����̂ŁA���|���㕔�ɔ�����Ɖ]�ӌ�����ł��Ȃ��낪�����ċ���B���ꂩ��לl�͋��낵���}�����R���i����́j���~���Ċۏ��Ȃɏo�āA�疾�{���łɒB����̂ł���A�����܂Ŕ�����̏ォ��O�\������͂��T��B
�@�{���ł̌����̎啔�͉��N���̎R���̓���̓��������ĉ���h���o�c����Ƃ����̂��A���q���Ȃ�
|
�������C
���R���i����́j�F�i�R���ƕ��n�̊Ԃ́j�X�����R���C�R�̎ΖʁD |
|
�S�S
�i�Łj
|
�̂ŏI�ɔp�Ƃ̔߉^�ɗ����������̔p�����C�������S�̈ʒu�Ɉڂ������̂ŁA����ɗׂĐV�z�̕��u��z���ł�����A���|�͋��閾�������N�ɔ����̋A�r�l�o�V����R�z���ĉ����Ę҂����Ŏ����ɂ��p�m�̒n�ł���A���͗{����ł���̂����I�ΐl���₦����L�l�ł��邩���m���֏o�铹�H���]���ƈقȂ��ė��h�ɉc�܂�ĎR�l�ɂ͍D�s���ł���B
�@�ۏ��Ƒ����̑�K���Ƃ̊W�͗P�؍��Ɗ����Ƃ̊W�̔@�������A���ۏ��̐�����K���ɒ����ŁA�₪�ď���̌����܂��Ⴊ����݂̂ł���B
�@�ۏ�����{���𐴐��܂Ŗ߂�̂͒��X�����铹�ł���A�Ȃ�}���ŕ����Ă��ꎞ�Ԕ��͂��T�鐴����������������ē����ɒB����ɂ͓Ԃ�����P��A�������̒���͑啪���|�ꂽਂߒ��]���]�O�����悭�Ȃ����A���̈ꕔ���������A�����ӂɒj铂̗Y�p���ނ��ċ���͈̂����i�ł͂Ȃ��B
�@���������N�ɓ����́u���v�A���̍��\�����ƂƂł����ċ���̂ł͂Ȃ����Ɩ^�����]�����{��́u���v�ɂЂǂ��ڂɂ����������́A�����c�������o�R��f�O�����ʂŁA���{�Ɏb���o��Ȃ������̂����ꂪ���R�̈�ł������A�\��N��̍����ł��u���v�͈ˑR�l�Ɍ��͂�Ȃ�����R�ē������邳���ł���B���A�O�ɓK�c�Ȉē��҂͂Ȃ����Ƒ{����������ŁA��������Ɖ]�Ӓj�����t�������A�吳�ܔN�ɎO�\��Ɖ]�ӂ���܂��i���j�R�����͌��\�N�ی��t���ő傪�����i�����܁j�������Ȓj�ŋɂ߂Ē��������ŁA���R�̗l�q�����X�ڂ����A���R�A���̖����Ȃ�m���ċ��邳����������͂ǂ��ł��悢�B�����͍��D�ē��҂��̂����ŏ��N�ɐ��E����B���l�͓����̏��R�͑��m���ċ���A�@��������������֍s���ėl�q�����Ă���ƌ����ċ�������ǂĂ͔����̈ē��ɂ����ɗ��l�ɂȂ邾�炤�Ǝv�ӁB���߂̎R�̈ē����͑O�������ꚢ�A���������ꚢ��\�K�A���Y�R���ꚢ���\�K�A�j铎R�u�É�蒆�{�K�������H�ɂċ���~�Ɖ]�ӎ��ł���A���l�ԂȂ�ē��Ҏ蒠���o�Ӊ����i�����炤�ƐM����B
�@�������璆�{�K�ɟd��̂ɂ͐�ꃖ����ʉ߂���̂��֗��Ŋ����Ǝv�ӁB���������ČÉ�J
|
���I�i���イ�����j�F��N���B�N���B |
|
�S�T
�i�Łj
|
�̈��g�������͏�������������P���ق��A��ɌÉ�J���班�������ɂ�������͑�w���H���C������Ă��邪�A���������n���̘H�����Ɖ]�ӂ̂��V����獻���ƍ��Ƃ��̂��ė��đ����H�ɂԂ��܂Ă邾���Ȃ̂����猩�����͂悢���A�����ɂ������Ɛ������A������P�v��������Ă��铒��̉����Ȃǂ͏��ɂ͂Ȃ���������������B�����֍s���ɂ͏��c���ʂ��čs���ƍ��y�ɉ��Ă����v������A�H�͏����܂͂�ɂȂ邪����ł��Ҋ���������Ԕ���������[�������̗��ɂ܂ŒB���邱�Ƃ��o����B
�@�É�J��粂͋t���i���������́j�����o�����̂ŋ����ׂ��쌴�ƂȂ蕗�v��������ʂ�ł͂Ȃ��A�����������̈�����̈ˑR�N�o���ċ���B�É�J�ŋ���n���ď����s���č��֏��l��B���ď\��O�����s���ƌ����̏��֏o��A�͈̂���̏��Ŋ����~�肽�肵�����A�O�\�ܔN�̑�r��ȗ��N�X���V�i�����́j�����T�i�o���āA���ׂ͈߂ɑ唼���܂��ċt��̈ꕔ�������c�ɂ����ʌ����ڂ炵�����̂ƂȂ����A���ݕ��̒n���ɂ�����̑傳�͂ƂĂ��Ȃ��B
�@��ꃖ���̖{����������̕��֓���ԓ��̓����̑��ɋ��������o���āA�ߏ��ɋ����V�R���q���Ă���A�����̗��ɂ̓�Ԃ̌o�c���ċ�����̂Ƃ��ŁA�悢�v�t���ł���A�R���̍����ɋ��̌Q�ꂪ�p�j���ċ���i����邭�͂Ȃ����A���߂Ď�����N���������ł������珮�悩�炤�Ǝv�����B
�@��ꃖ���̖{���͏捇�̃K�^�n�Ԃ��ʂ�ʂ�����A�����A���Ȃ�A�������y�ɉ��Ă��悭�Ȃ����l�����A�J��n�̒ʂ�ʂ̒��x�ɂ��Ēu���āA�����R�u��㉂ɂ���l�ȍלl��ʂ��Ēu�������K�c���Ǝv�ӁA���Âɓ���A���邱�Ƃ��K������ɂ悢�Ƃ͌��ւ܂��B
�@�O�{���̒��X�����R��ਂ߂ɔɐ�����l���A���R������ɂȂ�̂͂悢�������m��Ȃ����A�����̑O�ɂ͎��R�Ƃ����v�Ƃ��������O�����������Ȃ��ł��āT���܂Ӑl��̏Z��ł��隠�ł́A����Ȃ��Ƃ͐��ɂȂ�Ȃ���������ਂ߂Ɍ��\���Ǝv�ӁA��ꃖ�����d���������āA�d�A���^������Ă͓��ꂽ��
|
���N���������F
�����O�i����˂�j�F�������B�l�����B |
|
�S�U
�i�Łj
|
����̂ł͂Ȃ��B��������荇�ɂ��T��ƁA�N���U�j铎R�̒�͉��ŏo���ċ���Ƃł��A���͂����̂Ȃ�A�B�����ق�Ȃ�Ď�ʂ邢���Ƃ͂��ċ��Ȃ��ŁA�_�C�i�}�C�g�ŎR���ӂ��Ƃ��Ă��A�������̂炤�Ƃ���̂��炤�A�����Ă��ꂪ���ƂɌ��J������Ɖ]�ӂ̂ŌM�͂̈�ł���ӂƉ]�Ӑ��̒����B���q���@�̂����܂肾�Ɖ]���āA���{�l�����Ȃ��Ě��ɁA�i�V���i���p�[�N�݂̐����邱�Ƃ�m���ċ���҂͓��{�����ɉ��l���邾�炤�B�����Ă������ӂ��Ƃ������Ă��^�������₤�Ƃ���z���Ȃ��B�����͓e�p��邢���ƂŁA�L���ێq���T���t�����V�X�R粖��m�s���āA���đ������N�����Ȃ���A��ł��Ȃ����Ƃ���A������̂�萂̎R�ŁA�悭����������w�ɓO���ĉ��Ă̐^�������ߑ����ğd��҂��A�����m�s�d��Ɛ��q����T�҂̒��Ɋ��l���邾�낤�B
�@�v���Ԃ�Ő�ꃖ�����悭����ƁA�t�ׂ̍��X�Q�̈�킪���i���т����j�����ɖ������̂��A����ਂɃc���R�P���R��q���V���N�i�Q�Ȃǂ͑�ɚؔ�����āA�͂ɐ��c�����~�d�S�P�̊Ԃɂ��U����ŋ���B�ߔN�̓c���R�P���R�̛���c�����āA���ɓʂșJ�ː����̏o���Ɖ]�ӂ��Ƃ����A���̈ʂȂ�c���R�P���R�̕ی�����āA���̔ɐB���v������悳���Ȃ��̂��B���R�ɑ��c�̕ی�����ւĔV�𗘗p����̂͂悢�������A���R���s�i�������j���Ă�����Ȃ��l�|�������Ƃ���̂͏��シ�ׂ����ł͂Ȃ��B
�@�����̕����痈�Đ�ꃖ�����o�͂Â�鏊�ɁA���ݕ��̒n�}�ɂ͐ԏ��Ɖ]�ӉȂ�傫�ȏ����L���Ă���B�\�P�N�Ԃ��T�ɒ��z���ăR�q�����t�i���������{�����l�Ԃ����������A�s�����Ƃ����č��͑S�����~���A����Ȃ��Ȃ��č��͕��n�ɐ����`�����i���j�Ɨ���Đ̖̂��̂��Ƃ�����ċ���A�������Ƃč��r�͒n�}��ɂ��邵�Ă�����̑傫���ł͂Ȃ������B���ݕ���̒n�}���������̈�́A���`�̒r���̑傫�����P��ɕs���m�Ȃ̂ƁA�N�����i�����j�����̂ƁA�P���������̒n���Ȃ��ċ�����̂Ƃ̙��ʂ��A�P�ɛ��ۂɉ��������ċ��邱�Ƃ�����B���Ƀ���̋������Ђ����̂́A�V��R��̖��Ō×��ېl�ɂ����ł��悭�ʂ��ċ�����̂��A���܂�ɑ����ȗ�����ċ��邱�Ƃ��B��������铂ɉ��Č�̏���
|
���荇�i�Ă����j�F1 �A���B���B���y�̂��Ă����B�u���������荇���Ƃ͕t�����������Ȃ��v�@�Q �������B��ށB
���q���@�i�͂�����j�F���K���ō��̂��̂Ƃ��āA�ɓx�ɑ��d���邱�ƁB�����`�Y���w�q���@�x�ɁA�u�q���@�Ƃ͕č��l�̂�����
�@�@�@�I�[���}�C�e�B�[�E�h�������i���ׂĂ̓h���ł���j�Ƃ������t��|���v�A���̖{���L���ƂȂ��āA
�@�@�@�c��`�m�́u�O�c�̔q�����v�ł���A���V�@�g�́u�q�����̋��c�v�ł���Ƃ��]�����ꂽ�B
����������w�i���͂��j�ɓO���āF�����ɏ����Ă��邱�Ƃ��A�\�ʂ����łȂ��^�ӂ܂ŗ������邱�Ƃ̂��Ƃ��B�lj�͂ɒ����Ă��邱�ƁB
���ߑ��i�ق����j�F���܂��邱�ƁB�Ƃ炦�邱�ƁB
�������i������j�F�����B���ɁA���_�B�Z���B
�������i���傶��j�F�y�n���Ⴍ�Đ��͂��������A�������߂��߂��Ă��邱�ƁB�܂��A���̓y�n�B |
|
�S�V
�i�Łj
|
���}����l���v���邱��͛��ɔ���Ȃ��̂ł���B�j铐}���Ń�����Ēu�������̂́A�O�R�V�̏o�ė���O�R�̈ʒu��������Ђ͂��ʂ��Ǝv�͂��B�O�����R���L���Ă���R�̎��̏������ŁA�O�R�V����鑴�����ɂ��鏬�����A�ېl�͊O�R�ƌĂ�ŋ���B����͋߂��֍s���Ȃ��Ȃ��Ă͓��ꌩ���ʎR�ł���B�\�Ɍ��ӂ͍��O�R�V�̉��A��ɑ����̕��̏㗬�ɂ͉Ȃ藧�h�ȑ낪���邳���ł���B�Ԋ�̑�Ƃ����ӂ̂͂��ꂾ���Ǝv�ӁB
�@��ꃖ���̖{���́A�ĂуI�z�i���̑e�тɓ����Ă₪�ė�����̏����߂��ďҊ����_�ɏo�ĉ��H��߂��Ē��{�K�֟d���V�ł���B
�@���{�K���߂̎R���邫������ɂ́A�ĉ��֗���ňē����قւ悢�A�����͏������ܘY�Ɖ]�ӂ̂��g�p�������Ȃ荟�|�̎R��ɖ����l�ŁA�������ƂȂ����l�Ԃł���A����ł��H�ɂ͕s���m�Ȏ����Ȃ��ł��Ȃ������B
�@��������ʂ艜�܂ŕ���������A�ĂыA�H�ɂ����Ƃɂ���A�r���͈ꑫ�Ƃтɂ��ē��������H��������Ƃɂ���B���āA���q�R�A���_�����ʔT�����Ȃǂ֎U�����Č����A���L���邱�Ƃ��Ȃ����j�א�Ɉꌩ���h�Ȓދ����o����Œ��łł������A���ꂪ���������疶�~���ʂ֍s���ɕ֗��Ȃ��Ƃ��炤�B�����̂Ƒ哯���قł��邪�A�e�������@�`�����@�����@�������@�����������������@���Ƃ��@�o�������������������@�����������@���������@���������@�����@�m�����������@�ȂǂƉ]�ӊ�������v�i���傤�͂��j���啪�������l���A�Y���Ƃ��������i�Ђ��j�����̂͑��ς�炸�̓����r㻁A�������h�����߁A����Ȃ������H�̊ߋ��A���R�N�n�̖����̕s���D�ȏ�ʂɂ����Ȃ��A��������Ƃ����ǂ��邱�Ƃ��o�������Ȃ��̂ƍl�ւ���A��ɃR�N�n�̏�Ɏ����Ă͍��̌Z���ł��֗p���ꂽ���̂ł͂���܂��ɁA�����薠��B�i���j�炸�ɑ������̂����������炤�Ǝv�ӁB
�@�����R�Ɖ]�ӂƂ��܂�l�������Y�t�i��������j���ċ���̂��A���X�}�X�̏��̗l�Ɏv�ӂЂƂ�����A�����̓o�R�ƂȂ�m��ʂƁA�V��A�○���̐\���q�Ȃǂ̍s�������ł͂Ȃ��ƍl�ւĂ�l������l���A��������
|
���R�N�n�i������j�F�T���i�V
�������i�Ђ��j���F����B����������B
�����v�i���傤���͂��j�F�Ŕ�
���Y�t�i��������j�F�u�Y�v�͂Ȃ܂��A�u�t�v�͂��Ԃ���̈ӂŁA������������悭�A�����̐l�̌��Ɋ���Ƃ��납��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̐l�X�̕]���ɂȂ��Ēm��n�邱�ƁB�u�l�����Y�t����v |
|
�S�W
�i�Łj |
���Ȃ܂��̂���̓z���̊Ԃɗ��s����l�ȉ��X�A���v�X���Ƃ��A���Ƃ����C���t�Ɖ]�Ӕn��������������a���Ɋ������Ȃ��ŁA�̂Ȃ���̗l�q�̂��鏊�����ƂȂ��Ȃ������P�Ⴊ�Ȃ�����ƂāA�J�[���Ƃ��U�Ȃ�����ƂāA�R�x�����Ƃ��x�O������R�ł͂���܂��ƁA���܂�����ʒ��i���傤����j�����Ēu���B
|
���Ȃ܂��̂���i�����m��j�F����������̒m�������Ȃ��̂ɕ��m�������邱�ƁB�܂��A���̐l�B |
|
 �@�@
�@�@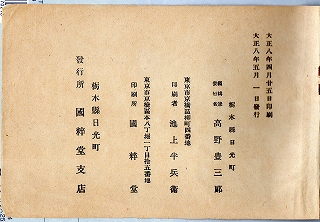
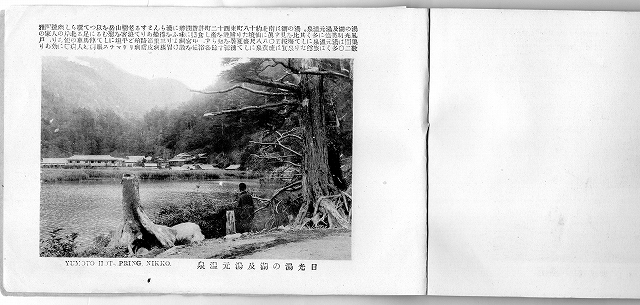
 �@
�@