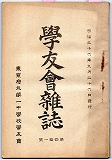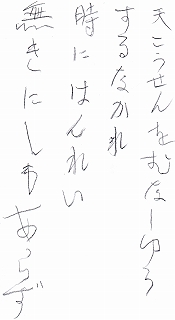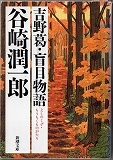| ���� |
�a�N�� |
�J��
����Y |
�c��
���� |
�K��
�H�� |
�o���� |
| 1828 |
�����P�P�N |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1829 |
12 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1830 |
�V�ی��N |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1831 |
2 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1832 |
3 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1833 |
4 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1834 |
5 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1835 |
6 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1836 |
�V�ۂV�N |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1837 |
8 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1838 |
9 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1839 |
10 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1840 |
11 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1841 |
12 |
�E |
�E |
�E |
�P�P���R���i����j�A�������܂��B |
| 1842 |
13 |
�E |
1 |
�E |
�E |
| 1843 |
14 |
�E |
2 |
�E |
�E |
| 1844 |
�O�����N |
�E |
3 |
�E |
�E |
| 1845 |
2 |
�E |
4 |
�E |
�E |
| 1846 |
3 |
�E |
5 |
�E |
�E |
| 1847 |
4 |
�E |
6 |
�E |
�E |
| 1848 |
�Éi���N |
�E |
7 |
�E |
�E |
| 1849 |
2 |
�E |
8 |
�E |
�E |
| 1850 |
3 |
�E |
9 |
�E |
�E |
| 1851 |
4 |
�E |
10 |
�E |
�E |
| 1852 |
5 |
�E |
11 |
�E |
�E |
| 1853 |
6 |
�E |
12 |
�E |
�E |
| 1854 |
�������N |
�E |
13 |
�E |
�E |
| 1855 |
2 |
�E |
14 |
�E |
�E |
| 1856 |
3 |
�E |
15 |
�E |
�E |
| 1857 |
4 |
�E |
16 |
�E |
�E |
| 1858 |
5 |
�E |
17 |
�E |
�E |
| 1859 |
6 |
�E |
18 |
�E |
�E |
| 1860 |
�������N |
�E |
19 |
�E |
�E |
| 1861 |
���v���N |
�E |
20 |
�E |
�E |
| 1862 |
2 |
�E |
21 |
�E |
�E |
| 1863 |
3 |
�E |
22 |
�E |
�E |
| 1864 |
�������N |
�E |
23 |
�E |
�E |
| 1865 |
�c�����N |
�E |
24 |
�E |
�E |
| 1866 |
2 |
�E |
25 |
�E |
�E |
| 1867 |
3 |
�E |
26 |
�E |
�E |
| 1868 |
�������N |
�E |
27 |
�E |
�E |
| 1869 |
2 |
�E |
28 |
�E |
�E |
| 1870 |
3 |
�E |
29 |
�E |
�E |
| 1871 |
4 |
�E |
30 |
�E |
�X���Q�R���i����j�A�H�����܂��B |
| 1872 |
5 |
�E |
31 |
1 |
�E |
| 1873 |
6 |
�E |
32 |
2 |
�E |
| 1874 |
7 |
�E |
33 |
3 |
�E |
| 1875 |
8 |
�E |
34 |
4 |
�E |
| 1876 |
9 |
�E |
35 |
5 |
�E |
| 1877 |
10 |
�E |
36 |
6 |
�E |
| 1878 |
11 |
�E |
37 |
7 |
�E |
| 1879 |
12 |
�E |
38 |
8 |
�E |
| 1880 |
13 |
�E |
39 |
9 |
�E |
| 1881 |
14 |
�E |
40 |
10 |
�E |
| 1882 |
15 |
�E |
41 |
11 |
�E |
| 1883 |
16 |
�E |
42 |
12 |
�E |
| 1884 |
17 |
�E |
43 |
13 |
�E |
| 1885 |
18 |
�E |
44 |
14 |
�E |
| 1886 |
19 |
�E |
45 |
15 |
�V���Q�S���A����Y�A���܂�� |
| 1887 |
20 |
1 |
46 |
16 |
�E |
| 1888 |
21 |
2 |
47 |
17 |
�E |
| 1889 |
22 |
3 |
48 |
18 |
�E |
| 1890 |
23 |
4 |
49 |
19 |
�E |
| 1891 |
24 |
5 |
50 |
20 |
�E |
| 1892 |
25 |
6 |
51 |
21 |
�E |
| 1893 |
26 |
7 |
52 |
22 |
�E |
| 1894 |
27 |
8 |
53 |
23 |
�E |
| 1895 |
28 |
9 |
54 |
24 |
�E |
| 1896 |
29 |
10 |
55 |
25 |
�Z���̔N�A��Ɖ̕���w�`�o��{���x���ό�����B |
| 1897 |
30 |
11 |
56 |
26 |
�R���Q���A�������R�z�Ŕ�Q���W�O�O�]���㋞�A����^�����J�n����B |
| 1898 |
31 |
12 |
57 |
27 |
�Z���̔N�A��y�⋉�F�����ƉG���w�w����y���x��n������B
�S���A�Ō����ؕ��g���u�w�N�m�� : ���������x�@���k��@�i���{�Ԛ�㉁j�v������B
|
| 1899 |
32 |
13 |
58 |
28 |
�E |
| 1900 |
33 |
14 |
59 |
29 |
�Q���P�R���A�������R�z�Ŕ�Q���Q�O�O�O���A�㋞�r���ٗтŌx�@���ƏՓ˂���B |
| 1901 |
34 |
15 |
60 |
30 |
�S���A�����{����ꒆ�w�Z�i������J���Z�j�ɓ��w�B
�P�Q���P�O���A�c���������������R�z�Ŏ����ɂ��Ė����V�c�ɒ��i�B
�@�@���i��́A�܂��H���������A������������������̂ł���
�P�Q���P�Q���A���]�������i�T�S�j
�Z���̔N�A�������ɗאڂ��鏼�ؑ������Q�̂��߂ɔp���ƂȂ�B���̂ق��A���ؑ��ɗאڂ���v�����A�m�c����������ɑO�サ�Ĕp���ƂȂ�B |
| 1902 |
35 |
16 |
61 |
31 |
�U���A���t�̊M���Œz�n���{���̌o�c�Җk���Ƃɉƒ닳�t�Ƃ��ďZ�ݍ��ށB
�V���A����Y�A�u�{�F��趎��@�R�W���v�Ɂu���������N���ɑ肷�隤���v�Ƒ肵�u�q�m���������U��Δ�����͂ӂ��ĊZ�̑��ɟN����Ȃ��v�̉̂\����B
�@�@�܂��A�����Ɂu�����I�ϔO�Ɣ��I�ϔO�v�����\����B |
| 1903 |
36 |
17 |
62 |
32 |
�S�i�K�j���A�P�O���A�J�菁��Y�A�n�ǐ���̒������B
�S���P�R���A���w�Z�߉����A���苳�ȏ����x���m������B
�X���A�J�菁��Y�Ƒ哇�G�����A���Łu�{�F��趎��@�S�P���v�ɁA�u����^�v�\����B
|
�i���j�K���\���̗[�s�ɏ��r���n�ǐ��̒����߂��B�ԏ�̏�ɁA�[�Ă��`�H�����N�����\�����[�L�������ނ肽�邪�@���Ԃ��Ȃ�A���̋�Q���������ւ��Â�ɂ�āA�����̍Ō�̌����͎O���ьႪ�e������ɓ������ʂ��U�g�ɋ��ւ��͂��点�A��F���[���Ȃ�āA���݂̏��R�͂��ڂ낰�Ȃ���������e�𐅖ʂɂ����ʁB
�͂邩�ɖ]�߂A������ѐl�������A�����k�C�l�Ƃ��ĎR�[���߂���A�ꐅ�B�j�ăT�^���̎g�A�߈��̎q�A��n�ǐ��삱�T�ɐ����邩�E�E�E�E�E�E�E�E�E�^���i�R�E�����j�͐��ʂ��тʁB��T����ė��؏E�ӏ����́A翉̂����ЂT�s����B�^�j�ē�n�ǐ���A���T�������U�y���锒�����ꂻ�����Ȃ��A����䩁X���鈯�j�Ă��ꂻ�����Ȃ��B�������������p�ɂ��ւ��A�R�炸�Ύ�����B�R��Ζ����A�j�ē��߈��̎q��n�ǐ���A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�^�v�ւ��ɓ������̏㑢���̐_�̌��ɂ��A����������������ꂽ����̂Ȃ�B�������n�A�O�\�݂̖��́A�F��Ă��߂�a���ēV�n�̍I���������ЂʁB�E�E�E�E�E�E�^���Ȃ邩�R�͎R�A�͎��R�ɗ��t���o�ցA�͎͂��R�ɔV��c���ɉ^�ԁA���Ȃ����Ĕ��Ȃ�؉ʂ���E�E�E�E�E�E�ƑR��ǂ��V��ߋ��̖��Ȃ肫�B���͚j�āA�E�E�E�E�E�E�Ȃ͕a���ɉ炵�q�͋Q�ɂȂ��E�E�E�E�V�~�ւ�ᓙ�O�\�݂̗��E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�j�ĉ����S�Ȃ�B���ڂ萯�̂��䢂ɘZ�\�N�A���I���p�̔@���Ȃ炸�A���R�͎l�G�����肩�ւ��ē����ƒn����ӂ��ǂ��E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�^�j�ďt�͗���ǂ��ԍ炩���A�ݍ��̗���͉��������J���̍����ƂȂ�A�߂Ȃ�����O�\�݁A�V�����ŋ��ׂǂ��V�������A�n�ɘ낵�ċ����ǂ��n���ւ��A�F�߂�a���ĞH���w�^���܂�ʁx�ƁA�����Ďw��͂��Ď���҂A�j�ĉ������Ȃ�B������i�Ђ�j���Ă��T�ɓ��ܕS�N�A���Â��̗��j�ɂ����̗ނ����ށB�i���j�j�ēŐ��ɓM��Ď�������F��A���ɂ����ꂵ�ᓯ�E��A�ޓn�ǐ��̔�����ւ�A�j�ĕx�m�R�旘�����A���ɔޓn�ǐ��̍߂��Ȃ点�B��H����̏��ɂ��A���ɓ��̗ނ����ށB�j�ăT�^���̎g�A�߈��̎q�A��n�ǐ���E�E�E�E�E�E
|
���N�����\�����[�L�F�[�g�F�̐��m�G�̋�
�����k�C�l�i�Ƃ����j�F
�������i�����j�F���������ƂȂ����A�l�ɂ������Ȃ����ƁB�@2.�C�����₩�Ȃ��ƁB
���J���i���傤���傤�j�F�Ђ�����Ƃ��Ă��̎₵�����܁B |
|
�@�@�܂��A�����Ɂu�Ċ��x�Ɂv�����\����B
�P�O���P�Q���A������A���_�ɓ]���A�K���H���E�䗘�F�E�����ӎO��ގЂ���B
�P�P���P�T���A�K���E��炪�����Ђ������u�����V���v�����s����B
�P�Q���A����Y�A�u�{�F��趎��@�S�Q���v�ɁA�u�t���H�J�^�v�E�u�Ƃ��ɂ����邤���v�\����B |
| 1904 |
37 |
18 |
63 |
33 |
�R���P�R���A�����V���u�^�I���Љ�}���v�i�K���H�����M�j�f�ڂ���B
�T���A����Y�A�u�{�F��趎��@�S�R���v�ɁA�u���Y�Ɠ�����`�v�\����B |
| 1905 |
38 |
19 |
64 |
34 |
�R���A�����{����ꒆ�w�Z�i������J���Z�j�𑲋Ƃ���B
�X���A��ꍂ���w�Z�p�@�Ȃɓ��w����B
�Z���̔N�A���{���Ȗ،����s��S�J�����S������A���̒n�ɍz�ł𒾓a������V���r�v��𗧂Ă�B |
| 1906 |
39 |
20 |
65 |
35 |
�Z���̔N�A�J�����̑S�悪������������A���N�̂U���Q�X���A�����p���ƂȂ�B
|
| 1907 |
40 |
21 |
66 |
36 |
�Q���S�`�V���A�������R�Ŗ\���A�R�����o�������B
�U���A�k���Ƃ̏��Ԏg�Ƃ̗���������̊�恂ɂӂ��B
�U���Q�X���A�Q�n���J�����ɗV���n���݂̂��ߋ������ގ��s�B
|
1907�N�܂łɗ����ނ��Ȃ�����������͋����j�ꂽ�B�������A�ꕔ�̑����͂��̌���V���r���ɏZ�ݑ������B�Ō�̑�����1917�N2��25�����낱�̒n�𗣂ꂽ�B |
|
| 1908 |
41 |
22 |
67 |
37 |
�V���A��ꍂ���w�Z�p�@�Ȃ𑲋Ƃ���B
�X���A�����鍑��w�����Ȃɓ��w����B |
| 1909 |
42 |
23 |
68 |
38 |
�Z���̔N��c��g���A�u���鋞�̌����E�@�����Č��_���v�ɂ�蓌���鍑��w���當�w���m�̏̍���B
�Z���̔N�A����Y���u�隠���{�v�A�u����c���{�v�ɓ��e�������e���v�ɂȂ�A���ӂƏő��̂��܂苭�x�̐_�o����ɂ�����B�i��ו��́w���߂肩����x��ǂ݁u�����Y�p��̌����v������B�@ |
| 1910 |
43 |
24 |
69 |
39 |
�U���A�K���H�����u�K�������i��t�����j�v�ɂ����đߕ߂����B
|
�H�����@��Łu���̓V�q�́A�쒩�̓V�q���ÎE���ĎO��̐_���D���Ƃ����k���̓V�q�ł͂Ȃ����v�Ɣ����������Ƃ��O���֘R��A��k�����[�_���N�������B
�鍑�c��O�c�@�ō��苳�ȏ��̓�k������������鎿�⏑����o����A���N��2��4���ɋc��́A�쒩�𐳓��Ƃ��錈�c���o���B���̌��c�ɂ���āA���ȏ����M�ӔC�҂̊�c��g���x�E��������B�ȍ~�A���苳�ȏ��ł́u����{�j�v�������ɁA�O��̐_������L���Ă����쒩�𐳓��Ƃ���L�q�ɍ����ւ�����B |
�X���A���R���O�A�a�ғN�Y�A��я���A����S�A�㓡���Y�A�ؑ�������Ƌ��ɑ�w�V�v���x��n�����邪���ւƂȂ�B
�P�P���A�i��ו��Ɖ�B�@ |
| 1911 |
44 |
25 |
70 |
40 |
�P���P�W���A��R�@�Ŕ������������B
�P���P�X���A���̐V�����u��k�����[���v�ɂ��Ă̎А���_����B
|
�u���������̑Η������������A���Ƃ̊��ɕ����邱�ƁA�ܑR��q����������ɁA�V���̎��ԔV����Ȃ锜����ׂ��B���������ȑ��̎咣�̔@���ꎞ�̕ϑԂƂ��ĔV���ʼn߂�����v�u���{�鍑�ɉ��Đ^�ɐl�i�̔�����ׂ��̕W���͒m�����s�̗D�����Í����I��A������`�����̖��۔@���ɍ݂�B�����̑����l��`�̓��ɔ��B���A�j�q���X�g���֔y�o���鎞��ɉ��Ă͓��ɋٗv�d��ɂ��Č����ׂ��炸�v |
�P���Q�S���A�K���H�����Y�����B
�Q���S���A �O�c�@�̑�c�m�������A������j���ȏ��̓�k�����[���ɂ��Ď��⏑���o����B
�Q���Q�V���A���j������ҁu�q�포�w�Z���{���j�ⓚ�v�����s�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@pid/769781�@�{���\
�Z���̔N�A��c��g�A�쒩�𐳓��Ƃ��闧��i�_�ҁj�������A�x�E�����ƂȂ�B
|
��c��g�́A�����Ȃō��苳�ȏ��̕Ҏ[�ɂ��]���������A���w�Z�̗��j���ȏ��ɓ�k�����̖k���E�쒩����ׂċL�q���Ă������߁A���̔N�A�쒩�𐳓��Ƃ��闧�ꂩ�����A���̐ӔC�����x�E�����ƂȂ�A���ȏ��̋L�q�͓쒩�����_�ɕύX���ꂽ�B�i�u��k�����[���v�j�B |
|
| 1912 |
�吳���N
�i�V�E�R�O
�@�@�����j |
26 |
71 |
�E |
1���A�����̕�σt�N���x���Ŏ����B
�S���A���s�ɗV�ԁB�_�o���オ�Ĕ�����B
�W���A���������s���i�ƂȂ�B
�P�O�����`�P�P�����{�A�g��̌�������K�˂��B
|
�g�슋�^�`���̕����i�S���j
���̈�@���V���^������a�̋g��̉��ɗV�̂́A���ɓ�\�N���܂��A�����̖�����吳�̏��ߍ��̂��Ƃł��邪�A���ƈ���Č�ʂ̕s�ւȂ��̎���ɁA����ȎR���A�|�ߍ��̌��t�ʼn]���u��a�A���v�X�v�̒n���Ȃ��ցA�����ɁA�o�����čs���C�ɂȂ������B�|���́v�b�͐悸���̈�����������K�v������B
�@�ǎ҂̂����ɂ͑����䏳�m�̕������낤���A�̂��炠�̒n���A�\�Ð�A�k�R�A���̑�������ł́A�����y���ɂ��Ɉ˂��āu�쒩�l�v���́u���V���l�v�ƌĂ�Ă�����̌���Ɋւ���`��������B���̎��V���A�|��T�R��̌����ɓ��点����k�R�{�Ɖ]�����������ۂɂ��킵�܂������Ƃ͐��̗��j�Ƃ��F�߂�Ƃ���ŁA�����ĒP�Ȃ�`���ł͂Ȃ��B��������܂���~���E��ʼn]���ƁA���ʏ����w�Z�̗��j�̋��ȏ��ł́A�쒩�̌�����N�A�k���̖����O�N�A���R�`���̑�ɗ������̘̂a�c���������A�����g�쒩�Ȃ���̂͂��̎�������Ƃ��āA����V�c�̉����X�N�ȗ��\�]�N�Ŕp�₵���ƂȂ��Ă��邯��ǂ��A���̂̂��Ëg�O�N�㌎��\�O���̖锼�A���Y���G�Ɖ]���҂���o�����̐e���������{��āA�}�ɓy���������P���A�O��̐_�����i�ʂ��j�ݏo���ĉb�R�ɗ����Ă�������������B
���̎��A����̒nj����ċ{�͎��Q�������A�_��̂����Ƌ��Ƃ͎��Ԃ��ꂽ���A�_���i���j�݂͓̂쒩���̎�Ɏc�����̂ŁA�펁�z�q���̈ꑰ���͍X�ɋ{�̍c�q�������ċ`���������A�ɐ�����I�ɁA�I�ɂ����a�ƁA����ɖk���R�̎�̓͂��Ȃ����g��̎R�ԕƒn�֓���A��̋{�����V���Ɛ��i�����j�߁A��̋{�𐪈Α叫�R�ɋ��ŁA�N����V���i�Ă��j�Ɖ������A�e�ՂɓG�̉M���m�蓾�Ȃ��k�J�̊ԂɘZ�\�L�]�N���_����i���Ă����Ɖ]���B�i���j
�u�g�슋 ���̘Z�A���̔g�v����ǂݎ���
�@�@�@�@�g��̌����n�������߂��T���̃��[�g�i�������j
| ��P�� |
�����i���j�����쑺�i���̂���j���T�R�V�c�̍c�q���q�{�̌������Г������i���j |
| ��Q�� |
���i���j������P�������k�R�̑��͍��i���j |
| ��R�� |
�k�R�̑��͍��i���j�����V���̌䏊�Ղł��鏬���i���Ƃ��j�̗����k�R�{�̌�擙�Ɍw�ł遨��䃖�����R���i���j���ܐF����i���j |
| ��S�� |
�R���i���j���ܐF����i���j���g���̗���ɉ����ĉ��遨��̌��i�ɂ̂܂��j���O�̌��̒J���I�N�^�}�K�����n���͌����i��O�\���i��j���ׂ�ׂǁi��j�j���������̏������B�������������̎R�j�̏����i���j |
| ��T�� |
�������̎R�j�̏����i���j����̌��i�ɂ̂܂��j�����̔g�i�����̂́j�i���j�������i���j
|
| ��U�� |
���̔g�i�����̂́j�i���j�܂������i���j�������i���j |
�Z���̔N�A�e�n����Q����B
|
|
| 1913 |
2 |
27 |
72 |
�E |
�Z���̔N�A��c��g�����s�鍑��w��C�u�t�ƂȂ�B |
| 1914 |
3 |
28 |
73 |
�E |
�E |
| 1915 |
4 |
29 |
74 |
�E |
�Z���̔N�A����Y�A�ΐ���ƌ����B
�Z���̔N�A����Y�A�w�����E���x�E�w�@��������x�w���˂Ɩ��V��x �\����B |
| 1916 |
5 |
30 |
75 |
�E |
�E |
| 1917 |
6 |
31 |
76 |
�E |
�T���A ��E�ւ������B
�U���A�ȂƖ������Ɓi���̉Ɓj�ɗa����B
�Z���̔N�A�H�열�V��A�����t�v�Ƃ̌𗬂��n�܂�B���̖��E�����q���D���ɂȂ�B
�Z���̔N�A����Y�A�w�l���̒Q���x�E�w�ْ[�҂̔߂��݁x�\�B |
| 1918 |
7 |
32 |
77 |
�E |
�E |
| 1919 |
8 |
33 |
78 |
�E |
�Z���̔N�A���E�q�ܘY�����B�_�ސ쌧���c���\�����ɓ]���B
�Z���̔N�A����Y�A�w�����ӂ�L�x�\����B |
| 1920 |
9 |
34 |
79 |
�E |
�P���P���A��c��g���u���{���m��c��g��M�@�����Ɨ��j�@��R���P���v�Ɂu���_�������v�\����B
�P���P�T���A��c��g���u���{���m��c��g��M�@�����Ɨ��j�@��R���Q���v�Ɂu�����_�������v�\����B
�Z���̔N�`�P�R�N�܂ŁA��c��g�����s�鍑��w�̋����ƂȂ�B |
| 1921 |
10 |
35 |
80 |
�E |
�Z���̔N�A�ȁE���������t�v�ɏ���Ƃ����O����|�������߁A�����Ɛ������B
|
| 1922 |
11 |
36 |
81 |
�E |
�E |
| 1923 |
12 |
37 |
82 |
�E |
9��1���֓���k�ЁB
|
���������̎R���Ńo�X�ɏ�Ԓ��ŁA���̒J���̓��������̂�����B���l�R�̎�̎���͊��ɑ����Ă��薳�����������A�ޏĂ��Ă��܂��B |
�X���S���A�c�������S���Ȃ�B
�Z���̔N�A����Y�A���s�s�㋞�擙���@������A������O�𓌎R�ʗv�@�����o�āA���Ɍ����ɌS�Z�b��y���i���E�_�ˎs���j�ɈڏZ����B
�Z���̔N�A����Y�A�w����x�\����B |
| 1924 |
13 |
38 |
�E |
�E |
�Z���̔N�A ����Y�A���ɌS�{�R���k���i���E�_�ˎs�����{�R���j�ɓ]������B
�Z���̔N�A����Y�A�w�s�l�̈��x�\����B |
| 1925 |
14 |
39 |
�E |
�E |
�E |
| 1926 |
���a���N |
40 |
�E |
�E |
�E |
| 1927 |
2 |
41 |
�E |
�E |
�E |
| 1928 |
3 |
42 |
�E |
�E |
�E |
| 1929 |
4 |
43 |
�E |
�E |
�E |
| 1930 |
5 |
44 |
�E |
�E |
�V���A�u���|�t�H 8(8)(�Վ�����) ���|�t�H�Ёv�Ɂu��O���{�̗��s�ɂ��āv�\����Bpid/3197602
|
| 1931 |
6 |
45 |
�E |
�E |
�P���A�u�������_. 46(1)(516) �V�N���S�j �v�Ɂu�����@�g�슋�v�\����B
�@�@�@�܂��A�����ɋ��{�p�g���u�E������v�\����B�@pid/10232193
�Q���A�u�������_. 46(2)(517)�@���j�v�Ɂu���� �g�슋�v�\����B pid/10232194
�Z���̔N�A����Y�A�Ð쒚���q�ƌ����B�؋��̂��߈ꎞ������R���Ă�B |
| 1932 |
7 |
46 |
�E |
�E |
�E |
| 1933 |
8 |
47 |
�E |
�E |
�Z���̔N�A�n���Ђ���w�t�Տ��x�����s�A�x�X�g�Z���[�ƂȂ�B |
| 1934 |
9 |
48 |
�E |
�E |
�E |
| 1935 |
10 |
49 |
�E |
�E |
�E |
| 1936 |
11 |
50 |
�E |
�E |
�P�P���`�P�W�N�P�P�����A���ɌS�Z�g�������тɏZ�ށB�ߏ����i�����傤����j
|
| 1937 |
12 |
51 |
�E |
�E |
�E |
| 1938 |
13 |
52 |
�E |
�E |
�E |
| 1939 |
14 |
53 |
�E |
�E |
�E |
| 1940 |
15 |
54 |
�E |
�E |
�E |
| 1941 |
16 |
55 |
�E |
�E |
�E |
| 1942 |
17 |
56 |
�E |
�E |
�X���A�����u���A�u椐ؒk�u�Ёv����u���{�������j�v�����s����B |
| 1943 |
18 |
57 |
�E |
�E |
�P�P���A���ɌS���蒬�ɏZ�ށB |
| 1944 |
19 |
58 |
�E |
�E |
�E |
| 1945 |
20 |
59 |
�E |
�E |
|
| ���� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�I����L�v��������ȏo�����@�i�쐬���j |
| 5��1�� |
�E |
| 5��2�� |
�E |
| 5��3�� |
�E |
| 5��4�� |
�E |
| 5��5�� |
�E |
| 5��6�� |
�E |
| 5��7�� |
�i���j(���݂�����͍�����㏼�i�܂ōs�����R�B���O�����d��Ƃ̎�)���R�����c�ɑa�J���鉪���u���y�ѓ��\����菑�ʓ����������B�����͈������������Ƃ���B���\���͑a�J�̉ו��O�\���i����������l��ᢑ������j��������R��B����ɂ��c�i�悤�₭�j���g���B�����ɃA���R�[���̎��z���Ȃ��B��H�ɂ͑f���炵���e���̈ꓙ������B�Ɛl�ȉ��O�o����N��ӌ��Ԃ�ɂĖ��ꓰ�ɘ�������桂Ȃ�B�������P�Ȃ����Ƃ��F��T�����߂���K�ɖ���B |
| 5��8�� |
�E |
| 5��9�� |
�E |
| 5��10�� |
�E |
| 5��11�� |
�E |
| 5��12�� |
�E |
| 5��13�� |
�E |
| 5��14�� |
�E |
| 5��15�� |
�E |
| 5��16�� |
�E |
| 5��17�� |
�E |
| 5��18�� |
�E |
| 5��19�� |
�E |
| 5��20�� |
�E |
| 5��21�� |
�E |
| 5��22�� |
�J�^�{�������J�ɂĊ����B�i���j�{�����݂�����ɋA��B�ߌ㉪�v�l���u�V�Q���L�V�X��O�q��W�@�I�N���@�}�c�R�v�Ɨ��d�B���ɗ\�������̒ʂ�ɂȂ肽��B�[�����������K�B������̉Ƃɟd�肵�R�Ȃ�B���������̎���m�点�������ɒ��i���j�Ԃ̖��Ȃ��B�[�H�����ɂ������熋��B�[�H�̔K�͋ʎq�̖ڋʏĂ���ÁT�A�^�J�i����ł����߂����́A�n���i���j�A���X�`���Ȃ�B |
| 5��23�� |
���^�i���j�i�i�����u�́j���͐���\������H�������ꂽ��q�ԂɈ��u���ꏰ�ɂ͗\�����N�̐l�ɑ��肽�铌�厛��œa���O���Ă̕����̓J�𐁂��V���̑�{��\������ꎲ���|�����肱��͍g�n�ɘa�̂���ߔ�������Ñ��̏��̈ߑ��ɂĕ\���������̂ɂė\�����肵�c���͂Ȃ܂߂��������̂Ȃ��肪���͐F�Ă��T�鎞�ɗp�ЂĂ��X�����₤�ɂȂ肽��B�\������肵�͏��a�Z�N���Ȃ�j���𑗂�o���@�Ƃ̑O�̔��̒����E�ɐ܂�Č����Ȃ��Ȃ�B�i���j |
| 5��24�� |
�E |
| 5��25�� |
�E |
| 5��26�� |
�E |
| 5��27�� |
�E |
| 5��28�� |
�E |
| 5��29�� |
�E |
| 5��30�� |
�E |
| 5��31�� |
�E |
| 6��2�� |
�E |
| 6��3�� |
�E |
| 6��4�� |
�E |
| 6��5�� |
�E |
| 6��16�� |
�E |
| 6��27�� |
�E |
| 6��29�� |
�E |
| 7��4�� |
�Z |
| 7��7�� |
���^�ߌ�l���l�l��ᢂɂĖ{���͗\�ƉƐl�ƃ��~�q�̎O�l�݈̂��z���B�i�����j���R������Ɏ�����łɍ�[�̉ו����������i�����j�����̘b�ɗ��O���O�n���Ђ̏��іΎ��������A���܂��ÎR�ɂ��R��������~�������Ē��x�ƂĂ��������i�u�א�v�̑��e���j����������Ȃ���S�ł��Ɖ]�Ђ�熋������R�ʘ������肵�͎c�O�Ȃ�B�[�т͏����̍D�ӂɂĔ��Ă𐆂��Ă���ӉZ�ɋ��R�����X�y�і��X�`�i�W���K���A�֎q�A�ʔK�A��������ÁT����j��������B�ÎR���ꡂ��ɏ㓙�Ȃ�B���~�q�ɂ͏��R�̒��傢�ɟ��ɓ��肽��₤�Ȃ�B�͌��ɏ����|���ŋ�����炵�����ۂ̉�������B�O�l�ɂĊX���U�����͌�����݂ĉ͎��̉������T�A��A�Q�B�����̘b�ɕꉮ�̓�K�ɂ����̐�Ўґa�J����Ɖ]�ӁB |
| 7��11�� |
�E |
| 8��8�� |
�E |
| 8��9�� |
�E |
| 8��12�� |
�E |
| 8��13�� |
���^�{�����c�ɂ�᱗��~��Ȃ�B�ߑO���i�䎁���ҏ��A�ؕ����莟�捡�����ɂ����K���ׂ��Ƃ̂��ƂȂ�B���Čߌ�ꎞ�ߍ��ו��搶����B�����㎞�߂̋D�ԂɂĐV�����ɂė����Ƃ̎��Ȃ�B�J�o���ƕ��C�~��Ƃ�U���ɂ��ĝ^�i���j���O�ɗ\��������肽���Ă���i���j���A�ݖ��F�̎�@�������w�A�ɃJ���Ȃ��̃��C�V���c�𒅁A�Ԕ�̔��C����i�́j������B�Ă��o����Ă��ꂪ�S���Y�Ȃ�Ƃ̎��Ȃ�B�R��ǂ��v�����ق���i��j��Ă�����ꂸ�A���X���C�Ȃ�B�ّ�͖����j�t��͐Ԋ◷�قɈē����B���قɂĖ�H�̌㖔���K�����K�ɂēn粎������ɖ�X����܂Řb���B�ו����������e�ЂƂ育�ƈꊪ�x�q�㉺���K�ҏ㉺���o���ė\�ɑ����B |
| 8��14�� |
�E |
| 8��15�� |
�E |
|
|
| 1946 |
21 |
60 |
�E |
�E |
�E |
| 1947 |
22 |
61 |
�E |
�E |
�E |
| 1948 |
23 |
62 |
�E |
�E |
�E |
| 1949 |
24 |
63 |
�E |
�E |
�X���P���A����Y���u�w�l���_�@�R�T���X�j�v�Ɂu�I����L�@�M�C���珟�R�܂Łv�\����B |
| 1950 |
25 |
64 |
�E |
�E |
�E |
| 1951 |
26 |
65 |
�E |
�E |
�U���A���I���삪�u���|�V�� 1(3)�@���|�V���Ёv�Ɂu�J�菁��Y�̐����v�\����Bpid/1747744
|
| 1952 |
27 |
66 |
�E |
�E |
�E |
| 1953 |
28 |
67 |
�E |
�E |
�E |
| 1954 |
29 |
68 |
�E |
�E |
�E |
| 1955 |
30 |
69 |
�E |
�E |
�E |
| 1956 |
31 |
70 |
�E |
�E |
�E |
| 1957 |
32 |
71 |
�E |
�E |
�E |
| 1958 |
33 |
72 |
�E |
�E |
�Z���̔N�A�a�c�F�b�ҁu (���N�������색�C�u�����[ ; 7)�������̖����吳���w�I�@�O�\���[�v�Ɂu��������L�v�����������B�@pid/1633430
|
�킩�ꓹ�@�@�����t
�����M�@�@�X���O
�t�̒��@�@���ؓc�ƕ�
�����@�@�Ėڟ���
�^�߁@�@�u�꒼�� |
��������L�@�@�J�菁��Y 71
�������҂ց@�@�L�����Y 99
������@�@�H�엳�V��
���݁@�e�r��
�Ձ@�v�Đ��Y |
�I�J�A�T���@�@�����t�v
��݁@�@�������Y
���������߂���@�@�ؓc����
����@�a�c�F�b
�����吳���w�N�\ |
|
| 1959 |
34 |
73 |
�E |
�E |
�E |
| 1960 |
35 |
74 |
�E |
�E |
�P�O���A����Y���u�������ǖ{�@�������̌O�r�F��@���@p73�v�Ɉ��̙��i�����j����B
�@�@����������������Ă̂ڂ���Ƃߎq��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���łɂ��肭���܂����炩�� |
| 1961 |
36 |
75 |
�E |
�E |
�E |
| 1962 |
37 |
76 |
�E |
�E |
�P�O���Q�W���`�R�W�N�R���P�O���܂ŁA�w�䏊�����L�x���w�T���f�[�����x�ɘA�ڂ���B
|
| 1963 |
38 |
77 |
�E |
�E |
�S���A�P�s�{�w�䏊�����L�x�𒆉����_�Ђ��犧�s����B |
| 1964 |
39 |
78 |
�E |
�E |
�E |
| 1965 |
40 |
79 |
�E |
�E |
�V���R�O���A����Y�A�S���Ȃ�B |
| 1966 |
41 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1967 |
42 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1968 |
43 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1969 |
44 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1970 |
45 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1971 |
46 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1972 |
47 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1973 |
48 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1974 |
49 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1975 |
50 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1976 |
51 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1977 |
52 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1978 |
53 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1979 |
54 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1980 |
55 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1981 |
56 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1982 |
57 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1983 |
58 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1984 |
59 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1985 |
60 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1986 |
61 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1987 |
62 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1988 |
63 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1989 |
64 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1990 |
�����Q�N |
�E |
�E |
�E |
�S���A�u�I�[��椕� = The all yomimono 45(4)�@p256�`257�@,���|�t�H�V�Ёv�Ɂu��O���{�̗��s�ɂ��āv�����������B[60���N�L�O �I�[���]���n����������]�@ pid/4437508 |
| 1991 |
3 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1992 |
4 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1993 |
5 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1994 |
6 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1995 |
7 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1996 |
8 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1997 |
9 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1998 |
10 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 1999 |
11 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2000 |
12 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2001 |
13 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2002 |
14 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2003 |
15 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2004 |
16 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2005 |
17 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2006 |
18 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2007 |
19 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2008 |
20 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2009 |
21 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2010 |
22 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2011 |
23 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2012 |
24 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2013 |
25 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2014 |
26 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2015 |
27 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2016 |
28 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2017 |
29 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2018 |
30 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2019 |
31 |
�E |
�E |
�E |
�E |
| 2020 |
32 |
�E |
�E |
�E |
�E |