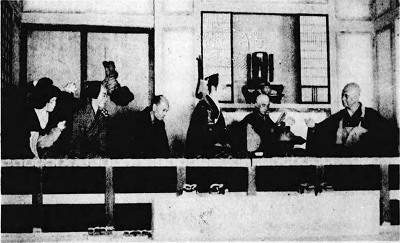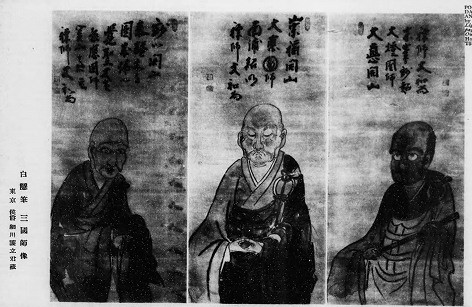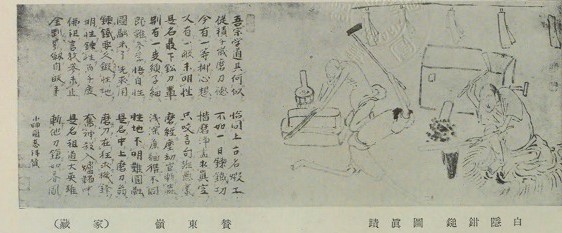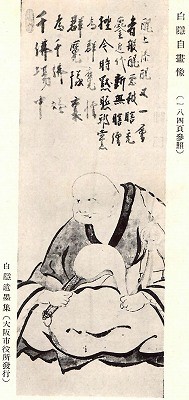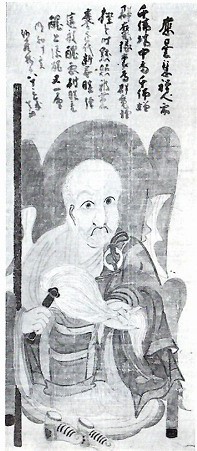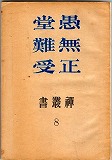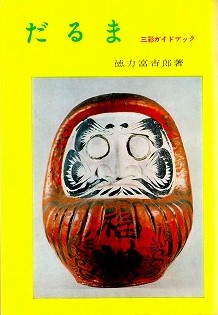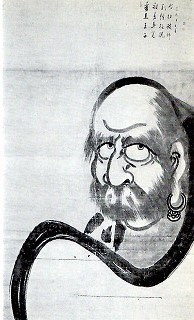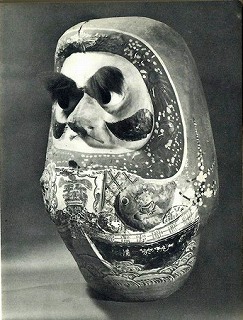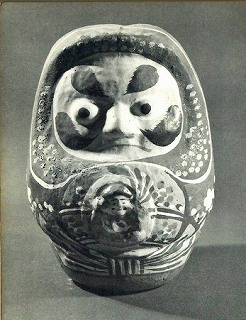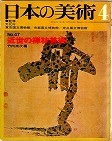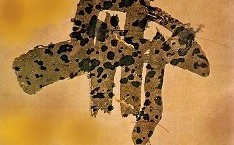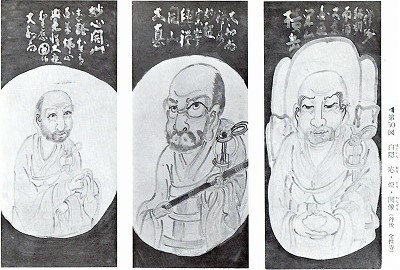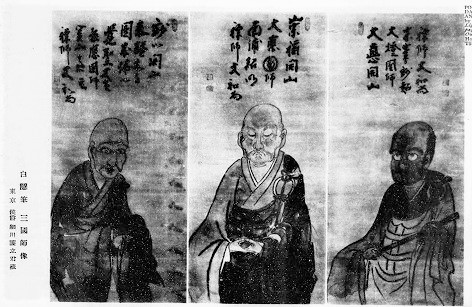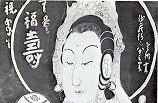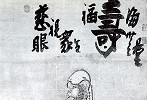| 西暦 |
和年号 |
年齢 |
出来事 |
| 1685 |
貞享2年 |
・ |
・ |
| 1686 |
3 |
1 |
・ |
| 1687 |
4 |
2 |
・ |
| 1688 |
元禄元年 |
3 |
・ |
| 1689 |
2 |
4 |
・ |
| 1690 |
3 |
5 |
・ |
| 1691 |
4 |
6 |
・ |
| 1692 |
5 |
7 |
・ |
| 1693 |
6 |
8 |
・ |
| 1694 |
7 |
9 |
・ |
| 1695 |
8 |
10 |
・ |
| 1696 |
9 |
11 |
・ |
| 1697 |
10 |
12 |
・ |
| 1698 |
11 |
13 |
・ |
| 1699 |
12 |
14 |
・ |
| 1700 |
13 |
15 |
・ |
| 1701 |
14 |
16 |
・ |
| 1702 |
15 |
17 |
・ |
| 1703 |
16 |
18 |
・ |
| 1704 |
宝永元年 |
19 |
・ |
| 1705 |
2 |
20 |
・ |
| 1706 |
3 |
21 |
・ |
| 1707 |
4 |
22 |
・ |
| 1708 |
5 |
23 |
・ |
| 1709 |
6 |
24 |
・ |
| 1710 |
7 |
25 |
・ |
| 1711 |
正徳元年 |
26 |
・ |
| 1712 |
2 |
27 |
・ |
| 1713 |
3 |
28 |
・ |
| 1714 |
4 |
29 |
・ |
| 1715 |
|
30 |
・ |
| 1716 |
亨保元年 |
31 |
・ |
| 1717 |
2 |
32 |
・ |
| 1718 |
3 |
33 |
・ |
| 1719 |
4 |
34 |
・ |
| 1720 |
5 |
35 |
・ |
| 1721 |
6 |
36 |
・ |
| 1722 |
7 |
37 |
・ |
| 1723 |
8 |
38 |
・ |
| 1724 |
9 |
39 |
・ |
| 1725 |
10 |
40 |
・ |
| 1726 |
11 |
41 |
・ |
| 1727 |
12 |
42 |
・ |
| 1728 |
13 |
43 |
・ |
| 1729 |
14 |
44 |
・ |
| 1730 |
15 |
45 |
・ |
| 1731 |
16 |
46 |
・ |
| 1732 |
17 |
47 |
・ |
| 1733 |
18 |
48 |
・ |
| 1734 |
19 |
49 |
・ |
| 1735 |
20 |
50 |
・ |
| 1736 |
元文元年 |
51 |
・ |
| 1737 |
2 |
52 |
・ |
| 1738 |
3 |
53 |
・ |
| 1739 |
4 |
54 |
・ |
| 1740 |
5 |
55 |
・ |
| 1741 |
寛保元年 |
56 |
・ |
| 1742 |
2 |
57 |
・ |
| 1743 |
3 |
58 |
・ |
| 1744 |
延享元年 |
59 |
・ |
| 1745 |
2 |
60 |
・ |
| 1746 |
3 |
61 |
・ |
| 1747 |
4 |
62 |
・ |
| 1748 |
寛延元年 |
63 |
・ |
| 1749 |
2 |
64 |
・ |
| 1750 |
3 |
65 |
・ |
| 1751 |
宝暦元年 |
66 |
・ |
| 1752 |
2 |
67 |
・ |
| 1753 |
3 |
68 |
・ |
| 1754 |
4 |
69 |
・ |
| 1755 |
5 |
70 |
・ |
| 1756 |
6 |
71 |
・ |
| 1757 |
7 |
72 |
・ |
| 1758 |
8 |
73 |
・ |
| 1759 |
9 |
74 |
・ |
| 1760 |
10 |
75 |
・ |
| 1761 |
11 |
76 |
・ |
| 1762 |
12 |
77 |
・ |
| 1763 |
13 |
78 |
・ |
| 1764 |
明和元年 |
79 |
・ |
| 1765 |
2 |
80 |
・ |
| 1766 |
3 |
81 |
・ |
| 1767 |
4 |
82 |
・ |
| 1768 |
5 |
83 |
・ |
| 1769 |
6 |
84 |
・ |
| 1770 |
7 |
・ |
・ |
| 1771 |
8 |
・ |
・ |
| 1772 |
安永元年 |
・ |
・ |
| 1773 |
2 |
・ |
・ |
| 1774 |
3 |
・ |
・ |
| 1775 |
4 |
・ |
・ |
| 1776 |
5 |
・ |
・ |
| 1777 |
6 |
・ |
・ |
| 1778 |
7 |
・ |
・ |
| 1779 |
8 |
・ |
・ |
| 1780 |
9 |
・ |
・ |
| 1781 |
天明元年 |
・ |
・ |
| 1782 |
2 |
・ |
・ |
| 1783 |
3 |
・ |
・ |
| 1784 |
4 |
・ |
・ |
| 1785 |
5 |
・ |
・ |
| 1786 |
6 |
・ |
・ |
| 1787 |
7 |
・ |
・ |
| 1788 |
8 |
・ |
・ |
| 1789 |
寛政元年 |
・ |
・ |
| 1790 |
2 |
・ |
・ |
| 1791 |
3 |
・ |
・ |
| 1792 |
4 |
・ |
・ |
| 1793 |
5 |
・ |
・ |
| 1794 |
6 |
・ |
・ |
| 1795 |
7 |
・ |
・ |
| 1796 |
8 |
・ |
・ |
| 1797 |
9 |
・ |
・ |
| 1798 |
10 |
・ |
・ |
| 1799 |
11 |
・ |
・ |
| 1800 |
寛政12年 |
・ |
・ |
| 1801 |
享和元年 |
・ |
・ |
| 1802 |
2 |
・ |
・ |
| 1803 |
3 |
・ |
・ |
| 1804 |
文化元年 |
・ |
・ |
| 1805 |
2 |
・ |
・ |
| 1806 |
3 |
・ |
・ |
| 1807 |
4 |
・ |
・ |
| 1808 |
5 |
・ |
・ |
| 1809 |
6 |
・ |
・ |
| 1810 |
7 |
・ |
・ |
| 1811 |
8 |
・ |
・ |
| 1812 |
9 |
・ |
・ |
| 1813 |
10 |
・ |
・ |
| 1814 |
11 |
・ |
・ |
| 1815 |
12 |
・ |
・ |
| 1816 |
13 |
・ |
・ |
| 1817 |
14 |
・ |
・ |
| 1818 |
文政元年 |
・ |
・ |
| 1819 |
2 |
・ |
・ |
| 1820 |
3 |
・ |
・ |
| 1821 |
4 |
・ |
・ |
| 1822 |
5 |
・ |
・ |
| 1823 |
6 |
・ |
・ |
| 1824 |
7 |
・ |
・ |
| 1825 |
8 |
・ |
・ |
| 1826 |
9 |
・ |
・ |
| 1827 |
10 |
・ |
・ |
| 1828 |
11 |
・ |
・ |
| 1829 |
12 |
・ |
・ |
| 1830 |
天保元年 |
・ |
・ |
| 1831 |
2 |
・ |
・ |
| 1832 |
3 |
・ |
・ |
| 1833 |
4 |
・ |
・ |
| 1834 |
5 |
・ |
・ |
| 1835 |
6 |
・ |
・ |
| 1836 |
7 |
・ |
・ |
| 1837 |
8 |
・ |
・ |
| 1838 |
9 |
・ |
・ |
| 1839 |
10 |
・ |
・ |
| 1840 |
11 |
・ |
・ |
| 1841 |
12 |
・ |
・ |
| 1842 |
13 |
・ |
・ |
| 1843 |
14 |
・ |
・ |
| 1844 |
弘化元年 |
・ |
・ |
| 1845 |
2 |
・ |
・ |
| 1846 |
3 |
・ |
・ |
| 1847 |
4 |
・ |
・ |
| 1848 |
嘉永元年 |
・ |
・ |
| 1849 |
2 |
・ |
・ |
| 1850 |
3 |
・ |
・ |
| 1851 |
4 |
・ |
・ |
| 1852 |
嘉永5年 |
・ |
・ |
| 1853 |
6 |
・ |
・ |
| 1854 |
安政元年 |
・ |
・ |
| 1855 |
2 |
・ |
・ |
| 1856 |
3 |
・ |
・ |
| 1857 |
4 |
・ |
・ |
| 1858 |
5 |
・ |
・ |
| 1859 |
6 |
・ |
・ |
| 1860 |
万延元年 |
・ |
・ |
| 1861 |
文久元年 |
・ |
・ |
| 1862 |
2 |
・ |
・ |
| 1863 |
3 |
・ |
・ |
| 1864 |
元治元年 |
・ |
・ |
| 1865 |
慶応元年 |
・ |
・ |
| 1866 |
2 |
・ |
・ |
| 1867 |
3 |
・ |
・ |
| 1868 |
明治元年
9・8
改元 |
・ |
・ |
| 1869 |
2 |
・ |
・ |
| 1870 |
3 |
・ |
・ |
| 1871 |
4 |
・ |
・ |
| 1872 |
5 |
・ |
・ |
| 1873 |
6 |
・ |
・ |
| 1874 |
7 |
・ |
・ |
| 1875 |
8 |
・ |
・ |
| 1876 |
9 |
・ |
・ |
| 1877 |
10 |
・ |
・ |
| 1878 |
11 |
・ |
・ |
| 1879 |
12 |
・ |
・ |
| 1880 |
13 |
・ |
12月、※片岡賢三編纂「諸宗説教三百題 第2篇」が「※出雲寺文次郎(出版人)」から刊行される。 pid/818478
|
夫死シテ後貞操ヲ守ラズ故畜生道ニ堕ス
開山ノ年忌ヲ勤ン為ニ娘ヲ身売ス
娘ノ願力ニ依テ清水寺観音母ノ化身ヲ知◇給フ
白隠禅師ノ堪忍ニ感ジテ菩提心ヲ起ス
継母ノ意ニ背ヌ故継母自然ト善心ニナル
亡霊善心女ニ付キ経文ヲ聞ク 今明治十三年ノコト |
◇〔バウ〕語ノ戒
大般若ノ札ニ恐テ嫉妬ノ念ヲ晴シ難
母ノ意ニ随テ乞食ニ衣服ヲ施ス
烏ト狐トノ口論
殺生ノ報ニ恐テ西国廻リヲナス
一銭ヲ寄附セシ功徳ニ依テ地獄ノ苦ヲ免ル |
偸盗ノ戒
恨ミ積デ我妻ト子トニ報
父ニ菩提心ヲ起サンガ為メニ命ヲ落ス
母ヲ殺サント思フ心ヨリ刃大蛇ト変ス
我身ヲ顧ミズシテ耻ヲウクル話
月小夜姫 初篇ニ洩タルヲ記ス |
※奥付から出版年・編纂者・出版社を変更する。 2023・1・17 保坂 |
| 1881 |
14 |
・ |
4月、吉岡信行が「求化微糧談 巻之3 上」を「北畠茂兵衛」から刊行する。 pid/816380
|
求化微糧談巻之三 上
信心因果ノ説/1p首弁
貧女一灯ノ説/2p右メン
四恩ノ内孝道ノ説/3p左メン
仏母降弔ノ事/5p左メン
孝道説ノ次/6p左メン
如来ノ父王臨終ニ弔慰ノ事/7p左メン
四恩ノ内衆生ノ恩ノ説/9p右メン
先世ノ父鶏ニ生之ヲ烹テ食事/11p右メン
下化ノ説上/12右メン
車牛ノ涎ニテ仏ヲ求ル歌ヲ書事/14右メン
下化ノ説次/15右メン
瑟ヲ抱テ斉門ニ立事/17左メン
四悪道転業ノ説/18右メン
|
今出川孝女玉櫛ノ縁/20p右メン
四恩ノ内王恩ノ説/20p左メン
獅ノ児鷲ノ雛ノ喩/22右メン
国王ノ恩ノ次/23左メン
聖天子民ヲ憫テ御資ヲ減シ賜事/25右メン
供養ノ説/25左メン
仏ノ因位為法売身割肉事/26右メン
熱田ノ孝女縁采女ノ縁/27左メン
四恩ノ内衆生恩ノ説/29右メン
仁医死狐ヲ葬テ福ヲ獲タル縁/30左メン
衆生恩ノ次/31右メン
太湖ノ念仏放生翁往生ノ事/33右メン
漁者劉成満船魚ノ大念仏ニ愕事/33左メン
堪忍ノ説/34右メン
|
至忠竜厖諫死ノ縁/34左メン
忍辱菩薩仙ノ縁/35右メン
白隠禅師忍辱行ノ縁/36右メン
堪忍ノ説/38左メン
清白犬飼氏ノ縁/40左メン
三界大夢ノ説/43右メン
僧護比丘孤独地獄ヲ見ル縁/44左メン
夢幻空華ノ説/46右メン
夢窓国師□童子ヲ吹滅ノ縁/47左メン
熊野坊ノ沙弥十三年一夢ニ愕事/49p右メン
切揚長兵衛鉱穴ニ三年填テ活還事/52左メン
今須宿妙応嫗成仏ノ縁/54左メン
追善ノ説 / 60右メン
・ |
|
| 1882 |
15 |
・ |
・ |
| 1883 |
16 |
・ |
○、この年、白隠慧鶴著,一諾編・元魯,実宗校訂「校訂版槐安国語 巻1~7」が「貝葉書院」から刊行される。 全巻:岡山県立図書館が所蔵
○、この年、白隠著逑 ; 東嶺注觧「毒語注心經」が「鈴木衣山(出版社)」から刊行される。 所蔵:九州大学 中央図書館 |
| 1884 |
17 |
・ |
7月、清水三五居士編輯「白隠禅師假名葎 2巻 乾ノ巻,坤ノ巻」が「三浦兼助/出版」から刊行される。 閲覧可能
見返しに「清水珊瑚居士編輯 浪越 其中書屋」とあり、また、「正宗國師ノ小傳:
臨濟沙門修道謹誌」を附す
明和庚寅 東嶺の序あり
収録内容:乾: 夜船閑話 / [白隠著] 白隠禅師施行歌 安心ほこりたゝ記
/ 白隠禅師作
収録内容:坤: 辻談義 / 白隠和尚述 主心お婆ゝ粉引哥
10月、大内青巒編「禅学入門」が「鴻盟社」から刊行される。 閲覧可能
注記 (曹洞)大智禅師, (曹洞)卍庵老人, (臨済)白隠和尚垂示 |
| 1885 |
18 |
・ |
4月、白隠述「安心ほこりたゝき」が「喜楽舎」から刊行される。 pid/1208549
部分タイトル ほこりたたき(白隠述) 十字盆わさん,六字読込の歌(空海作
9月、[白隠慧鶴著] ; 大灯国師編輯 ; 正宗国師編輯 「槐安国語」が「横山之成」から刊行される。 所蔵:群馬県立図書館
京都/横山之成出版社 京都/小川夛左衛門出版社 注記 曹渓菴蔵版
○、この年、慧鶴著「槐安國語 巻1~7」が「貝葉書院」から刊行される。 所蔵:山口県立山口図書館
○、この年、白隠慧鶴,一諾編輯,元魯訂校,宗實訂校「槐安國語 7巻」が「横山之成/小川夛左衞門(発売)」から刊行される。
注記 大徳寺藏版 注記 題簽の書名: 校訂槐安國語 注記 大燈國師、正宗國師編輯 注記
寛延3跋刊の再鐫
所蔵:京都府立京都学・歴彩館 |
| 1886 |
19 |
・ |
○、この年、白隠著「校訂槐安國語 一~五」が「平野平兵衛/出版社」から刊行される。 :島根県立図書館
出版地:大曽根村(愛知県)
○、この年、「夜舩閑話 白隠慧鶴」が「 菱澤重兵衛/出雲寺文次郎(発売)」から刊行される。 所蔵:京都府立京都学・歴彩館
出版社 菱澤重兵衛/出雲寺文次郎(発売) 注記 見返しに「京都書林 文鍾堂」とあり
12月、白隠禅師著「夜船閑話」が「貝葉書院」から刊行される。 pid/994576 閲覧可能
奥付に「出版人/菱澤重兵衛」とあり確認が必要 2023・1・17 保坂 |
| 1887 |
20 |
・ |
・ |
| 1888 |
21 |
・ |
・ |
| 1889 |
22 |
・ |
10月、慧鶴述「白隠和尚施行歌」が「出雲寺文次郎/出版社」から刊行される。 pid/823177 閲覧可能 重要
○、この年、大高文進編輯「往生浄土心得種(わうじやうじやうどこゝろえぐさ) 」が「澤田吉左衞門/出版」から刊行される。
往生淨土心得種序: 幽誉松月居士 (明治22)
部分タイトル 生死事大つねの用意 部分タイトル 無常迅速つねの用意和讚
部分タイトル 頓阿法師の浄土宗のこゝろをよめるながうたを附す / [(釋)頓阿撰]
部分タイトル 火急用意和讚 部分タイトル 白隱禪師の説示 / [(釋)白隱述]
○、この年、「淨土和讚圖會 慧鶴」が「和泉屋庄次郎」から刊行される。 参考:淨土和讚図会 大村屋惣兵衛板、安政5年2000円
|
注記 諸国賣捌書林: 木津屋藤兵エ ほか
注記 奥付の出版者名: 松沢庄次郎
内容: ほこりたゝき,因果和讚,地蔵尊和讚,西院の河原和讚,石女地獄和讚,血の池地獄の和讚,女人往生和讚,中将姫の和さん,一の谷組討和さん,熊谷發心の和さん,苅萱道心和讚,梅若丸和さん,道成寺安珍清姫和さん,阿波の鳴戸和さん,八百屋お七和さん・ |
|
| 1890 |
23 |
・ |
5月、白隠禅師 「夜船閑話」が「文光堂」から刊行される。 pid/823533 閲覧可能
12月、佐々木恵雲慧編集「白隠和尚転法捷径(てんぽうちかみち)」が「興教書院」から刊行される。 pid/823441 閲覧可能 |
| 1891 |
24 |
・ |
1月、饑凍編集; 寒餓校正「鵠林東嶺兩禪師毒語注心經 [白隠慧鶴頌] ; [東嶺圓慈注]
」が「矢野平兵衛」から刊行される。
タイトル別名 鵠林東嶺両禅師毒語注心経 毒語注心經:闡提翁 鵠林東領兩禪師毒語注心經
10月、「白隠法興利多々記」が「沢田文栄堂」から刊行される。 pid/823451 閲覧可能
○、この年、長岡乗薫編「※通俗仏教百科全書 第2巻 」が「開導書院」から刊行される。 pid/816886 閲覧可能
|
第壱 法事導師の心得/1p
第弐 狐つきの事/3p
第参 早合点あしき事/9p
第四 修学問答の事/10p
第五 剃髪染衣の事/11p
第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p
第七 修多羅の事/12p
第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p
第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p
第十 中陰法事の問答/14p
第十一 正法に不思議ある事/16p
第十二 法華経のありがたき事/17p
第十三 神霊の通力/20p
第十四 僧宝の徳たる事/21p
第十五 仏祖年代/23p
第十六 見てうたがひをはれたる事/25p
第十七 不用の用/28p
第十八 なければならぬ物の事/32p
第十九 一切智人の事/34p
第二十 平等心の譬喩/38p
第二十一 托鉢僧の心地/40p
第二十二 托鉢に施す心地/41p
第二十三 謡/42p
第二十四 教のありがたき事/45p
第二十五 のよし/48p
第二十五 今生現世の事/49p
第二十六 極楽法門/52p
第二十七 道理にかなひたる話/54p
第二十八 教誡田植うた粉ひきうた/57p
第二十九 讃岐の話/60p
第三十 聖教に符合する事/61p
第三十一 笑ひかへし/67p
第三十二 釈迦如来出入の事/70p
第三十三 恨をのこさぬ事/71p
第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p
第三十五 物しりがほの人にしめす/75p
第三十六 仏暦学べき事/77p
第三十七 仏法のおとろへたる事/79p |
第三十八 正月の事/80p
第三十九 考て見るべき事/82p
第四十 凡聖差別の事/84p
第四十一 宗旨の事/86p
第四十二 仏名会の事/90p
第四十三 人を見て法を説事/92p
第四十四 紛物の事/96p
第四十五 涅槃像の余意/101p
第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p
第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p
第四十八 功過録/111p
第四十九 おもしろき事/114p
第五十 おかしき事/117p
第五十一 戒定慧三学の事/120p
第五十二 夢の事/121p
第五十三 短命の小児親を
→済度する事/122p
第五十四 一如の事/125p
第五十五 聞法得益/129p
第五十六 地蔵菩薩の事/131p
第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p
第五十八 希有蓮華の事/138p
第五十九 仏智をおもふてみる事/140p
第六十 宿縁の事/141p
第六十一 慈悲心の事/142p
第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p
第六十三 光陰矢のごとし/145p
第六十四 神儒仏の尊き事/146p
第六十五 むかしもありたる事/148p
第六十六 日本に金銀のはじまり/150p
第六十七 仏暦中の邪義/152p
第六十八 普門律師直説/154p
第六十九 いろいろのはなし/157p
第七十 草茅奇言略評/166p
第七十一 強会弁をあはれむ/167p
第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p
第七十三 おもしろくおかしき事/175p
第七十四 仏説の代帰/177p |
第七十五 傍若無人の事/178p
第七十六 在家宗旨の事/182p
第七十七 母の恩の事/183p
第七十八 念仏のありがたき事/185p
第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p
第八十 いろはうた/190p
第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p
第八十二 倶生神の事に付問答/196p
第八十三 閻魔の事に付問答/196p
第八十四 梵字に付問答/197p
第八十五 木仏書像洗濯に付問答/198p
第八十六 実社の事に付問答/201p
第八十七 荒神に付問答/202p
第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p
第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p
第九十 朝日の免久美拝写/206p
第九十一 九郎本尊のうつし/211p
第九十二 往生の言/212p
第九十三 いろはの事/214p
第九十四 雛僧教育/216p
第九十五 邪神の事/220p
第九十六 愚痴の事/223p
第九十七 目前に見えるやうなる事/224p
第九十八 宰相が研究/226p
第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p
第百 石塔を立るに付問答/231p
第百一 形見に付ての問答/231p
第百二 院家院主の名称に付て問答/232p
第百三 清朝の念仏/232p
第百四 閻魔堂略縁起/236p
第百五 十王堂の額/238p
第百六 地獄の石碑/241p
第百七 神霊の事/244p
第百八 五明の事/247p
第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p
第百十 心の広き事/249p
第百十一 暦のはなし/250p
第百十二 又/252p |
第百十三 生類の上首/253p
第百十四 鯉のものいふ事/257p
第百十五 望遠鏡の事/258p
第百十六 冥加策進/261p
第百十七 徴ある事/263p
第百十八 尼の実意/265p
第百十九 蓮台のありがたき事/267p
第百二十 二十五の菩薩の事/270p
第百二十一 長浜白蛇の事/275p
第百二十二 孝行の壷/280p
第百二十三 今村の仏舎利/283p
第百二十四 梵暦策進の事/287p
第百二十五 祖師家の天文/291p
第百二十六 浄土真宗の御同行示談
→の事/295p
第百二十七 学問の感心/297p
第百二十八 白隠禅師作
→ほこりたたき註釈/302p
第百二十九 愚〔とつ〕悲歎述懐
→(ぐとつひたんじゅつくわい)/310p’
第百三十 教道に名利なき事/312p
第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p
第百三十二 畜生も恩を知る事/314p
第百三十三 不律不如注の事/315p
第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p
第百三十五 念仏の神おろし/324p
第百三十六 以呂波讃/330p
第百三十七 仏法の孝行/332p
第百三十八 往生の目出たき事/333p
第百三十九 才の賀/337p
第百四十 念仏滅罪の事/338p
第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p
第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p
第百四十三 地蔵記略出/340p
第百四十四 京都骨之屋町地蔵堂の額/345p
第百四十五 毘娑門和讃/346p
第百四十六 梵暦開祖普門律師仏
→法護持の事/348p
|
|
| 1892 |
25 |
・ |
10月、信暁著,江藤教道校「※山海里 中」が「修道館」から刊行される。 pid/820775 閲覧可能
|
壱 法事導師の心得/1p
第弐 狐つきの事/3p
第参 早合点あしき事/9p
第四 修学問答の事/10p
第五 剃髪染衣の事/11p
第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p
第七 修多羅の事/12p
第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p
第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p
第十 中陰法事の問答/14p
第十一 正法に不思議ある事/16p
第十二 法華経のありがたき事/17p
第十三 神霊の通力/20p
第十四 僧宝の徳たる事/21p
第十五 仏祖年代/23p
第十六 見てうたがひをはれたる事/25p
第十七 不用の用/28p
第十八 なければならぬ物の事/32p
第十九 一切智人の事/34p
第二十 平等心の譬喩/38p
第二十一 托鉢僧の心地/40p
第二十二 托鉢に施す心地/41p
第二十三 謡/42p
第二十四 教のありがたき事/45p
第二十五 のよし/48p
第二十五 今生現世の事/49p
第二十六 極楽法門/52p
第二十七 道理にかなひたる話/54p
第二十八 教誡出植うた粉ひきうた/57p
第二十九 讃岐の話/60p
第三十 聖教に符合する事/61p
第三十一 笑ひかへし/67p
第三十二 釈迦如来出入の事/70p
第三十三 恨をのこさぬ事/71p
第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p
第三十五 物しりがほの人にしめす/75p
第三十六 仏暦学べき事/77p
第三十七 仏法のおとろへたる事/79p
第三十八 正月の事/80p
第三十九 考て見るべき事/82p
第四十 凡聖差別の事/84p
第四十一 宗旨の事/86p
第四十二 仏名会の事/90p
第四十三 人を見て法を説事/92p
第四十四 紛物の事/96p
第四十五 涅槃像の余意/101p
第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p
第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p
第四十八 功過録/111p
第四十九 おもしろき事/114p
|
第五十 おかしき事/117p
第五十一 戒定慧三学の事/120p
第五十二 夢の事/121p
第五十三 短命の小児親を済度する事/122p
第五十四 一如の事/125p
第五十五 聞法得益/129p
第五十六 地蔵菩薩の事/131p
第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p
第五十八 希有蓮華の事/138p
第五十九 仏智をおもふてみる事/140p
第六十 宿縁の事/141p
第六十一 慈悲心の事/142p
第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p
第六十三 光陰矢のごとし/145p
第六十四 神儒仏の尊き事/146p
第六十五 むかしもありたる事/148p
第六十六 日本に金銀のはじまり/150p
第六十七 仏暦中の邪義/152p
第六十八 普門律師直説/154p
第六十九 いろいろのはなし/157p
第七十 草茅危言略評/166p
第七十一 強会弁をあはれむ/167p
第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p
第七十三 おもしろくおかしき事/175p
第七十四 仏説の代帰/177p
第七十五 傍若無人の事/178p
第七十六 在家宗旨の事/182p
第七十七 母の恩の事/183p
第七十八 念仏のありがたき事/185p
第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p
第八十 いろはうた/190p
第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p
第八十二 倶生神の事に付問答/196p
第八十三 閻魔の事に付問答/196p
第八十四 梵字に付問答/197p
第八十五 木仏画像洗濯に付問答/198p
第八十六 実社の事に付問答/201p
第八十七 荒神に付問答/202p
第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p
第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p
第九十 朝日の免久美拝写/206p
第九十一 九郎本尊のうつし/211p
第九十二 往生の言/212p
第九十三 いろはの事/214p
第九十四 雛僧教育/216p
第九十五 邪神の事/220p
第九十六 愚痴の事/223p
第九十七 目前に見えるやうなる事/224p
第九十八 宰相が研究/226p
第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p
|
第百 石塔を立るに付問答/231p
第百一 形見に付ての問答/231p
第百二 院家院主の名称に付て問答/232p
第百三 清朝の念仏/232p
第百四 閻魔堂略縁起/236p
第百五 十王堂の額/238p
第百六 地獄の石碑/241p
第百七 神霊の事/244p
第百八 五明の事/247p
第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p
第百十 心の広き事/249p
第百十一 暦のはなし/250p
第百十二 又/252p
第百十三 生類の上首/253p
第百十四 鯉のものいふ事/257p
第百十五 望遠鏡の事/258p
第百十六 冥加策進/262p
第百十七 徴ある事/263p
第百十八 尼の実意/265p
第百十九 蓮台のありがたき事/267p
第百二十 二十五の菩薩の事/270p
第百二十一 長浜白蛇の事/275p
第百二十二 孝行の壷/280p
第百二十三 今村の仏舎利/283p
第百二十四 梵暦策進の事/287p
第百二十五 祖師家の天文/291p
第百二十六 浄土真宗の御同行示談の事/295p
第百二十七 学問の感心/297p
第百二十八 白隠禅師作ほこりたたき註釈/302p
第百二十九 愚□悲歎述懐
→(ぐとつひたんじゅつくわい)/310
第百三十 教道に名利なき事/312p
第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p
第百三十二 畜生も恩を知る事/314p
第百三十三 不律不如法の事/315p
第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p
第百三十五 念仏の神おろし/324p
第百三十六 以呂波讃/330p
第百三十七 仏法の孝行/332p
第百三十八 往生の目出たき事/333p
第百三十九 歳の賀/337p
第百四十 念仏滅罪の事/338p
第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p
第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p
第百四十三 地蔵記略出/340p
第百四十四 京都骨屋之町地蔵堂の額/345p
第百四十五 毘沙門和讃/346p
第百四十六 梵暦開祖普門律師
→仏法護持の事/348p
・ |
※ 注:明治24年長岡乗薫編「通俗仏教百科全書 第2巻」と内容が同じため原本と確認要 2023・1・17 保坂 |
| 1893 |
26 |
・ |
2月、「婦人雜誌 7(1)(61) 」が「婦人雜誌社」から刊行される。 pid/1580111
|
講話/p1~5
渡世問答 / 小泉了諦/p1~5
演説/p5~8
文明の源泉 / 禿眞子/p5~8
説敎/p8~10
超世の悲願 / 龜山法因寺/p8~10
叢談/p10~21
孝行になるの傅授 / 脇坂義堂/p11~21
輯録/p21~27
|
佛敎慈善會社の必要―(施行歌) / 白隱禪師/p21~27
月報/p27~31
御歌會始/p27~28
皇太后陛下御手製の帷帳/p28~28
皇后陛下の御仁惠/p28~28
九條惠子/p28~28
近江婦人慈善會々市/p28~29
岡無外氏の義擧/p29~29
婦人佛敎演説/p29~29
|
福田會惠愛部の起因/p29~29
同會同部の移轉開院式/p29~31
伏見宮文秀女王殿下/p31~31
近衛高鳳尼の入寂/p31~31
寺院にて裁縫敎授/p31~31
長崎婦人會惣集會/p31~31
大日本佛/p31~31
・
・ |
○、この年、「孝道三教訓 宣契上人,白隠禅師 」が「出版社/福沢◆◆太郎 (印施)」から刊行される。
所蔵:東京大学 総合図書館
注記 明治26年に集誌とあり(讃歎者久良岐郡中村藤澤山主社門愚一) 発行社については再調査が必要 2023・1・18 保坂
|
孝行和讃 / 宣契上人 |
因に親の恩 / 白隠禅師 |
因に孝の道 / 白隠禅師 |
○、この年、「増補浄土和讃圖繪 慧鶴 」が「大村屋村松金八」から刊行される。
所蔵:天理大学 附属天理図書館 東京大学 総合図書館 重要
|
注記 題簽左肩双辺「増補 浄土和讃圖繪 全」(「増/補」は角書)(書名は題簽より)
注記 見返四周双辺有界「明治二十六年九月五日再版 [欄上横書] /ほこりたゝき 白隱和尚述 東照宮御神君台諭/増補 浄土和讃圖繪/東亰書肆 大村屋松村金八版」(「増/補」は角書)
注記 目録題「増補 浄土和讃図繪」(「増/補」は角書)
注記 奥付「安政三年五月十日原版/明治二十六年九月二日印刷/同年同月五日再版発行/印刷兼発行者 東京市 [住所略] 大村屋 村松金八」
注記 内容: 「東照宮御神君台諭」「ほこりたゝき」「孝行和讃」ほか13編を収める
注記 丁付: 甲-乙, 1-6, 1-43丁
注記 版式: 四周単辺7行(「東照宮御神君台諭」「ほこりたゝき」)・四周単辺9行(「孝行和讃」以下) |
○、この年、「粉挽歌 白隠慧鶴著,無能上人著,恵心僧都著」が「(横浜)/吉田藤助」から刊行される。 所蔵:石川県立図書館
粉挽歌(白隠慧鶴)、 無常和讃(無能上人)、 白骨観(恵心僧都) 内容については再確認が必要 2023・1・18 保坂 |
| 1894 |
27 |
・ |
3月、「白隠和尚転法捷径」が「 円頓学会(東叡山常照院住職 緑野長栄)」から刊行される。 pid/823442 閲覧可能
4月、長岡乗薫編「通俗仏教百科全書 第2巻」が「顕道書院」から刊行される。 pid/816889 閲覧可能
|
第壱 法事導師の心得/1p
第弐 狐つきの事/3p
第参 早合点あしき事/9p
第四 修学問答の事/10p
第五 剃髪染衣の事/11p
第六 衣の事を直綴と云は如何の問答/11p
第七 修多羅の事/12p
第八 亡者に剃刀を授ける問答/13p
第九 葬式の節墓所にて香を捻る問答/14p
第十 中陰法事の問答/14p
第十一 正法に不思議ある事/16p
第十二 法華経のありがたき事/17p
第十三 神霊の通力/20p
第十四 僧宝の徳たる事/21p
第十五 仏祖年代/23p
第十六 見てうたがひをはれたる事/25p
第十七 不用の用/28p
第十八 なければならぬ物の事/32p
第十九 一切智人の事/34p
第二十 平等心の譬喩/38p
第二十一 托鉢僧の心地/40p
第二十二 托鉢に施す心地/41p
第二十三 謡/42p
第二十四 教のありがたき事/45p
第二十五 のよし/48p
第二十五 今生現世の事/49p
第二十六 極楽法門/52p
第二十七 道理にかなひたる話/54p
第二十八 教誡田植うた粉ひきうた/57p
第二十九 讃岐の話/60p
第三十 聖教に符合する事/61p
第三十一 笑ひかへし/67p
第三十二 釈迦如来出入の事/70p
第三十三 恨をのこさぬ事/71p
第三十四 仏法をしらぬものにしめす/73p
第三十五 物しりぐほの人にしめす/75p
第三十六 仏暦学べき事/77p
第三十七 仏法のおとろへたる事/79p
第三十八 正月の事/80p
第三十九 考て見るべき事/82p
第四十 凡聖差別の事/84p
第四十一 宗旨の事/86p
第四十二 仏名会の事/90p
第四十三 人を見て法を説事/92p
第四十四 紛物の事/96p
第四十五 涅槃像の余意/101p
第四十六 生れかはるをたのしむ事/108p
第四十七 阿弥陀如来利益の事/109p
第四十八 功過録/111p
第四十九 おもしろき事/114p
|
第五十 おかしき事/117p
第五十一 戒定慧三学の事/120p
第五十二 夢の事/121p
第五十三 短命の小児親を済度する事/122p
第五十四 一如の事/125p
第五十五 聞法得益/129p
第五十六 地蔵菩薩の事/131p
第五十七 浄頗梨の鏡の事/134p
第五十八 希有蓮華の事/138p
第五十九 仏智をおもふてみる事/140p
第六十 宿縁の事/141p
第六十一 慈悲心の事/142p
第六十二 いろいろの物に生ずる事/144p
第六十三 光陰矢のごとし/145p
第六十四 神儒仏の尊き事/146p
第六十五 むかしもありたる事/148p
第六十六 日本に金銀のはじまり/150p
第六十七 仏暦中の邪義/152p
第六十八 普門律師直説/154p
第六十九 いろいろのはなし/157p
第七十 草茅危言略評/166p
第七十一 強会弁をあはれむ/167p
第七十二 於六殿の書置正念なる事/169p
第七十三 おもしろくおかしき事/175p
第七十四 仏説の代帰/177p
第七十五 傍若無人の事/178p
第七十六 在家宗旨の事/182p
第七十七 母の恩の事/183p
第七十八 念仏のありがたき事/185p
第七十九 名古屋法応寺の毘娑門略縁起/189p
第八十 いろはうた/190p
第八十一 篁朝臣の事に付問答/193p
第八十二 倶生神の事に付問答/196p
第八十三 閻魔の事に付問答/196p
第八十四 梵字に付問答/197p
第八十五 木仏書像洗濯に付問答/198p
第八十六 実社の事に付問答/201p
第八十七 荒神に付問答/202p
第八十八 法事に酒を出すに付罪福の問答/204p
第八十九 精進日とて肉食せざるに付問答/205p
第九十 朝日の免久美拝写/206p
第九十一 九郎本尊のうつし/211p
第九十二 往生の言/212p
第九十三 いろはの事/214p
第九十四 雛僧教育/216p
第九十五 邪神の事/220p
第九十六 愚痴の事/223p
第九十七 目前に見えるやうなる事/224p
第九十八 宰相が研究/226p
第九十九 たまよばいの事に付て問答/229p
|
第百 石塔を立るに付問答/231p
第百一 形見に付ての問答/231p
第百二 院家院主の名称に付て問答/232p
第百三 清朝の念仏/232p
第百四 閻魔堂略縁起/236p
第百五 十王堂の額/238p
第百六 地獄の石碑/241p
第百七 神霊の事/244p
第百八 五明の事/247p
第百九 なきむかしとはなられぬ事/248p
第百十 心の広き事/249p
第百十一 暦のむなし/250p
第百十二 又/252p
第百十三 生類の上首/253p
第百十四 鯉のものいふ事/257p
第百十五 望遠鏡の事/258p
第百十六 冥加策進/261p
第百十七 徴ある事/263p
第百十八 尼の実意/265p
第百十九 蓮台のありがたき事/267p
第百二十 二十五の菩薩の事/270p
第百二十一 長浜白蛇の事/275p
第百二十二 孝行の壷/280p
第百二十三 今村の仏舎利/283p
第百二十四 梵暦策進の事/287p
第百二十五 祖師家の天文/291p
第百二十六 浄土真宗の
→御同行示談の事/295p
第百二十七 学問の感心/297p
第百二十八 白隠禅師作
→ほこりたたき註釈/302p
第百二十九 愚◇悲歎述懐/310p
第百三十 教道に名利なき事/312p
第百三十一 弥陀悲母の大恩/313p
第百三十二 畜生も恩を知る事/340p
第百三十三 不律不如法の事/315p
第百三十四 三蔵の心をおもひみる事/319p
第百三十五 念仏の神おろし/324p
第百三十六 以呂波讃/330p
第百三十七 仏法の孝行/332p
第百三十八 往生の目出たき事/333p
第百三十九 才の賀/337p
第百四十 念仏滅罪の事/338p
第百四十一 日蓮上人の法語抜書/339p
第百四十二 存覚上人の法語抜書/340p
第百四十三 地蔵記略出/340p
第百四十四 京都骨之屋町地蔵堂の額/345p
第百四十五 毘娑門和讃/346p
第百四十六 梵暦開祖普門律師
→仏法護持の事/348p
|
6月、窮乏庵饑凍編「 白隠禅師法話集 巻之1 巻之2」が「小川多左衛門」から刊行される。 閲覧可能
巻之1/pid/823449 巻之2/pid/823450
○、この年、「遠羅天釜 巻之上-中,巻之下,續集」が藤井佐兵衛から刊行される。 所蔵:名古屋大学 附属図書館
寛延4年跋刊の後印 巻末に「明治廿七年改正正價表略書目」(京都書林山城屋藤井佐兵衛)を附す |
| 1895 |
28 |
・ |
2月、織田得能編「和漢高僧伝 巻下」が「光融館」から刊行される。 pid/817520 閲覧可能
|
道元 永平寺開基
親鸞 真宗開祖
弁円 東福寺開基
日蓮 日蓮宗開祖
祖元 円覚寺開基
睿尊 興正
普門 南禅寺開基
凝然 |
紹瑾 総持寺開基
妙超 人徳寺開基
師錬 虎関
疎石 天竜寺開基
宗純 一休
真盛 真盛派開祖
明忍慧玄 妙心寺開基
□宏 雲棲 |
天海 南光坊
宗彭 沢庵
知旭 藕益
元政
隆琦 隠元
道光 鉄眼
慈山 妙立
契沖 |
忍澂
光謙 霊空
慧鶴 白隠
普寂
飲光 慈雲
痴空 慧澄
・
・ |
6月、真宗學師藤井義住口述,真宗末資太田賢明編輯「法の馨 : 一名・家内法義示談」が「金池堂」から刊行される。
pid/818566 閲覧可能
|
亭主示談/1p
附 道歌
老人示談/23p
附 道歌
若衆示談/39p |
附 道歌
女人示談/53p
附 道歌
白隠禅師施行歌/73p
因果経和賛/74p |
古徳の遺訓/79p
恵信僧都の法語/79p
存覚上人の法語/80p
附 誡訓
他力念仏丸功能書/83p |
東照神君の遺訓/86p
治貞卿の壁書/87p
光国卿の壁書/88p
・
・ |
12月、山田孝道編「禅門法語集 : 校補点註」が「光融館」から刊行される。 pid/823256 閲覧可能
|
光明蔵三昧/1p
妻鏡/27p
大智法語/57p
十二時法語/63p
二十三問答/69p
一 道心おこすべき事
二 一心のむけやうの事
三 よしあしかぎりなき事
四 よしあしの源の事
五 根本のむまれしなざる事
六 仏生れ死にたまはぬ事
七 仏は人にかはりたる事
八 仏むしけらとなる事
九 妄念による事
十 現在の果を見て過去未来を知る事
十一 善根に有漏無漏のかはりある事
十二 浄土をねがふ事
十三 懴悔に罪をほろふる事
十四 懴悔に二つある事
十五 誓願の事
十六 廻向の事
十七 臨終の事
十八 何事も思はず徒らなるはあしき事
十九 祈祷の事
二十 仏と菩薩行の中にいづれ勝劣の事
二十一 心のなきを仏にする事
二十二 心のおこるをいかかすべき事
二十三 私のことはにあらず皆経文なる事
抜隊法語/99p
初端 成仏の直路
二 与熊阪男
二 与神竜寺尼長老
三 示中村安芸守月窓聖光
四 示赴臨終病者
五 示一方居士本間将監
六 依正法庵主強所望与之
七 与古沢尼公
八 井口禅門返答
九 井口殿御返事
十 又、比丘尼之御返事 |
塩山和泥合水集/131p
月庵法語/227p
一 示宗如禅尼
二 示慈雲禅尼
三 示宗三禅閣
四 示宗清禅閣
五 示存上人
六 示信女慶明
七 示妙光禅人
八 示在家女人
九 示慶中大師
十 又示
十一 示了仁居士
十二 示宗真居士
十三 答信秀禅人
十四 答在家人
十五 示宗通居士
十六 示簡入禅人
十七 示道漸居士
十八 示予州太守
十九 示明貞道人
二十 又示
二十一 示在家人
二十二 示在家人
二十三 答宰相中将殿間
一休法語/267p
一休骸骨/283p
不動智神妙録/291p
一 無明住地煩悩
二 諸仏不動智
三 間不容髪
四 石火之機
五 心の置所
六 本心妄心
七 有心之心無心之心
八 水上打胡盧子捺着即転
九 応無所住而生其心
十 不見放心
十一 急水上打毬子念々不停留
十二 前後際断
|
十三 内々存寄候事
盲安杖/317p
一 生死を知りて楽ある事
二 己れを顧みて己れをしるべき事
三 物ごとに他の心にいたるべき事
四 信ありて忠孝を勤むべき事
五 分限を見分けて其性性を知る事
六 とどまる所をはなれて徳ある事
七 己れを忘れて己れを守るべき事
八 立ちあがりて独りつつしむべき事
九 心を亡して心をそだつべき事
十 小利を捨て大利にいたるべき事
鉄眼法語/337p
一 色
二 受
三 想
四 行
五 識
無難法語/375p
月舟夜話/457p
卍庵法語/469p
莫妄想/489p
西来法語/507p
供養参/513p
行乞篇/525p
三帰依増語/541p
岸江小語/545p
身知夢/561p
誡殺生法語/565p
白隠法語/569p
遠羅天釜/581p
一 答鍋島摂州□近侍書
二 贈遠方之病僧書
三 答法華宗老尼之問書
四 答念仏与公案優劣如何之問書
宝鏡窟記/683p
夜船閑話/691p
辻談議/711p
粉引歌/723p
・ |
12月、慧鶴著「延命十句観音経霊験記上」が「経世書院」から刊行される。 pid/822881 閲覧可能
12月、慧鶴著「延命十句観音経霊験記 希有菴蔵版 下 」が「経世書院」から刊行される。pid/822882 閲覧可能
翻刻兼発行者 足利恵倫 |
| 1896 |
29 |
・ |
1月、進藤端堂編集「仮遠羅天釜續集」が「貝葉書院」から刊行される。
注記 : 本タイトル名は、各巻頭による(表紙、標題紙欠落のため注意) 所蔵:京都大学
人文科学研究所 図書室
|
遠羅天釜續集/白隠慧鶴 p.1-28
さし藻草/白隠慧鶴 p.29-98 |
反故集/鈴木正三p.99-190
莫妄想/鈴木正三 p.191-208 |
1月、「頓智と滑稽 2(1)」が「頓智と滑稽発行所」から刊行される。 pid/1601311
|
美妙の要素―附 面白の
→由來/犬丸太夫/p1~4
夢の利用/p4~4
馬面/p5~5
糞を喰らへ/p5~5
復讐奇談/p6~7
門松に靑竹を添る由來/p7~7
裁判/p8~8
別夢の判斷法/浮世や夢助/p9~9
四手男 / 岡鹿郞/p10~10
奇姓集/p10~10
|
半可の外人/p11~11
物嚊の博士/前田夏繁/p11~14
頓智の手代/三浦皆夢/p15~16
幼稚園敎科書/p16~16
古今該解畫談/p17~17
新年縁起六歌撰/p18~18
河野鉄兜狂歌談/p19~20
十四笑/p20~20
五藏の頭尾/p21~21
新年の貼札/p21~22
笛の名と馬の名/p21~21
|
淡然和尚/p23~23
御題の謎/p23~23
戀川春町/p23~23
落語/p23~23
落語/p23~23
女の俵/p24~24
心の目/白隱和尚/p25~25
理齋翁未來記/p25~25
古端唄/p25~25
馬道の良訓/p26~26
粥の十德/p27~27
|
祭禮法/p27
戰塲と詩會/p27
海坊主/p28
兒嶋高德新年作/兒德高德/p28
登高自卑の近譬/p29
内外觀 / 歸峰生/p30
雜草/p31
俳優年賀の言葉/p32~32
・
・
・ |
3月、進藤端堂編集「仮二十三問答」が「貝葉書院」から刊行される。
注記 : 本タイトル名は、各巻頭による(表紙、標題紙欠落のため注意) 所蔵:京都大学
人文科学研究所 図書室
|
二十三問答/夢窓國師p.1-46
鹽山和泥合水集 / 抜隊得勝p.47-168 |
不動智神妙録 / 澤庵禅師p.169-196
寶鏡窟之記 / 白隠禅師 p.197-21 |
10月、池田謙吉編輯「夜船閑話」が「池田謙吉」から刊行される。 序・巻末に「寶暦丁丑孟正」とあり 所蔵:東北大学 附属図書館
11月、「禅宗 (20)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006009
|
禪宗//1~2
雜感(二、三)//1~2
論説//3~14
言句伎倆如何か辨驗せん/大内靑巒/3~6
禪は神祕教なるか/鈴木大拙/6~10
廣語//14~20
妙法蓮華經展筵普説/白隱禪師/14~16
店上の餓夫/白隱禪師/16~20
史林//20~24
呂巖眞人//20~20
李遵勗//21~22 |
司馬光//22~24
詞苑//24~26
上甲璟巖・光萬丈・國山樵隱・常澄石門・
→齋木侃宗・峯尾宗悦・箕岡象外・
→高津森々・關谷禎造//24~46
雜録//26~32
渉獵隨筆/明堂居士/26~29
名流契悟録//29~30
一語千金//30~30
印度宗教事情/釋守愚/31~32
小説//33~47
|
迷悟/錦織可睡/33~47
雜爼//47~52
所謂四箇格言問題//47~48
宗教家懇談會//48~50
正覺會//50~51
南禪管長の開堂//51~52
哲學館十周年始業式//52~52
佛教專修學館//52~52
文壇の狡獪兒//52~52
・
・ |
12月、「禅宗 (21)」が「禅定窟」から刊行される。pid/11006010
|
禪宗//1~6
本誌改善の辭/明堂/1~4
虎壑師と山縣侯の宗教談//4~6
論説//7~17
不立文学/鈴木大拙/7~10
天台の三觀と曹洞の五位/蘆津實全/10~14
文學の鼓吹/加藤咄堂/14~171
特別寄書//17~21
宗教革新に於ける日本の位地(未完)/井上哲二郞/17~21
廣語//22~24
藕絲孔中/白隠禪師/22~23
應天龍長老需/白隠禪師/23~23
四部録開筵普説/白隠禪師/24~24 |
史傳//25~29
江西龍派和尚/足立栗園/25~27
杜衍と張方平//27~29
雜録//29~38
洪川禪師遺稿一則/茗溪樵者/29~31
渉獵隨筆/明堂居士/31~34
什□録/破草鞋子/34~35
名流契悟綠//35~37
滴水禪師と得庵居士//37~38
大内居士とヒプノチズム//38~38
金科玉條//38~38
詞苑//39~41
鐵牛禪師・鐵眼禪師・獨園禪師・柏樹軒・ |
→三笑軒・南方茗溪・國山樵隱・
→齋木侃宗・峯尾宗悅//39~41
小説//42~53
眞影/錦織可睡/42~53
雜爼//54~62
再び四箇格言問題に就て//54~61
學師會//61~61
救世軍//61~61
如何か之を感化せん//61~62
忸怩たることなきか//62~62
末法像教//62~62
其他數件/
・ |
○、この年、雲[コウ]智道/標註が「標註遠羅天釜 : 3巻,続集」を「出雲寺書店」から刊行する。
pid/1914675 国立国会図書館書誌ID:000001075242 |
| 1897 |
30 |
・ |
6月、「花の園生 (76)」が「文明社」から刊行される。 pid/1552645
|
社説/p1~4
貯蓄の事につきて/p1~4
敎訓/p4~12
法華宗老尼の問に答ふ/白隱禪師/p4~6
女子の體育(承前) / 櫻井錠二/p7~10
筆のまに[マニ] / 微笑子/p10~12
史傳/p12~17
とみの小川(其二) / 大内靑巒/p12~15
貞烈いし女の傳 / 霞北僊史/p15~17
|
散録/p17~28
門田の早苗 / 伴蒿蹊/p17~19
花の京 / みなし兒/p20~22
余が母 / 醒花庵主/p23~26
子守唄――作者不詳/p26~28
文藝/p28~32
とりかへ子 / 鐵笛道人/p28~31
和歌十一首/p31~32
雜報/p32~37 |
地久節の御祝賀/p32~33
立のぼる烟/p33~33
英照皇太后の御分塔/p33~34
體育雜話/p34~35
母の遺骨を抱いて高野山に登る/p35~36
結婚に就ての注意/p36~36
大梵鐘鑄造の計畫/p36~37
・
・ |
8月、「禅宗 (30) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006019
|
社説//1~4
坐禪の本義(中)//1~4
論説//4~7
儒と禪との關係(承前)/足立栗園/4~7
特別寄書//8~15
上州と禪宗/鈴木券太郞/8~11
善惡の標準(接前)/高洲生/12~15
懸賞論文//16~30
宗教の信念を眞理の上に立つるには
→哲學及び科學の助けを要すべきや否や
→/三寒子/16~30
廣語//31~32
答示某和尚/白隠禪師/31~32
史傳//33~36
日本佛寺建築沿革畧(承前)/塚本靖/33~36
雜録//37~55
禪餘漫録(二)/釋宗演/37~40
問答寳網に就きて/□崎正治/40~45
十年の昔(承前)/高洲山人/45~49
謠曲評釋(山姥)/大和田建樹/49~52
渉獵隨筆/明堂居士/52~54
名流契悟録/大癡道人/55~55
詞苑//56~56,57~58詩偈/柏樹軒 ; 鈴木無隠 ; |
→竹田默雷 ; 南方茗渓; 卷雲涯
→ ; 和田全明 ; 武内亨運 ; 湯本文彦
→ ; 陽谿天嶺 ; 後藤北溟 ; 以心居士
→ ; 國山樵隠 ; 井上固道 ; 齋木侃宗
→ ; 近藤圭齋 ; 森行山 ; 無位道人 ;
→東吾野人/56~56,57~58
雜俎//59~72
二十八祖論に就きて//59~61
北垣國道氏の天龍寺再建談//61~61
峨山師の氣□//61~62
似たることは頗る似たり//62~62
無邊侠禪の禪//62~62
鈴木大拙居士の來信//62~64
佛教有志家の消息//64~64
『太陽』記者の誤解//64~65
何ぞ吾が這裡を解せん//65~65
雜居準備護法大同團//65~66
武内又梅師の謙退//66~66
北海道の宗教//66~67
八丈嶋の宗教々育//67~67
新高山御命名の由來//67~68
時論//68~70
宗教分數法//68~69 |
國家と世界的宗教//69~70
神體の評價佛像の翫弄//70~70
風塵//70~71
各宗大會//70~70
各宗々議所條例案//70~70
各宗恊會々長森田悟由師//70~71
尼衆學林の認可//71~71
法相宗獨立の計畫//71~71
神祇官再興問題//71~71
淨土宗軍隊布教//71~71
增上寺住職//71~71
新刊寄贈數件//71~72
第一附録/
十牛圖頌講辯(紙面の都合により
→本號に限り休載す)/明堂居士
第二附録//1~8
録事//1~8
東福寺派録事//1~2
南禪寺派録事//3~4
南禪寺本堂再建事務本部録事//4~5
永源寺派録事//5~7
般若林録事//7~8
雜報/ |
9月、白隠著「白隠禅師寝惚之眼覚」が「前田文助/出版社」から刊行される。 閲覧可能 pid/823447
10月、「禅宗 (32) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006021
|
社説//1~8
僧侶の妻帶を論ず//1~5
宗派の小分離は斷じて不可なり//6~8
論説//9~11
禪宗の倫理によりて試みに倫理を論ず/加藤咄堂/9~11
特別寄書//11~21
善惡の標準(接前)/高洲生/11~16
勝宗十句義論に就きて/幤原坦/16~21
廣語//21~27
普説/白隠禪師/21~22
示諸禪人/木庵禪師/23~24
剩語/南源禪師/24~27
史林//27~35
日本佛寺建築沿革畧(承前)/塚本靖/27~35
雜録//35~57
數論派の輪廻説 /古河老川/35~41
拊背日記/愛楳仙士/41~48
渉獵隨筆/明堂居士/48~51
什麼録/破草鞋子/51~54
故紙録(承前)/橘染子/54~57
詞苑//58~59
詩偈/九峯詮禪師 ; 石屋□禪師 ; 鈴木寧馨 ; 常澄詔石
→ ; 安保土枕山 ; 牧野介川 ; 衣笠錦天/58~59
|
雜爼//60~69
内地雜居と外國語研究//60~60
戀愛で飯を食ふ者//60~60
人情界の大破壞時代//60~60
壽命と事功//61~61
印度に於ける宗教の盛衰//61~62
不良原因//62~62
内務大臣の宗教に關する談話//62~63
伊藤侯隨員の談話//63~63
輕罪犯人の增加//63~64
臺灣に於ける眞宗//64~64
印度救濟に關するダ氏の書簡/
住職罷免請求の訴訟//64~64
時論//65~67
一宗の宗是//65~66
宗教界の紛擾//66~67
佛教の一大耻辱//67~67
風塵//67~69
寶經塔落成//67~67
天台座主//67~68
少林會/
仁和寺住職//68~68
眞言宗長老//68~68 |
朝鮮王に經典を獻ず//68~68
幽齋公の法要//68~68
三十三間堂の修繕//68~68
本末寺院の關係調査//68~68
哲學館//68~68
哲學館校舍新築//68~68
久成僧正の入寂//68~68
德富猪一郞氏//68~68
宗教世界//68~68
眞宗新報//68~68
第一附録/
講演/
十牛圖頌講辯/田島明堂
第二附録//1~10
録事//1~10
六派本山録事//1~2
建長寺派録事//2~2
南禪寺派録事//2~3
般若林録事//4~5,9~10
南禪寺本堂再建事務本部録事//5~8
聯合本山録事//9~
・
・ |
|
| 1898 |
31 |
・ |
4月、平本正次編「白隠禅師寝惚之眼覚 (ねぼけのめざまし)」が「光融館」から刊行される。 pid/823448 閲覧可能
8月、平本正次編輯「勅謚正宗國師白隱和尚全集」が「光融館」から刊行される。 pid/823440 閲覧可能
10月、「禅宗 (44)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006032
|
論説//1~3
佛家發奮論/足立栗園/1~3
特別寄書//3~6
釋迦出世の年代に就て/桑原隲藏/3~6
廣語//6~13
興禪記/無象照禪師/6~10
學道須要集/一絲國師/10~13
史傳//14~28
日本佛教建築沿革畧/塚本靖/14~28
纂録//28~58
浴沂雜信/ふ、せ、せ、生/28~35
渉獵隨筆/明堂居士/35~38
什□録/破草鞋子/42~49
柳澤吉保の禪學/た、め、生/39~42
百妄想/村瀨元照/49~52
達磨大師安心法門/性圓/52~58
詞苑//59~61
達磨忌/一休純 ; 中巖月 ; 春澤恩 ; 元叟端; |
|
→大全雅 ; 伯林稜 ; 南溟化 ; 竺雲仙 ; 聞溪聰 ;
→桃隱朔 ; 景川隆 ; 悟溪頓 ; 特芳傑 ; 東陽朝
→ ; 大休々 ; 虎哉乙 ; 南化興 ; 湛月圓 ;
→愚堂寔 ; 一絲守 ; 柏樹軒 ; 藏□室 ;
→秋月古香 ; 西村醉處 ; 峯尾宗悅 ;
→安保土枕山 ; 淺谷月舟 ; 森行山/59~61 |
雜爼//62~63
時論概觀//62~63
淸國布教//62~62
免囚保護事業//62~63
彙報//63~82
釋尊降誕地//63~65
西藏探檢//65~69
非肉食主義//69~69
女宣教師//69~69
蓄妾家と妾の種類//69~70
白隱禪師の非蓄妾論//70~71
聖書の獻納//71~72 |
社寺法案//72~72
新潟に於ける宗演老漢//72~73
末の末也//73~73
當局者の無神經//73~73
世界の大都界//73~74
南美以教會統計//74~74
淸民又佛國教會堂を燒く//74~74
神宮教院の紛議//74~75
洪濟會の各宗管長に發したる書面//75~75
眞言宗の圖書館//75~76
監獄教誨師問題//76~80
社寺林管理法//80~80
黄檗宗の宗憲發布//80~81
一是一非 數件//81~82
附録//1~8
臨濟、黄檗各本山録事//1~6
地方教信數件//7~8
・ |
|
| 1899 |
32 |
・ |
3月、村上専精が「日本仏教史綱 下」を「金港堂」から刊行する。 pid/816950 閲覧可能
|
第三期 浄土、禅、日蓮、時代
第一章 本期仏教の大勢 / 1
第二章 南都仏教の状況 / 7
第三章 叡山僧侶の暴横及び元亀の大難並に其再建 / 11
第四章 頼瑜和尚の出世並に教相諸山の興廃 / 16
第五章 南北二京律宗の興廃 / 21
第六章 浄土宗の開立並に法然上人及び其門下 / 27
第七章 浄土宗の源流及び教義 / 33
第八章 聖光良忠及び証空上人 / 37
第九章 法然上人門下の異議 / 40
第十章 浄土宗の分派 / 45
第十一章 浄土真宗の開立並に親鸞上人及び其門下 / 50
第十二章 真宗の教義 / 55
第十三章 真宗の分派及び覚如存覚の二上人 / 58
第十四章 一遍上人の出世及び時宗の教義 / 63
第十五章 禅宗の伝来並に栄西禅師及び其門下 / 69
第十六章 栄西禅師以後の臨済禅の隆盛 / 73
第十七章 曹洞宗の伝来並に承陽大師及び其門下 / 83
第十八章 禅宗の源流並に教義 / 86
第十九章 聖一大応二国師の出世及び其門下 / 90
第二十章 夢想国師及び其門下 / 94
第廿一章 円明国師の出世及び曹洞宗の分派 / 97
第廿二章 日蓮宗の開立並に日蓮上人の出世 / 104
第廿三章 日蓮宗の教義 / 108
第廿四章 日蓮上人の門下並に日蓮宗の分派 / 113
第廿五章 日像上人の出世並に京都の日蓮宗 / 117
第廿六章 蓮如真慧の二上人及び本願寺高田の関係 / 123
第廿七章 蓮如上人滅後の真宗及び石山の戦争並に一向一揆/128
第廿八章 真盛上人の出世並に天台真盛派の分出 / 132 |
第廿九章 浄土宗白旗名越二流の繁栄 / 136
第三十章 皇室貴族の帰依並に諸寺の建立 / 140
第四期 諸宗持続時代
第一章 徳川氏の寺家制度及び崇伝長老 / 145
第二章 天主教の禁止並に宗門改め / 150
第三章 天台宗の状況並に天海大僧正 / 153
第四章 日光東叡両山の建立及び浅草寺 / 157
第五章 妙立霊空の出世及び円耳顕道の反抗並に華厳の鳳譚/162
第六章 天台宗学風の変動及び叡山安楽院の沿革 / 167
第七章 真言宗の状況並に正法律の興起 / 171
第八章 高野山学侶行人聖方の軋轢 / 177
第九章 智豊両山の由来並に其興隆 / 180
第十章 臨済宗の状況並に白隠禅師の出世 / 184
第十一章 曹洞宗の状況 / 190
第十二章 曹洞宗の復古並に月舟卍山の師資 / 194
第十三章 浄土宗の状況及び檀林 / 197
第十四章 東西両本願寺の分立及び其学黌 / 204
第十五章 両本願寺に於ける宗義の紛争 / 209
第十六章 日蓮宗中興の三師並に談林の起源 / 213
第十七章 日蓮宗不受不施派の興起 / 219
第十八章 黄檗宗の開立並に隠元禅師の事跡 / 223
第十九章 木菴高泉の二禅師並に其後の状況 / 226
第二十章 普化宗及び修験道 / 232
第廿一章 増上寺と両本願寺との宗名争論 / 236
第廿二章 神儒二道学者の排払論 / 239
第五期 明治維新以後の仏教
第一章 明治初年の状況 / 245
第二章 社寺局設置以後の状況 / 250
・ |
|
| 1900 |
33 |
・ |
1月、「三眼 (8) 」が「三眼社」から刊行される。 pid/1466720
|
羽衣之圖 / 口畫
新年の辭/p2~3
輿論は耶蘇敎を國害と認む/p3~4
バーロース博士に與る書 / 釋宗演/p5~7
森羅萬象/p8~29
名家宗敎意見 伯爵大隈重信君の意見/p29~32
小説 西遊記譯述――(圖入)/p32~36
新年雜詠――歌 / 高崎正風 ; 税所敦子 ; 佐々木信綱 ;
|
→木村正辭 ; 小出粲 ; 小池道子/p37~39
俳句 / 抱甕舍松舟 ; 眞風舍桑月/p39~42
陪鶴餘音――詩 / 三島中洲 ; 藤枝紫雪/p42~43
史傳逸事 白隱襌師の逸話/p44~44
金聲玉振 明倫歌集抜萃講義 / 佐々木昌綱/p45~46
翰影鱗光/p46~47
大穴牟遲命――附録 / 菊池容齋
・ |
3月、足立栗園が「近世徳育史伝」を「開発社」から刊行する。 pid/755195 閲覧可能
|
緒論 近世徳育の概観/1
第一 家康と天海/9
第二 惺窩と羅山/20
第三 沢庵禅師/34
第四 鈴木正三/44
第五 藤樹と蕃山/55
第六 時中と兼山/72
第七 惟足と闇斉/82
第八 元政上人/92
第九 隠元と鉄眼/101
第十 山鹿素行/109
第十一 順菴と白石/118
第十二 光国と澹泊斉/129 |
第十三 仁斉と東涯/134
第十四 徂徠と春台/143
第十五 懶斉と惕斉/152
第十六 貝原益軒/158
第十七 室鳩巣/166
第十八 荷田春満/175
第十九 石田梅巌/183
第二十 白隠禅師/192
第二十一 三輪執斉/201
第二十二 賀茂真淵/208
第二十三 湯浅常山/217
第二十四 伊勢貞丈/223
第二十五 手島堵庵/230 |
第二十六 本居宣長/238
第二十七 細井平洲/246
第二十八 中沢道二/253
第二十九 金峨と淇園/260
第三十 楽翁と栗山/268
第三十一 二洲と精里/275
第三十二 春水と拙斉/283
第三十三 竹山と履軒/290
第三十四 北山と鵬斉/296
第三十五 春海と静修/304
第三十六 幽谷と正志/311
第三十七 太田錦城/319
第三十八 慈雲尊者/324 |
第三十九 山陽と中斉/330
第四十 柴田鳩翁/337
第四十一 林述斉/345
第四十二 慊堂と竹堂/351
第四十三 平田篤胤/357
第四十四 延于と延光/365
第四十五 正鉄と規清/371
第四十六 佐藤信淵/381
第四十七 佐藤一斉/387
第四十八 艮斉と悔斉/394
第四十九 黒住宗忠/401
第五十 宕陰と息軒/407
附論 近世徳育の真相/413 |
4月、白隠禅師〔著〕「延命十句経霊験記 上・下」が「光融舘」から刊行される。 所蔵:千葉県立中央図書館・静岡県立中央図書館
7月、 「禅宗 (64)」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006052
|
禪宗//1~4
教化と戰爭//1~4
論説//4~12
宗教が外界と調和すべき程度に就て/來馬簾外/4~8
ヘーゲル氏の哲學を論ず/梅原薰山/8~12
普説//12~18
山堂間話/智覺禪師/12~15
三昧五三昧/大慧禪師/15~18
講話//18~26
十規論講話/高田道見/18~26
史傳//27~29
白隠禪師略行状/峨山禪師/27~29
纂録//29~50
禪と武士道/足立栗園/29~33
|
反古袋/森大狂/34~38
豈匏瓜齋漫録/櫻所居士/38~48
後藤某甲の殺業//48~50
詞苑//51~55
隆琦禪師・日高讓山//51~55
雜俎//55~74
臺灣に於ける各宗布教の眞相/新高山人/55~60
明暗雙々/△△生/61~62
本派東願寺と日本大菩提會//62~63
大日本菩提會趣意書及會員待遇法//63~65
基督教の大擧傳道//65~65
佛骨奉迎彙報//65~66
佛教の中心東京に移らんとす//66~66
女子大學創立事業の進行//67~67
|
アメリカン佛教々會//67~67
大谷派の臺灣及南淸布教//67~68
四國佛教團//68~68
各府縣に於ける慈善業//68~69
東京府下に於ける淫祠の信者//69~69
黄檗宗管長吉井虎林師//69~69
見性字好師の臺灣行//69~69
第九回夏期講習會//70~70
芳文會//70~70
眞美大觀//70~74
附録//1~24
聯合本山及地方教信//1~24
・
・ |
8月、「桑港仏教青年会会報 1(8) 」が「桑港仏教青年会」から刊行される。 pid/3551077
|
會報 印度饑饉に就て日本佛敎家に望む/p1~4
論説 吾人佛敎徒の傳道事業/p4~8
法語 施行歌 / 白隱禪師/p8~9
講演 印度に於ける社會階級制度と飢饉との關係/上田恭輔/p9~17
漫録 佛陀の摸倣/p17~19
漫録 天外漫筆(佛耶兩敎の比較)/p19~20
文苑 英詩 / ゼイ、ヴァード、ヘース/p21~21
文苑 漢詩 臨別告于靑年諸君・外數首 / 武田無堂 ; |
→角田松濤 ; 竹内立水/p22~22
文苑 和歌/稻葉正之 ; 竹島景尚 ; 酒井利泰 ; 町田さと子 ; 縣まさ子 ;
→ 山本翠園 ; 東海漁史 ; 叢完 ; 原臥龍 ; 竹内立水/p22~23
雜纂 英文大乘起信論序 / ポール、ケーラス/p24~25
雜纂 佛敎改革と眞宗 / 吉田素外/p25~27
雜纂 佛敎問答/p27~28
雜報 數件/p28~32
・ |
9月、足立栗園が「教訓俚歌集」を「開発社」から刊行する。 pid/755138 閲覧可能
|
第一章 謝恩、忠君、孝行
道歌四十三首
桑原冬夏の五恩冥加歌
扇の解
孝字の解
団扇の解
白隠禅師の御代の腹鼓
第二章 睦親及諸心得
道歌八首
心得歌二十二首
脇坂義堂の夫婦喧歌
老人六歌仙
第三章 知足、寡言、択友
道歌四十首
砂糖湯の解
第四章 用心、自省、慎独
|
道歌三十六首
大乗十乗
そこなふまい
中をとれ
第五章 耐忍、養生
道歌二十八首
中江藤樹忍字の書翰
多食の五害
辛棒は金
堪忍袋
手島堵庵の恕の解
第六章 勤勉、修養
道歌三十六首
商の字の解
大黒天の解
蟻と蜘蛛
|
ばくえ木の解
山東京伝の朝寐損者
第七章 正直、誠実、貞操
謙譲
道歌三十二首
親鸞上人田植歌
思ひ出しの歌、つくり出しのうた
運の字の解
七福神の神詠
第八章 節倹、慈善 (貪欲、吝嗇)
道歌三十首
金のなる木
見性成仏
五福伝授
童五用心
五用心
|
手島堵庵子者の戒
手島堵庵奉公人戒
白隠禅師施行歌の一節
第九章 快活、清廉
道歌八首
沢菴和尚垂示
一休仮名法語の一節
無難仮名法語の一節
第十章 座右銘、いろは歌
水戸光国の座右銘
細川三斉八ケ条
閑通和尚座右の銘
楠正成壁書
島津日新いろは歌
童子教訓
雑詠 |
12月、若生国栄が「活禅談 : 通俗平易」を「光融館」から刊行する。」 pid/822910 閲覧可能
|
挿画心字山水
序文
(一) 品性修養の必要
(二) 禅那を修める順序
(三) 普通仏教
(四) 仏教を学ふの主意
(五) 阿羅漢
(六) 娑婆の説明
(七) 都率の三関
(八) 禅は小麦
(九) 禅病
(一〇) 至中至正
(一一) 妙用
(一二) 絶対
(一三) 大丈夫
(一四) 百尺竿頭に一歩を進む
(一五) 阿闍梨
(一六) 和尚
(一七) 形山
(一八) 心月明
(一九) 厭世か貪世か
(二〇) 淡泊禅
(二一) 洒落禅
(二二) 頓智禅
(二三) 謹行禅
(二四) 駆虎禅
(二五) 忍辱禅
(二六) 勤王禅
(二七) 孝順禅
(二八) 無相の相。無名の名
(二九) 三界と六道
(三〇) 五戒と十善
|
(三一) 一心十界
(三二) 四聖
(三三) 六凡
(三四) 仏
(三五) 菩薩
(三六) 縁覚
(三七) 声聞
(三八) 釈迦文仏と孔夫子
(三九) 豊臣秀吉
(四〇) 名相と実相
(四一) 阿耨多羅三藐三菩提
(四二) 如来の説法。四弁八音
(四三) 如来の三十二相。八十種好
(四四) 平等と差別
(四五) 南無阿弥陀仏の説明
(四六) 万国は将に僧たらんとするか
(四七) 寿命長久
(四八) 生、住、異、滅、
(四九) 妙体と妙用
(五〇) 世界は真理の博覧会
(五一) 万里一条の鉄
(五二) 白隠禅師の隻手の声
(五三) 隻手の声如何が聞き得るや
(五四) 禅那如何が修すべきや
(五五) 結制。江湖会。法問。
(五六) 梅が香を桜の花に持たせつつ、
→柳の枝に咲かせてしかな
(五七) 妖怪を退治するの法
(五八) 我が智恵を自由自在に使用する法
(五九) 志は毘盧の頂顎を蹈み。
→行ひは嬰児の足下を拝す。
(六〇) 内地雑居以後の学禅者
|
(六一) 動と静
(六二) 円満なる智徳。万全なる幸福
(六三) 慾
(六四) 酒徳利の成仏
(六五) 唯有一乗法。無二亦無三。
(六六) ある人問ふ
(六七) 悟道の妙用は世事を達観して
→世事に還るに在り
(六八) 蚯蚓斬て両断となす
(六九) 法心坐禅
(七〇) 雲浄毒蛇
(七一) 副元帥平時頼
(七二) 盆来
(七三) 禅家の衛生
(七四) 粥に十利あり
(七五) 飲酒に三十六の過あり
(七六) 糞掃衣
(七七) 蔬食の三益
(七八) 黙々々々雷の如し
(七九) 禅者は排外主義にあらず
(八〇) 十後悔
(八一) 大乗の十来
(八二) 客の問ひに答ふ
(八三) 桃青芭蕉翁の古池の句中に禅味を含む
(八四) 五寸の真如と一尺の真如
(八五) 新年の声色
(八六) 禅榻夜話
(八七) 談片零語
(八八) 山岡鉄舟居士剣道を禅に得たり
(八九) 山水経
(九〇) 禅庭評語
・ |
○、この年、沼津児童文化会編集「郷土の昔ばなし 第12号 沼津児童文化会」に「原の白隠さん
/麻生鋭」が掲載される。
所蔵:静岡県立中央図書館 注: 「郷土の伝説民話集」より改題 |
| 1901 |
34 |
・ |
9月、欄木松次郎編輯「大福長者と成る秘伝」が「活用仏法協信教会」から刊行される。 pid/757687
閲覧可能
|
本書刊行の縁由/1
国と教/2
教と人/4
人と我/6
主と従/9
親と子/10
因と果/12
苦と楽/14
念仏と称名/17 |
徳川家康公の遺訓/18
尊円親子の訓誡/18
楠正成公の遺訓/19
水府光国卿の示訓/21
徳川六代家宣公の示訓/1
池田光政夫人の教訓/22
白隠禅師の施行歌/23
閑通和尚座右の銘/27
童子三十三訓/28 |
深草元政上人壁書/29
松平楽翁公座右の銘/31
沢庵禅師飲食の箴/32
熊沢蕃山先生の訓誨/32
因果経略和讃/36
桑原冬夏先生の恩歌/38
翠山居士無常の唄/39
古歌種々/41
・ |
11月25日、無難撰「至道菴無難禅師法語 上,下之卷」が書写される。 古典籍総合データベース(早稲田大学図書館) 重要
|
注記 漆山天童旧蔵資料
注記 題簽書名:無難禅師法語
注記 序:大徳牧宗 |
注記 千鍾房 明治22年刊の写の写
注記 一部朱書
注記 和装 |
注記 印記:樂□書
注記 附:至道菴無難禅師傳 白隱禅師和讃
巻次 上,下之卷 / |
○、この年、「近古名流手蹟 中」が「成章堂」から刊行される。 pid/852243
|
画家 英一蝶 享保九年 七十三歳/1
儒家 新井白石 享保十年 六十九歳/3
儒家 物徂徠 享保十三年 六十三歳/5
儒家 平野金華 享保十七年 四十五歳/6
儒家 室鳩巣 享保十九年 七十七歳/7
書家 細井広沢 享保二十年 七十八歳/11
歌人 百合女 享保年間(不詳)/14
釈家 僧南谷 元文元年 七十四歳/16
釈家 安積澹泊 元文二年 八十二歳/17
釈家 釈万庵 元文四年(不詳)/19
儒家 伊藤東涯 元文五年 六十七歳/21
儒家 三宅尚斉 寛保元年 八十歳/23
儒家 三輪執斉 寛保四年 七十六歳/26
儒家 宇野明霞 延享二年 四十八歳/27
儒家 太宰春台 延享四年 六十八歳/30
儒家 桂山彩巌 寛延二年 七十二歳/32
詩家 祗園南海 宝暦年間 七十五歳/35
歌人 羽倉在満 宝暦元年 四十歳/40
儒家 山県周南 宝暦二年 六十三歳/41
|
儒家 雨森芳洲 宝暦五年 八十八歳/43
詩人 猗蘭侯(本多忠統)宝暦七年 六十七歳/46
詩人 梁田蛻巌 宝暦七年 八十九歳/48
画家 柳沢淇園 宝暦八年 五十三歳/50
詩人 服部南郭 宝暦九年 七十七歳/51
儒家 成島錦江 宝暦十年 七十二歳/53
詩人 秋山玉山 宝暦十三年 六十二歳/56
儒家 岡竜洲 明和四年 七十六歳/58
釈家 釈白隠 明和五年 八十四歳/59
歌人 岡部県居(加茂真淵)明和六年 七十三歳/60
儒家 青木昆陽 明和六年 七十二歳/62
書家 松下烏石 安永元年 八十歳/64
画家 宮崎〓圃 安永三年 七十六歳/66
儒家 鵜殿士寧 安永三年 六十五歳/67
画家 建部凌岱 安永三年 五十六歳/68
儒家 松崎観海 安永四年 五十一歳/70
儒家 荻生金谷 安永五年 七十四歳/71
儒家 伊藤蘭嵎 安永七年 八十五歳/73
・ |
|
| 1902 |
35 |
・ |
2月、森大狂が「近世禅林言行録」を「金港堂」から刊行する。 pid/822934
閲覧可能
|
白隠禅師 / 1p
天桂禅師 / 22p
円瑞禅師 / 34p
馬蹄禅師 / 35p
月坡禅師 / 36p
密山禅師 / 37p
沢水禅師 / 40p
無得禅師 / 42p
全国禅師 / 44p
祖山禅師 / 46p
覚芝禅師 / 47p
黙子禅師 / 48p
印光禅師 / 49p
古月禅師 / 50p
嶺南禅師 / 53p
一丈禅師 / 54p
無聞禅師 / 55p
徳水禅師 / 57p
雪庭禅師 / 58p
曇屋禅師 / 59p
三洲禅師 / 60p
拈華禅師 / 63p
曹海禅師 / 64p
寂仙禅師 / 68p
月海禅師 / 69p
笑堂禅師 / 76p
宜黙禅師 / 78p
卍庵禅師 / 79p
遊女大橋 / 82p
指月禅師 / 86p
雲門禅師 / 89p
逆水禅師 / 91p
覚門禅師 / 92p
頑極禅師 / 94p
大潮禅師 / 98p
円通禅師 / 100p
法眼禅師 / 101p
面山禅師 / 103p
倫翁禅師 / 106p
愚谷禅師 / 107p
蘭陵禅師 / 108p
拙堂禅師 / 110p |
□年禅師 / 111p
悦厳禅師 / 113p
本光禅師 / 114p
慈門禅尼 / 116p
大休禅師 / 118p
池大雅 / 122p
明庵禅師 / 123p
月船禅師 / 126p
鉄文禅師 / 127p
遂翁禅師 / 133p
無学禅師 / 141p
素鋭禅師 / 142p
東嶺禅師 / 143p
滄海禅師 / 149p
天苗禅師 / 154p
金□禅師 / 155p
脱首座 / 157p
良哉禅師 / 158p
絶宗禅師 / 159p
阿三婆 / 163p
蘭山禅師 / 164p
峨山禅師 / 167p
葦津禅師 / 172p
円桂禅師 / 175p
快巌禅師 / 175p
環渓禅師 / 178p
悟庵禅師 / 179p
梁山禅師 / 180p
提洲禅師 / 182p
天猊禅師 / 185p
斯経禅師 / 186p
大同禅師 / 186p
層巓禅師 / 187p
頑極禅師 / 188p
長堂禅師 / 189p
劫運禅師 / 190p
天崖禅師 / 191p
愚庵禅師 / 192p
長沙禅師 / 194p
石衣禅師 / 195p
験長老 / 196p
関□禅師 / 196p |
慧昌禅尼 / 197p
善光禅師 / 197p
山梨了徹 / 199p
庄司幽徹 / 205p
阪自洞 / 206p
古郡兼通 / 207p
察女 / 208p
原駅老婆 / 211p
茶店老婆 / 212p
政女 / 212p
大典禅師 / 213p
寛田禅師 / 215p
洞水禅師 / 216p
天真禅師 / 217p
玄楼禅師 / 218p
霊潭禅師 / 221p
雲□禅師 / 223p
隠山禅師 / 227p
洞門禅師 / 233p
湛堂禅師 / 234p
仏星禅師 / 235p
性堂禅師 / 236p
誠拙禅師 / 238p
仏通禅師 / 243p
漢三禅師 / 246p
宜詳禅尼 / 247p
妙峰禅師 / 248p
活歩禅師 / 249p
良寛禅師 / 249p
行応禅師 / 259p
卓洲禅師 / 265p
雪関禅師 / 271p
田竹田 / 273p
太元禅師 / 275p
仙崖禅師 / 278p
道海禅師 / 283p
棠林禅師 / 284p
天猷禅師 / 286p
清蔭禅師 / 287p
金華禅師 / 288p
巨海禅師 / 289p
淡海禅師 / 290p
|
春叢禅師 / 291p
磨甎禅師 / 292p
古梁禅師 / 293p
象匏禅師 / 298p
黄泉禅師 / 300p
盤谷禅師 / 302p
真浄禅師 / 303p
大観禅師 / 304p
見泥禅尼 / 306p
顧鑑禅師 / 306p
玉澗禅師 / 311p
海山禅師 / 312p
風外禅師 / 313p
春応禅師 / 316p
妙喜禅師 / 317p
諦洲禅師 / 318p
綾河禅師 / 320p
耕隠禅師 / 321p
拙堂禅師 / 324p
◇天禅師 / 325p
通応禅師 / 326p
月珊禅師 / 327p
大拙禅師 / 329p
陽関禅師 / 332p
京〔サン〕禅師 / 333p
石応禅師 / 334p
迦陵禅師 / 335p
万寧禅師 / 336p
覚巌禅師 / 336p
大綱禅師 / 338p
宝船禅師 / 339p
大丘禅師 / 340p
伊山禅師 / 341p
智教禅尼 / 342p
筏舟禅師 / 343p
羅山禅師 / 345p
仏山禅師 / 347p
義堂禅師 / 349p
月潭禅師 / 351p
物外禅師 / 353p
純円禅尼 / 359p
蘇山禅師 / 360p |
天章禅師 / 365p
願翁禅師 / 366p
歌女 / 367p
薩門禅師 / 368p
大震禅師 / 369p
雪航禅師 / 371p
鉄翁禅師 / 373p
無三禅師 / 377p
晦巌禅師 / 379p
蓬洲禅師 / 386p
竜水禅師 / 388p
雪潭禅師 / 389p
長沙禅師 / 393p
橘仙禅師 / 394p
伊達自得 / 396p
奥宮慥斉 / 399p
西郷南洲 / 400p
儀山禅師 / 405p
超首座 / 407p
白翁禅師 / 409p
海州禅師 / 410p
綾洲禅師 / 413p
春日載陽 / 414p
奕堂禅師 / 416p
惟庵禅師 / 423p
馬応禅師 / 424p
泰竜禅師 / 425p
星定禅師 / 429p
環渓禅師 / 430p
越渓禅師 / 437p
愚渓禅師 / 441p
山岡鉄舟 / 442p
竜関禅師 / 450p
坦山禅師 / 452p
洪川禅師 / 462p
独園禅師 / 468p
匡道禅師 / 474p
潭海禅師 / 478p
無学禅師 / 482p
滴水禅師 / 482p
・
・
|
|
| 1903 |
36 |
・ |
7月、安部正人編「三舟秘訣 : 鉄舟・海舟・泥舟」が「有斐閣」から刊行される。 pid/777958 閲覧可能
|
三舟とは何そや/1p
鉄舟先生の秘訣/11p
(一) 鉄舟の性来/11p
(二) 父母の遺伝性より見たる鉄舟(海舟逸話)/16p
(三) 鉄舟の生母(鉄舟随筆)/21p
(四) 青年時代に於ける鉄舟の理想/23p
(五) 理想の極義/28p
(六) 剣。禅の奥義/29p
(七) 滴水の考案に就て/32p
(八) 商人の経歴談に就て/36p
(九) 滴水の考案と商人の談話に就て工夫す/39p
(十) 鉄舟豁然として省悟す/40p
(十一) 浅利又七郎秘法を伝ふ/42p
(十二) 剣法省悟の時/44p
|
(十三) 邪正弁/47p
(十四) 一刀流の仮名字目録/54p
海舟先生の秘訣/69p
(一) 初めて剣術を学ぶ模様/70p
(二) 夜中寒稽古の模様/72p
(三) 禅学をなせし理由及び其状態/75p
(四) 精神上の大作用/78p
(五) 処世哲学/83p
(六) 禅機と白隠/92p
(七) 禅機と西郷/94p
(八) 禅機の妙用/96p
(九) 禅機と外交/99p
(十) 精神的養生法/102p
泥舟先生の秘訣/105p
|
(一) 泥舟の見識/107p
(二) 修養の由来/109p
(三) 事跡と世評の誤解/113p
(四) 淋瑞律師と会合の奇跡/115p
(五) 仏教理と槍法/119p
(六) 槍法に悟入したる一奇跡/123p
(七) 二度淋瑞に会合せし大奇跡/125p
(八) 先生自覚の随筆一班/129p
(九) 行誡上人と会合に於て/132p
(十) 奕堂禅師を諭す/135p
(十一) 雲照律師と会合の大奇談/138p
(十二) 閻魔や釈迦の穴を堀る/140p
・
・ |
12月、三浦直正が「静岡県名勝誌 全」を「小池直次郎」から刊行する。 所蔵:静岡市立中央図書館
|
緒言、駿遠豆の地勢、県治上の沿革、気候、交通、伊豆国、彊域及地勢、沿革、賀茂郡、下田町、下田港、下田富士、海善寺、神子元島灯台、白浜神社、吉田松蔭遺跡、石室神社、手石弥陀窟、石廊崎灯台、松崎港、蓮台寺、田子港、帰一寺、宝蔵院、大沢鉱泉、鉱泉摘要、瀑布摘要、田方郡、熱海町、熱海温泉、■気館、湯前神社、天神社、柿本の社、大乗寺、誓欣院、行殿遺跡、貯水池、熱海公園、熱海八景、梅園の春暁、来宮の杜鵑、温泉寺の古松、横磯の晩涼、初嶋の漁火、錦浦の秋月、魚見崎の帰帆、和田山の暮雪、熱海名産、興福寺、伊豆山神社、伊豆山温泉、日金山、太田駒千代の古墳、一杯水、網代港、伊東村、伊東温泉、猪々人の温泉、山来湯、上の湯、伊東名勝遺跡、伊東十二景、伊東祐親入道寂心の墓、東林寺、伊東家の香花院、伊東の城趾、仏光寺、伊東朝高の庭墟、仏現寺、伊東祐親狩野の古跡、頼朝の遺跡、海津美神社、安宅丸の旧跡、異魚の産池、龍爪山、鎌田の城趾、宇佐美村、宇佐美の城趾及其末裔、豊公の朱印、織田信雄の禁制状、曼茶羅、羅漢の画、赤穂義士の遺物、秀衡の臣荻野其遺跡、頼朝遺跡、八幡三郎の遺跡、大見小藤太の遺跡、日蓮上人の遺跡、若宮八幡宮、河津股野の遺跡、伊東ヶ崎の洞窟、頼朝の鬢水及馬蹄石、最勝院金光明寺、韮山村、江川英龍の墳墓、江川氏累世の居邸、韮山城址、蛭ヶ小島、堀越御所、北条郷、平兼隆の館墟、国清寺、蔵春院、湯ヶ島鉱泉、上杉龍若丸の古墳、鸚鵡石、修善寺村、修善寺温泉、白糸の水簾、蝦蟇ヶ淵、修禅寺、三州園、指月殿、頼家の墓、範頼の墓、安達盛長の墓、正覚院、達摩山、戸田海水浴、露鑑製造の遺跡、瀬神社、禅長寺、三嶋町、三嶋神社、本覚寺、三嶋園、北条氏勝の城址、妙法華寺、頼朝義経対顔の地、千貫樋、鉱泉摘要、瀑布摘要、七嶋、大嶋、新嶋、利嶋、神津嶋、三宅嶋、御倉嶋、八丈嶋、駿河国、彊域及地勢、沿革、駿東郡、沼津町、沼津城址、浅間神社、丸子神社、日枝神社、乗運寺、光明寺、西光寺、道喜塚、車返坂、鶴亀墳、千本松原、沼津八景、髑髏塚、間門閻羅堂、尻無川、六代松、妙海寺、観音堂、平重盛の墓、牛臥海水浴、我入道海水浴、桃郷、楊原神社、宮内省御用邸、静浦海水浴、獅子浜、本能寺、獅子浜の城趾、八幡社、橘姫御遺体漂着遺蹟、江ノ浦、鷲頭山、金桜山、香貫山、原町、帯笑園、白隠禅師の遺跡、浮嶋沼、浮嶋ヶ原、興国寺城址、長久保城址、一柳直末の墓、愛鷹山、捕馬の故事、佐野瀑園、佐野原神社、 |
|
| 1904 |
37 |
・ |
2月、近藤常次郎が「仰臥三年 続」を「博文館」から刊行する。 pid/833200 閲覧可能 重要(仰臥禅)
|
巻上
第一章 養病大意/1p
第一節 緒論/1p
第二節 養病の本義/4p
第三節 知識概論/5p
第四節 人の一生/7p
五第節 確実なる人生観/9p
第六節 人生の欠陥/11p
第七節 生死の問題/13p
第八節 健病の二境/16p
第九節 病的生活の要領/18p
第十節 功名栄達の真相/19p
第十一節 病の福音/21p
第十二節 病的生活の時期及方法/26p
第十三節 運命観/33p
第十四節 結論/25p
第二章 病状随筆/37p
第一 理と実/37p |
第二 善と悪/38p
第三 余が今日此頃/39p
第四 禅友に答ふ/41p
第五 運命と開悟/44p
第六 吾が病生涯の事を記す/45p
第七 学者の病を論ず/48p
第八 病状八景/52p
第九 続「巌頭之感」/55p
第十 大悟徹底/56p
第十一 嬰浜君に答ふ/59p
第十二 夏の病状/61p
第十三 夢の治療的作用/63p
第十四 問疾の心得/68p
第十五 諦めと慰め/69p
第十六 看病の大要/70p
第十七 病状蒙求/71p
第十八 批評の答礼/73p
第三章 俳句記鈔/77p |
俳句七十七首並序/77p
第四章 枕頭玩占/88p
第一 某君の病を占ふ/88p
第二 紅葉山人に与ふる書/92p
第三 河西君を送る序/99p
第四 文学占話/106p
附録 筮占の批評/130p
巻下
第五章 仰臥禅話/136p
第一回 病気に対する失敗並に不平の事/136p
第二回 尿閉症発現の事/146p
第三回 病苦に対する精神上の変化の事/158p
第四回 死を諦め並に恩愛を絶つ事/170p
第五回 名誉心の断念し難き事/183p
第六回 悟道徹底の事/196p
第七回 養病十書の事/213p
・
・ |
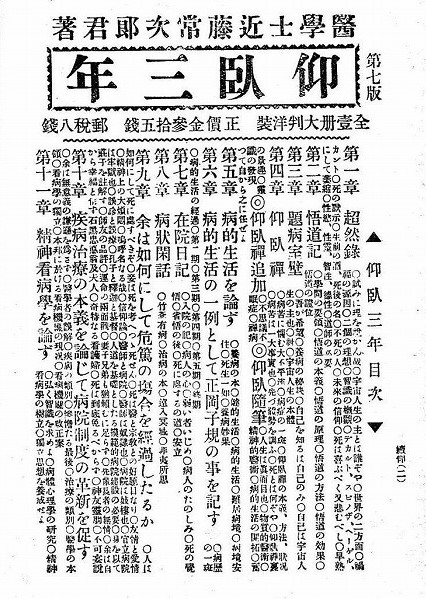
参考 近藤常次郎著「仰臥三年」 |
|
11月、釈宗演閲・大崎竜淵著「白隠禅師伝」が「文明堂」から刊行される。
(教界偉人叢書 ; 第5編) pid/823446 閲覧可能 重要
|
第一章 禅宗の起源及其法統/1
第二章 白隠禅師時代の臨済宗/11
第三章 白隠禅師及古月禅師略年譜/20
第四章 禅師の修養時代/36
第一節 幼年時代の禅師。休心房の予言。地獄の苦を恐る。日進上人の芝居を観る。/36
第二節 松蔭寺に出家す。懐疑に悩み苦悶を詩に遣る。心機一転文具を焼却す。
→英厳に於ける省悟。/48
第三節 正受老人に謁す。鬼窟裡の死禅和。飯山城下の托鉢。正受老漢の依嘱。/61
第四節 正受庵を辞す。洞山五位の訣を受く。白幽真人を訪ふ。夜船閑話。/75
第五節 佐倉に於ける問答。寿鶴道人に会ふ。荷葉団団頌に撞着す。鉄堂老漢を訪ふ。/89
第六節 小知識の説教を聴く。巌滝山の閑居。松蔭に於ける苦練。法華の深理に契当す。/100
第五章 禅師の応化時代/111
第一節 応化時代概観/111
第二節 最初の法幢/120 |
第三節 中国巡錫/126
第四節 祖師の遠忌/141
第五節 末後の一会/147
第六節 白隠禅師の入滅/150
第六章 鵠林門下の英才/152
第七章 近世の禅林/171
第八章 禅師の外教観/176
第一節 念仏と禅/176
第二節 法華と禅/196
第三節 儒道と禅/207
附録
白隠禅師著書/227
白隠禅師自刻の肖像(一葉)
・ |
|
| 1905 |
38 |
・ |
3月、裳華房編「座右之銘 : 先哲教訓 [正](先哲教訓)」が「裳華房」から刊行される。 pid/755591
|
一 豊臣秀吉 / 1p
二 千利休 / 2p
三 小早川隆景 / 4p
四 黒田如水 / 5p
五 細川幽斉 / 11p
六 加藤清正 / 13p
七 徳川家康 / 15p
八 藤原惺窩 / 15p
九 黒田長政/16p
十 藤堂高虎/17p
十一 前田利貞/20p
十二 伊達政宗/21p
十三 細川忠興/22p
十四 釈沢菴 / 24p
十五 中江藤樹/25p
十六 木下長嘯子/26p
十七 林羅山/27p
十八 江村専斉/28p
十九 釈元政/29p
二十 紀伊頼宣/30p
二十一 保科正之/30p
二十二 石川丈山/33p
二十三 荘田琳菴/34p
二十四 釈無難/35p
二十五 川村東村/36p
二十六 池田光政/37p
二十七 山鹿素行/39p
|
二十八 熊沢蕃山 / 44p
二十九 松尾芭蕉 / 48p
三十 小河立所 / 50p
三十一 水戸光圀 / 50p
三十二 安東省菴 / 51p
三十三 大槻茂慶 / 53p
三十四 向井去来 / 55p
三十五 島津綱貴 / 56p
三十六 伊藤仁斉 / 58p
三十七 大淀三千風 / 60p
三十八 浅見絅斉 / 61p
三十九 徳川家宣 / 63p
四十 大高阪芝山 / 65p
四十一 貝原益軒 / 66p
四十二 近松巣林 / 80p
四十三 細川宣紀 / 81p
四十四 四川如見 / 91p
四十五 佐藤直方 / 92p
四十六 新井白石 / 93p
四十七 荻生徂徠 / 94p
四十八 室鳩巣 / 97p
四十九 釈天桂 / 99p
五十 伊藤東涯 / 99p
五十一 三輪執斉 / 102p
五十二 雨森芳洲 / 106p
五十三 売茶翁 / 106p
五十四 中根東里 / 107p
|
五十五 永富独嘯菴 / 109p
五十六 林摩詰 / 110p
五十七 釈白隠 / 112p
五十八 吉益東洞 / 113p
五十九 平賀鳩渓 / 113p
六十 横井也有 / 115p
六十一 与謝蕪村 / 117p
六十二 伊勢貞丈 / 118p
六十三 手島堵菴 / 121p
六十四 三浦梅園 / 122p
六十五 津軽信明 / 126p
六十六 新井白蛾 / 129p
六十七 林子平 / 131p
六十八 釈東嶺 / 137p
六十九 小沢蘆菴 / 138p
七十 細井平洲 / 139p
七十一 波戸大華 / 141p
七十二 中井竹山 / 145p
七十三 釈慈雲 / 150p
七十四 畑黄山 / 151p
七十五 皆川淇園 / 152p
七十六 柴野栗山 / 154p
七十七 上杉治憲 / 157p
七十八 片岡鶴陵 / 161p
七十九 司馬江漢 / 162p
八十 尾藤二洲 / 163p
八十一 杉田玄白 / 165p |
八十二 岡田寒泉 / 165p
八十三 大田南畝 / 166p
八十四 太田錦城 / 167p
八十五 小林一茶 / 168p
八十六 松平定信 / 169p
八十七 塚田大峰 / 173p
八十八 頼山陽 / 174p
八十九 大久保忠真/175p
九十 大監後素 / 177p
九十一 中村忠昌 / 179p
九十二 渡辺華山 / 181p
九十三 平田篤胤 / 184p
九十四 古賀□菴 /185p
九十五 滝沢馬琴 / 188p
九十六 堀内素堂 / 189p
九十七 藤田東湖 / 190p
九十八 戸田蓬軒 / 193p
九十九 広瀬淡窓 / 193p
一〇〇 二宮尊徳 / 197p
一〇一 足代弘訓 / 198p
一〇二 島津斉彬 / 199p
一〇三 梁川星厳 / 200p
一〇四 釈月照 / 201p
一〇五 橋本左内 / 202p
一〇六 吉田松陰 / 215p
一〇七 佐藤一斉 / 217p
一〇八 水戸斉昭 / 220p
|
一〇九 安積艮斉 / 227p
一一〇 藤森弘菴 / 228p
一一一 羽倉簡堂 / 229p
一一二 佐久間象山 / 229p
一一三 真木和泉 / 230p
一一四 久阪玄瑞 / 234p
一一五 塩谷宕陰 / 236p
一一六 川路敬斉 / 237p
一一七 河井継之助 / 238p
一一八 横井小楠 / 238p
一一九 鍋島閑叟 / 239p
一二〇 山内容堂 / 242p
一二一 大国隆正 / 244p
一二二 安井息軒 / 246p
一二三 西郷南洲 / 247p
一二四 春日潜菴 / 250p
一二五 中村栗園 / 251p
一二六 松浦北海 / 252p
一二七 中村敬宇 / 254p
一二八 山岡鐵舟 / 256p
一二九 井上毅 / 258p
一三〇 勝海舟 / 259p
一三一 福沢諭吉 / 261p
一三二 伊藤圭介 / 267p
一三三 西村茂樹 / 268p
附録
万朝報懸賞座右銘 / 271p |
5月、平本正次編「白隠和尚全集. 第一巻」が「光融館」から刊行される。 3版 pid/904321
閲覧可能 重要
|
正宗国師年譜
傅法系譜
遠羅天釜
遠羅天釜續集
假名法語 |
さし藻草巻一
(勤発音菩提心偈附御垣守)
さし藻草巻二
邊鄙以知悟
夜船閑話 |
寶鏡窟記
述談議
主心お婆々粉引歌
施行歌
安心法興利多々記之序 |
安心ほこりたゝ記
大道ちょぼくれ
おたふく女郎粉引歌
・
・ |
|
| 1906 |
39 |
・ |
2月、原僧運が「一味の禅旨」を「光融館」から刊行する。 (禅学叢書 ; 第7編) pid/822836 閲覧可能 (2首の和歌あり)
|
死生の狂歌並に宇宙は心の事/1p
南無の声其儘仏なる事/18p
煩悩は仏の種子なる事/24p
盲人の心に思所皆仏なる事/30p
余が一生辻堂に生活を送る事/37p
各地の居士に答へ並に藤村操の迷死を憐む事/44p
母の死際に遺言の事附けたり余が所感の事/60p
霊山会上拈華の事/81p
|
九州二豪家妖怪の事/83p
万法帰一の事/98p
白隠禅師朽木の破片を示す事/103p
台南賢一居士へ返答の事/105p
某博士地獄極楽話の事/110p
嘘の世の中に生死変らぬ事/118p
任天居士仏教滅亡論の事/121p
我形体の老船を処する事/131p
|
知己より寄贈の詩歌の事/137p
禅は天地の大原理/143p
貴顕の門を敲て名剌に換る/161p
神子田有年君へ贈る/166p
道徳の御話と題して/183p
生死門題につきて/187p
仏教僧侶の為に人の嘲を解く文/194p
自跋/204p |
3月、加藤咄堂が「死生観」を「井冽堂」から刊行する。 増補15版 pid/752801 閲覧可能
|
第一章 死生観の変遷/1
(一)人生の大問題/1
(二)古代人類の死生観/6
(三)大和民族の死生観/14
(四)武士の死生観(上)/21
(五)武士の死生観(下)/32
(六)女性の死生観/40
第二章 武士道と死生観/44
|
(一)徳川時代の死生観/44
(二)山鹿素行の死生観/51
(三)白隠禅師の死生観/61
(四)大塩中斉の死生観/68
(五)吉田松陰の死生観/79
第三章 古聖の死生観/81
(一)釈迦の死生観/81
(二)基督の死生観/93
|
(三)孔老の死生観/99
(四)ソクラテースの死生観/105
第四章 近世の死生観/110
(一)近世哲学の一瞥/110
(二)科学の死生観/119
(三)科学に対する反動/125
第五章 死生問題の解決/130
(一)霊魂の断滅/130
|
(二)永久の生命/135
(三)人生の真義/140
(四)運命の是非/144
(五)死の興味/150
(補遺)死生雑話/1
・
・
・ |
8月、「風俗画報 (346)」が「東陽堂」から刊行される。 pid/1579812
|
少女ハンモツク――表紙畫 / 山本松谷/表紙
錦之御旗 / 松岡縁堂/口畫
論説 暑中休暇に就て / 山下重民/p1~3
人事門/p3~14
兒玉大將の葬儀 / 畫報生/p3~5
兒玉大將の葬儀圖 / 山本松谷
ムーア中將歡迎 / 山本松谷/p5~9
美濃十九條村諸神社祭典 / HT生/p9~10
富田一色の喧嘩祭 / 伊達菫/p10~10
興津海水浴開場 / 畫報生/p10~11
大阪小賣商人の呼賣 / 永井李蹊堂/p11~13
ゑはがき福袋 / 桔梗/p13~13
女土方 / 桔梗/p13~13
越後直江津附近婦人の勞働 / 淸水眞虎/p13~13
越後直江津附近婦人の勞働圖 / 淸水眞虎
滿洲の農業 / 淸水眞虎/p13~14
錦之御旗の二圖解 / 畫報生/p14~14
明治元年正月元日皇居御門前の圖/p14~14
會津兵伏見京橋に上陸の圖/p14~14
風俗柳樽其廿五 / 山本松谷
當世女百姿看護婦 / 濱田如洗
言語門/p15~17
甲斐方言考(下の六) / 三田村玄龍/p15~16
駿河富士郡内の方言 / 香雲/p16~17
坊主――(伊勢) / 伊達菫/p17~17
今泣いた兒――(伊勢) / 伊達菫/p17~17
飮食門/p17~18
秋元凉朝の會席獻立 / 桔硬/p17~17
諸國飮食の名物/p17~18
其一五三 滑川の黑作 / 瓦山人/p17~17
其一五四 早月川の茱萸 / 瓦山人/p17~18
其一五五 今石動の薄氷 / 瓦山人/p18~18
其一五六 ごへた餅――(美濃) / 風來庵/p18~18
其一五七 鈴の屋味噌――(伊勢松坂) / 風軒/p18~18
土木門 虎溪山脈の陶土 / 田中岩次郞/p18~19
器財門/p20~20
岐阜縣大野郡にて見たる蚤取道具 / 中野梅好/p20~20
井波の檜笠――(越中) / 瓦山人/p20~20
和田の紙煙草人――(越中) / 瓦山人/p20~20
動植門/p20~23
蚤の生涯 / 畫報生/p20~22 |
犀川の螢合戰 / 千里兵馬/p22~22
野馬燒印の圖並に考(五) / 久永章武/p22~23
遊藝門 各地子供遊/p23~24
其一二四 信濃子供遊 / 賀陽生/p23~24
其一二四 信濃子供遊圖 / 賀陽生
其一二五 岐阜近在の子供遊びの花籠 / 中野梅好/p24~24
衞生門 禮義廉恥の食養論(承前) / 石?左玄/p24~26
地理門/p26~
上野國の三碑 / 山下重民/p26~28
上野國の三碑圖 / 阪卷耕漁
濱松名所の栞 / 中村紫舟/p28~30
大和北葛城郡名勝誌(二十六) / 岡田竹雲/p30~31
越中の一の宮 / 瓦山人/p31~32
國分寺の古刹 其三九――下野國分寺 / 桔梗/p32~33
諸名所案内/p33~37
其四二一 花園村――(京都) / 宮島春齋/p33~33
其四二二 雨晴しの海水浴 / 瓦山人/p33~34
其四二三 山科の螢火――(加賀) / きの字生/p34~34
其四二四 釆石巖――(加賀) / きの字生/p34~34
其四二五 手叩の淸水――(加賀) / きの字生/p34~34
其四二六 明秀園――(加賀) / きの字生/p34~34
其四二七 篠原の松林――(加賀) / きの字生/p34~34
其四二八 長手島――(能登) / 五峰庵/p34~35
其四二九 子持山――(上野) / ちどり/p35~35
其四三〇 白隱禪師の遺跡 / 西尾東翠/p35~36
其四三一 浮島ケ原 / 西尾東翠/p36~36
其四三二 出雲國八束郡惠曇村陰陽石 / 小川寅一郞/p36~37
海外寫眞
露國水兵潜水服着
浦鹽砲臺
浦鹽海上結氷
女子永泳に就ての考案 / 畫報生/p37~37
勇壯なる入浴法 / 畫報生/p37~39
橫山博士の風穴探檢 / 畫報生/p39~39
郵便葉書の改正 / 畫報生/p39~39
臨時軍事費收支 / 畫報生/p39~40
馬匹改良の訓令 / 畫報生/p40~40
天狗神名帳 / 五明庵扇翁/p40~40
詞林 風俗畫讃拾遺/p41~42
風俗畫讃 僧、産婆
・ |
|
| 1907 |
40 |
・ |
11月、竹田黙雷述、中外日報社編「黙雷禅話 続 」が「興教書院」から刊行される。 pid/823527
閲覧可能
|
一 経典に読まるる勿れ/1
二 邪禅の流行/5
三 如来禅と祖師禅/6
四 賞罰一致/8
五 法演禅師の憂/9
六 老婆禅/10
七 老僧と洋行/11
八 再び如来禅と祖師禅/12
九 禅機拈弄の機関/13
十 禅坊主の境涯/14
十一 無作の妙用/15
十二 物我の一致/17
十三 急いて遣ては不可ぬ/19
十四 禅僧の祈祷/19
十五 白隠下の系統/21
十六 卓州隠山両派の系統/23
十七 白隠の述懐/25
十八 白隠の自画自賛/26
十九 石頭和尚の草庵歌/26
二十 出家と俗人/27
二十一 有無の商量/28
二十二 邪禅/29
二十三 精進心と妄心/30
二十四 造塔と静坐/31
二十五 少室夜坐吟/32
二十六 虚空の差別/33
二十七 丹霞和尚の玩珠吟/34 |
二十八 達磨の宝珠観/39
二十九 闡提翁/40
三十 寒林と胎宝/41
三十一 菩薩の境界/42
三十二 臨済の五山十刹/42
三十三 色衣と輪住/43
三十四 禅宗二十四流/44
三十五 再び五山十刹に就て/48
三十六 現在の安住/50
三十七 順逆二境/51
三十八 ヘボ知識/52
三十九 禅家と教相家の法戦/53
四十 船頭の実験談/57
四十一 唐の僧侶陶汰/58
四十二 漁夫の禅知識/58
四十三 竜淵東〓老師/59
四十四 師家のいろいろ/61
四十五 達磨禅経/66
四十六 大乗と小乗/66
四十七 老医の質問/67
四十八 肺病患者の引導/69
四十九 昔の法階/71
五十 腐敗又腐敗/72
五十一 僧堂常住/73
五十二 五山の連環会/74
五十三 茶禅一味/74
五十四 寒山拾得/76 |
五十五 南岳大師の偈頌/77
五十六 人境倶奪/79
五十七 収と放/83
五十八 臨済の四料揀/84
五十九 四料揀の略解/86
六十 翠巌頌略解/88
六十一 仏耶信仰の異同/89
六十二 禅と心理学/91
六十三 朴泳孝と禅/93
六十四 豪商の宗教事業/95
六十五 殺生に関する質問/97
六十六 絶待論と相待論/98
六十七 法然上人の殺生観/102
六十八 殺生に関する
→書簡の解答/104
六十九 人情の機微/105
七十 臨済禅の特色と
→悟後の修行/106
七十一 凡情退治の方便/107
七十二 臨済の三句/109
七十三 三句とは何ぞ/111
七十四 仏鑑禅師の偈頌/118
七十五 無学和尚の僧侶訓/120
七十六 昔の知識/120
七十七 五種の縁/121
七十八 布袋歌と一躯仏/122
七十九 吾に一躯の仏あり/124 |
八十 善慧大士の法身偈/125
八十一 禅に最も必要なる者/126
八十二 黙雷老漢の
→懐旧談/126
八十三 臨済の打爺/128
八十四 親の頭と酒徳利/129
八十五 臨済の宗名/130
八十六 臨済和尚の伝/131
八十七 画魔変人/135
八十八 変人と趣味/139
八十九 厠で大悟/140
九十 仙崕牧童の画賛/141
九十一 臨済の吹毛剣/141
九十二 三種の根器/142
九十三 境と法と人/143
九十四 精神と儀式/144
九十五 煩悩即菩提/145
九十六 三毒の水泡/147
九十七 修養の両面/148
九十八 隠れたる徳僧/149
九十九 薩南の護法家/149
百 囲碁と度生/150
百一 肺病慰問伝道/151
百二 白隠会下の大姉/155
百三 桶屋の頓悟/157
百四 依頼心と禅/159
百五 逆境の修養/161 |
12月、勝峰大徹著,足立栗園編「禅と長寿法」が「光融館」から刊行される。
pid/823243 閲覧可能
|
静坐内観之図/1
観念暗誦四則/1
気海丹田度数表/1
禅とは何ぞや/1 |
白隠禅師の内観法を論じて長寿法に及ぶ/6
夜船閑話序文講義/18
夜船閑話本文講義/20
錬丹秘要/130 |
引証之文/144
当世的長寿法/145
仙人的長寿法/148
禅家法語に現れたる長寿法/152 |
禅的長寿法の応用/160
白幽子伝/176
・
・ |
|
| 1908 |
41 |
・ |
7月、川尻宝岑が「白隠禅師毒語心経閑話」を「すみや書店」から刊行する。 pid/823418 閲覧可能
7月、「心の友 4(7)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539633
|
本領 氣合法に就て/p1~4
破邪顕正 / 角田雄三/p5~10
心身相關 / 木村德衛/p11~16
仰臥禪話 / 近藤常次郞/p16~19
苦中の妙樂 / 大愚/p20~21
通信精神叢話 / 無想/p21~25 |
感想録 / 大愚/p25~27
人の道 / 風翁居士/p27~29
友人に出養生を勸むる書 / 川合淸九/p29~31
實驗 治療數件 / 本部/p31~35
質疑解答/
徘句 / 齋藤松□/p35~36 |
和歌 / 鈴木重正/p36~37
通信/p39~40
會報/p40~40
・
・
・ |
8月、「心の友 4(8)」が「精神学院」から刊行される。pid/1539634
|
本領 感鷹瑣談(四)/p1~4
破邪顯正 / 角田雄三/p5~12
仰臥禪話 / 近藤常次郞/p12~16
俯仰録 / 豐信/p17~19
※夜船閑話(1) / 白隱禪師/p20~22 |
通俗精神叢談 / 無想/p22~25
感想録 / 大愚/p25~29
暗示の威力 / 津田常沒/p29~33
實驗 治療數件 / 本部/p33~36
質疑解答/ |
俳句 / 齋藤松鳩 ; 高橋桂舟/p36~37
和歌 / 鈴木重正 ; 伊藤美生/p37~39
通信/p39~40
會報/p40~40
・ |
9月、「心の友 4(9)」が「 精神学院」から刊行される。 pid/1539635
|
本領(感應瑣談(五))/p1~5
破邪顯正 / 角田雄三/p6~13
仰臥禪話 / 近藤常次郞/p13~15
東西敎育の調和 / 高島呑象/p16~18
俯仰録 / 豊信/p18~21 |
※夜船閑話(2) / 白隠禪師/p21~24
通俗精神叢談 / 無想/p24~27
精神の向上 / 大住舜岳/p28~31
實驗 治療數件 / 本部 ; 會員/p31~33
俳句 / 松島/p34~34 |
和歌 / 鈴木重正 ; 常子/p34~36
小説〔カイ〕 / 匿名/p36~39
通信/p39~40
會報/p40~40
・ |
※夜船閑話(1~2) 通番がなかったので仮に付与した。 確認要 2023・1・29 保坂
9月、孤峰智〔サン〕が「日本禅宗史要」を「貝葉書院」から刊行する。 pid/823428 閲覧可能 重要
|
総論
第一期 禅宗伝来時代
第一章 栄西禅師以前の禅/7p
第二章 臨済宗の伝来と栄西禅師/16p
第三章 曹洞宗の伝来と道元禅師/24p
第四章 栄西禅師以後の臨済宗/34p
第五章 円尓、南浦二禅師の出世と臨済宗/48p
第六章 道元禅師以後の曹洞禅/58p
第七章 寒巌、瑩山二禅師の出世と曹洞宗/62p
第八章 禅宗と文芸/69p
第二期 禅宗隆盛時代
第一章 夢窓国師及び其の門下と臨済宗の隆盛/76p
第二章 南北朝時代に於ける臨済禅の伝来/83p
第三章 曹洞各派の興起及び伝播/87p
第四章 通幻禅師及び其の門下/104p
第五章 雪江華叟二禅師の門下と臨済宗の伝播/111p
第六章 普化宗の伝来と虚無僧/118p
|
第七章 官刹及び僧録/122p
第八章 禅宗と文芸(上)/133p
第九章 禅宗と文芸(下)/140p
第三期 禅宗持続時代
第一章 徳川氏の施政と禅宗諸山の法度/149p
第二章 臨済曹洞二宗の状況/160p
第三章 曹洞宗の宗政と制度/172p
第四章 徳川上世に於ける済洞二宗の宗風/179p
第五章 黄檗宗の伝来と隠元禅師/190p
第六章 隠元禅師以後の黄檗宗/199p
第七章 月舟、卍山二禅師の出世と曹洞宗の復古/207p
第八章 心越禅師の来朝と曹洞宗の状況/229p
第九章 高泉禅師以後の黄檗山/237p
第十章 古月、白隠二禅師の出世と臨済宗の振興/242p
第十一章 峨山禅師及び其の門下/257p
第十二章 普化宗の跋扈/267p
第十三章 禅僧と文芸/276p |
10月、「心の友 4(10)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539636
|
本領 心靈講話/p1~6
養修とは何そ / 谷本富/p7~13
仰臥禪話 / 近藤常次郞/p13~17
精神的治療法 / 足立栗園/p18~20
通俗精神叢談 / 無想/p21~23 |
病をを癈める决定心 / 平井金三/p23~24
小學兒童の信仰 / 波六/p24~26
病魔は幸か不幸か / 中田重人/p26~28
井上侯の攝生談/p28~29
實験 治療數件 / 本部 ; 會員/p29~34 |
俳句 / 松塢 ; 松正/p34~34
和歌 / 伊藤美生 ; 鈴木重正/p34~37
通信/p38~40
會報/p40~40
|
11月、「心の友 4(11)」が「精神学院」から刊行される。 pid/1539637
|
本領 米國艦隊を迎ふるの辭/p1~2
修養とは何そ / 谷本富/p3~9
仰臥禪話 / 近藤常次郞/p10~15
科學と宗敎 / 谷津/p15~19
俯仰録 / 豊信/p20~22
通俗精神叢談 / 無想/p23~25 |
養生法 / 大澤謙二/p25~27
坐禪用の劍道 / 足立栗園/p27~28
斷雲三片 / 齋藤松塢/p28~29
治療數件 / 本部/p29~31
遠隔治療 / 會員/p30~30
俳句 / 松塢 ; 愚子 ; 凡哉/p31~32 |
和歌 / 鎌田與吉/p32~32
雑録/p33~36
通信/p36~39
會報/p39~40
・
・ |
〇この年、足立栗園が「偉人参禅録」を「光融館」から刊行する。 pid/822835
|
総論 / 1
第一編 上流悟道録 / 5
緒言 上流伝道の必要 / 5
(一) 家康と惺窩羅山 / 11
(二) 上流伝道の根拠 / 21
(三) 東照権現と天海僧正 / 28
(四) 妙心寺と大徳寺 / 37
(五) 沢庵、嶺南、雲居、大愚 / 45
(六) 蕃山、闇斎、仁斉、徂徠 / 54
(七) 天民、春台、直方、徳民 / 61
(八) 米沢興譲館と尾張明倫堂 / 70
(九) 二王坐禅と大梅山夜話 / 79
(十) 黄檗宗と心越派 / 87
(十一) 盤珪と沢水 / 95
(十二) 金峨、淇園、精里、竹山 / 103
(十三) 潜水、孤山、黙斉、白圭 / 111
(十四) 無難と白隠 / 119
(十五) 東嶺、古月、葦津、卓州、顧鑑/129
(十六) 儀山、蘇山、晦庵、海州、伊山/134
(十七) 上流伝道の効果 / 137
(十八) 儒仏の根本主義 / 144
第二編 武士参禅録 / 153
(一) 江戸武士と胆力養成 / 153
(二) 禅儒と無我の説法 / 163
(三) 剣道と禅 / 171
(四) 明朝と江戸幕府 / 180
(五) 勤倹尚武と禅儒 / 190
(六) 江戸武士と仮名法語 / 198
|
(七) 江戸武士と坐禅(1) / 206
(八) 江戸武士と坐禅(2) / 215
(九) 鵠林の禅風(1) / 224
(十) 鵠林の禅風(2) / 233
(十一) 鵠林門下の竜象 / 248
第三編 三教一致録 / 257
(一) 執中(尭舜) / 257
(二) 無妄(文王) / 260
(三) 守静(老子) / 262
(四) 一貫(孔子) / 265
(五) 忠恕(曽参) / 268
(六) 天人一致(孟子) / 272
(七) 虚而委蛇(荘子) / 275
(八) 仁義五常(董仲舒) / 279
(九) 無声無形(韓退之) / 280
(十) 雲天水瓶(李〔コウ〕) / 282
(十一) 己灰之木(蘇東坡) / 284
(十二) 性本情用(三安石) / 285
(十三) 窓前草生(周子) / 287
(十四) 沖漠無朕(程子) / 289
(十五) 格物致知(楊亀山) / 292
(十六) 天理全徳(朱熹) / 294
(十七) 宇宙吾心(陸象山) / 296
(十八) 黙坐澄心(李延平) / 298
(十九) 良知是道(王陽明) / 299
(二十) 心性不同(羅欽順) / 301
(二十一) 天徳至妙(菅原道真) / 303
(二十二) 今日を知れ(大江匡房) / 306
|
(二十三) 我身即神(北畠親房) / 308
(二十四) 神霊真心(忌部正通) / 310
(二十五) 神明広大(吉田兼倶) / 311
(二十六) 天人如一(藤原惺窩) / 313
(二十七) 丈夫主一(林羅山) / 315
(二十八) 止体寂然(中江藤樹) / 317
(二十九) 下済上行(熊沢蕃山) / 318
(三十) 数字祝文(山崎闇斎) / 320
(三十一) 不得止自然(山鹿素行) / 322
(三十二) 身外無道(伊藤仁斉) / 323
(三十三) 心外無道(伊藤東涯) / 323
(三十四) 唐土神道(物徂徠) / 263
(三十五) 理者気之理(貝原益軒) / 283
(三十六) 平坦易直(新井白石) / 293
(三十七) 心上有刃(室鳩巣) / 313
(三十八) 至善真智(三輪執斉) / 333
(三十九) 心一身主(石田梅厳) / 234
(四十) 心徳日新(手島堵庵) / 336
(四十一) 不一故兼学(服部天游) / 338
(四十二) 小鳥能学(柴野栗山) / 339
(四十三) 師説不泥(本居宣長) / 340
(四十四) 徳性問学(佐藤一斉) / 341
(四十五) 天地吾心(大塩後素) / 343
(四十六) 磊塊横胸(頼山陽) / 344
(四十七) 天津神の心(平田篤胤) / 346
(四十八) 笑談死生(藤田東湖) / 347
・
・
|
|
| 1909 |
42 |
・ |
1月、「禅宗 16(1)(166) 」が「禅定窟」から刊行される。 pid/11006141
|
題簽/富岡鐵齋
物菴禪話/近藤眞澄/2~17
濟世利民の法/棲梧寶嶽/17~20
我觀禪宗/忽滑谷快天/20~37
ウムマッカ本生譚/小島戒寳/37~44 |
明治禪風の獨創/來馬琢道/45~52
舊年陳暦/上村閑堂/52~60
詞苑/楞伽窟 外數氏/60~63
彙報 十四件//64~66
寄贈書籍及雜誌//66~66 |
聯合本山録事 數件//1~12
地方敎信 四件//12~12
新年附録//~24
・
・ |
2月、忽滑谷快天が「清新禅話」を「井冽堂」から刊行する。 pid/823172 閲覧可能
|
人道の大本(第一席)
一 愚かなる@猴の喩/1
二 焦門の高弟石山寺に会す/2
三 我は丈艸に与みせん/3
四 釈迦仏の平等主義/4
五 大乗仏教の平等観/6
六 大乗仏教の円融平等観/7
七 簡単なる円融の事実/9
八 梵綱経の平等一体観/10
九 孝悌と万有一体観/12
十 忠義と万象一体観/14
十一 一切の徳行と万有一体観/16
十二 王学の万有一体観/17
十三 芭蕉一茶の風流/20
十四 孝子三郎兵衛の譚/21
十五 汎心論より見たる一体論/23
十六 仁愛より見たる一体論/25
十七 永田佐吉仁孝の譚/26
十八 王陽明が科学的見地/28
十九 人間と禽獣との類同点/31
二十 社会と個人の相関/32
二十一 人道の大本は己れを
→推すに在り/34
二十二 平等と混同の別/35
二十三 王陽明の譬喩/39
人間の本性(第二席)
|
一 人間の真相果して如何/40
二 人生の表裏反覆/41
三 那先比丘の譚/43
四 人性論は四種に大別すべし/45
五 性善説の当否に就て/46
六 性悪説の当否に就て/48
七 善悪混在説の当否に就て/49
八 西山公の逸話/52
九 善悪混在説の欠点/54
十 善悪共無説の当否に就て/55
十一 善の種々なる階級/56
十二 善人と悪人とは五十歩百歩のみ/59
十三 人生は絶対善なり/61
十四 王陽明の至善説/62
十五 王氏の生死解脱/64
十六 禅の自性清浄心/65
十七 西山公仁徳の譚/68
徳行の基礎(第三席)
一 王陽明の道心人心と禅の真心妄心/72
二 命と理と性との合一/73
三 天意を体認するを要す/75
四 仁愛は天意に出づ/77
五 諸徳を一貫せる準則を要す/83
六 報恩主義の不徹底/84
七 交換主義の病弊/86
八 忠孝二道は至誠を以て一貫す/87
|
九 仁義も亦至誠に外ならず/88
十 至誠は自己の宝蔵なり/90
十一 坐禅と戒律の一致/91
十二 道元禅師の一法究尽/92
十三 他力念仏の一法究尽/94
十四 神道も念仏も其旨一なり/97
十五 至誠と生死透脱/98
十六 孝子慈母の至誠/100
十七 一貫の妙理/102
進徳の工夫(第四席)
一 儒者と禅僧の問答/105
二 治心の工夫に二あり/107
三 知行の一致と向内的工夫/109
四 二宮尊徳翁学者と僧侶を嫌ふ/110
五 向外的工夫と言行一致/112
六 白隠門下の狂僧/114
七 加藤清正の知行一致/115
八 知行は男女の如し/118
九 何を知り何を行ふか/119
十 賭博師が良心の非難/121
十一 誠は天の道なり之を誠にするは
→人の道なり/124
十二 遠くは諸を物にとり近くは
→諸を身にとる/126
十三 道徳は教ふべからず/127
十四 二宮尊徳翁と仁藤仁斉先生/134 |
8月、慧鶴著「遠羅天釜 : 白隠禅師」が「共同出版」から刊行される。 (公民文庫
; 第10冊) pid/822887 閲覧可能
|
答鍋島摂州□近侍書/1
贈于遠方之病僧書/59 |
答于法華宗老尼之問書/81
漢文無題(法華真面目)/112 |
答念仏与公案優劣如何之問書/129
答客難/165 |
8月、白隠禅師著,浜野知三郎 (穆軒道人) 校「夜船閑話」が「山本文友堂」から刊行される。 閲覧可能
10月、古屋鉄石(景晴)が「坐禅独修法 : 二十世紀式坐禅法」を「博士書院」から刊行する。 pid/822978
|
第一章 禅学とは何ぞや/1
禅学の流行
自己本来の心性の徹見
即心即仏
心が即ち禅
見性
不立文字
真理の動作
他力と自力
横尾賢宗、忽滑谷快天、勝峰大徹、元良勇次郎、
→村上精専諸氏の説
第二章 坐禅とは何ぞや/6
坐して精神を静む
実践的修養法
精神沈静の価値
慧能禅師、中峯大尚、大覚禅師、高島平三郎、
→王陽明諸氏の説
第三章 坐禅を行ふ準備/12
調身法
節せず
恣せず
沈黙教課
坐禅準備の六大要件
第四章 坐禅を行ふ方法/17
凡夫禅
小乗禅
大乗禅
最上乗禅
看話禅
黙照禅
調心法
半跏跌坐 |
結跏跌坐
吉祥坐
降魔坐
坐禅状態と催眠状態との比較
定印
気海丹田
情□
泣く為めに悲いのである
対比法
注意法
感情法
理性法
理想法
参禅
公案改良説
魔境
坐禅と幻覚錯覚
定力の効験
混沌無差別
八面玲瓏
経行
働禅
静立
立禅
柔道と坐禅
婦女坐禅法
第五章 坐禅を解く法/59
起坐法
出定法
催眠覚醒法と坐禅中止法との比較
体操中止法と坐禅中止法との比較
第六章 坐禅の効果/63
|
徳性の涵養
胆力の養成
忍耐の増進
大悟の徹底
苦悶の消失
健康の増進
処世の秘訣
成功の手段
安心の立命
身心脱落
悟道の境涯
万法唯心
心の本性
良知の意義
悉有仏性
戎定慧
精神の休養
如来禅
祖師禅
仏禅
菩薩禅
辟支仏禅
声聞禅
人天禅
外道禅
涅槃の意義
天地万有悉く禅定の姿
神経衰弱治療法としての坐禅
坐禅の効果と自己催眠の効果との比較
白隠禅師山田孝道、高島平三郎、
→釈宗演諸氏の説
・ |
○、この年、加藤教栄が「滑稽百話」を「文学同志会」から刊行する。 pid/882484 閲覧可能
|
中江兆民陰◇を杯とす/1
原坦山釈雲照を弄ぶ/1
越渓盲目にからかふ/2
西郷従道のいたづら/3
紫式部の「あさくそ丸」/3
◇白行灯を提げて関る/4
漬物の圧に石地蔵/4
蒸石博奕を好む/5
松田宗則一バイ担かる/5
桶屋の狂家/6
西山某石を煮ること三昼夜/6
金諸の法を教はる/7
孫三郎裸体となりて賊を走らす/7
山陽作詩を教ふ/8
君平糞を食はす/8
福沢桃介議論を茶にする/9
渡辺雄男掏摸の親分と間違らる/10
藪茂二郎の夏羽織/10
将軍の間抜け/11
竹を愛する人/11
おやおや火隈伯に足がある/12
ヒーローを一口一◇と読む/12
サンドウヰツチを感心す/13
米国に於けるハスバント/13
清国へ往診/14
お高祖頭巾の主/14
浪六と債鬼/15
広津柳浪探偵に窺はる/15
鏡花思案外史の好意を謝絶す/16
早川竜介金魚の失敗/16
犬養木堂小山久之助と語る/17
長谷川泰の磊落/18
大隈重信児島維謙と年若を争ふ/18
紅葉女流ハイカラに取巻かる/19
徳富蘇峯紙屑を売る/20
尾崎紅葉学堂に看板を奪はる/20
唖問答/21
片目の花嫁/22
根元通明嘱托講師を辞す/24
田中光顕便器で
→鶏肉を煮て食ふ/25
元田肇が財布の要心/25
杉孫七郎茶席ての失敗/26
神谷大周の豪宕/26
犬養木堂書生に教ゆ/27
前田正名の鼻クヤニツク/28
青生時代己代怡男の頓智/28
青木周蔵の今ソクラテスの綽名/29
水戸烈公の狂歌/29
千利休の頓才/30
前田慶次郎刀を帯びて
→風呂に入る/30
元就の大志/31
曽呂利の機智/31
加藤弘之辞表の理由/32
梅謙次郎百法の紙幣て尻をふく/32
広田華州蛙にあてらる/33
辞世と勘当と夜遊/33
也有狂歌にて債鬼を追ふ/34
画家の頓智/35
古着の離縁状/35
義堂西郷を叱す/36
章信貴客に接するを好まず/36
瑞軒漬物を売る/37
宗祗狂歌にて盗難を免る/38
時頼の狂歌/38
児玉中将新聞記者を冷かす/39
尾崎紅葉大に器量を下ぐ/39
宅青軒陶器の鑑定を誤る/40
|
金蘭斉の無頓着/41
沢庵和尚と蕎麦粉/42
竜馬南州を評す/42
脇坂七兵衛の才/43
白河楽翁候の狂歌/43
氏郷常に陣頭に立つ/44
三浦梧楼の戯言/44
兆民乞食に仮装す/46
群芳左手のお手際/46
担山握屁を嗅がす/47
湖山児童の書を損するを喜ぶ/47
鬼作左の書面/48
桜痴柳北に戯る/48
国貞己れの家に盗に入る/49
慈雲禅師盗に逢ふ/49
道灌屏風をたつ/50
若尾逸平の盗み儲け/51
江崎礼二の写開◇/51
岩谷松平に新造語あり/51
相馬永◇者に囚はる/52
仁斉◇を投ぐ/52
矢野二郎号令を忘る/53
柴田是真其の子を教訓す/53
蕪村句を題して債鬼を走らす/54
青崖の磊落/55
大隈伯優器を床間に飾る/57
大島中将の奇号/57
◇太火事に逢ふ/57
老人の呑気/58
幽◇柿を盗む/59
兆民と花嫁/59
半香自◇を破る/60
一休新左衛門に戯る/61
蜀山揮雲堂の禁酒を笑ふ/62
玉欄唐紙を被つて◇る/63
良寛児童と喜戯す/63
融川興中にて屠殺す/64
十返舎死後の戯れ/64
桃水糞桶を荷ふ/65
青崖裸体にて◇を作る/65
半香艶書にて改号す/66
白隠ぬれ衣を着せらる/66
為山の狂歌/67
永海書上に踊る/68
からかさの催促/68
滴水独園の病を見舞ふ/69
隆古三十五歌仙を画く/69
◇林三十七歌仙を◇く/70
象二郎尻を舐める/70
不死の若死/71
坦山京◇に説服せらる/72
象次郎村童の芋を持つ/73
暁斉外人を門弟とす/73
太郎兵衛の悪◇/73
華山謝罪状を懐にす/74
池辺葉永の◇美人論/75
大町桂月の立小便/75
危き金杉英五郎の命/76
◇灌猿を伏す/78
兆民火鉢に小便す/78
垣山の臨終/79
蜀山粗相を謝す/79
平八郎亀の生血をすする/80
◇茂の御礼/80
一茶の無頓着/81
普阿弥の六首/82
長沼熊掌を煮る/83
酒井抱一の◇度/84
◇外達◇を◇く/84
|
暁斉尻餅を攪て布袋となす/84
野崎真一士籍を脱す/85
勝川春章の即智/85
古筆了仲の諧◇/86
中村博士の国粋保存/87
福羽美静の衣服/88
山県侯爵洒落の鹽/88
田中正遣のかけおち/89
桂月の五つ紋の◇巻/89
大山大将の書画/90
野口勝一蛙を愛す/90
◇白の傲放と広言/91
会呂利の狂歌/91
春台徂徠に服す/92
内匠河成を苦しむ/93
河成内匠を驚かす/93
兆民乞食と相酌して夜をあかす/94
京◇の門札/94
元春醜女をめとる/94
一休袂より餅を出す/95
島羽僧正の奇才/95
江漢街上を逃ぐ/96
山陽の至孝/96
◇◇門弟に問ふ/97
兆民栗原に報ゆ/98
白猿の猿にしておけ/98
長兵衛謎を解く/99
敬沖公爵を驚かす/99
渡辺国武の吉原通ひ/100
鳥尾中将哲学者を抓る/100
放屁の一書生は松本介石/101
今西行の狂歌/101
凌岱の山の芋/102
兆民天水桶に浴す/103
蘭丸瓜を拾ふ/103
真虎夫婦喧嘩を仲裁す/104
山本権兵衛びやう衛の講釈/105
徳川慶喜公盗賊と
→間違へらる/106
元峰の◇丸/107
宗茂の◇男/108
多利雄の気長/109
覚殿の奇書/109
弁慶の味噌汁/109
兆民中井を欺く/110
弥九郎微を責む/111
一休魚を引導す/111
白隠の◇をくらへ/112
兆民の香◇/112
高山正之の豪放/112
良雄足をなむ/113
芭蕉孝子に恵む/114
大名竹/114
おどけ善光/115
◇拙伊達侯の頭を打つ/115
清正利休に服す/116
物外の@@/117
琴谷歯磨を懐にして殿中に上る/117
雅信画を暗記す/118
山崎闇斎の楽み/119
兆民の印絆◇/119
正則悪少年を懲す/120
田中正造残念二つ/120
久米桂一郎四洋人に化く/121
◇戸信六の◇大腕/121
◇沢深川八幡の神暴れになふ/122
蘭丸障子を閉づ/123
◇牙の奇癖/120
応挙の習字/123
|
金忠輔をかけて碁盤に対す/124
新平児童に美菓を興ふ/124
白露山深島一声/125
玄知の風流/125
早雲盲目を間者とす/126
義観火に投じて死す/126
義斉乞食と衣服を
→かへて着る/127
重清義経を蹴る/128
◇家の白信/128
雪舟縛されながら鼠を◇く/129
花◇父のために門を開かず/129
沈南蘋門弟に厳/130
長谷川主馬の風流/130
中井履軒の挨拶/131
老人のために読める也有/131
和尚の狂歌/132
大綱和尚の瓢◇◇/133
歌津右衛門の失敗/134
久保了意舟を呑まず/135
覚二の狂歌/139
守田宝丹不老不死の
→妙薬試験に大失敗す/136
鉄舟赤子居士に答ふ/137
坦山の奇虚/137
橋洲肖像の賛/138
海舟贋作を大切にす/138
峨山義に叱せらる/140
志賀理斉の庵/140
穆山達磨遊女対面の
→図に賛す/141
玄知近松を見る/141
義斉棺らり飛び出す/141
探幽馬履にて画を作る/141
兆民雨戸を釘付す/142
宗鑑の金のほしさよ/142
狂歌師の涙/144
良寛土に埋められんとす/144
山本権兵衛の悪戯/145
荒太郎江戸の湯を恐る/146
宗祇法師産婆の代理す/146
黒旧侯の家来竹を接ぐ/147
狂歌師の辞世/148
一休しの字を書く/148
蜀山人の禁酒/149
◇斉足にて紙を押ゆ/149
大雅堂の粗忽/150
東湖の四嫌ひ/150
柳北南◇の対句を書く/151
独園鉄舟を打つ/151
幣間の失敗/152
沢庵和尚よたか◇賛/153
潟やせんなん/153
棕隠人に雅号を授く/154
永庵自ら留守を使ふ/154
白隠大摺鉢を所望す/154
万亭応賀歌川豊斉
→百姓に縛らる/155
泥舟仕官を辞す/157
北山春安の無慾/157
渡辺華山子を戒む/158
画描道人/159
一休飴を食うて泣く/159
大下藤次郎点灯の
→お叱言を戴く/160
戸水博士の日露比較説/161
山陽岸駒を怒らす/162
慶次郎利家を冷水に入る/162
小楽沙上に馬を画く/163
|
川北温山の剛直/163
兆民為替にて尻をふく/164
環◇妓にヨシコノを教ふ/165
歌種草鞋を冠る/165
一休筍を取り戻す/166
幽斉と曽呂利との合作/167
旅僧の言訳/168
頭の風呂敷包み/168
幽◇、紹巴の上の句/169
小松帯刀のどと逸/170
浦井の鯉/171
細川藤孝の建札/171
蜀山の剛直/172
円山応挙の珍落?/173
奕堂蛇の頭を貪ふ/173
文山の画賛/174
一九借衣にて年礼す/175
国周十三両にて草双紙を質ふ/175
市川柳◇の病気見舞/175
独園壮士の胆を奪ふ/175
蜀山の狂歌/177
村重切先の饅頭を食はんとす/178
書家千虎の俳句/178
西有◇山釈迦の画像に賛す/179
独園の放縦/179
源頼政美人を撰む/180
ノウ、イエス博士井上甚太郎/180
得庵の打電伝三郎の返電/181
秀吉くんらんかんけんを解せず/182
一休の機智/182
彦左衛門の礼節の◇/183
蜀山人の仲裁/183
猿丸太夫の狂歌/184
河鍋暁斉の一◇◇/184
音之助の小便価五十石/185
原坦山某女と通ず/186
白石神たらんことを望む/186
竜関の大食/187
仙崖黒田侯の菊をかる/187
狂歌師の桂園一枝評/188
文晁富士越しの虎を画く/188
鉄舟竜雄を階下に投ず/189
一休木鉢売りに戯る/189
北斉鶏を走らして画を作る/190
仙崖踏◇となる/190
坦山と得庵との途上問答/191
梅謙次郎寛人を畑にまく/191
碩儒◇美三平の頑問固/192
津田休甫の「虎に毛抜」/193
神官環渓を苦しむる能はず/194
蓬洲の頓智/195
白隠舟子を驚かす/195
市川梅老蔵の洒落/196
明兆少時不動◇を◇く/197
方潭伏見人形を携へて
→講堂に入る/197
一休の即答/198
物外近藤勇を敗る/199
◇巌の神通力/200
明兆の廉潔/200
越渓三条公を一呑にす/201
座頭秀市の軽口/201
奕堂女郎屋にて朝斉を所望す/202
脇坂七兵衛裸体にて娘を嫁がす/202
南洲無三の喝に怕る/203
赤羽四郎生徒にもつ/203
鳥尾中将伊藤候を凹す/204
・
・ |
12月、「禅宗 16(12)(177) 」が「禅定窟」から刊行される。
|
口繪 新任南禪寺派管長猊下/
禪僧惠俊の切支丹改宗并に其の事業/新村出/2~27
秋冬雜題/八重櫻/47~48
便打老漢の逸事/千山萬水生/38~42
示衆數則/高津柏樹/33~37
他力易行辯/野崎鐵文/62~65
ウムマッカ本生譚/小島戒寳/48~52
金米糖と蓬莱豆/獅子窟道人/27~33
蒼龍窟洪川老漢/今津紹柱/52~62
燒跡の折釘/森大狂/42~47
佛傳涅槃篇を讀む/今津紹柱/65~70
詞苑//71~74
國山樵隱・菅原時保・苅谷無隱・
→竹窓道人外數人//71~74
彙報//74~86
|
東福寺開山忌//74~74
東都の禪學界//74~75
大光明寺の齋會//75~75
雪村忌//75~75
本號の口繪に就て//75~75
岡山曹源寺の道塲再興//75~76
古梁禪師の入牌式//76~77
建仁僧堂の入制式//77~77
崇福寺の開山忌//77~77
相國僧堂の入制式//77~77
大德僧堂の近况//77~78
金澤市の禪學會//78~78
金剛證寺經木堂の燒失//78~78
至道菴の見性會//78~78
梅林寺の臘八接心//78~79 |
相國管長の候補者//79~79
東福僧堂の入制//79~79
京大宗敎研究の近况//79~79
雪舟等揚の紀念碑//79~80
梅干和?の遷化//80~81
白隱禪師の書畫//81~82
黄檗僧堂の入制//82~82
黄檗山の追弔會//82~83
東京見性會の消息//83~84
山陰の思想界//84~84
漢陽開山忌//86~86
敎界近時 十四件//86~87
新刊紹介 一件//87~87
附録//1~7
聯合本山録事 六件//1~7 |
○、この年、好古社編「好古類纂 二編 第十一集」が「好古社」から刊行される。 pid/1245145
|
諸家説話
尾張三十六歌仙 武田信賢
森尚謙の棊箴 靑山淸吉
蜀山人の火をいましむる詞未完 靑山淸吉
儀禮部類
先朝歌御會始未完 伯爵 松浦詮
史傳部類
名家像傳 宮崎幸麿
生駒親正 |
戸田一西
稻葉貞通
黑田如水
南化和尚
隱元禪師
山鹿素行
松倉嵐蘭
露川坊
淺野長矩 |
武器部類
木原盾臣鉾盾圖説未完 内柴御風
風俗部類
時行修容 承前未完 靑山淸吉
古蹟部類
墓所集覽麻布區 承前未完 武田醉霞
附録
第四十四囘好古會記事
・ |
|
| 1910 |
43 |
・ |
2月、「禪學寳典」が「貝葉書院(京都)」から刊行される。 pid/1909574
|
達磨大師四行觀
頌古二首 南禪乾峰曇國師
三祖大師信心銘
石頭大師參同契
臨濟慧照禪師語録
芙蓉禪師祗園正儀
永嘉大師證道歌
寒山詩
永明智覺禪師埀誡
頌古三首 淨智無象照禪師
無門關
頌古五首 圓覺子元元國師
廓菴和尚十牛圖
坐禪儀
宏智禪師坐禪箴
頌古五首 建長靈山隱禪師 |
禪家龜鑑
頌古九首 建仁雪村梅禪師
禪關策進
承陽大師普勸坐禪儀
承陽大師坐禪箴
偈讃五首 永平開山元禪師
承陽大師自受用三味 附發願文
讃一首 永平開山元禪師
承陽大師學道用心集
頌古二首 永平開山元禪師
蘭溪禪師註心經
偈讃三首 建長蘭溪隆禪師
天龍夢窓國師遺誡
頌古三首 天龍夢窓石國師
興禪大燈國師遺誡
永源圓應禪師十件要須
|
常濟大師坐禪用心記
常濟大師三根坐禪説
發願文 大慧普覺禪師
寒林貽寳
附録
智者大師圓頓章
雙林善慧大士心王銘
南堂和尚辨驗十門
五家參詳要路門
頌古五首 大德宗峰超國師
荊棘叢談
面山和尚經行記
面山和向信施論
坐禪和讃 白隱慧鶴國師
・
・ |
6月、秋山悟庵が「青年と禅」を「文成社」から刊行する。pid/823174 閲覧可能
|
第一章 緒言/1
一 禅の呼声/1
二 国民の自覚/2
三 精神の飢渇/6
四 安心の要求/8
第二章 青年参禅の可否/10
一 現代名家の意見/12
第三章 禅/31
一 禅の名称及び意義/31
二 禅の種類/33
三 禅の目的/35
四 禅の将来/43
第四章 死禅/51
一 枯木禅/51
二 貴族的禅/56
三 隠居的禅/58
四 天狗禅/59
第五章 活禅/62
一 静中の動/62
|
二 古池の句と禅味/66
三 禅と学芸/69
四 平民禅/76
第六章 胆力養成/95
一 意志の修養/95
二 北条時宗の胆力養成/104
三 鈴木正三の胆力養成法/113
四 生死の関門を撃破せよ/116
五 偉人の死生観/126
六 堅忍不抜/138
七 雪村友梅/140
八 僧禅海/149
第七章 大勇猛の心/156
一 金剛不壊の大意志/157
二 虎口裡に身を横ふ(二祖臂を断つ)/160
三 美人の参禅(美人顔を焼く)/163
四 敵の牙営に突進せよ(上杉謙信)/179
第八章 長寿の法/184
一 身心調和の術(白隠の内観法)/187
|
二 精神を丹田に凝集ずるの効力/201
三 仏仙法(坦山の長寿法)/207
四 元気養成と筋力養成/215
五 心の主たれ心の使たる勿れ/221
第九章 自重自尊心/224
一 自重心と成功/224
二 自信力/232
三 言行一致/236
第十章 常識を逸するなかれ/243
一 平常心是れ道/245
二 日日の行為是れ正道/251
三 悪平等なるなかれ/254
第十一章 禅の道徳観/259
一 無我の観念/261
二 慈悲の観念/266
三 清廉高潔/276
四 寡慾勤倹/288
五 局量寛大/296
第十二章 赤裸禅(帰結)/305 |
9月、近重真澄(理学博士)が「参禅録」を「服部書店」から刊行する。 pid/823011 閲覧可能
|
緒言 / 1
禅哲学
宗教
学術
禅は不可解なり
禅の科学的心理学的並に医学的研究
禅の流行
禅学者の漫◇
余の願心
第一章 禅とは何ぞや / 9
禅は不可説なり
路逢剣客須呈。不遇詩人莫献
州勘庵主の話
不立文字。教外別伝
群盲評器。自然に滑稽に落つ
仏心和尚の話
婆子焼庵の話
仙崖和尚の話
禅は滑稽に非ず
禅を修むるには真面目なるべし
正三老人の語
真面目の効能
努力其者が禅に入るべき真個の手段
命懸けの際の心理状態
車窓より飛出せる旅客
戦争にて負傷せる軍人
無自覚の境界
無自覚の心理
大死一番
死して又蘇す
悟道の結果
禅観と俗諦との差
知行合一
無から有の生ずる適例
第二章 公案 / 37 |
禅は先づ赤裸裸ならんことを要す
禅須らく修むべきか否か
大疑の下に大悟あり
世尊拈華
頓悟と漸悟
最後の一重関
公案
公案の種類
法身
隻手の音声
趙州の無字
這箇什麼
法身は第一関にして又最後の一関なり
平田篤胤先生
機関
言詮
難透
坐水月道場。修空華万行
五位。十重禁
悟後の修行
生兵法を戒む
公案と身体の関係
第三章 座禅 / 66
外界に応ずる身体上の準備
座禅。公案。定力
座禅の方式
座禅の方式に関する得失を論ず
足を組むこと
最も安定なる平衡状態
脊梁骨を直立せしむること
最も長きに耐ゆる安座法
手を重ぬること
衝動的運動を防止す
下腹に力を入るること
力を丹田に籠むるは反動力を貯ふる所以なり |
腹で考ふること
素人の考へ方
座禅により究極到着すべき体格
第一特徴
安住不動。如須弥山
胆気圧人
第二特徴
第三特徴
肺臓の運動極めて遅緩となる
禅定の冬蟄状態説
第四章 禅観の科学的批評 / 98
禅観
認識及推理の方法の種類
三段論法及一段論法
相対的智識とは何ぞや
長の例
色の例
所謂事実とは何ぞや
認識にも推理にも共に等しく三段論法を用ゆ
三段式智識の欠点
第一の欠点
第二の欠点
第三の欠点
一段論法
一段論法と数学的絶対との差
無差別平等
却来底
時間の問題
禅の解析的論究の結果
宗教学より見たる禅
禅宗の一大長所
第五章 信心銘に就て / 139
第六章 結語 / 159
・
・
|
10月、服部俊崖が「白隠和尚言行録」を「内外出版協会」から刊行する。 (偉人研究 ; 第64編) pid/823439 閲覧可能
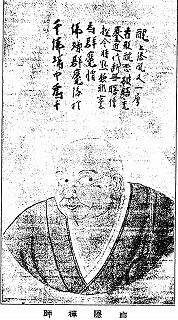 (所蔵:鹿王院) (所蔵:鹿王院)
|
一 浮島原 / 1p
二 地獄を恐る / 8p
三 香煙真直に立たせ給へ / 14p
四 出家 / 18p
五 馬翁に学ぶ / 22p
六 『禅関策進』に撞着す / 27p
七 書画を一炬に焼く / 29p
八 故郷に還る / 34p
九 半夜の鐘声 / 37p
一〇 正受老人に謁す / 41p
一一 飯山城下の托鉢 / 45p
一二 正受庵を辞す / 48p
一三 身火逆上す / 50p
一四 雪花霏霏として林葉に洒ぐ/60p
一五 驟雨車軸を流し泥水脛を呑む/64p
|
一六 手を出す勿れ / 67p
一七 岩滝山中の隠栖 / 70p
一八 松蔭寺に帰る / 72p
一九 白隠と号す / 75p
二〇 蟋蟀古砌に鳴く / 78p
二一 『神社考』を読む / 83p
二二 僧堂を建つ / 86p
二三 『虚堂録』を評唱す / 90p
二四 念仏禅を排す / 96p
二五 黙照禅を排す / 101p
二六 関鎖禅 / 105p
二七 『十句観音経』を弘む / 110p
二八 五位偏正の秘奥を発明す/113p
二九 一臠を嘗めて全鼎を知る / 125p
三〇 双手の音声 / 129p |
三一 『槐安国語』 / 134p
三二 池大雅来り謁す / 140p
三三 無量寺建つ / 145p
三四 三教一致 / 149p
三五 『宝鑑貽照』を著す / 157p
三六 竜沢寺建つ / 161p
三七 清女の木像 / 165p
三八 江戸に入る / 170p
三九 大吽一声 / 178p
附録
一 年譜 / 184p
二 系図 / 192p
・
・
・ |
11月、稲村修道編「和讃説教 : 布教新案」が「出雲寺松栢堂」から刊行される。 pid/822815 閲覧可能
|
第一座 地蔵和讃説教 / 1
地蔵和讃
説教
さいの河原の由来
死の問題
出家の述懐
世の中は理屈一点では行かぬ
甲斐の国の厳融房
死別の悲
死別の慰安
第二座 白隠和尚施行歌説教/23
施行歌
世の中は皆我利々々盲者
三世因果の道理
慈善事業
誤解されたる三世因果説
精神と肉体
業力輪廻説
強盗説法の因縁
因果を信ずる人
第三座 中将姫和讃説教/50
和讃
金剛刋定記の説
われらは法を聞くべき機也
中将姫
家庭教育と胎内教育
胎教 |
第四座 中将姫和讃説教(続)/64
妻や夫に先立たれた者の心持
姫の孝心
唐の陳叔達
照夜の前
継親について
姫の出家
雲雀山
清女の発心
仏教恋愛観
当麻曼荼羅の由来
第五座 祈祷和讃説教/68
祈祷和讃
ポールケラース博士
因果の小車
出家と宝石商人
他をそこなふは己を害するなり
善因善果悪因悪果
善業直ちにこれ祈祷
第六座 祈祷和讃説教(続)/102
国王の宝石注文
強盗の懴悔
宝石商人の遺言
他を助くるは吾身を助くるなり
第七座 熊谷発心和讃説教/111
和讃
熊谷発心の因縁 |
一の谷の悲劇
熊谷と経盛卿の消息
釈尊と羅?羅楽天と其子
法然上人
熊谷発心後の生活
坂東の阿弥陀仏
宇津宮頼綱
トルストイ曰く
宗教生活の妙味
第八座 追善和讃説教/129
和讃
追善の意義
先亡の追慕
京のある富豪の説話
法界に遍満する功徳
第九座 坐禅和讃説教/139
和讃
説教
白隠和尚
生死を超脱する生活
霊山会上の拈華微笑
仏性
自力宗他力宗
岡目八目
一刀両断
小野平左衛門の一子浅之丞
猫の祟 |
八太郎の機会
『障子の穴ふさぎ』
大乗禅
仁王経に曰
四智円満
此身此侭仏也
第十座 念仏和讃説教/165
帖外九百和讃
親鸞聖人
王舎城の悲劇
頻婆娑羅王
韋提希夫人
阿闍世王
極楽浄土
弥陀の悲願
他力の救済
称名相続
附録和讃集
孝行和讃
因果和讃
刈萱道心和讃
梅若丸和讃
阿波鳴戸和讃
安心ほこりたたき
・
・
・ |
〇この年、黒沢勇編「体育論 : 現代之諸名家」が「日本体育会」から刊行される。 pid/860338 重要
|
第一編 論説
一 女子と体育/1
二 審美上より体育の必要を論ず/5
三 体育に就ての所感/9
四 国際上より見たる体育の必要/19
五 体育の価値/24
六 国民体育を振興すべし/37
七 経済上より見たる体育/47
八 体育が経済と趣味とに及ぼす影響/54
九 体育上より犯罪の原因を論ず/57
一〇 遊戯論/62
一一 生存競争と体育の必要/80
一二 国民体育と国家活動力との関係/87
一三 品性修養の基礎/93
一四 体育と精神作用/111
一五 体育と文明との関係を論ず/118
第二編 学説
一 禅定と体育/134
二 白隠禅師の体育法(附同師独按摩の伝)/146
三 美育と体育/151
四 体育の二要件/155
|
五 精神的衛生/169
六 体育と栄養との関係/176
七 婦人の特別衛生/182
八 医薬を要せすして疾病を根治する体操法/206
九 英人の体格及び性質/216
一〇 体育時言/227
第三編 講演
一 体育普及の急務/246
二 浩然之気/262
三 人物養成上より見たる体育/275
四 邦人の体格/313
五 体育の目的に就て/361
六 米国婦人の体育と体育所感/364
七 欧洲の体育/374
八 最近欧米各国に於ける学校体操の趨勢/389
九 学校体操に就て/403
一〇 体育に就て/410
附録
第一部 競争遊戯
第二部 動作遊戯
第三部 行進遊戯 |
○、この年、足立栗園編「教訓俚謡集 : 高僧碩徳」が「森江書店」から刊行される。 pid/816349
|
(一) 渡世の船唄・天珪禅師/1
(二) 本心の歌・盤珪禅師/3
(三) 孝の道・紫笛上人/9
(四) 明徳和讃・手島堵庵/16
(五) 孝弟和讃・手島堵庵/21
(六) 親の恩・手島堵庵/24
(七) いろは歌・手島堵庵/28
(八) 孝行粉引歌・仰誓和尚/34
(九) 子守歌・知真庵主/39
(十) 弘誓の船・大我上人/49
(十一) 念仏安心歌・大我上人/50
(十二) 本心歌・桑原冬夏/54
(十三) 五恩冥加歌・桑原冬夏/57 |
(十四) 五恩冥加歌・桑原冬夏/58
(十五) 悟道法語・法忍律師/64
(十六) いろは心・法忍律師/66
(十七) 家内和合歌・大島有隣/70
(十八) 処世の道・大島有隣/80
(十九) 天命の歌・大島有隣/81
(二十) 安楽おこし・大島有隣/82
(廿一) 施行歌・白隠禅師/89
(廿二) 御代の腹鼓・白隠禅師/95
(廿三) 大道ちよぼくれ・白隠禅師/102
(廿四) 寝惚の眼覚し・白隠禅師/109
(廿五) お多福女郎粉引歌・白隠禅師/123
(廿六) 主心お婆粉引歌・白隠禅師/124
|
(廿七) 女庭訓誰か身の上・池田善次郎/137
(廿八) 善悪報の鏡・清水春斉/142
(廿九) 御高札のうつし/160
(三十) 金の生る木/161
(卅一) 善悪種蒔鏡/163
(卅二) 臼摺粉引歌・信暁上人/184
(卅三) 江口の君・信暁上人/185
(卅四) 念仏上人子引歌・弁瑞上人/188
(卅五) 児童孝行短歌・鵜殿長快/191
(卅六) 孝道手引草・大僊和尚/198
(卅七) 無相娘児省悟歌・湛道和尚/217
・
・ |
|
| 1911 |
44 |
・ |
2月、石上学人編「新註白隠法語集」が「富文館・富田文陽堂」から刊行される。 pid/823165
閲覧可能
|
夜船閑話 / 1
贈遠方之病僧書(遠羅天釜の一節)/40
見性成仏丸方書 / 68
仮名法語 / 73
辻談議 / 94 |
主心お婆粉引歌 / 115
坐禅和讃 / 127
安心ほこりたたき / 130
宝鏡窟記 / 140
施行歌 / 157 |
寝惚之眼覚 / 164
おたふく女郎粉引歌 / 178
大道ちよぼくれ / 198
・
・ |
12月、東洋医学会編「実験健康法」が「豊文館」から刊行される。 pid/836909 閲覧可能
|
一 緒言/1
二 人の最大希望と最大至宝/3
三 肉体と精神との関係/10
四 肉体と精神との調和/13
(一) 森林生活と健寿/13
(二) 植物と人生/15
五 身体の養成法/20
(一) 人の命に我は在り/20
(二) 食養生・飲食節あるべし/25
(三) 皮膚の抵抗力増進法/28
(四) 血液と気海丹田/32
(五) 血液の循環/34
(六) 腹部悪血の駆除法/37 |
六 生命の根本・息と力/38
(一) 強肺術/39
(二) 強心臓術/40
(三) 強胃腹術/41
(一) 呼吸法の試験法(仁木博士式)/50
(二) 呼吸の動と静/53
七 先哲現代実験健康長寿法・体育、運動、衛生/55
(一) 白隠和尚の運動法・(独り按摩)/55
(二) 平田翁の無病健寿法/60
(三) 西有稜山師の健寿法/62
(四) 根本通明翁の衛生法/66
(五) 南摩綱紀翁の運動法/73
八 精神の養生法/77 |
(一) 病は気の持ちやう/77
(二) 平田篤胤翁の病源説/88
(三) 白隠和尚の病源説/90
(四) 原担山和尚の病源説/92
(五) 白幽子の健寿術/96
(六) 白隠和尚の内観法/105
(七) 白隠和尚の精神養生法/108
(八) 白隠和尚の病中の公案/110
(九) 静座の・座禅儀/112
九 元気気活の養成/116
(一) 丹田は精力元気の蓄電器/116
(二) 元気活元即ち精力
附録 岡田式呼吸静座法/117 |
○、この年、来馬琢道編「禅宗聖典」が「無我山房」から刊行される。 pid/102566
|
一、 經典部
一 開經偈/1
二 舍利禮文・傳不空三藏作/2
三 妙法蓮華經觀音普門品・(略名觀音經)/3
四 同如來壽量品第十六・(略名壽量品)/12
五 同提婆達多品第十二・(略名提婆品)/20
六 同安樂行品第十四・(略名安樂品)/27
七 金剛般若波羅蜜多經・(略名金剛經)/40
八 摩訶般若波羅蜜多心經(略名般若心經)/63
九 大般若轉讀唱文/64
一〇 大佛頂萬行首楞嚴陀羅尼/65
一一 普囘向偈・眞歇清了禪師作/77
一二 楞嚴會序引文/77
一三 大悲心陀羅尼/78
一四 消災妙吉祥陀羅尼/79
一五 佛頂尊勝陀羅尼/80
一六 梵網菩薩戒經和譯(付説戒文)/82
一七 四十二章經和譯/99
一八 佛埀般涅槃略説教誡經(略名佛遺教經)/111
一九 施食文/122
二〇 甘露門和譯・瑞方面山禪師編/124
二、 支那諷誦部
二一 心王銘和譯・善慧大士作/127
二二 信心銘和譯・鑑智僧?禪師作/129
二三 參同契和譯・石頭希遷禪師作/132
二四 寶鏡三昧和譯・洞山悟本禪師作/133
二五 玄中銘和譯・同/135
二六 證道歌和譯・永嘉玄覺禪師作/136
二七 南嶽偈和譯・南嶽懷譲禪師作/142
二八 五位顯訣和譯・洞山悟本禪師作/144
二九 逐位頌功勳頌和譯・同/145
三〇 十牛頌和譯・廓庵師遠禪師作/147
三、 支那祖録部
三一 逹磨四行觀和譯・菩提逹磨大師作/150
三二 六祖法寳壇經和譯・大鑑慧能禪師説/153
三三 黄檗傳心法要和譯・黄檗希運禪師説/226
三四 〔イ〕山警策和譯・〔イ〕山靈祐禪師説/268
三五 臨濟録和譯・臨濟慧照禪師語録/276
三六 洞山録和譯・洞山悟本禪師語録/332
三七 碧巖集和譯・雪寶重顯禪師頌古/373
三八 興禪護國論和譯・建仁榮西禪師著/453
三九 普勸坐禪儀和譯・永平道元禪師著/527
四〇 坐禪箴和譯・同/530
四一 學道用心集和譯・同/531
四二 正法眼藏辨道話・同/545 |
四三 同 諸惡莫作・同/569
四四 同 佛向上事・同/579
四五 正法眼藏行持・同/589
四六 正法眼藏四攝法・同/646
五一 坐禪用心記和譯・總持瑩山禪師説/663
五二 傳光録釋迦佛章・同/674
五三 傳光録龍樹章・同/678
五四 傳光録逹磨章・同/685
五五 傳光録四祖章・同/692
五六 傳光録投子章・同/696
五七 傳光録如淨章・同/705
五八 三根坐禪説和譯・同/710
五九 明峯禪師法語・明峯素哲禪師説/712
六〇 峩山法語・峩山紹碩禪師説/715
六一 大應法語・南浦紹明禪師説/721
六二 大燈國師法語・大徳妙超禪師説/739
六三 聖一國師法語・東福圓爾禪師説/752
六四 夢中問答集・夢窓疎石禪師著/766
六五 一休骸骨・一休宗純禪師著/955
六六 徹翁和尚法語・徹翁義亨禪師説/963
六七 不動智神妙録・澤庵宗彭禪師著/964
六八 鐵眼法語・黄檗道光禪師著/986
六九 夜船閑話・白隱慧鶴禪師著/1024
七〇 指月法語二種・指月慧印禪師説/1038
七一 月舟法語・月舟宗胡禪師説/1058
七二 卍山法話・卍山道白禪師説/1068
七三 經行軏・面山瑞方禪師著/1099
七四 曹洞教會修證義・永平琢宗禪師
→總持楳仙禪師編/1102
七五 總持開祖教義抄・總持楳仙禪師編/1111
五、 日本諷詠部
七六 傘松道詠集・永平道元禪師咏/1121
七七 大智偈頌抄譯・祗陀大智禪師咏/1128
七八 坐禪和譯・白隱慧鶴禪師作/1137
七九 禪僧詩選和譯/1139
八〇 隱元詩鈔・黄檗隱元禪師咏/1151
六、 禪宗日用偈分類聚
八一 天童宏智禪師坐禪箴/1178
八二 大慧普覺禪師發願文/1178
八三 永平道元禪師發願文/1179
八四 祇陀大智禪師發願文/1180
八五 七佛通誡偈/1180
八六 雪山偈/1180
八七 梵唄文/1181
八八 見佛偈/1181 |
八九 燒香偈/1181
九〇 禮拜偈/1181
九一 讃佛偈/1181
九二 懺悔文/1182
九三 三皈戒文/1182
九四 三歸偈/1182
九五 四弘誓願文/1182
九六 散華偈/1183
九七 誕生會浴佛偈/1183
九八 佛像開眼偈/1183
九九 塔婆開眼偈/1183
一〇〇 出家得度偈/1184
一〇一 剃髪偈/1184
一〇二 搭袈裟偈/1184
一〇三 展坐具偈/1184
一〇四 洗淨偈/1184
一〇五 入浴偈/1185
一〇六 錫杖偈/1185
一〇七 楊枝偈/1185
一〇八 鳴鐘偈/1186
一〇九 聞鐘偈/1186
一一〇 展鉢偈/1186
一一一 十佛名號/1187
一一二 粥時偈/1187
一一三 齋時偈/1187
一一四 五觀偈/1187
一一五 施食偈/1188
一一六 食時誓願偈/1188
一一七 折水偈/1188
一一八 後唄文/1188
一一九 行鉢喝食語類/1188
一二〇 觀音十大願文/1189
一二一 延命十句觀音經/1190
一二二 地藏歎偈/1190
一二三 釋迦歎偈/1190
一二四 普回向/1191
一二五 備考/1192
附 卷頭目録
一 題偈・前圓覺寺釋宗演師/1
二 序・可睡齋日置默仙師/3
三 例言/5
四 繪目録/7
五 碧巖集對照目録/10
・
・ |
|
| 1912 |
45 |
・ |
1月、伊藤銀月が「岡田式呼吸静坐法と実験 」を「文栄閣[ほか] 」から刊行する。 pid/836765 閲覧可能
|
歓喜すべき現象/1
(一) 日本人復活の曙光/1
(二) 実に歓喜すべき現象/3
岡田式呼吸静座法とは何ぞや/7
(一) 岡田氏が呼吸静座法の他に優れる点/7
(二) 岡田式呼吸静座の実行方法と其効果/9
(三) 岡田氏の人格と岡田式呼吸静座法実行の光景/18
(四) 岡田式呼吸静座法と諸名士の実験談/25
強健法の歴史より見たる岡田式呼吸静座の価値/73
(一) 凡ての事物に歴史の究むべきあり/73
(二) 承陽大師の普勧座禅儀/74
(三) 白隠禅師の夜船閑話/80
(四) 貝原益軒の養生訓/104
(五) 平田篤胤の志都之石室/110
(六) 二木博士の腹式呼吸法/127
(七) 藤田霊斉氏の息心調和の修養法/148 |
(八) 強健法の歴史より見たる岡田式呼吸静座の価値/168
予の実験より見たる岡田式呼吸静座及び其他の強健法/174
(一) 自得の脳病治療法/174
(二) 予と気海丹田の修養/176
(三) 冷水浴万能論者たりし時代の予/177
(四) 旅行万能論者たりし時代の予/190
(五) 予と二木博士の腹式呼吸其他/191
(六) 予と岡田式呼吸静座/193
(七) 二木岡田式を併用する予の呼吸法/197
予の強健法と其の実効/198
(一) 静的方法と動的方法/198
(二) 動中動と静中静/199
(三) 訓練の結果と予/204
(四) 予と変難に打勝つ練習/206
附録 静座万能篇/211
・ |
6月、熊谷逸仙が「詳注 夜船閑話 全」を「宝永館」から刊行する。 pid/8235351 閲覧可能 重要
|
第一 上梓の由来/1p
第二 内観の秘訣/5p
第三 白幽仙人の生活状態/15p
第四 漢方の生理論/19p
第五 天台の止法/30p
|
第六 彭祖の和神導気法/32p
第七 蘇内翰の数息観/32p
第八 酥を用ゆる法/34p
第九 内観の効果/39p
附録
|
第一 錬丹秘要の一節/41p
第二 岸江小語の一節/44p
第三 安元法印養生歌/46p
第四 血液に付て/60p
・ |
7月、釋宗演が「坐禪和讃講話」を「光融館」から刊行する。 pid/822989 閲覧可能 重要
8月、阿部正信編「駿国雑志 自巻之40至巻之45 下」が「見書店」から刊行される。 pid/1239918 閲覧可能
|
相撲並行事
新七某
籠之助某
吉田善左衞門追風
鍜冶
五條義助
岡村助右衞門兼法
大村加卜
僧侶
役小角
鑑眞
行翁某
定榮大和尚
阿野禪師全成
西住法師
聖一國師
大應國師 |
宇津の山の桑門某
赤木僊某
嚴譽律師
宗祇法師
宗長居士
道白和尚
正廣法師
書行藤佛
祖益
良眞
辰應和尚
泉奘和尚
知短上人
因果居士
雪齋長老
鐵山和尚
大輝和尚 |
宥空和尚
知足院光譽
閑室長老
崇傅長老
慈眼大師
かしく坊
地藏坊
白隱禪師
幽焉
久圓
遊女
龜鶴
某女
少將
靜
豊里
小紫 |
松山
盲人
田中檢校柳一
河内檢校喜見一
伊豆惣檢校圓一
上山檢校俊一
醫家
片山與庵法印宗哲
望月忠庵宗慶
芥川小野寺正知
瀧野爲伯
半井瑞堅
今大路道三正盛
三雲施藥院
内田元庵正俊
坂本養順
伊丹道味 |
侍儒
林道春
林永喜
朝山素心
長者
粉川長者某
福井長者某
淨見長者某
手越長者某
鄕士
海野彌兵衛某
望月次郞右衞門某
安田淸助某
加藤平太夫某
高林金兵衞某
石川淸左衛門某
長谷川勇次郞某 |
|
| 1913 |
大正2年 |
・ |
10月、「白隱和尚垂示」が「民友社 」から刊行される。 (成簣堂叢書) pid/1883969
10月、秋山悟庵が「青年活禅」を「藍外堂書店」から刊行する。 pid/943838 閲覧可能
|
第一章 緒言/1
一 禪の呼聲/1
二 國民の自覺/2
三 精神の飢渇/6
四 安心の要求/8
第二章 青年參禪の可否/10
一 現代名家の意見/12
第三章 禪/31
一 禪の名稱及び意義/31
二 禪の種類/33
三 禪の目的/35
四 禪の將來/43
第四章 死禪/51
一 枯木禪/51
二 貴族的禪/56
三 隱居的禪/58
四 天狗禪/59
第五章 活禪/62
一 靜中の動/62
二 古池の句と禪味/66
三 禪と學藝/69 |
四 平民禪/76
第六章 膽力養成/95
一 意志の修養/95
二 北條時宗の膽力養成/104
三 鈴木正三の膽力養成法/113
四 生死の關門を撃破せよ/116
五 偉人の死生觀/126
六 堅忍不拔/138
七 雪村友梅/140
八 僧禪海/148
第七章 大勇猛の心/156
一 金剛不壤の大意志/157
二 虎口裡に身を横ふ(二祖臂を斷つ)/160
三 美人の參禪(美人顔を焼く)/163
四 敵の牙營に突進せよ(上杉謙信)/179
第八章 長壽の法/184
一 身心調和の術(白隠の内觀法)/187
二 精神を丹田に凝集するの効力/201
三 佛仙法(坦山の長壽法)/207
四 元氣養成と筋力養成/215
五 心の主たれ心の使たる勿れ/221 |
第九章 自重自尊心/224
一 自重心と成功/224
二 自信力/232
三 言行一致/236
第十章 常識を逸するなかれ/243
一 平常心是れ道/245
二 日日の行爲是れ正道/251
三 惡平等なるなかれ/254
第十一章 禪の道徳觀/259
一 無我の觀念/261
二 慈悲の觀念/266
三 清廉高潔/276
四 寡慾勤儉/288
五 局量寛大/296
第十二章 赤裸禪(歸結)/305
附録 禪と日本文藝
一 禪の日本文藝に及ぼせる影響/313
二 禪の日本文明に及ばせる影響/315
三 禪と詩/327
四 禪と美術/335
・
|
|
| 1914 |
3 |
・ |
4月、国民新聞社編「白隠和尚遺墨集」が「民友社」から刊行される。 pid/946023 閲覧可能 重要
白隱和尚 遂翁和尚 東嶺和尚
11月、秋山悟庵が「禅と英雄」を「中央書院」から刊行する。 pid/943524 閲覧可能
|
緒言 / 1
一、 禪とは何ぞや / 1
一 名稱及び意義 / 2
二 目的 / 4
二、 英雄とは何ぞや / 10
一 英雄の精神修養 / 14
二 堅實なる意志の修養 / 15
三 堅忍不拔―雪樹友梅 / 19
四 泰山の宏量大海の心―眞目昌幸 / 25
五 剛大なる膽力の養成 / 32
六 智仁勇三徳の涌養 / 34
七 生死透脱 / 36
八 禪の活語活用 / 40
三、 禪と英雄 / 43
一 源實朝の修養―榮西禪師 / 44
二 北條泰時と明惠上人―治國の大本 / 47
三 北條時頼と普寧禪との相見 / 54
四 北條時頼道元禪師について受戒す―道元禪師/58
五 北條時頼と聖一國師との問答―時頼の生死觀/62
六 北條時頼と彿光禪師―祖元禪師 / 65
七 北條貞時と一寧一山禪師―寧一山禪師 / 74
八 楠正成と楚俊禪師 / 78
九 正成正行への遺訓―明極禪師 / 83
一〇 藤原藤房と關山國師 / 86
|
一一 菊池武時と大智禪師―大智禪師/89
一二 足利尊氏と夢憲國師―夢憲國師/94
一三 細川頼之と通幻禪師―通幻禪師/97
一四 蜷川親當と一休禪師―一休禪師/99
一五 太田道灌と雲岡禪師―泰叟和尚/109
一六 武田信玄と快川國師 /117
一七 上杉謙信と宗謙和尚 / 120
一八 大内義隆と玉堂和尚 / 124
一九 前田利家と大造和尚 / 128
二〇 伊達政宗と東嶽和尚 / 130
二一 柳生但馬守と澤庵禪師 / 132
二二 鈴木正三の英雄訓 / 141
二三 山鹿素行の參禪 / 150
二四 大石良雄と正眼國師 / 152
二五 白隱禪師の武士訓 / 155
二六 東嶺禪師の武士訓 / 163
二七 勝海舟の禪劔の賜物 / 165
二八 山岡鐵舟の禪定力 / 170
四、 生死交謝の時如何 / 179
一 英雄の生死觀 / 179
二 源俊基 / 183
三 源具行 / 184
四 藤原資朝 / 186
五 楠正成 / 188 |
六 太田道灌 / 189
七 北條氏政 / 189
八 大内義隆 / 190
九 二條藤房信 / 191
一〇 冷泉判官隆豐 / 191
一一 岡部隆景 / 192
一二 吉田隆次 / 192
一三 天野隆良 / 192
一四 小幡義賢 / 193
一五 黒川隆像 / 193
一六 明智光秀 / 194
一七 伊達政宗 / 195
一八 聖遠監飽入道 / 195
一九 大石良雄 / 196
二〇 大高源吾 / 197
二一 山崎宗鑑 / 199
二二 森川許六 / 200
二三 廣瀬中佐 / 201
五、 禪の道徳觀 / 204
六、 新道徳と禪道 / 208
七、 歸結 / 214
補遺―井伊直弼の修禪 / 218
附録 遠羅天釜―
→鍋島侯近侍書/227
|
|
| 1915 |
4 |
・ |
5月、釈毒潭が「白隠禅師の言行」を「大島誠進堂」から刊行する。 pid/944020 閲覧可能
|
行の部
一、 緖言 / 1
二、 生誕 / 3
三、 幼年時代 / 5
四、 修養時代 / 13
五、 正受老人の痛棒を喫す / 27
六、 正受庵を辭去の後 / 38
七、 砂石集を讀んで感激す / 45
八、 小知識の法話に感ず / 57
九、 松蔭寺を董す / 63
一〇、 初開の道場 / 66 |
一一、 道俗の化益 / 71
一二、 初建の法幢 / 75
一三、 東嶺圓慈嗣法書を通ず / 85
一四、 東嶺圓慈再び參じて印記を受く/93
一五、 京師の傳道 / 98
一六、 正受老人の忌齋 / 103
一七、 東師の傳道 / 109
一八、 掉尾の化益 / 112
一九、 入滅 / 117
二〇、 禪師の風流敎?繪畫 / 123
二一、 禪師の略年譜 / 130
|
言の部
夜船閑話序 / 1
夜船閑話 / 1
辻談義 / 15
施行歌 / 26
寢惚の眼覺 / 29
おたふく女郞粉引歌 / 36
安心ほこりたた記 / 46
大道ちよぼくれ / 51
主心お婆婆粉引歌 / 56
坐禪和讃 / 62 |
5月、「風俗画報 (5月號)(469)」が「東陽堂」から刊行される。 pid/1579985
|
古代更紗 / 荒井寬方/表紙
挿花 / 筒井年峰/口繪
郭公 / 山中古洞/口繪
南京の女 / 山村耕花/口繪
柚湯に菖蒲湯 / 寺島德重/口繪
五月風俗暦―(十六頁續挿畫)
→/永田錦心/p1~16
子供の節句 / 公文菊仙
爪びき / 公文菊仙
早女少 / 公文菊仙
初つがを / 公文菊仙
女按摩 / 公文菊仙/p34~37
吹流 / 公文菊仙
五月の行事/p1~1
風俗と日本館 / 大塚保治/p2~5
新案足と手 / 和田垣謙三/p6~7
風俗閑話 / 江木定男/p8~10
風俗その折々 / 中川愛氷/p10~13
白耳義平時の風俗談/福岡秀猪/p14~15
風俗畫報の懷舊/寺崎廣業/p16~16
歌行脚 / 栗原定/p17~17
敬語と風俗 / 藤岡薇州/p18~19
犬猫の居らぬ島 / 吉田源之助/p20~21
|
香道の由來 / 宮崎鳥府/p22~23
鯉の瀧登り / 方寸庵主人/p24~24
枕草子に現はれたる社會/小林雨塔/p25~27
脚本寮番 / 長谷川時雨/p28~31
江戸時代の塚 / 松川碧泉/p32~33
女按摩 / 阿井飛洋/p34~37
足袋のことゝも / 一記者/p38~39
新聞歴史私見 / 藻絞生/p40~41
三月の演藝界/p42~43
茨城方言 / 蓋山處士/p44~45
十五名所の櫻樹/p45~45
詞林/p46~47
編輯局より/p48~48
口繪假裝大名行列と其見物
新聞歴更參照/p41~41
三の當う狂言
三十六歌仙―(素性法師と友則)/住吉如慶
山水 / 梁階
鍾馗 / 橋本雅邦
花下の水 / 下村觀山
晴靄 / 結城素明
お七吉三 / 鴨下晁湖
翁 / 土屋秀禾
|
盲人と春 / 初山櫻厓
美術史上の聖德太子 / 黑板勝美
紀念の畫帖 / 寺崎廣業
東亞特有の美術 / 前田默鳳
山水畫の沿革 / 中村不折
白隱禪師の畫 / 森大狂
寫生鳥の圖
容齋先生の攝生 / 岡田華筵
繪畫に現れたる動物 / 阿部若水
繪に就ての研究 / 中島春郊
筆持つ人筆つくる人 / 中川愛氷
徴古畫傳
畫談一覽
聖德太子一代繪卷中の蝦夷人の圖/
→鳥居龍藏
流行畫 / 神津港人
純正美術の需要 / 都子
何も彼も變つて居る / 和田三造
廣重の繪 / 小島烏水
畫界雜事
畫家消息
・
・ |
7月、家庭問題研究会編「御存知でせうか」が「平凡社」から刊行される。 閲覧可能
|
略
第四章 最新流行現代心身健康法
第一節 修養とは/151
第二節 二木博士の腹式呼吸法/153
第三節 岡田式静坐法の要領/156
|
第四節 藤田式息心調和の修養法/162
第五節 河合式椅子体操法/174
第六節 岩佐氏胸腹式。呼吸運動法/178
※第七節 白隠禅師の独按摩/182
第八節 平田翁の無病健寿法/185
|
第九節 各式の特徴。好む所に従ふがよい/186
第十節 全的修養の生理的基礎/192
第十一節 心身修養の心理的根拠/197
略
・ |
|
※第七節「白隠禅師の独按摩」(1915年7月(上段))と(1922年3月(下段))との比較
| No |
初傅(内容) |
No |
後傅(内容) |
| 1 |
手の平(ひら)をコスル
手の平(ひら)を摺る |
1 |
胸を左右よりこする。
胸をさする左右 |
| 2 |
両手で指を組む
もみ手 |
2 |
腹(はら)を左右よりさする |
| 3 |
指を組んだままでもみ手をする。
掌中を親指にてもむ |
3 |
手を上げて左右の耳を掴み捨てる如くする。
手を上げて左右の耳を撮み揺(ゆす)する如くす |
| 4 |
掌の中を親指でもむ。
手の指の筋(すじ)をもむ |
4 |
左右の耳朶をつまみ手を左右へ大きく開く。
左右の耳たぶをつまみ手を左右へ大に開く |
| 5 |
手の中指の筋をもむ。
指を引く |
5 |
足を以て尻(しり)を打ち、手を組み合せ胸を打つ |
| 6 |
指を引きのばす。
腕を逆さにこき上げる |
6 |
足を以て頭を打つ |
| 7 |
腕を逆にこき上げる。
頬を逆さにする上げる |
7 |
足首をふる。踵(かかと)爪先を以てふる。
足首をふる。 |
| 8 |
頬を逆にこき上げる。
鼻の左右をこする |
8 |
左右の拳(こぶし)で足の裏を打つ。
かかと爪先を以てふる |
| 9 |
鼻の左右をこする。
額(ひたい)を横にこする。 |
9 |
手の中指を合せ土踏まずに踏む。
左右のこぶしにて足の裏を打つ |
| 10 |
額(額)を横にこする。
眉を逆さにこする |
10 |
目をねむり、歯をたゝくこと十二偏。
手の中指を合せ土ふまずにて踏み目をねむり歯をたゝき 十二偏唾をばのむ三度 |
| 11 |
眉を逆さにこする。
耳を左右の掌に平にて摺下す |
11 |
足の甲(かう)をもむ |
| 12 |
耳を左右の掌にてすり下す。
耳を上中下へ引く |
12 |
足の指をひきのばす
足の指を引く |
| 13 |
耳の上中下を引く。
耳へ人さし指を入れ一度ぬきて打つ |
13 |
足の指のまたをもむ |
| 14 |
耳へ人差指を入れて一度ぬきて打つ。
こめかみを両手にてこする |
14 |
足の甲を裏へちゞめる
足の甲の裏へちゞめる |
| 15 |
こめかみを両手でこする。
脳をもむ(頭の中うづ巻よりひよめきを襟にかけもつせ) |
15 |
さんりの筋(すじ)をもむ |
| 16 |
頭から襟(えり)へかけて脳をもむ。
頭を左右へ振る |
16 |
股(また)の内外をもむ。
ももの内外をもむ |
| 17 |
頭を左右に振る。
弓左右三度ひく |
17 |
さんりを左右の拳(こぶし)にて打つ。 |
| 18 |
三拝 |
18 |
手を背で組み合せて腰骨(こしぼね)を打つ。
左右の手を脊え組み合せ腰骨を打つ |
| 19 |
左右の二の腕をつかみて上下する。
左右の三の腕をつかみ上下す |
19 |
仰臥して足を十分伸ばし、開くこと一尺、息(いき)三度する。
仰臥して足を開く一尺息三度 |
| 20 |
同所にて肩を廻す。
|
- |
- |
| 21 |
指を組て鼻の通りまで上げ、其れにて膝を打つ。
指を組み、鼻の邊りへ上げ膝を打つ |
- |
- |
| 22 |
左右の拳(こぶし)で臍裏脊肩を打つべし
左右のこぶしを以て臍裏脊肩(へそうらせたか)を打つ |
- |
- |
※ 出典元については現在調査中 (内容や表現法が一部で違うため確認が必要) 2023・2・17 保坂 |
11月、「眞人 (11月號)(53)」が「養眞會,眞人社」から刊行される。 pid/1510481
|
本領/p2~6
養生の根本義(六) / 藤田靈齋/p2~6
講説/p7~19
神人合體の境涯 / 松村介石/p7~10
肉體の鍛錬に就て / 齋藤俊太郞/p10~15
先づ君が罪惡の念を取り去れ/大浦正三/p16~19
偉人修養/p20~27
井上世外侯靑年時代の面影/野の人/p20~27
敎談/p28~33
|
※正宗國師白隱大和尚 / 野口復堂/p28~33
千紫萬紅/p34~35
草木を愛する心 / 川瀨專之助/p34~35
百歳談/p36~39
百一歳老翁の平常 / 靜觀道人/p36~39
實驗感想/p40~53
余が息心調和法の實驗 / 高橋金吉/p40~47
修養に依りて惡癖の矯正 / 安田麑/p47~50
先生に感謝す / 丸山富久/p51~51
|
感謝の中に月日を送る / 秋田かた/p51~53
會報/p53~64
藤田會長關西各支部出張概况報告/p53~58
養眞會各支部諸例會概况報告/p58~64
修養會/p64~66
養眞會本部婦人修養會/p64~65
小兒修養會/p65~66
其他/p66~66
・ |
12月、[眞人 (12月號)(54)」が「養眞會,眞人社 」から刊行される。 pid/1510482
|
本領/p1~6
歳晩之辭/p1~1
養眞の根本義(七) / 藤田靈齋/p2~6
講説/p7~22
空氣中の靈藥 / 池田天眞/p7~12
君は只君自身の事のみをなせ/大浦正三/p13~17
養眞の意義 / 大川周明/p17~22
偉人修養/p23~26
井上世外侯靑年時代の面影 / 野の人/p23~26
|
談叢/p27~34
靑年諸君に與ふ / 水野錬太郞/p27~34
敎談/p35~43
※正宗國師白隠大和尚 / 野口復堂/p35~43
千紫萬紅/p55~58
紅葉を追ふて / 川瀨專之助/p55~58
實驗感想/p44~54
息心調和法の効果 / 西伊三次/p44~47
余が入會の動機 / 萩原七郡/p48~49
|
起死回生 / 安田麑/p49~53
唯感謝あるのみ / 山本平吉/p53~54
會報/p59~64
養眞會本部竝各支部例會概况報告/p59~64
修養會/p64~64
小兒修養會/p64~64
質疑應答/p64~64
・
・ |
※正宗國師白隠大和尚 連番表示なしのため確認が必要 2013・1・1 保坂
7月、「脳力養成と神経衰弱自療法 伊藤尚賢 著 文盛館 1915 p/pid/935131/1/1
閲覧可能
|
第一編 記憶法
一 記憶の効力/1
二 如何にして記憶力を增進せしむべき乎/2
三 生理上の記憶/3
四 心理學上の記憶/9
五 記憶の變態/11
六 生理學的記憶力增進法/12
七 心理學的記憶增進法/15
八 記憶の法則/22
九 神經衰弱の大流行/30
一〇 神經衰弱の本態/31
一一 肉體的症候/33
一二 精神的症候/37
一三 神經衰弱の原因/41
一四 神經衰弱の根治法/43
一五 原因療法/44
一六 生活法の改善/46 |
一七 居住地の注意/47
一八 食餌療法/48
一九 運動療法/50
二〇 發聲運動と其注意/51
二一 睡眠療法/52
二二 作業の注意/57
二三 淸潔の注意/59
二四 水治療法/60
二五 電氣療法/67
二六 按摩療法/68
二七 藥物療法/69
二八 特殊療法/77
二木博士の腹式呼吸講話
(一) 腹式呼吸を修したる動機/78
(二) 平田先生の志都乃石屋/82
(三) 白隱禪師の遠羅天釜/92
(四) 露國小説に發奮/96 |
(五) 神經衰弱の全快/100
(六) 腹部の構造/103
(七) 三種の呼吸/105
(八) 肺尖呼吸の悪い譯/106
(九) 腹式呼吸は一番良い/107
(一〇) 腹の力の強さ/108
(一一) 文明の淺呼吸/109
(一二) 心臓の驅血力/110
(一三) 腹式呼吸の實習法/111
(一四) 立てる時の呼吸/116
(一五) 仰臥時の呼吸/117
(一六) 注意/118
(一七) 練習を終つた時/119
(一八) 終日行へ/120
(一九) 效果の顯はれた證據/121
略
・ |
|
| 1916 |
5 |
・ |
1月、高橋竹迷が「白隠禅師言行録」を「東亜堂書房」から刊行する。 pid/944065 閲覧可能 重要
|
第一章 聰序
第一節 白隱の搖籃 / 1
第二節 白隱の出世時代 / 8
第三節 白隱出世時代の佛教/14
第四節 白隱出世の本懐 / 18
第五節 白隱の生涯 / 24
第二章 出家以前の白隱
第一節 白隱の母 / 29
第二節 白隱の發心 / 36
第三節 白隱と專念行者 / 40
第四節 白隱の天神信仰 / 42
第五節 白隱の觀音信仰 / 45
第三章 出家と修行
第一節 白隱の出家 / 50
第二節 文字に耽溺す / 52
第三節 馬翁と禪關策進 / 58
第四節 美濃の行脚 / 62
第五節 四十二章經と精進勇猛/65
第六節 伊豫より故郷へ / 69
第四章 大悟と菩提心
第一節 英巖寺の大悟 / 75 |
第二節 正受老人の鉗鎚 / 79
第三節 正受老人の依囑 / 84
第四節 肺金を病む / 90
第五節 白幽眞人を訪ふ / 94
第六節 夜船閑話の獲得 / 101
第七節 菩提心の發起 / 108
第五章 悟後の修行
第一節 荷葉團團の頌 / 113
第二節 蔭涼寺の夜雪 / 117
第三節 大燈語録と一隻眼 / 121
第四節 岩瀧山の隱棲 / 125
第五節 松蔭寺の歸坐 / 131
第六節 法華經の大悟 / 134
第六章 機鋒と教義
第一節 佛國土の因縁 / 140
第二節 孤危險峻なる機鋒 / 143
第三節 見性と内觀 / 149
第四節 『神社考』と垂迹説 / 153
第五節 三教一致の思想 / 157
第六節 隻手の聲 / 163
第七章 應化と示寂 |
第一節 『十句觀音經』『五位口訣』及び『槐安國記』/170
第二節 三大供養 / 175
第三節 無量寺と龍澤寺 / 179
第四節 普門示現の利益 / 183
第五節 江戸の教化 / 187
第六節 大吽一聲 / 191
第七節 鵠林の門下 / 197
第八節 白隱の詞藻 / 203
附録
夜船閑話 / 207
遠羅天釜 / 231
遠羅天釜續集 / 328
坐禪和讃 / 365
大道ちよぼくれ / 367
御洒落御前物語 / 373
見性成佛丸方書 / 376
御代の腹鼓 / 379
施行歌 / 383
安心ほこりたた記 / 387
子守唄 / 393
・ |
3月、白隠禅師提唱,永田春雄編「碧巌集秘鈔」が「成功雑誌社」から再販される。pid/943581 閲覧可能 初版本は同年2月
|
第一則 達磨廓然
第二則 趙州至道
第三則 馬大師不安
第四則 德山複子
第五則 雪峰粟米
第六則 雲門好日
第七則 慧超問佛
第八則 翠巖眉毛
第九則 趙州四門
第十則 睦州掠虚
第十一則 黄檗瞳酒糟
第十二則 洞山麻三斤
第十三則 巴陵提婆宗
第十四則 雲門對一説
第十五則 雲門倒一説
第十六則 鏡淸□啄
第十七則 香林坐久成勞
第十八則 國師塔様
第十九則 倶胝一指
第二十則 龍牙禪板
第二十一則 智門蓮華
第二十二則 雪峰鼈鼻蛇
第二十三則 保福遊山
第二十四則 〔イ〕山劉鐵磨
第二十五則 蓮華峰庵主□□
|
第二十六則 百丈大雄峰
第二十七則 雲門體露金風
第二十八則 南泉不是心佛
第二十九則 大隋劫火
第三十則 趙州大蘿匐
第三十一則 麻谷持錫
第三十二則 定上座佇立
第三十三則 資福一圓相
第三十四則 仰山五老峰
第三十五則 文殊無着問答
第三十六則 長沙遊山
第三十七則 盤山三界無法
第三十八則 風穴鐵牛機
第三十九則 雲門花藥欄
第四十則 南泉一株花
第四十一則 趙州大死底
第四十二則 □居士好雪
第四十三則 洞山無寒暑
第四十四則 禾山解打鼓
第四十五則 趙州布衫
第四十六則 鏡淸雨滴聲
第四十七則 雲門六不収
第四十八則 王太傳煎茶
第四十九則 三聖透網
第五十則 雲門三昧 |
第五十一則 雪峰住庵
第五十二則 趙州石橋
第五十三則 百丈野鴨子
第五十四則 雲門展兩手
第五十五則 道悟不道不道
第五十六則 良禪客破三關
第五十七則 趙州不揀擇
第五十八則 趙州五年分疎
第五十九則 趙州至道
第六十則 雲門□杖化龍
第六十一則 風穴一塵
第六十二則 雲門秘在形山
第六十三則 南泉斬猫
第六十四則 趙州草鞋
第六十五則 外道問佛
第六十六則 巖頭黄巣収劒
第六十七則 傳大士講經
第六十八則 仰山呵呵大笑
第六十九則 南泉一圓相
第七十則 百丈咽喉唇吻
第七十一則 百丈咽喉
第七十二則 百丈咽喉
第七十三則 馬祖四句百非
第七十四則 金牛飯桶
第七十五則 鳥臼屈棒
|
第七十六則 丹霞喫飯了
第七十七則 雲門餬餅
第七十八則 開士入浴
第七十九則 投子□沸椀
第八十則 趙州急水上
第八十一則 藥山麈中麈
第八十二則 大龍色身
第八十三則 雲門古佛交參
第八十四則 維摩不二
第八十五則 庵主虎聲
第八十六則 雲門厨庫三門
第八十七則 雲門藥病
第八十八則 玄沙三種病人
第八十九則 雲巖通身手眼
第九十則 智門般若
第九十一則 鹽官犀牛
第九十二則 世尊陞座
第九十三則 大光作舞
第九十四則 楞嚴不見
第九十五則 長慶二種語
第九十六則 趙州三轉語
第九十七則 金剛輕賤
第九十八則 西院兩錯
第九十九則 國師十身調御
第百則 巴陵吹毛劒 |
6月、丸山小洋編「古今名僧手紙禅」が「須原啓興社」から刊行される。 pid/944105 閲覧可能
|
一 永平道元禪師 / 1p
二 無學祖元禪師 / 4p
三 永源寂室禪師 / 10p
四 夢窓疎石禪師 / 15p
五 宗峰妙超禪師 / 18p
六 素溪大智禪師 / 30p
七 中岩圓月禪師 / 42p
八 月庵宗光禪師 / 45p
九 拔隊得勝禪師 / 59p |
一〇 一休宗純禪師 / 73p
一一 一休和尚の母 / 84p
一二 萬瑛和尚 / 86p
一三 魯山玄〔バン〕 / 89p
一四 澤庵宗彭禪師 / 93p
一五 鈴木正三老人 / 111p
一六 隠元隆琦禪師 / 117p
一七 道鏡慧端禪師 / 122p
一八 天桂傳尊禪師 / 125p |
一九 白隠慧鶴禪師 / 128p
二〇 東嶺圓慈禪師 / 163p
二一 月湛洞水禪師 / 177p
二二 兼葭慈音尼 / 180p
二三 逸名 / 189p
二四 旃崖奕堂禪師 / 211p
二五 洪川宗慍禪師 / 214p
二六 覺仙坦山禪師 / 220p
二七 獨園承珠禪師 / 224p |
二八 鳥尾得庵居士 / 227p
二九 西有穆山禪師 / 231p
三〇 山岡鐵舟居士 / 234p
三一 森田悟由禪師 / 235p
三二 洞山悟本大師 / 249p
三三 蘇東坡居士 / 255p
三四 黄龍慧南禪師 / 260p
三五 仲盧明敎大師 / 263p
三六 元賢永覺禪師 / 266p |
9月、釈毒潭校訂「白隠禅師法語録」が「大島誠進堂」から刊行される。 pid/925789 閲覧可能 重要
|
白隠禅師年譜 / 1
坐禅和讃 / 12
夜船閑話 / 13
遠羅天釡 / 33 |
辻談義 / 147
施行歌 / 158
寝惚の眼覚 / 161
おたふく女郎粉引歌 / 168 |
安心ほこりたた記 / 178
大道ちよほくれ / 183
主心お婆婆粉引歌 / 188
・ |
○、この年、破有法王が「現代相似禅評論」を「周文社」から刊行する。 pid/943597 閲覧可能 取扱注意
|
第一篇 正法 / 1
第一章 生死事大 / 1
第二章 悟證の大事 / 7
第二篇 現代相似禪概觀 / 16
第一章 學人論 / 16
第一節 雲水 / 17
第二節 居士 / 20
第二章 師家論 / 24
第一節 總説 / 24
第二節 師家の相似語言 / 27
第三節 師家平常の言行 / 30
第四節 師家の心頭 / 35
第五節 結論(眞正の導師とは何ぞや) / 40
第三章 室内論 / 44
第一節 公案の眞義 / 44 |
第二節 相似禪内容の一般 / 49
第三節 見性論 / 56
第四節 室内穿鑿の概評 / 61
第五節 嗣法論 / 66
第六節 相似禪家風の異同 / 69
第三篇 相似禪内容詳論 / 76
第一章 隻手音聲及趙州無字 / 78
鑛二章 雜則部 / 97
第三章 本則部 / 128
第四章 五位 / 234
第五章 十重禁 / 250
第六章 虚堂代別 / 263
第七章 末後の牢關 / 307
第四篇 結論 / 309
第一章 相似禪の無意義を示す / 309 |
第二章 白隱論 / 314
第一節 行状に關する疑義 / 314
第二節 悟機に就ての疑義 / 320
附 東嶺の相似悟 / 320
第三節 修行事に關する識見の謬妄 / 329
一 見性に對する謬見 / 329
二 關鎖法財の誤解 / 333
三 悟後の修行 / 335
四 餘言 / 338
第四節 室内の杜撰 / 338
第五節 隻手音聲の批評 / 344
附録
澤水法語 / 5
拔隊法語 / 61
・ |
○、この年、近藤真澄が「禅学真髄」を「東亜堂書房」から刊行する。 所蔵:青森県立図書館 |
| 1917 |
6 |
・ |
1月、「眞人 (1月號)(67)」が「養眞會,眞人社 (東京市) 」から刊行される。 pid/1510495/1/1
|
本領/p1~8
年頭誡 / 藤田靈齋/p1~8
論壇/p9~28
人心維新 / 大川周明/p9~12
罪人に息心調和法を誨ふ可し/今村力三郞/p12~17
御前揮毫と息心調和法 / 高島北海/p17~19
一身を持て餘す生活 / 大浦正三/p20~23
余が息心調和法に依りて信仰上何を得し乎 /
→齋藤俊太郞/p24~28
|
所感/p29~33
會長の籠居修養せらるゝに就て /
→池田天眞/p29~33
敎談/p34~41
正宗國師白隱大和尚 / 野口復堂/p34~41
談叢/p42~50
祖國を顧みて / 近藤會次郞/p42~44
水底の眼鏡 / 川瀨專之助/p45~50
實驗感想/p51~72 |
余が心身の一變 / 菊池綾五郞/p51~61
私の實驗 / 吉川よし子/p61~62
修養の効果 / 辻村益枝/p62~64
修養三年 / 藤井建太郞/p65~68
余が入會の動機及感想 /
→園田鐵哉/p68~72
通信/p73~73
結氷期修養 / 福島達夫/p73~73
會報/p74~78 |
1月、「新人 18(1)」が「新人社」から刊行される。 pid/1510346/1/1
|
獨逸の媾和提議・其他―時評/p1~9
新春に際して國民の覺醒を促す/
→海老名彈正/p10~16
戰前に於ける歐洲の形勢 / 吉野作造/p17~22
國家と宗敎との關係を論じて宗敎法に及ぶ /
→佐伯好郞/p23~48
文明史上より見たる佛基兩敎の
→比較/上村邦良/p49~64
予が信仰の經? / 荒木眞弓/p70~71
くさもみぢ / 野口精子/p133~133
敎界人國記―(山梨縣) / 聖山生/p65~69,72~76 |
くぬぎ林 / 有田四郞/p80~80
春 / 久保竹二/p122~
沈默の聲 / 久布白直勝/p141~143
メシアの出現 / 海老名彈正/p81~90
ウイルソンの再選と平和運動の將來 /
→浮田和民/p91~96
西行と白隱より / 中村吉藏/p134~136
クリスマスの夜――
→(ソログーブ) / 山下義雄/p97~107
ロシア民話の現はれたる基督 /
→香川鐵藏/p108~114
|
ラフアエルの聖母に就て /
→ 中山昌樹/p115~121
近代個人主義道德と基督敎/
→村田四郞/p123~132
醫王祭の由來及び其意義/高田畊安/p78~79
日本讃美歌物語 / 三輪花影/p137~140
母敎會の友をたづねて/
→栗原陽太郞/p157~159
新刊紹介 / 記者/p159~160
附録 新自由意志論 / 海老名彈正/p145~156
・ |
1月、菅原洞禅が「和漢古今禅門佳話」を「丙午出版社」から刊行する。 (禅門叢書 ; 第9編) pid/944048 閲覧可能
|
前篇 一□石
至道無難禪師の前半生/1
關山と幸に愚堂の在る有り/6
日置默仙禪師發心の動機/8
承陽大師の脱落身心/11
水影を見て大悟せる洞山大師/13
眞桑瓜に釣られし大燈國師/16
淸凉殿上の大法戰/18
虎聖を陷倒せる大光國師/20
松に八十往生を誓つた南天棒/22
喫茶喫飯底の常濟大師/24
願行の模範なる復古翁卍山/27
石川素童禪師參禪の經路/31
趙州一僧の爲めに大道を説く/36
五祖會下の第一人盧行者/38
白隱に參じて剃髪せる大橋太夫/41
星見天海和尚の行履/46
楠田病院長の九寸五分/49
尼の侮辱に發奮せる?胝和尚/52
神機縱橫の狼玄樓/55
澤庵和尚江戸入の眞相/58
秋野孝道師の跣足參り/61
惟嚴禪師と李文公/64
神尾將軍の參禪振/65
妻女を離別せし今北洪川/69
心越禪師の膽力/73
三度勅使を固辭せる木禪庵/75
眞個の師家松蔭和尚/78
鳥尾得庵伊藤公を一喝す/80
楠公决死の前日/82
志閑禪師と末山尼/84
新井石禪師得度の因縁/87 |
一塵一芥も皆是佛種/90
居士渡邊無邊の熊の皮/93
中篇 二般土
自隱會下の俊才/97
東叡和尚陰德の行持/100
脚下の知れぬ拾得の詩偈/103
鬼文常と高津拍樹/105
面皮を燎きし女禪客/106
勝海舟の錬膽術/110
惡辣の師家を選んだ祥山和尚/112
辛辣無類の燒禾山/115
慢心の折伏に發奮せる東坡居士/118
發狂と誤られたる阿察女/121
餅屋の説明をやつた小僧さん/123
口頭三昧の釋宗演師/125
風外和尚と猫/129
不意に大悟せる張九成と
→夢想國師/131
興奮自在は禪の本分/133
臨濟打爺の拳/136
乃木大將の參禪談/140
冬が一所に來たか珍龍さん/145
白隱禪師の地獄極樂/148
穆山禪師の眞面目/151
身心の鍛錬より見たる伊藤公/153
居士の胸中を看破せる默雷禪師/159
一休禪師の女人濟度/160
峻嚴なりし淺野斧山和尚/166
卍庵毒藥を投ぜられて大悟す/168
禪的性格の三博士/170
信長の師傳平手政秀/175
道に親しき祖岳和尚/179 |
白樂天を歸服せしめた道林和尚/181
筆と舌の咄堂居士/184
昧を會得せる又十郞/187
遠羅天釜と二木博士の腹式呼吸/192
後篇 三昧境
文献院古道漱石居士/197
智辯博識の聖一國師/200
努力主義の兒玉玄海和尚/203
鐡舟居士の無刀流/208
元兵の膽を奪ひし佛光國師/209
河野盤洲參禪の動機/212
夢裡に入宋せる夢想國師/215
路傍の婆子に遣り込められし德山/217
反省會の米峰と禁酒會の米峰/220
一生菴主の正受老人/223
東瀛和尚と頭山滿/226
琢禪和尚の乞食連歌/229
妙心開山關山國師/231
禪機〔はつ〕溂たる侯大隈重信/235
豪膽無類の由利滴水/236
一休に水を浴せし華叟和尚/238
默童禪師と稻荷の檢査官/241
牛頭山の法融禪師/243
大入道狐わなに罹る/245
一日作さざれば一日食はず/247
黄檗鐵眼禪師の大藏經/248
古人の難行を範とせよ/251
丹田の修養に努められし鈴木充美/252
桃花一見豁然大悟/254
西鄕南洲の活作略/255
大火焔裡に示寂せる快川和尚/257
悟由禪師と虚空藏菩薩/259 |
4月、「新日本 = The new Japan 7(4);春季大附録號」が「新日本社」から刊行される。 pid/11186402
|
略
研究と觀察//63~
文化と犯罪(長論文)/井上忻治/63~
最新の印度/信夫淳平/77~
幼年勞働者の社會衛生/富士川游/81~
時代の犧牲者芳川鎌子を弔ふ/佐藤紅綠/85~
平塚明子論(長論文)/伊藤野枝/90~
痛快隨筆/生方敏郞/103~
海洋と大陸發展の關係を論ず(長論)/箕作元八/108~
余の見たる酒豪/大町桂月/130~
由緖ある櫻/戸川殘花/134~
花袋氏老いたるか外二篇(文藝評論)/西宮藤朝/136~
「放資」南洋放資觀/井上雅美/139~
新刊批評//141~
文藝大附録//1~
閨秀文藝//1~
チユーリツプ物語(小説)/田村俊子/1~
精神病(小説)/素木しづ子/16~
人形(小説)/岡田八千代子/28~ |
一樹の蔭(小説)/水野仙子/36~
三月の末(小説)/與謝野晶子/48~
豫言(小説)/尾嶋菊子/61~
春の感想//74~
和き光と惠(小品)/長谷川時雨子/74~
春光(小品)/尾島菊子/76~
我家の春(小品)/三宅やす子/77~
幻の家(小品)/日向きむ子/78~
櫻の蕾(小品)/生田花世子/79~
新婚の仲人(小品)/永代美知代子/81~
落花(小品)/國木田治子/82~
小説未遂犯の話(七十枚の長篇)/神近市子/83~
脚本//113~
白隱和尚/中村吉藏/113~
喜劇人形の家/佐藤紅綠/141~
西鄕と豚姫(四月上演割引券添ふ)/池田大伍/163~
米獨戰爭亞米利加征服(時事小説)/馬場孤蝶/193~
時事漫畫並に醉態百趣(百五十葉)/岡本一平/2~
・ |
5月、「新公論 32(5);5月倍號」が「新公論社」から刊行される。 pid/11005548
|
デモクラシーの心理/木村久一/68~82
稗史より見たる支那の國民性/安岡秀夫/83~108
亞細亞モンロー主義/兒玉花外/144~145
琴平神社の群蝶圖に就て/久保猪之吉/159~163 |
古傳説上の高千穗峰/喜田貞吉/254~254
印度の奇習良妻禁錮/河口慧海/260~261
七福神は世界的なり/谷本富/267~268
〈抜粋〉 |
5月、「新公論 32(6);臨時倍號5月號」が「新公論社」から刊行される。 pid/11005549
|
琴平神社の群蝶圖に就て/久保猪之吉/159~163
古傳説上の高千穗峰/喜田貞吉/254~254 |
七福神は世界的なり/谷本富/267~268
|
9月、荒井倉三郎が「実験岡田式静座法」を「日本書院」から刊行する。 (実験健康法叢書 ; 第1) pid/935590
|
(一) 靜坐の方法/1
一 靜坐入門の二要件/1
二 靜坐中兩足の重ね方/4
三 靜坐中の膝の割り方/6
四 靜坐中の胸、腹、臀/7
五 靜坐中の兩手の置き方/12
六 靜坐中の顏、目、口、呼吸/13
七 靜坐の時間/14
八 平生も矢張り靜坐の姿勢/18
(二) 呼吸の方法/20
一 正しからざる呼吸/20
二 正しき呼吸/22
三 人間本來の呼吸/25
四 靜坐中の呼吸/35
五 靜坐中息を吸ふ時/36
六 靜坐中息を吐く時/39 |
七 日常の呼吸/47
(三) 靜坐に伴ふ現象/54
一 靜坐中の心境/54
二 靜坐中身體の動搖/60
三 効顯を急ぐ勿れ/64
(四) 靜坐の原理/78
一 草木の成長する理/78
二 人間の根は重心/82
三 重心は即ち力の集中/83
四 心身は別物に非ず/88
五 先人の説ける心身一致/96
六 白隱禪師の内觀法/106
七 重心の安定と精力の集中/112
八 重心は心身の中央政府/115
九 精力集中必要の理/120
一〇 重心の安定と七情の調和/131 |
一一 重心安定の識別/137
一二 靜坐を撰んだ理由/145
一三 靜坐で病の癒る理/150
(五) 靜坐と婦人/155
一 靜坐に男女の區別なし/155
二 靜坐に對する謬見/157
三 婦人の健不健は重大問題/161
四 人體美と婦人の謬見/163
五 靜坐は婦人の修養に最適/168
六 婦人に及ぼす靜坐の効果/172
(六) 予の靜坐實驗と心身の變化/175
一 靜坐入門の動機/175
二 三日目に効果顯る/179
三 實驗者の實例/181
・
・ |
|
| 1918 |
7 |
・ |
9月、中村吉藏が「白隠和尚 : 戯曲集 : 外4(肉店 金力 世間 小山田庄左衛門)篇」を「天佑社」から刊行する。
pid/959401 閲覧可能
|
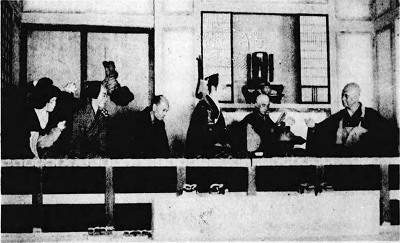
白隠和尚 (帝國劇場上演) |
自序/(略)巻頭の「白隠和尚」は目下、帝国劇場に於て、松本幸四郎、丈を主人公に、尾上松助、中村東蔵、市川米藏及び音羽かね子等の諸優に依り初演を行はれつゝあるものである、尚「世間」は嘗て同劇場に上演されしもの、その他の諸作も、早晩實演の機會を得る事と思ふてゐる。
大正七年九月、後隣の欅の森に油蝉の残暑を
熟りつゝある午後 著者
(登場)人物
白隠和尚
池田継政侯
酒屋六兵衛
お杉
八百屋久作
|
太郎兵衛婆
覺念
その他 侍、長老、雲水、参禅の子女大勢
場所 或る禅寺
時代 徳川九代将軍の頃
・ |
|
11月、「禅道 第一百號 特集白隠研究」が「禪道會本部」から刊行される。 頁 数:198頁 47名が執筆 個人蔵 重要 |
| 1919 |
8 |
・ |
12月、森大狂が「近古禅林叢談」を「蔵経書院」から刊行する。 pid/963150 閲覧可能
|
後陽成天皇 / 1
大雲和尚 / 2
鐵山和尚 / 3
大有和尚 / 4
虚応和尚 / 5
貴雲和尚 / 7
文之和尚 / 7
永雄和尚 / 10
清韓和尚 / 10
一峰和尚 / 11
門菴和尚 / 12
黒田長政 / 13
了翁和尚 / 14
菊径和尚 / 15
竜獄和尚 / 16
士峰和尚 / 17
崇伝和尚 / 18
古澗和尚 / 19
黙底和尚 / 20
不鐵和尚 / 21
好仁親王 / 22
烏丸光広 / 22
鐵村和尚 / 30
細川忠利 / 32
玉室和尚 / 34
奪叟和尚 / 35
江月和尚 / 35
嶺南和尚 / 36
清岳和尚 / 38
天庵和尚 / 38
沢庵和尚 / 39
宮本二天 / 52
十洲和尚 / 55
一糸和尚 / 57
柳生宗矩 / 60
小堀宗甫 / 62
土岐頼行 / 64
泰山和尚 / 64
関空和尚 / 65
徳川家光 / 66
片倉小十郎 / 67
万安和尚 / 68
鈴木正三 / 73
心雲和尚 / 79
高厳和尚 / 80
道者和尚 / 81
千宗旦 / 83
一庭和尚 / 91
雲居和尚 / 93
愚堂和尚 / 100
清厳和尚 / 104
木下利当 / 105
松平直基 / 106
中華和尚 / 107
松雲和尚 / 108
翠厳和尚 / 112
天室和尚 / 112
逸然和尚 / 113
別伝和尚 / 113
玉舟和尚 / 115
大愚和尚 / 116
白峰和尚 / 120
竜渓和尚 / 121
伊達安芸 / 124
如雪和尚 / 125
懶禅和尚 / 128
即非和尚 / 129
独立和尚 / 133
石川丈山 / 135
提宗和尚 / 137
了翁和尚 / 138
太岳和尚 / 138
了首座 / 139
杢之助 / 140
隠元和尚 / 140
明堂和尚 / 146
大眉和尚 / 147
傑外和尚 / 149
無難和尚 / 149
案山和尚 / 156
不中和尚 / 158
梅天和尚 / 159 |
鐵心和尚 / 166
黙玄和尚 / 168
後水尾天皇 / 170
獅厳和尚 / 172
慧林和尚 / 173
悦厳和尚 / 175
江雪和尚 / 176
松雲和尚 / 177
鐵眼和尚 / 178
祖道和尚 / 185
桃水和尚 / 186
木庵和尚 / 191
鰲山和尚 / 194
大顛和尚 / 195
山鹿素行 / 196
月舟和尚 / 197
大川和尚 / 198
賢厳和尚 / 199
独吼和尚 / 200
北山寿安 / 202
石水和尚 / 203
独本和尚 / 203
桂堂和尚 / 205
南源和尚 / 206
大用和尚 / 208
盤珪和尚 / 209
春沢和尚 / 215
独照和尚 / 216
松尾桃青 / 219
連山和尚 / 223
宝潭和尚 / 224
普峰和尚 / 226
潮音和尚 / 228
月舟和尚 / 232
高雲和尚 / 235
舜山和尚 / 236
心越和尚 / 237
天倫和尚 / 239
護洲和尚 / 241
風外和尚 / 242
独庵和尚 / 244
行厳和尚 / 246
鐵牛和尚 / 247
月畊和尚 / 248
大石良雄 / 249
雲山和尚 / 249
剛室和尚 / 250
月澗和尚 / 251
千呆和尚 / 253
損翁和尚 / 254
独湛和尚 / 255
梅峰和尚 / 257
痴絶和尚 / 258
徳翁和尚 / 259
霊峰和尚 / 261
鵬洲和尚 / 262
松雲和尚 / 263
丹嶺和尚 / 264
東鐵和尚 / 265
南海和尚 / 266
麟山和尚 / 266
良雪和尚 / 267
了然尼 / 267
鐵心和尚 / 269
黙室和尚 / 269
惟慧和尚 / 271
卍山和尚 / 272
柳沢吉保 / 274
橘染子 / 275
仏頂和尚 / 276
如実和尚 / 277
化霖和尚 / 279
慧極和尚 / 280
正受和尚 / 281
量外和尚 / 289
虎渓和尚 / 292
大光和尚 / 293
泰林和尚 / 295
東海和尚 / 296
隠之和尚 / 296
大心和尚 / 298
祖暁和尚 / 299
|
象海和尚 / 301
卓岩和尚 / 302
江外和尚 / 302
日初和尚 / 303
恕首座 / 303
団首座 / 304
慈仙和尚 / 305
痴兀和尚 / 305
栢翁和尚 / 306
天桂和尚 / 306
円瑞和尚 / 315
馬蹄和尚 / 317
月坡和尚 / 317
密山和尚 / 318
沢水和尚 / 321
無得和尚 / 322
全国和尚 / 324
祖山和尚 / 326
無著和尚 / 326
覚芝和尚 / 327
雪窓和尚 / 328
黙子和尚 / 328
印光和尚 / 329
的首座 / 330
体真尼 / 331
鐵文和尚 / 332
古月和尚 / 336
嶺南和尚 / 339
一丈和尚 / 340
無聞和尚 / 341
徳水和尚 / 342
雪庭和尚 / 343
大梅和尚 / 344
曇屋和尚 / 345
三洲和尚 / 345
拈華和尚 / 348
曹海和尚 / 349
寂仙和尚 / 352
笑堂和尚 / 353
月海和尚 / 354
宜黙和尚 / 361
卍庵和尚 / 361
指月和尚 / 364
雲門和尚 / 367
覚門和尚 / 369
頑極和尚 / 370
大潮和尚 / 374
円通和尚 / 375
法眼和尚 / 376
洞雲和尚 / 378
面山和尚 / 378
倫翁和尚 / 380
愚谷和尚 / 381
拙堂和尚 / 382
驢年和尚 / 383
悦厳和尚 / 384
蘭陵和尚 / 385
本光和尚 / 387
禅海和尚 / 389
慈門尼 / 391
明庵和尚 / 392
逆水和尚 / 395
白隠和尚 / 396
遂翁和尚 / 414
東嶺和尚 / 421
霊源和尚 / 426
葦津和尚 / 427
快厳和尚 / 428
大休和尚 / 430
峨山和尚 / 434 (
良哉和尚 / 439
円桂和尚 / 440
長沙和尚 / 441
愚庵和尚 / 442
天崖和尚 / 444
長堂和尚 / 444
層巓和尚 / 446
大同和尚 / 446
斯経和尚 / 447
天猊和尚 / 447
頑極和尚 / 448
劫運和尚 / 449 |
悟庵和尚 / 450
環渓和尚 / 450
梁山和尚 / 451
提洲和尚 / 453
滄海和尚 / 455
関?和尚 / 459
石衣和尚 / 460
験長老 / 460
脱首座 / 461
阪自洞 / 461
池大雅 / 462
山梨了徹 / 463
古郡兼道 / 468
庄司幽徹 / 469
慧昌尼 / 469
察女 / 470
遊女大橋 / 472
政女 / 475
原駅婆 / 476
茶店婆 / 476
月船和尚 / 477
実際和尚 / 478
竺源和尚 / 479
物先和尚 / 480
誠拙和尚 / 481
仙崖和尚 / 485
大巓和尚 / 489
阿三婆 / 490
善光和尚 / 491
蘭山和尚 / 492
無学和尚 / 495
素鋭和尚 / 495
天苗和尚 / 496
金〔レイ〕和尚 / 497
絶宗和尚 / 499
大典和尚 / 502
寛田和尚 / 504
澗水和尚 / 504
霊潭和尚 / 505
天真和尚 / 507
玄楼和尚 / 508
雲櫺和尚 / 511
湛堂和尚 / 514
前田土佐 / 514
隠山和尚 / 515
洞門和尚 / 520
松平不昧 / 521
仏星和尚 / 523
性堂和尚 / 524
仏通和尚 / 526
漢三和尚 / 528
華頂和尚 / 529
宜群尼 / 531
妙峰和尚 / 531
活歩和尚 / 532
良寛和尚 / 533
行応和尚 / 541
卓洲和尚 / 546
春叢和尚 / 551
雪関和尚 / 552
田能村竹田 / 554
太元和尚 / 556
棠林和尚 / 559
磨甎和尚 / 561
道海和尚 / 562
金華和尚 / 562
宙宝和尚 / 563
古梁和尚 / 564
象匏和尚 / 568
真浄和尚 / 570
大観和尚 / 571
盤谷和尚 / 572
見泥尼 / 573
香川景樹 / 573
黄泉和尚 / 574
顧鑑和尚 / 576
淡海和尚 / 579
清蔭和尚 / 580
巨海和尚 / 580
超首座 / 581
天猷和尚 / 583
湛元和尚 / 583
|
海山和尚 / 584
玉澗和尚 / 585
風外和尚 / 586
春応和尚 / 589
妙喜和尚 / 589
諦洲和尚 / 590
綾河和尚 / 592
耕隠和尚 / 593
拙堂和尚 / 596
回天和尚 / 596
通応和尚 / 597
京〔サン〕和尚 / 599
月珊和尚 / 599
大拙和尚 / 601
陽関和尚 / 603
石応和尚 / 604
覚厳和尚 / 605
迦陵和尚 / 606
大綱和尚 / 607
万寧和尚 / 608
智教和尚 / 609
伊山和尚 / 609
東海和尚 / 610
淵竜和尚 / 611
月潭和尚 / 612
筏舟和尚 / 614
仏山和尚 / 616
羅山和尚 / 617
竹院和尚 / 619
義堂和尚 / 620
物外和尚 / 622
天章和尚 / 627
純円尼 / 628
蘇山和尚 / 629
願翁和尚 / 633
歌女 / 634
大震和尚 / 635
薩門和尚 / 636
雪航和尚 / 637
鐵翁和尚 / 639
晦厳和尚 / 643
蓬洲和尚 / 648
竜水和尚 / 650
雪潭和尚 / 651
長沙和尚 / 654
橘仙和尚 / 655
無三和尚 / 656
伊達自得 / 658
奥宮慥斉 / 661
西郷南洲 / 662
愚渓和尚 / 663
儀山和尚 / 664
宝船和尚 / 666
大丘和尚 / 666
白翁和尚 / 667
海洲和尚 / 668
綾洲和尚 / 670
奕堂和尚 / 672
惟庵和尚 / 677
馬応和尚 / 678
泰竜和尚 / 679
星定和尚 / 682
春日載陽 / 683
環渓和尚 / 685
越渓和尚 / 691
山岡鐵舟 / 694
鰲巓和尚 / 700
竜関和尚 / 701
柏州和尚 / 703
坦山和尚 / 704
洪川和尚 / 713
独園和尚 / 718
匡道和尚 / 722
潭海和尚 / 726
無学和尚 / 729
滴水和尚 / 733
峩山和尚 / 739
大休和尚 / 743
洪岳和尚 / 746
・
・
・ |
|
| 1920 |
9 |
・ |
1月1日、喜田貞吉主筆、蘆田伊人編輯「民族と歴史第三巻一號 福神研究號」が「日本学術普及會」から刊行される。重要
1月15日、蘆田伊人編輯「民族と歴史第三巻二號 臨時増刊號 續福神研究號」が「日本学術普及會」から刊行される。
|
口絵 蓬莱山と松竹梅古圖
續福神研究號の發刊に就いて p1
千秋萬歳と大黒舞、附猿舞はし 京大國史研究室 岩橋小彌太君p7
笠島道祖神の研究 仙臺第二中學教諭 中西利徳君p17
土浴製品としての福神 長崎 本山桂川君p28
寶船 郷土趣味主幹 田中緑江君p38
三都の七福神廻り 同君p45
福を求むる心 尾州半田 磯谷才次郎君p46
|
支那に於ける福の神の俗説 文學士 那波利貞君p50
歳首に於ける招福の行事 風俗研究主幹文學士 江馬務君p62
三河地方に於ける福神信仰の状態 三州刈谷 加藤巌君p75
古羅馬の福神 京大講師文學士 植村清之助君p79
福神としての泰山府君 京大助教授文學士 西田直二郎君p83
蓬莱と松竹梅 帝室博物館学藝委員 高橋健自君p89
余白録 京都建仁寺蛭兒祠の詩(p49) ◎門松(p74) ○お陰参り(p82)
編輯餘談 福神研究號正誤表外數件 |
3月、高津柏樹が「まあ坐われ」を「日本図書出版」から刊行する。 pid/963172 閲覧可能
|
主心の坐処/1
大学の三鋼領/5
歳頭の一針/9
白隠時代の精神を/15
炉頭閑話/19
老爺の斧/25
百又と〔イ〕山の問答/34
嘘があれやこそ/36
何ぞ曽て飛び去らん/41 |
好雪片片の話/44
未審し壊か不壊か/49
禅は応用が大切/52
禅の功能/56
山僧大姉に論破さる/61
禾山和尚と山僧/64
禅定三昧/79
黄檗の禅風/87
相撲禅話/99 |
随意無礙の三昧/107
徳山和尚の機鋒/113
坐禅は作仏に非ず/123
芳草に随ひ落花を逐うて/127
狗子に仏性ありや/129
喫粥し了れりや/132
未だ唇を沾さず/134
智門の蓮華荷葉/136
洞山の寒暑廻避/138 |
洞山の麻三片/140
劉鐵磨の台山/143
百丈の濁坐大雄峰/146
雪峰の鼈鼻蛇/150
黄檗の□酒糟漢/153
主心お婆婆粉引歌/155
・
・
・ |
4月、禅学編輯局編「白隠和尚全集 : 勅謚正宗国師」が「光融館」から刊行される。
所蔵:青森県立図書館 札幌市中央図書館 版数不明
6月、幸田露伴が「日本史伝文選 下巻」を「大鐙閣」から刊行する。 pid/961905 閲覧可能
|
大久保彦左衛門/1
浜田弥兵衛/3
春日局/7
天海僧正/11
土井利勝/14
歌舞妓阿国/16
宮本武蔵/17
沢庵和尚/20
細川忠興/23
柳生宗矩/28
小堀遠洲/30
徳川家光/32
中江藤樹/36
徳川義直/39
由比正雪/41
林羅山/45
板倉重宗/48
松平信綱/53
小幡景憲/57
元政上人/60
野中兼山/64
日審上人/68
徳川頼宣/70
石川丈山/74
狩野探幽/77
鐵眼禅師/79
池田光政/80
山崎闇斎/85
山鹿素行/87
天竺徳兵衛/90
長沼澹斉/91
土佐光起/94
熊沢蕃山/95
井原西鶴/98
松尾芭蕉/100
木下順庵/104
河村瑞幹/107
徳川光圀/109
契冲阿闍梨/118
大石良雄/122
内藤丈草/135
向井去来/139
北村季吟/141 |
友禅/143
榎本其角/144
服部嵐雪/146
雨森芳洲/148
関孝和/154
伊藤仁斉/156
忍徴上人/158
菱川師宣/162
貝原益軒/164
竹本義太夫/166
柳沢吉保/167
秋色/168
尾形光琳。乾山/170
三宅観瀾/172
近松門左衛門/173
英一蝶/175
山中平九郎/180
新井白石/181
十寸見河束/186
園女/187
天野屋利兵衛/189
竹田出雲父子/192
荻生徂徠/193
東花房支考/197
横谷宗珉/198
紀文/199
天桂禅師/202
細井広沢/204
由縁斉貞柳/207
伊藤東涯/209
荷田春満。母深尾民/211
安積澹泊/214
上島鬼貫/217
紀海音/219
石田梅厳/221
八文字屋自笑。江島其碩/224
小川笠翁/226
太宰春台/227
橘守国/230
祇園南海/231
大岡忠相/236
市川柏筵/240
服部南郭/241 |
山脇東洋/245
売茶翁/249
僧樸/252
豊竹若太夫/254
深井志道軒/255
白隠禅師/256
加茂真淵/261
青木昆陽/263
吉益東洞/266
吸露庵綾足/272
加賀千代/274
大雅堂/276
賀川玄悦/278
平賀源内/280
富士谷成章/285
普寂律師/288
谷口蕪村/290
高芙蓉/292
祇園梶子/294
百合。玉蘭/296
大島蓼太/299
恋川春町/303
春秋庵白雄/302
竜門暁台/306
林子平/308
新井白蛾/311
高山彦九郎/314
谷風梶之助(二代目)/318
円山応挙/320
源鱗/322
朱楽管江/326
岩瀬京伝/328
伊藤若冲/329
細井平洲/333
小沢蘆庵/336
中井竹山/339
木村蒹葭堂/342
前沢良沢/344
慈雲律師/346
喜多川歌麿/350
奴の小万/352
皆川淇園/353
柴野栗山/358
|
狙仙/359
並木五瓶/361
橘千蔭/362
塙保己一/368
月仙/371
大屋裏住/372
小野蘭山/376
上田秋成/378
松村月渓/380
村田春海/382
山本北山/385
蒲生君平/388
喜三二/392
桂川甫周/393
中井履軒/395
古賀精里/396
杉田玄白/398
徳本行者/401
村瀬栲亭/404
市河寛斉/408
伊能忠敬/411
上杉鷹山/414
下斗米将真/418
式亭三馬/420
太田南畝/423
清元延寿斉/425
太田錦城/426
雷電/428
亀田鵬斉/430
菅茶山/431
高田屋嘉兵衛433
酒井抱一/440
近藤重蔵/441
松平定信/450
鶴屋南北/455
北川真顔/457
六樹園飯盛/458
十返舎一九/460
頼山陽/463
田能村竹田/466
月岡雪鼎/469
大監平八郎/470
岸駒/473 |
立原杏所/474
阿藤/476
谷文晁/481
渡辺華山/489
柳亭種彦/486
為永春水/484
香川景樹/491
村田了阿/494
平田篤胤/496
小山田与清/500
曲亭馬琴/502
葛飾北斉/508
朝川善庵/512
高野長英/514
国定忠二/516
篠崎小竹/521
八代目市川団十郎/524
斉藤彦麿/526
椿椿山/528
藤田東湖/529
広瀬淡窓/533
月性/535
梁川星厳/536
月照上人/542
徳竜講師/545
松本景岳/548
頼三樹/552
佐藤一斉/554
浮田一蕙/558
日輝上人/561
梅田雲浜/564
徳川斉昭/566
安積艮斉/575
慧澄律師/579
藤本鐵石/582
松本奎堂/583
緒方洪庵/585
武田耕雲斉/588
斉藤拙堂/598
坂本竜馬/604
監谷宕蔭/612
高杉晋作/618
・ |
6月、島地大等(だいとう)が「漢和對照妙法蓮華経」を「明治書院」から刊行する。 pid/3461575
|
開經偈/1
贊序/1
聖德皇太子御贊/1
傳敎大師御釋/3
弘法大師御釋/7
法然聖人法語/9
道元禪師法語/11
日蓮聖人法語/14
存覺上人法語/17
白隱禪師法語/21
妙法蓮華經/1
卷第一
序品第一/1
方便品第二/39 |
卷第二
譬諭品第三/83
信解品第四/145
卷第三
藥草諭品第五/177
授記品第六/193
化城諭品第七/211
卷第四
五百弟子授記品第八/261
授學無學人記品第九/281
法師品第十/291
見寶塔品第十一/309
卷第五
提婆達多品第十二/333 |
勸持品第十三/349
安樂行品第十四/359
從地涌出品第十五/389
卷第六
如來壽量品第十六/413
分別功德品第十七/431
隨喜功德品第十八/453
法師功德品第十九/465
卷第七
常不輕菩薩品第二十/491
如來神力品第二十一/505
囑累品第二十二/515
藥王菩薩本事品第二十三/519
妙音菩薩品第二十四/541 |
卷第八
觀世音菩薩普門品第二十五/557
陀羅尼品第二十六/575
妙莊嚴王本事品第二十七/585
普賢菩薩勸發品第二十八/599
梵文陀羅尼神呪/613
法華大意/1
法華略科/26
法華字解/1
法華歌集/1
刻經縁起/1
廻向文/1
・
・ |
7月、安松長一編「病弱の友に」が「晴之社」から刊行(再版)される。 pid/913994 閲覧可能
|
神言聖語篇/1p
五箇條ノ御誓文/2p
教育勅語/4p
戊申詔書/6p
軍人ニ賜リタル勅諭/8p
天津祝詞/17p
神言/18p
神訓/23p
神誡/26p
|
六根清淨大祓/28p
般若心經/30p
聖歌集句/32p
保健療病篇/47p
保健と療病の要訣/48p
醫藥療法/50p
鍼灸療法/53p
自然療法/53p
食養療法/57p
|
石塚式食養療法概要/58p
肺結核の食養療法 (岡部剛雄先生述)/64p
膓結核の食養療法 (同上)/79p
胃加答兒と膓加答兒の食養療法 (同上)/85p
精神療法/96p
坂井式聖座法 (坂井眞民先生述)/101p
坂井式活元調身術 (同上)/117p
夜船閑話 (白隱禪師遺稿)/123p
・ |
○、この年、川尻宝岑居士講話「白隠禅師毒語心経閑話」が「森江書店」から刊行される。 所蔵:東京都立多摩図書館
○、この年、衆善会編「古今禅林佳話集」が「衆善会」から刊行される。 pid/963239
|
元旦上堂 唐 虚堂禅師 / 1
後醍醐天皇との歌 臨済 大灯国師 / 2
大なる哉心 臨済 栄西禅師 / 3
最上の宝 唐 達磨大師 / 4
その日暮し 臨済 正受老人 / 5
垂訓 曹洞 道元禅師 / 7
坐禅の要術 曹洞 道元禅師 / 8
荻原法皇の后に示す 臨済 大灯国師 / 10
門松は冥途の旅の一里塚 臨済 一休和尚 /22
わしは恋をして居る 臨済 一休和尚 / 26
発願文 唐大恵禅師 / 28
船唄 曹洞 天挂禅師 / 29
四料簡 唐 臨済禅師 / 30
解打鼓 唐 禾山禅師 / 32
妖は徳に勝たず 臨済 大明国師 / 33
仏神へ祈願の教 臨済 夢窓国師 / 35
上皇師の為め庖厨せらる 臨済 大明国師/36
明徳至善の名大将 臨済 白隠禅師 / 38
坊主なりやこそ毛がない 曹洞 黙仙禅師/40
汝等の頭を摩でよ 臨済 寂室禅師 / 41
剣刄上の安禅 曹洞 石水和尚 / 43
落成式の祝辞 臨済 仙崖和尚 / 45
きやり歌 臨済 英宗禅師 / 47
六組大師の苦修 唐 恵能禅師 / 51
死を決す 唐 長沙和尚 / 57
莫妄想 唐 仏光国師 / 59
遺誡 臨済 大灯国師 / 61
病中の公案 臨済 白隠禅師 / 63
奈良の大仏に参詣せよ 臨済 友梅禅師/64
出家の動機 曹洞 穆山禅師 / 65
生れぬ先の父ぞ恋しき 臨済 白隠禅師/67
美人の鞭 臨済 竜関和尚 / 69
好箇仏殿、仏末不精 唐 神賛和尚 / 71
一日不作一日不食 唐 百丈禅師 / 73
炊事と無駄事 臨済 峩山禅師 / 75
此野郎武士に似合はぬ 臨済 誠拙禅師/77
花魁の図賛 臨済 沢庵和尚 / 79
不与麼に来る時如何 唐 普化禅師 / 81
西爪の商量如何 面山和尚 / 83
快馬鞭 臨済 東嶺禅師 / 85
さあ早く斬れ 臨済 独園禅師 / 86
拳骨和尚 臨済 物外和尚 / 89
唯一ときの夢の戯れ 臨済 夢窓国師 / 91
雲は青天に水は瓶 唐 薬山禅師 / 97
豪なる胆 曹洞 穆山禅師 / 99
達磨と妓女の図賛 曹洞 穆山禅師 / 100
念仏の法語 臨済 峩山禅師 / 101
宝玉は這裡にあり 曹洞 石屋禅師 / 104
娘生の面目 臨済 梅天和尚 / 109
柳生但馬守への教訓 臨済 沢庵禅師/111
瓢箪の句 臨済 大綱和尚 / 116
一休早書きの扇子 臨済 一休禅師/117
画禅一味の境 臨済 兆殿 司 / 119
住み慣れました 臨済 雲居和尚/ 122
|
如何で御座る柏餠 臨済 白隠禅師/123
礼を云ふと帳面が消る
→臨済 仙崖和尚/125
禅要に答ふ歌 臨済 無難禅師 / 129
傘下杖頭天地寛 臨済 雲居禅師 / 131
極楽の法話 臨済 一休和尚 / 134
妻へ離別状 臨済 洪川禅師 / 135
友愛の至味 臨済 洪川禅師 / 137
京の金閣寺 臨済 貫宗和尚 / 139
白木屋の家憲 臨済 無難禅師 / 140
一剣矢に倚つて寒し 臨済 楚俊禅師/141
活きた一切経 臨済 一休禅師 / 145
百万の蚊軍何者ぞ 臨済 宝鑑国師 / 147
新婦人の装をして 臨済 山崖和尚 / 149
一休問答 臨済 一休禅師 / 153
無実の濡衣 臨済 白隠禅師 / 159
孝心の深きと清廉 臨済 友梅禅師 / 165
曹源の一適水 臨済 滴水禅師 / 167
宗謙和尚と上杉謙信 曹洞 宗謙和尚/168
老婆を戒む 臨済 古梁禅師 / 169
若者の悪戯 臨済 雲居禅師 / 171
今日の味噌太だ美なり 臨済 盤珪禅師
藩政を諷す 臨済 仙崖和尚 / 174
女郎買 臨済 木堂和尚 / 175
それで天下が取れる 臨済 独園和尚/177
一指頭の禅 唐 倶胝和尚 / 179
三界の大導師 臨済 虚関禅師 / 186
泥中の蓮 曹洞 無三和尚 / 187
各宗祖師の図賛 臨済 一休和尚 / 189
師匠も敬服した 臨済 毒湛禅師 / 191
黄檗の仏法多子なし 臨済 臨済禅師 / 193
弊衣保存 臨済 峩山禅師 / 199
大鯛を仏様に 臨済 宗詮和尚 / 200
善悪の源? 臨済 夢窓国師 / 201
後水尾上皇と愚堂和尚 臨済 愚堂和尚/203
座右の銘 臨済 宗演禅師 / 207
太皷の音を描く 臨済 仙崖禅師 / 208
黄檗山門の扁額 黄檗 高泉禅師 / 209
老人六歌仙 臨済 仙崖和尚 / 210
新選組の領袖一本やらる
→臨済 物外和尚/211
お茶屋見物 黄檗 法眼和尚 / 214
乃公の提唱に糟はない 臨済 雪潭和尚/217
伊達自得の参禅 臨済 越渓和尚 / 218
女程芽出度ものなし 黄檗 覚之和尚/220
悪僧の悔悟 臨済 盤珪禅師 / 221
衆人に示して曰く 臨済 古梁和尚 / 222
毘慮頂上の作労 臨済 宗演禅師/223
冬扇 臨済 峩山禅師 / 224
一切経の開版 黄檗 鉄眼和尚/ 225
一喝光圀を驚かす 黄檗 心越禅師/229
十後悔 臨済 雲居禅師 / 230
それ猫が 曹洞 風外和尚 / 231
退屈せぬ工夫 臨済 沢庵和尚 / 232
|
酒は何より御馳走
→臨済 無難禅師/233
啜汁看経弥左衛門
→臨済 邃翁和尚/237
示衆十則 臨済 寂室禅師 / 238
風外の真風 曹洞 風外和尚 / 239
放屁一発のお詫び
→臨済 独山禅師/242
老〔シ(めす)〕牛汝来れりや 唐
→〔イ〕山禅師 / 243
清廉なる事 曹洞 道元禅師 / 247
慈の一字 臨済 峩山禅師 / 249
施行歌 臨済 白隠禅師 / 251
仏頂と芭蕉 臨済 仏頂禅師 / 255
北条時頼の参禅 唐 普寧禅師 / 257
教育談 臨済 峩山禅師 / 259
君辱臣死 曹洞 良雪和尚 / 261
辞世 臨済 沢庵和尚 / 262
禅僧と芝居 臨済 魯堂和尚 / 263
山県公爵に一拶
→臨済 峩山禅師 / 268
沢庵禅師の歌 臨済 沢庵和尚 / 269
臘八示衆 臨済 東嶺禅師 / 271
馬腹臚胎 臨済 関山国師 / 281
衆善奉行 唐 道林禅師 / 283
大梅山夜話 臨済 大梅和尚 / 285
嘘を戒め事業に就て
→臨済 拙堂禅師/286
九死一生坐禅の功徳
→臨済 盤珪禅師/287
疳癪治癒法 臨済 盤珪禅師/289
南洲と無参和尚 曹洞 無参和尚/291
それはお互さま 臨済 峩山禅師/292
我は醤油屋の伜 臨済 独園禅師/293
聞えたか忠孝の本体
→臨済 独園禅師/294
無茶の説 臨済 誠拙禅師 / 301
瓜や茄子の花盛り
→臨済 敬冲禅師 / 303
神に逢はせろ 臨済 峩山禅師 / 305
伊藤博文公の頓智
→曹洞 悟由禅師/ 308
乃木将軍と南天棒 臨済 鄧州禅師/311
一味の清涼 臨済 越渓禅師 / 313
蛇身と仏身 臨済 拙道禅師 / 314
山梨平四郎(戯曲)
→臨済 英宗禅師/ 318
安心して死ね! 臨済 誠拙禅師/340
祥瑞の語 臨済 仙崖和尚 / 342
祖鏡の引導結句無し
→曹洞 祖鏡禅師/343
臨終の覚悟はよいか
→臨済 夢窓国師/345
遺誡 臨済 夢窓国師 / 345 |
|
| 1921 |
10 |
・ |
1月、長沼賢海が「福神研究恵比須と大黒」を「丙午出版社」から刊行する。 pid/963256
|
上篇 夷神
第一章 夷社の沿革
第二章 夷神と三郎神及蛭子神 |
第三章 夷神の正体
第四章 夷神の性質
下篇 大黒天神 |
第一章 印度支那の大黒天神
第二章 伝神愷記の研究/186
第三章 平安時代の図像及記録 |
第四章 平安時代の其修法と信仰
第五章 鎌倉時代の大黒天神
第六章 室町時代の大黒天神 |
8月、羽場愚道が「白隠珍話」を「酒井出版部」から刊行する。 pid/915905
|
禪師の生涯 / 1
難船中の鼾聲 / 9
人生の果敢なさ / 11
浮世離れた溪中の石 / 14
天神樣信仰の由來 / 15
唯一言「ウンさうか」 / 19
我未來も覺束ない / 26
苦悶も懷疑も消えた / 30
お多福女郎の粉挽唄 / 33
|
南泉遷化の話 / 50
狐つき / 59
がん首とすひ口 / 61
眉間割り / 63
深夜に九尺の怪人 / 67
父の遺言 / 69
覺悟さつしやい / 72
お婆々粉引歌 / 76
施行せよ / 87
|
白隱と東嶺 / 101
安心ほこりたたき / 106
大道ちよぼくれ / 118
蛆が湧いた醤油 / 125
夢に母の古鏡 / 127
末後の會 / 129
大呼一聲 / 132
十句經と白隱 / 135
琴の崇り / 154 |
癲狂者の禮状 / 160
湯殿の水拔き穴から / 164
地獄歸へりの娘 / 173
盲子目を開く / 192
死んだ娘が蘇生した / 201
瀕死の病人全快 / 206
老婆の重病忽ち癒ゆ / 211
有難や十句經の利益 / 219
・ |
11月25日~29日、上野公園櫻岡日本美術協會に於て白隠和尚墨蹟展」が開かれる。
○、この年、「白隠和尚墨蹟目録 [出版者不明] 」が刊行される。 東京大学 史料編纂所 図書室図書所蔵:1016:1606800271790
大正十年十一月二十五日ヨリ向五日間上野公園櫻岡日本美術協會ニ於テ展観
12月、川上孤山が本山妙心寺編「 妙心寺史 下巻」を「妙心寺派教務本所」から刊行する。 pid/926993 1900円
|
總説
第參編 德川前期 / 33
第一章 鐵山、一宙時代 / 3
第二章 一絲、愚堂時代 / 74 |
第四編 德川中期 / 195
第一章 無難、盤珪、正受時代 / 195
第二章 無着、白隱時代 / 276
第三章 東嶺時代 / 335 |
第五編 德川後期 / 351
第一章 隱山卓洲時代 / 351
第二章 暘山 南海時代 / 372
第三章 維新前の妙心 / 402 |
12月、伊藤尚賢と森繁吉が「一人一人の体力精力能力増進法」を「一誠社」から刊行する。 pid/935678 閲覧可能
|
第一編 緖諭
第一章 健康増進法は科學的の
→研究を要す/1
第二章 健康とは何ぞや/13
第三章 年齢と職業によつて
→健康増進法は異る/21
第二編 先賢推獎健康法
第一章 如何なる健康法か/30
第二章 承陽大師の普勸坐禪義/32
第三章 白隱禪師の夜船閑話/36
第四章 白隱禪師の遠羅天釜/51
第五章 白隱禪師の獨按摩/88
第六章 水戸烈公獨按摩/92
第七章 本井了承の調氣の方/95
第八章 田中氏の修養必用十八段/98
第九章 櫻寧室主人の養生訣/107
第十章 考槃老人の延壽帯效用略記/121
第十一章 貝原益軒の養生訓 / 133
第十二章 平田篤亂の志都の石室/141
第十三章 塚田大峰の長生成功諭/154
第十四章 天仙子の神仙術/159
第十五章 禪定と健康法/168
第三編 現代の健康増進法
第一章 川合氏の吐納法/175
第二章 腹式呼吸法/199
第三章 岡田式呼吸靜座法/228
第四章 川合氏強健法/252
第五章 藤田氏の息心調和法/271
第六章 深呼吸健康法/278
第七章 シユミツトの呼吸體操/287
第八章 中村醫學士の腹壓固定法 / 290
第九章 村井氏の弦齋式新運動法 / 298
第十章 家庭呼吸體操法/321
|
第十一章 胸廓強壯運動法/341
第十二章 乾布摩擦健康法/343
第十三章 水原氏の信天養生術/346
第十四章 仙術より得たる室内運動法 / 355
第十五章 シユーベル氏の保健體操法 / 360
第十六章 早老豫防強健術/367
第十七章 ジヤストの自然的健康法/383
第十八章 地を利用する健康増進法/385
第十九章 登山/402
第二十章 冷水浴/406
第二十一章 海水浴/416
第二十二章 温泉浴/432
第十三章 ニツプの健康法/467
第十四章 日光浴/475
第十五章 空氣浴/479
第二十六章 カントの長壽健康法/483
第二十七章 エヂソンの減食健康法/489
第二十八章 麁食健康法/493
第二十九章 統計的健康長壽法/497
第四編 身體各部の健康増進法
附主要なる疾患の豫防法及治療法
第一章 健腦法
第二章 主なる腦神經疾患 / 519
第三章 毛髪の健康法/529
第四章 主なる毛髪病/536
第五章 皮膚の健康法/538
第六章 主なる皮膚病/557
第七章 眼と健康法/567
第八章 主要なる眼病/588
第九章 耳の健康法/592
第十章 主要なる耳の疾患/603
第十一章 鼻の健康法/608
第十二章 主要なる鼻の疾患/617
|
第十三章 咽頭及び喉頭の健康法/632
第十四章 主要なる咽喉病/635
第十五章 齒の健康法/639
第十六章 主要なる齒の疾患/649
第十七章 胃の健康法/656
第十八章 主要なる胃の疾患/672
第十九章 腸の健康法/679
第二十章 主要なる腸の疾患/692
第二十一章 肺の健康法/695
第二十二章 主要なる呼吸器病/715
第二十三章 心臓の健康法/725
第二十四章 腎臓の健康法/732
第二十五章 生殖器の健康法/743
第二十六章 主なる生殖器疾患/749
第五編 人による健康法
第一章 幼童の健康法/753
第二章 少年時代靑年時代の
→健康増進法/758
第三章 成年時代の健康増進法/763
第四章 老年時代の健康増進法/765
第五章 婦人の健康増進法/770
第六章 肥滿者の健康法/783
第七章 痩せた人の健康増進法/784
第六編 職業による健康増進法
第一章 商店員の健康増進法/786
第二章 學生の健康増進法/793
第三章 官吏會社員等所謂勤め人の
→健康増進法/801
第四章 軍人の健康増進法/802
第六章 實業家の健康増進法/806
第七章 農家の健康増進法/808
第八章 坐職者の健康増進法/810
第七編 藥の效用早わかり/812 |
○、この年、小林久太郎が「人の心」を「光文堂書店」から刊行する。 pid/931045 閲覧可能
|
緖言
第一編 大腦の抑制作用に就て/1
一 心ニ抑制ノアルベキ理由
二 不隨意的即チ植物性官能ニ對スル抑制作用
三 隨意的即チ動物性官能ニ於ケル抑制作用
第二編 抑制と道德の關係/28
一 抑制ト精力トノ關係
二 抑制トハ積極的忍耐ヲ云フ
第三編 古來の德育法/38
一 釋敎ニ於ケル德育法
二 孔子敎ノ德育法
三 常議ノ説明
第四編 佛敎の悟道をは自己抑制なり/51
一 釋迦ノ大悟ニ付テ
二 後継者ノ大悟ニ就テ
三 蒙山ノ大悟状態
四 雪岩ノ大悟ニ付テ
五 佛光國師ノ大悟ニ就テ
六 白隠ノ大悟ニ付テ
第五編 抑制と心身との関係/75
一 心理ノ推定
二 身體ニ及ボス影響
三 大悟ト資性トノ關係
四 余ガ禪ニ於ケル經驗
第六編 大悟と死との混同/94
|
一 生滅滅巳ノ誤解
二 抑制ハ平常ノ官語文字ヲ離ル
三 啓発ノ亂用
四 經典ノ解釋
第七編 佛敎と孔子敎等の一致/113
一 孔子敎ノ判
二 老子敬義ノ一致
三 莊子敎ノ一致
四 ソクラチスノ一致
五 基督ノ一致
第八編 個性と抑制との關係/157
一 細胞ノ個性
二 細胞ノ通有性
三 人問生存上ノ個性ノ通有性
四 精神界ノ個性ト通有性
五 抑制ノ共同作用元理
六 智ノ説明
七 勇ノ説明
八 帝王ニ對スル抑制
九 爲致者ニ對スル抑制
十 劍道ト抑制
十一 工藝ト抑制
十二 抑制ノ大用
十三 道德ハ相對的テルヲ要ス
第九編 神佛の存否/178
|
一 佛ノ本體
二 神ノ本體
第十編 靈魂なるものあることなし/189
一 心ノ作用低止スルガ死ナリ
二 吾人平常靈アルヲ知ラス
三 靈魂ノ抑制
四 天國ニ遊ビ極樂ニ入ル方法
第十一編 人惟其生を尊しと爲す/196
第十二編 日本の武士道/196
一 國體ト國是區別
二 武士道ノ根源
三 今ノ敎育法ノ誤謬
第十三編 我が見所/204
一 宇宙觀
二 人生觀
三 政治觀
四 善悪觀
五 凡聖區別ノ根底
六 理想的人物
七 抑制ト日常生活トノ關係
八 世界關
九 生死觀
第十四編 抑制を發達せしむる方法/225
一 孔子敎ノ抑制敎育法
二 東洋道德ト西洋道德ノ歸着/225 |
○、この年、高島平三郎編「精神修養逸話の泉 第16編」が「洛陽堂」から刊行される。 pid/954145
|
聖徳太子の聖徳と馬子/1
聖徳太子の遊行中の出来事/2
聖徳太子憲法十七条を定む/5
橘の郎女の奉納したる法隆寺の宝物/13
僧行基勅を奉じて大仏を落成す/15
行基嘗て口舌の教を説く/17
文珠の化身と称へられたる行基/18
僧行基臨終に弟子に誨ゆ/20
良弁二歳にして鷲に攫み去らる/20
最澄勅を奉じて唐に至る/21
最澄慇懃に徒弟に誨ゆ/23
空海五筆和尚と称せらる/23
嵯峨天皇と弘法大師の筆跡の話/24
慈覚大師洽く聖迹を巡拝す/26
円珍八歳にして因果経を読む/30
円珍衆弟子を誡む/31
老鍜冶生死の到来如何を問ふ/32
空也天下を遊行して風を化す/34
源信僧都空也に疑義を問ふ/35
勢至丸十五にして登山修行す/36
文徳天皇紀夏井を召させ給ふ/40
紀夏井大に民心を得たり/41
菅原道真修道の要を説く/43
菅原道真の吟詠/44
慈鎮の上りたる和歌/44
藤原兼実在家の念仏を問ふ/46
大江匡房天命を説く/49
俊寛僧都の鹿谷の会合/50
藤原成経平康頼孤島に読経す/53
平康頼法華経を俊寛に与ふ/58
有王丸鬼界島に其師を訪ふ/61
俊寛有王丸に因縁を語る/67
文覚上人神護寺の修造に志す/73
明恵上人夙に出世に志す/74
明恵高野に赴く途に故郷を念ふ/75
拇尾時代の明恵上人/76
明恵の不惜身命の修行/77
北畠親房の警語/79
明庵菩提樹を移植す/80
明庵同学を敬服せしむ/81
明庵茶樹を携へ帰る/82
栄西他郷に大に禅学を修む/83
道元曹洞禅の第五十一位につく/84
北条時頼入道して道宗と号す/86
|
俊〔ジョウ〕不可棄と名乗る/88
北条泰時明恵上人の言に感ず/89
忌部正道の神道を説く一節/90
建礼門院明恵上人の言に感ず/91
僧日蓮獅子吼を挙ぐ/92
護良親王大般若経中に隠る/95
戸野兵衛よく大塔宮を護り奉る/100
御醍醐帝法華経を持たせて崩じ給ふ/112
菊麿七歳にして仏に帰依す/114
宗純四十雀に引導を渡す/117
快川猛火裡に定化す/118
藤原惺窩豊太閤を評す/119
徳川家康天海の教を受く/120
天海藤原鎌足の例に傚ふ/121
天海其の姓氏を告げず/122
天海の公式法制と成憲百条/122
島津家久天海に教文の事を学ぶ/124
井上正利林羅山に句を請ふ/126
佐久間立斉の見た林羅山/127
狩野探幽の天才/128
探幽の画を貞室に賜ふ/129
沢庵奢侈の弊を諸侯に教ふ/130
沢庵諸侯伯に誨ゆ/131
沢庵禅師鍛錬の要を述ぶ/133
沢庵禅師石火の機を説く/134
加藤清正自助の言を述ぶ/136
雪潭犬山城主を喝破す/137
鈴木正三友人に真勇を教ゆ/138
了心庵大に二王坐禅を説く/140
了心庵の活修養語/143
徳川家光東寔禅師の窮追に会ふ/146
東寔儒家に奇答を放つ/147
松平信綱熊沢蕃山に師事す/148
池田光政蕃山の言に服す/149
莅戸太華能く自己を知る/150
太華能く其児を鑑識す/151
東嶺禅の修養者を説く/153
白隠の遠羅手釜の語/155
鍋島侯道を白隠に聞く/158
盤珪晩年にますます衛生を重んず/159
沢水和尚大に一武士を誡む/161
藪孤山細川銀台に王覇の事を説く/163
江村宗具の国歌/164
後水尾帝幕府の跋巵を慨かせ給ふ/166
|
野中兼山老夫と語る/167
松雲禅師と五百羅漢/169
松雲の勧化中の出来事/171
松雲いよいよ伊勢屋に入る/174
松雲遂に目的を完成す/178
象先和尚松雲の志を継ぐ/180
象先和尚の風格/182
徳川吉宗象先和尚に感ず/183
高橋鳳雲幼にして彫刻に巧なり/186
佐竹義真小坊主に志を問ふ/189
今易右衛門の逸事/190
近松門左衛門と曽根崎心中の句/192
不動金兵衛の逸事/193
整珉と高橋鳳雲/195
新井白石の艱苦に堪えし事/199
新井白石の考証精確/201
水足平之允と物徂徠/202
与謝蕪村の廉潔なる心事/204
金蘭斉の奇行/206
金蘭斉の奇行の二/208
谷伝右衛門田安家に事ふ/210
中村惕斉温厚なり/212
朋友文晁の精力に敬服す/212
頼山陽自像に自賛す/214
俳人梅室質素を重んず/215
梅室門人に俳味を語る/216
僧契冲無常歌を作る/217
桜井雪館文晁の画才を賞す/232
吉益東洞医学に志す/232
山脇東洋大に東洞を紹介す/235
前野蘭化大に蘭学を修む/236
俳人水巴の句/237
俳人卓池死期を語る/238
北斉の弟子と文晁の話/240
谷文晁に酒癖あり/248
文晁大に北斉を紹介す/249
文晁が残したる辞世/252
松尾芭蕉一生聾字を用ゐず/253
芭蕉祐天上人を信頼す/254
芭蕉変化の事を説く/256
榎本其角夢裡に口吟す/258
大雅堂の逸事数則/259
俳人鶯笠老婆と思はる/261
抱一上人の多趣多味/264
|
抱一大に其角を慕ふ/265
円山応挙の詩歌/267
小林一茶某宗匠を訪ふ/268
一茶盗賊と誤認せらる/270
一茶と加賀侯/272
市川白猿加茂季鷹を訪ふ/275
中島一鳳文晁を評す/277
谷口鶏口士人を頓悟せしむ/279
三井養安の人となり/280
小西来山の飄逸/283
平田篤胤其妻の言に感ず/284
平田篤胤本居翁の墓に展す/285
平田篤胤の鬼神新論の一節/287
惟然坊の風羅念仏/288
物外和尚の機智と拳骨/290
拳骨和尚の逸話のかずかず/291
草野正辰亦俳句に巧なり/294
俳人超波貧中に友を驚かす/295
俳人款冬の俳趣味/296
松崎白圭篠山侯の世子を戒む/298
伊藤東涯化物屋敷に寓す/299
俳人木斉の人となり/300
俳人素行の読経/301
俳人湖山天狗の鼻を挫く/304
十竹の自賛の語/306
俳人心敬老功の言を吐く/307
葛三門弟に風流の道を説く/308
僧潮音富貴貧賊を説く/309
大洲侯盤珪に参禅す/311
嶺南妙心寺に入る/313
大愚聞関と一見旧識の如し/313
鳳朗大に其の門下を撫育す/315
片桐鼎湖大に難字を用う/316
青木露水笛の三品を評す/318
永平寺環渓と団十郎/319
落合直養の摂養/320
福田行誡の奇警の語/323
雲照律師堅く戒律を守る/325
沢山保羅木戸孝允と親し/325
外山正一句を竹冷に質す/326
尾崎紅葉風流の心を失はず/327
大西祝哲学者にして文学を兼ぬ/328
中上川彦次郎の狂/330
・ |
|
| 1922 |
11 |
・ |
1月、「絵画清談 10(1)」が「絵画清談社」から刊行される。 pid/1500180
|
表紙繪 / 小室翠雲/表紙
諸大家作品寫眞版三十點――口繪
諸大家作品寫眞版十六點――挿繪
土田麥僊氏の畫論 / 不死鳥生/p1~5
美術記者十年記 / 添田達嶺/p6~9
田能村竹田の書簡/p10~10
サロンの日本美術部に就て/坂崎坦/p12~15
如是我觀録 / 山浦瑞洲/p16~20
|
大正十年の顧望 / 石井柏亭/p22~23
中林梧竹の遺墨 / 野田大塊/p24~24
京の三名匠―仁淸!/吉田紫浪/p25~26
美術界雜録/p27~32
日佛交換展へ出品の作品/p27~27
日野法界寺の壁畫模寫/p27~27
文藝院設置/p27~28
平和博美術部審査員銓衡難/p28~28
|
北京に日本畫展覽會/p28~29
高橋氏藏品十八萬圖/p29~30
※細川侯秘藏白隱遺墨公開/p30~30
日本南畫院東西融合/p30~31
水戸侯の入札卅二萬圓/p31~32
茂木家の入札/p32~32
平和博處置に書道會憤る/p32~32
・ |
3月、伊藤尚賢と森繁吉が「活きんとするものゝ為に」を「一誠社」から刊行する。 pid/912788
|
第一編 緒論
第一章 健康增進法は
→科學的の研究を要す/1
第二章 健康とは何ぞや/13
第三章 年齡と職業によつて
→健康增進法は異る/21
第二編 先賢推奬健康法
第一章 如何なる健康法か/30
第二章 承陽大師の普勸坐禪義/31
第三章 白隱禪師の夜船閑話/36
第四章 白隱禪師の遠羅天釜/51
※第五章 白隱禪の獨按摩/88
第六章 水戸烈公獨按摩/92
第七章 本井了承の調氣の方/95
第八章 田中氏の修養必用十八段/98
第九章 櫻寧室主人の養生訣/107
第十章 考槃老人の延壽帶效用略記/121
第十一章 貝原益軒の養生訓/133
第十二章 平田篤胤の志都の石室/141
第十三章 塚田大峰の長生成功諭/154
第十四章 天仙子の神仙術/159
第十五章 禪定と健康法/168
第三編 現代の健康增進法
第一章 川合氏の吐納法/175
第二章 腹式呼吸法/199
第三章 岡田式呼吸靜座法/228
第四章 川合氏強健法/251
第五章 藤田氏の息心調和法/271
第六章 深呼吸健康法/278
第七章 シユミツトの呼吸體操/287
第八章 中村醫學士の腹壓固定法/290
第九章 村井氏の弦齋式新運動法/298
第十章 家庭呼吸體操法/321
第十一章 胸廓強壯運動法/341
第十二章 乾布摩擦健康法/343 |
第十三章 水原氏の信天養生術/346
第十四章 仙術より得たる室内運動法/355
第十五章 シユーベル氏の
→保健體操法/360
第十六章 早老豫防強健術/367
第十七章 ジヤストの自然的健康法/383
第十八章 地を利用する健康增進法/395
第十九章 登山/402
第二十章 冷水浴/406
第二十一章 海水浴/416
第二十二章 温泉浴/432
第二十三章 ニツプの健康法/467
第二十四章 日光浴/475
第二十五章 空氣浴/479
第二十六章 カントの長壽健康法/483
第二十七章 エヂソンの減食健康法/489
第二十八章 麁食健康法/493
第二十九章 統計的健康長壽法/498
第四編 身體各部の健康增進法
第一章 健腦法/504
第二章 主なる腦神經疾患/519
第三章 毛髪の健康法/529
第四章 主なる毛髪病/536
第五章 皮膚の健康法/538
第六章 主なる皮膚病/557
第七章 眼と健康法/567
第八章 主要なる眼病/586
第九章 耳の健康法/592
第十章 主要なる耳の疾患/603
第十一章 鼻の健康法/608
第十二章 主要なる鼻の疾患/617
第十三章 咽頭及び喉頭の健康法/632
第十四章 主要なる咽喉病/635
第十五章 齒の健康法/639
第十六章 主要なる齒の疾患/649 |
第十七章 胃の健康法/665
第十八章 主要なる胃の疾患/672
第十九章 腸の健康法/679
第二十章 主要なる腸の疾患/692
第二十一章 肺の健康法/695
第二十二章 主要なる呼吸器病/715
第二十三章 心臟の健康法/725
第二十四章 腎臟の健康法/732
第二十五章 生殖器の健康法/742
第二十六章 主なる生殖器疾患/749
第五編 人による健康法
第一章 幼童の健康法/752
第二章 少年時代青年時代の
→健康增進法/758
第三章 成年時代の健康增進法/763
第四章 老年時代の健康增進法/765
第五章 婦人の健康增進法/770
第六章 肥滿者の健康法/783
第七章 痩せた人の健康增進法/784
第六編 職業による健康增進法
第一章 商店員の健康增進法/786
第二章 學生の健康增進法/793
第三章 官吏會社員等所謂勤め人の
→健康增進法/801
第四章 軍人の健康增進法/802
第五章 乘務員(汽車汽船電車等)の
→健康增進法/805
第六章 實業家の健康增進法/806
第七章 農家の健康增進法/808
第八章 坐職者の健康增進法/810
第七編 藥の效用早わかり/812
素人に使ひ得る藥物數百種の
→効用用法分量等を詳記す
・
・ |
12月、草村松雄編「白隠墨蹟」が「竜吟社」から刊行される。 ※細川侯爵家蔵版 pid/1014331 閲覧可能 最重要
○、この年、森江英二編「白隠禅師法語録 白隠慧鶴著」が「森江書店」から刊行される。 pid/1913708
|
白隱禪師年譜 / 1
坐禪和讃 / 12
夜船閑話 / 13 |
遠羅天釜 / 33
辻談義 / 147
施行歌 / 158 |
寢惚の眼覺 / 161
おたふく女郞粉引歌 / 168
安心ほこりたヽ記 / 178 |
大道ちよほくれ / 183
主心お婆々粉引歌 / 188
・ |
○、この年、白隠慧鶴著「※白隠墨蹟」が「斎藤赫夫(出版社)」から刊行される。 所蔵熊本県立図書館
※細川侯爵家蔵版本とは内容未確認 2022・12・24 保坂 |
| 1923 |
12 |
・ |
2月、竹田黙雷述「禅室茶談」が「中外出版」 が刊行される。 (中外叢書 ; 第1編) pid/976892 閲覧可能
|
ぶち壞し/1
一緒にグラグラ/1
佛教も嘘じや/2
釋迦も阿難も/3
經典/4
褌に三世諸佛の名/5
座具を縫ひつけた/6
佛を燒いて股あぶり/7
地藏に小便/8
凝りすぎちやイカン/9
知音どのなら/10
滴水滴凍/11
徹底/12 |
實行/12
牛の睾丸/13
四十七士/14
穩座す八疊敷/14
清水坂で/15
わしのお國は/16
精底一片/17
女に對する/18
白隱和尚/19
白隱と法華經/25
水は流るる/26
おさつ婆々/27
雪の肌へが/31 |
くれつけたか/32
殺せ殺せ/33
今死にやれ/35
一遍上人/37
偶像破壞/38
念佛と題目/41
お師家の大散財/41
五百羅漢が退散/42
涙が珠になる/43
庵原の清四郎/43
調子を合はす/46
茶禮/47
聖胎長養/49 |
仙人になりそくなつた男/54
黒衣同盟/62
玉日姫は醜婦/63
どうせんでも/64
頭から呑んじやつた/64
菩提評議/65
骨も殘さんじやつた/66
眞ツ先に振り切る/67
行誡さん/68
眞ツ裸で會見/68
目出度い歌/69
世間の順/70
雲門を憶ふ/70 |
4月、「六大新報 (1008)」が「六大新報社」から刊行される。 pid/7941936
|
農村敎化と寺院/p1~1
京都だより / 虚空洞/p2~2
世界思潮と日本の現状 / 長瀨鳳輔/p3~5 |
印度の福神 / 喜田貞吉/p8~9
文化と佛敎 / 片瀨仁貫/p5~8
太子像と大師の奇蹟 / 大野開藏/p9~12 |
内外彙報 公人私人/p13~15
・
・ |
7月、「雄弁 14(7);7月特大號 」が「大日本雄弁会講談社」から刊行される。 pid/11006734
|
『あゝさうか』(傑僧白隱の逸話)/伊藤銀月/270~276
西行天龍川の難/富士五郞/287~287 |
〈抜粋〉
・ |
9月、「名品綜覧 : 東洋芸術 第1集 第7編」が「美術資料刊行会」から刊行される。 pid/970515 閲覧可能
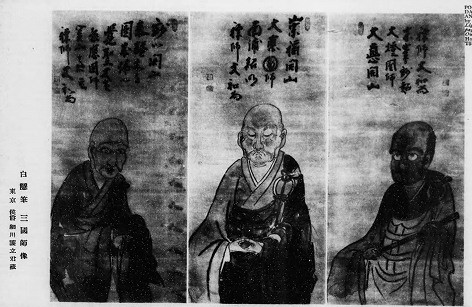
(関山?)考察中:保坂 宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)大燈国師 南浦紹明(なんぽしょうみょう)大応国師
|
樹下美人圖 二葉 京都 西本願寺舊藏
孔雀明王像 大和 法隆寺藏
藤原隆信筆僧文覺像 山城 神護寺藏
餓鬼草紙 七葉 備前 曹源寺藏
傳藤原信實筆歌仙切 東京 東京帝室博物館藏
諾矩羅尊者像 米國 ボストン美術館藏
山水圖 四葉 京都 高桐院藏
牡丹圖 二葉 京都 高桐院藏 |
妙澤筆不動明王圖 二葉 東京 東京帝室博物館藏
雪村筆花鳥圖 二葉 東京 東京美術學校藏
長谷川等伯筆松林屏風 二葉 東京 子爵福岡秀猪君藏
風俗圖屏風 二葉 米國 ボストン美術館藏
尾形宗謙筆住吉明神像 東京 東京美術學校藏
郎世寧筆桃花喜鵲圖 東京 田中慶太郎君藏
白隱筆三國師像 東京 侯爵細川護立君藏
・ |
〇この年、藤森成吉が「大地の匂ひ」を「人文社」から刊行する。 (自然を対象として ; 第1編) pid/977487
|
小品二點/1
春
若き人
花/9
北海道の樹/13
狩太の農場/28 |
行啓/46
宮島の月夜/54
海岸雜景/62
秋田の旅/71
思郷雜筆/74
昔こひしや/80
|
向日葵の花/84
桐の實/86
青春萬歳/90
メモランダム/95
一、 故郷十二篇
二、 對話四篇 |
雨/124
月/128
表現派の映畫/134
戀愛の考察/140
白隱の書畫/152
・ |
〇この年、小杉未醒が「画人行旅」を「アルス」から刊行する。 pid/971739
|
行旅篇
水國雜信/3
平泉誌/24
奧羽道中記/37
南下野の夏/71
庚申山記/78
琉球回想/86
蕉窓夜話/92
中華傳信録/97
唐土雜感/144
|
畫人三題/155
かみ方見物の案内/161
高野山の一挿話/168
濱寺日記/170
泛内海行/175
十津川日記/179
旅の歌ども/190
故郷篇
創世記の一節/209
老樵志異/212
|
華嚴瀑讃嘆/214
山村漫筆/219
曉山感傷/225
家居篇
田端/231
問に答ふ/236
禽獸草木/237
鳩/245
〔ニワトリ〕の決鬪/249
苑中の婦人/252
|
白隱和尚の繪事/261
壁畫/266
竪長の繪横長の繪/272
秋の美術期の前に/279
和漢比較漫録/305
連勺/314
諸國夜話/320
古支那人の言葉/356
・
・ |
|
| 1924 |
13 |
・ |
9月、東秀雄が「物いはぬ仏たち」を「貝葉書院」から刊行する。 pid/969712
閲覧可能
|
一 榮西禪師の我觀/1
二 逹磨幼時の至上寳/6
三 正受老人の一日觀/8
四 道元禪師の不思量底/12
五 雲在青霄水在瓶/14
六 大燈國師の提唱/22
七 仙崖和尚の遺偈/39
八 六祖大師の覺境/44
九 澤庵和尚の遊女畫賛/56
一〇 大悲院裡に齋あり/61
一一 西瓜の味は何處から/64
一二 一時の夢の戯むれ/67
一三 穆山禪師の賛歌/73
一四 峨山禪師の眞宗説法/75
一五 藥師如來の後光/79
一六 畫寢してゐた一切經/82
一七 雲居禪師の天狗鑑定/86
一八 「一」の一から「多」の一へ/93
一九 指一本から手一本へ/97
二〇 釋迦無爾世尊の法孫/101 |
二一 如何ぞ是れ百姓の久四郎/106
二二 廬山は煙雨浙江は潮/109
二三 迷悟の二つ皆牢門/112
二四 俺の提唱には粕はない/113
二五 磐珪和尚の對機説法/115
二六 心越禪師の棒喝/118
二七 澤庵和尚と稻葉濃州/120
二八 〔イ〕山禪師の老〔メス〕牛/124
二九 偉大すぎる歴史の誇/128
三〇 閑庭草木裏の佛法/132
三一 唯佛與佛知見の世界/136
三二 良雪和尚と大石良雄/139
三三 峨山禪師と山縣公爵/141
三四 藤原藤房の覺境/142
三五 道林禪師と白樂天/151
三六 勝敗は自己の内にある/155
三七 西郷隆盛と吉井友實/156
三八 咄忠君愛國の一手販賣屋/159
三九 後からつけた名まへ/160
四〇 誠拙禪師の無茶苦茶/165 |
四一 悟由禪師と春畝公爵/170
四二 絲屋の娘と拙道和尚/172
四三 おめでたい六字の句/180
四四 野狐鳴落す西山の月/181
四五 一休和尚の極樂法話/184
四六 楚俊禪師と楠正成/185
四七 和尚は竟に我黨の士/189
四八 珍重す大元三尺の劍/190
四九 白隱禪師の無辯明/192
五〇 一休和尚の空馳走/198
五一 此善男子を産まんが爲/200
五二 土人形を繋ぐが如し/202
五三 傘下杖頭の天地/203
五四 表現より含蓄への歩み/204
五五 自殺殺他の兇賊/208
五六 石水和尚と伊達安藝/212
五七 默仙禪師の駄洒落/215
五八 理屈をいふ者を逐へ/216
五九 臨濟禪師の垂示/218
六〇 佛光國師と北條時宗/222 |
11月、白井輝一良が「神仙道・土台記憶法・身心強健法」を「修真会」から刊行する。 pid/921291 閲覧可能
|
神仙道
神仙の存在
第一章 仙道と仙術/3
第二章 仙術の不思議/5
第三章 古今の仙人/8
第四章 修道の階梯/12
第五章 發心より仙道成就迄/28
第六章 參考資料/31?66
身心強健法
第一章 身心の健康/1
|
第二章 身体強健法/4
第三章 息法の効用/10
第四章 心識の修養法/13
第五章 佛家の身心修養法/14
第六章 仙家の身心修養法/37
第七章 古今の身心修養法/47
第八章 數息觀と内觀法/81
第九章 白隱禪師の『遠羅天釜』/109~205
土臺記憶法
緒言
|
第一章 記憶とは何ぞ/3
第二章 記憶を増進せしむる方法/6
第三章 記憶法の原理/9
第四章 記憶法の骨体/12
第五章 記憶法の方法/15
第六章 記憶法の要点/24
第七章 永續記憶法/25
第八章 記憶法の缺点と其の保護法/27
第九章 他山の石/28
第十章 結論/42 |
|
| 1925 |
14 |
・ |
○、この年、村田太平編「修養朗唱集 : 国民必携」が「使命社」から刊行される。 pid/915566
|
一、 皇國の使命 / 1
1、 天祖神勅 / 2
2、 神武天皇ノ大詔 / 5
3、 億兆安撫國威宣布ノ御辰翰/7
4、 五箇條ノ御誓文 / 10
5、 軍隊勅諭 / 11
6、 市町村制發布ノ際ノ御上諭/12
7、 憲法發布ノ御詔勅 / 13
8、 教育ニ關スル勅語 / 16
9、 戊申詔書 / 18
10、 國民精神作興詔書 / 20
11、 青年團ニ賜ヒシ令旨 / 23
12、 祈年祭祝詞 / 24
二、 明治天皇御製百首 / 27
1、 大御心(十首) / 28
2、 我が國體(十首) / 29
3、 敬神崇祖(十首) / 30
4、 御仁愛(十首) / 31
5、 日本の使命(五首) / 32
6、 御誠心(五首) / 33
7、 御精勵(十首) / 34
8、 大和魂(五首) / 35
9、 修學習業(五首) / 36
10、 御養老(五首) / 36
11、 御修省(十首) / 37
12、 御堅志(十首) / 38
13、 雪月花(五首) / 40
三、 昭憲皇太后御歌百首 / 41
1、 聖の御代(五首) / 42
2、 臣の忠節(五首) / 42
3、 尊き御國(五首) / 43
4、 玉串とりて(五首) / 44
5、 日本の使命(十首) / 44
6、 おほみなさけ(十首) / 46
7、 玉のひかり(十首) / 47
8、 御貞節(五首) / 48 |
9、 御謙徳(五首) / 49
10、 御確志(五首) / 49
11、 正しき道(十首) / 50
12、 まなびの道(五首) / 51
13、 民のなりはひ(五首) / 52
14、 ふるさとの花(十首) / 53
15、 花鳥の御興(五首) / 54
四、 修養百人一首 / 55
上、 國家的なる歌(三十三首) / 57
中、 社會的なる歌(三十三首) / 60
下、 個人的なる歌(三十四首) / 64
五、 興國雜纂 / 69
1、 繰返し歌(二十三首) / 70
2、 禁酒の歌(二十七首) / 73
3、 家庭川柳(十四句) / 76
六、 名家詩選正大録 / 77
1、 正氣之歌 藤田東湖 / 78
2、 幾度か辛酸を經て 西郷隆盛 / 85
3、 出郷之作 佐野作之助 / 86
4、 三度死を決して 藤田東湖 / 86
5、 妻は病床に臥し 梅田雲濱 / 88
6、 辭世 吉田松陰 / 89
7、 一穗の寒燈 木戸孝允 / 89
8、 題烏江廟 李太白 / 91
9、 謗者任汝謗 佐久間象山 / 91
10、 三典歌賦 作間久吉 / 92
11、 雙殉行 竹添進一郎 / 93
12、 絶命之詞 國分新太郎 / 96
13、 獄中之作 橋本左内 / 96
14、 棄兒之歌 雲井龍雄 / 97
15、 生子當如玉 河野鐵兜 / 98
16、 貧交行 杜甫 / 98
17、 才子事を過る 西郷隆盛 / 99
18、 進歩難し 中村正直 / 99
19、 正氣之歌 廣瀬武夫 / 100
20、 中庸 元田永孚 / 102 |
21、 才子才を恃む 木戸孝允 / 102
22、 忍 中江藤樹 / 103
23、 少年老い易し 朱熹 / 103
24、 大器晩成 範質 / 104
25、 見性 白隱禪師 / 104
26、 啾々吟 王陽明 / 105
27、 死不畏死 雲井龍雄 / 109
28、 富士山 乃木大將 / 109
七、 國民的新詩抄 / 111
1、 乃木將軍 森鴎外 / 112
2、 空は青雲 北原白秋 / 117
3、 勞働雜詠 島崎藤村 / 121
4、 座禪和讃 白隱禪師 / 127
5、 お祭 北原白秋 / 130
6、 富嶽の歌 土井晩翠 / 137
7、 旗手 大町桂月 / 140
8、 善人同盟歌 使命社主幹 / 147
八、 愛吟俳句集 / 153
1、 一系の天子 十五句 / 154
2、 一月 同 / 155
3、 二月 同 / 157
4、 三月 同 / 159
5、 四月 同 / 160
6、 五月 同 / 162
7、 六月 同 / 164
8、 七月 同 / 166
9、 八月 同 / 167
10、 九月 同 / 169
11、 十月 同 / 171
12、 十一月 同 / 172
13、 十二月 同 / 174
14、 恩愛 同 / 176
15、 同情 同 / 178
16、 修養 同 / 179
・
・ |
○、この年、鷲尾順敬編「国文東方仏教叢書 歌頌部」が「国文東方仏教叢書刊行会」から刊行される。
pid/1913678
|
佛足石歌 一卷 / 1
發心和歌集 一卷 選子内親王 / 15
法門百首 一卷 寂然 / 29
唯心房集 一卷 寂然 / 79
極樂願往生歌 一卷 西念 / 91
詠法華經百首和歌 一卷 慈圓 / 101
法隆寺寳物和歌 一卷 定圓 / 125
詠法華經唯識論和歌 一卷 / 135
金剛三昧院奉納短册 一卷 / 149
經旨和歌百首 一卷 / 171
法華經和歌百首 一卷 / 189
釋敎三十六人歌仙 一卷 榮海 / 207
法然上人和歌集 一卷 / 217
傘松道詠集 一卷 / 225
佛國國師和歌集 正覺國師和歌集 合一册 / 235
蓮如上人和歌集 一卷 / 261
山姥五十首 一卷 澤菴 / 277
勸心詠歌 一卷 無能 / 285 |
天桂和尚詠歌 一卷 / 293
蓮葉和歌集 一卷 大我 / 303
道歌二十一首 一卷 東嶺 / 343
慈雲尊者和歌集 一卷 / 347
言葉の末 一卷 / 401
碧巖百葛藤 一卷 巨海 / 433
釋敎百首 一卷 行誡 / 453
長松敎歌百首 一卷 日扇 / 471
和讃二十五題 一卷 / 481
極樂國彌陀和讃 千觀
二十五菩薩和讃 源信
來迎和讃 同
彌陀如來和讃 覺超
迎接和讃 永觀
觀音和讃 貞慶
述懷和讃 親鸞
法華和讃 日蓮
別願和讃 一遍 |
眞言安心和讃 叡尊
淨土門和讃 頓阿
往生和讃 他阿 /
末法和讃 蓮阿
掌中和讃
舍利和讃 /
同
天台大師和讃 源信
聖德太子和讃 思圓
役行者和讃
行基菩薩和讃
智證大師和讃 藤原通憲
慈惠大師和讃
空也聖人和讃
坐禪和讃 白隱
懺悔和讃 學信
・
・ |
|
| 1926 |
15 |
・ |
5月、 白隠と夜船閑話 野村瑞城 著 日本心霊学会 1926pid/935736/1/1 閲覧可能
|
第一章 白隱の一生と爲人/1
一、 緖説/1
二、 白隱の少年時代/4
三、 「禪關策進」の剌戟/8
四、 正受老漢瞋拳下の修業/12
五、 病難と其の治癒以後/17
六、 博大なる識見と業績/22
七、 五百年間出の偉人/24
第二章 『夜船閑話』の本文と譯註/25
一、 序文と其の意味/26
二、 本文と其の意味/47
第三章 其現代的批判/103
一、 宗敎と醫術は一元/103 |
二、 靜坐呼吸内觀の生理/108
三、 靜坐呼吸内觀の心理/116
四、 内觀と生命の實感/126
五、 民衆的敎化と獨特の健康法/130
六、 「夜船閑話」私考/135
第四章 白隱の逸話/144
一、 池田侯と白隱の無慾/144
二、 近衞關白とお淸と白隱/145
三、 嬰兒を抱き乍ら托鉢/147
四、 淸四郎と悟りの影法師/148
五、 今死ね今殺して了へ/149
六、 白隱の書と畫/150
七、 珍重すべきは德にあり/153 |
八、 日常觸目の活問題/155
九、 意表に出た化導方便/157
十、 隻手の妙聲を聽け/158
十一、 白隱を繞れる女性/160
第五章 白隱前後の内觀丹田説/164
一、 員原益軒の養生訓/164
二、 佚齋樗山の收氣術/171
三、 白井鳩州の赫氣術/174
四、 平田篤胤の氣海丹田説/176
五、 平野元良の撫摩禪帶法/184
六、 結論/189
・
・ |
9月、谷至道が「禅により心身を錬磨せる英雄」を「中央出版社」から刊行する。 pid/1018877 閲覧可能
|
一 禪宗の起源 / 1
二 上杉謙信の開悟 / 3
三 武田信玄の禪 / 13
四 坐禪の要 / 19
五 無三禪師と南洲 / 22
六 油斷大敵 / 27
七 北條泰時と道隆 / 29
八 北條時頼漆桶を脱す / 33
九 蒙古襲來と時宗の座禪 / 42
十 足利尊氏と無窓國師 / 53
十一 大田道灌と禪 / 61
十二 生死透脱 / 72
十三 伊達政宗の信念 / 86
十四 宮本武藏の參禪と劒法 / 90
十五 武士道と禪 / 102
十六 山岡鐵舟 / 116
十七 一矢を貫かんと豁然大悟 / 134
十八 坐禪と無我と慈悲 / 146
十九 井伊直弼 / 154
二十 坐禪の目的 / 165
二十一 伊達宗重の大悟 / 172
二十二 柳生但馬守の劍禪一致 / 178
|
二十三 齋藤道三の最後と禪味 / 188
二十四 山内一豊の參禪悟道 / 192
二十五 大内義隆と玉堂和尚 / 196
二十六 信長と松野一忠 / 201
二十七 白隱禪師の教旨 / 206
二十八 劍聖上泉伊勢守 / 217
二十九 卜傳の無手勝流 / 219
三十 奥村助右衞門 / 224
三十一 山鹿素行の參禪 / 229
三十二 禪の人鈴木正三 / 233
三十三 勝海舟 / 249
三十四 河村瑞賢 / 256
三十五 猫の妙術 / 260
三十六 劒禪一味 / 284
三十七 高橋泥舟 / 290
三十八 關山國師と藤原藤房 / 294
三十九 東嶺禪師の武士教訓 / 298
四十 浩然の氣 / 301
四十一 劍句禪句 / 308
四十二 精妙の禪 / 310
四十三 清廉高潔と武士道 / 314
四十四 寧一山禪師と北條貞時 / 322
|
四十五 一休禪師と蜷川親當 / 325
四十六 坐禪看話 / 330
四十七 劒と冥想 / 247
四十八 禪の痼疾 / 349
四十九 禪僧眞壁平四郎 / 369
五十 前田利家の參禪 / 375
五十一 實朝の修養 / 377
五十二 英雄たるの資格 / 379
五十三 藤原資朝と源俊基 / 392
五十四 光秀の禪味 / 394
五十五 力士大浪の禪 / 396
五十六 生死岸頭 / 408
五十七 大西郷の遺訓 / 414
五十八 源具行 / 418
五十九 生死透脱 / 419
六十 田能村竹田の畫禪 / 431
六十一 參禪より悟入までの徑路 / 434
六十二 史上英傑と禪 / 463
六十三 菊池武重及一門と大智禪師 / 466
・
・
・ |
○、この年、釈道円が「禅林逸話集」を「聖山閣書店」から刊行する。 pid/1018704 閲覧可能
|
拈華微笑/1
面壁九年/5
二祖斷臂/7
誰か汝を□す/8
風が動くか幡が動くか/10
青原和尚米の値をきく/11
佛樣なら疾くに死んだ/12
藥山禪師の無言の説法/14
遲刻の僧を小突き廻す/15
豚肉屋店頭の禪/17
一日作さずんば一日喰はず/18
〔イ〕山禪師の活機用/19
〔イ〕山和尚と鐵磨尼/25
大いに悟る者大に迷ふ/26
撃竹一聲に大悟す/28
天然禪師木佛を燒く/29
通身是れ手と眼/31
淡々として浮雲の如し/33
飯を食ふ珍石/35
是といふは是ち不是/36
南泉斬猫/38
趙州の石橋/40
大道長安に通ず/42
胸中大火/43
活殺自在の拳/45
台山婆子と趙州/46
捨て得ずんば擔いで行け/48
宇宙大の笠/49
臨濟打爺の拳/50
無爲の眞人とは是れ糞つ掻き/57
臨濟遷化と慧然禪師の一喝/58
徳山和尚茶店の婆子に參る/60
徳山和尚の大悟/63
獅子兒に馬乘り/65
巖頭和尚と徳山和尚の相見/66
志閑禪師了然尼に伏す/68
一粒の米/71
歸省禪師の峻嚴/73
法遠和尚油麺を竊む/75
翠巖の眉毛ありや/78
雲門禪師の隻脚/81
南山に雲を起せば北山に雨を下す/83
一路涅槃門何處にありや/84
仲興和尚師を擲る/86
慈明禪師と方會禪師/89
滿牀盡く撒ず雪の珍珠/94
法演禪師墮落を裝ふ/95
悟つても皆吐き出す/99
田を種え畑を耕す是れ禪/100
飛んだ清少納言/102 |
玄則禪師の大悟/103
露柱兒を生む/106
お經讀みのお經知らず/108
榮西禪師と道元禪師/110
道元禪師の入宋求法/112
師の阿聲を聞いて大悟す/115
孤雲禪師母の臨終を顧ず/117
寄進に驚喜して破門さる/120
紫衣の一老翁/122
佛光國師と北條時宗/124
瑩山禪師の大悟/127
大智禪師の禪機/129
居ながらにして舟を止める/131
坐禪せば四條五條の橋の上/133
太田道灌鐘聲に開悟す/134
心頭を滅却すれば火も亦凉し/136
一休禪師閉口まさる/137
十萬億土への道順/140
こいつが法は天下一/143
馬の繪に賛して曰く/144
一休和尚と一路居士/145
澤庵和尚の氣合/146
火事と聞いて高鼾/148
磐珪和尚の慈悲/149
一寸癇癪を起して見せろ/151
心越和尚の魂膽/152
良雪和尚と大石良雄/153
乞食桃水/155
醤油は土用に味噌は寒中に/157
正受老漢と白隱和尚/159
白隱禪師の望み/161
父無し兒を禪師に押しつく/162
阿三婆さんの見識/164
阿さつ婆さんの悟道/165
小僧の誠拙伊達侯を打つ/169
誠拙和尚寄附金の禮を言はず/170
顎長の長四郎/172
良寛和尚の自適生活/182
子共に置いてきぼり/184
虱に相撲を取らせる/187
蛆は逃げる故食ふを妨げず/188
無言の意見/189
鼻糞の丸藥/190
念佛を唱へて茶を呑む/191
月下に酒を忘却す/192
金を拾ふ樂しみ/194
良寛和尚の硬修行/195
拳骨和尚物外/197
老齡猶怪力衰へず/200
一拳門柱を凹ます/202
|
物外和尚の臨終の式/204
巨石二個の振分け荷物/206
物外和尚の風懷/209
近藤勇を木椀であしらふ/213
無三和尚の大喝/218
泥中の蓮華/220
うぬが力で動くものかは/221
大般若經の功徳/223
木堂和尚青樓に泊る/225
仙崖和尚踏臺になる/228
滿艦飾の老禪師/229
大鼓の音を繪に描く/232
仙崖和尚の畫賛/234
西郷南洲の剛膽/236
桐野利秋の情歌/238
時計持ちでなく鎖持ち/239
五尺の體を先ず捨てよ/240
活きた佛法の殺生戒/241
袈裟や衣は何でもよし/243
内閣を明け渡せ/244
突貰に如くものなし/245
大死一番せよ/247
悟りの押賣りか馬方坊主か/248
大自然の心を心とせよ/249
庵を燒き拂つて仕舞へ/250
飮んで一升に至れば/251
大含和尚賊を驚かす/253
眞淨和尚と井上侯/255
聞いて百文見て一文/256
天海禪師の訓誡/258
下駄の緒と玉の緒/260
天海禪師の識見/261
森田悟由師母堂の訓誡/262
敬冲和尚火災を悦ぶ/263
知事なんぞに用はない/264
坊主は無用の長物か/265
原坦山師の一掌/266
讀書には赤痢が一番/267
默仙禪師の巧妙なる説法/268
坊主なりやこそケガ無い/271
滴水和尚の活溌/272
竹田默雷師活きた逹磨を求む/274
橋本獨山師の珍公案/275
解らぬから聽きに來る/276
管長なんぞに爲るものでなし/277
一指頭の禪を眞似る小僧/278
極樂へ豆腐買ひ/280
夫婦喧嘩仲裁の禪機/282
・
・ |
|
| 1927 |
昭和2年 |
・ |
3月、「富留鏡 (6) 」が「古鏡社」から刊行される。 pid/1553825
|
卷物切――第一 / 後字多天皇宸/p1~3
了佐切――第二 / 五條三位俊成卿/p4~5
墨流切――第三 / 六條大藏卿有家鄕/p6~7
卷物切――第四 / 俊乘防重源/p8~9
墨蹟――第五 / 大燈國師/p10~11
墨蹟――第六 / 古嶽和尚/p12~13
二大字――第七 / 大林和尚/p14~15
消息――第八 / 大林和尚/p16~16
偈――第九 / 大林和尚/p17~17
勅書――第十 / 後陽成天皇宸/p18~19
佛祖正傳宗派――第十一 / 一凍和尚/p20~20
偈――第十二 / 一凍和尚/p21~21
|
布袋經業畫賛――第十三 / 白隱禪師/p23~24
一行書――第十四 / 白隱禪師/p25~25
金光明最勝王經圖―第十五/
→月心律師/p26~27
三大字―第十六/天祐和尚/p28~29
三大字―第十七 / 江雪和尚/p30~31
三大字―第十八 / 江雪和尚/p32~32
二大字―第十九 / 江雪和尚/p33~33
三大字―第二十 / 江雲和尚/p34~35
四大字―第二十一 / 江雲和尚/p36~36
三大字―第二十二 / 玉舟和尚/p37~37
甘露門寫眞―第二十三/p38~38
|
名印―第二十四 / 僊溪和尚/p39~39
三大字―第二十五 / 僊溪和尚/p40~40
二大字―第二十六 / 僊溪和尚/p41~41
三大字――第二十七 / 天室和尚/p42~43
坐雲亭寫眞――第二十八/p44~44
額――第二十九 / 江雪和尚/p45~45
坐雲亭腰掛透彫――第三十/p46~46
四大字――第三十一 / 淸巖和尚/p47~47
三大字――第三十二 / 實堂和尚/p48~49
三大字――第三十三 / 乾英和尚/p50~51
三大字――第三十四 / 傳外和尚/p52~53
茶道の源流――第三十五/p54~55 |
○、この年、亀川教信が「仏教の霊魂観」を「興教書院」から刊行する。 pid/1225705
|
第一章 靈魂觀念の發生と宗敎意識/3
死の驚異
存在と價値の問題
欲望よりの發足とその純化統一
死の解決
夢中の經驗と妄想の現象
靈魂觀念の變遷とその種々相
祖先崇拜と靈魂觀念
神話傳説中にあらはれたる靈魂觀念
宗敎信念の一内容としての靈魂觀念
宗敎の進歩と靈魂觀念の論理的進化
個體靈魂の信仰と神佛の信仰
靈魂不滅の念慮
第二章 古代印度に於ける靈魂論/34
古代印度の思想史とその哲學宗敎の
→中心問題
吠陀の生命觀
梵書時代の輪廻思想
哲學勃興時代の靈魂觀
經書時代諸派哲學の思想的相互影響
佛敎靈魂論の基礎
第三章 佛敎靈魂説の意義/58
萬象の目的論的説明
個體靈魂説の自家撞着
實踐的方面より見たる迷と悟
流轉と解説の根據
佛敎が無靈魂説と云はるゝ所以
第四章 無我の論點とその批判/76
神佛の解釋法
我執の脱却
因縁觀と無我説
根本佛典に説く我の吟味
|
犢子部の補特伽羅説並にその非難と會通
經量部の種子熏習説
有部の五蘊分柝論
縁起過程としての十二因縁觀
中道實相に即する無我觀
第五章 業の意義とその本質/114
羯磨とは何ぞ
超越的一神論に對抗の蜂火
業思想の明示せられし
→原始論部並にその系統
業の得名
業の本體
思に就て
表・無表業の意義
表・無表業に關する有部と經部との論諍點
無明縁起
第六章 業道の成立/147
因縁法としての苦感
人生觀に即する世界觀
心理的基礎に立つ業道の成立
實踐的宗敎的業道の成立
迷界流轉相としての十二因縁觀
十二縁起觀の解釋法に就て
縁起系列の首班に關する説明と批判
共業と不共業
引業と滿業
佛敎に於ける平等觀と差別觀
業道成立の時期
業の作者に就て
第七章 輪廻論と中有の思想/207
輪廻の主體に關する疑問
諸法無我の意義
|
隔生即忘の論理
釋尊の平等主義
無我説と輪廻の矛盾並にその解決
中有説の起源
原始佛敎徒の中有存在に就ての論議
中有の名稱・存在期間並にその形相
幽靈について
第八章 因果の法則/250
現象生起必然の理由
道德的因果論と哲學的・宗敎的因果論
佛敎因果の種別
六因
四縁
五果
至聖境への旅立ち
彌陀救濟敎に於ける因果法則成立の可能性
懺悔に就て
第九章 業と自由意志/289
業道の進展と宿命的決定論
運命論の意義
業道論に於ける道德批判の可能性
現在より未來への離繋
思の活動性と識の自由性
因縁和合説に於ける意志自由の根據
淨土他力門に於ける業力の取扱方
第十章 佛敎靈魂の批判/318
佛敎の哲學的特徴
佛敎靈魂論の合理的説明
靈魂に對する中觀系と瑜伽系との歸着點
業道に對する心理學・倫理學並に
→哲學上よりの批判
業道實義の發揚 |
○、この年、倉地円照編「禅の面目」が「万松会」から刊行される。 pid/1175140
|
雪江和尚相撲禪 寒松軒 今井福山 / 1
佛心 金閣寺主 伊藤敬宗 / 20
私の崇拜する澤庵和尚 宮内省圖書寮御用掛 猪熊信男 / 27
關山國師と其弟子 相國寺派管長 橋本獨山 / 34
栢堂和尚に就いて 靈雲院主 西山宗徹 / 37
物安餘滴 理學博士 近重眞澄 / 40
禪家に於ける食事法 東福寺派管長 尾關本孝 / 57
白隱と其時代 龍安寺主 大崎龍淵 / 65
泣も可なり笑ふも亦可なり 東洋大學敎授 加藤咄堂 / 74
禪の本質 春光院主 川上孤山 / 78
作務の宗敎 臨大監事 神間政進 / 82
無難禪師に就いて 選佛寺主 梶浦逸外 / 90
豪僧南天棒を想ふ 牧師 金子白夢 / 116
左邊底茶話 建仁寺派管長 竹田默雷 / 121
喫茶去 日本茶道學會長 田中仙樵 / 152
無住國師の統一思想 永興寺貫主 村上素道 / 159
法輪とは何ぞや 立命大學敎授 野々村直太郞 / 172
東嶺和尚と遂翁禪師 萬松會主幹 倉地圓照 / 186
虚堂智愚禪師 相國僧堂師家 山崎大耕 / 196
儀山和尚の印象 大德寺派管長 圓山要宗 / 202
瞋頭に角を載く 方廣寺派前管長 間宮英宗 / 207
炎梅雪蕉録 妙與禪林學長 松岡寬慶 / 217
東西兩洋人の見方と考方 文學博士 松本文三郞 / 230
誌公の禪風 妙心寺派宗會議長 後藤亮一 / 239
奇傑僧仙厓和尚の話 正法輪主筆 後藤光村 / 249
|
心 圓福寺僧堂師家 神月徹宗 / 277
心の奧底を極めよ 臨濟大學々長 古仲鳳洲 / 282
碧層夜話 妙心寺派管長 五葉愚溪 / 285
禪的生活 白華山主 虎溪文快 / 296
一休和尚と人間 妙心寺派布敎師 小村浩英 / 302
白隱禪師の一偈 隨〔オウ〕寺主 江西白牛 / 308
信字の解 臨大敎授 寺西乾山 / 312
印度の坐禪法 帝大敎授 手島文倉 / 314
精進に就いて ドクトルヲブヒロソフイ 天岫接三 / 321
愚堂國師と大愚禪師 聖澤庵主 蘆明道 / 330
禪道佛法の今昔 永平寺貫主 北野元峰 / 344
良寬和尚のこと 妙心寺派布敎使 岐津大拙 / 356
隱れたる一絲和尚の禪風 法常寺主 宮裡祖泰 / 363
一念子の看破 大中寺主 釋大眉 / 375
隱山卓洲の禪風 龍泉庵主 釋佛海 / 384
莞應禪師平生の一端 東光山主 柴田慈孝 / 395
坐禪及其目的 臨大敎授 日種讓山 / 400
宗敎の獨立性と禪 臨大敎授 久松眞一 / 414
寂室禪師の緊要一訣 國民新聞記者 森大狂 / 437
晦巖一流の家風 妙心寺派布敎師 森賢外 / 442
倩女離魂 妙心寺派前管長 關蘆山 / 447
一切の佛法は禪に歸す 慧林寺主 棲梧寳嶽 / 463
坐禪 天龍寺派管長 關精拙 / 470
參禪の階梯 建長寺派管長 菅原時保 / 481
貧乏と宗敎 谷大敎授 鈴木大拙 / 492 |
|
| 1928 |
3 |
・ |
5月、日本心霊編輯部編「「病は気から」の新研究」が「人文書院」から刊行される。 pid/1051084 閲覧可能
|
第一篇 人體生理と病理/1
第一章 靈の宿・精神の家/1
見えざる力と生理病理の知識
人體を内外兩部に分けて見る
何故人間は萬物の靈長たるか
細胞の靈動と人間の健不健
器官と十種に分る諸系統
第二章 人體の諸系統/8
第一 骨骼及筋肉
第二 皮膚
第三 消化器
第四 循環器系統
第五 呼吸器系統
第六 神經系統
第七 排泄器系統
第三章 奇蹟はあり得る/64
所謂素人診斷の知識について
知識を得よ而して知識を捨てよ
人體と生命と病氣と壽命と
第二篇 精神作用/70
第一章 精神より身體へ/70
所謂慢性病と心的作用
物質刺戟と精神刺戟の比較
精神作用と筋肉及皮膚の關係
血液の循環及血壓と精神作用
心臟の活動と精神作用
消化機能に對する精神作用
呼吸器に對する精神作用
五官器に對する精神作用
内臟變化と神經的衝動
第二章 内分泌と神經系統/88
新生面を拓いた内分泌説
内分泌腺の種類と作用
性格氣質も之と關係する
所謂精神力とアドレナリン
眞の精神力はホルモン作用にあらず
五十二の精神作用機關説
能率心理と精神的なる疲勞
動物性神經と植物性神經
眞性交感神經と副交感神經
微妙なる副交感神經
第三章 精神現象と副交感神經/105
感情意志の發動と植物性神經 |
醫學は漸次精神治療化すべし
第四章 適應作用と精神作用/109
生存を維持保續する本能
人體の妙機と適應作用
一本のまつ毛一筋の鼻毛にも
抗毒性抗菌性の存在
天は常に公平に人間に接する
一擧手一投足も自然の表現
病理學も企及し得ざる境地の出來事
病緑助緑は眞の病源に非らず
第五章 靈に從ふ衛生/121
強き意志と強き身體
身體の動作と精神療法
形人となり人亦形となる
第三篇 唯心醫學の提唱/125
第一章 暗示の效に就き/125
所謂精神力は觀念力である
福來博士の觀念生物説
觀念力と感覺との一例
催眠術も氣合術も加持祈祷も
臨床催眠術を一例として
暗示の効果は交感神經作用か
所謂暗示は信仰的刺戟である
或變動を生ぜしむべく與へらる觀念
觀念の力は創造する力である
第二章 肺患を例として/143
生理學的眞理と心靈學的眞理
肺病咯血の時に現はれる皮肉
肉體愛護と精神上の自覺
心は患者に治癒機轉を與ふ
肺病と現代醫學の學理的影響
如何なる療養書にも書いてない文字
全快を追廻はしてイては全快せぬ
第三章 一念と信念/156
如何にして心を活動させるか
無我中の觀念運動として
信の必要と私の一經驗
虚弱と病氣は乞食に似たり
第四章 療病の自力と他力/163
物質文明も精神の勝利
精神上に自力と他力あり
表現的他力の加被によりて
意思作用に著しき不思議力 |
感應は非科學的浪漫的にあらず
第五章 眞の精神作興/172
永井博士の唯心醫學論
所謂科學者の精神治療法論
肉體を物質界に置き心を靈界に置く
生命に移るべき生物學へ
汝の精神力を作興せよ
第四篇 病と氣の關係/181
第一章 疾病の眞因は何か/181
現代醫學の疾病分類
多く信ぜられる細胞病理説
生理的よりも倫理的なりとの説
根強く蔓る疾病に對する誤想
自然律に反したる制裁
疾病罪惡觀と所謂清淨療法
佛教の業感と疾病につき
人間の不徳が疾病の因
『病は氣から』の氣から
第二章 先人の氣説と病理學/194
其氣は觀念の雰圍氣にして活力
白隱禪師の所説と氣
貝原益軒の所説と氣
平田篤胤の所説と氣
臟器組織の變化と氣の力
極めて消極的の意味より見るも
氣は積極的に解釋せよ
氣の障と魔のつくといふ事
エネルギーの精神的價値
第三章 養氣説と其方法/208
氣の統整と肉體の考察
所謂養氣の法たる内觀法
□酥〔ナンソ〕の觀法をなすも亦可
觀念活動にも條件がある
慢性疾患者の心と生きる力
第四章 醫學眼で見る氣/217
昔の病理と今の病理の相違
醫學に於ける人間は下等動物
局所を見て中心より遠ざかる
疾病の倫理觀と所謂仁術
猿療治と病者の精神修養
第五章 結論/224
・
・ |
○、この年、野村瑞城が「白隠と遠羅天釜」を「人文書院」から刊行する。 pid/1077474
|
第一章 白隱の苦修と禪機/1
一、 陸離たる巨人の體驗/1
二、 白隱は如何なる人たりしか/6
三、 嶮峻なる門風と意志の尊重/9
四、 念佛禪默照禪の痛撃/12
五、 大慈物に應ずる化導/14
第二章 『遠羅天釜』の結構と内容/19
一、 『夜船閑話』と『遠羅天釜』/19
二、 その上梓と内容について/20
三、 特に讀者に對して一言す/25
第三章 答鍋島攝州侯近侍書の本文と譯註/30
第四章 遠方の病僧に贈りし書の本文と譯註/89 |
第五章 法華宗の老尼の問に
→答ふる書の本文と大意/114
第六章 念佛と公案と優劣如何の問に
→答ふる書の本文と大意/154
附載 客難に答ふ/180
第七章 白隱の健體康心法解説/188
一、 療病養心訓としての『遠羅天釜』/188
二、 病床を修養の道場とせよ/189
三、 白隱の所謂妄想と事實の認識/193
四、 患者の妄念は病氣恐怖心/198
五、 心氣の上昇を引き下げよ/202
六、 心氣と「本來の面目」と活元/205
|
七、 養心氣の方法としての調息/208
八、 坐禪式の呼吸と丹田の充實/213
九、 妄想の征服と數息觀及蘇東坡法/218
十、 正身偃臥法と坐禪及靜坐/223
十一、 調息と延壽禪帶の應用/226
十二、 「觀」及「内觀」について/230
十三、 白隱の教へし内觀法/233
十四、 所謂三昧状態と意志力/240
十五、 斯くして以て體驗せよ/242
第八章 結論/246
・
・ |
○、この年、木村岫三編「白隠禅師とその語録」が「甲子社書房」から刊行される。 pid/1225469
|
第一編 略傳
一 出家 / 5
二 求道 / 11
三 肺病の治療 / 19
四 悟後の修業 / 27
五 晩年の化導 / 35
第二編 法語録
一 夜船閑話 / 49 |
二 遠羅天釜 / 69
一 鍋島攝州侯近侍に答ふる書 / 69
二 遠方の病僧に贈りし書 / 104
三 法華宗の老尼の問に答ふる書 / 117
四 念佛と公案の優劣如何の問に答ふるの書/152
五 客難に答ふ / 173
三 辻談義 / 183
四 寢惚之眼覺 / 195
|
五 おたふく女郞粉引歌 / 203
六 安心ほこりたた記 / 213
七 大道ちよぼくれ / 219
八 主心お婆々粉引歌 / 225
九 施行歌 / 231
一〇 坐禪和讃 / 235
第三編 年譜
・ |
○、この年、釈宗演が「禅の真髄 : 生死解脱心眼開発」を「中央出版社」から刊行する。 pid/1224656 閲覧可能
|
修養處世篇
現代靑年と禪の修養/1
靑年と品性隋落
學生の坐禪法
坐禪の要心
歸家隱坐の消息
下腹に力を入れよ
品性の基礎
白隱和尚の悟道
事に臨み餘裕あり
心力の浪費
任運無功用
言語道斷の神境
世法と佛法/22
治生産業
「サメル」事
慈悲の本體
宗敎的生活
佛敎は若い人に入用
心の目を開く
實踐躬行/38
個人主義
上に立つ人
何の實がある
宗敎學校の弊
道德家でない
一行爲の德
迎合是れ事とす
なさけない有樣
感恩の精神
報恩/46
恩を知るは大悲の本
第一の恩
善業を開くの初門
眞の美人
苦は苦、樂は樂
極所に一線道を求めよ/59
活発々地の活動を要するの秋 |
絶對となれ
物に轉ぜらるな
極所に一線道を發見せよ
生か死かの活問答
自己の心を開發せよ
勇猛の一氣を養成せよ/70
順境と逆境
生命を等閑にするな
修養の必要
心を平靜ならしむる道/75
禪那
坐禪の利益
禪那は精神の蓄電池
無心の活動/80
日々是れ好日
有心と無心
無心の功果
無心と虚心
煩惱即菩提
度胸の得力
生死の透脱
有意義の生活
菩提の靈光/95
欲には善惡の二つあり
制欲するには如何
心は主にして身は從
絶對無差別の境
眞の修養
心の本體を徹見せよ
孟訶/104
「自心を了する」
確乎たる要心
余の坐右銘/113
學問と修養の別
楚人の弓
學問は虚飾に非ず
余の坐右銘
王者の師道/120 |
無相大師の眞面目
五十一才の初行脚
東海の道中に富士を見ず
峭拔峻從なる大師のおもかげ
萬法と侶たらざる者是什麼んぞ
國家の御奉公
人生と宗敎篇
人生と宗敎/141
人生の觀
名利の海に惑溺す
一切の現象は無常なり
人生と意義
禪の人生問題解決/151
生死問題解決
自己の心性を明めよ
南州翁の度胸
水月の境涯
執着を離れよ
宗敎の眞意義/157
「敎」
萬世不易の名言
食はず嫌ひ
佛敎に對する門外漢
維摩居士
剴切の實例
大極は無極
修道之謂敎
禪の敎養篇
坐禪は道德の根源なり/189
本當の佛敎者
體と用
怒るは我儘
禪と自然/196
禪の本領
逹了とは宇宙の眞理
髑髏は二八の美人
禪の自然觀
自然と一體になれ
|
敎外別傳不立文字/211
恁麼の淸淨身
過去の過去より
言語道斷心行所滅
禪と敎/220
敎と禪との由來
敎なる者の梗概
禪の相承
敎と禪と元來二途なし
敎禪の分岐
禪と勤儉/230
簡便の生活
「あるべきやうに」
禪の活用
禪は實行的なり
國師と時宗との問答
悟道篇
大信根/244
一大眞理
禪の効果
悟道/250
禪宗の究竟
禪と直覺
公案
法理と境涯
悟道の妙味
心境一如
禪の目的
眞如
忽然三昧
禪の苦修精勤
拂拳捧喝
哲學者の禪觀
禪、禪、禪
一念の擬議を挾まんや
平等即差別
・
・ |
|
| 1929 |
4 |
・ |
4月、静岡縣教育會編纂「阿倍川賢士傳 : 白隱禪師自筆」が「静岡縣教育會」から刊行される。
伊豆國田方郡北上村龍澤寺蔵
主催者:静岡縣教育會、静岡市教育會、安倍郡教育會
○、この年、人生哲学研究会編「名僧の人生観」が「洛東書院」から刊行される。
|
親鸞
日蓮
空海
西行
|
良寛
白隠
沢庵
一休
|
道元,夢想,一遍
法然
最澄
蓮如 |
○、この年、鷲尾順敬編「国文東方仏教叢書 第2巻第2輯」が「東方書院」から刊行される。 pid/1913622
|
寫眞 無難自筆 人に與ふる法語
同 山分挿繪二河白道圖
對問法語 一卷 實觀/1
成佛の直路 一卷 慈等/19
玉かゞみ 一卷 木食以空/61
對賓法語 一卷 學如/73
|
慈雲和上法語 一卷/127
玲瓏集 一卷 澤菴宗彭/185
祖心尼法語 一卷/209
人に與ふる法語 一卷 至道無難/249
おにあざみ 一卷 白隱慧鶴/267
千里一鞭 一卷 南溪老卵/317
十善戒信受の人に示す法語 一卷 寂室堅光/341
|
扣響集 二卷 鐵牛道機/357
法の道芝 二卷 貞極/419
燧□(ひうちぶくろ)…一卷 關通/489
山分…一卷 月感/535
安心問答…一卷 深勵/563
千代見草…二卷 日遠/571
・ |
5月、白隠著「勧発菩提心偈」が刊行される。 和装本 袋綴 謄写版 所蔵:人間文化研究機構 国文学研究資料館書庫
注記 底本の刊記: 宝暦第十庚辰歳(宝暦10[1760]年10月15日)
注記 「主心お婆々粉引歌」を付す
注記 巻末に「昭和四年五月/梅林十四世無學大和尚三十三回諱/同十五世猷禪大和尚十三階諱/齋會之日某印施」とあり
○、この年、岩谷愛石が「吾等は何の為に生きて居るか : 人生問題の解決」を「愛国青年社」から刊行する。 pid/1107547
|
略
七、 名僧の人生觀
一、 親鸞聖人の人生觀/167
(1) 絶對他力の信仰
(2) 徹頭徹尾信の一字
(3) 宿命物論的人生觀
(4) 人間の力は強い
二、 日連聖人の人生觀/177
(1) 日連聖人と親鸞聖人
(2) 傑僧日連の生涯
(3) 國家的宗教
(4) 奮闘多難の生涯
三、 弘法大師の人生觀/182
(1) 大師の一生
(2) 大師の生活
|
四、 西行法師の人生觀/185
(1) 愛慾の惱み
(2) 出家と戀
五、 白隱禪師の人生觀/190
(1) 禪の妙用
(2) 隻手の聲
六、 澤庵和尚の人生觀/195
(1) 此世の中は夢の如し
七、 一休和尚の人生觀/197
(1) 珍談奇行洒脱の生活
(2) 佛は元來水の如し
八、 即元禪師の人生觀/203
(1) 即身成佛一字不説の宗教
(2) 恰も釋迦の如き修道者
九、 夢想國師の人生觀/209
|
(1) 慈悲も無く方便もなし
(2) 生死の不安も苦しみもなし
一〇、 法然上人の人生觀/211
(1) 念佛宗の開祖
(2) 簡單直明凡夫の宗教
一一、 傳教大師の人生觀/215
(1) 僧侶の榮逹其極に逹す
(2) 我國最初の大師號
(3) 禁慾主義の人生觀
(4) 女人は悪魔の結晶
(5) 一大新宗教の出現
一二、 宗教の腐敗と
→信仰の滅亡/224
八、 神道各派の人生觀
一、 神も佛も同一である/228
|
(1) 兩部神道
(2) 黒住教
(3) 金光教
二、 天理教の人生觀/232
(1) 世界人類を一列に助ける
(2) 出直し立替の宗教
三、 日本神道と神の實在/234
四、 神仰無き生活は不安/236
九、 人生は苦か樂か
一、 慾望の世界に滿足は無い/238
二、 人生の幸福とは何か/240
三、 地位や名譽や財産では無い/242
四、 其精神的愉快とは何か/243
略
・ |
○、この年、福富織部「臍」を「万里閣書房」から刊行される。 pid/10297959
|
へその語源
一 へその意義/1
二 へその異名/3
三 へその種類/5
四 ○○○まつり/8
五 穴の説/9
へその經歴
一 臍の起源/13
二 臍の効用(高田義一郎)/17
臍の愚痴
一 新聞に現はれたへその泪
→(團々珍聞)/20
二 俳人の見たへその泪
→(うづら衣)/20
三 民謠に現はれたへその泪
→(浮れ草)/22
雷とへその關係
一 雷とおへそ/24
二 雷公とその連鼓/27
小咄と笑話
雷の玉子
雷公の災難
臍にかへてつかむ白銀
雷の仲間入
雷
雷のすて子
|
きおひと雷
雷の落ぞこなひ
雷
雷の玉子
雷
頓松と雷
雷への頼状
河童の昇天
雷の文章
西の雷
へその奇跡
二つの臍(キング十四、二)
臍中生五穀罔象(日本書記神代)
女の臍より出し石の話(松屋筆記)
臍中出屎(時還讀我)
創作二篇
臍の悲 正木不如丘/50
へそのない男 佐々木味津三/57
へその川柳/64
へそと俚諺
一 臍を噬むの意/66
臍(小説) 湖山人/67
木下藤吉郎(講談) 錦城齋典山/72
二 臍に徹すの意/90
池田光政公の改心
→(大衆小説) 青海洋三/91
|
三 へそを曲げるの意/115
光秀遂に臍を曲げた
→(講談) 揚名舍桃李/116
四 臍をかためるの意/132
宗五郎のほぞ(講談) 寶井琴窓/133
五 臍をすゑるの意/166
羽生郷右衛門(隨筆) 福本日南/167
六 へそ刮りの意/172
臍繰り(滑稽小説) 寺尾幸夫/174
七 臍で茶を沸すの意/195
臍茶六束
五右衞門風呂/201
彌次北江尻で馬士との問答/206
丸子の宿の夫婦喧嘩/208
江戸ツ子八百屋と
→上方のけち助/210
盲人と醉漢/218
漢學者氣質/223
臍の教訓
臍だ! 佐藤紅緑/229
臍隱居 驚光 堵庵/235
氣を臍下に練る法 平田篤胤/243
へその俳句/248
落雷の圖 英泉畫/249
昭和の黄表紙臍茶沸兵衛旅日記
→倉島たんろう作/250
|
臍 渡邊默禪/311
滑稽諷刺のおへそ/349
阿呆陀羅經(目覺めよ國民)
新版阿呆陀羅經(東京名物)
臍陀羅經
煩悶
白隱禪師の歌
道外物語の序
届書
楊弓
磊々問答
刮々坊主の話
臍の功徳
臍穴守禪師におくることば
女房
おへその茶
各地の方言
家庭スケツチ
雷公重箱
囓臍
臍の讃美
花車 村上浪六/367
臍の頌 横井也有/369
臍の力 佐藤紅緑/371
・
・ |
○、この年、昭和新纂国訳大蔵経編輯部編「昭和新纂国訳大蔵経 宗典部 第六卷 臨濟宗聖典」が 「東方書院」から刊行される。 pid/3434836
|
鎭州臨濟慧照禪師語録/1
碧巖録/49 |
無門關/171
希叟和尚五家正宗贊/207 |
興禪護國論/401
白隱禪師息耕録開筵普説/469 |
黄檗和尚太和集/539
・ |
|
| 1930 |
5 |
・ |
9月、国訳禅学大成編輯所編 「国訳禅学大成 第20巻」が「二松堂書店」から刊行される。 pid/1120192 閲覧可能
|
國譯佛光圓滿常照國師語録解題/1~5
國譯佛光圓滿常照國師語録/1~207
佛光圓滿常照國師語録原文/1~118 |
國譯五家參詳要路門解題/1~4
國譯五家參詳要路門序/1~5
國譯五家參詳要路門/1~58 |
五家參詳要路門原文/1~35
・
・ |
10月、国訳禅学大成編輯所編 「国訳禅学大成 第22巻」が「二松堂書店」から刊行される。 pid/1920780 閲覧可能
|
國譯大燈國師語録解題/1
國譯大燈國師語録/1
大燈國師語録原文/1 |
國譯白隱禪師息耕録開筵普説解題/1
國譯白隱禪師息耕録開筵普説印施解並序/1
國譯白隱禪師息耕録開筵普説並息耕録評唱剩語/1 |
白隱禪師息耕録開筵普説原文/1
・
・ |
○、この年、山本勇夫編「高僧名著全集 第12巻 白隠禪師篇」が「平凡社」から刊行される。 pid/1218401
|
總説 / 1
毒語心經 / 3
遠羅天釜 / 21
鍋島攝州侯の近侍に答ふる書 / 21
遠方之病僧に贈る書 / 51
法華宗老尼之問に答ふる書 / 62
遠羅天釜續集 / 93
念佛公案與優劣如何の
→問に答ふる書 / 93
客難に答ふ / 112
於仁安佐美 / 123
夜船閑話 / 167
假名法話 / 185
藪柑子 / 195
三敎一致の辯 / 211
寶鏡窟記 / 217
兎專使稿 / 225
尺牘 / 243 |
藥病相治の説 / 259
渡邊平左衞門に與ふる書 / 269
辻談義 / 273
見性成佛丸方書 / 281
寢惚之眼覺 / 283
安心法興利多々記 / 315
施行歌 / 319
大道ちよぼくれ / 329
御洒落御前物語 / 343
おたふく女郞粉引歌 / 349
主心御婆々粉引歌 / 375
御代の腹鼓 / 385
解説 / 395
一 禪師の學海 / 397
二 禪師の道機 / 398
三 禪師の提唱 / 398
四 禪師の德風 / 399
五 禪師の孝道 / 400 |
六 禪師の激勵 / 400
七 禪師の工夫 / 401
八 禪師の陰德 / 402
九 禪師の見性 / 403
十 禪師の翰墨 / 405
十一 禪師の動靜 / 405
十二 禪師の得處 / 406
十三 禪師の小院 / 406
十四 禪師の開講 / 407
十五 禪師の應請 / 408
十六 禪師の門下(其の一)/408
十七 禪師の門下(其の二)/408
十八 禪師の四哲 / 409
十九 禪師の諡號 / 410
二十 禪師の自讃 / 410
白隱禪師抄傅 / 413
一 總説 / 415
二 當時の禪門 / 417
|
三 禪師の幼時 / 419
四 無常を觀ず / 421
五 疑團の煩悶 / 423
六 出家行道 / 425
七 文藝に耽る / 427
八 筆墨を燒く / 429
九 疑團を解く / 431
十 珠玉瓦礫と化す / 433
十一 大悟徹底 / 436
十二 悟後の修養 / 438
十三 煙管問答 / 441
十四 七畫夜坐禪 / 443
十五 泥中の勸喜 / 445
十六 一掬の米粥 / 446
十七 大無量體得 / 449
十八 貧富超越 / 451
十九 求道完成 / 453
略註 / 457 |
研究課題:※喜田貞吉著「福神信仰の變遷(一・二・通番なし)」について確認が必要 2023・2・18 保坂
神道講座 第4(歴史編) 神道攷究会 編 神道攷究会 1930 pid/1185908
|
日本神話 松村武雄
氏神の發達 太田亮
本地垂迹説について 辻善之助
修驗道の發生と組織 宇野圓空
神道と陰陽道との關係 小柳司氣太
中世に於け神る人の社會的活動 魚澄惣五郞 |
神社を中心とする自治團體の結合と統制 平泉澄
神社と交通 中村直勝
上代風俗と神社 櫻井秀
※福神信仰の變遷 喜田貞吉
神社の人文地理學的考察 小田内通敏
・ |
神道講座 第9冊 神道攷究会/編 神道攷究会 1930 所蔵:宮城県図書館
|
神社制度上の諸問題1(足立収)
神社概説1(宮地直一)
神社建築に就いて1(角南隆)
武士道に就いて1(紀平正美)
※福神信仰の変遷1(喜田貞吉) |
原始神道の考古学的考察1(大場磐雄)
中古地方文化史上に於ける肥後国河上宮(西岡虎之助)
春日紀重と其神学(朝山晧)
神祇史研究法6(溝口駒造)
・ |
神道講座 第10冊 神道攷究会 編 神道攷究会 1931 pid/1034669
|
神社概説(二) 内務省神社局考證課長 文學博士 宮地直一/5
祭祀原論(一) 内務省考證官 座田司氏/19
武士道に就て(二) 東京帝國大學教授 文學博士 紀平正美/29
※福神信仰の變遷(二) 文學博士 喜田貞吉/51 |
神紋の研究(三) 文學博士 沼田頼輔/93
原始神道の考古學的考察(二) 内務省囑託 大場磐雄/147
風土記の考察 中山太郎/165
神祇史研究法(七) 東京帝國大學神道研究室主任 溝口駒造/199 |
|
| 1931 |
6 |
・ |
2月、 仏教文庫編集部編「白隠和尚文集」が「東方書院」から刊行される。
(仏教文庫 ; 12) pid/1109951/1/1 1500円
|
遠羅天釜/1
寶鏡窟記/88
辻談議/95
假名法語/104
さし藻草/113 |
邊鄙以知告/148
於仁安佐美/190
夜船閑話/231
施行歌/248
御代の腹鼓/251 |
大道ちよぼくれ/253
お多福女郎粉引歌/256
主心御婆粉引歌/257
安心ほこりたた記/261
・ |
|
8月、「藝術 9(14)」が「大日本藝術協會」から刊行される。pid/1560364
|
朝顏は夏の國手/p1~1
秀畝氏の個展 金剛と廬山 / 初風生/p2~2
白隱禪師の畫 / 森大狂/p2~3
繪に就ての研究 / 紫菫野人/p3~4 |
酸漿(『冩生帖より』の十四) / 竪山南風/p3~3
環堵畫塾の歡迎會/p4~4
白日莊の日本畫大家新作展/p4~4
愛氷雑記/p5~8 |
水に因む繪の展覽會/p5~8
結城孫三郞君の操り人形/p6~6
上總竹岡に遊ぶ/p7~7
美術界雜爼/p8~8 |
10月、原田祖岳が「正宗国師坐禅讃講話」を「正信同愛会」から刊行する。 (同愛叢書) 所蔵:横浜市立図書館
発行年再確認要 2023・1・2 保坂
正宗国師坐禅讃講話.原田祖岳/著 宗国師白隠禅師小伝.岩崎巍山居士/著
○、この年、茂野染石が「千本松原」を「沼津通信社」から刊行する。 pid/1175167
|
本町情話
二人のお半/1
夜逃する迄/5
梯子酒/7
小竹の話/13
港の一夜/15
叶の行衞/32
五月雨の小宴/37
富士太郞事件/42
轉々する女/47
暴風雨の中/50
憤怒のあと/53
夜逃した人々/59
親切な猛者/64
藝妓から娼妓へ/81 |
酒場めぐり/86
市長の戀/93
カフヱ巡禮/102
新人舊人
岩田實君/107
金子誠一郞君/109
山本淺五郞君/111
名取榮一君/113
大沼吉平君/115
鈴木俊三君/117
佐藤俊雄君/119
櫛部荒熊君/121
長倉信一君/123
長倉新太郞君/125
森田豊壽君/127 |
杉浦謙次郞君/129
脇田信吾君/131
小野道三郞君/133
岩崎竹次郞君/135
大橋平治君/137
渡邊汀一君/139
長倉已之吉君/141
土屋國太君/143
市川龜次郞君/145
稻葉勝太郞君/147
小川三郞君/149
鈴木幹君/151
感想閑話
人生の目的其他/153
山莊の梅/157 |
良寬の詩幅/162
白隱さん/167
淨瑠璃禮讃/172
牧谿か相阿彌か/181
舟仙の墓を尋ねて/184
棋道新話/191
馬門先生/198
俳人連山/206
院展見物/213
帝展見物/218
鬼又士郞傳/225
思出す人々/229
・
・
・ |
〇この年、高楠順次郎編「大正新脩大蔵経 第八十一巻 」が「大正一切経刊行会」から刊行される。 pid/3435991
|
二五六二 常光國師語録(二卷)・日本 空谷明應語侍者編 / 1
二五六三 大通禪師語録(六卷)・日本 愚中周及語侍者某甲編 /46
二五六四 永源寂室和尚語録(二卷)・日本 寂室玄光語 / 101
二五六五 佛頂國師語録(五卷)・日本 一絲文守語文光編 / 136
二五六六 大燈國師語録(三卷)・日本 宗峯妙超語侍者性智等編/191
二五六七 徹翁和尚語録(二卷)・日本 徹翁義享語遠孫禪興編/242
二五六八 雪江和尚語録(一卷)・日本 雪江宗深語遠孫禪悅輯/271
二五六九 景川和尚語録(二卷)・日本 景川宗隆語侍者某等編/286
二五七〇 虎穴録(二卷)・日本 悟溪宗頓語門人某等編 / 313 |
二五七一 少林無孔笛(六卷)・日本 東陽英朝語侍者某等編 / 347
二五七二 見桃録(四卷)・日本 大休宗林語遠孫比丘等編 / 412
二五七三 西源特芳和尚語録(三卷)・日本 特芳禪傑語遠孫宗怡重編/479
二五七四 槐安國語(七卷)・日本 白隱慧鶴語 / 511
二五七五 宗門無盡燈論(二卷)・日本 東嶺圓慈撰 / 581
二五七六 五家參祥要路門(五卷)・日本 東嶺圓慈編 / 605
二五七七 大鑑淸規(一卷)・日本 淸拙正澄撰 / 619
二五七八 諸回向淸規(五卷)・日本 天倫楓隱撰 / 624
二五七九 小叢林淸規(三卷)・日本 無著道忠撰 / 688 |
○、この年、飯田〔トウ〕隠が「参禅秘話」を「中央仏教社」から刊行する。 pid/1176834
|
通俗禪學譚 / 1-76
如何にして煩悶を慰すべきや / 77-92
禪とは何ぞや / 93-118
逹磨の骨髓 / 119-137 |
禪と戒 / 138-158
月と菩提心 / 159-196
元古佛「發願文」釋義 / 197-215
白隱禪師選述「坐禪和讃」皷吹 / 216-225 |
公案歌ものがたり / 226-293
引導禪 / 294-310
隨筆禪 / 311-352
裝幀 小川芋錢氏 |
○、この年、山本勇夫編「高僧名著全集 第12巻」が「平凡社」から刊行される。 pid/1218401
|
総説/1
毒語心經/3
遠羅天釜/21
鍋島攝州侯の近侍に答ふる書/21
遠方之病僧に贈る書/51
法華宗老尼之問に答ふる書/62
遠羅天釜續集/93
念佛公案與優劣如何の問に答ふる書/93
客難に答ふ/112
於仁安佐美/123
夜船閑話/167
假名法話/185
藪柑子/195
三敎一致の辯/211
寶鏡窟記/217
兎專使稿/225
尺牘/243
藥病相治の説/259
渡邊平左衞門に與ふる書/269
辻談義/273
見性成佛丸方書/281
寢惚之眼覺/283
安心法興利多々記/315
施行歌/319 |
大道ちよぼくれ/329
御洒落御前物語/343
おたふく女郞粉引歌/349
主心御婆々粉引歌/375
御代の腹鼓/385
解説/395
一 禪師の學海/397
二 禪師の道機/398
三 禪師の提唱/398
四 禪師の德風/399
五 禪師の孝道/400
六 禪師の激勵/400
七 禪師の工夫/401
八 禪師の陰德/402
九 禪師の見性/403
十 禪師の翰墨/405
十一 禪師の動靜/405
十二 禪師の得處/406
十三 禪師の小院/406
十四 禪師の開講/407
十五 禪師の應請/408
十六 禪師の門下(其の一)/408
十七 禪師の門下(其の二)/408
十八 禪師の四哲/409 |
十九 禪師の諡號/410
二十 禪師の自讃/410
白隱禪師抄傅/413
一 總説/415
二 當時の禪門/417
三 禪師の幼時/419
四 無常を觀ず/421
五 疑團の煩悶/423
六 出家行道/425
七 文藝に耽る/427
八 筆墨を燒く/429
九 疑團を解く/431
十 珠玉瓦礫と化す/433
十一 大悟徹底/436
十二 悟後の修養/438
十三 煙管問答/441
十四 七畫夜坐禪/443
十五 泥中の勸喜/445
十六 一掬の米粥/446
十七 大無量體得/449
十八 貧富超越/451
十九 求道完成/453
略註/457
・ |
○、この年、山本勇夫編「高僧名著全集 第16巻」が「平凡社」から刊行される。 参考 pid/1218460
|
夢窓國師篇
總説/1
夢中問答/3
二十三問答/167
一 道心起すべき事/167
二 一心の向けやうの事/167
三 善惡限りなき事/168
四 善惡の源の事/168
五 根本の生れ死なざる事/170
六 佛生れ死にたまはぬ事/171
七 佛は人にかはりたる事/172
八 佛むしけらとなる事/173
九 妄念による事/174 |
十 現在の果を見て過去未來を知る事/175
十一 善根に有漏無漏のかはりある事/176
十二 淨土をねがふ事/177
十三 懺悔に罪をほろぶる事/178
十四 懺悔に二つある事/179
十五 誓願の事/180
十六 廻向の事/180
十七 臨終の事/181
十八 何事も思はず徒然なるは惡しき事/183
十九 祈祷の事/184
二十 佛と菩薩行の中にいづれ勝劣の事/185
二十一 心の無きを佛にする事/186
二十二 心の起るを如何すべき事/188 |
二十三 私の言葉にあらず皆經文なる事/189
西山夜話/193
臨川家訓/209
夢窓國師和歌集/223
一休禪師篇
骸骨/3
狂雲集/11
卷上/11
卷下/59
摩訶般若波羅蜜多心經/107
解説/129
抄傳/143
・ |
○、この年、山本勇夫編「高僧名著全集 第18巻」が「平凡社」から刊行される。 pid/1218479
|
一遍上人篇
一遍上人語録 / 3
別願和讃 / 3
百利口語 / 7
誓願偈文 / 14 (0019.jp2)
時衆制誡 / 15
道具秘釋 / 17
消息法語 / 20
西園寺殿乃御妹の准后の御法名を一阿彌陀佛と
→さづけ奉られけるに其御
尋に付て御返事 / 20
土御門入道務内大臣殿より出離生死の趣御尋に付て御返事/21
頭辨殿より念佛の安心尋たまひけるに書て示したまふ御返事/21
結縁したまふ殿上人に書てしめしたまふ御法語 / 22
興願僧都念佛の安心を尋申されけるに書てしめしたまふ御返事/23
山門橫川の眞籍上人へつかはさるゝ御返事 / 24
或人念佛の法門を尋申けるに書てしめしたまふ御法語 / 25
或人法門を尋申けるに他阿上人歌集 / 143 |
→書てしめしたまふ御法語 / 25
上人いさゝか御惱おはしましけるとき
→書て門人にしめしたまふ御法語/27
最後の御遺誡 / 27
偈頌和歌 / 28
門人傳説 / 49
附録 / 83
播州問答 / 85
補足
奉納縁起記 / 111
一遍上人發願の事 / 111
私曰く / 117
道場誓文 / 119
知心修要記 / 121
念佛往生綱要 / 127
三心料簡義 / 133
他阿彌陀佛同行用心大綱 / 141
他阿上人歌集 / 143
|
解説 / 219
一遍上人略傳 / 227
他阿上人略傳 / 251
榮西禪師篇 /
興禪護國論 / 3
上 / 3
中 / 27
下 / 51
未來記 / 75
喫茶養生記 / 77
序 / 77
上 / 79
下 / 89
日本佛法中興願文/97
出家大綱 / 101
解説 / 117
・
・ |
○、この年、阿部芳春編「正受老人」が「臥月菴」から刊行される。 重要 pid/1177386
|
自序
第一篇 行録 / 1
一 略歴 / 1
二 年譜 / 2
三 名號 / 7
附 印章 / 11
四 法階 / 12
五 父母 / 13
六 出生 / 15
七 體貌 / 16
八 性質 / 16
九 成長 / 17
一〇 懷疑 / 17
一一 省發 / 18
一二 濳修 / 19
一三 出家 / 20
附 無難和尚 / 22 |
一四 參究 / 32
一五 行脚 / 33
一六 再參 / 35
一七 師の禪 / 36
一八 入山 / 39
一九 創菴 / 43
附一 現在の景觀 / 49
附二 水石と栂樹 / 49
二〇 菴住 / 52
二一 正念相續の努力 / 69
二二 披閲 / 73
附 譬喩觀 / 86
二三 大成の一面 / 88
二四 面目の瞻望 / 93
二五 手蹟 / 100
二六 門風 / 105
附 門下 / 107 |
二七 示寂 / 126
第二篇 鉗鎚白隱 / 129
一 白隱宗覺に遭ふ / 129
二 白隱老人の爐鞴に入る/133
三 白隱發明す / 137
四 發心の事 / 142
五 無相心地戒 / 143
六 寤寐恒一 / 149
七 洞上五位の訣 / 149
八 附囑 / 156
九 白隱辭去す / 157
附 白隱の成就 / 160
第三篇 語録 / 163
一 埀語拾遺 / 163
二 評註 / 169
三 詩偈 / 179
第四篇 附録 / 215 |
一 東嶺の思慕 / 215
二 兒孫の奠香 / 219
三 調査資料及調査の迹/222
附録
一 老人行録 / 239
三 當庵世代紀録 / 260
四 禪道略解 / 281
五 其後の菴 / 330
六 參詣案内 / 347
補遺 / 365
結尾 / 366
跋 / 366
編者後記 / 367
正誤 / 367
・
・
・ |
○、この年、谷林孝雄が「花を辿りて : 仏教血涙日記物語 谷林孝雄感謝之遺書」を「禅道修養婦人会」から刊行する。 pid/1036441
|
前篇 『愛別に歎くもの』
一、 古里/1
二、 實母に別れた時/3
三、 神戸にて下宿/4
四、 樂しき日/5
五、 小鳥は淋し/6
六、 姫路にて入學/7
七、 飮食店を開いて/8
八、 淋しい身の上/9
九、 惱みを知る頃/10
一〇、 坂本家へ預けられて/12
一一、 仲居に逢つた時/13
一二、 お爺さんの死/14
一三、 不和合の續く日/16
一四、 嗚呼姉さんはいづこ/17
一五、 夜行にて恒屋村へ/20
一六、 不運は募る/21
一七、 懷かしき山崎町へ/24
一八、 谷林實家にて/25
一九、 疥の苦しみ/27
二〇、 冬の頃/29
二一、 ままならぬ身の上/31
二二、 田舍路は暮るる/33
二三、 弱き性質/35
二四、 大阪への道中/38
二五、 瑞光寺にて/41
二六、 病む日の旅路/42
二七、 故郷は嬉し/45
二八、 逢ひに來た人/47
二九、 隨陽寺にて/49
三〇、 いつまで迷ふ/52
三一、 厭になる世の中/56
三二、 春雨は微笑む/58
|
三三、 改名して僧侶へ/60
三四、 幻の街/62
三五、 師匠と山崎へ/67
三六、 秋の旅路/70
三七、 青春の彼方/71
三八、 父母の心/73
三九、 常陰家を訪ねて/74
四〇、 小母さんからの初文/76
四一、 運命の歌/77
四二、 三大不幸/79
四三、 俳句を作りし頃/80
四四、 産業博覽會の日/84
四五、 彼の頃と此の頃/87
四六、 樂園の頃/90
四七、 悲しき別れ/92
四八、 手紙と悲曲/94
四九、 いざ震へよ勵め/96
五〇、 血涙復讐の叫び/98
五一、 血肉を裂く復讐の刃/107
五二、 感謝の言葉/111
後篇 『無常を叫ぶもの』
五三、 生ある物よ許して呉れ/117
五四、 巡禮女の夢/118
五五、 不思議なる幸福/119
五六、 懷かしの幻想/122
五七、 美人も僅かの幻影/126
五八、 我心戒律書/128
五九、 或る日の禮状/129
六〇、 佛心は強し/129
六一、 嗚呼母よ宿命の涙/137
六二、 靜ちやん懷かし/138
六三、 故郷よ涙を語る/138
六四、 初めて書く母への手紙/139
|
六五、 昔を語る悲痛な叫び/140
六六、 小母さんへの相談/142
六七、 小母さんの返事/145
六八、 靜ちやんの熱筆/146
六九、 父からの便り/147
七〇、 淋しい父の身の上/148
七一、 小母樣へ昔を語る/148
七二、 靜ちやんへ語る/150
七三、 母より嬉しき手紙/151
七四、 父へ寫眞を贈る/152
七五、 母へ身の上を語る/152
七六、 小母樣より悦こびの言葉/154
七七、 小母樣へ寫眞を贈る/155
七八、 おお妹よ懷かしの涙/157
七九、 妹へ初めて語る/158
八〇、 永井の主人より/159
八一、 山崎の隨陽寺より/160
八二、 母よりの返書聞くにつけても/160
八三、 主人へ別れの熱筆を震ふ/161
八四、 小母樣からの禮状/167
八五、 母へ柿の禮状/167
八六、 主人よりの葉書/169
八七、 父からの通知/169
八八、 小母樣へ一筆/169
八九、 母より涙の手紙/171
九〇、 母への返書涙を語る/173
九一、 ますのへ力の文/176
九二、 顏は知らねど母の文/179
九三、 可愛らしい妹の手紙/180
九四、 ああ妹ますのの身の上/181
九五、 すみ子よ懷かしの文/182
九六、 故郷の空/183
九七、 幻か涙の母/184
|
九八、 悦こびの小母/187
九九、 嘆きの夢/188
一〇〇、 縁がなす手紙/190
一〇一、 おりの姉さんより/191
一〇二、 母への文/191
一〇三、 嗚呼小母さん世の中は/192
一〇四、 母より聞く運命の涙/194
一〇五、 母よりの作歌/195
一〇六、 乳母よ懷かし/196
一〇七、 ああますのよ古里を語りて/196
一〇八、 歸らぬ决心/197
一〇九、 厚き母親の心/199
一一〇、 新らしき生活/200
一一一、 出發前の大多忙/202
一一二、 悲しき別れの手紙/204
一一三、 胸を裂く涙の手紙/205
一一四、 厚き詩と安名を拜領す/206
一一五、 過去を捨てて/206
一一六、 圓福寺專門道塲に於て/208
一一七、 奮戰よ悦こびの涙/210
一一八、 正受庵復興記念接心會/215
一一九、 幸福なる信者/217
一二〇、 多忙な西國巡禮/219
一二一、 駐在所へ熱筆を震ふ/223
一二二、 庵主さんより久しき文/226
一二三、 血涙因果最後の叫び/227
一二四、 琵琶歌無形に咲く花/236
附録
主心お婆々粉引歌・白隱禪師/241
・
・
・
・ |
○、この年、谷至道が「現代名士の参禅実話」を「中央出版社」から刊行する。 pid/1223922
|
座禪に於ける學理的研究 理學博士近重眞澄氏の話/1
河野廣中の參禪 何うして禪に入つた手/17
智者は默す 床次竹次郞の禪話/30
婦人禪を説く 伊澤修二夫人/33
色氣を去れよ 文豪漱石の參禪/45
桃下堂病院長 岡田乾兒の參禪―主人公は誰か―/56
精神修養と禪 心理學上より 文學博士元良勇次郞/64
參學者への注意 曹洞宗管長石川素堂/72
我が文字禪 文學博士上田萬年/77
雲水の苦行難行 峰尾大休和尚參禪の話/83
禪と催眠術と武士道 文學博士福來友吉參禪話/92
彈實の會 山岡鐵舟の參禪/103
禪に就いて 行住坐臥皆禪也 勿滑谷快天の話/110
禪の妙用 禪定と坐相 橫尾賢宗/119
算盤禪の由來 參禪は何にても出來る 早川千吉郞/130
軍神の參禪 乃木大將の禪を語る 追憶の心學道人/140
禪の本領 逃がす秘傳と遁げる奧の手 西鄕南洲/150
丹田の修養に 禪の効用は?鈴木充美/153
狐わなと大入道/156
由利滴水の豪膽 衣を縫ふに似てゐる/159
努力は人を造る 兒玉玄海和尚を語る菅原洞禪師/162
禪機?溂 侯爵大隈重信 櫻洲との論戰/169
二つの對立 東和尚と頭山滿 抵當の指一本/172
反省會の米峰 禁酒會の米峰 米峰に米峰の破戒/177
腹式呼吸 白隱の遠羅天金 二木博士の參禪/182
加藤咄堂居士 筆と舌は唯一の武器 語るはたゞ德の一字/187 |
悟由禪師に問ふ 白刄の刄渡りは何?伊藤博文の話/192
南條、村上の兩師 前田慧雲の三博士 禪的性格の持主/195
毒藥と禪 服毒して脱落 卍庵和尚の參禪/202
看破 居士の胸中は何か 竹田默雷/206
眞面目 穆山は斯く云ふ 眞實の禪/208
尾崎咢堂の雄辯 得意の譬喩 禪の本分からは/212
口頭三昧 時代と共に 釋宗演の禪/218
惡辣な師を選ぶ 冷水を浴び坐睡 祥山の參禪/224
無類の辛辣 叩き出された廣中 燒禾山の會/229
陰德の行持 肥桶を擔ふ 東和濬尚/233
熊の皮 居士渡邊無邊 參禪の動機/239
禪の入門 勝峰大徹和尚/243
新井石禪の得度 苦心の歴史 觀世音への祈願/261
得庵の一喝 伊藤公をへこます 無慈悲慘忍にやめよ/266
眞個の師家 雲水長者 松蔭和尚/269
神尾大將の參禪 座禪せよ 精神修養の根本義/273
臨濟の大悟 拳は悟の證 打爺拳の由來/279
跣足參り 記憶力の薄弱を嘆いて 秋野孝道/287
尼に遣り込められて 未來心不可得 德山和尚の大悟/291
夏冬一時に來たか/297
それ猫が 賊馬に騎つて賊を追ふ 風外の禪機/301
道に親しき祖岳 世話になる身で 他人の世話は出來ぬ/305
牛頭山の法融/308
倶胝一指頭 尼の侮辱に發奮するまで/313
丸寸五分の禪 楠田謙藏の參禪/319
・ |
|
| 1932 |
7 |
・ |
4月、峯玄光が「禅学観」を峯達夫(自費出版)する。 pid/1024979 閲覧可能
|
一 禪と修養 / 1
禪と工夫
修禪の階級
禪の倫理
四料簡大意
五位大意
坐禪の作法
二 禪と死生 / 18
自家頭上の問題
穆山の回顧
病中の工夫
尊貴なる一日
古禪僧の遺偈
三 禪と健康 / 40
發病と横死の因
澡浴の利益
嚼楊枝の利益
掃地の利益 |
經行の利益
婬慾と食慾
白隱の強健法
穆山の健康法
悟由の健康法
四 禪と武士道 / 62
武士道の萠芽と發達
禪と武士
時頼及時宗の禪的感化
楠公菊地兩氏の禪的感化
信玄謙信の禪的感化
鈴木正三と徳川武士
澤庵と徳川武士
山鹿素行大石義雄の禪的感化
五 禪と劍道 / 93
劍道の起源
宮本武藏
澤庵と柳生宗矩
|
不動智神妙録
山岡鐵舟の禪學
勝海舟の劍禪
六 禪と文學(上) / 113
佛典と文學
五山文學
雪村
虎關
義堂
絶海
中巖、別源、大智
隱元と心越
七 禪と文學(下) / 147
和歌禪
本心の歌
坐禪和讃
船歌
禪と謠曲
|
一休の謠曲
俳諧禪
松尾芭蕉
古池眞傳
芭蕉以後の禪味俳味
八 禪と繪畫 / 181
繪畫と宗教
密教的繪畫と禪の感化
雪舟
竹田
仙外、風外、鐵翁
九 禪と茶道 / 198
茶の傳來
珠光の茶禪
利休の茶道
澤庵の茶禪
賣茶翁
井伊直弼の茶禪 |
10月、「大日 (41)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(自畫讃頂相)」
が掲載される。 pid/1595747
|
白隱墨蹟――(自畫讃頂相)
滿洲國承認と東洋モンロー主義 / 相馬由也 / p11~19
血迷ふ米國戸惑ふ聯盟 / 秋澤次郞 / p19~21 |
高天原雜記(二十三) / 田中逸平 / p72~74
〈抜粋〉
・ |
11月、「大日(43)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(まゝつきはし) 」 が掲載される。 pid/1595748
|
白隱墨蹟――(まゝつきはし)
高天原雜記(二十五) / 田中逸平 / p67~70 |
〈抜粋〉
・ |
12月、「大日 (44)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(監前山深水寒)」
が掲載される。 pid/1595749
12月、「大日 (45)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(神農氏)」
が掲載される。 pid/1595750
|
白隱墨蹟――(神農氏)
高天原雜記(二十六) / 田中逸平 / p61~66 |
抜粋〉
・ |
○、この年、国訳大蔵経編輯部編「国訳大蔵経 : 昭和新纂 宗典部 第10巻」が「東方書院」から刊行される。
pid/1172352 閲覧可能
|
日本支那聖道門聖典
目次
大乘玄論・嘉祥大師撰 / 1
卷第一 / 1 |
卷第二 / 46
卷第三 / 91
卷第四 / 150
卷第五 / 214 |
原人論・宗密禪師撰 / 277
宗門無盡燈論・東嶺禪師撰 / 293
緇門崇行録・〔シュ〕宏禪師撰 / 393
敎誡律儀・道宣律師撰 / 465 |
聖德太子十七憲法・聖德太子撰 / 491
三敎指歸・弘法大師撰 / 495
八宗綱要・凝然大德撰 / 529
・ |
〇この年、「仏教信仰実話全集 第18巻 」が「大東出版社」から刊行される。 pid/1215219
|
第一 江戸時代(後期) / 1
一 正三老人 / 3
二 鐵眼道光 / 11
三 了翁道覺 / 21
四 華嚴鳳潭 / 26
五 正受慧端 / 30
六 秀道祖曉 / 43
七 天桂傳尊 / 51
八 澤水長茂 / 66
九 圓通と法眼 / 70
一〇 覺芝廣本 / 75
一一 華嚴曹海 / 77
一二 月海元昭 / 84
一三 頑極官慶 / 94
一四 白隱慧鶴 / 98
一五 面山瑞芳 / 126
一六 洞門の禪海 / 133
一七 大休と快巖/141
一八 鐵文道樹 / 152 |
一九 遂翁元盧 / 162
二〇 東嶺圓慈 / 172
二一 峩山慈棹 / 180
二二 絶宗無學 / 186
二三 おどけ善光 / 191
二四 大典顯常 / 196
二五 玄樓奧龍 / 200
二六 曇〔レイ〕泰禪 / 208
二七 隱山惟〔エン〕 / 216
二八 誠拙周樗 / 223
二九 光明佛通 / 237
三〇 華頂文秀 / 241
三一 大愚良寬 / 244
三二 太元孜元 / 263
三三 仙崖義梵 / 268
三四 古梁紹峨 / 283
三五 風外本高 / 291
三六 大拙承演 / 297
三七 義堂昌碩 / 303 |
三八 月潭全龍 / 306
三九 筏舟煩海 / 310
四〇 物外不遷 / 314
第二 明治大正時代 / 327
一 鐵翁祖門 / 329
二 晦巖道廓 / 341
三 雪潭紹璞 / 353
四 福昌無三 / 360
五 海州楚棟 / 365
六 奕堂旃崖 / 370
七 環溪密雲 / 384
八 越溪守謙 / 395
九 建仁龍關 / 404
一〇 坦山覺仙 / 410
一一 洪川宗温 / 431
一二 獨園承珠 / 445
一三 琢宗と楳仙 / 467
一四 無學文奕 / 477
一五 滴水宜牧 / 487 |
一六 峩山昌禎 / 499
一七 虎關宗補 / 521
一八 貫道周一 / 525
一九 南隱全愚 / 530
二〇 敬中文幢 / 536
二一 廣州宗澤 / 543
二二 東嶽承晙 / 548
二三 穆山瑾英 / 552
二四 宗詮眞淨 / 575
二五 大休悟由 / 585
二六 洪嶽宗演 / 595
二七 維室默仙 / 606
二八 石蓮實全 / 624
二九 黄檗柏樹 / 629 (
三〇 函應宗海 / 636
三一 鄧州全忠 / 640
三二 範之と得菴 / 65
・
・ |
○、この年、土屋大夢が「記憶を辿りて」を「土屋文集刊行会」から刊行する。 pid/1031631
|
幼時の記憶 / 1
名前の呼やう / 2
輪廻しと凧合戰 / 2
士族と平民 / 3
初めて小學校が出來た / 5
髪を剃る / 6
半髪と總髪 / 8
初めて牛肉を食ふ / 9
初めて靴を穿く / 10
初めての博覽會 / 10
木下家の事 / 11
寧は新しい女 / 12
木下家定に七人の男子 / 14
秀秋三十萬石の器 / 15
關ケ原に於ける秀秋 / 16
足守、日出の兩木下 / 18
人物輩出 / 20
美人系 / 21
日本一の大蘇鐵 / 22
朝日は豪邁なる婦人 / 23
高臺寺 / 23
木下家は徳川方 / 24
豐後灣と噴火山 / 26
日出は風光明媚の地 / 27
立石の金山發見 / 28
祿高は實收六分の一 / 29 |
藩士の節儉 / 30
豆腐は十萬石 / 31
武術文藝共に旺盛 / 32
瓦葺唯一軒 / 34
隣家の長澤氏 / 36
關謙之氏 / 37
土屋氏と日出 / 38
藩の奧方 / 40
變革の豫感 / 41
大樂源太郎の噂 / 42
父は教導團の教官 / 43
豐後から大阪迄二十六日間 / 45
帶刀が問題となる / 47
初めて見た大都會 / 48
初めて乘つた汽船 / 49
慘めな下等船客 / 50
初めて乘つた汽車 / 52
夏季に氷がある / 52
御殿を取捲いた長屋 / 55
人口漸く七十萬 / 56
火事は盛んなもの / 59
先づ煉瓦見物 / 61
初めて見た瓦斯燈 / 62
當時の新聞と記者 / 63
東京で最初の小學校 / 64
世界國盡しの暗誦 / 66 |
女生徒男生を凌ぐ / 68
快男兒と奇兒 / 68
美妙齋と嵯峨の舍 / 70
學校で第一の美人 / 71
戰爭中に博覽會 / 72
戰爭好きの別當 / 74
日本最初の工兵架橋 / 75
西郷星 / 76
叔父は漢學好き / 77
飯沼勝五郎の後裔 / 78
大久保公遭難と高谷塾 / 79
二葉亭と西源四郎 / 80
萩野由之と右田兄弟 / 81
團十郎の活歴 / 84
寄席と芝居 / 85
支那語の稽古 / 86
高谷先生の遺業 / 88
奎連鳴世録の卸賣 / 89
高谷先生と福澤先生 / 90
從兄洋學を勸む / 94
大阪迄獨り旅 / 96
濟美黌退塾 / 98
從兄が洋學の手解き / 99
神田共立學校 / 100
首藤諒の弟勘三郎 / 101
近藤攻玉社へ轉學 / 102 |
教員排斥運動に加入 / 103
先づ退學者が發言 / 105
レボリユーシヨン / 106
全生徒退校 / 108
明治學院の前身 / 110
初對面の高島嘉右衞門 / 111
獨立など問題でない / 114
金を賣つて入牢した話 / 117
土谷塾と英語學校 / 118
日光に轉地療養 / 119
歸途足尾廻りの失敗 / 120
美少年首藤勘三郎 / 122
果敢なき首藤の一生 / 124
首藤の豪放 / 126
哲學と數學 / 128
東京專門學校に入る / 130
鎌倉圓覺寺へ轉地 / 131
公案隻手の音聲 / 133
居士號を授けられる / 135
儒者と僧侶との問答 / 136
難行二年 / 139
當時の參禪者 / 141
年譜 / 143
跋・堀田宗一 / 153
・
・
|
○、この年、茂野染石が「香貫山」を「沼津通信社」から刊行する。 pid/1209059
|
情話選
女優になつた藝妓/1
小萬の半生/9
二度の引眉毛/12
半玉の圖/15
幸丸の死/18
夜更の拍子木/21
野球狂の客/25
昔のエロの話/29
或る日の藝妓屋/33
死んだ二人/37
女將とお茶屋/42
先斗町の一夜/45
銀座裏の女/65
|
カフエ廻り/84
當り年の藝妓/89
人物選
武藤正俊君/93
澤靜夫君/95
藤澤要君/97
矢部理朔君/99
佐藤快正君/101
湯山保壽君/103
庄司艮朗君/105
淸水行之助君/107
高田廣作君/109
中山吉平君/111
天岫接三君/113 |
森信吾君/115
安藤理造君/117
仁王藤八君/119
荒木孝繼君/121
小山田正直君/123
山崎劍二君/125
橫山定君/127
堀江淸吉君/129
平富榮一君/131
增田彌平君/133
梶賢雄君/135
杉山周藏君/137
望月米吉君/139
餘談選
|
天狗鼻くらべ/141
訪問手記/145
御舟氏の箇展/150
西光寺の縁起/154
カラヱの内幕/158
院展を觀る/161
沼津と帝展作家/168
白隱禪師と其藝術/172
帝展見物/203
本町論語/217
酒客と酒/221
・
・
・ |
○、この年、白隠慧鶴著逑 ; 東嶺圓慈注觧「毒語注心經」が「森江書店」から刊行される。
奥付に「明治十六年十月十八日届出 明治十七年三月六日出版」とあり 所蔵:埼玉大学 図書館:151422700 |
| 1933 |
8 |
・ |
1月、「大日 (46)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――三保富士」
が掲載される。 pid/1595751
1月、「大日(47)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――壽老人」
が掲載される。 pid/1595752
|
白隱墨蹟――壽老人
滿蒙開發の根本方針 / 村田懋麿 / p19~21 |
〈抜粋〉
・ |
2月、「大日 (48)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――鍾馗鬼」
が掲載される。 pid/1595753
2月、「大日 (49)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(月の夜梅)
」 が掲載される。 pid/1595754
3月、「大日 (50)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――西行法師」
が掲載される。 pid/1595755
|
白隱墨蹟――西行法師
國寳指定の權威を疑ふ / 松島宗衛 / p21~26 |
國際聯盟脱退の原理 / 岸原鴻太郞 / p70~70
〈抜粋〉 |
4月、「大日 (53)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(お炙) 」
が掲載される。 pid/1595757
|
白隱墨蹟――(お炙)
委任統治領は舌では動かぬ / 高木繁 / p16~18 |
高天原雜記(二十八) / 田中逸平 / p49~51
〈抜粋〉 |
5月、「大日 (55)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(懶(らさん)和尚)
」 が掲載される。 pid/1595758
※「大日 (54~57)」に「白隱墨蹟」欄あるか検討要 2022・12・17 保坂
7月、「大日(58)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(蘭花螳螂)」
が掲載される。 pid/1595759
|
白隱墨蹟――(蘭花螳螂)
和漢暦の占星記事の現代性(一) / 近膝芳一 / p39~43 |
高天原雜記(三十三) / 田中逸平 / p50~51
〈抜粋〉 |
7月、「大日(59)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(蔓瓜野獸)」
が掲載される。 pid/1595760
|
白隱墨蹟――(蔓瓜野獸)
北滿の日本人屯墾植民 / 山田武吉 / p11~13
和漢暦の占星記事の現代性(二) / 近藤芳一 / p46~50 |
高天原雜記(三十四) / 田中逸平 / p52~53
水戸藩史話 / 久木獨石馬 / p62~63
〈抜粋〉 |
8月、「大日 (60)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(草座達磨)
」 が掲載される。 pid/1595761
|
白隱墨蹟――(草座達磨)
水藩幕末の紛擾に處する會澤伯民の苦衷(一) / 石川諒一 / p34~39 |
和漢暦の占星記事の現代性(三) / 近藤芳一 / p41~45
水戸藩史話 / 久木獨石馬 / p59~61 |
8月、「大日 (61)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(布袋和尚)」 が掲載される。 pid/1595762
|
白隱墨蹟――(布袋和尚)
水藩幕末の紛擾に處する會澤伯民の苦衷(二) / 石川諒一 / p39~43
和漢暦の占星記事の現代性(四) / 近藤芳一 / p45~49 |
高天原雜記(三十六) / 田中逸平 / p53~55
水戸藩史話 / 久木獨石馬 / p59~61
北支那經輪を持て / 國松文雄 / p73~76 |
9月、「大日 (62)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(〔ビ〕猴 びこう)」 が掲載される。 pid/1595763
|
白隱墨蹟――(〔ビ〕猴 びこう)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(三) / 石川諒一 / p39~44
和漢暦の占星記事の現代性(五) / 近藤芳一 / p46~49 |
高天原雜記(三十七) / 田中逸平 / p56~58
何の爲に英語を學ぶか / 丸山莠三 / p61~62
〈抜粋〉 |
9月、「大日(63)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(鐵砲)」 が掲載される。 pid/1595764
|
白隱墨蹟――(鐵砲)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(三) / 石川諒一 / p43~47 |
高天原雜記(三十八) / 田中逸平 / p61~63
〈抜粋〉 |
10月、「大日(64)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(寒山拾得)」
が掲載される。 pid/1595765
|
白隱墨蹟――(寒山拾得)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(五) / 石川諒一 / p35~39
梅窓 / p40~40 |
和漢暦の占星記事の現代性(六) / 宅野田夫 / p41~47
〈抜粋〉
・ |
10月、「大日 (65)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(松茸) 」
が掲載される。 pid/1595766
|
白隱墨蹟――(松茸)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(六) / 石川諒一 / p35~40 |
高天原雜記(三十九) / 田中逸平 / p53~55
〈抜粋〉 |
11月、「大日 (66)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(鴉) 」 が掲載される。 pid/1595767
|
白隱墨蹟――(鴉)
太平洋會議と吾人の立場 / 千里槎客 / p15~17
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(七) / 石川諒一 / p26~31 |
高天原雜記(四十) / 田中逸平 / p48~50
〈抜粋〉
・ |
11月、「大日 (67)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(五位鷺)」
が掲載される。 pid/1595768
|
白隱墨蹟――(五位鷺)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(八) / 石川諒一 / p44~48 |
〈抜粋〉
・ |
12月、「大日 (68)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(瓢胎觀音)」
が掲載される。 pid/1595769
|
白隱墨蹟――(瓢胎觀音)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(九) / 石川諒一 / p30~34 |
〈抜粋〉
・ |
12月、「大日 (69)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(地藏菩薩) 」 が掲載される。 pid/1595770
|
白隱墨蹟――(地藏菩薩)
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(十) / 石川諒一 / p28~32 |
〈抜粋〉
・ |
○、この年、鷲尾順敬編「国文東方仏教叢書 法語部 上」が「東方書院」から刊行される。 pid/1242326
|
第二輯 國文 東方佛敎叢書
第一卷 法語部 上
寫眞 策彦周良筆大應國師法語
寫眞 古寫本空善聞書
法語 一卷 明惠高辨
邪正問答砂鈔 一卷 明惠高辨
廣疑瑞決集 五卷 敬西房信瑞
大應國師法語 一卷 南浦紹明
大燈國師法語 一卷 宗峰妙超
靈山和尚法語 一卷 徹翁義亨
紙衣謄 一卷 虎關師錬
月菴法語 一卷 月菴宗光
禪方便 二卷
空善聞書 一卷 空善
蓮如上人御物語次第
→一卷 蓮悟兼録
榮玄聞書 一卷 榮玄
勸修念佛記 二卷 一條兼良
麓草分 一卷 鈴木正三
石平山聞書 一卷
第二卷 法語部 下
寫眞 無難自筆人に與ふる法語
寫眞 山分插繪二河白道圖
對問法語 一卷 實觀
成佛の直路 一卷 慈等
玉かゞみ 一卷 木食以空
對賓法語 一卷 學如
慈雲和上法語 一卷
玲朧集 一卷 澤菴宗彭
祖心尼法語 一卷
人に與ふる法語 一卷 至道無難
おにあざみ 一卷 白隱慧鶴
千里一鞭 一卷 南溪老卵
十善戒信受の人に示す法語
→一卷 寂室堅光
扣響集 二卷 鐵牛道機
法の道芝 二卷 貞極
燧嚢 一卷 關通
山分 一卷 月感 |
安心問答 一卷 深勵
千代見草 二卷 日遠
第三卷 講説部
寫眞 永平發菩提心挿畫の一
寫眞 永平發菩提心挿畫の一の續
寫眞 釋迦如來策誕生
→曼多羅略解題畫
五常内義集 二卷
念佛名義集 三卷 聖光
淨土宗行者用意問答 一卷 良忠
圓頓戒要義 一卷 鎭增
妙法蓮華經大意 二卷 日遠
台宗綱要 一卷 靈空
眞言開庫集 二卷 蓮體
心經鈔 一卷 盤珪
佛祖正傳禪戒妙 一卷 萬仭
行乞篇 一卷 指月
道詠辨解永平發菩提心 一卷 東流
御文玄 一卷 法海
釋迦如來誕生曼多羅略解 一卷
第四卷 消息部
寫眞 親鸞聖人の慶信房に
→答ふる消息
寫眞 日像上人消息
寫眞 天海僧正消息
法然上人消息 一卷
親鸞聖人御消息集 一卷
末燈妙 一卷 從覺
親鸞聖人消息 一卷
惠信尼消息 一卷
一遍上人消息 一卷
日像上人消息 一卷
日輪上人消息 一卷
拔隊和尚消息集 一卷
日陣上人消息集 一卷
顯如上人消息 一卷
敎如上人消息 一卷
奧師消息集 一卷
天海僧正消息 一卷
|
澤庵和尚書翰録 一卷
第五卷 傳記部
寫眞 智證大師彫像
寫眞 解脱上人彫像
寫眞 蓮如上人畫像
寫眞 盤珪和尚畫像
眞言傳 七卷 榮海
解脱上人傳 一卷
隆實律師略傳 一卷
淨阿上人繪詞傳 三卷
國阿上人繪傳 五卷 相阿
日什上人自傳 一卷 日什
蓮如上人御若年の砌の事 一卷
蓮如上人御往生の奇瑞條々 一卷
桃水和尚傅賛 一卷 面山瑞方
大梅和尚年譜 一卷 玄芳
盤珪和尚行業略記
→一卷 逸山祖仁
德本行者傳 三卷 行誡
慧澄和上略傳 一卷 行誡
第六卷 寺志部
寫眞 信貴山縁起
寫眞 信貴山縁起
寫眞 石山寺縁起
南都七大寺縁起 一卷 實叡
廣隆寺大略縁起 一卷
淸水寺縁起 三卷
高雄山神護寺縁起 一卷
高雄山中興記 一卷
園城寺縁起 一卷
三井寺假名縁起 一卷
石山寺縁起 一卷
淸凉寺縁起 一卷
勸修寺縁起 一卷
信貴山縁起 三卷
眞如堂縁起 三卷
般舟三昧院記 一卷 三條西公條
宇治興聖禪寺記 一卷 中院通村
西芳精舍縁縁起 一卷 急溪中韋
|
山科實録 三卷 惠忍
敎行縁起 一卷
本願寺由來 一卷
政秀寺古記 一卷
阿彌陀寺記録 一卷
藏王堂再興縁起 一卷 快元
乙寶寺縁起 一卷
成相寺舊記 一卷 秀寬
書寫山縁起 一卷
白峯寺縁起 一卷 淸原良賢
竹林寺縁起 一卷
高野山事略 一卷 新井君美
四天王寺伽藍記 一卷
み山の枝をり 二卷 紹澄
身延鑑 三卷 日亮
第七卷 文藝部
寫眞 用明天皇職人鑑繪入本挿繪
寫眞 高信筆明惠上人 歌集奧書
小説六種
上野君消息 一卷
魔佛一如繪詞 一卷
玉藻草紙 一卷
月日のさうし 一卷
道成寺物語 三卷
二人比丘尼 二卷 鈴木正三
戲曲五種
阿彌陀胸割 六齣
釋迦八相記 五齣
念佛往生記 五齣 巣林子
用明天皇職人鑑 五齣 巣林子
おくめ粂之助 高野萬年草
→三齣 巣林子
歌謠
讃嘆敎化 一卷
法隆寺縁起白拍子 一卷 重懷
空也僧鉢扣歌 一卷 空也普明
延年連事並舞式 一卷
大風流 一卷
小風流 一卷 |
○、この年、伊豆碧山編「図像大集成 第4輯」が「仏教珍籍刊行会」から刊行される。 pid/1191026
|
第一圖 釋迦如來像(唐時代)和歌山 金剛峰寺/1
第二圖 釋迦如來像(唐時代)和歌山 晋門院/2
第三圖 釋迦如來像(堆古時代)奈良 法隆寺/2
第四圖 釋迦如來像(白鳳時代)奈良 蟹滿寺/2
第五圖 釋迦誕生像(天平時代)奈良 東大寺/2
第六圖 釋迦如來像(天平時代)京都 神護寺/2
第七圖 釋迦誕生像(天平時代)滋賀 善水寺/2
第八圖 釋迦如來像(弘仁時代)大阪 孝恩寺/3
第九圖 釋迦如來像(藤原時代)奈良 稱名寺/3
第一〇圖 釋迦如來像(藤原時代)京都 實林寺/3
第一一圖 釋迦如來像(鎌倉時代)京都 龍源院/3
第一二圖 釋迦如來畫像(鎌倉時代)京都 相國寺/3
第一三圖 釋迦誕生像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/3
第一四圖 釋迦如來像(鎌倉時代)紀州梅田 釋迦堂/4
第一五圖 釋迦如來像(鎌倉時代)京都 三室戸寺/4
第一六圖 釋迦如來像(鎌倉時代)尾道 西國寺/4
第一七圖 釋迦如來像(鎌倉時代)滋賀 常樂寺/4
第一八圖 釋迦如來像(鎌倉時代)京都 二尊院/4
第一九圖 釋迦如來像(鎌倉時代)京都 淨福寺/4
第二〇圖 釋迦如來像(鎌倉時代)京都 戒光寺/5
第二一圖 釋迦如來像(足利時代)出雲 華藏寺/5
第二二圖 釋迦如來像(江戸時代)京都 黄檗山大雄寶殿/5
第二三圖 釋迦如來像(江戸時代)京都 長福寺/5
第二四圖 釋迦如來像(江?時代)京都 南禪寺山門/5
第二五圖 藥師如來像(白鳳時代)奈良 新藥師寺/6
第二六圖 藥師如來像(白鳳時代)大阪 觀心寺/6
第二七圖 藥師如來像(白鳳時代)奈良 藥師寺/7
第二八圖 藥師如來像(白鳳時代)奈良 藥師寺/7
第二九圖 藥師如來像(弘仁時代)和歌山 五大院/7
第三〇圖 藥師如來像(弘仁時代)和歌山 龍泉院/7
第三一圖 藥師如來像(弘仁時代)奈良 元興寺/7
第三二圖 藥師如來像(弘仁時代)奈良 西大寺/7
第三三圖 藥師如來像(弘仁時代)京都 神護寺/8
第三四圖 藥師如來像(弘仁時代)大阪 孝恩寺/8
第三五圖 藥師如來像(弘仁時代)尾道 西國寺/8
第三六圖 藥師如來像(弘仁時代)滋賀 藥師堂/8
第三七圖 藥師如來像(藤原時代)奈良 南明寺/8
第三八圖 藥師如來像(藤原時代)滋賀 善水寺/9
第三九圖 藥師如來像(藤原時代)出雲 華藏寺/9
第四〇圖 藥師如來像(藤原時代)丹羽 寶林寺/9
第四一圖 藥師如來像(藤原時代)京都 神藏寺/9
第四二圖 藥師如來像(藤原時代)岐阜 願興寺/9
第四三圖 藥師如來像(鎌倉時代)和歌山 櫻池院/9
第四四圖 藥師如來像(鎌倉時代)和歌山 高室院/10
第四五圖 藥師如來像(鎌倉時代)滋賀 來迎寺/10
第四六圖 藥師如來像(鎌倉時代)和歌山 淨妙寺/10
第四七圖 藥師如來像(鎌倉時代)京都 寶菩提院/10
第四八圖 藥師如來像(鎌倉時代)京都 醍醐寺金堂/10
第四九圖 藥師如來像(鎌倉時代)滋賀 善勝寺/10
第五〇圖 維摩居士像(天平時代)奈良 法華寺/11
第五一圖 維摩居士像(鎌倉時代)奈良 興福寺/11
第五二圖 法相唯識曼荼羅像 奈良 興福寺/11
第五三圖 龍猛畫像(弘仁時代)京都 敎王護國寺/11
第五四圖 龍猛像(弘仁時代)和歌山 泰雲院/11
第五五圖 護法畫 像奈良 興福寺/12
第五六圖 惠果阿闍梨像 高知 金剛頂寺/12
第五七圖 日□連像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/13
第五八圖 富樓那像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/13
第五九圖 須菩提像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/14
第六〇圖 舎利弗像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/14
第六一圖 阿難像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/15
第六二圖 迦葉像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/16
第六三圖 羅□羅像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/17
第六四圖 迦旃延像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/17
第六五圖 阿那律像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/17
第六六圖 優婆離像(鎌倉時代)京都 大報恩寺/18
第六七圖 賓度羅跋羅墮闍像(江戸時代)京都 南禪寺山門/18
第六八圖 迦諾迦伐蹉像(江戸時代)京都 南禪寺山門/18
第六九圖 迦諾迦跋釐墮闍像(江戸時代)京都 南禪寺山門/18
第七〇圖 蘇頻陀尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19 |
第七一圖 墮矩羅尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七二圖 跋陀羅尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七三圖 迦理迦尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七四圖 伐闍弗多羅像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七五圖 戍博迦尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七六圖 半諾迦尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/19
第七七圖 羅怙羅尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第七八圖 那迦犀那尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第七九圖 因□陀尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第八〇圖 伐那婆斯尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第八一圖 阿此多尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第八二圖 注荼半陀迦尊者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第八三圖 伐那婆斯尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/20
第八四圖 那迦犀那尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/20
第八五圖 蘇頻陀尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/19
第八六圖 戍博迦尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/19
第八七圖 迦理迦尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/19
第八八圖 羅□羅尊者像(江戸時代)宇治 黄檗山/20
第八九圖 善財童子像(江戸時代)京都 南禪寺山門/20
第九〇圖 月蓋長者像(江戸時代)京都 南禪寺山門/21
第九一圖 善導大師像 滋賀 來迎寺/21
第九二圖 逹摩像 大和 逹磨寺/22
第九三圖 逹摩畫像 松江 天倫寺/22
第九四圖 逹摩像 京都 高相院/22
第九五圖 逹摩畫像 京都 東福寺/22
第九六圖 聖德太子像 愛知 性海寺/22
第九七圖 聖德太子像 奈良 興福院/22
第九八圖 聖德太子像 河内 叡福寺/22
第九九圖 聖德太子像 奈良 法隆寺/22
第一〇〇圖 聖德太子像 京都 藥薗寺/22
第一〇一圖 聖德太子像 尾道 淨土寺/22
第一〇二圖 聖德太子像 尾道 淨土寺/22
第一〇三圖 聖德太子像 尾道 淨土寺/22
第一〇四圖 聖德太子像 尾道 淨土寺/22
第一〇五圖 行基像奈良 西大寺/24
第一〇六圖 鑑眞像 奈良 唐招提寺/25
第一〇七圖 良辨像 奈良 東大寺/25
第一〇八圖 傳敎大師像 滋賀 延暦寺/26
第一〇九圖 勤操像 和歌山 普門院/27
第一一〇圖 弘法大師像 京都 大通寺/27
第一一一圖 弘法大師細部像 京都 大通寺/27
第一一二圖 弘法大師像 京都 神護寺/27
第一一三圖 慈覺大師像 滋賀 延?寺/28
第一一四圖 理源大師像 京都 醍醐寺/29
第一一五圖 良源像 京都 八角院/30
第一一六圖 俊仍像 京都 泉涌寺/30
第一一七圖 空也上人像 京都 六波羅密寺/31
第一一八圖 興敎大師像 京都 智積院/31
第一一九圖 榮西禪師像 京都 建仁寺/32
第一二〇圖 眞空上人像 京都 大通寺/33
第一二一圖 日蓮上人像 京都 本圀寺/33
第一二二圖 大明國師像 京都 南禪寺/34
第一二三圖 大明國師像 京都 南禪寺/34
第一二四圖 大燈國師像 京都 大德寺/34
第一二五圖 夢窓國師像 嵯峨 鹿王院/34
第一二六圖 夢窓國師像 嵯峨 妙智院/34
第一二七圖 無相大師像 京都 妙心寺/35
第一二八圖 無相大師像 京都 妙心寺/35
第一二九圖 親鸞上人像 京都 西本願寺/35
第一三〇圖 眞盛上人像 滋賀 西敎寺/36
第一三一圖 專譽上人像 奈良 長谷寺/37
第一三二圖 玄宥上人像 京都 智積院/37
第一三三圖 澤庵像 京都 聚光院/38
第一三四圖 鐵眼像 京都 寶藏院/38
第一三五圖 文覺上人像 京都 神護寺/38
第一三六圖 慈雲尊者像 京都 長福寺/39
第一三七圖 豪潮像 滋賀 延暦寺/40
第一三八圖 峨山像 京都 天龍寺/40
第一三九圖 白隱像 靜岡 松蔭寺/40
・ |
|
| 1934 |
9 |
・ |
1月、「大日 (70)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(寒梅)」 が掲載される。 pid/1595771
|
白隱墨蹟――(寒梅)
東亞樂園の設計素描 / 秋澤次郞 / p41~43 |
〈抜粋〉
・ |
1月、「大日 (71)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―布袋 」
が掲載される。 pid/1595772
|
白隱墨蹟――布袋
水藩幕末の紛擾に處せる會澤伯民の苦衷(十一) / 石川諒一 / p32~36 |
〈抜粋〉
・ |
2月、「大日 (72) 」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟」が掲載される。 pid/1595773
2月、「大日 (73)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(達磨)」
が掲載される。 pid/1595774
3月、「大日(74)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(達磨) 」 が掲載される。 pid/1595775
3月、「大日 (75)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(隻履達磨)
」 が掲載される。 pid/1595776
|
白隱墨蹟――(隻履達磨)
亞細亞遍路(七) / 田中逸平 / p64~65 |
〈抜粋〉
・ |
4月、「大日 (76 )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(布袋和尚)」
が掲載される。 pid/1595777
4月、「大日 (77)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(大燈國師) 」 が掲載される。 pid/1595778
5月、「大日(78 )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(達磨)
」 が掲載される。 pid/1595779
|
白隱墨蹟――(達磨)
日米國交の再檢討 / 秋澤次郞 / p17~19 |
明治神宮を通じて觀たる日本の國民性 / 山田司海 / p29~32
〈抜粋〉 |
5月、「大日 (79)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟―(出山釋迦)」
が掲載される。 pid/1595780
6月、「大日 (80)」が「大日社」から刊行される。 pid/1595781
|
白隱墨蹟―(隻履達磨)
民惟邦本―卷頭言 / p1~1
中外時事―遣滿使節宮を送り奉る=惡性の〔トク〕職罪責任=滿洲國承認の先驅=
→英國の正論家=救はれざる米國=強弩の末=日蘭會商代表の出發=
→濠洲親善使節を迎ふ=ブラジル移民法可決 / p2~6
政敎の拔本塞源――社説 / p7~10
國民精神の振興 / 副島義一 / p11~15
蒋提唱の支那の新生活運動 / 晩香園主人 / p16~18
撃鼓吹貝 / p19~19
新らしき三大思潮 / 栗岩英治 / p20~27
惰氣滿々の政局を詛ふ / 西村誠三郞 / p28~30
代辯聲明の奇功 / 高木繁 / p31~32
致誠日誌 / p33~33
神は南へ / 大三輪信哉 / p34~41
梅窓 / p42~42 |
内田翁の詞華 / 秋澤次郞 / p43~45
街路樹 / 芳洲生 / p46~46
本山松陰翁(六) / 關露香 / p47~50
財界雜爼 / 尺弓子 / p51~51
大庭柯公氏を夢みる(下) / 富永生 / p52~57
隨筆弘法大師(續) / 赤堀又次郞 / p58~61
水戸藩史話 / 久木獨石馬 / p62~64
滅び行く江戸名所 / 村田懋麿 / p65~67
老子歌評 / 中島氣崢 / p68~68
嵐の瞽使者(十九) / 千葉龜雄 / p69~72
新刊紹介寄贈雜誌 / p73~73
在留外人の眼に映じた歐洲政局と佛蘭西/S・S・G/p74~79
時事日誌 / p80~80
大絃小絃 / p81~81
裏畫 / 睡園生 |
6月、「大日(81 )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(布袋吹於福) 」 が掲載される。 pid/1595782
|
白隱墨蹟――(布袋吹於福)
國史を地方史の上に建てよ / 栗岩英治 / p37~41 |
〈抜粋〉
・ |
7月、間宮英宗が松田竹嶼編「禅とは是ぢや」を「日本禅書刊行会」から増修再販する。
pid/1133561 閲覧可能 初版:1921・3
|
主人公 / 1
瑞巖和尚の自問自答
徴兵令は一種の覺醒劑
生れて來た本意義を確得せよ
金錢に何んの威力がある
働く爲に働くに限る
那箇本來の面目 / 14
禪の有難いところ
眞理は唯一つ
住する所なくして其心を生ず
超越的な意味の偈示
禪機を全うする所以
力を以て爭ふべけんや
修行する程恥を知る
本來の面目中に活動する
結局五尺の飯袋だ
誠の力は天地間に響き渡る
借金の中へ飛び込む
扇子に對しても恥かしい
三界城と十方空 / 58
心は二三あるものではない
迷悟不二の好境涯
白隠のフン然うか
如來の光明 / 68
心の淨き人は幸なり
看る時見えず暗昏々
四無量心之れ光明
智惠の光明
閑不徹と大忙生 / 83 |
虚堂和尚の詩句
傍人の吟誦で啓發
簡禪師と徳山和尚との商量
明月大空に掛れるが如し
何事にも趣味 / 93
好き嫌ひは我儘の結果
悲みの中必ず樂あり
世の中には不幸も不平もない
一心に照鑑文を讀め / 106
人間は佛魔同體
取捨する能力が大切
怖るべき煩惱妄想の賊
無相の慈悲 / 115
衷心から流露する愛の心
水中の月の如く觀念せよ
投機の偈 / 122
機會は隨所にある
眞理の大機に投ぜよ
悉く私の心の顯現
山川草木總て佛祖の賜物
宗教の本當の妙味
茶禪一味 / 134
法源の古道場
六百年來の帆風門
幽寂の境涯
南無の解 / 139
此の世界は諸行無常
愚痴は道理に暗いから起る
本源に立ち返れば可い
|
碧巖録より / 151
圜悟禪師のこと
雲門の中興雪竇和尚
三歩と五歩
五歩には須く死すべし
虚榮の借着は不可
心に錦を着た乞食
懐中に爆裂彈
精神的大富豪となれ
天地と共に喜べ / 170
佛陀大悲の喜び
各階級其々喜ばせよ
貴き人生の寶玉
喜ぶも喜ばすも可なり
懐しき京の町 / 183
思へば恥かしい極み
鐵眼和尚に睨まるるやうな思ひ
八年目の會見
飾りなき所無限の妙趣
山窓閑話 / 192
我見我執を忘るるこそ妙
其道を進んで往けよ
眞淨老師の不撓不屈
松の雫
信頼する所へ飛び込め
直心是道場 / 214
童子の心は美しい
至る所總て修養の道場
火の熱いといふも妄語 |
惡い人でも自分の師匠
煩悶は何處から來るか
一切の念所を斷ぜよ
何處で題目を唱へても同じこと
無上の大きな寶
心の中の敵に打ち勝て
何處でも悟れる
心の持ち方一つ
十種の禪病 / 255
又一般病症である
宗教といふ藥
自信不及の病
自信のない動物
自力も他力も同じこと
自由を得ざる病
我見偏執の病は氣障
限量□臼〔カキュウ〕の人
機境不脱の病
少を得て足れりとするな
他流試合が肝要
正傳を尊んで旁宗をいやしむ
位貌拘束に捉はるるな
指磨淨盡
大悟徹底の人 / 298
根本的な宗教的な罪
光る素質はある
所謂佛作佛行
・
・ |
7月、「大日 (82)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(猿引翁)」
が掲載される。 pid/1595783
7月、「大日(83)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(鼠相撲)」
が掲載される。pid/1595784
|
白隱墨蹟――(鼠相撲)
鄕土研究界の現状(上) / 栗岩英治 / p16~22 |
武藏相模原紀行 / 小川柳坡 / p47~52
〈抜粋〉 |
8月、「日本及日本人 (8月1日號)(302)」が「政教社」から刊行される。 pid/1597236
|
新内閣――題詞
水さし三種 / 香取秀眞 / 口繪
大戰は霹靂の如く起る――題言 / p1~1
危局直前の贏弱内閣――主張 / p2~8
軍備の充實と經濟の發展 / 重訟淸行 / p9~12
外交・國防・政治の一元を論ず / 須山卓 / p13~22
日本の對支政策及び海軍政策――(外論二期)/末次政太郞/p23~27
對軍縮會議講策 / 東隅生 / p28~28
評林 / p29~29
國立公園の洋臭――千紫萬紅 / 乾?雪 / p30~31 (0045.jp2)
雲間寸觀 / p32~32
神意より見たる都市 / 丹羽生洲 / p33~35
警世詩話 / 凡山 / p36~36
安中藩主板倉勝明の事ども / 東山道人 / p37~43
言語の相違 / 佐野梅溪 / p44~44
佐藤信淵の事に就て / 赤堀又次郞 / p45~47
大夢語 / 大夢子 / p48~48
東方諸民族に關する事情 / 凌雲窟主人 / p49~51 |
壼中消息 / 無憂扇 / p52~52
日本文苑 / 館森袖海 / p53~55
俳句 / 寒川鼠骨 / p56~58
轉和白隱東嶺心經毒頌 / 村上霽月 / p59~59
露西亞文學に於ける歐羅巴的傾向(一) / 松井了隱 / p60~75
米十首集 / p76~76
易で釋く『竹取物語』(二) / 八木旭信齋 / p77~80
乘合船 / p81~81
堙滅せる古典を復活す(承前) / 岩出瓢翁 / p82~87
古今東西詩人年齡鑑 / p88~88
讀書日記(十六) / 銑鋧子 / p89~93
回敎精神の日本に於ける將來 / クルバン・ガリー / p94~94
豁然居士千日修業録 / 無念居士 / p95~96
日本英傑史謠(廿七) / 中島氣山 / p97~97
江戸時代の千社詣と千社札 / 遠峯章 / p98~99
内外半月誌――六月 / p100~103
玉石同架=新刊寄贈雜誌 / p104~104
・ |
8月、菅原洞禅が「禅門佳話」を「丙午出版社」から刊行する。 pid/1111421 閲覧可能
|
前篇一〔エイ〕石
至道無難禪師の前半生/1
關山と幸に愚堂の在る有り/6
日置默仙禪師發心の動機/8
承陽大師の脱落身心/11
水影を見て大悟せる洞山大師/13
眞桑瓜に釣られし大燈國師/16
清凉殿上の大法戰/18
虎聖を陷倒せる大光國師/20
松に八十往生を誓つた南天棒/22
喫茶喫飯底の常濟大師/24
願行の模範たる復古翁卍山/27
石川素童禪師參禪の經路/31
趙洲一僧の爲めに大道を説く/36
五組會下の第一人盧行者/38
白隱に參じて剃髮せる大橋太夫/41
星見天海和尚の行履/46
楠田病院長の九寸五分/49
尼の侮辱に發奮せる倶胝和尚/52
神機縱横の狼玄樓/55
澤庵和尚江戸入の眞相/58
秋野孝道師の跣足參り/61
惟嚴禪師と李文公/64
神尾將軍の參禪振/65
妻女を離別せし今北洪川/69
心越禪師の膽力/73
三度勅使を固辭せる木禪庵/75
眞個の師家松蔭和尚/78
鳥尾得庵伊藤公を一喝す/80
楠公决死の前日/82
志閑禪師と末山尼/84
新井石禪師得度の因縁/87 |
一塵一芥も皆是佛種/90
居士渡邊無邊の熊の皮/93
中篇二般土
自隱會下の俊才/97
東叡和尚陰徳の行持/100
脚下の知れぬ拾得の詩偈/103
鬼文常と高津拍樹/105
面皮を燎きし女禪客/106
勝海舟の錬膽術/110
惡辣の師家を選んだ祥山和尚/112
辛辣無類の燒禾山/115
慢心の折伏に發奮せる東坡居士/118
發狂と誤られたる阿察女/121
餅屋の説明をやつた小僧さん/123
口頭三昧の釋宗演師/125
風外和尚と猫/129
不意に大悟せる張九成と夢想國師/131
與奪自在は禪の本分/133
臨濟打爺の拳/136
乃木大將の參禪談/140
壙より掘出されたる通幻禪師/143
夏冬が一所に來たか珍龍さん/145
白隱禪師の地獄極樂/148
穆山禪師の眞面目/151
身心の鍛錬より見たる伊藤公/153
居士の胸中を看破せる默雷禪師/159
一休禪師の女人濟度/160
峻嚴なりし淺野斧山和尚/166
卍庵毒藥を投ぜられて大悟す/168
禪的性格の三博士/170
信長の師傅平手政秀/175
道に親しき祖岳和尚/179
|
白楽天を歸服せしめた道林和尚/181
筆と舌の咄堂居士/184
三昧を會得せる又十郎/187
遠羅天釜と二木博士の腹式呼吸/192
後篇三昧境
文献院古道漱石居士/197
智辯博識の聖一國師/200
努力主義の兒玉玄海和尚/203
鐵舟居士の無刀流/208
元兵の膽を奪ひし佛光國師/209
河野盤洲參禪の動機/212
夢裡に入宋せる夢想國師/215
路傍の婆子に遺り込められし徳山/217
反省會の米峰と禁酒會の米峰/220
一生菴主の正受老人/223
東瀛和尚と頭山滿/226
琢禪和尚の乞食連歌/229
妙心開山關山國師/231
禪機溌溂たる侯大隈重信/235
豪膽無類の由利滴水/236
一休に水を浴せし華叟和尚/238
默童禪師と稻荷の檢査官/241
牛頭山の法融禪師/243
大入道狐わなに罹る/245
一日作さざれば一日食はず/247
黄檗鐵眼禪師の大藏經/248
古人の難行を範とせよ/251
丹田の修養に努められし鈴木充美/252
桃花一見豁然大悟/254
西郷南洲の活作略/255
大火焔裡に示寂せる快川和尚/257
悟由禪師と虚空藏菩薩/259 |
8月、宝岳老師述,信濃教育会編纂「正受老人を看よ」が「信濃毎日新聞」から刊行される。pid/1024257 閲覧可能1000円
|
前篇
緒言/1
生立/5
わが身の觀音さま/6
悟を開く/12
よき師を求む/14
宗教のこと(一)/17
宗教のこと(二)/22
宗教のこと(三)/26 |
禪について(一)/29
禪について(二)/32
出家の機至る/36
明師に就く/38
行衞を晦ます/41
刻苦の光明/44
遍參/46
無欲/48
正受庵/50
|
三たび師の下へ/52
無難禪師のこと(一)/53
無難禪師のこと(二)/57
後篇
母を養ふ(一)/65
母を養ふ(二)/68
水戸公の招き/75
手洗石と栂の木/77
青ぶくれと狼/82
|
劍道の極意(一)/86
劍道の極意(二)/89
洒脱/93
白隱禪師(一)/96
白隱禪師(二)/100
栽松塔/104
・
・
・ |
8月、「日本及日本人 (8月15日號)(303)」が「政教社」から刊行される。 pid/1597237
|
黯無色――題詞
水滴二種 鶉と鹿 / 香取秀眞 / 口繪
鷹を以て鶴群を獲るの工夫――題言 / p1~1
華府條約の廢棄通告――主張 / p2~8
現下の日米關係概觀 / 近衞公 / p9~13
尺貫法存續の重要性 / 波多野二郞 / p14~16
道德經濟とアウタルキー / 養堂處士 / p16~17
六大國に跨る太平洋の活劇 / 末次政太郞 / p17~21
評林 / p22~24
雲間寸觀 / p25~25
敬天思想を呼び起せ――千紫萬紅 / 山田武吉 / p26~29
警世詩話(二) / 几山 / p30~30
外交・國防・政治の一元を論ず(下) / 須山卓 / p31~39
大夢語 / 大夢子 / p40~40
憐れなる北方の一民族より / ウイノクロフ / p41~45
ヒンデンブルグ元師 / 獨往子 / p46~46
亞細亞に於ける露國の動靜 / 凌雲窟主人 / p47~52
回敎徒は何を爲す可きか / 勿破滅道人 / p53~55 |
壼中消息 / 無憂扇 / p56~56
農村の子弟に望む / 小川冷光 / p57~60
獅眼鷹目 / 寸刀人 / p61~64
神號雷發 / 天孫兒 / p65~65
日本文苑 / 館森袖海 / p66~68
俳句 / 寒川鼠骨 / p69~71
轉和白隱東嶺心經毒頌(二) / 村上霽月 / p72~72
嗟陸天津子夫人 / 鼠骨 / p73~73
世界大山巨川鑑 / p74~74
一夜の舟行 / 月明瓜 / p75~79
乘合船 / p80~80
萬瀑洞を遡る / 閑雲 / p81~87
大日本書畫一覽 / p88~88
讀書日記(十七) / 銑鋧子 / p89~94
日本英傑史謠(廿八) / 中島氣山 / p95~95
内外半月誌 / p96~98
玉石同架=新刊寄贈雜誌 / p99~99
・ |
8月、「大日 (85)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(巖頭語)」 が掲載される。 pid/1595785
|
白隱墨蹟――(巖頭語) / (0007.jp2)
日米問題一九三六年への展望 / 井上淸純 / p11~19 |
〈抜粋〉
・ |
8月、福場保洲が「講の研究」を「東方書院」から刊行する。 (日本宗教講座) pid/1438259 閲覧可能
9月、「日本及日本人 (9月1日號)(304)」が「政教社」から刊行される。 pid/1597238
|
有宸憂――題詞
室町時代水滴四種 / 香取秀眞 / 口繪
辭世の英雄はなき乎――題言 / p1~1
姑息偸安の外交を排す――主張 / p2~8
農村を救ふ者は農民 / 大川澂光 / p9~12
道德經濟と世界平和 / 養堂處士 / p12~14
滿洲と拓務省 / 山田武吉 / p14~16
愈々となつてドカンとやれ / 甲原明 / p16~17
評林 / p18~19
盂蘭盆が三度ある話――千紫萬紅 / 無暦日生 / p20~23
雲間寸觀 / p24~24
眞日本 / 佐佐木四方志 / p25~46
日本人でない日本婦人 / 東隅生 / p47~47
警世詩話(三) / 凡生 / p48~49
「大戰は霹靂の如く起る」を讀みて / 志保井利夫 / p50~52
|
大夢語 / 大夢子 / p53~53
『日本若し戰はゞ』 / 黑眼子 / p54~60
面白い言葉 / 佐野梅溪 / p61~61
獅眼鷹目 / 寸刀人 / p62~67
壼中消息 / 無憂扇 / p68~68
日本文苑 / 館森袖海 / p69~71
俳句 / 寒川鼠骨 / p72~74
鶴お成り / 無窗居士 / p75~84
瀑觀詩程――(立山七十二首) / 國分靑厓 / p85~92
轉和白隱東嶺心經毒頌(其三) / 村上霽月 / p93~93
古今東西學者年齡鑑 / p94~94
白雲臺に登りて / 閑雲 / p95~98
乘合船 / p99~99
内外半月誌――(八月上旬) / p100~102
玉石同架=新刊寄贈雜誌 / p103~103 |
9月、「大日(86)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(鼠子槌子) 」 が掲載される。pid/1595786
|
白隱墨蹟――(鼠子槌子)
在滿政治機構の國策的改革 / 山田武吉 / p11~13
在滿機關の陸軍改組案 / 西村誠三郞 / p14~15 |
滿洲事變に依つて日本は何を得たか / 山田司海 / p24~28
第二回汎太平洋佛敎靑年大會に就て / 廣瀨了義 / p41~44
〈抜粋〉 |
10月、「大日 (88)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(栗文珠)」
が掲載される。 pid/1595775
10月、「大日 (89 )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(山水)
」 が掲載される。 pid/1595789
|
白隱墨蹟――(山水)
北滿屯墾團實際記録 / 山田武吉 / p19~24 |
〈抜粋〉
・ |
11月、「大日 (90)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(山水)」
が掲載される。 pid/1595790
|
白隱墨蹟――(山水)
風外和尚傳(二) / 加瀨藤圃 / p48~54 |
〈抜粋〉
・ |
11月、「大日 (91 )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(蛤蜊觀音)
」 が掲載される。pid/1595791
|
白隱墨蹟――(蛤蜊觀音)
風外和尚傳(三) / 加瀨藤圃 / p57~63 |
〈抜粋〉
・ |
12月、「大日(92)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(死) 」 が掲載される。 pid/1595792
|
白隱墨蹟――(死)
履霜堅氷至――卷頭言 / p1~1 |
風外和尚傳(四) / 加瀨藤圃/p58~62
〈抜粋〉
|
12月、「大日 (93)」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(拝牛)」
が掲載される。 pid/1595793
|
白隱墨蹟――(拝牛)
聖德太子と世界文化統一的使命 / 井上淸純 / p11~14 |
風外和尚傳(五) / 加瀨藤圃 / p63~69
〈抜粋〉 |
○、この年、東郷実が「精神日本の建設 : 農村問題と教育」を「玉川学園出版部」から刊行する。
(新日本教育叢書 ; 第1) pid/1076373 閲覧可能
|
前篇
一、 非常時日本の打開は農村から/3
二、 農村恐慌時代の出現/6
三、 農村行詰の眞相とその原因/8
四、 精神文化と物質文化/14
五、 フアウスト物語/17
六、 少女マーガレツテの墮落/22
七、 精神界に甦つて農業を初めたフアウスト/26
八、 外國模倣の弊を説いた南洲翁/29
九、 日本よ精神文化に還れ/35
一〇、 農村行詰の打開策/38
一一、 農政に主力を盡した鷹山公と
→フリードリツヒ大王/46
一二、 世界大戰と英獨兩國/49
一三、 先づ汝の鍬を政治家の頭に深く打ち込め/56
一四、 國難を立派に打開したデンマークの農民/59
一五、 國難と教育/65
一六、 百姓内閣の出現と農國デンマークの建設/71
一七、 國民高等學校と産業組合/74
一八、 デンマーク農民の眞劔な努力に學べ/78
一九、 愛に出發したデンマークの農業の發達/82
二〇、 建國の大精神に甦り、 |
→愛に出發せよ/86
二一、 武士の情/89
二二、 先づ感謝の念に目醒めよ/93
二三、 感謝に對する私の體驗/96
二四、 汝の權利を主張する前に
→先づ汝の義務を果せ/98
二五、 全體の幸福を目標として/105
二六、 國難は國民に犧牲を要求する/110
二七、 建國の大精神と昭和の新國是/116
二八、 天よりも高き我等の理想/119
後篇
一、 先づ教育の改善から/125
二、 創造的教育制度の確立/132
三、 教育の翻譯的内容を一掃せよ/135
四、 札幌農學校とクラーク先生/139
五、 日本には日本獨特のものを/143
六、 劃一主義に偏した日本の教育/149
七、 教育の要諦は角箱に丸杓子/152
八、 農村には農村の教育を與へよ/156
九、 杓子定規にも程度がある/160
一〇、 四民平等の教育に徹底せよ/164
一一、 先づ日本の歴史に出發せよ/170 |
一二、 日本商品の海外進出と
→産業主義/175
一三、 模倣から創造へ/180
一四、 力行的國民の完成/184
一五、 國民に精神力を與へよ/190
一六、 日本を救ふものは人格教育だ/194
一七、 子供よ大志あれ、大望あれ/199
一八、 正受老人と白隱禪師/204
一九、 吉田松陰とその教育/207
二〇、 教育は制度に非ずして『人』だ/211
二一、 先づ教育家としての
→天職に自覺せよ/215
二二、 人格教育の第一歩は
→小學教育から/219
二三、 小學校教員と師範教育の改善/222
二四、 宗教教育と家庭教育/228
二五、 三ツ兒の魂百まで/232
二六、 和協の心と愛の教育/238
二七、 光は日本の家庭より/243
二八、 第一の寶は『人』だ/246
・
・ |
〇この年、「皇道 第4号」が「大阪商科大学皇道研究会」から刊行される。 pid/1107747
|
吾等・田崎仁義 / 5
皇民意識・同 / 7
皇道原理・同 / 7
皇道經濟・同 / 8
吾等の任務・同 / 8
吾等の覺悟・同 / 9
一ケ年・同 / 10
生國魂神社參拜祝詞・池田近雄 / 11
謹奉賀皇太子殿下降誕歌並反歌・
→福島高商教授・葛西千秋 / 12
吾等同志・田崎仁義 / 13
皇道四原理・同 / 14
皇道の文化史的意識・小泉又三 / 22
感ずるままに・多田一雄 / 33 |
満洲國に於ける宗教及祭祀の
→状況に就いて・秋草實 / 38
皇道管見・吉田嘉祐 / 42
皇陵參拜記・土谷英二 / 47
伏敵門・吉田喜之 / 54
銷夏消息・田崎仁義 / 57
静岡、清水両市に於ける皇道會講演
日本平の大観
龍華寺及び鐵洲寺
清水の鈴興さん
興津の清見寺
白隱◇師の墓を原の松蔭寺に吊す
神道を研究せる東嶺◇師
沼津の大中寺
|
三重縣尾鷲引本に於て講演
神宮司廳及皇學館訪問
聯合艦隊の將士の神宮参拜
神風義塾見學 /
本居神社参詣
住友製鋼所事務所
→修養團講習會に皇道の講話
和歌(自第二十一回至第三十二回)
→附夏休暇の和歌 / 71
◇校舍に與ふる惜別の辭・小泉又三/ 93
消息・田所廣泰 白尾静二 平野正雄/ 96
例會報告 / 112
受贈圖書目録 / 117
・ |
○、この年、天岫接三が「白隠禅師坐禅和讃 : 聖典講義」を「仏教年鑑社」から刊行する。 pid/1234284 重要
|
口繪
國師號宣下詔書
禪師像(自作)
坐禪和讃(禪師直筆)
序文
序講 白隱禪師について / 1
第一講 衆生本來佛なり / 21
第二講 遠く求むるはかなさよ / 43 |
第三講 六趣輪廻因縁 / 63
第四講 摩訶衍の禪定 / 89
第五講 皆この中に歸するなり / 113
第六講 淨土即ち遠からず / 139
第七講 福を得ること限りなし / 163
第八講 自性即ち無性 / 183
第九講 因果一如の門 / 203
第十講 無相の相・無念の念 / 225 |
第十一講 四智圓明の月さえん / 251
第十二講 當所即ち蓮華國 / 275
白隱禪師傳法系譜 / 313
坐禪儀 / 315
白隱禪師年譜 / 319
註 / 349
・
・ |
○、この年、谷林孝雄が「悟道修養精話心の花 : 通俗平易」を「悟道修養部」から刊行する。 pid/1029023
|
第一説 修養の心 / 1
第二説 無限の寶 / 6
第三説 心の主人公/11
第四説 力強い心 / 15
第五説 眞劍の修養/19
第六説 苦樂 / 22
第七説 信仰の生活/29
第八説 正信と邪信/34
第九説 迷信打破 / 37
第十説 名は借物 / 40
第十一説 彼岸 / 44
第十二説 禪定 / 49
第十三説 生死 / 54
第十四説 さとり / 57
第十五説 犧牲心 / 62
第十六説 總ては心/71
第十七説 今生が大切/75
第十八説 人身受け難し/79 |
第十九説 遠離 / 84
第二十説 脚下を見よ / 89
第二十一説 本心は無我 / 92
第二十二説 光明 / 95
第二十三説 貪慾の炎 / 101
第二十四説 少慾は徳 / 105
第二十五説 無慾は美くし / 110
第二十六説 善惡 / 116
第二十七説 三毒煩惱 / 120
第二十八説 罪惡の消滅 / 126
第二十九説 深く學べよ / 129
第三十説 他力と自力 / 133
第三十一説 地獄と極樂 / 141
第三十二説 雪山童子 / 146
第三十三説 いろは歌 / 149
第三十四説 淺墓な夢 / 152
第三十五説 持戒 / 157
第三十六説 布施 / 162 |
第三十七説 忍辱 / 164
第三十八説 精進 / 169
第三十九説 智慧 / 173
第四十説 住所無き心 / 176
第四十一説 懺悔 / 180
第四十二説 煩惱即菩提 / 184
第四十三説 飾りを捨てよ / 188
第四十四説 悟りの入門 / 196
第四十五説 須彌の峯 / 205
第四十六説 三世心不可得 / 212
第四十七説 人に心を禪れ / 220
第四十八説 生老病死 / 224
第四十九説 人生の八苦 / 230
第五十説 五蘊 / 235
第五十一説 十二處十八界 / 237
第五十三説 四諦と八正道 / 243
第五十四説 十二因縁/246
第五十二説 四顛倒 / 240 |
第五十五説 六道輪廻 / 251
第五十六説 地藏菩薩 / 256
第五十七説 四聖 / 261
第五十八説 お佛壇と佛 / 266
第五十九説 目覺めよ勵め / 273
第六十説 三界は火宅 / 279
第六十一説 心の古里 / 284
第六十二説 浮世の流れ / 291
附録
摩訶般若波羅密多心經 / 298
般若心經和訓 / 298
白隱禪師座禪和讃 / 300
因果和讃 / 301
發菩提心空拳章 / 302
舍利禮文同和訓 / 305
四弘誓願文 / 306
・
・ |
○、この年、寺尾宏二が「後醍醐天皇と天竜寺」を「後醍醐天皇多宝殿再建奉賛会」から刊行する。 pid/1909221重要
|
總叙/1
本論/7
前編
一 皇室と嵯峨/7
二 本寺創立以前に於ける寺域/9
三 大覺寺統と嵯峨/16
四 後醍醐天皇/35
五 鎌倉末に於ける足利氏/49
六 足利尊氏/60
七 夢窓國師/85 |
中編
一 創建に至る迄/109
二 創建事情の推移/120
三 建立經過と天龍寺船/129
四 天龍寺落慶供養の盛儀/143
五 度々の臨幸/156
六 五山/161
後編
一 室町時代の天龍寺/169
二 戰國より德川時代へ/195 |
三 德川時代に於ける天龍寺/200
四 明治維新以降/211
附録/1
一 夢窓疎石法流系圖/1
二 白隱慧鶴法流系圖/3
三 天龍寺住持歴代/4
四 天龍寺塔頭子院/7
五 天龍寺所藏目録/13
六 天龍寺造營記/16
七 臨川家訓/39 |
○、この年、茂野染石が「駿馬豆人」を「沼津通信社」から刊行する。 pid/1025722
|
情話
初春の一夜/1
或藝妓の悲哀/20
カフエの話/25
濱叶濱勇/30
花柳噂の聞書/35
女給いろいろ/40
葉櫻月夜/45
お多福の死/62
往く女來る女/67
女給だん子/72
驟雨の後/77
あの妓この妓/89
成金三人女/94 |
富菊とは誰/104
當り歳の藝妓/107
菊の家喜美次/110
役者ぞろひ/115
散文
白隱禪師と私/121
沼津の贋書畫/127
市民市長説を笑/136
院展小感/141
小山田市長に與ふ/144
帝展瞥見/149
三國棋談/157
賀状を眺めて/163
藝妓三人/99 |
人物
伊東訥郎君/167
山本鷹藏君/169
緒明圭造君/171
中澤龍太郎君/173
山本廣君/175
湯山仁平君/177
植田彌太郎君/179
渡邊藤助君/181
廣田傳一君/183
黒田重兵衞君/185
村山義孝君/187
朝日原作君/189
菊地淡水君/191 |
河合貞治君/193
長倉詮郎君/195
廣木四郎君/197
浦六佐エ門君/199
仙石照君/201
三井純一君/203
根上信君/205
小久江文次郎君/207
吉田弘道君/209
山田福松君/211
立柄俊毅君/213
・
・
・ |
○、この年、伊豆碧山編「※図像大集成 第5輯」が「仏教珍籍刊行会」から刊行される。 pid/1191035
|
第一圖 不空金剛像 京都 高山寺/1
第二圖 不空金剛像 京都 敎王護國寺/1
第三圖 行敎律師像 京都 神應寺/2
第四圖 義淵僧正像 京都 神護寺/2
第五圖 行信僧都像 奈良 法隆寺/2
第六圖 大應國師像 京都 大德寺/2
第七圖 眞濟上人像 京都 神護寺/3
第八圖 眞紹僧都像 京都 禪林寺/3
第九圖 智證大師像 京都 園城寺/3
第一〇圖 解脱上人像 奈良 笠置寺/4
第一一圖 承陽大師像 越前 水平寺/4
第一二圖 承陽大師像 京都 興聖寺/5
第一三圖 眞空上人像 京都 大通寺/5
第一四圖 聖一國師像 京都 東福寺/6
第一五圖 圓鑑禪師像 京都 東福寺/6
第一六圖 南院禪師像 京都 南禪寺/7
第一七圖 常濟大師像 鶴見 總持寺/7
第一八圖 虎關禪師像 京都 東福寺/7
第一九圖 友梅禪師像 京都 建仁寺/8
第二〇圖 志玄禪師像 京都 慈濟院/8
第二一圖 無涯浩禪師像 京都 建仁寺/8
第二二圖 慈均禪師像 京都 南禪寺/8
第二三圖 周澤禪師像 京都 壽寧院/8
第二四圖 周信禪師像 京都 慈氏院/9
第二五圖 在光和尚像 京都 東福寺/9
第二六圖 普濟禪師像 京都 金地院/9
第二七圖 宗因禪師像 京都 龍安寺/9
第二八圖 華叟和尚像 京都 大德寺/9
第二九圖 春浦和尚像 京都 大德寺/9
第三〇圖 蓮如上人像 京都
→本願寺山料別院/10
|
第三一圖 特芳和尚像 京都 龍安寺/10
第三二圖 周麟像 京都 慈照院/11
第三三圖 宗牧禪師像 京都 大德寺/11
第三四圖 大体禪師像 京都 龍安寺/11
第三五圖 宗淑禪師像 京都 大德寺/11
第三六圖 月航禪師像 京都 龍安寺/11
第三七圖 玉仲和尚像 京都 大德寺/11
第三八圖 元佶和尚像 京都 圓光寺/12
第三九圖 日海上人像 京都 寂光寺/12
第四〇圖 本光國師像 京都 金連院/12
第四一圖 宗渭禪師像 京都 高桐院/12
第四二圖 即非禪師像 京都 萬福寺/12
第四三圖 獨立禪師像 京都 黄蘗山/13
第四四圖 性□禪師像 京都 萬福寺/13
第四五圖 大典禪師像 京都 慈雲院/13
第四六圖 白隱禪師像 京都 鹿王院/13
第四七圖 覺寶像 滋賀 延暦寺/13
第四八圖 滴水和尚像 京都 天龍寺/14
第四九圖 義演僧正像 京都 醍醐寺/14
第五〇圖 策彦禪師像 京都 妙智院/15
第五一圖 覺超僧都像 滋賀 延暦寺/15
第五二圖 法然上人像 京都 知恩院/15
第五三圖 虎林禪師像 京都 天龍寺/16
第五四圖 大應國師像 京都 鹿王院/16
第五五圖 宗鏡禪師像 京都 鹿王院/16
第五六圖 松永貞德像 京都 實相寺/16
第五七圖 鳳林和尚像 京都 鹿苑寺/16
第五八圖 北間和尚像 京都 鹿苑寺/16
第五九圖 西笑和尚像 京都 金閣寺/17
第六〇圖 養叟和尚像 京都 大德寺/17
第六一圖 大綱禪師像 京都 大德寺/17 |
第六二圖 大聖國師像 京都 高桐院/17
第六三圖 本光禪師像 京都 聚光院/17
第六四圖 佛性心宗禪師像 京都 龍源寺/17
第六五圖 大悲廣通禪師像 京都 高桐院/17
第六六圖 佛光國師像 京都 寶慈院/17
第六七圖 靈源和尚像 京都 天龍寺/17
第六八圖 英中玄賢禪師像 京都 天授菴/17
第六九圖 匝三毒湛像 京都 南禪寺/17
第七〇圖 有樂薺像 京都 正傳院/17
第七一圖 習鑑禪師像 京都 聽松院/18
第七二圖 融通念佛縁起圖 京都 禪林寺/18
第七三圖 釋尊の衆生薺度像/18
第七四圖 釋迦尊像/18
第七五圖 釋尊像/18
第七六圖 釋尊座像/18
第七七圖 釋尊立像/18
第七八圖 釋尊上首像/19
第七九圖 佛像首/19
第八〇圖 三尊佛像/19
第八一圖 日羅像 奈良 橘寺/19
第八二圖 僧形八幡禪像 奈良 東大寺/19
第八三圖 僧形八幡禪像 奈良 藥師寺/19
第八四圖 男神像 京都 松尾神社/19
第八五圖 女神像 京都 松尾神社/19
第八六圖 仲伸津姫命像 奈良 藥師寺/20
第八七圖 丹生明神像 和歌山 金剛峰寺/20
第八八圖 狩場明神像 和歌山 金剛峰寺/20
佛師の禁制六ケ條/21
佛工及び佛像畫師略傳/24
・
・ |
※「 国訳秘密儀軌 続図像部 第5輯 仏教珍籍刊行会」とは(pid/1241503)同本か確認が必要法 保坂 |
| 1935 |
昭和10 |
・ |
1月、「大日 (94) )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟」 が掲載される。pid/1595794
1月、「大日 (95) )」が「大日社」から刊行され、口絵欄に「白隱墨蹟――(古劍名)」
が掲載される。 pid/1595795
|
白隱墨蹟――(古劍名)
日本民族の正しき信仰 / 宇佐美景堂 / p29~30
鄕土史の編纂に就て / 赤堀又次郞 / p38~42 |
風外和尚傳(六) / 加瀨藤圃 / p65~67
〈抜粋〉
・ |
4月、釈瓢斎が「白隠和尚」を「人文書院」から刊行する。」 pid/1242642 閲覧可能
|
誕生/1
生立/13
無字/80
犬公方/95 |
懷疑/122
工夫/147
怪奇/156
接得/171 |
機發/194
透關/229
大悟/267
白幽/282 |
化導/296
門葉/318
入滅/324
・ |
|
7月、白隠著「藪柑子(ヤブコウジ)」が「竜吟社」から刊行される。 pid/1148985 (貳百部限定刊行) 閲覧可能
|
藪柑子解説/白隠和尚は、先妣五年忌に當りて、追修の爲めに、撰述して岡山候侍側に送りたるもの、即ち六十九歳の時なりとす。無生音を聞くの急要なることを説似して尤も親切を極めたり。自筆刻本に依れり。
本書は、白隠和尚全集発行の浄業に關し指導※鞭撻を賜りし諸先生に贈るため、同全集中より抜刷製本せるものなり。」 |
※鞭撻(べんたつ):① むちで打ってこらしめること。 ② 努力をおこたるなと強くはげますこと。叱咤激励(しったげきれい)すること。
9月、喜田貞吉が「福神の研究」を「日本學術普及會」から刊行する。 所蔵:県立長野図書館
9月、釈瓢斎が「瓢斎随筆」を「人文書院」から刊行する。 pid/1236049 閲覧可能
|
鴨水の荒魂/1
現成公案/7
素人の疑惑/13
梅天二階記/17
首塚眞僞/45
名族/47
楠伯爵/50
嘘の發達/52
|
詳考學/55
七生報國/58
南方蜂起/60
活史料/63
峽谷秘事/66
白隱和尚/69
日本騷動禪/95
指方立相/98 |
異安心/140
ヒヨツトコ安心/143
信州美人系/148
一茶は富農/156
俳壇下坐行/179
若槃面は笑ふ/189
蕪村と丈山/208
芭蕉と伊賀越/230
|
庄川峽の探勝/245
小豆島・遊女・瓢簟/259
茶人の感心/268
法隆寺俗談/277
名優不心得/309
鴈治郞氏と羽左衞門氏/312
・
・ |
9月、「塔影 11(9)」が「塔影社」から刊行される。 pid/1897466
|
表紙繪 / 菊池契月/表紙
題字/橫山大觀
扉繪/望月春江
口繪原色版
口繪寫眞版
僧畫寫眞版
展覽會出品寫眞版
坊さんの繪に就て / 正木直彦/p2~3
白隱師弟の繪事 / 森大狂/p4~9
|
良寬の書について / 相馬御風/p10~12
良寬和尚を尋ねて / 橫尾翠田/p13~15
畫僧風外 / 添田達嶺/p16~27
香積寺風外禪師 / 高橋竹迷/p28~32
仙厓の繪に就て / 安達荒村/p33~34
龍泰寺佛乘禪師 / 高橋竹迷/p35~38
僧畫の眞骨頂 / 神崎憲一/p39~41
日本畫壇囘顧四十年 / 關如來/p42~44
傳統禮讃 / 藤田嗣治/p45~47 |
わすれぬもの / 長谷川時雨/p48~49
橋本左内先生の肖像 / 島田墨仙/p50~52
さんいんの海岸 / 池田遙邨/p53~53
展覽會批評/p54~60
長唄の一蝶と歌麿 / 高澤初風/p61~61
畫壇鳥瞰/p62~65
カツト/翠雲、秀畝、紫峰、咄哉州、半圃
・
・ |
10月、淡川康一が「僧仙[ガイ]の絵画 : 近世の禅画を中心にして」を「高尾書林」から刊行する。 pid/1147258
|
近世の禪畫 / 1
仙厓の繪畫 / 9
聖福住山當時 / 16
|
虚白院時代 / 19
長養期の墨蹟 / 21
厓畫の特質 / 24
|
結辭 / 31
秋圃作 仙厓禪師頂相
仙厓作 寒山拾得圖
|
白隱作 ままの浮きはし圖
月船賛 文麗作 鐘旭圖
・ |
12月、日本歴史地理学会編「歴史地理 66(6)(431)」が「吉川弘文館」から刊行される。 pid/3566682
|
雜録 喜田博士より / 花見 ; 喜田貞吉/p80~86
紹介 新刊紹介/p87~91
福神研究(喜田貞吉著) / 花見朔巳/p87~87
日本書記纂疏(國民精神文化研究所編) / 石村/p87~88
眞福寺善本目録(黑板勝美編) / 桃/p88~88 |
曹洞宗大年表(大久保道舟編) / 花見/p88~89
鎌倉武士と禪(鷲尾順敬著) / 玉村竹二/p89~89
沈み行く東京(菊地山哉著) / 蘆田伊人/p89~90
京津間琵琶湖疏水開鑿の計畫 / 寺尾宏二/p92~93
・ |
12月、小田部荘三郎が「健康新道」を「春陽堂」から」刊行する。 pid/1049358 閲覧可能
|
第一 健康の創造と深呼吸の影響/1
健康破産時代の思ひ出/1
誤診から斷末魔へ/3
七ヶ年あまりの長患/7
二回の大手術と老看護婦の親切/11
急性骨髓骨膜炎と小兒の發育障害/13
強肺と肺病豫防への焦慮/16
深呼吸の原理を直覺するまで/19
驚異的なる深呼吸の效果/23
病弱な子を持つ親人への老婆心/28
第二 ホルモンと若返り法/35
老を早め死に急ぎつつある現代人/35
性的早老の根本的療法/38
ホルモン療法の歴史/41
傳説に現はれたるホルモンと犯罪/45
ホルモンの意義とその所在/47
ホルモンの本體とその使命/49
生殖腺ホルモン異常による男性體質の頽化/53
女性生殖腺の早朽による體質の頽化/57
ホルモンと榮養、糖尿病の症状とその豫防/59
甲状腺ホルモンの缺乏と一寸法師の由來/63
ホルモン療法に捉はれ過ぎるな/68
結核性ホルモン腺の治療について/72
性力の回復を自然に求めよ/75
姙娠と深呼吸/78
第三 深呼吸の原理と先哲の呼吸法/82
古人の生活と深呼吸/82
健康は先づ内臟から/86
深呼吸による全身筋骨の發達/90
深呼吸と胸腹腔内壓、血流及び淋巴流/93
深呼吸と動脈硬化 血壓亢進及び腦溢血/96
なぜ肺臟は結核に罹り易いか/99
肺尖の結核性素因と深呼吸の偉力/102
直接組織呼吸の殺菌力と
→結核菌の驅除運動/103
運動は結核菌の發育を阻止す/106 |
結締組織の増殖と動脈性充血の殺菌作用/108
深呼吸と肋膜炎/111
貝原益軒の丹田呼吸法/113
白隱禪師の内觀調息法/118
平田篤胤の數息呼吸法/122
平野元良の歌誦呼吸法/126
第四 深呼吸の型とその方法/134
スポーツ或は深呼吸法に現はれる
→呼吸式とその型について/134
初心者に對する深呼吸法とその回數/137
深呼吸運動はなるべく裸體で行へ/141
A級深呼吸法/144
B級深呼吸法/148
C級深呼吸法/156
第五 深呼吸と運動療法/161
呼吸器病患者に對する深呼吸療法/161
深呼吸療法の適否/167
運動療法の黎明/169
安靜療法に對する警鐘亂打/171
運動療法の分類とそれを行ふ順序/177
サラリーマンが勤務しながらの
→肺病治療法/183
第六 簡易體質改造法/190
手近にある榮養食/190
日光浴の原理と實際/199
深呼吸を基調とする一分間健康法/208
容易く出來る體力精力の増進法/214
強心強肺鍛錬法/223
スポーツマンの強肺増健法/229
青空恐怖症と深呼吸に對する
→二三の誤解/233
呼吸器病患者にすすめたい
→〔オン〕ニコニコ主義/239
第七 全快後記/248
難病を征服せる三青年/248
家庭と健康の創造/252
|
健康を創造して/257
十年の大患をK・O/258
五月四日の大喀血と早立二回戰の思ひ出
安靜禮讃、運動恐怖
安靜療法より取舵一杯の方向轉換
先づ飯より治せ
大根おろしとトマト
人間と兎の競爭
孔子の樂しみと保健の要諦
駿河富士に直面して深呼吸
外氣療法と空氣の美味
熱天凍地勞働の快味
何事にも無理は禁物
深呼吸法とその感想/285
深呼吸法と玄米食
零下十度に於ける深呼吸運動
深呼吸法の眞價
深呼吸體驗十年の記/291
死の宣告で蒼くなつた私
深呼吸に救ひ上げられて
喀血しながら深呼吸を行ふた實驗
深呼吸を行つて歩けなくなつた體驗
安心して出來る深呼吸の方法
活力増進法としての深呼吸
第八 小學兒童及び陸海軍人の
→健康増進と深呼吸運動/303
深呼吸運動による學童の胸圍増進/303
學童の胸圍増進は
→結核豫防への捷徑なり/309
深呼吸運動による胸圍の増進及び
→頸腺腫脹の解消/313
學童の體育上に及ぼす深呼吸と
→體操及び榮養食との影響/318
學校給食による學童の健康増進と
→深呼吸の實施/321
陸海軍人の深呼吸運動/324 |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第1巻」が「竜吟社」から刊行される。
pid/1236827
|
龍澤開祖神機獨〔ミョウ〕禪師年譜因行格(一―四四)/1
龍澤開祖神機獨〔ミョウ〕禪師年譜果行格(一―三四)/1
獨〔ミョウ〕禪師年譜補註(一―二六) / 1
荊棘叢談
序(一―二) / 105
本文(一―四二) / 107
壁生草
卷上(一―三二) / 1
|
卷中之上(一―三) / 1
卷中之下(一―一八) / 1
卷下(一―二〇) / 1
寶鑑貽照(一―三六) / 1
龍澤創建東嶺慈老和尚年譜(一―一〇二)/1
開山至道無難菴主禪師行録(一―一二)/1
即心記(一―五〇) / 5
自性記(五一―九八) / 55
|
正受老人崇行録(一―四六)/1-524
前付
白隱和尚全集發行趣旨 / 1-4
小引 / 1-6
白隱和尚全集(全八卷)解説 / 7-32
白隱和尚全集(全八卷)見返繪
→前相國寺派管長 橋本獨山師
・ |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第2巻」が「竜吟社」から刊行される。
pid/1236843
|
荊叢毒蘂
序 / 1
目録 / 5
卷第一 / 7
卷第二 / 43
卷第三 / 81
卷第四 / 101
卷第五 / 131
卷第六 / 165
|
卷第七 / 197
卷第八 / 227
卷第九 / 255
荊叢毒蘂拾遺
目録 / 303
本文 / 305
息耕録開筵普説
序 / 365
印施解 / 369
|
本文 / 375
息耕録評唱剩語 / 445-450
口繪 / 5
一 白隱和尚筆『法具變妖之圖』(其一) (京都金臺寺藏)
二 白隱和尚筆『法具變妖之圖』(其二) (京都金臺寺藏)
三 白隱和尚筆『法具變妖之圖』(其三) (京都金臺寺藏)
四 白隱和尚筆『法具變妖之圖』(其四) (京都金臺寺藏)
五 白隱和尚筆『法具變妖之圖』(其五) (京都金臺守藏)
・ |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第3巻」が「竜吟社 」から刊行される。 pid/1236865
|
評唱龍寶開山國師語録拙語 / 1
槐安國語標目 / 9
槐安國語開筵垂示 / 13
槐安國語
卷一 / 15
卷二 / 69
卷三 / 141
卷四 / 155
|
卷五 / 223
卷六 / 301
卷七 / 357
後序 / 369
槐安國語骨董稿
卷之上 / 379
卷之下 / 509-584
口繪 / 6 |
一 板本槐安國語序初丁 /
二 白隱和尚自筆註『大燈録』(京都 猪熊信男氏藏)
三 白隱和尚筆『大燈國師』(東京 侯爵細川護立氏藏)
四 白隱和尚筆『大燈國師示衆』(東京 侯爵 細川護立氏藏)
五 白隱和尚筆『大應國師』(東京 侯爵 細川護立氏藏)
六 白隱和尚筆『關山國師』(東京 侯爵 細川護立氏藏)
・
・ |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第4巻」が「竜吟社」から刊行される。
pid/1236889
|
寒山詩闡提記聞
寒山詩闡提記聞序(一―六) / 1
三隱詩集序闡提記聞(一―二〇) / 7
卷第一(一―九六) / 27 |
卷第二(一―一二二) / 123
卷第三(一―一一二) / 245
後記(一一三―一二〇) / 357
寒林貽寶 |
本文(一―一四) / 365
附刻(一五―二〇) / 379)
隻手音聲
本文(一―二〇) / 385-404 |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第5巻」が「竜吟社」から刊行される。
pid/1236900
|
布鼓 / 1
再□布鼓 / 19
假名因縁法語 / 87
遠羅天釜
序 / 105
卷之上 / 107
卷之中 / 153
卷之下 / 171
遠羅天釜續集 / 211
寶鏡窟之記 / 247 |
於仁安佐美 / 257
藪柑子 / 319
夜船閑話
序 / 341
卷之上 / 349
卷之下 / 367
邊鄙以知吾
卷之上 / 401
卷之下 / 427
さし藻草 |
卷一 / 451
卷二 / 477-512
口繪 / 7
一 駿河松蔭寺本堂と開山堂
二 伊豆龍澤寺禪堂
三 白隱和尚筆木額『大疑堂』(伊豆 龍澤寺藏)
四 白隱和尚筆木額『聽松窟』(駿河 松蔭寺藏)
五 白隱和尚作『お福の土像』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
六 白隱和尚自筆刻本『夜船閑話』(東京 石井光雄氏藏)
七 白隱和尚自筆刻本『遠羅天釜』(東京 石井光雄氏藏) |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第6巻」が「竜吟社」から刊行される。 pid/1236913
|
八重葎
卷之一 / 1
卷之二 / 49
兎專使稿 / 121
福來進女 / 149
壁訴訟 / 155
假名葎
卷一 / 163
卷二 / 177
おたふく女郞粉引歌 / 219
主心お婆々粉引歌 / 231
施行歌 / 239
安心法興利多々記 |
序 / 243
本文 / 245
大道ちよぼくれ / 251
子守唄 / 257
草取唄 / 263
善惡種蒔鏡和讃 / 269
坐禪和讃 / 283
孝道和讃 / 285
寢惚之眼覺 / 291
毒爪牙 / 301
杖山百韻 / 305
四智辨 / 323
藻鹽集
|
序 / 333
本文 / 335
讃語 / 345
雜纂 / 357
鵠林尺牘 / 379-540
口繪 / 7
一 白隱和尚自筆刻本『八重葎』
二 白隱和尚自筆刻本『兎專使稿』
三 白隱和尚自筆刻本『假名葎』
四 白隱和尚自筆刻本『おたふく女郞粉引歌』
五 白隱和尚作『お福の圖』(東京 侯爵 細川護立氏藏)
六 白隱和尚作板本『安心法興利多々記』
七 白隱和尚自筆刻本『坐禪和讃』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
|
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第7巻」が「竜吟社」から刊行される。
pid/1236926
|
退養雜毒海 / 1
宗門無盡燈論
序 / 59
品目 / 65
卷之上 / 67
卷之下 / 125
刻宗門無盡燈論録由 / 174
宗門無盡燈論願力辨 / 177
五家參詳要路門
序 / 187
第一 / 191
第二 / 200
第三 / 210
第四 / 222
第五 / 228 |
第五 / 228
附録二門 / 233
跋 / 245
東嶺和尚法語快馬鞭
序 / 247
卷之上 / 249
卷之中 / 265
卷之下 / 283
後序 / 292
自笑録
序 / 295
目次 / 297
卷上 / 299
卷中 / 343
卷下 / 415
|
笑禪師聚會品目 / 452
跋 / 454-456
口繪 / 8
一 東嶺和尚點眼、遂翁和尚筆『白隱和尚像』
→(東京 侯爵 細川護立氏藏)
二 東嶺和尚筆『東嶺和尚像』(伊豆 龍澤寺藏)
三 遂翁和尚筆『釋迦』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
四 遂翁和尚筆『文殊』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
五 遂翁和尚筆『普賢』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
六 東嶺和尚筆『達磨』(東京 阿部充家氏藏)
七 遂翁和尚筆『雪中の梅』(東京 金地院藏)
八 遂翁和尚筆『定上座圖』(東京 金地院藏)
九 東嶺和尚筆『禪經達磨之尊像』(伊豆 深澤貞吉氏藏)
一〇 東嶺和尚筆『達磨』(京都 後藤光村師藏)
一一 東嶺和尚筆『白隱和尚像』(伊豆 龍澤寺藏) |
○、この年、白隠和尚全集編纂会編「白隠和尚全集 第8巻」が「竜吟社」から刊行される。 pid/1236938
|
要行開山靈源和尚遺録
初卷 / 3
中卷 / 11
後卷 / 33
附録 / 43
開山靈源和尚法語雜集 / 51
寶藏萬藏塒 / 65
爛柘柴
序 / 79 |
目次 / 83
上篇 / 85
下篇 / 143
行状 / 199
扶宗大綱禪師斯經和尚遺稿 / 209
願心道場旨趣 / 271
圓桂祖純禪師語録 / 291
九峰和尚語録 / 343
拾遺 / 419-442 |
口繪 / 8
一 靈源和尚筆『達磨の圖』(侯爵 細川護立氏藏)
二 靈源和尚筆『麻三斤』(侯爵 細川護立氏藏)
三 遂翁和尚筆『鐘馗の圖』(侯爵 細川護立氏藏)
四 遂翁和尚尺牘(其一)
五 遂翁和尚尺牘(其二)
六 白隱和尚筆『濃陽富士山記』(美濃 富士神社藏)
七 白隱和尚筆註『法華經』(駿河 松蔭寺藏)
八 白隱和尚の靈塔(駿河 松蔭寺) |
○、この年、宮裡祖泰編「白隠禅師法語集」が「文仁会」から刊行される。 pid/1177895
|
白隱禪師略傳 / 3
坐禪和讃 / 6
施行歌 / 7
安心ほこりたゝき / 12
大道ちよぼくれ / 17 |
主心お婆粉引歌 / 22
おたふく女郞粉引歌 / 28
寢惚之眼覺 / 38
見性成佛丸方書 / 45
辻談議 / 48 |
假名法語 / 59
寳鏡窟記 / 70
夜船閑話 / 78
遠羅天釜 / 98
・ |
○、この年、妙心寺開創六百年紀念雪江禅師四百五十年遠諱大法会局編「 妙心寺六百年史」が「
妙心寺開創六百年紀念雪江禅師四百五十年遠諱大法会局」から刊行される。 pid/1214504
|
序
凡例
宗匠系譜略
序論
〔一〕 妙心寺開創以前の臨濟宗史概觀 / 3
〔二〕 妙心寺六百年史の時代區劃と
→其概要/33
本論
〔一〕 開創期
第一章 無相大師の宗風
(二) 花園法皇の御歸依と妙心寺開創/57
(三) 大師御傳考異 / 70
第二章 微妙大師の嗣法
(一) 授翁藤房論 / 76
(二) 妙心住後の授翁宗弼 / 84
第三章 無因因禪師と日峰舜禪師
(一) 無因宗因と應永の亂 / 89
(二) 龍雲寺時代と日峰の妙心寺復興/97
第四章 義天詔禪師及寺格寺統の諸問題
(一) 義天玄紹禪師 / 102
(二) 寺格・寺統の確立と發展 / 106
(三) 紫衣紛諍別記 / 121
(二) 發展期
第一章 中興雪江宗深禪師
(一) 當時に於ける五山の禪風 / 129
(二) 雪江禪師の家風 / 138
(三) 細川勝元の歸崇 / 147
(四) 義天と雪江並に門下の龍象 / 153
第二章 四派の發展 |
(一) 龍泉派の發展 / 161
(二) 東海派の發展 / 175
(三) 靈雲派の發展 / 198
(四) 聖澤派の發展 / 210
第三章 諸侯將の外護
(一) 發展期初頭の歸依者 / 222
(二) 武田信玄 / 233
(三) 上杉謙信 / 244
(四) 今川義元及織田信長 / 249
(五) 明智光秀及豐臣秀吉 / 257
(六) 桃山時代の諸公の外護 / 267
第四章 官刹・僧録の制定と妙心寺
(一) 五山十刹の制定及僧録司 / 282
(二) 家康の施政と臨濟諸山の法度/290
(持續期)
第一章 德川上世の禪風
(一) 妙心寺法度及出世停止 / 309
附記、春日局の功勞
(二) 濟洞二宗の宗風 / 323
第二章 受難時代の英傑
(一) 愚堂東寔 / 346
(二) 大愚宗築 / 359
(三) 一糸文守 / 362
(四) 至道無難 / 372
(五) 道鏡慧端 / 379
(六) 雲居希膺 / 382
(七) 嶺南崇六 / 392
(八) 梅天無明 / 394
第三章 古月・白隱の出世と臨濟禪の振興
|
(一) 古月及其門下の概觀 / 396
(二) 白隱の生涯 / 407
(三) 白隱門下の俊梁 / 424
(四) 鵠林下の居士大姉 / 441
(五) 白隱禪と黑豆法に就て / 447
第四章 無著禪師と祖芳和尚
(一) 無著祖芳前後に於ける
→思想界概觀 / 455
(二) 無著道忠禪師 / 461
(三) 草山祖芳師 / 481
第五章 峨山禪師と其門葉
(一) 峨山慈棹禪師 / 493
(二) 峨山下の諸師 / 495
(三) 隱山の家風 / 496
(四) 隱山下の諸師 / 498
(五) 卓洲の家風 / 508
(六) 卓洲下の諸師 / 510
(近世期)
第一章 明治以後の妙心寺一派
(一) 明治初期禪風の一班
(二) 明治時代の英傑 / 530
(三) 本派敎學の發達 / 545
(四) 宗政の變遷 / 553
(五) 妙心寺と開山遠忌 / 559
第二章 派内の現状
跋
遺芳餘曲
・
・ |
○、この年、姉崎正風編「人生逸話」が「厚生閣」から刊行される。 pid/1031327
|
荻生徂徠 太宰春臺を戒む/1
木戸孝允 音曲師になる事をやむ/2
渡邊華山 備前侯の先驅に蹴らる/2
木村重成 柔を以て剛を制す/6
加茂眞淵 妻と老人に勵まさる/7
若尾逸平 養家の家運を挽回して後に離縁す/9
高橋作左衞門 妻の心掛けに激勵さる/11
名妓幾松 橋下の乞食に情の竹皮包を與ふ/12
橋本左内 竊に乞食の脈を診る/15
松本順 古足袋を質屋に持ち込む/16
杉山和一 遲鈍の才を以て杉山流を開く/18
市川團十郎 天覽演技で體重が減る/20
乃木希典 誠忠を以て宮内大臣を低頭せしむ/22
豊臣秀吉 柴田勝家の按摩をとる/24
上田重安 忍耐して一番槍の勳功を示す/27
番頭吉松 大商店の一の番頭になる/29
大村彦太郎 白木屋の創立に就いて/31
佐藤直方 屋根替を中止して知人の急を救ふ/35
山中利右衞門 大晦日に商人の心掛けを説く/37
播隨院長兵衞 買つた大甕を店頭で破る/38
松本重太郎 魚屋と早起の竸爭をなす/41
古川市兵衞 昆布を噛つて根氣を徹す/42
棚橋絢子 好んで盲目學者の妻となる/44
山岡英子 屏風の蔭から挨拶す/47
百姓佐代 赤貧の中に夫の難病を治す/48
津田知常 幼主を輔けて商事に勵む/51
高久靄厓 田能村竹田に救はる/53
龜田鵬齋 正月に假病して寢込む/56
夏目漱石 後進の身の上を思ふ/58
中澤道二 富豪に娘の教養を暗示す/60
永富昌庵 美人に眷戀さる/61
稻村三伯 蘭醫の術を試みて旅費を作る/63
土方縫殿 町醫の評判を高む/65
乃木希典 歡迎に出た官民を恐縮せしむ/66
服部長七 自分の功績を他人に譲る/68
三橋成方 射撃の拙手に賞を與ふ/70
海老原穆 敵軍に多くの酒肴を贈る/71
福澤諭吉 砲聲を聞きながら遠大な抱負を述ぶ/72
山岡鐵舟 寢衣の儘で參内す/75
正宗と義弘 名刀鍛錬の苦心/78
中村仲藏 妙見菩薩に祈願して藝道を練る/80
狩野融川 繪の惡評を憤つて割腹す/81
小野さつき 白石河に散る宮城野の花/85
平康頼 流譎の島から卒都婆を流す/88
頼山陽 父の死後莊子を講ぜず/89
英一蝶 流謫十餘年毋を思ふ/90
加藤清正 主君の無事を祈る/91
天徳寺入道 武士道の精粹を説く/93
加藤清正 武將の胸に抱く哀れ/96
新納武藏 諸葛亮の志業を慕ふ/98
|
徳川家康 敵將平塚越中を赦す/99
石田三成 最後まで豊太閤の爲に頑張る/101
那波加慶 病者には針を立てる/104
一休和尚 豪商の家へ法衣を投げ込む/105
太宰春臺 滿開の紅梅を伐る/107
吉野太夫 頑固な舅の心を改む/109
瀬川太夫 常盤津の名手に金一封を與ふ/111
觀世太夫 隣室の謠ひ聲を止めさす/112
徳川家康 秀忠の旅情を慰む/114
松平信綱 雀の巣を探して屋根より墜つ/115
谷口蕪村 古狸の菩提を弔ふ/118
上泉信綱 握飯を見せて兇漢を捕ふ/120
大岡忠相 家僕の爲に悟りを開く/122
板倉重矩 鹿殺しの裁判をなす/124
直江兼續 冥途に三人を派遣して死者を呼ぶ/126
上杉治憲 庶民の爲に斷食修行をなす/129
後奈良天皇 般若心經を寫させ給ふ/131
白隱禪師 大名に味噌□の柏餠を進む/133
榮西禪師 藥師如來像の後光を貧者に與ふ/135
一休和尚 一日扇屋へ養子に入る/136
渡守の爺 村上義清の妻を救ふ/139
川添しま 靖國神社に合祀さる/142
江下武二 血痕ある手巾を少年に與ふ/147
乃木希典 夫人への小言を止む/152
長沼澹齋 破れ袴で兵學を講ず/153
豊臣秀吉 五大名の腰刀を言ひ當つ/154
武田信玄 能く山本勘助の器量を見抜く/156
蒲生氏郷 能く玉川左右馬の人物を見破る/157
徳川吉宗 新井白石の心底を探る/158
三宅圧之助 直情剛腹の精神を賞せらる/159
大久保彦左衞門 裸體で兜を冠つて挨拶す/162
十返舍一九 借着で年始廻りを濟す/163
勝川春章 一氣呵成に三川萬歳を描く/165
仙厓和尚 御禮を言へば帳面が消える/166
豊臣秀吉 千利休の膽力に感ず/168
山縣大貳 自若として論語を講ず/169
井上正鐵 道の爲に身を忘れる者/170
徳川光圀 心越禪師に心服す/171
大橋宗桂 將棋の手合せに工夫を凝らす/171
勝海舟 勝負を度外視して事に當れ/175
小村壽太郎 死生を意に留めず/176
安藤眞鐵 鴻池の一室に自刄せんとす/179
小早川隆景 會計役の過剩金を咎む/180
吉川元春 求めて醜婦と結婚す/182
加藤忠廣 美貌の婦人を所望す/184
大友義統 愛妾の行衞を探さしむ/185
伊藤仁齋 放蕩生を悔悟せしむ/187
鐵眼和尚 女縁を絶つて一切經を翻刻す/188
月僊和尚 誓願を達する爲に乞食と罵らる/190
池大雅 純情と熱心とで幟を書き直す/192
|
水野南北 觀相術の體驗を語る/196
圓山應學 弓の弦を描くのに三年の苦心/198
頼山陽 岸駒と智慧を竸ふ/200
仁科源藏 頼山陽の死を悼む/204
柴田是眞 十六羅漢圖に埀涎す/205
高久靄厓 蕎麥湯を飲んで竹田と語る/207
名人蝉丸 月下に秘曲を傳ふ/209
内藤丈草 右の親指を切つて決心を示す/211
徳川頼宣 記念の痣を大切にす/212
木戸孝允 禮拜の時間を嚴守す/213
松平信綱 臨終にも念佛を唱ふる暇を有せず/215
徳川光圀 僧侶に人命の尊さを示す/217
明慧上人 愚僧の首を刎ねよと叫ぶ/219
一休和尚 武士に地獄極樂を見せる/220
泰叟妙康 女の一言を聞いて悟る/223
無能和尚 悲戀狂女を救ふ/224
林子平 兄嫁の死屍と同衾す/226
青砥藤綱 我が影法師、見て悟る/228
山梨平四郎 泡沫を見て人生の無常を感ず/229
鍋島直茂 老齢に達しても參詣を廢せず/232
根岸鎭衞 床の間に桶と棒とを飾る/233
井伊直定 萬年青の赤顆を諸大名に贈る/235
飯尾宗藏 天平の珍寶を無雜作に領つ/237
澤庵禪師 一喝して家光の愛猿を威服す/239
徳川家光 閉門した侍臣を放免す/241
水野越前 愛妾の爲に政治を誤る/242
大江奉行 高潔を以て幕吏を遣り込む/245
水野出羽 上流濁れば下流は清まず/246
戸澤正胤 庶民と勞苦を共にす/248
二宮尊徳 成田不動明王の加護を受く/249
千葉周作 松火が消えて方角が分る/251
渡邊昇 少年書家の印象を打ち摧く/252
吉田松陰 大志にも自重を必要とする/254
陣幕久五郎 發憤して有名な力士となる/255
柏木屋理左衞門 惠比寿を見て
→金鑛採掘に投資す/257
石川總茂 廉潔な武士氣質を徹す/258
鍋島閑叟 花を持つて儒臣の病床を訪ふ/260
白崖實生 良師を得る事は容易でない/262
夢窓國師 忍辱行の體驗を示す/264
愚堂國師 酒豪を轉心させて悟道に導く/266
糟谷左近 酒を飲んで敵手の憤怒を解く/268
茶坊主正齋 毒茶を飲んで主君を救ふ/270
天野屋利兵衞 甘じて盜名を受く/271
田中源兵衞 徳川頼宣の前に槍先を示す/273
安田善次郎 強盜の度膽を抜く/275
高山彦九郎 一喝して二人の強盜を退く/277
名醫道庵 謀られて増上寺に行く/279
狩野探幽 謝禮の米數千俵を貧民に頒つ/281
西田宗勝 生き延びた幸福に滿足する/282 |
○、この年、近重真澄が「雪だるま」を「人文書院」から刊行する。 pid/1236538
|
1 信心銘新譯/1
2 君子に三畏あり/57
3 禪定力/60
4 出家/65
5 知行合一を論じて石田梅巖に及ぶ/68
6 居は氣を移す/73
7 月をさす指/75
8 危く一命を拾ふ/78
9 勤王僧鼎州和尚/82
10 白隱禪師讃辭/87
|
11 佛敎より觀たる佛敎/88
12 參禪餘話/99
13 いろは四十八則/101
14 藤村庸軒/128
15 飛行機日本刀、私/141
16 朝鮮海峽の一夜/144
17 科學亡國論/148
18 古銅器の話/159
19 仙人の話/168
20 道樂論/176
|
21 素人俳論/183
22 濁音の書き形はし方/186
23 詩の技巧と好惡/189
24 詩話/203
25 言志と虚構/208
26 詩と偈/213
27 和習と國粹/218
28 新體詩/225
29 律詩/229
30 唐か宋か/234
|
31 和韻/239
32 詩の添削/242
33 防空/247
34 蚊の説/248
35 小説祇園繪日傘/248
36 情痴/250
37 火/251
38 下墨と發墨/252
附録
39 禪林世語集 開德瀧衛編輯/1 |
○、この年、恩賜京都博物館編「妙心寺名宝図録」が「小林写真製版所」から刊行される。
pid/8311788
|
一 花園天皇御像(國寳) 絹本着色 一幅 妙心寺藏
二 花園天皇御像(國寳) 紙本墨畫 一幅 妙心寺藏
三 松源・運庵和尚像 紙本淡彩 双幅 妙心寺藏
四 虚堂和尚像(國寳) 絹本着色 一幅 妙心寺藏
五 大應國師像(國寳) 絹本着色 一幅 妙心寺藏
六 大燈國師像(國寳) 絹本着色 一幅 妙心寺藏
七 開山關山國師像 絹本着色 一幅 妙心寺藏
八 授翁和尚像 絹本着色 一幅 天授院藏
無因和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
日峰和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
九 日峰和尚像 絹本着色 一幅 養源院藏
義天和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
特芳和尚像 絹本着色 一幅 靈雲院藏
一〇 雪江和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
一一 悟溪和尚像 絹本着色 一幅 東海庵藏
景川和尚像 絹本着色 一幅 龍泉庵藏
特芳和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
一二 景堂和尚像 絹本着色 一幅 大心院藏
鄧林和尚像 狩野元信筆 絹本着色 一幅 龍安寺藏
大休和尚像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
一三 玉浦和尚像 絹本着色 一幅 慈雲院藏
直指和尚像 絹本着色 一幅 東林院藏
一宙和尚像 絹本着色 一幅 雜華院藏
一四 空山和尚像 山口雪溪筆 絹本着色 一幅 春浦院藏
單傳和尚像 絹本着色 一幅 智勝院藏
竺印和尚像 左近筆 絹本着色 一幅 龍華院藏
一五 文溪和尚像 山口雪溪筆 絹本着色 一幅 春浦院藏
臨濟和尚像 傳宗丹筆 絹本着色 一幅 天祥院藏
一六 大愚和尚像 元昭筆 絹本淡彩 一幅 雜華院藏
無著和尚像 紙本着色 一幅 龍華院藏
指津和尚像 傳應擧筆 絹本着色 一幅 蟠桃院藏
諸檀越眞影
一七 利貞尼公像 紙本淡彩 一幅 妙心寺藏
一八 豐臣棄丸像 絹本着色 一幅 妙心寺藏
一九 稻葉一鐵(淸光院殿)像 絹本着色 一幅 智勝院藏
石田爲成(壽聖院殿)像 絹本着色 一幅 壽聖院藏
二〇 石川一光(東海庵殿)像 絹本着色 一幅 東海庵藏
華嚴院日昇先公大禪定門像 絹本着色 一幅 靈雲院藏
福島正則像 絹本着色 一幅 海福院藏
二一 前田玄以(德善院殿)像 絹本着色 一幅 蟠桃院藏
前田玄以夫人(永福院殿)像 絹本着色 一幅 蟠桃院藏
二二 石河光元(國恩寺殿)像 絹本着色 一幅 大雄院藏
山内一豐像 絹本着色 一幅 大通院藏
生駒一生(玉龍院殿)像 絹本着色 一幅 玉龍院藏
二三 堀尾吉晴像 絹本着色 一幅 春光院藏
堀尾泰晴像 絹本着色 一幅 春光院藏
松平忠明(天祥院殿)像 絹本着色 一幅 天祥院藏
二四 牧村兵部(雜華院殿)像 絹本着色 一幅 雜華院藏
牧村牛之助像 絹本着色 一幅 雜華院藏
山名豐國(東林院殿)像 絹本着色 一幅 東林院藏
二五 細川昭元夫人(靈光院殿)像 絹本着色 一幅 龍安寺藏
二六 二條昭實夫人(華巖淨春女)遺像 絹本着色 一幅 雜華院藏
稻葉忠次郞夫人(涼岩受招信女)像 絹本着色 一幅 雜華院藏
二七 毛利秀就夫人(龍昌院殿)像 紙本着色 一幅 龍華院藏
春日局像 傳探幽筆 紙本着色 一幅 麟祥院藏
二八 三折全友夫人(長慶院殿)像 絹本着色 一幅 長慶院藏
伊達政宗夫妻像 有隣齋筆 絹本着色 一幅 蟠桃院藏
慈性院殿松月理貞尼大姉像 德榮筆 絹本着色 一幅 天祥院藏
二九 奧平信昌夫人(盛德院殿)像 絹本着色 一幅 大法院藏
日本畫之部
三〇 福富草紙(國寳) 紙本着色 二卷ノ内 春浦院藏
三一 瓢鮎圖(國寳) 如拙筆 紙本淡彩 一幅 退藏院藏
三二 福祿壽圖 雪舟筆 紙本墨畫 一幅 靈雲院藏
三三 山水圖 傳相阿彌筆 紙本墨畫 六曲?風一雙 妙心寺藏
三四 白衣觀音像 友淸筆 紙本墨畫 一幅 大心院藏
三五 山水花鳥圖(國寳) 傳狩野元信筆 紙本淡彩 四十九幅ノ内 靈雲院藏
三六-三七 瀟湘八景圖(國寳) 傳狩野元信筆 紙本墨畫 四幅 東海庵藏
三八 〔イ〕山□瓶圖 傳狩野元信筆 紙本墨畫 一幅 龍安寺藏
三九 竹雀圖 周德筆 紙本墨畫 一幅 退藏院藏
四〇 山水圖 紙本淡彩 襖四枚 天授院藏
四一 三平石鞏・趙州狗子圖 紙本墨畫 双幅 龍安寺藏
四二 寒山拾得圖(國寳) 海北友松筆 紙本着色 六曲屏風一隻 妙心寺藏
四三 三酸圖(國寳) 海北友松筆 紙本着色 六曲屏風一隻 妙心寺藏
四四-四五 猿猴圖(國寳) 長谷川等伯筆 紙本墨畫 双幅 龍泉庵藏
四六 鹿ニ紅葉圖 土佐光起筆 紙本着色 六曲小屏風一雙 天球院藏
四七 十二ケ月風俗圖 紙本着色 六曲小屏風一雙 東海庵藏 |
支那畫之部
四八 摩利支天像(國寳) 絹本着色 一幅 聖澤院藏
四九 中達磨左右豐干布袋圖(國寳) 紙本墨畫 三幅 妙心寺藏
五〇 羅漢像(國寳) 傳李龍眠筆 絹本着色 一幅 大心院藏
五一 十六羅漢像(國寳) 絹本着色 十六幅ノ内 東海庵藏
五二 十六羅漢像(國寳) 傳蔡山筆 絹本着色 十六幅ノ内 妙心寺藏
五三 達磨大師像 傳顏輝筆 絹本着色 三幅ノ内 天祥院藏
□居士參馬祖圖 絹本墨畫 一幅 天授院藏
五四 東方朔□桃圖(國寳) 傳張平山筆 絹本淡彩 一幅 春光院藏
五五 仙逸圖 文□明筆 絹本着色 一幅 妙心寺藏
五六 月下蘆雁・瀑邊群鵜圖 陳子和筆 絹本墨畫 双幅 東海庵藏
五七 鐵拐仙人圖 呉小僊筆 絹本淡彩 一幅 春光院藏
五八 柳立葵圖 傳呂紀筆 絹本着色 一幅 妙心寺藏
五九 喝石巖圖 絹本着色 一幅 春浦院藏
六〇 梅圖 雪湖筆 紙本墨畫 双幅 東海庵藏
六一 老子騎牛圖 呉秀谷筆 絹本着色 一幅 妙心寺藏
虎圖 絹本着色 一幅 東海庵藏
筆蹟之部
六二 花園天皇宸翰御消息 絹本墨書 一幅 妙心寺藏
花園天皇宸翰御消息 絹本墨書 一幅 妙心寺藏
六三 花園天皇宸翰御消息 紙本墨書 一卷 妙心寺藏
玉鳳院御物目録 紙本墨書 一卷 妙心寺藏
六四 後奈良天皇徽號勅書(國寳) 紙本墨書 一幅 靈雲院藏
東山天皇關山國師徽號勅書 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
桃園天皇關山國師徽號勅書(國寳) 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
六五 大燈録編輯仰書 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
後光嚴天皇知行綸旨 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
六六 自大燈國師授關山國師證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
自關山國師授授翁和尚證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
六七 關山號 大燈國師筆 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
大燈國師遺偈 關山國師筆 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
六八 自授翁和尚授無因和尚證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
授翁和尚消息 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
六九 自無因和尚授日峯和尚證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
山居頒 無因和尚筆 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
自日峯和尚授義天和尚證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
七〇 義天安名 日峯和尚筆 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
自義天和尚授雪江和尚證状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
七一 雪江和尚敷地寄附状 紙本墨書 一幅 龍泉庵藏
自雪江和尚授特芳和尚證状 紙本墨書 一幅 龍安寺藏
七二 關山號 雪江和尚筆 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
渡宋天神像 楊月筆 紙本墨書 一幅 退藏院藏
七三 景川和尚遺偈 紙本墨書 一幅 龍泉庵藏
東海菴四至方至 紙本墨書 一幅 東海庵藏
七四 偈 特芳和尚筆 紙本墨書 一幅 靈雲院藏
牧雲號 特芳和尚筆 紙本墨書 一幅 靈雲院藏
七五 東庵號 大休和尚筆 紙本墨書 一幅 大龍院藏
鄧林和尚消息 紙本墨書 一幅 龍安寺藏
七六 海山號 南化和尚筆 紙本墨書 一幅 雲祥院藏
宗亨安名 伯蒲和尚筆 紙本墨書 一幅 壽聖院藏
七七 法華經陀羅尼品(國寳) 藤原宣房筆 紙本墨書 一卷 天球院藏
法華經譬喩品(國寳) 藤原宣房筆 紙本墨書 一卷 天授院藏
七八 東海瓊華集 得嚴和尚筆 紙本墨書 一册 雜華院藏
村菴稿 小溪和尚筆 紙本墨書 一册 雜華院藏
七九 太平記(國寳) 紙本墨書 十二册ノ内 龍安寺藏
梅花盡無藏 紙本墨書 一册 龍華院藏
八〇 利貞比丘尼敷地寄進状 紙本墨書 一幅 妙心寺藏
春日局消息 紙本墨書 一枚 麟祥院藏
八一 琴楳書畫説 愚極筆 紙本墨書 一幅 大心院藏
柴山宗休消息 紙本墨書 一通 妙心寺藏
八二 懶齋號 策彦筆 紙本墨書 一幅 大龍院藏
龍華院號 隠元筆 紙本墨書 一幅 龍華院藏
美術工藝之部
八三 銅鐘(國寳) 一箇 春光院藏
豐臣棄丸像(國寳) 木造着色 一躯 隣華院藏
玩具船(國寳) 木造着色 一艘 玉鳳院藏
八四 靑磁袴腰香爐 一箇 妙心寺藏
靑磁桃子形香爐 一箇 聖澤院藏
屏風模樣高蒔繪料紙文庫 一箇 妙心寺藏
堆朱香盒 楊茂造 一合 東海庵藏
八五 九條袈裟細部 一領 龍安寺藏
天麟院寄附二十五條袈裟細部 義天拜領 一領 妙心寺藏
開山關山國師所用頭陀袋 一口 妙心寺藏
開山關山國師所用傳衣包裂細部 一枚 妙心寺藏
花園天皇御下賜七條袈裟細部 一領 妙心寺藏
・ |
〇この年、高津柏樹著,今立裕編「主心お婆々粉引歌提唱 : 白隠禅師」が「光融館書店」から刊行される。
pid/1053611
〇この年、茂野染石が「愛鷹山」を「沼津通信社」から刊行する。 pid/1053047
|
筆の滴
愛鷹山/1
白隱禪師の價値/5
好古癖人の癖/13
一夕話/16
伊豆の長八/25
天岫接三氏に與ふ/28
院展の印象/65
帝展の感想/71
駿豆の美術家/82
人の貌
富安寛君/91
|
森久彦君/93
秋山進君/95
伊藤徳藏君/97
池田章君/99
和田勤一郎君/101
岩瀬治三郎君/103
小塚吾一君/105
奧田金四郎君/107
臼井皎二君/109
井上健一君/111
鈴木信一君/113
長谷川茂治君/115
|
望月角太郎君/117
武藤作太郎君/119
奈良橋健三郎君/121
和田傳太郎君/123
鈴木進一郎君/125
八田良恭君/127
水口善三君/129
三浦清君/131
齋藤昌雄君/133
佐々木次郎三郎君/135
小池仙太郎君/138
柳の雨
|
午後の雨/141
春の夜の饒舌/159
とんぼ去る/175
凉み臺にて/178
尺八に唄ふ男/183
五六人の會話/189
滿壽子失踪/195
カフエー午前二時/200
惡玉善玉/205
金を捨てる/214
・
・ |
○、この年、三木鬼外編述「病魔よけ : 万民を幸福へ」が「大東京寿宝社」から刊行される。 pid/1092070
|
はしがき/1
無病は忠君愛國の基/2
白隱禪師の内觀法/19
貝益軒の養生法/20
年寄つても老いざる法/22 |
老衰の原因=便秘と食餌療法/24
老境の睡眠と不眠/25
新鮮なる空氣と日光/29
酒と煙草の長壽に及ぼす影響/30
人身磁力説/32 |
人身磁氣射出の方法/34
自己の弱點を改造すべし/36
人身磁氣によりて他人を支配することが出來る/38
手の助けによりて/40
最後に一言/40 |
○、この年、恩賜京都博物館編「鉄斎先生名画集 富岡鉄斎画」が「便利堂」から刊行される。 pid/8311787
|
賀陽宮御貸下
冨嶽圖 絹本着色 一幅/p1
久邇宮御貸下
瀛洲仙境・群仙祝壽圖 絹本着色 雙幅/p2
久邇宮京都御別邸御貸下
盆踊圖 絹本着色 雙幅/p4
般若心經并白衣觀音像 紙本墨畫 一卷 三重縣 龜井曉氏藏/p5
山水圖 絖本着色押繪貼 六曲屏風一雙ノ内
→京都市 佐々木惣四郞氏藏/p6
園菜果蔬圖 紙本着色 一卷 京都市 内貴富三郞氏藏/p7
玉堂富貴圖 絖本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p8
陸羽烹茶圖 絹本淡彩 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏
粟田陶窯・菟道製茶圖 絹本着色 雙幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p9
爰樂幽居帖 紙本着色 一帖 三重縣 筒井喜一郞氏藏/p11
幽人高致帖 紙本着色 一帖 三重縣 筒井喜一郞氏藏
南朝忠臣遺像・靖献遺言像圖 紙本着色
→六曲屏風一雙 京都市 佐々木惣四郞氏藏/p12
藤娘圖 蓮月尼賛 絹本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p13
花瓶圖 蓮月尼賛 紙本墨畫 一幅 京都市 杉浦三郞兵衞氏藏
桃林小亭圖 紙本淡彩 扇子一握 京都市 内貴富三郞氏藏/p14
八百遐齡圖 絖本淡彩 一幅 三重縣 龜井曉氏藏
層巒積翠圖 紙本淡彩 一幅 京都市 佐々木惣四郞氏藏/p15
溪山不盡圖 紙本淡彩 一幅 京都市 佐々木惣四郞氏藏
粗果野菜圖 紙本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p16
瓶中花卉圖 絹本着色 一幅 大阪府 松井貢氏藏
懸崕芝蘭圖 絖本墨畫 一幅 大阪府 山本藤兵衞氏藏/p17
富貴如意圖 紙本淡彩 一幅 京都市 石田吉左衞門氏藏
日本武尊尊像 絹本着色 一幅 大阪府 大鳥神社藏/p18
頌梅田雲濱七絶 紙本墨畫 一幅 大阪府 松井貢氏藏
冨嶽圖 紙本着色 一幅 大阪府 大鳥神社藏/p19
詩仙堂見取繪圖 紙本墨畫 一幅 京都市 岩井武俊氏藏
陸羽煎茶圖 紙本淡彩 一幅 京都市 岡岩太郞氏藏/p20
松芝不老圖 絖本淡彩 一幅 京都市 上河源右衞門氏藏
陸羽烹茶圖 絹本着色 一幅 京都市 内貴淸兵衞氏藏/p21
樂此幽居圖 絹本着色 一幅 堺市 中田作五郞氏藏
前赤壁圖 絹本着色 一幅 大阪府 松井貢氏藏/p22
關羽圖 紙本着色 一幅 大阪府 松井貢氏藏/p23
出山釋迦如來像 紙本淡彩 一幅 京都市 高田勝次氏藏/p24
梧桐月圖 紙本墨畫 一幅 三重縣 龜井曉氏藏
芸?淸馨圖 紙本淡彩 一幅 京都市 山田直三郞氏藏/p25
弔兼好法師墓詩 紙本墨畫 一幅 三重縣 龜井曉氏藏
天保九如圖 絹本着色 一幅 堺市 中田作五郞氏藏/p26
伐闍羅弗多羅尊者像 絹本着色 一幅 三重縣 龜井曉氏藏/p27
酒造圖 絹本着色 一幅 三重縣 筒井喜一郞氏藏/p28
へち貫點茶圖 絹本着色 一幅 三重縣 龜井曉氏藏/p29
伊勢大廟圖 絹本着色 一幅 堺市 大澤醇吉氏藏
溪山勝□圖 紙本墨畫 一幅 三重縣 龜井曉氏藏/p30
不盡山圖 紙本着色 六曲屏風一雙 京都市 柴田治右衞門氏藏/p31
松壑歸雲圖 紙本墨畫 一幅 大阪市 鹿田靜七氏藏/p32
三十六鱗圖 絹本墨畫 一幅 京都市 小山源治氏藏/p33
歡樂圖 紙本着色 一幅 京都市 鹽見淸右衞門氏藏/p33
竟陵茶隱圖 絹本着色 一幅 京都市 桑名鐵城氏藏/p34
文昌星圖 絹本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p35
秋景山水圖 紙本淡彩 六曲屏風一雙 京都市 宮田兵三氏藏/p36
老□度關・陸羽煮茶圖 絹本着色 雙幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p37
烏圖 紙本墨畫 一幅 堺市 前田長三郞氏藏/p39
山上憶良像 紙本淡彩 一幅 京都市 富岡益太郞氏藏
果物圖 紙本着色 扇面一幅 京都市 岩井武俊氏藏/p40
嘉定菓子并詩説 紙本淡彩 一幅 京都市 黑川正弘氏藏
豐太閤畫像 紙本着色 一幅 京都市 加藤英舟氏藏/p41
白衣觀音大士像 紙本淡彩 一幅 京都市 竹内新之亟氏藏
勾白字七絶 絹本着色 一幅 京都市 飯田新七氏藏/p42
藥王菩薩像 紙本墨畫 一幅 京都市 竹内新之亟氏藏/p43
靜舞圖 紙本着色 一幅 京都市 松本さだ氏藏
十六羅漢圖 紙本淡彩 一幅 東京市 丸山豐太郞氏藏/p44
漁樵問答圖 紙本着色 一幅 京都市 桑名鐵城氏藏/p45 |
山莊風雨圖 紙本着色 一幅 京都市 内藤乾吉氏藏/p46
松竹梅華圖 絹本着色 一幅 大阪市 松下齋藏氏藏/p47
層巒雨霽圖 紙本墨畫 一幅 京都市 内貴淸兵衞氏藏/p48
耶馬溪圖卷 紙本着色 一卷 福井縣 布施卷太郞氏藏/p49
福祿壽圖 紙本着色 一幅 大阪市 松下齋藏氏藏/p50
東坡戴笠圖 紙本淡彩 一幅 京都市 桑名鐵城氏藏
壽山福海・古石長椿圖 絹本着色 雙幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p51
天保九如圖 絹本淡彩 一幅 京都府 秋田三平氏藏/p52
思□採藥圖 絹本着色 一幅 京都市 某氏藏/p53
養素丘園圖 絹本着色 一幅 京都市 辻政良氏藏/p54
安倍仲麻呂明朝望月・圓通大師呉門隱栖圖
→絹本着色 六曲屏風一雙 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p55
高士觀瀑圖 紙本着色 一幅 東京市 丸山豐太郞氏藏/p57
溪山招隱圖 絹本着色 一幅 京都府 秋田彌之助氏藏
十牛圖意圖 絹本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p58
碧桃壽鳥圖 絹本着色 一幅 京都市 飯田新七氏藏/p59
蘓子笠屐圖 紙本淡彩 一幅 京都市 辻壽美氏藏/p60
王元士竹樓記 絹本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p61
東瀛三神山圖 絹本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p62
萬里尋親圖 紙本墨畫 一幅 京都市 桑名鐵城氏藏/p63
白幽山人像 紙本墨畫 一幅 京都市 杉本忠三郞氏藏
群僊高會圖 絹本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p64
三尾聚芳圖 絹本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p65
椿樹僊境圖 絹本着色 一幅 京都市 辻壽美氏藏/p66
高枕吾廬圖 絹本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p67
淸士歸山圖 絹本着色 一幅 京都市 田中新一郞氏藏/p68
三子痴懶圖 紙本淡彩 一幅 大阪府 松井貢氏藏
普〔ダ〕落山觀音像 紙本淡彩 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p69
蘭石圖 紙本淡彩 一幅 東京市 侯爵細川護立氏藏
魚籃觀音像 紙本着色 一幅 京都市 大島徹水氏藏/p70
漁村暮雨圖 紙本墨畫 一幅 京都市 某氏藏/p71
煙霞嘯傲圖 紙本淡彩 一幅 京都府 秋田彌之助氏藏
西王母像 紙本着色 一幅 京都市 田中新一郞氏藏/p72
霍壽千年圖 紙本着色 一幅 京都市 飯田新七氏藏
艤槎破浪圖 紙本着色 扇面一幅 京都市 内藤乾吉氏藏/p73
田家納凉圖 紙本着色 一幅 京都市 伊澤績子氏藏/p73
木米隱栖圖 紙本墨畫 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p74
占百花魁圖 絹本着色 一幅 京都市 伊澤彌生氏藏
蝸牛廬圖 紙本淡彩 一幅 京都市 諏訪蘇山氏藏/p75
菩提山寺圖 紙本淡彩 一幅 大阪市 水落庄兵衞氏藏
化城喩品圖 紙本墨畫 一幅 京都市 狩野直喜氏藏/p76
江山勝覽圖 紙本淡彩 一幅 東京市 侯爵細川護立氏藏
白隱訪白幽子圖 紙本淡彩 一幅 東京市 侯爵細川護立氏藏/p77
山碧水明處圖 紙本墨畫 一幅 京都市 長尾甲氏藏/p78
豐公娶婦圖 絹本着色 一幅 京都市 松本さだ氏藏
天保九如章圖 紙本墨畫 一幅 東京市 侯爵細川護立氏藏/p79
王子騎馬圖 紙本淡彩 一幅 東京市 正宗得三郞氏藏
擬赤壁遊圖 紙本墨畫 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p80
東坡品茶圖 紙本淡彩 一幅 東京市 正宗得三郞氏藏
前後赤壁圖 紙本着色 雙幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p81
閨窓修竹圖 紙本淡彩 一[幅] 東京市 正宗千代子氏藏/p82
八角圓堂圖 紙本墨畫 一幅 京都市 仁和寺藏
松芝不老圖 紙本淡彩 一幅 京都市 山口玄洞氏藏/p83
朱梅圖 紙本着色 一幅 京都市 某氏藏
貽咲墨戯 紙本着色 一帖ノ内 京都市 富岡益太郞氏藏/p84
撥雲尋道圖 紙本墨畫 一幅 京都市 大覺寺藏/p85
江山淸遠圖 紙本墨畫 一幅 京都市 本田成之氏藏
山碧水明處圖 紙本墨畫 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p86
東坡食芋圖 紙本淡彩 一幅 東京市 正宗得三郞氏藏
太秦牛祭圖 紙本墨畫 一幅 京都市 内貴富三郞氏藏/p87
畫師〔タッシン〕圖 紙本墨畫 一幅 神戸市 角田俊徹氏藏/p87
水鄕淸趣圖 紙本着色 一幅 京都市 諏訪蘇山氏藏
山輝水媚圖 紙本着色 一幅 京都市 知恩院藏/p88
桃林牧童圖 紙本着色 一幅 西宮市 辰馬悅藏氏藏/p89
榮啓期騎牛圖 紙本着色 一幅 京都市 山口玄洞氏藏
・ |
○、この年、松田勝好が「長寿指圧療法の秘訣 : 松田式霊的神経指圧術」を「静岡長寿指圧療法研究所」から刊行する。pid/1054594
|
第壹章 健康長壽法と宗教/1
第一節 我國に於ける長壽者/1
第二節 長壽と若返り法/4
第三節 人壽果して幾歳か/10
第四節 長壽健康法/17
第五節 各國の長壽者/22
第六節 偉人の長壽法/26
第七節 白隱禪師と氣海丹田法/38
第八節 彭祖の和神導氣の法/42
第九節 貝原益軒先生の長壽法/43
第十節 健康長壽と生活宗教/44
第十一節 現實の生活と信仰/49
第十二節 身延久遠寺刑部左衛門女房訓/52
第十三節 悟道とは何か/56
第十四節 宗教と自己の尊嚴/62
第十五節 生活宗教と詩/65
第十六節 觀念、心靈とは何か/89
第十七節 曉の鐘が鳴る/91
第十八節 健康長壽の標語/102
第十九節 松田式健康長壽法/108
第二十節 生活教宗道歌彌榮心經/112
第貳章 長壽指壓療法の原理と其實際/114
第一節 長壽指壓療法とは如何なるものか/114
第二節 指壓療法の發見者と民間療法/119
第三節 疾病とは何か/124
第四節 氣海丹田の指壓とその療法/136
第五節 神經と感情との關係/141
第六節 疾病治療法/144
第七節 病氣治療と神經系との關係/145
第八節 神經系統/149
第九節 ホルモンとは何か/163
第十節 福祿壽と長壽者/167
第十一節 腦神經中樞指壓法/171
第十二節 上頸交感神經指壓法/174
第十三節 延髓の指壓法/176
第十四節 迷走神經指壓法/176
第十五節 喉頭及氣管指壓法/179
第十六節 三叉神經指壓法/181
第十七節 顏面指壓操作法/182
第十八節 眼球指壓操作法/183 |
第十九節 頭部指壓法/185
第二十節 肩胛部指壓操作法/187
第二十一節 膊指壓法/188
第二十二節 腰部指壓法/190
第二十三節 薦骨及骨盤神經指壓法/192
第二十四節 脊柱操作及
→交感神經指壓法/193
第二十五節 下肢指壓操作法/199
第二十六節 肋間指壓操作法/202
第二十七節 腹部操作法/203
第二十八節 太陽神經叢指壓/206
第二十九節 松田式健康長壽自己指壓術/211
第三十節 指壓療法上の
→注意及長壽指壓法歌謠/212
第參章 疾病治療各論と藥草/219
第一節 消化器病/219
(イ) 胃膓加答兒、胃痙攣/219
(ロ) 胃擴張、胃下垂、胃酸過多症/220
(ハ) 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌/221
(ニ) 膽石病、肝臟病/230
(ホ) 盲膓炎/234
(ヘ) 腹膜炎/238
(ト) 蛔蟲、十二支腸蟲、〔ギョウ〕蟲病/241
(チ) 痔疾/243
第二節 神經系病/247
(イ) 腦溢血/249
(ロ) 腦貧血、腦充血/253
(ハ) 神經痛、レウマチス/256
(ニ) 神經衰弱、ヒステリー/263
(ホ) 癲癇/266
(ヘ) 脊柱カリエス/267
第三節 循環器病/270
(イ) 心臟病/270
(ロ) 腎臟病/273
(ハ) 動脈硬化症/278
(ニ) 腎盂炎/283
(ホ) バセドウ氏病/285
第四節 呼吸器病/287
(イ) 肋膜炎/292
(ロ) 肺炎、氣管支炎/298
|
(ハ) 肺結核/302
(ニ) 感冐、頭痛/308
(ホ) 咽喉加答兒/313
第五節 婦人病及子供の病氣/317
(イ) 子宮内膜炎/317
(ロ) 月經困難
→(不順、閉止、過多)/320
(ハ) 小兒胃腸加答兒/325
(ニ) 疫痢/325
(ホ) 肺炎/328
(ヘ) 腦膜炎/328
(ト) 痲疹/329
第六節 性病及精神病/331
(イ) 黴毒/332
(ロ) 痲病/336
(ハ) 生殖神經衰弱症/340
(ニ) 精神的/343
第七節 眼、耳鼻、齒及
→其他の疾病/348
(イ) 眼病/348
1、 加答兒性結膜炎/348
2、 疳眼/348
3、 鳳眼/349
4、 トラホーム/349
5、 色素性網膜炎(ソコヒ)/350
(ロ) 耳鼻の病氣/352
1、 中耳炎/352
2、 外耳炎/352
3、 皷膜/353
4、 肥厚性鼻炎/353
5、 蓄膿/353
(ハ) 齒の病氣/355
(ニ) 其他の病氣/356
1、 扁桃腺炎/356
2、 脚氣/357
3、 産褥熱/358
4、 中毒/359
5、 乳の病氣と乳を出す法/360
本療法の信念/362
結論/363 |
|
| 1936 |
11 |
・ |
1月、藤卷治吉が誠文堂新光社編「商店界 16(1) p97~99 誠文堂新光社」に「七福神の敎訓と商店經營法」を発表する。 pid/2250238
12月、高野辰之が「芸淵耽溺」を「東京堂」から刊行する。 pid/1218759 閲覧可能
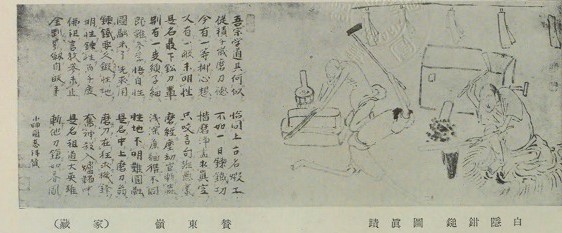
※けん‐つい【×鉗×鎚】:《「鉗」は金ばさみ、「鎚」は金づちの意》禅家で、師僧が弟子を厳格に鍛え、教え導くことをたとえていう語。 所蔵:信州飯山正受庵
|
書畫篇
一 書畫耽溺の囘顧 / 2
1 引 / 2
2 御宸筆 / 7
3 踏歌の宣命 / 10
4 費漢源の唐子圖 / 11
5 嶺南崇六の墨蹟 / 12
6 中尊寺經 / 13
7 慈鎭和尚の假名法華/15
8 韓長老の李白騎驢圖賛/16
9 山樂の蓮鷺 / 18
10 宗達の歌仙圖 / 20
11 傳吉田半兵衞筆美人畫/21
12 光起の蘇東坡 / 23
13 ※白隱の鉗鎚圖 / 23
14 遂翁の出山釋迦圖 / 25
15 文晁の富士山 / 26
16 結語 / 27
二 五山僧の墨蹟/29
1 和漢書道概觀/29
2 宋元渡來僧の墨蹟 / 32 |
3 入宋入元僧の墨蹟/37
4 不渡航僧の墨蹟/43
5 入明僧の墨蹟 / 45
6 不渡明僧の墨蹟/48
7 永正の江湖疏 / 52
8 結語 / 54
三 寂嚴と良寬 / 57
良寬の寃を雪ぐ
四 明治高僧の墨蹟/72
五 行草趣味 / 83
六 書道と學問 / 96
1 北島雪山 / 97
2 細井廣澤 / 98
3 松下烏石 / 101
4 澤田東江 / 102
七 畫僧雲室 / 106
八 待敎四畫 / 118
1 歡喜天か / 119
2 等墨の出山釋迦 / 121
3 異裝傅大士 / 123
4 大雅堂の自畫像 / 126 |
九 俳畫談 / 133
一〇 渡邊崋山と江戸名所圖會/147
一一 曝凉漫記 / 155
1 澤庵の名短文 / 155
2 芭蕉の短册 / 156
3 逸詩の幅 / 157
4 林谷の雅友圖卷 / 158
5 息軒の惡筆 / 159
6 行誡の行乞圖 / 160
一二 三紙片 / 162
三條實美公の遺墨
演劇舞踊篇
一 藥師寺の花會式 / 168
二 歌舞伎劇の前途 / 173
高時所感
三 古曲の將來 / 183
四 矢田よ、いづこ / 197
五 鞘當 / 206
六 梅幸惜し / 212
七 舊劇の上に見る國民性 / 217
八 レコード舞踊 / 232
|
追憶篇 /
一 楠公六百年祭に際して/238
二 大自信家如電翁 / 245
三 言海博士追憶 / 250
四 黑木君と私 / 260
五 龍江先生追憶 / 269
主張篇 /
一 凉を趁ふ / 276
二 山莊閑語 / 281
1 しほ時 / 281
2 藝と學問 / 284
3 湯の村へ / 287
三 馬糶 / 291
四 唱歌敎育の礎石 / 296
五 小説と感化 / 313
六 音樂家と著作 / 319
七 煙幕生活 / 328
八 敎材としての淨瑠璃/334
・
・
・ |
○、この年、間宮英宗が「延命十句観音経講話」を「仏教年鑑社」から刊行する。 pid/1215296
|
延命十句觀音經講話/1
觀世音・南無佛/6 |
與佛有因・與佛有縁/26
佛法相縁・常樂我淨/30 |
朝念觀世音・暮念觀世音/42
念々從心起・念々不離心/44 |
十句觀音經に關する文献/53
延命十句觀音經靈驗記/89 |
○、この年、二木謙三が「腹式呼吸と健康 : 附・精神と健康、脳を害さぬ勉強法、暗記の一方法」を「大日本養正会」から刊行する。 (大日本養正会叢書 ; 第3輯) pid/1026281
|
一、 腹式呼吸/1
こんなに弱い兒/2
全身病の巣/3
其上神經衰弱/4
平田篤胤先生の志都の石屋/5
百病は氣に生ず/6
平田先生の精神療法/7
平田先生の肉體強健法/8
氣海/10
不老不死の術/10
丹田/11
無病長壽の奇術/12
白隱禪師の遠羅天釡/13
心氣をして臍輪氣海丹田
→腰脚の間に充しむ/15
讀んで實行病氣も解消/17
十二歳の露西亞娘の鍛錬法/18
ひどい神經衰弱も腹式呼吸で/21
男の腦神經衰弱者/23
女のヒステリー患者/23
呼吸の起因/23
横膈膜/23
呼吸の種類/26
一、 肺尖呼吸/26
二、 胸式呼吸/26
三、 腹式呼吸/27
四、 胸腹式呼吸/27
肺尖呼吸の不利/27
胸式呼吸の缺點/28
胸腹式呼吸の長所/28
一名横膈膜呼吸/29
血の環りが良くなる/29
心臟/30
心臟へ血液の還流する理由/31
身體の血の循環/32
血液の分配/32
貧血の因/32
|
腹の動悸の強いのは/34
血の環りを良くするのには/34
膽力/36
物に恐れた場合の姿勢は/36
十四里の長距離競爭も
→腹式呼吸で第一着/37
腹式呼吸の神經に及ぼす作用/38
腹の働き/40
二、 腹式呼吸の方法/41
練習は二六時中/47
坐して行ふ姿勢/42
吸ふ息/43
吐く息/43
呼吸は鼻で/43
鼻でする理由/44
立つて行ふ姿勢/46
呼吸する限り一生續けよ/47
極意は不斷の努力から/48
動の呼吸/49
靜の呼吸/49
動中の靜、靜中の動/51
柳生又十郎の修行/52
油斷大敵、心の修行/54
健康と完全なる玄米菜食/57
三、 精神と健康/59
毎日愉快に過す事/59
笑ふ門に福來る/60
永久的の愉快/61
分に安ぜよ/62
精神の持ち樣で病氣を克服/64
生活は陽氣に/65
アア有難いの念/66
太陽に向つて深呼吸/67
穢れは氣枯れ/67
鹽を撒いて清める事のおこり/68
トマムの草分け八十三歳の關寛先生/69
有難い御製/71 |
四、 腦を害せぬ勉學法/72
頭腦の働く時と亂れる時/72
頭腦を二つに使ひ分ける當今の學生/73
學生の頭腦混亂の主因/74
學生神經衰弱の主因/76
頭腦を冷靜ならしむる必要/77
數學に苦しむ學生/78
一皮づつ剥いてゆく勉學法/79
余が神經衰弱中の勉學法/80
此方法を萬事に應用した/82
勉學中精力集中法/83
精力集中の敵/84
先づ姿勢を正せ/86
勉強中外邪と内邪/87
外邪降伏の姿勢/88
深遠なる古人の寓意/89
試驗前後の飮食法/90
生理的説明/91
試驗前は少食がよし/92
精進潔齋の覺悟/93
如何なる時に多食すべきか/94
五、 暗記法/96
暗記も亦學生にとりては一の苦み/96
暗記に必要なる四條件/97
暗記に必要なる時と場所の困難/98
散歩と同時に暗記する第一效果/99
散歩中暗記する第二效果/100
散歩中の暗記は時間勞力半減す/101
暗記は散歩と同時に行ふが最も可し/102
散歩中の暗記は腦に害なきか/103
日曜を散歩と暗記に兩用すべし/105
暗記しつつ散歩する時の態度/106
余が學生時代に於ける暗記の實驗/106
雨天にても實行に差支へなし/107
・
・
・ |
○、この年、慶応義塾大学編「国文教本 巻1」が「慶応義塾出版局」から刊行される。 pid/1025121
|
前編
思想の中庸・福澤諭吉/1
偶感・福澤諭吉/8
國語の尊重・福澤諭吉/9
國民精神作興に關する詔書・
→佐野善作・深作安文/14
鷹ヶ峰・本阿彌行状記/22
大虚庵主人・高安月郊/27
小園の記・正岡子規/30
ふところ日記・川上眉山/33
請壽句文・尾崎紅葉/36
悟道の意義・綱島梁川/37 |
丹田法・白隱禪師/40
一字千金・竹田出雲/44
紅流し・近松門左衞門/58
報徳教・二宮尊徳/68
ヒウマニスト二宮尊徳・田中王堂/72
混同祕策・佐藤信淵/75
水鷄笛・松尾芭蕉/78
幻住庵・松尾芭蕉/80
芭蕉論・得能秋虎/84
俳句の味・芭蕉遺語集/88
俳句/94
教訓の歌/97 |
川柳狂句/100
漢學先生・式亭三馬/104
言葉あらそひ・式亭三馬/111
初午は乘てくる仕合・井原西鶴/116
煎じやう常とは變る問藥・井原西鶴/120
近世和歌/125
東洋の詩歌・夏目漱石/130
千鳥の香爐・幸田露伴/133
後編
枕草子抄/139
源氏物語 桐壺 須磨/183
・ |
○、この年、広島逓信局編「不滅の光」が「広島逓友会」から刊行される。 (修養資料 ; 第7編) pid/1105687
|
人間道の完成 慶應大學教授 友松圓諦
(略)
吉田松陰先生に於ける國家觀 廣島高等師範學校教授 玖村敏雄
(略)
日本婦人の道 香川縣女子師範學校長 磯野清
(略)
白隱和尚と坐禪和讃 臨濟宗佛通寺派管長 山崎益洲
白隱和尚の生ひ立ち / 224
馬翁の親切 / 227
克苦の光明 / 229
大愚和尚の教へ / 233
夜船閑話 / 235
思ひ出さず忘れず / 237 |
不滅の生命 / 238
悟りの病氣 / 240
正受老人 / 243
鞭つ師 / 247
學得底より自得底へ / 248
涙する師 / 252
駿河へ歸る / 253
克苦と大道 / 255
馬鹿になり切る / 256
道は己にあり / 260
水の如く淡々たれ / 262
今を全ふす / 265
一歩一歩 / 266
|
惱みの種々相 / 268
生死を超へること / 269
聲なき聲を聽く / 271
腹力を養ふ / 272
唯一無二のもの / 274
三昧境 / 276
明鏡の冴へ / 277
あるがままの淨土の認識 / 278
そのままが眞實 / 281
人生に敵なし / 285
淨信の強さ / 286
隨處に主となる / 289
日日是好日 / 290 |
○、この年、松下正二郎編「 霊峰 : 山形県国民精神文化講習会誌」が「松下正二郎」から刊行される。 pid/1034838
|
序文
寫眞 道場全景
講師 諸先生の揮毫
寫眞 日本体操・坐禪・苅草 開墾・禊・除草
建國の歌 / 1
大高根農場歌 / 2
惟神のこころ / 3
般若心經 / 4
三綱領 回向 四弘誓願 / 5
白隱和尚坐禪和讃 / 6
舍規七則 食事五觀文 / 7
開卷の語 / 8
長官閣下告辭 / 9 |
答辭 / 10
國民精神文化同行會ニ於ケル
→總裁訓示/11
第一 趣旨 / 13
第二 主催 / 13
第三 會場 / 13
第四 期日 / 13
第五 講師縣官 / 13
第六 日程 / 15
第七 講習員及班の編成 / 22
第八 係員 / 25
第九 毎日の行事 / 26
第十 研究會について / 26 |
第十一 山形縣青年道場概要 / 27
第十二 靈山葉山について / 29
第十三 葉山登山記 / 31
第十四 北滿に於ける日本農業移民を訪ふ・
→山形縣國民高等學校長 西垣喜代次 / 34
第十五 縣官所感 / 38
脚下照顧 今田直己 /
道場雜記 鈴木佐光 /
風思録 高橋豊
第十六 講習員感想 / 47
第十七 山形縣國民精神文化同行會總會記 / 85
編輯後記 / 87
山形縣國民精神文化同行會規約 |
|
| 1937 |
12 |
・ |
1月、「大日 (142)」が「大日社」から刊行される。 pid/1595841
|
白隱墨蹟――(布袋蹴鞠圖) /※ 口繪
卷頭言=政海惑問 / 杉浦重剛 / p1~1
中外時事――主張 / p2~6
國妖の修祓――社説 / p7~8
日本主義者の政治觀 / 松田禎輔 / p9~14
日獨防共協定の由來 / 米田實 / p15~20
世界赤化政策の協同防止 / 山田武吉 / p21~24
支那擾亂と日本人の覺悟 / 井上右近 / p25~26
撃鼓吹貝 / p27~27
男女道愚見 / 原重治 / p28~30
致誠日誌 / p31~31
副島蒼海の出自 / 中島利一郞 / p32~35
賦得田家雪 / 小林正盛 ; 下村關路 / p36~36
生死岸頭の國運 / 甲陽道人 / p37~39
歌舞伎座觀劇書懷 / 松濤翠山 / p40~40
人間の利已心と佛敎信仰 / 田中香涯 / p41~47
昭和十二年歳候及流感治 / 岸原鴻太郞 / p48~48
|
日本賤民變遷史(十四) / 澤村晴夫 / p49~51
奉公 / 太平 / p52~52
視力保存 / 宅野田夫 / p53~54
街路樹 / 芳洲生 / p55~55
年頭漫語 / 草〔モウ〕庵布士 / p56~58
梅窓 / p59~59
江戸小唄の風味(一) / 湯朝竹山人 / p60~64
吾等の短歌 / p65~65
禪話百則(十四) / 村上素道 / p66~67
牛に對して琴を彈ず / 竹井十郞 / p68~71
巣鴨より / 水島爾保布 / p72~73
新刊紹介寄贈雜誌 / p74~74
在留外人の眼に映じた東・西兩洋の昨今 / S・S・G / p75~79
時事日誌 / p80~80
大絃小絃 / p81~81
裏畫 / 加瀨藤圃 / p86~
・ |
※ 口繪 白隱墨蹟――(布袋蹴鞠圖) の項で「口絵」と記載があったのは、本号だけであった。
そのようなことから、前後「白隱墨蹟」についての表記は、「口絵」として表記した。 2022・12・17 保坂
○、この年、梶浦逸外が「延命十句観音経霊験記:白隠禅師」を「尚志寮(京都)」から刊行する。非売品 所蔵:大阪市立図書館
○、この年、多田政一が「科学より学問へ日本保健学提唱」を「日本綜統学術院出版部」から刊行する。pid/1106419
|
自序/1~8
第一篇 自然と人生/1
第一章 學心追憶/1
第二章 自然立學/18
理の轉換
第二篇 科學と禪學/37
第一章 科學の家郷/37
理論は立場から
第二章 禪學の面目/46
第三章 學問の現成/54
自己を習ふとは
第四章 學人知新/70
學と道の人
行持の學風
道元と白隱の面目
科學上の學人
第三篇 日本學の把握/103
第一章 ものの哀れ/103
詩歌のあはれ
第二章 祭政と禮樂/122
道とは何ぞや
日本の大和道
第四篇 家庭の面目/141
第一章 仁和の發源地/141
家庭とは何ぞや
現代の常識
第二章 衣食住の行持/156
第三章 會得の教育に歸れ/169 |
第四章 田舎より都會へ/185
慾の觀察
田舎より都會へ
第五篇 日本保健學提唱/199
第一章 醫術の來し方/199
第二章 世界醫學近况/212
行持の醫學樹立
第三章 病人とは何ぞや/229
科學上の病人
第四章 病氣本來の意義/250
第五章 自然醫學と人爲醫學(足の科學論)/267
足が出來るまで
「くらげ」より魚へ
魚より陸上動物へ
動物から人間へ
足の能率と歩行
足心即全身と丹田の成立
第六章 足の機能の生理學/287
聖賢による正しき履物
日本的養生道要約
日本藥學とは何か?
第七章 自然と衣食住/313
美しき肉體
食物の基本原理
食事環境の重大性
第八章 文明人の食物に就いて/345
(第一類) 穀物類食餌
(第二類) 肉食類食餌 |
(第三類) 日常用食餌
(第四類) 糖類食餌
(第五及六類) 果物類食餌
(第六及七類) 野菜類に就いて
食養と循環
衣服と循環
第九章 保健の根本原理體系/392
生死一貫の養生道
日本的養生道要約
第六篇 學問春秋/417
第一章 學問風懷/418
有時而今
人境雙忘
道-機-妙-術
偶像即科學提唱
第二章 學人春秋/492
禪人
文人
第七篇 不言集/543
第一章 卷頭言集/543
忘年新歳
赤身之學
方便活道
病間自得
保健とは何ぞや
肉體と云ふ事
第二章 偶感小集/592
・
・ |
|
| 1938 |
13 |
・ |
5月14日~5月31日、「白隱禪師遺墨展覽會」が大阪市立美術館に於いて開かれる。
5月、大阪市立美術館編纂「白隱禪師遺墨集」が「大阪市役所」から刊行される。
奥付には「大阪市立美術館展觀記念圖録第七」とあり 所蔵:京都府立京都学・歴彩館 大和綴じ
5月、「美術 13(5) 」が「美術發行所」から刊行される。 pid/1579169
|
表紙 / 安井曾太郞/表紙
夜船閑話 / 白隱禪師/p3~11
遠羅天釜――(拔萃) / 白隱禪師/p12~17
假名法語 / 白隱禪師/p18~22
病中の公案 / 白隱禪師/p22~22
寢惚之眼覺 / 白隱禪師/p23~25
平左衞門に與ふる書 / 白隱禪師/p30~30
白隱の畫禪に就いて / 岡本かの子/p26~29
|
※白隱の繪 / 武者小路實篤/p29~30
室内――(原色版)/ボナール
太海風景――(原色版)/靑山義雄
ヒヨドリ――(原色版)/野口謙藏
國展評 / 福島繁太郞/p31~33
第十六回春陽會感想 / 倉田三郞/p34~34
第六回東光會展 / 鈴木武久/p35~35
主線美術協會展評 / 高間惣七/p36~36
|
唯型展 / 中川紀元/p38~38
連袖會第一囘展 / 佐波甫/p38~39
杜會展評 / 松島一郞/p39~39
山崎省三個展 / 栗原信/p37~37
安良里日記 / 中川一政/p40~40
松風園隨筆 / 兒島善三郞/p41~43
四月の博物館 / 廣瀨憙六/p44~45
・ |
参考 ※1941武者小路實篤著「人生と藝術 p188」に「白隱の畫や字を見て」の記述あり。
○、この年、伊藤康善編「療養聖典」が「自然良能社」が刊行される。 pid/1108705
|
養生編
一 榮西禪師「喫茶養生記」上巻/1
二 貝原益軒「養生訓」抄出 / 5
三 白隱禪師「夜船閑話」和譯/45
四 白隱禪師「尺牘」集 / 65
五 平田篤胤「志都能石屋」/75
六 櫻寧居士「養生訣」並評註/87 |
七 柳井三碩「寝ぬ夜の夢」附、
→座禪和讃/97
八 岡田虎二郎「靜坐」寸言録 / 105
自覺編
一 菜根譚俗譯 / 117
二 澤庵和尚「不動智神妙録」 / 131
三 鍋島藩「葉隱論語」抄出 / 145 |
四 綱島梁川文集 / 160
五 清澤滿之文集
→附録一茶一枚起請文/185
聖語編
一 栂尾明惠上人遺訓 / 201
二 道元禪師法語 / 206
三 般若心經(本文直譯)/218 |
四 源信僧都法語/224
五 法然上人法語/227
六 親鸞聖人法語/233
七 正信偈和讃/241
八 三帖和讃抄出/251
・
・ |
〇この年、宮裡祖泰編「白隠禅師法語集」が「神宮館」から刊行される。 pid/1025107
|
白隱禪師略傳 / 3
坐禪和讃 / 5
施行歌 / 7
安心ほこりたたき / 12 |
大道ちよぼくれ / 17
主心お婆粉引歌 / 22
おたふく女郎粉引歌 / 28
寝惚之眼覺 / 38 |
見性成佛丸方書 / 45
辻談議 / 48
假名法語 / 59
寳鏡窟記 / 70 |
夜船閑話 / 78
遠羅天釡 / 98
・
・ |
○、この年、「大衆仏教全集 第4」が「大衆仏教全集刊行会」から刊行される。 pid/1245972
|
奈良佛敎
一 道昭/5
二 義渊/19
三 行基/25
四 良辨/35
五 鑑眞/47
平安佛敎
一 最澄/65
二 空海/77
三 圓仁/87
|
四 眞如/95
五 圓珍/103
六 聖寶/111
七 空也/117
八 良源/127
九 性空/135
十 源信/145
十一 成尋/153
十二 覺鑁/163
鎌倉佛敎
|
一 法然/173
二 榮西/181
三 明惠/191
四 道元/201
五 祖元/209
六 圓爾/219
七 親鸞/231
八 日蓮/241
九 一遍/251
十 睿尊/259
|
室町佛敎
一 夢窓/269
二 關山/279
三 蓮如/287
江戸佛敎
一 天海/299
二 澤庵/309
三 隱元/321
四 白隱/331
五 慈雲/343 |
○、この年、日本社会学会編「社会学 : 日本社会学会年報 第5輯 秋季號」が「岩波書店」から刊行される。 pid/1214677
|
論説
朝鮮の巫團 秋葉隆/1
『隱居』について 大間知篤三/22
道德社會學(ethologie)の立場―日本道德史序説― 井上寬令/41
中世封建社會に於ける武士階級道德意職の一考察 ―法制、
→家訓、敎訓書を資料として― 櫻井庄太郞/76
道德規範に對する法規範の優位 田畑忍/97
アダム・スミスに於ける自然法的なるもの 淸水幾太郞/122
日本社會學會第十二囘大會研究報告アブストラクト
一 社會學論の部/166
體系的社會學の課題 關口節/166
米國社會學に於る方法論の一問題 難波紋吉/169
社會學史の問題學 早瀨利雄/172
社會科學の限界 淸水幾太郞/174
社會發展論の基礎問題 松本潤一郞/175
社會の對象化について 梯明秀/178
社會學に於ける現實性の問題 安西文夫/179
ゲマインシヤフトについて 岸川八壽治/182
文化成立の諸條件 小松堅太郞/184
社會誌學に於ける環境 今井時郞/186
認識論の社會的分裂と認識科學の確立 今田竹千代/188
二 道德・法律・政治及敎育の部/192
ホッブスに於ける道德と政治 重松俊明/192
道德的なるもの 井伊玄太郞/195
武士道の社會學的考察 阿部政太郞/198
社會變革期に於ける道德意識 井上寬令/202
帝國貴族院の法律社會學的構成 岩崎卯一/206
結合本位の法と公法・私法 高橋貞三/210
權力と支配 尾高邦雄/213
政治に於ける合理性と非合理性 臼井二尚/214
社會的事實としての敎育 池端榮/219
三 社會事業・社會政策及人口の部/220
社會事業の對象としての貧困の性質並に限界 竹中勝男/220
財源より見たる社會事業 森岡正陽/224
我國に於ける社會政策成立過程の史的分析 川上賢叟/225
本邦都鄙別人口比率の變動傾向 松田泰二郞 林惠海/228
戰爭と人口 圓地與四松/231
四 宗敎の部/234
宗敎社會學の對象に就いて 小口偉一/234
敎團の構成形式 久保田正文/236
|
僧伽 岩井龍海/236
原始佛敎々團に於けるアジールの問題に就て 福場保洲/239
『四方僧物』に就て 三枝樹正道/242
布施論 淺野研眞/245
東洋文化と基督敎 溝口靖夫/248
五 都市及農村の部/251
氏子集團の研究 鈴木榮太郞/251
飛騨白川村の大家族制に就て 井森陸平/258
信州更級村の同族組織 喜多野淸一/261
六 民族・國家及經濟の部/265
南洋群島原始社會の社會學的研究 大山産一/266
種族の問題 新明正道/268
國家理論と社會學 黑川純一/269
經營共同社會觀 岩間巖/271
上田作之丞の社會經濟思想 犬丸秀雄/273
經濟社會學について 北野熊喜男/277
七 社會意識の部/281
社會圈としての新聞讀者 三崎敦/281
日本封建社會意識論 櫻井庄太郞/285
社會形象としての志士の構造 綿貫哲雄/288
滿洲靑年の職業意識 秋葉隆/288
八 家族の部/290
嫂婚の問題 姫岡勸/290
婦人殊に妻の經濟的社會的方面に於ける機能の
→消失について 桑原博隆/293
ヘブライ家族觀の推移 山室周平/295
朝鮮の族譜に就いて 金斗憲/298
追加/300
人文主義の社會學的意義 ヨハネス・クラウス/301
本邦人口政策に就て 西野入德/306
少年と社會關係の異常性 三好豐太郞/309
日本社會學會第十二囘大會記録/311
日本社會學文獻解題昭和十一年一月―昭和十二年三月 小山隆/314
海外社會學近況
リットの時代精神論 新明正道/362
米國に於ける法律社會學 難波紋吉/364
ユーバンク氏の歐米社會學の比較 齋田隆/371
學界彙報/376
學會報告/379
・ |
○、この年、杉田平十郎が「絶対健康の理論と実際」を「東学社」から刊行する。 pid/1073115
|
序
第一章 緒論/3
一、 健康の眞意義/3
二、 健康第一主義の提唱/9
三、 健康法の目的/14
第二章 健康と現代文化/21
一、 現代人の健康状態/21
二、 健康と都會生活/25
三、 健康と職業婦人/35
四、 健康と空中イオン/40
第三章 東洋に發達せる健康法/47
一、 印度の□酥〔ナンソ〕法と坐禪/47
二、 支那に於ける健康法/51
三、 東洋健康法の特色/56
第四章 日本に發達せる健康法/61
一、 印度・支那健康法の影響/61
二、 白隱禪師の内觀法/63
三、 貝原益軒の養生法/66
四、 平野元良の健康術/69
五、 平田篤胤の呼吸數息法/72
第五章 西洋に發達せる健康法/77
一、 古代に於ける健康法/77
二、 中世期に於ける健康法/79
三、 西洋健康法の特色/87
第六章 食物中心の健康法/91
一、 石塚式食養法/91
二、 村井弦齋氏の自然食論/93
三、 澤村博士の能率増進食物説/96
四、 二木博士の少食菜食論/97
五、 フレッチャー氏の咀嚼主義/100
六、 高野式抵抗養生法/101
七、 長與博士の過食主義/104
|
八、 ブレーメル氏の過食養生法/107
九、 海水飮用健康法/108
一〇、 本章健康法の總評/112
第七章 運動中心の健康法/119
一、 岡田式靜坐法/119
二、 二木式腹式呼吸法/122
三、 藤田式息心調和法/123
四、 岩佐式強健法/126
五、 田澤式呼吸體操/128
六、 カアリー氏の欠伸利用健康法/129
七、 中井・十文字氏の自疆術/131
八、 川合式強健術/132
九、 江間式心身鍛錬法/134
一〇、 本章健康法の總評/135
第八章 皮膚中心の健康法/141
一、 玉利博士の冷水浴/141
二、 海水浴と海水温浴/142
三、 ニップの水治法/145
四、 日光浴と空氣浴/147
五、 本章健康法の總評/149
第九章 精神中心の健康法/153
一、 坪野平太郎氏の陽氣生活法/153
二、 佐藤博士の靈肉一致養成法/156
三、 本章健康法の總評/158
第一〇章 絶對健康と電氣醫學/163
一、 生體の電氣發生現象/163
二、 人體の電導並に電解作用/169
三、 電氣刺戟の生理的作用/174
四、 人體の電氣異常反應/189
五、 高周波の生物學的作用/197
六、 超短波の生物學的作用/201
七、 電氣の細菌に對する作用/206 |
八、 電氣醫學的健康法/210
第一一章 健康と慢性病/215
一、 慢性病は不治か?/215
二、 慢性病の種類と症状/219
三、 現代醫學の重大缺陥/232
四、 慢性病と精神療法/240
五、 慢性病と鬪病術/243
六、 慢性病と温泉療法/249
七、 慢性病と絶對療法/254
第一二章 不老長生法の前提/259
一、 萬人の望む不老長生/259
二、 生物の永久生存性/263
三、 人間の老衰變化/267
四、 老人の死亡原因/271
五、 長壽者の調査報告/274
第一三章 人間並に動物の壽命/285
一、 日本人の壽命/285
二、 支那人の壽命/291
三、 歐米人の壽命/297
四、 動物の壽命/304
第一四章 從來の不老長生法/311
一、 支那の不老長生藥/311
二、 スタイナッハの囘春法/318
三、 ホルモン強壮劑/325
四、 百五十歳長生法/328
五、 長壽十則と十二則/335
六、 無心配中庸説/340
第一五章 科學的不老長生法/347
一、 人間電池説と不老長生/347
二、 電氣醫學的不老長生法/352
・
・ |
|
| 1939 |
14 |
・ |
11月、禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (32)」が「禪學研究會」から刊行される。 pid/4414821
|
興禪護國( こうぜんごこく)/ 後藤瑞巖 / p1~5
尊皇と禪 / 山崎益洲 / p6~16
花園法皇の御證道と興禪護國 / 小笠原秀實 / p17~30
興禪護國と妙心寺 / 長谷部宗鑑 / p31~45
護國興禪の理論 / 柴野恭堂 / p46~59
興亞と禪 / 緒方宗博 / p60~72
護國の經典と興禪の意義 / 伊藤古鑑 / p73~84
支那的と日本的 / 福場保洲 / p85~103
鎌倉時代の禪宗と護國思想 / 大屋德城 / p104~114
|
江戸時代の禪宗 / 市川白弦 / p115~124
禪と茶道 / 柴山全慶 / p125~135
戰爭と國文學 / 鈴木重雅 / p136~143
武士道と禪 / 木村靜雄 / p144~151
夢窓國師と興禪護國 / 一井明文 / p152~159
菊池氏の誠忠と大智禪師 / 釘宮武雄 / p160~174
虎關師錬の元亨釋書と日本精神 / 福嶋俊翁 / p175~190
白隱禪師と興禪護國 / 對本愛道 / p191~206
勤王僧天章禪師の事跡 / 荻須純道 / p207~224 |
○、この年、白隠禅師原著, 原田祖岳校注「延命十句観音経霊験記」を「正信同愛会」から刊行する。 3版
(同愛叢書 ; 特輯) pid/1229756
○、この年、加藤咄堂編「日本精神文献叢書 心要篇 17巻」が刊行される。 pid/1257002
|
敍和論語抄(勝田充編) / 1-27
解題 / 2
和論語抄 / 3
五輪書(宮本武蔵) / 29-96
解題 / 30
序 / 31
地の卷 / 32
水の卷 / 47
火の卷 / 65
|
風の卷 / 83
空の卷 / 95
不動智神妙録(沢庵) / 97-121
解題 / 98
不動智神妙録 / 99
天狗藝術論 (丹羽佚斎)/ 123-180
解題 / 124
敍 / 125
大意 / 127
|
天狗藝術論卷一 / 129
天狗藝術論卷二 / 142
天狗藝術論卷三 / 152
天狗藝術論卷四 / 168
藝術論後 / 180
茶話指月集(藤村庸軒)/181-222
解題 / 182
自敍 / 183
藤村庸軒先生略傅 / 185
|
茶話指月集(上) / 186
茶話指月集(下) / 209
夜船閑話(白隠) / 223-245
解題 / 224
序 / 225
夜船閑話 / 231
配所殘筆(山鹿素行)/247-288
解題 / 248
配所殘筆 / 249 |
○、この年、村上専精が「日本仏教史綱 下卷」を「創元社」から刊行する。 (日本文化名著選) pid/1918560
|
第三期 淨土・禪・日蓮時代 / 1
第一章 本期佛敎の大勢 / 1
第二章 南都佛敎の状況 / 9
第三章 叡山僧侶の横暴及び元龜の大難并びに其再建 / 15
第四章 賴瑜和尚の出世并びに敎相諸山の興廢 / 22
第五章 南北二京律宗の興隆 / 29
第六章 淨土宗の開立并びに法然上人及び其門下 / 36
第七章 淨土宗の源流及び其敎義 / 43
第八章 聖光・良忠及び證空上人 / 49
第九章 法然上人門下の異義 / 54
第十章 淨土宗の分派 / 60
第十一章 淨土眞宗の開立并びに親鸞聖人及び其門下 / 67
第十二章 眞宗の敎義 / 72
第十三章 眞宗の分派及び覺如・存覺の二上人 / 77
第十四章 一遍上人の出世及び時宗の敎義 / 83
第十五章 禪宗の傳來并びに榮西禪師及び其門下 / 90
第十六章 榮西禪師以後の臨濟禪の隆盛 / 96
第十七章 曹洞宗の傳來并びに承陽大師及び其門下 / 109
第十八章 禪宗の源流并びに其敎義 / 114
第十九章 聖一・大應二國師の出世及び其門下 / 119
第二十章 夢窓國師及び其門下 / 124
第二十一章 圓明國師の出世及び曹洞宗の分派 / 129
第二十二章 日蓮宗の開立并びに日蓮上人の出世 / 138
第二十三章 日蓮宗の敎義 / 143
第二十四章 日蓮上人の門下并びに日蓮宗の分派 / 150
第二十五章 日像上人の出世并びに京都の日蓮宗 / 156
第二十六章 蓮如・眞慧二上人及び本願寺高田の關係 / 163
第二十七章 蓮如上人滅後の眞宗及び
→石山の戰爭并びに一向一揆/169
第二十八章 眞盛上人の出世并びに天台眞盛派の分出 / 175
|
第二十九章 淨土宗白旗・名越二流の繁榮 / 180
第三十章 皇室・貴族の歸依并びに諸寺の建立(三) / 186
第四期 諸宗持續時代 / 192
第一章 德川氏の寺家制度及び崇傳長老 / 192
第二章 天主敎の禁止并びに宗門改め / 198
第三章 天台宗の状況并びに天海大僧正 / 203
第四章 日光・東叡兩山の建立及び淺草寺 / 208
第五章 妙立・靈空の出世及び圓耳・顯道の反抗并びに
→華嚴の鳳潭 / 215
第六章 天台宗學風の變動及び叡山安樂院の沿革 / 222
第七章 眞言宗の状況并びに正法律の興起 / 227
第八章 高野山學侶・行人・聖方の軋轢 / 235
第九章 智・豐兩山の由來?びに其興隆 / 239
第十章 臨濟宗の状況并びに白隱禪師の出世 / 245
第十一章 曹洞宗の状況 / 253
第十二章 曹洞宗の復古并びに月舟・卍山の師資 / 258
第十三章 淨土宗の状況及び檀林 / 262
第十四章 東西兩本願寺の分立及び其學黌 / 271
第十五章 兩本願寺に於ける宗義の紛爭 / 278
第十六章 日蓮宗中興の三師并びに談林の起源 / 283
第十七章 日蓮宗不受不施派の興起 / 290
第十八章 黄檗宗の開立并びに隱元禪師の事蹟 / 296
第十九章 木菴・高泉の二禪師并びに其後の状況 / 300
第二十章 普化宗及び修驗道 / 308
第二十一章 增上寺と兩本願寺との宗名爭論 / 313
第二十二章 神儒二道學者の排佛論 / 318
第五期 明治維新以後の佛敎 / 323
第一章 明治初年の状況 / 323
第二章 社寺局設置以後の状況 / 330
略傳 / 338 |
○、この年、井上哲次郎等監修「禅の講座 第5巻」が「春陽堂」から刊行される。 pid/1221409
|
禪の生活(大峽竹堂)
一 序言 / 1
二 求道生活 / 5
三 禪の精神 / 22
四 禪の生活 / 32
五 禪と非常時 / 50
六 結語 / 56
禪的經濟生活(福場保洲)
一 經濟 / 61
二 原始佛敎々團の經濟生活/66
三 禪的生活 / 71
四 禪宗敎團の經濟生活/79
五 禪的經濟生活 / 95
雲水生活(間宮英宗)
序に代へて / 101
一 死んで來い / 105
二 もつと大きい處がある/106
三 逆境の妙味 / 107
四 一寸來い / 111
五 引ずり出す / 115
六 大堰川の氷中に坐す/117
七 道友の力 / 118
八 彼の犬を逐つて見ろ/119
|
九 禪狂僧 / 120
一〇 不曾彈動一條絃 / 123
一一 今に始めるぞ / 128
一二 嚴師の慈悲 / 129
一三 オー寒い / 136
一四 雪中の門宿 / 140
一五 坐睡 / 141
一六 飯盜人 / 143
一七 歩行にして水牛に乘る/144
一八 東嶽老師 / 146
一九 何ぢやこのざまは / 147
二〇 人を使ふには / 148
二一 時間を無駄にするな / 148
二二 山岡鐵舟居士 / 153
二三 如何なるか別法寺 / 154
二四 勘當 / 156
二五 初發心の菩薩 / 159
二六 行脚 / 161
二七 投宿の作法 / 162
二八 私鉢と木賃宿 / 169
二九 あまり―つらーい唐辛/171
三〇 四國行脚 / 175
禪の處世道(石井光雄) /
|
一 黑猫生の陳辨 / 179
二 參禪は必要であるか / 181
三 處世の要諦、只斯の如し / 213
四 執務の要諦 / 219
五 榮進せんとするには此呼吸 / 223
六 若き社員の成敗の岐路 / 228
七 美人の捌き方 / 236
八 學問と敎養 / 241
九 熱鬧中の避暑地 / 248
家庭の禪(中根環堂) /
一 家庭禪の提唱 / 257
二 禪的家庭の整理 / 262
三 家族の禪的心構 / 266
四 主婦の勤めと禪 / 268
五 食事の禪的心構へ / 274
六 家庭と宗敎 / 282
七 家庭禪の要領 / 297
西洋人の見たる禪(鈴木ビアトリス)/303
禪僧及禪的人物の參禪逸話(五)(宇井伯壽)
一 道元禪師 / 337
二 白隱禪師 / 345
三 北條時賴 / 355
四 北條時宗 / 366 |
|
| 1940 |
15 |
・ |
4月、慶応義塾大学編「国語教程 巻1」が「慶応義塾出版局」から刊行される。 pid/1056675
|
前編
自國の獨立・福澤諭吉/1
丹田法・白隱禪師/4
道教・岡倉天心/8
千鳥の香爐・幸田露伴/11
笈の小文・松尾芭蕉/16
俳句/34
川柳狂句/38 |
陣屋・一谷嫩軍記/41
御殿・伽羅千代萩/60
一字千金・菅原傳授手習鑑/79
近世和歌/93
毒酒を受太刀の身・武道傳來記/97
行水でしるる人の身の程・武道傳來記/109
世界の借家大將・日本永代藏/115
見立てて養子が利發・日本永代藏/120
|
鼠の文づかひ・胸算用/127
銀一匁の講中・胸算用/132
漢學先生・浮世床/139
言葉あらそひ・浮世風呂/146
後編
枕草子抄/155
源氏物語「桐壺」・「帚木」・「夕顔」/204
・ |
○、この年、山崎益洲述「無門の門」が「春陽堂書店」から刊行される。 pid/1687889
|
白隱和尚と坐禪和讃 / 3
人間本來の面目 / 67 |
女性と靜慮 / 87
自利利他の生活 / 119 |
尊皇に生きよ / 141
般若心經の大意 / 171 |
隨談聞書抄 / 229
・ |
○、この年、朝比奈宗源 輯「皇民道徳宝典 続」が「巌松堂書店」から刊行される。 pid/1089942
|
教育ニ關スル勅語
一 天孫降臨(日本書紀) / 1
二 神武天皇(日本書紀) / 3
三 崇神天皇(日本書紀) / 18
四 五箇條ノ御誓文ノ勅語 / 19
五 五箇條ノ御誓文 / 19
六 陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭 / 20
七 皇室典範及憲法制定ノ御告文 / 27
八 憲法發布勅語 / 29
九 清國ニ對スル宣戰ノ詔勅 / 30
一〇 露國ニ對スル宣戰ノ詔勅 / 33
一一 戊申詔書 / 35
一二 國民精神作興ニ關スル詔書 / 36
一三 踐祚後朝見ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語/38
一四 即位禮當日紫宸殿ノ儀ニ於テ
→賜ハリタル勅語 / 40
一五 國際聯盟脱退ニ關スル詔書 / 42
|
一六 支那事變勃發一周年ニ當リテ
→賜ハリタル勅語 / 43
一七 青少年學徒ニ賜ハリタル勅語 / 44
一八 紀元二千六百年ノ紀元ノ佳節ニ當リ
→賜ハリタル詔書 / 45
一九 明治天皇御製百首 / 46
二〇 聖徳太子憲法十七條 / 55
二一 大化改新之詔奉答(中大兄皇子)/59
二二 神器論抄(虎關師錬) / 60
二三 神皇正統記抄(北畠親房) / 62
二四 祈願開白文(東巖慧安) / 65
二五 直毘靈(本居宣長) / 68
二六 大祓詞 / 73
二七 弘道館記(徳川齊昭) / 75
二八 弘道館記述義抄(藤田彪) / 77
二九 和文天祥正氣歌(藤田彪) / 79
三〇 楠氏論(頼山陽) / 80 |
三一 七生説(吉田松陰) / 82
三二 士規七則(吉田松陰) / 84
三三 大學抄 / 86
三四 中庸抄 / 87
三五 論語抄 / 88
三六 孟子抄 / 91
三七 老子澤庵講話抄(澤庵宗彭)/93
三八 莊子抄 / 100
三九 傳習録抄(王陽明) / 102
四〇 菜根譚二十則(洪自誠) / 103
四一 妙法蓮華經如來壽量品偈 / 106
四二 信心銘(三祖僧□〔ソウサン〕)/108
四三 普勸坐禪儀(希玄道元) / 110
四四 不動智神妙録抄(澤庵宗彭)/112
四五 坐禪和讃(白隱慧鶴) / 115
四六 歎異抄(親鸞) / 117
後記 編者 |
○、この年、小野清一郎, 花山信勝編「日本仏教の歴史と理念」が「明治書院」から刊行「される。 pid/1687232 重要
|
序・高嶋米峰 / 卷頭
日本佛敎の源流としての三經義疏・花山信勝/1
聖德太子の御敎の一端・白井成允/27
憲法十七條の宗敎的基礎・小野淸一郞/59
奈良朝の寫經に就いて・石田茂作/85
傳敎大師と法華經・鹽入亮忠/117
弘法大師の眞言密敎・瀧野賴應/149
諸行往生思想より一向專修への開展・硲慈弘/185
明惠上人の華嚴思想・坂本幸男/241 |
親鸞聖人の太子奉讚・佐々木圓梁/283
日本學より見たる如來廻向と降臨思想について・小野正康/303
道元禪師の發心觀・佐藤泰舜/369
佛敎者の世間道德・石津照璽/399
江戸時代に於ける諸宗の唯識講學と其の學風・結城令聞/427
白隱禪師に依る日本の精神文化統一とその契機・西義雄/471
明治以後の日本佛敎に就いて・宮本正尊/529
本覺門と始覺門・ブルウノオ・ペッツォルド/565
喇嘛・多田等觀/593 |
○、この年、林岱雲編「禅宗心経註釈全集」が「文曜書院」から刊行される。 pid/1027456
|
禪宗 心經註釋全集序 / 1p
凡例 / 6p
開題 / 1p
原著序文並に玄談 / 15p
原著 / 33p
般若波羅蜜多心經註・南陽慧忠禪師
→芙蓉道楷禪師 |
註心經・蘭溪道隆禪師
般若心經解・一休宗純禪師
般若心經註解・圓耳虚應禪師
般若心經口譚・龍溪性潜禪師
般若心經假名法語・鐵眼道光禪師
心經註解・盤珪永琢禪師
般若心經止啼錢・天桂傳尊禪師 |
毒語註心經・白隱慧鶴禪師 東嶺圓慈禪師
般若心經鐵船論・心應空印禪師
心經忘算疏・黄泉無著禪師
原著跋文 / 222p
心經歌集 / 223p
・
・ |
○、この年、「日本精神文献叢書 第12巻」が「大東出版社」から刊行される。 pid/1256964
|
守護國界章 傳敎大師 / 2
祕密三昧耶佛戒儀 弘法大師/35
序 / 38
本文 / 44
孝養集 興敎大師 / 57
卷上 / 57
卷中 / 69
卷下 / 78
興禪護國論 榮西禪師 / 90
序 / 91
令法久住門第一 / 93
鎭護國家門第二 / 95
世人決疑門第三 / 97
古德誠證門第四 / 121
宗派血脈門第五 / 122
典據增信門第六 / 126
大綱勸參門第七 / 129
建立支目門第八 / 141
大國説話門第九 / 145
囘向發願門第十 / 150
一枚起請文 法然上人 / 155
小消息 法然上人 / 156
皇太子聖德奉讃 親鸞上人/158
白骨の御文章 善如上人 / 166
傘松祖師道詠 道元禪師/169 |
十種勅問 瑩山禪師 / 175
立正安國論 日蓮上人 / 185
釋氏廿四孝並序 元政上人/209
普靑山竺法曠
宋定林寺僧鏡
齊〔ギョウ〕下道紀
齊莊嚴寺道慧
梁光宅寺法慧雲
梁開善寺智藏
梁草堂慧約
周中興寺道安
隋慧日道場敬説)
唐韶洲能
唐睦洲陳尊宿
唐普光寺慧〔シン〕
唐安國寺子鄰
唐大梵寺代病
本朝和洲榮好
本朝智泉
本朝高野山祈新
本朝陽勝
周福光寺道丕
本朝叡山禪喜
本朝信誓
本朝三井證空
|
宋景德寺法雲
明法林寺大同
人となる道 慈雲尊者 / 221
淨宗護國篇並序 觀徹述良信録 / 227
佛法興隆の建白(佛敎開國論) 佐田介石 / 246
一 僧徒自分拂佛を招くの罪を擧ぐ / 249
二 排佛の可否を問答す / 250
三 僧徒の國財に衣食するは是れ尸位素餐なりや
→否やと問答す/255
四 僧徒の官施を仰ぎ檀施に依るは是れ國害に
→屬するや否やと問答す / 255
五 佛敎は虚誕なりや否やを問答す / 257
六 佛敎は實效ありや否やを問答す / 257
七 勸懲の道は敎法殊に最も勝ることを辨ず / 259
八 政敎一致を辨ず / 259
九 僧徒自ら信ずる者寡くして、而して人を勸むるは
→條理立たざることを問答す / 262
十 火葬の利害を問答す / 263
十一 諸記傳に但だ僧徒の惡のみを載せて善を
→載せざることを問答す / 265
十二 僧徒十種の國益を立てしことを辨明す / 267
十三 僧徒父母の家を出るは、孝道に於て虧くるや
→否やを問答す/303
十四 明君賢君、碩學大儒は、古來佛を信ぜざるや
→否やを問答す/304 |
○、この年、竹内四朗編 「皇紀二千六百年記念富士展覧会図録」が「芸艸堂」から刊行される。 pid/1685123
|
佳日の冨士(東都) 小豆島甘兆
露台の冨士(帝國ホテル) 同
登山圖繪 池田遙邨
頂上 同
雲表の冨士(紅葉台より) 稻葉春生
白糸橋遠望 同
原白隱寺 岩周巣
沼津冨士隱れ 同
吾妻路 岩佐古香
松並木 同 |
秋色冨岳 大矢峻嶺
白糸村の冨士 同
三路く茶屋 加藤晴彬
三保 同
東海道の春 川口呉川
川口村の雪 同
夏の冨士(身延山) 川本參江
海をへだてゝ(波切) 山本參江
白糸村 小松華影
山中湖畔 同 |
御殿場 小森綠光
冨士驛附近 同
田子の浦 柴原希祥
登山小景 同
黎明 土肥蒼樹
初冬 同
御殿場附近 中田晃陽
紅冨士(御殿場にて) 同
目黑冨士 八田高容
初雪(上井手村) 同 |
黎明 東原方僊
須山の晩秋 同
麗陽白峯 山本紅雲
松間夕照 同
精進湖畔 山本朝光
籠阪峠 同
・
・
・
・ |
○、この年、武者小路実篤が「蝸牛独語」を「中央公論社」から刊行する。 pid/1684551
|
十、 新しき村/167
父と母/173
西洋の字と東洋の字/175
獨逸とソ聯/177
米國/178
インド/181
室伏高信の汪兆銘會見記/182
英國/184
東の村/185
金で出來ない事/189
十一、 柿と蜜柑の畫/191
凱旋の勇士に/195
建國二千六百年/196
死/197
父としては/202
ヂッドの最近の日記/203
西洋人を/203
マッチの不自由/206
日本の南國について/209 |
美に就ての雜感/217
日本畫雜感/224
美術雜感/228
古徑、靱彦、華岳
美の追求/232
偶感
富岡鐵齊/237
白隱の繪/243
日本畫に就ての斷片/245
いゝ畫を見る喜び/251
美人畫雜感/255
アメリカで見た畫から/260
生と死/276
死の恐怖に就て/290
心の鍛錬/295
人生に就ての斷片/303
社會のためか、人間のためか/314
生活と文藝に就て/316
雜感/321 |
病床雜記/326
獨身婦人に與ふる書/335
ある空想家雜記/345
土地を見に行く前
希望の種
昨日土地を見に行つて
空想
不可能なこと
馬鈴薯
第二の新しき村/358
單純の美/364
果して彼等は老いぼれたのか/370
自分に許された仕事以外/375
愛鄕心と旅/379
花の美/384
ある日/389
買ひたいもの/392
映畫雜感/395
よき家庭/401
|
時間の空費/406
運命と死/410
鵠沼/418
秋の散歩/425
日本のことなど/428
歐洲旅行雜觀/437
白樺を出す前/446
木下の思ひ出/450
志賀直哉について/457
謙遜/469
僕の夢/472
チエッコ問題から/475
親切者/478
勝ちぬくことが/481
滿洲の作家に/485
東洋人が協力すれば/489
東亞の資源/492
立派なもの許り/495
後記 |
○、この年、 原田祖岳講「正宗国師白隠禅師坐禅讃講話」が「正信同愛会」から刊行される。 (同愛叢書 ; 第4輯) pid/1221108
|
第一章 序説/1
坐禪讃大綱/1
第二章 本文解説/4
第一節 本具佛性と迷妄生活/4
第二節 一切佛法と坐禪の功德/33
第三節 坐禪の實行とその功驗/73 |
第三章 終説/111
見性例話/111
附録 正宗國師白隱禪師小傳
→岩崎巍山居士遺稿
第一章 緖言/1
第二章 白隱禪師畧歴/3
|
第三章 附論/27
第一節 白隱の治病養心訓/28
第二節 巍山居士の食事概説/36
第三節 白隱の獨り按摩法/51
第四節 白隱の病魔退治護符/55
・ |
|
| 1941 |
16 |
・ |
5月、武者小路實篤が「日本の偉れた人々」を「河出書房」から刊行する。 pid/1882914
|
序
傳記・小説
親鸞の結婚/1
日蓮と千日尼/29
黑田如水/55
宮本武藏/81
白隱/111
賴山陽と川上儀左衞門/129
黑住宗忠/143
|
感想・人物評論
空海に就いて/171
柳里恭に就いて/189
宮本武藏の一面/197
自分の好きな日本畫家三四/221
黑住宗忠に就いて/229
黑住宗忠のこと/231
黑住宗忠のことなど/240
法然のことを一寸/249
|
一休和尚に就いて/255
西鄕隆盛と二宮尊德の挿話/275
西鄕隆盛と二宮尊德/277
前文西鄕の話の訂正/279
二宮尊德に就いて/284
二宮尊德の仕事の一つ/287
二宮尊德に就いて/298
二宮尊德/307
二宮尊德の言葉/337 |
『二宮翁夜話』から/340
二宮尊德の言葉をよんで/344
北齋雜感/349
雪舟に就いて/361
楠正成一卷書/365
三條實美公/371
・
・
・ |
5月、加藤咄堂が「修養大講座 第10巻」を「平凡社」から刊行する。 pid/1039692
|
從容録(三)/1
第十一則 雲門兩病/3
示衆/5
本則/8
本則の評唱/16
頌/19
頌の評唱/23
第十二則 地藏種田/27
示衆/27
本則/32
本則の評唱/38
頌/41
頌の評唱/46
第十三則 臨濟瞎驢/50
示衆/51
本則/54
本則の評唱/58
頌/60
頌の評唱/66
第十四則 廓侍過茶/69
示衆/72
本則/74
本則の評唱/78
頌/81
頌の評唱/84
|
第十五則 仰山挿鍬/87
示衆/90
本則/94
本則の評唱/96
頌/99
頌の評唱/102
第十六則 麻谷振錫/106
示衆/106
本則/109
本則の評唱/116
頌/122
頌の評唱/126
第十七則 法眼毫厘/131
示衆/134
本則/136
本則の評唱/140
頌/143
頌の評唱/146
第十八則 趙州狗子/150
示衆/150
本則/152
本則の評唱/163
頌/165
頌の評唱/171
第十九則 雲門順彌/176
|
示衆/176
本則/178
本則の評唱/182
頌/185
頌の評唱/190
第二十則 地藏親切/195
示衆/195
本則/198
本則の評唱/202
頌/205
頌の評唱/211
第二十一則 雲巖掃地/215
示衆/215
本則/218
本則の評唱/223
頌/226
頌の評唱/228
第二十二則 巖頭拜喝/231
示衆/231
本則/233
本則の評唱/240
頌/244
頌の評唱/248
第二十三則 魯祖面壁/253
示衆/253
|
本則/256
本則の評唱/261
頌/268
頌の評唱/273
第二十四則 雪峰看蛇/277
示衆/280
本則/283
本則の評唱/290
頌/293
頌の評唱/298
第二十五則 鹽官犀扇/302
示衆/302
本則/307
本則の評唱/313
頌/316
頌の評唱/320
夜船閑話/327
一、 不老長壽法源流/327
二、 白隱禪師と夜船閑話/335
三、 夜船閑話の内容/343
四、 刊行の由來と要旨
→(序文通釋)/381
五、 延命十句觀音經/395
・
・ |
6月、禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (35)」が「禪學研究會」から刊行される。
pid/4414824 (IRDB) 重要
|
花園法皇と禪 / 鎌田禪商/p1~29
本體的なるものへの具象的考察 / 小笠原秀實/p31~50
利休居士の遺偈について / 近重眞澄/p51~55 |
白幽子史實の新探究 / 伊藤和男/p57~81
禪宗學關係論文目録/p83~88
・ |
10月、福場保洲が「白隠」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第5) pid/1683818 最重要
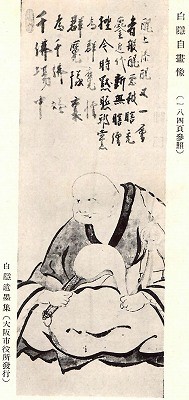 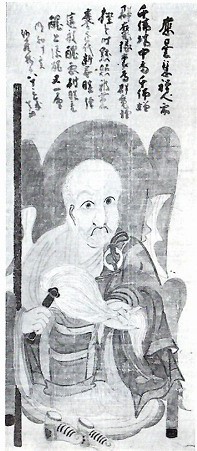
白隠自画像 福場保洲著「白隠」口絵より 伊勢 竜雲寺像 「日本の美術 No47
竹内尚次編 P37」より |
応曇慧禅人需
千仏場中爲千仏嫌
群魔隊裡為群魔憎
挫今時※黙照邪黨
※鏖近代断無轄僧
※這般※醜悪破轄禿
醜上添醜又一層
明和丁亥
沙羅樹下八十三歳老衲
|
曇慧禅人の需(もとめ)に応えて
千仏場中(せんぶつじょうちゅう)千仏に嫌われ
群魔隊裡、群魔に憎まれる
今時黙照(こんじもくしょう)の邪黨を挫(くじ)き
近代断無の轄僧(かつそう)を
→鏖(みなごろし)にする
這般(しゃはん)醜悪の破轄禿(はかつとく)
醜上醜を添う又一層
明和四年
八十三歳の老僧 |
※黙照(もくしょう): 黙々と坐禅するさまを形容したことば。
※鏖(みなごろし):ひとり残らず殺すこと。鏖殺(おうさつ)。
※這般(しゃはん):)これら。この辺。このたび。今般。
※醜悪(しゅうあく):容姿がみにくいこと。行いや心がけなどが卑劣で嫌らしいこと。また、そのさま。
・
・
・
・
・ |
|
仏という仏には嫌われ、悪魔という悪魔にも憎まれようが、
今時流行のただ坐って目をつぶっていれば、
悟りが開けると考えている間違った禅僧の者共の動きを抑える一方で、
近年勃興してきた、因果の理法を認めず、
社会の真実に目をやらず現世を享楽する堕落した
僧たちを皆殺しにしてやりたい。
見よ、
この自画像のとんでもない醜悪な面構えをした坊主を
醜い上にさらに醜さが重畳している。 |
|
第一章 白隱の時代の社會と思想/3
一 白隱の時代 / 3
二 社會組織 階級制度 / 4
三 思想 保守的と進歩的 / 12
四 蕉風と禪 / 25
第二章 白隱の生涯とその兒孫/32
一 白隱と生死の問題 / 32
二 因行の時代 / 35
(一) 在家時代 出家 / 35
(二) 危機 大悟 / 40
(三) 正受老人の鉗鎚 大悟/48
|
(四) 肺患治療と内觀 / 59
(五) 悟後の修行 行脚 歸山 / 64
(六) 悟後の修行の純熟
→法華妙理の悟了/71
二 果行の時代 / 79
(一) 不斷の自利々他の生活 / 79
(二) 遷化 大吽一聲 / 91
三 門下の兒孫 / 95
(一) 白隱門下の俊英 / 95
(二) 白隱の法孫 隱山系と卓洲系/112
第三章 白隱の家風・思想 / 118 |
一 傳承と創造 家風と思想 / 118
二 見性 無字・雙手音聲・死/124
三 四智 五位 / 132
四 相似禪の破斤 / 145
五 法華・念佛觀 三敎一致・至善/157
六 儒敎・神道・國體・政道觀/164
第四章 結び / 172
一 白隱の業績 / 172
二 白隱禪の時代的意義 / 183
追補註 / 189
・ |
11月、武者小路實篤が「人生と藝術」を「河出書房」から刊行する。 pid/1882986
|
笛吹く男
笛吹く男/3
人生に就て
人生に就て(その一)/13
人生に就て(その二)/35
文化と藝術/51
東洋文化のために/57
日本文化の目標/63
匹夫の志奪ふべからず/70
日本と支那と仲よくするには/75
聖人と英雄/87
臣民の道/96
家庭の幸福に就て
新戀愛と結婚/105
家庭の幸福に就て/114 |
他人への要求/124
隣組の道德/129
文學鑑賞に就て
文學鑑賞に就て/135
言志録より/147
『私は冒險と結婚した』に就て/156
『幸福な家族』映畫化その他/160
手紙の形で/166
新年/173
趙陶齋の畫/179
白隱の畫や字を見て/188
正倉院御物を拜觀して/193
負けるが勝ち
負けるが勝ち/205
壯年について/211 |
高村光太郞君に就て/219
周作人との友情の思出/221
周作人と私/227
長與兄弟/231
兄と弟/233
海/235
六月の思出/238
机の上/242
ローマ・フィレンツェの思出/244
二宮尊德
尊德の言葉/257
尊德の言葉など/279
櫻町の復興/288
人物記
1 鄭道昭/295 |
雪舟/300
偉い人間/304
2 尊敬すべき人/307
3 土佐光長/319
大雅堂の十便と蕪村の十宜/321
荻須高德氏の個展/323
瀧田樗陰/326
4 小人について/329
5 村上華岳/342
今の日本の要求する人/351
6 小出栖重の畫/356
趙陶齋/361
バーナード・リーチ/363
頭のいゝ作家/367
見返しの畫に就て/371 |
○、この年、伊藤古鑑が「臨済」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第2) pid/1683936 重要
|
臨濟の思想的基調 / 3
一 達磨大師の根本思想 / 3
二 二祖より六祖まで / 13
三 慧能大師の思想 / 21
四 南嶽と馬祖 / 27
五 百丈と黄檗 / 34
臨濟の時代的背景 / 44
一 臨濟の活動時代 / 44
二 臨濟と其當時の敎勢 / 49
三 臨濟と其當時の禪風 / 58
臨濟の修行と開悟 / 70
一 敎を捨て禪に入る / 70
二 黄檗棒下の臨濟 / 73
三 大地黑漫々 / 77
|
四 暗夜に光明 / 82
五 開悟への段階 / 86
臨濟の行持と末後 / 92
一 行雲流水の生活 / 92
二 臨濟破夏の因縁 / 97
三 黄檗の付法を受く / 100
四 臨濟の敎化 / 102
五 臨濟の遷化 / 107
臨濟の正法眼藏 / 111
一 喝 / 111
二 四料揀 / 115
三 三句 / 132
四 三玄三要 / 137
五 四照用 / 144
|
六 四賓主 / 146
臨濟の百醜千拙 / 151
一 但だ外に求むる莫れ / 151
二 什麼をか欠少す / 155
三 平常無事 / 162
四 一無位の眞人 / 168
五 無依 / 173
六 眞正の見解 / 177
雜篇 / 182
一 臨濟の家風 / 182
二 臨濟の研究資料 / 187
三 臨濟録の内容と刊行 / 191
四 臨濟と公案 / 194
五 臨濟正宗のこと / 197 |
○、この年、柴山全慶が「十牛図」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第3) pid/1682991
|
十牛圖 / 1
緖言 / 3
普明禪師牧牛圖頌/15
第一、 未牧
第二、 初調
第三、 受制
第四、 廻首
第五、 馴伏
第六、 無碍
第七、 任運
第八、 相忘
第九、 獨照
第十、 雙泯
普明禪師牧牛圖頌/57
一、 書物
二、 著者
|
三、 圖頌
四、 牛兒
五、 牧牛
六、 聖位
七、 禪の眞境
八、 思想的性格
廓庵禪師十牛圖頌/83
第一、 尋牛
第二、 見跡
第三、 見牛
第四、 得牛
第五、 牧牛
第六、 歸牛 歸家
第七、 忘牛存人
第八、 人牛倶忘
第九、 返本還源
|
第十、 入□(テン)垂手
廓庵禪師十牛圖頌/125
一、 書物
二、 著者
三、 圖頌
四、 牛兒
五、 牧牛
六、 聖位
七、 禪の眞境
八、 思想的性格
巨徹禪師和白牛圖頌/159
第一、 失牛
第二、 尋牛
第三、 見迹
第四、 見牛
第五、 得牛
|
第六、 護牛
第七、 騎歸
第八、 忘牛
第九、 雙泯
第十、 入□(テン) 厂+黒+土
巨徹禪師和白牛圖頌/201
一、 書物
二、 著者
三、 圖頌
四、 牛兒
五、 牧牛
六、 聖位
七、 禪の眞境
八、 思想的性格
十牛總頌 / 227
・ |
○、この年、市川白弦が「大慧」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第4) pid/1683368
|
前篇
序説 / 3
第一章 「肚」 / 12
第二章 禪機 / 19
第三章 矛盾 / 24
第四章 心 / 33
第五章 無 / 40
第六章 無字 / 54
第七章 公案 / 61
|
第八章 修爲 / 78
第九章 悟 / 85
第十章 宗敎的紛飾の脱落 / 92
第十一章 野狐禪 / 98
後篇
第一章 時代と傳記 / 113
第二章 著書、法系、交友 / 133
第三章 人としての大慧 / 140
第四章 大慧と宏智 / 145
|
第五章 大慧禪と宏智禪 / 150
第六章 默照禪への態度 / 156
第七章 道元の大慧評 / 164
第八章 大慧禪の特色 / 172
第九章 □杖子頭(しゅじょうす)の禪 / 188
第十章 「大慧武庫」に關する疑義 / 193
附録
一、 禪語小解 / 201
一、 索引 / 211 |
○、この年、佐倉啄二が「肚の人びと」を「富士書店」から刊行する。 pid/1040250
|
死あつて他なし・(楠木正成公と楚俊禪師)/1
一切を捨てて・(道林禪師と白樂天)/10
腰につけている石・(六祖彗能禪師のこと)/16
働かざる者食ふべからず・(百丈和尚のこと)/33
若し神風吹かざりせば・(北條時宗と佛光國師)/36
風を網で捕へる愚さ・(山縣元帥と峩山禪師)/67
肚の人・(法眼和尚、圓通和尚、
→大山元帥その他)/91
短氣ではいけない・(磐珪禪師のこと)/101
聲望は天下に・(大石良雄と良雪和尚)/108
身心脱落・脱落身心・(道元禪師のこと)/111
一本の指・(倶胝和尚のこと)/134
火焔の中に端坐・(快川和尚のこと)/140
一休和尚の横顔/142
滴水禪師と山岡鐵舟/160 |
一滴の水・(滴水禪師のこと)/177
廓の女・(木堂和尚のこと)/180
白隱と娘/184
末世の僧は祖師を賣る・
→(澤庵和尚のこと)/195
そんな寶を何處から・
→(石屋禪師のこと)/198
一匹の蜂・(神賛和尚のこと)/204
見知らぬ旅僧・(愚堂和尚と無難和尚)/207
流石の伊藤公も・(悟由禪師のこと)/216
泥中の蓮・(無三和尚のこと)/218
ただ一ときの夢・(夢想國師のこと)/220
雲は青天に在り・(藥山禪師と李?)/224
幸福者・(誠拙禪師のこと)/226
拂子を把つて・(祖鏡禪師のこと)/229
|
三年になります・(臨濟禪師のこと)/231
一塵一芥も皆是佛種・(魯堂和尚のこと)/235
物外和尚と近藤勇/241
朝から晩まで・(峨山禪師のこと)/246
太鼓の音を描く・(仙崖和尚のこと)/249
一超直入如來地・(伊達安藝と石水和尚)/257
今朝はよい天氣だ・
→(伊達自得と越溪和尚)/260
達磨不識の因縁透過・
→(上杉謙信と宗謙禪師)/263
門を叩く・(乃木大將と南天棒和尚)/265
何を爲さる・(水戸光圀と心越禪師)/267
俳聖芭蕉と禪/269
・
・ |
○、この年、柴野恭堂が「達摩」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第1) pid/1683402
|
序論
一 禪の概念について / 3
二 禪及び禪宗の起源―達摩渡來以前の思想界概觀 / 34
本論
一 達摩傳考 / 53
(一) 渡來の年代―梁武帝との謁見の事實―慧可雪中斷臂の因縁―
→皮肉骨髓の敎誡―楞伽經の傳授 / 53
(二) 缺齒の達摩―日本來朝説について / 68
二 達摩の思想と其解説 / 77
(一) 達摩の述作について / 77 |
(二) 二人四行觀について―漸修頓悟の意義 / 79
(三) 不立文字―禪の辯證法―最上乘禪(向上禪) / 96
三 達摩より慧能に到る思想的展開 / 131
(一) 慧可の思想―不可得―了々常知―無心論 / 131
(二) 僧□(サン)の思想―不二即 / 143
(三) 道信の思想と牛頭禪―定慧の問題 / 148
(四) 弘忍及び慧能の思想―頓悟頓修―南北二宗の對立の意義―
→如來禪の完成 / 155
餘論 印度傳燈説について / 191
追補註 / 200 |
○、この年、小野久三が「白隠禅師」を「道統社」から刊行する。 pid/1054358
|
序文
序章 白隱の修行とその生涯/1
一、 駿河の誇
二、 人世の無常を知る
三、 休心房の豫言
四、 地獄の恐怖
五、 天神を恨む
六、 拔刀して渡河
七、 遂に出家
八、 馬翁に師事
九、 祕書筆墨を燒く
一〇、 師恩に報ず
一一、 増上慢の天狗となる
一二、 宗格を知る
一三、 正受老漢の鉗鎚を受く
一四、 息道病む
一五、 肺を冐さる |
一六、 白幽眞人を訪ふ
一七、 夜船閑話の獲得
一八、 砂石集に感激
一九、 好道友を得
二〇、 大燈語録と一隻眼
二一、 小知識の法話に感ず
二二、 巖瀧山の修業
二三、 松蔭寺に還る
二四、 腐つた醤油
二五、 母の夢
二六、 十句觀音經の因縁話
二七、 遂翁參謁
二八、 京師の傳道
二九、 一夫多妻を排撃
三〇、 最助の江戸入り
三一、 掉尾の化益
三二、 入寂 |
第二章 白隱の逸話/128
一、 白隱の隻手
二、 葱好き
三、 これはうまい
四、 古堂に眠る
五、 借すと癖がつく
六、 兩親の年齡
七、 駕籠は駕籠
八、 意味深い方便
九、 平凡の非平凡
一〇、 牡丹餅を召しあがれ
一一、 念佛一回一文
一二、 他人は女房になれぬか
一三、 情夫にされた禪師
一四、 お三婆さんの見識
一五、 おさつ婆さんの悟道
一六、 奴婢も人の子
|
一七、 迷故三界城
一八、 同僚を救ふ
一九、 妾の參禪
第三章 白隱禪師の語録/180
一、 夜船閑話
二、 主心お婆々粉引歌
三、 施行歌
四、 大道ちよぼくれ
五、 安心ほこりたた記
六、 おたふく女郎粉引歌
七、 辻談議
八、 寢惚之眼覺
九、 御代の腹皷
第四章 白隱禪師略年譜/251
・
・
・ |
○、この年、杉本清治が「自ら生きる力」を「新興亜社」から刊行する。 pid/1072114
|
新體制と國民健康
第一編 新體制下の健康確保/3
第一章 國民健康法の提唱/4
戰爭と健康/4
從來の健康法は長續きしなかつた/6
飽きられない健康法をつくらなければならない/8
結核はなまけものの病/9
困つた人達/10
食ひ意地が胃腸をこわす/11
豫防法をやる人が少いのは情ない/13
臆劫がらずにやれる健康法はないものか/14
食を濫用するな/15
ある神經衰弱患者の話/16
先づ心を癒せ/20
お腹の状態を考慮せよ/24
一食絶食のやり方/25
對局便乘に非ず/26
夜食は止めよ/27
一日絶食の提唱/28
錠劑を服むやうに簡單でないが效果はある/30
運動のかたより/31
「國民健康法」の提唱/33
生命力の甦生/34
寢床の上でも出來る/36
入浴中を利用しての健康術/38
云ひまわしは不手だが效果はある/40
現代人の要求するスピード健康法
第一編 現代人は自然の健康法を忘れている/43
第一章 無代の治療劑、日光浴/44
日光は生命の源/44
日光浴の準備/46
日光浴の順序/47
日光浴は何に效くか/48
日光浴で丈夫になつた實例/49
第二章 冷水浴の效果/51
まづ冷水摩擦から/51
冷水摩擦の仕方と效果/52
冷水浴の方法/53
冷水浴をして宜い人、惡い人/55
第三章 知られない空氣浴/57
費用要らずに健康増進/57
貧血新陳代謝病はこれで治る/58
第四章 血液淨化と深呼吸/61
最も效果的な深呼吸の仕方/61
頭腦を明晰にし血壓を下げる/63
第五章 病氣を治す「水」/66
水は生命の源泉/66
健康を増す水の飮用法/68 |
ドイツで旺んな海水の飮用/70
第六章 胃腸の休養と斷食健康法/73
日本人は世界一の胃弱國民/75
斷食療法の準備/75
斷食療法の效果/79
第七章 全身健康法としての温浴/82
入浴も立派な健康法/82
最も效果的な入浴の仕方/84
家庭で温泉氣分/87
第二編 朝夕十分間の完全健康法/91
第一章 亞鈴體操/92
方法は簡單だが效果は素晴らしい/92
神經衰弱、胃腸病に絶好/93
怪力サムソンを倒した
→亞鈴體操の發明者/95
第二章 戸山學校式手拭體操/97
必ず效果のある健康法の仕方/97
手拭體操の仕方/100
第三章 血液循環とブラシ摩擦法/104
外國の大學でも之を實行/104
西川博士の創案せる方法/106
第四章 筋肉の賦活日本式木劍體操/108
劍道は世界に冠絶する心身鍛錬法/108
日本精神豊な木劍體操/110
一石三鳥の效果がある/113
第五章 乾布摩擦法/117
賀川博士推獎の健康法/117
まづ皮膚を丈夫に/118
感冐はこれでキツト防げる/120
第六章 拳固運動法/122
忽ち體力漲り氣分は爽快/122
第七章 鹽と人生、鹽摩擦法/125
體が温り夜は安眠/125
無鹽泉や海水浴に優る/127
第八章 健康棒應用強健治病術/129
棒一本で病氣が治る/129
健康棒の用ひ方/131
第九章 四つ這ひ健康法/134
健康を望むなら猿を眞似よ/134
人間は四つ這ひで歩くべきもの/137
邪念は飛び精神は爽快/138
第十章 毎朝排便無病健康法/141
便秘は健康と長壽の大敵/141
便所の中に四十分/142
便秘せぬ方法/145
第十一章 便秘知らずの腹部體操/148
病身が堂々たる偉丈夫に/148
腹部體操の仕方/149
|
第三編 精神的健康法/151
第一章 心が病めば病氣は治らぬ/152
心を明るくすれば肉體も健康/152
靈と肉との養生法/156
第二章 心氣轉換健康法/159
修養次第で出來る方法/159
心氣轉換で難病治癒/162
死の宣告を受けた身が更生/164
一悟一番暗黒から光明へ/167
第三章 起床前の寢床體操健康法/170
起床前に十分間一日爽快/170
慢性病が治る寢床體操/172
第四章 カアリー式強健法/175
疲勞倦怠征伐の妙法/175
カアリー式強健法の仕方/176
第五章 晝眠式強健法/179
睡眠は天與の健康法/179
晝眠一時間能率二倍/181
第六章 獨りマツサージ/185
無藥療法の大關格/185
獨りマツサージの仕方/186
往古の健康法を現代に生かせ
第一編 古人の工夫せる健康法/191
第一章 □酥〔ナンソ〕法/192
印度佛教徒の秘法/192
第二章 座禪/195
心の惱みと肉體の疾患を解決/195
座禪の仕方/196
第三章 白隱禪師の内觀法/200
禪師自ら難病を克服/200
内觀法とは/202
白隱の獨り按摩/207
第四章 貝原益の軒養生法/210
現代に生きる養生訓/210
氣を養ふ道/211
養生の術/214
按摩法/214
導引の法/216
第五章 佚齊樗山の收氣術/220
肚をつくる健康術/220
收氣術の仕方/221
第六章 平田篤胤の呼吸數息法/225
氣を錬る修行法/225
丹田に氣集れば無病長壽/227
第七章 平田元良の健康法/230
歌誦撫摩禪帶法/230
・
・ |
○、この年、谷至遉が「参禅」を「文学書房」から刊行する。 pid/1035245
1931年 中央出版社発行「現代名士の参禅実話」の改題
|
座禪に於ける學理的研究 理學博士近重眞澄氏の話/1
雪隱の進歩
禪定の抵抗力
禪と健康
一問題あり
河野廣中の參禪 何うして禪に入つた手/17
獄中へ禪書を携へて
無字の門關を透る
決斷とは何か
決斷力を打ち殺せ
楠正成と小村外相
智者は默す 床次竹次郎の禪話/30
婦人禪を説く 伊澤修二夫人/33
婦人の爲すべき座禪
平常心是道解乎
特に婦人に
座禪石
色氣を去れよ 文豪漱石の參禪/45
桃下堂病院長 岡田乾兒の參禪 主人公は誰か/56
仕事の間に
雪山會
哲學と禪
自己と這箇
精神修養と禪 心理學上より文學博士元良勇次郎/64
すべし、すべからず
漱石と共に
禪と主理主義
主意主義の修養法
參學者への注意 曹洞宗管長石川素堂/72
我が文字禪 文學博士上田萬年/77
雲水の苦行難行 峰尾大休和尚參禪の話/83
雲水の旅裝は?
掛錫を許さる
禪と催眠術と武士道 文學博士福來友吉參禪話/92
公案
催眠は無人格
達磨の八方睨み
度胸と武士道
彈實の會 山岡鐵舟の參禪/103
禪に就いて 行住坐臥皆禪也 勿滑谷快天の話/110
一元の活用
禪の眞髓
禪の妙用 禪定と坐相 横尾賢宗/119
謙信の參禪
算盤禪の由來 參禪は何にても出來る 早川千吉郎/130
|
先づ圓覺寺の玄關へ
寄宿舎で
警策の響き
軍神の參禪 乃木大將の禪を語る 追憶の心學道人/140
禪の本領 逃がす秘傳と遁げる奧の手 西郷南洲/150
丹田の修養に 禪の効用は? 鈴木充美/153
狐わなと大入道/156
由利滴水の豪膽 衣を縫ふに似ている/159
努力は人を造る 兒玉玄海和尚を語る 菅原洞禪師/162
禪機溌溂 侯爵大隈重信 櫻洲との論戰/169
二つの對立 東濠和尚と頭山滿 抵當の指一本/172
反省會の米峰 禁酒會の米峰 米峰に米峰の破戒/177
腹式呼吸 白隱の遠羅天釜 二木博士の參禪/182
加藤咄堂居士 筆と舌は唯一の武器 語るはただ徳の一字/187
悟由禪師に問ふ 白刄の刄渡りは何? 伊藤博文の話/192
南條、村上の兩師 前田慧雲の三博士 禪的性格の持主/195
毒藥と禪 服毒して脱落 卍庵和尚の參禪/202
看破 居士の胸中は何か 竹田默雷/206
眞面目 穆山は斯く云ふ 眞實の禪/208
尾崎咢堂の雄辯 得意の臂喩 禪の本分からは/212
口頭三昧 時代と共に 釋宗演の禪/218
惡辣な師を選ぶ 冷水を浴び坐睡 祥山の參禪/224
無類の辛辣 叩き出された廣中 燒禾山の會/229
陰徳の行持 肥桶を擔ふ 東和濬尚/233
熊の皮 居士渡邊無邊 參禪の動機/239
禪の入門 勝峰大徹和尚/243
喋舌らぬが
白地になるには
十牛の鬪
一休の情死
雲門の秘在形山
新井石禪の得度 苦心の歴史 觀世音への祈願/261
得庵の一喝 伊藤公をへこます 無慈悲慘忍にやめよ/266
眞個の師家 雲水長者 松蔭和尚/269
神尾大將の參禪 座禪せよ 精神修養の根本義/273
臨濟の大悟 拳は悟の證 打爺拳の由來/279
跣足參り 記憶力の薄弱を嘆いて 秋野孝道/287
尼に遣り込められて 未來心不可得 徳山和尚の大悟/291
夏冬一時に來たか/297
それ猫が 賊馬に騎つて賊を追ふ 風外の禪機/301
道に親しき祖岳 世話になる身で 他人の世話は出來ぬ/305
牛頭山の法融/308
倶胝一指頭 尼の侮辱に 發奮するまで/313
丸寸五分の禪 楠田謙藏の參禪/319
・ |
4月、龜川教信が「靈魂論」を「興教書院」から刊行する。 pid/1040347
|
一 靈魂問題の緊要性/1
一、 精神の力/1
二、 信の躍動相/4
三、 東亞的精神の創造性/7
四、 靈魂觀念の發生/11
五、 生命と靈魂/18
六、 靈魂觀念の進化/21
七、 日本的なものの見方/29
二 靈魂の意義/35
一、 靈魂の字義/35
二、 古代印度に於ける靈魂論/37
三、 釋尊の立場/41
四、 業道靈魂論確立の要求/55
|
五、 發展佛教の靈魂論/59
三 靈魂と無我/69
一、 佛教の無靈魂的色彩/69
二、 佛教無我説の唱導/75
三、 無我の論據/78
四、 現實の段階に於ける
→無我の役割/92
五、 相續の觀念/99
四 靈魂と業道/103
一、 業の意義/103
二、 業の體/112
三、 種子/122
四、 受報の時期/126
|
五、 業の種別/133
六、 業道成立の内感/155
五 靈魂と輪廻/160
一、 人生の苦感/160
二、 佛教の輪廻説/163
三、 無我と輪廻の調和/175
四、 地獄の實在/180
五、 十二因縁觀/197
六、 中有と幽靈/210
七、 輪廻の主體/238
六 靈魂と解脱/241
一、 靈魂論の歸結/241
二、 因果の法則/243
|
三、 業道と運命/259
四、 解脱の内容/285
五、 業感と如來他力/290
六、 廻向と滅罪/296
七、 信と懴悔/303
七 佛教靈魂論の合理性/315
一、 日常生活と佛教思想/315
二、 學的觀點/320
三、 道徳的觀點/325
四、 宗教的觀點/331
五、 むすび/337
・
・ |
6月、 伊藤康安が「坐禅十年」を「第一書房」から刊行する。 pid/1040722/1 閲覧可能
|
第一篇
坐禪十年/3
決戰體制と禪/3
坐れば解る/5
公案は手段/7
身心の大掃除/9
坐禪と健康/12
働くが修行/14
禪は非常時型/16
待つた無しの生き方/18
參禪の過程/20
入室參禪/26
生命を捨てる修行/29
參禪の餘興/32
法戰場裡の鍔ぜり合ひ/36
提唱の有難味/38
禪僧と婦人/42
提唱ぶりいろいろ/46
碧巖三則/52
公案のいろいろ/58
禪の大衆化/60
修證一如/61
禪は救ふ/65
普勸坐禪儀と遠羅天釜/66
物の極意はすべて禪/72
修證一如と見性主義/74
寺はどこに行く/76
生死を越えて/76
祖先を祭れ/79
自信なき僧侶の姿/82 |
金で昇る僧の地位/86
寺院に課せられた二つの役目/89
公卿の位倒れ/92
教義の宣布をどうするか/94
禪には教義なし/98
坐禪の指導が禪僧の役目/101
神棚と佛擅/105
寺院と檀家/107
大東亞共榮圈と佛教/110
第二篇
武士道と佛教/114
澤庵の不動智神妙録/114
不動智神妙録と太阿記/121
平安文學と佛教/128
顯密の二教/128
法華八講と物語/132
後七日御修法と山門四箇大法/138
諸法實相と即事而眞/143
鎌倉文學の特質/151
いくさの文學/151
教への文學/152
世捨人の文學/153
思ひ出の文學/155
法語文學/156
現代語と佛教/159
新聞雜誌に見える佛教語/159
禪語から來た俗語/163
法華經から出た現代語/167
密教關係の俗語その他/172
國定教科書と佛教語/175 |
第三篇
花に見る京の寺々/177
花と寺/177
兌長老と瑞溪周鳳/178
銀閣寺玄關の曲折味/179
寧一山の墓と義堂の像/180
天龍寺と鹿王院/182
鞍馬の山の雲珠櫻/184
旅に見る秋の寺々/187
學校參觀/187
妙喜庵と圓福僧堂/188
松花堂の舊居/191
寶珠院墓參り/192
信貴山毘沙門天/193
中宮寺の觀音と西大寺の
→愛染明王/196
薪の酬恩庵/198
雨の五山めぐり/199
虎關國師と正徹和尚/201
妙喜世界と摩利支天/203
隱山派の法窟/206
水郷一日一夜/208
晩涼月明のドライブ/208
夜目にも著るき水郷/209
樂しい旅にも一喜一憂/210
名に負ふ坂東太郎/211
餌と間違へて釣針を呑む/212
第四篇
庵・門・庭・墓/215
庵/215
|
門/220
庭/222
墓/225
夢窓國師素描/236
七朝國師/236
容姿端麗の美僧/237
轉錫遊方/239
著述と歌集/242
風流韻事/244
白隱禪師と日本佛教/246
日本佛教の正統/246
日本佛教の統一/249
日本佛教の純粹化/253
澤庵和尚の思想と生活/256
紫野の佛法/256
天下一變/262
羽州上ノ山の配所/267
品川に一寺建立/273
高邁な知性と豐富な趣味/281
尼になりたい女/292
十二月八日感激の放送/294
禪庵の正月/296
理趣分を考へる/297
禪庵十年/299
苦難の十年/299
わが父のこと/300
わが母のこと/303
禪庵の修繕/304
第二の難關/307
・
|
10月、禪學研究會 「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (37)」が「禪學研究會」から刊行される。 pid/4414826
|
禪宗の傳燈に就て / 伊藤古鑑/p1~11
虎關寃詞 / 福嶋俊翁/p28~41
終南山至相寺 / 古田紹欽/p118~124
むすびに就て / 福場保洲/p164~170
白幽子史實の新探究(續)/伊藤和男/p42~60
神祗に關する花園法皇の御態度/鎌田禪商/p61~85 |
大蟲宗岑禪師讃仰 / 松田奉行/p86~91
法系問題の一考察 / 緒方宗博/p125~131
王法不思議 / 山田虚室/p92~103
禪學の構造 / 對本愛道/p104~117
末法時代と我國中世禪僧の
→態度/荻須純道/p151~163
|
王陽明の思想と六祖法寳壇經/
→久須本文雄/p132~150
職能の倫理 / 市川白弦/p171~178
牧牛について / 柴野恭堂/p12~27
・
・ |
11月、鈴木大拙, 古田紹欽共編「盤珪禪師250年記念出版 盤珪禅の研究」が「山喜房佛書林」から刊行される。pid/1040766
|
盤珪の不生禪・鈴木大拙 / 1
我觀盤珪禪・朝比奈宗源 / 19
盤珪の易行禪・秋山範二 / 50
盤珪の思想・市川白弦 / 131 |
盤珪の行・伊藤古鑑 / 188
盤珪の生涯・照峰馨山 / 314
石門心學と盤珪禪・古田紹欽 / 403
禪の論理・紀平正美 / 420 |
近世臨濟禪の日本的性格・福場保洲 / 444
編輯後記(古田紹欽)
・
・ |
○、この年、北川桃雄, 奥平英雄共編「日本美術の鑑賞 近代篇」が「帝国教育会出版部」から刊行される。 pid/1068649
|
序
瓢鮎圖に題す・鈴木大拙 (1)/2~3
周文「江山夕陽圖」・福井利吉郎(2)/4~5
靈彩「寒山圖」・松本榮一 (3)/6~7
雪舟「天の橋立圖」・熊谷宣夫 (4)/8~9
雪舟の山水長卷・兒島喜久雄 (5)/10~11
茶釜・香取秀眞 (6)/12~13
醫光寺の庭・島崎藤村 (7)/14~15
藝阿彌「觀瀑僧圖」・脇本樂之軒(8)/16~17
相阿彌「山水圖」・志賀直哉 (9)/18~19
能面「孫次郎」・野上豐一郎 (10)/20~21
能面「痩男」・金剛巖 (11)/22~23
西芳寺林泉・谷川徹三 (12)/24~25
龍安寺の庭・志賀直哉 (13)/26~27
大仙院の庭・室生犀星 (14)/28~29
雪舟と雪村・岡倉天心 (15)/30~31
元信「雪景山水圖」・田中喜作(16)/32~33
松榮の畫境・土田杏村 (17)/34~35
三寶院の庭・金原省吾 (18)/36~37
日本の城・長谷川如是閑 (19)/38~39
永徳「花鳥圖」・田中喜作 (20)/40~41
永徳「唐獅子圖」・脇本樂之軒(21)/42~43
智積院櫻楓圖・福井利吉郎 (22)/44~45
智積院の襖の櫻・岡山巖 (22)/46~47
等伯「松林圖」・脇本樂之軒(23)/48~49
待庵・堀口捨已 (24)/50~51
源氏車競圖屏風・秋山光夫(25)/52~53
天球院朝顏圖・中井宗太郎(26)/54~55
桂離宮の美・ブルーノ・タウト(27)/56~57
桂離宮の歌・中村憲吉 (27)/58~59
孤篷庵・河合卯之助 (28)/60~61
繪唐津の茶碗・濱田庄司 (29)/62~63
彦根屏風・岸田劉生 (30)/64~65
湯女圖・阿部次郎 (31)/66~67
繩暖簾美人圖・藤懸靜也 (32)/68~69
宮本武藏の畫境・長與善郎 (33)/70~71
|
武藏「蘆雁の屏風」・平福百穗(34)/72~73
加賀光悦・奥田誠一 (35)/74~75
光悦の硯筥・柳宗悦 (36)/76~77
宗逹「扇面屏風」・田中喜作 (37)/78~79
宗逹の水墨畫・谷信一 (38)/80~81
探幽の特色・藤岡作太郎 (39)/82~83
日光廟・金原省吾 (40)/84~85
吉野山茶壺・奧田誠一 (41)/86~87
光琳の紅白梅圖・竹内栖鳳(42)/88~89
光琳の藝術・野口米次郎 (43)/90~91
色鍋島・新村出 (44)/92~93
白隱の逹摩・久松眞一 (45)/94~95
大雅「十便圖」賞嘆・小杉未醒 (46)/96~97
大雅堂と十便十宜・武者小路實篤(46)/98~99
蕪村「秋冬山水圖」・澤村專太郎(47)/100~101
蕪村「寒山拾得」・河東碧梧桐(48)/102~103
清長の美人畫・鏑木清方 (49)/104~105
偉大なる哉歌麿・野口米次郎 (50)/106~107
寫樂・仲田勝之助 (51)/108~109
應擧の襖繪・島崎藤村 (52)/110~113
呉春・望月信成 (53)/114~115
若冲・谷川徹三 (54)/116~117
浦上玉堂・橋本關雪 (55)/118~119
玉堂の山水・近藤浩一路 (56)/120~121
竹田「亦復一樂帖」・藤懸靜也(57)/122~123
竹田「梅花宿鳥圖」・田中豐藏(58)/124~125
崋山「鷹見泉石像」・平福百穗(59)/126~127
崋山「黄梁一炊圖」・藤森成吉(60)/128~129
北斎の富士・小島烏水 (61)/130~131
廣重の藝術・内田實 (62)/132~133
信樂の茶壺・柳宗悦 (63)/134~135
良寛の書・川崎克堂 (64)/136~137
鐵齋のよさ・武者小路實篤(65)/138~139
鐵齋のこと・長與善郎 (66)/140~141
解説・北川桃雄 奧平英雄/1~26
・
|
○、この年、宮裡祖泰編「白隠禅師法語集」が「木村書店」から刊行される。
pid/1055002
|
白隱禪師略傳 / 3
坐禪和讃 / 5
施行歌 / 7
安心ほこりたたき / 12 |
大道ちよぼくれ / 17
主心お婆粉引歌 / 22
おたふく女郎粉引歌 / 28
寢惚之眼覺 / 38 |
見性成佛丸方書 / 45
辻談議 / 48
假名法語 / 59
寶鏡窟記 / 70 |
夜船閑話 / 78
遠羅天釜 / 98
・
・ |
○、この年、中岡宏夫が「宗演禅師禅学精髄」を「高山書院 」から刊行する。 pid/1040800
|
序詞 鈴木大拙
例言 大我生
第一部
禪の眞髓 / 1
第一講 宗教の根本義 / 3
自己内容の聲 / 3
信仰と解信 / 8
萬法一に歸す / 14
第二講 平常心是れ道 / 20
挑栗三年柿八年 / 20
修養の三方面 / 28
錬出した心の光 / 37
第三講 物心一如 / 44
禪は心なり / 44
宇宙と同化せよ / 48
物みな神の光 / 53
修養の歸結 / 56
第四講 禪の修業 / 62
着實の工夫 / 62
〔ギャ〕地一下の消息 / 66
第五講 入室の資格 / 71 |
公案は病者の藥 / 71
天地を呑吐 / 73
第六講 教外別傳の一著 / 76
本來無一物 / 76
只是れ一枝の華 / 79
第七講 臨濟の禪 / 83
以心傳心 / 83
四料簡 / 87
人と境 / 91
大活現前 / 94
第二部
白隱禪師 坐禪和讃講義 / 97
白隱略傳 / 99
坐禪和讃 / 100
序説 / 102
禪とその修養 / 102
坐禪の方法 / 104
白隱の略歴 / 110
本文講議 / 113
衆生本來なり / 113
衆生近きを知らず / 115 |
六趣輪廻の因縁 / 125
大乘眞正の禪定 / 134
六波羅蜜 / 137
坐禪の功徳 / 149
即心即佛 / 151
聞法の益 / 154
自性即無性の妙見 / 158
因果一如 / 162
無相の相と相とす / 164
三昧無碍 / 169
即身即佛 / 175
第三部
座右銘講話 / 181
座右の銘 / 183
早起靜坐一〔チュウ〕香 / 184
既に衣帶を着くれば / 186
眠るに時を違へず / 190
客に接するは獨り居る如く / 193
尋常苟も云はず / 195
機に臨んで讓る勿れ / 196
妄りに過去を思ふ勿れ / 197 |
丈夫の氣 / 198
寢に就くとき / 198
第四部
釋宗演の生涯 / 201
概歴年譜 / 203
1 幼時 / 205
2 出家 / 207
3 俊崖和尚 / 209
4 參學行脚 / 211
5 儀山禪師に參究 / 213
6 圓覺寺洪川會下へ / 214
7 慶應習學 / 218
8 印度の苦行 / 220
9 圓覺寺派菅長 / 232
10 萬國宗教大會 / 233
11 日露戰從軍 / 235
12 歐米漫遊 / 237
13 南船北馬 / 238
14 遷化 / 241
15 宗演の性格 / 243
結言 / 255 |
○、この年、茂野染石が「白隠和尚」を「大日本教化図書」から刊行する。 pid/1040765
|
五百年不出世 / 1
白隱禪師の墓 / 10
二神足、遂翁東嶺 / 16
曹洞宗より臨濟宗へ / 22
臨濟宗の系統 / 30
我國現在の佛教 / 37
佛教各派の地盤 / 42
|
佛教各派の盛衰 / 49
清苦八十四年 / 54
行雲流水十五年 / 60
法華經の本懷 / 68
心肝挾鐵二十輩 / 75
三十餘年の應化 / 81
公案一千七百則 / 89 |
女人の公案四則 / 94
隻手の聲、双手の聲 / 100
白隱禪師の藝術 / 109
十方世界に現前 / 120
菩薩行のかずかず / 126
洛浦、臨濟末後の句 / 133
古徳は悉く長壽 / 138 |
高邁なる禪師の思想 / 147
御經となつた「坐禪和讃」 / 152
佛道千古の法燈 / 158
附録「夜船閑話」
・
・
・
|
○、この年、照峰馨山が「捨身の白隠」を「丁字屋」から刊行する。 pid/1040773
|
和尚の横顔/1
不安超克/27
一 雲に嘆ず/27
二 自己を眺める/31
三 煉獄の火焔/34
四 火に燒けざるものたらん/37
五 自己發見の道へ/44
六 禪の權威を疑ふ/46
七 刻苦光明の語に觸る/50
八 四十二章經の語に發明す/56
九 大震災裏の坐禪/61
一〇 遠寺の鐘聲/63
一一 宗格に遭ふ/70
正受老人/79
一 飯山城の狂兒/79 |
二 天主閣樓上の異變/83
三 無難を至道庵に訪ふ/85
四 庵主無慾/92
五 義公請すれども出でず/95
六 究明せんとする生の實體/98
七 群狼中の坐禪/103
龍虎相搏つ/107
一 老人省みず/107
二 相見/109
三 鬪ひ開かる/113
四 痛棒雨下/119
五 大死一番/123
六 老人感涙滂沱/130
七 別離の情/135
八 最後の懇囑/139 |
子弟の鉗鎚と白隱禪の性格/143
一 天下の大道場/143
二 大休と快岩/145
三 峨山/152
四 海に投ぜんとする刹那の
→自己發見/160
五 念佛禪と蚯蚓禪/163
六 その批判/170
七 大乘禪/174
八 生命の發見/178
九 隻手の聲/181
一〇 死地に投ず/189
一一 動靜一如/193
一二 火焔裡の轉法輪/198
一三 武士道の根柢をなすもの/199 |
結語/203
附録
語話
御代の復皷/207
御洒落御前物語/210
見性成佛丸方書/212
書簡
藪柑子/215
唄・歌・句・其他
草取唄/236
子守唄/239
藻鹽集/244
死/254
雜/256
讃の語/258 |
|
| 1942 |
17 |
・ |
| 1943 |
18 |
・ |
5月、 川辺真蔵が「近世禅僧伝」を「石書房」から刊行する。 pid/1040754 閲覧可能
|
配所の澤庵 / 1
隱元渡來の頃 / 31
盤珪和尚傳 / 61
賢巖と古月 / 79 |
月舟和尚 / 94
鷹峰の卍山 / 112
面山の「祖師墨蹟記」 / 128
最初の曹洞僧史傳の著者 / 150 |
良悟下三代記 / 159
一元紹碩のこと / 191
原の白隱もの / 196
鎌倉禪と鵠林下 / 205 |
享保に生れた人達 / 224
洪川和尚のこと / 240
禪僧もの閑談 / 255
・ |
7月、鈴木大拙が「禅思想史研究 第1 (盤珪禅)」を「岩波書店」から刊行する。 pid/1040736
閲覧可能
|
第一 不生禪概觀/1
第二 日本禪における三つの思想類型 道元禪、白隱禪、盤珪禪/65
第三 悟りと悟る/101
第四 慧能以後における悟るの道/199 |
第五 不生禪と白隱禪 附、念佛禪/247
第六 日本における公案禪の傳統/291
第七 盤珪禪の再敍/377
・ |
11月、「書之友 9(11)」が「雄山閣」から刊行される。 pid/1509691
|
一、高野切第一種 / 口繪圖版
二、栂尾切 / 口繪圖版
三、名家々集切 / 口繪圖版
四、朗詠集切 / 口繪圖版
五、尾上柴舟先生書 / 口繪圖版
女手(ひらがな)の眞髓と今後/吉澤義則/p9~14
古筆に於ける樣式 / 三條西公正 / p22~26
|
江戸時代の書の特徴 / 相澤春洋 / p15~21
文檢習字の動向と將來 / 鈴木羽村 / p2~4
白隱の書と良寬の書/内藤辰雄/p26~29,56
書道三味 / 後藤朝太郞 / p32~36
愛國俳句小論 / 加藤紫舟 / p30~31
多寶佛塔碑の學び方 / 板倉花卷 / p37~40
趙子昂千字文の學び方/桑原江南/p40~43
|
喪亂帖の學び方/鮫島看山/p43~46
九月號競書成績發表 / 審査部 / p50
九月號競書應募者氏名/競書部/p47
編輯後記 / 編輯部 / p60~60
附録 公卿上尊號奏碑 / p1~8
・
・ |
12月、柴山全慶が「禅学研究 38 p.1-30 禅学研究会」に「白隠系看話の一管見」を発表する。 (IRDB)
○、この年、高山峻講述「夜船閑話 : 白隠禅師闘病録 白隠 [著]」が「大法輪閣」から刊行される。 pid/1057312 重要
|
「夜船閑話」は鬪病録/3
白隱禪師の少年時代/4
信仰道に入つた動機/7
出家得道/11
禪師の病氣は何か/15
三日前に死を知る/18
夜船閑話の反響/20
夜船閑話の構成/22 |
不老長生の祕訣/24
晝は餓え夜は凍る/31
治癒の信念/35
理想的の疾病治療法/39
白隱の意氣/54
四弘の大誓願/57
精神と肉體の一致/69
死にもの狂ひの修行/77 |
漢洋醫學の融合/87
畸人白幽子/97
内觀の功を積まずんば/103
漢方の生理/108
養生と政治/118
養生の第一要件/130
錬丹の祕訣/135
眞の大神仙/141 |
生の象と死の象/146
二種の火/151
眞觀清淨觀/160
摩訶止觀の治療法/165
諸病自然に消滅す/170
酥を用ふる法/184
内觀の力/196
獲術下山/206 |
○、この年、伊福部隆彦が「禅道探究」を「今日の問題社」から刊行する。 pid/1040786
|
夢想國師語録
一、 惡魔について/7
二、 再び魔について/28
道元禪師語録
一、 眼横鼻直/41
二、 行の人生的意義/51
三、 出家の眞意義/61
四、 行持の功徳/68
五、 靈肉と生死/81
|
六、 迷ひと悟り/104
七、 佛道をならふといふは
→自己をならふなり/110
八、 神通/117
九、 大悟の生活/138
十、 修證一如の道/149
十一、 寺院建立/160
十二、 自己の價値/165
澤庵禪師語録
|
一、 人・天・一致の道/177
二、 得道人の消息/191
三、 小事即大事/197
鐵眼禪師語録
一、 吾我の見/207
二、 坐禪の心境/220
三、 百花本然の春/239
盤珪和尚語録
一、 不生の世界/249 |
二、 不生の佛心の體得/256
三、 修業者の心得/270
四、 活佛心/280
五、 大悟の奧/290
白隱禪師語録
一、 五欲と大悟/305
二、 悟後の生活/314
三、 儒にあらず、佛にあらず/324
四、 大道と個身/329 |
○、この年、壬生照順が「宗祖と指導精神」を「宮越太陽堂書房」から刊行する。 pid/1040218
|
日本佛教史の概觀・友松圓諦 / 1
正法久住
皇室崇佛
四民拜佛
師事佛道
僧尼國益
日本佛教史の特長
多面性
長壽性
抱擁性
適應性
本質性
實踐性
聖徳太子の御生涯と十七條憲法・江部鴨村/59
「聖徳」の起原
聖の意味
三寶興隆の大願
法隆寺の建造
三經義疏の御撰述
十七條憲法の精神「和」
篤敬三寶
傳教大師の生涯と山家學生式・鹽入亮忠/97
鎭護國家の佛教
日本佛教の源泉としての比叡山
比叡山の開創
|
青年最澄の理想
願文
佛教革新の方向
日本人的自覺
佛性問題の論爭
大乘菩薩僧の養成
弘法大師の生涯と法語抄・高神覺昇 / 137
宗教的天才空海
大陸に學ぶ
大師の法語を味ふ
法然上人と一枚起請文・藤井實應 / 161
第一 純正日本佛教の創立者
一、 純正日本佛教
二、 宗教改革
三、 其の時代
第二 人と教
一、 教化
二、 偉大なる凡人
第三 一枚起請文大意
一枚起請文
親鸞聖人と歎異抄・安藤良甫 / 203
利生出家
吉水入室
立教開宗
晩年の親鸞
|
強い聖人
温い聖人
冷い聖人
低い聖人
歎異眞信
本願念佛
凡人往生
日蓮上人と三大秘法稟承事・秋田雨雀 / 223
經典を誦する心
私の日蓮上人觀
土籠御書
三大秘法稟承
道元禪師と正法眼藏・山田靈林 / 251
修行者道元
眼横鼻直
空手にして還る
典座の教訓
天童山の正修行
正法眼藏について
寶藏おのづから開け
白隱禪師と坐禪和讃・山田靈林 / 283
白隱禪師の人となり
先づ坐れ
坐禪三昧
修行者の體驗にまつ |
○、この年、細田源吉が「信念の書 : 評論随筆集」を「東京書房」から刊行する。 pid/1123309
|
明惠上人寸描
上人の勤王先唱/3
幼時出家と、兩親を慕ふ至情/24
嚴しき戒行に生きた上人/36
上人の逸事/44
入寂/48
結語/50
御民の心
「葉隱」と「日暮硯」/53
象山の心構へ/61
傍若無人の山崎闇齋/66
闇齋と服部安休/69
渡邊崋山「八勿の文」を書く/72
勤王畫家草雲の壁書/75
御民の心極はまるところ/78 |
無私の道
この道を行く/94
二王坐禪の端的/96
白隱の掴んだ巖頭和尚/102
無所求行の洞山大師/105
母運子運/107
出家の母/111
明惠上人と西行/114
關山國師の坐禪/117
拔隊禪師の戒行/120
山僧の一訣/123
出家の出家/127
澤庵和尚の「只居れ」/131
至道無難禪師の出家ぶり/135
和歌に現はれなる佛家の心/141 |
俳人の境涯
芭蕉心境/153
芭蕉とか利休とか
古人心境
芭蕉の慈悲
芭蕉と門弟の間
芭蕉と長崎行
長崎の去來と支考
一茶心境/175
子を思ふ一茶
一茶の證文
蕪村心境/183
書畫三味
無常遁世/185
有常處世/189
|
月光露命/194
月と仙厓
盲人の名月句
木歩の至境
乞食井月
名月と寶井其角の一家
境涯の名句/206
俳聖鬼城
凡兆漫筆
秋帆白菊の句
春宵にものを思ふ
師表としての上杉謙信/224
上杉謙信の日常十六訓/260
後書/311
・ |
○、この年、飯田〔トウ〕隠 が「禅友に与へるの書」を「大東出版社」から刊行する。 pid/1040787
|
禪友に與へるの書/3
行録/3
第一 無學/17
第二 隻手/23
第三 機關・法身・言詮/27
第四 無關門/35
第五 碧巖/47
第六 葛藤集/61
第七 槐安國語/67
第八 臨濟録/69
第九 汾陽十智同眞/75
第十 首山綱宗偈/81
第十一 虚堂和尚代別百則/82
第十二 五位/88
第十三 末後牢關/104
第十四 最後の一結/108
隨感録/113
參禪夜話/195
嘘/197
山岡鐵舟が座右銘/198
漁師でも悟れる/201
頭陀之義附忠頭陀/202
我も亦人なり
→南天誓詞之松/203
林才裁松之因縁/204
拈花微笑/205
果斷禪 遺偈論/210
芭蕉に辭世なし/212
白隱の辭世借用
→辭世の盜賊/213
達磨の年齡 二祖最後/214
梁田蛻巖の語/215
脱去達磨/216
血達磨/217
上村大將の都々逸
→死は最後の戰/218
藕絲孔中弄快鷹/219 |
芥子納須彌/220
古來禪坊主の死樣/221
一休高野の敗缺/225
揮毫禪/226
翁/227
聞思修の事/228
南天棒の酒量/229
飮酒戒の事/230
性戒遮戒/231
死後斷滅か不斷滅か/232
芭蕉の俳禪/233
童子の事/237
起きて半疊、寢て一疊/238
北條早雲/239
横死/240
五蘊皆空/243
雪村友梅禪師の大膽
→大綱國師/245
牛背上張帆 行誡上人/246
徳本行者/248
四大假和合/249
南天棒の清貧/250
同情/252
沙石集/253
芙蓉楷禪師/254
徳翁良香禪師之勇猛/255
南天棒瑞巖の無敵刷新/256
南天棒投機の歌/258
スフィンクス/260
日本スフィンクス/261
寶日老人三首の歌/262
蜀山人の狂歌/263
菩提心の事/263
自己を知るべき事/266
見性の方法/267
只管打坐/268
公案工夫/270 |
素法身/272
聖胎長養/273
有省/273
只管打坐と公案工夫との關係/273
現成公案/277
烏丸光廣の歡喜地/279
禪語雜則/280
愚堂の半投機/282
噴血吶人/283
數學禪/284
天狗問答/285
鳥道、玄路、展手/286
勘忍/287
聖一國師と菅原爲長/291
大燈國御遺誡中の異説/292
日本の普化/293
頭陀行/294
〔キョウ〕慢/295
世渡の祕訣/297
□地一聲 釐牛愛尾/300
兩脊由來柎、雙眉元是單
→加葉豈不是偸羅國人乎/301
萬里遠征情/302
曹洞臨濟の接觸/304
荊叢毒蘂/305
正法眼藏/307
道元禪師の遺偈/308
如淨禪師の遺偈/310
久默斯要/310
禪樣/312
無人島/313
戒法/314
戒は一大事因縁/315
血脈 梵綱と法華/316
戒/318
聲聞戒と菩薩戒の區別/321
授戒の順序/322 |
攝の字 三聚/324
禪戒/326
頼春水の父の訓戒/327
六祖壇經の事/328
布薩/328
破戒汚戒 天邊月/329
大雅堂と玉欄/330
正傳の戒體/331
一休木劔禪/332
ジオゲネス 南禪寺/333
了然尼/334
了然尼/335
坐禪の法式/336
徑行 懺悔/337
虚空消殞/340
狙派禪師/342
道元禪師坐禪頌/343
白隱の八難透/344
虚堂頌/347
長沙蚯蚓/348
牛過窓櫺/348
婆子燒庵/350
疎山壽塔/353
南泉遷化/354
白雲未在/355
犀牛扇子/356
乾峰三種/358
葛藤集/361
二祖安心/362
放下着/364
孤峰不白/365
平地上死人無數/366
曹山大海/366
欽山巖頭雪峰/368
〔トウ〕隱年譜/371
著述目録 / 378
編輯後記/37 |
○、この年、堀口婆羅樹が「禅門逸話選」を「代々木書院」から刊行する。 pid/1057638
|
柳緑花紅
一日作さざれは一日食はず・百丈禪師/3
わしの提唱に糟は無い・雪潭和尚/5
いつか出頭の時あらむ・神讃和尚/9
鐘を禮拜す・悟由禪師/15
模範となる資格・盤珪禪師/17
本來無一物・六祖大師/20
この法衣に頼むがよい・一休禪師/25
眞の白状・桃水和尚/30
眼中に位階なし・泰龍和尚/34
泥中の蓮華・無三和尚/37
畫を描く秋ではない・鐵翁和尚/40
名は實の符牒・獨園禪師/44
萬歳の弔電・中原南天棒/49
空を掴まへる法・石鞏和尚/51
老翁なほ行ひ難し・道林禪師/53
正念相續・正受老人/55
大根の一葉・雲門禪師/57
月僊金由來・月僊和尚/58
大福帳の轉讀・大黒屋傳兵衞/62
去來無相
法衣に赤子を抱いて・白隱禪師/67
みやげの法衣・誠拙禪師/70
布施の功徳・誠拙禪師/73
戸を閉めて行け・大含和尚/75
五合庵・良寛和尚/77
佛像の後光を施す・榮西禪師/82
盜人に金を渡して來い・殘夢和尚/85
動かぬ石・天龍和尚/87
慈愛の力・慈門尼/90
不立文字・横尾賢宗/93
茶碗いつぱいの湯・退耕庵/95
天狗のいたづら・雲居禪師/96
遠路御苦勞・西郷南洲/98
|
火裏蓮・山岡鐵舟/103
絶對無我の威力・柏樹和尚と力士大浪/109
三千世界の烏・桐野利秋/114
米や着物は盜まれてよい・祥蕋和尚/117
生死透脱
一劍天に倚つて寒し・楠正成/123
血印の寄進状・菊地武時/127
電光影裏斬春風・祖元禪師/133
膽甕の如し・北條時宗/136
四十九年一醉間・宗謙禪師と上杉謙信/141
火おのづから凉し・快川國師と武田信玄/145
一跳直入如來地・伊達安藝/151
天地一無の禪・山内一豐/155
君辱めらるれば臣死す・
→良雪和尚と大石内藏助/158
一盃やらんか・穆山禪師/163
生道人は冷熱を知らず・慧春尼/168
知らぬ・縁徳禪師/173
言詮不及意路不到・松崎大尉/176
劍禪一致
無諍三昧・柳生但馬守/183
無手勝流・塚原卜傳/193
物來りて應ず・宮本武藏/197
臨濟録の提唱・山岡鐵舟/200
施無畏・山岡鐵舟/203
山は高く水は長し・高橋泥舟/204
お椀試合・物外和尚/208
猫の妙術/215
一衣一鉢
天下第一の寶・石屋禪師/225
乞食往來・桃水和尚/229
一切經の蟲干・一休禪師/232
まだ抱いているのか・坦山和尚/234
大火、生命を燒く・坦山和尚/236 |
茶屋はよいところ・法眼和尚/238
柏樹子の公案・白隱禪師と盜賊長四郎/242
夢のたはむれ・夢想國師/246
禪門の修行・希運禪師/250
戒法護持・隱元禪師/253
竹中宿の夜・愚堂國師と無難禪師/255
禪僧の女郎買ひ・木堂和尚/261
萬縁脱するところ・雲居禪師/264
活作略
地獄極樂・白隱禪師/271
踏臺・仙崖和尚/273
菊花狼藉・仙崖和尚/275
安心して死ねるぞ・誠拙禪師/278
棒喝は禪家の慣ひ・心越禪師/281
酒問答・坦山和尚/283
人形の聽講者・鳳端和尚/285
舌はあるかいな・風外和尚/287
にんじんの頭・奕堂禪師/289
疳癪玉・盤珪禪師/290
菓子屋の喧嘩/292
おどけ善光・善光和尚/295
無相大乘の極意・上泉伊勢守/298
狙ひが外れているぞ・勝海舟/302
當位即位/306
1 コーセン・黄泉和尚/307
2 吹いて行くわい・一休和尚/308
3 テンツク、テンツク・仙崖和尚/309
4 松に古今の色なし・赤松則村/311
5 沖の船・徳川家光と二人の雛僧/312
6 七福神・仙崖和尚/313
7 初雁・物外和尚/315
8 葵の花・桃水和尚/317
・
・ |
○、この年、日本社会学会編「社会学 : 日本社会学会年報 第9輯」が「岩波書店」から刊行される。 pid/1212677
|
論説
時代 綿貫哲雄/3
書社及社考―併せて助・徹の名義に及ぶ― 加藤常賢/26
社會強制の一研究―特に經濟的強制を中心として― 桑原博隆/96
アリストテレス國家論の性格 田中晃/136
都市密住地區の研究―人口現象についての
→一考察― 渡邊萬壽太郞/158
人間性における社會性と個人性について 松浦孝作/183
社會の論理と價値 石橋義弘/228
日本社會學會第十六囘大會研究報告/261
一 社會學論
社會科學に於ける物質竝びに物質的なるものの本質 桑原博隆/262
アダム・スミスの社會理論 大道安次郞/263
社會統制の二樣相 難波紋吉/264
社會層の變遷 臼井二尚/266
經濟社會學の一構想 高島善哉/268
歴史社會學の概念 新明正道/270
再びIntensive Methodに就て 秋葉隆/270
二 宗敎道德
南方民族の祭祀 增田福太郞/272
近世禪(臨濟)僧の國家意識 福場保洲/273
佛敎敎團の分離及結合 岩井龍海/274
佛敎社會學の課題 久保田正文/276
基督敎の日本的展開 高谷道男/277
三 社會意識
世界觀成立過程の究明 湯村榮一/279
宜傳に於ける眞實性 三崎敦/279
上代人名の考察 近澤敬一/280
時代 綿貫哲雄/281
義理と人情 齋田隆/281
四 家族及び民族
朝鮮の氏族に關する二三の考察 巾鎭均/283
李朝社會に於ける血縁の觀念形態 金斗憲/285
未開社會の家族に就いて 姫岡勤/286
日本家族制度の特質について 有賀喜左衞門/287
インドネシアの社會 川又昇/288 |
技術と民族 武田良三/289
濠洲北部直轄州に於ける原住民の現状及び彼等に
→對する政策 小寺廉吉/289
儀禮及び禮記に現れた宗族と家族 牧野巽/292
對立抗爭の原理 藤田進一郞/292
五 農村都市
東北農村に於ける特殊信仰について 及川宏/294
宮座の性格 岸川八壽治/295
農村社會調査の古代研究に對する意義 中井虎一/296
山形の獅子舞 古野淸人/298
支那都市の構造 宮崎力藏/300
都市の隣保團體の組織と機能 弓家七郞/300
國土計畫と都市の配置 奧井復太郞/301
同族組織と親方子方 喜多野淸一/301
六 人口
人口の立場より見たるアブラムとロト 西野入德/302
民族接觸と人口變動 小山榮三/303
人口と所得との關聯について 早川三代治/303
都市の計畫的配置と人口補給地域の設定 館稔/305
七 國家政治經濟
支那高利貸資本の分析 馬場明男/307
支那の社會と國家 重松俊明/308
輿論の政治性 川邊喜三郞/309
經濟倫理の問題 田村實/306
國家と社會との關係に就いての一考察 田畑忍/310
國家の權力と權威 岩崎卯一/312
社會學と文化政策 松本潤一郞/312
民族政策の問題について 加田哲二/314
八 社會政策社會事業
國土計畫に於ける生活圈の問題に就て 久山滿夫/315
我が國に於ける靑年問題の社會史的考察 櫻井庄太郞/316
事變と住宅問題に就て 靑野俊梁/317
戰時下國民生活の確保の倫理 川上賢叟/318
日本社會學會第十六囘大會記事/321
新刊批評/326
・ |
○、この年、「中宮寺の諸問題」が「鵤故郷舎出版部」から刊行される。 改訂版 pid/1040574
|
第一門 御本尊之研究
日本藝術精神史に於ける中宮寺本尊・
→京都帝國大學教授文學博士 植田壽藏/1
中宮寺本尊の研究・内藤藤一郎/11
中宮寺雜抄・前京都帝大總長文學博士 濱田青陵/19
中宮寺御本尊私攷・前東京美校教授 田邊孝次/24
中宮寺本尊の御眼と御手・大阪美術館主事 望月信成/31
中宮寺御本尊の年代に就いて・廣瀬直彦/35 |
第二門 天壽國曼荼羅之研究
太子の御信仰と天壽國曼荼羅の銘文・
→廣島文理大教授文學博士 福島政雄/39
天壽國曼荼羅と聖徳太子の教育思想・京都帝大講師 高橋俊乘/46
天壽國曼荼羅攷・藥師寺住職 橋本凝胤/52
天壽國とは何ぞや・東北帝大講師 大屋徳城/61
續天壽國繍帳の新研究・大阪毎日新聞社 青木茂作/74
天壽國曼荼羅銘文私考・會田範治/104 |
|
| 1944 |
19 |
・ |
8月、亀川教信が「縁起の構造」を「全人社」から刊行する。 pid/1040351 閲覧可能 重要
|
序論 佛教の行學的立場/1
一 佛教の核心/1
二 佛教學の方法論/3
三 佛教の主體的實踐的把握/7
四 佛教に於ける哲學的面/14
五 佛説根本資料の整理/20
六 無記法と有記法/31
七 矛盾の超克/42
第一篇 縁起の實踐的意義/49
第一章 縁起説の根本問題/51
一 縁起の語義/51
二 因果と縁起/59
三 觀行體驗としての十二縁起/75
四 諦・縁・度の關係/83
第二章 十二縁起の關説資料/97
一 原始資料の簡素性/97
二 根本資料に就て/104
三 縁起廣説經/114
第三章 十二縁起の理解/120
第一節 縁起支分の組織/120
一 縁起支數の問題/120
二 縁起の骨子/123
三 基本本際/127
第二節 縁起支分の内容/136
一 全縁起系列と各支分との關係/136
二 各支分の解説/139
三 苦諦と苦の超脱/149
第三節 縁起の解釋法/156
一 近代學者の諸説/156
二 縁起解釋の立場と古來の解釋法/160
三 時間的解釋/165
四 論理的解釋/169
五 一貫の根本義/174
第二篇 縁起の實相的内容/183
第一章 般若思想/185
第一節 空觀の體系/185
一 縁起説に於ける空觀の重要性/185
二 縁起即空/188
三 空と無我/196
四 原始佛教の空義より
→般若の空觀へ/199
第二節 般若經の出現/211
一 般若經典の成立/211
二 般若の中心思想/220
三 般若に於ける眞如觀/227
第二章 中觀學の縁起説/234
|
第一節 空觀の立場/234
一 中觀・瑜伽の對立/234
二 空觀の態度/246
第二節 龍樹の出世/249
一 龍樹の傳記/249
二 中論の綱格/252
第三節 否定の論理に基く
→矛盾超克の仕方/262
一 物自性の否定/262
二 八不に於ける存在實相の把握/269
三 縁生と縁成/275
第三章 空觀と有行/279
一 空の無限的統一/279
二 般若經より中觀教學へ/282
三 眞空妙有/291
四 積極的空義への教理的發展/297
第三篇 縁起の無盡的形態/303
第一章 華嚴經の綱格/305
第一節 華嚴經典の成立とその組織/305
一 時代的區分/305
二 成立史的組織大綱/311
第二節 華嚴經と空地/325
一 般若より華嚴への思想的移行/325
二 空地を背景とする華嚴經/334
三 普賢行の得證と空觀の體達/340
第三節 華嚴經の行學的性格/353
一 超説法の説法/353
二 海印三昧中一時炳現の法/363
三 菩薩修行の階位/366
四 三聖圓融としての經典觀/376
五 教學的論據/385
第二章 空と無礙/391
第一節 無礙の論證/391
一 現實的世界の具體的構造/391
二 法性融通と縁起相由/394
第二節 唯心説の體系/400
一 佛教唯心説の多含内容/400
二 華嚴經に於ける唯心説の文獻的詮索/402
三 唯心説の發展史的展開/409
四 一心法界の解明/418
第三節 空有合觀/426
一 縁成の體驗/426
二 教學的傳承/429
第三章 法界縁起説の核心/440
第一節 性起と縁起の不可分的關聯/440
一 如來藏と性起説/440
|
二 性起の意義/444
三 縁起と性起の關係/448
第二節 四種法界の體系/453
一 同別二教の立場と四種法界/453
二 法界の意義/458
三 四種法界の系列とその内容的説意/463
第三節 理事の關係/469
一 起信論の眞如觀/469
二 超越性と内在性/476
第四節 事事の即入/483
一 相反するものの自己同一/483
二 矛盾超克の現實的構造/491
三 行爲的自覺内容としての
→個と全の關係/508
第四篇 縁起の國家的受容/513
第一章 華嚴佛教の日本的攝受/515
第一節 日本國民性と縁起思想/515
一 佛教の國家的意義/515
二 縁起思想の普遍的浸透性/520
第二節 華嚴經の國家的感觸/523
一 超歴史の歴史觀/523
二 佛陀の事蹟とその國家的關心/525
三 華嚴經に露呈せる國家思想/531
第三節 佛教東漸と日本佛教の確立/534
一 私事佛教より國家佛教へ/534
二 奈良佛教の特徴/540
第四節 華嚴佛教の國土莊嚴的展開/544
一 國分寺と東大寺との關係/544
二 毘盧舍那佛造立の歴史的意義/549
三 毘盧舍那佛の教學的理解/554
第二章 法界縁起の日本的生態/567
第一節 日本精神と即入無礙の縁起觀/567
一 日本の「道」と華嚴佛教/567
二 御寶祚を景仰して
→華嚴佛身觀に及ぶ/571
三 縁起觀と敢鬪精神/577
四 八紘爲宇に見る即入無礙/584
第二節 縁起思想の行的把握/587
一 教學史的理解と教會史的展望/587
二 行門の顯揚者高辨/591
第三節 和の基底としての無盡縁起/602
一 和國の大使命/602
二 佛教的和の性格/606
第三章 縁起觀に基く無我の躍動/612
・
・ |
12月、古田紹欽が「愚堂・無難・正受」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第8) pid/1682864
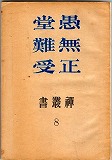
古田紹欽著 「愚堂、無難、正受」
(表紙)
|
序/私に本書「愚堂・無難・正受」の執筆題目が與へられた時、私は何の考へもなく無造作にお引受けした。といふのは愚堂国師の生まれた美濃の伊自良村大森は、私の故郷であり、その塔所(高井寺旧址)が又今猶私の実家の裏藪にあるといふ因縁からで、云ひ知れぬなつかしさを覚えたからである。子供の自分この竹藪の荒れた国師の墓の辺りで徒戯をし、親からよく祟りがあると云って叱られたものである。/扨(さ)て愈々原稿の督促を受けて、書かねばならぬ期目が来た。兼ねてから機会があったら、国師から無難・正受と展開して行く近世日本臨済禪の復興の経路を纏めて見たいと思ってゐたのであるが、筆を取る段になると仲々これが容易な課題でないことがわかった。取敢へず執筆の期日を約束よりも延ばして、色々と考へを纏めることにつとめたが、元々何の準備もなく、漠然とした気持から執筆をした気持から引受けたのであるから簡単に書ける理由がない。他の勉強の傍、四苦八苦して書いたのが此書である。私は今、約束を果して書上げた喜びよりも、恐ろしさの方を寧ろ強く見に感ずる。何か宗門に罪を犯したやうに思はれてならないのである。(以下略)
|
|
第一節 花園の佛法 / 1
第二節 愚堂東寔 / 20
(一) 歴修 / 20
(二) 出世 / 27
(三) 對御 / 31
(四) 遊化 / 37 |
(五) 對隱元 / 49
(六) 弟子 / 53
(七) 敕諡號 / 64
(八) 著書 / 65
第三節 至道無難 / 67
(一) 道心 / 67
|
(二) 行履 / 75
(三) 禪風 / 84
(四) 逸話 / 105
(五) 弟子 / 107
(六) 著書 / 110
第四節 正受慧端/178
|
(一) 就師 / 178
(二) 菴居 / 183
(三) 修行 / 189
(四) 弟子 / 198
(五) 追慕 / 207
第五節 白隱の寶鑑貽照 / 211 |
○、この年、荻須純道が「夢窓・大灯」を「弘文堂」から刊行する。 (禅叢書 ; 第7) pid/1683874
|
序説
一 時代の體驗と禪の傳來 / 3
二 五家七宗と二十四流 / 5
三 國民性と禪 / 8
四 臨濟禪の主流とその性格 / 9
本論
前篇 夢窓國師疎石
一 夢窓國師とその時代 / 14
(一) 國難に直面せる鎌倉武士と禪僧 / 14
(二) 禪宗の發展 / 22
二 夢窓國師の生涯 / 27
(一) 生立ちとその性行 / 27
(二) 修業時代の夢窓國師 / 30
(1) 知的絶望と更衣歸禪 / 30
(2) 行雲流水 / 32
(3) 佛國國師の提撕と大悟 / 38
(三) 活動時代の德風 / 42
(1) 韜光晦跡 / 42
(2) 北條高時の母覺海夫人の歸依 / 44
(3) 後醍醐天皇と夢窓國師 / 46
(4) 足利尊氏、直義等の歸依 / 53
(四) 天龍資聖禪寺と安國寺・利生塔 / 59
|
(1) 天龍資聖禪寺開創の意義 / 59
(2) 天龍寺の造營 / 61
(3) 安國寺・利生塔建立の趣旨/65
(五) 晩年の道風とその遷化 / 68
三 思想と遺芳 / 74
(一) 宗要 / 74
(1) はじめの詞 / 74
(2) 理致と機關 / 75
(3) 小玉を呼ぶの手段 / 76
(4) 學解と行道 / 80
(5) 敎外別傳・不立文字 / 84
(6) 心と性・見性 / 87
(二) 祖訓 / 90
(1) 名利を捨つ / 90
(2) 道 / 92
(3) 怨親平等の思想 / 96
(4) 禪と念佛 / 98
(三) 遺芳 / 102
(1) 西芳寺の庭園 / 102
(2) 天龍寺十境 / 105
四 夢窓門下と五山文化 / 112
(一) 夢窓門下の龍象 / 112 |
(二) 宋元文化の移植 / 117
後篇 大燈國師宗峰妙超
一 大燈國師の承けた法流 / 135
(一) 松源一流の禪法と應燈關の一流 / 135
(二) 大燈の師大應國師南浦紹明 / 140
二 大燈國師の生涯 / 143
(一) 生立ちと佛道入門 / 143
(二) 大悟と大應國師の記□〔きベツ〕 / 148
(三) 聖胎長養 / 153
(四) 正中の宗論 / 158
(五) 皇室の御歸依と大德寺の創建 / 163
(六) 花園・後醍醐兩天皇と大燈國師 / 167
(七) 遺訓と遷化 / 178
三 思想(家風) / 188
(一) 禪宗思想史上の大燈國師 / 188
(二) 大燈國師の思想的性格 / 195
(三) 扶桑第一の毒華 / 199
四 關山慧玄 / 208
(一) 大燈國師門下と關山慧玄 / 208
(二) 關山の行履 / 210
・
・ |
|
| 1945 |
昭和
20 |
・ |
○、この年、堀口義一が「禅門逸話選」を「大東出版社」から刊行する。 pid/1040784
|
柳緑花紅
一日作さざれは一日食はず・百丈禪師/3
わしの提唱に糟は無い・雪潭和尚/5
いつか出頭の時あらむ・神讃和尚/9
鐘を禮拜す・悟由禪師/15
模範となる資格・盤珪禪師/17
本來無一物・六祖大師/20
この法衣に頼むがよい・一休禪師/25
眞の白状・桃水和尚/30
眼中に位階なし・泰龍和尚/34
泥中の蓮華・無三和尚/37
畫を描く秋ではない・鐵翁和尚/40
名は實の符牒・獨園禪師/44
萬歳の弔電・中原南天棒/49
空を掴まへる法・石鞏和尚/51
老翁なほ行ひ難し・道林禪師/53
正念相續・正受老人/55
大根の一葉・雲門禪師/57
月僊金由來・月僊和尚/58
大福帳の轉讀・大黒屋傳兵衞/62
去來無相
法衣に赤子を抱いて・白隱禪師/67
みやげの法衣・誠拙禪師/70
布施の功徳・誠拙禪師/73
戸を閉めて行け・大含和尚/75
五合庵・良寛和尚/77
佛像の後光を施す・榮西禪師/82
盜人に金を渡して來い・殘夢和尚/85
動かぬ石・天龍和尚/87
慈愛の力・慈門尼/90
不立文字・横尾賢宗/93
茶碗いつぱいの湯・退耕庵/95
天狗のいたづら・雲居禪師/96
遠路御苦勞・西郷南洲/98 |
火裏蓮・山岡鐵舟/103
絶對無我の威力・柏樹和尚と力士大浪/109
三千世界の烏・桐野利秋/114
米や着物は盜まれてよい・祥蕋和尚/117
生死透脱
一劍天に倚つて寒し・楠正成/123
血印の寄進状・菊地武時/127
電光影裏斬春風・祖元禪師/133
膽甕の如し・北條時宗/136
四十九年一醉間・宗謙禪師と上杉謙信/141
火おのづから凉し・快川國師と武田信玄/145
一跳直入如來地・伊達安藝/151
天地一無の禪・山内一豐/155
君辱めらるれば臣死す・良雪和尚と大石内藏助/158
一盃やらんか・穆山禪師/163
生道人は冷熱を知らず・慧春尼/168
知らぬ・縁徳禪師/173
言詮不及意路不到・松崎大尉/176
劍禪一致
無諍三昧・柳生但馬守/183
無手勝流・塚原卜傳/193
物來りて應ず・宮本武藏/197
臨濟録の提唱・山岡鐵舟/200
施無畏・山岡鐵舟/203
山は高く水は長し・高橋泥舟/204
お椀試合・物外和尚/208
猫の妙術/215
一衣一鉢
天下第一の寶・石屋禪師/225
乞食往來・桃水和尚/229
一切經の蟲干・一休禪師/232
まだ抱いているのか・坦山和尚/234
大火、生命を燒く・坦山和尚/236 |
茶屋はよいところ・法眼和尚/238
柏樹子の公案・白隱禪師と盜賊長四郎/242
夢のたはむれ・夢想國師/246
禪門の修行・希運禪師/250
戒法護持・隱元禪師/253
竹中宿の夜・愚堂國師と無難禪師/255
禪僧の女郎買ひ・木堂和尚/261
萬縁脱するところ・雲居禪師/264
活作略
地獄極樂・白隱禪師/271
踏臺・仙崖和尚/273
菊花狼藉・仙崖和尚/275
安心して死ねるぞ・誠拙禪師/278
棒喝は禪家の慣ひ・心越禪師/281
酒問答・坦山和尚/283
人形の聽講者・鳳端和尚/285
舌はあるかいな・風外和尚/287
にんじんの頭・奕堂禪師/289
疳癪玉・盤桂禪師/290
菓子屋の喧嘩/292
おどけ善光・善光和尚/295
無相大乘の極意・上泉伊勢守/298
狙ひが外れているぞ・勝海舟/302
當位即位/306
1 コーセン・黄泉和尚/307
2 吹いて行くわい・一休和尚/308
3 テンツク、テンツク・仙崖和尚/309
4 松に古今の色なし・赤松則村/311
5 沖の船・徳川家光と二人の雛僧/312
6 七福神・仙崖和尚/313
7 初雁・物外和尚/315
8 葵の花・桃水和尚/317
・
・ |
|
| 1946 |
21 |
・ |
1月、野村瑞城が「白隠と夜船閑話」を「人文書院」から刊行する。 注記 序:小酒井不木 51版 |
| 1947 |
22 |
・ |
3月、藤本尚則が「苦難突破の伴侶」を「人文閣」から行する。 (新青年叢書 ; 5) pid/11176889
|
一、 處世の金科玉條/2~
二、 勝海舟當年の苦衷/2~
三、 世事みな碧翁の遊戲/3~
四、 人生の目的/4~ |
五、 十句觀音經を奬む/4~
六、 白隱禪師の『邊鄙以知吾』/5~
七、 最近十句經の靈驗/10~
八、 生死の境を超脱せよ/12~ |
九、 石の上にも三年/14~
一〇、 石頭草庵の歌/15~
(略)
・ |
○、この年、吉井勇が「墨宝抄」を「鎌倉文庫」から刊行する。 pid/1128146
|
墨寶抄/3p
續墨寶抄/9p
松花堂襖繪/15p
四條河原納涼圖/19p
羅漢圖/22p
南蠻屏風/26p
雙牛圖/29p
知恩院襖繪/31p
雲坪諸圖/36p
蝦蟆鐵拐/40p |
野馬圖/43p
白隱遺墨/45p
大乘寺襖繪/52p
幽韻微吟
祕佛發見/59p
東大寺伎樂面/66p
月光菩薩/69p
迷企羅伐折羅/72p
或る夜の夢/74p
螢燈籠/78p |
赤樂筒茶〔ワン〕/80p
高士埀釣圖火入/85p
鑑賞餘情
摠見寺襖繪/91p
酒鬼圖/97p
紫朝哀唱/101p
河童圖/106p
鳥渡る/115p
阿蘇山圖/119p
老遍路圖/122p
|
幻化/125p
風神雷神/127p
玄猿/129p
林間閑吟圖/131p
布袋圖/133p
愚庵和尚像/135p
東方遙拜/139p
蒼穹展/141p
後記/143p
扉畫 杉本健吉 |
○、この年、田村霊祥が「安眠治病法」を「天真道本部」から刊行する。 pid/1371932
|
第一章 緖論/p1
一、 心の内省/p3
二、 自力の福音/p20
第二章 白隱の内觀法/p29
一、 偉僧白隱禪師/p31
二、 夜船閑話/p44
第三章 生理的に見た内觀法/p59
|
一、 腹中心の生活/p61
二、 生命と呼吸の關係/p71
第四章 心理的に見た内觀法/p87
一、 觀念は力なり/p89
二、 潛在力説と内觀の心理/p100
三、 内觀法と自己暗示/p114
第五章 内觀法の實際に就いて/p129 |
一、 調整呼吸と心氣引下げ/p131
二、 内觀音と精神統一/p141
三、 内觀の念じ方/p152
第六章 結論/p169
安眠治病法のやり方/p180
・
・ |
○、この年、武者小路実篤が「宮本武蔵」を「山本書店」から刊行する。 pid/1134503
|
親鸞の結婚/3
日蓮と千日尼/31 |
黒田如水/59
宮本武藏/87 |
白隱/119
頼山陽と川上儀左衛門/137 |
黒住宗忠/153
・ |
○、この年、国華百粋 第4輯 毎日新聞社 1947pid/1124982/1
|
六一 不動明王像(青蓮院)・植田壽藏/5
六二 鳳凰堂扉繪來迎圖(平等院)・佐和隆研/9
六三 紫式部日記繪詞(蜂須賀正氏)・河本敦夫/12
六四 三十六歌仙切(遠山元一)・田中一松/15
六五 紅綸子地束熨斗模樣友禪染振袖
→(友禪史會)・並川安幸/18
六六 彌勒菩薩像(中宮寺)・井島勉/23
六七 善無畏像(一乘寺)・龜田孜/29 |
六八 那智瀧圖(根津美術館)・伊東卓治/32
六九 山水花鳥圖(大徳寺聚光院)・谷信一/35
七〇 柳圖(西本願寺)・土居次義/38
七一 和歌卷(團伊能)・小林秀雄/40
七二 難福畫(圓滿院)・上野照夫/45
七三 一晴一雨圖(中島俊司)・白畑よし/48
七四 三條左大臣實房公茸狩圖
→(大樹寺)・藤森成吉/51 |
七五 汐干狩圖(武岡忠夫)・加藤一雄/53
七六 白隱訪白幽子圖
→(細川護立)・正宗得三郎/56
七七 月光菩薩像
→(東大寺法華堂)・谷川徹三/58
七八 龍燈鬼像(興福寺)・野間清六/62
七九 牡丹孔雀圖(二條城)・藤原義一/64
八〇 雪の小面(金剛巖)・金剛巖/67 |
○、この年、古田紹欽が「禅論」を「金尾文淵堂」から刊行する。 pid/1040720
|
心學と禪佛教―梅巖・堵菴・道二の禪―/1
禪と三教思想/57
近世の神佛融和思想/90
禪と藝の道/110 |
盤珪の日本禪/126
日本禪僧の生死觀―白隱を通じて見る―/146
澤菴の死/164
武人の心構と禪/191 |
鈴木正三の禪/208
白隱に於ける公案禪の意義/224
・
・ |
|
| 1948 |
23 |
・ |
3月、藤本尚則が「苦難突破の伴侶」を「文徳社」から刊行する。 (新青年叢書
; 5) pid/11177358
|
一、 處世の金科玉條/2~
二、 勝海舟當年の苦衷/2~
三、 世事みな碧翁の遊戲/3~
四、 人生の目的/4~
五、 十句觀音經を獎む/4~
六、 白隱禪師の『邊鄙以知吾』/5~
七、 最近十句經の靈驗/10~
八、 生死の境を超脱せよ/12~
九、 石の上にも三年/14~ |
一〇、 石頭草庵の歌/15~
一一、 死して亡びざるもの/17~
一二、 釋迦の逸話/19~
一三、 日蓮、雪村、大燈の悟道/20~
一四、 邪氣病魔を拂ふの法/21~
一五、 九死に一生の實例/23~
一六、 明朗豪快な維新靑年/24~
一七、 長崎の梁山泊/27~
一八、 築地時代の大隈、伊藤/29~
|
一九、 大隈侯と澁澤伯/30~
二〇、 大きく淸く強く樂しく生きよ/31~
二一、 大輪廓の大西鄕(山縣有朋公談)/32~
二二、 淸廉な伊藤公(大隈重信侯談)/34~
二三、 強い信念の福澤翁(犬養毅氏談)/40~
二四、 樂天的な大隈侯(尾崎行雄氏談)/42~
二五、 心を大所高所におけ/46~
二六、 大我の偉人たるを期せよ/50~
著者紹介/奥付~
|
8月、伊藤和男が「真智の探究」を「河原書店」から刊行する。 pid/1040345
|
前篇 佛教の理解的研究/1
一 眞智と絶對愚/3
二 起信に於ける眞如の理解/28
三 衆生の還源性/59 |
四 無明の構造/85
五 理解的佛教學/107
後篇 正理學派の研究/119
一 眞智への道/121 |
二 神と創造の論理/142
三 解脱の問題/182
附録 白幽子史實の新探究(上・下)/219
・
|
10月18日から1ヶ月間、国立近代美術館に於て、白隠の代表作を網羅する金屏風六点を始め、大作百九点が陳列される。
出展:土屋常義著「白隠と岐阜県p3」より
12月、「三彩 (25) 」が「三彩社」から刊行される。 pid/7896176
|
原色版 観音図 / 白隠/p39~39
原色版 残雪 / 山本丘人
グラビア版 果樹 / 吉岡堅二/p11~11
グラビア版 収穫の風景 / 堀文子/p13~13
グラビア版 二人の少女 / 小郷良一/p12~12
グラビア版 秋田のマリヤ/福田豊四郎/p15~15
グラビア版 裸婦 / 向井久万/p16~16
グラビア版 犢 / 沢宏靱/p15~15
グラビア版 室内佛 / 高橋周桑/p18~18
グラビア版 初冬 / 奥村厚一/p17~17
グラビア版 木蔭 / 植村松篁/p12~12
グラビア版 花花 / 稗田一穗/p13~13 |
グラビア版 月響 / 加藤栄三/p14~14
グラビア版 作品 / 秋野不矩/p14~14
グラビア版 夕 / 廣田多津/p17~17
グラビア版 子供 / 菊池隆志/p18~18
グラビア版 鏡と裸婦 / 橋本明治/p16~16
オフセット版 素描雪の柳・婦人 / 上村松園
オフセット版 仔犬・豆の花 / 森田沙多
写眞版 人物図 / 白隠
写眞版 森の中の肖像 / 岩崎鐸
美術批評の在り方/p4~4
現代日本画の問題 / 河北倫明/p5~7
危機を行く日本画--創造美術
|
→第一回展評 / 柳亮/p8~10,19~21
審査風景 / 土門拳/p22~25
創造展へ / 宮川謙一/p26~26
〔彩滴〕 或る日本画家へ / Y・K/p31~31
定規 / 小杉放庵/p32~33
白隠和尚再鑑 /
→梅花草堂主人/p34~38,41~41
〔あと・らんだむ〕法隆寺壁画と西域画・
→ビニヨンの雪舟論/p42~43
作家寸描(2) 杉山寧 / 松原淑人/p44~44
溪仙と京都 / 中田宗男/p45~47
表紙 / 高橋周桑 |
〇この年、釈大眉が「無難禅師かな法語の講話」を「喜久屋書店」から刊行する。 pid/1157729
|
寫眞 至道無難禪師 自刻木像
はしがき
第一講 在家安心の骨髓/5
至道庵主の一生
日本の衆生は佛に近し
第二講 ある老人の物語/13
大道は方寸の中
死んで何處へ行く
身なければ佛なり
第三講 似て非なるもの/23
天然の外道
さとりの臭味を取れ
第四講 善惡因果/30
眞空妙有
禪と念佛
佛にはならぬが佛 |
第五講 惡業あるは身なり/37
罪の輕重
無作の妙用
第六講 内求と外化/44
生きることの意義
外に求むるな
佛法とは何ぞ
第七講 隨處に主となれ/54
大乘佛教の眼目
求むる所なく得る所なし
神詣でと内外清淨
大だわけとなれ
己を以て人を見る
特長を生かせ
第八講 無念/64
佛の大慈悲 |
平常の安心
さとりとは?
第九講 淫怒痴是れ梵行/71
大道は一如
遊女の見性
五種の禪
最上乘の禪
第十講 佛法は世法の中に/81
平常はみな佛
無所住の心
末法の世
宗教初門の第一歩
大道體得の正教
婦人への説法
第十一講 桃栗三年柿八年/100
大慈悲の顯現 |
願心は強くあれ
第十二講 自我の見を斷て/108
そのものになれ
山の奧もうき世
洞山無寒暑
第十三講 虚心にして道に入る/117
大安樂の法門
禪の本領
打成一片
自利より利他へ
傳統を尊べ
大道は平常底
大智は愚の如し
附録
自性記/129
至道無難禪師行録 東嶺 和尚撰/167 |
○、この年、田畑聴雪が「聴雪文集〔1〕」として「〔静岡・田畑聴雪写〕」を行う。 貴重自筆本 所蔵:静岡県立中央図書館
|
注記 内容:通俗阿呆陀羅経,大道ちょぼくれ,心眼にて総ての聖典を読め,人間の使命と其責任,聴雪体験仏教とは,原白隠和尚,熊沢竜海師
※ 詳細の調査が必要と思う 2022・12・29 保坂 |
○、この年、井上政次が「関東古寺」を「羽田書店」から刊行する。 pid/2476574
|
序
第一章 深大寺/p1
路
深大寺縁起
白鳳佛釋迦如來像
美と倫理と
境内
第二章 龍角寺/p23
筑波山遠望
印幡沼
夜刀の神
龍角寺僧坊
本堂
本尊佛首
白鳳期の古典的哲學に就いて
頸部以下
塔心礎 |
伽藍配置
第三章 日本美術史の流れ/p51
推古時代
推古後期
白鳳時代
天平時代
天平末期
弘仁時代
藤原時代
鎌倉時代
第四章 寶城坊/p117
ニイチェとゲーテ
相模大山
順路
寶城坊境内
寺務所
本堂 |
内外陣の哲學的意味
藥師三尊
弘仁密敎精神と藤原淨土敎精神
鉈彫樣式に就いて
前立諸尊
寺史
第五章 大善寺/p169
勝沼驛頭景觀
際涯性に就いて
葡萄畑と僧坊
本尊弘仁佛藥師如來
脇侍月光菩薩
山上藥師堂
寺史山門樓上
『理慶びくに記』
第六章 甲斐善光寺/p205
金堂南方阿彌陀三尊 |
藤原期淨土敎哲學と定朝樣式
北方阿彌陀三尊
修理明細書
第七章 東光寺・酒折/p223
幻の圓覺寺舎利殿
鎌倉時代精神
東光寺參道
白隠と毒語心經
藥師堂
酒折宮
日本武尊のこと
旅愁の歌
圖版目次/p1
『關東古寺』索引/p1
・
・
・ |
○、この年、吉田機司が「長生きと若返り : 四十からの養生法」を「不老閣」から刊行する。 pid/1156616
|
吉田博士の近業に題す・竹越與三郎
序文・佐々貫之
自序・著者
老・不老/1
人間は何歳まで生きられるか/3
男と女とはどちらが長生きするか/10
長壽者はどんな土地に多いか/14
長壽家族と遺傳/19
いくつから老人と言ふか/23
老衰の起る原因/28
不老長壽とホルモン/33
寄る年波に老の自覺/37
老人のからだ/42
齒と長壽との關係/48
老人の性格/52
耄碌は豫防出來るか/56
日本古來の不老長壽法/61
日本古來の不老長壽法/63
道三翁の「養生物語」/66 |
曲直瀬玄朔の延壽撮要/71
貝原益軒の「養生訓」/75
三浦梅園の長壽法/81
佐藤一齊の養生觀/86
白隱禪師の養生法/91
杉田玄白の長壽法/99
山東京山の「無病長壽養生
→手引草」/105
石黒忠悳の「長生法」/111
今や米國は「不老長壽藥時代」/119
原子爆彈以上と
やじACS血清研究熱/121
若返り法の今昔譚/129
始皇帝と家康/131
處女囘生術/137
若返りの靈藥/141
ブラウン・セカールの若返り法/147
スタイナハの若返り法/150
性ホルモン(生殖腺)/153 |
男性ホルモン/153
去勢/155
性徴/157
女性ホルモン/160
卵胞ホルモン/161
黄體ホルモン/163
美貌を永く保存する法/165
四十以後の性生活/170
不老回春「支那の
→房中術」/174
老人の罹り易い病氣と
→その豫防/181
老人の死因/183
血壓の話/188
腦出血は長壽の敵/193
癌の話/201
腎臟病の知識/206
老人の結核/211
感冒は萬病の基 |
→氣管枝炎・肺炎/214
老人と便秘/219
長生きと若返りの醫學
→四十からの養生法/223
人生は四十から/225
長壽は養生の總和/229
食養生/231
食餌の量/231
食物の質/233
菜食主義/236
酒と長壽/238
老人と煙草/242
保温と衣服/247
住居と轉地/250
長壽と運動/255
年齡と睡眠/259
長壽と疲勞/265
長壽と精神の持ち方/270
・ |
○、この年、楢橋渡が「ベルギーの女」を「国際出版」から刊行する。 pid/1156852
|
カマンスキーの告白/1
英雄の戀/12
ベルギーの女/20
明日の世界をはらむ女性/30
人間の反逆/36
苦惱の旅/38
考える喜び/41
かたちと自由/48
人間の悲哀/53
眞理の發見と迫害/57
宗教と民族の命運/63
科學の發見/67
不完全の美/71
教育について/74 |
ルネッサンスと
やじ近代個人主義の發見/77
繪は感覺の史/79
リズムの世界/82
雲/84
土に想う/87
悲しい表情/89
アランのこと/91
愛の詩人/97
靈と肉/101
フランスの悲劇/103
英國人/107
アメリカの自由の精神/110
ドレフユス事件の意義/113 |
新しき愛國の情/117
デマ/122
權威/124
都會/127
素直な氣持/130
水は教える/132
世わたり/134
大なることと小なること/137
反省/140
天は頭の惡いものを助けない/143
チャンス/145
弱さ/147
ソクラテス/149
ポォル・ロワイヤルについて/152 |
木下尚江先生の思い出/161
ポオル・ルックウル教授/167
シャルル・デュモン/172
二人の反逆者/178
反逆兒・日蓮とルーテル/188
二宮尊徳/193
白隱/199
須田忠/202
張吉龍君をめぐつて/206
大石寺詣り/212
滄浪閣日記抄/216
・
・
・ |
|
| 1949 |
24 |
・ |
11月、師友会編「師友 (2) 」が刊行される。 pid/1815878
|
卷頭 三つの斷案 //1
(三)嫁ぐ姪に / 佐久間象山/2
(四)到る處世に合はぬ後進に / 明王陽明/7 |
白隠禪師 / 川越龍方/12
心學の復興とMRA運動 / 龜井一雄/20
竹潭淸話 / 中島久萬吉/26 |
名作心解 蟇の宗敎 //34
世界通信・書架・近詠 //38
・ |
12月、日本歴史学会編「日本歴史 (21);昭和二十四年十二月號」が「吉川弘文館」から刊行される。 pid/10232501
|
町座の成立に就いて/赤松俊秀/2~11
町人の擡頭/永島福太郞/12~15
近世における日本商法發達史概觀/野津務/16~19
資本家的企業の成立と商人及び新人/宮本又次/20~26
時評//27~29
陵墓の學術的調査/大場磐雄/27~28
法隆寺五重塔と秘寶/福山敏男/28~29
友への手紙 : 歴史敎育の理想について/岡田章雄/41~45
中世文化の流れ : 高校日本史の單元指導/生江義男/46~48
社會科歴史の學習 : 生徒の立場から見た/降矢憲二/48~50
古代 (下) 日本史基礎講座 第三講/竹内理三/32~40 |
歴史手帖//30~31
象の渡來/沼田次郞/30~30
茶壺と宝石/岡田章雄/30~31
白隱の一夫一婦論/家永三郞/31~31
人物評傳//51~51
内村鑑三 : 近代精神の使徒/家永三郞/51~51
『アメリカ外交史』を貫くもの : ヒックス敎授の/蒲生俊仁/52~54
惱める人々への奉仕 (下) 忍性の社会活動/中村元/55~63
質疑應答//40~40
卑彌呼について/桃裕行/40~40
学界動向//64~64
編集後記//64~64 |
○、この年、禅の論攷 : 鈴木大拙博士喜寿紀念論文集 久松真一 編 岩波書店
pid/1160100
|
正宗國師の宗旨と息耕録開筵普説・朝比奈宗源/1
南陽慧忠の心經註疏・宇井伯壽/69
白隱禪の看話に就て・柴山全慶/83
禪的人格の自由性・柴野恭堂/123 |
自戒集に就て・古田紹欽/137
禪の將來性に就て・長與善郎/151
禪と美・柳宗悦/171
狂信・市川白弦/199 |
信仰の論理・柳田謙十郎/221
幽玄論・久松眞一/247
後記・久松眞一/289
・ |
〇この年、森本芳雄が「密教文化 1949(5-6) p.51-52」に「否定の論理」を発表する。 J-STAGE わかりやすい
○、この年、高野山大學學友會 編,伊藤光祐 編輯代表「失いし心を求めて」が「高野山出版社」から刊行される。 pid/11177420
|
一、 序文・佐和隆研
二、 失いし心を求めて 資延敏雄/1~ |
三、 死と生との間 森本芳雄/9~
四、 蝕ばまれいく童心 高橋厚温/14~ |
○、この年、陸川堆雲が「臨済及臨済録の研究」を「喜久屋書店」から刊行する。 pid/1157786
|
題字 釋宗活老師
口畫 臨濟慧照禪師塑像 臨濟塔 曾我蛇足筆臨濟禪師畫像
→正受老人書入臨濟録夾山鈔 臨濟關係略地圖
序文 棲梧寶嶽老師
同 文學博士 林屋友次郎先生
例言
第一章 臨濟録の序文に就て/1
第二章 馬防序文の研究/11
第三章 臨濟傳考/50
第四章 祖堂集及其の臨濟の異傳に就て 附り、普化傳及大愚傳/121
第五章 臨濟録の編者は果して三聖慧然なりや及其の疑問に就て/136
第六章 臨濟研究史書等年表/160
第七章 臨濟録が何故福州皷山にて重開せられたるか/164
第八章 臨濟録書史/168
第九章 臨濟三句中に於ける無着は人名に非ず又妙解は文殊に非ず/178 |
第十章 臨濟關係者法脈一覽圖表/206
第十一章 臨濟門下の諸師略傳/215
第十二章 臨濟及臨濟録に對する古人の論評/254
第十三章 臨濟に關する古人の偈頌/275
第十四章 四料簡に就ての古人の商量/288
第十五章 臨濟及臨濟録中に於ける諸種の問題/293
第十六章 臨濟録の諸鈔に就て/320
第十七章 朝鮮に於ける臨濟禪の推移/340
第十八章 現今の臨濟寺/347
第十九章 雪村友梅禪師と臨濟寺/358
第二十章 關山國師碧嚴集擧着中より臨濟に關する二則/362
第二十一章 皇室並に其御門葉及公卿と臨濟及臨濟録/365
第二十二章 臨濟禪師關係年表/385
圖表(折込)臨濟録三重開者及道行碑建設者關係法系/10~11
跋文 釋大眉老師/391 |
|
| 1950 |
25 |
・ |
4月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 27(4)(292)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885188
|
禪林詩評 / 高橋竹迷 / p3~3
養花の雨 / 巻頭言 / p3~3
兜率禅師の三関-1- / 菅原時保 / p4~7>
学と行 / 市川白弦 / p8~9
詩禪一味 / 峰尾大休 / p9~9
坐禅和讃講話-〔1〕- / 朝比奈宗源 / p10~14 |
正法目蔵釈意紹介 / p14~14
授戒会と灌仏会式 / 那須坦道 / p15~17
従容録風穴鉄牛提唱 / 原田祖岳 / p18~21
素人仏教 / 新井琴次郎 / p22~23
虚偽を離れて真実へ / 内山節定 / p24~26
山崎佐六君の追憶 / 平井海庵 / p27~27 |
一休と沢庵-8- / 松田奉行 / p28~29
猫柳 (俳句) / 今村野蒜 / p29~29
禪界時報 / p30~31
編集後記 / 飯塚夢袋 / p32~32
・
・ |
6月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 27(6)(294)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885190
|
禪林詩評 / 高橋竹迷 / p3~3
新樹の爽快 / p3~3
兜率禅師の三関-3- / 菅原時保 / p4~7
三要三玄と日本芸能-〔上〕-/島田春浦/p8~11
凡人凡語 / 今村野蒜 / p11~11
坐禅と中心 / 原田祖岳 / p12~13
平林寺大授戒会 / 野火止山人 / p14~16 |
しなうもの / 土屋寛 / p16~16
坐禅和讃講話-2- / 朝比奈宗源 / p17~21
青江政太郎氏よりの書簡 / p21~21
素人仏教 / 新井琴次郎 / p22~23
自然と人生 (女人禪) / 高橋實善 / p24~26
衣更(俳句) / 佛子露影 / p26~26
無明物語 / 小松法貫 / p27~27 |
一休と沢庵-10- / 松田奉行 / p28~29
初相見の原田老師 (詩)/若林泰子/p29~29
禪界時報 / p30~31
編集後記 / p32~32
乾坤唯一峰 (表紙畫) / 菅原時保
・
・ |
7月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 27(7)(295)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885191
|
禪林詩[評] / 高橋竹[迷] / p3 ~3
夏の快味 / 卷頭言 / p3~3
兜率禅師の三関-4- / 菅原時保 / p4~8
金剛道の生活 / 濱地天松 / p8~8
三要三玄と日本芸能-下-/島田春浦/p9~11
夜詠歌を聞く / 安田白牛 / p11~11 |
思想超越の禅 / 原田祖岳 / p12~14
自然と世相 (短歌) / 杉本寛一 / p14~14
路頭禪 / 小松法寛 / p15~15
坐禅和讃講話-3- / 朝比奈宗源 / p16~20
新[刊]紹介 / p20~20
無絃居士に質す / 長尾大學 / p21~22
|
托鉢から教へられる/風間光善/p23~25
素人仏教 / 新井琴次郎 / p26~27
一休と沢庵-11-/松田奉行/p28~29
禪界時報 / p30~30
編集後記 / 飯塚夢袋 / p32~32
・ |
8月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 27(8)(296)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885192
|
禪林詩評 / 高橋竹迷 / p3~3
炎熱修行の興味 巻頭言 / p3~3
兜率禅師の三関-5- / 菅原時保/p4~7
当世雲衲気質-1- / 須井宗謙/p8~10
路頭禪 / 小松法貫 / p11~11
坐禅和讃講話-4- / 朝比奈宗源/p12~16 |
心事未了 (俳句) / 佛子露影 / p16~16
相馬御風先生との宿縁 / 高橋竹迷 / p17~19
二菩薩僧の意義 / 原田祖岳 / p20~22
手紙禪 / 豊田大誓 / p22~22
七十三歳の今日 (女人禪)/若杉紀久子/p23~25
禪界ニュース / p25~25 |
禪界の三巨人に遇ふ / 山田曙山/p6~27
長尾大学師に答ふ / 新井琴次郎/p27~28
素人佛敎を読む / 岩田久之助/p28~29
暑中廣告 / p30~31
編集後記 / 飯塚夢袋 / p32~32
・ |
9月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 27(9)(297)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885193
|
詩禪一味 / 高橋竹迷 / p3~3
新秋早涼の一句 / p3~3
坐禅和讃講話-5- / 朝比奈宗源 / p4~7
当世雲衲気質-2- / 須井宗謙 / p8~10
大衆部出來せよ / 安田白牛 / p10~10
青山白雲 / 渡辺小洋 / p12~15 |
正法寺開山誕生記(劇)/海嶽翠巌/p16~17
書禅一味 / 渡辺喝山 / p18~21
素人仏教 / 新井琴次郎 / p22~23
仏祖の御命 / 小林全栄 / p24~26
尼僧の猛省を促す / 中村愛信 / p26~26
路頭禪 / 小松法貫 / p27~27 |
愚堂国師の屈棒〔東寔愚堂〕/
→柳沢玄藤/p28~29
禪界ニュース / p30~31
編集後記 / 飯塚夢袋 / p32~32
・
・ |
|
朝比奈宗源が「大乗禅27(4~9)(292~297)」に発表した「坐禅和讃講話-1~5-」迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻通頁数 |
発行年 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
27(4)(292) p10~14 |
1950-04 |
坐禅和讃講話-1- |
・ |
pid/7885188 |
| 2 |
27(6)(294) p17~21 |
1950-06 |
坐禅和讃講話-2- |
・ |
pid/7885190 |
| 3 |
27(7)(295) p16~20 |
1950-07 |
坐禅和讃講話-3- |
・ |
pid/7885191 |
| 4 |
27(8)(296) p12~16 |
1950-08 |
坐禅和讃講話-4- |
・ |
pid/7885192 |
| 5 |
27(9)(297) p4~7 |
1950-09 |
坐禅和讃講話-5- |
・ |
pid/7885193 |
|
11月、心編集委員会編「 心 : 総合文化誌 3(11)」が「平凡社」から刊行される。 pid/1763903
最重要
|
文化の滲透 / 安倍能成/1
米国教育使節団を迎えて / 天野貞祐/6
ニーチェの永劫回帰と神秘主義/高坂正顕/8
詩におけるニーチエ / 手塚富雄/23
原始ローマ演劇-2- / 新関良三/32
利休と私 / 柳宗悦/56 |
明治の一風俗--回想録の中より-2-/有馬頼寧/40
晩年 / 成瀬無極/50
珈琲香 / 上野直昭/37
ヒットラーと火焔の文字 / 武者小路公共/61
生成言 / 吉井勇/55
※白隱の畫に就て / 無車/49
|
日本脱出(長篇第九囘) / 正宗白鳥/90
服織 / 中勘助/80
眞理先生(長篇第廿一囘)/武者小路實篤/72
・
・ |
|
| 1951 |
26 |
・ |
6月、「世界仏教 6(6)(209) 」が「世界仏教協会」から刊行される。 pid/3556930
|
和と米国と日本――卷頭言/p9~9
特輯 聖德太子奉讃/p10~63
太子を想う / 高松宮//宣仁/10~11
世界の友に / 聖德太子会/p14~15
太子と仏教 / 福島//政雄/16~21
太子と浄土真宗 / 大谷//光照/22~23
太子と罪悪 / 亀井//勝一郎/24~25
聖徳太子と日本の理想 / 暁烏//敏/26~27
ひじりの宮のみ前にありて / 高松宮/p28~29
隨筆 太子讃 / 宮崎安右衛門/p38~40
聖德太子千三百卅年祭写眞/p12~12
太子記年祭に參列して / 野依秀市/p13~13
太子遺跡巡禮 / 村上義一/p36~37
太子年譜 / 編輯部/p40~40
磯長の御廟/p46~46
日本仏教の始祖として将た又哲人
→政治家としての聖徳太子 / 野依//秀市/41~43
太子まします / 大谷光暢/p43~43
皇室と仏教 / 禿[氏]//祐祥/34~35
和に就いて / 武者小路//実篤/30~33
創作 聖德太子 / 細田源吉/p47~55
太子薨去〔戯曲〕 / 寺田//弥吉/56~63
十七條憲法/p44~46
キリスト教信者としてのマッカーサー元帥に贈る
→仏教徒よりの餞け / 野依//秀市/64~76
仏教の科学性 / 山本//洋一/80~85
吉川英治氏の「親鸞」を糺す-6-祖師もふき出す
→新解釈 / 寺田//弥吉/90~95
敎界時評 / 伊藤康善/p96~97
煩惱救済のお藥師さん / 丸山功/p114~115
仏教徒は講和・再軍備・安全保障・平和に就て
|
→どう考えるか(座談会)/ 江部//鴨村 ; 草葉隆円 ;
→ 山下義信 ; 來馬琢道/98~107
法華経の理解 / 江部//鴨村/108~113
ステッド博士一族の消息 / 長井//真琴/86~89
信仰体驗記 佛敎の前に / 小林忠雄/p116~117
信仰体驗記 宇宙の神秘にふれて / 宮尾博次/p118~119
信仰体驗記 無碍の一道 / 杉本春雄/p118~119
俳句 / 森夢筆/p89~89
読者通信/p146~147
信火讃 / 季盛英正/p97~97
隨筆 録 / 室住熊三/p77~79
家庭の頁 粗食と美味 / 本山荻舟/p120~121
家庭の頁 一休さん / 宮尾しげを/p122~123
家庭の頁 兎の念佛 / 宮崎童安/p124~125
檀林皇后のこと〔嵯峨天皇皇后〕--仏教婦人銘々伝-3-
→/ 伊福部//敬子/126~128
家庭の頁 りらの香 / 岩野喜久代/p129~129
何故仏教は印度に滅びたか-3-
ヤコ簡易仏教概論-21- / 不屈信仰居士/143~145
わが崇敬せる高僧のおもかげ/p130~142
「中山流」日久師のことども / 布施//浩岳/130~133
洞門の偉僧懐奘禅師 / 東野//金瑛/134~136
盲目の律僧鑑真和上 / 大原//信三/140~142
一向禅の白隠禅師〔慧鶴〕 / 古田//紹欽/137~139
さんげ録――(十) / 野依秀市/p148~151
人生信仰質疑應答 迷信と正信 / 永田照二/p152~159
人生信仰質疑應答 恩知らずな心が救われる / 山瀨芙美子/p159~161
人生信仰質疑應答 氣休め説敎では駄目 / 伊藤曉学/p161~161
人生信仰質疑應答 殺人・自殺・心中と信仰 / 春田淸/p162~163
雜記 / 野依秀市/p164~168
・ |
○、この年、吉田絃二郎が「わが人生と宗教」を「万葉出版社」から刊行する。 pid/1659418
|
自序
初冬にをりて/7
究竟の言葉/15
思惟と孤獨/30
秋心經/41
涙の味はひを知る人間の生活/52
イワンの馬鹿の人々/63
無上の機縁/72
芭蕉の歩いた自然の道/81
|
路上素畫/86
キリストの言葉/101
死の感傷/109
一人苦しむ者/117
人生に就いて/124
芙蓉涅槃/136
内面の世界に生きて/147
人間の心についての感想/154
ナザレの貧兒/163 |
愛と憎/169
生活の深化/179
永遠の疑惑/188
憎みといふこと/198
柚子の花の散るころ/206
愛する心愛せらるる心/215
一切は靜かに忍ぶ/223
強く生きんがために/228
人生に對する二つの立場/236
|
若き時代へ/245
モンナ・リザとダ・ビンチ/259
若き日と美しき魂のために/266
基督の解放と無限/278
眞理に慕ひ寄る心/285
魂の言葉/295
白隱禪師と石/302
キリストに就いて/309
・ |
○、この年、伊福部隆彦が「宗教の知識」を「池田書店」から刊行する。 (今日の教養書選 ; 第9) pid/2940583
|
理論篇
序章 宗敎の二大別/p11
1、宗敎の目的と本書の目的/p11
2、宗敎の二大別/p14
第一章 神はあるか/p17
1、神はどうして認められたか/p17
2、神憑りの原理/p22
3、神憑りの神の正體/p26
4、神憑りの豫言は的中するか/p29
5、修驗者的豫言者について/p33
6、最初の結論と次の問題/p38
第二章 運命はあるか/p40
1、運命豫知法の原理/p40
2、易占其他に人生の眞實は
→つかまれてゐるか/p47
3、運命なるものなし/p53
第三章 地獄極樂の問題/p58
1、三世觀の根據/p58
2、道元禪師の?/p61
第四章 奇蹟について/p66
1、奇蹟談はどうして出來きたか/p66
2、存在する奇蹟/p73
第五章 眞の宗敎(一)~佛敎について~/p80
|
1、釋尊のなやみ/p81
2、釋尊の修行/p88
3、釋尊の大悟とその?容/p97
4、佛敎の現代的使命/p102
第六章 眞の宗敎(二)
→~キリスト敎について~/p106
1、イエスの出現以前/p106
2、ユダヤ人の矛盾/p111
3、イエスの見神/p113
4、イエスの生涯/p119
5、キリスト敎の成立/p126
第七章 惡魔とは何か/p129
1、あらはれたる惡魔の例/p130
2、惡魔とは何ぞや/p134
3、釋尊及びイエスに
→あらはれたる惡魔/p138
第八章 病氣災難と宗敎/p145
1、通俗宗敎の病氣災難觀/p145
2、知識階級的宗敎家の態度/p151
3、正しい宗敎の病氣災難觀/p154
第九章 現代の宗敎的課題/p158
1、現代人の不安とその特徴/p158
2、現代宗敎は何を應へ得るか/p163
|
3、宗敎の現代的課題/p171
實踐篇
第一章 病氣に對する生き方/p176
1、白隱禪師の場合/p176
2、西有穆山禪師の場合/p179
3、綱島梁川氏の場合/p181
第二章 災難に對する生き方/p191
1、大地震に遭ひたる友への手紙/p191
2、雙脚となりし傷痍軍人へ送る手紙/p197
第三章 經濟生活に於ける態度/p201
1、専門的宗敎家の場合/p203
2、一般在家人の場合/p206
第四章 老年の生活/p220
1、老年のなやみ/p220
2、五十嵐先生と西有禪師/p224
第五章 死の問題/p230
1、釋尊の弟子キサ・ゴータミの場合/p231
2、死者との交通/p234
3、死よりの解脱/p239
第六章 宗敎の極意/p250
1、宗敎の神秘/p250
2、幸不幸を超えて/p254
・ |
|
| 1952 |
27 |
・ |
5月、師友会編「師友 (31) ] が「師友会」から刊行される。 pid/1815851
|
内外淨化運動の提唱 /
先輩のユーモア / 杉浦重剛 ; 一休 ; 白隠 ; 天海 ; 円智 ;
→ 高橋泥舟 ; 坂本龍馬 ; 親鸞 ; 仙崖/1
老荘的政治観--経子講座 / 安岡正篤/2
愚かなる――兄弟の記録 / 湊邦三/14
ライマン山寺 / 吉村岳城/26
山本周五郞著(同氏傑作選集第一卷)日本婦道記 / 林/29
A・J・トインビー 深瀬基寬訳 試練にたつ文明(下卷) / 小林/30
|
安岡正篤著 校訂改版 政治家と実踐哲学 / 安岡正篤/32
安岡正篤著 老荘思想(改装版) //33
どういふ書物に親しむべきか / 小林/34
覚えがき--教育の本義 / 安岡正篤/35
摩訶般若波羅蜜多心経講話-7-竹潭清話 / 中島久万吉/37
世界通信 //42
クラブ便り //48
あとがき / 編輯部 |
6月、大倉精神文化研究所編「大倉山論集 1」が「大倉精神文化研究所」から刊行される。 pid/4412085
|
明治史の諸問題 維新前後の身分関係 / 新見吉治/p1~57
明治史の諸問題 明治社会の形成過程と
→西洋経済学の受容 / 岡田俊平/p58~83
明治史の諸問題 明治初期における日本社会学前史の研究--
→社会学者としての西周とコントの実証主義 / 早瀬利雄/p84~105
日本書紀各卷成立の一考察 / 藤井信男/p106~121 |
日本書紀の仏教伝来の記事 / 西田長男/p122~211
葛城・磯城・石上--日本古代史への一試見 / 森田康之助/p212~227
白隱の念仏論 / 古田紹欽/p228~236
新資料の紹介 山鹿素行晩年の政治論の著作について--
→問集の全文紹介 / 阿部隆一/p237~248
・ |
○、この年、青木茂が「療養 体験の哲学 : 道元 盤珪 白隠の歩んだ道」を「関書院(京都)」から刊行する。
所蔵:千葉県立西部図書館 愛知県図書館
○、この年、勝間田撫松が「振幅 : 歌集 著」を「立春短歌会」から刊行する。
(立春叢書 ; 第6) pid/1341905
|
序文 五島茂
潮騒 自昭和十三年至
→昭和十五年二月/1
瓦天女(六首)/3
若草山々燒(五首)/5
白隠遺墨展覧會(三首)/7
風車のある風景(三首)/9
海辺の家(八首)/10
送別(二首)/13
目白(三首)/14
オフイス(八首)/16
生駒立春山荘(三首)/19
熊野路(九首)/20
彦根八景亭(三首)/24
宍道湖(二首)/25
大山(三首)/26
樗紅葉(八首)/28
潮騒(二首)/31
松江冬日(二首)/32
霜夜(五首)/33
|
伊豆の海女(三首)/35
孔雀(七首)/36
田地(二首)/39
壯漢(五首)/40
拍手(二首)/42
ノモンハン戦印象(二首)/43
並河太を悼む(四首)/44
野火(二首)/46
海藻 自昭和十五年三月至
→昭和十八年/47
轉任(五首)/49
海藻(七首)/51
秒音(二首)/54
室戸岬(五首)/55
動物園(二首)/57
昭和風雲録を讀む(三首)/58
驛頭(四首)/59
三月十日(二首)/61
胡羅蔔の花(五首)/62
激動(二首)/64
|
悲歌 自昭和十九年至
→昭和二十三年/65
木蓮の花(三首)/67
悲歌(三首)/68
空の眞靑(七首)/70
花をささぐ(四首)/73
小蕗佃煮(四首)/75
封鎖生活(五首)/77
向日葵(長歌五首短歌五首)/79
諷刺詩(四首)/86
明暗 自昭和二十四年至
→昭和二十六年/89
ダンス・パーテイー(五首)/91
メーデー行進(十一首)/93
眞相(五首)/97
龍安寺石庭(六首)/99
湯の花澤温泉抄(十首)/101
停年退職(十一首)/105
はなびら(十首)/109
奇蹟(五首)/113
|
虞美人草の花(五首)/115
激流(五首)/117
日光(八首)/119
造花の花束(二首)/122
金閣寺炎上(五首)/123
父と子(十七首)/125
再會(五首)/131
白浜(五首)/133
鮮語(八首)/135
蟻族(五首)/138
修學院離宮(十四首)/140
講和近づく(八首)/145
加茂川出水(十一首)/148
相性論(七首)/152
ペルリン・アツピール(八首)/155
明暗(五首)/158
無牛庵歌會(十七首)/160
後記
・
・ |
○、この年、石川謙博士還暦記念論文集編纂委員会編「教育の史的展開 : 石川謙博士還暦記念論文集」が「講談社」から刊行される。 pid/3045237
|
石川謙博士近影
題辞 辻善之助
祝詞 吉田熊次
祝辞 乙竹岩造
祝辞 下村寿一
石川謙博士年譜・著書及び主要論文解題
教育史と人文理念 石山脩平/p3
ルネ・ユベールの教育史 波多野完治/p15
学校史上における二重制の問題 海後宗臣/p27
日本の大学の歴史的性格 皇至道/p37
私学の沿革と業績の二三 原田実/p49
教育と文化人類学―倫理学の主題をめぐつて― 長谷川鑛平/p67
日本教育史学の発祥 加藤勝也/p79
上代大学制の推移について 桃裕行/p103
綜藝種智院の教育とその教育史的意義 林友春/p123
国文学に描かれた教育側面観 金子彦二郎/p139
中世教育史と仏教 唐澤富太郎/p155
五山における二十四孝の摂取と活用 徳田進/p169
中世庶民教育の一形態―特に「講」について― 結城睦郎/p201
今川状について 尾形裕康/p219
家訓分類の方法 佐藤清太/p241
江戸時代における「純粋教育論」について 小林澄兄/p259
白隠の一立場―学僧・禅教育者としての― 古田紹欽/p269
中江藤樹の人と学と教育について 後藤三郎/p277
|
仏教の民衆教化―かな法語を中心として― 中村元/p295
「夢醉獨言」について 勝部真長/p335
私塾に集つた学徒の調査 武田勘治/p353
明治初期に於ける文明開化の教育意義―二つの啓蒙― 中山一義/p375
明治初期の歴史教科書と明治維新 大久保利謙/p393
明治時代における課外演説討論活動についての一考察 宮坂哲文/p409
明治時代の上京遊学 吉田昇/p429
森有礼の教育政策 土屋忠雄/p443
明治教科書の地方性 仲新/p473
終戦後における教師の思想傾向―日本教育史の一資料― 城戸幡太郎/p499
フィリピン教育史の輪廓―アメリカ治下の教育を中心にみる― 周郷博/p517
中国近世の族塾について 小川嘉子/p533
ソクラテスの教育思想の一考察 瀨川三郎/p551
プラトンの洞窟の比喩―その教育的意義― 稲富栄次郎/p575
プロタゴラス篇における教養の教師と徳育の問題 村井実/p589
中世ドイツ都市におけるドイツ語学校の成立について 梅根悟/p603
文芸復興期に於ける英国の教育思想 加藤猛夫/p627
平等教育の一試案―ルペルシエの国民教育に関する遺稿― 渡辺誠/p639
フレーベル教育学に於ける神の概念 荘司雅子/p665
ヘルバルトの「世界の美的表現」について 岩崎喜一/p693
跋に代えて 長田新
後記
執筆者一覧
・ |
○、この年、「夜船閑話 : 白隠禪師 」が刊行される。 [出版者不明]
本標題は題簽による 寶暦丁丑序刊本の複製 巻初に「白幽子墓石記」(木版画,折込)を付す
五つ目袋綴 所蔵:佛教大学 附属図書館図 佛書||471274209 |
| 1953 |
28 |
・ |
7月、「 墨美 (25) 」が「墨美社」から刊行される。 pid/8702574
|
慈雲尊者作品=Works by St.Jiun / 慈雲/p16~37
寸松庵色紙=Sunshoan-shikishi/p38~
高風会展作品=Works from the “Kofukai” Exhibition /
→入山東石 ; 柳田泰雲 ; 村田竜岱 ; 平尾孤往 ; 木村知石 ;
→ 山崎節堂 ; 津田翠岱/p40~
泉南大德書=Work by Daitoku Sennan / 泉南大德/p2~2
桑原空洞書=Work by Kudo Kuwabara / 桑原空洞/p3~3
慈雲尊者像=Portrait of St. Jiun / 山本義伸/p5~5
大梅禪師書=Work by Rev. Daibai / 大梅禪師/p6~6 |
白隱筆,達磨像=Portrait of Darma by Hakuin / 白隱/p9~9
慈雲尊者母公手翰=Calligraph of the Letter from Jiun’s Mother to Him/p13~13
慈雲尊者の書について=On the Calligraphs by St. Jiun / 神田喜一郎/p2~3
慈雲尊者の書を語る(座談会)=On the Calligraphic Art of St. Jiun
→(meeting) / 喜多楢藏 ; 久松眞一 ; 前田弘範 ; 水野鵜之助 ; 今春潮 ;
→淡川康一/p4~15
慈雲尊者の生涯から=From the Life of St. Jiun / 木南卓一/p16~19
寸松庵色紙=Sunshoan-shikishi / 春名好重/p39~39
表紙――慈雲尊者使用の僧衣=Cover: The Clerial Robe of St. Jiun |
10月、「社会人 (54)」が「社会人社」から刊行される。 pid/3552895
|
【第一線人物紹介】―(3)/大島一郎/p24~28
重光葵 / 大島一郎/p24~24
安倍能成 / 大島一郎/p24~25
長與善郎 / 大島一郎/p25~25
藤山愛一郎 / 大島一郎/p25~26
浅井清 / 大島一郎/p26~26
保利茂 / 大島一郎/p26~26
市川房枝 / 大島一郎/p26~27
近衛秀麿 / 大島一郎/p27~27
藤蔭静枝 / 大島一郎/p27~28
出光佐三 / 大島一郎/p28~28
石井漠 / 大島一郎/p28~28
【青銅の基督】―(6) / 長與善郎/p50~61
【神と男と女】 / 武者小路実篤/p62~76
【施行歌】 / 白隠禅師/p77~79
【封切映画紹介】/p80~86 |
大音楽会 / モス・フィルム/p80~81
ヨーロッパ一九五一年/
→イタリヤ・フィルム/p81~81
戦う雷鳥師団 / リパブリック/p81~82
水鳥の生態 / ディズニィ・プロ/p82~83
君を呼ぶタンゴ / ソノフイルム/p83~83
あばれ獅子 / 松竹/p83~84
急襲桶狭間 / 東映/p84~85
雁 / 大映/p85~86
【新聞ラジオ用語解説】/p87~97
竹島/p91~92
【人生行路】 / 竹岡健治/p98~102
科学と宗教 / 竹岡健治/p98~100
人間の自由 / 竹岡健治/p100~101
良心 / 竹岡健治/p101~102
【心の鐘】 / 風柳仙人/p103~108
|
我等の責任 / 風柳仙人/p103~103
うるおす心 / 風柳仙人/p103~104
三つの現われ / 風柳仙人/p104~104
善事断行の教養 / 風柳仙人/p104~104
善事継続の教養 / 風柳仙人/p104~105
困難に堪え得る教養 / 風柳仙人/p105~105
我がまま / 風柳仙人/p105~106
無知 / 風柳仙人/p106~106
新人 / 風柳仙人/p106~106
内在の自己 / 風柳仙人/p106~106
魅力 / 風柳仙人/p107~107
無限の力 / 風柳仙人/p107~107
上下協力 / 風柳仙人/p107~108
〈抜粋〉
・
・ |
○、この年、「 近世三百年史 : 1550-1850 画報 第9集」が「日本近代史研究会」から刊行される。 pid/3044262
|
口絵 浮世絵の黄金時代 鈴木春信
ひろがる真理の門 天文学・測量術の進歩 / p567
整う朝儀 大嘗会・新嘗会の復興 / p568
中京の繁栄 尾張宗春の「御乱行」 / p570
お国自慢・特産物の起源 染織・陶器その他数々 / p572
日本に来た中国画家 沈南蘋と伊孚九 / p574
君主は人民の公僕 フリードリヒ大王 / p576
「奉行のほかは見るべからず」 御定書百箇条 / p578
甘藷先生 青木昆陽 / p580
知足安分の教え 石門心学 / p582
おもちゃと遊戯 こどもの世界 / p584
小便公方 九代将軍家重 / p586
町人の儒学 懐徳堂と富永仲基 / p588
徂徠学の分裂 太宰春台と服部南郭 / p590
「民に代りて今日ぞうれしき」 七人童子快擧録 / p592
江戸のまつり 三社祭・山王祭・神田祭 / p594
日本文人画の先駆者 南海・百川・淇園 / p596
西洋近代音楽の誕生 バッハ・ヘンデル時代 / p598
百科全書 フランス啓蒙思想の開花 / p600
|
自然真営道 啓蒙思想家・安藤昌益 / p602
時代狂言の完成 並木正三 / p604
見たり聞いたりためしたり ちまたの話題 / p606
宝暦治水 薩摩藩士の悲劇 / p608
人体解剖のはじめ 山脇東洋と野呂元丈 / p610
藩札の話 / p612
封建支配の安全弁 民衆の信仰 / p614
プラッシーの戦い イギリスのベンガル制圧 / p616
「今の天下は危き天下」 幕府批判の先駆・宝暦明和事件 / p618
封建社会の英雄伝 「常山紀談」と「雲萍雑志」 / p620
御三卿のおこり 十代将軍家治 / p622
浮世絵の中興 政信・祐信・長春 / p624
「自然にかえれ」 ルソーとその同時代者 / p626
松坂の一夜 賀茂真淵の生涯 / p628
座頭金・からす金 高利貨と庶民生活 / p630
梅花仁王の門 大坂の奥印会所一揆 / p632
産業革命のスタート ワットと蒸気機関 / p634
臨済の中興 白隱禅師 / p636
・ |
○、この年、武者小路実篤が「人生読本」を「社会思想研究会出版部」から刊行する。 (現代教養文庫 ; 第101) pid/1660301
|
I
戸をたゝく音/11
人類と愛/12
人類と個人/14
自然・神・悪魔/17
人類が健全に生きるために/20
一休和?に就て/21
心のよろこび/30
生きること/32
人間が本当に覚りきれば/34
平和な景色/37
孔子の理想/39
「それから」に就いて/40
真理/42
老いたるレンブラント/46
二宮尊徳/47
もう一歩/51
白隠/51
疑問を入れよ/56
演説/57
桃の花/57
精神と肉体/61
釈迦と目蓮/64
|
赤坊の生長/66
淋しい谷/69
自己完成とは/71
自分と他人/75
或もの/76
孔子/77
「友情」より/87
自己の缺点/96
法然のこと/98
生長と調和/101
II
善と悪/103
耶蘇/105
俺達は杉の林/111
大なるもの/112
宮本武蔵/114
ほめられても/118
愛/119
あはよくば/119
釈迦の幼時/120
子供/121
誕生日に際しての妄想/126
男と女/127 |
孔子と顔回/131
人類と日本/134
傲慢/136
自分の尊敬する芸術家/137
名誉心/138
浦島/141
黒住宗忠のことなど/146
智恵/154
他人の生命/156
耶蘇と女性/157
自然、必然、当然/165
この道より/165
自己を完全に生かす/166
人間の苦痛/169
黒田如水/171
恋愛問題/174
学問/182
法然と信仰/184
III
ロダンと人生/189
金/195
「論語」より/201
天界の生活/203
|
中山美伎子/204
仏陀の最後/207
食欲/218
自分の生命/219
「耶蘇」より/221
主義/227
日本武尊/229
神よ/233
一休の独白/233
百里歩く人と、千里歩く人/237
食ふためには/238
偶像破壊/239
自己を生かす/239
ドストエフスキーの顔/244
道徳/244
悲痛/246
彼の特色/246
宗教の特質/248
火を/253
わかりきつたこと/254
人間は生れたのだ/256
・
・ |
○、この年、「近代日本美術全集 第1巻」が「東都文化交易」から刊行される。 pid/2468054
|
圖版 目録
1 狩野芳崖 不動明王 明治20年 紙本着色 157.6×78.8cm 東京都東京藝術大學
2 橋本雅邦 白雲紅樹圖 明治23年 第3囘内國勘業博 絹本着色 266.7×160.9cm 東京都 東京藝術大學
3 小堀靹音 武者圖(部分) 明治30年 第3囘日本繪畫協會共進會
→ 絹本着色 224.2×113.7cm 東京都 東京藝術大學
4 竹内栖鳳 あれ夕立に 明治42年 第3囘文展 絹本着色 169.5×85cm 京都府 飯田新七氏
5 菱田春草 落葉(部分) 明治42年 第3囘文展 紙本着色 六曲一雙 各156×365cm 東京都 細川護立氏
6 橫山大觀 流燈 明治42年 第3囘文展 絹本着色 143×51cm 東京都 松岡平市氏
7 富岡鐵齋 武陵桃源(部分) 大正12年 紙本着色 174.5×47.5cm 東京都 宮内廳
8 安田靱彦 夢殿(部分) 大正元年 第6囘文展 絹本着色 112×226cm 東京都 東京國立博物館
9 下村觀山 白狐(部分) 大正3年 第1囘院展 紙本着色 二曲一雙 各186.4×207.6cm 東京都 東京國立博物館
10 今村紫紅 熱國の卷(部分) 大正3年 第1囘院展 紙本着色 45.9×1000cm 東京都 東京國立博物館
11 河鍋曉齋 花鳥圖 明治14年 第2囘内國觀業博 絹本着色 102×71cm 東京都 東京國立博物館
12 安田老山 楓橋秋水 明治7年 東京都 朝倉文夫氏
13 田崎草雲 秋山幽隱圖 明治21年 第1囘日本美術協會展 絹本着色 98×65cm 東京都 日本美術協會
14 狩野芳崖 悲母觀音 明治21年 絹本着色 196×86.7cm 東京都 東京藝術大學
15 橋本雅邦 竹林猫圖 明治29年 第1囘日本繪畫協會共進會 絹本淡彩 136×51cm 東京都 東京國立博物館
16 野口幽谷 菊圖(部分) 明治15年 第1囘内國繪畫共進會 絹本着色 199×75cm 東京都 東京國立博物館
17 瀧和亭 松鶴遊鹿圖(部分) 明治28年 第4囘内國觀業博
→絹本着色 六曲一雙 各163.6×369.6cm 東京都 岩崎小彌太氏
18 長井雲坪 夏秋山水圖(部分) 明治27年 紙本墨畫 六曲一雙 各134.2×329cm 東京都 東京國立博物館
19 菅原白龍 溪山急雨圖 明治23年 紙本墨畫 128.8×45.2cm 東京都 本間久雄氏
20 川端玉章 荷花水禽圖 明治30年頃 絹本着色 175×84cm 東京都 東京藝術大學
21 岸竹堂 月下猫兒圖 明治31年 日本美術協會展 絹本淡彩 159.1×70.6cm 京都府 西村總左衞門氏
22 森寬齋 松間瀑布 明治23年 絹本着色 144×84cm 京都府 飯田新七氏
23 荒木寬畝 孔雀圖 明治23年 第3囘内國勸業博 絹本着色 148×260cm 東京都 宮内廳
24 渡邊省亭 雪中〔シャモ・軍けい〕圖 明治26年 シカゴ萬國博
→絹本着色 151.5×72.6cm 東京都 東京國立博物館
25 小阪象堂 野邊圖(部分) 明治31年 絹本着色 84.8×112.1cm 東京都 東京藝術大學
26 橫山大觀 瀟湘八景(江天暮雪) 大正元年 第6囘文展 紙本墨畫 八幅 各114×61cm 東京都 東京國立博物館
27 下村觀山 魔障圖 明治43年 第4囘文展 紙本墨畫 64×173.5cm 東京都 東京國立博物館
28 菱田春草 水鏡 明治30年 第3囘日本繪畫協會共進會 絹本着色 266×173cm 東京都 東京藝術大學
29 西郷孤月 花鳥 明治30年 第2囘日本繪畫協會共進會 絹本着色 72×134.5cm 東京都 東京國立博物館
30 寺崎廣業 溪四題(雲の峯) 明治42年 第3囘文展 絹本着色 二曲一雙 各132×64.5cm 文部省
31 川合玉堂 二日月 明治40年 東京觀業博 絹本着色 86.7×140cm 東京都 麻生多賀吉氏 |
32 富岡鐵齋 白隱訪白幽子圖 大正9年
→紙本淡彩 132.6×51cm 東京都 細川護立氏
33 竹内栖鳳 雨霽(部分) 明治40年 第1囘文展 紙本墨畫
→六曲一隻 各162×357cm 文部省
34 山元春擧 鹽原の奧(部分) 明治42年 第3囘文展 絹本着色
→繪卷四卷 各41.2cm×357.6cm 文部省
35 尾竹竹坡 棟木 明治43年 第4囘文展 六曲一雙 京都府 住友吉左衞門氏
36 池田蕉園 夢 明治41年 第1囘下萌會 絹本着色 130.6×146.4cm
→東京都 鈴木紋次郞氏
37 今村紫紅 近江八景(堅田の浮見堂) 大正元年 第6囘文展
→紙本着色 八幅 各166.9×57.4cm 東京都 東京國立博物館
38 小林古徑 異端 大正3年 第1囘院展 紙本着色 137×237cm
→東京都 東京國立博物館
目次
その展望/p3
1 明治初期の情勢/p6
1 維新後の衰退と文人畫の流行/p6
2 洋風畫の影響/p9
3 國粹主義と傳統畫派の復活/p11
II 明治中期の發展/p14
1 フェノロサと鑑畫會/p14
2 芳崖・雅邦の藝術/p17
3 東京美術學校と帝室技藝員/p19
4 新舊畫壇の交替/p21
III 明治30年代の昻揚/p23
1 岡倉天心の指導方向/p23
2 日本繪畫協會と日本美術院/p26
3 大觀・春草の朦朧體/p29
4 諸團體の分立/p31
5 京都畫壇の情勢/p33
IV 初期文展時代/p35
1 文展の開設と新舊兩派の對立/p35
2 初期文展の主要作品/p39
3 新日本畫の諸傾向/p44
・ |
○、この年、 野口兼資が「兼資芸談」を「わんや書店」を刊行、「白隱の言葉/p5」を掲載する。 pid/2463672 |
| 1954 |
29 |
・ |
4月、飯田□隠提唱,槐安国語提唱録刊行会編「槐安国語提唱録 : 大燈国師語抄
白隠著語並評唱」が「槐安国語提唱録刊行会」から刊行される。 pid/2968691
5月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 31(5)(350)」が「中央仏教社」から刊行さあれる。 pid/7885243
|
洞火劫然の消息 / 巻頭言/p3~3
仏教の理論と歴史 / 伊藤康安/p4~6
護命心と犠牲胎児供養 / 永久岳水/p7~9
私の長寿法 / 浜地天松/p9~9
晩翠軒俳句抄 / 八木泰洲/p10~11
映画『四人の母』を観る / 大学道人/p10~11
|
道歌評釈(三) / 島田春浦/p12~14
未到悟入録(三) / 竹楓荘逸人/p15~17
夢人夢話(遺稿) / 小松法貫/p18~19
猥芋閑話 (柳沢吉保公修禅) /
→柳沢翠巌/p20~22
附刻霊験金剛般若経 / 藤本隣道伝写/p23~27 |
鮎幟りの由来 / 村上福恵/p27~27
信仰の萃 / 内山節定/p28~29
禅林漫談白隠禅師と柏餅 / 長尾大学/p30~33
禅界時報/p34~34
・
・ |
|
| 1955 |
30 |
・ |
1月、淡交社編「淡交 9(1)(79)」が「淡交社」から刊行される。 pid/7890754
|
卷頭 原色口繪・靑磁鳳凰耳花生/p5~6
關守石 新年の辭 / 千宗室/p8~9
家の傳統と女性 / 古谷綱武/p10~16 |
茶のある話 對談 / 北川桃雄 ; 武者小路實篤/p17~25
七福神の正月 / 棚瀨襄爾/p26~29
略 |
1月、「浄土 = Monthly jodo 21(1) 」が「法然上人鑽仰会」から刊行される。 pid/6075490
|
佛心童心 / 吉田絃二郞/p2~4
對談 中共の宗敎事情 / 大谷光潤 ; 戒能通孝/p8~12
法然上人最後の正月 / 大橋俊雄/p24~24
念佛の聲するところ / 新保義道/p25~27
かがやきの美 / 上田理和/p21~21
御忌法話 / 須藤隆仙/p17~20
血みどろの生活 / 須藤隆仙/p17~20 |
眞淨土敎の世界的進出 / 椎尾辨匡/p5~7
童話 作つた凧 / 内山憲尚/p22~23
史話 白隱襌師と山賊長四郞 / 藤田和彦/p28~31
書の話 / 林錦洞/p15~16
誌上年賀 //p32~32
書評 / 真野龍海/p13~14
・ |
2月、「浄土 = Monthly jodo 21(2) 」が「法然上人鑽仰会」から刊行される。 pid/6075491
|
巻頭言/p1~1
雪の日 / 吉田紘二郎/p
ビルマ見聞記 / 石井真峯/p
ビルマの仏教 / 雲藤義道/p
ビルマから / 江守八重子/p12~12
袋中上人 / 大橋俊雄/p23~27 |
東洋人はかく考える / 鈴木大拙/p5~8
知・信・行 / 藤井実応/p
ある日蓮僧と語る / 須藤隆仙/p
史話 白隠禪師と山賊長四郎 / 藤田和彦/p29~32
浄土へのたより/p28~28
・ |
3月、「浄土 = Monthly jodo 21(3) 」が「法然上人鑽仰会」から刊行される。 pid/6075492
|
巻頭言/p1~1
遍路 / 吉田絃二郎/p2~4
如法に生きる / 中野剋子/p9~10
近詠五句 / 獅子谷如是/p15~15
小説 木曾亂入 / 鶴田湛泉/p27~31
薄命の佳人祇王 / 中村かね/p20~21
|
東洋人はかく考える(2) / 鈴木大拙/p5~8
宗教人ハイライト 晩年の西行 / 折原敎詮/p11~15
童話 逃げた小猿 / 山田巖雄/p17~19
史話 白隠禪師と山賊長四郎 / 藤田和彦/p22~26
淨土會員のページ/p16~16
租德諷詠 / 澤田岳潤/p32~32 |
4月、「日本及日本人 6(4)」が「日本及日本人社」から刊行される。pid/3368169/
|
芸術院について / 芳賀//檀/p6~11
民族的自尊心 / 窪田空穂/p12~16
ソ連外交政策の実体 / 猪俣//敬太郎/p18~25
ソ連の政変と今後の動向 / 丸山//直光/p26~33
日経連と日本ILO協会 / 荻島//亨/p34~38
生産性向上と国民経済の再編 / 堀田//征助/p40~43
郷土芸能の現情 / 宮尾//しげを/p44~47
諷刺の氾濫 / 古川//久男/p48~52
白隠禅師の遍歴時代 / 田中//忠雄/p54~61 |
庶民の神話観 / 長田//藤六/p62~69
渋沢青淵翁を偲ぶ / 諸井//貫一/p70~71
日本俳壇 / 矢田挿雲/p72~75
川柳仕訳帳-25- / 根岸//川柳/p76~81
古川柳辞典-19- / 根岸//川柳/p82~86
川柳日本抄/p87~87
室町期までの鳥居-3- / 根岸//栄隆/p88~92
落語の原語-1- / 落合//笑和/p93~100
・ |
6月、「社会人 (74)」が「社会人社」から刊行される。 pid/3552915
|
短歌入門――(1) / 佐佐木信綱/p5~9
家出防止の歌 / 鈍角夫 ; うらら/p10~11
神経症について / 日野原重明/p12~15
藥の使い方――(2) / 戸田進/p16~18
白血球と赤血球 / 真島光/p19~22
株式の話 / 穴見一三/p23~28
礼儀作法十六條――(2) / 竹岡寿々子/p29~37
第三 職場のエチケット / 竹岡寿々子/p29~34
第四 男女交際の仕方 / 竹岡寿々子/p34~37
施行歌 / 白隠禅師/p38~41
賢明なる努力 / 後藤静香/p42~48
人生十二章――(4)利財について / 友松圓諦/p49~55
釈迦の一生――(2) / 久保田正文/p56~59
日本民謠風土記――(4) / 町田嘉章/p60~65
関東地方の巻――(上) / 町田嘉章/p60~65
立志傳中の人(現存)――(7) / 岡田文夫/p66~71
日魯漁業社長 平塚常次朗伝 / 岡田文夫/p66~69
寿屋社長 鳥井信治郎伝 / 岡田文夫/p69~71
眞理先生――(G) / 武者小路実篤/p73~81
トルストイ文学講座 復活 / 岩淵兵七郎/p82~87
「伊勢物語」解説 / 岩淵兵七郎/p88~93
ベストセラーの紹介――(10)/p94~100
信長/p94~96
雪どけ/p96~98
山の音/p99~100
古典関係用語――(1) / 鈴木太郎/p101~105
ソ連の國情――(第十集) / 山野井乙彦/p107~111
世界の防衛條約早わかり―(7)中東防衛機構 / 長谷川誠一/p112~116
時事用語解説(六月版) / 森川三都夫/p117~129
ニュース解説(六月版) / 館野守男/p131~146
因果はめぐる / 朗/p147~147
|
國際情勢の見透し(USニュース)/p148~152
法律敎室――(7) / 八島留治/p153~160
刑法篇――(その二) / 八島留治/p153~160
手紙十二ヶ月(6月) / 千賀子/p161~167
服飾関係用語集[洋裁用具] / 有馬朗子/p168~169
指輪の知識 / 加藤とし子/p170~171
封切映画紹介 / 千賀子/p172~178
ナポリの饗宴 / ルックス/p172~173
名優中の名優 / 二十世紀フォックス/p173~173
ブルー・スカイ / パラマウント/p173~174
もず / ユニヴァーサル/p174~175
緑の火のエメラルド / MGM/p175~176
楊貴妃 / 大映/p176~177
心に花の咲く日まで / 大映/p177~178
蝶々夫人 / 東宝 ; ガローネ・プロ/p178~178
質問應答欄/p179~180
実力テスト/p181~185
スポーツ欄 / 林克己/p186~191
怒る前に反省せよ / 朗/p192~192
実録赤穗義士――(17) / 渡辺世祐/p193~204
(吉良邸討入)――(上) / 渡辺世祐/p193~204
四十七士のいで立ち / 渡辺世祐/p193~195
東西両軍に分かれ進撃 / 渡辺世祐/p195~196
大手軍の表門侵入 / 渡辺世祐/p196~199
搦手軍の裏門突入 / 渡辺世祐/p199~201
敵方の行動を封殺 / 渡辺世祐/p201~202
二時間にわたる激戦 / 渡辺世祐/p202~204
國際日記/p205~209
書道講座――(2) / 北田岳洋/p210~217
英文海外ニュース / ポール・中野/p223~218
・ |
12月、「 禅文化 1(3) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082207
|
-+口絵 鹿苑寺金閣、天竜寺庭園、白隠禅師墨蹟、長谷川等伯画
提唱 百丈野狐 / 山田無文 / p2~6
短歌 秋の歌(十首) / 小杉放庵 / p16~17
禅に於ける生産と勤労の問題(二)--インド思想を
→超えた発展 / 中村元 / p7~15
大燈国師の[墨]蹟 / 小林太市郎 / p18~22
随筆 土を殺す / 内島北朗 / p23~26
禅院の庭園(二) / 重森三玲 / p27~31
随筆 老僧の一喝 / 細見古香庵 / p32~33
大稚堂の俳禅境(二) / 人見少華 / p34~37 |
座談会 禪の海外進出に就て / 長尾雅人 ; 森本省念 ; 久松真一 ; 山田無文 ;
→緒方宗博 ;佐々木ルーズ ; 藤吉慈海 ; 木村静雄 ; 横山文綱 / p38~47
短歌 大徳寺山内(五首) / 三松荘一 / p48~48
英文 或る日の問答 / 山田無文 / p1~2
英文 禅とクエーカーとの異同 / 緒方宗博 / p3~7
英文 正法の西漸 / アイドマン / p8~11
英文 老子道徳経 / 緒方宗博 / p12~15
新刊紹介 / 木村 / p49~50
禅文化研究会報告 / p48~48
・ |
○、この年、直木公彦が「白隠の健康法と逸話」を「日本教文社」から刊行する。 (教文新書 ; 第10) pid/2968242
|
この本を讀む人のために―はしがきに代えて―/p1
1. 白隱禪師の人と著作/p3
2. 『夜船閑話』/p21
3. 内觀の實習・効果・その理由/p54
内觀の祕法
肉體的案靜法
精神集中と自己統一法
調息調心法による完全呼吸法
熟睡法
4. 軟酥の法/p76
5. 『遠羅天釜』/p82
遠方の病僧に贈りし書(意譯)
6. 病める友へ/p103
藥病相治の説
眼病の精神的治療法
7. 生も死も/p122 |
病中の公案
8. 療病法と悟り/p130
(1)一般的なこと
(2)坐禪觀法、靜觀法
(3)心氣を下部に下すこと
(4)心の持ち方
9. 正念の力/p140
10. 無我全托と感謝/p150
11. 白隱の民衆敎化/p159
12. 白隱禪師の逸話/p164
刀をふりかざして渡河
隻手の聲とお三婆さん
駕篭から轉がりおちる
わかい武士をしかる
念佛買いいれます
天桂の馬鹿坊主 |
葱と蕎麥
小出侯の金屏風
すり鉢松と池田候
赤子を抱いて雪中に托鉢す
おさつばあさんの泣きっぷり
治山治水の上林四十七囘
近衛關白と田子屋の娘物語
大名をしかって黍餅をくわす
婆をつれて參禪をする武士
つかうも人のかわい子よ
閻魔大王と『延命十句觀音經』
地獄極樂のありか
牛の尻穴
細川侯をいさめる
あとがき/p205
・ |
○、この年、梶浦逸外が「山之上村に於ける白隠禅師」を「正眼短期大学出版部(美濃加茂)」から刊行する。所蔵:岐阜県図書館
○、この年、武者小路実篤が「武者小路実篤全集 第10巻 (小説 第10) 」を「新潮社」から刊行する。 pid/1664256/1/1
|
ある母/7
ある父/25
久米仙人/57
ユダの辯解/63
ヨハネ、ユダの辯解を聞いて/73
エピソート/79
|
レオナルドの母/89
迦留陀夷/97
大國主の命/115
須佐之男の命と大國主の命/129
老彫刻家の道德心/139
黑住宗忠/145 |
白隱/165
A先生の遺稿/179
哲學者ラメーの死/257
宮本武藏/277
黑田如水/301
日蓮と千日尼/321
|
親鸞の結婚/341
齡/361
彼の日常生活/375
或る女の物語/411
後書き/435
・ |
○、この年、「講座日本語 第4巻」が「大月書店」から刊行される。 pid/2474124
|
1 日本人の言語観 池上禎造/p1
言語観とは
ものをいう態度と言語観
言語観のさまざま―ことばの本質と価値について
文字観
2 日本人の言語行動―言語版「菊と刀」―
→金田一春彦/p18
白隠と泉山
短く短く
理屈を言うな
宵屋町と西田哲学
トニー・谷も日本的
私は書いたらしい
もの言えばくちびる寒し
笑われないように
「君の名は」の人気
アイサツだけは例外
「粗品」の意味
自分を先生に任じた話
世の中は左様然らば
だれが玉杯に花を受ける
顔で笑って
3 言語生活の二十四時間調査 中村通夫/p40
二十四時間調査とは
調査法のあらまし
結果の二、三
4 日本人の読み書き能力 野元菊雄/p54
どうして「読み書き能力」を知る必要があるか
|
どのような調査がおこなわれたか
「日本人の読み書き能力」
「日本人の読み書き能力」
結果――総点について
結果――問題ごとについて
結論
5 言語技術のプリンシプルとタイプ 平井昌夫/p76
まえがき
話すことの目的
話す能力
話しコトバの機能
話すことの種類に応じた言語技術
聞く能力
6 日本語の性格に即した
→ものの言い方 堀川直義/p111
はしがき
文末で文意を決定する性格
非断定的特性
非論理的特性
ややこしい性格
相手によって変る特性
耳で聞く漢字の特性
7 日本語の性格に即した
→ものの書き方 松坂忠則/p131
文語体と口語体
敬体と常体
センテンスの長さ
まぎれない語法
|
予告用の副詞
重点のありかと語順
8 マス・コミュニケーション 乾孝/p151
マス・コミ研究の問題点
ゆがめられる世界像
マス・コミの内部矛盾
「伝え」の発展
いくつかの実例
マス・コミのカーテンを破るには
9 ことばの魔術 上甲幹一/p170
ことばの魔術という意味
チャッカリ魔術とウッカリ魔術
ことばの魔術の新解釈
ことばの魔力の悪用とその型
悪用例の分析と対策
ジェネラル・セマンティックスと
→ことばの魔術
10 ことばの治療 田口恒夫/p186
話しことばの障害
話しことばの病理学
話しことばの治療
スピーチ・センター
11 言語生活の方向 釘本久春/p199
基準の転換
近代日本語の成長
付録 言語生活小辞典 上甲幹一/p211
あとがき 上甲幹一/p221
・ |
○、この年、東京大学仏教青年会編「仏教聖典」が「三省堂出版」から刊行される。 pid/2991000
|
佛敎聖典目次
讀誦用聖典/p1
歸敬文/p1
摩訶般若波羅蜜多心經/p2
讃佛偈(大無量壽經)/p3
妙法蓮華經如來壽量品偈/p4
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品偈/p5
普回向/p7
四弘誓願文/p7
第一 印度の部/p1
阿含經/p3
法句經/p90
經集/p99
遺敎經/p107
大品般若經/p115
金剛經/p123
理趣經/p126
般若心經/p127
|
法華經/p128
華嚴經/p144
勝鬘經/p157
大無量壽經/p162
觀無量壽經/p178
阿彌陀經/p183
大般涅槃經/p184
維摩經/p190
金光明最勝王經/p199
楞伽經/p204
解深密經/p206
圓覺經/p212
大日經/p214
梵網經/p218
大智度論/p221
中論/p228
唯識三十論頌/p243
攝大乗論/p245
|
大乗起信論/p253
第二 中國の部/p269
往生論註/p271
摩訶止觀/p292
大乗玄論/p298
佛性義/p298
大乗法苑義林章/p316
唯識義林/p316
華嚴五敎章/p323
十不二門/p338
傳心法要/p346
臨濟録/p354
無門關/p359
第三 日本の部/p363
聖德太子集/p365
傳敎大師集/p375
弘法大師集/p406
惠心僧都集/p434
|
興敎大師集/p443
法然上人集/p452
榮西禪師集/p485
明惠上人集/p496
道元禪師集/p502
親鸞聖人集/p548
日蓮聖人集/p601
一遍上人集/p627
瑩山禪師集/p637
蓮如上人集/p646
澤庵禪師集/p656
鐵眼禪師集/p660
融觀上人集/p663
白隠禪師集/p669
あとがき/p1
著者年表/p1
・
・ |
○、この年、辻双明が「街頭の禅」うぃ「東洋経済新報社」から刊行する。 pid/2968351
|
序に代えて 鈴木大拙
『街頭の禪』に寄す 笠信太郞
はしがき/p7
街頭の禪
一 達磨の「九年面壁」について―毒殺された達磨の眞面目―/p3
二 達磨の「無功德」と「安心」/p8
三 機械文明の時代と禪/p12
四 生活の基礎として「精神の統制」/p21
五 禪と健康―長生きしている禪僧の生活―/p31
六 自隠禪師のことと「内観の法」/p37
自隠禪師のこと/p37
現実の生活と禪/p41
日常生活の中の禪/p43
白隠のすすめる「内観の法」/p45
七 至道無難禪師の禪風、その他のこと/p53
一商人から大禪師に/p53
「平常はみな佛」/p59
念佛について/p63
「守ることなき」境涯/p64
金銭と智慧について/p66
動物と禪/p69
禪僧と女性/p79
八 生死と禪/p85
|
宗敎の根本問題/p85
禪宗に於ける生死の超越/p87
「生死の中に佛あれば生死なし」/p90
「生死即ち涅槃」/p92
「なに物か死ぬる」/p97
禪客の臨終/p99
九 「無心」と澤庵禪師の「不動智神妙録」/p103
十 「愚の如く魯の如く」―馬鹿になる修行―/p111
十一 一滴の水・一片の紙/p116
水を惜む大拙先生/p116
茶椀を洗う老僧/p118
寶來家の用便紙と下駄/p120
西田幾多郎先生の杖/p125
十二 西田幾多郞博士と禪/p127
十三 「街頭の禪」ということ/p140
現代に生きる禪の道/p147
一 禪と現代/p149
二 欧米の人々と禪の道/p155
ヘルマン・ヘッセの禪/p155
ブラック並にサンソムの禪道観/p158
「禪」を求める欧米の人々/p161
三 現代の日本に於ける禪道の忘却と「禪の解放」/p163
眞の宗敎と眞の文化/p171 |
○、この年、伊福部隆彦が「禅の教えるもの」を「学風書院」から刊行する。 (誰にもわかる宗教講座 ; 第3) pid/2968702
|
夢窓國師語録
一、悪魔について/p12
二、再び魔について/p26
道元禪師語録
一、眼横鼻直/p36
二、行の人生的意義/p43
三、出家の真意義/p50
四、行持の攻徳/p54
五、霊肉と生死/p63
|
六、迷ひと悟り/p79
七、仏道をならふといふは
→自己をならふなり/p83
八、神通/p87
九、大悟の生活/p102
十、修証一如の道/p109
十一、寺院建立/p117
十二、自己の価値/p120
沢庵禪師語録
|
一、人・天・一致の道/p130
二、得道人の消息/p139
三、小事即大事/p143
鉄眼禪師語録
一、吾我の見/p152
二、坐禅の心境/p160
三、百花本然の春/p173
盤珪和尚語録
一、不生の世界/p180
|
二、不生の仏心の体得/p184
三、修行者の心得/p194
四、活仏心/p200
五、大悟の奥/p207
白隠禅師語録
一、五慾と大悟/p218
二、悟後の生活/p224
三、儒にあらず、仏にあらず/p230
四、大道と個身/p233 |
○、この年、河北倫明編「日本画のながれ」が「東都文化出版」から刊行される。
(近代美術叢書) pid/2474587
|
圖版 目録
1 福田平八郎 雨 紙本着色 110×87 昭和28年
2 上段 源氏物語絵巻 東屋の部分(原色版) 紙本着色 21.4×47.9 平安時代
下段 源氏物語絵巻 東屋
3 上段 平家納経 飯王品見返の部分 紙本着色 27.3×26.7 平安時代
下段 小林古径 竹取物語(部分) 紙本着色 45×128 大正6年
4 上段 小林古径清姫(部分原色版) 紙本着色 48×145 昭和5年
下段 小林古径 清 姫 六面の内 紙本着色
5 安田靱彦 御産の祷り 絹本着色 207×74 大正3年
6.7 上段 鳥獣戯画図巻 甲卷の部分 二卷の内 紙本墨画 30.9 平安時代
下段 下村観山 魔障図 紙本墨画 64×173.5 明治43年
8.9 上段 信貴山縁起絵巻 飛倉卷部分延喜加持巻部分三卷の内 紙本着色 31.5 平安時代
8 下段 吉川霊華 離騒 二幅の内 紙本淡彩 94×137 大正15年
9 下段 前田青邨 西遊記(部分) 紙本淡彩 35.4×2340 昭和2年
10 源頼朝像 絹本着色 139.4×111.9 鎌倉時代
11 安田靱彦 黄瀬川の陣(部分)六曲一双 紙本着色 167.5×371 昭和15年
12 菊池契月 南波照間 絹本着色 219×175.5 昭和3年
13 松岡映丘 右大臣実朝 紙本着色 145.5×155 昭和7年
14.15 上段 雪舟 山水図巻(部分) 紙本墨画 22.7×157.3 室町時代
14 下段 川合玉堂 暮雪 紙本墨画 61×75.8 昭和27年
15 下段 横山大観 生々流転(部分) 絹本墨画 56 大正12年
16 狩野元信 山水図 紙本淡彩 178×118 室町時代
17 橋本雅邦 白雲江樹 絹本着色 266.7×160.9 明治23年
18.19 横山大観 瀟湘八景 八幅の内 紙本墨画 各114×61 大正元年
20 上段 宗達 風神雷神図 二曲一双 紙本着色 各154×169.8 桃山時代
下段 尾形光琳 風神雷神図 二曲一双 紙本着色 各165×182 江戸時代
21 前田青邨 風神雷神 紙本淡彩 196×108 昭和24年
22 上段 宗達 田家早春 扇面散屏風部分二曲一双 紙本着色 18×57.3 桃山時代
下段 宗達 源氏物語図屏風 関屋 六曲半双 紙本着色 157×263 桃山時代
23 宗達 源氏物語図屏風 零標 六曲半双 紙本着色 157×263 桃山時代
24 菱田春草 黒き猫(部分) 絹本着色 150×51.5 明治43年
25 上段 今村紫紅 熱国の巻(部分原色版) 紙本着色 45×1000 大正3年
下段 速水御舟 名樹散椿 二曲一双 紙本着色 167×338 昭和4年
|
26 尾形光琳 紅梅図 二曲一双の内 紙本着色 156.4×172.6 江戸時代
27 前田青邨 紅白梅(部分)六曲半双 紙本着色 昭和29年
28 上段 徳岡神泉 菖蒲 紙本着色 昭和14年
下段 尾形光琳 燕子花図屏風 六曲一双の内 紙本着色 150.6×358.2 江戸時代
29 平福百穂 荒磯 (部分原色版) 二曲一双の内 絹本着色 142.4×151.5 大正15年
30 上段 池大雅 課農便図(十便十宜帖の内) 紙本淡彩 17.7×17.7 江戸時代
下段 池大雅 楼閣山水図屏風 六曲一双の内 紙本着色 169.6×373.9 江戸時代
31 上段 今村紫紅 春さき 紙本着色 48×54 大正5年
下段 富田溪仙 青嵐山水図屏風 六曲一双の内 紙本着色 175×372 大正年代
32 浦上玉堂 青山江林図 画帖の内 紙本着色 29×22 江戸時代
33 上段 村上華岳 山 紙本淡彩 91×121 大正14年
下段 小野竹喬 冬日帖 紙本淡彩 37×47.5 昭和3年
34 富岡鉄斎 白隠訪白幽子図 紙本淡彩 132.6×51 大正9年
35 小川芋銭 樹下石人談 紙本墨画 60.7×89.4 大正8年
36 上段 円山応挙 雪松図屏風(部分)六曲一双の内 紙本淡彩 155.5×361.8 江戸時代
下段 山元春挙 ロッキー山の雪(部分) 絹本墨画 221.2×174.5 明治38年
37 川端玉章 荷花水禽図 絹本着色 175×84 明治30年頃
38 上段 松村呉春 山水図屏風(部分)八曲一双の内 紙本淡彩 126.8×404.8 江戸時代
下段 竹内栖鳳 雨霽(部分)六曲一双の内 紙本墨画 162×357 明治40年
39 上段 岸竹堂 大津唐崎(部分)八曲一双の内 絹本墨画 159.1×430.2 明治9年
下段 西村五雲 秋茄子 絹本着色 163.5×201 昭和7年
40 川合玉堂 峰の夕 絹本着色 76.5×103 昭和10年
41 上段 橋本関雪 玄猿(部分) 紙本着色 139.3×157 昭和8年
下段 長谷川等伯 猿猴図(部分)六曲一双の内 紙本墨画 153.5×346 桃山時代
42 狩野長信 花下遊楽図屏風(部分原色版)六曲一双の内 紙本着色 194.4×356.1 桃山時代
43 舞踊図(部分) 紙本着色 80.3×25.2 江戸時代
44 鏑木清方 一葉女史の墓 絹本着色129×71 明治35年
45 上段 上村松園 晴日 絹本着色 74×86.7 昭和16年
下段 円山応挙 江口君 絹本着色 108.5×44.5 江戸時代
46 伊東深水 聞香(部分原色版) 絹本着色 150×157 昭和25年
47 寺島紫明 夕ぐれ 紙本着色 130×66.5 昭和29年
48 土田麦僊 舞妓林泉 絹本着色 215.2×100 大正13年
・ |
|
| 1956 |
31 |
・ |
10月、「 禅文化 2(6)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082210
|
アート口絵 大徳寺特輯 / 編集部/p11~11
提唱 奚仲造車 / 山田無文/p2~6
特別寄稿 禅に関する欧洲の関心 / 芳賀檀/p12~21
特別寄稿 元末名尊宿の日本への招聘 / 玉村竹二/p7~11
特別寄稿 慈雲と禅 / 木南卓一/p22~33
白幽子の人と書 / 伊藤和男/p40~48
|
インド人のアヒンサ(不殺生) / 春日井真也/p34~39
墨蹟鑑定から見た仙崖と良寛 / 淡川康一/p48~56
趣味の頁 禪僧の短冊 / 多賀博/p57~61
趣味の頁 竜門寺釜に就いて / 田淵正/p62~66
趣味の頁 二ッ割りの頭 / 横山幽石/p56~57
新刊紹介/p61~61,67~67 |
○、この年、 淡川康一が「白隠 : 生涯と芸術」を「マリア画房」から刊行する。 pid/2987475
|
表紙(表)
福寿布袋図 白隠作
白隠の畫について 武者小路実篤
白隠禅師の生涯と其芸術 |
墨蹟並解説
白隠・仙厓を語る
白隠芸術の特色(英文) 緒方宗博
表紙 (裏) 大疑堂(龍沢寺禪堂の額) 白隠筆 |
表紙 (裏) 浴仏偈 白隠筆
・
・
・ |
○、この年、古田紹欽が「禅茶の世界」を「春秋社」から刊行する。 pid/2477278
|
禅と茶について
茶と禅との関係 / p4
石と禅 / p13
一禅者の遺偈 / p18
茶を飲むべし / p23
茶について / p27
茶の湯は流行する / p31
茶に関する四つの記事/p37
『独語』における茶の
→批判の批判 / p44
井伊大老の独服 / p56
用不尽の道具 / p59
備忘二題 / p63
茶碗の美 / p67
潜戸にじり口など / p71
誠拙の無茶 / p75
|
墨蹟等について
墨蹟の美について(I) / p80
墨蹟の美について(II) / p89
翰墨禅(I) / p94
翰墨禅(II) / p99
墨蹟をこう見る / p105
大応国師とその墨蹟 / p109
大燈国師とその墨蹟 / p117
大燈国師筆看経榜について / p122
大燈偽墨蹟のこと / p128
大燈国師誹謗のこと / p133
大川普済について / p137
居涇禅師墨蹟について / p142
道元筆「正法眼蔵山水経」について / p148
附・道元筆「対大己五夏闍梨法」の断片/p153
大覚禅師画像・墨蹟の一由来 / p155
|
竺仙梵僊の画論 / p160
一山一寧の「雪夜の作」及び
→「後宇多法皇和韵偈」 / p170
大鑑禅師の遺偈 / p177
一休とその書蹟 / p182
一休の転宗 / p193
養叟とその墨蹟 / p198
利休居士号について / p206
利休、力□希〔リキイキ〕のことなど / p212
江月和尚讃仰 / p215
沢庵宗彭 / p221
淸巖の墨蹟 / p236
白隠の遺墨について / p241
・
・
・ |
○、この年、田中忠雄が「禅の人間像」を「誠信書房」から刊行する。 pid/2966911
|
第一 日常の章
1 死からの逃避―元峰のいわゆる現代病―/p2
2 日々の生活―雲門の生き方―/p13
3 靑くさい理論―趙州の應接ぶり―/p25
4 下半身の學―須佐之男の命と禪―/p36
5 有名への慾望―神父セルギイの場合―/p48
6 禪僧と女性―この斷ち難きもの―/p59
第二 人物の章
1 親鸞と道元―體質と氣質のちがい―/p74
2 遍歴時代の白隱―正受老人にまみえるまで―/p85
3 六祖慧能と船子德誠―衣鉢の繼承―/p98
4 乞食洞水―人間界からの脱出―/p111
5 奇傑祖曉―機鋒のたたかい―/p120
6 雲居希膺と山賊―坐禪の大作用―/p132
|
第三 對決の章
1 現代文明との對決―ノイローゼ、イデオロギー及び進歩主義―/p146
2 平等の説敎者を揶揄する歌―亂舞するタランテラ族―/p156
3 開發を拒否する辯論―コントン王の死―/p166
4 後進國の住民に與える文―心のなかの卑劣漢―/p180
5 現實主義への抗議―子供の夢をこわすもの―/p191
6 斜陽國の住民に與える文―前後截斷の生き方―/p202
第四 公案の章
1 萬里無寸草の處―洞山、石霜、太陽の葛藤―/p216
2 なりかけた佛―發心、修行、成道―/p226
3 妄想するなかれ―時賴、時宗、貞時の參禪―/p238
4 孤貧の公案―人間の幸と不幸―/p248
5 崇高な自種―蘇東坡の悟り―/p259
6 四句百非を超えた一句―馬祖、西堂、百丈の解答―/p270 |
|
| 1957 |
32 |
・ |
3月、陸川堆雲が「 禅学研究 47 p.85-108 禅学研究会」に「「東嶺和尚の無尽灯論の神道思想及び「吾道宮縁由」について」を発表する。
6月、「華道 19(6)」が「日本華道社」から刊行される。 pid/6028347
|
写真 原色版 / 大島立容
写真 目次 / 池坊専永/p3~3
池坊全国選抜秀作展伝統と創作展 /
永井華了 ; 亀沢香雨/p17~17
前田華風 ; 石山文恵 ; 宮本溪雄/p18~18
横山夢草 ; 黒飛松風 ; 中村亮一/p19~19
松尾琢磨 ; 菅文夫 ; 石橋あさの ; 松山晴嵐/p20~20
勝又芳江 ; 宮崎房枝 ; 渡辺芙紗子 ; 菊地如雪/p21~21
加藤一睡 ; 村上欣永 ; 武田芳雲 ; 山名田吉雄/p22~22
鳥井秀山 ; 村田弘州 ; 近藤菊枝 ; 松川ユキ/p23~23
立石智恵子 ; 曽山秀子 ; 宮内芳乃 ; 水上よろづ/p24~24
高野一花 ; 佐藤厳 ; 曽雌梅芳 ; 深田真水/p25~25
菊地芳玉 ; 馬場秋峰 ; 長峯むつ子 ; 細川りつ子/p26~26
地方華展から / 亀沢香雨 ; 横山夢草 ; 矢口博子/p28~28
地方華展から / 高山まさ子 ; 原豊華 ; 遠上美容 ;
→杉本冴子 ; 伊藤とよ/p29~29
いけ花における物と心 / 西堀一三/p4~7
|
関雪の作品をめぐって / 橋本節哉/p8~11
花の詩(1) / 佐々木邦彦/p11~11
立華講座(3) / 根〆蔵人/p12~13
創作のためのアドヴァイス(2) / 下店静市/p14~16
イマージュに就て(2) / 中村晉一/p27~27
我が道をゆく / 福田訓子/p30~31
池坊華道会全国支部長会議の開催/p31~31
かきつばたの試作/p32~32
かきつの話/p33~34
白隠禅師の画 / 安田光義/p35~35
六月の花に寄せて / 越智頼直/p36~36
家庭の花に思う / 菅原若子/p37~37
中国の選抜秀作展への回想 / 小林八太郎/p38~40
静岡県池坊いけ花秀作展と専永宗匠の来場 / 大島立容/p41~42
池坊東北連合華道展いけ花の歴史と作品展 / 平田宗玉/p42~43
池坊中部日本三県連合いけ花展伝統といけ花展 / 佐久間/p43~43
各地の花展から/p44~47 |
7月16日~21日迄、 白木屋に於いて「白隠禅師遺墨展」が開かれる。
主催: 日本経済新聞社. 後援: 文化財保護委員会, 東京国立博物館
7月、日本経済新聞社が「白隠禅師遺墨展」を「日本経済新聞社」から刊行する。
9月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 34(9)(399)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885286
|
白隠禅師 洞上五位偏正口訣
→(ホラ ジョウ ゴイヘンセイ クケツ)/p4~9
暑往寒来 / 杉本寛一/p9~9
碧巖集の畫と釋 / 大塚洞外/p10~11
永嘉大師証道歌提耳抄 / 井上義光/p12~15
高岡岸郎師より/p15~15
|
道徳禪(五) / 島田春浦/p16~19
殺生の悲しみ / 菱灰/p19~19
槐安国語談片(五) / 八木泰洲/p20~21
智慧の泉碧巌物語 / 花本貫瑞/p22~23
五位と易(III) / 佐橋法龍/p24~27
臨済録提唱(二〇) / 大道/p28~31 |
自己を知る人 / 梶原単堂/p31~31
古今禪者の墨跡 / 横山雪堂/p32~34
禅界時報/p35~35
編集後記/p36~36
・
・ |
11月、「禅文化 (9)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082213
|
アート口絵 東福寺--解説 / 福島俊翁 / p53~54
提唱 洞山麻三斤 / 山田無文 / p2~7
特別寄稿 秋灯清話 / 阪本勝 / p24~27
特別寄稿 禅の神秘(二) / ギルバート・ハイエット ; 小堀宗柏 / p7~13
マガタの祭--ギラッガ・サマッジャとスールャ・メーラー/梶山雄一/p32~39
禅と儒教--「禪海一瀾」を中心として / 木南卓一 / p14~24
禅宗建築隨想(5) / 横山秀谷哉 / p54~60 |
趣味の頁 二つの南泉斬猫図 / 土居次義 / p39~47
趣味の頁 姿貌の書畫 白隱について / 古田紹欽 / p27~32
随筆 陶器の鑑賞 / 内島北朗 / p47~49
随筆 鶏五徳 / 高嶋勘一 / p48~52
随筆 盤珪展 / 聴松堂主 / p51~54
新書紹介 / p60~62,23~24
・ |
○、この年、白隠慧鶴著「白隠禅師遺墨集」が「白隠会」から刊行される。図版〔77枚〕 所蔵: 静岡県立中央図書館
|
白隠禅師遺墨名宝展 白隠禅師遺徳顕彰会 編 図版13枚 ; 27cm 白隠禅師遺徳顕章会(静岡) 1957 注記 主催:静岡県教育委員会,白隠禅師遺徳顕彰会 出版年 1957 所蔵:青森県立図書館 静岡県立中央図書館
注 「白隠禅師遺墨集」と「白隠禅師遺墨名宝展」や展覧会の有無(図録)についても違いあるか検討が必要と思う。 2023・1・28 保坂 |
○、この年、長尾大学が「人間禅僧漫談」を「中央仏教社」から刊行する。 pid/2969617
|
(一)白隠禅師と柏餅摂待/p2
貧乏人の味
柏餅でがんす
耳を破る迅雷
(二)木堂和尚の登楼一泊/p6
禅僧を見る眼
色気と慾気と
寝るも坐るも
(三)誠拙禅師の布設強要/p10
慾の無い人間
安心して死ね
本当の坊さん
(四)夢窓国師の夢一場/p15
怒りの原因
無抵抗主義
侮悟させる力
(五)心越禅師の月下一喝/p20
亀とスッポン
ズドン一発
喝の使い分け
|
(六)雲居禅師と甲胄問答/p25
口約束でも
好敵ござんなれ
貸したが悪い
(七)愚堂国師と酒徳利/p31
恐人病の如し
荷物を肩に
自己を磨くの宝
(八)拳骨和尚と木椀二つ/p36
片眼の花嫁も
一握の鉄如意
内観して見よ
(九)一休和尚の迷信打破/p40
当たつて砕けろ
骨まで食う
自然のままの姿
(十)鉄眼禅師と一切蔵経/p45
我慢を摧く方法
執念深い奴
無より有を生ず
|
(十一)雪潭和尚の怒雷説法/p51
威張る役人
手足が震える
民情視察の僧
(十二)洪川禅師の糞桶修業/p56
糞小便の有難さ
何が悲しいか
社会の浄化
(十三)魯堂和尚の芝居見物/p61
割切れた感じ
師直の白髪首
何でも出来る
(十四)独園禅師と死中の活/p66
鼠が猫を食う
イエスの使者
死ぬ為の修行
(十五)仙崖和尚の帳消し/p71
礼は零となる
麦飯六杯傘一本
案外馬鹿だ |
(十六)峨山和尚と神の正体/p76
赤い唐がらし
サア逢わせろ
ゴミ箱禅ぢや
(十七)宗演禅師の金剛眼/p82
嘘から出た誠
之は偽物だ
先師の置みやげ
(十八)大明国師の妖怪退治/p86
片手に声あり
藁人形の如し
健全な信仰を
(十九)百丈禅師の作務三昧/p92
仂いて儲ける
三日間の絶食
極楽は何処に
(二十)真浄老師と鯛の折詰/p97
生ま臭さ坊主
三千年来の仏様
モロ肌ぬぐ |
○、この年、中岡宏夫編著「禅の精髄 : 宗演禅師」が「誠信書房 」から刊行される。 pid/2969253
|
序詞(鈴木大拙)
第一部 禅の真髄
第一話 宗教の根本義/p2
内心の声 / p2
信仰と解信 / p6
万法一に帰す / p12
第二話 平常心これ道/p17
桃栗三年柿八年 / p17
修養の三方面 / p24
心の光すなわち悟り/p32
第三話 物心一如 / p38
禅は心なり / p38
宇宙と同化せよ / p42
物みな神の光 / p46
精神の鍛錬 / p49
第四話 禅の修業 / p55
着実な工夫 / p55
??地一下の消息 / p59
第五話 入室の資格/p63
公案は病者の薬 / p63
天地を呑吐す / p65 |
第六話 教外別伝 / p68
本来無一物 / p68
ただ是れ一枝の華 / p71
第七話 臨済の禅 / p74
以心伝心 / p74
四料簡 / p78
人と境 / p81
大活現前 / p83
第二部 白穏禅師 坐禅和讃講義
白隠略伝 / p88
坐禅和讃 / p89
序説 / p91
禅とその修養 / p91
坐師の方法 / p93
白隠の略歴 / p99
本文講話 / p101
衆生本来仏なり / p101
衆生近きを知らず / p103
水中にいながら渇きを訴える / p105
長者窮子 / p107
六趣輪廻の因縁 / p112 |
大乗真正の禅定 / p120
六波羅密 / p123
坐禅の功徳 / p133
即心即仏 / p135
聞法の益 / p138
自性即無性の妙見 / p142
因果一如 / p145
無相の相を相とす / p147
三昧無碍 / p151
即身即仏 / p157
第三部 座右銘講話
座右の銘 / p162
早起静坐一□香 / p162
既に衣帯を着くれば / p164
眠るに時を違えず / p167
客に接する独りいるごとく/p169
尋常いやしくも云わず / p171
機に臨んでは譲るなかれ/p172
妄りに過去を想うなかれ / p173
丈夫の気 / p173
寝に就くとき / p174 |
第四部 釈宗演の生涯
概歴年譜 / p178
幼時 / p179
出家 / p181
俊崖和尚 / p184
参学行脚 / p187
儀山禅師に参究 / p189
円覚寺洪川会下へ / p190
慶応習学 / p195
印度の苦行 / p198
円覚寺派管長 / p210
万国宗教大会 / p211
日露戦従軍 / p212
欧米漫遊 / p214
南船北馬 / p216
遷化 / p219
宗演の性格 / p222
あとがき(今日に生きる禅)/p234
・
・
・ |
○、この年、クルト・ブラッシュ著・千足高保訳「白隠と禅画」が「日独協会」から刊行する。 pid/8798775
|
第一図 梵字
第二図 自画像
第三図 自画像
第四図 菩提達磨
第五図 菩提達磨
第六図 菩提達磨
第七図 蓮池観音
|
第八図 蓮池観音
第九図 観音菩薩
第十図 蛤蜊観音
第十一図 維摩居士
第十二図 苦行釈迦
第十三図 出山釈迦
第十四図 越後三尺坊 |
第十五図 雲門和尚
第十六図 大應国師
第十七図 大燈国師
第十八図 關山国師
第十九図 臨済禅師
第二十図 大燈国師
第二十一図 豊干 |
第二十二図 鍾馗
第二十三図 太公望
第二十四図 懶?和尚
第二十五図 鉄棒
第二十六図 帆
第二十七図 竹
第二十八図 まゝのつき橋 |
○、この年、福山秀賢編「仏教童話全集 12」が「大法輪閣」から刊行される。 pid/1630681
|
観音の図・(白隠禅師筆)
身がわり観音・浜田広介 黒崎義介・え/2
西行と天龍のわたし場・武者小路実篤 井上球二・え/18
沈んだ鐘・中河与一 池田仙三郎・え/26
トラの寺ものがたり・宮脇紀雄 太賀正・え/41
カサんぼう・魚返善雄 大石哲路・え/50
すいかと兄弟・みやざきあき子 原田ミナミ・え/66
だんご浄土・坪田譲治 太賀正・え/78
つばめの親・大関尚之 川本哲夫・え/88
村の兄弟・小川未明 神田美恵子・え/98
山かげの中納言・大森倖二 滝原章助・え/110
長鼻のぜんち・ふじい・ろとう 渡辺鳩太郎・え/126
|
天狗にもらった旗・吉村俊子 井江春代・え/137
カッパの子と三郎ちゃん・高橋良和 渡辺鳩太郎・え/154
ひじりと馬・大井しずか 川本哲夫・え/166
えんの下の耳四郎・島本久男/164
天上大風・良寛の書/24
一二三・いろは・〃/25
平家納経/17
願成寺のあみださま・しやしん/65
お話をする法然上人/97
歌を書く覚如上人/108
辻せっぽう/125
行道/153 |
○、この年、小野清一郎, 花山信勝が「 日本仏教の歴史と理念」を「明治書院」から刊行する。
pid/2979533 最重要 1940年版もあり
|
序 高嶋米峰
日本佛教の源流としての三經義疎 花山信勝/p1
聖徳太子の御敎の一端 白井成允/p27
憲法十七條の宗敎的基礎 小野淸一郎/p59
奈良朝の寫經に就いて 石田茂作/p85
傳敎大師と法華經 鹽入亮忠/p117
弘法大師の眞言密敎 瀧野賴應/p149
諸行住生思想より一向專修への開展 硲慈弘/p185
明惠上人の華嚴思想 坂本幸男/p241
|
親鸞聖人の太子奉讚 佐々木圓梁/p283
日本學より見たる如來廻向と降臨思想について 小野正康/p303
道元禪師の發心觀 佐藤泰舜/p369
佛敎者の世間道德 石津照璽/p399
江戸時代に於ける諸宗の唯識講學と其の學風 結城令聞/p427
※白隱禪師に依る日本の精神文化統一とその契機 西義雄/p471
明治以後の日本佛敎に就いて 宮本正尊/p529
本覺門と始覺門 ブルウノオ・ペッツォルド/p565
喇嘛 多田等觀/p593 |
○、この年、田中忠雄が「禅人禅話」を「誠信書房」から刊行される。 pid/2968367
|
インド 1 竜宮からの招待 摩拏羅、鶴勒那/p3
2 反骨 鶴勒那、獅子/p7
3 幻術師 婆舎斯多、不如蜜多/p11
中国 4 短気 達磨、磐珪/p19
5 けたのはずれた人間 達磨、慧可、僧〔サン〕/p25
6 奇宿し得てんや否や 道信、弘忍/p32
7 ノイローゼ 馬祖、大珠/p39
8 あやういかいな 道林、白楽天/p44
9 涼風 宝徹/p50
10 寝ぼけ顔 徳誠、夾山/p54
11 どろどろ料理 大偽山、香厳/p58
12 さかしらごと 趙州/p62
13 腹のぐりぐり 法眼、玄則/p66
14 意気投合 南泉、偽山、雲厳、洞山/p70
日本 15 老婆心 道元、懐弉、義介/p79
16 ドライ派 道元/p84
17 バケツの中の蟹 蘭渓、兀菴/p88
18 十三年の夢 無住/p92
19 身投げ上人 無住/p97
20 牛の睾丸 関山/p101
21 男女 一休、沢庵、覚芝 無難、古染、黙仙/p105
22 男の真骨頂 快川/p110
|
23 三人の山賊 雲居/p114
24 きもだま 雲居/p121
25 純情の限界 洞水/p125
26 立亡 風外、慧薫/p130
27 争議 盤珪/p135
28 ペニス切断 鉄眼、了翁/p140
29 伏見人形 鳳潭/p144
30 大役 月舟、祖曉/p148
31 石の地蔵 祖曉/p153
32 大衆の感激 曹海/p158
33 赤いかわうそ 白隠/p162
34 ぬれぎぬ 白隠/p166
35 なみだ一滴 良寛/p170
36 洒脱の妙味 仙崖/p177
37 もがき 玄楼、風外本高、変堂/p181
38 蚊帳一重 物外/p185
39 女菩薩 竜関/p191
40 異性 坦山/p195
41 くそ坊主 大拙、洪川/p202
42 正味の一つぶ 滴水、峨山/p207
43 豪勇無双 月潭、穆山/p212
44 山芋うなぎ 精拙/p219
|
45 ちんぷん、かんぷん 行脚僧/p224
46 自己愛 宗潭、興道/p229
47 恐ろしい医者 黙雷/p234
48 お茶の味 概念二人博士/p240
49 ユーモア 雄峯正忠/p244
50 本来の面目 ベルリンの犬/p248
51 一人よがり 仏陀、道元/p252
写真
自隠筆 達磨図(山本氏蔵)/p27
一休筆 条幅(二点)/p47
良寛筆 おかよ宛戒語(早川氏蔵)/p171
物外筆 鉄鉢/p187
安田靱彦筆 西有穆山肖像
→(静岡旭伝院蔵)/p213
挿絵 細木原青起
雲居と山賊/p115
蚊帳一重/p188
坦山と女/p197
豪勇無双/p214
恐しい医者/p237
・
・ |
|
| 1958 |
33 |
・ |
○、この年、久松真一が「禅と美術」を「墨美社」から刊行する。 pid/2485022
|
禅芸術の展望/p1
I 中国に於ける禅と芸術/p3
―禅と言語・動作・詩文・書画―
II 日本に於ける禅と芸術/p17
―在家禅の形成した生活体系―
禅芸術の理解/p21
I 禅芸術の性格/p23
七つの性格/p24
不均斉
簡素
枯高 |
自然
幽玄
脱俗
静寂
II 七つの性格の禅的根拠/p40
1 表現主体・活動領域・地域・時代/p40
2 時代と地域/p43
―史的根拠―
禅芸術の表現主体としての禅そのもの/p45
―禅的根拠―
I 禅とは何か/p47 |
(1) 自覚の無相性/p47
(2) 自覚の主体性/p51
(3) 自覚の能動性と
→活動領域/p55
II 禅と七つの性格/p58
無法
無雑
無位
無心
無底
無礙 |
無動
結語/p69
図版鑑賞/p71
図版/p1
図版用語略解/p16
作家略伝/p12
挿図目録/p11
図版目録/p7
索引
英文図版・挿図目録/p1
・ |
5月、心編集委員会編「心 : 総合文化誌 11(5) 」が「平凡社」から刊行される。 pid/1763994
|
道德敎育 / 小宮豐隆/2
ミリンダ王問経と那先比丘経-5(完)- / 和辻哲郎/4
千利休-2- / 唐木順三/11
行為の人シュヴァイツァー-2- / 高橋功/32
岩波茂雄伝をめぐって(座談会) / 小宮豊隆/39
久松博士の「禅と美術」を見,且つ読んで / 柳宗悦/57
|
ある古い日記のこと-5- / 渡辺一夫/20
アメリカ大学巡り-3- / 前田陽一/26
横山大観追悼 / 安田靱彦 他/62~66
東洋精神の新技法 / 安田靱彦/62
大觀さんを偲ぶ / 細川護立/64
あなぐま演劇学者 / 新関良三/70
|
人間をつくる小説 / 室生犀星/67
日本の風景-5- / 佐藤春夫/77
昔の家(詩) / 千家元麿/82
用なき生命 / 伊藤操/90
白雲先生-12- / 武者小路実篤/98
・ |
7月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 35(7)(412) 」が「中央仏教社」から刊行され表紙画に「白隠禅師」が掲載される。 pid/7885299
8月、河北倫明が「日本及日本人 9(7)(1389) p5~6, p7~8日本及日本人社」に「「日本の美術 小川芋銭 祭魚図」と「白隠 菩提達磨」」について発表する。 pid/3368207
8月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 35(8)(413) 」が「中央仏教社」から刊行され表紙画に「白隠禅師」像が掲載される。 pid/7885300
9月、「奎星 (71) 」が「奎星会出版部」から刊行される。 pid/1831463
|
同人作品/p2
弦巻松蔭 喜代吉郊人 田中栢翠/p2
山本潮鶴 林子翠 大楽華雪/p3
林露草 田中千古 遠藤南之/p4
杉原丘南 川辺清華 宇高示穹/p5
戸松秀月 藤原松園 住吉朴洞/p6
榊莫山 杉山泰雅 寺部葭江/p7
高橋竹村 佐藤道外 石井南耕/p8
杉谷瑞泉 永田双魚 高島谿雲/p9
小林湖東 藤村紫雲 野田栖石/p10
稲村雲洞 小川瓦木 森田大道/p11
錦織竹冬 春日浩洞 平間香舟/p12
鍋谷紅洋 足立華岳 藤原清洞/p13
月例作品/p14
島大雅 竹下升閒 堀三冬/p14
|
望月騰龍 小黒五陵 菅原白峯/p15
尾崎正義 間山啄水 田中東洋 前川古舟/p16
飛雲会展作品/p31
市村智孝 上松杜〔エキ〕 菅野清峯/p31
上羅裕久 西川久香 足立華岳/p32
榎本善宏 伊勢屋光華/p33
一九五八年のヴェニス展から / 上田桑鳩/p17
告白 / 戸松秀月/p18
四十代の抵抗 / 喜代吉郊人/p18
白隠禅師の遺墨を拝して / 杉谷瑞泉/p19
落書 / 浅野五牛/p20
阿波踊り寸感 / 田中栢翠/p22
中国大陸を思う / 杉原丘南/p22
随感 / 水越茅村/p23
近頃思うこと(愚墨思考より) / 大楽華雪/p23
|
講習を契機として / 田中千古/p24
芸術に関して / 錦織竹冬/p25
いなか / 小林湖東/p26
二つの収獲 / 野田栖石/p27
或る独者の迷言 / 住吉朴洞/p27
画線と書線の相違 / 春日浩洞/p28
偶感 / 佐藤道外/p29
玩珍会のこと / 栖遅堂主人/p29
思うこと / 石井南耕/p30
筆耕 / 小川瓦木/p30
飛雲展を終えて / 上羅裕久/p33
月例作品評 / 宇野雪村/p34
或る小個展(陶山高義君の
→大阪展) / 穎田島一二郎/p35
・ |
○、この年、白隠 著,柴山全慶訓註「毒語心経」が「其中堂」から刊行される。 pid/2982237
|
心經著語 并頌/p1
摩訶/p4
船若/p6
波羅蜜多/p8
心/p10
經/p12
觀自在/p14
菩薩/p16
行/p18
深搬若羅蜜多/p20
時/p22
照見/p24
五蘊皆空/p26
度一切苦厄/p28
舎利子/p30
色不異空空不異色/p32
|
色即是空空即是色/p34
受想行識亦復如是/p36
舎利子諸法空想/p38
不生不滅不垢不浄不増不滅/p40
是故空中/p42
無色無受想行識/p44
無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至
無意識界/p46
無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡/p48
無苦集滅道/p52
無智亦無得/p56
以無所得故善提捶/p58
依般若波羅蜜多故/p60
心無〔ケイ〕礙無有恐怖離一切〔テン〕倒夢想/p62
究竟涅槃/p66
三世諸佛依般若波羅蜜多故/p68
|
得阿耨多羅三藐三菩提/p70
故知般若波羅蜜多/p72
大神呪/p72
是大明呪/p74
是無上呪/p76
是無等等呪/p78
能除一切/p80
眞實不虚/p82
故説般若波羅蜜多呪/p86
即説呪日/p88
掲諦掲諦波羅掲諦羅僧掲諦菩提娑婆訶/p94
船若經/p94
興襌大燈國師 遺誡/p99
坐襌和譛/p100
・
・ |
○、この年、岸本英夫, 増谷文雄, 北森嘉蔵編「毎日宗教講座 第2 (人間の幸福と自由)」が「毎日新聞社」から刊行される。pid/2979729
|
彼岸の世界 増谷文雄/p7
自由 遠藤周作/p28
理想境の夢 武者小路実篤/p42
陽気ぐらし 中山正善/p62
人間の理想と取組んだ人々とその課題
ニルヴァーナ―釈尊―中村元/p85
摂理―イエス―北森嘉蔵/p98
小鳥も兄弟―フランチェスコ―ヘルマン・ホイヴェルス/p111
仏性―道元―圭室諦成/p121
|
高きは低い―白隠―古田紹欽/p133
情の至極―宣長―戸田義雄/p144
アラビアの予言者―マホメット―前嶋信次/p159
信念の幸福―清沢満之―脇本平也/p170
自然と人と聖書と―内村鑑三―鈴木俊郎/p180
理想を追求する幸福―デューウィー岸本英夫/p191
雨ニモマケズ―宮沢賢治―谷川撤三/p203
幸福と自由の諸型/p217
知恵の言葉・いのちの言葉/p271 |
○、この年、「美の美 第2集」が「日本経済新聞社」から刊行される。 pid/2485540
|
ウルビーノのヴィーナス(部分)ヴェチェルリオ・ティチーアノ 大久保泰(美術評論家)/p1
アマノオフィス二世の墓(部分)古代エジプト 武者小路実篤(作家)/p3
供物を捧げるおとめ(部分) B.C.5世紀末 大久保泰/p4
生活 パブロ・ピカソ 大久保泰/p5
ルドヴィチの王座(部分)B.C.500年ごろ 今泉篤男(東京国立近代美術館次長)/p6
蓮池観音 白隠禅師 松下隆章(文化財保護委員会美術工芸課)/p7
キレネのヴィーナス B.C.2世紀 田近憲三(美術評論家)/p8
うずくまるヴィーナス B.C.2世紀 大久保泰/p9
トルソー 古代インド彫刻 谷信一(東京芸術大学教授)/p10
彫刻された象牙板(部分)カピシ遺跡 アントワネット・オーシュコルヌ(パリ・ギメ博物館)/p11
黒陶俑・馬および武人 中国戦国時代 杉村勇造(東京国立博物館図書室長)/p12
乳虎□(重美)周時代 谷信一/p13
土偶 B.C.1世紀 野間清六(東京国立博物館学芸部長)/p14
薬師寺・本尊の台座(国宝)(部分)奈良時代 北川桃雄(共立女子大学教授)/p15
陶俑 唐時代初期 谷信一/p16
東寺・牛皮華鬘(国宝)藤原時代 野間清六/p17
源氏物語・東屋(国宝)(部分) 橋本明治(日本画家)/p18
扇面法華経(重文) 藤原時代 望月信成(大阪市立美術館館長、大阪市立大学教授)/p19
アダムとイヴ ミケランジェロ・ブオナルロティ 田近憲三/p20
浴みのスザンナ イル・ティントレット 大久保泰/p21
天の愛と地上の愛(部分)ヴェチェルリオ・ティチアーノ 田近憲三/p22
眠るヴィーナス ジョルジョーネ 大久保泰/p23
パリスの審判(部分) ピーター・パウル・ルーベンス 久富貢(東京学芸大学教授)/p24
ダナエ(部分) ハルメンス・ヴァン・ライン・レンブラント 田近憲三/p25
ゆあみの後 オーギュスト・ルノアール 大久保泰/p26
髪を梳る少女 橋口五葉 河北倫明(東京国立近代美術館事業課長)/p27
ひとり ポール・ゴーガン 久富貢/p28
思春期 エドヴァル・ムンク 久富貢/p29
行水 エドガー・ドガ 大久保泰/p30
朝粧 黒田清輝 隈元謙次郎(東京国立文化財研究所美術部第二研究室長)/p31
湯女 土田麦僊 隈元謙次郎/p32
青い背景の裸婦 ラウル・デュフイ 大久保泰/p33
ひまわり クロード・モネ プレストン・レミントン(米メトロポリタン美術館
→ルネッサンス・近代美術部長)/p34
牡丹 村上華岳 河北倫明/p35
静物 ジョルジュ・ブラック 大久保泰/p36
銀襖前の静物 安井曽太郎 河北倫明/p37
静物 中川一政 大久保泰/p38
石油ランプ ダヴィッド・ランバール シオマ・バラム(在パリ画家、美術評論家)/p39
静物 ファン・グリス 久富貢/p40 |
まり藻と花 山口蓬春 久富貢/p41
能面 坂本繁二郎 谷川徹三(法政大学文学部長)/p42
海草とうに ベルナール・ビュッフェ 福島繁太郎 (美術評論家)/p43
バタシイ橋 ジェームス・アボット・マクネル・ホイッスラア 本間久雄(早稲田大学教授)/p44
不忍池 小野田直武 隈元謙次郎/p45
山羊 浅井忠 隈元謙次郎/p46
サント・ヴィクトワールの山 ポール・セザンヌ 林武(洋画家)/p47
夏 アンリ・ルッソー 田近憲三/p48
樹下石人談 小川芋銭 河北倫明/p49
ミュルノー寺院 ワシリー・カンディンスキー 植村鷹千代 (美術評論家)/p50
ハンガリーの風景 モホリ・ナギイ 植村鷹千代/p51
満月 パウル・クレー 片山敏彦(ドイツ文学者)/p52
煙火 古賀春江 河北倫明/p53
樹木 速水御舟 河北倫明/p54
エスタックの家々 ジョルジュ・ブラック 植村鷹千代/p55
福浦船着場 中川一政 河北倫明/p56
郊外のクリスト ジョルジュ・ルオー 岡本謙次郎(明治大学助教授)/p57
雪の発電所 岡鹿之助 河北倫明/p58
ムーラン・ド・ラ・ギャレット モーリス・ユトリロ 大久保泰/p59
朝暉 梅原竜三郎 隈元謙次郎/p60
開いた窓 マチス 武者小路実篤/p61
アポロの像(部分) ギリシャ古期彫刻(B.C.6世紀) 大久保泰/p62
トトナック彫刻 メキシコ文化遺跡 (B.C.14~15世紀)笠置季男(彫刻家、二科会員)/p63
蛇女神 ミノア時代(B.C.16世紀) ウィリアム・ドーレー(米・ボストン美術館)/p64
菩薩頭部 トゥムシュク遺跡群 千沢禎治(東京国立博物館彫刻室長)/p65
ハッダの仏頭 後期ガンダーラ彫刻 谷信一/p66
観心寺・如意輪観音像(国宝)平安時代前期 谷信一/p67
正倉院・密陀絵盆 飛鳥時代 野間清六/p68
鵲尾形柄香炉(重文)飛鳥時代 岡田譲(東京国立博物館普及課長)/p69
郊壇窯青磁筍瓶 南宋時代 藤岡了一(京都国立博物館工芸室長)/p70
古瀬戸草葉文様瓶 鎌倉末期 田中作太郎(東京国立博物館陶磁室長)/p71
秋草蝶鳥文鏡 藤原時代 岡田譲/p72
染付の蓮子〔ワン〕 明時代初期 ジョン・A・ポープ(米・フリア美術館次長)/p73
花鳥沈金手箱 明時代 岡田譲/p74
舟橋蒔絵硯箱(重文)光悦 岡本謙次郎/p75
康熙五彩花鳥図瓶(重美)清時代 藤岡了一/p76
色絵鴛鴦香合 仁清 谷川徹三/p77
色鍋島青海波牡丹文皿 江戸時代 田中作太郎/p78
薩摩切子 ちろり 江戸時代 岡田譲/p79
・ |
○、この年、直木公彦が「 生きる力 : 白隠の健康法と逸話」を「竜吟社」から刊行する。 pid/2968267
|
改訂版に際して / p1
この本を読む人のために―はしがきに代えて― /p3
1. 白隠禅師の人と仕事 / p3
2 『夜船閑話』 / p24
3. 内観の実習・効果・その理由 / p56
内観の秘法
肉体的安静法
元気を下腹部に充たす法
精神の安静法
調息調心調身による完全呼吸法
熟睡法
4. 軟酥の法 / p79
5. 『遠羅天釜』 / p85
遠方の病僧に贈りし書(意訳)
6. 病める友へ / p105
薬病相治の説
眼病の精神的治療法
7. 生も死も / p123 |
病中の公案
8. 療病法と悟り / p13
(1)一般的なこと
(2)坐禅観法、静観法
(3)心気を下部に下すこと
(4)心の持ち方
9. 観念と心と霊と肉体との根本関係/p141
10. 無我帰一と感謝 / p149
11. 白隠禅師の民衆教化 / p158
12. 白隠禅師の逸話 / p163
刀をふりかざして渡河
隻手の声とお三婆さん
かごから転がりおちる
わかい武士をしかる
念仏買いいれます
天桂の馬鹿坊主
葱と蕎麦
小出侯の金屏風 |
すり鉢松と池田侯
赤子を抱いて雪中に托鉢す
おさつばあさんの泣きっぷり
治山治水の植林四十七回
近衛関白と田子屋の娘物語
大名をしかって黍餅をくわす
妾をつれて参禅する武士 /
つかうもの人のかわい子よ
閻魔大王と『延命十句觀音経』
地獄極楽のありか
牛の尻穴
細川侯をいさめる
原文・夜船閑話 / p203
原文・遠羅天釜 / p219
遠方の病僧に贈りし書
坐禅和讃 / p231
あとがき / p235
・ |
|
| 1959 |
34 |
・ |
2月、墨人会編「墨人(75)」が「墨美社」から刊行される。 pid/1862484
|
白隠とゴッホ / 森田子龍/2
久松真一先生の墨人展評 / 米田信夫 ; 佐藤中隠 ;
→吉田功 ; 谷口遊石 ; 大橋昭夫 ; 今岡徳夫/4
例月作品 / 前田秋信/6
例月作品 / 鈴木嘉雄/6
例月作品 / 間山啄水/7 |
例月作品 / 鬼塚政人/7
例月作品 / 佐藤中隠/8
例月作品 / 鈴木道生/9
例月作品から二点を選ぶ/
→鈴木嘉雄 ; 米田信夫 ;
→大橋昭夫 ; 辻太/9 |
臨書研究 / 井上有一 ; 樋口悌石 ; 山本文雄 ; 野村抱雲/12
一字習作 / 間山啄水 ; 佐藤中隠 ; 大沢華空/13
自由選題臨書 / 関谷義道 ; 小田秀幸 ; 野村抱雲 ;
→佐藤中隠 ; 前田秋信/15
短評 //17
墨人の眼 //16 |
2月、竹内尚次が國華編輯委員会編「國華 (通号 803) p.63~67」に「白隠慧鶴画序説-上-」を発表する。
3月、竹内尚次が國華編輯委員会編「國華 (通号 804) p.99~103」に「白隠慧鶴画序説-中-」を発表する。
4月、「禅文化 (15/16) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082217
|
アート 一、妙心寺の伽藍
アート 二、妙心寺の重宝
奉讃記念講演 無相大師をたたう / 山田无文 / p2~13
妙心寺の殿堂について / 荻須純道 / p14~27
妙心寺の障壁畫 / 土居次義 / p28~37
妙心寺塔頭の庭園 / 西付貞 / p40~52
歌集 石庭秘抄 / 高柳得賓 / p38~39
歌集 曾遊花園 / 露月句集より / p93~93
花園天皇と絵畫 / 森暢 / p56~58
禪宗建築隨想(七)妙心寺の伽藍 / 横山秀戴 / p123~127
花園の禪匠と学匠たち 関山國師 / 木村静雄 / p67~70
花園の禪匠と学匠たち 雲居--その晩年 / 福嶋俊翁 / p71~75
花園の禪匠と学匠たち 師蠻 / 今津洪嶽 / p76~80
花園の禪匠と学匠たち 無著和尚の学問 / 柳田聖山 / p81~86
|
花園の禪匠と学匠たち 古月から仙厓へ / 淡川康一 / p87~93
花園の禪匠と学匠たち 盤珪 / 市川白弦 / p94~97
花園の禪匠と学匠たち 愚堂 / 伊藤古鑑 / p98~102
花園の禪匠と学匠たち 無難 / 古田紹欽 / p103~109
花園の禪匠と学匠たち 白隱 / 柴山全慶 / p109~114
花園の禪匠と学匠たち 隱山・卓洲 / 横山文綱 / p115~119
隨想 無の一字 / 太室道者 / p53~55
隨想 妙心寺の四季 / 内島北朗 / p59~64
隨想 長岡の春を探る / 聴松堂主 / p120~122
隨想 妙心開山六百年遠諱によせる / 朝比奈宗源 ; 大森曹玄 ; 林恵鏡 ;
→ 関牧翁 ; 竹田益州 ; 加藤会元 / p65~66
隨想 無相大師遠諱香語 / p55~55,64~64,70~70,75~75,86~86
新刊紹介 / p80~80,102~102,127~127
・ |
7月、竹内尚次が國華編輯委員会編「國華 (通号 808) p.263~269」に「白隠慧鶴画序説-下-」を発表する。
9月、「墨美 (90)」が「墨美社」から刊行される。 pid/2362633
図版 白隠墨蹟 / / 8~35 本文 飯田の白隠展の感激を語る / 西村南岳
/ 2~7
12月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 36(14)(435)」が「中央仏教社」から刊行され表紙画に「白隠禅師」像が掲載される。 pid/7885318
○、この年、寺田透が「絵画とその周辺」を「弘文堂」から刊行する。 pid/2488413
|
古いうた―安井と梅原/p3
I
坂本繁二郎―自選囘顧展覽會の折に/p11
井上長三郞/p23
林武/p41
鳥海靑兒/p53
I アトリエ訪問/p53
II 鳥海靑兒/p60
III 厚塗りのマチェール/p77
IV 續・鳥海靑兒/p85
V 鳥海氏の近業の意味/p99
・
|
II
美の位置/p111
二つの視覺/p120
マチス嫌ひ/p127
フォーヴィスム/p137
I フォーヴィスムの再檢討/p137
II 日本のフォーヴ/p147
ルオー/p161
ルオー/p161
ミセレーレ/p166
ルオーのキリスト/p170
白隱のこと/p173
|
雪舟展所感/p183
大雅管見/p188
南畫史我觀/p194
加山又造/p201
III
ロマン・ロランの『ミレー』のこと/p221
『禪と美術」讀後/p236
二つの中世/p244
小林秀雄・『近代繪畫』讀後/p261
高村光太郞の藝術論/p282
バルザックの藝術觀/p294
あとがき/p311 |
○、この年、古田紹欽が「禅の茶・禅の書」を「春秋社」から刊行する。 pid/2968699
|
まえがき/p1
禅の茶
禅と茶と侘びについて/p4
佗びについて―紹?から利休の間にあって―/p20
茶の十徳の一つ―煩悩自在ということについて―/p29
只茶のみ/p36
茶にあっての独りということ/p41
林羅山と禅・茶/p47
日本の芸術―古いものと新しいもの―/p60
禅の書
夢窓疎石という人とその書蹟について/p86
※大橙国師の意志力について/p102 |
※大橙国師の黒蹟について―特に虚堂上堂語について―/p112
一休とその人からする書蹟について/p122
黒斎の「佛法王一般」について/p134
姿貌の書画―白隠について―/p140
白隠の書画の見どころ/p147
白隠の書について/p158
禅そのものによる書と画―「白隠の芸術」展によせて/p165
鈴木正三の禅と念佛と 「南無大強精進勇猛佛」とについて/p169
良寛さんとの「さん」に見る書/p180
黒蹟はこの意味で掛けたい/p187
黒蹟は第一というその一行ものについて/p193
仙厓の「次韻脚」の寒山拾得図について/p201 |
※「大橙国師」は「大燈国師」か? 誤植と思うので再調査要 2023・1・27 保坂 |
| 1960 |
35 |
・ |
3月、「在家佛教 (72)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6063754
|
忿り(詩) / 長田恒雄
根葉 / M / p1~1
煩悩具足 / 結城令聞 / p2~4
仏教にしたがう生活 / 山本杉 / p4~6
歓喜について / 金子大栄 / p14~24
白隠に学ぶ / 古田紹欽 / p26~35
けんいにまけるな(佛祖のことば) / 塩入良道 / p36~36
じようどにむまる(先徳のあゆみ) / 石上善応 / p37~37
某月某日 / 立花大亀 / p17~17
某月某日 / 柳宗悦 / p31~31
人間親鸞 / 藤島達朗 / p38~44
戒と律 / 平川彰 / p8~13
|
天竜山の仏頭(仏像鑑賞) / 北川桃雄 / p7~7
ならく(仏教語の解説) / R / p25~25
尼僧物語について(仏教問答) / tun / p54~55
正法眼蔵のこころ(11)辨道話 / 増水霊鳳 / p48~52
現代語訳根本仏教経典(3)伝道の決意をかたる諸経 / 増谷文雄 / p56~59
丸の内だより / 加藤辨三郎 / p45~4
新刊紹介 / 長田恒雄 / p53~53
赤色赤光・自色白光(読者だより) / p62~63
在家仏教 分会だより・在家仏教ニュース / p60~61
在家仏教刊行図書案内 / p46~47
在家仏教講演会案内 / p64~64
・ |
3月、「墨美 (95) 」が「墨美社」から刊行される。 pid/2362638
|
(略)
白隠筆 梵字 / / 5~5
白隠筆 山青一行 / / 5~5
白隠筆 燈影一行 / / 6~6
遂翁筆 寒山指月 / / 6~6
豪潮石寿像 堅山南風スケッチ / / 6~6
仙厓筆 湘南秋竹 / / 6~6
仙厓筆 芦蟹横行 / / 6~6
|
独湛筆 凉生一行 / / 7~7
白隠筆 名号 / / 7~7
慈雲筆 名号 / / 8~8
白隠筆 円相 / / 10~10
慈雲筆 円相 / / 10~10
珍牛筆 喫茶去図 / / 11~11
珍牛筆 永祖行実建撕図絵 / / 11~11
珍牛筆 牧牛図 / / 12~12
|
雲華筆 雲開一行 / / 12~12
雲華筆 懸崖垂珮図 / / 13~13
豪潮作 茶碗 / / 14~14
豪潮作 宝篋印塔 / / 15~15,16~16
豪潮律師の墨蹟 / 西村南岳 / 2~13
豪潮律師 / 後藤是山 / 13~16
豪潮律師の書 / 堅山南風 / 14~15
・ |
4月、「在家佛教 (73)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6063755
|
表紙 法隆寺釈迦尊 / 入江泰吉
降誕会(詩) / 長田恒雄
仏の微笑 / 鈴木大拙 / p2~4
親鸞の社会観 / 外村繁 / p4~6
白隠禅師とその画讃 / 柴山全慶 / p8~8
戦国武将と宗教 / 海音寺潮五郎 / p32~40
本願真実 / 曽我量深 / p20~30
こころをきよめる(仏祖のことば) / 田村完誓 / p46~46
げんざいいちねん(先徳のあゆみ) / 小島竹田 / p47~47
某月某日 / 久保田正 / p11~11
某月某日 / 若杉慧 / p23~23
大和古寺抄(1)法隆寺今古 / 北川桃雄 ; 入江泰吉 / p16~19
日常生活と真宗 / 金子大栄 / p41~43 |
きえん(仏教語の解説) / R / p7~7
戦争と仏教(仏教問答) / tun / p54~55
正法眼蔵のこころ(12)生死の巻 / 増永霊鳳 / p48~52
現代語訳根本仏教経典(4)最初の説法を語る諸経 / 増谷文雄 / p56~59
五合庵の庭(仏教説詰) / p35~35
ある商人(仏教説詰) / p37~37
丸の内だより / 加藤辨三郎 / p53~53
新刊紹介 / 長田恒雄 / p31~31
赤色赤光・白色白光(読者だより) / p62~63
在家仏教分会だより・在家仏教ニュース / p60~61
在家仏教刊行図書案内 / p44~45
在家仏教講演会案内 / p64~64
・ |
7月、「 禅文化 (19)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082220
|
表紙 白隱禪師壽 解説 / p2~2
グラフ 白隱禪師および弟子の墨跡 / p3~3,6~10
グラフ 還暦の山田无文老師近影 / p51~51
グラフ 『ながしま』 (無文老師短歌墨跡) / p52~52
無門關新講 兜率三關 (第四十七則) / 山田无文 / p12~16
晋山上堂法語 / 柴山全慶 / p17~23
禪の理解 / 柴山全慶 / p24~30
禪畫に見る白隱 / クルト・ブラッシュ / p31~44
醫学禪 / 長谷川卯三郎 / p53~68 |
ずいひつ 光の中の仏像 / 藤本浩一 / p78~84
渡宋天神考 / 横山文綱 / p69~77
香道史抄 (二) / 一色梨郷 / p49~48
還暦をむかえた無文老師 / p49~50
新刊紹介 「父母恩重經講話」 / 鎌田禪商 / p68~68
南宗寺の石庭復原成る / p48~48
扉 「唐きびと還暦偶感」 / 山田無文 / p11~11
編前編後 / p85~85
・ |
11月、山田無文が「坐禅和讃講話」を「妙心寺派宗務本所花園会本部」から刊行する。 pid/2968693
11月、「墨美 (102)」が「墨美社」から刊行される。 pid/2362645
|
部分図 / / 1~12
澤庵筆 1点 / / 26~26
一絲筆 8点 / / 27~30
雲居筆 1点 / / 31~31
風外筆 5点 / / 31~33
白隠筆 36点 / / 34~53
仙厓筆 12点 / / 54~60
遂翁筆 3点 / / 60~61 |
東嶺筆 6点 / / 62~64
欧洲禅画展 / クルト・ブラッシュ / 14~15
スイスに於ける日本禅画展の感想 / ブラッシュH. / 16~18
日本禅画の成立とその精神 / ローゼ・ヘンペル / 19~19
日本の禅とその絵画的表現--日本禅画展カタログ序文 / グリースマイエルV. / 20~23
新聞評から / / 23~25
欧洲禅画展目録 / / 16~17
・ |
12月、土屋常義が「岐阜大学学芸学部研究報告. 人文科学 (通号 9) p.96~108」に「岐阜県における白隠の足跡」を発表する。
○、この年、伊藤和男が「白幽子 : 史実の新探求」を「山口書店」から刊行する。 pid/2968282
|
序文
はしがき
前篇/p1
序/p2
一 白幽子傅の資料/p6
〔一〕 白幽子の靈名記/p7
〔二〕 白幽子の眞蹟/p9
〔三〕 白幽子の墓碑/p11
二 巷間の白幽子傅/p12
〔一〕 畸人傅/p12
〔二〕 玄同放言/p14
〔三〕 藤井象水/p17
〔四〕 本朝神仙記傅/p18
三 禪門内の白幽子傅/p19
四 丈山と白幽子との師弟關係/p21
五 年表/p26
中篇/p30
序/p31 |
白幽子傅の資料/p33
〔一〕 藤井象水撰「白幽子傅」/p34
〔二〕 宣遊草/p36
〔三〕 落栗物語/p37
〔四〕 譚海/p38
〔五〕 本朝神仙記傅/p40
〔六〕 西遊記/p42
〔七〕 梧窓漫筆(ごそうまんぴつ)/p43
〔八〕 良寛と白幽子傅/p44
〔九〕 其他の資料二三/p48
畸人傅所載の眞蹟について/p49
後篇/p51
一 新資料(史實・眞蹟・墓碑)/p52
〔一〕 峨山撰「白隱禪師略行状」/p52
〔二〕 白川地志/p53
〔三〕 眞蹟「七律詩」/p53
〔四〕 眞蹟「三社託宣」/p56
〔五〕 眞蹟「和歌一首」/p57 |
〔六〕 眞蹟「分得麻姑」/p58
〔七〕 眞蹟「生死事大」/p59
〔八〕 眞蹟「眞」/p59
〔九〕 人物百談/p59
〔一〇〕 墓碑/p60
〔一一〕 如意自晝賛/p60
二 思想/p61
〔一〕 〔ナン〕酥の法/p61
〔二〕 心統一法の起源/p66
〔三〕 白幽子の思想/p68
三 隱逸の宗敎性/p70
〔一〕 寒山の言葉/p72
〔二〕 白隱の言葉/p72
〔三〕 ソーローの言葉/p74
写真
(1)「白幽子靈名記」
(2)「白幽子箴」
(3)「七律詩」 |
(4)「儉」
(5)「眞」
(6)「和歌一首」
(7)如意自晝賛
(8)玉光明
(9)「三社託宣」
(10)「謹志箴」
(11)鐵齊筆「白幽子像」
(12)白隱禪師訪白幽子圖
(13)白幽子窟前の茶會
(14)「墓碑」
カット 白幽子款印「慈」
附録 夜船閑話/p77
あとがき/p92
・
・
・
・ |
○、この年、山本玄峰が「無門関提唱」を「大法輪閣」から刊行する。 pid/2968688
|
関 玄峰老師 筆
ぬらりくらり 玄峰老師 筆
穏坐(般若窟にて)
読経(終日金剛経を敬誦)
提唱(講座にて私註本無門関を開く)
長養(隠寮の手摺より庭前を見る)
寿譜
自序 禅宗無門関/p1
第一則 趙州狗子/p14
第二則 百丈野狐/p31
第三則 倶胝竪指/p48
第四則 胡子無鬚/p61
第五則 香厳上樹/p74
第六則 世尊拈華/p88
第七則 趙州洗鉢/p107
第八則 奚仲造車/p117
第九則 大通智勝/p121
|
第十則 清税孤貧/p130
第十一則 州勘庵主/p142
第十二則 巌喚主人/p150
第十三則 徳山托鉢/p162
第十四則 南泉斬猫/p173
第十五則 洞山三頓/p180
第十六則 鐘声七条/p191
第十七則 国師三喚/p203
第十八則 洞山三斤/p212
第十九則 平常是道/p220
第二十則 大力量人/p228
第二十一則 雲門屎□/p236
第二十二則 迦葉刹竿/p242
第二十三則 不思善悪/p251
第二十四則 難却語言/p283
第二十五則 三座説法/p293
第二十六則 二僧巻簾/p302 |
第二十七則 不是心仏/p312
第二十八則 久響竜潭/p320
第二十九則 非風非幡/p342
第三十則 即心即仏/p352
第三十一則 趙州勘婆/p362
第三十二則 外道間仏/p373
第三十三則 非心非仏/p382
第三十四則 智不是道/p390
第三十五則 倩女離魂/p395
第三十六則 路逢達道/p407
第三十七則 庭前柏樹/p412
第三十八則 牛過窓櫺/p418
第三十九則 雲門話堕/p426
第四〇則 □倒浄瓶/p434
第四十一則 達磨安心/p443
第四十二則 女子出定/p454
第四十三則 首山竹箆/p461 |
第四十四則 芭蕉挂杖/p465
第四十五則 他是阿誰/p467
第四十六則 竿頭進歩/p470
第四十七則 兜率三関/p478
第四十八則 乾峯一路/p487
黄竜三関/p492
あとがき/p497
附 白隠禅師臘八示衆提唱
朔日夜/p10
第二夜/p26
第三夜/p39
第四夜/p55
第五夜/p66
第六夜/p79
第七夜/p94
・
・ |
|
| 1961 |
36 |
・ |
1月、「禅文化 [6](1)(21)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082222
|
(表紙) 白隱禪師「牧牛圖」(部分)--解説 / p2~2
グラフ 丑歳の老大師般若窟近影 / p3~3
グラフ 白隱禪師・弘巖和尚・廣道等筆「牛」 / p4~5
グラフ 大和繪「駿牛圖」(部分) / p5~5
グラフ 越溪和尚賛陳素筆「牛」 / p5~5
グラフ 木庵・文應・頑極和尚墨跡 / p6~7
グラフ 仙厓作(塑像)「天神像」 / p8~8
グラフ 中川宋淵老師俳句「冬仕度」 / p9~9
グラフ 日展出陳作品「無門關より」(二點) / p9~9
解説 / p83~83
丑歳特集(1)關精拙老師筆「十牛圖」=Picture of Ten Oxen. / p11~11
無門關新講(第17講)倶胝竪指=Articles:"Gutei's Answer by Erecting
→His Finger." the 3rd chapter of Mumonkan. / 太室無文 / p14~21
般若窟玄峯老師頌 / 太室 / p3~3
太室老師香語 / p61~61
禪畫に見る「円相」の畫=Articles:Pictures of"Circularity"as a Symbol of
→Enlightenment in Zen Drawings. / クルト・ブラッシュ / p22~32
退藏院の方丈畫と渡邊了慶=Articles:Taizoin Priest's Chamber and
→Ryokei Watanabe. / 土居次義 / p42~47
佛教學・日本學軍事史の泰斗 ルノンドー將軍=Articles:General
→Renondeau,A Famous Scholer on Buddhism. / 柴田增實/p36~41
香道史抄(四)=Articles:Extracts from the History of Smelling
→Incense(4) / 一色梨郷 / p33~35
精進料理の解剖=Articles:Analysie of a Vegetable Diet.
→(Abstinence from flesh) / 長谷川卯三郎 / p48~55
|
ずいひつ 「鯉」=Short Pieces: The Carps. / 福田平八郎 / p63~65
ずいひつ 禪のムード=Short Pieces:Zen Mood. / 大井際斷 / p56~57
ずいひつ 一休の不覺=Short Pieces:Master I
→kkyu's Mistake. / 聽松山人/p57~58
ずいひつ 「愚堂見て歩る記」後記=Short Pieces:Supplements of the
→Tour on Gudo's Handwritings. / 高津文郁 / p58~59
ずいひつ 鷄の五德=Short Pieces:Five Virtues of A Cock. / 横山文綱 / p60~60
ずいひつ 俳句「初鏡」=Haiku:A New Year's Mirror. / 宇都千賀女 / p58~58
ずいひつ 句と文「老師て若いのやネ」=Haiku:He's Young,though
→ They Call Him,"Old Master!". / 一灯園姉水 / p59~59
ずいひつ 歌「正月のうた」=Uta:Songs of A New Year. / 井伊文子 / p56~56
ずいひつ 漠詩「拜觀愚堂和尚墨跡展」=Chinese Poem:Seeing Gudo's
→Handwritings Exhibition. / 淡川康 / p59~59
學長無文老師のご訪印 / p21~21
新刊紹介 「坐禪和讃講話」 / p82~82
新刊紹介 「土は生きている」 / p35~35
丑歳特集(2)『うしかひ草』 / p66~66
『宇しかひ草」について=On"Ushikaigusa." / 柴山全慶 / p67~70
宇しかひ草(全)=Ushikaigusa-A Book on Twelve
→Oxherds,Written in Kana.(Full Text) / p71~82
扉「うしどしのはる」 / 太室 / p13~13
“禪ピクトリアル”(秋日和) / p60~60
第六卷バックナンバー / p84~85
禪文化研究會の趣意と略規 / p87~87
・ |
3月、「禅文化 [6](2)(22)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082223
|
(表紙) 「残雪の石庭」 岡本東陽撮影 / 橫山文綱 / p2~2
グラフ 龍安寺古圖(1)傳相阿彌筆 義天玄紹禪師頂相 義天禪師と
→細川勝元の塔所 龍安寺庫裡 龍安寺石庭 義天和尚關係寺院/p2~6
グラフ 龍安寺知足のつくばい 龍安寺古圖(2)原在厚筆/p101~101,102~102
グラフ 禪園誌上美術館(2)細川昭元夫人像(龍安寺藏) / p9~9
グラフ 今日の墨跡(2)鎌倉圓覺寺 朝比奈宗源老師 / p11~11
グラフ 本文參照寫眞(義天和尚頂相・ハワイにおける北米開敎使・
→座談會スナツプ) / p10~10
無門關新講(第18講)世尊拈花 / 山田无文 / p14~24
海南流寓の東坡居士 / 藤林廣超 / p77~82
求む!ZEN宗匠>座談会< / p66~74
特集 龍安寺義天玄紹禪師 / 荻須純道 / p25~31
特集 白い庭苑 / 中村直勝 / p32~36
特集 義天和尚の法語と詩偈 / 木村黙宗 / p38~49
特集 短歌 龍安寺石庭 / 川田順 / p37~37
特集 俳句 龍安寺 / 山口誓子 / p51~51
特集 石庭と兄德兵衛 / 花柳德三尾 / p49~50
特集 義天さんの墓 / 木村靜雄 / p52~52 |
特集 細川昭元夫人像(禪園誌上美術館解説) / 森暢 / p64~65
特集 竜安寺こぼれ話 / p75~76
特集 庭師の名 / p65~65
特集 東漸行=北米開敎記録抄 / 松倉紹英 / p53~63
精進料理の解剖(2) / 長谷川卯一郞 / p91~93
香道史抄(5) / 一色梨郷 / p83~86
孤獨の隣人ソーロー(下) / 伊藤和男 / p87~90
随筆 訪中公演の想出 / 中村翫右衛門 / p94~95
随筆 一圓相 / 大森曹玄 / p96~97
随筆 經濟と禪 / 山本信吾 / p97~99
随筆 白隠さんの坐禪和讃 / 宮地富子 / p99~99
随筆 俳句「涅槃像」 / 大鶴直道 / p97~97
随筆 晩秋訪龍安精舎(漢詩) / 淡川康一 / p98~98
新刊・名著紹介・「白幽子」 / p82~82
「慈雲尊者」 / p93~93
「大正新脩大蔵經」 / p86~86
扉 紀のくにの海 / 太室 / p13~13
編前編後 / p100~100 |
7月、「伊那 9(7)(398) 」が「伊那史学会」から刊行される。 pid/4431234
|
口絵 白隠禅師筆坐禅自画像 / 宮下操
内輪助伝馬 / 平沢清人/p1~6
伊那谷南山地方の猪鹿防除(一) / 千葉徳爾/p6~12
前林発見の瓦塔について / 大沢和夫/p13~15
天竜峡の古いこと新しいこと(六) / 関島久雄/p15~21
|
伊那盆地の地形紹介(2)断層鞍部 / 三浦宏/p21~23
長野県文化財保護関係について / 宮下操/p23~25
伊那の石文を尋ねて(二九) / 牧内雅博/p26~28
お船一件 / 下平加賀雄/p28~31
樽拾い / 小塩緑郎/p31~33 |
8月、宮地富子が「禅文化 [6](2)(22)p99~99 禅文化研究所」に「随筆 白隠さんの坐禪和讃 」を発表する。 pid/6082223
9月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (276)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281487
|
須恵器――特に吉備の須恵器について / 鎌木義昌/p2~4
吉備の装飾須恵器をめぐって 座談 / A・B・C・D/p5~8
釉の色について / 内藤匡/p9~12
ちゃわん抄-152- / 加藤義一郎/p13~17
黄檗と臨済--随縁遊墨-34- / 中村余容/p18~22
安親の鐔-2- / 中村鉄青/p23~27
石と語る / 小林宗一/p28~30
蓑半農軒氏--愛蔵弁あり-86- / 邑木千以/p31~37
短冊覚え書-52- / 多賀博/p38~43 |
群馬発掘の古瀬戸瓶子 / 菊田清年/p44~58
白幽子の書について / 伊藤和男/p62~63
俳画指導(89) / 赤松柳史/p66~67
石皿と油皿 / 瀬良陽介/p60~61
九月・関西の美術館/p65~65
「友太郎の赤」と「永仁の壷」/p68~68
新刊紹介-今日庵歴代好み物集/p64~64
読者の声/p64~64,p65~65
編集室/p68~68 |
10月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (277) 」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281488
|
衣浦観革--日本一,瓦の仏像 / 小林宗一/p2~6
菊によって陶公を偲ぶ--随縁遊墨-35- / 中村余容/p7~10
ちゃわん抄-153- / 加藤義一郎/p11~14
釉の色について-2- / 内藤匡/p15~21
短冊覚え書-53- / 多賀博/p22~28
初期古瀬戸-1- / 菊田清年/p29~36
高岡市美術館--続・美術館めぐり-5- / 村松寛/p37~43
白幽子について(補遺) / 伊藤和男/p44~45 |
天命釜の鑑賞 / 細見古香庵/p46~50
俳画指導(90) / 赤松柳史/p52~53
古瀬戸瓶子の底作りについて/p51~51
新刊「古備前名品図譜」について/p54~54
十月・関西の美術館/p55~55
逸翁美術館第14回特別展列品目録/p56~57
ニセものめきき / 田子依/p58~58
編集室/p58~58 |
11月1日~11月12日迄、上野松坂屋に於いて「白隠・仙崖・円空・木喰展 : 近世異端の芸術」展が開かれる。
11月、「白隠・仙崖・円空・木喰展 : 近世異端の芸術(図録)」が「日本経済新聞社」から刊行される。
主催:日本経済新聞社 所蔵:横浜市立図書館
11月、本美術工芸社編「日本美術工芸 (278)」が「日本美術工芸社」から刊行される。pid/2281489
|
文房清玩(1)--随縁遊墨-36- / 中村余容/p3~7
洋画家の消息集覧-4- / 喜田幾久夫/8~15
ちゃわん抄-154- / 加藤義一郎/p16~19
釉の色について-3- / 内藤匡/p20~25
陳元贇陶製仏像 / 小林宗一/p26~28
短冊覚え書-54- / 多賀博/p29~33
白幽子と鉄斎--付・白幽子と貝原益軒 / 伊藤和男/34~39
石川県美術館--続・美術館めぐり-6- / 村松寛/p40~48 |
中村鉄青氏著「和鏡の研究」について / 細見古香庵/p49~54
祖母懐土の茶わん――矢野陶々のことども / 加藤増夫/p56~57
美術おおさか――パリの魅力 / 杉本亀久雄/p58~59
俳画指導(91) / 赤松柳史/p60~61
鼠鬚筆の賦/p7~7
穴がま/p15~15
十一月・関西の美術館/p55~55
編集室/p39~39,p62~62 |
12月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (279)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281490
|
初期古瀬戸-2- / 菊田清年/p2~11
短冊覚え書-55- / 多賀博/p12~17
ちゃわん抄-155- / 加藤義一郎/p18~23
中村不折--洋画家の消息集覧-5- / 喜田幾久夫/24~30
文房清玩(2)--随縁遊墨-36- / 中村余容/p31~35
伝統工芸展の陶芸・雑音 / 上口愚朗/p36~41
エジプト雑感 / 杉本亀久雄/p42~43
石に学ぶ / 小林宗一/p44~47
白幽子の墨跡 / 伊藤和男/p48~50 |
ヨーロッパ古美術の印象 / 細見実/p51~57
俳画指導(92) / 赤松柳史/p58~59
菊日和古香庵の懸釜――淡交会協賛 / 邑木千以/p60~61
「ようわんの夢」/p23~23
新刊紹介「古筆と短冊」(第六号)/p47~47
愚朗天宿断信/p41~41
十二月・関西の美術館/p57~57
編集室/p62~62
・ |
○、この年、「古典日本文学全集 第15 (仏教文学集)」が「筑摩書房」から刊行される。 pid/1661314
|
仏教文学集
〔最澄〕
発願文 勝又俊教訳 / 7
山家学生式 〃 / 9
顕戒論 〃 / 14
〔空海〕
三教指帰 渡辺照宏訳 / 24
〔円仁〕(慈覚大師)
入唐求法巡礼行記 堀一郎訳/58
〔源信〕
往生要集 堀一郎訳 / 82
〔法然〕
選択本願念仏集 増谷文雄訳/112
登山状 〃 / 127
念仏問答 〃 / 138
一枚起請文 〃 / 143
〔親鸞〕
正信念仏偈 増谷文雄訳/145
和讃 〃 / 148
|
書簡 〃 / 155
歎異抄 〃 / 163
〔日蓮〕
立正安国論 堀一郎訳 / 173
佐渡御書 〃 / 191
種種御振舞御書 〃 / 198
〔一遍〕
消息法語 増谷文雄訳 / 212
〔蓮如〕
御文 増谷文雄訳 / 217
〔明恵〕
阿留辺幾夜宇和 古田紹欽訳/222
(明恵上人遺訓)
〔南浦紹明〕
大応仮名法語 古田紹欽訳 / 226
〔瑩山紹瑾〕
瑩山仮名法語 古田紹欽訳 / 232
〔夢窓疎石〕
夢窓仮名法語 古田紹欽訳 / 234
|
夢中問答 〃 / 235
〔宗峯妙超〕
大燈仮名法語 古田紹欽訳/240
大燈国師遺誡 〃 / 248
〔拔隊得勝〕
塩山仮名法語 古田紹欽訳/249
〔沢菴宗彭〕
不動智神妙録 古田紹欽訳/254
東海夜話 〃 / 257
〔鈴木正三〕
驢鞍橋 古田紹欽訳 / 260
〔盤珪〕
盤珪禅師語録 古田紹欽訳/266
〔白隠慧鶴〕
坐禅和讃 古田紹欽訳 / 273
遠羅天釜 〃 / 274
於仁安佐美 〃 / 279
〔慈雲尊者飲光〕
人となる道 古田紹欽訳/281
|
十善戒相 〃 / 282
詩偈 西谷啓治訳 / 284
(大応・夢窓・大燈・寂室)
一言芳談 小西甚一訳/324
梁塵秘抄 〃 / 347
解説 唐木順三 / 359
文学上に於ける弘法大師
→幸田露伴 / 378
法然の生涯 倉田百三/388
親鸞の語録について
→亀井勝一郎 / 415
「立正安国論」と私
→上原専禄/423
日本の文芸と仏教思想
→和辻哲郎 / 434
付録 (語彙・主要経典) / 453
・
・
・ |
|
| 1962 |
37 |
・ |
1月、「禅文化 6(4)(24) 」が「禅文化研究所」から」刊行される。 pid/6082225
|
グラフ 「土」…(大津櫪堂老師筆) 勅題歌……近藤文光老師 古川大航老師近影・墨跡
植木憲道老師近影・
→墨跡 春叢和尚筆・冨士山図並賛=Graphs: A matchless pair in modern
Japanese Zen
無門關新講 第20講 徳山托鉢=Articles: Special Discourse on the Mumonkan,
Chap.
→XIII: "Master Tokusan Carries a Bowl." / 太室无文/p2~8
禅の虎談義=Articles: An Essey Associated with Tiger-Year / 柴山全慶/p25~27
寒山拾得に於ける二重人格=Articles: The Double Character of
→"Kanzan and Jittoku", Chinese Hermits / 淡川康一/p31~39
臨済義玄の人と時代=Articles: Master Rinzai Gigen: The Man and His Age / 柳田聖山/p9~23
白隠と無量寺=Articles: On Hakuin's Participation in Muryoji Temple / 秋山寛治/p48~58
香道史抄=Articles: The Extracts from the History of Smelling Incence / 一色梨郷/p28~30
土 / 高柳徳宝/p8~8
禅寺巡札・国泰寺=Articles: "Kokutaiji Temple"; The pilgrimage
Through Zen Temples (I) / 大石守雄/p40~41
大航・憲道両老師の寿幅/p39~39
白幽子墨跡踏査の記=Articles: A Report from the Exploration of Hakuyshi's
Writings / 伊藤和男/p42~47
新刊紹介 訓註「臨済録」 / 柳田聖山/p47~47
新刊紹介 「心理禅」 / 佐藤幸治/p47~47
|
3月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 39(3)(470)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885348
|
白隠和尚より無着道忠和尚へ宛てたる手紙について / 陸川堆雲/p3~11
現代語訳 臨済録(1) / 篠原寿雄/p12~18
宗教とは(5) / 井上大智/p18~19
趙州録の上梓について / 鈴木大拙/p20~22
趙州録の校訂と国訳の事に当つて / 秋月竜珉/p23~26 |
趙州録提唱(3) / 井上義光/p27~29
曹洞禅二三の問題(11) / 井上耕哉/p30~33
禅界時報 / 飯塚定香/p34~35
編集後記 / 秋月竜珉/p36~36
・ |
3月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (282)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281493
|
ルイジアーナ現代美術館(一)私の見た欧州 / 十河巌/p2~6
酸化第一鉄と青磁 / 内藤匡/p7~22
ちゃわん抄-157- / 加藤義一郎/p23~27
西王母と麻如--随縁遊墨-38- / 中村余容/p28~30
短冊覚え書-57- / 多賀博/p31~36
「日本名陶」をきる / 上口愚朗/p37~43
円空のそりかえる薬師如来 / 土屋常義/p44~46
円空仏写真譜一 / 後藤英夫/p47~50 |
白幽子墨跡たずねある記 / 伊藤和男/p51~55
俳画指導(95) / 赤松柳史/p56~57
三月・関西の美術館/p22~22
フランス美術展/p36~36
円空仏のその後/p46~46
画廊炎上/p58~58
編集室/p58~58
・ |
3月、禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky?" (52)」が「禪學研究會」から刊行される。 pid/4414838
|
妙心寺の開創について / 荻須純道/p1~10
蔭凉寺と白隱及關係の人々 / 陸川堆雲/p11~28
臨濟録ノート / 柳田聖山/p29~68
日本禪宗寺院に關する考察(2) / 大石守雄/p69~75
佛敎に於ける戰爭體驗(4) / 市川白弦/p76~132
呪術論 / 稻岡順雄/p133~149 |
メーグハシュリー比丘の法門 / 小林圓照/p150~172
大般若經の民俗信仰について / 橘恭堂/p173~183
書評 //p184~186
彙報 //p187~191
On Hakuin's "Commentary and Poems on Prajn
→Pramit-hridaya-stra"(1) / Eshin Nishimura/p200~193 |
4月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (283)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281494
|
わたしの見た欧州-2- / 十河巌/p3~8
馬地文釜の研究と発見 / 細見古香庵/p9~14
ちゃわん抄-158- / 加藤義一郎/p15~19
無文禅師--随縁遊墨-39- / 中村余容/p20~23
短冊覚え書-58- / 多賀博/p24~29
愛蔵弁あり-88- / 邑木千以/p30~36
円空上人伝-3- / 小林宗一/p37~40
沙魚壺(はぜつぼ)後日譚 / 加藤増夫/p41~43
|
「夜船閑話」と健康法--白幽子・白隠・良寛・益軒 / 伊藤和男/44~48
たくましい日本の文化 / 杉本亀久雄/p49~49
逸翁美術館春季特別展列品目録/p50~51
俳画指導(96) / 赤松柳史/p52~53
佐野乾山について / 上口愚朗/p23~23
四月・関西の美術館/p54~54
藤田美術館・大和文華館の春の展観/p43~43
編集室/p54~54 |
4月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 39(4)(471)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885349
|
随想 / 辻村公一/p2~3
現代語訳 臨済録(2) / 篠原寿雄/p4~7
永平頌古提唱(11) / 橋本恵光/p8~11
かれと我れ / 小林大信/p12~14
続挫折と転向(5) / 市川白弦/p15~18
曹洞禅二三の問題(12) / 井上耕哉/p18~21
|
趙州録提唱(4) / 井上義光/p22~25
宗教とは(6) / 井上大智/p25~26
松源録秘鈔(21) / 中島鉄心/p27~29
青い空のもとに(3) / 海童道宗祖/p30~32
続漢文典(17) / 松本如石/p33~35
編集後記 / 飯塚定香/p36~36 |
5月、竹内尚次が東京国立博物館編「Museum (通号 134) p.8~14」に「白隠ノート」を発表する。
7月、陸川堆雲 が「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 39(7/8)(474) p3~11 中央仏教社」に「※白隠和尚坐禅和讃に対する 盲信的礼讃と誤解を排す」を発表する。 pid/7885352 ※内容についての検討要 2023・1・10 保坂
8月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (287)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281498
|
伊吹山の11面観音 / 土屋常義/p2~5
伊吹山太平寺--円空上人考-1- / 小林宗一/p6~9
円空と木喰--短冊おぼえ書き-60- / 多賀博/p11~15
根来(ねごろ)について-3- / 細見良/p16~20
中国絵画の分宗-上- / 中村よう/p21~26
東京の土など--「新・佐野乾山」をつく / 上口愚朗/p27~32
スコットランド国立美術館(エディンバラー)--わたしの
→見た欧州-5- / 十河巌/p33~40
赤絵の説-1- / 米内山庸夫/p41~45
和田英作--洋画家の消息集覧-8- / 喜田幾久夫/46~52 |
白幽子は丈山の甥である / 伊藤和男/p53~54
茶わん閑日(1) / 櫟心居/p55~59
俳画指導(99) / 赤松柳史/p60~61
円空仏 薬師 / 土屋常義/p10~10
円空上人のお稲荷さま / 小林宗一/p10~10
名物本所載の茶わん数/p20~20
八月・関西の美術館/p20~20
新・佐野乾山についての追加 / 愚朗/p40~40
《佐野乾》問答/p62~62
編集室/p62~62 |
10月、日本美術工芸社編「日本美術工芸 (289)」が「日本美術工芸社」から刊行される。 pid/2281500
|
宇治白川--京阪神カメラ紀行 / 熊野紀一/p3~10
赤絵の説-2- / 米内山庸夫/p11~14
桃山時代室内装飾金具誌上展(二) / 細見古香庵/p14~18
志野釉の研究 / 上口愚朗/p19~24
画廊を見て,エスカルゴも食べて・パリ--わたしの
→見た欧州-7- / 十河巌/p26~30
維新百年--短冊おぼえ書き / 多賀博/p31~35
赤織不小鳥文平(3)茶わん閑日 / 櫟心居/p36~39 |
邯鄲夢の枕-1- / 中村よう/p40~44
続・白幽子と鉄斉--付白幽子墨跡・白幽子とソーロー/伊藤和男/p46~51
逸翁美術館第16回特別展列品目録 //p52~53
俳画指導(101) / 赤松柳史/p54~55
漢詩入門講座(一)中村餘容先生指導 //p44~45
小山冨士夫著「日本の陶磁」 //p25~25
十月・関西の美術館 //p51~51
編集室 //p56~56 |
10月、「 大乗禅 = The mahayana zen buddhism 39(10/11)(476) 」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885354
|
正受禅の提唱 / 秋月龍珉/p3~3
正受老人崇行録 / 今北洪川/p4~9
臨済正宗思想の打破と嗣法嫡旁観の無意義 / 陸川堆雲/p10~16,38~38
名声(短歌) / 正富汪洋/p17~17
原田祖岳老師の霊前に / 今成覚禅/p18~23,29~29
現代新葛藤集(20) / 島田春浦/p24~29
趙州録提唱(8) / 井上義光/p30~33
松源録祕鈔(24) / 中島鉄心/p34~38
いろは法語(3) / 井上大智/p39~39
かく味う(良寛の詩歌) / 小林大信/p40~45 |
無情説法(1) / 井上耕哉/p46~52
坐禅和賛につき再言 / 陸川堆雲/p52~53
現代語訳臨済録(6) / 篠原寿雄/p54~57
唐津青年僧グループ / 広高正道/p58~61
続漢文典(19) / 松本如石/p62~64
読者の声/p65~65
禅界時報 / 飯塚定香/p66~66
施本広告/p67~67
編集後記 / 珉/p68~68
・ |
10月、岐阜県立図書館に於て、県内作品42点を集めた白隠に関する展覧会が開かれる。
出展:土屋常義著「白隠と岐阜県p3」より 開催期間日時・展覧会名については不明
11月、古田紹欽が「白隠 : 禅とその芸術」を「二玄社」から刊行する。 pid/2968281
|
序
白隠が白隠になるまで / p9
白隠の禅
禅の真実性の追求 / p21
孤危嶮峻と世俗性 / p28 |
禅と学問の間 / p38
禅と念仏 / p55
「坐禅和讃」のこと / p73
白隠の芸術
禅を画く / p89 |
達磨図 / p113
臨済・大證の画像 / p119
自画像 / p126
戯画の中の禅 / p140
逸格の書 / p146 |
最晩年の白隠 / p162
あとがき
・
・
・ |
12月、山田無文が「白隠禅師坐禅和讃講話」を「春秋社」から刊行する。 pid/2968710
12月、「 大乗禅 = The mahayana zen buddhism 39(14)(479)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885355
|
巻頭言 / 大森曹玄/p3~3
自称法王氏に答える / 佐藤幸治/p4~6
無情説法(2) / 井上耕哉/p6~9
祖岳老師の霊前に(2) / 今成覚禅/p10~14
松源録祕鈔(25) / 中島鉄心/p15~17
現代新葛藤集(完) / 島田春浦/p18~19 |
かく味う(良寛の詩歌)(2) / 小林大信/p20~23
現代語訳臨済録(7) / 篠原寿雄/p24~27
趙州録提唱(9) / 井上義光/p28~30
続漢文典(20) / 松本如石/p31~33
禅界時報 / 飯塚定香/p34~35
編集後記 / 秋月竜珉/p36~36 |
○、この年、陸川堆雲が「夜船閑話 : 評釈」を「山喜房仏書林」から刊行する。 pid/2968709
|
口画写真
一、白隠禅師木像
二、夜船閑話(初板)
三、白幽子像 近世畸人伝所載
四、謹志箴 関西大学蔵
五、謹志箴 近世畸人伝所載
六、白幽子七言詩 関西大学蔵
七、白幽子八分の書
八、白幽子釈迦成道の詩自画賛
九、霊名記(乗願院過去帳)
十、乗願院
十一、白幽子石塔(芝の墓)
十二、白幽子石塔(法輪寺)
十三、白幽子隠対面図
十四、白幽子巌居の趾
十五、右巌前に立てる後藤伊山師
十六、仝 著者
自序/p1
例言/p3
第一章 夜船閑話の序/p10
書中多く気を練り/p12
諸子訂正伝写/p16
我に仙人還丹の秘訣あり/p24
我が此の気海丹田/p25
老僧初め参学の時難治/p29
此に於て真正参玄の上土/p34
稿中何の説く処ぞ/p37
|
第二章 夜船閑話本文/p41
或人曰く城の白川/p45
予則ち礼を尽くして/p50
内観の要秘を聞かん/p54
是の故に漆園曰く/p61
昔し呉契初石台先生/p67
是れ相火上り易き/p79
蓋し繋縁諦真の二止/p86
彭祖が曰く/p92
又蘇内翰が曰く/p93
走始め/p101
徐々として洞口を下る/p105
第三章 意訳口語夜船閑話/p113
第四章 余説及白幽子伝の新研究/p137
第一節医学参照文献の概要
(一)素問霊枢 黄帝 撰/p139
(二)医心方 丹波康頼 撰/p141
(三)支那医学史 陳邦賢 著/p142
(四)解体発蒙 三谷樸 著/p143
(五)日本医学史 冨士川游 著/p144
(六)日本衛生史 藤浪剛一 著/p144
(七)皇漢医話 久米嵓 著/p145
(八)医学文化年表 藤井尚久 著/p145
(九)その結び/p145
第二節白幽子伝参考文献/p147
(一)近世畸人伝及続篇 伴蒿渓 著/p147
(二)玄同放言 滝沢馬琴 著/p150 |
(三)白幽子(仙人) 橘南谿 著/p152
(四)白幽子伝 藤井象水 著/p155
(五)本朝神仙伝 宮地巌夫 著/p156
(六)白幽子 伊藤和男 著/p156
第三節白幽子伝の其他の資料/p157
(一)僧若霖について/p157
(二)石川丈山との関係/p162
(三)白幽子巌窟の今昔物語/p167
(四)白幽子谷に堕ちて死すこと/p172
(五)乗願院及芝の墓/p176
第四節白幽子は仮空の人か実在の人か/p178
A、白幽子伝の資料は余り多くない/p178
B、白幽子と白隠及び夜船閑話/p180
C、白幽子の実在と其の行衛/p180
第五節白幽子伝の概要要約/p181
第六節夜船閑話についてのいろ[イロ]/p183
(一)夜船閑話の注釈書/p183
(二)夜船閑話撰述の時期はいつであつたか/p184
(三)夜船閑話についての私見/p187
(四)夜船閑話の価値と其将来性/p189
(五)霊源和尚の手紙/p190
第七節白幽子の書との思想について/p192
白幽子関係地図/p196
第五章 白隠年譜草稿による夜船閑話の
→根拠の新発見/p197
あとがき/p202
・ |
○、この年、古田紹欽が「 白隠 : 禅とその芸術」を「二玄社」から刊行する。
pid/2968281
|
序
白隠が白隠になるまで / p9
白隠の禅
禅の真実性の追求 / p21 |
孤危嶮峻と世俗性 / p28
禅と学問の間 / p38
禅と念仏 / p55
「坐禅和讃」のこと / p73 |
白隠の芸術
禅を画く / p89
達磨図 / p113
臨済・大證の画像 / p119
|
自画像 / p126
戯画の中の禅 / p140
逸格の書 / p146
最晩年の白隠 / p162あとがき |
〇この年、今枝愛真が「禅宗の歴史」を「至文堂」から刊行する。 (日本歴史新書) pid/2969898
|
第一章 奈良平安時代禅宗の伝来
1 中国禅宗の興起 / p1
2 唐朝禅の摂取 / p3
3 宋朝禅の流入 / p7
第二章 鎌倉時代禅宗の興隆
1 兼修禅の勃興とその系譜/p13
栄西の黄竜派 / p15
円爾の聖一派 / p20
無本の法燈派 / p34
2 純粋禅の興隆とその系譜/p37
蘭溪の大覚派 / p41
兀菴の宗覚派 / p47
大休の仏源派 / p49
無学の仏光派 / p51
一山の一山派 / p57
東明の宏智派 / p60
清拙の大艦派 / p64
金剛幢下 / p65
明極と竺仙 / p66
禅宗と公武社会 / p69
第三章 五三派の展開
1 叢林と林下 / p72
|
2 五山機構の確立 / p73
安国寺の設置 / p73
五山 / p79
十刹 / p81
諸山 / p84
僧録の成立 / p108
蔭凉職 / p110
3 五山派の成立と
→その推移/p111
夢窓派の抬頭 / p111
春屋の登場 / p114
義堂と絶海 / p118
初期五山派 / p124
虎関と雪村 / p127
北山より東山へ / p129
中岩と夢岩 / p130
惟肖と厳中 / p133
瑞溪と希世 / p138
橫川と景徐 / p141
水墨画の流行 / p147
第四章 林下の形成と展開
1 曹洞教団の地方発展/p151
|
道元の思想とその特質/p151
初期教団の成立 / p158
三代相論 / p163
瑩山派の独立 / p163
仏慈禅師号問題 / p165
蛾山派の隆昌と全国的展開/p168
通幻派の発展 / p172
民衆化 / p178
江湖授戒会の流行 / p180
戦国大名との結合 / p181
永平寺の抬頭 / p183
日本曹洞第一道場 / p184
2 大応派の抬頭 / p188
大徳寺派の系譜 / p189
一休の気骨 / p192
妙心寺派の系譜 / p198
妙心寺の中絶 / p200
雪江とその門下 / p201
3 幻住派の勃興と
→臨在宗の統合/p209
一華碩由の登場 / p210
第五章 江戸時代禅宗の興起
|
1 明朝禅の伝来と
→その影響/p214
道者の教化 / p215
隠元とその門下 / p216
木菴と即非 / p219
2 曹洞宗の復興 / p222
ときのこゑ禅 / p223
月舟卍山の
→宗統復古運動/p225
天桂と面山 / p229
洞門の散聖 / p232
心越の来朝 / p234
3 臨済宗の進展 / p235
五山派の衰頽 / p235
大徳寺派の復活 / p236
妙心寺派の胎動 / p238
盤珪の不生禅 / p239
白隠による近代禅の成立/p242
隠山と卓洲 / p247
4 普化宗の抜扈 / p249
参考文献 / p252
索引 / p253
|
|
| 1963 |
38 |
・ |
1月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(1)(481)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885357
|
安那般那の法--数息観のすすめ / 中島鉄心/p4~7
兎歳新年賦 / 長尾大学/p25~25
家元思想に堕した現代の臨済禅界 / 陸川堆雲/p8~13
良寛の詩歌(3) / 小林大信/p14~17
永平頌古提唱(15) / 橋本恵光/p18~23
|
回顧録(上) / 島田春浦/p23~25
原田祖岳老師の霊前に(3) / 今成覚禅/p26~30
癸卯元旦賦 / 木田仁学/p30~30
松源録秘鈔(26) / 中島鉄心/p31~33,25~25
編集後記 / 秋月竜珉/p36~36 |
2月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(2)(482) 」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885358
|
真理禅・体理禅・仏道禅--禅についての覚え書(1) / 佐藤幸治/p2~4
米国だより / 佐々木承周/p5~7
現代語訳臨済録(8) / 篠原寿雄/p8~13
松源録祕鈔(27) / 中島鉄心/p14~16
日記小抄--鈴木大拙先生を訪ねて / 中島鉄心/p16~18
原田祖岳老師の霊前に(4) / 今成覚禅/p19~23 |
無情説法(3) / 井上耕哉/p24~27
回顧録(2) / 島田春浦/p27~29
良寛の詩歌(4) / 小林大信/p30~34
黙想のつどい案内 / 辻隻明/p35~35
編集後記 / 秋月竜珉/p36~36
・ |
2月、「禅文化 7(2/3)(27/28)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082228
|
グラフ 六祖図と六祖の遺蹟=Graphs: Portrait Paintings and Remains of Master Hui-neng
扉 画・賛 / 太室道人
特集・六祖慧能大師 慧能禅と現代=Articles: The Zen of Master Hui-neng and its Significance in the Present
Day / 鈴木大拙 / p2~10
特集・六祖慧能大師 禅的人間像=Articles: Neo-Zen Humanism / 久松真一 / p11~19
特集・六祖慧能大師 仏性南北無し=Articles: A Buddha-nature being neither South nor North. / 山田無文 / p21~30
特集・六祖慧能大師 六祖慧能禅師図説=Articles: On the Portrait Paintings of Master Hui-neng / 竹内尚次 / p31~39 (0021.jp2)
仏教東漸七十年の回顧=Articles: A Restropects of Seventy Years History of Zen Buddhism in the West / 緒方宗博 / p42~50
白隠和尚と了徹居士(上)=Articles: On the Relations between Master Hakuin and Ry tetsu, One of
the Followers / 秋山寛治 / p69~76
仙厓和尚の研究(一)=Articles: A Study on Master Sengai (1) / 三宅酒壺洞 / p58~63
香道史抄(九)=Articles: The Extracts from the History of Smelling Incence (9) / 一色梨郷 / p65~68
売茶翁の遺墨展を見て=Short Pieces: A Report from an Exhibition of Maisa-, a Founder of Maisa School of Tea Ceremony / 淡川康一 / p53~57
仙厓陶鈞之図=Short Pieces: On a picture of the Potter's Wheel drawn by Master Sengai
/ 内島北朗 / p20~20
竜吟庵の素朴性=Short Pieces: On the Simplicity of Zen Architecture in Ry gin-an Temple / 立花大亀 / p51~52
禅寺巡礼「恵林寺」=Short Pieces: Erin-ji Temple: A Pilgrimage through Zen Temples (4) / 大石守雄 / p40~41
千崎如幻先生のこと=Short Pieces: The Memory of Master Nyogen Senzaki /
棚橋秋旻 / p64~64
無門關新講 第23講 不思善悪=Articles: Special Discourse on the Mumonkwan Chap. 23rd, "Think of neither Good nor Evil" / 山田無文 / p77~84
新刊紹介 / p50~50,68~6 |
4月、鈴木大拙が「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(4)(484)p3~2 中央仏教社」に「白隠和尚坐禅和讃英訳」を発表する。 pid/7885360
4月16日~29日迄、「本間美術館」に於いて「日本肖像画 : 名作展」が開かれる。主催:本間美術館,山形新聞社
○、この年、「日本肖像画 :名作展図録」が「(酒田)本間美術館」から刊行される。
(名作展図録) pid/2507557
|
1 武智麿像 筆者不詳
2 南叟慧居士像 筆者不詳
3 一休像 墨斎筆
4 雪舟等楊像 徳力善雪筆
5 足利義政像 伝士佐光信筆
6 牡丹花肖柏像 筆者不詳
7 三条西実隆像 土佐光信筆
8 春屋宗園像 春屋自賛
9 千利休像 古溪賛
10 黒田長政像 江月宗坑 林羅山賛
11 沢庵宗彰像 啓叔宗通筆 春沢賛
12 長円源光像 筆者不詳 竺英賛
13 石川丈山像 丈山自賛
14 隠元隆琦像 喜多元規筆 隠元賛
15 狩野探幽像 伝桃田柳栄筆
16 狩野探幽像 伝桃田柳栄筆
17 高遊外像 三熊思孝筆
|
18 白隠慧鶴像 自画
19 慈雲像 義方筆 慈雲賛
20 三上孝軒池大雅対談図 池大雅筆
21 池大雅像 三熊思孝筆
22 細合半斎像 桑山玉洲筆
23 本間光丘像 公巌賛
24 木村巽斎像 谷文晃筆
25 円山応挙像 谷文晃筆
26 杉田玄白像 石川大浪筆
27 皆川棋園母像 円山応挙筆
28 林子平像 菅井梅関筆大槻磐溪賛
29 曾根原魯卿福原五岳叙別図 福原五岳筆
30 大田南畝像 鳥文斎栄之筆
31 上杉鷹山像 矢尾板惟一筆
32 亀田鵬斎像 自画
33 松村呉春像 岡本豊彦筆
34 良寛像 自画賛
|
35 谷文晃像 自画
36 近世名家肖像画巻
→柴野栗山他四十五人 谷文晁筆
37 佐藤一斎像 渡辺華山筆
38 大島真翁像 田能村竹田筆
39 徳川斉昭像 筆者不詳
40 武田耕雲斎像 筆者不詳
41 高野長英像 椿々山筆
42 藤田東湖像 筆者不詳
43 古岳上人像 岡田為恭筆
44 明治天皇尊影 五姓田芳柳筆
45 三上晴山像 狩野芳崖筆
46 横山大観像 安田靱彦筆
47 安井曾太郎像 前田青邨筆
48 おまつ像 岸田劉生筆
49 落合朗風像 自画
・ |
5月、 「伊那 11(5)(420) 」が「伊那史学会」から刊行され口絵に※「白隠禅師墨蹟」が掲載される。 pid/4431256
※ 解説文の有無については未確認 2022・12・22 保坂
6月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(6)(486)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885362
|
禅者の現代的課題--いわゆる大森ビジョンについて / 大森曹玄/p3~5
“ウソも方便”について / 長井真琴/p6~8
これが禅だ / 阪本雅城/p9~9
正受老人の詩偈(1) / 小林大信/p10~14
大信和尚紹介 / 伊藤探玄/p15~16
“碧巌集定本”について / 伊藤猶典/p16~18
“禅思想史体系”について / 伊藤英三/p18~19 |
松源録秘鈔(31) / 中島鉄心/p22~26
回顧録(5) / 島田春浦/p27~29
在家禅の問題--釈定光老師の宗教改革思想と
→その限界/秋月龍珉/p30~34
禅界時報/p35~35
編集後記 / 秋月竜珉/p36~36
・ |
7月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(7)(487)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885363
|
全人類倫理アッピール / FAS協会/p2~3
坐禅論余話 / 大森曹玄/p4~6
在家と出家 / 増田英男/p7~10
我が説禅 / 広高正道/p10~10
禅道小見(1) / 伊藤探玄/p11~14
米国便り(3) / 佐々木承周/p15~17
回顧録(6) / 島田春浦/p17~19
|
和歌 / 正富汪洋/p20~20
現代語訳臨済録 / 篠原寿雄/p21~25
正受老人の詩偈(2) / 小林大信/p26~28
偈頌と俳句 / 伊藤探玄/p28~30
これが禅だ(4) / 阪本雅城/p31~31
松源録祕鈔(32) / 中島鉄心/p32~35
編集後記 / 飯塚定香/p36~36 |
8月、古田紹欽が「仏教とはなにか」を「社会思想社」から刊行する。 pid/2966433
|
I 悟りに生きた人たち / p7
1 人間鴨長明 / p9
宗教的文学作品としての観賞
万丈記が書かれた時代的背景/
長明における出家遁世の意味
世俗と断ちきれなかった長明
失意の人々に共感をよせた心境
維摩居士の居宅に由来する方丈
長明の無常観とその信仰
自分を見とどけた長明
2 禅者芭蕉 / p34
芭蕉と禅
風雅の妄執
禅僧との出会
「古池や」の句について
仙厓の理解した句境 |
永遠の音をきく
「不動智神妙録」の味わい
動静一つの世界
山も庭も動く
悟らぬ人の尊さ
心の遍歴
3 信仰の人一茶 / p58
一茶の宗教的生いたち
ぶつかった心の関門
「おらが春」の宗教論 /
愚者の尊さを思う心境
明かるさの底に生きるさとり
II 禅のおしえる世界 / p73
1 現代の古典・寒山詩/p75
自然生活へのあこがれ
現代に生きる風狂の士
|
シナ料理と日本料理のちがい
秋到れば林の落葉するにまかす
寒山の人間性
独りみずから居すということ
2 仙厓の悟り / p100
臨済禅の三つの流れ
一声にとらえた極楽浄土
禅くさくない禅
禅茶一味の世界
3 臨済録の思想 / p117
菩提達磨の禅
つまらないくそかきべら
仏を否定する精神
徳山の棒・臨済の喝
仏法における一大事
絶対的立場でみる
|
4 「坐禅和讃」の心 / p146
瓦をみがいて鏡にする
自分が自分に出会う経験
この世にある蓮華の国
III 仏教への道 / p163
禅と浄土 / p165
坐禅も浄土もわかる心
外にある仏と内にある仏
仏になる、ならないおしえ
対立する仏と人のありかた )
浄土のある場所
禅と浄土をむすぶ路
「我が国」をみる目
あとがき / p191
・
・ |
8月、「日本美術工芸 (299) 日本美術工芸社 [編] 日本美術工芸社 1963-08pid/2281510/1/1
|
トレドとバルセローナ(スペイン)・カタルニア美術館--
→わたしの見た欧州-17- / 十河巌/p2~10
床の間飾り十二カ月-7- / 細見古香庵/11~14
古作伊勢芦屋釜発見 / 細見良/p15~17
陶狂のネゴト / 上口愚朗/p18~21
京都の短冊--短冊おぼえ書き-72- / 多賀博/p22~27
詩仙堂採訪と白幽子展墓 / 伊藤和男/28~33
石榴(ざくろ)(54話)随縁遊墨 / 中村餘容/p34~36
白〔ワン〕(10)茶わん閑日 / 櫟心居/p38~45 |
石の幻想――「図鑑揖斐川石」より //p46~49
俳画指導(111) / 赤松柳史/p50~51
中村餘容先生指導(一一)漢詩入門講座 //p36~37
サラリーマンの古美術 //p33~33
骨董――某月某日 //p45~45
八月・関西の美術館 //p51~51
新刊紹介 //p52~52
編集室 //p52~52
・ |
|
伊藤和男が「日本美術工芸 (276~299)」迄に発表した白幽子に関する論文名の一覧表
| No |
雑誌通番号 |
発行年月 |
論文名と収録頁 |
pid |
| 1 |
日本美術工芸 (276) |
1961-09 |
白幽子の書について / 伊藤和男/p62~63 |
pid/2281487 |
| 2 |
日本美術工芸 (277) |
1961-10 |
白幽子について(補遺) / 伊藤和男/p44~45 |
pid/2281488 |
| 3 |
日本美術工芸 (278) |
1961-11 |
白幽子と鉄斎-付・白幽子と貝原益軒 / 伊藤和男/34~39 |
pid/2281489 |
| 4 |
日本美術工芸 (279) |
1961-12 |
白幽子の墨跡 / 伊藤和男/p48~50 |
pid/2281490 |
| 5 |
日本美術工芸 (282) |
1962-03 |
円空のそりかえる薬師如来 / 土屋常義/p44~46
円空仏写真譜一 / 後藤英夫/p47~50
白幽子墨跡たずねある記 / 伊藤和男/p51~55
円空仏のその後/p46~46 |
pid/2281493 |
| 6 |
日本美術工芸 (283) |
1962-04 |
円空上人伝-3- / 小林宗一/p37~40
沙魚壺(はぜつぼ)後日譚 / 加藤増夫/p41~43
「夜船閑話」と健康法-白幽子・白隠・良寛・益軒/伊藤和男/44~48 |
pid/2281494 |
| 7 |
日本美術工芸 (287) |
1962-08 |
伊吹山の11面観音 / 土屋常義/p2~5
伊吹山太平寺-円空上人考-1- / 小林宗一/p6~9
円空と木喰-短冊おぼえ書き-60- / 多賀博/p11~15
白幽子は丈山の甥である / 伊藤和男/p53~54
円空仏 薬師 / 土屋常義/p10~10
円空上人のお稲荷さま / 小林宗一/p10~10 |
pid/2281498 |
| 8 |
日本美術工芸 (289) |
1962-10 |
続・白幽子と鉄斉-付白幽子墨跡・白幽子とソーロー/伊藤和男/p46~5 |
pid/2281500 |
| 9 |
日本美術工芸 (299) |
1963-08 |
詩仙堂採訪と白幽子展墓 / 伊藤和男/28~33 |
pid/2281510 |
|
9月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(9)(489)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885365
|
現代の顔(1)加藤耕山老師/p2~2
禅旋風の根拠 / 土岐湘山/p3~7
大森ビジョンを読みて / 井田磐楠/p8~10
坐禅和讃三言 / 陸川堆雲/p11~12
雑言 / 阿部芳春/p12~13
禅道小見(3) / 伊藤探玄/p14~18
現代語訳臨済録(14) / 篠原寿雄/p19~24 |
松源録秘鈔(34) / 中島鉄心/p25~27
八月号読後感 / 広高正道/p27~28
正受老人の詩偈(3) / 小林大信/p29~32
趙州録を拝読して / 中島鉄心/p33~34
禅界時報 / 飯塚定香/p35~35
編集後記 / 秋月竜珉/p36~
・ |
10月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(10)(490)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885366
|
現代の顔(2)鈴木大拙博士/p2~2
線・参禅秘録(1) / 秋月竜珉/p3~5
禅道小見(4) / 伊藤探玄/p6~9
禅門今昔夜話(1) / 陸川堆雲/p10~13,16~16
回顧録 / 島田春浦/p14~16
短歌 / 正富汪洋/p17~17
現代語訳臨済録(15) / 篠原寿雄/p18~22
狂信者 / 梶原単堂/p22~22 |
これが禅だ(5) / 阪本雅城/p23~23
米国便り(4) / 佐々木承周/p24~25
松源録秘鈔(35) / 中島鉄心/p26~28
語録文法断片(2) / 秋月竜珉/p29~29
正受老人を仰ぐ(4) / 小林大信/p30~32
続・漢文典(22) / 松本如石/p33~35
編集後記 / 飯塚定香/p36~36
・ |
11月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 40(12)(492)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885368
|
現代の顔(3) / 久松真一/p2~2
続・禅旋風の根拠 / 土岐湘山/p3~12
禅道小見(5) / 伊藤探玄/p13~16
現代語訳・臨済録(16) / 篠原寿雄/p17~21
回顧録(9) / 島田春浦/p22~24
松源録秘鈔(36) / 中島鉄心/p25~27
|
米国便り(5) / 佐々木承周/p27~28
正受老人の詩偈 / 小林大信/p29~32
禅門今昔夜話(2) / 陸川堆雲/p33~35
良書紹介/p36~36
編集後記 / 秋月竜珉/p38~38
・ |
11月、陸川堆雲が「考証白隠和尚詳伝」を「山喜房仏書林」から刊行する。 pid/2968294 最重要
|
口絵写真
推薦のことば、鈴木大拙博士 巻頭
自序 / p1
凡例 / p3
第一章 総説 / p13
第二章 自隠年譜について / p20
第三章 自隠の青年時代 / p29
第四章 荊棘叢談と
→近世禅林僧宝伝について/p114
第五章 白隠門下の諸問題 / p128
第六章 白隠伝の関係書 / p185
|
第七章 白隠の著述 / p193
第八章 座禅和讃について / p231
第九章 読神社考弁疑について / p251
第十章 白隠の或る時の思索 / p259
第十一章 白隠の内面生活など / p274
第十二章 荊叢毒藥の刊行事情と当時の
→出版背景及辺鄙以知吾の禁書 / p294
第十三章 白隠の余り知られぬ半面 / p310
第十四章 白隠より無着和尚へ宛ててる
→手紙について / p314
第十五章 白隠と松蔭、竜沢、至道菴 / p330
|
第十六章 白幽子について / p352
第十七章 白隠の先輩及交遊の人々/p363
第十八章 白隠遺蹟訪問記 / p382
第十九章 白隠和尚通略伝 / p393
第二十章 白隠年譜と同年譜草稿
→対比及備考 / p443
第二十一章 結論 / p547 (0282.jp2)
附録 東嶺和尚の無尽燈論の神道思想及び
→「吾道宮縁由」について / p549
あとがき / p580
・ |
11月、「墨美 (132)」が「墨美社」から刊行される。pid/2362453
|
カンジンスキー外 //13~13
ピカソ,ブリアン //14~14
マチウ,ガウル //15~15
アルプ,カポグロッシ //16~16
白隠 //17~20
東嶺 //21~21
慈雲 //22~22
江口草玄 //23~23
池田水城 //24~24
井上有一 //25~25
松井如流 //26~26 |
森田竹華 //27~27
森田子龍 //28~28
西川寧 //29~29
関谷義道 //30~30
手島右卿 //31~31
上田桑鳩 //32~32
山崎大抱,比田井南谷 //33~33
ゴッホ,クレー //34~34
ミロ,アッペル //35~35
ミショー,ビッシェール //36~36
ブリュニング,アルコプレイ //37~37 |
書法と形象展のカタログについて / 三崎義泉/2~3
東洋の文学・東洋の書 / シャールシュミュト・
→リヒターイルムトラウト ; 三崎義泉/4~10
書--「書」を「日本のカリグラフィー」と訳するのは
→正しくない / 森田子竜/10~12
欧米旅行記 / 森田子竜/38~39
日本の書家の一つのアピール--欧米での
→講演原稿 / 森田子竜/40~42
反響 //42~44
書とニューヨーク画壇 / 森田子龍/44~44
・ |
12月、「みづゑ (706)」が「美術出版社」から刊行される。 pid/2241974
|
インドのミニァチュア――男に心を寄せてはずかしがる女 //p1~
インドのミニァチュア――クリシュナと牧女たち //p3~
オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘 / ギュスタヴ・モロー/p29~
示現 / ギュスタヴ・モロー/p31~
婚礼の準備 / 池田満寿夫/p69~
曇日の桜島 / 大久保泰/p79~
セビラの行列 / 野口彌太郎/p85~
橋の記録 / 中野淳/p87~
インドのミニァチュア――クリシュナの武勇譚と恋物語 //p5~
世界近代彫刻シンポジウム野外展 / カルデナス ; 毛利武士郎/p17~
明清絵画展より / 八大山人 ; 石濤 ; 文伯仁/p37~
郎世寧(4)〈戦後の新発見・中国の美術〉―乾隆皇帝と
→香妃の図2巻より //p49~
「生活の中の禅」展より / 風外 ; 白隠 ; 仙厓/p61~
〈フォト・インタヴュー〉大久保泰 / 酒井啓之/p75~ |
クリシュナの武勇譚と恋物語--インドのミニァチュア / 上野照夫/p13~16
ギュスタヴ・モロー--世紀末の幻視者たち-1- / 野村太郎/p26~34
明清絵画と近代--中国明清美術展を機に / 佐々木剛三/p35~45
郎世寧の「乾隆皇帝と香妃の図」--戦後の新発見・
→中国の美術-4- / 杉村勇造/p46~57
「生活の中の禅」から受けた印象 / バラムS. ; 大島辰雄/p58~65
変貌する版画--戦後美術の展望-5- / 浜村順/p66~71
海外雑記帖 / 村木明/p72~73
職業画家になるの弁 / 大久保泰/p74~74
リオ・グランデの聖像たち--芸術紀行・アメリカ美術の
→断面-1- / 桑原住雄/p81~83
美術界展望 / 南英明/p84~89
画廊から / 植村鷹千代/p90~92
1963年度総目次 //p93~95
・ |
○、この年、上田桑鳩が「書道鑑賞入門」を「創元社」から刊行する。 (創元手帖文庫) pid/2499998
|
理論の部
はじめに/p4
書はどの芸術分野に属するか/p10
文字と書との関係について/p17
書の特質について/p20
書は人を表わす/p31
書は生活体験を表わす/p56
書の伝統/p60
書の構成要素/p79
書の美しさを感じることについて/p97
鑑賞の仕方/p131
特殊な作品の鑑賞について/p141
書の変遷〔中国の部〕/p172
書の変遷〔日本の部〕/p192
鑑賞の部
帝王の書(その一)孝謙天皇書/p206
帝王の書(その二)唐太宗書/p207
平復帖 陸機書/p208
離落帖 藤原佐理書/p210
綾地切 伝藤原佐理書/p212
|
性集 伝藤原公任書/p213
賀蘭汗造像記/p214
現代の書 比田井南谷書
→(墨象)/p216
現代の書 著者書
→(耀の字による作品)/p217
本阿弥切 伝小野道風書/p218
小島切 伝小野道風書/p219
池大雅書/p221
貫名菘翁書/p222
甲骨文(古文)/p224
鐘鼎文(古文、金文)/p226
石門頒/p228
百石卒史碑(乙英碑)/p229
継色紙 伝小野道風書/p230
升色紙 伝藤原行成書/p232
伊都内親王願文 橘逸勢書/p234
争座位稿 顔真卿書/p236
自叙帖 懐素書/p238
多胡郡碑/p240
|
高野切 第一種 伝紀貫之書/p242
紙撚切 伝藤原佐理書/p244
寒食帖 蘇東坡書/p246
寒食帖跋文 黄山谷書/p247
比田井天来書/p248
積時帖 虞世南書/p250
道因法師碑 欧陽通書/p252
土に書いた書(その一)専/p254
土に書いた書(その二)瓦当/p255
喪乱帖 王義之書/p256
論経書詩 鄭道昭書/p258
法華義疏 聖徳太子書/p260
現代の書 宇野雪村(渓)/p262
現代の書 小川瓦木(回生)/p263
王鐸書/p264
鄧石如書/p266
開通褒斜道刻石/p268
一條摂政集 西行法師書/p270
十五番歌合切 伝藤原公任書/p272
白隠書/p274
|
慈雲書/p275
高野切 第一種 伝紀貫之書/p242
版書「焚」 榊莫山作/p276
灌頂記 弘法大師書/p278
爨宝子碑/p280
劉石庵書/p282
大沢竹胎書(宮沢賢治の詩)/p284
船首王後墓誌/p286
趙之謙書/p288
関戸本古今集 伝藤原行成書/p291
西本願寺三十六人集の内順集
→ 藤原定信書/p292
副島種臣書/p294
十七帖 王羲之書/p296
蘭亭叙 王羲之書/p298
消息 伝藤原行成書/p300
のれん 井原思済作/p302
背景としての書 著者作/p303
〔付録〕 書道史略年表 /
→巻末別綴折込 |
○、この年、「県指定文化財調査報告書 第6巻 p21 岐阜県教育委員会」に「禅昌寺蔵白隠絵画・書跡」が掲載される。 pid/2476519
○、この年、荻須純道が「京・鎌倉の禅寺」を「教育新潮社」から刊行する。
(日本のお寺シリーズ ; 6) pid/2971504
|
〔口絵写真〕 / p3
はじめに / p35
I 寺歴と開祖伝 / p45
建仁寺
(一) 建仁寺のあゆみ/p47
(二) 栄西禅師 / p51
東福寺
(一) 東福寺のあゆみ / p57
(二) 聖一国師 / p63
南禅寺
(一) 南禅寺のあゆみ / p70
(二) 大明国師・南院国師/p79
天竜寺
(一) 天竜寺のあゆみ / p82
(二) 夢窓国師 / p85
相国寺
(一) 相国寺のあゆみ / p96
(二) 春屋妙葩禅師 / p99
|
大徳寺
(一) 大徳寺のあゆみ/p103
(二) 大燈国師 / p106
妙心寺
(一) 妙心寺のあゆみ/p114
(二) 無相大師 / p118
建長寺
(一) 建長寺のあゆみ/p125
(二) 大覚禅師 / p127
円覚寺
(一) 円覚寺のあゆみ/p130
(二) 仏光禅師 / p133
向嶽寺
(一) 向嶽寺のあゆみ/p136
(二) 抜隊得勝禅師 / p138
国泰寺
(一) 国泰寺のあゆみ/p140
(二) 慈雲妙意禅師 / p141
|
方広寺
(一) 方広寺のあゆみ/p142
(二) 無文元選禅師 / p144
永源寺
(一) 永源寺のあゆみ/p146
(二) 寂室元光禅師 / p147
仏通寺
(一) 仏通寺のあゆみ / p150
(二) 愚中周及禅師 / p152
万福寺
(一) 万福寺のあゆみ / p154
(二) 隠元隆琦禅師 / p156
II 宗義と実践 / p159
達摩大師と禅の意義 / p161
はじめに
達摩大師とその禅法
達摩大師について
禅の大成者としての六祖/p174
|
六祖とその時代
六祖の求道と教化
南宗禅と北宗禅
臨済禅師とその宗風/p188
臨済の出ずるまで
臨済禅師について
臨済禅師の思想
坐禅と公案 / p198
禅の清規 / p201
現代の僧堂 / p204
III 白隠禅師坐禅和讃 /p207
(一) 坐禅和讃の主旨/p209
(二) 坐禅和讃解説/p212
(三) 白隠禅師について/p216
・
・
・
・ |
|
| 1964 |
39 |
・ |
1月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(1)(495)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885371
|
碧巌集定本を読みて / グンデルト/p4~5
白隠和尚詳伝を読む / 大森曹玄/p6~7
禅道小見(6) / 伊藤探玄/p8~11
禅門今昔夜話(3) / 陸川堆雲/p12~15
現代語訳臨済録(17) / 篠原寿雄/p16~19 |
秋冬の色 / 安田光義/p20~21
趙州録の再版に因みて / 鈴木大拙/p22~22
同洋装増幀版について / 秋月竜珉/p22~24
漫画・無字さん(1) / 阪本雅城/p24~24
回顧録(10) / 島田春浦/p25~27 |
松源録秘鈔(37) / 中島鉄心/p28~30
正受老人を仰ぐ(6) / 小林大信/p31~33
編集後記 / 飯塚定香/p36~36
・
・ |
2月、 原田龍門が「坐禅和讃講和」を「人間禅教団」から刊行する。 (人間禅叢書,
第4編)
2月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(2)(496)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885372
|
世界連邦日本仏教徒協議会の訴え / 朝比奈宗源/p2~3
禅道小見(7) / 伊藤探玄/p4~7
禅門今昔夜話(4) / 陸川堆雲/p8~12
回顧録(11) / 島田春浦/p12~14,27~27
松源録秘鈔(38) / 中島鉄心/p15~17 |
正受老人を仰ぐ(7) / 小林大信/p18~21
現代語訳臨済録(18) / 篠原寿雄/p22~27
洪川禅師無字の歌 / 秋月竜珉/p28~33
禅界時報/p34~34
編集後記 / 秋月竜珉/p36~ |
5月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(4)(498)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885374
|
巻頭言 真正見解 / 秋月竜珉/p3~3
臥禅独語 / 長井真琴/p4~6
風外道人(写真解説) / 竹内尚次/p7~7
禅道小見(9) / 伊藤探玄/p8~11
在家禅の確立 禅界の一大急務/p12~14
禅門今昔夜話(5) / 陸川堆雲/p14~17
現代語訳・臨済録(20) / 篠原寿雄/p18~23 |
回顧録(12) / 島田春浦/p24~26
松源録秘鈔(40) / 中島鉄心/p27~29
春の色 / 安田光義/p30~31
正受老人の偈頌(8) / 小林大信/p32~34
禅思想研究資料(1) / 伊藤英三/p35~41
編集後記 / 秋月竜珉/p42~42
・ |
6月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(5)(499)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885375
|
巻頭言 絶対矛盾的自己同一/秋月竜珉/p3~3
禅道小見(10)/伊藤探玄/p4~7
禅門今昔夜話(6)/陸川堆雲/p8~11
現代語訳臨済録(21)/篠原寿雄/p12~18
回顧録(13)/島田春浦/p19~21
|
松源録秘鈔(41)/中島鉄心/p22~25
正受老人偈頌解(9)/小林大信/p25~28
維摩詰像解説/竹内尚次/p29~29
国訳改編伝心法要/伊藤英三/p30~37
編集後記/秋月竜珉/p38~38 |
6月、竹内尚次編・通山宗鶴校閲・鈴木大拙・ 田中一松監修「白隠. [本篇]と[解説]」が「筑摩書房」から刊行される。
[本篇 箱入]: pid/8798776 [解説:付: 別綴 図版解説57p 箱入] pid/8798777
|
白隱慧鶴基本年譜 / p1
禪と白隱 鈴木大拙 / p23
白隱の人と藝術 / p45
白隱遺墨總目録 巻末
白隱 遺墨總目録
鑑賞篇〔繪畫〕
鑑賞篇〔書蹟〕 |
主題篇〔繪畫〕
逹磨像
祖師像
釋迦像
觀音像
佛畫
神祇像 |
福神圖
布袋圖
人物圖
山水・鳥獸・木石
資料篇〔書蹟〕
一字關
偈頌 |
假名法語・和歌
法語
名號
印證
草稿(卷子・折本・經册)
書簡
・ |
7月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(6)(500) 」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885376
|
巻頭写真 白隠自画像 / 竜沢寺蔵 / p2~2
同上解説 / 竹内尚次 / p3~3
哲学十話(上) / 務台理作 / p4~11
達磨・道元の歌 / 正富汪洋 / p12~12
岸本英夫博士の“わが生死観”を拝読して/西木孝子/p13~19
禅道小見 / 伊藤探玄 / p20~24
禅門今昔夜話(7) / 陸川堆雲 / p25~28
現代語訳 臨済録(22) / 篠原寿雄 / p29~33 |
正受老人の詩偈(10) / 小林大信 / p34~37
禅会紹介(1)東京寸心会 / p37~37
松源録秘抄(42) / 中島鉄心 / p38~42
われらの禅の目指すところ / 岡田仏心 / p43~45
禅会紹介(2)担雪会 / p46~46
改編国訳伝心法要(中) / 伊藤英三 / p47~55
暑中互礼 / p56~59
編集後記 / 飯塚定香 / p60~60 |
7月、釈大眉が「座禅和讃物語」を「誠信書房」から刊行する。 pid/2966952
|
一、 坐禅和讃と白隠禅師の生涯 / p1
二、 坐禅と日本婦人 / p15
三、 衆生と仏 水と氷 / p30
四、 近きを遠きに求む / p42 |
五、 大乗の禅定とその功徳 / p53
六、 六度と念仏と懺悔 / p60
七、 坐禅と滅罪 / p70
八、 自性即ち無性 / p79 |
九、 因果一如と無相無念 / p86
一〇、 四智円明 / p97
一一、 当所即ち運華国 / p107
・ |
注記 白隱禪師筆「自画像自賛」あり
8月、東京国立博物館編「 Museum (161) 」が「東京国立博物館」から刊行される。 pid/4429550
|
菩薩像における鬢の耳にかかる形式について--法隆寺伝来
→旧御物金銅仏の作例を中心として / 千沢楨治 / p2~8
細字法華経 / 飯田瑞穂 / p9~13
延幹の書跡 / 小松茂美 / p14~16
玳瑁張経台と華角張りの手法について / 木内武男 / p19~23
漆皮箱 / 岡田譲 / p24~28
薬師如来坐像と釈迦如来坐像--平安在銘彫刻資料-7-/佐藤昭夫/p29~32 |
新刊紹介 杉村勇造編槐安居楽事/堀江知彦/p33~33
新刊紹介 竹内尚次編・著白隠/田山方南/p33~33
美術界通信 / p34~34
原色版 撥鏤の尺と針筒・
→法隆寺献納宝物(解説) /荒川浩和/p17~18
表紙 光背・法隆寺献納宝物(解説)/金子良運/p23~23
・
|
9月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(7)(501)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885377
|
現代の顔(4) / 伊藤探玄/p2~2
禅界紹介(3) / 碧雲会/p3~3
禅道小見(12) / 伊藤探玄/p4~7
米国便り(承前) / 佐々木承周/p7~9
回顧録(14) / 島田春浦/p10~12
短歌 / 正富汪洋/p13~13
現代語訳臨済録(23) / 篠原寿雄/p14~17 |
禅門今昔夜話(8) / 陸川堆雲/p18~22
松源録祕鈔(43) / 中島鉄心/p23~25
正受老人の詩(11) / 小林大信/p26~29
国訳改編伝心法要(下) / 伊藤英三/p30~37
禅界時報 / 飯塚定香/p38~39
編集後記 / 秋月竜珉/p40~40
・ |
10月、片山鉄之助が「羽後公論 162 p8~9」に「白隠と正受庵(一)」を発表する。
10月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 41(8)(502) 」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885378
|
現代の顔(5)陸川堆雲/p2~2
現代の顔(6)島田春浦/p2~2
巻頭言 / 秋月竜珉/p3~3
哲学十話(下) / 務台理作/p4~11
川尻宝岑・坐禅の捷径(1) / 伊豆山善太郎/p12~17
井田磐楠翁の生涯と禅(1) / 大森曹玄/p18~20
抱石庵断章 / 今井富士雄/p21~25
禅会紹介(4)鉄舟会/p25~25
歌俳禅想 / 陸川堆雲/p26~31 |
禅道小見(13) / 伊藤探玄/p32~39
松源録秘鈔(44) / 中島鉄心/p40~42
回顧録(15) / 島田春浦/p43~45
虚堂録義解発刊について / 岡田仏心/p46~50
慶弔両端の法兄 / 長尾大学/p50~51
正受老人の詩偈(完) / 小林大信/p52~56
禅界紹介(5)正修禅会/p57~57
禅学研究資料・臨終偈(1) / 伊藤英三/p58~65
編集後記 / 秋月竜珉/p66~66 |
|
小林大信が「大乗禅(471)~(502)」に発表した論文の一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
刊行年月 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
39(4)(471) p12~14 |
1962-04 |
かれと我れ / 小林大信 |
. |
pid/7885349 |
| 2 |
39(10/11)(476) p4~9・p40~45 |
1962-10 |
正受禅の提唱 / 秋月龍珉/p3~3
正受老人崇行録 / 今北洪川
かく味う(良寛の詩歌) / 小林大信 |
. |
pid/7885354 |
| 3 |
39(14)(479) p20~23 |
1962-12 |
かく味う(良寛の詩歌)(2) / 小林大信 |
. |
pid/7885355 |
| 4 |
40(1)(481) p14~17 |
1963-01 |
良寛の詩歌(3) / 小林大信 |
. |
pid/7885357 |
| 5 |
40(2)(482) p30~34 |
1963-02 |
良寛の詩歌(4) / 小林大信 |
. |
pid/7885358 |
| 6 |
40(6)(486) p10~14・p15~16 |
1963-06 |
正受老人の詩偈(1) / 小林大信
大信和尚紹介 / 伊藤探玄 |
. |
pid/7885362 |
| 7 |
40(7)(487) p26~28 |
1963-07 |
正受老人の詩偈(2) / 小林大信 |
. |
pid/7885363 |
| 8 |
40(9)(489) p29~32 |
1963-09 |
正受老人の詩偈(3) / 小林大信 |
. |
pid/7885365 |
| 9 |
40(10)(490) p30~32 |
1963-10 |
正受老人を仰ぐ(4) / 小林大信 |
. |
pid/7885366 |
| 10 |
40(12)(492) p29~32 |
1963-11 |
正受老人の詩偈 / 小林大信 |
. |
pid/7885368 |
| 11 |
41(1)(495) p31~33 |
1964-01 |
正受老人を仰ぐ(6) / 小林大信 |
. |
pid/7885371 |
| 12 |
41(2)(496) p18~21・p28~33 |
1964-02 |
正受老人を仰ぐ(7) / 小林大信
洪川禅師無字の歌 / 秋月竜珉 |
. |
pid/7885372 |
| 13 |
41(4)(498) /p32~34 |
1964-05 |
正受老人の偈頌(8) / 小林大信 |
. |
pid/7885374 |
| 14 |
41(5)(499) p25~28 |
1964-06 |
正受老人偈頌解(9)/小林大信 |
. |
pid/7885375 |
| 15 |
41(6)(500) p34~37 |
1964-07 |
正受老人の詩偈(10) / 小林大信 |
. |
pid/7885376 |
| 15 |
41(7)(501) p26~29 |
1964-09 |
正受老人の詩(11) / 小林大信 |
. |
pid/7885377 |
| 17 |
41(8)(502) p52~56 |
1964-10 |
正受老人の詩偈(完) / 小林大信 |
. |
pid/7885378 |
| 18 |
42(2)(508) |
1965-02 |
・ |
. |
pid/7885384 |
| 19 |
42(3)(509) p26~27 |
1965-03 |
小林大信君を弔う / 伊藤探玄 |
. |
pid/7885385 |
※小林大信和尚は、論文「正受老人の詩偈(完)」の完結後、お亡くなりになられた御様子です。謹んでお悔やみ申し上げます。 2023・1・30 保坂 |
11月、片山鉄之助が「羽後公論 11.12月併用号 163 p7~9」に「白隠と正受庵(二)」を発表する。
11月、心編集委員会編「心 : 総合文化誌 17(11)」が 「平凡社 」から刊行される。 pid/1764072
|
再び東洋的なるものについて / 鈴木大拙 / 2
日本教育の行くえ / 天野貞祐 / 7
罪責-ローマ法王と天皇の場合 / 竹山道雄 / 14
世界の新情勢と日本の外交 / 長谷川才次 / 26
災害について / 坪井忠二 / 32
電子計算機と機械翻訳 / 彌永昌吉 / 41
第一次大戦とイギリス労働党 / 関嘉彦 / 46
座談会 科学技術を巡って / 石川一郎 ; 久田太郎 ; 橋本宇一 ;
→桑田勉 ;馬場有政 ; 安倍能成 / 54
更級日記と浜松中納言物語 / 土居光知 / 71
ルネッサンス科学史に於ける芸術家の役割 / 下村寅太郎 / 82
ハウプトマンのギリシャ悲劇(一) / 新関良三 / 94
証言 / 和辻哲郎 / 104
元良勇次郎博士の心理学の基本思想 / 高橋穣 / 111
孔子も神の子であるという説 / 吉川幸次郎 / 121
白隠の達磨 / 麻生磯次 / 126
アリストテレスの「エンテレケイヤ」を旋って / 渡辺一夫 / 133
偶然 / 福原麟太郎 / 141
へーグだより / 田中耕太郎 / 145
南インド最はての旅(一) / 中村元 / 152
西欧覊旅覚書(一六) / 市原豊太 / 160
筑紫路点描(上) / 嘉治隆一 / 167
南方熊楠翁-高野の一と月 / 信時潔 / 176
留学時代の高橋里美さん / 務台理作 / 181 |
西田幾多郎先生の話 / 木村素衛 / 187
アフリカ襍記(十) / 高橋功 / 190
ウォールポール時代 / 浅尾新甫 / 198
スコットランド・ハイランドからのイヌワシの情報 /
→大原総一郎 ; セント・ゴードン / 201
巴里日記(一) / 小宮豊隆 / 204
我が生ひ立ち(自叙伝その四八) / 安倍能成 / 211
座談会 バーナード・リーチを囲んで/B・リーチ;浜田庄司;志賀直哉;
→松方三郎; 武者小路實篤/215
雀と猫 / 志賀直哉 / 228
褒□〔ホウジ〕の笑い(小説) / 井上靖 / 329
たぬき――a farce(一) / 大佛次郎 / 298
蒲郡の半日 / 谷川徹三 / 230
ヴィヨン詩篇 / 鈴木信太郎 / 252
Le mortel(小説) / 石田春夫 / 283
玉虫 / 幸田文 / 232
蛙 / 唐木順三 / 279
小暴君(戯曲) / 里見弴 / 234
渋温泉(小説) / 網野菊 / 272
湖畔新秋(俳句) / 富安風生 / 270
随筆(十二) / 中勘助 / 260
貝殼(小品) / 木村修吉郎 / 321
のんき者のんきな造物者に逢う(詩) / 武者小路實篤 / 312
・ |
12月、佐藤幸治が「禅のすすめ」を「講談社」から刊行する。 (講談社現代新書) pid/2969289
|
まえがき/p3
はじめに―わたしたちの周辺から/p13
1 宗教と科学を包む禅/p25
〈1〉 禅と宗教/p26
〈2〉 宗教と人間/p34
〈3〉 宗教・科学と禅/p38
2 健康法としての禅/p43
〈1〉 静座と無心の効果/p44
〈2〉 白隠禅師の内観のすすめ/p51
〈3〉 静座法のいろいろ/p55
3 からだに対する東洋の知恵/p61
〈1〉 「気」というもの/p62
〈2〉 気質を変える/p65
〈3〉 ヨーガ・錬丹・気功療法/p72
|
〈4〉 心身不二の思想/p79
4 禅の科学的真理性/p83
〈1〉 座禅と脳の働き/p84
〈2〉 呼吸の調整/p91
〈3〉 禅と恐迫観念/p97
〈4〉 禅と精神分析学/p101
〈5〉 不立文字とはなにか/p107
5 西洋人はなぜ禅にひかれるか/p111
〈1〉 危機を救う世界観として/p112
〈2〉 科学者をも共感させる/p119
6 禅と日本文化/p125
〈1〉 芸術との関係/p126
〈2〉 対立をこえて/p132
7 悟りとはどういうことか/p141
|
〈1〉 ある中学教師の体験/p142
〈2〉 真実の自己にめざめる/p148
〈3〉 見性に導く薬/p153
〈4〉 悟りの世界の姿/p157
8 禅を学ぶにはどうすればよいか/p165
〈1〉 じっさいにやってみる/p166
〈2〉 ひとりで座禅するには/p172
〈3〉 十牛の図―真実の自己を求めて/p175
終わりに―これからの展望/p184
付録1/p192
付録2/p194
索引
・
・ |
○、この年、須磨弥吉郎がとき出版後援会編「とき : 須磨日記」を「とき編纂会」から刊行する。 pid/8798784
|
見かえし
八嶽之朝彩(原色)/p2~3
ときが世に出るまで/p5
雹到蓼科弦月微(原色)/p6~7
斉白石日本に還る(原色)/p8~9
自選14作/p11
大明成化赤絵大罐(原色)/p13
鼈甲宮夢遊図(原色)/p14
|
瓷と彫(原色)/p15
お嫁さん(原色)/p16
北京哈達門(原色)/p17
蓼科之暁(原色)/p18
白隱和尚木彫擁鳩像(原色)/p19
マドリッド郊外馬蹄鍜冶屋(原色)/p20
河南鄭州鉄仏寺仏頭(原色)/p21
梅花草堂文庫入口の図(原色)/p22
|
赤城山立干荒河畔(原色)/p23
南朝古戦場慈湖之図(原色)/p24
古像(原色)/p25
望岳(原色)/p26
とき(須磨日記)/p27
(以下略)
・
・ |
○、この年、荒井荒雄が「仰臥禅 : 白隠禅師内観の秘法による心身改造」を「明玄書房」から刊行する。 pid/2969928
|
第一編 仰臥禅の提唱
第一章 ストレス学説と東洋の叡智/p17
第二章 禅の再認識/p23
第三章 白隠禅師の臥禅/p26
第四章 仰臥禅の立場/p57
第二編 仰臥禅の行い方
第三編 仰臥禅の深層心理学
第一章 無意識の世界/p79
第二章 観念運動と自己催眠/p92
第三章 自己暗示/p97
|
第四章 仰臥禅の公案/p107
第四編 仰臥禅の生理学
第一章 哲学的生理学的なる丹田呼吸/p121
第二章 丹田呼吸の功徳の生理学的考証/p132
第三章 呼吸の回数/p154
第四章 禅における脳波と仰臥禅/p168
第五章 数息観/p175
第五編 森田療法と仰臥禅
第一章 森田学説/p183
第二章 神経症には器質的病変があるか/p189
|
第三章 絶対矛盾の自己同一/p198
第六編 無痛分娩法と仰臥禅
第一章 分娩痛の疑問と仰臥禅/p216
第二章 条件反射と分娩痛/p220
第三章 仰臥禅の公案と
→精神的無痛分娩法/p222
第四章 丹田呼吸と無痛分娩法/p225
第五章 無痛分娩法を補う仰臥禅/p227
・
・ |
〇この年、家永三郎が「日本思想史に於ける否定の論理の発達」を「新泉社」から刊行する。 (叢書名著の復興 ; 10) pid/12262559 |
| 1965 |
40 |
・ |
1月、「禅文化 (35)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082230
|
グラフ 禅画松竹梅・禅の彫刻他
無門關新講 第28講 大通智勝 / 山田無文 / p4~
「寒山詩」私解(一) / 福島俊翁 / p46~51
清見寺陽春和尚(上)陽春と白隠 / 秋山寛治 / p54~58
心敬僧都の歌・連歌論と時代思潮としての禅--
→禅の芸術性の問題 / 北山正迪 / p59~70
禅宗史話 五家七宗(2)臨済宗 / 荻須純道 / p71~80
インドを語る(2)インド博物館と
→仏舎利容器とについて / 春日井真也 / p21~33 |
禅宗秘話(1)紫衣をめぐる問題 / 桜井景雄 / p36~43
フランス系仏教学者(4)
→シモンヌ・ヴェイユについて / 柴田増実 / p12~20
わが道場 永源寺 / 関雄峰 / p44~45
大学の禅会 般若団 / 清水秀男 / p10~11
随筆 禅縁の不思議 / 坂村真民 / p34~35
書燈 / p52~53
・
・ |
1月、「日本及日本人 (春季)(1429)」が「日本及日本人社 J&Jコーポレーション」から刊行される。 pid/3368248
|
カット / 高松健太郎 /
近世日本8人の人物 / 田中忠雄 / p6~67
大智禅師と菊池一族--特集・近世日本8人の人物 / 田中 忠雄 / p6~13
白隠の禅風--特集・近世日本8人の人物 / 今枝愛真 / p14~21
仙崖の大黒天像--特集・近世日本8人の人物 / 古田紹欽 / p22~25
蓮如--宗教的使命感の問題と真宗本願寺の近代化--特集・近世日本8人の人物 /
笠原 一男 / p26~35
法然上人--その社会観と浄土往生思想--特集・近世日本8人の人物 / 波多野 述麿
/ p36~43
一糸文守--尊皇抑覇の清僧の生涯--特集・近世日本8人の人物 / 鈴木 助次郎 /
p44~52
沢庵和尚--柳生但馬守との交遊--特集・近世日本8人の人物 / 綿谷 雪 / p54~61
上杉鷹山--会津米沢藩領主の理想的封建政治--特集・近世日本8人の人物 / 猪俣
敬太郎 / p62~6
〈略〉 |
2月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 42(2)(508)」が「中央仏教社」から刊行する。 pid/7885384
|
現代の顔(9) / 苧坂光竜 / p2~2
巻頭言 洞上秘訣 / 白隠禅師 / p3~3
英文禅書とその邦訳の意義 / 鈴木大拙 / p4~
キリスト教世界の人々におくる新らしい公案 / 秋月竜珉 / p6~8
禅会紹介(8)真人会 / 元 / p9~9
自主性の確立 / 苧坂光竜 / p10~13
坐禅之捷径(3) / 伊豆山格堂 / p14~18
禅道小見(16) / 伊藤探玄 / p19~24 |
生活の中の禅(1) / 小山止敬 / p25~28
回顧録(17) / 島田春浦 / p29~31
正法眼蔵讃偈(3) / 木田仁学 / p32~34
禅門今昔夜話(11) / 陸川堆雲 / p35~38
松源録祕鈔(47) / 中島鉄心 / p39~41
仏教童話 権じいさん(下) / 井上芳雄 / p42~47
編集後記 / 秋月竜珉 / p48~48
・ |
3月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 42(3)(509)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885385/1/1 重要
|
牡丹曼茶羅頌 / さやますすむ/p2~3
世界の禅者 鈴木大拙博士小伝 / 秋月竜珉/p4~16
ヘリゲル著“弓と禅”序 / 鈴木大拙/p17~18
回顧録(18) / 島田春浦/p19~21
禅道小見(17) / 伊藤探玄/p22~26
小林大信君を弔う / 伊藤探玄/p26~27
坐禅之捷径略註(4) / 伊豆山格堂/p28~31
松源録秘鈔(48) / 中島鉄心/p32~34 |
短歌・南ベトナム / 井上芳雄/p35~35
中近東諸国に核禁を訴えて / 河野宗寛/p35~35
禅門今昔夜話(12) / 陸川堆雲/p36~39
国訳・円悟語要(2) / 伊藤英三/p40~45
関東地方禅会案内一覧/p46~50
禅界時報 / 飯塚定香/p51~52
編集後記 / 秋月竜珉/p54~54
・ |
6月、「禅文化 (37) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082232
|
特輯 臨済義玄禅師千百年 表紙 白隠禅師画賛 臨済禅師図部分
特輯 臨済義玄禅師千百年 グラフ 特輯 臨済禅師示寂千百年
特輯 臨済録新講 一無位の眞人 / 山田無文 / p4~8
特輯 臨済禅師千百年に想う / 竹田益州 ; 梶浦逸外 ; 山田無文 ;
→ 近藤文光;村瀬玄妙 ;陸川堆雲;古田紹欽;松倉紹英/p18~21
特輯 臨済禅師伝 / 陸川堆雲 / p9~17
特輯 臨済の思想 / 柳田聖山 / p22~28
特輯 臨済義玄像図説 / 竹内尚次 / p36~48
寒山詩私解(三) / 福嶋俊翁 / p52~59 |
禅俳僧虚白の生涯 / 高橋浩州 / p62~69
禅宗秘話(3)僧録の話 / 桜井景雄 / p74~80
墨蹟と今日の書 / 中島皓象 / p29~31
如是我聞 / 岩野菊代 / p70~71
英文禅籍管見 / 緒方宗博 / p49~51
兎角禅 / 小西仏舎 / p72~73
わが道場 瑞巌寺 / 加藤隆芳 / p32~33
大学の禅会 東北薬大坐禅会 / 中川孝 / p60~6
書燈(臨済録新研究書一覧) / p34~35 |
○、この年、古田紹欽が「禅僧の遺偈」を「春秋社」から刊行する。 pid/2968310
|
序 まず・生と死ということから / p1
風狂の自由人―一休宗純 / p11
温柔の禅者―養叟宗□(ようそう そうい)/ p19
転換期の禅者―春浦宗煕 / p26
朕の師・天下の模範―古岳宗亘 / p35
一国の宗・百世の師―大林宗套 / p43
才気撥刺の禅―東陽英朝 / p51
火中に坐す傑僧―快川紹喜 / p59
悠々として迫らず―春屋宗園 / p67
檀興の禅者―古渓宗陳 / p75
文化人の禅者―江月宗玩 / p83
「夢」の一字―沢庵宗彭 / p91
快活の最後―清岩宗渭 / p99
この人を世に知らせたい―愚堂東寔 / p107
孤高非情の禅者―大愚宗築 / p115 |
死に習えと教える―鈴木正三 / p123
道骨石の如し―雲居希膺 / p131
救世の大士―鉄眼道光 / p139
曹洞禅の宗風この人によって興る―月舟宗胡 / p147
乞食の聖者―雲渓桃水 / p155
無位の一庵主―正受老人 / p163
遺偈なき吽声―白隠慧鶴 / p171
願心道場の設立―斯経慧梁 / p180
武渓の毒淫―月船禅慧 / p189
関東の臨済禅を復興す―誠拙周樗 / p197
その洒脱な生涯―仙厓義梵 / p205
独り空盂を抱く―大愚良寛 / p213
幕末・明治の禅界をになう―儀山善来 / p221
あとがき / p229
・ |
○、この年、長谷川直義が「産婦人科領域における心身症診療の手引」を「金原出版」から刊行する。
(新臨床医学文庫)/pid/2429067
|
I. まえがき/p1
II. 診断に関する検討/p3
A. 従来,行われてきた診断法/p3
1. 精神分析/p3
1) 自由連想法/p3
2) 防衛機制の理解/p4
3) パーソナリテー形成の理解/p7
2. 心理テスト/p9
1) 矢田部・ギルフォード性格検査/p10
2) ミネソタ多面的人格目録(MMPI)/p14
3) コーネル・メディカル・
→インデックス(CMI)/p19
4) ロールシャッハ・テスト(RT)/p25
5) 画題統覚検査法(TAT)/p26
3. 身体的方法/p29
1) 脳波(EEG)/p29
2) 皮膚電気反応(GSR)/p33
3) 指尖容積脈波/p38
B. 新しい診断法/p40
|
1. 器質的疾患に対する検査/p40
2. いかなるときにPSDの疑診をおくか/p42
3. いかなるときにPSDと確診するか/p44
1) 面接法/p44
(1) 面接の要領/p44
(2) 面接上の一般的注意/p53
2) 産婦人科版TAT/p55
3) サイコアナライザー/p64
III. 治療に関する検討/p82
A. 従来,行われてきた治療法/p82
1. 心理療法/p82
1) 支持療法/p83
2) 表現療法/p83
3) 洞察療法/p85
4) 訓練療法/p85
5) 催眠療法/p86
6) 精神分析療法/p87
7) 森田療法/p87
8) 自律訓練法/p88
|
9) 白隠内観法/p88
2. 薬物療法/p90
1) クロールジアゼポキサイド/p91
2) インシドン/p91
3) ジアゼパム/p92
3. 電撃療法/p93
4. 持続睡眠療法/p94
5. 絶食療法/p94
B. 新しい治療法/p95
1. 新しい向精神薬のスクリーニング・テスト/p96
2. 系統的PSD療法としての自己鍛練法/p105
1) 絶食療法/p105
2) 自律訓練法/p109
3) イメージ法/p115
4) 生活指導/p118
IV. むすび/p121
参考文献/p122
附) 心身症クリニーク・カルテ(実例)/p125
・ |
○、この年、佐藤得二が「仏教の日本的展開」を「桂書房」から刊行する。 pid/2979569
|
緒論 奈良朝までの概観 / p3
イ 渡来と弘布 / p3
ロ 権勢と腐敗 / p9
第一章 世界観の鍛錬 / p12
一 最澄と空海 / p12
二 天台の教理 / p18
イ 円融三諦 / p18
ロ 一念三千 / p24
ハ 天台の教判 / p29
三 真言の教理 / p34
イ 六大体大と四曼 / p34
ロ 三密と阿字本不生 / p44
四 二宗の堕落 / p50
第二章 因果法の緊縛 / p56
一 平安朝民衆の信仰 / p56
イ 神と仏 / p57
ロ 因果応報 / p60
二 因果の教理 / p64
三 小乗と大乗 / p67
四 因果の脅迫 / p69
第三章 浄土の幻影 / p72
一 厭世思想 / p72
二 阿弥陀仏と誓願 / p74 |
三 黎明つぐる往生要集 / p78
イ 厭離穢土門 / p80
ロ 欣求浄土門 / p85
ハ 残された二つの使命 / p89
四 智慧は往生に要なし / p90
イ 法然上人 / p90
ロ 選択本願念仏集 / p95
五 弥陀にはからわれまつる道 / p103
イ 親鸞上人 / p103
ロ 真の福音 / p111
ハ 戒律を越えて / p115
ニ 絶対他力 / p118
第四章 己心の認得 / p123
一 脚下照顧の道 / p123
イ 達磨大師 / p123
ロ 師弟の道 / p135
ニ 大いなる哉心や / p144
イ 栄西禅師 / p144
ロ 興禅護国論 / p146
ハ 妙超と白隠 / p156
三 身をあらい心を洗う / p162
イ 道元禅師 / p162
ロ 葛藤を纏う / p178 |
ハ まさしく面を洗う / p192
四 道元の訓える学道の用心 / p204
イ 為他の志気 / p204
ロ 愛名は犯禁よりも悪し / p211
ハ 衣糧を煩う勿れ / p219
ニ 豊屋は邪命に依る / p226
第五章 国家と教法者 / p233
一 時嶮しくして法翳る / p233
イ 日蓮上人 / p233
ロ 法に依りて人に依らず / p240
ハ 徹底は力なり / p248
二 正法を立てて国を安んぜん / p252
イ 立正安国論 / p252
ロ 破邪の道 / p260
ハ 平民的信仰 / p272
ニ 仇敵に依る鍛錬 / p280
三 山に隠れて国家を祈る / p285
イ 最後の仇 / p285
ロ 日蓮と現代 / p296
余録 / p308
年表 / p312
・
・ |
○、この年、山田無文が「手をあわせる」を「春秋社」から刊行する。 (しんじん文庫 ; 第3集) pid/2968841
|
はしがき / p1
手をあわせる / p9
わが心の遍歴 / p51
母をかたる / p99
禅のさとり / p105
禅とは心の名 / p127
大歓喜へさそう / p133 |
大燈国師―私の好きな日本人(I) / p139
白隠禅師―私の好きな日本人(II) / p145
枯淡の味 / p151
憶いでの嵐山 / p157
中国で何を見たか / p165
中国で何を聞いたか / p171
中国の宗教政策 / p177 |
真理の芽生え / p185
立って歩く / p191
東西のかけ橋 / p195
川口慧海師もことども(斎藤佐次郎) / p201
・
・
・ |
|
| 1966 |
41 |
・ |
2月、徳力富吉郎が「だるま」を「三彩社」から刊行する。 (三彩ガイドブック) pid/2508841
また、「同本 p62」に「法輪寺蔵の白隠禅師筆達磨大師図」が掲載される。
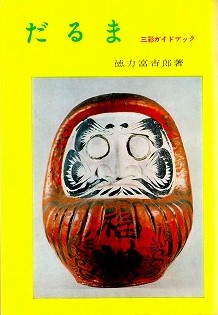  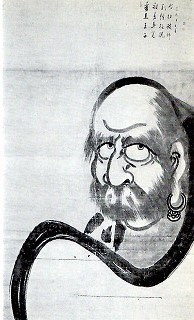 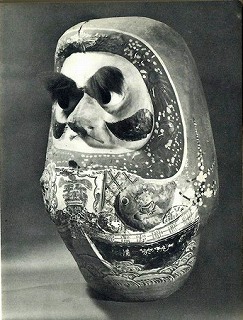 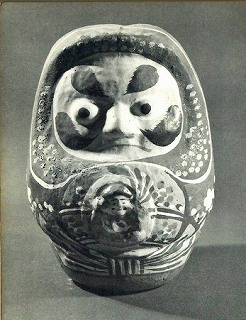
徳力富吉郎著「だるま」の表紙 同本p62に描かれた達磨大師図(法輪寺蔵) 達磨像(三州 正宗寺蔵) 2仙台だるま(寶船) 3 仙台だるま(大黒天)
|
序/p7
一 だるまさん/p9
二 達磨大師/p12
三 聖徳太子と達磨大師の
→不思議な出会い/p15
四 起上り小法師/p19
五 茶禅一味の達磨/p22
六 俗信仰と達磨/p24
七 朝日に輝やく/p26
|
八 達磨の俳句/p28
九 酔な達磨/p31
十 だるまの玩具(附不倒翁のこと)/p33
十一 目無しだるま/p41
十二 達磨市の歴史/p46
十三 達磨の狂歌と川柳/p47
十四 達磨と性神/p49
十五 達磨市/p52
十六 起上り達磨の生産地/p54
|
十七 京都にできた新達磨堂/p66
図版解説/p69
あとがき/p75
口絵 目次<グラビヤ>
<東北地方>
<関東地方>
<中部地方>
<近畿地方>
<中国地方>
|
<四国地方>
<九州地方>
<沖縄>
<大韓民国>
<中華人民共和国>
<その他>
・
・
・ |
3月、「禅文化 (40))が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082235
|
グラフ 永源寺と寂室禅師=Photos: Eigenji Temple in Shiga Pref.
→and Calligraphy of Jyakushitsu Zenji
臨済録新講 臨濟録新講その三=Articles: A Special Discourse on the
→Rinzai-roku (Lin-chi lu) / 山田無文/p4~12
寂室元光の生涯=Articles: Life of Jyakushitsu Zenji /古田紹欽/p30~37
寂室禅師の風藻=Articles: Zen Poems written by Jykushitsu Zenji /
→福島俊翁/p18~27
永源寺行 / 井伊文子/p38~41
私の読書遍歴 / 山田無文/p42~50
狼玄楼と白隠和尚=Articles: kami-genr, Soto-Zen
→Master, and Hakuin Zenji / 陸川堆雲/p51~53
禅宗史話 永明延寿の思想と実践=Articles: A Talk on the Zen
|
→Patriachs(10)Eimei Enjyu, Yung-ming Yen-shou (904-975) and
→His School /荻須純道/p74~80
清韓をめぐる五山の学侶=Articles: Seikan Bunei Zenji and the Zen
→Buddhist Scholars Surrounding Him / 加藤正俊/p62~67
ブッダ伝(二)=Articles: Buddhist History of India (VI)/春日井真也/p54~59
柳沢里恭と禅=Articles: My Literary Meanderings/山田重正/p13~17
わが道場 宝福寺 / 岡田□道/p28~29
大学の禅会 日本女子大学微笑禅会/田中怜子/p60~61
慈眼堂と洗心寮 / 大山澄太/p68~71
回顧と展望 / 木村静雄/p72~73
書灯/p41~41,50~50,71~71,73~73
・ |
5月、村田全, 茂木勇が「数学の思想」を「日本放送出版協会」から刊行する。
(NHKブックス) pid/1381580
|
はしがき/p3
第I部 その底に流れるもの/p9
I 学問か数学となる/p10
1 数学と創造的精神/p10
2 ギリシャの数学/p17
3 中世の四科・近世の数学/p25
II ユークリッドへの道―論証について―/p38
1 『原論』と論証の精神/p38
2 数か図形か/p49
3 『原論』の起源を求めて/p56
4 ふたたび論証の精神について/p63
III 零が使われるまで―記数法について―/p69
1 インドの"数学"的知識/p69
2 位取り記数法/p73 |
IV 不可能の証明
→―記号の方法について―/p83
1 三つの不可能問題/p83
2 記号代数の歩み/p94
V 数学的無限論の問題/p105
1 数学史における無限像/p105
2 ギリシャの求積法/p113
3 無限を捉える/p121
VI 微分積分学への道―
→一つの記号的無限小数学―/p132
1 求積問題と接線問題/p132
2 微分積分学という体系/p149
第II部 現代数学の背景/p161
VII 数と図形/p162
|
1 実の数・虚の数/p162
2 方程式の根を求めて/p172
3 ユークリッドの幾何学を超えて/p181
4 位置と形相の幾何学/p197
VIII 集合と構造/p206
1 はじめに集合あり/p206
2 公理的方法/P220
3 代数的構造のいろいろ/p228
4 位相的構造とは/p244
IX 現代に生きる数学/p254
1 偶然の処理/p254
2 オペレーションズ・リサーチ(O・R)/p261
3 電子計算機/p272
4 数学は生きている/p281 |
6月、「墨美 (157)」が「墨美社」から刊行される。 pid/2362477
|
特集・日本の国宝--書/2~41
那須国造碑 //4~4
宇治橋断碑 //5~5
多胡郡碑 //6~6
王羲之書 孔侍中帖 //8~8
光明皇后臨 楽毅論 //9~9
顔真卿書 争座位稿 //11~11
空海書 灌頂歴名 //12~12
空海書 三十帖策子 //15~15 |
空海書 風信帖 //16~16
空海書 七祖像賛 //17~17
藤原行成書 白氏詩巻 //19~19
高野切第一種 //20~20
曼殊院古今集 //21~21
藤原伊房書 十五番歌合 //23~23
伝藤原俊成書 詞花集切 //24~24
伝藤原定家書 小倉色紙 //25~25
大燈国師書 関山字号 //27~27 |
白隠書 忍字 //28~28
良寛書 酒の歌 //29~29
後鳥羽上皇宸翰 熊野懐紙 //33~33
蘇東坡書 寒食帖 //36~36
日本の国宝・書--NHK教養特集(座談会)/吉川幸次郎/2~37
書における「読む」ということ / 森田子竜/38~41
現代美術における伝統 / 森田子龍/42~42
・
・ |
7月12日、鈴木大拙が亡くなる。(95歳)
9月、「禅文化 (40) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082235
|
グラフ 永源寺と寂室禅師=Photos: Eigenji Temple in Shiga Pref. and Calligraphy of Jyakushitsu Zenji
臨済録新講 臨濟録新講その三=Articles: A Special Discourse on the Rinzai-roku (Lin-chi lu) / 山田無文 / p4~12
寂室元光の生涯=Articles: Life of Jyakushitsu Zenji / 古田紹欽 / p30~37
寂室禅師の風藻=Articles: Zen Poems written by Jykushitsu Zenji / 福島俊翁 / p18~27
永源寺行 / 井伊文子 / p38~41
私の読書遍歴 / 山田無文 / p42~50
狼玄楼と白隠和尚=Articles: kami-genr, Soto-Zen Master, and Hakuin Zenji / 陸川堆雲 / p51~53
禅宗史話 永明延寿の思想と実践=Articles: A Talk on the Zen Patriachs(10)Eimei Enjyu, Yung-ming Yen-shou
(904-975) and His School / 荻須純道 / p74~80
清韓をめぐる五山の学侶=Articles: Seikan Bunei Zenji and the Zen Buddhist Scholars Surrounding
Him / 加藤正俊 / p62~67
ブッダ伝(二)=Articles: Buddhist History of India (VI) / 春日井真也 / p54~59
柳沢里恭と禅=Articles: My Literary Meanderings / 山田重正 / p13~17
わが道場 宝福寺 / 岡田□道 / p28~29
大学の禅会 日本女子大学微笑禅会 / 田中怜子 / p60~61
慈眼堂と洗心寮 / 大山澄太 / p68~71
回顧と展望 / 木村静雄 / p72~73
書灯 / p41~41,50~50,71~71,73~73 |
11月、三彩社編「古美術 (15) 」が「三彩社」から刊行される。 pid/6063310
|
特集・押出仏 / 9~58
原色版 押出阿弥陀三尊及び二比丘像
→<東京国立博物館蔵> / p9~9
原色版 押出阿弥陀三尊像 / p10~10
原色版 押出如来三尊像 / p11~11
原色版 押出半跏思惟像 / p12~12
原色版 薩摩切子鉢 / p77~78
原色版 長谷寺縁起絵巻 / p83~84
原色版 聖一国師墨跡 / p85~87
原色版 青釉黒彩透彫花文装飾瓶/p93~94
原色版 織部黒茶碗 / p95~96
原色版 祥瑞鳥摘茶器 / p101~102
原色版 殷饕餮文方鼎 / p103~104
グラビヤ 押出仏 / p13~28
グラビヤ 打出しの技法 / p51~54
グラビヤ 浄土寺 / p115~122
写真版 押出仏 / p29~30
写真版 海雲百拙の作品 / p59~62
写真版 白隠の手紙 / p110~111
|
表紙 押出千体仏
押出仏について / 久野健 / p31~48
押出仏技法考 / 石田尚豊 / p49~50,55~58
名品鑑賞 薩摩切子鉢 / 岡田譲 / p79~80
名品鑑賞 長谷寺縁起 / 宮次男 / p81~82
名品鑑賞 東福寺開山 聖一国師の墨蹟 / 田山方南 / p88~89
青釉黒彩透彫花文装飾瓶 / 深井晋司 / p90~92
名品鑑賞 織部黒茶碗 / 加藤土師萌 / p97~98
名品鑑賞 祥瑞鳥摘茶器 / 十和田湖月 / p99~100
殷周の方鼎について / 水野清一 / p105~108
播磨別所--浄土寺 / 永井信一 / p123~129
海雲百拙の画蹟・法蔵寺の作品を中心に--新資料紹介-8-/大槻幹郎/p63~67
八百善老人古美術放談--古美術夜話-2- / 井上昇三 / p68~73
白隠の手紙・その教団形成--日本の手紙-15-/竹内尚次/p109~109,112~112
滴翆美術館--美術館探訪-14- / 田中日佐夫 / p130~131
読書欄 / 杉山二郎 / p131~132
古美術用語解説--絵画篇-1- / 鷲塚泰光 / p133~135
編集雑記 / p136~136
・ |
○、この年、紀野一義が「禅 : 現代に生きるもの」を「日本放送出版協会」から刊行する。
(NHKブックス) pid/2969947
|
第一章 坐禅と禅/p11
無明の中にうごめくもの
空しさと空と歳月
第二章 沈黙と禅/p21
沈黙の世界
沈黙と寂
ことばは杭の如く突っ立つ
いのちの賭け
リルケの詩
鳥の歌うが如く
永遠につながる話
底抜け
第三章 色即是空 空即是色/p55
虚空を遍歴するような人生
むなしさと仏のいのち
死ねば仏のいのちに帰る
徒労に賭けるいのち
夏の夜の怪異
君看よ双眼の色語らざれば
→憂いなきに似たり
|
無限の桃花水を逐うて流る
命二つの中に生たる桜かな
結語
第四章 唐時代の巨匠たち/p97
大悲の風動く六祖慧能
心は虚空のごとし 馬祖道一
柄が何になる 石頭希遷
高高たる山上に向って立ち深深たる
→海底に行くべし 薬山惟儼
願わくは婆婆の永えに苦海に
→沈まんことを 趙州従〔シン〕
独坐大雄峯 百丈懐海
凛々たる孤風 黄檗希運
豪放悪辣な臨済将軍の風 臨済義玄
父母未生已前の汝 〔イ〕山霊祐
道い得るも三十棒道い得ざるも
→三十棒 徳山宣艦
第五章 日本の禅匠たち/p149
父母の縁尽きなば 夢窓国師
学道の人は貧なるべし 道元禅師
|
死してなお師のかたわらを去らず 孤雲懐奘
漆黒の暗夜に悟る 一休宗純(一)
雀を葬る一休 一休宗純(二)
ただ土になりて念仏修業せらるべし 鈴木正三
仏にならぬが仏 至道無難禅師
仏が喜び仏が呼ぶ 盤珪禅師
南無地獄大菩薩 白隠禅師
仙桂和尚は真の道者 良寛和尚
山岡鉄舟の真面目
終戦の詔勅と玄峰老師 山本玄峰
第六章 禅と文化/p207
花を見て花を見ず
墨絵の世界
茶道と能と一休
桑山左近の露地庭と慈光院
無茶という茶
無法と宗教と芸術
松平不昧公の慎独
井伊直弼の独座観念
・ |
○、この年、淡川康一が「茶掛としての禅画」を「河原書店」から刊行する。 (日本の美と教養) pid/2509166
|
自序
緒説 / p1
第一章 禅文化としての宋元古画 / p5
第二章 禅画の流派より見たる南画と北画/p35
第三章 禅画としての足利水墨画 / p43
第四章 古墨蹟 / p58
第五章 古墨蹟の書風とその語句 / p77
第六章 近世の禅画 / p86
第一節 風外慧薫と一絲文守 / p97
第二節 白隠 / p108
第三節 白隠系統の禅画 / p128
第四節 古月系統の禅画、特に仙厓と誠拙/p152
第五節 居士の禅画と禅家の南画 / p174
結語 / p180
図版
一 白隠作 隻手布袋図 / p205
二 白隠作 摺鉢図 / p207
三 仙厓作 寒山拾得図 / p209
四 仙厓作 臨済栽松図 / p211
五 仙厓作 三福人図 / p213
六 仙厓作 利休図 / p215
七 仙厓作 盲人提燈図 / p217
八 卓洲作 半身達磨図 / p219
九 雪潭作 布袋瞎睡図 / p221 |
一〇 愚渓作 睡り布袋図 / p223
一一 猷禅作 墨梅図 / p225
一二 大綱作 円相 / p227
一三 霊源作 舟中布袋図 / p229
一四 弘巌作 住吉社頭図 / p231
一五 遂翁作 臨済钁地図 / p233
一六 風外慧薫作 蘆葉達磨図 / p235
一七 風外本高作 淡彩山水図 / p237
一八 心越作 水墨山水図
→(神吉主膳讃) / p239
一九 無学文奕作 茶碗羽箒図 / p241
二〇 南天棒作 祖師面壁図 / p243 (
二一 洪川作 円相 / p245
二二 東嶺作 瓢図 / p247
二三 隠山作 三十棒図 / p249
二四 中野龍田作 水墨山水図 / p251
二五 梧庵作 飛泉図 / p253
二六 方巌作 煎茶器図 / p255
二七 山添蠖軒作 徳山焼経図 / p257
二八 大釜菰堂作 西瓜蜻蛉図 / p259
二九 近重物安作 和敬清寂図 / p261
三〇 物先作 懶□〔ラサン〕芋図 / p263
三一 大綱筆 「空華室日記」
→中の一節 / p265 |
三二 黙雷作 半身達磨図 / p267
三三 東海作 枯柳蒼鷹図 / p269
三四 東嶺作 主人公図 / p271
三五 大巓作 半身達磨図
→(松平不昧讃)/p273
附録第一 欧洲における近世禅画展/p275
附録第二 禅画の十二個月
→(筆者拙墨)/p285
正月 寿老乗亀図 / p287
二月 大黒天像 / p289
三月 蜆子和尚図 / p291
四月 釣釜図 / p293
五月 鍾馗図 / p295
六月 香厳撃竹図 / p297
七月 瓜図 / p299
八月 葡萄図 / p301
九月 布袋指月図 / p303
十月 達磨図 / p305
十一月 寒山拾得図 / p307
十二月 財神釣河豚図 / p309
牧童図 / p311
布袋和尚図 / p313
永源寺偶成 / p315
・ |
○、この年、桑原住雄が「日本の自画像」を「南北社」から刊行する。 pid/2510552
|
藤原信実「中殿御会図」(模本)部分/p1
吉山明兆「自画頂相」/p3
雪舟/p5
松花堂昭乗「自画像」/p7
岩佐又兵衛/p9
円空「自刻像」/p11
池大雅「三上考軒池大雅対話図」/p13
白隠「円相内自画像」/p15
良寛「自画賛」/p17
木食「自刻像」/p19
谷文晁/p21
司馬江漢/p23
田能村竹田「自画賛」/p25
葛飾北斎「自画像」/p27
岡田三郎助「自画像」/p29
熊谷守一「ローソク」/p31
萬鉄五郎「雲のある自画像」/p33
前田寛治「自画像」/p35
高村光太郎「自画像」/p37
木村荘八「自画像」/p39
須田国太郎「自像」/p41
岸田劉生「自画像」/p43
有島生馬「十月亭自像」/p45
黒田清輝「自画像」/p47
関根正二「自画像」/p49
林重義「自画像」/p51
久保守「自画像」/p53
中村彝「髑髏を持てる自画像」/p55
清水多嘉示「自画像」/p57
青木繁「自画像」/p59
|
梅原竜三郎「自画像」/p61
安井曽太郎「自画像」/p63
中川紀元「自画像」/p65
向井潤吉「自画像」/p67
海老原喜之助「自画像」/p69
木内克「自画像」/p71
甲斐仁代「自画像」/p73
小出楢重「帽子をかぶった自画像」/p75
佐伯祐三「自画像」/p77
岡鹿之助「自画像」/p79
杉本健吉「自分の顔」/p81
長谷川利行「自画像」/p83
角浩「自画像」/p85
福沢一郎「自画像」/p87
田村一男「自画像」/p89
三雲祥之助「自画像」/p91
山口薫「自画像」/p93
坂本繁二郎「自像」/p95
石井柏亭「自画像」/p97
竹久夢二「旅」/p99
小川芋銭「自画像」/p101
牧野虎雄「自画像」/p103
荻須高徳「自画像」/p105
野口弥太郎「自画像」/p107
佐藤忠良「自画像」/p109
麻生三郎「自画像」/p111
児島善三郎/p113
森芳雄「自画像(少年期)」/p115
松本竣介「画家の像」/p117
仲田好江「自画像」/p119 |
小泉清「自画像」/p121
石井鶴三「緑陰裸身」/p123
靉光「枯木のある自画像」/p125
北脇昇「自我像(蓋然の像)」/p127
朝井閑右衛門「涅槃像」/p129
太田聴雨「二河白道を描く」/p131
辻永「自画像」/p133
横山大観「座右銘」/p135
川端実「ガラス工場」/p137
関野準一郎「オカリナ吹き」/p139
鶴岡政男「喰う」/p141
浜田知明「歩哨」」/p143
佐野繁次郎「自画像」/p145
村井正誠「大きな顔」/p147
中村研一「自画像」/p149
中村岳陵/p151
前田青邨「自頭」/p153
朝倉摂「告発’61」/p155
小倉遊亀「画人像」/p157
北川民次「画家の家族」/p159
中山巍「室内」/p161
宮本三郎「妻と私と」/p163
高畠達四郎「画家と家族」/p165
井上長三郎「落馬」/p167
森田元子「黒衣」/p169
香月泰男「神農」/p171
棟方志功「好麗自板像」/p173
池田満寿夫「私をみつめる私」/p175
・
・ |
|
| 1967 |
42 |
・ |
3月、岡山大学教養部編「岡山大学教養部紀要 (3) 」が刊行される。 pid/1768956
|
アイリス・マードックの「鐘」の象徴手法 / 菅好雄 / 1
J.D.Salinger;NINE STORIESと白隠「隻手の音声」(公案) / 安藤正瑛 / 29
I.マードック論--Against Drynessの実践 / 室谷洋三 / 55
Hebbelにおける「個」と「全」の関係--殊に悲劇<Herodes und Mariamne>に関連して
/ 小島康男 / 91
Port-Royalの成立過程-2- / 岡部喬 / 113
対島の僻地的部落のこどもの人格とその背景についての調査報告--特に諸種の知能検査の結果を中心として
/ 南条正明 / 125
岡山市民の憲法意識 / 上野裕久 / 1 |
3月、 「ノートルダム清心女子大学紀要. Kiyo (3)」が「 ノートルダム清心女子大学英文学科」から刊行される。 pid/2221445
|
Caliban's Dream: Kainos and Kairos in The Tempest / Sister Frances St.Anne O'Keefe ; S.N ; D. / p1~17
Hawthorneの人間観と孤独の問題 / 小田朗美 / 19~27
Theatre of the Absurd: Valid Theatre or Outrageous Impostor? / Sister Adrian
Woerl ; S.N.D. / p29~69
J.D.Salinger(1919-)と「隻手の音声」(公案)--"A Perfect Day for Bananafish"(1948)の場合 / 安藤正瑛 / 71~90
Henry James's The Wings of the Dove――Spirituality and Materialism / Yuzuru
Nobuoka / p91~104
ゴールズワージーのフォーサイト物語りを中心として / 矢野万里 / 105~118
Between Conception and Creation: A Study of the Historicity of Shaw's Saint Joan / Sister Francesca Dunfey ; S.N.D. / p119~135
Ambiguity in Emily Dickinson / Sister Ellen Mary Hickey ; S.N.D. / p137~147 |
3月、東嶺禅師御撰:禅文化研究所資料室編「白隠禅師年譜」が「龍澤寺」から刊行される。
龍澤開祖神機独妙禅師年譜 折り込図(白隠史蹟略図)あり
6月、「禅文化 (45) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082240
|
表紙 白隠和尚筆 「定」
白隠禅師二百年遠諱記念講演 勇猛の二字/山田無文/p4~8
白隠と大雅 / 竹内尚次 / p32~45
沙門白隠の周辺--東嶺・遂翁両和尚と
→住吉屋文五郎の遺墨 / 秋山寛治 / p18~25
白隠の道場に眠る修業僧たち / 鈴木富次郎 / p46~47
大拙翁との出会い / 森本省念 / p26~31
寒山詩私解(八) / 福嶋俊翁 / p9~16 |
禅宗史話 大慧宗杲 / 荻須純道 / p74~80
歴史の中の禅 / 西村恵信 / p48~54
不徹寺蔵の盤珪国師の書翰について/藤本槌重/p62~71
随想 曹源一滴 / 清水公照 / p55~59
海外の窓 台湾の仏教事情 / 藤吉慈海 / p60~61
海外の窓 一万坐運動 / 奥田仁芳 / p72~73
書灯 / p8~8,17~17,59~59,73~73
・ |
10月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 44(9)(536)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885412
|
黄檗宗における白隠下の法燈 / 秋月竜珉 / p3~3
わが半生の記 / 村瀬玄妙 / p4~12
月桂寺禅話(3) / 松尾太年 / p13~21
陽の当らぬ場所 / 鎌田禅商 / p22~27
正法眼臓物語(10) / 永久岳水 / p28~32,39~39 |
続・妙好人について(1) / 楠恭 / p33~39
インドを旅して(15) / 千地琇也 / p40~47
宗門無尽燈論(3) / 東嶺禅師 / p48~52
編集後記 / 秋月竜珉 / p54~54
・ |
12月、生長勇が「精神身体医学 7(6) 1 p.384」に「白隠弾師の内観法「軟酥(なんそ)の法」(治療)(第8回日本精神身体医学会総会)」を発表する。
|
江戸時代中期の禅の高僧・白隠は、自ら病に苦しみながら丹田呼吸法・内観の法によって快癒した。それを記した『夜船閑話』を通して、心と体の一致を追い求めたその生涯をたどる。 |
○、この年、生長勇が「臨床心身医学」を「朝倉書店」から刊行する。 pid/1382353
|
1 心身医学の概念/p1
(1) 心身医学とはどのようなものか/p1
(2) 心身症とはどのように理解したらよいか/p2
(3) 地球の地面に立ち上がった動物が人間である/p3
2 心を科学する/p7
(1) 脳のはたらき/p7
(2) 大脳辺縁系と辺縁皮質/p9
(3) 感覚/p10
3 心と体を結ぶかけ橋/p13
(1) 内部環境と外部環境/p13
(2) 自律神経系/p15
(3) 視床下部/p17
1) 視床下部と性行動/p18
2) 視床下部と脳下垂体/p19
(4) 内分泌/p20
1) 副腎皮質ホルモン/p20
2) ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)/p21
3) 消化性潰瘍とACTH,副腎皮質ホルモンACH/p22
4 本能と情動/p24
(1) 病は心から/p26
(2) 騎手と馬/p26
5 知能と記憶/p29
6 心身症を三つに大別する/p32
(1) 深層心因性の心身症/p32
(2) 中層心因性の心身症/p38
1) 病気は幼児期につくられる/p38
(3) 表層心因性の心身症/p44
7 心身症とその周辺/p51
(1) 眠り/p51
(2) 眠りの型/p52 |
(3) 夢のない睡眠はあるか/p53
(4) 不眠症/p54
(5) ノイローゼによる不眠/p55
(6) 眠りと注意の集中/p56
(7) 夢遊病と寝ぼけ/p58
(8) 精神疾患による不眠/p58
(9) 心身症は精神病ではない/p59
8 胃腸は情動の反響板である/p62
(1) 怒りの胃と消化性潰瘍/p65
(2) 憂うつの骨と癌/p68
(3) 胃癌になったらもう遅い/p76
(4) 腸の病/p78
1) 刺激結腸/p78
2) 虫垂炎/p81
(5) その他の腹部神経症/p85
1) 空気嚥下症(呑気症)/p85
2) 内臓下垂症(胃下垂症を主とす)/p86
3) 神経性腹部緊満症/p86
(6) 胆嚢・胆道疾患/p86
1) 胆道ジスキネジー/p86
2) 胆道系の神経調節/p88
3) 癪の病はなぜ婦人に多いのか/p89
4) 胆道ジスキネジーと
→狭心症様症状群/p91
9 医源性疾患/p93
(1) 心臓神経症/p95
(2) Poly Surgery Caseおよび
→術後癒着症/p98
10 薬病両忘/p106
(付) 心身医学で取扱う病気/p108 |
11 治療/p111
(1) 催眠/p112
(2) 他者催眠/p113
(3) 森田療法/p114
(4) 自己催眠/p115
1) 自律訓練法/p115
2) ヨガと禅/p117
(5) 生長(Ikenaga)の自己催眠/p120
1) 自隠禅師の内観法/p121
2) 心を手術する/p128
3) 二念を継がず/p129
4) 弛緩/p131
5) 言葉暗示/p132
6) 言葉の身体支配/p132
7) 言葉暗示による治療/p133
8) 特殊言葉暗示/p136
9) 軟酥の法/p136
12 治験例/p140
13 心身症発生の素質と忍容力/p165
(1) 可愛い子には旅をさせよ/p166
(2) 未見の我/p170
14 心の平和を守る三つの原則/p174
(1) 仲よく生きねばならない/p174
(2) 楽しく生きねばならない/p178
(3) 正しく生きねばならない/p183
15 西洋医学と東洋の知恵/p188
参考文献/p193
索引/p195
・
・ |
〇この年、「大正新脩大蔵経 第81巻 (続諸宗部 12) 」が「大正新脩大蔵経刊行会」から再版される。 pid/3000963
※高楠順次郎編「大正新脩大蔵経 第八十一巻 」(1931年版) 再版かについては未確認 2022・12・21 保坂
|
二五六二 常光國師語録(二卷) 日本 空谷明関應語 侍者 編 / p1
二五六三 大通禪師語録(六卷) 日本 愚中周及語 侍者某甲 編/p46
二五六四 永源寂室和尚語録(二卷) 日本 寂室玄光語 / p101
二五六五 佛頂國師語録(五卷) 日本 一絲文守語 文光 編/p136
二五六六 大燈國師語録(三卷) 日本 宗峯妙超語 侍者性智等 編/p191
二五六七 徹翁和尚語録(二卷) 日本 徹翁義享語 遠孫禪興 編/p242
二五七八 雪江和尚語録(一卷) 日本 雪江宗深語 遠孫禪悦輯/p271
二五六九 景川和尚語録(二卷) 日本 景川宗隆語 侍者某等 編/p286
二五七〇 虎穴録(二卷) 日本 悟溪宗頓語 門仁某等 編 /p313
二五七一 小林無孔笛(六卷) 日本 東陽英朝語 侍者某等 編/p347 |
二五七二 見桃録(四卷) 日本 大休宗林語 遠孫比丘等 編/p412
二五七三 西源特芳和?語録(三卷) 日本
→特芳禪傑語 遠孫宗怡重 編/p479
二五七四 槐安國語(七卷) 日本 白隱慧鶴語 / p511
二五七五 宗門無盡燈論(二卷) 日本 東嶺圓慈 撰 / p581
二五七六 五家參祥要路門(五卷) 日本 東嶺圓慈 編 / p605
二五七七 大鑑淸規(一卷) 日本 清拙正澄 撰 / p619
二五七八 諸回向淸規(五卷) 日本 天倫楓隱 撰 / p624
二五七九 小叢林淸規(三卷) 日本 無著道忠 撰 / p688
・ |
○、この年、西谷啓治編、鈴木大拙監修「講座禅 第4巻 (禅の歴史 日本)」が「筑摩書房」から刊行される。 pid/2969745
|
日本禅宗史―臨済宗―吉田紹欽 / p5
日本禅宗史―曹洞宗―鏡島元隆 / p89
日本における臨済禅の展開―大森曹玄/p127
日本における曹洞禅の展開―竹内道雄/p149
道元―榑林晧堂 / p175
峨山―佐橋法龍 / p193 |
大燈―荻須純道 / p203
夢窓―平田高士 / p233
一休―平野宗浄 / p249
無難―辻雙明 / p263
沢庵―永田豊州 / p275
白隠―通山宗鶴 / p289 |
盤珪―藤本槌重 / p309
鉄眼―赤松晋明 / p327
寂室―関雄峰 / p337
抜隊―三輪燈外 / p351
山岡鉄舟―大森曹玄 / p361
日本の禅(座談会) 苧坂光龍 唐木順三 芳賀幸四郎/p373 |
○、この年、柳田聖山が「臨済の家風」を「筑摩書房」から刊行する。 (日本の仏教 ; 第9巻) pid/3004655
|
はじめに
第一の章 興禅護国論〔栄西〕
一 仏教のふるさと / p5
末法思想
山を下る聖たち
インドへの里程
二 葉上の流れ / p26
入宋沙門栄西
密教の菩提心
日本仏教の中興
三 大いなるかな心や / p47
『興禅護国論』の成立
王法と仏法
禅宗の独立
四 鎌倉の新星 / p69
寿福寺と建仁寺
僧は貧なるべし
喫茶の功徳
第二の章 夢中問答〔夢窓〕 |
一 バサラの時代 / p91
喫茶往来
乱世の徒然
放下の禅師
二 幻住の思想 / p108
九想の図
ひとり坐禅
投機の偈
名聞を逃れて
理致と機関
三 あえて世間に入る / p133
太平興国南禅寺
一片の間雲変態多し
密教と浄土教
坐禅石の庭
第三の章 龍宝語録〔大灯〕
一 二十年来辛苦の人 / p159
書写山に祈る
雲門の再来 |
祥雲庵夜話
二 教外別伝の立場 / p173
正中の宗論
億刧相い別れて
古仏の家風
三 日本禅の胎動 / p184
花園院の批評
五山の文化
心の師となりて
第四の章 遠羅天釜〔白隠〕
一 江戸の新仏教 / p201
黄檗山万福寺の開創
関東ラッパ
美濃のばんたろう
二 白隠誕生 / p214
地獄の匂い
自叙伝の試み
古人刻苦光明必ず盛大なり
三 五百年間出の人 / p229 |
正師に遇う
禅の宗教改革
法施のつとめ
四 隻手の工夫 / p243
隻手に何の声かある
大疑の下に大悟あり
相似禅を破析する
五 新しい日本禅の出発 / p257
大陸仏教を叱る
一粒の麦もし死なば
悟後の修行
六 痴聖の遊戯 / p269
禅画の世界
シジフォスの神話
参考文献 / p279
年表 /
・
・
・ |
○、この年、武者小路実篤が「わが道を生きた人たち : 愛される偉人像」を「芳賀書店
」から刊行する。 (青春の手帖) pid/2998038
|
日蓮と千日尼/p3
白隠/p19
仙涯和尚/p28
一休と地獄太夫/p41
|
牧谿と梁楷/p66
池の大雅/p124
マチス、ルオー、ドラン、ピカソ訪問記/p146
ユダの弁解/p168
|
宮本武蔵/p176
黒田如水/p193
黒住宗忠/p207
・ |
○、この年、古田紹欽が「禅の文化」を「角川書店」から刊行する。 (角川新書) pid/2968719
|
はじめに / p3
序説 / p9
禅文化の位置 / p10
禅宗と禅 / p12
静的禅と動的禅 / p13
大陸文化の日本的消化 / p16
日本独特の禅文化 / p17
禅の芸術―浄土教芸術との対比―
禅・浄芸術の素地 / p22
禅宗と浄土教の特質 / p24
浄土教芸術以前の問題 / p26
華麗な浄土教芸術 / p30
禅の「仏」のとらえ方 / p32
浄土教芸術の限界 / p35
禅芸術の可能性 / p36
禅画と水墨画 / p38
ひょうたんなまず / p39
花を開く画師 / p40
禅・浄の美意識の違い / p43
禅浄一教思想 / p45
禅と文学 / p49
|
多い禅宗文献 / p50
五山文学の確立 / p51
瓢鮎図の賛 / p54
禅宗仮名法語 / p57
沢庵と和歌 / p59
白隠の農民文学 / p60
禅と武術 / p63
活人剣とは / p64
盤珪禅師の兵法 / p66
無心の心 / p68
敵もなく我もなし / p70
心外無兵法 / p71
能と禅 / p75
金春禅竹 / p76
『六輪一露之記』 / p77
密教的影響 / p78
無相の一理に帰す / p82
理想即現実 / p84
総合・完成の美 / p86
習道上の悟り / p89
謡曲「芭蕉」 / p90
|
悟りの境地 / p93
耳に見つ目にきく / p95
禅と茶 / p99
茶の精神 / p100
禅茶の伝統 / p100
珠光の茶の精神 / p103
茶禅一体を確立した紹歐と利休/p107
仏祖の行ないのあとを学ぶ/p110
無一物即無尽蔵の世界 / p113
茶の実践 / p120
体験的認識 / p120
仏教文化の今日的意義/p122
松平不味の実践 / p126
大円鏡中独楽自在の境地/p128
喫茶喫飯六十八年の遺偈/p131
禅と庭 / p135
夢窓・大灯の築庭 / p136
即心即仏・非心非仏 / p141
心の世界でみる庭 / p143
茶室と露地 / p144
墨跡 / p151 |
茶室の物掛け / p152
書跡と墨跡の違い / p153
「文句の心」をみる / p155
書は人を現す / p157
大灯・夢窓・一休の墨跡/p158
書の自由さと無限さ / p160
禅画 / p163
禅画と普通絵画との違い/p164
禅と自由 / p166
禅的自由と作品 / p168
絵に禅をみる / p170
真空妙有 / p172
散るゆえ花は美しい / p174
「無」の禅 / p176
絶対「無」とは / p178
月か団子か桶の輪か / p180
禅画の画法 / p181
墨の無限性 / p183
描かれている空白 / p186
・
・ |
○、この年、関谷義道が「漢字学習と書の学習」を「創研社」から刊行する。 pid/3446605
|
はしがき
一. 文字を「書くこと」の学習とは/7
二. 文字を「書くこと」がどのように変革されてきたか/8
1. 「文字」の面からは―漢字を中心にして
→―どのように変革されてきたか/8
(1) 漢字はどのようにしてつくられたのか/9
(2) 現在は漢字の状況はどうなっているか/25
(3) 書く漢字の範囲はどうきめられているか/27
(4) 漢字の字体の基準はどうきめられているか/37
(5) 筆写字体の許容範囲はどう考えるべきか/49
2. 文字を「書くこと」の目的の面からは、
→「書くこと」にどのような変革があったか/52
3. 文字を「書くこと」の用具・用材の面からは、
→「書くこと」にどのような変革があったか/56
4. 文字を「書くこと」の書くという面からは、「書くこと」に
→どのような変革をもたらしたか/61
5. 文字を「書くこと」は人間が書くことである。そのことが
→「書くこと」にどのような変革をもたらしたか/74
三. 文字を「書くこと」の学習―漢字を中心にして―/80
1. 文字を「書くこと」の学習の目的/80
2. 文字を「書くこと」の学習の教育的目的/85
四. 硬筆によって「書くこと」の学習の実際/93
第1段階 文字を正しく形を整えて書く学習/93
第2段階 文字を能率的に速く書くための学習/186
五. 毛筆によって「書くこと」の学習の実際/196
第1段階 文字を毛筆で書くことで自分をきたえる/200
1. 伝張即之の「方」の書に学ぶ/200
2. 大燈国師の「桂」の書に学ぶ/202
3. 大燈国師の「関」の書に学ぶ/204
4. 三輪田米山の「林」の書に学ぶ/206
5. 三輪田米山の「為」の書に学ぶ/208 |
6. 良寛の「風」の書に学ぶ/210
7. 一休の「衆」の書に学ぶ/212
8. 白隠の「孝」の書に学ぶ/214
9. 三輪田米山の「地」の書に学ぶ/216
10. 蘇東坡の「春」の書に学ぶ/218
11. 橘逸勢の「河」の書に学ぶ/220
12. 橘逸勢の「我」の書に学ぶ/222
13. 嵯峨天皇の「雲」の書に学ぶ/224
14. 勧善文の「調」の書に学ぶ/226
15. 慈雲の「想」の書に学ぶ/228
第2段階 文字を毛筆で書くことにおける自分の
→可能性を試みみいだす/230
1. 筆圧の加え方の実験学習「生」/232
2. 運筆の速度の実験学習「流」/234
3. 虚筆の動きの遠近高低の実験学習「行」/236
4. タッチの強さの実験学習「音」/238
5. 送筆のしかたの実験学習「石」/240
6. 筆軸のにぎり方と構え方の実験学習「我」/242
7. 筆の毛のそろえ方の実験学習「松」/244
8. すみの濃さとふくませ方の実験学習「香」/246
9. 点画のくみたて方の実験学習「地」/248
10. 紙面の形・字の大きさ・配字の実験学習「妙」/250
第3段階 文字を毛筆で書くことで、あらわれる自己を創造する/252
1. 文字を書くことを自分のものとする創作「月」/254
2. 筆で書くことを自分のものとする創作「想」/259
3. 墨を使って書くことを自分のものとする創作「和」/262
4. 紙に書くことを自分のものとする創作「道」/265
5. 書くことの動きを自分のものとする創作「要」/268
6. 書を書くことにおいて、めざす生き方を
→自分のものとする創作「情」/271
第4段階 自由創作の学習/274 |
○、この年、松原泰道が「禅の人生観 : 松原泰道集」を「教育新潮社」から刊行する。
(昭和仏教全集 ; 第5部 6) pid/2969666
|
口絵(著者近影)
はじめに
Ⅰ 禅のたたずまい
だるまさんのお話/p9
私たちのねがい
→ー仏教の人間像の禅的展開ー/p19
杖ことば/p52
五つの目ー人生の認識ー/p71
白隠禅師の死生観/p87
「夜船閑話」の示すもの/p93
禅者はこのように生きた/p99
三代仏教外伝/p109
しあわせはここから来る
→ー大乗の十来についてー/p120 |
Ⅱ 日日好日
初心忘るべからず/p127
今日好日/p130
えびす大黒天の話/p135
彼岸讃歌/p143
彼岸からのよびかけ/p147
花の王子誕生ー花まつりの心ー/p150
ぼん近し/p157
Ⅲ 涙の先覚者
仏はつねにいませども/p177
安らぎへの道しるべ/p188
涙の先覚者/p194
一期一会のわかれかな/p200
雨か嵐かしらねども/p202 |
Ⅳ 考える土
新家庭に送る手紙/p206
考える土/p214
六つのしつけ ー彼岸を願う人ー/p224
かたすみにともしびをー人生と職業ー/p227
小さいことでも少しでもー児童法話ー/p241
Ⅴ 世間
時間を耕す/p244
世間/p247
サンタクロースおやじ論/p250
石/p252
コマ/p256
葉ざくら/p259
障子のつくろい/p263 |
○、この年、中山正和が「創造工学的手法」を「産業能率短期大学出版部」から刊行する。 pid/2513904
|
序にかえて 創造工学とは
第1章 発想
第1節 記憶について/p8
経験的な考え方/p8
潜在する記憶(電気刺激)/p12
潜在する記憶(催眠)/p13
要約/p15
第2節 大脳生理/p17
基礎/p17
脳の発達/p20
記憶/p25
要約/p29
第3節 深層心理/p31
意識と潜在意識/p31
抵抗の排除/p33
意識と意志/p35
心療内科/p40
要約/p43
第4節 情報収集/p44 |
情報の集中/p45
エントロピー/p48
時間の逆行/p50
時空世界/p55
虚の世界/p57
要約/p60
第5節 発想の技法(その1)/p62
問題提起から問題把握まで/p62
脱線的手法/p70
感覚的手法/p78
自律化/p87
要約/p88
第6節 発想の技法(その2)/p90
睡眠/p90
催眠/p93
自律訓練法/p97
オート・コンディショニング/p101
白隠禅師の方法/p102
内観の秘法/p102
|
軟酥の観/p103
自己催眠とアイデア/p104
要約/p107
第7節 発想技法の訓練/p108
グループの編成/p108
性格テスト/p109
「気がつく」能力/p113
共通の本を読む/p116
催眠経験/p116
技法の練習/p117
合宿/p122
効果の測定/p123
第2章 有効化
第1節 計画の技法/p130
システム/p130
行動の原則/p132
目的を決める/p134
いろいろなやり方を
→比較する/p136
|
行動を決定する/p141
手順を決める/p143
KJ法の利用/p150
要約/p154
第2節 提示の技法/p156
セールスマンを見習え/p158
潜在意識を攻撃する/p161
誠意/p171
提示の時機/p172
要約/p174
第3節 展開の技法/p175
情報収集と分析/p175
修正行動/p180
リーダーは1人/p185
要約/p191
第4節 有効化技法の訓練/p192
第3章 まとめ
あとがき/p199
参考文献/p201 |
|
| 1968 |
43 |
・ |
5月25日~6月30日迄、神奈川県立近代美術館に於いて「画家としての白隱展」が開かれる。、
8月、「三彩 (233)」が「三彩社」から刊行される。 pid/7896385
|
鏑木清方の画帖朝顔日記/11~17
特集I 鏑木清方の画帖朝顔日記 画帖朝顔日記について / 鏑木清方/p17~17
特集I 鏑木清方の画帖朝顔日記 〈原色版〉画帖朝顔日記 / 鏑木清方/p11~11
特集I 鏑木清方の画帖朝顔日記 〈写真版〉画帖朝顔日記 //p13~13
特集II 白隱 白隠暼見 / 大岡信/p37~41
特集II 白隱 白隠の書 / 岡部蒼風/p42~43
白隠(特集)/25~43
特集II 白隱 〈グラビヤ版〉 //p25~36
高山辰雄の「唐詩選」リトグラフ展をみて / 中村渓男/48~55
特集III 高山辰雄の唐詩選 高山辰雄「唐詩選」をみて / 中村渓男/p48~48
特集III 高山辰雄の唐詩選 〈原色版〉 //p49~50
特集III 高山辰雄の唐詩選 〈写真版〉 //p51~54
特集III 高山辰雄の唐詩選 〈表紙解説〉 //p55~55
新宮殿障壁画 上村松篁の花鳥屏風 / 橋本喜三/p18~18
新宮殿障壁画 〈原色版〉新宮殿障壁画 //p19~19
現代作家論 山田申吾 温かい作風 / 北山桃雄/p64~64,67~67
|
現代作家論 山田申吾 〈原色版〉冬山 //p65~65
現代作家論 平川敏夫 平川敏夫論 / 山岸信郎/p58~58,61~62
現代作家論 平川敏夫 〈原色版〉樹 //p59~60
自作を語る(シシリー迄の夏の旅) / 田村孝之介/p70~70
〈原色版〉ニース //p71~71
新発足の創作画人協会展 / 三宅正太郎/p72~73
連載 東洋画論に求める(4)〈東洋画と高さ〉 / 吉村貞司/p20~24
連載 岡倉天心の書簡(2)高橋大華宛未発表書簡をめぐって / 匠秀夫/p44~47
連載 美術周縁記(8)美術うちそと / 水沢澄夫/p74~77
連載 美術時評(8)〈素材恐るべし〉 / 中原祐介/p56~57
連載 書評 〈幻想芸術 / マルセン・ブリヨン〉 / 駒井哲郎/p68~68
連載 書評 〈明代絵画史浙派研究 / 鈴木敬〉 / 吉村貞司/p69~69
連載 美術メモ 〈ダダ展・円心展・太郎爆発展・ネパール秘宝展〉 / 大島辰雄 ; 田近憲三他/p78~81
連載 卓上メモ / 藤本韶三/p63~63
展覧会評 / 三宅正太郎 ; 松原叔 ; 田近憲三 ; 山岸信郎 ; 田中日佐夫 ; 田宮文平/p82~84,89~92
〈写真版〉 //p85~88 |
10月、「三彩 (236)」が「三彩社」から刊行される。 pid/7896388
|
秋の団体展-1-院展・二科・行動展(特集)/11~26
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展 院展評 / 多田信一/p23~25
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展 二科展・行動展評 / 野村太郎/p25~26
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展 <原色版>大物浦/前田青邨/p11~11
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展<原色版>青い山脈/東郷青児/p17~17
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展 <グラビヤ版> //p19~22
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展 <写真版> //p13~16
特集I 秋の団体展(I)--院展・二科展・行動展<表紙解説>白隠/片岡球子/p26~26
安藤広重(特集)/31~51
特集II 安藤広重 浮世絵の美学--広重をめぐって / 栗田勇/p43~48
特集II 安藤広重 広重の芸術 / 山口桂三郎/p49~51
特集II 安藤広重 <原色版> 大はしあたけの夕立(名所江戸百景) //p31~31
特集II 安藤広重 <原色版> 萩に蛙(四季の花尽) //p41~41
特集II 安藤広重 <グラビヤ版> //p33~40
特集III 世界の偉大な写真家展 「写真」を観る--ジョージ・イーストマン・ハウス・
→コレクション展に寄せて / 細江英公/p68~68,73~73
特集III 世界の偉大な写真家展 <グラビヤ版> //p69~72
特集III 世界の偉大な写真家展 飛翔するピカソ / 中山公男/p54~54
|
特集III 世界の偉大な写真家展 <原色版> リグノー夫人像 //p55~55
特集III 世界の偉大な写真家展 中川清の彫刻 / 中村伝三郎/p60~61
特集III 世界の偉大な写真家展 洋風画雑感 / 陰里鉄郎/p52~53
特集III 世界の偉大な写真家展 戦争から遠く離れて--戦争画と反戦画展(2)/大島辰雄/p62~64
連載 東洋画論に求める(6)<宇宙感覚について> / 吉村貞司/p27~30
連載 主題と変奏(4)<ヌードII> / 坂崎乙郎/p57~59
連載 美術時評(10)<美術の交流について> / 中原佑介/p66~67
連載 書評 西洋の誘惑--中山公男著 / 佐々木英也/p74~74
連載 書評 アメリカ--東野芳明著 / 星菫/p75~75
連載 美術メモ 彫刻シンポジウム / 三木多聞/p76~77
連載 美術メモ 宗像大社展 / 江川和彦/p78~78
連載 美術メモ コンピューターアート展 / 藤堂弘道/p79~79
連載 卓上メモ / 藤本韶三/p65~65
連載 読者欄 / 合田微雪/p80~80
展覧会評 / 三宅正太郎 ; 松原叔 ; 田近憲三 ; 山岸信郎 ;
→田中日佐夫 ; 田宮文平/p81~84,91~93
展覧会評 <原色版> オフェーリア / ルドン/p85~85
展覧会評 <写真版> //p87~90 |
11月、「親和 (180)」が「日韓親和会」から刊行される。 pid/2252061
|
日韓親和会の親善訪問団々長として / 鈴木一/p6~11
対談・交流は密接に・速やかに / 金山政英 ; 鈴木一/p1~4
韓国での一週間(座談会) / 親善訪問団員/p14~20
Eさんへのたより / 鎌田信子/p12~13
時評/p21~26
全羅南道華厳寺で飲んだ茶 / 中谷忠治/p27~30
|
韓国の俚諺(俗談)(11) / 相場清/p37~38
第十九回朝鮮学会大会 / 宮原兎一/p5~5
近代日韓墨蹟集・白隠禅師と朝鮮虎 / 李英介/p39~40
虹のかかる前(十五) / 湯浅克衛/p31~36
残影(11)現代韓国文学翻訳 / 朴花城 ; 建部喜代子/p41~52
・ |
○、この年、森田子竜が「書 : 生き方のかたち」を「日本放送出版協会」から刊行する。 pid/2517583
|
はじめに/p4
書のすすめ・自分にめざめるために
勉強のおおすじ――古典の勉強を柱に―/p15
見るということ――鑑賞の意味と態度――/p20
書くということ(一)――臨書の意味と態度/p26
感動のままに・そして手ごたえを大事に
ちから―刹那刹那をたくましく強く押しきる―<始平公造像記>/p33
重さ――抑える力のあり方――<建中告身帖>/p41
密度――進む力の圧縮――<薦季直表>/p51
ひびき――手の解放・立ちあがる筆―
→<雁塔聖教序><聖武天皇雑集>/p57
リズム――緩急・抑揚、しぜんな流れ―<枯樹賦>/p67
学書法の反省・書法探求のすじみち
用筆法――内の躍動と手のわざ――<光明皇后臨 楽毅論>/p77
線質(一)――それを生み出すもの――<久隔帖><灌頂記>/p84
線質(二)――その先に生き方を見つめつつ―
→<温泉銘><争座位稿>/p94
かたち(一)――字姿のなかにあるもの――
→<良寛書 橋杭の詩><皇甫誕碑>/p101
かたち(二)――字配り(紙面構成)を生み出すもの――
→<高野切第三種><離洛帖><寸松庵色紙><継色紙>
→<許友書><慈雲書>/p109
空間(一)――余白の充実――<白詩巻>/p118
空間(二)――静まりかえる世界――<大燈国師書 関山号>/p125
作品づくり・創作の意味と態度
われわれの文字――漢字とかな――<小倉色紙>
→<良寛書><白隠書>/p133
自分で書く――ほかのだれでもない自分の書を―/p139
臨書と創作――歴史・社会をいかに生きるか―/p148
書の構造・書は生き方のかたち
書くということ(二)――簡素な構造・豊富な表現―/p155
筆とは何か――自由への場としての用具―/p160
書を読むということ――文字を読むことではない―/p166
現代の書・現代あるべき書を求めて
時代と書――時代とともに――<蘭亭叙><寒食帖>/p177
|
人と書――人とともに――/p185
個性と書――人十色――
日に新しく――一碑一面貌――<喪乱帖><姨母帖>
場を生きる――そこで形をとる――<三十帖策子><風信帖>
境涯――自由さ・豊かさ――<鉄斎の書><白隠の畫>
現代ある書――採否はあなたに――<現代作品十二点>/p198
現代あるべき書――永遠にして現代に独自なるもの――/p205
その主体――不易なるもの・伝統――
その場――流行するもの・現代の諸条件――
その書――不易流行――
あとがき/p216
挿図目次
秋萩帖/p17
良寛所持の秋萩帖/p17
賀蘭汗造像記/p36
鄭長猷造像記/p36
竹山連句/p46
顔氏家廟碑/p49
劉石庵書/p55
貫名菘翁臨枯樹賦/p72
一山一寧書/p73
白隠書「孝」/p83
漢委奴国王金印/p133
十七帖/p138
関戸本古今集/p138
白隠書「暫時不在」/p139
牧谿筆柿図/p173
泰山刻石/p178
礼器碑/p178
宗璟碑碑側記/p188
罔極帖/p189
七祖像賛/p191
モンドリアン作品/p210
シュネイデル作品/p211
宋版木版経/p213 |
○、この年、大森曹玄が「禅の高僧」を「筑摩書房」から刊行する。 (グリーンベルト・シリーズ) pid/2968340
|
はしがき/p3
一 道元禅師/p11
1 学問と禅/p11
2 循界蔵さず/p14
3 毛並みのよさ/p16
4 邂逅/p19
5 愛名は犯禁よりも悪し/p25
6 よく見ればなずな花咲く/p28
7 三心とは/p32
二 夢窓疎石/p35
1 夢窓に対する批判/p35
2 歴参/p37
3 撃砕す虚空の骨/p42
4 煙霞の痼疾/p47
5 天龍寺造営の意義/p55
6 夢窓の禅風/p60
7 夢中問答/p65
三 抜隊得勝/p68
1 『塩山仮名法語』/p68
2 端的これ何ものぞ/p71
3 罰酒神/p77
|
4 大疑/p80
5 六波羅蜜は一心の妙用/p86
四 一休宗純/p90
1 頓智の一休/p90
2 純一無雑/p93
3 一所不住/p100
4 自讃毀他/p104
5 異類中行/p108
6 看経すべからず/p118
7 誰れか我が禅を会す/p123
五 沢庵宗彭/p126
1 白鴎紅塵に走らず/p126
2 紫衣事件/p130
3 夢/p135
4 心を留めるな/p137
5 不動智/p139
6 石火の機/p144
7 心の置きどころ/p147
六 鈴木正三/p150
1 正三は死ぬと也/p150
2 四民徳用/p157
|
3 土くれ/p160
4 何くそッ/p163
5 せぬときの座禅/p172
七 正受老人/p181
1 気宇寛宏/p181
2 懐疑と省発/p183
3 万法如々/p186
4 隠栖/p191
5 母の李雪/p194
6 剣技を闘わす/p196
7 狼群中に正念相続/p200
8 形見の蹲踞/p201
9 道わじいわじ/p203
10 正受禅の特徴/p204
11 聖人一日暮し/p206
八 白隠と般珪/p208
1 大慧と宏智/p208
2 一切は不生でととのう/p212
3 因行格の白隠/p218
4 一闡提/p225
5 億劫別れて須臾も離れず/p229 |
○、この年、飯塚関外が「禅のこころ 」を「講談社」から刊行する。 (講談社現代新書) pid/2969732
|
序 中川宋淵 / p3
まえがき / p4
第一部 実践篇 / p11
1 禅というもの / p13
〈1〉 ほんとうの禅とは
〈2〉 禅の名称と意味
〈3〉 坐禅
2 禅の実践生活 / p33
〈1〉 禅への出発
〈2〉 きびしさと静けさー
→禅堂の生活
〈3〉 一般の人の参禅
〈4〉 修禅の内容
3 禅の錬成風景 / p57
|
〈1〉 提唱と独参
〈2〉 「公案」という宿題
4 坐禅和讃 / p75
〈1〉 平易に庶民に訴える
〈2〉 古今に絶する大自覚
〈3〉 果てしない転落
〈4〉 向こう岸への乗り物
〈5〉 澄みきった月のように
第二部 歴史篇 / p99
5 インドから中国へ / p101
〈1〉 インドの禅ー静かな瞑想の伝統
〈2〉 インドの心から中国の心へ
〈3〉 迫害にたえてー初期の中国禅
6 中国禅の興隆期ー唐代 / p121
|
〈1〉 道信と弘忍ー修業の場も整う
〈2〉 大物中の大物、慧能
〈3〉 動的な禅へー慧能の弟子たち
〈4〉 禅宗の発展と分化ー二甘露門
〈5〉 馬祖から臨済への系譜
〈6〉 石頭から曹洞禅へ
〈7〉 唐詩にうたわれた禅
7 中国禅の最盛期ー宋代/p165
〈1〉 豊かな人間味の禅ー宋禅
〈2〉 静かな打坐の禅ー曹洞
〈3〉 宋哲学の中心問題となる
〈4〉 禅がはじめて日本へ渡る
8 日本への禅の伝来 / p189
〈1〉 新興武士の心をとらえる
|
〈2〉 禅を持って帰った日本禅僧
〈3〉 時宗と宋禅僧の師弟愛
9 日本禅の独立と隆盛 / p207
〈1〉 大応国師と大燈国師
〈2〉 達磨以来の禅僧、関山
〈3〉 妙心寺系以外の名禅僧
10 禅の系譜と禅文化 / p239
〈1〉 室町以降の傑僧
〈2〉 足利文化と禅
〈3〉 沢庵和尚と柳生宗矩
〈4〉 家光に禅を説いた愚堂
〈5〉 現代禅の
→産みの親ー白隠和尚
11 現代人のために / p267 |
○、この年、武者小路実篤が「若き日の為に」を「東方社」から刊行する。 pid/1673646
|
影響を受けた人々/5
僕の青少年時代/29
友情の歴史/38
笛吹く男/86
人生に就て/93
文化と芸術/113
文学鑑賞に就て/119
言志録より/130
「私は冒険と結婚した」に就て/138
「幸福な家族」映画化その他/142
趙陶斎の画/147
白隠の画や字を見て/155 |
正倉院御物を拝観して/159
高村光太郎君に就て/168
周作人との友情の思い出/170
周作人と私/175
長与兄弟/179
兄と弟/181
海/183
六月の思い出/186
机の上/190
ローマ・フィレンツェの思い出/192
尊徳の言葉/201
尊徳の言葉など/221 |
桜町の復興/229
鄭道昭/234
雪舟/239
偉い人間/242
尊敬すべき人/245
土佐光長/256
大雅堂の十便と蕪村の十宜/259
荻須高徳氏の個展/261
滝田樗陰/264
村上華岳/267
小出楢重の画/276
解題 中川孝/281 |
○、この年、鈴木大拙著「鈴木大拙全集 第4巻」が「岩波書店」から刊行される。
|
禪思想史研究 第四/p1
禪と念佛の心理學的基礎/p187
附録
大燈百二十則/p373
大燈國師行状/p395
後記/p401
目次
日本禪思想史の一斷面―大燈百二十則に
→因みて著語一般のもつ意味―
槐安國語を讀みて/p39
第一 「著語」文學の將來などにつきて/p41
第二 「上堂」文學などにつきても/p65
禪と白隱/p111
一/p113
二/p119
三/p124
四/p133
五/p138
佛果碧巖破關撃節の刊行に際して/p141
|
公案論/p175
一 禪の公案/p177
二 古聖の公案に對する態度/p178
三 公案の意義/p179
四 公案は修行の實際上如何なる
→働きをするか/p180
五 公案には兩重の作用あり/p181
六 禪の特色/p182
七 公案を説くものの心掛け/p184
目次
前篇
第一 知識を越えたる經驗/p195
第二 禪に於ける悟の意義/p200
第三 悟の主要なる特徴/p205
第四 公案制度發生前に於ける悟の
→心理的先行條件―實例數項/p212
第五 禪經驗を決定する諸要因/p227
第六 心理的先行條件と
→禪經驗の内容/p239
|
第七 禪史初期に於ける
→禪的修行の技術/p251
第八 公案の發生とその意義/p260
第九 看話工夫に關する實際上の諸敎訓/p268
第十 看話工夫に關する諸種の
→一般的敍述/p274
第十一 禪經驗の個人的記録/p278
第十二 工夫的精神の意義と機能/p284
後篇
第一 看話の工夫と念佛/p303
第二 念佛と稱名/p309
第三 淨土門に於ける稱名の價値/p316
第四 稱名の心理および看話工夫との交渉/p325
第五 念佛行の目的は何か/p334
第六 念佛の神祕主義と稱名/p340
第七 經驗と理論化/p344
第八 公案及び念佛に關する白隱の見解/p348
附録 禪經驗の諸形相―十八項/p355
後記/p371 |
|
| 1969 |
44 |
・ |
2月、古田紹欽が禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (通号 57) p.233~249」に「鉄山宗鈍 (禅と日本文化の諸問題・荻須純道教授還暦記念特集)を発表する。 pid/4414843
|
禅と日本文化の諸問題/p1~408
荻須純道博士近影 /
荻須純道博士略歴・著作目録 //p1~7
日本中世禅思想の展開--臨済禅を中心として / 荻須純道/p1~51
日本禅の特色 / 柳田聖山/p53~99
法燈円明国師之縁起について--中世における唱導と
→絵解の一例 / 宮崎圓遵/p101~114
僧伝小考三題 / 玉村竹二/p115~142
中岩円月の中国文学的背景 / 久須本文雄/p143~164
絶海中津と明僧との交渉--文学へのいましめ / 牧田諦亮/p165~180
瑞溪周鳳の『刻楮集』について / 伊藤東慎/p181~205
華叟宗曇とその門下 / 平野宗浄/p207~232
資料1.大機弘宗禅師行実碑銘/p219~220 |
資料2.養叟和尚法語/p221~232
鉄山宗鈍 / 古田紹欽/p233~249
斯経慧梁と江湖道場の開創について / 加藤正俊/p251~267
徒然草の思想--特に仏教文学作品としての
→一試論 / 鷲山樹心/p269~289
謡曲における禅語の二三について / 佐竹大鑑/p291~310
鈴木正三の念仏禅 / 藤吉慈海/p311~329
禅における宗教と文化の関係--「転」の宗教と
→「幽」の文化の相即 / 西村恵信/p331~358
無諍の論理--「仏教における戦争体験」(六) / 市川白弦/p359~381
禅と日本文化の将来 / 西谷啓治/p383~408
花園大学研究室彙報 //p409~414
石庭(英文) / 森暢/p1~16 |
3月、柳田聖山が「禅の語録 1 達摩の語録 : 二入四行論」を「筑摩書房」から刊行する。 pid/12273325
|
筑摩書房が刊行した「禅の語録 1~20」迄の内訳一覧表
| No |
巻数 |
発行年 |
著者名 |
内容 |
pid |
| 1 |
禅の語録 1 |
1969・3 |
柳田聖山 |
達摩の語録 : 二入四行論 |
pid/12273325 |
| 2 |
禅の語録 2 |
1971・3 |
柳田聖山 |
初期の禅史 1 |
pid/12273378 |
| 3 |
禅の語録 3 |
1976・6 |
柳田聖山 |
初期の禅史 2 |
pid/12269315 |
| 4 |
禅の語録 4 |
1976・2 |
中川孝 |
六祖壇経 |
pid/12268755 |
| 5 |
禅の語録 5 |
2016・4 |
入矢義高 |
馬祖の語録 |
- |
| 6 |
禅の語録 6 |
1970・3 |
平野宗浄 |
頓悟要門 |
pid/12273384 |
| 7 |
禅の語録 7 |
1973・11 |
入矢義高 |
□居士(ほうこじ)語録 |
pid/12271139 |
| 8 |
禅の語録 8 |
1969・12 |
入矢義高著 解説(柳田聖山) |
伝心法要・宛陵録 |
pid/12273311 |
| 9 |
禅の語録 9 |
1971・12 |
鎌田茂雄 |
禅源諸詮集都序 |
pid/12269667 |
| 10 |
禅の語録 10 |
1972・4 |
秋月龍珉 |
臨済録 |
pid/12273308 |
| 11 |
禅の語録 11 |
1972・12 |
秋月龍珉 |
趙州録 |
pid/12268995 |
| 12 |
禅の語録 12 |
2016・4 |
入矢義高監修・唐代語録研究班編 |
玄沙広録 上(禅の語録, 12a) |
- |
| 12 |
2016・4 |
入矢義高監修・唐代語録研究班編 |
玄沙広録 中 (禅の語録, 12b) |
- |
| 12 |
2016・4 |
入矢義高監修・唐代語録研究班編 |
玄沙広録 下(禅の語録, 12c) |
- |
| 13 |
禅の語録 13 |
1970・11 |
入谷仙介, 松村昂 |
寒山詩 |
pid/12273377 |
| 14 |
禅の語録 14 |
1981・5 |
荒木見悟 |
輔教編 |
pid/12273258 |
| 15 |
禅の語録 15 |
1981・1 |
入矢義高, 梶谷宗忍, 柳田聖山 |
雪竇頌古 |
pid/12272227 |
| 16 |
禅の語録 16 |
1974・7 |
梶谷宗忍, 柳田聖山, 辻村公一 |
信心銘・証道歌・十牛図・坐禅儀 |
pid/12273309 |
| 17 |
禅の語録 17 |
1969・5 |
荒木見悟 |
大慧書 |
pid/12273324 |
| 18 |
禅の語録 18 |
1969・10 |
平田高士 |
無門関 |
pid/12273438 |
| 19 |
禅の語録 19 |
1970・8 |
藤吉慈海 |
禅関策進 |
pid/12273383 |
| 20 |
禅の語録 20 |
2016・4 |
小川, 隆 |
「禅の語録」導読 索引あり |
- |
|
5月、荻須純道編「禅と日本文化の諸問題」が「平樂寺書店」から刊行される。 pid/12273179
|
日本中世禅思想の展開-臨済禅を中心として(荻原純道)
日本禅の特色(柳田聖山)
法燈円明国師之縁起についてー中世における唱導と
→絵解の一例(宮崎円遵)
僧伝小考三題(玉村竹二)
中岩円月の中国文学的背景(久須本文雄)
絶海中津と明僧との交渉-文学へのいましめ(牧田諦亮)
瑞溪周鳳の『刻楮集』について(伊藤東慎)
華叟宗曇とその門下(平野宗浄)
鉄山宗鈍(古田紹欽) |
斯経慧梁と江湖道場の開創について(加藤正俊)
徒然草の思想-特に仏教文学作品としての一試論(鷲山樹心)
謡曲における禅語の二三について(佐竹大鑑)
鈴木正三の念仏禅(藤吉慈海)
禅における宗教と文化の関係-「転」の宗教と「幽」の文化の相即(西村恵信)
無諍の論理-「仏教における戦争体験」6(市川白弦)
禅と日本文化の将来(西谷啓治)
禅における人間尊重観-特に黄檗・臨済父子の禅を中心として(西義雄)
The stone garden(Toru Mori)
・ |
7月、日本歴史学会編「日本歴史 (254)」が「吉川弘文館」から刊行される。 pid/7910314
|
平頼盛について / 多賀宗隼/p1~5
少弐頼尚と南淋寺 / 川添昭二/p6~10
譜第の意味について / 米田雄介/p11~19
鴨長明と念仏聖 / 桜井好朗/p20~28
宝山寺蔵契沖阿闍梨伝記資料続拾 / 岩本次郎/p29~34
松浦党一揆契諾の法的性格--試論 / 森本正憲/p35~46
宝暦七年発行の讃岐高松藩銀札について / 城福勇/p47~61
山室軍平と社会事業 / 三吉明/p62~72
日本史研究講座(8)古代国家の形成 / 佐伯有清/p73~85
文化財レポートー15-/86~101
文化財レポート(15)新指定の文化財 //p86~97
香川県・宮が尾古墳の壁画 / 松本豊胤/p97~101
人物素描 宮崎車之助 / 中野健/p102~104
歴史手帖 当代記小考 / 伊東多三郎/p105~108
歴史手帖 明治の街頭風景 / 岡田章雄/p108~110
研究余録 白隠伝補訂 / 辻達也也/p111~113
研究余録 板沢武雄先生著シーボルト伝について /
→竹内精一/p113~117 |
研究余録 氏子札 / 春原源太郎/p117~119
書評と紹介 住田正一・内藤政恒共著『古瓦』 / 石田茂作/p120~120
書評と紹介 水野祐著『日本国家の成立--
→古代史上の天皇』/福井俊彦/p120~122
書評と紹介 下出積与著『神仙思想』 / 村山修一/p122~123
書評と紹介 岡田章雄訳『エルギン卿 遣日使節録』 / 進士慶幹/p123~125
書評と紹介 岩橋小弥太著『上代食貨制度の研究(第一集)』/竹内理三/p125~127
書評と紹介 園田日吉著『江藤新平伝』 / 杉谷昭/p127~128
書評と紹介 横山昭男著『上杉鷹山』 / 榎本宗次/p128~129
書評と紹介 渡辺久雄著『条里制の研究--
→歴史地理学的考察』/倉田康夫/p129~130
書評と紹介 竜丘村誌編纂委員会編『竜丘村誌』 / 片山勝/p130~133
書評と紹介 岡登貞治編『文様の事典』 / 鈴木敬三/p133~135
書評と紹介 目崎徳衛著『平安文化史論』 / 高橋富雄/p135~135
日本史関係雑誌論文目録 / 小川博/p136~140
新刊書案内 / 吉川弘文館編集部/p141~141
学界消息 //p142~144
口絵=高階仲章自筆請文 / 山本信吉
|
9月、「禅文化 (54)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082249
|
表紙 仙厓和尚画賛「柳図」
扉 海清寺僧堂師家 春見文勝老師画賛「行乞図」
グラフ 特集 淡川禅画楼開館
禅文化公開講演録 中道をゆく / 山田無文/p4~15
二つの道号記--秉心宗彝と大光古岸と / 秋山寛治/p22~36
「開山墨跡」考 / 永島福太郎/p37~43
心なき天地山川の声 (洞山良价)―祖堂集ものがたり
→第四話 / 柳田聖山/p67~76 |
雲水日記(4) / 佐藤義英/p16~21
三つの自然視(2) / フレッド・クランジ ; 烏有子/p60~66
隠者 白幽子のこと--二六〇回の忌に / 伊藤和男/p46~55
随草 川端康成氏の講演 / 市原豊太/p56~59
俳句 新涼 / 河野義海/p44~45
新刊紹介 / 柴山全慶 ; 陸川堆雲 ; 玉村竹二 ;
→唐木順三/p36~36,43~43,55~55,59~59
・ |
11月、「芸術新潮 20(11)[(239)]」が「新潮社」から刊行される。 pid/6048490
|
特集 1・この秋日本で売った西洋美術と値段 <原色版> ボッティチェルリ、ティントレットなど
→初見の古典からフランスの新人たちまで / 安東次男/p3~24
私ならこれを買う / 安東次男/19~24
特集 2・「紅葉」を描いた日本の千年 <原色版> 扇面法華経冊子、源氏物語、仏画、絵巻、
→三十六人歌集、琳派、文人画、華岳、梅原 / 栗田勇/p65~79
紅葉の美学 / 栗田勇/75~79
特集 3・ロココの夢 「十八世紀フランス美術展」の下見 <フットライト>
→(41)<原色版> / 森茉莉/p116~119
モーツァルトへの旅 ザルツブルク / 東山魁夷/p54~57
藝術新潮欄<原色版> ぴ・い・ぷ・る / 河盛好蔵 ; 川島理一 ; 山口長男 ;
川崎小虎 ; 川崎春彦 ;
→ 矢内原伊作 ; 香月泰男 ; 福沢一郎 ; 曽宮一念 ; 森省一郎 ; 北杜夫
; 近岡善次郎/p40~41
藝術新潮欄<原色版> LP //p146~147
藝術新潮欄<原色版> 案内 //p148~149
藝術新潮欄<原色版> スター・ダスト //p135~141
藝術新潮欄<原色版> ワールド・スナップ //p144~145
連載 ゴッホ論(5) / A・アルトー/p42~45
連載 かくれ里(11) 滝の畑<原色版> / 白洲正子/p46~51
連載 骨董百話(11) 白隠・達磨図<原色版> / 小山冨士夫/p120~121
連載 現代作家のなかの伝統(11) 利根山光人の「ナイヴテ」(ルポルタージュ)<原色版>
/ 大岡信/p100~105 |
女流美術史家の回想(3) / 白畑よし/p156~160
随筆 画道への動機 / 宮城音蔵/p83~83
随筆 能面打ちに凝った男 / 金春信高/p88~88
随筆 異国の友人たち / 福井良之助/p107~107
随筆 三人たりない殉教者 / 坂本満/p108~108
随筆 わが空想の画廊 / 池田龍雄/p150~150
随筆 逃書の弁 / 豊福知徳/p153~153
随筆 売れない彫刻 / 平櫛田中/p154~154
叡山から消えた仏たち <発掘>(47)<原色版> / 久野健/p90~97
新発見の「ボッシュ」への疑問<真贋>(71)<原色版>/江原順/p124~132
バッハの悪魔と神 西方の音(42) / 五味康祐/p110~112
やまとの女人(11) / 岡部伊都子/p58~59
音楽と求道(23) 信濃の人たちと共に / 尾崎喜八/p62~63
一枚のレコード(23) シューベルト「歌曲集」第5集 / 吉田秀和/p84~86
随筆 クラーべに貰った二枚の絵 / 宮田重雄/p80~80
随筆 関東の仏 / 麻生三郎/p89~89
随筆 長谷川利行の贋作鑑定 / 井上長三郎/p99~99
随筆 キリスト教美術の死角 / 大野忠男/p113~113
・ |
○、この年、「日本の思想 第10」が「筑摩書房」から刊行される。 pid/2971553
|
解説 禅と歴史 唐木順三 / p1
大燈国師語録 / p33
夢窓 夢中問答集(抄) / p95 |
鈴木正三 驢鞍橋(抄) / p173
盤珪禅師語録 / p249
白隠 遠羅天釜(抄) / p325
|
訳者あとがき / p383
禅家語録関係略年表 / p386
参考文献 / p394 |
○、この年、尾崎秀明が「白隠禅師 坐禅和讃」を「週刊名古屋社」から刊行する。
付:延命十句観音経抄訳 |
| 1970 |
45 |
・ |
3月宮下操が「 伊那 18(3)(502) p1~2 伊那史学会」に「口絵 白隠石」を発表する。 pid/4431339
4月、文化庁・東京・京都・奈良国立博物館監修、竹内尚次編「「日本の美術 47 近世の禅林美術」が「至文堂」から刊行される。 pid/7962206
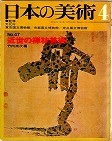 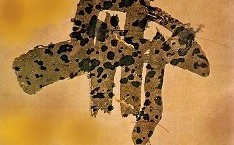
日本の美術4 (表紙) 無 (一部拡大図) |
図版解説/表紙 白隠 無字
無の一字関は、中国で形成され、わがくにに現に生きている禅宗の哲理を表現する。唐時代の高僧趙州従〔シン〕(777~ 897)の語録「狗子(くし)に佛性有りやまた無しや」無、によるもので、また一箇の無字は印度仏教の「空」から離脱した中国禅独自の成立を示す。白隠の「隻手(せきしゅ)の音聲(おんしょう)」をきけ、がこれに当り、白隠禪の南宋虚堂禅より遡って唐朝禅への復古への指向を示している。
・ |
|
禅林美術 // p17~18
近世の禅林美術 // p19~20
1.中世から近世への叢林 // p19~19
2.近世の叢林 / / p19~19
3.近世禅林美術の展開 // p19~20
澤菴 // p22~27
一絲 // p28~33
白隠 // p34~43
白隠下の龍象と教団鵠林 白隠下の領袖
→古月派教団と白隠の教団
|
→白隠教団の組織と
→「林下」の純粋性//p44~47
仙厓 // p48~52
1.仙厓の法系 // p48~48
2.博多の仙厓 // p48~50
風外慧薫 // p57~61
心越 // p62~64
洞上の諸匠 // p65~68
良寛 // p69~71
香積寺風外 // p72~77 |
黄檗派 // p78~96
1.初渡の明僧 // p79~80
2.黄檗派教団の東渡 // p80~83
3.木庵と即非 // p83~84
4.後期の黄檗派 // p84~86
5.黄檗派教団の展開とその文化 // p86~87
おわりに // p88~96
図版目録 // p99~100
近世の禅林美術の鑑賞と鑑識 // p101~102
・ |
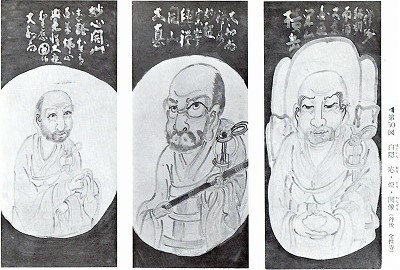 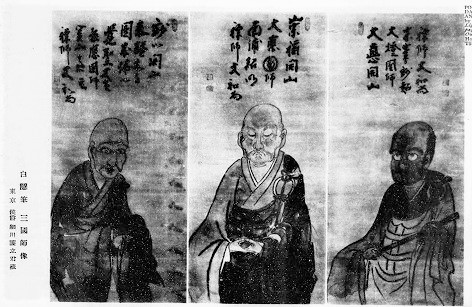
関山 大燈国師 大応国師 第50図 (丹後 全性寺) T12年 「名品綜覧 : 東洋芸術 第1集 第7編 美術資料刊行会」より 細川侯爵家蔵版
4月、飯島町文化財調査委員会編「文化財写真集 第2集 白隠禅師遺墨集」を「上伊那郡飯島町/飯島町教育委員会」が刊行する。
所蔵:県立長野図書館
6月、川村美陽子が「仏教史研究 2 p.38-40」に「家永三郎著 『日本思想史に於ける否定の論理の発達』 」を紹介する。
10月17日~11月3日、島根県立博物館に於いて「 禅画展 : 細川家永青文庫 風外,
彗薫,一絲文守,慧鶴」が開かれる。
また、「風外慧薫, 一絲文守, 白隠慧鶴 [ほか(図録)」が「島根県立博物館」から刊行される。
12月、「在家佛教 (201)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6063883
|
平和 / p5~5 (0004.jp2)
ありがたさについて / 金子大栄 / p6~16
生活の講座 人間の汚染 / 佐古純一郎 / p18~20
生活の講座 小さきは小さきままに / 西本宗助 / p20~22
生活の講座 機械文明のゆくえ / 武藤義一 / p22~25
生活の講座 自から律する力 / 横山邦雄 / p25~27
親鸞と善鸞 / 加藤辨三郎 ; 早島鏡正 ; 脇本平也 / p36~44
神護寺 薬師如来(表紙仏像解説) / p17~17
在家仏教協会の仕事 / p4~4
在家仏教講演会案内 / p88~88
在家仏教刊行図書案内 / p45~45
|
コマ文庫刊行図書案内 / p1~1
金子大栄選集案内 / p49~49
こころのうち / 葉上照澄 / p50~55
白隠禅師の坐禅和讃 / 古田紹欽 / p30~35
私の人生ノート 日々是好日 / 竹村吉右衛門 / p62~78
文学と仏教 90 和讃 / 長田恒雄 / p79~81
鎌倉記(74)化粧坂と曾我五郎時致 / 三浦勝男 / p46~48
善?(大手町だより) / p87~87
古寺抄 美濃の寺--新長谷寺・正眼寺 / p82~86
美濃・飛?の寺々をめぐって / p56~60
インド仏蹟めぐりの会案内 / p28~29 |
○、この年、「鈴木大拙全集 第27巻 (講演集第2,雑集第1)」が「岩波書店」から刊行される。 pid/2968733
|
講演集 二/p1
創造の本能性/p7
色即是空/p13
禪と哲學/p26
東洋の考へ方/p45
無題/p71
在家佛敎/p76
わが眞宗觀/p83
本願の根元/p104
妙法について/p118
親鸞聖人の思想―宗祖生誕會
→記念講演より―/p135
日本人の生活/p143
禪に關/p153
在家の佛敎/p177
慧能禪と現代/p188
任運騰騰/p199
淸澤滿之は生きてゐる/p206
日日新たなり/p221
東洋思想の特質とタゴア/p227
念佛の本義/p242
キリスト教と佛敎/p251
知と行/p277
|
日日新たなり/p298
人間について/p307
彼岸と此岸/p320
明治と昭和/p329
「大用現前」/p338
雜集 一/p345
明治十八年(一八八五年)/p351
小楠公賛/p351
聞子規有感/p351
後醍醐帝論/p351
雷説/p352
客舍聞砧/p353
喜友人至山莊/p353
轉禍爲福説/p354
明治二十七年(一八九四年)/p355
何故に働かざる乎/p355
明治三十年(一八九七年)/p359
富者の世界觀(米國の富豪イ・シ・ダラー氏
→に就きて)/p359
明治三十一年(一八九八年)/p369
施家谷所觀/p369
妄想録/p382
明治三十二年(一八九九年)/p403 |
思ひ出づるまま/p403
明治三十三年(一九〇〇年)/p415
米國通信(僧侶の肉食に就きて)/p415
明治三十五年(一九〇二年)/p419
海外より見たる故國/p419
明治四十五年(一九一二年)/p423
禪學論數則/p423
大正二年(一九一三年)/p429
禪の發足鮎/p429
大正四年(一九一五年)/p435
副會長となりて/p435
大正五年(一九一六年)/p441
信仰の確立/p441
寮に入るときの覺悟/p449
筆にまかせて/p460
碧巖集に就きて/p470
タゴア氏の講演をききて修禪のことに及ぶ/p474
盛岡紀行/p481
白隠禪の難者に答ふ/p487
後記/p515
・
・
・ |
○、この年、福嶋悠峰が「図書日曜随筆集 第8巻」を「下野新聞社」から刊行する。 pid/2934863
|
猿と刀/p1
春は来て居る/p8
兵法というもの/p12
河竹黙阿弥/p16
兵法の起源/p22
白隠と赤子/p28
猿回しを懐う/p31
兵法の発展/p40
信玄と孫子/p47
名を改める/p53
火星の伝説/p61
小鳥さん/p69
堅香子の花/p72
釈迦と初鰹/p76
|
武田家の人々/p83
ニンニク社長/p90
屁放りの翁/p98
今日の小唄会/p103
菅丞相/p108
靄崖の偽物/p120
岡相実貞入道と小幡勘兵衛景憲/p126
忙し過ぎる/p133
詩作する若い女/p139
腮長さん/p145
明日の文楽/p151
弥陀の浄土/p156
越中万葉植物園/p164
立山に遊ぶ/p169
|
一茶を偲ぶ/p174
春日山城趾/p179
海音寺君に与う/p185
寺井の井戸/p194
文字の謎/p200
謎は〝用〟の字/p204
麦や節と平家踊/p209
秋の色香/p215
盛遠の恋/p220
鳥羽の恋塚/p226
お陽さまの旅/p231
人間の秋/p235
能因の歌/p243
詩人と強盗/p249
|
湯の湖の紅葉/p255
御不浄談義/p261
鮭漁りと東海村/p267
塩膚木の紅葉/p274
合気道とは!/p280
足を痛めて/p286
人間ドック入り/p290
宿に初雪/p298
真柄の太郎太刀/p302
太陽は繞る/p309
年の瀬に/p313
・
・
・ |
○、この年、荒井荒雄が「仰臥禅 : 白隠禅師内観の秘法による心身改造」を「明玄書房」から刊行する。
○、この年、「延命十句観音経霊験記」が「山喜房仏教書林」から刊行される。
参考 この頃(発行年不明)、長野県信濃美術館が「信州の白隠」を刊行する。 |
| 1971 |
46 |
・ |
5月、岐阜県下呂町地蔵寺の調査のに、矢沢氏宅に於て「百壽大幅」圖を発見する。
出展:土屋常義著「白隠と岐阜県p3」より
7月、「禅文化 (61)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082256
|
表紙 白隠禅師墨蹟「寿と円頓章」 / 加藤正俊
グラフ 丹後全性寺墨蹟特集(上) / 加藤正俊 ; 宝積玄承
扉 竜沢寺僧堂中川宋渕老師書 |
直指庵と蘭谷元定 / 大槻幹郎 / p17~23
〈抜粋〉
・ |
7月、「武者小路実篤が「新潮社」から刊行される。 (日本文学全集, 7)
|
不幸な男 / 武者小路実篤 [著]
幸福者 / 武者小路実篤 [著]
友情 / 武者小路実篤 [著]
白隠 / 武者小路実篤 [著] |
愛と死 / 武者小路実篤 [著]
兄弟 / 武者小路実篤 [著]
馬鹿一 / 武者小路実篤 [著]
今にやるぞ / 武者小路実篤 [著] |
真理先生 / 武者小路実篤 [著]
解説:p.545-554 (市原豊太)
・
・ |
12月、淡交社編「淡交 25(12)(299)」が「淡交社」から刊行される。 pid/7890961
|
グリーン・ピープル / 千宗室/p30~32
湿潤の文化と乾燥の文化 / 會田雄次/p33~39
近世岡山町人と茶湯--河本家と国冨家 / 原田伴彦/p40~49
紅い葉と赤い実 / 澤野久雄/p69~71
白隠 禅僧素描(3) / 紀野一義/p56~63
原色版 家元好み物 / 濱本宗俊/p5~6
原色版 歴代家元茶杓 / 高原杓庵/p7~8
原色版 茶碗の美 / 佐藤雅彦/p9~10
原色版 露地 / 中村昌生/p11~12
遼廓亭 茶室随想(12) / 清水一/p51~55
捨てられた海辺 風に托す想い(12) / 串田孫一/p165~173
モドキの二の舞 続・虚仮の戯言(12) / 坂東三津五郎/p64~68 |
残像拾遺 続・能に描かれた人びと(24) / 権藤芳一/p72~74
一期一会 わび茶道の心理学(七) / 安西二郎/p158~160
グラビア 各地の献茶・供茶、北陸地区大会、四国地区大会/p17~28
グラビア 一行物(十二)/p13~16
グラビア 茶会記の世界 大名茶会/p81~84
グラビア わが家の庭 津山・安田宗見邸/p77~79
原色版解説 圓能斎(その四)家元好み物 / 濱本宗俊/p117~118
原色版解説 又□斎・圓能斎 歴代家元茶杓 / 高原杓庵/p119~121
原色版解説 萩・仁清 茶碗の美 / 佐藤雅彦/p122~124
原色版解説 又隠 露地 / 中村昌生/p125~127
略
・ |
○、この年、読売新聞静岡支局編「ふるさとの歴史」が「静岡谷島屋」から刊行される。 pid/9569072
|
すいせんのことば 竹山祐太郎
まえがき
古戦場
いまは昔、水鳥の羽音(富士川)/2
梶原景時父子の最後の地(狐ケ崎)/6
ミカン山にのこる五輪の塔(手越河原)/10
不毛の地いま発展の一路(三方原)/14
城
松にしのぶ戦国(横手城)/20
南朝方の拠点城(井伊城)/23
石にしのぶ栄華(大津城)/26
戦乱の中のロマンス(安倍城)/29
世に出た武田の遺跡(久能城)/33
攻防十年の長期戦(高天神城)/37
全国最後の山城(山中城)/40
徳川〝悲劇〟の舞台(二俣城)/44
三日月池におもかげ残す(横須賀城)/47
強い市民の郷愁(浜松城)/50
家康「タイ事件」の亀甲城(田中城)/54
六大名城の誇り(掛川城)/57
老中「田沼」の本拠(相良城)/61
天領の中の小城(小島城)/64
町の中心が城跡(沼津城)/67 |
家康の〝隠居所〟(駿府城)/70
庭園
連歌師〝宗長の庭〟(柴屋寺)/84
生き続ける〝美〟(清見寺)/87
よみがえる江戸時代庭園
→の遺構(医王寺)/90
太田道灌が改築(喜久屋)/94
遠州流の名園(本興寺)/97
神苑に歴史の重み(三島大社)/100
室町の作庭江戸時代に完成(大福寺)/103
麗姿富士を背景に(竜華寺)/106
井伊大老のぼだい寺(竜潭寺)/109
代官の夢のあと(浮月楼)/113
賤機山ろくの名園(臨済寺)/116
人物
役人から作家に(十返舎一九)/120
義賊の証拠なし(日本左衛門)/123
〝無欲虚心〟教える(白隠禅師)/127
幕末に活躍した韮山代官
→(江川太郎左衛門)/130
薄幸な〝背くらべ〟の作者(海野厚)/133
尊王敬幕の国文学者(賀茂真淵)/136
社会開発につくした〝天竜翁〟 |
→(金原明善)/143
シャムに雄飛した風雲児(山田長政)/147
天下ねらう〝慶安の変〟の
→中心人物(由井正雪)/152
幕末夜話のヒロイン(唐人お吉)/157
自動織機の発明から築いた企業
→(豊田佐吉)/161
米の研究から発見した
→ビタミンB1(鈴木梅太郎)/164
楽器製造の基礎を築く(山葉寅楠)/167
武士の浮世絵師(恋川春町)/170
マチマチな人物の評価(清水次郎長)/173
宗教より強い産業功績(聖一国師)/176
遠州が生んだ〝女医のシンボル〟
→(吉岡弥生)/179
自然の美を詠んだ万葉の歌人(山部赤人)/183
日本写真師の始祖(下岡蓮杖)/186
苦難五年、箱根用水を完成(友野与右衛門)/189
命がけで地租改正(岡田良一郎)/193
苦節40年茶の品種改良(杉山彦三郎)/196
壁画芸術の発見者(伊豆の長八)/199
絶賛あびた美声の〝プリマドンナ〟(三浦環)/20
・ |
|
| 1972 |
47 |
・ |
1月、「禅文化 (63)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082258
|
表紙 仙厓禅師画賛「ねずみ」 / 淡川康一
グラフ 臨済・黄檗各派管長墨蹟集
扉 岡山県宝福寺忘路庵画賛
正受老人を憶う / 山田無文 / p65~79
禅僧房号考 / 今枝愛真 / p58~61
遊戯と浄土--「梁塵秘抄」を素材として / 横井清 / p44~50
ジャワの仏教遺蹟を尋ねて / 小林円照 / p29~38
沢庵禅師と不動智神妙録(二) / 大森曹玄 / p13~19 |
参・西国巡礼歌(6)禅的なうなずき / 松原泰道 / p51~57
禅学は何のために / 西村恵信 / p20~28
白隠の股錐稿 / 町田瑞峰 / p39~43
荒川豊蔵さんをたずねて / 宝積玄承 / p62~64
深山遠谷の心--徒然草第七十五段に関聯して/唐木順三/p4~12趙
禅界だより / p80~80
書灯 / p28~28,57~57,61~61
・ |
6月、「禅文化 (65) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082260
|
表紙 白隠禅師画「蘆葉達磨」
グラフ 特集・根を下す海外の禅
扉 無文老師メキシコ墨蹟展のポスター
特集 根を下す海外の禅 メキシコ講演 心の清きもの / 山田無文 / p4~7
特集 根を下す海外の禅 座談会 根を下す海外の禅 / 山田無文 ;
→鈴木宗忠 ; 島野栄道 ; 盛永宗興 / p12~22
特集 根を下す海外の禅 無文老師メキシコの旅 / 山村文彦 / p8~11
特集 根を下す海外の禅 俳句 / 安原格二 / p11~11
仏教講座 第一講 仏陀の生涯とその教え / 藤吉慈海 / p43~50 |
講座 宗教学のすすめ(一) / 西村恵信 / p36~42
書(1)人語の響 / 山田伍雲 / p63~69
祖堂集ものがたり第十三話 ある終末(洞山と
→その弟子たち) / 柳田聖山 / p70~80
参・西国巡礼歌(8)禅的なうなずき / 松原泰道 / p23~29
一元紹碩について--落ち穂拾いの記(一) / 加藤正俊 / p51~54
仏蹟巡拝記--抄 / 冨士玄峰 / p55~62
文化の素材 禅と紙 / 寿岳文章 / p30~35
書灯 / p29~29,35~35,42~42,50~50,80~80 |
9月、山田無文が「坐禅和讃講話 : 白隠禅師」を「春秋社」から刊行する。 所蔵:高知県立図書館
10月1日~11月26日まで、(三島)佐野美術館第一展示室に於いて「白隠その禅と禅画」展が開かれる。
10月、佐野美術館編「隠 : その禅と禅画(図録)」が「三島佐野美術館」から刊行される。
12月、 「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 49(12)(590)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885465
|
巻頭言/p3~3
白隠禅の本質/秋月龍珉/p4~9
筆禅道(遺稿)/横山天啓/p10~11 |
中国禅宗史綱(五) 棲霞寺の禅と曇遷/八木信佳/p12~21
瑩山禅師伝(十四)/東隆真/p22~32
一休和尚伝(四)/安宅雅夫/p32~36 |
臨済録試講(十五)/原田龍門/p37~51
・
・ |
12月、真流堅一が熊本大学教育学部編「熊本大学教育学部紀要. 第2分冊, 人文科学 (通号 21) p.83~104」に「白隠禅における人間形成の思想」を発表する。
○、この年、寺田透が「生への意志 : 1956-1960 」を「思潮社」から刊行する。
(シリーズ名:寺田透・評論 ; 第5) 所蔵:東京都立多摩図書館
|
文芸批評の問題.平野謙『政治と文学の間』
小島信夫『裁判』
寝てゐる男.加藤周一『運命』解説.正宗白鳥『懐疑と信仰』
大雅管見.唐木順三『詩と哲学の間』
福田・中村訳、C.ウィルソン『アウトサイダ-』
中野重治『事実と解釈』
立原のこと.絵画について
その文学的感想.半日.富士正晴『游魂』 |
椎名麟三作品集』第2巻解説.前から考へてゐたこと
太宰治.中村真一郎『回転木馬』
石川淳『白頭吟』
文芸時評.三島由紀夫『橋づくし』・中村真一郎『天使の生活』・
→福永武彦『心の中を流れる河』
芸術家と芸人.私は「勤務評定』をかう考へる.今度のカゼイン展をみて.
→南画史我観.小林多喜二のこと.偽善・偽悪.続・
→鳥海青児.朔太郎管見.深沢七郎小論.
|
→人間存在における悲劇と喜劇
『禅と美術』読後.文学座公演『国性爺』
白隠のこと.椎名麟三.講演・詩・リリシズム.伊藤整『氾濫』
武田泰淳『森と湖のまつり』
わたしの古典.小林秀雄『近代絵画』続後.
→葉山嘉樹と平林たい子
『新日展』の老人達
『文学その内面と外面』 |
○、この年、水野弘元, 平田高士編「道元・臨済禅家集」が「玉川大学出版部」から刊行される。 (世界教育宝典, 仏教教育宝典 5)
|
道元 総説 / 水野弘元
普勧坐禅儀 / 佐藤達玄校注
学道用心集 / 佐藤達玄校注
永平清規 / 佐藤達玄校注
|
正法眼蔵 / 佐藤達玄校注
正法眼蔵随聞記 / 佐藤達玄校注
臨済禅家 総説 / 平田高士
喫茶養生記 / 栄西著 ; 平田高士校注
|
大灯国師仮名法語 / 平田高士校注
夢窓国師夢中問答集 / 平田高士校注
夜船閑話 / 白隠著 ; 平田高士校注
遠羅天釜 / 白隠著 ; 平田高士校注 |
○、この年、「世界教育宝典 仏教教育宝典 5」が「玉川大学出版部」から刊行される。 pid/3038039
|
道元
総説 水野弘元/p5
普勤坐禅儀 佐藤達玄 校注/p21
学道用心集 佐藤達玄 校注/p29
永平清規 佐藤達玄 校注/p51
典座教訓/p53
大己五夏の閣梨に対するの法/p73
辧道法/p81 |
日本国越前永平寺知事清規/p95
赴粥飯法/p143
吉祥山永平寺衆寮箴規/p161
正法眼蔵 佐藤達玄 校注/p171
辧道話/p175
行持/p184
菩提薩捶四摂法/p201
生死/p209 |
正法眼蔵随聞記 佐藤達玄 校注/p213
臨済禅家
総説 平田高士/p255
喫茶養生記(栄西) 平田高士 校注/p269
大灯国訪仮名法語 平田高士 校注/p283
夢窓国師夢中問答集 平田高士 校注/p295
夜船閑話(自隠) 平田高士 校注/p361
遠羅天釜(白隠) 平田高士 校注/p385 |
○、この年、「日本書道大系 7 (江戸・明治・大正)」が「講談社」から刊行される。
|
口絵 本阿弥光悦
口絵 本阿弥光悦
口絵 池 大雅
概説
江戸時代の書道 加藤湘堂
明治・大正・昭和(前期)
→の書道 竹田悦堂
日本の篆刻 北川博邦
15 松花堂昭乗
16 松花堂昭乗
17 松花堂昭乗
18 明正天皇
19 江月宗玩
20 沢庵宗彭
21 宮本武蔵
22 中江藤樹
23 小堀遠州
24 小堀遠州
25 木下長嘯子
26 近衛信尋
27 徳川家光
28 中院通村
29 松永貞徳
30 後光明天皇
31 岡本半介 |
32 千 宗旦
33 林 羅山
34 前田利常
35 清巌宗謂
36 古筆了佐
37 松平信綱
38 後西天皇
39 即非如一
40 石川丈山
41 石川丈山
42 独立
43 深草元政
44 隠元隆琦
45 狩野探幽
46 山崎闇斎
47 後水尾天皇
48 徳川綱吉
49 飛鳥井雅章
50 小野お通
51 佐々木志頭磨
52 山内一豊夫人
53 荒木素白
54 木庵性〔トウ〕
55 山鹿素行
56 寺田無禅 |
57 熊沢蕃山
58 小堀權十郎
59 小堀大膳宗慶(小堀二代)
60 松尾芭蕉
61 高泉良偉
82 伊藤東涯
83 荷田春満
92 山県大貳
95 白隠
96 賀茂真淵
98 平賀源内
104 池 大雅
105 池 大雅
106 池 大雅
107 池 大雅
108 池 大雅
112 與謝蕪村
148 小林一茶
150 松平定信
151 頼 山陽
152 頼 山陽
153 良寛
154 良寛
155 良寛
156 良寛
|
157 良寛
158 本居大平
160 屋代弘賢
167 仙厓
168 仙厓
208 川路聖謨
251 巌谷一六
252 巌谷一六
253 巌谷一六
254 巌谷一六
306 日下部鳴鶴
307 日下部鳴鶴
308 日下部鳴鶴
309 日下部鳴鶴
312 富岡鉄斎
313 富岡鉄斎
334 犬養 毅
335 犬養 毅
385 会津八一
401 高村光太郎
433 池 大雅
日本近世書人略伝 竹田悦堂編
日本印人略伝 北川博邦編
〈抜粋〉
・ |
|
| 1973 |
48 |
・ |
2月23日~3月25日迄、BSN新潟美術館に於いて「白隠名品展」展が開かれる。
2月、「白隠名品展」の図録が「BSN新潟美術館」から刊行される。 付: 白隠名品展作品解説(12p)
2月、白田劫石述「白隠禅師坐禅和讃新講」が「人間禅教団」から刊行される。(人間禅叢書 第6編)
8月、「芸術新潮 24(8)[(284)]」が「新潮社」から刊行される。 pid/6048535
|
略
〈眞贋〉(116) 隠者・白幽子考--〈アート写真版〉 / 伊藤和男/p148~155
藝術新潮欄--〈原色版・アート写真版〉 //p41~51
ぴ・い・ぷ・る / 山田光 ; 各務鉱三 ; 福田蘭童 ; 多田美波 ; 佐藤潤四郎 ; 神代雄一郎
;
→豊口克平 ; 仲田好江 ; 堂本尚郎 ; 芹沢銈介 ; 淡島雅言/p56~57
LP //p166~167
案内 //p52~53
連載 戦後美術品移動史--〈原色版〉((8))鈍翁・益田孝の蒐集品(V) /
→ 田中日佐夫/p98~103
連載 日本美術誌((19))補陀洛渡海 / 栗田勇/p78~83
|
連載 「あんつぐ」骨董買い美学((20))洗硯 / 安東次男/p128~131
連載 〈骨董百話〉--〈原色版〉((56))鎮海仁寿府銘三島皿 / 小山冨士夫/p126~127
連載 唐招堤寺への道--〈アート写真版〉((2))唐招堤寺(一) / 東山魁夷/p106~111
西方の音 音楽に在る死(4) / 五味康祐/p122~124
新連載 秘蔵--〈原色版〉((2))フィレンツェ国立図書館蔵
→「ヴィスコンティ家の時?書」 / 辻佐保子/p116~121
古美術 〈原色版〉 新発見・法然上人の「夢の善導像」 / 徳永弘道/p60~63
古美術 〈原色版〉 幻のインドネシア絣 (イカツト) /
→マイケル・ガウォスキー ; ワンダ・ワーミング/p64~67
・ |
8月、白隠禅師提唱 ; 永田春雄編「碧巌集秘抄」が「鵠林山松蔭禅寺(沼津)・至言社」から復刻される。 pid/12270489
注記 大正5年刊の複製 限定600部 復刻版
9月、「禅文化 (70) 特集 近世禅の先覚者」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082265
|
表紙 井澤寛州筆「茶〔ワン〕図」
アート 藤田美術館『墨蹟』展特集
扉 三島・竜沢寺中川宋渕賛 / 鈴木宗忠
平和への道(下) / 山田無文 / p5~14
参・西国巡礼歌(十三)--禅的なうなずき / 松原泰道 / p26~31
明極楚俊の詩 / 蔭木英雄 / p32~39
茶の心 / 堀内宗完 / p47~53
講座宗教学のすすめ(六) / 西村恵信 / p40~46
文化の素材「筆の本始」 / 中田勇次郎 / p56~61
講演 芸術と生命力 / 岡本太郎 / p15~25
特集 近世禅の先覚者
沢庵宗彭--紫衣事件に対する一見解/玉村竹二/p106~111
|
雲居希膺--その大悟と念仏禅 / 木村静雄 / p112~117
盤珪永琢--盤珪さんに学んだこと / 古賀英彦 / p101~105
鉄牛道機--その人と生涯 / 林雪光 / p95~100
卍元帥蛮--革新をめざして古徳を探る / 荻須純道 / p72~77
無著道忠--現代禅学の指標 / 平野宗浄 / p90~94
古月禅材--骨清の人 / 古田紹欽 / p78~82
自隠慧鶴--白隠の禅と現代 / 大森曹玄 / p118~123
高峰東晙--五山文学研究の先駆者 / 伊藤東慎 / p83~89
座談会 鈴木正三を語る / 柳田聖山 ; 藤吉慈海 ; 大森曹玄 / p62~71
禅文化研究所創立十周年を迎えて / 村上慈海 / p4~4
読者の声「禅文化」誌によせて / p54~55
書灯 / p25~25,46~46,61~6 |
11月、土屋常義が「東海女子短期大学紀要 = The journal of Tokai Women's Junior College 4 p.8a-1a」に「白隠と岐阜県」を発表する。
|
| No |
. |
白隠の作品名 |
所在地 |
No |
. |
白隠の作品名 |
所在地 |
| 1 |
. |
濃陽富士山記 |
美濃加茂市山ノ上富士神社蔵 |
32 |
. |
欠 |
欠 |
| 2 |
. |
百壽大福 |
下呂町矢沢家蔵 |
33 |
. |
壽老 |
高富町南泉寺 |
| 3 |
. |
武川家白隠の位牌 |
下呂町武川家 |
34 |
. |
達磨像 |
揖斐 円通寺 |
| 4 |
. |
達磨像(横65糎竪132糎) |
下呂町火打東泉寺蔵 |
35 |
. |
欠 |
高山市 宗献寺 |
| 5 |
. |
秋葉山大権現(横26糎竪133糎)
金比羅山大権現(横26糎竪133糎)
※南無観世音菩薩(構38糎竪132糎) |
下呂町火打東泉寺蔵
下呂町宮地地蔵寺
※下呂町宮地地蔵寺 |
36 |
. |
欠 |
高富町南泉寺 |
| 6 |
. |
船子夾山図(せんすかつさん) |
揖斐川町瑞岩寺蔵 |
37 |
. |
達磨像 |
関市 梅竜寺 |
| 7 |
. |
一休和尚 半切 |
美濃市清泰寺 |
38 |
. |
蓮花観音 |
関市 梅竜寺 |
| 8 |
. |
大般若波羅密多経(横12糎竪95糎) |
美濃市清泰寺 |
39 |
. |
柱杖仏子図 |
美濃市清泰寺 |
| 9 |
. |
白沢図(密画彩色) |
岐阜市大竜寺蔵 |
40 |
. |
寿老人図
布袋図 |
美濃市清泰寺 |
| 10 |
. |
白衣観音像 |
岐阜市大竜寺蔵 |
41 |
. |
常念観音 |
美濃市清泰寺 |
| 11 |
. |
布袋凧 横物 |
武儀村天正寺蔵 |
42 |
. |
出山釈迦 |
養老町 大通寺 |
| 12 |
. |
出山の釈迦 画仙紙全紙 |
禅昌寺蔵 |
43 |
. |
自画像 |
養老町 大通寺 |
| 13 |
. |
達磨像(横55糎竪135糎) |
伊深正眼寺蔵 |
44 |
. |
定水印和尚像 |
神戸町 瑠璃光寺 |
| 14 |
. |
辻談議拾遺 折本一冊 |
萩原片山家蔵 |
45 |
. |
碧巌録開筵拙語 |
神戸町 瑠璃光寺 |
| 15 |
. |
神機独妙禅師消息二巻 |
萩原片山家蔵 |
46 |
. |
天神図 |
萩原町 千田富三蔵 |
| 16 |
. |
秋葉山大権現・金比羅山大権現 |
片山家蔵 |
47 |
. |
布袋図 |
萩原町 田中利十二蔵 |
| 17 |
. |
木版彩色観音像 一軸 |
片山家蔵 |
48 |
. |
猿 |
萩原町 中田盈畴蔵 |
| 18 |
. |
神農画像 |
片山家蔵 |
49 |
. |
金棒図 |
萩原町 熊崎みさゑ蔵 |
| 19 |
. |
壽字 一軸 |
片山家蔵 |
50 |
. |
みぞさざい |
萩原町 粥川高行蔵 |
| 20 |
. |
法号 四軸 書画 八軸 |
禅昌寺蔵 |
51 |
. |
乗船観月 |
萩原町 千田由二蔵 |
| 21 |
. |
欠 |
欠 |
52 |
. |
遊仙記巻 |
八幡町 慈恩寺 |
| 22 |
. |
欠 |
欠 |
53 |
. |
虚堂像 |
関町 梅竜寺 |
| 23 |
. |
欠 |
欠 |
54 |
. |
馬翁香語(横130糎竪54糎) |
大垣市 瑞雲寺 |
| 24 |
. |
欠 |
欠 |
55 |
. |
達磨 |
美濃加茂市 祐泉寺 |
| 25 |
. |
欠 |
欠 |
56 |
. |
秋葉山大権現・金比羅山大権現 |
美濃加茂市 山之上町 鹿野真蔵 |
| 26 |
. |
欠 |
欠 |
57 |
. |
白隠の手紙 |
美濃加茂市山之上町 鹿野正則蔵 |
| 27 |
. |
欠 |
欠 |
58 |
. |
秋葉山大権現・金比羅山大権現 |
美濃加茂市山之上町 鹿野正則蔵 |
| 28 |
. |
欠 |
欠 |
59 |
. |
達磨 |
美濃加茂市山之上町 山田甚松蔵 |
| 29 |
. |
欠 |
欠 |
60 |
. |
達磨 |
高山市宗祐寺 |
| 30 |
. |
欠 |
欠 |
61 |
. |
金毘羅山大権現・秋葉山大権現 |
金山町玉竜寺 |
| 31 |
. |
欠 |
欠 |
ー |
ー |
ー |
ー |
|
|
(末尾の文章より) 以上県内における白隠の重なる遺品について列挙した。昨年秋、岐阜県内における、市町村指定文化財について、文化財保護協会より、市町村宛、報告を依頼して、名簿を作った。それによると、白隠の市町村指定文化財となっているものゝ,余りに少ないのは意外に思った。県内の作品を列挙してみて、その多くに驚くのであるが、県重要文化財指定は、禅昌寺と大竜寺と慈恩寺であるが、市町村指定は、わずかに、二、三点に過ぎない。白隠の遺品については、更に、研指定をはじめ、市町村指定についても、検討を要するでないか。勿論、国の指定についても、大に考慮して戴きたいものである。 |
|
土屋常義著「白隠と岐阜県」の論文から国県市町村に於ける文化財の指定に関することに、同様な思いをいたしました。関係各位のみなさまに更なる御一考と御尽力をお願いする所存です。本表は論文の内容から岐阜県を一例に掲げてみましたが全国的に見ては如何なものかと心配になりました。白隠禅師の御業績を顕彰し、また末永く継承なされますよう、文化財の指定にされますことも、また、新たな道かと思いました。
2023・2・12 保坂
|
11月、 淡交社編「淡交 27(11)(322)」が「淡交社」から刊行される。 pid/7890984
|
本を知るべし / 千宗室/p22~23
白隠慧鶴 禅僧列伝(11) / 芳賀幸四郎/p28~34
田能村竹田 近世芸術家師友録(11) / 赤井達郎/p124~133
カラー 花入の鑑賞 / 大河内定夫/p5~6
カラー 高麗茶碗 / 藤岡了一/p7~8
カラー 蹲踞の造形 / 辻晋堂/p9~10
カラー 窓の意匠 / 橋本帰一/p11~12
炉辺文学の系譜 古典への慕情(11) / 石田吉貞/p24~27
愛すればこそ 舞台に見る日本のこころ(11)/河竹登志夫/p118~123
オーストラリアのお茶 / 千宗室/p42~45
グラビア オーストラリアに茶道芽生える・淡交会諮問委員会/p17~20
グラビア 黄檗の三筆周辺(下)近世能書銘々伝(11)/綾村坦園/p13~16
グラビア 沖縄の茶(上)/p53~57
グラビア 飛鳥の寺 古寺散策(11)/p59~60
飛鳥の寺 古寺散策(11) / 田中阿里子/p61~65
原色版解説 黄瀬戸立鼓・備前銘鬼の腕
→花入の鑑賞(11) / 大河内定夫/p157~159
原色版解説 遠州高麗・釘彫伊羅保 高麗茶碗(11)/藤岡了一/p160~163
原色版解説 青岸寺 蹲踞の造形(11) / 辻晋堂/p164~167
原色版解説 民家の窓 窓の意匠(11) / 橋本帰一/p168~170
|
黄檗の三筆周辺(下)近世能書銘々伝(11)/綾村坦園/p181~184
沖縄の茶(上)茶の湯人国記補遺 / 村井康彦/p46~52
懐石 お茶事の解説 / 井口海仙/p140~140
グラビア お茶事の解説 飯後の茶事 風炉(3)/井口海仙/p141~151
グラビア お道具のはなし(11)釜と炉縁/p177~180
グラビア 茶の光と影 落葉/p153~156
グラビア 宗旦のわび茶/p93~100
ふるさとの味 「郷土の茶料理」取材うら話(23)/三田富子/p188~189
『又玄夜話』 茶書つれづれ(11) / 熊倉功夫/p68~69
時鳥 添状と名器(11) / 高原杓庵/p66~67
陶芸対談(11)小森松菴 / 杉浦澄子/p70~74
特集 宗旦のわび茶 宗旦伝とその資料 / 永島福太郎/p75~83
特集 宗旦のわび茶 〝わが友宗旦〟と光悦はいう/吉村貞司/p84~92
難波古京の道 道の古代史(16) / 上田正昭/p106~117
続・続幽静庵茶話(11)札幌の茶席 / 井口海仙/p36~41
虹 茶事随想(23) / 鈴木宗保/p134~139
初冬に思う 弥栄子の目(11) / 塩月弥栄子/p101~104
暖 趣向のお茶(11) / 山藤宗山/p186~187
小説(その11)色絵曼陀羅 / 邦光史郎 ; 三田村宗二/p204~216
略 |
11月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 50(12)(602)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885477
|
巻頭言/p3~3
「法華を転ずる」ということ--『六祖檀経』から / 秋月龍珉/p4~12
破餓鬼禅/p13~18
瑩山禅師伝(二十一) / 東隆真/p19~25
作者の言葉 / 西山宗舟/p26~26
禅と武士道 / 秋月龍珉/p27~29
臨済録試講(二十四) / 原田龍門/p30~45
|
一休和尚伝(十) / 安宅雅夫/p46~51
「趙州録」を味読する(四) / 秋月龍珉/p52~53
白隠禅師の一生 / 土岐禾村/p54~70
耕山老師の面影 / トマス・L・カーシュナー/p71~71
書評再録『坐禅に生きる』 / 秋月龍珉/p72~76
臨済宗師家名簿/p77~79
作者の言葉 / 西川宗舟/p80~80 |
12月、 「禅文化 (71)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082266
|
表紙 山本玄峰筆「関」一大字
アート 雪潭・邃巌・巨海三禅師遺墨集
毒語心経講話(一) / 山田無文/p4~12
参・西国巡礼歌(十四)--禅的なうなずき / 松原泰道/p13~19
文化の素材「硯の原理」 / 中田勇次郎/p63~66
中世における禅文学の展開について / 安良岡康作/p24~30
中世文学に見る禅家の思想 / 中川芳雄/p44~49
負の沈黙 / 荻昌弘/p59~62
|
講座 宗教学のすすめ(七) / 西村恵信/p52~58
剣と禅 / 奈良本辰也/p67~73
雪潭・邃巌・巨海三禅師小伝 / 加藤正俊/p20~23
俳句 蘭山句集抄 / 今長谷蘭山/p42~43
詩 傳言板 / 竹中郁/p50~51
座談会 鈴木正三と近代思想 /
→ 柳田聖山 ; ゴンサルベス ; 藤吉慈海/p32~41
書灯/p19~19,30~31,58~58 |
|
| 1974 |
49 |
・ |
1月、 大乗禅 = The mahayana zen buddhism 51(1)(603)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885478
|
表紙画 白隠禅師
巻頭言/p3~3
人間の意味とその追求の方法 / 原田龍門/p4~10
臨済禅における 人間の意味とその追求の方法 / 西村恵信/p11~21
一休和尚伝(11) / 安宅雅夫/p22~27 |
隠れた禅の高僧--釈宗活と西山禾山 / 秋月龍珉/p28~33
禾山玄皷禅師略伝 / 秋月龍珉/p34~42
禅僧と女性 / 秋月龍珉/p43~48
臨済録試講(25) / 原田龍門/p49~57
・ |
3月、「禅文化 (72) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082267
|
表紙 中原鄧州筆「亀之図」
アート 南天棒老師五十年奉賛特集
扉 海清寺 春見文勝画賛
豪僧 南天棒特集 南天棒老師をたたえる / 春見文勝/p12~18
豪僧 南天棒特集 南天棒の歌 / 南天棒老師道歌集より/p20~21
豪僧 南天棒特集 南天棒の書に思う / 猪崎久太郎/p19~19
豪僧 南天棒特集 南天棒と乃木将軍 / 宝積玄承/p22~25
毒語心経講話(二) / 山田無文/p4~11
雲門一曲の清韻 / 中川徳之助/p66~73 |
私訳 寒山詩 / 代田文誌/p26~29
講座 宗教学のすすめ(八) / 西村恵信/p47~52
『禅の神髄従容録』と著者安谷白雲 / 大森曹玄/p74~77
仏教との出会い / 八木誠一/p59~65
古寺探訪--但馬の宗鏡寺 / 岡部恒/p53~58
俳句 非佛鈔 / 永田耕衣/p38~39
祖堂集ものがたり第十六話 雨だれの音--鏡清と大慈 / 柳田聖山/p30~37
参・西国巡礼歌(十五)--禅的なうなずき / 松原泰道/p40~46
書灯/p46~46 |
6月、「禅文化 (73)」が「禅文化研究所 」から刊行される。 pid/6082268
|
坐禅儀 / p4~7
坐禅への道 / p8~8
坐禅儀講話 / 山田無文 / p9~9
第一講 みんなが菩薩 / p9~13
第二講 動静へだて無く / p13~17
第三講 目を開けて / p17~22
第四講 神気朗然たり / p22~23
第五講 龍の水を得るが如く / p23~28
第六講 珠を探るには / p28~34
すわる--身・息・心の調和/大森曹玄/p35~3
一、坐禅の目標 / p35~35
|
外人の見た禅 / p35~39
新しい目標 / p39~40
坐禅とは / p40~42
二、坐禅の仕方 / p42~42
すわる前の準備 / p42~44
すわるにはどうするか / p44~45
1 身相を調える / p45~50
2 気息を調える / p50~53
3 思量を調える / p53~56
すわる / p56~56
公案と参禅 / 平田祖英 / p57~57
|
一、公案の成立とその意義 / p57~59
二、公案工夫について / p59~61
三、参禅について / p61~61
禅会用語解説--役名・行事・禅堂用語・
→食堂用語・その他 / p62~65
臨済・黄檗全国禅会一覧 / p66~79
臨済・黄檗各派専門道場総覧 / p80~81
表紙 白隠筆 鐵字横物
アート 一行書『近世禅林墨蹟』より
カット / 野尻弘
・ |
7月、「歴史と旅 1(7)」が「秋田書店」 pid/7947187
|
江戸の平和開城に幕臣たちの不満がうずまく 連載史伝
→江戸城明け渡し / 海音寺潮五郎 ; 御正伸/p286~299
ずいひつ 天愚孔平と私 / 小島貞二/p138~139
ずいひつ 唐臼の音 / 富山和子/p139~141
ずいひつ 江戸柴・京柴 / 長崎盛輝/p141~142
ずいひつ 最上紅花と上方 / 真壁仁/p142~144
ずいひつ アフガニスタン滞在の六年 / 渡辺弘/p144~145
特集 技術の歴史 大坂城の巨大石垣の謎 / 岡本良一/p42~47
特集 技術の歴史 戦国武将加藤清正の治水土木/片山丈士/p48~52
特集 技術の歴史 日本刀はいかに鍛えられたか/佐藤寒山/p54~58
特集 技術の歴史 火薬はどうして作られたか/大森実/p59~63
特集 技術の歴史 痛みの解放、麻酔薬の出現/宗田一/p64~68
特集 技術の歴史 日本の毒薬と毒殺 / 宗田一/p69~73
特集 技術の歴史 繩文人の漁法 / 楠本政助/p80~84
特集 技術の歴史 江戸時代の捕鯨術 / 大村秀雄/p74~79
カラーグラビア 奈良・明日香--古代技術の旅 / 井上博道/p11~
大匠師良弁--東大寺・石山寺の造営 / 村松貞次郎/p36~41
古代の造船術と航海術 / 清水潤三/p85~89
東西建築の音響装置 / 伊藤仁/p108~112
錦帯橋はどうして作ったか / 伊藤正一/p90~94
日本の探鉱技術 / 葉賀七三男/p114~120
飢饉に学んだ農民の知恵 / 筑波常治/p96~101
箱根用水の先進的工法 / 朝比奈貞一/p102~107
ねり塀の秘密 / 島田清/p53~53
和算について / 野口泰助/p95~95
鎌倉大仏の耐震構造 / 相馬孝昭/p113~113
世界最初のヒコーキ / 野沢正/p121~121
歴史ニュース便覧 仲泊貝塚保存への動き 輪島の「天堂城趾」に脚光
→国宝級の仁王像を発見 古武術の奥義八ミリに収める
→武蔵自筆?「五輪の書」 白鳳様式の三尊?仏出る
→白鳳時代に釉薬の技術 大津京推定地付近で木筒
→「琥珀」の原産地を赤外線でピタリ 「匂りの池」跡から木樋発見
→ 火繩銃はこうして作る 天狗党と久慈舟運 //p200~208
茶の間のミニ歴史 ペットブーム / 岡田章雄/p232~235
まげもの専科 大名行列 / 稲垣史生/p282~285
姓氏・紋章お国めぐり 千葉県 / 丹羽基二/p146~149 |
グラビア 明治建築を訪ねて神戸 / 井上博道 ; 編集部/p163~,275~277
グラビア 藩政秘話 武蔵・忍藩 その城下町 / 小野成視/p171~178
藩政秘話 武蔵・忍藩 江戸の北門に名家の史話 秩父箱訴事件、
→房総警備に譜代の名門忍藩阿部・松平家は
→揺れ動く! / 柳田敏司/p179~185
江戸幕府の地方官 駿府町奉行 彦坂九兵衛光正 大御所家康の
→側近として駿府の民政に腕をふるった
→名行政官の事績!/村上直/p188~197
味に歴史あり 宮崎県の大根 / 多田鉄之助/p133~133
毒のあることば 五日の京兆 / 大北仁也/p199~199
旅つれづれ / 秋/p186~187
イラスト合戦記(4)長篠設楽原合戦記 / 藤田茂/p134~137
年中行事 七夕 / 新田庄司/p162~162
年中行事 盂蘭盆 / 新田庄司/p198~198
わたしの歴史散歩 信玄、志賀城攻めの跡をゆく / 寺山佳代/p236~241
研究レポート まぼろしの磐余京 / 津田由伎子/p242~251
特別読物 沖繩のペリー提督--ボアード水兵事件と
→琉球政庁 / 石野径一郎/p122~132
催しものあんない //p210~210
読者ひろば //p304~305
次号予告 //p252~253
出版広告 //p259~
扉の解説 / 松本茂/p193~193
デスク・メモ / 横田整三/p306~306
カラーセクション ヨーロッパの城と宮殿
→ハイデルベルクの古城 / 田村秀夫/p211~217
カラーセクション 民家の旅 京都の家並 / 近岡善次郎/p218~221
カラーセクション 風俗画の四季 おんなの装い(1) / 遠藤武/p222~225
カラーセクション 名作と名城 土井晩翠「天地有情」の
→仙台城 / 江崎俊平/p226~231
古寺の美を訪ねて(7)西の京薬師寺 / 町田甲一/p278~281
世界の大奥 中国編 後宮における妃嬪の地位 / 大空不二男/p254~258
覊旅の歌一〇〇選 / 阿部正路/p300~303
漂泊の句一〇〇選 / 楠本憲吉/p300~303
連載 こころへの旅立ち 鈴木正三 / 水上勉 ; 冬島大二郎/p150~161
・ |
7月、「太陽 12(7)(134)」が「平凡社」から刊行される。 pid/1792514
|
襌 風〔サン〕水宿の禅僧たち / 古田紹欽 ; 細江英公 / 13
大燈 京都大徳寺の開祖 / 京都大徳寺 ; 鎌倉建長寺 / 19
一休 風狂の生涯 / 堅田祥瑞寺 ; 薪一休寺 ; 京都真珠庵 / 22
無難 素朴な弘法宣布 / 信州飯山正受庵 / 39
白隠 臨済中興の祖 / 三島龍沢寺 ; 原松蔭寺 / 42
盤珪 不生不滅の禅を説く / 大洲如法寺 / 51
正三 悟りを開いたさむらい / 足助恩真寺 / 63
良寛 一衣一鉢の漂泊 / 玉島円通寺 ; 国上山五合庵 / 67
永平寺 雲水の生活 / 秦慧玉 ; 坂本真典 / 83
禅問答というもの / 入矢義高 / 94
日本の禅 お茶づけの味 / 古田紹欽 / 96
特集ガイド 禅寺めぐり/林健太郎; 坂井三郎; 雲輪瑞法; 堀内恒夫/98
|
今月の人 朝比奈宗源 鎌倉円覚寺管長 / 渡辺克己 / 174
連載小説 男振(おとこぶり) / 池波正太郞 ; 中一弥 / 153
人形の誘惑 処女マリアの黒い純白 / 種村季弘 ; 大辻清司 / 148
世界の旅 オリエント特急 / 向田直幹 / 134
宋赤絵人形 / 谷川徹三 ; 脇坂進 / 132
日本お伽月報 一寸法師 / 赤瀬川原平 / 145
さぁーナニを食おうかな(13)食通の鑑!食事の前に
→スポーツを / 東海林さだお / 126
藝人樂屋噺 / 高英男 ; 荒木経惟 / 129
小説絵巻(第四十九回)「賢木(その二)」舟橋聖一 源氏物語 /
→ 舟橋聖一 ; 守屋多々志 / 161
一九七四年度第十一回太陽賞発表 / / 105 |
8月29日、柴山全慶が亡くなる。80歳
9月、「禅文化 (74)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082269
|
毒語心経講話(三) / 山田無文/p4~11
手が見た世界--陶芸の心 / 八木一夫/p70~77
訪中・西安への旅 / 木村静雄/p20~26
ナグプール(龍宮)日記 / 冨士玄峰/p52~60
禅文化周辺 / 市川白弦/p61~69
古寺探訪--備前曹源寺 / 岡部恒/p40~44
文化の素材「植物油」 / 山崎成子/p45~61 |
俳句葛の花 / 伊藤紫皐/p38~39
祖堂集ものがたり第十七話 諸悪莫作,衆善奉行--
島鳥〔カ〕和尚と白楽天 / 柳田聖山/p27~36
参・西国巡礼歌(十六)禅的なうなずき / 松原泰道/p12~19
柴山全慶老師を偲ぶ/p37~37
書灯/p19~19,60~60,69~69
・ |
9月、「歴史読本 19(10)[(227)] 」が「中経出版,新人物往来社 Kadokawa 」から刊行される。 pid/7975197
|
特集 お城の科学
これからの城郭研究 これまで片寄り勝ちであった城郭研究に
→警告と光明を投げかける / 奥田直栄/p40~47
城下町からみた城郭考 城と城下町との関連を二本松、彦根城などを例に検討/矢守一彦/p48~55
日本城郭四つの契機 日本における城郭発達史のモメントとは何であるか!/櫻井成廣/p56~62
戦国のヘソ近江の城郭 近江の観音寺、安土、八幡城の相関関係を解明すると/田中政三/p66~75
金沢城と辰巳用水 加賀百万石の宿願であった用水の見事な土木工学とは / 中井安治/p76~81
鉢形北条氏の室山城塞 秩父の霊峰武甲を
→仰ぐ要衝に位置した中世城塞を推察 / 大野鴻風/p140~145
石垣の譜--技術集団穴太衆 石垣を数百年に亘って
→築いてきた技術集団穴太衆とは / 徳永真一郎/p82~92
渇殺の城 包囲戦のさい城兵たちは何を食べどのように戦ったか / 能坂利雄/p128~139
あしかびの城 沼地に忍城を築いた武蔵武士の意地と名誉の陰には?/井口朝生/p146~157
特別企画 城郭を科学する 濠と繩張り 石垣の構造 大黒柱と天守の構造
→籠城施設(穴蔵・台所・井戸) 瓦と屋根 塗籠と壁 枡形と門・
→櫓 石落しと銃眼 / 平井聖 ; 河東義之/p95~127
グラビア カラー名城 亀山城/p13~13
グラビア 特集グラビア 古式穴太流石垣積み/p15~19
グラビア 夏休みの旅 ふるさとの城下町/p20~27
グラビア 武具発掘の旅 下仁田合戦血染めの兜/p28~30
グラビア カラー古地図 長野市善光寺明細図/p94~94
グラビア 絵はがき近代史 日露戦没東京凱旋門/p160~163
グラビア 鑑賞・鐔いろいろ 銘紀宗長作/p159~159
グラビア 史蹟を訪ねて 越後高田/p164~174
ずいひつ チベットと日露戦争 / 田中克彦/p31~33
ずいひつ 古書よお前もか / 赤木駿介/p33~34
ずいひつ 虹と赤褌 / 大羽弘道/p34~36
ずいひつ 文宝四宝 / 切通耕道/p36~38
ずいひつ 歴史の裏 / 熊王徳平/p38~39 |
姓氏百話 出雲神族の末 / 渡辺三男/p64~65
時代考証事典 名月と美女 / 稲垣史生/p244~247
隠者・白幽子を考察する / 伊藤和男/p230~243
帝国陸軍の造反第一号 / 横倉辰次/p250~257
カラー古地図 長野市善光寺明細図 / 岩田豊樹/p94~94
古書への手引き うひ山ふみ/p228~229
歴読ジャーナル 遺跡・学界・時代劇・小説・同人誌/p188~197
歴史ニュース 咸臨丸の沈没をうらづける最後の記録 足利学校も修理資金難!
→宝くじを発行 津軽探った南部隠密の報告書見つかる 種子島以前に鉄砲があった
→ 伝来異説 ペリー来航七年前に民間人の黒船記録 千利休は島流しか?
→和歌山で新説でる/p287~295
大国魂神社の烏団扇と烏扇 / 田中正明/p222~226
まんが・かわら版 / 永美ハルオ/p63~63,93~93,221~221,301~301
新・歴史人物風土記 宮崎県(第4回)孤児の父と外交官 福祉に力を注ぐ人道家と
→日向気質が生んだ名外交官の話 / 八尋舜右/p198~203
今月の史蹟の旅 新潟県上越市高田地区 頸城平野の守り越後高田城 日本一の豪雪地
→越後高田に御家騒動と戊辰史蹟を訪ねて / 加藤蕙/p175~187
れきどく図書室/p248~249
出版だより/p270~270
歴史研究会だより/p271~271
次号予告/p272~273
読者のページ/p296~300
編集デスク/p302~302
三大歴史長篇 蒼き蝦夷の血 宇治川を渡り都入りした範頼・
→義経軍は木曽義仲軍を追討した! / 今東光/p204~220
三大歴史長篇 会津士魂 鳥羽伏見に敗れた忠義に殉じる
→会津武士団の東帰は悲壮であった / 早乙女貢/p258~268
三大歴史長篇 続武田信玄 信長は威信を顕示するため正倉院御物の
→蘭奢香を朝廷に所望した / 新田次郎/p274~286
|
10月、陸川堆雲評釈著述「評釈夜船閑話」が「山喜房仏書林」から刊行される。 pid/12217899 所蔵:群馬県立図書館
附: 白幽子の新研究
10月、「歴史と旅 1(10)(10)」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947190
|
徳川処遇で西郷、木戸、大久保の意見は対立する
→連載史伝 江戸城明け渡し / 海音寺潮五郎 ; 御正伸 / p288~301
歴史ニュース便覧 新発見あいつぐ山城の研究--
→山頂にも迫りくる開発公害 / 伊礼正雄 / p198~202
歴史ニュース便覧 箱根芦の湖底に杉林 “沖繩のロゼッタ・ストーン”発見
→大化改新の舞台に疑問 北海道先住民の墓群発掘
→小浜藩のキリシタン弾圧資料 エゾキリシタン裏付け
→古照遺跡から高床式の遺材 仁徳陵発掘文書みっかる/p202~209
江戸幕府の地方官 江戸町奉行・大岡越前守忠相 世に名判官として |
→知られる江戸南町奉行の虚実と
→行政の実態を描く! / 村上直 / p190~197
イラスト合戦記(7)元寇文永の役 / 藤田茂 / p134~137
年中行事 亥の子 / 新田庄司 / p162~162
新連載 古城・館址探訪 第三回武蔵国(3) / 西ヶ谷恭弘 / p128~133
わたしの歴史散歩 俊寛僧都の墓を訪ねて / 石母田俊 / p236~242
研究レポート 山田長政の生地雑考 / 五井野貞雄 / p243~245
連載 こころへの旅立ち 白隠 / 水上勉 ; 冬島大二郎 / p150~160
・ |
11月、「歴史と旅 1(11)(11)」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947191
|
海舟は慶喜を水戸から江戸に呼び戻す運動を始めた 連載史伝
→江戸城明け渡し / 海音寺潮五郎 ; 御正伸 / p286~300
年中行事 冬至 / 新田庄司 / p162~162
新連載 古城・館址探訪 第四回武蔵国(4) / 西ヶ谷恭弘 / p122~131
わたしの歴史散歩 俊寛僧都の墓を訪ねて(下) / 石母田俊 / p238~244
わたしの歴史散歩 手賀沼のほとり / 蒼海芳雄 / p245~249 |
特別読物 北海道秘史・滅びゆくコタン / 三好文夫 / p110~121
古寺の美を訪ねて(11)唐招提寺 / 町田甲一 / p278~281
世界の大奥 中国編 宮廷の遊楽 / 大空不二男 / p254~258
漂泊の句一〇〇選 / 楠本憲吉 / p302~305
連載 こころへの旅立ち 白隠 / 水上勉 ; 冬島大二郎 / p150~160
・ |
12月、「歴史と旅 1(12)(12)」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947192
|
連載史伝 江戸城明け渡し / 海音寺潮五郎 ; 御正伸 / p282~295
歴史ニュース便覧 北海道開拓史に新しい視点 手すぐい風俗絵巻
→ギャンブル連歌の大流行 朝倉遺跡に武家屋敷街
→「古九谷」古窯跡を発掘 海底百年、開陽丸キャッチ
→すり替わった“秀吉大判” 西南の役、会津士族戦闘記録
→弥生時代の遺跡から文字 幻の小田原城絵図を発見
→伊達正宗の遺体を発掘 草津の宿場史 / p200~209
グラビア 明治建築を訪ねて“明治村”/根本陽子/p163~169,275~277
グラビア 藩政秘話 松前藩 その城下町 / 本誌写真部 / p171~178
藩政秘話 松前藩 北辺守る外様小藩の史話 / 榎森進 / p179~189
|
わたしの歴史散歩 信濃の道祖神祭--祭礼と人形とに
→見る庶民の哀歓 / 会田弘志 / p238~244
わたしの歴史散歩 歴史と文学の甲州路--
→塩山市およびその周辺ある記 / 遠藤博文 / p245~251
特別読物 元禄裏面史 『松蔭日記』と柳沢吉保/祖田浩一/p102~111
世界の大奥 中国編 断袖の癖 / 大空不二男 / p254~258
羇旅の歌一〇〇選 / 阿部正路 / p296~299
漂泊の旬一〇〇選 / 楠本憲吉 / p296~299
連載 こころへの旅立ち 白隠 / 水上勉 ; 冬島大二郎 / p150~160
・ |
○、この年、柴山全慶が「白隠禅師坐禅和讃禅話」を「春秋社」から刊行する。 pid/12272067
○、この年、「達磨図幅 白隠著」を「二玄社」が刊行する。 所蔵:兵庫県立図書館 大きさ、容量等
1軸 ; 66cm |
| 1975 |
50 |
・ |
1月、「歴史と旅 2(1)(13) 」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947193
|
グラビア おとぎ話と民話の里 木曽路の浦島太郎 / 小野成視 / p163~166,200~203
歴史ニュース ダイジェスト “銅鐸鋳型の原型”発掘 / p276~277
歴史ニュース ダイジェスト 小田原にかくれキリシタンの教会跡 / p282~282
歴史のある寺(1)鎌倉満福寺・吉野金峰山吉水院<源義経ゆかりの寺>/徳永隆平/p230~233 |
漂泊の句百選 / 楠本憲吉 / p252~253
連載 こころへの旅立ち 白隠 /
→ 水上勉 ; 冬島大二郎 / p152~161
〈抜粋〉 |
2月、「歴史と旅 2(2)(14)」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947194
|
連載史伝 江戸城明け渡し / 海音寺潮五郎 ; 御正伸 / p322~335
≪ずいひつ≫ 高寺八講 / 藤沢周平 / p190~191
グラビア 古戦場 日本縦断 函館 会津 長篠 天目山 姉川 賤ヶ嶽
→千早・赤坂 一ノ谷・屋島・壇ノ浦 / p19~34
古戦場ミニガイド 五稜郭 / p60~61
古戦場ミニガイド 天目山 / p72~73
古戦場ミニガイド 長篠 / p82~83 |
古戦場ミニガイド 長久手 / p84~85
グラビア おとぎ話と民話の里 因幡の白兎 /
→本誌編集部 / p163~167,192~195
グラビア 歴史のある街 土佐高知 / 本誌編集部 / p169~181
歴史ニュースダイジェスト 邪馬台国のナゾ解明か? / p308~309
歴史ニュースダイジェスト 日本人の起源をさぐる / p310~310
連載 こころへの旅立ち 白隠 / 水上勉 ; 冬島大二郎 / p232~242 |
|
新田庄司が「歴史と旅 1~2(1~15)」に発表した「年中行事」についての内訳一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
発行年 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
歴史と旅 1(7)p162~162
p198~198 |
1974-07 |
年中行事 七夕 |
. |
pid/7947187 |
| 2 |
年中行事 盂蘭盆 |
. |
| 3 |
歴史と旅 1(10)(10)p120~120
p162~162 |
1974-10 |
大谷探検隊 |
. |
pid/7947190 |
| 4 |
年中行事 亥の子 |
. |
| 5 |
歴史と旅 1(11)(11)p162~162 |
1974-11 |
年中行事 冬至 |
. |
pid/7947191 |
| 6 |
歴史と旅 2(1)(13)p258~258 |
1975-01 |
年中行事 |
. |
pid/7947193 |
| 7 |
歴史と旅 2(2)(14)p290~290 |
1975-02 |
年中行事 |
. |
pid/7947194 |
| 8 |
歴史と旅 2(3)(15)p258~258 |
1975-03 |
年中行事 |
. |
pid/7947195 |
|
3月、「禅文化 (76) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082271
|
毒語心経講和(四) / 山田無文/p4~11
聖徳太子と仏教 / 梅原猛/p29~42
梅花禅 / 堂谷憲勇/p43~52
古刹の命運--播磨法雲・宝林寺 / 岡部恒/p53~59
祖堂集ものがたり(第十八話) 赤眼の帰宗 / 柳田聖山/p60~69
随筆 鑑定 / 八木一夫/p20~21
随筆 あしびと悲歌 / 松本仁/p21~23 |
随筆 猫の恋 / 永田耕衣/p23~25
随筆 インディオと大豆 / 高田慧穣/p25~27
一休づかれ--今のところは馬祖道一 / 富士正晴/p12~19
十年の歩みを祝う/p28~28
書灯 「大燈禅の探求」平野宗淨著
→/「禅問答」秋月龍珉著 / 木村 ; 西村/p19~19,42~42
・ |
4月、笠原一男編集指導「人物探訪・日本の歴史 済世の名僧 11」が「暁教育図書」から刊行される。 pid/12206443
|
◆親鸞と念仏の源流 笠原一男 5
親鸞誕生 6
仏教への道 8
法然に入門 11
越後配流 12
布教活動と入滅 15
念仏の源流 16
念仏の系譜 19
庶民に愛された蓮如 20
〔鼎談〕動乱期に生きた名僧 笠原一男,田村芳朗,水上勉 21
親鸞(浄土真宗)―煩悩具足の生き仏 笠原一男 29
源信(浄土教)―地獄の中に極楽を見いだした人 石田瑞麿 41
空也(民間浄土教)―巷の念仏者 石田瑞麿 44
良忍(融通念仏宗)―幸せを分け合う念仏者 大橋俊雄 46
法然(浄土宗)―民衆宗教のパイオニア 大橋俊雄 48
一遍(時宗)―さすらいの宗教家 大橋俊雄 53
蓮如(浄土真宗)―乱世の庶民に愛された教祖 笠原一男 56
大和清九郎(妙好人)―期待される念仏者たち 小栗純子 63
教主善兵衛(隠れ念仏)―隠れ念仏始末記 小栗純子 66
◆日蓮とその弟子 高木豊 69
日蓮の出生 70
日蓮の修行と修学 72
立正安国論 74
龍口の危難と佐渡配流 77
蒙古の襲来 79
日蓮の示寂 80
日蓮の弟子 81
日親・拷問を恐れぬ行動家 83
日奥・反権力の傑僧 84
日蓮(日蓮宗)―われ日本の柱とならむ 高木豊 85
日蓮を受け継ぐ人々―六人の本弟子 高木豊 97
日親(日蓮宗)―鍋かむりの受難僧 中尾堯 101
日奥(日蓮宗)―権力に屈しなかった傑僧 圭室文雄 104
隠れ題目始末記 圭室文雄 106
◆禅の求道者たち 今枝愛真 109
道元・曹洞宗の開祖 110
紹瑾・曹洞教団の立役者 112
栄西・臨済宗発展の祖 113
疎石・臨済禅の確立者 114
沢庵・剣禅一致を説く 115
白隠・臨済宗中興の祖 116
道元(曹洞宗)―坐禅に生涯をかけた学僧 今枝愛真 117
瑩山紹瑾(曹洞宗)―道元を受け継いだ求道者 今枝愛真 122
栄西(臨済宗)―二足のわらじをはいた教祖 今枝愛真 124
夢窓疎石(臨済宗)―戦国乱世の政治顧問 今枝愛真 126
沢庵(臨済宗)―武将の心を支えた禅僧 今枝愛真 128
白隠(臨済宗)―民衆の味方になった禅傑 今枝愛真 130
◆天台と真言密教 下出積與 133
最澄・天台宗の開祖 134
空海・真言密教の大成者 137
最澄(天台宗)―一隅を照らした済世の僧 下出積與 141
空海(真言宗)―慈悲と叡智の済民の僧 佐和隆研 146
役小角―"まじない"の源流 下出積與 152
■諸宗派の群像 154
中山みき(天理教)―自ら神になった女性 小栗純子 154
川手文治郎(金光教)―災いの神を幸せの神へ 小栗純子 158 |
お珊・お竹と自雲―はやリ神の系譜 宮田登 160
家行と兼倶―伊勢神道から吉田神道へ 西垣晴次 162
■奇僧・悪僧列伝 寺内大吉 164
文覚―弱き者の味方に生きた奇僧 164
策伝―落語の鼻祖といわれる説教僧 164
桃水―求道心に燃えた乞食僧 165
愚安―母妹を求めて放浪する禅僧 166
崇伝―徳川家康側近の政僧 166
天海―家康を支えた温容なる策士僧 167
安楽坊遵西―男根を斬られた女犯僧 168
小野僧正文観―肉体に法悦を求めた妖僧 168
延命院日当―淫欲をほしいままにした大破戒僧 169
■渡来僧 石田瑞麿 170
鑑真―執念で渡来した律宗の祖 170
無学祖元―円覚寺開山の第一祖 171
隠元隆琦―天皇に尊崇された黄檗宗の開祖 172
■資料
宗教史概説―日本人と宗教 笠原一男 173
関連年表 小栗純子 173
目で見る日本の宗派系統図 小栗純子 178
名僧絵地図・生没年表 圭室文雄 180
仏像の見方 佐和隆研 182
名僧ゆかりの地の旅 圭室文雄 184
関東周辺 184
近畿周辺 185
北陸周辺 187
中国・四国・九州周辺 188
歴史用語解説 圭室文雄,小栗純子 189
■コラム
転女成男の救い 笠原一男 32
隠すは上人、せぬは仏 笠原一男 35
空也と聖 菊地勇次郎 44
女人正機 笠原一男 58
日蓮はセンダラか 中尾堯 86
日蓮の女性観 中尾堯 88
法華一揆 圭室文雄 104
道元はなぜ越前に去ったか 山本世紀 118
たくあん漬けの由来 圭室文雄 128
心頭を滅却すれば火もまた涼し 圭室文雄 130
教派神道 小栗純子 156
おかげまいり 西垣晴次 162
■歴史異聞余聞
親鸞は実在したか 松野純孝 38
妻をもった親鸞 松野純子 39
法然は文盲か 大橋俊雄 52
蓮如は宗教家か政治家か 真継伸彦 62
日蓮は予言者か 戸頃重基 94
龍口の法難は事実か 戸頃重基 95
玄明の追放事件―道元の潔癖さ 山本世紀 121
密教とは何か 佐和隆研 151
■人物余話
親鸞を取り巻く高弟たち 松野純孝 40
忍性と然阿良忠 高木豊 96
駆け込み寺・東慶寺 圭室文雄 132
最澄の高弟・円仁 下出積與 145
・ |
4月、 「芸術新潮 26(4)[(304)] 」が「新潮社」から刊行される。 pid/6048555
|
奈良の「ほんもの」<特集> //p2~29
特集 1 奈良の「ほんもの」 <グラビア・原色版> 再建された法輪寺三重塔(その再建過程)、再興された薬師寺金堂、蘇る斑鳩の塔(法起寺三重塔)、修理進む大仏殿、新築された興福寺講堂、海竜王寺の今昔、観光にゆらぐ奈良(海住山寺、般若寺、秋篠寺、中宮寺)、新築ラッシュの収蔵庫(法輪寺、大安寺、興福寺、聖林寺、法隆寺)、戦後の新建築(唐招提寺南大門、長谷寺五重塔、室生寺仁王門、平城宮跡集会場、春日大社宝物殿) / 飛鳥園 ; 野中昭夫 ; 松藤庄平/p3~20
「青丹よし奈良の都は」…… / 青山茂/p21~29
特集 2 日本絵画のなかの言葉<原色版・グラビア> 三十六人集(素性集) 平家納経(薬王品見返し)
最勝王経変相図 宗達・光悦 四季草花和歌巻 種字曼荼羅図 扇面法華経図(泉殿群女図・泉殿図)
方便法身尊号 蕪村筆十宜図(宜秋図) 如拙筆瓢鮎図 白隠筆七福神寿舟 仙厓筆円想(これくふて茶のめ) 岸田劉生筆麗子五歳像 //p69~80
解説 / 宗左近/p68~68,81~85
連載 十一面観音巡礼(完)<原色版>熊野詣 / 白洲正子/p58~65
西方の音 ベートーヴェン弦楽四重奏曲作品131 / 五味康祐/p137~139
〈抜粋〉
|
6月、「禅文化 (77) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082272
|
表紙 無難筆「平常道」 / 木村
アート 特集 無難禅師の芳躅 / 編集部
扉 妙心寺 玉鳳院前景
特集 無難禅師の芳躅 至道無難の禅--身をなくすの一大事/大森曹玄/p38~45
特集 無難禅師の芳躅 無難の菴主禅--愚堂・無難・正受・
→白隠の系譜から / 古田紹欽 / p58~64
特集 無難禅師の芳躅 無難禅師のあしあと / 小池心叟 / p53~57
特集 無難禅師の芳躅 伝灯の祖師 至道無難 / 宝積玄承 / p48~52
自己を忘るる / 山田無文 / p4~15
祖堂集ものがたり(第十九話)玄沙地獄 / 柳田聖山 / p72~81
古寺探訪--建仁寺久昌院 / 岡部恒 / p65~71 |
随筆 茶と禅の周辺 / 堀内宗完 / p31~32
随筆 知っていること / 村上三島 / p32~34
随筆 母として女として / 池坊保子 / p34~35
随筆 栂尾 / 竹中玄鼎 / p35~37
短歌 / 西谷得宝 / p46~47
座談会--アンベトカルの仏教復興運動とインドの
→カースト制 / 堀沢祖門 ; 山折哲夫 ; 藤吉慈海 ;
→ 冨士玄峰 / p20~30
慈恩寺の塔と杜甫 / 土岐善麿 / p16~19
書灯 / 加藤 / p19~19
・ |
9月、「禅文化 (78)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082273
|
表紙 堪忍袋の図 玄峰画賛
アート 特集 玄峰老師遺墨集
扉 清水公照画賛
毒語心経講話(五) / 山田無文/p4~11
弓と禅 / 中西政次/p74~81
初期黄檗の画僧 逸然性融について / 大槻幹郎/p66~73
高村光太郎における愛からの脱落 / 松原哲明/p12~19
祖堂集ものがたり・第二十話
→一つ家に遊女もねたり萩と月 / 柳田聖山/p44~59
古寺探訪--※美濃小島瑞巌寺 / 岡部恒/p60~65
参考:愚堂東寔筆蹟(岐阜県指定重要文化財)
仙厓筆紙本水墨宝満山之図(岐阜県指定重要文化財)[ ]円空仏(町指定文化財)
|
随筆 碧落の碑 / 北原隆太郎/p37~38
随筆 黄檗宗の安心 / 村瀬玄妙/p38~41
随筆 無 / 清水公照/p41~43
座談会 アンベトカルの仏教復興運動と
→インドのカースト制(承前) / 堀沢祖門 ; 山折哲雄 ;
→藤吉慈海 ; 冨士玄峰/p20~28
玄峰老師の思い出 / 平井玄恭/p29~33
玄峰老師略年譜/p34~36
書灯 / 宝積/p11~11,59~59
・
・
・ |
12月、「 禅文化 (79)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082274
|
表紙--一休禅師自号自賛墨蹟
アート--特集--一休禅師
扉--一休禅師御廟前門
一休存在の歴史的意義 / 芳賀幸四郎/p10~19
一休宗純皇胤説の再確認 / 玉村竹二/p62~72
一休の反骨精神にちなんで / 市川白弦/p33~40
一休禅の嘘--幽霊と正躰 / 古田紹欽/p26~32
涅槃堂裡の禅--一休と徹翁 / 柳田聖山/p41~49
一休断片 / 富士正晴/p20~25 |
一休和尚年譜事考 / 平野宗浄/p83~90
再説・仏界入り易く魔界入り難し / 岡松和夫/p73~82
堅田の一休--この地の禅縁と気風について / 森龍吉/p54~61
一休さんを思う / 山田宗敏/p50~51
一休さんのこと / 立花大亀/p52~53
一休和尚略年譜/p91~93
毒語心経講話(六) / 山田無文/p4~9
表紙解説 / 加藤/p19~19
・ |
○、この年、紀野一義が「名僧列伝 2 (禅者 2)」を「文芸春秋」から刊行する。 pid/12223728
2:良寛,盤珪,鈴木正三,白隠 |
| 1976 |
51 |
・ |
1月、「墨美 (257)」が「墨美社,書道出版社」から刊行される。 pid/2362577
|
近世禅林墨蹟--思文閣美術館主催
→近世禅林墨蹟展より / p1~64
白隠慧鶴 / / 1~
古月禅材 / / 7~8
白隠慧鶴 / / 8~22
大休慧昉 / / 23~23
霊源慧桃 / / 24~24
良哉元明 / / 25~25
遂翁元盧 / / 26~31
東嶺円慈 / / 32~36
滄海宜運 / / 37~38
天倪慧謙 / / 39~39
|
蘭山正隆 / / 40~40
峨山慈棹 / / 41~42
隠山惟□(イエン)/ / 43~43
誠拙周樗 / / 44~46
弘巖玄猊 / / 47~48
卓洲胡僊 / / 49~50
仙厓義梵 / / 51~58
春叢紹珠 / / 59~59
大観文珠 / / 60~61
月船禅慧 / / 62~62
近世禅林の流れ--紫衣事件を起点とする / 加藤正俊 / p4~6
作者略伝(没年順) / 加藤正俊 / p62~64
|
3月、 「禅文化 (80)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082275
|
表紙 白隠筆 杵図
アート 竜安寺所蔵「近世禅林墨蹟展」より
毒語心経講話(7) / 山田無文/p4~9
妙心寺蔵竜虎図 屏風の筆者について / 土居次義 / p10~15
正眼僧堂の祖 雷鳴り雪潭 / 古田紹欽 / p16~21
渡唐天神画像をめぐって(上)五山文学の一断面 / 蔭木英雄 / p29~39 |
古寺探訪--丹後久美浜・宗雲寺 / 岡部恒/p63~69
墨蹟鑑賞(1) / 編集部/p22~28
沈黙に抗って言葉を刻むもの / 紀野一義 / p40~45
表紙解説 / 加藤 / p9~9
〈抜粋〉
・ |
4月、池田政章が「書斎の窓 = The window of author's study (252) p40~47有斐閣」に「白隠・円空との再会 (1)」を発表する。 pid/3437242
6月、池田政章が「書斎の窓 = The window of author's study (253) p31~37有斐閣」に「白隠・円空との再会 (2)」を発表する。pid/3437243
6月、「禅文化 (81)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082276
|
口絵 東山・慈照寺
特集 銀閣寺と東山文化
東山殿義政 / 永島福太郎/p4~9
東山山荘の造営と東山文化の性格 / 芳賀幸四郎/p10~17
義政と東山山荘の世界 / 藤岡大拙/p18~18
東山殿から慈照寺へ / 川上貢/p26~34
|
慈照寺庭園の考察 / 森蘊/p35~44
足利義政と銀閣の庭 / 吉村貞司/p45~52
慈照寺と慈照院 / 玉村竹二/p53~65
慈照寺世譜 / 有馬頼底/p66~71
毒語心経講話(八) / 山田無文/p72~76
銀閣寺境内図/p77~77 |
7月、池田政章が「書斎の窓 = The window of author's study (254) p38~45有斐閣」に「白隠・円空との再会 (3)」を発表する。pid/3437244
9月、「禅文化 (82)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082277
|
口絵 大津瀝堂老師追憶特集
扉 大津瀝堂老師筆「達磨図」
毒語心経講話(九) / 山田無文/p4~10
仙人の道 / 森三樹三郎/p21~28
日本水墨画の成立 / 源豊宗/p52~61
壇徒安心章の禾山 / 古田紹欽/p79~84
祖堂集ものがたり・第二十二話 そのまた草鞋をつくる人
|
→--睦州と臨済 / 柳田聖山/p29~41
渡唐天神画像をめぐって(下)--五山文学の一断面/蔭木英雄/p62~71
古寺探訪--烏丸光広と太秦法雲院 / 岡部恒/p72~78
墨蹟鑑賞(二) / 岡部恒 ;加藤正俊 ;木村静雄 ;古賀英彦 ;宝積玄承/p42~51
大津瀝堂老師 追悼座談会 / 有馬頼底 ; 上田閑照 ; 梶谷宗忍 ;
→ 片岡仁志 ; 辻村公一 ; 西谷啓治他/p11~19
書灯 / 玉村竹二/p28~28 |
9月23日~10月13日、熊本県立美術館に於いて「近世禅林美術 : 白隠と仙厓を中心に/永青文庫展 2」が開かれる
9月、熊本県立美術館編「近世禅林美術 : 白隠と仙厓を中心に」が「熊本県立美術館」から刊行される。
12月、「太陽 14(12)(163)」が「平凡社」から刊行される。 pid/1792350
|
巻頭言 書を書くこと / 中川一政 / 14
書のおどろき・書のたのしみ / 大岡信 / 49
墨のさまざまな美――平安朝の仮名の美を中心にして / 中田勇次郎 / 19
書のさまざまな用――個性的な墨蹟の楽しさをたずねる / 大岡信 / 31
色紙・短冊――細川ガラシア・近衛信尹・平賀元義・太田垣蓮月・泉鏡花・釈迢空・高浜虚子・坂口安吾 / / 32
手紙 藤原佐理・吉田兼好・織田信長・淀君・本阿弥光悦・松花堂昭乗・良寛・南方熊楠・田村俊子・太宰治 / / 38
日記 定家筆土佐日記・紫式部日記・明恵上人夢記・国木田独歩欺かざるの記・岡倉天心支那旅行日誌 / / 52
禅画・文人画 白隠・仙厓・與謝蕪村・池大雅・富岡鉄斎・小川芋銭・頼山陽 / / 55
写経 五月一日経・久能寺経・二月堂焼経・扇面古写経・紫紙金字華厳経・過去現在因果経・岡本かの子
/ / 63
略 |
12月、「禅文化 (83)米国結制記念特集」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082278
|
米国結制記念特集
禅は諸道の根元 / 山田無文 / p4~5
仏法東漸--大菩薩劇 / 嶋野栄道 / p6~10
雲水団米国を行く--結制団の日記から/木村静雄/p11~21
アメリカにおける禅 / 大森曹玄 / p22~29
大菩薩への道 / 宝積玄承 / p30~37
花薬欄 米国結制団と共に / 中津哲夫 / p38~39 |
花薬欄 ファインダーよりの米国結制 / 栂正隆 / p40~41
花薬欄 米国結制団に参加して / 森本睦宗 / p41~43
花薬欄 米国結制団の思い出 / 山口孝次郎 / p43~44
古寺探訪--白隠ゆかりの寺・その一 正受庵/古賀英彦/p46~51
墨蹟鑑賞(三) / 編集部 / p52~62
伊勢と甲州--夢窓疎石の生いたち その一/柳田聖山/p64~75
・ |
○、この年、荻須純道が「禅研究所紀要 (通号 6・7) p.p43~52」に「白隠の禅と念仏について (愛知学院創立百周年記念号) 」を発表する。 |
| 1977 |
52 |
・ |
3月、「禅文化 (84) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082279
|
表紙 仙厓筆 大黒天図
口絵 竜安寺所蔵「仙画厓展」より
毒語心経講話(十) / 山田無文 / p4~11
釈尊の教団(一) その組織 / 平川彰 / p70~77
禅と文化 / 西谷啓治 / p17~27
甲州より奥羽へ--夢窓疎石の
→生いたち(そのニ) / 柳田聖山 / p42~53
ソーロウに於ける「こころ」の問題 / 伊藤和男 / p54~62
フランスで思う--サムライの文学 / 柴田増美 / p33~40 |
マルロー禅 / 竹本忠雄 / p12~16
古寺探訪--白隠ゆかりの寺・そのニ 正宗寺 / 古賀英彦 / p64~69
花楽欄 わが花物語 沈丁花 / 松本仁 / p28~29
花楽欄 明恵上人と坐禅 / 葉上照澄 / p29~30
花楽欄 忘れえぬS和尚の教え / 門脇佳吉 / p30~32
花楽欄 俳句 田荷軒空溝 / 永田耕衣 / p32~32
書灯 大森曹玄著『碧巌録』上・下二巻 / p41~41
〔新刊書案内〕 / p63~63
・ |
4月、勝又俊教,渡辺照宏,堀一郎,増谷文雄,古田紹欽,西谷啓治,小西甚一訳「教文学集」が「筑摩書房」から刊行される。
(古典日本文学 ; 14)
|
最澄 発願文 勝又俊教 訳
山家学生式 勝又俊教 訳
顕戒論 勝又俊教 訳
空海 三教指帰 渡辺照宏 訳
円仁 入唐求法巡礼行記 堀一郎 訳
源信 往生要集 堀一郎 訳
徒然 選択本願念仏集 増谷文雄 訳
登山状 増谷文雄 訳
念仏問答 増谷文雄 訳
一枚起請文 増谷文雄 訳
親鸞 正信念仏偈 増谷文雄 訳
和讃 増谷文雄 訳
書簡 増谷文雄 訳
歎異抄 増谷文雄 訳
日蓮 立正安国論 堀一郎 訳
|
佐渡御書 堀一郎 訳
種種御振舞御書 堀一郎 訳
一遍 消息法語 増谷文雄 訳
蓮如 御文 増谷文雄 訳
明恵 阿留辺幾夜宇和 古田紹欽 訳
南浦紹明 大応仮名法語 古田紹欽 訳
瑩山紹瑾 瑩山仮名法語 古田紹欽 訳
夢窓疎石 夢窓仮名法語 古田紹欽 訳
夢中問答 古田紹欽 訳
宗峯妙超 大燈仮名法語 古田紹欽 訳
大燈国師遺跡誡 古田紹欽 訳
拔隊得勝 塩山仮名法語 古田紹欽 訳
沢菴宗彭 不動智神妙録 古田紹欽 訳
東海夜話 古田紹欽 訳
鈴木正三 驢鞍橋 古田紹欽 訳
|
盤珪 盤珪禅師語録 古田紹欽 訳
白隠慧鶴 坐禅和讃 古田紹欽 訳
遠羅天釜 古田紹欽 訳
於仁安佐美 古田紹欽 訳
慈雲尊者飲光 人となる道 古田紹欽 訳
十善戒相 古田紹欽 訳
詩偈 西谷啓治 訳
一言芳談 小西甚一 訳
梁塵秘抄 小西甚一 訳
解説 唐木順三 著
文学上に於ける弘法大師 幸田露伴 著
法然の生涯 倉田百三 著
親鸞の語録について 亀井勝一郎 著
「立正安国論」と私 上原専禄 著
日本の文芸と仏教思想 和辻哲郎 著 |
4月、「墨美 (270)」が「墨美社」から刊行される。 pid/2362590
|
近世高僧墨跡--A氏コレクション/加藤正俊/p2~6
春屋宗園・江月宗玩 / / 7~7
雲居希膺・清巖宗渭・独立性易 / / 8~8
澤庵宗彭・即非如一 / / 9~9
至道無難・鉄眼道光 / / 10~10
盤珪永琢・月舟宗胡 / / 11~11
心越興儔・大心義統 / / 12~12
独湛性瑩・鳳潭僧濬 / / 13~13
百拙元養・古月禅材 / / 14~14 |
白隠慧鶴 / / 15~20
寂巖諦乗 / / 21~21
遂翁元廬 / / 22~22
東嶺円慈 / / 23~24
霊源慧桃・峨山慈棹 / / 25~25
曇寧明逸(明月上人) / / 26~26
桂洲道倫 / / 27~27
慈雲飲光 / / 27~30
誠拙周樗 / / 31~31
|
隠山惟〔エン〕・弘巖玄猊 / / 32~32
卓洲胡僊・峻山天如 / / 33~33
豪潮寬海 / / 34~36
仙厓義梵 / / 37~40
春叢紹珠 / / 41~41
近世高僧墨蹟 / 加藤正俊 / 2~6
略伝と釈文--没年順/加藤正俊/p42~52
・
・ |
4月、鈴木学術財団編「日本大蔵経 第86巻 宗典部:禅宗章疏. 1」が「鈴木学術財団」から刊行される。 改訂増補版 pid/12264467
|
興禅護国論3巻(栄西)
大燈国師語録2巻(性智[等]編) |
不動智1巻(沢庵)
沢庵和尚玲瓏随筆4巻 |
盤珪仏智禅師法語2巻
夜船閑話2巻(白隠) |
鉄眠禅師仮字法語1巻
・ |
5月14日~6月19日、佐野美術館に於いて「白隠 : 細川コレクションによる
: 特別展」が開かれる。主催: 佐野美術館, 三島市教育委員会
5月、佐野美術館学芸部編集企画「白隠 : 細川コレクションによる : 特別展」が「佐野美術館」から刊行される。
6月、笹尾哲雄が「近世に於ける妙心寺教団の研究」を「普門山大悲禅寺」から刊行する。
6月、「禅文化 (85) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082280
|
毒語心経講話(十一) / 山田無文 / p4~10
釈尊の教団(二)--僧伽の儀式 / 平川彰 / p11~18
鎌倉と京都--夢窓疎石の生いたち、その後 / 柳田聖山 / p65~76
大覚拾遺録をめぐって / 古田紹欽 / p59~64
講演 芸術と宗教--真実の自己をつかまえる / 岡本太郎 / p19~27
古寺探訪--白隠ゆかりの寺(その三) 白川禅窟 / 古賀英彦 / p30~35 |
花薬欄 わが花物語 百日紅 / 松本仁 / p36~37
花薬欄 棟梁 北島先生と私 / 須原耕雲 / p37~38
座談会 現代に生きる仏教を求めて / 西村恵信 ; 安原実 ;
→松原哲明 ; 藤原東演 ; 宮田正勝 ; 宝積玄承 / p39~58
研究所だより / p28~29
書灯 / 門脇佳吉 / p18~18 |
9月、「禅文化 (86) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082281
|
毒語心経講話(十二) / 山田無文 / p4~9
釈尊の教団(三)--袈裟について / 平川彰 / p10~17
老荘思想と現代 / 村上嘉実 / p18~25
夢窓ばなれ--今は雪竇さん / 柳田聖山 / p67~76
インド哲学者としてのソーロウ--ソーロウ哲学の原点/伊藤和男/p59~66
殊光伝書『お尋の事』にあらわれた芸道精神 / 倉沢行洋 / p42~51
古寺探訪--白隠ゆかりの寺 その四・美濃巌滝山/古賀英彦/p54~58 |
花薬欄 わが花物語 本犀 / 松本仁 / p37~38
花薬欄 生きがい / 安藤正瑛 / p38~40
花薬欄 テレビの前で / 永井路子 / p40~41
談話 湘山老師と現代の禅 / 久松真一 / p26~34
談話 池上湘山老師略伝 / p35~36
書灯 / 玉村竹二 ; 田鍋幸信 / p25~25,51~53
・ |
10月、鎌田茂雄が監修: 古田紹欽, 入矢義高「日本の禅語録 第19巻 白隠:夜船閑話・遠羅天釜・藪柑子」を「講談社」から刊行する。
(禅入門 ; 11) pid/12271789
11月、禅文化研究所編「禅文化研究所紀要 = Annual report of the Institute for Zen Studies (9)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/4414919
|
山田無文老師喜寿記念特集/p1~544,巻頭2p
〔山田〕無文老師略歴/巻頭1p
原始経典の冥想試論 / 玉城康四郎/p1~57
戒律と食物の関係 / 平川彰/p59~77
Vajra-cchedikaにおける歴史創造の論理 / 常盤義伸/p79~106
シャンカラにおける瞑想 / 中村元/p107~134
ヨーガ者における直観と開悟 / 木村俊彦/p135~150
喜風 禅思想史の一つの課題 / 柳田聖山/p151~193
『金剛経口訣』と『六祖壇経』 / 中川孝/p195~219
唐代禅家点描 / 古賀英彦/p221~245
程門諸子に於ける禅的なもの / 久須文雄/p247~272
|
明末の禅僧無念深有について / 荒木見悟/p273~296
臨済録叙説 / ドミエヴィル ; 林信明/p297~326
蘭溪道隆と樵谷惟僊との交友関係の変遷 / 玉村竹二/p327~342
大燈国師破尊宿夜話の研究 / 平野宗浄/p343~381
禅文化の一縮図から--瓢鮎図をめぐって / 古田紹欽/p383~390
伯蒲恵稜と紫衣事件 / 加藤正俊/p391~435
徳川初期における臨済禅の低迷とその打開 / 木村静雄/p437~448
人間東嶺の苦悩 / 西村恵信/p449~476
禅とキリスト教と哲学 / 西谷啓治/p477~494
無的主体性の論理 / 柴野恭堂/p495~517
宗教体験としての禅と念仏 / 藤吉慈海/p519~ |
12月、「禅文化 (87) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082282
|
毒語心経講話(十三) / 山田無文 / p4~10
釈尊の教団(四)--食物の問題 / 平川彰 / p11~18
建仁寺と首楞厳経--中世漂泊(その一) / 柳田聖山 / p54~63
臨済の全体作用とある修道女体験 / 門脇佳吉 / p19~27
佐々木指月の生涯(上)--北米開教秘話 / 堀岡弥寿子 / p64~76
一衣帯水--日中友好親善の旅 / 有馬頼底 / p43~48
古寺探訪--白隠ゆかりの寺(その五) 美濃瑞雲寺
→霊松院/古賀英彦/p49~53 |
花薬欄 わが花物語--びわ 福寿草 梅花/松本仁/p38~39
花薬欄 道縁 / 柳瀬有禅 / p39~41
花薬欄 慶州 / 岡松和夫 / p41~42
座談会 西田幾多郎の書と人 / 山内得立 ; 片岡仁志 ;
→木村静雄 ; 加藤正俊 ; 宝積玄承 / p28~37
展示室だより / p10~10
書灯 / 古賀 ; 加藤 / p18~18,63~63
・ |
12月、村木弘昌と佐藤道平が「調和道・実修の解説 : 丹田呼吸健康法」を「調和道協会」から刊行する。 所蔵:島根県立図書館
○、この年、浅見高明 が「武道学研究 9(3) p.1-5」に「膀下丹田に関する実験的研究」を刊行する。 J-STAGE
○、この年、小浜市史編纂委員会編「小浜市史紀要 第4輯 」が「小浜市教育委員会」から刊行される。
|
若狭の駆込み寺 / 網野善彦著
史料紹介 若狭国宮川庄関係史料 / 須磨千頴著
「おり米」と寛永一九年の騒動 / 藤井譲治著
若狭国名の原型考証試論 / 岸部光宏著
『渓心院文』による常高院をめぐる人々 / 渋谷美枝子著
小浜における杉田玄白、中川淳庵両家の遺跡、遺品について/田辺賀啓著
西依家について / 赤見貞著
文化財の今昔 / 岩見健太郎著
|
若狭の縄文時代に関する覚え書き(一) / 森川昌和∥著
白隠禅師と若狭 / 安田宗浩∥著
ふるさとの神体山 / 三国正二∥著
幕末における小浜藩の土木工事 / 柴田伊左衛門∥著
若狭における「浄土真宗」の宗名公称について / 東条義山∥著
小浜市史社寺文書編々纂から / 加納頴一郎∥著
小浜市の石造遺物・金工品の新例 / 杉本泰俊∥著
金屋・遠敷・古津遺跡発掘調査略報告 / 小浜市教育委員会∥ |
|
| 1978 |
53 |
・ |
2月、「書と人物 第2巻」が「毎日新聞社」から刊行される。
|
僧侶と書 3
僧侶の書風 今枝愛真 4
高僧の墨蹟―その心の世界
仏教文化の推移と僧侶の書流
小伝・墨蹟 今枝愛真,
→石田尚豊,林幹彌,
→菅原昭英,今泉淑夫 14
鑑真 14
道鏡 16
良弁 18
善珠 20
最澄 22
空海 24
円仁 26
円珍 28
安然 30
聖宝 32
良源 34
永観 36
覚鑁 38
重源 40
文覚 42
法然房 44
貞慶 46
栄西 48
慈円 50
俊? 52
明恵房 54
証空 56
道元 58
親鸞 60
兀庵普寧 62
蘭溪道隆 64
円爾 66
日蓮 68
無学祖元 70
良忠 72
大休正念 74
叡尊 76
宗性 78
他阿 86
凝然 88
|
宗峰妙超 90
清拙正澄 92
湛睿 94
虎関師錬 96
竺仙梵僊 98
夢窓疎石 100
義堂周信 102
絶海中津 104
聖冏 106
一休宗純 108
日親 110
桃源瑞仙 112
真盛 114
蓮如 116
顕如 118
木食応其 120
教如 122
以心崇伝 124
天海 126
江月宗玩 128
沢庵宗彭 130
清巌宗渭 132
隠元隆琦 134
即非如一 136
鉄眼道光 138
盤珪永琢 140
月舟宗胡 142
心越興儔 144
古月禅材 146
白隠慧鶴 148
寂厳 150
慈雲飲光 152
仙崖義梵 154
図版目録 156
図版目録
(略)
・
・
・
・
・
・ |
1 癡兀大恵 遺偈 重要文化財 願成寺
2 聖徳太子 法華義疏 宮内庁御物
3 王義之 七月帖 故宮博物院
4 親鸞 教行信証稿本 国宝 東本願寺
5 栄西 盂蘭盆一品経縁起 国宝 誓願寺
6 蘭溪道隆 金剛経 国宝 龍光院
7 張即之 金剛経 国宝 智積院
8 宗峰妙超 看読真詮榜 国宝 真珠庵
9 夢窓疎石 古徳偈 五島美術館
10 木庵性〔トウ〕 偈
1 鑑真 東大寺宛書状 正倉院宝物文書
2 道鏡 東大寺一切経司宛牒 正倉院宝物文書
3 良弁 造東大寺司宛牒 正倉院宝物文書
4 善珠 小繩宛書状 正倉院宝物文書
5 最澄 空海宛尺牘(久隔帖) 国宝 奈良国立博物館
6 空海 泰範宛尺牘(風信帖) 国宝 教王護国寺
7 円仁 上奏文案 四天王寺
8 円珍 福州温州台州求法目録 国宝 園城寺
9 安然 大徳宛書状 青?院
10 聖宝 処分状 国宝 醍醐寺
11 良源 遺告 国宝 廬山寺
12 永観 請文 東大寺
13 覚鑁 持明房真誉宛書状 龍光院
14 重源 一宮造替神殿宝物等目録奥書
→重要文化財 玉祖神社
15 文覚 大夫属入道宛書状案 重要文化財 神護寺
16 法然房 正行房宛消息 重要文化財 興善寺
17 貞慶 仏舎利安置状 重要文化財 海住山寺
18 栄西 言上状 興福寺
19 慈円 書状 重要文化財 陽明文庫
20 俊〔ジョウ〕 勧縁疏 重要文化財 泉涌寺
21 明恵房 上蓮房宛書状 重要文化財 陽明文庫
22 証空 正行房宛消息 興善寺
23 道元 普勧坐禅儀 国宝 永平寺
24 親鸞 消息 西本願寺
25 兀庵普寧 尺牘 重要文化財
26 蘭溪道隆 諷誦文 重要文化財 建長寺
27 円爾 遺偈 重要文化財 東福寺
28 日蓮 諸人御返事 重要文化財 本土寺
29 無学祖元 上堂法語 重要文化財 五島美術館
30 良忠 付法状 光明寺
31 大休正念 舎利啓白文 重要文化財 東京国立博物館 |
32 叡尊 法花寺宛書状 重要文化財 西大寺
33 宗性 願文集跋 重要文化財 東大寺
34 忍性 審海宛書状 称名寺
35 南浦紹明 法語 重要文化財 龍光院
36 一山一寧 進道語 重要文化財 根津美術館
37 他阿 寿阿弥陀仏宛書状 長楽寺
38 凝然 禅明御房宛書状 重要文化財 東大寺
39 宗峰妙超 法語 重要文化財 龍光院
40 清拙正澄 古則
41 湛睿 輪如御房宛書状 称名寺
42 虎関師錬 坐禅語・与中洞禅人法語
→重要文化財 大和文華館・個人
43 竺仙梵僊 諸山疏 国宝 龍光院
44 夢窓疎石 偈頌 天龍寺
45 義堂周信 華厳塔勧縁偈?序 重要文化財 黄梅院
46 絶海中津 道号頌
47 聖冏 讓状 常福寺
48 一休宗純 尊林道号頌 畠山記念館
49 日親 法式 本法寺
50 桃源瑞仙 利渉守?宛尺牘 慈照院
51 真盛 十念名号 成願寺
52 蓮如 専光寺宛書状 専光寺
53 顕如 浄興寺宛書状 浄興寺
54 木食応其 書状 応其寺
55 教如 善福寺宛書状 善福寺
56 以心崇伝 遺偈 金地院
57 天海 中根正盛宛書状
58 江月宗玩 狩野探幽宛書状
59 沢庵宗彭 古則 高桐院
60 清巌宗渭 一行書
61 隠元隆琦 徳川家綱宛謝恩偈 内閣文庫
62 即非如一 下火偈 崇福寺
63 鉄眼道光 山崎半右衛門宛書状 宝蔵院
64 盤珪永琢 一行書 光林寺
65 月舟宗胡 三行大字 大乗寺
66 心越興儔 曼陀羅関記 祗園寺
67 古月禅材 遺偈 福聚寺
68 白隠慧鶴 公案評語 永青文庫
69 寂厳 杜甫飲中八仙歌 三学院
70 慈雲飲光 和歌 法楽寺
71 仙崖義梵 遺偈 聖福寺
・ |
3月、「芸術新潮 29(3)[(339)] 」が「新潮社」から刊行される。 新潮社 1978-03 pid/6048590 重要
|
デッサン入門 //p5~44
特集 <オフセット> デッサン入門 線の初まり=ラスコー壁画 内なる光を示す素描=デューラー
→ 線そのものの魅惑=ダ・ヴィンチ 燃える線=地獄草紙 心の印のような点々=ゴッホ
→空間に拡がる線=等伯/セザンヌ 東と西の鉄線描=ヴァン・エイク/枕草子絵他
→東西がミックスした素描=ペルシャのミニアチュール 詩的な琴線=クレー
→壁に引かれた線=法隆寺壁画/ミーランー 壁に引かれた線=法隆寺壁画/ミーランの壁画
→ 様ざまな絵付の線 無線の線=スーラ/宗達 ヴィジョンの線=ボッティチェルンジェロ
→空気まで描いた線=レンブラント ※線のドラマ=白隠 表情を描ききった素描=
→グリュネワルド面と線の融合=ゴヤ 内的な動きを示す素描=ドガ 繊細で高貴な線=
→ワイデン 祈りの線=華岳匂いの絵=ルノアール 抽象的で具体的な線=ムア
/p5~32
特集 デッサンの東と西 <対談> / 平山郁夫 ; 前田常作/p33~44
高山辰雄とわたし〔含 「聊斎志異」原作〕 / 森敦 著抄訳/p88~93
高山辰雄の「聊斎志異」 <オフセット> 「若き日に」「笑いのこぼるるがごとく」「美少年」
→「浮き寝の宿」「そのかおりにも」「石を愛して」 //p89~93
高山辰雄の「聊斎志異」 高山辰雄とわたし / 森敦/p88~89
異形の建築「ガウディ」を剥ぐ <オフセット> 篠山紀信の「ガウディ」
→フィンカ・グエルの馬小屋/カサ・ミラ/ベル・エスグァルド邸/
→グエル公園/コロニア・グエル教会/カサ・バトロ //p97~104
異形の建築「ガウディ」を?ぐ 「ガウディ」二人三脚 <対談> / 磯崎新 ; 篠山紀信/p105~109
フットライト <原色版> 国立民族学博物館/金沢厚生年金会館 //p113~113
連載 菱田春草 近代日本画家略伝(3)<原色版>写生図 / 近藤啓太郎/p114~121
連載 野間・大御堂寺 新・観光バスの行かない……(3) / 岡部伊都子/p128~131
瓦版日本風土記(3)高松/全国版 //p139~149
随筆欄 <原色版> / 麻生三郎他/p51~52
随筆欄 水子観音私記 / 窪島誠一郎/p48~50
随筆欄 戦後美術の出発 / 野間宏/p50~50,53~54
随筆欄 私の動物体験 / P・デイビス/p54~55 |
随筆欄 書画展を終えて / 高橋新吉/p55~56
随筆欄 わが書斎のビゴー / 宇都宮泰長/p56~57
随筆欄 すまい方実験中 / 松本弘子/p57~58
随筆欄 廂髪 三十八年以後 / 曽宮一念/p58~59
随筆欄 呉清源を写す / 柿沼和夫/p59~60
案内 音楽 演劇 美術展 初めてのココシュカ展/パリ青年ビエンナーレ展回顧 //p77~79
読物 風の柱--チャンスン紀行 / 岡本太郎/p156~162
黒川紀章の「利休ねずみ考」(フットライト) / 栗田勇/p110~112
連載 日本の親しき友への手紙(3) / 池田満寿夫/p94~95
連載 中国画人伝(3)<原色版>呉歴「江南春色図」より / 陳舜臣/p134~135
連載 世界のオークションに選ぶ「空想の美術館」(36)<原色版>ヤン・ファン・ホイエン
→「河岸の町の塔」 / 山田智三郎/p132~134
連載 気まぐれ美術館(51)ゴルキという魚<原色版>
→松田正平「三匹の雑魚」/洲之内徹/p122~127
藝術新潮欄 <オフセット> 特集 絵本の「絵」を考える //p61~63
藝術新潮欄 <オフセット> スター・ダスト 印象深い中国出土文物展/
→デュビュッフェの自伝的一点/明るい色彩に転換した小山田二郎/関根正二作の面/
→李禹煥の〝たらし込み〟/鈴木治のパラドックス/原色の大樹・田淵安一/
→佐熊桂一郎の初期の一点/馬場彬のユーモア/草月会館のオープン/メリヨンと
→ブレダン/伝統と現代の邂逅・フィリップ・モーリッツ/
→貴重な写本黙示録の復刻 //p65~69
藝術新潮欄 <オフセット> オークション サザビーの現代絵画 //p70~71
藝術新潮欄 <オフセット> スター・ダスト 川崎小虎回顧展/小川哲男の粉引/
→二つのフランス・オペラ/ブームの去らない「つかこうへい」/
→久しぶりの一柳慧+小林健次のリサイタル //p72~73
藝術新潮欄 <オフセット> 新人 / 川口政宏/p74~74
藝術新潮欄 <オフセット> ワールド・スナップ //p75~76 |
3月、「禅文化 (88) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082283
|
表紙 仙厓筆 観音図
口絵 三生軒 猷禅玄達禅師遺墨
扉 大菩薩禅堂
毒語心経講話(十四) / 山田無文 / p4~11
釈尊の教団(五)--教団統制の問題 / 平川彰 / p12~65
檀林寺縁起--中世漂泊(その二) / 柳田聖山 / p66~76
禅宗寺院と渡辺了慶--東福寺普門院丈画を
→中心として/土居次義 / p20~30
仏心--関 / 安藤正瑛 / p54~59 |
佐々木指月の生涯(下)--北米開教秘話/堀岡弥寿子/p32~39
古寺探訪--白隠ゆかりの寺(その六) 泉州蔭涼寺/古賀英彦/p60~65
花薬欄 北のそらから / 藤田渓山 / p48~49
花薬欄 一日一生 / 東昇 / p49~51
花薬欄 栄西の遺跡と興禅会 / 山口康夫 / p51~53
禅と茶道 / 圓山傅衣老師 / p40~44
傅衣室老師のこと / 山本禅登 / p45~47
書灯 / 秋月龍珉他 / p19~19,31~31
・ |
6月、「禅文化 (89) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082284
|
表紙 一絲文守筆 達磨図
口絵 一絲文守遺墨
扉 永源寺派管長関雄峰 布袋図
毒語心経講話(十五) / 山田無文 / p4~12
釈尊の教団(六)--二百五十戒 / 平川彰 / p13~20
納敗詩抄--中世漂流(その三) / 柳田聖山 / p57~67
潭海玄昌の存在 / 吉田紹欽 / p30~39 |
沢庵和尚の大和名所 古跡めぐりの記/永島福太郎/p49~56
古寺探訪--白隠ゆかりの寺・その七 飛騨宗猷寺/古賀英彦/p43~48
花薬欄 掃除談義 / 岡田熙道 / p40~41
花薬欄 機械化 / 村上三島 / p41~42
回顧と感想 / 伊豆山善太郎 / p21~29
存在のスケールについて / 下村寅太郎 / p68~75
書灯 / 茶経評他 / p20~20,67~67 |
8月、福場保洲著「白隠 臨済禅叢書 5」の改訂版が「東方出版(大阪)」から再刊される。 pid/12269828
8月、柴山全慶著「十牛図 臨済禅叢書 3」の改訂版「東方出版(大阪)」から再刊される。 pid/12269841
9月、古田紹欽が「白隠 : 禅とその芸術」を「木耳社」から刊行する。 pid/12271193
9月、「禅文化 (90)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082285
|
毒語心経講和(十六) / 山田無文 / p4~14
釈尊の教団(七)--二百五十戒(続) / 平川彰 / p15~22
架空対談 正法眼蔵の周辺--中世漂泊(その四)/柳田聖山 / p66~77
清浄と汚穢--中世文化史への一視点/横井清/p58~65
古寺探訪--白隠ゆかりの寺・その八 飯田大雄寺/古賀英彦/p38~43
暮しの中の禅 / 梅原諦愚 / p50~57
花薬欄 問答 / 富士正晴 / p44~45 |
花薬欄 「セ・ラ・ヴィ」ということば / 林信明 / p45~47
花薬欄 無準師範の書 / 永田耕衣 / p47~49
この人にきく 大森曹玄老師を迎えて
→/木村静雄 ; 宝積玄承/p23~37
書灯 『大燈』(『日本の禅語録』六)平野宗浄著/西村/p22~22
書灯 『五山詩僧』--(日本の禅語録八) / 伊藤東慎/p57~57
扉 / 北浜普門 |
12月、「日本瓦斯協会誌 = Journal of the Japan Gas Association 31(12)」が「日本瓦斯協会」から刊行される。 pid/2337838
|
記念講演 時事放談 / 竹村健一/2~12」が「
西欧諸国の高齢化対策 / 佐原秋雄/13~23
世界のガス会社(10)アメリカ:エル・パソ社 / 荻野弘/24~32
日本瓦斯協会第3回安全衛生管理研究会 事例発表
→(1)TKJ法による安全活動 / 斉藤弘業/33~37
昭和53年秋の叙勲 //38~39
全国各地で“ガス展"開催 //40~56
ガス会社めぐり 水島ガスを訪ねて / 角一真由美/57~62 |
随筆/虎舞にかける祈り / 今人隆一/63~64
味じまん/いも煮とどんがら汁 / 武田辰夫/65~66
私の健康法/白隠禅師の健康法 / 小関剛/67~68
海外トピックス //69~72
昭和53年8月の概況 / 資源エネルギー庁ガス事業課/73~73
ガス統計(昭和53年8月分) //74~75
日本瓦斯協会誌第31巻主要目次 //76~80
・ |
12月、「禅文化 (91)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082286
|
毒語心経講話(十七) / 山田無文 / p4~16
釈尊の教団(八)--二百五十戒(三) / 平川彰 / p17~24
将軍脱出--中世漂泊(その五) / 柳田聖山 / p65~77
精進料理の成人病に対する効果/大島正徳/p43~48
愚菴義龍禅師遺嚮 / 加藤正俊 / p35~42
古寺探訪--白隠ゆかりの寺(その九)
|
→ 駿河松蔭寺 / 古賀英彦 / p55~60
花薬欄 チンパンジーと禅文化 / 河野太通 / p49~50
花薬欄 想い出の千崎如幻師 / 村野孝顕 / p50~52
花薬欄 竜安寺の石庭とカシオペア座 / 水野欣三郎 / p52~54
この人にきく 建仁寺派管長 竹田益州老師/木村静雄 ; 宝積玄承/p25~34
書灯 / 福島俊翁 ; 加藤正俊他 / p24~24,61~61,64~64 |
|
古賀英彦が「禅文化 (83~91)に発表した「古寺探訪--白隠ゆかりの寺(その一~九)迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻号頁 |
発行年月 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
禅文化 (83)p46~51 |
1976-12 |
白隠ゆかりの寺・その一 正受庵 |
・ |
pid/6082278 |
| 2 |
禅文化 (84) p64~69 |
1977-03 |
白隠ゆかりの寺・そのニ 正宗寺 |
・ |
pid/6082279 |
| 3 |
禅文化 (85) p30~35 |
1977-06 |
白隠ゆかりの寺(その三) 白川禅窟 |
・ |
pid/6082280 |
| 4 |
禅文化 (86) p54~58 |
1977-09 |
白隠ゆかりの寺 その四・美濃巌滝山 |
・ |
pid/6082281 |
| 5 |
禅文化 (87) p49~53 |
1977-12 |
白隠ゆかりの寺(その五) 美濃瑞雲寺・霊松院 |
・ |
pid/6082282 |
| 6 |
禅文化 (88) p60~65 |
1978-03 |
白隠ゆかりの寺(その六) 泉州蔭涼寺 |
・ |
pid/6082283 |
| 7 |
禅文化 (89) p43~48 |
1978-06 |
白隠ゆかりの寺・その七 飛騨宗猷寺 |
・ |
pid/6082284 |
| 8 |
禅文化 (90) p38~43 |
1978-09 |
白隠ゆかりの寺・その八 飯田大雄寺 |
・ |
pid/6082285 |
| 9 |
禅文化 (91) p55~60 |
1978-12 |
白隠ゆかりの寺(その九) 駿河松蔭寺 |
・ |
pid/6082286 |
|
|
| 1979 |
54 |
・ |
3月、荒井荒雄が「夜船閑話 : 白隠禅による健康法」を「大蔵出版」から刊行する。 (大蔵新書 ; 11)
3月、「禅文化 (92) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082287
|
毒語心経講和(十八) / 山田無文/p4~13
睡虎の塔--中世漂泊(その六) / 柳田聖山/p22~33
東嶺の風土 / 西村恵信/p34~42
釈尊の教団(九)--二百五十戒(四) / 平川彰/p14~21
善財童子の求道ものがたり(一)--菩薩道五十三次 / 小林圓照/p43~48
インド 仏蹟巡拝記念特集 禅とは心の名なり / 山田無文/p49~49
インド 仏蹟巡拝記念特集 ネパール・インド仏跡の旅 / 木村静雄/p67~77 |
インド 仏蹟巡拝記念特集 インド点描--
→仏蹟巡拝の旅から / 宝積玄承/p50~61
花薬欄 仙人七葉窟 / 有馬頼底/p62~63
花薬欄 仏蹟をたずねて / 江里康則/p63~65
花薬欄 仏陀礼拝の道 / 鈴木喜郎/p65~66
書灯 / 西村恵信他/p21~21,48~48
・ |
4月、白隠禅師原著, 原田祖岳 校注「延命十句観音経霊験記 」が「大蔵出版」から再刊される。 2版 pid/12270264
6月、柳田聖山, 加藤正俊が「白隠」を「淡交社」から刊行する。 (文人書譜, 9)
6月、「禅文化 (93)」が「禅文化研究所」から」刊行される。 pid/6082288
|
毒話心経講話(十九) / 山田無文/p4~12
釈尊の教団(十)--二百五十戒(五) / 平川彰/p13~20
狂雲子の「狂」--一休の粧い / 古田紹欽/p42~46
善財童子の求道ものがたり(ニ)--菩薩道五十三次 / 小林圓照/p30~37
岡倉天心と禅 『茶の本』をめぐる一考察 / 堀岡弥寿子/p61~72
※光は東から--ソーロウに於ける東洋思想の体験 / 伊藤和男/p53~60
花薬欄 柴山老師とエスペラント / 中村文峰/p47~48 |
花薬欄 足を洗われた天香さん / 石川洋/p48~50
花薬欄 間宮老師と柿二つ / 岡本良蔵/p50~52
鈴木大拙博士の書翰/p38~40
仏通寺派管長 藤井虎山老師 / 宝積玄承/p21~29
信心銘閑話(一) / 大森曹玄/p73~76
書灯 / 藤吉慈海/p72~72
・ |
6月、家永三郎教授東京教育大学退官記念論集刊行委員会編「古代・中世の社会と思想」が「三省堂」から刊行される。 pid/12240783
|
舂米部と丸子部 : 聖徳太子子女名義雑考 / 黛弘道著
朝集使二題 : その起源と形式化について / 直木孝次郎著
古代沖の島の祭祀 / 井上光貞著
アマテラスの原像 / 鶴岡静夫著
法興寺の創建 / 田村圓澄著
院政期における女房の絵画製作: 佐の局と紀伊の局/秋山光和著
|
中世宗教史における神道の位置 / 黒田俊雄著
親鸞の宗教的主体の成立 / 二葉憲香著
親鸞研究の根本問題 : 九つの問い / 古田武彦著
親鸞における否定の論理 : 悪人正因と悪人正機 / 熊田健二著
鎌倉仏教における国王のイメージ : 日蓮を中心に / 高木豊著
一歴史学者のあゆみ : 家永教授に聞く / 家永三郎 [述] |
8月、松居桃楼が「禅の源流をたずねて : 天台小止観講話」を「柏樹社」から刊行する。
8月、小松茂美編「日本書蹟大鑑 第22巻」が「講談社」から刊行される。
|
1 白隠慧鶴
2 賀茂真淵
3 寂厳
4 冷泉為村
5 建部綾足
6 日解
7 宮崎□圃
8 万仞道坦
9 加賀千代女
10 谷川士清
11 池大雅
12 歌川
13 平賀源内
14 大谷永庵
15 湯浅常山
16 滋野井公麗
17 松下烏石
18 三井親和
19 横井也有
20 与謝蕪村
21 富士谷成章
22 加藤枝直
23 高芙蓉
24 池玉瀾
25 近衛内前
26 荷田蒼生子
27 九条尚実
28 大島蓼太
29 趙陶斎
30 三浦梅園
31 渋井太室
32 東坊城益良
33 龍公美
34 高山彦九郎
35 林子平 |
36 円山応挙
37 山本以南
38 沢田東江
39 宇田川玄随
40 澄月
41 森尹祥
42 梅荘顕常
43 小沢蘆庵
44 関其寧
45 菱田縫子
46 韓天寿
47 本居宣長
48 細井平洲
49 日野資枝
50 花扇
51 大塚蒼梧
52 木村蒹葭堂
図版目次
1 白隠慧鶴 大燈国師
→示衆法語
2 白隠慧鶴 法語
3 白隠慧鶴 二大字
4 白隠慧鶴 観音自画賛
5 白隠慧鶴 一行書
6 賀茂真淵 富士の詞
7 賀茂真淵 詠草
8 賀茂真淵 詠草
9 賀茂真淵 万葉新採
→百首解稿本
10 賀茂真淵 書状
11 寂厳 飲中八仙歌
12 寂厳 一行書
13 寂厳 一行書
14 寂厳 二大字
15 寂厳 屏風 |
16 冷泉為村 書状
17 冷泉為村 和歌懐紙
18 冷泉為村 詠草
19 冷泉為村 詠草
20 冷泉為村 般若心経
21 建部綾足 片歌
22 日解 書状
23 宮崎□圃 七言律詩
24 宮崎□圃 七言絶句
25 万仞道坦 一行書
26 万仞道坦 七言二句
27 加賀千代女 消息
28 加賀千代女 消息
29 加賀千代女 俳句
30 加賀千代女 自画賛
31 加賀千代女 色紙
32 加賀千代女 俳句
33 谷川士清 書状
34 池大雅 書状
35 池大雅 一行書
36 池大雅 一行書
37 池大雅 和歌
38 池大雅 五言一句
39 池大雅 七言律詩
40 歌川 色紙
41 平賀源内 書状
42 平賀源内 書状
43 大谷永庵 書状
44 大谷永庵 書状
45 湯浅常山 詩
46 滋野井公麗 詠草
47 松下烏石 一行書
48 三井親和 五言二句
49 三井親和 七言二句
50 横井也有 賛 |
51 横井也有 自画賛
52 与謝蕪村 書状
53 与謝蕪村 書状
54 与謝蕪村 書状
55 与謝蕪村 書画戯之記
56 与謝蕪村 自画賛
57 与謝蕪村 自画賛
58 与謝蕪村 短冊
59 富士谷成章 短冊
60 加藤枝直 書状
61 加藤枝直 詠草
62 高芙蓉 臨蘭亭序
63 池玉瀾 詠草
64 近衛内前 書状
65 荷田蒼生子 消息
66 九条尚実 和歌懐紙
67 大島蓼太 書状
68 大島蓼太 書状
69 趙陶斎 五言絶句
70 趙陶斎 一行書
71 三浦梅園 五言律詩
72 三浦梅園 七言絶句
73 三浦梅園 七言絶句
74 渋井太室 尺牘
75 東坊城益良 和歌懐紙
76 龍公美 一行書
77 龍公美 一行書
78 高山彦九郎 書状
79 高山彦九郎 詠草
80 高山彦九郎 一行書
81 高山彦九郎 一行書
82 林子平 書状
83 林子平 詩書
84 円山応挙 書状
85 円山応挙 五言絶句
|
86 山本以南 詠草
87 沢田東江 一行書
88 宇田川玄随 書状
89 澄月 書状
90 澄月 和歌懐紙
91 森尹祥 鑑識語
92 梅荘顕常 書状
93 小沢蘆庵 書状
94 小沢蘆庵 和歌懐紙
95 小沢蘆庵 和歌懐紙
96 小沢蘆庵 詠草
97 関其寧 一行書
98 菱田縫子 詠草
99 韓天寿 五言律詩
100 本居宣長 書状
101 本居宣長 書状
102 本居宣長 書状
103 本居宣長 詠草
104 本居宣長 詠草
105 本居宣長 詠草
106 本居宣長 詠草
107 細井平洲 七言絶句
108 細井平洲 七言絶句
109 日野資枝 書状
110 日野資枝 詠草
111 花扇 和歌
112 花扇 一行書
113 大塚蒼梧 故実抜書
114 木村蒹葭堂 書状
115 木村蒹葭堂 書状
・
・
・
・ |
9月、「禅文化 (94) 特集・東福寺と聖一国師」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082289
|
特集・東福寺と聖一国師
聖一国師とその家風 / 荻須純道 / p20~26
聖一国師の『十宗要道記』をめぐって/古田紹欽/p73~78
聖一国師の法諱は辯円か円爾か/玉村竹二/p40~50
東福寺と京狩野 / 土居次義 / p64~72
東福寺の頂相 / 金沢弘 / p27~39
東福寺の伽藍と塔頭の変遷 / 川上貢 / p80~89 |
聖一和尚の遺偈のこと--中世漂泊(その七)/柳田聖山/p51~63
聖一国師と三教思想序説 / 福嶋俊翁 / p79~79
毒語心経講話(二〇) / 山田無文 / p4~14
信心銘閑話(ニ) / 大森曹玄 / p15~19
書灯 『白隠』柳田聖山・加藤正俊共著 / p39~39
書灯 『禅の高僧』大森曹玄著 / p78~78
・ |
12月、「禅文化 (95)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082290
|
特集=東西霊性の交流
心の清きもの / 山田無文/p5~5
東西霊性の交流の実施まで / 大森曹玄/p6~7
メッセデ修道院の生活 / 藤吉慈海/p31~37
修道院管見--禅堂と修道院 / 河野太通/p23~30
東西霊性の交流とは何であったか--
→マリアラーハ大修道院に生活して / 西村恵信/p38~45
ケルン「墨蹟展」を中心にして / 寺山葛常/p8~14
巻藁射礼 / 須原一夫/p15~18
茶道による霊性の交流 / 千坂秀学/p19~22
特廻廊の翳のなかで / 岡田徹/p46~50 |
我がメッシュデの日々 / 古賀英彦/p51~53
修道院の対青少年活動 / 桐田清秀/p54~55
聖オッテイリエン修道院の記 / 鈴木格禅/p55~57
霊性の交流に参加して / 岡部恒/p57~59
沈黙と讃美--トラピスト
→修道院体験記 / 宝積玄承/p60~71
毒語心経講話(二一) / 山田無文/p83~93
善財童子求道ものがたり(三)--菩薩道五十三次 / 小林圓照/p72~80
朝比奈宗源を憶う / 木村/p82~82
書灯 / 加藤正俊 ; 玉村竹二/p80~81
・ |
12月、圭室文雄, 大桑斉編「近世仏教の諸問題」が「雄山閣出版」から刊行される。 pid/12220906
|
政治と仏教 幕藩制国家の仏教統制-新寺禁止令をめぐって 大桑斉著
近世寺檀制度の成立についてー幕府法令を中心に 西脇修著
近世日蓮教団の本末関係-肥後六条門流を中心にして 池上尊義著
近世曹洞宗の本末制度について 山本世紀著
近世曹洞宗僧録寺院の成立過程-遠江可睡斎の場合 広瀬良弘著
近世大坂の真宗寺院-都市寺院の形態と町人身分 上場顕雄著
近 世における大徳寺教団-延享の末寺帳を中心として 竹貫元勝著
近世の時宗についてー中世との対比を中心に 梅谷繁樹著
民衆と仏教 近世浄土宗における理想的僧侶像 長谷川匡俊著 |
二十四輩考-覚如・蓮如の東国布教と二十四輩巡りについて 中根和浩著
日向県藩における帯解き仏法の摘発と寺請-幕藩制成立期の
→民衆統制 星野元貞著
江戸の不動信仰-目黒不動の場合 坂本勝成著
遊行第四十九代上人-法の廻国について 圭室文雄著
思想と仏教 平戸藩「浮橋主水一件」と江月宗玩 村井早苗著
白隠禅の思想史的意義 船岡誠著
東本願寺と茶の湯 谷端昭夫著
・ |
|
| 1980 |
55 |
・ |
3月、下呂町史編集委員会編「飛騨下呂 : 図録」が刊行される。 pid/9538177 1000円
|
景観/7
飛騨木曽川国定公園/8
空からみた下呂/16
原始時代と下呂石/23
先土器文化/24
繩文文化/26
弥生式土器と須恵器/44
古代・中世のおもかげ/49
神々と仏/50
山の中の廃寺/60
山城の跡/64
働く近世の人びと/67
山に働く/68
村々の山/98 |
検地帳/120
峠と道/122
北方に雄飛した豪商/127
飛騨屋久兵衛/128
下呂に足跡を残した僧たち/133
円空/134
白隠/160
東嶺/162
明治・大正・昭和 あの日あの時/165
庁舎の新旧/166
町並みの今昔/172
橋と鉄道/192
電気と郵便/204
学校/212 |
戦時/238
催し事/248
生業/254
民具/266
失われゆく風習/282
防災と災害/294
観光施設/302
神社と寺院/307
石仏とお堂/323
花笠まつり/399
地芝居/411
温泉/427
解説/441
・ |
3月、「禅文化 (96) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 1980-03pid/6082291/1/1
|
毒語心経講話(二二) / 山田無文/p4~12
信心銘閑話(三) / 大森曹玄/p13~15
釈尊の呼吸法 / 村木弘昌/p42~50
願王全提と石仏師 / 小松光衛/p68~77
五輪書と姿三四郎 / 柴田増実/p29~36
日本における芸術と生活/ピエール・ド・ベテュヌ;野尻命子/p58~67
花薬欄 奇想の典型 / 永田耕衣/p37~38
|
花薬欄 奏でられた生命の響き合い / 安斎伸/p39~41
花薬欄 短歌・春立ちぬ / 松本仁/p36~36
善財童子の求道ものがたり(四)苦薩道五十三次 / 小林圓照/p51~56
虚堂下獄の真相(その八)中世漂泊 / 柳田聖山/p16~28
林晦宗老師をおもう/p57~57
久松真一先生ご逝去 / 木村/p56~56
・ |
6月、「禅文化 (97)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082292
|
特集・抱石庵久松真一の世界
久松先生と私 / 藤吉慈海/p20~29
驀直去 / 北原隆太郎/p30~39
答処に問処あり--久松先生のこと / 倉沢行洋/p40~43
ポストモダニスト / 北山正[迪]/p44~48
火〔エン〕裏に身を横たう--中世漂泊 その終章 / 柳田聖山/p49~70
この人にきく--久松真一先生 / 宝積玄承/p76~92 |
毒語心経講話(二十三) / 山田無文/p5~18
信心銘閑話(四) / 大森曹玄/p71~75
善財童子の求道ものがたり(五)--
→菩薩道五十三次 / 小林圓照/p93~103
釈尊の呼吸法(二) / 村木弘昌/p104~113
書灯 / 久須本文雄/p19~19
・ |
9月、「禅文化 (98)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082294
|
毒語心経講和(二十四) / 山田無文/p5~10pid/6082294
特集・中国禅宗祖石をたずねて
嵩山少林寺 / 村瀬玄妙/p13~17
臨済禅師澄霊塔に詣でて / 勝平宗徹/p18~24
少林寺初祖庵 / 編集部/p25~29
趙州観音院 / 編集部/p30~35
江南の祖塔を巡拝して / 小堀南嶺/p36~47
杭州・禅の祖蹟 / 小森慶晃/p48~53
|
訪中印象(絵と文) / 桜井一溪/p54~59
古黄檗を訪ねて / 當山禅昭/p60~64
泉涌寺月翁智鏡の出自 / 玉村竹二/p66~67
毒語心経講和(二十四) / 山田無文/p5~10
新人銘閑話(五) / 大森曹玄/p68~75
善財童子の求道ものがたり(六)--菩薩道五十三次 / 小林圓照/p76~86
釈尊の呼吸法(三) / 村木弘昌/p87~96
書灯 / 柳田聖山/p65~65 |
12月、「禅文化 (99) 1980-12 pid/6082295
|
口絵 南中国禅宗史蹟の旅 / 前田広心/p5~16
特集・南中国禅宗史蹟の旅 禅源を訪ねる南中国の旅/置塩龍吟/p36~43
特集・南中国禅宗史蹟の旅 六榕寺にて--
→ある中国女性への鎮魂 / 乃村正之/p44~47
特集・南中国禅宗史蹟の旅 曹渓山南華寺 / 松尾静明/p48~49
特集・南中国禅宗史蹟の旅 丹霞山--丹霞焼仏の故地/木下政雄/p50~52
特集・南中国禅宗史蹟の旅 中国で会った仏者たち/星雅江/p53~57
特集・南中国禅宗史蹟の旅 華南を行く 禅源随想/長谷川星漢/p58~65
特集・南中国禅宗史蹟の旅 南中国行脚記録-- |
→これから中国祖蹟を尋ねる人のために / 大沢秀寿/p66~73
東西霊性の交流--諸宗教間の対話の経験と思想 /
→J・V・ブラフト ; 岡田徹/p74~88
毒語心経講和(最終回) / 山田無文/p17~22
捨てきる--藤井虎山老師に聞く/p23~34
信心銘閑話(六) / 大森曹玄/p89~94
釈尊の呼吸法(四) / 村木弘昌/p95~104
読者欄「一〔チュウ〕」/p105~107
・ |
|
山田無文が「禅文化(71)~(99)」に発表した「毒語心経講話(一~二十五)」迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
発行年月 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
禅文化 (71) p4~12 |
1973-12 |
毒語心経講話(一) |
. |
pid/6082266 |
| 2 |
禅文化 (72) p4~11 |
1974-03 |
毒語心経講話(二) |
. |
pid/6082267 |
| 3 |
禅文化 (74) p4~11 |
1974-09 |
毒語心経講話(三) |
. |
pid/6082269 |
| 4 |
禅文化 (76) p4~11 |
1975-03 |
毒語心経講和(四) |
. |
pid/6082271 |
| 5 |
禅文化 (78) p4~11 |
1975-09 |
毒語心経講話(五) |
. |
pid/6082273 |
| 6 |
禅文化 (79) p4~9 |
1975-12 |
毒語心経講話(六) |
. |
pid/6082274 |
| 7 |
禅文化 (80) p4~9 |
1976-03 |
毒語心経講話(7) |
. |
pid/6082275 |
| 8 |
禅文化 (81) p72~76 |
1976-06 |
毒語心経講話(八) |
. |
pid/6082276 |
| 9 |
禅文化 (82) p4~10 |
1976-09 |
毒語心経講話(九) |
. |
pid/6082277 |
| 10 |
禅文化 (84) p4~11 |
1977-03 |
毒語心経講話(十) |
. |
pid/6082279 |
| 11 |
禅文化 (85) p4~10 |
1977-06 |
毒語心経講話(十一) |
. |
pid/6082280 |
| 12 |
禅文化 (86) p4~9 |
1977-09 |
毒語心経講話(十二) |
. |
pid/6082281 |
| 13 |
禅文化 (87) p4~11 |
1977-12 |
毒語心経講話(十三) |
. |
pid/6082282 |
| 14 |
禅文化 (88) p4~11 |
1978-03 |
毒語心経講話(十四) |
. |
pid/6082283 |
| 15 |
禅文化 (89) p4~12 |
1978-06 |
毒語心経講話(十五) |
. |
pid/6082284 |
| 16 |
禅文化 (90) p4~14 |
1978-09 |
毒語心経講和(十六) |
. |
pid/6082285 |
| 17 |
禅文化 (91) p4~16 |
1978-12 |
毒語心経講話(十七) |
. |
pid/6082286 |
| 18 |
禅文化 (92) p4~13 |
1979-03 |
毒語心経講和(十八) |
. |
pid/6082287 |
| 19 |
禅文化 (93) p4~12 |
1979-06 |
毒話心経講話(十九) |
. |
pid/6082288 |
| 20 |
禅文化 (94) p4~14 |
1979-09 |
毒語心経講話(二〇) |
. |
pid/6082289 |
| 21 |
禅文化 (95) p83~93 |
1979-12 |
毒語心経講話(二一) |
. |
pid/6082290 |
| 22 |
禅文化 (96) p4~12 |
1980-03 |
毒語心経講話(二二) |
. |
pid/6082291 |
| 23 |
禅文化 (97) p5~18 |
1980-06 |
毒語心経講話(二十三) |
. |
pid/6082292 |
| 24 |
禅文化 (98) p5~10 |
1980-09 |
毒語心経講和(二十四) |
. |
pid/6082294 |
| 25 |
禅文化(99) p17~22 |
1980-12 |
毒語心経講和(最終回) |
. |
pid/6082295 |
|
○、この年、大西良慶が「坐禅和讃講話」を「大法輪閣」から刊行する。 pid/12215730 |
| 1981 |
56 |
・ |
3月、山田無文が「毒語心経講話 : 白隠禅師」を「禅文化研究所」から刊行する。pid/12225698
3月21日~4月19日、BSN新潟美術館に於いて「白隠 : 作品とその心」展が開かれる。
3月、BSN新潟美術館編「白隠 : 作品とその心」が「BSN新潟美術館」から刊行される。 所蔵:新潟県立図書館
序に「第二回白隠名品展に寄せて」とあり 注 第一回があったか再調査が必要 2023・1・22 保坂
3月、「禅文化 (100) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082296
|
●一〇〇号記念特集 禅のこころ / 大森曹玄/p5~10
●一〇〇号記念特集 禅の生活 / 平田精耕/p11~20
●一〇〇号記念特集 看脚下 / 松原泰道/p21~27
●一〇〇号記念特集 自然ということ / 紀野一義/p28~35
●一〇〇号記念特集 在家禅のすすめ / 秋月龍珉/p36~43
●一〇〇号記念特集 日本臨済禅の流れ / 荻須純道/p44~54
●一〇〇号記念特集 佗茶の根源としての一休の茶 / 吉村貞司/p55~64
●一〇〇号記念特集 教壊ということ / 柳田聖山/p112~125
●一〇〇号記念特集 講演 禅芸術雑感 / 古田紹欽/p66~75
●一〇〇号記念特集 講演 臨済録雑感 / 入矢義高/p126~137
随筆 禅批判三種 / 伊豆山格堂/p76~77
随筆 機縁の書 / 中田勇次郎/p78~82
随筆 夢失わず / 直原玉青/p83~85 |
随筆 茶禅一味の眼目 / 千宗室/p86~87
随筆 武野紹鴎の茶と禅 / 堀内宗完/p88~89
随筆 禅による教育 / 中西政次/p90~91
随筆 足の人 / 坂村真民/p92~93
随筆 立派に死ねる覚悟 / 奈良本辰也/p94~95
随筆 老斑童子 / 永田耕衣/p100~105
随筆 文学者と宗教 / 岡本和夫/p106~111
一〇〇号のあゆみ / 木村静雄/p96~97
一〇〇号を記念して無文老師にきく/p98~99
梶浦逸外老師を送る / 栽松完道/p138~142
書灯 / 久保田諄/p65~65
読者欄「一〔チュウ〕」/p139~142
・ |
4月、高神信也が「智山学報 (通号 30) p.p103~117」に「江戸仏教の特質-2-白隠の人と思想」を発表する。 J-STAGE
5月、「宝生 30(5)(609)」が「わんや書店」から刊行される。pid/7927811
|
口絵 弓八幡 / 三川泉
口絵 草紙洗 / 今井泰男
口絵 百万 / 田中幾之助
口絵 志賀 / 渡辺他賀男
口絵 巻絹 / 宝生英照
口絵 桜川 / 小林与志郎
口絵 舎利 / 金森秀祥
口絵 翁 / 島村巌 ; 藪俊彦
口絵 羽衣 / 宝生英雄
口絵 小鍛冶 / 供田清作
口絵 箙 / 高橋右任
口絵 雲林院 / 佐野萌
|
口絵 忠度 / 辰巳孝
口絵 吉野静 / 小川芳
口絵 葵上 / 衣斐正宜
口絵 鶴亀 / 宝生英雄
口絵 熊野 / 辰巳孝
謡い方講座(72) 生田敦盛(二) / 宝生英雄/p4~5
白隠の「謡之十徳」 / 田辺啓三/p6~7
“足の向くまま” 湯島・上野・浅草の
→能画額を見て歩く(上) / 藤城繼夫/p8~11
講座 「宝生流地拍子」補遺15 / 佐藤芳彦/p16~17
講座 地拍子八ツ割付 生田敦盛(2)/p18~19
<寄稿> 実盛の兜(三) / 岩下庄之助/p26~28
|
九段下より(118) 佐渡にて / 佐藤芳彦/p30~32
国立能楽堂(仮称)建設について/p13~15
各地だより 小布施賀宝会二周年記念/p34~34
各地だより 長岡宝生会春季謡曲大会/p34~34
各地だより 田島と桑折の謡会/p35~35
各地だより 相模原市謡曲会(宝生)
→橋本公民館文化祭参加謡会/p35~36
各地だより 第一回素謡会(謡曲教室)/p36~36
各地だより 北陸銀行謡曲サークル/p36~36
宝生ニュース/p20~23
番組の記録/p37~39
・ |
7月、亀山卓郎が「禅文化 (101) p170~185 禅文化研究所」に「特集 一絲文守禅師 白隠の画における<樹の葉>の意義について--正しい鑑賞のために」を発表する。 pid/6082297
7月、白隠著述,東嶺注解,大森曹玄[訳]著「毒語注心経」が「春秋社」から刊行される。 pid/12225699
10月、大井満が「白隠ものがたり : 夜船閑話に寄せて」を「春秋社」から刊行する。
11月、名著出版編「歴史手帖 9(11)(97)」が「名著出版」から刊行される。 pid/2246757 重要
|
白隠とその時代―近世の民衆文化と民俗 / 高橋敏/p4~8
静岡県の地の神信仰 / 富山昭/p9~13
名主日記にみる村の民俗 / 川崎文昭/p14~21
玉除け・徴兵逃れとしての龍爪信仰/中村羊一郎/p22~28
駿河の民俗芸能―観音信仰と田楽(田遊び)/八木洋行/p29~33
遠州七不思議 / 石野成子/p34~36
浜名湖周辺の共同風呂 / 小杉達/p37~42 |
静岡県民俗学刊行書目録 / 杉村斉編/p43~50
長楽・穴闇考(11)地名研究の焦点 / 池田末則/p51~51
戦国・近世初頭の山城発掘――鹿野城址発掘調査から(9)
→歴史考古学レポート/p52~53
郷土誌寸評/p54~54
地方史出版ニュース/p55~55
地方史雑誌・文献目録 / 飯澤文夫/p56~65 |
12月、 森優が大道学館編「臨牀と研究 = The Japanese journal of clinical and experimental medicine 58(12)(683) 赤ページp1~2 大道学館出版部」に「白隠著「夜船閑話」(12) 」を発表する。
|
森優が「臨牀と研究 58(1~12)(672~683)」に発表した「白隠著「夜船閑話」(1~12) 」の内訳一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
発行年月 |
論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
臨牀と研究 58(1)(672)p1~2 |
1981-01 |
白隠著「夜船閑話」(1) |
. |
pid/3426789 |
| 2 |
臨牀と研究58(2)(673)p1~2 |
1981-02 |
白隠著「夜船閑話」(2) |
. |
pid/3426790 |
| 3 |
臨牀と研究58(3)(674)p1~2 |
1981-03 |
白隠著「夜船閑話」(3) |
. |
pid/3426791 |
| 4 |
臨牀と研究58(4)(675)p1~2 |
1981-04 |
白隠著「夜船閑話」(4) |
. |
pid/3426792 |
| 5 |
臨牀と研究58(5)(676)p1~2 |
1981-05 |
白隠著「夜船閑話」(5) |
. |
pid/3426793 |
| 6 |
臨牀と研究58(6)(677)p1~2 |
1981-06 |
白隠著「夜船閑話」(6) |
. |
pid/3426794 |
| 7 |
臨牀と研究58(7)(678)p1~2 |
1981-07 |
白隠著「夜船閑話」(7) |
. |
pid/3426795 |
| 8 |
臨牀と研究58(8)(679)p1~2 |
1981-08 |
白隠著「夜船閑話」(8) |
. |
pid/3426796 |
| 9 |
臨牀と研究58(9)(680)p1~2 |
1981-09 |
白隠著「夜船閑話」(9) |
. |
pid/3426797 |
| 10 |
臨牀と研究58(10)(681)p1~2 |
1981-10 |
白隠著「夜船閑話」(10) |
. |
pid/3426798 |
| 11 |
臨牀と研究58(11)(682)p1~2 |
1981-11 |
白隠著「夜船閑話」(11) |
. |
pid/3426799 |
| 12 |
臨牀と研究58(12)(682)p1~2 |
1981-12 |
白隠著「夜船閑話」(12) |
. |
pid/3426800 |
|
○、この年、高神信也が「智山学報 30(0) p.103-117」に「江戸仏教の特質(二) : 白隠の人と思想」を発表する。J-STAGE
○、この年、鎌田茂雄が「日本の禅語録 19 白隠慧鶴」を「講談社」から刊行する。
|
| 1982 |
57 |
・ |
1月28日~2月2日迄、名古屋・松坂屋本店リビンザ1階催事場に於いて「禅の世界と白隠
: 特別展 : 現代に生きるその心」展が開かれる。
1月、白隠 [作] ; 禅文化研究所編 「 禅の世界と白隠 : 特別展 : 現代に生きるその心(図録)」が「松坂屋本店・便利堂」から刊行される。
主催: 臨済宗妙心寺派愛知西教区青年僧の会, 禅文化研究所, 中日新聞本社
1月、「禅文化 (103)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082299
|
口絵 「禅の世界と白隠展」から / p3~3
随処に主と作る / 山田無文 / p19~27
新春対談 現代と禅--ロボット文化と手のひら文化/平田精耕;草柳大蔵/p28~41
愚芸愚談 「あほかいなの哲学」 / 藤山寛美 / p42~59
こうりんさま / 加藤隆芳 / p60~62
ヨーロッパにおける禅(一) / 野尻命子 / p63~68
華南禅蹟をめぐる / 澤井進堂 / p69~76
白隠門下の女性禅者の消息 / 町田瑞峰 / p77~89
白隠の滝見観音図と達磨図画賛四題について / 亀山卓郎 / p90~104 |
信心銘閑話(九) / 大森曹玄 / p105~107
般若心経を語る / 藤吉慈海 / p108~132
禅仏教をゆく(その一) / 柳田聖山 / p133~148
読者欄「一〔しゅ〕」 / p149~152
海外禅センター通信 / p153~153
龍安寺での坐禅会を終わって / p154~161
全国の禅会あんない / p162~169
書灯 / p170~171
・ |
4月、「禅文化 (104) p139~142 禅文化研究所」に「特別展「禅の世界と白隠」を終わって」が掲載される。 pid/6082300
4月、「在家佛教 (337)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064019
|
春風 / 増谷文雄 / p5~5
白隠の養生法--『夜船閑話』について / 鎌田茂雄 / p6~13
自由無礙の世界 / 鈴木宗忠 / p20~28
和雅の声 行と行間について / 今井美沙子 / p14~15
和雅の声 紫山老師に従って / 高橋新吉 / p16~17
和雅の声 「行」とは / 知切光歳 / p18~19
ちょっと坐ってみませんか / 寺沢行信 / p30~33
静坐の行 / 柳田誠二郎 / p34~37
修行ということ / 立花大亀 / p38~41
如是我聞 / 松原泰道 / p48~51
快復期 / 友田俊治 / p74~77 |
人この道を歩む 身で学ぶ / 尾上梅幸 / p58~67
佛の里国東〔みほとけと私〕 / 寺田豪延 / p42~46
現代語訳(4)鈴木正三著・萬民徳用 / 江原通子 / p52~56
教行信証のおことば(119)一乗海 / 加藤辨三郎 / p68~72
阿含経典・第二部長量の経典群(20)大いなる死(その二十)/増谷文雄/p82~88
在家佛教三十周年 轍の跡(4) / 本誌編集部 / p78~81
今月の表紙 / p57~57
京都の寺々を巡る会御案内 / p92~93
編集後記*次号予告 / p91~91
協会案内〔講演会・講座・佛蹟めぐりの会・協会の仕事〕 / p94~95
・ |
4月、三彩社編「古美術 (62) <特集> 白隠」が「三彩社」から刊行される。 pid/6063357
|
図版 カラー 婚礼調度/p5~
図版 図版 中国陶磁/p29~
図版 図版 根付/p58~59
図版 図版 白隠/p65~
図版 図版 古九谷/p85~
図版 図版 久保惣コレクション/p106~
図版 図版 山水図/p126~
図版 白黒図版 白隠/p69~
図版 白黒図版 日本の石の空間(4)石の文様、石の花/p117~
晴れの飾り婚礼調度<特集> / 荒川浩和/p4~25 |
近年発見の窯址出土中国陶磁 / 弓場紀知/p27~40
元画鑑賞-1-曹知白 / 近藤秀実/p42~55
白隠<特集> / 吉村貞司/p61~83
古九谷試論-3- / 浅井啓三/p84~98
自然への回帰--ボ-ド・ガヤ-の古代文明 / 岩崎巴人/p99~104
日本の石の空間-4-石の文様,石の花 / 海野弘 ; 村井修/p109~124
一山自画賛山水図について / 中村渓男/p125~129
妙心寺海福院の曽我蕭白 / 土居次義/p130~135
カザ-ル・コレクションの根付について / 村越英明/p57~60
久保惣コレクション--東洋古美術展 / 中野徹/p105~108 |
6月、結城令聞 [ほか]編「日本佛教の宗派 2」が「大藏出版」から刊行される。 (講座佛教 ; 第7巻) 改訂4版
|
融通念仏宗 杉崎 大愚 9ー28
1 開宗と良忍 9
最初の念仏宗
良忍の生いたち
仏勅の霊感
念仏の勧め
念仏弘通の遍歴
2 教団の発展 14
法灯の中絶
中興の法明上人
再興の大通上人
3 理論と実践 18
主張の典拠
宗名
融通とは
融通の実践
融通の四種観
根本教義
根本義の解釈
教判
念仏行
理論と実践の相即
4 本宗の他力思想 27
自力と他力
絶対の念仏
浄土宗 石井教道,大橋俊雄 29ー62
1 浄土宗とは 29
2 主張の典拠と浄土祖師 31
所依経典の必要
主張の典拠
浄土五祖
法然
3 浄土教的仏教批判 36
聖道門・浄土門
万人救済の教
4 阿弥陀仏とその浄土 38
阿弥陀仏
阿弥陀仏への帰依
浄土
5 浄土行人とは 42
5 1 浄土行人の心構え
→(安心ー三心ー二河白道)
5 2 浄土行人としての歩み
→(難行と易行ー正行と助行)
5 3 浄土行人の態度
→(念仏の生活ー四修の態度)
6 浄土宗の流れ 52
法然の門弟
鎮西聖光
良忠とその門流
聖冏と教線の拡張
徳川幕府と浄土宗
捨世派
律僧
檀林
明治以後の宗勢
7 浄土宗独特の法式 60
7 1 御忌
7 2 お十夜
浄土宗西山派 三浦 一道 63ー78
1 派祖とその門流 63
浄土宗西山派
証空の著書
証空の門流
2 教義の組織 66
所依の経典
浄土教の拠点
証道の相承
3 浄土と阿弥陀仏 68
聖道門の浄土観
浄土門の浄土
仏
諸仏と阿弥陀仏
別願酬因の阿弥陀仏
4 往生と念仏 74 |
往生
念仏と観仏
本願の念仏
桟法一体の念仏
真宗 桐渓 順忍 79ー130
1 真宗の成立 79
浄土真宗の呼称
真宗の開創
教団の現状
親鸞の略伝
本願寺の成立
東西本願寺の分裂
本願寺派
大谷派
諸分派
高田派
仏光寺派
興正派
木部派
越前四カ本山
三門徒派
誠照寺派
山元派
出雲路派
所依の聖教
三経の隠顕
七祖相承
七祖聖教
親鸞の撰述その他
2 真宗の立場 93
救済思想の展開
慧の性格
浄土教の発生
救済教の性格
真宗の地位
相承の教判
難易二道
自力他力
聖浄二門
二蔵二教
親鸞の教判
相対的教判
絶対的教判
真仮偽判
真仮偽判への批判
親鸞の真意
個と全との問題
異信仰者への態度
3 阿弥陀仏と人間 107
二種の法身
久遠実成の仏
本師本仏
真如と如来
人間論
罪悪思想の展開
人間の本質的悪
4 救済の問題 115
救済の問題
本願
真仮の願
第十八願
名号と光明
全徳施名・名体不二
光明の調熟と摂取
信心正因
三心即一心
聞名即信心
信心廻向
二種深信
称名の報恩と正定業
名号と信心と称名
他力廻向
悪人正機
5 信仰と生活 126
得益と生活 |
現生正定聚
往生浄土
往生即成仏
信仰と生活
真俗二諦
時宗 寺沼 琢明 131ー148
1 時宗の成立 131
時宗の概観
一遍上人
教団の拡充
2 宗史の概要 134
隆盛期
衰勢期
維持期
反省期
3 時宗念仏の特質 140
二つの相承
時宗と時衆
所依の経論
批判の基準
名号絶対
只今の念仏
独一の名号
往生の真相
宗風の一班
→(附一法式行事ー附二時宗の古書目)
臨済宗 山田 無文 149ー178
1 仏教をこう考える 149
疑いから出発仏教をこう考える
釈尊の苦悩
釈尊の悟り
拝むに価するもの
尊厳なる自覚
2 大乗をこう思う 156
大乗思想のおこり
釈尊の根本精神
六波羅蜜
3 禅宗をこう見る 162
日本仏教の理想
的々相承の信仰
拈華微笑
禅宗の信条
4 臨済禅師の宗風 166
中国禅宗の成立
禅宗の分派
臨済禅師
臨済の面目
無位の真人
賓主互換
臨済の四料簡
宗風の真意
5 応・灯・関の一流 174
開山と語録
妙心寺の法灯
大応・大灯・関山
白隠禅
宗風の特徴
曹洞宗 山田 霊林 179ー218
1 仏法の判釈 179
仏語の相承
仏語と禅者
仏心の相承
正法眼蔵と拈華微笑
天童山に於ける偉大な相見
仏真の相承
青年洞山の聖感
2 本尊の礼仰 191
本尊釈迦牟尼仏
釈尊の本身
本尊の尊像
承陽大師
常済大師
3 安心立命 20
仏の慧命の正伝者
即心是仏 |
南無帰依仏
払いのけられない罪業
仏光の下に罪業なし
感激から行われる仏座
坐の実修方式
4 修証義 210
善美な生活とその信証
自分自身の正しい見究め
懺悔の偉大な妙徳
仏戒を正伝して仏位に入る
仏行に生きる純浄の生活
今日今時の此の実践こそ
黄檗宗 赤松 晋明 219ー230
1 黄檗の伝来 219
黄檗
黄檗の伝来
黄檗の宗祖
宗名のおこり
2 黄檗の禅風 223
黄檗の禅
禅浄一味
念仏公案禅
宗意安心
3 黄檗の異彩 227
建築
美術
食作法
鉄眼の一切経
鉄眼禅師
一切経版木
日蓮宗 茂田井 教亨 231ー266
1 日蓮宗の母胎 231
日蓮宗の源流
実在の意識に生きる釈尊
思想の源流としての天台大師
法華経の玄義
三種の教相
法華経の解釈
法華経の実践法
先蹤としての伝教大師
社会的背影
2 日蓮宗の成立 238
日蓮聖人の求道
日蓮宗の開宗
立正安国の運動
法難の体験を通して
日蓮教義の確立
3 教義の概要 244
法華経の二大テーマ
二種の法華経
五義の教相
教
機
時
師
国
一念三千と日蓮の解釈
妙法五字
三大秘法
本門の本尊
本門の題目
本門の戒壇
安心
4 教団の形成 261
日蓮の同心
日蓮の外護者
北陸の教線
身延山の道場
5 教団の理想 264
立正安国
個の救済
時の自覚
個と社会の止揚
・
・ |
7月、「禅文化 (105) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082301
|
表紙 / 岩上観音 ; 遂翁元盧/p2~2
口絵 / 卓洲禅師150年報恩接心/p3~3
対談 キリスト教・仏教・科学 / 平田精耕 ; 持田信夫/p11~20
人物中国禅宗史--ノスタルジアとしての禅者たち(一)菩提達磨・
→二祖慧可 / 西村恵信/p21~35
韓国の仏教文化財 / 李喜益/p36~48
ヨーロッパにおける禅(三) / 野尻命子/p49~59
関雄峰老師の思い出--「しゅんさん」のこと / 後藤芳子/p60~65
久松真一先生の書 / 森田子龍/p66~93
|
中グラビア/p83~90
白隠の象徴と寓意の画による説法--
→大着色横幀蓮池観音図の怪 / 亀山卓郎/p94~126
白隠門下の女性禅者の消息 / 町田瑞峰/p127~141
禅仏教をゆく(その二)壁観バラモン / 柳田聖山/p142~154
信心銘閑話(十一) / 大森曹玄/p156~159
禅文化夏期教養講座案内/p160~160
読者欄「一〔シュ〕」/p164~166
海外禅センター通信/p167~170 |
11月、鎌田茂雄が古田紹欽, 入矢義高監修「遠羅天釜 白隠〔原著〕」を「講談社」から刊行する。
(禅の古典, 11)
12月、「 歴史と旅 9(14)(114) 」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947294
|
日本人と占いの歴史 / 山田宗睦 / p36~41
占星術 生まれた瞬間の惑星と星座の位置で決定する運命 / 門馬寛明 / p42~51
易占い 八卦の組み合わせが織りなす陰と陽の易経の世界 / 金谷治 / p52~61
十二支 子丑寅の生まれ年は人の性格と運命を物語るか? / 永田久 / p62~71
暦占い 六十干支・七曜・六曜などで判断する年月日の吉凶 / 岡田芳朗 / p72~81
日本史の予言者たち 弘法大師空海―仏法の予言者 / 神坂次郎 / p82~87
日本史の予言者たち 安倍晴明―平安の名陰陽師 / 駒敏郎 / p88~93
日本史の予言者たち 新井白蛾―江戸の易断中興の祖 / 戸部新十郎 / p94~99
日本史の予言者たち 出口王仁三郎―神がかりの予言者 / 杜山悠 / p100~105
日本史の予言者たち 高島嘉右衛門―諸国大道易者の元締 / 祖田浩一 / p106~111
自分でできる占いの手引き / 浅野八郎 / p164~175
【カラー口絵】 占いと祭り / p11~21
【グラビア】 城郭の吉相凶相 / p22~34
王城・城郭の地相と方位 / 西ケ谷恭弘 / p122~129
戦国武将の占いと迷信 / 小和田哲男 / p130~137
特集読物 神社仏閣の占い祭礼 / 倉林正次 / p146~151 |
特集読物 民間行事の中の占い / 牧田茂 / p152~157
特集読物 故事伝承に見る夢占い / 橋本万平 / p138~145
特集読物 古今東西、数字のジンクス / 綿谷雪 / p158~163
紋章百話(50)<月星信仰と星紋> / 丹羽基二 / p286~289
奥州街道独歩(10)<白河・根田・小田川> / 橋本三喜男 / p232~235
名僧・怪僧・悪僧伝【白隠】 / 寺内大吉 / p226~231
特別読物 若狭武田氏の盛衰(中) / 大森宏 / p236~241
歴旅情報コーナー 歴史ニュース・ダイジェスト 山吹の里は豪族山吹氏の故地・
→越生町 八薩大菩薩の崇敬願う足利尊氏の遺書 埼玉県内に眠る徳川家の
→埋蔵金十万両 わが国最古、二万年前の線刻礫が出土 三角縁神獣鏡の
→数量問題に答える新説 後墳期最大の高床式倉庫群跡を発掘! / p299~303
新連載小説予告 / p194~194
好評三大連載 新撰組が行く(最終回) / 童門冬二 ; 東啓三郎 / p270~283
好評三大連載 淀どの哀楽(第二十回) / 安西篤子 ; 井出文蔵 / p312~323
好評三大連載 まぼろしの女王 卑弥呼(最終回) / 邦光史郎 ; 北原悌二郎 / p182~193
〈抜粋〉 |
|
| 1983 |
58 |
・ |
2月、伊豆山格堂が「夜船閑話 白隠 [原著]」を「春秋社 pid/12215419
2月、紀野一義 が「名僧列伝 2(禅者 2) 良寛.盤珪.鈴木正三.白隠 」を「角川書店」から刊行する。 (角川文庫) pid/12223320
2月、秋山寛治が「沙門白隠」を「秋山愛子/出版社」から刊行する。 pid/12269261
2000円 重要 著者の肖像あり
3月、故釈瓢斎著「白隠和尚」が「平河出版社」から刊行される。 (秋月龍珉選禅書復刻シリーズ ; 1) pid/12271102 重要
4月、山田無文が「白隠禅師坐禅和讃講話」を「春秋社」から刊行する。 pid/12269181
5月、沼津市歴史民俗資料館編「白隠とその時代」が「沼津市歴史民俗資料館」から刊行される。
○、この年、「市制六十周年記念特別展 (仮)白隠とその時代」展が開催される。 会期・会場の記載なし
タイトル名と開催時期が未確認なため(仮)と表示する 2013・1・22 保坂
7月、萩原町(岐阜県)教育委員会編集「飛騨路と白隠」が「萩原町教育委員会」から刊行される。
7月25日~9月30日、萩原町禅昌寺歴史資料館に於いて「(仮)飛騨路と白隠」展が開催される。
タイトル名未確認なため(仮)と表示する 2013・1・22 保坂
8月、吉村貞司が「芸術新潮 34(8)(404) p78~79 新潮社」に「※史上最大の毒は白隠」を発表する。 pid/6048655
また、森浩一が「同号 p15~19」に「
アート・ニューズ [話題の二展より] 眼でみる古代日鮮交流史」を発表する。
※内容については注意が必要と思う 2023・1・22 保坂
10月、荒井荒雄が「仰臥禅 : 白隠禅師内観の秘法による心身改造」を「明玄書房」から刊行される。 pid/12269850
10月、若林淳之が「静岡県の歴史 : 近世編」を「静岡新聞社」から刊行する。 pid/9539217
|
はじめに/9
駿遠豆と幕藩体制/15
一 天正十八年のあとさき/17
小田原征伐のあとで/17
関ヶ原合戦と大名の動向/23
二 検地の進展と百姓/28
ある「土地売買証文」/28
自称「郷土」の抵抗/33
三 徳川家康と駿府/42
江戸幕府の開設/42
家康と駿府/44
大御所政治――駿府政権――/50
二つの東照宮/53
四 二人の悲劇大名の論理/59
天野三郎兵衛の逐電/59
駿河大納言忠長の改易/67
幕藩体制社会の成立と駿遠豆/71
代官 大名 旗本 百姓/75
一 幕政の軌跡/77
山田長政の郷愁/77
総髪の謀反者正雪/81
孝子中村五郎右衛門/89
二 代官支配の村々/98
代官の系譜とその変質/98 |
代官支配の村々/106
三 駿遠豆の大名/111
大名の配置と大名領/111
諸藩の横顔/120
四 旗本領の村々/145
旗本領の分布/145
相給・三給等の村々/148
主な旗本と旗本領/159
五 村と百姓/174
村さまざま/174
村役人―村方三役―/181
百姓と村落生活/184
近世駿遠豆文化の展開/195
一 近世駿遠豆文化の環境/197
交通ネットワークの形成と文化/197
領主支配の特質と文化/201
二 近世駿遠豆文化の諸相/207
江戸地廻りの文化/207
ある出開帳/214
庶民文化の〝花〟俳諧/219
生活体験から科学への傾斜/228
三 国学の発達とその実像/235
駿遠豆三国の国学の系譜/235
国学運動の実像/239 |
『遠江国風土記伝』とその周辺/243
四 文化荷担者群像/248
帰化僧や白隠/248
駿遠画壇の群像/253
近代への道程/263
一 封建的危機と領主層/265
小島藩の藩政改革/265
身分制社会の動揺/275
意次と忠邦――悲運に泣く改革者たち―/284
二 封建的危機と農民層/295
駿遠領国の義民伝承/295
義民増田五郎右衛門のこと/302
義民伝承にならない義民/311
商品流通の発展と生産者農民/315
三 下田開港のあとさき/325
ペリー来航の波紋/325
下田開港/328
プチャーチンの来航と安政大地震/333
ハリスと玉泉寺/343
下田その日その日/348
幕末期における駿遠の表情/355
一 「ええじゃないか」の高揚/357
二 行きは官軍、帰りは仏/372
参考文献/381 |
10月、淡交社編「淡交 37(10)(445) 」が「淡交社」から刊行される。 pid/7891107
|
巻頭言 一〔ワン〕による国際交流 / 千宗室/p22~23
特集 茶入の世界 / 林左馬衞/p24~34
特集 茶入の世界 名品の鑑賞 / 林左馬衞/p35~42
口絵カラー 茶花 秋明菊 / 山藤宗山/p142~144
口絵カラー 味ごよみ みのりの秋 / 黒田宗光/p140~141
小説 小林一三 日日これ夢(10) / 邦光史郎/p222~233
歌壇 / 米田登/p218~219
俳壇 / 後藤比奈夫/p220~221
連載随想 書庫のなかから(10) / 千宗之/p76~79
連載随想 泉への招待(22) / 三浦綾子/p86~87
連載随想 こころのたて糸(10) / 松原泰道/p84~85
グラビア 第69回夏期講習会/p17~20
グラビア 京洛の書 / 井上隆雄/p13~16
グラビア 茶入荘・炉(1)/p113~119
グラビア 香付花月・風炉(4) / 千宗室/p57~68
グラビア 道具随想二題 / 目片宗允/p71~74
グラビア 茶の湯釜の鑑賞 / 大西清右衛門/p164~164
グラビア 茶のあるくつろぎ 梅棹忠夫氏 / 葛西宗誠/p157~159
第12回裏千家ハワイセミナー/p197~208
ハワイセミナーに参加して/p210~215
第69回夏期講習会/p176~177
第5回学校茶道担当者講習会/p178~179
裏千家学園学生募集/p175~175 |
今月の書架/p166~166
総本部だより/p188~189
月釜ご案内/p185~187
東西南北/p182~184
きりぬきジャーナル/p180~181
るびるびるびぃ/p216~216
告知板/p234~237
読者応募エッセイ 娘・息子に伝えたいお茶/p172~174
茶会記 淡交会記・一般会記/p238~246
青年淡交 青年部の工芸家 玖須朋弘氏/p162~163
青年淡交 青年部ブロックてい談/東北 /
→ 鎌田宗州 ; 鈴木祐太郎 ; 徳丸宗明/p167~171
茶道と私 学校茶道体験論文より/p190~196
秋の衣更え 季節の装い / 塩月弥栄子/p132~133
兼載 連歌師たちの茶の湯 / 戸田勝久/p146~152
詳解「山上宗二記」(10) / 筒井紘一/p121~130
白隠禅師(1)禅僧の逸話 / 西部文浄/p44~52
茶館 中国の茶あれこれ / 周達生/p102~104
醤油 味噌 てんぷら たべもの事始 / 大塚滋/p88~93
鑑賞 日本の詩歌(10) / ヘルベルト・プルチョウ/p80~83
質問室 / 川島宗敏/p145~145
山梨県 茶の湯の旅/p134~139
芸能とその衣裳 中世芸能の世界 / 守屋毅/p94~ |
11月、淡交社編「淡交 37(11)(446) 」が「淡交社」から刊行される。 pid/7891108
|
巻頭言--道統ということ / 千宗室/p22~23
グラビア鵬雲斎家元が北京大学で特別講義/p189~196
●特集/茶人のための古筆入門 / 春名好重/p24~31
●特集/茶人のための古筆入門 名品の鑑賞/p32~46
●口絵カラー 茶花--紅葉 / 山藤宗山/p142~143
●口絵カラー 味ごよみ 炉びらき / 黒田宗光/p144~145
●小説/小林一三 日日これ夢〈十一〉 / 邦光史郎 ; 野尻弘/p216~227
●歌壇 / 米田登/p212~213
●俳壇 / 後藤比奈夫/p214~215
●連載随想 書庫のなかから〈十一〉 / 千宗之/p76~79
●連載随想 泉への招待〈二十三〉 / 三浦綾子/p50~51
●連載随想 こころのたて糸〈十一〉 / 松原泰道/p48~49
宗之若宗匠のご婚儀
グラビア アイルランド大統領・ヨルダン国両夫妻にご呈茶/p19~19
グラビア 京洛の書 / 井上隆雄/p13~16
グラビア 茶道資料館秋季特別展--宸翰/p17~18
グラビア 壺荘付花月 炉〈一) / 千宗室 ; 業躰部 ; 編集部/p57~68
グラビア 茶入荘 炉〈二〉/p113~119
グラビア 道具随想二題 / 目片宗充/p71~74
グラビア 茶の湯釜の鑑賞 / 大西清右衛門/p164~165
グラビア 茶のあるくつろぎ/月山真一氏 / 葛西宗誠/p157~159
アイルランド大統領・ヨルダン国王両夫妻にご呈茶/p174~175
第24回北海道地区大会/p176~177
各地の献茶式/p178~178
|
第69回夏期講習会を受講して / 田中祇悠 ; 小室宗正/p198~199
総本部だより/p204~205
月釜ご案内/p201~203
東西南北/p206~208
告知板/p228~230
裏千家学園学生募集/p97~97
きりぬきジャーナル/p210~211
るびるびるび/p52~52
『茶道の原流』全六巻刊行/p140~140
わが師--読者応募エッセイ / 戸倉雅子 ; 橋詰宗陽/p186~188
茶会記--宗家会記・淡交会記・一般会記/p232~254
●青年淡交 青年部の工芸家/石田安弘/p162~163
●青年淡交 青年部ブロックてい談/関東第二--青年部だより
→/ 高野孫左衛門 ; 中込佶 ; 品川一郎/p179~185
留め袖--季節の装い5 / 塩月弥栄子/p128~129
心敬--連化師たちの茶の湯 / 戸田勝久/p146~152
詳解「山上宗二記」〈十一〉 / 筒井紘一/p130~139
白隠禅師〈二)禅僧の逸話 / 西部文浄/p80~88
茶外の茶--中国の茶のあれこれ / 周達生/p89~91
ようかんまんじゅう--たべもの事始 / 大塚滋/p121~127
鑑賞 日本の詩歌〈十一) / ヘルベルト・プルチョウ/p92~96
質問室 / 川島宗敏/p197~197
長野県--茶の湯の旅/p166~173
禁食・過差・傾奇--中世芸能の世界 / 守屋毅/p98~104 |
|
| 1984 |
59 |
・ |
1月、「禅文化 (111) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082307
|
巻頭 本号のことば/p3~6
カラーグラビア 修道士が体験した日本の僧堂生活/p7~16
第二回 東西霊性交流を終えて 扉はこわされた / 奥村一郎/p22~24
第二回 東西霊性交流を終えて 友情確認の第一歩を築く / 楢崎一光/p24~27
第二回 東西霊性交流を終えて 今後の交流計画のために / 門脇佳吉/p27~29
第二回 東西霊性交流を終えて ヨーロッパ側からの報告 / 野尻命子/p30~41
随想 禅風余話 / 大山澄太/p114~119
随想 生かされてここに生きる--東光禅話より / 栽松康雄/p89~93
坐禅と作務で情緒障害児童をなおす―少林寺の
→青少年育成センターを訪ねる/p77~88
後近代人を産み出す「モダン危胎」 / 常盤義伸/p42~60
人物中国禅宗史(七)ノスタルジアとしての禅者たち / 西村恵信/p94~108
白隠が描いたお多福女郎の意味とその真作・贋作 / 亀山卓郎/p120~145 |
グラビア 寺西家の蔵書/p61~64
寺西乾山 妙心寺派の子弟薫育に生涯を捧げた儒者/p65~70
祖父・寺西乾山をしのぶ / 飛世充子/p71~72
達磨さん 別れてから百年ぶり名古屋城天守閣で
→お猿と再会/p73~76
禅・こぼれ話/p109~113
書灯/p150~150
読者欄「一〔シュ〕」/p146~149
『禅文化』既刊号の内容案内/p152~153
寄贈書一覧/p151~151
執筆者紹介/p154~154
禅文化研究所の本/p156~166
編集後記「蛇足」/p155~155 |
3月、心山義文が「国史学研究 10 p.132-146」に「白隠における三教一致論 」を発表する。
6月、山田無文が「毒語心経毒語註 白隠 [原著]」を「禅文化研究所」から刊行する。2版 所蔵:大阪市立図書館 pid/12220974
7月、後藤大用が「無に生きる禅」を「鴻盟社」から刊行する。 pid/2529722
|
第一章 禅のかなめ/p11
第二章 無とは何か/p19
第三章 無の人生観/p28
第四章 無に生きるの道/p35
第五章 無の思想/p51
第六章 無の活動/p74
(1) 無の活作用/p74
(2) 魂の自由/p82
(3) 崇高なる仏性/p86
(4) 円融和合/p90 |
第七章 無に生きた好例/p95
(1) 恵能/p95
(2) 徳山/p107
(3) 白隠/p115
(4) 無に生きる観音/p121
第八章 正しい信仰/p137
(1) 信仰とは何か/p137
(2) 主観の信/p140
(3) 信仰の主体性/p144
(4) 客観の信/p147
|
(5) 正信の生活/p151
(6) 現代宗教批判/p155
第九章 「信」についての
→炉辺談話/p162
第十章 純禅の「信」/p173
第十一章 無の芸術/p184
(1) 無の表現/p184
(2) 庭園/p189
(3) 絵画/p193
(4) 禅詩/p198
|
(5) 和歌/p206
(6) 俳諧/p209
(7) 能楽/p214
(8) 謡曲/p218
(9) 茶道/p221
(10) 華道/p226
(11) 書道/p230
第十二章 般若心経秘要/p233
第十三章 「無に生きる禅」の特徴/p246
・ |
7月、竹山道雄が「文芸春秋 62(8) p77~78」に「白隠その他」を発表する。 pid/3198478
また、下河辺淳が「同号p86~87」に「新疆ウイグル自治区を旅して」を発表する。
7月、日本思想史懇話会編「季刊日本思想史 (23)」が「ぺりかん社」から刊行される。 pid/7949995
|
美術の思想<特集>/p3~102
上代彫刻にみる造顕意識の変遷 / 田中嗣人/p3~27
藤原美術の本質と造型思想-上代仮名を中心に / 小川光暘/p29~48
卑俗なるものと新風--「東北院職人歌合絵」の成立 / 片野達郎/p49~65
道具と美術のあいだ--茶の世界における造型物の
|
→鑑賞について/玉虫敏子/p66~86
白隠思想の辺縁系--イマジネ-ションと芸術観 / 泉武夫/p86~102
研究論文募集のお知らせ/p28~28
前号の訂正/p103~
・ |
8月、静岡県日本史教育研究会編「静岡県の史話 下」が「静岡新聞社」から刊行される。
pid/9539402
|
81 浅間さんと臨済寺―家康が尊崇/8
82 駿府城の造営―小田原城にならう/12
83 伊豆の世襲代官―江川太郎左衛門/16
84 三島暦―東国に広く流布/19
85 四四歳の花嫁―旭姫の悲劇/22
86 山中城―豊臣と北条の攻防/26
87 連歌から能楽へ―家康時代/30
88 江戸御打ち入り―駿府から江戸へ/34
89 豊臣体制下の駿遠豆―配下の
→部将で固める/38
90 天下分け目の戦――駿遠武将の去就/42
91 五十三次の整備――家康、
→東海道を掌握/46
92 大御所駿府へ――事実上の首都に/50
93 駿府九十六ヵ町――家康の都市計画/54
94 駿府町人の特典―幕府が助成金/58
95 スペインの鼓笛ひびく―国際都市駿府/60
96 切支丹とタバコ――西欧文化上陸/64
97 按針と伊豆石―増築の江戸城へ/68
98 舟運の発達――富士川と天竜川/71
99 天竜美林―江戸庶民の建築用材/74
100 駿遠のやきもの―志戸呂焼と賤機焼/77
101 日本一のおごりもの―大久保長安/81
102 忠臣か?―片桐且元/85
103 明神か権現か―家康の尊号/89
104 駿府寺めぐり―家康にゆかり訪ねて/91
105 浄瑠璃の始まり―小野於通/93
106 タイに散った風雲児―山田長政/95
107 忠長狂乱―恐いもの知らずの次男坊/97 |
108 駿府天領に―忠長改易以後/101
109 蜂起不発―由比正雪/104
110 遠州三山―由緒ある名刹/108
111 身延紀行と伊豆行脚―三百年前の旅/112
112 富士講のにぎわい―信仰と相互扶助/118
113 新田開発――水とのたたかい/122
114 日和の港――下田/126
115 鎖国下の外交――朝・蘭の使節/130
116 夢は枯野を――芭蕉の旅/133
117 甲州との接点――梅ヶ島温泉/137
118 宝永の大噴火―伊奈忠順の奔走/141
119 引佐のイグサ―旗本近藤家が奨励/145
120 凧あげと大念仏――四百年の歴史/147
121 戯曲と郷土――歌舞伎名場面/150
122 静岡県の和紙――ミツマタの発見/154
123 白浜の天草漁―天明ごろから本格化/157
124 新しい息吹き――国学/159
125 白隠さん――易しい教え/162
126 小島藩一万石――苦しい台所/166
127 相良藩と田沼意次―異例の出世/168
128 一九と春町――駿河出身の戯作者/171
129 東海道有情―弥次喜多道中にみる/175
130 海道名物―安倍川餅/179
131 一揆と打ちこわし―封建制の破綻/183
132 砂糖きび栽培――駿遠が最初/187
133 浜名湖の藻――大切な肥料/191
134 首切り正月―義民増田五郎右衛門/193
135 駿遠の七藩――譜代の小藩分立/195
136 代官支配――駿遠豆の天領/199
|
137 かつお節――奈良時代から特産/201
138 藩校――新時代への模索/204
139 秋葉三尺坊――神仏混淆の典型/208
140 文政茶一件―茶の流通めぐる訴訟/212
141 報徳の教え――二宮尊徳/216
142 百姓どもは下駄かさ無用―天保の改革/220
143 伊豆の長八――こて絵の美/224
144 囲碁名人――丈和と秀和/228
145 下田開港――松陰密航に失敗/232
146 下田流れて三島は焼けて―安政の
→大地震/236
147 ディアナ号沈没―戸田で洋船造り/240
148 ハリス江戸へ――天城をこえて/244
149 開国の犠牲者―唐人お吉/248
150 写真師誕生――下岡蓮杖/252
151 幕末姫様道中―金も時間もかかる/256
152 熱海の義人――釜鳴屋平七/260
153 外人、熱海へ―湯治、保養に人気/264
154 幕末ロシアへ密航――橘耕斎/267
155 王政復古――幕に立った神官たち/271
156 西郷・山岡会談―江戸城明け渡し約す/275
157 咸臨丸と次郎長―〝賊軍〟の
→遺体引き揚げ/279
158 駿府藩の新生―慶喜来る/283
159 おとまりさん―旧幕臣のあえぎ/287
160 府中学問所―豪華な教授陣/291
あとがき/295
・
・ |
9月1日~9月23日ほか、秋田市美術館ほかに於いて「白隠 : 生誕三〇〇年記念
特別展」が開かれる。
第1会場:秋田市美術館 主催:秋田市美術館・秋田魁新報社
○、この年、佐野美術館〔三島〕 企画・図録編集「白隠 : 生誕三〇〇年記念
特別展」が刊行される。
12月、新保哲が「印度學佛教學研究 33(1) p.p250~252」に「白隠の布教について (大正大学における第35回〔日本印度学仏教学会〕学術大会紀要-1-)」を発表する。 pdf
○、この年、山内長三が「白隠さんの絵説法」を「大法輪閣」から刊行する。 pid/12216615
○、この年、高山峻が「白隠禅師夜船閑話」を「大法輪閣」から刊行する。 所蔵:滋賀県立図書館 |
| 1985 |
60 |
・ |
1月、秋月龍珉が「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 62(1)(732)p4~9 中央仏教社」に「白隠禅の本質」を発表する。
また。「同号p2~3」に「白隠禅師坐禅和讃」が掲載される。 pid/7885607
1月3日~13日迄、大丸ミュージアムに於いて「関西の書家100人展 : 併催一休と白隠の書」展が開かれる。
1月、サンケイ新聞大阪本社/編集・丸岡宗男監修・岸岡正樹撮影「関西の書家100人展 : 併催一休と白隠の書」が「サンケイ新聞大阪本社」から刊行される。
3月、黒沢脩ほか編「静岡の歴史と人物 : 加藤忠雄著作集」が「加藤忠雄著作集刊行会」から刊行される。 pid/9539752
|
郷土編
一 人物/3
1 聖一国師/3
2 曾我兄弟の仇討/8
3 今川氏の人々/13
4 雪斉略伝/20
5 家康と靜岡
→(付・徳川家達公と静岡県)/29
6 由井正雪事件/42
7 伊奈忠順―宝永噴火の救世主/48
8 友野与右衛門―
→苦難にみちた箱根用水の建設/58
9 江川坦庵―明治前夜の先覚者/64
10 清水次郎長と咸臨丸事件/76
二 文化財あれこれ/83
1 了仙寺と玉泉寺(下田市)/83
2 吉田松陰寄寓の跡(下田市)/86
3 洋式帆船建造地(戸田村)/88
4 白隠禅師の墓(沼津市)/91
5 清見寺(興津)/94
6 臨済寺(静岡市)/96
7 浅間神社(静岡市)/98
8 久能山(静岡市)/101
9 柴屋寺(静岡市)/104
10 新居関所の跡(新居町)/107
11 駿遠豆の国分寺/109
12 国宝久能経について/112
三 登呂/117
1 登呂遺跡が世に出るまで
→(付・登呂公園の構想)/117
2 登呂遺跡/125
3 登呂の思い出/132
(一)遺物を焼く/132
|
(二)標柱建設の巻/133
(三)遺物奪還の巻/134
(四)闇米・闇焼酎の巻/136
(五)講演会を聞いて/138
4 資料(登呂遺跡調査後援会設立趣意書)/141
研究編
一 静岡県の典籍と古写経/145
1 家康の文化的事業/145
2 静岡県の書跡と典籍/176
3 鉄舟寺の大般若経/186
4 藤枝清水寺の縁生論/189
5 禅林の文化的事業/194
6 国宝久能経解説/196
7 戦後に写した「久能経」―
→田中親美翁聞書― 竹田道太郎/201
二 安倍城・大井川川会所・諏訪原城/209
1 安倍城/209
2 大井川川会所/215
3 諏訪原城/221
三 静岡種三椏栽培の始原について/229
四 みかんの歴史/235
五 駿府城/242
六 警察制度の変遷/252
葵文庫・交友・随想編
一 葵文庫と加藤忠雄/263
1 地方文化と町村図書館/263
2 天覧を仰ぎし図書のことなど/270
3 静岡の大火/282
4 いつ読むか、どう読むか/284
5 葵文庫の防火活動/288
6 図書館関係論文及び随筆等目録/293
7 回想の加藤忠雄先生 平野日出雄/297
二 交友/302
|
1 古谿荘遊記(田中光顕氏)/302
2 静岡市立高等学校校歌(土岐善麿氏)/309
3 美意延年(新村出氏)/312
三 随想/316
1 わが青春/316
2 ふるさとと私/321
3 サトヤマスト/323
4 夏と旅/327
5 きけわたつみのこえ/330
6 お国かたぎ/334
7 梅雨/336
8 鮎/337
9 かつお/339
加藤忠雄先生の思い出
一 加藤忠雄先生の思出 天野保雄/343
二 加藤先生と富士文庫 石川軍治/345
三 無宗教葬 海野秀雄/350
四 会者定離 小沢誠一/354
五 加藤先生を偲んで 北山宏明/356
六 加藤忠雄先生の御霊前に
→捧げる詞 佐久田昌一/358
七 広い海のような人 鱸正太郎/360
八 加藤先生の面影 鈴木与平/362
九 加藤忠雄氏の想い出 徳川慶光/364
一〇 完爾 春田鐵雄/366
一一 加藤忠雄先生への追想 松浦國男/369
一二 加藤先生を偲ぶ 三島輝穂/371
一三 文化推進の原動力―
→加藤先生と登呂遺跡― 森豊/373
一四 出会いと別れ 渡邊福太郎/376
加藤忠雄略暦/379
加藤忠雄著作目録/382
あとがき/389 |
3月、平野宗浄, 加藤正俊編「栄西禅師と臨済宗」が「吉川弘文館」から刊行される。 (日本仏教宗史論集,
7)
|
栄西 : その禅と戒との関係 / 石田瑞麿 [執筆]
栄西の一心戒について / 荻須純道 [執筆]
栄西の密教について / 多賀宗隼 [執筆]
栄西研究 / 古田紹欽 [執筆]
栄西と今津・誓願寺 / 川添昭二 [執筆]
栄西元久元年の運動方針について / 菅原昭英 [執筆]
栄西の入宋帰朝と鎌倉行化 / 葉貫磨哉 [執筆]
禅宗の日本的展開 / 藤岡大拙 [執筆]
初期妙心寺史の二、三の疑点 / 玉村竹二 [執筆]
|
関山慧玄伝の史料批判 / 加藤正俊 [執筆]
林下における教団経営について :
→大徳寺徹翁義亨を中心として / 竹貫元勝 [執筆]
一休和尚とその弟子達 / 平野宗浄 [執筆]
徳川初期における臨済禅の低迷とその打開 :
→ 白隠禅出現の時代背景 / 木村静雄 [執筆]
無著道忠の学問 / 柳田聖山 [執筆]
人間東嶺の苦悩 : その身体と精神、情
→と非情の葛藤をめぐって / 西村恵信 [執筆] |
3月、淡交社編「淡交 39(3)(464) 」が刊行される。 pid/7891126
|
特集 白隠さんの世語のこころ / 重松宗育 / p24~44
カラー 白隠さんの世語のこころ / p5~9 |
〈抜粋〉
・ |
7月、「 禅文化 (117) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082313
|
人生いささかも詐謀あることなし--黄檗山万福寺管長
→村瀬玄妙老師を訪ねて / p7~15
グラビア 寺宝探訪(6)続京都龍宝山大徳寺 / p55~69
玄沙の泣きどころ / 真継伸彦 / p16~22
雪峰山で考えたこと / 平野宗浄 / p23~31
古仏ぞ恋うる〈新・禅仏教をゆく・第三話〉 / 柳田聖山 / p32~54
仏教東漸史の断章--東西の出会いと現状〔序〕 / 多田稔 / p71~76
菩薩道に生きる人びと(付新鮮な
→アメリカ仏教のこころ)/金三友/p77~85
ともに道を求めて--キリスト教修道僧と禅修行僧の
→対話 / ピエール・ド・ベテュヌ ; 岡田徹〔訳〕 / p92~102
提唱 傅大士心王銘 / 山田無文 / p116~127
地道な努力こそ自己を救う道 / 堀尾成仙 / p110~114
禅寺にはバッハが似合う〔京都舞鶴・妙心寺派長雲寺〕 / p115~115 |
カンボジア難民救援活動の報告 / RACK事務局/p128~134
いっぷく拝見 / p103~103
禅会だより 千葉・龍泉院参禅会 / p139~139
禅会だより 臨黄各山・専門道場の夏期講座禅会案内/p141~141
禅会だより 春季坐禅会の報告 / p140~140
禅会だより だるま寺暁天講座 / p134~134
書灯 / p142~143
読者欄〈一〔シュ〕〉 / p144~145
寄贈書一覧 / p143~143
『禅文化』バックナンバー / p148~148
禅文化研究所の本 / p155~159
第20回禅文化講座のご案内--白隠禅師生誕三百年記念特集/p149~149
執筆者紹介 / p152~153
編集後記〈蛇足〉 / p152~153 |
9月、「プレジデント = President 23(9)」が「プレジデント社」から刊行される。 pid/2802639
|
「禅のこころ」に学ぶ――「人との出会い」を大切にしてこそ人生は豊かになる /
松原泰道 / p42~51
禅は「人間肯定」の思想である――多様な可能性を秘めた個々人の人間的完成ということが、禅における要諦
/ 百瀬明治 / p54~67
道元 「只管打坐」で拓いた「純一なる仏法」の道――既成仏教に飽き足りない青年僧は長い求法の旅の末、正伝の教えに邂逅した / 秋月龍珉 / p70~81
栄西と白隠 「日本臨済禅」に「開祖」二人あり――「開祖」栄西は宋から臨済禅を伝え、「中興の祖」白隠は近代教団の基礎を築いた
/ 西村恵信 / p82~91
一休 「風狂」に生きた「孤高」の禅者――「頓智小坊主の一休さん」で庶民に親しまれた名僧の実像 / ひろさちや / p94~103
沢庵「快僧」が到達した「天上天下無一物」の世界――天皇から授けられた紫衣も、禅林の最高位も、彼は弊履の如く捨て去った
/ 浜野卓也 / p106~115
千利休 「茶禅一味」に秘められた苛烈なる精神―― 一見枯れた「佗数寄」の茶とは裏腹に最期まで権力者と対決した「激しい禅」
/ 岩崎呉夫 / p118~129
山岡鉄舟「剣禅一如」の士「江戸無血開城」へ奔る――徳川慶静の密命を受けた鉄舟は西郷隆盛と談判。彼の禅魂が江戸を戦火から救った / 津本陽 / p132~141
真藤恒と『正法眼蔵』――「電電意識革命」を推進した確固たる精神力の奥義 /
小堺昭三 / p142~151
(略) |
10月、「禅文化 (118)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082314
|
巻頭カラー / 中国明末の絵画
龍沢寺と白隠 / 鈴木宗忠 / p11~23
東嶺和尚と非人情の世界 / 西村恵信 / p24~43
グラビア 寺宝探訪(7)京都覚雄山鹿王院 / p75~75
明末四僧--その人と絵画について(一) / 泉谷博古館 / p70~74
磨鏡台の朝(第四話)新・禅仏教をゆく 第四話 / 柳田聖山 / p87~115
仏教東漸史の断章〔一〕国際山大菩薩禅堂金剛寺 / 多田稔 / p46~57
百雑砕 鈴木大拙と沢木興道 / 藤吉慈海 / p44~45
チベット巡拜の思い出 ●妙心寺派海清寺春海文勝老師に聞く / p58~62
提唱 傳大士心王銘〔第二講〕 / 山田無文 / p126~134
厳しく、楽しく、親子100人が集う--夏休み禅寺生活体験学習を終えて/p142~149
金閣長老の清貧 / 西村恵信 / p139~139
謾説(1)禅文化・文化禅 / 退屈庵老人 / p124~125 |
花薬欄 禅問答 / 松尾静明 / p63~63
花薬欄 あの世 / 堀浩良 / p64~65
花薬欄 水子供養に思う / 芳井敬郎 / p65~67
花薬欄 牛島仙人 / 釈元孝 / p67~68
花薬欄 日航機の事故に / 土井道子 / p68~69
いっぷく拝見 / p116~121
研究所所蔵墨蹟展のあんない / p122~123
禅会だより 〔両忘禅協会・東京支部〕 / p140~140
書灯 〈新刊書案内〉 / p150~151
『禅文化』バックナンバー / p152~152
禅文化研究所の本 / p155~160
編集後記 〈蛇足〉 / p154~154
・ |
|
| 1986 |
61 |
・ |
1月、「禅文化 (119)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082315
|
仏教と唐代の文学 / 孫昌武 ; 衣川賢次 / p25~42
明末四僧--その人と絵画について〈二〉 / p130~136
対談 科学と宗教--21世紀が求めるもの / 泉美治 ; 平田精耕 / p11~24
仏教者が現代社会に学ぶもの / 河野太通 / p55~69
仏教東漸史の断章〔二〕 東西の門戸サンフランシスコ/多田稔/p72~82
白隠禅とその芸術との接点 / 古田紹欽 / p83~93
グラビア 寺宝探訪(8) 続・京都 覚雄山鹿王院 / p43~53
百雑砕 西田天香と久松真一 / 藤吉慈海 / p70~71
嗚呼、我が生涯の師〈柴山全慶老師の思い出と聴聞記〉/辻光文/p102~118
提唱 傅大士心王銘 〔第三講〕 / 山田無文 / p137~149
花薬欄 堂々めぐり / 村本詔司 / p94~95
花薬欄 芽生 / 柳田静江 / p95~96 |
花薬欄 窓辺から / 堀尾孟 / p97~98
花薬欄 禅との邂逅 / 稗田操子 / p98~99
漫説 田舎のお寺でやっこらさ/窮屈庵主/p100~101
いっぷく拝見 / p123~129
催し案内 〔禅の世界と仙厓展〕 / p54~54
催し案内 〔白隠・禅と芸術展〕 / p91~91
催し案内 〔臨済・黄檗・曹洞管長・貫首墨蹟展〕/p151~15
書灯 〈新刊書案内〉 / p150~151
『禅文化』バックナンバー / p152~152
禅文化研究所の本 / p155~155
編集後記 〈蛇足〉 / p153~153
・ |
2月8日~3月11日迄、佐野美術館に於いて「白隠・禅と芸術展 : 生誕三〇〇年記念」展が開かれる。
作品解説: 渡辺妙子, 飯田孝子 主催: 佐野美術館・三島市・同教育育委員会他
2月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 63(2)(743) p64~65中央仏教社」に「白隠禅師坐禅和讃」が掲載される。 pid/7885618
4月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 63(3)(744) p72~73中央仏教社」に「白隠禅師坐禅和讃」が掲載される pid/7885619
4月、「禅文化 (120)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082316
|
おのおの方、おん試みてみなはれ! 中川宗淵老師の風光/p19~26
人みな如来なり / 丸田元親 / p52~59
私の十句経 / 芦田正憲 / p60~69
グラビア 寺宝探訪(9) 禅の世界と仙厓展より(一) 博多聖福寺/p7~18
仏教東漸史の断章(三)
→サンフランシスコ禅センター / 多田稔 / p28~36,38~44
禅と儒教との葛藤 / 荒木見悟 / p70~81
百雜砕(3)鈴木正三と椎尾弁匡 / 藤吉慈海 / p46~47
明末四僧 その人と絵画について(三) / 泉屋博古館 / p109~117
カラー 重光の芸術 / p83~86
ぞうきん和尚 重光--その人と芸術 / p87~101
東漸禅窟の人--千崎如幻の生涯(1) / 藤本光城 / p123~137
提唱 傅大士心王銘 第四講 / 山田無文 / p138~14 |
謾説(3)不思議なき世界なんぞ / 哲禅居士 / p50~51
いっぷく拝見 / p102~108
『白隠禅師の画を読む』の著者 亀山卓郎氏に
→人文科学奨励賞 / p37~37
催し案内 第2回 市民禅講座 / p48~48
催し案内 第2回 夏休み禅寺生活体験学習 /
→花園大学宗教部 ; 禅文化研究所/p49~49
書評 藤吉慈海編 『真人久松真一』 /西村恵信/p82~82
書灯 既刊・新刊案内 / p150~151
愛語の世界:慈しみの本 / p118~118
『禅文化』バックナンバー / p152~152
禅文化研究所の本 / p155~158
編集後記 蛇足 / p153~153 |
7月、八戸市博物館編「東北の土人形 : 特別展図録」が刊行される。
7月27日~9月23日、八戸市博物館に於いて「東北の土人形 : 特別展」が開かれる。
|
カラー図版 1
東北の土人形 13
下川原人形 15
花巻人形 18
附馬牛人形 26
中山人形 30
八橋人形 33
小坂人形 35
鵜渡河原人形 37
瓦人形 41
相良人形 46
小菅人形 53
堤人形 55
根子町人形 61
「東北の土人形」出品目録 64
「東北の土人形」出品目録
No.作品名 寸法(cm) 所蔵
<下川原人形>
1 おいらん 14.2 中川秀敏
2 馬乗り 12.5 中川秀敏
3 お多福 10.4 中川秀敏
4 福助 11.9 中川秀敏
5 大黒 9.2 中川秀敏
6 えびす 10.3 中川秀敏
7 三味線弾き 12.7 中川秀敏
8 三味線弾き 12.4 中川秀敏
9 立女 15.5 中川秀敏
10 角力取り 14.2 中川秀敏
<花巻人形>
11 内裏 19.0 花巻市教育委員会
12 三番叟 20.8 花巻市教育委員会
13 かめ割温公 17.2 村田柴太
14 花車 20.0 村田柴太
15 大黒 24.7 村田柴太
16 えびす 23.8 村田柴太
17 福禄寿 41.5 村田柴太
18 亀かつぎ 26.5 村田柴太
19 鯛車 29.0 村田柴太
20 鯛抱き 22.5 村田柴太
21 牛乗り天神 16.0 村田柴太
22 獅子舞 16.0 村田柴太
23 和藤内 12.3 村田柴太
24 熊谷直実 29.0 村田柴太
25 虚無僧 18.7 村田柴太
26 力士 19.1 村田柴太
27 力士 27.0 村田柴太
28 釣三昧 16.1 村田柴太
29 太鼓打ち 16.4 村田柴太
30 おいらん 18.5 村田柴太
31 笠踊り 17.0 村田柴太
32 三味線美人 17.8 村田柴太
33 福唐子 24.5 花巻市教育委員会
34 唐子 11.0 花巻市教育委員会
35 義経 23.5 花巻市教育委員会
<附馬牛人形>
36 天神 22.5 遠野市立博物館
37 内裏 31.0 遠野市立博物館 |
38 五人囃子 12.0 遠野市立博物館
39 二福神 21.2 遠野市立博物館
40 武者 21.3 遠野市立博物館
41 布袋かつぎ 13.8 遠野市立博物館
42 三番叟 14.5 遠野市立博物館
43 えびす 21.2 遠野市立博物館
44 大黒 19.0 遠野市立博物館
45 猫 16.0 遠野市立博物館
46 犬 12.0 遠野市立博物館
47 鶏かつぎ 16.7 遠野市立博物館
48 子守り 15.8 遠野市立博物館
49 山姥と金時 18.3 遠野市立博物館
50 金時 11.5 遠野市立博物館
<中山人形>
51 天神 17.0 秋田県立博物館
52 おいらん 23.0 秋田県立博物館
53 常盤御前 19.5 秋田県立博物館
54 内裏雛 15.0、13.4 秋田県立博物館
55 高砂 21.0、21.0 秋田県立博物館
56 えびす 18.0 秋田県立博物館
57 布袋 16.7 秋田県立博物館
58 平敦盛 18.0 秋田県立博物館
<八橋人形>
59 内裏雛 23.0、28.0 秋田県立博物館
60 三人官女 18.0、17.2、13.4 秋田県立博物館
61 五人囃子 14.3、17.5、13.5、
→17.7、13.8 秋田県立博物館
<小坂人形>
62 武内宿弥 19.0 秋田県立博物館
63 神功皇后 17.0 秋田県立博物館
64 金時 15.7 秋田県立博物館
65 高砂 21.0、20.0 秋田県立博物館
<鵜渡河原人形>
66 花咲じいさん 17.3 酒田市立資料館
67 布袋 16.0 酒田市立資料館
68 舞女 25.7 酒田市立資料館
69 桃太郎 16.0、13.3、15.0 酒田市立資料館
70 桃太郎 28.5 酒田市立資料館
71 舞女 27.0 酒田市立資料館
72 虎 16.5 酒田市立資料館
73 弁慶 20.0 酒田市立資料館
74 牛若丸 26.5 酒田市立資料館
75 おばこ 16.0、20.2、16.5 酒田市立資料館
76 舌切りすずめ 20.0 酒田市立資料館
77 町娘 25.0 酒田市立資料館
<瓦人形>
78 山姥と金時 19.5 致道博物館
79 犬 26.0 致道博物館
80 犬型 致道博物館
81 犬乗り 20.5 致道博物館
82 えびす 19.8 致道博物館
83 大黒 20.2 致道博物館
84 馬乗り大黒 20.5 致道博物館
85 内裏雛 21.8、19.8 致道博物館
86 内裏雛型 致道博物館
87 姉様 20.7 致道博物館
88 金時 14.8 致道博物館 |
89 鯛持ち 15.8 致道博物館
90 車引き布袋 19.3 致道博物館
<相良人形>
91 鯉金 15.0 山形県立博物館
92 内裹雛 14.2、13.2 山形県立博物館
93 内裹雛 15.6、13.9 山形県立博物館
94 子供力士 17.3 山形県立博物館
95 力士 21.0 山形県立博物館
96 力士 22.0 山形県立博物館
97 お多福 14.3 山形県立博物館
98 力士 17.8 山形県立博物館
99 鯉金 16.8 山形県立博物館
100 矢とぎ 9.3 山形県立博物館
101 矢とぎ 9.5 山形県立博物館
102 矢とぎ 9.5 山形県立博物館
103 だるま 10.3 山形県立博物館
104 亀かつぎ 17.0 山形県立博物館
105 春駒乗り 12.8 山形県立博物館
106 三番叟 18.7 山形県立博物館
107 三番叟 18.7 山形県立博物館
108 獅子舞 17.3 山形県立博物館
<小菅人形>
109 内裏雛 19.5、17.0 山形県立博物館
110 軍人 22.0 山形県立博物館
111 子守り 21.5 山形県立博物館
112 舞女 21.5 山形県立博物館
<堤人形>
113 静御前 14.1 仙台市博物館
114 内裏雛 13.6、9.1 仙台市博物館
115 五人囃子 10.0 仙台市博物館
116 天神 11.0 仙台市博物館
117 天神 11.6 仙台市博物館
118 大黒 12.0 仙台市博物館
119 えびす 9.5 仙台市博物館
120 えびす大黒鯛つり 11.7 仙台市博物館
121 鯛抱き 12.0 仙台市博物館
122 花車 20.5 仙台市博物館
123 越後獅子 17.0 仙台市博物館
124 政岡 16.5 仙台市博物館
125 春駒乗り 12.7 仙台市博物館
126 うさぎ持ち 15.0 仙台市博物館
127 傘持ち 16.4 仙台市博物館
128 瓢乗り 12.5 仙台市博物館
129 鯉金 22.2 仙台市博物館
130 獅子かつぎ 13.3 仙台市博物館
131 太鼓打ち 10.5 仙台市博物館
<根子町人形>
132 鯛乗り 14.0 福島県歴史資料館
133 平敦盛 10.7 福島県歴史資料館
134 熊谷直実 13.3 福島県歴史資料館
135 子連れ 11.8 福島県歴史資料館
136 座美人 8.2 福島県歴史資料館
137 獅子かつぎ 10.4 福島県歴史資料館
138 天神 8.5 福島県歴史資料館
139 和藤内 12.8 福島県歴史資料館
140 俵乗り大黒 10.0 福島県歴史資料館
141 鯛かつぎ 17.3 福島県歴史資料館 |
10月、「禅文化 (122)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082318
|
一休を語る 独創のための独走 / 中川一政 ; 柳田聖山/p7~28
概説 日本禅宗史(一) / 竹貫元勝/p29~42
仏教東漸史の断章--青い目の禅僧たち〔五〕 / 多田稔/p44~68,70~70
英米禅文学の紹介(1)ワーズワースの禅 / 重松宗育/p100~114
百雑砕 白隠慧鶴と仙厓義梵 / 藤吉慈海/p97~99
一字子に思う--墨蹟研究会ぼ発足を願って / 重松輝宗/p83~88
東漸禅窟の人(3)千崎如幻の生涯 / 藤本光城/p119~133
坐して自己を見つめ、遊びつつ学ぶ--●禅寺生活体験学習を終えて/p137~145 |
グラビア 寺宝探訪--福岡市美術館「仙厓展」より(11)
→ユーモアにつつまれた禅のこころ/p71~82
謾説 禅はうしろばかりを振り返っている / 異/p134~135
いっぷく拝見/p89~95
禅文化講座と墨蹟展のお知らせ/p136~136
報告 アメリカ禅センター交流の旅/p147~149
〈抜粋〉
・ |
11月、山内舜雄が「禅と天台止観--坐禅儀と『天台小止観』との比較研究」」を「大蔵出版」から刊行する。 |
| 1987 |
62 |
・ |
1月、 芸術新潮 38(1)(445) 新潮社 新潮社 1987-01pid/6048698
|
書はなぜ伝世したか 有名人の書--道鏡/平清盛/豊臣秀吉/細川ガラシャ/日蓮他
//p6~16
書は人なり 自由な禅僧の書--一山一寧/一休宗純/良寛/大燈国師/白隠他 //p32~37
書は人なり 遺偈と絶筆の凄味--聖一国師/清拙正澄/正岡子規他 //p38~40
優雅なかな文化 調度手本--継色紙/高野切/寸松庵色紙/石山切/元永本古今集/伴大納言絵詞他 //p41~49
ART NEWS アート・ニューズ ラウシェンバーグ世界巡作興行 //p74~77
ART NEWS アート・ニューズ 全長四〇メートルの「方丈記」絵巻 / 佐多芳郎/p78~79
展覧会案内 //p92~93
次号予告 //p61~61
[新連載] 暮しの八卦 春夏秋冬(1) 神々のすまい / 清家清/p102~104
[新連載] 本朝巨木伝(1) 板の根 サキシマスオウノキ[西表島] / 牧野和春/p106~107
[連載] 気まぐれ美術館(156) 糸杉、オリーヴ、そして海 / 洲之内徹/p97~101
[連載] 芸術新潮料理百科(25) 一月 慈姑 / 竹内廸也 ; 利根山光人/p108~109
大特集 日本の書 / 小松茂美/p4~72
名品篇・解説 / 小松茂美/p4~49
型より入れ型を破れ 三筆--空海の真筆は?/嵯峨天皇/橘逸勢 //p18~24
型より入れ型を破れ 三跡--小野道風/藤原佐理/藤原行成 //p24~27
型より入れ型を破れ 書流とは何か //p28~29
型より入れ型を破れ 寛永三筆--本阿弥光悦/近衛信尹/松花堂昭乗 //p30~31
心にひびく書、安らぐ書 / 大岡信 ; 小松茂美 ; 森田子龍/p50~61
わが家の正月の書 須田剋太 白洲正子 梅原猛 岩崎巴人 俳韻津月杖 辻清明 藤田慎一郎
藤田吉香 安達瞳子 関牧翁 //p64~72
STARDUST 小清水漸の水中花 ベテランなるほどの味 現代彫刻五人展 渋い! 杢田たけを いよよ華やぐ須田寿 究極の細密 Vサインひとすじ “宵待草”がきこえる 今様室内画 地物 一閑張り 小泉淳作の風格 陶雲垂れこめる ミニ本の密かなヌード 素肌で勝負 スクリーンごしのサカイトシノリ 焼け跡を片付ける 黙した彫像 中西夏之の人気 シュネーズ流新聞の使い方 内藤礼の「黙示宮」 伊東敏光の蚤かエイリアンインド直輸入の仏伝レリーフ 皺のある風景 ロックからテンペラへ 第1回TOM賞 すっきりなった 紙を丸めてなぜ作品 追悼 山下菊二 追悼 オノサトトシノブ [中原佑介] / 渡辺隆次 ; ノーランド ; 斎藤真一 ; 松浦章博橿尾正次 ; 中村豊 ; 新妻実 ; 剣持和夫 ; 斎藤あきひこ ; 山領直人 ; 恒松正敏 ; 小山田二郎 ; 三谷巍/p80~86
WORLD シュナーベル二年振りの新作 ミロの彫刻大回顧展 新発見「北斎」の水彩画 生地での八大山人展 //p88~89
マーケット “初日の出”の値段 //p90~91
音のある仕事場(13)ベートーヴェン交響曲第七番 / 新宮晋/p110~111
西行(10)鴫立沢 / 白洲正子/p112~115
非公開ギリシアの聖域アトスを撮る / ゴラーズ・ヴィルハー/p116~125 |
7月、「禅文化 (125)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082321
|
版画 妙好人 浅原才市のことば(12) / 山田喜代春 / p91~94
宏智正覚の研究のこぼれ話 / 石井修道 / p27~40
東嶺禅師にみる白隠禅の真面目 / ミッシェル・モール / p41~54
カラーと文 インド私記 / 平野宗浄 / p20~26
禅定、それともパン?--インドにおける仏教復興運動 / 真継伸彦 / p11~19
虚堂録を読む(3) / 平田精耕 / p85~90
概説 日本禅宗史(4) / 竹貫元勝 / p55~76
アメリカにおけるD・T・鈴木 / カール・ジャクソン ; 多田稔 / p117~126
草庵の四季 朝茶 / 柳田静江 / p110~113
海清寺僧堂第四回禅蹟巡拝の旅 絵と文 祖師を恋う / 春見文勝 / p131~136 |
海清寺僧堂第四回禅蹟巡拝の旅 カラーと
→文 大〔ユ〕嶺に達す / 小倉賢堂 / p137~151
天竺の土 釈尊を偲ぶ印度国覊旅 / 青山康子 / p114~116
東漸禅窟の人--千崎如幻の生涯(6) / 藤本光城 / p95~106
謾説 同調者よりも批判者に、より懇切であれ / p108~109
いっぷく拝見 / p77~84
書灯 <既刊・新刊案内> / p152~153
『禅文化』 バックナンバー / p156~156
禅文化研究所の本 / p157~
編集後記 <蛇足> / p155~155 |
7月、水上勉が「一休・正三・白隠 : 高僧私記」を「筑摩書房」から刊行する。 (ちくま文庫)
9月19日~10月18日迄、富岡美術館に於いて「白隠の描く観音図 : 秋季展(前期)
」展が開かれる。
9月、富岡美術館編「白隠の描く観音図 : 秋季展(前期)」が「富岡美術館」から刊行される。
所蔵:京都府立京都学・歴彩館
10月、池田魯参が駒澤大学仏教学部研究室 編「駒沢大学仏教学部論集 = Journal of buddhist studies (通号 18) p.p435~443」に「山内舜雄著「禅と天台止観--坐禅儀と『天台小止観』との比較研究」を紹介する。
○、この年、佐藤政男, 弓削春穏 述,飯山市有線放送農業協同組合編「語り部の語るふるさと飯山 続 」が「ほおずき書籍」から刊行される。 pid/9540615
|
あふれるふるさと愛 飯山市教育長 浦野昌夫
序 飯山市有線放送農業協同組合長 牧野伊勢次郎
歴史
一 飯山事始め/4
(一)初めて「飯山」と書かれた古文書
(二)「飯山之内へちい」という所
(三)いいやまの語源考
(四)飯山城、岩井備中守信能に預けられる
(五)飯山町生みの親―岩井備中守信能
二 飯笠山神社と加佐郷の由来/19
三 本多氏と葵神社/23
四 奥信濃の文明開化/27
(一)マントルと銀時計
(二)断髪異開
(三)顔戸開成所
(四)はじめての新聞
五 寄宿舎もあった下水内高等小学校/35
六 二部制の下水内高等女学校/39
七 飯山~豊野間の乗り物の変遷/41
八 「善光寺地震」よもやまばなし/46
(一)飯島元町長の記録
(二)『信州善光寺大地震焼失水押之次第』
・
|
民俗・伝説
一 お城の正月/54
二 道陸神の火祭り/56
三 太田の大五輪塔と双体道祖神/60
四 今も伝わり残る庚申信仰/63
五 勇壮無比の富倉のヒャットウ/68
六 ふるさとの伝説/71
(一)桜井戸にまつわる歴史話
(二)桜井戸伝説
(三)広く伝わった「松山鏡」
(四) 鬼女紅葉退治伝説の背景
(五)「鬼女紅葉退治」伝説
七 おたや物語/88
(一)東本願寺派の説教所
(二)モミの木とおたやの井戸
(三)善光寺仁王様製作のアトリエ
八 雪に関する民話/96
九 常盤の民話「地蔵さんの恩返し」/99
自然・風土
一 参勤交代と飯山街道/104
二 親しまれている高社山/108
三 ガンギと中門のある民家/113
四 雪害をなくすために/117
|
五 飯山の乾期と火災/121
六 水内の湖はあったのか/124
七 温泉の話/128
八 天然ガスの話/132
九 千曲川の変遷と洪水の歴史/135
(一)大昔から川筋は動いていた
(二)死者一万人の寛保大洪水
(三)昭和五十七年にも大きな水害
人物誌
一 木曽義仲と志妻の小次郎/148
二 親鸞と蓮如―その史実と伝説/151
(一)布教の跡をたどって
(二)信越国境中心に伝えられた伝承
(三)磯部六か寺の由来
三 正受老人の一生/160
(一)十六歳で観音様の悟り
(二)江戸の無難禅師に弟子入り
(三)正受庵に住み親孝行
(四)手洗い石とツガの木
(五)白隠禅師の慢心へし折る
(六)八十歳、座禅を組んだまま遷化
四 藤村は飯山を二回訪れた/181
あとがき |
|
| 1988 |
63 |
・ |
1月、「在家佛教 37(426)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064091
|
特集 菩提とは 菩提心 / 高橋良和 / p7~9
特集 菩提とは 煩悩を具足して大涅槃に至る / 石田瑞麿 / p10~21
特集 菩提とは 菩提 / 村瀬玄妙 / p22~24
特集 菩提とは ブッダガヤーの大塔と菩提樹 / 金治勇 / p25~27
特集 菩提とは 佛弟子とは / 二橋進 / p28~35
白隠禅師「施行歌」拾い読み / 大下一真 / p50~54
塩焼の魚は生きている / 長沢武 / p56~61
沢庵禅師の生死観 / 鎌田茂雄 / p64~75
随縁自在(1)宇宙人への初だより / 松居桃樓 / p36~40
親鸞の世界(1) / 早島鏡正 / p44~48 |
佛教の現代的意義(六) / 玉城康四郎 / p82~87
東京のなかの寺(10)西新井大師 / 辻野透 / p76~81
加藤辨三郎・言葉抄 / p88~90
常不軽菩薩と良寛禅師 / 小松正衛 / p62~62
生きとし生けるもの / 松尾静明 / p63~63
佛教風物誌(13)加持祈祷 / p55~55
今月の表紙 / p43~43
協会の仕事案内 / p94~95
編集後記 / p93~93
・ |
2月、松ケ岡文庫編「公益財団法人松ケ岡文庫研究年報 = The annual report of researches of the Public Interest Matsugaoka Bunko Foundation (2) 」が「松ケ岡文庫」から刊行される。pid/4424617
|
敦煌本『壇経』、『曹渓大師伝』および初期禅宗思想 / 楼宇烈/p1~28
『伝法正宗記』諸本の系統 / 椎名宏雄/p29~59
条件句構成のウニハ続貂-松ヶ岡文庫蔵
→『無門関抄』を資料として/来田隆/p61~84 |
洞門抄物の発生とその性格 / 石川力山/p85~109
維摩経と西田哲学-Yamakaの論理について/橋本芳契/p111~134
白隠が沙羅樹下の老衲と成るまで / 古田紹欽/p135~141
・ |
3月、竹内尚次が駒沢宗教学研究会編「宗教学論集 = Journal of religious studies (通号 14) p.p161~184」に「「白隠和尚自画賛集」と東嶺和尚書入「荊叢毒蕊」および甲州巡錫三ケ寺について」を発表する。 重要
3月、荒井荒雄が「夜船閑話 : 白隠禅による健康法」を「大蔵出版」から刊行する。 (大蔵新書 ; 11)
6月、古岡滉が「財界forum 7(6)(154) p28~29 財界フォーラム」に「私が感銘を受けた本『坐禅和讃講話』」を発表する。pid/2885584
6月、村木弘昌が「白隠禅師『夜船閑話』に学ぶ丹田呼吸法」を「三笠書房」から刊行する。
7月、「禅文化 (129)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082325
|
百年前の大拙書翰(一) / 井上禅定/p89~108
野糞恵能 / 岩崎巴人/p7~20
虚堂録を読む「7」 / 平田精耕/p83~88
グラビア 寺宝探訪(17) 京都・慈照院(続)/p71~82
概説日本禅宗史(八) / 竹貫元勝/p21~47
相見--抱石先生 / 柳田静江/p114~118
俚謡・俚諺を賛した白隠の画 / 亀山卓郎/p48~70
仏教東漸史の断章〔十一〕鈴木大拙-
→東西の出会いの成就 / 多田稔/p133~149
|
言葉による対話と心の対話 / ピエール・ド・ベチュヌ/p127~132
書評 谷川敏朗編『良寛の書簡集』を手にして / 柳田聖山/p110~111
「謾説」 禅は大乗なのか小乗なのか/p112~113
いっぷく拝見/p119~126
書灯/p150~151
『禅文化』バックナンバー/p154~154
禅文化研究所の本/p155~157
編集後記〈蛇足〉/p153~153
・ |
12月24日、山田無文が亡くなる。(88歳)
12月、常盤義伸訳「大乗仏典 : 中国・日本篇 第27巻 白隠」が「中央公論社」から刊行される。
1988・12 /pid/12286412
息耕録開筵普説 息耕録評唱剰語 解説. 白隠略年譜・参考文献:p429~438 |
| 1989 |
64 |
・ |
1月、「在家佛教 38(439)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064104
|
特集 いのち 佛のおんいのち / 西川玄苔 / p7~9
特集 いのち ブッダのいのち / 玉城康四郎 / p10~21
特集 いのち 生命が成熟するということ / 吉野弘 / p22~24
特集 いのち 生かされる / 近田昭夫 / p26~34
対談 静坐のこころ / 柳田誠二郎 ; 石上善応 / p40~44
仮面の生涯 / 岩本泰波 / p48~57
随緑自在(1)本願に遇う / 竹下哲 / p36~39
佛たちのみすがた(1) / 西村公朝 / p60~63
随聞記の世界(完)まさしき功は坐にあるべし/水野弥穂子/p66~70
白隠 その生涯における思考と行動(1) / 古田紹欽 / p72~77
選択集略義(1)選択本願念佛ということ / 竹中信常 / p78~82 |
東京のなかの寺(22) 成田山深川不動 / 辻野透 / p84~89
佛教入門(1)佛教は「見方革命」である / ひろさちや / p90~95
歎異抄(1) / 加藤辨三郎 / p96~100
女性の宝 / 鳥居良禅 / p46~46
わが師櫻井鎔俊和上 / 百々海怜 / p47~47
佛教風物詩(25)蟻の熊野詣で / p71~71
今月の表紙 / p35~35
協会の仕事案内 / p64~65
在家佛教講演会案内 / p103~103
編集後記 / p102~102
・ |
2月、 「在家佛教 38(440)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064105
|
特集 凡夫について 人間は化物 / 金治勇 / p7~9
特集 凡夫について 凡夫という思想 / 田丸徳善 / p10~20
特集 凡夫について 凡を脱し聖に入る / 平井玄恭 / p21~23
特集 凡夫について 凡夫の宗敎 / 高橋弘次 / p24~30
隨縁自在(2) 自力からの解放 / 竹下哲 / p32~35
対談 いのちをみつめて いのちとは何か-医学の進歩によって現代人が
→問われているもの。 / 藤村志保 ; 石上善応 / p36~44
回想・金子大榮 / 伊東慧明 / p46~52
佛たちのみすがた(2) / 西村公朝 / p56~60
佛教と現代(7) / 玉城康四郎 / p80~85
白隠その生涯における思考と行動(2) / 古田紹欽 / p62~66 |
選択集略義(2)二門・二道のこと / 竹中信常 / p68~72
東京のなかの寺(23)元浅草誓教寺 / 辻野透 / p74~79
佛教入門(2)相手の立場に立てない / ひろさちや / p88~93
歎異抄(2) / 加藤辨三郎 / p94~98
耕田 / 中村昌道 / p54~54
信火ともれば善知識 / 橋本随暢 / p55~55
佛教風物誌(26)造寺・造塔 / p53~53
今月の表紙 / p31~31
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103 |
3月、「在家佛教 38(441)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064106
|
特集 生きること 生の依るところ / 金子大榮 / p7~9
特集 生きること 生きるということ / 杉靖三郎 / p10~20
特集 生きること 生きることと生かされること / 毛利孝一 / p22~24
特集 生きること 生きるために / 藤島建樹 / p26~35
特集 生きること 人生の法則 / 野上正行 / p52~57
髄縁自在(3)目ざめて生きる / 竹下哲 / p44~47
対談 韓国の仏教 / 洪潤植 ; 石上善応 / p36~42
佛たちのみすがた(3) / 西村公朝 / p48~51
佛教と現代(8) / 玉城康四郎 / p88~93
白隠(三) 遠羅天釜から夜船閑話へ(1) / 古田紹釿 / p58~62
選択集略義(3)二行・二業のこと / 竹中信常 / p66~70 |
東京のなかの寺(24)練馬 広徳寺 / 辻野透 / p72~78
佛教入門(3)こだわりなく見る / ひろさちや / p80~85
歎異抄(3) / 加藤辨三郎 / p94~98
聖典のことば 心を佛地に樹てる / 西谷恵光 / p64~64
わが善知識 親鸞一人がため / 長松時見 / p65~65
佛教風物誌(27)鳥羽離宮 / p63~63
今月の表紙 / p21~21
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103
・ |
4月、「在家佛教 38(442)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064107
|
特集 心の依りどころ みずからを灯す / 松原泰道 / p7~9
特集 心の依りどころ 自らを灯明とせよ / 平川彰 / p10~20
特集 心の依りどころ わが回想の島崎藤村 / 江原通子 / p21~23
特集 心の依りどころ 自灯明 / 松野純孝 / p24~26
特集 心の依りどころ 彼岸のこころ / 西村恵信 / p28~35
親鸞聖人の非の立場 / 池田勇諦 / p72~81
随縁自在4 目ざめて生きる 続 / 竹下哲 / p36~39
対談 東慶寺今昔 / 井上禅定 ; 石上善応 / p40~46
佛たちのみすがた 4 / 西村公朝 / p48~52
佛教と現代 9 / 玉城康四郎 / p82~86
白隠 四 遠羅天釜から夜船閑話へ 2 / 古田紹欽 / p66~70 |
選択集略義 4 本願力不思議 / 竹中信常 / p53~57
東京のなかの寺 25 深川 浄心寺 / 辻野透 / p88~88
佛教入門 4 ゴミ・欠点を肯定する / ひろさちや / p60~65
歎異抄 4 / 加藤辨三郎 / p94~98
一子地 / 石畠俊徳 / p58~58
七十年の善知識 / 大塚賢譲 / p59~59
佛教風物誌 28 寺院の庭 / p71~7
今月の表紙 / p27~27
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103 |
5月、「在家佛教 38(443)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064108
|
特集 大悲あまねく 俳人山頭火の佛心 / 大山澄太 / p7~9
特集 大悲あまねく 大悲弘く普く化す / 坂東性純 / p10~20
特集 大悲あまねく 大悲普く / 佐古純一郎 / p21~23
特集 大悲あまねく 衆生本来佛なり / 余語翠厳 / p24~29
特集 大悲あまねく 浄土の讃歌 / 名畑崇 / p30~36
宗教サミット / 葉上照澄 / p58~62
随縁自在(5)人生の方向を定めて / 竹下哲 / p38~41
対談 共生 / 佐橋慶 ; 石上善応 / p42~48
佛たちのみすがた(5) / 西村公朝 / p50~55
佛教と現代(10) / 玉城康四郎 / p76~80
白隠(5)遠羅天釜から夜船閑話へ(3) / 古田紹欽 / p64~68 |
選択集略義(5)念称是一と廃立義 / 竹中信常 / p70~74
東京のなかの寺(26)東上野源空寺 / 辻野透 / p82~87
佛教入門(5)差別をするな! / ひろさちや / p88~93
歎異抄(5) / 加藤辨三郎 / p94~97
有無超越 / 川口定光 / p56~56
泉下の旧友 / 小笠原隆元 / p57~57
佛教風物詩(29)顕教と密教 / p55~55
今月の表紙 / p99~99
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103 |
6月、「在家佛教 38(444)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064109
|
特集・人間性とは 人間-この尊く不思議なるもの / 平沢興 / p7~9
特集・人間性とは 人間としての釈尊 / 中村元 / p10~19
特集・人間性とは 人間 / 高史明 / p20~22
特集・人間性とは 諸悪莫作 / 奈良康明 / p24~36
他力による目覚めと苦の克服 / 奈倉道隆 / p52~60
随縁自在6 二十一世紀への贈り物I / 竹下哲 / p38~41
対談 善光寺物語 / 鷹司誓玉 ; 石上善応 / p42~48
佛たちのみすがた6 / 西村公朝 / p62~65
佛教と現代11 / 玉城康四郎 / p88~92
白隠六 遠羅天釜から夜船閑話へ4 / 古田紹欽 / p71~75
選択集略義6 一念大利無上功徳 / 竹中信常 / p66~70 |
東京のなかの寺27 田端 大龍寺 / 辻野透 / p76~81
佛教入門6 悪人であることの自覚 / ひろさちや / p82~87
歎異抄6 / 加藤辨三郎 / p94~98
大安慰 / 橘感月 / p50~50
すべてが善知識 / 中村啓識 / p51~51
佛教風物誌30 聖人と上人 / p61~61
今月の表紙 / p23~23
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛敎講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103
・ |
7月、「在家佛教 38(445)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064110
|
特集 自在の世界 無の自在 / 余語翠厳 / p7~9
特集 自在の世界 自在の風光 / 鎌田茂雄 / p10~20
特集 自在の世界 自在 / 田辺和子 / p22~25
特集 自在の世界 いのちの念佛 / 早島鏡正 / p40~50
随縁自在7 二十一世紀への贈り物II / 竹下哲 / p26~29
対談 衆生とともに / 藤本幸邦 ; 石上善応 / p30~37
佛たちのみすがた7 / 西村公朝 / p68~71
佛教と現代完 / 玉城康四郎 / p84~92
白隠七 遠羅天釜から夜船閑話へ5 / 古田紹欽 / p72~76
選択集略儀7 光明遍照十方世界 / 竹中信常 / p60~64 |
大阪のなかの寺1 四天王寺 / 友田俊治 / p78~82
佛教入門7 感謝のこころを持とう / ひろさちや / p54~59
歎異抄7 / 加藤辨三郎 / p94~98
自然法爾 / 恒吉静雄 / p66~66
葉上照澄阿闍梨 / 樫田瑞元 / p67~67(
佛教風物誌 31 ヘレニズムと佛教 / p53~53
今月の表紙 / p39~39
協会の仕事案内 / p100~100
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103 |
7月、 「日本仏教学会年報 = The journal of the Nippon Buddhist Research Association (54) 」が「日本仏教学会 日本仏教学会西部事務所」から刊行される。 pid/4417648
|
仏道の体系/p1~412,1~106
仏道体系の反省と創造 / 玉城康四郎/p1~19
仏道の体系より証道の施設へ / 長谷部幽蹊/p21~45
無量寿経類における仏道の体系 / 香川孝雄/p47~64
初期仏教における「念仏」の体系について / 徳岡亮英/p65~87
如来蔵 アーラヤ識説の成立根拠--悟りの原理と
→迷いの原理の自己同一性 / 久保田力/p89~107
宗密における仏道の<体系化>--儒道二教の組込み方を
→中心として / 木村清孝/p109~121
天台学の教観の体系化について / 池田魯參/p123~136
五大院安然における台密の体系 / 三崎良周/p137~154
最澄における仏道の体系--天台智頭と比較して / 清田寂雲/p155~167
道綽の聖浄二門判の基盤 / 小倉求/p169~181
法然浄土教の実践体系とその内実 / 藤堂恭俊/p183~195
親鸞における仏道の体系--教判論の
→基底について / 山崎龍明/p197~211
親鸞の仏道体系--如来の誓願と「行信」 / 三明智彰/p213~226
親鸞聖人に於ける仏道の体系 / 徳永大信/p227~234
浄土真宗における仏道の体系 / 仲尾俊博/p235~249
親鸞における仏道 / 紅楳英顕/p251~266
白隠禅に於ける修道体系の性格-
→『宗門無尽灯論』をめぐって/西村惠信/p267~281 |
『正法眼蔵』に基づく仏道の体系(1)
→「正伝」の仏道 / 東隆眞/p283~297
道元禅の体系 / 原田弘道/p299~313
中世京都日蓮教団の機構 / 糸久宝賢/p315~324
仏道の体系と瑜伽の階梯--
→<菩提心修習>に関連して / 生井智紹/p325~352
アティシャにおける仏道の体系 / 矢崎正見/p353~370
現代スリランカ仏教徒の仏教受容体系 / 神谷信明/p371~381
古ウパニシャッドにおける実践の問題--内観によるアートマンの
→認識に到る道 / 細田典明/p383~397
大乗菩薩道への視点 / 瓜生津隆真/p399~412
現代スリランカの仏道と戒律--Katik vata制定の
→背景 / 橘堂正弘/p95~72
ツォンカパにおける仏道体系 / ツルティム・ケサン/p73~58
ダルマキールティにおける仏道 / 稲見正浩/p59~42
種子の本有と新熏の問題について / 山部能宜/p43~31
瑜伽行派の仏道体系の基軸をめぐって(1) / 阿理生/p29~
初期仏教における業の消滅 / 榎本文雄/p1~1
彙報 //p413~424
日本仏教学会会則 //p425~426
日本仏教学会会員名簿 //p107~166
・ |
7月、「空 : 禅と健康と創造性 No.41 特集白隠の生涯」が「日本仰臥禅協会」から刊行される。 所蔵:岐阜県図書館
8月、「在家佛教 38(446)」が「在家仏教協会」から刊行される。pid/6064111
|
特集 道理 自然法爾の医学 / 村尾勉 / p7~9
特集 道理 水は下りさまに流る / 藤吉慈海 / p10~15
特集 道理 日本的なるもの / 源淳子 / p16~19
特集 道理 心そのままが佛 / 田上太秀 / p20~28
特集 道理 人は何で生きるか / 川畑愛義 / p48~58
随縁自在(8)大肯定の生活 / 竹下哲 / p30~33
対談 肖像彫刻のことなど/橋本堅太郎 ; 石上善応/p34~40
佛たちのみすがた(8) / 西村公朝 / p42~45
華厳経入門(1)『華厳経』のあらまし / 木村清孝 / p84~89
白隠(八)遠羅天釜から夜船閑話へ(6) / 古田紹欽 / p60~64
選択集略義(8)三心のこと / 竹中信常 / p66~70 |
大阪のなかの寺(2)勝鬘院・愛染堂 / 友田俊治 / p72~76
佛教入門(8)ほんのちょっと余裕を / ひろさちや / p78~83
歎異抄(8) / 加藤辨三郎 / p94~98
古寺拝観の旅と故理事長 / 露崎寿朗 / p90~93
汝等比丘 / 竹内万成 / p46~46
一冊の本 / 松尾静明 / p47~47
佛教風物誌(32)大月氏国と安息国 / p41~41
今月の表紙・ガンジス河 / p29~29
協会の仕事案内 / p100~101
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p103~103 |
9月、「在家佛教 38(447)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064112
|
特集 生死を超える 生死を超える / 井伊文子 / p7~9
特集 生死を超える 生死 / 平川彰 / p10~1
特集 生死を超える 超える / 平田博永 / p18~21
特集 生死を超える 念佛の心がまえ / 水谷幸正 / p22~31
特集 生死を超える 「白い道」に聞く / 金石晃陽 / p50~57
随縁自在9 倶会一処 / 竹下哲 / p32~35
対談 祇園精舎を発掘して / 網干善教 ; 石上善応 / p36~42
佛たちのみすがた9 / 西村公朝 / p44~48
華厳経入門2 「華劇経」のあらまし / 木村清孝 / p68~72
白隠九 「宝鑑貽照」を著わす7 / 古田紹欽 / p80~85
選択集略義9 白道を歩む / 竹中信常 / p74~78 |
大阪のなかの寺3 北野大融寺 / 友田俊治 / p60~64
佛教入門9 生かされているわたし / ひろさちや / p88~93
歎異抄9 / 加藤辨三郎 / p94~98
無碍の光 / 貞包哲朗 / p58~58
江部鴨村師 / 吉田国広 / p59~59
佛教風物誌33 オアシス都市 / p67~67
今月の表紙・カピラ城址 / p87~87
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~10
・ |
10月、「在家佛教 38(448)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064113
|
特集 彼岸への道 この舟の水を汲めかし / 江原通子 / p7~9
特集 彼岸への道 ひと日ひと日の往生 / 岩本泰波 / p10~21
特集 彼岸への道 彼岸と四聖諦 / 井上善右衛門 / p22~25
特集 彼岸への道 自己に遇う / 島崎光雄 / p26~32
行基のはなし / 平岡定海 / p54~61
随緑自在(10)二重戸籍の住人 / 竹下哲 / p34~37
対談 正法に不思議なし / 嶋野榮道 ; 石上善応 / p40~46
佛にちのみすがた(10) / 西村公朝 / p48~51
華厳経入門(3)「華厳」の意味 / 木村清孝 / p82~86
白隠 『息耕録開莚普説』から『槐安国語』まで(1)/古田紹欽/p76~81
選択集略義(10)人中の芬陀利華 / 竹中信常 / p70~74 |
大阪のなかの寺(4)崇禅寺 / 友田俊治 / p64~68
佛教入門(10)恩を知った人間 / ひろさちや / p88~93
歎異抄(10) / 加藤辨三郎 / p94~98
不断煩悩得涅槃 / 村木茂 / p62~62
一偈 / 近藤喜一郎 / p63~63
佛教風物誌(34)中国初伝 / p53~53
今月の表紙・白象降下 / p39~39
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~101
・ |
11月、「在家佛教 38(449)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064114
|
特集 佛の世界 佛の世界は闇の中 / 小倉玄照 / p7~9
特集 佛の世界 大日如来の世界 / 勝又俊教 / p10~19
特集 佛の世界 人情的佛の世界」 / 佐藤密雄 / p20~23
特集 佛の世界 人となる道 / 西川玄苔 / p24~30
特集 佛の世界 禅と念佛 / 清成昭典 / p46~51
特集 佛の世界 随縁自在 11 如来と等しい人 / 竹下哲/p32~35
特集 佛の世界 対談 ブッダの道 / 丸山勇 ; 石上善応/p36~42
特集 佛の世界 佛たちのみすがた11 / 西村公朝 / p54~58
特集 佛の世界 華厳経入門4 思想のポイント/木村清孝/p82~86
特集 佛の世界 白隠十一 『息耕録開筵普説』から
→『槐安国語』まで2 / 古田紹欽 / p70~75 |
特集 佛の世界 選択集略儀11 念佛の永遠性 / 竹中信常 / p64~68
特集 佛の世界 大阪のなかの寺5 平野大念佛寺 / 友田俊治 / p76~80
特集 佛の世界 佛教入門11 預っている「自分」 / ひろさちや / p88~93
特集 佛の世界 歎異抄11 / 加藤辨三郎 / p94~98
特集 佛の世界 善人・悪人 / 和田隆 / p61~61
特集 佛の世界 一字一句 / 阿部英雄 / p62~63
特集 佛の世界 佛教風物誌35 東伝余語 / p53~53
特集 佛の世界 今月の表紙・舎衛城より祇園精舎を望む / p45~45
特集 佛の世界 協会の仕事案内 / p102~102
特集 佛の世界 在家佛教講演会案内 / p104~104
特集 佛の世界 編集後記 / p101~101 |
11月、河野太通が「白隠禅師坐禅和讃を読む」を「佼成出版社」から刊行する。 (仏教文化選書)
|
1 坐禅和讃のこころ
2 迷いの闇路 |
3 すべてが帰するもの
4 自覚のすすめ |
5 自由への飛翔
6 喜びの歌 |
|
12月、「 在家佛教 38(450)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064115
|
特集 この世の利益 「ため」からの脱却 / 余語翠巖 / p7~9
特集 この世の利益 火宅の利益自然なる / 山崎龍明 / p10~21
特集 この世の利益 無功徳 / 鎌田茂雄 / p22~25
特集 この世の利益 心身の安らぎをうるために / 伊原照蓮 / p26~32
宿業に生きる / 野田風雪 / p54~61
随縁自在(完)願いに生きる / 竹下哲 / p34~37
対談 韓国の佛教 / 黄寿永 ; 石上善応 / p38~44
佛たちのすみがた(完) / 西村公朝 / p48~51
華厳経入門(5)佛のさとりの場 / 木村清孝 / p82~86
白隠(十二)『息耕録開筵普説』から『槐安国語』まで(三)/吉田紹欽/p68~73
選択集略義(完)窓前に遺すこと莫れ / 竹中信常 / p74~79 |
大阪のなかの寺(6) 伝法正蓮寺 / 友田俊治 / p62~66
佛教入門(12)佛教者らしい祈り / ひろさちや / p88~93
難異抄(12) / 加藤耕三郎 / p94~98
不生不滅 / 山本文渓 / p52~52
足利浄円先生 / 西村侃二 / p53~53
佛教風物誌(36)舎利塔・頭塔 / p81~81
今月の表紙 ブッダガヤー大塔夕景 / p47~47
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~101
・ |
○、この年、日本仏教学会編「仏道の大系」が「平楽寺書店」から刊行される。
|
仏道体系の反省と創造 / 玉城康四郎著
仏道の体系より証道の施設へ / 長谷部幽蹊著
無量寿経類における仏道の体系 / 香川孝雄著
初期仏教における「念仏」の体系について / 徳岡亮英著
如来蔵=アーラヤ識説の成立根拠 / 久保田力著
宗密における仏道の 体系化 / 木村清孝著
天台学の教観の体系について / 池田魯參著
五大院安然における台密の体系 / 三崎良周著
最澄における仏道の体系 / 清田寂雲著
道綽の聖浄二門判の基盤 / 小倉求著
法然浄土教の実践体系とその内実 / 藤堂恭俊著
親鸞における仏道の体系 / 山崎龍明著
親鸞の仏道体系 / 三明智彰著
親鸞聖人に於ける仏道の体系 / 徳永大信著
浄土真宗における仏道の体系 / 仲尾俊博著
親鸞における仏道 / 紅楳英顕著 |
白隠禅に於ける修道体系の性格 / 西村惠信著
『正法眼蔵』に基づく仏道の体系 / 1東隆眞著
道元禅の体系 / 原田弘道著
中世京都日蓮教団の機構 / 糸久宝賢著
仏道の体系と瑜伽の階梯 / 生井智紹著
アティシャにおける仏道の体系 / 矢崎正見著
現代スリランカ仏教徒の仏教受容体系 / 神谷信明著
古ウパニシャッドにおける実践の問題 / 細田典明著
大乗菩薩道への視点 / 瓜生津隆真著
現代スリランカの仏道と戒律 / 橘堂正弘著
ツォンカパにおける仏道体系 / ツルティム・ケサン著
ダルマキールティにおける仏道 / 稲見正浩著
種子の本有と新熏の問題について / 山部能宜著
瑜伽行派の仏道体系の基軸をめぐって / 1阿理生著
『アビダルマディーパ』における仏道の体系 / 三友健容著
初期仏教における業の消滅 / 榎本文雄著 |
○、この年、出光美術館編「出光美術館館報 67」が「出光美術館 」から刊行される。
|
トルコ共和国アタチュルク国際平和賞授与式における謝辞
三笠宮崇仁/著,白隠とその書画 |
古田紹欽/著,『出光コレクションによる日本陶磁展』報告,
→昭和63年度事業報告 |
|
| 1990 |
平成2年 |
・ |
1月、「在家佛教 39(451)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064116
|
特集 真実の世界 佛の慈悲を見落すな / 長澤武 / p7~9
特集 真実の世界 畏れのないこと / 玉城康四郎 / p10~20
特集 真実の世界 方便と真実 / 塚本啓祥 / p22~25
特集 真実の世界 日日是れ好日 / 西川玄苔 / p26~31
特集 真実の世界 まことの眼 / 大須賀発蔵 / p32~42
行基とその時代 / 田村圓澄 / p70~75
この人と一時間 道、天地に通ず / 千地琇也 / p50~56
講座佛教(1)原始佛教入門 / 阿部慈園 / p44~48
華厳経入門(6)ヴァイローチャナ佛の世界 / 木村清孝 / p82~86
白隠(13)『寒山詩闡提記聞』を読む上 / 古田紹欽 / p58~63 |
親鸞・道元(1)罪悪深重 / 岩本泰波 / p64~68
大阪のなかの寺(7)あみだ池 和光寺 / 友田俊治 / p76~80
佛教入門(13)「あきらめ」の哲学 / ひろさちや / p88~93
歎異抄(13) / 加藤辨三郎 / p94~98
佛教風物誌(37)卒塔婆から五重塔へ / p49~49
今月の表紙・ガンダーラの佛陀禅定の像 / p21~21
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~101
・ |
1月、法蔵館編「仏教 (10) 」が「法蔵館」から刊行される。 pid/2256260
|
山河の親切――わたしの参禅記 / 岩田慶治/p2~6
わが参禅記――キリスト教との対話 / 門脇佳吉/p7~12
八海山――装丁紀行 / 司修/p13~14
禅と「日本禅」 / 加藤周一 ; 山折哲雄/p16~38
機縁 / 上田閑照/p40~43
身心論――禅修行における心と身体 / 松本晧一/p44~51
大安心をサイエンスする / 中山正和/p53~62
禅の言説戦略 / 橋爪大三郎/p63~68
禅についての禅的考察 / 池田晶子/p69~76
ユングと『十牛図』 / 秋山さと子/p78~85
修行ということ / 沖本克己/p86~91
坐禅の大脳生理学 / 平井富雄/p92~99
禅と身体――宗教の解剖学(七) / 養老孟司/p100~108 |
達磨神話と歴史性 / 田上太秀/p110~118
道元の身心脱落体験を解読する / 東隆真/p119~127
日本人の原像――良寛さんの旅 / 栗田勇/p129~135
上向く「大拙」と下向く「寸心」 / 西村恵信/p143~148
ここに仏者あり――西谷啓治先生のこと / 海野マーク/p149~154
白隠禅と現代 / 平田精耕/p156~162
盤珪禅――「不生の仏心」を生きる / 秋月龍珉/p163~169
ヨーロッパ禅の試み / 宝積玄承/p174~179
道元参究――現代における道元学の系譜 / 石井修道/p180~186
古典ゼミ・仏教のありか/p136~142
Book Review/p171~173
写真提供 禅文化研究所/p39~39,p52~52,p77~77,p109~109,
→p128~128,p155~155,
|
2月、「在家佛教 39(452)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064117
|
特集 佛の智慧 佛の智慧 / 松野純孝 / p7~9
特集 佛の智慧 佛智の世界に生きる / 早島鏡正 / p10~19
特集 佛の智慧 衣裏?珠 / 横山邦雄 / p20~28
特集 佛の智慧 人間の救いなき状況 / 小林博聞 / p30~36
特集 佛の智慧 釈尊の遺された教え / 前田恵學 / p38~46
この人と一時間 忘己利他 / 山田恵諦 / p48~56
講座佛教(2)佛教の歩み(上) / 山口恵照 / p60~64
華厳経入門(7)光の家にて / 木村清孝 / p90~94
白隠(14)『寒山詩闡提記聞』を読む中 / 古田紹欽 / p72~77
親鸞・道元(2)諸悪莫作 / 岩本泰波 / p66~70 |
大阪のなかの寺(8)黄檗宗 鉄眼寺 / 友田俊治 / p78~82
佛教入門(14)彼岸に渡る / ひろさちや / p84~89
歎異抄(14) / 加藤辨三郎 / p96~100
諸悪莫作 / 田中孝 / p58~58
人の縁 / 斎藤敬 / p59~59
佛教風物誌(38)陰陽五行説 / p37~37
今月の表紙 クシナガラの涅槃堂 / p29~29
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~101 |
3月、「在家佛教 39(453)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064118
|
特集 いのちに遇う いのちの帰趣 / 井上善右ヱ門 / p7~9
特集 いのちに遇う またいただいた命 / 毛利孝一 / p10~21
特集 いのちに遇う いのちに遇う / 竹下哲 / p22~32
特集 いのちに遇う いのちについて / 松原泰道 / p34~36
特集 いのちに遇う 佛教の生死観 / 藤田宏達 / p38~47
この人と一時間 聖徳太子と六十余年 / 花山信勝 / p56~63
講座佛教(3)佛教の歩み(下) / 山口恵照 / p50~55
華厳経入門(8)菩薩の実践 / 木村清孝 / p82~86
白隠(完)『寒山詩闡提記聞』を読む 下 / 古田紹欽 / p70~75
親鸞・道元(3)諸悪莫作 / 岩本泰波 / p64~68 |
大阪のなかの寺(9)聖天山正圓寺 / 友田俊治 / p76~80
佛教入門(15)すべてを「空」と見る / ひろさちや / p88~93
歎異抄(15) / 加藤辨三郎 / p94~98
易往無人 / 鎌田健 / p48~48
南原繁先生 / 橋本寛 / p49~49
佛教風物誌(39)石窟寺院 / 路 / p81~81
今月の表紙 霊鷲山への道 / p33~33
協会の仕事案内 / p102~
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / S / p101~101 |
5月、禅文化研究所編「禅文化研究所紀要 = Annual report of the Institute for Zen Studies (16) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/4414926
|
白隠慧鶴の「隻手音声」を『遠羅天釜』と『洞山五位頌』とに聞く / 常盤義伸/pp1~25
真実在の探究--「種の論理」と「場所の論理」をめぐって / 川村永子/pp27~53
ポストモダンの思惟 / 石井誠士/pp55~93
西田幾多郎の経験--西田哲学の宗教的性格についての試論-1- / 山田邦男/pp95~130
青年久松真一の危機と師西田幾多郎--心理学的考察 / 村本詔司/pp131~165
白居易詩における老荘と仏教--その「長慶集」から「後集」以後への変化について / 下定雅弘/pp167~193
舎利信仰と僧伝におけるその叙述--慧洪「禅林僧宝伝」叙述の理解のために / 西脇常記/pp195~221
黄竜慧南の臨済宗転向と〔ロク〕潭懐澄--附論「宗門〔セキ〕英集」の位置とその資料的価値
/ 西口芳男/pp223~250
遺民僧晦山戒顕について / 野口善敬/pp251~274
新羅円光「世俗五戒」の思想的背景 / 中島志郎/pp275~300
退耕行勇とその門流について / 中尾良信/pp301~326 |
8月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 67(7)(794)」が「中央仏教社」から刊行される。 pid/7885669
|
『伝光録』入門(35) / 東隆真/p3~6
人間観自在菩薩(22) / 野中日文/p7~10
陽田寺便り / 飯塚定香/p11~11
『正三』の読み方・生かし方(7) / 鳥居祖道/p12~17 |
禅語カレンダー/p18~19
『禅とイエス・キリスト』を読む / 木村清一/p20~25
洞上五位偏正口訣/p26~33
「場所的論理と宗教的世界観」について(5) / 中山延二 ; 本多正昭/p34~45 |
11月、西村恵信が「白隠入門 : 地獄を悟る」を「法蔵館」から刊行する。
|
内容説明:徳川時代中期、衰弱の途にある日本臨済禅を復興し、「五百年間出」の人とよばれた傑僧・白隠。烈しい修行の末に見性悟得したその境地を、数多くの和讃や仮名法語につづり、民衆教化の一方、雲水育成にも尽力した生涯を、現代の臨済禅をになう著者が平易にまとめあげた一冊。 |
|
第1章 白隠の前半生
第2章 白隠のことばと心(菩薩の利他行;坐禅のすすめー 「坐禅和讃」;勇猛精進の道を行く;病床の友へ)
『夜船閑話』私訳 「BOOKデータベース」 より |
○、この年、大島建彦編「大黒信仰」が「雄山閣出版 1990 (民衆宗教史叢書,
第29巻)
|
大黒・夷二福神並祀の由来 : 夷神と三郎殿との混同 :
→大黒と夷神との入替り / 喜田貞吉
大黒神像の変遷 / 喜田貞吉 [
大黒神考 / 喜田貞吉
大黒天再考 / 長沼賢海
大黒天神信仰 / 宮崎英修
マノフィカ(Manofica) : 印相と大黒天 / 西岡秀雄
大黒天 / 及川大渓
福神 : えびす・大黒 / 大護八郎
|
千秋万歳と大黒舞 : 附猿舞わし : 正月の門づけ / 岩橋小弥太
福神狂言の形成 / 金井清光
中国地方に於ける大黒巡遊 / 勝部正郊
恵比寿・大黒・福の神 / 宮田登
宮城県の農耕儀礼の一考察 : 大根をめぐる伝承を中心として / 杉山晃一
大黒さまの「かるいひも」 / 佐藤満洋
大黒様 / 小野重朗
大黒信仰研究の成果と課題 / 大島建彦 |
|
| 1991 |
3 |
・ |
2月、春見文勝が「坐禅和讃法話 : 白隠禅師」を「春秋社」から刊行する。
|
1段 衆生本来仏なり、水と氷の如くにて
2段 衆生近きを知らずして、遠く求むるはかなさよ
3段 夫れ摩訶衍の禅定は、称嘆するに余りあり
4段 一坐の功を成す人も、積みし無量の罪ほろぶ |
5段 況や自ら廻向して、直に自性を証すれば
6段 因果一如の門ひらけ、無二無三の道直し
7段 この時何をか求むべき、寂滅現前する故に
「BOOKデータベース」 より |
3月、花園大学文学部編「花園大学研究紀要 (23)」が「花園大学文学部」から刊行される。pid/1764430
|
今まで歩いてきた道 / 入矢義高 / p1
倫理と宗教の関係の問題--絶対無の視点において/川村永子/p15
中世後期における曹洞宗と臨済宗 / 中尾良信 / p39
白隠慧鶴の「偏正回互秘奥」理解と「隻手音声」公案/常盤義伸/p63 |
伊藤若冲と曽我蕭白をめぐる禅僧 / 加藤正俊 / p115
「沙門良寛--自筆本『草堂詩集』を読む」柳田聖山/北川省一/p147
「日本禅宗史」竹貫元勝 / 上田純一 / p154
・ |
4月、「企画展 白隠禅師 [パンフレット] : 鹿島町立歴史民俗資料館入館のしおり」を「八束郡鹿島町立歴史民俗資料館」が刊行する。
1枚(2折) ; 26×37cm(折りたたみ26cm)
5月、「日本仏教学会年報 = The journal of the Nippon Buddhist Research Association (56)」が「日本仏教学会 日本仏教学会西部事務所」から刊行される。 pid/4417650
|
仏教と女性/p1~283,1~64
説話文学の仏教と女性 / 渡邊守順/p1~14
『死霊解脱物語聞書』の研究 / 関山和夫/p15~28
法然上人の女人往生論 / 福原隆善/p29~42
親鸞における女人成仏の問題 / 安藤文雄/p43~57
親鸞の女性観--著作にみる女性の往生・
→成仏の問題 / 栗原広海/p59~78
道元禅師の比丘尼・女人観 / 吉田道興/p79~96
日蓮聖人の女性観 / 桑名貴正/p97~111
日蓮聖人と女性信徒 / 渡辺宝陽/p113~125
仏教の性差別 大無量寿経三十五願の
→フェミニズムからの解釈 / 菱木政晴/p127~140
真宗と性差別 / 尾畑文正/p141~152
白隠と女性 / 常盤義伸/p153~166
韋提別選の正意 / 浅井成海/p167~183
法華経における女性 / 苅谷定彦/p185~200
『瑜伽師地論』菩薩地における女人成仏の構造について
|
→--階位説との関連において / 清水海隆/p201~211
生命体としての宇宙--マンダラと元型「母」 / 立川武蔵/p213~227
シンポジウム『仏教と女性』 //p229~283
基調報告 仏教におけるフェミニズムと
→アンティフェミニズム / 梶山雄一/p240~246
基調報告 女性論一般 / 古橋エツ子/p247~251
基調報告 仏教と女性差別 / 源淳子/p251~258
基調報告 仏教と女性 / 前田恵学/p258~265
Sujata-vyakarana / 藤村隆淳/p55~64
『律経』にみる触女学処 / 中川正法/p43~54
南インドの文化・社会における女性と女神の問題(序) / 山下博司/p27~41
インド思想にあらわれた女性の譬喩 / 石飛道子/p15~25
インド古典演劇論における8種のヒロイン / 上村勝彦/p1~13
彙報 //p285~299
日本仏教学会会則 //p300~301
日本仏教学会会員名簿 //p65~125
・ |
9月、「在家佛教 40(472)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064137
|
特集 人間の願い 人間の願い / 中村元 / p10~23
特集 人間の願い 人間の願い / 森本和夫 / p7~9
特集 人間の願い 人間の願いと大悲の願い / 小野蓮明 / p24~26
特集 人間の願い 人間の願い / 源淳子 / p27~29
特集 人間の願い 不請の友 / 西川玄苔 / p30~37
特集 人間の願い ある石工の話 / 辻野透 / p38~40
法然上人 / 田村圓澄 / p42~53
龍澤僧堂清話(上) / 中川球童 ; 阿部英雄 / p54~64
大乗佛教のこころ(9)禅宗 / 平川彰 / p90~94
臨濟録物語(5) / 中村文峰 / p84~88 |
禅僧の風光(9)白隠慧鶴 / 鎌田茂雄 / p72~76
日本佛教の背景(9)安土・桃山・江戸時代 I / 坂本正仁 / p66~70
福岡の寺(9)幻住庵 / 那須博 / p78~82
浄土和讃(11) / 加藤辨三郎 / p96~100
二人の高僧(11)良忍・明遍 / p71~71
今月の表紙・佛足石 / p65~65
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / 藤田宏達 / p104~104
編集後記 / p101~101
・ |
|
| 1992 |
4 |
・ |
1月、杉全泰写真 ; 野木昭輔文による「白隠を歩く」が「佼成出版社」から刊行される。 (写真紀行日本の祖師 )
3月、重松宗育が花園大学文学部編「花園大学研究紀要 (24) p241」に「「白隠入門」西村恵信」を紹介する。pid/1764431
4月、 「在家佛教 41(479)」が「在家仏教協会」から刊行される。 pid/6064144
|
特集・大いなる悲しみ 大悲の願船 / 早島鏡正 / p16~28
特集・大いなる悲しみ 大悲 / 石田瑞麿 / p8~11
特集・大いなる悲しみ 不在する大悲 / 源淳子 / p12~15
特集・大いなる悲しみ 白隠禅師の健康法 / 中村文峰 / p30~39
特集・大いなる悲しみ 空也の痩せ / 辻野透 / p40~42
大平記と東大寺 / 平岡定海 / p54~63
風雪抄(4) 人のこころ(下) / 常磐井堯祺 / p44~53
大東佛教のこころ(16) 一体三宝と別相三宝 / 平川彰 / p88~93
佛教伝来(4) 托鉢のブッダ / 上原和 / p70~75 |
天台宗の思想と実践(1) / 木内堯央 / p64~69
心の影--青春日記(4) / 金子大榮 / p76~81
福岡の寺(16) 善導寺 / 那須博 / p82~86
浄土和讃(18) / 加藤耕三郎 / p94~99
民俗信仰(3) 自然神・人間神 / 路 / p87~87
今月の表紙 ・バングラデシュの佛塔 / p29~29
協会の仕事案内 / p102~103
在家佛教講演会案内 / p104~104
編集後記 / p101~101 |
4月、「自治実務セミナー 31(4)(358)」が「第一法規株式会社」から刊行される。 pid/2827381
|
巻頭言――政治に活力を / 降矢敬義
入門講座――続・自治体行政学入門(61)町村と国土(4)/大森彌/p2~5
随想――麦を潰す / 岸康彦/p36~36
政策づくりセミナー――政策の構想と法務(その4) / 河中二講/p16~17
実務と理論 //p6~15,37~37,58~61
市は一般会計で駐車場を整備・運営してよいか―公営企業の限界/p6~7
市の清掃局は処理の困難さを理由として廃棄消火器の収集・
→処分を拒否できるか――市町村の廃棄物処理責任/p8~9
懲戒免職の審査請求中に市議会に当選した市職員は免職処分が
→取り消された場合給与請求権を有するか――
→懲戒免職処分係争中の立候補の届出 //p10~11
一定区域内に営業用ビルの立地を希望する者から企業立地協力金を募る旨の
→開発要綱を作成することができるか――寄附をめぐる問題 /p12~13
選挙期間中に立候補者が戸別に選挙騒音の謝罪挨拶を
→行うことができるか――戸別訪問類似行為の禁止 //p14~15
弁護士月記(17)――プリペイドにみる行政の効率化 / 橋本勇/p37~37
新・自治の常識(34) //p58~61
特別講座――地域経営における行政の機能と効果(95)
→地域経営の基本問題(つづき) //p38~41
教養講座――3大都市圏・私鉄比較(2・完) / 昇秀樹/p42~45
|
体験的地方自治論(68)生活大国の実現(2) / 久世公堯/p46~49
地域リポート(20)にっぽんのいいとこ和歌山県 / 有岡宏/p50~53
実務講座 //p18~35
地域政策――地域づくり関連施策 //p18~19
地域政策――特殊地域の振興(5) / 澤田史朗/p20~22
企画――これからの公立文化ホール(3・完) / 橋本博己/p23~24
土地対策――土地開発基金 / 吉川浩民/p26~29
災害対策――被災者に対する救済援助措置 / 古賀浩史/p30~31
人事管理――完全週休二日制の導入 / 滝川伸輔/p32~35
実務演習 //p54~57
地方行政――条例制定請求代表者証明書 / 寺田文彦/p54~55
地方行政――スポーツ振興基金 / 加藤雅広/p56~57
セミナー資料室――連邦制と道州制(45) / 小西敦/p62~65
受験チャネル――地方税(24)地方たばこ税 //p66~68
景気の視点(1)景気動向指数(D.I.) //p69~69
書評――都市づくり条例の諸問題(成田頼明編著) //p25~25
自治の潮 //p70~72
白隠禅師の夜船閑話 //p70~71
バイオ芝生の研究開発 //p70~71
遺伝子とパチンコ //p71~72 |
4月、荒井荒雄が「白隠禅 : 死の準備教育」を「大蔵出版」から刊行する。
7月、「 労働衛生 33(7)(388) 労働省労働基準局安全衛生部 監修 中央労働災害防止協会
1992-07p/pid/2243656/1/1
|
OPINION'92薬のあゆみ / 宮崎利夫/p6~7
特集 働く女性の健康管理/p8~8
(FART1)座談会「今,なにをすべきか?女性が求める職場像」 / 川辺ヒロ子 ; 小西勝己 ; 斎藤知子 ; 箕輪尚子 ; 皆川洋二/p9~21
(PART2)提言「新しい職場内での“Women's Health Care"」 / 堀口文/p22~25
歴史に学ぶ健康の知恵 白隠慧鶴「迷わぬ“坐禅"で健康を得る」 / 宮本義己/p28~29
音の種類で感じ方はどう変わるか?(Ⅱ)集中(耳より健康講座・聴覚機能と健康管理) / 武田真太郎/p30~31
ひと 元田紀雄/p33~33
海外文献サマリー 職業性ばく露におけるテトラヒドロフランの生物学的モニタリング / 水口晴夫/p34~35
こころとからだの交差点 宗教を考える / 養老孟司/p37~37
ドクター日記 海外巡回健康相談 / 佐藤勝/p41~41
健康について 笑い飛ばしてストレス解消! / ジョン・カビラ(J-WAVEナビゲーター)/p42~43
メンタルヘルス企業はいま 心の定期健康診断とメンタルヘルス活動 / 福山美代子/p44~45
心理相談心得帳 / 藤井久和/p46~46
略 |
7月、「大乗禅 = The mahayana zen buddhism 69(6)(815)」が「中央仏教社」から刊行される。pid/7885690/1
|
巻頭言 / 秋月龍珉/p2~2
東西宗教交流学会 第10回学術大会記録(下) <講演2> / ブラフト/p4~16
東西宗教交流学会 第10回学術大会記録(下) <討論2> / 横田俊二/p17~23
東西宗教交流学会 第10回学術大会記録(下) <総合討論1・2> / 八木誠一/p24~34
陽田寺だより / 飯塚定香/p35~35 |
8月の禅語歳時記 / 木村清一/p36~39
人間観自在菩薩(41) / 野中日文/p40~43
『無門関』参究覚書(8) / 野飼祖芳/p44~48
不生で生きる(6) / 鳥居祖道/p49~57
『洞上五位偏正口訣』対比 / 野飼祖芳/p58~66 |
8月、直木公彦が「白隠禅師 : 健康法と逸話」を「日本教文社」から刊行する。
8月、禅文化研究所編集部作,辻井宏寿画「白隠和尚物語 第4巻 (慢心篇)」が「禅文化研究所」から刊行される。
12月、大沼栄穂が「国際関係研究 13(2) p61~83 日本大学国際関係学部国際関係研究所」に「白隠「坐禅和讃」における蓮華国について」を発表する。 pid/1406790
12月、笠井昭が「印度學佛教學研究 41(1) p.p274~278」に「白隠禅の思想的背景 (愛知学院大学における第43回〔日本印度学仏教学会〕学術大会紀要-1-)」を発表する。 J-STAGE |
| 1993 |
5 |
・ |
2月、衣斐弘行が「在家佛教42(489) p24~38 在家仏教協会」に「特集 聞くということ 涅槃図のこころ」を発表する。1993-02/pid/6064154/1
2月、禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (71)」が「 禪學研究會」から刊行される。pid/4414857
|
『蒲室集抄』について--『蒲根』『蒲〔ゲツ〕』を中心として/飯塚大展/1~36
白隠「濃陽富士山記」について / 荒川元暉/37~65
壇経雑識 / 古賀英彦/67~84
西明寺と吐蕃仏教 / 沖本克己/85~112
パ-リ仏教聖典に見られる禅定思想と食物との関係/竹内良英/113~147 |
禅に於ける「形而上学的なるもの」と
→「実存的なるもの」 / 西村惠信/1~21
花園法皇・日峰禅師関連年表--初期妙心寺史年表稿 /
→小林賀照 ; 雄山学人/23~109
禅学関係雑誌論文目録(1990年) / 中尾良信/111~119 |
10月、「禅文化. (150) 禅文化研究所創立三十周年記念特集」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082346
|
禅文化研究所創立三十周年に当って/平田耕作/p7~8
禅文化研究所創立三十周年記念特集
禅・文・化 / ウルス・アップ / p9~11
禅と名教 / 荒木見悟 / p11~13
千崎如幻の縁 / 井上禅定 / p13~15
一〇〇号まで / 衣斐弘行 / p16~17
禅画閑話 / 岩崎巴人 / p17~19
狂相 / 上田閑照 / p20~22
禅文化研究への期待 / 大槻幹郎 / p23~24
偶感 / 沖本克己 / p25~27
辞典に見る関山慧玄の伝 / 加藤正俊 / p27~30
寸心、無字透関九十年 / 北原隆太郎 / p30~32
『禅文化』と「禅文化」 / 倉沢行洋 / p33~35
何とかしよう / 河野義海 / p35~36
大覚禅師の心と禅文化研究所の在り方/小島岱山/p37~39
禅と私 / 直原玉青 / p39~41
世界の中の禅 / 重松宗育 / p42~43
シナ禅・日本・ヨーロッパ(一) / 柴田増実/p44~46
禅文化三十年滞米三十年更参三十年/嶋野栄道/p46~48
日本人の特性 / 千宗室 / p48~50
「禅文化」の用紙 / 竹中玄鼎 / p50~52
研究所と私 / 竹貫元勝 / p52~54
オランダで白隠を読む / 常盤義伸 / p54~57
禅 『禅文化』の編集をしていた頃の話 / 西村惠信 / p57~59
|
禅文化の原点 / 野口浩堂 / p60~61
転轆々阿轆々 / 則竹秀南 / p61~63
今、求められているもの / 蓮沼良直 / p63~65
禅文化研究所本『臨済録』のこと / 平野宗浄 / p65~67
飽書の時代 / 福富雪底 / p67~69
三十年の歴史に提案する / 古田紹欽 / p69~71
禅無しとは道わず / 宝積玄承 / p71~73
三十周年を迎えて思うこと / 細川景一 / p73~75
新時代に向って / 嶺興嶽 / p76~77
「手をあわせる」の頃 / 柳田聖山 / p78~82
禅 行脚 / 柳田宗葩 / p82~84
玄奘三蔵法師、天竺ルート中の幻のバルカ国、発見!?/ 松原哲明/p116~126
内なる深淵に呑まれて(後編)/スティーブン・アンティノフ ; 村上俊/p128~146
寺の活動 ザ・ゼン・クラブ / 千坂成也 / p94~97
グラビア 寺宝探訪(38) 『盤珪禅師遺芳』より(三) / p103~110
マハーバーラタ(十四) 〔第一巻「発端」
→その六・祖先の祖先(二)〕 / 木下長宏 / p85~92
済公伝〔十二〕 / 水上勉 ; 李建華 / p98~102
禅学点描(四) / 西口芳男 / p111~115
いっぷく拝見 / p148~155
『禅文化』バックナンバー / p158~158
禅文化研究所の本 / p159~162
編集後記〈蛇足〉 / p157~157
・ |
|
| 1994 |
6 |
・ |
2月、衣斐弘行が「在家佛教 43(501) p42~53 在家仏教協会」に「遺偈に学ぶ」を発表する。pid/6064166
2月、小野恭靖が「阪教育大学紀要 第I部門:人文科学 42(2) p.189-213 大阪教育大学」に「白隠慧鶴『施行歌(せぎょううた)』研究序説」を発表する。 (IRDB)
|
内容記述 近世(江戸時代)民謡の最大の特徴は、その教訓的内容にあると言ってよい。それらのうちの多くは、児童向けに親への孝を説いた歌謡で占められる。このような内容の歌は一般的には儒教的道徳によるものと受け取られるが、実はこの時期には禅宗を中心とした仏教や心学の立場から創作されたものが圧倒的に多い。本稿では近世民謡へのひとつのアプローチとして、江戸時代中期の禅僧で臨済宗中興の祖とも仰がれる白隠慧鶴作の和讃『施行歌(せぎょううた)』をとりあげる。まず、その基礎的研究として諸本を調査した結果、全体を四つの系統に分類できることが判明した。そこで各系統ごとに本文を掲出し、比較検討を試みた。 |
3月11日~4月10日、飯田市美術博物館に於いて「白隠 : 伊那谷にも訪れた禅の傑僧
特別展」が開かれる。
また、飯田市美術博物館編「白隠 : 伊那谷にも訪れた禅の傑僧 特別展 展覧会図録」が刊行される。 3000円
白隠 特別展 飯田市美術博物館 1994年3月11日~ 4月10日
|
「達磨像」(1751、1758頃、1767)
「達磨・臨済・雲門像」
「草坐達磨像」
「巌頭和尚像」
「虚堂像」
「大応・大燈・関山像」
「乞食大燈像」
「大燈像」
「愚堂像」
「正受老人像」
「円相内自画像」
「自画像」
「出山釈迦像」
「観音十六羅漢図」
「蛤蜊観音像」 |
「蓮池観音像」
「涅槃経油鉢図」
「秋葉三尺坊像」
「関羽像」
「鍾馗像」
「白澤図」
「恵比寿寿老図」
「隻手布袋図」
「芭蕉翁像」
「寿老人図」
「吉田のゑんこう」
「壽布袋図」
「布袋すたすた坊主図」
「お福団子」
「順の舞」 |
「塞耳猿猴図」
「柿本人麿像」
「□猴(ビコウ)採水月図」
「鼠師槌子図」
「大極嶺」
「佛祖三経会名員」
「楊柳観音像」
「蓮池観音像」
「出山釈迦像」
「層巓達磨像」
「樹下坐禅自画像」
「重離六爻」
「隻履達磨像」
「壽布袋図」
「蓮池観音像」 |
「達磨像」
「龍杖図」
「大応・大燈・関山像」
「法華開講偈」
「鵠林老師法華会上語録」
「法華会衆次名員」
「法華会中金銀米銭出入記」
<テキスト>
・槇村洋介 「伊那谷と白隠」
・作品解説
・略年譜
・
・ |
9月、「プレジデント = President 32(9)」が「プレジデント社」から刊行される。 pid/2802746
|
「空」を生きる、「おかげさん」を生きる――「仏の心」を語り続ける現代の名僧が、
→この時代を生き生きと生きる智慧を教授する/松原泰道 ; 清水公照/p46~51
「仏の言葉」二六二文字を解説する / 秋月龍珉/p52~55
道元――虚空を実践すれば、煩悩の世界は越えられる / 中野東禅/p78~83
一休――「色即是空」無明に身を置く / 紀野一義/p84~89
白隠――素直になれ、裸になれ、カラッポになれ / 尾関宗園/p92~97
空海――読み、写し、聞き、そして「菩薩」となれ / 松永有慶/p100~104
覚鑁――「真雷」を唱えよ、されば迷いは雲散する / 眞柴弘宗/p106~111
円仁――救いも、悟りも、唱えることにあり / 小林隆彰/p114~119
女たちの「般若心経」――岡本かの子、祇王寺智照尼、そして瀬戸内寂聴。
→彼女たちの自由な精神を支えたものは / 古屋照子/p126~133 |
「心経」このエキソチズムとエロチシズム――この経典はなぜ日本人の精神に根づいたのか、
→そしてその魅力とは。若き仏教学者二人が語りつくす / 中沢新一; 宮坂宥洪/p134~140
「小さな大叙事詩」中国へと至る――インドで生まれたこの経典は鳩摩羅什、玄漢三蔵らの
→訳業により東アジアの民衆に / 鎌田茂雄/p58~63
「禅仏教」は心経をどう読んだか――道元、蘭渓道隆、一休らへと続く、中国禅の成立から
→「心経」理解までの系譜 / 池田魯參/p64~69
「密教」は二六二文字をこう理解する――中国僧窺基、法蔵らの研究は、空海ら「日本密教」の
→濫筋を開くことになった / 金岡秀友/p70~75
若き門主はなぜ「禁断の経典」を繙いたか――異端の念仏者・大谷光瑞は宗派の枠を超え、
→仏教の原点から探究し直そうと考えたのだ / 上山大峻/p120~125
(略)
|
9月、小倉不折が「墨美を探る :文人・高僧の書画の世界」を「秀作社出版」から刊行する。
|
はじめに 1
一 書美の構造 4
一 1 伝統と創造 4
一 2 文字と書との関係 5
一 3 書体美について 9
一 3 甲骨文
一 3 鐘鼎文
一 3 大篆
一 3 小篆
一 3 古隷
一 3 八分隷
一 3 章草
一 3 草書
一 3 楷書
一 3 行書
一 3 仮名
一 4 書風美について 13
一 4 民族性
一 4 時代性
一 4 唐様と和様
一 4 流派
一 4 個性や境涯
一 5 毛筆使用の意義-毛筆の発達と書 18
一 6 墨使用の意義-墨の発達と書 22 |
一 7 硯使用の意義-硯の発達と書 27
一 8 紙使用の意義-紙の発達と書 30
一 9 用筆法 34
一 9 執筆法
一 9 腕法
一 9 用筆法
一 10 運筆法 41
一 11 線について 45
一 12 結構法について 52
一 13 布置章法について 55
一 14 余白について 60
一 15 精神性について 66
一 16 率意の書と刻意の書 71
一 17 手紙の書について 76
一 18 美術観の東西の相違 86
二 異質の書美-文人の書美の背景 89
二 1 正系と傍系 89
二 2 主な傍系の書 91
二 3 文人的思想 97
二 4 書画同源と書画一致 100
二 5 書線と画線の相違 105
二 6 書法の画線への影響 106
二 7 書画の線が求めるもの 110
二 8 詩・書・画三絶 114 |
二 9 写意について 118
二 10 胸中の丘壑、万巻の読書 123
二 11 狂について 「□狂」の場合 128
二 12 拙を求める 132
三 文人七人の書道観 139
三 1 池大雅の書 139
三 2 富岡鉄斎の書 144
三 3 副島蒼海の書 150
三 4 三輪田米山の書 154
三 5 北大路魯山人の書 160
三 6 高村光太郎の書 165
三 7 会津八一の書 172
四 墨蹟の書美-禅と書の出会い 179
五 禅僧六人の書道観 187
五 1 大燈国師の書 187
五 2 一休宗純の書 194
五 3 白隠慧鶴の書 200
五 4 慈雲尊者の書 208
五 5 仙厓義梵の書 215
五 6 大愚良寛の書 222
参考文献 235
おわりに 237
・
・ |
10月、「禅文化. (154)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082350
|
生命の讃歌 『坐禅和讃』を読む / 盛永宗興 / p7~28
夢窓疎石と徹翁義亨 / 竹貫元勝 / p88~94 |
〈抜粋〉
・ |
11月、衣斐弘行が「在家佛教43(510) p36~48 在家仏教協会」に「特集 佛の徳性 'こころの歌 」を発表する。 pid/6064175 |
| 1995 |
7 |
・ |
1月、「禅文化. (155)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082351
|
高峰顕日と南浦紹明 / 竹貫元勝 / p64~70
地球の緑と日本の緑 / 立花吉茂 / p109~113 |
〈抜粋〉
|
3月、中島玄奘が「正宗国師白隠禅師伝」を「松蔭寺」から刊行する。 所蔵:静岡県立中央図書館
4月、「禅文化. (156)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082352
|
阪神大震災によせて 真の復興の実現に向けて / 盛永宗興/p7~24
阪神大震災によせて 生也全機現、死也全機現/平出精擇/p25~28
阪神大震災によせて 脚跟猶未点地--
→阪神大震災のこと/沖本克己/p29~42
阪神大震災によせて RACKの活動 / 神足守正/p43~46
阪神大震災によせて 人間って素晴らしい / 柳田宗葩/p134~137
パミールの旅 / 西躰宗光/p106~111
春屋妙葩と定山祖禅 / 竹貫元勝/p123~133
グラビア--寺宝探訪(44)精拙元浄墨蹟(三)/p71~82
中国仏教(五) / 柳田聖山/p83~97
漢詩雑感--曹源池 / 佐々木容道/p98~104 |
三余居窓話(六)骨を折る / 西村惠信/p65~70
禅宗の教団(一)その思想と変遷(1) / 沖本克己/p112~122
特集 朝比奈宗源老師 懐旧三話--
→朝比奈宗源老師のこと / 衣斐弘行/p47~56
特集 朝比奈宗源老師 朝比奈老師のことども / 松原哲明/p57~64
ルポ是地斯寺(3)太平山 祥瑞寺 大徳寺派 / 岡村完道/p138~143
いっぷく拝見/p144~151
『禅文化』バックナンバー/p154~154
禅文化研究所の本--図書案内/p155~158
編集後記--〈蛇足〉/p153~153
・ |
5月、武田鏡村が「歴史と旅 22(8)[(331)] p268~269 秋田書店」に「時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 白隠慧鶴 日本の禅の確立者」を発表する。 pid/7947508
|
〈略〉
時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 円空 諸国を放浪した造仏聖 /
武田鏡村 / p264~267
時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 良寛 風流な乞食僧 / 豊島泰国
/ p274~277
時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 白隠慧鶴 日本の禅の確立者 / 武田鏡村 / p268~269
時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 鈴木正三 武士の先死観を提唱した禅僧
/ 武田鏡村 / p270~271
時代を彩った各界の人々 大江戸人物志 宗教家 木喰五行 諸国に残す木喰仏 /
豊島泰国 / p272~273
〈略〉 |
6月6日~7月23日迄、渋谷区立松涛美術館に於いて「近世宗教美術の世界
: 変容する神仏たち」展が開かれる。
6月、渋谷区立松涛美術館編「近世宗教美術の世界 : 変容する神仏たち」が「渋谷区立松涛美術館」から刊行される。
注記 出品作家: 英一蝶, 白隠慧鶴, 葛飾北斎 [ほか]
7月、「禅文化. (157)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082353
|
圜悟の墓所を訪ねて ある『碧巌』の旅 / 中西久味 / p97~103 |
〈抜粋〉 |
9月、白田劫石述「白隠禅師『主心お婆々粉引歌講話』」が「人間禅教団」から刊行される。(人間禅叢書
第9編)
10月、「禅文化. (158) 特集 盛永宗興老師追悼」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082354
| |
特集 盛永宗興老師追悼 栽松 / ウルス・アップ/p8~10
碓菴老漢のこと / 飯塚大幸/p10~12
正師との出会い / 大木宗玄/p12~17
盛永宗興老師を送る--諷経葬弔辞 / 河野太通/p17~19
碓庵老師を偲ぶ / 笹尾哲雄/p19~21
碓庵老師--直心の人 / 島崎義孝/p21~25
宗興老師のこと / 千宗之/p25~28
碓菴・盛永宗興老師を憶う / 竹中玄鼎/p28~31
距離の感覚--盛永宗興老師の面目 / 西村惠信/p31~36
真の大学人--宗興老師のこと / 濱崎正規/p36~39
妙応無方にして、朕跡を留めず / 福井友栄/p39~41
碓庵宗興老師に師事して / 鉾之原妙鈴/p42~44
解脱さえ求めぬ知足 / ミッシェル・モール/p45~46
父のこと / 盛永・コルカット・暁子/p47~49
碓菴宗興老師を哭す / 柳田聖山/p50~54
盛永御老師の思い出 / 湯木貞一/p54~56
|
済公伝〔十九〕 / 水上勉 ; 李建華・訳/p138~143
夢窓詩雑感 拈華嶺 / 佐々木容道/p102~107
村上俊君を悼む / 入矢義高/p81~83
訥弁の達摩 / 村上俊/p84~101
グラビア 寺宝探訪(46) 翠巌承堅墨蹟(二)/p71~80
山の畑を耕す--山菴雑記 / 古田紹欽/p112~115
三余居窓話(八)--蜂と燕の季節 / 西村惠信/p130~136
禅宗の教団(三) / 沖本克己/p119~128
鉄山宗鈍と閑室元佶 / 竹貫元勝/p57~65
天山南路の旅一万三千キロ--シルクロードに魅了されて / 藤原東演/p66~70
竹林寺和尚様のこと / 柳田宗葩/p108~111
出家の常識・非常識(一) / 水田全一/p116~118
いっぷく拝見/p144~151
『禅文化』バックナンバー/p154~154
禅文化研究所の本/p155~158
編集後記<蛇足> / Y/p153~153 |
10月、栗田勇が「謎の禅師白隠の読み方 : <息>によって心身を養う「夜船閑話」の知恵」を「祥伝社」から刊行する。
(ノン・ブック)
11月、武田鏡村が「 歴史と旅 22(17)[(340)] p330~333 秋田書店」に「江戸の名僧智識 白隠 地獄こそ仏なり」を発表する。 pid/7947517
|
求法の情熱と済世の慈悲・・現代人の心の糧となる仏法者の群像!
→ 日本の名僧・高僧88人 巻頭史論 鎮護国家から
→衆生済度へ / 山田宗睦 / p35~41
飛鳥・奈良仏教の先達者
慧慈 飛鳥仏教を招来した聖僧 / 武光誠 / p42~45
玄昉 才あれども行いに治あらず / 伊藤悠可 / p50~53
行基 民衆に慕われた慈悲のひじり / 寺内大吉 / p54~59
鑑真 失明してもなお屈せず渡来 / 和湖長六 / p60~63
道鏡 法王は帝位簒奪をもくろんだか / 寺内大吉 / p64~69
良弁 天平の花咲かせた大仏開眼 / 和湖長六 / p70~73
道昭 日本で最初に火葬された人 / 伊藤悠司 / p46~47
義淵 玄昉、行基ら俊才を育てる / 伊藤悠司 / p48~49
日本各地の霊峰と開山伝説 / 加藤蕙 / p78~83
【コラム】 出家第一号は女性だった / 川副春海 / p74~75
【コラム】 奈良仏教と葬送儀礼 / 加藤義諦 / p76~77
平安仏教の求法者たち
最澄 智慧をきわめて生死を離れる / 高橋富雄 / p84~89
空海 日本仏教の源流真言密教の大成者 / 百瀬明治 / p90~95
徳一 悟りは人により相違あり / 高橋富雄 / p98~101
円仁 唐に求法の初志を貫く / 玉城妙子 / p102~105
円珍 夢のお告げに従い唐に渡る / 山崎龍明 / p106~109
空也 いずくにも身を捨ててこそ / 寺内大吉 / p110~115
良源 生けるものはすべて成仏できる / 吉田茂 / p116~119
源信 救われざる衆生のために祈る / 寺内大吉 / p124~129
真如法親王 インド求道の途次に死す / 豊島泰国 / p132~135
覚〔バン〕 すべての罪業を一身に受ける / 生駒忠一郎 / p140~143
泰範 天台宗から真言宗への転身 / 吉田茂 / p96~97
寂心 『日本往生極楽記』を成す / 玉城妙子 / p120~121
増賀 名利を捨てた奇行の数々 / 豊島泰国 / p122~123
覚猷 戯画のパイオニア鳥羽僧上 / 高木純一 / p130~131
行尊 厳しい修行で高徳を得る / 生駒忠一郎 / p136~137
良忍 口誦念仏への道を開く / 生駒忠一郎 / p138~139
[コラム] 曼荼羅宇宙に座す仏尊のすべて / 大宮司朗 / p144~145
[コラム] 大師信仰と高野聖 / 百瀬明治 / p146~147
[コラム] 夢を商う寺僧たち / 藤原成一 / p148~149
鎌倉仏教の旗手
西行 身を捨ててこそ身をも助けめ / 寺内大吉 / p150~155
重源 戦さをよそに大仏再建の大勧進 / 寺内大吉 / p156~161
法然 念仏を唱えれば人は救われる / 渡会恵介 / p162~167
栄西 禅宗の確立者にして茶の元祖 / 左方郁子 / p174~177
慈円 名利の二道を歩いた人生 / 石丸晶子 / p178~181
親鸞 善人は往生す、まして悪人は / 武田鏡村 / p182~187
明恵 半世紀遅かった高僧 / 鷲津清静 / p190~193
道元 五欲・五蓋を捨てて無の境地をめざす / 中嶋繁雄 / p194~199
忍性 社会事業の十の大願 / 武田鏡村 / p206~209
日蓮 弾圧に挫けぬ不屈の戦闘的仏法者 / 畑山博 / p210~215
一遍 民衆の心をつかむ踊り念仏 / 大宮司朗 / p218~223
一山一寧 元から渡来した京都五山の祖 / 戸田実山 / p226~229
蓮生 〝坂東の阿弥陀仏〟と称えられる / 左方郁子 / p168~169
文覚 頼朝に旗揚げを勧めた荒法師 / 左方郁子 / p170~171
俊寛 平氏追討に失敗、鬼界ケ島へ / 左方郁子 / p172~173
善鸞 父親鸞と信仰上の対立 / 武田鏡村 / p188~189
叡尊 戒律の復興に情熱を傾ける / 山崎龍明 / p200~201
唯円 異端を歎き師の言行録編む / 山崎龍明 / p202~203
蘭溪道隆 宋より渡来、建長寺開山 / 中嶋繁雄 / p204~205
無学祖元 円覚寺開山の宋の渡来僧 / 中嶋繁雄 / p216~217
日朗 師への献身的奉仕に生きる / 畑山博 / p224~225
鎌倉五山の文化 / 加藤義諦 / p230~233
室町・戦国の高僧
夢窓疎石 迷いも悟りも一つなり / 井門寛 / p236~239
文観 勅命により関東調伏 / 羽生道英 / p240~243 |
満済 室町幕府の黒衣の宰相 / 西村孝文 / p246~247
一休 風狂禅の中に生きる恋法師 / 藤原成一 / p248~251
日親 苛酷な拷問にも屈せぬ信念 / 畑山博 / p252~255
蓮如 飯も食えずして何の念仏ぞ / 寺内大吉 / p256~261
木喰応其 人助けは堂塔建立に優る / 山本兼一 / p270~273
顕如 抜き難し、南無六字の城 / 百瀬明治 / p276~279
瑩山紹瑾 曹洞宗中興の名僧 / 中嶋繁雄 / p234~235
宥快 高野山教学の大成者 / 井門寛 / p244~245
〔バン〕阿 武家の野心を捨てて得度 / 羽生道英 / p262~263
雪舟 明国に学んだ天才画僧 / 羽生道英 / p264~265
太原崇孚 駿河今川氏の大軍師 / 橋本三喜男 / p266~267
快川紹喜 心頭滅却すれば火も涼し / 橋本三喜男 / p268~269
安国寺恵瓊 毛利の軍僧から僧侶大名へ/橋本三喜男/p274~275
京都五山の文化 / 加藤義諦 / p280~283
[コラム] 天文法華の乱 / 西村孝文 / p284~285
江戸の名僧智識
隠元 明文化をもたらした黄檗僧 / 桜井裕 / p290~293
天海 天下人家康を動かした黒衣の宰相 / 豊島泰国 / p294~299
崇伝 幕府の諸法度を起草した政僧 / 小和田哲男 / p302~305
沢庵 剣禅一致の境地に立つ / 山本兼一 / p308~311
金谷上人 聖と俗を生きた稀代の異才 / 泉秀樹 / p316~319
円空 鉈彫りの素朴な円空仏 / 平上信行 / p320~323
隆光 俗説「生類憐みの令」進言 / 小和田哲男 / p326~329
白隠 地獄こそ仏なり / 武田鏡村 / p330~333
江戸の名僧智識 良寛 死ぬ時には
→死ぬがよく候 / 橋本三喜男 / p338~341
江戸の名僧智識 木喰五行
→千体仏を祈願の廻国僧 / 佳川文乃緒 / p342~345
照 国のため君のための露命 / 一坂太郎 / p354~357
教如 東西に分裂した本願寺 / 百瀬明治 / p286~287
鈴木正三 仁王禅を提唱した三河武士 / 桜井裕 / p288~289
策伝 『醒睡笑』で落語家の始祖 / 豊島泰国 / p300~301
日奥 邪法を捨て正法に帰依せよ / 山本兼一 / p306~307
一絲文守 仏道の奥底を求めた天才僧 / 平上信行 / p312~313
盤珪 人はみな不生の仏心を持つ / 大宮司朗 / p314~315
祐天 淨土宗教団のトップに立つ / 大宮司朗 / p324~325
慈雲 正法律の復興に捧げた生涯 / 桜井裕 / p334~335(
仙厓 庶民禅を打ち立てた「博多っ子」 / 桜井裕 / p336~337
武田物外 拳骨和尚の異名もつ傑僧 / 平上信行 / p346~347
太田垣蓮月 陶器を焼く歌人の尼憎 / 佳川文乃緒 / p348~349
江戸の名僧智識 野村望東尼 勤皇に生きた
→美貌の尼僧 / 佳川文乃緒 / p350~351
江戸の名僧智識 月性 法談で説く海防論 / 一坂太郎 / p352~353
[コラム] 虚無僧と武士の駆込寺 / 藤原成一 / p358~359
[コラム] 江戸時代の檀家制度 / 武田鏡村 / p360~361
[コラム] 即身仏になった僧 / 加藤蕙 / p362~363
[コラム] 延命院事件の?末 / 泉秀樹 / p364~365
近代仏教の碩学たち
河口慧海 初のチベット入りの苦難行 / 川副春海 / p370~373
大谷光瑞 中央アジア探検の不朽の業績 / 高野澄 / p374~377
福田行誡 維新動乱期の仏教界の柱石 / 高野澄 / p366~367
島地黙雷 政教分離と信教の自由を唱導 / 高野澄 / p368~369
鈴木大拙と近代仏教の碩学 / 島田裕巳 / p382~385
[コラム] 本門仏立宗の教団拡大 / 西村孝文 / p378~379
[コラム] 漂泊と乞食僧の系譜 / 鷲津清静 / p380~381
口絵 <カメラ紀行> 弘法大師空海62年の生涯 / p11~18
グラビア 善人なおもて往生す 親鸞聖人の足跡 / p19~26
グラビア われ日本の柱とならん 日蓮聖人の足跡 / p27~34
出版広告 / p387~394
編集後記 / 鈴木亨 / p386~386
・
|
|
| 1996 |
8 |
・ |
1月、「禅文化. (159)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082355
|
対談 白隠の禅 / 柳田聖山 ; ミツシエル・モール / p15~29 |
〈抜粋〉 |
2月、「歴史と旅 23(3)[(344)]」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947521
|
略
第二特集/不老不死伝説 不老長寿への儚き憧憬 / 三谷茉沙夫/p236~241
第二特集/不老不死伝説 武内宿禰 五代の天皇に仕えた大和豪族の祖/阿部正路/p242~247
第二特集/不老不死伝説 八百比丘尼 妙薬人魚の肉で得た不老不死/田井友季子/p248~253
第二特集/不老不死伝説 常陸坊海尊 死せずして時をさまよう / 早川純夫/p254~257
第二特集/不老不死伝説 サン=ジェルマン伯爵 万能の不死者 / 豊島泰国/p258~261
第二特集/不老不死伝説 彭祖 悠久の生を得た中国の神仙 / 伊藤悠可/p262~265
カラー&モノクロ口絵・記事
ふるさとの歴史(246)古代ロマンの香り漂う日向路 / 編集部/p163~170,172~181
遣唐使の旅 <栄叡・鑑真と大明寺> / 川田秀文/p16~17,200~201
歴史の肖像傑作選 <野村望東尼>/p18~18
ヨーロッパ古城紀行 <テージョ河畔の貴婦人ベレンの塔/ポルトガル> /
→勝井規和 ; 悦子/p171~171
歴史の時鐘 <岩槻の時の鐘/埼玉県岩槻市本町>/p19~19
カメラ太閤記 <墨俣一夜城/岐阜県安八郡墨俣町墨俣>/p20~21
島の風土記 <隠岐島/島根県>/p22~23
石仏を歩く <塩田平の夫婦道祖神/長野県上田市野倉> / 石堂秀夫/p26~27
みちのく歌枕吟行の旅 <美豆の小島/宮城県鳴子町>/p28~29,234~234
歴史のかけ橋 <阿波のドイツ橋/徳島県鳴門市>/p30~31
|
誌上特別展<銅鐸の美展神奈川県立博物館>/p24~25
歴史トピックス <小像の表現する古代風俗さまざま装飾付き恵器>/p32~33
諸国人物志(117)東京都(下) / 吉田茂/p184~191
藩史ものがたり(143)備中松山藩(上) / 松本幸子/p192~199
歴史ロマンを求め、東へ西へ 松浦武四郎・北への旅(2)<象潟> / 本間寛治/p203~207
歴史ロマンを求め、東へ西へ 良寛の歩いた道(14)<五合庵―寺泊・野積・牧ヶ花>
/
→武田鏡村/p208~213
歴史ロマンを求め、東へ西へ 世界史の女性(2)<クレォパーラ> / 遠藤紀勝/p214~217
歴史ロマンを求め、東へ西へ 神仏の坐す山(2)<磐梯山> / 和田作蔵/p218~219
歴史ロマンを求め、東へ西へ 北国街道独り歩き(14)<有馬川・名立> / 玉城妙子/p220~223
歴史ロマンを求め、東へ西へ 多摩川を湖る(7)<川べりの緑地帯> / 中村吾郎/p224~229
歴史ロマンを求め、東へ西へ 山手線史跡散歩(14)<五反田・大崎>/p230~233
略
<読者レポート> 総野の一隅に眠る土佐勤皇党有志 / 川本斉一/p312~317
<読者レポート> 阿波水軍の本拠地 椿泊へ / 福崎正/p318~321
新養生訓 「白隠」 / 大宮司朗/p235~235
女人の寺 「小野小町と随心院」/p298~298
略
・ |
3月、松原哲明が「あさひ銀総研レポート 5(3)(108) p36~39 あさひ銀総合研究所」に「内観の秘法―白隠」を発表する。 pid/2886101
4月、「禅文化. (160)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082356
|
夢窓疎石における<和歌>と<笑い> / 西山美香 / p122~133
夢窓詩雑感 梵音閣 / 佐々木容道 / p94~99 |
〈抜粋〉
・ |
4月、衣斐弘行が「在家佛教45(527) p36~44 在家仏教協会」に「人間の絆 」を発表する。 pid/6064192
7月、「禅文化. (161)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082357
|
卵枢転 白隠語録のオランダ語 / 石川光庸 / p120~123
伝弘法大師真蹟「法華経」について / 橋本敬一 / p117~119
雲居希膺と賢谷宗良 / 竹貫元勝 / p96~104
三余居窓話(十一)二足草鮭の楽しみ / 西村恵信 / p62~67
|
夢窓詩雑感 山居 / 佐々木容道 / p86~91
カラーグラビア 背姿 / 北脇昇 / p71~72
禅の画家たち(三) / 木下長宏 /
〈抜粋〉
|
9月、小島寅雄 書・画 ; 加藤僖一 撮影・編集「白隠禅師坐禅和讃」が「新潟/良寛研究所」から刊行される。
所蔵:新潟県立図書館
10月、「禅文化. (162)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082358
|
夢窓詩雑感 投機 / 佐々木容道 / p118~124
三余居窓話(十二)識羞の旅 / 西村恵信 / p112~117 |
〈抜粋〉
・ |
11月、古田紹欽編集・解説「禅と芸術 1」が「ぺりかん社」から刊行される。
(禅と日本文化 : 叢書, 1)
|
1: 日本文化と禅 / 古田紹欽 [執筆]
日本の禅・日本人の美意識 / 柳田聖山 [執筆]
禅と美術 / 鈴木大拙 [執筆]
禅芸術の理解(1) / 久松真一 [執筆]
禅と美 / 柳宗悦 [執筆]
無の芸術 : 禅の立場から / 山口諭助 [執筆]
道元 : 中世芸術の根底 / 唐木順三 [執筆]
|
芸術境としての禅 / 小笠原秀實 [執筆]
東洋の近代芸術に及ぼした禅の影響 :
→とくに董其昌の南宗北宗画論について / 小林太市郎 [執筆]
絵画と禅 / 須田剋太 [執筆]
禅芸術雑感 / 古田紹欽 [執筆]
不立文字の芸術 : 解説に代えて / 古田紹欽 [執筆]
掲載論文の出典および筆者紹介: 1: p333-336. |
12月、衣斐弘行が「在家佛教 45(535) p60~73 在家仏教協会」に「禅からの教え 」を発表する。 pid/6064200
○、この年、韓炳玉が博士論文 「墨蹟の地域的展開とその特質 : 韓国の禅僧の書と中国・日本の禅僧の書との比較検討」を発表する。 pid/3117684
|
序論 / p1
第一節 本研究の目的と意義 / p2
第二節 研究方法-墨蹟資料の収集と分析- / p8
第三節 研究対象 / p12
註 / p14
第一章 中国・日本・韓国と墨蹟研究 / p16
第一節 本研究における「墨蹟」 / p17
1 「墨蹟」の概念 / p17
2「墨蹟」の性格 / p27
3「墨蹟」の筆法 / p32
第二節 先行墨蹟研究 / p33
1 日本における先行墨蹟研究 / p33
2 中国における墨蹟研究の現状 / p36
3 韓国における墨蹟研究の現状 / p40
註 / p47
第二章 中国の墨蹟 / p52
第一節 墨蹟より見た中国禅宗史概略 / p53
第二節 中国の禅と墨蹟 / p57
1 文献にのみ記録された墨蹟 / p57
2 現存する墨蹟検討 / p73
第三節 禅と書の融合 / p85
1 中国書法史及び三地域の墨蹟史における釈智永の影響/p85
2 中国書法史及び三地域の墨蹟史における釈懐素の影響/p95
第四節 宋代の禅と士大夫の書 / p107
1 宋代の禅と墨蹟 / p107
2 蘇東坡 / p109
3 黄山谷 / p114
4 宋代思想家の禅味の書 / p123
註 / p131
第三章 日本の墨蹟 / p145
第一節 墨蹟隆盛の原因 / p147
1 墨蹟より見た日本禅宗史概略 / p147
2 墨蹟尊重の理由 / p149
第二節 日本において尊重された墨蹟の種類及びその内容/p156
1 日本の墨蹟 / p156
|
2 日本の墨蹟の分類 / p157
3 日本の墨跡の内容 / p159
第三節 日本的墨蹟の成立 / p174
1 日本的墨蹟の意義 / p174
2 一休宗純の墨蹟 / p180
3 沢庵宗彭の墨蹟 / p184)
4 白隠慧鶴の墨蹟 / p194
註 / p207
第四章 韓国の墨蹟 / p218
第一節 韓国墨蹟の成立 / p219
1 墨蹟より見た韓国禅宗史概略 / p219
2 韓国書芸史と墨蹟 / p224
第二節 韓国の禅と墨蹟 / p233
1 禅と書 / p233
2 文献にのみ記録された墨蹟 / p235
3 現存する墨蹟の検討 / p239
第三節 金正喜の禅と書の融合 / p275
1 金正喜と墨蹟 / p276
2 略伝 / p277
3 禅との関係 / p278
4 書風の変遷からみる禅的表現 / p279
註 / p291
結論 / p298
第一節 墨蹟の地域的展開 / p299
1 三地域の禅宗の師承関係 / p299
2 墨蹟における三地域の師承関係 / p300
3 三地域における将来墨蹟 / p301
4 三地域における文化的墨蹟の展開要因の比較 / p302
第二節 墨蹟の性格と筆法 / p304
1 墨蹟の性格の比較論的検討 / p304
2 墨蹟の筆法の比較論的検討 / p308
作品目次 / p312
参考文献 / p323
謝辞 / p344
図版(別冊) |
|
| 1997 |
9 |
・ |
1月、「禅文化. (163)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082359
|
寛保二年の白隠禅師龍潭寺結制をめぐって(1) / 巨島泰雄 / p111~120
グラビア 寺宝探訪(51)亀岡・龍潭寺〔一〕 / p89~
主人公とは誰か 無門関を読む(2) / 柳田聖山 / p38~46
禅者森本省念老師 / 山田邦男 / p28~32
高野山私史(3) / 上田真而子 / p131~140
禅宗の教団(7) / 沖本克己 / p121~130
大黒雑感 福泉寺南無道場掃除学部 / 無着とき / p101~103
眞月庵孝道義忠尼老師 / 鈴木法音 / p79~82
夢窓詩雑感 渡月橋 / 佐々木容道 / p104~110
|
三余居窓話(13)四国お遍路の旅 / 西村惠信 / p83~88
太極と季弘大叔 / 竹貫元勝 / p56~62
カラーグラビア 切り裂く音 / p71~
禅の画家たち(5) / 木下長宏 / p73~78
白秋の「大神戸復興歌」をめぐって / 北原東代 / p64~70
蔭涼軒後藤瑞巌老師事蹟(5) / 島崎義孝 / p47~55
白隠禅師仮名法語・余談(1) / 芳澤勝弘 / p141~147
〈抜粋〉
・ |
2月、古田紹欽編集・解説「禅と芸術 2 」が「ぺりかん社」から刊行される。 (禅と日本文化
: 叢書, 2)
|
2: 心境と表現 / 矢代幸雄 [執筆]
禅芸術とは何か / 芳賀幸四郎 [執筆]
禅芸術の理解(2) / 久松真一 [執筆]
禅と諸芸 / 久松真一 [執筆]
禅の表現美 / 古田紹欽 [執筆]
禅画にみる円相の画 : 芸術・美術を超越した
→神韻縹渺たる円相とは / クルト・ブラッシュ [執筆]
書と禅 / 大森曹玄 [執筆]
西田幾多郎先生の書と人 / 久松真一 [執筆]
|
禅宗美術としての墨蹟と絵画 / 源豊宗 [執筆]
近世禅僧の絵画 : 白隠・仙厓を中心に / 辻惟雄 [執筆]
禅の思想と文芸・美術 / 石田一良 [執筆]
"止観的美意識"の源泉と展開 : 自然の美の見方 / 三崎義泉 [執筆]
空の藝術 : 空即是色の藝境 / 倉澤行洋 [執筆]
禅の藝術をめぐって : 解説 / 倉澤行洋 [執筆]
2の編集・解説者: 倉澤行洋
掲載論文の出典および筆者紹介:. 2: p348-351
・ |
4月、「禅文化. (164) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082360
|
八幡市本妙寺の「江月宗玩宛沢庵宗彭書状」について / 竹中友里代 / p40~45
グラビア 寺宝探訪(52)亀岡・龍潭寺〔二〕 / p89~
高野山私史(4) / 上田真而子 / p46~55
寛保二年の白隠禅師龍潭寺結成をめぐって(2) / 巨島泰雄 / p126~132
禅宗の教団(8) / 沖本克己 / p25~32
大黒雑感--したいことが見えるまで / 無着とき / p67~70
ベルリン・トルファン・コレクションの禅籍資料について/西脇常記/p108~111
綿繍段(1) / 鈴木法音 / p17~24
夢窓詩雑感 泊船庵 / 佐々木容道 / p101~107 |
三余居窓話(14)母ふたり / 西村惠信 / p33~39
円爾弁円と蘭渓道隆 / 竹貫元勝 / p116~125
カラーグラビア 人物と背景の関係 / p71~
禅の画家たち(6) / 木下長宏 / p73~79
海、山、谷戸の街より(1)桜の陰影/北原東代 p112~115
蔭涼軒後藤瑞巌老師事蹟(6) / 島崎義孝 / p56~65
白隠禅師仮名法語・余談(2) / 芳澤勝弘 / p138~146
〈抜粋〉
・ |
6月、禅文化研究所編「禅文化研究所紀要 = Annual report of the Institute for Zen Studies (23)」が「禅文化研究所」から刊行される。pid/4414933
|
禅門に於ける伝灯の性格 / 西村恵信/p1~16
禅と民主主義 / 常盤義伸/p17~55
『禅策問答』について / 沖本克己/p57~88
大乗諸法二辺義について--竜大本『西天竺沙門菩提達摩禅師観門法
→大乗法論』の再検討(1) / 西口芳男/p89~125
最澄が伝えた初期禅宗文献について / 伊吹敦/p127~201
南宋代の臨済僧による絵画解釈について / 道津綾乃/p203~221
『夢窓国師語録』南禅録・註(3) / 佐々木容道/p223~289
禅経験と宗教経験--白隠における見性の
→特色をめぐって / 冲永宜司/p291~332
『大乗荘厳経論』の修行道--『荘厳経論』は
|
→「五道」を説くか /岩本明美/p1~22
集体書評 方広〔ショウ〕主編《蔵外仏教文献》第一輯/p23~128
前言 / 衣川賢次/p24~28
残禅宗文献(天竹国菩提達摩禅師論,禅策問答,息諍論) /
→唐代 語録 研究班/p29~39
仏為心王菩薩説頭陀経 / 伊吹敦/p40~71
仏説孝順子修行成仏経 / 斉藤隆信/p72~87
最妙勝定経 / 落合俊典/p88~91
仏母経 / 直海玄哲/p92~96
附録 北京図書館所蔵敦煌遺書勘査初記 / 神野恭行 ;
→方広〔ショウ〕/p97~128 |
7月、「禅文化. (165)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082361
|
巻頭 カラー 白隠慧鶴筆「富士裾野大名行列図」 / p7~
グラビア 寺宝探訪(53)亀岡・龍潭寺〔三〕 / p107~
夢窓詩雑感 雪中下山 / 佐々木容道 / p22~27 |
禅宗の教団(9) / 沖本克己 / p50~58
白隠禅師仮名法語・余談(3) / 芳澤勝弘 / p129~137
抜粋〉 |
10月、「禅文化. (166)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082362
|
『夢中問答集』における<譬え話> 夢窓疎石が
→自画像に託したもの/西山美香/p7~18
塚田耕雲老師 信州正安寺大梅道場主 / 宮崎次一 / p28~34
グラビア 寺宝探訪(54)亀岡・龍潭寺〔四〕 / p89~
禅宗の教団(10) / 沖本克己 / p79~88
|
夢窓詩雑感 客中偶作 / 佐々木容道 / p35~40
三余居窓話(16)秋立ちぬ / 西村惠信 / p50~57
白隠禅師仮名法語・余談(4) / 芳澤勝弘 / p117~126
『多効能・漢語大詞典索引』の完成について / 芳澤勝弘 / p138~139
〈抜粋〉 |
〇この年、末木文美士編集解説・古田紹欽, 柳田聖山, 鎌田茂雄 監修「禅と思想」が「ぺりかん社」から刊行される。
(叢書禅と日本文化 ; 第8巻)
|
監修のことば
凡例
日本禅における三つの思想類型 道元禅、白隠禅、盤珪禅 鈴木大拙 11
禅における生産と勤労の問題 インド思想を超えた発展 中村元 43
奈良時代の禅 末木文美士 77
仏照徳光と日本達磨宗 石井修道 109
道元の時間論 玉城康四郎 163
七十五巻本『正法眼蔵』編纂説再考 袴谷憲昭 217
日本天台本覚思想の形成過程
→とくに宋朝禅との関連について 田村芳朗 235 |
鎌倉期初頭に観る禅密の交流と瑩山禅師 竹田鉄仙 255
日本中世禅思想の展開 臨済禅を中心として 荻須純道 291
宋学の伝来と禅僧の宋学観 芳賀幸四郎 343
鈴木正三の禅 藤吉慈海 369
白隠禅の思想史的意義 船岡誠 415
盤珪と藤樹・蕃山 近世初期における仏教と儒教との
→交渉の一断面 源了円 445
禅と心学 伊豆山格堂 463
解説 末木文美士 485
索引(人名、書名、事項) 巻末 |
|
| 1998 |
10 |
・ |
1月、「禅文化. (167)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082363
|
近代日本と世界II 西田幾多郎と鈴木大拙 / 上田閑照/p7~27
第五回東西霊性交流レポート パウロと
→白隠の光体験について / 安永祖堂/p28~32
第五回東西霊性交流レポート 修道院生活管見 / 島崎義孝/p33~43
大徳寺夜話 開山大灯国師 / 山田宗敏 /p44~49
禅宗の教団(十一) 余談と変見(その二)
→北京図書館訪問記 / 沖本克己/p50~61
|
夢窓詩雑感 虎谿 / 佐々木容道 / p83~87
三余居窓話(十七) 向上の一路 / 西村惠信 / p124~131
海、山、谷戸の街より(四) 寒梅 / 北原東代 / p112~115
清規から見た「喫茶去」 / 能仁晃道 / p116~122
白隠禅師仮名法語・余談(五) お多福美人のこと/芳澤勝弘/p132~139
〈抜粋〉
・ |
3月、衣斐弘行が「在家佛教47(550) p34~43 在家仏教協会」に「縁と三徳六味の心」を発表する。 pid/6064215
4月、「禅文化. (168) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082364
|
シカゴ万国宗教会議(1893年)--釈宗演の講演 / p7~19
戦争という手段に訴える前に / 安永祖堂 ; 釈宗演 / p7~12
過去の空白は埋められるか?--万国宗教会議における釈宗演の
→演説原稿について考える / ジュデス
→スノ-ドグラス ; 安永祖堂 / p13~19
大徳寺夜話--養叟と一休 / 山田宗敏 / p63~67
山頭火と放哉--「自由律俳句」詩人と仏道(1)/上田閑照/p20~29
イベントとしての宗教 / 平塚景堂 / p98~101
奈良の茶の湯私観 / 泉田宗健 / p32~39
三余居窓話(18)我ら高校3年生 / 西村恵信 / p40~49
大黒(だいこく)雑感--お寺を亡ぼすのはだれ? /無着とき/p68~70
死のうた生のうた / 佐伯裕子 / p30~31
出家の常識・非常識(11)「持鉢(じはつ)」を洗う/水田全一/p58~62 |
夢窓詩雑感--退耕庵 / 佐々木容道 / p79~83
沢彦宗恩と快川紹喜 / 竹貫元勝 / p124~131
グラビア 寺宝探訪(56)京都・東福寺 / / p71~78
白隠慧鶴と近世歌謡(1)白隠禅画の画賛にみる歌謡(上)/小野恭靖/p84~97
禅宗の教団(12) / 沖本克己 / p102~112
蔭涼軒後藤瑞巌老師事蹟(9) / 島崎義孝 / p113~123
錦繍段(5) / 鈴木法音 / p50~56
白隠禅師仮名法語・余談(6)遊女大橋こと慧林尼 / 芳沢勝弘 / p132~141
いっぷく拝見 / / p142~149
『禅文化』バックナンバー / / p152~152
禅文化研究所の本 / / p153~
編集後記 <蛇足> / / p151~151
〈抜粋〉 |
7月、「禅文化. (169)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082365
|
夢窓詩雑感--那智観音 / 佐々木容道 / p79~84
山頭火と放哉--「自由律俳句」詩人と仏道(2)/上田閑照/p95~104
以心崇伝と江月宗玩 / 竹貫元勝 / p118~126
グラビア 寺宝探訪(57)京都・東福寺〔二〕 / / p71~78 |
白隠慧鶴と近世歌謡(2)白隠禅画の
→画賛にみる歌謡(下) / 小野恭靖 / p21~31
白隠禅師仮名法語・余談(7)魚鳥図のこと / 芳沢勝弘 / p137~144
〈抜粋〉 |
9月、 牛込覚心が「生と死の『白隠禅師坐禅和讃』」を「大蔵出版」から刊行する。
|
第1章 衆生本来仏なり(「智慧」をいただく;ゆったりやろうよ;思考の一時停止;和讃入門 ほか)
第2章 大乗の救い(仏のライセンス;仏はあなたの中にいる;生死を支える四つのもの;さまざまな教え ほか)
第3章 この身が仏(ほんとうの幸福とは;宇宙に連なる自性;すべての帰元するところ;仏の智慧)
「BOOKデータベース」 より |
10月、「禅文化. (170)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082366
|
山頭火と放哉 「自由律俳句」詩人と仏道(3) / 上田閑照 / p86~98
栄西と行勇 / 竹貫元勝/p100~105
白隠慧鶴と近世歌謡(3)白隠禅画の画賛にみる芸能風俗 / 小野恭靖 / p58~70
禅宗の教団(13) / 沖本克己 / p48~56
九山宗用と、その門流 / 笹尾哲雄/p18~21
夢窓詩雑感 龍門亭 / 佐々木容道 / p79~84
|
織田有楽と茶室「如庵」 / 泉田宗健 / p38~47
グラビア 寺宝探訪(58)京都・東福寺(3) / / p71~78
三余居窓話(20)厠を拝む / 西村惠信 / p112~117
白隠禅師仮名法語・余談(8)『へびいちご』
→発禁のこと / 芳澤勝弘 / p138~147
〈抜粋〉 |
11月、 丹生川村史編集委員会編「丹生川村史 民俗編」が「丹生川村」から刊行される。
|
口絵
発刊に当たって
はじめに
例言
第一章 乗鞍岳山麓に住む人々 1
第一節 村の沿革概要 1
第二節 農山村に生きる 4
第三節 各集落の昔のくらし 7
|
山口村・町方村・坊方村・大谷村・小野村・根方村・白井村・
芦谷村・板殿村・日面村・日影村・駄吉村・塩屋村・旗鉾村‘
岩井谷村・池之俣村・久手村・瓜田村・法力村・殿垣内村・
小木曽村・下坪村・大萱村・桐山村・細越村・新張村・
下保村・柏原村・三之瀬村・森部村・大沼村・折敷地村 |
第二章宗教性に富んだ年中行事 27
第一節 春の行事 27
一、正月の準備 27
二、正月 30
三、七日正月と小正月 31
四、山神まつりと二十日正月 35
五、節分と初午 36
六、ひな祭りと端午の節句 38
七、田植え 41
第二節 夏の行事 42
一、七夕と盆 42
第三節 秋の行事 46
一、村祭りと村の神社 46
二、庚申講 54
三、収穫の秋 55
第四節 冬の行事 58
一、雪国の冬 58
第三章 自然と共生した衣食住 61
第一節 衣のくらし 61
|
衣服・男の仕事着・女の仕事着・手甲とたすき・
うでぬき・帯と下着・職人の帯・麻布・綿織物・
染め物・着物の仕立て・着物の管理とつくろい・
大正以前の髪型・かねつけ・衣生活の民具から |
第二節 食のくらし 71
|
稗と麦・団子・餅・花餅とあられ・味噌とたまり・漬物・
塩・豊富な山菜・あぶらえ・箱膳・
ふだんの副食物・食事の回数とわりご弁当・
晴れの食・石臼・朴葉の利用・台所の革命と食・
食生活の民具の一部から |
第三節 民家 94
|
飛騨の民家・主な住居の平面図・囲炉裏と煙出し・
仏間と仏壇・馬屋・水屋・カマド・風呂と便所・
樽葺き屋根・樽葺き屋根からトタン葺きへ・
母屋の改築 |
第四節 建築と習俗 109
|
火の用心・火伏せの札・石場かち・青ネバの壁・
大工仕事のはじめと建て前・名大工の建てた家・
石垣のある家
|
第四章 うるおいのある社会生活 115
第一節 集落 115
第二節 集団 117
第三節 助け合い 120
第四節 トコロヅキの実態 122
第五節 交易 127
第六節 人の一生 135
第五章 ひたむきな職人の世界 145
第一節 稲作 145
第二節 稗作 152
第三節 養蚕 156
第四節 木地師 164
第五節 炭焼き 169
第六節 本村と関係のある彫刻師 172
|
石神梅之丞と牛の彫刻・石神梅之丞の牛の値段・
浄願寺のさると左甚五郎・松田亮長の道具箱・
谷口与六と還来寺山門の竜・
大坪藤平(東平)の恵比寿大黒
|
|
第七節 その他の職人 187
第六章 聖地としての山の信仰 193
第一節 自然崇拝としての聖地 193
|
乗鞍山上に現れた五色雲・乗鞍の神々・日抱尊宮・
火傷の跡のある御神像・古代の乗鞍・
明覚法印の乗鞍縁起・円空と乗鞍・
飛州志にでる騎鞍権現・雨乞い
|
第二節 乗鞍を開山した人々 199
修験者による開山・木食秀全と乗鞍開発・板殿仙人
第三節 信仰の山の観光開発 205
第四節 十二ケ岳の信仰 207
第五節 その他の信仰 210
|
なくなった歓喜天像・庚申講参加記・孟蘭盆・精霊迎え・
盆踊り・祖霊崇拝とトコロヅキ・トコロヅキと山の神・
久手のトコロヅキ・トコロズキ考・
日輪神社の山の神祭り・雛人形の信仰・
三峰神社とごんぼだね
|
第七章 祭りと芸能 229
第一節 例祭における芸能の概要 230
第二節 闘鶏楽 239
第三節 獅子舞 241
第四節 板殿の歌舞伎と獅子舞 245
第八章 石仏の里・円空仏の里 251
第一節 石仏の所在 251
第二節 石仏はいつごろから造られたか 257
第三節 霊場めぐり 267
一、千光寺新四国八十八か所霊場 267
二、正宗寺三十三所観音 282
第四節 サイノカミ(道祖神) 287
第五節 庚申石仏 298
第六節 観音信仰 313
第七節 地蔵信仰 319
第八節 その他の石仏 328
|
大日如来‘弁才天・不動明王・役行者・十王・狛犬・
巡拝塔と廻国塔・馬鳴菩薩
|
第九節 主な木仏 342
|
両面宿灘像・千光寺仁王門の金剛力士像・
その他の木仏‘聖徳太子像と白隠禅師・円空・
円空仏のメッカ丹生川村・アクレ薬師・
円空と両面宿灘像・両面宿灘像の斧・
円空仏のほほえみ・岩舟不動の円空仏・
文化財指定の円空仏
|
第九章 神社・寺院から発行されたお札 355
第一節 お札について 355
|
下大谷両家のお札・枚数の多いお札・
タイムカプセルから出たお札・お札の中の梵字・
大下家お札集計・大谷家お札集計
|
第二節 大下家お札一覧 364
第三節 大谷家お札一覧 390
第四節 お札の調査を終えて 426
|
巡礼の旅・お札を通して見た本村との関係県・
養蚕の神仏‘松倉観音の絵馬・大黒像と恵比須像
|
第十章 語り伝える伝説と史話 431
第一節 地名・姓氏伝説 433
第二節 金塊・金鶏・長者伝説 445
第三節 乗鞍伝説 453
第四節 街道伝説・温泉伝説 459
第五節 怪淵・カッパ・大蛇伝説 465
第六節 凶作・雨乞い・日和乞伝説 474
第七節 宗教伝説 479
第八節 大木伝説 492
第九節 名馬伝説 497
第十節 その他の伝説 502
第十一章 民謡と童謡 519
第一節 民謡 519
昭和五十六年調査の民謡・大正三年発行の村誌掲載の民謡
第二節 童謡など 527
轟々・言葉遊ぴ・童謡・今後の調査課題 |
第十二章 方言文化 541
丹生川村の方言分類 541
一、自然 543
二、動物 550
三、植物 556
四、人体 567
五、人生・生活 579
六、衣服と容姿 584
七、飲食と嗜好 590
八、住居 601
九、社会と交際 607
十、生産消費 621
十一、行動と性情 628
十二、事物・時所 639
十三、農山村 654
十四、習俗と信仰 669
第十三章 諺・俗信・民間療法 681
第一節 諺 681
第二節 俗信 681
気象・禁忌・縁起・伝承
第三節 民間療法 696
北方田口登志雄家‘大谷家信応家に伝わる薬種
第十四章 なつかしい民具の数々 703
第一節 特色のある民具 703
|
自然の草木を生かす・創造的なくらしと民具・
シナ皮を利用した民具・山ブドウの皮を利用した民具・
蔓を利用した民具・樹木を利用した民具・
木のまた利用の民具・木のこぶ利用の民具
|
第二節民具を調べて 715
|
村の民俗資料館など二軒の民目・
大谷家に現存する民具の特色・大谷家民具の概要
|
第三節 民具資料目録 721
|
衣・食・住・農耕・畜産’養蚕製糸・山仕事’
土木石割り・大工・手細工・運搬・育児・信仰’
その他・民具写真の一部・民具調査を終えて
|
コラム 八買嘉かぶら 26山で働く人々の禁忌 60
弥惣マス 191江戸時代中期のダンス(飛騨の匠の作か)192
盤持石(力石)調査から 250
仏の手の組 322
狩猟 540
お鍬信仰 680
食合せ 702
囲炉裏のぬくもり 788
民俗編の編集を終って
参考文献
村史編集委員会
度量衡換算表
年代表
付丹生川村地図
コラム 八買嘉かぶら 26
山で働く人々の禁忌 60
弥惣マス 191
江戸時代中期のダンス(飛騨の匠の作か) 192
盤持石(力石)調査から 250
仏の手の組 322
狩猟 540
お鍬信仰 680
食合せ 702
囲炉裏のぬくもり 788
民俗編の編集を終って
参考文献
村史編集委員会
度量衡換算表
年代表
付丹生川村地図
・
・
・
・
|
12月、鈴木省訓が「駒沢女子大学研究紀要 5 p.51-66」に「古月禅と白隠禅の通路」を発表する。 |
| 1999 |
11 |
・ |
1月、「禅文化. (171)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082367
|
白隠慧鶴と近世歌謡(4)白隠禅画の画賛にみる言語遊戯・
→諺・その他 / 小野恭靖 / p31~41
禅宗の教団(14) / 沖本克己 / p87~98
関山に慧眼の諱を与えた禅匠 / 加藤正俊 / p56~61
夢窓詩雑感--護法 / 佐々木容道 / p81~86 |
グラビア 寺宝探訪(59)京都・東福寺〔四〕 / p71~80
三余居窓話(21)兎の記憶 / 西村恵信 / p106~113
白隠禅師仮名法語・余談(9)「布袋携童図」のこと / 芳沢勝弘 / p124~133
〈抜粋〉
・ |
1月、「歴史と旅 26(2)[(397)]」が「秋田書店」から刊行される。 pid/7947574
|
特別読物 八百万の神と日本人の神信仰 地域社会・
→日常生活の中で人の必要性に応じて生滅、
→禍福をもたらす神社 / 宮田登 / 36~43
特別読物 自立する現代の神と仏たち 神は仏と
→習合して日本的文化を形成してきたが今は
→互いに独自の道を歩む / 阿部正路/44~49
特別読物 釈尊の教えと日本人の仏教観
→多数の宗派―、釈尊の教えはどのようにして
→日本人に浸透していったか/ひろさちや/50~57
特別読物 病を癒す神仏への信仰 ハイテク医療が
→発達した現代も神仏に病気平癒の願かけする
→姿はつづく!! / 立川昭二 / 342~351
八百万の神々への祈り
除厄の神 素戔嗚尊 / 嶋津宣史 / 58~61
五穀豊穣の神 豊受大神 / 森本仙介 / 62~65
山の神 木花咲耶姫神 / 阿部正路 / 66~67
防火の神 迦具土神 / 阿部正大 / 68~71
防風の神 天御柱神 / 阿部正路 / 72~73
事業繁栄の神 宇迦之御魂神/井後政晏/74~77
商売繁盛の神 事代主神 / 尾崎友季 / 78~79
経営手腕の神 吉備津彦神 / 塩崎昇 / 80~81
航海安全・豊漁の神 住吉三神/尾崎友季/82~85
交通安全の神 猿田彦大神 / 鎌田東二 / 86~89
陶器の神 埴安彦神 / 阿部正大 / 90~91
医薬の神 少彦名神 / 森本仙介 / 92~93
織物の神 天羽槌雄神 / 阿部正大 / 94~95
酒造の神 大山咋神 / 井後政晏 / 96~97
製塩の神 塩土老翁神 / 尾崎友季 / 98~99
刀・包丁の神 金山彦神 / 尾崎友季 / 100~101
菓子の神 田道間守神 / 塩崎昇 / 102~103
土建の神 大山祇神 / 阿部正大 / 104~105
不動産業の神 阿遅〔スキ〕高日子根神 /
→井後政晏 / 106~107
倉庫業の神 天香山神 / 井後政晏 / 108~109
縁結びの神 大国主神/白山芳太郎/110~113
夫婦和合の神 伊邪那岐・伊邪那美神 /
→森本仙介 / 114~115
安産の神 玉依姫神 / 阿部正路 / 116~117
延命長寿の神 武内宿禰 / 森本仙介 / 118~119
知恵の神 思兼神 / 白山芳太郎 / 120~121
学問の神 菅原道真 / 稲田智宏 / 122~123
芸能の神 天鈿女命 / 稲田智宏 / 124~125
言霊の神 天児屋神 / 白山芳太郎 / 126~127
占いの神 太玉神 / 白山芳太郎 / 128~129
力技の神 天手力雄神 / 稲田智宏 / 130~131
武道の神 建甕槌神 / 塩崎昇 / 132~133 |
仏典が示す知恵と教え
阿含経 / 阿部慈園 / 134~137
般若心経 / 久保田展弘 / 138~141
華厳経 / 久保田展弘 / 142~145
維摩経 / 藤原成一 / 146~149
法華経 / 羽田守快 / 150~153
浄土三部経 / 久保田展弘 / 154~157
涅槃経 / 藤原成一 / 158~161
弥勒経 / 藤原成一 / 162~165
金光明最勝王経 / 山崎龍明 / 166~169
楞伽経 / 山崎龍明 / 170~173
梵網経 / 久保田展弘 / 174~177
大日経 / 小峰彌彦 / 178~181
金剛頂経 / 小峰彌彦 / 182~185
理趣経 / 小峰彌彦 / 186~189
わが家の聖典
天台宗 円頓章 / 羽田守快 / 190~193
真言宗 秘蔵宝鑰 / 本多隆仁 / 194~197
浄土宗 一枚起請文 / 武田鏡村 / 198~201
浄土真宗 正信念仏偈 / 武田鏡村 / 202~205
臨済宗 白隠禅師坐禅和讃/戸田実山/206~209
曹洞宗 正法眼蔵 / 竹内弘道 / 210~213
日蓮宗 立正安国論 / 武田鏡村 / 214~217
時宗 一遍上人語録 / 武田鏡村 / 218~221
俗信の神仏
鍾馗 / 中村光行 / 222~225
仁王 / 用川眞澄 / 226~229
牛頭天王 / 山本兼一 / 230~231
犬神 / 山本兼一 / 232~233
宇賀神 / 藤巻一保 / 234~235
金神 / 藤巻一保 / 236~237
歳徳神 / 藤巻一保 / 238~239
金精神 / 山本兼一 / 240~241
神農 / 山本兼一 / 242~243
第六天魔王 / 藤巻一保 / 244~245
コロポックル神 / 高橋道弘 / 246~247
船霊 / 豊島泰国 / 248~249
蔵王権現 / 藤巻一保 / 250~251
蘇民将来 / 藤巻一保 / 252~253
疫病神 / 豊島泰国 / 254~255
貧乏神 / 大宮司朗 / 256~257
式神 / 大宮司朗 / 258~259
ザシキワラシ / 前川さおり / 260~261
オシラサマ / 長谷川浩 / 262~263
ひだる神 / 大宮司朗 / 264~265
付喪神 / 大宮司朗 / 266~267
|
橋姫 / 大宮司朗 / 268~269
祈願と魔除けの神仏
お賓頭盧 / 中村光行 / 270~271
撫牛 / 豊島泰国 / 272~273
身代わり地蔵/用川眞澄/274~275
とげ抜き地蔵/用川眞澄/276~277
水子地蔵 / 用川眞澄 / 278~279
角大師豆大師/豊島泰国/280~281
摩多羅神 / 高橋道弘 / 282~283
淡島神 / 豊島泰国 / 284~285
銭洗弁天 / 天堂晋助 / 286~287
田の神 / 桑原重美 / 288~289
シーサー / 桑原重美 / 290~291
石敢当 / 桑原重美 / 292~293
祈願成就詣で
六阿弥陀参り/菊森慎太郎/294~295
六地蔵参り/菊森慎太郎/296~297
お百度参り / 市原真琴 / 298~299
千社参り / 平木健介 / 300~301
裸参り / 平木健介 / 302~303
丑の刻参り / 市原真琴 / 304~305
おけら参り / 菊森慎太郎 / 306~307
胎内巡り / 菊森慎太郎 / 308~309
抜け参り / 菊森慎太郎 / 310~311
初詣 / 平木健介 / 312~313
十三参り / 市原真琴 / 314~315
で ガン封じ寺 / 天堂晋助/316~319
ボケ封じ寺 / 天堂晋助 / 320~321
中風除け寺 / 天堂晋助 / 322~323
ぽっくり寺 / 天堂晋助 / 324~325
エイズ除け神社/天堂晋助/326~327
彼岸への旅立ち
補陀落山 / 高橋道弘 / 328~331
ニライカナイ/出口富美子/332~333
三途の川 / 中村光行 / 334~335
即身仏 / 西村孝文 / 336~337
弥陀来迎 / 西村孝文 / 338~339
黄泉国 / 西村孝文 / 340~341
カラー口絵 諸病平癒の願かけ//11~
グラビア 御利益の宝庫・
→浅草寺を歩く//19~
グラビア 東京の御利益
→スポット巡り//23~
編集後記 / 星野昌三 / 354~354
・
・ |
4月8日~5月9日、熊本県立美術館に於いて「永青文庫展 : 白隠と仙厓 第17回 細川護立コレクションの原点」展が開かれる。
4月、熊本県立美術館編「永青文庫展 : 白隠と仙厓 第17回 白隠と仙厓 : 細川護立コレクションの原点」が「熊本県立美術館」から刊される。
4月、衣斐弘行が「在家佛教48(563) p62~67 在家仏教協会」に「禅と念佛 」を発表する。 pid/6064228
4月、「禅文化. (172)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082368
|
白隠慧鶴と近世歌謡(5)おたふく女郎・粉引図と粉引歌 / 小野恭靖 / p36~45
夢窓詩雑感--〔ヘン〕界一覧亭 / 佐々木容道 / p79~84
夜船閑話(やせんかんな)白隠と良寛 / 加藤正俊 / p54~62
グラビア 寺宝探訪((60))南明禅師(一) / / p71~78
三余居窓話(22)時計エレジー / 西村惠信 / p46~53 |
自然について / 平塚景堂 / p102~105
白隠禅師仮名法語・余談(10)「毛槍奴立ち小便図」
→ひめもそ・このかみ」 / 芳澤勝弘 / p132~141
〈抜粋〉
・ |
6月、古谷稔が「茶道の研究 44(6)(523) p36~39 三徳庵,茶道之研究社」に「書との出会い(6)白隠慧鶴筆 円相図賛「遠州浜松」」を発表する。 pid/7892084
7月、「禅文化. (173)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082369
|
鈴木大拙における「東洋的な見方」 / 上田閑照 / p41~56
一休宗純の幼年期--嵯峨地蔵院のこと / 加藤正俊 / p62~70
ポケットに歌を--寺山修司 / 佐伯裕子 / p38~40
夢窓詩雑感 仏成道 / 佐々木容道 / p79~84
|
グラビア 寺宝探訪(61) 南明禅師(二) / / p71~78
三余居窓話(23)キェルケゴールへの旅 / 西村恵信 / p100~107
白隠禅師仮名法語・余談(11)「軸中軸」について/芳澤勝弘/p132~141
〈抜粋〉 |
10月、「禅文化. (174)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082370
|
禅の智恵に学ぶ / 安永祖堂/p7~23
鈴木大拙における「東洋的な見方」 / 上田閑照/p41~56
一休宗純の幼年期--嵯峨地蔵院のこと / 加藤正俊/p62~70
ひつじの啼いた河--臨済院記念碑除幕式訪中団
→に参加して / 細川太輔/p32~37
ポケットに歌を--寺山修司 / 佐伯裕子/p38~40
|
<夢窓詩雑感>聚散因縁 / 佐々木容道 / p79~82
グラビア 寺宝探訪(62) 夢窓国師(一) / / p70~70
三余居窓話(二十四)感傷の秋 / 西村惠信 / p114~121
白隠禅師仮名法語・余談(十二)地獄のこと その一/芳澤勝弘/p136~145
〈抜粋〉
・ |
10月、津川秀夫が「現代のエスプリ = L'esprit d'aujourd'hui (通号 387) p.68~75」に「軟酥の法 (イメージ療法 ; 臨床イメージ法の実際と新しい試み) 」を発表する。 |
| 2000 |
12 |
・ |
1月、「禅文化. (175)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082371
|
真宗文化と禅仏教 / 柳田聖山/p7~22
恩師 明道老師を偲んで / 新谷宜脩/p23~25
大珠院--WEST / トーマス カーシュナー/p26~29
手記 月影抄--樵月庵耕雲老師(6) / 木内樵山/p56~64
三人の女性と大拙先生(第1回) / 上田閑照/p39~55
関山慧玄の甥にされてしまった雲山の
→戸惑い(1)/加藤正俊/p30~38
デタラメダ! / 佐伯裕子/p66~70
出家の常識・非常識 (18)「在家僧侶」
→養成講座/水田全一/p104~109
ブッダガヤの流れ星 / ブライアン バークガフニ/p110~117
時・時の大拙先生(第1回)"And then" / 岡村美穂子/p99~103 |
夢窓詩雑感 亀頂塔 / 佐々木容道/p79~85
グラビア 寺宝探訪(63)夢窓国師(二) //p71~78
三余居窓話(25)孫の恵生に伝えたいこと / 西村恵信/p92~98
錦繍段(12)天隠竜沢撰 宇都宮遯庵解説 (楷書部分) / 鈴木法音/p86~91
二十世紀の重さ / 平塚景堂/p118~121
1999年、25年目の竜宮城レポート(1) / 富士玄峰/p134~140
白隠禅師仮名法語・余談(13)白隠の地獄について
→(その2)/芳沢勝弘/p123~133
いっぷく拝見 //p141~147
『禅文化』バックナンバー //p150~150
禅文化研究所の本 //p151~154
編集後記<蛇足> //p149~149 |
3月、小野澤隆が富士フェニックス短期大学編「富士フェニックス論叢 (8)
p.73~83」に「禅語の英訳についての一考察--白隠禅師著『夜船閑話』をめぐって」を発表する。
3月、ルッジェリ, アンナが「人間文化学研究集録 9 1 p.95-109 大阪府立大学大学院」に「禅公案の一考察」を発表する。 (IRDB)
4月、「禅文化. (176)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082372
|
バチカン・レポート / 安永祖堂/p50~60
沓沢慈眼と「世中道歌百諭」 / 笹尾哲雄/p61~63
関山慧玄の甥にされてしまった雲山の戸惑い / 加藤正俊/p21~34
木草は自分の心--若山牧水の歌 / 佐伯裕子/p46~49
時・時の大拙先生-2-ブライス先生のこと
→死んでからでは遅くはないか / 岡村美穂子 / p85~89 |
夢窓詩雑感 辞世 / 佐々木容道 / p79~83
グラビア 寺宝探訪(64)夢窓国師(三) / / p71~78
三余居窓話(26)郷愁の地蔵菩薩 / 西村恵信 / p64~70
白隠禅師仮名法語・余談(14)「小車の翁」図について
→/ 芳沢勝弘 / p130~140
〈抜粋 |
5月、直木公彦 が「白隠禅師 : 健康法と逸話」を「日本教文社」から刊行する。
7月、「禅文化. (177) 」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082373
|
達磨大師坐像小考 --埼玉・平林寺像を中心に / 花村統由/p23~33
近世禅宗史寸考--古月の法嗣、北禅道済は実在したか / 能仁晃道/p48~52
手記 月影抄--樵月庵耕雲老師(8) / 木内樵山/p15~22
林恵鏡老師の思い出 / 笹尾哲雄/p53~57
時・時の大拙先生(3)的はずれ コスモスの救い / 岡村美穂子 / p110~117
夢窓詩雑感 寓居 / 佐々木容道 / p81~86
|
グラビア 寺宝探訪(65)夢窓国師(四) / / p73~80
三余居窓話(27)初めての中国 / 西村惠信 / p87~93
白隠禅師仮名法語・余談(15)すたすた坊主と
→ちょぼくれ坊主 / 芳澤勝弘 / p133~142
〈抜粋〉
・ |
9月、木村俊彦編「新発見白隠自筆自伝書」が「山喜房佛書林」から刊行される。
|
白隠禅師自筆自伝書解読解題 / 木村俊彦 著
重賞下勇士列名之端由 / 白隠慧鶴 著
新発見白隠自筆自伝書の研究 / 木村俊彦 著 |
白隠年譜について / 陸川堆雲 著
草稿本『勅諡神機独妙禅師白隠和尚年譜』訓読 / 陸川堆雲 著
白隠の著述 / 陸川堆雲 著 |
10月、「禅文化. (178)」が「禅文化研究所」から刊行される。 pid/6082374
|
ブッダフェイス--無門関を読む(9) / 柳田聖山/p7~14
常照皇寺阿弥陀如来及び両脇侍像について / 花村統由/p23~37
茅葺屋根と宝石の小箱 / 泉田宗健/p124~132
手記 月影抄--樵月庵耕雲老師(9) / 木内樵山/p107~113
破茅庵主祖諄について / 笹尾哲雄/p15~18
妙心寺第七世明江叡西堂(2) / 加藤正俊/p50~60 |
おかしければ笑う、悲しければ泣く--
→正岡子規の歌 / 佐伯裕子/p114~117
時・時の大拙先生(4)同行人 / 岡村美穂子 / p38~41
夢窓詩雑感 因乱書懐 / 佐々木容道 / p81~86
乞食桃水絵伝(2) / 能仁晃道 ; 面山瑞方 / p61~66
白隠禅師仮名法語・余談(16)播州姫路一揆のこと / 芳澤勝弘 / p142~145 |
10月10日~11月26日迄、渋谷区立松涛美術館に於いて「Zenga : 帰ってきた禅画
: アメリカギッター・イエレン夫妻コレクションから = Zenga : the return from America : zenga from the Gitter-Yelen collection」展が開かれる。 東京会場:渋谷区立松涛美術館
10月、山下裕二監修・矢島新ほか編「Zenga : 帰ってきた禅画 : アメリカギッター・イエレン夫妻コレクションから = Zenga : the return from America : zenga from the Gitter-Yelen collection」が「浅野研究所」から刊行される。
11月3日~11月19日、飯田市美術博物館に於いて「白隠禅師 : 仏道者からの21世紀への提唱 : 天地を貫く魂の姿、その精神と教え : 特別企画展」が開かれる。 主催: 白隠展実行委員会, 飯山市美術館博物館
11月14日から12月9日、花園大学歴史博物館第二展示室に於いて「観る読む悟る白隠
: 傑僧とその一門 : 花園大学歴史博物館開館記念特別展」が開かれる。
11月、花園大学歴史博物館編「観る読む悟る白隠 : 傑僧とその一門 : 花園大学歴史博物館開館記念特別展」が「花園大学歴史博物館」から刊行される。 所蔵:京都府立京都学・歴彩館
12月、禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" (79) 」が「禪學研究會」から刊行される。 pid/4414865
|
日記類に見る絶海中津--「坦率性」に注目して/朝倉和/p1~16
僧伝小考二題 / 加藤正俊 / p17~24
見性成仏説と宝性論 / 古賀英彦 / p25~47
『挿注参釈廣智禅師蒲室集』引用漢籍及び漢詩について/孫容成/p48~74
禅宗東西祖統説考--柳田聖山先生の「禅宗東西祖統対照表」を
→めぐって / 田中良昭 / p75~127
表現の問題--西田哲学と田辺哲学を介して / 花岡永子 / p128~149 |
「弁邪正説」訓註(下) / 廣田宗玄 / p150~178
僧を改めて徳士と爲す--北宋徽宗時代の
→仏法受難 / 吉川忠夫 / p179~198
白隠慧鶴における洞上五位の一考察 /
→ Anna Ruggeri / p199~221
禅学関係雑誌論文目録(1997年) / / p1~1
・ |
○、この年、大慧宗杲[撰]「大慧宗門武庫」が「禅文化研究所」から刊行される。 和装本
(善本覆刻叢書, )
|
駿河三島龍沢寺豊洲禅師手沢本
白隠提唱書入本/東嶺講評書添
皇都 植村藤右衛門, 小川源兵衛 安永5年再刻の影印 |
上下合本 題簽の書名: 大慧普覺襌師宗門武庫
附: 雪堂行和尚拾遺録
・ |
|
| 2001 |
13 |
・ |
1月、山下裕二が「ユリイカ 33(1) (通号 442) p.158~168」に「若冲・白隠・コンテンポラリー (特集 2001年大江戸文化の旅 ; ヴィジュアル・スペクタクル) 」を発表する。
1月、渡辺守邦, 後藤憲二編「新編蔵書印譜」が「青裳堂書店」から刊行される。 (日本書誌学大系 ; 79)
2月24日~4月22日迄、神奈川県立歴史博物館に於いて「Zenga : 帰ってきた禅画
: アメリカギッター・イエレン夫妻コレクションから = Zenga : the return from America : zenga from the Gitter-Yelen collection」展が開かれる。 神奈川展:神奈川県立歴史博物館
3月、中華佛学研究所聖厳博士古稀記念論集刊行会編「東アジア仏教の諸問題
: 聖厳博士古稀記念論集」が「山喜房佛書林」から刊行される。
|
『法華経』に於けるデーシャナー / 三友量順 著
『息諍論』考 / 木村清孝 著
『二入四行論』文献研究史 / 田中良昭 著
善導と法然 / 高橋弘次 著
善導大師の浄土教とその周辺 / 深貝慈孝 著
人間浄土ということ / 沖本克己 著
大乗起信論の再検討 / 吉津宜英 著
中国における石刻経の濫觴 / 桐谷征一 著
中国の仏教と民衆 / 永井政之 著
了世と知訥 / 中島志郎 著
東西文明止場の構造・試論 / 竹内明 著
日蓮の『立正安国論』執筆に関する研究 / 北川前肇 著
・ |
日蓮聖人の代受苦思想 / 庵谷行亨 著
中世仏教説話に見られる日本人の意識 / 蓑輪顕量 著
白隠慧鶴禪師の法語及び禪畫に於ける政治批判 / 芳澤勝弘 著
General preface / Mitomo kenyo 著
Preface / Bhikkhu Huimin 著
A short introduction to the life of Ven. Sheng-yen / Lee Chih-fu 著
Sabbatthivada(Sarvastivadin) or Sabbatthavada(Sarvarthavadin) / 三友健容
著
A study on Yingen Ryuki / 竹貫元勝 著
How can grasses and trees attain Buddhahood / 末木文美士 著
Buddha within and beyond history / 下田正弘 著
Characteristics of transmission in Zen Buddhism / 西村惠信 著
The approaches of early-medieval Chinese Buddhists to other religions / Young-ho Kim 著
A study on a catalogue of Buddhist Library in T'ang's China / 手島一真
著
・ |
3月、畠山忠が兵庫大学短期大学部研究集録編集委員会編「兵庫大学短期大学部研究集録
(35) p.137~143」に「<ノート>白隠と天風--神経症並びにその周辺領域の境界例」を発表する。
3月、ルッジェリ, アンナが「人間文化学研究集録 101 p.59-69大阪府立大学大学院 人間文化学研究科」に「白隠と現代の公案の問題 : 『十牛図』および『洞山五位』を通して」を発表する。 (IRDB)
3月、白隠慧鶴原著,芳澤勝弘訳注禅文化研究所編「白隠禅師法語全集 第9冊 (遠羅天釜) 」が「禅文化研究所」から刊行される。
4月28日~6月5日迄、山口県立美術館に於いて「「Zenga : 帰ってきた禅画 : アメリカギッター・イエレン夫妻コレクションから = Zenga : the return from America : zenga from the Gitter-Yelen collection」展が開かれる。 山口展:山口県立美術館
6月、白隠慧鶴原著,芳澤勝弘訳注,禅文化研究所編「白隠禅師法語全集 第11冊(假名因縁法語・
布鼓・諫言記)」が「禅文化研究所」から刊行される。
7月、矢島新が國華編輯委員会編「國華 106(12) (通号 1269) p.27~29,図25」に「白隱筆 達磨圖 」を発表する。
7月。形山睡峰が「大法輪 68(7) p.100~103」に「白隠禅と健康法 (特集 坐禅・瞑想とは--真の目覚めへの道) 」を発表する。
10月、岡部王成が「大法輪 68(10) p.154~159」に「白隠『夜船閑話(やせんかんな)』の真実義--内丹術を蘇生させた白隠禅」を発表する。
11月、栗田勇が「※白隠禅師の読み方 : 今に甦る「心と体の調和-内観法」の極意」を「祥伝社」から刊行する。
(祥伝社黄金文庫) 注記 「※謎の禅師白隠の読み方」(平成7年刊)の改題 所蔵:静岡県立中央図書館
11月、白隠慧鶴原著,芳澤勝弘訳注,禅文化研究所編「白隠禅師法語全集 第12冊 (隻手音聲 三教一致の辯 寶鏡窟之記 兎專使稿)」が「禅文化研究所」から刊行される。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 179) p.133~142」に「白隠禅師仮名法語・余談(17)梁田蛻巌との邂逅 」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 180) p.129~146」に「白隠禅師仮名法語・余談(18)俳人・高月狸兄のこと 」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 181) p.123~133」に「白隠禅師仮名法語・余談(19)盆山図について」を発表する。
○、この年、山下裕二が「IS : Panoramic magazine : Intellect & sensitivity
(86) p.75~80」に「古美術の20世紀--視線の変節(6)1959年の白隠--欧米が熱狂したZEN 」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 182) p.108~117」に「白隠禅師仮名法語・余談(20)鳥刺し図について」を発表する。 |
| 2002 |
14 |
・ |
2月、水上勉が「水上勉自選仏教文学全集 5」を「河出書房新社」から刊行する。
2月、芳澤勝弘訳注「白隠禅師法語全集 第13冊」が「禅文化研究所」から刊行される。
|
お婆々どの粉引き歌
寝惚之眼覚
御洒落御前物語 |
安心法興利多々記
福来進女
見性成仏丸方書 |
御代の腹鼓
大道ちよぼくれ
おたふく女郎粉引歌 |
施行歌〔ほか〕
・
・ |
3月、小野恭靖が「江戸期流行歌謡資料の基礎的研究」を「大阪教育大学教育学部」から発表する。 (IRDB)
|
本研究はさらなる資料の発掘と位置付けが切望される、江戸期の流行歌謡を取りあげて基礎的な作業を行うことを眼目とした。当初は諸図書館や文庫に収蔵されている未紹介の流行歌謡資料の閲覧調査を志し、『ありまぶし』や『潮来絶句』などの資料整理を行った。その後、禅僧の著作、商人の売り立ての歌謡、様々な絵画などを資料として、そのなかに書き入れられた江戸期流行歌謡を析出することに力を注いだ。禅僧の著作に関しては、研究期間以前に既に考察した盤珪永琢、白隠慧鶴作の教訓歌謡研究を踏まえて、新たに大愚良寛・古月禅材の歌謡について、流行歌謡の観点から紹介と分析を行った。商人の売り立ての歌謡に関しては、江戸期に大量に残された商人の歌謡を、売り立ての歌謡(物売りの歌)と、商人の売り立てをもとに新たに歌謡に仕立て直した歌(売り声の歌)の2種に分類して考察した。絵画資料と歌謡との関係をめぐっては、禅画(白隠慧鶴・仙厓義梵)、おもちゃ絵、江戸期美人面、近世初期風俗画、風流踊絵、赤木の判じ物等の絵画資料を用いて位置付けを行った。また、研究期間中、眼目に据えたもう一点は、江戸期流行歌謡の各句索引作成の試みであった。これについては近世小唄調と称される7・7・7・5の歌形の歌謡の各句を、分割してカードに起こした後、五十音順に配列し、清書原稿を作成した。現存は見直し検討作業を行っているが、近時の刊行を目指している。この書は歌謡研究者のみならず、近世文学研究者や一般の日本古典文学愛好家の待望の書であり、刊行が実現すれば座右に置かれるべきものである。今後しばらくは、刊行の実現に向けて引き続き努力をはかっていきたいと考えている。
平成10年度~平成13年度科学研究費補助金 基盤研究(C)(2) 研究成果報告書 |
3月、小島稔豊が「日本医事新報 (4064) p.57~59」に「MEDICAL ESSAYS 医僧・白隠」を発表する。
3月、 Anna Ruggeriが博士論文「禅公案の思想的研究 ー白隠慧鶴を中心としてー」を発表する。
4月、「江戸の宗教美術 : 円空・木喰/白隠・仙厓/良寛」が「学研」から刊行される。(日本美術全集;23) 所蔵:新潟県立図書館
10月、「週刊日本の美をめぐる (通巻22号) 江戸5 仏のおしえ 円空 白隠」が「小学館」から刊行される。
(小学館ウィークリーブック) 所蔵:島根県立図書館 岐阜県図書館
11月、花園大学編集「※花園大学歴史博物館図録」が「花園大学」から刊行される。
※『花園大学歴史博物館開館記念特別展 : 見る読む悟る白隠 : 傑僧とその一門』と『花園大学歴史博物館2001年度秋季特別展 : 森寛斎と森派の絵画』を再録したもの
11月29日、 家永三郎が亡くなる 。(89歳)
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 184) p.125~134」に「「猿廻図」と「猿曳の翁図」-白隠禅師仮名法語・余談(22) 」を発表する。
|
芳澤勝弘が禅文化 (163~184)に発表した「禅文化研究所 白隠禅師仮名法語・余談(1~22)迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
発行年 |
発表論文名 |
内容 |
pid |
| 1 |
禅文化 (163) p141~147 |
1997-01 |
余談(1) 表題なし |
. |
pid/6082359 |
| 2 |
禅文化 (164) p138~146 |
1997-04 |
余談(2) 表題なし |
. |
pid/6082360 |
| 3 |
禅文化 (165) p129~137 |
1997-07 |
余談(3) 表題なし |
. |
pid/6082361 |
| 4 |
禅文化 (166) p117~126 |
1997-10 |
余談(4) 表題なし |
. |
pid/6082362 |
| 5 |
禅文化 (167) p132~139 |
1998-01 |
余談(五) お多福美人のこと |
. |
pid/6082363 |
| 6 |
禅文化 (通号 168) p.132~141 |
1998-04 |
(6)遊女大橋こと慧林尼 |
. |
. |
| 7 |
禅文化 (通号 169) p.137~144 |
1998-07 |
(7)魚鳥図のこと |
. |
. |
| 8 |
禅文化 (通号 170) p.138~147 |
1998-10 |
(8)『へびいちご』発禁のこと |
. |
. |
| 9 |
(禅文化通号 171) p.124~133 |
1999-01 |
(9)「布袋携童図」のこと |
. |
. |
| 10 |
禅文化 (通号 172) p.132~141 |
1999-04 |
(10)「毛槍奴立ち小便図」「ひめもそ・このかみ」 |
. |
. |
| 11 |
禅文化(通号 173) p.132~141 |
1999-07 |
(11)「軸中軸」について |
. |
. |
| 十二 |
禅文化(通号 174) p.136~145 |
1999-10 |
(十二)地獄のこと その一 |
. |
. |
| 13 |
禅文化(通号 175)1 p.123~133 |
2000-0 |
(13)白隠の地獄について(その2) |
. |
. |
| 14 |
禅文化 (通号 176) p.130~140 |
2000-04 |
(14)「小車の翁」図について |
. |
. |
| 15 |
禅文化 (通号 177) p.133~142 |
2000-07 |
(15)すたすた坊主とちょぼくれ坊主 |
. |
. |
| 16 |
禅文化 (通号 178) p.142~145 |
2000-10 |
(16)播州姫路一揆のこと |
. |
. |
| 17 |
禅文化 (通号 179) p.133~142 |
2001- |
17)梁田蛻巌との邂逅 |
. |
. |
| 18 |
禅文化 (通号 180) p.129~146 |
2001- |
(18)俳人・高月狸兄のこと |
. |
. |
| 19 |
禅文化 (通号 181) p.123~133 |
2001- |
(19)盆山図について |
. |
. |
| 20 |
禅文化 (通号 182) p.108~117 |
2001- |
(20)鳥刺し図について |
. |
. |
| 21 |
禅文化 (通号 183) p.123~132 |
2002- |
(21)大道芸人の舌耕・と白隠法語 |
. |
. |
| 22 |
禅文化 (通号 184) p.125~134 |
2002 - |
「猿廻図」と「猿曳の翁図」(22) |
. |
. |
|
○、この年、能仁晃道が「禅文化 (通号 185) p.40~48」に「 近世禅宗史寸考 清見寺の陽春と法常寺の大道-そして白隠禅師」を発表する。
○、この年、竹下 ルッジェリ・アンナ(Anna Ruggeri) が「博士論文 禅公案の思想的研究」を発表する。
|
| 2003 |
15 |
・ |
2月、芳澤勝弘・神野恭行,西村惠学共編「白隠禅師法語全集 総合索引 : 語彙索引 和語・和訓索引 人名索引 寺社名索引 引書索引」が「禅文化研究所」から刊行される。
|
芳澤勝弘訳注「白隠禅師法語全集1~14 別冊 」についての内訳一覧表
| 全集No |
巻頁 |
発行年 |
白隠著名 |
訳注・共編者名 |
その他 |
| 1 |
第1冊 |
1999.5 |
辺鄙以知吾 ; 壁訴訟 |
芳澤勝弘 |
. |
| 2 |
第2冊 |
1999.8 |
於仁安佐美 |
芳澤勝弘 |
. |
| 3 |
第3冊 |
1999.9 |
壁生草 ; 幼稚物語 |
芳澤勝弘 |
. |
| 4 |
第4冊 |
2000.7 |
夜船閑話 |
芳澤勝弘 |
. |
| 5 |
第5冊 |
2000.1 |
高塚四娘孝記/八重葎(ヤエムグラ) ; 巻之1 |
芳澤勝弘 |
. |
| 6 |
第6冊 |
2000.3 |
延命十句経霊験記/八重葎(ヤエムグラ) ; 巻之2) |
芳澤勝弘 |
. |
| 7 |
第7冊 |
1999.12 |
策進幼稚物語 ; 高山勇吉物語/八重葎(ヤエムグラ) ; 巻之3 |
芳澤勝弘 |
. |
| 8 |
第8冊 |
2000.5 |
さし藻草 ; 御垣守 |
芳澤勝弘 |
. |
| 9 |
第9冊 |
2001.3 |
遠羅天釜 |
芳澤勝弘 |
. |
| 10 |
第10冊 |
2000.10 |
仮名葎 |
芳澤勝弘 |
. |
| 11 |
第11冊 |
2001.6 |
假名因縁法語 ; 布皷 |
芳澤勝弘 |
. |
| 12 |
第12冊 |
2001.11 |
隻手音聲 : 三教一致の辯(一名:藪柑子)・寶鏡窟之記・兎專使稿 |
芳澤勝弘 |
. |
| 13 |
第13冊 |
2002.2 |
お婆々どの粉引き歌 寝惚之眼覺 御洒落御前物語 安心法興利多々記
福來進女 見性成佛丸方書 御代の腹鼓 大道ちよぼくれ
おたふく女郎粉引歌 施行歌 子守唄 草取唄 坐禪和讚 善惡種蒔鏡和讚
孝道和讚 藻鹽集 |
芳澤勝弘 |
. |
| 14 |
第14冊 |
2002.2 |
延命十句經を勸む 看病の要諦 庵原平四郎物語 病中の覺悟
親類の不和合を諫める 眼病の妙藥 死字法語 |
芳澤勝弘訳注 |
. |
| 別冊 |
別冊 |
2003.2 |
総合索引 : 語彙索引 和語・和訓索引 人名索引 寺社名索引 引書索引 |
芳澤勝弘・神野恭行,西村惠学共編 |
. |
|
3月、笠井哲が「印度學佛教學研究 51(2) p.688-693 」に「白隠の丹田呼吸法の系譜」を発表する。 J -STAGE
○、この年、矢野豊彦が「禅 (11) p.69~76」に「白隠禅師の『独り按摩』 独りあんま(前編)」を発表する。
○、この年、大野栄人が「禅研究所紀要 (26~)」と「 愛知学院大学文学部紀要
= Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin University:愛知学院大学論叢(~
33)」に 「『天台小止観』の研究(1~ 9)」を発表する。
|
| No |
雑誌名頁
禅研究所紀要 |
発行年月 |
論文名 |
雑誌名頁
愛知学院大学論叢 |
発行年 |
論文名 |
| 1 |
(通号 26) p.103~134 |
1998-03 |
『天台小止観』の研究(1) |
欠(不明 ) |
. |
. |
| 2 |
欠(不明 ) |
. |
. |
(通号 28) p.274~248 |
1998 |
<訳注>『天台小止観』の研究(2) |
| 3 |
(通号 27) p.33~72 |
1999-03 |
『天台小止観』の研究(3) |
欠(不明 ) |
. |
. |
| 4 |
欠(不明 ) |
. |
. |
(30) p.402~387 |
2000 |
<訳注> 『天台小止観』の研究(4) |
| 5 |
(29) p.47~101 |
2001-03 |
『天台小止観』の研究(5)-1 |
欠(不明 ) |
. |
. |
| 6 |
(30) p.53~115 |
2002-03 |
『天台小止観』の研究(5)-2 |
(31) p.284~243 |
2001 |
<訳注> 『天台小止観』の研究(6) |
| 7 |
(31) p.87~138 |
2003-03 |
『天台小止観』の研究(7) |
欠(不明 ) |
. |
. |
| 8 |
欠(不明 ) |
. |
. |
(32)p.248-209 |
2002 |
<訳注>『天台小止観』の研究(8) |
| 9 |
欠(不明 ) |
. |
. |
(33) p.228~178 |
2003 |
<訳注>『天台小止観』の研究(9) |
|
※ 論文内容に欠番が多かったので再調査が必要 2023・2・6 保坂 |
| 2004 |
16 |
・ |
1月、山下裕二が「美術の窓 = The window of arts 23(1) (通号 249) 2004-01 p.14~23」に「インタビュー 山下裕二氏が選ぶ魅力的な人物画
蕭白・雪村・白隠 (巻頭特集 '04人物画セレクション70)」を発表する。
2月、山田無文が「坐禅和讃講話 ; 自己をみつめる ; 仮名法語意訳」を「禅文化研究所」から刊行する。
(無文全集 / 山田無文著, 第12巻)
4月、野口剛が「茶道雑誌 68(4) p.40~46,16~19」に「京都文化博物館 特別展 白隠禅師生誕320年「白隠 禅と書画」展」を発表する。
4月10日~5月23日、京都文化博物館に於いて「特別展 白隠禅師生誕320年「白隠 禅と書画」展」が開かれる。
主催: 京都文化博物館, 日本経済新聞社, 京都新聞社
5月、沖本克己が「大法輪 71(5) p.46~53」に「泥と蓮 白隠禅師を読む(1)なぜ白隠なのか」を発表、連載を開始する。
8月、「大法輪 71(8) 特集「地獄」を考える p.63~126」が「大法輪閣」から刊行される。
|
南無地獄大菩薩--白隠の地獄観 原 東演 p.64~68
日本人と地獄 藤井 正雄 p.69~73
これが地獄だ--『往生要集』にみる八大地獄 村越 英裕 p.74~81
地獄の住人たち--白描画で描く 牧 宥恵 p.82~87
法話・閻魔さんと地蔵さん 松浦 俊海 p.88~92
日本文学と地獄 志村 有弘 掲載誌 p.93~97
|
「節談」が説く地獄 谷口 璽照 掲載誌 p.98~101
子供たちに地獄を教えよう 現代人と地獄 諸橋 精光 p.102~106
チベット仏教の説く地獄 正木 晃 p.107~111
ダンテ『神曲』の地獄 平川 祐弘 p.112~115
道教の説く地獄田中 文雄 p.116~119
全国「地獄」ガイド 下嶋 敏夫 p.120~125 |
8月、公方俊良が「空海たちの般若心経 : 六人の名僧が説く智慧と空の世界 :
智光 最澄 盤珪 空海 道元 白隠」を「日本実業出版社」から刊行する。
9月8日、水上勉が亡くなる。(85歳)
10月、松下宗柏が「禅と念仏 (18) p.98~103」に「白隠禅師伝(5)正受老人の荒療治」を発表する。
10月25日~11月27日、花園大学歴史博物館第2展示室に於いて「2004年度秋期特別展「白隠 禅画と墨蹟新出:龍雲寺コレクション」」展が開かれる。
10月、花園大学歴史博物館編集「白隠 : 禅画と墨蹟 : 新出:龍雲寺コレクション」が「花園大学歴史博物館」から刊行される。
○、この年、矢野豊彦が「禅 (12) p.70~77」に「白隠禅師の『独り按摩』 独りあんま(後編)」を発表する。
○、この年、徳田泰伸が兵庫大学論集編集委員会編「兵庫大学論集 (9) p.111~118」に「書評 荒井荒雄著『夜船閑話--白隠禅による健康法』大蔵出版」を紹介する。
○、この年、三浦雅彦が日本思想史学会編「日本思想史学 (36) p.100~120」に「鈴木正三の門流と近世洞済をめぐる一考察--白隠と面山の視点から」を発表する。
○、この年、日比野秀男が「常葉学園大学研究紀要. 教育学部 = Tokoha Gakuen University research review. Faculty of Education (25) p.47~58」に「瓢箪から駒--白隠禅師の見た朝鮮通信使」を発表する。
○、この年、浅井京子が早稲田大学會津八一記念博物館編「早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要
(6) p.1~14」に「白隠画研究へのアプローチ」を発表する。
○、この年、河合正朝が「Booklet 12 p.7-16」に「白隠と禅画 : 室町時代の禅僧が描く水墨画との比較において(芸術のロケーション)」を発表する。 (IRDB)
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 191) p.81~90」に「碁をうつ白隠像」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 192) p.115~122」に「見上げてみれば鷲頭山--白隠の上求菩提下化衆生」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 193) p.107~114」に「白隠禅画とメビウスの環--表がそのまま裏になる世界」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 194) p.103~109」に「白隠のミソサザイ図--せっかい・すり鉢・擂粉木(すりこぎ)」を発表する。
|
| 2005 |
17 |
・ |
3月、堀内伸二, 東方研究会著「白隠直筆『法華経細注』の研究 ]が「堀内伸二(出版社)」から刊行される。
注記 文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書
4月、松下宗柏が p.98~103」に「白隠禅師伝(最終回)白隠禅の開花」を発表する。
|
松下宗柏が「禅と念仏 (~19)」に発表した「白隠禅師伝(1~6)迄の内訳一覧表
| No |
雑誌名「禅と念仏」と頁数 |
発行年月 |
論文名 |
| 1 |
禅と念仏( ) |
・ |
※ |
| 2 |
禅と念仏( ) |
・ |
※ |
| 3 |
禅と念仏( ) |
・ |
※ |
| 4 |
禅と念仏( ) |
・ |
※ |
| 5 |
禅と念仏(18) p.98~103 |
2004-10 |
正受老人の荒療治 |
| 6(最終回) |
禅と念仏(19) p.98~103 |
2005-04 |
白隠禅の開花 |
※白隠禅師伝(1~4)については内容不明なため調査要 2023・1・10 保坂 |
5月、芳澤勝弘が「白隠 禅画の世界」を「中央公論新社」から刊行する。
9月、山折哲雄, 末木文美士編著「名僧たちの教え: 日本仏教の世界」が「朝日新聞社」から刊行される。 (朝日選書 ; 784)
|
はじめに-名僧が開いた日本仏教の世界とは 山折哲雄 3
日本仏教の特徴とその流れ 末木文美士 13
第一章 仏教伝来とその広がり-飛鳥・奈良時代
第一章 聖徳太子 石田尚豊,新川登亀男 21
第一章 行基 千田稔,北条勝貴 31
第一章 コラム 東大寺ゆかりの名僧-良弁と重源 北条勝貴 36
第一章 鑑真 東野治之,蓑輪顕量 41
第一章 役小角 宮家準,浅田正博 51
第二章 密教の隆盛-平安時代
第二章 最澄 栗田勇,田村晃祐 61
第二章 空海 松長有慶,頼富本宏 70
第二章 円仁と円珍 栗田勇,大久保良峻 80
第二章 空也と源信 速水侑,池見澄隆 90
第二章 覚鑁 宮坂宥勝,吉田宏哲 99
第二章 西行 高橋英夫,山田昭全 107
第三章 民衆に広がる仏教-鎌倉時代
第三章 法然 石上善応,町田宗鳳,林田康順 121
第三章 栄西 中尾良信,西村恵信 130
第三章 コラム 蘭渓道隆と無学祖元が
→伝えた中国の禅 浅見竜介 136
第三章 親鸞 山折哲雄,佐藤正英 139
第三章 道元 大谷哲夫,石井清純 148
第三章 明恵 奥田勲,西山厚 157
第三章 日蓮 渡辺宝陽,佐藤弘夫 166
第三章 一遍 栗田勇,今井雅晴 174
|
第三章 叡尊と忍性 松尾剛次 183
第三章 運慶 水野敬三郎 190
第三章 女性仏教者たち(無外如大ほか) 勝浦令子 194
第三章 コラム 仏教は女性をどうみたか 西口順子 197
第三章 コラム 尼門跡とは 久保貴子 200
第四章 権力に抗する仏教-室町・安土桃山時代
第四章 無窓疎石 末木文美士,佐々木容道 205
第四章 蓮如 山折哲雄,山崎竜明 212
第四章 日親 中尾堯,寺尾英智 221
第四章 一休 末木文美士,松岡心平 228
第四章 雪舟 島尾新 237
第四章 利休 熊倉功夫 243
第五章 幕藩体制の中の仏教-江戸時代
第五章 天海 菅原信海,千田孝明 251
第五章 沢庵 船岡誠,伊藤克己 259
第五章 隠元と白隠 西村恵信,安永祖堂 267
第五章 良寛 栗田勇,竹村牧男 276
第五章 円空 長谷洋一,佐藤もな 285
第六章 新しい仏教をめざして-明治以降
第六章 清沢満之・鈴木大拙・田中智学 福島栄寿,安富信哉,
→竹村牧男,大谷栄一 293
第六章 コラム 田中智学と日蓮主義 大谷栄一 301
第六章 大谷光瑞と河口慧海 上山大峻,奥山直司,正木晃 306
第六章 あとがき 末木文美士 315
第六章 名僧・高僧一覧 316 |
○、この年、「禅文化 (通号 198) p.73~80」に「グラビア ※無窮子蔵近世禅林墨蹟 白隠」が掲載される。 |
| 2006 |
18 |
・ |
○、この年、「禅文化 (通号 199) p.73~80」に「グラビア ※無窮子蔵近世禅林墨蹟 白隠」が掲載される。
※通番の有無については未確認 2022・12・24 保坂健次
1月、田中大三郎監修「白隠禅師墨蹟集」が「六藝書房 」から刊行される。
3月、沼津市史編さん委員会, 沼津市教育委員会編「沼津市史 通史編 近世」が刊行される。
|
序
凡例
第四編 近世の沼津
第一章 江戸時代の幕開けと沼津 2
第一章 第一節 近世前期の政治支配 2
第一章 第一節 一 中村一氏の駿河支配と
→横田村詮の法度 2
第一章 第一節 二 大久保忠佐と天野康景 10
第一章 第一節 三 初期代官支配と旗本知行地 18
第一章 第二節 近世の村の成立 32
第一章 第二節 一 土着・移住と村の開発 32
第一章 第二節 二 寛文延宝の検地と村の拡大 40
第一章 第二節 三 近世の村の成立と展開 52
第一章 第三節 近世の町宿の成立と支配 62
第一章 第三節 一 東海道宿場の設置と街道の整備 62
第一章 第三節 二 元禄期の沼津宿と原宿 73
第二章 沼津の村と町 82
第二章 第一節 村・町の概要 82
第二章 第一節 一 村むらの様子 82
第二章 第一節 二 沼津と原 94
第二章 第一節 三 一九世紀の村の変動
→(石川村を中心に) 111
第二章 第一節 四 災害に見舞われる 123
第二章 第二節 村・町の生業と生活 138
第二章 第二節 一 石の切り出しと人びとの動き 138
第二章 第二節 二 往還稼と小作人 157
第二章 第二節 三 人びとの生活 167
第二章 第二節 四 家と女性 183
第二章 第三節 騒動と事件 197
第二章 第三節 一 宿の事件簿 197
第二章 第三節 二 村の事件簿 203
第二章 第三節 三 村役人と小前百姓の
→対立から村方騒動へ 209
第三章 助郷と入会・協同 222
第三章 第一節 宿と助郷 222
第三章 第一節 一 宿駅の役割と助郷 222
第三章 第一節 二 宿財政の困窮と宿助成 228
第三章 第一節 三 宿・助郷の協同と争い 234
第三章 第二節 街道を行き交う人々と情報 245
第三章 第二節 一 街道を行き交う人々 245
第三章 第二節 二 街道を行き交う情報 250
第三章 第三節 協同と入会 261
第三章 第三節 一 愛鷹牧と山麓の農村 261
第三章 第三節 二 「愛鷹山論出府日誌」に
→みられる争論 276
第三章 第三節 三 用水をめぐる協同と争論 282
第四章 近世沼津の文化 291
第四章 第一節 東海道沼津と文化 291
第四章 第一節 一 文化は西から―上方文化との交流 291
第四章 第一節 二 並河誠所と川合隣山 297
第四章 第一節 三 朝鮮通信使との接触 304
第四章 第一節 四 白隠と沼津 314
第四章 第一節 五 京風文化と植松家 326
第四章 第一節 六 植松家と帯笑園 338
第四章 第二節 城下町沼津と文化 349
第四章 第二節 一 文化は東から―大江戸文化との
→交流 349
第四章 第二節 二 藩士と百姓・町人 353
第四章 第二節 三 町人の学問―三枚橋鈴木家の家学 360
第四章 第二節 四 藩医島津家の医と学問 369
第四章 第三節 村の文化・町の文化 381
第四章 第三節 一 古きを温ねて 六代松碑の建立 381
第四章 第三節 二 村の寺子屋・町の手習塾 392
第四章 第三節 三 俳諧の流行 404
第四章 第三節 四 地芝居の流行 422
第四章 第三節 五 草莽の国学者たち 433
第四章 第三節 六 洋学と海外への関心 447
第四章 第四節 信仰と儀礼 459
第四章 第四節 一 沼津の寺社 459
第四章 第四節 二 祭の風景 473
第四章 第四節 三 巡る信仰・訪れる信仰 481
第五章 近世後期の沼津と政治支配 497
第五章 第一節 沼津藩成立と水野氏 497
第五章 第一節 一 沼津移封前の水野氏とその系譜 497
第五章 第一節 二 沼津藩の成立と沼津城 505
第五章 第二節 沼津藩初期三代の推移 520
第五章 第二節 一 沼津藩と幕政とのかかわり 520
第五章 第二節 二 沼津藩の領国支配 536
第五章 第二節 三 家臣の構成と暮らしのすがた 554
第五章 第三節 幕末の沼津 566
第五章 第三節 一 沼津藩と異国船警備 566
第五章 第三節 二 幕政の動揺と沼津藩 575
第五章 第三節 三 幕府の滅亡と沼津藩の去就 583
第五章 第三節 四 幕末の騒乱と民衆 592
あとがき 602
通史編「近世」執筆分担一覧 606
通史編「近世」資料提供者及び協力者 612
沼津市史編さん関係者名簿 614
写真・図・表一覧
索引
写真・図・表一覧
・本巻に掲載した写真・図・表について、資料および写真
→所蔵者・作成者・出典などを各編の章ごとに記した。
→ただし、資料の所蔵者と写真の所蔵者が異なる場合は、
→写真の提供者を併記した。
・人名・団体名については敬称を略した。
・執筆者提供の写真および図版と、市史編さん係撮影による写真
→および作成図版は記載を略した。
・図版等を転載する際一部加筆修正したものもある。
【写真】
〔1章〕
1 中村一氏肖像 (京都市)妙心寺大龍院所蔵 静岡県立中央
→図書館歴史文化情報センター提供
2 横田村栓肖像 (米子市)妙興寺所蔵静岡県立中央図書館
→歴史文化情報センター提供
3 上石田村に宛てた横田村栓の法度井口亘生所蔵
4 中村忠一の墓所 (米子市)感應寺静岡県立中央図書館
→歴史文化情報センター提供
5 大久保忠佐の墓所 妙伝寺(沼津市東間門)
6 興国寺城絵図 根古屋自治会所蔵 沼津市歴史民俗資料館保管
7 天野康景の墓所 西念寺(小田原市)
8 徳川頼宜肖像 和歌山県立博物館所蔵静岡県立中央図書館
→歴史文化情報センター提供
9 野村彦太夫為重の墓所 永明寺(沼津市幸町)
10 『駿河国明細高附』 沼津市教育委員会所蔵
11 久松家先祖の由緒書 沼津市教育委員会所蔵
12 広沼・浮島ケ原と新田村 望月宏充所蔵
13 浮島沼の風景 富士市立博物館所蔵・提供
14 寛文12年石川村検地帳 森修彦所蔵
→沼津市明治史料館保管
15 現在の門池とその周辺
16 牧堰用水系統図 飯田貞雄所蔵
17 原六軒町の浅間神社 (沼津市原)
18 沼津山王前の一里塚 沼津市歴史民俗資料館所蔵
19 黄瀬川橋(東街便覧図略) 名古屋市博物館所蔵
20 駿州沼津古城之図 間宮義高所蔵 沼津市明治史料館保管
21 沼津宿絵図 沼津市歴史民俗資料館所蔵
〔2章〕
1 駿州駿河之郡上香貫村絵図 鈴木勝所蔵
→沼津市歴史民俗資料館保管
2 岡一色村絵図 岡一色自治会所蔵 沼津市明治史料館保管
3 駿河国駿東郡東間門村縮図 田中恵一郎所蔵
→沼津市明治史料館保管
4 木賃宿 豊橋市二川宿本陣資料館所蔵静岡県立中央図書館
→歴史文化情報センター提供
5 沼津宿大旅籠藤田屋絵図 沼津市教育委員会所蔵
6 沼津宿間宮本陣絵図 間宮義高所蔵 沼津市明治史料館保管
7 原宿絵図 杉山浩章所蔵
8 小林村のようす(『嘉永七甲寅歳 地震之記』)
→山崎英彦所蔵
9 沼津城絵図 神戸潔所蔵
10 「巡夜約正」(『原宿植松家日記』より) 植松靖博所蔵
11 内匠丁場新切開山麓絵図 勝呂安所蔵
12 昭和30年代の戸田の石搬出の様子
13 枝家主法愚案 和田夏樹所蔵 沼津市明治史料館保管
14 大泉寺 (沼津市東熊堂)
15 孝行者伝兵衛の文書 鈴木道矢所蔵 沼津市明治史料館保管
16 臨産・乳飲子養育の図 (『小児?育金礎標』より)
17 病気をひきおこすと考えられた「虫」
→(『小児□育金礎標』より)
18 端午の節句の図 (『女四季用文章女小学教草』より)
19 ひな祭りの図 (『女四季用文章女小学教草』より)
20 婚礼の様子 (『女大学操鑑』より)
21 火あぶり木架図 江川家所蔵 伊豆の国市教育委員会提供
22 お白洲取り調べ図 伊豆の国市教育委員会所蔵・提供
23 大通寺 (沼津市原)
24 淡島の石丁場跡 (沼津市内浦重寺) |
25 博打風景 (「徳川幕府刑事図譜」より)
→静岡県立中央図書館所蔵
26 『原宿植松家日記』の中の張り紙 植松靖博所蔵
27 木瀬川村の村絵図 江川家所蔵
28 村役人の退役願 大古田忠雄所蔵
〔3章〕
1 原宿助郷図 静岡県立中央図書館所蔵
2 御大名帳 沼津市教育委員会所蔵
3 日記・見聞雑記 植松靖博所蔵
4 紀州家七里飛脚 逓信総合博物館所蔵・提供
5 駿州駿東郡・富士郡三牧大絵図 加藤敏之所蔵
6 文久二壬戌年御捕馬御用塩谷豊後守殿駿州
やJ日愛鷹御牧場出張之図(部分) 世古直史所蔵
7 野馬と焼印を押す位置 (『駿国雑誌』より)
8 元野牧捕え込みの模型
9 『愛鷹山論出府日誌』の表紙 長倉政子所蔵
10 愛鷹山論絵図 沼津市教育委員会所蔵
11 牧堰
12 門池の中に築かれた「安政島」
13 狩野川通御普請所絵図 鈴木勝所蔵
→沼津市歴史民俗資料館保管
〔4章〕
1 渡部十左衛門宛並河五一郎(誠所)書状
2 『発音捷径』 国立国会図書館所蔵
3 『駿州名勝志』 国立公文書館所蔵
4 浮絵原・吉原より見る富士之景 本間美術館所蔵
5 朝鮮人江戸道中行烈 京都大学附属図書館所蔵・提供
6 東海道五十三次 原 名古屋市博物館所蔵
7 東海道五十三次 原 奈木盛雄所蔵
8 「富嶽百景」来朝の不二 (芸艸堂発行『富嶽百景』より転載)
9 原 原井慈鳳所蔵
10 曲馬 山内カズヱ所蔵 (大法輪閣出版発行
→「白隠さんの絵説法」より転載)
11 曲馬図 東京国立博物館所蔵・提供
12 張果老図 (静岡市清水区興津)東勝院所蔵
13 白隠慧鶴墓塔 松蔭寺(沼津市原)
14 白隠「地獄極楽変相図」 (沼津市大塚)清梵寺所蔵
15 白隠「猫の巻物」(部分) 植松靖博所蔵 佐野美術館提供
16 白隠自画像自画賛 (三島市)龍沢寺所蔵
→三島市教育委員会提供
17 白隠『於仁安佐美』 秋山太郎所蔵
18 池大雅の斯経宛蘭渓依頼の画料受領の書状 植松靖博所蔵
→ 佐野美術館提供
19 円山応挙「双鶴図」 東京国立博物館所蔵・提供
20 植松蘭渓像(円山応端筆) 植松靖博所蔵 静岡県立中央図書館
→歴史文化情報センター提供
21 葛鳥石筆額字「曳尾亭」 (沼津市原)徳源寺所蔵
→佐野美術館提供
22 『金生樹譜別録』の植木窖 国立国会図書館所蔵
23 帯笑園之図(部分) 植松靖博所蔵
24 「帯笑園縮緬」(『松蘭譜』雑花園文庫) 小笠原亮所蔵
25 江戸「流行料理包丁」番付 沼津市明治史料館所蔵
26 文政再版改正江戸図(部分) 国立歴史民俗博物館所蔵
27 田辺四友 田辺俊一所蔵
28 『発音捷径』序(鈴木仰山筆) 国立国会図書館所蔵
29 『中庸繹解』跋(鈴木舜民筆)
30 島津退翁肖像 島津邦彦所蔵
31 島津一斎木像 島津邦彦所蔵
32 文覚六代助命の図 (西村青帰画)市川匡夫所蔵
33 天保8年「沼津本町絵図」の「六代御前旧跡」部分
→浅間神社所蔵
34 六代松碑の現状 (沼津市東間門)
35 種玉庵漣山の「咏古松」 沼津市明治史料館所蔵
36 田中仲二郎門人奉納灯籠 (沼津市東間門・妙伝寺)
37 田中仲二郎墓碑 (沼津市東間門・妙伝寺)
38 桃源院舜政筆子塚(沼津市大平)
39 長福寺日勝筆子塚 (沼津市西浦木負)
40 西尾麟角顕彰碑 (沼津市千本)
41 重寺村天満大自在天神棟札 (沼津市内浦重寺)
42 女大学宝箱 大川宏和所蔵 沼津市歴史民俗資料館保管
43 算術問答書 大川宏和所蔵 沼津市歴史民俗資料館保管
44 新編赤野往来 植松靖博所蔵
45 雨の日数 (「近世・近代ぬまづの俳人たち」より転載)
46 六花庵官鼠肖像 (沼津市浅間町)東方寺所蔵
47 「俳関」の額 勝俣誠所蔵 三島市郷土資料館提供
48 種玉庵漣山肖像 水口直幸所蔵 三島市郷土資料館提供
49 穂麦庵士敬肖像 相磯文宣所蔵
50 潮来舎砂明肖像 沼津市明治史料館所蔵
51 鷲頭明神社 (沼津市大平)
52 重寺観音堂の人形浄瑠璃絵馬 (沼津市内浦重寺)
53 仮名手本忠臣蔵奉納絵馬 (沼津市内浦長浜)安養寺所蔵
54 芝居見舞到来控 和田夏樹所蔵 沼津市明治史料館保管
55 文楽「伊賀越道中双六」沼津の段 十兵衛吉田玉男
→平作吉田文吾
→出上実提供 協力:NPO法人人形浄瑠璃文楽座
56 東海道 沼津(三代歌川豊国筆) 沼津市明治史料館所蔵
57 植松東渚 植松春子所蔵
58 竹村茂雄 土屋浩一所蔵
59 和田宜歳 栢森甫宗所蔵
60 「入学問答」稿本に付された石橋常則の序文
→国立歴史民俗博物館所蔵
61 「誓詞帳」に記された羽田清助の入門時の署名
→国立歴史民俗博物館所蔵
62 富士万こと羽田直秀 羽田祥一所蔵
63 深沢雄甫(文温) 世古明夫所蔵
64 沼津藩士武田簡吾が刊行した 『輿地航海図』
→ 沼津市明治史料館所蔵
65 駒留良蔵
66 第一小学校内の道喜塚
67 永明寺 (沼津市幸町)
68 沼津に遺る宗門人別帳 森修彦所蔵 沼津市明治
→史料館保管・土町区有文書 沼津市歴史民俗資料館所蔵
69 木瀬川の鶴亀観音 潮音寺 (沼津市大岡)
70 現在の山王宮 (沼津市平町)
71 現在の浅間宮 (沼津市浅間町)
72 白砂運びの儀式を行う神職と当殿御前女
→(『鎮座八百八十年記念誌』より転載)
73 小屋敷の庚申塔 (沼津市小屋敷)
74 『駿河記』に掲載された黄瀬川観音
75 赤野観音堂 (沼津市柳沢)
76 木食観正碑 (沼津市鳥谷)
77 唯念名号碑 (沼津市大平)
78 新玉稲荷神社 (沼津市下河原町)
79 楊原神社内の吉田神社 (沼津市下香貫楊原)
〔5章〕
1 傳通院本堂 (東京都)傳通院提供
2 沼津城絵図 田中恵一郎所蔵
3 傍示杭
4 『御代々略記』 早稲田大学図書館所蔵
5 田沼意次肖像 牧之原市相良史料館所蔵
→静岡県立中央図書館歴史文化情報センター提供
6 『沼津略記』 早稲田大学図書館所蔵
7 水野忠成肖像 (京都市)妙心寺福壽院所蔵
→静岡県立中央図書館歴史文化情報センター提供
8 駿州沼津水野出羽守御入部行列絵図(部分) 西尾市岩瀬文庫所蔵
9 印旛沼普請工事の刷物 沼津市明治史料館所蔵
10 沼津城絵図 沼津市明治史料館所蔵
11 大浜陣屋絵図 杉浦弘所蔵
12 沼津城瓦 平松太計彦所蔵
13 瓦の刻印 沼津市教育委員会所蔵
14 沼津城瓦 沼津市教育委員会所蔵
15 五泉陣屋絵図 鈴木勝所蔵 沼津市歴史民俗資料館保管
16 忠友の絵画 沼津市明治史料館所蔵
17 『駿藩士録』静嘉堂文庫所蔵
18 『駿藩士録』静嘉堂文庫所蔵
19 布衣装束の江川英龍 江川家所蔵 伊豆の国市教育委員会提供
20 川奈砲台跡
21 大行寺の日露交渉の碑 (沼津市戸田)
22 ディアナ号の模型 沼津市戸田造船郷土資料博物館所蔵
23 忠寛の詠歌短冊 沼津市明治史料館所蔵
24 阿部千萬多肖像 個人蔵 本間美術館保管
25 服部純(峰次郎・弁内)肖像 松永容子所蔵
26 水野忠誠肖像 鈴木典所蔵
27 水野忠敬肖像 水野忠璋所蔵
28 霊山寺 (沼津市本郷町)
29 鍵屋に残る扁額 枚方市教育委員会所蔵・提供
30 ヘダ号模型 沼津市戸田造船郷土資料博物館所蔵
31 『水野伊織日記』 水野幸所蔵
32 お札降りの様子 望月宏充所蔵
33 郷筒について記した文書 西熊堂自治会所蔵
→沼津市明治史料館保管
34 駿東赤心隊旗図 (清水町)八幡神社所蔵
→清水町教育委員会提供
【図版】
〔1章〕
1 近世初期駿東郡域の支配関係年表図
2 元禄15年(1702)沼津の領主と支配地 |
3 延享4年(1747)頃の領主と支配地
4 石川村小字名入り地図
5 15か村の牧堰門池用水依存率
→(牧堰門池用水沿革史より)
6 沼津駅家文書(『駿河志料』巻九十六)
〔3章〕
1 愛鷹牧士を勤めた家の変遷
2 尾上牧付村落図
3 元野牧付村落図
4 霞野牧付村落図
5 天保4年払馬の売却先
6 谷戸川用水と二つの井組
〔4章〕
1 並川誠所・川合隣山学統図
2 朝鮮通信使経路図 (三宅英利「近世の
→日本と朝鮮」講談社学術文庫参照)
3 植松家系図
4 植松蘭渓と家族
5 鈴木家系図
6 鈴木家学統図
7 島津家系図
8 島津家学統図
9 沼津市域筆子塚の分布
10 洋学者系統図
〔5章〕
1 沼津藩水野家系図
2 沼津藩成立前の駿州駿東郡中・南部の
→支配別郷村分布図
3 沼津藩成立当初(安永6年末)の
→水野家支配郷村(城附地)分布図
4 沼津藩3万石当時の駿州駿東郡中・
→南部の支配別郷村分布図
5 伊豆における沼津藩領
【表】
〔1章〕
1 沼津市域の天正~寛永期検地帳
2 牧堰の割
3 沼津代官の推移
4 元禄~安永期の村高と領主
5 慶長14年 石川村検地帳
6 沼津市域の寛文・延宝検地帳
7 寛文12年 石川村検地帳の字名と筆数
8 石川村検地帳の田畑・名請人の推移
9 寛文12年 石川村検地帳
10 延宝2年 上石田村検地帳
11 上石田村の出入作高
12 「寛永改高」と「元禄郷帳」の村高の変化
13 近世初期の大平村略年表
14 大平村の山林分割
15 牧堰井組15か村の用水掛り高
16 東海道宿村の往還道間数と掃除丁場
17 木瀬川橋の掛替と修理一覧
18 「原宿三町差出帳」の比較
19 元禄7年 沼津宿の定助郷と
→大助郷および増助郷
20 元禄7年 東海道原町助郷帳
21 沼津宿の人馬継立数
〔2章〕
1 村むらの概要
2 村むらのようす
3 我入道村の状況
4 沼津三町の構成
5 沼津本町御用金
6 明治3年沼津上土町の構成
7 沼津宿内の社寺・神社
8 原町の入作・出作
9 大塚町の入作・出作
10 享保11年原宿への助郷勤高
11 享保12年原宿への助郷勤高
12 享保13年原三町の家数・人口
13 宿役人・本陣・脇本陣・旅籠屋の持高,
→家内召使の変遷
14 原宿の構成
15 原宿内の社寺など
16 往還掃除担当
17 原駅の軒並
18 本陣・脇本陣・旅籠屋
19 石川村の構成
20 石川村階層構成
21 農民の持高と家族構成
22 女性筆頭者の家
23 通婚圏
24 奉公人(雇用・放出)推移
25 石川村の見分願
26 上小林村の概要
27 上小林村の階層構成
28 沼津の災害
29 城内の被害の様子
30 城の周辺の被害
31 灰寄人足
32 消火活動への慰労
33 残存石数
34 石丁場預石数
35 三の丸修復時入用石
36 本丸・小天守台修復入用石
37 石垣普請入用石(請負人太田屋)
38 石垣普請入用石(請負人九左衛門)
39 松平家の丁場預かり人の御目見得帳より
40 石切人足
41 植松家の土地所持の状況
42 延享~寛延期の和田屋の棚おろし残高
43 嘉永6年分 和田家の年間生活諸
→経費と小作料代金
44 祝儀の件数
45 寄せられた祝儀品
46 七五三の祝儀品(1)
47 七五三の祝儀品(2)
〔3章〕
1 享保12年原宿の御伝馬高・歩行高
2 文政2卯年原宿人足駄賃
3 文政2卯年原宿馬賃銭
4 享保10年沼津宿助郷村々
5 享保10年原宿助郷村々
6 文政3年原宿増助郷村々
7 文政2年原宿惣人馬立辻
8 天保12年原宿拝借金・借金書上
9 寛政8年沼津宿助成金・運用
10 文化期の助郷積立金の運用
11 享保15年助郷東西組合
12 近世後期・助郷東西組合
13 文政5年公家衆賃銭未払い分
14 文政5~6年囚人護送時の人馬役(下り)
15 天保7年の愛鷹牧の収支
16 文久3年野馬方御貸附金
17 香貫用水に関する両香貫村明細帳の記述
〔4章〕
1 植松蘭渓の京土産
2 浮世絵に描かれた沼津の朝鮮通信使
3 漢詩唱和
4 白隠の曲馬図
5 駿河の因縁話
6 延命十句観音経の霊験
7 植松応令江戸立寄先
8 沼津市域にみる庶民の武術学習者
9 東間門村の持高構成
10 沼津市域の筆子塚
11 明治2年の沼津の教育
→((1)子ども(2)弟子(筆子))
12 「大平年代記」の地芝居((1)若者の地芝居(
→2)鷲頭山祭礼狂言)
13 沼津市域の竹村茂雄門人一覧
14 地誌より見る沼津市域の近世寺院
15 浅間宮祭礼の当番組
16 横道巡礼
〔5章〕
1 三河国領内の郷村及村高
2 駿東郡中・南部の江戸時代郷村変遷対照表
3 安永6年沼津藩成立前の
→支配者別郷村・村高数
4 沼津城の城地の規模と面積
5 沼津城の城郭構成
6 伊豆国・駿河国(除駿東郡)所在の
→沼津藩領郷村の村高比較表
7 三河国所在の沼津藩領郷村の年次別村高表
8 初期の沼津藩台場大砲数
・
・ |
3月、野村英登が花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism (1) p.247~265」に「白隠の修養法と道教の錬金術--内観・軟酥の法と内丹」を発表する。
4月、河崎晃一監修「山本發次郎コレクション : 遺稿と蒐集品にみる全容」が「淡交社」から刊行される。 重要 1000円
(自費出版「山本發次郎遺稿」(山発産業 昭和28年刊) の改題改訂版)
|
山本發次郎遺稿 : 書道私論
白隠禅師の絵画表現
白雲荘放談
佐伯祐三遺作蒐集について
白隠芸術の特異性
無名の書聖三輪田米山
正岡子規
独立日本の行く道
|
『山本發次郎遺稿』序文 / 山本清雄 [著]
山本發次郎とコレクション : 「野獣派」と山本發次郎 / 橋爪節也 [著]
蒐集家・山本發次郎 / 河崎晃一 [著]
新茶室巡り九 : 小田坂の山荘山本發次郎を訪う/ 中井浩水 [著]
※対談「武者小路実篤氏と山本發次郎氏の対談会」
関西趣味人列伝(五) : 山本發次郎氏/ 中井浩水 [著]
大大阪と文化(抜粋) / 伊達俊光 [著]
珍コレクション物語(抜粋) / 洲之内徹 [著] |
山本 發次郎(やまもとはつじろう、1887年(明治20年)5月[1] - 1951年(昭和26年))は、日本の実業家、美術コレクター
9月、沖本克己が「大法輪 73(9) p.172~177」に「泥と蓮 白隠禅師を読む(29・最終回)どう見ても--おわりにかえて」を発表する。
|
沖本克己が「大法輪」に発表した「泥と蓮 白隠禅師を読む(1~29)迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻号頁 |
発行年月 |
論文名 |
内容 |
| 1 |
71(5) p.46~53 |
2004-05 |
白隠禅師を読む(1)なぜ白隠なのか |
, |
| 2 |
71(6) p.42~49 |
2004-06 |
白隠禅師を読む 滔々たる流れ |
, |
| 3 |
71(7) p.134~141 |
2004-07 |
白隠禅師を読む 傑物・白隠の登場 |
, |
| 4 |
71(8) p.127~133 |
2004-08 |
白隠禅師を読む(4)修行と大悟 |
, |
| 5 |
71(9) p.136~143 |
2004-09 |
白隠禅師を読む(5)坐禅和讃(1) |
, |
| 6 |
71(10) p.156~162 |
2004-10 |
白隠禅師を読む(6)坐禅和讃(2) |
, |
| 7 |
71(11) p.146~153 |
2004-11 |
白隠禅師を読む(7)坐禅和讃(3) |
, |
| 8 |
71(12) p.156~163 |
2004-12 |
白隠禅師を読む(8)毒語心経(1) |
, |
| 9 |
72(1) p.148~155 |
2005-01 |
白隠禅師を読む(9)毒語心経(2) |
, |
| 10 |
72(2) p.152~159 |
2005-02 |
白隠禅師を読む(10)毒語心経(3) |
, |
| 11 |
72(3) p.155~163 |
2005-03 |
白隠禅師を読む(11)毒語心経(4) |
, |
| 12 |
72(4) p.148~155 |
2005-04 |
白隠禅師を読む(12)毒語心経(5) |
, |
| 13 |
72(5) p.162~168 |
2005-05 |
白隠禅師を読む(13)毒語心経(6) |
, |
| 14 |
72(6) p.148~155 |
2005-06 |
白隠禅師を読む(14)毒語心経(7) |
, |
| 15 |
72(7) p.158~165 |
2005-07 |
白隠禅師を読む(15)毒語心経(8) |
, |
| 16 |
72(8) p.148~154 |
2005-08 |
白隠禅師を読む(16)毒語心経(9) |
, |
| 17 |
72(9) p.63~71 |
2005-09 |
白隠禅師を読む(17)毒語心経(10) |
, |
| 18 |
72(10) p.156~163 |
2005-10 |
白隠禅師を読む(18)毒語心経(11) |
, |
| 19 |
72(11) p.152~159 |
2005-11 |
白隠禅師を読む(19)毒語心経(12) |
, |
| 20 |
72(12) p.152~159 |
2005-12 |
白隠禅師を読む(20)隻手音声(1) |
, |
| 21 |
73(1) p.180~187 |
2006-01 |
白隠禅師を読む(21)隻手音声(2) |
, |
| 22 |
73(2) p.154~161 |
2006-02 |
白隠禅師を読む(22)隻手音声(3) |
, |
| 23 |
73(3) p.158~165 |
2006-03 |
白隠禅師を読む(23)隻手音声(4) |
, |
| 24 |
73(4) p.156~163 |
2006-04 |
白隠禅師を読む(24)隻手音声(5) |
, |
| 25 |
73(5) p.174~181 |
2006-05 |
白隠禅師を読む(25)隻手音声(6) |
, |
| 26 |
73(6) p.172~179 |
2006-06 |
白隠禅師を読む(26)隻手音声(7) |
, |
| 27 |
73(7) p.160~167 |
2006-07 |
白隠禅師を読む(27)隻手音声(8) |
, |
| 28 |
73(8) p.174~179 |
2006-08 |
白隠禅師を読む(28)隻手音声(9) |
, |
| 29 |
73(9) p.172~177 |
2006-09 |
白隠禅師を読む(29・最終回)どう見ても--おわりにかえて |
, |
|
11月、村越英裕が「大法輪 73(11) p.109~113」に「白隠(八畳石/松蔭寺/正受庵など) (特集 名僧ゆかりの遺跡・寺院ガイド)
」を発表する。
○、この年、浅井京子が早稲田大学會津八一記念博物館編「早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要 (8) p.1~12」に「白隠の達磨図」を発表する。 |
| 2007 |
19 |
・ |
3月、芳澤勝弘が花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism (2) p.97~129」に「白隠の漢文語録『荊叢毒蘂』刊行の経緯梁田蛻厳・池大雅との関わりについて」を発表する。
|
雲棲[チュ]宏の評価をめぐって 野口善敬 p.1~27
新選分類集諸家詩(抄出本)解題と翻刻 堀川貴司 3 p.29~41
ふたりの浄覚 千田たくま 3 p.43~66
鹿王院蔵『仏舎利伝記』翻刻と紹介 西山美香 p.67~74
寛永版「心宗禅師録」について--特に版本「虎穴録」に見えない法語・
→偈頌の紹介 横山住雄 p.75~95 |
白隠の漢文語録『荊叢毒蘂』刊行の経緯梁田蛻厳・
→池大雅との関わりについて 芳澤勝弘 p.97~129
隠元隆[キ]の天童法難について 林 觀潮 p.131~149
白隠の唯識観--『四智辨』を通して Anna Russeri p.151~179
花園天皇関係史料・研究文献目録稿 坂口太郎,芳澤 元 p.1~46
大本山南禅寺蔵<高麗版> 一切経[エ ユレ] 近藤利弘,任京美 訳 p.47~52 |
3月、兪 炳根が博士論文「白隠系看話の思想史的研究」を発表する。 佛教大学文学部
5月、沖本克己が「泥と蓮 白隠禅師を読む : 坐禅和讃 毒語心経 隻手音声」を「大法輪閣」から刊行する。
|
序章 禅宗史と白隠
第1章 著作と生涯 |
第2章 坐禅和讃
第3章 毒語心経 |
第4章 隻手音声
終章 白隠をどう理解するか |
6月、形山 峰が「大法輪 74(6) p.90~93」に「白隠の死の教え (特集 死についての教え ; 仏教の生死観)」を発表する。
7月、青柳恵介が「芸術新潮 58(7) (通号 691) p.146~151」に「柳孝 骨董一代記(第18回・完)白隠の書と志野の茶碗 」を発表する。
12月、「週刊仏教新発見 28 朝日新聞社」に「大徳寺 妙心寺 : 一休、沢庵、盤珪、白隠ら名僧を輩出」が掲載される。(朝日ビジュアルシリーズ)
12月、小野澤隆が「浜松大学研究論集 = Academic journal of Hamamatsu University 20(2) p.409-417」に「『夜船閑話』(白隠禅師著、宝暦七年京都松月堂版)の解題及び-序-の英訳
」を発表する。 (IRDB)
12月、「別冊太陽 : 日本のこころ (通号 150) p.134~139」に「白隠 (江戸絵画入門--驚くべき奇才たちの時代 ; 禅画)」が掲載される。
○、この年、浅井京子が早稲田大学會津八一記念博物館編「早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要
(9) p.1~16」に「白隠の行状と作画活動」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 203) p.87~90」に「白隠の蟹払子図--狂言『蟹山伏』のこと 」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 204) p.127~130」に「白隠の巡礼落書図--白隠禅画の創意」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 205) p.137~143」に「阿弥陀窟参拝記--南伊豆手石・白隠の『宝鏡窟之記』の霊場」を発表する。
○、この年、小濱聖子がお茶の水女子大学大学院『人間文化創成科学論叢』編集委員会編「人間文化創成科学論叢 10 p.2-1~8」に「白隠における戒の二重性」を発表する。
○、この年、竹下ルッジェリ アンナが京都外国語短期大学機関誌編集委員会編「京都外国語大学研究論叢
= Academic bulletin, Kyoto University of Foreign Studies (通号 70) p.297~304」に「久松真一の禅--新たなパラダイムの可能性」を発表する。 |
| 2008 |
20 |
・ |
1月、水野隆徳が禅文化研究所編「禅文化研究所紀要 = Annual report of the Institute for Zen Studies (29) p.189~228」に「仏教経営倫理学試論--素野福次郎の経営哲学と道元・正三・白隠」を発表する。
2月~6月、村越英裕が「大法輪 75(2~6) p.213~217」に「そのまま唱える 現代語訳『白隠禅師坐禅和讃』(1~5) 」発表する。
3月、沖本克己が「大法輪 75(3) p.86~90」に「白隠のとらえ方 (特集 〈老いと病い〉についての教え ; 仏教の老い・病いのとらえ方)」を発表する。
3月、小濵聖子が「人間文化創成科学論叢 10 1 p.2.1-2.8 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科」に 「白隠における戒の二重性」を発表する。 (IRDB)(機関リポジトリ)
3月、竹下 ルッジェリ アンナが花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism (3) p.1~24」に「白隠と菩提心思想」を発表する。
4月1日~6月29日、松島瑞巌寺に於いて「白隠禅画墨蹟展 1」展が開かれる。、
4月、花園大学国際禅学研究所編集「図録:白隠禅画墨蹟展」が「松島瑞巌寺宝物館青龍殿」から刊行される。
|
ごあいさつ/起雲軒 吉田道彦/[著]
凡例
謝辞 |
白隠禅師とその禅画・墨蹟について/芳澤勝弘/[著]
図版
解説/芳澤勝弘/[著] |
出品リスト
編集後記/瑞巌寺宝物館 学芸員 堀野宗俊/記
・ |
6月、小野澤隆が「浜松大学研究論集 = Academic journal of University of Hamamatsu 21(1) (通号 39)6 p.93~99」に「『夜船閑話』英訳者Wilhelm Schiffer及び英文による白隠と臨済禅の概要」を発表する。(IRDB)
7月、「季刊 永青文庫 : 平成20年度夏季展 白隠とその弟子たち-みんな白隠が好きだった- Summer No.63」が「永青文庫」から刊行される。 所蔵:熊本県立図書館
7月、芳澤勝弘が「白隠禅師の不思議な世界」を「ウェッジ」から刊行する。 (ウェッジ選書 ; 33. 「地球学」シリーズ)
別タイトル 地球学シリーズ : 21世紀の地球と人類のかかわりを考える
8月、帯津良一が「白隠禅師の気功健康法 : 新呼吸法「時空」実践のすすめ」を「佼成出版社」から刊行する。
8月、仙石規監修「沼津今昔写真帖 : 保存版」が「郷土出版社」から刊行される
|
カラー口絵 1
沼津御成橋
沼津駅南口
香貫山香稜台
千本公園入り口
刊行にあたって《仙石規》 5
凡例・表紙カバー写真説明 10
変貌する風景と街並み
沼津駅前ビル 沼津市 12
沼津駅南地下道 沼津市 13
馬力が停車する沼津駅付近 沼津市 14
現高沢公園東側 沼津市 15
高島町 沼津市 16
アーケード商店街 沼津市 17
松菱百貨店を望むアーケード商店街 沼津市 18
沼津大手町交差点付近 沼津市 19
沼津駅西側 沼津市 20
市場八幡前の通り 沼津市 20
上土センター街 沼津市 21
上本通町 沼津市 21
仲見世商店街 沼津市 22
浅間町商店街 沼津市 23
通横町北 沼津市 24
通横町南 沼津市 24
三枚橋通り 沼津市 25
水没した平町方面を蓮光寺から望む沼津市 26
本町通り南口 沼津市 27
百貨店開店のアドバルーンと永代橋沼津市 28
市役所前御幸町交差点 沼津市 29
六軒町(沼津銀座) 沼津市 30
鉄砲町 沼津市 31
旧国道一号線、沼津商業高校付近沼津市 32
沼津第四小学校裏の土手 沼津市 33
香貫山より黒瀬橋を望む 沼津市 34
香貫山より望む狩野川河口 沼津市 34
黒瀬橋より三園橋を望む 沼津市 35
黒瀬橋より大岡方面を望む 沼津市 36
子どもたちが釣りをする三園橋たもと沼津市 37
門池 沼津市 38
獅子浜 沼津市 39
淡島 沼津市 40
井田 沼津市 41
鮎壺の滝 長泉町 42
黄瀬川べりの親子 長泉町 43
柿田川釣り風景 清水町 44
魚町 沼津市 45
高山競馬場跡 沼津市 45
市場町から御成橋を望む 沼津市 46
狩野川右岸から御成橋を望む 沼津市 46
清水町伏見 清水町 47
園児たちが七夕の笹を手に
→行進した千本緑町 沼津市 47
三島競馬場跡 長泉町 48
田園の広がる竹原地区 長泉町 48
特集 海岸と海水浴場 49
千本浜
海の家
貸ボートで波立つ海に
千本浜市営プール
|
牛臥海岸
原の海岸
我入道浜海の家
大瀬崎
思い出の道、港、鉄道
沼津駅 沼津市 54
西武百貨店開店後の沼津駅南口 沼津市 55
沼津機関区 沼津市 56
御殿場線大岡駅 沼津市 57
東海道線原駅 沼津市 58
御殿場線下土狩駅 長泉町 59
新幹線高架工事現場 沼津市 59
東名バス沼津北口停留所 沼津市 60
沼津インター開設当時の
→東名高速道路 沼津市 61
八間道路 沼津市 62
我入道の渡し 沼津市 63
沼津港魚市場西側 沼津市 64
沼津魚河岸 沼津市 65
港湾水揚げ状況 沼津市 66
三津・淡島間のボート乗り場沼津市 67
三津乗船場 沼津市 68
特集 過ぎ去った日々の乗り物 69
チンチン電車(1)
チンチン電車(2)
蛇松線
原駅構内のトロッコ
NKKタクシー
御成橋下流に停泊する竜宮丸
竜宮丸海底透視装置
牛臥沖を行く竜宮丸
三津に停泊する第二駿河丸
懐かしの建物点描
沼津市役所 沼津市 74
御幸町沼津市消防香貫分遣所沼津市 75
沼津市産業会館の竣工 沼津市 75
沼津社会保険出張所庁舎 沼津市 76
原公民館 沼津市 76
沼津商工会議所と沼津信用金庫沼津市 77
駿河銀行本店 沼津市 77
沼津市営水族館 沼津市 78
香貫山の頂上にあった天文台 沼津市 79
丹沢楽器店 沼津市 79
本町角の古安 沼津市 80
市川時計店と布沢呉服店 沼津市 80
大黒屋菓子店 沼津市 81
大平旅館 沼津市 82
いせう商店 沼津市 82
三光楼 沼津市 83
沼津医師会病院 沼津市 83
沼津市立病院 沼津市 84
沼津市医師会館 沼津市 84
静岡医療センター(旧東静病院)清水町 85
酒井医院 沼津市 85
小原自動車 沼津市 86
静岡トヨタ沼津営業所 沼津市 86
明電舎 沼津市 87
東洋電産 沼津市 87
赤武商店 沼津市 88
|
集 街にやってきた大きな百貨店 89
建設中の沼津西武
西武開店外観
西武開店ファションショウ
西武開店時店内風景
都まんじゅうに群がる子どもたち
食堂
特集 銀幕が呼んだ熱狂 93
セントラル劇場
東海劇場(のちの東映パラス、
→東映シネマ1・2)
沼津映画劇場
第一劇場(のちにボウルビル)
銀星座(のちの東海劇場)
セントラル劇場
文化劇場
特集 暮らしのなかで 100
仲見世商店街南口付近の群衆
沼津駅前の学生ブラスバンド
駅弁屋の茶瓶を馬車で
→出荷した沼津駅構内
昭和天皇・皇后沼津駅にて
沼津御用邸裏牛臥海岸
千本公園でのNHKのど自慢大会
ふれあい広場でダンスを披露
三津水族館遠足
三津水族館イルカショー
三津、淡島付近の海女
香貫山撮影会
日枝神社の七五三
下香貫の雪景色
玉造神社の大木を切る
システムキッチンにちゃぶ台
ポリバケツをゴミ収集車へ
巡回文庫
第一小学校図書室で行われた
→社会学級新年会
静岡県自動車学校沼津分校卒業写真
オート三輪の売り出し
ホテルスカンジナビア
[笑顔いっぱいの子どもたち]
これから地引網
タイヤのチューブを浮き輪に
鮎壺の滝で遊ぶ子どもたち
健康優良児
回転遊具で遊ぶ子どもたち
フラフープをして遊ぶ女の子
ひな祭り
キャッチボールをする子どもたち
片浜小学校の交通公園
馬力がいた上土
内緒話はあのねのね
幼稚園のクリスマス会
[地域を支えた産業]
静浦の煮干し作り
ミカン収穫風景
特集 沼津の祭り 112
沼津夏祭り
秋祭りでおめかし
|
狩野川花火大会
沼津夏祭りの物売り
丸子・浅間神社例祭
浅間様のお祭りへ
沼津市高島町の山神社祭礼
山神社祭礼の相撲大会
市場八幡神社の祭礼
市場八幡神社の踊り
城岡神社祭礼
神明神社祭礼
原浅間神社の秋祭り
原白隠祭り
大瀬神社祭典
特集 駿東を襲った水害 118
御成橋から見た狩野川台風の濁流
壊れた埠頭
傾いた沼津港灯台
三つ目ガード上の線路を歩く
冠水した三つ目ガード
山王通り狩野川台風で浸水
豪雨後の原小学校
三枚橋地区の浸水
懐かしき学び舎
四恩幼稚園 沼津市 122
聖マリア幼稚園 沼津市 123
ルンビニ幼稚園 沼津市 124
花園保育園 沼津市 125
沼津市立第一小学校 沼津市 126
沼津市立第二小学校 沼津市 127
沼津市立第四小学校 沼津市 128
沼津市立片浜小学校 沼津市 129
沼津市立愛鷹小学校 沼津市 130
沼津市立金岡小学校 沼津市 131
沼津市立開北小学校 沼津市 132
沼津市立原小学校 沼津市 133
清水町立清水小学校 清水町 134
沼津市立第一中学校 沼津市 135
沼津市立第二中学校 沼津市 136
沼津市立第四中学校 沼津市 137
静岡県立沼津東高等学校沼津市 138
静岡県立沼津西高等学校沼津市 139
静岡県立沼津工業高等学校沼津市 140
静岡県立沼津商業高等学校清水町 141
特集 スポーツに沸いた町の人々 142
下河原子ども会球技大会優勝記念
第十二回国民体育大会静岡大会開会式
第十二回国民体育大会軟式野球会場
沼津東高ホッケー部関東大会優勝
沼津第三中学校野球部静岡県大会優勝
[東京オリンピック聖火リレー]
東京オリンピック聖火リレー聖火通過式
旧一号線、警察署前から三島方面へ
旧東海道を行く聖火リレー
あとがき 146
写真・資料提供者および
→お世話になった方々 147
主な参考文献 147 |
10月、沖本克己が「大法輪 75(10) p.108~112」に「白隠の手紙 (特集 高僧・名僧の手紙--手紙から生き方を学ぶ ; 高僧・名僧の手紙)」を発表する。
10月、三宅秀和が「茶道の研究 53(10) (通号 635) p.20~24,1」に「永青文庫 美の扉(10)師から弟子へ--白隠慧鶴筆 大燈国師像 」を発表する。
12月22日、早稲田大学小野記念講堂に於いて「 シンポジウム「何故いま白隠画か」」展が開かれる。主催: 早稲田大学會津八一記念博物館
12月、浅井京子編集「「何故いま白隠画か 報告書」」が「早稲田大学會津八一記念博物館」から刊行される。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 207) p.49~58」に「白隠ゆかりの地を歩く--鮎壷の滝・柳沢の八畳石・赤野観音」を発表する。
○、この年、松下宗柏が「禅文化 (通号 209) p.140~145」に「世界に拡がる、隻手の音声」を発表する。
○、この年、芳澤勝弘が「禅文化 (通号 210) p.16~20」に「抱石庵(ほうせきあん)と白隠墨蹟--久松真一記念館を訪ねる」を発表する。 抱石庵の所在地: 〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光228ー2
○、この年、大橋修が「西日本短期大学保育学科研究論集 (2) p.23~28」に「白隠とJ・H・シュルツの、いわゆるイメージ療法」を発表する。 |
| 2009 |
21 |
・ |
2月、渡邊義行が日本教育医学会編「教育医学 = The journal of education and health science 54(3) (通号 253) p.213~227」に「江戸時代僧侶の行脚距離に関する研究 --白隠和尚が歩いた距離」を発表する。
2月、三宅秀和が「茶道の研究 54(2) (通号 639) p.20~24,1」に「永青文庫 美の扉(14)白隠の弟子、遂翁元盧の地蔵菩薩像」を発表する。
3月、千坂英俊が花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism
(4) p.47~67」に「白隠墨跡和歌考」を発表する。
3月、沼津市史編さん委員会, 沼津市教育委員会編「沼津市史 通史別編 民俗」が刊行される。
|
序
凡例
通史別編 民俗
第一章 沼津の町
口絵
第一節 東海道と狩野川 6
第一節 宿場町と城下町
第一節 沼津町の周辺
第一節 狩野川の水運と水害
第一節 温暖な気候と西風
第二節 町場の構成 12
第二節 町内の組織
第二節 三枚橋の各町内
第二節 上土の各町内
第二節 本町の各町内
第二節 城内の各町内
第三節 農耕と地曳網 21
第三節 稲作と畑作
第三節 農産物の取引
第三節 千本浜の地曳網
第三節 水産物の取引
第四節 商売と諸職 27
第四節 商店街の変遷
第四節 商人の伝承
第四節 職人の組織
第四節 職人の伝承
第五節 社寺の祭りと行事 33
第五節 日枝神社の祭り
第五節 丸子・浅間神社の祭り
第五節 そのほかの神社の祭り
第五節 寺院の行事
第五節 川施餓鬼と沼津夏まつり
第五節 商店の行事
第六節 日常のくらし 42
第六節 商家の店がまえ
第六節 職業ときもの
第六節 日常のたべもの
第二章 大岡と金岡
口絵
第一節 愛鷹山と根方 50
第一節 大岡・金岡の変貌
第二章第一節 愛鷹山と天候
第一節 愛鷹山の共有地
第一節 稲作と畑作
第一節 根方街道の往来
第一節 市街地との交渉
第一節 村境の民俗
第二節 黄瀬川と用水 57
第二節 灌漑の用水
第二節 牧堰・門池用水
第二節 田の水もち
第二節 水系の環境
第三節 旧村の組織と役割 61
第三節 区と自治会
第三節 町内と組
第三節 葬式のつきあい
第三節 忌中念仏・忌中題目
第三節 婚礼のカネオヤ
第四節 社寺の信仰の基盤 64
第四節 氏神と氏子
第四節 祭りとオセック
第四節 高尾山の祭り
第四節 ガイキバアサン
第四節 菩提寺と檀家
第四節 念仏・題目の講
第四節 大題目と大念仏
第四節 社寺への参詣
第五節 一年の仕事と行事 72
第五節 正月の用意
第五節 正月の行事
第五節 二番正月の行事
第五節 山の神の祭り
第五節 春・夏の行事
章 第五節 春・夏の農作業
第五節 盆の行事
第五節 秋・冬の行事
第五節 秋・冬の農作業
第六節 日常のくらし 82
第六節 農家のすまい
第六節 農民の仕事着
第六節 日常の食事
第六節 都市化と民俗
|
第三章 愛鷹と浮島
口絵
第一節 愛鷹山と浮島沼 92
第一節 愛鷹山麓の集落
第一節 愛鷹山の開墾
第一節 愛鷹山の信仰
第一節 愛鷹山麓の馬
第一節 赤野観音の競馬
第一節 浮島沼
第一節 放水路の整備
第一節 深田での米作り
第二節 組織と活動 100
第二節 行政区の変遷
第二節 増えてゆく自治会
第二節 旧村を引き継いだ自治会
第二節 愛鷹コミュニティセンターの誕生
第二節 公民館結婚式
第二節 夜学舎から自治会館へ
第二節 愛鷹民具館
第三節 年中行事の変化 106
第三節 記録された年中行事
第三節 正月を迎える
第三節 二番正月
第三節 一月末の行事
第三節 春・夏の行事
第三節 茶摘みと田植
第三節 盆を迎える
第三節 秋・冬の行事
第三節 自治会・コミュニティ
→センターの行事
第四節 生活の変遷 120
第四節 昭和初期の農事日誌
第四節 養蚕の終焉と畑作
第四節 沼津茶のブランドノラギの工夫
第四節 茶園の根方ドレス
第四節 伝承される味
第四章 原と片浜
口絵
第一節 街道沿いのくらし 136
第一節 原・片浜の変貌
第一節 集落と家並
第一節 地割と旧家
第一節 屋敷構え
第一節 ダシバン
第一節 街道と馬車
第一節 土埃の道
第二節 松林の自然とくらし 143
第二節 千本松原
第二節 松葉掻き
第二節 松葉小屋と松葉講
第二節 キノコ採り
第二節 ウサギと松虫
第二節 ハマッキ
第二節 薪採り
第三節 荒浜の漁とくらし 149
第三節 アラハマ
第三節 オオアミ時代
第三節 津元・ハモウド・ヨリキ
第三節 浜小屋と高見
第三節 オオアミの構造
第三節 操業方法
第三節 魚の分配
第三節 ナマスと盗み魚
第三節 出荷
第三節 水産加工
第三節 漁の時間
第三節 浜の食生活
第三節 観光地曳と釣りブーム
第四節 浜の日常生活 159
第四節 風と漁
第四節 風と屋敷構え
第四節 生活用水と井戸
第五節 砂地の農業と用水 162
第五節 農業
第五節 バラスの土壤
第五節 農業用水と井戸
第五節 スイコミ
第五節 沼と川のめぐみ
第五節 砂畑の作物の変遷
第六節 行事と信仰 167
第六節 正月行事とオンベコンベ
第六節 雛祭りと浜遊び |
第六節 大瀬さんの石日々の神祭り
第六節 寺づくし
第六節 原の白隠さん
第六節 要石の信仰と津波浜の葬式
第六節 屋敷神と墓地
第六節 漂着した神仏
第五章 香貫と大平
口絵
第一節 狩野川と沼津アルプス 180
第一節 五山七峠の沼津アルプス
第一節 狩野川左岸の集落
第二節 香貫用水と農業 183
第二節 内膳掘・泣き堀
第二節 アクスイと堰
第二節 水車小屋の生活
第二節 用水路の管理
第二節 蔬菜と桃
第二節 ナナイロ畑
第二節 牛と馬
第二節 女性の引き売り
第三節 大平の水害と農業 191
第三節 洪水の記録
第三節 洪水の記憶
第三節 狩野川台風
第三節 江川の水門とヤミズ
第三節 政戸のオカズイモン
第三節 旱魃と溜池・用水
第三節 粘土質の土壤
第三節 米と麦
第三節 レンコン栽培
第三節 イチゴ栽培
第三節 大平石
第三節 トンボ笠とノラギ
第三節 志下との交流
第四節 一年の行事と運営 200
第四節 正月
第四節 ドンドン焼き
第四節 山の神
第四節 青年の組織
第四節 楊原神社・大朝神社の祭礼
第四節 天王様
第四節 辻切り
第四節 サイノカミとオチョウネン
第四節 盆
第四節 地蔵講から夏祭りへ
第四節 吉田神社の祭礼
第四節 鷲頭神社の祭礼
第四節 禰宜番の役割
第四節 大念仏講
第四節 大平の講
第六章 我入道と静浦
口絵
第一節 漁師町と漁の村 222
第一節 地区のあらまし
第一節 我入道の河岸
第一節 狩野川での遊び
第一節 狩野川口の遭難
第一節 男山と女山
第一節 牛臥山
第一節 松林と別荘
第二節 我入道と静浦の漁撈 227
第二節 我入道の漁場
第二節 我入道漁師の一生
第二節 我入道のサバ船
第二節 漁師と学問
第二節 ソトウミの釣漁
第二節 マグロ船とバカザメ
第二節 サバ船の漁場キンハモ
第二節 静浦の浜と洞の漁
第二節 浜の地曳網
第二節 沖のマカセ網
第三節 魚行商に行く
第三節 魚を食べる
第四節 海の行事と信仰 247
第四節 船霊信仰
第四節 船の目玉
第四節 船祝い
第四節 大漁祝い
第四節 大瀬祭り
第四節 小正月とサイノカミ
第四節 踊り初めと水祝儀
第四節 節分と八日節供
|
第四節 七月盆
第四節 ヤイシを祀る
第四節 海上禁忌
第五節 漁場の社会と人生儀礼 256
第三節 漁場の日常生活 239
第三節 百姓漁師
第三節 静浦の漁師石屋
第三節 鰹節製造
第三節 漁家の内職
第三節 沼津通い
第五節 産育と漁
第五節 ふたつの名前
第五節 貰い子
第五節 長男と舎弟
第五節 女中奉公
第五節 少年と老人
第五節 ハマオリの磯
第七章 内浦と西浦
口絵
第一節 富士を望む集落 268
第一節 海辺の村
第一節 道中歌
第一節 海岸地形と山地
第一節 地先の島と岬
第一節 三津は小江戸
第一節 家並と間取り
第一節 風の名
第二節 洞・磯の漁とくらし 273
第二節 オオアミの種類
第二節 イカツケのハチダ
第二節 西浦のシメロ
第二節 漁場と網の改良
第二節 ネコサイ網
第二節 大謀網と出稼ぎ漁民
第二節 イルカ追込漁ブリ刺網
第二節 旋網の時代
第二節 ウズワ釣り
第三節 洞の棚田とミカン畑 282
第三節 乏しい耕地
第三節 ジミカンと温州
第三節 朝日受けと夕日受け
第三節 ミカン採りと出荷
第三節 炭焼きと樟脳屋
第四節 海の道・峠の道 287
第四節 海岸道路と峠道
第四節 自転車通学と三津坂
第四節 沼津通い
第四節 清水通い
第四節 観光開発と水族館
第四節 自動車
第五節 海辺の食とくらし 292
第五節 くらしの水
第五節 日常の食事と魚
第五節 マグロの内臓など
第五節 ウツボ料理
第五節 マゴチャとタタキ
第五節 ナマスの種類
第五節 磯の食べ物
第五節 食生活と用具
第五節 水車と精米
第六節 海の行事と信仰 298
第六節 お山を仰ぎ潮花(しょばな)を撒く
第六節 正月の準備
第六節 正月の菱餅
第六節 お雑煮
第六節 初参り
第六節 仕事始め・乗り初め
第六節 二番正月
第六節 天王祭り
第六節 盆カマと川勧請
第六節 岬と島の神々
第六節 エビス
第六節 村芝居と芸能
第七節 若者組の変遷 305
第七節 若い衆と宿
第七節 宿勤めの廃止まで
第七節 宿寝の若い衆
主要な参考文献目録 309
あとがき 311
通史別編「民俗」執筆分担一覧 313
沼津市史編さん関係者名簿 314
索引
|
8月、司馬春英, 渡辺明照編著「知のエクスプロージョン : 東洋と西洋の交差」が「北樹出版」から」刊行される。
|
比較哲学への道 認知科学と仏教思想 / 司馬春英 著
空論の行方 / 渡辺明照 著
「自由」の多義性と日本的受容について / 寺田ひろ子 著
無底の底 / 小野純一 著
リクールの『悪の象徴論』と日本神話 / 岩澤知子 著
必然性と人間 / 津田良生 著
悪と罪を超えて / 角田玲子 著
白隠の戒律観についての一考察 / 小浜聖子 著
保田與重郎の和泉式部論 / 岡山麻子 著
内観と伝灯 / 春近敬 著
意識・身体・世界 フッサール現象学と
→数学基礎論論争 / 司馬春英 著
意識科学、現象学における自己言及性 / 佐藤勇起 著
ヒュレーとは何か / 阿部旬 著
フッサール現象学における他者問題 / 佐藤加世子 著 |
第四のスタンスと志向スタンスの綻び / 小林玄順 著
心的なものの物的なものへの非還元性 / 渡辺隆明 著
源流への遡行 交わりの不安 / 嶋田毅寛 著
ニーチェのニヒリズムとハイデガーの「根拠」論 / 西野輝生 著
道徳的感性と芸術の視座 / 吉田杉子 著
スピノザにおける関係性について / 鈴石忠司 著
アウグスティヌス『三位一体論』における「信」 / 御園崇 著
西洋思想史上におけるプロティノス哲学の存在意義 / 後藤仁 著
アリストテレス『ニコマコス倫理学』に見る人間観の一側面 / 雪田江美 著
現代社会の状況 コミュニティ形成における装置 / 臼木悦生 著
国家はいらない / 久保紀生 著
「他」宗教理解の難しさ / 松野智章 著
〈学校〉の意味の再構成へ向けて / 常盤浩史 著
ジャック・デリダによる「合衆国独立宣言」の脱構築 / 原田敦 著
・ |
9月、芳澤勝弘が「Will : マンスリーウイル (57) p.150~157」に「著者インタビュー 芳澤勝弘監修・解説『白隠禅画墨蹟』 」を発表する。
12月、三宅秀和が「茶道の研究 54(12) (通号 649) p.20~24,1 」に「永青文庫 美の扉(24)白隠慧鶴筆 巌頭和尚語「暫時不在如同死人」を発表する。
○、この年、松下宗柏が「禅文化 (通号 211) p.105~111 禅文化研究所」に「地球曼荼羅--白隠禅師の『百寿図』に寄せて」を発表する。
○、この年、花園大学国際禅学研究所編,芳澤勝弘監修・解説「白隱禪画墨蹟 墨蹟篇
白隱 [書]」が「二玄社」から刊行される。
○、この年、花園大学国際禅学研究所編,芳澤勝弘監修・解説「白隱禪画墨蹟 禪画篇
白隱 [画],」が「二玄社」から刊行される。
○、この年、花園大学国際禅学研究所編,芳澤勝弘監修・解説「白隱禪画墨蹟 解説篇
白隱 [画]」が「二玄社」から刊行される。
○、この年、岩本 一が「ライフデザイン学研究 = Journal of human life design (5) p.31~40」の「Zen and health (1) Hakuin's 'Naikan no Hiho' and 'Nanso no Ho' 〔禅と健康(1)白隠の「内観の秘法」と「軟酥の法」〕」を発表する。 |
| 2010 |
22 |
・ |
1月、小林忠が「江戸の絵画」を「藝華書院」から刊行する。 国立国会図書館書誌ID:000010672159
|
第三章 大雅蕪村正譎論 『十便十宜帖』を中心に 305
第三章 大雅の禅味と蕪村の俳味 310
第五章 「舞踊図屏風」 512
41 池大雅 「浅間山真景図」 個人蔵 p.70-71
42 池大雅 「瀟湘勝概図屏風」 個人蔵 p.72-73
43 池大雅 「芳野山図」 川端康成記念会蔵 p.74
44 池大雅 「洞庭秋月図」(『東山清音帖』より) 個人蔵 p.75
45 池大雅 「江天暮雪図」(『東山清音帖』より) 個人蔵 p.75
46 池大雅 「葛の葉図」 個人蔵 p.76
47 池大雅 「関羽図」 個人蔵 p.77
48 池大雅 「釣便図」(『十便十宜帖』より) 川端康成記念会蔵 p.78
49 池大雅 「課農便図」(『十便十宜帖』より) 川端康成記念会蔵 p.78
50 与謝蕪村 「宜夏図」(『十便十宜帖』より) 川端康成記念会蔵 p.79
51 与謝蕪村 「宜暁図」(『十便十宜帖』より) 川端康成記念会蔵 p.79
52 与謝蕪村 「夜色楼台図」 個人蔵 p.80-81
53 与謝蕪村 「鳶鴉図」 北村美術館蔵 p.82-83
54 与謝蕪村 「鳶図」 個人蔵 p.84
55 与謝蕪村 「雨乞の」自画賛 個人蔵 p.85
56 与謝蕪村 「朧月画賛」 個人蔵 p.86
〈抜粋〉
【挿図】
1-13 「富士曼荼羅図」 浅間神社蔵 p.167
1-14 狩野元信 「富士曼荼羅図」 浅間神社蔵 p.167
1-15 伝祥啓 「富嶽図」 東京国立博物館蔵 p.168
1-16 伝雪舟 「富士清見寺図」 永青文庫蔵 p.169
1-17 雪舟 「天橋立図」 京都国立博物館蔵 p.169
1-18 長谷川等伯 「松林図屏風」 東京国立博物館蔵 p.170-171
1-19 阿弥派 「三保松原図」 頴川美術館蔵 p.171
2-25 葛飾北斎 『隅田川両岸一覧』 国立歴史民俗博物館蔵 p.259
3-14 池大雅 「渭城柳色図」 敦井美術館蔵 p.296
|
3-15 池大雅 「梅花黄鳥図」 個人蔵 p.297
3-16 池大雅 「箕山瀑布図」 個人蔵 p.297
3-17 池大雅 「林外望湖図」 個人蔵 p.298
3-18 池大雅 「三上孝軒・池大雅対話図」 東京藝術大学芸術資料館蔵 p.299
3-19 池大雅 「蘭亭修禊、龍山勝会図屏風」 静岡県立美術館蔵 p.300-301
3-20 池大雅 「西湖春景、銭塘観潮図屏風」 東京国立博物館蔵 p.300-301
3-21 池大雅 「柳下童子図屏風風」 京都府蔵 p.302
3-22 梅原龍三郎 「噴煙」 東京国立近代美術館蔵 p.303
3-23 池大雅、与謝蕪村 「十便十宜帖」(全図) 川端康成記念会蔵 p.308-309
3-24 白隠 「達磨図」 永青文庫蔵 p.310
4-1 円山応挙 「江州日野村落図屏風」 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 p.364-365
4-2 池大雅 「王維詩意図」 静嘉堂文庫美術館蔵 p.367
4-3 仙厓 「指月布袋図」 出光美術館蔵 p.370
4-4 与謝蕪村 「富嶽列松図」 愛知県英術館蔵(木村コレクション) p.374-375
4-5 浦上玉堂 「山紅於染図」 愛知県美術館蔵(木村コレクション) p.375
4-6 椿椿山 「花卉図額」 旧荻野コレクション p.376-377
4-7 岡本豊彦 「夜漁図」 旧荻野コレクション p.379
4-8 中林竹溪 「山水舟行図」 旧荻野コレクション p.379
4-9 富岡鉄斎 「如意図」 飯田市美術博物館蔵(井村コレクション) p.380
4-10 岡本豊彦 「山水図袋戸」 飯田市美術博物館蔵(井村コレクション) p.382-383
4-11 幸野楳嶺 「白衣観音図」(左) 飯田市美術博物館蔵(井村コレクション) p.384
富岡鉄斎 「芦葉達磨図」(右) 飯田市美術博物館蔵(井村コレクション) p.384
4-22 葛飾北斎 「鴫立沢の西行図」 ワルシャワ国立博物館蔵 p.405
4-30 葛飾北斎 「冨嶽三十六景・尾州不二見原」 ボストン美術館蔵(スポルディング・コレクション) p.421
4-31 歌川広重 「桶屋の富士」 ボストン美術館蔵(スポルディング・コレクション) p.421
4-32 歌川国芳 「讃岐院眷族をして為朝をすくふ図」 スプリングフィールド美術館蔵 p.424
4-33 喜多川歌麿 「両国橋橋下の釣り」 スプリングフィールド美術館蔵 p.425
4-34 魚屋北渓 「月下虎図」 スプリングフィールド美術館蔵 p.426
〈抜粋〉
・ |
2月、芳澤勝弘が國華編輯委員会編 「國華 115(7) (通号 1372) (特輯 逸格逸品 第7輯)
p.29~30,11」に「白隱筆 觀音圖贊 」を発表する。
3月、向江勇樹(文学部史学科3年)が「教職への道 No.30 p.30- 31 別府大学教職課程委員会」に「隻手の音声(せきしゅのおんじょう) ー介護等体験の報告ー 」を発表する。 (IRDB)
3月、千坂英俊が花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism (5) p.33~53」に「白隠墨跡和歌考(2)」を発表する。
4月24日~6月6日、出雲文化伝承館に於いて「出雲の白隠さん : 心に響く禅画の秘宝」展が開かれる。
4月、芳澤勝弘監修出雲文化伝承館編「出雲の白隠さん : 心に響く禅画の秘宝」が刊行される。
共催: 臨済宗妙心寺派, 臨済宗妙心寺派山陰西教区, 花園大学国際禅学研究所,
出雲市, 出雲市教育委員会, 出雲市教育文化振興財団, 山陰中央新報社
作品解説・釈文: 芳澤勝弘
5月、辻惟雄,村上隆が「芸術新潮 61(5) (通号 725) p.140~145」に「辻惟雄×村上隆 ニッポン絵合せ(7番)白隠慧鶴」を発表する。
8月、沖本克己が「大法輪 77(8) p.110~113」に「白隠と般若心経 (特集 これでわかる般若心経 ; さまざまな般若心経理解)」を発表する。
9月15日~11月14日、松島瑞巌寺宝物館青龍殿に於いて「白隠禅師禅画墨蹟展 2」が開かれる。
9月、芳澤勝弘監修「白隠禅師禅画墨蹟展 2」が「瑞巌寺」から刊行される。
参考:編集: 江上正道 (花園大学国際禅学研究所), 新野一浩 (瑞巌寺), 千葉千恵
(瑞巌寺), 堀野宗俊 (瑞巌寺宝物館顧問)
9月、高橋利郎が「江戸の書」を「二玄社」から刊行する。
|
江戸時代の書 6
慶長~寛永の華 11
本阿弥光悦 12
近衛信尹 15
烏丸光広 18
松花堂昭乗 20
宮廷と書流 25
後陽成天皇 26
尊純法親王 27
後水尾天皇 28
良純法親王 30
飛鳥井雅章 31
後西天皇 32
霊元天皇 33
近衛家煕 34
茶の湯の世界 39
古田織部 40
織田有楽 41
沢庵宗彭 42
江月宗玩 44
千宗旦 45
小堀遠州 46
金森宗和 47
片桐石州 48
川上不白 49
松平不昧 50
武家とその周辺 53
徳川家康 54
伊達政宗 55
春日局 58
徳川家光 59
徳川吉宗 60 |
松平定信 61
飄然と生きる 65
松尾芭蕉 66
与謝蕪村 68
池大雅 70
小林一茶 76
京阪の文人 79
石川丈山 80
高遊外 81
十時梅厓 82
皆川淇園 83
上田秋成 84
岡田米山人 85
浦上玉堂 86
村瀬栲亭 87
菅茶山 88
雲華大含 89
田能村竹田 90
貫名菘翁 92
頼山陽 94
篠崎小竹 98
広瀬旭荘 99
文化文政の江戸文人103
市河寛斎 104
大田蜀山人 105
亀田鵬斎 106
中井董堂 108
大窪詩佛 109
菊池五山 111
亀田綾瀬 112
市河米庵 113
唐様の能書 119 |
佐々木志津磨 120
北島雪山 121
林道栄 122
細井広沢 123
関思恭 124
三井親和 125
松下烏石 126
趙陶斎 128
龍草盧 129
韓天寿 130
沢田東江 131
狩谷〔エキ〕斎132
巻菱湖 133
小島成斎 136
生方鼎斎 137
中沢雪城 138
書と学芸 143
藤原惺窩 144
林羅山 145
木下順庵 146
伊藤仁斎 147
貝原益軒 148
新井白石 149
荻生徂徠 150
伊藤東涯 152
太宰春台 153
服部南郭 154
秋山玉山 155
中山高陽 156
中井竹山 157
中井履軒 158
柴野栗山 159 |
古賀精里 160
館柳湾 161
佐藤一斎 162
広瀬淡窓 163
立原杏所 164
梁川星巌 165
渡辺崋山 166
藤井竹外 167
佐久間象山 168
河野鉄兜 169
国学・和歌と仮名171
契沖 172
賀茂真淵 173
本居宣長 174
橘千蔭 175
香川景樹 176
大田垣蓮月 177
大隈言道 178
冷泉為恭 179
破格の僧 183
嶺南崇六 184
深草元政 185
一絲文守 186
白隠慧鶴 188
諦乗寂厳 190
月船禅慧 192
慈雲飲光 193
明月曇寧 195
誠拙周樗 196
仙厓義梵 197
良寛 199
方寸にみる江戸 203 |
細井九皐 204
趙陶斎 204
高芙蓉 204
池大雅 205
浜村蔵六<二世> 205
前川虚舟 206
巻菱湖 206
細川林谷 206
海保酔茗 207
田邊玄々 207
益田遇所 208
羽倉可亭 208
浜村蔵六<四世> 208
掲載作品資料 210
参考文献 220
関連年譜 223
収録人物一覧(五十音順)227
収録人物一覧(生年順)229
コラム
寛永の三筆の周辺 22
近衛家煕のまなざし 36
定家愛好 51
松平定信と『集古十種』 62
旅と書画 77
黄檗僧と中華趣味 100
西から来る、西へ行く 116
江戸の墨帖 139
文字の表情 170
国学と仮名 180
破格の書 201
市島春城印章コレクション209
・ |
9月、國華編輯委員会編「國華 116(2) (通号 1379) (特輯 白隱) p.3~59」が刊行される。
|
白隱型達磨像の成立 芳澤勝弘 p.23~35,5
白隱筆 半身達磨像 辻惟雄 p.36~38,7
白隱筆 蓮池觀音像 山下裕二 p.39~42,9
白隱筆 富士大名行列圖 芳澤 勝弘 p.43~45,11
白隱筆 大燈國師像 三宅秀和 p.46~49,13
|
白隱筆 渡唐天神圖 島尾新 p.50~52,15
白隱筆 布袋すたすた坊主圖 淺井 京子 p.53~54,17
白隱筆 朱衣達磨像 矢島 新 p.55~57,19
白隱筆 隻履達磨像 加藤 陽介 p.58~59,21
・ |
11月、芳澤勝弘が「目の眼 No.410」に「特集:白隠を読み解く:禅の大改革者からのメッセージ 江戸という時代を内包した巨人」を発表する。
700円 内容未確認なため調査要 2023・2・3 保坂
12月11日~翌年2月2日、美濃加茂市民ミュージアムに於いて「美濃の白隠」展が開かれる。
12月、美濃加茂市民ミュージアム, 早稲田大学編「美濃の白隠」が「美濃加茂市民ミュージアム・早稲田大学」から刊行される。 (美濃加茂ふるさとファイル ; no.15)
○、この年、「禅文化 (通号 215) p.73~80」に「巣松翁蔵 禅林墨蹟--白隠慧鶴」が掲載される。
○、この年、大野妙恵が「禅 (32) p.101~103」に「図書紹介 『遠羅天釜』(白隠禅師著) 」の紹介を行う。
○、この年、竹下 ルッジェリ・アンナが京都外国語大学機関誌編集委員会, 京都外国語短期大学機関誌編集委員会編「京都外国語大学研究論叢
= Academic bulletin, Kyoto University of Foreign Studies (通号 76) p.277~288」に「白隠禅師の『遠羅天釜』(1)禅病をめぐって 」を発表する。
○、この年、浅井京子が早稲田大学會津八一記念博物館編「早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要 (12) p.1~8」に「飯山から美濃加茂へ--白隠の修行時代 」を発表する。
|
| 2011 |
23 |
・ |
2月10日~3月10日、早稲田大学一二五記念室に於いて「美濃の白隠」展が開かれる。
2月、西村惠信が「茶道雑誌 75(2) p.35~42」に「白隠禪師「坐禅和讃」を読む(1)茶と禅の出会い」を発表、連載を開始する。
3月、半田栄一が「宗教研究 84(4) p.1328-1329」に「白隠の禅と現代統合医療(第十六部会,<特集>第六十九回学術大会紀要)」を発表する。 J-STAGE
3月、千坂英俊が花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism (6) p.63~85」に「白隠墨跡和歌考(3)白隠慧鶴と夢窓疎石」を発表する。
4月、横田喬が「大法輪 78(4) p.164~171」に「白隠禅師蛍雪記(新連載・1)」を発表、連載を開始する。
|
横田喬が「大法輪 78(4)~79(1) 」に発表した「白隠禅師蛍雪記(新連載・1~10)」迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻頁 |
発行年 |
タイトル名 |
内容 |
| 1 |
大法輪 78(4) p.164~171 |
2011-04 |
小説 白隠禅師蛍雪記(新連載1) |
. |
| 2 |
大法輪 78(5) p.152~160 |
2011-05 |
小説 白隠和尚蛍雪記(2) |
. |
| 3 |
大法輪 78(6) p.169~177 |
2011-06 |
小説 白隠和尚蛍雪記(3) |
. |
| 4 |
大法輪 78(7) p.179~187 |
2011-07 |
小説 白隠和尚蛍雪記(4) |
. |
| 5 |
大法輪 78(8) p.180~188 |
2011-08 |
小説 白隠和尚蛍雪記(5) |
. |
| 6 |
大法輪 78(9) p.166~174 |
2011-09 |
小説・白隠和尚蛍雪記(6) |
. |
| 7 |
大法輪 78(10) p.155~163 |
2011-10 |
小説・白隠和尚蛍雪記(7) |
. |
| 8 |
大法輪 78(11) p.163~169 |
2011-11 |
小説・白隠和尚蛍雪記(8) |
. |
| 9 |
大法輪 78(12) p.195-203 |
2011-12 |
小説・白隠和尚蛍雪記(9) |
. |
| 10 |
大法輪 79(1) p.202-209 |
2012-01 |
小説・白隠和尚蛍雪記(10) |
. |
|
5月、朝比奈宗源が「人はみな仏である : 白隠禅師坐禅和讃・一転語」を「春秋社」から刊行する。
7月、帯津良一が「大法輪 78(7) 2011-07 p.72~77」に「 白隠禅師の『夜船閑話』と丹田呼吸法 (特集 仏教の智慧で現代病を乗り越える ; 仏教の智慧で病いを治す)」を発表する。
8月、宮里立士, 佐藤哲彦 編集・解題「書物通の書物随筆 第2巻」が「ゆまに書房」から刊行される。
(書誌書目シリーズ ; 97) 注記 民友社昭和5年刊の複製
|
赤堀又次郎『紙魚の跡』
解題 佐藤哲彦
紙魚の跡 目次
奈良繪(二十四孝の一) 口繪
學習院の聯 一七
仁孝天皇の叡旨
宇多天皇の圓堂の御誓願
天地萬物皆我有 二一
人間の欲望
岡本況齊
加茂眞淵と曲亭馬琴 二六
支那文化の影響
國語の復興
印 三三
印材
篆刻
御璽、國璽
高芙蓉
印に用ゐる語
紙 三八
麻紙
斐紙
穀紙
檀紙
局紙
模造紙
美濃紙
紙の加工
紙の大さ
紙細工
硯石、硯箱 四三
硯石の保存石
硯材名硯
諸飾、片飾
墨 四九
墨を惜むこと金の如し
油煙、松煙
唐墨、和墨、牛王墨
鈴木梅仙、白隱 |
からすみ
筆 五四
筆に用ゐる毛
天筆、筆平師
風景と交藝 五九
八景、十勝、三景
外國の名勝を模す
晴耕雨讀 六四
詩を作るより田を作れ
王仁の子孫等の生活
柿本人麿の生活
讀書と批判 六九
信じて讀む
讀みて批判する
靑葉若葉枯枝 七三
日光の地理
鹿島の鷺
奈良みやげ 七七
平安京へ遷都
奈良の古儀
京みやげ 八一
鹿の子しぼり
西陣織
檢校保已一 八四
群書類從の編纂、出版、代價
令義解等の出版、其影響
梵字と漢字 八八
漢字の普韻の整理
梵字の書法から行草書
正岡子規の歌學思想 九二
科學と萬葉集
詠歌と批評
芭蕉と其周圍 九五
其性格と其句
物質と精神
沼波瓊音 一四一
泰時と秀吉との心理 九九
泰時の尊王
秀吉の大内裡跡の破壞 |
香道 一〇三
其藝術化
東西文化の差違
出版 一〇八
其年代、地理、技術等
佳吉文庫の建設
名工田村鐵之助 一一一
出版の爲のに描いた給繪? 一一一
出版為豫期せぬ繪? 一一一
木版色綱の再興 一一四
古?の複製 一一七
需要者の相違 一一九
眞美大觀、合の子版 一二四
實大の複製 一二六
同好會の複製 一二七
順序ずり 一二九
建築の繪圖 一三〇
聖徳太子の御影 一三二
高橋岡倉二氏の追善 一三三
震災 一三四
孔雀明王の像 一三六
分業綜合の妙 一四〇
世界的藝術 一四〇
繪巻物について 一四二
繪畫と時問 一四三
出版及び製本の變化 一四五
繁より簡へ 一四六
經文に關係たもの 一四七
傳記な描いたもの 一五四
寺の縁起 一五八
神社の縁起 一六一
儀式に關したもの 一六七
事件に關したもの 一七一
古繪巻と活動寫眞 一七四
日本の繪畫及彫刻 一七八
釋迦來迎圖 一七八
鯛と金魚の相貎、刀劒の鑑定 一八〇
表情を現した作、寫樂と白隱 一八三
猩々狂齊と菊地容齊 一八三 |
泉爲恭と田中訥言と浮田一惠 一八四
狩野探幽と圓山應擧と尾形光琳と 一八五
佛教の發達と藝術の進歩と 一八六
須彌山説と二十八天と 一八五
梵天帝釋と四天王 一九一
五十二位 一九二
生天説の一變した成佛説 一九三
法華經と仁王經と 一九五
密敎、〓身成佛と繪畫 彫刻 一九六
四種曼荼羅 一九七
兩界曼荼羅 一九九
淨土教 二〇〇
佛畫佛縁の行語 二〇〇
三身説 二〇二
佛畫より人間畫に 二〇三
かう云ふ事を述べたい 二〇四
刊誤、大日と彌陀、十二光佛 二〇六
圖書館の囘顧 二〇八
内典、外典 二〇八
四天寺經藏 二〇九
元興寺經藏 二一〇
興福寺經藏 二一二
治承の亂、諸寺兵火にかゝる 二一四
東大寺經藏 二一六
法隆寺經藏 二一八
顯教、密教 二一九
比叡山經藏、傳教大師書寫及將來 二二〇
前唐院、慈覺大師の將來 二二二
後唐院、智證大師の將來 二二四
東寺大經藏、弘法大師の將來 二二九
北山の靈巖寺經藏、圓行の將來 二三〇
小栗栖の法琳寺經藏、常曉の將來 二三〇
安祥寺經藏、少僧都〓運の將來 二三一
圓覺寺經藏、僧正宗叡の將來 二三四
法身舎利、論義、深秘 二三四
聖武天皇の大藏經の跋 二三六
光明皇后の大藏經の跋 二三六
伊勢の式年御遷宮 二三七
・
|
9月、貫元勝が淡交社編「淡交 65(9) (通号 807) p.64~67」に「禅僧の略歴 白隠慧鶴」を発表する
10月、西村惠信が「プレジデント = President 49(34) (通号 別冊) p.71-78」に「栄西と白隠 : 「日本臨済禅」に「開祖」二人あり : 栄西の九代のちに断絶していた臨済禅を再興した白隠 (禅的シンプルライフ ; 名僧に学ぶ)」を発表する。
12月、形山睡峰が「大法輪 78(12) p.122-124」に「白隠禅師坐禅和讃 (特集 葬儀・法事の《お経》入門) 」を発表する。
○、この年、「禅文化 (通号 222) 2011 p.73~80」に「※丈山文庫蔵 禅林墨蹟 白隠と東嶺」が掲載される。
※ 丈山文庫:〒444-1221 愛知県安城市和泉町上之切13
○、この年、半田栄一が「比較思想研究 (38) p.48-56」に「白隠の禅思想と「軟酥の法」」を発表する。
○、この年、「禅文化 (通号 222) 2011 p.73~80」に「丈山文庫蔵 禅林墨蹟 白隠と東嶺」が掲載される。
著者名がなかったので再調査が必要 2023・1・23 保坂
|
| 2012 |
24 |
・ |
3月、富士市教育委員会編「富士市の文化財」が「富士市教育委員会」から刊行される。
|
指定文化財
【特別名勝・史跡】富士山 1
【指定文化財&登録文化財マップ(天然記念物を除く)】 2
I 有形文化財
I (1) 建造物
I (1) 【国指定重要文化財】 4
I (1) 「1」 古谿荘/岩淵
I (1) 【静岡県指定文化財】 5
I (1) (2) 旧稲垣家住宅/伝法・広見公園
I (1) 【富士市指定文化財】 6
I (1) (3) 瑞林寺伽藍/松岡・瑞林寺
I (1) (4) ディアナ号の錨/五貫島・三四軒屋緑道公園
I (1) (5) 稲葉家住宅/岩淵
I (1) <広見公園内の富士市指定文化財> 8
I (1) (6) 樋代官植松家住宅
I (1) (7) 原泉舎
I (1) (8) 樋代官植松家住宅長屋門
I (1) (9) 杉浦医院
I (1) (10) 眺峰館
I (1) (11) 旧松永家住宅
I (1) (12) 五輪塔/富士市立博物館内
I (2) 彫刻
I (2) 【国指定重要文化財】 10
I (2) 「13」 木造地蔵菩薩坐像/松岡・瑞林寺
→(富士市立博物館複製展示)
I (2) 【富士市指定文化財】 11
I (2) <岩本・實相寺の富士市指定文化財> 11
I (2) (14) 木彫仁王像(金剛力士像)
I (2) (15) 木彫七福神
I (2) <原田・妙善寺の富士市指定文化財> 12
I (2) (16) 扁額(句額)
I (2) (17) 木造十一面千手観音坐像
I (2) (18) 木造広目天・多聞天立像
I (2) (19) 木造薬師如来坐像/比奈・医王寺 14
I (3) 工芸品
I (3) 【静岡県指定文化財】 15
I (3) (20) 太刀/鷹岡本町
I (4) 書跡・典籍・古文書
I (4) 【国指定重要文化財】 15
I (4) 「21」 紙本墨書 法門百首/平垣本町
I (4) 【富士市指定文化財】 15
I (4) <富士市立博物館で見られる富士市指定文化財> 15
I (4) (22) 紙本墨書 稿本 田子のふるみち
I (4) (23) 紙本墨書 高林山法田禅寺記
I (4) (24) 紙本墨書 富士郡今泉村往古高抜差邑寶鑑
I (4) (25) 紙本墨書 福寿山瑞林禅寺記/松岡・瑞林寺
I (4) (26) 中村家文書/永田北町・
→富士市立中央図書館保管 17
I (4) (27) 實相寺一切経/岩本・實相寺 18
I (5) 考古資料
I (5) 【富士市指定文化財】 19
I (5) (28) 比奈東坂古墳出土品/伝法・富士市立博物館
I (5) (29) 医王寺経塚遺物/比奈・医王寺
→(富士市立博物館複製展示)
II 史跡
II 【国指定史跡】 20
II 「30」 浅間古墳/増川
II 【静岡県指定史跡】 21
II (31) 琴平古墳/中里
II (32) 伊勢塚古墳/伝法・玄龍寺
II (33) 庚申塚古墳/東柏原新田
II (34) 岩淵の一里塚/岩淵
II 【富士市指定史跡】 23
II (35) 千人塚古墳/神谷
II (36) 稲荷塚古墳/船津
II (37) 実円寺西第1号墳/三ツ沢
II (38) 山ノ神古墳/東柏原新田
II (39) 雁堤/岩本・松岡
II <比奈・竹採公園内の富士市指定史跡> 25
II (40) 竹採塚
II (41) 白隠禅師の墓
II <今泉・善得寺公園内の富士市指定史跡> 26
II (42) 善得寺墓群のなかの大勲策禅師の墓
II (43) 善得寺墓群のなかの太原雪斎の墓
II (44) 金原明善翁らの大規模植林地 26
III 民俗
III 【静岡県指定有形民俗文化財】 27
III (45) 浮島沼周辺の農耕生産用具/伝法・富士市立博物館
III 【富士市指定無形民俗文化財】 28
III (46) 鵜無ケ淵神明宮の御神楽/鵜無ケ淵
III (47) 大北のカワカンジー/北松野
|
III (48) 木島のナゲダイマツ/木島
IV 天然記念物
IV 【静岡県指定天然記念物】 31
IV (49) 富知六所浅間神社の大クス/
→浅間本町・富知六所浅間神社
IV (50) 慶昌院のカヤ/中里・慶昌院
IV (51) 富士岡地蔵堂のイチョウ/富士岡・富士岡地蔵堂
IV 【天然記念物マップ】 32
IV 【富士市指定天然記念物】 32
IV (52) 船津浅間神社のクス/船津
IV (53) 神谷神明宮のムクノキ/神谷
IV (54) 間門浅間神社のシイ/間門
IV (55) 今宮浅間神社のスギ/今宮
IV (56) 鵜無ケ淵神明宮のクス/鵜無ケ淵
IV (57) 十王子神社のイチョウ/今泉
IV (58) 十王子神社のクス/今泉
IV (59) 水の上のタイサンボク/今泉
IV (60) 本国寺のボダイジュ/今泉
IV (61) 曽我寺のカヤ/久沢
IV (62) 曽我寺のシイ/久沢
IV (63) 瑞林寺のモッコク/松岡
IV (64) 瑞林寺のヒイラギ/松岡
IV (65) 医王寺のマキ/比奈
IV (66) 一色のカヤ/一色
IV (67) 八幡穴(溶岩洞穴)/久沢
IV (68) 不動穴(溶岩洞穴)/大淵
IV (69) 厚原風穴(溶岩洞穴)/厚原
IV (70) 本照寺のカヤ/厚原
IV (71) 白髭神社のヒイラギ/大淵
IV (72) 木之元神社のムクロジ/鈴川
IV (73) 常盤家のイヌマキ/岩淵
IV (74) 慈林寺のイヌマキ/中之郷
IV (75) 横割八幡宮のクスノキ/横割
登録文化財
I 有形文化財
I (1) 建造物
I (1) 【国登録文化財】 34
I (1) 「1」 常盤家住宅主屋/岩淵
I (1) 「2」 旧岩淵火の見櫓/南松野
I (1) 「3」 旧順天堂田中歯科医院診療所兼主屋/吉原
富士市の文化財 見どころいろいろ(未指定文化財)
【富士市の文化財見どころいろいろマップ】 36
I 建造物 38
I (1) 實相寺伽藍/岩本・實相寺
I (2) 王子特殊紙(株)FP事業本部第一製造所レンガ造工場
→(旧富士製紙第一工場)/入山瀬・王子特殊紙(株)
I (3) 金正寺山門/平垣本町・金正寺
I (4) 小澤家石蔵/原田
II 歴史を物語る資料たち~富士市立博物館
→収蔵品を中心に~
II 【出土品いろいろ】 40
II (5) 天間沢遺跡出土品
II (6) 東平第1号墳出土品
II (7) 中原第4号墳出土品
II (8) 沢東A遺跡出土子持勾玉
II (9) 東平遺跡出土「布自」銘 墨書土器
II (10) 国久保古墳出土品「雁木玉」/
→富士市埋蔵文化財調査室保管
II <富士川西岸の考古資料> 43
II (11) 木島遺跡出土品
II (12) 山王遺跡出土品
II (13) 浅間林遺跡出土品
II 【歴史資料】 44
II (14) 四季加嶋風俗図屏風
II (15) 吉原宿伝馬朱印状(複製展示)
II (16) 駿河国富士山絵図
II (17) 原田製紙第1号機(1/2模型)
III 路傍の石造文化財
III 【信仰篇】 46
III i 道祖神 46
III i <富士山と双体道祖神>
III i (18) 双体道祖神・抱肩握手/久沢
III i <市内の道祖神/祈りの造形>
III i (19) 単体・丸彫/伝法
III i (20) 単体・丸彫/宮島
III i (21) 単体・丸彫/浮島
III i (22) 双体・交盃/南松野
III i (23) 双体・抱肩握手/天間
III i (24) 自然石・文字道祖神/岩本
III ii 馬頭観音 47
III ii <馬頭観音アラカルト>
|
III ii (25) 馬頭観音/大淵
III ii (26) 馬頭観音/久沢
III ii (27) 馬頭観音/今宮
III ii (28) 馬頭観音/南松野
III ii (29) 馬頭観音/天間
III iii 観音信仰 47
III iii (30) 万太郎塚・三十三所観音/宮島
III iv 地蔵信仰 48
III iv (31) 笠被り地蔵/中之郷・宗清寺
III v 庚申信仰 48
III v (32) 庚申塔(宝篋印塔型)/木島室野
III v (33) 庚申塔(宝塔)/今泉・十王子神社前
III v (34) 庚申塔(青面金剛)/柚木・天白神社
III vi 信仰と石造物群 49
III vi (35) 妙松寺の石造文化財/北松野・妙松寺
III vi (36) 清正公堂の七夜待石仏群/南松野
III 【道しるべ】
III i 仁藤春耕の道しるべ 50
III ii 室伏半蔵の道しるべ 51
III ii (37) 半蔵道しるべ第2号/久沢
III ii (38) 半蔵道しるべ第4号/久沢
III iii 富士山道道しるべ 51
III iii (39) 富士山道道しるべ/松岡・水神社
III 【文学碑~市内の句碑を訪ねて】 51
III (40) 松尾芭蕉句碑I/富士町・富士市交流プラザ
III (41) 松尾芭蕉句碑II/伝法・カンカン堂
III (42) 松尾芭蕉と郷土の俳人たち~乙児・芭蕉・
→白盆~/岩淵吉津
III (43) 黒露句碑/鈴川
III (44) 白芹句碑/北松野・はたご池池畔
III (45) 松井管雅句碑/比奈
IV 史跡と伝説
IV 【頼朝伝説】 53
IV (46) 平家越/新橋町
IV (47) 横割八幡宮/横割
IV (48) 日吉神社(山王さん)/鮫島
IV (49) 和田神社(義盛さん)/今泉
IV (50) 呼子坂/宇東川西町
IV (51) 鎧ケ淵/原田
IV 【曽我物語】 54
IV (52) 曽我八幡宮/厚原
IV (53) 曽我寺/久沢
IV (54) 五郎の首洗い井戸/厚原
IV (55) 玉渡神社/厚原
IV (56) 虎御前の腰掛石/伝法
IV 【伝説と民話】 56
IV (57) 生贄伝説/鈴川町、中柏原新田
IV (58) お不動さんの白蛇/神谷
IV (59) 雁堤の人柱/松岡
IV (60) はたご池/北松野
IV (61) 石神さん/南松野
IV (62) 八王子神社のイド/大淵
IV (63) いぼとり不動/原田
IV (64) 身代わり地蔵/吉原・陽徳寺
IV (65) 黒仏/増川・円照寺
IV 【近代遺産】 60
IV (66) スイホシと昭和放水路/沼田新田
IV (67) 加島水門/岩本
IV (68) 岩淵水門/岩淵
IV 【身延道】 61
IV 【東海道】 62
V 郷土を彩る画人たち
V 【鈴木香峰】 64
V 【井上恒也】 65
V 【近藤浩一路】・【神戸麗山】 66
V 【徳岡神泉】 67
V 【大村西崖】 68
VI 富士山信仰とかぐや姫伝説 70
VI ◆東泉院跡/今泉◆富知六所浅間神社/浅間本町
→◆滝川神社/原田◆今宮浅間神社/今宮
→◆寒竹浅間神社/富士岡◆飯森浅間神社/宇東川
→◆富士山村山口登山道◆富士塚/鈴川 72
VII 富士市内の祭り
VII ◆吉原祇園祭/吉原 73
VII ◆オテンノウサン/市内 74
VII ◆毘沙門天大祭/今井◆甲子神社祭典/富士本町75
VII ◆宮下のオクリガミ/宮下◆
→岩淵鳥居講/岩淵・八坂神社76
<資料>指定文化財一覧 78
・
・ |
3月、 安永祖堂が禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky" / (90) p.1-27」に「白隠下「五位」に於ける「仏向上」 : 「正中来」と「兼中到」をめぐって」を発表する。
5月、写真記録刊行会編「日本の美 : 写真記録 中部1」が「日本ブックエース」から刊行される。 国際情報社昭和42年刊の複製
|
カラー
富士山 9
新雪の秀峰富士
厳冬の富士
火口
山肌
黎明の富士
雲海に浮かぶ富士
影富士
初秋の富士の裾野
樹海
西湖
富士と私 文・林武 25
南アルプス連峰 26
観音岳より北岳・聞ノ岳を望む
主峰北岳
鳳凰三山薬師岳
兎岳
小渋川上流
原生林<鳳凰山>
苔むした倒木
光を閉ざす原生林
南アルプスの印象 文・深田久弥 36
ホウオウシャジン<鳳凰山・地蔵岳>
ハイマツの花<荒川岳>
タカネビランジ・オンタデ
→・コイワカガミ・イワウメ
八ヶ岳 40
厳冬の八ヶ岳<赤岳>
冬の中岳
川と溪谷 42
寸又峡
昇仙峡
白糸の滝
大井川の砂州
天竜峡
富士川
伊豆半島<グラビアにつづく> 50
伊豆の最南端・石廊崎
伊豆東海岸のハイウェイ
波勝崎
国士峠からの天城連山
湯ヶ野の山間の村
久能山東照宮 113
社殿側面の唐獅子
神楽殿
久能山参道
版画にみる富士と宿場 116
冨嶽三十六景「凱風快晴」
東海道五拾一二次之内「三島」
盆地と平野のみのり 120
ブドウ<勝沼>
茶摘み<日本平>
|
ミカン畑と富士
移り変わる伝統工芸 124
甲州印伝
金剛石目塗漆器
和染<唐草模様>
勇壮なる祭 128
武田二十四将行列
凧上げ祭<浜松>
信玄ゆかりの寺々<グラビアにつづく> 130
恵林寺四脚門
山門<かつての鐘楼>
夢窓国師の庭
炎上に残った楼扉
信玄を模した不動明王像
小桜韋威鎧<武田家重宝>
グラビア
伊豆の風光<カラーよりつづく>
→ 文・岡田喜秋 57
西伊豆田子港暮色
天城山麓のワサビ沢
石囲いをした仲木の漁村
岩礁の多い仲木の海岸
熱海夜景
城山からの修善寺の眺望他
東海の陽光 66
三保の松原
焼津の屋並
朝の浜名湖
千浜の砂丘
久能の石垣イチゴ
焼津のカツオ節干し
牧ノ原の茶園
相良の船どまり
静岡市
四季の富士 文・岡田紅陽 76
峻烈の富士
煤煙にけぶる富士
桜花盛る河口湖からの富士
動の荒波と静の富士<伊豆大瀬岬から>
霧の山中湖に映える富上
晩秋の富士
厳冬の富士<忍野から>
身延山 文・土師清二 86
女人祈願<七面山入口の滝行>
早朝の身延山<竹之坊と西谷>
久遠寺三門
宗祖の草庵跡
七面山麓の祈願所
天竜川を下る 文・新田次郎 92
西渡付近の天竜川
天竜杉
白壁の土蔵<二俣>
河口<掛塚橋付近> |
街道の面影 98
岡部の松並木
新居関所跡
旅人必携の薬類と道中案内書
料理屋の戸袋を飾る紋どころ
丸子のとろろ汁他
駿河と遠江の寺 文・加藤忠雄 104
方広寺本堂
籠沢寺山門と石段
龍華寺
可睡斎の屋根
本興寺の襖絵
清見寺の庭
白隠禅師の墓<松蔭寺>
臨済寺遠望
山間に英雄生きる<カラーよりつづく>
→ 文・土橋治重 137
雲峰寺石段
快川自筆の石塔と山門<恵林寺>
景徳院山門
向岳寺他
甲府盆地 144
甘草屋敷<二百年前の農家>
桑畑<竜王付近>
ブドウ畑と農家
ブドウ棚と勝沼の町並み
白壁の家<青梅街道別田付近>
笛吹川
大菩薩峠 152
妙見山の頂き<大菩薩連嶺>
峠道の三介庵<中里介山執筆の場>他
遺跡と遺構 文・小川龍彦 156
登呂遺跡
田ゲタとクワ
江川邸内部
韮山の反射炉
甲斐国分寺跡
下田 文・松本龍雄 162
城山公園から眺めた下田港
なまこ壁の民家
玉泉寺本堂
柿崎神社の吉田松陰像
城山公園にある開国記念碑
伊豆と交学 文・高杉一郎 168
修禅寺境内の鐘楼
桂川にかかる桂橋
天城山中の林道
指月殿
湯ヶ野温泉
河津七滝の一つ釜滝
天城の山道と丸木橋
口絵解説 177
・ |
9月、芳沢勝弘が「「瓢鮎図」の謎 国宝再読ひょうたんなまずをめぐって」を「ウェッジ
」から刊行する。
|
第1章 賛詩の意味(賛詩を読む;心はとらえられるか ほか)
第2章 賛詩をどう解釈するか(詩作の現場をあきらかにする;大岳周崇 ほか)
第3章 画の意味するところ(どこが目新しいか;男の手の形 ほか)
第4章 「瓢鮎図」のその後(白隠の「鰻のぼり」;白隠が描く「心模様」の絵 ほか)
対談 「瓢鮎図」をめぐって×芳澤勝弘×ノーマン・ワデル(欧米に紹介された「瓢鮎図」;なぜ国宝なのか ほか) |
|
9月、西村惠信が「茶道雑誌 76(9) p.128-136」に「白隠禪師「坐禅和讃」を読む(余滴)別に是れ一壺の天 : 自然と人間の共存的世界」を発表、連載を終える。
|
西村惠信が発表した「白隠禪師「坐禅和讃」を読む(1~14)」迄の内訳一覧表
| No |
雑誌巻号頁 |
発行年月 |
論文名 |
内容 |
| 1 |
75(2) p.35~42 |
2011-02 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(1)茶と禅の出会い |
. |
| 2 |
75(4) p.37~43 |
2011-04 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(2)白隠という人について |
. |
| 3 |
75(6) p.117~123 |
2011-06 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(3)「坐禅和讃」成立への道 |
. |
| 4 |
75(8) p.39~46 |
2011-08 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(4)衆生本来仏なり |
. |
| 5 |
75(10) p.125~132 |
2011-10 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(5)衆生近きを知らずして 遠く求むるはかなさよ |
. |
| 6 |
75(12) p.43-50 |
2011-12 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(6)六趣輪廻の因縁は、己が愚痴の闇路なり |
. |
| 7 |
76(2) p.30-38 |
2012-02 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(7)夫れ摩詞衍の禅定は称嘆するに余りあり |
. |
| 8 |
76(3) p.112-121 |
2012-03 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(8)一坐の功をなす人も積みし無量の罪ほろぶ |
. |
| 9 |
76(4) p.52-62 |
2012-04 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(9)辱くもこの法を一たび耳に触るとき |
. |
| 10 |
76(5) p.30-40 |
2012-05 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(10)況んや自ら回向して直に自性を証すれば |
. |
| 11 |
76(6) p.140-150 |
2012-06 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(11)因果一如の門開け無二無三の道直し |
. |
| 12 |
76(7) p.117-126 |
2012-07 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(12)無念の念を念として謡うも舞うも法の声 |
. |
| 13 |
76(8) p.109-117 |
2012-08 |
白隠禪師「坐禅和讃」を読む(13)この時何をか求むべき寂滅現前する故に |
. |
| 14 |
76(9) p.128-136 |
2012-09 |
「坐禅和讃」を読む(余滴)別に是れ一壺の天 : 自然と人間の共存的世界 |
. |
|
9月、石川九楊が「名僧の書 : 歴史をつくった50人」を「淡交社」から刊行する。
|
はじめに//2
第一章 建国・擬似中国時代の僧―
→国づくりを担った7人
奈良写経 国づくりの書//12
金剛場陀羅尼経巻一
和銅五年長屋王願経
鑑真
恵雲 王国之立国・日本//18
鑑真奉請経巻状
恵雲書状(佐官御所宛)
道鏡 抽斗(ひきだし)の多い書//26
道鏡筆 牒
最澄
空海 比叡山と高野山//34
最澄筆 泰範宛尺牘(久隔帖)
空海筆 最澄宛尺牘(風信帖)
空海 もうひとつの顔//43
空海筆 真言七祖像行状文
空海筆 崔子玉座右銘断簡
円珍 万葉仮名から女手へ//48
円珍筆 遍昭宛書状
第二章 日本文化確立時代の僧―
→日本仏教を拓いた8人
西念 片仮名の歌//56
西念筆 極楽願往生歌
西行 新古今時代の古今思慕//63
西行筆 一品経和歌懐紙
法然 粘りと切れと覚悟//70
法然筆 正行房宛書状
栄西
俊□ 〔シュンジョウ〕黄庭堅の書の衝撃/78
栄西筆 誓願寺盂蘭盆縁起
俊?筆 泉涌寺勧緑疏
親鸞
恵信尼 茫洋と逆説//86
親鸞筆 教行信証(坂東本)
恵信尼筆 覚信尼宛書状
明恵 線の太さと信仰の強靭//95
明恵筆 上覚御房宛消息
第三章 大陸からの亡命僧とその影響―
→政治と学問に勤しんだ16人
道元 圭、直、振幅//98 |
道元筆 普勧坐禅儀
蘭溪道隆
無学祖元 二人の亡命僧の力//105
蘭溪道隆筆 法語
無学祖元筆 上堂語
日蓮異形の書//114
日蓮筆 立正安国論
日蓮筆 大曼荼羅本尊
円爾
癡兀大慧 末期の書の魅惑//122
円爾筆 遺偈
癡兀大慧筆 遺偈
一山一寧
雪村友梅 大陸の自信、弧島の律義//130
一山一寧 雪夜作
雪村友梅筆 梅花詩
宗峰妙超 墨蹟の和様化//138
宗峰妙超筆 徹翁字号
宗峰妙超筆 関山字号
夢窓疎石
義堂周信
絶海中津 大陸の書との遠近//146
夢窓疎石筆 偈語
義堂周信筆 華厳塔勧縁偈并序
絶海中津筆 東山偈
大智 黄庭堅の謙虚な学習//156
大智筆 東谷明光除夜偈
一休宗純 墨蹟の変質//161
一休宗純筆 漁父偈
古嶽宗亘
一絲文守 月と団子そして龍―
→異界への通路//168
古嶽宗亘筆 円相
一絲文守筆 円相
第四章 政教分離後の僧―
→表現へと向かう19人
以心崇伝
天海 法的な骨と優柔の肉//178
以心崇伝筆 桂光院輓詩并序
天海筆 夢想語
藤原惺窩
林羅山 鮮やかな気どりと変哲なき
|
→書きつけ//186
藤原惺窩筆 林羅山宛書状
林羅山筆 賛
沢庵宗彭
江月宗玩 苦と憂いと//195
沢庵宗彭筆 「秀嶽」
江月宗玩筆 「一曲兩曲無人會」
清巌宗渭 一行書//203
清巌宗渭筆「拈華迦葉微笑」
隠元隆琦
即非如一 近世墨跡の行手を暗示//206
隠元隆琦筆 三幅対「萬徳法中王」
即非如一筆 「雲連分紫山」
契沖 学の繊細//214
契沖筆 万葉代匠記序
白隠慧鶴 書ならざる書//219
白隠慧鶴筆 巌頭和尚語
→「暫時不在如同死人」
白隠慧鶴筆 自画像
寂厳 伸縮自在のからくり細工//226
寂厳筆 飲中八仙歌
慈雲飲光 筆蝕の直接性と不立文字//235
慈雲飲光筆「常在霊鷲山」
風外慧薫
東嶺円慈
妙喜宗績 三つの奇書//242
風外慧薫筆 三社託宣
東嶺円慈筆 双幅「一華開五葉
→結果自然成」
妙喜宗績筆 遺偈
仙厓義梵 円相・方相・三角相//252
仙厓義梵筆「○△□」
良寛 自省する筆蝕、批評する書//258
良寛筆 菓子屋三十郎宛書簡
良寛筆 七言絶句「夢左一覚後彷彿」
良寛筆 六曲一双詩屏風 第二屏
蓮月尼 「刻り」と「距離」の近代性//276
蓮月尼刻 和歌「万世も…」急須
蓮月尼筆 鬼念仏図自画賛/
→雨夜たぬき図自画賛
(以下略)
・ |
12月、芳沢勝弘が「白隠禅画をよむ 面白うてやがて身にしむその深さ」を「ウェッジ」から刊行する。
|
第1章 白隠漫画
第2章 白隠禅画のキャラクター
第3章 文字絵の意味 |
第4章 白隠禅画のモノ
第5章 富士山と鷲頭山
第6章 軸中軸と劇中劇 |
第7章 方便・からうそ、おもちゃ
第8章 「心」を描きあらわす
おわりに 私と白隠 |
|
12月22日~翌年2月24日、東急文化村に於て「白隠展 : 禅画に込めたメッセージ」展が開かれる。
広瀬麻美ほか編集「白隠展 = Hakuin : 禅画に込めたメッセージ」が刊行される。 共同刊行: 浅野研究所
○、この年、「人間会議 27 p.246-249 事業構想大学院大学出版部」に「ART&EVENT 白隠展HAKUIN 禅画に込めたメッセージ 白隠の禅画・墨蹟100点を一堂に展示」が掲載される。
○、この年、竹下 ルッジェリ・アンナが京都外国語大学機関誌編集委員会, 京都外国語短期大学機関誌編集委員会編「研究論叢
= Academic bulletin / Kyoto University of Foreign Studies, Kyoto Junior
College of Foreign Languages (通号 80) p.215-227」に「白隠禅師の『遠羅天釜』(2)念仏と公案をめぐって
」を発表する。 (IRDB) |
| 2013 |
25 |
・ |
1月、「芸術新潮 64(1) (通号 757) 大特集 よみがえるスーパー禅僧 白隠 (はくいん)」が刊行される。
|
グラフ 禅力疾走セレクション/ p.12-21
生きている白隠と対峙せよ! /山下 裕二 p.22-25
しりあがりさん、白隠キャラを描いてください。 : /マンガ家 しりあがり 寿,山下 裕二 p.26-33
絵解き白隠伝 : つけたり……用語解説+禅宗法系図 p.34-41
わしの話を聞け! : スーパー禅僧のメッセージを読みほどく/芳澤 勝弘 p.42-63
太さの思想、斜線の批評 : 破調の書が秘めるもの/石川 九楊 p.64-71
呼吸アドバイザー 椎名由紀さんに聞く 白隠伝授の健康法、ZEN呼吸法とは?/椎名由紀
p.72-75
手紙から見える素顔 /ノーマン ワデル 1 p.76-78
ぼく、辻先生の授業で白隠の名を知りました。 : guest 辻惟雄 MHO MUSEUM館長/辻
惟雄,山下 裕二 p.79-87 |
1月、芳澤勝弘, 山下裕二監修 「別冊太陽 (203) : 日本のこころ」が「平凡社」から刊行される。
|
白隠の生涯 (白隠 : 衆生本来仏なり) p.6-22
達磨 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力) p.26-39
祖師 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力)
p.40-45
観音 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力) p.52-57
流行神と伝承 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力)
p.62-69
福神 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力) p.70-75
円相 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画、その空前絶後のど迫力)
p.77-79
白隠に惹かれた人々 細川護立と永青文庫 (白隠 : 衆生本来仏なり) 三宅秀和
p.80-82
白隠の自画像 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選) 矢島新 p.84-91
さまざまな富士山図 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く)
p.95-101
擂鉢図(すりばちず) (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く) p.102-105
白隠漫画 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く) p.106-109
布袋というキャラクター (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く)
p.110-115
お多福というキャラクター (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く)
p.116-119
「心」を描く (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選 ; 白隠禅画を読み解く) p.120-125
白隠の書の魅力 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選) 笠嶋忠幸 p.126-135
白隠の弟子たち (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠禅画傑作選) 瀧瀬尚純 p.136-141
白隠の言葉 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠の禅) 芳澤勝弘 p.146-149
白隠が用いた禅の「公案」 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠の禅) 細川晋輔 p.150-153
禅師、かくの如く自愛せり : 『夜船閑話』に学ぶ禅的養生法 (白隠 : 衆生本来仏なり
; 白隠の禅) 玄侑 宗久 p.154-157
白隠の著作 (白隠 : 衆生本来仏なり ; 白隠の禅) 西川秀敏 p.158-160
白隠年譜 (白隠 : 衆生本来仏なり) 瀧瀬尚純 p.162-165 |
2月、橋本麻里が「美術手帖 65(979) p.101-114」に「山下裕二さんに聞く、白隠の魅力! 白隠 : 技を脱した、超絶"無"技巧派」を発表する。
2月、「美術の窓 = The window of arts 32(2) (通号 373) 」が「生活の友社」から刊行される。
|
アーティスト・白隠を想う (L’oeil 美は語る(15)白隠)/島尾 新 p.176-181 |
財界人も魅了した白隠の健康法 (L’oeil 美は語る(15)白隠) p.182-184 |
2月、則竹秀南が「みんな、仏さま : 白隠禅師「坐禅和讃」を生きる」を「春秋社」から刊行する。
2月、辻惟雄, 泉武夫, 山下裕二, 板倉聖哲 編集「日本美術全集 14」が「小学館」から刊行される。
|
版 もくじ 4
はじめに 辻惟雄 6
ミヤコに奇想横溢―18世紀の京都画壇 辻惟雄 170
伊藤若沖 生涯と画業 岡田秀之 180
応挙の力、芦雪の奇 金子信久 188
せめぎあい、継承する、日本の文人画―関西を中心に 安永拓世 197
若沖『動植綵絵』の妙技―生命の美しさの表現追求 太田彩 206
江戸時代後期の書 髙橋利郎 209
図版解説 213
関連年表 276
序文英訳・英文作品リスト 283
図版もくじ
第一章 伊藤若冲
第一章 1 動植綵絵(どうしょくさいえ)(全三〇幅)伊藤若沖
第一章 1 1-1 動植綵絵(どうしょくさいえ)芍薬群蝶図(しゃくやくぐんちょうず)
第一章 1 1-2 動植綵絵(どうしょくさいえ)梅花小禽図(ばいかしょうきんず)
第一章 1 1-3 動植綵絵(どうしょくさいえ)雪中鴛鴛図(せっちゅうえんおうず)
第一章 1 1-4 動植綵絵(どうしょくさいえ)秋塘群雀図(しゅうとうぐんじゃくず)
第一章 1 1-5 動植綵絵(どうしょくさいえ)向日葵雄鶏図(ひまわりゆうけいず)
第一章 1 1-6 動植綵絵(どうしょくさいえ)紫陽花双鶏図(あじさいそうけいず)
第一章 1 1-7 動植綵絵(どうしょくさいえ)大鶏雌雄図(たいけいしゆうず)
第一章 1 1-8 動植綵絵(どうしょくさいえ)梅花晧月図(ばいかこうげつず)
第一章 1 1-9 動植綵絵(どうしょくさいえ)老松孔雀図(ろうしょうくじゃくず)
第一章 1 1-10 動植綵絵(どうしょくさいえ)芙蓉双鶏図(ふようそうけいず)
第一章 1 1-11 動植綵絵(どうしょくさいえ)老松白鶏図(ろうしょうはっけいず)
第一章 1 1-12 動植綵絵(どうしょくさいえ)老松鸚鵡図(ろうしょうおうむず)
第一章 1 1-13 動植綵絵(どうしょくさいえ)芦鵞図(ろがず)
第一章 1 1-14 動植綵絵(どうしょくさいえ)南天雄鶏図(なんてんゆうけいず)
第一章 1 1-15 動植綵絵(どうしょくさいえ)梅花群鶴図(ばいかぐんかくず)
第一章 1 1-16 動植綵絵(どうしょくさいえ)棕櫚雄鶏図(しゅろゆうけいず)
第一章 1 1-17 動植綵絵(どうしょくさいえ)蓮池遊魚図(れんちゆうぎょず)
第一章 1 1-18 動植綵絵(どうしょくさいえ)桃花小禽図(とうかしょうきんず)
第一章 1 1-19 動植綵絵(どうしょくさいえ)雪中錦鶏図(せっちゅうきんけいず)
第一章 1 1-20 動植綵絵(どうしょくさいえ)群鶏図(ぐんけいず)
第一章 1 1-21 動植綵絵(どうしょくさいえ)薔薇小禽図(ばらしょうきんず)
第一章 1 1-22 動植綵絵(どうしょくさいえ)牡丹小禽図(ぼたんしょうきんず)
第一章 1 1-23 動植綵絵(どうしょくさいえ)池辺群虫図(ちへんぐんちゅうず)
第一章 1 1-24 動植綵絵(どうしょくさいえ)貝甲図(ばいこうず)
第一章 1 1-25 動植綵絵(どうしょくさいえ)老松白鳳図(ろうしょうはくほうず)
第一章 1 1-26 動植綵絵(どうしょくさいえ)芦雁図(ろがんず)
第一章 1 1-27 動植綵絵(どうしょくさいえ)諸魚図(しょぎょず)
第一章 1 1-28 動植綵絵(どうしょくさいえ)群魚図(ぐんぎょず)
第一章 1 1-29 動植綵絵(どうしょくさいえ)菊花流水図(きっかりゅうすいず)
第一章 1 1-30 動植綵絵(どうしょくさいえ)紅葉小禽図(こうようしょうきんず)
第一章 2 釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)伊藤若沖(いとうじゃくちゅう)
第一章 3 仙人掌群鶏図襖(さぼてんぐんけいずふすま)伊藤若沖
第一章 4 鳥獣花木図屏風(ちょうじゅうかぼくずびょうぶ)伊藤若沖
第一章 5 象(ぞう)と鯨図屏風(くじらずびょうぶ)伊藤若沖
第一章 6 虎図(とらず)伊藤若沖
第一章 7 百犬図(ひゃっけんず)伊藤若沖
第一章 8 葡萄図(ぶどうず)伊藤若沖
第一章 9 糸瓜群虫図(へちまぐんちゅうず)伊藤若沖
第一章 10 果蔬涅槃図(かそねはんず)伊藤若沖
第一章 11 四季花鳥図押絵貼屏風(しきかちょうずおしえばりびょうぶ)伊藤若沖
第一章 12 菜蟲譜(さいちゅうふ)伊藤若沖
第一章 13 花烏版画(かちょうはんが)雪竹に錦鶏図(せつちくきんけいず)伊藤若沖
第一章 14 花鳥版画(かちょうはんが)鸚鵡図(おうむず)伊藤若沖
第二章 曾我蕭白
第二章 15 鷹図(たかず)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 16 雲龍図(うんりゅうず)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 17 月夜山水図屏風(げつやさんすいずびょうぶ)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 18 雪山童子図(せつせんどうじず)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 19 美人図(びじんず)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 20 群仙図屏風(ぐんせんずびょうぶ)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 21 寒山拾得図屏風(かんざんじつとくずびょうぶ)曾我瀟白(そがしょうはく)
第二章 22 風仙図屏風(ふうせんずびょうぶ)曾我蕭自(そがしょうはく)
第二章 23 商山四晧図屏風(しょうざんしこうずびょうぶ)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 24 □居士・霊昭女図屏風(ほうこじれいしょうじょずびょうぶ)
→(見立久米仙人)(みたてくめせんにん)曾我蕭白(そがしょうはく)
第二章 25 唐獅子図(からじしず)曾我瀟白(そがしょうはく)
第三章 円山応挙と京都画壇
第三章 26~27 松(まつ)に孔雀図襖(くじやくずふすま)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 28 郭子儀図襖(かくしぎずふすま)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 29~30 七難七福図巻(しちなんしちふくずかん)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 31 藤花図屏風(ふじはなずびょうぶ)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 32 雪松図屏風(ゆきまつずびょうぶ)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 33 人物正写惣本(じんぶつせいしゃそうほん)円山応挙(まるやまおうさよ)
三章 34 江ロ君図(えぐちのさみず)円山応挙(まるやまおうさよ) |
第三章 35 牡丹孔雀図(ぼたんくじゃくず)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 36 雲龍図屏風(うんりゅうずびょうぶ)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 37 爆布古松図(ばくふこしょうず)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 38 龍門鯉魚図(りゅうもんりぎょず)円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 39 大石良雄(おおいしよしおず)図円山応挙(まるやまおうきよ)
第三章 40 虎図襖(とらずふすま)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 41 龍図襖(りゅうずふすま)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 42 白象黒牛図屏風(はくぞうこくぎゅうずびょうぶ)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 43 群猿図襖(ぐんえんずふすま)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 44 海浜奇勝図屏風(かいひんきしょうずびょうぶ)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 45 龍図襖(りゅうずふすま)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 46 方寸五百羅漢図(ほうすんごひゃくらかんず)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 47 富士越鶴(ふじごえつるず)図長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 48 山姥図(やまんばず)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 49 雨中釣燈籠図(うちゅうつりどうろうず)長沢芦雪(ながさわろせつ)
第三章 50 白梅図屏風(はくぼいずびょうぶ)呉春(ごしゅん)
第三章 51 柳鷺群禽図屏風(りゅうろぐんきんずびょうぶ)呉春(ごしゅん)
第三章 52 太夫雪見図(たゆうゆきみず)山ロ素絢(やまぐちそけん)
第三章 53 楊貴妃図(ようきひず)源琦(げんき)
第三章 54 松下飲虎図(しょうかいんこず)岸駒(がんく)
第三章 55 雪中燈籠猿図(せつちゅうとうろうさるず)森狙仙(もりそせん)
第三章 56 雪中松(せつちゅうまつ)に兎(うさぎ)・梅(うめ)に鴉図屏風
→(からすずびょうぶ)葛蛇玉(かつじゃぎょく)
第四章 大雅・蕪村と文人画
第四章 57 楼閣山水図屏風(ろうかくさんすいずびょうぶ)池大雅(いけのたいが)
第四章 58 瀟湘八景図屏風(しょうしょうはっけいずびょうぶ)池大雅(いけのたいが)
第四章 59 龍山勝会・蘭亭曲水図屏風
→(りゅうざんしょうかいらんていきょくすいずびょうぶ)池大雅
第四章 60 浅間山真景図(あさまやましんけいず)池大雅(いけのたいが)
第四章 61 瀟湘八景図(しょうしょうはっけいず)(東山清音帖)(とうざんせいいんじょう)池大雅
第四章 62 洞庭赤壁図巻(どうていせきへきずかん)池大雅(いけのたいが)
第四章 63 五百羅漢図(ごひゃくらかんず)池大雅(いけのたいが)
第四章 64 十便図(じゅうべんず)池大雅(いけのたいが)
第四章 65 十宜図(じゅうぎず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 66 山水図屏風(さんすいずびょうぶ)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 67 夜色楼台図(やしょくろうだいず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 68 富岳列松図(ふがくれつしょうず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 69 峨嵋露頂図巻(がびろちょうずかん)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 70 鳶鴉図(とびからすず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 71 新緑杜鵑図(しんりょくとけんず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 72 竹林茅屋・柳蔭騎路図屏風(ちくりんぼうおくりゅういんさろずびょうぶ)与謝蕪村
第四章 73 山野行楽図屏風(さんやこうらくずびょうぶ)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 74~75 奥(おく)の細道画巻(ほそみちがかん)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 76 太祗馬提灯図(たいぎうまちょうちんず)与謝蕪村(よさぶそん)
第四章 77 墨梅図(ぼくばいず)祗園南海(ぎおんなんかい)
第四章 78 天台石橋図(てんだいしゃっきょうず)祗園南海(ぎおんなんかい)
第四章 79 墨竹図掻取(ぼくちくずかいどり)祗園南海(ぎおんなんかい)
第四章 80 藍中狭蘭図(らんちゅうきょうらんず)柳沢淇園(やなぎさわきえん)
第四章 81 天台岳中石橋図襖(てんだいがくちゅうしゃっさょうずふすま)
→彭城百川(さかきひゃくせん)
第四章 82 梅図屏風(うめずびょうぶ)彭城百川
第四章 83 山水図屏風(さんすいずびょうぶ)彭城百川
第四章 84 東雲篩雪図(とううんしせつず)浦上玉堂(うらかみぎょくどう)
第四章 85 雙峯挿雲図(そうほうそううんず)浦上玉堂
第四章 86 山紅於染図(さんこうおせんず)浦上玉堂
第四章 87 奇峯連聳図(きほうれんしょうず)
→(『如意道人蒐集書画帖』)(によいどうじんしゅうしゅうしょがじょう)浦上玉堂
第四章 88 山雨染衣図(さんうせんいず)浦上玉堂
第四章 89 兎道朝暾図(うじちょうとんず)木米(もくべい)
第四章 90 亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)水天空濶図・牡丹図
→(すいてんくうかつずぼたんず)田能村竹田(たのむらちくでん)
第四章 91 暗香疎影図(あんこうそえいず)田能村竹田
第四章 92 桃花流水図(とうかりゅうすいず)田能村竹田
第四章 93 雁来紅群雀図(がんらいこうぐんじゃくず)田能村竹田
第四章 94 松竹梅図(しょうちくばいず)岡田米山人(おかだべいさんじん)
第四章 95 青緑山水図(せいりょくさんすいず)岡田米山人
第四章 96 騎牛吹笛図(きぎゅうすいてきず)岡田米山人
第四章 97 春靄起鴉図(しゅんあいきあず)岡田半江(おかだはんこう)
第四章 98 重山雲樹図(じゅうざんうんじゅず)中林竹洞(なかばやしちくとう)
第四章 99 四季花鳥図屏風(しきかちょうずびょうぶ)山本梅逸(やまもとばいいつ)
第五章 白隠
第五章 100 達磨像(だるまぞう)白隠慧鶴(はくいんえかく)
第五章 101 大燈国師像(だいとうこくしぞう)白隠慧鶴
第五章 102 達磨図(だるまず)「どふ見ても」白隠慧鶴
第五章 103 豊干(ぶかん)・寒山拾得図屏風(かんざんじつとくずびょうぶ)仙厓(せんがい)
第五章 104 指月布袋(しげつほてい)仙厓
第五章 105 ○△口図(まるさんかくしかくず)仙厓
・ |
3月、ヤン C. ベッカーが花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢
= Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism
(8) p.1-10」に「欧米における白隠禅画の受容 : 鈴木大拙による禅画解釈とその影響」を発表する。
3月、横田喬が「白隠伝」を「大法輪閣」から刊行する。
月刊『大法輪』平成23年4月号から平成24年6月号まで連載した「白隠和尚蛍雪記」をまとめたもの
3月、木村俊彦が禪學研究會編「禪學研究 = Studies in Zen Buddhism = The "Zengaku kenky?" (91) p.191-201」に「大峡秀榮独語訳『ZEN』と洞上五位偏正口訣」を発表する。
3月、小濱聖子が「お茶の水女子大学人文科学研究 9 p.1-12」に「白隠の報恩観」を発表する。 (IRDB)
3月、松下宗柏が「白隠禅との出会い」を「教育評論社」から刊行する。
|
第1部 ラサールボーイの禅修行(ラ・サール時代;激動の大学生活;龍澤寺への道;雲水修行;老師との日々)
第2部 原の白隠さん(白隠伝;白隠の庶民説法)
|
3月、京丹後市史編さん委員会編「京丹後市の美術 : 京丹後市史資料編」が刊行される。
|
凡例
第一章 京丹後市の指定文化財
第一章 第一節 彫刻 2
第一章 第一節 1 千手観音立像(縁城寺)
第一章 第一節 2 薬師如来坐像及び両脇立
→日光・月光菩薩像(円頓寺)
第一章 第一節 3 薬師如来及び両脇侍像(成願寺)
第一章 第一節 4 阿弥陀如来立像(本願寺)
第一章 第一節 5 阿弥陀如来坐像(全徳寺)
第一章 第一節 6 阿弥陀如来坐像(長安寺)
第一章 第一節 7 阿弥陀如来坐像(遍照寺)
第一章 第一節 8 阿弥陀如来坐像(如意寺)
第一章 第一節 9 阿弥陀如来立像(岩屋寺)
第一章 第一節 10 伝地蔵菩薩立像(泰平寺)
第一章 第一節 11 十一面観音菩薩立像(上山寺)
第一章 第一節 12 観音菩薩坐像(岩屋寺)
第一章 第一節 13 観音菩薩立像(徳運寺)
第一章 第一節 14 地蔵菩薩立像(地蔵院)
第一章 第一節 15 金剛力士像(如意寺)
第一章 第一節 16 金剛力士像(仲禅寺区)
第一章 第一節 17 神像(大宮神社)
第一章 第二節 絵画 30
第一章 第二節 18 当麻曼茶羅図(本願寺)
第一章 第二節 19 松井康之像(宗雲寺)
第一章 第二節 20 玄圃霊三関係資料(宗雲寺)
第一章 第二節 21 松井与八郎像(宝泉寺)
第一章 第二節 22 方丈障壁画(慶徳院)
第一章 第二節 23 釈迦十六善神像(岩屋寺)
第一章 第二節 24 地蔵菩薩像(岩屋寺)
第一章 第二節 25 五大尊像(岩屋寺)
第一章 第二節 26 毘沙門天像(岩屋寺)
第一章 第二節 27 斎宮大明神縁起(竹野神社)
第一章 第二節 28 等楽寺縁起(竹野神社)
第一章 第二節 29 如意輪観音像(縁城寺)
第一章 第二節 30 十王図(縁城寺)
第一章 第二節 31 倶生神像(縁城寺)
第一章 第二節 32 釈迦十六善神像(常立寺)
第一章 第二節 33 不動明王像(常立寺)
第一章 第二節 34 京極家歴代藩主肖像(常立寺)
第一章 第二節 35 揚柳観音像(岩屋寺)
第一章 第二節 36 大江山鬼退治図(岩屋寺)
第一章 第三節 工芸 82
第一章 第三節 37 金銅装笈(縁城寺)
第一章 第三節 38 熊野十二社権現懸仏(円頓寺)
第一章 第三節 39 木造扁額(如意寺)
第一章 第三節 40 鋳銅手錫杖(縁城寺)
第一章 第三節 41 鋳銅五具足(縁城寺)
第一章 第三節 42 銅鰐口(加茂神社)
第一章 第三節 43 銅鰐口(木橋区)
第一章 第三節 44 線刻薬師如来御正体(木橋区)
第一章 第三節 45 石造宝篋印塔(縁城寺)
第一章 第三節 46 石燈籠(大宮売神社)
第一章 第三節 47 石燈籠(溝谷神社)
第一章 第三節 48 狛犬像(高森神社)
第一章 第三節 49 立石大逆修塔(森本区)
第一章 第三節 50 元尾坂寺宝篋印塔(蓮華寺)
第一章 第三節 51 石造宝篋印塔(上山寺)
第一章 第三節 52 石造五輪塔(上山寺)
第一章 第三節 53 十三仏石塔(福昌寺)
第一章 第三節 54 石造宝篋印塔(野中区)
第一章 第三節 55 石造二重宝篋印塔(宗雲寺)
第一章 第三節 56 肥後の墓(宗雲寺)
第一章 第三節 57 石燈籠(八幡神社)
第一章 第三節 58 松井与八郎の墓(宝泉寺)
第一章 第三節 59 法華経大石塔(丸山区)
第一章 第三節 60 古瀬戸茶壷(万休院)
第一章 第四節 書跡・典籍・古文書 100 |
第一章 第四節 61 円頓寺惣門再興勧進状(円頓寺)
第一章 第四節 62 縁城寺縁起(縁城寺)
第一章 第四節 63 日興筆本尊曼茶羅(常徳寺)
第一章 第四節 64 日親筆本尊曼茶羅(常徳寺)
第一章 第四節 65 丹哥府志の原本(京丹後市)
第二章 京丹後市内の美術工芸品
第二章 第一節 京丹後市の仏教美術 106
第二章 第二節 京丹後市の彫刻
第二章 第二節 (一) 古代の彫刻 117
第二章 第二節 (二) 古代彫刻各個解説 122
第二章 第二節 (二) 1 阿弥陀如来坐像(縁城寺)
第二章 第二節 (二) 2 如来形坐像(縁城寺)
第二章 第二節 (二) 3 薬師如来坐像(萬歳寺)
第二章 第二節 (二) 4 薬師如来坐像(広通寺)
第二章 第二節 (二) 5 薬師如来坐像(正徳院)
第二章 第二節 (二) 6 薬師如来坐像(龍雲寺)
第二章 第二節 (二) 7 薬師如来坐像
第二章 第二節 (二) 8 持国天・多門天立像(隣海寺)
第二章 第二節 (二) 9 阿弥陀如来坐像(雲龍寺)
第二章 第二節 (二) 10 薬師如来坐像
第二章 第二節 (二) 11 如来形立像(円頓寺)
第二章 第二節 (二) 12 阿弥陀如来立像(甲山寺)
第二章 第二節 (二) 13 薬師如来坐像(泰平寺)
第二章 第二節 (二) 14 薬師如来立像(東岳寺)
第二章 第二節 (二) 15 薬師如来坐像(遍照寺)
第二章 第二節 (二) 16 薬師如来坐像(宝勝寺)
第二章 第二節 (二) 17 薬師如来坐像(宝泉寺)
第二章 第二節 (二) 18 如来形立像(宝泉寺)
第二章 第二節 (二) 19 如来形坐像
第二章 第二節 (二) 20 天部形立像
第二章 第二節 (二) 21 薬師如来坐像
第二章 第二節 (二) 22 地蔵菩薩立像(縁城寺)
第二章 第二節 (二) 23 地蔵菩薩立像(円頓寺)
第二章 第二節 (二) 24 観音菩薩立像(延命寺)
第二章 第二節 (二) 25 菩薩形立像(正福寺)
第二章 第二節 (二) 26 観音菩薩立像(大雲寺)
第二章 第二節 (二) 27 聖観音菩薩立像(如意寺)
第二章 第二節 (二) 28 聖観音菩薩立像(宝珠寺)
第二章 第二節 (二) 29 地蔵菩薩立像(本願寺)
第二章 第二節 (二) 30 地蔵菩薩立像
第二章 第二節 (二) 31 地蔵菩薩立像
第二章 第二節 (二) 32 菩薩形立像
第二章 第二節 (二) 33 菩薩形立像
第二章 第二節 (二) 34 地蔵菩薩立像
第二章 第二節 (二) 35 聖観音菩薩立像
第二章 第二節 (二) 36 不動明王立像(縁城寺)
第二章 第二節 (二) 37 不動明王坐像(円頓寺)
第二章 第二節 (二) 38 天部形立像(常立寺)
第二章 第二節 (二) 39 天部形立像
第二章 第二節 (三) 中・近世の彫刻 143
第二章 第二節 (四) 中・近世彫刻各個解説 148
第二章 第二節 (四) 40 大日如来坐像(縁城寺)
第二章 第二節 (四) 41 阿弥陀如来立像附
→春日厨子(縁城寺)
第二章 第二節 (四) 42 薬師如来坐像(浄名庵)
第二章 第二節 (四) 43 薬師如来及両脇侍像(願興寺)
第二章 第二節 (四) 44 菩薩面(個人蔵)
第二章 第二節 (四) 45 金剛力士像(円頓寺)
第二章 第二節 (四) 46 女神坐像(大宮売神社)
第二章 第二節 (四) 47 女神坐像(大宮売神社)
第二章 第三節 京丹後市の絵画
第二章 第三節 (一) 京丹後市の絵画概説 155
第二章 コラム 智海と不動明王 166
第二章 (二) 絵画各個解説 168
第二章 (二) 1 阿弥陀如来像ならびに
→文殊菩薩像・普賢菩薩像(縁城寺)
第二章 (二) 2 千手観音像(縁城寺) |
第二章 (二) 3 地蔵菩薩像(縁城寺)
第二章 (二) 4 不動明王像ならびに二童子像(縁城寺)
第二章 (二) 5 不動明王像ならびに二童子像(縁城寺)
第二章 (二) 6 不動明王像ならびに二童子像(縁城寺)
第二章 (二) 7 十二天像(縁城寺)
第二章 (二) 8 真言八祖像(縁城寺)
第二章 (二) 9 青面金剛像(縁城寺)
第二章 (二) 10 三十番神像(縁城寺)
第二章 (二) 11 金剛界種子曼茶羅図(縁城寺)
第二章 (二) 12 光明曼茶羅図(縁城寺)
第二章 (二) 13 出山釈迦像ならびに蓮に小禽図(縁城寺)
第二章 (二) 14 滝見観音像ならびに
→黄蜀葵図・芙蓉図(縁城寺)
第二章 (二) 15 請雨観音像(縁城寺)
第二章 (二) 16 地蔵菩薩像(慶徳院)
第二章 (二) 17 寿老人ならびに梅鶴図・竹鶏図(慶徳院)
第二章 (二) 18 阿弥陀聖衆来迎図(常立寺)
第二章 (二) 19 束帯天神像(岩屋寺)
第二章 (二) 20 仏涅槃図(万松寺)
第二章 (二) 21 本堂障壁画(万松寺)
第二章 (二) 22 山水図(万松寺)
第二章 (二) 23 野晒図・幽霊図(福寿院)
第二章 (二) 24 釈迦十六善神像(龍雲寺)
第二章 (二) 25 許由巣父図(龍雲寺)
第二章 (二) 26 役行者像(円頓寺)
第二章 (二) 27 釈迦十六善神像(延命寺)
第二章 (二) 28 不動明王像(甲山寺)
第二章 (二) 29 弘法大師像(甲山寺)
第二章 (二) 30 仏涅槃図(宗雲寺)
第二章 (二) 31 楊柳観音像(宗雲寺)
第二章 (二) 32 維摩居士像(宗雲寺)
第二章 (二) 33 鴿図(宗雲寺)
第二章 (二) 34 虎溪三笑図ならびに山水図(宗雲寺)
第二章 (二) 35 鬼退治図(東岳寺)
第二章 (二) 36 仏涅槃図(遍照寺)
第二章 (二) 37 虚空蔵菩薩像(遍照寺)
第二章 (二) 38 僧形八幡神像(宝珠寺)
第二章 (二) 39 金剛宝塔図(宝泉寺)
第二章 (二) 40 住吉神像(宝泉寺)
第二章 (二) 41 寿老人図(宝泉寺)
第二章 (二) 42 山水図(宝泉寺)
第二章 (二) 43 仏涅槃図(本願寺)
第二章 (二) 44 阿弥陀来迎図(本願寺)
第二章 (二) 45 阿弥陀三尊来迎図(本願寺)
第二章 (二) 46 滝見観音像(本願寺)
第二章 (二) 47 山水図(本願寺)
第二章 コラム 白隠の絵画 203
第二章 第四節 京丹後市の工芸品
第二章 第四節 (一) 京丹後市の工芸品―
→仏教関係品を中心に― 204
第二章 第四節 (二) 京丹後市の石造美術―
→中世石造塔を中心に― 217
第二章 コラム 笈の文様 221
第二章 第五節 京丹後市の書跡・典籍・古文書 222
第三章 論考編
第三章 (一) 平安時代後期の仏像の
→製作工房と製作技法 226
第三章 (二) 平安時代の神像 230
第三章 (三) 伝承に彩られた"ほとけ"たち 234
第三章 (四) 雷を鳴らす鬼・石を投げる鬼 238
第三章 (五) 京丹後市内の経塚遺物と鏡 242
附編
(一) 仏像の種類と造像技法 250
(二) 用語解説 256
主な参考文献
協力機関・協力者
写真提供・京丹後市史編さん委員 |
3月、 大垣市編「大垣市史 通史編 自然・原始-近世」が刊行される。
|
口絵
序
例言
第一部 自然(省略)
第二部 原始(省略)
第三部 第一章 古代国家の形成 一九四
第一節 大化前代 一九四
第一節 ヤマト王権の時代 (一九四)
第一節 ヤマト王権と西濃地方 (一九五)
第一節 国と県 (一九六)
第一節 国 (一九七)
第一節 県 (一九九)
第一節 部民 (二〇〇)
第一節 屯倉 (二〇〇)
第一節 古代人名からみた西濃 (二〇一)
第一節 大化前代の西濃地方 (二〇三)
第二節 律令国家の成立と美濃 二〇四
第二節 律令国家への道 (二〇四)
第二節 大化の改新と評の成立 (二〇六)
第二節 白村江の戦いと唐人捕虜 (二〇七)
第二節 壬申の乱と美濃 (二〇八)
第二節 地方行政組織の整備 (二一〇)
第二節 ミノにおける変遷 (二一二)
第二節 古代寺院の成立 (二一五)
第二節 律令国家の成立 (二一五)
第三部 第二章 律令国家の展開と大井荘の成立 二一七
第一節 奈良時代の政治と関国美濃 二一七
第一節 平城遷都 (二一七)
第一節 聖武天皇と大仏開眼 (二一七)
第一節 奈良時代の終焉 (二一九)
第一節 地方行政の整備 (二一九)
第一節 東山道と駅家 (二二〇)
第一節 関国美濃 (二二〇)
第二節 古代美濃の景観と大垣 二二一
第二節 一 東山道と不破関 二二一
第二節 一 古代の交涌 (二二一)
第二節 一 駅伝制 (二二二)
第二節 一 駅路と伝路 (二二三)
第二節 一 初期駅路と墨俣 (二二四)
第二節 一 駅路の改廃と後期駅路 (二二六)
第二節 一 不破関 (二二九)
第二節 二 国府と官衙 二三〇
第二節 二 国府 (二三〇)
第二節 二 御旅神社 (二三三)
第二節 二 国分寺・国分尼寺 (二三三)
第二節 二 郡と郡家 (二三六)
第二節 三 条里の施行 二三九
第二節 三 条里とはなにか (二三九)
第二節 三 美濃の条里とその特徴 (二四二)
第二節 三 不破郡と多芸郡の条里 (二四五)
第二節 三 安八郡条里 (二四六)
第三節 大井荘の成立 二四九
第三節 一 東大寺領荘園の成立と経営 二四九
第三節 一 土地政策の転換 (二四九)
第三節 一 初期荘園 (二五一)
第三節 一 東大寺領荘園の成立 (二五二)
第三節 一 開墾型村落 (二五三)
第三節 一 東大寺領荘園の経営 (二五四)
第三節 二 大井荘の成立 二五五
第三節 二 大井荘の四至 (二五五)
第三節 二 大井荘の成立事情 (二五九)
第三部 第三章 律令国家の変質と大垣 二六四
第一節 平安初期の政治と社会 二六四
第一節 平安遷都 (二六四)
第一節 格式の編纂 (二六四)
第二節 延喜式の世界 二六五
第二節 『延喜式』の美濃関連記事 (二六五)
第二節 美濃の特産物-繊維製品- (二六五)
第二節 美濃の特産物-紙- (二六六)
第二節 美濃の特産物-須恵器- (二六七)
第三節 地方の疲弊 二六八
第三節 広野河事件-前提- (二六八)
第三節 広野河事件-経緯- (二六八)
第三節 広野河事件-背景- (二六九)
第三部 第四章 荘園公領制の成立と大垣 二七〇
第一節 律令体制の崩壊と大井荘 二七〇
第一節 延喜・天暦の治 (二七〇)
第一節 天暦四年「東大寺封戸・
→荘園井寺用雑物目禄」 (二七一)
第一節 国衙の変質=受領の登場 (二七二)
第一節 国衙との対立の始まり-長久相論 (二七三)
第一節 雑役をめぐる問題 (二七四)
第一節 検田と収公をめぐる問題 (二七五)
第一節 天喜の検田-国使の入部を止めよ (二七七)
第一節 康平・治暦の相論-続く相論 (二七九)
第二節 院政期の大井荘 二八〇
第二節 後三条天皇の親政と延久の荘園整理令 (二八〇)
第二節 延久整理令と大井荘四至の確定 (二八一)
第二節 典薬尞草薬使問題-延久相論のその後 (二八三)
第二節 承保の新制 (二八三)
第二節 大井荘・加納をめぐる相論 (二八四)
第二節 源義綱との対立 (二八六)
第二節 封戸の問題 (二八八)
第二節 伊勢神宮役夫工米をめぐって (二八九)
第二節 東大寺の大井荘検注と
→天平勝宝八歳施入状 (二九二)
第二節 保元の新制と大井荘四至 (二九三)
第三節 大井荘をめぐる人々 二九五
第三節 国衙領と皇室領荘園の形成-朝廷 (二九五)
第三節 愁状と善状-受領の群像(1) (二九七)
第三節 美濃源氏の成長-受領の群像(2) (二九九)
第三節 在庁官人と安八郡司-宮道氏を中心として (三〇三)
第三節 東大寺-華厳会・法華会と大井荘 (三〇六)
第三節 荘官と住人-下司大中臣氏の登場 (三〇九)
第三節 結びにかえて-中世荘園・大井荘の成立 (三一四)
第五章 古代の文化 三一五
第一節 仏教文化の広がり 三一五
第一節 古墳から寺院へ-古代寺院の創建 (三一五)
第一節 美濃国分寺 (三一六)
第一節 平安仏教の成立 (三一八)
第一節 天台宗の広まり(1)-最澄創建伝承の寺々 (三一八)
第一節 天台宗の広まり(2)-円仁・良勇・源信など (三二〇)
第一節 真言宗の広まり (三二二)
第一節 庶民信仰-虚空蔵信仰 (三二四)
第二節 古代の神社 三二五
第二節 式内社 (三二五)
第二節 帳内社(1)-不破郡 (三二七)
第二節 帳内社(2)-安八郡 (三二八)
第四部 中世
第四部 第一章 鎌倉時代の大垣 三三二
第一節 保元・平治の乱 三三二
第一節 保元の乱 (三三二)
第一節 源義朝と平治の乱 (三三三)
第一節 青墓宿と大炊氏一族 (三三五)
第二節 源氏と平氏 三三六
第二節 源頼朝の挙兵と美濃 (三三六)
第二節 墨俣川の合戦 (三三八)
第三節 守護・地頭 三四一
第三節 大内惟義 (三四こ)
第三節 地頭の押妨 (三四二)
第四節 承久の乱と美濃 三四四
第四節 墨俣川の布陣 (三四四)
第四節 杭瀬川の戦い (三四六)
第四節 寛喜の飢謹 (三四七)
第五節 荘園郷保の変遷 三四八
第五節 市域の荘園郷保 (三四八)
第五節 国衙領 (三四九)
第五節 青柳荘 (三五〇)
第五節 尼寺荘 (三五一)
神宮領 (三五四)
第五節 伊勢神宮領中河御厨 (三五五)
第五節 津布良開発御厨と津布良荘 (三五六)
第五節 御裳濯川堤の河籠米 (三五九)
第四部 第二章 鎌倉時代の大井荘 三六〇
第一節 大中臣氏と大井荘下司職 三六〇
第一節 開発領主大中臣氏 (三六〇)
第一節 大中臣氏の歴代 (三六二)
第一節 信清 (三六二)
第一節 長増・清則 (三六二)
第一節 則綱 (三六三)
第一節 源平の争乱と康則の継職 (三六三)
第一節 笠縫堤の修復 (三六五)
第二節 下司職相論 三六七
第二節 大中臣奉則と康則の嫡女成仏との相論 (三六七)
第二節 大中臣奉則と康則の次女妙蓮・
→夫平秋友との相論 (三六八)
第二節 美濃守護大内惟義のもとでの訴訟 (三六九)
第二節 建保の荘田数・所当の注進状 (三七一)
第二節 大中臣奉則と平教円との相論 (三七二)
第二節 北白河院のもとでの対決 (三七三)
第二節 大中臣奉則と左衛門少尉惟宗言光との相論 (三七八)
第二節 大中臣則親と惟宗言光との相論 (三七九)
第二節 則親と慶秀との私合戦 (三八〇)
第三節 東大寺僧の補任 三八一
第三節 惟宗言光の没落 (三八一)
第三節 東大寺僧隆実の補任 (三八三)
第三節 大中臣観音丸と隆実子鶴菊の訴訟 (三八四)
第四節 永仁の検注 三八八
第四節 永仁の検注 (三八八)
第四節 大井荘実検馬上取帳 (三九〇)
第四節 大井荘検注名寄帳 (三九四)
第四節 大井荘の諸階層 (三五四)
第四節 下司・公文・田所の三職分 (三九五)
第四節 下司名 (三九五)
第四節 公文名 (三九五)
第四節 田所名 (三九五)
第四節 荘官名 (三九七)
第四節 有司名 (三九七)
第四節 間人名 (三九七)
第四節 百姓名 (三九九)
第四節 神仏分 (四〇〇)
第五節 中世大井荘の景観と大垣 四〇三
第五節 大井荘実検馬上取帳案 (四〇三)
第五節 永仁取帳の条里と大井荘 (四〇三)
第五節 永仁取帳の条里と安八郡条里 (四〇七)
第五節 土地利用と大井荘の開発 (四〇八)
第五節 八幡神社と大宮 (四〇九)
第六節 三職体制の成立 四一一
第六節 三職体制の始まり (四一一)
第六節 石包符下・国吉符下・公珍符下 (四一二)
第六節 華厳会料 (四一二)
第六節 法華会料と未進の進行 (四一五)
第四部 第三章 南北朝期以降の大垣 四一七
第一節 南北朝期の大井荘 四一七
第一節 動乱・取中の大井荘 (四一七)
第一節 観応の擾乱と半済 (四一八)
第一節 南北朝期法華会料の納入状況 (四一九)
第一節 公文藤原宗光の失脚 (四一九)
第一節 貞治三年の大洪水 (四二二)
第一節 中村弾正事件 (四二四)
第一節 逃亡農民と逃散 (四二五)
第二節 室町時代の大井荘 四二六
第二節 下司隆賢の失墜 (四二六)
第二節 下司源隆と大井荘の逃散 (四二六)
第二節 学侶御領石包名の成立 (四二七)
第二節 大垣氏の動き (四二八)
第二節 応仁文明の乱 (四三〇)
第二節 代官西尾兵庫助直教 (四三二)
第二節 大井荘の終焉 (四三三)
第四部 第四章 産業・文化 四三五
第一節 刀剣 四三五
第一節 西濃の刀工 (四三五)
第一節 赤坂の兼元 (四三六)
第二節 交通と文化 四三七
第二節 京鎌倉往還 (四三七)
第二節 宿駅 (四三七)
第二節 通行する人々『吾妻鏡』 (四三九)
第二節 通行する人々(紀行文) (四四〇)
第二節 叡尊の通行 (四四二)
第二節 飛鳥井雅有の通行 (四四三)
第二節 室町時代の通行 (四四五)
第二節 『碧山日録』と若森里 (四四九)
第二節 美濃国の遊女(傀儡女) (四五〇)
第二節 遊女と今様 (四五一)
第二節 後白河法皇と青墓の遊女 (四五一)
第二節 神楽の沢右近二郎 (四五三)
第三節 浄土真宗の広がり 四五四
第三節 一 美濃における寺院の分布 四五四
第三節 一 真宗寺院の数と割合 (四五四)
第三節 二 初期真宗 四五五
第三節 二 親鸞 (四五五)
第三節 三 美濃への伝播、真宗高祖列坐像 四五七
第三節 三 浄源寺 (四五七)
第三節 三 専精寺 (四五八)
第三節 三 安養寺 (四五九)
第三節 三 雲芳寺 (四六〇)
第三節 三 聚楽寺 (四六〇)
第三節 三 長源寺 (四六一)
第三節 三 等覚坊 (四六一)
第三節 三 本願寺の成立 (四六二)
第四節 浄土真宗の発展と一向一揆 四六三
第四節 一 本願寺の発展 四六三
第四節 一 蓮如の時代 (四六三)
第四節 一 実如の時代 (四六七)
第四節 二 石山本願寺と一向一揆 四六九
第四節 二 西美濃一〇箇所の活躍 (四六九)
第四節 二 年中行事 (四七一)
第四節 二 三十日番衆 (四七二)
第四節 二 雑事番役 (四七六)
第四節 三 美濃の一向一揆 四七七
第四節 三 美濃の錯乱 (四七七)
第四節 三 多芸一揆 (四八〇)
第四節 三 斎藤道三と真宗寺院 (四八一)
第四節 四 織田信長との戦い 四八四
第四節 四 石山本願寺合戦 (四八四)
第四節 四 長島一揆 (四八五)
第四節 四 教如の徹底抗戦 (四八九)
第五部 近世
第五部 第一章 織豊政権の成立 四九二
第一節 織田信長の経略 四九二
第一節 信長の西濃侵入 (四九二)
第一節 西美濃三人衆の内応と西美濃衆 (四九二)
第二節 豊臣政権下の大垣 四九六
第二節 秀吉と大垣城 (四九六)
第二節 稲葉氏と池田氏の領地争い (四九八)
第二節 赤坂村と興福地村の太閤検地 (五〇〇)
第二節 城と城主 (五〇二)
第三節 大垣城と城主 五〇五
第三節 東大寺城 (五〇五)
第三節 大カキノ城 (五〇五)
第三節 歴代の城主 (五〇五)
第四節 関ケ原合戦と大垣城 五〇八
第四節 石田三成と大垣城 (五〇八)
第四節 東軍の西上 (五〇九)
第四節 西軍の陣営 (五一〇)
第四節 杭瀬川の戦い (五一一)
第四節 大垣開城 (五一一)
第四節 関ケ原合戦 (五一二)
第四節 七騎多門 (五一二)
第四節 おあむ物語 (五一三)
第五部 第二章 幕藩体制の成立 五一四
第一節 関ケ原合戦後の大垣 五一四
第一節 幕府直轄領の成立 (五一四)
第一節 大垣地域の領主 (五一六)
第二節 大垣城主 五一八
第二節 松平氏 (五一八)
第二節 石川氏 (五一八)
第二節 松平氏 (五一九)
第二節 岡部氏 (五二〇)
第二節 松平氏 (五二三)
第二節 戸田氏 (五二四)
第五部 第三章 大垣藩政の展開 五二五
第一節 大垣藩の成立 五二五
第一節 戸田氏鉄の大垣入部 (五二五)
第一節 氏鉄の治政 (五二六)
第一節 島原出陣 (五二八)
第一節 戸田氏の格式 (五三〇)
第一節 江戸屋敷 (五三一)
第一節 京都屋敷 (五三四)
第一節 大坂屋敷 (五三五)
第一節 三之丸御殿 (五三六)
第一節 馬屋 (五三七)
第一節 戸田氏庸入城行列 (五三九)
第一節 戸田家の家宝 (五三九)
第一節 藩主の墓所 (五四〇)
第一節 戸田家の信仰 (五四二)
第一節 藩士永田家の信仰 (五四四)
第二節 大垣藩の職制 五四五
第二節 藩法「定帳」 (五四五)
第五部 第三章 第二節 家臣団の組織 (五四六)
第二節 家臣団の統制 (五四八)
第三章 第二節 軍役 (五四九)
第三章 第三節 城下町大垣 五五〇
第三章 第三節 城下町の成立 (五五〇)
第三節 町の発展 (五五一)
第三節 町制と町役 (五五一)
第三節 町方支配 (五五三)
第三節 職業構成 (五五四)
第三節 町人の生活 (五五四)
第三節 町人の家格 (五五四)
第三節 大垣藩の商人 (五五五)
第四節 地方支配 五五六
第四節 筋分け (五五六)
第四節 郡奉行 (五五七)
第四節 代官 (五五九)
第四節 村方三役とその任務 (五五九)
第四節 郷宿 (五六二)
第四節 農民統制 (五六六)
第四節 人心の掌握 (五六六)
第四節 治安維持 (五六九) |
第五部 第四章 大垣藩政の発展 五七〇
第一節 藩政の展開 五七〇
第一節 家老の立場 (五七〇)
第一節 郡奉行の仕事 (五七一)
第一節 延宝の大暇 (五七三)
第一節 元禄の家中改革 (五七四)
第一節 赤穂事件と大垣藩 (五七五)
章 第一節 延享の永暇 (五七七)
第一節 盛枡騒動 (五七七)
第一節 飛騨騒動と出兵 (五七九)
第一節 三業騒動と大垣藩 (五八一)
第一節 万寿騒動 (五八三)
第二節 藩財政の推移 五八四
第二節 寛政の改革 (五八四)
第二節 天保期の財政難 (五八七)
第二節 江戸藩邸の経費 (五八八)
第二節 藩札の発行 (五九〇)
第二節 藩札の流通 (五九二)
第三節 大垣藩預所の支配 五九五
第三節 預所の成立 (五九五)
第三節 寛延の増地 (五九六)
第三節 宝暦の付替 (五九六)
第三節 明和の増減 (五九七)
第三節 安永の増地 (五九八)
第三節 文化の付替 (五九九)
第三節 預役所の行政区画 (五九九)
第三節 貢租と納入 (六〇〇)
第三節 年貢米の廻送 (六〇二)
第三節 預所の農民統制 (六〇三)
第五部 第五章 幕末の大垣藩政 六〇六
第一節 藩政改革 六〇六
第一節 藩財政の窮乏 (六〇六)
第一節 小原鉄心の改革 (六〇七)
第一節 調達金 (六一〇)
第一節 遊学生派遣と大砲鋳造 (六一一)
第二節 ペリー来航と浦賀出兵 六一二
第二節 浦賀奉行の出兵依頼 (六一二)
第二節 異国船来航の農村への影響 (六一四)
第二節 ペリーの再来航 (六一四)
第二節 ペリー来航ころの世相 (六一六)
第二節 大垣藩の軍制改革 (六一七)
第二節 勤王の志士梁川星巌 (六一八)
第三節 幕末の政治情勢 六一九
第三節 東禅寺事件 (六一九)
第三節 和宮降嫁の準備 (六二一)
第三節 援夷と皇居警衛 (六二四)
第三節 八月一八日の政変 (六二六)
第三節 禁門の変と大垣藩 (六二八)
第三節 天狗党の西上 (六三〇)
第三節 長州征伐と将軍宿城 (六三三)
第三節 氏彬の出坂と病死 (六三五)
第三節 第二次長州征伐 (六三五)
第三節 長州征伐の献金と従軍 (六三六)
第三節 慶応の軍制改革 (六三七)
第三節 藩政改革 (六三八)
第五部 第六章 江戸時代の経済 六四〇
第一節 検地と貢租 六四〇
第一節 一 検地 六四〇
第一節 一 慶長検地 (六四〇)
第一節 一 石盛の決定 (六四一)
第一節 一 内検 (六四三)
第一節 二 新田開発 六四三
第一節 二 戸田氏鉄の新田開発 (六四三)
第一節 二 大垣輪中の新田開発 (六四四)
第一節 二 樋門設置 (六四七)
第一節 三 本年貢と小物成・運上 六五三
第一節 三 検見と定免 (六五三)
第一節 三 年貢率の変化 (六五五)
第一節 三 小物成 (六五六)
第一節 三 運上 (六五六)
第一節 三 口米 (六五六)
第一節 四 課役 六五七
第一節 四 課役 (六五七)
第一節 五 調達金・御用金・献金 六五七
第一節 五 天保九年冥加講加入金献金 (六五七)
第一節 五 嘉永四年調達講法 (六五八)
第一節 六 年貢の割付と納入 六五九
第一節 六 御年貢井萬納方割符引入 (六五九)
第一節 六 年貢の納入 (六六〇)
第一節 六 北方村の年貢搬出 (六六〇)
第二節 村の財政 六六一
第二節 村入用 (六六一)
第二節 馬瀬村の村入用 (六六一)
第二節 中曽根村の村入用 (六六二)
第二節 村入用の割付 (六六四)
第二節 村入用出入 (六六四)
第二節 村借・郷借 (六六五)
第二節 兼帯庄屋(名主)と村財政 (六六六)
第三節 曲辰業の発達 六六七
第三節 一 大垣藩・幕領預所の農政 六六七
第三節 一 戸田氏鉄の勧農政策 (六六八)
第三節 一 藩法「定帳」の中で (六六八)
第三節 一 植付時期注進 (六六八)
第三節 一 いもち病と対応 (六六九)
第三節 二 農業の概況と経営 六六九
第三節 二 農業の概況 (六六九)
第三節 二 農業経営 (六七三)
第三節 二 地主・小作制度 (六七五)
第三節 二 稲の品種と肥料 (六七八)
第三節 三 農作物と工芸作物 六七八
第三節 三 農作物 (六七八)
第三節 三 工芸作物 (六七八)
第三節 四 耕地の水損と堀田造成 六八〇
第三節 四 水損所 (六八〇)
第三節 四 堀田(重田) (六八一)
第三節 五 林野の利用と山論 六八二
第三節 五 林野の利用 (六八二)
第三節 五 山野論の発生 (六八三)
第四節 治水と用水 六八五
第四節 一 治水 六八五
第四節 一 水害の歴史 (六八五)
第四節 一 慶安三年の洪水 (六八五)
第四節 一 元禄一四年の洪水 (六八七)
第四節 一 悪水と水門築造 (六八七)
第四節 一 往還対立 (六八九)
第四節 一 大谷川改修計画 (六九一)
第四節 一 川通り取払 (六九三)
第四節 一 高淵新川計画 (六九六)
第四節 一 鵜森伏越樋の設置 (六九八)
第四節 一 鵜森伏越樋の拡充 (六九九)
第四節 二 用水 七〇〇
第四節 二 大垣市域の用水 (七〇〇)
第四節 二 山王用水 (七〇一)
第四節 二 柿木戸用水 (七〇一)
第四節 二 水論 (七〇三)
第五節 商工業の発達 七〇四
第五節 一 各地の商工業 七〇四
第五節 一 在町の様子 (七〇四)
第五節 一 商工業と諸職 (七〇五)
第五節 一 赤坂の石灰・大理石・赤土 (七〇八)
第五節 一 焼き物(温故焼・巨鹿城焼) (七一〇)
第五節 一 製瓦業 (七一〇)
第五節 一 醸造業 (七一一)
第五節 一 大垣の和菓子 (七一三)
第五節 一 角屋の商売 (七一五)
第五節 二 金融 七一六
第五節 二 百姓への貸付金 (七一六)
第五節 二 頼母子講 (七一七)
第五節 二 百姓の借金と返済 (七一八)
第五部 第七章 江戸時代の交通 七二一
第一節 美濃路大垣宿 七二一
第一節 幕府の宿駅制度 (七二一)
章 第一節 美濃路の概要 (七二一)
第一節 大垣宿の概要 (七二三)
第一節 問屋場 (七二五)
第一節 人馬の継立 (七二六)
第一節 継飛脚 (七二六)
第一節 助郷人馬 (七二七)
第一節 大垣藩百疋伝馬 (七二八)
第一節 高札場 (七二八)
第一節 竹島本陣 (七三〇)
第一節 竹島本陣の起源と歴史 (七三〇)
第一節 竹島本陣の構造 (七三三)
第一節 文化サロンとしての本陣 (七三六)
第一節 関札 (七三八)
第一節 脇本陣 (七三九)
第一節 脇本陣の構造 (七四二)
第一節 文化サロンとしての脇本陣 (七四三)
第一節 脇本陣の料理 (七四三)
第一節 旅籠屋 (七四四)
第一節 茶屋 (七四四)
第一節 立場 (七四五)
第一節 一里塚 (七四五)
第一節 松並木 (七四六)
第一節 渡船と船橋 (七四七)
第二節 中山道赤坂宿 七四八
第二節 中山道の成立 (七四八)
第二節 赤坂お茶屋屋敷の造営 (七四九)
第二節 お茶屋屋敷の利用 (七五〇)
第二節 お茶屋屋敷の廃絶 (七五一)
第二節 赤坂宿の概要 (七五二)
第二節 人馬の継立 (七五三)
第二節 赤坂宿本陣 (七五三)
第二節 赤坂宿脇本陣 (七五五)
第二節 赤坂宿脇本陣の構造 (七五六)
第二節 旅籠屋 (七五七)
第二節 茶屋 (七五八)
第三節 主な通行 七五八
第三節 巡見使 (七五八)
第三節 大名行列 (七五九)
第三節 紀州徳川家の通行 (七六〇)
第三節 将軍家茂の上洛 (七六〇)
第三節 和宮の通行 (七六〇)
第三節 和宮の食事 (七六一)
第三節 婚礼道具の通行 (七六二)
第三節 朝鮮通信使 (七六二)
第三節 朝鮮通信使の宿舎全昌寺 (七六三)
第三節 「上判事第一船」屏風 (七六六)
第三節 朝鮮通信使行列の影響 (七六七)
第三節 琉球使節 (七六八)
第三節 御茶壼の通行 (七六八)
第三節 象とラクダの通行 (七七〇)
第三節 伊能忠敬測量の旅 (七七〇)
第三節 庶民の旅 (七七〇)
第四節 大垣藩の水運 七七一
第四節 河川交通 (七七一)
第四節 船町湊の成立と繁栄 (七七二)
第四節 船町の常夜燈 (七七二)
第四節 住吉燈台 (七七三)
第四節 船入り (七七四)
第四節 船板塀 (七七四)
第四節 大垣藩の水運組織 (七七五)
第四節 船町川と水運 (七七五)
第五節 船町湊の船問屋 七七六
第五節 谷家とその屋敷 (七七六)
第五節 船問屋谷九太夫 (七七八)
第五節 船問屋の船荷扱い (七八〇)
第五節 瀬取賃 (七八三)
第五部 第八章 江戸時代の社会 七八五
第一節 武士の生活 七八五
第一節 殿様のくらし (七八五)
第一節 将軍への献上品 (七八八)
第一節 殿様の御成り (七八九)
第一節 家老のくらし (七九四)
第一節 定帳の規定 (七九七)
第一節 郡奉行中西彦左衛門 (七九九)
第一節 馬術師範永田次郎左衛門 (八〇一)
第一節 藩医江馬春齢 (八〇二)
第一節 武家奉公人のくらし (八〇四)
第二節 町人の生活 八〇五
第二節 定帳の規定 (八〇五)
第二節 「座右秘鑑」にみる町人のくらし (八〇七)
第二節 家屋敷の売買 (八一二)
第二節 掘り抜き井戸 (八一二)
第二節 城下町の飲み水 (八一三)
第二節 三清水 (八一四)
第二節 遊郭の設置 (八一四)
第二節 火災 (八一六)
第三節 農民の生活 八一八
第三節 氏鉄の法度 (八一八)
第三節 定帳の規定 (八二〇)
第三節 生活の規定 (八二二)
第三節 村法・郷例 (八二五)
第三節 農家の屋敷 (八二八)
第三節 大垣とその周辺のお札降り (八二九)
第四節 戸数・人口の推移 八三三
第四節 大垣町の戸 (八三三)
第四節 俵町の戸口 (八三五)
第四節 職業別戸口 (八三六)
第四節 赤坂筋の戸口 (八三七)
第四節 小泉村の戸口 (八三七)
第四節 戸口の移動 (八三七)
第五節 飢謹と救助 八四〇
第五節 天保の飢謹 (八四〇)
第五節 農民の生活窮乏 (八四二)
第五節 備荒貯蓄 (八四三)
第五節 夫食貸与 (八四四)
第五節 疫病と予防 (八四五)
第五節 種痘 (八四六)
第五部 第九章 文教の発達 八四八
第一節 儒学の振興 八四八
第一節 一 儒学の創始 八四八
第一節 一 近世の儒学 (八四八)
第一節 一 大垣藩の藩儒の招請 (八四九)
第一節 一 古文辞学派の興隆 (八四九)
第一節 一 守屋峨眉 (八五〇)
第一節 一 守屋東陽 (八五一)
第一節 一 福田太室・福田少室 (八五一)
第一節 一 喜多村抱節 (八五二)
第一節 一 大石桂林 (八五二)
第一節 一 大橋襲石 (八五二)
第一節 二 化政・天保期の儒学 八五三
第一節 二 小川政延 (八五三)
第一節 二 河合東皐 (八五三)
第一節 二 岡田主鈴 (八五三)
第一節 二 戸田睡翁 (八五三)
第一節 二 菱田毅斎 (八五四)
第一節 三 白?社と同人 八五四
第一節 三 白?社の創設 (八五四)
第一節 三 頼山陽の美濃来遊 (八五五)
第一節 三 江馬細香 (八五五)
第一節 三 梁川星巌 (八五六)
第一節 三 金森匏庵 (八五七)
第一節 四 咬菜社の結成 (八五七)
第一節 四 小原鉄心 (八五八)
第一節 四 鳥居研山 (八五八)
第一節 四 宇野南村 (八五八)
第一節 四 松倉瓦鶏 (八五八)
第一節 四 鴻雪爪 (八五九)
第一節 四 高岡夢堂 (八五九)
第一節 四 井田澹泊 (八六〇)
第一節 四 菱田海? (八六〇)
第一節 四 渓毛芥 (八六一)
第一節 四 木蘇大夢 (八六一)
二節 藩校による教育 八六二
第二節 一 藩主の文教奨励と藩校設置 八六二
第二節 一 藩主の文教奨励 (八六二)
第二節 一 藩校致道館と儒官 (八六二)
第二節 一 校舎 (八六三)
第二節 一 教則 (八六三)
第二節 一 教職員体制 (八六四)
第二節 一 貢進生・他修学生 (八六五)
第二節 二 藩校関係諸儒 八六六
第二節 二 水野陸沈 (八六六)
第二節 二 佐藤龍涯 (八六六)
第二節 二 井上果斎 (八六六)
第二節 二 野村藤陰 (八六七)
第三節 大垣の心学と国学 八六七
第三節 一 心学講舎の深造舎 八六七
第三節 一 藩主戸田氏教と心学 (八六八)
第三節 一 久世友輔と深造舎 (八六八)
第三節 一 久世順矣 (八六九)
第三節 一 浦上梅亭 (八六九)
第三節 一 柳瀬彦七郎 (八六九)
第三節 二 国学の発展 八七〇
第三節 二 西濃の国学 (八七〇)
第三節 二 大矢重門 (八七一)
第三節 二 田中美芳 (八七二)
第三節 二 河地重矩 (八七二)
第三節 二 下里延平 (八七二)
第三節 二 加藤東流 (八七三)
第三節 二 飯沼長城 (八七三)
章 第四節 俳譜の興隆 八七四
第四節 一 芭蕉の来遊と大垣俳壇 八七四
第四節 一 芭蕉の大垣来遊 (八七四)
第四節 一 元禄時代の大垣の俳人 (八七八)
第四節 一 谷木因 (八七八)
第四節 一 近藤如行 (八七九)
第四節 一 宮崎荊行 (八七九)
章 第四節 一 高岡斜嶺 (八八〇)
第四節 一 高岡怒風 (八八〇)
第四節 一 鍛冶竹戸 (八八〇)
第四節 一 浅井左柳 (八八〇)
第 第四節 一 中川濁子 (八八〇)
第四節 一 戸田如水 (八八〇)
第四節 一 深田残香 (八八一)
第四節 二 美濃派の動向と
→その後の大垣俳壇 八八一
第四節 二 各務支考と大垣の俳人 (八八一)
第四節 二 美濃派の分裂と継承 (八八二) |
第四節 二 岡崎風盧坊 (八八二)
第四節 二 大谷文寿坊 (八八二)
第四節 二 岡田冬恕坊 (八八三)
第四節 二 軽花坊 (八八三)
第五節 科学の発達 八八四
第五節 一 医学 八八四
第五節 一 江馬蘭斎と蘭学 (八八四)
第五節 一 江馬家と好蘭堂門人 (八八五)
第五節 二 植物学(本草学)・化学 八八六
第五節 二 宇田川榕庵 (八八六)
第五節 二 飯沼慾斎 (八八七)
第五節 三 数学 八八八
第五節 三 和算と数学者 (八八八)
第五節 三 水野陸沈と門人 (八八九)
第五節 三 浅野孝光と門人奉納算額 (八八九)
第五節 四 砲術の改良 八九〇
第五節 四 大垣藩の砲術の改良 (八九〇)
第五節 四 久世喜弘 (八九〇)
第五節 五 考古学 八九一
第五節 五 考古学 (八九一)
第五節 五 谷理九郎 (八九一)
第五節 五 谷鼎 (八九二)
第六節 武術 八九二
第六節 一 砲術 八九三
第六節 一 田付流砲術 (八九三)
第六節 一 大垣藩田付流祖正景 (八九四)
第六節 一 二代目正澄以後 (八九四)
第六節 一 高木貞清・吉田剛中 (八九五)
第六節 一 西洋流砲術の修得 (八九五)
第六節 二 剣・槍・長刀・万力鎖術 八九六
第六節 二 一刀流古藤田弥兵衛家 (八九六)
第六節 二 万力鎖の正木利充 (八九六)
第六節 二 槍・剣の清水武八郎 (八九七)
第六節 三 射術(弓術)・馬術・柔術 八九七
第六節 三 射術 (八九七)
第六節 三 伊丹長政 (八九七)
第六節 三 酒井長職 (八九七)
第六節 三 松井喬房 (八九八)
第六節 三 馬術 (八九八)
第六節 三 永田春方 (八九八)
第六節 三 永田正方 (八九八)
第六節 三 白井直達 (八九八)
第六節 四 兵学 八九九
第六節 四 八田和救 (八九九)
六節 四 山本治義 (八九九)
第六節 四 佐竹五郎義著 (八九九)
第七節 美術・芸道・工芸 九〇〇
第七節 一 美術 九〇〇
第七節 一 狩野派 (九〇〇)
第七節 一 傍島洞竹・洞仙父子 (九〇〇)
第七節 一 戸田氏庸 (九〇〇)
第七節 一 田中洞慶 (九〇〇)
第七節 一 南宋画 (九〇〇)
第七節 一 江馬細香 (九〇一)
第七節 一 河島養素 (九〇一)
第七節 一 傍島甘谷 (九〇一)
第七節 一 菅竹洲 (九〇一)
第七節 一 張紅蘭 (九〇一)
第七節 二 芸道 九〇二
第七節 二 書道 (九〇二)
第七節 二 茶道 (九〇二)
第七節 二 華道 (九〇三)
第七節 二 囲碁 (九〇三)
第七節 二 桑原道節 (九〇三)
第七節 二 囲碁家系譜 (九〇四)
第七節 三 工芸・その他 九〇五
第七節 三 金工 (九〇五)
第七節 三 平山耕雲 (九〇五)
第七節 三 刀匠・鍛冶 (九〇五)
第七節 三 武具師 (九〇五)
第七節 三 彫工・鋳物師 (九〇五)
第七節 三 船工 (九〇六)
第七節 三 時計師 (九〇六)
第八節 庶民教育 九〇六
第八節 一 私塾の教育 九〇七
第八節 一 大垣地方の私塾 (九〇七)
第八節 一 光風霽月舎 (九〇八)
第八節 一 塾主の身分 (九〇八)
第八節 二 寺子屋 九〇八
第八節 二 寺子屋の始まり (九〇八)
二 寺子屋の教育 (九一一)
三 祭礼芸能の執行と若イ者 九一一
第八節 三 若者による神楽導入 (九一二)
第八節 三 祭礼奉芸に奉仕する若イ者 (九一二)
第八節 三 今宿村の若者組 (九一二)
第八節 三 祭礼奉芸への批評 (九一三)
第五部 第一〇章 寺社と信仰 九一四
第一節 幕藩体制下の宗教 九一四
第一節 キリスト教の伝播 (九一四)
第一節 キリスト禁教 (九一四)
第一節 寺院制度 (九一五)
第一節 宗門改 (九一六)
第二節 浄土真宗の隆盛 九一七
第二節 近世以前からの寺院と改宗 (九一七)
第二節 宗派別寺院 (九一八)
第二節 浄土真宗の東西分派 (九一八)
第二節 西濃の触頭 (九一九)
第三節 禅宗等諸宗派の動向 九二〇
第三節 一 禅宗 九二〇
第三節 一 臨済宗の広布 (九二〇)
第三節 一 荒尾円成寺出身の耕隠禅師 (九二一)
第三節 一 大垣の曹洞宗 (九二一)
第三節 一 全昌寺 (九二二)
第三節 二 浄土宗 九二二
第三節 二 大垣の浄土宗 (九二二)
第三節 二 戸田家菩提寺圓通寺 (九二三)
第三節 三 日蓮宗その他 九二三
第三節 三 異安心問題 (九二四)
第三節 三 西濃巡礼所 (九二五)
第三節 三 遊行上人尊任来垣 (九二六)
第三節 三 白隠禅師と大垣 (九二六)
第四節 神社と祭礼 九二七
第四節 一 主な神社と地域 九二七
第四節 一 多い神明・八幡・稲荷神社 (九二七)
第四節 一 除災の神須佐之男・津島・
→牛頭天王・秋葉・水神社 (九二八)
第四節 一 山岳信仰の熊野・白山・日吉神社(九二八)
第四節 一 開拓神白髭・諏訪神社 (九二九)
第四節 二 神社の祭礼と芸能 九二九
第四節 二 八幡神社の年中行事 (九二九)
第四節 二 例大祭と軸 (九三〇)
第四節 二 祭礼行列 (九三二)
第四節 二 各軸の芸能 (九三三)
第四節 三 藩屋敷における芸能 九三四
第四節 三 藩主家の祝儀と芸能 (九三四)
第四節 三 藩主家芸能の影響 (九三四)
第四節 四 村の祭礼と奉芸等 九三五
第四節 四 大垣藩主と領村の神社 (九三五)
第四節 四 祭礼執行の承認 (九三五)
第四節 四 祭礼芸能の抑制 (九三六)
第四節 四 荒川村の松阪踊り (九三六)
第四節 四 赤坂村の御鍬祭 (九三七)
第四節 四 長松村の諸記録に見える祭礼 (九三七)
第五節 庶民の寺社参拝と石仏信仰 九三八
第五節 一 庶民の寺社参拝 九三八
第五節 一 寺社参拝 (九三八)
第五節 一 遠隔地の寺社参詣 (九三八)
第五節 二 石仏・石碑の建立 九三九
第五節 二 石仏・石碑の種類 (九三九)
第五節 二 多い地蔵菩薩像 (九四〇)
第五節 二 水害除けの竜王社・水神 (九四〇)
第五節 二 街道筋に多い馬頭観音像 (九四一)
第五節 二 大神宮燈籠 (九四一)
第五節 二 文人碑・句碑 (九四一)
年表
索引(人名・地名・事項)
あとがき
執筆者
参考文献
資料提供者および協力者
大垣市史編集関係者名簿(平成二十四年度)
付図 二枚 A2版
大垣市付近古代中世広域図
大井荘付近 条里遺構図
図説・古武道史
古武道のあらまし
たたき合いから兵戦へ 一七
武道・武術・武芸・武技 一八
武芸四門と武芸十四事 二〇
武芸十八般の分類 二一
平山行蔵の新分類 二五
十能・六芸・七芸 三〇
兵法の意味 三三
近代武道はスポーツ 三四
刀術
唐風武術と『源家訓閲集』 三六
地方武士勃興期の剣術 四〇
京八流と鬼一法眼 四三
義経剣法の流裔 四四
京流・山本勘助道鬼 四七
神道流・飯篠長威斎家直 五七
鹿島神陰流・松本備前守政信 五九
新当流・塚原卜伝 六〇
ト伝の"一つ太刀" 六二
『ト伝百首』の武道歌 六四
真壁暗夜軒と霞流・桜井一族 六九
天流・斎藤伝鬼房 七〇
有馬神道流の系譜 七二
師岡一巴と微塵流・根岸兎角 七三
念流の祖・念阿弥慈恩 七四
中条流と小田流 八〇
二階堂平法と堤宝山流 八二
念首座流から馬庭念流へ 八三
中条流・富田流代々 八五
富田越後守と戸田越後守 八七
疑問の戸田清元 八八
鐘巻自斎と佐々木小次郎 九一
一刀流・伊藤一刀斎 九二
小野次郎右衛門忠明(神子上典膳) 九五
典膳と善鬼の血闘 九六
東軍流・川崎鑰之助 九八
丹石流・衣斐丹石入道 一〇一
示現流・東郷肥前守重位 一〇二
陰の流・愛洲移香斎久忠 一〇八
新陰流・上泉伊勢守秀綱 一一一
疋田流・疋田豊五郎景兼 一一七
タイ捨流・丸目蔵人佐長恵 一一九
柳生宗厳と但馬守宗矩 一二三
柳生十兵衛と飛騨守宗冬 一三一
柳生十兵衛と荒木又右衛門 一三三
沢庵禅師の痛評 一三七
『不動智神妙録』と『大阿記』 一四〇
武術の心法の変遷 一四二
柳生如雲斎と連也斎 一四四
円明流から二天一流へ 一四六
何人も居た宮本武蔵のにせ者 一五六
『五輪書』の肝要点 一五八
自由創造の剣法 一六一
吉岡流・吉岡憲法代々 一六八
二階堂平法の終末 一七〇
武者修行の実態 一七三
将軍家光の武術上覧 一七五
寛永御前試合の三種の勝負付け 一七七
珍無類な試合出場選手たち 一七九
他流試合の変遷 一八二
粗野から洗練へ 一八四
奥山流から無住心剣へ 一八五
真心影流の防具改善 一八九
心形刀流・伊庭是水軒と柳剛流 一九三
無眼流の気術と文人派の収気術 一九八
忠孝真貫流・平山潜 二〇一
鏡新明智流・桃井代々 二〇四
神道無念流の名手たち 二〇六
中西派一刀流から北辰一刀流へ 二一三
講武所の設立と男谷信友 二一七
撃剣会から競技武術へ 二二二
居合
鞘の中にある勝利 二二六
神夢想林崎流・林崎甚助重信 二二七
田宮流・田宮平兵衛重正 二二九
無楽流と片山伯耆流 二三一
水野流と新田宮流・和田平助 二三三
無外流・辻月丹 二三五
浅山一伝流と不伝流 二三七
その他の居合諸流派 二四〇
柔術・拳法・空手
中国拳法と陳元贇の来朝 二四二
良移心当流・起倒流と扱心流 二四五
三浦流と制剛流 二四八
二つの揚心流 二五三
竹内流・荒木無人斎流の伝系 二五七
関口流・関口柔心 二六五
渋川流と井沢蟠竜軒の『武士訓』 二六八
その他の柔術諸流派 二七〇
日本伝講道館流・嘉納治五郎 二七二
含気道・植芝盛平 二七三
空手と流系 二七五
槍術・薙刀・手裏剣
槍の発達 二七八
宝蔵院流・覚禅房胤栄 二八一
樫原流・疋田流・富田流・無辺流・本間流 二八四
五ノ坪流・内蔵助流・伊岐流・大島流その他 二八五
伊東紀伊守佐忠と管槍の流派 二九三
薙刀の沿革 二九五
薙刀の流派 二九六
手裏剣の種類と蔵髪・腰間の二術 三〇〇
手裏剣の流派 三〇一
鉾・杖・棒術と捕具の術
鞍馬鉾と大和鉾 三〇四
杖の古型は矛 三〇五
杖術の流派 三〇六
棒の種類 三〇七
棒術の流派 三〇九
十手・鎖鎌・万力鎖その他 三一一
むすび 三一四
索引 三三五
図絵目録
[兵法秘伝書]図巻(部分) 見返
武器武具いろいろ(「訓蒙図彙大成」より) 二二
墨僊画の武芸十八般へ(「写真学筆」より) 二六
由比正雪の道場へ黄表紙「菊水」勝川春山画) 三一
武芸立身館双六(一陽斎豊国画) 三二
「六韜」虎韜巻 三六
「虎の巻」いろいろ 三七
「虎の巻」相伝血脉 三八
牛若丸剣法修業図巻(部分) 四三
真鍋家本「源家訓閲集」十二天巻(断簡) 四四
中井家本「天真正神道流図解皆伝書」(部分) 四五
山本勘助在判「軍法兵法記剣術之巻」(全巻) 四八
「念流正法未来記」獅子之巻(全文) 七六
「念流正法未来記」虎之巻(全文) 七七
夢想剣心法書 九三
東軍流免許状 九九
丹石流極秘伝書(部分) 一〇二
「武備志」刀の条、影流目録 一一〇
上泉秀綱伝書の巻末承伝(部分) 一一三
柳生流三学伝書の図巻 一二四
鍋島伝書「進履橋」奥書承伝 一三四
荒木又右衛門の戸波宛入門誓紙 一三六
「不動知神妙録」写本の冒頭 一三八
宮本武蔵肖像(「耽奇漫録」所収) 一四七
[円明流兵法三十五ヵ条」(全文) 一四八
宮本武蔵筆の柔術目録(断簡) 一五六
宮本武蔵筆「五輪書」の冒頭 一五九
「一刀流兵法伝書」(全文) 一六二
他流試合禁止の誓紙 一八三
「夕雲先生兵術伝法書」巻首と巻末 一八六
「直心流神谷伝心斎改兵法根元書附」 一九〇
「直心流霊剣伝受書附」 一九二
「心形刀流諸目録」(全文) 一九四
「猫の妙術」のさしえ(「田舎荘子」より) 二〇〇
「天狗芸術論」の内容 二〇一
白隠禅師「夜船閑話」の冒頭 二〇二
「神道無念流目録」(全交) 二〇八
「講武所規則覚書」 二一八
「千葉撃剣会」(芳年筆錦絵三枚続) 二二二
大久保一郎撃剣会のポスター 二二三
「片山伯耆流居合腰廻伝書」の冒頭 二三三
「無外流秘書」の巻頭 二三六
「浅山一伝流口伝書」(全文) 二三八
陳元贇の肖像(「好古類纂」より) 二四四
芝愛宕山の起倒流拳法碑 二四八
「柔術三浦流目録」の冒頭 二四九
制剛流伝書(全文) 二五〇
秋山派揚心流伝書(全文) 二五四
「真神道流極意秘訣書」(全文) 二五八
関口新心流目録へ(部分)同免許添書(巻首) 二六六
倉田宗倫「打出杭」の巻末 二六九
「四身多久間見日流和緯尽」(全文) 二七〇
槍の種類(「武用弁略」より) 二七九
「宝蔵院流百首」の巻末 二八一
「種田流鎗術免許状」(全交) 二八六
「橘神軍伝」静流長刀の条 二九八
「先意流薙刀目録並序」の巻首 二九九
笄形の蔵髪手裏剣
→(「武門故実百箇条細註」より) 三〇一
「天心流棒術目録」(全文) 三〇六
番所の三道具(「武用弁略」より) 三一〇
戸田流分銅鎖(「柔術槍棒図解秘訣」より) 三一二
・ |
6月、松下宗柏が「白隠禅との出会い」を「教育評論社」から刊行する。
8月、「 仏教を歩く no. 25 (隠元白隠) 」が「朝日新聞出版」から刊行される。 (週刊朝日百科) 改訂版
8月、辻惟雄著,青柳正規, 河野元昭, 小林忠, 酒井忠康, 佐藤康宏, 山下裕二
編集委員「辻惟雄集 2 (「あそび」とアニミズムの美術)」が「 岩波書店」から刊行される。
|
「をこ絵」の世界 《鳥獣戯画》と「をこ絵」
日本美術に流れるアニミズム
仏教と庶民の生活 近世禅僧の絵画 |
白隠《半身達磨像》〈永明寺本〉
東北に残る円空仏・円空の生地を訪ねて
木喰と東北・上越 |
天龍道人源道の仏画
・
・
|
9月、小濵聖子が「博士論文 白隠の修行観」を発表する。 (IRDB)
10月、松下宗柏が「大法輪 80(10) p.96-98」に「山本玄峰(やまもとげんぽう)師(1866~1961) "今白隠"と呼ばれた老師 (特集 弟子が語る〈昭和の名僧〉名言集) 」を発表する。
10月、高階秀爾 監修「富士山」が「美術年鑑社」から刊行される。 (日本の美 ; 5)
|
序 大原美術館館長、東京大学名誉教授 高階秀爾 3
富嶽百撰―近世までの名作・近現代の名作 目次 6
富士山の世界文化遺産登録―
→日本人にとっての意義 前文化庁長官 近藤誠一 8
日本絵画にみる富士 秋田県立
→近代美術館館長 河野元昭 14
描かれた江戸の富士―富士山・江戸城・日本橋―
→江戸東京博物館館長 竹内誠 22
信仰における富士 国際日本文化研究センター
→名誉教授 山折哲雄 26
文学における富士 法政大学社会学部教授 田中優子 30
工芸にみる富士 茨城県陶芸美術館館長、
→多治見市美濃焼ミュージアム館長 金子賢治 34
凡例 38
富嶽百撰―近世までの名作50 高階秀爾撰 39
富嶽百撰―近世までの名作 作品解説執筆者一覧 104
富嶽百撰―近現代の名作50 高階秀爾撰 105
富嶽百撰近現代作家略歴(生年順) 160
富嶽百撰―近現代の名作 作品解説執筆者一覧 164
現代作家―物故編 編集部撰30 165
現代作家220 197
資料編
「富士山」に関する主な美術展一覧 418
「富士山」年表 422
掲載作家索引 429
監修者・論文執筆者紹介 430
協力者一覧 431
富嶽百撰 目次
[近世までの名作50]
秦致貞「聖徳太子絵伝」 40
円伊「一遍聖絵」 42
作者不詳「遊行上人縁起絵第二巻」 44
作者不詳「遊行上人縁起絵第八巻」 44
作者不詳「伊勢物語絵巻」 46
作者不詳「聖徳太子絵伝」 48
作者不詳「聖徳太子絵伝絵巻」 50
作者不詳「聖徳太子絵伝」 51
伝雪舟「富士三保清見寺図」 52
狩野元信印「富士参詣曼茶羅図」 54
作者不詳「月次風俗図屏風」 55
作者不詳「山王霊験記」 56
仲安真康「富嶽図」 58
伝賢江祥啓「富嶽図」 59
式部輝忠「富士八景図」 60
作者不詳「富士三保松原図屏風」 62 |
作者不詳「富士に杉図屏風」 64
狩野山雪「富士三保松原図屏風」 66
伝俵屋宗達「業平東下り図」 68
狩野探幽「富士山図」 69
英一蝶「富士山図」 70
木村探元「富嶽雲烟之図」 71
作者不詳「竹取翁并かぐや姫絵巻物」 72
尾形光琳「富嶽図扇面」 74
尾形光琳「業平東下り図」 75
渡辺始興「氷室の節供図」 76
白隠慧鶴「富士大名行列図」 77
宋紫石「富嶽図」 78
与謝蕪村「松林富士図」 79
池大雅「寓士十二景図一月・八月」 80
円山応挙「富士図」 81
司馬江漢「駿州薩陀山富士遠望図」 82
野呂介石「紅玉芙蓉峰図」 83
亜欧堂田善「駿河湾富士遠望図」 84
小田野直武「富嶽図」 85
仙厓「富岳図」 86
狩野惟信「富嶽十二ヶ月図巻」 87
谷文晁「隅田川両岸図」 88
長沢蘆雪「富士越鶴図」 89
酒井抱一「富士山図」 90
狩野永岳「富士山登龍図」 91
鍬形恵斎「隅田川図屏風」 92
作者不詳「武蔵野図屏風」 94
喜多川歌麿「一富士二鷹三茄子」 96
葛飾北斎「冨嶽三十六景凱風快晴」 98
葛飾北斎「冨嶽三十六景神奈川沖浪裏」 99
歌川広重「冨士三十六景武蔵小金井」 100
歌川広重「冨士三十六景駿河三保之松原」 101
歌川国芳「東都富士見三十六景
→新大はし橋下の眺望」 102
歌川国芳「東都富士見三十六景
→昌平坂の遠景」 103
[近現代までの名作50]
柴田是真「富士田子浦図」 106
高橋由一「牧ヶ原望嶽」 107
富岡鉄斎「富士山図」 108
チャールズ・ワーグマン「富士遠望図」 110
小林清親「従箱根山中
→冨嶽眺望一月上旬午後三時写」 111
五姓田義松「田子之浦図」 112
ジョルジュ・ビゴー「富士(沼津江浦)」 113
|
竹内栖鳳「富士」 114
横山大観「或る日の太平洋」 115
横山大観「朝陽霊峰」 116
岡田三郎助「富士山(三保にて)」 118
和田英作「三保富士」 119
大下藤次郎「富士を望む」 120
石川欽一郎「駿河湾」 121
山元春挙「富士二題秋晴・雨模様」 122
川合玉堂「三保富嶽之図」 123
下村観山「三保富士」 124
木村武山「羽衣」 126
平福百穂「富嶽図」 128
今村紫紅「大井川箱根山・大井川のうち」 129
松岡映丘「富嶽茶園」 130
安田靫彦「木花開耶姫」 131
梅原龍三郎「朝陽」 132
金山平三「雪の十国峠」 133
川瀬巴水「山中湖の晩秋」 134
吉田ふじを「富士山」 135
川端龍子「影富士」 136
小野竹喬「春朝」 137
奥村土牛「富士越えの龍」 138
堂本印象「霊峰飛鶴」 139
玉村方久斗「旅僧仰富士図」 140
小倉遊亀「青巒」 141
徳岡神泉「富士山」 142
児玉希望「不尽(富士)」 143
林武「赤富士」 144
小山敬三「雲中富嶽」 145
伊東深水「富士」 146
小松均「富士山」 147
牛島憲之「黎明富士」 148
向井潤吉「春昼富士」 149
棟方志功「富嶽頒のうち
→赤富士の柵・黒むらさきの柵」 150
長谷川三郎「星空の富士」 151
片岡球子「富士」 152
東山魁夷「秋富士」 153
高山辰雄「不二」 154
奥田元宋「富嶽秋耀」 155
加藤東一「富士」 156
横山操「富士雷鳴」 157
加山又造「青富士」 158
平山郁夫「暁春橘富士」 159
・
|
10月、芳澤勝弘が「現代思想 41(14) p.103-107」に「白隠の「富士大名行列図」 (特集 富士山と日本人 : 自然・文化・信仰 ; 民俗/宗教 : 禅・富士講)」を発表する。 また、「同号 p.108-121」に宮崎ふみ子が「富士山とみろくの世 : 不二道の社会的活動 」を発表する。
10月、新村拓が「日本仏教の医療史」を「法政大学出版局」から刊行する。
|
生を脅かす病
仏教の病因論と治方論
交錯する祈療と医療 看取りと往生
天皇を看取る |
時衆・遊行聖における病
絵巻にみる病の図像
病に向けられた仏教者の目
薬種の栽培と製薬に励む寺僧 |
僧と医師を兼ねる者たち
沢庵と白隠の医学
明治の医療政策と仏教
・ |
10月、秋月龍珉が「白隠禅師 : 仏を求めて仏に迷い」を「河出書房新社」から刊行する。
(河出文庫 ; あ23-1) 講談社 1985年刊の再刊
10月、「白隠 紙芝居 1組 (32枚) ; 15×11cm」が「青幻舎」から刊行される。
(ちいさな美術館)
〇この年、「聚美 (6) 特集 白隠」が「青月社」から刊行される。
|
白隠禅画の表現 : 宗教的メッセージの伝達方法 /芳澤 勝弘 p.12-53
変革者白隠 : 自己表現としての素朴を築いた巨人/矢島 新 p.54-65 |
欧米からみた白隠禅画 /ヤン・クレメンス ベッカー p.66-69
・ |
〇この年、久松真一が「禅文化 (227) p.7-8,表紙」 に「表紙解説 無 白隠慧鶴筆 紙本墨書 四三・六×四二・二cm 久松真一記念館蔵」を発表する。 久松真一記念館の所在地: 〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光228ー2 058-231-5317
〇この年、浅井京子が「聚美 (9) p.54-63」に「白隠八十代の禅画 禅的メッセージへの共感 (特集 素朴絵の魅力 : 素朴表現の多様性と特質)」を発表する。
〇この年、RUGGERI, TAKESHITA Annaが京都外国語大学機関誌編集委員会, 京都外国語短期大学機関誌編集委員会編「研究論叢
= Academic bulletin / Kyoto University of Foreign Studies, Kyoto Junior
College of Foreign Languages (82) p.315-321 京都外国語大学国際言語平和研究所」に「白隠禅師の『遠羅天釜』の伊訳(その1) Traduzione
italiana dell' Oradegama di Hakuin Zenji(1)」を発表する。
|
| 2014 |
26 |
・ |
2月、「正論 (505) p.14-17」に「Shigyo Sosyu Collection 憂国の芸術(第1回)「禅の真髄」白隠と慈雲」が掲載される。
2月、三宅秀和が「茶道の研究 59(2) (通号 699) p.20-24,1」に「青文庫 美の扉(74)「寿」の一字 : 白隠の場合、細川綱利の場合」を発表する。
3月、竹下ルッジェリ・アンナが花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism
(9) p.47-68」に「日本の禅宗における女性観 : 白隠禅師の場合(1)」を発表する。
4月、上村貞嘉が「白隠禅師の足跡」を「淡交社」から刊行する。
6月、三宅秀和が「茶道の研究 59(6) (通号 703) p.22-26,1」に「永青文庫 美の扉(78)白隠慧鶴筆 布袋携童図について」を発表する。
6月、西村惠信が「※坐る : 白隠禅師坐禅和讃を読む」を「禅文化研究所」から刊行する。
|
はじめにー「坐る」ということについて
白隠という人について
「坐禅和讃」成立への道
凡夫がそのまま仏である
仏を求める間違い |
愚痴こそ迷いの根源
坐禅こそ仏道修行の根本
一回の坐禅で無量の罪も滅びる
坐禅のことを知るだけでも
自分の本性を見とどける |
真実の世界が眼前すれば
悟りの風光
ここが浄土、私が仏であった
現代人と坐禅
・ |
※「茶道雑誌」(河原書店刊) の連載 (2011年2月から14回連載) に訂正加筆したもの
6月、日本石仏協会編集「日本の石仏 No.150(2014夏) 特集 石に刻まれた「僧・聖・行者」 p35」に「白隠石」のことが紹介される。
|
内容(長野県関係):p5 一心行者/p8 願王全堤/p15 修那羅大天武/p17 聖宝/p20 泰賢行者/p24 等順/p28 播隆/p35 白隠石
|
6月、実存思想協会編「実存思想論集 29 道・身心・修行」が「理想社」から刊行される。
|
日本の武道の思想 : 『五輪書』と『弓と禅』について / 魚住孝至 [著]
世阿弥『伝書』における稽古の思想 : 稽古における序破急/西平直 [著]
道は無窮なり : 道元の身学道 / 井上克人 [著]
仏教における修行 : インド・チベットの伝統から / 吉村均 [著]
フッサールとフィンクにおける脱現在化について / 池田裕輔 [著]
レヴィナスとヴァール : 「下降的超越」の概念をめぐって/木元麻里 [著]
白隠の戒律観 / 小濵聖子 [著] |
酒井潔著『ライプニッツのモナド論とその射程』 / 山内志朗 [著]
井潔/佐々木能章/長綱啓典編『ライプニッツ読本』/橋本由美子[著]
齋藤元紀著『存在の解釈学『存在と時間』の構造・転回・反復』/村井則夫[著]
澤田哲生著『メルロ=ポンティと病理の現象学』 / 本郷均 [著]
森一郎著『死を超えるもの3・11以後の哲学の可能性』 / 田端健人 [著]
田端健人著『学校を災害が襲うとき教師たちの3・11』 / 山本英輔
・ |
8月、瓜生中が「大法輪 81(8) p.214-217」に「雑学から学ぶ仏教(第51回)白隠禅師に学ぶ」を発表する。
9月、高橋敏が「 白隠 : 江戸の社会変革者」を「岩波書店」から刊行する。
(岩波現代全書 ; 042)
9月、衣斐弘行が「大法輪82(9)」に「仏教の眼 伊勢型紙と白隠」を発表する。
○、この年、「禅文化 (234) 特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(前) 」が「禅文化研究所」から刊行される。
|
禅 : いまを生きる (特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(前)) 堀尾 行覚
p.10-13
つれづれに思う (特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(前)) 有馬 賴底 p.16-19
誌上提唱 『臨済録』上堂 ヤケクソの世界 (特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(前)) 山川宗玄
p.20-30
臨済禅師・白隠禅師遠諱記念講演会 父母未生以前の面目 (特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(前)) 姜尚中
p.31-42 |
○、この年、尾西正成が書学書道史学会編集局編「書学書道史研究 = Calligraphic studies (24) p.59-73」に「白隠慧鶴「面壁達磨」と文字絵の周辺」を発表する。 J-STAGE
○、この年、小濵聖子が「比較思想研究 (41) p.106-114」に「禅浄双修の是非に関する比較思想的考察 : 白隠の雲棲〔シュ〕宏批判をとおして」を発表する。 |
| 2015 |
27 |
・ |
3月、竹下 ルッジェリ・アンナが花園大学国際禅学研究所編「花園大学国際禅学研究所論叢
= Annual report of the International Research Institute for Zen Buddhism
(10) p.53-70」に「日本の禅宗における女性観 : 白隠禅師の場合(2)」を発表する。
4月、松下宗柏が「大法輪 82(4) p.72-75」に「白隠禅師に学ぶ : 『夜船閑話(やせんかんな)』『遠羅天釜(おらてがま)』の健康法 (特集 不安… 怒り… ウツ病… 不安をなくす 心と身体の調節法 ; 生活に活かす仏教の調節法) 」を発表する。
6月、西村惠信が「白隠入門 : 地獄を悟る」を「法藏館」から刊行する。
|
画ではなく、「ことば」から新しい白隠を知る! 「日本臨済禅中興の祖」と称えられる傑僧・白隠。その生涯と思想を、遺された法語から解き明かし、独自の白隠像を平易に描いた画期的な入門書。
|
9月、花園大学歴史博物館編「平林寺 : 武蔵野の禅刹 : 伝来の書画名宝展 :
中興開山鉄山宗鈍禅師四〇〇年遠諱記念」が刊行される。
9月24日~12月12日、花園大学歴史博物館に於いて「武蔵野の禅刹平林寺:
伝来の書画名宝展 : 中興開山鉄山宗鈍禅師四〇〇年遠諱記念」が開かれる。 主催: 花園大学歴史博物館, 禅文化研究所
10月10日~11月8日迄、飯田市美術博物館に於いて「信州の祈りと美 :
善光寺から白隠、春草まで」展がひらかれる。
10月、飯田市美術博物館編「信州の祈りと美 : 善光寺から白隠、春草まで」が刊行される。
注記 平成二十七年度文化庁重要文化財等公開促進事業
10月、辻惟雄, 泉武夫, 山下裕二, 板倉聖哲編集委員「日本美術全集 11」が「小学館」から刊行される。
|
はじめに 泉武夫 6
信仰と美術-聖なる世界と心の表われ 泉武夫 170
悩める神の願い-神仏習合と日本古代宗教文化 サムエル・C・モース 185
神仏と人の織りなす造形 清水健 193
近世の宗教美術-内なる仏と浮世の神 矢島新 210
霊木と仏像 井上大樹 204
蔵王権現の信仰とイメージ 藤岡穣 207
社寺縁起と素朴絵 泉万里 217
図版解説 220
序文英訳・英文作品リスト 301
図版もくじ
第一章 信仰の芽生え
第一章 1 しゃがんで手を合わせる土偶(どぐう)
第一章 2 土偶(どぐう) 山形県立博物館
第一章 3 土偶(どぐう) 茅野市尖石縄文考古館(ちのしとがりいしじようもんこうこかん)
第一章 4 顔(かお)をつけた土器(どき)
第一章 5 珍敷塚古墳壁画(めずらしづかこふんへきが)
第一章 6 須弥山石(しゆみせんせき)
第二章 仏の像と世界観
第二章 7 菩薩立像(ぼさつりゆうぞう)
第二章 8 玉虫厨子(たまむしのずし)
第二章 9 菩薩半跏像(ぼさつはんかぞう)
第二章 10 六観音立像(ろくかんのんりゆうぞう) 法隆寺(ほうりゆうじ)
第二章 11 薬師如来(やくしによらい)及び両脇侍像(りようきようじぞう) 薬師寺(やくしじ)
第二章 12 大仏蓮弁(だいぶつれんべん) 須弥山図(しゆみせんず)
第二章 13 十一面観音菩薩立像(じゆういちめんかんのんぽさつりゆうぞう) 聖林寺(しようりんじ)
第二章 14 薬師如来立像(やくしによらいりゆうぞう) 多田寺(ただじ)
第二章 15 菩薩形立像(ぼさつぎようりゆうぞう) 常念寺(じようねんじ)
第二章 16 菩薩形立像(ぼさつぎようりゆうぞう) 正花寺(しようけじ)
第二章 17 菩薩坐像(ぼさつざぞう) 養花院(ようかいん)
第二章 18 線刻磨崖仏像(せんこくまがいぶつぞう)
第二章 19 仏足石(ぶつそくせき)
第二章 20 男神立像(だんしんりゆうぞう)
第二章 21 僧形男神坐像(そうぎようだんしんざぞう)
第二章 22 男神坐像(だんしんざぞう) 松尾大社(まつのおたいしや)
第二章 23 地蔵菩薩立像(じぞうぼさつりゆうぞう) 法隆寺(ほうりゆうじ)
第二章 24 東寺講堂諸尊像(とうじこうどうしよそんぞう)
第二章 25 両界曼茶羅図(りようかいまんだらず)(子島曼茶羅)(こじまをんだら)
第三章 山林の霊力と浄士信仰
第三章 26 薬師如来立像(やくしによらいりゆうぞう) 神護寺(じんごじ)
第三章 27 薬師如来(やくしによらい)及び両脇侍像(りようきようじぞう) 勝尾寺(かつおじ)
第三章 28 阿弥陀如来坐像(あみだによらいざぞう) 仁和寺(にんなじ)
第三章 29 阿弥陀如来(あみだによらい)及び両脇侍像
→(りようきようじぞう) 清涼寺(せいりようじ)
第三章 30 十一面観音菩薩立像(じゆういちめんかんのんぼさつりゆうぞう)
→霊山寺(りようせんじ)
第三章 31 如意輸観音菩薩半跏像(によいりんかんのんぼさつはんかぞう)
第三章 32 宝誌和尚立像(ほうしおしようりゆうぞう)
第三章 33 如意輪観音菩薩像(によいりんかんのんぼさつぞう)
第三章 34 春日補陀落山曼茶羅図(かすがふだらくせんまんだらず)
第三章 35 九体阿弥陀像(くたいあみだぞう)
第三章 36 阿弥陀如来(あみだによらい)及び両脇侍坐像(りようきようじざぞう)
→保安寺(ほあんじ)
第三章 37 地蔵菩薩(じぞうぼさつ)及び龍樹菩薩坐像(りゆうじゆぼさつざぞう)
第三章 38 菩薩坐像(ぼさつざぞう) 常楽寺(じようらくじ)
第三章 39 阿弥陀如来立像(あみだによらいりゆうぞう) 大通寺(だいつうじ)
第三章 40 阿弥陀聖衆来迎図(あみだしようじゆらいごうず) 安楽寿院(あんらくじゆいん)
第三章 41 阿弥陀聖衆来迎図(あみだしようじゆらいごうず) 長谷寺(はせでら)
第三章 42 長谷寺縁起絵巻(はせでらえんぎえまき)
第三章 43 千手観音菩薩坐像(せんじゆかんのんぼさつざぞう)
第三章 44 男神坐像(だんしんざぞう) 二上射水神社(ふたがみいみずじんじや)
第三章 45 毘沙門天立像(びしやもんてんりゆうぞう)
第三章 46 聖観音菩薩立像(しようかんのんぼさつりゆうぞう)
第三章 47 十一面観音菩薩立像
→(じゆういちめんかんのんぼさつりゆうぞう) 弘明寺(ぐみようじ)
第三章 48 薬師如来(やくしによらい)
→及び両脇侍像(りようきようじぞう) 宝城坊(ほうじようぼう)
第三章 49 千手観音菩薩立像(せんじゆかんのんぼさつりゆうぞう) 恵隆寺(えりゆうじ)
第三章 50 役行者半跏像(えんのぎようじやはんかぞう)・前後鬼坐像(ぜんごきざぞう)
第三章 51 三佛寺奥院(さんぶつじおくのいん)
→(投入堂(なげいれどう)・愛染堂(あいぜんどう))
第三章 52 蔵王権現立像(ざおうごんげんりゆうぞう) 三佛寺(さんぶつじ)
第三章 53 蔵王権現立像(ざおうごんげんりゆうぞう) 大峯山寺(おおみれさんじ)
第三章 54 虚空蔵菩薩坐像(こくうぞうぼさつざぞう)
第三章 55 虚空蔵菩薩懸仏(こくうぞうぼさつかけぼとけ)
第三章 56 帝釈天立像(たいしやくてんりゆうぞう)
第三章 57 摩多羅神坐像(またらしんざぞう) 覚清(かくせい)
第三章 58 金銅装笈(こんどうそうおい) 慈光明院(じこうみよういん)
第三章 59 金銅装笈(こんどうそうおい) 松尾寺(まつおでら)
第四章 都の雅びと諸方の仏神
第四章 60 紺紙銀字法華経(こんしぎんじほけきよう) 巻五
第四章 61 法華経方便品(ほけきようほうべんぼん)(竹生島経)(ちくぶしまきよう)
第四章 62 普賢菩薩騎象像(ふげんぼさつきぞうぞう)
第四章 63 普賢菩薩像(ふげんぼさつぞう)
第四章 64~65 平家納経(へいけのうきよう)
第四章 66 大威徳明王像(だいいとくみようおうぞう)
第四章 67 愛染明王像(あいぜんみようおうぞう)
第四章 68 不動明王坐像(ふどうみようおらざぞう)
第四章 69 弥勒菩薩坐像(みろくぼさつざぞう)
第四章 70 毘沙門天坐像(びしやもんてんざぞう)
第四章 71 両部大壇具(りようぶだいだんぐ)
第四章 72 牛頭天王立像(ごずてんのうりゆうぞう)
第四章 73 大将軍神像(だいしようぐんしんぞう)
第四章 74 天神坐像(てんじんざぞう)
第四章 75~76 松崎天神縁起絵巻(まつざきてんじんえんぎえまき)
第四章 77 僧形八幡神像(そうぎようはちまんしんぞう)
第四章 78 藤原道長経筒(ふじわらのみちながきようづつ)
第四章 79 金銀鍍双鳥宝相華文経箱(きんぎんとそうちようほうそうげもんきようばこ)
第四章 80 金銅経箱鷺脚台付(こんどうきようばこさぎあしだいつき)
第四章 81 弥勒菩薩像(みろくぼさつぞう)
第四章 82 兜率天曼茶羅図(とそつてんまんだらず)
第四章 83 千体愛染王画巻(せんたいあいぜんおうがかん)
第四章 84 春日千体地蔵像図(かすがせんたいじぞうぞうず)
第四章 85 千手観音菩薩立像(せんじゆかんのんぼさつりゆうぞう)
→(三十三間堂諸尊)(さんじゆうさんげんどうしよそん)
第四章 86 厨子入千躰地蔵菩薩像(ずしいりせんたいじぞうぼさつぞう)
第四章 87 天部形立像(てんぶぎようりゆうぞう)
|
第四章 88 八幡二神像(はちまんにしんぞう)
第四章 89 伝池田八幡本地仏坐像(でんいけだはちまんほんじぶつざぞう)
第四章 90 十一面女神坐像(じゆういちめんじよしんざぞう)
第四章 91 女神坐像(じよしんざぞう)及び小女神坐像(しようじよしんざぞう)
第四章 92 太郎天(たろうてん)及び二童子立像(にどうじりゆうぞう)
第四章 93 熊野本地仏像(くまのほんじぶつぞう)
第五章 神と仏のあやなす世界
第五章 94 興福寺曼茶羅図(こうふくじまんだらず)
第五章 95 春日宮曼茶羅図(かすがみやまんだらず)
第五章 96 春日宮曼茶羅図(かすがみやまんだらず) 観舜(かんしゆん)
第五章 97 春日神鹿御正体(かすがしんろくみしようたい)
第五章 98 日吉山王曼茶羅図(ひえさんのうまんだらず)
第五章 99 石清水八幡曼茶羅図(いわしみずはちまんまんだらず)
→(男山八幡宮曼茶羅)(おとこやまはちまんみやまんだら)
第五章 100 熊野本地仏曼茶羅図(くまのほんじぶつまんだらず)
第五章 101 那智瀧図(なちのたきず)
第五章 102 吉野曼茶羅図(よしのまんだらず)
第五章 103 熊野十二社権現御正体(くまのじゆうにしやごんげんみしようたい)
第五章 104 熊野速玉大社古神宝類(くまのはやたまたいしやこしんぽうるい)のうち
→桐蒔絵手箱(きりまきえてばこ)
第五章 105 釈迦如来立像(しやかによらいりゆうぞう) 善慶(ぜんけい)
第五章 106 水晶製五輪塔形舎利容器(すいしようせいごりんとうがたしやりようき)
第五章 107 興正菩薩坐像(こうしようぼさつざぞう) 善春(ぜんしゆん)
第五章 108 舎利安置状(しやりあんちじよう)
第五章 109 金銅八角五輪塔形舎利容器(こんどうはっかくごりんとうがたしやりようき)
第五章 110 輪宝羯磨蒔絵舎利厨子(りんぼうかつままきえしやりずし)
第五章 111 宝珠台(ほうじゆだい)
第五章 112 春日龍珠箱(かすがりゆうじゆばこ)
第五章 113 不空羅索観音菩薩坐像(ふくうけんさくかんのんぼさつざぞう) 康慶(こうけい)
第五章 114 地蔵菩薩立像(じぞうぼさつりゆうぞう) 金剛證寺(こんごうしようじ)
第五章 115 不動明王立像(ふどうみようおうりゆうぞう)
第五章 116 頬焼阿弥陀縁起絵巻(ほおやけあみだえんぎえまき)
第五章 117 因幡堂縁起絵巻(いなばどうえんぎえまき)
第五章 118 一字一仏法華経(いちじいちぶつほけきよう) 序品(じよほん)
第五章 119 阿字義(あじぎ)
第五章 120 紺紙金字法華経宝塔曼茶羅(こんしきんじほけきようほうとうまんだら) 巻六
第五章 121 白描絵料紙理趣経(はくびようえりようしりしゆきよう)(目無経)(めなしきよう)
第五章 122 春日名号曼茶羅(かすがみようごうまんだら)
第五章 123 日像曼茶羅本尊(にちぞうまんだらほんぞん)
第五章 124 二河白道図(にがびやくどうず)
第五章 125 當麻曼茶羅図(たいままんだらず)
第五章 126 終南山星曼茶羅図(しゆうなんざんほしまんだらず)
第六章 夢想と参詣
第六章 127 春日明神影向図(かすがみようじんようごうず)
第六章 128 阿弥陀六地蔵十羅刹女像(あみだろくじぞうじゆうらせつによぞう)
第六章 129~130 春日権現験記絵巻
→(かすがごんげんけんきえまき) 高階隆兼(たかしなたかかね)
第六章 131~132 石山寺縁起絵巻(いしやまでらえんぎえまき)
第六章 133 法然上人像(ほうねんしようにんぞう)(鏡御影)(かがみのみえい)
第六章 134 善信聖人絵(ぜんしんしようにんえ)(琳阿本)(りんあぽん) 覚如詞書(かくによ)
第六章 135 光明本尊(こうみようほんぞん)
第六章 136 聖徳太子絵伝(しようとくたいしえでん)
第六章 137 親鸞聖人絵伝(しんらんしようにんえでん)(万福寺本)(まんぷくじぼん)
第六章 138 一流相承系図(いちりゆうそうじようけいず)
第六章 139 束帯天神像(そくたいてんじんぞう)
第六章 140 維摩像(ゆいまぞう)
第六章 141 藤原鎌足像(ふじわらのかまたりぞう)
第六章 142 豊臣秀由像(とよとみひでよしぞう)
第六章 143 三十三所観音像(さんじゆうさんしよかんのんぞう)
第六章 144 富士曼茶羅図(ふじまんだらず) 狩野元信印(かのうもとのぶ)
第六章 145 成相寺参詣曼茶羅図(なりあいじさんけいまんだらず)
第六章 146 那智参詣曼茶羅図(なちさんけいまんだらず)
第六章 147 笠置寺縁起絵巻(かさぎでらえんぎえまき)
第六章 148~149 かるかや
第六章 150~151 つきしま
第七章 信仰の民衆化
第七章 152 十一面観音菩薩(じゆういちめんかんのんぼさつ)及び善女龍王立像
→(ぜんによりゆうおうりゆうぞう)・善財童子立像(ぜんざいどうじりゆうぞう)・円空(えんくう)
第七章 153 不動明王(ふどうみようおう)及び二童子立像(にどうじりゆうぞう) 円空(えんくう)
第七章 154 荒神像(こうじんぞう) 円空(えんくう)
第七章 155 護法神像(ごほうしんぞら) 円空(えんくう)
第七章 156 金剛力士(こんごうりきし)(仁王)(におう)
→立像(りゆうぞう) 吽形(うんぎよう) 円空(えんくう)
第七章 157 子安観音菩薩坐像(こやすかんのんぼさつざぞう)
→(立木仏)(たちきぶつ) 木喰(もくじき)
第七章 158 十六羅漢像(じゆうろくらかんぞう) 木喰(もくじき)
第七章 159 五智如来坐像(ごちによらいざぞう) 木喰(もくじき)
第七章 160 六観音立像(ろくかんのんりゆうぞう) 宝積寺(ほうしやくじ)
第七章 161 出山釈迦図(しゆつさんしやかず) 白隠(はくいん)
第七章 162 蛤蜊観音図(こうりかんのんず) 白隠(はくいん)
第七章 163 隻履達磨図(せきりだるまず) 白隠(はくいん)
第七章 164 虚堂智愚像(きどうちぐぞう) 白隠(はくいん)
第七章 165 暫時不在如同死人(ざんじふざいによどうしにん) 白隠(はくいん)
第七章 166 布袋(ほてい)すたすた坊主(ぼうず) 白隠(はくいん)
第七章 167 馬祖(ばそ)・臨済画賛(りんざいがさん) 仙厓(せんがい)
第七章 168 坐禅蛙画賛(ざぜんがえるがさん) 仙厓(せんがい)
第七章 169 鳥鷺争局(ううそうきよく)(囲碁)(いご)画賛(がさん) 仙厓(せんがい)
第七章 170 頭骨図画賛(ずこつずがさん) 仙厓(せんがい)
第七章 171 羅漢寺石仏(らかんじせきぶつ) 円龕昭覚
→(えんがんしようがく)・逆流建順(ぎやくりゆうけんじゆん)
第七章 172 五百羅漢坐像(ごひやくらかんざぞう) 松雲元慶(しよううんげんけい)
第七章 173 五百羅漢図(ごひやくらかんず) 加藤信清(かとうのぶきよ)
第七章 174 五百羅漢石仏群(ごひやくらかんせきぶつぐん) 伊藤若沖(いとうじやくちゆう)
第七章 175 五百羅漢図(ごひやくらかんず) 狩野一信(かのうかずのぶ)
第七章 176 版画(はんが) 帝釈天像(たいしやくてんぞう)
第七章 177 版画(はんが) 文殊菩薩像(もんじゆぼさつぞう)
第七章 178 大津絵(おおつえ) 青面金剛(しようめんこんごう)
第七章 179 大津絵(おおつえ) 阿弥陀三尊来迎図(あみださんぞんらいごうず)
第七章 180 鹿島神(かしましん)の鯰絵(なまずえ)
第七章 181 福助(ふくすけ)の有卦絵(うけえ) 歌川芳藤(うたがわよしふじ)
第七章 182 熊野観心十界曼茶羅図(くまのかんじんじつかいまんだらず)
第七章 183 十王図(じゆうおうず)
第七章 184 六道絵(ろくどうえ)
第七章 185 八岐大蛇退治図絵馬(やまたのおろちたいじずえま) 堤等栄(つつみとうえい)
第七章 186 天岩戸図絵馬(あまのいわとずえま) 堤等川(つつみとうせん)
第七章 187 天地二大字(てんちにだいじ) 良寛(りようかん)
・ |
11月、岡部守成が「丹法入門 : 白隠「内観法」の真実」を「論創社」から刊行する。
○、この年、「禅文化 (通号 235)特集 臨済禅師・白隠禅師遠諱に向けて(後)」が「禅文化研究所」から刊行される。
|
誌上提唱 『臨済録』上堂 葛藤からの解放 小倉宗俊 p.12-20
臨済禅師肖像雑考 福島恒徳 p.21-30
禅ってなに? 横田南嶺,姜尚中,佐々木 閑 p.31-44 |
白隠禅師『荊叢毒蘂』の初版本と、その書き入れについて芳澤勝弘 p.45-53
ヨーロッパにおける白隠禅の萌芽 寶積玄承 p.54-60
特別展覧会「禅 : 心をかたちに」羽田聡 p.61-67 |
○、この年、 「禅文化 (238) 特集 武蔵野の禅刹平林寺」が「禅文化研究所」から刊行される。
|
由緒と建築 平林寺縁起 : 堂宇で綴る歴史 p.10-19 松竹寛山
平林寺世代表 p.20-22
平林寺と人物 平林寺中興 鉄山宗鈍と徳川家康 p.24-34 田中潤
平林寺と人物 松平信綱と平林寺 p.35-46 根岸茂夫
自然環境 平林寺境内林の自然 p.47-55 荒尾精二 |
平林寺伝来の書画名宝 p.73-80
平林寺の寺宝 グラビア作品解説 p.81-88
臨済禅師一一五〇年・白隠禅師二五〇年遠諱
→記念企画講演から 時流と禅 : 唐と宋の禅比較 p.89-101 安永祖堂
・ |
|
| 2016 |
28 |
・ |
1月、境野勝悟が「白隠禅の言葉 : 生きる喜びが湧いてくる教え」を「海竜社」から刊行する。
3月、芳澤勝弘が「白隠禅画の教え : 日めくり」を「東京美術」から刊行する。
3月、芳澤勝弘が「白隠 : 禅画の世界」を「KADOKAWA 」から刊行する。 中央公論新社 2005年刊の加筆修正 (角川ソフィア文庫 )
3月、芳澤勝弘編著「新編白隱禅師年譜」が「禅文化研究所」から刊行される。
3月、竹下, ルッジェリ・アンナが「花園大学国際禅学研究所論叢 = Annual report of the international research institute for zen buddhism 12 p.1-25 花園大学国際禅学研究所」に「日本の禅宗における女性観 : 白隠禅師の場合(3)」を発表する。 (IRDB)
4月16日~6月26日、東北歴史博物館, 瑞巌寺宝物館に於いて「大白隠展
: 現代によみがえれ、下化衆生の精神 : 東日本大震災復興祈念 : 臨済禅師一一五〇年遠諱記念
: 白隠禅師二五〇年遠諱記念 : 瑞巌寺国宝本堂修繕完成記念/主催: 大白隠展実行委員会」展が開かれる。
4月、大白隠展実行委員会編集/芳澤勝弘監修「大白隠展 : 現代によみがえれ、下化衆生の精神
: 東日本大震災復興祈念 : 臨済禅師一一五〇年遠諱記念 : 白隠禅師二五〇年遠諱記念
: 瑞巌寺国宝本堂修繕完成記念」が「大白隠展実行委員会」から刊行される。
4月12日~5月22日、京都国立博物館に於いて「禅 : 心をかたちに : 臨済禅師一一五〇年白隠禅師二五〇年遠諱記念」展が開催される。
4月、京都国立博物館, 東京国立博物館, 日本経済新聞社文化事業部編集「禅
: 心をかたちに : 臨済禅師一一五〇年白隠禅師二五〇年遠諱記念」が「日本経済新聞社」から刊行される。
4月12日~5月22日、大阪市立美術館に於いて「王羲之から空海へ : 日中の名筆漢字とかなの競演
: 大阪市立美術館開館八十周年記念公益社団法人日本書芸院創立七十周年記念
: 特別展」が開かれる。
4月、読売新聞社編「王羲之から空海へ : 日中の名筆漢字とかなの競演 : 大阪市立美術館開館八十周年記念公益社団法人日本書芸院創立七十周年記念
: 特別展」が「読売新聞社」から刊行される。
|
ごあいさつ 3
王義之書法の近代日本における受容
→西嶋慎一(日本書芸院学術顧問、書道文化研究家) 8
漢字の晴と褻・仮名文字の特性
→名児耶明(財団法人五島美術館副館長・学芸部長) 10
特別展「王義之から空海へ」に寄せて
→富田淳(東京国立博物館学芸企画部企画課長) 12
台北から来日の名跡について
→弓野隆之(大阪市立美術館学芸課長代理) 14
凡例 16
中国書蹟
1 張芝 八月帖(「玉煙堂帖」)東京台東区立書道博物館 18
2 鍾□(しょう よう) 薦季直表(「真賞斎帖」
□火後本)東京台東区立書道博物館 19
3 鍾□(しょう よう) 宣示表(「宋拓晋唐小楷」)
→奈良寧楽美術館 20
4 (○) 李柏尺牘稿 京都龍谷大学図書館 22
5 王義之 孔侍中帖 東京前田育徳会 24
6 王義之 十七帖(上野本)京都国立博物館 26
7 王義之 十七帖(王穉登本)東京台東区立書道博物館 28
8 王義之 楽毅論(「小楷四種合冊」)
→東京三井記念美術館 38
9 王義之 蘭亭序(呉柄本)東京国立博物館 30
10 王義之 蘭亭序(開皇本)東京三井記念美術館 32
11 王義之 蘭亭序(韓珠船本)東京台東区立書道博物館 34
12 王義之 蘭亭序(呉平斎本)東京三井記念美術館 36
13 王義之 蘭亭序(潁井本)東京三井記念美術館 37
14 王義之 黄庭経 東京五島美術館 39
15 王義之 集王聖教序(上野本)京都国立博物館 40
16 王義之 集王聖教序(松烟拓本)東京三井記念美術館 41
17 王義之 集王聖教序(黒川本)兵庫黒川古文化研究所 42
18 王義之 集王聖教序 整本
→埼玉淑徳大学書学文化センター 44
19 王献之 地黄湯帖 東京台東区立書道博物館 46
20 (○) 大智度論巻第八 京都国立博物館 48
21 仏説歓普賢経 東京台東区立書道博物館 49
22 (○) 摩訶般若波羅蜜経巻第十四
→東京台東区立書道博物館 50
23 大般涅槃経巻第十一 東京三井記念美術館 51
24 妙法蓮華経巻第三 京都国立博物館 52
25 妙法蓮華経巻第七 東京三井記念美術館 53
26 智永 真草千字文 54
27 智永 真草千字文(関中本) 東京国立博物館 55
28 虞世南 孔子廟堂碑(臨川李氏本)
→東京三井記念美術館 56
29 (○)欧陽詢 化度寺碑 京都大谷大学博物館 58
30 欧陽詢 九成宮?泉銘(海内第一本)
→東京三井記念美術館 60
31 □遂良(ちょ すいりょう) 世説新書巻第六抄本
→文化庁 66
→孟法師碑(臨川李氏本 )東京三井記念美術館 62
32 □遂良 文皇哀冊 東京国立博物館 64
33 世説新書巻第六抄本 文化庁 66
34 賀知章 草書孝経 宮内庁三の丸尚蔵館 65
35 顔真卿 争坐位文稿 東京台東区立書道博物館 68
36 蔡襄 致杜君長官尺牘(離都帖)台北國立故宮博物院 70
37 蘇軾 次弁才韻詩 台北國立故宮博物院 72
38 (○)蘇軾 李白仙詩 大阪市立美術館 74
39 黄庭堅 王史二氏墓誌銘稿 東京国立博物館 76
40 黄庭堅 致天民知命大主簿尺牘
→台北國立故宮博物院 78
41 米□(べいふつ) 紫金研帖 台北國立故宮博物院 80
42 (○)米□(べいふつ) 草書四帖 大阪市立美術館 82
43 米□(べいふつ) 虹県詩 東京国立博物館 84
44 米□(べいふつ) 群玉堂米帖(上)東京五島美術館 88
45 米□(べいふつ) 群玉堂米帖(下)東京国立博物館 86
46 呉□ 急足帖 東京国立博物館 89
47 圜悟克勤 与虎丘紹隆印可状 東京国立博物館 90
48 虚堂智愚 与照禅者偈頒 東京国立博物館 92
49 張即之 金剛般若波羅蜜経 京都智積院 94
50 趙孟□ 蘭亭十三跋 東京国立博物館 96
51 趙孟□ 仇鍔墓碑銘 京都陽明文庫 98
52 趙孟□ 与中峰明本尺牘 東京静嘉堂文庫美術館 100
53 趙孟□ 致中峰和尚尺牘 台北國立故宮博物院 102
54 (○)一菴 中峰明本像自賛 兵庫高源寺 106
55 中峰明本像 自賛 107
56 鮮于枢 七言絶句二首 台北 國立故宮博物院 109
57 元人雑書 台北國立故宮博物院
57 57-1 康里□□ 致彦中 110
57 57-2 楊載 水竜吟牘 110
57 57-3 周馳 致義斎廉訪尺牘 111
57 57-4 衰桷 呈承旨大参相公尺牘 111
57 57-5 虞集 尺牘 112
57 57-6 饒介 中峰幻住像偈 112
58 楊維禎 銭譜跋語 台北國立故宮博物院 114
59 沈度 楷書蘇載墨君堂記 三重澄懐堂美術館 116
60 沈粲 書古詩 台北國立故宮博物院 117
61 沈周 化鬚疏 台北國立故宮博物院 118
62 祝允明 臨黄庭経 三重澄懐堂美術館 120
63 祝允明 臨王義之帖 台北國立故宮博物院 122
64 祝允明 草書七言律詩 台北國立故宮博物院 124
65 文徴明 草書千字文 台北國立故宮博物院 126
66 文徴明 楷書史記刺客列伝 三重澄懐堂美術館 128
67 文徴明 自書七言律詩 台北國立故宮博物院 130
68 文徴明 行書前後赤壁賦 台北國立故宮博物院 132
69 陳淳 草書杜甫秋興詩 台北國立故宮博物院 134
70 王寵 辛巳書事七首 台北國立故宮博物院 136 |
71 王寵 草書千字文 台北國立故宮博物院 137
72 徐渭 赤壁賦 138
73 董其昌 尺牘稿 140
74 董其昌 臨十七帖 台北國立故宮博物院 142
75 董其昌 行書崑山道中書 三重澄懐堂美術館 144
76 董其昌 行書七言絶句 京都萬福寺 145
77 張瑞図 草書五言律詩 台北何創時書法藝術基金會 146
78 張瑞図 行書七言絶句 徳島県立文学書道館 147
79 黄道周 行書五言律詩 台北何創時書法藝術基金會 148
80 黄道周 草書答孫伯観詩 三重澄懐堂美術館 149
81 倪元□ 行書左思蜀都賦 兵庫黒川古文化研究所 150
82 倪元□ 行書七言絶句 台北何創時書法藝術基金會 151
83 王鐸 行書贈単大年家丈 台北何創時書法藝術基金會 152
84 王鐸 臨淳化閣帖 台北何創時書法藝術基金會 153
85 王鐸 臨淳化閣帖 大阪市立美術館 154
86 王鐸 臨王渙之二●帖 徳島県立文学書道館 156
87 傅山 行草書李商隠詩 台北何創時書法藝術基金會 157
88 傅山 薔盧妙翰 台北何創時書法藝術基金會 158
89 傅山 太原段帖 台北何創時書法藝術基金會 160
90 許友 自詠詩 広島ふくやま書道美術館 162
91 許友 草書七言絶句 台北何創時書法藝術基金會 164
日本書蹟
92 金剛場陀羅尼経 文化庁 166
93 金光明最勝王経巻第三・巻第四 奈良国立博物館 168
94 賢愚経残巻 兵庫白鶴美術館 170
95 隅寺心経 京都国立博物館 172
96 竹生島経(法華経序品)滋賀宝厳寺 173
97 (○)色紙法華経巻第八 兵庫白鶴美術館 174
98 ○中尊寺経(正法華経) 大阪大念仏寺 175
99 扇面法華経冊子巻第一・巻第七 大阪四天王寺 176
100 法華経巻第一 大阪市立美術館 175
101 神護寺経(大智度論) 京都神護寺 175
102 (○)太山寺経(無量義経) 兵庫太山寺 177
103 空海 聾瞽指帰 和歌山金剛峯寺 178
104 空海 風信帖 京都東寺(教王護国寺) 182
105 空海 灌頂歴名 京都神護寺 184
106 空海 金剛般若経開題残巻 奈良国立博物館 186
107 空海 金剛般若経開題残巻 京都国立博物館 187
108 (○)空海 崔子玉座右銘 和歌山宝亀院 188
109 (○)空海 崔子玉座右銘 東京大師会 188
110 最澄 久隔帖 奈良国立博物館 190
111 嵯峨天皇 光定戒牒 滋賀延暦寺 192
参考図版1 伝橘逸勢 伊都内親王願文 御物 193
112 小野道風 三体白氏詩巻 大阪正木美術館 194
113 藤原佐理 詩懐紙 香川県立ミュージアム 196
114 藤原佐理 国申文帖(女車帖) 東京春敬記念書道文庫 196
115 ○藤原佐理 頭弁帖 広島ふくやま書道美術館 197
116 藤原行成 白氏詩巻(後嵯峨院本) 大阪正木美術館 198
117 藤原行成 本能寺切 京都本能寺 200
118 藤原行成 屏風詩歌切 201
参考図版2 韓藍花歌切 正倉院 202
参考図版3 正倉院万葉仮名文書 正倉院 202
参考図版4 正倉院万葉仮名文書 正倉院 202
参考図版5 藤原定家 臨紀貫之「土佐日記」
→東京前田育徳会 203
119 稿本北山抄紙背仮名消息 京都国立博物館 203
120 伝紀貫之 自家集切(貫之集) 東京国立博物館 204
121 伝小野道風 秋萩帖 東京国立博物館 205
122 手鑑 野辺のみどり 東京前田育徳会 206
123 手鑑 かりがね帖 文化庁 205・208
124 手鑑 谷水帖 大阪逸翁美術館 210
125 ○伝紀貫之 高野切第一種(古今集巻第一)
→ 埼玉遠山記念館 212
126 (○)伝紀貫之 高野切第一種(古今集巻第一)
→福岡石橋美術館 214
127 伝紀貫之 高野切第一種(古今集巻第二十)
→高知県立高知城歴史博物館 215
128 (○)伝藤原行成 大字和漢朗詠集切 京都北村美術館 216
129 ○伝藤原行成 大字和漢朗詠集切 東京国立博物館 218
130 伝藤原忠家 和歌体十種 東京国立博物館 219
131 伝藤原行成 歌仙歌合 大阪和泉市久保惣記念美術館 220
132 源兼行 高野切第二種(古今集巻第二) 222
133 ○源兼行 高野切第二種(古今集巻第二)
→京都陽明文庫 224
134 源兼行 高野切第二種(古今集巻第三)
→東京三井記念美術館 225
135 源兼行 高野切第二種(古今集巻第八)
→山口毛利博物館 225
参考図版6 源兼行 平等院鳳鳳堂色紙形(上品下生)
→京都平等院 226
136 源兼行 栂尾切(桂本万葉集断簡) 京都野村美術館 227
137 源兼行 栂尾切(桂本万葉集断簡) 奈良大和文華館 228
138 源兼行 雲紙本和漢朗詠集 宮内庁三の丸尚蔵館 229
139 源兼行 関戸本和漢朗詠集切 東京五島美術館 230
140 源兼行 関戸本和漢朗詠集切 東京国立博物館 232
141 伝紀貫之 高野切第三種(古今集巻第十八)
→東京静嘉堂文庫美術館 234
142 伝紀貫之 高野切第三種(古今集巻第十八)
→兵庫香雪美術館 234
143 (○)伝藤原行成 蓬来切(拾遺抄)東京五島美術鋤 235
144 伝藤原行成 蓬来切(拾遺抄) 236
145 伝藤原行成 蓬来切(拾遺抄) 237
146 伝藤原行成 近衛本和漢朗詠集 京都陽明文庫 238
147 ○伝藤原行成 伊予切(和漢朗詠集) 埼玉遠山記念館 240
148 伝藤原行成 伊予切(和漢朗詠集) 240
149 伝藤原行成 伊予切(和漢朗詠集) 京都北村美術館 240
150 伝藤原行成 法輪寺切(和漢朗詠集) 東京国立博物館 241 |
151 伝宗尊親王 有栖川切(元暦校本万葉集断簡) 241
152 伝紀貫之 寸松庵色紙(古今集) 242
153 (○)伝紀貫之 寸松庵色紙(古今集) 京都野村美術館 242
154 伝紀貫之 寸松庵色紙(古今集)
→東京静嘉堂文庫美術館 243
155 伝紀貫之 寸松庵色紙(古今集) 京都泉屋博古館 243
156 伝藤原行成 升色紙(深養父集) 東京三井記念美術館 244
157 (○)伝小野道風 継色紙(古今集) 東京国立博物館 245
158 伝小野道風 継色紙(古今集) 東京三井記念美術館 246
159 伝小野道風 継色紙(古今集) 兵庫滴翠美術館 247
160 (○)伝小野道風 継色紙(古今集) 文化庁 246
161 (○)伝小野道風 継色紙(古今集) 大阪逸翁美術館 245
162 伝藤原行成 関戸本古今集切 大阪逸翁美術館 248
163 伝藤原行成 関戸本古今集切 東京国立博物館 249
164 伝藤原行成 曼殊院本古今集 京都曼殊院 250
165 伝小野道風 本阿弥切(古今集) 京都国立博物館 250
166 伝小野道風 本阿弥切(古今集) 東京五島美術館 252
167 ○伝小野道風 本阿弥切(古今集) 京都陽明文庫 253
168 伝藤原行成 針切(重之の子の僧の集)
→大阪市立美術館 254
169 伝藤原行成 重之集 愛知徳川美術館 255
170 伝小野道風 小島切(斎宮女御集) 京都野村美術館 256
171 伝小野道風 小島切(斎宮女御集) 257
172 伝小大君 香紙切(麗花集) 大阪逸翁美術館 258
173 伝小大君 香紙切(麗花集) 258
174 伝小大君 香紙切(麗花集) 東京五島美術館 259
175 伝藤原公任 下絵和漢朗詠集切 268
176 藤原伊房 十五番歌合 東京前田育徳会 260
177 藤原伊房 藍紙本万葉集 京都国立博物館 262
178 藤原定実(推定) 筋切・通切(古今集)
→兵庫滴翠美術館 264
179 藤原定実(推定) 筋切・通切(古今集)
→京都野村美術館 265
180 藤原定実(推定) 筋切(古今集) 東京国立博物館 266
181 藤原定実(推定) 通切(古今集) 267
182 藤原定信 石山切貫之集下 京都北村美術館 270
183 (○)藤原定信 石山切貫之集下
ヤコ大阪和泉市久保惣記念美術館 272
184 藤原定信 岡寺切(本願寺本三十六人家集・順集)
→東京根津美術館 269
185 伝藤原公任 石山切伊勢集 274
186 ○藤原伊行 戊辰切(和漢朗詠集) 京都泉屋博古館 276
187 ○藤原定信 戊辰切(和漢朗詠集) 277
188 藤原教長 今城切(古今集) 東京五島美術館 278
189 藤原俊成 了佐切(古今集) 279
190 藤原俊成 昭和切(古今集) 280
191 ○藤原俊成 日野切(千載集) 京都陽明文庫 281
192 西行 一品経和歌懐紙 京都国立博物館 282
193 伝西行 小色紙(俊忠集切) 東京春敬記念書道文庫 284
194 (○)藤原俊成・伝西行・藤原定家 小色紙三筆
→京都冷泉家時雨亭文庫 285
195 ○藤原定家 熊野懐紙 286
196 藤原定家 熊野懐紙 京都泉屋博古館 287
197 伝藤原顕輔 鶉切(古今集) 埼玉遠山記念館 288
198 蘭渓道隆 風蘭偈 東京五島美術館 289
199 一休宗純 虚堂智愚普説語 東京出光美術館 290
200 慈雲飲光 不能損一毛 大阪新美術館建設準備室 291
201 白隠慧鶴 青面金剛 大阪新美術館建設準備室 292
202 白隠慧鶴 寿字円頓章 293
203 近衛信尹 檜原図屏風いろは屏風 京都禅林寺 294
204 本阿弥光悦 花卉蝶摺下絵新古今集和歌巻
→京都野村美術館 295
205 本阿弥光悦 書状 大阪城天守閣 296
206 松花堂昭乗 三十六歌仙帖 東京国立博物館 297
207 ○近衛家煕 予楽院臨模手鑑 京都陽明文庫 298
208 池大雅 草書芝草詩 京都府立総合資料館
→(京都文化博物館管理) 300
209 良寛 詩書屏風 東京西新井大師 302
210 良寛 自詠和歌 東京西新井大師 304
211 良寛 般若心経 東京西新井大師 305
篆刻
212 左軍丞□ 京都大谷大学博物館 306
213 竿□ 京都大谷大学博物館 306
214 凌江将軍章 京都大谷大学博物館 306
215 漢匈奴悪適尸逐王 京都大谷大学博物館 307
216 関内侯印 京都大谷大学博物館 307
217 □馬都尉 京都大谷大学博物館 307
218 陳豫鍾 沈湖居 308
219 趙之□ 誦先人之清芬 308
220 趙之□ 大小二篆生八分 308
221 徐三庚 芙蓉盒 広島ふくやま書道美術館 309
222 徐三庚 藜光閣 309
223 呉昌碩 蒲作英 310
224 呉昌碩 観自得斎徐氏子静珍蔵印章 310
225 呉昌碩 蒲華 310
226 呉昌碩 万事随縁是安楽法 311
227 呉昌碩 抱員天 311
228 呉昌碩 美意延年 311
229 黄士陵 学而不厭 309
臨帖の系譜―本展列品から見えてくるもの― 中村史朗 313
<赤壁賦>と文徴明・徐渭 中村伸夫 314
敦煌写本にみる楷書表現の完成―
→南北朝から唐へ― 鍋島稲子 315
難波津の市美に咲くや書の精華―
→書の名数から見た本展の意義― 森岡隆 316
作品解説 317
「王義之から空海へ」関係略年表 356 |
4月、内田啓一監修「見て感じるかわいい禅画 : 白隠と仙厓」が「三才ブックス」から刊行される。 (三才ムック ; vol.874)
5月、矢島新が「かわいい禅画 : 白隠と仙厓 = Zen paintings: Kawaii : Hakuin and Sengai」を「東京美術」から刊行する。
5月、「日本書法 12(2) (通号 38) p.4-7」に「記念特別展 大阪市立美術館開館80周年記念 公益社団法人 日本書芸院創立70周年記念
王羲之から空海へ : 日中の名筆 漢字とかなの競演」のことが掲載される。
5月、「大法輪 83(5) 特集 白隠(はくいん) : その人と禅 ; 白隠の教え」が「大法輪閣」から編まれる。
|
法話 白隠と現代 : 私が「白隠さん」に親しむわけ/西村惠信 p.60-65
白隠の生涯/足立宜了 p.66-70
臨済禅師から白隠へ : 臨済宗の流れ/笠 龍桂p.72-77
白隠の書画 /芳澤 勝弘 p.78-82
白隠の公案 : 隻手(せきしゅ)の音声(おんじょう) /松下宗柏 p.83-86
白隠さんはこんな人 : 逸話(いつわ)紹介 /杉田 寬仁 p.87-91
庶民に説いた白隠の教え/山田真隆 p.92-95
『白隠禅師坐禅和讃(ざぜんわさん)』全訳・解説/服部雅昭 p.96-103
|
病を治す『夜船閑話(やせんかんな)』/衣斐弘行 p.104-107
『遠羅天釜(おらてがま)』と動中(どうちゅう)の
→工夫(くふう)/金嶽宗信 p.108-111
『毒語心経(どくごしんぎょう)』を読み解く : 見性の眼を
→確かめるための書/形山睡峰 p.112-115
庶民のための『おたふく女郎粉引歌(じょろうこなひきうた)』/西村惠学 p.116-119
白隠が勧める『延命十句観音経(えんめいじっくかんのんぎょう)』
→全訳・解説/住谷瓜頂 p.120-125 |
7月、 「大徳寺 ; 妙心寺 : 一休、沢庵、盤珪、白隠ら名僧を輩出」が「朝日新聞出版」から刊行される。2007年版の改訂版
(朝日ビジュアルシリーズ, . 仏教新発見 : 週刊日本の名寺をゆく;
28)
注記 特別付録: すべての災難を除く白衣観音立像写仏用紙(1枚)
9月、石川九楊が「石川九楊著作集 3」を「ミネルヴァ書房」から刊行する。
|
日本語の手ざわり 日本語の輪郭 日本語とはどういう言語か 日本語の書法 日本語とはなにか
文字とはなにか 日本文化とはなにか 日本文化論再考 日本語のかたち 声と筆蝕
文字と文明 書くことの終焉 時代をかろやかに追走する「丸文字」 丸文字症候群考
当世文字現象考 新字体現象の意味するもの はやる毛筆恐怖症候群 ヘタウマ現象考
言葉に仕える文字、明朝体 ゴチック体の変奏 書き文字考 『文字の宇宙』と現代タイポグラフィ
文字と印刷 肉筆、毛筆、明朝体 近代知識人の手紙考 良寛の楷書ノオト 〈流れ〉消えた近代歌人の書
年賀状の由来と歴史 近代に、書とは何であったか 白隠型と良寛型の競演 芸術家の書 書は、文字の「美的工夫」だろうか 会津八一の書の魅力と限界 「書は人なり」を超えて
書と〈線性〉 文字と字画 日本文字と中国文字 日本の書と中国の書 仮名の形象
仮名の構成 草書体とはなにか 現代楷書論 現代行書論 現代草書論 反書・裏文字・神秘文字
文字形象の進化論メモ 痩せること、痩せた書 太い線、肥えること 偽字考 文字の視線
みづみづしからみづくさしへ みづぐきのあとのながれ 書-解体する風景 一枚の書の誕生 |
9月、荒了寛 絵と文「雲の上は青空じゃ = The Blue Sky is Above the Clouds」が「里文出版」から刊行される。
シリーズ名:羅漢さんの絵説法 9 白隠禅師 戒語抄 英語抄訳付
10月18日~11月27日、東京国立博物館に於いて「禅 : 心をかたちに : 臨済禅師一一五〇年白隠禅師二五〇年遠諱記念」展が開催される。
10月10日~12月10日、花園大学歴史博物館に於いて「第1期白隠禅師二百五十年遠諱記念:正受老人と信濃の白隠」展が開かれる。
10月、細川晋輔が「わたしの坐禅 : 白隠禅師坐禅和讃」を「青幻舎」から刊行する。 国立国会図書館書誌ID:027692664
10月、中山喜一朗と山下裕二が「別冊太陽 : 日本のこころ (243) p.126-133」に「中山喜一朗×山下裕二 それぞれの偏愛対談 私の仙厓、私の白隠。 (仙厓
: ユーモアあふれる禅のこころ)」を発表する。
○、この年、ダヴァン ディディエが「聚美 (19) p.62-70」に「展覧会案内 臨済禅師一一五〇年・白隠禅師二五〇年遠諱記念 創りあげられた現代禅
: 禅 心をかたちに」を紹介する。
○、この年、原田香織が「東洋学研究 (53) p.67-79」に「白隠禅師における中世思想 : 能楽の視点から」を発表する。
○、この年、臨済宗黄檗宗連合各派合議所,妙心寺派教学研究委員会,禅文化研究所が臨済宗黄檗宗宗学概論
: 臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念刊行」を「臨済宗黄檗宗連合各派合議所」から刊行する。 所蔵:京都府立京都学・歴彩館 |
| 2017 |
29 |
・ |
3月、竹下ルッジェリ・アンナが「宗教研究. 別冊 90」に「白隠禅師の門下の女性弟子―お察および恵昌尼の場合―
: 第75回学術大会紀要特集」を発表する。
4月3日~6月10日、花園大学歴史博物館に於いて「第2期白隠禅師二百五十年遠諱記念:原の白隠さん : 松蔭寺と静岡沼津伝来の禅画・墨蹟」展が開かれる。
4月、松下宗柏が「大法輪 84(4) p.86-89」に「白隠禅(はくいんぜん)とマインドフルネス (特集 マインドフルネスと坐禅・瞑想 ; 伝統仏教とマインドフルネス) 」を発表する。
5月、花園大学歴史博物館編集「白隠 : 白隠禅師二百五十年遠諱記念」が「花園大学歴史博物館」から刊行される。
5月12日、花園大学に於て「臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念事業
白隠禅師シンポジウム ~白隠禅を現代にどう生かすか~」が開かれる。
|
提唱式講演 白隠前後無白隠 後藤栄山老師 (瀧澤僧堂師家)
発表1
白隠墨蹟2500点 ー墨蹟大調査と図録発刊を通じてー
白隠禪画墨蹟における関防印・落款について
白隠禅を現代にどう生かすか 『白隠禅師座禅和讃』を中心にして
現代社会に活かしていくための白隠禅師座禅和讃
たち返り、たち返りつつ、祖師の春 ー「無相の白隠」の探求ー |
江上正道
冨増健太郎
小澤英夫
蘆田太玄
松下宗柏 |
講評 野口善敬先生
発表2
白隠 ー法話としての和歌ー
慈雲尊者と臨在禅
白隠の見た黄檗禅・・・・黄檗の禪は念佛禪か
白隠慧鶴と愚堂東寔 |
千坂英俊
村上宗博
西川秀敏
瀧瀬尚純
|
講評と総括 芳澤勝弘先生 |
8月2日~9月10日、長野県飯山市美術館に於いて『ーこの人なくして白隠なしー正受老人と白隠禅師』展が開かれる。
10月14日~11月26日、高知県立歴史民俗資料館に於いて「今を生きる禅文化
: 伝播から維新を越えて : 白隠禅師250年遠諱記念特別展」が「高知県立歴史民俗資料館」で開かれる。
10月9日~12月9日、花園大学歴史博物館に於いて「第3期白隠禅師二百五十年遠諱記念:白隠とその弟子たち」展が開かれる。
○、この年、禅文化 (243) p.57-80」に「臨済禅師1150年 白隠禅師250年遠諱 雲衲報恩大摂心 写真展 (特集 遠諱報恩大摂心からの一歩)」のことが掲載される
また、横田南嶺が「同号 p.10-15」に「臨済禅師1150年・白隠禅師250年 大遠諱雲衲報恩大摂心を終えて」を寄稿する。
○、この年、「禅文化 (244) p.73-80」に「白隠禅師250年遠諱記念 特別展「原の白隠さん」より 松蔭寺と静岡沼津伝来の禅画・墨蹟」のことが掲載される。
○、この年、「禅文化 (245) p.73-80」に「白隠禅師250年遠諱記念 特別展「白隠とその弟子たち」より」のことが掲載される。
○、この年、志水一行が「禅文化 (246) p.7-8,表紙」に「表紙解説 鉄山宗鈍像 自賛 一幅 紙本着色 94.6cm×42.1cm 元和元年(一六一五)
平林寺蔵」を発表する。 |
| 2018 |
30 |
・ |
1月1日~2月12日迄、九州国立博物館に於いて「白隠さんと仙厓さん」展が開かれる。
1月、九州国立博物館編「白隠さんと仙厓さん」が「九州国立博物館」から刊行される。 所蔵:栃木県立図書館
2月10日~3月25日迄、「駿河の白隠さん : 白隠禅師二五〇年遠諱記念展」が「静岡市美術館」で開かれる。
2月、静岡市美術館編「駿河の白隠さん : 白隠禅師二五〇年遠諱記念展」 が「静岡市美術館」から刊行される。
主催: 静岡市美術館, 佐野美術館, 静岡市 [ほか]
3月、竹下ルッジェリ・アンナが「宗教研究. 別冊 91 」に「白隠禅師の門下の女性弟子―政女および大橋女こと慧林尼の場合― : 第76回学術大会紀要特集」を発表する。
3月、芳澤勝弘, 山下裕二, 石川九楊ほかが「白隠 : 禅のこころを描く」を「新潮社」から刊行する。
(とんぼの本, )
|
巻頭言 生きている白隠と対峙せよ!(文・山下裕二)
禅画をよむ スーパー禅僧の仕掛けとたくらみ(解説・芳澤勝弘)(社会諷刺;心の図像化;達磨 ほか)
墨跡をよむ 太さの思想、斜線の批評?破調の書が秘めるもの(解説・石川九楊)
禅と白隠の基礎知識(監修・文・芳澤勝弘)(禅宗とは?禅画とは?;禅宗法系図;禅の用語解説 ほか)
対談 山下裕二のTalk about Hakuin(しりあがりさん、白隠キャラを描いてください。
“白隠マンガ”guestしりあがり寿;永青文庫の白隠について教えてください。
“愛蔵者は語る”guest細川護煕;ぼく、辻先生の授業で白隠の名を知りました。“美術史の中の白隠”guest辻惟雄) |
3月、 北村欽哉著 ; 鈴木真弓編「静岡県の朝鮮通信使 : ユネスコ「世界の記憶」登録記念
: 静岡県朝鮮通信使研究会10周年」 が「静岡県朝鮮通信使研究会」から刊行される。 所蔵:静岡市立中央図書館 講座レジメ集成 2007年~2017年
|
はじめに、静岡県朝鮮通信使研究会の発足とその活動内容、朝鮮通信使とは何か 北村欽哉、本書の構成について、講座レジメ・その他の講座一覧表、消えた朝鮮(通信使)伝承―日本坂・朝鮮巖・起木梅伝説― ブログ解説、朝鮮通信使が楽しんだクルージング船と南蛮船の謎、龍潭寺の絵心経、「朝鮮通信使」・高校生の認識度の変化、足利義満の東アジア共同体構想 ブログ解説、吉川氏を通して見る日朝関係―壬辰・丁酉戦争 朝鮮通信使 韓国併合―、小島藩惣百姓一揆―白隠と朝鮮通信使の関係―ブログ解説、大名夫人の朝鮮通信使見物 ブログ解説、駿府城の被虜人允福について―駿府から見た徳川家康の日朝外交―ブログ解説、朝鮮通信使の峠越 ブログ解説、『■齋』の謎を追う、興津宿朝鮮船漂着一件 ブログ解説、朝鮮通信使と富士山―使行録を中心にして―、今絶・金絶・記松知名考―「試行録」にある今切の呼称について―、渡来人ロマン―駿河国を中心とした朝鮮伝承―、『熊谷家伝記』より見たる朝鮮通信使と鉄砲伝来、扁額作成年の試論―朝鮮通信使揮毫の書をいつ扁額にしたのか―、国際交流の舞台となった江尻宿―朝鮮通信使を中心にして―、徳願寺(沼津原宿)の一行書をめぐって ブログ解説、何故清見寺にはたくさんの朝鮮通信使扁額があるのか―「小華」を中心にして―、江戸時代の日朝関係と教科書、朝鮮通信使とその経路 ブログ解説、あとがき 北村欽哉、プロフィール、静岡県朝鮮通信使研究会からの御案内 北村欽哉 |
5月26日~7月1日迄、「駿河の白隠さん : 白隠禅師二五〇年遠諱記念展」が「佐野美術館」で開かれる。
11月3日~12月9日迄、富士山かぐや姫ミュージアム(富士市立博物館)に於いて「かぐや姫の里と白隠さん
: 無量禅寺再興に尽力した人々の事跡を訪ねて : 富士山世界遺産登録五周年記念展」展がひらかれる。
11月、富士山かぐや姫ミュージアム(富士市立博物館)編「 かぐや姫の里と白隠さん
: 無量禅寺再興に尽力した人々の事跡を訪ねて : 富士山世界遺産登録五周年記念展
」が刊行される。
12月、竹下ルッジェリ・アンナが「印度學佛教學研究 67(1) (通号 146) p.63-69」に「鈴木大拙における白隠禅師の理解」を発表する。 J-STAGE
また、柳幹康が「同号p.292-286」に「隠慧鶴と『宗鏡録』」を発表する。
12月、禅文化研究所編「臨済禅師1150年白隠禅師250年大遠諱記録」が「臨済宗黄檗宗連合各派合議所臨済禅師1150年白隠禅師250年遠諱大法会事務局」から刊行される。普及版
○、この年、吉田恵理が美術フォーラム21編「美術フォーラム21 = Bijutsu forum 21 / 38 p.99-105」に「江戸絵画史における白隠 (特集 禅とZEN ; ZEN)」を発表する。
|
特集 禅とZEN(高橋範子編集)
禅
黙庵霊淵筆《四睡図》小考(ユキオ・リピット)
禅と室町文化――相国寺創建の風景(高橋範子)
禅を見せる――室町殿会所の演出(畑 靖紀)
隠遁の造形――中国と日本(救仁郷秀明)
高城寺旧蔵の《十六羅漢図》にみる禅の要素(橋本遼太)
雪舟と王維と――東京国立博物館本《破墨山水図》再説(橋本 雄)
雪舟筆《天橋立図》の事情(瀬谷 愛)
ある禅僧の肖像――大照院所蔵《言如円遵》をめぐって(荏開津通彦)
ZEN
「禅の拡張」寸見――鈴木大拙、世阿弥、ジョン・ケージ(島尾 新)
茶禅一味(田中仙堂)
鈴木大拙のZEN師の教えを伝えるということ(猪谷 聡)
江戸絵画史における白隠(吉田恵理) |
禅と笑い 仙厓の場合(黒田泰三)
近世の禅画――白隠・仙厓そして(浅井京子)
菅原通済と常盤山文庫(福島洋子)
金閣再建――ZENが繋いだ縁(利行榧美)
特別寄稿
1970年の「禅と絵画と書、ボストン美術館100年祭記念展」を顧みる―
→或る米国日本美術研究者の道程(マニー・ヒックマン)
資料紹介
鶴亭《梅に叭々鳥図》(町立久万美術館蔵)(平井啓修)
相国寺所蔵名品紹介
盛懋《陶淵明栗里図》(河野道房)
現代作家紹介
チェルフィッチュの〈映像演劇〉解釈試論―
→《渚・瞼・カーテン》を手がかりに(越前俊也)
・ |
○、この年、出光佐千子が「出光美術館研究紀要第二十四号p137~211」に「白隠門下と大雅 ー自性寺大雅堂の襖貼付書画をめぐってー」に「」を発表する。 |
| 2019 |
31 |
・ |
2月24日~4月28日、愛媛県西条市立小松温芳図書館・郷土資料室に於いて「白隠禅師とその弟子たち」展が開かれる。
2月、河野徳峰が「白隠禅師とその弟子たち : [特別企画展図録]」を「西条市立小松温芳図書館・郷土資料室/長福寺」から刊行する。 所蔵;愛媛県立図書館
2月、村松哲文が駒沢大学仏教文学研究所編「駒沢大学仏教文学研究 (22) p.145-162」に「日本における達磨図の展開 : 白隠と風外慧薫に共通すること」を発表する。
|
駒澤大学仏教文学研究所公開講演会録 「鎮魂」と「調伏」 佐伯 真一 p.3-25
駒澤大学仏教文学研究所公開講演会録 高僧絵伝と幽霊画 : 死者救済の思想と図像化 堤 邦彦 p.27-56
仏教文学におけるインド説話流布の事例研究 袴谷 憲昭 p.59-88
禅林の厠掃除 : 雪隠という美称、及び浄頭職の変遷 大澤 邦由, 劉 勤 p.89-111
月坡道印と小澤蘆庵の「十牛図」 伊藤 達氏 p.113-143
日本における達磨図の展開 : 白隠と風外慧薫に共通すること 村松 哲文 p.145-162 |
2月、「芸術新潮 70(2) (通号 830) p.49-51」に「技巧を捨てて世俗化に抗う 白隠慧鶴 一六八五-一七六八 (特集 正統なんてぶっ飛ばせ!
奇想の日本美術史 ; 奇想青年期 徳川の平和(パックス・トクガワーナ)は奇想の楽園[江戸時代])」が掲載される。
4月、松下宗柏が「大法輪 86(4) p.129-133」に「白隠が説く信仰と心構え (特集 仏教《信仰》入門 ; ブッダ・祖師が説く信仰と心構え) 」を発表する。
7月、原田香織が「国際禅研究 = International Zen studies 3 p.95-115」に「白隠禅師と能楽 (国際禅研究プロジェクトが武漢大学で共催した国際シンポジウム「Chan・Zen・Seon
: 禅的形成及其在世界的展開」特集(2))」を発表する。 (IRDB)
8月、島尾新が「茶道の研究 64(8) (通号 765) p.3,30-34」に「水墨清韻(13)白隠「隻履達磨」 : アマチュアの達成」を発表する。
12月、柳幹康が「印度學佛教學研究 68(1) (通号 149) p.314-307」に「白隠慧鶴と菩提心の判」を発表する。
○、この年、鈴木省訓が「禅文化 (253) p.19-27」に「古月禅と白隠禅 : 禅修行の諸問題再考 (特集 枯禅の真髄 : 古月禅材)」を発表する。
○、この年、瀧瀬尚純が「曹洞宗総合研究センター学術大会紀要 20 p.67-72」に「五百年間出」の語をめぐって : 白隠慧鶴評価の変遷」を発表する。
○、この年、西村則昭が人間学部篇「仁愛大学研究紀要. (18) p.21-36」に「ラカンと禅仏教(5)白隠布袋画に描かれたメビウスの帯」を発表する。
|












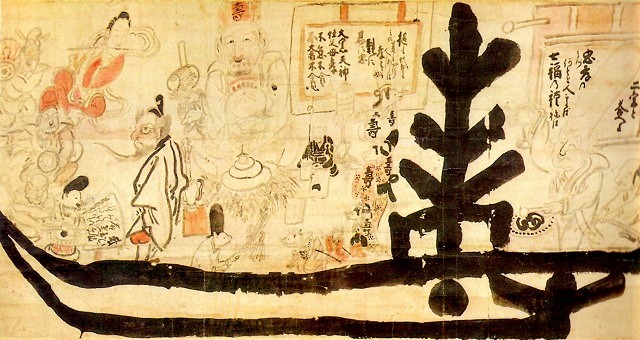


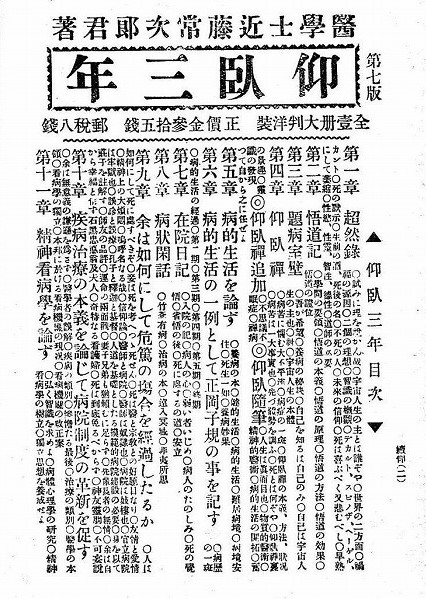
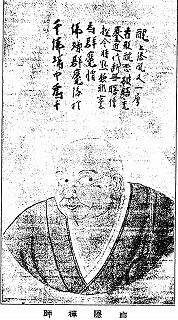 (所蔵:鹿王院)
(所蔵:鹿王院)