| ���� |
�a�N�� |
�E |
�o���� |
| 1868 |
������ |
�E |
�E |
| 1869 |
2 |
�E |
�E |
| 1870 |
3 |
�E |
�E |
| 1871 |
4 |
�E |
�E |
| 1872 |
5 |
�E |
. |
| 1873 |
6 |
1 |
8���Q�O���A�V��V������������Îᏼ���Ő��܂��B |
| 1874 |
7 |
2 |
�E |
| 1875 |
8 |
3 |
�E |
| 1876 |
9 |
4 |
�E |
| 1877 |
10 |
5 |
�E |
| 1878 |
11 |
6 |
�E |
| 1879 |
12 |
7 |
�R���A ��؋`�@��,�e�r��[�{�u�V��V���w ���v���u�k���Ɂv���犧�s �k�Ō��Ƌ��l�����Bpid/831008�@�@�{���\
�X���A ��؋`�@��,�e�r��[�{�u�V��V���w ��v���u�k���Ɂv���犧�s�����B�@pid/831007�@�{���\ |
| 1880 |
13 |
8 |
�E |
| 1881 |
14 |
9 |
�E |
| 1882 |
15 |
10 |
�P�O���Q���A���쐴�F�����܂��B |
| 1883 |
16 |
11 |
�E |
| 1884 |
17 |
12 |
�E |
| 1885 |
18 |
13 |
�P�P���P�T���A��K���e�����܂��B |
| 1886 |
19 |
14 |
�E |
| 1887 |
20 |
15 |
�E |
| 1888 |
����21 |
16 |
�E |
| 1889 |
22 |
17 |
�T���Q�V���A�R�{�ꐴ�����ꌧ�i����Îs�j�Ő��܂��B
�P�O���A�����Еҁu���m�{�Y趎� 6(97) �v�����s�����B pid/3559055
|
����ꝉ��T���L / ��я��M / p501�`504
����@(���)�n���m�O�� / p536�`536
����@(����)���z�m���z / p536�`536
����@(��O�Z)�� / p536�`536
|
����@(��O��)�ω� / p536�`536
����@(��O��)�s�E���V�����m�� / p536�`536
����@(��O�O)����m���� / p536�`536
����@(��O�l)�M���j�A�e / p536�`536
|
����@(��O��)����g�V�P�� / p536�`536
����@(��O�Z)����j���J�m萌W / p536�`536
����@(��O��)�����m�o�����j��i���R�g�j�A�e / p536�`536
�q�����r |
�P�O���A��㕀�삪�u�����V�F (23)p 28�`���F�Ёv�Ɂu�A�t���J���n�ɛ{���s�v�\����B�@�@pid/1784459
�P�P���A�����Еҁu���m�{�Y趎� 6(98) �v�����s�����B�@pid/3559056
|
趘^�@�ϐk�Ɖ��̐��` / p583�`583
趘^�@�F�{�����k�Г��L / p583�`584
����@(��l��)��� / p588�`588
����@(��l��)����m�e�� / p588�`588
����@(��܁Z)�{�탒��Y����/p588�`588
����@(��܈�)���z�m���z / p588�`588
����@(��ܓ�)�n���m���z / p588�`588
����@(��O)�y�p�g / p588�`588 |
����@(��l)��S�\�� / p588�`588
����@(��܌�)�{���j�A�e / p588�`588
����@(��ܘZ)��^�i�S��j�A�e / p588�`588
���@�n���m���z(���\�Z�j��S�Z�Z��) �e�r��[/p589�`590
���@�n���m�O��(���\���j��S��\����)/�e�r��[/p590�`590
���@���z�m���z(���\���j��S��\���)/�e�r��[/p590�`590
���@��(���\���j��S�O�\��) / ���A���A /p590�`590
���@����m����(���\���j�S�O�\�O��) /��������/p591�`591 |
���@����g�V�P��(���\���j
�@�@����S�O�\�ܖ�) / ���X�،� / p591�`592
���@�_�S�j�A�e(���Z�j��S��) / p592�`592
���@�l�ރm���I(���\�Z�j��S�Z���)/p592�`592
���@�����m����
�@�@��(���\�Z�j��S�Z���)/��㕀��/p592�`594
(��)
�E |
�P�P���A���V�R�����u�����V�F. (24) p24 ���F�Ёv�Ɂu���i�V��N�j�䎿�� �v�Ƒ肵������s���B�@�@pid/1784460
�P�Q���A�V��V�U���u�����V�F (25)p25�@���F�ЂɁu���V�N�j���t�v�Ƃ��āA���̎���ɓ�����B�@�@pid/1784461
|
���V�N�j���t / �V��V�U / 25
���V��N�j�䎿�� / �[�ێq / 26
�Z�p�m���o�����g���m���o�����g�������Y������ / ���_��F���� / 26 |
�䚠��@�m���v���j / ��㕀�� / 27
�q�����r
�E |
|
| 1890 |
23 |
18 |
�P���A�u�����V�F (26)�v���u���F�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/1784450
|
趋L �[�ێq�j���t / �V��V�U / 22
�Z�p��m���o�����g���m���o�����m�������Y������ / ���_��F���� / 26 |
�䚠��@�m���v�j / ��㕀�� / 27
�x�ߗ�g���{��m����̕t���s / / 28 |
�P���A�����Еҁu���m�{�Y趎� 7(100)�v�����s�����B�@�@pid/3559058
|
�j���@���m�{�Y趎��m�ޕS�j���j�X / �n粍^�� / p1�`1
�j���@���m�{�Y趎���S�j�mᢙ[���j�X/�a�c�_���O/p1�`2
�j���@���m�{�Y趎���S�j�mᢙ[�j�A�L�e/�N�����/p2�`4
�j���@�{�Y趎��w椃m���v / �O��G / p4�`5
�j���@�{���S�j�̏j� / �e�r��[ / p5�`7
�_���@���m�{�Y趎��m��S�j�j�o�������j�����Z�e
�@�@���{�⌤����m�֗����F�� / �����O�V / p7�`9
�_���@�`���[���X�A�_�[�E�䃓���B / ������g / p9�`21
�_���@�S�� / �O�R���� / p21�`31
�_���@���{�m�鑔�y(����) / ���������� / p31�`34
�_���@�陂��ۊ�����̂�
�@�@���R(���ؔŚ����) / �؈䐳���� / p34�`37
�_���@�ΒY�m���p�y�q���m�ѐ����j�A�e/���c�v�Y/p37�`42
�_���@�Ԃ݂�_�� / �ΐ�� / p42�`43
�_���@�n�k�y���z / 萒J�C�i / p43�`45
�_���@�\�[�_�H�ƃm�i�� / ����沋g / p45�`47 |
�_���@�U���}�z�j�A�e / �������K / p47�`49
趘^�@�l�̞ق� / ��c���Njg / p49�`51
趘^�@�k�C���m�n�������j�t��
�@�@������/�_�ۏ���/p52�`55
�@�l�p�Ȃ鎆���꓁�ɂĘZ�j�ɐ鎖
�@�@��(����) / �c�����m / p55�`57
�@�n��g���̏��� / p57�`58
趕�@�j�E�g���� / p58�`59
趕�@�ŗ����ɉ��鉻�{��̖J�܋� / p59�`59
趕�@�p���[�̌��� / p59�`61
趕�@�A�C�t�F�����̍���(����) / p62�`62
趕�@�p���c���{��N�� / p63�`64
趕�@趎��� / p64�`64
趕�@�����p�ɉ��Č�����n��(����) / p64�`64
��]�@�����ɛ{�����{���L���ɔV�l�m�l / p65�`66
�{���L���@�������{�� / p66�`66
|
�{���L���@���������{�� / p66�`66
�{���L���@�H�{�� / p66�`66
�{���L���@���N�{�� / p67�`67
�{���L���@�����Λ{�� / p67�`68
�{���L���@���ƛ{�� / p68�`68
����@�\�l�� / p68�`70
���@�Ύj / HM / p70�`70
���@�d�̓m������ / �e�r��[ / p70�`70
���@���z�m���z⍈ꌎ��� / p70�`70
���@�n���m���z / p70�`70
���@�p�x���O���X���R�g�j�t�e / p70�`71
���@�p�i�}�m���p / p71�`71
���@�ʉ_�j�A�e / ���ȑ�{�^ / p71�`71
���@鄐k�� / 萒J�C�i / p71�`72
���@�F���j�A�e / �݉��R�p�^ / p72�`72
�E |
�@�@�@�@�������Q�O�N�A�N�w���Âɂ��A�@���̃Z�C�����s�̑s�s��J����Ă���̂ŁA�������ɁA���̋L�q���Ȃ��������v�@�Q�O�P�P�E�Q�E�P�Q�@�ۍ�
�R���A�̗�؏d�����u�o�܉́v���꒼�V���E��ꐴ�O�Y�i���s�l�j�����s����B�@�@pid/754765�@�@�{���\
|
�V���N�� /
���y /
���� /
�ېH�_ /
�A /
���� /
�_�� /
��n�o�c /
���_ /
�c�� /
�O�� /
�K�� /
���� /
���� /
���� /
���H /
�V�~ / |
�Ր� /
� /
�펪���{ /
���� /
�H�� /
���H /
�䐅 /
���� /
���� /
���� /
���O /
�n�� /
�ߕ� /
���� /
�b�q /
���� /
���� / |
���� /
���R /
���� /
�M�� /
�w�H /
���� /
���� /
�R�w /
�_�� /
�O�m /
�A�� /
�O�v /
���� /
�O�T /
���_ /
�j�� /
���� / |
���� /
�j�w /
���S /
���� /
�ɐ��{ /
�x��{ /
�M�c�{ /
�F��{ /
�n�z�{ /
��_�� /
�V�Ѝ��� /
���_�a /
�a�^�� /
��� /
���� /
�Ў� /
�P�� / |
�����_ /
�����_ /
��a�� /
���� /
����� /
������� /
�F�N�� /
�_���� /
������ /
������_�� /
�另�� /
������ /
���䍰�Č� /
���P /
�l�p�l�E�� /
�J�p���_�� /
���� / |
�S���A��㕀�삪�u�ɗ��� (��16��) p48�`48�@�ɗ��Ёv�Ɂu����̘b���v�\����B�@pid/1481685
�T���A��㕀�삪�u�ɗ��� (��17��) p19�`20�@�ɗ��Ёv�Ɂu����̘b���v�\����B �@pid/1481686�@�ʔԂȂ��̂��ߒ���
�P�Q���A��㕀�삪�u���w�G�� (98) p5�`5�����w�فv�Ɂu�v���@�v�\����B�@�@pid/1529729 |
| 1891 |
24 |
19 |
�P���A��㕀�삪�u�ɗ��� (��25��) p39�`41�ɗ��Ёv�Ɂu��x��@�̋N���v�\����B�@�@pid/1481694
�R���A�����������u���w�G�� (105) p2�`2 �����w�فv�Ɂu��Z�n�ɈӂȂ炸�v�\����B�@�@pid/1529738
�V���A��㕀�삪�u���w�G�� (113) p7�`8�@�����w�فv�Ɂu���{�ɛ{�m���v�_�j�v�\����B�@�@pid/1529746
�X���A���J��炪�u��Տj���R�� : ����{�鍑�v���u���J���^�啪���v���犧�s����B�@pid/815747�@�@�{���\
|
�l���q
���n��
�F���V�c�� |
�F�N��
�I����
�c��Տt�H |
�_���V�c��
���P�ē~
�_�{�_���� |
�V����
�V����
�E |
|
| 1892 |
25 |
20 |
�E |
| 1893 |
26 |
21 |
�E |
| 1894 |
27 |
22 |
�Q���Q�P���A�_�c�����܂��B |
| 1895 |
28 |
23 |
�E |
| 1896 |
29 |
24 |
�E |
| 1897 |
30 |
25 |
�E |
| 1898 |
31 |
26 |
�����̔N�A�����������ҁu�_���p�� ����1�`8 �v���u�_�{���@ �v���犧�s�����B�@�@
pid/815633
|
����1 �_���ܕ������� ���V1/�g���K�a
���R��֖� / �דc�ݖ�
�_����Ӎu�k / �g��ґ�
����ЋL / �k���e�[
�_������ / �x��폲
���͉ƌn��
�_���ⓚ / �֓��F��
���^�E�דc�����`�L
���{���I�̈ٓ��{�y���ߖ{
�Î��L�̈ٓ��{�y���ߖ{
����2 �_���ܕ������� ���V2/�g���K�a
���L���� / �m������
�^�ߐ_�q�l / ���R�c�^��
���p���_ / ���M�F |
�g�c�ƌn�� / ����t��
���R�_�А_���̎� / ����t��
��떃�������� / ���ΐ��n
���^�E��ΐ^�����`
�Ì�E��ٖ̈{�y�ђ��ߏ�
���쎮�ٖ{�y�ђ��ߏ�
����3 ���H���l�_
�@�@�� 1�V��/�Z�l������
�_���ܕ������� ���V3/�g���K�a
�������_���} /�{������
����^ / �{������
�����I�^�� / �i������
�v�Ηw�Ȓ��� / �O�c�Ĉ�
���^�E�{���钷���`
|
�_���ƌ� / �ɐ����
���H���l�_ 3�V��/�Z�l������
�����I�ٖ̈{�y���ߍl�ؗ�
����4 �V�� ����1-5 / �����l��
�فX���� / ���X�؍���
�_�_�̍��l ���V1,2/���R�c�^��
���H���l�_ 2�V��/�Z�l������
�_���ܕ������� ���V4/�g���K�a
���^�E���c�Ĉ��̓`
�ߋ`���ٖ{�y�щ��ߗ�
����5 �_�_�̍��l
�@�@�����V3,4/���R�c�^��
�r�V�ޏ� ��1 / ��ސ���
�_���ܕ������� ���V5 / �g���K�a |
���^�E�_���w���`
�L�������m�e���a���`
����6 �r�V�ޏ� ��2 / ��ސ���
���P���V���� 1�V�� / �Z�l������
�_���ܕ������� ���V6 / �g���K�a
���H���l�_ 4�V�� / �Z�l������
���^�E���Z�@�����`
����7 �_���ܕ�������
�@�@�����V7-9/�g���K�a
�V�� ����6-10 / �����l��
���H���l�_ 5�V�� / �Z�l������
����8 �_���ܕ�������
�@�@�����V10-12/�g���K�a
���P���V���� 2-5�V���E |
|
| 1899 |
32 |
27 |
�E |
| 1900 |
33 |
28 |
���A���̔N�A�V��V�����A�V�������s�鍑��w�̗��H�ȑ�w�������ɔC������A�����w�����ɋΖ�����B |
| 1901 |
34 |
29 |
���A���̔N�A �ؑ� ���i�Ђ����j���u�s���������@�r�����������]�a���������������������������@�g���������� 1(0) p.F35-F38�v�Ɂu�ܓx�̉����\�n�X���j���P���V�V�L�N���m���v�\����B�@�@J-STAGE |
| 1902 |
35 |
30 |
�P���A�ؑ��h�i�Ђ����j���u�x�ω�Z���̔����v�̘_���\����B�@���e���m�F�̂��ߒ����v�@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�Q�@�ۍ� |
| 1903 |
36 |
31 |
�R���Q���A �X�{�Z���i�낭���j���ޗnj����S�D�c�����i���F����s�j�Ő��܂��B |
| 1904 |
37 |
32 |
�E |
| 1905 |
38 |
33 |
���A���̔N�A�V��V�����A�����ȗ��w���Ƃ��ăh�C�c�ɏo���A�Q�b�V�������c�V���h���m�̊������ēV���w�ɋ��������B |
| 1906 |
39 |
34 |
�P���A ��˒������u�����V���w�v���u�����فv���犧�s����B�@�@ (�鍑�S�ȑS�� ; ��140��)�@pid/830988�@�{���\
|
���́@���̓��T�^���y���W / 3
���́@���ʎO�p�@ / 10
��O�́@���W�Ԃ̊W / 18
��l�́@�n���̌`��y�傳 / 23
��́@���� / 32
��Z�́@�a�C�� / 48
�掵�́@�V���̎����a / 57
�攪�́@���z�̉����^�� / 62
���́@���z�̑ȉ~�^�� / 72
|
��\�́@�n���̉^���y�V�ɔ��ӏ�����/88
��\��́@�� / 101
��\��́@�f���i����j / 111
��\�O�́@�f���i����j / 133
��\�l�́@�� / 146
��\�́@���z / 162
��\�Z�́@�H / 175
��\���́@���L���� / 198
��\���́@���y�͓� / 218
|
��\��́@���s���y�N�ʎ��� / 239
���\�́@���z�̋��� / 252
���\��́@�V�̗� / 262
���\��́@���̑���@ / 270
���\�O�́@�ܓx�̑���@ / 282
���\�l�́@�o�x�̑���@ / 292
���\�́@���ʊp�̑���@ / 305
�E
�E |
�Q���P�Q���A���������_�ˎs�Ő��܂��B
�P�Q���A�T�C�����E�j�E�R������,��˒������u���C�V���w : �F�������v���u�։ؖ[�v���犧�s�����B
pid/831018�@�{���\
|
���́@�V���w�ŋ߃m�i�� / 1
�ŋ߃m�����씼���j�y�u
������m�\��
���b�N�V����y�n�[�o�[�h�V����m����
���́@�P���m���x / 17
���C�m���m�召�n�����j�W�X�A
�̎��m���x
�ߐ����x�m�Ӌ`
���m�F�m���x�j�y�{�X�e��
�ʐ^���x
�V���m�ʐ^�T��
���z�m�P�����x
��O�́@�����y�r���m���� / 32
�����m����
����̂߂Ƃ肠�A�������
���C�m�����@
�����g���̃g�m�W
��l�́@�P���\�y�r���m�� / 43
�Ԍo�y�Ԉ�
���Ëy���Î���m�P���\
�ߐ��m�P���\
�A���a�����_�[���ǂ�Ђނ��Ă��
�V�����t�F���h���ǂ�Ђނ��Ă��
�g�[�����ǂ�Ђނ��Ă��
�M�����ǂ�Ђނ��Ă��
�J�v�e�[�����ǂ�Ђނ��Ă��
���C�m��
��́@�P���m�����Ƃ� / 63
�����Ƃ镪�͏p�m����
���o�j�f�Y�������Ƃ�m����
�����Ƃ���g�g��
�P�������Ƃ�m����
�����Ƃ镪�̓j�˃e���^�����ʃm�[�T
��Z�́@�P���m�ŗL�^�� / 84
���^���g���^���g�m���
�^���m���T�m��i���R�g
��i���ŗL�^�����L�X�����m�\
���C�m�^���j�փX���F����
�P���m�����^��
���z�m�^��
���z���_�m�ʒu
���z�^���m���T
�掵�́@�ό��� / 106
�T���ό��� |
�ό����m�ό��Ȑ�
���݂����A���Ď�ό���
���邲�[���ό���
�ׁ[���A�炢���ό���
�������m�����ό���
���[���A��������[�m�ω�
�ό����m���ޖ@
�P�����x�m�����ω�
�ό����̂����Ƃ�
�攪�́@�V�� / 141
���[���A���邮��
�V���m�\
��ܕS���\��N�m�炢����
��Z�S�l�N�m���Ԃ�鐯
�ā[����ˁ[
�����肪�V��
�邵�����V��
���́@�P���m�N�T���� / 162
��������j�փX����o�҃m��}
��������m�ŋ߃m������
�ʓ����y�ʐ^�p�]����
�����T��
��\�́@�P���m�̌n / 177
�o��
�ʒu�A���ʊp�y����
�A���m�O��
���肤���y�Ղ낳������m�A�n
����ӂ��A������m�O��
������m�̌n
�O�A���y�r�������n
������I�A���n
���Q
���Q���j���P���ό���
��\��́@���_ / 207
���炢����m�启�_
���������i�����_
���_�����j�ʐ^�m���p
���_�m�\��
��\��́@�P���m�g�� / 220
�P���m���ʋy�r���x
�e���C�m���c�����g�M�g�K
�@�@���r�V�L���كi��
�A���n�m���ʋy�r���x
���C�m�����n�C�̃i�� |
��\�O�́@���C���W�_ / 248
�P���m�ꐶ�U
���C���W�g�����Ƃ�m�W
��\�l�́@�F���̑g�D / 258
�F���n�L���i���J
��ԓ��m���C�m�r�u
��̓g�F���g�m�W
���C�m�r�u�j�A�L�\�i��������
��\�́@�V���j���P�����m���z / 271
���ᐯ�m���z
�]�������m���z
����V�������m�ŗL�^�����L�X�����m���z
��ܗރm�����Ƃ鐯�m���z
��\�Z�́@���C�m�W�Q / 291
�Ղꂟ�ł�
���܁A�ׂ�ɂ���
�Ղ�[����
���炢����
��\���́@��̓m�g�D / 298
��̓m����
��̓j���X�����ᐯ
��̓j���X���]������
��͒��m��P��
��\���́@���m���g���x�g�m�W/310
�V���m�e�����j���P������
����n��̓j���e��i��
��\��́@�ŗL�^���m���v�I����/318
�ŗL�^���m����
�����x���L�X�����m���ώ���
���y�r���ރm�����Ƃ鐯�m
�@�@���ŗL�^���m����
�P�v�e�[�����m����
�ŗL�^���g���z�^���g�m�W
���\�́@��ԃj���P�����C�m���z/336
��X�m�����j���P�����m��
��ԃj���P�����C�E�m�L�T�m�T�Z
���m���ώ���
��̓m�����m�z����
���_
���^ / 353
���m�ŗL���̕\
�N�T�����y�r�ŗL�^���m�\
������I�A���n�m�\
�E |
|
| 1907 |
40 |
35 |
�P�Q���A��˒��U���u�Ȋw���E 1(2)�@p182�`185�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu�V���{��ᢌ��̝ɗ�v�\����B�@pid/1501016
�P�Q���A��˒��U���u�Ȋw���E 1(3)�@ p20�`22�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu�V���{��ᢌ��̝ɗ�(���O����) �v�\����Bpid/1501017
���A���̔N�A�V��V�����A�h�C�c����A������B |
| 1908 |
41 |
36 |
�P���A�ؑ��Ă��u�n���w�G�� 15(172) �@ p.1-11�v�Ɂu�ܓx�̉��ɏA��(�����l�\�N�\�ꌎ�����n���{���ɉ�����u�b�̑��)�v�\����B�@J-STAGE�@�@�d�v
�P���A�u�Ȋw���E 1(4)�v���u�Ȋw���E�Ёv���犧�s�����B�@pid/1501018
|
�p���l�̟���(���O����)/�e�r��[/p1�`3
�����̌��� / �r�؍G / p57�`59
���̘b / ��˒��U / p75�`78
|
�M��A���̗t�̓��� / �O�D�{ / p33�`34
���q���̘b / ����� / p67�`70
���̌`��ƍސς̎Z�@/�R��Õv/p71�`74 |
萍F�a�搶�I�O�ՊJ����
�@�@���/���V����O��/p96�`96
萍F�a�搶�̎��� / �ђ߈� / p92�`94 |
�Q���A��˒��U���u�Ȋw���E 1(5)�@ p48�`52�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu�f�l�V���{���������v�\����B�@pid/1501019
�T���A��˒��U���u�Ȋw���E 1(9)�@p776�`778�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu�̌������V���v�\����B�@pid/1501023
�@�@�܂��A�O�D�{���u���� p760�`762�@�v�Ɂu�M��A���t�̓����v�\����B�@
�V���A��˒��U���u�Ȋw���E 1(12)�@ p39�`41�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu�̌������V���v�\����B�@pid/1501026
�X���A��茧���V�X�Վ��ܓx�ϑ������ؑ��h���u�ܓx�ω��ɏA�āv���u�Վ��ܓx�ϑ����v���犧�s����B�@
pid/830977�@�{���\�@�@�d�v
|
���v/p1
�ϑ��̕��@�Ɗ�B�y�ё��g�p�@�@/p10 |
�ϑ��@ /p15�@�d�v
�ܓx�̉��Ƒ��̌��ۂƂ�萌W�@/p20 |
���_�@/p22
�E |
�P�P���A�c�T�u�����ҁu�{���O�a���ɏj�Փ�����v���u���W�� �v���犧�s�����B�@pid/815238�@�{���\ �d�v
|
���с@�O�a���ɐ_�y��
���́@����
���́@�c��a
��O�́@�_�a
��l�́@�_�y�� |
���с@��Տj��
���́@�V�N
���́@�F���V�c��
��O�́@�I����
��l�́@�t�H��G�c��� |
��́@�_���V�c��
��Z�́@�_����
�掵�́@�V����
�攪�́@�V����
�E
|
���^
���́@�F�N��
���́@���P
�c����
�E |
|
| 1909 |
42 |
37 |
�E |
| 1910 |
43 |
38 |
�E |
| 1911 |
44 |
39 |
�V���A�u�V������ = The astronomical herald 4(4)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3303884
|
�����k�L�l / ���{�m �a�c�Y�� / p37�`38
�����V���{�̖ړI / �G�X�A�G�X�A�n�c�t ;
�@�@�� �����C�F / p38�`43
�隠�{�m�@������ / p43�`44
��ˎ��̔��m�_�� / p44�`45
�V���{�N�� / p45�`45
���z���K�y / p45�`45
|
�A���̗��u�x�ƌ��x��萌W / p46�`46
�a���̔��̌^ / p46�`46
��̉��v��� / p46�`46
���z�g�|�����I�V�� / p46�`46
�ؐ��̑攪�ʐ� / p46�`47
�X�y�N�g�����ނ�茩�������/p47�`47
�ΐ��Ɠy���̍� / p47�`47
|
���̎������x�̝ɗ� / p47�`47
�V���{�k�b�� / p47�`47
���̉��� / p47�`47
�����̘f������� / p48�`48
�����Q / p48�`48
�����̓V�� / p48�`48
�E |
�X���A��˒��U ���u�w�� 2(10)p52�`61�@�x�R�[�v�Ɂu���z�̘b�v�\����B�@pid/1536061p/
|
| 1912 |
�吳�� |
40 |
�P���A��˒��U ����p�����w��ҁu��p�����w���� (5)p127�`132�@��p�����w��v�Ɂu�V���R�̓V���i�v�\����B�@pid/1513072
�S���A��˒��U���u�w�� 3(4)p22�`27�@�x�R�[�v�Ɂu�������Ɖ��������v�\����B�@pid/1536067
�T���A��˒��U���u�w�� 3(5)p59�`63�@�x�R�[�v�Ɂu�������Ɖ��������v�\����B�@�@�ʔԂȂ��@ pid/1536068
|
| 1913 |
2 |
41 |
�Q���A��˒��U���u�w�� 4(2)�@p48�`53�@�x�R�[�v�Ɂu��ɏA���āv�\����B�@�@pid/1536075
�@�@�܂��A �咬�j�����u����p109�`112�v�Ɂu�d�U�̕x�m�R�v�\����B
�T���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 6(2) /p1�`15���{�V���w��v�Ɂu�x�S���̗�@�Ɩk�l���� �v�\����Bpid/3303908�@�@�@�d�v
�T���A���s���w��ҁu�|�� 4(5) �v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B�@pid/3547541
|
������ꈢ���S�̌��`�ɏA���� / ���{���O�� / p1�`19
�x�ߏ��̗�@ / �V��V�U / p20�`38
�����������䐻�̔����˓����]�ɂ���/�嗺�O��/p39�`50
�N�吒�` / ����� / p50�`78 |
�Չ��E�R�� / ��،Y / p78�`79
ᡉN�O���O�����s�����ٗ�������/������/p80�`81
�b�ޔn�J�w�Ɖ䚠�^ / �j�ΐ� / p82�`88
�A�P�N�m�N�� / �[�c�N�Z / p88�`93 |
�b��@�{���L�� / p93�`94
�b��@�V����] / �O ; OF / p94�`95
�b��@����趎� / p95�`95
��㉁@���O�q���� |
�U���A���s���w��ҁu�|�� 4(6) �v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B pid/3547542
|
�x�ߏ��̗�@�\�\(���O) / �V��V�U / p1�`21
�����������䐻�̔����˓����]�ɂ��ā\(����)/�嗺�O��/p21�`30
�����S��萂��ā\�\(����) / ���c�@�� / p30�`37
���R�Ɣ��p��萌W�ɏA�Ă̛{�������ɂ��ăJ���g�ȑO��
�@�@���Չ����{���V�@�������� / �A�c���U / p38�`56
�암�{���ƕ���l / �F�}�ƗY / p57�`84 |
�����B�@ / �Ԗx������ / p84�`88 (0046.jp2)
���@���W�Ɍ������錻��� / ��ؒ��K / p88�`96
�����Û��N�́w�k�x��椂� / TN / p96�`97
�b��@���s�隠��{���ȑ�{�j�{�Șҋ㌎
�@�@���Ȍ�{�N�u�` / p97�`98
�b��@���s�隠��{���ȑ�{���{���L�� / p98�`100 |
�N�{�ϗ��{������ / p98�`98
���{�� / p98�`98
��N�@�͛{�� / p98�`98
�x�ߛ{�� / p98�`99
���^�@�b�̗t�킯�̙� / ���䉳�j / �`p24
�E |
7���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 6(4) p37�`39�@���{�V���w��v�Ɂu�����̑傳 �v�\����B
�V���A���s���w��ҁu�|�� 4(7 �v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B pid/3547543
|
���Ƃ̐��� / �s������ / p1�`15
�x�ߏ��̗�@�\�\(���O) / �V��V�U / p16�`33
���r�F�l�\�\(����) / ������ / p34�`40
��P�^ / ���c���U / p41�`53
���L�V�R�p�ł̓��{���T / �V���o / p53�`59
|
�����_�����̌��� / �ΙɗǕv / p59�`69
�J���g�� / TT�� / p69�`74
�y�g���[�����ɂ� / ��ː� / p74�`75
�K�ؔ��m�́w����̙J�l�x / �A�c���U / p75�`79
�b��@���s���ȑ�{�{�N�x���Ƙ_�� / p79�`81 |
�b��@���s���ȑ�{�����{������ / p81�`82
���^�@�b�̗t�킯�̙Ɂ\�\(����) / ���䉳�j / �`p30
�Y����l�N����`�ژ^
��㉁@�w椏��q�x / �ۏM��
�E |
�V���A�ؑ��Ă��u���k��w���� (68/69)�@ p1�`9�@���k��w��v�Ɂu�ܓx�̉��ɏA�āv�\����B�@pid/1488689
�W���A���s���w��ҁu�|�� 4(8) �v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B �@�@pid/3547544
|
����ړ����{�ɛ������̔�] / �[�c�N�Z / p1�`16
���Ƃ̐����\�\(���O) / �s������ / p16�`26
���q�̎�(�|�I����N���I�f��) / ��c�q / p26�`28
����C���� / �H�c�� / p28�`38
���I�ԓx�ƒm�I�ԓx�ʂ���{���̔ᔻ/�A�c���U/p38�`48 |
�Z���r�A�{�m���@�̐錾�� / �j�Q�� / p49�`55
�ڈΌ�{�̕@�c�㌴�F������
�@�@�����̒��q / ���c�ꋞ�� / p55�`66
�����_�����̌����\�\(���O) / �ΙɗǕv / p66�`75
�p�������\�\(��) / �_�c��� / p75�`80 |
�b��@���s�隠��{��l��u�K��/p81�`82
�b��@���s���ȑ�{���{������/����/p83�`84
�b��@�V������ / p84�`84
�b��@��趎� / p84�`84
�����\�����ߏo���B / ������� / �`p15 |
�X���A��˒��U���u�w�� 4(9)�@p22�`32�@�x�R�[�v�Ɂu�k�ɐ��v�\����B�@�@pid/1536082
�@�@�܂��A���P�P�オ�u����p67�`76 �v�Ɂu�`�O���X�͂̔����s�v�\����B
�X���A���s���w��ҁu�|�� 4(9) �v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B pid/3547545
|
���S�ɉ����钼�V�Ɣ��� / ���c������ / p1�`17
�x�ߏ��̗�@�\�\(����) / �V��V�U / p17�`45
����ړ����{�ɛ������̔�]�\�\(���O)/�[�c�N�Z/p46�`61
|
����^ / ����� / p62�`83
������ / �g�V�`�� / p83�`91
�����_�����̌����\�\(����)/�ΙɗǕv/p91�`101
|
�b��@�V���Љ� / O�AF ; �� / p101�`102
��㉁@�Ón��̃S�u�����D
��㉁@�Ón��̃S�u�����D��� / �V���o |
�@�@�@�V��V�U���u�x�ߏ��̗�@�v�ɂ��Ă̈ꗗ�\
|
| �m�� |
�G���� |
���s�N�� |
�^�C�g���� |
�L�� |
������ |
| 1 |
�|�� 4(5) |
1913-05 |
�x�ߏ��̗�@ |
. |
pid/3547541 |
| 2 |
�|�� 4(6) |
1913-06 |
�x�ߏ��̗�@�\(���O) |
. |
pid/3547542 |
| 3 |
�|�� 4(7) |
1913-07 |
�x�ߏ��̗�@�\(���O) |
. |
pid/3547543 |
| 4 |
�|�� 4(8) |
1913-08 |
�@�@�@(�����e) |
���q�̎�(�|�I����N���I�f��) / ��c�q
�ڈΌ�{�̕@�c�㌴�F�����Ƒ��̒��q / ���c�ꋞ�� |
pid/3547544 |
| 5 |
�|�� 4(9) |
1913-09 |
�x�ߏ��̗�@�\(����) |
�Ón��̃S�u�����D��� / �V���o |
pid/3547545 |
|
�@�@�@�Q�l�@�V��V�U���u�x�ߏ��̗�@�v�@ [�o�Ŏҕs��]�@�@���L �w�Y���x��4�N��5,6,7�j�ʍ�
�@�@�@�@�����F���s��w ���w������ �}���ٓ��m�j�@�K��||�I2||S||13494068
�@�@�@�@���_���͌|�� 4(5)�` 4(7)�A4(9)�ɏ�������Ă���Ǝv���̂ŁA���s��w�����{�ɂ��Ă͊m�F�v�@�Q�O�Q�Q�E�Q�E�Q�S�@�ۍ�
�P�O���A��˒��U ���u�N�ɂ��������̘b�v���u�哨�t�v���犧�s����B�@pid/1899256�@�{���\
|
���́@���̒P��
���́@����̊ϔO
��O�́@��N�̊T�O |
��l�́@���z��
��́@��N�̋敪�@�ƐߋG
��Z�́@���A��y���A�z�� |
�掵�́@���j�Ɗ��x
�攪�́@���s��ɂ���G��
���E�ŋߎO�S�P�N�p�V��ƕ\ |
|
|
| 1914 |
3 |
42 |
�S���A���������i�X��_�Ћ{�i�j���u�F�N�Ջy�V���ՔV�Ӌ` . �F�N�V������ՂɊւ���_�ЍՎ��ɏA���āv���u��ʌ��_�E��v���犧�s����B�@�@�@pid/944833�@�{���\�@�@�d�v
|
��/���F��/�Q
��/�Y�c�h��Y
�͂�����/��������/1
���ҁ@�F�N��/1
���́@�吳�ېV�̌���/2
���́@�F�N�Ղ̈Ӌ` /5
��O�́@�F�N�Ղ̋N��/12
��l�́@�F�N�Ղ̉��v/14
��́@��ՋV�̕ϑJ/22
��Z�́@�V�N����/36
�掵�́@�j���������_/39
�攪�́@�F�N�ՂƐ_�Ђ�/43
���ҁ@�V����/46�@
���́@�V���Ղ̐��_/46/
���́@�ł��d����ՓT/48
|
��O�́@�V���Ղ̉��v/52
��l�́@�{���̌䐷�V/56
��́@�_�{�̚���/62
��Z�́@�V���ՂƑ另�Ղ�/66
�掵�́@���J�̈Ӌ`���s/72
��O�ҁ@���_/77�`80
�t�^�@�F�N�V���_��ՂɊւ���
�@�@���_�ЍՎ��ɏA��/1
��@��Վ�����/4
��@�։��ƕ����y��/5
�O�@�C�P/5
�l�@�_�E�̐E��/5
�܁@���i�g�̏j���t��/7
�Z�@�䕼���P��/7
���@���募�i�g�̖��i/7
|
���@�F�N�ՔǕ��̋V/8
��@��ʓI����/9
�\�@�䕼���y���A�_�a�i��/9
�\��@�V��/11
�\��@�j��/12
���F�N�Ջ{�i�j��/13
���F�N�Օ��募�i�g�j���i�������Ёj/15
���F�N�ՎЎi�i�Џ��j�j��/17
���F�N�Օ��募�i�g�j���i�{�p�Јȉ��_�Ёj/18
���V���Ջ{�i�j��/19
���V���Օ��募�i�g�j���i�������Ёj/21
���V���ՎЎi�i�Џ��j�j��/22
���V���Օ��募�i�g�j���i�{�p�Јȉ��_�Ёj/23
�E
�E |
�U���A�ؑ��� ���u�w�� 5(6) �@p15�`21�@�x�R�[�v�Ɂu���E�I�ܓx�V�����v�\����B�@pid/1536092
�X���A�V��V�U���u ���N (132)p64�@�����V��Ёv�Ɂu�A��Ȃ鐯�̐��E�v�\����B�@pid/1793899
|
�A�C�k���N��湎�(���L) / ����x���� / p34
�ؑ\��ԒT�� / �V���P�� / p38 |
�A��Ȃ鐯�̐��E / �V��V�U / p64
�q�����r |
�X���A��˒��U���u�w�� 5(10)�@p209�`217�@�x�R�[�v�Ɂu��V���{�҃j���[�R�����v�\����B�@pid/1536096
�X���A�����Еҁu���m�{�Y趎� 31(9)(396)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/3559354
|
趘^ / p37�`45
���s�隠��{���Ǝ��j���P�����T�i���� / ���Q�� / p37�`38
���s�隠��{���Ǝ��j���P�����T�i���� / �c粍��� / p38�`38
���s�隠��{���Ǝ��j���P�����T�i���� / ������ / p38�`38 |
���s�隠��{���Ǝ��j���P�����T�i���� / ����� / p38�`39
���s�隠��{���Ǝ��j���P�����T�i���� / �V��V�U / p39�`39
�q�����r
�E |
|
| 1915 |
4 |
43 |
�P�O���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 21(10)(252)�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@pid/3364897
|
����X�Ǝ��o�S / �r粋`�� / p1�`3
����X�ɏA�Ă̏��� / ���{���m �c���`�� / p3�`6
�������Ȃ̍D�@ / ���{�m �I������ / p7�`9
����X�����i�Ȃ�Ӗ��̒��F / ���{�m �c���`�\ / p9�`13
����X�ɂ��Ă̏��� / ���䓙 / p13�`16
���v�Е� / ���{�m �⋴���� / p17�`18
|
���b�掌�V�� / �O��d�� / p18�`34
���\���_�Ղ̍l / ���{�m �{�n���� / p35�`37
�ܐ߂̕��P�ɂ��� / �N��G / p37�`41
����X�v�` / �A�ؒ���Y / p41�`51
����X�̈Ӌ` / ���㚠 / p52�`58 (0029.jp2)
�另�Ղ̍��{�` / ���{���m ������ / p58�`71
|
�������Șҍs�͂ꂵ���ʎ��̗R�� / �a�c�p / p71�`76
�F�N�ՂƑ另�ՂƂ�萌W / �R�{�M / p76�`87
���T�Ƙa�� / ���{���m ���X�ؐM�j / p88�`90
�b�� / ����䷎O / p91�`113
��� / p�i47�j�`�i52�j
�E |
|
| 1916 |
�吳5 |
44 |
�Q���A�V��V�U���u�V���_ 31(2);2���j p 122�`123�@�V���_�Ёv�Ɂu��\���̐��v�\����B�@pid/11005533
�S���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 9(1) /p1�`4���{�V���w��v�Ɂu�V铂̉��z�^�� �v�\����B �@pid/3303946
�W���A�V��V�U�������Еҁu���m�{�Y趎� 33(8)(419)�@p28�`38 �����Ёv�Ɂu�_���@���Ə\��x �v�\����B�@
�@�܂��A�u����p65�`65�v�Ɂu���Ƌ{�O�S�N�ՋL�O���v�̋L�����f�ڂ����B�@pid/3559377
�P�O���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 9(7) p73�`77���{�V���w��v�Ɂu��͂̌��ƉF���\���_ �v�\����Bpid/3303952 |
| 1917 |
6 |
45 |
�Q���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 23(2)(268)�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@�@pid/3364913
|
�_�� / p85�`136
�܉Ӟ��䐾���̗R�� / �q�� ���q������ / p85�`102
�c���̎��N�� / �A�ؒ����� / p103�`108
�Ì�Е� / ���c�٘Q / p108�`123
��£��ʣ�̖{�� / ���эD�� / p124�`136
趕� / p137�`137
�����̉��N�� / �Ԗx������ / p137�`145
�ЂƂ��̋� / ��c��� / p145�`149 |
���ʂ���ꂽ�鍂�{����搶/���c����/p149�`154
���� / p154�`154
���Ȉꌎ�ڒ�����c�e�V�]���V�q��/���Y�d��/p154�`154
�b�� / p155�`162
�F���V�c�䎮�N�� / p155�`155
�I���� / p155�`155
�F�N�� / p155�`155
�O�{�Ҍ����� / p155�`156
|
��l��Վ�{ / p156�`156
�F���V�c�_�{�䑢�z / p156�`156
�͈��D�� / p156�`157
���s������ / p157�`158
�F���`�m�ՓT / p158�`158
�i���j
�E
�E |
�Q���A��˒������u�V���w�Z�u�v���u����V�Ȋw�� �v���犧�s����B�@pid/955285 �{���\
|
���u�@�V��̊ώ@ / 1
���u�@�f���̘b / 56 |
��O�u�@��̘b / 113
��l�u�@���z�̘b / 159 |
��܍u�@��̘͂b / 204
��Z�u�@�F���̊J� / 233 |
�R���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 23(3)(269)�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@pid/3364914
|
�����̈Ӌ` / �I������ / p167�`177
�ɐ��_�{�K���̘��͐M�ɏA���� / �ΙɗǕv / p177�`19
���쎞��ɉ�����d�������n���d�z�ݛ��q���ܥ
�@�@���d���ӂɏA����/ꝓc����/p192�`201
�������x�m�J���͑�l�̉ƏW / ����v�U / p202�`210
趘^ / p211�`238
�Ց�趘b / ��џ� / p211�`216
|
�Ԗ��趋L / �Ö��� / p216�`223
���{�{���Ó���^�̒E�R / �⋴���\�� / p223�`232
�R�쐳��B��� / �{�ԗǎO�� / p232�`238
���� / p239�`244
���n�܈ʑ���N��� / ���c���� / p239�`241
���ȐV�N / �R�c���� / p241�`241
���ؗF�g�쎁 / ��{���N / p241�`241 |
�ԍ炭�O / �O��d�� / p242�`243
�c�q��� / ���� / p244�`244
�b�� / p245�`247
�F�N�� / p245�`245
�m�F�V�c��� / p245�`245
�����{�Z�����c / p245�`245
�i���j |
�V���A�V��V�U���u�@�� : �@�������� 4(7)p660�`669 �@�@�؉�v�Ɂu�@�ƓV���v�\����B�@pid/7929037
�V���A�����×Y���u����̔閧�v���u�t�z���v���犧�s����B�@�@�@ pid/1876536
�@�{���\�@
|
���� / 1
�M�y�n�C / 1 |
�����V���y�_ / 19
�� / 29 |
�C�� / 65
�E |
�P�O���A�ؑ��Ă������Еҁu���m�{�Y趎� 34(10)(433)�@p9�`17 �����Ёv�Ɂu�_���@�ܓx�̉��j�A�e�v�\����B�@pid/3559391
�P�Q���A��˒��U���u�w�� 8(13)�@p22�`26�@�x�R�[ �v�Ɂu���i����j�؏M����K���C�܂Łv�\����B�@�@pid/1536138
���A���̔N�A����w�p������ҁu �ŋߗ����w�̐i���v���u����c�����َG�����v���犧�s�����B�@pid/980949
|
�ŋ߉F���i���_�[�T�E���{���m�@�V��V�U / 51
�ŋߓV���{�̐i���E���{���m�@��˒��U / 77 |
�q�����r
�E |
|
|
| 1918 |
7 |
46 |
�P���A�V��V�U ���u�j�� 3(1) �@ p.18-42�@�j�{������ (���s�隠��{���ȑ�{��)�v�Ɂu<����>��\���h�̙B�҂�_���v�\����B�@�@�iIRDB�j
�Q���A�V��V�U ���u�V������ = The astronomical herald 10(11) p121�`123�@���{�V���w��v�Ɂu��\���h�̙B�҂ɏA�āv�\����Bpid/3303969
�P�P���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 9(11)�@p1�`27�@���O�o�ň���v�Ɂu�ΐ��̋L���ɂ��č��B����̐���N��Ɗ��x�I�O�@��ᢒB�Ƃ�_���\(��)
�v�\����B
�@�܂��A���c������ ���u���� p27�`53�v�Ɂu�_���ɉ����锽�{�n��瑎v�z�v�\����B�@pid/3547607
�P�Q���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 9(11)�@p1�`27�@���O�o�ň���v�Ɂu�ΐ��̋L���ɂ��č��B����̐���N��Ɗ��x�I�O�@��ᢒB�Ƃ�_���\(��)
�v�\����B�@pid/3547608�}�^
|
| 1919 |
8 |
47 |
�R���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 25(3)(295)�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@pid/3364938
|
���c�ɉ����鐭铘_ / ���{���m �g�c�F�� / p1�`18
��O�_�В��Ö��̐_�a�l(�) / ����ʚ� / p19�`39
�ɐl�P���w�}�����l� / ꝓc���� / p39�`45
�o�_���y�L�̌��� / �⍪������ / p45�`58
�ĂщC���Ɩk���x�߂ɏA�� / �ޓc�V�� / p59�`63
�����V�N�O���(����) / ���Y�d�� / p63�`63
���t���O��� / ���l / p64�`64 |
�튊���i / ���R���� / p64�`65
��O�e���r�� / p65�`66
�b�� / p67�`83
�F�N�� / p67�`67
�m�F�V�c���� / p67�`67
�������a�������V / p67�`70
�{�i�C�� / p70�`70 |
�͈�m���ʃ����J���V���w�L��ʎ{�݃j萃X�����c / p70�`77
�͈璺��ᢕz / p77�`79
�͈璺�߂̗v�y / p79�`79
�c�q���犯���V�C / p79�`80
���\�o�ɐ_�Ќ��݂̋c / p80�`80
�c�T�u�������{�@��{�L�� / p80�`83
�i���j |
|
| 1920 |
�吳9 |
48 |
�P���A�V��V�U���u�Ȋw���E 13(5)�@p3�`6�@�Ȋw���E�Ёv�Ɂu���z�̗��j�Ɗ����v�\����B�@ pid/1501085
�W���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 11(8)�@ p1�`28 ���O�o�ň���v�Ɂu�Ăэ��B����̐���N���_���\�\���A���r�����_�B�̔N��ɏA�āv�\����B
�@�܂��A�������O ���u����p72�`76�v�Ɂu�̏W��x�m�̐���ɂģ����ށv�\����Bpid/3547628
�X���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 11(9)�@ p1�`28 ���O�o�ň���v�Ɂu����Ɍ������鏔��̗�@��_���v�\����B�@�@pid/3547629
���A���̔N�A��˒������u�ʑ��V���w�u�` �@�㊪�v���u�哨�t�v���犧�s����B
pid/951229�@�{���\�@�@�u���t�v���Ȃ��̂Œ���
|
���ҁ@�`�_
���́@���_ / 1
���́@���W�@ / 9
��O�́@�V���{�p��B / 36
|
��l�́@�V���̏C��/83
���ҁ@���z�n
��́@�n�� / 102
��Z�́@�� / 120 |
�掵�́@���̉^�� / 158
�攪�́@�f���̉^�� / 167
���́@�H / 181
��\�́@�ݗL���� / 194 |
��\��́@���z�n�ט_ / 208
��\��́@���z / 308
�E
�E |
�X���A��˒��� ���u�ʑ��V���w�u�` �@�����v���u�哨�t�v���犧�s����B�@�@pid/951230�@�@�{���\
|
��O�ҁ@�P���E�̌���
��\�O�́@�P���̊T�_/1
|
��\�l�́@�̌��� / 98
��\�́@�d���y�A��/165
|
��\�Z�́@���Q�y����/200
��\���́@���_ / 222
|
��\���́@���z�̉^��/263
��\��́@�� / 287 |
�P�O���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 11(10)�@ p1�`28 ���O�o�ň���v�Ɂu����Ɍ������鏔��̗�@��_���\�\(��)
�v�\����B �@pid/3547630
�P�P���Q�U���A��˒������S���Ȃ�B�@�i�S�Q�j
�P�Q���A�V��V�U�����s���w��ҁu�|�� 11(12)�@ p32�`62 ���O�o�ň���v�Ɂu����Ɍ������鏔��̗�@��_���\�\(�O�A��)�v�\����B�@pid/3547632
���A���̔N�A�V��V�U���x�ߊw�� �ҁu�x�ߊw = Sinology 2(6)�@p387�`415�@ �O�������[�v�Ɂu���x�܍s���Ɓk���傭�l��(��)�v�\����B�@pid/1564809
���A���̔N�A�V��V�U���x�ߊw�� �ҁu�x�ߊw = Sinology 2(7)�@ p495�`516 �O�������[�v�Ɂu���x�܍s���Ɓk���傭�l��(��)�v�\����B�@pid/1564810
���A���̔N�A��Ƒ������u���Ƃ̍��J�v���u����{���������v���犧�s����B�@�@pid/1886599
|
�`��
���� ��ՂƏ��� / 1
���� �{���O�a ���_�Óa�E�_���q/11
��O�� �j�E�Փ��֖� / 17
�{��
�k���l �P��̏j�E�ՁE�L�O��
���� �l���`�E�ΒU�� �ꌎ���/25
���� ���� �ꌎ����E��� / 31
��O�� ���n�� �ꌎ�O�� / 35
��l�� ���n �ꌎ�l�� / 37
��� �V�N���� �ꌎ�ܓ� / 40
��Z�� �F���V�c���� �ꌎ�O�\��/42
�掵�� �I���� �\��� / 47
�攪�� �F�N�� �Ǖ��l�� ��ՓT�����\���� / 55
���� �m�F�V�c���� ��\���/63
��\�� ���R�L�O�� �O���\�� / 66
��\��� �t�G�c�ˍ� �t�G�_�a�� �t���̓�/78
��\��� �_���V�c�� �l���O�� / 82
��\�O�� �����_��� �l���O�\�� / 87
��\�l�� �C�R�L�O�� �܌���\���� / 93
��\�� �_�{������ ����ᢌ��Z���l���ՓT�Z���\����/103
��\�Z�� �c�@�{��a�C �Z����\�ܓ�/108
|
��\���� ���P �Z���O�\�� / 110
��\���� �����V�c�� �����O�\�� / 118
��\��� �V���ߍ� �����O�\��� / 131
���\�� �H�G�c�ˍ� �H�G�_�a�� �H���̓�/132
���\��� �����_�ЏH�G��� �\����\�O��/132
���\��� �_���� �\�����\���� / 133
���\�O�� �V���ߏj�� �\���O�\���/140
���\�l�� �V���� �\�ꌎ��\�O�� / 150
���\�� ���i�V�c���� �\�\��� / 160
���\�Z�� �_�{������ ����ᢌ��@�\�l��[�ՓT] �\�����\����/164
���\���� ������_�� �\���{/164
�k���l �Վ��̑�T
���� �����N�� / 168
���� �䑦���X�y�另�� / 171
��O�� �_�{���N��J�{ / 208
���^
��A���V�c�䐳�C���T / 1
��A�c���o�ɗ� / 11
�O�A�c�����J�� / 58
�l�A�_�{���J�� / 85
�܁A�_�Ѝ��J��⍍Վ� / 87
�E |
�@�@�@�@�@���@�F�N�ՁA�����ՁA�_���Ղ̓������P�V���œ��ꂳ��Ă��闝�R�͂���̂��@�����v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�X�@�ۍ�
|
| 1921 |
10 |
49 |
�Q���A�V��V�U���Љ�猤����ҁu�Љ�Ƌ��� 1(2)(2)�@p22�`29 ����{�}���v�Ɂu�V�n�͔@���ɂ��đn���������v�\����B�@pid/1479605
�R���A�V��V�U���Љ�猤����ҁu�Љ�Ƌ��� 1(3)(3)�@p39�`46 ����{�}���v�Ɂu���V�n�͔@���ɂ��đn���������v�\����Bpid/1479606�@�@���ʔԂ��Ȃ������̂ōČ����v�@�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�P�R�@�ۍ�
�U���A�V��V�U���u���{ 1(6)�@p122�`125�@���{�Ёv�Ɂu�V��̎И�g�D�v�\����B�@pid/1539482
|
| 1922 |
11 |
50 |
�P���A�V��V�U�������Еҁu���m�{�Y趎� 39(1)(484) �@p16�`23�v�Ɂu�_���@���̋g����萂�����M�v�\����B�@
�@�@�܂��A ���c�v�g���u���� p28�`34�v�Ɂu�_���@�A���̑c��v�\����Bpid/3559442
�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 15(2) �v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304019
|
�^���@�k / ���{�m �������� / p19�`22
�V��
�����Q�A�f�������
���˖]�����̐����@(�Z) / ���嗝�{�m �R�萳�� / p22�`24
�吳�\�N�������V��(��) / ���{�m �_�c�� / p24�`26
���z���Ƀ��r�a�E���̑��݁A�O���̓��H�A�{�N�㌎�̊F�����H / p26�`27
�G���P�a���A���f���G���X�̝����A���f���A�����_�A���������J / p27�`28
�V���V���ɏ��߂Ė]�������g���l�͒N���A�I���̓V���{�� / p28�`29 |
�{�N�d�d���ׂ��T���a�� / p29�`30
�k����R���^�̝̌����A�I���I�����_���̝̌����A
�@�@���A�X�g���m�~�c�V���E�i�n���q�e���A
�@�@���㌎��\���̓��H�o���V���� / p30�`31
�A�C���V���^�C�����̘Ғ��A�V���{�k�b���L��/p31�`31
���z�A���H�A���A�̌����A���̉��� / p32�`32
�E
�E |
�R���A�ѓ����v���u���m�w�� = The Toyo Gakuho 12 (1) p46-79�@���m���Ɂv�Ɂu�x�ߌ×�@�P�_�v�\����B�iIRDB�j
|
��A���������̎戵�ɂ���
��A�����_��
�O�A�\��x�̋N���ɂ���
�l�A�k�l�̌��q�ɂ��� |
|
�܁A��\���h�̋N���ɂ���
�Z�A�t�H�̗�@�ɂ���
���A�b�Ќ��n�ɂ���
�E |
|
�S���A�u�{�Y 39(487)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/3545391
|
���z�̌��� / �V��V�U / p14�`23
�N�̙B�� / �{���ΘZ / p53�`53
�k�����y�K���]�����̖����ɏA���� / �������U / p145�`149
�A���̑c�� / ���c�v�g / p150�`151 |
�k���h�������L�� / �O������ ; ������������ ;
�@�@���X�i���\�� ; �\�������� ; ���Z������ / p155�`157
�q�����r
�E |
�V���A�u�{�Y 39(490)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/3545394
|
��㉁@��V�R�ڂ��B�e�����x�m�R�̖k�ʁA
�@�@���ԐΎR���茩���鐹�P�ԁ\�\�A�[�g�y�[�p�[�� / ���c
椕� / p2�`160
���R�I�З͂̐��� / �{�鉹���� / p2�`8
�C�m���ƎR�x�� / ���c�v�g / p9�`9 |
���[���� / �V��V�U / p10�`18
���J�̐����̎��Ɛ����̎� / �����畽 / p56�`57
�k�И��h�������L�� / �O�V���q ; �K�⏉���� / p155�`157
�q�����r
�E |
�X���A�V��V�U���u�{�Y 39(492) p2�`11�@�����Ёv�Ɂu���v�\����B
�@�@�܂��A���c���u��������v�Ɂu�J���}�c�̗с\�\�D�y���� �v�\����Bpid/3545396
�@�@�@�@���@�B�e�҂ɕ��c�Ƃ���͕̂��c�v�g���m�̂��Ƃ��@�m�F�v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�P�Q�@�ۍ�
�X���A�u�V������ = The astronomical herald. 15(9)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/3304026
|
�V���ƍq�C(��) / ���{�m ���q�L�g / p135�`140�@�@�d�v
�V�� / p133�`133
�f�������A�����Q / p134�`134
�V铖]����(�O) / ���{���m �R�c�K���� / p140�`144
���ꔪ�N�ɉ����鑾�z�R���i�̃y�N�g���A�������V���A
�@�@���C�����̐ԓ��̈ʒu / p144�`145 |
�ΐ��̎��z���ԁA���������L�@ / p145�`147
�p���ɉ�����Ď��@�āA��A�ɉ�����M�j�A�����̌ߖC�A
�@�@�����R�����V���i���̟d���A�������� / p147�`147
���z�A���A�̌����A���̉��� / p148�`148
�E
�E |
�P�O���A�u�V������ = The astronomical herald. 15(10)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304027
|
�C�����O�̘f��(��) / ���{�m �S�Z�͗Q / p151�`154
�V�� / p149�`149
�f�������A�����Q / p150�`150
�V���ƍq�C(��) / ���{�m ���q�L�g / p154�`161�@�@�d�v
�P���̉��x / p161�`162 |
�M�d�r�ɂŐ��̌��x�𑪂邱�ƁA��d���̋O���̗��S���A
�@�@���������x�v�ɂ�鐯�̌��P�̌��� / p162�`163
�����A���s�V���i���S�ܓx�A�_���X�s�̎s���V���i�A
�@�@�����������V���{�k�b���L�� / p163�`163
���z�A���A�̌����A���̉��� / p164�`164 |
�P�O���A�V��V�U���u�{�Y 39(493) p26�`36�@�����Ёv�Ɂu�鉤�{�Ƃ��Ă̓V���{�v�\����B pid/3545397
�܂��A���c�v�g���u���� p122�`124�v�Ɂu�A���̑c�� �v�\����B
�P�P���P�V���A�A�C���V���^�C�����m���_�ˍ`�ɓ�������B
�P�P���Q�T���`�P�Q���P���A�A�C���V���^�C�����m�A�����鍑��w���w�������w���������u���ŁA���ƂɌ����w�p�u�����i���ۂɂ͂Q��E�ʖ�F�Ό����j���s���B�i���{�ł̍u���͂W��s��ꂽ�B�j
|

�����鍑��{�ōs��ꂽ�u����̌�̋L�O�B�e
�@�@�@�@�@�@�@�u���{�̓V���w�̕S�N�@���G�m���U�T�v�@���ʁ@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�P�R�@�ۍ�@�@�@ |
|
�P�P���Q�X���t�A�Ό����������V�����|���Ɂu���ΐ������̘b�i���j���f�̗���v�\����B
|
�Ό����������V�����|���Ɂu���ΐ������̘b�i��`���j�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�����V���f�ړ� |
�薼 |
���e |
| 1 |
1922-11-19 |
���ނ�̐F�E�_�̚ʼn� |
. |
| 2 |
1922-11-21 |
����߂��� |
. |
| 3 |
1922-11-22 |
�D�ɂ�l |
. |
| 4 |
1922-11-23 |
�n���Ƒ��z |
. |
| 5 |
1922-11-25 |
�G�[�e�� |
. |
| 6 |
1922-11-26 |
���ԂƋ�� |
. |
| 7 |
1922-11-28 |
���w�ƒ��� |
. |
| 8 |
1922-11-29 |
���f�̗��� |
. |
|
�P�Q���Q�X���A�A�C���V���^�C�����m�A��i�`���u�Y���ہv�ɂăp���X�`�i�Ɍ����o�q�i�����j����B
�P�Q���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 3(25) p1�`2�@�����V���w��v�Ɂu�V�����ۂɏA�āv�\����B �@pid/3219747
�@�@�@�܂��A�i���D���� �_�ˁj���{���ꂪ�u����p20�`23�@�v�Ɂu�Ï��Ɍ��������̋L�^�̐F�X�Ə������猩���V���{�̐i���v�\����B
�P�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 15(12)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304029
|
�C�����O�̘f��(�O) / ���{�m �S�Z�͗Q / p183�`192
�V�� / p181�`181
�f�������A�����Q / p182�`182
�A�C���V���^�C���͎��̘Ғ��A�������鑾�z���y�̑{���A
�@�@���o�[�h�a��(�����Nc)�A
�@�@���X�N�������v�a��(�����d�N) / p193�`194 |
�����v���̃y���C���T���a��ᢌ��A�^��̐V��ᢌ��̓d��A�唽�˖]�����A
�@�@�����{�V���{������d����L�� / p194�`194
�吳�\��N�e���̛��ƕ\(����) / p195�`195
�����A���z�A���A�̌����A���̉��� / p196�`196
�E
�E |
�P�Q���A�̈�˒������u�V���w���`�v���u�哨�t�v���犧�s�����B�@�@pid/960501�@�{���\�@
�@�@
�@�@�V���{���`�i���j |
���Ŕ��s�ɂ���
�@�{���͂��Ɓu�����V���{�v�Ƒ肵�A�����ٕS�ȑS���̈�Ƃ��Ċ��s���ꂽ���A���̌�v������łƂȂ��ě{�E��芉�]����ċ������́A�A���䚠�V���{�E�̗��j�I�ꖼ������{���̑S�������ł��u�V���{���`�v�Ɖ��肵�č]�ɕ�����͕��t�̋Ӊ��[������|�ł���B
�@�{���ł����s������c���Đ����ȍZ�����s�͂ꂽ�����V���i���_�c���w�{�m�̘J���L���A�V���ӂ��B
�@�@�吳�\�N�\���@�哨�t�@����
�@�@�@�@���_�c���w�{�m���_�c���̂���
|
|
���� / 1
���́@���̓��T�^���y���W/3
���́@���ʎO�o�@ / 11
��O�́@���W�Ԃ̊W / 19
��l�́@�n���̌`��y�傳/24
��́@���� / 33
��Z�́@�a�C�� / 50
�掵�́@�V�̂̎����a / 59
�攪�́@���z�̉����^��/65
|
���́@���z�̞�~�^�� / 75
��\�́@�n���̉^���y�V�ɔ��ӏ�����/91
��\��́@�� / 104
��\��́@�f���i����j / 114
��\�O�́@�f���i����j / 137
��\�l�́@�� / 150
��\�́@���z / 167
��\�Z�́@�H / 180
��\���́@���L���� / 203
|
��\���́@���y�͓� / 224
��\��́@���s���y�N�T���� / 245
���\�́@���z�̋��� / 259
���\��́@�V�̗� / 269
���\��́@���̑���@ / 277
���\�O�́@�ܓx�̑���@ / 289
���\�l�́@�o�x�̑���@ / 300
���\�́@���ʊp�̑���@ / 313
�E |
|
| 1923 |
12 |
51 |
�P���A�V��V�U���u�{�Y 40(496)p28�`38�@�����Ёv�Ɂu��̝̑J�v�\����B�@�@pid/3545400
�@�@�܂��A���c�v�g���u���� p112�`117�v�Ɂu�ʛ��Ǝ�q�̎U�z�\�\(�O)�v�\����B
�P���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 16(1)p3�`7�@���{�V���w��v�Ɂu�������ɏA��(��) �v�\����B�@pid/3304030
|
�����ɏA��(��) / ���{���m �V��V�U / p3�`7
�f�������A / |
�ݚ��V���{�����`���ɉ��ĉ����ꂽ�錈�c����(��) / p7�`9
�q�����r |
�Q���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 16(2)p19�`23���{�V���w��v�Ɂu�������ɏA��(��)�v�\����B�@pid/3304031
�R���A�u�{�Y 40(498)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/3545402
|
���M�����Ƃ��ẲA�z�܍s�� / �V��V�U / p20�`31
�ʛ��Ǝ�q�̎U�z / ���c�v�g / p67�`71 |
��{���яq�V�̏��V / ��F��M / p88�`94 (0
�q�����r |
�S���A�V��V�U���u�{�Y 40(499)p122�`129�@�����Ёv�Ɂu���M�����Ƃ��ẲA�z�܍s���v�\����B�@�@pid/3545403
�T���A�V��V�U���u�{�Y 40(500) p64�`70�@�����Ёv�Ɂu�V�n�J蓘_��]�v�\����B�@�@pid/3545404
�U���A�u�C�Ƌ� = Sea and sky 3(6)�v���u�C�m�C�ۊw��v���犧�s�����B�@�@�{���\
|
�_�̍��� / ����N�� / p75�`76
�P���̉^��(��) / 萌���g / p76�`82
�D�y�ɉ������̖��x�Ɵ��� / ����N�� / p82�`83 |
�n��������(���Z) / �Ϗ\�g / p83�`85
趕� �܌��̉J / p85
���^ �P���̉^��(����) |
�V���A�u�C�Ƌ� = Sea and sky 3(7)�v���u�C�m�C�ۊw��v���犧�s�����B�@pid/3307387�@�@�@�{���\
|
���Ɉ˂蟆�����肷�鎞�̌덷 / �U�R��O / p88�`92
���z���\�����镨�� / 萌���g / p92�`95
�k�����m�ɋN�肵��O�̒ØQ�ɏA����(��)/�{�c�Վ�;萘a�j/p95�`98
�P���̉^��(��) / 萌���g / p98�`100
�Љ� ���R�E�̐� / �W�[�A�V�[�A�V���v�\�� / p100�`106
�~�J�V�� / p106 |
�~�J / p106
�x���Z�t�n�^ / p106
�U�R�Z�t�z�C / p106
���c�C�m�����i�� / p106
���q�E�R�{�E�����z�C / p106
�E |
�V���A�ѓ����v���u���m�w�� = The Toyo Gakuho13�i2�j p157-233�@���m���Ɂv�Ɂu��x�̌×�Ɩi�ɐ����̔N��v�\����B�@�iIRDB�j
�W���A�u�{�Y 40(503)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/3545407
|
���[�̐��Ղ����� / �V��V�U / p2�`7
��s�@����B���_�̛��� / �����畽 / p8�`9,19�`19 |
���囵�̐��� / �e���c���� / p10�`19
�q�����r |
�X���A�u�{�Y 40(504)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/3545408
|
�\���@�莚 / ���Y�d��
��㉁@�f�����������̓��Ԑ����ƌ��R�� / ���R
��㉁@�L���i�_���c�L�[��T���\���s�[�N�ƃ��[�L���E�C�X/�㌴
��㉁@�|�c�_���ɍ݂�A�C���V���^�C���� / �|��
�_�� / p2�`128
铈�����̐V�@�^ / �������N / p2�`19
�x�m�R�̓��L�A�� / ��������� / p20�`25,46�`46
�s�s�v�`�̘b / ���c�ˎO / p26�`32,33�`35
�x�߉���趍l�\�\(��) / �c粏��Y / p36�`41
���ɏA�� / �؈��n�O / p42�`46
�n�\�ɐ��ލ��� / ���@�� / p47�`51
�����̎ / ���X�ؒ����� / p52�`58
���j�y�юZ�p��萂����͉ȏ��̉��P/�C�ߏ�����/p59�`69
�����̎n�܂� / �R���ɗY / p70�`81 |
���������̉̓��L / ���R�g / p82�`90
�W���X�p�[�̌��n�� / �㌴�h�� / p91�`93
�畆�N��ەa�̐�����萂���ꎄ�� / ���沖� / p94�`97
�Z��z�̊�b / ��F��M / p98�`102
�Vᢖ��ƐVᢌ� / XYZ / p103�`103
�A�C���V���^�C���̉F���� / �|�����j / p104�`107
��s�@���핢�ނƂ��Ă̖؍ނ̗��p / �X�J���Y / p108�`113
��`�̗��p / ��c�� / p114�`119
�V���������͈�@�y�O������K�@ / ������ / p120�`128
�C�O�� / �e���q / p129�`131
�隠�{�m�@�L�� / p132�`133
�k�И��h�������L�� / �i�k����;���Z������;���炬���� ;
�@�@�����쑪��; ��������;�F�{����;�D�y����;�㓡����;
�@�@����c�� / p134�`141 |
�P�Q���A�V��V�U���u�V������ = The astronomical herald 16(12)p179�`184�@���{�V���w��v�Ɂu�̌����_�v�\����B�@pid/3304041
|
| 1924 |
13 |
52 |
�V���A��˒������u �V��̐��E�v���u�Í����@�v���犧�s����B�@pid/982246�@�{���\
|
�͂����� / 1
��@�V���i / 11
��@���̂��� / 26
�O�@�� / 48
�l�@���z�̉^�� / 68
|
�܁@���z�n�i����j / 90
�Z�@���z�n�i����j / 101
���@�V���̐��� / 119
���@�����Ɛ��̖��i / 127
��@�P���i����j / 136 |
��Z�@�P���i����j / 145
���@���_�Ɛ��� / 158
���@��� / 169
��O�@�F���̍\�� / 174
�E |
�P�P���A�u�V������ = The astronomical herald 17(11)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304052
|
�V�� / p161�`161
�ŋ߂̈ܓx�̉��������Ƌy�ߔN�̖k�ɋO���ɏA��/���{���m �ؑ���/p163�`166
�f������� / p162�`162
���z�̎��z�Ƒ��埆�̈�ʑ�z��(�O) / ���{�m 萌���g / p166�`169
�����̉��� / p169�`170
�̌���������AF / p170�`171
�̌������V�� / p171�`171
�n���̌`�� / p172�`173
�C�������̐V������a�� / p173�`173
�����Ɛ��̌��̋����Ƃ̔�r / p173�`173 |
�V�̌��� / p173�`174
�t�C���X�����a��(����l�Nc) / p174�`174
�o�[�f��ᢌ��̈�V� / p174�`174
�����\�O���̊F�����H / p175�`175
�H�����̎q�ߊ� / p175�`175
�� / p175�`175
�V���{�k�b���L�� / p175�`175
�D���y���q�����C���l / p175�`175
�\�̓V�� / p176�`176
��������z���������Q��̌�������̉���/p176�`176 |
�P�Q���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 5(48)p1�`5�@�����V���w��v�Ɂu��@�����̖��v�\����B�@pid/3219766
���A���̔N�A���j�u�K��ҁu���n����V���� ��1,2�S�v���u�Y�R�t�v���犧�s�����B�@�@pid/1078773
|
�w���S�x�@���n����V����
��A�@���n�����̎v�z�V�E���{���m�E�O���� / 1
��A�@���n����̐����E���{���m�E�ΐ��㏼ / 6
�O�A�@���n�И��ɉ�����_���̙����E�V�䗴�� / 12
�l�A�@���n�����̐��Y�H���E���{���m�E�ݏ㊙�g / 21
�܁A�@���n�И��ɉ�����@���E�����يӍ���E�Óc�h�� / 25
�Z�A�@���n�@���Ƃ��Ă̐��B�퐒�`�E�o���ċg / 31
���A�@�_�Ђ̋N���E���{���m�E�v�ĖM�� / 43
���A�@�_�b�̈Ӌ`�E���{���m�E�������Y / 59
��A�@���{���j����̔_�k�E���V�q�F / 63
��Z�A�@���j����ɉ�������J�̌`���E���{���m�E�{�n����/68
���A�@���{���j����̕����E�����يӍ����E��������/75
���A�@���n����̕���E����E�����يӍ���E�㓡���/97
��O�A�@���搧�̉��v�E���嚖���E�~������ / 124
��l�A�@���n����ɉ����镶��E���_�O / 138
��܁A�@���n����̌�ʁE���勳���E�������� / 142
��Z�A�@���n����̕������E���{�m�E�������� / 149
�ꎵ�A�@���n����̌��z�E�H�{���m�E萖�� / 158
�ꔪ�A�@�Y�p�̋N���E�~�V�a�� / 165
���A�@��Ղ���ς����n�����̒n�����E���{�m�E��������/171
��Z�A�@���n�����̕����E�����g�U / 183
���A�@���n����̐l����E���{���m�E�������U / 186
���A�@���n������Y�p�E���勳���E�I�i�Y / 198
�w���S�x�@���n�����j
��㉁@���{���n����ɉ�����j�q�����䂵�Ď��ɍs���|
�@�@�������يӍ����@���������l暁@�H�{���m�@�ɓ��������` |
��A�@�n���̍\���y���睈���E���������t�͛{�Z���������B�U/1
��A�@���n����̐����̕��z�Ɵ���E���{���m�@���R�����Y / 13
�O�A�@�����睂̐ՁE���{���m�@�����Y / 22
�l�A�@��O�I�l�ށE�Λ{���m�@���J�����l / 36
�܁A�@���n�l�ށE������ / 55
�Z�A�@���n����̓V���{�E���{���m�@�V��V�U / 71
���A�@���{���Âɉ�����x�ߕ����̙B�ҁE�����يӍ����@��������/79
���A�@���n����̍H�Y�E����u�t�@�X������ / 88
��A�@�A�W�������̋N���E�����يӍ���@�㓡��� / 98
��Z�A�@���n����̌��z�\���E�H�{���m�@�������� / 119
���A�@���n�@���Ƃ��Ă̑��z���`�E�o���ċg / 125
���A�@�G�X�L���[�l��̌��n�����E�����يӍ���@�Óc�h��/137
��O�A�@���ט��̐Ί펞��E���{���m�@�������U / 150
��l�A�@���n����̐H���E���c���� / 164
��܁A�@�A�C�k�̌n���E���{�m�@���c�ꋞ�� / 171
��Z�A�@���p�������ɏA�ЂāE���嚖���@�~������ / 180 (
�ꎵ�A�@���ė����̐Ί펞��E�h�N�g���I�u�t�C���\�q�[�@�ڐ�q�V�U/192
�ꔪ�A�@�_��ƌܞ��䐾���E���{���m�@�F���� / 202
���A�@���n����̌���E���{�m�@�������� / 205
��Z�A�@���n�����̖����Ƒ��E�M�E���{�m�@�������� / 217
���A�@���n�����̉}���v�z�E�V�䗴�� / 250
���A�@���{�Ñ�̑����E���{�m�@��㑽�� / 262
��O�A�@���{�Ί펞�㖯�O�̐�����ԁE�J��֗Y / 271
��l�A�@���n����̍����E���{���m�@�O��ċg / 291
��܁A�@��㕶���ɛ������l�@�E�V�ؐᑺ / 299
�E |
|
| 1925 |
14 |
53 |
�P���A�����C�F���u�Ȋw��� 4(1);�V�N���S�ŐV�ț{�����j p98�`100�@�������V���Ёv�Ɂu��̓V���v�\����B�@pid/10984487
�R���V���t�A�呠�Ȉ���Ǖҁu���� �@3760���v�̍L�����Ɂu���ȔN�\(�ۑP��������)
�v�̂��Ƃ��f�ڂ����B
���{�}�C�N���ʐ^ pid/2955908
�T���A���w��o�ŕ��ҁu���m�{�Y趎� 41(506)�v���u���w��o�ŕ��v���犧�s�����Bpid/3559446
|
����V���{�̖�� / �V��V�U / p2�`8
��ނ����裂̉�̌��� / ���c�v�g / p35�`40 |
�A���{�����V����V�R�L�O���ۑ��\�\(��) / �O�D�{ / p55�`62
�q�����r |
�U���A���쏑�X�ҁu���j�ƒn�� 15(6)�v���u���쏑�X�v���犧�s�����B�@pid/3566909
|
�����V�n�J蓂̔N��ɏA�ā\�\(��) / �V��V�U / p1�`11
�و挤���҂Ƃ��Ă̐V�䔒�\�\(��) / �V���o / p11�`15
�k�ԍP�R�̍��J�\�\(��) / ���Ȓq� / p16�`28 |
�����\�ɘłƂ��̋Ɛ� / ���쐳 / p28�`40
�q�����r
�E |
�U���A�u�V�E = The heavens 5(54) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3219772
|
�O�V���ߐڂ̓V��(��)
�F���̍\���ɂ���(��) / ���T�����h�V���i�� CVL�V�����G�[/p203�`211
�����k�G���y�C�l���Z�o����`���@/���s�隠��{������ ��c�t/p212�`229
�V�����ۂ̘���ɂ���--(�{����V�ۗ���坰�����) /
�@�@�����s�隠��{�� �R�{���C / p230�`242 |
�V���E�̎G��АM / p243�`243
����Ɯ䓚 / p244�`244
�{�N�����̓V����\ / �V�����D��
�@�@�����������/p246�`253
�ʐM���ҏS����葴�� / p254�`255 |
�V���A���쏑�X�ҁu���j�ƒn�� 16(1)�v���u���쏑�X�v���犧�s�����B�@pid/3566910
|
�����V�n�J蓂̔N��ɏA�Ą���(��) / �V��V�U / p1�`11
�����{���C�̍��u�Ɗ��ƂɏA���� / ���q���� / p12�`26 |
�q�����r
�E |
�V���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 5(55)p256�`263�@�����V���w��v�Ɂu����V���i�̐V���ɍۂ��āv�\����B�@pid/3219773
�P�O���A�V��V�U�����w��o�ŕ��ҁu���m�{�Y趎� 41(6)(510)�@p1�`14�v�Ɂu���z�̎����I�������n��̌��ۂɋy�ڂ��e���v�\����B�@pid/3559450
�P�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 18(12)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304065
|
�V�� / p177�`177
�ߐ������{�ƓV���{(���A��) / �w�����[�E�m���X�E���b�Z�� ;
�@�@�������C�F� / p179�`184
�f������� / p178�`178
�̌������V�� / ���{�m �_�c�� / p184�`187
���N�ꌎ�\�l���̓��H / p187�`188
�a������� / p188�`188 |
�������� / p188�`188
���{�V���{���O�\�ܙd����L�� / p188�`188
���T���̌�������Z�N�̐��Z�ɑ� / p189�`189
�吳�\�ܔN�e���̛��� / p190�`190
�����C���l / p191�`191
�����A���z�A���A�����Q�A�̌����A���̉��� / p192�`192
�E |
�P�Q���A�ѓ����v���u�x�ߌÑ�j�_�v���u���m���Ɂv���犧�s����B�@
�@�@�@(���m���ɘ_�p ; ��5)�@pid/1920990�@�{���\�@�d�v�@�����V�̐}������
|
���� ���_ / 1
���� �x�ߌÑ�V���{�̐��� / 5
��O�� �F�������_�Ƒ���A�z�܍s / 6
��l�� �����Ƒ��̖��i / 31
��� �����ܐ��̉^�s�Ə\��C�\��\���h/48
��Z�� �~���y / 73
�掵�� �V���̊�B / 82
�攪�� ��@ / 95
���� ���x�y�ё��ٖ̈� / 115
��\�� �k�l�y�ѓ쒆�� / 135
��\��� �×�̘Z���[����v / 149
��\��� ������ƎO���� / 180
��\�O�� �Ύ�y�щ[�� / 203
��\�l�� �I�̏T�� / 211
��\�� �ؐ��I�N�@ / 218
��\�Z�� ��@�ƈ� / 225
��\���� ��@�Ɖ��� / 234
|
��\���� ��@�Ɲɛ{ / 241
��\��� �V����@�Ɛ��C���` / 249
���\�� �V����@�̐E�� / 259
���\��� �Ñ�V���{�̐����N�� / 268
���\��� �x�߂Ɛ����Ƃ̉F�������_�V���{��@���̔�r / 292
���\�O�� �Ñ�ɉ����铌���̌�ʂƝD������̎x�ߛ{�E / 342
���\�l�� �D������̋L�^�ɉ�����V����@
�@�@��(�`�L�C���t�H�y�ђ|���I�N) / 366
���\�� �t�H�̓V����@ / 378
���\�Z�� ���B����̓V����@ / 395
���\���� ���S���S�̓V����@ / 418
���\���� �Ñ�̈╨�̖������ɉ�����V����@ / 449
���\��� ���_ / 458
���_
��x�̌×�Ɩi�ɐ����̔N�� / 465
����
��v�V����(�{���O���řҏ�) / �ɖ�
|
����(�{���O��řҏ�) / �ɖ�
�� �����_
�� ����_
�O �V�s�_
�l �V��
�� �t��
�Z ��
�� ���v /
���_ ��x�̌×�Ɩi�ɐ����̔N�� �ڎ�
�� ���_
�� ��x�×�̎O����
�O ��O���̗�@�̓���
�l �i�ɈȌ�̓V���{
�� ��\���h�����̔N��
�Z ��\���h�̙B��
�� �i�ɂ̓V���{��Rig�]Veda�̐���
�E |
|
| 1926 |
���a�� |
54 |
1���A�u�V�E = The heavens 6(61) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219779
|
�p�[�f���̛���(ᢌ��҃o�[�f���m����)
���z�n�̋N��(2) / �p�����[�����V���{���X�� J.H.�W�[���X/p55�`62
�����Ƒ��̘A�z / ���̐쐶 / p63�`66
���ʓV���ʑ��u�b ���̉m��/���s�隠��{���������{�m ��c��/p67�`69
�ʐM / p69�`69
���y�T��ᢌ��҃V���[���ɋ��v��� / �O�p�����[�����V���{���X��
�@�@����M.J.�W�����\�� / p70�`76 |
�����̑��Z�Ȝa���E/���s�隠��{
�@�@���������{���m �R�{�ꐴ/p77�`80
�V���{�E�ŋ߂̌��� / �r�ؗ��{�m / p81�`94
���� / p80�`80
�ⓚ / p95�`95
�p�����ARATUS-"Phcnomena"�(I) / p96�`97
�̓V����\/�V�����D���V���������/p98�`105
�� / p106�`106 |
1���A�V��V�U���u���R�Ȋw (1)�@p221�`231�@�����Ёv�Ɂu�a���̌����v�\����B�@pid/1478676
�Q���A�u�V�E = The heavens 6(62)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3219780
|
��� ��V�̐����̔��V--�n�[�o�[�h��{�V���i�B�e
�V���{���茩���� �x�ߏ��̕��� / ���s�隠��{�͎�
�@�@�����{���m �V��V�U / 107�`108
�`���t�̑��z�K�y�V���Ƒ��̕��@ / ���s�隠��{�͎�
�@�@�����{���m �R�{���C / 109�`122
�C���h�m�Ō������� / �R�{���C / 123�`127
�V���{�̚��� / ������r�Y / 128�`129
���ʓV���ʑ��u�� �� / ���s�隠��{ ���͎����{�m ��c�t/130�`132
�V���{�E�ŋ߂̌���--���z�R���i�̗��_--
�@�@���Q�_�̕��z / �r�ؗ��{�m / 133�`141 |
�W���r�V�V���i�̕v�l�i�� / / 142�`145
�V铕��ʑ���@�ɏA�� / ��� �Óc��V / 145�`146
���D���V�����ɂĐ�肹��--
�@�@���Z�T���̌����ژ^/�r�c����/147�`
�a������� / 148�`
�p�����ARATUS-"Phenomena"�(2)/ 50�`151
�{�N�O���̓V����\--�V�����D���V���������/152�`159
趕� / / 108�`,129�`,146�`
�ʐM /127�`�@
�ⓚ/149�` �@��/160�` |
�R���A�V��V�U ���u�����w���� 3(3)�@p163�`171�@���������w������v�Ɂu�l�̉^����萂�����M �v�\����B�@pid/1544671
�T���A�V��V�U���u�v�z (5)(55) p115�`132�@��g���X�v�Ɂu�V���{���茩����x�ߏ��̕����v�\����B�@pid/3198759
�T���A�u�V�E = The heavens 6(65) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B1926-05
|
��� �G��������t���C���h���q���m���}������(����)
�w���̋L�O���x(�ɓ���) / �R�{ / p271�`271
���̋L�O�� / ���͎����{�m ��c�t / p272�`275
趕� / p275,303,309,315
�F���̍\���ɂ���(6��) / ���T�����h�V���i��
�@�@��C.V.L. �V�����F�[ / p276�`288
���v�̘b / ���{�m ��c�t / p289�`303
|
�ʐM / p288�`288
���E��T���v�̗� / ���{���m �R�{���C / p304�`309
���̋L�O�ɍۂ��� / �H�{�m ���V�F�� / p310�`312
�t���C���h���q���m���}�ւ� / ���{���m �R�{���C / p313�`315
�{�N�Z���̓V����\--�V�����D���V��������� / p316�`323
�V�����D��� / p324�`236
�E |
�U���A�u�V�E = The heavens 6(66)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219784
|
���̐���--���
���{��v���c���݂��̌䍹���� / p327�`327
�l���Ɖ]�ӌ��t / ���� ��R�� / p328�`331
���̌� / �R�{���C / p331�`331
���v���[�X�̐��_��--桐� / p332�`337
���ʓV���ʑ��u�b--�V���̈ʑ� /
�@�@�����s�隠��{���͎� ��c�t / p338�`343
��--�� / �������H / p343�`343
��חނ̐���� / ���R ����痢 / p344�`346 |
���y�я͓� / �I�� ��ꠍF���Y / p347�`353
趕� �ʐM �� / p346,353,379�`381
1925�N�ɉ����鑾�z����V���y�a�� / p354�`363
���鐅�j���̌ߌ� / �R�{���C / p364�`365
�w���E���Ƒ��z�M / �D�y �ēc���F / p366�`367
�p�����ARATUS-"Phenomena"�(5) / p368�`369
�{�N�����̓V����\--�V�����D��
�@�@���V�����a��� / p370�`378
�E |
�V���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 6(8/9)(67)�@p381�`394 �����V���w��v�Ɂu���m�Ñ�V���{�j��j�v�\����B
�@�@�܂��A��c�t���u����p 414�`416�v�Ɂu�O�V���̋��--���ʓV���ʑ��u�b(4)�v�\����B�@�@pid/3219785
|
�R�y���j�N�X�R--���
���m�Ñ�V���{�j��j / ���s�隠��{�͎����{���m �V��V�U/381�`394
�ΐ����߂Â� / ���s�隠��{�͎����{���m �R�{���C / 395�`398
���̃G�l���M�[���� / �p���P���u���c�a��{�͎� �G�c�a���g��/399�`413
�O�V���̋��--���ʓV���ʑ��u�b(4) / ���͎����{�m ��c�t/414�`416
����ƣ�̐��� / ���{���m �R�{���C / 417�`421
���˖]�����җ� / ���s�V���i �����v / 422�`427
������~�J�ɏA�� / �����隠��{�͎����{���m �����畽 / 428�`429 |
���̐��E���̋ɒZ�d�g / �R�{���C / 430�`
�{�[�f�� ���˖]���������
�@�@���s�P�����O���ߋ�/�����v/431�`
�p����--�A���[�g�X�̓V�ێ�(6)/432�`433
�{�N���㌎�̓V����\--
�@�@���V�����D���V���������/434�`449
�ⓚ�� / / 450�`
��� /450�`�@�@�@�ʐM /451�`452 |
�X���A�u�V�E = The heavens 6(68) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219786
|
��ޏF�x���̐V�����ԓ��V ���{�a���䔃��̖]����
�{�p�����`�������s�Ɍ}�ւ�--�ɓ��� / p453�`453
�V���Ɖq���̕��� / ���s�隠��{�͎����{���m �R�{���C/p454�`463
�P�������{�ŋ߂̌���/�p���P���u���a��{�͎� E�A��~����/p464�`473
���o���v�ƕ���--���ʓV���ʑ��u�b(5) /
�@�@�����s�隠��{���͎����{�m ��c�t / p474�`477
�V�̉� / ���� ��R�� / p478�`482 |
���˖]�����җ�(2) / ���s�V���i �����v/p483�`489
���{�a���䔃��̖]�����ɏA��/
�@�@������ �ܓ�ꎎO/p490�`493
�\���̓V����\--�V�����D�V���������/p494�`501
�a������� / �R�{ / p502�`502
���{�{�p��������� / p503�`505
���D���y���� / p506�`508 |
�P�O���A�V��V�U���u���|�t�H 4(10)p 8�`9�@���|�t�H�V�Ёv�Ɂu�啶�� �v�\����B�@pid/3197560
�@�@�܂��A�H�c�J�����u����p10�`13�v�Ɂu�H�ՂƂ��Ă̛D�����v�\����B
�P�O���A�u�V�E = The heavens 6(69) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219787
|
���[�t��t���E���z�[�t�A�̑�
�đ����m�{�p���c�ƓV���{--�ɓ��� / �R�{ / p509�`509
�V���{��̃t���E���z�t�A / ���s�隠��{�͎����{���m �R�{���C / p510�`512
�P�������{�̍ŋ߂̌���(2) / �p���P���v���c�a��{�͎� E��`��~����/p513�`524
���o�y���v--���ʓV���ʑ��u�b(6)/���s�隠��{���͎����{�m ��c�t/p525�`527
�ΐ��ʏ�ɂ���͂���铂Ȋ{���`/�W���}�C�J�V���i W�H��s�P�����O/p528�`530
�ΐ����V���ɂ��� / ���s�V���i �����v / p531�`533
��O����m�{�p���c / p533�`537
�X���[�h�����ˋ� / �����v / p538�`539
���씽�˖]���� / �����v / p540�`541 |
�w���E������铂ɂ��ꂽ / p542�`542
���X�킪���Y�̔��ˋ� / p542�`542
�e���t�A�͎��̒�N熐E / p542�`542
�X�R�t�C���h���̑��z�g���V�� / p542�`542
�ⓚ�� / p543�`543
�Y�x�L�����u / �j�t�� / p544�`54
�{�N�\�ꌎ�̓V����\--�V�����D��
�@�@����������� / p546�`553
���D��� / p554�`554
�E |
|
���s�隠��{���͎����{�m ��c�t�@���ʓV���ʑ��u�b�i1�j�`(6)����\
| . |
�G���� |
���s�N |
�_���� |
�L�� |
pid |
| 1 |
�V�E6(61) p67�`69 |
1926-01 |
���ʓV���ʑ��u�b ���̉m�� |
. |
pid/3219779 |
| 2 |
�V�E6(62) 130�`132 |
1926-02 |
���ʓV���ʑ��u�� �� |
. |
pid/3219780 |
| 3 |
�V�E6(66) p338�`343 |
1926-06 |
���ʓV���ʑ��u�b--�V���̈ʑ� |
. |
pid/3219784 |
| 4 |
�V�E6(8/9)(67)414�`416 |
1926-07 |
�O�V���̋��--���ʓV���ʑ��u�b(4) |
. |
pid/3219785 |
| 5 |
�V�E6(68)p474�`477 |
1926-09 |
���o���v�ƕ���--���ʓV���ʑ��u�b(5) |
�d�v |
pid/3219786 |
| 6 |
�V�E6(69) p525�`527 |
1926-10 |
���o�y���v--���ʓV���ʑ��u�b(6) |
�d�v |
pid/3219787 |
|
�P�P���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 6(70)�@p555�`572�@�����V���w��v�Ɂu��y�ѕ��ʂ�萂�����M�v�\����B�@pid/3219788
���A���̔N�A�������m�җ�j���ҁu�x�ߊw�_�p : �������m�җ�j��v���u�O�������[�v���犧�s�����B�@pid/1918048
|
�挾
�������m�җ��`��
�������m����N�\
�k������̏w�T�E�B�c���{�m ���_������ / 1
���펞��̕��Ёc�j�t��g / 13
�ܛ����`���ɏA���āc���{�m ���Ȓq� / 43
�@�����̌��z�鎮�Ǝx�ߘZ����
�@�@�����z�鎮�ɏA���āc���{���m �_�c�k�� / 93
�i���S�T����������S�ɏA���āc���{���m �H�c�� / 117
�x�ߗ��j�L�q�N���l�c���{�m �O�H���` / 149
�S�{�j��ɉ����鍒���Ƃ̒n�ʁc���{�m �{�c���V / 173
Le �� k'ong-heou et le qobuz�cPaul Pelliot / 207
�k�x�ߐ�`�ב��l�c���{���m ����� / 211
�쒩�ɉ�����m�����ʂɏA�Ă̏������c���{�m ���蕶�v/313
�ɗz�h�v���蕶�̉���c���{�m ������ / 327
���ɓs��Վv���Z�S�l�c������ / 373
�R��C�Ǝ��S�Ўq�l�����c���{���m ��쒼�� / 377
�����B�c���{���m ���P������ / 405
��{�j�����Ƃ��Č�����_�ՋL�c���{�m �����`�Y / 445
�x�ߐl���NJO�l���Ӑl���`�i���鉏�R
�@�@����萂���^�c���{�m �ߔg���� / 475
���������c���U�� / 543
�O���㚢����萂����l�@�c�~������ / 547
�@������Ɏx�߂ɘҏZ����
�@�@������l�ɏA���āc���{���m �K����U / 565
���j�����ɉ�����x�ߒm���̕K�v�c���{���m �K���� / 661
�ٕ{�̌����c���{�m �q�Ε��l�� / 671
���@�̘͂��ɏA���āc���{���m ���m�� / 701
���N�̛�ɏA���āc���{���m ���{���O�� / 731
�Z���I����c�B���� / 751
���x�ƌV�A�c���{���m ���c沔� / 757
���Ȃ��物���ւ̐��ځc���{�m ��ؐ��Z / 777
�K���]�Ȍė�����̊JᢂɏA���āc���{�m �L���� / 819 |
���C�v�j�b�c�́u�x�߂�
�@�@���ŋߎ��v�ɂ��āc���{���m ����� / 865
��i�O���������c���{���m �O�Y���s / 881
���x���l�c���{���m �����ɋg / 919
���m�V���{�j��j�c���{���m �V��V�U / 953
�����{���S�����Z���L�c���{���m ��،Y / 979
�ܑ�v���ɉ��������̓y��
�@�@�������ɏA���āc���{�m ���{������ / 1013
�k�x�ߐ�`�ב��l �ڎ�
��A����
��A������̐����ƌ����{
�O�A����т̖{��
�l�A�����̐����ƈӋ`
�܁A����
�Z�A����
���A�k���̈�
���A�k���̓�(��āA�� ��`�A�制)
��A�k���̎O
��Z�A��Ð��k�ב��̓����ړ�
���A�t�H���㐼�k�ב��̓����ڏZ
���A����
�� �n���ٓ��\
���m�V���{�j��j
�����B
�C�B
��\���h�Ɠy�\�B
�t�H�̗��ƎO���_�B
��@�̐����Ɗ��x�I�N�@�B
�܍s���B
�Ð̐��S�B
�������̐���B
����B
�E |
���A���̔N�A����g���u�V�E�АM�v���u���w��o�ŕ��v���犧�s����B�@�@�@pid/1021465
|
�������� / 1
��̋�̖���� / 1
�P���̕��z��͌n / 22
���͌n�Ə���͌n / 28
�������� / 43
���H��� / 48
�V铉��x�Ƒ����� / 70
���z�����Ɵ��ۂ̝̒� / 98
���z�̓��̒n���ɉe������\�� / 98
���z�ʂ̝̓��Ƃ͔@���Ȃ���̂� / 101
���z�ʝ̓��̐��� / 109
���z�����ɔ����t�˂̝̉� / 115
���z�t�˂̝̉��͟���ɂǂ��
�@�@�@���e�����y�ڂ����炤�� / 120
|
�\����萂��铝�v�I���� / 138
�J�ʛ����y�̓��v�I���� / 145
�������؛����y�̓��v�I���� / 154
�u�����b�N�i�[�̟���z������/158
�P���̉^�� / 163
���̈ʒu / 164
���̌ŗL�^�� / 166
�A���̉^�� / 169
�A���̌��x�ƃX�y�N�g�� / 172
���̋O���̓��v / 174
���̌ŗL�^���ƃX�y�N�g���K��/177
���̌ŗL�^���Ƒ��z�n���g�̉^��/180
���̎����^���Ƒ��z�n�̉^��/185
�P���̐⛔�^�� / 188 |
���� / 190
���z�����҂̖� / 195
���C�J�W�_�҂��V��������
�@�@���G�l���M�[�̖�� / 211
���̂܂��� / 241
�d�����z�`�� / 262
���z�̕����� / 262
�d���`���̖ړI�Ɨv�| / 265
������ƃX�y�N�g�� / 268
�X�y�N�g�����番�鎖�ǂ� / 270
�d�������̎B�e���@ / 275
�d�����z�`���̛���ƌ��� / 277
���z���y�̑���� / 281
�E |
|
| 1927 |
2 |
55 |
�P���A�u�V������ = The astronomical herald 20(1)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����Bpid/3304079
|
�̓V�� / p1�`2,20
�ܓx�̉��ԂɏA��(��) / ���{���m �ؑ��� / p3�`6
���z�̛����I����(��) / ���{�m �앍���v / p6�`10
���X�y�N�g���̕���(��) / �t�@�E���[���� / p10�`12 |
�f���_ / �����c�F�� / p12�`14
�V���� / �_�c�� / p14�`15
�V���Љ� / p15�`15
趕� / p15�`19 |
�Q���A�u�V������ =The astronomical herald 20(2)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304080
|
�V�� / p21�`21
�ܓx�J���ɏA��(��) / ���{���m �ؑ��� / p23�`29
�f�����惊 / p22�`22
���z�̛����I����(��) / ���{�m �앍���v / p29�`33
���X�y�N�g���̕���(��) / �t�@�E���[�͎� / p33�`35
�V���� / p35�`37
�����V���i(�O��)���^�V���ɂ�鑾�z�K�y�T��--�̌������V��/p35�`36
�̌������V�� / �_�c�� / p37�`37
�V�Y�Љ� / p37�`38
�V���{�T�V / �V��V�U / p37�`37
���V�E�АM / 萌���g / p37�`38
|
趕� / p38�`39
���z�K�y�̐V���_ / p38�`38
�ؐ����ʐ��̌��x�̝̉� / p38�`38
���f���̋O���\ / p38�`38
�v���L�V�}��P���^�E�����̋��� / p38�`38
��̐V�����Z�T���H�̌��� / p38�`38
�V���{�҂��] / p38�`39
���f�� / p39�`39
�����C���l / p39�`39
�O���̓V�� / p40�`40
��������z���������Q��̌�������̉��� / p40�`40 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V�E�АM�@�@���e�̊m�F�v�@�@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�R�@�ۍ�
�R���A�����C�F���u�Ȋw��� 8(3);3���j p390�`391 �������V���Ёv�Ɂu�t���̘b�v�\����B
�V���A���쏑�X[�ҁu���j�ƒn�� 20(1)�v���u���쏑�X�v���犧�s�����B�@�@pid/3566934
|
�x�ߏ��̋I�N�ɏA�� / �V��V�U / p1�`21
���U�����̎j�ւɏA�ā\(��) / �n粐��S / p21�`38
�\�������@�Ɨ��n�̏\��\�@�Ƃ̔�r/�q����/p38�`54 |
�R�A�C�ݍ��u�����\�\(��) / ���q���� / p69�`85
�q�����r
�E |
�V���A�����×Y���u�~�N���l�V�A�������v���u�����@�v���犧�s����B�@�@pid/1449078
�@�@�@�{���\
|
��m���� ��c������ / 1
�O�� /
���́@�`�� / 3
��@�|�i�y��� / 3
��@���j�A�n�� / 10
�O�@�Z�� / 33
�l�@���� / 50
�܁@�B�� / 69
�Z�@��� / 82
���@�푰 / 104
���́@�M�� / 119
��@���n�M�� / 119
��@�_ / 135
�O�@�Ћy�ˑ� / 168
�l�@���J / 183
�܁@����m�� / 199 |
�Z�@���y���� / 219
���@���f�A�։} / 232
���@�֊��A���M / 248
��O�́@�И� / 266
��@�����I�g�D / 266
��@�����g�D / 301
�O�@�И𐧓x / 327
�l�@�S�Z�g�D / 350
��l�́@�l�� / 365
��@�K�P���� / 365
��@��Z / 374
�O�@���I���K / 381
�l�@�r�� / 392
��� /
���́@�g�� / 409
��@�핞 / 409 |
��@��g / 429
�O�@���g / 468
�l�@笐g�� / 500
���́@���Z / 505
��@�T�� / 505
��@���q / 511
�O�@�Z��y�������� / 535
�l�@���O�ݔ��y�Ƌ� / 551
��O�́@�Z�H / 558
��@�H�� / 558
��@�Z�� / 576 (
�O�@�Z�H��� / 584
��l�́@���� / 600
��@�� / 601
��@�ŕ� / 606
�O�@�� / 612 |
��́@�M�� / 619
��@�T�� / 619
��@�M�̍\�� / 624
�O�@�M�� / 638
�l�@�q�C�p / 640
��Z�́@�H�Y / 672
��@�����y�H�� / 673
��@�D�� / 680
�O�@�ҕ� / 688
�l�@�����A�͏� / 697
�܁@��ʋy�L�Ή� / 709
�掵�́@���퐶�� / 727
��@���H���� / 727
��@���� / 732
�O�@��� / 751�� / 775
���i�y��v�������� / 805 |
�W���A���쏑�X�ҁu���j�ƒn�� 20(2)�v���u���쏑�X�v���犧�s�����B�@pid/3566935
|
������œ��̚z���ɏA���� / �H�c�� / p1�`7
���U�����̎j�ւɏA�ā\(��) / �n粐��S / p7�`20
�z�K�̌�n�Ɛz�K�_�Ё\(��) / �O�㍶�� / p20�`29
�a���Ɠ����ۏ��\(��) / ���c��Y / p30�`42 |
����������p�@�ɂ��R�c�����n�����������l�\(���m�O) / �������g / p43�`56
�R�A�C�ݍ��u�����\�\(��) / ���q���� / p56�`66
�q�����r
�E |
�W���A�V��V�U���u���|�t�H 5(8)p 16�`18 ���|�t�H�V�Ёv�Ɂu�����ƛ{�ҁv�\����Bpid/3197566
�W���A�V��V�U���u���؛{�� (1)�@ p20�`21�@���؛{��{�v�Ɂu�k���̓V�d�v�\����B�@�@pid/1596904
�X���A���쏑�X�ҁu���j�ƒn�� 20(3)�v���u���쏑�X�v���犧�s�����Bpid/3566936
|
�z�K�̌�n�Ɛz�K�_�Ё\(��) /�O�㍶�� /p32�`38
����������p�@�ɂ��R�c�����n�����������l�\(���m�l)/�������g/ p39�`45 |
�R�A�C�ݍ��u�����\�\(��) / ���q���� / p45�`52
�q�����r |
�P�O���A�u�V�E = The heavens 7(80) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219798
|
�A���S�[���� / ���s�隠��{�u�t���{�m �|�c�V���� / p437�`442
�R�{�͎��̢�\��������ˋ� / p443�`443
�\�ꌎ�̓V��(�����ē�) / p444�`445
���˖]�����̒q��(4) / ����V���䏕�� �����v/p446�`456
�ߑ㕨���{�ɉ�������ʗ��y�ѓ��v�w(�|�) /
�@�@���Q�c�`���Q����{ �x������_�����m / p457�`468
�����̑��z�ʒʉ� / ���s�隠��{���͎����{�m ��c�t/p469�`471
���̋��� / ���� �ēc���F / p472�`474
�F�������{�͎������ / p475�`475 |
�k������ / ���� ����痢 / p476�`480
趕� / p481�`481
1929�N�x�̉p���� / p481�`481
�F���o�̉_ / p481�`482
�k�C���l���̑��z�ʉ� / p482�`482
�̌������ / p482�`482
�V���Љ� / �R�{ / p483�`484
�y�ђʐM / p485�`486
�E |
�P�P���A�u�Ȋw��� 9(6)�Վ�����;���{�̉ț{�E�j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984512
|
�\�� ����/���n�F�l��
���g�O�������A��/ / 1�`8,9�`16
�ɔ\���h�Ƃ��̑������\/ / 8�`8
���{�ț{�̓a�������隠��{�e�͎�����i���̈�j//2�`3
���{�ț{�̓a�������隠��{�e�͎�����i���̓�j//4�`5
���{�����{�E�̓l/ / 6�`7
�z�E�̞܈З����{������/ / 9�`9
��鄒��̒������������m/ / 1�`1
���{�l�ޛ{�E�̍v�َ�/ / 10�`11
���{�̓V���{�E/ / 12�`13
���{�D���̐i��/ / 14�`15
�L�O���ׂ�������/ / 16�`16
��/ / 17�`17
���{�ɉ�����ț{�Ƃ��̛���/�Ό��� / 18�`21
���{�̓����{/�ΐ��㏼ / 22�`29
���{�Λ{��ᢒB�ɍv�ق��鐼�m�{��/�x�m���/30�`32
���{�l�ޛ{��ᢒB/�������U / 33�`42,250�`250
���{�{���{�̊T�v/��������� / 43�`49,250�`250
���{�l�̉ț{�I�\��/���R���� / 50�`57,250�`250
�{�M���{�E��ᢒB/���P�ØZ�� / 58�`64
�䂪���̑����{/��ؕ� / 65�`74,125�`125
���{�ɉ�����V���{�j/ABC / 75�`109
���{�ɉ�����D���̐i��/�R�{���U/110�`118,179�`179 |
�{�M�ыƂ�ᢒB/�{���ΘZ / 119�`125
�\��ꔂ��d�˂�Ƃ�����{���{��/�ēc�Y�� / 126�`128
�����吳���{�n���{�E�̉��/�V����l / 129�`
�隠�{�m�@�܂����o���ꂽ�����{��/�O�D�_���� / 138�`144
�V���{�E�̎v�Џo�����k��F�Ђ����l�搶�ƓV���i/���R�M / 145�`147
���{�ɉ�������i����p��ᢒB/�{��Ո� / 148�`154
�䚠�ɉ����鉻�{�H�Ƃ�ᢒB/����� / 155�`160
���{�n�k�{��ᢒB/�������ʖ呾�� / 161�`164,125�`125
�{�M����i���{��ᢒB/�n��ݎ��� / 165�`
�R�����Ƃ���ᢒB/�鏊���S / 172�`179
�����ȍ~�̓��{���z/�ݓc���o�� / 180�`187
���Y�{�E�̉��/���[�� / 188�`195
�A�C���X�^�C���ғ��L/�Ό��� / 196�`201
���{�̍�峛{�y��峛{��/�O�D�_���� / 202�`210,144�`144
�����ېV��䚠�_�Ƃ�ᢒB/�j�_���� / 211�`217
�s�����B���{��ोc�����ᔻ/���c�`���� / 218�`222
�䚠�̓��HᢒB�j/�q�F�� / 223�`234,249�`249
���{�A���{ᢒB�j/���c�O�v / 235�`241
���{�����{�E�̍���/�|�����j / 242�`244
�䚠�ɉ�����ꀋۛ{�̋N��/�|�������� / 246�`249
���E�Ɍւ��ț{�E�̏\��Ɛ�/�������� / 251�`260
�]�ˎ���̉ț{��/�X�L�O / 261�`265
�䚠���v��ᢒB/�X������ / 266�`272 |
|
| 1928 |
3 |
56 |
�S���A�x�ߊw�Еҁu�x�ߊw = Sinology 4(4)�v���u�O�������[�v���犧�s�����B�@pid/1564832�@�@�d�v
|
��A���� / �V��V�U / p472�`474
��A�����u���S�ɉ���������N��̐��Z / �V��V�U / p474�`48
�O�A�V�����̕��@�y�эޗ� / �V��V�U / p486�`488
�l�A���G�� / �V��V�U / p488�`496
�܁A���̑��Ɠ��̊��x / �V��V�U / p496�`505
�Z�A��������\ / �V��V�U / p506�`510
���A�N������ / �V��V�U / p510�`526
���A����� / �V��V�U / p527�`538 |
��A���Ɵu�� / �V��V�U / p539�`561
�\�A�����̐ϔN / �V��V�U / p561�`597
�\��A�Ø҂̌��� / �V��V�U / p597�`604
�\��A�����N��̌��� / �V��V�U / p604�`609
�\�O�A�P�_ / �V��V�U / p609�`617
�\�l�A�v�|�T�� / �V��V�U / p617�`619
(1)�������t�H�Ɏ�����D�������N�\ / / p485�`485
(2)�������t�H�Ɏ��錎�x�\ / / p490�`490 |
�T���A�u���R�Ȋw 3(2)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1478682
|
�}�z���c�g�͓k�w�l�̕�� / ���
�A�����j�E�X�̏ё� / ���
�ܓx�̉��ɏA�� / �ؑ��� / p1�`36
�z�����������̑���ƛ��� / �V���ʒj / p37�`57
�����{ᢒB�̎����� / ����C���� / p58�`72
���{�Q���̊C�ݒn�` / �ґ����� / p73�`85 |
�ꓪ峗ނ̐��B������� / ���c�S�M / p86�`92
�A�����j�E�X���B / ����ޒ�� / p93�`10
�u���I�̎И��v�ɏA�Ă̋^�` / ���˕ۗY / p108�`122
�����c�R�ւ̗� / �I�{�ꐳ�� / p123�`146
���E�e�����ؕ��� / ������� / p147�`160
���R�M���m������ɖK�� / �L�� / p161�`164 |
�X���A�u�Ȋw��� 11(3);9���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����Bpid/10984522
|
�\�� �ΐ���茩����y���Ƃ����ʐ�/���n�F�l��
�V铛����`��/ / 365�`
�q�ߋV/ / 365�`365
���{�B��̎��ݓV���i/ / 366�`367
���_�Ɛ���/ / 368�`
�ŐV�`�g�O�������A��/ / 369�`,409�`
�s�Ђ̕X�ɕ��ꂽ�V��/ / 369�`
���{�ŏ��̃J���`���o�[���ˋ�/ / 370�`
�R���N���[�g���D�̖h�g����/ / 372�`
���E�B���覐E/ / 376�`
�ˍ��s�Ř_�҃I�[���A�E���c�a/ / 409�`
���{�ō��ꂽ�}�s�p�d���@萎�/ / 410�`
�ŐV�ț{�O���t/ / 412�`
�I�o����Y�w�̝ЊR/ / 416�`
�ɓ��� �V���Ɛl��/�R�{���C / 377�`377
���̃��}���X/ / 378�`408,417�`443,447�`453,512�`512,530�`530
�ŋ߂̓V���{�E�ɉ����钿��/�R�{���C / 378�`385
�����猩���n��/�����C�F / 386�`387
�n���ɋ߂��f���Ɖ����f��/�_�c�� / 388�`391
�ΐ��Ăђn���߂Â�/�����v / 392�`393
���ʂɟk���̏����/�����C�F / 394�`400
�ꓙ���̌ːВ�/����Ǖ� / 401�`404,408�`408
����Ɍ����鐯/��K���e / 405�`408
�F���ɉ�����䂪�n���̈ʒu/�R�{���C / 417�`420,512�`512
�V�E�̏����y���̘b/�n粕q�v / 421�`424,530�`530
�Ñ�}�����̗�ƓV���m��/��K���e / 425�`429
�s���~�c�h�͓V���i��/��L�� / 430�`431
���E�B��̃A���]�i��覐E/��L�� / 432�`437,512�`512
�n���I�ł̎�/�Έ�d�� / 438�`439
���K���̐��/�@������v / 440�`443
�V铐i���_�̐L�W/萌���g / 447�`453
�����Ҏ�/�����t�v / 444�`445
��ƌ���/ / 456�`459,465�`467,470�`472,481�`485,�i���j,523
�q�~�̓�匤�����Ƒq�~�V���i/�����Ƌv / 456�`459
�ʕ����q�̗����L/���엘�� / 465�`467 |
�x�[�N���C�g�̊��/���ܟF�P�q / 470�`472,483�`483
�����ƉE���̖��/���c�`���� / 481�`483
�^�ĐV����b/������ / 484�`485
�����̌Q���ƔאB/�����V / 488�`489
�k�X�̌��X�s�c�c�x���Q���Q��/���X�ؕF���� / 492�`496
���A�C�_�O���X�̘b/����ޒ�� / 500�`504
�ʑ��n�k�{�u�b/���x�M�� / 513�`518,523�`523
�ț{�E�j���[�X/ / 454�`455,460�`464,�i���j,502�`504
�R��s��Â̊��������d��/���쏹�� / 454�`455
�j�����̎�̐��E�Iᢌ�/ / 460�`461,530�`530
�X�̑�p�����鍻�V���J�E�Q���̘b/ / 462�`464
�n�k���m�̏�������/ / 468�`469
��߉f�`�̑S�����オ�҂�/�d�R�͐� / 477�`479
���҂̃}�X�N/ / 480�`480
��铒~���@�̘b/�e�n�ٕ� / 486�`487
���Y���犢�z���Ƃ��/ / 490�`491
���C�U�O���t��ᢖ�/ / 497�`497
�����̌��t�̐V?��/ / 498�`499
�����m��Д�s�͏I�ɏo�҂ʂ�/ / 502�`504
�ț{���� ���Ԗ���/�b��O�Y / 505�`511
�������ɗ����p�L��/ / 519�`528,532�`537
ᢖ��j���[�X/�V�{���K�� / 532�`533
���˖]�����̍���/�����v / 519�`523
���������@�̍���/�d�R�͐� / 524�`528
���{���/�V���� / 534�`535
椎қ��/ / 536�`537
�㌎�̉��Y/�ǐ�p�� / 531�`531
���E����`��/ / 473�`476
�㌎�̟���/ / 538�`539
�ț{�t�H/ / 529�`530
�����t�H/��K���e / 540�`543
�ђ����/I�EM�� / 544�`544
�{�E�\�b/ / 446�`446
�~�V���ƒn���̔�r/ / �ڎ���`
�E |
�P�O���A�u�Ȋw��� 11(4);10���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984523
|
�\�� �v���y���[�̖������҂̑��s�D/���n�F�l��
��揂Ŗ����������]�̗�����/ / 550�`
���E��̓�H���Ƃ��ėL���ȒO�߃g���l��/�n粊� / 559�`566
���z�����œd�����N���Vᢖ�/��L�� / 584�`854
�V铐i���_�̐L�W/萌���g / 609�`614
���f���͂ǂ��Ɍ����邩/�_�c�� / 625�`625 |
����ȑM���̐�铂͉���/�n��ݎ��� / 628�`629
���z�����̛���/�Γ��O / 646�`648
���˖]�����̍���/�����v / 657�`660
�����t�H/��K���e / 668�`671
�i���j
�E |
�P�P���A�u�Ȋw��� 11(5);11���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984524
|
�\�� �G�@�̏P�҂�������Ö�̐M�j/���n�F�l��
�ŐV�`�g�O�������A��/ / 673�`680,681�`688
�����{�䌤���Ɍ�M�S�Ȃ� ����É�/ / 673�`673
���R�@�̒������/ / 674�`675
�k�̒a��/ / 676�`677
���A��ɒT訂̚�r�ɏ���o�[�h�����̈�s//678�`679
�k�ɒʉߙ��߂̃C�^�����j/ / 680�`680
�̞�t/ / 681�`681
���E�ő�̑�q��DR��Z���j/ / 682�`
�ŐV�ț{�O���t/ / 684�`685
�����ԃj���[�X/ / 686�`687
���͂ȉp���R�̋@�B���R/ / 688�`688
�ɓ��� �ț{�I���������Ԑ�/�R�c�K���� / 689�`689
�����{�䌤���Ɍ�M�S�Ȃ� ����É�/�����A����/690�`691
�@���ɂ��ċL�������i�����邩/ / 692�`701
1�Λ{�I�L�����i�@/�����ΔV / 692�`695
2�S���{�I�L�����i�@/���c�Җ� / 695�`701
�؏e�̒m��/�i���� / 703�`705
�s���ɐ���関�҂̑��s��/�R��P�l / 706�`707
���ؓ|�I�@�B���R�̏o��/�ǖ��j / 708�`713
�����������̑嗬��/�_�c�� / 714�`716
�o�[�h�����̓�ɒT訔�s�R�[�X/ / 717�`717
�J�����̖��p/�������� / 718�`720
����ȐH�p��/���엲 / 721�`723
�O�g��ߓ����T訋L/�i��K��v / 724�`725
�p�������h���̖h�K/ / 726�`727
����Ȏ��R�Ɛl�q�Ƃ̗ގ�/�e�n�ٕ� / 728�`732
�s���̓D�삪�Y��ɂȂ�/�����O�� / 733�`736
�l铉i�v�ۑ��̘b/��[�j�E / 737�`739 |
�P�������ł���܂�/ / 742�`742
��߉f�`���D�̎��/�d�R�͐� / 760�`760
�����Ɛ瓇��ᢌ����ꂽ�{���̐V�Y�n/���엘�� / 743�`746�@�d�v
���ɕ����G�j�X�̒�/��ސL / 747�`749
�V铐i���_�̐L�W/萌���g / 761�`766
�ʑ��n�k�{�u�b/���x�M�� / 767�`768,769�`772
�ț{���� ���Ԗ���/�b��O�� / 773�`779
�������ɗ����p�L��/ / 750�`752,758�`760,780�`783,786�`793
���z�����̛���/�Γ��O / 750�`752
���˖]�����̍���/�����v / 780�`783
�A�}�`���A�ɂ��o�҂�����������/�d�R�͐� / 786�`787
���{����̍���/��L�� / 758�`760
�ƒ�̃x�[�W/ / 788�`791
�Y�E�d�E���z�̗L���g�p�@/�X������ / 788�`789
�ѐD���̌�������/�i���� / 790�`790
�s�̍���/�R�k������ / 790�`790
�d���Ǝ����Ɩ�/��|�r�O / 791�`791
����̏��Ί�/��L�� / 790�`791
椎қ��/ / 792�`793
�d��̔z���@/�X�ǗY / 792�`792
��鄗p����R�C���̍���/�j�_�h�� / 793�`793
�k�b��/ / 740�`741
�W�]�i/ / 784�`784
�����̉��Y/�ǐ�p�� / 785�`785
�\�ꌎ�̟���/ / 794�`795
�����t�H/��K���e / 796�`799
���E���X�`��/ / 753�`757
�ђ����/�{���� / 800�`800
�k�C�ɌQ�����邤�݂��炷/ / �ڎ���`
|
�P�P���A�E�I���T�����v��Еҁu���v�ǖ{�v���u�E�I���T�����v��Ёi��\�F�ԏ�����j�v���犧�s�����B�@pid/1176195�@�@�{���\
|
���́@���� / 1
���́@�w���x / 3
���߁@���̎�� / 3
���߁@���̑���@ / 12
��O�߁@���� / 16
��l�߁@���� / 27
��ܐ߁@�� / 32
��O�́@���v / 43
���߁@�����v / 44
���߁@�ȈՓ����v / 45
��O�߁@���������v�̍�@ / 47
��l�߁@��قȂ�����v / 50
��ܐ߁@�����v / 53
��Z�߁@��㊎��v�ƃ����v���v / 61
�掵�߁@���R / 63
�攪�߁@�d�ʎ��v�̉��v�T�v / 64
���߁@�d�ʎ��v / 70
��\�߁@�l�`���v�Ǝ��v�i / 73 |
��\��߁@�L���Ȃ鎛�@�̎��v / 81
��\��߁@��g���A�u���v / 90
��\�O�߁@�咆���v / 94
��\�l�߁@���v�K���X / 96
��\�ܐ߁@���v�p�Z�� / 97
��\�Z�߁@���v�̑� / 97
��\���߁@������ / 103
��\���߁@�b�j / 105
��\��߁@����̏��p / 106
���\�߁@���v�̌� / 106
���\��߁@�ŗ����̎��v / 108
���\��߁@�����̎��v / 112
���\�O�߁@�p���̎��v / 117
���\�l�߁@�Ě��̎��v / 119
���\�ܐ߁@���{�̎��v / 121
��l�́@���v�̍\�� / 138
���߁@���v�@�B�̗v�� / 138
���߁@���� / 138 |
��O�߁@�咆���v�̓��� / 141
��l�߁@�֗���u / 142
��ܐ߁@�d����u / 144
��Z�߁@�����@ / 145
�掵�߁@�E�i�@ / 156
�攪�߁@�V���N���m�[�����v / 163
���߁@�d�����v / 165
��́@���v趘b / 166
���߁@���R�I���p / 166
���߁@�ʒu��� / 166
��O�߁@���x���� / 167
��l�߁@��y���� / 168
��ܐ߁@���v�Ɩ� / 169
��Z�߁@���v�Ɛ� / 169
�掵�߁@���͂̉e�� / 171
�攪�߁@�咆���v�̑傫�� / 172
��Z�́@���v�C�U�܂�W / 174
���^ �E�I���T�����v��萂����b / 185 |
�P�Q���A�u�Ȋw��� 11(6);12���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984525
|
�\�� ���E��̑�q��D�c�G�c�y�������j�̃L���r��/���n�F�l��
�ŐV�`�g�O�������A��/ / 801�`808,809�`816
��/ / 801�`80
�c�G�c�y�������j�q��D�吼�m������Ђɐ���/802�`803
���s���ւ�ė��R�C���̗̈�// 804�`805
�⚎�������ɂނ錎���E�̒���// 806�`807
�l�S�ݔN�O�̉ڂ̉���ᢌ@/ / 808�`808
���ݓ�畤�̔��j/ / 809�`809
���₩�ȋ�̃j���[�X/ / 814�`815
�ŐV�ț{�O���t�k���̈�l/ / 810�`811
�ŐV�ț{�O���t�k���̓�l/ / 812�`813
�Z���̉��L/ / 816�`816
�ɓ��� �����{�ѐ[���l�ւ�/�e���c���� / 817�`817
�l�S�ݔN�O�̉ڂ̉���ᢌ�/�����l�� / 818�`823
�ؑ\��͒�̒��ˋ��H��/��{��Y / 824�`828
���̉���/���V���� / 829�`831
�S�݃{���h�̒�X����/�L�� / 832�`832
�p�ӎ����ȃo�[�h�����̓�ɒT�/�������� / 833�`835
���h�����Ԃ̒m��/���{���\ / 836�`840,907�`907
|
�߂����������Ӌ@�B��ᢖ�/��䈤�Y / 841�`843
�Vᢖ��̓V�R�F�f�`�̐��/�d�R�͐� / 844�`845
�q��D�͋�̉���/�L�� / 846�`848
�A���̐V��������/���엘�� / 849�`852
��s�@�����p�������{�[�g/ / 853�`853
���d�r�̕s�v�c/�L�� / 854�`855
���N�̈�/����È��� / 856�`856,857�`857
�Vᢖ��C�����p�̐���ᢓd��/��|�r�O/ 858�`859
���{��̖��É��^��/�����g / 860�`864
�������O�ɐA���雉�/����Ö� / 865�`868
�v�l�̙B�B��萂��邠�雉�/���؊ш� / 872�`873
�N���X�}�X���Ə@�͎�/��[�j�E / 874�`875
��U�ȉΎ��̛��/�����g / 876�`877
��敂͉��̂悭�L�яk�݂��邩/���P�Ĉ� / 884�`887
���E�ŌÂ̘@�̛�/������ / 888�`894
�_�S����͔@���ɂ��č������邩//902�`904,905�`907
1�A�_�S����̍����@/�~�c�\����/902�`904,905�`905
2�A�_�S����̑f�l�Ö@/�n粍t�� / 905�`907
�ɂ��сA���̘��h�Ǝ���/�����\�� / 881�`883
|
�ț{���� ���Ԗ���/�b��O�� / 895�`901
�������ɗ����p�L��/ /
���z�����̛���/�Γ��O / 909�`911,868�`868
���˖]�����̍���/�����v / 917�`921
�ƒ�̃y�[�a/ / 913�`916
1�A���N�ҕ��̎d�グ��/�i���� / 913�`913
2�A�ǂ����Ĕ��≘��𗎂���/�d�R�͐�/914�`914
3�A�d���̎g�Е�/ / 915�`915
4�A�d���������̍���/ / 916�`916
���]�����ś�����V铛���/���c��V��/912�`912
�t�d�r�̍���/���ѐ��� / 912�`912
�\�̟���/ / 922�`923
�����t�H/��K���e / 924�`927
�\�̉��Y/�ǐ�p�� / 908�`908
�k�b��/ / 869�`869
�W�]�i/ / 870�`871
�ђ������/�{���� ; �o�ŕ� / 928�`928
�E
�E |
|
���n�F�l�����u�Ȋw���v�̕\���� �ɂ�������ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
��i�� |
���e |
pid |
| 1 |
9(6)�Վ�����;���{�̉ț{�E�j |
1927-11 |
���� |
�E |
pid/10984512 |
| 2 |
11(3);9���j |
1928-09 |
�ΐ���茩����y���Ƃ����ʐ� |
�E |
pid/10984522 |
| 3 |
11(4);10���j |
1928-10 |
�v���y���[�̖������҂̑��s�D |
�E |
pid/10984523 |
| 4 |
11(5);11���j |
1928-11 |
�G�@�̏P�҂�������Ö�̐M�j |
�E |
pid/10984524 |
| 5 |
11(6);12���j |
1928-12 |
���E��̑�q��D�c�G�c�y�������j�̃L���r�� |
�E |
pid/10984525 |
|
���A���̔N�A�V��V�����u����݂ƓV���v���u�O�������[�v���犧�s����B�@pid/1188795
|
��@�鉤�{�Ƃ��Ă̓V���{ / 1
��@�k���̓V�d / 18
�O�@�V���{���茩����x�ߏ��̕��� / 22
�l�@���m�����̕�����萂���_॑��� / 62
�܁@���m�����̕�����萂���_॑��� / 81
�Z�@���e���e�l / 113
|
���@�x�ߏ��̋I�N / 117
���@�����V�n�J蓂̔N�� / 143
��@���x�I�N / 169
��Z�@�\��x�ׂ̋N�� / 177
���@�V�̗� / 198
���@��ƔN���s�� / 211
|
��O�@����y�ѕ��ʂ�萂�����M / 231
��l�@�l�̉^����萂�����M / 276
��܁@���s���z������̖�� / 296
��Z�@�ߐ��ɉ������ƓV���{�̗��j / 305
�ꎵ�@����V���{ / 334
�E |
���A���̔N�A�V��V�����u���m�V���w�j�����v���u�O�������[�v���犧�s����B�@�@�@pid/1875543�@�@�d�v
|
���@�d�v
���� ���m�V���{�j��j / 1
���� �����̔N�� / 34
��A����
��A�����u���S�ɉ���������N��̐��Z
�O�A�V�����̕��@�y�ь����ޗ�
�l�A���G��
�܁A���̑��Ɠ��̊��x
�Z�A��������\
���A�N������
���A�����
��A���Ɵu�� |
�\�A�����̐ϔN
�\��A�Ø҂̌���
�\��A�����N��̌���
�\�O�A�P�_
�\�l�A�v�|�T��
���
��O�� ��\���h�̙B��
��l�� �t�H����
��ܕ� �ΐ��̋L���ɂ��č��B����̐���
�@�@���N��Ɗ��x�I�N�@��ᢒB�Ƃ�_��
��Z�� �Ăэ��B����̐���N���_��/398
�掵�� ����Ɍ������鏔��̗�@��_��/429
|
�攪�� �D���`���̗�@ / 517
��A����
��A��@��ᢒB
�O�A�����̗�
�l�A�t�H����̗�ƍ��B�̗�@
�܁A�D������ɉ������@�̐i�z
�Z�A�D������趎�
���A�Ø҂̌���
���A�D���I�N
��A�D���`���̒���
�\�A�v�|�T��
���� ���x�܍s���Ɓk�Z���M���N�l�� / 619 |
���A���̔N�A��싳���җ�L�O��ҁu�x�ߊw�_�p : ��싳���җ�L�O�v���u�O�������[�v���犧�s�����B�@pid/1913948
|
�Ԙ��l �����c���䏬���� / 1
�[��ꓹ�c���{���m �����Վ��� / 5
�ʏ������c���{���m ���P������ / 9
�x�ߌÑ�̖����ɏېl��
�@�@���N���ɏA���āc���{���m ���{���O�� / 63
�s�V�q�B�l�c���{���m ����� / 89
�߁����l�ɂ��āc���{���m ���c沔� / 243
|
�B�̘^�c���{���m �����i���� / 261
�x�߂̍F����ɖ@�����茩����x�߂̍F���c���{���m �K����U/269
�J���g�ɉ�����h�ƒ���ɉ�����h�c���{���m ���䌒���� / 373
�O���@�����X�ɏA���āc���{���m ���m�� / 417
�t�H�����c���{���m �V��V�U / 447
�Ղ̏\���ɛ�����^��c���{���m �F��N�l / 523
�i���j |
|
| 1929 |
4 |
57 |
�P���A�V��V�U���u�j�� 14(1) p.17-40�@�j�{������ (���s�隠��{���{����)�v�Ɂu<����>�x�ߌÓT�̔N��ɏA�āv�\����B�iIRDB�j
�T���A�ѓ����v���u���m�w�� = The Toyo Gakuho 17�i4�j�@p449-497�@���m�����v�Ɂu�x�߂̌×�Ɨ���L���i��j�v�\����B�@�iIRDB�j
�U���A����痢 �V�����D�����u�V�E 9(100) p.377-382�v�Ɂu�q�~�V���i�v�\����B�@IRDB
�W���A�ѓ����v���u���m�w�� = The Toyo Gakuho 18(1) p58-118�@���m���Ɂv�Ɂu�x�߂̌×�Ɨ���L���i���j�v�\����B�@�iIRDB�j
�W���A�u�Ȋw��� 13(2);8�����Ė��M�j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984533
|
�\��/�����E
�n�[�t�g�[�� ���E�ܑ̌��/ / 185�`192
�K���a�X�͏�k����̋�s/ / 185�`185
�k�q�]�̃W�����N�ƎO�����/ / 186�`187
�B���Ǝ��̃��C���̗���/ / 188�`189
�������ɂ��_�j���[�u�̗�/ / 190�`191
�_������i�C���̑�×�/ / 192�`192�@�d�v
�ŐV�`�g�O�������A��/ / 193�`200,241�`248
��x�ڐ���/ / 193�`195
�u�����̕���/ / 196�`197 |
���I���ɉ�������p�V����/ / 198�`199
�V���R�Ƃ��̕���/ / 244�`245
���M�������C�y����i�C����k��/�ꎁ�`�� / 223�`228
����Ă̓��̌ߌ�/萌���g / 249�`251
�i�s�̗����L����/�������ʖ呾�Y / 281�`283
�O�V�R�̈��/�n��ݎ��Y / 286�`287
�z���̎��R�Ɛl/�ɔg���Q / 288�`289
�x�m�̗o��ē��߂���/�Ό������Y / 345�`353
�쒆�̐���/��K���e / 382�`383
�E |
�X���A�u�V�E = The heavens 9(103) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219821
|
�ԎR�V���i����(������) / p483�`483 �iIRDB�j
�ԎR�V���i / ���{���m �R�{���C / p484�`521�iIRDB�j
��ԎR��Ƃ��Ӗ� / p521�`521 �iIRDB�j
�V���{�E��趕�АM / p522�`522
�{�N�\���̓V�� / �j�t�ʋ` / p523�`525 |
���s�V���{�� / p526�`527
�ԎR�V���i�����L�O�j�ꎟ�� / p528�`529
�ԎR���H�̕W���Ɉ��ސl�̖��̝ɁX / p529�`529
��������� / p530�`530
�E |
�X���A�u �Ȋw��� 13(3);9���F���y�V��j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@�@pid/10984534
|
�\�� ���U�쌴�����ނ��A�C���V���^�C����/�����E
�O�F�� ����/�����E / 386�`387
�n�[�t�g�[��/ / 385�`385,388�`388
�������̖ԏ_/ / 385�`385
噍��A���^���X���̕���/ / 388�`388
�ŐV�`�g�O�������A��/ / 389�`,469�`
���c�N�V���i�N���X���[���˖]����/ / 389�`
�q�A�f�X���Q�ƃw���N���X������/ / 390�`
���ՓV���i�߂���/ / 392�`
�W�����A�ɐV�݂̑�]����/ / 394�`
�A���h�����_���启�_�ƃz�����X�a��/ / 396�`
�͂̐S�f/ / 469�`
�l�Û{�����ɜ�p���ꂽ�q����/ / 470�`
�g���c�N����/ / 472�`
���{��̑�Î��J����/ / 474�`
���̃t�C����/ / 476�`
�F���y�V铂̕�/ / 398�`467
�ɓ��]�_ ���f���̔�����/���R�C�� / 398�`399
���_/�E���Y / 400�`403
�P���̉^���Ƌ�͌n�̉��z/�����C�F / 404�`406
���̐_�O���J���X�y�N�g��/�_�c�� / 407�`411
�n���埆�ɛ����鑾�z�����̉e��/�����畽 / 412�`413
�S�x�ܓx�̘b/����Ǖ� / 414�`417
�A�C���X�^�C���V�F���̔��S/����Ǖ� / 418�`420
�ؐ����ʐ�/�����v / 421�`425
�埆�Ȃ��r�����錎���E/�k���F���� / 426�`429
�W�[���X�̐V�F���V/�R�萳�� / 430�`432
�܌�����̊F�����H�V���̝��l/ / 433�`445
1�A�X�}�g���ɉ�������I�V���̌���/�R�{���C / 433�`438
2�A�n�҂ɉ�������I�V�����s�L/�@������j / 438�`445
���z���t�ː��̂��̌�̌���/萌���g / 446�`447
�̌����Ƃ����V���@/�j�t�ʋ` / 448�`452
�V��̋���X/��K���e / 453�`457 |
��̎�ނƉ��v/�����C�F / 458�`460
�|���l�V�A�����Ɛ�/��K���e / 461�`465
�{�\�V����/���؉p�� / 466�`467
���̌�/�c���� / 468�`468
�Ќ����]�ӂ܂�/���c�ꋞ�� / 477�`479
�[�ۂ̑���/�g�c�l�� / 480�`481
�ʔ������̐���/���c������ / 482�`484
�����J�[�X���m/���V���O�� / 485�`487
�����̕a��/���P�� / 488�`489
��S�N�O�̖�/�����g / 490�`491
���ƌ��/���엘�� / 492�`492
�є��Ɣ畆�̈�B/�������j / 493�`495
�����o�[�O�ւ̑���/�������� / 496�`498
�F�ʂƕ���/�������� / 498�`500
�F�̏o�雍��/���c�\�採 / 500�`502
峎p�S��/�咬���� / 502�`504
��ᢌ��̒[��/�H�R�t�� / 504�`507
������s�@�Ɩ�����s�@/�������� / 508�`510
�i�]�ב��̊��K/�����c / 511�`516
�Z�����g���c�R���N���[�g/�i�䏲���� / 538�`539
�ț{���� ���֔��/�V��~�Y / 557�`561
���ʍu��/ / 517�`523,533�`537
��p�S���{�u�b/�W�H�����Y / 517�`523
���{����/���c�lj� / 533�`537
���p�L��/ / 543�`556
�f�l���ʖ@/�ĎR�Y�O�� / 543�`547
�V铛����̎B���/�����v / 548�`553
�������[�^�[�̍���/�R�k������ / 554�`556
�ŐV�ț{�O���t/ / 525�`532
�ț{�j���[�X/ / 540�`542
�쒆�̐���/��K���e / 562�`
�ђ������/ / 564�`
�㌷�����̌�/ / �ڎ���`
|
�P�O���A�V��V�U���x�ߊw�Еҁu�x�ߊw = Sinology 5(3)�@p327�`433�@ �O�������[�v�Ɂu�������̌��� �v�\����B�@ pid/1564836
|
�������̌��� / p327�`433
��A���� / p328�`334
��A�������� / p334�`356 |
�O�A�x�ߏ��ɉ������@��ᢒB/p356�`365
�l�A���ނƘ�� / p365�`368
�܁A�N�㐄��̉\���������/p368�`397 |
�Z�A�t�H�Ȍ�Ǝv�͂�T���� / p398�`423
���A�t�H�ȑO�Ǝv�͂�T���� / p423�`430
���A�������ʊT�� / p430�`433 |
11���A�u�V�E = The heavens 10(105) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219824
|
�ԎR�V���i�̢�q�ߐ��٣ / p��㉛���
"1929�N"�𑗂�(�ɓ���) / p39�`40
��ᢎ���15�Z���`�ԓ��V / �ԎR�V���i �����v / p41�`47
�V�x���A�֗��������� / ��� �A�Ó��g / p48�`52
�{�N8��27���ɏo�������嗬�� / �I�� ��ꠍF���� / p53�`56
�{�N�\�̓V�� / p57�`59
�~�閟�k / ���� �ǖ�p�V�� / p60�`62 |
��m�点(�_�ˎx�����) / p62�`62
�V�������� �a�� / p63�`64
�V���{�͎��叟��(�싅�D�L��) / p64�`64
�ʐM�� �r�؏r�n����� / �r�؏r�n / p70�`72
�x���ʐM / �������� / p73�`73
�V�����D���`���L�� / p74�`74
���^��V����b�(31) / ���㒉�h / p121�`121 |
���A���̔N�A���s�鍑��w�ԎR�V����ҁu���s�鍑��w�ԎR�V����v���u���s�鍑��w�ԎR�V����v���犧�s�����B�@�@pid/1187658
|
�ԎR�V���i / 1
(��)�@���� / 1
(��)�@�ԎR�V���i�̌��� / 7
(�O)�@��ȓV���@�B / 16
(�l)�@���L���鏔�@�B�̔\�͂ƃv���O���� / 28
(��)�@�ԎR�V���i�̈ʒu / 35 |
(�Z)�@�ԎR���H / 35
(��)�@�V���i�̐l�� / 37 (
(��)�@�V���{�͎� / 37
�u�ԎR�v�Ƃ��Ӗ� / 38
�ԎR���H�̕W���Ɉ��ސl�̖��̝ɁX / 39
�E |
|
| 1930 |
���a5 |
58 |
�P���A�V��V�U���u�Ȋw��� 14(1);�V�N���S�jp 16�`20 �������V���Ёv�Ɂu���M�̍����ƂȂ��A�z�܍s���v�\����B�܂��A���쐴�F���u�����@p47�`51�v�Ɂu���̋g����萂�����M�v�\����B�@pid/10984538
�P���A ��K���e���u������� : �V�����M�v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/1178377
|
��\������z�� / 1
���鐯�̙B�� / 11
�݂��S���� / 25
��ɘV�l�����͂� / 32
�k�l�����̙B�� / 42
�u��v����T�� / 59 |
�B���Ƃ��Ӑ� / 84
���H�̐��̃��}���X / 90
��͍l� / 106
����Ɍ����鐯 / 117
���ɐe���ނɂ� / 131
�{�\�V���{ / 169 |
���̉��� / 182
�����\��������� / 194
���̖����E���̖��� / 207
��m�|���l�V���̐� / 219
���H�̙B�� / 236
�Ñ�}�����̗�� / 246 |
�R���A�u���b�g 3(3)�v���u���b�g�Ёv���犧�s�����B�@pid/1497609
|
��s�����Ɠd���T�ԁ\�\(�ɓ���) / p1�`1
�ț{�����ޖ����̓��� / �V��V�U / p2�`3 |
�{�M�ɉ�����ᢓd���H�H���ɏA�� / �_���M���� ; �V��ċg / p4�`11
������s�䏄�K���挈��\�\�����Ղ̉� / p35�`35 |
�X���A�u�Ȋw��� 15(3);9���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984543
|
�ɓ��]�_ �V���Ɛl��/�V��V�U / 374�`375
�_�O�I�}����̓�͉�����/�����C�F / 387�`392
�����V���i�̃A�C���X�^�C����/�@������j/401�`404
�S�V����̈ꓙ�������/��K���e / 405�`425
1�A�V���E�X/ / 406�`406
2�A�J�m�[�v�X/ / 407�`407
3�A�����[�K/ / 408�`408
4�A�P���^�E���X/ / 409�`409
5�A�J�y��/ / 410�`410 |
6�A�A���N�g�E���X/ / 411�`411
7�A���Q��/ / 412�`412
8�A�v���L�I��/ / 413�`413
9�A�A�P���i��/ / 414�`414
10�A�y�e���M�E�Y/ / 415�`415
11�A�A���^�C��/ / 416�`416
12�A�A���f�o����/ / 417�`417
13�A�\���ː�/ / 418�`418
14�A�A���^���X/ / 419�`419 |
15�A�|���c�N�X/ / 420�`420
16�A�X�s�[�J/ / 421�`421
17�A�t�I�}���n�E�g/ / 422�`422
18�A���O���X/ / 423�`423
19�A�f�l�u/ / 424�`424
�u�ț{�ҖK��v���s����`��
�@�@���V��V�U���m/ 426�`427
�E
�E |
�P�P���A�u�Ȋw��� 15(5);11���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984546
|
�u�����̃A�C���X�^�C���͎�/ / 757�`757
�ɓ��]�_ �V铂Ɖ䓙/萌���g / 774�`775
�ț{�E�ŋ߂̃j���[�X/ / 776�`790,796�`825,828�`833 |
��萂��錤���u�n�蒹�v�̍s��/�K�c���X / 776�`779
�\�ꌎ�̓V��/�_�c�� / 936�`937
�����ӏ�/��K���e / 938�`939 |
�����̔N�A�ѓ����v ���u�x�ߗ�@�N���l�v���u�����@�v���犧�s����B�@�@pid/1177084�@�@�d�v
|
���́@�x�ߌÑ��@�T�_ / 1
���́@�x�ߗ�@�̋N����萂���B�� / 21
��O�́@�����̗�@��萂���L�^ / 61
��@���� / 61
��@���X / 62
�O�@���S / 66
�l�@���S / 76
�܁@�ď��� / 81
�Z�@����� / 85
���@���� / 95
��l�́@�t�H�̋L���Ɋ܂܂ꂽ���@ / 97
��́@���B����̋L���Ɋ܂܂ꂽ���@ / 135
��@���� / 135
��@�ΐ� / 135
�O�@��U�~�� / 152
�l�@�O�� / 155
�܁@�[�@ / 155
�Z�@���H / 161
���@�C / 164
���@�b�q���n�Ƃ��邱�� / 170
��@�A�z�܍s / 172
��Z�́@�j�L�̗����Ɗ����̗����u / 177
�́@����əB�͂肽��×� / 193
�攪�́@�����̑g�D�ƉF�������_ / 209
���́@�Ñ�V���{�̐����N�� / 231
��@���� / 231
��@�~���y / 232
|
�O�@�k�� / 242
�l�@���\�Z�N�T���̗�@ / 244
�܁@�ؐ��I�N�@ / 254
�Z�@���� / 262
��\�́@���x�̋N���ɏA���� / 263
��@���_ / 263
��@���x�̋N����萂������ / 263
�O�@�܍s���̗R�� / 266
�l�@���x����̖ړI / 270
�܁@�\���̈Ӌ` / 274
�Z�@�\��x�̈Ӌ` / 295
���@���x�̈Ӌ`��萂���ِ��̔ᔻ / 322
���@�\��x�Ɠ��� / 334
��@�܍s�������̔N��Ɗ��x�̋N�� / 336
�\�@�u�������̔ᔻ / 339
��\��́@ꟓT�̒����ɏA���� / 355
��\��́@���B����̒���N�� / 361
��\�O�́@���B�����̓��N / 383
��\�l�́@�C���t�H�ɂ����@�̋L�� / 405
��\�́@���P���P�Ǝ����̔N�� / 411
��@���� / 411
��@���P���P��萂��鍪�{���� / 411
�O�@�E�Õ������̐��P���P / 412
�l�@���������u�̐��P���P / 415
�܁@����ɉ�����P����鮂̈Ӌ`�\���A��] / 418
�Z�@���������u�̋L�ڂɛ����鎩�Ȃ̌��� / 428
���@�C���Ș҂̏����̔ᔻ����\�i�ʍفA��
|
�@�@����x�߁A��[�C��] / 430
���@�C���Ș҂̏����̔ᔻ����\�`�m�G�c�n / 432
��@�C���Ș҂̏����̔ᔻ���O�\������ / 434
�\�@�V��V�U���m�̐��̔ᔻ / 442
�\��@���P���P�����Ӌ` / 444
�\��@���P���P��p�ЂċL���ꂽ�����̗�� / 444
�\�O�@�O�����萄�肵��������
�@�@���N��\���A����ɂ��鎑�� / 446
�\�l�@�O����Ȍ�ɉ��Đ��肳�ꂽ�����̔N�� / 453
�\�܁@�����̔N���萂���q�E�̙J�l / 458
��\�Z�́@�m�Z���M���N�n��Ət�H���� / 459
��@�m�Z���M���N�n��Ƃ͉����� / 459
��@�m�Z���M���N�n��̑g�D / 460
�O�@�m�Z���M���N�n��{�s����̗���̋L�^ / 476
�l�@�m�Z���M���N�n��̛��� / 486
�܁@�m�Z���M���N�n���P�_�� / 490
�Z�@�m�Z���M���N�n���P�_�� / 495
���@�t�H���� / 508
��\���́@�x�߂̌Ñ�ɉ�����H�ƍ�Ƃ̒q�� / 521
��@���S���S�t�H�Ɍ������H�̋L�� / 521
��@������ɉ�����H�̎Z�@ / 528
�O�@�����̓��H�L���Ɋ܂܂ꂽ�Z�@ / 535
�l�@���S�t�H�̓��H�L���Ɋ܂܂ꂽ�Z�@ / 546
�܁@�t�H�̗�@�\��Ɖ[ / 551
�Z�@��\���h�ƍ�Ƃ̋N���\���A�C�ɂ��� / 561
���@�x�߂ɉ�����H�ƍ�Ƃ̎Z�@�̋N�� / 578�E
��\���́@��\���h�̙B�� / 593 |
�����̔N�A�R�{�ꐴ���u�W���V���w�v���u�V�����D��v���犧�s����B�@�@pid/1225852
|
���́@�V�� / 1-21
���߁@�V�����W�Ƒ��̎�v�y / 1
���߁@���� / 5
��O�߁@�V����̏���̉^�s / 13
���́@�V铉^���̗��_ / 22-75
���߁@�Ñ�l�̓V铘_�\�V���� / 22
���߁@�n���� / 24
��O�߁@��V铂̉^���_ / 28
��l�߁@�O���v�f / 33
��ܐ߁@�O�V铂̉^���_ / 43
��Z�߁@���� / 47
�掵�߁@�V铂̎��z�ƌ`�� / 63
�攪�߁@���z�n�̍\���Ɛi�� / 69
��O�́@���ʓV���{ / 76-137
���߁@���������̉^�s�\?�����W / 76
���߁@���H�ƌ��I�y�ё��̗ގ����� / 80 |
��O�߁@��@��X / 88
��l�߁@���Ə͓� / 102
��ܐ߁@�A�x���V�I�� / 105
��Z�߁@���� / 108
�掵�߁@�ŗL�^�� / 117
�攪�߁@���̓V���ʒu�Ƒ��̖ژ^���тɐ��� / 120
���߁@�n���埆�Ɉ�������̋��� / 128
��\�߁@�n���̌`���Ƒ傫�� / 131
��l�́@�V铂̕����{ / 138-284
���߁@�V铕����{�̕��@ / 138
���߁@���z / 148
��O�߁@�V�����ʐ� / 167
��l�߁@�a���Ɨ������̑� / 189
��ܐ߁@�P���̕������ނƐF / 200
��Z�߁@�V铂̎����^�� / 211
�掵�߁@�d���ƘA�� / 214 |
�攪�߁@�̌��� / 232
���߁@���_�Ɛ��� / 270
��́@�V铉F���Ƒ��̐i�� / 285-316
���߁@�V铂��`�ɂƋ�ԕ��z / 285
���߁@�V铂̉^�� / 297
��O�߁@�V铂̐i���ƉF���̑g�D / 303
��Z�́@�V�������̕��@�Ɗ�B�ݔ� / 317-368
���߁@���n�I�̊Țd�Ȋ�B / 317
���߁@�]�����Ƒ��̎�� / 319
��O�߁@�Œ�@�\�q�ߐ��@ / 326
��l�߁@�^�z�@�\�ԓ��V / 330
��ܐ߁@������B�y�ѓV�����v / 336
��Z�߁@�V���i / 357
����
�E
�E |
���A���̔N�A��c�����u�Ύ����o�̌����v���u���m���Ɂv���犧�s����B�@ (���m���ɘ_�p
; ��12)�@pid/1078164
|
���́@���_
��@���� / 1
��@�����̍ޗ� / 2
�O�@�V���̐��x / 4
�l�@�ޗ��̐M���x / 14
�܁@���̏ƍ� / 16
���́@�Ύ���\���h���V��
��@�k�Ɉʒu�̎Z�o / 22
��@��\���h���V���N�� / 27
�O�@��\���h�ԓ��̜A�x�@
�@�@���J�����S�̏ꍇ�A�����
�@�@���ꍇ�i���Ɋs��h�̏ꍇ�j/33
|
�l�@�p�����̋L���y�ёv�_���V���u/43
�܁@�V����B / 53
�Z�@���܂��V���y�ы��ɓx�̍ċᖡ/62
���@��\���h�����l / 72
��O�́@�Ύ��������V��
��@�Ύ��������V�� / 78
��@�����̌�F / 85
�O�@���ɓx�\�x�̍� / 96
�l�@�L�q�̕s�[���Ȃ鐯���y��
�@�@�������͂ꂽ��V�ۍl�����̐�/99
�܁@���̔��j / 105
�Z�@���̐����̋ᖡ / 114 |
���@�����V���̔N�� / 119
���@���h�̓x / 123
��l�́@���\�̛��Ƌy�ѓ��h�x�Ę_
��@�Ø҂̐��\ / 125
��@�V�ۍl���Ɛ��C�l���Ƃ�
�@�@�����Ɓi���̈�j/130
�O�@�V�ۍl���Ɛ��C�l���Ƃ�
�@�@�����Ɓi���̓�j/137
�l�@���h�x�̍ċᖡ / 151
�܁@���h�x�̔N�̉� / 175
�E
�E |
|
| 1931 |
6 |
59 |
�S���A�u�V������ = The astronomical herald 24(4) �v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304131
|
���_�̔ޕ�(�l) / ���{���m �����Y�S / p61�`65
�ŕ���L�Ɍ������V�����V���ƎO�����T�̈��T / �����C�F / p65�`68
�E�H���t����C�G��(��) / G�S��r�[���X / p69�`72
�V铖]�����ɏA����(��) / M�A��G���X���C / p73�`75 |
趕� / ���� ; �c�� / p75�`78
�V�� / �����V���� �앍 / p79�`79
�V�� / ���� / p79�`80
�̌������V�� / p3�`6 |
�V���A萌���g���u�Ȋw 1(4)�@p143�`144�@��g���X�v�Ɂu���z�g���Ƒ��z���z �v�\����B�@
�@�@�܂��A ����\�g���u���� p160�v�Ɂu�j�̊J�Ԃɛ�����O�E�̉e���ɏA�āv�\����B�@pid/3217596
�W���A�ѓ����v���u���������u�� ��40�S�v���u����������v���犧�s����B�@pid/1147784�@�@�{���\�@�d�v
|
��@��@�Ɛ萯�p / 1
��@��@�̑n�n�҂�萂���B�� / 2
�O�@�Z��̌×�ƌ㊿�̎l���� / 3
�l�@�l����̍\���@ / 3
�܁@�O���̑�����Ǝl����Ƃ̔�r / 9
�Z�@�`�̊{�k�Z���l�� / 13
���@�`�ȑO�̗�@�\�����Ƒ��̐���N�� / 16
���@�ؐ��I�N�@ / 20
��@�ؐ��I�N�@�̎n�߂č��ꂽ�N�� / 25
|
��Z�@�\��C�A�\�A��\���h / 30
���@����̑g�D / 41
���@�萯�p�̌����Ƃ��ẲA�z�܍s / 45
��O�@�\���\��x�̖��� / 47
��l�@�b�Ђƍb�q / 53
��܁@�D������y�ё��̈Ȍ�ɉ�����A�z�܍s���̗��s / 56
��Z�@�l����Ȍ�̗�@ / 57
�ꎵ�@�x�߂̌×�Ɛ��m�̌×�Ƃ̔�r�\���������̌��� / 61
�E |
�P�Q���A�u�V�E = The heavens 12(129) �v���u�����V���w��v���犧�s�������B�@�@pid/3219848
|
�A�����J�`�� / ��c�t / p3�`22
������Y�ɂ��ԎR�̒��i��X/p23�`27
�V���� / �����v / p28�`29 |
1932�N�ꌎ�̓V�� / p30�`33
�V�����D���V�������� ���a�� ������/p34�`36
������̕� / p37�`38 |
���^"1932�N�̗���\"
�E
�E |
|
| 1932 |
7 |
60 |
�Q���X���A��㏀�V�����I���ւ̉����^�����A�����c�ɈÎE�����i�����c�����j�B
�S���A�����C�F���u�V������ = The astronomical herald 25(4) p64�`67�@���{�V���w��v�Ɂu�u�C�������鏉���v�ɂ��āv�\����B
�S���A�u�V�E = The heavens 12(133)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219852
|
������v�ۓV���N���u��25�W���ːԓ��V / p(��㉛���)
�{�E�̍���(�ɓ���) / p163�`163
�ܓx�V������ / �ܓx�V������ ���{���m �ؑ��� / p164�`170
�ʑ��u����V���{ABC�(4) / ���{���m �R�{���C / p171�`174
�V���d��̘b(4) / ���{���m ��c�t / p175�`179
�����Ռ�����r / ����痢 / p179�`179
�ԎR�V���i�̌��{�H�� / �ԎR�V���i �����v / p180�`185
�V���ꢈ�s�熓T(�C�����E���܂�) / XY���e / p186�`187 |
�V���V�m��(6��) / p188�`189
���s�V���{���X�����T / p190�`191
�V�����D���V���������������z / p192�`196
�V���� / �ԎR�V���i �����v / p197�`197
�{�N�܌��̓V�� / p198�`201
�q�~�ʐM / p202�`202
��� / p203�`203
�E |
���A���̔N�A�u�̈�㏀�V�����Ǔ��^�v���u����w�Z������v���犧�s�����B�@pid/1100313
|
���ÔV���N���I���𓉂ށ@�c������ / 7
���O�U����ǜ傷�@���J�R / 17
�Ǔ����������L
�@�@���i���a���N�O����\�Z�������ꋴ�{�m���فj
����@�����i�Y�搶 / 20
����@�V��V�U�N / 22
���O�@�y��ыg�N / 24
���l�@���{�d�ЌN / 26 |
���܁@�����U�N / 28
���Z�@�|�������Y�N / 30
�����@�Z�ʏG�Y�N / 31
�����@�������O�Y�N / 32
����@����沑��Y�N / 38
����Z�@�i�āj�y��ыg�N / 39
�����@�}�������N / 40
�����@�ؑ��ގ��N / 42 |
����O�@���c�m�{�N / 44
����l�@�H�R�����N / 46
����܁@�����[���N / 48
����Z�@���G��N / 50
���ꎵ�@�ԉ��q�v�N / 51
�lj�����@�]�����Y�N / 57
�lj�����@���n�M���N / 58
�E |
���A���̔N�A�_�c�Ε��u�N��Ώƕ֗����A�z��Ώƕ\�v���u�Í����@�v���犧�s�����B�@�@pid/1159683
|
�}�� / 1
�N�㛔�ƕ\ / 1�`168
�����E�X���iJ�DD�D�j�����߂�\
�@�@���i���I�\�U�O�P�N�ȑO�j / 2�`3
�A�z��ƕ\�i���I�T�O�P�\�P�X�O�O�N�j/51�`161
��������̃����E�X���iJ�DD�D�j |
�@���i���I�P�X�O�P�\�P�X�T�O�N�j/163�`165
�N�j�����i�{�M�̕��j / 169
�N�j�����i���N�̕��j / 173
�N�j�����i�x�߂̕��j / 176
��]�\ / 183
���̏��ɂƎ��� / 190 |
��� / 191
�A�z��ƕ\ / 191
�����E�X���iJ�DD�D�j / 194
�����E�X��ƃO���S���I��/195
��]�\ / 196
���̏��ɂƎ��� / 197
|
���A���̔N�A��؎l�Y���u�_�ЂƋ��y���� : �_�Њw�K�ĂƐ_�Вn���w�v���u��ʎЁv���犧�s����B�@�@pid/1076360
|
���ҁ@�_�Ћ���Ƌ��y���� / 1
�_�Ђ̋��y����I�Ӌ`�i�����j / 3
�_�ЂȂ����y���� / 10
�_�Л{�̌��ݎ� / 12
�_�Ћ���{�̌��ݎ� / 14
�_�Ќ����̑��� / 15
�_�Вn���Ƌ��y���� / 17
�_�Ќ����̎菇�ƕ��@ / 19
�_�Ћ���ƐN�^�� / 27
���{���_�Ȃ����y�ț{ / 34
���ҁ@�_�Л{�K�w���ā@�菇�ƕ��@/39
���� / 41
�����ҊT�� / 43
�q���N / 43
�q���N / 44
�q��O�N / 45
�q��l�N / 47
�q��ܔN / 49
�q��Z�N / 51
�s�s�ҊT�� / 53
�q���N / 53
�q���N / 54
�q��O�N / 56
�q��l�N / 58
�q��ܔN / 60
�q��Z�N / 63
�e���_�Л{�K�w���� / 65
�q���N�E�e���_�Л{�K�w���� / 67
�l���@�₵�� / 67
�܌��@���X / 68
�Z���@���P�̍s�� / 69
�����@�N��̐X / 70
�����@�R�Ɛ_�ЁE�C�Ɛ_�� / 72
�㌎�@�H�G�c�ˍ� / 73
�\���@�_���Ղ̐��_ / 74
�\�ꌎ�@�����߂ƐV���� / 75
�\�@�_�傳�� / 76
�ꌎ�@���܂��� / 78
�@�F�N�Ղ̈Ӌ` / 79
�O���@�t�G�c�ˍ� / 81
�q��l�N�E�e���_�Л{�K�w���� / 85 |
�l���@���y�Ɛ_�� / 87
�܌��@�����_�� / 88
�Z���@���ƂƐ_�� / 90
�����@�A���n�Ɛ_�� / 92
�����@�q�C�Ɛ_�� / 93
�㌎�@��S�\���Ɛ_�� / 95
�\���@���K / 98
�\�ꌎ�@���_�ƎY�y�_ / 101
�\�@�s�Ɛ_�� / 103
�ꌎ�@�_�ЂƐ��� / 105
�@���ߍ� / 108
�O���@�� / 110
�q��Z�N�E�e���_�Л{�K�w����/113
�l���@�_�Ђƒn�撲�� / 115
�܌��@���Ɛ_�� / 118
�Z���@���P�̐��_ / 121
�����@��ΐ_�� / 126
�����@�C�Ɛ_�� / 129
�㌎�@�_�ЂƐN�� / 132
�\���@�_�ЂƋ��y�j / 135
�\�ꌎ�@�_�ЂƋ��y�Y�p / 142
�\�@�_�Ђƌ�� / 149
�ꌎ�@�_�А��x�̘b / 151
�@�_�Ћ���Ƌ��y���� / 153
�O���@�䂪�������Ɛ_�� / 158
�`�� / 160
��O�ҁ@�_�Вn���{���� / 163
�͂����� / 165
�C�Ɛ_�� / 171
���Ɛ_�� / 171
���Ɛ_�� / 182
�q�C�Ɛ_�� / 187
���Ɛ_�� / 188
�����Ɛ_�� / 190
�R�Ɛ_�� / 193
�R�ԂƐ_�� / 193
�ΎR�Ɛ_�� / 197
�ΎR�O�֎R�Ƌ�`�_�� / 198
����Ɛ_�� / 200
�i�R�Ɛ_�� / 203
���Ɛ_�� / 204
|
�ΐ��Ɛ_�� / 205
��Ɛ_�� / 210
���� / 210
������Ɛ����_�� / 211
殗��Ɛ_�� / 212
���Ɛ_�� / 215
�썇�Ɛ_�� / 217
��������� / 220
��̎����Ɛ_�� / 222
����Ɛ_�� / 224
�p���Ɛ_�Ђ̒n���I�l�@/227
�n�����Ɛ_�� / 227
�_�ЂƓs�s / 239
����Ɛ_�Ђ̒n���I�l�@/243
�͂����� / 243
���쑺���Ɣ_�Ɛ_ / 244
�ߑ�s�s�Ɣ_�Ɛ_ / 246
��a����Ɨ��c�_�� / 248
�ނ��� / 250
�Y�ƂƐ_�Ђ̒n���I�l�@ / 251
�͂����� / 251
���D�H�ƒn��ɉ�����_��/253
�i�R�n��ɉ�����_��/258
�ނ��� / 266
�����Ɛ_�Ђ̒n���I�l�@/ 266
�ɐ��_�{�̐����n���I�l�@/ 267
�V�̓y�E�A���n�Ɛ_�� / 273
�Ҍ�ɗՂ݂� / 276
�k���^�l
���V�䑺�n�撲�� / 281
���ƒn�撲�� / 281
�n�撲���̈Ӌ` / 282
���V�䑺�̒n���I�ʒu / 287
�����Ɨp���Ƃ�萌W / 288
���V�䑺�ɉ�����_�Ђ̕��z/294
�_�Ђ��@���Ȃ�
�@�@���e����{���ɋy���Ă��邩/296
�ނ��� / 303
�X�|�[�c�Ɛ_�Ђ̋���I�Ӌ`/307
�u�����v / 320
�E |
|
| 1933 |
8 |
61 |
�R���A���X�ؕF��Y���u�h������ 2-3 p.14-21�@�����@�v�Ɂu���n�I�M�̌`�Ԃƕ��z�v�\����B�@ �iIRDB�j
�S���A���X�ؕF��Y���u�h������ 2-4(���N���S��) p.140-147�@�����@�v�Ɂu���n�I�M�̌`�Ԃƕ��z 2�v�\����B�@ �iIRDB�j
�W���A�V��V�U ���u��Ǝq 14(8)�@p18�`21���{��������v�Ɂu���߂̑����ɂ����v�\����B�@�@�@pid/1552701
�P�O���A�V��V�U���������L�O����u���� (11)�@p1�`25�@�������L�O��v�Ɂu�Y�� �A�z�܍s���ƌ���̉ț{�v�\����B�@pid/7956976
�P�P���A�����l�Êw��ҁu�����{���n�_�Ɓv���u�����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@pid/1213272�@�@�@�d�v
|
��ꕔ�@�_�l��
�\���������ƌ��n�_�Ɩ�� �X�{�Z�� / 1
��n����ւƔ_�� �X�{�Z�� / 19
���{�V�Ί펞��ƒ{�Ƃ��Ă̔n�����ɏA���� ���ǐM�v/36
��������`�̌��n�_�ƓI�v�f ���X�Ĉ� / 43
���n�_�ƂɏA���� �ۖΕ��d / 48
�k�n��萂��鑖��
���˂̑Ő��Ε� �q���C�Z / 61
���ɂ��̑�`�i�ɂ���
�Ăя��̊��ɏA���� �_�p��� / 82
�_�v���֓y��l ���열�Y / 101
������������y��̍l�@
�E |
��@��
�}����G�����o������ ���R������ / 113
���}�O�|��ᢌ�������
�}�Oᢌ��̖����Ί� �X�{�Z�� / 116
����ᢌ��̖�������y�� ���V��v / 118
�O�͚�ᢌ��̖�������\�����y�� �X�{�Z�� / 120
�M�Z���厛�̖�����L����y��� ���X�Ĉ� / 121
�b�㚠ᢌ��̖�������\�����y��� �m�ȋ`�j / 122
���̂��Ƃ����O�̜\�����y��ɂ��� ��؏� / 123
�֏�ᢌ��̖��v�����̓y���i�Ƒ���� ����`�� �X�{�Z��/125
���O���`���L�˂̖�����L����y�� / 128
���ނ��o�����G�� �[�V���s / 131
�V�����̒lj� �X�{�Z�� / 133 |
�@�@�@���F�k�u�l�Êw ���{���n�_�Ɓv pid/3548063�l�ł́A�^�C�g���Ɂu�l�Êw�v���t������Ă������������@�m�F�v�@�Q�O�Q�Q�E�X�E�P�V�@�ۍ�
���A���̔N�A���R�������u��@�y���@ �v���u�P���Ёv���犧�s����B 1933/pid/1237073
|
��@���z�� / 9
��@���A�� / 20
�O�@�x�����ƃM���V���� / 47
�l�@�t�����X���a�� / 58
�܁@���@���LjĂ̕��ދy�ѕ]�_ / 66 |
�Z�@�T�ɂ��� / 110
���@���{�ɍs�͂ꂽ�鎞���@ / 122
���@���Ǝ� / 155
��@��p���̉��ǂɏA�� / 160
�\�@�Ď��@�̌��� / 180 |
�\��@��\�l���ʎZ�@ / 184
���^
��@���ɖ@�̉� / 191
��@�ڊі@��ۑ����� / 195
�O�@�x�ʍt�Ɨ�̉��� / 202 |
|
| 1934 |
9 |
62 |
�Q���A�V��V�U���u�V�E = The heavens 14(155)p167�`168�@�����V���w��v�Ɂu�^�F���s�k�v�\����B�@pid/3219876
�@�@�܂��A���R ����痢���u���� p169�`172�v�Ɂu��̐����v�\����B
�R���A�u�Ȋw�ƌ|�p 2(3)�v���u�������v���犧�s�����B�@pid/1469726
|
���p�̓� / ����ꐭ / p4�`7
���p�ɉ������ / ���n�F�l�� / p58�`60
�C�̘b / �V��V�U / p67�`69 |
���{�̏o�҂�桁\(���b) / ����R��q / p74�`74
�ߕ��Ǝ� / �v�����v / p75�`76
�q�����r |
�R���A���쐴�F���u �V������ = The astronomical herald 27(3) p41�`47���{�V���w��v�Ɂu�J�ƓV���V�̒����v�\����B�@�@pid/3304166
�X���A�u�V������ = The astronomical herald 27(9)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304172
|
���B�̗�Z�{�ҏ��o���\���搶��
�@�@�����̎g�p�V���V / ���c�C�n / p161�`168
㔎x�ߐ����nj�(��) / �����C�F / p168�`172
�]�������ɓV铛�����萂��鎄��
�@�@��(�� /�ˏ�ۏ�/p172�`176
趕� / p176�`177 |
�G���P�a���\�O���j�a�̐V���˖]�����\�������ۂ̊e�n����ɂ��ā\
�@�@���V���Љ�\�Z���ɉ����鑾�z�K�y�T���\�����̏C���l/p176�`177
�V��--���z�̃E�H���t�K�y�� / p178�`179
�㌎�̓V�� �����Q �̌��� ����(�O��)�Ō�����
�@�@�����̉��� �f������� ���� / p179�`180
�E |
�P�P���A���쏑�X�ҁu���j�ƒn�� 34(4/5)�v�����s�����B�@�@pid/3567021
|
�Ñ�ɉ����铌����ʂ̖���萂��V����@��
�@�@�����ʂ�茩����l�@ / �V��V�U / p1�`14
��k��������蓂���Ɏ��镶�{�j�̈�� / ���蕶�v / p15�`25
���{���I�ÌP��� / �_�c����� / p26�`39
�����ɏA�� / �{��s�� / p40�`59
���k�n���ɉ�������n�����i�W�̈�l�@�\�\�Γ�N��
�@�@�������p�S / ��c��g / p60�`77
����郙B�l / ����貕� / p78�`136
����@���̓��F / �L���� / p137�`153
���l�A��\�̓��{�n�� / ���c���t / p154�`169
�ؕ����� / �ߔg���� / p170�`199
�囏�߂̕�K�� / ������V�O / p200�`211 |
�X�E�C�X���M�̐����Ƒ��̌��� / ������ / p212�`227
�������Â̕����j�I�l�@ / �C����Y / p228�`242
���g�v�c�鐹�|�v / �H�c�� / p243�`249
�z���V��P�u�����Ɩk�C���J��� / �q��M�V�� / p250�`291
�x�͈ɒB���� / �������� / p292�`342
�Ǔ��L�@�����Γ씎�m������ / ����� / p343�`344
�Ǔ��L�@�������m�̎v�o / �V���o / p345�`348
�Ǔ��L�@���m�R䵂̉��e / �q��M�V�� / p349�`351
�Ǔ��L�@�����搶�̒lj� / ���Ȓq� / p351�`353
�V���Љ� / p354�`358
�V�c�ƚ��j�̐i�W / ���� / p354�`356
���]���S�Z�j�̌��� / ���� / p356�`358 |
���A���̔N�A�����U����ҁu���֍u�� ��2���@�����ُo�ŕ��v�Ɂu���M ���s�隠��{�`�� ���{���m �V��V�U�� �v�\����B�@�@pid/1225963
�����̔N�A�����⎟���u�c�V�_�v���u�����������_�ъw�Z�������u��v���犧�s����B�@pid/1234720
|
�͂�����
���́@���_
���߁@�_�ЂƑ��_ / 1
���߁@�_���Ɉ��߂�_�Ђ̍ՓT�ƍs�� / 2
��ꍀ�@�F�N�� / 2
��@����� / 3
��O���@�c�A�� / 3
��l���@�U�n�� / 4
��܍��@�_�R�� / 4
��Z���@�V�R�� / 5
���́@�c�V�_
���߁@�c�V�_�̎��` / 5
��ꍀ�@�_�_(��) / 5
��@�_�_(��) / 7
���߁@�c�V�_ / 8
��ꍀ�@�c�V�_��萂��鐬�`�����̍l� / 8
��@�ɐ��_�{ / 12
��O���@�j�א_�� / 14
��O�́@�c�V�_��
���߁@�c�V�_���̋N��(����) / 17
��ꍀ�@�c�� / 17
��@�_�Ђɉ�����c���̕�d / 18
���@�ɐ��_�{ / 18
���@�����ЏZ�g�_�� / 19
��O�@�����Џo�_��m / 21 |
��l�@�������j�א_�� / 21
��܁@�����Ѝ���_�{ / 21
��Z�@�����Ў����_�{ / 21
���߁@�c�V�_���̋N��(����) / 22
��ꍀ�@�c�قƓc�ٖ@�t / 22
��@�\�ق̐_�� / 24
��O���@�c���c�ق�萂��鐬�`�����̋L�� / 25
��O�߁@�F���˂ɉ�����c�V�_���̑n�n / 31
��ꍀ�@�F���˂ɉ�����h�_�v�� / 31
��@�c�V�_���n�n�l�@ / 34
��l�߁@�c�V�_���̕�d�����T�ꍇ / 37(
��ܐ߁@�c�V�_���̞鎮 / 38
��Z�߁@�c�V�_���̘_�c / 40
�掵�߁@���Z�������_�ѝ��Z���s�V�R�ՍՓT / 42
��ꍀ�@�O�� / 42
��@�V�R�ՍՓT���敍�J�Z�L�O�� / 42
��O���@�ՓT���a�i�� / 44
��l�́@�c�V�_�̑�
���߁@�c�V�_���̎�ނƌ`�� / 46
���߁@�c�V�_���̌����Ƒ����� / 48
��O�߁@�c�V�_�������̔N�� / 50
��l�߁@�c�V�_�Ձ\�c�V�_�u / 52
��ܐ߁@�c�V�_�Α���萂���B?�Ɗ�K / 57
��́@�p�F���˒n���̌�c�A��
���߁@�����Ж����_�{ / 60 |
���߁@�����Ў��Z���_�{ / 62
��O�߁@���𒆎АV�c�_�� / 65
��l�߁@�������Жq���_�� / 65
��ܐ߁@�����Ћ{��_�{�ʋ{�Ö�_�� / 66
��ꍀ�@�c��c�� / 66
��@��c�A�� / 68
��Z�߁@���Z�������_�ћ{�Z���s��c�A�� / 68
��ꍀ�@���T�L�O�����c�̐ݒu / 69
��@��c�A�Վ��T / 69
��O���@�����̉ӏ� / 70
��Z�́@���̒n���ɉ������c�A��
���߁@�����ЉF���_�{ / 72
���߁@�����Ј��h�_�� / 74
��l�߁@�������j�א_�� / 76
��ܐ߁@�����Џt���_�� / 77
��Z�߁@�����Б���_�� / 77
�掵�߁@�����Ѝ���_�� / 77
�攪�߁@�����Ў����_�� / 79
���^
�������n�\ / 80
�ҍl���� / 82
������ / 83
�c�V�_��L / 86
�E
�E |
|
| 1935 |
���a10 |
63 |
�P���A�u�Ȋw��� 24(1);�V�N�j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@pid/10984599
|
�{�������S ���M�̉ț{�I����/ / 35�`64,72�`76
1�E���T�m⬂�萂�����M/�V��V�U / 35�`37
2�E�Ƒ��Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂�/�ݓc���o�� / 38�`40
3�E���x�Ƌ㐯�̖��M/�����C�F / 41�`48
4�E���M��ւ�ꀋ�/�ޗǖ�_ / 49�`52
5�E�葊�̉ț{�I���^/�{���Ǖ� / 53�`57
|
6�E�j���̑����Ɩ��M/���c�`���� / 58�`59
7�E���K���̖͂��M/����r�Y / 60�`64
8�E�ߕ��ƐF�ʂ̎��͓I�Ӌ`/�������� / 72�`74
9�E�F�ʂɌ��ꂽ��X��/��_�N���� / 74�`76
�o�r�����o�y�̐萯�V����/��K���e / 128�`132
�E |
�U���A�u���R. (1)�v���u��C���R�Ȋw�������v����n�������B�@�@pid/1564690�@�@�d�v
|
�\���莚 / �D�v / �\��
����
ᢙ���� / �V��V�U / p1�`1
��r�Ɏ� / �V��V�U / p2�`4
�x�ߔ_���̕��� / ��������� / p5�`8
�����ۂ̟��]�l / �����̖� / p9�`12
�ϓ֒����Y�p���W���V�L / p13�`27
�����ƒ��ח،ꏴ / �ؑ������� / p28�`30
������̗d�� / KOMIYA�EY / p31�`32
���i��� / �쑺���� / p33�`33
�Z�� / p34�`38
�R���W�@�̎v�o / �������O / p39�`45
|
���J�s / �~�c�� / p46�`49
�p����V�\�\�o�� / ������v / p50�`52
������ / ���c�ƕ� / p53�`61
�����搶��z�� / �������G / p62�`64
���H�V����m�s / �����G�Y / p65�`71
�p�i�}�^�͂��j���[���[�N�� / �Lj퐶 / p72�`76
�����u��⽌����v / �ؑ��N�� / p77�`81
�f�`�ɏA�Ă̊��z��O / �͍��l�� / p82�`83
���� / p84�`93
��̎���\�\���� / ����C / p94�`100
�N���u�� / p101�`111
�ҏS��L / p112�`112 |
�X���A�����C�F���u�Ȋw��� 24(9);9���j p 88�`91�������V���Ёv�Ɂu�u�\�O���c�v�̐V���ׁv�\����B �܂��A�{�c�������u�����@p68�`69�v�Ɂu萓���k�Ђ̉�ځv�\����B�@pid/10984607
�X���A�u�l�Êw 6(9) �v���u�����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@ pid/3548084
|
�������g�Ɠ����Ƃ�萌W�ɂ���/���R������/p400�`411
�l����j�y��_ / ���R��Ēj / p412�`417
��`��`�y��ɏA�� / �����N�� / p381�`383
�}����Ȗk�ɉ�����㊕������/���c���u/p418�`425
|
�}�O����̜\�����y��/�O�F������/p384�`386
���Μ\������ւ̊L�� / ���эs�Y / p426�`426
���w���W����_���̔��p / ���ƕv / p390�`394
���V�����̂��� / ���X�Ĉ� / p387�`389
|
�ˉ��Õ�ᢌ@�̎v�o/�c�����q/p394�`396
�V�� / �X�{ ; ���i / p397�`399
ᢌ@ᢌ� / p389�`389,399�`399
�ҏS�҂�� / �\�����`�\���� |
���A���̔N�A�u����⑾���m����j��L�O���v���u����⑾���m����j��L�O��v���犧�s�����B�@pid/1123835
|
���V�⑾���m���j��L�O�����S�� / 1
���V�⑾���m���j��L�O���̊T�� / 5
���s�ɉ�����L�O�W�T�� / 5
���s�ɉ�����j�ꉃ�� / 11
ᢋN�l�`��@����F�ꎁ�̈��A / 12
�V��V�U���̏j� / 13
ᢋN�l�`��@����Ջg���̈��A / 38
���s�����H�Y�{�Z���Ɛ��`��@
�@�@�����c���M���̏j� / 56
�q�����܂ŗ��������Ӂr
���V�⑾���m�B / 61
���� / 61
���́@���N���� / 63
�c���̏A�{�A�����V�{ / 63
���́@�C�{����@�������Ζ� / 66
��Z�A�J���{�Z�A������{�ݛ{���ɑ���/66
������{������ / 67 |
��O�́@�C�O���{���� / 69
�Ո헯�{�A�d�� / 69
��l�́@�H�ȑ�{�������� / 71
��́@���s�隠��{
�@�@�����H�ȑ�{������/75
���s�隠��{�̑n�� / 75
��Z�́@���s�����H�Y�{�Z������/78
���s�����H�Y�{�Z�̑n�� / 78
�掵�́@���ނ̌� / 81
�攪�́@萌W���Ƌy�ю / 83
萌W���� / 83
�䗿�lj��q���_������ / 84
���{�q�������������� / 84
�����_�ޗ��r������ / 85
�����W���� / 85
�H��{�Z�i�H�{�@�j / 86
���s�����펎鄏� / 87
|
���{�H�ƒ����� / 87
�隠���p�@�W�T���i��W�j / 88
�_�����ȓW�T���i�_�W�j / 89
�V�����A�������A���ى��A���K���A
�@�@�����a�H�Y���� / 90
���Ɏq�������� / 92
� / 93
������p�H�ƈ����h��i�̐���/94
���́@熗ߏ��W / 97
�{���y�ь��� / 97
���T���A�W�T���y�ы��i�� / 99
�ĈʁA�ę��A�J�� / 101
���^
���V�⑾���m�җ�y�ьËH�j���/1
���V�⑾���m�N�� / 1
�E
�E
|
���A���̔N�A���c���j�ҁu���{�����w�����v���u��g���X�v���犧�s�����B�@pid/1259451
|
�̏W���ƍ̏W�Z�\ ���c���j / 1
�n���ɋ��Ď��݂����������̕��@ �܌��M�v/23
�A�C�k�����̖K�k ���c�ꋞ�� / 45
�쓇�j��s���̏W�k �ɔg���Q / 85
���ԐM�̘b ���Y���� / 117 |
�C�̙����ɂ��� �N�c���� / 145
�̘b�̍̏W 萌h�� / 171
�������Ղ̘b ��Ԓm�ĎO / 197
�������������y�l �㓡���P / 233
���������̊��s ���Y�חY / 259
|
���Ղ̘b �ŏ�F�h / 281
�����{�Ɛl���n���{�Ƃ̋� ���X�ؕF����/309
�՚ҙ_���ɉ����閯���{�I���� �����Y/327
�ŗ����ɉ����閯���{�I���� ���{�M�A/373
���{�����{�u�K�����k��L�^ / 397 |
�X���A��c��g���u���_�����v���u���{�w�p���y��v���犧�s����B 1935/pid/1452499
�{���\
|
�u���_�����v���� / 1
���_���v�T�� / 7
�F��_�l / 28
�u�q�j���v�Ə����ăE�K�m�~�^�}��椂ގ��̍l/47
���K�Γ_���J�̗R�� / 54
�����_�̐��� / 66
�ΎO���l / 84 |
�ΎO���_���l / 139
���K�_���̝̑J / 150
���K�_�l / 180
������V���l / 201
燍˓V���l / 214
���R��ƚ�V�l�l / 235
���_�Ƃ��Ă̕z�ܘa���@�����R�E��/242 |
�g�˓V���l / 256
���_�Ƃ��Ă��́X / 261
�������_�l / 265
䶋g��V�ƕ��喾�_ / 289
���c�_�Ə����ăT�C�̐_��椂ގ��̍l/296
�E
�E |
�@�@���e�F�吳�X�N�P�����s�@�u�����Ɨ��j�@��R����P�j�@���_�����j�v�@�P���P�T�����s�@�u�����Ɨ��j�@��R����Q�j�@�����_�����j�v�@
���A���̔N�A����g�Ɨ�،h�M���u�V���w�ʘ_�v���u�n�l���فv���犧�s����B�@pid/1212645
|
���́@�V���{��ᢒB / 1
���́@�V�� / 45
��O�́@�V铂̍��W / 62
��l�́@���W�̕ / 77
��́@�� / 94
��Z�́@�� / 106
�掵�́@�f���^���_ / 117
�攪�́@�V铂̋����y�ё傫�� / 147
|
���́@�n�� / 160
��\�́@�� / 179
��\��́@���z / 203
��\��́@���f�� / 229
��\�O�́@�O�f�� / 246
��\�l�́@�a���Ɨ��� / 263
��\�́@���� / 276
��\�Z�́@�����̉^�� / 290
|
��\���́@�̌��� / 299
��\���́@��d�� / 312
��\��́@���_�Ɛ��� / 322
���\�́@�����̈ꐶ / 343
���\��́@�F���̍\�� / 357
���^ / 377
�L������ / 1-15
�l������ / 1-10 |
�����̔N�A��{���ꂪ�u���_�Ǝ��q�v���u�ܐF�����[�v���犧�s����B�@�@pid/3436710
|
�ɐ��_�{�䛍��
�o�_��Ќ䛍��
���E�̍��V���i�{��j
�r�ؒ�v�t���莚
����P���搶�莚
���ҁ@���q�ׂ̕����̐_�� / 1
���́@���_�Ǝ��q�Ƃ�萌W / 1
���́@���Ƃ̗����ƍ��J�̓� / 7
��O�́@�_�����{ / 17
��l�́@������ΕK���_�Ќ��͂���{ / 33
�F���V�c�����e
��́@�Ր���v�Ƃ��ӎ� / 46
��Z�́@���F��{ / 51
�掵�́@���J�̎�� / 58
�攪�́@���_�Ɛl�ސ��������� / 64
���́@�_���ƚ��h�̊��� / 82
�����_�Ќ䛍��
��\�́@�F��ɛ�����_�� / 100
��\��́@�ɐ��_�{�喃�i���D�j�`��ɏA���� / 116
|
��\��́@�o�_��_�ƎY�y�_�Ƃ̌�萌W���Ɍ�S / 129
��\�O�́@�C���Ȃ鎁�q�Ƃ��Ă̐S�� / 141
�i��j�@�_�I���J����ɏA���� / 141
�i��j�@�_�`�̐S�� / 142
�i�O�j�@�_�`���� / 144
�i�l�j�@�_�O���䉓�����ׂ��� / 145
�i�܁j�@����Λ�̎d���ɏA���� / 147
��\�l�́@��Ȃ��c�J�� / 149
��\�́@������������ǂ� / 161
�i��j�@�ҋ{�ƕ����V�R / 161
�i��j�@�Ղ�̘��p�ɏA���� / 163
�i�O�j�@���M�Ȃ����X�̂������戵�ЂɏA���� / 164
�i�l�j�@�_�O�����ɏA���� / 166
�i�܁j�@�V�_�n�_�̌P�` / 170
�i�Z�j�@���_�ƎY�y�_�Ƃ̍����ɏA���� / 171
���R�y��搶�މr��铂̉�
���ҁ@�`�����ׂ�������ՓT�̗R�� / 177
���� / 177
���@���� / 178
|
���@�l���` / 180
��O�@���n�� / 181
��l�@�F�N�� / 183
��܁@�I���� / 187
��Z�@�t�H��G�̍c�ˍՕ��ɐ_�a�� / 189
�掵�@�_���V�c�� / 193
�攪�@�ЉċG�H�̐_�ߍ� / 195
���@�V���� / 197
��\�@���P�̐_�� / 200
��\��@�_���� / 205
��\��@�����ߍ� / 208
�����_�{�䛍��
��\�O�@�V���� / 211
��\�l�@�吳�V�c�� / 216
��\�܁@���ߍՐ_��җ� / 218
��O�ҁ@��_�������ˍ��̉�� / 221
���^
���@�_�{���Ɋ������Ј��T�\ / 1
���@�\��������`�� |
|
| 1936 |
11 |
64 |
�P���Q�Q���A�X�{�Z���i�낭���j�����q�Ɋy���̉����Ō��j�ɂ��S���Ȃ�B�@�i�R�Q�j
�P���A�u���R (2)�@p2�`4�@��C���R�Ȋw�������v�Ɂu�N��C���V�u��椂ށv�\����B�@pid/1564691
�Q���A�V��V�U���u�w�l�V�F 30(2)�@ p70�`73�@�w�l�V�F�� �v�Ɂu���M�Ŕj �v�\����B�@�@pid/3562612
|
���M�ɂ��Ă̍��k�� / �v�z������ ; �������� ; �����G�� ; �����ĕ� ; �|�����j ;
�@�@�@���яt�Y ; �щ̎q ; �R��e�� ; �H�m�g�� ; �H�m���Ǝq / p54�`69 |
���M�Ŕj / �V��V�U / p70�`73
�q�����r |
�R���A�����C�F���u�y���j�k (54) p14�`25�y���j�k��v�Ɂu�J�ƓV���V�̒����v�\����B�@pid/7913030
�S���A�V��V�U���u�������� 25(4) p36�`39,5�`5�@��������Ёv�Ɂu���O�ٕ�--��Ɩ��M �v�\����B�@pid/6080298
�V���A�V��V�U���u���R (3) p2�`7�@��C���R�Ȋw�������v�Ɂu�h�B�V�����v�\����B�@pid/1564692
�X���A�ؑ��Ă��u���{�������琔�w��G�� 18(5)�@ p297�`312�@���{�������琔�w��v�Ɂu�ܓx�m�̉��j�A�e (On the variation of latitude) �v�\����B�@pid/1518024
�P�O���A�u�Ȋw�y��. 1(1)�v���u�ț{�y���N���u,�O�ȓ��v����n�����s�����B�@ pid/11185131
|
�ț{�y���E�n���j�E�ڎ�
�ț{�҂ƃy��/�Ό��� / 2�`
�ț{�ɉ����隠�ۋ���/F�E�X���[�J�[/7�`
笕M/ / 50�`
�q���b/���V�B�g / 50�`
���O�Ɖ�U/�X��� / 55�`
�I/�ΐ�G�} / 98�`
�◬�ɋ���/���v���C�� / 58�`
�Ո�̎��R�ț{�҂��Ύ҂̘�/���쐭�C/17�`
���ۃy���N���u���j/�y�c�K / 50�`
�{�p�j�̝Ж�/�K�����Y / 10�`
��������E�ۂ�/�����q / 71�`
���{�l�����̈����/���� / 79�`
�c���و��k���m��Łi���k���j/�c���و��k ;
�@�@���Ό��� ; ���c�\��Y ; �����d�� ; �y��s�� ;
�@�@�������V ; �u���ɗ� ; ���c�����Y ; ���c���v ;
�@�@�����c��ߕv ; ���ꗲ�O�Y ; ���c�P�Y / 22�`
�d�͚��z�Ę_ुi�И����]�j/���M�Y/64�`
�H�ƊE�ɉ�����X���̜�p/�u���ɗ�/74�`
�ț{�ʐM�ɂ̂���/�؉��ۑ���/79�`
�N���u�Ɋ�]����/���c�\����/80�` |
�Ў�@����/�V���ʒj / 44�`
�ț{���]/�|�����j / 82�`
�Q�[�e���Λ{/����[�i / 84�`
�ł֎q/ / 90�`
�C�U�����{/���ؕs�@�u / 92�`
���_�i�Z�́j/�V���g / 95�`
���ڂ߁i�Z�́j/�F�s�쌤 / 95�`
�ț{�ҏ��B ����ᢐ��{��W�E���[/�i��ਕ�/96�`
�x�e��/ / 96�`
�ț{�҂ʼn̂��r�ސl�X/���R�� / 101�`
�B���a�͂������Ȃ邩/����Z�Y / 68�`
���U�̐E���ɂȂ��/�R����� / 104�`
�������n�C�L���O/K�EO�ET / 108�`
���E�ț{���/�Έ�F�K ; �F�쐪�v / 113�`
�ț{�y���N���u����/ / 118�`
�V���Љ�/ / 116�`
�ҏS��L/ / 132�`
���{��̉��߂Ɛ����@�i���C�{���茩����j/�c���و��k / 120�`
�\��/���j
�ڎ��J�b�g/�{�c�d�Y
�E |
�P�P���A�V��V�U���u�Ȋw�y�� 1(2)�@p 2�` �ț{�y���N���u,�O�ȓ��v�Ɂu������ʂ�萂�����M/�v�\����B�@�@pid/11185132
�P�Q���A�֓��C���u�����w�� = Journal of Oriental studies 7�@p42�`89�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu�v��̐��h�v�\����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@pid/3558883
|
�͓���zᢌ��̈╨�\��Ƃ��ĐVᢌ���
�@�@���Õ�o�y�i�ɏA���� / �~������ / p1�`41
�v��̐��h / �֓��C / p42�`89
��������ɉ����锱���������x / ����Ύ� / p90�`102
���Z�T�̍s�p�ɏA���� / �������g / p103�`134
�����O���j�X���Ƃ��Ă��p���͊t���U�����\
�@�@�����ɔn�R�Y�����ɂ���/�O���J�G/p135�`159
�ŋ�(���N�Ȍ�)�̌�����\(㔕�)/�����F����/p160�`247
�ŋ߂ɉ����鐅�S�������\��ɓA������
�@�@���Ɛтɂ��� / �X���O / p248�`265
���{�Ɉ⑶����ɕ��{�Ƒ��̉e���\�������U����W�����ēy�B��
�@�@�����V�����U���Ɨ��ډ����B�ɏA���� / �˖{�P��/p275�`352 |
椏������`�L�\�\(��) / �S�{���{������ / p353�`382
���p�����}�������ɏA���ā@��� / �����C�� / p383�`385
�k�x�j�֒������s���L / �����C�� ; ���A�q�Y / p386�`394
�b��@����������̈ٓ� / p395�`395
�b��@���������� / p395�`395
�b��@�J���T�N�L�O�u����/�������g;�H�c��/p395�`397
�b��@�A㔍u���� / �����`�Y ; ���_������ / p397�`401
�b��@���j�k�b�� / �~������ ; �q���l�� ; �O���J�G ;
�@�@�������C�� ; �˖{�P�� ; �����F���� ; ���A�q�Y ;
�@�@���g��K���� / p401�`405
�b��@�x�ߗ��s / p405�`406
�b��@�{���o�ŕ� / p407�`407 |
�P�Q���A�V��V�U���u�Ȋw�y�� 1(3)�@p 14�` �ț{�y���N���u,�O�ȓ��v�Ɂu������ʂ�萂�����M�i�����j�v�\����B�@pid/11185133
���A���̔N�A�R�{�ꐴ�ҁu�}���V���u�� ��1�� (�V���Ɛ���)�v���u�����t�v���犧�s�����B�@�@pid/1230597
|
�V���Ɛ��̉^�s(��) �R�{���C
���́@�V���̉�� / 13
���߁@�܂Òn���̌`���� / 13
���߁@���̈ʒu��
�@�@���\�͂����\�V�����W/15
��O�߁@�V铂̈ʒu�͊p�x�ő���/21
��l�߁@�嚢�Ə��� / 25
���́@�V铂̓����^�s / 28
���߁@�n���̎��z / 28
���߁@���̏o�� / 31
��O�߁@�q�ߐ��Ɛ��̓쒆 / 36
��l�߁@�����^���̒��S�� / 39
��ܐ߁@�����v�̌��� / 44
��Z�߁@�V铂̍��x�̎����� / 50
�掵�߁@�V���V�ƓV�ۋV / 59
�攪�߁@�o���̕��� / 62
���߁@�����̋��܂Ɛ������ʒu/65
��\�߁@���ɂ����p�̑��� / 67
|
�����̗��j�Ƌ��E�� ���㒉�h
���́@���� / 77
���߁@����l�Ɛ��� / 77
���߁@���̔��̗v�f / 79
��O�߁@�ڂ�䂭�V�̌i�ہ\�V��/85
��l�߁@�̂�Ȃ��V�̌i�� / 88
���́@�����̗��j / 95
���߁@�����̋N�� / 95
���߁@�t�G�j�V������M���V���� / 98
��O�߁@�M���V������ / 101
��l�߁@�ߑ�ɉ�����̑J / 108
��ܐ߁@�x�߂̐����y�я\��{ / 111
��O�́@�����p�Ђ���
�@�@�������Ƃ��̋��E��/114
���߁@�����p�Ђ��鐯�� / 114
���߁@�����̋��E�� / 128
��O�߁@�������S�����Ɲ��p / 132
��l�́@���\�Ɛ��� / 138-152
|
���߁@���\ / 138
���߁@���� / 142
��O�߁@�V���V�Ɛ������� / 150
����Ɍ����閈���̐����ē� ����痢
�ꌎ�̓�V�y�іk�V�̐��� / 156
�̓�V�y�іk�V�̐��� / 164
�O���̓�V�y�іk�V�̐��� / 173
�l���̓�V�y�іk�V�̐��� / 183
�܌��̓�V�y�іk�V�̐��� / 192
�Z���̓�V�y�іk�V�̐��� / 198
�����̓�V�y�іk�V�̐��� / 204
�����̓�V�y�іk�V�̐��� / 211
�㌎�̓�V�y�іk�V�̐��� / 217
�\���̓�V�y�іk�V�̐��� / 223
�\�ꌎ�̓�V�y�іk�V�̐��� / 229
�\�̓�V�y�іk�V�̐��� / 233
�o�ዾ�E���]���� �������{ ��K���e
�ꌎ�`�\�� |
|
| 1937 |
12 |
65 |
�S���A�u�V�E = The heavens 17(193) �v���u�����V���w��v���犧�s�����Bpid/3219914
|
�ΐ��͉��̈�ʂ̋������䂭�� / �G�C�g�P�����m/p251�`252
�ؑ����m�̂��Ƃǂ� / �ΐ�ď� / p253�`256 �@�d�v
�Q����`�����F�� / �I������ / p257�`261
���N��,�V���Ɉ˂鉆������ / p262�`262
�����̑��z���S�� / ���� / p263�`263
�q�~�V���i�����z / ���R�H�Y / p264�`266
�������V���n�Ƃ��Ă̈����R / �{�c��/p267�`268
���˂���� / p269�`270 |
�V�E�V�m��(6��) / p271�`272
�C�O���� / p273�`273
�ԎR����� / �Ԑ��l / p274�`274
�V�������� �������������̌�������z / �r�،��Z / p275�`279
1937�N5���̓V�� / p280�`280
�V���E / p281�`281
�V���ē� / p282�`283
�n������� / p284�`286 |
�T���A�V��V�U���u���R (5)p2�`4�@��C���R�Ȋw�������v�Ɂu�����t���v�\����B�@�@pid/1564694
�@�@�܂��A�ؑ����g���u���� p86�`97�v�Ɂu�\�Z���I�̖��\�����I�̎n�߂ɉ�����[�V���C�g�m(��h���n��)�̊�ɉf��������{�v�\����B
�U���A�u�V������ = The astronomical herald 30(6)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304205
|
������̏����@�Ət�C�̏����ď��@�ɏA��/�����C�F/p91�`92
�G�b�f�C���g���V���������_(��)/���{���m ���Y�Y�S/p92�`97
�t�����{���̍s�����H�V��(�l)/���{�m ��،h�M/p97�`101
��\���d����L�� / p101�`103
趕� / p103�`104
Ca��Na�Ύ~���̔�r�\�V���f���̔��j�\�̌����P�t�F�E�X��VV�\
|
�@�@���f�ҍ��Đ��\�E�C���N�a���Ƒ��̃X�x�N�g���\
�@�@���O���O��X�N�G�����b�v�a���\�O���ɉ����鑾�z�K�y�T���\
�@�@�������C���l / p103�`104
���z�̃E�I���t�K�y�� / p105�`105
�Z���̓V�� �����Q �̌��� ����(�O��)�Ō����鐯�̉���
�@�@���f������� ���� / p105�`106 |
�V���V���Aḍa�������[�Ƃ��钆�ؖ����Ƃ̊ԂŋN���������͏Փˎ����B�s�x�ߎ��ς̎n�܂�t
�V���A���z�j�n������ҁu���z�����_�p�v���u�]�h�����Ёv���犧�s�����B�@�@
|
���z�ז� / ���ڌ�[��]
�십�� / �C�v��[��]
�����V���ݐ��� / ���ڌ�[��]
�u�����R�]���J���͓� / ���ڌ�[��]
���������V�Jᢓ��k / ���ڌ�[��]
�z�V�� / �C�v��[��]
��z���I���� / ������[��]
��贔V�� / ���V�s[��]
���z�������g�k / ������[��]
�����Õ����R����B�d�����͗��� / ���ڌ�[��]
�c������� / �u��[��]
��w�k�n���n�I�T�� / �E�N�g[��]
|
�Y�p����Õ����⚬���@�Ș^ / �{�ύX[��]
�ΏB�A�R�@�Ί�Vᢌ��o���������V�N�� / �T���V[��]
�싞�K�ËL / �u��[��]
�͎R����Սl / �u��[��]
�I�O�l�É��͍N / ���ڌ�[��]
���]�ʗL�V�Ί펞�㕶���� / �Ӎs�V[��]
�Ί�I�`���o�n�w�V�T�� / ���V��[��]
���]�Ί�N��I���_ / ���ڌ�[��]
���z���� / ���ڌ�[��]
�o���ڌ��_���z������ / �C�v��[��]
���z�j�n������_��V��] / ���{�M�A[��]
���z�����V�T�� / �h�c[��] |
�W���A�����C�F���u�V������ = The astronomical herald 30(8) p130�`131�@���{�V���w��v�Ɂu�����E�X���̋N���ɏA���āv�\����B�@pid/3304207
�P�O���A�u�V�E = The heavens 18(199) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219920
|
�i�s�����ɊJ�݂���ԎR�V���i�o����(�\��)
�t�C���X���a���ƌ̏�ꠘa�}��(��㉛���)
���̍��̘b��"���V��"�̂��� / �R�{���C / p1�`3
�v�Z�̎d��(3) / �n粕q�v / p4�`9
�ďF�s����(6) / �R�{���C / p10�`12
�ԎR����� / p13�`13
�����v����11cm Triplet�ɏA�� / �ǖ�r�Y / p14�`28
1937�N12���̓V�ۘ��� / p6�`8
|
�~���̘b / �R�{ / p1�`5
���˂���� / �r�،��Z / p29�`29
�V��������: ���z / p30�`30
�ԎR�V���i���i�s�o���̐V�� / ���{���j / p31�`31
��낱��(��) / �q���q / p32�`33
1937�N�x�ڋ߂̉ΐ��V����(1) / ��粐� / p34�`36
�x������� / p37�`38
1938�N����\ / p39�`40 |
�P�O���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 8�v���u���s��w�l���Ȋw�������v���犧�s�����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@pid/3558884
|
�Ë��̉��{������萂���l�Û{�I�l�@ / �~������ / p32�`55
|
���J�����S���̐��S / �M���C / p56�`74 |
�P�P���A�V��V�U���u�w�l�V�F 31(11)p82�`85�@�w�l�V�F�Ёv�Ɂu���C��ď鐶���v�\����B�@pid/3562633
�P�P���A�n粕q�v���u��<�����>�v���u�P���Ёv���犧�s����B�@�@����
�P�Q���P���A�싞�U�����߂�����B�s�싞�����t
�P�Q���A�u���R (6)�v���u��C���R�Ȋw�������v���犧�s�����B�@pid/1564695
|
��㉛���
���x������g / �V��V�U / p4�`11
�V�������݂�ਂ� / ��������� / p10�`17
���������nj� / ������ / p18�`20
�D�Ђ̐Ղ�K�˂� / �K�����F / p21�`22
��펞�ǂƌ������� / �C�� / p22�`25
���̈Ș҂̕����X�� / ���� ; �~�c��� / p26�`34
�֎ꏑ�M�W�Ɍ�����ނ̌��N�ɏA��(��) / ���U / p26�`34
��C�f�` / �쏟�q�� / p35�`35
�ď鏬�L / �C�엲�� / p38�`44
|
�J���i�Ɋ� / �q�� / p45�`46
���S / �y / p47�`50
������ / ���c�ƕ� / p51�`55
�k�x�s��枂��� / �����G�Y / p56�`65
�옱�̗� / �ؑ��N�� / p66�`100
�A�i�N���I���̊�����(���O) / ����C / p101�`105
������趋L / p106�`110
�O�j�ڎ� / p111�`111
��L / p112�`112
�E |
�P�Q���A�u�V�E = The heavens 18(201)�v���u�����V���w��v���犧�s�����Bpid/3219922
|
���l5�Ă̑唽�ˋ��͌^(�\��)
�_���`���̋L�O�B�e(��㉛���)
�\�� �C�����ꎁ�̞�� / �R�{�ꐴ / p73�`73
�v�����f�X����� / R�J��g�����v�� / p74�`76
���v�Z�̎d��(5) / ����u�t �n粕q�v / p77�`81
1937�N�x�ڋ߂̉ΐ��V����(3) / ��粐��� / p82�`86
�ďF�s����(8) / �����͎� �R�{���C / p87�`94
|
1938�N2���̓V�� / p24�`22
�������ĕ��p��m��@ / �R�{���C / p17�`21
�V�ďЉ�:���d���t�V���p���M / �ǖ�p�V�� / p95�`96
�V�E�V�m��(4��) / p97�`99
�V��������: ������V���ʥ���z / ��ꠍF��Y / p100�`102
�_�˂ɉ����鏺�a12�N�x�`�� / p103�`103
�x���ʐM(���) / p104�`104 |
|
�@�v�Z�̎d��(1�`5) �̓���\�@����u�t �n粕q�v
| �E |
�G�����ƕŐ� |
���s�N |
�_���� |
�v�Z�̓��e |
pid |
| 1 |
�V�E 17(197) p395�`400 |
1937-08 |
�v�Z�̎d��(1) |
�i�v�Z�̓��e�f�ڗ\��j |
pid/3219918 |
| 2 |
�V�E 17(198) p434�`437 |
1937-09 |
�v�Z�̎d��(2) |
�i�v�Z�̓��e�f�ڗ\��j |
pid/3219919 |
| 3 |
�V�E 18(199)�@p4�`9 |
1937-10 |
�v�Z�̎d��(3) |
�i�s�����ɊJ�݂���ԎR�V���i�o����(�\��)
�ԎR�V���i���i�s�o���̐V�� / ���{���j / p31�`31
�i�v�Z�̓��e�f�ڗ\��j |
pid/3219920 |
| 4 |
�V�E 18(200)�@p50�`53 |
1937-11 |
�v�Z�̎d��(4) |
��Â̓V���i��(��������)
��Â̓V���i(�V���j����) / �X���� /p42�`44
�x�ߎ��̂ɍۂ���N�̓��H���v�� / �{�c�� / p54�`56
�i�v�Z�̓��e�f�ڗ\��j |
pid/3219921 |
| 5 |
�V�E 18(201) p77�`81 |
1937-12 |
�v�Z�̎d��(5) |
�������ĕ��p��m��@ / �R�{���C/ p17�`21
�i�v�Z�̓��e�f�ڗ\��j |
pid/3219922 |
|
���A���̔N�A�W�[���Y��,�M������u�_��̉F�� : �V�����w�̉F�����v���u�P���Ёv���犧�s�����B�@pid/1149540
|
���� / 1�`3
�ڎ� / 7�`9
���́@�łэs�����z / 11�`55 |
���́@�ߑ㕨���{�̐V�V�n / 26�`60
��O�́@�������t�� / 61�`97 (
��l�́@�����������ƃG�[�e�� / 98�`139 |
��́@���͍��ׂƂ��� / 140�`188
桎ҕ��L / 189�`193
���� / 194�`200 |
�����̔N�A���c���g�ҁu�c�I���ܕS��\�ܔN�V���Ռ�����k���v���u���c���g�^�v����(��茧)�v���犧�s����B�@�@�@�a�{pid/1104354
|
��@��k��萂��钍�ӎ��� / 1
��@��k�v�c / 5
�O�@��k���{�� / 7
�l�@�d�펮�ɉ����鍐熁A�j熁A��� / 16
�܁@�d�펮�@�U�n���ɉ����銴�z��� / 20
�Z�@�������� / 21
������[�� / 21
|
�V���̌�V / 22
���@�{���O�a�ɂ��� / 24
�V�h�䉑�`�V / 28
�ɐ��_�{�ҝ` / 29
�Z���_�Йҝ` / 30
���@���_�� / 34
���@�������e���ʂւ̎ӏ� / 34
|
��@���^ / 36
�F�N�� / 37
�_���� / 37
���a���c / 38
�V���Օ������̗R�� / 40
�������v�A���璲���\ / 50
�E |
�@�@�����ۑ�F����Ƃ̊W����_�O�ɕ�����܂ł̏�Ԃ͍��Ă̂܂܂��A����Ƃ����Ă܂ʼn��H�������B�@�m�F�v�@�@�Q�O�Q�Q�E�R�E�P�@�ۍ�@
|
| 1938 |
13 |
66 |
1���A���j�w������� �u���j�w���� = Journal of historical studies 8(1)�v���u�ѕ����o�Łv���犧�s�����B�@�@pid/3565982
|
���{�ˈًL�̈�l�@ / ���f�V / p2�`13
���{�ɉ�����喾�ߌ����̌n�� / �m��c� / p14�`14
�����O���j��ɉ����鉺萎����̈Ӌ`�\�\(��) / �Έ�F / p15�`42
�������N�������ɏA���� / �����O�� / p43�`57
�j���[�g���Ɨь� / ����s / p58�`58
�}�C�l�b�P����j��`��ᢐ���ɂ��ā\�\�`�����[�X�A��r�@�h�ɂ��
�@�@�����̏Љ�Ɣᔻ / �ь����� / p59�`64
�d�ڂƓW�]�@��N�x�̗�j�{�E / p65�`87
��A���{�j / ���{�j���� ; ���{ ; �镔 / p65�`70
��A���m�j/���m�j����; �u�c�s����; ��؏r; ������; �ǖ쒉��; �͕h����/
p71�`84 |
�O�A���m�j / ���m�j���� ; ���������� / p84�`87
�����И��\���̗����Ɠ��ꉻ�ɛ����鏔���� / �lj����� / p88�`90
�Љ�Ɣᔻ / p91�`112
�����@�ۉ��G�q���@���{�_���w�l��� / �镔� / p91�`96
�����@�n粕q�v���@��(�����) / ����s / p96�`97
�����@D.K.Lieu ; The Growth and Industrialization of
�@�@��Shanghai.China Institute of Economics and Statistical Research.
�@�@��Shanghai 1936.pp.473. / �u�ꌴ�i / p97�`104
�_���@���{���g�@�\���\��x�l / �쒷�� / p104�`112
�E |
�P���A�ɓ��S�傪�u�V�E = The heavens. 18(202) p122�`122�@�����V�������v�Ɂu�V���E�X(��)�v�\����B �iIRDB�j�@pid/3219923
�Q���A�u���|�t�H 16(2)�v���u���|�t�H�V�Ёv���犧�s�����B�@pid/3197699
|
�Ԋ~�̜� / ����C�V / p6�`8
���C�̘b / �c�����̖� / p8�`11
��C�������ɏA�� / ���c�Εv / p28�`29
�x�߂̑�{��@�����邩 / �V��V�U / p34�`36
�h�B�Ɋ��R����K�� / �������� / p36�`37
���̂Ɠ��{�̎g�� / �R�{�p�� / p52�`56
�x�ߖ������̐��� / ���J��@���� / p58�`65
�R��������R�͉\�� / ��c�� / p66�`74
���̂̉e���Ɖ�D���S�Z�̓��� / �ې쌫���� / p76�`85
����̂͐��E��D��ᢓW���邩����k�� / �����O�M�� �q�i
�@�@�� ���R���� ���\�� ; ���h�ʐM�Ў劲 �ΐX�B�m ;
�@�@������������ �����o�� ; �O���ȏ�� ���J�엹 ;
�@�@���C�R�卲 ����A�� / p86�`110
�X�^�[�������܂̛��� / ���R��Y / p112�`119
|
���̒n��̍�� / �������N / p138�`146
���I�Ȑ��_(�И����]) / �͖얧 / p158�`165
�k�x���{�F / �ݓc���m / p166�`178
�싞��b / ���g�~ / p180�`188
�k���̕��l / ����m�s / p190�`198
�싞�n�R����(㉂ƕ�) / ����I�� / p204�`207
�싞��U���D�n�R�L / ���Y�t�H�n�R�L�� ����p��/p208�`217
�싞�E�o�L / �Ո�t�����N�t���^�[�L�� �����[��A�x�b�N/p250�`253
�k�x�D��̒n�`�ƒn�� / �e���c���� / p298�`301
�A�P�v�� / p304�`306
�����s�i�ȂƔߌ�(���a�I���]) / M�M�M/p322�`326
�ҏS��L / p464�`464
<����>
�E |
�T���R�P���A�R�{�ꐴ�����s�鍑��w���ˊ�ސE����B
�U���A�u���R (7)�v���u��C���R�Ȋw�������v���犧�s�����B�@�@pid/1564696
|
���j / �V��V�U / p2�`6
�]��̔_��(��) / �ؑ��N�� / p7�`25
�k�x�߂̐ΒY�y�c / �������G / p26�`48
������ / ���c�ƕ� / p49�`57
�x�߂̕����{�݂ɛ����� / �V��V�U / p58�`59
���߂��N���[�N�k�` / �h�c / p60�`63
�k�����L / ⨎O�� / p64�`68
���������������𓉂� / �ؑ��N�� / p69�`71
�ď��L / �C�엲�� / p72�`76
����越� / �Җ�וv / p77�`79
�L�ܒ�錫 / ����_ / p80�`81
�V�D�� / �C�엲�� / p82�`83
|
�������Ǝv������ / T�EK / p84�`86
�吢�E���� / ����`�� / p87�`87
譗V趉r / ���C / p88�`89
椋ߏd�������m�����R�� / ���c�Ύ��� / p90�`91
���V�܁\�\�f�` / ����C / p92�`94
�A�p�[�g�̓��L / ���U / p95�`96
���߂�Ⴋ���� / ������ / p97�`100
�u�����A�ǂ������H�I�v / ��C�M / p101�`106
������趋L / p107�`109
�O�j�ڎ� / p110�`110
��L / p110�`110
�E |
�V���A�u���|�t�H 16(11)�v���u���|�t�H�V�Ёv���犧�s�����B�@pid/3197708
|
�t�G�m���T�搶 / �ܓ��x�g / 10�`13
�k�Ђ̎v�o / �I�����v / 18�`20
�D���n���̕����{�� / �V��V�U / 82�`85 |
�F�M�A�t�K�j�X�^�����d���(���O) / �k�c���� / 172�`179
<����>
�E |
�V���A�u���|�t�H 16(12)�v���u���|�t�H�Ёv���犧�s�����B�@pid/3197709
|
��������--�E���犿���̊C�R�q���
�@�O���ɉ�����̌����ȘA���Ԃ�
�@�Z�Z����̒n�����j�
�@�͖塗g�q�]�㖄�߂��G�O�㗤����)
�����s�f�g���b�N�s / ����� / p132�`151
���F�������{�����ٖK��L/�O�D�B��/p152�`159 |
������܂܂̎x�ߣ�������k��--�o�Ȏ�--��C���R�ț{�������� �V��V�U
�@�� �S�Z�{���m ���ؗF�O�� ���H�������� �ؕ镐���v
�@�����������C�R���� ���p�O�� �O�c�@�c�� �ԏ����� �O�c�@�c�� �ɓ��x�l
�@�����H�ҋ��� �������V�� �]�_�� ����� / p160�`181
<����>
�E |
�W���A�u���|�t�H. 16(13)�v���u���|�t�H�V�Ёv���犧�s�����B�@ pid/3197710
|
�\�� / ����f��
�ڎ��J�b�g / ���c������
�V���x�V�R���Ȃ�����r���R�� / �q��x���� / p5�`6
�����@�̚� / �x���M��
�������� / �I�ؗE�V�� / p7�`8
�q�ǂ����� / �q���y�O / p8�`10
���F / �}�ԝܗY / p10�`12
���B��J���������W�K / ���c���Y / p12�`14
�J���C�r�����W / �ȓ��g�F / p15�`17
����ƕ��C / ��Ց�� / p17�`18
����h�̓D�_ / �Óc�� / p18�`21
���I / �������� / p21�`24
��������ӂ�(㉂ƕ�) / �����܉_ / p24�`28
�쑺�C�Y�Ƌ��{��M�̈��� / ���q�O�� / p28�`29
�U�R�ނ̋L / �ΐ�ӈ� / p30�`31
暐l���� / �{�V�T / p31�`34
�w�̌m�� / ���슨�� / p34�`35
���ꈤ��̐��_ / �ۉȍF�� / p35�`39
�Ă̊p�� / ���q�d�Y / p39�`41
��V�̈�}�b / �ɒB�F�r / p41�`42
�x�߂����o��� / �������� / p42�`43
�ΌQ�̎v�Џo / ���c�۔n / p43�`45
���Y�t�H / / p46�`47
���t�H / / p56�`57
��D���S�Z铐��̋�������k��-�o�Ȏ�-���q��V�� ���ؚ��
�@�@������ꝋg �x�ؕ��� �O��P �n����U/ p58�`87
�͈�̊v�V����� / �r�ؒ�v ; ���R���� / p120�`128
���ω����̓r�Ƒ�O�� / ���쐳�� / p88�`102
�����|���̐V����(���E��b) / ���誎m / p48�`54
�e�㥎И𐭍�ً̋}�ۑ� / �������\�� / p130�`142
���x�S�Z���̛݂��� / �ؑ������� / p108�`117
�`�G�c�N��ㅂ�^�F�̐��� / �ɓ����� / p144�`152
�\�������n���`�� / �쑽����� / p164�`175
������ꂽ���p / �g��p�� / p200�`203
�Q����� / �Љ��c�� / p204�`205
�S�Z�E���ʐ���--�S�Z���]/�O��P / p176�`180 |
���������̈����--�И����] / �V������ / p154�`161
�C�R�q����̍s�� / �|�{�d�� / p222�`231
���̐��E���隤��--�t���� / ���� / p48�`54,257�`
��p�i����ə|����--�t���� / ���� / p268�`273
�l�����ŋ� / / p376�`385
�ٓN�� / / p376�`378
�����M�s / / p379�`380
���c���U / / p381�`383
��]�X�~ / / p383�`385
���{�̕]�� / / p276�`281
[�h�����] / / p216�`
�h�����Ƃ��Ă̖k�x���͓k / ���|�B�O / p290�`295
�l�ƞ� / �Ό��� / p9�`
�ӕ��q�� / �k�����H / p13�`
���̈���N / ���[ / p17�`
�������_ / ���앓�q / p11�`
�䓪�V�� / ������� / p15�`
���ʂɌ����L�҂̒m��--�V�����]/�c�����l/p252�`257
�ԏ����Ƌ�ǕԂ�--㉂ƕ� / �L���C�� / p232�`237
�������J��F�̊�̖��������� / �͍��ǐ� / p237�`240
����䂩���b / ���J�쎞�J / p244�`250
�C�ƎR--㉂ƕ� / ���q���� / p242�`243
�㒹�H�V�c�Ƣ�����悤� / �n粐�~ / p194�`198
�����u�m�̘a�� / ��c�� / p182�`191
�I�z�[�c�N�C / ��敐�v / p208�`214
�������o���̍� / �n��P�� / p296�`302
�ٕ��P���L / �����`�] / p282�`287
���V�A�̐�����c�߂�� / �V�����g / p358�`364
������Q�L / �g�A���� / p366�`374
���J����� / �����G�� / p346�`355
�����͈���̊j�S���Ղ����k��--�o�Ȏ�--���P���O��
�@�@�� �ؓ����悤 ��˔����� �ؑ����` �q���y�O �����d��
�@�@���V�j�V�� ���J��@���� �O�֓c���� /p314�`343
�x�߂ɂ��Ⴋ�F�� / ���\���q / p260�`267
�b�̋��� / �e�r�� / p192�`193
�q�� / ���얲�� / p404�`420 |
� / / p398�`399
�V�� / / p399�`400
���� / / p400�`402
��� / / p402�`
�Λ{�펯 / �⌴�C / p104�`105
�Λ{�ⓚ / ���{�s��Y / p104�`105
�� / ������T / p129�`
�Z�� / / p162�`
�V���w / �]�쐶 / p162�`163
�o�� / �ߕ��� / p163�`
���n / ���c�� / p181�`
�J���� / ��[�� / p199�`
���� / ��]�Ǒ��� / p206�`207
���R�[�h / K�EN / p221�`
�S���t / �x���� / p251�`
�f�` / ���� / p258�`259
�� / Y�EM�搶 / p288�`
�l��V�� / �ؒJ�� / p288�`
���� / ���c���� / p289�`
�l�����V�� / �ԓc���c�� / p289�`
�V���Љ� / / p385�`
�C��R����� / �g�c���� / p386�`387
�\�� / ���{ꝏ� / p403�`
�ڥ����� / / p422�`423
�����̗� / / p424�`
��e�ƏЉ� / / p501�`
�A������ / / p502�`
�����L / / p503�`
�㗝���ē� / / p504�`505
��Ԏ����\ / / p508�`511
�ҏS��L / / p512�`
����f�`�_ / �ѓ��� / p388�`395
���{��椎�-���Y���]/�����m��/p304�`311
���� / �ѕ����q / p426�`444
�O������� / �ΐ�B�O / p446�`476
�� / �����Ґ� / p478�`500 |
�W���P���A�V��V�����ߘJ�̂��ߓ싞�ŋ}������B�i�U�U�j
�W���A�u�V�E = The heavens 18(209)�@p333�`333�����V���w��v�Ɂu���� �V��V�U���m���������v���f�ڂ����B�@pid/3219930
�X���A�u�V������ = The astronomical herald 31(9)�@p177�`177���{�V���w��v�Ɂu�V��V�U���m�̐����v���f�ڂ����B�@pid/3304221
�P�O���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 9�v���u���s��w�l���Ȋw�������v���犧�s�����B�@�@ (���s��w�l���Ȋw�������I�v)pid/3558885
|
�����⒍�� / ��쒼�� / p1�`9
�x�߂̏ٝÕ��Ƒ��̋N���� / ��،Y / p10�`29
�p��{�X�L���`���k�R�E�l������ / �g��K���� / p30�`56
�u������Ɍ��������ە������ɏA����/����Ύ�/ p57�`111
�x�ߌ����ق̍̕��ɂ��� / ���A�q�Y / p112�`146
�j�L�������̏����� / �������� / p147�`157
�v��̍c��i�ɏA���� / �����x / p158�`196
���B���_�ɉ����鑢�_�ӎ�ɏA����/������l/p197�`217
��缝� / �n粍K�O / p218�`260
椏������`�L�\�\(�O) / �S�{���{������/p261�`314
�_���ΌA�����L / �����C�� / p315�`345
�V�x���L / �M���C / p346�`358
���]�@���]�@鰝玞��V�����@�k��螁@
�@�@�������I���� / �F�s�{�C�g / p359�`372
���]�@�\�c�����@�X�L���ߓV����/ �g��K����/ p372�`378
���]�@���쏟�N桒��@��㖼�`�L/ �g��K����/ p378�`386
�{���P�{��v / p387�`391
�b��@�{���̉��i���тɉ��g / p392�`395 |
�b��@�����ړ� / p395�`397
�b��@�������� / p397�`400
�b��@�o�ŕ� / p400�`402
�b��@�����̏o�����тɗ��{ / p402�`403
�b��@�J������L�O�� / p403�`410
�b��@���J����u���� / p410�`411
�b��@���j�k�b�� / �g�� ; ���� ; �M�� ; �n� ; �X ; �Ëg ;
�@�@�@�����A ; ���q ; ��� ; ���� / p411�`414
�b��@趎��� / p414�`415
�b��@�k����u�K�� / p415�`416
�b��@�x�ߌ�{�u�K�� / p416�`417
�b��@���s�隠��{�ݛ{���ؖ���⍂т�
�@�@�@���ޏF�����{�����Ғ��b�� / p417�`417
�b��@��Ȃ�ҖK�� / p417�`417
���^�@Erganzungsband zu den Neugebauers
�@�@�@��Sterntafeln. / �\�c���� / p1�`43
���^�@�A���o�[�X�����Ϛ������@�ɂ���/�����/p44�`53
�E |
�P�O���A�u�V������ = The astronomical herald 31(10)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304222
|
7�̐V�̌���/��،h�M;�Ô����H/p181�`183
���z�R���i��X�y�N�g����萂���
�@�@�������̌���(II)/�������v/p184�`189
|
�f���_�ɏA��(II)/���V�i��/p190�`193
�V�锎�m�� / ���R�C�� / p193�`194
�V��V�U�搶�lj� / ��c�t / p194�`195
|
�ܓx�V�����͓��P�ɂ̌���/p196�`196
���z�̐��Z�ʒu�̏C��/p196�`196
�q�����r |
�P�O���A�r�؏r�n���������L�O�� �ҁu���� (16) p17�`26�@�������L�O��v�Ɂu�̐V��V�U���m�Ǝ��̉��̎x�ߕ����v�\����Bpid/7956979
�P�P���A�u�j�w17(2)p.325-327�Ap327-328�Ap.328-330�O�c�j�w��v�Ɂu���x�l�Û{�����Ǐ��{�Ǖv�����\�����BIRDB
|
| �G���f�ڕ� |
�_���� |
������ |
| �j�w 17(2)�@p.325-327 |
(��)�싞�̒���(�x�ߛ{�p�������l�Û{�Ǖ�) |
���{�M�A,�ۍ�O�Y,�����G�Y |
| �j�w 17(2)�@p327-328 |
�i��)�Y�B�̒��� |
���{�M�A,�����G�Y |
| �j�w 17(2)�@p.328-330 |
(�O)�싞�̍Ē���(�x�ߛ{�p�������l�Û{�Ǖ�) |
���{�M�A |
|
���A���̔N�A�呐���ҁu���������� : �Ȋw�Ґ��z�v���u��̑q���X�v���犧�s����A�V��V�U�́u�x�߂̑�{�@�����邩�v�����������B�@pid/1219103
|
�n�N ���������� / 9
�Z��w�{ �c������ / 13
������ᢂ� �O�}�F�Y / 20
�s�𐫂Ǝ��R�ƂȂ� �Ð쐰�j / 25
��� �|�����j / 30
�����ƕ����Ǝ�҂� �㒗����� / 33
�O���R�̉Ό� �c���ُG�O / 37
�l���̏H ���{���q / 43
�e���r�W�����ƃI�����s�b�N
�@�@������������/50
���̎ �e���c���� / 57
�� �{�����V�� / 61
����̌� �L�؊O��Y / 66
��i�ƍ�� ���c���� / 71
�i�s�̐����ƂƋ��܌v �����C��/76
�s���Ȃ铑�� �������N / 82
�����Ԃ̓D���� �ޓc���� / 86
�ț{�x���� �{�鉹���� / 90
�d���҂�� �������P / 95
�u�k���l�v������L ���� / 100 |
�A���E�V�A������ �������U / 104
�O���̜��K�� ���� / 109
笎���V �y��s�� / 114
�C��萂���}�b �X���p / 118
���̛��� �c�����n / 125
�A�����J�̓c�q ���R�C�� / 129
�䚠�F���_��ᢒB �K�؈��Y / 133
�r�������� �����V / 139
���Â̘b �����Ĉ� / 143
����� ���X�ؒ����� / 147
���ق̗��z �����d�� / 152
���w�̕]�J �������� / 157
����P�^ ����� / 161
�c�������d��萶�����c��
�@�@����� �R�{�m��/170
�ʕ����̊��z ���P�� / 177
�d�ƏL�߂��R�߂� ��ؗf�� / 183
�����̞قƋꙧ �R�{���� / 186
�ț{�`�� �쑺���^ / 190
�������P �Ό��E / 194 |
�������̐E�\�ƞ鎮 �쑺������/197
����f�@���� �L�ؐ��� / 204
�ڈ̉��� �i��� / 208
�ț{�Ɛ_�� �ғ��� / 215
�䓙�̍K�� ��쐽�� / 219
���̏ꍇ ���|����Y / 223
�͛{�̑�ƃE���[�u�X�^�[�搶��
�@�@����� ��ؕ� / 228
���̑�� ���؏��� / 233
��̓� ��͓����q / 238
���Ȏ�`�̂��Ƃǂ� ��K�E�g / 242
�傫�Ȍ��z �������� / 245
�ʐ�㐅�ׂ� �Ό��� / 250
�c�E��E���E�e�E�c�� �ɓ����{ / 255
�x�߂̑�{�@�����邩 �V��V�U/261
��@ ��ؐ����� / 267
���� ���x�M�� / 272
A��B�̊Ӓ� ���c��� / 277
���m�̕K�v���x 萌���g / 282
�E |
�����̔N�A�c��P�g ���u���J�Ɣ_�Ɓv���u�������v���犧�s����B�@�@pid/1216881
|
���́@�䂪��铂Ɣ_�� / 1
���́@�_�ЂƂ͉��� / 5
��O�́@�����̐��� / 8
��l�́@�_�͚��̑�{ / 14
��́@�j����������� / 20
��Z�́@�F�N�� / 23
�掵�́@�_���� / 26
|
�攪�́@�V���� / 28
���́@�另�� / 37
��\�́@�������ЂƔ_�� / 41
��\��́@�_�ƂƏ��_ / 52
��\��́@���X�Ɣ_�� / 57
��\�O�́@�_���Ɣ_�� / 62
��\�l�́@���_�� / 72
|
��\�́@�F�J / 75
��\�Z�́@���_ / 79
��\���́@�j�א_�� / 90
��\���́@�����V�c�Ɣ_�� / 94
��\��́@�����V�c�ƒ{�Y / 101
���\�́@����F�肵���� / 110
���\��́@�������� / 118
|
���\��́@�{�_�� / 123
���\�O�́@�Õ��� / 127
���\�l�́@���A� / 130
���\�́@�Ύ��L / 133
���\�Z�́@�c�ق̐_�� / 150
���\���́@���_ / 152
�E |
|
| 1939 |
14 |
�E |
�R���A�u���R (8)�v���u��C���R�Ȋw�������v���犧�s�����B�@�@pid/1564697
|
���� / p1�`2
�̐V�鏊�����V�L�� / p3�`14
����铂���ꂽ�钢�� / p17�`24
���Ԃ��炩�����V��N / �D�c�� / p25�`26
�V��Z�̒ǜ� / �o�萳�� / p26�`28
�V�锎�m���� / �؏��� / p28�`29
�V�鏊���̎� / �����V�� / p30�`31
�V�锎�m�̒ǜ� / �ЎR���v / p31�`32
�V�锎�m���� / �c�������q�� / p33�`35
�̏�C���R�ț{���������V�锎�m������/�D�ÒC����/p35�`36
�V�锎�m���Â� / ������O / p37�`38
�̐V��搶���� / �e�n沋g / p38�`40
�V���l���h�炵��� / �ڋ{�� / p40�`41
���V�锎�m / ���V�B�g / p42�`42
�V�锎�m���� / �y��ыg / p42�`43
Shinjo Hakusi no Mitama ni / Tanakadate�]Aikitu /p44�`44
�V��N���� / �������P / p45�`47
���V�锎�m / �ߏd���� / p48�`49
�V�锎�m������ / ���䌳�� / p49�`50
�V�锎�m�̎v�o / ��쒼�� / p50�`52
�V�锎�m�̎v�o / �O�Y�e���� / p53�`56
�ț{�̗E�ҐV�锎�m�̕��e / �����d�� / p57�`64
�lj� / ��䌹�� / p64�`65
�V�锎�m���Â� / ���ˊm���� / p66�`67
�{�E�̗E�m�V��V�U���m / �哇���� / p68�`72
�V�锎�m���Âт� / �������� / p73�`74
�V�锎�m��ɂ� / �ؑ��� / p75�`75
�̐V�锎�m���� / ����� / p76�`77
�V�锎�m�� / ���o���� / p77�`78
�V�锎�m / �K�����Y / p78�`79
�V��N�𓉂� / ��K�E�g / p80�`80
�V�锎�m������ / �����C�� / p80�`82
�̐V��V�U�N������ / ���������� / p82�`86
�V�鏊���N�� / p87�`100
�V�鏊������ژ^ / p100�`105 |
���̉́\�\���V�{�l��r / p105�`110
�ț{���_�̏}�͎� / ���� / p111�`112
�V��搶�̒lj� / ��c�t / p112�`115
�ߕ� / �R�{���C / p116�`116 (
�V�锎�m�Ɠ싞�̌Õ��ۑ�����/���{�M�A/p116�`121
�V��搶�Ǝ����X / �Ԗx�p�O / p122�`125
�V��搶������ / �ۍ�O�� / p125�`127
�V�邳�� / �R�{���F / p128�`128
�V�锎�m�Ǝ� / ���q�ؖ��� / p128�`129
�V��搶������ / ���䌹�� / p130�`132
���V���� / ���R���� / p133�`134
����̔� / ���F�V�� / p134�`135(
�V��搶��債�� / ���|���v / p135�`137
�V��搶������ / �n粋`�� / p137�`140
�V��搶���Â� / �\�c���� / p140�`144
�z�Џo / �r�؏r�n / p145�`149
�V�鏊���Ǝ� / �y�c�B / p150�`163
�V��搶������ / �K�����F / p164�`166
�V��搶��Î��ȚL�V / ���� / p166�`167
�V��搶�̒lj� / ���� / p167�`169
�w�����x / �����G�Y / p170�`181
�V��搶�̒lj� / ��c������ / p181�`185
���V��搶 / �k�q�c / p185�`186
�㒎���L��� / ���� / p186�`192
�z�Џo / �y�c�R�� / p193�`196
�嘩�̌䐸�_ / ������ / p197�`198
�搶�̕��k�{�E�l / �C�엲�� / p198�`199
�̐V��搶������ / �����d�� / p200�`201
���Ԃ̐� / ���{�`�F / p202�`205
�V��搶�̎v�o / �ؑ��N�� / p206�`207
�̑�Ȃ���{�� / ��������� / p208�`212
�w���R�x / �����̖� / p212�`214
�V�鏊���Ƃ���ǂ̎��� / ��쑾�� / p214�`216
���̓�ᢌ�̏����Ƒ��̒lj�/������E�q��/p217�`220
�E |
�T���A�ѓ����v���u�V����@�ƉA�z�܍s���v���u�P���Ёv���犧�s����B�@�@pid/1246210�@�{���\
|
��@�x�ߌÑ�̗�@ / 13-31
��@�V���{���猩���x�߂̌Ñ㕶�� / 32-47
�O�@�x�ߌ×�̓��F / 48-64
�l�@�x�߂̗�@ / 65-115
�܁@�A�z�܍s�� / 116-182
��@���� / 116
��@�A�z�܍s���̑n�n��萂���B�� / 121
�O�@�A�z�܍s���̊�{�I���� / 130
|
�l�@�A�z�܍s���Ɛ萯�p / 151
�܁@�A�z�܍s���Ɠ����� / 164
�Z�@�A�z�܍s���̐����N�� / 178
�Z�@�x�ߌÑ�̓V�{ / 183-193
���@�Ñ�x�߂̓V����@�y�ь܍s�v�z / 194-226
���@�x�ߐ萯�p�̌`���� / 227-241
��@����̗�@��茩���鍶�B�̙E�� / 242-309
��@���� / 242 |
��@��Â�芿��Ɏ���܂ł̗�@�̝̑J / 243
�O�@����̗�@�ƊO���̌×�@�Ƃ̔�r / 263
�l�@�t�H�̗�@ / 271
�܁@�����B�̗�@ ���� / 274
�Z�@�����B�̗�@ ���� / 287
���@���������u�Ɍ�������t�H����̗�@ / 294
���@�����B�͊��̗��k�L���l�̙E�� / 298
�\�@�Ăэ��B����̎����_�� / 309-354 |
�V���A���{�M�A���u�j�w 17(4)�@p.1a(529a)-84(612)�@�O�c�j�w��v�Ɂu�]��K�ËL�v�\����B �@�iIRDB�j
�V���A �M���C���u�����w�� = Journal of Oriental studies 10(2)�@p110�`134�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu�\�ǂɂ��āv�\����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558887
�W���A�u�I�����Z�S�N 2(9)�v���u�I�����Z�S�N��j��v���犧�s�����B�@pid/1387600
|
����ޥ�x�S�Z铐���
�@�@���������t��/�ؑ�������/p2�`4
�Ă䂭���{�� / ������ / p5�`7
�M�l�C�OᢓW�̍��k��(�I) / p8�`13
�C�̓��{�̐� / ��K���e / p14�`16 |
�I�����Z�S�N�j�T�]�c�ψ�����
�@�@����ܓ��ʈψ���݂����/p16�`16
�I�����Z�S�N��j��b��/p16�`16
���y�̊�(���d)/�����`�V/p22�`27
�Z�я��� �C���̈��/���{��/p18�`19 |
�V�엎�� �Ă̊C/�j���G/p20�`21
�L�O������ / p28�`28
�V�f�`�Љ� / p17�`17
�Z�� / p29�`29
�E |
�P�Q���A��K���e ���u�����W�]. 9(12)(102)p17�`21 �����W�]�Ёv�Ɂu�{���@�א��̌ÓV�����v�\����B�@pid/3555513
���A���̔N�A�V��V�����u���M�v���u�P���Ёv���犧�s����B�@�@pid/1917666
|
���� �`�_ / (10)
���� �ț{�Ɩ��M / (10)
���� ���M�����Ƃ��ẲA�z�܍s��/(38)
���� �e�_ / (68)
���� �̍ЂƖ��M / (68)
���� ���̋g�� / (75)
|
��O�� �ł���ߋ㐯 / (89)
��l�� �����Ђ��̋S�� / (98)
��ܐ� ����� / (109)
��Z�� ���� / (114)
�掵�� �c��ʔ��T / (120)
�攪�� �E��Ɩ��M / (128)
|
���� ��ƔN���s�� / (137)
��O�� ���M�������� / (148)
��l�� ��������̛��� / (158)
��� �ØҎ��҂̖��M�V / (176)
��Z�� ��̝̑J / (156)
�掵�� �����Ɩ��M / (202) |
���A���̔N�A���c�ڌo�����u���̎j���v���u���̐�g��v���犧�s����B�@pid/1035636
|
�`�� / 1
���� / 19
�c����ᢏ� / 19
�c���̊m�� / 28
�c���̐��J / 34
���� / 41
�c���̓��J / 41
�V�c�̑��i / 46
�c��̑��i / 54
��O�� / 61
�c��㋏� / 61
�_���c�@���� / 63
�іL�c������ / 65
�O���V�c�̍c�� / 66
�����V�c�̍c�ʁE�㒹�H�V�c�̍c��/69
�����V�c�̍c�� / 71
���c�V�c�̍c�� / 73
��l�� / 80
�O��_�� / 80
�_���J / 86 |
�_���N�� / 94
���������� / 100
�_��̈ړ��@�E�_��/108
��ܕ� / 125
�_�_���J / 125
���J / 145
�F�N�� / 155
������ / 159
�_���H�� / 160
���P / 161
�_�ߍ� / 162
�_�R�� / 163
�V�R�� / 164
����� / 164
���_�� / 165
�N�ԍ� / 166
�O�}�� / 166
���R�� / 167
�N���� / 168
�N�� / 169
|
������ / 170
��a�Օ����� / 170
���܍� / 172
�m��_�� / 173
���_�� / 175
���\���� / 176
���_�� / 178
�_�� / 182
�ɐ��_�{ / 186
������ / 189
���_�̎� / 190
�R��̐_�ʂ̎�
��a�̐_�ʂ̎� / 198
�͓��̐_�ʂ̎� / 209
�a��̐_�ʂ̎� / 216
���Â̐_�ʂ̎� / 219
��Z�� / 225
���� / 225
�����̈� / 230
�����̓� / 240 |
�����̎O / 248
�掵�� / 254
�����`�� / 254
�c�ʂ̎��� / 256
�_�ʂ̎��� / 266
�וʂ̎��� / 277
�o������̎��� / 284
���j / 289
�攪�� / 301
���y / 301
�c�� / 316
䵉��Ƙŋ� / 326
���� / 356
���� / 356
��Â̕��� / 379
�ʕ��̐� / 388
�R���̐� / 395
�E
�E
�E |
���A���̔N�A��K���e�������V���ٕҁu�V���ǖ{�v���u�����V���فv���犧�s����B�@�@pid/1055543
|
�M�҂̂��Ƃ� / 2�`5
�~�̋�i�I���I�����A�������A�f�ҍ��A�Ԏq���A
�@�@���I���A�匢���A�������j/6
�t�̋�i���q���A�C�֍��A�G���A�������A雍��A
�@�@����F���@���F���A�����A�������A�،����j/14
�Ă̋�i噍��A�����A�w���N���X���A�Ս��A
�@�@���h���A�������A�ˎ���A�R�r���j/25
�H�̋�i�J�V�I�y�A���A�A���h�����_���A�y�K�X�X���A
�@�@�����r���A�싛���A�����A�~���A�y���Z�E�X���j/36
��ɕ��߂̐��� / 44
���̝� / 50
�����̂����� / 50
�����\ / 51
���̓��� / 52
�V���̓��T�^�� / 52
��̋�E�k�̋� / 53
�_�ɂ̋� / 54 |
�k�ɐ��E�ԓ��̐��� / 55
���z�ƌ��̉^�� / 56
�P���Ƙf�� / 58
�k�ɐ��̌��o���� / 59
��F���� / 60
�j�P���n�ƋǕ��P���n / 61
�V�̐�͐��̑�W�� / 61
��F���̑� / 64
�n���Ƌ�͌n�̔�r / 66
�V���p�� / 67
�A���h�����_���启�_ / 68
���z�n�̈ꑰ / 70
�f���̕\ / 72
���f�� / 73
�O�f�� / 75
�����̐e���z / 79
���� / 80 |
��Ԃ̐��� / 81
�ΐ� / 82
�V��̉��u�a���v / 84
���z�ƒn�� / 88
���� / 88
�V�̐ԓ� / 90
���z�̓쒆 / 92
�t�H���E���E�~�� / 92
���̘b / 95
���H�ƌ��H / 100
�������E�߂��� / 102
�v���l�^���E���̋@�\ / 105
�v���l�^���E���̍\�� / 108�`114
�h�[���ɉf���� / 110
�{��ᢍs�ɂ��� / 115
�E
�E |
|
| 1940 |
���a15 |
�E |
�P���A��K���e���u�����W�]. 10(1)(103)p78�`78�����W�]�Ёv�Ɂu��א��̌ÓV����������v�\����B�@ pid/3555515
�V���A���c�S�g���u�j���ƍ������_�v���u���t����ǁv���犧�s����B (���{���_�p�� ; 16)�@�@pid/1909300
|
��A�_�_���h�̐��_ / 1
��A���̏j�� / 2
�O�A���̍ՓT / 8
�l�A���݂���j�� / 12
�܁A�F�N�� / 19
�Z�A�Z���̌����� / 34 |
���A���c�̕��̐_�̍� / 36
���A�t���� / 42
��A��a�� / 45
�\�A���� / 52
�\��A���P�� / 54
�\��A�N�� / 63 |
�\�O�A������ / 68
�\�l�A�M�_��J���p��� / 70
�\�܁A�o�_�����_�ꎌ / 76
�\�Z�A�V�_�̚掌 / 82
�E
�E |
�W���A�u�I�����Z�S�N 3(8)�v���u�I�����Z�S�N��j��v���犧�s�����B�@pid/1387613
|
�{�M���R�ț{�̌������� / 萌���g / p2�`4
�]�ˎ���̉ț{�ɂ��� / ������ / p6�`10
萍F�a�Ɠ��{�̝ɛ{ / �O��`�v / p20�`23
���w�� / �|�����j / p11�`12
�q����{ / ������ / p12�`14
�d�����{ / ��� / p14�`16
�n�k���{ / �����C / p16�`17
|
�������Z��������S / p5�`5
�I�����Z�S�N��j�e�����F����������S / p18�`19
���R�ˌ�˙ҝ`���H���ǍH���N�H�՛������S / p29�`29
�I�����Z�S�N��j��l���ٓ� / p30�`30
�I�����Z�S�N��j���ӖF���^ / p30�`30
���{���j㉉�(��) / ���R�ĒB / p24�`25
���ॖ���p�� / ���ؒߕF / p26�`28 |
�P�O���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 11(3)�v���u���s��w�l���Ȋw�������v���犧�s�����B �@(���s��w�l���Ȋw�������I�v)pid/3558892
|
�x�ߌÓ�����̐�����萂���l�Û{�I�l�@ / �~������ / p1�`34 |
�_����@�l / �M���C / p35�`65 |
���A���̔N�A�����E���u�ĂƓ��{�����v���u�鋳���[�v���犧�s����B�@pid/1245516
|
���́@�ĂƓ��{���j / 1
���́@�j�̐_�b / 13
���߁@���V���ɉ������j�� / 13
���߁@�V���~�Ղ��V����n / 25
��O�߁@�唪�F�ɉ������j�� / 38
��l�߁@�j��̙B�d / 48
��O�́@�ꗱ�l�� / 59
���߁@�Ă��� / 59
(��)�@�ĐH���� / 62
(��)�@�Q�[ / 62
(�O)�@�Z���Ƃ��Ă̕� / 77
(�l)�@���S�ė{�H / 81
(��)�@�m�̌��� / 90
���߁@�_���̗� / 94
(��)�@�j��̐h�� / 94
(��)�@�ő�̈�Y / 100
(�O)�@�i����ǂ̓w�� / 109
��O�߁@�N�̉� / 117 |
(��)�@�F���T�_�� / 117
(��)�@�ْ��Ɍ��ꂽ����S / 121
(�O)�@���S�̕\���Ƃ��Ă��j�� / 137
��l�߁@�_�̜� / 140
(��)�@誐g�_ / 140
(��)�@�V�Ƒ�_��沎��_ / 145
(�O)�@�V�n�̉� / 150
��l�́@�ĂƖ����I�M�� / 157
���߁@���Ɍ��ꂽ��h���ꗱ�� / 157
(��)�@�j�̖��i / 157
(��)�@�Ă̖��i / 162
(�O)�@�j�Ɉ���ŏo�҂����i / 167
���߁@�j�Ɛ_�� / 177
(��)�@�F�N�� / 178
(��)�@�j�� / 184
(�O)�@�L�R�_�� / 195
(�l)�@�����ՁE�c�� / 196
(��)�@�c�A�_�� / 201
|
(�Z)�@�F�J�ՁE�F���� / 205
(��)�@����ՁE���_�� / 206
(��)�@�����_�� / 207
(��)�@�_���H / 207
(�\)�@����� / 209
(�\��)�@�_���� / 211
(�\��)�@������ / 213
(�\�O)�@�V���� / 214
(�\�l)�@�另�� / 218
��O�߁@�c��̈�P / 223
(��)�@�ꗱ�`�� / 223
(��)�@�H��̑��d / 233
(�O)�@�c��̘��� / 238
(�l)�@���H���V / 249
��́@�ĂƏ@�� / 253
���߁@�m���Ɗ��� / 253
���߁@�H���Ɛ��� / 261
��O�߁@�s / 267 |
�����̔N�A�c���ɓ������u�_���N�w�v���u�������X�v���犧�s����B�@�@pid/1255792
|
���́@���_ / 1
(��)�@�_���̔ᔻ�I���� / 1
(��)�@�_���̈Ӌ` / 15 (
(�O)�@�_�b�y�B���̈Ӌ` / 21
���́@���E�V / 26
(��)�@�V�V�䒆��_�ƎY�˂̐_ / 26
(��)�@�ʓV�_�Ɛ_������ / 36
(�O)�@�����V�Ɛi���v�z / 41
��O�́@���f�̚��y�C���ݕ����Y/49
��l�́@���V���ɉ�����_�b / 61
(��)�@�F����̐_�b / 61
(��)�@�V�Ή��˂̐_�b / 63
(�O)�@���V���̘��c�Ƒ嚠�呸�̚�樂�/65
(�l)�@�V���~�� / 69
��́@�c�c�_�O�c�_�̓�d�� / 73
(��)�@�V�Ƒ�_�̓�d�� / 73
(��)�@�O�c�_�̓�ʐ� / 82
(�O)�@���V���̓�d�� / 88
��Z�́@����V / 90
|
(��)�@������� / 91
(��)�@��铂̎�ނƔᔻ / 98
(�O)�@�_����� / 107
�掵�́@�����V / 111
(��)�@�����̖ړI / 111
(��)�@�Ր���v / 117
(�O)�@�V�c�̖{�� / 125
�攪�́@�O��̐_�� / 130
(��)�@�O��̐_��̋N�� / 136
(��)�@�O��̐_��̗��j / 136
(�O)�@�O��̐_��̈Ӗ� / 140
���́@�l���V / 148
(��)�@�_�Ɛl�Ƃ�萌W / 148
(��)�@�~�R�g / 152
(�O)�@�l���̖ړI / 154
��\�́@�_���V / 157
(��)�@���� / 158
(��)�@�ˍ� / 172
(�O)�@�_�� / 184 |
��\��́@�Ґ��V / 192
(��)�@���� / 192
(��)�@�n���ɞق̔ᔻ / 202
��\��́@�_����ᢒB / 218
��\�O�́@�_�̛����V / 232
��\�l�́@�_���V / 268
(��)�@����͂̐_���V / 270
(��)�@�_���̐_���V / 281
��\�́@�����J�l��铌n/290
��\�Z�́@�����V / 324
(��)�@���䍰 / 324
(��)�@���{���_ / 335
(�O)�@��铂̖{�` / 343
��\���́@�Ґ_�̓��̋/359
(��)�@�Ґ_�̓��Ɛ_������ / 359
(��)�@�Ґ_�̓����͈� / 368
(�O)�@�Ґ_�̓��ƍc�R / 377
(�l)�@�Ґ_�̓��ƛ{�� / 389
(��)�@�Ґ_�̓��Ɠ��� / 405 |
(�Z)�@�Ґ_�̓����Y�� / 410
(��)�@�Ґ_�̓����S�Z / 422
��\���́@�Ґ_�̓��ƙ�p
�@�@��(���ÁA���A���f)/429
��\��́@�N���� / 436
(��)�@�N���� / 436
(��)�@�N���Ղ̖{�` / 443
���\�́@���J / 456
(��)�@���J�̐��_ / 456
(��)�@�F�N�� / 465
(�O)�@���P / 478
(�C)�@���P�̏j�� / 478
(��)�@�S�P / 485
���\��́@�F��ƓV�C/501
(��)�@�F�� / 501
(��)�@�V�C / 520
���\��́@�_���̊v�V/538
�E
�E |
�����̔N�A�n�ӕq�v���u��v���u�P���Ёv���犧�s����B�@�@pid/1262463
|
���́@���_ / 23
���߁@1262463? / 23
���߁@���z��Ƒ��A�� / 25
��O�߁@��@�Ƃ��ӂ��� / 28
��l�߁@� / 30
��ܐ߁@��Ɩ��M�A�N���s�� / 31
���́@��ɕK�v�ȓV���{�I���� / 34
���߁@�V���y�ѐ��̈ʒu / 34
���߁@���z�̎��^�� / 38
��O�߁@�V铂̏o�� / 45
��l�߁@�V���̎��^�� / 52
��ܐ߁@���A�̎��^�� / 54
��Z�߁@�H / 61
�掵�߁@���� / 63
��O�́@��̊�{�T�� / 68
���߁@�� / 68
���߁@�N / 81
|
��O�߁@�� / 82
��l�߁@��@�̌��� / 84
��l�́@���ԏT���̎�X / 93
���߁@�T / 93
���߁@�{�A���x / 96
��O�߁@�җ�T�� / 101
��l�߁@�I�N�@ / 114
��ܐ߁@�i�N��(�ݔN��) / 125
��Z�߁@�@�͏�̍Փ� / 130
��́@���z��@ / 137
���߁@�G�a�v�g�� / 137
���߁@�y���V���� / 139
��O�߁@���[�}�� / 143
��l�߁@�����E�X�� / 144
��ܐ߁@�O���S���[�� / 147
��Z�߁@�鎮 / 156
�掵�߁@���z��̌��� / 158
|
�攪�߁@�t�����X���a�� / 160
���߁@��@���ǂ̖�� / 163
��\�߁@���E��(����) / 167
��Z�́@���A��@ / 168
���߁@�}�z���c�g�� / 168
���߁@���_���� / 172
��O�߁@�o�r���j���� / 179
��l�߁@�M���V���� / 180
��ܐ߁@�C���h�� / 183
��Z�߁@�x�ߗ� / 189
�掵�́@趐ߋy�ї / 201
���߁@�܍s�� / 201
���߁@趐� / 203
��O�߁@� / 207
��l�߁@���M / 215
�攪�́@��{ / 223
���߁@�V铗� / 223
|
���߁@���{�̗�{ / 225
��O�߁@�{��A���{�� / 235
���́@���{�̗�v / 243
���߁@��Â̗�@ / 243
���߁@�x�ߙB�҂̗�@ / 246
��O�߁@��A�З� / 250
��l�߁@�勝�� / 251
��ܐ߁@����� / 258
��Z�߁@������ / 264
�掵�߁@�V�ۗ� / 269
�攪�߁@�����ܔN��?�� / 271
���^
���v�Z�\ / 278
���� / 298
�E
�E
�E |
���A���̔N�A��������ďC�u���������w ��12 �n�������{�y�ѓV���{�v���u�͏o���[�v���犧�s�����B�@�@pid/1063552
|
�d�́@�؈䒉��
�n�����E�n�d���@���R�v��
�n�k�@�{���O�g |
�V���V���S���@�ؑ���
�V铕����{�@萌���g�@���c�ǗY
�V铛����@�y����Y |
�S�ܓx�y�ю��̑���@�{�n���i
�E
�E |
���A���̔N�A���V�k���E�Q���l ��,���{��j, �M�������u�x�ߐ��w�j�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/1869952
|
���� ��� ����� / 1
���� ��� ������ / 6
��O�� ��O �ߌÎ��� / 28
��l�� ��x��Z�̗A�� / 42 |
��� �V���p / 48
��Z�� �v���̝ɛ{ / 75
�掵�� ��l �ߐ����� / 121
�攪�� ��Z�p / 132 |
���� ���m��Z�̗A�� / 141
��\�� ��� �ŋߐ����� / 192
���^
�d�v�l���������� / 219 |
|
| 1941 |
16 |
�E |
�P���A�u�Ȋw��� 30(1);���a16�N1���j�v���u�������V���Ёv���犧�s�����B�@�@�@�@pid/10984658
|
���{�ț{�_/������ / 17�`22
���h���ƂƉ��{�H��/���؏��� / 23�`27
���S�E��鄎�����̕�/ / 28�`54
ᢖ���ᢌ��̊�/�c���k�����E�l�O�� / 28�`31
�ۉ��ނƂ��Ă̋�����/�������g / 32�`36
��鄐S���{�̏ꍇ/�ː�s�j / 37�`42
�d�q������u�Ƃ��̜�p/������ ; �R�����l / 43�`50
�~��̊J�����i/�����ӓ� / 51�`54
�q��@�p�j�����̏d�y/�쏟���� / 60�`64
���j��Q�̉ț{�I����/������ / 73�`80
�e�ԐƘI����/���� / 55�`55
�����f�`�̎��y���]��/�g�c�S�� / 109�`109
�v�Z�ڂ̒m��/����p�� / 110�`111
�����̐��_�ƕ��@/�e�r�ٕ� / 117�`117
�����l���y�`/�s���� / 85�`85
�q�O���r�A�Łr/ / 1�`,6�`8,65�`72
�כ{�ɐu���i���ؒ厡���m�j/ / 1�`1
������鄏�������/ / 2�`
�啗�������݂�/ / 6�`8
�C�R�H���ɂ�/ / 65�`65
�Ě����i�ւ閳�G�͑�/ / 66�`67
�R�c�z�̐Ղ�������/ / 68�`69
�����̋@�B������/ / 70�`71
�~�R�̕\��/ / 72�`72
���������������̎B���/�x���ǒj / 4�`5
�Ă̕i��ӕʖ@/�ߓ��ݑ��� ; �}�����v / 118�`126
|
�C�O�ț{���/ / 135�`135
�q�c�g���[�ƞ�������/ / 22�`22
�H�ƐV�ۑ�/ / 98�`108
��p�H���������/��c�v�h / 98�`103
�h���O���̐V�������p�@/���i������ / 104�`108
���z�M�̍H�Ɖ����/�����G�� / 91�`94
�������˛{����i���j/��� / 95�`97
���{���ƌ��z(3)/�Ό����� / 86�`90
��ۂ̂��Â��Ák�ț{�L�҂��S�����l/�����Y / 112�`116
�j�̎����ƕė���ᢈ�/��J�`�Y / 15�`
��͞�/�ɓ��i�V�� / 56�`59
�V�t��i�o��j/�ѓc��� / 59�`59
�q�A�[�g�F���Łr/ /
���q�����C����/ / 12�`
���E�ő�������/ / 14�`
���@/ / 14�`
�������e�̊���/ / 15�`
���I�̐V�B�e�@/ / 15�`
�Ή��ɑςւ��/ / 16�`
�������`����/ / 16�`
�n���Ɍ��͂ꂽ�����̚�/ / 16�`
������ �n�ނ������q�Ι���/�]���S���q / 81�`84
�c���A����̐V�炵���H�v/�n粌R�� / 128�`130
���ʍu�� ���R���ۂƕ����\��/����G�� / 134�`131
�\�� �v������������呎����鄏�/ /
�ђ��ʐM/ / 136�`136 |
�R���A�u�V���w�y�n�������w�M���S�� 1(2)�v���u�w�p������c�v���犧�s�����B�@�@pid/1548199
|
�_�� / p1�`36
���z�V�����ݒu�ɏA�� / ��c�t / p1�`3
1936,37,38��3�N�Ԃɉ������ݚ������ܓx�V�����V�����ʂ�
�@�@�������ɏA��/�ؑ���/p4�`7
�{�M�ΎR��̃��a�E���ܗL�� / �ǎR�N�� / p8�`12
|
���a15�N8��2���A���{�C�ɋN���n�k�Ôg�̒�����/�{������/p13�`21
�n�k�v�ɏA�� / �������ʖ呾�� / p22�`36
�V���{�{�M�ψ����u�����L�� / p37�`44
�n�������{���X���L�����^ / p45�`45
�E |
�S���A�ѓ����v���u�x�ߌÑ�j�_�v���u�P���Ёv���犧�s����B�@�@pid/1918019�@�@�{���\
|
���� ���_ / 23
���� �x�ߌÑ�V���{�̐��� / 2
��O�� �F�������_�Ƒ���A�z�܍s / 28
��l�� �����Ƃ��̖��i / 57
��� �����ܐ��̉^�s��
�@�@���\��C�\��\���h / 76
��Z�� �~���y / 104
�掵�� �V���̊�B / 116
�攪�� ��@ / 131
���� ���x�y�т��ٖ̈� / 152
��\�� �k�l�y�ѓ쒆�� / 176
��\��� �×�̘Z��Ɓu����v / 194
��\��� ������ƎO���� / 230
��\�O�� �Ύ�y�щ[�� / 258
��\�l�� �H�̏T�� / 267
��\�� �ؐ��I�N�@ / 275
��\�Z�� ��@�ƈ� / 283
��\���� ��@�Ɖ��� / 293
��\���� ��@�Ɲɛ{ / 300
��\��� �V����@�Ɛ��C���` / 310
���\�� �V����@�̐E�� / 321
���\��� �Ñ�V���{�̐����N�� / 332
���\��� �x�߂Ɛ����Ƃ̉F�������_�A
�@�@���V���{�A��@���̔�r / 359
���\�O�� �Ñ�ɉ����铌���̌�ʂ�
�@�@���D������̎x�ߛ{�E / 415
���\�l�� �D������̋L?�ɉ�����V����@
�@�@��(�`�L�C���t�H�y�ђ|���I�N) / 443
���\�� �t�H�̓V����@ / 456 |
���\�Z�� ���B����̓V����@ / 475
���\���� ���S���S�̓V����@ / 502
���\���� �Ñ�̈╨�̖������ɉ�����V����@/536
���\��� ���_ / 546
���_
�� ��x�̌×�Ɩi�ɐ����̔N�� / 557
�� ���_ / 557
�� ��x�×�̎O���� / 558 (
�O ��O���̗�@�̓��� / 560
�l �i�ɈȌ�̓V���{ / 584
�� ��\���h�����̔N�� / 611
�Z ��\���h�̙B�� / 619
�� �i�ɂ̓V���{��Rig-Veda�̐��� / 625
�� �x�ߕ����n��҂Ƃ��̐���̖@�� / 643
�� �x�ߕ����̑n��� / 643
�� �x�ߕ�������̖@����萂��錤���̋N��/653
�O ���Ă̐�������������̖@�� / 669
�C �w��
�� �ی`
�n �`��
�j ����
�z �z��
�w ���
�O �u�Е����̔N�� / 698
�� �u�Е����Ƃ��̒��Ɍ�������@ / 698
�� �u��̗�@��萂���B���I�����̐��� / 699
�O �u�Ђ�ᢌ@�����ɂ����@���� / 708
�l ���̎������������ĉ��ׂ������ʂ�
�@�@��������V���{�I�ᔻ / 715 |
�� �u�u��v�̑g�D����ꂽ���̔N�� / 716
�Z �u�Ј╨�̍l�Û{�I�ᔻ / 724
�� �u�Ђ�ᢌ@�����ɂ����@���������̔N�� / 727
�� �u�Е����̒��ɂ���u�v / 736
�� �u�u��v�Ƃ��Ӗ��i�y�џu�Е�����
�@�@�����ɂ��銱�x�̕\ / 739
�\ �u�Е����͝D���ʗp�����̈�� / 743
�l �x�ߓN�{�̌��� / 746
�� ���� / 746
�� ���S / 746
�O �^�� / 756
�l �V�q / 768
�� �̓�q / 771
�Z �x�ߓN�{�̕����ƉA�z�܍s�� / 785
�� 羟��Ўq�ƉA�z�܍s�� / 788
�� ���B����ƉA�z�܍s�� / 793
�� �Ўq䤎q�̓����� / 798
�\ ���_ / 807
����
��v�V����(�{���Z�ܕřҏ�) / �ɖ�
����(�{���Z�Z�řҏ�) / �ɖ�
�� �����_
�� ����_
�O �V�s�_
�l �V��
�� �t��
�Z ��
�� ���v
�E
|
�T���A�u���R. (11)�v���u��C���R�Ȋw�������v���犧�s�����B�@�@pid/1564700
|
����x�߂ɉ������i�������̕��z�\
�@�@��(�ΒY������) / �\���P�V�� / p5�`18
���E�ދߊ��ΎR�� / ���^�� / p19�`31
���������ɏA�� / �k�C�l / p32�`36
�Տ���W / p37�`37
���N / ���� / p38�`67
�l��ۍ��P� / �m�_ / p68�`73
��C�a�ƃA�a�\�����a / ��R�p�Y / p74�`76
�l��̍�� / ��]�v�v / p77�`80
�y�R�s / ���U�� / p81�`82
�֎ꏑ�M�W�Ɍ���邻���S�Z���/���q/p83�`84 |
����퓩��{�N��u���e / ���� / p85�`85
��C���H�� / �V�c� / p86�`88
�ʋΓ��L�\(���l�Z)�䓙�̜債��VAN�ɑ���/���U/p89�`94
�B���Z���̉� /�� / p95�`99
�Ǔ���b�\�A�C�J�C������ / �`�� / p100�`100
�N���~�����\��趋L / ���ʝɐM / p101�`114
������趋L�\�����a��l�N�\�����a�\�ܔN�\�ꌎ/p115�`116
趕� / p116�`117
�ҏS��L / p118�`118
�E
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���ŏI�����m�F�v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�P�O�@�ۍ�
�T���A�u�V�E = The heavens 21(240)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219961
|
��㉛��� �����v
(����笕M)����ƓV���{ / ���{���m �R�{���C/p169�`171
�Λ{�Ƒ����@�Ǝ��v�����p/�h�O�g�� �}���E�X��t�@���b�g/p172�`178
���̋L�O���̂��߂� / ����Ǖ� / p178�`178
�W���V���p��\(��) / p179�`181
�ΐ����E�̎��� / R�G��G�C�g�P�����m / p182�`185
1941�N�Z���̓V�� / p324�`326
�V�����������݂Ƃ��Ă̐��E��̗̍p�ɂ���/��{�i/p185�`188
|
�c���F���� / p319�`323
���̋L�O�����}�ւėv�]�� / �g�c�R�j / p188�`189
�V���{�I�Ɏ� / �����Y / p190�`190
�q�~�V���i1939-1940�N�x�̋Ɛѕk�I�v69�l/p191�`192
�V��������:����,������,�a��,���z,���� / p193�`198
�e�n���̂���� / p199�`200
�ҏS����� / p200�`200
�E |
�U���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 12(1)�@�v���u���s��w�l���Ȋw������,���������������v���犧�s�����B�@
(���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558894
|
���q���f�̏q��N��l / ���{���O�� / p1�`33
�����⒍�� / ��쒼�� / p34�`38
���҂̋L�^�Ƃ��Ă�ꝍb���Ɠ���� / �������v / p39�`70
�@�k�Q�C�l�B���l / �X�O���O�� / p71�`98
�u������@�Ɏ���x�ߗ�@�j / �M���C / p99�`139
椌��ȑI�L�\�\(�O) / �S�{���{������ / p140�`168
�b��@�{���ڊ� / p169�`169 |
�b��@�����ٓ� / p169�`170
�b��@�������c���y�������C / p170�`170
�b��@�����o�� / p170�`171
�b��@������J�u���� / p171�`172
�b��@趎��� / p172�`172
�b��@��Ȃ�ҖK�� / p172�`172
�b��@�����{����̎����ϔC / p172�`172 |
�V���A�u��K���e���u�V�E 21(242) p.253-255�����V�������v�Ɂu�A�C�k�B���̐���(��)�v�\����B�@ �iIRDB�j
�W���A��K���e���u�V�E 21(243) p.286-287�����V�������v�Ɂu�A�C�k�B���̐���(��)�v�\����B �@�@�iIRDB�j
���A���̔N�A���{�M�L���u�]�쓥�� ���a13�N�x�v���u�O�c�j�w��v���犧�s����B�@
�@�@�@ (�c���`�m��w���w���j�w�Ȍ����� ; �b�� ��1��)�@pid/1918268
|
���c����M�O / 1
�]�쓥��(���a�\�O�N�x)�҉���
�@�@�����{�M�A �ۍ�O�� �����G�Y
��A�������싞�܂� / 7
�o� / 7
��C���싞�� / 12
��A�싞�̒��� / 13
(�C)�������������@���j�ꌾ������/13
�u��ᢌ@(��ꎟ����O��) / 16
��l��ᢌ@�\��\��ᢌ@ / 18
��q�Rᢌ@ / 23
�����̒��� / 26
������ / 28
(��)���I��鄏� / 32
(�n)�Õ��ۑ��� / 36
(�j)�Z���� / 40
������ / 40
|
�W�{�N�W / 42
�싞����C�܂� / 43
�O�A�Y�B�̒��� / 46
�������� / 47
�l�A�Ó��ΌՎR��� / 51
���� / 53
���R�� / 54
�A�R�@ / 56
�Ó� / 57
�Ó��̔N���萂���_�/61
�Ó����߂̒n�� / 63
���j / 66
�����S�� / 68
�y�� / 72
���ށA��O�ށA����/72
�D�F���͐ԐF�y�� / 77
�K�F�y�� / 78
|
�Ί� / 91
�L�i�Ε� / 91
�k�Z���l���� / 99
�k�Z���l�����o�y�╨ / 102
����AB / 102
�l���� / 109
���֏��� / 110
���k�g�E�l / 111
�c�B / 113
�Y�B���߂̒��� / 116
�ݏ��� / 118
�܁A��C / 119
���ט������� / 119
�N�W�l�ÕW�{�ژ^ / 122
���{�M�A�͎����҂�
�@�@�������ЂɏA���āc���R�x�m�v/145
���� |
�����̔N�A���Ό��M���u�j���̌����v���u�������v���犧�s����B�@�@pid/1040200
|
���́@�i���_�j���n�@���ɏA���� / 1
��@��@���N���_ / 1
��@���R�����` / 7
�O�@���ːM�� / 10
�l�@�ˍ��̗V�� / 13
�܁@���l�̎��I���� / 15
�Z�@���ːM�� / 20
�i�P�j�@����
�i�Q�j�@����
�i�R�j�@�ق���
�i�S�j�@����
�i�T�j�@���̑�
���́@�j���̌�` / 41
���߁@�u�̂�v�̌�`�ɂ��� / 41
I�@�����ގ���ɂ��u�̂�v�̌�`���� / 44
�C�A�@�̂��
���A�@���̂�
�n�A�@���̑�
II�@�u�̂�v���g�̗p�Ⴉ�炷���`����
III�@�u�̂�v���ˍ��z�ڑ��̑� / 52
���߁@�u�Ɓv�̈Ӌ`�ɂ��� / 57
�k�ƂȂӁl / 57
�u�Ɓv�Ɓu�ȂӁv�̕����E�u�ƂȂӁv�̌�`
�k�Ƃ��Ӂl / 66
�k���ˁl / 70
�k���ˁl / 74
�k��ʒu�ˁE�f�ˁl / 78
��O�߁@�u�̂�Ƃ��Ɓv�l / 82
�C�A�@�V�Z�����z���ٌˌ������� / 85
���A�@�V�Ïj���T���j���� / 89
�n�A�@���b�̑��j���� / 93
�j�A�@�ߏW���̖@���� / 93
��O�́@�j���̖{���I���� / 96
�k���˂̊��p���錾�@�˗͂��z�ڂ��錾�l/96
�k�ˍ��E�˗͂̎��I�z�ځl / 100
�k���ːM�l / 104
|
�k�䌾�郊�l / 106
�k���͈ˑ��l / 112
�k�{�����N�l / 113
�k���l / 115
�F�� / 123
���� / 127
�t�㉺�� / 133
�F��E���� / 135
���� / 136
��l�́@�j����ᢐ��I���� / 138
���߁@���n�j�� / 138
���߁@�j����ᢐ��I�����i��j / 163
�i�@�����O�̝̑J�j
��O�߁@�j����ᢐ��I�����i��j / 167
�i�\�����͂̊����j
�i�P�j�@�i���̏j�� / 167
�i�Q�j�@�_�������̏j�� / 168
�i�R�j�@�{�����N�̝ďq / 170
�i�S�j�@�����@�E�@�E����@��ᢐ� / 172
�i�T�j�@栚g�@��ᢐ� / 182
�i�U�j�@����ďq�@��ᢐ� / 184
�i�V�j�@���_ / 185
��́@�V���~�Ղ̐_���Əj�� / 188
��Z�́@�j���Ɛ閽�Ƃ�萌W / 205
�i�P�j�@�t��铏j�� / 224
�i�Q�j�@�閽铏j�� / 232
�C�A�@�F�N�Տj��
���A�@���P
�n�A�@�ɐ��_�{�̏j��
�掵�́@�閽铏j���̉��� / 248
�攪�́@�j���e�� / 275
��@�u�䖼�Ҕ�������ҁv�E�u��ҁv�̌P����/275
�C�A�@�A������Տj���́u�@����ҁv
���A�@�F�N�Տj���i�V�Ƒ���_���j��
�@�@���u�c����_�\���g�v
�n�A�@�F�N�Տj���i�������j�́u��u��ҁv |
�j�A�@�N�Ώj�Վ��́u�i����ҁv
��@�V���Ձi���另�Տj���j�̐��_�ɂ��� / 292
�O�@�A������Տj���ɂ��� / 304
���́@���j����ʂ��Č�����
�@�@�����{���_�ƌ�l���S�� / 325
��@�_���Ղ�S / 325
�C�A�@���䔽�n�̐��_
���A�@�c�˟d��̐S
��@�j�����̂�S�i�����̟�鮁E���B�̐��_�j/330
�O�@���ӂ̐��_�E��樂̐S / 332
�l�@����搉̂̐S / 337
���� / 339
��\�́@���j���̐���N�� / 342
�`�_ / 342
�t���Տj�� / 349
����ՁE�v�x�ÊJ�Տj�� / 359
�ɐ���_�{�̏��j�� / 369
�i�P�j�@�g�̏j�� / 369
�C�A�@�F�N�Տj��
���A�@�_���Տj��
�n�A�@�V���e��������j��
�j�A�@�J���_�{�j��
�i�Q�j�@��_�{�X�i�̏j�� / 395
�C�A�@�_���ՁE�����Տj��
���A�@�_�ߍՏj��
�F�N�ՁE�����Տj�� / 404
�o�_�����_�ꎌ / 416
�另�Տj�� / 420
���c���_�Տj�� / 423
���̑� / 432
���_ / 435
��\��́@�j�������j / 438
�C�@�j���̌������ɏA���� / 438
���@�j���̌�`�ɏA���Ă̏����� / 459
�n�@�j���̐���N���萂��鏔�� / 468
�j�@�j���������� / 471 |
���A���̔N�A�����E���u�ĉ��̏��v���u�鋳���[�v���犧�s����B�@�@�@pid/1066123
|
���́@�ĂƓ��{���j / 1
���́@�j�̐_�b / 13
���߁@���V���ɉ������j��/13
���߁@�V���~�Ղ��V����n/25
��O�߁@�唪�F�ɉ������j��/38
��l�߁@�j��̙B�d / 48
��O�́@�ꗱ�l�� / 59
���߁@�Ă̓� / 59
�i��j�@�ĐH���� / 59
�i��j�@�Q�[ / 62
�i�O�j�@�Z���Ƃ��Ă̕� / 77
�i�l�j�@���S�ė{�H / 81
�i�܁j�@�m�̌��� / 90
���߁@�_���̗� / 94
�i��j�@�j��̐h�� / 94
�i��j�@�ő�̈�Y / 100
�i�O�j�@�i����ǂ̓w�� / 109
��O�߁@�N�̉� / 117 |
�i��j�@�F����_�� / 117
�i��j�@�ْ��Ɍ��ꂽ����S/121
�i�O�j�@���S�̕\���Ƃ��Ă��j��/137
��l�߁@�_�̜� / 140
�i��j�@誐g�_ / 140
�i��j�@�V�Ƒ�_��沎��_ /145
�i�O�j�@�V�n�̉� / 150
��l�́@�ĂƖ����I�M�� / 157
���߁@���Ɍ��ꂽ��h���ꗱ��/157
�i��j�@�j�̖��i / 157
�i��j�@�Ă̖��i / 162
�i�O�j�@�j�Ɉ���ŏo�҂����i/167
���߁@�j�Ɛ_�� / 177
�i��j�@�F�N�� / 178
�i��j�@�j�� / 184
�i�O�j�@�L�R�_�� / 195
�i�l�j�@�����ՁE�c�� / 196
�i�܁j�@�c�A�_�� / 201 |
�i�Z�j�@�F�J�ՁE�F���� / 205
�i���j�@����ՁE���_�� / 206
�i���j�@�����_�� / 207
�i��j�@�_���H / 207
�i�\�j�@����� / 209
�i�\��j�@�_���� / 211
�i�\��j�@������ / 213
�i�\�O�j�@�V���� / 214
�i�\�l�j�@�另�� / 218
��O�߁@�c��̈�P/223
�i��j�@�ꗱ�`�� / 223
�i��j�@�H��̑��d/233
�i�O�j�@�c��̙B�� / 238
�i�l�j�@���H���V / 249
��́@�ĂƏ@�� / 253
���߁@�m���Ɗ���/253
���߁@�H���Ɛ���/261
��O�߁@�s / 267 |
���A���̔N�A�X�{�Z�����u���{�_�k�����̋N�� : �l�Êw���茩������{���n�_�Ƃ̌����v���u���发�[�v���犧�s����B�@pid/1066435
|
��
��ꕔ�@�`�_
���{�ɉ�����_�ƋN�� / 1
��n����ՂƔ_�� / 11
�\���������ƌ��n�_�� / 31
�_�ƋN���Ɣ_�k�И� / 51
��@�e�_�E�\�����y��̌���
�\�����y�팤���j / 64
|
�\�����y��ɉ������� / 83
�ϕ��`�Ԃƒ��U�`�� / 94
�ԐF�h�ʓy�� / 105
���������Ɏg�ӓy�� / 11
��O���@�e�_�E�_�k�����̏��`��
�����ʂ���`�ɏA���� / 126
�Ε����̏��`�Ԃƕ��z / 143
�\�����Z��� / 163 |
�\���������̖a�D / 169
���Ɣ_�k���̋G�� / 182
��l���@���_ /
�\�������� / 201
���{�Ñ㐶�� / 211
��L
�E
�E |
|
| 1942 |
17 |
�E |
�S���A�]���������u�_�������v���u�������@�v���犧�s����B�@�@�@pid/1140570 �@�{���\
|
���s�̗R�� / 1
�ጾ / 5
�ڎ� / 7
�ܕ����_���̑c�q�ҋy�ё��̐_����
���̈�@�x���s�� / 1
���̓�@���� / 2
���̎O�@�s�����_���� / 3
�C�@�V�n�l�O�ː� / 3
���@�_�_�� / 6
���̎l�@�x���ƍs�y�ё��̒��� / 8
���̌܁@�ƍs���_���� / 11
�C�@�_���V / 11
�B��_���_
���ҁ@�g�c���䋨�A�B��_����n����/17
���́@�g�c�����X�{�p���u���� / 18
���́@�g�c���䋨�̐l�ƂȂ� / 21
���̈�@���䋨�̗��B / 21
���̓�@�{�����s / 22
���̎O�@���䋨�_�_���̕�����d��/24
��O�́@�_���n���̔N���y�ё��̓I /26
���ҁ@�_����̛{���y�эs�� / 30
���́@�_����̛{�� / 30
���̈�@���䋨�̐_���V / 30
���̓�@���{�@���_���A
�@�@���܂��B��_���Ɖ]�Ӗ��` / 33
���̎O�@���I���y��誗H�� / 34
���̎l�@�O�㖭�d�\���_�� / 36
���̌܁@�_�ߔ� / 39
���̘Z�@���V���̐� / 41
���̎��@�_�l����� / 41
���́@�_���̋V�� / 43
���̈�@�\���_�� / 432)
���̓�@���� / 47
|
��O�́@�B��_���̔�] / 48
��O�ҁ@�_���O�z�̎�i / 57
���́@�V�ꏊ�̌����y�ёg�D / 58
���̈�@�n���̗R�ҋy�єN�� / 58
���̓�@�V�ꏊ�̑g�D�\�� / 61
���̎O�@�g�c�����V�ꏊ�͑��R����
�@�@���V���͋[��������̂Ȃ�/63
���́@�ɐ���_�{�̐_���V�ꏊ�ɍ~�Ղ����ӗR�𖧑t��/66
��O�́@���t�����肵���� / 72
���̈�@�_�{�̐_�ˏ����ɍ~�Ղ����ӂƂ��Ӗ��M���ɍs�͂�/72
���̓�@�_�{�̌䐊���y�ѓ�{�_���̊m�� / 73
��l�́@��{�_���̍R�t / 78
��́@�m�����ᕼ�g�Ҍ����߂�� / 80
��Z�́@�n���y�ъ��E�̙E�� / 82
���̈�@�n���̙E�� / 82
���̓�@���E�E�i / 88
��l�ҁ@�B��_���O�z�̌��� / 95
���́@�B��_���A�����ɍs�͂� / 95
���́@�_�_�����_�a���V�ꏊ�ɑJ�����ɐ_�F����ਂ�/98
��O�́@�����̐_�Г��ɎЊi�_�K���j������ / 100
��l�́@�����̐_�E���x�z�� / 106
��́@�_�E�ɐ_�����Ղ����� / 125
��ܕҁ@�g�c�������̕K�v�ɔ����ě{���̉��v�����/132
���̈�@�������N�̉��v / 132
���̓�@�c��O�N�̉��v / 136
���_ / 137
�o�������_��̎��ւƛ{��
���́@�����_��̎��тƐ��i / 141
���̈�@�����_��̌n���Ɨ��� / 141
���̓�@�����_�厖�� / 143
�C�@�Ï����̏N�W�y�ъ��s / 143
���@���q / 145
�n�@�c��吅�_�Е��� / 148
|
�j�@沋{�蕶�ɑn�� / 148
���̎O�@��क़_ / 150
���̎l�@�����_��̐��i / 169
���́@�{�� / 173
���̈�@�{�� / 173
���̓�@�{���`�_ / 175
���̎O�@�����̐_�� / 177
���̎l�@�F�����Ɠ��O��{ / 179
���̌܁@�����̐_�Ɛl铂̐_ / 182
���̘Z�@�O�ɐ� / 185
���̎��@�_���_ / 186
�|�������N�_�s孋����̎��y�ћ{����[
���� / 191
���̈�@�����N�ƖH���L�������Ƃ�萌W / 193
���̓�@����\�O�N�����N�F����
�@�@���ދ������߂�� / 198
���̎O�@���a�l�N�̕ߔ� / 205
���̎l�@�����N�����y�юR�p���Ǝ��Ƃ�萌W/210
���̌܁@�����N�Ȏq�̍s�� / 212
���̘Z�@�{���̈�[ / 213
�Z�̈�@�N���̟��{ / 214
�Z�̓�@�b�� / 216
�Z�̎O�@��� / 218
�Z�̎l�@�_���� / 218
�F�N�Տj���c��_�{熕ʂ̎�
�Վ�v王{���É��a����O�u�`�ĕ� / 223
�g�c�Ƃ̋g�c�_�Ђɉ������d����
�@�@�����̐M�̈��
���̈�@�g�c�_�Ђɉ������d / 232
���̓�@�������̏o�� / 235
�]�������搶���N�� / 241
�]�������搶������T / 246
�E |
�V���A�u�V������ = The astronomical herald 35(7)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304270
|
�閾��s�p����ɉ����鐄�Z�Ɨ��(I) / �����C�F / p79�`83
�������̖{��(I) / �Ô����H / p83�`88
�����C���l / p89�`89
IV���ɉ����鑾�z�K�y�T�� / p89�`89
���z�̃E�H���t�K�y��(1942,I II III��) / p89�`89
�{������̑��z�K�y�V�� / p89�`90
�{�NVIII-XI�����f�ҍ��Đ��̐H�ɂ��� / p90�`90 |
�a������� / p90�`91
�����Q / p91�`91
�̌��� / p91�`91
����(�O��)�ɉ����鐯�̉���(VII��) / p92�`92
VII���̑��z�����f���y�ѐ��� / p92�`92
�E
�E |
�W���A�u�V������ = The astronomical herald 35(8)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304271
|
�閾��s�p����ɉ����鐄�Z�Ɨ��(II) / �����C�F / p93�`100
�������̖{��(II) / �Ô����H / p101�`106
�����C���l / p106�`106
V���ɉ����鑾�z�K�y�T�� / p107�`107
|
�����Q / p107�`107
�̌��� / p107�`107
����(�O��)�ɉ����鐯�̉���(VIII��) / p108�`108
VIII���̑��z�����f���y�ѐ��� / p108�`108 |
�P�O���A�c��P�g�q�u���J�Ɖƒ�v���u����j�k��v���犧�s�����B�@�@pid/1098887�@�@�{���\
|
���́@�_�� / 1
���́@���_ / 3
��O�́@���J�Ɩ��� / 5
��l�́@���J�̋N�� / 6
��́@���J�Ɛl�� / 8 |
��Z�́@���_�̍� / 10
�掵�́@���J�Ɣ_�� / 12
�攪�́@�F�N�� / 16
���́@�_�R�� / 18
��\�́@�V�R�� / 20 |
��\��́@���J�ƍH�� / 22
��\��́@���J�Ƌ��� / 25
��\�O�́@���J�Ə��� / 26
��\�l�́@���J�ƛ{�Z / 27
��\�́@���J�Ɖƒ� / 29
|
��\�Z�́@�M�\ / 32
��\���́@���� / 34
��\���́@�_�Йҝ`�S�� / 35
�E
�E |
�P�P���A���{�����u���{�̂��āv���u�w�F�فv���犧�s����B�@�@pid/1739368�@�{���\
|
�������A���Ă̓��{ / 1
�V�Ƒ�_�A�c���Ɍ܍��̎�q����������/3
��Ì���V�c�_���Ɍ�S�𒍂�������/8
��Â̐H�� / 13
���̌�̌���V�c�̔_������� / 17
�����Ȍ�c���̔_������� / 21
���ƁE�ˎ哙�̔_������ / 27
���F�N�ՁE�_���ՁE�V���� / 32
���{�̕Ă͐��E�� / 40
���E�ɂ����j�̎�� / 43
�j�̉� / 49
�Ԃ��盉�ɂȂ�܂� / 52
�� / 56
���Ă̐F / 57
���Ẳ�U / 59
���āE�����āE���āE�f / 62
�j�͔̍|�ɒ��d�@�ƈڐA�@ / 64
|
���܂��������܂ł̑�� / 67
��q�I��(�I��) / 69
���Ђ��� / 71
���܂� / 72
�c�� / 74
�{�c / 80
�c�A / 82
���� / 85
��� / 88
�j�̕��� / 94
�ǂ���j����邪�悢�� / 97
���{�̕Ă̕i�� / 100
�A���͔|����鈮 / 101
���H�S�O�\���j / 102
�_�ш��j / 105
��V�� / 106
���� / 108
|
�V�� / 108
���̑��̎�Ȃ�i�� / 109
�L�N�Ƌ��� / 112
�j�̊Q���̂��낢��Ƃ��̑��Q/117
�Q����h���ɂ��Ă̐F�X�̕��@/121
�L���E�W�K�K���{ / 125
�q�Q�i�K�~�d�A�u / 127
��夒� / 128
�O����夒� / 130
�C�l�m�A�����V / 132
�C�l�h���n���V / 134
�c�g���V(䚒�) / 136
�^�e�n�}�L / 138
�C�i�S / 139
�c�}�O�����R�o�q / 140
�C�i�d�}���R�o�q / 144
�q���g�r�E���J / 145
|
�Z�W���E���J / 146
�g�r�C���E���J / 148
�N���J�����V / 148
�C�l�K�����V�A�n���K�����V�A
�@�@���N���K�����V / 150
�j�̕a�� / 151
�j��ƓV�R�̗� / 154
���n�̚��͂�ς萐�n�̚� / 158
���N���i�s / 163
�哌�����Č��ƕ� / 168
�O���ā\�O�� / 170
�Ă̂��Ђ݂� / 176
��U�̕� / 179
�m�Ɩ��k / 182
�Ă̔тɂ��� / 185
�Ă̔т̖� / 192
���Ă�厖�� / 194 |
|
���F�N�ՁE�_���ՁE�V�����i�S���j�^�O�A�\�����l�ɁA�܍��̎�q�͐_�l���璸���A���̈�ĕ��͐_�l���炨���ւĒ������̂ŁA�������N�\�����ɋF�N�Ղ��s�͂�A�\���\�����ɐ_���ՁA�\�ꌎ��\�O���ɐV���Ղ��s�͂�܂��B�^�F�N�Ղ́A���̔N�̔_�앨���\�����鯂�Q�����̂��߂ɕs��ɂȂ�ʗl�A�_�ɂ��F��V����邨�ՂŁA�_���h���A�_�сA�܂��A�����v���������S�ɂ�邨�܂�ł��B���ɂ��肪�����ɂ݂ł���܂��B�^���̓��A�V�c�É��͋{���O�a�ɂ����Č�e���炨�Ղ���s�͂����Јɐ��_�{�ւ͂����g�����������͂��ɂȂ��āA������䌣��V����A�����ЁE�����Ђł͕{�p�m�������Ă��Ղ����������ɂȂ�A�s�E���E���̂��{�ł����ꂼ��Ɏs�������������ĐV�N�Ղ��������ɂȂ�̂ł��B�^���̂��Ղ̌��́A�����_��ɂ͂��܂��Ă��̂ł����A���{���̋V�X�Ƃ��čs�͂��l�ɂȂ����̂́B�V���V�c�̌䎞����ŁA��m�̘������́A�����₦�Ă�̂ł����A�������̐[���v���ɂ�薾����N�Ɍ�ċ��ɂȂ�A����ȗ�������㔂��čs�͂�Ă�邨�Ղł��B�^�F����̒��ɂ́A���̑����A�Ӗ��[�����Ղ̎����悭�����Ă�Ȃ��l������܂��A�ǂ����\�������悭�o���Ă����ʼn������B�^�_���ՂƂ̎��́A�����͑����Ă��ł����B�R�����͂�������A�͂����肵�����𑶂��Ȃ��l������܂�������A���T�ɉ��߂Ă��b�������܂����B�^�_���Ղ́A�ɐ��̓��{�A�O�{�ɁA���̔N�Ɏ�ꂽ���Ă̏���������ւɂȂ邨�������B�Ȃ����̓��A�{���ł͌�y�q�̋V���s�͂����ЁA�����ł́A�V�c�É���e�炨�Ղ���s�͂����ӂ̂ł��B�������Ė��A�ɐ��ւ͂����g���������͂���܂��B�^���Ă��̓��A�ɐ��̙_�{�ւ����ւɂȂ邨�ẮA�ǂ��Ŏ�ꂽ�̂��Ɛ\���܂��ƁA����͌��a���c�Ɛ\���āA�_�{�̌�c�ł���点�ɂȂ����Ăł��B���̌�c�́A�ɐ��̂��{����o���ɂȂ��Ĉ˗����N���Â��Ă���c�ł��B�^�Z���n�߂Ɍ�c�A�̐_���Ƃ��ӎ����s�͂��̂ł����A���̎��́A�c�̌l�i�����j�̏��ʼn��y��t���A����ɂ�ēc�A���i�s���A�A��I��ƁA��c�����������l�̒j���B���̌�c�̒��ɂ͂����āA���邮����Ȃ���u���̈�ɕ������͂�ȁA�������ȁv�ƁA�S�ɋF��Â��܂��B���ꂪ�I���Ɠc�̂��ŁA���q�ɂ�ėx���͂��܂�܂��B������͔q�ώ҂ō��R�̗l�ɂȂ�܂��B�^�Ȃِ_�l�ւ́A���Ă̊O�Ɍ��A�ʕ��A��A����сA���d�A�����A�����Ȃǂ������ւɂȂ�̂ł����A�����̕����A�݂Ȃ��ꂼ��ɍk�삷��Ƃ���A���i�Ɓj��Ƃ���A��������Ƃ���Ȃǂ��A�̂��炿���Ƃ��܂��Ă�āA�ނ�݂₽��̕i�X�͌����Đ_�l�ւ͂����ւɂȂ�Ȃ��̂ł��B�^�ȏ�̂����֕���_�l�ɂ���������̂͌��a�i�݂��j�̌�ՋV�Ɛ\���A�U���ā@�V�c�É����璺�g���ȂČ䌣��ɂȂ镼���i�ւ��͂��j��_�l�ɂ����Ȃւ�����i�ق��ւ������j�Ƃ��ӂ��Ղ肪�Ƃ�s�͂����܂��B�^����Ƃ��ӂ̂́A�ܐF�̌��A�����A�ȁA�ؖȁA�����ǂł��B�^�_���Ղ́A�䂽���ɂ݂̂����V�������Ă�_�ɂ��T���Đ_�����ӂ���鐽�ɏd��Ȍ�Ղł���܂���
�@�O�{�ł͏\���\�ܓ��̗[�Ə\�Z���̒��Ƃɑ���a�A�\���\�Z���ɕ̌�V�B
�@���{�ł͏\���\�Z���̗[�Ə\�����̒��Ƃɑ���a�A�\���\�����ɕ̌�V���s�͂����܂��B
�@�c���A�{���ł͂������������ɂ��������Ȍ�y�q�������s�͂��̂ł��B�������Ė��@�É���e��A�{���̌����Ɍ�q���点���܂��B�^�ȂفA���̓��A�S���̊����ЁE�����ЁE���̑��A�s�E���E�����̐_�ЂŁA���Ղ̋V�����s�͂�܂��B�^�V���Ձi�\�ꌎ��\�O���j�i�ȉ��E���j |
�P�P���A���{�Ȋw�j�w����u�Ȋw�j���� (3)�v���u���{�Ȋw�j�w��v���犧�s�����B�@pid/2380252�@�{���\
|
�Z�z趝� / �O��`�v / 2�`32
���Њ� / ��c�t / 33�`60 �d�v
���[�}���{�����̔w�i(��) / �ߓ��m�� / 61�`83
�{�C���̎��R�V����щ��{�I�Ɛтɂ���(��)/�����Y/84�`107 |
�������ΐ��c�j�����S��(�O) / �O�}���� / 108�`118
�����ϊق̓V����諾Ɏt�͏��{�Ƃɂ���/�c������/119�`129
�����^���w�Ύd�����L�x(��) / �����x�Y / 130�`147
�E |
|
| 1943 |
18 |
�E |
�P���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 13(2)�@�v���u���s��w�l���Ȋw�������A���������������v���犧�s�����Bpid/3558899
|
�|�e�Ǝx�ߌÑ�̋L�^ / �������v / p1�`26
�����@�ɉ���������V�����p/�M���C/p27�`45
���嘩�_���e�ׂ̊��U�{���� / ������l / p119�`175 |
�i���j���B�d�`�R�ߓx�g�n���\�\(�l) / ���}�W / p46�`98
�ю����`�Z�莑����� / �S�{���{������ / p99�`118
�E
|
�Q���A�u����{�� 42(2)�v���u����{�Ёv���犧�s�����B�@pid/1545724
|
��������i�̊ȑf���\�\�ɓ��� / p1�`1
�K�������͂̍\�z / ���X��M���� / p2�`12
���P�P�H(�O�Z) / �C� / p13�`15
��� / p16�`18
�䂪����������� / �i����U / p19�`21
|
�S���D�Ǒ���q�˂�(��) / ���c��� / p22�`24
�_�Ɨ� / p25�`30
�_�c�I�s / �����m�� / p31�`32
�V�n�J蓂��͈�(�Z) / ��`�� / p33�`34
�F�N�Ղɂ��� / �_�_�@�͖��� / p35�`37
|
�̒d / p38�`38
�o�d / �싛�q / p38�`38
�b�� / p39�`40
�ҏS����� / p41�`41
���a�\���N�x����w�������^�C�����\
|
�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 36(2)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304277
|
����nj�(I) / �����C�F / p13�`17
�DूƓV���{ / 萌���g / p18�`21
�����C���l / p21�`21
XI���ɉ����鑾�z�K�y�T�� / p22�`22
|
���z�̃E�H���t�K�y�� / p22�`22
�{������̑��z�K�y�V�� / p22�`22
�J�D��ŏ��̟^�F�V������ / p23�`23
�����Q / p23�`23 |
�̌��� / p23�`23
����(�O��)�ɉ����鐯�̉���(II,III��)/p24�`24
II���̑��z����y�јf�� / p24�`24
�E |
�R���u�V������ = The astronomical herald 36(3)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304278
|
���H������ / �����H / p25�`30
����nj�(II) / �����C�F / p31�`32
�����C���l / p32�`33 |
XII���ɉ����鑾�z�K�y�T�� / p33�`33
���˖]���� / �����v / p33�`35
�����Q / p35�`35 |
I �̌��� / p35�`35
����(�O��)�ɉ����鐯�̉���(IV��) / p36�`36
II���̑��z����y�јf�� / p36�`36 |
�S���A�u�V������ = The astronomical herald 36(4)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304279
|
����nj�(III) / �����C�F / p37�`41
���z�K�y��萂��铝�v�I�l�@(I) / ���ۏ� / p41�`45
�����C���l / p45�`46
���z�̃E�H���t�K�y�~(1942 X.XI.XII) / p46�`46
�{������̑��z�K�y�V�� / p46�`46
�������V�� / p46�`47 |
I���ɉ����鑾�z�K�y�T�� / p47�`47
�����Q / p47�`47
�̌��� / p47�`47
����(�O��)�ɉ����鐯�̉���(V��) / p48�`48
IV-V���̑��z����y�јf�� / p48�`48
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���×�nj�(I)�`(III)�́@�P�X�S�S�E�R�ɐ���\������@���ɏd�v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�P�V�@�ۍ�
�X���A�M���C���u�����w�� = Journal of Oriental studies 13(4)p1�`38�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu���v��@�j�v�\����B�@ (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@pid/3558901
�X���A���쌪���������m����ҁu�X�}�g�������v���u�͏o���[�v���犧�s����B (�����m�S��)�@
�@pid/1062694�@�@�{���\
|
���� ����Jᢐ���Ɩ����{ / 3
����
���� �X�}�g�����ɉ����閯���̊T�v/17
���� �o�^�N���̌��� / 43
���� / 43
��ꍀ ���� / 44
��� ��� / 47
��O�� �ڗ�萌W / 55
��l�� �Z���̖��x�y���z / 64
��܍� �����ƕ����g�� / 72
��Z�� ���� / 96
�掵�� �H�l���K / 106
�攪�� �o�^�N�����Y�p / 120
��㍀ �o�^�N���Ƀg�[�e�~�X���X���肵��/138
��\�� ���҂ɉ�����o�^�N�n����ᢓW��/144
��\�ꍀ �����{�I������
�@�@���o�^�N����ᢓW��/162
��O�� �K�����̌��� / 173
��ꍀ �ڗ� / 173
��� �Z���̖��x�y���z / 183
��O�� �X�}�g�����חށA����
�@�@���ސl���A����/187
��l�� �K���� / 206
��܍� �K�������Y�p / 225
��Z�� ���҂ɉ�����K������ᢒB/233
��l�� �N�u���̌��� / 243
���� / 243
��ꍀ 铎� / 244
��� �И��\���ƕ���/249
�v�� / 270
��� �����X�}�g����ЋL/273
|
���� / 273
��ꍀ �p�_���O����V�E
�@�@�@���W�����W�����O��/277
��� �o�^���O�E�A���㗬�̒T��/317
��O�� �V�E�W�����W�����O����
�@�@���V�A�N�Ɏ��� / 344
��Z�� �~�i���K�o�E�̖�����/379
���� / 379
��ꍀ �Z�� / 380
��� �H�� / 382
��O�� ��� / 385
��l�� �l�H�I�g铝̌`�E���X /386
��܍� �ߕ��E���F�E�p�J�� / 389
��Z�� ���� / 392
�掵�� ���E�����E�ƒ{ / 393
�攪�� �_�� / 398
��㍀ �y�n���L / 403
��\�� �n�D�i / 405
��\�ꍀ �ߋ�E�V�E�E������P/407
��\�� ���� / 411
��\�O�� �A���E�M�� / 413
��\�l�� ���ƁE�ʉ݁E�̔��K��/415
��\�܍� �ړx�E�d�� / 421
��\�Z�� �X�}�g���ɉ�����Ñ��
�@�@�@���x�ߓ���E�X�}�g������̓y��E
�@�@�@�������̍H�Y / 424
��\���� ���D�E�b�� / 432
��\���� �����E�D� / 434
��\�㍀ �@���E�И�萌W / 442
���\�� �����E�Ȃ̒n�ʁE�q / 457
���\�ꍀ �o�Y�E���S / 468
|
���\�� �@�́E�V�X�E�_�b�E
�@�@�����M�E�Ύt/475
���\�O�� �����E�G�߁E�V�� / 492
��O��
���� ��i�Ɠ��{�l / 501
��ꍀ �쑾���m�ɉ�����
�@�@�@���l�ޕ��z�Ƃ��Ă̌ܙ��� / 501
��� �ѐA��ɉ�����쑾���m������
�@�@���O��̙��� / 510
��O�� �����̏K���Ƒ��������� / 512
��l�� �M��ڏZ�ɍۂ��Ă̓��{�l�̓K�䐫/514
��܍� �@���ɂ��ΐA���n������
�@�@�@�����K�Ȃ炵�ނׂ��� / 520
��Z�� ���� / 526
���� ��������̑f���ƏK���E�Ăѓ��{�l��
�@�@�@���M��鉻�\�͂ɏA���� / 531
�T�� / 531
��ꍀ �푰�\�͂̏���� / 533
��� �v�z�A�@�́A�И��\���̖�� / 551
��O�� �Ăѓ��{�l�̔M��鉻���ɏA����/557
��O�� ���m�ɉ����鍬���̖�� / 573
��ꍀ ��m�ɍ����Z�������R / 573
��� �����Z�̎푰�����{������ / 575
��O�� ���{�l��̐��� / 577
��l�� �l��J���̉� / 581
��܍� ���������̕K�v�� / 583
��Z�� �n���C�ɉ����鍬���̌��� / 585
�掵�� �V�n���C�E�A�����J�l��� / 590
�攪�� ���� / 594 (0308.jp2)
��m�����̐��S�ҏ����ΗY�卲���Â� /597
�����×Y�����@�Ȃ͂q�L/619�` 632�@ |
�@ |
���\�O�� �A���E�M�� / p414�`p415
�i��)�����X�}�g���ʼn^���p�Ƃ��ďd�v�Ȃ͉̂��Ƃ����Ă��M�ł���B��^�̏M�̓W�����[���i�������������j�Ƃ��ӂ��A��Ƃ��ċ����p�ƍ��X�p�ł���B�܂��傫�ȋ���߂�ɂ��g�͂��B���͌^�}�����Ŏ����B�N�����O�i�j�����������j�Ƃ��Ӗő����A�����͒������Z�āA���̍ł��A�����͖�P�E�T�Ă���B�̍Ō����ܑ͌W�������B�ő��̏ꍇ�ɂ͞��k�J�W�l�͎l�\���g�ւ�B�����ĎO�܁`�l�l�l������B��������菭����ɂ͒��𗧂āA�������班���O�ɂ͉����̂��鏬��������A���O�̏��ł��Ղɂ͎�x�������B���Ɏ������@�����k�z�o�V���l�ɍg���̕z�𐂂炵�A�w�i�ւ����j�ɂ͑�������B���M�͑��̏��L���ŏU����������Ǘ�����B(��)
|
�X���Q�U���A�ؑ����i�Ђ����j���S���Ȃ�B�@�i�V�Q�j
�P�O���P�Q���A����⑾���S���Ȃ�B�i�W�T�j
�P�O���A���q�R�����u�_���S�b�v���u����Ёv���犧�s����B�@pid/1040087�@�@�{���\
|
�_�� / 3
�u�_���v�̌P�ݕ� / 5
�_���̍��{���_ / 5
�_���̐��X��` / 7
��铂Ɛ_�� / 11
��铐_���Ə@�h�_�� / 22
�_���勳 / 24
���Z�� / 25
�_���C���h / 25
��Ћ� / 26
�}�K�� / 27
���s�� / 28
�听�� / 28
�_�K�� / 29
��ԋ� / 29
�S�� / 30
�_���� / 30
������ / 31
�V���� / 32
�_���Ƙŋ� / 33
�_���̎g�� / 34
�_���̛��� / 39
�{�n��瑐� / 44
�R���ꛉ�_���E�_���K���_���E
�@�@���@�ؐ_�� / 46
�ɐ��_�� / 49
|
�{瑉��N�_�� / 51
�����_���E�g�c�_���E�g��_���E
�@�@�������_���E���͐_���E�y���_��/52
���Ð_���E���ː_�� / 57
�����Ȍ�̐_�� / 61
���V�� / 72
�����O�_ / 75
�Y�� / 76
�V�ߖ����̐_�� / 77
����̐_�ɂ܂��܂��V�c / 79
�킪�@���͓V�c�É��Ȃ� / 82
�_ / 83 (0049.jp2)
�_?���h / 85
�h�_ / 87
�h�_���c / 88
�c���_�E�c��_�E���_�A�c�_�E��_ / 91
�c�䑷�� / 93
�_�R�ꖽ�E�_�R�\�� / 94
�_�{ / 95
�_�{�̑喃 / 99
�_�� / 100
�Њi / 102
�_�Йҝ`�̍�@ / 104
�_�Ђɚ�铂řҝ`�����@ / 107
��̋{���`�� / 110
�_���_�E / 111
|
���q / 111
�j�� / 112
�_�� / 118
���� / 120
��H�� / 121
���A� / 122
���� / 125
�ʋ� / 126
���A / 127
���� / 128
���� / 131
�� / 131
�_�I / 132
�_�I�̍Ղ�� / 134
���J / 136
�Ր���v / 137
���J�� / 138
�F�N�� / 141
���P / 144
�S�P�̋N�� / 147
�l���` / 149
���n�� / 151
�I���߂ƌ����� / 152
�_���V�c�� / 157
�V���� / 158
�t�H�̍c�ˍ� / 160
|
�_���� / 163
�V���� / 163
������ / 166
��Ր_�Ɣz�J�_ / 166
���_ / 169
�Y�y�_ / 171
�N��_ / 172
������ / 173
���j�מ� / 176
�������� / 177
���V�{�� / 180
�욠�_�� / 181
�R�_ / 182
��F / 184
�܌� / 185
�_���F���V / 186
�_�����E�V / 192
�_�������V / 197
�����Ă��~�܂� / 204
�_�����V / 207
�_���b���V / 214
�_���l / 219
���{�l�ō��̗��z / 220
�唺�Ǝ��̉� / 221
�E
�E |
�P�P���A�u�V������ = The astronomical herald. 36(11)�v���u���{�V���w���v���犧�s�����B�@pid/3304286
|
�ؑ����m���Â�/��������/p117�`119
�×�f�Л{ / ��c�t / p119�`124 |
�����C���l / p124�`125
IX���ɉ����鑾�z�K�y�T�v/p125�`125 |
���a�\��NI���̑��z����y�јf��/p125�`126
����\ / p126�`126 |
�P�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 36(12)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304287
|
�×�Ќ�(��c���m�ɜ�ւ�) / �����C�F / p127�`
�����C���l(XI����) / p143�`143 |
�����Q / p143�`144
�̌��� / p143�`144 |
II���̑��z,���y�јf�� / p144�`144
�E |
|
���쐴�F���u�V������26(6)�`36(12)�v���\�����x�ߐ����E��֘A���nj���������\
| �m�� |
�G�����ƕ� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
�V������ 26(6) p105�`108 |
1933-06 |
�x�ߐ����nj�(��) |
�E |
pid/3304157 |
| 2 |
�V������ 26(7) p123�`129 |
1933-07 |
�x�ߐ����nj�(��) |
�E |
pid/3304158 |
| 3 |
�V������ 27(8) p141�`147 |
1934-08 |
㔎x�ߐ����nj�(��) |
�E |
pid/3304171 |
| 4 |
�V������ 27(9) p168�`172 |
1934-09 |
㔎x�ߐ����nj�(��) |
�E |
pid/3304172 |
| 5 |
�V������ 27(10)p185�`190 |
1934-10 |
㔎x�ߐ����nj�(�O) |
�E |
pid/3304173 |
| 6 |
�V������ 27(11) p207�`210 |
1934-11 |
㔎x�ߐ����nj�(�l) |
�E |
pid/3304174 |
| 7 |
�V������ 27(12) p221�`226 |
1934-12 |
㔎x�ߐ����nj�(��) |
�E |
pid/3304175 |
| 8 |
�V������ 35(7) p79�`83 |
1942-07 |
�閾��s�p����ɉ����鐄�Z�Ɨ��(I) |
�E |
pid/3304270 |
| 9 |
�V������ 35(8) p93�`100 |
1942-08 |
�閾��s�p����ɉ����鐄�Z�Ɨ��(II) |
�E |
pid/3304271 |
| 10 |
�V������ 36(2) p13�`17 |
1943-02 |
��nj�(I) |
�DूƓV���{ / 萌���g / p18�`21 |
pid/3304277 |
| 11 |
�V������ 36(3) p31�`32 |
1943-03 |
��nj�(II) |
�E |
pid/3304278 |
| 12 |
�V������ 36(4)p37�`41 |
1943-04 |
��nj�(III) |
�E |
pid/3304279 |
| 13 |
�V������ 36(11) p119�`124 |
1943-11 |
�×�f�Л{ / ��c�t |
�E |
pid/3304286 |
| 14 |
�V������ 36(12) p127�` |
1943-12 |
�×�Ќ�(��c���m�ɜ�ւ�) |
�E |
pid/3304287 |
|
���A���̔N�A�\�c�������u��̖{���Ƃ��̉��ǁv���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@�@pid/1063830
|
��@���_ / 1
�k��l�@��̎��` / 1
�k��l�@��̋N�� / 2
�k�O�l�@���R�����@�� / 4
�k�l�l�@��@�̎O�̕W���^ / 5
�k�܁l�@� / 10
��@���z��̗��j�Ƃ��̓��� / 16
�k�Z�l�@�G�W�v�g�� / 16
�k���l�@���[�}�� / 20
�k���l�@�����E�X��̐����Ƃ��̌�/24
�k��l�@�O���S���I��Ƃ��̙B�d / 33
�k��Z�l�@���s���z��̓��� / 39
�O�@���A���z��̗��j�Ƃ��̓���/58
�k���l�@�V�ێ��� / 59 |
�k���l�@��� / 65
�k��O�l�@��\���h�Ǝ�� / 70
�k��l�l�@�t�H�ƌ��� / 77
�k��܁l�@�O���_ / 88
�k��Z�l�@�\��N���[�@�Ǝ��\�Z�N�@/91
�k�ꎵ�l�@�I�N�@ / 94
�k�ꔪ�l�@��@���莞��ɉ�����
�@�@�@�����A���z��Ƃ��Ă̎x�ߗ�/98
�k���l�@��x�� / 108
�l�@�{�M��@�̉��v�@���̈� / 121
�k��Z�l�@��Â̗� / 122
�k���l�@�x�ߗ�̓n�� / 127
�k���l�@�����c���Ȍ�
�@�@�@���勝����ȑO�̗�@ / 136
|
�܁@�{�M��@�̉��v�@���̓� / 159
�k��O�l�@�ۈ�t�C�ƒ勝���� / 160
�k��l�l�@�勝�ȍ~�̉��� / 187
�k��܁l�@���c�����y�т��̑� / 202
�k��Z�l�@�����ȑO�̉���_��
�@�@�@�����z��̗̍p / 210
�k�l�@���@�̉��v / 232
�Z�@��̉��� / 265
�k�l�@���m��Ƃ��̉���R�̙d��/265
�k���l�@�����Ȍ�̉䂪���ɉ�����
�@�@�@�����z����Lj� / 276
�k�O�Z�l�@�^�ď����̑��z����lj^��/294
�k�O��l�@���s�����y�Ɛ��E�� / 298
�k�O��l�@�V�������݂Ƒ哌����̐���/308 |
�����̔N�A�]�����N���u�_�Ђƍ������v���u�}��t�v���犧�s����B�@pid/1040090
|
���́@�_���ɂ��� / 1
�_�ЂƉ䓙����
�_�ЂƐ_��
�Ð_���̈Ӌ`
��铂Ɛ_��
���́@�_�Ђɂ��� / 19
�_�Ђ̐���
�_�Ђ̎�ނƎЊi
���Ƃ̍s���Ɛ_��
�_�˂��ˑ�
�Гa
�ʋ{�Ɲ��ЂƖ���
�_���_�E
�_铂ƕ���
��O�́@�Ր_�ɂ��� / 37
�Ր_
�_��
|
���h�ҝ`
�����Ԑ�
������
�ȈՎ��p
�ɐ��_�{
沎��_�{
�����_�{
���_�ƎY�y�_
��l�́@���J�ɂ��� / 67
���J�̖ړI
���J�͚��Ƃ̑�T
���J�̓��e
���J�͚���ł���
�S�͉䚠���̑���
�Ր���v�̖{�`
���J��܂Ƃ�
���J��
|
�{���O�a�̐���
�另��
�_����
�V����
���n��
�F�N��
�{�����J�Ɛ_�{���J�Ɛ_�Ѝ��J�Ƃ�萌W
���
��́@�_���Ə@�� / 111
�@���Ƃ�
�_���̏@���I�s��
�_�ЂƏ@�h�_���Ƃ̍���
�@�h�_����ᢐ�
��Z�́@�_�Ђƚ����� / 120
�������Ƒ��̝̉�
�_�Ђƌl��`
�_�Ђƌ�����`
|
�_�Ђƒ����̖��
�掵�́@�ƒ���J�ɂ��� / 131
�_�I�̕��V�͚����̋`��
�ƒ�Ɛ_�I
�_�I���V�̍Ղ��
�_�I����̌�_�
�_�I����̏ꏊ
���r��
����㊂Ƒ��̒����
��ƍ嗧
�O��
���^ / 13
��A�@�ƒ���J�ƍs����@
��A�@�S�s���ɏA����
�O�A�@�����M���̍��J�_�ɏA����
�l�A�@�_�{�y�������Ј��T
�E |
���A���̔N�A�哌���w�p������u��x�̕����v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@�@�@pid/1044578
|
��@�J�X�g�ƈ�x�̎И��@�P�g��
��@�܂ւ��� / 2
��@�J�X�g�̊T�O / 4
�O�@�J�X�g�̋N�� / 9
�l�@�J�X�g�̑f���Ƃ��̐��i / 17
�܁@�J�X�g�̓N�{ / 27
�Z�@�J�X�g�̎И�I�e�� / 3
���@�J�X�g�̌��� / 40
���@��x�̎И� / 43
��@�J�X�g�̌��y�ћ��� / 51 |
�\�@���Ƃ��� / 56
��@�ŋ��̈�x�I���i�@������l
��@���� / 60
��@�����̐����I�M�� / 68
�O�@�嘩�ŋ��̐M�� / 79
�l�@�����̏o�Ƙŋ� / 83
�܁@����ŋ��̓N�{ / 99
�Z�@��x�ɉ�����ŋ��̖ŖS�ɏA���� / 113
�O�@�C�X���[����x�̕����@���R����
��@�͂����� / 122 |
��@�C�X���[�����̕��� / 126
�O�@�C�X���[����x���� / 130
�l�@�@���v�z / 141
�܁@����ƕ��{ / 149
�Z�@���z�E��`�E���فE�뉀 / 154
�l�@��x���p�̗��z�@���ƕv / 171
�܁@��x�̎��R�ț{�@�M���� / 227
��@��x�̓V���{ / 230
��@�ɛ{ / 264
�� / 287 |
�Z���̔N�A���{���g���u�x�ߌÑ��@�j�����v���u���m���� �v���犧�s����B�@ (���m���ɘ_�p ; 29)�@pid/1063829
|
����
���́@�\���\��x�̋N��
���߁@�\���\��x�̖�� / 3
���߁@���n�����̗�@ / 12
��@�Ñ㕶���̌����@ / 12
��@�V����@�m����ᢒB�^�� / 15
�O�@���E���ᢒB�K��̗�@�m������ / 22
�l�@��OᢒB�K��̗�@�m������ / 28
�܁@�������ė����y���̗�@ / 51
��O�߁@�Ñ㖯���̌×�@ / 65
��@���n�̌×�@ / 65
��@���c�̌×�@ / 77
�O�@���y�̌×�@ / 82
�l�@�o�r���j�A�̌×�@ / 86
�܁@�����䘱�y�ш�x�̌×�@ / 93
��l�߁@�x�߂̌×�@ / 98
��@�x�ߍŌÂ̗�@ / 98
��@�x�ߗ�@ᢒB�̑��K�� / 101
�O�@�x�ߗ�@ᢒB�̑�O�K�� / 120
�l�@��\���h�@�̗R�� / 123
|
�܁@�b����������̓V����@�v�z / 154
�Z�@�x�ߗ�@ᢒB�̑�l�K�� / 191
���@�_�������̗�@ / 194
��ܐ߁@�\���\��x�̗R�� / 227
��@���̌��E / 227
��@�\�����̗R�� / 230
�O�@�\��x���̗R�� / 236
�l�@���� / 272
���́@���S�t�H�̗�@
���߁@���̈Ӌ` / 337
���߁@���S�̗�@ / 338
��@���S���т̍쐬�N���萂��鏊�� / 338
��@���S���т̍쐬�N���萂���ڌ� / 363
�O�@���S�Ɍ��͂ꂽ���@ / 393
��O�߁@�t�H�̗�@ / 408
��@�t�H�̗�@��萂��鏔�� / 408
��@�V��ѓ��_���m�̏����ɛ�����ᔻ / 420
�O�@��[�@�̑n���萂��雉�� / 430
�l�@�t�H��@�̐��� / 445
�܁@���� / 459
|
��O�́@�D���`�y�ъ����̗�@
���߁@���̈Ӌ` / 475
���߁@�\���̋N�� / 476
��@�\�Ə\�� / 476
��@�\�������萂��鏔�� / 482
�O�@�~���y����̌��� / 486
�l�@��\���h�̓x�ɂƓ~���y / 490
�܁@�\������̎��� / 498
��O�߁@������̐��� / 502
��@������̗R�� / 502
��@����̕���� / 506
�O�@����̔z�c��萂����� / 513
�l�@����̒n���v�z�ƕ�����̊��� / 521
��l�߁@�k���Z���M���N�l��̖{�� / 524
��@���i�y�ћ����̋N����� / 524
��@�k�Z���M���N�l�����̔ے� / 530
�O�@���x�I�N�@�̖�� / 536
�l�@���� / 557
�E
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@���@������i���傭�ꂫ�j�́A������̈�ŁA�`����O���̌���6�N�i�I���O105�N�j�܂Ŏg���Ă������A���z��̗�@�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͌Ñ�̒鉤�̖��B���ɓ`����Ă����Ƃ����×�A�ØZ��̈�B
���A���̔N�A�M�������u�x�߂̓V���w�v���u�P���Ёv���犧�s����B�@pid/1878453
|
���� / 1
���� �x�߂̓V���{ / 13
��A�V���{�̋N�� / 13
��A�u��̓V���{ / 28
�O�A��@��ᢒB / 39
�l�A�_�V��萂��鏔�� / 48
�܁A�x�ߓV���{��ᢒB�Ƃ��̓���/58
���� �_���̗�@ / 72
��A�͂����� / 72
��A�O���̗�@ / 73
�O�A�㊿�l����̎{�s / 87
�l�A�㊿�̓V���{ / 94 |
�܁A���@��ᢒB / 102
��O�� �@��̓V���{ / 105
��A[�@�ȑO] / 105
��A�@��̗�@ / 113
�O�A���k�V���N�l�Ƃ��̓V���{�I�Ɛ� / 119
��l�� ����V���{�ɋy�ڂ��������̉e��/126
��A���̙͂B�҂ƓV�� / 126
��A����ɉ����鐼���V����@�̗A��/130
�O�A�E���ᢐ� / 143
�l�A�V����@�̗A�� / 147
��� �����o�y�̗ / 168
��A�������j / 168 |
��A������ᢌ��Ɨ / 174
�O�A�؊Ȃɂ݂�������̗� / 181
�l�A���v�̗ / 202
��Z�� �V���V�� / 211
��A�k�����p�V���i / 211
��A���͎t�̐��삵���V���V��/218
�O�A�ӋV�Ƃ��̗��j / 226
�掵�� �x�߂̐��� / 238
��A�����̗��j / 238
��A�����̓��� / 247
�O�A�����̖��i / 255
�攪�� �v��̐��� / 26 |
���A���̔N�A�u�x�ߒn�����j��n 8�� �x�߉ț{��S�Z�j�v���u���g�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1042379
|
���ҁ@�x�߉ț{�j
���́@�V����@�E�\�c���� / 1
���߁@���� / 3
��@�T�_ / 3
��@�n�҂̏����� / 4
�O�@�x�ߏ��V���{���Վ�ᢓW / 8
�l�@����̌��� / 12
���߁@�_�V�� / 13
��@�_�V�� / 13
��@��鏂̖@�Ƒ��̓V�� / 16
�O�@���S�Ɍ�������鏂̖@ / 22
�l�@��V������ / 26 |
�܁@�ӓV�̖@�Ƒ��̓V�� / 33
�Z�@�ӓV�����睂Ɓk�Z���M�l�ʍt / 40
���@��V���ƟӓV���̘_� / 4
��O�߁@���S���� / 50
��@�����A�\�A��\�l���A
�@�@�@����\���h�A�`�鍨�U / 50
��@�X�L���߂Ɍ������V�ۂ��V���N�� / 58
�O�@���߂�茩����ꟓT�̐��� / 71
�l�@�ď����̐��� / 76
��l�߁@��@ / 91
��@���ȑO�̗�@ / 91
��@�O���_ / 94 |
�O�@���x�I�N�@ / 97
�l�@���Ȍ�̗�@ / 99
���́@�ɛ{�E�M���� / 103
�͂����� / 105
���߁@�Ñ�̝ɛ{ / 108
���߁@��͎Z�p / 114
��O�߁@���J�y�ёc�t�V���q / 123
��l�߁@��͈ȊO�̌Ýɛ{�� / 128
��ܐ߁@����̎Z�{���x / 139
��
�E
�E |
���A���̔N�A�����V���ЉȊw�����ҏW���ҁu�����w�Z�V���ނɂ�鎩�R�ώ@�̋����v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/1062970
|
�t���҂� / 1
���݁E���勳���E���{���m�@�{�c���� / 2
�e�t�E�_�яȔ_����鄏�Z�t�@�͓c�} / 4
�q�o���E�_�яȔ_����鄏���@�m���x�V�� / 6
���_�J�E������{�u�t�@���O / 9
�~�d�X�}�V�E���{���m�@�Ð쐰�j / 12
���قЎ��E�����ț{���������E���{���m�@�n��e���Y / 14
�������̐��b�E����������u�t�@�����t�Y / 16
�t���E�A�����t�����@���㒉�h / 18
���p�E�O�����V����Z�t�@�_�c�� / 21
�����P�E�Óc�m����{�Z�����@�O�Λ� / 24
�͂���E���H�Ȓ����x�ʍt���������@���c�ÐM / 26
���̂����E���H�Ȓ����x�ʍt���������@�����N / 28
�Ă̂��� / 31
�t�E���叕�����E���{���m�@�����Εv / 32
�J�c���E���Y�u�K���������E���{���m�@������㏼ / 34
���͔|�E�_�яȔ_����鄏�Z�t�@�n���� / 36
�c�A�E���勳���E�_�{���m�@����\�g / 39
�Ď��E�����������������@�n粕q�v / 42
�~�J�E�������ۑ�Z�t�E���{���m�@���R�v�� / 44
���сE���{���m�@�؉��A�� / 46
�[�x�v�E�������ۑ�Z�t�@�q�ΘZ�Y / 48
���[�܂�E���j�c��{�u�t�@��K���e / 50
�����ԉE���{���m�@���V�E�u�q / 52
�I�E�����Ț����ďC���@�������Y / 54
�Ẳ_�E�������ۑ�Z�t�E���݁@�������� / 56
���E�k�叕�����@�g�c���� / 59
�A�T�K�z�E���������t�����E���{���m�@�ۈ�R�m / 62
���₯�E��勳���E�Λ{���m�@�؉��Ǐ� / 64
|
�H�ɂȂ� / 67
�H�̎����E���勳���E���{���m�@�{�c���� / 68
��峁E�O�{�K�@�����@����푾�Y / 71
�����E�����ț{�����ٚ����@�Ô����H / 74
��S�\���E�������ۑ�Z�t�@��J���� / 76
�Ƃ肢��E�������_�����E�_�{���m�@�i��ЎO�Y / 78
�b�B�̏H�E�����ȑ̈犯�E�Λ{���m�@�V����j / 80
�H�̂Ƃ�ځE�_�яȔ_����鄏�Z�t�@�؉����� / 82
������E�����ʼnY�d�����������@���c��Y / 85
�b���E���勳���E�_�{���m�@����\�g / 88
���E�������ۑ�Z�t�@��J���� / 90
�g�t�Ɨ��t�E���叕�����E���{���m�@�����Εv / 92
�C�e�t�E���勳���E���{���m�@����l / 94
�~���}�ւ� / 97
���t�����E����_�{�����Y�{�����@���R���V / 98
�Ƃ�͂��E���叕�����E�Λ{���m�@�����x�Y / 100
���킩���E���������E���{���m�@��ꝋg / 102
���E�������ۑ�Z�t�E���{���m�@���R�v�� / 105
���g�v�E���������E���{���m�@��ꝋg / 108
�ЂтƂ����₯�E�c�叕�����E�Λ{���m�@�����q�Y / 110
�t�N�W���T�E�E���{���m�@�q��x���Y / 112
�H�����E���k��勳���E�H�{���m�@�{�鉹�ܘY / 114
���������E�O�����������D�{�Z�����@�I������ / 117
�X���Z���E���嗝�{�������A�����@���X�؏��F / 120
���������肱�ڂ��E���勳���E�H�{���m�@�������s / 122
���O���E��勳���E���{���m�@��_�N�ܘY / 124
�t��҂E�����Ț����ďC���@�����p�j / 126
���Z�� / 128
�E |
|
| 1944 |
19 |
�E |
�P���A�씨�K�v���u���ʐ��{�v���u�n�l���فv���犧�s����B�@���łr�P�T�E�X
|
���́@���ʎO�p�@
�P ���ʎO�p�`
�Q�@���ʎO�p�`�̊�{����
�R�@�����̌���
�S�@���p���ʎO�p�`
�T�@�ɎO�p�`
�U�@�c���������������̌���
�V�@�m�����������̌���
���́@�n��
�P�@�n���̌`
�Q�@����
�R�@���]�y�ь��]
��O�́@�V�̍��W
�P�@�V��
�Q�@�V�����W
�R�@���x�ƕ��ʊp
�S�@�Ԉ܂Ǝ��p
�T�@�ϑ��҂��씼���ɋ���ꍇ
�U�@�Ԍo�ƐԈ�
�V�@���o�Ɖ���
�W�@��o�Ƌ��
�X�@���W���݂̊W
�P�O�@������
�P�P�@���ϑ��z��
�P�Q�@���p���
��l�́@�f���̌��]
�P�@�j�����������̖@��
�Q�@��铉^��
�R�@�ȉ~�O��
�S�@�O���v�f |
�T�@���z�n
�U�@���z�n�ɑ�����V�̂̎���
�V�@�n�����]�ɔ��Ӓn����̏����ہi�G�߁j
�W�@����
��́@��
�P�@�P����
�Q�@��A�N�A�P���N�A�ߓ_
�R�@��
�S�@���ϑ��z��
�T�@���ώ��y�эP�����̑��݊��Z
�U�@�W����
�V�@���p���
��Z�́@�C��
�P�@�C��
�Q�@���܂̖@��
�R�@�V�̂̋C��
�S�@�V�������̏������ꍇ�̋C��
�T�@�C���̈�ʎ�
�掵�́@����
�P�@����
�Q�@�n�S����
�R���ʊp�y�э��x�ɋy�ڂ��n�S�����̉e��
�S�@�����a
�T�@�Ԍo�Ԉ܂ɑ���n�S�����̕
�U�@�N�T����
�V�@���o���܂ɑ���N�T�����̕
�W�@�Ԍo�Ԉ܂ɑ���N�T�����̕
�X�@�N�T�����̑���
�攪�́@���s��
�P�@���s�� |
�Q�@���o���܂ɋy�ڂ�
�@�@���N�T���s���̉e��
�R�@���s���̑ȉ~
�S�@�Ԍo�Ԉ܂ɋy�ڂ����s���̉e��
�T�@���s���퐔�̑���
�U�@�f�����s��
�V�@���T���s��
���́@���y�͓�
�P�@��
�Q�@���̐Ԍo�Ԉ܂ɋy�ڂ����̉e��
�R�@�͓�
�S�@�X�ɑ���͓�
�T�@�f����
�U�@���ϐԓ��y�ѐ��̕��ψʒu
�V�@�i�N�ω�
�W�@���ԓ��y�����ʒu
�X�@���̎��ʒu
��\�́@���y�ܓx�̑���
�P�@���z�P���x�@
�Q�@���̒P���x�@
�R�@�����x�@�ɂ�鎞�̑���
�kA�l�q�ߐ��̓����œ���̐���
�@�@�����x���������Ȃ鎞���𑪒肷��@
�kB�l���z�����x�@
�kC�l�ߌ�Ɨ����̌ߑO�ɑ��z��
�@�@�������x�����ϑ�����@
�S�@�ِ������x�@
�T�@�ܓx
�U�@�P���̎q�ߐ���̍��x�𑪂�@ |
�V�@�T�ɐ��̏�o�߁A
�@�@�����o�߂����ɑ���@
�W�@�C�ӈʒu�̐��̍��x�Ɉ˂�@
�X�@�q�ߐ��ŋɂ��ߖT�Ŋϑ�����@
�P�O�@�C�ӎ��̖k�ɐ����x�Ɉ˂�@
��\��́@�o�x�̑���
�P�@�o�x
�Q�@���ԉ^���@
�R�@�L���d�M�@
�S�@�V�̌��ۂ𗘗p����@
�T�@�����d�M�ɂ��@
��\��́@���ʊp�̑���
�P�@���ʊp
�Q�@���ʕW
�R���̑I���N
�S�@���ɐ��̍ő嗣�u���ߖT��
�@�@���ϑ��Ɉ˂�@
���
�k1�l����
�P�@���z
�Q�@���z�퐔
�R�@�����ʓ��˗�
�S�@���ώZ��
�T�@�n���S�̂Ɏ���˗�
�U�@���ߗ�
�V�@����ܓx���̓��˗�
�W�@���ߗ������Ȃ�ꍇ�A
�@�@���n�\�ʑS�̂̓��˗�
�k2�l���̎��^��
�k3�l�k�ɋy��ɒn���ɉ����锖�� |
�P���A���c�S�g�������ȋ��w�Ǖҁu�j���ƍ������_�v�����s����B�U���@���łP�T�N�V��
�Q���A�u�Ǐ��l 4(2);2���j�v���u�������v���犧�s�����B�@pid/11208916 ��
|
���_�̓��\�ېV�j�S���i���j�\/�ǖ�W / 1�`
�����j�V�𐳂�/�c�����Y / 5�`
�o�Ŏ��Ɛ����Ƒ���趎��ᔻ/�쑺�d�b / 9�`
�����Ɛ_�\���̒q�d�\/�ѐM / 12�`
�S�Z �ېV�S�Z�Ƒ����h�\�R���a�Y���w�����f�Վj�x�𒆐S�Ɂ\/���J�\���� /14�`
�����{ ���{�j�V�̈�V�\�u�N���搶��e�v�Ɓu�㏠�L�v�̙B���\/����C /18�`
�N�{ �����̎R���\�c�����Y���u�����v�\/�O�V��j / 20�`
�Y�� �H���������x�̌���/����o / 22�`
�Z��椕� ����������������ɂ���/�������� / 24�`
�v�z ���y�̏�/���㎟�j / 26�` (
�ț{ �g�]�搶�ƌ䒘���u�ɛ{�v/���쏟�� / 28�`
�ț{ �M���C�N�̐V���u�x�߂̓V���{�v/�r�؏r�n / 30�`
�ҏS�҂̓��\���k���\/�[���K�� ; �����G�� ; �_�R�T�� ; �����A ; ��������/31�`
|
�V�����ޖژ^ ���a�\���N�\��/������ �Ҏ[ / 45�`
������ ���E���� �\��/ / 54�`
���{�o�� ���E���� ��Z��/ / 57�`
�c�����Y���u�Øœ����v/�y�偠�v / 60�`
�����E�^/ / 63�`
趎��E/ / 63�`
���^�@�����Ȕ[�{�E? ���a�\���N�\�i�S�j/ / 64�`
����z�{�ژ^ ���a�\���N�\��/������ �Ҏ[ / 65�`
���`�ځi���ꌎ������ꌎ�O�\����j/ / 67�`
�ҏS��L/ / 67�`
�哌���D�萌W趎��L������(24)�\���\�ꌎ���l�� ���\���ܓ��\/ / 68�`
�V�������v ���a�\���N�\��/������ / 72�`
�E |
�Q���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 14(2)�v���u���s��w�l���Ȋw������,���������������v���犧�s�����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558903
|
�����y����k��ᢌ��̌Ë� / �~������ / p1�`36 |
������@�j / �M���C / p110�`128 |
�R���A�u�V������ = The astronomical herald 37(3)�@ p25�`25 ���{�V���w��v�Ɂu�w�×�Ќ��x����\�v���f�ڂ����B�@pid/3304290
�R���A �n�ӕq�v���u��̘b�v���u���i���v���犧�s����B�@�@pid/1720138�@
�{���\
|
���� ��̂���܂� / 2
���� ��ɕK�v�ȓV���{ / 18 |
��O�� �� / 76
��l�� ���z��@ / 104 |
��� ���A��@(���͗�) / 132
��Z�� ���A���z��@ / 139 |
�掵�� ���{�̗� / 154
�攪�� ��̉��� / 197 |
�R���A�u�V�E = The heavens 24(272) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219993
|
����笕M:�����V���i�͑`�J����,�D���
�@�@���{���q�ߐ���褓��X / �R�{���C / p71�`73
����(�g�D,�ϑ���,������萂����) / p70�`70
�����x�V�̓}���X��萌W���� / ��K���e / p74�`76
�{�N�x�̓V铈ʒu����̕W���� / p76�`76
����䓚(2��) / p76�`76
�⋾�����ɉ�����A�����j�����̉��֕��ɏA��
�@�@��(�I�v90) / ���F�� / p77�`79
�����V���{���}��ژ^ / p79�`79
���������v�̈�l�@ / �R�{���C / p80�`84
�Ҏ���20���̓��I���ꗗ�\(�O�j"�r���}�̓��I"�Ǎe) / p84,85
|
���^:�j�E�J�����ʓV���{�v�j(8) / p45�`48
�W���V���p��\(24) / p86�`87
�c���:1943�N���̉����ϑ��� / �R�{���C / p88�`88
�V���Љ�:"�x�ߌÑ��@�j����" / ���{���g / p89�`89
�V��������:����(�ܘZ������,���a16�N�O����
�@�@���V����,���2��) / �����V������ / p90�`98
���V��(�G���X�̘���) / p95�`95
���z(�{�N��O�����̍��y�V�����) / p97�`97
�������̕� / p97�`97
�a���E�̋ߏ� / p97�`97
�{�N�ܘZ���̓V�ۘ��z / p100�`100 |
�S���A��K���e���u���������{�̐��̖{�v���u�����Ёv���犧�s����B�@���R���F�G�@�@pid/1720137
�{���\
|
(���{��)
�l�� �t�̖�̐� / 4
�܌� ��t�̂���̐� / 23
�Z�� �h��̖�̐� / 36
���� ���Ȃ��� / 52
(�����x��)
|
���� �C�ׂŌ����� / 74
���� �R�Ō����� / 88
(���{��)
�㌎ ���H�̐� / 106
��E�\�� �\�ܖ�̖��� / 122
�\�ꌎ ��������Ɛ� / 136
|
�\�� ����������� / 150
(��O�{��)
�ꌎ �����̐� / 170
�� �ߕ�����̐� / 182
�O�� �~�炭����̐� / 192
�l�G�̐��� |
�t�̐��� / 2
�Ă̐��� / 72
�H�̐��� / 104
�~�̐��� / 168
�E
�E |
�V���A��K���e���u��m 30(7)p17�`21�@��m����v�Ɂu��\�����̘b�v�\����B�@�@pid/1489918
�P�P���A�u�V�E = The heavens. 24(278) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@ pid/3219998
|
����痢���̏ё��Ɨ��N�� / p230�`230
����҂Ƃ��Ă̐���痢�N���v�� / �R�{���C / p231�`234
����搶������ / ��ꠍF���� / p234�`236
����搶�Ǝ� / ���c�B / p236�`237
�v�Џo�Â�܁T�̋L / �Y����� / p237�`239
�q�~�V���V�̐���厖���Â� / �����g�� / p240�`242
����痢�搶���Â� / �Έ�I�j / p242�`242
|
����搶�䑸���̎v�Џo / �c���i���� / p243�`243
�D�͂Ƃ��Ă̓V���m�� / p243�`243
�{����ɉ����鐅��痢����e���̖ژ^ / p244�`245
���� / p245,247
�{���V�������� ����(��151���:���a12�N�O,
�@�@���l��) / �����V������ / p246�`247
���V���p���X�Ƒ����S�H(���߂̓V��) / p248�`248 |
�P�Q���A�u�V�E = The heavens. 25(279)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3219999
|
(����)���{�Վ��̓V���{ / �R�{ / p2�`2
����Ɍ�����P���̝ɂɂ��āk�I�v95�l/���㒉�h/p3�`8
�ؐ��ϑ��̛��� / �ɘ@�p���Y / p9�`15
�W���V���p��W(27) / p16�`17 |
�{���ϑ������� ������(��152��,���a12�N
�@�@���ܘZ����������) / p18�`19
���� / p19�`19
�]�����ɂ��V�����̐e���ړx�̐V�K�� / p20�`20 |
���A���̔N�A��K���e���u�}����S�V������ : ���p�E�ϑ��p�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1063812
|
��ꕔ�@���n�E�ގx�̐���
�{���̗p�@ / 3p
�p�ꗪ�� / 4p
�k�V�̏T�ɐ� / 5p
�������
�t�iI�j��̋� / 6p
�iII�j�k�̋� / 7p
�āiI�j��̋� / 14p
�iII�j�k�̋� / 15p
�H�iI�j��̋� / 20p
�iII�j�k�̋� / 21p
�~�iI�j��̋� / 26p |
�iII�j�k�̋� / 27p
��������
�P�@��F�E�R�L�E�����q/8p
�Q�@���F�E�� / 9p
�R�@���q�E�I�E�Z���V/10p
�S�@�C�ցE�R�c�v�E��/11p
�T�@�����E�V�� / 12p
�U�@�����E�k���E�،�/13p
�V�@�w���N���X�E�� / 16p
�W�@���E�ցE�| / 17p
�X�@�h�E�����E��E�C�� / 18p
�P�O�@噁E�ˎ�E�슥 / 19p
|
�P�P�@�R�r�E���r�E�싛 / 22p
�P�Q�@�y�K�X�X�E��E�� / 23p
�P�R�@�P�t�F�E�X�E�J�V�I�y��/24p
�P�S�@�A���h�����_�E�y���Z�E�X/25p
�P�T�@�f�ҁE�O�p�E���r / 28p
�P�U�@�����E�o�q / 29p
�P�V�@�~�E�G���_�k�X�E�e / 30p
�P�W�@�I���I���E�匢�E���� / 31p
���@������̐��� / 32p
�i���^�j���ɂ����p�E��������/43p
�E
�E
|
���A���̔N�A����啶���u�ߐ��ɉ�����_�_�v�z�v���u�t�H�Ёv���犧�s����B�@pid/1040098
|
���� / 3
���́@�� / 8
���߁@�_�Е� / 8
��@�P��� / 8
�C�@�_�{ / 8
���@�ΐ����� / 12
�n�@��Ύ� / 20
�j�@�t���� / 25
�z�@�������Ƌ{ / 25
��@�Վ��� / 28
�C�@�_�{ / 31
���@�ΐ����� / 44
�n�@��Ύ� / 47
�j�@�M�z�\�� / 51
�z�@������ / 51
�w�@����� / 51
�g�@�j�� / 52
�`�@�t���� / 52
���@�F���{ / 53
�k�@���ŋ{ / 55
���@�������Ƌ{ / 56
���߁@�R�˕�/56
�C�@�_���V�c�� / 58
���@��O�����R�� / 63
�n�@��a�E�͓��E���ÁE�a�R��/63
�j�@�R��E�O�g���R��/64
�z�@�_���c�@�� / 66
���� / 66
���́@��F�� / 69
���߁@���Ќ�F��/69
�C�@�V�ی��N / 69
���@�V�ۏ\��N / 70
�n�@�V�ۏ\�l�N / 70
�j�@�O���O�N / 70
�z�@�O���l�N / 71
�w�@�Éi�O�N / 71 |
�g�@�Éi�Z�N / 72
�`�@�������N / 75
���@������N / 80
�k�@�����O�N / 82
���@�����l�N / 83
���@�����ܔN / 83
���@�����Z�N / 86
�J�@�݉����N / 87
���@���v���N / 88
�^�@���v��N / 89
���@���v�O�N / 89
�\�@�������N / 90
�c�@�c�䌳�N / 91
�l�@�c���N / 91
���߁@��Ќ�F�� / 93
�C�@������ / 93
���@�����F�{�E���{ / 97
�n�@�ΐ����� / 97
�j�@�t���� / 98
�z�@�M�c�� / 99
�w�@�k��� / 99
�g�@�F��� / 100
�`�@�_���� / 101
���@�������� / 102
�k�@�p�F�R�� / 102
���@������ / 103
���@�H�t�_�� / 105
���@���� / 107
�J�@�@���� / 108
���� / 108
��O�́@�_�Ѝs�K / 110
���߁@�_�Ђƍs�K / 110
���߁@��ΎЍs�K / 111
��O�߁@�ΐ����Ѝs�K/113
��l�߁@��a�s�K�̝�/115
��l�́@��@�� / 116
|
���߁@�O���ƌ�@��/116
���߁@������ / 118
��O�߁@�_�{ / 120
��l�߁@�ΐ����� / 121
��ܐ߁@��Ύ� / 122
��Z�߁@�t���� / 125
��́@�_�j�E�_�K�̐鉺 / 127
���߁@�_�j�̐鉺 / 127
���߁@�_�K�̐鉺 / 131
��Z�́@�ՋV�p�V�̕��� / 138
���߁@����̕��ÓI�X�� / 138
���߁@�F�N�Սċ��̋c / 139
��O�߁@�_�_���ċ��̋c / 141
��l�߁@�V�{�ċ��̋c / 154
��ܐ߁@������݂��̋c / 159
��Z�߁@����j�̕��� / 159
�掵�߁@�R�˂̕��� / 162
��@�R�˂̌�C�� / 162
��@�R�˂̕��� / 165
�攪�߁@���˗��̕��� / 169
���߁@�_���Ւ��p�V�̕��� / 170
��\�߁@�V���Ւ��p�V�̕��� / 171
��\��߁@�k��Վ��Ղ̕��� / 172
��\��߁@�t�����p�V�̕��� / 173
��\�O�߁@�g�c�Ղ̕��� / 176
��\�l�߁@�_���Վ��Ղ̕��� / 178
��\�ܐ߁@�匴��Ղ̕��� / 180
��\�Z�߁@�����Ղ̕��� / 180
��\���߁@�����А_�ق̕��� / 182
��\���߁@�k��А_�ق̕��� / 182
��\��߁@��ΗՎ��Ոꕑ�̕���/184
���\�߁@�ΐ����Վ��Ոꕑ�̕���/184
�掵�́@�_�Ђ̑n�� / 185
���߁@�_�АM�� / 185
���߁@�_���V�c�Бn���̋c / 190
��O�߁@����{�̑n�� / 192
|
��l�߁@����Ђ̑n�� / 198
��@�F���̓���� / 199
��@����̓���� / 200
�O�@���É��̓���� / 200
�l�@����_�Ђ̞ܗ` / 201
�܁@�v�⌺����Б��z�̋c / 206
��ܐ߁@���R�_�� / 207
��Z�߁@���s���� / 209
�掵�߁@������ / 210
�攪�߁@���Ƌ{���J / 214
���߁@�@���� / 215
�攪�́@�_�_���̋��� / 217
���߁@����� / 217
��@����� / 218
��@������ / 219
�O�@�R���� / 219
�l�@�Øa��� / 220
�܁@�R���ˊ�� / 221
�Z�@���ؘa�� / 221
���@�O�������� / 223
���@�ߓ��F�� / 225
���߁@������ / 226
��O�߁@�_���� / 231
��l�߁@�g�c�Ƃ̐_�������^�� / 237
��ܐ߁@���˂̐_������ / 239
��@���˔� / 239
��@�R���� / 242
�O�@���Z���� / 245
�l�@�Øa��� / 246
�܁@���m�� / 248
��Z�߁@�u�m�̐_���I���{ / 248
�掵�߁@�K���̊��� / 259
���_ / 264
������ / 267
�E
�E |
���A���̔N�A�M�������u�x�ߐ��w�j�T���v���u�R�����X�v���犧�s����B�@�@�@pid/1063492
|
���_ / 1
���́@�Ñ�̝ɛ{ / 11
��A�@�L�ɖ@ / 11
��A�@��@�Ɲɛ{ / 15
�O�A�@����̎И��Ɲɛ{/18
�l�A�@�Z�̎g�p / 21
���́@��͎Z�p / 30
��A�@��͎Z�p / 30
��A�@����̝ɛ{ / 43
��O�́@���J�y�ёc���V���q/48 |
��A�@�Z���̝ɛ{ / 48
��A�@���J / 53
�O�A�@�c���V���q / 57
��l�́@�Z�S�\�� / 65
��A�@���q�Z�S���̑�/65
��A�@�Z�S�\���̗��B/76
��́@�@���̝ɛ{/80
��A�@���k�V���N�l�̋Ɛ�/80
��A�@����̎Z�{ / 82
�O�A�@��x�ɛ{�̗A��/88
|
��Z�́@�v���̝ɛ{�ƓV���p/94
��A�@�x�ߝɛ{�̔�� 94
��A�@�`����A�k�P / 98
�O�A�@�����A�鐢�� / 104
�l�A�@�V���p�A�l���p / 109
�܁A�@�����̋Ɛ� / 117
�掵�́@����̝ɛ{ / 123
��A�@���l�ɛ{�̖u�� / 123
��A�@�\���o���̗��s / 126
�O�A�@����̝ɛ{�� / 130
|
�攪�́@���m�ɛ{�̗A��/135
��A�@�鋳�t�̓n�҂Ɲɛ{/135
��A�@���m�ɛ{�̓��e / 151
���́@����̝ɛ{/ 156
��A�@�����̝ɛ{ / 156
��A�@�ÎZ���̍Ğ��� / 161
�O�A�@��НDैȌ�̝ɛ{/171
���� / 180
�E
�E |
���A���̔N�A�M�������u�@����@�j�̌����v���u�O�ȓ��v���犧�s����B�@ (���m��p�������ƕ�)�@pid/1063834
|
�����@�\�c�������m
�ጾ
���� / 1
���́@�@��̗�@ / 8
���́@����̗�@ / 21
��@���_ / 21
��@�����̗�@ / 24
�O�@�����̗�@ / 32
�l�@�ӓ��̗�@ / 44
��O�́@�@����@�̊�{��� / 53
��l�́@�����V�����l / 61
��@�����V�p / 61
��@�������p / 74
�O�@�㓹�p / 83
|
�l�@���� / 91
��́@������p / 95
��@�������̌v�Z / 95
��@���H�̌v�Z / 101
�O�@�埥��ɉ�������H�v�Z / 107
�l�@�閾��ɉ�������H�v�Z / 114
�܁@���� / 129
��Z�́@�㎷��̌��� / 134
��@���_ / 134
��@�ϓ��̌v�Z / 141
�O�@�����̈ʒu�v�Z / 146
�l�@���̎��� / 151
�܁@���H�̌v�Z / 153
�Z�@���H�̌v�Z / 159
|
���@�㎷��Ɠ����@ / 170
���@���� / 173
�掵�́@�㎷��̖{�� / 177
�v�|�T�� / 200
���^ /
�u������@�Ɏ���x�ߗ�@�j / 205
�͂����� / 207
��@��@�̊m�����閘 / 214
��@����̗�@ / 219
�O�@�O������̗�@ / 230
�l�@���̗�@ / 238
�܁@��k������̗�@ / 243
�Z�@�@��̗�@ / 254
�E |
|
| 1945 |
���a20 |
�E |
�E |
| 1946 |
21 |
�E |
�P���A �M�������u�����w�� = Journal of Oriental studies 15(2)p1�`22 �@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu���m�V���{�̓��Q�\�C��̗�@�v�\����B
(���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558907
�R���A����k������l���u��������趎��v���u�S�����[�v���犧�s����B�@ pid/2421690
|
�� ������ / p1
�� �h�B�V���� / p8
�O �V���q�C / p15
�l ��x�̓�m�q�C�̓��� / p20
�� �֑D / p24
�Z �d / p33
�� )�{�l / p38
�� �������j�j趍l / p46
�� 㔒������j�j趍l / p57 |
��Z ���� / p68
��� �J�ʌv / p74
��� �[�x�v / p81
��O �z���u�Չ� / p87
��l ���ڍl / p95
��� �{� / p102
��Z �k�ӂ������l / p108
�ꎵ ���� / p116
�ꔪ ��ꉂƉ�� / p126
|
��� �Z���̟��ۛ{�� / p130
��Z ������蹍� / p137
��� �N�����N�̒n�k�� / p147
��� ������囍� / p151
��O �l��ۍ��P� / p160
��l �������̉��� / p171
��� ��꒹ / p181
��Z �Ջu�̎Γ� / p186
�� �������l / p189 |
�W���A���쐴�F���u���{���I�̗���ɂ��āv�����s����B�@�K���ō���40�y�[�W�@�d�v
�����̔N�A�����ؐM�j���u���̗w�̌����v���u�l�����@�v���犧�s����B�@�@pid/1069686
|
����
���̉��
���L���{���I���� / 1
��{�����@��������� / 128
�ݗt�W���� / 131
���S�W������ / 151
㔓��{�I���� / 154
�c���_�{�V�������� / 155
�Ì�E�⏊�� / 157
����{������P���ˈًL����/158
|
�������M�c��_���N���� / 159
�{�����ߏ��� / 161
�Չ̕����� / 163
�������q�B��� / 173
�헤���y�L���� / 174
�d�����y�L���� / 178
�O�㕗�y�L���� / 180
��O���y�L���� / 183
�Е� / 185
�j���掌�y�ьꎌ |
�F�N�� / 191
���P�� / 194
�o�_�����_�ꎌ / 196
���掌 / 198
�r�Ύ� / 198
������ / 199
���ۓs���̂��q / 200
�V�����̐� / 200
��b�����̑i / 201
�E
|
����揂̊T�V
���� / 205
���������_���̉�� / 208(
���́@�o�����쎞��y�ј���̍�ɏA���� / 208
���́@�����_���̉�揂̐����Ƃ��̝̑J / 219
��O�́@�j���掌�y�ьꎌ�ɏA���� / 224
��l�́@�����_���̉�揌����̗��j / 227
��́@���p���y�љҍl���� / 232
�E
�E |
|
| 1947 |
22 |
�E |
�U���Q�T���A�\�c����,�M�����������������������u�������������������� ��19���@��������u�̌����v���u�S�����[�v���犧�s����B�@pid/1070983�@�@�ŏd�v�@
|
�O���p�̌��� / 1
���_ / 2
��@��������Ƃ��̗�@ / 6
�@�k��l�@��������Ɏ���ߒ� / 6
�@�k��l�@��p�b�q�� / 14
�@�k�O�l�@�����{�s�̗�@ / 19
�@�k�l�l�@�l����Ƒ������萌W / 27
�@�k�܁l�@����Ȍ�ɉ����鑾�����ᢓW/34
��@�O���p�̖@�� / 44
�@�k�Z�l�@�N���̒����Ə͓��� / 44
|
�@�k���l�@�ߟ��Ƒ��z�̈ʒu / 51
�@�k���l�@�����H�̌v�Z / 60
�@�k��l�@�ܐ��̉^�s / 66
�@�k��Z�l�@� / 77
�O�@�O����̐��� / 87
�@�k���l�@������ƎO���� / 87
�@�k���l�@�O����̖��` / 90
�@�k��O�l�@���C�@�Ɨ / 98
�@�k��l�l�@�~�����V�ɂ��� / 102
�@�k��܁l�@�O����̐��� / 107
|
�l�@�����̍Ζ� / 113
�@�k��Z�l�@���I�N�@ / 113
�@�k�ꎵ�l�@�����̍Ζ� / 128
�܁@���S�̌��� / 137
�@�k�ꔪ�l�@�u���̔N�� / 137
�@�k���l�@���e���e�l / 150
�@�k��Z�l�@�t�H�̓V�� / 158
�@�k���l�@�t�H�̓��H / 165
��������u椏�趋L / 181
�E |
|
| 1948 |
23 |
�E |
�W���A���������u�������� (�ʍ� 4) p.40�`43�v�Ɂu�����Ñ�Ȋw�v�z�̈���v�\����B
�P�O���A��K���e���u������݂��� 1(1) p.40�`43�v�Ɂu���h����-�k���h�E�l�h�E���h�l �v�\����B
���A���̔N�A�\�c�������u��w�j�_�v���u�����Ёv���犧�s����B�@�@pid/1377900
|
���� ���_
�k��l �R���~ / p1
�k��l ��̏��� / p3
�k�O�l ���R�����@�� / p5
�k�l�l ��@�̎O�̌^ / p6
�k�܁l ��p��ƛ���� / p12
���� ���z��
�k�Z�l �G�W�v�g�� / p16
�k���l ���[�}�� / p19
�k���l �����E�X�̉��� / p24
�k��l �����E�X��ƃA�E�O�X�c�X / p28
�k��Z�l�����E�X��ƃR���X�^���`�k�X / p32
�k���l �T���̖��i�Ə��� / p34
�k���l �O���S���I�� / p36
�k��O�l �O���S���I��̙B�d / p43
�k��l�l �͘��Ƃ��ẴO���S���I�� / p45
�k��܁l ������ / p49
�k��Z�l �����E�X�����y�эΎ�� / p51
��O�� ���A���z��
�k�ꎵ�l ��x�y�ѐ��m�̑��A���z�� / p62
�k�ꔪ�l ������Â̗�@�\�k�Z���L�l�ʍt / p66
�k���l ��� / p73
�k��Z�l ��\���h�Ǝ�� / p78
�k���l ���߂Ət�H / p85
�k���l �O���_ / p97
�k��O�l �\��N���[�@�Ǝ��\�Z�N�@ / p100
�k��l�l �I�N�@ / p103
�k��܁l ���Ȍ���ߗ�@ / p106
��l�� ���{�ɉ������@�̉��v(��)
�k��Z�l ��Â̗� / p123
|
�k�l ��@�̓n�� / p128
�k�l �A�z���̊�����
�@�@�������͈琧�x / p138
�k���l ���M趗� / p144
(��) ���C��萂������ / p145
(�C) �ܐ� / p145
(��) �k�l���� / p152
(�n) ���j�� / p153
(�j) ��j�� / p154
(�z) ��\���h / p156
(��) �܍s���x��萂������/p157
(�C) ���T / p157
(��) �܍s / p159
(�n) ���x / p160
(�j) �㐯 / p161
(�O) �����̋g����萂������/p163
(�C) �\�� / p163
(��) �\��^ / p165
(�n) ���� / p166
(�j) �\����ƓV��V��� / p167
(�z) �Ɠy / p168
(�w) �M�\ / p168
(�g) �O���� / p168
(�`) ���̋g�� / p169
(��) �Z�j�� / p170
(�k) ���E / p171
�k�O�Z�l �v�ߊv�� / p173
�k�O��l ���\����Ɠ�S�\�� / p175
�k�O��l �ފ� / p176
��� ���{�ɉ������@�̉��v(��) |
�k�O�O�l �ۈ�t�C�ƒ勝�̉��� / p180
������ / p208
�k�O�l�l ����̉��� / p211
�k�O�܁l �����V�ۂ̉��� / p228
�k�O�Z�l ���c�����Ƃ��̑� / p236
�k�O���l �����ȑO�̘_���
�@�@�������̑��z��̗p / p248
(�C) ���a�q�C�L / p249
(��) �I�����_���� / p250
(�n) ����|�R�̑����댾 / p251
(�j) �{�������̘_�� / p258
(�z) ���䗚���̉���� / p260
(�w) �R��崓��̖��̑� / p264
(�g) �V�S���Ԃ̓V�� / p268
(�`) �V����ߕ�����ݐ��c��� / p270
(��) �V�����ԂƐ��여 / p273
(�k) �����M���̑��z�����x / p275
(��) �����̑��z��̗p / p277
�k�O���l ���@�̉��v
�@�@���\���̏o�������\ / p291
��Z�� ��̉���
�k�O��l ��������Ȍ�̓��{�ɉ�����
�@�@�����z����Lj� / p312
�k�l�Z�l �^�����
�@�@�����z����lj^�� / p324
�k�l��l ���s��̉��LjĂƂ��Ă�
�@�@�����E�� / p331
�k�l��l ����Ă̕K�R�I�d�� / p336
�E
�E |
|
| 1949 |
24 |
�E |
�P���A���������u���� (�ʍ� 7) p.33�`40�v�Ɂu�����̌Ñ�Ȋw�v�z�ɂ��āv�\����B
�R���A�n�ӕq�v���u��̂Ȃ肽��: ���N�����̂��߂Ɂv���u�����V���Ёv���犧�s����Bpid/1338549
�@�@�����F�v�����Q���ɐ����ԍ�:529-52 (�ǂݕ�) �����������@��:�����[�����h��w�^pid/8372892
|
���́@��̂���܂� / 1
�P�@��Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂�
�Q�@��̂�����
�R�@�Ȃ���͏d�v��
���́@��ɕK�v�ȓV���w / 26
�P�@�V���Ɛ��̈ʒu
�Q�@���z�̌������̉^�s
�R�@���A�̌������̉^�s
�S�@�V���̌������̉^�s
�T�@�����H
|
��O�́@��̑g�� / 93
��l�́@���A��@�i���͗�j / 103
��́@���A���z?�@ / 111
�P�@�x�ߗ�
�Q�@���x
��Z�́@���z�� / 125
�P�@�G�W�v�g��
�Q�@���[�}��
�R�@�����E�X��
�S�@�O���S���[�� |
�T�@�e���̉���
�U�@�T
�V�@�I��
�掵�́@�V������ / 158
�P�@�O���S���[���㞓_
�Q�@��̉��Lj�
�R�@���E��
�攪�́@���{�̗� / 176
�P�@���{��̗��j
�Q�@��ɂ��邳���趐� |
�R�@�j�Փ�
���́@�� / 205
�P�@���Ƃ͂Ȃɂ�
�Q�@�n���̎��z
�R�@���̑���
�S�@��
�T�@���̐�������
�U�@���@�i�T���}�[�^�C���j
�E
�E |
�U���A�u�V�E = The heavens (307)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220006
|
������ ���ׂĎ��ؓI�� / p165�`16
�����v�l / ���㒉�h / p166�`168
���E�� / p168�`168
�����v�̐v�ƍ�}/
�@�@�������P�v/p169�`176
|
�����͂���� / ��{�i / p177�`178
�M���V���̐����Ɛ�(2)/��K���e/p179�`181
�ܓx�ϑ����\�N�L(2)/�������F/p182�`185
�ꓙ������(��) / �˓c���v / p186�`188
7���̓V�ێ����\�� / p189�`189 |
�ϑ�������:����,�a��/
�@�@�������V������/p190�`192
NEWS / p193�`193
�ǎ҂̕�:��������,����/p194�`196
�E |
�U���A�������Y���u���ʂ̊v���u�n���Ёv���犧�s����B�@�@ (�Ȋw�̐�
; ��29)
|
��P�́@���w�Ƌ��� / 1
��Q�́@���ʂ̐��� / 5
��R�́@���[�N���b�h�w / 12
��S�́@�[�N���b�h�w / 24
��T�́@���ʊw�C�ȉ~�w�C���E�ˉe�w/40 |
��U�́@���W�̘b / 52
��V�́@n�����ւ̊g�� / 65
��W�́@�����̘b / 73
��X�́@�ϊ��Ƃ������� / 81
��P�O�́@�����܂��͕����t��/95 |
��P�P�́@���� / 115
�Q�l�� / 125
���^ / 127
���� / 134
�E |
�U���A�K���������Y���u�����̊��o : �Ȋw�̐� 28�v���u�n���Ёv���犧�s����B�@�@pid/8372678�@�@
�V���A���R�����u���{�{�m�@�I�v 7(2) p.109-139�v�Ɂu�F�N�Ղ̌��� (��) (���a��\�l�N�����\�����)�v�\����B
J-STAGE�@�d�v
�V���A���R�����u���{�{�m�@�I�v 7(3) p.225-238�v�Ɂu�F�N�Ղ̌��� (��) (���a��\�l�N�����\�����)�v�\����B
J-STAGE�@�d�v
|
���́@���_
���́@�F�N�Ղ̏j��
�@�i��j�@����
�@�i��j�@����
�@�i�O�j�@����̒��S�ɂ���
�@�i�l�j�@�u��N�c�_���v�ɂ���
��O�́@�F�N�Ղ̖{��
�@�i��j�@�N���̖L�����F���
|
�@�i��j�@�����ՂƂ̊W
�@�i�O�j�@���J��ɂ�����F�N�Ղ̒n��
�@�i�l�j�@��N�_
��l�́@�F�N�Ղ̐����N��
��́@�F�N�Ղ̍Փ�
��Z�́@�F�N�Ղ̎{�s
�掵�́@���_
�E |
�X���A����g(�肫��)���u��Ɵ���v���u�Í����@�v���犧�s����B�@
�P�O���A�u�V���ƋC�� 15(10)�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@pid/2356965
|
�����\�\Scientific American����� / / 6�`11
�F�����ƒn��������� / �������� ; ����K�j / 12�`15
�ܓx�V�����̎g�� / �������F / 16�`19
z��ᢌ��� �ؑ��Đ搶�̑z�o / �r�c�O�� / 20�`21
����Ɠ��̓n�� / �������g / 22�`25
�k�ț{�j�u���l���E���̊��� / ���nj��� / 26�`27
�����E�����߂��� / ���R��j / 28�`30
|
�L�e�B�䕗 / �E�c���� / 31�`31
�k�V�����͎��l�]�����̕���\ / �����V����V�����k�W / 32�`32
�k���ۂ��͎��l�_�̓i�[����ł��� / �R�c���� / 33�`33
10���̓V�� / �Ô����H / 34�`34
(�����̞ق����V���V��)�V��ᢌ��̊�� / ��萳�� / 35�`35
�w�Z���۔ǂ̂��߂�(2) / �ɍ�B�F / 36�`37
(�\���c�Ԃ̓��L)���䕗���ɂ��� / �v�ėf�F / 38�`38 |
�P�P���A�{�n���i���u�Ȋw���� 9(11)(101) p 31�`34�����V���Ёv�Ɂu���̉^�����猩��Βn���ɋ���������v�\����B�@pid/2335601
���A���̔N�A�n�ӕq�v���u��̂Ȃ肽�� : ���N�����̂��߂Ɂv���u�����V���Ёv���犧�s����B�@�@pid/1338549
|
���́@��̂���܂� / 1
�P�@��Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂�
�Q�@��̂�����
�R�@�Ȃ���͏d�v��
���́@��ɕK�v�ȓV���w / 26
�P�@�V���Ɛ��̈ʒu
�Q�@���z�̌������̉^�s
�R�@���A�̌������̉^�s
�S�@�V���̌������̉^�s
�T�@�����H
��O�́@��̑g�� / 93
��l�́@���A��@�i���͗�j / 103
��́@���A���z��@ / 111
|
�P�@�x�ߗ�
�Q�@���x
��Z�́@���z�� / 125
�P�@�G�W�v�g��
�Q�@���[�}��
�R�@�����E�X��
�S�@�O���S���[��
�T�@�e���̉���
�U�@�T
�V�@�I��
�掵�́@�V������ / 158
�P�@�O���S���[���㞓_
�Q�@��̉��Lj�
|
�R�@���E��
�攪�́@���{�̗� / 176
�P�@���{��̗��j
�Q�@��ɂ��邳���趐�
�R�@�j�Փ�
���́@�� / 205
�P�@���Ƃ͂Ȃɂ�
�Q�@�n���̎��z
�R�@���̑���
�S�@��
�T�@���̐�������
�U�@���@�i�T���}�[�^�C���j
.�E |
���A���̔N�A�M�������u�����̓V���w�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B�@�@�@pid/1160277
|
���� / 1
���́@�����̓V���{ / 1
��A�@�V���{�̋N�� / 1
��A�@�u��̓V���{ / 12
�O�A�@��@��ᢒB / 21
�l�A�@�_�V��萂��鏔�� / 27
�܁A�@�����V���{��ᢒB�Ƃ��̓���/34
���́@�_���̗�@ / 43
��A�@�͂����� / 43
��A�@�O���̗�@ / 43
�O�A�@�㊿�l����̎{�s / 54
�l�A�@�㊿�̓V���{ / 58
|
�܁A�@���@��ᢒB / 64
��O�́@�@��̓V���{ / 66
��A�@�@�ȑO / 66
��A�@�@��̗�@ / 71
�O�A�@���k�V���N�l�Ƃ��̓V���{�I�Ɛ�/75
��l�́@����V���{�ɋy�ڂ��������̉e��/80
��A�@�ŋ��̙B�҂ƓV�� / 80
��A�@����ɉ����鐼���V����@�̗A��/83
�O�A�@�E���ᢐ� / 90
�l�A�@�V����@�̗A�� / 93
��́@�����o�y�̗ / 106
��A�@�������j / 106
|
��A�@������ᢌ��Ɨ / 110
�O�A�@�؊Ȃɂ݂�������̗�/115
�l�A�@���v�̗ / 129
��Z�́@�V���V�� / 135
��A�@�k�����p�V���i / 135
��A�@�鋳�t�̐��삵���V���V��/138
�O�A�@�ӋV�Ƃ��̗��j / 143
�掵�́@�����̐��� / 150
��A�@�����̗��j / 150
��A�@�����̓��� / 157
�O�A�@�����̖��i / 162
�攪�́@�v��̐��� / 168 |
|
| 1950 |
���a25 |
�E |
�P���P�O���A���쐴�F���S���Ȃ�B�i�U�W�j
�Q���A�{�n���i���u�Ȋw���� 10(2) (�ʍ� 104) p.52�`54�v�Ɂu���̈�鐫�ƌo�x�ω�-���a24�N�x������-�v�\����B
�@�@�܂��A������ ; ���{���O���u���� p3�`5�v�Ɂu���q���e�̉e������������L����ABCC�v�\����B pid/2335603
�Q���A�{�n���i���u�V������ = The astronomical herald 43(3) p.24�`27�v�Ɂu�o�x�ω��ɂ��āv�\����B�@pid/3304314
�U���A�u�V������ = The astronomical herald 43(7)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304318�@�d�v
|
�N���_�C�W�F�X�g���W / p69�`79
On Political Astronomy / �R�{�ꐴ / 69
���ʂƔʂƂ�g�������J�Z�O�����^���n�ɂ���/���g�d��/69
������{�V���w�j�N�\�̕ҏW / ���������Y / 69
�]�ˎ���̓V���L�^ / �_�c�� / 69
�ڕ��ʓǎ��̐��x�ɂ��� / ���������Y / 69
�當�����H�̒��S���ɂ��� / ��c�t. ���g�d�� / 69
�ΐ��̋Ɋ��Ɋւ��錤�� / �����P�v / 70
�C��̒��N�����ω��Ƃ��̌��� / �_�c�� / 70
��]�̋ߎ��v�Z�ɂ��� / �A�O�ɔ� / 70
���i�ւтÂ����j�������Q�ɂ��� / �ē��]�Z / 70
�����V����ɉ����闬���ʐ^�ϑ��k1�l/�L���G�Y. �x�c�O��Y/70
���H���ɂ����鐅������p�̕ω��ɂ��� / �˖{�T�l�Y / 70
���a�I�]�\�f�̎��C��p�����V�����܂ɂ��� / �{��� / 71
�����V���t�V���V�̎����ϑ��ɂ��� / �r�c�O�Y. �㓡�i / 71
������覐ɂ���/ �_�c��. ���R��j / 71
������̋C�A�ɑ�����̉e�� / �ؓc���� / 71
����ɉ�����q�ߋV�ϑ��ɂ���/���؏d��.�ؓc����.���㌹�g/71
Chandler�T�����̒n�����]�ɋy�ڂ��e�� / ������ / 72
�P���̎��ʌv�Z�Ɍ���ꂽ�N�����ɂ��� / ��،h�M / 72
�P�����ʌv�Z�ɂ��Ă̍l�@ / �|�� / 72
�����ϑ��ɉ�����Key error�ɂ��� / �㓡�i / 72
�����ϑ��ɂ�鑊�Όl�� / �Ҍ��V��. �ɓ�����q / 72
�����V���V�̃X�P�[���퐔�ɂ��� / �������F / 72
�o�x�ω��ɂ��� / �{�n���i / 73
���̎q�ߐ��ϑ��ɂ��� / ����O�� / 73
�͓��퐔�ɑ��郍�b�X���̉e�� / �������F / 73
�������v��r��u / �{�n���i / 73
�n���̎O���s���ɂ�鎩�R�͓��T���̉����ɂ���/�{���/73
1949�N�̒������y�ѕs�K���ό�����
�@�@���ϑ��ɑ�E�ɏ� / �_�c��. ���v�Ԑ���/ 74 |
�g�[���X�̏�̓����Ȑ��ɂ��� / �Y���Y / 74
�����̌��d�ϑ��k2�l / ��P / 74
�������̕Ό��ɂ��� / �Ô����H / 74
���f���q���_�̔����T�� / �H�R�O / 74
���ԗ����̂̕Y���ɂ��� / ���㒉�h / 74
���z�������̋P�x���z / ��P / 74
�ό����̎ʐ^�ϑ� / ���ۖ� / 74
�����̃��[�_�[�ϑ��k��2��l / �Ô����H / 74
200Mc���z�d�g�̊ϑ� / �������v. ��؏d�Y. ��R�j��/75
���Ό��t�C���^�[�̉��x���ʂɂ��� / �C��a�O�Y/75
�M���X�y�N�g�g���ɂ�����z������
�@�@�@���P���ւ̓]���ɂ���/�{�{�����Y. ������/75
���z�R���i�̘A�����ɂ��� / ���E�[�\ / 75
�t���E���z�[�t�A�[����equivalent width��
�@�@������/�����P�O�Y / 76
�M���X�y�N�g���ɉ�����A�������̏����ɂ���/���G�v/76
�ア�z�����̉��ӌ��� / ������O�Y / 77
���z��俊O�X�y�N�g���ɂ��� / �ΒÑ���Y / 77
��O�̒ቷ�x�ʂ̉��x�ɏA���� / ���c�ǗY / 77
�f���_�ƐV�� / ��؋`�� / 77
�f���_���t�ˈ��ɂ��� / �C��a�O�Y / 77
�f���_���t�ˏ�ɂ��� / �{�{�����Y / 77
Cosmological Application of Birkhoff
�@�@��Relativity Theory / �����G�� / 78
�ߋ������̋�ԉ^���k4�l / �������k�Ƃށl / 78
��͌n�̖c���ɂ��āk4�l / �L�ؐ��� / 78
��͌n���_�̏W�c�ɂ��� / �����È� / 78
�P���n�ɂ�����fluctuate����͂̏�̋�����
�@�@���m�����z�ɂ��� / �������u�Y / 78
�n�������\���Ɋւ��鎎�_ / �����È� / 78
7���V�ۚ� / p80�`80 |
�R���A���c�������u�V������ = The astronomical herald 43(4) p37�`37�@���{�V���w��v�Ɂu���쐴�F��������� �v�\����B
�W���A�������ҁu����݂Ɛ����v���u�����V���Ёv���犧�s�����B (�ڂŌ���Љ�� ; ��25���j
�P�Q���A�@���������u�����w�� = Journal of Oriental studies ���s��w�l���Ȋw�������I�v�@19 p 65�`75�@���s��w�l���Ȋw�������E���������������v�Ɂu�����ɉ�����C�X�����V���w�v�\����B�@ pid/3558913
�@�܂��A�k���l�Y���u�����@p76�`101�v�Ɂu�����͔|�A���̋N���v�\����B
���A���̔N�A�R�{�ꐴ���u �}���V���u�� ��3�� (�n���ƌ�)�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s�����B�@pid/1372774
|
�n���̍\���y�ѐ����j �������ʖ呾��
���� �n���{�`�_ / p11
���� ��� / p32
��O�� ���� / p52
��l�� ���� / p64
��� �n���̗��j / p90
�n���y�ь��̉^�� �M���C /
���� �n���̉^�� / p104
���� ���̉^�� / p127
|
��O�� ���� / p139
���Ƒ��V���@(��) ���㒉�h
���� ���A / p150
���� ���̕����� / p169
��O�� �]�������V���� / p184
���̘b �n粕q�v
���� ���̎�X / p208
���� ��̊�Ƃ��Ắu����̒����v / p210
��O�� ���z�̎��^�� / p214
|
��l�� ���̎��^�� / p219
��� ���Ԏ����̎�X / p220
��Z�� ���z�� / p226
�掵�� ���A�� / p230
�攪�� 趐� / p235
���� �V��� / p241
��\�� ���{���� / p242
�E
�E |
|
| 1951 |
26 |
�E |
�Q���A�M���C���u�Ȋw���� 11(2)(116)p62�`63�@�����V���Ёv�Ɂu���t�̌v�Z�v�\����B�@�@�@pid/2335616
�R���A�u�V���ƋC�� 17(3)�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@�@pid/2356981
|
����̓V�����Z���g��J�����̉� / ��K���e / 28�`29 |
�t�̌���=���������V���v�� / �Ô����� / 30�`30 |
�S���A�u�V���ƋC�� 17(4)�@�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@pid/2356982
|
�V���{�̏������� / �R�{���C / 3�`8
���ƓV���� / ��K���e / 18�`19 |
��9��S���{������ᢖ��H�v�W��� / / 28�`29
�E |
�U���A�u�V���ƋC�� 17(6)�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@pid/2356984
|
���Ǝ��� / �Y���� / 16�`17 |
�D���O�� / ��K���e / 26�`27 |
�W���A������ �����{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j���� = Journal of history of science, Japan (�ʍ� 19) p.19�`25�v�Ɂu�����̎��v�v�\����B
�P�P���A��K���e���u�V���ƋC�� 17(11)�@p 26�`27�@�n�l���فv�Ɂu�k�ɐ�����v�\����B�@�@�@pid/2356988
�����̔N�A�r�؏r�n���u�V���N��w�u�b : �Ñ�̎������߂�b�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B�@�@pid/1370078
���A���̔N�A����g���u���R���ۂ̗\��v���u�O�����v���犧�s����B (�A�e�l�V�� ; ��42)�@pid/1370389
|
���� / p1
���� �V�ۂ̘���/p9
I ���z�n�̏��� / p9
II �P���E�̌��� / p36 |
���� ���E���ۂ̘���/p48
I �G�ߘ��� / p48
II �V������ / p54
��O�� �C�� / p88 |
I �������� / p88
II �ØQ�ƍ��� / p96
III �C���ُ̈�/p105
��l�� �n�� / p109 |
I �n�����Ɠd�g / p109
II �n�k�y�щΎR���/p118
�E
�E |
|
| 1952 |
27 |
�E |
�R���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies 21�@���s��w�l���Ȋw�������I�v�@p217�`225�@���s��w�l���Ȋw�������E���������������v�Ɂu�u��̗�@--����o���̘_���ɂ����v�\����B �@�@pid/3558915
�S���A�M�������u�V������ = The astronomical herald 45(5) p.70�`72�v�Ɂu�����Ñ�̗�@�v�\����B�@pid/3304340
�P�Q���A�X�c�N�V�������{�@���w��ҁu�@������ = Journal of religious studies (�ʍ� 133) p.358�`361�v�Ɂu���ؐ_�l�v�\����B
�����̔N�A�n�ӕq�v���u����݂ƓV���v���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B�@(���w�V������ ; 7)�@�@�@pid/1629985
�@�@�@
�@�@�@����݂ƓV���i�\���j�@
�@�@�@�@�@�r�T�W�E�U�@�����P�O�� |
�܂�����
���́@�V���w�̂����� / 1
���́@�n���̎��]�\�� / 5
��O�́@�n���̌��]�\�G�߁\�N / 31
��l�́@���̉^�s / 66
��́@�V�� / 101
��Z�́@���Ƃ��̉��p / 115
�掵�́@��Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂� / 152
�攪�́@���A��@ / 164
���́@���A���z��@�\���{�̋���/169
��\�́@���z�� / 178
��\��́@�T�A���N���j�� / 188
|
��\��́@�V������\���E�� / 198
��\�O�́@��ɋL�ڂ���鎖�� / 205
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�B
�B
|
|
���A���̔N�A�M�������u���R�Ȋw�j ��1 (�Ñ�E������)�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B (�Ȋw�j�����
; ��4)�@pid/2421520
|
�܂�����
���� �Ñ㕶�������̉ț{ / p2
�G�W�v�g / p2
�p�r���j�A / p9
�C���h / p15
���� / p20
�Ñ�l�̉F���V / p27
���� �M���V�A����̉ț{ / p31
�ț{�̒a�� / p31
�C�I�j�A�̉ț{�ҒB / p33
�s�^�S���X�{�h / p38
�G���A�{�h / p42
���q�{�h / p46
�q�b�|�N���e�X���Λ{ / p47
|
�M���V���{�y�̉ț{ / p50
�v���g���𒆐S�Ƃ��� / p54
�A���X�g�e���X / p60
��O�� �A���L�T���h���A����̉ț{ / p69
�A���L�T���h�������� / p69
�ɛ{�y�ї͛{ / p71
�V���{�y�ђn���{ / p82
�Λ{���̑� / p90
��l�� �O���R�E���[�}����̉ț{ / p93
�O���R�E���[�} / p93
�v�g���}�C�I�X�̋Ɛ� / p94
�ɛ{��ᢓW / p100
�Λ{���̑� / p106
���[�}�̉ț{ / p109
|
��� �C�X��������̉ț{ / p116
�����̖K�� / p116
�C�X��������̉ț{ / p120
�C���h�̉ț{ / p127
�����̉ț{ / p134
�����l��ᢖ� / p142
��Z�� �����̃��[���b�p�ț{/p147
�A���r�A��胈�[���c�p�� / p147
�A���x���g�X�ƃ��[�W���E�x�[�R��/p154
�萯�p�ƘB���p / p159
���l�c�T���X�Ɖț{���� /p162
�\�ܐ��I�̉ț{�� / p167
���� / p170
�E |
|
| 1953 |
28 |
�E |
�R���A��K���e���u���N�V���w�v���u�O�[�Ёv���犧�s����B�@pid/1622900
|
I�@���ƉF��
�P�@�����i�P���Ƙf���E�����E���{�̐��A
�@�@�����{�Ō����邨���Ȑ����\�A�M���V�������̓Ǖ��j/3
�Q�@�k�ɂ��߂��鐯���i�V���E���T�^���E�T�ɐ��E
�@�@���o�����E�N�T�^���j / 12
�傮�܍��Ɩk�l���� / 15
�k�l�������w�i���̖��E���̊w���E�Ԍo�Ԉ܁E���̌��x�E
�@�@�����̐��E���̋����E���N�E�V���P�ʁE
�@�@�����̊p�����E���x�j/17
�����܍��Ɩk�ɐ��i�k�ɐ��E?���j / 28
��イ���E�P�t�G�E�X���i�ό����G�[�^�j / 31
�J�V�I�y�����̂v���i�v����k�ɐ��E��d���E�A���j / 33
�R�@��̋�̐����i�쒆�E�q�ߐ��o�߁j / 37
��A�@�H�̐��� / 39
�y�K�X�X���̑���`�i����`����k�ɐ��j / 39
�A���h�����_���Ƒ启�_ / 42
�������@���Ђ����@�������i�t���_�j / 43
��������ƕό����~���i�����j / 45
�y���Z�E�X���ƕό����A���S�[���i�H�ό����j / 47
��A�@�~�̐��� / 50
���債����i�J�y���j / 50
���������̓c�i���c�E�X�o���E�A���f�o�����j / 51
�I���I�����Ƒ启�_�i�x�e���M���[�X�E���Q���E�启�_�j/54
���������@�͂ƍ��@�G���_�k�X�� / 57
�傢�ʍ��̃V���E�X�i���F��j / 57
�����ʍ��i�v���L�I���j�A���S���i�J�m�[�v�X�j / 60
�O�A�@�t�̐��� / 62
�������́u��K�}�v�i���O���X�E���̉����j / 63
�ӂ������i�J�X�g���E�|���b�N�X�j���ɍ��i�v���Z�[�y���c�j
�@�@�����݂ւэ��@�R�b�v���@���炷���@
�@�@�����Ƃߍ��i�X�s�[�J�j/65
�����������̃m�V�`�i�A���N�g�D�[���X�E�t�̑�O�p�j / 70
����ނ���@���肢�ʍ��@���݂̂��� / 71
�l�A�@�Ă̐��� / 73
�w���N���X���Ƒ启�c�i���c�j / 73
�ւт������E�ւэ� / 74
��������̑�r���i�A���^���[�X�E���̐F�j / 76
�Ă�т�� / 79
���č��Ɠ�l�Z���@�݂Ȃ݂̂���ނ�� / 80
���ƍ��̃^�i�o�^�i���F�[�K�E���̌ŗL�^���E
�@�@�������̖k�ɐ��j/82
�킵���̃q�R�{�V�i�A���^�C���E�Ă̑�O�p�j / 85
�͂����傤���̑�\���i�f�l�u�E�ΒY�Ԃ���j / 86
�€���@�݂����ߍ��@�݂Ȃ݂̂�����
�@�@���i�t�H�[�}���n�E�g�j/88 |
�S�@��ɂ��߂��鐯�� / 91
�P���^�E���X���@�������ݍ��@
�@�@���݂Ȃ݂��䂤�����i�S�V�̈ꓙ���̕\�j / 93
�T�@�d���ƘA���i�������̓�d���E�A���E�d���̐F�E�����A���E
�@�@�������A���j/96
��d���̊ϑ��i��������d���̕\�E�]�����̕����́E
�@�@�����]�����̐ڊ���Y�j / 102
�U�@�ό����i�H�ό����E�Z�T���ό����E���T���ό����E
�@�@�@���s�K���ό����j/105
�ό����̊ϑ��i�����ȕό����̕\�j / 108
�V�@�V���i�e�B�R�̐V���j / 112
�W�@�����i�U�J���c�E���c�E�����ȎU�J���c�̕\�E
�@�@�������ȋ��c�̕\�j / 114
�X�@�����̉F���\��͌n�i�V�̐�E�j�P���n�E�Ǖ��P���n�j / 119
�P�O�@���_�i��͌n���_�E�U�����_�E�Í����_�E�f���_�E
�@�@����͌n�O���_�E�����Ȑ��_�̕\�j / 123
II�@���z�n
�P�@���z�n�̈ꑰ�i���f���E�O�f���E���f���̕\�j / 131
�Q�@���f�� / 134
��A�@�����i�ő嗣�u�j / 134
��A�@�����i�O���E�����ő嗣�u�E�ő���x�E�����E
�@�@�������ő嗣�u�E��T���j / 138
�n���i�����_�E�ߓ��_�E���E�E�o���x�j / 144
�R�@�O�f���i�ՁE���E���s�E�t�s�E���E���E����j / 148
��A�@�ΐ��i�ΐ��̏ՁE�u�^�́v�Ȃ���́E�ΐ��̉q���j / 150
��A�@���f���̌Q��i�{�[�f�̖@���E���f���̔����E�G���X�j / 156
�O�A�@�ؐ��i�_�̑сE��ԓ_�E�u�K�����I�̎l�̌��v�E
�@�@�@�����̑��x�����j/161
�l�A�@�y���i�����O�E�y���̉q���j / 167
�܁A�@�V�����i�V�����̔����j / 173
�Z�A�@�C�����i�C�����̔����j / 176
���A�@�������i�������̔����j / 179
�S�@�a���i�j�E�R�[�}�E���E�T���a���E�n���[�a��
�@�@���E���{�l�̜a�������L�^�E�a���������E�A�}�`���A�̎d���j/181
�T�@�����i�����̐��́E覐�覓S�E�����Q�E�d���Ɨ����Q�j / 190
�����̊ϑ��i�����ȗ����Q�̕\�E�����ϑ��m�[�g�̗�j / 196
�U�@�������ƛ����Ɓi�������E�Γ��Ɓj / 199
�V�@���z�i���z�̉��x�ƔM�ʁE���z�̌��x�E���_�E���W�I�V���w�j / 201
���z�i�����E�t���_�ƏH���_�E�t���E�Ď��E�H���E�~���j / 208
�����@�Ə\��{ / 212 �@�@������
�W�@���@�i���z�ƌ��̎����a�E�d�g�̉����E���ʂ́u�C�v�ƎR�E
�@�@�����]�ƌ��]�j / 214
���̈ʑ��i�P�����ƍ�]���E�ʑ��E����E���z�̂����Ȑ��l�\�E
�@�@�����̂����Ȑ��l�\�j / 222
�X�@���H�ƌ��H�i���H�E�F���H�E���H�E�����H�E�H�̗p��E���H�j / 227 |
�V���A������,�{�{�����Y���u���������˂āv���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@ (�ڂł݂�Љ��� ��; ��59��)
�X���A�K���������Y������ƈ�w�̉�ҁu�f�ڎ� ����ƈ�w 1(3) p.157�`160�v�Ɂu�����̊��o-1-�v�\����B
�P�O���A�K���������Y������ƈ�w�̉�ҁu�f�ڎ� ����ƈ�w 1(4) p.244�`246�v�Ɂu�����̊��o-2-�v�\����B
�P�P���A�K���������Y������ƈ�w�̉�ҁu�f�ڎ� ����ƈ�w 1(5) p.306�`308�v�Ɂu�����̊��o-3-�v�\����B
���A���̔N�A�����p�����u�{���Ɛ��v���u�b���Ёv���犧�s����B�@pid/1341809
|
���E��K���e
���Ɛ��ƁE�{�Z
�����ǂ̈ʂ��������� / 1
�����̓V���m���ɂ��� / 10
�����̓ǂV���� / 20 |
�O�����ƃv���V�I�X�̍� / 30
�����Ɠ��{�̐� / 39
�u��͓S���̖�v�̐� / 48
���V�R�F�f��u��͓S���̖�v / 61
�����̐��̕\���ɂ��� / 69
|
�����ƃ}�����������Ԃ��� / 80
���Z�t�̉_�ɑ���X�e�[�g�����g / 90
�{���̍�i�Ɍ���ꂽ�� / 105
���Ƃ��� / 145
�E |
|
| 1954 |
29 |
�E |
�W���A�{�n���i���u�V������ = The astronomical herald 47(8) p.115�`117�v�Ɂu��\��-���̗R��,���e,�Ӗ�,���p�ɂ��āv�\����B
�P�O���A�����������{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j���� = Journal of history of science, Japan (�ʍ� 32) p.15�`18�v�Ɂu�ߐ������ɓ`����ꂽ���m�V���w�v�\����B
�P�P���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies 25�v���u ���s��w�l���Ȋw������,���������������v���犧�s�����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@/pid/3558919
|
�� / �H�c�� / p1�`3
�� / �L�˖Ύ� / p4�`5
�����o�y�̈�Q�̓�����ɏA���� / �~�� ���� / 1�`21
�����̔_�� / �V�� ���V�� / 22�`40
�Ўq�̏t�H����� / ��� ���� / 41�`58
�E�q�w�c / �F�s�{ ���g / 59�`84
���V����V���y�ѓ����ց\�_������ɉ�����
�@�@���V�q�̛{/�ؑ� �p��/85�`104
������{���@���ɂ��� / �ɓ� ���� / 105�`119
�͐��l�S�̐����ɂ��� / ����� ��v / 120�`140
����Ӌ����m�̋��^�ɂ��� / �ēc �����Y / 141�`16
�����o�ފ�ɂ��ā\�����K�`���̉� / ���쐴�� / 161�`177
�����܂���ʂ��Ă݂��Ñ��C�f�Ղɂ��ā\�٘Q���
�@�@����C�܂�/����h/178�`200
�����R�c�̍\���ɂ��� / �쏟 �`�Y / 201�`220
��q�̏��Ɍ������ΓI�l�� / �d�� �r�Y / 221�`233
�È�Z���ϐ����䌱�L�̏o���\�W��ӕ~�A�v�������
�@�@����������鄋L/�˖{�P��/234�`250
|
��ƈђx���m�ɂ��� / ���L�q�Y / 251�`263
�����ɉ����閯�����������̈�ߒ��\
�@�@�����B�吹��m���a���ɂ��� / �q�c ���� / 264�`286
���缣�Ŗ{�����Ǝ��� / �q�c �~�V�� / 287�`304
����������˂ց\�͏��C�𒆐S�Ƃ��� / ���� �`�� / 305�`330
�ӋV�Ɵӏ� / �g�c ���M / 331�`348
AI / �q�� ���l�Y / 349�`363
�A�W�A�_�Ƃ̓����\���ɒ����ɂ�����
�@�@���k��������߂��� / �� �S�� / 364�`385
��
���w�I�_���w�ƕُؖ@�I�_���w�Ƃ̊W�\�`���[���Y��p�[�X��
�@�@���_���v�z���߂��� / ��R �t�� / 495�`512
���l�T���X�̔��p�ƎЉ�\�~�P�����W�F����
�@�@���ꍇ/��c �Y��/513�`534
��
����j���e / ���� ���v ; �s�����g ; �����C / 674�`707
���s��{�l���ț{?�������v / / p709�`718
�E |
���A���̔N�A��{���Y���u�@���j���� 1954(4) p.1-18�v�Ɂu��䌴���ߍl�v�\����B�@J-STAGE
���A���̔N�A�����ɋg���u�_��j�̐V�����v���u��g���X�v���犧�s����B�@�@pid/2982585
|
���с@�_��j�̊J蓐_ / p1
���́@�J蓐_ / p1
���́@���ؐ_�ɏA���� / p51
���с@���f��_�̑�� / p69
���́@�V�V�䒌 / p69
���́@����E�Ƃ��邱�� / p122
��O�с@���f��_�̚��m���� / p143
���́@�V�䒌�����E�ɏ����Ě��y���_�� / p143
���́@���y���� / p178
��l�с@���f��_�̏��_���� / p188
���́@�d���˒q�_ / p188
���́@�Ɏדߊ̖錩���K�� / p202
��O�́@�O�_�̐��a�y�ё��̕��� / p225
��ܕс@���V���ƓV���~�Ղ̏� / p244
���́@�V�Ƒ�_�Ƒf�����Ƃ̐��� / p244
|
���́@�V�Ή��˂̐_� / p272
��O�́@�V���~�� / p317
��Z�с@�H���̐��E / p352
���́@�f���� / p352
���́@�嚠�喽�i荁j / p371
��O�́@���F�����i荁j / p371
��l�́@�F�ΉΏo�����ƖȒÌ����i荁j / p371
�掵�с@�_��j�̌��\ / p372
���́@�_��j��萂���Øҏ��Ƃ̉��� / p372
���́@�_��j���̐_�X�̌䐫�� / p379
��O�́@�_��j��ɕ\�͂ꂽ��H�����E / p383
��l�́@�_��j�̐��_�y�т��̍�ਂ���ꂽ�鐄��N�� / p392
���Ƃ����i�a�c�C�j / p429
����
�E |
|
| 1955 |
���a30 |
�E |
�P���A�n�ӗ@���u�_�ƋZ�p���� 9(1)(97)p 77�`77�É����_�Ƌ����g��������v�Ɂu�x�����˂Δ��肵�Ȃ���q�Ƃ��̌����v�\����B�@pid/2355561�@�@ �d�v
�V���A�u�V�E = The heavens 36(364)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220027
|
���ɂ���̐��E(3) / �n�[���[��V���v�� / p169�`173
"���E��"�ʐM / / p173�`173
����������̓V�����m(1) / �����C / p174�`175
�N�ł��o����Z�t���E�X���f���^���̊ϑ� /
�@�@���X�v���E���V���䒷 ���J���f�J���v / p176�`181
��̔��� / / p181�`181
�C���h�̌�����D�� / �P�g�� / p182�`185
|
"�ΐ��ʐM�Ƃ�" / ���؎� / p185�`186
���E��̎��j�Ƌ���̘Z�j / �ΐ�h�� / p187�`188
�萯���m(���O��) / ��K���e / p188�`188
�yO. A. A.�ϑ����z�ؐ��q���̂������ڊϑ��� / / p189�`189
�y���V�F��N���u���z�������c�ē�(5) / ����� / p190�`191
1955�N�����̓V�ۗ\�� / / p192�`192
�ҏW����� / / p192�`192 |
�X���A�������ꂪ�u�_�яȐ��Y�u�K��������. �l���Ȋw�сi�P�jp15�`52�v�Ɂu�䂪���Ñ���̌n���v�\����B
�@�@�@ ��������}���كf�W�^���R���N�V�����i�d�q���ЁE�d�q�G���j�@�{���\
�P�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 49(1)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304386
|
�\���ʐ^-����ܓx�ϑ����ɐV�݂��ꂽ�ʐ^�V����
�d���g�V���w�Ɣ����q�V���w / �������v / p3�`3
��--���P�c�g�����w / �ē����� / p4�`5
����̎ʐ^�V���� / �������F / p6�`8
S.C.�`�����h���[�ɂ���(��) / ������ / p9�`10
�т�Ƃ��炷 / / p10�`10 |
������--�A���}�Q�X�g(1) / �M���� / p11�`14
����A���o��-����s�Ɍ��݂��ꂽ�ؑ��h���m�̋���,
�@�@�������V���䌩�w��X�i�b�v�W / / p15�`15
1���̓V���� / / p16�`16
���^ 1956�N�V����,�����f���o��},�����\��,���{�V���w��������
�E |
���A���̔N�A���щp�v�ďC�u�n�w����u�� ��15�����@�n�w�̌����j�Ƌ���j�n�w����̖ڕW�v���u�������X�v���犧�s�����B�@�@pid/1372825
|
�ďC�҂̂��Ƃ� ���щp�v
I �n�w�����̗��j ��萳�v
�܂����� / p2
I �����̂����ڂ� / p3
(1) �m���̂߂� / p3
(2) �i�C����̂͂��� / p5
(3) ���z��(�G�W�v�g��)�̗̍p / p6
(4) �}���ق̂͂��܂� / p7
II �M���V���C���[�}�̎��� / p7
(1) �z��̎Љ�ƉȊw / p7
(2) �^���X�̍l�� / p8
(3) �Ȋw�̂����ڂ́\�\�V���w / p9
(4) �n���̌`�ɂ��Ă̍l���̂͂��܂� / p10
(5) �M���V���Ȋw�̓��� / p12
(6) �n���̑傫�����ǂ̂悤��
�@�@�@���m�낤�Ƃ����� / p14
(7) ���[�}����ɂȂ��Ȋw��
�@�@�@���i�܂Ȃ������� / p15
(8) �R�x�������̕��\�\�X�g���{�[ / p16
III �����݂̒��� / p17
(1) ���[�}�鍑�̕��� / p17
(2) �T���Z������ / p19
(3) �Q���}�������̉Ȋw / p19
(4) �A���r�A�l�̒n�w���� / p20
IV ���l�b�T���X�\�\�Ȋw�̕��� / p20
(1) �Ȋw�j��ő�̊v�� / p20
(2) ���I�i���h�E�_�E���B���`�̂����� / p22
(3) �n�����̂����� / p24 |
(4) �z���w�̕��\�\�A�O���R�� / p26
(5) ���l�b�T���X���̒n�w / p28
V �ߑ�n�w�̏o�� / p29
(1) �ߑ㎩�R�Ȋw�̒a�� / p29
(2) �ߑ㎩�R�Ȋw�̓��F / p30
(3) �I�����_�Ȋw�̓��{�ւ̗��� / p32
(4) �K�����C�ƒn�����̔��W / p33
(5) �P�v���[�̐��U / p34
(6) �ߑ�̒n���z���w / p37
(7) �ߑ�n�w��̂����Ȕ��� / p38
VI �Y�Ɗv���̎��� / p40
(1) �@�B�����ꂽ�Z�p / p40
(2) �Ȋw�v�z�̔��W / p41
(3) �n���̂������̌��� / p43
(4) �n���z���w�̖��i / p43
(5) �������Ɖΐ��� / p44
(6) �Ð����w�̒a�� / p46
(7) �ߑ㕨�����w�ƍz���w / p47
VII ���{��`���W�̎��� / p48
(1) ��K�͂ȋ@�B���� / p48
(2) �X�y�N�g�����͂ƓV�̕����w / p51
(3) �n�������w�̔��W / p52
(4) �C�ۊw�ƋC�ێ��� / p52
(5) �X�͂̌��� / p53
(6) �\���n���w�̂����� / p54
(7) ��Ίw�̒a�� / p58
(8) �`���[���X�E���C�G����
�@�@�@���n���w�̌��� / p58
|
VIII 20���I�̒n�w / p59
(1) ����Ȋw�Ƃ��̔w�i / p59
(2) ����̒n�w / p60
���� / p63
II �n�w����̗��j ���R��
(1) ���{�ł͋ߑ�Ȋw���ǂ̂悤��
�@�@�@������ꂽ�� / p66
(2) �n�w���ӂ��ގ��R�Ȋw�͂ǂ̂悤��
�@�@�@�������������� / p67
(3) �n�w�Ƃ������Ȃ����܂ꂽ
�@�@�@���w�i�Ƃ��̖��_ / p72
(4) �����炵���n�w����̂����� / p75
III �n�w����̖ڕW �̑��
(1) ���ꂩ��̒n�w����̕��� / p80
(2) �n�w����̂������̓� / p83
(3) �}�H�ȁu�����v�̎��� / p85
(4) ��������Ă��鋽�y�̌��� / p88
(5) �n�w����̌��� / p91
�\�\���t�̈ӎ��\�\ / p91
�\�\�����ɂ�����ʓ��\�\ / p92
�\�\����ƒn�ɂ͂낤�\�\ / p93
(6) ��������n�w���� / p95
IV �n���w�j�������
�@�@�@���ŋ߂̖�� ���щp�v / p99
���^ �n�w�j�N�\ / p105
�Q�l���� / p112
���� / p113 |
���A���̔N�A�M�������u�V���w�j�v���u���q���X�v���犧�s����B�@ (�Ȋw�E�Z�p�j�S��)�@pid/1374754
|
��1�� �Ñ�̓V���w / p1
��2�� �M���V�A�̓V���w / p19
��3�� �����̓V���w / p36
��4�� �R�y���j�N�X�ƃ`�R�E�u���� / p51
��5�� �P�v���[�Ƃ��̉^���@�� / p66 |
��6�� �K�����I�E�K�����C / p75
��7�� ���L���̖͂@�� / p87
��8�� �O���j�b�W�V����̓V���w�� / p105
��9�� �P���V���w�̊J��� / p119
��10�� �K�E�X�ƃx�b�Z�� / p127 |
��11�� �C�����̔��� / p139
��12�� �V�̕����w�̒a�� / p147
��13�� 20���I�̓V���w / p176
���� / p215
�E |
���A���̔N�A���s��w�l���Ȋw�������������w���m�F���������H�c�����u�E�ޗǎ���̕��� p101�@���c��i�H�Ɓv�Ɂu�Z�A�ޗǎ���̎��R�Ȋw�v�\����B�@pid/2972820 |
| 1956 |
31 |
�E |
�R���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies �@���s��w�l���Ȋw�������I�v�@26�@p90�`103�@���s��w�l���Ȋw������,���������������v�Ɂu�����V���w�ɂ�����ܐ��^���_�v�\����B�@pid/3558920
�V���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies (�ʍ� 26)p90�`103�v�Ɂu�����V���w�ɂ�����ܐ��^���_�v�\����B
�P�O���A�����������m�j������ҁu���m�j���� 15(2) p.235-251�v�Ɂu�u��Ɋւ����,�O�̖��v�\����B�iIRDB�j
���A���̔N�A��쐭���Y���u�@���j���� 1956(6) �@p.253-254�v�Ɂu�i���]�j��{���Y���u�u��䌴���ߍl�v(�@���j�����l��)�v���Љ��B�@J-STAGE
���A���̔N�A�吼���ꂪ�u�Q�{�̍��́v���u�_�{�i���������v���犧�s����B�_�{���{�p�� ; ��3�W�@�@pid/2981643
|
��
�ɐ��ҋ{ / p1
��A�@�����֝ЂƏ����̈ɐ��ҋ{ / p1
��A�@�ҋ{�j��̊c������ / p2
�O�A�@�ߐ��̙ҋ{ / p7
�l�A�@�S���҂Ɛ���� / p8
�܁A�@�������҂� / p14
�Z�A�@�ҋ{�X���̝̑J / p23
���A�@�ҋ{�������i / p35
���A�@�ҋ{�X����̎O�咹�� / p46
��A�@�_�s��萖�{�� / p49
��Z�A�@���n�_�s / p55
���A�@�_�s�̙ҋ{㉙� / p59
���A�@�V�c�A�c���q�A�c���y��
�@�@���M���̙ҝ`/p77
��O�A�@���l�̙ҝ` / p81
��l�A�@�k�J�C�E�m�H�l��̙ҝ` / p88
��܁A�@�{�ҕ��l�u�m�̙ҝ` / p97
�ɐ��̌�t / p123
��A�@��t�̋N�� / p125
��A�@��t�ƒh�� / p131
�O�A�@��t��㊒� / p134
�l�A�@�t�E�� / p141
�܁A�@��t�̊K�� / p143
|
�Z�A�@�h�Ɖ�� / p145
���A�@�t�E�@�̑ҋ� / p151
���A�@������`�����t�E�@ / p152
��A�@���h / p154
��Z�A�@�_�s�̎И�g�D / p157
���A�@��t�̖ŖS / p160(
���_�� / p163
��A�@�_�{�y�_�s�̐_�� / p165
��A�@��t�@�̐_�� / p166
�O�A�@�_�ق̓��� / p168
�l�A�@�_�ق̑t�s / p170
�܁A�@�_�ِE / p174
�Z�A�@�_�ِE�̕��� / p176
���A�@�_�ٔ��l�Ǝ��s�̐l�� / p178
���A�@�_�ٗ� / p180
��A�@�_�ِE��㋏� / p182
��Z�A�@�_�ِE�̔��E / p183
���A�@���Ђ̐_�� / p186
���A�@�_�� / p187
��O�A�@�_�ى� / p188
��l�A�@�F���̐_�� / p189
��܁A�@�_�{���s�̐_�� / p192
�_�s�F���R�c / p195
��A�@���̉F���R�c / p197 |
��A�@�x�����ƍr�ؓc�� / p199
�O�A�@�_�H�R�ƌ\��� / p202
�l�A�@�R�c�����̊J�� / p204
�܁A�@�ɐ��̑�͋{�� / p205
�Z�A�@�{��͓��̝̑J / p206
���A�@�{��̔×� / p211
���A�@�{��̎��� / p215
��A�@�\���̉��ĕ� / p219
��Z�A�F���Z���A�R�c�\���� / p220
���A���@�s�v�n / p225
���A�@�]�ˎ��㏉���_�s�̌ˌ� / p226
��O�A�@�_�s�̐��� / p234
��l�A�@�_�s�s��n�h�Ύ{�� / p238
��܁A�@�R�c�̎Y�y�_�ƌ䓪�_�� / p240
��Z�A�@�R�c�s���̎��@ / p246
�ꎵ�A�@���Ǝs�Ɠy�q / p256
�ꔪ�A�@�R�c�H�� / p264
���A�@�_�s�̐���� / p270
��Z�A�@�F���R�c�Z���̊K�� / p273
���A�@�R�c�O���ƉF������ / p281
���A�@�R�c�t�s / p293
��O�A�_�s���Y�l�� / p306
��l�A�@�����Ȍ�̉F���R�c / p308
���� |
|
| 1957 |
32 |
�E |
�U���A�u�V�E = The heavens 38(387) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/3220050
|
�y�����z���̒��͍L������?! / �R�{�ꐴ / 145�`146
�ߔN�̑�a���̃��X�g / / 146�`146
�����������Q�y�I�v179�z / ��ꠍF��Y / 147�`153
�A�[�T��X�^������G�f�B���g�����`(3) /
�@�@���X�y���T��W���[���X �z�C�e�C�J / 154�`158
1952�N7�`8���̗����ϑ��̐����y�I�v180�z / �͖쌒�O / 159�`164
�����̎��[ / ����� / 165�`165
|
�ҏW����� / / 165�`165
���[�̉� / �ΐ�h�� / 166�`167
�����ψ����(9)�y��(10) / ��ꠍF��Y / 167�`168
��l���ψ����c / / 169�`170
�o�C�G�����̃��X�g(15) / �_�c��Y / 171�`171
�y1957�N�����̓V�ہz�ܐ����ڂ�� / �R�{���C / 172�`172
�E |
�V���A���R�����u���{��Îj���� 1(7) p.137�`141�v�Ɂu�ŋ߂̏�Ð_���j�����ɂ��āv�\����B
�V���A����K�삪�u��̍Ձv���u��菑�X�v���犧�s����B�@ (�����E���|�o�� ; ��13)�@pid/9543327
|
��̓`�� / 1
�ӂ��̌o�H / 1
���{�����̏o���n / 7
�ԕĂ̓`�� / 9
�Ă̎��� / 13
�Ă̂��� / 13
�Ăƍΐ_ / 17
�T�Ă̕��@ / 19
�Y�ĂƑ����� / 22
�L��F��̏��� / 27
�c�A���� / 27
�܂䂾�� / 37
�ł����� / 45
���ؐӂ� / 50
�j���_ / 55
���ǂ� / 61
�N�肢 / 75
���肢 / 75
�݂����c�q / 78
�͂܋| / 84
�����א_�� / 88
�c��� / 94
�c����̗v�� / 94
�c��̍� / 98 |
�c���邵 / 102
��d���̓��̐��i / 107
�쓇�̎�ǂ� / 111
�c�A�͂��� / 118
�c�A�����ޓ� / 118
�c�̐_���낵 / 122
���c�A / 126
�ԓc�A / 130
��̏o�Y / 133
�c�A�J�� / 135
�g���� / 135
�Ԗ� / 143
�D���� / 146
�c�A�I���̍� / 153
����݂� / 153
��̃T�m�{�� / 156
�Ƃ��Ƃ̍� / 161
�����̍� / 165
�A�t���� / 168
�[�߂̐ߋ��Ɣ_�� / 170
���̉� / 170
�����{�Ɠc�� / 174
������ / 182
���ǂ����_ / 182 |
���F�� / 186
���˂��著�� / 191
�J��F��̕��� / 195
�J��̗ތ^ / 195
�n���ӂ� / 198
�J��x�� / 201
��c���� / 205
�Q�� / 208
���Ƃ� / 210
���[�Ɣ_�k / 215
���[�̓c���� / 215
�}���n / 219
���n�ՂƂ̂Ȃ��� / 222
����V�� / 227
�엊�� / 227
���n�Ƌ����\�� / 230
�V���� / 235
������ / 238
�쓇�̃X�N�}�_�� / 241
���n�̍� / 246
�Ƃ��Ƃ̍� / 246
�����̍� / 251
�쓇�̎��n�� / 256
�֊��̌`�� / 256 |
�쓇�̐��� / 264
�\���� / 269
�卪�̔N�Ƃ� / 269
�ĎR�q�� / 272
�m�S�C / 275
��̎q / 277
�Ղ̎��� / 277
��̐_�Ɠc�̐_ / 281
ⴂ̐_ / 283
�c�̐_�����̐M��/287
�c�̐_�Ղ̎��� /287
���쏜�� / 292
�R�g�_�̋��� / 298
�j���{ / 302
�R�g�_�Ɣ_�_ / 306
�c�̐_�̍Տ� / 310
�œc / 310
�h��a�̓c�A / 314
�a�c / 318
�_�l�̑����ʂ���/326
�O�p�c / 329
�E
�E
�E |
�W���A�u�V������ = The astronomical herald 50(9)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304407
|
�F�����ُ̈푝�� / �͕h���� / p141�`144
�\���ʐ^����
�y���[�V���s / ��c�� / p145�`148
�V�̊ϑ��̂�����--�V�̊ϑ��ƘI(8) / �������F / p149�`152
�V���Љ�--�V�V���w�u��(�P���Д�),��(�\�c������)
�@�@���ό����̒T��(���ۖΒ�) / / p153�`154 |
�G��--�V�^�̌��w�p���v,�K�X���_�̌d����\��,
�@�@���A�����h����[�����h�d���̑��z�����ւ̌��� / p154�`155
�{���ѓ����V����ɕ��ꂽ�����ϑ�(1956�N) / p156�`156
Echo �� Echo / / p156�`156
����A���o�� / / p157�`157
10���̋� / / p158�`158
|
�P�P���A���R�����_���j�w��ҁu�_���j���� = The shinto history review 5(6) p.456�`475�v�Ɂu�Ñ�l�̊C�_�M��--���t�W�E���y�L��ʂ��āv�\����B
���A���̔N�A���R����������w����w���ҁu������w�w�|�I�v �Љ�Ȋw (�ʍ�
7) p.63�`80�v�Ɂu�Ñ�l�̊C�_�M��--�L�I��ʘH�Ƃ��āv�\����B
�����̔N�A�r�؏r�n, �����Y�S���� �u�V�V���w�u�� ��1���v���u�P���Ќ����t�v���犧�s�����B�@pid/1373785
|
���s�̎� �ڎ� ���G / p1
I�D �g���~�[�Ȍ�̐��� ���㒉�h
II�D �Ñ�̐��� ��K���e
I�D �o�r���j�A�̐��� / p47
II�D �t�G�j�L�A�̐��� / p59
III�D �w�u���C�̐��� / p61
IV�D �G�W�v�g�̐��� / p63
V�D �M���V���̐��� / p69
III�D ���j�I�ɂ݂��Ð��} ��K���e |
IV�D �A���r�A�̐��� ����k�C�^���l
V�D �����E���N�E���{�E��x�̐��� �M����
I�D �����̐��� / p123
II�D ���N�̐��} / p145
III�D ���{�̐��} / p147
IV�D �C���h�̐��� / p154
VI�D ���\�Ƌߑ㐯�} ���ۖ�
I�D ���\���Â��݂Ȍ����� / p157
II�D �ЂƂЂƂ̐��\�ɂ��� / p161 |
III�D �ߑ㐯�} / p176
VII�D �l�G�̐����Ƃ��̌��� �����
VIII�D ���{�̐��� ��K���e
IX�D ���̈ʒu�̕\�킵�� ����O�Y
X�D ���ނƂ��Ă̐��������̍��� �|��
I�D ���������̂ق������� / p259
II�D ���������̍�肩�� / p260
III�D ���������̍�肩�� / p268
�E |
���A���̔N�A�g�c���M �Ғ��u�����ƍ����̍� : �C�����������s�̋L�^�v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B (�O��V��)�@pid/2977847
|
�� �M���� / p1
�C�����̗�
�iI�j�o���܂� �g�c���M / p11
�iII�j�e�w�����܂� �g�c���M / p17 |
�iIII�j�e�n�̗��ƋA���܂� �g�c���M / p31
�C�����e�n�̋L�^
�iI�j�e�w�������ӂ�
�@�@���_�}���F���g�o�� �\�����{�v / p81 |
�iII�j��̍����̗� ���J�D�� / p116
�iIII�j�n�}�_������ �g�c���M / p167
�iIV�j�}�U���f�������� ���� / p183
�iV�j�A�[���p�C�W�������� �g�c���M / p209 |
|
| 1958 |
33 |
�E |
�P���A�M���� ; �l���m���u�V������ 13(1)(86)�@p 3�`3�@����R�V������v�Ɂu���ꂩ��̓V���w�v�\����B�@pid/2382847
�P0���A�n�ӗ@���{�������u�_�Ƃ���щ��| 33(10) �v�Ɂu�x�m�����u�������(�L���x�c)�v�̔��藦�ቺ�̌����Ƃ��̑�-�P-�v�\����B
�P�P���A�n�ӗ@���{�������u�_�Ƃ���щ��| 33(11) �v�Ɂu�x�m�����u�������(�L���x�c)�v�̔��藦�ቺ�̌����Ƃ��̑�-2-�v�\����B
���A���̔N�A�M������������, �T�䏟��Y, �����^���ҁu���m�v�z�u�� ��3��
(���m�I�l�ԑ�) p173�`�@�������v�Ɂu�U�@�����Ȋw�v�z�v�\����B�@pid/2942083
���A���̔N�A�����Ő����u���{�����j�b ��1�v���u�����Ő��^���钬 (�L����)�v���犧�s����B�@
1958�@pid/2972511
|
�k��l�@���{�Ί펞��̐l�햯���ɂ��� / p1
�k��l�@���{��̌n���ɂ��� / p3
�k�O�l�@���{�̓��펞��S�펞��ɂ��� / p4
�k�l�l�@���j������{�ɉ������m�����̎O�h / p6
�k�܁l�@�k�N���n������o�_�푰 / p7
�k�Z�l�@���ē����̎��� / p8
�k���l�@�c�c�V�Ƒ�_ / p11
�k���l�@�fᵖ� / p14
�k��l�@�喤�M�����F�������y�o�c / p16
�k�\�l�@�o�_�썑�g�ߔh�������̍��V���ɂ���/p17
�k�\��l�@�o�_�֔h���̎g�ߔ��D�n�ɂ��� / p19
�k�\��l�@�헤�������ɂ��� / p22
�k�\�O�l�@�V�t�F�ɂ��� / p25
�k�\�l�l�@�M�Z���z�K�_�Ћy�ѐ��������_�Ђɂ���/p27
�k�\�܁l�@�V�����X�n�������~�Ղɂ��� / p29
�k�\�Z�l�@�F�ΉΏo�����ɂ��� / p30 |
�k�\���l�@�k�E�K���t�L�A�G�Y�l���ɂ��� / p31
�k�\���l�@�L�I�̔N�I�ɂ��� / p32
�k�\��l�@�C�O�Ƃ̌��ɂ��� / p33
���^�@�n��̍��V��
�k��l�@�V��̍��V���ƒn��̍��V�� / p34
�k��l�@�V����~�藈����`��������s / p35
�k�O�l�@���ؐ_�Ђɂ��� / p36
�k�l�l�@�O��S�����_�Ђɂ��� / p38
�k�܁l�@�c��S���ؐ_�Ђɂ��� / p39
�k�Z�l�@���V���F�R / p39
�k���l�@���V���C�O���ɂ��� / p40
�k���l�@���V���헤���ɂ��� / p41
�k��l�@���V���ߍ]���ɂ��� / p42
�k�\�l�@���V����a���ɂ��� / p43
�k�\��l�@���V���ɐ����ɂ��� / p43
�E |
���A���̔N�A�u�p�F�i�Ђ��j�R�v���u�c�싽�y������v���犧�s�����B �@pid/3027720
|
�� ����ѕ� / p1
�ڎ� / p4
�F�R�̗��j �ؓ��r�v / p1
�O�� / p3
���́@�Ñ�̕F�R / p6
���́@�C�����̔��W / p19
��O�́@���������̕F�R / p30
��l�́@��������̕F�R / p34
��́@���q����̕F�R / p65
��Z�́@��k������̕F�R / p80
�掵�́@��������̕F�R / p86
�攪�́@���y���R����̕F�R / p100
�ߐ�����ɉ�����p�F�R�̎Љ�\�C����
�@���W���p�F�R�̕���ߒ��\ ����o/p113
�܂����� / p115
���́@�F�R�R��̐����g�D / p116
��@���储��э���� / p116
��@��m / p122
�O�@���g�E�T�� / p131
�l�@��g�E�哪�E���ʓ� / p133
���́@�C�����W���̍\�� / p143
��@�V�E�@�E���E�̋@�\ / p143
��@���Ƃ̋@�\�ƌo�� / p152
��O�́@�F�R�R���̌o�� / p160
�O�A�p�F�R�̊ό��q / p358
�l�A�p�F�R�̊ό��� / p364
�܁A�F�R��O���i�ό��W���j / p368
�Z�A�p�F�R�̊ό��v�f / p373
���A�p�F�R���R�[�X�� / p376
�F�R�̕��w�m�[�g�\���̕с\ �Z���q��/p379 |
��@���� / p160
��@���� / p169
��l�́@�W������̗v���Ƃ��̉ߒ�/p190
��@�F�R���ނ̗v�� / p190
��@�W������̉ߒ� / p203
�F�R�̍Վ��ƐM�� ���X�ؓN��/p221
�܂����� / p223
�p�F�R�_�ЂƏC���� / p225
�F�R�̍Վ��Ɠ`�� / p231
��A�ߐ������܂ł̍Վ� / p231
��A�Վ��̕��S / p244
�O�A�Վ��Ɠ`�� / p254
�R���ڗ��ɂ�����M�Ɠ`�� / p307
��A���Ђ̂܂� / p307
��A���̑��̐M�s�� / p320
�O�A�s���ƏK�� / p325
�l�A�֊��ƌ� / p332
���@���ؐ_�ЂƋ{�� / p337
���Ƃ��� / p349
�Q�l�����ƕ��� / p350
�ό��n�Ƃ��Ẳp�F�R �˖{�E��/p353
��A�M�̎R����ό��̎R�� / p355
��A�p�F�R�ւ̓� / p356
�a�̕� / p381
�o��� / p406
������ / p439
���^�� / p472
���Ƃ��� / p479
�F�R�������� �����L / p483
�p�F�R�y��l ������Y / p503 |
�F�R�̌��z�ƒ��� �l�c�G / p515
�Гa�̌��z / p517
�V�Ƃ̌��z / p524
���� / p529
ⵂƌ��@�F�R�ɉ�����z��ⵋy��
�@���F�R�b��̓`���ɂ���
�@���{�i�x��/p533
�p�F�R�̐A�� ����� / p545
��
��A�A���i�� / p549
��A�}���l�G�̐A�� / p555
�i��j�@�t�̕� / p556
�i��j�@�Ă̕� / p578
�i�O�j�@�H�̕� / p601
�i�l�j�@���̕� / p611
�O�A���炵���A�� / p630
�l�A�A���G�L / p653
�܁A�A���̏W�ē� / p656
�F�R�̓��� ���q�_ / p663
�܂����� / p665
�M���� / p666
���� / p681
��� / p701
������ / p703
���� / p704
������ / p705
���̑��̓��� / p718
�p�F�R�C�ێu �����p�r / p723
���M�҈ꗗ / p745
�㏑ / p749 |
���A���̔N�A�r�؏r�n, �����Y�S���� �u�V�V���w�u�� ��12���@�V���w�̗��j�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s�����B�@pid/1372736
|
I�D ���m�V���w�j �r�؏r�n
I �Ñ�M���V�@�̓V���w / p19
II �����̉Ȋw�Í������
�@�@���T���Z���������ɂ�����V���w / p4
III ���l�b�T���X���̓V���w / p60
IV �ߐ��V���w�j�T�� / p77
II�D ���m�V���w�j �M����
|
I �� / p107
II �����瓂���܂� / p115
III �v���疾�� / p125
IV ���m�V���w�̓`�� / p134
V �ϑ���B�Ɗϑ����@ / p141
III�D �]�ˎ���̓V���w �_�c��
I �]�ˎ��㏉���ɂ�����V���w / p151 |
II �]�ˎ��㒆���̓V���w / p154
III �]�ˎ������̓V���w / p162
IV �]�ˎ���̓V���ϑ��Z�p �n�ӕq�v
V�D ����V���{�̓��� ���������Y
VI�D �������̗� �O�R�m�Y
�E
�E |
���A���̔N�A�H�c�����u�H�c���m�j�w�_���W ���� (����E�@����)�v���u���m�j������v���犧�s����B�@pid/2990211
|
���R�����l / p1
�k�\�c�l�s��̉��R�蕶 / p39
���R�����q�̓n���� / p44
���R���̘œT�ɏA�� / p49
���R���̓V�n���z�_���S / p64
���R���@���S����i�̝Е� / p143
���R桖{���d�̋��q�_���`�` / p148
�g���R���ؚ��S�̝Њ� / p183
���{�əB�͂�g�z���ɏA�� / p206
�V�o�@�g�z�͟k�S�ɏA�� / p215
�i���S�T��_�_��� / p235
�i���S�T����������S�ɏA���� / p240
�i���S�T�u�������S�ɏA���� / p270
��`�i�͑吹�����d�@�]�y�ё�`�i��
�@�@���錳���{�S�k�ɂɂ��� / p292
���E�R�b�N���������͈╶�ɎO
�@�@���iTurkische Manichaica aus
�@�@�� Chotscho III von Prof�D A�D
�@�@�� von Le coq�j / p308
�f�D�ԁ@�o�y�@���R�������͓k
�@�@���F�蕶�̝Њ� / p325
��桂̘œT�ɂ��� / p348
�ޖ���@�ґ��@��ᶔV�L��� / p358
���� / p360 |
���̎O�\�����M�����ߎ��V�掏/p365
�g�z���U���������u�� / p385
���כ����玚���̝Њ� / p396
�_�O�����̐V���� / p420
�؈�桌�̕ҎҔn�����K / p435
����C���� / p445
�C���Әa���E��桟ތ�[�҉�� / p454
�Ñ��̏@�͓I�����K���@
�@�@�����Â̛ސl/p461
�k�������̊Ԃɉ�����ނɏA����/p473
�g���R���Ƙ��� / p490
�V�Ɓk�P���l�ƌV�A�� / p513
���ق̟ӒE�Ƃ��Ӗ��i�ɂ���/ p526
趎[
�y���I�iPelliot�j���̒������ט����s�@
�@�@�������Ύ��⏑ᢌ��̎���/ p533
��J�[�����̐��� / p541
��ّp������j��椂� / p546
����l���� / p553
�����j?�������̒T�K / p559
�����l�����ɂ��� / p565
�O�Âɂ�����R�Y���t����ᢌ@ / p569
���z�ȏ����̎v���o / p580
�j���N�W�ƂƂ��Ă̓������m / p583 |
�K�����m�u���m�����j�_�p�v��/p589
�������m�̎v���o / p592
�_�c�N�̒lj� / p598
OBITUARY NOTE KOsaku
�@�@��HAMADA / p605
���������������Ǝ�씎�m/p607
���[�h���t���m / p613
�����[���m�̉��o / p622
�䂪���̓����{�ƃy���I�͎�/p628
�ŋߘI�s�ʐM / p641
�A���L�T���_�[�O��������/p646
�p���̈����� / p654
���嗘�̉Ă̗� / p657
�b���ł������� / p663
�ǖk�s�I�̈�� / p669
�����U����r���Ȃ��� / p676
�ڞى�� / p680
������_�ق̋V / p683
���Ƃ��� / p687
���� / p1
��v�� / p1
��㉚���
�E
�E
|
|
| 1959 |
34 |
�E |
1���P�U���A�R�{�ꐴ���S���Ȃ�B�i�U�X�j
�P���A�M�������u�V������ 14(1)(98) p3�`3�@�@����R�V������v�Ɂu19���I�̖]�����Ƃ��̐����(1)�v�\����B�@pid/2382859
�Q���A�M����; �l���m���u�V������ 14(1)(99) p11�`11�@����R�V������v�Ɂu19���I�̖]�����Ƃ��̐����(2)�v�\����B
�V������ 14(2)(99)�@�@����R�V������ ����R�V������ 1959-02/pid/2382860
�T���A��{�i���u�V�E = The heavens 40(409) p160�`163�@�����V���w��v�Ɂu�V���w�̌̋�(1)�v�\����Bpid/3220072
|
�R�{�V����ւ̓������� / �Љ��ǎq / 174�`175
�R�{�搶 / �{����F / 175�`175 |
|
�U���A�u��{�i���u�V�E = The heavens 40(410) p188�`192 �@�����V���w��v�Ɂu�V���w�̌̋�(2)�v�\����Bpid/3220073
�V���A��{�i���u�V�E = The heavens 40(411) p213�`217�@�����V���w��v�Ɂu�V���w�̌̋�(3)�v�\����B�@ pid/3220074
�W���A�_�ސ쌧�����ɕҁu���Ɍ��� (48)�v���u�_�ސ쌧�����Ɂv���犧�s�����B�@pid/3432067
|
�o��m�s�̂��Ɓ\�\���ɕ����l�]�^(��) / �ѐ��h / p1�`2
���ɂɓ`����ꂽ�� / �_�c�� / p2�`4
�������L / �����^�� / p4�`5 |
���Ȃ̍�ҁu�����[�v�͈����� / �O���v�] / p6�`8
�ʐ^�����E�_�ސ쌧�����ً���l������A�G�M / / p8�`8
�E
|
�P�Q���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies���s��w�l���Ȋw�������I�v 30�@p1�`38 �@���s��w�l���Ȋw������,���������������v�Ɂu����ɂ�����ϑ��Z�p�ƐΎ����o�̐����v�\����B�@pid/3558924
�P�Q���A�r�c�O�Y���u���{�앨�{���I�� 28(2) p.25�v�Ɂu��̔���Ɋւ��錤�� : ��1�� ��̕䔭��}���ɑ���M�EH�܂̌��� (��124�� �u����)�v�\����B�@�@�@�Q��ɂ��Ă͂P�X�U�O�N�V�����Q�Ƃ̂���
���A���̔N�A���R�����u������w�w�|�I�v. �Љ�Ȋw 9 p.25-33�v�Ɂu��T�N�Ԃɉ����镾�����V�Ɛ_���v�z(��) �v�\����B
���A���̔N�A���c�F�N���u�O���S���[��̕����j�I���� : ���s��̋N���ƕ��y����щ��ǖ��v���u���{�j������v���犧�s����B�@�@�@pid/1377869
|
��
�͂�����
��1�� �O���S���[��ȑO�̏��� / p1
1�D �G�W�v�g�� / p1
2�D ���[�}�� / p3
3�D �����E�X�� / p6
4�D �L���X�g����� / p9
(1) �T�̍��� / p9
(2) ����� / p11
��2�� �O���S���[�� / p15
1�D �O���S���[13���̉��� / p15 |
(1) ����C�^�ƌo�� / p15
(2) ����̗��j�I�Ӌ` / p17
2�D �O���S���[��̕��y / p21
(l) �J�g���b�N�����̉��� / p21
(2) ��n�n���̉��� / p21
(3) �X�C�X�n���̉��� / p22
(4) �h�C�c�����̉��� / p22
(5) �p���̉��� / p23
(6) ���̑��̍����̉��� / p24
��3�� �O���S���[��̉��ǖ�� / p31
1�D �O���S���[��̌��_ / p31
|
2�D ����^���̗��j / p33
(1) �t�����X�v���� / p33
(2) ��1�����E���܂ł̉���^�� / p37
(3) ���ۘA���ɂ��������^�� / p40
(4) ���ۘA���ɂ���������� / p45
3�D ������̌��� / p48
���� / p53
�t�_ ���{�ɂ�����O���S���[��̗̍p / p63
�\��������̌o�߂Ƃ��̗��j�I�Ӌ`�\
�E
�E |
���A���̔N�A�n�ӕq�v���u�����V���w�v���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B�@ (�V���w�S��)�@pid/1377660
|
���� �v�Z��ʘ_ / p1
���� ���ʎO�p�@ / p39
��O�� ��Ԗ@ / p57
��l�� ��b�I�ɛ{ / p108
��� �V�����W�Ɠ��T�^�� / p124
��Z�� �n�� / p166
�掵�� ���� / p174
�攪�� ���s�� / p198
���� �v�Z��ʘ_ / p1
���� ���ʎO�p�@ / p39
|
��O�� ��Ԗ@ / p57
��l�� ��b�I�ɛ{ / p108
��� �V�����W�Ɠ��T�^�� / p124
��Z�� �n�� / p166
�掵�� ���� / p174
�攪�� ���s�� / p198
���� ���Ə͓� / p205
��\�� �V�� / p223
��\��� �ݗL���̖͂@�� / p237
��\��� ��铖�� / p247 |
��\�O�� �V铂̈ʒu���Z / p263
��\�l�� �O������ / p290
��\�� ���̉^�� / p302
��\�Z�� �H / p312
��\���� ���� / p347
��\���� �V铗� / p366
��\��� �V�ۗ�̍��� / p373
��u / p421
���\ / p433
���� / p44 |
���A���̔N�A�̎R�{�ꐴ���u�l�\���l�̓V���Ɓv���u�P���Ќ����t�v���犧�s����B�@pid/1377605
|
�ŏ��̓V���w�҃q�p���R�X C�ES�E�����h/p2
�R�y���j�N�̏��` / p6
�e�C�R�E�v���[�w�̐��U / p27
���[�n���E�P�v���� �|�c�V��Y/p49
�K�����I�` / p58
�f�J���g�ɂ��� / p79
�w�x���E�X�`�̃X�P�b�` / p84
�w�x���E�X�̍� / p86
�z���N�X�̒Z�����U / p88
�j�E�g���` / p91
�t�����X�`�[�h���` / p129
���̕ǂ�˔j����W�E�n�[�V�F��
�@�@��N�EA�E�}�b�P���W / p149
�J�����[�l�E�n�[�V�F�� / p154
�{�[�f�̖@�������҃{�[�f / p160
���v���[�X���` / p163
�h�u�����` H�E�P�� / p174
�̑�ȃA�}�`���A �I���x���X/p175
|
�V���w��̃t���E���z�[�t�A/p181
�w���P�̓` S�E���b�Z���W���[/p185
�A���Q�����f���̓` / p188
���������E���b�Z���̏��`/p194
���x���G�̓` / p199
�K���̓` / p210
�A�_���X�̓` / p214
�a���Ɛ����̔����҃X���t�g/p219
�̌������O���Â� / p222
�J�~���E�t�����}������ / p224
�����w�҃f�j���O�̏��` / p227
�J�v�^�C������ / p231
�����w�҃h���C�� / p235
�a�������҃��[�h���� / p238
���ʊw�҃O�h�G�[�J / p243
�ΐ��ƃp�[�V�o���E���[����
�@�@��J�EA�E�p�^�\�� / p244
�V�̎ʐ^�̊J��҃o�[�i�[�h/p255 |
�o�[�i�[�h�搶�̂��� / p272
��V�̊J��҃C���l�X �h�E�V�b�^�[/p282
�~�X�E�J�m�����j�̂��� / p289
�a���w�҃N���������� / p291
���z�w�̊J��҃w�[�����m / p293
Z���̖ؑ��h���m / p296
�V��V�����m / p297
���R�������m / p299
�w�����E�m���X�E���b�Z�����m
�@�@��A�EH�E�W���C/p302
�w�ҋy�ы��t�Ƃ��Ẵt�C�V�����m
�@�@�����������E�N���E�h / p307
�A�C���X�^�C���̏��` / p313
�A�[�T�E�X�^�����E�G�f�B���g��
�@�@�����` S�EJ�E�z�C�e�J�[ / p317
���_�ϑ��ƎO�q / p339
�V���J���c�V���h�Ɠ��{�V���w��/p341
�����v�N�̎� / p342 |
|
| 1960 |
���a35 |
�E |
�P�O���A����G�C�q ; ����������u�������ǖ{�v���u�V���R�������쎝��v���犧�s�����B
|
���G�ʐ^/1/2/3
�v�����[�O/4
�������J�n���N�{�q�P�����/5
�����R���������P�̘b./27
�������������/61 |
����������������/68
�V���R����������/69
���d�s�v�c�̓�����/72
�������̌O�r�F��/73
�t�^�k�̏����E��̏���/74 |
�������Q�w�ƋI���{���ό��n�}
�������ē��E���t
�E
�E
�E |
�U���A�M���� ; ���j���u�V������ 15(6)(115) p43�`43�@����R�V������v�Ɂu���ߓ��̗����A��ĥ�o�[�i���a�����ς�v�\����B�@�@pid/2382876
�V���A�r�c�O�Y���u���{�앨�{���I�� 28(4) p.380�v�Ɂu��̔���Ɋւ��錤�� : ��2�� �͔|���q�̋x�����̕i��ԍ��� (��127�� �u����)�v�ɂ��Ĕ��\����B�@�@�P��ɂ��Ă͂P�X�T�X�N�P�Q�����Q�Ƃ̂���
���A���̔N�A��g�{��������ҁu��g�{���̌��� ��1�v���u���s����w��g�{��������v���犧�s�����B�@pid/3025897
|
�_��
��A���_�V�c��G�{�̌����@�R��������
�����\�����V�c�̓�g�{�\
���́@���_�V�c�I�̋L�q
���́@���j�̉�ڂƘ`�̌܉�
��O�́@�_��ɒ��������g�{
��l�́@�Z�g�̑�_�̍Ղ̒�
��́@�n�]�Ƒ��
���^�\�N�\�Ǝ����\
���@�N�\
��A��g�{�����̔��@�@�R��������
����
���́@��������ܑw�̏���
���́@��ꎟ�@���x
��O�́@��@���x
��l�́@��O���@���x
��́@��l���@���x
����
�O�A�@�~�⒬�̍l�Êw�I�����i���j�@�������P
�����@���؍F����
�_��
��A�m���V�c���Ë{�̌����@�R�������Y / p1
����
���́@��G�{�ƃX�~�m�G
���́@��g�̖x�]��
��O�́@�V���]���Ǝ������P
����
��A��g�{�̔��@ �R�������Y / p29
��@�����@��ꎟ���@�`��l�����@
��@������@�@�W�w�Z�\���̍\����
�O�@��Z�����@�@���O�E�ƕ⓱����
�l�@�掵�����@�@�d�X���Џ��q�ɑO
�܁@�掵�����@�@�s�c���K���Z��~�n
�Z�@�掵�����@�@�Ăя��q�ɑO����
|
���@����@���{���z�j�\��g�{���_�\
�O�A��g�{���ɑ���l�Êw�I�����@�����P��/p47
��@�͂�����
��@�h�n�_�̒����i��������j
�O�@�k�n�_�̒����i�掵�������j
�l�@�i�E�j�n�_�̒����i��Z�E���������j
�܁@�x������\�ɂ��Ă̈�A��̖��
�Z�@�ނ���
���@�d�X���Џ��q�ɍ\�������̊�d��\�ɂ���
�l�A��g�{�n������̕��ʌ��� ������ / p77
���^
��A�X�ƎЂƋ{�\�_�ϔO�̕ϑJ�ƎГa�̌`���\ ���؍F���Y / p85
��A�����|�p�̍\���I���i�\��t���̓����\ ���^�| / p101
���E�NjL�E�g�D
��A�F���V�c�����L��{�̌����A���@�{�_�v�| �R�������Y / p1
��@����
��@�����̏���
�O�@�����ꂽ�J�����b
�l�@�X�~�m�G�̑�_
�܁@�i���̕�Ȃ�_
�Z�@�L�I���`�̐���
���@�����L��{
��A�u���������v�ƌ��z�̔����A���{����|�v�� ���^�| / p49
�O�A��g�{���攪���E��㎟���@������ �������P / p63
��@�͂�����
��@�j�n�_�̒����i�攪�������̈�j
�O�@�l�n�_�̒����i�攪�������̓�j
�l�@�m�n�_�̒����i��㎟�����j
�܁@�V�������L���ɂ���
�Z�@�ނ���
�l�A��g�{����\�����@�������� �m/p77
�܁A�L�I�𒆐S�Ƃ���Ñ��g�N�\ ���؍F��Y / p81
���^
��g�{���@�����ɂ��� �R�������Y / p1
|
|
| 1961 |
36 |
�E |
�P���A�_�c���Y ; �z�ڒ��k�t�E�l; �X���O���W���Еҁu�W��. 15(1)(158) p130�`137�v�Ɂu���o�E�֍u�M�L--�����E���H�Ƃ��̎���v�\����B�@
�@�܂��A��ؑ�ق��u���� p42�`47�v�Ɂu���{�l�̐S�v�\����B�@�@pid/7890828
�Q���A�k���l�Y ; �c�� ; �z�ڒ��k�t�E�l ; �X���O ; ���������W���Еҁu�W��
15(2)(159)�@ p112�`119�@�W���Ёv�Ɂu�u���o�v�֍u�M�L(��) �v�\����B�@
�@�܂��A���؏��O ; ���O���u���� p68�`75�@�v�Ɂu�`�����p�̃X���C�h����--�w��сx �v�\����B�@pid/7890829
�R���A�k���l�Y ; �c�� ; �z�ڒ��k�t�E�l ; �X���O ; ���������W���Еҁu�W�� 15(3)(160) p108�`�@�W���Ёv�Ɂu�u���o�v�֍u�M�L(�O)�v�\����Bpid/7890830
�P�P���A���R�����_���j�w��ҁu�_���j���� = The shinto history review 9(6)�v�Ɂu���ߎ���̑�_�_�Ёv�\����B
�����̔N�A�ؐM�����m�_���u��\������Ɋւ��錤���v�\����B
���A���̔N�A���R�� ��������w����w���ҁu������w�w�|�I�v �Љ�Ȋw (�ʍ� 11) p.1-6�v�Ɂu��T�N�Ԃɉ����镾�����V�Ɛ_���v�z-��-�v�\����B |
| 1962 |
37 |
�E |
�R���A ���������u�����w�� = Journal of Oriental studies 32�@p p313�`332�@���s��w�l���Ȋw������ �v�Ɂu�����Ȋw�Z�p�j�����v�\����B(���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@pid/3558926
�S���A�_�c���u���{�Ï��ʐM 27(4)(393) p 2�`4���{�Ï��ʐM�Ёv�Ɂu�×�W�߁v�\����B�@�@pid/10232449
�P�O���A���؏[���u�R����{���{���u p.63-75�v�Ɂu�q����l�v�\����B�@�@�@�iIRDB�j
���A���̔N�A�u���{�Ȋw�Z�p�j�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2428260
|
��
���G
���{�̉Ȋw�̗��j ���S�� �������ȑ�w���� / p1
���{�̋Z�p�̗��j �֖썎 ������w�����E�H�� / p11
�V�� �M���� ���s��w�����E���� / p23
��w �_�c�� �����l������w���� / p43
���w ���^�� ���{�Ȋw�j�w��ψ� / p67
���� �e�r�r�F ���{�Ȋw�j�w��ψ� / p95
���w �c���� �����H�Ƒ�w���� / p125
��w �Ό��� ���l�s����w�u�t�E�㔎 / p153
��w �咹���O�Y �c���`�m��w�u�t�E�㔎 / p175
��w ���������Y ���M��w�����E�� / p197
���� ���v�O ���s��w�����E���� / p229
�n�} ���V���O �������ی�ψ���E���� / p259
���� ���^�� ���{�Ȋw�j�w��ψ� / p285
��� �哇�����Y ���C��w�����E���� / p301
�ʐM �R�����v ���M�����َ��Ɖے� / p321
��� ���V���O �������ی�ψ���E���� / p347
��� �e�n��v �������������فE�����Z�� / p384
�̍z�E��� ���эs�Y ���s��w�u�t / p391
�̍z���t�c�~ ���s��w�����E���� / p394
���S �ѓc���� �������S�������Ζ� / p415
���� ���搳�F �������E���R�c�ψ� / p443
���� �r�؍G ���֓����ꐻ�|���k�� / p470
|
�b�� �O����h�v �����|�p��w������ / p481
���� ���q�� �V�����O�쏊�� / p501
���� �L�n���� ���h�j�w������E���� / p521
�}�� ��ˋv ���É��H�Ƒ�w�����E�H�� / p545
���v ����ޒ�� �����Ȋw�����ٍH�w�ے� / p567
���D ��g�����Y ��������w���� / p589
�y�� �����原�Y ������w�������E�H�� / p623
���z �֖썎 ������w�����E�H�� / p663
���F �㑺�Z�Y ���w�|��w�����E���� / p709
�D�� ���c�p�� �쓇�D���������� / p729
���� ���R�x�m�v ���������� / p763
���� ���X�E �k�C����y���X�������� / p780
���H ���c�� �������������ٔ��p�ے� / p795
�_�� ���q�Y ������w�����E�_�� / p817
���Y ���c���� ���Y�����Y�����ْ� / p841
�ы� ���O�j ����ѐ��j�������E���� / p863
���� �`�� ���O�H��������� / p887
�t�^
���� / ����3
�������� / ����3
�l������ / ����29
���G�E�}�} / ����36
�Q�l���� / ����48
���{�Ȋw�Z�p�j�N�\ / ����53 |
���A���̔N�A�Ε�c�����ҁu�Ñ�j�u�� ��2 (���n�Љ�̉��)�v���u�w���Ёv���犧�s�����B�@pid/2973553
|
���́@�����\�_�k�E�q�{�����ȑO�̌��n�����́\ �a������ / p1
���́@�_�k�E�q�{�̋����̂̏��ތ^ / p17
��@�_�k�E�q�{�̊J�n�ƃI���G���g�̋����� �쑺��� / p18
��@�Ñト�[���b�p�̍��� �p�c���q / p49
�O�@�V�嗤�̌`�����\�A�����J�嗤�̒�Z�_�k�̂͂��܂�\ ���c�a�v / p91
�l�@�����A�W�A�ɂ�����_�k�����Ɩq�{���� ���R�z�� / p127
�܁@���A�W�A�_�k�Љ�ɂ������̌^ �a������ / p157 |
��O�́@���n�����̘_ ����� / p199
��_ /
��E���̋N�� �������� / p242
�n��_ �������Y / p269
�`�����̔_�k���� �Γc�p��Y / p284
���{�̋��Ί핶���Ɠꕶ���� �ڑ� / p301
�E |
���A���̔N�A���s��w�w�p�������ҁu�����̏\���H : �C����,�A�t�K�j�X�^��,�p�L�X�^�������̋L�^�v���u���}�Ёv���犧�s����B�@pid/3021661
|
�C�����̟��\�Ƃ��ɃJ�i�[�g�ɂ��ā\�@�D�c���Y / p3
�C�����́C��Ƃ��Ĕ_���ɂ�����ƒ{���{�ɂ��ā@�������s / p23
�V�q���̗��j�ƎЉ�@�⑺�E / p50
�C������̗��j�@��{�p�� / p60
�����ƋZ�p�@�g�c���M / p80
�C�����l�ËL�@�і��ޕv / p97 |
�q���h�D�E�N�V����k�̕�����Ձ@���쐴�� / p106
�C�X�����̓V����Ɗϑ���B�@������ / p144
�C�X�����������\���̌n���I�T�ρ@�H�c�� / p156
�P�X�T�X�N���s��w�C�����C�A�t�K�j�X�^���C
�@�@�@���p�L�X�^���w�p�������̐��ʊT�v / p175
�j�֗v�� / p178 |
|
| 1963 |
38 |
�E |
�R���A�c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (1)�v���n�������B�@pid/1764551
|
�ɐ��_���ƌÓT / �v�ۓc�� / p1
���{���I�P����b�P�e / ���{�ꖯ / p18
�Ñ㓹���̈�l�@ / ���R�� / p33
�ɐ���̌��� / ������ / p72
|
�דc�t����ݖ��̏j�������Ɖ�ΐ^���\�\�_�{���ɏ��U�
�@�@���ٖ{��j����Ɋւ��錤�� / �J�Ȍ� / p94
��
�E |
�T���A�L�E�{�n�������җ�L�O�o�ňψ�����u�L�E�{�n�������җ�L�O�_���W�v���u�}��o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@�@�@���M�������u�V���E�X�̏o���ƃG�W�v�g�����̔N��v�����\�i���e�j����Ă���炵�����m�F���K�v�@�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�Q�P�@�ۍ�
�@�@�@�@�@�����}���فF�����s�������}���ف@�����R�[�h�F1125742335 �@�@�@�_�ސ쌧�����}����
�U���A�u�_�Ɛ��E 58(7)�v���u���F�Ёv���犧�s�����B�@pid/1756719
|
���d�͔|����̌��ĕi��������q�̋x�����ɂ�������}�C���̖ԍ͔| / �R�萳�} / 176
����c��ㆍ͔|�̎{��@�Ɋւ��鎎����쑐�n�̔엿�̎�ނɊւ��鎎�����
/ ����ז� / 182
�q�����r |
�V���A ��،h�M���u�V���ƋC�� 29(7)�@p14�`17 �n�l���فv�Ɂu�w�}���V���u���x-�n���̉^���v�\����
�@�@�܂��A�{����F���u����p18�`22�v�Ɂu����]���V�ۋV�̍����v�\����B�@�@pid/2356715
�V���A�K���������Y���u�����Ƒ��z�R���p�X�v���u��g���X�v���犧�s����B�@ (��g�V��)�@pid/1379962
|
�܂�����
���̍q��p
1 ���̓n�� / p2
2 ���c�`���̓n��̕���/p8
3 �`���o�g�̋A�� / p15
4 �v���s���͍���s��/p22
5 �͍���s�̉\�� / p26
6 ���ʒm�o�̔\�� / p33
7 �n���̎��]�ɔ����͂�
�@�@���n���C�ւ̔���/p39
|
8 ���N�h���Ƒ��z / p45
9 ���o�ɂ�鑃�Ƃ̂Ȃ��� / p62
10 �A���̍��W�� / p66
11 ���̑��z�R���p�X / p72
12 �`���o�g�̐���^�� / p86
�~�c�o�`�̍q��p
1 �~�c�o�`�̋A�� / p96
2 �~�c�o�`�̋A���ƐG�p�̓��� / p104
3 �Ԃ̋����ƕ�����m�点��~�c�o�`�̃_���X/p11
4 �V���̔����Ƃ��̈ʒu��
|
�@�@��������~�c�o�`�̌��t/p123
5 �Ό��ɂ�鑾�z�̈ʒu�̑��� / p128
6 ���z�̕����Əd�͂̕����̓ǂ݂���/p137
7 �~�c�o�`�̑��z�R���p�X / p145
8 ���z�R���p�X�ƒn���I�ڕW�̋���/p161
���̍q�C�p
1 �T�P�A�}�X�̉�A�� / p170
2 �̋��̉͂̂ɂ��� / p177
3 ���̑��z�R���p�X / p188
������ / p202 |
�P�O���A��،h�M ���u�V���ƋC�� 29(10)p42�`44 �n�l���فv�Ɂu�w�}���V���u���x��̘b�v�\����B�@�@pid/2356718
�P�P���A��،h�M���u�V���ƋC�� 29(11)�@p22�`25�n�l���فv�Ɂu�w�}���V���u���x�V���P�ʂ̘b(1)�v�\����Bpid/2356719
�@�@�܂��A�{����F���u����p33�`35�v�Ɂu���ݓ����v�̍����v�\����B
�P�Q���A��،h�M���u�V���ƋC��29(12)�@��24�`27 �n�l���فv�Ɂu�w�}���V���u���x�V���P�ʂ̘b(2)�v�\����B�@pid/2356720
�@�@�܂��A�{����F���u����p42�`44�v�Ɂu�V���v�Z�ډ���v�\����B
���A���̔N�A����Ǖ����u���E��E�v���l�^���E���v���u�|�v���Ёv���犧�s����B�@ (�V���C�ې}�� ; 6)�@pid/1629977
|
�����V����̓V�����i�o�y�s�j�A
�@�@���̗̂�A���{�̃v���l�^���E���A���B
�@�@���i�J���[�y�[�W�j / 1
���E�̃v���l�^���E���A
�@�@���v���l�^���E���̑g���āA���B
�@�@���i�A�[�g�y�[�W�j / 8
��
���̂����� / 17
���̗���
���̂��낢�� / 20
�P�����Ƒ��z��
���z���͂Ȃ��ӂ��낢��
�W���� / 30
�W�����Ƃ�
���t�ύX��
���̑���ƕ� / 38
�����V����̎�������
���{�̕� |
���v�̔����Ɛi�� / 46
��
����݂̕W�� / 52
�����ɕK�v�Ȃ����
�Ɠ�l�ߋC
�t���E�H���̒���̒���
�Ď��E�~���̒���̒���
���t����̓���
�N�̂͂��߂ƈ�N�̓���
���݂̂��Ђ�
���{�̗̐̂� / 62
���A��
���{�̋���
�\�ܖ�Ə\�O��
���{�̗�̗��j
�߂��炲��݂Ɩ��M
���܂ꌎ�Ə\��x
���E�̂���݂̗��j�Ɖ����� / 72 |
����݂̔��B
�����E�X��
�O���S���I��
���낢��̉����
�A�P���X�̐��E��
�����E�X�ʓ�
�V�̂���� / 80
���ȔN�\
�V�̈ʒu�\
�O���̓V�̗�
�v���l�^���E��
�v���l�^���E�� / 82
�v���l�^���E���̋N���Ɣ��B
�v���l�^���E���̍\��
�v���l�^���E���̉^�]
�v���l�^���E���̉��o
�E
�E |
�����̔N�A��،h�M���u�V�V���w�ʘ_�v���u�n�l���فv���犧�s����B�@pid/1379787
|
��1�� �V���w�̔��B
��2�� �V��
��3�� �V�̂̍��W
��4�� ���W�̕
��5�� ���Ɨ�
��6�� �f���^���_
|
��7�� �V�̂Ƃ��Ă̒n��
��8�� ��
��9�� ���z
��10�� �f��(I)
��11�� �f��(II)
��12�� �a���Ƙf���ԕ��� ) |
��13�� �P��
��14�� �A��
��15�� �ό���
��20�� �P���Ɛ��c�̐i��
��21�� ���z�n�̋N��
���� / p343 |
|
|
| 1964 |
39 |
�E |
�Q���A�ΐ�h�����u�V�E = The heavens 45(465) p52�`56�@�����V���w��v�Ɂu���ɉ����v�\����B�@pid/3220128
�R���A ��،h�M���u�V���ƋC�� 30(3)�@p40�`43 �n�l���فv�Ɂu�w�}���V���u���x(9)�V���w�ɂ����鐔�l�̐��x�v�\����B�@pid/2356723
|
��،h�M����}���V���u���(1�`9)�̓���\
| . |
�G�������� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
29(2) p10�`14 |
1963-02 |
(1)�O�����߂��鑾�z�n
|
. |
pid/2356710 |
| 2 |
29(4) p26�`29 |
1963-04 |
(2)�����Ɛ� |
. |
pid/2356712 |
| 3 |
29(5) p14�`17 |
1963-05 |
(3)���z������ׂ� |
. |
pid/2356713 |
| 4 |
29(7)�@��14�`17 |
1963-07 |
�n���̉^�� |
. |
pid/2356715 |
| 5 |
29(8)�@p34�`37 |
1963-08 |
(4)��͌n�̔��� |
. |
pid/2356716 |
| 6 |
29(10) p42�`44 |
1963-10 |
��̘b |
. |
pid/2356718 |
| 7 |
29(11)�@p22�`25 |
1963-11�@ |
�V���P�ʂ̘b(1) |
. |
pid/2356719 |
| 8 |
29(12) p24�`27 |
1963-12 |
�V���P�ʂ̘b(2) |
. |
pid/2356720 |
| 9 |
30(3) p40�`43 |
1964-03 |
(9)�V���w�ɂ����鐔�l�̐��x |
. |
pid/2356723 |
|
�R���A�M�������u�V�V���w�u�� ��12���@�V���w�̗��j�v���u�P���Ќ����t 1964p/pid/1372455
|
I�D ���m�V���w�j �r�؏r�n
I �Ñ�M���V�@�̓V���w / p19
II �����̉Ȋw�Í������
�@�@���T���Z���������ɂ�����V���w/p49
III ���l�b�T���X���̓V���w / p60
IV �ߐ��V���w�j�T�� / p77
II�D ���m�V���w�j �M����
I�D �� / p107 |
II �����瓂���܂� / p115
III �v���疾�� / p125
IV ���m�V���w�̓`�� / p134
V �ϑ���B�Ɗϑ����@ / p141
III�D �]�ˎ���̓V���w �_�c��
I �]�ˎ��㏉���ɂ�����V���w/p151
II �]�ˎ��㒆���̓V���w / p154
III �]�ˎ������̓V���w / p162 |
IV�D �]�ˎ���̓V���ϑ��Z�p �n�ӕq�v
V�D ����V���w�̓��� ���������Y
�܂����� / p185
1901�N / p188 �`���`1963�N / p237
VI�D �������̗� �O�R�m�Y
VII�D �V���E�X�̏o����
�@�@���G�W�v�g�����̔N�� �M���� / p269
�t�^ ����V���w�N�\ / p279 |
�@�@�����Ł@�P�X�T�W�N�@�Ҏ҂��r�؏r�n, �����Y�S���҂����M�����ɕς��VII���Ɂu�V���E�X�̏o���ƃG�W�v�g�����̔N��v���lj����ꂽ�Ǝv����B�@
�@�@�@�@�@�m�F�v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�Q�P�@�ۍ�
�R���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies 35�@p543�`549�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu�X�^�C�������������̗�v�\����B (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558929
�T���A����Û������{���͛{��ҁu�����@�� = The Journal of eastern religions (24) p52�`53���{���͛{���v�Ɂu�V���Љ� �M���C�u�����Ñ�̉ț{�v �v���Љ��B�@pid/7912575
�W���A�_���w��ҁu�_���w (42)�v�����s�����B�@pid/2263664
|
���l / �⋴���푾 / p1�`13
�\�����l--���̗��j�Ɩ��� / �g��Ǘ� / p14�`29
�Ր_�_�ɉ������Ƒ����̊���(4)--�`�L���e-5- / ����啶 / p30�`42 |
�_���V�c�I�V���~�Ղ̔N���ɏA�� / ����ҔV / p43�`55
�F�N�Ղ̋N���ɂ��� / �F�c�g�V�� / p56�`65
�E |
�X���A�u�V�E = The heavens 45(472) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220135
|
�\�� �������t�߂̎ʐ^
���G �����̃X�P�b�`
�ԎR�V����ł̑��z�ϑ��� / ����s�Y / p235�`238
���݂̂��������Q�ɂ��� / ��ꠍF��Y / p238�`243
1964�N�̋����ϑ��� / �n�ӏ� / p244�`247
�����{�����覐Υ�����o������ / ��ꠍF��Y / p247�`249
�N���R�r�A������(6) / ���J���Y / p249�`252 |
�V���Љ� / H / p252�`253
�ԎR����� / I / p253�`254
�V�� / p254�`255
�����ψ����(96) / ��ꠍF��Y / p256�`256
�����ǂ���� / p256�`257
�V�E7��������\ / p257�`257
�E |
�P�O���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies 36 p611�`632�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu��X����v�\����B�@(���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@pid/3558930
�P�Q���A�ΐ�h�����u�V�E = The heavens 45(475) p332�`333�@�����V���w��v�Ɂu�̎R�{�ꐴ���m�̎Ⴋ���̂��Ɓv�\����B�@pid/3220138
���A���̔N�A�M�������u�����Ñ�̉Ȋw�v���u�p�쏑�X�v���犧�s����B�@ (�p��V��)�@pid/1380155
|
�܂����� / p3
�� �����̋N�� / p9
���Ί펞�� / p9
������Ɨ��R�� / p12
����̏o�� / p16
����̗p�r / p19
����Ɛ�� / p20
�����̎g�p / p25
�u��̗�@ / p30
������ / p32
�������̓W�J / p35
�� ������S�� / p40
�u����v�̘Z�� / p40
����̉��w���� / p42
�S�̎g�p�Ɛ��B�Z�p / p47
�^�J�ƃA���~�j���[�� / p53
�����̃K���X / p58
�O �S�Ƒ��̎��� / p62
|
�퍑�̎��� / p62
���R�N�w / p67
�n�q�Ƃ��̉Ȋw�m�� / p73
�V�q�ƕ��m / p77
�l �V���ƒn�� / p88
���ƌv�Z / p88
��͎Z�p�ƒ������w / p90
�V���w�҂̒n�� / p96
�F���� / p99
��@�̊�{ / p101
�V���ϑ� / p103 (
�萯�p�Ɨ / p106
����̑��n / p108 (
�n�}�̍쐻 / p111
�� �����̈�w / p115
�㐹�G�F / p115
�f�f�Ǝ��� / p119
��w�v�z / p127 |
�_��Ɩ� / p131
�O�ȓI��p / p134
�Z ��A�O�̉Ȋw��B / p138
���t�̒n�k�v / p138
�����v�Ɛ����v / p142
�L��ꉎ� / p148
���^�ӓV�V / p150 (
�� �����l�̔��� / p155
���[���b�p�̐V���� / p155
��ς̎� / p157
����p�Ƃ��̐��` / p160
�Ζ�ƉΊ� / p163
�w��� / p166
���̎w�쐫�̔��� / p167
�Ίp�̔��� / p172
�� �����̕��� / p17
�����̓Ǝ��� / p175
�ߋ��Ə��� / p178 |
|
| 1965 |
���a40 |
�E |
�W���A��K���e���u�V�E = The heavens 46(483) p.210�`211�v�Ɂu����䶗��̋�j �v�\����B
�X���A �{����F���u�V���ƋC�� 31(9)p33�`33�@�n�l���فv�Ɂu�ǎ҂̃R�[�i�[����H�̖����ƏH���ɂ悹�ģ�v����e����B�@�@pid/2356741
�P�P���A�������Y���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 66(11) p.106�`109�v�Ɂu���R�����u�_�Ђƍ��J�v�v���Љ��B
�P�P���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies 37 p1�`40�@���s��w�l���Ȋw�������v�Ɂu�v������ɂ�����Ȋw�Z�p�̓W�J
�v�\����B�@ (���s��w�l���Ȋw�������I�v)�@�@pid/3558931
���A���̔N�A���R�����u�_�Ђƍ��J : ���_���j�̌����v���u�������v���犧�s����B�@�@�@pid/2979566
|
���ҁ@�_�_���̌��� / p1
���́@�_�_���̐��� / p3
���́@�_�_���l�̌��� / p15
���߁@�ޗǎ���̐_�_����C/p15
���߁@���b���b�哈 / p58
��O�߁@�������b�ށk�e�l���C/p67
��l�߁@�ΐ쒩�b�N�� / p92
��ܐ߁@�����^�l��O / p117
��Z�߁@�咆�b���b�����C/p142
���ҁ@�_�Ђƍ��J / p167
���́@���ߎ���̑�_�_��/p169
���́@����_�Ђ̐��� / p205
|
��O�́@���А��x�ɂ�����_�̈ʊK/p230
��l�́@���啼�i�l / p250
��́@�F�N�Ղ̌��� / p267
���́@���_ / p267
���߁@�F�N�Ղ̏j�� / p271
��O�߁@�F�N�Ղ̖{�� / p287
��l�߁@�F�N�Ղ̐����N�� / p312
��ܐ߁@�F�N�Ղ̍Փ� / p319
��Z�߁@�F�N�Ղ̎{�s / p324
�掵�߁@���_ / p330
��O�ҁ@�ÓT�Ɛ_���v�z / p333
��́@���{���I�̐�C�Ɋւ����l�@ �\ |
�@�@���̐��ɂ��ā\ / p335
���́@�a���Ѝl / p365
��O�́@�Ñ㓹���̈�l�@ �\
�@�@�����{��L�̓`��ʂ��ā\ / p383
��l�́@�Ñ�l�̊C�_�M�� �\
�@�@�����t�W�E���y�L��ʂ��ā\ / p427
��� / p450
���� / p464
���G�ʐ^
�c���_���V�����i���q���㏑�ʁj�_�{���ɑ�/p1
�~�R�C���V�����i���q���㏑�ʁj�_�{���ɑ�/p2
�E |
�Z���̔N�A����S���u�o�_�����y�L�_�� ��2�� �{�ҁv���u����c��w�Ñ�j������v���犧�s����B
�@�@�@(���{��j�����p�� ; ��2��)�@pid/3027838
|
�� �攪�\���o�_�����@�o�_��БO�{�i�@��Ƒ���
�}�� / p1
���с@���� / p3
���_ / p5
���߁@�Ñ�o�_�̌����Ɓw�o�_�����y�L�x / p6
���߁@�w�o�_�����y�L�x�����j�T�� / p18
���́@�u���y�L�v�Ƃ������̗̂R�� / p53
���߁@�킪���ɉ�����u���y�L�v�Ƃ������̂̋N�� / p54
���߁@�w���y�L�x�Ƃ������̗̂̍p�̗R�� / p65
���́@�w�o�_�����y�L�x���������̍l�� / p81
���߁@���� / p82
���߁@�Ñ��@�j�I�l�@ / p85
��O�߁@�V���ܔN�������ݘ_ / p104
��l�߁@�V���ܔN�̏o�_�̗� / p108
��O�́@�n���Ƃ��Ắw�o�_�����y�L�x / p117
���߁@�����v���I�L�ڂɂ��� / p118
���߁@���E�A�����I�L�ڂɂ��� / p128
��O�߁@����Ɖ��y�̒n���I�L�ڂɂ��� / p193
��l�߁@���� / p212
��l�́@�j���Ƃ��Ắw�o�_�����y�L�x / p215
���߁@���� / p216
���߁@�w�o�_�����y�L�x�̓��� / p223
��O�߁@�o�_�����A������̓��@ / p246
��l�߁@�w�o�_�����y�L�x�̎j���I���l / p263
���с@�e�� / p265
��́@�o�_�����l / p267
���߁@�n�������̈Ӌ`�Ƃ��̕��@ / p268
���߁@�o�_�����Ɋւ���]���̏��� / p272
��O�߁@�o�_�������̒� / p290
|
��l�߁@�o�_���E�o�_�S�E�o�_�� / p302
��Z�́@��ɐ얼�`�l / p307
���߁@��ɐ�Ȃ閼�̗̂R�� / p308
���߁@��ɐ�̌��`�\��r���C�j�I�l�@/p315
��O�߁@��ɐ�̌��`�\�_�b�w�I�l�@ / p319
��l�߁@��ɐ�B���̔��W / p325
�掵�́@������ˍl / p335
���߁@�u����_��v�\����̐��� / p336
���߁@�u����_��v�̙B�� / p345
��O�߁@�u����_��v�̐_�b�̖{�� / p354
��l�߁@������_ / p362
�攪�́@�o�_�Ó��Ƃ��̗��� / p371
���߁@���� / p372
���߁@�o�_����̈ʒu / p377
��O�߁@�������H�̗��� / p394
��l�߁@�x�����H�̗��� / p408
��ܐ߁@���� / p418
���́@�V���ȑO�̏o�_�̎��@ / p423
���߁@���� / p424
���߁@���ݎ��ƐV���@�\�@�̗��� / p428
��O�߁@�z�{���ƐV���@ / p448
��l�߁@�o�_�̐V���@�ƐV����郉@�� / p470
�����@�w�o�_�����y�L�x�́u�M�Ɓv�ɂ��� / p476
��\�́@�o�_�̎l�Y�ƌÑ�̐��R / p503
���߁@�o�_�̎l�Y�\�u�Y�v�Ɓu�_�v / p504
���߁@�u�\�D���v���̍ג���
�@�@��������u�D�v�ɂ���/p515
��O�߁@�V���ܔN�c���̏o�_�̊C�h�̐�/p523
��l�߁@�Ñ㐅�R�Əo�_�� / p532
|
��\��́@�Ñ�o�_�̘ʕ��� / p549
���߁@�Ñ�o�_�̋ʍ암�Ƃ��̈�� / p550
���߁@�Ñ�o�_�̍U�ʋZ�p / p562
��O�߁@�u�O��_��v�Əo�_�̌��� / p582
��l�߁@�Ñ�o�_�̋ʍ암�Ƙʕ��� / p617
��\��́@�o�_�����̍��J�`�� / p625
���߁@���� / p626
���߁@�F��E�n�z����Ђ̍Ր_ / p629
��O�߁@�_���̉��߂Ɣ�r�_�_�j�I�l�@ / p645
��l�߁@�o�_�����̍��J�`�Ԃ̎j�I�l�@ / p636
��ܐ߁@���� / p675
��Q�с@���� / p681
��\�O�́@�w�o�_�����y�L�x�̐_�b / p683
���߁@�w�o�_�����y�L�x�̐_�b�̊T�v / p684
���߁@�_�����Ƒ��_�n�̐_�b / p710
��O�߁@�{���͖��Ƒ��_�n�̐_�b / p728
��l�߁@�匊�����Ƒ��_�n�̐_�b / p753
��ܐ߁@�������b�Ö얽�ƍ����_�b / p791
��Z�߁@�o�_�_�b�̑̌n / p829
���_�@�o�_��j�_ / p837
���߁@���� / p838
���߁@�o�_�l�̐l��w�I�l�@ / p843
��O�߁@�l�Êw���茩����o�_�� / p864
��l�߁@�o�_���̐����\�n�z���̝��� / p889
��ܐ߁@�n�z�ƈӎ��̍R�� / p916
��Z�߁@�o�_�����ƃl�I�R�n������ / p930
�掵�߁@�o�_�����̏o�_�x�z�`�� / p952
�� / p975
�E |
|
| 1966 |
41 |
�E |
�R���A���������u�����w�� = Journal of Oriental studies (�ʍ� 37) p.1�`40�v�Ɂu�v������ɂ�����Ȋw�Z�p�̓W�J�v�\����B
�S���A�������l���u�������\�L�^�W 1(0) p.3-4�@�A�����w���ߌ�����v�Ɂu���q�̋x���� (�A���̋x��)�v�\����B
J-STAG�d�@�@�d�v
|
�i�܂������̕����i�S���j�j���q�̋x�����͕i��܂��͌n���ɂ� ���Ē��������ق��݂����`�`���ƍl������B
����������������ɕq���Ȃ̎�q�ł͋x���������A�܂���������Z�������݊��Ȉ�ł͋x�����ア
�B���������̊W�̓C���h�̂悤�ȁA�������ꂽ�n��̈�ɂ��ĔF�߂��邱�Ƃł�
���āA��ʂ� �� ���ɓ��{�̈�ɂ����Ă͂��̂悤�ȕ��W�͌��o����Ȃ��B�܂��쐶��͋x�����ɂ߂ċ������o�䐫�Ƃ̑��ւ�
0�D48���x�ł���A�� �� ���̌`���Ƃ̊Ԃɂ��L�ӂȑ��ւ́A�F�ߓ�B���̂悤�ɋx���͑��`���Ƃ͖{���I�ɂ͑��ւ������ʓƗ��`���ƍl������B�������x�����x���̂��̂͐e�A���̐���������q�`�����̏����i�����C�{��A�����x�A��q�����ʒu�j���͂��ߎ��n�����Ȃǂɂ���Ē��������̒��x���قɂ����B |
|
�i1�j����ߒ��̐������Ƌx�� |
�i2�j�x����j�邽�߂̏��� |
�i3�j�x���Ɣ���j�Q���� |
�V���A����m�[���u�Ñ���{�l�̐��_�\���v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/2967761
|
��@�w���t�W�x�ɂ���ꂽ��@���ӎ��̍\��/p7
��@�_�̕\���ɂ��� / p9
��@�u�V�n�̐_�v�̗p��� / p13
�O�@�u�V�n�̐_�v�̌�` / p18
�l�@�_�k��p�ƌÑ㉤�� / p31
�܁@���Ɩ��Ƃɂ�����썰�� / p52
�Z�@�썰�Ɛ_�Ƃ̊W / p69
��@�Ñ���{�l�̎��R�ς̍\�� / p75
��@���@�ɂ��� / p77
��@���n�S���Ǝ��R�Ƃ̊W / p84
�O�@�W�c�\�ۂƂ��Ă̎��R�ς̐����̌_�@/p92
�l�@�G�̂ɂ����鎩�R�� / p113
|
�܁@�����ɂ����鎩�R�� / p132
�Z�@�҉̂ɂ����鎩�R�� / p141
���@���i�ӎ��̐��� / p148
�O�@�Ñ���{�l�ɂ�����_�b�̋@�\/p157
��@���{�l�ɂ�����_�b�̓`�� / p159
��@�_�b�̒�`�ɂ��� / p165
�O�@�L�I�̐_�b�̍\�� / p169
�l�@�����݂̐_�b / p176
�܁@�V�̐Ή��ˉB��̓֘b / p195
�Z�@�V���~�Ղ̐_�b / p209
���@��p�̐��E�Ƃ��̘_�� / p215
���@�ے��I�\���Ƃ��Ă̐_�b / p223
|
��@���Ɛ_�b�̐����̊�� / p231
�\�@�_�b�̋@�\�ƍ\�z�� / p241
�l�@�Ñ���{�l�̑z���͂̍\��/p249
��@�z���͂ɂ��� / p251
��@���A�lj�ɂ�����z���� / p259
�O�@㊕������ɂ�����z���� / p266
�l�@�퐶�����ɂ�����z���� / p278
�܁@�Õ������ɂ�����z���� / p286
�Z�@���R�Ɛl�� / p297
���@�z���͂̋@�\�ɂ��� / p307
���Ƃ��� / p313
���� |
�X���A�������l���u���{趎� 16(3) p.206�v�Ɂu���q�̋x���� : �i��ԍ��ق��䂫�N�������@�\�ɂ��� : ���{���w���29��u����u���v�| : ��ʍu���v�\����B�@
�P�P���A�u�V������ = The astronomical herald 59(12)�v���u���{�V���w�� �v���犧�s�����B
�@�@�@�@�V������59(1)�`59(12)�Ɍf�ڂ��ꂽ�V����,���_�߂���(1) �`�i12�j�̈ꗗ�\
|
| �m�� |
�V�������@���� |
���s�N |
�^�C�g���� |
�o���� |
| 1 |
59(1) p14�`14 |
1965-12 |
�V�ۗ�-2���̓V����,���_�߂���(1) |
pid/3304516 |
| 2 |
59(2)�@p38�`38 |
1966-01 |
�V�ۗ�-3���̓V���� (���_�߂���(2)�@�\���Ȃ� ) |
pid/3304517 |
| 3 |
59(3) p62�`62 |
1966-02 |
�V�ۗ�-4���̓V����,���_�߂���(3) |
pid/3304518 |
| 4 |
59(4) p86�`86 |
1966-03 |
�V�ۗ�-5���̓V����,���_�߂���(4) |
pid/3304519 |
| 5 |
59(5) p108�`108 |
1966-04 |
�V�ۗ�-6���̓V����,���_�߂���(5) |
pid/3304520 |
| 6 |
59(6)�@p132�`132 |
1966-05 |
�V�ۗ�-7���̓V����,���_�߂���(6) |
pid/3304521 |
| 7 |
59(7) p154�`154 |
1966-06 |
�V�ۗ�-8���̓V����,���_�߂���(7) |
pid/3304522 |
| 8 |
59(8)�@p176�`176 |
1966-07 |
�V�ۗ�-9���̓V����,���_�߂���(8) |
pid/3304523 |
| 9 |
59(9)�@p196�`196 |
1966-08 |
�V�ۗ�-10���̓V����,���_�߂���(9) |
pid/3304524 |
| 10 |
59(10) p216�`216 |
1966-09 |
�V�ۗ�-11���̓V����,���_�߂���(10) |
pid/3304525 |
| 11 |
59(11) p238�`238 |
1966-10 |
�V�ۗ�-12���̓V����,���_�߂���(11) |
pid/3304526 |
| 12 |
59(12) p262�`262 |
1966-11 |
�V�ۗ�-1���̓V����,���_�߂���(12) |
pid/3304527 |
|
�P�P���A�K���������Y���u�����̑̓����v�v���u��g���X�v���犧�s����B�@ (��g�V��)�@pid/2429504
|
�܂�����
1 �~�c�o�`�ƉԂ̗��� / p1
2 �~�c�o�`�̎����w�K / p13
3 �~�c�o�`�Ɠ����v / p30
4 �̊O���v���̓����v��/p40
5 �n���̍B�����ł̎���/p46
|
6 ���������ԊԊu�� / p51
7 �~�c�o�`�̓n�m�q�� / p58
8 �~�c�o�`�ƕ����v / p72
9 ��ӑ��x�Ƒ̓����v / p80
10 �~�c�o�`�̐����Ƒ̓����v / p97
11 ���낢��ȓ����̓������s��/p106
|
12 �̓����v�̒��� / p118
13 �S�L�u���̑̓����v / p130
14 ���������̑̓����v / p162
15 �_�o�זE�̓������� / p182
16 �l�Ԃ̑̓����v / p192
�E |
���A���̔N�A��c�c�����u���{�����̂ӂ邳�� : ����A�W�A��얯���������˂āv���u�p�쏑�X�v���犧�s����B (�p��V��)�@pid/9545216
|
�͂��߂� / 9
�i��j ����A�W�A�Ɠ��{ / 9
�i��j ���{�����̋N�� / 10
�i�O�j ����̌����@ / 17
�� ����A�W�A�ւ̐e�ߊ�/20
�Y�ꂦ�ʐl�X / 20
����̔w�i / 22
��Ɛg�Ԃ� / 24
�q�ǂ��̗V�Y / 27
����n�Ƃ����� / 30
���y�̉A�e / 32
�� �����̈߁E�H�E�Z / 37
�i��j �����Ə������ / 37
�������閯�� / 37
�㒅�ƃT���� / 40
�㒅�ƃY�{�� / 43
�㒅�ƃv���[�c�E�X�J�[�g/45
�ѓ��� / 47
�������̌n�� / 49
�Q�^�ƃn�_�V / 53
�i��j �H���ƐH�� / 55
���`�ƃE���` / 55
�R�V�L�ƃi�x / 57
�ԕĂƍ��� / 60
���H���̂��낢�� / 62 (
���`�ƃX�V / 65
���Ǝ� / 66
�i�O�j ���ƌ��z�̗l�� / 69
���Ƃ̎O�l�� / 69 |
�����Z���̋N�� / 73
�ڂ̍����̐��E / 74
���� / 76
�t�����z�� / 78
��ƒ��� / 81
�O ���Z�p�Ɣ_�� / 85
�i��j ��앶���̐��� / 85
�Ă������琅�c�k��� / 85
�������獑�Ƃ� / 86
���̂��܂��� / 89
�i��j �V�������̈��/92
�d�� / 92
�c�A�� / 93
�`���G�C�E�J�� / 94
���c�̊Ǘ� / 94
��� / 96
�E���Ǝ��[ / 96
���~�̎��� / 99
�i�O�j �^�C�E���[���̈��/100
�i�l�j ���Z�p�ƎЉ� / 102
���Z�p�̔�r / 102
���Љ�̔�r / 104
��앶���̔�r / 106
�l �_���̐l�� / 108
�i��j �l���̔�r�����w/108
�������l�X / 108
�����A�^�C�E�k�[�A��/109
�����A�N���[���� / 112
��얯���̐l�� / 115 |
�i��j �a�� / 116
�o�Y�O�� / 116
���Ղ� / 119
���[�N�E�`�����[�v / 121
���� / 123
�i�O�j ���N�� / 124
���N�̂��邵 / 124
�R�[���E�\�V�� / 126
�i�l�j ���� / 130
��炢 / 130
���� / 132
������ / 133
�T���R�b�g�E���[�� / 135
�r�e�B�E�Z�[�� / 136
�i�܁j ��@ / 140
�m�� / 140
�T�h�E�N�� / 142
�i�Z�j �� / 147
����� / 147
�� / 149
���� / 151
�i���j �l���̔w�i / 154
���̗։� / 154
�����̕\�� / 157
��{���̗x�� / 158
�� ���K�Ƃ��̍Ղ� / 161
�i��j �����ȑO / 161
����̐��E / 161
�v���E�u�[�� / 163
|
�s�[�̉� / 165
�i��j �ŗL�M�̓W�J / 168
���K�̑n�� / 168
���W�^�[���I / 170
�Ƃ̃s�[�K�̍Ղ� / 173
���̃s�[�K�̍Ղ� / 175
�i�Ղ̌p�� / 176
�s�[�M�̓W�J / 178
�s�[�M�ƃJ�~�M�� / 183
�i�O�j �N���[�����̑��K / 185
�j�A�E�^�[�̉� / 185
�Փ��l / 187
�Z ���̋V�� / 190
�i��j ��̏@�� / 190
�i��j �^�C���̈��V��/192
�V�������̏ꍇ / 192
�^�C�E���[���̏ꍇ / 197
��Ƃ��̗։� / 198
�i�O�j �N���[�����̈��V��/199
���K�̍Ղ�(1) / 199
�X�L���ꎮ / 200
���c�A�� / 200
�J���� / 201
�E���͂��߂̎� / 202
���K�̍Ղ�(2) / 203
�đq�̍Ղ� / 206
�g���C�E�J���E�v���A�� / 208
�J�~�̑̌n / 210
�� �G�߂̍Ղ� / 214 |
|
| 1967 |
42 |
�E |
�T���A�u�Ȋw���� 27(5)(312)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335382
|
�C�����lj� / �����ɓs�q / 54�`55
�@�����lj�̊痿���߂����� / �X��ꐴ / 56�`59
�F���J���̈Ӌ`(��F����ԣ�ւ̏���-1-)/�{�n���i/93�`100 |
���{�̊�G��\�\���������@�����lj� / 7�`9
�q�����r
�E |
�U���A�ݓВj���u�q�C�p : �C�ɒ��ސl�Ԃ̗��j�v���u�������_�Ёv���犧�s����B�@ (�����V��)�@pid/2513599
|
�͂��߂Ɂ\�\�q�C�p�Ƃ� / p3
�C�������} / p8
I �I�f���b�Z�C�A�ȑO / p2
�i�C���̉͏M
�v���g�ւ̍q�C
�m�A�̔��M
�t�F�j�L�A�l�I�f���b�Z�C�A
II �M���V�A�E���[�}���� / p22
�A�t���J��q
�n���m�̍q�C
�Z�p�Ɨ\��
III �w�����[�q�C���܂� / p35
�����̍q�C
�����ɂ����铌�m�ւ̍q�C
��������
�����Ԃ̍q�H
IV �����m�����̐��E / p48
�|���l�V�A�l�̐�c
�J�k�[�ɂ��q�C
�|���l�V�A�l�̓V���q�@
|
V ���@�C�L���O�̊��� / p61
�m���}���l�̒T��
���@�C�L���O�D
�ŏ��̃A�����J�������@�C�L���O�̍q�C�p
�A���r�A�l�̍q�C
VI ��q�C���� / p77
��q�C�ւ̑ٓ�
�w�����[�q�C��
���̖����z��
�V�嗤�̔���
�}�W�F�����̐��E���
���j��
�Ñ�̃A�X�g�����[�x
�R�[�h�����g
�N���X�E�X�^�t
�o�b�N�E�X�^�t�f���B�X�E�R�[�h�����g
�m�N�^�[�i��
VII �Ȋw�I�T������Ɠ��{�̋ߐ� / p114
�h���[�N
����嗤�̒T�� |
�L���v�e���E�N�b�N�B
�����Ƙ`��
���{�l�̊C�O���W
���Պۂ̉���
VIII �q�C�Z�p�̐i�� / p133
�C�}�̗��j ���͂ƍq���̑���
�����V����Z���V��
�T���𑪂�
�o�x�̔���
���ʂ̒T�m
�q�@�����̔��B
�ʒu�̐�
�d�g�̕��ʑ���
�o�Ȑ��q�@����
���[�_
�v���I�ȍq�C�v��
�D���̎�����
�q�C�p萌W�N�\ / p173
�ߑ�E�ߐ��T���N�\ / p185
�E |
�U���A�u�Ȋw���� 27(6)(313)�v���u�����V���Ёv��������B�@pid/2335383
|
���{�̖쒹(���W) / 31�`59
�����`����"�n��"�̃��[�g ���̕W�������ɂ����Ɨ�����/�g�䐳/31�`37
�n��̏Փ����N�������� / ���щp�i / 38�`42
���Ԍ����ւ̃A�v���[�` / �Y�{���I / 43�`47
�w�K�\�ׂ͂� / �u���� / 48�`51
��������"����"���炩��� / ����L�� / 52
���C�`���E�͌��Ȃ��� / �X��ꐴ / 53�`56
��̗l�t�N���E�̔閧 / ���c���v / 57�`59
�Ղ�ނȂ��� ���̔��y�V�̂��ƂȂ� / �������� / 100�`102
�g���[��L���j���������̂������� / ���͍s / 86�`87
������10�N ���{�]�����N�`��(���N�`������-4-) /�~�c�q�Y/119�`123
�n�蒹�̊ϑ���n ����,�V�l,����,�S�R,�p�� / 15�`30
�グ���ɂ̂錴�q�͔��d �A�����J,�C�M���X,�t�����X, |
�@�@�@���C�^���A,�J�i�_,�h�C�c,�\�A / 63�`73
�~�`�D�y���[���k�O���r�A�l / �C �� ���� ������ / 74�`77
���p������}���錴�q�͔��d / ��{���쁠�k���܂��l / 79�`85
�l�H�q���̉^��(�F����Ԃւ̏���-2-)/�{�n���i/91�`99
���̇����S�N�w����p�̈��S���ɂ���(2)/�匴��/103�`110
�������݂߂� �����i���̋@�\�\�\���R������
�@�@����`�w�I���_�𒆐S��/�ؑ�����/111�`118
���E�̖쒹�k�O���r�A�l / �^���܈� / 7�`9
�T���S�ʂ̐����\�\��㊂̊C���� / �ِΏ� / 10�`
���[�y�̐��E �`���E�̉H��k�O���r�A�l / �|���Õv / 12�`13
��㊂̃T���S�� / �g�����d / 10�`11,88�`90
�i���j
�E |
�P�P���A���{�����w��� �u���{�����w��� (54)�v���u���{�����w��v���犧�s�����B�@pid/2206554
|
��������������ɂ�����\���_--���c�����w�ƎЉ�l�ފw / �������� / 1�`9
�~���z���--���������m�c�N���̌��^ / ����d�N / 10�`21�@�@�d�v
���꥓n���쓇�̖咆�ɂ��Ă̗\���I�� / �R�H���F / 22�`34
�ߑエ��ыߑ㉻�̖��ɂ��� / ���R�a�F / 35�`39
���q��א_�ЉΖh���̑���ɂ��� / �c������ / 40�`44
��|�̎��ٕϣ�̎��� / �ؑ��� / p45�`45
����r�ԓ��̂��Y�Ə��o / ������� / 46�`47 |
�����Љ� / / p48�`52
�w�E�L�� / / p52�`56
�V������ / / p56�`58
�G���_���v�� / / p58�`62
���{�����w��ڎ�(��49���`54��) / / p63�`64
�@���d�����̎v���o / �Βˑ��r / p65�`65
�E |
�P�Q���A�u�Ȋw���� 27(12)(319) �v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335389
|
�����������Ȃ��� �������N�`��(���N�`������-7-)/�~�c�q�Y/.104�`108
�|�̉Ԃُ͈�Ȃ̂� / �����^ / 87�`89
�ԓ��z���ċ��Ǝ��K�\�\�C�ł������鐅�Y���Z��//70�`73
�����Љ�̃_�C�i�~�b�N�X / �쑺�r�� / 111�`117 |
��F����ԣ�ւ̏���-8-���z�n���̏��V��/�{�n���i/91�`97
�A�����J�̉F���J���\�\10�N�̃g�s�b�N�X / / 7�`11
�E���������� �L�̊��������k�O���r�A�l/�|���Õv/12�`13
�q�����r |
|
�~�c�q�Y���u�Ȋw���� 27(3�`12)�v���\�����u���N�`������i1�`7)�v�̓���ꗗ�\�@�@
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
27(3) p.95�`99 |
1967-03 |
�����Ă��鉻�� ���c |
. |
pid/2335380 |
| 2 |
27(4) p.117�`121 |
1967-04 |
���������A��-��-���c |
. |
pid/2335381 |
| 3 |
27(5)�@p.119�`123 |
1967-05 |
1�K5�Ђ̎� �j���� |
. |
pid/2335382 |
| 4 |
27(6) p.119�`123 |
1967-06 |
������10�N ���{�]�����N�`�� |
. |
pid/2335383 |
| 5 |
27(8) p.119�`123 |
1967-08 |
"�������s"���p�����N�`���̔�Ȋw |
. |
pid/2335385 |
| 6 |
27(11)�@p.118�`123 |
1967-11 |
���P�Ɋw�� �|���I�E���N�`�� |
. |
pid/2335388 |
| 7 |
27(12)�@��.104�`108 |
1967-12 |
�����������Ȃ��� �������N�`�� |
. |
pid/2335389 |
|
�P�Q���A�u�V�E = The heavens 48(511)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220174
|
�\���ʐ^ ���z�̃v���~�l���X
���o�ʐ^ ���ʃR�y���j�N�X�R�t��
�����Q�̓˔��I�o���ɂ���/�����F��Y/p325�`330
���S�~�ɂ��ߎ��ȉ~ / �������B / p330�`335
�ܓx�ω��ɂ�����Z���̖�� / �ΐ�h�� / p335�`337
�y�V���j���[�Y�zICARUS�̐ڋ� / / p337�`338 |
�ԎR����� / ���͍G�� / p338�`339
�y���Z�n�w�z���̎O�p���� / �������B / p339�`340
�a���m�[�g / H / p340�`341
���z�ی��� / �ɓ��P�D / p341�`344
�����ψ����(133) / �����F��Y / p344�`346
�V�E11��������\ / / p346�`346 |
���A���̔N�A�W���b�N�E�t�B�l�K����,�O�}�{���m��u�����N��w�v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�@pid/2972227
|
�����҂̓��{�łւ̏� / p1
���� / p2
�t�\�ꗗ / p13
���L���ꗗ / p22
�P�@�P�s�{�ƒ�����s�� / p22
�Q�@�����Ƃ��̊֘A���� / p25
�R�@�I�� / p31
��ꕔ�@�Ñ�ɂ�����
�@�@���N��w�I������ / p1
��@���� / p3
�P�@�q�u������ / p4
�Q�@�M���V�A���� / p4
�R�@���[�}���� / p5
��@�Ñ�ɂ����鎞�̌v���@ / p6
�C�@���̒P�� / p6
�P�@�� / p6
�Q�@�T / p15
�R�@�� / p17
�S�@�N / p18
���@�� / p22
�P�@�G�W�v�g�� / p22
�Q�@�o�r���j�A�� / p30
�R�@�C�X���G���� / p32
�S�@�p���X�e�B�i�ɂ�����
�@�@���o�r���j�A�� / p37
�T�@�N�������̗� / p44 |
�U�@���x���� / p50
�V�@�M���V�A�� / p57
�W�@�}�P�h�j�A�� / p58
�X�@���[�}�� / p69
�n�@��������щ��̓����N / p72
�P�@�G�W�v�g / p72
�Q�@���\�|�^�~�A / p76
�R�@���_���l / p82
�S�@�M���V�A / p86
�T�@���[�} / p87
�j�@�I�� / p94
�P�@�I�������s�A�h / p94
�Q�@���[�}�s�I�� / p96
�R�@�Z���E�R�X�I�� / p99
�S�@���_���l�̋I�� / p102
�T�@�f�B�I�N���e�B�A�k�X�I�� / p109
�U�@�N���X�g�I�� / p110
�O�@�����N���X�g���̔N��L�^�� / p113
�P�@�N��L�ƔN��L�^�� / p113
�Q�@�A�t���J�k�X�́w�N�㎏�x / p118
�R�@�G�E�Z�r�I�X�́w�N��L�x / p124
��@�����Ɍ���ꂽ
�@�@���N��̏���� / p149
��@�ߑ㏔�w�҂ɂ��
�@�@�@�������N��w�̏��̌n / p151
�P�@�W�F�C���Y�E�A�b�V���[��
|
�@�@�@���w���E�V��N��L�x / p151
��@���� / p153
�P�@�A�u���n�� / p153
�Q�@�o�G�W�v�g / p153
�R�@���_�ƃC�X���G���̏��� / p154
�S�@���_�����̖��� / p160
�T�@�C�F�z���L���̕ߎ� / p170
�U�@�C�F�[�L�G�����Ɍ�����N�� / p171
�V�@�ߎ����Ȍ�̔N�� / p173
�O�@�V�� / p175
�C�@�C�G�X�̐��U / p175
�P�@�C�G�X�̒a�� / p175
�Q�@�C�G�X�̐鋳 / p215
�R�@�C�G�X�̎� / p237
�S�@�C�G�X�̐��U�̗v���
�@�@���\�ȔN��\ / p249
���@�y�e���̐��U / p252
�P�@�u�ނ͂ق��̏��������v / p252
�Q�@���[�}�ɂ�����y�e�� / p253
�n�@�p�E���̐��U / p267
�P�@�K���I / p267
�Q�@�t�F���b�N�X��
�@�@���|���L�E�X�E�t�F�X�g�D�X / p275
�����͐ߍ��� / p1
��ʍ��� / p6
�Q�l���� / p17 |
���A���̔N�A�M�������u �v������̉Ȋw�Z�p�j�v���u���s��w�l���Ȋw�������v���犧�s�����B�@ (���s��w�l���Ȋw������������)�@pid/2422240
|
���� / p1
�v������ɂ�����Ȋw�Z�p�̓W�J (�M����) / p1
�v�̎��R�N�w (�R�c�c��) / p33
�v������̐��w (�M����) / p53
�v������̓V���w (�M����) / p89
�v���̈�� (�{���O�Y) / p123 |
�����{���̓`���Ƌ����̖{�� (�����אl) / p171
�v���̌R���Z�p (�g�c���M) / p211
�v��̐��Y�Z�p (�g�c���M) / p235
�v���j (�c��) / p279
���V���v�ɂ��� (�c��) / p329
���̉����w�_���x�̌��� (�V�쌳�V��) / p341
|
|
| 1968 |
43 |
�E |
�Q���A�u�Ȋw���� 28(2)(321)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335391
|
�ً}���@�Ɠ��{�Ñ�j�\�\�����I�ȕ���������� / �ʗ��M / 37�`41
�s���~�b�h�̓�\�\���̐��̂ɉȊw�̃��X�� / ����B�Z / 42�`47 |
����"����"(��F����ԣ�ւ̏���-10-) / �{�n���i / 118�`124
�q�����r |
�R���A�u�Ȋw���� 28(3)(322)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335392
|
���[���b�p�̎��R���݂� ���{�̗ъw�������������/�l���j�p/87�`93
��Ղ̕�ɂ��߂���\�\����̒������ɓ��s����/�g�{����/58�`62 |
�������Ă���V��(��F����ԣ�ւ̏���-11-)/�{�n���i/118�`124
�q�����r |
�S���A�{�n���i���u�Ȋw���� 28(4)(323)�@p 118�`124�@�����V���Ёv�Ɂu�F���Ԃւ̏���-12- �F���̒��̐������ہv�\����B�@pid/2335393
|
�{�n���i���u�Ȋw���� 27(5)�`28(4)�v�ɔ��\�����u�F���Ԃւ̏���(1�`12)�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
27(5)(312) p93�`100�@ |
1967-05 |
�F���J���̈Ӌ` |
, |
pid/2335382 |
| 2 |
27(6)(313) p91�`99 |
1967-06 |
�l�H�q���̉^�� |
, |
pid/2335383 |
| 3 |
27(7)(314) p95�`101 |
1967-07 |
�F����Ԃւ̃��P�b�g |
, |
pid/2335384 |
| 4 |
27(8)(315) p96�`102 |
1967-08 |
�n����f�f���� |
, |
pid/2335385 |
| 5 |
27(9)(316) p94�`100 |
1967-09 |
�n����C�̉ʂ� |
, |
pid/2335386 |
| 6 |
27(10)(317) p94�`101 |
1967-10 |
�n�����C���̔��� |
, |
pid/2335387 |
| 7 |
27(11)(318) p87�`93�@ |
1967-11 |
�f���Ԏ���Ƒ��z�v���Y�} |
, |
pid/2335388 |
| 8 |
27(12)(319) p91�`97 |
1967-12 |
���z�n���̏��V�� |
, |
pid/2335389 |
| 9 |
28(1)(320)�@p135�`141 |
1968-01 |
�f���̐��E |
, |
pid/2335390 |
| 10 |
28(2)(321) p118�`124 |
1968-02 |
����"���� |
, |
pid/2335391 |
| 11 |
28(3)(322) p118�`124 |
1968-03 |
����������V�� |
, |
pid/2335392 |
| 12 |
28(4)(323) p118�`124�@ |
1968-04 |
�F���̒��̐������� |
, |
pid/2335393 |
| - |
29(3)(335) p.126�`127 |
1969-03 |
�F���J���߂��鍑�ۋ��͂̔g��(�_�d) |
, |
pid/2335405 |
|
�U���A�u�Ȋw����. 28(6)(325)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@�@�@�@pid/2335395
|
�����m-���̐��̂�T��(���W) / 31�`61
������m���㣂̂������j�I�Ӗ� / ��c�Y�� / 31�`33
�n���ő�̊C�m ���������̔�߂�i�]/����ʕ�/34�`39
�����m�̑��凌Y�����̂����� / �r��G�r / 40�`42
�������x�z�������̗��� / ����r�v / 43�`48 |
�����m�n�k�т̂��Ԃ� / �Ζؐ��v / 49�`53
�L���鋙��ƐH��̐V�� / �����@�� / 54�`55
�C�͎����̕�� �����"���Y�H��"���J����҂��Ă���/���c��O/56�`61
��n�\���x���͂��� �M���˗ʑ���m�[�g���� / �y���� / 89�`94
�i���j |
�P�O���A�����������N�w����u���N�w�� = Journal of the Academic Association of Koreanology in Japan (�ʍ� 49) p.427�`434�v�Ɂu�����w�҂̒n�]���v�\����B
�P�Q���A�K���������Y���u�����Ə��v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@�@ (NHK���Ȋw�u�� ; 7)�@pid/1383143
|
�� / p5
���� ���̂Ɗ� / p11
1�|1 �����I���� / p15
(��) �Α���
(��) �h�����̐�
(�O) �ۖڕW��
(�l) �����j�^��
(��) ������
(�Z) ���̑��̑���
1�|2 ���� / p23
1�|3 �{�\�s�� / p25
(��) �{�\�s���Ƃ͉���
(��) �M���h��
(�O) �{�\�s�������̊K�w�\��
1�|4 �w�K / p39
1�|5 �m�\ / p42
���� ���̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V���� / p45
2�|1 �~�c�o�`�̃R�~���j�P�[�V���� / p46 |
2�|2 �j�z���U���̃R�~���j�P�[�V���� / p54
2�|3 ���̃R�~���j�P�[�V���� / p59
��O�� �h�������̐����w / p61
3�|1 �E�F�[�o�[�E�t�F�q�l���̖@�� / p62
3�|2 �������˂Ɗw�K�@�̗��p / p64
3�|3 �d�C�����w�I���@ / p67
��l�� �h���̎�e / p69
4�|1 ���n�l�X�E�~���[���[�̓��ꐨ�͐�/p70
4�|2 �]����Ƃ��Ă̎�e�� / p71
4�|3 �e��̎�e�� / p73
(��) ��
(��) ��ƕ@
(�O) ���A���̑��̋@�B��e��
��� �_�o�̓`����M�� / p111
5�|1 �_�o����ۂ̍\�� / p112
5�|2 �C���p���X�̐����Ƃ��̓`�� / p119
5�|3 �_�o�זE����_�o�זE�ւ�
�@�@�@���C���p���X�̏�肩���\�V�i�v�X/p126 |
��Z�� �]�̏�� / p135
6�|1 �����_�o�n�̐i�� / p136
(��) ���Ғœ���
(��) �Ғœ���
6�|2 �����_�o�n�̉�H�� / p159
�掵�� ���̂̎������� / p169
7�|1 �_�o�n�ɂ��^���x�z/p170
7�|2 �z�������ɂ��̂̒���/p178
�攪�� ��`�̏�� / p185
8�|1 ��`�q�̓`����Í� / p186
8�|2 m�\RNA�ɂ��^���p�N����/p194
8�|3 ��`�̈Í��ƍזE�̕���/p200
���� �d�q�`��Ɛl�H���� / p203
9�|1 �l�ԂƋ@�B / p204
9�|2 �l�H�`�� / p207
9�|3 �l�H���� / p21
���Ƃ��� / p217
�E |
���A���̔N�A��Ƒ��邪�u�o�_�_���̌��� : ��Ƒ���搶�ËH�j��_���W�v���u�_���w��v���犧�s����B�@pid/3451611
|
���Ӂ\�X����
���ˑ�R�@�X������
����̎�
�o�_�����p���@�̌����@����啶 / 1
�o�_�����̐_�ꎌ�t��Ə��ʂɂ��ā\
�@�@���w�o�_�����y�L�x������̈�ᔻ�\�@���c�r�t / 21
�o�_�Ə@���̔�r�j�I�l�@�@�����ލ� / 53
�o�_�ƌF��@���c���� / 73
�o�_��_�Ɛ_���v�z�@�v�ۓc�� / 93
�o�_���w�̖��@�X�c�N�V�� / 113
�o�_��Ђ̐M�Ɛ_�А_���@���R�� / 135
|
�o�_�����y�L�ɂ��Ă̓�A�O�̖��@��{���Y / 161
�o�_�����̓��Q�\�o�_�Ɠ����Ƃ̕�������ɂ��ā\�@����S / 187
�C��l�\���̌P�݂ƈӖ��\�@���Ñf�F / 215
�֓��s�d���_�Ђ̔@���Ձ@���c���j / 235
���������{�������̗R���@�������Y / 263
�����_�Ђ̑n���Ǝu�m�̍��J�@�����ʖ� / 301
�_�����_�\�_���̊w�p�I�����ɂ��ā\�@���ь��O / 325
��磎Ɂ@��Ƒ���搶�@�߉e�E�N�� / 353
���^�@�j��
�ËH�j�ꎖ�ƕ����N�l
�E |
���A���̔N�A�����G�O�Y���u�܂� : ���������̑f�^�v���u���p�o�ŎЁv���犧�s����B�@pid/9545935
|
�� �{�c���� / 9
�� �_�̍� �V����߂����˂��
�V�~��_ / 15
�˂��̍����Ƃ��d�v / 18
�ړ�����͂Ȃ₩�Ȑ_���� / 20
�l���܂��_���� / 24
�� �K��_ �ً������藈�����
�g�V�h���ƃi�}�n�Q / 39
�܂ڂ낵�̊C��y�y / 45
�ٖM�̐_ / 50
�O � ���������̒��
|
��Ɠ��{�l / 59
�\�j�̍� / 63
�c�A�̍� / 75
����̍� / 86
�l �� ���̓����ƙ�p�t����
�_��d��������� / 99
�~�ՂƉ� / 101
��t�̉� / 102
�C���̉� / 108
�� ���� �\�ȑO�̖�����
���ʂ�����Ƃ������� / 115
|
�����n��̉��ʌ� / 116
���{�I���y������ʌ� / 122
�Z �l�` �M����ŋ��܂�
�_�V��l�` / 145
�ӏ܂���l�` / 153
�� ���� ��̌|�p�̓W�J
�����Ƃ������� / 161
�炫�������y���x / 168
��v�܂�� / 185
���Ƃ��� / 200
�E |
|
| 1969 |
44 |
�E |
�Q���A�c����V�����u�Ñ�w 15(3)�@p203�`210�@�Ñ�w����v�Ɂu���{��@�j�̂����ڂ�--����������@�j���Q�l���āv�\����B�@�@�@pid/2227303
�R���A�u�Ȋw���� 29(3)(335)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B �@pid/2335405
|
�����Ƃ�����������(���W) / 31�`54
�Ɋ��̐� �n�����"�����n��"�������� / ���[��Y / 31�`35
�����Ɛl�ԂƂ̂������� �k���l�̐����Ɛ��� / �n�Ӑm / 36�`40
�����Ă䂭�q�g�̑ϊ��\�� / �g�����l / 42�`43
�����͂ǂ̂悤�ɂ��Ċ����ɑς��邩
�@�@�@�� ����K���ł̎��b��ӂ̓��� / �ɓ��^�� / 44�`48
�����ɑς���A�� ���̒ቷ�̌��E�ɂ��� / ���䏺 / 49�`54
���a43�N�x�����܂̐l�X / ������ / 90�`94
�J���V�E���Ƌ؎��k �]���ߘY���̋Ɛ� / ������/90�`91
�C�O�ł������]�� �쒷�ތ����O���[�v / �~�����v/91�`92
�C�^�C�C�^�C�a�̋��� ���쏸���̋ꓬ / ������� / 93
�p�v�A���̖��o�ׂ� �j���[�M�j�A��
�@�@��i���n�����ɓ����� / ���ېk��/117�`119,�O���r�A7�`9
���鏬���ȑ�w�̌����L�^�k�����̗ӎ����̌����l/�я��a��/122�`124
�p�v�A���̖��o�����\�\�j���[�M�j�A��
�@�@�����l�H���������������˂� / ���ېk�� / 7�` |
�A�|��8���̑D������ / 10�`11
<���������̐����w>�����͎���̇� / 12�`14
�l��,�����܂��\�\�F���q�C����̐��A�|��8��/WWP/15�`23
�X�^�[�g��������̑�^�v�Z�Z���^�[ / 24�`30
����g���l�����@�� / 63�`71
�ቷ�Ɛ����k��������,���ቷ���琶�Ԃ铮���l
�@�@�@��(�O���r�A) / �Γc�ΗY / 72�`76
�������a�������̕��݂Ɛl��-3-
�@�@�@����������ǂ�l�Ԗ͗l / ����P�O�Y / 79�`86
�͊w����-11-������є��N�� / �؈䒉�� / 111�`116
�F����s�̈�w������w �A�|��8���ɂ݂�
�@�@�@�����̓����Ə���(�����̘b��) / �����k�������l / 88�`89
�}�u�i�̂��ƂȂǁk�����w�Ƃ́l(�Ղ�ނȂ���)/���c�v/120�`121
�F���J���߂��鍑�ۋ��͂̔g��(�_�d) / �{�n���i / 126�`127
�i���j
�E |
�S���A��،h�M���u�V�V���w�ʘ_�v���u�n�l���فv���甭�s����B�k5�ŁF��������Łl
�S���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 44(4) p.693�`694�v�Ɂu����ɂ����锭�萫�̖��_-3-�K�������萫�ƒቷ���萫�̊֘A�v�\����B
|
����ɂ����锭�萫�̖��_�i1�`3�j�̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
| 1 |
43(7) p.1153�`1154 |
1968-07 |
��䔭�萫�̊ȈՌ���@ |
�E |
| 2 |
43(8) p.1295�`1296 |
1968-08 |
��̔��菔�����Ԃ̑��� |
�E |
| 3 |
44(4) p.693�`694 |
1969-04 |
�K�������萫�ƒቷ���萫�̊֘A |
�E |
|
�T���A�_�ސ쌧�����ɕҁu���Ɍ��� 15(5)(157)�v���u�_�ސ쌧�����Ɂv���犧�s�����B�@pid/3432175
|
���a6�N�̔{��� / �_�c�� / 1�`5
���{�ŌẨ~�o���̈ʒu--�k���q�~�o���̖���
�@�@��������~�o���̖͕� / ���Ȃ��E�����Ђ� / 6�`10 |
���́u�P�����C�s�v�ƎQ�w�̗�-��- / �O��//�v�] ; �O����s�q / 11�`15
�k�_�ސ쌧�ɐ����l���V�唦���C�̖����ɂ��� / �O�c���d / 16�`17
�E |
�T���A���������u�j�� = The Journal of history 52(3) p.1�`13�v�Ɂu�����Ԃɂ����鐼�m�Ȋw�̗A���v�\����B
�T���A�L���G�Y���u�V������ = The astronomical herald 62(5) p.104�`107�v�v�Ɂu���{�V���w�j�����ɂ��� �M�������ɕ����v�\����B
�U���A��K���e���u����̊� 10(6) p146�@����]�_�Ёv�Ɂu�q�Ǒz�r���Ƌ��ɘZ�Z�N�v����e����B�@pid/1771671
�W���A�M�������u�����̓V����@�v���u���}�Ёv���犧�s����B
�P�Q���A�����������m�j������ҁu���m�j���� 28(2�E3) p.1�`13�v�Ɂu�����V���w�̔��B�Ƃ��̌��E�v�\����B�@�@�@ |
| 1970 |
���a45 |
�E |
�P���A�ыI�����u�j�� = The Journal of history 53(1) p.1�`31�v�Ɂu��䌴���߂Ɋւ��鏔���v�\����B�@
�R���A�u�����w�� = Journal of Oriental studies (�ʍ� 41) p.763�`765�v�Ɂu��������������ژ^�v���f�ڂ����B
�R���A����c��w�l�Êw����u�Ñ� = Journal of the Archaeological Society of Waseda University (53)�v���u����c��w�l�Êw��v���犧�s�����Bpid/6062490
|
���c�����摜���̔N��Ƃ��̖���/���a��/p1�`5 �iIRDB�j
�_�b�ƍl�Êw--��a���쐬���̃A�E�g���C��/����T��/p6�`25
���쌧�a�c�������̐Ί�V����/�R�{��v / p26�`32
�����u�˓��[������㊕��O�����t���� |
�@�@�����������̓y��ɂ��� / ���c���v / p33�`42
�X�����ʑ����f�̏W�̓y�t��ƎC���y��ɂ���--���k������
�@�@���C���y��̐����Ɋւ��鎎�_ / �k�P�� / p43�`50
�E |
�S���A ���������u�Ȋw���� 30(4)(349)�@p111�`114�@�����V���Ёv�Ɂu���̉Ȋw�j����35�N(���a44�N�x�����܂̐l�X)�v�\����B�@pid/2335419
�S���A�x�����i�Ƃ݂��������j���u�ږ��:��Ǝ_���߂���Ñ���{�l�����v���u�w���Ёv���犧�s����B�@�@
pid/12238663
|
�͂��߂�
��@���D�E���n
|
�̋��ɂ������ā@�x���̉Y�@�����ƕ��Ɓ@���˓��C�̒����}�@���˓��̕����@�Ñ㐣�˂̌�ʁ@�����̈Ӗ��@���D�E���n�@���{�̓����̕����̍��@����̕������@�����̕��z�@�l��I�ȈႢ�@�߂����̐_�̕��z�@�_���Љ�̈Ⴂ�@�͐�Ƃ��ߒr�@
�쒩�N�Ƃ�萌W�@�����ƊC���� |
��@�C���̌S�A�O���̋�
|
�C���̒O���@�O���̈╨�Ɠ`���@�u�O���v�Ƃ����r���@�^������Ƃ߂ā@�O���_�Ё@�O���̒n�w�Ǝ����@��ƏW���@���j�̐��V�@�Ñ�̐��n�u�O���v�@�O���́u����v�@�����Ɠ��g�@�Ñ�C�����ƒO���@�O���Õ��Q�̈╨�@�s�v�c�ȐΊ��̕����@�W���ƕ�n�@��̃}�W�b�N�@����n�_�Ƃ̉\���@�퐶���c���̔����@���H�ƒr�@�x���^�؊�̔��@�@�L�k�R�̏Z�����@�O�����Ί�̔����@�鋫�u�C�����v�@�C���̃V���A�@��̖����@�_���`���Ǝ�� |
�O�@�_���߂���l�X�@�@�[�g�r�m�I�_�[
|
�������̎_�@�������̎_�@�g�r�E�g�r�m�I�@�����_�̔����@�}�R�����r�@
�Њ�̗��@���ւ̏o���@�_�A�������@��_���ƃg�r�_�@�����̐_ |
�l�@�Ñ�ߋE�Ɨ��_�@�[�g�r�ƃi�K���[
|
�_���̓����@�J�W���̍ՋV�@�o���F�Ƌ��F�̃g�r�@����S�A�x�V���̓`���@�I�������N�@�i�K���ց@�O�䎛�E�����R�@���R�̎��Ӂ@�g�r�ƃi�K�̌����@�y�O�������@
�T���ƃw�r�ƌ��̐_ |
�܁@�_�Ƌ��������@�[�Ƃ��ɃJ���E�J���i���j�[
|
�ւƓS�@�J���͓��̋`���@�c���K���̑����@�������R�@�C�J���E�}�K���@�퐶�̓y��q���@�e�n�̃J���E�J���@�ޗǕ���̃J���@���R�̃J���E�J���@��䗋��̌Õ��@
�_���̌�ց@�����^���i�K���g�r |
|
�Z�@�ږ�Ắg�S���h�@
|
�_�Ɛ_���@�g�r�ƃi�K���@�_���c�@�̐_����@�J�W���̎�p�@�_�J�V�Q�̑��݁@�u�_�v�����������P�@�ꍑ�̊@�t�@���@�m���@�鍆�𖼂̂�@���@
�����̐��L�~�@��̃}�W�b�N�@���N�����Ƃ̗ގ��@�@ |
���@�������͂ǂ���
�@�i��j�@�הn�䍑�ւ̓�
|
�n���̌�`�@�`�l�`�̋L�q�@�����̘_���@�Z�\�x�قǂ̃Y���@�s�퍑�͂ǂ����@���������Y���Ă���@�����̘_���@�䗦�ƌ֒��@�����̘_���@�����Ɠ����Ƃ̊W�@
�����ƕ����Ƃ̑g�����@�`���I�ȏs�ʐ��@���n�̗L���Ƃ��̎g�p�@�@�C�l�̗L���@ |
�@�i��j�@�u�������A���n���C�A��]���A���L���v
|
�������͈̔́@�����痢�̍��@�u���A�n���C�A�痢�v�̕����̏d�v���@
�����̓�l�痢 |
�@�i�O�j�@�z���E���n���E��z��
|
�����̈Ӗ��@�z�͓߉ꂩ�@����̎֕R�@�ږ�ĂƐ_���c�@�@�`�l�`�̘_���\���ɂ��������ā@���n�̈Ӗ��@�ہE�ʂ̌�`�@��z�̓ǂ݂����@�N�i���̈ʒu�@��l�̐_�b |
���Ƃ���
�E
�E
�E
�E
�E |
|
�R�[�q�[�^�C���^���̖{�́A������\��̍��ɍw���������N���N����{���B�܂��A㕌���ՂƂ��g�샖����Ղ̑�����Ă��Ȃ����ゾ�����̂ŁA���v���ƌÓT�I�Ȏ����ƂȂ��Ă��܂������Ǝv�����A���e�̒��z�͂Ƃ����z�͂��ƂĂ��L���ŁA���낢��Ȉ��o���Ɍq�����Ă���悤�ȋC�����Ă���B���͂��̂ւ�̂Ƃ���ɁA�ǂ����A�Ђ��ꂽ�悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�˗��A���͑啪���ɋ�����������Ȃ���A�������Ղ�Z�����R�̍��������E�P���A�ܘ_�A�F���̔����{��䋖�R�𒆐S�Ƃ������Ε����Ȃǂ��肪�Ȃ��B�܂��A�Y�Ɩʂł͌�����Â����u�ꑺ��i�^���v�ȂǁA���̃��j�[�N�Ȏ��݂͑S���ɍL�������Ǝv���B���ɂƂ��Ă��啪�͕̂悤�ȂƂ��낾�Ǝv���Ă���A�B�i�ۍ�L�j
�@�@�Q�l�F2000�E2 �啪���n���j������ҁu�啪���n���j : ���x�����搶�Ǔ����W ��P�V�U���v�����s����� |
�T���A���c�ەv �����i�������j���u�_�ƋZ�p 25(5) p.218�`222�v�Ɂu�č��̒����Ǝ�q�̋x�����v�\����B
�@�@ �@�@�@�@�@�@�����́u�������v���A�����v�@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�X�@�ۍ�
�U���A���{�V����������u���{�V��������� 4(2)(14)�v���u���{�V��������v���犧�s�����B�@pid/3204884
|
1970�N3��7���̊F�����H�ϑ��̗\���� / �ؑ����� / p43�`46
�勝�����N�Ԃ̐��� / �_�c�� / p47�`54 |
1964�N�̕ό����̊ϑ� / ���{�V��������ό����� / p55�`71
�}�����̗� / ��{�i / p72�`78 |
�V���A�}�����v,���c�k�삪�u�앨�w�����W�^ 13(0) p.7-8�v�Ɂu���R�s�Ó���� (�퐶�O�`���) �̍앨����юG����ނɂ��āv�\����B�@ J-STAGE
|
�� �� �� ���i�S���j�^���҂�͎j�O�i�퐶�O �E���� �j�Õ� �C���j�e�� �̈� �� �� �蔭 �@�A�����
�Ƃ��ɍ� �� �̂������C�Z�ނƐ��c�G����ނ̕ϑJ�ɂ��Č������u ���Ă���B�^���R���Ó���Ղ͈���̉��ϒn�ɂ����āC�여 ���ċ��J���痬�H�J���n�тɏo�����삪���ɕ��Č`��
�� ��� ���R��h�̍Ŗk �̗�̏�ɂ���Ƒz�肳��Ă������C���@ ���Ă݂�ƍʼn��w�̖퐶�O���̏W���̊�Ղ͊��F����
�w�ł� �����B�É����o�C �̐��c��Ձi�퐶�� ���j���� ���퐶�O���̓y��
�� �� ���Ă��Č��ݓ��{�ŌÂ̔_�ƈ�� �ł͂Ȃ����ƍl �����Ă���B�{��Ղ͏W���ϗ��n
���������n�ɐ� ������ ���Ꮌ�n �œo�C�� �� �̂悤�ɍL��ł� �� 10�`20 m
���ʂł���B ���̏���n������ �̂��ŋ}���ɖ��܂� ���̂��퐶�����̂��Ƃ�
�� ��B����Ɉ��� �̖{�������̂������߂��C���̒J�������w�Ŕ� ��ꂽ�� ��
����ɂ́C�O���̏W���̂����������n�̗����ɁC�_���S�ƃ}���K���̌ݑw�̑��݂�������
�c���c�܂�C�� ��ɔ����n �̖ʂ܂Ŗ��ς��i�n�\�ɁC�� �������̏W�����c��
�ꂽ�̂ł���B�퐶����̊��c�̏��30cm�̕��ʂɏ𗢐��̓c�ʂ��F�� ���C���̖ʂƖ���10�N�̍Ō�̐��c�ʂƂ̊Ԃ���70cm�ʼn������̊��c�̓y��\��
����� ���Ă��̕��߂̕���̑͐ς̑��x ���� ���� �� ��B �i�a������ �l�Êw����
�� 15�� ��� ���v�|�j���҂�͍ʼn��̐��F�V���g�i��39�N�����Ă����c�w�̕\�ʂ��
140 �`180m ���j����1968�N8�����Y�������C�l�m���d�� �肠����������}��̂����܂܂̐��� �̖��Y���̈���A���͒Y���������������B���炩�ɐ�����Ղƍl���Ă��̖퐶���ɂ������̎�q�C��������c���̑��̎G����ނ����̕��@�ɂ���Č��� �� ���B
�������@�i�S���j
�퐶�e�� �̑͐ϑw ���瑽���̎��� ���̏W ���C��������̂悤�ȕ��@�Œ� �� ���� �B
1�D ���ΒY�������ł܂����y�w�ł͗�����ɐ� �������� ���� �� ���������iX10�`
60�j�ŃC�l�C�m �i�b�C�t�j����A����������� ���Â��ɕM��ɐ��H�𗬂��Ȃ�
��y��� ���ċ����ɂƂ炦���� �B
2�D ���̑����w�ł�500���̓y���召�̖Ԗڂ̋��ԏ�ŐÂ��ɐ��������瓱 ���������Ő� �C�L�@���Ɠy����ʂɂ��ėL�@��������ђ����������� ������ ���ĐA����������o���� �B
3�D �T�� �v���y�w �̓y��100�`200cc �r�[�J�[ 10 �` 20g ���� �C�Y�_ �J��50���t��Y��
���Ă� �������܂��Č�ɓy������ �L�@�������āC������K�[�[�Ɋg���Č���
�C���ۂɂ͓y���ƗL�@���𗣂���̂��ނ��������̂ŁC���ݒቓ�S�������p���Ă��ꂪ�\���ǂ������������ł���B |
�P�O���A�}�����v,���c�k�삪�u���{�앨�{���I�� 39(2) p.97-98�v�Ɂu���R�s�Ó����(�퐶�O���`���)�̍앨����юG����q�ɂ��āv�\����B
�P�Q���A���{�V����������u���{�V���������4(3)(15) �v���u���{�V��������v���犧�s�����Bpid/3204885
|
1966�N�̕ό����ϑ� / ���{�V��������ό����� / p77�`98
�����ϑ�1966�N������ / ���эO�� / p99�`100 |
���i11�N�̉�×� / �_�c�� / p101�`105
�a���̋N���Ƌߋ����P���̊W�ɂ��� / �O�J�N�N / p106�`118 |
|
| 1971 |
46 |
�E |
�P���A���������u�Ȋw���� 31(1)(358) p56�`58�@�����V���Ёv�Ɂu�ߋ����疢���ւ̓����v�\����B�@�@pid/2335428
�R���A�u�}�� (259) �v���u��g���X�v���犧�s�����B pid/3447799
|
�n���w�Ғ����]�̂��Ɓ\�\�n�[�o�[�h��w�̓��A�W�A�p��/�M����/p22�`27
�i��ו��ƒÓc���E�g�\�\��t�������߂����� / �_�萴 / p34�`41 |
�w�l�E�i��ו��x�̍l�� / �H�둾�Y / p42�`46
�q�����r |
�S���A���c�ەv,���R���`���u���{�앨�{���I�� 40(1) p.145-146�v�Ɂu����}�������ƈ��q�̋x�����Ɋւ��錤�� : ��4�� ���~�K���̎_�f���D�Ƌx�����Ƃ̊W�v�\����B
|
�u���{�앨�{���I���v�ɔ��\���ꂽ�u����}�������ƈ��q�̋x�����Ɋւ��錤��
: ��1�`4��v�ɂ��Ă̘_�����e�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���Җ� |
pid |
| 1 |
35(3) p.283 |
1966-12 |
���~�K���ɑ��݂��锭��}����������q�̔���ɋy�ڂ��e�� (��142��u����j |
���c�ەv |
�[ |
| 2 |
36(2) p.294 |
1967-06 |
���~�K���ɑ��݂��锭��}�������̓����ɂ��� (��143��u����) |
���c�ەv |
�[ |
| 3 |
36(2) p.295 |
1967-06 |
��q�̐��������肨��є���}�������ɋy�ڂ��e�� (��143��u����) |
���c�ەv,�a��O�Y |
�[ |
| 4 |
40(1) p.145-146 |
1971-04 |
���~�K���̎_�f���D�Ƌx�����Ƃ̊W |
���c�ەv,���R���` |
�[ |
|
�U���A�����������J�j�w��ҁu���J�j�d = The journal of history of Ryukoku University (�ʍ� 64) p.1�`24�v�Ɂu�����Ñ�̓��ƓS�v�\����B
�U���A���{�V����������u���{�V��������� 4(4)(16)�v���u���{�V��������v���犧�s�����B�@�@�@pid/3204886
|
��
���{���I�̗���ɂ��� / ���R��� / p150�`158
���{�I���ƘZ�\���x / ��{�i / p159�`168
�����w�Z�ɂ���i����N�O�������/��������/p169�`174
�X���܌˒��̖ӗ� / ���c�F�N / p175�`179
���������` / �n�ӕq�v / p180�`184
�R��崓��̓V���w / ������ / p185�`188
�V�����C���N�\ / ��萳�� / p189�`194
�؍��_����ɂ��� / ���R�� / p195�`196
�}���̓V���`�ە��� / ��K���e / p197�`200
�������ʌo�߂̌ËL�^�ɂ���/�ē�����/p201�`204
��\�O�铃 / ���֕q�s / p205�`207
�ٗ�̎Z�z / �K���G�v / p208�`210
|
�u�Z�p�L�v�Ɋ֘A���� / �����a�v / p211�`215
�GંɏE�������̐��w�� / ����� / p216�`216
���n�w�ψ���Ɠ��{�̑��n�w / ����z��Y / p217�`220
���������̕����w / ���{���� / p221�`226
�������S�R�s�ɂ�����C�ێj���ƓV���̋Q�[ / �r��G�r / p227�`228
���v���Ǝ�q���̋C�ۂɂ��� / ���䎟�v / p229�`232
�Â����N�̉J�ʌv�ɂ��� / ���{���g / p233�`236
�n�k�̏鑊�B���c���� / ����h���Y / p237�`244
�R������s���S���u���̋����"�I����"�ɂ��� /
�@�@�@������h�O ; ������ ; ����_ / p245�`248
���t�W���\�̖��̂ɂ��� / �����G�� / p249�`255
���Ƃ��� / p256�`256
�E |
�W���A�M�������u�o�ϕ]�_ 20(8) p.78�`87�v�Ɂu���j�I��Y�ƐV���� (���v�㒆���̔��W����(���W))�v�\����B
�X���A�M�������u�Q�� 26(9) p266�`267�u�k�Ёv�Ɂu�����āv�\����B
�@�܂��A���؍F���Y���u����p270�`271�v�Ɂu�֔V�Q�c�@�Ƌ{�q�v�l�v�\����B�@�@pid/6047655
�X���A�u�����Ȋw 9(9)�v���u�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/3213011
|
����(���W) / 5�`72
���Ԃɂ��� / �����r�j / p5�`5
���Ԃ͂Ȃ������֗���邩 / �T�� � / p6�`13
�ߋ��Ɩ����͑Ώ̂� �f���q�_�̎��� / �X�c ���l / p14�`19
�M���ۂƓ��v�͊w�ɂ����鎞�� / �˓c ���a / p20�`24
�����_ / �c�n���v / 26�`29
�����̎��Ԙ_ / �O�} �[�{ / p31�`35
�n�����]�̈�l�� / �|���� / p36�`41
���q���v / ���c���� / p42�`49
|
��������--�̓����v�ɂ��� / �K���������Y / p50�`55
�S���I���� / ���c ���q / p56�`61
�R���s���[�^�Ǝ��� / ���� ���� / p62�`67
�����N�w�ɂ����鎞�� / ���� �ǒj / p68�`72
�u�[���㐔�u�`(3) / ��菺�O / p73�`80
�ޗ��͊w��b���_(7) / ������O / p81�`89
���] / ��X���q / p90�`93
�R���s���[�^��j���[�X / �ҏW�� / p94�`95
�E |
�P�Q���A���{�V����������u���{�V���������5(1)(17) �v���u���{�V��������v���犧�s�����Bpid/3204887
|
��B��ɂ��� / �n�ӕq�v / p1�`4
1969�N�̉����ϑ��� / �ؑ����� / p5�`6
�����ϑ�1969�N������ / ���эO�� / p7�`8
1967�N�̕ό����ϑ� / ���{�V��������ό����� / p9�`41
���f�������� / �_�c�� ; �Y�c�� / p42�`52 |
�ؐ��̑�Ԕ��Əd�͔g / �O�J�N�N / p53�`64
���ߓ���ɂ��� / ���R�d / p65�`89
���c�O�v����N�\ / ���c�O�v / p90�`92
���Ñ�ꏬ�w�Z�����̗��� / �_�c�� / p93�`96
�E |
|
| 1972 |
47 |
�E |
�T���A�{�� ��F���u�V������ = The astronomical herald 65(6)�@ p143�`146 ���{�V���w��v�Ɂu�l�ԓ����v�v�\����B�@�@pid/3304599
�U���A���{�V����������u���{�V��������� 5(2)(18)�v���u���{�V��������v���犧�s�����B�@pid/3204888
|
�����ˌÕ��lj�V���l / ��{�i / p97�`104
�Ăѐ�B��ɂ��� / �n�ӕq�v / p105�`108
1968�N�̕ό����̊ϑ� / ���{�V��������ό����� / p109�`146 |
�n���̋ɉ^���Ɠ��g�Ƃ̊W / �O�J�N�N / p147�`164
�������ɂ�������{�̎�����̌����ɂ��� / ���ʖ��l / p165�`174
���Õ��ɂɂ��� / �_�c�� / p175�`175 |
�V���A�M�����������V���Еҁu�����W���[�i�� 14(27)(695)�@p63�v�Ɂu�P�v���[�̖��v�\����B�@�@
�V���A���������u�Ȋw���� 32(7)(376)�@p 52�`56�@�����V���Ёv�Ɂu24��,60��,60�b�̗R���v�\����B�@pid/2335508
�V���A�u���R = Nature 27(7)(316)�v���u�������_�Ёv���犧�s�����Bpid/2359485
|
�����˂̎l�_����h�Ǝn�� / ��K���e / 46�`51
�Ί�̓���T�� ���j�𒆐S�Ƃ�����Ճ��[�g/ ��ؐ��j / 63�`71
���ɐ��_����-6(��)-���ɐ��_��X����
|
�@�@���V���������w�ւ̓�����? / ���c�� / 52�`62
���R�̕����� ���ؕ�-7-�}�c�ƃ}�c�� / �l���ԉp / 24�`25
�q�����r |
�W���A�u���R = Nature 27(8)(317)�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B�@pid/2359486
|
�������z�̒��̋Z�p������̗m�����z������� / �R�{�w�� / 57�`59
�X�тƐ�(���R�̕����� ���ؕ�-8-) / �l���j�p / 24�`25
�������ꂽ���h�}(���R�̂Ђ��) / �x�������� / 111 |
���V��Ɏc����(���R�̂Ђ��) / ��K���e / 112
�q�����r
�E |
�X���A�і�,�X���M�����u�M�є_�� 16(2) p.115-120�v�Ɂu���q�̋x��������є��萫�Ɋւ��錤��:1.���x����ю_�f�����̉e���v�\����B�@�@�@J-STAGE
�P�Q���A�u���R = Nature 27(12)(321)�@�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B�@pid/2359490
|
�}���̎��_�Ǝ��̏ی`���� / ��K���e / 50�`55
�����m�w�҂�ǐՂ��� ��������F�c���佂̕� / ���ƒB�� / 82�`88 |
�q�����r
�E |
���A���̔N�A�_���c�@�_���W���s��ҁu�_���c�@�v���u�c�w�ّ�w�o�ŕ��v���犧�s�����B1972
|
�_���c�@�̐���(����)
���ɂ�����_���c�@��(�ѓc����)
�����ɂ�����_���c�@��(�v�ۓc��)
�ߐ��ɂ�����_���c�@��(�g��Ǘ�)
����ɂ�����_���c�@���[���������̗v��(����)
�_���c�@����̍��ۏ(��쐭���Y)
�_���c�@����̍����(����[��)
�_���c�@�V�������`���ƍl�Êw�[
�@�@���C�l���̊��_(����ǎO)
|
�_���c�@���߂���n��(���c����)
�_���c�@���߂���I�E�L�̏��`-����
�@�@���_���c�@�I�̐����ɂ���(�c����)
�_���c�@�I�Ɠ��{���I�̋I�N(���c�r�t)
�_���c�@�̎R��(����J��)
�_���c�@�̓`���n(�~�c�`�F)
�_���c�@�̕�Ր_��(�g��Ǐ�)
���N�ɂ�����Z�g��_���Ղ�
�@�@�����Ր���(�����m��)
|
�_���c�@�Ɛ_��(���R��)
��Ր_�Ƃ��Ă̐_���c�@(���{�ꖯ)
�_���c�@���J��_��(���c�ĕv)
��@�_���c�@�ƏZ�g���(��������)
�_���c�@�Ɨ��j����(�R���N��)
�_���c�@�𒆐S�Ƃ������{�I�E�Î��L��
�@�@���ҔN�ΏƎj��(�c����)
�_���c�@���������ژ^(�n�ӊ�)
�E |
|
| 1973 |
48 |
�E |
�P���A�_�{�i���L�� �u���_ (97) �_�{�i���v�̕\���Ɂu�c��_�{�̌���q ������v���f�ڂ����B�@pid/7930639
�R���A�����V����ҁu�����V����� 16(2)(61)�v�����s�����B�@pid/2322304�@�@�d�v
|
�����̓��ʌo�߂ɂ���,���ɖ���7�N(1874)12��9�� ���{�ɂ�����
�@�@���ϑ��ɂ��Ă̒���-��- / �֓����� / 259�`385
OKITAC-5090�ɂ�郊�X�g��������LISP 1.5 / ���R�q�[ / 386�`392
�n����̈�_�ɌŒ肵���ϑ��҂ɂƂ��ĉ��N���Ƃ�
�@�@���F�����H������@����邩 / �ē����� / 393�`415
|
���×�@�ɂ��� / ���c���j / 416�`423
���쌧�ؑ]�n���̓V�̊ϑ������̒�������/������w �����V���� ��͌n��/424�`433
����10�N(1877)�̉ΐ���ڋ߂Ƃ����鐼�����ɂ��� / �֓����� / 434�`463
�q�ߊ��狁�܂�ُ��C�� / �[�J�͔V�� / 464�`469
�E |
�R���A���������u���J��w�_�W = The journal of Ryukoku University (�ʍ� 400�E401) p.558�`571�v�Ɂu�����ɂ����鐯���̐����ߒ��v�\����B
�R���A�u �݉Ƙŋ� (228)�v���u�݉ƕ�������v���犧�s�����B�@�@pid/6063910
|
�O�� ���������� / �R���� / p5�`5
���]�@�� ���Βk�� ������ �ޗǍN��/p6�`18
���̂��̌��t �M������炶/�{������/p20�`20 |
���̂��̌��t ���ւ̊���/��K���e/p21�`21
���̂��̌��t �S�̗�/��i�C�_/p22�`22
�� |
|
�U���A�{����F���u�V������ = The astronomical herald 66(7)p170�`172�@���{�V���w��v�Ɂu���ԉ_�̋���(�����͂���b-7-)�v�\����B�@�܂��A�u����p181�`181�v�Ɂu�V�ۗ�--���{�o�x�̊�_�v���f�ڂ����B�@pid/3304613
�X���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 74(9)�@�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@
pid/3365443�@�@�d�v
|
�������ꎄ�L--�F�������̕��� / ���c���F / p1�`18
10���I�ɂ�����_�Ѝs��--�F�N�Ղ���F�N����/���c���i/p19�`32
10���I(�����`����N��)�̐_�Еꗗ�k�\�l / 28�`32 |
���u�ьÁv��Ӎl--���{���L�E���t�W�̏ꍇ
�@�@���k�{��74��6��(���a48�N6��)�ɑ����l / ��{�M�� / p33�`42
�쑺����ҁu�֑�K�E�q��̘b�W�v / ���c�� / p43�`46 |
�P�Q���A�u�V�E = The heavens 54(583)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220246
|
�I�[�X�g�����A�̌��n�G�撆�̐� / �{����F / p315�`318
�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-2- /�c� / p322�`324 |
�ԎR����� / Y.F. / p327�`328
�E |
|
�V�E = The heavens 54(582�`585)�Ɏ��e���ꂽ�c//᧒��u�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-1�`4-�v �̓���\�@ �@
| . |
�G�������� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
54(582) p293�`295 |
1973-11 |
�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-1- |
|
pid/3220245 |
| 2 |
55(583) p322�`324 |
1973-12 |
�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-2- |
|
pid/3220246 |
| 3 |
55(584) p8�`9 |
1974-01 |
�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-3- |
|
pid/3220247 |
| 4 |
55(585) p44�`45 |
1974-02 |
�A�}�`���A�V���ƃG�W�v�g�̌ÐՂ�����-4- |
|
pid/3220248 |
|
�P�Q���A�u���j�ǖ{ 18(14)�v���uKADOKAWA,���o�o��,�V�l�������Ёv���犧�s�����B�@�@pid/7975187
|
����{�j / �a�̐X���Y / p29�`39
�����鋌��𗝉����邽�߂̎����/�L���G�Y/p66�`73
������Ƃ��̎v�z�I�w�i / �M���� / p96�`103
���m�̓V����E���j�� / �_�c�� / p142�`151
���{�̌��n��@�ƒ��N�Ñ��/��J���j/p130�`137
����ݐl���� / �n�ӕq�v / p82�`93
���E���������n��������̂��ׂ�/���c�F�N/p40�`53
���{�e�n�ō��ꂽ��̂��ׂ�/���c�F�N/p54�`63
�K�g���� �V�ҏW�E���j�N�\ ����E����V��
�@�@���Ώƕ\/���j�y���N���u��/p328�`362
�]�ˏ����̒m�b�E�召�� / �i�m�c�� / p166�`169
����ɐ�����ӗ� / �������Y / p170�`177
�m��ꂴ��ɐ���E�_�{��̌n��/��쌛��/p178�`183
���{�×�̌v�Z / ���c���j / p120�`129
�����͂��̂悤�ɕς��Ă��� / ���{���� / p254�`265
��������̌����Ɩ��_ / ���c�F�N / p188�`199
���܂̗�̉��Ǔ_�Ɖ��ǖ@ / �\�c���� / p200�`205
��Ɋւ��邳�܂��܂ȋ^�� / ����Ǖ� / p74�`81
�l�Ԃ��Ƃ�܂������Ǝ��R�� / �}�g�펡 / p380�`387 |
�V�����ۂƌ���̓V����/��J�L�a/p388�`392
�J�����_�[����E���̖�����
�@�@���f�U�C���̕ϑJ / ���r���O / p394�`401
���ʊ�� ����݃G�s�\�[�h�W ���
�@�@���m����Z�Z/p402�`430
�N���ꗗ / p364�`371
�j���Ɩ��N���j�� / p372�`375
�^����̒��̗��� / p280�`285
�^����̗R�� / p431�`431
�F���̐_��E�萯�p�̒m�� / p286�`293
�a�������̗R�� / p376�`379
��@�W�N�\ / p432�`435
��Ɋւ���Q�l������Z�Z�� / p436�`443
�ҏW��L / p444�`444
�T���� / ��K���e / p64�`65
�j�Փ��̕ϑJ / �������v / p94�`95
��ƋG�� / ������ / p118�`119
�L���V�^���Ƒ��z�� / ��萳�� / p138�`141
�n�}����̔N��L / ��c�L�� / p152�`155 |
��������� / �쑽����V / p184�`187
�G� / �L���C�ܘY / p206�`209
����̃I�����_�� / ���`�j / p266�`269
�ÓT���w���ӏ܂��邽�߂̗��
�@�@���m�� / �z�K�t�Y / p210�`219
�����w��茩����̒m�� / �q�c�� / p294�`303
��ʂ̖��M��� / ��،h�M / p270�`279
�\���\��x�̋N���Ɠ`�� / �|���ƕv / p104�`109
��ɂ܂�鑭�M�E���Ƃ킴 / ������ / p304�`313
����l�ɕK�v�ȗ�̒m��/�r��G�r/p110�`117
��𗘗p�����헪��p��
�@�@���f�[�^20 / �V����v / p314�`327
�N���ɂ��Ă̊�b�m�� / ���c�F�N / p156�`164
���J���[���G �]�ˁE�����̑召��E���� / p13�`13
�O���r�A �ڂŌ�����{�̗� / p221�`221
�`�����ւ�ɐ��_�{�E��̍ՓT / p240�`240
����R���N�V�����喼���v / p246�`246
�����Ƃ����ݕt�^ ���p����ݕ֗�
�@�@�����a49�N��20���I�̐����J�����_�[��̉�� |
|
| 1974 |
49 |
�E |
�P���A�u�����Ȋw 12(1)(127) ��(���W)�v���u�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/3213039
|
��(���W) / 5�`99
��̔����Ɣ��W / �L�� �G�Y / p5�`9
�����̗�@ / ���� �� / p10�`15
���m�̗� / �e�r �r�F / p16�`21
�I���G���g�̗� / � ���v / p22�`27(
���{�̗�@ ���̑召������I�\��܂� / ���c ���j / p28�`34
�����̉��� / ���c �F�N / p36�`41
���Ԃ���݂̂��낢�� / ���c �F�N / p42�`43
�V�������畨������ / �Ք� ���v / p44�`50
�V�̂̈ʒu�̐��Z�ƓV�̗� �q�C�� / �i�y �W / p52�`62
�������肤���� / / p63�`64
����Ŗł̘b / �F�� �����q / p66�`67
|
��Ɋւ��邱�ڂ�b / �ꏼ �M / p68�`72
���N���j�\�E���x�\�Ƃ��̈�ʉ� / ��x ���c / p73�`88
�㐯���v�Z���鎮 / ���� �T�V / p89�`91
���{���I�̋I�N���� �_���ې��I�̂Ȃ� / ���� �L / p92�`99
�_�o��H�Ԃւ̐����H�w�I�A�v���[�`-5-���v�_�o�͊w-2-��X��
�@�@���_�o��H�̋����I��ԕ����� / �×� �r�� / p100�`106
�O���t�ƒu���Q-10- / �|�{ �F�q / p107�`112
�����Ȋw���W�ꗗ / / p113�`113
�ޗ��͊w��b���_-18-�e�_-6- / ���� ��O / p114�`116
�R���s���[�^��j���[�X / �ҏW�� / p118�`119
�����Ȋw�����\�� / / p119�`119
�����Ȋw�O�����e / / p119�`119 |
�P���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 49(1) p.49�`50�v�Ɂu���n��ɂ�������́u�߁v�̋敪�@�v�\����B
�T���A�n�� ����,���X�؍��������s��w�l�ފw������ҁu�G���l�ފw 5(2) p.91�`111�v�Ɂu���̋N���Ƃ��̓W�J���߂����āv�\����B
�V���Q�X���A�_�c���S���Ȃ�B�i�W�O�j
�W���A�����V������u�����V����� 17(1)(64)�v���u�����V����v���犧�s�����B�@�@pid/2322307
|
1973�N6��30���A�t���J���H�ɂ����鑾�z�R���i��
�@�@���ʐ^�ϑ� �����Ɨ\���I���� / �֓����� / 1�`39
�j���[�g�����t�B���^�[�̔Z�x���� / ���{�x�O / 40�`46
���Y�l�H�q���̌��w�ϑ� / ���R�q�[ / 47�`58
�q�ߊ̎��v�C���l�ɂ��� / �[�J�͔V�� / 59�`69
|
��^�ʐ^���p�}�C�N���t�H�g���[�^�[ / �Γc�k�P�C�l�� / 70�`82
�����V���䏊�� �V����w�W�a�����ژ^ / ���c���j / 83�`122
�V�̎ʐ^�����Ɋւ��鏔���� / �֓����� / 123�`193
�Ε����߉�܊i�q�̎��� / �Γc�k�P�C�l�� / 194�`199
���{�Ŏg��ꂽ�×�@-1-�V�P�� / ���c���j / 200�`211 |
�P�O���A�u�V���ƋC�� 40(10)�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@pid/2356927
|
�A�}�`���A�V���̊J���,�_�c�ΐ搶 / �L���G�Y / 12�`12
�_�c�ΐ搶�������� / ���R��j / 13�`13 |
�����v�̗��j�ƊȒP�ȍ��� / �{����F / 14�`19
�E
|
�P�Q���A�u�Ñ�w���� (74)�v���u�Ñ�w������v���犧�s�����B�@pid/6062571
|
���n�E��_�k<���W> / p1�`48
���n�E�Ñ�̔_�k���߂�����<�V���|�W�E��> / ���È� ; �n������ ;
�@�@���H�R���o�Y ; ��؏d�� ; �Ζ씎�M ; �X�_�� ; ���c���F/p1�`26
����̐H���ɂ���--�����n���͊��敛����
�@�@���H���𒆐S�� / ���{���i / p27�`29
�l���ʂɐ��������퐶�ؐ��k��--�E���n����
|
�@�@�����S�Ƃ���/�����v/p30�`32
�؊Ȃɂ݂�A�����H���Ƃ��̎Y�n / �C���a�O / p33�`35
�C���������ɂ�����_�k�앨 / �Ε���O�j / p36�`38
�u�芙�v�ɂ��Ă̎G�l / �Y�c�m�q / p39�`44
�֓��n���̐Ε����ɂ��� / �֏r�F / p45�`48
�E |
�P�Q���A��t��F���C���Z�N�^���D���ҏW�ψ���ҁu�C���Z�N�^���D�� 11(12)(132)�@p14�`17�@ ��������������v�Ɂu�����̓��������\�\�����͂˂ނ�̂��낤���v�\����B�@�@pid/2367650
�P�Q���A�g��T�q�����{�����w��ҁu�����{����= The Japanese journal of ethnology 39(3)p.209-232�v�Ɂu�ɐ��_�{�l : ���{�ɐ����钆���̓N���@�v�\����B �@J-STAGE�@�d�v
|
�͂��߂�
�T�A�z�܍s�v�z�̊T�v
�P���{�Ƒ���
�Q����
�R�܍s
�S�܍s���}�\
�T�܍s���}�\�̌���
�U�ܐ��E�\��x�Ƒ���
�V�\��
�W�Ռo
�X�㐯
�P�O�A�z�܍s�v�z�̓��{�ւ̓n��
�U�ɐ��_�{�̔�_����Ɩk�l
�P�V�Ƒ�_�Ƒ���
�Q���҂̏K��
�R���E�`����
�S���E�h�ԕ���
|
�T���{�ɂ�����k�l�� ��
�U�����ɂ�����k�l �� ��
�V�k�ɐ��i����j�Ɩk�l����
�W�O�{�����`��
�X�L���_�̏o��
�P�O���{�ƊO�{�̔�_
�P�P�㐯�ɂ����鐼�k
�P�Q�O�{�����̐���
�P�R�R�M����a
�P�S�R�M����a �L���_
�P�T���L�͗A昂�
�P�U�L��Ǝ~�R�C
�V�r�Ջ{�l
�P�r�Ջ{�ɂ���
�Q�����A���}�c���m�{
�@ �E�k���E�n�̋{
�@ �E���{�ے��̋{
|
�@�E�����}�c���m�{
�R�������{���n�M��
�S���{���n�M�}�ƉA�z�܍s�K���̋{
�T���{�ݕ~�n�l
�U��\�N���N�J�{�̈Ӗ��������
�V�r �Ջ{�Ƒ��ʋ�
�W�ɐ��_�{�ƌ܍s�v�z
�P��E�\�̐�
�Q���F
�R�ܐߕ�
�X�V���V�c�ƈɐ��_�{
�P�V�����ƌ܍s
�Q�V���V�c�ƈɐ��_�{
�R�ɐ��_�{�̕ω�
������
�E
�E |
���A���̔N�A�F�{�������ҁu�F�{���j�֖����V�R�L�O�������v���u���Ёv����Ċ������B ���łP�X�R�P�N�@pid/9769267
|
�F�{���j�֖����V�R�L�O�������E�����ڎ�
�ʖ��S�]�c���D�R�Õ������i��j / 7
�ʖ��S�]�c���D�R�Õ������@���i���j / 15
�ʖ��S�]�c���D�R�Õ������@���i����j / 52
�ʖ��S�]�c���D�R�Õ������@���i�NjL�j / 54
�ʖ��S�]�c���D�R�Õ������@���i�ċL�j / 58
�i���j�ʖ��S�]�c�������H���V���Õ� / 63
���Ŗڎ�
�}���ڎ�
�F�{���j�֖����V�R�L�O�������E�����ڎ�
�� �F�{�p���ɉ����铺�����g������ / 111
�� �F�{�p���ɉ�����ΐl�Ƒ��̕\���̌Õ� / 128
�O �F�{�p���ɂ�ᢌ@����ꂽ���v�Ȃ�
�@�@���Õ��̒����i����j/157
�l �F�{�s�t�����k���_�ЌÕ��o�y�̐l���ɏA���� / 200
�}���ڎ�
�F�{���j�֖����V�R�L�O�������E��O���ڎ�
�� �F�{�p���ɉ�������ʕی쌚����
�� �F�{�p���ɉ�����Ñ�b�ƌÊ�
���Ŗڎ�
�F�{���j�֖����V�R�L�O�������E��l���ڎ�
��A�j��
��A�V�R�L�O��
���Ŗڎ�
�t�^ �F�{�p�j�֒�������ڎ� �F�{�p�͈���j�֒�����
�� ���蔪���{�y�Õ��������i�F�{�s�j / 549
�� ���������i�O���S�j / 563
�O ���N�̈�ցi�O���S�j / 567
�l ���q�؎�S��y���i�O���S�j / 569
�� �O�p���̌Õ��i�F�y�S�j / 573
�Z ���������A�Z�t���i�F�y�S�j / 576
�� �ԓc�_�Д\�ʁi�F�y�S�j / 579
�� �D��_�Ёi�ʖ��S�j / 583
�� �]�c���D�R�Õ��i�ʖ��S�j / 588
��Z ���䑺�̐ΐl�i�ʖ��S�j / 596
��� �H�`�r粝ЊR�̐ΘŁi���{�S�j / 605
��� ���i�����i���{�S�j / 607
��O �P�˂̐ΐl�i���{�S�j / 611
��l �E�q�����i�e�r�S�j / 616
��� �e�r�\�^���`���i�e�r�S�j / 622
��Z ���h�_�Ћy���h���Õ����A�����i���h�S�j / 628 |
�ꎵ ���c�����i��v��S�j / 639
�ꔪ �ʏ����i��v��S�j / 643
��� �����L�ˁi���v��S�j / 655
��Z �����L�ːl���i���v��S�j / 656
��� ���㑺�g��R���̌Õ��i���v��S�j / 662
��� �팴�̑叾���i���v��S�j / 663
��O ����_�Џ�{�K���i����S�j / 670
��l ����_�В��{�K���̛�⸈i����S�j / 678
��� �����隬�i���k�S�j / 685 (
��Z �萬���y�����i�����S�j / 691
�� ����Ó��y�ő��i�����S�j / 708
�� ���Ŏ����i�V���S�j / 720
��� �����یZ��̎��y����隬�i�V���S�j / 722
�ڎ�
�F�{�p�F�{�s�o�����p�Џo���_�Ћ����E���p�O���S���R���_��
�@�@�����O���ێ����n������ �R�`�����T
���� ���� / 744
���� �����Ȃ鏊�� / 745
��O�� ���ޛ{��̈ʒu / 745
��l�� �X�[�����K�������{���ޚ����� / 746
��� ���ޛ{���ʂ̌��� / 749
��Z�� �ɐB�@ / 756
�掵�� �������e�ȓ��ɐ��O���ۂƖ��ڂ̗މ�����
�@�@���F�����ȂƔO�����Ȃ̓��� / 757
�攪�� ���O���ۂ�����ނ��鏊�� / 764
���� ����p�ˎ�����̎j�I���� / 767
���Z�� �Y�n�Ɗ� / 776
����� �Y�� / 784
����� �̏W�@�y�ё��̎��G / 785
���O�� �����@ / 786
���l�� ���i�����@ / 787
���� ���� / 788
���Z�� �{�B�d�� / 789
��ꎵ�� �Y�n / 790
��ꔪ�� �ڐA��� / 791
����� �u�t�����f���}�v�Ɓu�v���V�I���v / 793
���Ŗڎ�
�t�^�O �F�{���u�����E���ցE�Õ���E�V�R�L�O���j�փX���K���v
�@�@������Ɋւ��鎑���i�吳�l�N�j
�吳���̌F�{���j�֒����ۑ����Ƃɂ��� / 797
�E |
|
| 1975 |
���a50 |
�E |
�S���A�u�Ȋw 45(4)�v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�@�@pid/3218135
|
�s���ւ̐_�o�����w�I�A�v���[�`--Neuro-ethology<���W>/p193�`247
�s���̐_�o�����w / �K���������Y / p193
Ethology�Ƃ͉��� / �����q�� / p194�`198
���Ғœ����̍s�����߂̐_�o�@�\ / ���c�h�� / p199�`204
�����V���`���E�̍s���Ƃ��̐_�o��� / �����Ö� / p205�`211
�_�o�s���w�ւ̈�`�w�I�A�v��-�` / �x�c�M�� / p212�`219
�t�F����������s���w�� / �R�c�� / p220�`225
�ߑ������̎��o--����̃��U�C�N���ƍ����j��-�����̋@�\/�R���P�v/p226�`232
�s�������w�ւ̃V�X�e���H�w�I�A�v��-�` / ������ / p233�`238
���G�l���M-�����w��������12GeV�z�q������ / �e�r�� ; �����ÉE/p239�`247
�����a�F��Ɋւ���s���s���R��--����鐅���a�� |
�@�@�@����w�E�s��(�t�H-����) / �y�䗤�Y / p248�`249
�����M�̃s-�N���x�ɂ���(�t�H-����) / �i�c���i / p249�`250
�H�Ɨp���M�F�̍œK���䗝�_�ɂ���(�t�H-����) / ���i�Ȍ� / p250
�����ƌ��� / �����G�r ; �����N�� / 250�`251
���q����l�Ԃ� / S.E.�����A ; �n�ӊi ; ����V�k�P���V�l�� ; ����h /
251�`252
�[������p�f / �F�m���� ; ������� / 252�`253
�����̋N���Ɣ��W / L.E.�I�[�Q��; ����h;�_���_;�쑺�z;�O�H�C�g / 253�`
Environmental Impact Assessment--Principles and Procedures /
�@�@�@��SCOPE ; �����v�� / 253�`254
�Ȋw���� / / 254�`256
�E |
�T���A�^�|�풉���_���j�w��ҁu�_���j���� = The shinto history review 23(3) p.p112�`141�v�Ɂu�F�N�ՂƐV���Ղ̔Ǖ����߂�����v�\����B
�T���A��t��F���u�������v�̘b�v���u�������_�Ёv���犧�s����B (���R�I��)
�U���A�g��T�q�����{�����w��ҁu�����{���� = The Japanese journal of ethnology 40(1) �@ p.p1�`15�v�Ɂu���ɐ��_�{�l--�Ղ�Ɛ����v�\����B�@J-STAGE�@�@�d�v
|
�͂��߂�
�T �ɐ��_�{�̍Ղ�Ɛ���
�i1�j �_���Ղɂ�����k�l�̐���
�i2�j �G�����Ղɂ�����k�l�̐���
�i3�j �O�ߍՂɂ�����k�l�̑������� |
�i4�j �F�N�Ղɂ�����k�l�̐���
�U �ɐ��_�{�̍Ղ�ɂ݂�n��̐���
�il�j �_���Ռߍ��i���܂̂����E���E���߁j�̋V�̊T�v
�i2�j �_���Ռߍ��̋V�̍l�@
�i3�j �����ے��̑��ʋ� |
�i4�j ���ʋ��̋`
�V �����{�l
������
�E
�E |
�V���A�M�������u�݉Ƙŋ� (256)p32�`32 �݉ƕ�������v�Ɂu���̂��̌��t �m�D�y�v�\����B�@
�@�@�܂��A���������u���� p6�`13�v�Ɂu���n�ŋ��̐����v�\����B pid/6063938
�V���P�P���A�{���w�_�w���ɂ�����,�u���B�ΎR�D�n�т̓����v���e�[�}�� ����,�V ���|�W�E�����J�����B
�@�@�o�Ȏ҂�81����,���L6���̘b��҂ɂ��u�� ��,����ɂ��Ă̓��_���s��ꂽ�B�i�v��j
�@�@�@���\�ҁF�⌳����,�����G�u,�����M,���ʒ�,�u��q��,�R�c���O �@�@
�f�ڎ� �_�Ɠy�؊w� 44(7) 1976 p.470-474 �@�i-STAGE
|
II. �ΎR�D�y��̐�������
�\�\�ʕ����𒆐S�Ƃ������ێ��@�\�ɂ��ā\�@�@���� �G�u*
���B�̎R�D��n�ɂ͒����������̈قȂ�ΎR�D���ݑw ���`�����Ă���,�ݑw
�̌���,�g�������k�n�Ƃ��Ă̓���,�� ��킯,���������ɑ傫�ȉe�������炵�Ă���ƍl������B�����݂��`������\�I�ȉΎR�D�y��(�N���{�N,�A�J�z��,�V���X)�ɂ����镨���I�����̑��ᐫ�������B�����y���,�{�茧����(�s
����)�ɕ��z����l�Ɠ�,�{�茧����(���� �E���� ��)�ɕ��z����\�������̍��F�ΎR�D�y(�N���{�N)�Ɖ��ԃJ
�b�F�ΎR�D�y(�A�J�z��)�̌ݑw�y��ł���B�y��̈�ʓI�������݂邽��,�����y��̗��x���z����эz���g���ׂ��B�y��̕\�ʂ���
- �t - �C�E�� ��"��"�Ƃ��Ē�ʓI�ɋ��߂邽�ߔ�\�ʐς̑�����s�����B���̔�\�ʐς̑����,Brunauer���̑����q�w�z���_�Ɋ�Â�BET����p����N2�z���ɂ���\�ʐς̒�
��H2O�z���ɂ���\�ʐς̒���s�����B�܂�,�ΎR�D�y��̐e�����ɂ��Ă�,��
�F�ΎR�D�y(�N���{�N)�� �K���X���ΎR�D�y(�A�J�z��,�V���X)�ɔ�ׂėL�@���ܗʂ�����߂đ����̂ŗL�@��(���A)�̕��q�\���ɐe����
�̖��[����ʂɂ���Ƃ�,�o�Ɏq�Ƃ��Ă�H2�n���q�����f�����ɂ�肱��ɋz������ƍl�����B������y��̐e�����̒��x��,N2�z���ɂ���
�\�ʐϒl ��H2O�z ���ɂ���\�ʐϒl�̔�ɂ��\�킳���Ƃ�,�e�����w�����Z�o�����B�i���j�@�i-STAGE��� |
�X���A�R�c�@�r���u�w���{�x�Ĕ��� : �����킽���̓��{�� �R�c�@�r����W�v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s����B�@pid/12210005
�P�Q���A���������u�V������ = The astronomical herald 69(1)p17�`21 ���{�V���w��v�Ɂu�~�S�V���}�ƃw�x���E�X���} �v�\����B�@pid/3304646
���A���̔N�A�x���F�����u�M�є_�� 19(1) p.1-6�v�Ɂu���}���[�V�A�ɂ�����Ē����ɓ��̔��C�ۋy�ђ������̐����\�͂Ɋւ��錤���v�\����B�@ J-STAGE
|
| 1976 |
51 |
�E |
�T���A�u�Ȋw���� 36(5)(422)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335554
|
����������V���N���[�h--�A�t�K�j�X�^���̃t�@�C�U�o�[�h(�J���[)/�X�c�E��/p7�`11
�F�{����ւ������K���X--�R�N�}���K���X(�J���[) / ��c�^�� / p12�`13
�H�тō��^���ԂȂ���(�J���[) / ���{�Ɏ� / p15�`19
���������-17-�����ƒ����ɑς���"�j���H"(�L�N��)(�J���[)/���E/p20�`21
�I���f�킷�l�H�� / �ΐ�o�Ŏʐ^���� / 88�`92
�e�q�Ō�荇����I���`��(�O���r�A) / ������v / p93�`98
�~�N���̑f������ʂ���--�Љ��G�v����(���̓� �O���r�A)/���X�ؕ�/p100�`105
���~�W���p�V�J���������璆 / �R�{�I�V / p106�`110
���W �F���l�ƌ�M����@ / / 39�`39
�Ăт����̓d�g��T���o�� / �����L�� / p40�`44
�A���e�i1000�̋���v���� / ���ыv / p45�`48
���������̉\�Ȑ��͖��� / �������v / p49�`52
�n���O�̐����͊�Ȏp? / �哇�טY / p53�`56 |
7���ɉΐ��̐�����T�� / �{�{�����Y / p57
��������l�H�Ȃ����ɖ�� / �w�R�`�v / p60�`62
�l�H���������̊y���� / �@�����q / p63�`66
�����O�ɍL����w�b�h�z�� / ������ / p68�`71
����--�����������ɉΎR�ƒn�k?(���z��Ƃ̃i�]-5-) / �������v / p112�`115
�~�w�̐ȏ��ɃC�L�Ȍv�炢(�p�Y���V�т̊y����-49-) / �����y -N / p116�`119
���͉��Ɠ����c�g(�v���Ⴂ�̉Ȋw�j-17-) / �؍��v / p121�`126
�_�C���̒l�i�͉��Ō��܂�(��������������) / �ɓ��T�� ; ���{� / p72�`77
�������y���̃K���X��(�Ñ�j���Ȋw����-5-) / �����G�u / p78�`81
�����z������--�َ��Ɋ�`��U�����鋰��(���w����̗��Ƃ��q-5-)/���v/p83�`86
���[�̐A�����ޗ���(���荇�킹������-12-) / ���ю� / p128�`131
�g�s�b�N�X��i�E / / 23�`38
�q�Ղ�ނȂ��ǁr�l�Ɠ����ɋ��ʂ̕\�� / �ː�K�v / 132�`133 |
�U���A�g��T�q�����{�����w��ҁu�����{����= The Japanese journal of ethnology 41(1) p.30-56�v�Ɂu���X�ɐ��_�{�l : �_�ߍՂƓ�l,�y�у��L�X�L�ɂ��āv�\����B�@�@
J-STAGE �@�d�v
|
�� �͂��߂�
�_�ߍՂƂ��̓�
�ڎ�
�� �ÓT�ɂ݂��l
1�D �V���I�\�N�̋L��
2�D ���̒����̏�Ɠ�l
3�D �����ÓT�ɂ݂��l
4�D �_�ߍՂƓ�l
�� �_�ߍ�
1�D�_�ߍՂ̖{��
2�D�_�ߍՂƕ_��
3�D�����Õ����ɂ݂�_�ՂƂ��̍Օ����� |
4�D �@�a
5�D �@�a�̈ʒu
�l ��l
1�D��\���h
2�D�l�h
3�D����
4�D�l�h�ƌ��z
5�D�l�h
6�D�_�Ƃ��Ă̓�l�i����j
7�D�_�Ƃ��Ă̓�l�i����j
�� �V���V�c�̉Γ�
�Z �ɐ��_�{�̍��J�\�� |
�� �ɐ��_�{�ƃN ��
�� ���L �E�X�L�ɂ���
1�D�O�e�����̒���
2�D�X�L��l���a��
�� �ɐ��_�{�̍Չ��\��
1�D �V�n���ꑊ�̑��^
2�D �����V�n���ꑊ�̑��^ �ꓺ���ƑO����~��
3�D ���{�E�O�{�̎O���\��
�\ �A�
������
�E
�E |
�U���A��쓹�Y�����{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j����. [��U��] = Journal of history of science, Japan. [Series �U] 15 (�ʍ� 118) p.p93�`98�v�Ɂu�Ñ�C���h�̗�@--���F�[�_�[���K�E�W���[�`�B�V��Vedangajyotisa��5�N�����ɂ����v�\����B �@�@�{���\
�U���A�����G�u,���X�{��,���g�F�s���u���{�앨�w���B�x����� (42) p.49-53�v�Ɂu�F�{�E��m�����(�ꕶ�ӊ�����)�y��� plant opal ���́v�\����B�@�@�@�@�{���\
�V���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ�����u�����l�Êw�W���[�i�� (125)�v���u�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051558
|
�፡���̌��t�� �n�敶���Z���^�[�ݒu�ւ̊��] / p1�`1
���A�t���J�I�s / ��Q�`�� / p2�`5
���Ñ�y��ٓy�Ɋ܂܂��v�����g�E�I�p�[���̌��o/�����G�u/p6�`10
�������O��S���S��Ղ̏o�y�� / �����q�� ; ���{�� / p11�`12
���m���{�쑺�`�X���Ղ̒��� / ���{���� / p13�`15
����u�� �퐶�y��--���C����(4) / �g���O / p16�`18
�����C���h�E�r�[���x�g�J�̊�lj�Q(III) / �R������ / p19�`22 |
�F�{����̊L�˔����̐Ζ_/�K��؉m��; ����j/p23�`25
�����E�ш��Տo�y�̎g�����y��/���쏇��;�֓��/p10�`10
�ᕶ���ژ^�� / p26�`30
��l�Ãj���[�X�� / p31�`35
�O���t ���m���{�쑺�`�X����
�O���t �����E�ш��Տo�y�̎g�����y��
�E |
���Ñ�y��ٓy�Ɋ܂܂��v�����g�E�I�p�[���̌��o/�����G�u
�@�@
�@�@�E�F�{�E��m����Ձi�ꕶ�ӊ������j�̓y��ܗL�w����
�@�@���o���ꂽ�C�l�@���זE�l�v�����g�E�I�p�[�� |

�F�����E�ߒ���Ձi�퐶�O���j�̓y��ܗL�w���猟�o���ꂽ
���V�@���זE�l�v�����g�E�I�p�[��
|
�X���A�V���{�o�ŎЕҁu�����]�_ (185)�v���u�V���{�o�ŎЁv���犧�s�����B�@�@�@pid/1799416
|
�⍻�q�̎v���o / ��K���e / 11
���[�̍� / �ё� / 12 |
���͓S����̌��z / �勴��� / 14
�肢���� / ���c�q�q / 15 |
(��)
�E |
�X���A�u�n�� 21(9)�v���u�Í����@�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7893421
|
�Ă̎v�z<���W> / p13�`61,�}����9p
�ĐH�̎v�z / �ʋZ�ĕF / p13�`23
��̋N���Ɠ`�d--���{�̈��
�@�@������/�n������/p24�`34 |
�ĂƔ_���Љ�/�I�������Y/p35�`44
�ĂƍՋV / �c������ / p45�`52
�Ă̗��� / ��˗� / p53�`61
�l�Y�~�̐��� / ���X���b/p134�`135 |
�Ĕ��k��̌��w���//p153�`153
���G �����E���_�Ђ̓c�A�_��/�������b/p1�`9
�q�����r
�E |
�X���A�����G�u���u�l�Êw�G�� = Journal of the Archaeological Society of Nippon 62(2) p.p148�`156�v�Ɂu�v�����g�E�I�p�[�����͂ɂ��Ñ�͔|�A���╨�̒T���v�\����B
�P�P���P�R���A��c�����S���Ȃ�B�i�W�S�j
�P�P���A���c�ەv���u���w�Ɛ��� 14(11) p.696-702�v�Ɂu�C�l�̐���ƐA���z�������v�\����B�@J-STAGE
|
��q�̋x���Ɣ���
���� �ƐA�� �z���� �� |
�o�n �ƐA ���z������
���^�Ɖ��w�I���� |
���ԓI�����Ɖ��w����
�E |
�P�Q���A�R���Y���u�Ȋw����. 36(12)(429)�@p78�`81�v�Ɂu�lj�Ɏc��z�����̊G�̋�(�Ñ�j���Ȋw����-12��-) �v�\����Bpid/2335561
|
�Ȋw����. 36(1�`12)�ɋL�ڂ��ꂽ�Ñ�j���Ȋw����1�`12���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G�������ʂƕŐ� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
36(1)(418)p78�`81 |
1976-01 |
�ړ���������E�����C��(�Ñ�j���Ȋw����-1-) / �R�{���v |
. |
pid/2335550 |
| 2 |
36(2)(419)p78�`82 |
1976-02 |
�C�l�̉ԕ��Ŕ_�k�j������(�Ñ�j���Ȋw����-2-) / ������ |
. |
pid/2335551 |
| 3 |
36(3)(420)p78�`81 |
1976-03 |
�Z�p�ʂ��猩���퐶�̑D(�Ñ�j���Ȋw����-3-) / �Έ䌪�� |
. |
pid/2335552 |
| 4 |
36(4)(421)p78�`81 |
1976-04 |
�Y�f14�̗ʂŌÂ��𑪂�(�Ñ�j���Ȋw����-4-) / �؉z�M�F |
. |
pid/2335553 |
| 5 |
36(5)(422)p78�`81 |
1976-05 |
�������y���̃K���X��(�Ñ�j���Ȋw����-5-) / �����G�u |
. |
pid/2335554 |
| 6 |
36(6)(423)p78�`82 |
1976-06 |
�������ލ��j�̐��a�w(�Ñ�j���Ȋw����-6-) / �ߓ��S�O |
. |
pid/2335555 |
| 7 |
36(7)(424)p78�`82 |
1976-07 |
�G���̎�q�Ŕ_�k��m��(�Ñ�j���Ȋw����-7-) / �}�����v |
. |
pid/2335556 |
| 8 |
36(8)(425)p120�`123 |
1976-08 |
X���ŕ�����ނ̌��Y�n(�Ñ�j���Ȋw����-8-) / �������M |
. |
pid/2335557 |
| 9 |
36(9)(426)p128�`131 |
1976-09 |
�D�����A���Ƃ̂������(�Ñ�j���Ȋw����-9-) / ���J�Ŏq |
. |
pid/2335558 |
| 10 |
36(10)(427)p128�`131 |
1976-10 |
�C��Ɨ��j���l����n���C(�Ñ�j���Ȋw����-10-) / ��䒼�l ; ��菲�� |
. |
pid/2335559 |
| 11 |
36(11)(428)p128�`131 |
1976-11 |
�הn�䍑�ɂ������閧�q��(�Ñ�j���Ȋw����-11-) / ���g�B�Y |
. |
pid/2335560 |
| 12 |
36(12)(429)p78�`81 |
1976-12 |
�lj�Ɏc��z�����̊G�̋�(�Ñ�j���Ȋw����-12��-) / �R���Y |
. |
pid/2335561 |
|
�P�Q���A�u�V�E = The heavens 57(12)(619) �v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220282
|
�\���ʐ^ �I�[�X�g�����A���H / ��c���ǎ��B�e
���G�ʐ^ �ؐ��ʂ̓W�J�} / �{��M���B�e
�k�����V���w��l����ɉ����錤�����\�̊T�v-2-
�@�@���P���̐��H���� / ����//���B / p323�`327
�V�����ɂ�鐯�H / ���J��//��Y / p327�`329
���쒉���̢�L�^��ɂ݂�a���̂���/�ē��`�M/p329�`330
|
�y�V���j���[�X�z / H / p330�`331
��c���搶���] / p331�`331
�E�C�g�R�E�X�L / p331�`332
���z�ی���No.72 / ���X���� / p332�`335
�إ�y���ی��� / ���їE / p336�`338
�a���ی��� / �֕� / p338�`339
|
�����������(244)/�M�ےj/p339�`341
�y�}���z���l�グ�ɂ��� / p341�`341
�����ǂ���� / p341�`341
���a52�N�̗���\ / �_�c��Y / p344�`345
�V�E11�����̐���\ / p335�`335
�E |
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (9)�v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����Bpid/7957060
|
���R�Ȋw�I�l�Êw�j�̈��--�ߏd�^���ƕl�c�k�� / ���эs�Y / p1�`5
��e�ωt�̃V���`���[�V�����J�E���^�[�ɂ���P�SC�N�㑪�茋�� / �R�c�� / p7�`13
�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(1)����C�l�ȐA���̌]�_�̕W�{�ƒ�ʕ��͖@
/ �����G�u / p15�`29�@�d�v
���p�́g㊕��C�i�h�ɂ��� / �O�c�ەv / p31�`41
�m�����v�Z�@�̓y��ւ̉��p / �~�c�b�q�Y / p43�`51
���̓��ʑ̔�ɂ��Y�n���͂̎���--�{�M�o�y�̐����Ȃ�тɌÑK�ɂ��� / �R���Y ; ���Z���� / p53�`58�@�@�d�v
�ԊO�z���X�y�N�g���ɂ�����߂̎Y�n���� / ����Ǝq / p59�`64
�{�b��̕��ˉ�����--�{�b��Y�n���͂̕��@�ɂ��� / �O�җ��� / p65�`76
�Y�n����ɂ����铝�v�I��@ / �������M / p77�`90
�������^ / p91�`100 |
���A���̔N�A����m�[���u�Ñ���{�l�̐��_�\�� ���v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/2967800
|
��ꕔ�@�Ñ���{�l�̏@���ӎ�
��@�_�Ђ̐��Ԋw / p11
��@���ƕ��@ / p13
��@�_�Ђ̐��Ԋw�ɂ���/p18
�O�@��_�_�� / p25
�l�@�ɐ��_�{ / p29
�܁@�F��O�R / p37
�Z�@�o�_��� / p44
���@�z�K�_�� / p54
���@�_�ЂƎ��R�Ƃ̊W/ p66
��@���R�Ɛ_�����Ԍo���̉�H/p71
�\�@�_�Ǝ��R�����Ԍo���̉�H/p76
�\��@���`�������_ / p82
�\��@���P�̏j�� / p87
��@���{�̐_�X / p93
��@�V�n�����_�b�Ɛ_ / p95
��@�����ɂ���ďo������_�X/p100
��@�Ñ���{�l�̐l�Ԉӎ�
��@�Ñ���{�l�̐l�Ԉӎ� / p109
��@�l�Ԉӎ��̊�ɂ��� / p111
��@��������̂ƌ����Ȃ����� / p114
�O�@�_�̎��R�� / p126 (0067.jp2)
��@����̘_�� / p135
��@���{�����̔ߌ��̈Ӗ� / p137
��@�_�̝|�̌��@�Ɗ���̐��E/p146
|
�O�@��O�̗ϗ� / p153
��@�ΔV�����̎��i�ɂ���/p155
��@�����Ȉ������߂鏗 / p161
��O���@�Ñ���{�l�̎��R�ӎ�
��@�Ñ���{�l�̎��R�� / p171
��@���ƕ��@ / p173
��@�_�Ǝ��R / p176
�O�@�`�{�l���C�̎��R�ς̍\��/p186
��@���s���l�̎��R�� / p199
��@���o�̗D�� / p201
��@���l�̉̂̍\�� / p204
�O�@���l�̎��R�o�� / p209
�l�@��̈�ߖ@ / p214
�܁@���l�̋�Ԉӎ� / p219
�O�@�I�єV�̐��E / p223
��@�]���_�Ƃ��� / p225
��@���t�̉̕��ƌÍ��̉̕�/p227
�O�@�_�b�̎��R�Ƃ̑r�� / p229
�l�@���e�̔� / p235
��l���@�Ñ���{�l�̕��w�ӎ�
��@���w�ƕ��w�ȑO / p241
��@���w�ȑO�̍��ׂƕ��w�ӎ�/p243
��@����̔��ɂ��� / p245
�O�@���R�ւ̎u�� / p250
��@�Ñ���{�l�̕��w�ӎ� / p253
|
��@�Ñ�̘_�ɂ�����S�Ǝ� / p255
��@�É̂̊T�O / p259
�O�@�S�̎��R�� / p263
�l�@�É̂ɂ����錾�t�̋@�\ / p271
�܁@���̐V�������o / p275
��ܕ��@�Ñ���{�l�̎��Ԉӎ�
��@�Ñ���{�l�̎��Ԉӎ��̐���/p283
��@���ۓI���ԂƋ�̓I���� / p285
��@���Ȃ鎞�ԂƑ��Ȃ鎞�� / p289
�O�@�������鎞�� / p294
�l�@��͔̍|�Ɣ_�k�V�� / p299
�܁@�F�N�Ղɂ����鎞�Ԉӎ� / p308
��@�`�{�l���C�̎��Ԉӎ� / p313
��@�s�q�Ȏ��Ԉӎ� / p315
��@�ߍ]�r�s�̉̂̐����̔w�i / p318
�O�@�ߍ]�r�s�̉̂̍\�� / p322
�l�@�l���C�̎��Ԉӎ��̍\�� / p330
�O�@�Ñ���{�l�̎��Ԉӎ��̓W�J / p335
��@�Ñ㕶�w�ɂ�����G�ߊ��̕ϑJ/p337
��@�唺�Ǝ��̎��Ԉӎ� / p348 (
�O�@�w�Í��W�x�ɂ����鎞�Ԉӎ� / p376
�l�@�������{�l�̎��Ԉӎ��̐���/p400
���Ƃ��� / p409
����
�E
|
���A���̔N�A����@�h�ďC:���䏟�V�i���u�_�Ɠm�v���u�_�Ɠm���s��v���犧�s�����B�@pid/12266358
|
�_�ޔ��̓m(�؋I��)
�_�ЗтƎ��R�ی�(�n��)
���N�̐X(��������)
����(�ѓc����)
�R�E�m�E��(�r�Ӗ�)
�_�̂��킷�m(�ΐ_�b�q�Y)
�J�~�ƃ���(�Γc���)
�O���Ǖ�(�ɓ����Y)
�R�Ɖ_�ƈ(��c�c��)
�_�ƍ�(��R�t��)
�_�{�̌�[�R�ƌ�_�̂���(�F�m��F)
�_�X�̖{��(�~����)
������R(���c�C��)
�_�X�̂ӂ邳��(�i�R�t��)
�����j�ɂ�����R��(���؍O�Y)
�㕐�����̎R�Ɛ��ƐX(���s�r�Y)
�m�Ǝ�(��Y�o)
�_���Ȃ�̓���(�N���C�i�[�E���[�[�t)
�u�_�V�сv�̐S(�S�i����)
�T�J�L�̗��j(�ߓ��씎)
���E�̐_��(���䏟�V�i) |
���{�̎R�{�Ɗ؍��̓��R(���䓿���Y)
���N�J�{(���������Y)
���E�X�сE�_��(���J��)
��F�R�Ɖz���̋{(���{����)
�_�l�̍�(�����)
�o�̐X(���搳�j)
�_�Ђ̓m�Ɛ_�E�_��(��쐭���Y)
�R�̐_�̖�(��t����)
�_�ƎЂƓ��{�l(�ː����)
�X�̖��{�̍Č��Ƃ��Ă̐���Ԃ̍\��(�˓c�`�Y)
�_���Ɠ��{�̐S(���c�p�G)
���{�l�̎��R�ςƎO�֎R�M��(���R�a�h)
�u�Ёv�Ɓu�m�v�̕����ɂ���(���{�ꖯ)
�u�_�Ɠm�v�ɂ���(�F��h)
�_���܂苋����(�����r�v)
��[�n��(���|���_)
�努��(���c�q��)
�l�̎��R�̐M��(������V)
�K���A�̐X(�W���[�N�E�v�Y�[�� �J�����Y��)
��{�R�ƎR���E�ؖ{��(�Ð�^��)
�_�͍s���䂯�E�����͗��܂�(�x�c�g�Y) |
�_�ւ̌h�i�A�m�ւ̊���(�{�c����)
�_�̓m(�{�c����)
����̐X����(�����Č�)
�X�̐��z(���{�M�L)
�����Ñ�̎ЂƗёp(���{�떾)
�m�ւ̈��ƈؕ|���c(��q�Y)
���̐_�X(�O�Y�Y��Y)
����̐X�Ɛ_�З�(���O)
����̐_�Ɠm(�{��h��)
���R�Ɛ_��(�O�֔֍�)
�╔�̓~��(���R��d)
�{���g�b�N���ɂ����鐹���ƏW��(��������)
�_�؎v�z�ƉA�z���E�����̌���(���R�C��)
����Ԃ̌���(���i����)
�_�{�̐X(�����)
�_�{�{��тƎ�(�R�����q)
�G���U�x�X�����ƃg�C���r�[���m(���h)
�ꏼ�R(�ᏼ����) �����̐_(�a�̐X���Y)
�킪����̐X(�����Y)
�E
�E |
|
| 1977 |
52 |
�E |
�P���A�u����v�z 5(1)���W=���m�v�z����v���u�y�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6055334
|
���W=���m�v�z����
�@���m�v�z�ւ̏��� �Ȃ��A���܁A���m��? / ������ / p76�`78
�@���m�v�z�ւ̏��� �A�W�A�A���m�w�A�����w/�����G�F/p104�`107
�@���m�v�z�ւ̏��� ���m�ւ̏��� / �ʏ�N�l�Y / p79�`87 |
�����̎v�z �����N�w�̍Č��� / ���J�� / p92�`93
�����̎v�z �����l�̎v�z�ƍs�� / �M���� / p88�`91
�V���̎v�z �ӓׂ̈ӎ�--�V���v�z��
�@�@�@�����Ԃɂ��� / �厺���Y / p132�`138
|
�Q���A�u���{�_�b�ƍ��J�v���u�L�����o�Łv���犧�s������B �@ (�u�����{�̐_�b / �w�u�����{�̐_�b�x�ҏW����, 7)
|
���{�_�b�ɂ����鍒��M�� / ����d�N [
���{�_�b�Ƒc��M�� / �{�c�o
���{�_�b�ƃV���[�}�j�Y�� / ���䓿���Y
���{�_�b�ɂ����鐬�N���V�� / �R�ܓN�Y |
�ɐ��_�b�̍\�� / �F�c�g�V��
���{�_�b�ɂ����鎀�̋V�� / �y��쎡
���{�_�b�ɂ������L�V�� : ���y�L�𒆐S�� / �����a�F
���{�_�b�ɂ����鍥���V�� : �Î��L�̍���杂�ʂ���/�⋴���i |
�������߂����� : �L�I���疜�t�� / �g�c�`�F
�̊_���߂����� / ���䖞
�E
�E |
�Q���A�u�V������ = The astronomical herald 70(3) �v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3304661
|
����A���o��--���E��覐E���z�},��c���搶���Â� / / p60�`60
��c���搶�𓉂� / �|�� ; �n�ӕq�v ; �O�J�N�N ;
�@�@���Β˖r ; �ґ����V ; �{�n���i / p63�`68
�Z�C�t�@-�g���NGC1068��NGC4151�̍\�� / ���� �� / p69�`74
���E��覐E / ����a�v / p75�`77
�V�����l�V��-�Y-12-��V�� / �c�� �_�` / p78�`79
�ŋ߂̊ϑ��q����Solar Maximum Mission--
�@�@��NASA�EGSFC����� / ��� ����Y / p80�`83 |
�f����(I) / / p83�`83
���{�w�p��c��71���(��) / / p84�`84
�G�� / / p84�`84 (
�w���襌f����(II) / / p84�`85
�ʐ^�W�ɂ̂�Ȃ��V�̎ʐ^(3)�
�@�@���V�ۗ�(3���̓V����) / / p86�`86
�E
�E |
�R���A�_�{�i���L���u���_ (111) �v���u�_�{�i���v���犧�s�����B�@�@pid/7930653
|
���G �c��_�{�E�L���_�{�ȉ����{�Ђ�
�@�@�����ċF�N�Ղ��Ƃ�s��ꂽ�B
���G ���a�\��N���U�̓��킢
���G ���c���t������b
�@�@���ȉ��t���\���_�{�ɎQ�q
���G �_�{���h�o�n��
���G �喃��n��
�Ñ��실���̂ƍ��J / ������V / p1�`9
����Ɠ��̐_�̍Ձk�J�l/�^�|�풉/p10�`17
|
�ĂƓ��{�l�̐M�� / �}�g�펡 / p18�`25
��ƈ� / �����̏F / p26�`32
�����F�Ղ̂��� / ���|���� / p33�`35
�Q�{�L��� / �ʐ���Y / p36�`42
���W �퍑����̖k�����Ɛ_�{ / ���R�G / p43�`48
���W ���ӂɂ��� / ���R�� / p49�`54
���W �O�d�����ɉ�����ɐ��u / �x�N / p55�`62
���W �_�{�̌䉖�ď���
�@�@�����z�ɂ���/���[�v/p63�`70 |
���W �Q�{�y�Y�̓�̓��� / �l����� / p71�`75
���W �\���̒W���L�ɂ��� / ������ / p76�`82
���W ���n�Βk �u�X�Ƃ₵��v /
�@�@������@�h ; ��R�t�� / p83�`94
���W ���{�_�y�a���C�H�����H�ɂ��� / p94�`95
���W �_�{�̍ՓT / p96�`98
���W �b�� / p98�`106
�E
�E |
�R���A�c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (15)�v�����s�����B�@pid/1764563�@�@�d�v
|
����l�̑㖼���A�̐��� / ���{�ꖯ / p1
�o�_�����y�L�ɂ�����匊�����̓`���Ɋւ����l�@--
�@�@���_��S���R���̢�Z�R��𒆐S�� / ���䎡�j / p11
���{�ɐ�����l--���ƕ��� / �k���l�� / p30
���U��b--���ȋ���ォ��ς��m�����_�ƕ��ƕ����
�@�@�����y��y�ɂ��� / �������T / p57
|
��������L��ƏДb�A�� / ����B / p107
���_���� / ����� / p123
�Î��L�Ɠ��{���I--���ؐ_�ɂ��� / ���쏇�y / p169
�D�ʐ_�l--��Z�g��А_��L��_���̊����̈Ӗ�������� / �^�|�풉 / p18
���{�@���j��������--��t���̑n���Ƌ����Č��Ƃ߂����� / ���R�� / p198
�E |
�S���A���J���I���ݗt�w��ҏS�ψ���ҁu�ݗt (�ʍ� 94) p.p26�`43�v�Ɂu�F�N�Տj���ɂ��Ă̈�l�@�v�\����B
�V���A�R�c�@�r���u�Ԃ̕����j�v���u�ǔ��V���Ёv���犧�s����B
�X���A�u�����Ȋw 15(9)(171)�v���u�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@�@ pid/3213084
|
����<���W> / p5�`80
�s���W�t ���Ԙ_ / �n�ӌd / p5�`21
���Ԃ͉�X�ɂƂ��ĉ����Ӗ����邩 / �n�ӌd / p5�`9
�F���_�̎��� / ���� ���� / p10�`15
���͉߂��䂭--���v�͊w���� / �s�}��i / p16�`21
�������ԥ�Z������ / �x����Y / p22�`40
�V������ / �x ����Y / p22�`27
�������˂炤--�������v / ��t ��F / p28�`33
���܂⎞�Ԃ̓~�N���ł��� / �]�� �m / p34�`40
���Ԃ̐S�� / p41�`49
�̌��I���Ԃ̌��ۊw�I���_�a���w/����P��/p41�`45
���Ԃ̘_��--�����E�����E���� / ������v / p46�`49
|
���ԂƘ_��(�G�k���]) / �� �� / p50�`51
Finite Markov Chains / �����`�� / p52�`52
��]����~�̔�����-8- / ���� ���� / p54�`55
���Ԃ̑��� / �F�q���� / p57�`66
���Ԃ̑��� / �F�q ���� / p57�`60
���ԂƋ��� / ��� �c / p61�`66
���Ԃ̎v�z / �쌴�h�� / p67�`80
�j-�`�F�̉i�p��A�� / �쌴 �h�� / p67�`71
�������ɉr�܂ꂽ���l�T���X����<����>/�X�������q/p72�`76
���Ɖi��--�@���I���� / ��� �c / p77�`80 >
�ǂ���ɗ����Ē��߂邩 / Th. / p81�`81
�E |
�P�O���R�O���A��K���e���S���Ȃ�B�i�X�Q�j
�P�P���A�Ό����������{���w����ҁu���{���w 26(11) p.p78�`87�v�Ɂu���L���w�ɂ����鎞��--�����ƌ������߂����� (�Ñ㕶�w�ɂ����鎞��<���W>)
�v�\����BJ-STAGE
�P�Q���A�����������{���w�j�w����u���w�j���� = Journal of history of mathematics, Japan (�ʍ� 75) p.p1�`8�v�Ɂu�����̐��w(���ʋL�O�u��)�v�\����B
�P�Q���A�ΐ�h�����u�����w���Z����w�I�v = Bulletin of Seikatsu Gakuen Junior College 1 p.115-124�v�Ɂu�����v�̌����Ƃ��̍����v�\����B�@�iIRDB�j
�P�Q���A�n���������u��̓��v���u���{�����i�m�g�j�j�o�ŋ���v���犧�s����B
|
| 1978 |
53 |
�E |
�P���A���c���j�Ғ��u���{���I������T�v���u�Y�R�t�o�Łv���犧�s�����B�@��������}���ُ���ID:000001362847
�@�����ɕt�^�ɁA�K���ō���40�y�[�W�̎��Ɣłł��������쐴�F���u���{���I�̗���ɂ����v�����������B
�P���A�u�V������ = The astronomical herald 71(2)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B �@pid/3304673
|
�k��K���e�搶�Ǔ��l / p33�`40,�}����1p
��K���e�搶�𓉂� / �����P�O�Y / p33
��K���e�搶�Ǔ� / ���b / p34�`35
��K���e�搶�����Âт��� / ���X�K�� / p36�`37
���̕��l--��K�搶�Nj� / ��萳�� / p37
���e�搶�̂͂���--���l�A�̂��ƂȂ� / �Γc�ܘY / p38�`40
�����ژ^ / / p40�`40
�_�X�g�̐��� / �R�{�N�� ; ���J�씎�� / p41�`44
1977�N5��10���̑�� / ���䈮 / p45�`47
�₳�����V���w�V��-�Y-1-�V�̗͊w-2-
|
�@�@���V�̗͊w�̘b / �ÍݗR�G / p48�`51
�F�����̕��˂ٕ̈����̔��� / ��ÍW / p52�`52
�G�� / �����m�� / p53�`53
���z�ёq�V����̎v���o--���
�@�@���������̂��Ƃǂ� / �r��F / p54�`54
��ˏ��w���ɂ�錤����IX(���a37�N�x)--
�@�@�����ʕΌ��x�ƌ��̒n���I���� / ����a�v / p55�`56
�^���������2���̓V���� / / p57�`57
�V���ϑ��{�݂߂���<�k��֓�> / ����r�j / p58�`58
�E |
�P���A�����p�����u�V���ƋC�� 44(1)�@p13�`13�@�n�l���فv�Ɂu��K���e�搶���Âԁv����B�@pid/2356811
�R���A���R���v,�m���g��,����F�p���u�≮��Õ����@�����T��v���u����������ψ���v���犧�s����B
�iIRDB�j
�R���A�_�{�i���L���u���_ (114) �v���u�_�{�i���v���犧�s�����B pid/7930656
|
�\�� �c��_�{���ǎ� ��Ր_
���G �_���ՁA�V���ՁA�����ՁA�喃��n�ՁA
�@�@���p�ŁA�������A�Q���������[�A���U���i�A
�@�@�������e��b�Q�q�A���{�_�y�a�㓏��
�S�h�̈ɐ������Ƒ�_�{�@�y�̔���/�ؓ��ˑ�/p1�`7
��e����̍{ / �`�{�� / p8�`14
��������ɂ�����ɐ��̒d / ���@�Y / p15�`21
�u�Ȃق�Ёv�l / ���{�ꖯ / p22�`27
�V�Ƒ�_�Ɛ_�y�̉� / �ɓ����` / p28�`33
|
�_�{�̐_�_�� / ����v / p34�`38
�ɐ��_�{�Ɗ����� / ���茒 / p39�`45
�c���E�����u�a�E��������
�@�@���Q�{�ɂ��� / ���؊��Y / p46�`52
�ƏW�ɂ݂鐴���� / �������K / p53�`62
���ǐ_��Ɛ��s�k�� / �����P�� / p63�`75
�O���̐_���� / �{�{��� / p73�`79
�ɐ��w�Ƌ{��̓n / �a�c�� / p80�`87
�_�{�̉� / �����T�� / p88�`94
|
�_�{�Ǝ� ���{�̎��_ / ���іΐ� / p95�`97
�_�{�Ǝ� �{��т̂��Ƃǂ� / �ޗljp�� / p97�`100
�b�� �`�P�{�̌����^�� / �����P�a / p101�`103
�b�� �_�{���N�J�{��p��
�@�@�����̕����� / �X���� / p104�`108
�b�� �_�{���N�J�{��p�ޏC�P / �X���� / p109�`109
�b�� �_�{�̍ՓT / p110�`112
�b�� ���� / p112�`127
�E |
�R���A���X�ؗ�, ��t��F�ҏW�u���Ԑ����w�v���u���q���X�v���犧�s�����A
�W���A�K���������Y���u�d�q�ʐM�w� = The Journal of the Institute of Electronics and Communication Engineers
of Japan 61(8) p.p817�`822�v�Ɂu�����̊��o��e�v�\����B�@�@pid/2342403
�P�O���A���������u�V������ = The astronomical herald 71(11) p.p291�`293�v�Ɂu���O��--�r�ؐ搶�̉����o (�r�؏r�n�搶�Ǔ�)�v�\����B
�P�O���A�����v�ҁu�F�� : �嗤�����Ɠ��{�Ñ�j�v���u�g��O���فv���犧�s�����B�@�@pid/9636190
|
�� �����v
��ꕔ ���_ �����v / 1
�� �Ñ�F�������̖�� / 3
1 �F���V���|�W�E���ƉF�������̐��i / 3
2 ��j������ / 7
3 ���P���@�Ƃ��̍s�� / 11
�� �F���ɂ�����l�Êw�����̊T�v / 17
1 ���a�O���܂ł̌��� / 17
2 ���a�㔼�̌��� / 24
��� �V���|�W�E����F�� / 31
�� �Ñ�F�������̗��j�I���i�\�V���|�W�E����
�@�@�@���������\ �����v / 33
�� �Ñ�F���ƋE������ ���c�x�m�Y / 48
�O �Ñ�F���ƒ��N���� ���J�� / 64
�l �Ñ�F�������ƌ��n�@�� �c������ / 87
�� �F���_�{�̋N���Ɣ��W ���씦�\ / 105
�Z �Ñ��B�ɂ������ɕ{�ƉF�� ���R�� / 129
�� ���_�\�Ñ�F�����������̏����\ / 147 |
1 �F���Ñ�̐��Y�Ɋւ����� / 148
2 �F���Ñ�ƋE���̊W / 160
3 �F���Ñ�ƒ��N�����̊W�Ɋւ����� / 172
��O�� �Ñ�F���̈╨ / 185
I ���N���������o�y�Ƃ��̖��_ / 187
�� �ʕ{��Ջً}���@�����T��\���N���������o�y��Ղ�
�@�@�@�������\ �F���s����ψ��� / 188
�� ��B�̓����\�F���s�ʕ{��Տo�y�̏������ɂ��ā\ ���q�m�� / 201
�O ���N���������Ɠ��{�̓����\�L�{�_�ƎЉ�̃J�l����
�@�@�@�����{�_�ƎЉ�̃J�l�ց\ �����^ / 213
�l �F���s�����������̐��i ���c�x�m�Y / 231
II �F�����������̃Z���l�� / 235
�� �k�Z���l�� ��g�c�O / 236
�� �F�������Տo�y�̃Z���l���ɂ��Ă̒� �Ԋ��P�� / 245
III �F���V�������m�@�̑Y���Ƃ��̖��_ / 253
�� ���{�̑Y���\�F���V�������m�@�����߂����ā\ ��㐳 / 254
�� �F���̑Y�� ���q�a�� / 262
���M�ҁE�V���|�W�E���Q���ҏЉ� / 304 |
�P�P���A�u�V������ = The astronomical herald 71(12)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304683
|
���͐i�����Ȃ�!--�F���c���Ǝ��Ԃ̗��� / ���c��� / p316�`316
����Ǖ�������Â�� / �L�ؐ��� / p320�`320
�����V����ł̐���Ǖ��� / �Ք����v / p321�`322
�ܓ��v���l�^���E���ł̐���Ǖ��搶�̎v���o/���щx�q/p323�`324
��ˏ��w���ɂ�錤����(���a51�N�x)--
�@�@�����ʐۓ��̐��l�v�Z / ������ / p325�`325
�����v�̕ς�_�l2�� / �{�� ��F / p326�`328
|
�f���̕����w-2-���Ɩؐ�-2-
�@�@��(�₳�����V���w�V��-�Y-3-)/�{�{ �����Y/p330�`333
�w���� / / p334�`334
���] / ��t���o�� / p334�`334
�G�� / �Ɛ��� ; �����m�� / p336�`337
�V���ϑ��{�݂߂���(XII)�R�����B�����--
�@�@��12���̓V���� / �R�c�`�O / p338�`338 |
�P�P���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (155)�v���u
�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051588
|
�s�����̌��t�t �V�������̍Č��Ɠ��{ / �����t�� / p1�`1
���]��l�Â̗� / �����O�� / p2�`8
����錧���勴�E����Ղɂ�����ꕶ�y��Đ���\ /
�@�@�@����菃�� ; ���� ; �C�V�� / p9�`12
����t���D���s�����R�{�����Ղ̒��� /
�@�@�@�����蕶�� ; ���Y�G��Y / p13�`17
���X�s�K���ق̔��@���� / ��{�`�Y / p18�`20
���������{���s���R��Ղ̒��� / ���]�F�� / p21�`23 |
������Ꝅ�������ɂ���--��䎁�ւ̔��_/���Y��/p24�`26
�����}�o���Ɖ����� / �]��P�\ / p17�`17
�s�V�����]�t �w�ꕶ�L�˂̓�x / �]��P�\ / p27�`27
�s�����ژ^�t / p28�`30
�s�l�Ãj���[�X�t / p31�`35
�O���t ����t���{������
�O���t ���X���K����
�E |
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (11)�v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����Bpid/7957062
|
�M���~�l�b�Z���X�@�ɂ��ēy�E�Đ̔N�㑪�� / �s��đ� ; �������� / p1�`7
�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(2)�C�l(oryza)���A���ɂ�����@���זE�]�_�̂̌`�� / �����G�u ; ���X�؏� / p9�`20
��Տo�y�̋����̓���ɂ��� / ���P�� / p21�`31
�u��X�����͖@�ɂ��T�k�J�C�g�Ί�̌��Y�n����(6) / �m�ȓN�j ; �������M ; ���؋`�� / p33�`47
�q�Տo�y�{�b��̃P�C��X������ / �O�җ��� / p49�`69
��j�͖@�ɂ��y��̎Y�n����(1) / ���F�P�l / p71�`83
��Ղ̎��C�T�� / �c���� ; �����N ; ��{�\�� / p85�`94
�Ί퓙�s��`�ȍl�ÕW�{�̌`�ɑ���ȕւȐ}�`�F���@ / �������� / p95�`110
�l�È╨�̕ۑ��@--����ɂ�����Ǝ�╨�̏����@�𒆐S�� / ��c���� ; �H�R���� / p111�`126
���R�Ȋw�̌��p--�l�Êw�҂���̎��� / �R����Y ; ���q�_�� ; ���ђB�Y ; �����^
; �����W�� ; ������ ; �������M ; ����q�� ;
�@�@�@�������a�Y ; �O�앶�v ; ���q���O�Y ; �������� ; ���J�Ŏq ; ���c�z��
/ p127�`157
���������Љ �l�Êw������(Le Centre de Recherches Archeologiques)�𒆐S�ɂ���
/ �R����Y / p159�`165 |
���A���̔N�A�{��͂��u�n���̉�] : ���ԁE�ʒu�E���x�̘b�v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@ (NHK�u�b�N�X)�@pid/9670072
|
���� �n���͉�� / 13
�f���Ƃ��Ă̒n�� / 14
�܂邢�n�� / 20
�Ԃꂽ�n�� / 23
�n���͉�� / 27
���܂̉^�� / 28
���Ə͓� / 29
�ɉ^�� / 33
�ܓx�ω��̔��� / 36
���� �ܓx�͕ς� / 41
�V���ܓx�A�o�x / 42
���̍��W / 45
�z���{�[�E�^���R�b�g�@ / 46
�V���V / 49
���ۈܓx�ϑ�����(ILS) / 54
z���̔��� / 59
��C�̋��� / 66
�ϑ��̃v���O���� / 74 |
���̈ʒu�Ɛ��\ / 79
�`�����h���[�^�� / 93
�N���^�� / 100
���������R�͓� / 102
������ / 110
�ɂ̉i�N�^�� / 114
���ۊ��p���_(CIO) / 121
���V�V���V(FZT) / 123
��O�� ���𑪂� / 127
�P���� / 128
���z�� / 130
���E�� / 133
�������Ȃ�n���̎��] / 142
�����v����@�B���v�܂� / 150
�������v / 152
���q���v / 156
��\�� / 160
���ی��q�� / 166
|
�����Ƌ��萢�E�� / 171
��l�� �o�x���ς� / 177
�o�x�ω� / 178
�q�ߋV����ʐ^�V������ / 179
�A�X�g�����[�u / 186
���ۋɉ^���ϑ�����(IPMS) / 194
��� �V�����ϑ��Z�p�̓o�� / 201
�l�H�q���̃h�b�v���[�ϑ� / 202
������ѐl�H�q�����[�U�[�ϑ� / 208
����������v / 218
�d�͂̐�Α��� / 221
��Z�� ���ےn���^���ϑ����Ƃ� / 231
�ɉ^���ƒn������ / 232
�Òn���C�w�Ƌɂ̉i�N�ω� / 241
�����q���Ƌɉ^�� / 247
���ےn���^���ϑ����Ƃ�
�E
�E |
|
| 1979 |
54 |
�E |
�R���A�c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (17)�v�����s�����B�@pid/1764567
|
�_���L��c�@�I�裏��̒����̐V��--����͂Ƃ��/���{�ꖯ/p1
���������ɂ���--�b�㍑����������ʂ���/ ���c����/ p10
���D����ƏW���ژA�̕����� / ����B / p24
��������̎����� / ���R�� / p56
��R��ƕ���̐����ƈӋ`(�� �Z����R��ƕ��) /�J�Ȍ�/ p98 |
��c�H���Ɠ�����--�������w�Ɠ��{���w�Ƃ̊W/�����/p149
�q�K�ƒZ��-1-�Z�̊v�V���z�̋O�� / ���Y�p�V / p189
�_�Ѝ����Ƒ��Ղ�̕ω�--������c��
�@�@��(�O�d���x��S�x��̓�)�̎��� / ���䎡�j / p219
�� |
�S���A �ݓВj���u�]�� 10(4)(105)�@p80�`82�@���C���猤�����v�Ɂu�������Ȋw���� �q�C�p�ƌÑ㕶���v�\����B�@pid/7928150
�S���A�u�Ȋw���� 39(4)(457)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335229
|
�i���j
���W�4�����̐����w� / / 36�`36
�������v�����e��̃��Y��/��{���� ;��t��F/p37�`42
�����Ɍ��ʓI�ɑΏ�����@ / ���X�ؗ� / p43�`47
�H���ƌ��N�̈ӊO�ȊW / �ؑ��C�� / p48�`52
��̌����ڂ͎����ŕς��? / �������� / p53�`57
�����ʼn��тĂ���1���̒��� / �ÍݗR�G / p58�`61
�F���l�ƌ�M���悤 / p63�`72
�z�����A���f�q�h�̔g�����g�� / �X�{��� / p63�`67
�����莆�����łɓ͂��Ă���? / �哇�טY / p68�`72
��p,�C�^�Y��,�����ĉ��w / ���P���L�V / p74�`78
�R���s��-�^-�̌������C�M���X�ɖK�˂�/����Ǒ�/p119�`123
�זE������~�߂�V����--�~���~���_/��g�m��/p124�`127
�Ղ�ނȂ��Ǣ���飂Ƣ��£ / �����j�q / 130�`132 |
�j���[��Z�N�\���W�[(4)���̕�����
�@�@���j���z����������� / �a�]���� ; �ҏW�� / 81�`86
���`�����ŏ����ꂽ��m�A�̔��M�(���-4-) / ����v / p87�`90
�n���𑪂�-16-�d�͂̍�p�ŋO�����ς� / ��˓��j / p93�`96
�ʎ��̔�����m�����~�o�G����
�@�@��(���҂ɂ��ꂽ������-16-)/����ꖞ/p98�`101
�X�C�Z���̗R��(���̊Ԃ̃~�N���O���t�B�A-28-)/���c�P��/p128�`129
���͌Ă�ł���-4-�ω��ɕx���ʂ̒n�`���y������
�@�@�@��(���䈮�̓V�̊ϑ�����) / ���䈮 / p103�`107
��g�[�����̃\�[���[�W���Z�� / �O�쐴�u / 108�`112
���̓� �t�W�}�����̕ی��i����`���Y���r����/���J�Y�I/113�`118
�Ǐ��R�[�i�[ / / 133�`140
�݂�Ȃ̍L�� / / 141�`142 |
�V���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (20)�@���W�E�Ñ�̗�Ƒ����ݗ��̕掏�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947780
|
���W�E�Ñ�̗�Ƒ����ݗ��̕掏
�@�Βk ��(��)���E�Ñ㎁���E�Ñ���J / ���C�Y ; ����˗Lj� / p40�`62
�@�Ñ�̗�Ƒ����ݗ��掏���̗�� / ��J���j / p2�`9
�@�����ݗ��̕掏�̗�� / �F�c�g�V�� / p10�`19
�@�����ݗ��̕掏�Ɋ֘A���� / ���{���� / p20�`23)
�@�����ݗ��̕掏�Ɓw�����{�I�x--���t�y���x�̈Ⴂ�ƌM�ܓ��ɂ��� / ��O��
/ p24�`39
�@���Ñ�j�ʐM���ʔŁ� �����ݗ��̕掏�o�y���߂����� / �ҏW�� / p63�`85
�@ |
�@��B�����̏،�(�l)�u�����v�_���ɂ��� / �Óc���F / p86�`97
�@�u鰐W���Z�����v�͐������Ȃ�--�Óc���F���ɓ����� / ���{���T / p106�`121
�@�z�S�{�l--�u�V�v�̍b���ʑ��݂̉\�� / ���菺��Y / p133�`149
�@�؍��x�Ε擥���L(�O) / ���R�` / p98�`105
�@�z�O�o�y�̓����̑D�� / �������� / p122�`132
�@�C���������������n���L--����̎����l�Êw�̂��߂� / ��؏��T / p150�`175
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p176�`214
|
�V���A���s��Փ���A�W�A�����Z���^�[�ɉ��āu�]��f���^�E�V���|�W�E���v���J�����B
�P�O���A���c���j�����N�w��ҁu���N�w�� = Journal of the Academic Association of Koreanology in Japan (�ʍ� 65) p.257�`284�v�Ɂu���×�@�ɂ�����̐��Z�ɂ��ā^�t�\�k���x���Z�\(AD445�`661)�l�v�\����B�@
�d�v�@��������}���ُ���ID�F373029
�P�Q���A�u�_�w���� 58(3/4)�v���u���R��w���������Ȋw�������v���犧�s�����B�@�@�@pid/2354462
|
�}�����v���m����
�}�����v���m�����_������ђ����ژ^ / / 101�`116
���R���Ó���Ղ̏o�y����̎�ޓ���̌���--
�@�@�����{�e�n��ՊԂ̎c������̔�r�Ƃ��ꂩ�猩���_�k�� |
�@�@���`�d�ƌ`�Ԃ̐��� / �}�����v ; ���c���q / p117�`179
�q���^�C�k�r�G�ɂ����鍂�߈ʕ�����̔����ɂ���/�����v/p181�`190
�k�_�w�����l��58���ڎ�(���a54�N) / ����2p
�E |
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (12) �v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����B pid/7957063
|
K-Ar�@�ɂ��Ⴂ�N��̉ΎR��̔N�㑪�� / ������Y / p1�`13
���R���ː��������o�ɂ��N�㑪�� I�D����ESR�N�㑪�� / �r�J���f ; �O�؏r�� / p15�`23
���R���ː��������o�ɂ��N�㑪�� II�D���[�U�[��N�����N�㑪�� / �r�J���f
; �L�v�X���B / p23�`27
�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(3)�����E�t���(��P��)���c����ьQ�n�E
�@�@���������(�퐶����)���c�ɂ�����C�l(O.sativa.L)���Y���ʂ̐��� / �����G�u / p29�`42
�؎��╨�̓���ƁC���ꂩ��l�����邱�� / ���q���O�Y / p43�`53
���{����ђ����o�y���풆�̉��̓��ʑ̉� / �R���Y ; ���Z���� ; ��������
; ������ ; ������H ; �n��f�F / p55�`65
�Ñ㊢�̏Đ����x�̐���ւ̓S--57���X�o�E�A�[���ʂ̉��p / �|�c���F�Y ; �x�i�� / p67�`78
�Ί퐻������ɂ�镜���I�Ί팤���@--�Ί퐻���������ѐΊ�v���̂��߂̊�b�f�[�^
/ ���� / p79�`96
�o�y�؍ނ̃��O�j���Ɋւ��錤�� / �식�� ; �ʈ�� / p97�`104
���W�]�� �N�㑪�� 1�D??C�N�㑪�� / �؉z�M�F / p105�`108
���W�]�� �N�㑪�� 2�DTL�N�㑪�� / �s��đ� / p108�`110
���W�]�� �����E�� 3�D�ꕶ����͔̍|�A�� / ���쏺�� / p110�`114
���W�]�� �����E�� 4�D��Ղ̈�[���琶�������l������E / ���J��P�a
/ p114�`118
���W�]�� �ގ��E�Y�n�E�Z�@ 5�D�ގ��E�Y�n�E�Z�@ / �������M / p118�`123
���W�]�� �ގ��E�Y�n�E�Z�@ 6�D�ގ��E�Y�n�E�Z�@ / ���R�r�v / p123�`126
���W�]�� �T���E�����@ 7�D��Ո╨�̒����@�Ɋւ��錤�� / �ڑ� / p127�`130
���W�]�� �ۑ��Ȋw 8�D�ۑ��Ȋw�Ƃ� / �ɓ����j / p131�`134
���R�Ȋw�̌��p--�l�Êw�҂���̎��� / ���{�� ; ������ ; ���쏺�� ; ���{�b�s / p135�`138
�������̕ۑ��Ɋւ��鍑�ۉ�c�Q���� / ��c���� / p139�`141 |
|
|
| 1980 |
���a55 |
�E |
�Q���A���J�c�ꂪ�u�m��ꂴ��Ñ� : ��̖k�O�l�x�O���䂭�v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@pid/12238866
|
���e�����^���{�̒������A��a�̎O�֎R�[�ɂ��锢����ђʂ��铌���̒�����ɁA���̂��Ñ��Ղ��_�X�ƕ��ԁI���A�N���A�Ȃ�̖ړI�ł������̂��H�A�}�`���A�Ñ�j�Ƃ̔��z���q���g�ɂ��āA���j�̓�ɒ��݁A�Ñ㍑�Ƃ̔閧���ɂ�����̑��ʎt�̑��݂ɓ�������X�������O�Ȓm�I�T���̏��B�@CiNii Books |
|
��P�́@��ȈÍ�
��Q�́@���z�̓��͑��݂��邩
��R�́@����ǂ���
��S�́@�L�[�E���[�h��{��
��T�́@�_�Ђ̂��镗�i
��U�́@�����̂��������� |
��V�́@��ƊC�̂�������
��W�́@���z���˂�w���N���X
��X�́@�s�m�����Ƃ߂�
��P�O�́@�_�X�̍�
��P�P�́@�킾�݂���
��P�Q�́@���ؓ`�� |
��P�R�́@���z�̓����䂭
��P�S�́@���̑��ʎt
��P�T�́@���z�̎q��
�I�́@�Ȃ��A���z�M�ɂ�����邩
�E
�E |
|
�R���A�Ñ㕶�w��� �u�Ñ㕶�w (19) �v���u�Ñ㕶�w��v���犧�s�����B�@�@pid/6062655
|
���{��ًL<���W> / p1�`53
���W�E���{��ًL �w���{��ًL�x�Ɓ��\����/���c��b/p1�`7
���W�E���{��ًL ��ًL�̎��Ԉӎ� / ���쐳�� / p8�`16
���W�E���{��ًL ���b�̗��ʂƌ`��--����@�t�̑�����
�@�@�����b���߂����� / �Ë��M�F / p17�`25
���W�E���{��ًL ��ًL���b�́�����--�������聄
�@�@�����z�ɂ����镧�Ƃ̏o� / �O�Y�C�V / p26�`34
���W�E���{��ًL ��ًL�̗̉w--�����O�\���b�𒆐S�Ƃ���/
�@�@���ߓ��M�` / p35�`46 |
���W�E���{��ًL ��H�l--��ًL���b�̌`��/�ۍ�B�Y/p47�`53
�u���s�݁v杂̕���--�������z�ƕ\���̜��Ӑ�/�ē��p��/p54�`64
�u慉̓|��v�̘_ / �g�c�C�� / p65�`76
���t�W����g��]�̂̌n��--�{����̂���
�@�@���{��]�̂� / ����s / p77�`89
�u�Ñ㕶�w�v���ژ^ / / p95�`99
������� / / p99�`104
��� / / p90�`94
�E |
�V���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (24)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@ pid/7947784�@
|
���W ���{�Ñ�̑��z���J�ƕ��ʊ�
�@�Βk �u���z���v�ƌÑ�̕���/������O ; ���J�c��/p50�`73
�@���{�Ñ�̑��z�M�Ƒ�a���� / ���O�� / p2�`14
�@�A�z�܍s�v�z�̕��ʂƓV�c�� / �ɓ��^�� / p15�`23
�@���z���J�ƌÑ㎁��--���u���𒆐S�Ƃ���/���C�Y/p24�`35
�@���{�Ñ�M�ɂ݂铌����--�u���z�̓��v
�@�@�@���́u�ւ̓��v / �g��T�q / p36�`49
�@���z���J�ƌÑ㉤��(��) / ��a��Y / p74�`94 |
���{�Ñ㍑�Ƃ̐���--�w�Î��L�x�́u���_�v��
�@�@�@���ʘH�Ƃ���(��) / ���c���j / p95�`109
��������k�{�E�l�������͏Ɩ��ł��Ȃ�--�����o�y����
�@�@�@����������Óc����ᔻ����(��) / ���쐳�j / p110�`117
�l�����l(��) / �앛���� / p118�`137
�w���{�I�x�̂͂���(��) / �p���m / p138�`157
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p158�`211
�E |
�W���A���w�ٕҁu�n���̐��E (35)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@�@pid/1737910
|
�ΐ��� �i�V���i���Y���ƌl��` / ��c�[�� / 4
���{�����̈ʒu/�����B=�X�g���[�X;�ؕ�;��c�[��;�ĎR�r��/6
�퐶�Љ�-�����Ƙ`�l / �X�_�� / 24
�����̖퐶����q�V���|�W�E���r / ��R�t�� ; �~���� ;
�@�@�@���͍���Y ; ��c�[�� ; ���搳�j ; �X�_�� / 52
�����s���̓�\�\�̓����v�̎d�g�� / �K���ݚ摾�Y / 72 |
���̃��Y��-�l�ԂƓ����q�V���|�W�E���r / �~���� ; �͍���Y ;
�@�@�@���K���ݚ摾�Y ; ��c�[�� ; ��t��F / 90
����ɂ��Ă����ƌ�낤 / �X�B / 106
�ϖe����q���̐��E�q�V���|�W�E���r/��R�t��;�~����;�͍���Y;
�@�@�@����c�[�� ; ���J��G ; �X�B / 12
�������q(9)�\�������@�̎v�z(��) / �~���� / 150 |
�X���A ���c�ەv���u�A���̈ꐶ�ƃG�`���� : �A���E�̖��@�g���v���u���C��w�o�ʼn�v���犧�s����B (���C�Ȋw�I��)
�P�O���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (25)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947785
|
�Βk ���A�W�A�j�̓��{�Ɗ؍�--�������j��
�@�@�@������� / �^�~�� ; ���G�Y / p2�`22
�w���{���I�x�ɂ����ꂽ�g�J���l--�u�B���E�ɉq���E�����l�v
�@�@�@���y����--�q�ᔻ�ɂ������ār / �ɓ��`�� / p23�`31
�����]�̐킢�O��ɂ����铌�A�W�A�--�u���{���I�v��
�@�@�@���ڂ�l�T�ɂ��� / ���ќ��q / p32�`45
�F�������̒a�� / �c������ / p46�`65
�w�V����^�x�̓�--�C�߂ƍݓ����N�l / ������ / p66�`77
�Ñ��C�f�Ճ��[�g�ƒ��N(��)--�����_�b�𒆐S��/���ݖQ/p78�`89 |
�؍��̉���Ɖ��˂̈ʒu--���z���J��
�@�@�@���Ñ㉤��(��) / ��a��Y / p90�`114
��B�����̏،�(��) / �g�c���F / p115�`127
�w���{�I�x�̂͂���(��) / �p���m / p128�`151
���{�Ñ㍑�Ƃ̐���(��)--�w�Î��L�x�́u���_�v��
�@�@�@���ʘH�Ƃ��� / ���c���j / p152�`171
�u�הn�㍑�v�_�ւ̔���--�Óc���F���֓�����/���{���T/p172�`181
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p182�`216
�E |
�P�P���A���������u�����V���w�E���w�W�v���u�����o�ŎЁv���犧�s����B�@ (�Ȋw�̖���)
|
�����V���w���w�W
�����̐��w�ƓV���w / ������ [��]
�w��͎Z�p�x��� / �쌴�G�� [��]
���J����͎Z�p (�t�C���Z�o)
�Ђ炩�ꂽ�F���_ : ����ɂ����� /���{�h�� [��] |
��鏎Z�o
�쌛
�ӓV�V
�V�̌`�̂ɂ��� (�w�W���x
�@�@����11�u�V���u�v��E�V�̂�� |
�V���w�̃o�r���j�A�E�M���V�A�E���� /
�@�@�����{�h��, �ҏW�� [��]
�����V���w�E���w�N�\: p393-401
���L �����t�^: �V���w�̃o�r���j�A�E
�@�@�@���M���V�A�E���� / ���{�h��, �ҏW���� |
�P�P���A���w�@��w�_���j�w��ҁu�_���j�̌��� : �{�n���ꔎ�m�O�\�N�ՋL�O�_���W�v���u�p���Ёv���犧�s�����B�@�@
pid/12267721
|
�ޗǎ���ɂ�����_�{�̓��@�a�ɂɂ��� ���R�q�j��
�c���@�����E���{�̎��ւƌc���@�����̗��j�I�Ӌ`-
�@�@����_�{���N�J�{�̓`���Ɋւ����l�@ �����ލ쒘
���j�Ƃ��Ă̏Z�g���_ �ߓ��씎��
�{�n���m�̐_�_�j�����ɂ��� �ēc����
���쎮�_�����o�_���ɂ�����u���Ѝ��v�Ɓu���Ёv�ɂ��� �Βˑ��r��
�ዷ���_�����ɂ��� �O������
�Y�R�_�Ə\�����q�ɂ��ā[���R�����M�̓W�J �����d�Y��
��g�R����̐_�l ���q�w��
�t���ԓ��q�Ɠ���䶗� �i�������Y�� |
����ȉ��g�c�Ɨ��̏ё��� ���c���j��
�ߐ��̏������ �~�c�`�F��
��������̎u�� ���R����
�F��R�̑��_ �{�蓹����
�{�n�搶�̎v���o �ɒB�F��
�{�n�搶�̎v���o �J������
�{�n����搶�ƍZ����\��ЋL �O��������
�{�n���ꔎ�m��v����
�_���ꗗ ���w�@��w�_���j�w���:p396�`401 �t:�Q�l����
�E |
|
| 1981 |
56 |
�E |
�P���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶��. (26)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947786
|
�C�k �C��̓��Ɓw���̐_�̑��Ձx / ��������;�J�쌒��;�{�c�o/p58�`84
��B�̓������ / ���c�x�m�Y / p2�`10
�����S�ɂ���--���k�����̗��j�I��i�� / �ѓc����/p11�`21
�u���v�̔Đ��E�I�ꌹ�l / ���^�� / p22�`31
�����̍Ղ� / ���ژa�� / p32�`37
���_�ƓS / �^�|�풉 / p38�`48
�̘b�ɂ݂�S�̓`��--�m���Ɖꉤ�̘b/���/p49�`57
�ޏ����E�ږ�Ă��߂��鏔��� / ���{���v / p85�`97 |
�Ñ�j�ւ́u�Ȋw�v�̓K�p�ƌ��E / �o���� / p98�`107
�Õ��E�퐶��Ղ̈ʒu�ݒ�--�Ñ㉤����
�@�@�@�����z���J(�O) / ��a��Y / p108�`130
�w���{�I�x�̂͂���(���̈�) / �p���m / p132�`141
�l�����Ǎl(��) / �앛���� / p142�`157
�Ñ��C�f�Ճ��[�g�ƒ��N(��) / ���ݖQ / p158�`168
�Ñ�j�ʐM / ����m�q�E�� / p169�`206
�E |
�P���A�c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (19)�v���u�c�w�ّ�w�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1764569
|
�o�_�����_�ꎌ�Ɍ����颔T�_�ޔ���ɂ���/���{�ꖯ/p1
�_�ߍl / �J�Ȍ� / p12
��r�̐_�̕��� / �^�|�풉 / p31 |
��V��p��g�W��Ƣ���� / ����B / p45
���쏬���m-�g--���������Í�����<������>�̔\/������/p91,�ʕ\7��
�� |
�P���R�O���A�{�{��ꂪ�S���Ȃ�B�i�V�R�j
�Q���A�I���\��u���m�����v�ҏW�ψ���ҁu���m���� = The studies of Asia and Africa (�ʍ� 60) p.p71�`97�v�Ɂu�Ñ㒆���ɂ�����F�N�Ղ̌��n�S���_�v�\����B
�U���A���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j���u���{�앨�w��I�� 50(2) p.143-147�v�Ɂu�V�}�T�C�R��q�̔���Ɋւ��錤���@��7��@�~�V�}�T�C�R��q���̔���}�������i����3�j�v�\����B�@J-STAGE
|
�~�V�}�T�C�R��q�̔���Ɋւ��錤��(1�`��11)���ł̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N |
�_���� |
���Җ�
|
pid |
| 1 |
45(2) .p243�`247 |
1976-06 |
�P�@�̎��̌o�ߊ��Ԃ���ь�����������ɋy�ڂ��e�� |
��J�L�F,���ؗǎO,���ؖF�} |
J-STAGE |
| 2 |
45(2) p248�`253 |
1976-06 |
�Q�@����̑��i�Ǝ�q�̒����@ |
��J�L�F,���ؗǎO,���ؖF�} |
J-STAGE |
| 3 |
46(1)p.159-160 |
1977-04 �@ |
��3�� �~�V�}�T�C�R��q�̋x������ |
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j,�c�Ӗ�,��J�L�F,��ؗ��Y,���q�ǎO |
CiNii Articles |
| 4 |
46(2)p.119-120 |
1977-10 |
��5�� �~�V�}�T�C�R�x����q�̐����I���� |
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j,�c�Ӗ�,��ؗ��Y,���q�ǎO |
CiNii Articles |
| 5 |
47(1) p.25-30�@ |
1978-03 |
�R�@-3-�~�V�}�T�C�R��q�̋x������
|
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j,�c�Ӗ�,��J�L�F,��ؗ��Y,���ؗǎO |
J-STAGE |
| 6 |
47(1)p.143-144 |
1978-04 |
��6�� �~�V�}�T�C�R��q���̔���}������(����2)�@ |
���ؖF�},���J�쒉�j,���c�ەv,�c�Ӗ�,��ؗ��Y,���ؗǎO�@ |
CiNii Articles |
| 7 |
47(2)p.197-205�@ |
1978-06 |
�S�@��4�� �~�V�}�T�C�R��q���̔���}������ |
���ؖF�},���J�쒉 �j,���c�ەv,���ؗǎO,��ؗ��Y |
J-STAGE |
| 8 |
47(2) p.79-80�@ |
1978-10 |
��7�� ��n�ߒ��ɂ����锭��}��������
�@�@�@���ܗʂ���є���K���̐��� |
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j,�c�Ӗ�,��� ���Y,���ؗǎO |
CiNii Articles |
| 9 |
48(1) p.46-51 |
1979-03 |
�T�@��5�� �~�V�}�T�C�R�x����q�̐����I���� |
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j,�c�Ӗ�,��ؗ��Y,���ؗǎO |
J-STAGE |
| 10 |
48(2)p.311-316 |
1979-06 |
�U�@��6�� �~�V�}�T�C�R��q�̔���}������(����2)�@ |
���ؖF�},���J�쒉�j,���c�ەv,�c�Ӗ�,��ؗ��Y,���ؗǎO |
J-STAGE
|
| 11 |
50(2)p.143-147 |
1981-06 |
�V�@��7��@�~�V�}�T�C�R��q���̔���}�������i����3�j |
���ؖF�},���c�ەv,���J�쒉�j |
J-STAGE |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���s�N�����ɕ\����������m�����������肵�Ȃ��̂ōĒ������K�v�@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�W�@�ۍ� |
�S���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶��. (27) ���W�E�Õ��̔����v���u��a���[�v���犧�s���s�����B�@pid/7947787
|
���W�E�Õ��̔��� �Βk
�@�Õ��̔���--���`���a���
�@�@�@�@���O����~�����߂�����/����˗Lj� ;�Ζ씎�M/p2�`26
�@�Õ��̖{���Ƃ��̔��� / ���菺��Y / p27�`43
�@�O����~���̐����Ɠ��� / �d�����v / p44�`57
�@�x�Ɠm�ƌÕ�(��)--�s�F��x�ƈψ��R / ������O / p58�`69
�@�O����~���̃��[�c��������--�ŌՒ�
�@�@�@��������݂�/�c���ߎq/p70�`76 |
�@�O����~���̕��ʐ� / ���Ëg / p77�`91
�@�w���{�I�x�̂͂���(���̓�) / �p���m / p92�`107
�@�p�\�̗��ƍ��ۊW / �c���� / p108�`117
�@���ؓ`���Ɠ~����--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(��) / ��a��Y / p118�`140
�@�l�����Ǎl(��) / �앛���� / p141�`151
�@���N�j�����ɂ����ĒB���������ʂɂ��� / �p���� / p152�`161
�@�Βk �����Ñ�j�̏���� / �p���� ; ���G�Y / p162�`174
�@�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p175�`223 |
�U���A�u�Ȋw���� 41(6)(483) �v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335255
|
�h�炮"�R���s��-�^-�_�b"(�g�s�b�N�X) / ���c���� / p30�`31
����̗��͂ǂ��܂ŕK�v��(�g�s�b�N�X) /���J��/p33�`34
�X�y�[�X�V���g�� �n���n���̏���s / WWP / 28�`29
�K���}�������̌��͒����q�����ق� / / 23�`27
���W ���ꂪ�Ñ�l�̐�������-
�@�@���l�Î��R�Ȋw�̂�����//36�`36
���ꂪ�Ñ�l�̐�������<���W> / p37�`67
�ߋ��������������V������@ / �n�Ӓ��o / p37�`39
�����K���X���؋��Â����� / �����G�u / p40�`43
�ԕ����番������̋ꓬ / ������ / p44�`47
�q���E�^���̗��p�͓ꕶ���� / �����T�V / p48�`51
�ꕶ�l�͍͔|�\�o��H�ׂ�? / �ߐ{�F�� / p52�`55
��Ղ̊L�k����T�鐶���� / ���r�T�q / p56�`59
���ʐ������������y��̎Y�n / �O�җ��� / p60�`63
�_�f�������C��ϓ��̐� / �͍��M�a / p64�`67 (
�C���ɐ�����������}�X�̉ԁX(�J���[) / ���슲�Y / 12�`
�����̒��̋G�ߑ�����ǂ�--�C���ɐ�����
�@�@���������}�X�̉ԁX / ���슲�Y / p70�`74,12�`15
���R-�h���f�W�^������ / ������j / p75�`79
|
���S�ȏd���_��̓o�� / �������� / p81�`85
�ʂ�𑝂�����̃T���S�̉ԉ� / �ɓ����q / p7�`11
���S�N�O�̕�����`����n���͊���Q / �ʗ��M / p16�`17
�����̊�-54-�V���N��-�h�̑�����`����
�@�@���\�A�̃^�W�N�l / �������N / p18�`19
�猩��l�Êw-6-���������ɍL����ΐς݂̕�Q
�@�@����������s���������Q / �����N�v / p105�`109
���z�M��n���ɒ~����n�E�X--���X�؝��
�@�@��(�������Ă܂���) / ������ / p112�`115
��K�Δ��@�͍��������n / �{�{�C�Y / p116�`118
�F���𑪂�-18-�V�������͔M�Z�������̖\��/�����M��/p87�`90
�i���̐v-18-����Ȋp�����Ă��܂����V�J / ���і��j / p93�`96
��H�w����-10-�l�ԂƋ@�B�̓K�����߂���/�g�{���/p99�`102
�I-�f�B�I������-6-AM�̉���FM���ǂ�? / �]��O�Y / p120�`123
�H-6-���̐H�����x�z����ۗ� / ������ / p125�`129
����ςɂ�鋰�|(�v�����i-�h) / �ɑ�h�� / p130�`131
�Ǐ��R�[�i�[�w�������̐��E�x�w���ؕ��y�L�x
�@�@���w�E�ƂƂ��Ă̏y�Ō�w�x�ق� / / 133�`139
�݂�Ȃ̍L�� / / 140�`141 |
�V���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (28)�v���u��a���[�v���犧�s�����B pid/7947788
|
���k ���ΐM�Ƒ��z���J / ���O�� ; ����ǎO / p2�`24
�Z�b������ / ���{���k / p25�`37
�Ñ�M�Z�ɂ����鋐���J / �ˌ��� / p38�`47
�����C���̓� / �����ّ�w�Ñ�j�T�������Δ�/p48�`56
���R�Ƌ��Ƒ��z���J--���z���J����
�@�@�@�����{�_�b(��)/�C�ȉ�V/ p57�`71�@�d�v
���i��Ɖv�c�̊�D--�u�n���v�Ƃ��Ă�
�@�@�@�����R�ƎO�֎R/���{�b��/p72�`83
�������@ ���{���̋��ΐ��q / ���֗Y / p84�`97
|
�ɐ��_�{�Փ��l / �g��T�q / p98�`107
�O�֎R���J��㕌����--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(��)/��a��Y/p108�`129
�����Ñ㕶���̓ǂݕ�--�Óc���F���� / ���菺��Y / p130�`135
�Ñ�v�Ɠ~���E�Ď��̓��̏o�E���̓���--
�@�@�@���Óc����p���_�Ɠs�� / ���{�����Y / p136�`144
�Ñ�j�����ɂ������Ȋw�I��--�o��������
�@�@�@�����_����/���{���T/p145�`153
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p154�`200
�E |
�V���A���J�c��(NHK�`�[�t�f�B���N�^�[)���u���� 15(7)�@p380�`389�@�u�k�Ёv�Ɂu�Ñ�j�̓���Ɍ���������z�̓���v�\����B �@pid/3367412�@
�W���A���J�c�ꂪ�u�m��ꂴ��Ñ� �� (�����̂�����)�v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@pid/12240295
�X���A�����G�u���u���R = Nature 36(9)(427) p78�`85�������_�Ёv�Ɂu�Ñ���Ɠc���--�v�����g��I�p-�����͂ɂ݂���Z�p�v�\����B�@pid/2359676
�P�O���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (29)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947789
|
�Βk �Ñ�̑D�ƊC��̓� / �ݓВj ; ����ǎO/p2�`27
�Ñ㓌�C�̊C���ʂƑD / �������� / p28�`41
�k�̊C�݂� / �V�쒼�g / p42�`50
�Ñ�V�i�C��ʂƓ쓇--�w�@���x�̗�����
�@�@���ł̐������߂����� / �{�ʓc�e�m / p51�`71
�Õ����㏉���̑D�ƍq�C�ɂ���/���X�؍F�j/p72�`85
�Ñ���V�i�C�������ƑΔn�C��--���ݖQ
�@�@���ᔻ�ɂ����� / �r�|���� / p86�`93
|
�x�Ɠm�ƌÕ�(��) / ������O / p94�`103
�������Ə헤--���z���J���Ɠ��{�_�b(��)/�C�߉�V/p104�`115 �d�v
�V���V�c�N��l / ���菺��Y / p116�`125
�V�ƌ䍰�_�Ђ̈ʒu--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(�Z) / ��a��Y / p126�`144
�u�����Ñ㕶���̓ǂݕ��v�ᔻ--���菺��Y���� / �Óc���F / p145�`151
�C������l���l--�w���{���I�x�ɂ݂���
�@�@�@���u�B��(��)�v�̏ꍇ / �ɓ��`�� / p152�`158
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p159�`203 |
|
��a��Y�����u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (24�`29)�v�ɔ��\�����u���z���J�ƌÑ㉤��(��`�Z)
�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G���ʔԕ� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
(24)p74�`94 |
1980-07 |
���{�Ñ�̑��z���J�ƕ��ʊ� ���z���J�ƌÑ㉤��(��) |
�E |
pid/7947784 |
| 2 |
(25)p90�`114 |
1980-10 |
�؍��̉���Ɖ��˂̈ʒu--���z���J�ƌÑ㉤��(��) |
�E |
pid/7947785 |
| 3 |
(26)p108�`130 |
1981-01 |
�Õ��E�퐶��Ղ̈ʒu�ݒ�--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(�O) |
�E |
pid/7947786 |
| 4 |
(27)p118�`140 |
1981-04 |
���W�E�Õ��̔��� ���ؓ`���Ɠ~����--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(��) |
�E |
pid/7947787 |
| 5 |
(28)p108�`129 |
1981-07 |
�O�֎R���J��㕌����--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(��) |
�E |
pid/7947788 |
| 6 |
(29)p126�`144 |
1981-10 |
�V�ƌ䍰�_�Ђ̈ʒu--�Ñ㉤���Ƒ��z���J(�Z) |
�E |
pid/7947789 |
|
�P�P���A�u �V���ƋC�� 47(11)�v���u�n�l���فv���犧�s�����B�@pid/2356857
|
���W��Â��V���w�ɂӂ�Ă݂悤 / / 26�`38
���W 3.����V���w�ɂ��M�d�Ȓ����̓V������/�{����F/21�`25 |
�����͂���(19)(�F���𑪗ʂ�����@) / �g�c�����Y / 50�`51
�E |
�P�Q���A���c���j���u���ȔN�\�ǖ{�@����݂ƓV���E���́v���u�ۑP������Ёv���犧�s����B
�@
�@�@�@���ȔN�\�ǖ{�@����݂ƓV���E���́i�\���j�@�g�Q�E�S�@��W��
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (14)�v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����Bpid/7957065
|
��j����@�ɂ��N�㑪�� / �����a�v / p1�`24
�Ñ�S��̕��� / ��_���O ; ��F�� / p25�`38
�Ñ�̑@�ہE��������ъ痿�̕��� / ���؊�� / p39�`53
�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(4)�F�{�n���ɂ�����ꕶ�y��ٓy�Ɋ܂܂��v�����g�E�I�p�[���̌��o
/ �����G�u / p55�`65
�����g�p�������Ƃ��̉\��(���k��w�g�p�������`�[���ɂ�錤���� ����4)
/ �ڑ� ; �����m ; ���q���� / p67�`87
�ۑ������������o�y�؍ނ̕����Ɛ��@���萫 / ���V���� ; �c�V�R ; ���{�� /
p89�`102
�M���~�l�b�Z���X�@�ɂ�铩��̐^�䔻�� / �s��đ� ; ���F�P�l / p103�`110
�������Љ� �������������������� / �n���v�v / p111�`114
�������Љ� SAS(Society of Archaeological Sciences)�̍ŋ߂̓����ɂ���
/ ���r�T�q / p115�`120
|
���A���̔N�A�_�c�T�邪�Î��L�w��ҁu�Î��L�N�� = Transactions of the Kojiki Academy (�ʍ� 24) p.p115�`133�v�Ɂu���ؐ_�̐��i�ƃ^�J�~���X�q�v�\����B
���A���̔N�A�u�C��j�w�v���s�ψ�����u�C��j�w ��3���v�����s�����B
|
�Z���j�Ɍ�����։� / ���菺��Y
�V���隬���l / �������Y
�z�O�ɂ����閳���̑� / ���c�F�Y
�u��a�c�����v���ɂ��� / �h�쒼�O
�킽�������։�̕������߂��� / �c��͎q
�ዷ�ɂ����閄���������̔��@�ƕی�^�� / ���W |
�̑���L / �����q
������I�s / �q�J�悵�q
�u�����̋��v�G�� / �S�c�k��
�ʌ��̈ꗢ�� / ���䕽���Y
���؍��� / ���{���O
�������܂�̐l�ɕ��� ���˘Q�m���ߘb / �ēc�C�Y |
|
| 1982 |
57 |
�E |
�P���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (30)���W�E�O���I�̘`�� �v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947790
|
���W�E�O���I�̘`��
�@�Βk �O���I�̘`��--�E���Ɩk��B/���c�x�m�Y ;�Ζ씎�M/p2�`28
�@鰎u�`���`�ƊC�쓇 / ���Ί� / p29�`41
�@�`�l�̖@ / ��ё��� / p42�`51
�@��A�O���I�ւ̃A�v���[�`�̑O��/���쒉��/p52�`65
�@鰎u�`�l�`�ƍ]�� / �����G�O�Y / p66�`81�@�@�d�v
�@�O�A�l���I��̎��p���ƎO�p���_�b��/���쐳�j/p82�`103
�@��g�哹�̓� / ���Ԉ��l / p104�`117 |
�@�V�������`���ɂ݂�O�@�\�̌n�̈�\--�P��������
�@�@�@�����̎��� / ������ / p118�`129
�@�V���V�c�Ɓw���{���I�x--���菺��Y����
�@�@�@�������� / ��a��Y / p130�`138
�@��B�����̏،�(�ŏI��) / �Óc���F / p139�`147
�@�V�n�n���_�b�̉F����(��) / �ɓ��^�� / p148�`157
�@�x�Ɠm�ƌÕ�(��) / ������O / p158�`169
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p170�`217 |
�P���P���t�A�����V���Ɂu��̐�c�����ߓ������������E���t�A�_�썂�n�ցv�Ƒ肵�A�����w�����ٍ��X�؍��������A���哌��A�W�A�����Z���^�[�n�����������܂��������œ�l�̌����҂̂��Ƃ��f�ڂ����B
�P���A�{�� ��F���u�V������ = The astronomical herald 75(2) p.p47�`49�v�Ɂu�����V���w�j�̗��v�\����B
�Q���Q�U���t�A���ǔ��V���ɌÎs�Õ��Q�̒��̉��Õ�����W�����N�^�\���D�̏M�^���ւ��o�y����B
�R���A�������K,�{��M��,����R���q,�c������,������,�}�����v,���q���O�Y,�����G�u,�n�Ӑ�,�����F�K,�����N�H,�ޗǍ�a�T,�呺��,���쏺��,�����T�V,�R�c��,����h���u�ؔ���Ձv���u���Îs����ψ���v���犧�s�����B�iIRDB�j
|
�v��^�ؔ���Ղ́A���Y�n���u�˒n�̖k�[�A�ߊ��R���h���������ΎR��蓌�L�т��u�˂̐�[����쑤�̒�n���Ɉʒu����B
�@�ؔ��n��ł́A�ꕶ����O���`�������̊L�ˁA�y�B��y�B��A�a�A�ꕶ����ӊ��㔼�`�퐶���㒆�����̐��c�Ղ�Z���ՁA�a�A�⊻������o�����B�k���u�˕����ɕ��A���Z����`�����A�u�ˎΖʂɂ͊L�˂��`�����A�쑤�̒�n�ɐ��c���`�����Ă������m�F�����B�����Ԓn��ł́A�ꕶ����ӊ��I���̍Y��ƁA������ݏ�̈�\�A�퐶����O�������̒��������o�����B�╨�́A�ꕶ�y���퐶�y��A�ʕ��y��A�ΐ��i�A�ؐ��i�A���p�킪�o�y�����B
�@�ؔ���Ղ́A�ꕶ����ӊ��㔼�̐��c�̔����ɂ��A���{�ŌÂ̈���ՂƂ��Ē��ڂ��W�߁A�d�v�Ȓ������ʂƂȂ����B |
�S���A���������V���}���ٕҁu�r�u���A : �V�������ٕ� = Biblia : bulletin of Tenri Central Library (�ʍ� 78) p.p2�`18�v�Ɂu���m�E�̕��V��ɂ����v�\����B
�U���A�i�c�v���u��Ɛ肢�̉Ȋw�v���u�V���Ёv���犧�s����B(�V���I��)
|

��Ɛ肢�̉Ȋw�i�\���j�@�r�U�P�E�T�@�P�R�� |
|
�X���A�ؐM���u���Ɨ�v���u������w�o�ʼn�v���犧�s����B�@ (UP�I��, 226)
|

�@���Ɨ�i�\���j |
|
�P�O���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (33) �v���u��a���[�v���犧�s�����Bpid/7947793
|
���W1 �R�n���������������̐V�W�J �R�n�����Ɠ��{�̓��ꍑ�� / �]��g�v /
p2�`41
���W1�E�R�n���������������̐V�W�J ���{�l�ƋR�n����--�]��g�v���Ƃ̎��^����
/ p42�`63
���W2 ���{�Ñ㉤�����J�Ǝ�p �_�Ɖ��Ɩm / �i���v�b / p64�`78
���W2 ���{�Ñ㉤�����J�Ǝ�p �^�t�}����V�Ƌ��c�����摜�� / �X�r�� / p79�`91�@�@�d�v
���W2 ���{�Ñ㉤�����J�Ǝ�p ��D�̐}���I�l�@--�̐Α����Ɠ��� / �d�����v / p92�`121
���W2 ���{�Ñ㉤�����J�Ǝ�p �V�u�퐢�v�l--�퐢�_�̕��z�ƍl�Êw�I�m����ʂ��� / �r�|���� / p122�`148
�w���N��I�x�Ƃ��̐��j(��) / ��ɓ����Y / p149�`161
�����Ƃ��̋��_(��) / �������� / p162�`172
�p�\�̗��ɂ�����ɉ�̒��R�l / �ʏ閭�q / p173�`182
�Ñ�j�ʐM / ����m�q�� / p183�`214 |
�P�O���A���쐳�j���u�הn�䍑�̋� : �O�p���_�b���̓�������v���u�V�l�������Ёv���犧�s����B�@pid/12238343
�P�Q���A�u���j�Ɨ� 9(14)(114) �v���u�H�c���X�v���犧�s�����B�@�@pid/7947294
|
���{�l�Ɛ肢�̗��j / �R�c�@�r / p36�`41
�萯�p ���܂ꂽ�u�Ԃ̘f���Ɛ����̈ʒu�Ō��肷��^�� / ��n���� / p42�`51
�Ր肢 ���T�̑g�ݍ��킹���D��Ȃ��A�Ɨz�̈Ռo�̐��E / ���J�� / p52�`61
�\��x �q�N�Ђ̐��܂�N�͐l�̐��i�Ɖ^����邩�H / �i�c�v / p62�`71
��肢 �Z�\���x�E���j�E�Z�j�ȂǂŔ��f����N�����̋g�� / ���c�F�N / p72�`81
���{�j�̗\���҂��� �O�@��t��C�\���@�̗\���� / �_�⎟�Y / p82�`87
���{�j�̗\���҂��� ���{�����\�����̖��A�z�t / ��q�Y / p88�`93
���{�j�̗\���҂��� �V�䔒��\�]�˂̈Ւf�����̑c / �˕��V�\�Y / p94�`99
���{�j�̗\���҂��� �o�����m�O�Y�\�_������̗\���� / �m�R�I / p100�`105
���{�j�̗\���҂��� �����ÉE�q��\�����哹�Վ҂̌��� / �c�c�_�� / p106�`111
�����łł���肢�̎���� / ��씪�Y / p164�`175
�y�J���[���G�z �肢�ƍՂ� / p11�`21
�y�O���r�A�z ��s�̋g������ / p22�`34
����E��s�̒n���ƕ��� / ���P�J���O / p122�`129
�퍑�����̐肢�Ɩ��M / ���a�c�N�j / p130�`137
���W�Ǖ� �_�Е��t�̐肢�� / �q�ѐ��� / p146�`151
���W�Ǖ� ���ԍs���̒��̐肢 / �q�c�� / p152�`157
���W�Ǖ� �̎��`���Ɍ��閲�肢 / ���{���� / p138�`145
���W�Ǖ� �Í������A�����̃W���N�X / �ȒJ�� / p158�`163
�m�X�g���_���X�̑�\���Ɠ��{ / �ܓ��� / p112�`121
�O���r�A�ƋL�� �������Ɩ���Ɩ��������̌F�{ �ӂ邳�Ƃ̗��j(89) /
�@�@���{���ҏW�� / p195�`205,212�`221
�O���r�A�ƋL�� �y���j�g�s�b�N�X(52)�z�e�̍�����������{���ɉ��P���
�@�@���V������I�I / �{���ҏW�� / p206�`209,222�`225
�O���r�A�ƋL�� ���{�̓�(53)�������O�d�� / �����p�v / p210�`211
���������]�����e�q�Ƃ��̉Ƒ�(��) / �R�c�엝�v / p176�`181
�Ï�E�ٚ��T�K(98)������(��) / �����I��� / p260�`267 |
�J���[�Z�N�V���� �O���u�̗��\���� / �ї� / p243�`247
�J���[�Z�N�V���� ������̋{�߂���\���� �o�H / �Ζؒ參 ; ���|�x / p248�`253
�J���[�Z�N�V���� ���Ɖ��~��K�˂ā\�H�� / �ēc���F / p254�`258
�܂����̐��(106)���]�˂̂���ׂ��� / ��_�j�� / p324�`327
��͕S�b(50)�������M�Ɛ��䁄 / �O�H��� / p286�`289
�ɂ��ۂ�ƉȒ�(�ŏI��)�����̒m�V�� / ��v�ێ��j / p268�`269
���B�X���ƕ�(10)�����́E���c�E���c�쁄 / ���{�O��j / p232�`235
���m�E���m�E���m�`�y���B�z / ������g / p226�`231
���ʓǕ� �ዷ���c���̐���(��) / ��X�G / p236�`241
�𗷏��R�[�i�[ �u�Ɩ�ƕc���v�̐f�f�� / �O�H��� / p304�`305
�𗷏��R�[�i�[ �V�����Љ� / �{�n����Y / p306�`307
�𗷏��R�[�i�[ ���y���Љ� / p308�`308
�𗷏��R�[�i�[ �Â����̂���Ȃ� / p309�`309
�𗷏��R�[�i�[ �ǎ҂Ђ�� / p310�`311
�𗷏��R�[�i�[ ���j�j���[�X�E�_�C�W�F�X�g �R���̗��͍����R�����̌̒n�E�z����
�@�@�����F���F�̐��h�肤���������̈⏑ ��ʌ����ɖ��铿��Ƃ̖������\����
�@�@���킪���ŌÁA�N�O�̐����I���o�y �O�p���_�b���̐��ʖ��ɓ�����V��
�@�@���Õ����ő�̍������q�ɌQ�Ղ@�I / p299�`303
����� / p284�`285
�n���̂͂Ȃ����g�g�L�̒n���ƕc���� / �U�F�� / p290�`290
���J�b�g�̉�� / ���c�F�N / p303�`303
�o�ōL�� / p291�`298 �@�@�������\�� / p328�`329 ���ҏW��L / p330�`330
�V�A�ڏ����\�� / p194�`194
�D�]�O��A�� �V��g���s��(�ŏI��) / ����~�� ; ���[�O�Y / p270�`283
�D�]�O��A�� ���ǂ̈��y(���\��) / �����Ďq ; ��o���� / p312�`323
�D�]�O��A�� �܂ڂ낵�̏��� �ږ��(�ŏI��) / �M���j�Y ; �k�����Y / p182�`193
�E |
���A���̔N�A�M�������u�����Ȋw�j�������ӂ肩������ : �M��������L�O�_���W�̊��s�ɂ������āv�����s����B
�@�@ �����F���s�{�����s�w�E���ʊف@�@�S�W���@�o�ŎЁF�M���� |
| 1983 |
58 |
�E |
�P���A���R�����c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (�ʍ� 21) p.p81�`109�v�Ɂu�ɐ��_�{�ɂ�����Ó`��--�u���_�{���G���L�v (�k�c�w�ّ�w�l�n���S���N�ċ���\�N�L�O��)�v�\����B�@pid/1764571
|
�k�c�w�ّ�w�l�n���S���N�ċ���\�N�L�O�� / p1�`559,����2p
�� / �����@2p
�_���̌����I�@���� / ���c�d�� / p1
�O��̐_��ɂ��� / ���{�ꖯ / p20
�Î��L�Ҏ[�̎��� / ���c���� / p42
�O�����V��͒j�ӋC���X���Z�g��_��-��Z�g��А_��L�����
�@�@���_���l�� / �^�|�풉 / p58
�ɐ��_�{�ɂ�����Ó`��--����_�{���G���L� / ���R�� / p81> |
�ߐ܂ɉ������߂��S�P / ���]�a�� / p110
�n���y�l�̓o��--�������l���l / �R���v���Y / p127
�k���d���ƐM�Z�����E / ���[ / p149
�r�ؓc���Ìn�}�̏o�� / �c���� / p164
�m�ԂƐ���--��㓪�ɐ�]���ׂ���l / ����� / p175
�ɐ��X�������Z��--�������w�����W�
�@�@�����_�{��铔�ɂ��Ă̎��n������/�_�쐴�G/p200
�� |
�P���A�u�� 57(1)[(670)]�@�v���u�V����,�W�F�C�e�B�[�r�[,���{��ʌ��� ,���{���s����v���犧�s�����Bpid/7887919
|
�J���[�O���t �����E�_�b�Ɛ_�y�̗�/�n���Y�g ; �ɓ����� / p10�`20
�_���ւ����A���i�Β|����/�ΐX���Y / p25�`31
���O�͂̊�Ձu�ԍՁv/�R�{�G�� ; �{���� / p34�`38
���W �_�X�̗��� �Ր_�̓�Ɛ_��/���{���� / p49�`57
���W �_�X�̗��� �k���w�ŋI�s�l�����R��ɂ�/�����G�r / p58�`69
���W �_�X�̗��� �o�_�����I�s/��F / p69�`75
���W �_�X�̗��� �u�̒��v�̃��}��/��ˎ��� / p76�`79
���W �_�X�̗��� �O�֎R�ƌÑ��Ղ̓��ǂ�/���J�c�� / p103�`105
���W �_�X�̗��� �_�Ɨ�̎R�A���R���̕���/�A���� / p106�`109
���W �_�X�̗��� �_�̐����Ɂu�H�R������v/�����G�O�Y/p110�`111
���W �_�X�̗��� �g���ÕF�Ɠ����Y�`��/���O���Y / p112�`114
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� �_�b�ւ̏��� / p82�`84
|
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� ���V���͉�����? / p84�`85
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� �_���^ / p86�`87
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� �H�T�̐_�X / p88�`89
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� ��ڂł킩��_�Ќ��z/p90�`91
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� �S�������s�r / p92�`92
2�F���W�K�C�h �_�l�E�_�ЎG�w�S�� �����ʐ_�Ђ��ꂱ�� / p93�`96
�{�����W�K�C�h �S�����w�ŃK�C�h �_�Жk����삩�� / p116�`124
�{�����W�K�C�h �S�����w�ŃK�C�h �����̏o����30�I / p125�`127
�{�����W�K�C�h �S�����w�ŃK�C�h �t���ĂԊ�ՁE
�@�@����K/���p�䐳�� / p128�`130
��
�E |
�P���A�u�����Ȋw 21(1)(235)�v���u�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/3213151
|
�͂���<���W> / p5�`69
�m�Z���n / ���� ���Y / p5�`8
�]�ˎ���̋����w--�����w�̂͂��܂�/��X�� /p9�`13
��̂͂��܂� / �ΐ� �h�� / p14�`23
�����_�̔��� / �W�� ���Y / p24�`26
�v�Z�L���̎n�܂�--�L���̗��j�Ɋw��/�Ж�P��Y/p27�`29
���Z��� / ���^�� / p30�`32
�A���S���Y��--��̓I�Ȍv�Z�@/ �a�c�G�j/p33�`35
�g�|���W-�̂͂��܂� / ���� �p�F / p36�`43
�����Ɩʐ� / �ꏼ �M / p44�`47 |
�G���W�j�A�����O���܂ނ��� / �\�� �� / p48�`51
�d�͊T�O�̂͂��܂� / �����i�N / p52�`54
���Ԏq���_ / �J����F / p55�`58
�_���Ƙ_���w�Ƃ̎n / �g�c�ĕF / p59�`62
�l�����Ƃ͂���--�p�����j�f�X�̓� / ��㒉 / p63�`65
����̋N�� / ���{���T / p66�`69
Dr.SMITH�̖��@�w(�p�Y��-15-) / ���R�P�v / p70�`72
�S���I�N���X�^�����O�Ɠ��v�I�N���X�^�����O/�֓��čK/p73�`79>
�k�����Ȋw�l1982�N(1�����`12����)
�@�@�����ڎ�(Vol.20.No.223�`Vol.20.No.234) / p81�`83 |
�R���A������N�����u�W�]�A�W�A�̍l�Êw : ������N�����ފ��L�O�_�W�v���u�V���Ёv���犧�s�����B
pid/12171793�@�d�v
|
���^���̓�O�ɂ��� : ���敁�i���R�Õ�
�@�@���V�o���𒆐S�Ƃ��� / ������N
�����Ë������̗ޕʓI���� / ������N
�敶�ѐ_�b���ƌÕ����� / ������N
��������̌��� / ������N
�u�����f�[�W�E�R���N�V��������Ɋ֘A���� / ������N
���m�������p�ɂ�����I�N�T�X���h / ������N
���̔��� / ������N
�y�Q�����̌��� / ������N
�ؓ�o�y�̏������� / ������N
���������ԓ�̓� / ������N
�ږ�Ă̓����S�� / ������N
�O����~���̋N�� / ���֏�
�������݂��퐶����̐���̌��� / �ߓ�����
�����̎n�܂�ƏI��� / �����^
�Ñ㐅�c�̓�̌^ / �s�o��C�u
�C�l�тƂ̕� / ���J�^��
|
��J�Õ����߂����� : �Õ��Q�Ɗ��� / �X�_��
�o�_�̉ƌ`�Ί� / �a�c����
���A�W�A�j��ɂ�����S�ϑO���Õ��̈ʒu / �����O��
���N�Ñ�̘A�앶 / ���J��
����̋�Ղɂ��� / �H�R�i��
�����퍑����̖��������ɂ��� / �]������
�ŋ������`�d�̈�l�� : �}���z�u����̍l�@ / �����Y
�u�����ɂ����鋾�̏o�y��ԁv��� / ���{���i
���R������o�y����̒����W���� / �����r��
�u�A��������̓����ӏ��ɍ̂�ꂽ�쐶�����Z�� / �і��ޕv
�ΌA���@�̕ϑJ : �C���h���璆���܂� / ���J���j
�o�[�~���[���ΌA�̑Y�������� / �{����
�����A�W�A�ƃC�[�V�����@�� / �R�c����
�k�P�C�l�o�ƘŔ� / �K�R���i
���[�^���̋ʍ�H�[�� : �C���h�E�O�W�����[�g�n���ɂ�����
�@�@���U�ʋZ�p�̓`�� / ��������
���錕���̔c�����@�ɂ��� / �얔���q |
�R���A�F�J�ۍF�������o�ώj�w��ҁu�����o�ώj�w = The journal of historical studies : the politico-economic history (�ʍ� 200) p.p371�`380�v�Ɂu�F�N�Օɂ��� (���{�����o�ώj�w�������n��20���N�L�O�_�p)�v�\����B
�R���A���蒨�i���Ñ㕶�w��ҁu�Ñ㕶�w (�ʍ� 23) p.p1�`10�v�Ɂu���쎮�̋F�N�Ղ̏j���ɂ���--���̐����̎��� (�j���E�閽<���W>)�@�v�\����B
�R���A�і�,�����F������������w�_�w���ҁu��������w�_�w���w�p�� = Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University (�ʍ� 33) p.p1�`6 �v�Ɂu���q�̋x��������є��萫�Ɋւ��錤��-11-�x�������Ɠ����W�x�������l�����Ƃ̊W�v�\����B
|
�і��E�X���M���E�P�쐳�ȁE�c����Y�E�����m��Y�E�����F�����u���q�̋x��������є��萫�Ɋւ��錤��:�i1�`�P�P�j�v�̘_������\
| �m�� |
�G���@�����@�� |
���s�N�� |
�_���� |
���� |
�{���`�� |
| 1 |
�M�є_�� 16(2) p.115-120 |
1972-09 |
.���x����ю_�f�����̉e�� |
�і�,�X���M�� |
J-STAGE |
| 2 |
�M�є_�� = 16(4) p.270�`275 |
1973-03 |
�x�����Ɛ��������̊W |
�і�,�P�쐳�� |
J-STAGE�@ |
| 3 |
�M�є_�� 17(4) p.245�`249 |
1974-03 |
���n��q�̔��萫����ю�q�̋x�����Ɛ��������̊W |
�і�,�P�쐳�� |
J-STAGE |
| 4 |
�M�є_�� = 19(3�E4) p.p156�`161 |
1976-03 |
�}�������y�уI�[�L�V�̎�q���̑��ݕ��ʋy�т����̎�� |
�і� |
J-STAGE |
| 5 |
�M�є_�� 20(3) p.p164�`171 |
1977-02 |
��̋z����q�̍��������ɂ��x���Ŕj |
�і� |
J-STAGE |
| 6 |
�M�є_�� 23(1) p.p1�`5 |
1979-06 |
�x����q�̔���}�������̃K�X�N���}�g�O���t�B�[�ɂ�铯�� |
�і� |
J-STAGE |
| 7 |
��������w�_�w���w�p��(�ʍ�29) p.p11�`20 |
1979-03 |
������̔���ɂ�锭��}�������̌�����тɎ�q�̋x�����x�Ƃ̊W |
�і�,�c����Y |
IRDB |
| 8 |
��������w�_�w���w�p��(�ʍ�29) p.p21�`32 |
1979-03 |
�o�n�����тɎ��n��̉��x��������q�̋x������щn�̕ϐ��ɋy�ڂ��e�� |
�і�,�����m��Y |
IRDB |
| 9 |
��������w�_�w���w�p��(�ʍ�30) p.p1�`9 |
1980-03 |
�_�f����ѐ�������q�̋x���������тɔ���}�������̕s�������ɋy�ڂ��e�� |
�і� |
IRDB |
| 10 |
��������w�_�w���_�ꌤ����(�ʍ�5) p.p1�`7 |
1980-03 |
ABA(�A�u�V�W���_)�̎{�p����q�̋x������є���ɋy�ڂ��e�� |
�і� |
IRDB |
| 11 |
��������w�_�w���w�p��(�ʍ�33) p.p1�`6 |
1983-03 |
�x�������Ɠ����W�x�������l�����Ƃ̊W |
�і�,�����F�� |
IRDB |
|
�R���A���w�@��w���{�����������n���S���N�L�O�_���W�ҏW�ψ���ҁu�ېV�O��ɉ����隠�w�̏����
: �n���S���N�L�O�_���W�v���u���w�@��w���{�����������v���犧�s�����B�@pid/12222741
|
�c�T�u�����ƌÓT�u�K�Ȃ̑n�� : <�n���w�Z>�̌n�� / �����Y��
"�Ґ_����"����鏔���ɏA�� : ������_���̈�� / ���}���t�v��
�Øa��̍��w�Ɖ��F�b / �������v��
���F�b�́u���v�̖�� : �钷�E�Ĉ��Ƃ̔�r��ʂ��� / ���h�J���F��
�n粏d�Ίہw�V�䒆��_�l�x�G�� / ���Ñf�F��
�����ɉ�����匠�ƚʏ����C / ����啶��
�����ՙՂ̖����j�_ : �o���Ɓw�����I���x�̊W�𒆐S�� / �H���M�p��
��؏d���̐_�T���� / ������i��
�J�X�P�b�̌Î��L�Z������ : �������疾����
�@�@���Î��L�����j�̈�Ƃ��� / �؎�����
���w�҂Ɗw�Z��� : �c�w���ݗ����߂��� / ��{���ے�
�_���Ղ̌ËV�����ƌ�ސ��� / �������K��
�{���L�o�` / ��؏~�� |
�c���̌�w���ƍ��w�Ƃ��Ắu�~���̓��v : ��Ƃ��Ė������
�@�@����̂ɋ���� / �˓c�`�Y��
���䏬��̃L���X�g���ςƁu�����̐��v:�钷�́u���̂̂��͂�v�_
�@�@���Ƃ̋ߎ����ɐG������� / �i������
�_�����h�ʔh�����̉ߒ� : ������N�ɂ�����W�J / �F�쐳�l��
���������ɂ����鍑��w���� / �v��}���q��
���������@�_�̐��i : �����̈������߂����� / ���V�m�꒘
���w�҂ɂ݂�<����>�T�O�̗��� : �u�����ւ̊S�v�Ƃ���
�@�@�����_���� / �匴�N�j��
�_�АV��Еҁw�ߑ�_�А_���j�x�ɉ����閾���O����
�@�@���_���j�̕]���ɂ��� / �G�����X�g�E���R�o���g��
�n�ӏd�Ίۍl / ��c������
�E |
�R���A�啪��w����w���ҁu �������� : ���R�E�Љ�E����v���u�啪��w����w���v���犧�s�����B�@pid/9774981
|
�����̂��Ƃ� ����w���� �u��j��
���_ ���������̒n�ʁ\������_�ƘZ�����R�\ �x�����E�O�{���M / 1
I ���R�E�Y��
1 ���������̒n�` ��c�� / 17
2 ���������̒n�� �X�R�P���E������ �x�ܘY�E�Í�r�K / 29
3 ���������̋C�� �쐼���E�H���D�� / 63
4 �������������̐��� �u��j���E���c���v ���ΓN�j / 72
5 ���������̊C�Y���Ғœ��� �g�c���Y�E�匎�P �c�ӐM�F�E�������� / 85
6 ���������̒��� ���я��E���i�M�` �ۖ����� / 97
7 ���������̐A�� �����חY / 102
8 ���������\��n�k�k���̊��A�� �~�ÍK�Y / 116
9 ���������Ƃ��̎��Ӓn��̐A�����Ɛ��F�̐��ɂ��� �����G�E��������
�@�@�@�������m�q�E�����C�� ������~�q�E��c���K �ĉ����j�E�O�{���M / 128
10 ���������̒��� ���R���Y / 140
11 ���������̐��Y�� �V���� / 149
12 ���������̐��Y�Ɓi����1�j�\�͔|���Ɓ\ �ؒJ�v�M / 161
13 ���������̐��Y�Ɓi����2�j�\����@�\ �ؒJ�v�M / 175
14 �ؑ��D
(1)�]�ˎ���̑D �ѐ��� / 188
(2)���D �䗲 / 201
15 ���������̐��S�ƒb���̈�� ���閾�� / 210
II �Љ�E����
1 ���O�b�Ɋւ����l�@ ���ʕ{���� / 223
2 ���������̌����\�����{�̍Ր_�ɂ��ā\ �_�ˋP�v / 235
3 �Z���R���������Ɠ��R�h�C�� ������ / 245
4 �������n���ɂ�����L���V�^����� �����m�O�E�H�R�o�u�� / 261 |
5 �n�z�˂ɂ�����鉺���E�ݒ����Ƃ̎j�I�W�J�\�≮�c�Ƃ𒆐S�Ƃ��ā\ �L�c���O
/ 273
6 ���������̍z�R �͖쏺�v / 286
7 ����������ɂ����閾���O���̍s�� ���ێ� / 303
8 ���������̓���і�Ƃ݂����� ���ڔE / 313
9 ���������n��ɂ�����_�Ƃ̕ϖe �o�c�a�v / 329
10 ���Y��㗬�C��ˎ������C���암���̎Љ�\���\�����n���̏W����
�@�@�@���Љ�\�����͂̂��߂̎��_�\ ���n�O / 346
11 ���F�сE���g�_�Ђ̍��J�ɂ��ā\�R�l�Ƃ��̎��Ӂ\ ������ / 362
12 �����n���̏Ĕ��i�i�M�m�j�`������ ��������q�E�������q�q / 375
13 ���������̐l�X�̐H���� �����e���q / 389
III ����E����
1 ���������̋��當�� ���ъ / 403
2 ���������ɂ����鎄�w�u�K���Z�v�̓W�J�ߒ� �쑺�V�E�㓡���G ��䐳���E�R�ݎ��j
/ 417
3 ���������ɂ����鐶�k�̉ƒ됶���Ɋւ���F���Ǝ��� ��{����b / 461
4 ���������Z���̈玙�ӎ��Ǝ��� ���ˈ��q / 474
5 �����n��̗c������(I)�\���j�ƌ���\ �O������ / 485
6 �����n��̗c������(II)�\�e�ƕۈ�҂̏A�w�O����ρ\ �O�c�� / 497
7 �����n��̗c������(III)�\�A�w�O���̒m�I�����ƕ�e�̑z�萅���ɂ��ā\
�g�{�[�O/510
8 ���������ƒn��ی��\��q�ی��𒆐S�Ƃ��ā\ �����V�� / 519
9 ����������Z���̌��N�ƗV�� �����F�E�Z�c�� �����i�E���{��Y �Ï錚��
/ 531
10 �啪�����������̉\�\�� �����v��Y / 579
11 �����̊��p�̎�ނ̎��ԁ\�啪���������������̏ꍇ�\ ��F�� / 586
12 ���������̕��w ���X�؋ϑ��Y�E�]�㊰�m / 592
IV ����
1 �L�㍑�S�����i���������W���j / 607
2 ���������W�����ژ^ / 612 |
�S���A��t��F���u�j���[�g��3�i4�j�@p11�`12�@������v�Ɂu�����Ǝ��v�v�\����B�@pid/3211558
�V���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (36)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947796
|
�C�k �ŋߏo�y�̈�Ղƈ╨--��ɓ����{��
�@�@�@�����S�� / ��O�� ; ��ˏ��d ; ���Α���Y / p2�`32
�X��������Ղł̖퐶���c���@�̈Ӌ`/�H�y�P��;�������v/p33�`40�@�d�v
�Ñ㋏�و�ՂƂ��Ē��ڂ����O�b��I��� / ���鐳 / p41�`49
��썑�̉𖾂̎肪����ƂȂ�R���p�� / �����h�� / p50�`61
���q�s�����Ղ̒����T�v / �`���C�� / p62�`69
���b���ɂ��� / �O�V������ / p70�`94
�`���E���鎁�E�h�䎁 / ��a��Y / p95�`114
|
�Ώ�_�{�ƕ����� / �{�ʓc�e�m / p115�`127
���敔�Ɣ���--�b��̒n���Ɗ֘A����/�����/p128�`139
��і쎁�W�����̊�b�l�@(��) / ���j�N / p140�`155
�������l�����̎���(��) / �����O�N / p156�`169
�O�p���_�b���̛�䁁�P���`���ɂ���--�w������x
�@�@���R���_�͐������Ȃ�(��) / ���{���v / p170�`182
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p183�`222
�E |
�W���A�r��h���u�����v���ŌẨȊw���u�v���u�C�Ёv���犧�s����B
�@�@
�@�@���v���ŌẨȊw���u�i�\���j |
|
�X���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (37)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7947797
|
�C�k �Ñ�؍��Ɠ��{--�؍����R�s���k���C�l����
�@�@�@���Õ��Q�𒆐S��/�{���� ; �A���� ; �\�h�K/p2�`38
�C�ߓ��{�{�̉��s��� / �X�r�� / p39�`59
�Ñ�����𗬎j�̏��i�K / ���J�� / p60�`71
�ܐ��I�̊O��--���N�W�𒆐S�Ƃ���/��R����/p72�`83
�͓��̋���Õ��ƌÑ㒩�N(��) / �x�c�[�� / p84�`107
�m��ꂴ��Ñ�Ɗ؍� / ���J�c�� / p108�`129 |
���N������[�ɘ`�l�͂�����--����P�ÕF�`���̂��Ӗ�/��a��Y/p130�`145
�V���ɔ������ꂽ�����Ƃ́u�m���ˌÕ��Ί��}�v / ����M�i / p146�`153
��і쎁�W�����̊�b�I�l�@(��)--���N�Ƃ������
�@�@�@����і쎁�W���� / ���j�N / p154�`173
���E�x�Ɠm�ƌÕ�(��)--�v�c��D�̌��� / ������O / p174�`188
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p189�`224
�E |
�X���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 5(9)(48)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@
pid/7952649
|
���؉Ȋw�j�Z�~�i�[�̂��� / �M���� / p2�`3
�؍��̓`���J��(��)�J���[�O���r�A
�@�@���؍��̓`���J�� / ���ߑ� / p15�`16,21�`23
�؍��|�\�j�̍\�} / �J�O / p24�`30
���N�̈������ / ���{�K�v / p4�`9
���N�����̉ȋ��ɂ��� / ���ݓ� / p10�`14
���{�j�ɐ������؍��̐l �S�ω��� / �i���� / p31�`36
�V���̋��Ε� ��R�V���E���� / �c���r�� / p37�`40
�؍��̓`���X�|�[�c �R�� / ���{���N / p41�`41
�؍��̔N���s�� �����̍s�� / �C���� / p42�`44 |
�؍��̗��j�� �w�P�������x�Ɗ֘A���� / ����� / p45�`47
�؍��̖��b ������ƍ��J�� / �c���a / p48�`49
�]���̖{ �w�؍��Î��T�K�x / �R�c�C / p50�`50
�]���̖{ �w�؍���̌`���x / ��� / p51�`51
�}�X�R�~�_�� ��s�͋@�\���ے��� / �؍����� / p52�`52
�}�X�R�~�_�� �{��ʂ��������A�o / ���N���� / p53�`53
�ǎ҂̂Ђ�� ���O���t�@�E�g���T�� / ���R���q / p54�`54
�؍������E�̓��� / p55�`56
�؍������@����� / p57�`57
�E |
�P�O���A������ ; ���c�ەv���u�_�ƋZ�p�������� D p33�`102�@�_�ѐ��Y�Ȕ_�ƋZ�p�������v�Ɂu����̓o�n�ߒ��ɂ�������k�̖����Ɋւ��錤���v�\����B�@�@pid/2311593
�P�P���A�K���������Y������ƈ�w�̉�ҁu����ƈ�w 31(11) p.p1070�`1078�v�Ɂu�������v�̎��̂�T�� (�����̃��Y��<���W>) �v�\����B
���A���̔N�A������,���c�ەv���u���{�앨�w��I�� 52(1) p.80-83�v�Ɂu����̓o�n�ɋy�ڂ����݊k�̖����@�u�h�h�h�@���݊k�ɂ�����ł�Ղ�̒~�ς���у��O�j���̌`���Ƃ����Ɋ֘A����Q�C�R�̍y�f�����ɂ����v�\����B
J-STAGE
|
����̓o�n�ɋy�ڂ����݊k�̖����@�i�h�`�u�h�h�h�j����ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
�_���� |
���e |
| 1 |
51(1) p.97-104 |
1982 |
1981-07 |
�o�n�ߒ��ɂ�������݊k�̖��@�����̓��� |
|
| 2 |
51(1) p.105-109 |
1982 |
1982-01 |
�o�n�ߒ��ɂ�������݊k�̌���������ьċz��ӂ̐��� |
|
| 3 |
51(3) p.349-353 |
1982 |
1982-01 |
���݊k�ɂ����邯���f�C���C�J���E������уJ���V�E���̋Ǎݐ��ɂ��� |
|
| 4 |
51(3) p.354-359 |
1982 |
1982-01 |
�o�n���x�̈قȂ���݂̂��݊k�ƕė��̌`�ԓI�����ɂ��� |
|
| 5 |
51(4) p.529-534 |
1982 |
1982-01 |
���݊k����̐��������ƕė��̔���ɂ��� |
|
| 6 |
51(4) p.570-576 |
1982 |
1982-01 |
�Y�������̖������݂���ѕs�����݂ւ̈ڍs�ɂ��� |
|
| 7 |
52(1) p.73-79 |
1983 |
1982-07 |
���B�������ɂ����邯���_����уJ�������݊k�̌`�Ԃ���ы@�\�ɋy�ڂ��e�� |
|
| 8 |
52(1) p.80-83 |
1983 |
1982-07 |
���݊k�ɂ�����ł�Ղ�̒~�ς���у��O�j���̌`����
�@�@�������Ɋ֘A����Q�C�R�̍y�f�����ɂ��� |
|
|
|
| 1984 |
59 |
�E |
�P���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 6(1)(52)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@pid/7952653
|
�؍��̑D�Ɠ��{�̑D / ���ؓN / p2�`3
�؍��̏��� �J���[�O���r�A �؍��̏��� / ���싨 / p15�`23
�����̗�--������������߂�����/�؉����; �{����F/p4�`9
�u�ՋT��v�⍏��̐��E--�����͂Ă�
�@�@�@���Ñ㓌�x�ߊC���� / �n�ӌ��q / p30�`35
���ތk�̐l���Ɗw��(��) / �����i / p10�`14
�j�Г��v�m��(���Y)�� / ���㋜ / p24�`29
�V���̋��Ε� ��R�V���E��O��A��l��/�c���r��/p36�`40
�؍��̓`���X�|�[�c ���� / ���{���N / p41�`41
�؍��̔N���s�� 12���̍Ύ����� / �C���� / p42�`44
|
�؍��̗��j�� �w�����b�l�x / ����� / p45�`47
�؍��̖��b �s�v�c�Ȏ�u���������q/�c���a/p48�`49
�]���̖{ �w�؍��l�Ɠ��{�l�x / ���e�_ / p50�`50
�]���̖{ �w��̎��x���x / �{��s�� / p51�`51
�}�X�R�~�_�� �l���m��(���Y)�̋��� / �\�E���V�� / p52�`52
�}�X�R�~�_�� �u���U�Ƒ��{���v�̏I�� / �������� / p53�`53
�ǎ҂̂Ђ���O���t�@�E�g���T�� / ���� / p54�`54
�؍������E�̓��� / p55�`56
�؍������@����� / p57�`57
�E |
�S���A������,���c�ەv���u���{�앨�{���I�� 53(1) p.106-107�v�Ɂu�C�l�ɑ���G�`�����̐�����p�Ɋւ��錤�� : ��9�� �C�l����̃G�`�����������n�̕i��ԍ��فv�\����B�@�@
|
�u���{�앨�w��I���v�ɔ��\�����u�C�l�ɑ���G�`�����̐�����p�Ɋւ��錤���i�P�`9�j�v��
�@�@�@�@�u�������ɂ�����C�l��q�̃G�`���������Ǝ�q���͂̕i��ԍ����v�ɂ����̘_���ꗗ�\
| �m�� |
�G�����s������ |
���s�N |
�_���� |
���� |
���e |
| 1 |
48(4) p510�`516 |
1979-12 |
-1-�C�l�萶���̐L���ɂ���ڂ��G�`�����̉e�� |
������,���R���`,���c�ەv |
. |
| 2 |
49(1) p15�`19 |
1980-03 |
-2-���f�h�{���C�l�t�̃G�`���������ɋy�ڂ��e�� |
������,���c�ەv |
. |
| 3 |
49(2) p.366-372 |
1980-06 |
��6�� �_�C�Y����уC�l�c�A���̍��̐����ɂ���ڂ��Y�����f�Ƃ��ɃG�`�����̉e�� |
���R���`,���c�ەv |
. |
| 4 |
52(2) p.170-171 |
1983-10 |
��4�� �C�l����̃G�`���������ʂ̕i��ԍ��� |
������,���c�ەv |
. |
| 5 |
52(2) p.172-173 |
1983-10 |
��5��C�l����̐�������уG�`���������ɂ���ڂ������}���܂̉e�� |
������,���c�ەv |
. |
| 6 |
52(2) p.174-175 |
1983-10 |
��6�� ���f���x���̈قȂ�C�l�c�̐���y�уG�`���������ʂɂ���ڂ������}���܂̉e�� |
������,���c�ەv |
. |
| 7 |
53(1) p.102-103 |
1984-04 |
��7�� �C�l�t�̃��`�I�j��,ACC�ܗʂ���уG�`���������ʂɂ���ڂ����f�̉e��. |
������,���c�ەv |
. |
| 8 |
53(1) p.104-105 |
1984-04 |
��8�� �C�l�������їt�g�̃G�`���������ʂɂ���ڂ����`�I�j�������ACC�̉e�� |
������,���c�ەv |
. |
| 9 |
53(1) p.106-107 |
1984-04 |
��9�� �C�l����̃G�`�����������n�̕i��ԍ��ف@ |
������,���c�ەv |
. |
| 10 |
68(1) p.156-157 |
1999-04 |
�������ɂ�����C�l��q�̃G�`���������Ǝ�q���͂̕i��ԍ��� |
�i�V�� �V���n�U�[�h,�����v��
���c�ەv |
. |
�@�@�@�@�@�@�@�@���@�t�^���ꂽ��Ԃ��������肵�Ȃ������̂Ŕ��s�N�ŏ��ɂ����̂Œ��ӂ��K�v�@�@�Q�O�Q�Q�E�P�O�E�X�@�ۍ� |
�S���A�n�������A����R�Z�Y(��) �u�����]��n���̈�앶�� ���̊w�ۓI�����v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s�����B�@�d�v
|
���́@�k�������߂�����
���́@�v�E��������k�E�l�c�����c���߂����ā@
��O�́@������߂����� |
��l�́@���E������̕��k�E�l���߂�����
��́@���i�앨�̓W�J
�I�́@�@�]��_�ƂƓ��{ |
|
���k�E�l�c�i���ł�j�F���ł�B�͓c�ƂƂ��ɍ]��n���Ɍ�����A�͂̈ꕔ��r���h�ň͂��Ċ��A�c�n�ɂ����Ƃ���B
�����c�i���ł�j�F �v�����v�ɂ����Ē��]�����A�]��n���̎��n�тɌ�����A�Ꮌ�n�ɒ�h��z���Ĉ݂͂���Ŋ��A�k��\�ȓy�n�ɂ����Ƃ�����͓c�Ƃ����B |
�S���A�ΐ�h��,�ΐ얾�F���u�����Ȋw 22(4) p.p82�`83�v�Ɂu�V�����������߂�Nomograph�v�\����Bpid/3213166
�S���A�u���R = Nature 39(4)(459)�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/2359445
|
�t��҂��� / ��{�� / 50�`51
�A�C���V���^�C���������������v�Z�@ / ���X�،��� / 52�`53 |
��Ă��裂Ƣ������̐����w / ��t��F / 54�`55�@�@�@�d�v
�E |
�U���A�n������, ���c���ҁu�쓇�̈�앶�� : �^�ߍ����𒆐S�Ɂv���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@pid/9774816
|
�͂�����
I �쓇�̔_�k�ƈ��
�u�쓇�v�̔_�Ɗ�� ���J�D�� / 2
�쓇�̓`���I���_�k�Z�p ���X�؍��� / 29
���d�R�̈�̌n���\�H�k���C�l�Ăƍݗ��� �n������/67
II �쓇�̈��Љ�ƕ���
�ΊO�W����݂������Ñ�j�\�쓇���j�̗����̂��߂� ���c��/94
�쓇�̈��V��\����E���d�R�E�^�ߍ� �Ί_���F/126
�쓇���N���`���̌n�� ��ё��� / 160
�����E�Ƃ��Ă̍\���ƒ��� ���J�I�v / 191 |
�^�ߍ��Љ�̓쓇�I���i�\�\���̐��Ԃ�
�@�@���\���ւ̎��_ �ѓ��� / 213
III �^�ߍ����̈��
�^�ߍ����̐��c���n�ƈ��Z�p�\�H�k���C�l�ē���
�@�@���ȑO�̓`���I���̑̌n�𒆐S�� �c���k�i/232
�^�ߍ����ɂ����鐅�c�̕��ނƍݗ��̈��_��@���R���v / 263
�^�ߍ��_���̐����\�\���\���Ƃ̑Δ䂩�����V�n / 295
�^�ߍ����W�����ژ^ ����V�n / 324
��������
�E |
�U���A���蒨�i���u�w�� (�ʍ� 534) p.p2�`14�v�Ɂu�F�N�Ղ̏j���̖��_-��-�v�\����Bpid/3373547
�W���A���蒨�i���u�w�� (�ʍ� 536) p.p2�`15�v�Ɂu�F�N�Ղ̏j���̖��_-��-�v�\����Bpid/3373549
�V���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (40�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947800
|
�V���E�������̎���--�V���V�c�̍c�q������
�@�@�@�����S�� / ���؍F���Y ; ����d�� / p2�`26
�V���E�������̎���--���Ɍ�{�ɂ���/�O�J�Ĉ�/p27�`39
�V���E�������̕��� / �c������ / p40�`48
��F�c�q�Ƒ�F�� / ����Ǎ� / p49�`59
�V���E�������ƌÎ��L / �����Y / p60�`68
�V���V�c�Ƒ��ԍs�{ / �ˌ��� / p69�`79
��a�̏I�����Õ�--��E�I�����Õ��̕��z��ʂ���/��X�/p80�`91 |
�`�{�l���C�́u�_�v--�V���V�c�Ɠ���(��) / ��a��Y / p92�`123
���������Ǝהn�䍑�̓��J--�͓���
�@�@�@���������߂�����/�J�쌒��/p124�`137
��ρu�i���v--�ď̂̔w�i���߂���� / �ɓ��`�� / p138�`151
�؍��O����~�����Ǝs���G�l���M�[--�I��������
�@�@�@���u����̓^�� / ������ / p152�`156
�剻�̉��V�Ƃ͉��ł�������--���̈Ӌ`�ƐM�ߐ�/���ҋ`��/p157�`173
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p174�`215 |
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (41)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947801
|
�C��藈��_--���ڏM�Y��� / �쑽�H / p127�`147
�����ƓV�c��--�V���V�c�Ɠ���(��) / ��a��Y / p148�`168 |
�_��ȜR�����������m�[�g / ��ؐ��� ; ���ۗǎq / p169�`188
�q�����r |
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (17)�v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����Bpid/7957068
|
�������Ղ̍l�Òn���C�@�ɂ��N�㑪�� / �ɓ����� ; ���}���� / p1�`24
��j����W���ɂ������܂ꂽ�S�y�̎Y�n / �V��N�� ; �R��T�� / p25�`33
5�`6���I�̑�㓩�W�Y�{�b��̕��z(��1��)�X���R�ˌÕ�(���쌧)�C
�@�@�������Õ�(��������)�C�V�����(��茧) / �O�җ��� ; �����^���� ; �r���k��
; ��a�� ; ��G�Y / p35�`50
�V�R�����ɂ����F�z�̃��[�U�[��N���� / �O�D���B ; ���c�דT / p51�`60
���̗@�\ / ���ь� ; �������a ; �ߓ����� / p61�`72
�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(5)�v�����g�E�I�p�[�����͂ɂ�鐅�c���̒T��
/ �����G�u ; ���R�^�� / p73�`85
��Տo�y�̓�����̂̊�b�I����(2)�����L�c�l�̑̏d�E�������̐��� / �����݂��q / p87�`107
������ւ̐���ɂ�����Z�@�̍l�@�Ƃ��̏Đ�����--���X���R�Õ��o�y����~������
/ �e�c�@�F / p109�`127 |
���A���̔N�A�n���������u���{�̈��_�k�����̓W�J�ƌn���ɂ��Ă̊w�ۓI�����v�\����B
�@�@�@�����ȉȊw������⏕���������ʕ��^���s��w
���A���̔N�A�����w���u�k���ɂ�����ߐ��I�x�z�̐��`�����̊�b�����v�����s�����B
|
�O�c�������n�Ɛ��� / �؉z���O
�O�c�����̉ƒ�����(�f�`) / ����T��
����˂́u�v�������v�ɂ��� / ���c�ÕF
��̕��m�ɂ�����喼�ӎu / ������� |
�։�ɂ����鏉�������ƑD���O���̐��� / ���c�F�Y
�ዷ���O���S�����n�ӘZ�Y�E�q��ƕ������ژ^
����˂ɂ�����̍��ݕ��̗��j�I���� / ����ߎq
�E |
|
| 1985 |
���a60 |
�E |
�P���A���R�����c�w�ّ�w�ҁu�c�w�ّ�w�I�v (23)�@ p1�c�w�ّ�w�v�Ɂu�_�{�̌��z�l���ƍ��J���x�ƂɌ��ꂽ����㖖���̎v�z�ƐM�v�\����B�@pid/1764573
�P���A���蒨�i���u �w�� (�ʍ� 541) p.p15�`28�v�Ɂu�F�N�Ղ̏j���̔��z�v�\����B�@pid/3373554
�R���A�������ꂪ�u��y���Õ����@�������v���u�m��������ψ���v���犧�s����B�@�iIRDB�j
�R���A�����[���m�j������ҁu���m�j���� 43(4) .p734�`739�v�Ɂu�q���]�E�Љ�r�n������,����R�Z�Y�ҁu�����]��̈�앶��--���̊w�ۓI�����v�v���Љ��B �iIRDB�j
�R���A�u���j�ǖ{ 30(5)(403)�v���uKADOKAWA,���o�o��,�V�l�������Ёv���犧�s�����B�@�@pid/7975357
|
���W ���{�ɒ��Ñ㕶���͂������I�H ����l�̑z�������Ñ㕶���̓�ɒ��ށI
���m�Ȃ�ꕶ���Ε��� / �����ǓT / p46�`55
�X�g�[���T�[�N���Ɠ��k���� / �u�Γc�i�� / p56�`63
�֍����O�V�@�ʼn��� / �O����v / p64�`70 |
�Î��L�ɂ݂��鑾�ẨȊw/����ē�/p72�`79
����ɂ��������z�̓� / ���J�c�� / p90�`97
�q�����r
�E |
�S���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (43)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947803
|
���W1�o�_�̓����̓� ���W2�D�����蕶�̓�
�Ñ㓌�k�Ɖz�Əo�_--���{�C�����Ɓu�n�捑�Ɓv/�V�쒼�g ; ��e����/p2�`31
�O�ܔ��{�̓��� / �������� / p32�`45
�o�_�̓����̓�--�o�_����쒬�r�_�J��Տo�y�̓���/����S/p46�`61
�o�_�r�_�J�̓�����ʏo�y�Ɏv�� / �R�{�� / p62�`70
�n�z�Ɠ��� / ���J�� / p71�`75
���{�C�����̈��--�V�쒼�g�w�H�c���l�̓�x��ǂ��/���G�Y/p76�`77
���o�_�����Ɩ퐶���� / �����ۍF / p78�`87
�_�ޔ��R�̐M�Ɠ��� / ���c���� / p88�`97 |
�D�����蕶���݂� / �]��g�v / p98�`115
�����Q���́u�D������̌����v��ǂ�� / ���i� / p116�`129
�D�����蕶�́u�`�v�Ɠn���W�c / ���쐳�j / p130�`140
�D�����蕶���߂�����--�V���|�W�E���u�l�E�ܐ��I�̓��A�W�A�Ɠ��{�v�T���L/���ژa��/p141�`150
�ѐ���Ւ����̈Ӌ`--�j���ɖ�����肳��Ă��Ȃ��u�N�j�v������ / ���c�x�m�Y
/ p151�`153
�w�S�ϋL�x�w�S�ϐV��x�̎j���I���l(��)�ܐ��I�`�ό��̈�l�@ / ���j�Y / p154�`171
�w�Î��L�x�̓V�n�J蓐_�ƍ��V��--�V���V�c�Ɠ���(���̈�) / ��a��Y / p172�`194
�Ñ�j�ʐM / ����m�q�E�� / p195�`227
�E |
�V���A���юO�����u�d�Ō��� (7)(429)�@p74�`76�@���{�d�Ō�������v�Ɂu�Ď��Ɠ�\�l�ߋC�v�\����B pid/2762786
�X���A���蒨�i���u�w�� (�ʍ� 549) p.p2�`17�v�Ɂu�F�N�ՈȑO-��-�v�\����B�@pid/3373562
�P�O���A���{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j����. Journal of history of science, Japan [��U��] = [Series �U]�v���u���{�Ȋw�j�w��v���犧�s�����B�@pid/11683921
|
�֍F�a�̉~���Ȑ��̌����ɂ���--
�@�@�����Ɂu���ʑS�`�v�Ɣ�r���� / ���ї��F, �c���O / / 149�`154 |
�؍������{�����̐����Ղɂ��� / �{����F / / 164�`170
�E |
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (45)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947805
|
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B ���k�� �퐶����Õ������
�@�@����k��B / ���c�x�m�Y ; �������� ; ���c���F ; ���R�M�p / p2�`49
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B �u�퐶�v����
�@�@���u�Õ��v��--�V�������_�̂��߂� / ������ / p50�`58
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B �ѐ���ՁE�╨�̈Ӗ��������/���J��/p59�`61
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B �O�E�l���I�̑Δn / �i���v�b / p62�`72
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B �O���I�̌F�{�n��--�ŋ߂�
�@�@�����@���ʂ��� / �G���u / p73�`80
���W1�@�O�E�l���I�̌Ñ�k��B �Ñ�j�ʐM(���ʔ�)/�ѐ�����; �{��i�c/p81�`84
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i p85�`96
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �����́u�`�d�v�Ɠn���l�̕��� / ���쐳�j/p97�`105
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �`���Ɠ����v�z / ����d�� / p106�`115
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ ���{�ɂ�����A�z���̓`���ƕ��y / �H������/p116�`130
|
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �w�}�㍑���y�L�핶�x�Ɍ���O���M��(��)�ֈ�́u�����v��
�@�@���@���j�I�Ӌ` / �{�����l / p131�`150
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �ۂ̒��R�E�ۂ̏���́u�ہv�Ƃ������̂ɂ���/�ʏ閭�q/p151�`157
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �ؒn���̐��E��--�����Y�牡�s��
�@�@����e���߂����� / ���쐳�D / p158�`172
�ً}�E�r�_�J��Ղ̓����o�y���߂����� �r�_�J��Ղ�
�@�@�������o�y���߂���ŋ߂̐V���L�� / p173�`191
�ً}�� �r�_�J��Ղ̓����o�y���߂����� �퐶�����̌���������--���E���E���o�y��
�@�@���r�_�J��� / �ߓ����� / p192�`194
�ً}�� �r�_�J��Ղ̓����o�y���߂����� �r�_�J��Փ�Z��
�@�@���u�Ȃ��v / �����O ; �����F ; �r���� / p195�`203
�����_�Õ��Ƃ��̎���(��) / �͏�M�F / p204�`219
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p220�`253 |
�P�P���A���蒨�i���u�w�� (�ʍ� 551) p.p30�`46�v�Ɂu�F�N�ՈȑO-��-�v�\����B�@pid/3373564
���A���̔N�A��R�t��, �n�������� �u��앶�� : �Ɨt���ѕ����̓W�J�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B�@ (�����V��)�@pid/11991131
���A���̔N�A��{�����Ñ㕶�w��ҁu�Ñ㕶�w (�ʍ� 25) p.p67�`76�v�Ɂu���ؐ_�_�v�\����B�@�@�d�v
���A���̔N�A�u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw = Archaeology and natural science : ���{�������Ȋw� (18) �v���u���{�������Ȋw��v���犧�s�����B pid/7957069
|
�l�Êw�ɂ�����ԕ��E���╨�ɂ���͂̊�b�I��� / �s�͎O�� / p1�`15
���@�̊�d�C�Õ��̕��u���y����ѓ������[�ۂ̔S�y�̉��͎c�����C�Ǝ��@���̊�d�̔N�㑪��ւ̉��p / ���}���� / p17�`37
�����q���ˉ����͂ɂ��b�߂���ё������n��×q�o�y�i�̕��� / �͓��B�Y ;
�㐼���i ; �ɓ��� / p39�`49 (
���ˉ����͂ɂ��Ë�J�̎Y�n���� / �͓��B�Y ; �̏���O�j / p51�`76
���{�̌Ñ��Ղɂ����钩�N�����Y�����y��̌��o(��2��) / �O�җ��� ; ���䍄 ; ������ ; �R����T / p77�`91
�ߋE�̈�ՂƊւ��ΎR�K���X�̓��� / ���c�j�N ; ���R��Y ; �Γc�u�N / p93�`110
���v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(6) / �����G�u ; ���X�؏� ; ���R�^�� / p111�`126
�����m�[�g ���V���YBeach rock�̎c�����C�ɂ��Ă̗\���I�����ƍl�Êw����ђn���Ȋw�ɑ���Ӌ`/���}����;�㕔�؎i;�ɓ�����/p127�`134 |
|
���u�l�Êw�Ǝ��R�Ȋw =���{�������Ȋw� (9�`18 �v)�܂łɌf�ڂ��ꂽ�u�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I����(1�`6 )�v�̓���\
| �m�� |
���{�������Ȋw��@�� |
���s�N |
�_���� |
���\�� |
pid |
| 1 |
(9)p15�`29 |
1976 |
����C�l�ȐA���̌]�_�̕W�{�ƒ�ʕ��͖@ |
�����G�u |
pid/7957060 |
| 2 |
(11)p9�`20 |
1978 |
�C�l(oryza)���A���ɂ�����@���זE�]�_�̂̌`�� |
�����G�u�E���X�؏� |
pid/7957062 |
| 3 |
(12)p29�`42 |
1979 |
�����E�t���(��P��)���c����ьQ�n�E�������(�퐶����)���c�ɂ�����C�l(O.sativa.L)���Y���ʂ̐��� |
�����G�u |
pid/7957063 |
| 4 |
(14)p55�`65 |
1981 |
�F�{�n���ɂ�����ꕶ�y��ٓy�Ɋ܂܂��v�����g�E�I�p�[���̌��o |
�����G�u |
pid/7957065 |
| 5 |
(17)p73�`85 |
1984 |
�v�����g�E�I�p�[�����͂ɂ�鐅�c���̒T�� |
�����G�u ; ���R�^�� |
pid/7957068 |
| 6 |
(18)p111�`126 |
1985 |
�k�v�����g�E�I�p�[�����͖@�̊�b�I�����l |
�����G�u�E���X�؏��E���R�^�� |
pid/7957069 |
|
|
| 1986 |
61 |
�E |
�P���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (46)�@���W �퐶����Õ��֍��v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947806
|
���W �퐶����Õ���
�@�Θ_ ���n���W���Ƙ`���̑嗐/�Ζ씎�M ; �s�o��C�u/p28�`46
�@���n���W���Ƃ͂Ȃɂ� / �Ζ씎�M / p2�`14
�@�Õ�����ւ̓]���ƍ��n���W�� / �s�o��C�u / p15�`27
�@�O�A�l���I�̓��Ɛ� / ����� / p47�`61
�@��B�̖퐶����Õ��� / ����M�s / p62�`68
�@�o�_�ɂ�����Õ��o�����̓��� / �O���Ȋ� / p69�`83
�@�����̌Õ�����o�����Ƃ��̑O�� / �c���V�j / p84�`94
�@�퐶����̑�a�́u�����v�̍\��--
�@�@�@�����ÁE����Ղɂ��� / ���c�O�Y / p95�`101
�@�R�A�̖퐶����I�����̓y��̗l�� / �����^�� / p102�`113
|
�@���シ��Ñ�o�_--�r�_�J��Ղ͌��/�����ӌ�/p114�`131
����̈ꌾ���_�ƗY���V�c / �ˌ��`�M / p132�`151
�Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i / p152�`161
��R�����̍Č��� / ���菺��Y / p162�`176
��і�Ɓu�����v--�u�����̓��v���l���邽�߂�/���j�N/p177�`188
鰎u�`�l�`�̉Ȋw--���̒��؎v�z��
�@�@����a�̌ꌹ / ���䎠 / p189�`201
�w�}�㍑���y�L�핶�x�Ɍ���O���M��(��)�ֈ�́u�����v��
�@�@���@���j�I�Ӌ` / �{�����l / p202�`214
���m�،Õ��̏o�y�n����߂�����--�ŋ߂̐V���L������/p215�`221
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p222�`250 |
�Q���A�����F�ꂪ�����ȕ� �u�������� = The monthly journal of Monbusho (1306) ���傤�����v�Ɂu�������Љ� ����(���ˉ��Õ��Q�o�y)�v�\����B�@pid/2227775
�S���A�Ñ�w�������� �u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (47)�@�@��a���[ 1986-04/pid/7947807
|
���W1 �ŋߘb��̈�ՁE�╨���߂�����
�@�@'85�N�l�Êw�̐��ʂƖ��_ / �X�_�� / p2�`45
�@ ��㔪�ܔN�̊؍��l�Êw�E / ��X�G�v / p46�`53
���W2 ���k�ɂ�����Õ������̖G��ƓW�J
�@ �l���I�����玵���I�܂ł̓��k�̗��j��
�@�@�@���ǂ��W�J���邩/�����x�Y/p54�`61
�@�֓��n���ɓW�J����Õ��̎��ԓI���� / ��ˏ��d / p62�`72
�@���k�쉏�ɓW�J����Õ��̎��ԂƂ��̐��i / �ɓ����O / p73�`82
�@���k�ɂ������^�Õ��̎��ԂƂ��̕ҔN�I����/���Ƙa�T/p83�`94
�@���{�C���s������ɂ�����Õ��̎��ԂƓW�J/��藘�v/p95�`104
|
�Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i / p107�`120
��蔒���_�ЂƏ����_�k / ����� / p121�`131
�n���[�a���ƓV���V�c / �r�|���� / p132�`137
�L�I�Ɗ؍�--�L�I��@���ɓǂނ� / ������ / p138�`145
�V�����Ɓw�d�������y�L�x / ���{���k / p146�`155
�w鰎u�E�`�l�`�x�����L���́w�������ǂݕ��x��
�@�@����/�ɐ��v�M/p156�`177
�V���V�c�́u�a���m�ˁv--�V���V�c��
�@�@������(����2)/��a��Y/p178�`196
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p197�`228 |
�V���A��a��Y���Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (48) p54�`92��a���[�v�Ɂu���W1 �Ñ㉤���ƍc�q���� �V���V�c�̏o��--���c�q�Ƒ�C�l�c�q�v�\����B�@�@pid/7947808
�W���A���ƍN�V�����u�C����݂��הn�䍑�v���u�����@�v���犧�s����B�@pid/12237633
�P�O���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (49) �v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947809
|
���W2 �הn�䍑�Ƙ`�l�`
�@�`�����ږ�Ă̑ѕ����g�͌i����N���O�N�� / �b�㓹�V/p146�`161
�@鰎u�`�l�`�̉Ȋw--�u��v�E�u�i�v���̊m���_�I����/���䎠/p162�`175
�@�Δn�E���n�������ɂ��w鰎u�x�`�l�`�s���L����
|
�@�@�@������/�ї��N��/p176�`193
�����R�Ɣ��R�M�ɂ���(��)
�@�@�@�������R�o�Q�L/���J�c��/p194�`207
���E�V���V�c�̏o��--���c�q�Ƒ�C�l�c�q/��a��Y/p209�`249 |
�P�Q���A���A�W�A�̌Ñ㕶�����l�����l�����ȉ�ҁu�Ñ㕶�����l���� (15)�v�����s�����B�@pid/7951399
|
�k�O�E�l���I�l �הn�䍑�̑�|�� / �k���� / p4�`13
�k�O�E�l���I�l �_���V�c������ / �Γn�O�Y / p14�`17
�k�O�E�l���I�l �R���I���n����݂��Óc�j�w�ւ̋^�� / ���q���Y / p18�`27
�k�O�E�l���I�l �R�n���������������ւ̋^�� / ���q���Y / p28�`38
�k�O�E�l���I�l ���_�V�c�ƒֈ��ˎR�Õ� / �ώ� / p39�`61
�k���E�����I�l �w�O���u�x���̑���̗�--�הn�䍑�_�������̂��߂�/�b�㓹�V/p62�`105
�k���E�����I�l �V�����ɂ����铌�A�W�A� / ���ьb�q / p106�`119
�k���E�����I�l �����ɘM�ꂽ����̗�--�����c���P�O�����̐^��/��ˑד�Y/p120�`190
�k���E�����I�l �c�@�E�c���q�Ƃ��Ɏ���--�V�����������ɏI����/��ˑד�Y/p191�`207
�k��E�ʎj�E���̑��l ���N��Ɓw�L�E�I�x�̋L�q�ɂ��
�@�@����ΔN��(��)�������ʂɂ���@�� / ���{�����Y / p208�`258
�k��E�ʎj�E���̑��l �퐶����̎O��̐_�� / �i��s��v / p259�`286
�k��E�ʎj�E���̑��l ���A�W�A�ɂ����鋤���́E�@���E
�@�@�����Ƃ��l����--���ƁE���͋@�\�̓W�J / �R������ / p287�`299 |
�k��E�ʎj�E���̑��l ���{���������̗��j(14)���W��(5)/��[�͕v/p300�`319
�k��E�ʎj�E���̑��l �ꌠ�������卑���{ / �z�R�� / p320�`370
�k��E�ʎj�E���̑��l ���S�]�N�O�̈ꖇ�̒n�}(村�鈒�)/�O���F�j/p371�`385
�f�B�X�J�b�V�������[�� �f�B�X�J�b�V�������|�[�g(��O��)
�@�@���u������_�������ɂ��āv / �R������ / p386�`387
�f�B�X�J�b�V�������[�� �������ɓ����� / ���ьb�q / p387�`388
�f�B�X�J�b�V�������[�� �z�������錴�e�� / �e�n���� / p388�`390
�f�B�X�J�b�V�������[�� �쌒������
�@�@�����ᔻ�ɂ��Ĉꌾ / ���c���ˎq / p390�`390
���l�ʐM / �K���i / p61�`61
���l�ʐM / ���ݖQ / p119�`119
�ލ� / ���P�` / p394�`394
�E
�E |
�P�Q���A�u���j�ǖ{ 31(22)[(422)]�@���W ��̗��j���u�Îj�Ó`�v�v���uKADOKAWA,���o�o��,�V�l�������Ёv���犧�s�����Bpid/7975396
|
���W ��̗��j���u�Îj�Ó`�v ���W�J���[ /
�@�@���O���r�A �Îj�Ó`--���̒m��ꂴ����� / ���V���s�� / p22�`22
�u�Îj�Ó`�v ���W�J���[ / �O���r�A ����ɐ�����Ñ㕶��--�Ìy�̎��D/�R�c����/p24�`25
�u�Îj�Ó`�v ���W�J���[ / �O���r�A �֒f�̔�{��ǂ�--��
�@�@���㋌���{�I�听�o / �����F�F / p26�`29
�u�Îj�Ó`�v �����j�_I--�Îj�Ó`�͉�����邩!?
�@�@�� ���E���ꂽ���j--�Îj�Ó`�̐������� / �����F�F / p38�`45
�u�Îj�Ó`�v �����j�_II--��̈ٓ`����T��! �u�L�I�v�ƌÑ㍋���`��--
�@�@���������̐_�b�`�����߂����� / ���c���� / p46�`53
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �|������ �_�ƉF���̑n���_�b
�@�@��--�F���n������l�ނ̒a���ɂ܂ł���Ԑ�j�����
�@�@���l�ޕ��������j / ���V���s�� / p58�`65
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ ��S���� ���u�L�I�v�_��n��--
�@�@���F�����������i�K���珑���������\���ܐ�N�̗��j�ɐ��ނ��̂� / �ዽ���F
/ p66�`73
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �{������ �x�m�Ñ㉤�����S�j--
�@�@���x�m�R�[�ɒz���ꂽ���V���������̑��݂𖾂炩�ɂ���ْ[�̏� / ���Ί�O/p74�`81
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �E�G�c�t�~ �Ñ㐢�E�̑�S�Ȏ��T--
�@�@���V����@����n�C�e�N�܂ŁB�L�������ŒԂ�ꂽ�Ñ㕶���̑S�e / �ዽ���F
/ p82�`89
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �������� ���j������������L�^--
�@�@���h�䎁�Ƃ̐����_���ɔs�ꋎ��H�c�֓��ꂽ�����Ƃɓ`���鏑/�i���F��/p92�`99
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �G�^�` �V�n�n���̈�取����--�V�Ƒ�_�͎���
�@�@���j�_������!? �z�c�}�������`����Ռ��̏��j / �{�c���юq / p100�`107
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ �������O�O�S�� �Ñ�Ìy�����ւ̒�����--
�@�@���Ñ�Ìy�����̑��݂Ɛ��������j���B
�@�@�����̋��قɖ������^���Ƃ� / �u�Γc�i�� / p108�`115
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�Ɓu�L�I�v�̈Ⴂ��₤ ���̑��̌Îj�Ó` / �����F�F / p116�`121
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� �e�����ꂽ���j�� / ���c���� / p124�`131
�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� �O�ꕪ��!�Îj�Ó` / �ђ��� / p132�`145
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� ���݂����_�㕶�� / �ؑ��M�s / p146�`153
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� ���̃E�K���t�L�A�G�Y�� / �����f
/ p156�`161
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� ���N��
�@�@���u�Îj�Ó`�v�Ɛ_���V�c / �����f / p162�`169
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�𑽊p�I�Ɍ������� ���{����_�����c�_�̔閧/���V�F�/p170�`177
�u�Îj�Ó`�v �Ñ㍋���Ìn���֗� / �ҏW�� / p180�`181
�u�Îj�Ó`�v �Îj�Ó`�ɑ���^�` / �ҏW�� / p182�`185
�u�Îj�Ó`�v �����W�G�b�Z�C ���s���E�̗��j�w / �r���`�Y / p54�`55
�u�Îj�Ó`�v �����W�G�b�Z�C ���ĂΊ��R / �L�c�L�P / p90�`91
�u�Îj�Ó`�v �����W�G�b�Z�C �����̉e / �������� / p122�`123 |
�u�Îj�Ó`�v �����W�G�b�Z�C �Îj�Ó`�̃��A���e�B / ���Õ��F / p154�`155
�u�Îj�Ó`�v �����W�G�b�Z�C �u�����v�̂�����L�� / �R�c���I / p178�`179
�u�Îj�Ó`�v �����j�_--���j�͐�Ɂu�������v��!? �w�Î��L�x�w���{���I�x
�@�@���ւ̋^��--�Îj�Ó`�̑ɂɂ��鐳�j�u�L�I�v�B���̐�������
�@�@���M�����邩? / ������ / p186�`195
�u�Îj�Ó`�v �������W--�Ñ�j�̈ł̎R���������! �Ñ�̖���������R--
�@�@�����̉���������p�ȂǁA�Ñ��a����ƑΛ�������̎R���T��! /
�@�@����c���� ; �v�ۓc�W�O / p260�`277
�J���[ / �O���r�A ���E�̌Ñ��� �A���R�[���E���b�g
�@�@��(�J���{�W�A) /�^���{/p20�`20
�J���[ / �O���r�A �ӏ܁E�\���낢�� ���B�����Z �P�t��,
�@�@�����a�b�ДN �O��/p213�`213
�J���[ / �O���r�A ����@�̗� �ɑ����L�O���̊� / ���{���s / p214�`215
�J���[ / �O���r�A ���j�����ق߂��� �ΐ��؋L�O��(��茧) / p216�`218
�J���[ / �O���r�A �j�ւ�K�˂� �ޗnj����g�� / p219�`226
�J���[ / �O���r�A ��ǃA���O�� ��C�푈�ɎU�������Ց��m�����
�@�@���u��ÔˍZ���V�فv���� / p30�`31
�J���[ / �O���r�A ��ǃA���O�� ���{�ŌÂ̑O����~����? ���������s�s��
�@�@���ÌÐ��|��Ղ��甭�@ / p32�`33
�J���[ / �O���r�A ��ǃA���O�� �֓���k�Ђ���T���t�����V�X�R��
�@�@���V��,�����Ŕ��� / p34�`35
�u�Îj�Ó`�v �D�]�A�� �告�o�]���L((12)) / ������� / p200�`203
�u�Îj�Ó`�v �D�]�A�� ���ɂ܂锎���j((11)) / ���g�B�Y / p240�`243
�u�Îj�Ó`�v ����l�؎��T / ��_�j�� / p207�`210
�u�Îj�Ó`�v �]�ˌÒn�}�U�� / ��c�L�� / p228�`229
�u�Îj�Ó`�v �������Ђ������̒��l�������j / p197�`197
���ނ��� / ���Ւ� / p204�`205
�u�Îj�Ó`�v �����z���Y�̃h�N�k�� / ���Ȃ��悤���낤 / p206�`206
�u�Îj�Ó`�v �i���n���I�̂�] / p211�`211
�u�Îj�Ó`�v �W���[�i�� �����̓��{�j / ��X�a�� / p244�`245
�u�Îj�Ó`�v �W���[�i�� �����̐��E�j / ���q�j�N / p246�`247
�u�Îj�Ó`�v �W���[�i�� �V��Ճ��|�[�g / �����O�Y / p248�`249
�u�Îj�Ó`�v �W���[�i�� ���j���w�̉� / �Έ�y�m�� / p250�`251
�u�Îj�Ó`�v �ǎҏ��Ґ�--�Ì�O�I���̒n�͎]����!? /���萳/p256�`258
�u�Îj�Ó`�v [�j�ւ�K�˂�]�ޗnj����g��--�X�Ɛ��̉����ɌJ��L����ꂽ
�@�@����쒩�̐��j�������� / ���g�� / p230�`239
(��)
�E |
�P�Q���A �ߒJ�q�Y���u�u���v�̐��E�v���u�V���Ёv���犧�s����B�@ (�V���I��)
|
| 1987 |
62 |
�E |
�P���A���A�W�A�̌Ñ㕶��. (50)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947810
|
�r�_�J�_���Ղ̎��� / ��c���� / p2�`8
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v�Ǝ��̎j�� / �]��g�v / p9�`12
�c���Ԏ�ƕ����h�I / ��ё��� / p13�`20
��B�̓�����肻�̌�--��������
�@�@�@�����^�y���i / ���c�x�m�Y / p21�`29
�剻�u���V�v�ق́u�E���v�ɂ��� / ��e���� / p30�`37
���Z�N��㔼�ɂȂ��� / ���B�� / p38�`52
�Ԗ����̑ΐV������ / ����d�� / p53�`59
�C���_�b�̒a�� / �J�쌒�� / p60�`68
���̓� / �c������ / p69�`82
�W�H�p��~�m�̎����߂����� / ���؍F���Y / p83�`87
�L�I�̗��j�I�`���Ƃ��̌����@ / ���O�� / p88�`93
�Ñ�̍q�C--�V�_�{�I�̈�l�@ / ��O�� / p94�`104
�������Տo�y�a���Ԃ́u�r�v�ɂ���/����S/p105�`117
�Ñ�����؎O�� / �Ζ씎�M / p118�`119
���m�،Õ��Ί��O�o�y���̈Ӗ� / ��{�p�� / p119�`121
���E���E�ʂƁu�O��̐_��v / ����� / p121�`123
���ь����̌������m�،Õ� / ��c�G�� / p123�`125
�u�ϐΒˁv�Õ������ւ̏�O / ��ˏ��d / p125�`127
�H���R--�O����~���̑c�^ / ���{���� / p127�`129
�Ă̏������� / ����˗Lj� / p129�`132
�]�c�D�R���f�z / �I�m�� / p132�`134
�S�핶���̍Č��� / �E�c���Y / p134�`135
�G�N�A�h���ɂ͓n��Ȃ��������y��/������/p136�`138
�@���������Ƃ̏o���� / �����^�� / p138�`140
�n��̘_�� / ���菺��Y / p141�`142
�䒌�ɓꕶ���E��T�� / �������� / p143�`144
�u���P�R�v��ǂ��� / ���ژa�� / p144�`146
�ΐ�ɂ��� / ���J�� / p146�`148
�o�_�ƒ}�� / �����ۍF / p148�`149
�o�_�����o�y�w���� / ������� / p150�`151
���m�،Õ����@�Ɨ��̔��� / �x�c�[�� / p151�`152
�Ί��̐��� / �ԕǒ��F / p153�`154
�Ƒh�햁��� �����ČՓ��� / ���쐳�D / p154�`156
�؍��̗����� / �Ζ؉딎 / p156�`158
�����l�Êw�Ɗw�ی��� / �ݓВj / p158�`159
���̘@�r�Ɛ��̗V�� / �X�_�� / p159�`161
�������ِ̊Ո�\--���E�����s�̈�Ղ� |
�@�@�@���֘A���� / ����ǎO / p161�`163
���A�W�A�̊��l�Êw�ƋZ�p����/���c�쌛/p163�`164
�˕�̐��D / �a�c�� / p165�`167
�o�_��_�̐_�� / ���C�Y / p168�`170
�\�ܔN�ڂ̍����� / �㌴�a / p170�`171
���������ԌS�ɂ�����~���P�ƃI�z���P/��R����/p171�`173
�u�`�v�ɂ��čl�������� / �앛���� / p173�`175
�V���̑��ԍs�{���c�Ӑ} / �ˌ��� / p175�`177
�ܐ��I�j�Č����ւ̑z�� / �F�q�_�� ; ���j�N / p177�`178
�ߐ{������̍L������ / �����L�� / p179�`180
�ڈ̗D�k�� / ���o���o / p180�`182
�h��ڈE�����̖��̗R�� / �ˌ��`�M / p182�`184
���{���ƋN���_�̍Č��� / �F�c�g�V�� / p184�`186
�n���g�̃n������ / �������� / p186�`188
�o�H�̑�̌��z / �V�쒼�g / p188�`189
����i�M�����̍L�J�y���蕶�ɂ���/����Ǎ�/p190�`191
�_�������ƒ����F / �{�ʓc�e�m / p191�`193
�����ƓV���~�Ր_�b�Ɛ_�������`��/�O�V������/p193�`195
�V�c�̃t�H�[�N���A / �{�c�o / p195�`197
�}���j�v / �R�c�@�r / p197�`198
���ɂ����镐��̕��^�ɂ��čĘ_/���c����/p198�`200
�Ñ�j�ɂ�����K���X�̖�� / �R����Y / p200�`203
�u�ޗNJw�v�G�L �O�̓��� / �R�� / p204�`205
�u�\�O�ˁv�V�l / �r�c���� / p205�`208
���ƌÑ�y���V�A / �ɓ��`�� / p208�`210
�������R���� / �ɓ��� / p210�`211
�u�k���C�l���V��v�l / ��J���j / p211�`213
�J�~�ƃz�g�P / ������O / p213�`215
�Y���I�̖��ڌÌ�i�q�g���n�o�j/���^��/p215�`217
�`�Ƙ`�I���E�̖͍� / �������� / p217�`219
�����������Ñ�j�Ɠ��� / �����O / p219�`221
�u���h�ËL�v�Ɓu�_�O�Ó`�v / �c������ / p221�`223
���N�����Ɣ�Ḏɓߕ� / ������ / p223�`224
�`���̖Ô� / ���z���O�Y / p225�`226
���x�ߊC��n�铹 / �i���v�b / p226�`228
�������ȂЂ� / �����i / p228�`229
�u�L�I�Ώƕ\�v�P�� / ���쏇�y / p229�`231
��앶���̒S����͔�E����n��/�����G�O�Y/p231�`233
|
�������Óߐ_�̐_�b�ɂ���/����m�[/p233�`235
�Ñ�̓S�Ɛ_�X / �^�|�풉 / p235�`237
������ƍ������ / ���J�c�� / p237�`238
�헤�Ɓk�J�K�C�l / �O�J�Ĉ� / p239�`240
�L�E�̎��w�̕��� / �R��ɓ��� / p240�`241
�o�_�����y�L�́u����Ȃсv��
�@�@���S�Ɓu���Ɂv / �R�{�� / p242�`244
�ǒn�}�L�� / ���d�C / p244�`246
���m�V�c�̖��̒��̃T�z�r�� /
�@�@�@���g�c�֕F / p246�`248
�}�Ǝ� / �g��T�q / p248�`250
�N�z�͓̉� / ����ܗY / p250�`252
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v��
�@�@�������I�Ӌ` / ���G�Y / p254�`255
�u�Ñ�v�ւ̊m���Ȏ��_ / ������ / p255�`257
�R�n�������Ƃ̍ŏ��̋@��/���쐳�j/p257�`258
��̒� / ���쒉�k�q���l / p258�`260
���A�W�A�̌Ñ㕶����
�@�@�@���S����/�͏�M�F/p260�`262
�_���������ɂ�������
�@�@���S�����Ă��邱�� / ���ќ��q / p262�`263
���B�̗� / �����Y / p263�`265
�O���l�̌Ñ�j�����ɂ悹��/��ؖ���/p265�`267
�p���ւ� / ������ / p267�`268
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v
�@�@���n�������̂��� / �L�c�L�P / p268�`270
���a�̓��{�j�w�E�̌��� / �p���m / p270�`270
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v�Ǝ� / ������ / p271�`272
�p���͗͂Ȃ� / ���{���T / p272�`273
�����I���ɂ��Ă̋^��Ɓw���{���I�x--�V���V�c��
�@�@���o���Ɋ֘A����/��a��Y/p274�`294�@�d�v
�Ί����^�� / ���؋��� / p295�`305
12�N�ԕ\����S������/�ˈ䏹��/p306�`307
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p308�`337
�����ܘb�g�Ñ�j�ʐM�h /����m�q/ p338�`338
�G������A�W�A�̌Ñ㕶������ڎ� / p339�`359
�ҏW��L / ��a��Y / p360�`360
�E |
�Q���A���z���O�Y,��эO�q���u�Ɖ����������Ñ���{�v���u�V�l�������Ёv���犧�s����B
|
���e�����^��a�̍����c��ˌÕ��o�y�̂�����u�Ɖ������v�ɂ́A�S���̌���?�����E���a�E���q�E�a��?���}������Ă���B���̐���N��͂��悻�S���I�O���Ɛ��肳��A�܂��ɓ����̍����i���鉤���j�̏Z���̋�̓I�ȍ\�}�ƍl������B�܂��A���̍����������́A�������铌��A�W�A�̎R�x���������̉Ɖ��Ƃ̗މ����������B����͉����Ӗ����邩�H�{���́A�Ñ�j�w�҂ƌ��z�ƂƂ̋����ɂ��A��������A���{�l�̃��[�c�ƌÑ㍋���̐���������T�낤�Ƃ�����̂ł���B |
|
�����@�퐶�l�͍����������ɏZ�^5
��P�́@�Ɖ��������߂����ā^13
���� �Ɖ������̔w�i�^23
���� �Ɖ������̓��e���́^44 |
��O�� �ړx�Ƃ��Ă̐l�̐��@�^
��Q�́@�Ɖ������̕����^61
���� �����̍\���ƍ\���^61
���� ���a�̍\���ƍ\���^110 |
��O�� ���q�̍\���ƍ\���^138
��l�� �a�ɂ̍\���ƍ\���^148
��R�́@�Ɖ������͒N�̂��߂ɂ��������^157
�E |
�R���A�u�T�Ԓ����S�����{�̗��j�S�V�i�ʊ��T�V�T�j�u�Ñ�R�@��ƔN���E�x�ʍt�v�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B
�R���A�����]����q���_�����������ҁu��q�R�_�W (�ʍ� 21)�@p.p127�`141�v�Ɂu�_�{�F�N�ՊT�ρv�\����B
�R���A�u�C���j���� : Journal of the Japan Society for Nautical Research (44)�v���u���{�C���j�w��v���犧�s�����Bpid/2642120
|
�u�����{�I�v�V������8��10��������ɂ��� / ���R�G / p1�`13
����˂ɂ����鋛�̗��ʂƓ���--�����K�����̎���/������/p14�`37
�e�n���a�R�I�s--�I�Y�E�{�ÁE���˂�3�` / ��g�����Y / p38�`45
�ߌ~�ƁE�W���������Y / ����N�� / p46�`51
����A�W�A�̖ؑD�Ɋւ��鎑��-1- / ���c�[�v�` / p52�`70
���i19�N,�z�O���O���V�ۉY�|�����E�q��D�u��` |
�@�@�@��(�j���Љ�) / ���c�F�Y / p71�`76
����8�N,����ˉ��Ĉɗ\�������D�Y��`
�@�@�@��(�j���Љ�) / ����r�K / p77�`80
�V���Љ� / ���씎 ; �Έ䌪�� / p81�`83
�C���j�����ژ^ / �R�c�N�� ; ���씎 ; �ёv / p84�`94
��L�� / / p95�`97 |
�S���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (51)���W �i���l�N�̋����߂������v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947811
|
���W �i���l�N�̋����߂�����
�@ ��㔪�Z�N�l�Êw�̐��ʂƖ��_--�i���l�N��
�@�@�@�������߂����� / �X�_�� / p2�`34
�@�u�i���l�N�v�͑��݂�����--���Y���̗L�͎���/���쐳�j/p35�`37
�@�s���R�ȉˋ�N��--鰏�������� / ���J���� / p38�`41
�@�N�����g���̌i���l�N�h���߂�����--���U�̊����������
�@�@�@�����]�̈���� / �⌳�`�� / p42�`43
�@ �u�i���l�N�v���̍s�� / ���{���� / p44�`49
�@�s���ƍl�Êw--�i���l�N�����̕���v������/������/p50�`58
�@�i���l�N�̋����߂����� / �Ñ�j�ʐM���ʔ� / p59�`75
���z ��渂̔� / ���i�ވ� / p76�`78
���z �g���ؐ��q�h�Ɓg���̍��h / �����G�O�Y / p79�`81 |
���z ���W���ٕ� / �O�Y�����q / p82�`84
���z ���������Ƒ�F�c�q / �������q�q / p85�`88
�����L�J�y������̖n���� / �����L�� / p89�`106
���m�،Õ��̈Ƌ���--���̎v�z����T��/��������/p107�`141
�]���A�X�^�[���̓n��--�V���V�c�҉̓���
�@�@����ǂ��� / �ɓ��`�� / p142�`161
�V���V�c�҉́u�R�����v���� / �ؑ���b�q / p162�`180
��C�l�c�q�Ɗ��c�q�̉�H--�V���V�c��
�@�@���o�����߂����� / ��a��Y / p181�`218
�u鰎u�`�l�`�̉Ȋw�v�ւ̋^��--�I�O��̊m���_/�]����/p219�`222
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p223�`236
�E
|
�U���A�����G�u�����s��w����A�W�A�n�挤���������ҁu����A�W�A���� = Japanese journal of Southeast Asian studies 25(1) p.p140�`150�v�Ɂu�v�����g�E�I�p�[�����͂ɂ��퐶���㐅�c��\�̌���--�Ƃ��ɒ���E�ڋv����Ղ���ѐX�E������Ղ̐��c��\�ɂ���
(�n������������ ���L�O��--�M�уA�W�A�̈�ƈ��) �v�\����B�@
|
(�n�����������ފ��L�O��--�M�уA�W�A�̈�ƈ��)�@
�f�ڎ� ����A�W�A���� = Japanese journal of Southeast Asian studies �@���s��w����A�W�A�n�挤�������� �� 25(1)
| �m�� |
�_�����ƌf�ڕ� |
���Җ� |
�iIRDB�j�� |
| 1 |
p.p3�`169,�@�n�����������ފ��L�O�ё�����1�� |
�E |
�E |
| 2 |
����A�W�A���� = Japanese journal of Southeast Asian studies�@25(1) p.p3�`160 |
�E |
�E |
| 3 |
�M�уA�W�A�̖쐶��̕��z�Ƃ��̓����@ p.3-27 |
�ЎR���v |
�iIRDB�j |
| 4 |
�A�W�A�͔|��̐��Ԍ^�Ɛ��ԓI�����@ p.28-38�@�@ |
�������l |
�iIRDB�j |
| 5 |
�A�W�A�̗���,���̕��z�Ɠ����ƌn���@ p.39-50�@ |
�p�c�d�O�Y |
�iIRDB�j |
| 6 |
����A�W�A�̕���Ƃ��̐��ԁ@�@ p.51-61 |
��V�㏀ |
�iIRDB�j |
| 7 |
A Model for Evaluating Climatic Productivity and Water Balance of
�@�@��Irrigated Rice and Its Application to Southeast Asia �@ p.p62�`74 |
�x�] ���@ |
CiNii Articles |
| 8 |
���k�^�C�E�h���f�[�����ɂ�����V���c���̎��� �@p.75-84�@ |
���c�r�Y�E�{��C�� |
�iIRDB�j |
| 9 |
�_���, �G��, �� : ���W�����E�v���A���K�����n�ɂ����锨�n�k����߂���
�@�@�@���G�ߐ��Ɣ_��Ƃ̃^�C�~���O�@ p.85-108�@ |
�\�����F |
�iIRDB�j |
| 10 |
�C���h�l�V�A,�����|���B�̐����Ɨ����@ p.109-124�@ |
�L������ |
�iIRDB�j |
| 11 |
�x���K���E�f���^��n���̈�� : �o���O���f�V�������n���ɂ�����A�E�X�E
�@�@�@���U�d�A�}���̍��d�͔|�ƃp�[�{�C���h�ĂɊւ���m�[�g �@ p.125-139 |
�����a�Y |
�iIRDB�j |
| 12 |
�v�����g�E�I�p�[�����͂ɂ��퐶���㐅�c��\�̌���--�Ƃ��ɒ���E
�@�@���ڋv����Ղ���ѐX�E������Ղ̐��c��\�ɂ��ā@�@p.p140�`150�@ |
�����G�u |
�iIRDB�j |
| 13 |
Rice in Malaya--A Study in Historical Geography/by R.D.Hill(1975)--
�@�@�@���}���[�����ɂ�������̓W�J�Ƃ��̒n�搫�@p.p151�`160 |
������� |
�E |
| 14 |
�n���������������Ɛіژ^�E�����@/ p.p161�`169 |
�E |
�E |
|
�V���A��t��F���u������v�������Ă���v���u���E���E�珑�[�v���犧�s����B
(�₳�����Ȋw, )
|
�Ⴊ�����̂Ȃ��H
�I�X�̂����͉��H
�����ɂ�����������Ă݂悤
����炪�ł���̂͒��Ɨ[�� |
��̂P��
�������̂P��
�l�Y�~�̎��v
��̎��v |
�g���������h�Ɓg���傤�ǁh
��̎��v�͂ǂ��ɂ��邩�k�ق��l
�E
�E |
�V���A��a��Y���Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (52) p197�`223�@��a���[�v�Ɂu�_���`���Ɛp�\�̗��̎���--�V���V�c�̏o���Ɗ֘A���āv�\����B�@�@pid/7947812
�P�O���R�O���A�Ԗx�����u���{��j�w�G�� 33(4)�@���{��j�w��v�Ɂu�����Ȋw�j���ۉ�c�E1987���s�V���|�W�E���v���Љ��B
�P�O���R�P���`�P�P���T���A�������s���ۘ��قɉ����āu�����ț{�j���ۘ��c:1987���s�V���|�W�E���v���J�����B
�@�@
�@������A�V���|�W�E���ɎQ�������{���A�����A���R�A����A�g�c�A���A���J��A�Ð�A��o�A���A�{���i�B�e�F�{���j�@�u���{�̓V���w�̕S�N�@
p156�v���]��
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶��. (53)�v���u��a���[�v���犧�s�����Bpid/7947813
|
���W �w鰎u�x�`�l�`�̐��E
�@�w鰎u�x�`�l�`���߂����� / ����S / p2�`25
�@����I�v�l�@����݂� �w鰎u�x�`�l�`�̍s��/���i�͐�/p26�`50
�@��G�̒n�}�ƒ���
�@�@�@�����Γ`--�R���n�����_���l����/�O���F�j /p51�`79
�@�Z���̗R��--����͊Ƙ`�Ɏc���Ă���/���ƍN�V��/p80�`97
�@���{���핶���̊��(��)--鰎u�`�l�`��
�@�@�@�����E / �F�c�쐳�� / p98�`114
�@�u�הn�㍑�v�E�u�הn�i���v���čl / ���䎠/p115�`122
���z ��s�̎הn�䍑�Nj� / �ݓВj / p123�`125
���z �V���j�̔ڜ\�� / �㓡���Y / p126�`128 |
���z �����Ɩ��� / ���Ί� / p129�`131
���z �쐫���̎v���o / �L�c�L�P / p132�`134
�Õ�����O�E�����̐�����ɂ���--���ɓޗǖ~�n����
�@�@����^�Õ��̈ړ��Ɋ֘A���� / ���r�Ǖ� / p135�`145
�Z���I�k�����g���̉���--�u�����v�u�ʓT�v��
�@�@���^�e�y�ʂ��� / ������Y / p146�`151
���ÓV�c�O�N�̒������ɂ��� / ��ь��i / p152�`157
�}��쐅�n�̕lj�Õ��̔푒�҂ɂ���/�ۓc���q/p158�`198
�`�{�l���C�̈��R��̉̂��߂�����--�V���V�c��
�@�@���o���Ɋ֘A���� / ��a��Y / p199�`213
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p214�`238 |
�P�Q���A���A�W�A�̌Ñ㕶�����l�����l�����ȉ�ҁu�Ñ㕶�����l���� (17)�v�����s�����B�@pid/7951401
|
�]��g�v��ɋނ�ł����\�グ�܂� / ���A�W�A�̌Ñ㕶����
�@�@���l����� ; ���l�����ȉ� / p2�`3
�k���ʊ�e�l �ΞˎR�����Ɍ������Z�_�k������
�@�@�@���V�q�R�n����--�Ñ���{�R�n�������Ɛ����ߒ��̔�r����
�@�@�@�������̏Љ� / �]��g�v / p6�`24
�����u���I�v�l / ���菺��Y / p43�`44
����l�V���|�� �}�N���j�̎���--��Z�N�w��� / �R������ / p45�`67
����j�̒��ɐ����鎄�̌Ñ�j�ςƕ��@�_ / �����j / p68�`73
�w�O���u�x�u鰏����Γ`�v�́u���v�ɂ���--�u�]�v�u���v�̓ǖ@/����ǕF/p74�`89
�w鰎u�`�l�`�x�͐������ǂ܂�Ă���̂�
�@�@�@��(1)�l���̕\���ɂ���/���R�חY/p90�`100
�`����m����̓��ɂ��铹���I���� / �b�㓹�V / p101�`135
�w鰎u�x�̔㏼�V���ɂ���--�����u鰏��v�T�������l����
�@�@��(1) / �O���F�j/p136�`158
���i����̏���聄 �i���l�N��@�̉�(1) / ���{�����Y / p159�`179
���i����̏����(��)���i���l�N��@�̉�(��) / ���{�����Y / p180�`187
���`���j�����E�O���I�̘`�� 鰎u�`�l�`��d�\���_/���c�Èˎq/p188�`203
�O�E�l���I�̘`���Ɠ��� / �t�� / p204�`216
�הn�䍑�_���Ǝ��̌Ñ�j�� / ���q���Y / p217�`219
�_���c�@�Ƒ����� / �ώ� / p222�`247
�u���_�V�c�n�����v��_--���{�����Y���ɓ����� / �ώ� / p248�`252
���l���b / �Γn�O�Y / p255�`259
�Đ� �w�@���x�J�c��\�N�̘`�� / �K���B / p260�`266 |
���ʕ��V�l / �勴�P�� / p267�`285
�ŋ߂̃x�g�i���l�Êw / �_�J�^��Y / p286�`292
�u�����v�ɂ���(1) / �i��s��v / p293�`308
�}�g�R���J�Ɛp�����`�� / �k������ / p309�`313
��e �����̐��_ / �������푾�Y / p314�`315
�ΎM���z / �������q / p316�`320
���� �w�I�ɍ����y�L�x���z / �R���i�q / p321�`335
���� �����̌Ñ�j(��4��)���剻�̓�/���ژa��/p336�`346
���{���������̗��j(16)�y�n�W��(2�j/��[�͕v/p347�`368
�]��g�v��P���L�O�_�����W�E���l�����ȉ�n��
�@�@���\���N�L�O���Ɋ� / p369�`398
�]��g�v���̎P���ɂ悹�� / �i��s��v / p369�`370
���Z�ȁA���Z�ȍ]�� / ���c�Èˎq / p370�`371
���N�l��̎v���o / �R���i�q / p372�`372
���l���̉�ƍ]�c����̑z���o / ���c�Èˎq / p372�`374
�\���N���}���đz������ / ���~�� / p374�`375
���l���\���N���L�O���� / �x�]���} / p375�`376
�����Ȃ����l�Ƃ��ĉ�̂��߂�ᶗ͂��ĉ�������
�@�@�����㒱�q����Ɋ��� / ���c�Èˎq / p376�`377
�n�������_�̏Љ� / �R������ / p377�`391
���[����ɕ�����u�V�������̋��S�v/��ˑד�Y/p391�`394
(��)
�E |
�P�Q���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� �ʍ��Ñ�j�K�g�@�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947814
|
��`�l���I�̓��{ / ������ / p2�`13
�הn�䍑�ȑO �w�R�C�o�x�Ɓw�_�t�x / �����q�Y / p14�`16
�הn�䍑�ȑO ���� / ��J���j / p17�`21
�הn�䍑�ȑO �`�l�A / ���썂�s / p22�`24
�הn�䍑�ȑO �����I�N�̓�������̑z�� / �����萶 / p25�`28
�w鰎u�`�l�`�x���߂����
�@ �w鰗��x�Ɓu�`�l�`�v/���ёו�/p29�`31
�@ �w�䗗鰎u�x�Ǝ����n��/�O�ؑ��Y/p32�`34
�@�w�הn�ꍑ�x�ɂ���/�Óc���F/p35�`39
�l�Êw���猩���הn�䍑 ���n���W��/���쒉���k�����Ђ�l/p40�`46
�l�Êw���猩���הn�䍑 ���`���a�� / �R�ݗǓ� / p47�`51
�l�Êw���猩���הn�䍑 �O�p���_�b�� / ���{���� / p52�`55
�l�Êw���猩���הn�䍑 �r�_�J�̐���Q/��������/p56�`59
�l�Êw���猩���הn�䍑 ���� / �쌫 / p60�`63
�l�Êw���猩���הn�䍑 �����E�����̒��^/���c�x�m�Y/p64�`67
�l�Êw���猩���הn�䍑 �ʂƎהn�䍑 / �������� / p68�`71
�הn�䍑�ƑΊO�W �����������Ǝהn�䍑/�����萶/p72�`75
�הn�䍑�ƑΊO�W �i�n���Ǝהn�䍑 / ���c�p�O / p76�`78
�הn�䍑�ƑΊO�W �e鰘`���̏̍� / ����� / p79�`80
�הn�䍑�ƑΊO�W ��`�l���I�̒��N / �c���r�� / p81�`83
�הn�䍑�ƑΊO�W ���N�����̋��S�ƏK��/�������i/p84�`87
�הn�䍑�ƑΊO�W �w�O���j�L�x�Ǝהn�䍑/��؉p�v/p88�`90
�הn�䍑�̎��R�ƕ���
�@�הn�䍑�̎��R��/���c�쌛/p91�`93
�@�`�l�̕��� / ��ё��� / p94�`96 |
�@�Ñ�̍q�C�p / �ݓВj / p97�`100
�@���� / ������j / p101�`103
�@�הn�䍑�̈ߕ��ɂ���/���c���m�q/p104�`106
�@�O���I�̐_�_���J / �앛���� / p107�`112
�@�הn�䍑�Ɠ��� / �d�����v / p113�`115
�@�Ñ�̎�Ǝהn�䍑 / �s�ьM / p116�`118
�@��l�Ɖ��� / ������� / p119�`120
�הn�䍑����̋E���Ƃ��̎���
�@��a�E�͓��̈��/�Ε����u/p121�`132
�הn�䍑����̋E���Ƃ��̎���
�@�הn�䍑����̋ߍ]/�ێR����/p133�`140
�@�g���̈�� / �ԕǒ��F / p141�`144
�הn�䍑����̋�B
�@�הn�䍑����̒}�� / ���c�N�Y / p145�`148
�@���m�� / �T��P��Y / p149�`153
�@��`�l���I�̑Δn / �i���v�b / p154�`157
�הn�䍑�Ȍ� �u��z���Ə������v / ����S / p158�`162
�הn�䍑�Ȍ� �הn�䍑�̓��J / ���{���T / p163�`165
�הn�䍑�Ȍ� �R�n���������������ƍl�Êw/���쐳�j/p166�`169
���� / ������ / p170�`172
������� / ������ / p173�`175
�p�ꎫ�T/�r�m����;�������Y;�����C; �����a; ����ǎj/p176�`210
��Ւn�} / p211�`215
�N�\ / p216�`217
�E |
�P�Q���A���䌧���������j�҂���ە��u���䌧�j���� ��5���v�����s�����B�@�@�iIRDB�j
|
�����̊C���ዷ�̉Y�X / �Ԗ�P�F
����E���u�����̌`���ߒ��Ƒ��H�S�� / ���菺��Y
�z�O�{���̎�{���x���Ƃ��̍��o�������ɂ��� / �֓��Ñ� |
���䌧���L�͒n����s�̐����ߒ� / �ē������Y
�ÊG�}�����ዷ�̉Y�X / ���c�F�Y
�E |
|
| 1988 |
63 |
�E |
�P���A �����x���q���u���Z�~ : ���w�Z�~�i�[. 27(1)(314)�@ p32�`34�v�Ɂu�����Ȋw�j���ۉ�c1987���s�V���|�W�E���ɎQ�����āv�\����B�@pid/2383645
�P���A�ΐ�h�����u�����Ȋw 26(1) p.p65�`69�v�Ɂu����̑I���̐��� (�q���g--�����̕⏕��<���W>)�v�\����B�@pid/3213211
�P���A �c�w�ّ�w���u�c�w�ّ�w�I�v (26)�v���u�c�w�ّ�w�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1764576
|
�L�I�̉̊_�̉̂̉��� / ���{�ꖯ / p1
������--�|�C���ς��鑾�q�ƈ�x�̐��_-��- / �������T / p15
����P���̊J���Ɠy�n���p / ���{���� / p43 |
���R�����_���������y�ь����Ɛ� / p229�`236
�q�����r
�E |
�Q���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (54)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947815
|
���W �������q�̎��� �������q�ƕ��� / �c������ / p2�`14
���W �������q�̎��� �������q�̏�{�̏��ݒn���߂�����/�㌴�a/p15�`27
���W �������q�̎��� �ޗnj�����s��V�{��Ղ̎��Ӌ`/�����^��/p28�`33
���W �������q�̎��� �������q�̕��i--��{�Ə����c�{/��c��/p34�`43
���W �������q�̎��� �������q���߂����� / ����d�� / p44�`63
���W �������q�̎��� �������q�̍��j�Ҏ[�̗��j�I�Ӌ`/�c���k�l/p64�`73
���W �������q�̎��� �������q�쐻�̗��j�� / ������ / p74�`82
���z ��r�����j�̕K�v�� / ���G�Y / p83�`85
���z �k�ӏo�y�̎������O�݊��� / �V�쒼�g / p86�`88
���z�@�k�^�C�l���̗x�� / �����i / p89�`91
���z �A�z�܍s�̗��A�� / �g��T�q / p92�`95
�@�����`���̍��ؖ����߂����� / �ɓ��`�� / p96�`105
�{�^�y��ɂ���--���̗� / �J�쌒�� / p106�`112 |
���{���핶���̊��(��)鰎u�`�l�`��
�@�@�����E/�F�c�쐳��/p113�`123
���R�����l���� / �v��Y��Y / p124�`142
�퐶���㖖����Õ����㏉���ɂ�����
�@�@�@���g���n�y��̓���/���c��/p143�`154
���{�C��n��C��̓�(��)�݊C�g��
�@�@�@���C���j�I����/��c�Y/p155�`173
�V���̖V�������ƒ��c�� / ����L�u / p174�`186
�����̐E�\�Ɛ����ɂ��� / �H������ / p187�`197
�Ñ㓌�k�̃A�X�J�E�_�� / �c�{�� / p198�`211
鰎u�̈���̕��s�\��--�ݓВj����
�@�@�������Ɋ�/�e�n����/ p212�`219
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p220�`250
|
�S���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (55)�v���u��a���[�v���犧�s�����Bpid/7947816
|
���W ���{�_�b�ƌÑ�j ���y�L�̐_�b / ����S / p4�`16
���W ���{�_�b�ƌÑ�j ���b����
�@�@���c�_�V�������̖���/�d�����v/p17�`25
���W ���{�_�b�ƌÑ�j �c���Ԏ��
�@�@���������̍��̖̎�/�g�c�֕F/p26�`40
���W ���{�_�b�ƌÑ�j ���ʂ̐_�b / ��{�p�� / p41�`49
���W ���{�_�b�ƌÑ�j ���D���b�ƃX�T�m���m��/���䐴��/p50�`58
���W ���{�_�b�ƌÑ�j �n������݂��؍��Ɠ��{��
�@���~�Ր_�b--����I�ƃj�j�M�m�~�R�g�𒆐S�ɂ���/������/p59�`67
���z �_�b�����E�ЂƂ̉ۑ� / ��c���� / p68�`71
|
���z �čl�@�������_�b--���c�̍����߂����� / �����ۍF/p72�`75
���z �u�ْ[�̏��v�ɂ��� / �c������ / p76�`77
�u�n���҂̑��v�͂Ȃ���--�Ñ���{�̐l�����߂�����/���B��/p78�`92
���{�����̃��[�c�ƐH���� / �������V/ p93�`109
�V���M�Ƒ��z��(��) / �x���� / p110�`121
�܂ڂ낵�̟݊C(��) / ���J�c�� / p122�`135
��߁E�{�V���߂Ɠ����s�䓙 / ��ˑד�Y/p136�`147
�Ώ�_�{�ƃ��j���E������--�Ñ㎁���Ɛ_��(1)/��a��Y/p148�`179
���{�C��n��C��̓�(��)�݊C�g�̊C���j�I����/��c�Y/p180�`206
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p207�`239
�E |
�T���A���o�ϗ^���u���{�Ñ�j�_�S�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@
|
�O����~���̓����w�i�_�ɂ��ā[�ږ�Ă̋S���������ւ̋^�� ���o�ϗ^��
���_�T���̊�b�I�l�@ ����J����. �V���\�l�N�O���p�\�ق̍Č��� �O�M���V��.
�G�˂̐��ɂ��Ă̈�l�@ �����떾��.
�����n���̌`���Ƃ��̐M�ߐ�-�x�͐�Ԑ_�Ћ����w�a玎��n�}�x�ɂ��� ��엲�E��.
�s�鐧�ȑO�̎s�Ɋւ����l�@ �����C�璘
�Ñ�̗�@�ɂ��ā[���{�ɂ�����{�s�̌`�� ��؎O�Y��.
�������ݒu�Ƃ��̈Ӌ` ��K�[�v��
�ˍ����߂��鏔��� �����p�d�� |
�����E���ܓƓ��V��V-�_��i�_��N�\�������̉��� ���ёו���
���鋞�̐l�����v�ƊK�w�\���̊o�� �S��������
���t�W�Ɍ��ꂽ��̋g��-���R��ԂƓs�s��� �i������
�ޗǎ���̐ΐ쒩�b��-�ΐ�N���𒆐S�� ����O�q��
���c�i�N�����@�Ɋւ����E�O�̎��p-���̖ʐϋK��𒆐S�� �r��G�K��.
��~���l ���؈�D��
�����ƒn��Љ� �N�ؒ�
�E |
�V���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (56)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947817
|
���W1 �Ñ���J�ƌÕ��̖ؐ��i �u�����v���S���Ɩؐ��i���߂�����/��ˏ��d/p2�`7
���W1 �Ñ���J�ƌÕ��̖ؐ��i �ؐ�����͇��̏��և��� / �������� / p8�`16
���W1 �Ñ���J�ƌÕ��̖ؐ��i �ؐ��̏��֍Ę_ / �������v�� / p17�`33
���W1 �Ñ���J�ƌÕ��̖ؐ��i �l���Õ��@���� / �������G / p34�`54
���W1 �Ñ���J�ƌÕ��̖ؐ��i �Βk �Ñ�̍��J�V����߂�����--�ؐ��i��
�@�@�@����ʏo�y�Ɋ֘A���� / �J�쌒�� ; ��a��Y / p55�`79
�Ñ�j�ʐM���ʔ� �l���E����Õ��̖ؐ��i���߂����� / p80�`89
���W2 �S�������́u���v�Ɖ��� �Õ��̕ϊv--�����̏ꍇ / ����� / p90�`99
���W2 �S�������́u���v�Ɖ��� �u�����v���S���ɂ��� / �u�c�x�� / p100�`103
|
���W2 �S�������́u���v�Ɖ��� �Βk �u�����v�S�������ƌÑ㓌��/����˗Lj�;
�������/p104�`137
�Ñ�j�ʐM���ʔŢ��������S�����߂����� / p138�`149
�L�I���j����̓� / �b��K�ߘY / p150�`157
�Ė��E�V�q�����L���̓���--�Ė��I���w�Ƒ��b�ӕ~�̖��ɂ��� / �X�r�� /
p158�`173
�V���M�Ƒ��z��(��) / �x���� / p174�`184 �@�@�d�v
�܂ڂ낵�̟݊C(��) / ���J�c�� / p185�`199
��_�_�ЂƎO�֎��ƃI�z��--�Ñ㎁���Ɛ_��(2) / ��a��Y / p200�`225
�ً}�� ���m�،Õ��̔푒�� / �ҏW�� / p226�`235
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p236�`266 |
�W���A�C�ے� �ďC�u�C�� (376) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B�@�@pid/3203729
|
�N�j�b�s���O�u���{�؍L�v��� / �ԒÖM�v / 4�`8
���{�̓V�� 1988�N�t(3�`5��) / �͌����Y / 9�`10
�M�т̏z�� 1988�N�t(3�`5��) / �R�c�^�� / 11�`13
�I�������G���E�j�[�j�� / ������ / 14�`17
�����̓�\�l�ߋC<1> / �k�`���l���� / 18�`20
�G���j�[�j���ƌo�ϊ��� / ���q�� / 29�`32
�쒘�V���n 20 / ���{���g / 32�`33
�C��ω��ɂ��Ă̐V��� No.5 / ���{���g / 36�`36
�ӂ������铌���̔M�і� / ���q�� / 37�`37 |
���E�̋C��l����݂���v�s�s�̋C�� / ��{�� / 3�`3
�C�ۂ̐؎�<227>�C�ێ����G�l���M�[�̐؎�(��) / ���R�v�� / 34�`34
���w�V�C�}�̘b<26> / ��Ԙa�� / 40�`41
���̐��b(11) / �؊W�q / 42�`43
�S��28�n�_�̍~���ʂ̌o�N�ω� / �����K�v / 45�`47
�k1988�N6���̋L�^�l"�Ђ܂��摜"�E���E�̓V��E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T�� /
�@�@�����쐳�� ; �O�Y�F�h ; �^�ܑ�a�� ; �܃m��M�Y ; �C�ے��n�k�ΎR��
/ 22�`28
<�O���r�A>���h�R���� / ���{�� /
�E |
�X���A�C�ے� �ďC�u�C�� (377) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B pid/3203730
|
�A�����J�������̊��� / ���B�Y / 4�`8
�u�Ђ܂��v�̃X�g���b�`�h�E���B�b�T�[�`���ɂ���/�k���R��/8�`11
���g���䕗����� / �؍F / 12�`15
�C�ېR�c��̗��j�ƍŋ߂̓��\���� / �`���j / 16�`20
�x�m�R�̉_<��> / ���R�� / 30�`31
�쒘�V���n 21 / ���{���g / 29�`29
�C��ω��ɂ��Ă̐V��� No.6 / ���{���g / 32�`33
�u�V�E�G�����āv�Ɋւ��� / �⍪�����q / 33�`33
�����̓�\�l�ߋC<2> / �k�`���l���� / 36�`39 |
���E�̋C��l����݂���v�s�s�̋C�� / �ێR�F�K / 3�`3
�C�ۂ̐؎�<228>�ΎR�̐؎� / ���R�v�� / 34�`34
���w�V�C�}�̘b<27> / ��Ԙa�� / 40�`41
���̐��b(12) / �؊W�q / 42�`43
�S��28�n�_�̍~���ʂ̌o�N�ω� / �㌴�_�V / 45�`48
�k1988�N7���̋L�^�l"�Ђ܂����"�E���E�̓V��E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T��/
�@�@�����c�T�V ; �ыv�� ; �^�ܑ�a�� ; �c��G�� ; �C�ے��n�k��R�� / 22�`28
<�O���r�A>���v������ / ���{��
�E |
�X���A���A�W�A�̌Ñ㕶�����l�����l�����ȉ�ҁu�Ñ㕶�����l���� (18)�v�����s�����B�@pid/7951402
|
�ɂ����錠�͂̌`��--�����A�W�A�ɂ����遄�����́E�@���E
�@�@�����Ƃ��l����(6) / �R������ / p2�`12
�����h��Ƒ�a�����̐��� / �ώ� / p13�`37
�i����̏����k���l--�i���l�N��@�̉�(3) / ���{�����Y / p38�`63
�u���m�k�݁v��ㅂ��� / ����ǕF / p64�`82
�����L����d�\���_ �k�퐶�j�����E�O���I�̘`�l / ���c���ˎq / p83�`89
�הn�䍑�̈ʒu�Ɠ��J�̓��@ / ���q���Y / p90�`104
��l�Êw�I�l�Êw / �Γn�O�Y / p105�`106
�y�펞��̓��{--�ꕶ����̐�������(1) / �F�c�쐳�� / p107�`114
|
���ʕ��V�l(2)����(����)�Ɗe�_ / �勴�P�� / p115�`141
�l���q�Ɠ��{�l / ���R���q / p142�`159
���[���̌Ñ�j--���[�ɂ͌Ñオ�����Ă��� / �b�㓹�V / p160�`198
�u�����v�ɂ���(2) / �i��s��v / p199�`205
���{���������̗��j--�ΊW��(1) / ��[�͕v / p206�`224
�����s�{�������u���닮������㍑�s�V�}�v�ώ@���ʑ��� / �O���F�j / p225�`228
�f�B�X�J�b�V�������[�� / ���q���Y ; ���{�����Y ; ���ьb�q ; �e�n���� /
p229�`235
����\ / �i��s��v ; ���їǕF / p89�`89
�E |
�P�O���A�����G�u���u�y�Ɗ�b 36(10) p.3-6�@�y���H�w��v�Ɂu�v�����g�E�I�p�[���ƈ��N���v�\����B
�@�{���\�@PDF�@�d�v�@�@���ҏ���: �{���w�_�w���@
|
1�D �͂��߂�
2�D �v�����g�E�I�p�[���iplant opal�j�Ƃ��̕��͖@
�@2�D1 �v �����g�E�I�p�[���̎c����
�@2�D2 �K���X�E�r�[�Y�@
3�D ���{�ɂ�������̋N�� |
4�D ��j����̐��c���̒T��
5�D ����̉ۑ�ꌻ�ݐi�߂Ă��錤��
�@5�D1 �C�l�@���זE�] �_�̌`��̈���ԍ�
�@5�D2 �A�W�A�ɂ����钲������
6�E �J���ƕ������̕ی� |
6�D1 �}���ȍ��y�̊J��
6�D2 �����ꂽ�������ꐅ�c��
6�C3 �����ƒ��a�̕K�v��
�E
�E |
�P�O���A�C�ے� �ďC�u�C�� (378) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B�@�@pid/3203731
|
��6���n�k�\�m�v��Ƒ�4���ΎR���Η\�m�v���
�@�@���T�v / �C�ے��n�k�ΎR�� / 4�`8
���{���V�C�L���̉����ɂ��� / �C�ے��\�ʕ�� / 9�`9
�~�G�A�W�A�����X�[���̌����Ɨ\�� / ���㏟�l / 10�`13
�A���X�J�����L / �E�c���� / 14�`18
�x�m�R�̉_<��> / ���R�� / 34�`35
�쒘�V���n 22 / ���{���g / 20�`20
�C��ω��ɂ��Ă̐V��� No.7 / ���{���g / 32�`33
�����̓�\�l�ߋC<3> / �k�`���l���� / 36�`38
|
���E�̋C��l����݂���v�s�s�̋C�� / ���������v / 3�`3
�C�ۂ̐؎�<229>�����̋C�ۊw�Ҏ�����̐؎� / ���R�v�� / 19�`19
���w�V�C�}�̘b<28> / ��Ԙa�� / 40�`41
���̐��b(13) / �؊W�q / 42�`43
�S��28�n�_�̍~���ʂ̌o�N�ω� / �����O�u / 45�`47
�k1988�N8���̋L�^�l"�Ђ܂��摜"�E���E�̓V��E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T�� /
�@�@���ɒB�N�O ; �x��ەF ; �^�ܑ�a�� ; ��c�� ; �C�ے��n�k�ΎR�� / 22�`30
<�O���r�A>�_��x���� / ���{��
�E
|
�P�P���A�C�ے� �ďC�u�C�� (379) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B�@�@pid/3203732
|
������\��̉�� / �؍F / 4�`7
1988�N���{�̓V��� (6�`8��) / �n�����Y / 8�`11
1988�N�M�т̏z�� (6�`8��) / �I�؋` / 12�`14
�n���P�[���u�M���o�[�g�v�W���}�C�J�̎S�Ђ��݂�/���P��/15�`15
�~���Z���ԗ\��̊T�v / �q���N�� / 30�`34
�t�����Ƃ͉��� / ���{���g / 16�`18
�����̓�\�l�ߋC<4> / �k�`���l���� / 35�`37
�C��ω��ɂ��Ă̐V���No.8 / ���{���g / 38�`39 |
���E�̋C��l����݂���v�s�s�̓V�� / ���쐳�j / 3�`3
�C�ۂ̐؎�<230>�E�F�Q�i�[�̐؎� / ���R�v�� / 20�`20
���w�V�C�}�̘b<29> / ��Ԙa�� / 40�`41
�G�k ����6 / �؊W�q / 42�`43
�S��28�n�_�̍~���ʂ̌o�N�ω� / �i�c�m�� / 45�`47
�k1988�N9���̋L�^�l"�Ђ܂��摜"�E���E�̓V��E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T��
/
�@�@���R�{��p ; ���쐴�� ; �^�ܑ�a�� ; ���R�� ; �C�ے��n�k�ΎR�� / 22�`28
<�O���r�A>�l�g���� / ���{�� |
�P�Q���A�C�ے� �ďC�u�C�� (380) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B�@pid/3203733
|
�ŋ߂̊C�m�C�ۊϑ��D�̌��� / �R�{�F�� / 4�`8
1988�N���E�̓V�� / ���B�Y / 10�`13
1988�N�V��ƎЉ�E�o�� / �����m�i / 14�`18
�����_�{�̓V�C�\��� / �c���|�j / 19�`20
�C��ω��ɂ��Ă̐V���No.9 / ���{���g / 30�`31
�����̓�\�l�ߋC<5> / �k�`���l���� / 32�`35
�쒘�V���n 23 / ���{���g / 36�`36
�C�ɏ������� / �}���K�j / 42�`42 |
���E�̋C��l����݂���v�s�s�̋C�� / �����O�u / 3�`3
�C�ۂ̐؎�<231>�O�������b�̐؎� / ���R�v�� / 9�`9
���w�V�C�}�̘b<30> / ��Ԙa�� / 38�`39
�G�k ����7 / �؊W�q / 40�`41
�S��28�n�_�̍~���ʂ̌o�N�ω� / ���c�O�Y / 43�`45
�k1988�N10���̋L�^�l"�Ђ܂��摜"�E���E�̓V��E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T��
/
�@�@���s���� ; �O�Y�F�h ; �^�ܑ�a�� ; �V�����N ; �C�ے��n�k�ΎR�� / 22�`28
<�O���r�A>�������� / ���{�� /
|
�P�Q���A�u���j�ǖ{ 33(24)(491)���W �Ñ�V�c�ƂƏ@���̓� �v���u KADOKAWA,���o�o��,�V�l�������Ёv���犧�s�����B�@pid/7975445
|
���W �Ñ�V�c�ƂƏ@���̓�
�@�J���[ �Ñ�V�c�ƂƓ������ / /
�@�J���[ ����ɐ����铮������-�Ñ�l�̉F���� / /
�@���W �Ñ�V�c�ƂƏ@���̓�
�@�J���[ ��-�l�`�̐��E / /
�@���j��h��ւ���ؗ�Ȃ�o�y�i ���m�،Õ���
�@�@�@�@���n���l�����F���� / �������� / 220�`227
�@ �y�ً}�z �������͍������w�� �u�������Ɩ؊ȁv�o�y���画������
�@�@�@�@���������̕ς̐^��! / ���q�T�V / 140�`147
�@ �y�ً}�z �J���[ �u�������Ɩ؊ȁv�o�y / /
�@�J���[���� ���m�،Õ��̐Ί��J��! / / 80�`81
�@�Ñ�l�Ə@�� �Ñ�l�̎����� / ���C�Y / 30�`39
�@�Ñ�l�Ə@�� ���E���ؐM�ƌÑ�̐_�X / ��ё��� / 40�`47
�@�Ñ�l�Ə@�� ��a�����ƌ��n�_�� / ���o�`�� / 48�`55
�@�Ñ�l�Ə@�� �_�Ђ̋N���Ɛ��n�̊m�� / ���c���� / 56�`63
�@�Ñ�l�Ə@�� �A�z���ƌÑ���{ / ���R�C�� / 64�`71
�@�Ñ�l�Ə@�� �Ñ���{�Ɠ����`�� / ���c�q�O / 72�`79
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �V���[�}�����ږ�Ă̋S��/���X�؍G��/82�`89
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �V�c�Ƃ̎��_�@
�@�@�@�@���ɐ��_�{�̋N��/�F�c����/90�`97
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �F�������M�Ɠ��� / ���씦�\/98�`105
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �������q�ƉA�z�܍s�v�z/�c���k�l/106�`113
|
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �����牮�̎��Ɛ����_���̐^��/��c��u/114�`121
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �ٍb�p�ɒ����������̑̌��ғV���V�c/��a��Y/122�`130
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �啧�J��Ɣ����_���鎖�� / �{��m��Y
/ 132�`139
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �|�퓹���̏h�j��� / ���c���� / 148�`155
�@���Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �ޗǁE�����̉����ƎR�x�@�� / �v�ۓc�W�O
/ 172�`179
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p �`�����������_�g�����{���� / ��������
/ 180�`187
�@�Ñ�V�c�ƁE��a�����Ə@���E��p ��p�Ƃ��Ẳ��� / �������R / 166�`171
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �Ñ㓁���ɂ݂�V�c�ƂƓ������E / ���쐳�D
/ 196�`203
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �S���ƑO����~���̒a�� / �d�����v /
188�`195
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �Õ����c�Ƒ����V��̕��� / �]�Y�m / 204�`211
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �����ˁE�����R�Õ��ɂ݂钆���v�z/�Ԋ��P��/212�`219
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �����ɍʂ�ꂽ�L�I�_�b / �O�J�Ĉ� /
246�`253
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �Ó`���ɂ݂�_��ւ̓��� / �����@�F / 254�`261
�@��ՁE�╨�����Ñ�V�c�Ƃ̏@�� �Ñ���{�̑��z�M��/���J�c��/262�`269
���W���� �퐢�ցE�E�E ���삪�p�j�������s�s�ɂ���Ђ낰����
�@�@�@�@���A�j�~�Y����p����!/�|�͐� /270�`291
���W �Ñ�V�c�ƂƏ@���̓� ���W���� ������N�̐��� ������̓s�T��������
�@�@�@�@�����V���g���g���ނƕS�ύċ��h���V�̕��p�� / �헅 / 292�`315
���W �Ñ�V�c�ƂƏ@���̓� ���ʊ�� ���{������ՒT�K���T �Ñ�V�c�ƂɎ�����Ă���
�@�@�@�@�������v�z����╨�E��Ղ̓������ / ��c�� ; �����O / 317�`337
���j���w�ܕ�W / / 228�`228
�E |
|
| 1989 |
64 |
�E |
�P���A��c�}���q ; �Γc�ܘY ; ���b���u������ (214)�@p20�`28�}�����[�v�Ɂu��K���e�����Â�Łv�\����B�@pid/3364498
�P���A�C�ے� �ďC�u�C�� (381) �v���u���{�C�ۋ���v���犧�s�����B�@�@pid/3203734
|
���ꂩ��̋C�ۋƖ� / �e�r�K�Y / 4�`7
�ŋ߂̗\��͓����Ă��邩 / ��˗��� / 10�`13
�A���X�J�k�Ɍ��B�e�L / �������� / 14�`17
���z�����ɒ��ڂ��悤 / ���{���g / 18�`21
1988�N�̓V��<�䕗> / ��ѐ��K / 30�`32
1988�N�̓V��<��J> / ����O�W / 32�`37
�����̓�\�l�ߋC<6> / �k�`���l���� / 38�`41
�E�G�U�[����L<1��> / �{�� / 3�`3 |
�C�ۂ̐؎�<232>�O���[�V�A���������̐؎� / ���R�v�� / 9�`9
�쒘�V���n 24 / ���{���g / 29�`29
�G�k ����8 / �؊W�q / 42�`44
WMO��C�w�ψ���<1> / ��ؐM�Y / 45�`47
�k1988�N11���̋L�^�l"�Ђ܂��摜"�E�V�C�}���L�E���{�̓V��E�n�k�ΎR�̊T��
/
�@�@�������� ; �^�ܑ�a�� ; ��c�� ; �C�ے��n�k�ΎR�� / 22�`28
<�O���r�A>���[���� / ���{��
�E |
�P���A�����o�ŕ��u���j�蒟 17(1)(183) �v�����s�����Bpid/2246626
|
�A�z�t���P�k�W���l / ���c���i / p4�`7
�g���ƉA�z���\�\�����̐����߂����� / �������� / p8�`10
�A�z�� ��Υ���{���Ɨ肋V���� / �R������ / p11�`13
�ߐ��A�z���g�D�̒n���g�y / �؏ꖾ�u / p14�`16 |
�A�z�����������ژ^ / p17�`20
�n���j�G�������ژ^/���V���v/p30�`46
�n���j�o�Ŗژ^ / p26�`29
�S���Â����̏�� / p47�`48 |
�������z ���j�Ǝ� / �������� / p3�`
�s�s�̓J�I�X�̉�(1)�]�˗���/����[/p21�`25
�E
�E |
�R���A�l�Êw������ҏW�ψ���ҁu�l�Êw���� 35(4)(140)�v���u�l�Êw������v���犧�s�����B�@pid/6057634
|
�Ó���Օۑ�20���N�L�O�W��̋L�^ �Ó���Օ����َ����ɂ��� / �ߓ��`�Y
/ p38�`54
�Ó���Օۑ�20���N�L�O�W��̋L�^ 80�N��̕��������߂����ƕۑ��^�� /
����� / p55�`68
�_�� �퐶����̐ΐ�����̔��B�ƒn�搫--�Ƃ��ɑŐ����V�ɂ��� / ���ؕ��F
/ p69�`96
�_�� ���Õ��ɂ��ޗǖ~�n�̐����j�I����(��) / �g���� / p97�`113
�����m�[�g �ߔN�̏����_�Ƙ_�ɂ���(��) / �X�{�a�j / p114�`125
�W�] �Ó���Օۑ��^���Ȍ�20�N / ����G / p1�`1
�W�] ���Q���w��j�Ձu�����L�ˁv�̊�@ / �����̎��R�ƕ�����Y������ / p14�`15,17�`21
�W�] ���Q�������s�u�����L�ˁv�̕ۑ��v�]�ɂ��� / �l�Êw������ψ��� /
p22�`22
�q�����r |
�R���A�i�c�v���u�N���s�����u�Ȋw�v���� ��̂Ȃ��̕����ƒm�b�v���u���{�o�ϐV���Ёv���犧�s����B�@
�T���A�u���j�Ɨ� 16(8)(221)�Վ��������v���u�H�c���X�v���犧�s�����B�@pid/10998585
|
�j�b�E��b�E�`���ɂ܂ꂽ�Î��Ђ�K�˂�!! ���j�̕�� �_�Ў��@����
���_�^���j�̒��̐_�Ɛ_�� �ޗǁE��������̐_�Ђ̂��肩������T��
�@�@�����{�j�̂Ȃ��̐_�X�̑���/�R�c�@�r / 36�`41
���ʓǕ�/�M���j�Y ; ������F ; ������ ; ���Ζ[�q ; �n��b��
�@�@��/ 42�`49�A230�`253�A262�`268
�_�b�̒��̐_�� ���{�a���Ɛ_�X/�M���j�Y / 42�`49
�`���̐_�Е��t/������F / 230�`237
�퍑�����Ɛ_�Е��t/������ / 238�`245
���l�䂩��̎��Ɛ_��/���Ζ[�q / 246�`253
���̖�Վ��@/�n��b�� / 262�`268
���ʋI�s �l�����\���D�����q�L ��ԎD����R�������C���a��
�@�@�����ܔԑP�ʎ��A����̔����ԑ�E����K�˂�/�����Ďq / 254�`261
�E�ޗǎ���̐_�Ў��@/�i�O ; ������q ; ��q�Y ; �҃~�`�q / 50�`71
�����_�{ ���T�R�[�̏���_����̋{��/�i�O / 50�`51
�Ώ�_�{ �Ñ�̍����������̕����/�i�O / 52�`53
�� �剻���V�Ɣl/������q / 54�`55
�l�V���� �������ŖS�ƎႫ���̑��q/������q / 56�`57
�@���� ���E�ŌÂ̖ؑ����z/��q�Y / 58�`63
�t����ЂƋ����� �������̉h��/������q / 64�`69
������ ���m�Ӑ^�a��n���̗��@���@/�҃~�`�q / 70�`71
��������̐_�Ў��@/�҃~�`�q ; ���쐟 ; �i�O ;
�@�@���ݍG�q ; ���i�`�O ; ���i�^��Y ; �m�R�I / 72�`115
�����_�{ ���������Âԋ��s�Đ��̖�/�҃~�`�q / 72�`73
��� ���̈ӂ̂܂܂ɂȂ�ʎR�@�t/���쐟 / 74�`79
�������� �O�@��t�̊J������ꍂ��R/�i�O / 80�`83
������ ���c�����C�n���̖���/�ݍG�q / 84�`85
�k��V���{ ���삩��w��̐_���܂ւ̓]�g/�ݍG�q / 86�`89
�V���� ���咲���`���Ɛ��c�R�l�C/���i�`�O / 90�`91
�ΎR�� �������Ɨ��a�䂩��̏��l�̎�/�ݍG�q / 92�`93
�����@ �Ɋy��y��O�����������̉h��/�҃~�`�q / 94�`97
�ΐ��������{ ���̐_�A�����M�̑�����/���i�^��Y / 98�`99
���鎛 �m���i���R��ƍR��/���i�^��Y / 100�`101
�F���� �F��O�R�ƔM���I�M�u�a�̌F��w�v/���i�^��Y / 102�`105
�Z�g������ ����l�J��̔O������/���쐟 / 106�`107
�Ɣn�� ����ی��p�C�s�̕��@�̎�/���쐟 / 108�`109
������ �ؑ]�`���̋���/�m�R�I / 110�`111
�{���� ���ƌ��B������/�m�R�I / 112�`113
�ԊԐ_�{ ���ƈ�刣��A�g�̉��̓s/�m�R�I / 114�`115
���q����̐_�Ў��@/���{�O��j ; �Γ��G�v ;
�@�@���O�R�i ; ������ ; �˓c�� ; �����ɗY / 116�`141
�߉������{ �Ós���q�ɒ��܂鐴�a�����̎��_/���{�O��j / 116�`121
������ ���B�������O��̉h��/�Γ��G�v / 122�`125
�C�T�� ���ł�̌Ù��ɏ��R���Ƃ̔ߌ�/���{�O��j / 126�`127
���q�R ����̕{�̗ՍϑT/�O�R�i / 128�`131
�f���� �������̕��/������ / 132�`133 |
�r��{�厛 �J�c���ł̒n�Ɍ����@�@��{�R/�˓c�� / 134�`137
�i���� �����J�R�̑����@��{�R/�����ɗY / 138�`141 (0072.jp2)
��k���E��������̐_�Ў��@/�m�R�I ; ���R�F�G ; �H���� ;
�@�@���S������ ; ��{���� ; ���i�`�O ; �˓c�� / 142�`177
����R�� �Ԃ����R���Ɉ����g��R/�m�R�I / 142�`145
����_�� ��ؐ����Ɓw�����L�x�̐��E/���R�F�G / 146�`147
��o�� ��k������̕���/���R�F�G / 148�`149
���t�� �������S���̋L�O��/�H���� / 150�`153
��t�� �����`���̓��R�R��/�H���� / 154�`155
����_�� �V����������m�̗�/�S������ / 156�`159
�g���V ����Ꝅ�̉��/�H���� / 160�`161
��̑P���� �M�Z�P�����ƍb��P����/��{���� / 162�`165
�b�ю� ���c�O��̉h���Ɩv��/��{���� / 166�`167
�{�\�� �D�c�M���A�e�Ɣ��̍���/���i�`�O / 168�`171
������ �S�R�Ď��A�G�g�̍����U��/�˓c�� / 172�`173
��펛 �G�g�A���̉Ԍ��̐���/�S������ / 174�`175
�L���_�� �������ʂ�ؗ�ȖL����/�S������ / 176�`177
�]�ˁE�ߑ�̐_�Ў��@/���c���� ; �c�c�_�� ; ���{�O��j ; ������ ;
�@�@���~�J�^�� ; �����k�O ; ���R�F�G ; �F�s�{�ג� / 178�`229
���E���{�莛 ��Ɉ����ꂽ�^�@�{�R/���c���� / 178�`183
�������Ƌ{ �_�N�ƍN�J�鍋���ȗ�_/�c�c�_�� / 184�`187
�哿�� ���x�f�߂Ǝ��ߎ���/�c�c�_�� / 188�`189
���c�� �s����ꂽ���l�~�ς̋퍞�ݎ�/���{�O��j / 190�`191
�쑽�@ �V�C�m��Ət���ǂ̐���/�c�c�_�� / 192�`193
�{���� �U���̈������܂�������������/������ / 194�`195
�썑�� �����R�j�g�̕�j���@�̌���/������ / 196�`197
��x�� �ԕ�ˎ�Ǝl�\���m�̖���Ù�/�~�J�^�� / 198�`201
�@�؎� �剜�X�L�����_���G���z���̗�/���c���� / 202�`203
�ʐ� �n���X�؍݁A�{�M���̑��̎���/�~�J�^�� / 204�`205
���T�� ���Δh�Q�m�̓��T���P������/�~�J�^�� / 206�`207
���A�_�� �����̑卖�Ə��A�̕揊/���c���� / 208�`209
���R�� �ˉ^�������������W�싓���̒n/���c���� / 210�`211
�p���� �����̐V��g�䂩��̌Ù�/�����k�O / 212�`213
�䍁�{�_�� ���H�����푈�̎F�R�w�n/�����k�O / 214�`215
���i�� ���`������̑�]�ˑ��s���@/�����k�O / 216�`219
��� �p�V�����O!�k�z�푈�̐k���n/�����k�O / 220�`221
�����_�{ �s�S�̐���̐X�A�����̕���/���R�F�G / 222�`225
�����_�� ��v�҂̌䍰��l�Z���]���J���/�F�s�{�ג� / 226�`22
������̋{�߂���/�� / 269�`374
�����������߂���/�r��_�V / 375�`447
�J���[���G�^�퍑�O�啐���Ǝ���/ / 11�`18
�O���r�A�^�_�ƂȂ��퍑�����ƕ��/ / 19�`34
����/ / 448�`449
�ҏW��L/ / 450�`450
�\���^���t���i�������j |
�U���A�{����F���u�V������ = The astronomical herald 82(7) p190�`190�@���{�V���w��v�Ɂu���{�ɉe����^���������̓V����w�ғ`(1)--�m��s�v�\����B�@�@pid/3304817
�V���A �{����F���u�V������ = The astronomical herald 82(8)p218�`218�@�@���{�V���w��v�Ɂu���{�ɉe����^���������̓V���w��(2)�s��h�v�\����B�@pid/3304818
�V���A���ѕV�������s����w�@�w��ҁu�����s����w�@�w��G�� 30(1) p.p11�`63�v�Ɂu���ߓV�c���ɂ��Ă̈�l�@--�F�N�Ղ�f�ނƂ���-1-�v�\����B
�W���A��t��F���u�Ȋw���� 49(8)(583)�@ p18�`21�@�����V���Ёv�Ɂu�����̑����@�\���i����̂͂Ȃɂ��v�\����B�@pid/2335796
�X���A���J�c�ꂪ�u���j�ǖ{ 34(18)(509)p166�`173�v�Ɂu���z�̓��A�_�̓��v�\����B�@pid/7975462
�P�O���A�i�c�v�����{��������ҁu���Ɨ�̉Ȋw�v���u���{�����o�ŋ��� �v���犧�s����B(NHK�s����w�^�e�L�X�g�{)
�@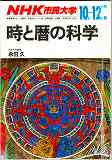
�@�@���Ɨ�̉Ȋw�i�\���j
|
| �m�� |
�������e |
�������@�i�ĕ������ȗ��j |
| 1 |
���Ԃ���� |
10��2������ |
| 2 |
�T�̐����Ə��� |
10��9������ |
| 3 |
�j���̈Ӗ� |
10��16������ |
| 4 |
���z��̌����@�[�G�W�v�g�̗�[ |
10��23������ |
| 5 |
�\���̕��݁@�[���[�}�̗�[ |
10��30������ |
| 6 |
���̖��̗R�� |
11��6������ |
| 7 |
�O���S���I��̍\�� |
11��13������ |
| 8 |
���{�̉���� |
11��20������ |
| 9 |
�A�z�܍s�� |
11��27���� |
| 10 |
�\���\��x |
12��4������ |
| 11 |
��\�l�ߋC |
12��11������ |
| 12 |
�l���̉F���� |
12��18������ |
|
�P�O���A��ʼnp�Y���s���̌Ñ㌤����ҁu�s���̌Ñ� 11 p199�`202�@�r���b�W�v���X�v�Ɂu�Ђ�� ���������Ȃāu�V���V�c�̏o���v������v�\����B
�@pid/4422384
�P�P���A���J�c�ꂪ�u���w 57(11) p.p58�`75�v�Ɂu�쓇�̐_�̂Ɗ؍��̛މ�--���̌�q(�Ђ݂̂�)�^�̛ޑc�_�b���߂����� (�V�쓇�̗w�_<���W>)�v�\����B |
| 1990 |
�����Q�N |
�E |
�R���A�ߓ��鏺���u�Ȋw���� 50(3)(590) p35�`39�����V���Ёv�Ɂu�~�����x�z����`����--�V�}���X�S���̕ω����ׂŔ����v�\����B�@�@pid/2335803
�R���A���A�W�A�����𗬎j����� �u���j�ǖ{ 35(5)[(520)]�@p264�`277 �@KADOKAWA�v�Ɂu���j��� Net Work �l�b�g���[�N ���J���[�� �����E�]��ɖ퐶�����̌��_
�y�ً}���k��z �g��P����ՂƁu��̓��v�̌�����T��v�����B�@pid/7975472
�S���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ�. 1(1)(1)�v���u��C�ُ��X�v����n�������B�@�@ pid/4425916
|
���ʊ�e �����w���ɂ��x�n���ɂ悹�� / ���� / p2�`3
���W �������������l���� ���܁A�Ȃ�������
�@�@�C�k �V�������������̑n�����߂����� /
�@�@�@�@����؍F�v ; ���c���Y ; �_�c�דT / p4�`11
�@�@�����\���{��̏h�� / �쌳�e�Y / p12�`16
�@�@�����̊������� / ����Y��Y / p17�`21
�@�@���N�̊������� / ���{�K�v / p22�`25
�@�@���������[�}���ŏ����l�X--�x�g�i����
�@�@�@�@���������� / ��{�M�q / p26�`30
�@�@�������猩���������� / M�EL�E�V�F���[�h / p31�`3
�@�@�l�p���F���͐����̂т�--�����������̖���/�������q/p36�`41
�A�� ���{�̕��i�����(1)���A�W�A�̌��ց\�Δn�ɂ�/��o���Z/p44�`48
�A�� �����̏�������(1)��l�I���� / ������� / p49�`52
�A�� �k���Ύ��L(1) / �^ / p54�`55
�A�W�A�̗�(��1�b)�u���Ɨ�v / ���c�F�N / p56�`60
�A�� ����������������(1)���㒆���ɂ�����
�@�@�@�������̎g�p��/�͑�/p61�`63
�A�� �H�̕�����(1)�t�O�Ɠ��̉� / �ԏ��I�F / p64�`65
�A�� ���t�W�̕����R���e�N�X�g(1)�I��R�Ƌg�� / �����i / p66�`71
|
�V���\�����������I���E / �䏮�q / p72�`76
��p��ɂȂ������{�� / �����V / p78�`82
�؍��̎I�`���ɂ��� / ���c�� / p83�`87
�A�� �A�W�A�̃}���K(1)G�EM�E�X�_���^����
�@�@�@���C���h�l�V�A�̃}���K / ����k�� / p88�`91
�A�� ���m�w�̌n��(1)�����Γ� / �a��l / p92�`96
�A�� ��a���S�b(1) / �O���[�vC / p98�`101
�A�� ���A�W�A���j�̗��K�C�h
�@�@��(1)�����͖k�ȁk�^�N�l�� / ��c�G�� / p112�`113
�������@���(1)�O���̎� / A / p42�`43
�����ْT�K(1)����L���� / A / p102�`103
�����O�� �k����
�@�@������ƃO���[�v�u�C�n�v/�@��/p104�`105
���] ���B�����w�����̐H�����x/��쎠�j/ p108�`109
���[�h�E�{�b�N�X / A / p53�`53
Q��A / �R�ۍK�q ; T ; ���J��� ; A / p97�`97
�A�W�ANOW / �� / p106�`107
�V���Љ� / T ; A ; Y / p110�`111
�C���t�H���[�V���� / p114�`115 |
�S���A�S�������u�G������. �ʍ�, �u����u���v�| (29) p.75-76�v���u�쐫���юG���^�쐶���q�̋x�����̌n���ԍ��فv�\����B
�T���A���֏�, �X����N�ďC���A�W�A�����𗬎j������ҁu�� : ���̌����ւ̓� : �����]�삩��g��P���v���u���A�W�A�����𗬎j������v���犧�s�����B(����2�N5��19��-20��,)�̃e�L�X�g
�T���P�X���`�Q�O���A����s������قɂ����āu��2������F�D����V���|�W�E���u�����̎���'90�E��̓�--�g�샖����Ղƒ����E�]�앶���v���J�����B
�T���A�����@ ���u�������ɂ�. 1(2)(2) p104�`105�v�Ɂu�����O��(2)�ϏB���Ƀ��[�c�����߂āv�\����B�@pid/4425917
�U���A���c�F�N�� �w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 1(3)(3) p56�`60��C�ُ��X�v�Ɂu�A�W�A�̗�(��2�b)�u��\�l�ߋC�v�v�\����B�@�@pid/4425918
�U���A��t��F���u�ʐ����� 41(2) p.141�v�Ɂu�����T�����Y���̐����w�I�@�\ : ��𒆐S�ɂ��āv�\����B
�V���A���{���������������ҁu�����I�v (163)�v���u���{���������������v���犧�s�����B�@pid/1386023
|
�͂����� / p3�`6
���� �另�Ղւ̗����̑ԓx / p11�`20
�͂��߂� �另�ՏȎ@�̎��� / p11�`12
�另�Ղ���т��鐹���̗��O / p12�`14
�����V�炪�_�V�ɋÏk / p14�`15
�Z�p�͕������������� / p15�`17
�z�O�������̓����� / p17�`19
�킪�_���͈�̐����ߒ� / p19�`20
���� ��Ƒ��z / p21�`26
����Ɠ��_�ւ̏o� / p21�`23
��Ƒ��z�ւ̗�͍����I�s�� / p23�`25
�Ղ莖�Ɛ��莖 / p25�`26
���� ��̐��� / p27�`40
��̈،h�����J�� / p27�`28
����`�Ԃ̈ێ��͖��C�̐S�� / p28�`30
��̐����ւ̋V�� / p30�`33
|
���_����o���̂��̂� / p33�`35
�_�a�̋V�͑�T�̊j�S / p35�`37
�������܂����ʂ���� / p37�`38
�s�ׂƎ������另�Ղ̖{�� / p38�`40
��O�� �l�̐��� / p41�`70
��̐�������V�c�̐����� / p41�`43
�����݂͐����̝|�� / p43�`46
�_���I��Ԃ̎O�ʈ�� / p46�`47
�V�Ïj���ƃc�~�P�K�� / p47�`49
���S?�����K�R�̈Ӗ� / p49�`52
�����̂����ɇ��m�낵�߇������ / p52�`53
���ؓI�P�K���ƃ~�\�M�̖{�| / p53�`55
�����Ղ͐_���̐^�� / p55�`57
�~�^�}�̌����Ȃ���� / p57�`60
���q�����ޜ������}�K�c�q / p60�`62
�����̎�ɐ_��咼���_ / p62�`63
|
�����Ղ̈Ӌ`�ƋV�� / p63�`66
���ƋՇ������z�I�l�i�̗^�� / p66�`68
��ߎ��Ƃ��Ă̐_�y�� / p68�`70
��l�� �l�ƈ�Ƃ̏o� / p71�`81
�Ґ_�̓����̓��� / p71�`72
�l�ƈ�Ɛ_�̈�̉� / p72�`73
�_�X�͋C�I�l�i�� / p73�`74
���R�Ɛl�i�̌����ɂ݂��O / p74�`75
�_�l���т������쇁�̌��� / p75�`77
���̔q�̂ƒ���̑��� / p77�`79
�H�̐��ʂɂ݂�另�Ղ̌[�� / p79�`81
�w�o�ɗ߁x�ɂ݂��n���V / p82�`82
��ϋV���另�{�S�} / p83�`83
�另�{(�a)���} / p84�`84
���a�另�{���ʐ} / p85�`85
�E |
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (65) �v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7947826
|
���W1 ���N��ƌÑ���{�� ���{��̑c��͊؍���ł��� / ������ / p2�`18
���W1 ���N��ƌÑ���{�� ���N��ƌÑ���{�� / �p���A / p19�`37
���W1 ���N��ƌÑ���{�� �w���{���I�x�̂Ȃ��̒��N��--���t�����
�@�@�@�����{��ƒ��N��Ƃ͈قȂ��Ă��� / ���{���T / p38�`60
���W1 ���N��ƌÑ���{�� ���{��`���ɂ�����
�@�@���I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�̗v�f / ��R�� / p61�`75
���W1 ���N��ƌÑ���{�� �u�Ñ���{��͂Ȃ������v�� / �����i / p76�`88
���W2 �הn�䍑���߂����� �J�k�[�ŒT��הn�䍑�ւ̓�/���ƍN�V��/p89�`105 �d�v
���W2 �הn�䍑���߂����� �ѕ��̓���Ɖ�m�E����̓� / �b��K�ߘY / p106�`115
|
���W2 �הn�䍑���߂����� �w�����䗗�x���� �u鰎u�v��
�@�@���u�������n���v���߂����� / �x������ / p116�`138
���W2 �הn�䍑���߂����� ����Õ��Ɣ���`��(��)--�הn�䍑
�@�@��������^�Ɋ֘A���� / ��a��Y / p139�`164
�Օ���Տo�y�̓��� / ����ǎO / p165�`175
�u�l���v���u�C�߁v�ɂȂ���--��́u���k���C�l�v����̐��� / ���؈�O / p176�`183
���쌜�Γ��Ȃǂɂ݂铡���s�䓙(��) / ��ˑד�Y / p184�`201
�Ñ�j�ʐM / ����m�q�E�� / p202�`229
�E |
�P�P���A �w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ�. 1(8)(8) �v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425923
|
�A�� ���{�̕��i�����(8)��Έ�� �ꕶ�l�̕��i/��o���Z/p50�`55
�A�� �����̏�������(8)��������E��Ǝ��Ɛ��̎�/���O/p68�`71
�A�� ���m�w�̌n��(8) / �_�c�k�� ; ����R�� / p100�`105 |
�����������̕ی�Ɨ��o(��) / �����r�� / p89�`94
�q�����r
�E |
�P�Q���A�i�c�v���u��̒m�b�E�肢�̐_��v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B
�P�Q���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 1(9)(9)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425924
|
�����G�b�Z�C �u�[�^����I���R / �{������ / p2�`3
�����G�b�Z�C �����ꎫ�T�G�� / ������Y / p4�`5
�����G�b�Z�C �܂́u�䂤�v / �����q�q / p6�`7
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ ���x�Ɨ� / �M���� / p8�`13
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ �\���\��x�̃��[�c / ��J���j / p14�`20
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ ���{�̗�Ɗ��x / ���c�F�N / p21�`26
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ �^�C�̗�Ə\��x / ���A�� / p27�`31
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ �l�p�[���̗�Ƃ��炵 / ���c���q / p32�`36
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ �\���\��x�Ɛ�p
�@�@���Պw���w�ƌ܍s�E���x�̊W�ɂ��� / ���V�G�� / p37�`41
���W �\���\��x �A�W�A�̓V���E��@ ��炵�̂Ȃ��̏\��x / ��쌛�� / p42�`45
�A�� ���{�̕��i�����(9)�ꒃ���@ / ��o���Z / p48�`53
�A�� �H�̕�����(9)�h���̒��� / �ԏ��I�F / p54�`55
�A�� ���t�W�̕����R���e�N�X�g(9)�퐢�ƖH� / �����i / p56�`61
�A�� �k���Ύ��L(9) / �^ / p62�`64
�A�� �����̏�������(9)���z�̑��E���] / ���O / p66�`70
�u���]��(��) / ��c�i�� / p72�`77
�����������̕ی�Ɨ��o(��) / �����r�� / p78�`83 |
�{�̕��ׂ����ɂ��� �̂̒����A���̒��� / �����r�j / p84�`89
�ٗ�̑�p�`�L���w�u�[�� / �����V / p90�`94
�A�� �A�W�A�̃}���K(9)��܍̃��b�g���������}���[�V�A�̃}���K��/����k��/p95�`99
�A�� ���m�w�̌n��(9)��ؑ�� / �g�c�Ћ� / p100�`105
�A�� ���A�W�A���j�̗��K�C�h(9)�����V�d�E�C�O��������z�[�^���s/��c�G��/p112�`113
�������@��� �Ñ㓌�k�^�C�̎Y�ƂƎЉ�ϓ� ���ƓS�ƃm��������� / p46�`47
��a���S�b �؍�3 / p106�`109
�����ْT�K �����c�B������ / p110�`111
�����O�� ���`�̉��y�G�� / �����S�� / p114�`115
�A�W�ANOW �A�W�A�݂̊�o�����u�E���v�̔g / p116�`117
���] ���c�����w�]�ˊ��w�̐��E�x / �������� / p118�`119
���[�h�E�{�b�N�X / p65�`65
Q��A / p71�`71
�V���Љ� / p120�`121
���ɂ����C�u�����[ / p122�`123
�C���t�H���[�V���� / p124�`125
�ǎ҃t�H�[���� / p126�`127
�E |
�@�@���u���������̕ی�Ɨ��o(��E��) / �����r�́v�@�d�v�@�Q�O�Q�Q�E�W�E�P�U�@�ۍ� |
| 1991 |
3 |
�E |
�P���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (66)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947827
|
���W ���{�_�b���߂����� �����Ñ�̑��ʋV��Ƒ另��/�����/p2�`13
���W ���{�_�b���߂����� �_�b�w�Ɠ��{�j / ���O�� / p14�`24
���W ���{�_�b���߂����� ���H���҂��P��V�� / �R��ɓ��� / p25�`33
���W ���{�_�b���߂����� �I�z�i���`�_�b�ƒ����̖��b/�ɓ����i/p34�`43
���W ���{�_�b���߂����� �ꕶ�̐_�b�Ɛ̘b����і���/�g�c�֕F/p44�`57
���W ���{�_�b���߂����� �j�j�M�m�~�R�g�ƃ��R�u / ��{�p�� / p58�`68
���W ���{�_�b���߂����� ���{�_�b�Ɩ����w / ��{���� / p69�`79
���W ���{�_�b���߂����� �A���m�E�Y���̌Ñ�w / �C���a�O / p80�`94 |
���W ���{�_�b���߂����� �_��ȃn�j����
�@�@�@���_�b�Ɠ��{�_�b / �]�g / p95�`103
�|�����`����G�� / ���J�� / p104�`109
�הn��(��)�����߂�����/���{���T ;�Óc���F/p110�`145
���쌜�Γ��Ȃǂɂ݂铡���s�䓙(��)/�ˑ��Y/ p146�`163
�Ñ㒩�N��œ��{�̌ÓT�͓ǂ߂邩(��)/���[�K�Y/p164�`188
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p197�`225
�w�Ԃ��Ƃ�Y�ꂽ�w�҂� / �p�z�A / p189�`196 |
�P���A�u�}�� (425)�v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�@pid/3448131
|
�V�E�Ύ��L �� / ���c���j / p8�`9
�Îj���| �������p�s�̓� / ���{���� / p26�`31 |
�c���ӎ��ƉڈΒn�T��(��) / ��ΐT�O�Y / p32�`37
��_�Ȑ��� / ������ / p60�`63 |
�q�����r
�E
|
�Q���A�u�}�� (426)�v���u��g���X�v���犧�s�����B pid/3448133
|
�Îj���| �����́u�Պ�v��(��) / ���{���� / p28�`33
�c���ӎ��ƉڈΒn�T��(��) / ��ΐT�O�Y |
�� / ������ / p60�`63
�q�����r |
|
�R���A�u�}�� (427)�v���u��g���X�v���犧�s�����Bpid/3448135
|
�Îj���| �����́u�Պ�v��(��) / ���{���� / p30�`35
�c���ӎ��ƉڈΒn�T��(��) / ��ΐT�O�Y / p36�`41 |
�����Ȏ��R�̎O�� / ������ / p60�`63
�q�����r |
|
�R���A���c�F�N���w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ�2(3)(12) p72�`77��C�ُ��X�v�Ɂu�A�W�A�̗�(�ŏI��)�C�X������(���)�v�\����B�@ pid/4425927
�@�@�@�@���c�F�N���u�A�W�A�̗�(��1�`6)�v�ɔ��\�����_���̈ꗗ�\
|
| �m�� |
�G���� |
���s�N |
�_���� |
�q���� |
| 1 |
1(1)(1) �@p56�`60 |
1990-04 |
�A�W�A�̗�(��1�b)�u���Ɨ�v |
pid/4425916 |
| 2 |
1(3)(3) �@p56�`60 |
1990-06 |
�A�W�A�̗�(��2�b)�u��\�l�ߋC�v / ���c�F�N |
pid/4425918 |
| 3 |
1(5)(5) �@p72�`77 |
1990-08 |
�A�W�A�̗�(��3�b)�Z�j�ɂ��� / ���c�F�N |
pid/4425920 |
| 4 |
1(7)(7) �@p76�`81 |
1990-10 |
�A�W�A�̗�(��4�b)���\��� / ���c�F�N |
pid/4425922 |
| 5 |
2(1)(10)�@p80�`86 |
1991-01 |
�A�W�A�̗�(��5�b)��\���h�Ɠ�\���h / ���c�F�N |
pid/4425925 |
| 6 |
2(3)(12) �@p72�`77 |
1991-03 |
�A�W�A�̗�(�ŏI��)�C�X������(���) / ���c�F�N |
pid/4425927 |
|
�S���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (67)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947828
|
���W �V���V�c�̎��� �u�V�Ƒ�_�v�ƓV���V�c / �c������ / p2�`23 �@�@�d�v
���W �V���V�c�̎��� �\�s�c���̐��U / ����S / p24�`35
���W �V���V�c�̎��� �V���V�c�̓����Ƃ��̎��� / ����d�� / p36�`43
���W �V���V�c�̎��� �V���V�c�� / ���F���� / p44�`55
���W �V���V�c�̎��� �w���{���I�E�p�\�I�x�ȊO�̎j����
�@�@�@�����ꂽ�p�\�̗�/�q�{��G/p56�`68
���W �V���V�c�̎��� �p�\�̗��Ƙ`������i
�@�@�@�����≤�̋^�f/��ˑד�Y/p69�`81
���W �V���V�c�̎��� �ِ��E�V���V�c���߂�����/�L�c�L�P ;��a��Y/p82�`101
���W �V���V�c�̎��� �V�q�E�V����Z����ƈٕ��Z��� /��a��Y / p102�`113
���{�l�̑��E��--�n���ƃl�ƃi�J / ���c���� / p114�`127 |
���k�n���Õ��o�����̏��l��--�n�P�X�Õ���
�@�@�@���֘A���� / ��ˏ��d / p128�`138
����l�Êw�̂����� / �t�ꎵ�O�j / p139�`159
�āX�_�u�f�Η��E�ɉq�v�l / �ɓ��`�� / p160�`166
�Ñ㒩�N��œ��{�̌ÓT�͓ǂ߂邩(��)/���[�K�Y/p167�`191
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p198�`234
�v����������قǂقǂɂ��ė~����--�p���A��
�@�@�@���ɓ����� / ���{���T / p192�`197
�ҏW���� / �Óc���F / p235�`237
�Óc���F���{���T�Βk�u�הn��(��)����
�@�@�@���߂����āv�ɂ��� / �ҏW�� / p238�`244
|
|
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���i40�j�` �i67�j�v�ɔ��\����Ă����V���V�c�̏o���A�y�ѓ����֘A�̈ꗗ
| �m�� |
�G���ʔԕ� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
�s���̌Ñ�(11) p199�`202 |
1989-10 |
�Ђ�� ���������Ȃāu�V���V�c�̏o���v����� / ��ʼnp�Y |
, |
pid/4422384 |
| 2 |
�Ñ㕶�����l����
(29) p112�`140 |
1993-12 |
�V�q�V�c�ƓV���V�c�̏o�� / �ώ� |
, |
pid/7951413 |
| 3 |
(40) p92�`123 |
1984-07 |
�`�{�l���C�́u�_�v--�V���V�c�Ɠ���(��) / ��a��Y |
, |
pid/7947800 |
| 4 |
(41) p148�`168 |
1984-10 |
�����ƓV�c��--�V���V�c�Ɠ���(��) / ��a��Y |
, |
pid/794780 |
| 5 |
(43) p172�`194 |
1985-04 |
�w�Î��L�x�̓V�n�J蓐_�ƍ��V��--�V���V�c�Ɠ���(���̈�) / ��a��Y |
, |
pid/7947803 |
| 6 |
(45) p85�`96
(45) p106�`115 |
1985-10 |
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i
���W2�@�O���M�ƌÑ���{ �`���Ɠ����v�z / ����d�� |
, |
pid/7947805 |
| 7 |
.(46) p152�`161 |
1986-01 |
�Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i |
, |
pid/7947806 |
| 8 |
(47) p107�`120
(47) p178�`196 |
1986-04 |
�Ñ���{�ƍ]��̓���(��) / ���i���i
�V���V�c�́u�a���m�ˁv--�V���V�c�Ɠ���(����2) / ��a��Y |
, |
pid/7947807 |
| 9 |
(48) p54�`92 |
1986-07 |
���W1 �Ñ㉤���ƍc�q���� �V���V�c�̏o��--���c�q�Ƒ�C�l�c�q / ��a��Y
|
, |
pid/7947808 |
| 10 |
(49) p209�`249 |
1986-10 |
���E�V���V�c�̏o��--���c�q�Ƒ�C�l�c�q / ��a��Y |
, |
pid/7947809 |
| 11 |
(50) p274�`294 |
1987-01 |
���I���ɂ��Ă̋^��Ɓw���{���I�x--�V���V�c�̏o���Ɋ֘A���� / ��a��Y |
, |
pid/7947810 |
| 12 |
(51) p181�`218 |
1987-04 |
��C�l�c�q�Ɗ��c�q�̉�H--�V���V�c�̏o�����߂����� / ��a��Y |
, |
pid/7947811 |
| 13 |
(52) p197�`223 |
1987-07 |
�_���`���Ɛp�\�̗��̎���--�V���V�c�̏o���Ɗ֘A���� / ��a��Y |
, |
pid/7947812 |
| 14 |
(53) p199�`213 |
1987-10 |
�`�{�l���C�̈��R��̉̂��߂�����--�V���V�c�̏o���Ɋ֘A���� / ��a��Y |
, |
pid/7947813 |
| 15 |
(67) p36�`43
(67) p82�`101
(67) p102�`113 |
1987-10 |
���W �V���V�c�̎��� �V���V�c�̓����Ƃ��̎��� / ����d��
���W �V���V�c�̎��� �ِ��E�V���V�c���߂����� / �L�c�L�P ; ��a��Y
���W �V���V�c�̎��� �V�q�E�V����Z����ƈٕ��Z��� /��a��Y |
, |
pid/7947828 |
|
�T���Q�T���`�Q�U���A�����s��������كz�[���ɉ����āu�g��P����Ղƒ����]�앶����T��V���|�W�E���v���J�����B
�T���A�g��P����Ղƒ����]�앶����T��V���|�W�E�����s�ψ���ҁu�Ñ�e�N�m�|���X�ƌ��z
: �[���@���i�c�Ƌg��P�����ނ��ԁ[ �f�X�P�����F�D����V���|�W�E���v���u��P����Ղƒ����]�앶����T��V���|�W,�E�����s�ψ���v�v���犧�s�����B
�T���A�i�c�v�����傤�����ҁu�I 8(5) p94�`96�@���傤�����v�Ɂu�w�ۓI������l��(60)��Ɛl��(��) �v�\����B�@pid/4422944
�U���A�i�c�v�����傤�����ҁu�I 8(6)�@p94�`96 ���傤�����v�Ɂu�w�ۓI�����\�l��(61)��Ɛl��(��) �v�\����Bpid/4422945
�U���A���l�Êw��ҁu�𗬂̍l�Êw�v���u���l�Êw��v���犧�s�����B�@�@ (���l��, ��8��)
|
���ɂ������y�펞�㌤���̌���Ɖۑ� / �؍�N�O��
���ɂ�����ꕶ���㌤���̌���Ɖۑ� / �x�c�h�꒘
���ɂ�����퐶���㌤���̌���Ɖۑ� / ������Y��
���ɂ�����Õ����㌤���̌���Ɖۑ� / ���Z�ӈ�Y��
���ɂ�������j���㌤���̌���Ɖۑ� / �ߓ��r�F��
���l�Êw�j (2) ��������� : ��ՁE�╨��
�@�@�������ƌ����̗��j / ���v�d����
�ߗׂ̌�����Ί핶���Ɍ����鍜�p�� / ���{�A�ʒ�
���B�ɉ�����ꕶ���O���̓y�핶�� / �͌��哿��
��B�ꕶ���O���̃s�G�X�E�G�X�L�[�� : �`�ԋ敪�ɂ���Ղ�
�@�@���c���̈�� / �{�c�h��
���`�[�t�ɂ�����|�W�E�l�K�]��:�u���`�����v�̐����ߒ�/�c���ǔV��
���̂���ꕶ�y�� : �����y��̌n���𒆐S�Ƃ��� / ����������
�g�D���y�팤���̏���� / �n�Ӑ���
����Y�Y�L�˔��@�̃W���S���̏�r���̈Ӌ` / �k����K��
���B�ɂ�������`���̌n�� / �؍��L�璘
������������Ղ̊�� / �������꒘
���ɂ�����퐶�����Ղ̈�l�� : ��쒬�{�n�u�˂�
�@�@���퐶��Ղɂ��� / ���c���꒘
�F�{�s�t�R��Տo�y�̖퐶����l�� / �����F�K��
|
�]��n��ɂ�����S�z���� / ���Ό���
�L����l�̌^���w / �V�c�h����
�����㊿������ : �_�b�摜�Ɗe��O�p�����̂ɂ��� / �����v��
���ǒ������̌n�� / ���؋���
���ꕽ��̎�n���Ƃ��̉�� / �����G�s��
�Ύ��A�Ί��̐ԐF�痿 / �{�c���q��
�Õ�����̔��D�ɂ��� / �㑺�r�Y��
�ʐF�lj�̏o���ƒ}��̍ʐF�lj�Õ� / ���c�Β�
������ɍ��܂ꂽ�����̒��ׂƗ� / ���ؐ�����
���ʕ����_ / ���B���q��
�L�O�k���̌Õ��������W���̈�l�� : �\�@ / �Ĕ��r�
�ޗǎ���̕�������Ɣ�� : �w���{��ًL�x�𒆐S�Ƃ���/��a�q��
�p�I�w�l / �r���k�꒘
�V�o�����E�i�v�O�N���o�� / ���c�x�m�Y��
�߉މ@�R�������̌o�� / �����L��, �����F��
���鍂���n�� : ����ܔ��p���o�y��ɂ��� / �T�c�C�꒘
����̍L��y��E�T�Čn�y��̕ҔN�ɂ��� / �����i��
�e��(�ȑł�)�ɂ��� / �����ג�
�C�i�ƃg�h / ����h����
�E |
�V���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (68)�@���W ����Ƙ`��--�Ñ���{�Ɗ؍��v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947829
|
���W ����Ƙ`��--�Ñ���{�Ɗ؍�
�@���C�听�Õ��Q--����@�����̊T�v�Ɛ���/�\�h�K/p2�`18
�@����Ƙ`��--�Ñ���{�Ɗ؍�/��ؖ��� ; ���Α���Y/p19�`42
�@�c�B�E����H���Q����N������ / ���J�� / p43�`54
�@�听���Õ��Q�Ɓu�C�߁v�_ / �c���r�� / p55�`69
�@�ْC�Ɖ���̓S / ���� / p70�`83
�@�听���Õ��Q�ƋR�n�������������� / ���쐳�j / p84�`93
���V�i�C�ɂ�����C�㑼�E��(��)
�@�@�@����r�����w�I�l�@/��ؖ��j/p94�`107
|
���ʕ��V�l--���ʕ��̑��`����(��) / �勴�P�� / p108�`128
�O�d����E���w�A�̐��i�Ƃ��̌`���v�� / �O�c���l / p129�`147
���ʎ��ƃJ���X / ��t���T�� / p148�`169
���ʏh�T�Ƌ��E�̐ΐ_�X�N�i�q�R�i / ���c�쑥 / p170�`183
�����_���ƗǕ�--���厛�啧������j / ���㓹�� / p184�`197
�ܐ��I�������̑����ƒ���--�Y���E
�@�@�@�����J�V�c�𒆐S�� / �X�r�� / p198�`215
�u�āX�_�w�f�Η��E�ɉq�x�l�v�Ɋ֘A���� / ��㎟�j / p216�`218
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p219�`246
|
�X���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (337) ���W�E���čl���v���u�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051767
|
���W�E���čl
�@�፡���̌��t�▖�i��Y�搶�̈�P / �Ԋ��P�� / p1�`1
�@����k��̓��` / �����O�� / p2�`6
�@�퐶���c���l���� / �c�蔎�V / p7�`11
�@�����݂����{���̌��� / �a�����v�� / p12�`18
�@�����{�ւ̈��`�d���l���� / �֖�T�F / p19�`24
�@�Ă̐H�ו�--�����Ɛ��� / �ԕ��юq / p25�`30
|
�h���܂�(��)�h��H�ׂ� / ���{���v / p31�`35
���{�ɂ�������̋N���Ɠ`�d�Ɋւ���C
�@�@�@�@���j�̍l�@/�����G�u/p36�`39
�q�_���r �t�����X�^���w�̌��� / �|���r�� / p40�`46
�q�l�Ãj���[�X�r / p6�`6,35�`35,46�`46
�q�����ژ^�r / p47�`48
�E |
�X���A�u�V�當�� = Ritual culture (16) �v���u�V�當���w��v���犧�s�����B�@ �@pid/7957040
|
���{��O���Ɍ���V�當�� / �N�䏟�V�i / p2�`18
���̓��ɂ������@�̓��퐫 / ���x�@�c / p19�`22
�c�苤�s / ��c�@�� / p23�`30
�i���V��̔w�i / �����y / p31�`39
�V�N�̏�����Ɠj�h�s��--�V���o�����t�ƁE�����Ƃ�
�@�@���ꍇ�𒆐S�Ƃ��� / �����A�V / p40�`48
�����̃C�L�~�^�} / �c����� / p49�`56
�C����ƈ / ���Ώ��b / p57�`64
|
���̗��j�ɂ����鐶���ƋV�當�� / �I�J�@�� / p65�`68
�u�V�ƒn�Ɓv�� / �k������ / p69�`72
�����͐S / �ҋ`�� / p73�`76
�U�蒃�̏K�� / ���Ԍ��O / p77�`89
�Ղ�̕ϑJ / �n�ӗǐ� / p90�`9
��[�N���̒���--�u�����̖��l�v�u���E�Ёv�ɂ��ӂ��/�L�R���/p99�`112
�o�Y�̕���--�}�N���r�L�𒆐S�� / �L���G�� / p113�`124
���l���V��̌��� / �y�q���Y / p125�`134 |
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (69)���W �l�Êw����݂��Ñ���{�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947830
|
���W �l�Êw����݂��Ñ���{
�@�o�_�̂�����Õ�����̊J�n / �n�Ӓ�K / p2�`13
�@�Βk�u�l�Êw����݂��הn�䍑�v���߂�����/��ˏ��d;��a��Y/p41�`51
�@�V�~�����[�V�����ɂ���Օ��z�̐��� / �y�쏺�� / p52�`67
�@�Õ�����ւ̈ڍs���̓����Љ�--
�@�@�@�@���k�֓������n���𒆐S�ɂ��� / ���{���N / p68�`77
�@�k����B�ɂ�����Õ��o�����̓y�� / �폼���Y / p78�`91
�@�Ñ�g���n���ɂ�����n������ / �����r�v / p92�`115
�@�Βk �퐶���ォ��Õ������--�O�A�l���I��
�@�@�@�@������{ / ����O ; ��a��Y / p116�`14
|
�@�הn�䍑�ւ݂̂� ���R���������ٓ��ʓW�}�^���/p147�`151
���{�̌Ñ�D(��) / ���ƍN�V�� / p152�`162
����S���u�\�s�c���̐��U�v�ɂ���/���菺��Y/p163�`165
���V�i�C�ɂ�����C�㑼�E��(��)
�@�@�@����r�����w�I�l�@ / ��ؖ��j / p166�`179
���ʕ��V�l--���Ǖ��̑��`����(��) / �勴�P��/p180�`199
�ߐ{�]�蕶�Ƒ����ݗ� / �ɓ��^�� / p200�`213
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p214�`240
�E
�E |
�P�Q���A�����G�O�Y���u�{�̑�. 14(5)(100) p58�`61�@���w�فv�Ɂu�����Ύ��L�\���{�ƒ��� (�ŏI��) ��Ƒ��z�ƒ��v�\����B�@pid/3475180
�@�@�@�@�@�����G�O�Y���u�����Ύ��L�[���{�ƒ��� (1�`10)�v�ɘA�ڂ����_���̈ꗗ�\
|
| �m�� |
�G���� |
���s�N�� |
�_���� |
�o���� |
| 1 |
14(1)(96)�@ p50�`53 |
1991-0 |
���{�ƒ��� (�V�A��) �����Ɩ� |
pid/3475170 |
| 2 |
14(2)(97) �@p50�`53 |
1991-02 |
���{�ƒ��� (2) �ߕ��ƋS |
pid/3475171 |
| 3 |
14(3)(98)�@ p52�`55 |
1991-04 |
���{�ƒ��� (3) ���Ղ�Ə㖤�� |
pid/3475172 |
| 4 |
14(4)(99)�@ p42�`45 |
1991-05 |
���{�ƒ��� (4) �[�߂̐ߋ��Ɠc�A���� |
pid/3475173 |
| 5 |
14(5)(100)�@ p50�`53 |
1991-06 |
���{�ƒ��� (5) / �i�\���Ȃ��̂��ߊm�F�v�j |
pid/3475174 |
| 6 |
14(6)(101)�@ p56�`59 |
1991-07 |
���{�ƒ��� (6) ���[�Ɩ~ |
pid/3475175 |
| 7 |
14(7)(102)�@p58�`61 |
1991-08 |
���{�ƒ��� (7) �����\�ܖ�ƍj���� |
pid/3475176 |
| 8 |
14(8)(103)�@ p58�`61 |
1991-10 |
���{�ƒ��� (8) �ފ݂Ƒ��z�M�� |
pid/3475177 |
| 9 |
14(10)(105)�@ p52�`55 |
1991-11 |
���{�ƒ��� (9) �V���Ղƈ
|
pid/3475179 |
| 10 |
14(11)(106)�@ p58�`61 |
1991-12 |
���{�ƒ��� (�ŏI��) ��Ƒ��z�ƒ� |
pid/3475180 |
|
|
| 1992 |
4 |
�E |
�P���A��㖱���u�V�E = The heavens 73(1)(800)�@p3�`5�Ap14�`14�@�����V���w��v�Ɂu�V���w���̂�����-4-�n����̐����̒a��-3-�E�̎R�{�ꐴ�搶�ؕĒ��̌�Ɛсv�\����B�@pid/3220463
�P���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (70)���W �Ñ�e�N�m�|���X�ƌ��z�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947831
|
���W �Ñ�e�N�m�|���X�ƌ��z
�@�𑀂�l���� / �~���� / p2�`17
�@���J���k�� �}������͌Ñ�n�C�e�N�s�s�������� / ���u�q ;
�@�@��������N ; �X�_�� ; ���c�N�Y ; ���J���� / p18�`34
�@���������V���|�W�E�� �Ñ�L���C�������Ƃ��̔w�i / ���u�q ;
�@�@���~���� ; �����v ; ���c���� ; ���،��a�� ; �������� ;
�@�@��������N ; �������� ; ���c�N�Y ; ���֏� ; �X����N/p35�`91
�@���{�����̌��������z�ɂ݂� / ������N / p92�`100
�@���z����̕�I / �я��� / p101�`105
|
�@���z����̕�II / ���^�� / p106�`109
���z�Ƙ`�� / ���i���i ; �X�_�� ; ���֏� / p110�`122
���������V���|�W�E�� �Ñ㉝���A�`�ƌ��z / ���֏� ; ���^�� ;
�@�@�@�����i���i ; �я��� ; �X�_�� ; �����F�K ; �a�����v�� ;
�@�@�@�������G�T ; ���J���� / p123�`173
�������̉B���� / �������b / p174�`191
���{�̌Ñ�D(��) / ���ƍN�V�� / p192�`202
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p203�`232
�Ñ�j�ʐM���ʔ� �؍�����o�y�����k�{�E�l�����s�ԕ���/�ҏW��/p233�`236
|
�R���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 3(3)(24)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425939
|
�����G�b�Z�C �\�N�O�̖k����z�� / �֖�Y / p2�`3
�����G�b�Z�C �X�̓s�\�k�� / ���ۋv�� / p4�`5
�����G�b�Z�C �k���̒lj��\��ǂ̒� / ������v / p6�`7
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �����̐� / �g���쑾�Y / p8�`12
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �k���̊X / ���Ύ� / p13�`20
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� ���̂��� �����̏��l��E�l���� / �������
/ p21�`27
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� ���o�̐�����
�@�@���k���̉����g�V�����h�̌|�l���� / �g��ǘa / p28�`34
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �C���e���Q���`���̒[�ߐ�
�@�@���D�v�Ɓw�k��������S�x / ����ȎO / p36�`42
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �V�ɂƖk�� ���邢�͘V�ɂ̖k�� / �����P�v / p44�`50
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �k����������ɂ� / �ː�F�Y / p51�`57
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �R���� ���� / �����P�v / p35�`35
���W �g�Â��悫�k���h�����߂� �R���� ������ / �g���쑾�Y / p43�`43
�ΕӖ��M(12)��̕��������ɂ䂩�� / �����r�j / p60�`63
�A�� ���{�̕��i�����(24)���ŏI�������̔��� / ��o���Z / p64�`69
�d�q����̊����_(12)�u���L�v�ƃ��[�v�� / �c������ / p70�`71
�]�ˎ���̊����a��(��) / ���열�v / p72�`76
�o���̑��Ɨ��Ղ̑� �������]�ȕ��������^ / ���F�� / p77�`81
|
���F�����̐����X�� �����E�o�L / ��g�~ / p83�`91
�A�� �������w�m�[�g(6)�u�Z�́v�Ɓu�o��v / ���Y�F�v / p92�`93
�A�� ���t�W�̕����R���e�N�X�g(24)���ŏI���_揂Ȃ� / �����i / p94�`99
�A�� ���m�w�̌n��(24)�V��V�� / �M���� / p100�`105
�A�� �A�W�A�̃}���K(24)���ŏI�u�����p�Y�`�v��`
�@�@������p�̓A�� / ����k�� / p107�`111
���A�W�A���j�̗��K�C�h(24)���ŏI��
�@�@���߁E����j�̈�ՁE�k�� / ��c�G�� / p116�`117
�����O�� �A�U�� �w�������Ă��̋L�x�����Ɏv�� / ���N / p58�`59
�����E�؍����̃��m�S�b �؍� �{�X(�o�X) / �˓c��q / p112�`113
�����ْT�K ���������� / p114�`115
�A�W�ANOW �W���P�ɔ��Ԃ������k���N / p118�`119
���] ���R���w�l�� ���ܔ��|���Z��x / �ҍN�� / p120�`121
���[�h�E�{�b�N�X / p82�`82
Q&A / p106�`106
�V���Љ� / p122�`123
���ɂ����C�u�����[ / p124�`125
�C���t�H���[�V���� / p126�`127
�E |
�R���A�Ñ㕶�w��ҁu�Ñ㕶�w (31)�v���u�Ñ㕶�w��v���犧�s�����B�@�@pid/6062667
|
���{���I<���W> / p1�`46
���W�E���{���I �w���x�̏���-���{���I�́u�j�v��
�@�@�����@�ɂ���/�������u/p1�`10
���W�E���{���I �w���{���I�x-���_-�{�����猩���ꍇ / �؎��� / p11�`20
���W�E���{���I �����ƌ��t���邢�͘a��Ɗ���̊��� / �R�c���� / p21�`26
���W�E���{���I �Ñ���{�̎���(�ӎ��ƕ\��) / �������V / p27�`35
���W�E���{���I �w���{���I�x�Ɛ��E�@��--���邢�́A
�@�@�����H�ɊJ���ꂽ�e�L�X�g/�֓��p��/p36�`46
�������g�̍\��--�Ñ�a�̂̏C���@�̊�b / �ߓ��M�` / p47�`56
|
�|���_--��������Ӗ��̃_�C�i�~�Y��/�g����I/p57�`67
�u���Ɍ���(��)�v�Ƃ��������Ƃ� / �^���� / p68�`7
�卑��_�b�̍\�z--�������
�@�@���\�Ȃ炵�߂�_��/�}����q/p79�`88
���
����̎��] / / p90�`9
�Ċ��Z�~�i�[���� / / p92�`98
������� / / p99�`105
�E |
�R���A�Ð�~�ꂪ�����j�w��ҁu�q�X�g���A = Historia : journal of Osaka Historical Association (�ʍ� 134) p.p1�`22�v�Ɂu�F�N�ՁE�����Ղ̖{���v�\����B�@�@�d�v�@�@��������}���ُ���ID�F3464017
�R���A�R�c�c�Z, �c���W�ҁu�s�����ț{�j���ۘ��c:1987���s�V���|�W�E���t��
�v���u���s��{�l���ț{�������v���犧�s�����B
�S���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (71)���W ���{�̌Ñ�j�����\����Ɣᔻ�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947832
|
���W ���{�̌Ñ�j�����\����Ɣᔻ
�@�Ñ㕶���j�����̉ۑ�/��c����/p2�`10
�@�U�В������ւ̋^��--�ݏr�j���̍������߂�����/�����L��/p11�`19
�@�`�Ɓw���{���I�x / ���G�Y / p20�`28
�@���z�̕����ƌÑ���{���� / ��ё��� / p29�`33
�@�����w����݂����{�̌Ñ� / �J�쌒�� / p34�`53
�@�L�I�_�b�����{�l��ʂɂƂ��Ď��Ӗ��Ɖ��l
�@�@�@���̔F����/�g�c�֕F/p54�`63
�@�u�`�l�v�Ƃ͂Ȃɂ�--���N�Ɠ��{�̌Ñ� / ���B�� / p64�`78
�Βk ���{�Ñ�j���߂�����--���ɘ`�Ɖ����
�@�@�@���W�ɂ��� / ����d�� ; ��a��Y / p79�`96 |
���Ñ㐯�M���_(��) / ���{�� / p97�`107
�n�j���̑����Ɠ��{�̑����Ƃ̔�r/�]�g/p108�`125���ʔԂȂ�
�͓��O�쌧�̌Õ����z�Ƃ��̈Ӗ�(��)/�O�c���l/p126�`139
�g���^�}�P�̐��̂����� / �ї��N�� / p140�`158
�����ێR�Õ��u�Ύ��ʐ^�v�^���L/�g�c���i/p159�`167
���C�Ǔ����Õ��Q���@�����T�v
�@�@�@��/���`��w�Z������/p168�`187
���C����̈�ՂƏo�y�╨�ɂ��� / �\�h�K / p188�`189
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p193�`229
�u����v�ɂ���--�����V���O���\�Z������
�@�@���ӂ�� / ��a��Y / p190�`192 |
�U���A�a���v�w��ҁu�a���v = Journal of the Wadokei-Gakkai (1)�v���u�a���v�w��v����n�������B�@pid/3201893
|
���̊ϔO / �ߍ]�_�{�{�i �����v�� / p1�`�P
�䂪���̎������x�ɂ��� / ���{//���� / p3�`14
�]�ˎ���̗�{�ōs�� / �n��//�q�v / p15�`24
�a���v�@�\�Ƃ��̍�� / ����//���e / p25�`29
���z�̐j / NAWCC��9�x���� ���䐟�v / p30�`31
�ɔ\���h�̐��h���V�ɂ��� / �c��//�|�j / p32�`41
�����v����^���L / �吼//���� / p42�`50
|
�䐬������̂��炭�莞�v / �V��//�P���Y / p51�`55
�v���� / �\�c�U�q / p56�`57
�Î��v�R���N�V�����̐��� / NAWCC��131�x�� �Έ�i�N / p58�`59
����̒��̎��� / ����//�� / p60�`63
��Ȏ��v / �p�����z / p64�`65
���z �e���v / �͍��� / p66�`66
�a���v���݃��X�g(����) / �㓡//���j / p67�`70 |
�V���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (72)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947833
|
��
���W �Ñ�̎��� ����V���{���Ƃ���`��--
�@�@�@�������M���߂����� / ��a��Y / p68�`100
���W �Ñ�̎��� �m���̐����Ɗ����ɂ��� / �H������ / p101�`124
�ŋ߉����Ղ̏o�y�╨�̉��߂��߂���
�@�@�@����̖��_ / �\�h�K / p125�`138
�Đ����J��Ɛl������--���Q����
�@�@�@���q���Č����Ă��� / �ᏼ�Lj� / p139�`158 |
���Ñ㐯�M���_(��) / ���{�� / p159�`171
�͓��O�쌧�̌Õ����z�Ƃ��̈Ӗ�(��) / �O�c���l / p172�`181
�V���V�c�\�l�N�́w���Q�x�ɂ��� / ��ь��i / p182�`185
�Βk ���ÁE����Ղ̘O�t��
�@�@�@���G���߂����� / ����d�� ; ��a��Y / p186�`199
���ÁE���̘O�t�G�̈Ӗ� / �����^ / p200�`202
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p203�`237
�E |
�W���A�_���w����u�_���w (153/154)�v�����s�����B�@pid/2263773
|
�_��������E�������߂����� / �H���s�l / p1�`23
��������c�s�����_�Џ��� �����另�V�L--����Ɩ|��/�����c����/ p24�`99 |
�F�N�Տj��(�j���Љ�) / �X�c�N�V�� / p100�`106
�E |
�P�O���A�ߓ��鏺���u��������ъ��������� 38(0) p.122-127�v�Ɂu�~���M�������Ɍ��������ꂽ�S�@�\�ω��Ɠ~�����ٓI�`����(�Z�~�i�[�u�ቷ�Ɛ����v)�v�\����B�@�@ J-STAGE
�P�Q���A�s���̌Ñ㌤����ҁu�s���̌Ñ� 14 �v���u�r���b�W�v���X�v���犧�s�����B�@�@pid/4422387
|
�Óc���F�u���^ ���j�Ɖ̂̐^�� / p6�`56
�C���^�r���[ �O�p���_�b���͔ږ�Ă̋���--
�@�@���v��Y��Y���ɕ��� / ���c�F�� / p57�`75
���W�E�`�l�`�Ǝהn�㍑ / p77�`77
鰎g�����Ɓw鰎u�`�l�`�x�̐V���ȗ��� / �؍��h�v / p78�`93
�הn�㍑�̖ŖS--�Ñ��B�̉������ / ��c�� / p94�`105
�w�O���u�x�̗��P�ʂɂ���--�u�ԕǂ̐�v���^��/�Γc���F/p106�`122
�w�@���k���l���`�x�̏ؖ�--������̍s�H / ���r / p123�`135
�����_�� / p137�`137
�_���c�@���b�̔\�v�f / �����H�x�� / p138�`148
�`���̗���--�}���N�ֈ��
�@�@�����o���V�q�̍��̖@�����x / ���c�C / p149�`171
���@�̌Ñ�N����--���������Ɍ���Ñ㑜 / �É�B�� / p172�`181
�쒆�����ӕ�F���̑�����Ɣ���v�ґ��ɂ��� / �`���� / p182�`197 |
�Ђ�� / p198�`198
�ɓs���A��]�˂̓� / �֓������ / p198�`203
�ꕶ�l�̊X���̃��}�� / �A���d�� / p204�`206
�ֈ�N�͐����Ă��� / �����D / p207�`208
�u�j��v���l���� / �x�i���O / p209�`212
�����I�Ñ�̒��̔��R�M�� / ����p�� / p213�`216
�s���̌Ñ㌤����̏Љ� / p217�`226
�����w���ۉ�c�ɂ�����Óc�j�w�̏Љ� / p����
�gGOLD SEAL AND KYUSHU DYNASTY�h
�@�@��(�u����Ƌ�B�����v) / �㑺���N / p243�`227
��E�����W / p76�`76
���e�K�� / p136�`136
�ҏW��L / p244�`244
�E |
�P�Q���A��㖱���u�V�E = The heavens 73(12)(811) p363�`365 �����V���w��v�Ɂu�V���w���̂�����(��2��)-3-�萯�p�ƓV���w�v�\����B�@�@pid/3220474
�P�Q���A���[��������w�I�v�ҏW�ψ���ҁu����w�I�v = Reitaku University journal (�ʍ� 55) p.p1�`21�v���u�_��̃n�j���̐_��v�\����B |
| 1993 |
����5 |
�E |
�P���A�u�Ȋw���� 53(1)(625)�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2335468
|
�n�C�e�N�������u�Ñ�j�̓�v<���W> / p12�`25
�v�����g��I�p-������--���{�̈��̃�-�c�͗g�q�]���� / �����G�u / p12�`17
DNA����--���{�l�ƃC���f�B�A���͢�Z��������� / ���X�ؕq�T / p18�`21 |
���ʕ��ͥ�A�C�\�g-�v����--�����l�ނ�
�@�@���x�W�^���A�������� / �ԑ�� / p22�`25
(��) |
1���A�u�V�E = The heavens. 74(1)(812)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@ pid/3220475
|
�\������ H���ɂ�鍕�_�����̈� / �����O
���G�ʐ^ OAA����̋L�O�ʐ^
�V���w���̂�����(��2��)-4-�����Ɨ�̔��B / ��㖱 / p3�`6
��10�f���͑��݂��邩 / ���J���Y / p6�`13
1993�N�̓��E���H����ѐ����̓��ʌo��-2- / �R������ / p13�`19
�����Ɏ��Y������Â� / ����P�� / p20�`22
���f���j���[�X / ���J���Y / p22�`22
|
�y�V���Љ�z / ���J�� / p23�`24
���z�ی���No.264 / ��ؔ��D / p24�`26
�ΐ��ۂ����(No.2) / �� ; ���� / p27�`28
�إ�y���ی��� / �{�� ; ��c / p28�`29
�����ی��� / �M ; ��c ; ��� ; �a�� ; ��� / p29�`31
�x������ / ���{ ; ���� ; �R�c / p32�`32
��V�E���73�����ڎ� / / p33�`34 |
|
��㖱���u�V�E72(788�`812)�@�u�V���w���̂�����-1�`7�A��2��1�`4�v�v�̓���\
| . |
�G�����ƕ� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
72�i1�j(788) p.p3�`5 |
1991-01 |
-1-�V���w�̎n�܂� |
. |
pid/3220451 |
| 2 |
72�i3�j(790) p.p67�`69 |
1991-03 |
-2-�����̎n�܂� |
. |
pid/3220453 |
| 3 |
72�i4�j(791) p.p99�`102 |
1991-04 |
-3-�����̂�����-1- |
. |
pid/3220454 |
| 4 |
72�i5�j(792) p.p131�`134 |
1991-05 |
-3-�����̂�����-2- |
.. |
pid/3220455 |
| 5 |
72�i11�j(798) p.p344�`346 |
1991-11 |
-4-�V���w�̔F���ƒn��-1- |
. |
pid/3220461 |
| 6 |
72�i12�j(799) p.p375�`377 |
1991-12 |
-4-�n���̒a��-2- |
. |
pid/3220462 |
| 7 |
73�i1�j(800) p.p3�`5 |
1992-01 |
-4-�n����̐����̒a��-3- |
. |
pid/3220463 |
| 8 |
73�i2�j(801) p.p39�`43 |
1992-02 |
-5-�ł��߂��P���E���z�@ |
. |
pid/3220464 |
| 9 |
73�i3�j(802) p.p71�`74 |
1992-03 |
-6-���z�ƒn���@ |
. |
pid/3220465 |
| 10 |
73�i4�j(803) p.p103�`109 |
1992-04 |
-7-�V���w�̌�����B |
. |
pid/3220466 |
| 11 |
73�i8�j(807) p.p231�`233 |
1992-08 |
(��2��)-1-�V���w�����̍� |
. |
pid/3220470 |
| 12 |
73�i9�j(808) p.p263�`265 |
1992-09 |
(��2��)-2-���Q�Ɛ����@ |
. |
pid/3220471 |
| 13 |
73�i12�j(811) p.p363�`365 |
1992-12 |
(��2��)-3-�萯�p�ƓV���w�@ |
. |
pid/3220474 |
| 14 |
74�i1�j(812) p.p3�`6 |
1993-01 |
(��2��)-4-�����Ɨ�̔��B |
. |
pid/3220475 |
|
�Q���A�u�V�E = The heavens. 74(2)(813) �����V���w��v���犧�s�����B�@�@ pid/3220476
|
�\���ʐ^ �����{�����̓����v
���G�ʐ^ 12��24�����̕������H / ��������
�z��-�X P.�^�b�g�� / ���J��//��Y / p39�`41
�씼���̓����v / �吼//���� / p41�`43
�䂪���F�^-5- / ��//�ےj / p43�`46
�ΐ��̖͗l�Ƃ��̖�-30- / ����//�P�v / p46�`49
�y�V���j���[�X�z / p49�`50
���f���j���[�X(5��) / ���J�R��Y / p50�`52
���f���j���[�X(11��) / ���J���Y / p52�`54 |
�y�V���Љ�z / ���J���Y ; �������B / p54�`56
���z�ی���No.265 / ��ؔ��D /56�`59
�ΐ��ۂ����(No.3) / �� ; ���� / p59�`60
�إ�y���ی��� / �{�� ; ��c / p60�`61
�a���ی��� / 萕� / p61�`62
�����ی��� / �M ; ��c ; ��� ; �a�� ; ��� / p62�`65
�y�����z / �R�{�i / p62�`62
�x������ / ���{ ; ���� ; �R�c / p66�`66
�E |
�Q���A���c�F�N ���w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 4(2)(35)p68�`73�v�Ɂu���t�тƂƗ� ���z�������Z�N�ɂ������āv�\����B�@ pid/4425950
�T���Q�X���`�R�O���A���Îs����ّ�z�[���ōs��ꂽ�V���|�W�E���ŁA���J���k��w�C�l���}�������x���J�����B
�T���A�u���{�����̌��_���� : �v���O���� : '93�����ؗF�D����V���|�W�E���v���u�g�샖����Ղƒ����]�앶����T��V���|�W�E�����s�ψ���v�ɂ�芧�s�����B
�T���A�_�{�i���L���u���_ (164) �@�\���@�_�{�i���v�Ɂu����q�v���f�ڂ����B �@pid/7930707
�V���A�n���������u��̑�n : �u��̓��v����݂���{�̕����v���u���w�فv���犧�s����B�@�@
|
��앶���������ɖ₤
�P�@���̌����i�q�R�Ɉ��r
�Q�@�A�W�A�̈�앶�����q�����Ɉ��r |
�R�@���{�ւ̎�e�ƓW�J�q�C��n������r
�S�@�u�C��̓��v�V�l
�E |
�V���A�Ñ�w�������� �u���A�W�A�̌Ñ㕶�� (76) ���W �Ñ���߂��鏔���v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947837
|
���W �Ñ���߂��鏔���
�@�_�A�E��t�E�Q����(��) / ���i���i / p2�`15
�@�ߍ]��Ë{�Ǝu�ꊿ�l / �R���K�v / p16�`50
�@�h��̕ςƃ��J�^�P�� / �i��ËL�v / p51�`73
�@�w���{���I�x�Ƒc��`��--�n�c�E��c�E
�@�@�@����̗p����߂����� / �c���� / p74�`92
�@�w���{���I�x�Ҏ[���߂���A�d(��)/��ˑד�Y/p93�`105
�@�Ñ�u��̓��v�l / ���ƍN�V�� / p106�`126
�@�g��P����Ղɂ݂�������
|
�@�@�@���K���ɂ��� / �щؓ� / p127�`139
�@�ÖE���q�n���͎הn�䍑�� / �|����v / p140�`160
�@���t�тƂ̂Ȃ��̊O�� / �Бq�t / p161�`167
�@��썑�̕����ƃy���V�A(��) / ��㎟�j / p168�`179
�@�_��ȃn�j���Ɠ��{�́u�c�J���v�K�� / �]�g / p180�`199
�@�h�h�i���Ɓj�̐��z--(����1)�������[�g / ���J�� / p200�`211
�@�Q�����̏o���Ɠꕶ�y��--�Q���Ɨ�����
�@�@�@�@���l�Êw(��) / ��a��Y / p212�`240
�@�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p241�`272 |
�W���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 4(8)(41)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425956
|
�����G�b�Z�C ��������� / ���c�� / p2�`3
�����G�b�Z�C �؍��ԑg���� / ���c���� / p4�`5
�����G�b�Z�C �~�̉� / �W�c�m / p6�`7
���W ���E�C�l�̗�����
�@�@�@���A�W�A�̐���k�앶�� �����s�����猩��/��ё���/p8�`11
�@�@�@��̂����� / �����m��Y / p12�`21
�@�@�@�_��̍l�Êw�ƒ������̋N�� / �����T�� / p24�`29
�@�@�@����S�����g�����h�ƕ���
�@�@�@�@�@���~���I���̂ӂ邳�Ƃƕ��� / �����G�O�Y / p30�`35
�@�@�@���N�����̓� ���W���ɂ݂�_�k����/���J��/p38�`43
�@�@�@�ꕶ����̐H���� / �X�쏹�a / p46�`50
�@�@�@�퐶���̂����炵������ / �H�y�P�� / p51�`56
�@�@�@�R���� ��q / ���}���D�F / p22�`23
�@�@�@�R���� ���`�����̌n�� / �����G�O�Y / p36�`37
�@�@�@�R���� �X�Y�������̌����i�����߂�/����F��/p44�`45
�V�A�� �A�W�A���l�̗�(1)�����ƕ��l
�@�@�����A�W�A�̎��q���l / ������ / p57�`62
�ΕӖ��M(28)�j�ċʔt�ɉԂ����� / �����r�j / p64�`67
�d�q����̊����_(29)�ɂȂ銿���ӎ�/�]�n���/p68�`69 |
��a�O�R�̎�p�� �u���n�M�v��
�@�@���u������p�v�̎R / �g��T�q / p72�`77
�A�� �����̂͂Ȃ�(5)�k�v�̈��(2) / �ĎR�Б��Y / p80�`81
�����|�\���ڂ�����(9)�s���ȍق���
�@�@������������ / ������ ; �c�����a�q / p82�`90
�A�� �������w�m�[�g(23)�u���̐��v��
�@�@���u���̐��v(�O)/���Y�F�v/p98�`99
�A�� �������j�U��(17)�m��u����� / ����N / p100�`105
�A�� ���A�W�A�����̗�(17)�`�K���M��(2)/�����G�O�Y/p106�`107
�A�� ���m�w�̌n��(41)�Ғ��l�Y / ���Ԋ��O / p108�`113
�A�� �A�W�A�V�l�T����(17)���|�d�ē�i
�@�@���w�H�e�̕���x����遃����/�����F�I ; �˒����v/p114�`118
�����O�� �A�C�k��w�K�^���̌��� / ����T / p70�`71
�����ْT�K �k�������� / p78�`79
�n����ǂ�(�ŏI��)��n����̎v�z / ���䐟�v / p91�`91
�����̐��E �`�n�c�� / p92�`93
�V�����`�[���� / �R�c���I / p94�`95
�����̐؎� �_�c / p97�`97 (
�߂���̂��ׂ��� from�y�L�� ���ׂ��̃X�X��/�J��h�q/p120�`121 |
�X���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 4(9)(42)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����Bpid/4425957
�@�@�A�� ���m�w�̌n��(42)�L�˖Ύ�/�i�c�p��/p106�`111 �@�@�@�@�@��p�̎��_�M��/��ؖ��j/p97�`105
�P�O���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (77)���W �ꕶ�̐}���ƐM�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947838
|
���W �ꕶ�̐}���ƐM��
�@�����`�Z���Ɍ��鏗�_�̎q�{�ƎY���̕\��/�g�c�֕F/ p2�`16
�@��䌴�̘_--�R�����j�u���v�w�̉���Ƃ��̍ē�/���؋��M�g/p17�`36
�@�L�ʕP�̗��}�Ɠꕶ���I(��)�q�X�C�ƎL�Ǝ��n��� / �c���� / p37�`56
�@�ꕶ����̋T�`�y���i�̐}�� / �����閾 / p57�`72
�@�ꕶ�y��́u�ꕶ�v�ƉQ����--�Q���Ɨ�����
�@�@�@���l�Êw(��)/��a��Y/p73�`106
�_�A�E��t�E�Q����(��) / ���i���i / p107�`122
��썑�̕����ƃy���V�A(��) / ��㎟�j / p123�`141
|
�Ñ���{�ɂ�����~���̓��̏o��--(���̈�)�����V�c
�@�@�@���ɂ��V�_���J�� / ��t���T�� / p142�`157�@�d�v
�`���j���̓o��ƌp�� / �b��K�ߘY / p158�`171
�_�������̊C����--�`���̐��b�ƋV��(��)/�Ŗ����/p172�`179
�O�p���_�b���l--�i����N����
�@�@�@���O�p���_�b�� / ���c���� / p180�`201
�w���{���I�x�Ҏ[���߂���A�d(��) / ��ˑד�Y / p202�`211
�h�h�̐��z(����2)�k��胋�[�g / ���J�� / p212�`225
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p226�`256
|
�P�P���A���X�؍���, �X���[�q�ҁu���{�����̋N�� : �����w�ƈ�`�w�̑Θb�v���u�u�k�Ёv���犧�s�����B
�d�v
|
���{�����̋N�����l���� : ��`�w�Ƃ̑Θb�Ɋ��҂������ / ���X�؍���
��`�w�ƌn���_ : �p�^�[������v���Z�X�� / �X���[�q
���{�l�͂ǂ����炫���� : ��`�w����݂������S���C�h�̊g�U / ������
���{�̉ƒ{���� : ���̌n���Ɠ`�� / ���V��, �c�����Y�� |
�}�E�X����݂����{�l�̋N�� / �Đ씎��, �X�e�a�Y
��`�w����݂���̓`���ƈ�앶���̎�e / �����m��Y
�G���ƃ��`�̖����A���w / ��{�J�j
�哤���y�H�i�̋N�� / �g�c�W�� |
�P�P���A�s���̌Ñ㌤����ҁu�s���̌Ñ� 15�v���u �r���b�W�v���X�v���犧�s�����B�@pid/4422388
|
�Óc���F�u���^ �}������ƋߋE�剤 / �Óc���F / p6�`61
�C���^�r���[ �Ñ�V�c���Ɠ��{�C����--���菺��Y���ɕ��� / ���菺��Y ; ���c�F��/p62�`74
�w�O���u�x�����_ �w�O���u�x�ɂ�����Z���E�������݂̘_���� / �`���� / p75�`92
�w�O���u�x�����_ �Z�����E�������̍Č��� / �ѓ��i�� / p93�`109
�u��B�v�̐��� ��B��_��--�����j���ɂ݂���u��B�v�̕ϑJ / �É�B�� /
p110�`123
�u��B�v�̐��� ��B�̏����͂ǂ̂悤�ɐ݂���ꂽ�� / �����V�q / p124�`137
�����_�� �w�@���x�ɂ݂��闬����--�����S�̓��E���s�ܓ��ɂ��Ď���C��/���c�C/p138�`156
�����_�� ��B����������݂�w���{���I�x�����ߒ��Ƌ敪�̌���/�O���j/p157�`169
�Ђ�� �w�Î��L�x�̐��� / ��Η��F / p170�`174
�Ђ�� ���ǂƖS���̖�--�Ö��S�O�����ǂ� / �x�i���O / p175�`182
�Ђ�� �L�E�I�E���I�ɂ����錳���̖��� / �֓������ / p183�`188
|
�Ђ�� ������̉�� / ����p�� / p189�`192
�Ђ�� �w����A<�`��>�n�}�x�ɂ��� / �����D / p193�`201
�Ђ�� �w�势���x�̔��� / �R���T / p202�`205
�����m�[�g �N���Ɠ`�d--�|�E�y��E�͔|�A���_ / �֓����� / p206�`215
�����m�[�g �Ñ��̌����Ɨ���\�̍쐬 / �R���E�C / p216�`236
�����m�[�g �w�����{�I�x�ɂ�����u�]�v�̗p��Ɓu�]�v���̎{�s/�Γc���F/p237�`249
�s���̌Ñ㌤����̏Љ� / �֓����� / p250�`260
���e�K�� / p261�`261
��E�����W / p262�`263
�ҏW��L / ���c�F�� ; �É�B�� ; �Γc���F ; ����F�v ; �����H�x��/p264�`264
�E |
�P�P���A�u�l�Êw�j���� = Studies on the history of Japanese archaeology (2) �v���u���s�ؗj�N���u�v���犧�s�����B�@pid/4427237
|
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� �������}�ʼn���� ���̊G���`���ꂽ�y��Ђɂ���
/ ������ / p2�`5
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� �u�Î�����v�ƐX�{�Z�� / ��a�G / p7�`12
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� ���Òr�ł̑w�ʔ��@�̎���--1922�N19�˂̐X�{�Z�� / �ɓ���
/ p13�`18
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� �~�������̌Õ��挤�� / �����F�v / p19�`22
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� �I�N����������^���w�� / �R�{��a / p23�`31
�y���W�z �X�{�Z���̑O���� �X�{�Z���Ɠޗǎ��㕭�挤���ɂ��Ă̊o�� / ���c�D��
/ p33�`44
���_�l�� �u��n����ւƔ_�Ɓv�̍����I�Ӌ` / �R��� / p45�`50
���_�l�� ���эs�Y�u�퐶���y��̗l���\���v�̈Ӌ` / �ԐL�� / p51�`57
�������� �X�{�Z������ژ^�E�N�� / ���s�ؗj�N���u / p3�`31 |
�P�Q���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 4(12)(45)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425960
|
���W �����{�����z--���̋����Ǝ��� ��������̓��{��--
�@�@�����N�����̘`�� / �c��a�� / p41�`46
�A�W�A���l�̗�(5) ���l�Ƃ��̓`�d--���A�W�A�̗쒹���l/������/p60�`65
���]����̍l�Êw�V����--�h�铌�A�W�A
|
�@�@���Ñ㐢�E�ŌÂ̏�s����/������/p76�`85
�A�� ���m�w�̌n��(45)���V�K���/���V�F�O/p104�`109
�����ْT�K �����Q���L�O�� / p86�`87
�q�����r |
�P�Q���A���A�W�A�̌Ñ㕶�����l�����l�����ȉ�ҁu�Ñ㕶�����l���� (29)�v�����s�����B�@pid/7951413
|
����Z�����W�� ��B�Ɏc��A�C�k�����̍��� / ���c�� / p2�`16
����Z�����W�� �퐶�l�Ɠ��������ꕶ�l / �ɓ��ʍO / p17�`25
���R�n�����������������W�� �O���I�ȑO�̖k���V�q�R�n�����̗��j�E
�@�@�@���̈�E�����P��(�O�E�l) / �b�㓹�V / p26�`45
���R�n�����������������W�� �p�\�̗��͏_�R���뉤���� |
�@�@���������ÂȂ� / ��c�� / p46�`71
�w���{���I�x�ҔN�̓������ / �䌴���J / p72�`85
�V�q�V�c�ƓV���V�c�̏o�� / �ώ� / p112�`140
�q�����r
�E |
�Z���̔N�A�a�����v�����u���w�G�� 43(4) p.589-602�v�Ɂu��B�k���Ñ��Ղ̒Y���Ă̗������ψقɊւ���l�ÁE��`�w�I�����v�\����B
J-STAGE�@�@�d�v |
| 1994 |
6 |
�E |
�P���A�Ñ�w���������u���A�W�A�̌Ñ㕶��. (78)�@���W �Ñ�̏����v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947839�@
|
���W �Ñ�̏���
�@�Βk �Ñ���{�̏������� / ����d�� ; ��a��Y / p2�`25
�@���Ï����,���{�̑��V���@������!--���܂�ɂ��ߏ��]������Ă���
�@�@�@��,���{�ŏ��̏��� / �L�c�L�P / p26�`33
�@�c�ɁE�Ė��V�c / ���R���s�j / p34�`46
�@�����V�c�̎�p / �g��T�q / p47�`55
�@�Ñ�̏I���̉e��--�{���E��l���e����q/�R���q�b�q/p56�`64
�@詐_�E�ϐΒˌÕ��ƋR�n / �������V / p65�`73
�@�����ӏ����猩���T�`�y���i / �����閾 / p74�`83 |
�@�w�돑�x�̕}�K�� / �ї��N�� / p84�`102
�@ �w���g�q�x���l--�������̒�N / �k�_�O / p103�`111
�@�Ñ�ɂ�����~���̓��̏o��(����2)--���{�e�n�Ɍ�����
�@�@�@�@���~���̓��̏o�� / ��t���T�� / p112�`139�@�d�v
�@�h�h�i���Ɓj�̐��z--����3 �V���}�j�Y�� / ���J�� / p140�`154
�@�ꕶ�y��̎ւƖ���Q����--�ꕶ�Ɨ�����
�@�@�@�@���l�Êw(�O) / ��a��Y / p155�`190
�@�_�������̊C����--�`���̐��b�ƋV��(��)/�Ŗ����/p191�`201
�@�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p202�`236 |
�Q���Q�R���t�A�����V���[���Ɂu���{�̃R���A�]��N�����E�����̋��������ŕ���E�Ñ���`�q�̌����i�ށv�Ƒ肵�����o���ŁA�a�����v���A�X���[�q�A�����m��Y���̌��������\�����B
|
�͔|��ƈ�앶���^�i�����������������シ�钆�ŁA�j���{�_�k�����̌��������Ă��鍲�X���i�����j���́u�]��Ŕ_�k���n�܂�������A�_��͂܂����Ί펞�ゾ�����Ƃ��������L�͂ɂȂ��Ă��āA�_��N�����͓���Ȃ��Ă����͎̂��������A���Ƃ����Ă܂����͓I�����E�E�E�E�E�E�v�B�]����ɏ�芷����ׂ����ǂ����A�܂������Ă��邻�����B�^���̓_�A�n�����́u�A�b�T���E�_����͍��ł��������Ǝv���Ă���v�Ɩ������B�u���͐A���Ƃ��Ă̈��_�k�̋N���͕ʕ��B���ꂪ������������Ė��f�B
�@�@�i���E�r���E���̓����̐V���L����ǂ݂Ȃ���A�n�����m�̌����̐��ʂ�V���ɐ݂��悤�Ǝv�����B�Q�O�Q�Q�E�X�E�P�U�@�ۍ�j |
�R���A��{���ꂪ�u�������� 6 p.319-324�v�Ɂu<���]�ƏЉ�>�n���������w��̑�n-�u��̓��v����݂���{�̕����x
�v���Љ��B
�R���A�u�������ɂ�. 5(3)(48)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4425963
|
�����G�b�Z�C ���j�̂Ȃ��̋� / ��o���Z / p2�`3
�����G�b�Z�C �����������s / �I���M�v / p4�`5
�����G�b�Z�C �����̑傫�� / ���c�G / p6�`7
���WI �ߐ����A�W�A�ƃL���X�g���\������������ �\�Z���I���[���b�p��
�@�@���A�W�A�� / �G���Q���x���g�E�����b�Z�� ; �������p / p8�`17
���WI �ߐ����A�W�A�ƃL���X�g���\������������ ���A�W�A�z���̋��_�E
�@�@���}�J�I / �������p / p18�`24
���WI �ߐ����A�W�A�ƃL���X�g���\������������
�@�@�����ؐ��E�ƃL���X�g������ / �g�c�� / p25�`30
���WI �ߐ����A�W�A�ƃL���X�g���\������������ �L���X�g���Ə\�Z�E�����I�̓��{
�@�@���L���V�^�������猩�����������̏o� / ������ / p31�`36
���WI �ߐ����A�W�A�ƃL���X�g���\������������ �L���X�g����
�@�@�����A�W�A�ɂȂɂ������炵���� / ���c�� / p37�`43
���WII �����k� ���Ă̓��m�w / �~���R ; �z�g�`�M ; ���c���Y ; �X���F�v / p44�`56
�ΕӖ��M(35)���ŏI�� ����ꂪ���O�l���� / �����r�j / p58�`61
�A�W�A���l�̗�(8)�P���̌n�� ���A�W�A�̗쒹���l / ���c�L�� / p62�`67 (
���ʂ̈ٗށE�f��̈ٗ� / �鏷 / p68�`73
�A�� �����̂͂Ȃ�(12)��v�̈��(5) / �ĎR�Б��Y / p74�`75
�d�q����̊����_(36)���ŏI�� ���E�̒��̓��{����߂����� / �I�c����Y
/ p76�`79 |
�A�� �������w�m�[�g(30)�u�_�S�����v�̃C���[�W / ���Y�F�v / p88�`89
�A�� �������j�U��(24)���ŏI�� �i�n�J�Ɋ��� / ����N / p90�`95
�A�� ���A�W�A�����̗�(24)���ŏI�� �F�����Ǝ˓��_�b�̍L����/�����G�O�Y/p96�`97
���A�� ���m�w�̌n��(48)���ŏI�� ���c�i�l / ���c���� / p98�`103 (
�A�� �A�W�A�V�l�T����(24)���ŏI�� �M�̊ē�i�w����A�킪���@
�@�@���P���ʕP�x����� / �Ύq�� ; �˒����v / p104�`113
�����̐؎聃�ŏI�� �u�ёa��100�N�v / p57�`57
�����O�����ŏI�� '93����������t�F�X�e�B�o���ɎQ������ / ���ˍG / p80�`81
�����ْT�K���ŏI�� �����w�Z / p82�`83
�����̐��E���ŏI�� �n���͔����发�w�V�q�x / p84�`85
�V�����`�[���偃�ŏI�� / �R�c���I / p86�`87
�߂���̂��ׂ���|from�\�E�����ŏI�� ���O���ꂱ�� / �˓c��q / p116�`117
�A�W�ANOW �h�����Ñ㒩�N�̎n�c�u�d�N�v / p118�`119
���] ���������w�O���u���`�̐��E�x / �x�� / p120�`121
Q & A / p114�`114
���[�h�E�{�b�N�X / p115�`115
�V���Љ� / p122�`123
���ɂ����C�u�����[ / p124�`125
�C���t�H���[�V���� / p126�`127 |
|
�A�� ���m�w�̌n��(1)�`�i48�j�@����\
| �E |
�G������ |
���s�N�� |
�Ώێҁ^���M�� |
�L�� |
�q���� |
| 1 |
1(1)(1)���m�w�̌n���i1�j p92�`96 |
1990-04 |
������ / �a��l |
|
pid/4425916 |
| 2 |
1(2)(2)���m�w�̌n���i2�j p92�`96 |
1990-05 |
�Óc���E�g / �a��l |
|
pid/4425917 |
| 3 |
1(3)(3)���m�w�̌n���i3�jp94�`98 |
1990-06 |
�����ɋg / ������ |
|
pid/4425918 |
| 4 |
1(4)(4)���m�w�̌n���i4�j p100�`105 |
1990-07 |
��J���� / ��R��s |
|
pid/4425919 |
| 5 |
1(5)(5)���m�w�̌n���i5�jp100�`105 . |
1990-08 |
�Γc���V�� ; �a�c�v�� |
|
pid/4425920 |
| 6 |
1(6)(6)���m�w�̌n���i6�j p100�`105 |
1990-09 |
������ ; �~���� |
|
pid/4425921 |
| 7 |
1(7)(7)���m�w�̌n���i7�jp100�`105 |
1990-10 |
�������� / �����F�Y |
|
pid/4425922 |
| 8 |
1(8)(8)���m�w�̌n���i8�j p100�`105 |
1990-11 |
�_�c�k�� ; ����R�� |
|
pid/4425923 |
| 9 |
1(9)(9)���m�w�̌n���i9�jp100�`105 |
1990-12 |
��ؑ�� / �g�c�Ћ� |
|
pid/4425924 |
| 10 |
2(1)(10)���m�w�̌n��(10) p100�`105 |
1991-01 |
��،Y / ���V�G |
|
pid/4425925 |
| 11 |
2(2)(11)���m�w�̌n��(11) p100�`105 |
1991-02 |
�H�c�� / �Ԗ�p�� |
|
pid/4425926 |
| 12 |
2(3)(12)���m�w�̌n��(12) p102�`107 |
1991-03 |
�߉ϒʐ� / �c������ |
|
pid/4425927 |
| 13 |
2(4)(13)���m�w�̌n�� (13) p100�`104 |
1991-04 |
�ؐ��Z / ���J�^�� |
|
pid/4425928 |
| 14 |
2(5)(14) ���m�w�̌n��(14) p103�`108 |
1991-05 |
�����Q�� / ���c�퐬 |
|
pid/4425929 |
| 15 |
2(6)(15) ���m�w�̌n��(15) p101�`106 . |
1991-06 |
�K��諑� / ��g�� |
|
pid/4425930 |
| 16 |
2(7)(16)���m�w�̌n�� (16) p101�`106 |
1991-07 |
�ёו� / ���c�� |
|
pid/4425931 |
| 17 |
2(8)(17)���m�w�̌n�� (17) p99�`104 . |
1991-08 |
���폇���Y / �_���`�� |
|
pid/4425932 |
| 18 |
2(9)(18)���m�w�̌n���i18) p101�`106 |
1991-09 |
��쒼�� / ��쒼�� |
|
pid/4425933 |
| 19 |
2(10)(19)���m�w�̌n���i19) p99�`104 |
1991-10 |
�s���k�T���l���Y / �����q |
|
pid/4425934 |
| 20 |
2(11)(20)���m�w�̌n�� (20) p100�`105 |
1991-11 |
�����`�Y / ���J�� |
|
pid/4425935 |
| 21 |
2(12)(21)���m�w�̌n��(21) p94�`99 |
1991-12 |
�͌��d�C / ���R���O |
|
pid/4425936 |
| 22 |
3(1)(22)���m�w�̌n���@(22) p98�`103 |
1992-01 |
�����F�V�g / �F�쐸�� |
|
pid/4425937 |
| 23 |
3(2)(23)���m�w�̌n��(23) p100�`105 |
1992-02 |
����T�� / ���c���V�� |
|
pid/4425938 |
| 24 |
3(3)(24)���m�w�̌n���i24�jp100�`105 |
1992-03 |
(24)�V��V�� / �M���� |
|
pid/4425939 |
| 25 |
3(4)(25)���m�w�̌n���i25�jp106�`111 |
1992-04 |
�@�@/ �������� |
|
pid/4425940 |
| 26 |
3(5)(26)���m�w�̌n���i26�jp102�`107 |
1992-05 |
���쎞�Y / �����^�u�Y |
|
pid/4425941 |
| 27 |
3(6)(27)���m�w�̌n��(27)�@p104�`109 |
1992-06 |
������ / �c���r�� |
|
pid/4425942 |
| 28 |
3(7)(28)���m�w�̌n��(28)p106�`111 |
1992-07 |
���R��� / �D�؏��n |
|
pid/4425943 |
| 29 |
3(8)(29)���m�w�̌n���i29)p104�`109 |
1992-08 |
�g��K���Y / �a��l |
|
pid/4425944 |
| 30 |
3(9)(30)���m�w�̌n��(30)p108�`113 |
1992-09 |
���T���Y / ���V���� |
|
pid/4425945 |
| 31 |
3(10)(31)���m�w�̌n��(31)p106�`111 |
1992-10 |
�Εl�����Y / ����� |
|
pid/4425946 |
| 32 |
3(11)(32)���m�w�̌n��(32)p108�`113 |
1992-11 |
�m��c�@� / �r�c�� |
|
pid/4425947 |
| 33 |
3(12)(33)���m�w�̌n��(33)p108�`113 |
1992-12. |
�F��N�l / �A��l�� |
|
pid/4425948 |
| 34 |
4(1)(34)���m�w�̌n��(34) p108�`113 |
1993-01 |
�~������ / �c���� |
|
pid/4425949 |
| 35 |
4(2)(35)���m�w�̌n�� (35) p104�`109 |
1993-02 |
�q�Ε��l�Y / �ː�F�Y |
|
pid/4425950 |
| 36 |
4(3)(36)���m�w�̌n�� (36) p106�`111 |
1993-03 |
�_�c���Y / ������v |
|
pid/4425951 |
| 37 |
4(4)(37)���m�w�̌n�� (37) p104�`109 |
1993-04 |
�O���M�� / ����v |
|
pid/4425952 |
| 38 |
4(5)(38)���m�w�̌n�� (38) p102�`108. |
1993-05 |
�r���G / �E���� |
|
pid/4425953 |
| 39 |
4(6)(39) ���m�w�̌n��(39) p102�`108 |
1993-06 |
���J�� / ����ȎO |
|
pid/4425954 |
| 40 |
4(7)(40)���m�w�̌n�� (40) p108�`113 |
1993-07 |
�����S�n / �{�c�Z |
|
pid/4425955 |
| 41 |
4(8)(41)���m�w�̌n�� (41) p108�`113 |
1993-08 |
�Ғ��l�Y / ���Ԋ��O |
|
pid/4425956 |
| 42 |
4(9)(42)���m�w�̌n��(42) p106�`111 |
1993-09 |
�L�˖Ύ� / �i�c�p�� |
|
pid/4425957 |
| 43 |
4(10)(43)���m�w�̌n��(43) p104�`109 |
1993-10 |
��Ց�� / ���c�ΗY |
|
pid/4425958 |
| 44 |
4(11)(44)���m�w�̌n��(44) p103�`113. |
1993-11 |
���c�L�� / �]��g�v . |
|
pid/4425959 |
| 45 |
4(12)(45)���m�w�̌n��(45) p104�`109 |
1993-12 |
���V�K��� / ���V�F�O |
|
pid/4425960 |
| 46 |
5(1)(46)���m�w�̌n��(46) p108�`112 |
1994-01 |
���q�i�� / �͖�Z�Y |
|
pid/4425961 |
| 47 |
5(2)(47)���m�w�̌n��(47) p104�`109 |
1994-02 |
�����i�C�� / ���R�g�A |
|
pid/4425962 |
| 48 |
5(3)(48)���m�w�̌n�� (48)���ŏI��p104�`109 |
1994-03 |
���c�i�l / ���c���� |
|
pid/4425963 |
|
�R���A�u�n�j (�A�J) ���̎Љ�ƕ��� : ���������v���u���V��w����A�W�A������v�����s����B�@
|
�n�j (�A�J) ���̎Љ�ƕ��� : ��������,( 1�`7�j����ꗗ�\
| �m�� |
�_���� |
���� |
���e |
| 1 |
�n�j���E�A�J���Ɠ��{���� |
��c�F |
�E |
| 2 |
�n�j (�A�J) ���̕��q�A�����ƎЉ�\�� : �����I�A�C�f���e�B�e�B�[�̊�� |
���씎�i |
�E |
| 3 |
�A�J (�n�j) ���̈��V��ɂ��Ă̊o������ |
�����搴 |
�E |
| 4 |
�k���^�C�y�ђ����_��Ȑ��o�Ŕ[�ɂ�����n�j���̕����ƎЉ� |
�|���� |
�E |
| 5 |
�A�J���̎��������o�� |
�`���u�E�J�`��=�A�i���_ |
�E |
| 6 |
���o�Ŕ[�n�j���R�˂̍l�@ : �n���w�I���_��� |
�V�c�q�Y |
�E |
| 7 |
�n�j�Љ�ɂ����鐹�Ȃ��� |
���[�� |
�E |
|
�S���A �Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (79)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7947840 �@�@�d�v
|
���W �C�ƐX�̍�--���{ / �~���� / p2�`12
���W �O����Ñ���{�߂� / ����N�� / p13�`24
���W ���È�Ք��@�̐�B / �����v / p25�`29
���W �C�l���}������--鰎u�̐l�`�Ɩ��I�� / ���u�q ; ����� ; �������K ;
�@�@�@��������N ; ���J�� / p30�`44
���W ����--���ܕ����̏\���H��(��ꕔ) / ���X�؍��� ; ���،��a�� ;
�@�@�@�� �������� ; �������K ; ���J�� ; �я��� ; �X�_�� ; �a�����v�� ;
�@�@�@�����֏� / p45�`79
���W ����--�������̏\���H��(��2��) / ���u�q ; �����G�T ; ����� ;
�@�@�@�����i���i ; �X�_�� ; ���c�N�Y ; ���֏� / p81�`109
���W �`�l�͊C��n������ / ���X�؍��� ; ����� ; ���i���i ; �я��� ;
�@�@�@���X�_�� / p110�`130
���W �C��n�����Ñ�搧 / ���c���� ; ����� ; ������ ; ���،��a�� ;
|
�@�@�@���я��� ; ���J���� / p131�`155
���W �O�ςƖ퐶�Љ� / ���u�q ; ���֏� ; ���쐽�i ; ���J�� ;
�@�@�@����эO�q ; �������� / p156�`177
���W �Ñ�̑D�Ƃ��̎���--�C����̐V������ / �����v ;
�@�@�@�����X�؍���; ���J��; �X�_��; ���J����/p178�`192
���W �Ñ�ɉ�X�͉����w�Ԃ� / ������N ;
�@�@�@�����i���i ; ���֏� / p193�`200
�u�Ή��v�y��ƉQ����--�Q���Ɨ����̍l�Êw(�l) /
�@�@�@����a��Y / p201�`237
�u�E�Y�v�ɂ��� / �J�쌒�� / p238�`242
�ڐ؈�Տo�y�̓y��ɂ���/���J�s����ψ���/p243�`244
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p245�`286
�E |
�S���A�n������, ����R�Z�Y�ҁu�����]��̈�앶�� : ���̊w�ۓI�����v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s�����B�@pid/11992889
�U���A�g�c�֕F���u���������� 41 p.97-103�v�Ɂu���{�̐_�b����эՋV�Ɍ�����A���z�ƈ�̌��т� (�A�W�A�̏@���ɂ݂�_)�v�\����B
|
�v��E���^�^���{�_�b�ő��z���_�A�}�e���X�́C�����Ɉ�̏��_�Ƃ����Ȃ���قnj����ɁC���ƌ��т����Ă���D���̏��_�ƈ�̌��т��͂܂��C�另�Ղ�ɐ��_�{�̍��J�ɂ��C���ĂɊŎ�ł���D���̏�C�V�̐Ή��̐_�b�Ɍ���Ă���C�A�}�e���X�̐����ƐU�镑���ɂ́C�C���h�V�i�Ȃǂ̐_�b�ň�̐_��ɂ��Č���Ă��邱�ƂƁC���炩�ȕ������F�߂��C���̂��Ƃ��炱�̏��_���C��̐_�i�����ꂽ���݂Ƃ��݂Ȃ���ʂ��C�����Ă������Ƃ��M����D���̂悤�ɑ��z�ƈ���C����̐_�i�Ɍ��т�����X���́C���{�̖��Ԃ̐M��Ղ�ɂ������Ό�����D���̌����ȗ�̈�Ƃ��āC�ԕĂ̎�q���U���C�V���ƌĂ�鑾�z�_�I�_�i�̌�_�̂Ƃ��āC���d�Ɏ�舵���Ȃ��琒�߂�C�Δn�̓��_�̍Ղ���C�����邱�Ƃ��ł���B |
�V���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 5(7)(52)���W ����̕����j--�A�W�A�̐萯�p�Ɛ��̐M���v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����Bpid/4425967
|
�����G�b�Z�C �ؗ�Ȃ�f�H / �잊�|�� / p2�`5
�W���A�� ���A�W�A�ɂ�����u�a�̗��s�Ɓu�鍑�̈�Áv
�@�@�@��(1)�R�����̗��s�Ƌߑ㒆���Љ�/�ѓ���/p68�`74
�ǐ� ���������̊�@�ƍĐ��̉�V���厖�����
�@�@�����������E / ���ˍG / p76�`84
���W ����̕����j--�A�W�A�̐萯�p�Ɛ��̐M��
�@�����̐��� / �M���� / p8�`13
�@�Ñ㒆���̓V���w�Ɛ萯�p / ���{�h�� / p14�`23
�@�����̃z���X�R�[�v--���V���
�@�@�@�������𗬎j�̈�ʑ� / ���R�� / p24�`32
�@���ɂ܂������_�X--�������Ԃ̐��M�� / �A���_ / p33�`39
�@�k�ɐ��Ɩk�l���� / �m�J�M�v / p40�`47
�@��͓`��--�V�̐�̃C���[�W / ������ / p48�`54
�@�����̖��Ɛ�--�����S���̕����Ɛ� / �@�����Y / p55�`60
�@���ꂽ�V�����w���o���o�x--�Ñ���{�̐�����
�@�@�@���萯�p / �V��o�T�j / p61�`67
�A�� �������Čv��}��(4)��n�̍��̋��Ԏ�/���c���/p6�`7
�A�� �]�ː���ƒ����̎�(4)������Ɛ_�_ /�E����/p75�`75
�A�� �����̗�����(4)�u���v�Ɓu���v--�Í������� |
�@�@�@������/���ғN��/p86�`87
�A�� �A�W�A���l�̗�(12)�V�q�̗�b
�@�@�@�����A�W�A�̗����l / ���c�L�� / p88�`93
�A�� �����j�̂Ȃ��̏���(4)�K�̐�����/�Ɍ��O/p94�`99
�A�� �������w�m�[�g(34)�u���V�Җ��߁A
�@�@�@�����V�ґ��ȉ��v / ���Y�F�v / p100�`101
�A�� ���Ă̓��m�w(4)�}���N�E
�@�@�@���I�[�����E�X�^�C�� / �~���R / p102�`107
�A�� �����̂͂Ȃ�(16)��v�̈��(9)/�ĎR�Б��Y/p108�`109
�A�� �A�W�A�̕�(4)[��p]���Ǝ��� / �X�G�� / p110�`113
�A�� �A�W�ANOW�u���݊W�v�̕��G�������f���o�� / p114�`115
�A�� ���] �����쎟�Y���w���w�œǂޑ�p�x/���i���`/p116�`117
�A�� ���ɂ��t�H�[�������Q���l���}�ɂ���/���`/p124�`127
���[�h�{�b�N�X / p85�`85
�V���Љ� / p118�`119
���C�u�����[ / p120�`121
�C���t�H���[�V���� / p122�`123
���G �F��̕��i(4)�p�O���̍��V�����}�[ / �����h
�E |
�V���A�����G�u�����{�Ȋw�҉�c�ҁu���{�̉Ȋw�� 29(7)(318)p30�`31�v�Ɂu<�k�b��>����,�Ȃ�����N����Ȃ̂�? �v�\����B�@pid/3209644
�W���A�����G�u���u����� 3 p.17-27�@�����j������v�Ɂu���N���ƍr�_�J��Ձv�\����B�@ �iIRDB�j
�P�O���A�c����, �����^�ҁu���@���Ȋw����v���u��g���X�v���犧�s�����B�@ (��g�V��, �V�Ԕ� 355)
|
�����̍�����Ȃɂ��킩�邩 / �����
���b�_���������E / ����v�j
�g�C���̍l�Êw / �����, ��������, �������q
�N�ւ�����j��ǂ� / ���J���
���̋N�������߂� / �����G�u
���@�l�����������Ñ�Ƒ� / �c���ǔV
��ՒT���̉Ȋw / �����N |
�n�k�l�Êw�̒a�� / ���숮
�R���s���[�^���p�p / �X�{�W
�{�b��Ə��ւ̎Y�n�������� / �O�җ���
���̃��[�c�����߂� / �H�y�P��
������Ύ��̌��N�f�f / ���c���l
�������ۑ��̂��߂̉Ȋw / ��c����, ��˗���, ���㗲
�E |
�P�O���A�y�Еҁuimago 5(11)�v���u�y�Ёv���犧�s�����B�@pid/1746299
|
���Ɩ� / ��t��F / 36
�����̑����@�\ / �{�Ԍ��� / 40
�̓����v�̂��肩��T�� / �쑺�_ / 52
��`�q�̂Ȃ��̎��v�\�\�V���E�W���E�o�G��
�@�@�@�����v�ˑR�ψّ� / �J������ / 64
�C�m���ɂ����鐶���̎������Ƃ��̋@�\�\�\
�@�@�@���������Y���̒����T�C�N���ւ̓K��/�O�}���s/72
���Ԑ����w����݂��q�g�̎��� / ���R�^ / 104
�J���̌���ɂ����鎞���Ƃ́\�\���Ζ��ƕϑ��Ζ���
�@�@�@�����S�Ƃ��� / ��a�q / 122
���o��D�P��o�Y�ƃ��Y�� / �哇�� / 134
���ǂƖ���\�\�]�������͐������Y���ɂǂ� |
�@�@���֗^����̂� / ���쏹�� / 143
���Ȃ鎞�ԂƊO�̎��ԁ\�\����v��̓��݉�=�i����
�@�@�@���\�ɂ����͉̂���/������/160
�������v�̃��Y��&�u���[�X�\�\�זE����Ɍ��鎞�ԇ��̑��e/�Ԓr�w/172
�A���͊�����������邩 / �����T�i / 185
��l�̂��Ȃ������Ŗڊo�����v�͖�̂��낤���\�\�萯�p��
�@�@�@�������w�I���v / ���{�Ďq / 200
���̃��Y���Ɛl�� / ���h�� / 212
����l�̑̓����v �����ɂƂ��Ď��ԂƂ͉����\�\������T�a�
�@�@�@���̓����v / �������v ; ��㏹���Y / 84
�q�����r
�E |
�P�P���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 5(11�j(56)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����Bpid/4425971
�@�@�@���W �Ղ̎v�z���̌����Ǝ��H ��ƈՐ� / ���c�F�N / p44�`52
�P�P���A�s���̌Ñ㌤����ҁu�s���̌Ñ� 16�v���u �r���b�W�v���X�v���犧�s�����B�@�@�@pid/4422389
|
�u���^ �ꕶ�_�k�ƈ�� / ������ / p5�`35
�u���^ �Î��L�ƗV��--�Ñ㉹�̉� / ���R��� / p36�`77
�הn�㍑�͌��ǂǂ��ɂ������̂� / ����p�� / p78�`96
���Γ`�����́u���V�v�ƒ��� / �؍��h�v / p97�`116
�u�`�̌܉��v�͂Ȃ����� / �쑺�� / p117�`132
���C�n�y��̘`��(���}�g�^�P��)���b / �����F / p133�`146
�����E�����E����^����̏�����
�@�@�������������̑��� / �`���� / p147�`166
���w���{���I�x�����ߒ��̌��� / �O���j / p167�`180
�`���̗�@�Ǝ������x / ���c�C / p181�`199
���Ђ�� ������̑����I�Ñ� / ���R�� / p200�`202
���Ђ�� ����ȉ�������� / ���茒��Y / p203�`206
���Ђ�� �u�`�����̏�\���v�ɂ��� / �ѓ��i�� / p207�`213
���Ђ�� �Î��L�����̓��T�� / ���{���g / p214�`223
|
�������m�[�g�� �u�]�v�̓ǂݕ��ɂ��� / ���菺��Y / p224�`229
�������m�[�g�� ��l�̐_���V�c / ��c�� / p230�`238
�������m�[�g�� �V�V�����`�����݂��u�L�v�u�I�v
�@�@���u���y�L�v / ���{�Z�v / p239�`250
�������m�[�g�� �u���ꋮ����㍑�s�V�}�v�Ɍ���
�@�@�����{���y�� / �x������ / p251�`262
�������m�[�g�� �הn�䍑�_--�u鰎u�`�l�`�v��
�@�@�������j�� / ����F / p263�`277
���w�������O�O�S���x�������ā� /
�@�@�� �֓����� ; �i���B ; ���c�� ; �Γc���F ; �쑺�� / p278�`304
���s���̌Ñ㌤����̏Љ��
�@�@����� �����W ���e�K�聄 / p305�`317
���ҏW��L�� / p318�`319
�E |
���A���̔N�A������\�� �H�ّP���i���炭�悵�䂫�j���u�킪���Ñ�̈��_�k�����ɂ����鐶���l�Êw�I��@�̊J���v�\����B
�@�@ (�Ȋw������⏕��(��������(B)(1))�������ʕ�, ����4-6�N�x) �@�������S��:
���钼,�����G�u,�����m��Y,�����ߘY |
| 1995 |
7 |
�E |
�Q���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (82)���W �O����~���̏o���ƌÑ���{
�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947843
|
���W �O����~���̏o���ƌÑ���{
�@�؍��̑O����~���ƌÑ���{ / ���J�� / p2�`11
�@��A�O���I�̑O����~�� / �Ζ씎�M / p12�`24
�@�R�n�������ƌÕ��̋N�� / ���쐳�j / p25�`41
�@�؍��̑O����~�� / ���i� / p42�`53
�@��a����̋N����ƑO����~�� / ������ / p54�`62
�@�Õ��̋N���Ǝהn�䍑 / ���菺��Y / p63�`72
�@�u�R�n���������������v�ƑO����~��/��a��Y/p73�`79 |
�ꕶ�l�̓V�̊ϑ��\�@--�哒���𒆐S�Ƃ���/�y�~��/p80�`89
���V�i�C�ɂ�����Ñ�̍q�@ / ���ƍN�V�� / p90�`107
�F�l--�F�ƉG / ���J�� / p108�`114
�V���E�����V�c�ƐM�Z(��)--�M�Z���s�v���
�@�@�������_��Ղɂ��Ă̈�l�@ / �{�V�a�� / p115�`133
�Ã��[���b�p�ƃG�[�Q�C�E�L���V�A�̉Q����--�ꕶ�Ɨ���
�@�@�@���̍l�Êw(��) / ��a��Y / p134�`179
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p180�`216 |
�R���A����G���Ғ��u�����V���E��w�Ɛ���w�v���u�ܗ����w��v���犧�s�����B�@
�@�@�@���L �]�Ō����w�V�w�^���x�̏���E��_�E�]��
�R���A�����ΐ����u�j�� 55(2) 1995-03 p.18-36�v�Ɂu�u��m�����w�v�Ə����×Y�v�\����B�@�@ �iIRDB�j
�U���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ�����u�Ñ�j�̊C (0)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@�@�@pid/4428398
|
�u�]���v�̎Z�p / ���i�a�j / p2�`19
�u���k�݁v�́u���v�͑�C���w��/�쌚��/p20�`23
���n���͏o�_�ł��� / �R�c�� / p24�`30
���W���̖�� / �F���쐳�� / p31�`38
�C���E�C��_�̍l�@ / �d���p�Y / p39�`46
�卑��Ɠ��� / �n���`�C / p47�`52
�u�ї��v�̓R���h���ł͂Ȃ�
�@�@���A�z�E�h���ł����� / ����p�� / p54�`59
|
�ѕ��S�͋N�_���o�ߒn�� / �؍��h�v / p60�`69
�w�@���x�k���l���`�́u�@�ӕ��v�Ɓu�ΏB�v�ɂ��� / �쑺�� / p70�`76
�w�������x�Łu�����]�̐킢�v�̔N�����l���� / �ێR�W�i / p77�`81
�O���ێR��Ղ̓��ꐫ / �֓����� / p82�`83
�Z���Β˂̕]�����߂����� / �����F / p84�`88
�w�O���j�L�x�`���X�����{�̎j���ᔻ / �`���� / p90�`99
�u�Ñ���{�C�����v�̏I����
�@�@���u�Ñ�j�̊C�v�̏o�� / ���菺��Y / p100�`100 |
�V���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (390)���W�E���V�i�C���߂��钆���E���N�E���{�̕������v���u �j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051820
|
��O���r�A��؍��ϏB�����암�E�ˋ��ʍ��R���œ��{�̓ꕶ����
�@�@�@�����n���ɂ܂ők���Ք��� / �]��P�\ / p1�`2
�፡���̌��t��i���_�I�l�Êw / �͌��哿 / p3�`3
���W�E���V�i�C���߂��钆���E���N�E���{�̕�����
�@���V�������̒����]��n���C�ؔ������암�C����B�n����
�@�@�@�������𗬂ɂ���/�]��P�\/p4�`6
�@�E����j�����̌� / ���z�� ; �������� / p7�`9
�@�V�Ί펞��ɂ�����ؓ������𗬂�
�@�@�@���V���Ȕ��@���� /�C�F�� ; ��������/p10�`14
|
�@��j����ɂ�����]��Ɠ��{�̈�앶��/�я���;�㓡��F/p15�`17 �d�v
���P�� ���������Ƒ�p / �v���O / p18�`23
���P�� �m�c����Ղ̔��@�����O�� / ���m�M�C / p24�`27
�����e�� �ꕶ����̕��ɂ���Č`�����ꂽ
�@�@�@�����j�┭�A�̂̔��� / �������� ; ���Ì��� / p28�`31
���j�Ռ����ē��� ���w��j�ՁC��茧�k��s����R�z�Έ�\��
�@�@�@���u���R���j�̍L��v�\�j�Ռ����\����/�]��P�\/p32�`33
�������وē��� �L�쒬�Õ�����������
�@�@�@��(���́F���ӂ�s�A�L��) / ���茹���Y / p34�`36 |
�W���Q�V���t�A�����V���j���[�X�ǐՁE�b��̔��@���Ɂu�g�q�]���E�����悪�r���E�C�l�͂ǂ�������{�ɗ����H�E����������Ք����v�̌��o���Ōf�ڂ���A�L�����ɑ��R�i������������j��Ղ̓������������`�[���Ƃ��Ĕ��@�����ɉ�������{���_�w���̓����G�u�����i�n��_�w�j�̂��Ƃ��f�ڂ����B
�Z���̔N�A�a�����v�����u���A�W�A�̈��N���ƌÑ��앶�� : �����ȉȊw������ɂ�鍑�ۊw�p����
: �E�_���W�v�s����B
���A���̔N�A�o�����q�����m�_���u���{�Ǝ��ӃA�W�A�̓`���I�D���̕����n���w�I�����v�\����Bpid/3102502
|
�͂����� / p8
��1�� �`���I�D���̕����n���w���r�����w�@
�@�@�@���`���̕��@�Ɖۑ�` / p10
�͂��߂� / p10
��1�� �D���w�W�Ƃ��������̈楕����j���� / p13
��1�� �n���w������w�ɂ����錤���̔w�i / p13
��2�� �����̈�̋��E�ƒ��S�n�̐ݒ� / p16
(1) ���E�̐͏o / p18
(2) ���l���̒��S�ƕ������S / p19
��3�� �����j�����̂��߂̔N��̈� / p20
��4�� �����̈楕����j�����̉ۑ� / p23
��2�� ���{�ɂ�����`���I�D�������̌��� / p27
��1�� �����^���̌Ñ�D������ / p27
��2�� ���{���������̌`���_�ƑD�� / p29
(1) �����Y�̈�싙�������������ƑD / p29
(2) �{�{���̓��{�����_�ɂ݂�W�J / p31
(3) ���쒉�Y�̑�p�����A�W�A���� / p33
(4) ���{�M�L�̑D�������Ɩ����l�Êw�̗��� / p35
��3�� �܂Ƃ� / p37
��2�� ���{�Ǝ��ӃA�W�A�̓`���I�D���@
�@�@�@���`�Z�p�����̒n���I�̈�Ƃ��̓��ԁ` / p42
�͂��߂� �`���I�D���̕��� / p42
��1�� �k���̎�̏W�����Ǝ���D / p44
��1�� �A�C�k�̎���D / p44
��2�� �k���̎���D / p46
��2�� �����{�̃A�}���ƕ��� / p49
��3�� ���{�C����V�i�C���݂̔��D�Ƌ��� / p53
��1�� �ؔ��ƒ|���̕��z / p53
��2�� ���{���݂̔��D / p55
(1) �z�O�C�݂̔��D / p55
(2) �Δn�̃U�C���N�u�l / p58
��3�� �؍����݂̔��D / p59
(1) �T�˓��̔��D / p59
(2) �]�����̔��D / p61
(3) �ϏB���̔��D�Ɖ����� / p63
��4�� �l�@ / p71
��4�� �P�ޙ��D�̕��Ր��ƌŗL�� / p74
��1�� ���{�̒P�ޙ��D / p74
(1) �k�C���A�C�k�̃`�v / p74
(2) �c��̃R�u�l / p75
(3) �j���̃G�O���u�l / p76
(4) ��������c��̃h���{ / p79
(5) ���{�C�����̒P�ޙ��D / p79
(6) ��q���ȓ�̃}���L�u�l / p81
(7) �܂Ƃ� / p83
��2�� ���ӃA�W�A�̒P�ޙ��D / p85
��5�� ���D�̔��e���Ɨތ^�� / p89
��1�� ���D�̔��e�� / p89
��2�� ���D�̕��� / p90
��3�� ���D�̕��z / p92
��6�� �k���n��ɂ�����^�i���B�̙��D / p94
��1�� �A�C�k�̖D���D�C�^�I�}�`�v�Ɩk���̑D / p94
��2�� ���k�k���Ɩk�C���̃��_�}���� / p98
��3�� �ԟD�ƘE / p100
(1) �k���n���i�漏ԟD / p100
(2) ����n���i�菱E�̎�e / p101
��7�� ����n��ɂ�����^�i���B�̙��D / p104
��1�� ����̖D���D / p104
��2�� �E�̌��@ / p105
��3�� �蒅���Ȃ��������D / p106
��4�� ��p���~���̃^�^�� / p109
(1) �����D�Ɨ����D / p110
(2) ���~�̑D���� / p111
(3) �D / p113
��8�� ���{�Ǝ��ӃA�W�A�n��̃V�L���B�̙��D ���z
�@�@�@������ʂ��ނ̌ď� �ڒ��܂Ƃ��ẴE���V
�@�@�@�� ���D�̓W�J / p115
��1�� �{�E�`���E�^�̙��D / p119
(1) �����m�݂̃{�E�`���E / p119
(2) �O�ʐ��̑D / p179
|
(3) ���쌧�z�K�̃}���^�u�l / p124
(4) ���ꌧ���i�̃}���R�u�l / p125
(5) �o�_�n���̙��D-�����^��\���R��g���h- / p127
(6) �O�����݉̒Ò��̃J�b�R�u�l�Ƒ�D�n�̃}���^ / p130
��2�� ���ӃA�W�A�ɂ݂�V�L���B�̙��D / p131
��9�� �����Z�p�̒n��I�W�J(1)-�ዷ�p�ȓ���
�@�@�@���C�D��h�u�l����߂�����- / p134
��1�� �ዷ�p�ɂ݂颃h�u�l��Z�p / p134
(1) �ዷ�p�̒P�ޙ��D / p134
(2) �ዷ�p�����̃g���u�g / p137
(3) ���l�p�̃R�`�u�l / p142
(4) �։�p�̒n���ԗp�}���L�u�l / p145
(5) �l�@ / p147 (
��2�� �\�o������т̒n���ԥ��u�ԃh�u�l / p150
(1) �ΐ쌧�H����n���̒n���ԑD / p150
(2) �\�o�������Y�̃}���L�u�l / p152
(3) �\�o�����g���̒�u�ԋ��ƃh�u�l / p154
(4) �x�R�p�̒�u�ԃh�u�l / p159
��3�� �V����H�c���ʂɂ�����h�u�l�̓W�J / p163
(1) �V�����̒n���ԃh�u�l / p163
(2) �H�c���̒n���Ԃƒ�u�Ԃ̃h�u�l / p166
��4�� �l�@�\�Z�p�`�d�̕������\ / p169
��10�� �����Z�p�̒n��I�W�J(2)-�h�u�l�Z�p��
�@�@�@���͐�ɂ�����W�J- / p172
��1�� �ዷ�p��x�R�p�ɂ�������̑D / p172
(1) ���s�{�R�ǐ�ƕ��䌧�㓪����̐�D / p172
(2) �x�R���_�ʐ�̃T�T�u�l / p175
��2�� �V�����r��ƎO�ʐ�̃J���t�l / p177
(1) �r��J���t�l�̑D�̍\�� / p177
(2) �O�ʐ��̑D / p179
(3) �ߐ����r��̊ۖؑD / p180
(4) �ߐ����r��̂���ނ����� / p183
��3�� �H�c���đ��̐�D / p186
(1) �đ��̑O��p���̑D / p186
(2) �I���L����̐�D / p189
��4�� �l�@ / p191
(1) ��D�̓S�J�X�K�C�ɂ��� / p191
(2) ��ƊC�̌��Ƃ��݂킯 / p192
��11�� �O��p���̙��D / p194
��1�� ��B�{���̙��D / p194
(1) �ߐ����̐�D / p194
(2) ��B�����̃N�X�̙��D / p195
(3) ���[�X���������Ō����D�@�`���D�̐��\�` / p198
��2�� ���{�Ǝ��ӃA�W�A�̑O��p���̙��D / p200
��3�� ���ꌐ�o�y�̙��D / p204
��12�� ��ґD�̈Ӗ�-�O��p���Ƃ̊֘A��- / p210
��1�� ���{�ŏo�y������ґD / p210
(1) �D�^���ւƖؐ��i / p211
(2) �v��Տo�y�̎��D / p212
(3) ���{�̓�ґD�Z�p / p213
��2�� �C���h�l�V�A��}�h�D�����̓�ґD�A���X�A���X / p214
(1) �D�̍\�� / p216
(2) �������@ / p217
��3�� ��҂ł��邱�� / p218
(1) ��҂̋Z�p�I�Ӗ� / p218
(2) �S�̎Љ�ɂ������҂̈Ӗ� / p222
(3) ��҂̕����j�I�Ӗ� / p223
�I�� �D�������̏��̈�Ƃ��̑��`�� / p228
��1�� �Ǝ��ӃA�W�A�̑D�������̗̈� / p228
��2�� �̈���\������v�f�̈Ӗ� / p231
��3�� ��w�����̗̈�`���Ƃ̂������ / p233
(1) ��w�����َ̈��� / p234
(2) �n�楖��������`���ɂ������D������ / p235
��4�� �X�ѐ��ԂƑD���Z�p / p238
(1) �X�ѐ��Ԃ̈Ӗ� / p238
(2) ���D�Ɣ��D�̐��Ԋw�I��Ղ̑��� / p240
��5�� �Z�p�̌p���� / p245
���� / p251
�} /�@�\ /�@�ʐ^ /
�E |
|
1996 |
8 |
�E |
�P���A�啪�����F�����y�L�̋u���j���������ٕҁu���ƒ��]���� : ���E���E�؍��ۃV���|�W�E���v���u�啪�����F�����y�L�̋u���j���������فv���犧�s�����B�@�@�����F�啪�����}����
�P���P�S���i���j�A�ʕ{�r�[�R���v���U�@�t�B���n�[���j�A�z�[���ɉ��đ啪������ψ���C�啪�����F�����y�L�̋u���j���������َ�Âɂ��u���ƒ��]����
: ���E���E�؍��ۃV���|�W�E���v�Ƒ肵���V���|�W�E�����J�����B�D
�Q���A�u�Ñ�w���� (133) �v���u�Ñ�w������v���犧�s�����B�@pid/6062600
|
�R���Ɠ�ʋT,�ʔłɂ��� / �c���� ; ���w�� / p1�`6
�Îs�E�S�㒹�Õ��Q�̔푒�҂̐��i����_����,
�@�@�����_,�m����̐� / �R������ / p7�`16
�Ώ�_�{���x�������̉��� / �����[�O / p17�`20
�ꕶ�y��Đ����@�����ւ̎����I����/������F/p21�`31
���W �n�k�̍l�Êw-2-���{(1) / 32�`39
�����s��ɂ�����n�k�̍��� / ���c�M�v / p32�`37
|
�c�䒆��Ռ��o�̕��� / ��䐳�� / p38�`39
����́u�c�v�ł͂Ȃ�--�u�ŌÂ̖n���y��v�ɂ悹��/����O/p42�`42
�a�����v���ҁw���A�W�A�̈��N���ƌÑ��앶���x /�����T��/p43�`45
�s�����ُЉ�t ���{���߂����� / �����O / p46�`47
�s����ʐM�t �Ñ�w������E�~�G���ʊ��
�@�@���u�X�{�Z����60�����L�O�c�A�[�v / �����^�� / p48�`48
�s�Ñ�w�����@����23�t ���_�E���m���琄�Âɉ��������R�r / �X�_�� |
�R���A���˗�,�F�c�ÓO�N,�����G�u���u���w�G����Breeding science 46(1)
p.61-66�v�Ɂu�����C�l�̈��픻�ʂɂ�����@���זE�]�_�̌`��Ɩ��̌`�ԁE�����`���̊W�ɂ��āv�\����B�@�@
�@J-STAGE
�R���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (3)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4428401
|
������ / �����F / p�\2
�l�Êw����݂��הn�䍑��a�� / �Γc���F / p2�`14
�הn�䍑�̒n�����ɂ��� / �v�ۓc�t / p15�`24
�u�]�v�Ɓu���v�̎g�������ɂ���--���莁��
�@�@�����̔ᔻ�ɉ����� / �؍��h�v / p25�`39
�p���V�c�A�����v�k(��)�ǐ��̓W�J(��) / �x������ / p40�`52
�u�Ñ�N���v�͓�����Ɏ��݂��Ă����̂� / ����p�� / p53�`58
�O����~�������_�ւ̈ꎋ�_ / �����F / p59�`72
���n��������--�z�P�m�R�����x�������n������ |
�@�@������ ���r�R�Õ����n������� / �Ę^�` / p73�`90
�_�d���T�ڔ���(����1)���]��N���_���E�u�]�Ǝ��v�_���E
�@�@���הn�䍑���ݒn���_�� / �`���� / p91�`95
�����Z�N�̐l���C�̂��߂����� / �d���p�Y / p96�`105
���V����Ղ̊�ړx�ɂ��� / ���菺��Y / p106�`109
�V���|�W�E���� �y�t�H�[�����u�O��������v
�@�@�����l����z�ɎQ������ / ��G / p110�`114
�ҏW��L / ���� ; �` / p115�`117
�E |
�R���R�O���t�A���{�o�ϐV���������Ɂu���̋N���E�g�q�]�������悪����E��Ղ���͔|�C�l�H�u�P���N�ȏ�O�v�����v�̌��o���Ōf�ڂ����B
|
�d���R�i�z�E�g�E�U���j��Ղɒ����^��\�܁A��\�Z�̗����A���s�s�̍��ۓ��{���������Z���^�[�ŊJ���ꂽ���ۃV���|�W�E���u���ƒ��]�����v�ł��A���̋N���]��������Ƃ���ӌ������������B�^������N�����l�Êw�����������͎���N�O�̉͛G�n�i���ڂƁj��Ղɂ��āA�u�ؐ��E�����̔_��ɁA�������̌����A���A�ʊ������A�ƂĂ��ŌÂ̈�앶���̐ՂƂ͍l�����Ȃ��B�����ƌ��n�I�ŃV���v���Ȉ�앶�����������͂����v�Ɛ����B���̎l���A���Â���Ղ����钷�]��������ɖK���v��𖾂��ɂ����B�^���̒�����Ŕ��Z�N��㔼���甭�@�������i�݁A�l�Êw�҂̊S���W�߂Ă���̂��Γ�Ȃ̜d���R�i�z�E�g�E�U���j��ՁB�������̌����҂͔���[���N�O�̈�앶���̐ՂƂ݂Ă���A����b�Γ�ȕ����l�Êw�����������́u�d���R�̃C�l���͔|�C�l�ł��邱�Ƃ́A�����̊w��ŃR���Z���T�X�Ă���v�ƌ�����B�^�P�Ȃ�C�l�͔̍|�����Ƃ����̂Ȃ�A���̋N�����ꖜ�N�ȏ�O�ɂ����̂ڂ�\�����w�E���ꂽ�B跛َl��A����w�@���@���A�������k����w�����炪�Љ���Γ�Ȃ̋�巊��i���傭����j��Ղ����̌��̈���B�^��N�̔��@�����ŁA�ꖜ�N�N�ȏ�O�ƌ������Ղ���C�l���݂��o�y�B�������ɂ��ƁA�����Č��������v�����g�E�I�p�[���i�C�l�̗t�Ɋ܂܂��K���X���זE�̔����j�͂������ʁA�쐶�̃C�l�ɋ߂����A�쐶�̃C�l�ł͂Ȃ����Ƃ��킩�����B�������́u�N�㑪��͏I����Ă��Ȃ����A�l�Êw�҂̗���Ō����A�ꖜ�N����ƍl���Ă悢�v�ƁA���M�����Ղ肾�B |
�S���A�_�{�i���L���u���_ (173) �v���u�_�{�i���v���犧�s�����B�@pid/7930716
|
�\�� ���y�E�ӈ���
���G ���������N�E�����̏o�E�F�N��
�ɐ��_�{�Ǝ� / ���ў� / p1�`8
�ɐ��_�{�Ɗȑf�̐��_ / ���c���F / p9�`13
��\�ꐢ�I�ɐ_�Ђ͂ǂ��Ȃ� / ��㏇�F / p14�`17
���ꂩ��̐_���E�Ɛ_�{ / �͖�P / p18�`23
�����u�C�Z�q�J���v / �����Y / p24�`24
�{ / ����C�c / p25�`30
�`�P�Ɠ��N�̐̂𗷂䂭 / ���~�q / p31�`36
�ʂ�̌�� / �c��m / p37�`41
�։��E�嗈�c�� / �q�c���� / p42�`47
�Îs�E�瑩�����̂����� / �N�䎡�j / p48�`54
�ɐ��̕��ꂠ�ꂱ�� / ���c�F�K / p55�`62
�����`���Ɛ_�{ / ���ǍG / p63�`67
�R�c��s�剪�����ƈɐ� / ���G�� / p68�`72
�_�{�Ɩk���e�[--�����Ƃ̊C���ʂ��߂����� / ����F�F / p73�`77
��Z�\���_�{���N�J�{�L�^�f�搻����I���� / �c���i / p78�`88
�_�l�Ƃ̂ӂꂠ�� / �쑺�^�� / p89�`91
�������̈ɐ� / �R���L�� / p92�`95
�ɐ��A�v���o�G�� / �������N / p96�`98 |
���N�ɖ�����ꂽ�ɐ��_�{ / ���������� / p99�`100
�_�{�ɎQ�q���� / J�ER�E�}�N���[�h / p101�`102
�ɐ��_�{���h��̉ߋ��E���݁E���� / ���d�� / p103�`110
�_�{���p�ُ��� �_�{���i��� / p111�`113
�_�l�Ɏ���� / �����T�q / p114�`119
���h�_�А��܂�Ɛ_�{�Q�q / ��{���q / p120�`121
�{�[�C�X�J�E�g�����Ɛ_�{��d / ���c�� / p122�`123
�_�{�̋C�����ɂӂ�� / F�E���@�C�b�[�b�J�[ / p124�`124
�b�� �_�{�̍ՓT / p128�`130
�b�� ���� / p130�`141
�b�� �r�c�Վ�l�_�Ж{�����ق� / p62�`62
�b�� ���N�̑喃�Ɨ�̕� / p67�`67
�b�� �_�E�{���@�֕��ʉے����k�������C�� / p72�`72
�b�� �o��E�ɐ��̏t / �y��I�I�q / p88�`88
�b�� ���{���q�Q�c�@�c���̎Q�q / p110�`110
�b�� ���������N���j���ċ㌎����J�ق����� / p113�`113
�b�� �X�����䂭�]�b / p125�`125
�b�� ����_�{�喃�Еz�����S���Ҍ��C�� / p126�`126
�b�� �_�{�ό���̒Z�́E�o��̕�W / p143�`143
�E |
�T���A�u�V�E = The heavens 77(5)(852)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220530
|
�\���ʐ^ �݂肵���̍����P�v��
�����P�v�O��̗��� / p2�`2
�Ǔ�������P�v�搶���Â� / ���R��j ; ��㖱 ;
�@�@���M�ےj ; �R�{�i ; ����� ; ���{�B��Y ; �Љ��ǎq ;
|
�����c�B ; ���� ; �{����F ; �v�ۓc�x ; ������
�� ; �������j ; �k���d�Y ; ���R�� ; �c���Y ; ���B�� ; �����琳 ;
���k���_�� ; ����q�� ; ���r�F ;
���ɒO�s�����ǂ������Ȋw�� �a�O�b�� / p3�`31
|
�U���A�r���G���u�A���̈�`�ƈ��v���u�{�����v���犧�s����B�@
|
��P���@��b�ҁi�זE����Ɛ����G���F�̂ƃQ�m���G��`�̖@���@�ق��j
��Q���@�����@�i�͔|�A���̋N���ƈ��G���B���앨�̈��G
�@�@�����B���A���̈��@�@�ق��j |
��R���@�ڕW�ʂ̉ۑ�ƈ��֘A����i���ʁA���v���ւ̑ϐ�
�@�@������ѕi���̈��G�ϕa������ёϒ����̈��G
�@�@���V�i��̑��B�Ɠo�^�E���y�G��`�����̕ۑ��Ɨ��p�j |
�U���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���� �u�Ñ�j�̊C (�ʍ� 4) �v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4428402
|
������ / ����p�� / p�\2
�Ñ㐔�w�E�`�l�`�E�l�Êw--�Γc���F����
�@�@������������ / ����p�� / p2�`26
�����B�� / �n���`�C / p27�`38
�g��P���̒�����ʂ��Ă݂��Ă����V�����הn�䍑��--�O�t�E
�@�@���{���E�@�t�E��� / �������� / p39�`43
���J�������؍�(��)����Õ��̔푒�� / �����t / p44�`54
�w���{���I�x�Ɍ����Ñ㒩�N�L�� / �O���j / p55�`59
�p���V�c,�����v�k(��)�ϐ��̓W�J-��- / �x������ / p60�`70
|
�R�A�I�s / ���菺��Y / p71�`79
�V���| �u���{�C�O��Õ����Ȃ��O���
�@�@������ꂽ�̂��v�L / �d���p�Y / p80�`89
���������Ɗ��ˌÕ����@���������Љ� / ����p�� / p90�`94
�r��]����Ռ��������Əo�y�w���̔N�֔N�㑪�莑��--
�@�@���t�E�N�֔N�㑪��ɂ���V���� / �Ę^�` / p95�`105
�M���~�l�b�Z���X�@�ɂ��~�����ւ�
�@�@���N�㑪�� / �O����d�` / p110�`106
�ҏW��L / ���� ; �` / p111�`113 |
�V���A�����m��Y���uDNA������앶�� : �N���ƓW�J�v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B
(NHK�u�b�N�X, 773)
|
�P�@��̗�����
�Q�@���[�c�����߂� |
�R�@�i�킽���̌Z��W
�S�@��̈�앶�� |
�T�@�C�l�̂�����
�E |
|
|
���e�����^�������]�ȁE�͛G�n��Ղ̔����ɂ��A��̋N�����߂���_���ɍĂщ������B�I���O�T�O�O�O�N����̖������]�����悩��o�y���A�ʐ��Ƃ���Ă����u�A�b�T���[�_��N�����v�ɋ^�₪�悳�ꂽ�̂ł���B��̌����͂ǂ����A��̋N�������Ƃ߂���̂��B�C�s�̈���`�w�҂��A��̗t�Α̂c�m�`�̕��͂ƃt�B�[���h�E���[�N����A�]���̏������l�@���Ȃ����A�V���̃o�b�N�{�[���������Ă䂭�B����ɁA��̓`�d�̃��[�g�����ǂ�A���{�ƃA�W�A�̈�앶�����čl����B�@CiNii Books��蕡�� |
�W���A�u�G���l�Êw (56)�v���u�Y�R�t�v���犧�s�����B�@�@pid/7956574
|
���W ���̓`�d�ƒ��]���� / 5�`76
���W ���̓`�d�ƒ��]���� ���G(�J���[)
�@�@�����W�������_�k�Љ� �����͛G�n���
���W ���̓`�d�ƒ��]���� ���G(�J���[)
�@�@�� ���]���E������̔_�k���
���W ���̓`�d�ƒ��]���� ���G(���m�N��)
�@�@�� ���]���E������̔_�k�֘A�╨
���W ���̓`�d�ƒ��]���� ���G(���m�N��)
�@�@�����_�k������Â��鍩��
���W ���̓`�d�ƒ��]���� ���G(���m�N��) ���ƌÑ���
���̊��l�Êw / ���c�쌛 / p14�`17
���̋N���Ɠ`�d / 18�`43
���E�ŌÂ̓y��ƈ��̋N�� / ������ / p18�`21
�u������씼���ʁv�Ɓu�������씼���ʁv / ���c�쌛 / p22�`26
��̃�-�c / �����m��Y / p27�`31
���ƒ��]���� / ������ / p32�`34�iIRDB�j
��앶���̒a�� / �����T�� / p35�`38
���{�̈��̎n�܂� / �O�R�G�� / p39�`43 |
���Ɗ��l�Êw / 44�`69
���̔��W�������������� / �����w / p44�`48
���̊g��ƋC��ϓ� / ����m�V / p49�`53
���`�����l�X / �����F�K / p54�`58
���_�k�ƍ��� / �X�E�� / p59�`63
���ƂƂ��Ɋg�債���a�C / �������� / p64�`69
���Ɩ퐶����--���{���̌n���ƏƗt���ѕ����_/����O/p70�`76
�ŋ߂̔��@���� �ΐ��i���ʂɕ��������O���Õ�--
�@�@���ޗnj����̎R�Õ� / �������G ; ���{�r�� / p81�`82
�ŋ߂̔��@���� ���蓌�R�������H--�����s������������
�@�@���k���n��̈�� / ���c�F�G ; ��W�� / p83�`84
�A�ڍu�� ��䎞��j-30-�W�����\������{��
�@�@��(1)�Z��(���O) / �ь��� / p85�`92
���] / / p93�`95
�_���W�] / / p96�`97
���E��V���ꗗ / / p98�`99
�l�Êw�E�j���[�X / / p100�`102
��5��Y�R�t�l�Êw��ܐ}�����\ / / p103�`103 |
�W���A�u�Ñ�w���� (135) �v���u�Ñ�w������v���犧�s�����B�@pid/6062602
|
�����ϐΕ�ɂ����銻�̌��� / ���эF�� ; ���m��/p1�`6
�u�`���嗐�v�l / �O��P�� / p7�`19
���c�����摜�������̉��� / �����[�O / p20�`25
�C���h�l�V�A�E�X���o���̓y�����K�˂�/���{�m��/p26�`35
�s���W�E�n�k�̍l�Êw4�t-���Ɍ�(1)- / 36�`44
���f�w�Ɉ����ꂽ�G���Z����--������/�R���j�N/p36�`38
|
���Ɍ��암�n�k�ƌc�������n�k / ���숮 / p39�`44
�u���]�v�E���A�W�A�̈��N���ƌÑ��앶���ɑ���
�@�@��������\�҂Ƃ��Ă̑z�O / �a�����v�� / p45�`47 �@�iIRDB�j
�s�˕�ψ���t ���I�ΒˎR�Õ����@�����̌��w/��������/p48�`49
�s�Ñ�w�ւ̒t �l�Êw�Ɨ��j�̂͂��� / ���{���i / p50�`50
�s�Ñ�w�����@����21�t �n���Q���̂���_�` / �X�_�� |
�P�O���A���{�Ȋw�҉�c�ҁu���{�̉Ȋw�� 31(10)(345)�v���u���{�Ȋw�҉�c�v���犧�s�����B�@pid/3209671
|
<���̂��Ƃ�>�j����ƍ��ێi�@�� / �R�c�p�� / p3�`
���W ��B�ƃA�W�A--���̌��т��ƌ𗬂ւ̎��_ / ���W�܂����� / p4�`
���̋N���Ɠ`�d--���������𗬂̒ꗬ / �����G�u / p517�`521 �d�v
�������ړ����C�l�E���J�ނɂ݂�A�W�A��
�@�@�����{�̌��т� / �n�ӕ��� / p522�`526
���V�i�C�̎����Ǘ�--�C����̔��z / ���c�b�� / p527�`531
�n��ɍ��������n���������f��--��B�ƃA�W�A�Ƃ�
�@�@���𗬂ւ̈���� / �쌴�I���Y / p532�`536
1996�N�x���{�Ȋw�҉�c�������������������v�� / p25�`
<�k�b��>�|�[��������W���o��=�v��50�N�ɂ悹�� / �ɓ��� / p26�`27
������{�̍s�������V�X�e�� / �x//�됰 / p540�`544 |
���L�^�̌��J�Ɗw��̎��R / �Β�//�L�� / p545�`549
�����E���̏o���p�����ŏI������
�@�@�������R���� / �{�ԐT / p550�`554
�u���ۍv���_�v��������a��`��--���a�̂��߂�
�@�@�������I�G-�g�X�̊o���� / �ɓ�//���F / p555�`559
<���]>������w����h�C�c�X�|�[�c�j�����x/�����K��/p48�`
�č��Ȋw�A�J�f�~�[�Ғr������
�@�@���w�Ȋw�҂��߂����N�����ցx / �n�ӍV / p49�`
��� / p50�`
�Ȋw�҂����� / p51�`55
�ҏW��L / ������ / p56�` |
�P�O���A���[�����u�����ƈ : �n�j�̕����Ɠ��{�̕����v���u�ߑ㕶�|�Ёv���犧�s����B
|
���e�����^�_��ƈɐ������ԕ����B�X�ƈ�̕�������Ă��n�j�Ɠ��{�B�����̂��̂�����n�j�E��Ɛ�������{�B�@�@CiNii Books
��P�́@�n�j�̐�����?�������q�𒆐S�Ƃ��ā@�i�����Ăɂ����鐹���I��G���݂̃A�}�g�D�i�����Ձj�G�����̐����j
��Q�́@�n�j�����ɂ����鐹�Ȃ��ԁ@�i�]���̑����̋V�����猩���_��̐��i�G���݂̃A�}�g�D�i�����Ձj���猩���_��̐��i�G�_�厩�̂̍l�@�j
��R�́@�����Q��L�@�i���q���ցG���얜���̑��V�G����������郂�[�s�[�G���̋��]�G��������I���āj
��S�́@�����ƈ�@�n�j�����ƌÑ���{�����̔�r�@�i�n�j�����ɂ����鐹���G�n�j�����ɂ������G���{�����ɂ����鐹���G���{�����ɂ������j |
�P�P���A�V���|�W�E���w���N����T��x���s�ψ�����Ǖҁu�V���|�W�E�����N����T��
: �����E���R��Ղɂ�����Ñ㐅�c���v���u���{�������Ȋw��V���|�W�E���w���N����T��x���s�ψ���v���犧�s�����B
|
���N����T�� : �V���|�W�E�� : �����E���R��Ղɂ�����Ñ㐅�c���
�V���|�W�E�����N����T�� : �����E���R(������������)��Ղɂ�����Ñ㐅�c���
�V���|�W�E���Ñ���̋N�� : �����E���R��Ղ̒���
Symposium : search of the origin of rice cultivation : the ancient rice
cultivation in
�@�@�@��paddy fields at Cao xie shan site in China |
�P�Q���Q�W���t�A�����V���Ɂu�{�Ó��Ƀh�������E�����ς��R�O��ȏ㔭���E���Ό������E���n���Ɛ[���W������[�g���Ɍ��v�Ɖ]�����o���Ō��n��K�ꂽ�Ζ씎�M���������勳���i�l�Êw�j�̂��Ƃ��f�ڂ����B
���A���̔N�A��t��F���u ���炾�̒��̖�ƒ� : ���Ԑ����w�ɂ��V��������ρv���u�������_�Ёv���犧�s����B
(�����V��, 1315)�@�@CiNii Books���
|
��P�́@��N�ɂȂ��Ă킩��������
��Q�́@��
��R�́@���鎞��
��S�́@�����̎��] |
��T�́@�������v�̐���
��U�́@�����Ɣ���
��V�́@��s���ƒ��s���̐i��
��W�́@�l�̎��v |
��X�́@���Q
��P�O�́@���Y���ϒ�?����ƈُ�̂�����
��P�P�́@�������v�̎���
�E |
|
| 1997 |
9 |
�E |
�P���A�u�V�E = The heavens 78(860)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@�@pid/3220546
|
�\��:��Éw�̖k��35�x���j�������g
�����V���w��̖����ƈψ� / p3�`3
�f���炵���F���ւ̔� / ���c//��� / p3�`6
JR��Éw��ʂ�k��35�x�� / ���J���Y / p7�`7
��̐}��(11����) / p7�`7
�P���̎O�p�����J�^���O / ���J��//��Y / p8�`11
���{�ɊW���鏬�f���̖��� / ���J���Y / p12�`13
�V���ɔ������ꂽ�y���q�� / H / p13�`13 (0007.jp2)
�Љ�܂�!���̖{��Z�����f�B�s�e�B�[�覐� /
�@�@�� �������B ; ���J���Y / p14�`14
������v�̉̔����ɂ��� / �呺��F / p16�`16
|
�V���j���[�X / p17�`17
���z�ی���No.312 / ��ؔ��D / p18�`20
�إ�y���ی���(10-11��) / �{��M / p21�`22
���V��1956C�͏��f��1988X B5�ł����� / p22�`22
�����ی���No.482 / ��c���� / p23�`24
�a���ی��� / �֕� / p24�`24
�V���j���[�X / p24�`24
����V���̏W��'96 / �H / p26�`27
����9(����1997)�N�V������ / �{����F / p28�`29
�x������ / ���{�B��Y / p30�`30
�����ǂ����(22)����� / p30�`30 |
�P���A���{�P�v�����{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j����. Journal of history of science, Japan [��U��] = [Series �U]�@p260�`270�Ap97�`103�@ ���{�Ȋw�j�w��v�Ɂu���{����V���w�j�ɂ�����V��V���̖��� �A��V���̋�͊T�O�̊m���ߒ��v�\����B�@pid/11683966
�P���A���O��, ����Âق������u�Ñ���{�l�̐M�ƍ��J�v���u��a���[�v���犧�s����B
|
���{�Ñ�̑��z�M�Ƒ�a���� / ���O��
���z���J�ƌÑ㎁�� : ���u���𒆐S�Ƃ��� / ���C�Y
�ɐ��_�{�Փ��l / �g��T�q
�������ƐΏ�_�{ / �{�ʓc�e�m
�_�Ɖ��Ɩm�� / �i���v�b
�����Ñ�̑��ʋV��Ƒ另�� / �����
�V���E�������̕��� / �c������
�]���A�X�^�[���̓n��:�V���V�c�҉̓�����ǂ���/�ɓ��`�� |
�{�^�y��ɂ��� : ���̗� / �J�쌒��
�����`�Z���Ɍ��鏗�_�̎q�{�ƎY���̕\�� / �g�c�֕F
�ؐ������"�̏���"�� / ��������
�Đ����J��Ɛl������ : ���Q���͟q(������)���Č����Ă���/�ᏼ�Lj�
���{�l�̑��E�� : �n���ƃl�ƃi�J / ���c����
���C��y�_ / ��؟ޒj
�n�j���̑����Ɠ��{�̑����Ƃ̔�r / �]�g
�E |
�@�@�@�@���u�Ñ���{�l�̐M�ƍ��J�v�͎G���u���A�W�A�̌Ñ㕶���v�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���̑I�W�ňꕔ�^�C�g��������Ă����̂Œ��ӁA�܂��A���̓���ꗗ�\
|
| �m�� |
�_���� |
�@�@���e |
| �G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���Җ� |
pid |
| 1 |
���{�Ñ�̑��z�M�Ƒ�a���� |
(24)p2�`14 |
1980-07 |
���� |
���O�� |
pid/7947784 |
| 2 |
���z���J�ƌÑ㎁�� : ���u���𒆐S�Ƃ��� |
(24)p24�`35 |
1980-07 |
���� |
���C�Y |
pid/7947784 |
| 3 |
�ɐ��_�{�Փ��l |
(28)p98�`107�@ |
1981-07 |
���� |
�g��T�q |
pid/7947788 |
| 4 |
�������ƐΏ�_�{ |
(36) p115�`127 |
1983-07 |
�Ώ�_�{�ƕ����� |
�{�ʓc�e�m |
pid/7947796 |
| 5 |
�_�Ɖ��Ɩm�� |
(33) p64�`78�@ |
1982-10 |
�_�Ɖ��Ɩm |
�i���v�b |
pid/7947793 |
| 6 |
�����Ñ�̑��ʋV��Ƒ另�� |
(66)p2�`13 |
1991-01 |
���� |
����� |
pid/7947827 |
| 7 |
�V���E�������̕��� |
(40)p40�`48 |
1984-07 |
���� |
�c������ |
pid/7947800 |
| 8 |
�]���A�X�^�[���̓n�� :
�@�@�� �V���V�c�҉̓�����ǂ��� |
(51)p142�`161 |
1987-04 |
���� |
�ɓ��`�� |
/pid/7947811 |
| 9 |
�{�^�y��ɂ��� : ���̗� |
(54)p106�`112�@ |
1988-02 |
���� |
�J�쌒�� |
pid/7947815 |
| 10 |
�����`�Z���Ɍ��鏗�_�̎q�{�ƎY���̕\�� |
(77)p2�`16�@ |
1993-10 |
���� |
�g�c�֕F |
pid/7947838 |
| 11 |
�ؐ������"�̏���"�� |
(56)�@p8�`16 |
1988-07 |
���� |
�������� |
pid/7947817 |
| 12 |
�Đ����J��Ɛl������ :
�@�@�����Q���͟q(������)���Č����Ă��� |
(72) p139�`158�@ |
1992-07 |
���� |
�ᏼ�Lj� |
pid/7947833 |
| 13 |
���{�l�̑��E�� : �n���ƃl�ƃi�J |
(67)p114�`127 |
1991-04 |
���� |
���c���� |
pid/7947828 |
| 14 |
���C��y�_ |
(68) p94�`107
(69) p166�`179 |
1991-07
1991-10 |
���V�i�C�ɂ�����C�㑼�E��(��E��)��r�����w�I�l�@
|
��؟ޒj |
pid/7947829
pid/7947830 |
| 15 |
�n�j���̑����Ɠ��{�̑����Ƃ̔�r |
(66)�@p95�`103
(71) p108�`125 |
1991-01
1992-04 |
�����i�Q�_���E�ʔԂȂ��j |
�]�g |
pid/7947827
pid/7947832 |
|
�Q���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (53)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@�@pid/6067760
|
���{�l�ƈ� / �n������ ; �J�쌒�� ; ���{�h�� / p4�`5
�l��N�O�́w��̓��{�j�x���p������ / p6�`7
�A�W�A�j���猩����قȓ��{�̈�� / p7�`12
���������ɂȂ������`��̌��� / p12�`14
��쌗�ƕ������̍��� / p14�`16
���ꌳ�_�ւ̔ᔻ / p16�`19
����̍ݗ���ƃu�� / p19�`22
�_���̃j�q���Y�� / p22�`24
�����ʂ����y�n�ƈ� / p24�`27 |
�_�Ђ̐ԕĂƐ_�� / ����q�� / p28�`33
�Δn�E���Ă̐ԕē`���ƏK�� / ��c�g�Z / p34�`35
�����n�j���Ɠ��{�Ƃ̈��V�� / �]�g / p36�`41
[�A��] �V�Ɉ�ԋ߂��ɏZ�ގR�̐l�X �ŏI�� ���t���̂ӂ邳��
�@�@�������~���ւ��� / �������� ; ���{�h�� / p42�`59
[�A��] ���������V�̋��܂����i(2) / �k�i�� / p60�`66
���c�@�l���{�i�V���i���g���X�g����̃��b�Z�[�W
�@�@��[��N���ӂ肩������] / �R���ʑ��Y / p67�`67
�E |
�S���A�ߓ��鏺���u �t�@���}�V�A 33(4) p.351-355�v���u��̉��������M�������̓~���@�\�v�\����B�@ J-STAGE�@�d�v
|
1�͂��߂�
2�S���̒ቷ��Q
3�ቷ�ɋ����S��
4 �~������@�\�̉𖾂�ڎw���� |
��5 �~���ɓ��ٓI�ȃ^���p�N��
6�@�~���͑̓��Œ��������B
7�@������
�E |
��5 �~���ɓ��ٓI�ȃ^���p�N��
|
�@1987�N�ɉ�X�̃O���[�v�� ����āA���̃N���C�e���A�ɍ��� 4 ��̌����^���p�N�������o���ꂽ�B���̃^���p�N���͊̑��ŎY������A�~�����Ɍ����Z�x���� 1�^20�ɂ܂Ō������� �B�~���Ɋւ��^ ���p�N���Ƃ��Ă͏��߂Ă̔����ł������B���̌����^ ���p�N���́C�����ɂ܂Œቺ �����̓��łقڈ��ɕ� ����Ă���A�~�������قƂ�ǂ̓����q���P��I�ɒ��� ����Ă��邱�Ƃ������Ă����B4��� �^ ���p�N���͐V�K�^ ���p�N���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A���̕��q�ʂɂ����HP�[20�CHP�[25�CHP�[27������ HP��55�Ɩ������ꂽ�B�i���j |
|
�U���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���� �u�Ñ�j�̊C (8)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4428406
|
������ / �؍��h�v / p�\2
�w�S�ϐV��x�̎j�����l--��x����������ꂽ
�@�@���S�ω��� / �`���� / p2�`26
�u����m����V���v�G�l / ���i�a�j / p27�`35
�y���x�~�z����Ђ�� / / p36�`47
�ꕶ���z�p-�g2 / �L����q / p36�`41
�w�@���x�̐`�����ƈΏF / �����t / p41�`43
���ߐ��x���琄�@���镡�������������_/���R��/p43�`47
�Z�����̐��w�Ɨ��j�w--�R�c���S���Ɩ؍��h�v����
|
�@�@���^�₨�������� / ����p�� / p48�`74
�u�ΊC���v�l / �x������ / p75�`86
�w���M�x�̗p�r�ɂ��� �Ę_ / ����O�Y / p87�`106
���m�����(�l���ˏo�^���u��Q)���@�����T�v������
�@�@��(�Ę^) / ��R������ψ��� ; ���]������ψ���/p107�`111
���a�ˌÕ��̒������ʂɂ���
�@�@��(�Ę^)/ �V���s����ψ��� / p112�`122
�ҏW��L / ���菺��Y ; �`���� / p124�`124
�E |
�V���A�V�J���Y���{���Еҁu�����{ : ���߂Ƌ��ނ̌��� 42(8)(615)�@p10�`10�@�{���Ёv�Ɂu���W �Ñ㕶�w�̏펯Q �� A A�@���(����w���܂�) Q���̗�@�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂� �v�\����B�@pid/8099659
�X���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (�ʍ� 9)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ����v���犧�s�����B�@pid/4428407
|
������ / ����p�� / p�\2
�u�`�̌܉��v�Ƃ��̑O�� / �쑺�� / p2�`38 (
�y���x�~�z����Ђ�� / p39�`51
���ߐ����̎��� / �͖�G�� / p39�`41
��_�_ / �O���j / p42�`47
�u���O�N�v���Ǝהn�䍑 / �Γc���F / p48�`51
6���I�̉��P�n�� / �d���p�Y / p52�`68
�����l�̓n������ / ����ǕF / p69�`76
�w�Î��L�x�͖����̏��ł��� / �`���� / p77�`85
�Î��L���������ƌÎ��L�����j / ����p�� / p86�`90
|
�H�g��s���ˌÕ����n������� / ���菺��Y / p91�`96
�����{�R�Õ��̒����������� / ���Ύs����ψ��� / p97�`103
�����{�R�Õ��̒��� �������� �����{�R�Õ����n
�@�@��������ɎQ������ / ����� / p104�`105
�����{�R�Õ��̒��� �������� �����{�R�Õ�
�@�@�������w���� / ���菺��Y / p106�`107
�����{�R�Õ��o�y�́u���O�N�v���ɂ��� / �쑺�� / p108�`116
���a�ˌÕ��o�y���ւ�
�@�@�������G��ɂ��� / �V���s����ψ��� / p117�`127
�ҏW��L / ���菺��Y ; �`���� / p128�`129 |
�P�P���A�u�V�E = The heavens 78(870)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220556
|
���z�K������^�V�ۑ䣂̕����o�� / �{����F / 11�`13
�Ñ���{�l�͐��ɋ������Ȃ������� / �����L�� / 14�`16 |
���R��e�B�A���V���ق̌��w / �h�^�� / 28�`29
�E |
�P�Q���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ�����u�Ñ�j�̊C (10)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4428408
|
������ / ���菺��Y / p�\2
�����Əo�_--���Ί�q��Ղ̔�����
�@�@���_�@�Ƃ��� / �Ɠc���n / p2�`18
�הn�䍑�ʒu�_ / �k���� / p19�`21
���k�Õ������̓� / �֓����� / p21�`24
�u���O�N�v���ƕ��i�K��l�_���̌n��/�Γc���F/p24�`30�@�d�v
��Պw����݂�����(�u�Ñ�w�����v
�@�@��139�����]��) / �X�_�� / p31�`3
�w鰗��x�̐����N��Ę_(1)���Q��u鰗��S�{�v��
�@�@���߂����� / ���i�a�j / p34�`44
���̎�ޗ��s(��) / �x������ / p45�`55 >
�v�ۓc�����w�הn�䍑�͂ǂ��ɂ��������x
�@�@����ǂ�� / ���菺��Y / p56�`59 |
�B�c���珗�����̘_�� / ����p�� / p60�`64
�u�w�Î��L�x�͖����̏��ł���v��_ / �`���� / p65�`79
�_���c�@����z���h�H�� / �n���`�C / p80�`85
��̓�����--�i�s�I�E��B�����L��A to Z/���c��/p86�`101
����s������Ռ����L / �k��݂�q / p102�`107
������Տo�y�̌��z����(�Ę^)/�{�{����Y/p108�`110
�u��15���~��-�W�A��in���̉��Õ��Q�v���
�@�@��(�Ę^) / �L���s���j�Ȋw���玖�ƒc / p111�`114
�u���̉��Õ��Q�v���n������ɎQ������/�v�ۍk�� p115�`116
�ە@�R1���Õ���2�����@�����̐���
�@�@��(�Ę^) / ���{�V������ψ��� / p117�`125
�ە@�R1���������w���� / �d���p�Y / p126�`128
�{���ւ̗��M�E�ҏW��L / p129�`132 |
���A���̔N�A�����G�u�i�{���w�j�������ȉȊw������⏕���������ʕ��u���c���ȑO�̈�쑶�ۂɊւ�����ؓI�����v�\����B�@�@��������}���ُ���ID�F000007056038
�@�@�@�����F���N�����E�v�����g�E�I�p�[���E�ꕶ���㌏�E������Ձi�y���s�������j�E�ؐ��_��
|
| 1998 |
����10 |
�E |
�Q���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶��. (94)���W �Ñ���J�Ɖ����v���u��a���[�v���犧�s�����B�@
pid/7947855
|
���W �Ñ���J�Ɖ��� / 2�`64
���{�Ñ㉤���_�b�ƌܕ����̖�� / ���O�� / p2�`11
���������Ɠ��̍��J / �����i / p12�`21
�_�b�̐S���w����݂��Ñ㉤�� / ����חY / p22�`29
��q�M�ƍĐ���V / �R��ɓ��� / p30�`39
�`���_�̍��J�ƐM�� / ���C�Y / p40�`51
����l / �a�c�� / p52�`64
�w鰎u�x�`�l�`�Ǝהn�䍑(��) / �R���K�v / p65�`90
�����{�R�Õ��o�y�́u��3�N�v���ɂ���/�쑺��/p91�`107
|
���i�K�鋾�ƎO�p���_�b���̊W/���菺��Y/ p108�`124
�u�R�n�������v���ւ̎��_�I�W�]--�u�הn�䍑�v���ւ�
�@�@�������ɂ��G��� / ���c�ƌ� / p125�`142
�����`�Γ�(�Ε)�̋N������т��̓`�d/�F��Ɏq;�щؓ�/p143�`163
�S�����P���̐[�w(2)���������̌𗬂������� / ���ϗm / p164�`171
�������̕ς��߂��鏔��̍l�@(3) / �������b / p172�`184
�����وē� ���{����(����)��(������)������/�����/p186�`188
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p189�`224
�E |
�S���A�����G�u���u���̋N����T��v���u��g���X�v���犧�s����B�@�@ (��g�V��, �V�Ԕ� 554)
|
���e�����^�^���c���̔��ˁE�`�d�ɂ��āA���܂Ȃɂ��킩���Ă��邩�B���҂��V�������͕��@���v�����g�E�I�p�[���@���킩��₷��������A���̕��@�����ɁA�퐶�_�k�̕����ɒ��݁A�ꕶ�_�k�̉\����_���A����ɐ��E�ŌÂƖڂ���钆���E���]�f���^�̐��c���̔����o�߂����B�@CiNii Books��� |
|
�P�@�v�����g�E�I�p�[�����͖@�Ƃ�
�Q�@�퐶����̐��c��� |
�R�@�Ĕ��̗���K�˂�
�S�@�ꕶ�_�k�̉\�� |
�T�@���̔��˒n�����߂ā@�����E���]�f���^�̔��@����
�ނ��� |
�T���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (95)�v���u��a���[�v���犧�s����B�@pid/7947856
|
���W �Ñ㎁�����߂����� / 2�`87
�Ñ㎁���̓`���Ɠ`�� / �����L�� / p2�`10
���b(����)���̎��_���߂����� / �u�c�x�� / p11�`19
�������Ɠn������--�A���m�q�{�R�`�����߂�����/�勴�M��/p20�`34
�������Ƒ�a���� / ������ / p35�`43
�������̐���--�u�����v�̃E�W���Ɓu�A�v�̃J�o�l/�쌫/p44�`53
�h�䎁�Ɗ�����--�h�䎁�͔��_�_�������� / ���я͐m / p54�`64
�`���E�`�����E�����M�� / ��a��Y / p66�`87
�ً}�C�k ���ˌÕ����@�̈Ӗ� / �͏�M�F ; �{���W�� ;
�@�@�@�����R�ьp / p88�`129
|
�Ñ�j�ʐM���ʔ�(1)���ˌÕ��ł̔������߂�����/�ҏW�� p130�`135
�Ñ�j�ʐM���ʔ�(2)
�@�@���L�g���Õ��̓V�̐}�E�lj���߂�����/�ҏW��/p136�`139
�w鰎u�x�`�l�`�Ǝהn�䍑(��) / �R���K�v / p140�`160
�w鰎u�x�ȊO�̒��������́u�הn�䍑�v / ��a��Y / p161�`178
�Ñ�������̒������Ɛ`�� / ��t���T�� / p179�`197
�O����~���́u��v���u�Z�v�� / �r�|���� / p198�`204
�����E���Z�̖퐶�n�� / ���J�ɕ� / p205�`221
�����وē�--�ŎR�����ŎR�Õ��E�͂ɂ픎����/����/p222�`224
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p225�`271 |
�W���A�{��,��F���u�����Ñ㌤�� 2 p.48-56�@�Ñ㌤���ҏW���v�Ɂu�L�g���V���}����v�\����B�iIRDB�j
�W���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (96)�v���u��a���[ �v���犧�s�����B�@pid/7947857
|
���W �������}�g�����̎���--���ˌÕ����߂����� / 2�`87
���˂̋������������ / ������N / p2�`6
���ˌÕ��ƎO�։��� / ��c���� / p7�`18
�O�p���_�b���Ə������}�g����(��)���^���̖�����
�@�@�����ł����ʂ���� / ���쐳�j / p19�`33
�O���Õ�����̐��_ / �C���a�O / p34�`47
�`���̗��Ə������}�g���� / ��a��Y / p48�`78
���ˌÕ��Ǝl�����R--�푒�Ҙ_�̂��߂�/���{����/p79�`87
���W �݊C����1300�N--�Ñ���{�ƊC���̐��� / 88�`149
�Ñ㓌�k�A�W�A�������̑Γ��{�ʌ�--�q�E
�@�@�������E�݊C�𒆐S�� / �����s / p88�`95
�݊C�ŖS��̓��k�A�W�A��������
�@�@���𗬁E���Ղ̏��� / �����h�I / p96�`107 |
������̌����� / �͏�m / p108�`117
�݊C�l�Êw�̌���Ɖۑ�--�݊C�s��̕ϑJ��
�@�@�����n���l���� / �����F�F / p118�`138
�k���A�W�A�����̗��j�ɂ�����\�O�h�l��
�@�@����渂̓� / �G�����X�g�EV.�V���t�N�m�t / p139�`149
�w�����x�n���u�`�l�𒍂́u�@�n�ϖʁv�ɂ���
�@�@��--�@�~�E�b�k�T���l�E��t�ÎO���̉���/�����萶/p150�`164
�]��l�n���`���͂ǂ��܂Ŏj����(��) / �����ꌛ / p166�`179
�ݎ�y��̏ے���(��) / ��J�^ / p180�`197
�u�ږ�Ă̕�v�Ɓu�ږ�Ă̋��v / ��a��Y / p198�`210
�����وē� �k��B�s���l�Ô����� / ���ۏٔ��Y / p211�`214
�Ñ�j�ʐM(1997�N12���`1998�N2��) / ����m�q / p215�`247
�E |
�X���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ��� �u�Ñ�j�̊C (13)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4428411
|
������ ���R��_�̃C���^�[�i�V���i���Y�� / ����p�� / p�\2
��洂̑��N�ƐW�����f�_���߂�����--�w鰗��x��
�@�@�������N��čl(2) / ���i�a�j / p2�`24
���x�~ ����Ђ�� �\�o���w�s / �d���p�Y / p25�`28
���x�~ ����Ђ�� �c�ʌp���j�z������
�@�@������{�鍑���@ / ����p�� / p28�`33
���x�~ ����Ђ�� �L�g���V���}�ɂ���/���쐴��/p33�`38
���x�~ ����Ђ�� ���{�����̕���䑢����/�֓�����/p38�`44
|
��F�I�s / ���菺��Y / p45�`56
�Î��L�E���{���I�̓`���܂��Ă���
�@�@���A�z��/��c��/p57�`71
�u�`�̌܉��v�Ƒ品���ƓS���� / �����t / p72�`82
���P(���Ƃ���)(�퍑)�ƌZ��(������) / �����C / p83�`100
�����Љ� ����s�铇��ՊO�R���c�n�攭�@����
�@�@����(��)�ɂ��� / �R�c�N�� / p101�`126
�{���ւ̗��M�E�ҏW��L / p127�`129 |
�X���A�w�������ɂ��x�ҏW���� �u�������ɂ� 9(9)(102)���W �݊C��--������O�Z�Z�N�E�S��u�C���̐����v�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@pid/4426017
|
�����G�b�Z�C ���ɂƂ��Ă̕�����Y / �d�}�L / p2�`5
�W���A�� �^冂̖��� �����E�Z�������ɂ��ƂÂ�������(III)/��ё���/p90�`95
�ǂݐ� �L�g���̐��� / �{����F / p80�`87
���W �݊C��--������O�Z�Z�N�E�S��u�C���̐����v / / p11�`11
�@�݊C�̍��ƍ\�� / ��ؖ��� / p12�`22
�@�݊C�Ɠ��{�̌��� / �Έ䐳�q / p23�`31
�@�������猩���݊C�� / ���q�C�� / p34�`41
�@�݊C�̈�Ղ������� / �c���W�� / p44�`51
�@�݊C�̌|�p / �����F�F / p54�`59
�@�݊C���̕��w�\���݉��V���j�T�� / �g�ˉ��� / p60�`67
�@���펞��̟݊C�n���nj� / �k���G�l / p70�`75
�@�y�R�����z�݊C�������_�`(1)���鋞�o�y�̟݊C�؊�/�����u/p32�`33
�@�y�R�����z�݊C�������_�`(2)�݊C�̌��� / �����u / p42�`43
�@�y�R�����z�݊C�������_�`(3)�㋞����{�o�y�̘a���J��/�����u/p52�`53
�@�y�R�����z�݊C�������_�`(4)�C��n�����݊C�y / �����u / p68�`69
�A�� ���������̂�����(6)�V���̗� / ��g���q / p6�`9 |
�A�� �����̂��Ƃ킴(18)�q�b / ��얾���� / p10�`10
�A�� �ÓT���̓���(12)���ŏI���� / �͍��Րl / p76�`79
�A�� ���m�ҋƓ���(6)?�̎�ނ������Ȃ�킯�\�˗��҂̗~���Ɠ����V��/���t��/p88�`89
�A�� �L�[���[�h�Ɍ��钆���̔����I(18)1983/1984 / ���쌪�� / p96�`97
�A�� �L�^�C���V(18)������������� / ���}�� / p98�`101
�A�� ���ٖM���̂Ȃ��̕��w�҂���(6)���u���\�P���u���b�W�̉ߌ��ȗ���/����K��/p102�`107
�A�� �A�W�A�̕�(54)[����]�������߂������z���� / ���쌪�� / p108�`112
�A�� �`�������W�I�N���X�����p�Y��(42) / ���������q / p113�`113
�A�� �A�W�ANOW���`�͍Đ�����̂� / / p114�`115
���F���� ���] �_�ސ��w������w�ȕҁw�����ʑ����|�ւ̎����x/�����L/p116�`117
���F���� �����w�őO��(27)[����Љ�] / ���c�ΐl / p120�`121
���F���� �V���Љ� / / p118�`119
���F���� ���C�u�����[ / / p122�`123
�C���t�H���[�V���� / / p124�`127
���G �����̂�������(18)��ߋ@ / �����L�O
�E |
�X���A�Ԗ�P�F���u�C���Ɠ��{�Љ�v���u�V�l�������Ёv���犧�s����B
|
�_�ƒ��S�̗��j�ςɋ^��������_�Ɩ��̎��_����V�������{�̗��j�����\�z���Ă������҂��A�ŐV�̌������ʂ���ɊC���̎����𖾂炩�ɂ��X�Ȃ���j����`���o���B�@�@�u�_�ѐ��Y�W���������@�֑����ژ^�v��� |
|
�C���Ɠ��{�Љ�/8
�C�̗̎�@�������Ə\�O��/50
�\�o�̒���/74
���C���̒ÁE�h�Ɠ����̉���/132 |
�͊C�̐��E�@�����E���Z/162
�I�B�̎R���ƊC��/178
���C�̐E�l�E���l�Ɠs�s/206
���˓��̓��X�@���w�����ɂ݂�̓�/242 |
�C���ʂ̗v�ՁA�@��/283
���E�ɊJ���ꂽ���{��/308
�V�������j�w��n��j����/330
�E |
�P�P���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (97)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947858
|
���W �V���V�c�̎���--�L�g���Õ��̕lj�Ɋ֘A����/2�`102
�L�g���Õ��̑��c�Ɣ푒�� / ���؍F���Y / p2�`12
�L�g���Õ����}--�ւ݂̂� / ���{�h�� / p13�`31
�L�g���Õ��ƍ����ˌÕ�--�lj�̔N��ςƍ���̔��@�E
�@�@���ۑ��E���J�̖�� / �㌴�a / p32�`42
�L�g���Õ��̎l�_�}�ɂ��� / �S������ / p43�`47
�L�g���Õ��Ɠn������ / ��c�� / p48�`57
�L�g���Õ��V���}�Ɠ��A�W�A�̓V���w/�{����F/p58�`69
�r��Տo�y�؊Ȃ̍l�@--�u�V�c�v�n�o����
�@�@�������Ǝv�z / �R���K�v / p70�`82
�V�c�؊ȂƃL�g���Õ� / ��c���� / p83�`85
�V�q�E�V���ٕ��Z������߂�����--
�@�@�����������ɖ₤ / ��a��Y / p86�`102
|
㕌���ՂƔ���Õ��̏o�� / ���{�P�F / p104�`110
�ؖk�����n��̎O�����㓺�� / ���i�L�� / p114�`123
�O�p���_�b���Ɣږ�Ă̋S�� / ��a��Y / p124�`153
�O�p���_�b���Ə������}�g����(��)���^���̖�����
�@�@�����ł����ʂ���� / ���쐳�j / p154�`171
�]��l�n���`���͂ǂ��܂Ŏj����(��) / �����ꌛ / p172�`183
�ݎ�y��̏ے���(��) / ��J�^ / p184�`194
�����وē� �ޗǍ���������������������/��{�\��/p195�`199
�Ñ�j�ʐM���ʔ� ����Õ���
�@�@����~�����@�������߂����� / �ҏW�� / p111�`113
�Ñ�j�ʐM / ����m�q / p200�`232
�E
�E |
�P�Q���A�x�������u�ʕ{�j�k 12 �@ p.37-55�ʕ{�j�k��v�Ɂu�g�r(����)�_�Ɠ�������v�\����B�iIRDB�j
�P�Q���A�� �˗�,�F�c�� �O�N,�� �ˉ�,� �]��,�A �_��,���X�� ��,�����j,�����G�u���u���w�G����Breeding science 48(4) p.387-394�v�Ɂu�v�����g�E�I�p�[���̌`��݂������E���ܑS�R���(6000�N�O�`����)�ɍ͔|���ꂽ�C�l�̕i��Q����т��̗��j�I�ϑJ�v�\����BJ-STAGE
���A���̔N�A���[�����u��r�v�z���� 24 p.8-14�v�Ɂu���ƍĐ� : �Ñ���{�ƃn�j���̔�r�v�\����B |
| 1999 |
11 |
�E |
�P���A�w�������ɂ��x�ҏW���ҁu�������ɂ� 10(1)(106)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@�@pid/4426021
|
�����G�b�Z�C �鋫�E�����̑��ɂ� / ���z���O�Y / p4�`5
�Z���W���A�� ���Ă̖���������˂�(��) / �r�c�I / p76�`83
�ǂݐ� �����̏������l��ǂ� / ���` / p88�`96
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� / 11�`65
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� / / p11�`11
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� ����(����) / ���j / p12�`17
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �n�j��(�_��̏�������(1))/���/p18�`19
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� ���X��(�_��̏�������(2))/�a�J���]/p20�`21
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �i�V��(�_��̏�������(3))/�a�J���]/p22�`23
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �`�x�b�g / �O��L��Y / p24�`27
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �����S�� / �t�t�o�[�g�� / p28�`31
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �؍� / �O�H�� / p32�`37 (
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �x�g�i��/���[�e�B�E�L���E�X�A��/p38�`41
>
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �J���{�W�A / �ۈ��q / p42�`45
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �^�C / ���㒉�� / p46�`49
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �}���[�V�A / ���ˊ��v / p50�`53
|
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �~�����}�[ / ���O / p54�`57
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �C���h�l�V�A / �������� / p58�`61
���W �A�W�A�̂�����--�V�N�̍Ղ�Ɩ��� �C���h / �������� / p62�`65
�V�A�� �N�a�V�H�Y�s(1)����(��)--���x�̈�Ղ߂��� / �떀����Y / p66�`69
�A�� ���������̂�����(10)�����̗� / ��g���q / p6�`9
�A�� �����̂��Ƃ킴(22)���������� / ��얾���� / p10�`10
�A�� ���m�ҋƓ���(10)�d�����l������ɂ�--�����ɂȂ�܂łƁA�Ȃ��Ă���/���t��/p70�`71
�A�� �����̔��w�\�Z�����l�̌Q��(4)����A�藈����A
�@�@���]��������ށ\�k���l�M/���c���}/p72�`75
�A�� �L�^�C���V(22)�C���^�[�l�b�g�̂Ȃ��́u�����v / ���}�� / p84�`87
�A�� �ɂقœǂފ���(4)�����̉� / �ؑ��N�� / p97�`97
�A�� �L�[���[�h�Ɍ��钆���̔����I(22)1991/1992 / ���쌪�� / p98�`99
�A�� �A�W�A�̕�(58)[��p]���f�B�A�~�b�N�X�ōL�����p�̃e���r�l�`��/�ۖڑ��l/p100�`104
�A�� �`�������W�I�N���X�����p�Y��(46) / ���������q / p105�`105
�q�ٖM�r�̂Ȃ��̕��w�҂���(10)������--��Β��̍��` / 縌}�� / 106�`111 |
�Q���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (98)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7947859
|
���W ���{�Ñ�j�Ɠ��{�_�b / 2�`142
�Βk �_�b�Ɠ��{�l--�_�b���Ȃ����������͖����Ȃ���?/�͍����Y;�g�c�֕F/p2�`22
�k�{�R�ɂ��C�̝��a�̈Ӗ��ƁA�T���^�r�R���C�œM�ꂽ�킯/�g�c�֕F/p23�`39
�V�c���̐����Ɖ����_�b / ������ / p40�`48
�ݗt�O�R�̂̐_�b--�S�ϋ~���E�Ė������ƍȑ����̉� / �Ŗ���� / p49�`71
���_�M���痴(�_)�M��--���E���Ñ㕶���𗬂̈�l�@ / ���ϗm / p72�`91
�����_�b�Ƃ��Ă̈ꐡ�@�t / �O�c���l / p92�`107
�`���_(�V�g���J�~)�^�P�n�c�`--�r�Ԃ�_��ގ�����D��/�Ð�̂�q/p108�`115
|
�̘b�u�����[�v�E�u�����[�v�Ƒ��`�̏���̕t�����ꕶ�y��(��)/�����T�q/p116�`135
��_(���Ȃǂ̂���)�Ƒh�h(�\�c�f) / ���J�� / p136�`142
㕌���Ղ̔������Õ��̒���(��)/���{�P�F/p144�`160
�V���V�c�̓o���]--���Q�̕��p�ƐM�Z���s�E�s�{���c�̔w�i / �{�V�a�� / p161�`171
�O�p���_�b���Ɛ_��v�z�Ɛ����/��a��Y/p172�`199
���R�E�V���J���ƃA�T�N���n�� / ���֏� / p200�`214
�����وē� �H�c���������� / �V�쒼�g / p215�`217
�Ñ�j�ʐM(1998�N6���`1998�N8��)/����m�q/p218�`255
|
|
���J�Ē��u �h�h�i���Ɓj�̐��z�@���́i�P�j�`�i�S�j�v�܂ł̓���\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
(76)p200�`211 |
1993-07 |
�h�h�̐��z(--(����1)�������[�g |
. |
pid/7947837 |
| 2 |
(77)p212�`225 |
1993-10 |
�h�h�̐��z(����2)�k��胋�[�g |
. |
pid/7947838 |
| 3 |
(78)p140�`154 |
1994-01 |
�h�h�̐��z--�i����3�j �V���}�j�Y�� |
. |
pid/7947839 |
| 4 |
(98) p.136�`142 |
1999-02 |
��_(���Ȃǂ̂���)�Ƒh�h(�\�c�f) |
. |
pid/7947859 |
|
�R���A�{����F���u�l���w�� = Journal of humanities (�ʍ� 82) p.45�`99�v�Ɂu���{�̌Ð��}�Ɠ��A�W�A�̓V���w�v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�u�V�E = The heavens 80(3)(886)�@�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220582
|
�n�ӕq�v�搶�̂������̕�ɐڂ��� / �{����F / p131�`133
�n�ӕq�v�搶�̎v���o / �ē����� / p133�`134
�n�ӕq�v���m�̈�Y / �������B / p134�`136 |
�V�������w���_(12) / �k���_�� / p151�`152
�z�E�L����50�N(10) / �� �� / p153�`155
�E |
�R���A���F����,��X�,�͏�M�F,��c����,�S������,�{����F,��c�r��,�b���J��O,���L�N,�X����,��˗��ۂ��L�g���Õ��w�p�����c�ҁu�L�g���Õ��w�p�������i�������������������� ��3�W�j�v���u������������ψ���v���犧�s�����B�@IRDB
�U���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ�����u�Ñ�j�̊C (16)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4428414
|
�y�������z��j���[�X�ɂǂ��Ώ����邩 / ���菺��Y / p�\2
���[���b�p�̐_�b�_�Ɋw�ڂ�--�_���V�c���\�_��
�@�@������I�\�z / �`���� ; ����p�� / p2�`9
����Łu�c���j�ρv�̕��@�ᔻ / �R�����v / p10�`1
�R�����v���̘_�l�u����� �w�c���j�ρx�̕��@�ᔻ�v
�@�@����q�ǂ��� / �ˌ��`�M / p15�`17
�R�����v���̒ˌ��`�M���̈ӌ������ɂ���/�ҏW��/p18�`18
����ɂ��Ă̎G�� / �ԓc�O / p19�`21
�Ñ�j���r�ޖ��t�̐l����(3)
�@�@���Õ��Ɋւ��̂ɂ��� / ����N�M / p22�`25
�Z���̊�{����ɐ荞��--����p��u�`�l�`�̒Z����
�@�@�������Ñ�V���w�v��ǂ�� / �J�{�� / p26�`28 |
�Î��L���������Ɋ� / �͉z���i / p28�`29
�u���^ �u�O�����v�Ƃ͉��� / �ߓ��`�Y / p31�`65
���P(�퍑)�Ɗ��� / �����C / p66�`85
��_���o�_ / ��c�� / p86�`99
��B�������ᔻ(2) / �쑺�� / p100�`126
�u鰗��v�̐����N��čl(3)
�@�@���u�������́v���߂����� / ���i�a�j / p127�`140
�N�֔N��@�Ɩ퐶���E����̗�N�� / �R�����v / p141�`159
���k���l / ����p�� / p160�`169
�쓌�ԒˌÕ��ƌ�~�����N�Γ� / �`���� / p170�`174
�{���ւ̗��M�E�ҏW��L / ���c�� / p175�`177
�E |
�W���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (100)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@�@pid/7947861
|
�n��100���L�O���卆 / 1�`400
�n��100���ɂ������� / �]��g�v ; ��a��Y / p2�`5
���h�}�Ɨ�@ / ��c���� / p6�`9
�ݗt��u�ى��v / �ɓ��� / p10�`19
���{�̐ϐΒˌÕ������̌���Ɖۑ�/��ˏ��d/p20�`28
�ږ�Ẳ����ɂ͂ǂ��
�@�@����������������? / ��ё��� / p29�`33
�u���v�����y��̎j�I�Ӌ`--�V����������
�@�@�����\�E���߂��鏊�� / ��e���� / p34�`42
�����_�̎��� / ����d�� / p43�`46
�Ԑl�c���̗� / �J�쌒�� / p47�`58
�L�I�`���ɂ݂�����j�̗ڂ�
�@�@���͓����� / ���؍F���Y / p59�`70
�������ɂ����锒�P��A / �����i / p71�`80
�Ñ���{�l�̋� / ������N / p81�`84
���{�����_�b�ɕ\��ꂽ�T���v�z/���O��/p85�`95
�u�L�J�y���蕶�v�̐^��--�R���j�w�I�������@�ɂ��
�@�@���h�K�N�L���̌��� / �����w / p96�`111
�����ˁE�L�g���Õ��Ɠ��A�W�A / ���� / p112�`113
3�`5���I�̓����{�݂ƕ��A / �Ζ씎�M / p114�`116
�N�q(�Ƃ���)�̏��� / �������� / p118�`118
�k���N�ɗ����� / �㌴�a / p119�`120
�O���ێR��ՍŐV��� / ���c�N�� / p121�`122
���A�W�A�̒��̍����� / ���{����1 / p122�`124
�l�i�G���̍l�Êw / ���쐳�j / p125�`126
�C�O���o�����Õ�����̔n�� / �͏�M�F / p126�`128
�E�n�E�Z�b / �ˌ��� / p128�`130
�u'98�k�P�C�l�䒆�������������ۊw�p������v��
�@�@���Q������ / �ߓ����� / p130�`132
�Ί킩��S��ւ̓]���Ƃ� / �����M�s / p132�`134
����Õ��̌��` / ���Α���Y / p134�`137
���t���z�Ɗy�Q�̎��ԋ���--�O�p���_�b���y�Q����
�@�@�������߂����� / ���J���� / p137�`139
�I�I���}�g�̌Õ��Q�Ɓw鰎u�`�l�`�x--���ˌÕ���
�@�@��"����"���� / ��ؖ��� / p139�`141
�l�Êw�ƒ��--�n���̗��ꂩ��/��������/p141�`144
�הn�䍑�_���̗h�� / ������ / p145�`146
���D�l / �C���a�O / p146�`148
�n���l�̂��̌���l���� / ���v / p148�`149
���n���̘`���� / �s�o��C�u / p150�`151
�Z���ΒˌÕ��z���N��̂䂭��/����O/p152�`154
�u�ʁv�����Ɏv��--�Ëʌ����̍��ۊw�p��c��
�@�@���o�Ȃ��� / �������� / p154�`156
�ꕶ�l�̓V�̊� / �y�~�� / p156�`158
���؏o�y�̊���ݕ� / ���J�� / p158�`160 |
�g�샖����ՁE���m�،Õ��E���r�R�Õ�--�o�y��
�@�@�������i�̐��i�Δ� / �z�ڏ��Y / p160�`162
�����������w���Ƃ͂��� / �\�o�� / p162�`164
㕌���Ղ̕ϑJ�ƋߔN�̒��� / ���{�P�F / p164�`167
�Â�����̕����̔����ɑz�� / ������� / p167�`168
�g���r�p���͕S�ϑ厛�� / ���я͐m / p168�`170
�����唎���ّ��̓��� / �x�c�[�� / p170�`172
�V���E�����˂ƍ��c���� / �O�����m�Y / p172�`173
�g�������̈�� / �ԕǒ��F / p174�`175
�z�K��Ђƌ䒌 / �{����� / p176�`177
���z�ƍl�Êw�̂͂��܂� / �{�{����Y / p177�`179
�ɓs���E�j�Ր����ւ̒� / ���c�N�Y / p179�`181
�ŐV�l�Êw���Ƃ�܂�"�������Ȋw"/�R�ݗǓ�/p181�`183
���]�ȏЋ���R�Ŕ��@���ꂽ�z����
�@�@������ / �F��Ɏq ; ���u�� ; �щؓ� / p183�`189
�Y�������̓�֓�--�㑍�����S��
�@�@���ꍇ / ���C�Y / p190�`192
�O�֎R�l / ��{�p�� / p192�`194
�u�O�悵�v�̓� / ������O / p194�`195
�R�c�j��E�S�ϐl���ʐl���Ę_ / �������g / p196�`197
�Î��L�̐_�b�Ɠ��{���I�́u�_�b�v / ���䐴�� / p198�`199
�_�_�K���̃��S�X�ƃp�g�X / ���c���� / p200�`202
�Ñ�j�̍��� / ������ / p202�`203
�u�g��v�Ɓu�g�w�v�̈Ӌ` / �����L�� / p204�`206
�F��Ăɂ��� / �⌳�`�� / p306�`208
�헤�����y�L��ǂ� / �u�c�x�� / p208�`209
鰎u�`�l�`�Ɠy�t���`�� / �����^�� / p209�`21
�_��I�����ƌ����҂̋����� / ��c�� / p211�`212
�n�j���́u�[�c�@�v�Ɠ��{�́u���O�v / �]�g / p212�`214
�H���̊�|�V���Ɗ����V�c�̕� / �����O / p214�`216
��̎����Ă����S�l��� / ���c���m�q / p216�`218
�u�k�u���l�c���v����n--���V����Ղ�
�@�@�����Ă̈�l�@ / �ʏ閭�q / p219�`220
�w�k�R���x�Ɖݕ��o�� / �c���~�� / p221�`222
�쌩�h�H�`���Ɠy�t����
�@�@���ψ��R�Õ�(�ޗnj�) / �ˌ��`�M / p223�`225
�������q�ƓV�q�V�c / ���R���s�j / p225�`227
�C�����̋�Ԏv�z / �������q / p227�`230
�E�c���M�`���̃n�P(�k�n�N�l) / �i���v�b / p230�`232
�N���̋N�� / �i���� / p232�`234
"�Ɨt���ѕ����_"����̒E�o / �����G�O�Y / p234�`236
�V�l�⌾ / �Óc���F / p236�`238
�p�\�̗������j�̎����敪���߂�����/����Ǎ�/p238�`239
��r�R�_�Ђ̓��_�M�ƕ��� / �ז�� / p240�`242
�p�̒��Ƃ��̑O�� / �{�ʓc�e�m / p242�`244
|
�Y�꓾�ʐ�t�̌��t--�R���A���ǁA
�@�@������O�搶 / �O��P�� / p244�`246
�p�̓V�c�Ƒ������Ɖ͕�/�O�V������/ p247�`248
�w�a�����ڏ��x�R���s���[�^�V��/������/p249�`250
�ɕ������l / ��O�� /p251�`252
�{�Ղ̐���(�������傤) / �O�Y�����q / p253�`254
�C�l�E�J�C�R�E�V�� / �{�c�o / p255�`256
�u����v�̈Ӗ� / ���{���T / p257�`259
�����Ε�c���ւ̉�A / �R���K�v / p259�`261
�o�_�̍��씪�V�� / �R��ɓ��� / p261�`263
�_�b�̐S���ƌ��� / ����חY / p263�`265
�I�z�N�j�k�V�����̌��B�����玝���A�����Ղ�
�@�@���Ӗ��Ɩ��� / �g�c�֕F / p265�`267
�u���{�v�͉����� / �g�c�F / p267�`269
���_�u�k�l������
�@�@�����^�E�S�ϊω��v / �g��T�q/p269�`275
���{�Ñ�ɂ�����Ζ�̕��p/�a�c��/ 276�`277
���߂łƂ�100�� / ���G�Y / p278�`279
�������̖��ɂ��Ă̒�/�����/p279�`280
100�������Ɋ� / ���c�x�m�Y / p280�`281
�Ñ�j�͐l�ނ̑�����Y / ������ / p282�`283
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v
�@�@��100���Ɋ� / �������� / p283�`285
���O���[�o���Ȏ���� / ���菺��Y / p285�`287
�Ñ�j�����̃x���`���[�� / �L�c�L�P / p287�`289
�u���A�W�A�̌Ñ㕶���v�Ƃ�
�@�@���l�����I / �V�쒼�g / p289�`290
100���ɓ������Ă̂�������
�@�@����̗J�� / ���c�ƌ� / p290�`292
�s���̂��߂̌Ñ㎏ / �O���F�j / p293�`295
�u���S�v���u�Ɓv�� / �ԕ��юq / p295�`297
�Ñ�j�u�[���̉Ԃ͊J������/������/p297�`299
100������̐V���ȏo�� / ���c�쌛 / p299�`300
100���̂��d�� / ���i�� / p300�`301
�x�{�K���Ȃ��M�Z�̈ɓ߂�
�@�@���o�y������ / ��a��Y / p302�`313
�Ñ�j�ʐM(1998�N12���`
�@�@��1999�N2��) / ����m�q / p322�`356
�Ǔ��E��ؕ��� / �]��g�v / p316�`317
�Ǔ��E���{���� / ��a��Y / p318�`320
�Ǔ��E���B�� / �]��g�v / p320�`321
100�����}���� / �ˈ䏹�� / p314�`315
���[�v���Ƌ��� / ����m�q / p356�`356
�G������A�W�A�̌Ñ㕶������ڎ� / / p358�`399
�ҏW��L / �����G�q / p400�`400
|
�W���A�u�V������ = The astronomical herald 92(9)�v���u���{�V���w��v���犧�s�����B�@pid/3304943
|
SKYLIGHT<�����̏œ_> �������̑����ϑ�--�n�O�f�����o�Ɍ����� / ������
; �����lj� / p433�`438
SKYLIGHT<�����̏œ_> M82����̔M����--�X�^�[�o�[�X�g��͂�X���ϑ�
/ �ߍ� / p439�`447
�V���V<�Ǖ�> �O��̃A�C���V���^�C�����̕��� / �ē����� / p448�`453
�V���V<�Ǖ�> �t���C���g���b�q�ƃA�C���V���^���� / �����L�� / p453�`454 |
���] �F���̃V�i���I / ���V���P / p455�`455
���{�V���w��1999�N�H�G�N��v���O���� / / p456�`485
����� / / p486�`494
�E |
�X���A�u���w = Chemistry 54(9)(580)�v���u���w���l�v���犧�s�����B�@�@pid/3349406
|
"�V����"�l�Êw�ւ̗U��--���R�Ȋw�ɉ�����ꂽ�l�Êw����/�O�җ���/p11�`11
���W 5000�N�̃^�C�����[�v--��������Ȋw��:�ꕶ�l��
�@�@���P�~�J�����C�t / �É���w�_�w�� �����m��Y�搶�ɕ��� / p12�`36
�C���^�r���[ �ꕶ�l�̃��C�t�X�^�C��--DNA���͂��������_�k�̋N��
�@�@���É���w�_�w�� �����m��Y�搶�ɕ��� / ����/�m��Y / 12�`17
�ꕶ�l�̖L���Ȑ�����T�� / 20�`36
�ŐV�̔N�㑪��@�ł͂���ꕶ�y�� / �g�c�M�v / 20�`23
�Ί�E�ʗނ����ǂ�����--���ގY�n���͂ŒT��ꕶ����̌��� / �m�ȓN�j/24�`27
�A�X�t�@���g�����ǂ�����--�ꕶ����̃n�C�e�N�ޗ� / ���}������ / 28�`30
�ꕶ����Ɉ�삪�n�܂��Ă���!? / �����G�u / 31�`33
�������ő�W����T��--�ꕶ����Ɏ��Â���!? / �X�E�� / 34�`36
�V���[�Y �������ւ悤����! / �����Č����� / p37�`42 |
��� �����f�t���[����--B-C-N�n�Ɍ��ꂽ�o�b�L�[�I�j�I��/�� �`�Y/p43�`46
��� �v�Z���w�͍��c ab initio�@�Ƒ�ꌴ���v�Z�@���r����/�c�� ��`/p47�`52
�G�|�j�~�[����w�ԉ��w�̊�b�̊�b �X�g���b�J�[���� / ��D �j / p53�`55
�����[�A�� ��B���w�҂���̎莆--21���I�̉��w��S���M�N�� / �œN�v / p56�`57
Tu�搶�̉p���莆�Y��u��(9)�ʍ������̎莆 / Anthony T. Tu / p58�`60
�A�� �������̃A�����J���w�L--�A�����J�̃|�X�h�N / ���J���V / p61�`61
BOOKS���w�̖{���� / / p62�`63
1999�N�̉��w--�������w�҂ɂ��ŐV�̃g�s�b�N�X / ���ی[ / p64�`73
���q�ԗ͌�����(AFM)�ʼn��w������������!? / ���{�R���� / 68�`69
���Ɩ��̂����ʕ��͂Ń^���p�N���̗��̍\�������� / �Җ{�a�Y / 70�`71
�����𐫃v���X�`�b�N���q�v�̍ŋ߂̓��� / ���ђ��� / 72�`73
�ҏW������--�����\�� / / p74�`74 |
�P�O���A�����G�u���u�_�Ɠy�؊w� 67(10)(�ʍ� 575)�@p.1049-1054�v�Ɂu�v�����g�E�I�p�[�����͖@�Ɛ��c���T���@�@(���W �_�Ɠy�؊w��n��70���N�L�O�� ; 70���N�L�O���u��)�v�\����B�@(1999.8.3.�� ����w���c�u���ł̍u���L�^)�@J-STAGE
�P�P���A�Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (101)�v���u��a���[�v���犧�s�����B�@pid/7947862
|
���W ���A�W�A�̒��̌Ñ���{ / 2�`109
�V���[�}�j�Y���Ɛ_����݂�
�@�@�@�����̌Ñ�_���ƌ|�\/������/p2�`10
�S�ρA�V���̋߂��ɂ��������ɂ��� / �p�W�U / p11�`23>
���̑��`�j(��) / ���ϗm / p24�`39
�z�����n�q���Ė퐶���������� / ���ƍN�V�� / p40�`57
�؍����݂́w���s�x�͕s�\������ / �����p�i / p58�`73
�]�A���A�������@(��) / ��_�� / p74�`84
|
�V���~�Ղ̕�--�\�̕�����N�V�t������ / �Ŗ���� / p85�`109
�ŋ߂̎O�p���_�b���_�ɂ��� / ���菺��Y / p110�`126
�L�g���Õ��E�����˂̐��}�̓`����T�� / ���ƓO�Y / p127�`145
�A�}�e���X�̍��V���x�z�ƃI�z�N�j�k�V�̍����/������v�q/p146�`163
���������ɂ݂�הn�䍑�E������ / ��a��Y / p164�`183
�~�m�n���ƔZ���Ƌg�� / ���֏� / p184�`198
�Ñ�j�ʐM 1999�N3���`5�� / ����m�q / p199�`231
�E |
���A���̔N�A���[���u�H�������������̕� (�ʍ� 10) p.9�`16�v�Ɂu�_��ȃn�j���́u���H�v���� �v�\����B
���A���̔N�A���c�F�Y�����䌧���։ꍂ���w�Z ���u���䌧���։ꍂ���w�Z�@�����W�^ ��32���v�Ɂu�k���ɂ�����C���̐����E�C�䂳��̑咹���̍ގ��ƎY�n�ɂ��āv�\����B�@�n���\���N�L�O���̎������ / �Z�j������
|
| 2000 |
12 |
�E |
�P���A�r���G���u�C�l�ɍ��܂ꂽ�l�̗��j�v���u�w��o�ŃZ���^�[�v���犧�s����B
�P���A�u�V�E = The heavens 81(1)(896)�v���u�����V���w��v���犧�s�����B�@pid/3220593
|
���_ ������̑��l��--�k�ɐ��̕��������Ƃ��� / �k�� �_�� / p11�`14 |
�V�������w���_-22- / �k�� �_�� / p47�`48 |
�P���A�{����F���u���u�Б�w���H�w������ = The science and engineering review of Doshisha University 40(4) p.75�`78�v�Ɂu���A�W�A�V���w�j�̌��� (���u�Б�w���H�w��������37�����\��u���\�e�W)�v�\����B�@�@
�Q���A�啪���n���j������ҁu�啪���n���j : ���x�����搶�Ǔ����W ��P�V�U���v�����s�����B�iIRDB�j
|
�y�җ��搶�����^p1�`2
���ђ����^p3-4�@
�\���Ƃ��Ă̕y�җ��_�@�@���n�@�O�^p4
�����E�_���ꗗ�^p5-8�@
���j�[�N�Ȋw���Ō[���@���] �G���^ p9
�i�s���j�@�@�^��10
�y�җ��搶�Ƃ̏o��@���� �אM�^p11
�y�Ґ搶���Â�Ł@��� �ێ��^p12
�̕y�җ��搶�̌��ɕ�����@�؋� �����^p12 |
�y�Ґ搶���Â�Ł@�͖� ���v�^p13�@
�i�s���j�@�@�^p14
�y�Ґ搶�̌�����𓉂ށ@�Ó��c ���^p15�@
�y�Ґ搶�Ǝ��@���� �߁^p16�@
�Ҏ��̖��@�ƕx���_�Ё@���� �I�^p17
�t�]�̔��z�����u�^�v�@�|�i �����^p18�@
�y�җ��搶���Âԁ@�L�c ���O�^p19
�y�җ������̐����������ށ@���� ���\�^p20�@
�y�җ��搶�̌䖻�����F���ā@���� ���l�^p21 |
����������������Ă��������ā@��� ��Y�^p22�@
�y�Ґ搶�̎v���o�@���{ ���Z�^p23
�y�Ґ搶�̑z���o�@�S�� �x�b�^p24�@
�y�җ��搶�̒Ǔ��ɂ悹�ā@���o�̐_
�@�@���u���c�a(�Ђ��ǂ�)�v�@�X�R �a���^p25�@
�y�җ��搶�Ɓw�啪���j�x�ߌ���j��S�����ā@�g�c �L���^p26
����啪���ߐX���i�[�i���E�P�j
�������V���L�uꠂ̗t�v���i���E�P�j
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@���x�����F�F���הn�䍑�_��
�Q���A�� �q��,���[���i��j������w�I�v���ҏW�ψ���� �u����w�_�p �@
(�ʍ� 11) p.101�`118�v�Ɂu�|�� �Œ艻���ꂽ�_�b�Ɛ��������Ă���_�b--���{�́u�L�I�_�b�v�Ɖ_�쏭�������̐_�b�Ƃ̔�r�v�\����B
�R���A�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ�����u�Ñ�j�̊C (19)�v���u�Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4428417
|
�y�������z�V���ȃ~���j�A���̗��j�w�Ƃ� / �쑺�� / p�\2
�O����~���ώ@���--�O��������E���o�E�O���������E
�@�@�������E�i�ƎΖ� / �ߓ��`�Y / p2�`26
�u���v�| �O�����E���p�Ę_ / �ߓ��`�Y / p27�`33
���x�~ ����Ђ�� �u�_�v�̔ݏؖ�/����p��/p34�`36
���x�~ ����Ђ�� �w���s�I�x4�N�̉��--
�@�@���B���ꂽ�@���N�� / �`���� / p37�`44
�Ǖ����ꂽ�A���m�E�Y��--�����j����
|
�@�@���R�����g�Ɋ�/����p��/p45�`54
�X�N�i�q�R�i�̌�`�Ɩ{��--�J���c�_�Ƃ��� / �n������ / p55�`68
���P(�퍑)�̉Η��_ / �����C / p69�`89
�����ċy�я����� / ��c�� / p90�`103
�w鰗��x�̐����N��čl(4)���������Ȃ� / ���i�a�j / p104�`115
����ו����ƊL�ւ̓� / ��J�K�s / p116�`133
�{���ւ̗��M�E�ҏW��L / p134�`137
�E |
�U���Q���A���������S���Ȃ�B�i�X�S�j
�U���A�_�{�i���L�ҁu���_ (186) �v���u�_�{�i���v���犧�s�����B�@�@pid/7930729
|
���G �F�N�ՁE�_�{�喃��Еz�I���ՁE���t������b�̎Q�q�E�\��쌴���S�E�_�{��[�告�o
�O�g���䎡�̐^�����q�˂� / �c���� / p1�`9
�V�^����(�Z) / �N�䏟�V�i / p10�`10
����q�l / �����d�F / p11�`20�@�d�v
�w�ɐ��Q�w��䶗��x�Ɏv�� / �N�l�q�g�E�y�g�� / p21�`27
���̌���������_�{�̌䗿�� / ���{�c�G�s / p28�`33
�u���{�̏@�����y�v�̌��_--�t�B�[���h�g���b�v��ʂ��đ̌���������/�㑺�q��/p34�`38
�킪���̂��{����ɎG�{ / �R�{�k�� / p39�`44
�������тƉ����_��Ƃ̊W�ɂ��� / ���䊼�F / p45�`52
�䑕���_��V���[�Y(�O)��m��Ȃ����n/ �і앐�N / p53�`61
|
�O�{�_�y�a�̐v�ɂ���--��[�Z�p�ɂ��`���̑n�� / �ؓ��C / p62�`71
�_�{�O��V���[�Y(��)�_�{�̐_�c�E�䉀 / ������Õv / p72�`79
�b�� �O�{�_�y�a���z�H���i����(��) / �������T / p80�`80
�b�� �_�{���p�ُ������i��� / ���� ; �[�c / p81�`82
�b�� �Z�́E�o��̓��e������ / p83�`83
�b�� �����\��N�x�_�{�ό���̒Z�́E�o��̕�W / p84�`84
�b�� �����\��N���{�Q�q�l�����ʕ\ / p85�`85
�b�� �_�{�̍ՓT(�\����O���܂�) / p86�`8
�b�� ���� / p89�`100 (0050.jp2)
�b�� �z�[���y�[�W�u�ɐ��_�{�v�J�݂̂��m�点 |
�X���A�R�����v���Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (21) p.114�`136�v�Ɂu���c�����摜���ɂ��āv�\����B
�P�O���A���{�����l�Êw��ҁu���{�����l�Êw���� (10)�v���u���{�����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�@pid/2252217
|
�������N���_�̌��� / �����T�� / 1�`12
�_�k�N�����_�ƒ����ɂ�������_�k�̊J�n/�{�{��v/13�`24
�����V�Ί펞�㕶�����ɂ�������_�k�̓W�J/��������/25�`50
�V�Ί펞���Ղ̓y�남��ѓy��̃v�����g��I�p�[������--
�@�@���]�h�Ȃ𒆐S�Ƃ��� / �F�c�ÓO�Y ; ���ˉ� ; �����G�u/ 1�`67
�����V�Ί펞��ɂ�����ƒ{�N���̖�� / �����T�� ; �͖�/68�`81
������]�̒n��o�y�Ðl���̐l�ފw����
�@�@�� / �R���q ; �����F�� ; �����N�H / 82�`100
�ꕶ�����ɂ�����_�k / ������ / 101�`113 |
���}�̏W�� / ���c�K�� / 114�`139
�����L���`������������S�F��ՌQ�̋��Ί��
�@�@�����̈ʒu�Â� / ���ԕ� ; ���쐳�q / 140�`144
��������Ղ̔��@���� / ���� ���� �l�� �����c / 145�`149�@�d�v
�J�ĉ�����ɂ�����Ñ�̖�����
�@�@�����핶���̒��� / ���c���� / p150�`151
1999�N�����l�Êw�֘A�����ژ^ / �v����� ;
�@�@�����K�R���Y ; ��엲 / 152�`158
�b�� 1999�N�x�̊��� / p159�`162 |
�P�O���A�ߒJ�q�Y���u���Ǝ� : �i�[�K : ���Ђ̏ے��ƖL���Ȑ��̐_�v���u�W�p�Ёv���犧�s����B (�A�W�A���䂭)
�P�O���A�쓹���j, �ߓ��鏺, �X�c�N�v�ҁu�~������M���ށv���u������w�o�ʼn�v���犧�s�����B
|
�͂��߂Ɂ@�쓹���j
I�@�~���Ƃ͂Ȃɂ�
��1�́@�~�����ہ@�X�c�N�v�@3
1�[1�@�~�z����@3
1�[2�@�~���̏�ԁ@3
1�[3�@�����I�~���@6
1�[4�@�~�����̃G�l���M�[���@9
1�[5�@���r�o���@10
1�[6�@�T�N���Y���@11
1�[7�@�~���ƔɐB�����@14
1�[8�@�P�Ɛ��ƏW�c���@15
1�[9�@�x���̋敪�@16
1�[10�@�ω������̓~�z���@17
�R����1�@�����̋x���@���c�p���@24
��2�́@�~���̐��Ԋw�@�쓹���j�@31
2�[1�@�~������M���ށ@31
2�[2�@�~������O���[�v�Ǝ�@48
2�[3�@�H���Ɠ~���@59
2�[4�@�~���ꏊ�@63
2�[5�@�~������̖ڊo�߁@68
2�[6�@�~���̊J�n�@76
2�[7�@�~���̏I���ƊJ�n�̃Y���@80
2�[8�@�ɐB�Ǝq�ǂ��̐����@81
2�[9�@�~�����l����@87
II�@�~������M����
��3�́@�R�E�����@�D�z���Ё@103
3�[1�@�R�E�����ɂƂ��ē~���Ƃ́@103
3�[2�@�̐H�ʂƃG�l���M�[���x�@105
3�[3�@�~���ւ̏����@110
3�[4�@�~���ꏊ�̑I���@113
3�[5�@�~���̊J�n�Ɠ~���@116 |
3�[6�@�~�����Ԓ��̊o���ƍs���@118
3�[7�@�z�~�W�c�̌`���@122
3�[8�@�~�����ۂ̒n���I���ف@124
3�[9�@�~���ƔɐB�̒��߁@126
3�[10�@�~���̐i���@130
��4�́@�V�}���X�@�쓹���}�q�@143
4�[1�@�~������V�}���X�@143
4�[2�@�~���̂��߂̐H�������Ɠ~�������@145
4�[3�@�~���J�n�̏����@148
4�[4�@�~�����̍\���@152
4�[5�@�~�����Ԓ��̃V�}���X�@155
4�[6�@�~���̏I���@157
��5�́@���}�l�@�œc�j�m�@162
5�[1�@�~������l�Y�~�@162
5�[2�@�~���ƃ��}�l�̐��ԁ@164
5�[3�@�����x���@177
5�[4�@����̉ۑ�@181
��6�́@�N�}�[���ԓI���ʂ���[�@�H���r�T�@187
6�[1�@�N�}�Ƃ��������@187
6�[2�@�q�O�}�Ɠ~���@191
6�[3�@�A�����J�N���N�}�Ɠ~���@196
6�[4�@�c�L�m���O�}�@201
6�[5�@�N�}�̓~�����l����@206
��7�́@�N�}�[�����I���ʂ���[�@�ؓc�q�j�@213
7�[1�@�N�}�̓~���Ƃ́@214
7�[2�@�~�ᒆ�̑�Ӂ@216
7�[3�@���������w�I����ь��t�w�I�����@221
7�[4�@�A�f�^�N���A�`�j���l�@221
7�[5�@�~���Ɛ��B�̊W�@222
7�[6�@�z�b�L���N�O�}�@228
7�[7�@���ꂩ��̌����@229 |
��8�́@�A�J�l�Y�~�Ɠ����x���@�X�c�N�v�@234
8�[1�@�����x���Ƃ͂Ȃɂ��@234
8�[2�@�����x���̋@�\�@235
8�[3�@�G�]�A�J�l�Y�~�̓~������@239
8�[4�@�A�J�l�Y�~�̉Ċ��x���@243
8�[5�@���������x���@245
8�[6�@�A�J�l�Y�~���̓����x���@247
�R����2�@�}�E�X�ɓ����x����
�@�@�@���U������@�֓��P�v�@254
III�@�~�������̉��p
��9�́@�~������@�ߓ��鏺�@261
9�[1�@���q���x���ł̗����Ɍ����ā@261
9�[2�@�~�������̕��݁@263
9�[3�@�~������@�\�ւ�
�@�@�@�����q�I�A�v���[�`�@269
9�[4�@�~�������̉\���@287
�R����3�@�~���Ɣ]�����ϐ��@�I������@295
��10�́@�q�g�w�̉��p�@�ߓ��鏺�@297
10�[1�@�~���Ƒ̉��ቺ�@297
10�[2�@�~���̗L�p���@297
10�[3�@��̉��̉��p�ƒቷ�ϐ��@301
10�[4�@�~���ގ��̐������ہ@303
10�[5�@�̉��������Ȃ��~���@307
10�[6�@�l�H�~���͉\���@308
10�[7�@�����ƔN�����Y���@310
10�[8�@�����ی�@�\�Ƃ��Ă̓~���@312
�R����4�@�����Ɠ~���@�[���̐��Ă�
�@�@�@����Ȃ��W�[�@��[�M�j�@316
���������@327
�����������@333
�ҎҁE���M�ҏЉ�@336 |
�����̔N�A�Ȉ���,�勴�R�N�v���{���w�j�w��ҁu���w�j���� = Journal of history of mathematics, Japan (�ʍ� 164) p.1�`25�v�Ɂu�����Ñ�ɂ���������H�̊J�n�I�������̎Z�@�ƊO��̗�@�Ƃ̊W�v�\����B |
| 2001 |
13 |
�E |
�Q���T���t�A�ǔ��V���[���Ɂu�~������߂�s�v�c�ȗ́^���Y�������ތ�������ς��v�Ƒ肵�����o���ŃO���[�v���[�_�ߓ��鏺�����̌������Љ���B�@�g�o�i�~�����ٓI����ς����j
�@�@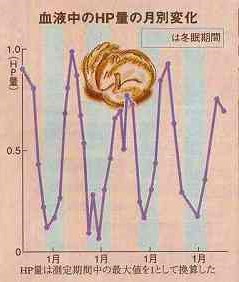 |
�i���j�~������O���[�v���V�}���X�̌��t�����甭�������g�o�i�~�����ٓI����ς����j���B�^�O���[�v���[�_�[�̋ߓ��鏺����炪�������g�o�́A�~���̎��͂ƃ����N���ĔZ�x���ω�����B���t���̂g�o�̔Z�x�́A�������̉Ăɍ����Ȃ�A�~�����͓�\���̈�܂Œቺ����B���������ω��́A�C������̒����ɊW�Ȃ������I�ȔN�����Y��������ł��邱�Ƃ�˂��~�߂��B�^�V�}���X���~���ɓ���ꍇ�́A�C���Ƌ��ɂg�o�̃��Y�����d�v�ŁA�g�o�̔Z�x���Ⴂ�����ɋC���������邱�Ƃ��A�~���̏����ɂȂ��Ă���Ɣ��������B�^�V�}���X���̃O���[�v�ɕ����A���ꂼ��̎������T�x�ƂQ�R�x�ɕۂ������Ŏ��炵���Ƃ���A���̔�r����A����ɋ����[�����Ƃ��������Ă����B�^�V�}���X�̎����͏\��N�ŁA�����傫���̃��b�g�Ɣ�l�{�������B�V�}���X�̕�������������̂́A�~�������邩��ƍl�����Ă����B�����A�Q�R�x�ƒg���������Ŏ����A�~�������Ȃ��Ȃ����V�}���X���A�̓��łg�o�����̃��Y��������ł���A�����悤�ɒ���������Ɣ����B���ɂ͒Z���̌̂��������A�����͂g�o�̃��Y�������Ȃ����̂������B�^�u�~���̖{���͑̉��̒ቺ�ł͂Ȃ��A�g�o�̃��Y���ɂ���B���ꂪ���̖̂h��@�\�����߁A�����ɖ𗧂��Ă���B�v�Ƌߓ�����͐�������B�i���j�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���T���t�A�ǔ��V���[����蕔�� |
�R���A���яt���� �u���A�W�A�̓V���E��w�Ɋւ��鑽�p�I�����v���u�哌������w���m�������v���犧�s�����B�@
|
�܂������@���яt��
�w��������o�x�ɂ��ā@����^��@1
�w�哂�A�z���x�̍l�@�[���{�̓`�{�𒆐S�Ƃ��ā[�@�R�������@47
�䂪���V���E���ʎj��ɂ�����I�N�^���g�E�Z�L�X�^���g�@�����m�@71
�������̗�ɂ���(����) �[�吴������\���N�I���ʏ�(��������}���ّ�)�[�@��J���j�@121
�����Ñ�ɂ�����ՂƗ�@�̌��A�W �[�T�C���̍\���ƌ����𒆐S�Ƃ��ā[�@�l�v�Y�@155 |
�V�����̍\�z�ƌ`����w�I�l�@�@�I���\��@191
�Ñ㒆���ɂ����鐳���_�̍����̕ϑJ�Ƃ��̈Ӌ`�ɂ���
�@�@�� �[�u���j���v�Ɨ�w�E��@���Ƃ𒆐S�Ƃ��ā[�@���яt���@223
�w���ʑS�`�x�Ƃ��̐��w�I���e���߂����ā@���ї��F�@265
���Ƃ����@���ї��F�@(1)
�E |
�R���A�� �q��,�� ����,���[���i��j���u��r�����w��� = Journal of comparative folklore 21(1-4) (�ʍ� 103-106) p.1�`24�v�Ɂu�������쏭�������̈�앶���ƈ��_�b�v�\����B
�U���A ���{�P�v,�����L��,�g�c�Ȏq�����{�Ȋw�j�w����u�Ȋw�j����. [��U��] = Journal of history of science, Japan. [Series �U] 40(218) p.104�`106 �v�Ɂu�A�S�� �V�镶�Ɍ�����ҁw�V�镶�ɖژ^�x�v���Љ��B�@�@�i-STAGE �@��id/1168398
�U���A���i�a�j���Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (24) p.102�`115�v�Ɂu�w鰗��x�̐����N��čl(��)�@鰐W���鰎j�Ҏ[�Ɓw鰗��x�̓����v�\����B
|
���i �a�j���u�Ñ�j�̊C�i10�`�Q�S�j�v�ɔ��\�����u�w鰗��x�̐����N��čl(1�`�T)�v���̓���\
| �m�� |
�G�����Ɗ��E�� |
���s�N |
�_���� |
���e |
pid |
| 1 |
�Ñ�j�̊C�i10�jp34�`44 |
1997-12 |
(1)���Q��u鰗��S�{�v���߂����� |
. |
pid/4428408 |
| 2 |
�Ñ�j�̊C(13)p2�`24 |
1998-09 |
��洂̑��N�ƐW�����f�_���߂����� |
. |
pid/4428411 |
| 3 |
�Ñ�j�̊C(16)p127�`140 |
1999-06 |
�u�������́v���߂����� |
. |
pid/4428414 |
| 4 |
�Ñ�j�̊C(19)p104�`115 |
2000-03 |
���������Ȃ� |
. |
pid/4428417 |
| 5 |
�Ñ�j�̊C(24) p102�`115 |
2001-06 |
鰐W���鰎j�Ҏ[�Ɓw鰗��x�̓����i���j |
. |
- |
|
�V���A�{�� ��F���u�V�E = The heavens 82(914) p.459�`462�v�Ɂu�M�����搶�̂������v����B�@�@�@�@
�X���A���{�Ȋw�j�w��ҁu�Ȋw�j����. Journal of history of science, Japan [��U��] = [Series �U]�v���u���{�Ȋw�j�w��v���犧�s�����Bpid/11683985
|
���R�����Ɨ�ؐ����Y--�V���w�҂̊S�ɓ����ꂽ�����j����� / �g�c�Ȏq / / 129�`136
�A�S�� �́E�M�����搶�̋ƐтƗ��� / �{����F / / 158�`160 |
|
�P�O���A���a�����u���k�w. [��1��] 5 p.186�`200�v�Ɂu �w�C��̓��x�čl--���B�E���������ƃ��I�X�E�^�C�̃A�J���̈��E��p���V��̔�r����
(���W �C�Ɠ��̖����j)�v�\����B
�P�P���A���䐟�v���u���v�̂͂Ȃ��v���u�Ђ炢���v�X�i�s��j�v���犧�s����B
|
���䎞�v�X�Ǝ�-���ɂ����ā@1
���́@�����v��@�����v�E�����v�E�Ύ��v�E�����v�@11
���́@I�@���͂ǂ̂悤�Ɍv���Ă������@12
���́@I�@��̒a��
���́@I�@���z��̋N���̓G�W�v�g
���́@I�@���҂���������ǂ�
���́@I�@�O���S���I��̒a��
���́@I�@�������B�̗ގ���
���́@I�@�ŏ��ɗ����������
���́@I�@�Ñ㒆���̓V���w
���́@I�@�V����̑��c�ƓV���V�̔���
���́@I�@�����̗�͎��R��
���́@I�@���x�����߂����̎�����
���́@II�@�����v�̕��݁@18
���́@II�@�����v�̎n�܂�
���́@II�@�G�W�v�g�̓����v
���́@II�@�f���X���̓����v
���́@II�@�|���y�C�̓����v
���́@II�@���[�A�l�̓����v
���́@II�@�y�\�Ƃ�ꂽ�����̓����v
���́@II�@���N�̋����k�L�l
���́@III�@��̒������v��@22
���́@III�@�����v
���́@III�@�j�[�_�����������������v
���́@III�@���⎞�v������
���́@III�@���E�ő�̐����v
���́@III�@��ނ������Ύ��v(���E�\�N���v�A�Γꎞ�v�E
�@�@�����Վ��v�E���D)
���́@III�@�����v���v
���́@III�@�����v
���́@�@�B���v�̏o���@�����v���玺�����v�ց@29
���́@I�@�����v�̒a���@30
���́@I�@�C���@�ƃN���v�V�h��
���́@I�@�@�B���v�̏o��
���́@I�@�����v�̓��l�b�T���X�Ɏn�܂�
���́@I�@�C�^���A�̓����v
���́@I�@���[���b�p���s�s�̓����v
���́@I�@�����v�̍\���Ǝd�g��
���́@II�@�[���}�C�̔����@37
���́@II�@���^���̎���
���́@II�@���I�i���h�E�_�E�r���`�̃o�l
���́@II�@�[���}�C���v�̔���
���́@II�@�j���[�����x���N�̗�
���́@II�@���O�H�Ǝ��v�Â���
���́@II�@�[���}�C�̋ϗ͋@�\
���́@II�@�������u�ɂ�����
���́@III�@�����̎������v�@42
���́@III�@�h���f�B�̓V�����v
���́@III�@���v�����̉ߓn��
���́@III�@�����^���N���b�N
���́@III�@�X�C�X���v�̎n�܂�
���́@IV�@�U�q���v�̒a���@47
���́@IV�@�U�q�̓������̔���
���́@IV�@�U�q���v�̔���
���́@IV�@����������
���́@IV�@�����̐U�q���v
���́@IV�@�����h���̕ϖe
���́@IV�@�����h���̎��v�E�l�g��
���́@IV�@�N�������g�̃����O�P�[�X�E�N���b�N
���́@IV�@�A���N���E�i�@�̔���
���́@IV�@�������C�����U�q
��O�́@���ƍI�k�����Ƃ߂ā@53
��O�́@I�@�ؗ�ȑ������v�@54
��O�́@I�@���z���̃t�����X
��O�́@I�@�u�[�����[�N�E�N���b�N
��O�́@I�@�G�i�������v
��O�́@II�@�̑�Ȏ��v�E�l�u���Q�@57
��O�́@II�@�W�����̎��v�Y��
��O�́@II�@�p���Ŋ����u���Q
��O�́@II�@���ʂȋ@�\�ƃc�[���r����
��O�́@II�@���액�G���v�u�}���[�E�A���g���l�b�g�v
��O�́@II�@���@���v�T���p�`�b�N
��O�́@II�@���E�ō��̎��v�R���N�V����
��O�́@II�@���ÃR���N�V����
��O�́@II�@�������v���C������
��O�́@II�@���p���v�̂��̌�
��O�́@III�@�C�M���X�̉������@70
��O�́@III�@��������̐ݗ�
��O�́@III�@�t�b�N�̃q�Q�[���}�C
��O�́@III�@�̑�Ȑe���g���s�I��
��O�́@III�@�o�[���[�̃��b�N�����ő��u
��O�́@III�@�N�H�[���̃��s�[�^�[�E�E�H�b�`
��O�́@III�@�j�u�̃��[�}�����ő��u
��O�́@III�@�O���A���̒��i�A���N���E�i�@
��O�́@IV�@�C�m���v�̊J���@76
��O�́@IV�@�|���h�̏܋����������C�M���X
��O�́@IV�@�؍H�E�l�n���X���̒���
��O�́@IV�@�傫������H1
��O�́@IV�@H2����H3�ւ̒������̂�
��O�́@IV�@H4�̊����Ɨm�㎎��
��O�́@IV�@�P���h�[���̊C�m���v
��l�́@�E�i�@�̉��ǂƎ��R�U�q�̔����@81
��l�́@I�@�E�i�@�̐i���@82
��l�́@I�@�N���b�N�ƒE�i�@
��l�́@I�@�E�H�b�`�ƃq�Q�[���}�C
��l�́@I�@�V�����_�[�E�i�@�Ɠ�d�E�i�@
��l�́@I�@�f�e���g�E�i�@
��l�́@I�@�Y�Ɗv���Ǝ��v
|
��l�́@I�@�}�b�W�ƃ��o�[�E�i�@
��l�́@I�@��O�p�̒E�i�@�ƕ��
��l�́@I�@�r�b�O�E�x���̒E�i�@
��l�́@II�@�U�q�ƒn���̎��ԁ@89
��l�́@II�@�O���A���̐���U�q
��l�́@II�@�n���X���̐L�k��U�q
��l�́@II�@�g���[�g���̉~���U�q
��l�́@II�@�d�C�̕��݂Ǝ��v
��l�́@II�@�d�����U�q�̒a��
��l�́@II�@�d�����[�^�[���v
��l�́@II�@���ϑ��z���ƕW����
��l�́@II�@�P�ʂ̓���Ɛ��E�W����
��l�́@II�@��\���ƒn���̎��]���x
��l�́@II�@�^�R�U�q�̒a��
��́@�킪���̎������x�@97
��́@I�@�����̎��v�@98
��́@I�@�w���{���I�x���Ђ��Ƃ�
��́@I�@�V�q�V�c�̘R��
��́@I�@���x���Ӗ��������
��́@I�@�S����
��́@I�@��߂ƉA�z��
��́@I�@���V�c�Ɓw���쎮�x
��́@I�@�����l�Ɏ���w���쎮�x��
�@�@�������@�ƕS����
��́@I�@�R���ɂ�鎞���@�̏I��
��́@II�@�������̎������x�@106
��́@II�@�C�s�̎������������
��́@II�@�X�Ɠ_�͖邾���̎������x
��́@II�@������
��́@II�@���@���畐�Ƃ�
��́@II�@�ƌP�Ɍ����镐�Ƃ̎���
��́@II�@�����Z�ƕ�Z��
��́@III�@�]�ˎ���̎������x�@112
��́@III�@�]�˂̎���
��́@III�@�\�ǂƃP���y���̗����L
��́@III�@���\�̏��͎O����
��́@III�@���i���̏�������K�˂�
��́@III�@��������Ă������̏�
��́@III�@���얋�{�Ɓw���쎮�x
��́@III�@�w���쎮�x�̎���
��́@III�@�w���쎮�x�ƞ����̕��y
��́@III�@�ӂ����і����Z�ƕ�Z�ɂ���
��Z�́@�]�ˎ��㏉���̎��v�@119
��Z�́@I�@��؎��v�@120
��Z�́@I�@�U�r�G���̎��v
��Z�́@I�@�ƍN�̃X�y�C�����v
��Z�́@I�@�v�\�R�̎��v�]�b
��Z�́@I�@�G���Ǝ��v
��Z�́@I�@�ƌ��̎��v
��Z�́@I�@������̃X�y�C�����v
��Z�́@I�@�F���v�̍\��
��Z�́@II�@�a���v�ւ̓������@129
��Z�́@II�@���{�ŏ��̎��v�t
��Z�́@II�@�։����̓�؎��v
��Z�́@II�@��؎��v�Ƙa���v�̔�r
��Z�́@II�@���v�Ƃ��炭�蕶��
��Z�́@III�@�]�˂̗�Ǝ��v�t�@134
��Z�́@III�@�y���ƂƍK�����
��Z�́@III�@�a��t�C�ƒ勝��
��Z�́@III�@���\���̖��{�V����
��Z�́@III�@�ܑ㏫�R�j�g�ƌ��\����
��Z�́@III�@�]�˂Ƌ��s�Ŋ������v�t����
��Z�́@III�@���p�m���̉���
�掵�́@����̎��v�t�����@141
�掵�́@I�@���w�̕����ƒ���@142
�掵�́@I�@����o��
�掵�́@I�@���R�g�@�Ƌ��ۂ̉��v
�掵�́@I�@����̓V���w�Ǝ��v
�掵�́@I�@�꒚�e���v�Ɗ��������
�掵�́@II�@��p���v�t�E�K��g�Y���q��@146
�掵�́@II�@�����w����̎��v�t�x�̂���
�掵�́@II�@�K��g�Y���q��̋Z�ʂƂ��̑Ή�
�掵�́@II�@�]�ˏ�厞�v�̉���
�掵�́@II�@�����������g�Y���q��
�掵�́@II�@���v�Ɠ�ؓS�̊W
�掵�́@II�@���v�̋@�B���i�Ɛ^�J
�掵�́@III�@�g�Y���̎���@152
�掵�́@III�@�K��g�Y�������������v
�掵�́@III�@��ᴎ��v����ɏC��
�掵�́@III�@���Ϗ��Ɍ���C�����e
�掵�́@III�@���Ϗ����琄���ł��邱��
�掵�́@III�@�����{�Ƃ̉������v
�掵�́@III�@�nj��䎞�v�̏C��
�掵�́@III�@��ࣂƋP���V���̊nj����v
�掵�́@III�@�{�̂̓C�M���X���U�q���v
�掵�́@IV�@���̑��̒���̎��v�t�����@163
�掵�́@IV�@������v�t�E�䔦�h�O
�掵�́@IV�@�\���̎��v�t
�掵�́@IV�@�{�ƈȊO�ł̎��v�t�̊���
�掵�́@IV�@�䔦���ꑰ�̏���
�掵�́@IV�@�K�쎁�̎q��
�攪�́@�e���v�a���v��
�@�@���]�ˎ���̉Ȋw�҂����@167
�攪�́@I�@�e���v���v�o��@168
�攪�́@I�@�c������Ɛܒ��w�h
�攪�́@I�@�e���v�a���v�Ɗ������
�攪�́@I�@�r�ؑ�a�k�e���l��
�@�@�����s���\���鎞�v�t
|
�攪�́@I�@�揊���甭�@���ꂽ�������v
�攪�́@I�@�c���ӎ��̓�̉������v
�攪�́@I�@�����v�̕��y
�攪�́@I�@�V�я�̎��v
�攪�́@II�@�V����Ɗ�����@176
�攪�́@II�@����Ɩ��c����
�攪�́@II�@�掖�ق̑o��
�攪�́@II�@���h���V�͐U�q���v
�攪�́@II�@�V����Ɗ�����
�攪�́@II�@�ɔ\���h�Ɓw���{�`�n�}�x
�攪�́@II�@�q�ߐ����������ʂ̂�������
�攪�́@II�@�q�ߐ���x�͓�\������
�攪�́@II�@�w�������f��x�ƓV�ۗ�
�攪�́@III�@�����̖ؐ��厞�v�@184
�攪�́@III�@�א씼���́w�@�I�}�b�x
�攪�́@III�@�헤�̂��炭��ɉꎵ
�攪�́@III�@�ɉꎵ�̖ؐ��厞�v
�攪�́@III�@�O�̗֗�
�攪�́@III�@���̕����Ɨ�����u
�攪�́@III�@���v�Ŗ�������J��
�攪�́@III�@�V�[�{���g�̗���
�攪�́@III�@�V�[�{���g����
�攪�́@III�@�I�����_���w�������䔦�h�O�̎��v
�攪�́@III�@���h�E���h�̏��蒌���{炋Z�p
�攪�́@III�@�K���X�̎g�p
�攪�́@III�@���ʂɂȂ����a���v�̎��(�E���v�A�����v�A
�@�@���ڎ��v�A�T�Z���v�A��㎞�v�A���U���v�A
�@�@����U���v�A�������v�A����Ȏ��v)
�攪�́@IV�@�c���v�d�̖��N���v�@200
�攪�́@IV�@����F���́w���m���C�V�荏�����x
�攪�́@IV�@�v���Ăɐ��܂ꂽ�V�˔�����
�攪�́@IV�@���炭��l�`
�攪�́@IV�@���v�t�ւ̓]�g
�攪�́@IV�@�{��R�V
�攪�́@IV�@���N���v
�攪�́@IV�@���N���v���C������
�攪�́@IV�@�v�d�̂��̌�
�攪�́@IV�@�~�O���t�������v
�攪�́@IV�@�L�k����j
�攪�́@IV�@����@���̉~�O���t�������v
���́@�����ېV�̎��v�t���猻���
�@�@���d�q���v�v���܂Ł@213
���́@I�@�����̐��m���v�@214
���́@I�@�A�����J�Ɍ��コ�ꂽ�a���v
���́@I�@�t�@�u���u�����h����̐ݗ�
���́@I�@�t�@�u���u�����h�̌���
���́@I�@�������N�̌��Ďg�߂Ǝ��v
���́@I�@���v���N�̌����g�߂ƃI�����_���w��
���́@I�@�ƖƘa�{�䂩��̉������v
���́@I�@��C�푈�̏��s�����������m���v
���́@I�@�����V���{�ƌߖC�h��
���́@I�@�V����̏��łƐ��w��
���́@II�@��������Ǝ��v�̔��W�@223
���́@II�@����̕z��
���́@II�@����̗�����
���́@II�@����N�������g��
���́@II�@����@�g�́w����فx
���́@II�@���������̎��v�t
���́@II�@���ѓ`���Y�@�����[���Y�C�|�����E�q��C
�@�@������ɘa���C�V��펵�C���q�����C���K���C
�@�@����쓿�O�Y�C���J�O�Y
���́@II�@�����ɂ����鎞�v���H�Ƃ̋���
���́@II�@�吳�̎��v�ƊE
���́@II�@�吳���̕��䎞�v�X
���́@II�@�펞�̐��Ɋ����܂ꂽ���a�O��
���́@III�@���������Y�Ɛ��H�Ɂ@235
���́@III�@�������v�X�̗h����
���́@III�@���H�ɂ̐ݗ�
���́@III�@�ŏ��̉��Ď��@���s
���́@III�@���Ď��@�̓y�Y
���́@III�@���I�푈�Ƌߑ�H�Ɖ��ւ̓]��
���́@III�@�����̋⎞�v�ɂȂ����u�G�L�Z�����g�v
���́@III�@���{�ŏ��̘r���v�u���[�����v
���́@III�@���^���v�̕��y�Ɓu���̋L�O���v
���́@III�@�֓���k�Ђɂ��Ō��ƍċ�
���́@III�@���Y�ŏ�8�^�u�Z�C�R�[�v��
�@�@���S�����v�u�Z�C�R�[�V���v
���́@III�@���C�o����ƃV�`�Y���̓o��
���́@III�@���œd�C���v�̑�l�C
���́@III�@�����̎��ƌR�p���v�̐��Y
���́@IV�@�����ƐV����@246
���́@IV�@�������~���v�̉��s
���́@IV�@�V�@�\�̊J�����߂�����
���́@IV�@�V�`�Y���̑ϐk���u�u�p���V���b�N�v
���́@IV�@���Y�������r���v�̒a��
���́@IV�@���Y���̖h���r���v
���́@IV�@�d�C�����v�Ɠd�r�r���v
���́@IV�@�g�����W�X�^�|���v
���́@IV�@���q���v�Ɖ[�b
���́@IV�@�u�A�L���g�����v�Ɓu�X�s�[�h�}�X�^�[�v
���́@IV�@�Z�p�̔������Ȃ����������I�����s�b�N
���́@IV�@�G���N�g���j�N�X����̃N�H�[�c���v
���́@IV�@���E���̃N�H�[�c�r���v
���́@IV�@�@�B���[�u�����g�r���v�̒���
���́@IV�@���Ԃ̖����Ɛl�ނ̐���
�����ȎQ�l�����@262
�a�m���v�֘A�N�\�@����
�E |
���A���̔N�A�{�� ��F���u�Ȋw�j���� 40(219) p.158-160�v�Ɂu �́E�M�����搶�̋ƐтƗ���(�A�S��)�v����B�@J-STAGE |
| 2002 |
14 |
�E |
�P���A�u��` : �����̉Ȋw 56(1) ���W(2)�M���ނ̓~���@p.49�`80,�}2�v�����s�����B
|
���W(2)�M���ނ̓~��
�@�~���̂����݁^ �ߓ� �鏺 p.50�`55
�@�]�Ɠ~���^ �c���L,�����_�l p.56�`60 |
�@�~���ł��Ȃ������̑̉��ቺ���ہ^ �֓� �P�v p.61�`67
�@�~���̉��p(1)�S����p�ƒ�̉��Ö@�^ ��J �� p.68�`73
�@�~���̉��p(2)�]�ቷ�Ö@�^ �� ���V�@ p.74�`80 |
�R���A���c�v�����u��ƕx�̋N�� : ��ς݁E�N�ʁE���^�����v���u�����Ёv���犧�s����B
|
���e�����^���҂́A���c���j�́u�g�r�̖݁E�g�r�̕āv�̘_�|���㐢�̌����҂ւ̖���N�Ƃ��Ē����ɎƂ߁A������b�u�g�r�v�̉𖾂ɂނ��A���ʂ����Ē��������Ɏ��g��ł���B�~�n���ɓ������w���ɂ�����I�J��B�@CiNii Books |
|
��P�́@�u�g�r�̖݁E�g�r�̕āv�čl
��Q�́@�F�U��Ղ�ƃg�r�V�o |
��R�́@�x�̖ؓn���ƌ��̐�
��S�́@��ς݂Ɨ��K�_�@�g�r�v�̑��� |
��T�́@��ς݂��K
��U�́@��ƔN�ʁ@�x�̖��� |
�R���A���[�����A�W�A���������w��ҁu�A�W�A������������ 1(0)�@ p.37-67�v�Ɂu�n�j�̐V��:�\�Ƃ̍ՂƂ��Ă̐V���\�v�\����B �i-STAGE
�P�Q���A�����j���Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (30) p.2�`24�v�Ɂu���c�����摜���̖����ɂ��Ă̈ꎎ�_�v�\����B�@�@ |
| 2003 |
����15 |
�E |
�Q���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 78(2) p.277�`284�v�Ɂu���͔_�k����o�����c���--�N�����̍čl(5)�v�\����B
|
�u���ؔ_�k����o�����c�k��--�N�����̍čl(1�`5)�v���e�ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
| 1 |
77(10) p.1058�`1064 |
2002-10 |
���ؔ_�k����o�����c�k��--�N�����̍čl(1) |
�E |
| 2 |
77(11) p.1172�`1177 |
2002-11 |
���ؔ_�k����o�����c�k��--�N�����̍čl(2) |
�E |
| 3 |
77(12) p.1274�`1280 |
2002-12 |
���ؔ_�k����o�����c�k��--�N�����̍čl(3) |
�E |
| 4 |
78(1) p.19�`27 |
2003-01 |
���ؔ_�k����o�����c�k��--�N�����̍čl(4) |
�E |
| 5 |
78(2) p.277�`284 |
2003-02 |
���͔_�k����o�����c���--�N�����̍čl(5)�@ |
�E |
|
�U���A�S�ˍ����E���]�E���ŕ��E���T�E�b���S���u�y�؊w��_���W 2003(736) p.1-17�v�Ɂu���{�E�g��P�����u��ƒ����E�]��y�Ƃ��̒n�ՍH�w�����ƍ\�z�Z�p�v�\����B�@J-STAGE
|
���^�^���{�͌Â����璆���Ƃ̌𗬂�����A���ɍ]��n���Ƃ̊W���[���ƌ����Ă���B���{���ꌧ�̋g�샖�����u��̌����͒����̍]��n���ɓ_�݂���y�Ƃ��Ղł͂Ȃ����ƍl������B���҂�͋g�샖�����u��ƒ���
�E�]��ɂ�����l�̓y�Ƃ��ɑ� ���Ēn�ՍH�w�I���꒲���Ǝ������������{��,�g
�샖�����u��ƍ]��y�Ƃ��̐��y�̒n�ՍH�w�����𖾂炩�ɂ����B����Ղ̐��y�͂悭���ߌł߂��Ă���A�����̐�[�̓y�؋Z�p����g����Ă���悤�ł���B����Ղ̍\�z�ɂ�,�Œz�H�@���g�������Ƃ��m�F����A���ʂ̔Œz�H�@�͗���Ղ̖��ڂȊ֘A����\���Ă���B |
�V���A�S�ˍ���,���]���u�n�ՍH�w�������\�� ���\�u���W JGS38(0) p.31-32�v�Ɂu�Œz�Z�p�̃�-�c�Ƃ��̕ϑJ�v�\����B�@J-STAGE
�P�Q���A���q�����Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (34) p.42�`50�v�Ɂu��N�_�ƋF�N�Ձv�\����B�@�d�v
�P�Q���A���x�M�v���O�D�a�`�E����O�F�ق����u���{�̌ÎЁ@�ɐ��_�{�@p82�`101�@�W���Ёv�Ɂu�_�{�̌ËV�͌��v�\����B
|
�O�́@�O�{�[���a�i�݂��j�s�_���Ղ�L���_�{
�����̐_��
�����H���̐_
�_�̌��ɑ�����
�_��J���l
��A�Q���ƌ���
��A�C�P�i����͂j
�O�A�����[�i�ق��Ă�ق��̂��j�̋V��
�l�A�j���i�̂�Ɓj
�܁A�q�� |
��́@���{�[�V�Ƒ�_�Ɛ_����
��_�͕̂�
�q�����L�̐_��
���V���i�Ёj����~���i�~���j��
�_���̑��
�։�
�_���̏z��
�_�{�̎��N�J�{
�E
�E |
���A���̔N�A���[�����u��r�������� 8 p.67-87���V��w��r�������������Z���^�[�v�Ɂu�������߂����� : �n�j���̏ꍇ�v�\����B |
| 2004 |
16 |
�E |
�Q���A���[��������w�I�v���ҏW�ψ���ҁu����w�_�p�@ (�ʍ� 15)�@ p.39�`49�v�Ɂu�o�����N���r�^�����̈�E�c��Ձv�\����B
�S���A�{����F���u���{��w�� (11) p.1-9�v�Ɂu�L�g���Õ��̐V�摜�Ɠ��A�W�A�̓V����@�v�\����B
�V���A�S�ˍ���,���],�Y,���̎��S�炪�u�n�ՍH�w�������\�� ���\�u���W
JGS39(0) p.15-16�v�Ɂu�Œz�Z�p�̃��[�c�𒆍��E�Ǐ���ՌQ�ɒT��v�\����B�@�@�@J-STAGE
�P�P���A�O�}�{�a���Ď��L�O�_�W���s��Ғ��u�O�}�{�a���Ě�L�O�_�W�v���u�������[�v���犧�s�����B�@
|
�O�}�{�a����߉e�^�O�}�{�a���䗪���@i
�O�}�{�a���䒘��ژ^�@vii
���@��{�p��@xi
�ጾ�@xvii
�_��
�J�b�c�@�l�b���̃��[�}����ʑ��̏��L�҂ɂ��ā@�����K�@3
�A���@�[���Ƃ��̊��品�@����a���@19
�������u�\�ljM�@�r�c���@33
�m�b�̑��Ձ@�r�c�T�@59
��Z�O��N�ɃA���R�[���E���b�g��K�ꂽ�X�{�E�ߑ��v��[�̏����@�Α�Ǐ��@69
�w�A���r�A���E�i�C�g�x�̉��@��㐐�q�@85
�^�_���̌����@��{�p��@96
���z�̋P�����u���{�v-�C�X�^���u���ݗ��C�����l�����̃y���V�A�l���w�A�t�^���x��
�@�@�₶�L������-�@�C�[���W���E�A�t�V���[���C�i��j�H�c����@109
�����A�i�g���A�̍����y��@�呺�K�O�@121
�y���V�A���w�ɂ����鏗�����̏��@���c�b���q�@140
�]���A�X�^�[���Ɛ_���`�@���c�����@152
�~�g���X���ƃR�}�Q�l�@����p�Y�@165
�C�X���G�����G���E�Q����Ց掵�����@��������@�u�c�돺�@178
�Ñ�C�����̎˗�Ɖ����@�����s��@193
�t�@���[�e�B- (falati) �l -��㐢�I�㔼�G�W�v�g�́u���Q�ҁv (mutashanid)-�@�������@204
�m�P�c�n�����Ɓm�P�c�n���@���֏��@218
���l�T���X����ɂ�����w�u���C�����̒a���@���R�h��@230
<�����̌_��>�ƃC�X���[���̐_��Ɓ@���c�Ɂ@243
����������Ђƍ����Ɍ��钆���C���h�m�̓����f�� -�v���J�b�g�ł̒�������-�@�h�����@255
�V�i�C�����i�[�N�[�X�R�̃A���r�A���ǔ蕶�ɂ��� -�O�ܔN�蕶��
�@�@���l�ܔN�蕶���߂�����-�@�쏰�r�v�@263
�u�g�z�v���̎w���Ƃ���@�����`�O�Y���{�@277
�X����Ԓ��̛_�c�M�@�E�����@287
�V�i�C�R�ƃK���K�[�͂��Ăт��܂����́@�v�ۓc�W�O�@300
�E�f�B���[�iⲋL�@�K�R���i�@311
���ғ`�Ƃ��Ẵ��n���}�h�` -�C�u���E�C�X�n�[�N�́w�a���ғ`�i�V�[�t�j�x�̏ꍇ-�㓡���@323
�u�O�f�A�̔�v�ɂ���1-�u�֎q�ɍ�������_�v-�@���ѓo�u�q�@339
�l�N���|���X�E�e�[�x�̐V������ꔪ�����̍�����̈ʒu�@�ߓ���Y�@352
�p���~���̕�Ɍ��郉���v�Ǝ��҂ɂ��ā@�������G�@363
�R�c�Ў��Y�ƃg���R�E�^�o�R�@��{�ׁ@381
�C�X���[������ɂ����郉�X�^�[�E�X�e�C�������K���X�@�^���m�q�@394
���s���������ّ��u�����o���}�v�ɂ��� -�������p�Ɍ�����
�@�@�����A�W�A�I�v�f�̌���-�@���R��Y�@408
�A�u�E�V���x���_�a�̒����t�s�C�A�C�̔蕶�ɂ��ā@��ؔ��i�@425
�����w�Ƃ��Ă̕��������@���蒼���@438
�N�����[���@���W�c�̗�Ɠ����v�@�������j�@450
����A�W�A�ɂ����镟�B�ږ��̊����ƕ��B���̐����@�c���ꐬ�@467
�������_�i���j�̋N���@�c�ӏ����@480
���w�E��w�E�d�w�K���X��̋Z�@�ƌn���@�J�ꏮ�@499
�u�M���{�A�̎R�X�ƍ��n�̖��v�i�j�T���G����E���a�j�@�Ñ��r�v�@514
�V�q���̖ѐD��-�����R���N�V��������-�@�����O�ێq�@522
�l��ɂ���-�u���k�̗]�v�̂͂Ă�-�@�ː�F�Y�@537
�����Z�\�l�T���I�����@���c���Y�@557
���㒓���C�����S�����g�A�A���@�l�X���n�[���E���T�[�G�h�b���T���^�l�@
�@�@���n�[�V�F���E���W���u�U�[�f�C�i��j�����D�q�@578
������̎莆-�G�W�v�g�É����̉��Ɗ���-�@����q�@592
���@�C�V�F�[�V�J�w�h�̌��q�_���߂����ā@���������@605
�p���~���l�̎���̐��E�ρ@������N�@616
�f�����W���ƃI���G���g�}���w�@�O�c�k��@629
�^�b�V���Ɋ�lj��K�˂�-�Ñ�T�n���l�̌|�p-�@���c���`�Y�@637
�A�r���h�X�̃Z�e�B�ꐢ���Փa�̍��J�ƍՎi�ł��鉤��
�@�@�����J�����ɂ��Ă̈�l�@�@����♎q�@658
�X���`-�����Ñ�ɂ�����n��_�̎c��-�@�X��q�@674
�A�b�o�[�X������̗�����@�X�{�����@686
�T䢍����ԉ��Ɓm�h�E�n���Ɋւ���E�C�O�������̔����@�X���F�v�@703
�}���[�����̍��ی��Ս`�J�� Kalah �Ɋւ���V�j���@�Ɠ��F��@717
�V�����|���I���ƃk�r�A�����@����v�@730
���������Y赋L�@���R���@743
�G�W�v�g�É����r�[�������̈�l�@�@�g���쎡�@761 |
Syncretism and Two-way Traffic �V���N���e�B�Y���Ɠ������ʁ@
�@�@��R.J.Zwi WERBLOWSKY�CR.J.�c���C�E���F���u���E�X�L�[�@783(31)
Diadems and Strips of Gold from Kultepe/
�@�@��Kanish �L�����e�y�^�J�j�V���o�y�̉����������^������Ɗ��H�i
�@�@��Tahsin Ozguc�C�^�t�X�C���E�I�Y�M���b�`�@788(26)
Changing Western Attitudes to Japanese Music ���{���y�ɑ���ω�����
�@�@�������̑ԓx�@Ury EPPSTEIN �E���E�G�b�y�V���^�C���@813(1)
���� ���X�^-�ʑ�M �I�v�̕��@������j
���M
�A�i�g���A�l�Êw�������@���m�e���@817
�|�[���E�y���I�̔����A�������߂����ā@�H�R���a�@819
�a���ƓȖ،��I���G���g����@���v�s�a�v�@821
�a���ƕ����F���Y�@�r��ʎq�@823
�u�S��\�܂Łv�����C�� -�O�}�{�j�w��
�@�@������Ȃ�W�听������ā@�Γc�F�Y�@825
�u�������v-�w�m�̑��������߂ā@�_�Y�O�@828
�{���܂̂��l���ɂӂ�ā@�ɓ��M�@830
�S�̕����@��t����@832
�O�}�{�a���Ɓu�Ñ�j�̉�v�@����@834
������̂��Ɓ@���R�I�q�@837
���s�ł̌�u���ɐS����ā@�]���V�@839
��⊾�̃C���^�r���[�@�V��ˈ�@842
�ߐ{���[�x�ɂā@���c���q�@844
���a�\���N�����Z���@��R�v�v�@846
�V�������́u���M�v�@���c���q�@849
�Ñ���{�̂�����-�E���{�E�_�b���߂����ā@���{����@852
�O�}�{�a���Ɓu�ɂЂȂߌ�����v�@���[���@857
�l�Ԃ̗��j�́u�푈�̗��j�v���@�Бq���Ƃ��@859
�Ώ̂Ɣ�Ώ̂ɂ��ā@������j�@862
�O�}�{���m�e���a������w�ɂ��}�����ā@����O���@864
�{�l�Ɛ�O���@�쑺�r���@867
�R�w�@��w�j�w�ȂɎO�}�{�u�t�������������������@�C�ꌒ���@870
�w�҂Ƃ��Ă̋{�l�@���ьb�q�@871
�X���^���E�C�u���[�q�[�����̌�@���������@874
�a������̉��b-�o�Ől�Ƃ��ĉ̐l�Ƃ��ā@�O�@876
�C�X�^���u�[�����́@�a��K�q�@879
���q�@�́u�������l�}�v�̎��ɂ��ā@���i�M�F�@882
����q�u����u���̎v���o�@��؏��@884
���N�j���Ɂ@�猺���@886
�O�}�{���܁A�O��搶�A�V�V���[���@���蒼���@888
�O�}�{�a���Ɩ��S���@�Óc���́@891
�����Ȏv���o�@���R��s�@893
����J�̍~��ߌ�@����G���@895
�{�l�ƃ^�e�Љ�@������}�@896
�O�}�{���m�e���a���Ď��̌�j�ɊăG�[�Q�C����
�@�@���I���G���g�ց@���͖����@898
�a���ƍ]��搶�Ǝ��Ɓ@�j�b�T���E�A�i�r�A���@901
�O�}�{�l�̂���-�_�����͂������������@���{�����@903
�Ñ�G�W�v�g�̋��E�͔n�E�� �G���@���J���@�@906
�O�}�{���m�e���a���Ď��j�ɓ����ā@���R��v�@908
�O�}�{�l�Ď��̂��j�ɍۂ��ā@���R���m�q�@910
�a���ɗ�܂���ĎO�\�N�@���������@913
���{�a����� ��́u�}�`�m�q�v�̎v���o�@���u�Îq�@915
�g�z��V�́A�����n�܂�ā@�����M�F�@917
�a���ƒ����@���s���@920
�A�i�g���A�ւ̗�-��㔪�Z�N�@�O��o���q�@922
�u�o�x���̓��v�ɂ悹�ā@�X�����q�@925
�������̃o�O�_�[�h�@�X�{�N�Y�@927
�O�}�{���m�e���a���̕Ď������Ƃق��ā@���c����@930
����Ȃ邲�������@���c���b�@932
�a���Ɖ��R�s���I���G���g���p�ف@�������j�@934
�R�w�@��w���璆�ߓ������Z���^�[�ց@�g�c�͈�Y�@936
��@�������j�@941
���M�ҏЉ�@945
�҈ꗗ�@952 |
�����̔N�A�g�쐳�q���u���{���C�ۊw��G�� 41(4) p.141-154�v�Ɂu�Ñ㒆���ɂ�����G�ߔF���ƋG�ߊw�̔��W �v�\����B�@�@�@�@�@�@�i-STAGE
���A���̔N�A�{�� ��F���u���� (�ʍ� 78) p.46�`61�v�Ɂu�L�g���Õ��̓V���}�͕���̋�--���A�W�A�̒��̓��{ (���W �����W�̃A���P�I���W�[)�v�\����B
�@�܂��A�����b�����u����p.62�`73�v�Ɂu���{�l���`���������N����̓n���l--�ϐΒˌÕ��E�q�A�n���n�����̑��Ձv�\����B
���A���̔N�A���J�ɕ����Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (118) p.98�`118�v�Ɂu���\�剤�ɂ���--���c�����摜���̖������ǁv�\����B |
| 2005 |
17 |
�E |
�P���A���X�ؐ��g���u�_���@�� = Journal of Shint�@ studies (197) p.1�`28�v�Ɂu�ԕĂƓV�c�̍Ղ�--�ԂƂ�ڂƈ�M��ʂ��āv�\����B
�P���A�啔�u�ۂ�����w�@��w��w�@�ҁu����w�@��w��w�@���w�����_�W = Seinan Gakuin University Graduate School graduate studies in literature (24) p.532�`465�v�Ɂu��̑��}�Ƒc����J�ɂ���--�V�k�O�ƊC�_��(�E���W���~)�Ɓv�\����B
�T���A���c�x�m�v���u�h�a�w����w�l���Љ�Ȋw�������N�� 3�@p.147-164�v�Ɂu�����E�]��́k�P�c�l���Ɋւ����l�@ : �͛G�n��ՂƓ��R��Ղ���v�\����B�@�@�iIRDB�j�@�d�v
�P�Q���A�r���G���u���̋N�� : �C�l�w����l�Êw�ւ̒���v���u�u�k�Ёv���犧�s����B�@
(�u�k�БI�����`�G ; 350)
|
���e�����^���̃��[�c�͏Ĕ��_�Ƃł͂Ȃ��B�T�g�C���Ȃǐ��ӂ̍��؍͔|�ɋN�������A�u�������v�͔|���琶�܂ꂽ�B�C�l�w�Ő�[�̒m�����琅�c���Ƃ������E�̔_�Ə�A�ł����j�[�N�Ȕ_�k�����̃��J�j�Y�����𖾂��A�Ɨt���є_�k�_���͂��߂Ƃ������̏��������𔗂�BCiNii Books��� |
|
���́@�C�l�ɔ�߂�ꂽ�������̗��j
��P�́@�͔|�C�l�̋N���@�@�ʐ��ւ̋^��
��Q�́@����͍��͂���n�܂����@�@�C�l�͔|�̃��[�c��T��
��R�́@���͔_�k�ւ̗�?�_�삩�瓌��A�W�A�ɍ��Ղ����ǂ�
��S�́@�ǂ̂悤�ɂ��ăC�l�͍͔|�����ꂽ��
|
��T�́@���c���Ɓu�z�v�l�@�@�^�C��n�l�̃A�W�A�W�J
��U�́@�l�Ԃ̗��j�����܂ꂽ�C�l�̑��l��
��V�́@���ꂪ�ǂ̂悤�Ɉ�����{��
�I�́@���c���Љ�Ƃ͉���
�E
|
|
| 2006 |
18 |
�E |
�P���A�啔�u�ۂ�����w�@��w��w�@�ҁu����w�@��w��w�@���w�����_�W = Seinan Gakuin University Graduate School graduate studies in literature (25) p.298�`274�v�Ɂu�� ��̑��}�Ƒc����J�ɂ���--��(���ꌧ������)�̃V�k�O�v�\����B
�P���A�r���G���u�{ 31(1) (�ʍ� 354) p.58�`60�v�Ɂu�C�Â���Ȃ������s�v�c--���c���@�v�\����B
�Q���A�ߓ��鏺���u���{�w�G�� 127(2) p.97-102�v���u�~���������V���Ȑ�����w�̈�\�~���𐧌䂷��V�X�e���\�v�\����B�@J-STAGE
|
���^�^�M���ނ̓~���������~�������ɐ����Ƃ����ɓx�̒�̉����������Ƃ͗ǂ��m���Ă���B����ɁA�ۂ┭�K�������Ȃǂɂ���R���������A�]��S���ł͒ቷ���_�f�A��O���R�[�X�ɂ��ϐ��������Ƃ̋����[�����Ȃ���Ă���B���̂��Ƃ���C�~�����ۂɂ͎�X�̗L�Q�v������q���琶�̂�ی삷��@�\���֗^���Ă���Ƃ̎w�E���Ȃ���A�ŋ߁A������w����ł̊S�����܂����B���ɁA�~�������Ɋւ��̓����q�ɂ͌Â����狭���S�����T������Ă��������������A�ߔN���̑��݂��^�⎋����Ă����B����ɂ́A�~�������G�Ȑ��̋@�\�̓����ɂ�錻�ۂł��邱�Ƃ�A���̔�����1�N�̒����������������ƁC�̉��ቺ�ɂ�萶�̔������������}������邱�ƂȂǁA�����̏�Q�ƂȂ�[���Ȗ�肪�ւ���Ă����B���̗l�ȏ��ŁC��X��1980�N�㏉���Ɏn�߂��S����������|���ɁA�~���ɃJ�b�v������V���Ȉ��q���V�}���X�̌������甭�������B�~�����ٓI�^���p�N���iHP�j�Ɩ������������̂́A�~�����������肷��N�����Y���ɂ�萧�䂳��A��������]���ւƗA������ē~������ɐ[���ւ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B�����ł́A�~�������̌������_���܂߂āA��X�����o����HP�����̂����߂Ă̓~���z�������Ƃ��ē��肳���܂ł̌o�܂��T�����C���ł̐V���ȉ��p���߂��~�����ۂɂ��ďq�ׂ�B |
�R���A�a���r�q���\�����w�����q��w�Z����w�����ꍑ���w��ҁu�\��������
(12) p.51�`57�v�Ɂu "���ؐ_"�ɂ��āv�\����B
�R���A�����T�ꂪ�u�����w�l�ԎЉ������j���ꕶ���w�n�v�Ɂu���]������V�Ί핶���̐A���l�Êw�I�����v�\����B
�@�@�@�����Ȋw�ȉȊw������⏕���������ʕ��@�@�@�iIRDB�j
|
�͂�����
��1�́@�����̊T �v�^�����T��@1
��2�́@�҂ݕ� �^���i�Ēm15
��3�́@�؊�E�ؐ��i�^�����R���q37
��4�́@�؊�E�ؐ��i�̎��퓯��^��؎O�j�E�A�_��E�\��C��79 |
��5�́@�ԕ����́E�]�����́E�������^��������97
��6�́@�v�����g�E�I�p�[�����́^�F�c�ÓO�N�E�A�_��104
��7�́@��ՊT�v�i1�j�F�]���c���R��Ձ^������119
��8�́@��ՊT�v�i2�j�F�]�Y���ƎR��Ձ^��@127
�E |
�X���A�ߓ��鏺���u�Ȋw 76(9) (�ʍ� 889) p.934�`941�v�Ɂu���̒��� "�~�����q"�������ɔ���������--�����̐_��ɂ܂Ŕ����\�N�]�v�\����B
�P�P���A�ߓ��鏺�������o�Ŋ�����Еҁu�`�����j�_�y�f 51(13) (�ʍ� 713) p.1847�`1853�v�Ɂu�M���ނ̓~���𐧌䂷��`����������--���z���甭���܂Łv�\����B
�P�Q���A���[��������w�I�v�ҏW�ψ���ҁu����w�I�v = Reitaku University journal 83 p.21�`35�v�Ɂu�c��I�̗R��� �v�\����B
���A���̔N�A�r���G�����a�������� �u���E���a���� = Quarterly journal on peace studies and peace policies 32(4) (�ʍ� 171) p.33�`40�v�Ɂu�A�W�A���� ���A�W�A�o�ϔ��W�̃G�[�g�X������c���Љ�--���c���̋N������̍l�@�v�\����B |
| 2007 |
19 |
�E |
�P���A���ƍN�V�����u�C����݂��ږ�ď����̎��� : �����u�הn�䍑�v�u�b�N���b�g�v���u�����v���犧�s����B
|
��P�́@���z�ւ̊C�̓�
��Q�́@�ږ�Ă̐��R
��R�́@�������̓�ҍp�� |
��S�́@�ږ�Ă̒��v
��T�́@��̗��s�L
��U�́@�������̈ʒu |
��V�́@����Ɛ풆�J�s
��W�́@�������}篘`���ɔh��
�ǘ^�@�ѕ��S�͂ǂ����@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�uBOOK�f�[�^�x�[�X�v ���
�P���A�{����F���u���u�Б�w���H�w������ = The science and engineering review of Doshisha University47(4) p.124�`129�v�Ɂu�L�g���V���}�ƍ����̐��} (��44�u�Б�w���H�w�������������\��,2006�N�x���u�Б�w�n�C�e�N�E���T�[�`,�w�p�t�����e�B�A�����V���|�W�E���u���\�e�W)�v�\����B
�P���A�{����F�������Y�p�{��ҁu�����Y�p = Ars buddhica (290) p.43�`48,�}����1p�v�Ɂu�L�g���V���}�Ɠ��A�W�A�̌Ð��} (���W �����ˁE�L�g���Õ��lj�)�v�\����B
�Q���A�{����F���u���o�T�C�G���X 37(2) (�ʍ� 425) p.95�`98�v�Ɂu�l�Êw�E�V���w �k�l�����Ɠ��m�̐����v�\����B
�S���A��엘�O���u�R���s���[�^�[�摜��͂ɂ�閾�����̌Ñ��ՁE�╨����̕����̌��o
: �����ˌÕ��lj您��ѐΐ_��Տo�y�؊ȗ�v���u���{�j�w�N���ʘ_���W �Ñ�2-2005�N
�w�p�������s�� �ҏW �����o�Łv�ɏ��������B
�U���A�ߓ��鏺���u�������� 88(3) p.463�`468�v�Ɂu�N�����Y�������ޓ~�����䕪�q�Ǝ��� (���I�V�X�e���̏��_(6)) �v�\����B�@IRDB
|
�͂��߂��i�S���j�^�����ނ̓~���́A�~�G�ɑ̉���ቺ���������ȓK�����ۂƂ��Ēm����B���ɁA�������ɑ�����~�������ł́A�~�������ɂ�
�O���߂��܂Œቺ�����̉��Œ����Ԑ������邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ���A���̎����ɂ͑̂���̉��ɑ���ϐ����l�����Ă���ƍl�����Ă���B���̂悤��
�O���߂��܂ő̉����ቺ����ƁA��ӂ͋ɓx�ɗ}������đ̓��ł̐����ێ��Ɋւ�鉻�w�����͒��������������B�Ⴆ�A�S���̔�������
1/50�ȉ��Ɍ������A�̂������M�ʂ� 1/100�قǂɂȂ�B�܂�A�~����Ԃł͑�ӑ��x�����\���́[�ɂ܂Œቺ����̂ł���B�^��ӑ��x�͓����̎����Ɩ��ڂɊW���Ă���ƍl�����Ă���B��ӑ��x���x�������قǎ�������������ł���B�܂�A�̏d���y���قǎ������Z�����ƂɂȂ�A�������قǎ������Z���Ƃ̎��R�E�̌��ʂƗǂ���v����B�Ƃ��낪�A�~�������͗�O�I�Ɏ������������Ƃ��m���Ă���B���ꂪ��q�����~���ɂ���ӑ��x�̒ቺ�ɋN������ƌ����Ă���B�Ⴆ�A�ݎ��ڂ̃��X�Ȃ̓~�������ł���V�}���X(�̏d
80g) �̎����� 11�N�ɒB���A�W���X(�̏d 350g) �ł� 9�N�قǂł��������ڂ̃R�E�����Ɏ����ẮA��O�ł̒�����������
38�N�̍Œ�����(�̏d 7g) ������Ă���B�Ƃ��낪�A�����ݎ��ڂł����������œ~���ł��Ȃ����b�g(�̏d
450g)��}�E�X(�̏d 40g) �̎����́A�������� 2-3�N�����Ȃ�Ȃ��B�܂�A��X���ǂ������ɗp����~���ڂŔ�r���ł��A�~�������͖�
4�{�����������邱�Ƃ����炩�Ȃ̂ł���B�^���̂悤�ȋ����ׂ������́A�̉��ቺ�ɋN�������ӗ}���ɂ���Đ����\�Ȃ̂��낤���B�����ł́A�����̌������~�����̑�Ӓቺ�ɂ���Ƃ̏]���̍l���ɐG��Ȃ���A���̍l������X�̒��N�ɂ킽��~�������̈�[���Љ��B |
�X���A�̋{�{��ꂪ�u�Ȃ������b : ���j�ƕ��y�̖����w�v���u�͏o���[�V�Ёv���犧�s����B
|
�`�l�����̊C / �a�̐X���Y �q���J�c�� �\��
�����G�k / ����N�F, �牮�B �q
���O�̃G�l���M�[��Nj����� / �_����Y �q
���㖯���w�̉ۑ� / �J�쌒�� �q
�����̓`���҂Ƃ��Ă̘V�l / �R����q �q
|
�ӊO�ɒm���ʍs���̗R�� / �q�c�� �q
��ƈ͘F���̖�Ȃ� / ���� �q
���b�̂��鐶���E���b�̂Ȃ����� / ��♈�Y �q
���R����� / �썇���� �q
���i�����邱���� / ���@�� �q |
|
| 2008 |
20 |
�E |
�R���A���{�V���w��S�N�j�Ҏ[�ψ���ҁu���{�̓V���w�̕S�N�v���u�����Ќ����t�v���犧�s����A�{����F���u��P�O�́@�V���w�j�v�����M����B
�S���A�r���G���u���n���� : �u���{�l�v�����̓�ɔ���v���u�u�k�Ёv���犧�s����B�@
(�u�k�БI�����`�G, 411)
|
���e����/�Ă���H�Ƃ���u�����v�̃��[�c�͂ǂ����B���]�������R�����������N�쐼�����k��B�B�M�𑀂���ƂƂ��ɋ����ƂƂ���u�z�v�n�̐l�тƂɂ��̌��͂���B�C�l�w�ɉ����A�l�Êw�E����w�̍ŐV�̐��ʂ����A�u���{�l�v�����̉ߒ��𑍍��I�ɕ`���B�@CiNii Books��� |
|
��P�́@�퐶�����͂ǂ����痈����
��Q�́@���N�����̈��n���� |
��R�́@���n�����̏M�ƍq�C
��S�́@���n�����͂ǂ��ɒ蒅������ |
��T�́@���{�l�̒��̓n����
��U�́@�n�����ɂ���ē��{��͂ǂ��ς������ |
�X���A���i�a�j���Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (53) p.40�`47�v�Ɂu�I�N�@�ɂ��Ă̓�A�O�̃R�����g�v�\����B
|
| 2009 |
21 |
�E |
�P���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 84(1) p.22�`28�v�Ɂu���̋N������݂����c�̍ĕ]��--�������ɂ悹�āv�\����B
�P���A���ƍN�V�����Ñ�w�������ҁu���A�W�A�̌Ñ㕶�� (137) p.135�`142�v�Ɂu�Ñ�j�̋A�S�l�\���N�Ԃ̓�v�\����B
�Q���A�{�ʓc�e�m���u�ɐ��_�{�ƌÑ���{�v���u������ �v���犧�s����B
|
���e����/�L�I�̓`���̂ق��ɂ͎j���I�ɂ���߂Č���ꂽ�ɐ��_�{�������̗��j���A�����w���邢�͖����w�̐��ʂ����p���ĉ𖾂��A���̐����̐^���ɂ��܂�B�@CiNii Books |
|
�P�@�L�I�̓`���ƍ{
�Q�@�u�_�{�v�̑n�݂Ƃ��̈Ӌ`
�R�@���I�́u�։��v�I��`���Ƒ另�Ղ̖{�`
�S�@�X�T�m���̐_�i�ƃI�z�Q�c�q���^�̐_�b
�T�@��������P���Ɛ��т��߂�����
|
�U�@�Ñ�ɐ��̕��y�Ɨ��j
�V�@�O�{�L��_�Ɠ��{�C��̌��_�M��
�W�@�p�����ʑO�I�̈ɐ��_�{�E�u���_���J�v�Ƒh�䎁�̐���
�X�@�V�Ƒ�_�ɐ��J�J�̓`���Ɓu�h�䍑�v�@�@���C��_�{�����Ɗ֘A����
�P�O�@�u�{�v�̕����ƈɐ��_�{�̍ĕҁi���_�j |
�R���A����b�q�������w����w�l�ԕ��������I�v�ҏW�ψ���� �u�����w����w�l�ԕ��������I�v (11) p.27�`48�v�Ɂu�A�z�܍s���Ƒ����̐F�ʕ���--�M�c�_�{�̋F�N�ՁE�V���Ղ̌��n������ʂ��āv�\����B
�X���A�G���Ñ�j�̊C�̉���u�Ñ�j�̊C ��57���v���u�Ñ�j�̊C�̉�v���犧�s�����B�@�����F���䌧���}����
|
���E�j�̋��ʋI�� / ����p��
�u��Ë��v�_�̌��݂Ɖw������ / �N��M��
�����ꉼ���̍��{�I�� / ��c��
�u�O�p���_�b��鰋����v�͊�@�ɕm���Ă��邩 / ���i�a�j |
����ꂽ���g�̐ΒI�����Õ� / �d���p�Y
��ƍ��� / �����C
�L���a�F�w�O����~�����Ɓx(�l�E��)��ǂ�� / �͖�G��
�E |
�P�O���A ���ƍN�V�����u�C����݂����{���̋N�� : �_�������͘`���]�̎��сv���u�����@�v���犧�s����B
|
���e����/�w�L�I�x�ɋL���ꂽ�u������v�A�u�V���~�Ձv�y�сu�_�������v�̐��b�͉ˋ�ł͂Ȃ��A�����̔��f�ɈႢ�Ȃ��B����͎��ۂ̗��j�̉����ɓ��Ă͂܂�̂��B�l�@�̌��ʁA�u�`�̌܉��v���オ�n�܂钼�O�̎����ƍl����B�@�@CiNii Books |
|
��P�́@�����̑D
��Q�́@�`�����R�̕��U
��R�́@�܌ӏ\�Z������̒��N���� |
��S�́@���x���̖���
��T�́@�L�J�y����̔蕶
��U�́@�u������v�Ɓu�V���~�Ձv�̎��� |
��V�́@�u�_�������v�͘`���]�̎���
��W�́@��S�̗��j�Ҏ[
�E |
�P�Q���A���[��������w�I�v�ҏW�ψ���ҁu����w�I�v = Reitaku University journal 89 p.33�`50�v�Ɂu��M�̕ϖe--�Ñw�̈�M���炢�̂��̕����ցv�\����B�@�@�iIRDB�j
�P�Q���A���i�a�j���Ñ�j�̊C�ҏW�ψ���ҁu�Ñ�j�̊C (58) p.46�`51�v�Ɂu���x�~ ����Ђ�� �I�N�@�ɂ��Ă̎G���v�\����B |
| 2010 |
22 |
�E |
�U���A�w�p�������s��ҏW�u���{�j�w�N���ʘ_���W �Ñ�2-2008�N�v���u�����o�Łv���犧�s�����B
|
�Ñ���{�̐_���M�� / �k��/���M
�Õ��푒�҂ƃJ�~ / ���/�T��
��ߎ{�s���ɂ�����n�����J�̓W�J / �{��/�`�a
�Ñ�z�����̗��ߍ��J�ɂ��� / �x��/�S��
�w�Ì�E��x����Z�A�֕������~�L�����߂����� / ���c/�o
�����a�̐��� : ����������Ɓu��⦁v�̊W / �Ζ�/�_�i
�čl�u�F���V�c���v : �u������q�v�n�J�̎v�z�w�i / �Ζ�/�_�i
�������̐_�̋@�\�ɂ��� : �w���̕���W�x���\��̑�O�\��b�𒆐S�� / �lj�/��q
���Ɛ_���l�Êw / ���R/���
�w���{���I�x�����`���L���Ɩ��@�v�z : ����2 / �g�c/��F
�w���{���I�x�����`���L���Ɩ��@�v�z : ����3 / �g�c/��F
�{���J���̏��݂ɏA���� : �i��`�������̑Ó����ƕ�� / �/���o�T
���P�Ɠ��� : �u�Ԍ��u�t�v�̖������߂����� / �R�{/�K�j
�ɐ���_�{��(��������)�̈ړ]����߂����� / ���c/�o
�I�����E����`���Ɩk��p�� : �L�����̑n���ƈړ]���߂����� / �n��/�P�M
���@�y�Ђ̊�b�I���� : ��������𒆐S�Ƃ��� : �O�� / �g�V/�z
�����h�H���� : ��C�̕�̏o�����߂����� / ����/�F�P
���q�́w���L�x��ǂ� : ���X �w�Q�V��ܑ�R�L�x�Ɍ�����v��̓��퐫 / ���/�ז�
�b��s�E�i�����ؑ��n����F�����ɂ��� : �V��n�m�`���ɂ��Ă̈ꎎ�_ /
����/����
�蒩���߂����A�O�̖�� : �m�j�ʎ��^�̖��𒆐S�ɂ��� / ����/����
���{�ÁE������������������������� / �R�{/�ו���/�q�q
�k�l��䶗��̕��`���Ɖ~�`�� : �����̌o�܂ƙ�䶗��f�U�C�����_����̉��� /
����/�q��
���������������̐����Ɗؔ����̗v�f / �X/��v
�����S�̐����ƃX�����~�R�g : ���Ƌ����𒆐S�� / ����/���V
�����V���v�z�����ȑO�̘`���̓V�̊ςɊւ���o�� : �V�̐M�Ɨ� / ��/�_�u
���{�Ñ�̉F���\���_�Ə����A�z���Z�p�̋N�� : ���ɊW�V���ƘR�����߂�����
/ ��/�_�u
�������w���Ɠ��{�����̌`�� / �Ð�/�ޒÎq
�ۊ֊��̉����ƎC�E���m�m�P�ϔO : �����������Ƃ��� / ���/���V
�얀�C�@�ɂ�錶�o��p�Ɯߍ� / ���R/���q
���@���̌`�����߂��鏔��� / ����/���� |
��������̓V�c�r��̕ϑJ : 4 �\�I�𒆐S�� 1 / �c��/���|
�y�z�E�z���؊Ȃ���݂��Ñ�̎����ɂ��� / �ēc/���q
�R�㉯�ǂ̐_����b�Ɛ_������ / �C��/����
���{���s�l / ���/�K�i
�w��������x�̔N���s���ʉߋV��ɂ��� / �R��/�T
�ʌo���̏��L : �u���v�̏�ʂ̕������� / ����/��
���ꒅ���M�l�̓`�� : �F��̓`���Ƃ��̈ӎ��\�� / ���{/��V
�鎭���ƍ��c�����C / �R�c/�Y�i
�Õ��o�y�̓S���E�S���̕������Ə⊪�� : �D���Ȃǂ̎�ނƎd�l / ��c/�ނ�
�Ñ�ɂ�����u�����ҁv�̕� : ����s������Ղ�
�@�@���y�B��SK1226�̔푒�҂��߂����� / ����/�G�Y
���_�o�y�̖n���y��o�� / �ˌ�/��
���q�̊��ɋL�����ꂽ���O�͒N�� : ���ˎs��n���p���Ւ��ҎR�n��o�y��
�@�@������l���������̌��� / ���/���F
�헤���V���S�Ɏ��ӎ��@�Ɛ��Y��Տo�y�������̗l�� :
�@�@���j�ՐV���p���ՁE��쌴���q�Տo�y�����𒆐S�� / ���/���F
�M�Z�������Տo�y���������E�����ƊW�×q�ՌQ�̍l�@ / �q�V/���K
�w�@���x�`���`�̎j���I���i�ɂ��� / �|�{/�~��
��؏d���ƕ��y�L : �w�헤�����y�L��x���ʍ��Ɖ�� / �t��/���s
�O�Y������̌Ñ���Ε��֘A���� / �Îs/�W
�Îʌo�����̉\�� : ���s�m���o�ɂ��� / �|�{/�W
�Îʌo����̐_�� : �V����N���s�m���o�̎�����߂����� / ����/�c��
�o�������̈Ӌ` : ��������q�x�_�̎��� / �|�{/�W
�u����e����27�H���e�����v���߂����� / ����/����
��������̌ËL�^�Ɓw���E�L�x�����l�N�� / �O��/��
�_���b�j���W��(�ۊ֊��܂ŕҔN�j��) / �ߓ�/�D�a
�w�V�_�M�ҔN�j���W��-��������E
�@�@�����q����O����-�x��������(�e) / �|��/���j
�w������C�x�ҔN�����e : ���Ïˎl�N���V����N / �}��/����
���e�يW�����ژ^ / ��Y/����d��/�q�F |
�W���A���R�ьp�搶�ËH�L�O�_�W���s����u���{��w�����_�p : ���R�ьp�搶�ËH�L�O�_�W�v���u�Y�R�t�v���犧�s�����B
|
��w�����̌��������߂� �ꕶ����̑��`�y���i�Ɋւ����l�@ / �������T
�Z���p��V��ɂ�����ꕶ�y�� / �����k��
�ꕶ�y��̃C���[�W / �Έ䏠
�����̋N�� / ���ѐ�
����̓`�d�ƕώ� / ��ؕq�O
�퐶�����̓��Q / ���c�N�Y
�_�_�M�̌��_�ƌÕ����� ������̑��P���J / �r���
�Õ������Ɠ������e / �Ζ씎�M
���J�╨���猩���Ñ���J�̌p���ƒf�� / �啽�� ��
���Õ������㔼����I�����̓S�V�̕ϑJ / ����m ��
���n�̋��� / ������ ��
���{�o�y�̊p�t���߂����� / �؉��j ��
�ő咷�̑o�����品�ɂ��� / �������j ��
���J�Ɋ֗^�����Ñ㎁�� / ��{�a�r ��
�q�����ʖ��[��\�ɂ݂�"���܂�����" / ���X�؏� ��
�����_�{�Ɓu�m���̋��ޏ��v / �����q ��
���ʕ����ʂ̐��l���Ɋւ����l�@ / ���S�� ��
�O��������Ƃ��̎��� / ������v ��
�ޗnj��O�֔n��R�m�_��Ղ̍��J�l�Êw�I���� / �ÒJ�B
���Q���o���Տo���̔w�i�ɂ��Ă̗\�@ / ���]��
�Õ�����O���̍������قƂ��̍\���Ɋւ���ꎄ�� / �Đ�m��
���E�̌Ñ�ɂ�����_�k���J�ɂ݂��鋤�ʐ� / ���c�G
���J��Ղ̗��n�ɂ��� / ��������
�u�A���v�Ƃ͉��� / �J���N�_
���{�����̌`���ƕϗe �F��l / �ؖL
�u���[�_�А����̊�w�v�o�� / �V��w
�ޗǎ��㏉���́w���I�x��萂����l�@ / ���`�l
|
�����_�S�ɂ�����_�˂̏W�� / �����a�q
�w�d�������y�L�x�̍��J��� / �F��~�q
���g�_�{����Ղ̔��@�Ɛ��� / ����䌚
�~���̓������@�Ɋւ���w���j�I���� / ��������
���Ɍ��וz�P�X��Տo�y�؊ȂƓV���l�E�ܔN�̟݊C�g / ��ؖ���
�������̑�n������\ / �|�c���h
��ɗ��� / �C���a�O
���a�J�{�ɂ��� / �������K
�ɐ��_�{�F�N�Ղƌ�c�펪���n�s�� / ���X�]
���^�u�_���l�Êw�v���_ / �[�V���Y
�Ñ㒩��ɂ�������J�̕����I�\�� / �����F�m
����������̑������ / �Ζ؉딎
�����R�o�y���ɂ��� / ���엲�u
�u�����{�g���Ð_�Ёv�ɂ�����u�G�}�v�ɂ݂���J��
�@�@���l�Êw�I�����ƍ���̓W�] / �����ꐰ��
���R�M�̏��i�K / ���}��
�u��������菑�v�����̊�ȓ`�{ / ������
�u�܂�тƁv�̗��K / ���쒼�V
����ɂ������w���� �J�{���p�����鎟����Ƃ͒N�Ȃ̂� / �Έ䌤�m
�@������Ɛ_�А_�� / ���{����
�ϗe����@���I�`���̊�w��T�� / �����u���G
�������̕ۑ��Ɗ��p���l���� �j�Ղɂ������\�ۑ��ɂ��� / �ؔɕv
�n��Љ�̍Đ��Ƃ����ϓ_����d�q�����ꂽ
�@�@�������فE�}���ق̎����̊��p���l���� / �R�����H
�v�ĖM���̖ʖ� : �w�ĉ����L�x�̔����ق�
�@�@���ւ���L�q�̕]�����l���� / �R�{�N��
�E |
�P�O���A�ґ�������u���{���I�̗� : ���×� BC660�`AC697�v���u���Ƃ�����Ёv���犧�s�����B
�@
�@�@�@�����F�����������}���� ���������}�����@�@�i |
| 2011 |
23 |
�E |
�R���A�e�n�ƕv�����쎮������ҁu���쎮���� (27) p.74�`106�v�Ɂu���}�g�����̋F�N�ՂƎO�ցE����̐_�v�\����B�@
�V���A���i�a�j���u�v�ʎj���� 33(1) p.43-51���{�v�ʎj�w��v�Ɂu�w��鏎Z�o�x�ɂ݂��鐔�l�ɂ��� : �ꐡ�痢���̈Ӗ�������́v�\����B�@�@��������}���كf�W�^���R���N�V����
�����̔N�A�����m, ������邪�u�F����5000�N�j = Five Thousand Years of Cosmic Visions : �l�ނ͉F�����ǂ��݂Ă������v���u������w�o�ʼn� �v���犧�s����B
|
�͂��߂�//i
��I�� �Ñ�E�����̉F����//1
��1�� �Ñ�V���w�ƉF���ρ\�l�啶����
�@�@���V�嗤//3
1.1 �F���ςƂ�//3
1.2 �Ñ�G�W�v�g�̉F����//4
1.3 �o�r���j�A�ƃ��_���̉F����//7
1.4 �����̉F����//10
1.5 �C���h�̉F����//13
1.6 �V���E�̌Ñ�F����//15
��2�� �V���w�̔��˂ƒn����//18
2.1 �Ñ㕶���̒a���ƋC��ϓ�//19
2.2 �V���w�a���̊�����//21
2.3 ��\�l�ߋC�̋N��//22
2.4 �b�����Ɍ��ꂽ�C��ϓ���
�@�@�������V���w�̒a��//27
��3�� �M���V�A�̉F���ρ\�V������
�@�@���w�I�F��//29
3.1 �����̉F����//29
3.2 �n���̑傫���̑���//34
3.3 ���S�~�Ǝ��]�~���f��//35
3.4 �q�b�p���R�X//37
3.5 �g���~�[�ƃA���}�Q�X�g//39
3.6 �A���e�B�L�e���̋@�B//42
��4�� �����̉F����//46
4.1 �A���r�A�E�C�X�����̉F����//46
4.2 �������e�����E�̉F����//53
4.3 �Ñ�E�����Ɏg�p���ꂽ�V���ϑ��V��//57
��II�� ���z���S������P���̐��E��//63
��5�� ���z���S���ƃR�y���j�N�X�v��//65
5.1 �R�y���j�N�X//65
5.2 ���z���S��//68
5.3 �R�y���j�N�X���̕��y�Ɖe��//75
5.4 ������Ԃɕ��z�����P���Ƃ����l���̒a��//76
��6�� �����ϑ��ɂ��ƂÂ��^��
�@�@���f���^���̔����\�e�B�R�ƃP�v���[//79 |
6.1 �e�B�R�Ƃ��̓V����//79
6.2 �e�B�R�̉F���̌n//83
6.3 �P�v���[�Ɖΐ��O���Ƃ̊i��//84
6.4 �P�v���[��3�@��//87
6.5 �f�J���g�Ɗw�I�F��//93
��7�� �F�����̊g��\�]�����̔�����
�@�@�����L���̖͂@���̔���//95
7.1 �]�����̔����������炵���V���ȉF����//95
7.2 �j���[�g���Ɩ��L���̖͂@���̔���//103
7.3 ���L���̖͂@���̕��y�ƃj���[�g���͊w�I�F����//106
��8�� �n�����̌�����P���V���w�̒a����//111
8.1 �N�����������̑O�j//111
8.2 ���s���̔���//113
8.3 �N�������̌��o//117
8.4 �n�[�V�F���ƍP���V���w�̒a��//119
8.5 �V���w�̑����I���W�Ƌߑ�̓V����̖���//121
��III�� �V�̕����w�Ƌ�͉F��//129
��9�� �V�V���w�̑䓪�Ɣ��W//131
9.1 �V�V���w�̒a��//131
9.2 �P���X�y�N�g���̕���//137
9.3 �w���c�V���v�����O�[���b�Z���}//141
��10�� ���z�E���̕����̉𖾂�//145
10.1 ���z�̕����w//145
10.2 �������ł̌��q�j�����Ɛ��̐i��//149
10.3 �ό����Ɛ��_�̐���//156
��11�� ��͌n�Ƌ�͂̔���//160
11.1 �n�[�V�F���̉F��//160
11.2 �P���̋�������Z�p�̊J��//161
11.3 �u��_���v�����͂̉F����//165
��12�� �F���c���̔����ƃr�b�O�o���F���_//173
12.1 ��ʑ��ΐ����_�ƃt���[�h�}���F�����f��//173
12.2 �n�b�u���̖@��//175
12.3 �r�b�O�o���F���_�̒a��//177
12.4 �F���}�C�N���g�w�i���˂̔���//179
12.5 �r�b�O�o���F���_�ƃI���o�[�X�̃p���h�b�N�X//183
12.6 �C���t���[�V�������_�̓o��//183 |
��IV�� �F���ɂ�����l�Ԃ̈ʒu//187
��13�� ���z�n���̕ϑJ//189
13.1 ���z�n�V���w�̒�ƕ���//189
13.2 ���z�n�̋N���_//195
13.3 �f���Ȋw�̒a���Ɣ��W//199
��14�� �������͂ǂ����痈�����\
�@�@���n���O���������߂�//204
14.1 �ߑ�ȑO�̒n���O�����v�z//204
14.2 �ق��̘f���ɐ����̎肪��������߂�//210
14.3 �d�g�V���w�ƈِ������̒T��//214
��15�� �����̎ړx�̒T���\���[�g���@��
�@�@������Ƒ��n�w�̒a��//220
15.1 �n���̑傫���ƌ`//220
15.2 ���[�g���@�̋N���C����ƕ��y//225
15.3 �V���P�ʂ̗��j�\�F���̑傫���𑪂�ړx//231
��16�� �F���ς̕\���@�\
�@�@�����\�Ɛ��}�̗��j�I�ϑJ//235
16.1 ���m�̐��\�E���}//235
16.2 ���A�W�A�̐��\�E���}//242
16.3 �V���w�̔��W�ɔ������܂��܂ȉF���̕\���@//247
���^//249
A �V�����F���ς̖��J��//251
A.1 �_�[�N�}�^�[//251
A.2 �_�[�N�G�l���M�[//256
A.3 ���݂̕W���F�����f��//259
A.4 �V�����F����Z�p�i��//261
A.5 �V�����F���ς̖��J��//264
B ETI�͖{���ɂ���̂��\��14�͂ւ̕��//266
B.1 ETI�̑��݂𐄒肷�鍪��//267
B.2 ETI�̔F��//271
������//277
�Q�l�}���ƕ���//279
�}�\�o�T�ꗗ//289
�l������//292
�����E��������//301
�E |
|
| 2012 |
24 |
�E |
�U���A���[�����u�f�ڎ� ��r�������� = Journal for the Comparative Study of Civilizations 17 p.59-74�@���V��w��r�������������Z���^�[�v�Ɂu�_��ȃ_�C���Љ�ɂ����鎩�R���q�ƕ����\
�u�ːS���q�v�Ɓu����M�v�̕ϗe�\�v�\����B�@�@�@�iIRDB�j
|
�͂��߂�
��_�C���̞ːS���q�Ƃ��̕ϗe
�P�V�[�T���p���i�E�ИA�n��
�Q���G�n��
�R���{
��_�C���̞ː_���q�Ƃ��̕ϗe |
�O�_�C���̍���M�Ƃ��̕ϗe
�P�g�͒n��
�Q�V�[�T���p���i�E�ИA�n��
�R���G�n��
�S�u�n���n�I��q�˂�
�l���G�n��ɂ������������� |
�P����������̓`��
�Q����������̎l�̏@�h
�R���G�n��̏��������
�܂ނ���
�E
�E |
�P�Q���A�����r�͂��u���s�w����w�l�ԕ����w���@Faculty of Human Cultural Studies, Kyoto Gakuen University29 p.95�`124�v�Ɂu�����̓�E�O�̖��ɂ��āv�\����B�@�@�iIRDB�j
���A���̔N�A�S�ˍ���,���T���u�y�؊w��_���WC�i�n���H�w�j 68(4) p.621-632�v�Ɂu�g�샖�����u��̍\�z�Z�p�̃��[�c�Ɠ`�d�v�\����B�@�@J-STAGE |
| 2013 |
25 |
�E |
�S���S���A�Ɨt���ѕ����_��W�J�������X�؍������S���Ȃ�B�i�W�R�j
�U���A���ƍN�V�����u���j���� 55(6) (�ʍ� 612) p.42-48�v�Ɂu�הn�䍑�͋�B�E�ߋE�ǂ����������(��z���Ƃ̐푈���ɑJ�s����) �v�\����B
�U���A���[�����w��r���������x�ҏW�ψ���� �u��r�������� = Journal for the comparative study of civilizations (18) p.47-68�v�Ɂu����� : �����X�[�����n�т̈�����v�\����B�iIRDB�j
|
�� ����
�@�P�����̎�
�@�Q�����X�[�����n�т̐���
�@�@�@���̂��̍����Ƃ��Ă̐���
�@�@�A���̐S���Ƃ��Ă̐���
�@�@�B�c�삪�h�鐹��
�@�R�����Ə�����
�@�S�����ƈ |
��
�@�P�����X�[���n�т̈
�@�Q��M�̌Ñw
�@�R��̕ϖe
�@�@�@��̕ϖe
�@�@�A��̌`�ۉ�
�@�@�B��ϖe�̈Ӗ�
�E |
�O ������
�@�P������_�I�i�c��I�j�͏����i��e�j�̉��g
�@�Q��͏���
�@�R����p������̂͏���
�@�S��Ƃ��ẴA�}�e���X
�@�T�����S�̔��W�Ƃ�������
�@�ނ���
�E |
|
| 2014 |
26 |
�E |
�R���A�Ŗ��đ��Y���R���w�@���U�w�K�Z���^�[�ҁu��w���v�Ɛ��U�w�K : �R���w�@���U�w�K�Z���^�[�I�v (18) p.5-19�v�Ɂu�w�K�҂̐Ղ�ǂ��� : ���X�h��̏ꍇ�v�\����B
�R���A�{��,��F,���c,���� ���s��w�l���Ȋw�������������A�W�A�l�����w�����Z���^�[���u�Z���^�[�����N��
2013�@p.20-24�v�Ɂu�Ȋw�j���������������f�[�^�x�[�X �������M�^�w�җ�@�u�`�x�i���a15�N�E17�N
2���j ��� �B�ꂽ�̍˂̓V���w��Y�v�\����B �iIRDB�j
|
���W�@�Ȋw�j���������������f�[�^�[�x�[�X�i���c�����ҁj
��T��
�@�Ȋw�j�������f�W�^���E�A�[�J�C�u�̍\�z���������c�����@ 3
�y���^�z�Ȋw�j���Ƀ��X�g�@�L���r�l�b�g��������
�@�@���i�����r�G�E��������쐬�j
��U�с@�Ȋw�j���������������I
�@(�P) �M�����M�^�w�җ�@�u�`�x�i���a15�N�E17�N�j
�@�@�y���z�B�ꂽ�̍˂̓V���w��Y���������������{����F�@20
�@�i�Q�j �X���V���ҁw�{���o�W���x��Q���e�{
|
�@ �����אl�ҁw�d�S�V�C�{���x���M���e
�@�@�y���z�Ö{�����̕����ƒ��������� ����������c�����@25
�y���ʊ�e�z
�@�@�l�����Ȋw�j�Ɨ��`�i�P�j�`�i�R�j������������������X������@32
��V�с@�l�����A�[�J�C�u�X�i20�j
�@�w�j�L���`�Ñ��x�i���ꝑ��Y���m��^�j������������V����@37
�y���ʊ�e�z
�@�@�w������ߎj�L���`�Ñ��x��e�V�������l�i���^�j���́@�B���@43
�E |
�T���A���m���r���u�������� (85) 2014-05 p.15-34�v�Ɂu�Ìy�������ۓI�V���w�ҁv�\����B
�W���R���A���菺��Y���S���Ȃ�B�i�W�V�j |
| 2015 |
27 |
�E |
�Q���A�e�n�ƕv�����쎮������ҁu���쎮���� (30) p.3-28�v�Ɂu�o�_�����_�ꎌ�t��V��ƋF�N�Ձv�\����B�@
�Q���A�ʍ����j�����q�őO���V���[�Y�r�ҏW���ҁu�הn�䍑�����̍őO�� 2015�N�Łv���u�����v���犧�s�����B�@
(�őO���V���[�Y)
|
�w���{���I�x�Ɓw鰎u�`�l�`�x / ������
�w鰎u�x�`�l�`���������� / �g�c����
鰎u�`�l�`��������œ������� / �ɓ����Y
�הn�䍑�Ƃ� / �_�c�ґ�
�ږ�Ă͒N�� / ���i�a�j
�_�������ɂ�����הn�䍑�̌��� / ���菟
�`���������Ƃ� / �|���h��
�הn�䍑�̓��}�g���k��B��? / ���؛�
�e鰘`���̋��� / ���V�a�O
���E�u�`�l�`�v���������_ / �s��q�v
��B���E�E�����͍��{�I�Ɍ��ł��� / ������F
�הn�䍑�_���ɑ�O�̎��_ / ���Y�ےB�N
�הn�䍑��������! / �R�c�i�]
|
�Î��L�Ҏ[��O�S�N�Ɏv�� / ��ؑבS
�������ւ̂ƂĂ����V�ȓ��ē� / �����j��
�u�ږ�Ă̍��̈ʒu�v�Ɩ��_ / ��C��
�w�`�l�`�x�s�ΊC���E��嗦�t�V�l / ���e����
�ږ�čݓ�����Ɉًc���� / �\���Lj�
�הn�䍑�Ɣږ�ĂƑ�^ / ���c�W
�הn�䍑���̖{�M�Ñ�j�w����̍l�@ / ��������
�הn�䍑�͂ǂ��ɂ������̂� / �L����
�w�O���u�x�͈ꗢ�����[�g���ŏ�����Ă���̂� / ���ֈ�
�ޗǖ~�n��蔭�M����הn�䍑��B�� / �ѓc����
�u���}�g�E�`�E��a�v�̋N�������� / �p�c���j
�s��B���t�s�퍑�͌j�쒬! / ���J�g��
�u���c�הn�䍑�E���B���v�ɂ��� / �]�������� |
�R���A���i�a�j���u�v�ʎj���� = Bulletin of the Society of Historical Metrology, Japan 37(1) (�ʍ� 43) p.59-67 ���{�v�ʎj�w��v�Ɂu�Ñ㒆���̓�\�l�ߋC�ɂ��āv�\����B��������}���كf�W�^���R���N�V����
�U���A���[���i�����͂��E�݂̂�j���u��r�������� = Journal for the Comparative Study of Civilizations 19 p.129-152�@���V��w��r�������������Z���^�[�v�Ɂu�A�W�A�̐V���\���̂��̌p���E�����E�Đ��\
�v�\����B�@�iIRDB�j
�P�Q���A�����r�͂��u���s�w����w�l�ԕ����w��I�v�@35�@p.61-96�v�Ɂu�O�p���_�b���̓�E�O�̖��ɂ��āv�\����B�@�iIRDB�j
���A���̔N�A��铹�����u����w���m�j�_�p = Western history essays, Kansai University (18) p.45-62�v�Ɂu��G�W�v�g�̓s�s�A�N�~���̏d�v�� : �I���O1��N�I�ٕ̈��������Ɖ����\��{ (���W �x�V��ݐ搶�Ǔ�)�v�\����B |
| 2016 |
28 |
�E |
�Q���A�R�c���傪�c�{�ّ�w�l���{��ҁu�c�{�٘_�p = Kogakkan studies in the humanities 49(1) (�ʍ� 288) p.31-59�v�Ɂu�ɐ��_�{�ɂ����錳�\�N�Ԓ��V�ċ��ɂ��� : �F�N�ՁE�_��ߍՍċ�������Ƃ��āv�\����B
�W���A�X�_�꒘���X�_�꒘��W�ҏW�ψ���� �u�`�l�`�ƍl�Êw�v���u�V��Ёv���犧�s����B�@ (�X�_�꒘��W, ��4��)
|
�Õ��ƕ���̗p��ɂ��� : �ږ�Ă̙n�̉��߂̑O��Ƃ���
�g��P������הn�䍑��������
�u鰎u�`�l�`�v�ƍl�Êw
�`�l�A�Ɖ�m
������o�y�̘`�l���A�Ɠ�A�O�̖�� : ���W���̋Ɛт𒆐S��
�Ñ�ɂ�������{�ƍ]��
���@���������̔N��̉���
���������Ɓw���t�W�x�̕\�L
���{�����ɂ����镶���ƋL��
|
�ֈ�̕悩�敭��
���܍l�Êw����<�L�I>������
���y�L�ƍl�Êw
���_�E���m���琄�Âɉ��������R�r
�ÓT�̒n���ƈ�Ֆ�
�l�Êw����݂�������e : ���b���o�y�Õ��Ɖ����̑��c
�w���t�W�x�ƍl�Êw
��쎛�̓y���Ɛl�����ɂ���
�E |
�X���A�e�n���v���u�Ñ㉤���̏@���I���E�ςƏo�_�v���u�����Ёv���犧�s����B ��������}���ُ���ID:027607991
|
���{�Ñ�j�ɂ�����o�_�̓��ꐫ�̉𖾂Ɍ�����
�I�I�i���`�E�X�N�i�q�R�i�̍����_�b�ƈ��M��
�A�����J�q�R�_�b�ƈ��M��
�C�_�{�K��_�b�ƈ�˂̍��J
�Ñ㉤���ƑD������
���}�g�����̏@���I���E�ςƏo�_ |
�o�_�������_�˂��߂��鏔���
�Ñ㉤���Əo�_�̋�
���}�g�����̐V���Ɠԓc
���}�g�����̋F�N�ՂƂ��̍Ր_�E�ՋV�_�b
���}�g�����̋F�N�ՂƎO�ցE����̐_
�ŗ������ƃ��}�g�����̋F�J���J |
�o�_�����_�ꎌ�t��V��̈Ӌ`
�o�_��_�̍��J�ƕ������̃^�}�t���V��
�o�_�����_�ꎌ�t��V��ƋF�N��
�E
�E
�E |
|
| 2017 |
29 |
�E |
�V���A����N�N���u�_���@�� = Journal of Shint studies (247) p.53-86�v�Ɂu�Ñ�F�N�Ղ̍��J�\���Ɋւ����l�@�v�\����B
�P�O���A���c䵎i���_���j�w��ҁu�_���j���� = The shinto history review 65(2) (�ʍ� 276) p.150-181�v�Ɂu�Ñ�̍��ƍ��J : �F�N�Ղ̕�����T��v�\����B
�P�Q���A�w�M��������W�x�ҏW�ψ���ҁu�M��������W ��1���@��{�����̓V����@�v���u�Ր쏑�X�v���犧�s�����B
|
��{�����̓V����@ |
�����̓V����@ �u��̗�@ �u��Ɋւ����A�O�̖�� |
|
| 2018 |
����30 |
�E |
�R���A����, �v�X�U�Y, �g�쌒�ꂪ�u���� :�N������ǂ݉������{�j�v���u���Y�t�H
�v���犧�s����B
(���t�V�� ; 1156)
|
�͂��߂�-����(�N��)�Ƃ͉���-�@3
���́@�����������̗�ƔN���@21
���́@��@�u��v�ɋL�����N����
���́@��@1�@���������̎v�z�Ɛ��x
���́@��@2�@�u���×�v�u�V�P��v�̓`�d
���́@��@3�@�A�z��Ƒ��A��E���z��
���́@��@���ォ�琴���܂ł̔N��
���́@��@1�@�`�̎n�c��ɂ��I�N
���́@��@2�@���̕��邪�n�߂��N��
���́@��@3�@��㉤���N���̓���
|
���́@��@3�@�R���� �x�g�i���Ɛ��Ă̔N��
���́@��@3�@�R���� ���N�O���Ɵ݊C�̔N��
���́@���ߍ��Ƃ̐����ƔN���@45
���́@��@�u�剻�v�ȑO�̋I�N�݂̍��
���́@��@1�@�u�`���v����̔N���Ɗ��x
���́@��@2�@�������q�䂩��̎��N��
���́@��@3�@���ɍ��ꂽ"�Ñ�N��"
���́@��@���N���̐����Ɩ@����
���́@��@1�@���V�̐�킯�u�剻�v�n��
���́@��@2�@�u��賁v�Ɓu�钹�v�̉��� |
���́@��@3�@�u���v�����̉���I�Ӌ`
���́@�O�@�ޗǎ���̑�n�E�ː�����
���́@�O�@1�@���ʂɊւ���n����
���́@�O�@2�@�ޗǎ���ɑ����ː�����
���́@�O�@3�@�l���N���ƍF���E�̓�����
���́@�O�@3�@�R���� �u���O��v�̔N��\�L
���́@�O�@3�@�R���� �s�v�c�ȁu���P�v�Ɓu���P�����v
(��)
�E
�E |
�T���A�����ѕF���u���o�T�C�G���X 48(5) (�ʍ� 563) p.96-99�v�Ɂunippon�V����Y(��15��)�A�C���V���^�C����(��)�v�\����B
�U���A�����ѕF���u���o�T�C�G���X 48(6) (�ʍ� 564) p.98-101�v�Ɂunippon�V����Y(��16��)�A�C���V���^�C����(��)�v�\����B
�X���A���c�L,�R�{�T��,�\�����c��`�m��w���g�I�v���s�ψ���ҁu�c��`�m��w���g�I�v.
���R�Ȋw 64 p.11-20�v�Ɂu�����v�V���w : �����v�𗘗p�����n���O���̗��S������v�\����B�@�@IRDB�@ |
| 2019 |
�ߘa�� |
�E |
�T���A�g�c�����{���j�w��� �u���{���j (852) p.1-16�v�Ɂu���{�Ñ�ɂ������@�̎{�s�Ɖ^�p�v�\����B
���A���̔N�A���[�����u���������������_���W(7) p.47-55 p.47-55�v�Ɂu�n�j�������̎��n�����L�^(����3)�v�\����B
|
���[�����u���������������_���W (4�`7) �V���E��E���� : �n�j�������̎��n�����L�^�`(����3)�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�_���W���� |
���s�N |
�_���� |
���e |
| 1 |
(4) p.65-77 |
2016 |
�n�j�������̎��n�����L�^ |
�E |
| 2 |
(5) p.47-58 |
2017 |
�n�j�������̎��n�����L�^(2)�@ |
�E |
| 3 |
(7) p.47-55 |
2019 |
�n�j�������̎��n�����L�^(����3) |
�E |
|
|
| 2020 |
2 |
�E |
�P���A�g�������R����w����w���L��헪���ҁu�R����w����w�������_�p = Bulletin of the Faculty of Education, Yamaguchi University 69 p.271-276�v�Ɂu�u�����{���́v�̊�� : �F�N�Տj�������_�Ƃ��āv�\����B�@IRDB
�Q���A�i�c�v���u��Ɛ肢 : ��߂�ꂽ���w�I�v�l�v���u�u�k�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@(�u�k�Њw�p����, [2605]�^�u��Ɛ肢�̉Ȋw�v(�V���� 1982�N��)�̉���j
�R���A��������F���u������w���w���I�v = Journal of the Faculty of Literature, Chuo University (282) p.71-89�v�Ɂu�F�N�E�����E�另�Ղ��u�_�R�ꖽ�E�_�R�\���̖����Ȃāv�s�����Ƃ̈Ӗ��v�\����B
�R���A��،���,�y�쐽�i,������,���쒼�q,����T�V�i����w�_�w���j�^���؏����i�k�C����w��w�@�_�w�������j�^�ؑ����s�i�X���Y�ƋZ�p�Z���^�[�_�ё����������j�^�Ô������i�_���@�\���k�_�ƌ����Z���^�[�j�^���^��,�V�����i�R�`���_�Ƒ��������Z���^�[�j�^���쐳���i�������_�Ƒ��������Z���^�[��Òn�挤�����j�^�啽�z���i�_���@�\�����_�ƌ����Z���^�[�j�^�����P�`�i�O�d��w��w�@���������w�����ȁj�^��t����i�_���@�\�����{�_�ƌ����Z���^�[�^�]���r�G�i��B��w�_�w���j���u���{�앨�w��u����v�|�W 249(0) p.3-3 �v�Ɂu�����q�̋x�����Ə��~���d���͔|�̍ŏI�o�藦�̊W�ɂ��āv�\����B�@�@
J-STAGE
|
�y�ړI�z�i���j���́u���~�d���v�œ��ɖ��ƂȂ�̂͏t�̏o�藦���Ⴂ���Ƃł���B����Ɏ��펞�̎�q�̋x�������ǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩���炩�ɂ������B |
|
| 2021 |
3 |
�E |
�Q���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 96(2) p.121-124�v�Ɂu����팤���̒��̈�f��(2)��`�I���l���͍͔|�A���Ɣ_�k�̋N���n���������v�\����B
�R���A�r���G���{�����ҁu�_�Ƃ���щ��| 96(3) p.191-193�v�Ɂu����팤���̒��̈�f��(3)�͔|�͈�N���A�����炩? : ��z�~�̎��݂���l����v�\����B
�@�@�@���u��팤���̒��̈�f��(1)�v�ɂ��ėL�����܂߂Ę_�����e�̊m�F���K�v�@�Q�O�Q�Q�E�X�E�P�V�@�ۍ�
�X���A���c�L,�R�{�T��,�\�����c��`�m��w���g�I�v���s�ψ���ҁu�c��`�m��w���g�I�v. ���R�Ȋw 68 p.33-47�v�Ɂu�����v�V���wII : ���������v�ƃA�i�����}�v�\����B�@IRDB |
| 2022 |
4 |
�E |
�E |
| 2023 |
5 |
�E |
�E |
| 2024 |
6 |
�E |
�E |
| 2025 |
7 |
�E |
�E |