�������̓��X���牫�ꏔ���ɂ����Ă̖����|�\�����j �@�@�@�@�@taityujyounin.html
�@�@�@�[�K�W���}���̎��̉��ɏW�܂�[
|
�Q�O�Q�R�E�U�E�P�X�@�^�p�̊J�n
�Q�O�Q�R�E�P�O�E�R�O�@�^�p�̍ĊJ�n
�Q�O�Q�R�E�P�P�E�P�O�@�R�V���ъ֘A�̈ꕔ��lj�����B |
|
�͂��߂�
�@�E�ƌR�l�ł��������l����O�̂��ƁA�܂��A���B�̂��ƂȂǂ�����܂Ō����j�Ƃ��Ē��ׂĂ܂���܂����B���܂��Ȃ��ɐ��܂ꂽ���́A�ԎK�т��ĈΒe�̌��Ђ�c��ڂ̌l�Ɍ��Ȃ���炿�܂������A�������A������A�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���w�Q�N�����R�N���̍��̏o�����ł��B
�@���݁A�E�N���C�i�ł͕s�𗝂Ȃ��Ƃ������S���ɂ݂܂��B���j�w�Ƃ͓�x�Ƃ��̂悤�ȎS�����J��Ԃ��Ȃ��悤�w�Ԃ��̂ł����ƂĂ��c�O�ł��B�����A�����j���n�߂��̂��A�������������҂����̔M���v����T���o���A�㐢�ɓ`�������Ǝv��������ł��B
�@���������w�R�N���ƂȂ�A��N�̏H�̉^����ł́u����̃G�C�T�[�v��x�邱�Ƃňꐶ�������K���Ă��܂����������ɃA�L�V�f���g���N����A�^����ɏo�邱�Ƃ��o���܂���ł����B
�@�G�C�T�[���痬��o��A���̓Ɠ��̃��Y���≹�K�ɁA�Y�ꂩ���Ă����������̂��Ƃ��v���o���̂͂Ȃłł��傤�B
�@���͂��āA�����ɐH�ׂ邨�G�ς̂��ƂɊւ���Z�������������Ƃ�����܂����B�݂̌`�͂ǂ��ł���A���a�P�O�Z���`���̘o�̒��ɖ݂Ɨ��������邱�Ƃł����B�݂͎ς�̂ł͂Ȃ��Z�C���̒��ŏ�����č���܂��B�����̒��Ƀ^�b�v���̐������A�����O���O���ϗ��Ăď����グ�܂��B�����āA�����オ�����Ƃ���ʼnP�̒��ɓ���A�n�ŝȂ��Ė݂ɂ���̂ł��B�݂́A�₪�Đ_�ƂȂ��J���܂��B�����̍s���͂��������A�ʂĂ��Ȃ��������̌̋����v���o���s�v�c�Ȏ��Ԃ̂悤�ɂ��v���ĂȂ�܂���B�����������悤�ɁA��l�����̉������̐H�ו����Ɗ����Ă��܂��B
�@��\��̑O���A���͎O�i�M���̎��]�Ԃ𑆂��Ŏl���܂ōs�������Ƃ�����܂����B�r���A�m�������̈ɗnjΖ�������ł́A���c���j�̕l�ӂɑł���ꂽ�u���V�̎��v�̂��Ƃ��v�������ׂȂ���A�������̂��Ƃ��v���܂����B
�@���ɂƂ��ē썑�A����́A�����������̌̋��̂悤�ɂ��v���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B�������āA���̃K�W���}���̎��̉��ɏW�܂�ł��B |
| ���� |
�a�N�� |
. |
�o���� |
| 1881 |
����14 |
. |
. |
| 1882 |
15 |
. |
. |
| 1883 |
16 |
. |
. |
| 1884 |
17 |
. |
. |
| 1885 |
18 |
. |
. |
| 1886 |
19 |
. |
. |
| 1887 |
����20 |
. |
. |
| 1888 |
21 |
. |
. |
| 1889 |
22 |
. |
. |
| 1890 |
23 |
. |
. |
| 1891 |
24 |
. |
. |
| 1892 |
25 |
. |
�P�Q���A����P���u���������{�� 4(50) p.486-490�v�Ɂu���z�杁v�\����B �@�э���i�n�u�j�@PDF |
| 1893 |
26 |
. |
�Q���A����P���u�����w�G�� 5(52) p.42-45�v�Ɂu���z��(���e)�v�\����B�@PDF
�S���A����P���u�����w�G�� 5(54)p.123-126�v�Ɂu���z��(��O�e)�v�\����B�@PDF
�V���A����P���u�����w�G�� 5(57) p.279-281�v�Ɂu���z��(��l�e)�v�\����B�@PDF |
| 1894 |
27 |
. |
�W���A����P���u�����w�G�� 6(70) p.296-298�v�Ɂu���d�Rꝍ̊l�I���v�\����B�@�@�@PDF |
| 1895 |
28 |
. |
�P�P���A�O�،��A��,����P���u�����w�G�� 7(85) p.380-391�v�Ɂu���d�R�m���ށv�\����B�@�@�@PDF
|
| 1896 |
29 |
. |
. |
| 1897 |
����30 |
. |
. |
| 1898 |
31 |
. |
. |
| 1899 |
32 |
. |
. |
| 1900 |
����33 |
�E |
�P�O���A�����O�Ⴊ�u�����l�ޛ{��趎� 16(175) p.21-38�v�Ɂu ����m�u�����݁v��Ɂu������v�o���ɏA�āv�\����B�@J-STAGE�@�d�v
���A���̔N�A�{�����V����t�����ŐM�V���i�A�z�E�h���j�̌������s���B |
| 1901 |
34 |
�E |
�P�P���A�����O�Ⴊ�u�����l�ޛ{��趎� 17(188)p.43-49�v�Ɂu����l�Óy���G�b�v�\����B�@J-STAGE�@ |
| 1902 |
35 |
�E |
�P�Q���A���U�O�Ⴊ�u�����l�ޛ{��趎� 18(201) p.95-105�v�ɗ����G�L(��) �v�\����B�@�@J-STAGE |
| 1903 |
36 |
�E |
�P���A�����O�Ⴊ�u�����l�ޛ{��趎� 18(202) p.152-158�v�Ɂu�����G�L (��)�v�\����B�@�@J-STAGE
�W���A�����O�Ⴊ�u�����l�ޛ{��趎� 18(209)p.448-457�v�Ɂu�����G�L (�O)�v�\����B�@�@�@J-STAGE |
| 1904 |
37 |
�E |
�E |
| 1905 |
38 |
�E |
�U���A����P, ���Ǖۈ꒘�A���䎞�h�Z�{�u����p�p�����_�Ƌ��ȏ� �ɔV��,�ɔV���v���u�������v���犧�s�����B
�X���A����P, ���Ǖۈ꒘�A���䎞�h�Z�{ �u����p�p�����_�Ƌ��ȏ� : �Z���p �ɔV��,�ɔV���v���u�������v���犧�s�����B |
| 1906 |
39 |
�E |
�E���������G�����R�X�N�A�D�y�_�w�Z�{������A�O��ׁA�{���d�v�����ɂ���ē��{�ōŏ��̊����A���������s���܂����B�����ɎQ�������{���d�v�́A���̌㋽���̉���ɋA��A�_�ƐU���ɓw�߂܂����B�T�g�E�L�r�̐V�i��̓����A�T�c�}�C���̐����A�͔|�@�̌��������s���܂����B�o���E��������Ɉ��ДV���Z���Ƌ����Łw�V��Ï��S�W�x�����s���Ă���A���͔̍|�@�ɂ��Ă�������i�߂Ă����Ǝv���܂��B�c�O�Ȃ��疢���w�V��Ï��S�W�x�̑��݂��m�F���Ă��Ȃ��̂��c�O�ł��B�i���X���҂����������j�@�@�{���d�v�̖��́u�����A�������T��v�̒��ŋ��R�����邱�Ƃ��ł��܂����B�@�@�Q�O�P�U�E�X�E�Q�V�@�ۍ� ���ꌧ�����Ǝ�������@�{���d�v
�P�O���A�����O�Ⴊ�u�����̌��� ��v���u�����O��v���犧�s�����B�@�@pid/992456�@�@�@�{���\
|
���́@�����̖��̍l
�i��j�@�x�ߎj��̗���
�i��j�@�{�M�j��̝t��
�i�O�j�@�����A�t��̈ٓ�
�i�l�j�@�����A�t��̋N��
�i�܁j�@����n�߂ė����Ə̂�
���́@�����̊J蓒k
�i��j�@���R���ӁA�J蓂̊� |
�i��j�@�i�I�����j�o���A�̏�����̐�
�i�O�j�@��V�`�A�v�����i�I�K���j�̐_�b
�i�l�j�@�i�A�}�~�N�j�̉��A���̈��
�i�܁j�@�l��_
��O�́@�������v���j�j�_
�i��j�@�����@�w�V�����萼�Ў���Ɏ���
�i��j�@�j�_�̈�
�i�O�j�@�����@�@�x����揮�b�u����Ɏ��� |
�i�l�j�@�j�_�̓�
�i�܁j�@�j�_�̎O
�i�Z�j�@��O���@���������菮?����Ɏ���
�i���j�@�j�_�̎l
�i���j�@��l���@���玞���菮����Ɏ���
�i��j�@�j�_�̌�
�i�\�j�@�j�_�̘Z
�E |
�P�Q���A�����O�Ⴊ�u�����̌��� ���v���u�����O��v���犧�s�����B�@pid/992457�@�@�@�{���\
|
���́@�����̒n��
��A�@�����̈ʒu�y���
��A�@�����̒n�`�y�n��
�O�A�@����{���̒n�`�y�n���A�i�}�A��j
�l�A�@�C��
�܁A�@�A��
�Z�A�@���� |
���́@�����̐l��
��A�@��c�y�l��
��A�@�Y��
�O�A�@����
�l�A�@�@��
�܁A�@����
�E |
��O�́@�����̖�������
��A�@�ߔe�`�̐l��
��A�@���Y�̕�F
�O�A�@��̎c��
�l�A�@�c�ɂ̗��H
�܁A�@�����̔��e
�E |
|
| 1907 |
40 |
�E |
�V���A�����O�Ⴊ�u�����̌��� ���v���u�����O��v���犧�s�����B�@pid/992458
�@�{���\�@�@�@�d�v
|
���́@����̌���
���́@�_��
��A�@������
��A�@���ނ�
�O�A�@������y��������
�l�A�@�������Ƀ�
��O�́@����
��A�@�Z��
��A�@�L��
�O�A�@����
�l�A�@���� |
��l�́@���w
��A�@�����ۂӂ�
��A�@����������
�O�A�@�q���
�l�A�@���w
�܁A�@���s��
��́@�Y��
��A�@����
��A�@�g�x
�E
�E |
��Z�́@�a���y�a��
��A�@�ۂ̉�
��A�@�Z�́A����
�掵�́@�蕶�A�y����
��A�@�悤�Ƃ�̂Ђ̂���
��A�@�������V�������_�L
�O�A�@�ƕ���
�l�A�@�䋳��
�܁A�@����
�E
�E |
���A���̔N�A�u��y�@�S�� ��17���v���u��y�@�@�T���s��v���犧�s�����B
|
���J�����l�`(���o)
�@�R��l��`(����)
�{���c�t�`�L�G��(�^��)
�����l�����L,
�@�R��l�`
,�@�R��l�`�L
,�@�R��l�`�G��(�Ԉ�)
�@�R��l�`,������l�`(����)
�R����l�`(����) |
���_��l�s�ƋL,
��y�{�����m�`(�S��)
�V����`(����)
�������t���`
,������l�`,��@�썑��(�ǐM)
���O�m�`(�M�g)
�̔O��l�s��L(����)
�e����l�G���`(�)
�����ӏ�l�s��(����) |
�`�d�R�J�c�ۗ���l�`(��_)
�I���q�������J�c�M�_��l�`(����)
�ܒ���l�`
��ޏ�l���`
,���ؘa���s��L(�ϑR)
�ϐ�l�s�ƋL(�ϑR)
�����@�J��Ȕ���l�s��L(�f�M)
�E
�E |
|
| 1908 |
41 |
�E |
�E |
| 1909 |
42 |
�E |
�Q���A����P���u�����w�G�� 21(244) p.84-88�v�Ɂu�����̗��֗�(�����n���{)�v�\����B�@PDF |
| 1910 |
43 |
�E |
�E |
| 1911 |
44 |
�E |
�E |
| 1912 |
45 |
�E |
�S���A���{���w�ҁu���m�p�k�v���u�������v���犧�s�����B�@�@pid/816422�@ �{���\
|
��@�Ȕ���l�ƑT�m�Ƃ́��� / 1
��@�}����l�ƎR�� / 2
�O�@���\��l�Ɣ��l / 5
�l�@����l�̈ꖇ�N���� / 7
�܁@���{��l�ƈ����p�m / 9
�Z�@���{��l�ƘV��k / 11
���@���\��l�Ǝ��� / 12
���@�����l��O�ɑI���W���u��/14
��@�O���l���ɏK�������� / 15
��Z�@���L��l�Ɠ��� / 17
���@�`�R��l�ƒ��q / 19
���@�����l�ƈ����u�Ƃ̖ⓚ / 21
��O�@�ї_��l�̎t���w / 25
��l�@�s�r��l�Ɣ��m / 26
��܁@�~����t�ƊÑ����Y���� / 28
��Z�@�ψ���ɕ����s�ɂ��Ĉ��S������/1
�ꎵ�@�����ӏ�l�̎̎q�~�{ / 35
�ꔪ�@���@���t�ƞ�t / 37
���@�S�V��l�Ǝt�h�� / 39
��Z�@�֒ʏ�l�̌哹�O�� / 41
���@�~����t�ƈ�� / 43
���@�L��T�t�ƈ��T�� / 45
��O�@�s�r��l�̏��W�`�� / 48
��l�@�~����t�Ɛ^�ϖ[���� / 49
��܁@�@����ƕ��� / 52
��Z�@�ܒ���l�̒Ґ��@ / 53
�@���L��l�̌�c�� / 55
�@�����ӏ�l����ގ������� /56
���@���L��l�Ɛ������� / 59
�O�Z�@�w�M��l�A�ˎ҂��|���ɓ���/60
�O��@���A��l�Ɛ����̈����m / 62
�O��@�F�J�@���[�ƉF�s�{���� / 64
�O�O�@�~����t�Ɛ�����ɕ� / 69
�O�l�@���_��l�ƌ���ْ̏� / 70
�O�܁@���{��l��Ֆ��O�̏��� / 7
�O�Z�@�~����t�̌�ՏI / 75
�O���@�@����l��q�B�ɐ��r���ʂ�/78
�O���@�s�r��l�k�����o�o�ł̊��i/79
|
�O��@�~����t�Ɩ@�@�[�M�� / 81
�l�Z�@�쌵��l�̌䐸�w / 84
�l��@�~����t�Ɛ��@���t / 85
�l��@���{��l�ƈ��m / 87
�l�O�@�ϒq���t�Ɠ���ƍN�� / 88
�l�l�@������l�̟��E / 91
�l�܁@��b��l�̈ꖇ�N���� / 93
�l�Z�@�L��T�t�ƒ�q�^ / 95
�l���@�w�M��l�̑�_ / 97
�l���@�}����l�̍F�{ / 99
�l��@�쐐��l�ƈ��a�m / 101
�܁Z�@��ɏ�l�ƈ��l / 103
�܈�@���L��l��l�������ʂ�/104
�ܓ�@�����ӏ�l���������ʂ�/106
�O�@�쌵��l�ƈ��l / 110
�l�@�s�r��l�̋Ɋy�Q�� / 111
�܌܁@�����ӏ�l�������~�Ћʂ�/112
�ܘZ�@�~����t�ƈ��l / 117
���@�S�V��l�d����ގ����ʂ�/117
�ܔ��@�s�r��l�ƓD���� / 128
�܋�@�~����t�ƈ��ڎ��J�ዟ�{/130
�Z�Z�@�s�r��l�ƈ��̐l / 132
�Z��@�~����t�ƈ������l�Y / 133
�Z��@�s�r��l�ƌ�H / 139
�Z�O�@�s�r��l�̌�ՏI / 141
�Z�l�@�~����t�Ƙ@���[ / 143
�Z�܁@���^��l�Ƌ{���H / 147
�Z�Z�@�쐐��l�ƑT�m�^ / 150
�Z���@�s�r��l�ƃj�R���C / 152
�Z���@����l�Ɣ��Y�� / 153
�Z��@�s�r��l�̊��������� / 155
���Z�@���L��l��ɑc�`��ㆂ��ʂ�/157
����@�~����t�Ɛ��ϖ[���q��l/158
����@���L��l�s�m�O�������͂�ʂ�/162
���O�@�����ӏ�l���_�������ʂ�/163
���l�@�~����t�ƌ\�O�l�̓���/166
���܁@�S�V��l�ƒ����T�t�Ƃ̖ⓚ/169
���Z�@�@����Ɠ��� / 175
|
�����@���L��l�페�����r���ʂ�/178
�����@���{��l�ϔY�ގ��̉� / 179
����@�������t�ƑT���[ / 182
���Z�@�s�r��l�ƐF�쎁 / 182
����@���_��l�̌䐸�� / 185
����@�~����t�Ƙ@���[ / 187
���O�@�E�L��l��q�̕]�_������/189
���l�@�����ӏ�l�ɐ���_��
�@�@���Q�Ă��ʂ�/191
���܁@���@�[�얲�ɂ���
�@�@�����S������/193
���Z�@���A��l�ƈ��|�W / 198
�����@���\��lᚕa�҂������ʂ�/201
�����@���_��l�ƒ�q�^ / 203
����@�����ӏ�l�D�v��x���ʂ�/204
��Z�@���L��l�ƈ��M�� / 207
���@��ޏ�l�ƌǐ� / 209
���@�B�@�[�ێ�̕��������� / 213
��O�@�����ӏ�l���������� / 214
��l�@����l�o�l�B�� / 217
��܁@�^����l������ʂ� / 219
��Z�@��b��l�Ɨ��_��l / 220
�㎵�@�����ӏ�l�Ɛg�㖼�� / 221
�㔪�@�o�_��l�Ɠ���ƍN�� / 224
���@�����ӏ�l�����������ʂ� / 229
��Z�Z�@�~����t�Ə��[ / 232
��Z��@���`��l�Ɣq�d�@ / 223
��Z��@�T���[�@��̕s�R�����肷/236
��Z�O�@��ޏ�l�ƔG�����q / 228
��Z�l�@���_��l�ƖL�c�^ / 241
��Z�܁@�����ӏ�l�Ɨ͎m�ܘY/242
��Z�Z�@�^�ϖ[�ƒ������t / 246
��Z���@�L��T�t�Ɣԏ� / 247
��Z���@�~����t�ƒ������t / 248
��Z��@�I���W�Ɠ�c��l / 249
���Z�@�~����t�Ɛΐ�T�� / 250
���^�@���m���` / 252�[269
�E |
�U���A���R�����ȁu���ꖯ�w���ǂ� : ���@���G�[�V�����v���u�哹�Ёv���犧�s�����Bpid/854731�@�{���\�@�d�v |
| 1913 |
�吳�Q�N |
�E |
�U���A�u�~�Z 3(5) p56�`58��J�h���P����{���v�Ɂu�ʐM ����p���z�𐬐ѕv���f�ڂ����B�@pid/1887487
�X���A�C�쐶���u������� (449) pp36~37�@���z���v�Ɂu��㊂̎����v���\����Bpid/1579965
�P�O���A�u���Ɛ��E 4(10)�v���u���ƌ�����v���犧�s�����B �@pid/1549342
|
�k�_���l/p396~412
�i�s�ɉ���A���O����c�����y
�@�@��ᢉ萬��/�O���/p396�`412
�k�����H�Ɓl/p412~417
�������̐������o�@ / YK��/p412~415
�������������@ / YK��/p415~416
���������H��E�F���̜�p�@ / YK��/p416~416 |
�I���Y�H��p�����̐��� / YK��/p416~417
�D㣗p�����̓����ɏA�� / YK��/p417~417
�k�����_�Ɓl/p418~418
����̈ىԎ�p / KO��/p418~418
�k�Y�Ƌy���ƌ����l/p419~420
�B���n�̎Y�z�y���ƌ��� / KO��/p419~420
�k�����l/p421~424
|
��㊓��ƒ��� / �]�g����/p421~424
�V���ē�/P424~424
���C�b/p425~426
�ʑ����p(��)/p426~427
趕�y���v/p428~430
�E
�E |
�P�P���A�u���Ɛ��E 4(11)�v���u���ƌ�����v���犧�s�����B�@pid/1549343
|
�k�_���l/p432~434
�O�l���i�s���V/
�@�@���v�����Z���w�[���c�q/p432�`434
�k�����H�Ɓl/p434~442
�o�c�e�������������@ / YK��/p434~437
���D㣃`���[�u�C�Ď�� / YK��/p437~440
�A���������u / YK��/p440~441
���Y�E�F�͎����u / YK��/p441~442 |
�k�����_�Ɓl/p442~451
�䗥�o���̙������ / KO��/p442~443
����엿�Ƃ��ē�����
�@�@�����/�n���\��/p443�`444
����엿�Ƃ��ē�����
�@�@����鄕]/�G�c�v�X/p444�`445
�p�̃M�j�A�ɉ���\��N�Ԃ�
�@�@���엿��� / �n���\��/p445�`445
|
�k�Y�Ƌy���ƌ����l/p445~451
��x�̛�����A�O�Ɍ�/KO��/p445~451
�k�����l/p452~472
��㊓��ƒ���(��)/�]�g����/p452�`457
�V���ē�/p458~459
���C�b/p459~459
�ʑ����p(��)/p460~461
趕�y���v/p462~472 |
�P�Q���A�u���Ɛ��E 4(12)�v���u���ƌ�����v���犧�s�����B�@pid/1549344
|
�k�]�_�l/p474~476
�i�s���Ɨ������̑Ë��@��/p474�`474
�Ě�������?�Ă̒ʉ�/p474~476
�O����/P474~
�k�����_�H�Ɓl/p477~489
���̏ɉ���p�ɋy�ق�
�@�@�������̉e�� / KE��/p477~481
�@�B�H��ɉ�����C�̏����/p481�`488 |
���d��ᢓ��@���p��
�@�@�����v/�G�c�`�a�[�z�[��/p481�`488
�I�]����p����������@/YK/p488~488
�p�̃M�j�A�ɉ���\��N�Ԃ�
�@�@���엿���/�n���\��/p488�`489
�k�B���n�̎Y�Ƌy���Ɓl/p489~490
�J���{�a���ljԁA�O�Ɍ�/p489~490
�k�����l/p490~499 |
��㊓��ƒ���(�O)/�]�g�ː�/p490�`494
�V���ē�/p494~495
�ʑ����p(�I)/p495~497
趕�/p497~498
���v/p498~499
�p��/p1~2
�E
�E |
|
| 1914 |
3 |
�E |
�P���A�u���Ɛ��E 5(1)�v���u���ƌ�����v���犧�s�����B�@�@pid/1549345
|
�k�����_�H�Ɓl/p2~31
�Ό������@�ɉ����鉷�x�̒���/KY��/p2~5
�����̌��{�̎�� / KY��/p5~6
�����̐������ɉ������z������
�@�@���@�����������ׂ�[��] / YK��/p6~7
�z�������H��ɉ�����
�@�@���@�B�̋ߋ�/�j����/p7�`21
|
���ɉ�����X���Ƃ̋ߙv/��������/p21�`27
����x�|���g���R�̊���_�Ƃ�萂���
�@�@�����ӎ��� / KE��/p27~31
�k�B���n�̎Y�Ƌy���Ɓl/p31~34
�啂̗{���ɂă}�����A���
�@�@�����₷�O�l��/p31�`34
�k�����l/p34~46
|
�Z���i�W�����j�ɉ����鍻���̔�������
�@�@��萂��钲�� / �����/p34�`40
��㊓��ƒ���(�l) / �]�g�ː�/p41�`43
趕�/p44~44
���v/p44~46
�E
�E |
�Q���A�u���Ɛ��E 5(2)�v���u���ƌ�����v���犧�s�����B�@pid/1549346
|
�k�]�_�l/p50~52
�����N�x�̉Z��������
�@�@��/ �u�����Z���w�[���c�q/p50�`52
�k����_�Ɓl/p53~60
���̏����V��/�I�[���A����
�@�@���X�[�T�A�X�g/p53�`54
�������̐����������/YK��/p54~56
���t�ɋy�ڂ����Y�̍�p / YK��/p56~58 |
�����H��ɉ�����F���Ǘ�/YK��/p58~60
�k�l/p60~65
�i�s���Ƃ�ᢓW��/�K����/p60�`65
�k�l/p65~65
�p���̎����i�s����/p65~65
�k�V���ē��l/p65~66
�Ɍ�/p65~66
�k�����l/p66~68 |
��㊓��ƒ���(�l) / �]�g�ː�/p66�`68
�k�Z�b�l/p68~86
�������{����鄊O�Ɍ�/p68�`71
�B���n�̎Y�Ƌy���Ɓ\
�@�@����m��敊O�ꌏ/p71�`81
�C�O�����n�ʐM/p81~82
趕�/p82~84
���v/p84~86 |
|
| 1915 |
4 |
�E |
�P�P���A���ꌧ�����Ǝ�����ҁu���ꌧ�����Ǝ������ ��1���v���u���ꌧ�����Ǝ�����v���犧�s�����B
�@pid/928451/1/1�@�@�{���\
|
�����i�T�g�E�L�r�j�͔|���/1
�k��m�[�T/1
���@��ގ��/3
���A�@�l�������ԋ�����鄁@����/19
��O�@�l�������ԋ�����鄁@����/23
��l�@�G�ߎ�鄁@����/27
��܁@�G�ߎ�鄁@����/32
��Z�@�}�c�[�Ǎ��莎�/38
�掵�@�}�c�@���/42
�攪�@�A�@���/44
���@��ʎ�鄁@����/49
��\�@��ʎ�鄁@����/51 |
��\��@���o�@���/53
��\��@�A�͖@���/56
��\�O�@���k��Ɏ��/60
��\�l�@�|�y��Ɏ��/65
��\�܁@�֍͖@���/71
��\�Z�@��c����/74
��\���@�{������/78
��\���@�엿���{��鄁@����/81
��\��@�엿���{��鄁@����/86
���\�@�엿�p�ʎ�鄁@����/91
���\��@�엿�p�ʎ�鄁@����/95
���\��@�엿�p�ʎ�鄁@���O/105 |
���\�O�@�엿��ގ�鄁@����/108
���\�l�@�엿��ގ�鄁@����/118
���\�܁@���J�엿���/123
���\�Z�@���쎎�/128
���\���@��y���p���/132
���\���@�͔�����r���/138
���\��@�Ӕ�����r���/142
��O�\�@�엿�k�����/147
��O�\��@�O�v�f�K�ʎ��/150
��O�\��@����j���X�������r���/156
�����V���\/161
椒J�R��m��������/172 |
|
| 1916 |
5 |
�E |
�E |
| 1917 |
6 |
�E |
�Q���A���ꌧ�����Ǝ�����ҁu���ꌧ�����Ǝ������ ��2���v���u���ꌧ�����Ǝ�����v���犧�s�����B
pid/928452�@�{���\
|
�����i�T�g�E�L�r�j�͔|���/1
�k��[�T/1
���@�}�c�[�Ǎ��莎�/3
���@�A�͖@���/5
��O�@���k��Ɏ��/7
��l�@�|�y��Ɏ��/9
��܁@��i�O�i�c���[���/11
��Z�@�������{���/14
�掵�@�哤�����{���/17
�攪�@�엿�p�ʎ�鄁@����/20
���@�엿�p�ʎ�鄁@����/23
��\�@�엿��ގ�鄁@����/25
��\��@�엿��ގ�鄁@����/31 |
��\��@���J�엿���/33
��\�O�@���K���y�O�v�f�K�ʎ��/35
��\�l�@�Ӕ�����r���/42
��\�܁@�͔�����r���/44
��\�Z�@����j���X�������r���/45
��\���@�֍͖@���/47
��\���@�ΊD���f�{�p���/49
��\��@�����{�Ɏ��/53
���\�@����m�v�f���D���X�����ʍ��莎�/55
�����@�͗t�핢���/57
�����@�L���l�Ǝ��/59
����O�@�e�퓤���A�����ʍ��莎�/61
�Ï������琬���/67
|
���@�l�H��z/67
���@����@���j��c�m���/69
��O�@�������/71
趎�/103
���@����c��/103
���@��c�z�z/104
��O�@���ƌ��K���{��/105
��l�@�u�b/106
��܁@�ň��o��/106
��Z�@����ᢎ�/106
���^/107
�����V���\/107
�E |
|
| 1918 |
7 |
�E |
�P�O���A���������������Ҏ[�^�����p�y�؉ەҁu�����p�y�؎j�v���u�����p�y�؉ہv���犧�s�����B
�@�@�@�@���L ���ʔŁ@�@�o�ŔN�͊����̖}��ɂ��(�吳���N�\��)
�P�P���A���ꌧ�����Ǝ�����ҁu���ꌧ�����Ǝ������ ��4���v���u�i�������j���ꌧ�����Ǝ�����v���犧�s�����B�@�@�@�@pid/928453�@�{���\
|
��ꍀ�@�����i�T�g�E�L�r�j�͔|���/1
�k��[�T/1
���@�}�c�[�Ǎ��莎�/3
���@�A�͖@���/5
��O�@���k��Ɏ��/6
��l�@�|�y��Ɏ��/8
��܁@��i�A�O�i�c���`���/10
��Z�@�������{���/12
�掵�@�哤�����{���/15
�攪�@�엿�p�ʎ�鄁@����/17
���@�엿�p�ʎ�鄁@����/19
��\�@�엿��ގ�鄁@����/21
��\��@�엿��ގ�鄁@����/24
��\��@���J�엿���/26 |
��\�O�@���K���y�O�v�f�K�ʎ��/29
��\�l�@�Ӕ�����r���/34
��\�܁@�͔�����r���/36
��\�Z�@�֍͖@���/38
��\���@�ΊD���f�{�p�@���/40
��\���@�����{�Ɏ��/43
��\��@����m�v�f���D���X��
�@�@�����ʍ��莎�/45
���\�@�͗t�핢���/47
���\��@沋��l�Ǝ��/48
��@三ȐA�����ʍ��莎�/51
��O���@�Ï������i��m�琬/53
��l���@����/57
���@�����������x���/57
|
���@�ΊD���������/58
��O�@��㉷�x���/59
��l�@�����A�M���������A�ԓ��m�S�Z��r���/60
��܁@�ΊD���p�ʎ��/62
��Z�@�엿�m�����i���j�y�{�X�e���������/65
�掵�@�����}���/65
��܍��@趎�/67
���@���ƍu�K/67
���@����c��/68
��O�@��c�z�z/68
��l�@�o��y���z�z/69
��܁@�E���o��/69
��Z�@�����mᢎ�/70
�掵�@���V�l/70 |
|
| 1919 |
8 |
�E |
�S���A�u�_�Ɛ��E 14(5) �v���u���F�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1756992
|
��l�̝��悷�ׂ��`�����̍ŏ����x/�i���/2
��������Ɣ_�Ƒg�D�̊v�V / ������/13
�_���ƌR���Ƃ̐��\ / �^���R/22
����̕K�v�Ƒ��Ӓ� / 萍��G�O��/30
�Q��{����ř��̜�p / ����h�O/40
�������ɛ�����Ě��̔_�n�ݔ�/��L��/51
�����̍��_����� / ���c�`/60
�_�����̛����@ / �l�G�̗�����/68
�_�ƙ������i�Ɣ_�p������ |
�@�@�����Ǖ��y/����Ǔ�/73
�����{���ɉ�����R���͔|/�ɓ��M��/76
��q�̘��[ / �ɓ�����/80
��n���p�@ / �吳�_�v/87
��錜�c�]���́k�����l�͔|/�㕔�F�g/88
��㊒n���ɉ�����h�c�ɂ���
�@�@��/ �{���c�v ;�x���s�U/94
���̏��y�͔| / �v�ۖ؍P�g/100
�����̋� / �Z�ʎi�_�v/105
|
���苍�� / ���{�k��/106
�䚠�̌���Ɨ{�̕��y/���P�F�g/108
�����`���B / �����{�l/111
����̈ڐA�@ / �u��玟/118
���Ƃ͔̍|�@ / �x�쓍��/121
���� �Z�� �a�� �o�� //126
���j���� �͑����� / ���c�V�q/139
�E
�E |
�T���Q�P���i�������ړ��j�A�ɓ��đ��Y�e�u�����A�����^�v���u�ɓ��đ��Y�v���犧�s����B�@
�@�@�@�}�C�N�� / �I�����C�� ; 41�� ; 27.5�~19.2cm
|
���L �����͑�1-11, 19-25�����ӂɂ�� ��12-18, 26-41���̑��ӏ���: �����A�����b
���L ��e�{����t
���L ��41�������Ɂu�吳���N�܌�������p�e�����ڃX �ɓ��đ��Y�L�v�Ƃ���
���L ������� : [���ʎ���] |
���L ��L: �ɓ��đ��Y�L
���L �ɓ�����
���L ���� : �a��
�E |
|
| �m�� |
�����A���̏W�n |
�̏W���� |
�̏W�� |
���e |
pid |
| 1 |
����{���ߔe�ߖT�� |
(�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592315 |
| 2 |
����{���� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592316 |
| 3 |
����{�������n���� ��� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592317 |
| 4 |
����{�������n���� ���� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592318 |
| 5 |
����{�������n���� ��Q |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592319 |
| 6 |
����{�������n���� ��l |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592320 |
| 7 |
�����p�{�� |
�������l�N�Z�� |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592321 |
| 8 |
�����p���d�R�Q�� �Ί_�� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592322 |
| 9 |
�����p���d�R�Q�� ���\�� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592323 |
| 10 |
�����p���d�R�Q������E �o�ߚ��� |
�������l�N�l�� |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592324 |
| 11 |
���Z���p���� ��q�� |
�������l�N |
�c���ߎO�Y |
. |
pid/2592325 |
| 12 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592326 |
| 13 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592327 |
| 14 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592328 |
| 15 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
�{���\ |
pid/2592329 |
| 16 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592330 |
| 17 |
���Z���p�����哈 |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
�{���\ |
pid/2592331 |
| 18 |
����{�� �� |
���������N |
�Ɖ����� |
. |
pid/2592333 |
| 19 |
����{���ߖT |
���������N���A���A���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592333 |
| 20 |
����{���ߔe�ߖT |
���������N���A���A���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592334 |
| 21 |
����{���ߔe�ߖT |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592335 |
| 22 |
����{�� �ߔe�k�J�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592336 |
| 23 |
����{�������n�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592337 |
| 24 |
����{�������n�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592338 |
| 25 |
����{�������n�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592339 |
| 26 |
�����{�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592340 |
| 27 |
�����{�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592341 |
| 28 |
�����{�� |
���������N�܌� |
���Ït�F |
. |
pid/2592342 |
| 29 |
�������d�R�� �Ί_�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592343 |
| 30 |
�������d�R�� �Ί_�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592344 |
| 31 |
�������d�R�� �|�x�� ���� �V�铈 ���_�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592345 |
| 32 |
�������d�R�� ���\�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592346 |
| 33 |
�������d�R�� ���\�� |
���������N���� |
�ɓ��đ��Y |
. |
pid/2592347 |
| 34 |
�Ԏq�t�A�� ���� |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592348 |
| 35 |
�Ԏq�t�A�� ���� |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592349 |
| 36 |
�Ԏq�t�A�� ���Q |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592350 |
| 37 |
�Ԏq�t�A�� ���l |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592351 |
| 38 |
�Ԏq�t�A�� ���� |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592352 |
| 39 |
�d�q�t�A�� ���q�A�� |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592353 |
| 40 |
�rꏐA�� |
������\�N |
�c����� |
. |
pid/2592354 |
| 41 |
�@�i�̏W�n�̋L�ڂȂ��j |
������\���N |
���V���V�� |
��41�������Ɂu�吳���N�܌�������p�e�����ڃX �ɓ��đ��Y�L�v�Ƃ��� |
pid/2592355 |
|
�P�O���A�ɔg���Q���u���ꏗ���j�v���u���X�v���犧�s����B�@�@pid/18702231�@�{���\�@�@�d�v
|
�×����ɉ����鏗�q�̈ʒn/1p |
���ނ̗��j/111p |
��㊂̕w�l��/141p�@������������ |
�P�Q���A���ꌧ�����Ǝ�����ҁu���ꌧ�����Ǝ������ ��5���v���u���ꌧ�����Ǝ�����v���犧�s�����B
�@pid/928454/1/34�@�{���\
|
��ꍀ�@�����i�T�g�E�L�r�j�͔|���/1
�k��[�T/1
���@��ގ��/3
���@沋��l�Ǝ��/8
��O�@�֍͖@���/10
��l�@�A�͖@���/12
��܁@�ΊD���f�{�p�@���/14
��Z�@���f���엿��ގ��/17
�掵�@�������{���/19
|
�攪�@�A�����/21
���@���k��Ɏ��/24
��\�@��i�O�i�c���[���/25
��\��@����m�v�f���D���X�����ʍ��莎�/28
��@�������/31
���@�����������x���/31
���@����`�C�����/31
��O�@�K���M���������y�ԓ��S�Z��r���/32
��O���@趎�/35
|
���@���ƍu�K/35
���@����c��/36
��O�@��c�z�z/36
��l�@�o��y���z�z/37
��܁@�E���o��/37
��Z�@�����mᢎ�/38
�掵�@���V�l/38
�E
�E |
���A���̔N�A�ꔦ�������u���s�ܒ�佊J��ǒ�ܒ���l���B�v���u�ܒ�佁v���犧�s����B�@ |
| 1920 |
9 |
�E |
�U���A�{���c�Ⴊ�u�l�ޛ{趎� 35(6-7) p.160-200�v�Ɂu���d�R��������v�\����B�@�i�S���b�j�@J-STAGE
�V���A�����ȕҁu�j�֖����V�R�I�O�������� ��8���v���u�����ȁv���犧�s�����B�@�@pid/976790�@�{���\
�@�@�@�@�����s�N�ɒ��ӁF�吳�X�N�V���i�ŏI�Łj�@�Q���i�\���j�@�@
|
�a���c�r�i���ނ������j�y������i��イ���イ���������j�m�Y�n�j�փX�����m�@���������F������s�V���@��
�j�֖����V�R�I�O���������l�����@���w���m�@���쎡�[ |
�X���A���ꌧ�����Ǝ�����ҁu���ꌧ�����Ǝ������ ��6���v���u���ꌧ�����Ǝ�����v���犧�s�����B
�@pid/928455�@�@�{���\
|
��ꍀ�@�����i�T�g�E�L�r�j�͔|���/1
�k��[�T/1
���@��ގ�鄁i��N��j/3
���@��ގ�鄁i��N��m��j/8
��O�@��ގ�鄁i��N��m��j/13
��l�@沋��l�Ǝ��/17
��܁@�֍͖@���/19
��Z�@�A�͖@���/21 |
�掵�@�ΊD���f�{�p�@���/23
�攪�@���f���엿��ގ��/26
���@�������{���/28
��\�@�A�����/31
��\��@���k��Ɏ��/33
��\��@��i�O�i�c���[���/35
��\�O�@����m�v�f���D���X��
�@�@�����ʍ��莎�/37 |
��@���ƍu�K/39
��O���@趎�/41
���@��c�z�z/41
���@�o����/41
��O�@����o��/41
��l�@����ᢎ�/42
��܁@���V�l/42
�E |
�X���A�e�����F�ҁu���ꌧ�ē��v���u�e�����F�v�����s����B�@�@pid/961035�@�@�{���\
|
�ʒu�y���/1
�C��/2
�n�`�y�n��/8
�L�p�A��/10
�����E/21
���/23
�ː��y����/26
�E��/27
�O���ݗ��l�����ɑ����z/27
�y�n/29
�Y��/30
�_�� |
���Y
�q�{
�z��
�H��
����
��Ћ�s/39
�Y�Ƒg��/42
�s��/44
�吳�Z�N�x���ꌧ�Γ��Ώo���Z/47
�吳���N�x�Ώo�\�Z/49
�c��/52
�S�撬����/55 |
����/61
�@��/75
�N���s���y�V�y/76
����/82
����j�T��/85
�������n�}/98
���Ɨ��j/102
�̐l���`/106
���|�y����/149
��S��/187
�E
�E |
�P�Q���`���N�̂R���ɂ����āA���c���j����B�A���ꗷ�s���s���B |
| 1921 |
10 |
�E |
�R���R���A���������a���c�r���u�a���c�r�i���ނ������j�̓D�Y�`���A���Q���v�̖��̂ō��̓V�R�L�O���Ɏw�肳���B
�S���A�����ȕҁu�j�֖����V�R�I�O�������� ��21���F���ꌧ�j���P���A���j�փX�����m�v���u�����ȁv���犧�s�����B�@�@�@pid/976803�@�@�{���\�@�@�@
�@�@
�@�@�@�������̕��i���������j |
�j�֖����V�R�I�O���������l�����@���쎡�[
��@����/1
��@��㊓��m�n��/1
�O�@����g�A��/3
�l�@�h�c�����n/7
�܁@������/8
�Z�@�ւ���/10
���@���Ђ邬��/13
���@���/15
�i�C�j�@�����܂�/15
�i���j�@������/16
�i�n�j�@���͂Ă����m����/17
�i�j�j�@�Ԗ�/17
�i�z�j�@�ł�����/18
��@�͔͓I�X��/19
�\�@�����j���P����㊓��m�A���ی��ԋy����m����/22
�\��@�ی�X�x�L�����y�ی�@/23
�\��@���_/26
|
���A���̔N�A��w���m�{�����V�����u���ꌧ���d�R�S�ɉ�����u�}�������v�\�h�j�փX�������v���u�����ȉq���ǁv���犧�s����B�@�����F�Ȍ��E�@�c�ӑ��@�@pid/985176�@�@�{���\�@ |
| 1922 |
11 |
�E |
�P���A�{���c�Ⴊ�u�l�ޛ{趎� 35(6-7)�@p.160-200�v�ɔ��d�R���������O�j���)�v�\��������B�@�@J-STAGE
|
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_�����i�ʔԂ��t�^����Ă��Ȃ��̂Œ��Ӂj |
. |
| 1 |
�l�ޛ{趎� 35 (6-7)p.160-200 |
1920-(6-7) |
���d�R�������� |
. |
| 2 |
�l�ޛ{趎� 35(8-10) p.237-272�@�@ |
1920-(8-10) |
���d�R��������(�O�j���)�@ |
. |
| 3 |
�l�ޛ{趎� 35(11-12) p.303-328 |
1920-11-12) |
���d�R��������(�O�j���)�@ |
. |
| 4 |
�l�ޛ{趎� 36(1-3) 1921 p.38-64�@ |
1921-(1-3) |
���d�R��������(�O�j���)�@ |
. |
| 5 |
�l�ޛ{趎� 36(4-7) p.108-140 |
1921-(4-7) |
���d�R��������(�O�j���) |
. |
| 6 |
�l�ޛ{趎� 36(8-12) p.213-239�@ |
1921-(8-12) |
���d�R��������(�O�j���)�@ |
. |
| 7 |
�l�ޛ{趎� 37(1-3) p.59-75 |
1922-(1-3) |
���d�R��������(�O�j���) |
. |
|
�W���A�{���c�Ⴊ�u�j�w 1(4) p.117(595)-137(615)�@�O�c�j�w��v�Ɂu�������d�R�̖��̌����v�\����B�@�iIRDB�j
�P�P���A�k�����H, �R�c�k��劲�u ���Ɖ��y 1(3)�v���u�A���X�v���犧�s�����B�@pid/2286213
|
�o���o��/�k�����H/p2~5
�ٕ������� / �����y�V��/p6~9
�d��Ԃ����� / �����Ґ�/p10~14
� �䂪�Ƃ̉� / �����Ґ�/p15~15
��l�ƂȂ�� / �͈����/p16~16
�l�Ԍċz�̚��V / �⍲������/p17�`17
�Â����J�̚� / ����/p18~18
�u�� / ��ؓĕv/p19~20
��U�{ / �����l/p21~21
�ь�̖� / �R�{��/p22~22
�킪�U���� / �H�열�V��/p23~24
�����_�A��a�������C�A / �|�F����/p25�`32
��揎��_ / �����l/p33~37
�Z���Ǝ�(�) / �D�쏯��/p38~43
�����[�C���O�����h����(�O)/�W�����E�m�I�E�w�����G/p44~48
���H�R�[�K��L / �����Ґ�/p49�`50 |
�R�[��l��L / �k�����H/p51~53
��Ȃɉ����鎍���ƎU�� / �R�c�k��/p54�`56
��揋y�ѐ��َ���̘I�������� / �����`�v/p57�`61
��揂Ɖ��قɉ����隠�����Ƃ�萌W / ���R�[/p62�`66
�E�G�[���X��揂ɏA���� / �K���h���c�g/p67�`70
���d�R�Q���̖�� / �c粏��Y/p71�`76
��揂̗��s�ɏA���� / �x�q��/p77�`79
��Ȏ҂̌��t / �R�c�k��/p80~81
��揖�揂Ƒ��̉��� / ���V�q�F/p82�`89
���p�E���� / �R�{�C/p90~91
�Ԃ����̉Ƃ�� / �k�����H/p92�`100
pen�ƃo�g�� / ���H ;�k��/p101~103
����̖؎R(���H��) / �R�c�k��
�I���X(���H��) / �R�c�k��
�K��(�I����) / �R�c�k��
���(�ʍ�����) |
�P�Q���A�����y�V�����u���������������W�v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/977897�@�@�{���\
|
�������՚�
�������՚�/5
�ɕ�����/7
�c�NJԗ�/9
�������̉���/11
�����̎�/13
���Ó��ɂ�/15
�A�n�������ɂ�/17
����O�\�Z��/19
�c�ɎO��/21
�ߔe��
�ߔe��/24
�C�s/26
���ٗ[��/28
�ԕ��ӂ�/30
�ߔe���i/32
�ߔe���i/34
�Ί��c/36
�V��L/38
�Ғ��J��/40
�ً��̋S/42
��ਂ̎^/44
�g��Ջ�/46
��J�H��/48 |
�������e��/50
���/52
�x�ߕ��Ȃ�Տ�/54
�/56
��������/58
����̂���̂��߂�/60
���f
���f/64
�o���a/66
����/68
�ÉƔ���/70
�r�Q/72
�����ӂ�/74
�J���y�S/76
����/78
������/80
�p������/82
�R����ɂ�/84
����Ֆ���/86
�Ñ㗮����/88
�����|�����b
�����|�����b/92
������N/94
���ސl/96 |
�N�앗/98
���i/100
�[�엮���_�l����/102
������v��/104
�C���k/105
���P��/107
�_�ւ̕�
�_�ւ̕�/110
�E���/112
���ł�/114
�c�Ƃ̉ƒ{/116
��Ӌ��n�Y/118
�V椒J�R/120
�a�����p��/121
�����c����/123
�������v/125
������H/127
�����`�i/129
�R���D/131
�扮���V/132
�j���̉Ƃɔ����/134
�їV��/136
��ɔg���Q��/138
����ɑ���/140 |
�F���[�i/142
�����`�]�C���
�����`�]�C���/146
�쓇�ٕ�/148
���d�R�/150
�ِ��A�J�C�k�R/152
���ēn�C������/155
���d�R����/157
�g�Ɗԓ�/159
�g�ƊԂ̐ԖI/161
���Ԃӂ�/162
�쓇��/165
�������/168
���g���w�Ԃ�/170
�앗�s/172
�w��Ԃ̂₤��/174
��̗�/176
���\��/178
�o�ߚ���/180
��t��/182
���������������W�ɂ��Ă̌㏑/185
���d�R���q�L/198
�E
�E |
|
| 1923 |
12 |
�E |
�Q���A�{���c�s���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 29(2)(342)�@p68�`75�v�Ɂu���d�l�̐M����(��)�v�\����B�܂��A�\�x�j���Y���u����/p76�`80�v���u��܋{�Ȃ�{�����̚掌�̔�̌����^���v�\����B�@�@pid/3364986
�R���A�c�ӏ��Y���u���c�@�l�[�����8��u���W�F�i�p�y�����̉��y�ɏA���āv���u�[��������v���犧�s����B
pid/976730/1/1�@�{���\
�@�@ �@ �@
|
�J�����//�����������@/1
�i�s�y�����̉��قɏA���āi�u���j/�c粏��Y�@/4 |
���\/38
���t�y��������/40 |
��i�ژ^/41
���^�i�{���sy�E���j/1 |
�U���A���q����, �^�����������u������N�j�v���u�i�ߔe�j���X�v���犧�s����B �@pid/978658
|
���ҁ@�Ñ�I
���́@��㊐l�̎n�c/1
���́@�J蓐�/26
��O�́@�Ñ�̖{�y���/39
���ҁ@�l�����̋��S
���́@�w�V�����I/55
���́@�p�c�����I/76
��O�́@�@�x�����I/78
��l�́@�O���̌��/92 |
��́@���v�Љ����I/154
�O�ҁ@���~�����O��
���́@�����������i�@�Z��I/195
���́@�c���O�̖{�y���/243
��O�́@�_�ЂƏ@��/261
��l�́@����/304
��́@���J���I/354
��Z�́@����/395
��l�ҁ@���~�������� |
���́@�����L�����h�@�Z��L/418
���́@�c������̖{�y���/452
��O�́@���K�̑g�D/469
��l�́@���x/484
��ܕҁ@�����������
���́@�����s������@�ܑ�I/547
���́@���Y/568
��O�́@�����ƍH�Y/606
��l�́@�����I/645 |
|
| 1924 |
13 |
�E |
�S���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 30(4)(356)�v���u���{�@��{�v���犧�s�����B�@pid/3364999
|
���Y�̎��b䵛ԉ��ɏA�� / ���c�V��/p1�`14
���͖@�ɉ����鐬���r��̗��_ / ������O�Y/p15�`41
����@��̏����(����)������w�����x�̌���(㔂�) / ���c����/p42�`48
���d�R�̘ی�(��) / �{���c��/p49�`65 |
���R���x�̋N�����v(��) / ��M��/p66�`73
�߉r�\�� / ���Y��/p74~74
�b��/p75~78
�v��/P79~88 |
�S���A��ɏ�i�c�ҁu���d�R����揎��v���u���y�����Ёv���犧�s�����B�@pid/1904800�@
(�粑p�� 30)
|
�h�ʒ���/3
�Ԕn��/9
�����_��/16
�M�z��/18
�ʛ�����/22
�ł�/24
�U�ʉԐ�/31
�z���/34
�͂Ȃ�܂ʑO�ʓn��/36
�����ʂςȐ�/40
�������~��/43
�܂�̂ӂܐ�/46
�������ܐ�/48
���炭����/51
�܂�������/52
���ʂʂׂܐ�/54
��������/58
�d�[�Ԑ�/66
���Ǔc��/69
�a���/72 |
�㌴�ʓ���/78
�匴�z�n��/78
�Ì��̉Y��/80
�g�Ì��̉Y��/83
����ΐ�/84
�o�ߔe��/86
������/88
�z�N��/93
���₢������/100
������/102
�\�Ӑ�/104
������ӂ���/108
�����₰��/110
���ې�/112
�������/114
�ڂ��ۂ���/116
���肿�Ԑ�/118
�ڏo�x��/121
�悤�ق���/123
���U�O��/124 |
���������/129
��ǎR��/131
������/133
�̂Ƃ�ܐ�/135
�Ƃ�ܐ�/138
�e����/145
�약��/148
��Ꝑ�/153
��c��/154
�Ƃ܂�����/158
�R����ΐ�/160
������/161
�v��R�z�n��/162
�����/164
�����ݐ�/168
�z�n��/170
�����ܐ�/173
�R��ʂ��Ԃ��ܐ�/175
�Ђ��߂��/177
�K����/179 |
���_��/181
��q���/184
���Ԑ�/186
�₭����ܐ�/190
��R���/193
��R��/196
����/199
������/202
�ۓ��~�R��/207
�܂�/208
���Ԃ낤��/213
�璹��/216
�g�ƊԂʓ���/217
��J��/220
���т�Ԑ�/223
���₫��/225
ꝋv����/227
�o�ߚ��ʔL����/230
�Ȃ��Ȃ��/233
����ˁ[��/236 |
�P�O���Q�P���A����j�ю��Ւn�Ɂu�ܒ���l�s����v�����������B
|
�i�\���j
|
�@�@�ܒ���l�s����
�@�ܒ���l�n燘@�Г��ϗǒ�g�j�X�V����\��N�������B�e�c�j�r���\�l�Ί��\�����m�������t�g�V�e�䔯�X��\�܍Γ������㎛�j�e��y�m�����������N�\��Όc�����N���̒n�j�������m���叮�J���[�N�A�˃V�j�ѐ��Ƀ��ߔe�����R�m�[�j���e���V�e�l���m���{�Z�����������փ��P�j�P���m���j�V�Ԑe�����푴����^���V�g�]�t�ރJ�ӔN�ƃg�V�f�����������O��V���Y�����V�e�Ï������ؖȓ����B�d�V�ȃe��������m���Y�g�i���p�������V�j���t�j���������M�j��N���m�i������l�����l�P�N�����j�Ճ~����j���M�Z���m���j�y�q�O��m�O�@��g���������m���������j�{�p�j���P����y�O�Ńn���j���N�X�g�]�t��l�ؗ����j���q�j�����_���L�������L�A���d����J�������O�\�Z�i�m�A�����������g�V�e���s�@�уe�����R�ܒ�佃j�U�X��l�@�����������e�n�j�z�V���i�\�ܔN�R�隠�O�m��j�o���\�ɁA��t�A�߉ރm�ΘŎO铃����~����O�őӃ��Y���N������\������������������j�J���X�攪�\��
�@�@�@�@��z�@�m���@���R���ǒ�
|
|
|
|
�i�����j
|
�I���@���@����@�@�@�@�@�@�@���@�@�[��
�@�@�@�@�V������\�Z�㑷�@�c�����鏑
䴐��������@
�@�@�@�@������y�@����
�@�@�@�@���s�{�R�m���@
�吳�\�O�N�\����\����@�j�ю��Ճj���V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ŋ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����j�֕ۑ���
|
|
|
�@�@�@���R�����L�i�Q�����E�j�@���a9(1934)�N4��11���i�v�j�@�@�@�@�@
�@�@�@���F���ۂ̖����̔z��i�c���j�ɂ��Ă͖��m�F�Ȃ̂Ō�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ����肢���܂��B�@�@�������ց@��A���H�@�@�Q�O�Q�R�E�T�E�Q�T�@�ۍ�@
�@�@�@���a�S�N�Q�����s�@�c���Ԓm���ҁu�ߔe�Î��W�F���a�Q�N�\�ꌎ����X�L�O�@�S�@p56�`57�v���]�� |
| 1925 |
14 |
�E |
�P���A�{�Ǔ��s�ҁu�F�ӑp�� 11 ����̐l�`�ŋ��v���u���y�����Ёv���犧�s����B�@pid/1904770�@�{���\�@�d�v
|
�����^���c���j
�}��@
��`�܁@�i�ȗ��j
�Z�@��
�� �͂�����/1
�� �`�����_���[��ᢌ�/2
�O �A���j�����K��/3
�l �A���j�����̐���/4
�� ���ꖼ�i�̉���/7 |
�Z �l�`���ЂƂ��Ẵ`�����_���[/9
�� �l�`�y�т��̑��̕��i��u/13
�� �`�����_���[�̋N��/17
�� �R�Ҙb��萗�����o�������/20
�E�`�W���[�E�k�E�E�^(��m�s�̉�)/21
���}�u�V(�R��)/26
��Z �蕶��O��/33
����̎�/33
�O��̕���/36 |
���̉���/40
��� ���̑��̏o�����Z��/46
�W���[���V���[�E�K�E��������(�ēy�@�̕��i)/47
�W���[���V���[�E�K�E�O�u����(�ēy�@�̍F�@)/59
�}�}�E���E�j���u�c(㋐e�O��)/65
�`�����W�����E�i�K���[(���҂̗���)/75
���}�E���[�T�[(�n������)/89
�g�D�C�E�T�V�E���[(���h����)/98
���^ �����ǎ��ȏW/111 |
�@�@�Q�l�F�}��@�Z�@���u���^�̋����ǎ��ȏW�͈ɔg���Q���������ꂽ���̂ŁA����͖����O�\��N�ɏN�W����ꂽ���̂��ƂƂ��ӁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��r����̂ɋɂ߂ėL�v�Ȏ����ł���B�����ɋނ�Ŏӈӂ�\���B�v
�@�@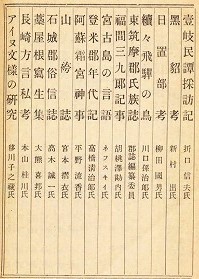 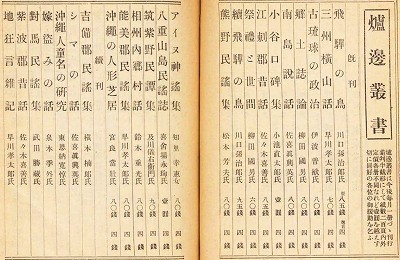
�@�@���łɋL���ꂽ�u�粑p���v�̓��e�ꗗ�\�@ |
|
�Q���A�@�������Y���u����ʐ^�� ��1�S�v���u�������Y�v���犧�s����B�@�@pid/967840�@�@�{���\
�@�@
�@�@�@�l���A�@���\���d�[�̌䍖 |
���l���A�@���\���d�[�̌䍖�i�S���j
�̂��牫��ł͐X�т𐒔q�������������B�̂��ăE�K���ƌ��ӁA�E�K���̍ł��ȒP�Ȃ��͍̂��F����ւċ���B�����͑c�[�i�\�i�C�j�̐����C�݁A�����Y�i�ɖʂ������ɂ������i�E�K���j�ŁA���Ă̓_�ɂ悭��������ԂŁA���������������T�X����X�тɈ͂܂�A���Вm��ʐ_�X�������o����A�w��ɗ��r���E�A���肵�̂�����ł���B�^���̑O�ɏ����������̗��̂�����ł��炤�B�ʔ������Ƃɂ͔��d�R�̌�Ԃɂ͂ǂ�ȏ������A�ǂ�ȂɌÂ���Ԃł������̂���̂ɔ����A�{�Ó��̌�Ԃɂ͒������Ȃ��A�X�ɉ���{���ɂ��V���������������邯��ǂ��Â����̂͂Ȃ��A���T�����������ΐl�ޛ{��ʔ������Ƃ������邩���m��ʁA���d�R�ɉ������Ԃ̒����͊m�Ɍ������ׂ����̂ł���B
|
|
��A�@�p�鐳�a
��A�@�ߔe�s�̈ꕔ
�O�A�@�}���v�V�L�ƒ���
�l�A�@����`
�܁A�@��O�n���^���R�̐Ԗ�
�Z�A�@������
���A�@�m�Ԃ͔̍|
���A�@����n���̊��
��A�@�����̃m���V
��Z�A�@�c���
���A�@�q���M�_�}�V
���A�@����
��O�A�@���\���ǐ�̍g����
��l�A�@�s�O��
��܁A�@�A�_��
��Z�A�@�^�V�`
�ꎵ�A�@���Ă̐���M |
�ꔪ�A�@����̑�K�W���}��
���A�@�Ί_���Ə������쎢��
��Z�A�@�g�̏�_�ЂƑ�����
���A�@�c���A�_��
���A�@���̑�
��O�A�@�ĝ���
��l�A�@���͎R�̐[�J
��܁A�@���\�����Ǎ`����
��Z�A�@����̕���
�A�@���d�R�̊��ߐ������ƍ�c��
�A�@�鉺�k��
���A�@�Ί_�̜A�����錴��ƒ|�x��
�O�Z�A�@���d�R�V����
�O��A�@����̋��]
�O��A�@����̃Z�~
�O�O�A�@���\���̃I�z�o�q���M
�O�l�A�@����㗤�L�O�� |
�O�܁A�@���S��
�O�Z�A�@�w�S�ƎR���̔�
�O���A�@�D���`
�O���A�@�{�����V����
�O��A�@���d�R�x��̓���
�l�Z�A�@���ޒ�
�l��A�@���\���̋��]
�l��A�@���Ǎ��隬
�l�O�A�@�������̖k���������
�@�@�������Y�i�������Չ���
�l�l�A�@�n�e���}�M��
�l�܁A�@�N�C����i�ꖼ���ґ�j�ƒ���
�l�Z�A�@�I�L�i�n�P�t�`�N�^�E
�l���A�@����n���`�q���M�̏���
���l���A�@���\���d�[�̌䍖
�l��A�@���K�r
�܁Z�A�@���⓰ |
�S���Q�O���A���c���j���u�C�쏬�L�v���u�剪�R���X�v���犧�s����B�@���Ł@
�S���A�ɔg���Q�Z���u�����낳���� ��1-8 �v���쓇�k�b��v���犧�s�����B
pid/1870285�@�{���\
|
��� ������傫�݂���������{�̌䂳���� �Ö��\�N
��� ����z�҂�������{�̌䂳���� ��?�l�\��N�܌���\����
��O �������N���Ȃ�������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��l ��������A���������́A�������o�� �V�[�O�Nᡈ�O������
��� �V���₷�ցA�����������ӂ�������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��Z ������N�A���݁A�N���Ȃ��A���T�Ƃӂ݂�����A���݂́A�́A�������o�� �V�[�O�Nᡈ�O������
�掵 �V���₷�ցA���������A���Ȃ��A�͂Ђ́A������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
�攪 �V���₷�ցA���������A���Ȃ�������˂₩��A���������A�������o�� �V�[�O�Nᡈ�O������ |
�T���A���c���j���u�C�쏬�L�v���u�剪�R���X�v����Ĕł���B�@
�@�@���ŁF���N�S���Q�O���@�@�@pid/1871757�@�{���\�@�d�v
|
��
�C�쏬�L
�� ���炢���n��/1
�� �n��̓��/8
�O �C�䂩��/14
�l �Ђ���̉�/20
�� �������̂قƂ�/27
�Z �n�̓�/33
�� �����֍s���H/39 |
�� ���ꂸ�݂̓�k/45
�� �O������/51
��Z �������ł���/57
��� �����̏��v��/63
��� �����̓y/69
��O �����҂�_/74
��l �R���D/80
��� ���_�̍���/86
��Z �p��̉�/92 |
�ꎵ �����̘b/97
�ꔪ ���x�̉��/103
��� �����Ȍ��/108
��Z �v���̛�/119
��� ���P�̐l��/124
��� ���z�ƈ�/134
��O �b�����}�_/140
��l �͂����/145
��� �ԖI�S��/151 |
��Z �{�Nj�/156
�� ��F�l/161
�� ꝉ���m��/166
��� ��g�Ɗ�/172
�o�ߚ��̏�����/179
��̓����C��/203
�Y������������/233
��策����̓�/313
���� |
�T���A�{���c�Ⴊ�u㔔��d�R�̖��̌����v���u�j�w 4(2) p.111(271)-139(299)�@�O�c�j�w��v�ɔ��\����B�@ �iIRDB�j
�T���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w 2(5)(13)�v���u�������@�v���犧�s�����B�@�@pid/3549054
|
�Î��L�_�b�̑g�D�Ƒ��̐����̎���/���c��/p1�`20
�R�㉯�ǂɂ��� / �{�萰��/p21�`43
�O�\����(����)�̎��`�ɂ���/�R�����j/p44�`64
����������ݗt��`�ɏA���� / ��ΐV/p65�`79 |
�Y�p�͈�̈Ӌ` / �E�c�Ί�/p80�`90
�����͎��̛��ہ@�����{�Z���{��鄚���u椂̖��ɂ���/�k����/p91�`99
�b��@��㏗�q����{�Z���{��鄖��/p99�`
�b�� �ԃy���𝦂���/p101~ |
�U���A�ɔg���Q�Z���u�����낳���� ��9-13�v���u�쓇�k�b��v���犧�s�����B�@�@pid/1870295�@�{���\
|
��� �V���₷�ցA���������A���Ȃ�����[�C��]�́A���˂�A�������o���V�[�O�Nᡈ�O������
��\ ���肫�A��Ƃ́A������䂳�����V�[�O�Nᡈ�O������
��\�� ��ƁA������䂳����
��\�� ����[�C��]�́A�����сA������䂳�����V�[�O�Nᡈ�O������
��\�O �D��Ƃ́A������䂳�����V�[�O�Nᡈ�O������ |
�X���A�ɔg���Q�Z���u�����낳���� ��14-22�v���u�쓇�k�b��v���犧�s�����B�@
pid/1870303 �@�{���\
|
��\�l ����[�C��]�́A��A������䂳����
��\�� �V���₷�ցA�����������Ȃ� ���炨�����A�����T��A��ނ��A�����낳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��\�Z �V���₷�ւ����������Ȃ� ���A��u�삨����䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��\�� ���[����̂�����䂳����
��\�� �V���₷�ւ����������Ȃ� ���ܒ�������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��\�� ����˂�A�������A�͂Ȃ������A������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
��� ���߂�������䂳���� �V�[�O�Nᡈ�O������
����� ���߂̓�܂��肨�����o�� �V�[�O�Nᡈ�O������
����� �݂��₽���肨�����o�� |
�P�O���A�{�R�j�삪�u�F�ӑp�� 20 �^�ߍ����}���v���u���y�����Ёv���犧�s����B�@pid/1904766�@ �{���\�@�d�v
�@ �@ �@ |
���C���l�[�i�����j
(��)�]���ē����̑D����҂��Ɛr���Ȃ���̂�����B��x���`�̑D�e���݂Ƃ߂�ƁA�ȑO�͑��̐l�X���ɌˊO�ɔ�яo�����ߍ����A�u�C���l�[�@�C���l�[�v�ƌĂт�Ȃ���A�c�[�̃i���^�_�ɌQ��W�ЁA���X�Ƃ��ċC�i����ӂ��L��A���̂��T�͂���Ȃ������ȁA���̃C���l�[�̐l�X�̏㗤��҂���т��B(��)�́A�o�M�����ł͑D�������Ɛ�Ð��������̎Ⴂ���������i���^�_�ɑŏW���āA�A�_���t�ŕ҂��X�̑�����u���Ȃ�ׁA���̑����𗚂����l�͑������̑����̎���ɂ���������ɂ��u���������Â��ꂽ�[�Ƃ��ӂ₤�Șb���A�����Ɠ������l�̌����猾�Е������ꂽ���̂ł���B
�@����(����)�ɂ��u(��)���Ȃ��F���ɒ��d�Ɉ����B���J�ɂ��ĂȂ��ĉ���(������)�ɒu���Ȃ��B
�@�@�u�����y���z�v�̑S�Ă̈Ӗ�������
|
|
�͂�����/1
���C���l�[/1
�i���^�_/2
�c�[/4
�F�Ǖ��x/6
�h�D�i��/7
�n���B��/8
����/10
����/11
����/12
���c/16
�Ă̓��R��/16 |
�Ɖ�/18
�\��/20
�葫�����/22
�Ύ���/23
�Ԏ�/24
�Ɣ�/26
�J�C�^�[�Y/26
�Ɏ�/33
�N�~���[/34
���/38
����/40
�|/42 |
�T�J�C�E�C�\�o/43
����/44
���I��/49
�o�Y/51
�V��/52
���/54
�����ޕr/55
�k��/56
�k�n/58
�P�Ƌn/59
��a��/60
��n/62 |
���V/63
�N���s��/67
�t�[���k��/71
�T�o���k��/72
�h�D���m���k��/72
�X�����M/74
���/82
�ی�/94
����/105
�E
�E
�E |
�P�P���A�������Y���u����ʐ^�� ��2�S�v���u�������Y�v���犧�s����B�@�@pid/967841�@�@�{���\
|
��A�@���d�RꝂƃn�u
��A�@�ߔe�E�q�_�i��V�j
�O�A�@�V���b�v
�l�A�@�����̐���
�܁A�@���ǐ�̏M��
�Z�A�@���X��i��V�j
���A�@�p�p���i�Z���j
���A�@�v�ē����Â̊C��
��A�@�rꏂ̔���
��Z�A�@���d�R�����ƈ��c�����Y��
���A�@�{�Â̓V�R��
���A�@�K�W���}��
��O�A�@�v�ē���
��l�A�@����隬�i��V�j
��܁A�@�����̐���
��Z�A�@���b�`�̂���
�ꎵ�A�@�q���M���h�L |
�ꔪ�A�@���d�R���약�̖q��
���A�@�њ��C�썲�ۂ̕�i��V�j
��Z�A�@����͔̍|
���A�@�o�ߌ��S�i
���A�@�n�}�a���`���E
��O�A�@�����V���i��V�j
��l�A�@�����Y�i
��܁A�@�܂ň�R�n�e�C�V
��Z�A�@�����r�i��V�j
�A�@�n�v�n�`
�A�@���ق����т��Â�
���A�@�t�N���x���K���̈�
�O�Z�A�@�������i��V�j
�O��A�@�Y����V�����@
�O��A�@��㊂̎X���
�O�O�A�@�\�e�c�̎���
�O�l�A�@�약�s�̌�ؖ{����{�B�� |
�O�܁A�@�q���i��V�j
�O�Z�A�@�v�Ă̌}�̏�
�O���A�@���V�ԋ{
�O���A�@��㊂̊L��
�O��A�@�A�J�e�c�̘V��
�l�Z�A�@������ƃT�L�V�}�n�}�o�E
�l��A�@�n�u�J�d��
�l��A�@�������i��V�j
�l�O�A�@�Ï��̉�
�l�l�A�@�v�ē����P��ƃt�g�����̎���
�l�܁A�@�k�g��
�l�Z�A�@�R���̓c��
�l���A�@�����R�����̃I�z�o�q���M
�l���A�@�ɕ�����
�l��A�@�J�~�[�O���[�̉�
�܁Z�A�@���{�Ŏm�̎q������߂�@
�@�@���i�͓����桁j |
���A���̔N�A�c�����O�Y�ҁu�{�Ó��̉́v�����s�����B�@�@�약���\[����]�@�@�{���\�@�d�v
|
�����{�B�c�����O�Y�w�{�Ó��V�́x�̎ʖ{�̈�ł���B�c����1893�N�`1897�N�ɉ��ꌧ�q�풆�w�Z�̍��ꋳ�t�Ƃ��ĉ���ɑ؍݂��A���̊Ԃɋ{�Ó��Ŗc��Ȑ��̗̉w���̏W���A�w�{�Ó��V��
��x�w�{�Ó��V�� ���x(������w�����}���وɔg���ɏ����j��҂B�{���͂���Ɍ��t���čĕҏW�������̂ł���A�쐬��1925�N�`1935�N�Ɛ��肳��Ă���B�\�����Ԃ��Ɂu����^���[�약���\�v�Ƃ���A����ɂ́u��Ï��L�v�̏���������B���^���e�̓A���O48��A�g�[�K�j48��A�j�����̎��̃A�[�S3��A���NJԂ����6��A�j�҂��I��Č�ɉ̂Ӊ�5��A�r�Ԃ̂����A�[�S21��A�q���7��ł���B�V���K���u�n���C��w��ߕ��ɑ��w�{�Ó��̉́x��b�E�����W�v(�w���ꕶ���x69���A1987�N10���j�ɁA�ȒP�ȏ����̐����Ɠ����̐����E���������B |
���A���̔N�A�����ȕҁu���V�R�I�O�������� �A���V����2�S �v���u�����ȁv���犧�s�����B
�@�@�����F�ΐ쌧���}���فF002072635�iE���Ɂj
|
�����^�C�g�� �{�莭�����������j���P���A�� ���쎡�[ �s�䖦�h�S�����n,���������L���p�����P��,�{�茧�� ���m�����j���Q���j���P���A�� �g��`�� ���m�����ˍ�M�ѐ��A����n���j�������m���� ���Q�����c�����j���P���������m�k���n,���m���������m��������� �k�C���̐A�� �O�D�w �T��,��y������,�~�R������,�o�ʉ���N�o�n�y���߃m�R�� �D�y�_�Ћ����m�g�R���m����,���ꌧ�j���P���A�� ���쎡�[ �D��,����m�n��,�C��g�A��,�h�S�����n,������,�ւ���,���Ђ邬��,���(�����܂�,������,���͂ł�,����,�Ԗ�,�ł�����)�͔͓I�X��,�����j��������m�A���ی��ԋy����m���ӂق��@�@�Ċm�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�S�E�V�@�ۍ� |
���A���̔N�A�h�����h�ҁu�������������p�� �B�L�����v���u�������������p�����s��v���犧�s�����B�@�@pid/1913655
|
���� ���ꚠ�t�`��
�� ��䚠�t�`��
�� ��m���V�C����
�{���B�ҏ@�嗪��c�B �l�� �喻/1
�ܒ���l�B ���/373 |
���b�R�J�R�����t���N �O�� ���C/399
���������N�� �O��/423
�ˋ�a���N�� ��� �q�H/517
�{���B�ҏ@�嗪��c�B�ژ^
�ɔV�� �V�� |
�ɔV�� �k�U
�ɔV�O �k�U
�ɔV�l ���{
�E
�E |
|
| 1926 |
15 |
�E |
�W���A�c�����O�Y���u�A�������G�� 3(8) p.190-193�v�Ɂu������㊂̃V�C�N���V���[�v�\����B�@
�X���A�����p���_��������ҁu�Ï��l�H��z��{�������сv���u�����p���_��������v���犧�s�����B���ʔ�
�P�O���A�ɔg���Q���u�����Í��L�v���u���]���@�v���犧�s����B�@pid/1833206�@�@�{���\�@
|
�� �Ǔ���̗���/1
�� �����j��ɉ����镐�͂Ɩ��p�Ƃ̍l�@/73
�O ���c�F�_�̈Ӌ`��ᢌ�����܂�/227
�l �쓇�̉�揂Ɍ��ꂽ��̗�����/263
�� �×����̉�揂ɏA����/283
�Z �Վ����x(�����肭�킢�ɂ�)/335 |
�� �����Ñ�̗���(�����͂�̗V��)/361
�� �x�߂̓����Ɨ����̑ԓx/379
�� �ɂ���/399
��Z ����p���̃��h��/407
��� �w�n�����L�x���Љ/449
��� �p�˖�������/483 |
��O �����ǎ��ȏW�ɂ���/499
��l ������̕�C���v/521
��� ������̝Ɏ��ɂ���/553
���^
���{����̎v�o/581
�E |
�@�@
�@�@গ��D���Z�i�O�F�Ō�㉁^�����j |
|
�@�@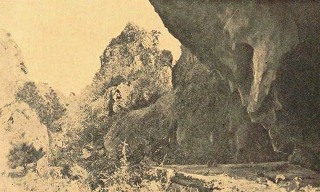
|
|
�P�O���A�ɔg���Q���u�Ǔ���̗����j�v���u�t�z���v���犧�s����B�@�@ �@pid/2390503�@�@�{���\
|
��@�w�쓇�x�̏�/1
��@�w��܂Ɨ��x/20
�O�@�O�R�C���Ǝx��萌W/43
�l�@�O�R����ƊC�O�f��/77
|
�܁@�����W�܂ƍՐ���v/125
�Z�@���Î��̐����ƙ_������/158
���@�����|���Ȍ�/215
���^�ڎ�
|
�쓇�̎��R�Ɛl/233
�×����̓l/260
���c�F�̘b/297
�×����̕���/303 �@�k�ЏĎ��E���y�c�Ǒ� |
�@�@�@�ʐ^����
|
�×����̕���/303 �@�i�ꕔ���L�ڗ\��j�k�ЏĎ��E���y�c�Ǒ� |
�P�Q���A�a�J�������u���z�搶�Ï��̗R���v���u�i��ʌ��k�����S�Y�a���j��ʊÏ������Ƒg���������v���犧�s����B�@pid/1188669
|
����
�Ï��̗R��/1
�Ï��̌��Y�n�ɏA��/1
�Ï��̙B���ɏA��/5
����
��؍��z�搶�̙B�L/10
���z�搶�̗c���y�щƌn/12
���z�搶�̗��g/15
��O��
���l/23
�A����@/25
|
���z�_�Л�ɊÏ�����n/34
����A�{�����v
����p���Ï��͔|�ɏA��/35
���́@�Ï��̎�c/36
���́@�Ï����̍k��(���n)/39
��O�́@�y�߂̎�ނƊÏ��Ƃ�萌W/41
��l�́@�Ï����̐A�t/42
��́@���ۊQ�ƊÏ��Ƃ�萌W/51
��Z�́@�Ï����A�t�Ǝ��߂Ƃ�萌W/47
�掵�́@�Ï����A�t�̒���/53
�攪�́@�Ï��̝��n���y������/53
|
���́@�Ï��͔|��萂��_�Ǝ҂̒��ӂ��ׂ�����/58
����p�_����鄏�ᢕ\�\�Ï��͔|�@/60
�������Ï������n�͔|�@�v��/81
�Ï��g�Ԏ��ᢌ��ƈ琬�̗R��/87
��l��
�m�{�̗R��/90
���z�搶�̒���/95
��ʊÏ������Ƒg�����v/99
�_�ƔN���s�����T�\/114
�V�����@�ی��W/117
��̘b/125 |
���A���̔N�A�V�_�����ҁu�ږ��V�F�v���u�i�����j�ږ��V�F�Ёv���犧�s�����B�@pid/1017924
|
�嚠���I�C�OᢓW�E�Ҏҁ@�V�_����/1
�����܂̝���
�l�����̋}��
�l���̑������Ƒ�����
�C�O�̛��ɂƉ�㊐N
�C�OᢓW�̗v�f
�S�Z�I�C�OᢓW
�^���b�����̓����Ɠ��{�����̊C�O���W�E
�@�@���O���ș��o���@�i������Y/15
�l��ޕʂ̍���
���H�Ɋ�^�F�l�̓���
�^���b�����̊���Ɛ��|
�ؐH�Ɋ���{�l�̓���
�l�̌��ƚ��Ƃ̌�
���ۊԂ̔����Ɣr���S�Z
���E�̗��j�͐��E�̖@���
�隠��`�̌�T
���{�����̑�g��
�����ɉ�����ږ����E
�@�@�����_���@�|������/39
���j�����V����^�F�ڐA���̛���
���ט�������ᢓW�Ƒ�a�����̐ӔC
�A���{��ᢒB�ƈږ�����
�ڐA���̖{��
�l���ߏ�ƊC�OᢓW
�������ƚ������S��
���{�Ɖ���p�̈ږ�����E
�@�@���Ҏҁ@�V�_����/57
���{�̈ڐA������
�ڏZ�g���@�̛����𑣐i����
������筂ꂪ���̉��
���⛉�s�̏H
����̍��{�I���v
����p�~�Z�̍��{��E
�@�@������p���c���@���c�g��/65
�N�q���̗Y��𑣂��E
�@�@���Λ{���m�@�n������/69
���_����̋}��
�l�i����
����
�ӔC�V�O
�l�̊���d������X�Ɖ]��
�����ƓK��
�p��ਁA����ਁA���E��ਁE
�@�@���O�c�@�c���@�Í菮��/77
����p�ږ��ɏA���āE�O���������@�y�����/84
�o�҂ƈږ�
�ږ��͊O���̗{�q
�l�Ԃ̒����ƒZ��
�M�p�Ɠ����͑��`
���ɓ���ċ��ɜn��
����p���̒��ӂ��ׂ�����
�C�O��ᢓW����Ƃ���ޓV���� |
�@�@�����N�Ɋ��o���E���{�A���ʐM�В��@
�@�@�����{�A�����k�����@�����p�Y/91
�ږ����ƛ��ƛ{�Z���Ɛ����N�E
�@�@���_�{���m�@������/104
�l���̗|��
�A���̓��@
�_���ڐA�̋}��
����p���~�ӂ͈ڐA��
�_�{�C���ҏ��N�̐ӔC
�e����{�Z���Ɛ����N�̕��N
�C�O��ᢓW����N�ɂ�����/111
���ʖڂȊ������@���t�`����b�@����X���Y
�V���͂킪�Ɓ@�M���@�c���j�݁@�ɍ]����
�����ɓ��ӟN�Ԃ���@�@�{���m�@�����i�Y
���E�̋��܂Ŏq����B���@�����ĕ�
�ڏZ���̂悫�s������@�@�{���m�@��N
���E�ōł���Ȑl�����@
�@�@���O�c�@�c���@�Í菮��
�F��͔\�ɂ��炸�@�@�{���m�@�����C��
�l�������̉��ف@�O�c�@�c���@�_�c���Y
�ŏ����S���Y�ꂸ�Ɂ@
�@�@���O�_���������@�ߌ����g�Y
�f�ӂȂ���@�O�c�@�c���@������
�ږ����Ɖ�㊈ږ��E
�@�@���C�O���Ɗ������Ё@�ʒu����/117
�����v�z�ƊC�OᢓW
���S�߂��p��
�И��Ǖ⏕�����ږ��������ւ��p�����S��E
�@�@���Ҏҁ@�V�_����/121
�u���W���ږ��⏕�̎��
��㊈ږ��͉��̜��܂�Ȃ�����
�������ւ��p�����S��
�ږ��Й��@��
�����̑���`�͌���
�ږ��n�̒ʗp��
�����K���̑�����҂����E
�@�@���C�R�����@���ߌ��a/130
�͂�����
�s��n�̕����K�������
�������S���̗v
�ږ��𑗂镃�Z�ɖ]��
�z���ɉ�������{�l�̛��ҁE��㊒����V��
�@�@�������x�ǒ��@���ߔe�O�Y/136
�����͖M�lᢓW�̗��z���E
�@�@��������棗̎��@������Y/145
�����̊T�v
�l��
����
�ݕ�
�G��
�n��
�Y��
�f�� |
�����f��
�n�q
���
��]
�����R���J��҂̑z�o�E
�@�@���Ō��k��/157
�͂�����
���̘�����I�肵����
�����̚�����
�A�E����܂�
�������̉���
�����̔_�q��
�_�q���ʂ̙�������
�L�]�Ȃ�q�{�̛���
�_�q���ʙ����ҋ���
���������Y������
�����̋���
���z�I�̃A���A���T�ڏZ�n�E
�@�@���Ҏҁ@�V�_����/193
�A���A���T�ڏZ�n�̌���
�ڏZ�n�S�z�̈�ʌv�`
�ڏZ�n�S�z����
�M�Z��ēy�n�g��
�ڏZ���n�̑I����ɍw��
�ڏZ�n�J�ݏ���
���{�̗ȉ��ƕ⏕
�ڏZ�҂̕�W�n�q���A
����
��m�ϔC�����̛̂��ҁE
�@�@���Ҏҁ@�V�_����/220
���Ɠ������S��
���ƒn
����p����ᢓW�n
����p�����҂̌���ɏA�āE
�@�@���Ҏҁ@�V�_����/224
��㊑��̉���
萓�萐������n���̉���p
�@�@���l�������`�ɂƐE��
�a�эH����
���ւ铯�E���~��
����Ɛ�����
���~
�q�����
��قƓq���̕��Q
�E�Ƃ̙J�l
���Ӗ܂�}���܂�
�ږ��ۂ���݂���E
�@�@����㊋y����p�l�劲�@
�@�@����X������/250
�u���W�����s�ڐA���ē�/253
��Ă̛��ɔ�I������E�ؑ�����/271
�䓇�_�o�I���k�n�̛���/282
�n�q��㔂Ə���/296 |
|
| 1927 |
���a�Q�N |
�E |
�P���A�����y�V�����u���͂܂�����v���u�t�H�Ёv���犧�s����B�@pid/1188856�@�@�@�{���\
|
�l��
������� ���/2
�ԔL�V�� �Y��/13
�V�ׂ� �ْk/23
���͂܂����� �ےk/36
���D�l �J��/57
�m�Ƌ�冋o �V��/75
�n�R�r�_ �J��/100
���w�A�A���ƂȂ� ���Y/106
�~���̏t �Y��/111
����Â��� 趋L/121
����̐� ���L/126
��s��o�l�̎� �p�L/133 |
�s��Z�� 趕M/140
��S�� 笑z/145
������ւ̉��] ����/151
�u�D�v�̓��� 越�/155
�������E�������� ���^ /161
���ՕP �V��/167
�D�����L �L�^/173
������ 笕M/178
���R�Y��k�� ���M/184
���`�u ���z/192
�������� �咣/199
�ԉ�
�J���̉� ����/209 |
�� �]/213
�l���ƃy���J�� 笑z/216
�J�v�ԉ� ����/221
���Z�L �/225
��p���� ���z/229
�Z�̓V�n ����/233
�Ė� �Y��/236
��d�� 笋L/239
�|�v�l 笋L/244
��Ɖԉ� �L/248
��J���s ��L/253
���ȂƕS���� ���z/257
�쐶�̓��� ����/262 |
���悵��悵 ���M/265
�~��趕M �/272
�ҏt趕M �]/277
�ᒹ�Ɠ~� ����/286
���E 笕M/292
�~���L ���L/296
�~�̂Ђ� ���L/299
����
���L ��z/302
���f ����/309
�c�NJԌQ���V�L �I�s/318
�E
�E |
�S���A���{�`�p����ҁu�`�p 5(4)([35])�v���u���{�`�p����v���犧�s�����B�@�@pid/3224397
|
�_�� ��A萖�C�����ǍH���ɏA�� / �����ȉ�萓y�؏o������ �ЎR�叼/1�`7
��A��V�������Ĕ�������l��҂ċ��� / �O���s��i�x�X�� ������O�Y/7�`12
��A����(����)�`�ɏA�� / �����s�� �����H�n/12�`16
��A�����z�`�v�`�ƍ����s / �H�{�m �c���F�F/17�`20
��A������B�̐U���͎O�r�`�̗��z�I�����ɘւ� / �喴�c�s�� ���h���Y/21�`23
��A�����p���ݗ��`�s / ���ݗ� ����\���Y/24�`26
趘^ ��A萖�詓��Ɩ�i�̉q(��) / ��i���Ƙ��c��/27�`36
��A�ᏼ�`�T�� / �ᏼ�z�`�������Ў����� ���{�����Y/36�`53
��A���q�z�`�v�`��v / �������� �ǖ쏬�q���|��/53�`57
��A���Í`�ɏA�� / ���Ò� ��萐��j�Y/58�`63
��A����`�̍���(��) / ����s����/63�`68
��A���Z���`���C���Ƃ̉��v(��) / ���Z���p�y�؉�/68�`73
��A�{���p�`�s�T��(��) / �{���p�y�؉� ��t��/73�`78
��A�啪�` / �啪�p�y�؉�/78�`85 |
��A���_�`�s���v�T�v / ���_�s�`�s��/85�`92
���� ��A�����s��Ó������Ɣ��T��--�A�C���`���S�Z�I���--�A
�@�@�����َs�̍`�s�{�ݛ���--�A�a�̎R�z�`����--�A�`�s������x���`��--�A
�@�@����萎s�ݏ㉮��ݔ�����--�A���Z���`�s�C�z�H���̐i��--�A
�@�@����A�`�È�q�̟���--�A��ꝍ`�̟��� //93�`97
��� ��A���I����d�]�c���� //98�`99
��A��l�d�ʏ��`���o���� //99�`105
��A�����`�C�z�v�`��萂��雉�n���� //106�`107
�i���j
���^ ��A�S�Z�{�k�̋�B�nj� / ���{��{�͎� �����U/120�`122
��A�ߔe�`�̗��j / ����p�������ْ� ����������/122�`128
��A�����j�ւɕx�߂铂�� / ��딒�N/128�`134
��A�V���Љ� //135�`135
�E |
�S���A�ɔg���Q�i���� �ӂ䂤�j���u�쓇�̗̉w�ɏA����: �ɔg���Q�u���v���u�w�|�u���ʐM�Ёv���犧�s����B
�@�@�����F���ꌧ���}����
�X���A����P���u�����w�G�� 39(467) p.355-368�v�Ɂu�������ʂɉ�����W�����ݍ̏W�T��v�\����B�@�@PDF��
�X���A�Ζ�H�l���u�����哇�������v���u�����@�v���犧�s����B�@�@pid/1453838�@�@�{���\�@�d�v
|
��������
�ɔg���Q��
����
�j���ƕ���
�����哇�̎j���ƕ���/3
�쓇��Ǝ���/31
�����哇�̌É�
���̉�/49
�v�Е��̉�/55
�Ԃ̉�/57
�v�Џo�̉�/61
�|����/68
�哇�Ì꒐��/84
�哇�l���ƕ�����/122
����
�����哇�Ñ�̑���/153
�T�C�v��
�哇�̔T�C�v��/179
�ޏ��ϐM�Ƒ����Q/188
�V���[�}�j�Y������o����/194 |
�ޏ��̎�p/197
���x
�����x/207
�����x�̕��ٌn��/213
������ʊT�v/216
�X�y�C�����D�̑����m�q�H/219
�X�y�C�����D�Ƒ哇/222
�����x�̃X�y�C����/228
�����x�̎�/230
�ݖ�Зx/236
����x�ɏA����/240
���
�哇�̎O����/251
�哇�̎O�����̑t�@/257
�O�����̍�@�K��/259
�O�����̒����@/260
���
���������Ɩ��/265
��揉r�Q���̈�/267
�哇��揂ّ̞�/272 |
��揂̐�����U/277
�哇��揃J���e���̎�/278
�哇��揃��`�����߂̎�/288
�Ðm�����l�Ɨ����g��/296
�哇�̓�̐l/308
�ꐫ�����̂��G���/312
���X�̉�/319
���̐����ƏM/322
�j�b
����Ɖ��v�C����/333
�������隬���݂̈��/340
���s���̍Ŋ��ƞܑ��v�̜�/352
�s���_�Ѝ��J/360
���_/375
�ٕ�
�Q���̓��i�Ζ�H�l�ҋȁj/�ɓ�2
��������x�̎O�������i�Ζ�H�l�����j/247
�����哇��描r�ǐߕ��i�Ζ�H�l�ҋȁj/273
����
�T�C�v�ڍ՞ٗp�ʂׂ͂�/�ɓ�1 |
�P�P���A���w��o�ŕ��ҁu���m�{�Y趎� 43(11)(535)�v���u���w��o�ŕ��v���犧�s�����B�@�@pid/3559475
|
���f���̑��̐��� / ���R�C��/p613�`617
��̌��{���͂ɏA�ā\�\(��) / �؈䐽����/p617�`621
�u�݁T���v�̘b / �O��a�p/p621~627 |
�������ق̒��q�Ɖ��K�\�\(��) / �R�����j/p627�`635
���@�����̐i���Ƒ��̕��͓I��p / A�a���j�I�[ ;�F�쐪�v/p635~649
�ΐ쥉����_���m�_ू̗֊f�\�\(��) / ��������/p650�`656 |
�P�Q���A���w��o�ŕ��ҁu���m�{�Y趎� 43(12)(536) �v���u���w��o�ŕ��v���犧�s�����B�@�@pid/3559476
|
�}�[�X�����x���g���[�̋Ɛ� / �N�����/p665�`667
�����̔\�� / �J�Ò��G/p667~669
�{�M�Y�Ζ��̐����y�ё���p��萂��錤��/�c���F�Y/p669�`679
�C�Y����(�d����)�̒t�����̏K���ɏA��/���c������/p679�`684
�D�����P���A���̎��R�ț{�y�Λ{�ɉ�����Ӌ` |
�@�@�@�� / �t�C�c�V���[ ;�䌴�r�j/p684~687
�������ق̒��q�Ɖ��K�\�\(��) / �R�����j/p687�`696
�t���l���̎��� / ��S��/p697�`700
�G���C�e���v���X���w���R�N�{�̚�����b�x�ɏA��
�@�@��/�I������/p705�`711 |
���A���̔N�A�ɔg��N���u�썑�̔��S���v���u���V�Əo�ŕ��v���犧�s����B�@�@pid/1176332
|
�c��搉�/1
��ɓ����l/3
�V��/4
�Бz/5
|
�욠�̔��S��/8
�욠�̎��R��/14
�_���̉x��/28
���̎����/37 |
�c�q/44
�s��/55
�_���̃o�`���X/61
���s���_��/67 |
�_���U���̌�/81
�_����/97
�y���Y�p/104
�y�֊҂�/112 |
���A���̔N�A�c�ӏ��Y���u�����̉S�Ɨx�v���u�镔�b�z���v���犧�s����B�@
(���{�����p�� ; [��5])�@pid/1226529
|
�ɓ��哇�̖��/1
�哇�ւ̗�/1
���c�̎�×x/6
���B�߂ƌ��/9
���̔�����Ƒ哇��/15
�K�c�V���K�V���߂Ƃ���/20
�哇�̉��K/23
�����ւ̗��\�\���̏�/24
�哇������N��ᢚ���/27
���c���̉S�Ɨx/30
�����̑���/32
������p�@�ƎO����/34
����˂���Ɓu�J���`�����v��/36
�O��y�ѐ_�Ó��̉S/38
�d�H���}��/40
���n�̌Þٕ�/45
���n�ɂ���ٕ��̎��/45
�`��/46
�Ղ�̑D�S/48
���n�r��/50
��c�Ђ�揂�/51
��葊���/52 |
������i�R��/53
���삨������/54
�i�R�߁A�ꖼ���炬/58
�t��̕�/63
���q�S���/67
���\�߂Ɩ�C�Ԑl�`/71
����ƍ��n����/73
�~�x�Ɛr��x/78
���̂������x/93
�V���̔_�ƉS/94
�Õ��̎O�ԙ�/99
�Ε�/102
���K��/102
���̏����q�x/105
���n�Ǖ��x�Ƒ���/108
���]�Â�蓌����/110
�����y�l�̉���/113
�������s��ᢒ[/113
�唑�����_��/117
�I�R�c�N�C�̕��Q/121
�ɖk�̈ꏬ���~��/124
�M�����[�N�y�уI���c�R�̉���/127 |
�I�R�c�N�C�̓˔j/135
�A�C�k�����̖K��/140
�A�C�k�̕��x/143
�A�C�k�̉��/145
�A�C�k�̞ي�/148
�[��̑���/153
�Ō�̖��k��ɂ�/159
�k�C����蓌����/162
��k�Ђɉ����錤���ޗ���
�@�@���s�v�c�Ȃ�^��/166
�̂Ɨx�̚��\�\����/169
�������ٌ����̕K�v/169
�\���ɕY�ӑ哇�̉���/172
����������G��Ȃ��/176
�����̗x��/179
��̉��٘�/184
�ߔe�̟c�}���x��/195
�������ْ�����/199
���D�̉���/203
�������������M/206
�{�Ó��̈��/208
㉂̔@���哇/213 |
�V���Ɍւ锪�d�R�̖��/216
�Y��Ȃ�W���o�̓�d��/221
�i�s�אl�̉��قƗx/225
���/225
���{���̕��x/227
�i�s���ى��t��/230
�גn�ւ̗�/237
���ׂ̑����/242
�p�[������/245
�n�c�N�ׂ̉���/248
�ד��{�Z�ƏU���̉�/250
�p�[�����Дאl�̉S�Ɨx/253
���Ǝ�ؓJ/256
�����ЂƓ����K/259
�Έׂ̉S�Ƌn�̞�/261
�ɓ�̃��C�ЂɌ���/264
���C�Дאl�̉��قƗx/268
�U���̉Ƃ�
�@�@���ד��͈珊�̏���/270
�E��熂��ğd�H�ɂ�/272
�E
�E |
���A���̔N�A�{�ǒ����ȁu�y���@�쓇���� ��1�S�v���u���v���Џ��X�v���犧�s�����B�@�@�d�v
�@�@�@�����F�����|�p��w �����}���� ��1�S GBb/187/1 18803350646
|
��1�S. �ق����Ăӂ�
������
����̉� |
��
����ǂ��̉�
�� |
��F�̏���
���S
�������������� |
|
|
| 1928 |
3 |
�E |
�S���A�{�Ǔ��s���,�{�ǒ���̕��u���d�R�×w. ��1�S�v���u���y�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1195201
|
����/1
�}��/1
����/1
��@�h�̒��E�����^/9
��@�L�E�����^/17 |
�O�@�L�E�W���o/23
�l�@�x���̏����E�����^/27
�܁@�W���o�K�̃\�[�\�[�}��ˁE�����^/39
�Z�@�����E�����^/49
���@�n�E�����^/63 |
���@���U�g�[���E�����^/77
��@�����lj��E�����^/93
��Z�@�N�C�`���x/107
���@���/115
���@�����I��/123 |
�S���A�u�����|�p 1(4)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@pid/1524711
|
�����̉��� / �R�����j/p1~6,8,10
���d�R�̘h�̉� / �{���c�/p11�`24
�V���E���x���V�閯�(���O) / ���V�ʕF/p25�`39
�u���y���x�Ɩ�揂̘��v�̙d�� / �F�J�C����/p41�`46
���d�R�̉��قƕ��x / ���q��i�k�W�����l�i��������������j/p47�`60
���d�R�̖�� / �{���c��/p61~69
���B���˂̕��x�u���Ԃ�v���� / ������/p70�`76
���ې_����Ċ_�_�� / ���ې_�ЎЖ���/p77�`83
���x�ɉ�����������p�I��� / �k�씎��/p84�`88
��㊖�揞ٕ��\�\(�����߁E�h�̒��Ԃ�) / �R?���j/p7,9
���ԂԂ��\�\(��㉉��) / �ڎ��� |
�ЕЌ�/p40~40
��趎��Љ�/p96~96
������k/p60~60
���{��描W���̘����W/p96�`96
�������J��/p89~95
����
���ԂԂ� / ���
�h�̒��Ԃ�/p21~21
���܂��͗x/p69~69
���Ԃ�/p73~73
��Ċ_�_���ޏ����D/p81~81 |
�U���A�u�����|�p 1(6)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1524772
|
���̗��j���Y�p / ���c���j/p1�`12
������E�̕@�c�ʏ钩���N�� / �ɔg���Q/p13�`39
�\�ق̉�(���O) / �R��ٓ�/p41~56
���d�R�̕��x�̈�� / �����Z�g/p57�`72
�����c���V�� / �⋴���\��/p73�`75
�H�c�p��قŕ����������܌����� / �����O��/p76�`77
�p�������Ɣ\�����̌��� / �|��������/p80�`82
�ĂƎq���̉� / ����������/p84�`85 |
���d�R���̕����] / ����/p86~92
��揞��}�\�\(������) / �R�����j/p78�`79
�g�x�w���̂̉��x�\�\(��㉉��) / �ɔg���Q/�ڎ���
�Z�g�̌�c�A / �Z�g�_�ЎЖ���/p40�`40
�{���̐V�����v�`/p83~83
�������J��/p93~96
�����E�}��
�E |
���A���̔N�A�u�����y���x�Ɩ��w ��R��v���u���{�N�فv���犧�s�����B�@�@pid/1454730
|
��ꕔ
�����x ���m�p
�NJ|�� �����p |
�����c�ƒ�����x �A���p
�܂���� �ΐ��p
���d�R����� �����p |
�x�e
���
���_�� �����{ |
���d�R�����x �����p
���Ԃ� ��X�p
�E |
�@�@�@�@�@�����y���x�Ɩ��w ��R��@���\���̓����ɂ��Ă͋L�q���K�v�@�@����L�ڗ\��@�Q�O�Q�R�E�X�E�P�P�@�ۍ� |
| 1929 |
4 |
�E |
�Q���A�c���Ԓm���ҁu�ߔe�Î��W�F���a�Q�N�\�ꌎ����X�L�O�@�S�v���u�c���Ԓm���v���犧�s�����B�@
�@�@�@pid/1191462�@�{���\�@�@�d�v
|
���^����c���Ԓm���N�m�Ďu�f�A�ߔe�̖������Ճ\�m���m�Û����N�W�Z�����u�ߔe�Û��W�v�g�C�t���q���҃}���A�����Z���������E�j�i�b�^�m�n�A�r�_���@�j�K�V�^�R�g�f�A�ߍ��������Փ��m�ۑ��g�C�t�R�g�K�������f�����Z�������y�������Z���������҃m�����V�^�R�g�n���Ɋ�o�V�C���ۃf�A���A���V�R���n�Ճ����p�o�J���f�i�N���m�{�p�A��j���ăm��i���j���e�����j���w�����e���s�Z�����c�c�A�����E�f�A���B��M�f�n���s��w�K��N���j����V�e�S���m�u���y�j�����Җ���v�i�����m�����\�Z�����^�A�\�m�����m��߃j�u�]�����{�j�փX�������n�P���j�����W���I�f�A�b�e�n���j�փX�������n�g�J�N���Ճj���Z�����A�]�b�e���j���{�S�̃m���j�������X���R�g�n�A�[���j�o���i�J�b�^�A�ŋߍK�j�V�e�n���j�m�����K���j�i���A�e�n�m���u�����҃K�A���o�X���j���b�^�A���n�w��m�^�����j�c��j�σw�i�C�E�E�E�E�R�m���냒���s�X�����K���y�j�m�����j�������L�Z�������l�X�m�A�������t�m�����`�j���i���o�A�]�m�]�O�m�K�g�X�����f�A���v�g�A���K��X�K���ꌤ���m�L�Ӌ`�i�R�g���@���j�k�c�e�䃋�m�f�n�i�J���E�J�B�{�p�n�J�P�����^�����f�A����i���v���L�V�^ਃ��j�җ��J���ꎞ�n���j�p���m�j��T���^���ヂ�A�b�^�K�A�R���n�V�V�C���݃j�Z�E�T���e���c�^�g�C�t�߃������i�C����K�A�b�^�J���m���i�C�K�A�c���m�l�X�K�×����m�����j�����m�����K�i�N�A��T�j�R�������J�V�e�P�i�V�^���E�i�R�g������i�������f�A�b�^�B�R���j�ߔN�j�i�b�e�A���y�m�����K�A���O�m�w�k�m��j���b�e�惊���n���^ਃ��j�A���V�N�ڊo���e���e�A�ߋ��j���P������m�������A�h�E���������~�j�o�T���^���E�f�A�����i���g���\�m���J�K�F�������^�m�n�A��X�K�c��m�^���j�փ��g�X�x�L�R�g�f�n�i�J���E�J�B��j�����m�����m�����i�����׃g�V�e�n�V�V�C�����n�A�ÃC���m�m��j�z�d�J�����g�C�t�R�g�K���b�e�L�e�A�ÃC���m�g�S�N�����c�e���������m�f�n�i�C�g�C�t�R�g�j�i�b�^�A���`�����V�l�g�n�ÃC���j���L�V���J���R�����P�p�X�����m�f�i�N�e�n�i���k�g�C�b�e�����B�ߋ��������V���j�����J�X���o�A�\�m�l�n���j���L�Z�U�R�g�j���e�A��Ãm���q�֖��i������j�A���i�P���o�i���i�C���E�j�i���B�\���f��X�n�V�g�p�g�m�s���I萌W�����L���J�j�V�e�A�ߋ��ɍ��U�Z�����������d�V�A�R���g�֗��V�e����i���j���B�V���x�L�V�`�����i��X���R�g���Ӄb�e�n�i���i�C�B���y���j�R�����c���ԌN�K�A�\�m���y�^���ߔe�s�m�������ՁA�R�����q�q�^���A�ߔe�f�����V�^���y�m�������Љ�Z���E�g�Z�������m�����L��R�m�Ӗ��J���o�X���m�f�n�i�J���E�J�g�v�n�����A�{�e�����n�����K�i�P���o����K�i�C�A����K�i�P���o�R��������X���g�C�t�l�w�n�N���i�C�{���j���i��j�b�e���j���̋��Ճi�h�m�R�������J�j�V�^�ȏ�n�R�������s���əB�w���n��X�������m�q���m�`���f�n�i�J���E�J�@�@
���a�l�N���t�@�@�@���ꌧ���}���ً��y�������j�e�@�@�����������i�܂����� �����j
|
���L��i�Ђ����傤�j�G�u�L�v���u��v���I���Ӂ@���ɁA���ɁA�ŏI�Ȃǂ̈ӁB�@�m���n���܂��܂Ȍo�߂��o�Ă��ŏI�I�Ȍ��_�Ƃ��ẮB�܂�Ƃ���B���ǁB
���s��(�ӂ��イ)�F���܂ł������Ȃ����ƁB�łт邱�ƂȂ��A�Ȃ����㐢�Ɏc�邱�ƁB�܂��A���̂��܁B�s�ŁB |
|
�̏�ӂ邫�����^�N��������^�����ӐS���^�����ӐS���M���肯��
���Ȃ���ɖ����������^����Ƃ��^�x�Ƃ��Ȃ镶���߂Ă����@�@�����۞�
��(��)�ߔe�s���ƛ{�Z���@���_�G��
��(��)�n�Õ~�B��
�������߂��^�c���u���Ȃ��^���̐����^���ƂȂ���^���ʂ��@�m�� |
|
|
�_�Џ@�͒���/1
�`������/2
�O�d��/3
�ՊC��/4
�_�ԃm�R��/5
�V������R��/5
�W�Δ�/6
�Z�g/6
�䕨��/7
������/8
���ʼn�/8
����/9
�O�Ўq/9
���ۍt�܃m��/9
�V���_/10
�����V�䉮�m��/10
�O���l��/11
�x�ߐl�m��/12
���������R��/12
������/13
�����R���_����/13
�E�q�_/14
�ߔe�R��/14
�ߔe�n�U�R��/15
�ߔe�Γa�m�R��/15
�N�c�n�U�m�R��/15
�����n�U�m�R��/16
�Z�����m�R��/16 |
���\�ɓ��m�R��/16
���E���m�R��/16
�^�E�}�X�m�R��/17
�ԏ�ԃm�R��/17
�����_�m�R��/17
�Z�`�A���ԃm�R��/17
�������P�m�R��/17
�t�i�}�V��_�m�R��/17
��ԔV�R��/18
�r�_���m�R��/18
�R�o�c�J�T�m�R��/18
���V�ܐm���m�R��/18
�T�Z�E���m�R��/18
���O�d��m�R��/19
���D�x�m�R��/19
�ߔe�����x�m�R��/20
���m�R��/20
�N�c�m�R��/20
�����m�O�m�R��/20
�����V�����R�n�e�[�X�m��/20
�Ғ����n�m��/20
গ��D�m�R��/21
�����V���m�R��/21
�����n�m�R��/21
����n�̎�/22
�{炎n�m�R��/22
�L���o�w�m��R��/22
�����T�X�̗R��/22 |
���C�m�X�~�m�R��/23
�Z�g�V�R��/23
�V���̓m��/24
�L���m�n/25
�͋уm�n/25
����m�R��/25
���W�n�m��/30
���ޔn�m�R��/31
�j�҃m�R��/31
�������m�Ӌ`/32
�v�ē��僈��������
�@�@���ʃT�S�����R/33
�v�Βn���Òn/33
���g�]�|/33
���i�[���j�t�w���ރm�o�|/34
�t�N�}�`�m��/34
�i�P�w�t���m�R��/34
���ʐ�/34
���уg����/35
�w�K�} (�c���}�A�T�[)/35
�p���m�Ւ���/36
��_�R��/37
��O�֍s�ٚ�?�R/37
��樃m����/38
�������x������/39
�����Y�k�{�������v/39
�ΐ��u�K���L�O��/39
���@����/40 |
�욠��/41
�����߃m�蕶/42
�������m�ꗮ����/43
���s���Q�Ҕ�/43
���G��l�B�L/44
�����R����/46
���㒉���蕶/47
���d�L�O��/47
�g��{/48
�g�㉈�v/48
�ܒ���l�蕶/56
���������m�蕶/57
����_�m�z���j�|��/58
�C�U�@�蕶/59
�^�Z���蕶/59
������蕶/59
�^粗N�c��m��/61
�O�Z��m����/62
�O�Z��E�u���W��/63
�V�������_�L (�їف�)/63
�v�q�蕶 (�����@)/64
�V�������_�L (����)/65
�V�������_�� (������)/67
�V����{�� (���ی�)/67
�V���[�����K�L/69
�_�{�I�_/69
�E�q�_�V�z���|��/71
萒�_���L/73 |
�S���A���s���w��ҁu�|�� 20(4)�v���u���O�o�ň���v���犧�s�����B�@�@pid/3547728
|
�ݗt�W���S��������熏��ɏA���� / ���c��Y/p1�`29
�������Y�����\�\(��) / ���ѐ�/p30�`43 |
���쏉���������`�̑m�ܒ��ǒ� / �����S��/p44�`72
�p�������̕��z�\�\(��) / ���K��/p72�`90 |
�T���A�O���Еҁu���Ɠ`�� ��2�N(5)�v���u�O���Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/1483484
|
�잊�x/���
���N�ƋȐ�/���
�~�̐_��/���
��_�V�c���A�̔���/���
����ܔ����|�̏�/��
�X�l�_ / ���R����/p2~3
�B���ƕ��{ / �����Z�g/p4~7
�^�_���ɏA���� / ����F��/p7�`7
�y���B���O�� / ���ΐ��H/p8~10
���H����L / ������/p11~14
�V������/p14~14
������艮 / �������J/p15~15
���ď�B���ɏA���� / ��c��g/p16�`16
�Ȗ��p���̔��ď�B�� / ��������/p16�`17
��X�p���̔��ď�B�� / ����쏁����/p17�`17
|
�B���̓��� / ��ؕq/p18~22
���n��n�ǍՂɏA���� / ��ؐM��/p23�`25
���[�̖�� / �c�����/p26~28
���D�ƕЎR�a�̘b / NM��/p28~29
�瓇�A�C�k�̘b / �y��v��/p30�`31
�암�u�엘�H�v�y�u�v�����H�v / ���V�J��/p32�`32
�����̙B�� / ���钩�i/p33~37
�������d�R���ɉ�����l���̘b / ���q����/p37�`41
��]�R�B���l / �R�{����/p42~47
�잊�x / �c���M�l/p47~48
������V��萂��鎖 / ����C����/p48�`57
�Z���ƕ��� / ���쑼�ƕv/p57~60
���R�����̌`�e�@ / �����m��/p61�`63
���R�����r�����B�� / ����C/p64�`65
�ҏS��L/p66~66 |
�T���A�����Z�g���u�����|�p�p�� ��1�� �v���u�n���Џ��[�v���犧�s����B�@pid/1452710�@�i��
5���ƕ\�L����j
|
��@���X�_�ٍu/1
��@���\�܍��̐_��/14
�O�@�_�ٓa/23
�l�@�����A���q���A�㌩/37 |
�܁@�䑩/46
�Z�@��ʂƊ������/55
���@�Ƃ����/64
���@�_�ى�/73 |
��@�_�ق̋Ȗ���/84
��Z�@�_�ق̋Ȗ���/102
���@���q�̎�/117
���@���̎�/127 |
��O�@�ҍl����/149
��l�@�����̂��ق�/154
�E
�E |
�W���A�u�����|�p 2(8)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@pid/1524786
|
�g�x��ȑO / �܌��M�v/p1~22
���ꂸ����/p23~64
�h���̋��� / ���m����/p24�`36
�{�̈�B����b / ���R����/p37�`47
�̑ԕ����j�̈�Ж�/�k�씎��/p48�`60
���g�����̎��� / �R��W�O��/p61�`64
�O�B�c���̖~�x�� / �|���p����/p65�`76 |
�ɓ������̐��ˑ��� / ���{���Y/p78�`80
����Ƃ��̂ނ̍s�� / �q���~/p77�`77
���n�̎��q / ����lj�/p80~80
�������J��\(�������\��\��)/p82�`84
�����}��
�����̑g�x�� / ���
�����ޏ��̍Վ����x��/p4,5 |
�����v�u���̖��_��/p8,9
�������ښ��\���ʏ�d����/p21�`21
���n�̛����\����
�ɓ������̐��ˑD���x��/p78,79
���ꂸ�݂̚��\�\���`/���c���ʋv/�\��
�E
�E |
�X���A������w���ꍑ���w����u����ƍ����w 6(9)(65) �v���u�������@�v���犧�s�����B�@pid/3549106
|
�Ȓ��n�Չ��Ƙa�������̔�]�\�\(��) / �X���O��/p1�`27
�K�ᕑ�̗��c�ƋȖڂɏA���� / ���c������/p28�`53
�������̌h�ꏕ�����V����V���ɏA����/���V�K�g��/p54�`63
�V�l�����\�\(��) / �����S��/p64~85 |
�ݗt���䏬�V / �ьß�/p86~91
�����ɉ�������S�̖��H�ƔO���y���ݍ̌����\(��)/�R�����j/p92�`107
�b�� 趎��v��/p108~108
�E |
�P�O���A�ɔg���Q���u�����Y�ȏW : �Z���v���u�t�z���v���犧�s����B�@�@�d�v�@�{���\�@�@�@pid/1194473
|
�����j�ݑ��
�܌��M�v����/1
������E�̕@�c�ʏ钩���N��/1
�}��/1
�O�ҁ@(���C�����\���N�����\����A
�@�@�����H�V���j�t�_���g���o��V
�@�@�������V����)
��ԁ@�_�̂��˂�/4
��ԁ@���肱��/5
�O�ԁ@��q���ǂ�/18
�l�ԁ@�썲�ۓG��/22
�ܔԁ@���}���ǂ�/51
�Z�ԁ@���S����/53
���ԁ@���Ƃ��ǂ�/89
���ԁ@���m�g�ւ̙�/91 |
��ԁ@���_/193
�\�ԁ@�܂���ǂ�/194
��ҁ@(���C�����\���N����
�@�@�����l���d�z�V���j�t
�@�@���_���g���o��V�����V����)
��ԁ@�V�l�V��/199
��ԁ@��O�}��/205
�O�ԁ@�����q/208
�l�ԁ@����/247
�ܔԁ@�܂���ǂ�/253
�Z�ԁ@�F�s�V��/254
���ԁ@�����ǂ�/301
���ԁ@���G��/303
��ԁ@�V����ǂ�/453
�\�ԁ@����/455 |
�\��ԁ@���_/500
���
��@������/503
��@�萅�V��/536
�O�@���̔V��/580
�l�@�ݍΓG��/634
�����^(�g�x��萂��錤������)
���D�n�҂Ɨx/(������݉ƁX�}�^�m�Ԓ��͎��k) 677
�g��Ɣ\�قƂ̍l�@/(���ꌧ���}���ْ��^����������) 679
�g���g�x�k�p/(������) 725�@
�g���g�x����/(����^�C���X�V����M�^���g����) 730�@
�g���g�x���S����/(�����V����M�^���c���~�i���傤�Ӂj���k)755
�g���g�x�̌^/(�����V����M�^���c���~)�@758�@�@
�������Ǝ��S����/(���{�m�^�����[����) 765�@�@
�g���g�x�Ɍ��ꂽ��ʊK���x/(���{�m�^�����[����) 777
|
�@�@�@�@�@�����^(�g�x��萂��錤������)�@�u
�g���g�x�v�Ƃ���͖̂{���ł́u�g�x�v�Ƃ������̂ŏC�������B�@�Q�O�Q�R�E�X�E�P�R�@�ۍ�
�P�P���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w 6(11)(67)�v���u�������@�v���犧�s�����B�@�@pid/3549108
|
����̂�Ƃ��ӌ�̈Ӌ`�ɏA���ā\�\(��) / �k����/p1�`19
�����V�������\�\(��) / �]������/p20�`41
���邩��l / �}�y����/p42~59
�����ɉ�������S�̖��H��
�@�@���O�ŋy���ݍ̌����\(��)/�R�����j/p60�`76
|
�Ȓ��n�Չ��Ƙa�������̔�]�\�\(��) / �X���O��/p77�`85
�������q�O�S�`�`�̚����{�I�����\(�O)/ �㐳����/p86�`101
�헤���y�L�̐Ղ�K�˂� / �v������/p102�`104
�O�̑ԓx / �r�cꝊ�/p104~108
�b�� 趎��v��/p108~109 |
���A���̔N�A��J��w���j������ҁu���{���m�摜�I�v���u�������h�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1176565
|
��@��m���s��/1
��@�����a��/2
�O�@�Α��m��/3
�l�@���͑�t�Ő�/4
�܁@�O�@��t��C/5
�Z�@������t����/6
���@�m�����Z/7
���@�m������/8
��@��m�s���m/9
��Z�@�m�����R/10
���@�q暑�t����/11
���@�m���v�M/12
��O�@������t����/13
��l�@����l/14
��܁@���d��m���nj�/15
��Z�@����m���m�C/16
�ꎵ�@�ܑm�����S�k�o���l/17 |
�ꔪ�@���͑�t�S/18
���@���S��l/19
��Z�@�m���U�r/20
���@������t����/21
���@��E��l��c/22
��O�@�m�s����/23
��l�@�Ւq�@�ɑ��m������/24
��܁@������l����/25
��Z�@������t�e�a/26
�@���Ə�l����/27
�@���S�W�t����/28
���@���ꚠ�t����/29
�O�Z�@������t���@/30
�O��@������l����/31
�O��@������F�b��/32
�O�O�@�@���������t�S�S/33
�O�l�@�ÑR�������V/34
|
�O�܁@�哕���t����/35
�O�Z�@�������t�a��/36
�O���@���Иa�����N/37
�O���@���S��l����/38
�O��@�������t����/39
�l�Z�@�@�g�@�y�@���Z/40
�l��@�@�d����W�t�@�k�C�l/41
�l��@���@�����W�t���P/42
�l�O�@��x�W�t�@��/43
�l�l�@������t����/44
�l�܁@�d����t����/45
�l�Z�@�@�_�@�t/46
�l���@���@��l����/47
�l���@�m�����GꟐ�/48
�l��@�͘@�В���a��/49
�܁Z�@�@�̍@�`��/50
�܈�@�ܒ���l�ǒ�/51
|
�ܓ�@�����t�V�C/52
�O�@�V��W�t�@�d/53
�l�@�����t誌�/54
�܌܁@�c���W�t����/55
�ܘZ�@���F�a������/56
���@�^�Ɣ\�����@/57
�ܔ��@�S�z�W�t���Q/58
�܋�@�_�t��苗���S/59
�Z�Z�@�E����l�M��/60
�Z��@�`�R��l�Ǐ�/61
�Z��@�P�K�a���m�\/62
�Z�O�@���Y��l�m�/63
�Z�l�@����a������/64
�Z�܁@���_���ҟZ��/65
�Z�Z�@�����@�u�t�[��/66
�E
�E |
|
| 1930 |
���a5 |
�E |
�P���A�u�����|�p 3(1)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@�@1930-01�@�@pid/1524791
|
�����̎��q�� / ���܌���/p1~5
�}�O�Ǝ�S�R���̂����q�� / ������v��/p6�`6
��O�O�{��S�����̎��q�� / ���O/p6�`6
誊���c�����{�̎��q�� / ���Y�ꕗ/p7�`9
������殐_�Ђ̎��q���\(��㉉��)
�d���Òn�̎��q�� / ����F��/p10�`17
�d���K�یS�_���̎��q���\
�@�@��(�}�ʁ\���Ђ炢�̛���) / �吼�\����/p18�`18
�l���̎��q���\(�}���\�F�a���̔��b���x��)/p19�`19
���Ó卡�Â̏����q / �h�����v/p20�`21
���̎��q�� / ��ؑ���/p22~24
���s�̎��q�� / ���і�/p24~25
�I�ɋ��{�̎��q�� / �����C�O/p26�`28
�ɐ��̎��q�� / ������/p29~31
�����n���̎��q�� / �؈䒉�F/p32�`35
���O�͂̎��q�� / ������/p35�`41
�M�Z��c�̎��q�� / ���V���g/p42�`62
�M�Z���̑�_�� / �����ɒj ;�\�J��/p63~75
��M�Z�ɉ�������̎��q�� / �F�J��/p75�`76
�p���ʎ��q趍l / ����lj�/p77�`79
�p���ʎ��q�̘b/p80~85
�z�㏬��J�̎��q�� / ��r�|��/p86�`88
���n���{�`�̏����q�� / ����G�v/p89�`93
�z���ː��S�x�c�̌܃b���q / ���c��J/p93�`93
�ː��_�Ђ̎��q����� / �X������/p93�`93
�z�O����̂����q�@�� / �ؓc�ޚ��n/p94�`94
���͍����S�哇�̎��q�� / ��n�|��/p95�`96
���U���_�Ђ̎��q�� / ��n�|��/p97�`100
���U���̐_�قƋʐ�̚��q / �R�{����/p101�`104
���U�������q�̎��q�� / ���c���/p105�`110
�������q���q������ / �����C��/p110�`114
���U�Ԓˑ����ۂ̎��q��/�喒�F���� ;
|
�@�@���k�씎�� ;�{��������/p115~122
���U��z���ǎ��q�� / ���p�䐳�c/p123�`127
���U�O��̎��q�� / �喒�F���� ;�k�씎�� ;
�@�@�����t�ÕF ;���`猋g/p128~136
���U�h�m�{�̎��q�� / ���V����/p137�`137
���U�������z�K�_�Ђ̎��q�� / ����F����/p138�`141
��쓡���̎��q���� / ������/p142�`146
�����d���̎��q���� / ���@����/p147�`154
�����萔����q / ���R�h�R/p155�`157
���`�N�ÌS���т�㹌ۗx / �\�o�\�Z/p157�`157
����睌S���_���̎��q�� / �{�c����/p158�`168
���O�n���̂����x�Ƃ�����x��� / �V����/p169�`176
�H���k�S�n���̍��X�Ǖ�/p176�`176
���j�̎��q�� / ������/p177~190
�������k�S�̎��q���̎� / �V���g?/p190�`190
���y�ߋ�̎��q�� / ���䕐�Y/p191�`197
�e�n�̎��q�� / ������v��/p198�`200
��z�͘����� / �k�씎��/p201�`204
���q�����l / ���R����/p205~216
���q�����߂���� / ���쓍�j/p217�`220
�䓪�_���̋L������ / �z���x�Y/p221�`225
���q���̉����j�I�J�l / �|��������/p226�`232
�ŗL�̎��q�ƗA���̎��q / �����Z�g/p233�`242
���q���l / ���c���j/p243~260
���q���̛��� / ���@/p28~28
�����/p262~262
�ҏS��L/p261~261
���R�[�h�쐬�ɏA����/p104~104
�V���Љ�/p262~262
�������J��\�\(�ꌎ�������\�l�\�ꍀ)/p263�`270
���撔殐_�Ђ̎��q���� / �g������/���
�H�c�̍��X�Ǖ��̎��q�� / �|���F����/�\�� |
�Q���A�u�����|�p 3(2)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@pid/1524792
|
���Z�ō����� / ��d����/p1�`1
�����I���b�R�̍��z / ��ؑ���/p2�`3
�M�Z�ؑ\�R���̍��� / ���x��/p4�`4
�������a�����N / ���萳�G/p5�`34
�x�̕������Ɖ���ᢐ��ɏA���� / �|��������/p35�`42
�����Y�p�̕ۑ��ɛ�����l�ւ̈�� / �}�g����/p43�`44
����ߐ߂̙B�� / �k����/p45~64
�P�҂̎� / ���쓍�j/p65~66
�ʐ쑺���X�͂̍Ղ蚒�q�����̋L/p67�`77
�H���k�S���m���̞��V�� / ��ؒ|�V��/p78�`78
�d�������R�̒ǙT / ���c����/p79�`81
�O�͏C�����̋S�� / �P�C�E�E�C��/p81�`87
���n����b�_�Ђ̓c�V�� / ����G�v/p87�`88 |
�F�s�{��r�Ђ̂������Ղ� / �Ж�����/p89�`90
�F��ߒq�_�Ђ̋����_���Ղ� / �Ж�����/p90�`91
�ɘ��̘Ŏ��u���̓��v / ����q�Y/p91�`92
��������O�_�Ђ̌�|�_�� / �ڎ���
�~���@���R�[�h�쐬����/p77�`77
���^��/p93~93
�V���Љ�Z��/p94~95
�O�z�z�[���̗��������V��/p44�`44
���q���j�NjL / ����F��/p92~92
�ҏS��L/p93~93
�������J��\�\(�p�����V���O���㍀)/p96�`102
��������O�_�Ђ̌�|�_�� / ��� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�z�z�[���̗��������V�ā@�����A�ǂ�ȕ��ɂ��Ă͌������K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�X�E�X�E�@�ۍ�
�S���A�u�����|�p 3(4)�v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1524794
|
�����̕��x / �����Z�g/p1~24
�������x������ / ���쓍�j/p43�`46
���i�̂����J / �����|�R�l/p25�`38
���ėڗ��Ɣ��i / �����q/p39~42
���O�d�}�_�Ђ̔���� / �k��Ώ�/p65�`75
����睂̗��əB�͂鑾�X�_�� / �{�c����/p76�`83
�P�˓��C���Γ��̖~�x/p47~55
���ʼnS�\�\(�ٕ��Ɖ��) / �����C��/p56�`57
����ԁX�c���́u�ւ��܂����v / �P������/p58�`58
�������R�� / ��ؕq��/p59~63 |
�ɓ����P�̔n���x / �t�ƕv/p63�`64
���N�̐��l�` / �㌴���Z/p55~55
�V���Љ�/p84~84
�ҏS��L/p85~85
�����������̂��� / �{�c/p83~83
��趎�/p84~84
�O�j�v��/p85~85
�������J��\�\(�l�����������ꍀ)/p86�`90
�������R�Ղ̎R�� / ���
��Â̋N�P�\�\�\��� / �|�؋I�F/�\�� |
�V���A�u �����w 2(7)�v���u�����w��v���犧�s�����B�@�@pid/1583607
|
����Ɛ��(��) / �������Y/p411~428
�Ղ̐_�l�Ƃ��Ắu�݂₤�ǁv / ����F����/p429�`435
�I�ɂ̚��̒[�S / ����F��/p437�`438
���g�̊njς��̑� / ���c��/p439�`439
�@��Ƒ��� / �{�{/P440~440
�u�I�ɂ̚��̒[�S�v�NjL / ���/p440�`440
���V���S�꒚�c���̖K�L / �_�c����/p441�`445
�y�������S���������� / ��������/p445�`447
�悩���ƑٙZ�̔��� / ��a��/p447�`448
��B�ȑő��n�� / ����������/p449�`451
�H�c�p���p�S�{�쑺�n�� /���c���u/p451�`452
��㊂̔N���s�� / �����R��/p452�`452
��O���ދn�S�Ζؒ��э��Y / �؉�����/p453�`453 |
�Z�O�����̘b / ���䕶��/p453~453
�̘b�ܕ� / �_�c���� ;�K����Y/p454~455
沌㒼���n���̖��ԙB����� / ���R���Y/p455�`456
�H�c�p�Y���S�n���A������ / �����F�P�q/p456�`456
���j����Z���u���^ / �L�X�i��/p457�`458
�M�B����܌S����s��̎�{�S / �L��썶�ʖ�/p458�`461
�\�o�H��S��{���� / ����t�m/p461�`464
����ⓚ/p465~466
�{�E����/p467~467
�����{萌W�����v��/p467~468
�����{萌W�V���v��/p468~468
�����{�k�b���L��/p468~468
�E
|
�W���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w�V(8)(76)�v�v���u�������@�v���犧�s�����Bpid/3549117
|
������̕ꉹ�g�D�ƌ��≻�̖@�� / �ɔg���Q/p1�`30
���H�r���l�\�\���ƏW�̌������̈� / ���c���v/p31�`53
�����Ɩ{�n���{�Ɓ\�\(��) / �}�y����/p54�`77
���̌��������\�\(��) / �]������/p78�`102 |
�Β˗����ɏA���� / ���R��/p103�`110
�V���Љ� ���Y�{�T���ɏA���� / �v�� ;�Z�R�M��/p110~112
趎��v��/p112~113
�E |
�P�P���A�{���c�Ⴊ�u���d�R��b : �����d�R���`���v���u���m���Ɂv���犧�s����B�@
(���m���ɑp��, ��2)
�@�@pid/1870265�@�@�@ �{���\
|
�����@
�i�����ɋL���ꂽ���t�́u���a�l�N�\�\����v�A���t�Ȃ��j
�}��
�i���ޗ���\
�n������\
���d�R���������̖K�n��
���d�R���`��/1
I.����/1
(1) ���d�R��/1
(2) ���d�R��̓��F/2
���d�R�ꎵ�ꉹ���`����/5
���d�R�ꉹ�C�\/6
II.ᢉ�/9
1.�ꉹ/10
A.����ɂ���ܕꉹ/10 |
(�C) �G�i���̗�/10
(��) �I�i���̗�/12
B.����ɖ����ꉹ/14
2.�q��/17
III.����Ƃ̉��C��r/31
1.�ꉹ/31
A.�Z�ꉹ/31
B.���ꉹ/34
(�b) �d�ꉹ��蒷�ꉹ�ɂȂ�ꍇ/34
(��) ��ꉹ��蒷�ꉹ�ɂȂ�ꍇ/36
C.��d�ꉹ/39
2.�q��/40
3.����/54
4.����/56
V.��@/59 |
1.����/59
2.�㖼��/62
3.�Ɏ�/65
4.����/66
5.������/79
5.�`�e��/84
7.����/86
8.����/88
9.��㔎�/97
10.���Q��/98
11.�W��/100
V.����/101
���d�R��b �b��/1
���d�R��b ����/1
�E |
�P�Q���P�Q���A�ɓ��đ��Y���u������i�Ǖ����A�����[�v���u�ɓ��đ��Y�v���犧�s����B
�@�@�a�{�@�@pid/2537303�@�@�{���\
�@�@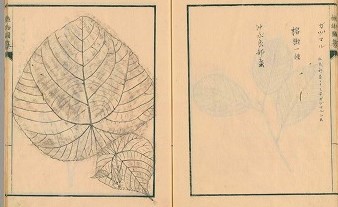
|
|
���A���̔N�A�{�ǒ���̕�,�{�Ǔ��s����u���d�R�×w ��2�S�v���u���y�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1904794
|
����(��)
����(��)
�}��/1
����/1
���A�����J���E�����^/9
���A�E�t�i���E�����^/25
��O�A�C�O�W���[�}�E�����^/35
��l�A�R�C�i�[�E�����^/55
��܁A�R���E�����^/85 |
��Z�A��L�h�[�E�����^/111
�掵�A�Ԓ��̖ڍ��I�E�����^/125
�攪�A�F���̉��E�����^/141
���A�Ì��̉Y�̃u�i���[�}�E�����^/165
���Z�A�i�T�}���E�����^/177
����A�J�ǃJ���[�E�����^/191
����A�V��̐߁E�����^(����Ђ̉�)/197
���O�A�J��Ђ̉�(����Ђ̉�)/201
���l�A��R��/217
|
���܁A����/235
���Z�A�f���T��/247
�Z����
���̈�A�x���̏����E����(���S��)
���̓�A�n�E�����^(���S�O�Z��)
���̎O�A�N�C�`���x�̖��i(���S��Z����)
���^
���d�R��揂������Č���(�����O����)/269
�E |
���A���̔N�A���𑀕ҁu�쓇���������v���u���]���@�v���犧�s�����B�@�@
(���ꎏ�p��)�@�@pid/1823862
|
��b����ɂ���
ᢉ��\�L�@�ɂ���
��b�̕�
����
�� �V��/1
�� �Ύ�/3
�O �n��/5
�l ����/7
�� ����/8 |
�Z �A��/14
�� �l��/17
�� ���/23
�� �ߐH�Z/27
��Z ���/33
��� �l��/38
��� �/39
�㖼��/43
�`�e��/44 |
����/47
����/49
����̕�/53
�⒐
���^
���R�B�M�^���C���C�؈�桌ꗮ�ꛔ��
�C�������I���^�ꉹ���
�N���b�t�H�[�h��������b�U��
�E |
|
| 1931 |
6 |
�E |
�P���A�O���Еҁu���Ɠ`�� ��4�N(1)(35)�v���u�O���Ёv���犧�s�����B p/pid/1483504
|
��A�����_�{�A���X��/���
��A�Ȃ��݂̖�/���
�t�҂�S / �܌��M�v/p2~11
�t�̎��� / �q��x����/p12~16
�̖����̂��� / ��c��g/p17~26
��鏼 / ���R����/p27~31
�u�Ð�I�s���S�����\(���ƓA�o�����ߓ�) / ����P�V��/p32�`38
���\�C�P�r / ���X�؊�P/p39~42
�V�t�F����Ƒ��̈ٙB / ���Ëv��/p43�`47
�l�Â̓�ɉ� / ����������/p48�`50
�����P�� / �i��ꝕF/p51~55
�ɘ��̙B�� / ��c�B��/p56~58
�X�}�����ɏA���� / �I�R��v/p42�`42
���y�ߋ�̏Љ���/
�V���Љ�/p120~120
�������߂̃X�P�[�g��/p47~47
�X�L�[�X�P�[�g��s��A�O���������q�����ɏA����/p55�`55 |
�O�����i�Ԃ̊���/p111~111
������ƚ������Ƃ̔�r���� / �ɔg���Q/p59�`92
�o�_�����̓� / ������/p93~98
�u�G�I�сv�Ɍ��ꂽ�钷����� / �{�R�j��/p98�`102
�����S�����ډ��(��) / �員���F/p103�`104
��������̝̉E�� / �X�L�O/p105�`111
�l�̉��� / ��蒱��/p112~120
�䚠�̒�����Ҙb / ���c����/p132�`138
��̉��� / �����Z�g/p121~125
�r�̊ߋ� / ��苐��/p126~126
���y�ߋ��c���ē� / �L���o����/p127�`131
�킪�W����\(�����̎����_�w��) / �ΖėY/p139�`147
�R�A�̉���܌i / �g�c����/p148�`152
�ɐ��̗������ / �����쎟��/p153�`159
�ӏH���珉�~�̎��R / ��������/p160�`164
�ӂƂ��뗷 / ���J��L/p165~166
�B���̏W / ����F����/p167~171 |
�Q���A�O���Еҁu���Ɠ`�� ��4�N(2)(36)�v���u�O���Ёv���犧�s�����Bpid/1483505�@�@
|
��A�������d�R�̃I���g�x�Ƒ���/���
��A���o�ߚ���/���
�ޗ��p���S�O�֒��́u��_�_�Ёv�Ú�/��
���b笍l / �������Y/p2~11
�O����K�̍e�{�� / ����v�\/p12�`18
�i�R�J�}�h�̖��������Ƃ��ӎ� / ����F��/p19�`21
���B�̐�l�B�� / �������V��/p22�`28
�Ñ�́u���ǐv�ɏA���� / �R��������/p29�`31
�Y�o�����̘ی� / �R��������/p31�`31
�l�̉��� / ��蒱��/p32~36
��̉��� / �����Z�g/p37~38
���剮���剮 / �y������/p39~41
�d���̑������n�U / �Ǔc�F��/p41�`41
����趋L�\�\(�}�O) / ��Í���/p42�`42
�A���a�S�N�̓�揂ƕ��� / ���nj[��/p43�`43 |
�z���̈��A / ���c�đ���/p44~50
�����S�����ډ��(��) / �������F/p51�`53
揋�㉔n���p�� / ���c���H/p54�`58
���Ȃ薟�k / �����쎟��/p59~63
���y�ߋ��c���ē�(��) / �L���o����/p64�`69
���O���Y�əB����T�˂� / ���c�F��/p70�`76
�u�n���v�S�̏�i�\���y��� / �c���쑽��/p77�`78
�����߂̕� / ���ɍ���/p79~82
����ҋ{���� / �M�d�F/p83~87
��������̝̉E�� / �X�L�O/p88�`95
����ʍs�ƙB�n / �c���đ���/p96�`103
�v�o�̗����L / �{���O��/p104~109
�V���Љ�/p69~69
�ҏS��L/P110~110
�E |
�Q���A�{���c�s���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 37(2)(438) �@p50�`66�v�Ɂu���������̉��C�ɏA����(��)�v�\����B�@�@pid/3365080
|
�{���c�s���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 27(4)(320)�`37(2)(438)�ɔ��\�����_���̓���\
| �m�� |
�G���i���w�@�G���j���� |
���s�N�� |
�_�����̃^�C�g�����i�ʔԂ̗L���ɂ��Ă͂��̂܂܂��L�ڂ����j |
pid |
| 1 |
27(4)(320)�@p32�`54 |
1921-04 |
�������d�R�����̖��w�@ |
pid/3364963 |
| 2 |
27(5)(321) ���Ȃ� |
1921-05 |
�������d�R�����̖��w |
pid/3364964 |
| 3 |
27(6)(322)�@ p�`53 |
1921-06 |
�������d�R�����̖��w |
pid/3364965 |
| 4 |
27(8)(324)�@p42�`58 |
1921-08 |
�������d�R�����̖��w |
pid/3364967 |
| 5 |
27(9)(325)�@p14�`26 |
1921-09 |
�������d�R�����̖��(��) |
pid/3364968�@ |
| 6 |
27(12)(328)�@p40�`61 |
1921-12�@ |
�������d�R�����̖��w(�Z) |
pid/3364971 |
| 7 |
28(3)(331)�@p44�`60 |
1922-03 |
�������d�R�����̖�� |
pid/3364974 |
| 8 |
29(2)(342)�@p68�`75�@ |
1923-02 |
���d�R�l�̐M����(��) |
pid/3364985 |
| 9 |
29(3)(343)�@p62�`85 |
1923-02 |
���d�l�̐M����(��) |
pid/3364986 |
| 10 |
29(7)(347)�@p52�`81 |
1923-07 |
������A�����d�R��̌���(��) |
pid/3364990 |
| 11 |
29(8)(348)�@p54�`76 |
1923-08 |
������A�����d�R��̌��� |
pid/3364991 |
| 12 |
29(9)(349)�@p53�`65 |
1923-09 |
������A�����d�R��̌���(��) |
pid/3364992 |
| 13 |
30(1)(353) �@p65�`72 |
1924-01 |
�d�R�̘ی�(��) |
pid/3364996 |
| 14 |
30(2)(354) �@p55�`68 |
1924-02 |
���d�R�̘ی�(��) |
pid/3364997�@�@ |
| 15 |
30(3)(355)�@p43�`58 |
1924-03 |
���d�R�̘ی�(�O) |
pid/3364998 |
| 16 |
30(4)(356)�@p49�`65 |
1924-04 |
���d�R�̘ی�(��) |
pid/3364999 |
| 17 |
37(1)(437)�@p36�`60 |
1931-01 |
���������̉��C�ɏA���� |
pid/3365079 |
| 18 |
37(2)(438) �@p50�`66 |
1931-02 |
���������̉��C�ɏA����(��) |
pid/3365080 |
|
�R���A��y�@�T���s��ҁuj��y�@�S�� ��17���@���S�@�B�L�n���v���u��y�@�T���s��v����Ċ������B�@pid/1226394�@�{���\�@
|
��@��c�ʙB
�K�J�����l�B �� ���S/1
�@�R��l��B �O ����/19
�{���c�t�B�L㉎� �l ?��/53
�����l�����L ��/85
�@�R��l�B ��(�k�)/90
�@�R��l�B�L ��/94
�@�R��l�B㉎� �� �Ԉ�/241
�@�R��l�B ��Z/283
������l�B �� ����/378 |
�R����l�B �� ����/406
��棏�l�s�ƋL ��/412
��@���B����
�ēy�{�����m�B �� �S��/416
�V����B(�m�B��) �� ����/502
�������t���B ��/586
������l�B ��/592
�ď@�욠�� �� �ǐM/601
���O�m�B �� �M�g/616
�i�O��l�s��L �� ����/626
|
�[����l㉎��B �� �/685
��笈ӏ�l�s�� ��k�Q���l��/702
�`�d�R�J�c�ۗ���l�B �� �ˉ_/711
�I���q�������J�c�M棏�l�B �� ����/720
�ܒ���l�B ��/726
�˛�l���B ��/741
��暘a���s��L �� �ϑR/747
�ϐ�l�s�ƋL �� �ϑR/754
�����@�J��Ȕ���l�s��L �� �f�M/766
�E |
�R���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w 8(3)(83)�v�v���u�������@�v���犧�s�����Bpid/3549124
|
�C�������L���ڂ̌×�����ɂ��� / �ɔg���Q/p1�`10
�]�ꂩ�牀���܂� / �u�c�`�G/p11�`20
�{���钷���{�_�̓��ِ��Ƃ��̐����ߒ� / �r�ؗǗY/p21�`60
���ː߂��Y�p�_�\�\(�O) / ���쒉��/p61�`86
�����͈�ɉ����鑽椎�`�\�\(��) / �@�c�P��/p87�`96
���a�ܔN���������ژ^/ ��c�đ���/p97�`104 |
�V���Љ�@��桌�������u�b�ɂ��� / �v������/p104�`105
�V���Љ�@������W���� / �╣������/p105�`110
�b��@�ÓT�ۑ����l�����s�ɂ��� / �╣/p110�`112
�b�� ����/p112~112
�b�� 趎��v��/p113~114
�E |
�S���A�u�����w������ = The bulletin of the Phonetic Association of Japan ��5�N(2)(22)�v���u���{�����w����v���犧�s�����Bpid/1535086
|
�A�N�Z���g�����@��萂������ / ���K�D��/p2�`3
�͈璺��̘N椋y��椂̃A�N�Z���g�ɂ��� / �O���/p4�`5
��22�����L��/p6~7
���ꉹ����̒��� / �Ë`���j������/p7�`7
�����ɂ��L�ߎq���̖��߉� / �X���r/p8�`8
����͂ƌܒi�����̈��u�A�N�Z���g�ɂ��� / �O���/p9�`9 |
����������(3)/p10~13
�{���c�ᎁ�̋Ɛє��d�R��b�\�\(�Љ�)/p14�`14
������������̂����/p14�`14
�R�g�}�^����/p17~17
�����������n���\�\(�؎�p)/p16�`16
�����A�A�������T�A�����ژ^/p18�`20 |
�W���U���A���{�N�ى�قɉ����āu�������x�ÓT��������v���J�����B
�W���A�����|�p�̉�ҁu�������x�ÓT��������v���O�����v���u�����|�p�̉�v���犧�s�����B�@�@�d�v
�@�@�@�@10p�@�����F���ꌧ���}���فF1001059912�@�@��Ït������ �}�C�N���ʐ^�����{
�@�@�@�@��ÁF�����Y�p�̉� ���E���F���a6�N8��6�� ���{�N�ى�� ���������F�����ē���(1��)����@ |
| 1932 |
7 |
�E |
�S���A�O���Еҁu���Ɠ`�� ��5�N(4)(52)�v���u�O���Ёv���犧�s�����B�@pid/1483519
|
�V�����̑m��/���
�V�����V�L / ���V�J��/p2~7
�V��̘b / �����Z�g/p7~13
����誂��ɏA���� / �I�R��v/p14�`23
�d���̎d���S����椂ނ� / �͖{���`/p23�`23
���B�R�c�̔���?�Ɛ�N�� / �͖{���`/p24�`28
����� / �x�c��/p28~30
�Ƃ�ƂƂ�̂� / ���؈ɕ�/p30�`32
��̂� / �䌴����/p33~35
�m�E�ʖ哇�̋w�� / ���M�v/p36�`39
��{�����\���P�����X�I�s(�l) / ��g��� ;�O�����x/p40~46
�ؐS���m�̌��p / 趉�原��/p46�`46
�S���N�̖��� / �c���ȗ��q��/p47�`53
�����S�����ډ��(�\��) / �員���F/p54�`58
�쓇�k�b/p59~74 |
�\�g���̂��I���� / �ɔg���Q/p61�`66
�����̃V�k�O/p60~60
��� / �ˑ܌���/p66~67
��㊘ی��W��(�O) / ���钩�i/p68�`73
��E��揁u骋��̉́v / ��q�s��/p75�`75
������ / �^����/p74~74
���� / �C�䗲/p35~35
���C�V�� / ����������/p13~13
�c���̃T�[�r�X/p35~35
����/p39~39
�a�D�̘b/p23~23
�ɓ��̉���/p58~58
������̟N/�\��
�ҏS��L/P76~76
�E |
�T���A��[�Α����u�����̕���v���u���������Ёv���犧�s����B�@�@�@�@�{���\
|
��@���̂̊ӏ�/1
��@�{���i�̈� ������/10
�O�@�����̜��i�C��ߘb�j ��/17
�l�@�ɏW�̉� 粖���/27
�܁@�䖳�U���₪�� �匓�v��/28
�Z�@�]���̎�́i�A�J�}�^�[��j ��/30
���@���K����� �W��/36
���@�ӕ~�{��
�@�@���i�������̐l���������j �ӕ~��/40
��@�k�J��������� �S���߁B�ɖ�g��/45
��Z�@�Ȃ̖S�� �ɖ�g��/54
���@�C�₩�炠/56
���@���q���O�̎O�{�Վ�/58
��O�@��[��v�߂��� ���P�ߎU�R��/60
��l�@�ɕ����̖��U��/65
|
��܁@��Ȃ��v ������ĕ�/67
��Z�@���D�w��/68
�ꎵ�@�ӂ�������̌��/70
�ꔪ�@�O�Ȃ̎�/79
���@����ȋe �U�R��/81
��Z�@�悾�O���� �{������/84
���@��V�� ������ĕ�/86
���@���炢�����~
�@�@�� ���ɕ����ߍ�c��/90
��O�@�����̐S��/96
��l�@�Y�ꑐ/101
��܁@��ʉ��� ���ɕ�����/103
��Z�@�Ƃ̉Ƃ̉֎q �F�n����/105
�@���〈��� ������/107
�@��̂����������B
|
�@�����C�c�`�N�A�^�c�`�N �œ���/110
���@�v�ǔg�̂�a��/113
�O�Z�@�o����̂���/117
�O��@�ɍ]�����b/119
�O��@�k�R����/121
�O�O�@�_�J�Ɗۖڂ���
�@�@���i�_�J�̈�b�j ��/125
�O�l�@���c�̎萅 ���[�ߑ匓�v��/137
�O�܁@�v�ē�����/140
�O�Z�@�ݍ��� 粖���/142
�O���@�Ԃ̓�/144
�O���@�J��ǂ肵�āi���̂ƒn���j/154
�O��@�É̂������˂�/176
�l�Z�@�͌P�̉���/202
�E |
�W���A�u �h������ 1-8(�h���S��)�v���u�����@�v���犧�s�����B
|
���t������@�@���c�ꋞ�� �@ p.1-3
�u�l�ނƌ���v�]�@�@���щp�v p.2-4
���g�Ɩ����@�@���R���Y p.5-7
�A�C�k���|�@�@���c�ꋞ�� p.8-13
�A�C�k�̓��n�Ɠ`���@�@�����@ p.8-9
�A�C�k�Ƒ����|�@�@���쌪�� p.10-12
�����`�G���̕��g�@�@�����@ p.13-13
�쓇���|�i�͂Â��j�@�@�ɔg���Q p.14-22
��p�ב��̎h�@�@�Ö쐴�l p.23-26
�}�[�V�����l�̕��g�@�@���J�����l p.27-35
�z�����H�̕��g�@�@�����@ p.35-35
�u���W�|�p�v�lj��@�@�������v p.36-37
���g��k�@�@���яȎO p.36-39
���͂�Ɛl��w�@�@�����@ p.39-39
���{�̐Ί펞��ɕ��g�̕��K�������炤���@�b��E p.40-43 |
�l��鎏 4�@�@�R������Y p.44-48
���[�S�[�X�����B���̗� �N���s�i�l��������̋L�@���q���� p.49-57
�p�ڒ� 1�@�@�{�c���` p.59-60
��m�Q���̕ꌠ���@�@���J�����l p.63-69
�R���{�c�N�������_�n�� �̔�������Y���m�E
�@�@���̒؈䐳�ܘY���m�̘_���@�O��,�@�x p.70-72
���䔎�m�ƕs�V�����̖�@�@���c�v�g p.73-76
�����̒؈䂳��@�@�g��,���Y p.76-78
�A�C�E�h����������@�@�����T�� p.78-81
���`�A���l ���@�@���쌪�� p.83-84
�A�т𗬂��@�@�����@ p.84-84
�Y����`�����N�@�@�����@ p.84-84
���{���Â̕��� 2 ���y��̋N���@�@�R�c���j p.85-90
�ȋʂə��܂ꂽ�b�@�@�����@ p.90-90
�����̏W�@�@�@����F���Y p.91-95 |
�X���A���{�}���ً���}���َG���ҏW�ψ���ҁu�}���َG�� = The Library journal 26(9)(154)�v���u���{�}���ً���v���犧�s�����Bpid/11230181
|
���a���N�����������ݘ�����//���ԁ`
�I�B�c粔˔ł̘ŏ�/�����S��/225�`
�A���N�T���h����������/����/228�`
���Ҏ�L���_/�����@��/232�` |
�b��//242�`
�V�������d��//242�`
�c���g��������//242�`
�_�ސ��p���|䇘���Ú����ىĊ��u��//243�` |
�C�O�����َ���//243�`
�V���Љ�//243�`
�����ُT�Ԙ���//246�`
�V�������ژ^//���^�` |
�P�O���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w 9(10)(102)�v�v���u�������@�v���犧�s�����Bpid/�P3549143
|
�C���_���l / ���ǎ玟/p1~18
����͎��ܒ��ɔ� / ���؎s�V��/p19�`32
����̉��ɗ� / �u�c���`/p33~48
�ߐ���揌`�Ԃ̐��� / ���c������/p49�`71
�����̌������Y�\�\�N���C�j�� / �ɔg���Q/p72�`90
�ݗt�W�ɉ�����栚g�̝̂̑J / �X�{���g/p91�`108
�̍��̖{���Ƃ��̔�]�ӎ��̓W�J / ���c���v/p109�`122
�Í��W�̖��͂� / �����S��/p123�`138
�V�Í��a�̏W / �Έ䒼�O��/p139�`154
������_ / ��c�p�v/p155~180
��ڏW�̓����\��҂Ƃ�萌W�A
�@�@�����ԏW�Ƃ�萌W/���Ɍi����/p181�`200
|
�����W�̍l�@ / �V���C��/p201~217
�x�m�J���͂Ƙa�̎j�V / �v������/p218�`236
�����V�h�a�ِ̂̑� / ����䔎O/p237�`263
�r�ؓc�畐�̐��U / �ɓ����Y/p264�`279
�m�Ԃ̋�̘Z��ړ�\�O�[ / ���c���n/p280�`299
�x�l�n�� / �e���Y/p300~314
����炪�t��̈ꒃ / �������/p315�`333
����̈�l�@ / �c���C��/p334~353
�V���Љ�@�Lj����������Z�g����ډ�/�����S��/p354�`355
�V���Љ�@���c�ꋞ������
�@�@������ꉹ�C�_�/�R���疜����/p355�`357
�b�� 趎��v��/p357~360 |
�P�O���A���R������ȁu���F���S�v���u��A���ٛ{�Z�v���犧�s�����B�@�@pid/1881215
|
1.�ޏF���S/1
2.���X��/5
3.���͌�/9 |
4.�͖،�/13
5.�Â̗�/17
6.�x�߂̉œ�/21 |
7.���̂���/27
8.�����Y/31
9.�D��/35 |
10.��������̉S/39
11.�I�������g�~��/43
12.�t��/45 |
�P�Q���A�l�c�ˁk�k��l���u�h������ 1-12 p.32-37�@�����@�v�Ɂu����̗� 6��7�v�\����B
|
�l�c�ˁk�k��l���u�h������ 1-5�`12�v�ɔ��\�����u����̗�1�` 6�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
1-5 p.4-7 |
1932-05 |
����̗��@�@ |
. |
| 2 |
1-6 p.3-8 |
1932-06 |
����̗� 2�@ |
. |
| 3 |
1-7 p.29-34 |
1932-07 |
����̗� 3�@ |
. |
| 4 |
1-8 (�h���S��) p.59-62 |
1932-08 |
����̗� 4�@ |
. |
| 5 |
1-9 �@p.42-45 |
1932-09 |
����̗� 4�@ |
. |
| 6 |
1-11 p.34-38 |
1932-11 |
����̗� 6�@�@ |
. |
| 7 |
1-12 p.32-37 |
1932-12 |
����̗� 6��7�@ |
. |
|
���A���̔N�A�����S�͂��u�����Ƒܒ���l�v���u�����S���i����o�Łj�v���犧�s����B �@26p�@�����F���É��s�}�����@�d�v
���A���̔N�A�u���ꌧ�t�͊w�Z�n���\���N�L�O���v���u���ꌧ�t�͊w�Z�w�F��v���犧�s�����B�@pid/1915339
|
����
�����t������
�{�Z������
����͈�j�v...����������
�}�� �ڎ�/1
���� ���
����/7
���� ����͈�̕���/24
���� ���͂Ǝ��̙͂B��/29
��O�� ���l�̟d�����͈�/32
���� ����/36
���� ���b�u�̎O�R����ƕ���/36
���� ���͂Ƃ��̉e��/41
��O�� ���̗͂����Ǝ��̝͂���/45
��l�� �C�O��ʂƕ���/48
��O�� �ߐ���
���� �͈�̖u��/59
���� ������࣏n�Ɛ���/91
��O�� �{�Z�̐ݗ�/93
��l�� �C�O���{���͈�/123
��� ���_�̐ݗ�/128
��Z�� �ȝ�������鄐��x/130
�掵�� ���q�̛����͈�/135
��l�� ����
�u�p����͈�/140
�{�Z���v�T��/157
��z�^
��A�p�E���̕� |
���T�[��...���������/171
�n���\���N���j����...
�@�@���j�_������/172
���p...�O�c�S����/173
�ق����肵���z�̜��...�ÒJ�Ύ�/175
��ڏ\�L�P�N...�V�܊��/177
���K�̂قƂ�����̂т�...�a�c�씪��/178
�쓇�̑z�o...�j�_���O��/179
��z�^�̓�O...�k���d�h/184
���...���јa��/186
��ڎO�\�N...���_�G��/188
�v�o�̂܂�[�}�j]...���͒��B/190
�ΘZ�N�L����㊎t�͎����
�@�@�����z...������/192
��㊍ĔC�L...�ߐX�K�q/197
��A�����̕�
�p�͈炩��V�͈��...���c���~/212
�����I�O...�Ɖ�����/216
�l�\�N�O�̎v�o...���Ït��/220
�L������܁T��...�����[����/225
�債����Z�̍���...�O�ԗNjV/228
�ݍZ�\��N�̎v�o...�������r/233
��z��...���������C/236
��ڂ���...�R���Ēj/239
�鎞��̎v�o...�L��P�@/242
���ƋL�O�̊���...�c�R����/246
��̑O�̎v�o...��䋭�q/251
����̖����l�Ԃł��肽��... |
�@���o�ߗ䌘�T/253
��z�^...���ܐ��q/258
���ɕ��Ԃ܁T��...�Ýɐ���/262
���̍�...���Ǖ�����/265
�u�v�Џo�v�Q���̋���...��È��A/267
�S�t�ƖS�F��...�c������/269
���̃N���X�\�\��N�g...�{����/275
�v�Џo...�Ô[����/277
�吳���N�x����\��N�x�̍�...
�@�@�����n����/280
�O�A�ݍZ��
���O�Z�N�̕�Z����...���c������/286
�\���җ���
�{�Z�E��/293
�������X��/297
��Z�g��/325
�b��
�n���\���N�L�O�����S�ߋL?/327
�{�Z�̕�
��A�L�O���ȑO/327
��A�L�O���c������/329
�O�A�L�O���c���L�^/330
�������̕�
��Z�n���\���N�L�O�����S�ߕ�/347
�L�O�^���ōH��������/355
�F���^/359
�L�O���Ɲ��x�r�Z��/363
�ҏS��L/364 |
|
| 1933 |
8 |
�E |
�U���A�c���Ԓm�����u�����c�曐�Ӂv���u�c���ԗE�v���犧�s����B�@�@�@���F1962�N�Ł@�Q�Ł@pid/3451297
�W���A�R���i�g���u�R���i�g�W�v���u�V�������[�v���犧�s����B�@pid/1214637�@�@�����F���ꌧ���}���فi�����{�j
|
�l�Ԃ͋��Ȃ�(�ꖋ)/3p
����@�@��L(�O���Z��)/17p
�閾�n��(�l������)/59p
�y�������L(�Z���\���)/105p |
�V��㊎���(�l������)/159p
�X�s���ۂ̎�(�l����)/205p
�ߔe�l���̟���(�l����)/245p
�҂���T��(�ꖋ)/291p |
�M���͂��������(�l��)/319p
����
�}�A�����g���̛���/379p
�����Ȃ���������/397p |
�X�܂ꂽ�֔���̘b/423p
���M���ɏ㉉�ژ^/435p
�E
�E |
�P�Q���Q�W���A�^���� �����i�܂����� �����j���S���Ȃ�B�i���N�T�W�j
���A���̔N�A�u�ܒ���l�r��W�ϖژ^�v���u�ܒ���l�䉓��r��v���犧�s�����B
�@�@pid/1918236�@�K���ō��@�@�{���\�@�d�v |
| 1934 |
9 |
�E |
�R���A��y�@�T���s��ҁu��y�@�S�� ��17���v���u��y�@�T���s��v����Ĕ̂����Bpid/12263941
�{���\
|
���S�@�B�L�n��
��@��c�ʙB
�K�J�����l�B �� ���S/1
�@�R��l��B �O ����/19
�{���c�t�B�L㉎� �l ?��/53
�����l�����L ��/85
�@�R��l�B ��(�k�)/90
�@�R��l�B�L ��/94
�@�R��l�B㉎� �� �Ԉ�/241
�@�R��l�B ��Z/283 |
������l�B �� ����/378
�R����l�B �� ����/406
��棏�l�s�ƋL ��/412
��@���B����
�ēy�{�����m�B �� �S��/416
�V����B(�m�B��) �� ����/502
�������t���B ��/586
������l�B ��/592
�ď@�욠�� �� �ǐM/601
���O�m�B �� �M�g/616 |
�i�O��l�s��L �� ����/626
�[����l㉎��B �� �/685
��笈ӏ�l�s�� ��@�k�~���E�l��/702
�`�d�R�J�c�ۗ���l�B �� �ˉ_/711
�I���q�������J�c�M棏�l�B �� ����/720
�ܒ���l�B ��/726
�˛�l���B ��/741
��暘a���s��L �� �ϑR/747
�ϐ�l�s�ƋL �� �ϑR/754
�����@�J��Ȕ���l�s��L �� �f�M/766 |
���A���̔N�A�{�Ǔ��s���u�쓇�p�l�v���u�ꐽ�Ёv���犧�s����B�@�@pid/1453472
|
������������̛���/1
��@������ �쓇����
��@�쓇�����̗̈�y���c
�O�@�쓇�����̓���
���̌�{�I����/8
��@����
��@���{���I�́u���v�́u���v��
�O�@�u���v�̏���
�l�@�u���v���u���v�`�p��
�܁@�M��̓�
�Z�@�B���̓�
���@���y���ތ�
���@����萂������
��@����̉��C�{�I�l�@
��Z�@���_ �j�W�̌ꌴ
���L
���̌ꌴ���ɏA����/63
�u�����v�̌ꌴ�ɏA����/68
��@�A�b�R��
��@�Ï���萂������
�O�@�Ï��ȑO�́u�����v
|
�l�@�u�����v�̌ꌴ
�A�_����萂���l�@/87
�쓇�����̏W�s�r/102
��@�͂�����
��@�̏W��̌v�c
�O�@������艂���哇��
�l�@�哇�k���̕ˌ�
�܁@��� �R������
�Z�@�{�Â̓��X
�����L��/133
��@�����̖��i
��@�����n�q
�O�@���l�̈��A�Ԃ�
�l�@���̎q��
�܁@���l�̂Ȃ�͂�
�Z�@���̂Ȃ�͂�
���@�_���
�����̗ܐ�/150
�쓇��������V����
�@�@���{�M�Ñ�̕��K/160
���������ɉ����遨 |
�@�@�����Ƃ̍\���y���K/177
��@����
��@������铍�
�O�@��n���̔r�u
�l�@���Ƃ̕���
�܁@���[�̙��c�y�p�r
�Z�@�Ɖ������̏���
���@�Ɖ����z�̏���
���@�Ɖ����O�̏��ݔ�
��@�Ƒ���̋V���j�T
��Z�@�Ɖ��̕ی�y�Ӗ�
���d�R�Q���̓y���H�Y/207
���ԓ��L��/235
�g�Ɗԓ��̘b/241
���d�R�̖��/256
���d�R�̘h�̉�/269
���d�R�����̉Y�D�̉�/282
���Ԑ߂ɏA����/291
�|�x���̋���/305
�ɕ������I�s/330
���ޏ��b/370
|
��@�͂�����
��@�T���e�B�����[
�O�@���⓰
�l�@�_�l�Ƃ��Ȃ�_
�܁@���M
�Z�@�����t
���@�ی�
���@��X
��@�q���
���ޖ��`�l/392
��@�z���C�g�}���i���l�j��
��@�����i�����j��
�O�@���ތ�̌n��
�l�@���ސl�̐����y���j
�܁@���_ �C�l������
�Z�@���� �E�Ƃ�铎��E
�@�@�����i�E�K��
�C�₩��l/405
����
�E
�E |
|
| 1935 |
10 |
�E |
�Q���A�Ì����ۂ��^�������u�������w�F��c�߁i��E���j�v���u �R�����r�A�i��O�v���犧�s����B�@�@�{���\
�@�@�@�i��j�Fpid/1317188�@�i���j�Fpid/1317189
�S���A������w���ꍑ���w��ҁu����ƍ����w 12(4)(132)�v�v���u�������@�v���犧�s�����B
pid/3549173
|
�D�L���ꌤ���j / ���ؕ�/p1~19
�����L����������j / ꝓc������/p20�`34
�`�S�L��\�䕨�ꌤ���j / �ΏZ�莟/p35�`53
�_�c�����L�y�ѐV�t�W�̌����j / �⍲��/p54�`69
揋ȥ���������j / ��X�����O/p70�`92
�ߐ����������j�� / �d�F�B/p93�`113
�̕���r�{�����j / ��笌���/p114�`130
�ߏ������j�̈�� / �ߓ����`/p131�`143
�ėڗ������j / �ߌ���/p144~163
����̌��� / �c���C��/p164~185
�`�G���o�������L�O���S
�@�`�G���o�����搶�̎v�Џo / �o�`�G���[/p187�`191
�@�`�����u�����搶������ / ���q�R�O��/p192�`194
�@�����搶�̓쓇�ꌤ�� / �V���o/p195�`200
�@�l�Ƃ��Ẵ`�G���o�����搶/�����ؐM�j/p201�`211
�@�`�G�[���o�����搶�̎莆/�s�͎O��/p212�`220
�@�`�G�C���o�����搶�ƃA�C�k��{/���c�ꋞ��/p221�`227
�@�`�G���o�����搶�Ɨ�����/�ɔg���Q/p228�`243 |
�@�C�R���{������̉����搶�̎v�o / �ؑ��_�g/p244�`245
�@�@��V���O�X��W���p�j�[�X��ɏA���� / ��������/p246�`247
�@�[�l���A�ɉ�����`�G���o�����搶�̐���/���Y���l��/p248�`251
�@�`�����o�����搶�Ƣ���D� / �H�R���v/p252�`255
�@���c�`�����h�z�e���ɉ����搶��K�˂� / ����`��/p256�`257
�@�����`���C���o�����搶�̍Ō�̒������z?
�@�@�@����l�͂܂������Ă��/���얫/p258�`260
�@�`�G���o�����搶���z�^��l�͂܂������Ă��/�g��r�U/p261�`271
�@�`�G���o�����搶�̒Ǔ����̊��� / ���R�F��/p272�`282
�@�����`�����o����������_���ژ^ / ⨌ܕS��/p283�`293
�@�W�T��O�L / �Γc���V��/p294�`299
�b�� �V���Љ�/p300~302
�u���{���{���u�v / �X�{���g/p300~301
�u�ݗt��a�u�l�v / �X�{���g/p301~302
�b�� �{�E����/p302~306
�b�� 趎��v��/p306~310
�b�� �v�^ / �����S��/p311~314
�E |
�S���A�c���Ԓm���� �u��������L�N�Ӂv���u�c���Ԓm���v���犧�s�����B�@�@pid/1236982�@�@�{���\ |
| 1936 |
11 |
�E |
�Q���A�M�����Ǖ����u�����Ƒܒ���l�v���u�h���@�ю��v���犧�s����B�@�d�v
�@�@�@�@�@�@��l�O�S�N��恗�����ՎQ�q�L�O
�S���A�O���Еҁu���Ɠ`�� ��9�N(4)(100)�v���u�O���Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1483566
|
�������j�ׂ�㉔n���� / ���V�J��/���
���S�̛�� / ���c���j/p1~4
�W�̘b / �܌��M�v/p5~7
���n�R���Ƃ��̕��� / �������V��/p8�`22
�P��萂��鑭�M / �ێR�{/p23�`30
���q�̋R�@�ƃn�J�} / �{�{����/p31�`35
�ցk�����l��萂��ē�O / ����������/p36�`39
�O��ɉ�����L�O���V�O�ƕ��@ / ���Y�חY/p40�`42
�u��Ԃ�v�̉� / ����쏁����/p43�`46
���̑��M�Ƌ��̙B�� / �����c��/p47�`51
�����̏ۊ��������[ / ��Ït��/p52�`54
�}���̂��ƂȂ� / ����F����/p55�`61
���趍l / �L��썶�ʖ�/p62�`78
���l�̕����\�\(�R���p�k�����S) / �q�c����/p79�`89
��˂̖j���ނ菬���ɂ��� / �]�n�C/p90�`93
齂ƊD�` / �N�쏟��/p94~96
�|�� / 趉�原��/p97~100
�~�[�T���̖� / �쑺�B�l/p101~103
�쓇�əB�͂鐶�B�퐒�`�̐� / ������/p104�`106
�R�ł̎���Y�ꂽ�� / �V�c�l��/p107�`112
���̌Ռ�� / ���c�v�g/p113~119
�䂪���ɉ������n��㔂̍��� / ��c��g/p120�`
���k������k/���c�ꋞ��
���`��S�̑����t / ����t�M/p136�`145
㩂̞鎮�ƕ��� / ���c���u/p146�`156
�Ӗ� / ���s���O/p157~159
�����{�ِ����̙d�� / �k����/p160�`162
�O�n�̒��ҕw�� / ������/p163~166
�Â̓��b / �������ݎq/p167~170
�̘b趍l / �R��������/p171~178
�����R�W�̘̐b / 萌h��/p179~185
�B���E���{�Ɍ��͂ꂽ������̂���[�C��] / ���Ëv��/p186�`189
�M�Ր_���̕ˌ� / �{�R�j��/p190�`195
���h�̕��Ղ� / ���؎O��/p196~199
�V���́k�T���Q�C�l�Ɩk�̎��q / �v����/p200�`204
���H�̖������x�ɂ��� / ���{�c����/p205�`214 |
���w�����̃v������� / �����Z�g/p215�`217
�u���h�����v�̎��ȂɏA���� / ���钩�i/p218�`222
���ِl�`���̂���[�C��] / �{��������/p223�`225
�Ԝ��C�������L�{��?�� / ����v�\/p226�`233
����O�S����̐w�L�͔��d�R����� / ���쎢/p234�`234
�l���i�Ɣ����u / �{���c��/p235�`237
��a�\�O����ᢌ@ / ���ΐ��H/p238�`241
�H�̏ނ̉� / �����C��/p242~243
���N�̎O�̓s�� / �ؒJ����/p244�`245
���̖����̖� / ���R�b�]/p246~249
�\�o������F�̊C / �����W��/p250�`252
�F���y�` / �[�x�d�Y/p253~258
�����Ɠy�n�ƌ��t / �����Z��/p259�`262
�Z�\���Ђ̘b / ���J��L/p263~265
���܋r�J�̗� / �g�c������/p266�`268
�R���y�n�̒n���I�l�@�\�\(�����p�����S) / �R����v/p269�`279
�����u���i�n���v�ɏA���� / �c����/p280�`284
�i�F�ƌ܊� / �ґ�����/p285~289
���R��趋L / �F�J�C����/p290~294
��Ғ��Ԃ̋K�� / �L�ꋱ��/p295�`304
�����x�@���x�̔_���̔��� / �c���đ���/p305�`307
���{�̔_�ƂƔ_�� / ��������/p308�`314
�V�����s�̎И� / �V���C��/p315�`320
�I�B���P�����̏Z�g�x / �J�{������/p4�`4
���͂�ЂƂ��T�݁\�\(���F�s�}�S) / �c���~��/p30�`30
蹍Ղ�\�\(���F�s�}�S) / �c���~��/p93�`93
�͓��̘b / �����原��/p100~100
�̘b�̃��s���[�O / ���s���O/p170�`170
���j�́u�Жڂ̕��v����݂� / ��ؔ�/p321�`321
�N��q�˂� / �c���ȗ��q��/p315�`323
�V���L�O�Ղ��V������/p324~325
��\�d���y���x���/p7~7
����ɉ��閯���{�u�K��/p279�`279
�V������/p189~189
��L/p326~326
�Ô��p�s�r�̎v�Џo / �K�c�Q�S/p322�`325 |
�T���A�u�Z�̌��� 5(5);5���j�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1098702
|
��i���l�W//2�`25
����/���R��/2�`4
�����/���V��/5�`7
���햟��/���鈣����/8�`10
���̏t/���쒼����/11�`13
������/���{����/14�`16
�����s/���A/17�`19
��̗z��/�ēc�Y��/20�`22
�ӂ�O�X�̉�/�ؖ�N�v/23�`25
�Z�̖̂{���Ƃ��Ă̕�����/
�@�@�����J��@����/26�`35
�s���s���ɑ�/�y��P��/36�`41
��R�q���̖��̊ӏ�/�F�s�쌤/42�`50
�ӔN�̒������g���̉�/
�@�@���g�c���r/51�`54
�`�e�����ɂ���/����v�U/55�`62
��i//64�`87
�t���O�l/�y������/64�`65
�킪�q�𑗂�/�a�c�R��/66�`67
������/�����C��/68�`68
���V��/���{�喳/69�`69
��\���/�e�r��/70�`70
�k��/�|��������/71�`71
��̌���/��������/72�`72
����/�剮�d��/73�`73
����/�O�c��/74�`74
�����̌Ós/���P����/75�`75
��/�o�c���O��/76�`76
�J������/��藲��/77�`77
���ɂ�����/�݂������q/78�`78
|
���t趉r/����嗲/79�`79
�t��/���㑽���q/80�`80
�����炬/�R�p�q/81�`81
��q�̐���/�ܓ�����q/82�`83
��s�ٝ�/�唺�v�g/84�`84
?�j���[�X/����A��/85�`85
���̂ӁA����/���{���̎q/86�`86
�q�̕a�ޏt/�o�Ӗ쏻�q/87�`87
�̒d�ܑ�/���R�ē���/88�`94
�̐l��B�\�I�єV�\/�Έ䏯�i/95�`103
���N�����̘ҖK/�ɔg���Q/104�`115
��r/�� ���]�/118�`120
���]玁�̈��//121�`133
���̎v�o/���]����/121�`125
���]�q���Â�/�����ؐM�j/125�`126
���]�q��/�V���g/127�`128
���]�J���q�̉��Џo/���q���b/128�`132
���]玁�̂����Ђ�/
�@�@�������Y�q/132�`133
��i//134�`153
��/���R�ē���/134�`135
����/�J�C/136�`137
��펞����/���@���Y/138�`139
�k������˂�/���Ĕ���/140�`140
�X��ދ�/���{�Ǒ���/141�`141
�킩����/�����p�q/142�`142
�߉r���/�������q/143�`143
�V���U��/��c����/144�`144
�t��/�ؓ��▾/145�`145
�s�̓~/������/146�`146
|
�������t��/��萞Ĉ���/147�`147
�q��/���쐅��/149�`149
�q��M��ʂ�/�ĎR����/148�`148
��������/���c�Q�g/150�`150
�S�ɂ��������/�ǖ엜��/151�`151
�F�Ɋ�/�����p��/152�`153
���E��i/�㎁/166�`167
�I�҂̌��t/�k�����H ;�g��E ;
�@�@���O�c�[��/168�`168
�̒d���]/���c����/154�`159
��������i�Z�́j/�����ԔV��/116�`116
���R�Ȏp�ԁi���j/�o�c����/160�`161
�̒d�ߏY//162�`163
�̒d����//164�`164
�ݗt�W�̑�������
�@�@�����\���//170�`192
�����E��ӁE�`�E��桁E�ӏ�/
�@�@���V���C��/170�`179
�C熁E���@�E�̊i/
�@�@�����p�䐳�c/180�`184
���ٓE�v/�������d/185�`192
�Z��/�k�����H �I/194�`198
�Z��/�g��E �I/199�`203
�Z��/�O�c�[�� �I/204�`206
�ҏS�P�^//208�`208
�\��/�ޒJ���l��
�莚/����ďM
��/���P����
�E
�E |
�T���A�ɔg���Q���u���N�^���̗��K�v�� [�ɔg���Q] ���犧�s����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002087482
�@�@�@�@���L �u�Z�̌����v���a11�N5������������(2���j
�U���A�u�����ÓT�Y�\����v���u���{��������v���犧�s�����B�@�@�u�������{�����v��12�����a11�N6�� �����@�@�d�v
�@�@�@11p�@�����F���ꌧ���}���فF1001692183
|
�g�x��̘b �܌��M�v
�g�x�̓Ǝ��� �ɔg���Q |
�䎌�E�G�E�����Ȃ� �����[����
�����̑��ŋ� ��Ït�� |
���x��������� �����Z�g
�E |
�U���A�u�A�̂Ɣo�~ (2���j)(2)�v���u�o�~������v���犧�s�����B�@�@�@pid/1526532
|
�k���ƘA�̍� / ���
���Z�̎捇���_/�e���Y/p1�`17
�k���ƘA�̍��ɏA����/����v�U/p18�`32
��D�ƙ{�/ �r��`�Y/p33~44
�ܒ���l�M�̔o�~�A�̏�/���c���v/p45�`51
�ꒃ�̏��˓�� / ���{ ;�쓇/p52~55 |
�u���{���v�u�ƘA�鏴�v�y�сu�}�g�ⓚ�Ɯ���V���Ƃ�萌W�v�ɏA����/�y����/p56�`61
�����̔��� / ���ؑ���/p62~65
�@�L�A�̒�����(��)/�ɒn�m�N�v/p66�`69
趎��_�����]�\(�A��萌W)/���q������/p70�`72
�ҏS��L
�E |
�W���A�{���c�Ⴊ�u�����y�� 25(8);8���j p2�`7 �����y�����s���v�Ɂu�����d�R��揂��V�܁i��j�v�\����B�@pid/11004575
�X���A�{���c�Ⴊ�u�����y�� 25(9);9���j�@p18�`28�@�����y�����s���v�Ɂu�����d�R��揂̊ӏ܁i��j�v�\����Bpid/11004576
�@�@�@�@���@�����ł̌f�ڂɂ��Ă͂P�O������P�P�������������Ԃ������̂œ��e���m�F���ł��Ȃ������B�@�Q�O�Q�R�S�E�P�V�@�ۍ�
���A���̔N�A�ܒ����u�����_���L�v���u�剪�R���X�v���犧�s�����B�@pid/1257261�@�@�@�d�v
|
�����_���L/1
��������/123
�_���W����/149
��k���˒n�W/189
�����W/265 |
�ܒ���l�B�L����/295
�ܒ���l���q�ژ^�����/379
��@����/381
��@���q�̕�/402
�O�@���^���̕�/517 |
�l�@�؎��̕�/521
�܁@趂̕�/547
�� �ܒ���l�B�L�������/560
�� ��㉉��/574
�Z�@��L/577 |
|
| 1937 |
12 |
�E |
�U���A�u����y�� 4(3)�v���u����y�����s���v���犧�s�����B�@pid/1489877
|
���
�U���o���X�E�l�O���g�̌���Ɠy�� / �Lj䜨��/p1�`11
�����ȉߊ�^ / ���t�c�~/p12~23
�i�s�ɉ������C������̍l�����x / ���{����/p24�`31 |
�����y����茩���鍂�V�������̖k��� / ��Ð���/p32�`48
���l����̔Ќˌ��\(��) / �����F�u/p1�`16
�b��/p49~58
�E |
�V���A�F�ˎj������ҁu���썑�j�p ��2�S �v���u�F�ˎj������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
|
�������Ƃ��Ӓn���ɂ��ā@�n粐��q��
�������y��ᢐ��̎p �R�����W ��
�`����Ԏ����ɏA���� �F�h�� ��
�F�˂ɉ����鋽�y���x�̈ꌤ���i��j�@�쑺�m
ꎕj���䌾�s�^�i㔁j�@�@���P��@���Ì��݉Ƒ�
|
�@�@�����ꌧ���}���� ���T�e���ʎ����� SK/200.5/N48/2 1002089405 �ݏo�֎~ �@�@���s�N�F1937(���a12).12������m�F�v �m�F�ρ@�Q�O�Q�R�E�T�E�P�X�@�ۍ�
���A���̔N�A�ɔg�搶�L�O�_���W�ҏS�ψ���ҁu�쓇�_�p�v���u�������Ёv���犧�s�����B�@�@�@�@pid/1824724
|
�ʈ˕P�̖��...���c���j/1
���������̏o��...�܌��M�v/23
�����哇�̍��X�Ɣ\�C�̐���...������/80
�R���̌��...�{������/95
�ɕ�������ʂ����V����N���̍s��...���ܑS�/110
�~��(�{)�̌��`��萂��錤��...�{���c��/124
�����ɉ����閯�Ƃ̍\���Ƒ��̔z�u...���܌�����/144
���d�m�𒆐S�Ƃ����n���̈�l��...���܌���/155
�{�Ó��̖���...�����Y/176
�g�x �썲�ۓG���̌^...�n������/190
�{�Õ����𒆐S�Ƃ���...�o�V�B�q/211
�A�N�Z���g�Ɍ��ꂽ������Ɠߔe��...���s���a/223
���s�̊i�u�҂�v�̚��������̊��p�ɏA����...���@�����P/242
��㊂ɉ����鋴��ᢒB...�_�c���P/259 |
�����Ø҂̓y�n���ʖ@...�{���ċP/264
�A��趍l...�����[����/277
�A�C�k���l��...���c�ꋞ��/309
�u�Ï��v��\�͂����N�����̕��z�ɏA����...���q�i��/321
���ɉ�����g�s���i���p�ɏA����...���{�i�g/342
�����댤���O��...���钩�i/363
�p�C�t�^�E�t���^�J�E�����O�h�E...���q��i�c/376
�Ö[趋L...�R�鐳��/402
���ߖ���...�x�����C/415
�̕���...���ܐ��q/419
�ɔg�N�Ǝ�...�Ɖ��G/426
�ɔg���Q�搶�_���������ژ^...���钩�i/430
�ɔg���Q�搶�N��...���钩�i/451
�E |
�Z���̔N�A�u�ܒ���l���M�̗����_���L���{�n�߂Č��J�v���u�F�ˎj������v���犧�s�����B
�@�@�@�@�@�@�@�u�썑�j�p�v��2�S����,�[���b�N�X�����{
�@�@�@�@�@�@�@�@���ꌧ���}���� ���T�e���ɂP K/18/Ta21/ 1001812187 ���y���� �ݏo�֎~ �@�u�썑�j�p�v��2�S�ł͏�������Ă��Ȃ������B�@�ۍ��@ |
| 1938 |
13 |
�E |
�R���A�M�����ǍƂ��u�ܒ���l : �ܒ���l�O�S�N�剓����C�L�O�v���u�h���@�ю��v���犧�s����B
�@pid/1230939
�V���A���������L�O�{��ҁu�����_���L �ܒ��� �v���u���������L�O�{���v���犧�s�����B
�@�@�@����: �ܒ��ǒ��l�B(�����S����)�@�@�@�@�@�I�v��39-��44�̕���������ɂ��Ĕ��s
�W���A �ɔg���Q���u���Ȃ�_�̓��v���u�y�Q���@�v���犧�s����B�@�@pid/1461681�@�@
�@�{���\�@�@�d�v
|
�i���j���{�����{�̕����c���j�搶�ɕ���
��
�ڎ�
���Ȃ�_/1
�쓇�Ñ�̑���/27
���N�l�̕Y���L�Ɍ��ꂽ�\�ܐ��I���̓쓇/73 |
�����Ȃ���l/145
�����Ďт�ᢐ�/175
���������/209
�e���l�̐�����/227
���d�R�̂܂����V��/241
���K�}���ƃ��[�A�\�r/253 |
�A���S�Ɍ��ꂽ�N�C�L���[�x/265
�S�E趘b/277
�×����̕������l�@���āu����āv��ᢒB�ɋy��/289
������l/319
�쓇���j��s���ɂ���/367
�̐_�lp439 |
�@�@
�@�@�����Ȃ���l/p153��� |
|
�P�Q���A�u����y�� 5(1/2) �v���u����y�����s���v���犧�s�����B�@ 1938-12�@/pid/1489879
|
���
�C���h�l�V�����ʂƖ���萌W��������������
�@�@����⬁u�~�n���I�v / �ڐ�q�V�U/p1�`8
�����̉��فA���x�ɏA����(��) / ��Ð���/p9�`43 |
�[�߂̐ߋ���i�s���y�ߋ� / ���Ԛ�/p44�`52
�p���E���╨�̏o�y��Ԃ�������� / ��ؐ��Y/p53�`61
�b�� 趘^�\�V���Љ�\�{�E�����\���̑�/p63�`71
�E |
���A���̔N�A�ԏ��q��, �H�t���ҁu���N�ޑ��̌��� �㊪�v���u��㉮�����X�v���犧�s�����B
�@�@pid/1256388
|
��@�ޑc�B��/1
�̕P/3
��/58
��@�\��Վ�/61
���@����\��Վ�/63
��/120
���@�G�R�\��Վ�/125
��/184
�O�@���J�j��/191
��@�����j��/193
��@�����j��/193
�O�@��ďj��/195
�l�@�n�_�j��/197
�܁@���j��/198
�Z�@��囒�j��/199 |
���@�̊ԏj��/199
���@��j��/200
��/201
�l�@�����_��/203
���@�����{��/205
���@����]��/223
��O�@�����j��/250
��/251
�܁@�w����/255
���@����w����/257
���@�G�R�w����/271
��/277
�Z�@���̌�/279
��@���̌�\�O��/281
��@���̌�\�㐶/313
|
��/335
���@�Z�B���_��/339
���@���d�{�����{��/341
���@�e�R���{��/357
��O�@���č�/369
��l�@�����{��/388
��܁@����{��/415
��Z�@�O���{��/429
�掵�@���S�{��/436
�攪�@�V�剤�{��/460
���@�͓V�j�{��/467
��\�@�����c��{��/480
��\��@���N�����śa�{��/496
��\��@�_�m�s��/503
��\�O�@���g�{��/507 |
��\�l�@�����{��/519
��\�܁@�R�Y�{��/525
��\�Z�@��O�{��/529
��/536
���@趕�/545
���@�����掌/547
���@�ӋS�H���L/556
��O�@�����Z��/563
��l�@�Ӑl���k�S/566
��܁@�Ӑl�ŗ�/569
��Z�@�����J/570
�掵�@�O�_�j��/573
�攪�@�}�����y�S/577
��/578
�E |
|
| 1939 |
14 |
�E |
�Q���A�u����y�� 5(3/4)�v���u����y�����s���v���犧�s�����B�@ 1939-02pid/1489880
|
���
�o�^���ƃ��~�̔�r�A���̓y���i�ɂ���/�Lj䜨��/p1�`5
�g���׃��~���̏o�Y��萂��镗�K / ���쒉�Y/p6�`17
�����̕��x�A���قɏA����(��) / ��Ð���/p18�`45
�o�ߚ����w�l�̓��n / �a�c�i/p46�`53 |
�s�i���d�z�\�J�������t�G���X�͎��̂��Ƃǂ��\/��萏�v/p54�`66
A���m�̎���ɓ��ւ��ɔ\�Ë鎁�̏��� / K��/p67~82
���Ԕ� / �Lj䜨��/p83~84
�i�k�B�l�_��Ί펞���Ւ������� / �{�{���l/p85�`86
�b�� 趘^�\�V���Љ�\�\�{�E�����\�\���̑�/p87�`91 |
�R���A�u�h������ 5-2 �v���u�����@�v���犧�s�����B
|
���̘b�@�l�c�� p.1-7
���̖��́@�����Z�Y p.8-11
�̓��n�@��Ð��� p.11-13
�ÎR�A���ؚ��O�Y���㉇��̂��Ɓ@ p.13-13
|
������@�O���|�� p.14-19
����̍��ȁ@����F���Y p.20-23
�哯�]�̐���D�@������ 1 p.24-25
����̃C�V�K���g�[�@�{������ p.26-31 |
�A�C�k�ƃT���Z�E�E���@�͖�L�� p.32-34
�[�����杁@�L�X�i�� �����@�@ p.32-35
���W�Ƃ��Ă̓��c�_�@���c�v�g p.36-38
�E
|
�S���U���A�����O�Ⴊ�S���Ȃ�B�i���N�F�V�S�j
�T���A�u���|�t�H 17(9) �v���u���|�t�H�Ёv���犧�s�����B�@pid/3197728
|
�ڎ��J�b�g / ����\����
���͐��� / �����d��/5�`6
���m�l����ߑ� / �������N/6�`8
�W㉂ɂ��� / �����z/8�`10
�W�����v���Z / ����C�V/10�`12
趎i�P�J���ؑi�� / �H�c�J��/12�`15
�ωJ�؉ԓ����� / ������/15�`18
���Y���������� / �ǖ�ǎO/18�`20 |
壂̂Ђ���(㉂ƕ�) / ��������/20�`22
���@�I���Y / �y��s��/22�`23
���̌��Е� / �c粏��Y/23�`24
�̐l���ΊC�l / �O�D�B��/25�`27
�D���ƌ���(㉂ƕ�) / ���c�e��/27�`29
�������̖�� / �Ό���/29�`31
���d�R���̏t / �ɔg��N/31�`33
����Ə��� / �{�V�r�`/33�`35 |
���q�V�S�̛{������ / ���N����/35�`37
��DूƖ�����裍��k�� / ���c�� ;���c�N�� ;
�@�@������o�u�� ;�_��F�� ;�F�욢�� ;
�@�@�����{�M�A/142�`170
���Y�t�H //40�`41
��
�E
�E |
�P�O���A�ɔg���Q���u���{�����̓�Q : ���Ȃ�_�̓����сv���u�y�Q���@�v���犧�s����B�@�@
�@�@pid/1463515�@�@�{���\�@�d�v
|
���ɑウ��/p1
�̐_�l/p439 |
�N�����̘ҖK/p467
�e�������_/p499 |
���܂݂�l/p523
����/p1 |
�@�@�@���T�Q�U�@�ʐ^���T�Q�U�@�ʐ^�@���T�Q�U�@�ʐ^
���A���̔N�A�����l�ފw��E���{�����w��������ҁu�����l�ފw����{�����w��������I��
��3�� �v���u�����l�ފw��E���{�����w������������v���犧�s�����B�@�@�@�@�@pid/1115072
|
��㉁@�o�Ȏ҉e��
��
�ڎ�
��������/1
�o�ȎҖ���/2
�v���O����/4
����S�ߎ���/8
���J�u�����^/13
�������U�@�l�ޛ{���茩����
�@�@���u���W���E�y���[�����ɏA��/13
�����q�g�@�y�w偙B���ɏA��/14
��ʍu�����^
�_�������@�đ͐ς�����j���
���ǐM�v�@���{�V�Ί펞����חނɂ���
���l���j�@�_�ސ��p���L�ˈ�ՊԂ̌�ʂɏA��
�ъ@��@�䕨�Α������i���ɏA��
�K�R���i�@�_�ސ��p�e���E
�@�@����m�{�_�L�ˏo�y�̔����Ȃ�y��ɂ���/26
���֗Y�@��t�p���쑺ᢌ��̖ؐ��i�����ɏA����
���������@�Õ��̐⛔�N��
�I�����Y�@�l��Ɛl��S���{
�����N���@���J�И��ɉ�����Y�̊������܍�
�Ό������@���{�_�����z�̖����{�I�l�@
���퐴���@���{��揂̈ꐫ��
�ыԌ�@�A�C�k�؊���̋N���ɏA��
���敐���@�A�C�k�̌��n���؋�u�n�i���v�Ƒ��n����
|
�v�ێ���F�@�k�C������������̑��ɉ�����o�Y�y���̈��/51
�����N�v�@�A�C�k�̖ؔ�D�i���`�b�v�j/57
���F�h�@���N���ԐM�ɉ�����\��/59
�Lj䜨�ρ@�i�s�ꉹ�C�g�D/63
�O�g���\�@�g���ׂɕY�����陊�M/66
���쒉�Y�@�B���ɂ��g���׃��~����
�@�@���t�B���c�s���E�o�^�������Ƃ̌���/68
���Y����@�p���I�����̃V���}�j�Y��/71
���{�M�A�@�j��萂��铌�옱�ט���b/74
���R�p�i�@��VꀓŊ��҂�铎��l�ޛ{�I����/77
���R�p�i�@�H�c�p�l�̐l�ޛ{�I����/78
�R�{���@�������Ðl�̎菶����ɏA��
���쌪���O�O���@�ޏF���M�͏Ȑԕ�ᢌ@�̌Ðl���ɏA����/84
�Z�ʍ썶�ʖ�@�ɓ�����@
�@�@����瓇�o�y�̐瓇�A�C�k���⍜�̐l�ޛ{�I����/85
�{�c���`�@�����l��铎�/90
��萏�v�@�i�s�{���Z���w�l�������W�{���T/92
�{���x�U�@�i�s�אl�̐l��^/94
���c�O�Y�@�l�Ϗ��ϊ��R�͂�
�@�@�����t����萌W�y�l�ވړ��Ɵ����y���t���̉e��/96
����ۑ�w�ޖ֎x���������x�u�����^
�]��g�v�@�V���ȕS�˕_���߂ɉ����錳���
�@���i���k���Õ����̈⚬/99
���c���Y�@�ޖւ̖���/106
�������v�@�Ðl��ɏA�Ă̊nj�/110
�E |
|
| 1940 |
15 |
�E |
�T���A�u���R�Ȋw�Ɣ����� 11(5)(125)�v���u�����Ȋw�����فv���犧�s�����B�@pid/2376738
|
1.�J�����_�[ / �A���{��/2�`3
1.��m�ɢ�}���O���[�u���T���/���q��/4�`12
1.�J���V�J�̏K�����Ǝ��ؖ@/���c����/13�`14 |
1.�J���V�J(���j�f�ڂ̕��)/�S�P���Y/15�`15
1.�H����̍̏W����� / ���}����/16�`17
1.��W�{�̕ۑ��ƍ������� //18�`19 |
1.�{�ٜb��趕� //20�`20
�E
�E |
�P�O���A���{�A���w��ҁu�A���w�G�� 54(646)�v���u���{�A���w��v���犧�s�����B�@pid/2360595
|
���E�L�E�����̂��ѕa�A�����̍ޗ�.II../ ���� ����/373~377
�J���c���O�T�Ȃ̐��F�̌���,IX..�J���b�N�X��j�`BOOTT�̌�������ɂ�����\�����G�� / �c������/378~388
��}���O���[�u��y�[�n�Y�A���m�ُ퍪�m���^�j�A�C�e / ���q��/389�`403
Aegilops ovata L.�m�lਓI����铃g�����l�{� / �����C��/404~412
������ԃj�A���A��铃m�d���x���\���X���ꍇ�j���P���g�D�����@�m���p����
/ ���c��/413�`421
趘^ //422�`423
���^ //424�`426
��� //25�`26 |
���A���̔N�A���@�������u��y�@�ǖ{�v���u�@�R��l�r��v���犧�s����B�@�@�@pid/1047364
|
���ҁ@���j
���́@�ב��̐��U/7
�ב��y�n�y�ю���
�a���y�ѐ��З���
�o�Ƌy�яC��
�~���Ɛ���
�l�\�ܔN�̋���
�ł̓���
���́@�ŋ���ᢒB/27
���n�̎���
���h�̎���
�嘩�ŋ��̋��N
��F���̊J��
��F���̊�ƍs
�嘩�ŋ��̏��`��
�O�ł̓�
��O�́@�@�R��l/53
�a��
�c�N����E���̈�P
�o��
�b�R�֓o��
���J�ւ�誓�
�{����K
�����J�@
���։���
�匴�k�`
���厛�u��
�������l�X
�a�̋y�ѐ�W
���Q����
�����y�ѓ���
�Ō�̔��Q
�݂˂��鉶��
|
�P���@�ēy�B����c/109
�͂�����
������F
�V�e��F
���a��t�E���^�W�t
�P����t���̂ق�
�i���j���M�m�s
��l�́@��c���猻��܂�/121
���c������l
��O�c�R����l
�]���ꗹ����l
�掵�c��棐��g��l
�i�O��l
�[����l�ƈȔ���l
�ܒ���l
�V�q���t�����l
�E�L��l�Ƌ`�R��l
萒ʏ�l�Ɠ��{��l
�@�F��l
�s�r��l
���ҁ@���`
���́@�ēy�̋��`/191
�ɖ@�R��t�Ɉ˂�
�ēy�̏@��
�t������
���˂��S�E�_�E��
����
���\�ɘ�
�\�ɂ̖{��
�\�ɂ̟ēy
���S����
���s����
�O�Ŏ҂̑ԓx |
�O��s�V
�����E����
���ƔO��
���́@�M�̛���/224
��
���\�ɘ�
����Ȃ����̂�
����Ȃ���
��O�́@�����̟ēy/242
���ς̐��E�Ƃ��Ă̟ēy
�ɞٟēy
�`������ēy
���l���̊�铂Ƃ��Ă̟ēy
��l�́@�M�̊l��/259
�~�]�̐���
�������ނ�S
��ӐS
�[��������
�܂�����
���S�Ɖ]�ӂ���
�M�ւ̍s�
�M�̔|�{
��́@�O�ł̈Ӌ`/284
�A�`�̔O��
�얳���\�ɘł̈Ӌ`
�ō��ŏ��̔O��
��Z�́@�M�̐���/300
�l�Ԋ����ւ̐M��
�M�I�ȉƒ�y�юИ�
�O�ŐM��肷�隠���M�O
�掵�́@�O�łƓ��{���_/321
�@�R��l�ƔO�Ō욠
�d�ꐫ�ƔO�ŐM�� |
��O�ҁ@����
���́@�����v�f�Ƃ��Ă�
�@�@���O��/329
���́@�M������Â���
�@�@��ਂ̏@�h�Ǝ��@/336
��O�́@���@�̍\���y�ы@�\/344
���@�Ƃ��ӂ���
���@�ɉ����鋳���{��
�@���V���̈Ӌ`
��l�́@�M�C�{��
�@�@���K�v�ȏ�����/357
�Œd
�{��
�ʔv
���ؓ����y�ы��֕�
�s�ɕK�v�ȏ������
��́@�M�C�{�@
�@�@���Ƃ��Ă̍s�V/382
���{�I�ȏC�{�s��
����s��
���۔O��
��Z�́@�l���̍ő�V�X/398
���ՂƑ�Ƒ���`
�ՏI�̗p��
���V�y�єN��@��
�掵�́@�c��ւ̕s/415
���Ղ��~
�{��S
����̈Ӌ`
�攪�́@�M���i�̕��@/428
�ʎ��O��
�C�{�T�Ԃ���ފ�
�ēy�����L�̏C�{�� |
���A���̔N�A��p���{�����Ǖҁu�V�R�I�O�������� ��4�S�v���u��p���{�����ǁv���犧�s�����B
pid/1114820/1/1�@�@�Q�l
|
���@���ݒn�y�r���i/1
���@���v/2
��O�@��r�ΊC�����уm�A���{�I���e/4
��@�{�����ђn��m����y�r�y��/4
��@�{�����уm�A���Q���{�I�Q�n/6
�O�@�A���Q���m����/7
�i�C�j�@�k���i���ђn��j/7
�i���j�@�����i�����n��j/8
�i�n�j�@�왽�i�a�ђn��j/9
�l�@���Y�A���m���/10
�܁@���Y�A���m�����`/10
�Z�@���Y�A���m�A�����n�I�n��/12
���@�{�����уm����/14 |
��l�@�{�����уm�V�R�ی왽��g�V�e���j���ӃX�x�L����/14
��@����A���m������E���j����A���Q���m����/14
�i�C�j�@�߂Ђ邬�m�{�M�����n�g�V�e�m����E/14
�i���j�@���Ȃ͂܂����m�{�M�����n�g�V�e�m�k���E/16
�i�n�j�@���ڂ��i࣐S�j�m����/17
�i�j�j�@�Ƃ��܂����m�Q��/18
�i�z�j�@���킽���������ǂ��m�Q��/18
�i�w�j�@�Ƃ������m����/19
�i�g�j�@�����m�Q��/19
�i�`�j�@������܂�i�Վ��j�m����ᢈ�m���V/20
��@�{�����уj���e�n���eᢌ��Z�����^���A��/20
�i�C�j�@���������i�V�i�j/20
�i���j�@�����͂��i�V�i�j/21 |
�i�n�j�@���₭�܂߂Â��i�V�i�j/21
�O�@�{�����ђ��j�L�p�A���K���V�N沕x�j�����X���R�g/22
�l�@�E�v/23
��܁@�V�R�I�O���g�V�e�ی�X�x�L����j�A�e/24
��Z�@�V�R�I�O���g�V�e�{�����ѕۑ��m���@/24
���l
��r�ΊC�����уw�m��ʘH/25
����/1
����/1�`14
���^
��r�ΊC�����ѐA���ژ^/��1�`17
�E
�E�E |
���A���̔N�A�m���@�z���t��ҁu�^�����p ��4�S (�����ɐs�����O����)�v���u���{�R�m���@�z���t��v���犧�s�����B�@�@�@pid/1687793
|
�Ή��ƔO�ł�����́E�O�c�㐐/1
�Ή��̗D�k�ǁ@���ԗ���E�蜨�c/23
�ܒ���l�E�����S��/31
�O�ł̒�P�Ɉ炭�܂ꂽ�Ή��̎l�u�m�E�s���P�Y/45
���{�s�҂ɂ��āE�����C�V��/59
|
�V��w�쑺�]����x�E�������/63
�����ېV�Ɵēy�@�m���\���ɐ_���a���̌욠�^���\�E�L������/75
�@����̐M�Ƙa�́E�f���m/99
�����ېV�ƛ{�V��m���E���쏇�F/129
�ېV�̏}��҂ӋΉ��m�܍l��l�E���엹��/175 |
|
| 1941 |
16 |
�E |
�P�O���A�u�C 11(10)(121)�v���u��㏤�D������Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1557482
|
����̊C / ��v�ۈ���/�\��
�ň�Ƃ���ǂ���\��㉛����\���v�ƒ��/p1�`4
�����m�̌��� / ���c��/p6~8
�ޏF���s�̈�� / �x�S�v/p9~11 |
�j��ɉ�������{�Ɠ�m / ���{�F����/p12�`15
�v�P�^ / �a�ҏt��/p16~19
�ň�̈�� / �҉i/p20~21
蜂�ԓs���X�N�� / �|�c����/p22�`25 |
��㊓r��\�� / �r�蒉�F/p26~27
��㊂̉��قƕ��x / �����Z�g/p26�`28
�E
�E |
�P�O���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 47(10)(566)�v���u���w�@��w�v���犧�s�����B
pid/3365209�@�@�d�v
|
��� �y���̎Đ_������_��C�^�R
���ԐM�����̈Ӌ` / �{�n����/p4�`12
�����Ɛ��̐_ / ���c���j/p13~18
�c�̐_��R�̐_ / ����F����/p19�`35
���u�T�l / ��؞��O/p36~59
������揂Ɩ����M�̌i�V / �P�c�r����/p60�`76
�����_�̐M��--�������Ȑ��̒n�������̎����Ƃ���
�@�@��/�����O��v/p77�`82
�����q�_�̌���--���Ƀ^�^���𒆐S�� / �Βˑ��r/p83�`90
���X�̒n�_���� / �{�{���/p91�`98
�������{�Ɍ��ꂽ�閯�ԐM��--���̕��ꏴ/�������O/p99�`105
���`�ɉ�����q�̐_�̐M�� / ����t�M/p106�`108
��\�O��l / ���R�M����/p108~112
ⴐ_�ɏA���� / ���ؐ���/p112~113
���d�M�ɏA�� / �p�c����/p113�`118
|
�����̉̐_ / ��Ït��/p118~120
�y���̎Đ_�ɏA�� / �j��a�Y/p121�`129
�֏�̐_�� / ���q�v/p130~136
����Ύ����㏑ / �a�c���v/p137�`143
�q���_����--��X�p�܌˒��n�� / �\�c����q/p144�`151
�����ɉ�����G�r�X�_�̐_� / �N�c����/p152�`164
���c�_�̖{���ƌ`�� / ���c�v�g/p165�`174
�����_��萂��鏔��� / ���욢��/p175�`199
�̐_�l / �員���F/p200~212
����̖\��--���p�䐳�c�搶"
�@�@���_�ى̌���"�ɂ悹�� / ���i����/p213�`214
�r�ؗǗY���Z�����R���{�\�䕨�� / �p�쌹�`/p214�`216
����̂Ɩ�����ɂ��� / �R��O��/p216�`218
[���{���{�̓��ꐫ��nj� / �P�c�r����/p218�`219
�ҏS��L(��̊��z) / ���萳�G/p220�`220 |
���A���̔N�A�����Z�g���u���y���x�Ɩ~�x�v���u�������[�v���犧�s����B�@�@ pid/1238774�@�@�d�v�@�Q�T�O�O�~
|
��
�~�x�̌���
�͂�����/3
�~�x�̖��i/5
���ǂ����/8
���ǂ�ꏊ/11
���ǂ�l�X/14
���ǂ�S��/18
�V�~�̉�/23
�ւ��ǂ�̒��S/28
�����Ƃ�/35
���ǂ�̑g�D/41
���ǂ�̉�/50
���̉���/57
�ߏւ��̑�/68
���ǂ�̐U/76 |
�~�x�Ɯ���/87
�ی�Ɯ[��/95
�~�x�̕���/101
�~�x�Ǝ���̐F/111
��������̗��s/118
�����̗��Q/130
�H��Ɩ~�x/138
�_���ƌ��/145
�V�����X��/155
�~�x�̌���/166
�~�x�̋L�q�̕��@/177
�~�x�̍ŋ߂̕���/183
�����x�Ɗ|�x/201
�ɐ��x����ɐ�������/216
�ŗL�̎��q���ƗA���̎��q��/229
�]�̓��̓V����/247 |
�V�l����N�Ə��N���Y�p/260
�����܂�/269
�z���̓c�q��?����/284
�����p��揕���Ɩ�揌�/299
�I�����Z�S�N��j�����y���x/305
���nj�ٖ��/316
�_����ق̐V�X��/323
�_���̔N���s���ƌ����^��/329
���Ɛ̂̑��ŋ�/342
����/351
���
(��)�@�����N�Ԃ̐V���̖~�x
(��)�@�啪�p���n���̖~�x
(�O)�@���i�̉̕���ŋ�
(�l)�@�x�R�p���쒬�̖鍂�s��
��� �������g |
���A���̔N�A�i�c�����Y, �哇����, �O�c���ɑ����� �u�푈�Ǝ� ���S�v���u�R��[�v���犧�s�����B�@�@
�@(���㎍���� ; ��1�S)�@�@pid/1128819/1�@�@ 13640�~
|
����
�_�ւ̍���E��㐅��/95
��C趑����E����сE�r�c����/32
���E���O�сE��]���Y/12
�M�������E����сE����S��/112
��]����E���l�сE�����y�V��/53
�t�̓��̏����E���O�сE��ƌ���/19
㔝D��ʐM�E�]����ۑ��Y/72
�w�E�a���C�Y/102
���l�сE������/80
��e�E����сE�쒷�����v/48
���S�E���c���U�g/100
�C�䂩�E���蕐�Y/86
��Z�E�O�c�����U/106
���̏�E�R�V����/109
�����̉��A���͑嗤�����E����сE�R�{�a�v/38
�˂��ЁE����сE��c�Ξ�/68
�ΐ؏�̉́E�哇����/104
|
�����E����сE�����V�g/5
��p�E�i�c�����Y/90
���݂�E�ސؓN�v/46
�ɂ̗U�ЁE�g�c���n/24
�]�_
���O�́w�������L�x�E�ǖ�W/122
����Ǝ����_�E�ۓc�o�d�Y/144
����g�C�c���l�̉^���E�Β��ێ�/151
�J���c�T�ƝDुE�����E�����`�F/162
�p�g���Dॎ��l�E�i�c�����Y/177
��桕]�_
�V�^���b���{�̉ߒ��E�E�C���w�����E�f�C���^�C�@�V�c����/203
�Dूɂ��āE�V�������E�x�M�C/244
��桎���
�h�i�ȗV�сE���l�сE�C�����J�K���g�E�}���A�[���E�����V�����/248
���E����сE�e�I�h�I���E�V���g�����@��{�z�Y�/254
�c���̂��߂Ɂi���O��j�E�r�G�[���E�W�����E�W���E��/257
��L/260 |
���A���̔N ����Еҁu������W �I�����Z�S�N�Łv���u�R��[�v���犧�s�����B�@�@pid/1128843
|
�ɓ��M�g/9
����씪/27
���`ꝔV��/41
���萴��Y/49
����\�O�Y/71
��]���Y/85
���q����/91
����S��/107
���������Y/131
�����V�g/147 |
��������/159
�y�����/177
�H�R�C�O/183
���c���U�g/191
������/209
�팩�P�g/231
���i����/251
�n�����ӎq/291
�{�V����/299
�O�b�����U/315 |
�X�c����/333
�R�V����/341
�R�{�a�v/359
���؏d�g/389
�g�c���n/395
���c��/6�m2
�C�V����V��/6�m3
�ɓc�k�e�c�l/6�m4�E5
���䐳/6�m6
���������Y/146�m2�E3 |
���c����/146�m4�E5
�y�勓/146�m6
���V��Y/298�m2�E3
�����u��/298�m4
�R���O/298�m5
����N��/415
��L/427
��i�ڎ�/429
�E
�E |
|
| 1942 |
17 |
�E |
�P�Q���A�{���ØZ��,���䒼�q�G�u��m�̐A���v���u���{�Ёv���犧�s�����B�@pid/1720158�@�@�{���\
�@�@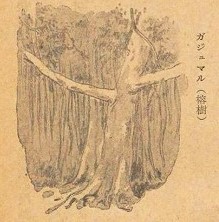
�@�@���䒼�q�G |
�����^���̏��́A���Ď������A��m�e�n���A������ɂ킽���āA�����A�����ɂ��邢���\�N�Ԃ̌����̈�[�ł���Ƃ���́A��m�̎�v�ȐA���ɂ��Ă̌������A�킪���������N�̂��߂ɁA���������Ȃ�Ƃ��A���̎Q�l�ɂȂ�ƍl�ւď��������̂ł���B�^��m���A���E�̎�����ɂł��邱�Ƃ́A���܂����ɂׂ̂�܂ł��Ȃ��A�Ζ����A�c�A�āA�����A�S���A���q�����X�A�d�v�����͂قƂ�ǖ����Ƃ����Ă����ʂ�������ɂ��邪�A����A�A���ɂ����Ă��A�H�p�ɂȂ���́A�Ƌ�A�ƍ��ɂȂ���́A��p�ɂȂ���́A�Ϗܗp�ɂȂ���̓��X���A���ꂱ�������ǂق�A���푽�p�A�����ɂ���A�݂Ȃ��ꂼ��̎�����ȂւĂ�B�^�i���E�X�s�j�^���������N�B�^�@���m�̓V�n�́A�傫���Ђ낪��B���݂̈ӋC�ɂ��ӂ�āA���N�̖����̗͋���������Ђ�����҂��]��ł��B���̐��E�̕�ɂ��A��S�w�́A�J�Ă����A���ɂ킪���{�̕K���s�s��铐��͂ł���̂ł���B�^�@�哌���̍��{�I���݁A��邬�̂Ȃ���b�A�S�N�A��N�A���\�ݔN�̑�v���A�{�����炢�������Ȃ�Ƃ��A������Ƃ��낪����A���ɂƂ��Ė]�O�̌ł���B�^�ȂفA�{���̕��͂ɂ����ẮA�{�e�I�Y���́A�M�S�Ȍ䋦�͂��������B���L���Ă����ӈӂ�\����A
�@�@�@���a�\���N�l���@�@�@�@�@�@�@�ъw���m�@�{���ØZ
|
|
����
���q��
�� �`��/3
�� �ÁX���q/13
�O �������q/21
�l �����q/24
�� ���̑��̞��q/26
�ʛ���
�� �`��/34
�� �h���A��/36
�O �}���S�X�`�[��/40
�l �}���S�[/43
�� �p�p��/45
�Z �p���̎�/47
�� �o�i�i�̐F�X/52
�� �p�C�i�b�v��/56
�� ���̑��̉ʕ�/58
�S������
�� �`��/65
�� �p���S���� �ꖼ�w�x�A�S����/68
�O �K�^�y���`���ƃo���^/74
�l ���{�l�̃S���͔|�̌��c/76
���ؗ�
�� �`��/79
�� ���h/80
�O �K�h �ꖼ�G��/84
�l �c����[ �ꖼ�c��]/87
�� ��� �ꖼ���O�i���o�C�^�[/90
�Z �`�[�N/92
�� �}�n�S�j�[��/94 |
���E�Z�ؗ�
�� �`��/95
�� ���h[ �ꖼ��h]/97
�O ����[ �ꖼ����]/103
�l �^�}�����h��[ �ꖼ�_�ʎ�]/108
�� �}�`����/110
�Z �N���g����/112
�� �R�J�̎�/114
�� �R�Z�E�̎�/115
�� �g�o(�f���X)/116
�\ ���̑�/118
�� �H�`�Ȃ̎���
�� �`��/121
�� �O���o��/123
�O ���I��/126
�R�[�q�[��/129
�J�J�I��/133
�L��������/137
�A�J�V�A����
�� �`��/141
�� �����V�}�A�J�V�A �ꖼ���b�g���̎�/143
�O �A���r���S���̎�/146
�l �J�e�L���A�J�V�A[ �ꖼ�����Z�̖�]/147
�� �����c(�t�@���l�V�A�i�E�A�J�V�A)/149
�Z �r���}�l���̎�/151
�ؖ�������/153
�Վ���
�� �`��/155
�� �K�W���}��(�Վ�)/157
�O �A�J�E(�ԞՎ�)/159 |
�l ��x����/161
�� ��t�S�� �ꖼ��x�S���̎�/163
�Z �o��������/165
�� �}���o�Վ�/167
�}�j����/169
�T�C�U����/171
�J�|�b�N �ꖼ�ؖȎ�/173
�o���T�̎�/175
�t�N�M(����)/177
�e���n�{�N(�����{)/179
�Ԗؗ�
�� �P����/181
�� �Ή���/183
�O �����/184
�l �́X��/185
�� ꏞS��/186
�Z �^�E�I�K�^�}/187
�� ��S�@/189
�� �C�J�_�J�d��/191
�J�i������/193
�ʒE���i�J�~���c�f �j/195
�W���[�g/197
�}���O���[�u(�g����)
�� �`��/199
�� �I�z�o�q���M/204
�O �S�o���m�A�V/206
�|��/209
�W�����O��/211
�I��/215
�E |
���A���̔N�A�ɔg��N���u�ӂ邳�ƕ���쓇�̏�M�v���u���{���_�Ёv���犧�s����B�@�@pid/1043839
|
��M�̙ɗx/9
�X�o���͏���/23
�т̍���b/35
�k�Ƒ��/48
��C�̋��v/55
��㊂̉�/67
�쓇�̖��/79 |
�Ǔ��Y���L/91
��̌Q�̓n�鍠/104
���⓰����/111
�܌��̊C/132
�G�͌���/144
�Y��������r/158
�̂��S�ӗH��/167 |
�Ǔ��̋�/183
��ւ̜���/193
�E���̋G��/199
�h�̉�/206
᱗��~�̖�/214
���Ă̖�̊C/226
���샖������/233 |
���H�̘b/264
�D�J/271
�̌�/276
�����̉H��/286
�쓇�̐A��/312
�E
�E |
|
| 1943 |
18 |
�E |
�S���A�ɔg��N��,������G�G�u�l���̂����v���u ������������v���犧�s�����B�@�@pid/1169786�@�@�{���\
|
�͂�����/1
�R�r�̑�������/3
���Ɖ_��/10
�������/23
�R�r�̉�/31
��̖�/41 |
�G�̘b/50
���I�̗�/60
���̐_����/75
�̋ʂ�ގ������b/84
��J/96
���������̘b/102 |
���@�g�Ђ̖V����/113
�l���̂���/129
�������l/135
�ɂȂ��j/145
ꝂɂȂ��j/158
��a�_�̘b/169 |
�A���p���̂���/178
�S�̊≮/185
�_������/198
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�c�Ӑ搶�җ�L�O�_���W���s��ҁu�������y�_�p : �c�Ӑ搶�җ�L�O�v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B�@pid/1069246
|
���E���{���m�@�c������/1�`3
���E���{���m�@��������/1�`2
�c粐搶�җ�j�́@�哌���a�فE����������쎌�@�{�铹�Y���
�c粏��Y�搶�N��/1�`5
���a�\���N�����E�\/6
�c粏��Y�搶����N�\/1�`5
�}��/1
�}�O���������Ўu��_�Ђ̕��قɂ��ā@
�@�@�����̖����{�I�����E���Ð��V/3
�ߗ��̎Z�@�ɂ��āE�Έ䕶�Y/27
���m����@�̐��_���N���̞ٕ��E�o�_�H�h�a/45
�\�Ă�ׂ����揁E����ʘY/63
�哌���Y�\�̗ގ����E��썂��/89
�G�C�ƃT�G�Y���̃t���Q�E�n���X�E�G�b�J�[�g/97
���َ撲�|�̗��l�B�i�������َj�e�j�E�����G/105
�\�㕽�ϗ��̛��p�ƖM�قւ̜�p�E�������Y/125
�}�C�����l�j�ي핪�ޖ@�̌����Ƃ����V�����x��
�@�@���ي핪�ޖ@�E���c���Y/139
�M�ٖ��̎�̏��@�y�щ����ɏA���āE�����d��/157
�̕���̉��ٓI���o�E�͒|�ɏr/175
�O�����̃T�n���ɏA���āE�Ð�p�m/193
�ٛ{�O�͂̊J�łɏA���āE��粐��Y/213
�M�ق̐����Ɖ̎��̃A�N�Z���g�E���c��t�F/245 |
�������̌��ՁE���V����/287
���وȑO�E�����Z�g/363
��ق̊nj��g�D�@�����ɂ��āE��ؐ��U/373
�������N�ٕ��E�v����/387
�x�ߕ��ق̈Ӌ`�ɂ��āE��Ɉ�/433
���k�n�����Ԃɍs�͂�鉡�J�̗�E���c����Y/443
��㉹�ٞي�V�̔֓J�ɏA���āE�َR�b��/457
�x�ߌÓT�Ɍ����鉹���V�E������/491
�_�W����٘_�l�E��結���/505
��ٍl�E�H�ˌ[��/531
���ٔ����ɂ��āE�ь��O/571
�u�ۈ珥�́v�S�����@���E���́u�N����v���_�l�E���o�v�Y/603
�O���̖Ƌ���E���c�����Y/643
ⵋȞق̓W�J�Ɍ��隠���I�����E���c�l��/653
���{��揂̐��@�������^��_��
�@�@���i���{��揌`�Ԙ_�̒��u�Ȍ^�ҁv�j�E���c�Ï�/669
���d�R�Ö�揉̎��̌����E�{���c��/717
�M�قƗ������قƂ̞ٗ��I萌W�E�R�����W/741
���ՐV���̎l���q�ɂ��āE������/789
��̔�u���l�E���ਐb/823
�匴�ɉ�����H�̘_ुE�g�c�P�O/845
���M�җ���/1�`7
���ŕ/8 |
���A���̔N�A���J�����u���{�������x�̌����v���u���X�v���犧�s�����B�@�@pid/1125406�@�@�d�v
|
�u���{�������x�̌����v�ɂ��āE�`沋g/2
�����Ɣ��d�R
�����Ɣ��d�R�E���J��/4
�����̕��x/5
��O�x�i������ĕ��E���Ă��Ԃ��j
��˗x�i�������E�l�G�����E���d���ݍE
�@�@�����s�����E�ݍΓG���j
���x�i�l�|�x�E�����Ԃ��E�ԕ��߁j
�[�x�i�x��V��E���₮�E���Ȃ�E�J���O�x�E
�@�@���_�璹�߁E���Ԑ߁E�O���_�߁j
�������r���E�i�i�{�j
���d�R�̕��x/31
�ɗx
�}�~�h�[�}
���̕�
��������
�z�N��
�X�|��
����
�ڏo�x��
�L�C�����̗x
�Ì��ʐ�
�h�̒���
�����s�E������/62
���d�R�Q���E�ɔg��N/96
�ɗx
�}�~�h�[�}��
��������
�h�̒���
�w���K���g����
�q��S
���̕�
�z�N��
��������
�X�|��
�ڏo�x��
����c��
���d�R�̖�揁E��R�_��/108
�V�_�悵�q����̒lj��E���J��/123
�����̋��y���x
�����̋��y���x�E�Ԗ����Y/132
��̕�
���y���~�x
�U�x
�����˗x
�����x |
�}����
�o���o�x
�r�x
��ː_��
�n�x
�蔏�q�x
�F�P�x
���v��
�呾�ۗx
�ו��x
�Ԋ}�x
�����̖�描Љ�E��R�_��/155
�B����
�P���ۗx�i�����E�ܞ��E�l�߁E����j
�����̗����L���E������/166
�F���Ɖ����哇
�F���_�x���̑��E�Ԗ����Y/174
��˗x
�t�Z�x
���ۗx
�F���_�x
�z�x
�V���K�o�o�T��
����
�}�x
������
�ËՐ�
���~�x
�v����~�x
�\�̕�
�����哇�E�Ԗ����Y/196
�������ǂ��i���ڂ���́E���炵�₰�E���݂����j
�ߓc�܂�
��x��
�j�����
���X�̉�
�������̉�
����ߐ�
��˂Ɠ��k
��˂̐_�����x�E����P�t/212
���ё�
�_��x
���q��
���U���q
���k�n���̋��y���x�E����P�t/229
�ҍ��x |
�c�A�x
�S����
�x
���x
���i����Ԃ�j
��x
�H�c����
�u�ᚠ�v�ɏA���āE����P�t/248
���i���̈Ӌ`
���y�F
�\�����o
�u�ᚠ�v�i�i�{�j
�u�ΔȂ̍��X�v�i�[�T�j
�x�̕��i��
����
���N���y���x�u�P�R�^�[���v�E�O���@�q/266
�ؐ��r�搶�Ƒm���̂��Ƃǂ��E�O���@�q/273
�t���B�E������/277
�u�t���B�v�̎���
�c���̏����
�Ɖ����x
�t���̉Ƃ̒��x
����ɒ��雔
�Ís�r�g
�싞�s��{�j
�{�g��
����
�W���y��
�܍s���Ɖ���
����
�w���̒���
��l�̕�
���~
�t��
���O
����
�[�q
�n��
�{�g
�R�z
郔n
���N���趋L�E��R�_��/311
�i�s
�i�s�̈�ہE�����d�q/332
��L�E���J��/346
�E |
���A���̔N�A�u��̐��� : �Ȋw���M�v���u��Ώ��[�v���犧�s�����B�@�@pid/1124207
|
�����̕��z�Ɠ�m�����E���c�\��Y/3
��C�̋��E�c�����n/16
�{���l�I�̉��E���q�����Y/26
�M��ɂȂ�����炽�ʂ��E�Έ��/32
���ӂ�E�c���N�V��/39
��C�̋����E�O�Y��V��/51
������חށE���c�O�Y/62
����ƊQ峁E�쑺����/69
��m�̐H�p���E�c�����n/77 |
���m��壉E�ݓc�v�g/95
����̓�峁E�����t�Y/98
����̋��̘b�E�����V/106
��m�Ǔ��̎v�o�E���c�\��Y/119
��m�̒��ށE���c���V��/126
�ʂ̒��E�w�R�`�v/156
�A����
�{�p�T���E�������O/171
�{�C�e���]���t�̂��Ƃǂ��E�ēc�j��/179 |
�A�������E�������O/185
����x�̐A���E�R�{�R��/196
����̐A���E���蒼�}/212
����̐A�������E�ēc�j��/220
�r���}⍂Ɉ�x�̐A���E��������/227
��̉ԁE��̛��E���蒼�}/246
�}���O���[�u�E���q��/253
�M��ʛ��ƃr�^�~���E�R�{��/260
�E |
|
| 1944 |
19 |
�E |
�Q���A�{�����ꂪ�u�쓇�o���v���u���s���Ёv���犧�s����B�@ (����p��)�@�@pid/1460042�@�@�{���\�@�@
|
��/1
�I�s��
���d�R趋L�i�K���E�V��I�s�j/1
�o�ߚ����I�s/28
���d�R���n����/60
趋L�� |
���趋L/113
��㊂́u�C�V�K���g�[�v/127
�Ί��c�ɏA��/134
�ٚ��D�����G���L/140
�A�_���X�̓ߔe�����^/171
���d�R�̋��y�ߋ�/190 |
�ɛ{������
�����И��̝ɛ{/201
��㊂̘b/204
�o�ߚ����́u�o���U���v�u�J�C�_�[���v�y�сu�Ɣ��v/223
���������܁i���������j/250
�����̎Z�@��/277 |
�P�P���A�ɔg��N���u�������y�L�v���u�����v���犧�s����B�@�{���\�@�@pid/1460043�@�@�T�O�O�~
|
��/1
�_�������މ���/1
��M�̈������l/11
�h���̂ӏ����l/29 |
�E����/44
�l���̘b/60
��������/77
���{�Ɨ���/94 |
�N�앗/112
�����̍r��/129
���d�R�Q���̖��/149
�j����/201 |
�N���s��/220
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�]�����������������ҁu������������ ��1�S �v���u�@���فv���犧�s�����B�@�@pid/1040304
|
ᢊ����
�x�ߘŋ����n�̔N���Ǝl�\����S�E�]���M��/1
�ŋ���e�ɉ�����x�߂Ɠ��{�E�˖{�P��/27
�a���̋���E�c������/50
�v�Ҕ��摜�̖���l�E�]���M��/100
��誂Ƒ嗤�̍u�S�E�ɓ����O/119
���{���ƂƘŋ������@�E�ޗǎ���ɉ����隠�ƂƘŋ��E�������/129
�_���Ƙŋ��Ƃ̌��@�ŋ��B�҂��ޗǒ������܂ŁE�c������/139
�����R�M�̙B���Ƒ��̎v�z�I�W�J�E���c����/149
�_���̎��S���q�y�̎v�z�E�Γc�T��/173
���@�v�̏@�T�I�J�l�E�������S/196
�q�d�E���߁E�O�ł̖��@暋��l�̈�̌����ɂ��āE�ˏ��[��/201
�ēy���k���₹������������Ղ̈��E�����S��/211
���������Ɛ��W�W�E�����p�~/221
���쎞��ɉ�����ēy�@���̘B���E�O�c�S�M/246 |
�������{��萂����l�@�E�������r/254
�p�ؚ��S�B桍l�E��������/268
�x�߂ɉ�����ؚ��{�����E�Έ�r��/296
���t���l�������E�~�����/300
�b���ŋ��ɉ�����~�V�̌����E���i�˖P/311
�W�����̘ŋ��E���R���D/321
�ēy�@�`��ᢒB�l�H�E���S�E/356
�嘩�ŋ��̋��N�Ɵēy�S�T�E���V�E��/363
�哌�����݂̎w�������E�������R/367
�@�R���{�̘_���I�l�@�E�؈�r�f/373
�@�R��l�Ƃ��̎���@���j���ɉۑ�E���r��/377
�x�ߘŋ��̌���Ƒ������E�]������/382
�N���V���i�_�̐��`�E�ɓ��M�C/385
�b��
�E |
|
| 1945 |
20 |
�E |
�E |
| 1946 |
21 |
�E |
�P�P���A�ɔg���Q���u������j���� : ���{�̏k�}�v���u����N�������������ǁv���犧�s����B
�@�@210p�@�����F���ꌧ���}���فF1005905490 |
| 1947 |
22 |
�E |
�V���A�R����W���u�������y�̊T�� ���w���E�M�y(����)���@�̐V����v�� : -�ܓx�\���_-�v���u�R����W�v���犧�s����B
�@�@ ���ʍ��@�P�S���@�@�����F��㊌����}���فF1001675139
�W���P�R���A�ɔg ���Q�i���� �ӂ䂤�j���S���Ȃ�B�@(���N�V�P�Ζv)
�P�O���A�{�Ǔ��s���u���{�̋��X�v���u (�ޗnj�)�{���Ёv���犧�s����B�@�@pid/8795501
�@�@�@�����������@��: �����[�����h��w�v�����Q���Ɂ@�@�v�����Q���ɐ����L��: DS-0217
|
��
�� ���k�̏���/11
�� ���ږ��̃o�[�`��/15
�O �t�W�����O�K���H/18
�l ���i�͝���/25
�� ���C�z�C��ƐK��/30
�Z ���͏K��/33
�� ���l�̑�/37
�� ���z�̊C/42
�� �I�c�̌Y��/50
��Z ���ډ��̔N��/54 |
��� ��萂̉�/59
��� ���X�ؕ��ꉥ�ƃL���^���|/63
��O �s���邷�j���̎R�c�H/69
��l �R�Ԃ̔_�����q��/75
��� ���R�̌Ǒ��O�ʂ̐���/87
��Z �֓��̊C��/95
�ꎵ ����̕���/101
�ꔪ ���Ă̊�K�ّ�/106
��� �̉����̐l�X/111
��Z ���䗯�k����̉�/118
��� �����̉�㋂�����/123 |
��� �}�Ẩ̖ԕP/129
��O �������̑�����/136
��l ��q�����̑��ؐ�/145
��� ��̓��̐D��/157
��Z �����̘މ��Ɖ�㊂̘މ�/161
�� �܌A�̐��/169
�� �Ί_���ƕ�/175
��� �Ă̓�/181
�O�Z �g�Ɗԓ�/189
�E
�E |
�P�Q���A���c���j���u��㊕����p���v���u�������_�� �v���犧�s����B�@pid/9580761
|
�Ҏ[�҂̌��t ���c���j/1�@
���̖A �����R/5
�E���}�͉�㊂̌��i�Ȃ�� �ɔg���Q/23
��㊂̓y�� �j�_���O��/33
�n���� �����[����/55
���쎢���Ɛ��ؔC�N �哇�A/73
���̍�� �܌��M�v/81
���I�����̎��R�ƃ~�\�M ����F�Z��/107
�Z�a�i�˗́j�̐M�ɂ��� �����P��/125 |
���{�� ���ܐ��q/153
�ݗt�Ɛ_�� �������� ���E��㊐_���̓��{�Ñ�_���j��/171
���d�R������ �{���c��/217
�����̒n���Z�@ �{������/235
�����̓������\���i�咆�����j �n��ݚ摾��/253
�쓇�̓��n�i�j�ˁj�ɂ��� ������v/269
���Z�ޔg�̐l�X ���܌���/295
���ލl ���c���j/313
���Ƃ���/341 |
�P�Q���A�R����W���u�������y�ɋ����Č��o�����������@�Ɋւ���V�����T�v
: -�ܓx�\���_-�v���u�R����W�v���犧�s����B �@�@���ʍ��@�Q�O���@�����F��㊌����}���فF1001675121 |
| 1948 |
23 |
�E |
�Q���A�ɔg���Q���u������j����v���u�i�z�m�����j�}�J���[���{�莛�v��������s�����B�@�����F���ꌧ���}����
�V���A���钩�i�����{�����w��ҁu�����{���� = The Japanese journal of ethnology 13(1) p.69�`78�v�Ɂu�ɔg���Q�搶�̐��U�Ƃ��̗����w�v�\����B J-STAGE
�P�Q���A���{�����w��ҁu�����{���� = The Japanese journal of ethnology 13(2) �v���u���{�����w��v���犧�s�����B
|
����̍���--����F���Y���̍e�{��ǂ݂� ���쐴�q p.89�`100
���{���������̌����Ɠ��{���Ƃ̌`��(���k��) �����Y,������Y,�]��g�v�� |
�Ñ�Ɩ؏M�̔��� ���{�M�A p.107
�A�C�k�̃`���V�ƃ��V�A�̃S���f�B�V�`�F �@�]��g�v p.82�`88 |
|
| 1949 |
24 |
�E |
�R���A�ʑ㐨�@�_���u�e�a�v���u�}�J���[���{�莛�v���犧�s����B�@�@pid/11934732�@pid/11934732
�@�@�@���L �@�@��l450��䉓���L�O�o��
�V���A�u���@ (5) �v���u�R��[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1834112
|
���S ����⑾����i�W //1
�]�_ ��]�̎� / �����P��/28
����̝D�� / �R�V����/34
�V�O�i���ɏA���� ����� / �����P��/36
�T ���ܕ� / �������/43
�`�� / �ѓC/52
�قƂ� ���O�� / �����V�g/55
�����B / �����C����/60
|
�ߊ� / �ߓ����l/69
���� ����� / �O�c�����U/74
�킪���킪��̉� / �쒷�P���v/78
�J�Ԃ̉� / �R�{���}/80
���� / �Z�ԑ���/82
桎� ���̂̂킩��(���S) / ���c���U�g/84
���k ������p / �ʒu���q ;�������/86
趋L ��X�� //89
|
�S / �����V�g/89
�n�����L / �O�c�����U/89
���Ԑ���� / ��c�F�c��/92
�㋞���X / �쒷�P���v/93
���z�ɂ��� / �������/95
�E�ƍ� / �ߓ����l/96
�ٓr / �����P��/98
�E |
�P�O���A���ǓS�v���u���d�R�Jᢎ��� : �_���ږ���茩���{�S�̕��y���тɐ��������ɂ��āv���u���d�R�_�э����w�Z�v���犧�s����B
�P�O���A�R�����j���u����̕��x�ɂ��� : -�̎��Ɖ��-�v�����s����B
�@�@�@���L ���ʍ��@�@���L �p���t���b�g�o�C���_�[����@�@�����F���ꌧ���}���� |
| 1950 |
25 |
�E |
�X���A�R�����j���u�����T���y : �y�� ��1�W�v���u�����̉��y�o�ŕ��v���犧�s����B
�@(�����ƌܐ����E���L)�@�@�����F���s���}����
|
��O��
�w�l�����x
�V��������̗x
�O�y���̘b |
�J���̘b
�ÓT�w�l���x��
�X����
�l�c�|�x |
���s�̋�
��g���q��
���d�R�����w
�����哇���w |
�P�P���A�����P�������{�����w��ҁu�����{���� = The Japanese journal of ethnology 15(2)�@ p.144�`145�v�Ɂu�ɔg���Q���u������j����v�v���Љ��BJ-STAGE
���A���̔N�A���{�����w����ҁu�ŋ߂ɂ����鉫�ꌤ���T�ρv���u���{�����w����v���犧�s�����B
�@�i�����w���� ; ��15�� ��2���j�@cid/3449776
|
��㊌����̐��ʂƖ��\�ɓ��̂��Ƃ\�E�Γc�p����/1
��㊌����j�\��㊌����̐l�Ƃ��̋Ɛс\�E���钩�i/2
��㊗��j�T���E�����[����/15
�l�ފw���猩�������l�E�{�c���`/23
�l�Êw���茩�������\������j�w�Ɋւ���o���\�E��������/31
������T�_�E�{���c��/39
��㊂̖����ƐM�E���܌���/50
��㊂̑����g�D�E��Ït��/63
������̌����\�����댤���̕����ƍďo���\�E�����P��/67
��㊂̖��Y�E���@��/80
���{�����w�Ɖ�㊌����E�員���F/86
��㊊W�}���ژ^�E���钩�i/121
�C�_�{�l�E���c���j/92
�����ꑰ�_�E�܌��M�v/108 |
�q���]�r
�����[���Ձw�쓇���y�L�x
�@�@���\��㊁E�����哇�n�������\�E���钩�i/142
�ɔg���Q�w��㊗��j����x�\���{�̏��}�\�E�����P��/144
�������w�剂���j�x�\���������������\�E�員���F/145
���c���j�ҁw��㊕����p���x�E���钩�i/146
�q�����ƒʐM�r
�����w�����ٝ��U��㊖���ژ^
�@�@���\�ےJ�����i�U�j�\�E�{�{�]����/136
�G�ߓ����ɉ��~�_�E���܌���/62
���M�ҏЉ�/91
��㊌����Җ���/107
�ҏW��L/148
�q�p���v��r |
|
| 1951 |
26 |
�E |
�R���A��Y�����u�_�Ɣ��B�j������� ��34���v�Ɂu����ɂ�����Ï����j�v�\����B�@�@pid/12615698
�S���A�{�c�����ҏS�u���ꏔ���̌×w�ƕ��x�v���u�����|�\�̉�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@��Ït�����Ƀ}�C�N���ʐ^�����{ �܂Ƃ� �@�@48p �����F���ꌧ���}���فF1001678760
�S���A���o�[�g�E�V���[���b�h��,����ܘY��u������ : �i���j��㊂̝D���v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/1690294
|
���{�ł̏���/39
�����i���Łj�̏���/45
���́@������������/55
���́@�n���l�ӂ̋�����/83
��O�́@���{�R�̓r�N�Ƃ�����/113 |
��l�́@�������̎��̛��J/147
��́@�t����D�a�@�ɂ�/173
��Z�́@�ō��w�����ɂ���/195
�掵�́@�������p��D�̎w����/211
�攪�́@��㊓��i�U/225 |
���́@��ւ̏㗤/255
���Ƃ����i��҂̌��t�j/294
���^�\���������m�e�D骂ɂ�����
�@�@�����ė��R���͂Ȃ�тɎ����ҕ\
��㊍�D�ɉ�����A�����J�͑D�̑����\ |
�V���A���@�����P���u����̔ߌ� : �P�S���̓����߂���l�X�̎�L�v���u�ؒ����[�v���犧�s����B�@pid/1659382
|
��@�͖C�ˌ��n�܂�/1
��@������/10
�O�@���Ǝ�/14
�l�@����̍�/16
�܁@�Ō�u��/20
�Z�@���S���\����Ɖ_���\/22
���@�����̓�/25
���@��������/27
��@�ŏ���ฐ�/31
��Z�@��������/33
���@���O��/38
���@���O��/46 |
��O�@���n���̕��폱/54
��l�@�a�@�ړ�/62
��܁@�^�˂̏�̛{�F/94
��Z�@���F/106
�ꎵ�@�n�Õ~�ǎq/116
���@�Ύ��̌R��/123
���@���ɗp��/125
��Z�@����̗Ζ�\�[��̐����\/128
���@���R�r�̎��\�Ō�̙B�߁\/131
���@�g���Ō�̓��\�r�،R�ƈɍ��㓙���\/139
��O�@�e���/142
��l�@���E�o/156 |
��܁@���̉��U/163
��Z�@���/190
�@�ܓ��̟c��/200
�@����/211
���@���̜f�r/218
�O�Z�@�{�F�̎��Ə���/233
�O��@�����˔j/240
�O��@�P�S���̓�/247
�O�O�@�r�ƁT����/261
�O�l�@��/267
�O�܁@�č��������/270
�E |
�P�Q���A���a�c�^�~���u�����p�A����� �S�v���u���z�����[�v���犧�s����B�@�@ �����Ł@�@ ���ŁF���a6�N2��
�@�@�@�@���L ���c�@�l�����[���Օ��Ɏ��W����(����ID�F 1007162892�j |
| 1952 |
27 |
�E |
�Q���A�u���ԓ`�� 16(2)(165) �v���u���{�����w��,���ԓ`���̉� �H�c���X�v���犧�s�����B�@�@pid/2264388
|
���ꖯ���̌��� / ���c����/50
����̑��X--��X�����c�`������̃m�����x / �h��/55
�g�E�}�C���ƃ\���W���}���\��a���P�J�̕搧�Ɩ~�s��/�x����/p17
�����̌��㐫--�����w�����Ė����w���炵�߂���� / �q�c��/69
�݂ƊԐH / �X������/p26
�J�h�ɂ��� / �i�C�ꐳ/p27
�f�c�R�{ / ���Y�N��/p27
���ƒ�-17-�����̉� / ���c����/76
12���Ɛ��� / �X�r�G/78
���������� / �Ñ閾�v/p32
|
������ / ���c�m��/81
�ߍ]�̗��� / �����ǗY/83
�c�̐_�� / ���c��/86
���搧���� / �R�c�O��/68
���|�̋֊����M / �����h��/73
�����Љ�/p39
���{�����w���(12)/p44
�����w��������(41)/p46
�V������Љ�/p16
�����̌����ɂ��� / ���쐴�q/88 |
�U���A�������[�ق���; �V��S�v��; ���a�c�^�~��; Walker,EgbertH�ҁu����A�����v���u�����č������{�v���犧�s�����B�@�@�@���L ���{�F�����č������{���s(1952)�u����A�����v�}�C�N���ʐ^�����{
�W���A�ʑ㐨�@�_���u�����Ǝx�߂Ƃ̊W�v���u�i�z�m�����j�}�J���[���{�莛�v���犧�s����B
|
���^�F�j���́A�}�J���[���{�莛�Z�E�ʼn���o�g�̋ʑ㐨�@�_��1952�N6������z�m������KAHU�����ǂɂčs�������^�C�g��(8��V���[�Y)�̃��W�I�ԑg���I������ɏ����q�ɂ��ďo�ł������̂ł���B�u�������c�_�v���n���C�̉���Љ�ɓ������������S�����͈̂ɔg���Q�ł��������A���̈ɔg�́u�������c�_�v���ł������Ɍp�������̂��ʑ㐨�ł������B�u�����v�Ɓu�x�߁v�̌n���I�s�A������`���Ȃ���A�u���{�v�Ƃ̌n���I�A�������咣���Ă���l�q������������B |
�W���A�c�ӏ��Y���u���������b�̎蒟 1(1) p.118�`122�@���������Ёv�Ɂu���ꕑ�x�̂䂭���v�\����B
�P�O���A�����|�\�̉�ҁu�|�\���� (1)�v���u ���P�����X�v���犧�s�����B�@�@pid/1770224
|
�|�\�����̂��Ƃ� / �܌��M�v/1
���Ɨx�� / �܌��M�v/2
�|�\�Ƌ��Z / ���p�䐳�c/4
�K���̢�\����� / �O�������Y/9
�����̕��W / �{�c����/13
|
�͎��l / �S�i����/19
����̌É̗w / ���܌���/35
�F�ԂƖ����|�\ / ��������/43
�l�`�ŋ��ϑJ�}�j-1- / �{��������/28
�����̎��q��-�k1�l- / �q�ѐ���/51
|
�������q������-1- / �{�c����/63
�Y�\���] / �r�c�\�O��/26
�|�\�}����� / �r�c��O�Y/59
�|�\�����N�\ / �S�i����/71
�E |
�P�Q���A�u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (�ʍ� 10�E11) �v���u���m���y�w��v���犧�s�����B
|
�O�������Ȃɉ�����u���v�Ɓu�w���v���Ƃ�
�@�@�����y�I�Ӌ`�Ɩ{���@���c�Ï� p.1�`17
�����u�k�����̋|�Ղƌܒi���K�����̎����@���� p.18�`32
�������y�j��-1-�@�R�����j p.33�`53
�����@�R��i������y�����ژ^-��-�@���o�v�Y p.54�`66
�ẨS (��)�@�@���c����Y�@ p.67-73
�y�킩�猩���u�������v�@�X ���O p.74�`75 |
���c�Ï͒��u���W�I�M�y�̊ӏ܁v�@�g��p�m p.76�`77
�ˈ�c���O���u�\�|�_�v�@�g��p�m p.78�`79
�R�����j���u�����̉��y�v�@�ݕӐ��Y p.79�`80
�V�Ԑi�꒘�u�̗w�j�̌����v�@����ʘY p.80�`81
Claudie Marcel-Dubois:Les Instruments de
�@��Musique de L'Inde Ancienne�@�@�ݕӐ��Y p.84�`88
�p���_���M��v�� ���̒����@�������Y�@ p.en5-en21,104 |
|
| 1953 |
28 |
�E |
�R���A�ʑ㐨�@�_���u���c�h���v���u�i�z�m�����j�}�J���[���{�莛�v���犧�s����B�@�@pid/11934766
�S���A�����|�\�̉�ҁu�|�\���� (2)�v���u���P�����X�v���犧�s�����B�@�@pid/1770225
|
����j�Ɋ� / �͒|�ɏr/1
�����|�\�̌�����嗤�ɋ��߂�--���y�|�\���� / ��������/2
����̌É̗w-2- / ���܌���/10
�O�͍��k�݊y�̑��X�ōs�͂ꂽ�_�y / �ɓ��L�� ;�ɓ��d�g/16
�R������ÌS�e�n�J�̢�_��� / �H�Ö���/21
�����Ղ蕷��--�{�錧�I���S�Ëv�ё����� / ��ؐ��F/28 |
��O�y�|�\�����ς� / ���p�䐳�c/34
�����̎��q��-2- / �q�ѐ���/47
�������q������-2- / �{�c����/49
�����Y�\�� / �c������/53
�Y�\�����N�\(��) / �S�i����/55
�����|�\�̉�X�� / |
�S���A�{�Ǔ��s���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 54(1) p61�`70�v�Ɂu�������w�Ɩ����v�\����B�@�@pid/3365247
�X���A�u��y = Monthly jodo 19(9)�v���u�@�R��l�r��v���犧�s�����B�@pid/6075475
|
���H�̊��� / �g�c����N/p1�`3
���H�̊��� �������M�ƕ� / �O�}������/p12�`14
���H�̊��� ��m�̎p / ���X���R/p16�`17
���H�̊��� �����ɎQ������ / �x����}�q/p15�`15
�ފ݂Ɏv�� / �ˏ��w�l/p8�`10
�ފ݂Ɏv�� �M�� / ���웑�q/p24�`26
�ފ݂Ɏv�� �����݂قƂ� / �ēc���P/p20�`23
�ފ݂Ɏv�� ����̏@���Ƒܒ���l / ���R����/p28�`29 |
�ފ݂Ɏv�� ��߂�ꂽ���S / �ҏS��/p30�`32
�ފ݂Ɏv�� ����̒Z��/p18�`19
�ފ݂Ɏv�� ��y�ҏS�̂ǂ�/p11�`11
�ފ݂Ɏv�� ��y�o�d / p29�`29
�ފ݂Ɏv�� ���E��/p27�`27
�\�P�@�� / ���쐳��/p4�`7
��y�ۈ�̃y�[�W/p10�`10
�E |
|
| 1954 |
29 |
�E |
�S���A�`�����i���w�i�j�_���Y��;�����G�B�� �u����̒n�� [�{��],�@�m���^�n�@2���v���u�w���̗F�Ёv���犧�s�����B4
�@�@�@���L ���E���Z�p �Љ�Ȋw�K����
�@�@�@���L ���^: ����̎��R,�Љ�,�Y��,�f�ՂɊւ��鎑���Ƃ��Ď��W��������
�S���A������w�_�w���ҁu������w�_�w���w�p�� (1)�v���u������w�_�w���v���犧�s�����B�@pid/1758869�@
|
���������Y���ۗނɊւ��錤���k�p���l / ���˒��G/p1
��t�̓������ɂ��� / ���ǓS�v/p57
��t�̐A�����ɂ��� / ���a�c�^�~/p75
�E |
�N���C��������Gymnodactylus albofasciatus
�@�@��kuroiwae Namiye�ɂ��� / ���ǓS�v/p90
�q���Ƃ��ẴM���E�M�V�o / ���r��/p93
���� ���v��茩������̉�㊔_�ƊT�� //p97 |
�P�Q���A�{���c�s���u�G�������{���� 18(4) p.369-379�v�Ɂu���������Ƃ��̌��� : �������̉����ᔻ �v�\����B�@J-STAGE
���A���̔N�A�����v�q���u�����̖��w�G�������w�̋N���ƕϑJ(�ӏܕ�)�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s����B�@pid/2468585
|
�͂�����/p2
��A �I�����̂ł�������/p2
��A �I�����̓��e/p6
�O�A �E�^(����)�ƎO����/p19
�l�A �{�ÂƔ��d�R�̖��w/p32
�������y�̓���(�ӏܕ�)/p39
��A �����ÓT���y�ɂ���/p40
��A ����(���e�E���e)/p44
|
�O�A ���S���̑��ɂ���/p47
�l�A �������K�_/p58
�̎����/p85
�͂�����/p86
��㊖{���̕�(�O�Z��)/p87
�ɍ]���̕�(�l��)/p95
�{�Ó��̕�(��܋�)/p96
���d�R���̕�(��l��)/p99
|
�y��
��㊖{���̕�(�O�Z��)/p4
�ɍ]���̕�(�l��)/p54
�{�Ó��̕�(��܋�)/p59
���d�R���̕�(��l��)/p67
���w(�ӏܕтɌf�ځE�Ő��͖{���̕ł�����)
�J����(�ӏܕтɌf�ځE�Ő��͖{���̕ł�����)
�E |
|
| 1955 |
30 |
�E |
�Q���A�u��y = Monthly jodo 21(2)�v���u�@�R��l�r��v���犧�s�����B�@pid/6075491
|
������/p1�`1
��̓� / �g�c�h��Y
�r���}�����L / �Έ�^��
�r���}�̕��� / �_���`�� |
�r���}���� / �]�甪�d�q/p12�`12
�ܒ���l / �勴�r�Y/p23�`27
���m�l�͂����l���� / ��ؑ��/p5�`8
�m�E�M�E�s / �������/ |
������@�m�ƌ�� / �{������/
�j�b ���B�W�t�ƎR�����l�Y / ���c�a�F/p29�`32
��y�ւ̂����/p28�`28
�E |
�R���A���֏�v���u�����{���� 19(2) p.107-141�v�Ɂu���d�R�Q���̌Ñ㕶�� : �{�Ǔ��s���m�̔ᔻ�ɓ����v�\����B�@J-STAGE
�R���A�u���{�Ï��ʐM 20(3)(308)�v���u���{�Ï��ʐM�Ёv���犧�s�����Bpid/10232365
|
���Ɨ����Ɩ{/���֏�v/1�`2
�����̎��v�����u���v������v/������Y/2�`3
���E�̌Ö{����ۋL/���R���P/4�`6
�Րl�b (15)//7�`7
�\�����˂̉��O/���������q/10�`10
�������̎v�Џo (��)/���g����q/10�`11
|
���E�̕S�Ȏ��T/�a�F/8�`9
�����吳�̏��l�C�ԕt//15�`15
�S���Ö{�������L/�D���O�f�l/12�`14
���V��//19�`19
�����̌��i���j/�Ζ؈��O/3�`3
�����}���W����/�V��h���Y/20�`20
|
�����̎���//16�`18
��[�N������//16�`19
������//2�`6
�Ö{�̔��ژ^//21�`27
�T������//28�`28 |
�P�P���A���y�V�F�Е��u���y�|�p 13(11)�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/2293796
|
�Ăѓ��{���w�̉��g�D�ɂ��� / ���v/77�`89
�n��ɂ������Ă̖��w�̏����ɂ��� / �ԋ{�F��/57�`66
�n�`���g�E�[�������_ / ���a�j/29�`38
�_���s�b�R�����߂����� / ����`�Y/8�`14
���[�c�A���g�̃I�y������(6) / �n�ӌ�/39�`52
����V�A�l�d�t�ȣ�ɑ���10�N(8) / ��n����/53�`56
�}���h�������y�̌��� / ������/67�`70
�~�����w���̉��y�E.����(���k��) / ���q���q/15�`28 |
����̉��y�E�̌��� / �Ԑ����F/115�`116
���y�Ƃ̔��� / �k�����M ;��㗊�L ;���c�쒼/71�`73
���E���y�̒��� / ���a�j ;�Ҍ[�� ;�֓C/105�`114
�X�g�����C���X�L�C�̐V��u�f�C�����E�g�}�X���Âԁv/105�`108
�A�~�[���t--20.5���I�̍�ȉ�/109�`111
�㌎�̉��t��] / �������Y/90�`102
�W���Y �f�� ���R�[�h ���� / ���� ;H2O ;�y�b�g/74~76
�E |
|
| 1956 |
31 |
�E |
�S���A���v�`������w�j�w�E�n���w��ҁu�j�� = Shisen : historical & geographical studies in Kansai University (�ʍ� 4) �v�� �u�я��̌����ɂ��āv�\����B
�U���A���c���j���u�C�쏬�L�v���u�p�쏑�X�i�p�앶�Ɂj�v���犧�s����B
�V���A�{���c�v������Ҏ[�u�{���c�v�v���u�����Ȃ�Ёv���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004820302�@�i 289p�@
|
�}�� (�ʐ^�E�{��S�v �{��搶�����̂Ԓn �@�{��搶��n)
�{��S�v�搶�̈�ь����ɂ��� �{�� 贓T
�{��S�v�搶���ь������ƌv�揑
�Y�ƐU���̑�v�l�{��S�v�搶�̈̋ƌ��ь����ɂ���
�Ɛт����̂ԋ{��S�v�搶-���������ƋƐ�- ���Ǔ���
�������Ɩu�����O��ɂ����鉫㊓��Ƃ̎���Ƌ{��搶�̖��� ��鏹��
�����_���v�̐���-�{��搶�����̂т�- ����Q��
�_���ւ̕�d�ɐs�����ꐶ �ʏ�_��
�v���o����� (�{��S�v�N������ ���˒���
��s��ړ��̂���ɂ� ���L�K���Y
�������Ђ������������ ���D��
�َq�����ׂĐ��������b �����q��
�ǂȂ��ė����������� ����^�K
�䂫�Ƃǂ����q��ւ̋��� �{��m�l�Y
�g�S�v�搶�h�̖ʉe �ʏ�T�Y |
���t�ĂՐ搶 �{�� ���K
�c�_���M������� �����x ����
���Ƃ��������w���� ��l �G��
���ڂ�b ��� ����
�������炻���� ���� ����Y
�Z�S�v�Ǝ�) �{�� ���s
��e �u���Ƙ_���E�ӉZ�̃x�g�a�ۂɊւ��錤��
���L�F�ۊw�Ƌ{��搶 ���܌���
�{��搶���L�O����A�� �V��S�v
��㊌����ƈӌ���(�吳8�N7��)
�k����P�Ƒ����v(���a9�N3��9���`14���F�����V��)�v
���ʎn��(���a9�N8��28���F�����V��)
�������Ǔ��k(�E�v)
�{��S�v������(1877�`1914)
�E |
���A���̔N�A��w��A�������哇���������ψ���ҁu�����̓��X�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/2984506
|
�����̒�/p2
�W��/p4
���w�Z/p8
���ǂ��̂�����/p10
��Ǝq/P12
�Z���Ɩh��/p14
���q/p18
�J���Ɣ�/p24
���n/P28 |
�h�S/P32
�m�ԕz/p35
�哇�c���M/p38
�s��/p40
�T���S��/p44
���Ɛ���/p50
�^���ƌ��/p56
�n��̕���/p66
��F�����̑���/p68
|
1.�m��/p68
1.�V��ԍՂ�/p68
2.�Ջ�/p78
3.�g�l��/p80
4.�m���̎�����/p82
2.�J�g���b�N/p84
3.�V����/p87
4.�_��/p88
5.���^/p90
|
6.�N��W�c/p91
��`��r/p94
����/p96
���݂̑��ŋ�/p99
���̗x��/p106
�����x��/p107
�L�N�x��/p110
���
�����̓��X/p3 |
|
| 1957 |
32 |
�E |
�P���A�w���Y�x�ҏW�ψ���ҁu���Y (60)�v���u���{���Y����v���犧�s�����B�@�@pid/7931847/1/1
|
�u���v�ȑO�ƈȌ㖯�|�قƍ��� / ���@�x/p4�`7
���|�_�ɂ���(��) / ����/p8�`13
��㊎��s�v�c / �і�q/p14~18
���R���̎G�� / �O���g�V��/p19�`20
��B�E�ȓ��̓y�� / �ߓ����k/p21�`24
���v�ԓ����Y�̋ߋ� / �l�c���i/p25�`26
�c���́u�S�ʁv / ���c����/p26~26
���F�� �Ð��ˁE�R��?�E���낵�� //p27�`27
�O���t �ɖ����E���t�̒��� //p28�`32
���t�̒��� / �Ίۏd��/p33~35
�o�_�E��Â̊��� / ���X�[�O��/p36�`38 |
���Z�����̂���� / �ێR���Y/p40�`41
�W���� ���斯�|���c�V��W //p39�`39
�~���W�A���߂��� //p42~42
�u���|�v�G�� //p24~24
�����ē� //p45~45
�����݂���� //p46~46
���{���|�وē� //p47~49
���{���|������ //p50~50
�n�������� //p51~55
�M�ҏЉ�E��L //p56~56
���a�O�\��N�x���ڎ� / / p57~ |
�R���A�V�铿�S���u�k�R�j�b�v���u�V�铿�S�^����^�C���X�Ёv���犧�s����B
�S���A��c�������u��㍻����������� �i�S�����j�ʍ��@��㍻��������v�Ɂu����Ɖ����̍��������@���āv�\����B
�S���A�`�����_���Y���u �w��������xNo.031�@�������{�����nj��������ہv�Ɂu�Ï��̓`���ƏW���̕ϑJ�v�\����B
�T���A�u���y�L���{ ��1�� (��B�E�����)�v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@pid/2530167
|
��B��
��/p1
�_�k�̂͂��܂�/p15
��̓n��/p21
�嗤�����Ƃ̂Ȃ���/p31
��Ƃ̂Ȃ���/p57
�C�̉���/p69
���Ƃ̍őO���Ƃ���/p85
�f�ՂƐ푈/p101
�C���Ђ炢���l�X/p115
�ӓy�̖�/p131
��B�Љ�̂��肩���/p149
���N�̖��Ɠ��H����/p167
��ؖf�ՂƃL���V�^��/p175
��B�̎c������/p207
�җ��R���̑��X/p221
|
�N�W���Ƃ�/p235
���̕���/p251
���m���x�Ǝ�ґg/p277
����̖�/p293
�ߑ�Y�Ƃ̂�������/p299
�����
�����̗��j/p319
�����̏K��/p347
�����̗�/p355
�퐢�̍�����/p363
�����̌|�\/p381
�R�Ɛ�̂�������/p387
���X�̘b/p393
��B�n���E�����S�}
��B�E�������j�N�\
�ʍ� |
�킽�݂̋{/P75
�����w���̋�S/p76
�͂�����/p77
����̋���/p78
������铇���_��/p191
���m��֊C��C��/P192
���{����̕���/p193
��̂��ۉ�/p194
�R�̖��낵��/p243
�g�l�Z�̓V����/p244
�C�̌b�݂̊�~/p245
�ԓ��̐��ˊJ��/p246
�L�̖ʂ̂͂Ȃ�/p375
�����P�̂͂Ȃ�/p378
�E
�E |
�T���A���ꐶ�����猤����ҁu����A���̏W�֗��v���u���ꐶ�����猤����v���犧�s�����B�@
�@�@���L �\�t(�V���ؔ�)�F�ʑ㐨�F�Y�i���܂悹�[�������j�����S�L���@�����F���ꌧ���}����
�U���A�܌��M�v���܌����m�L�O��ҁu���{�|�\�j�m�[�g�v���u�������_�Ёv���犧�s����B�@�@�@pid/2483217
|
�͂��߂�/p1
�� �C�̐_���Y�\/p3
�� �R�̐_���Y�\/p9
�O ���ǂ�/p14
�l �_�قƐ_�V�т�/p22
�� �_�ق̎�/p30
�Z �_�ق̍̕�/p37
�� �ԂƐ��/p42
�� ���V��/p45
�� �Ȃق�(�����E����)/p54
�\ �c�V��/p63
�\�� �V��/p70
�\�� �S/p77
�\�O �O�ŗx��/p84
�\�l �o�_�̓c�V��/p90
�\�� �c���k�^�}�C�l��萂��錋�_/p98
�\�Z �c�ق̊T�_/p105
�\�� �e�\��ᢐ�/p114
�\�� ������/p124
�\�� �c�ق̎��/P132 |
��\ �c�ٔ\�ƍ���/p139
��\�� ���ƕ��i��/p146
��\�� ���c�قƕ�����/p151
��\�O �c�فE���ق̐���/p155
��\�l �c�فE���ق̎��/p162
��\�� �c�ق̔\�Ƃ��̐�y�Y/p171
��\�Z �ȕ�/p174
��\�� �K�ᕑ��ᢐ�/p182
��\�� �K�ᕑ�̎���/p189
��\�� �K�ᕑ�̓����Ə���/p197
�O�\ �K�ᕑ�̐�s�Y/p206
�O�\�� �O�ŗx��Əo�_�̂���/p214
�O�\�� �O�ŗx�肩��̕��W��/p223
�O�\�O �u���Ԃ��v�Ƃ��ӌ�(��)/p233
�O�\�l �u���Ԃ��v�Ƃ��ӌ�(��)/p241
�O�\�� �u���Ԃ��v�Ƃ��ӌ�(�O)/p250
�O�\�Z �����x��Ƌ_��������/p258
�O�\�� ��㊂̔O�ŗx���E
�@�@�@�������R�O��/p268
�O�\�� �o�_�����E�̕��W�̍��g��/p276 |
�O�\�� �E�Ɖԓ���/p284
�l�\ �ԓ��ƎR�i��/p293
�l�\�� ���o�̕��i�y�і�/p302
�l�\�� ���Ԃ���/p310
�l�\�O �ŋ��E�ԓ��y�і�l�̎��/p316
�l�\�l �쌩�h�H�E�l�`�ŋ��̕��i/p324
�l�\�� ���̗V��/p330
�l�\�Z ���~/p338
�l�\�� �����ƌ�����/p344
�l�\�� �̕��W�ŋ��̂قߎ��Ɯ��Ԃ�/p351
�l�\�� �����Ɖ̕��W�ŋ���/p356
�\ �_�����x/p362
�\�� �t����{��Ղ�/p379
�\�� �l�`�̘b/p396
�̕��W�ŋ���ᢐ�/p402
�ƌ�ᢐ��̖����I�Ӌ`/p423
���Ƃ���/p433
����/p437
�E
�E |
�U���A�`�����_���Y���u�w��������xNo.033�@�������{�����nj��������ہv�Ɂu (����)�j���̖����v�\����B
�V���A�`�����_���Y���u�w��������xNo.034�@�������{�����nj��������ہv�Ɂu���Ɩ����`����̗̐̂��v�\����B
�V���A�w���Y�x�ҏW�ψ���ҁu���Y (55)���ꖯ�|���W�v���u���{���Y����v���犧�s�����B�@pid/7931842�@�d�v
|
���ꖯ�|���W/p3~56
�̍��������z����/p3~3
�s�퉫� / �͈䊰���Y/p4~5
��㊂̐����ƐD�� / �㑺�Z�Y/p6�`8
��㊂̎��| / ���c�C�H/p9~11
�����̖����Ɨx�� / �c����/p12�`13
�����̐H�ו��Ǝs�� / ���_����/p14�`17
��㊂̕��X�� / �͈䕐��/p18~19
��̍� / ����q�Y/p18~19
��㊗����L / �і�q/p20~31
���|���@�c���}���� / �R����/p32�`35
���҂��ꂽ���|���@�c/p36~37 |
�g�Ԃ̍��� / �����Y/p38~40
�O�p��� / �g�c����/p41~41
�،����o�� / ���c���/p42~43
��\�����{���|����S�����L/p44�`47
�S�����^�W����/p48~49
�V���Љ�/p50~50
�~���W�@���߂���/p51~51
�V���b�s���O�K�C�h/p52~52
�����݈ē�/p54~54
���|������/p55~55
�M�ҏЉ�E�ҏW��L/p56~56
�E |
�W���A�u�n�� 2(8)�v���u�Í����@�v���犧�s�����B pid/7893192
|
��ɑ嗤�̉Ȋw�̔����J�����l�X-1- / �ۖ��r��/p753�`763
���{�̗����Ƃ��̐U�� / �R�K�F��/p764�`777
���t�� / ���c�P�Y/p788~791
�����̒n���I��ϓ_ / ���슲��/p791�`793
����̈�ۂƒn���̖�� / �����쐳��/p793�`798
��ɎG�� / �g��Y/p798~801
����A�W�A������� / �����`��/p801�`806
�I�����_�ł������l / ���쑸��/p807�`810
�C�X�^���u�� / ���x��/p810~817
�[�C���Ƒ�m������ / �{�cᨎ�/p817�`822
�C�X�}�C���A�ւ̗� / �����h�m/p822�`826
�s�s�K�� �����݂���s / �ҏW��/p838�`839
�؎�n���w�j-8- / ���R�r�Y/p826~833
�n���̍l�����ɂ��� / �U���ǖ�/p778�`783
�n�撲���̉�z / ���c�h��/p843�`850 |
����s�n��̔_�Ƃɂ��� / ���ѐ��O/p784�`786
���� �n���w������(I)--���������w/p840~841
���� ���{�����̍\���ތ^/p841�`842
���� ������/p842~842
���v��������/p840~840
���{�̒������/p840~841
�Վ��H/p841~841
�V�����n������/p841~842
�n��ƌo��/p842~842
�l���n�����T/p842~842
�n���f��] �C�^���t�C�����u���z�̒鍑�v /
�@�@�� �Γc�p��Y ;���x�� ;�{���L��/P834~837
���E�̐Ζ�-2- / �n�ӈ�v/p851~855
�ǎҒk�b��/p856~856
�����\��/p850~850 |
�P�O���A�˖{�����u�����c�R�Ō�̓� : ���R�叫�c���È�`�v���u�˖{���v���犧�s����B�@pid/3454084�@�戵����
|
���@��粐��O/1
���c���U/4
���҂̌��t/9
���с@�I�D�ւ̋��/1
��������蜂�/3
��������������/5
��\����ʌR�̕Ґ�/9
�z������P���ɏd�y/11
��荎��ʂ̑�C�Ƌꜻ/14
���z���雔�ĝD�@/17
�{�y���D�̗v�j����/20
�c���R�i�ߊ��̍�D�v�`/22
�ՌR�̍~��/27
�c�����ɉ��シ/30
���v�l�̌���/35
��㊝D������/38
�{�y���D����/40
�I�D�ւ̋��/48
�Ō�̐��Љ���/52
���с@�c�R�Ō�̓�/57
�R�i�ߊ��̘���/59
��N���Z������/62
���ʎt�����E�Q����/69
�t���ƂƂ��ɋ{���/74
������̐���/77
�囒�I�D�ɗ܂�/85
���J�~����̌���/92
�n�e���ɕ���/95 |
�⌾�ɟk�邻�̐Ԑ�/103
�⍜������/108
��O�с@���R�̐��U/113
���́@�כ{����/115
�p�ˌ̎R�ɟd��/115
�r���Ȑe�F�s��/121
���I�D���̊���/123
�����̌R���`��/124
��������p�����{/126
�v�킴��A���X�J�s/128
���́@�B������/131
���L�V�R�����Ƃ���/131
�Җd�{���Ζ�/133
��C���̏o��/134
�k�ނ��z�i/138
���V���g���̞w���i��/141
�t���Җd�����痷����/145
�����X���ɓ���/148
��O�́@�����Ƃ��Ă̌㔼��/152
�����Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�X����D/152
���R����������/154
�䓇�ō��w������`��/156
���R�a��/164
���R�N���d����/165
���Ƃ�㔂��҂��琬/170
�s�_����/174
���^�@�c���囒���ȏW/178
��l�с@�c���囒���Â�/199 |
���}�Ȕ�}�Z�E�R�{�V��/201
�ꓰ�̈����E���c�M�j/203
����D�p���c���E������/204
�p�����{����E�������O��/206
���˗���������E��ؕ���/212
�_�ɒʂ���l�i�E����Ύ}/215
���L�V�R���ݕ����E��c�O��/217
�c�������̗F�b�E���c����/219
���V���g����������E��؋�/222
�����Ƃ��Ă̑쌩�E���ѐm/225
���x�̎t�����E�a���C��/227
���F�����̌����i�ߊ��E���?�O��/230
�w�͂̓V�ˁE�l���ȓ�/232
�䓇�R�i�ߊ��̌��сE�a�m���/234
���|�����̌��ӁE�ы��/240
�Ō�̎v���o�E���c���}/246
���R��{�Z���E�g�����O/248
�R�i�ߊ��Ɩ����E�����C?/250
�������Ȏ����E�s�j��/255
�̐l���ÂтāE�c����/258
�����ÂтāE�c�����S/261
�̐l�e�F���ÂԁE������/264
���R�̑쌩�E�C���Ĉ�/267
�{���Ċ����c�āE�c���r��/271
�c���囒���N��/277
���Ƃ���
�E
�E |
�P�P���A�����M�j ���V���{���w��ҁu�V���{���w 12(11)�v�Ɂu����̌×w�I�����ɂ��āv���u�V���{���w��v���甭�\����B
���A���̔N�A�`�����i���w�i�j�_���Y���́u�C�w���s�̞x�v���u����ό��v���犧�s�����B�@ 24p �@�d�v
�@�@�@�����F���ꌧ���}���ف@���T�e���ɂP K/374/O52/ 1005054448
���A���̔N�A�����[���Ղ��u�����̗��j�v���u�������v���犧�s����B�@ (���{���j�V��)�@pid/2994127
|
��@�J蓓`��/p1
��@�����Ɖ��/p8
�Ύv�Ɨ���/p10
�O�@�쓇����/p16
�l�@�ג��`��/p17
�S�����E�S�E���E����/p25
�܁@�w�V����/p28
�Z�@�p�c����/p29
���@�O�R����/p33
���@�@�x����/p36
��@���v�W/p38
��Z�@�O�\�Z���ږ��̓n��/p43
���@���b�u����/p47
�_�D�Ì����k���낭�����l/p49
�O�R�̌`���@�k�R�Ď�@����͗�/p51
���s�̌���/p54
���튢���@������/p55
���@���~��������/p57
�ɕ�����/p57
�S�i��@���݂Ă���̐_�@�ʗ�/p60
�����W��/P64
��������/p68
�c���O�ɂ����铇�Î��Ƃ̊W/p72 |
�̑Η��@����/p77
��O�@�c���̖��ƎF���̐��o�c/p81
�c����/p83
�˖��R�̐험/p84
��l�@���Î��̗��������@��/p85
���Î��̐��o�c/p86
��܁@�����g�ƍݔԕ�s/p89
��Z�@���ی��Ƃ��̐���/p92
�����̂���/p94
�H�n�d�u�̊�_/p95
�������c�_�̍���/p97
�ꎵ�@��Ƃ��̐���/p99
�]�����̖��@���s�l�S��/p108
���M�n�C�̔�p�@���M�@�n�C�l��/p110
����@�����l�ՖԋЁ@�]�q/p113
�i�v����/p115
�C�\���ˈ�/P120
�ꔪ�@�����߂Ɨ�����̐���/p122
�����ꐹ���̒���/p122
�����߂̏Z��/p124
�����߂̘a�������Ɋւ���m��/p126
�����ɂ��ė�����̌���/p129
�|�Ƃ̐i�s/p132
|
���@�����̊w��Ǝl���ی���/p138
��Ă�窈�/p140
��Z�@�����̕��_/p142
��/p144
���@�����ېV�Ɨ���/p146
���@��p����/p148
��O�@�Ō�̍���/p151
��l�@�������/p153
�m�����̉���/p158
��܁@�ʊK�g�D/p161
�喼���@�m���@����/p162
���m�s/p164
���@���q�@�i�@�e��/p168
�e�_��@����@���V�q�e�_��@
�@�@���}�o�V�e�_��E�}�o�V�q�E���m/p173
���E��/P178
���y�і�/p182
��Z�@�����̍Ō�/p185
�Ђ߂�蕔��/p188
�@���{�s��̂���悹�����A
�@�@���h���̓�\��x��/p189
�������/p192
�y�n���/p194 |
���A���̔N�A�����[���Ղ��u����O�j�v���u������E�����v���犧�s����B�@pid/2994125
|
��A�O���̈Ӌ`/p1
���̌�捇��a�̌���
�����̕��͂��Ȃĉ����̏���
�h���̉��
��A��㊏O�j�̌���/p2
�������ɑ�����x�����̌���
�@���̗����͉�㊂ɂ��炸
�����Ɖ��
���{�̍c��
�ג��`��
�����Ȍ�̒��v
���̉��_����
�����A�i�v�͌o�Ϗ�̋\�ԍs��
�i�v�͗L���Ȗf��
��
���l���n�i |
�N����@�y����
�F���Ƃ̊W
�Δn�Ɖ��
�O�A��m�e�n�Ƃ̌���/p24
���ۓs�s�Ƃ��Ă̓ߔe��
������܂Ɨ�����͗�
��OጂƓ����
��m�f�ՑD�̉�
��m�f�Ղ̐���
�������ɑ��锌���߂̏���
�l�A�F���̑Γ���/p30
���ʏ��i���
�����̓��{�����ւ�
�����s��
�ĕj�Ɛċ�
�܁A���m�����Ƃ̌���/p38 |
���Ðĕj�̊O���ӌ�
����f�ՂƗ����f��
���җՋ@�̏��u
�ĕ����Ə��̒���
�R�͒���
�Z�A��p����/p46
�����ˎ��̑���
����������莩�猈��
���A�����ېV�Ɖ��/p48
�����˂̐ݒ�
�ŐЂ̕��
�Ύx�W�̒f��
���A�������Ɨ�������/p50
��A��㊂̏O�W���ڂ݂�/p54
�E
�E |
���A���̔N�A���c�����u����̌�ʎj�v���u���s�o�Łv���犧�s����B�@pid/2994130
|
���
����@�_��̘b/p1
��ʂ̉\��/P2
����ƐM��/p4
�[�ӓ��̘b/p10
�ȒÌ���/p13
����@��ʂ̊J�n/p17
�����͂��܂�/p19
�O���@�����̂�����/p34
�����̑����Ɠ�����/p36
�����̎p/p41
�l���@��ʐe�P�̎���/p47
��ʔ��W�̉\��/P49 |
�����O���̌��/p52
��������̌��/p59
�G�g�Ɖ���/p71
��ʎj��̑m���̒n��/p76
�܊��@��ʔɌ��̎���/p93
�c�����̌���/p95
����g�b�̓����w��/p98
�������̖K��/p107
�����߉��̉���/p116
I�@���{�̑ԓx/p117
II�@�F���̑ԓx/p119
(��)�n���ƐŐ�/p120
(��)�����ƎF��/p126 |
(�O)����Ɩ��f��/p134
(�l)�ٍ��Ԃ�̏���/p139
�Z���@�����ېV�Ȍ�/p151
�ېV�̗����ɋꂵ��/p153
�Q�i��`�̔p�˒u��/p158
�p�˒u���̒f�s/p164
��㊋A�����̗���/p168
��藎����̉���/p174
����
�ꕔ�@��㊂ւ̂Ђт�/p178
���_����
I�@�̗w�ɂ���/p179
II�@�a�E�����ɂ���/p189 |
�����x
I�@��������̐����g�D/p195
II�@�y�n���x/p204
III�@�ыƐ��x/p209
���̑�
I�@�H�|�ʂ̌���/p211
II�@�����E����E�K��/p212
�@�{�y�ւ̂Ђт�/p220
�����ېV�Ɖ���/p220
�ʘH
��㊂𒆐S�Ƃ��Ă̌�ʘH/p233
�{�y�𒆐S�Ƃ��Ă̌�ʘH/p240
���Ƃ��� |
|
| 1958 |
33 |
�E |
�T���A�{�슰�Y���u�|�\�̓��E���d�R�v���u���d�R�|�\�㉇��v���犧�s����B�@
|
�v���O�����Əo����
���d�R�̎��R�Ɖ̕��i�c�ӏ��Y�j |
�����Ȗڂ̉���i�{�Ǔ��s�j
���̓��E���d�R�i�R�V�����j |
�����D�i�ɔg��N�j�D���d�R�|�\
�E |
�@�@�@�@�@�@�����G���s���}���� �����s�������}���� �����������}���� ���ꌧ���}����
�V���A�V�铿�S���u���Ô�̍H�H�l�ɂ��āv���u�V�铿�S�v���犧�s����B
�@�@�@�@���L ���ʎ��� ���������v�T����(1958�N7��)�@���ꌧ���}���ف@�@�����{�́u�������v�T�v�ɂV���Ă͖��m�F�@�Q�O�Q�R�E�U�E�P�@�ۍ�
�V���A�R�V���т��u��{�@�R�V���ю��W�v���u�����[�v���犧�s����B
�P�P���A�M�P���Ǖ����u�����Ƒܒ���l : �V�Ԑ^������a400�N�Օ�]�v���u���@�ю��v���犧�s����B�@�@
�@�@����:1938�N3����
�P�P���A�u���l��w�_�p 10(1)�@���l�s����w�J�w�\���N�L�O�_���W�v���u���l�s����w�w�p������v���犧�s�����B�@pid/1726965
|
���j�ɂ�������߂Ə��q�̖�� / ���F�F���Y/1
��Ƃ̍����o�ϓI�E�\�Ƃ��̑��� / ���c�p��/25
�P�C���W�A���̌n�̊�{�������ɂ��Ă̈ꔽ��/�����L�O�Y/47
�������f�ՂƏ��Ǝ��{ / ������n/81
�Y�ƍ`�p�̌`��--���{�`�p�o�ϒn��`���_����/���K�Y/101
�q������PR�v�z�Ƃ��̔ᔻ / �y���D�d/135
�ߑ㌴���v�Z�̉ۑ� / �g�c��Y/153
�ے��Ƃ��Ẳ�v / �����i/179
�X�^�b�t�̌o�c�Ǘ��I�Ӌ` / �X�{�O�j/205
�J�g�W�̊�{�I�ۑ�--�J���@�I���ʂ���̈�l�@/�ѐM�Y/227
�����̕�����--���@��\�l���ꍀ�̉���/���c���i/259
�������搿�����̌��p--�ؒn��̌������承�i
�@�@��(����)����̖�� / �ΐ엘�v/279 |
�ߋ��I���{�ɂ������j���[�g���ɂ���--
�@�@�������Ȋw�̎�e�̎d���ɂ��Ă̌����̎���/�O�}����/303
�`����w�I���̂Ɨϗ��w--�A���X�g�e���X�ϗ��w����/�Ύ�،���/365
�A���h����}�����I�_-6-���́s�_��t�Ɓs���t / ���ˌ��Y/391
�W�F�X�X��t�����V�X�R��J�u�����̈ꏑ�� / ���v�Ԑ�/423
���i�L�̎��ɂ���--�������w�j����-10- / �g���쑾�Y/455
������̓��َ�--�Y�ӓ����̓W�J�Ɣ͎��ɂ���/�c���v��/521
�A�����J�p��ɂ�����g�p���x�� / �R���K��Y/719
�}���O���[�u�Ɋւ��鏔��� / ���q��/p545�`578
�T�P��}�X�̊� / ����ʕv/p581
�}���K�j���g���[ / �c���`�Y/p635
�����V�̗����g��2,3�̎��� / ���^��/p649
�ʎq���v�͊w�Ɋւ����l�@ / �s�}��i/p683 |
�Q���A�u�w��������xNo.038�v���u�������{�����nj��������ہv���犧�s�����B
|
��̖����j(1)(�`�����_���Y)
(��������w��)���肯����̔��̍Đ��ɂ��Ă�
�@�@���ώ@(�ӎm�����Z �{��K�O�E���ǐ��s)
������Ƃ��������̐���(�ߔe���Z ���ꏟ)
���̎����Ɖ��w��i�ɑ����R��(�R�U���Z �{��O��)
�A�t���J�}�C�}�C�ɂ���(�m�O���Z ���c�`�O)
���t�^�ɂ���(�ߔe���Z �����הC)
�W�����̌ċz�ɂ���(���Z ��)
�~�~�Y�̍Đ��ɂ���(�����_�э��Z �ʌ�����)
�g���t�J�N�C�J�ɂ���(���Z ���z���M) |
�����ނ̐��F�̂ɂ���(���Z �`���K�q�E����a�q)
�ΐ�ߍx�ɉ���������ڂ̕��z��ԂƏo����(�ΐ썂�Z �m�O�)
�ԕ�(���Z ���ܖM��)
�ǒJ���ɉ�����A�����z(�ǒJ���Z �V������)
�Y�_������p�ƌ��̊W(���Z ��R��)
�l�̈�`(�k�R���Z ����z�q�E���@���[�q�E�n�v�n���q)
�V�_�̑O�t�̌`���Ɨ{��(�k�R���Z ��������)
(���z)40�N�̕ƒn������Ȃ݂�(���ɔ�����)
(����)�e���̓�������̌���(�������玑��)
�E |
���A���̔N�A�u���m���y�����@(14�E15) �������@���W�F�O�����̌����@�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s�����B
|
�_��
���m�̎O�����ɂ��� �c�ӏ��Y / p5
�O���̋N���ɂ��Ă̐V�� �ь��O / p15
�O���`���l �g��p�j / p29
�������y�j��(��) �R�����j / p55�`91
����
�u���v�̎O�����ɂ��� �c�ӏ��Y / p93
�Û����̎O���}�ɂ��� �g��p�j / p95
���k��
�O���t���͂�� / p101
���s�O���������\ / p129
�Љ�Ɣᔻ / p133
�u�������y�j�j�v
�u���m���y�j�v
�u�M�y�ӏ蒠�v
�u�����哇��揋ȕ��W�v
�u���k�̂��ׂ����v
�u���{��揎��؏W�v
�u�����O������Ӂv
�u�����|�\�v
�u�M�y���ȑI��ꊪ�E���S��v |
�u���y�����w�v
�u���y�|�p�w�v
�u���y����v
�u�V�䐺���听�����v
�u��y��E��v
�u�������̉��K�v
�u��r���y�w�v
�uMusikalische Volkerkunde�v
�uEthno�]Musicology�v
�uNovthern Indian Music Volume I��II
�uGroue��s Dictionary�v
�uJournal of the International Folk Music Council�v
�u♗��O�l�v
�b��
�{�w�����L�^�E�������\�v�| / p175
��������E�z�w�W�u�`��� / p228
�p���_���M���v�� /
�⺂̕��� �ݕӐ��Y / p231
�O���������ւ̎�� �g��p�j / p233
English Summary / p52
THE ORIGIN OF THE K��UNG�]HOU Shigeo Kishibe / p1 |
|
| 1959 |
34 |
�E |
�P���A���@���h���u�k���̐A�� = The Journal of Geobotany = The Hokuriku journal of botany 8(1) p.30-30�@�k���̐A���̉�v�Ɂu����̃t��������鋫�E���i��j�v�\����B
|
���@���h���u�k���̐A�� = The Hokuriku journal of botany�v�ɔ��\�����u����̃t��������鋫�E���i��`��j�v���̓��e����\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
��ȓ��e |
| 1 |
�@���m�F |
. |
. |
. |
| 2 |
�@���m�F |
. |
. |
. |
| 3 |
�@���m�F |
. |
. |
. |
| 4 |
6(2) p.61-61 |
1957-04 |
����̃t��������鋫�E���i�l�j |
. |
| 5 |
6(3)p.89-89 |
1957-07 |
����̃t��������鋫�E���i�܁j |
. |
| 6 |
7(1) p.5-5 |
1958-01 |
����̃t��������鋫�E���i�Z�j |
. |
| 7 |
7(2) p.64-64 |
1958-04 |
����̃t��������鋫�E���i���j |
. |
| 8 |
7(3)p.100-100 |
1958-07 |
����̃t��������鋫�E���i���j |
. |
| 9 |
8(1) p.30-30 |
1959-01 |
����̃t��������鋫�E���i��j |
. |
|
�Q���A���{�����w��ҁu���{�����w��� (5)�v���u���{�����w��v���犧�s�����B�@�@pid/2206571
|
�Ί_���̕䗘�� / �{�c����/p1�`9
�����哇�̐�c�� / �k���r�v/p10�`13
�떓�̑� / �{�{���F/p13~16
��㊒|�x���̘b /�� �����B�v/p17�`30 |
���V���̈��s���Ɛ��n�M�� / �ɓ�����/p31�`43
�ŋ߂̃h�C�c�����w�W���� / ��[�L�F/p43�`43
�_���Љ� ����d�N���w�Ă̌������_���T���x / �������v/p44�`45
�V���Љ� �w��L�� ����/p45~48 |
���{�����w��� (6) ���{�����w�� �� ���{�����w�� 1959-03pid/2206572/1/1
|
���i���Ƃ킴�j�̋���I�����ɂ��� / �員�䂫/p1�`5
�̘b�ɒ�������������M / ����/p5�`9
�M�B���{�n���̎��[�l�`�̌��� / �c����/p9�`12
���V�c���̑� / �a�c���v/p13~14
�g���{�K�~���杁\�\����]�֣̎�NjL / �א�q���Y/p14�`15
��㊒|�x���̘b(2) / �������B�v��J�c/p15�`23�@�@
�ɓ�������̎�ґg / �h��/p24�`27
|
�g�c�̌�t�̎��� / ��X�`��/p27�`33
���h�����̖��� / �|�c�U/p33~40
���] ���w�@��w�����w�����O�\��N�x�����̖K��L���s��������
�@�@����ےÐ��\���̃K�}�̌���� / �ŏ�F�h/p41�`42
�V���Љ�E趎��v��/p42~45
�w��L���E����/p45~47
���ڎ�/P48~49 |
�S���A�u���x���� (9)�v���u���x�����k�b��v���犧�s�����B�@�@pid/6064257
|
���_�M�̌����ɂ��� / ��V���͎�/p1�`1
���Ɛ��_ / �ŏ�F�h/p1~4
�Ƃ̐_�̐��_�I���i / ���c�m��/p4�`7
���M�Ɛ��_�M�� / �哇���F/p7�`11
��������� / �\�c����q/p11�`12
�����n���̐��_�M�̏��� / ��������/p12�`14
�b��̐��_ / ��X�`��/p14~16 |
�쐞�G�L / �r�c�a��/p16~19
�]��O�L�̐��_ / �א�q���Y/p19�`21
�����哇�̐��_ / �R������/p21�`22
��㊂̈�˗�q / ���c����/p22�`25
�E���f�B�[�l / ��[�L�F/p25~28
��Ɋւ���P���g�̖��ԓ`�� / �Ό��V��/p28�`29
���Ƃ���/p30~30 |
�S���A�R�����j���u�����|�\�S�W ��1 (�����̉��y�|�\�j) �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@
�@�@pid/1658749�@�@552p,�}��12 �@�����F��㊌����}���فF1004846562
|
���G�ڎ�
��i�P�j�@�Ԓ�y����q�̖쑺�H�H�l�̏��������̊�
��i�Q�j�@�ƌn���R�����x�i�����O�\�Z�̐�j�̉r��
�O�m��i�R�j�@���h���̏ё�
�O�m��i�S�j�@��������n�߂ɗw�����D�����̕���
�O�m�O�i�T�j�E�l�i�U�j�@���{�̂����낳�����Ƃ��̊y��
�l�m��i�V�j�E��i�W�j�@�v�����̂�B�̐_�V�тƂ�����̎���
�l�m�O�i�X�j�@���������̎��̂�̜ԚL������̎��Ƌȕ�
�܃m��i�P�O�j�E��i�P�P�j�@���삢�ɂ�Ƃ��̎��Ƌȕ�
�Z�m��i�P�Q�j�@�ďꂨ�ԁi������N�̂��V���莮�T��j
�Z�m��i�P�R�j�@�����T�ɗw��ꂽ���삢�ɂ�̎��Ƌȕ�
���m��i�P�S�j�E��i�P�T�j�@�P���ۂƂ��̎��Ƌȕ�
���m��i�P�U�j�E��i�P�V�j�@�~�x�Ƃ��̎���
��i�P�W�j�@�O���̂̎���
��Z�m��i�P�X�j�E��i�Q�O�j�@�������Ƃ��̎��Ƌȕ�
���m��i�Q�P�j�E��i�Q�Q�j�@���Y�n�Ƃ��̎��Ƌȕ�
���m��i�Q�R�j�`�O�i�Q�T�j�@�؈�ƍ����J���E�؈�̎���
��O�m��i�Q�U�j�E��i�Q�V�j�@���˕��x�Ƃ��̎��Ƌȕ�
��l�m��i�Q�W�j�E��i�Q�X�j�@�v�Ă̐��_�Ƃ��̎��Ƌȕ�
��܃m��i�R�O�j�E��i�R�P�j�@�ʼnԌۂ̗x��Ƃ��̎��Ƌȕ�
��Z�m��i�R�Q�j�`�l�i�R�T�j�@গ��D�����Ƃ��̎��Ƌȕ�
�ꎵ�m��i�R�U�j�E��i�R�V�j�@�j�g�����Z�Ƃ��̋��ە�
�ꔪ�m��i�R�W�j�`�O�i�S�O�j�@�\�ӕ��Ɯ\�Ӑ߁E���̂̎��Ƌȕ�
���m��i�S�P�j�E��i�S�Q�j�@�l�|�x��Ƃ��̎��Ƌȕ�
��Z�m��i�S�R�j�E��i�S�S�j�@���q���Ƃ��̎��Ƌȕ�
���i�S�T�j�@�쓇�x
���m��i�S�T�j�@�c��g�̍s��ƘH���y��
���m��i�S�V�j�@�H���y�̊y�ȑ���
��O�m��i�S�W�j�E��i�S�X�j�@�c��g�̌���y���t�Ƃ��̊y��
��l�i�T�O�j�@���y���t
��܁i�T�P�j�@�O�������J��
��Z�i�T�Q�j�@�V�^�O���P�[�X�ƉƓ`�̎O��
�m��i�T�R�j�`�l�i�T�U�j�@���y�̃I�[�P�X�g�����Ƒ��ҋȑ�����
�m��i�T�V�j�`���i�U�R�j�@���y���̗��j
���i�U�S�j�@�ɍ]�����搶�̏��M�Ɨ���
�O�Z�i�U�T�j�@�_�R���ǐ搶�̕���
�O��i�U�U�j�@�J�c�T�[�h��̗��y���w
�O��i�U�V�j�@�J���c�E�U�c�N�X���m�̃T�C��
�O�O�i�U�W�j�`�i�V�Q�j�@�����[���q�ܑ�R���ƌn
�O�l�i�V�R�j�`�i�V�T�j�@���ۉ�c�_���Ƌc����
|
�i�V�U�j�@���ٔ鏑�T�C��
�ڎ�
�������y�̂��肩���Ƒ̌�/3
��A�@��y/12
I�@�ŗL�|�\/12
II�@���{�|�\�̗���/59
III�@�x�ߌ|�\�̗A��/99
IV�@�s������/119
��A�@�O���ƎO���y/154
I�@�O���y�̔����Ɨ�������/154
II�@�����̗w�̎��^�Ƃ��̔����@
�@�@���\�{�M�̓s�X��̌��c�ɂȂ������́\/177
III�@�O���y��/193
IV ���y���H�l�̉��v/218
V�@�y�T�_/242
�O�A�@�O���y�̗��h�Ɗy�Ɨ�`/297
�ÓT�y�̕����Ɩ{�M��̌ې�/297
I�@�X����/299
II�@���o��/327
III�@����/338
IV�@���x�c��/375
V�@�쑺��/387
VI�@���x�c���Ɩ쑺��/421
�l�A�@����/430
�܁A�@��������/445
I�@���̖͐̂�V��/445
II�@���e��/455
III�@�̂Ɍ���ꂽ�p��/464
IV�@�����]���̂Ɛ̗̂���O����/467
V�@�c�ӏ��Y�搶�𗮋��Ɍ}��/470
VI�@���R�����搶�̂���/473
VII�@�掵�ۖ������y��c�ɏo���L�^���z/474
VIII�@�O�l�E�݊O���y�l�̗��y��/490
�Z�A�@�킪�w���ƌ���/494
I�i�w���j�@���@�ɂ���ĉ������E�����̔��˂ƍ����̒n
�@�@���@�\�~���[�ŋ����ė����ō����\/494
II(�w��) �ꌳ�_ �\�������@�̌��_�\/507
III(����) �w�u���C�����Ɨ����|�\/513
���A�@�e�ʂ̂��Ƃ�/526
���A�@���Ƃ���/550 |
�W���A�u�|�p�V�� 10(8)�v���u�V���Ёv���犧�s�����B�@�@
|
����̌|�p�n�}�@�@�R�V�� �� p.42�`46
��Ƃ̂����H�|--
�@�@���s�����p�u�����Ɣ��p�v�W���݂� �����͑��Y p.143�`145
�_�X�̕ϖe-4- �}�����I A,���� �� �� p.47�`53
���͐��E����--���E�ꗬ��]�Ƃ̐���8�l�̍�� p.54�`73
���E���p�j���f-2- �g�� �펡 p.74�`82
���{�|�p�ւ̒��� �U�b�L�� O. �� p.84�`101
���|�H���ƒn����� �Έ� �ߎO p.218�`221
���W�E����Ȕ��p��]�Ƃ��� �F�� �O �� p.102�`120
����"�c����w"--
�@�@�����閯�Ԍ����Ƃ̃v���t�B�� �|�c�����Y p.121�`123
�T�̏�--�����W���݂� �e�[�� C.S p.124�`126
�U�����J�@ ���� �p�� p.127�`129
�K�E�f�B�B�e�L ���g�͌� �G p.139�`142
|
��Ƃ̂����H�|--
�@�@���s�����p�u�����Ɣ��p�v�W���݂� �����͑��Y p.143�`145
���m���p�ق͊J�ق�������� �v�ے原�Y p.146�`157
�V���̉^��-2-�@�@�������[ p.158�`163
�ʐ^�Ƃ̊O�V �y�匝 p.173�`176
���W�E����N��Ƃ̎�--
�@�@����ۊG��ɏ}�������R�N�� ����Ēj �� p.188�`203
�T�[�J�X�����_--�`�F�R�E�T�[�J�X���ς� ���q �S�� p.204�`206
���b�l--������n��l-8- ���� �V�g p.225�`237
�Z���t�̂Ȃ����f��--�u���̓��v�ւ̈�̎��݁@�V�����l p.244�`248
���郆�_���l�̎� �j ���L�q p.256�`260
����l�̂��߂�LP300�I-8- �g�c�G�a p.262�`273
���W�E�V�˂͂ǂ��֍s�� p.274�`296
�E |
�P�Q���A�����v�q�����y�V�F�Еҁu���y�|�p 17(13) p.39�`43�v�Ɂu�����̖������y�̓����ɂ��āv�\����B
���A���̔N�A�u����啜���H�����v���u�������{�������ی�ψ���v���犧�s�����B
���A���̔N�A�ɔg��N���u���ꕗ�y�L�v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/9543485
|
�͂�����/1
�_�������މ���/11
���{�Ɨ���/17
�l���̘b/30
�N�앗/41
��M�̎��l���[�i�r/49
�h�̉�/63 |
������/70
�����̍r��/81
�E����/92
�����̖��t������/99
�{�Ó��̃A���S/110
�l����/131
���d�R�Q���̖��w/136 |
�A���̘b/166
���̗��{/171
���n����/183
�������v/188
���̘b/201
�����̕��x/213
�Ŏւ̘b/219 |
�����̉��y�Ǝ֔��/230
�쓇�̐A��/236
�����Ύ��L/244
��㊂��̂��������/281
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�u�������v�� 1959�N�Łv���u�����������ی�ψ��v���犧�s�����B�@pid/2526634
|
�}��
�@�߁A�K��/p1
�������ی�@/p2
�������ی�ψ���c���K��/p7
���������R�c��K��/p8
���������R�c��c���K��/p9
���ʏd�v�������y�яd�v�������w�菑�K��/p9
�j�ՁA�����A�V�R�L�O���ۑ��{�K��/p14
���ʏd�v�������y�яd�v�������䒠�K��/p14
�j�ՁA�����A�V�R�L�O���䒠�K��/p15
���ʏd�v���������͏d�v�������̊Ǘ��Ɋւ���
�@�@�����o�����Ɋւ���K��/p15
���ʏd�v���������͏d�v������
�@�@�����n�\�o�����Ɋւ���K��/p16
���ʏd�v���������͏d�v�������̏o�i����
�@�@�����J�̐\�o�y�є�p���S�Ɋւ���K��/p17
���ʏd�v���������͏d�v�������̏o�i����
�@�@�����J�ɋN�����鑹�Q�̕⏞�Ɋւ���K��/p17
���U���������@���o���K��/p18
���ʎj�ՁA�����A�V�R�L�O�����͎j�ՁA�����A
�@�@���V�R�L�O������ύX�����\���K��/p19
��Ք������o���K��/p20
�������ی�@�̋K��ɂ���t�����⏕����t�K��/p20 |
���ʏd�v�������A�d�v�������w����тɐ��/p22
���ʎj�ՁA�����A�V�R�L�O���y�юj�ՁA�����V�R�L�O���w��/p23
�����̑[�u���u���ׂ����`�������̑I��/p24
���������̎w��/p24
�w�蕶�������T/p25
�w�蕶�������/p31
�O���� �q�̓앗��/p32
�O���� �앗��/p32
�O���� �m�O��H/p33
�O���� �v��t�a/p33
�O���� �v��t�a/p34
�O���� �v�t�̍�/p34
�O���� ����/p35
�ʗ˔�/p35
�V����/p36
������/P37
������/p38
�ψ����/p43
������/p45
�����̎O���� �r�{��P/p45
���d�R���ԓ����X�L�˔��@�T�� ���{�G�� C�EW�E�~�[����/p55
�X��p����R�L�˂̒����T�v �����j ���a�c�^�~/p78
�ÉF�����̊C�_�� �R��A���A�V��/p95 |
|
| 1960 |
35 |
�E |
�U���A�u�������v�� 1960�N�Łv���u�������{�������ی�ψ���v���犧�s����B
|
�}��
�w�蕶�����ꗗ/p1
���`�������ꗗ/p7
�w�蕶�������/p11
�������/p12
�|�x���U����/p12
���A�m�������n��/p13
�q�W�싴�y�ю�t���H/P13
�m�O���/P14
�������/P15
��u����/P16 |
�D�Y�̃j�c�p���V�Q��/p16
�����̃q���M�A�~�~���`�V�_�A
�@�@���m���V�Q��/p17
���Ԑ�̃q���M��/p17
�D���̃��G���}�n�}�S�E/p17
�r��̃J���r�U�N��/p18
�Č��̃m���V/p18
�{����Ԃ�
�@�@�������L���E�`�V���m�L/p18
�{�ǐ�̃q���M��/p19
���v�ۂ̃��G���}�V�^��/p19 |
�c�����p�̃q���M��/p20
���g�̃T�L�V�}�X�I�E�m�L/p20
���g�̃^�C�i�K�[�O���C�A���Q�p/p21
�F���̑�\�e�c/p21
�v�Ă̌}�̏�/p21
�ψ����/p28
�����̍����u�䊥�D�x�N���v �r�{��P/p29
������
�����̊L�˕��z�ƕҔN�̊T�O��� ���a�c�^�~/p32
�Î�[���L�˔��@�� �V�c�d�� �������G/p39
��u�쑺�A�J�a�����K�[��Ւ����T�� ���{�L�q/p64 |
�V���A����G���u���ꔪ�d�R�v���u�Z�q���[�v���犧�s�����B (������c��w�l�Êw�������� ; ��7��)�@pid/3026330
|
���@��l�M��
�쐼������K�˂ā@����G/p1
�����@����G/p3
���d�R�̐M�ƌ|�\�@�{�c����/p11
�����̐_�X/p13
�E�u�E�����̉�/p15
����/p16
���X�̍�/P16
�|�\�̏�/p18
����/P20
����/p21
�Ԃ܂����܂�/p22
�j���ƖԂ݂̂�/p23
গ��D/P23
�A���K�}/p24
���q��/p25
�_�x/p26 |
���x/p26
���d�R�̗w/p26
���d�R���x/p27
�w�ȁE����/p28
�u��/p30
�g�x/p30
���d�R�̗w�ꗗ/p30
���d�R���x�ꗗ/p32
���d�R�̗̉w/p34
��A�^�ߍ����̗x��/p34
��A���\���̍Չ�/p36
�O�A���ԓ��̗̉w/p43
�l�A�����̗x��/p46
�܁A�|�x���̉�/p47
�Z�A�g�Ɗԓ��̉�/p49
���A�Ί_���̌×w/p55
���A�Ί_���약�̉�/p62 |
���A�{�Ó��̐������₮/p66
�����d�R�Q���̐A���̐��ԁ@�c�Әa�Y/p69
���d�R�Q�����������̊T�v�@���鐴��/p77
���d�R�A�N�Z���g�̊T�ρ@�H�i��}/p93
���d�R�̍l�Êw�@�������q�@�ʌ����Y�@
�@�@�@����쐴�@�l����/p101
�g�Ɗԓ������c���L�ˁ�
���\�������ԑ��E���ѕ����L�ˁ�
�Ί_�����R���L�ˁ�
����
����@����G/p165
�k���^�l
���d�R�̘m�Z�ɂ��ā@
�@�@���V�C�ی��@�����g����/p176
��㊂̋I�N�@�@���c�F�N/p181
�g�Ɗԓ��̐A���@���a�c�^�~/p188
�E |
�P�O���A�O�����Y���|�\�w��ҁu�|�\ 2(10)(20)�@p65�`65�@�|�\���s���v�Ɂu����G���u��㊔��d�R�v�v���Љ��B
�P�O���A���H�}��������Еҁu���z�E 9(10) �v���u���H�}���v���犧�s�����B�@�@pid/2205679
|
�����J�Еa�@�����@(�]�x���a�@) / ���X�d�F/p1,p51
�Љ�ی����l�����a�@ / �R�c�猚�z������/p4,p56
�k�撡�ɋy�ь�� / ���z���[�h������/p6,p60
�咣��A�����J���ꏄ���ģ / �R���o/p9
1945-1959 ���(3) / �����v�Y/p11 |
�������y�L(���䌧�̊�) / ���c�O ;�]��O�l/p16
�����u�˂̖���-����w�̏Z�� / �Ό�����/p23
��X�X�|�[�c�L��v��� / ���������Y/p30
���{���z�̊C�O�i�o�ɂ��� / ���c�Òj/p36
�� |
�P�P���A�u���y�̕����� ��13 (�F�{,�{��,������,����)�v���u�فv���犧�s�����B�@pid/2476207
|
�F�{���̕����� ���v�d��/p1
�i�ȗ��j
���������̕����� �⌳����/p63
�i�ȗ��j
����̕����� �������i �O�Ԑ��K �����v�Y �V�铿�S �R���③ ���a�c�^�~/p93
����̕������ی�{�݂���ѐ���/p95
�ߔe�s/p96
�k��/P114 |
����/p123
�암/p129
�擇/p134
�n��ʎw�蕶�����ꗗ
�F�{��/p145
�{�茧/p155
��������/P160
����/p166 |
���A���̔N�A�|�������u��̊�E���j�v���u����������v���犧�s����B�@�@
pid/2993985
|
��E���j�N��\/p15
���́@��E���̒a��
��̖���/p1
��@�S�K���̂͂Ȃ�/p5
�O�@�S���N�ȑO�̊�E��/p7
�l�@��������l���Z��/p9
�܁@�Z���̐�c/p14
�Z�@��������̈�K/p21
���@�Z�g�C�_�̗����q/p26
���@�V�����Ƃ̂Ȃ���/p31
��@��a���t���g������/p32
��Z�@�Â������̃i�]/p35
���́@�{�y�Ƃ̌��т�
��@�쓇�Ƒ�a����/p39
��@�ג��̗���/p41
�O�@�r���������ꂽ��/p49
�l�@�����ؑ��̗���/p52
�܁@�����̋M�C������/p71
��O�́@����Ƃ̊W
��@���v�̂Ă�܂�/p73
��@�@�x���Ɗ�E��/p75
�O�@���A�l�̎q��/p76
�l�@�������D�̏P��/p79
�܁@��C�̐勫/p83
�Z�@���Â̗�������/p87 |
��l�́@���������̋��
��@�{�y�ւ̕��A/p94
��@�ˍ����Ə����ւ̎{��/p95
�O�@�哇��s���̐ݒu/p104
�l�@���a�̌Ð����v/p104
�܁@��E���㊯���̊J��/p109
�Z�@���������̂͂��܂�/p115
���@�˒��̍������グ/p116
���@�����̑��Y�Ɠ����̔_�z��/p119
��@������[/p129
��Z�@�������グ�ւ̒n�Ȃ炵/p130
���@�o�ϓ�吭��̂���/p145
���@�N���̐ϋɐ���/p151
��O�@�n�_�̓z�ꉻ�Ƃ��̑�/p167
��l�@�ː�����̐Ő�/p176
��� ���X��/P188
��́@�V����ւ̕����
��@�t���ɕ����ԓ��̎p/p196
��@���x�̉��p/p204
�O�@�x�@���x�̔���/p215
�l�@�s�������̈ڂ肩���/p220
�܁@���琧�x�̐L��/p226
�Z�@�ʐM�E���/p239
���@�d�C/p249
���@���Ɣ��W�̑��ǂ�/p250 |
��@���̑��̎Y��/p272
��Z�@�����m�푈�Ɗ�E��/p290
���@�ČR�����̓��̕����/p294
��Z�́@�@���E�M��
��@���쐒�q/p297
��@����/p302
�O�@�L���X�g��/p305
�l�@�V����/p307
�܁@��{��/p310
�Z�@���E���a���c/p310
���@�_�Е��Ղ̗R��/p312
�掵�́@���j�����ܘb��
��@�s�J�s�J�����E�̋�R/p325
��@�F�q�\��/p326
�O�@���l/p327
�l�@�����̏㍑����/p333
�܁@������@�̌��B/p334
�Z�@���w�̍Đ���/p336
���@�̐l�[��̂���͉�/p338
���@�m�ԉ����/p339
��@���]�������ƈꓝ/p339
��Z�@����̖��o�w��/p343
���@�n�����J�ҁ\�T���L��/p345
���@�Y�����E�Y���D�E�O���D/p348
��O�@�l���Ō��铇�̗��j/p354 |
���A���̔N�A�{�c�������u�}�^���{�̖����|�\�v���u�����V���Ёv���犧�s����B�@pid/9580731
|
���{�̖����Y�\/1
�����Y�\�̊T��/5
(1) �_�y/8
�i�C�j �ޏ���/11
�i���j �{��̐_�y/11
�i�n�j �o�_���̐_�y/12
�i�j�j �ɐ����̐_�y/14
�i�z�j ���q�_�y/15
(2) �c�y/16
�i�C�j �\�j�s��/16
�i���j ��c�A�_��/18
(3) ����/19
�i�C�j �O���x/20
�i���j �~�x/21
�i�n�j ���ۗx/21 |
�i�j�j 㹌ێ��q��/22
�i�z�j ���̗x/22
�i�w�j ���x/23
�i�m�j ������̕���/24
�i�`�j ��������/24
�i���j ���蕗��/25
�i�k�j �A�C�k�̕��x/25
�i���j ����̕��x/25
(4) �j���Y/26
�i�C�j ���K�_/26
�i���j ��H����/27
�i�n�j ������/27
(5) �O����/28
�i�C�j ��y/28
�i���j ���y/28 |
�i�n�j ���N/29
�i�j�j ��\�ܕ�F���}��/31
�i�z�j �U�y/32
�i�w�j �\�E����/32
�i�g�j �l�`�ŋ�/33
�i�`�j �̕���ŋ�/34
(6) �ʁE�y��/35
�i�C�j ��/35
�i���j �y��/35
�Y�\�̌��p/37
����/38
(1) �����Y�\�E���y�Y�\/38
(2) �Y�\�̒�`/38
(3) �s�����Y�\��/41
(4) ���y�Y�\�̓��F/43 |
(5) �����Y�\�����̗��j/44
(6) �̏W�@/47
�~�x����t�B�[�`���[����
�@�@�����{�̖������x/49
�S�������Y�\��i�s���{���ʁj/55
�㋞�����Y�\�ꗗ/86
���y���x�Ɩ��w�̉�/86
�S�������Y�\���i�Y�p�Ձj/89
�s���{���ʌf�ڐ}�^/93
���{�̖����Y�\�Q�l����/98
�����Y�\���z�}/����
���Ƃ���/121
�}�Ŗژ^
�E
�E |
���A���̔N�A���a�c�^�~���u�T���i�E�R���j�l�v���u���ΎY�ƌ������v���犧�s����B�@���L �d�q�����ʋ@�ɂ�镡���@pid/12616363�@�@�@ |
| 1961 |
36 |
�E |
�R���A�u������������ (10)�v���u��y�@���w�@,��y�@���w�@������,���������������v���犧�s�����B�@pid/4417918
|
���厛�\�ⓚ�ɏA�� / �ݐM�G/p1�`15
�M�@�ƐM�@ / ����m�Y/p17~25
�@�R��l�̏�y��-���̎��@���������߂�����/���g���C/p27�`38
�@�R��l�G�`�̎�ނƂ��̌n��̍l�� / ����c/p39�`52
���M�[�X��ɂ���--���Ɏ������N�����y�юl���`��
�@�@�����҂Ɋւ��鎄�� / �O�c�S�M/p53�`67
�@�R��l�s���}�̍O�`�ɓw�߂��l�X- |
�@�@����ɉ�����J�ɂ��� / �����S��/p69�`83
�@�R��l�Əd����l--���P����t���̈�l�@ / ���Ҍ���/p85�`95
�@�R��l�`������ҁu�@�R��l�`��
�@�@�������j�I�����v��1�� / �k���O/p97�`99
�b��/p101~102
�u�������������v(��6���`��10��)���ڎ�/����1�`�Q
�E |
�T���A�����v�Y�ҁu����̏� : �w���ꌚ�z�m�x��Փ��W�� �암�ҁv���u���ꌚ�z�m��v���犧�s�����B
�@�@�@�����{�@23p�@�����F���ꌧ���}���فF1008904391
|
��
����̏��
��u����
��R��� |
�Đ{���
�������
�ʏ���
�m�O��� |
�嗢���
�_�ԏ��
���c�����
��u����� |
�����
���
����̏�Օ��z�}
�E |
�U���A�V�Ԑi��A�u�c���`�A��쌚�u�����{�̗w�W�� ��2�v���u�������o�ŕ��v���犧�s�����B�@�@pid/1356271
|
�͂�����
���
���@�����N����/7
��@�J��/7
��@�啗��/8
�O�@������/11
�l�@�A��/12
�܁@�A���{�i�Z�a���{�j/13
���@���鎛�`�L�����J��/15
��O�@�ِ��鏴���`��/19
��l�@��v���Ȋ��E�P�c�r�ܘY/23
��܁@�V�ҋ����̗w�W/26
��Z�@���m�����T���̉�/29
�掵�@���ׂ���/30
�攪�@������w�����J��/31
���@�O�B�݊y�S�̓c�́i�V���̓c�́j/32
��\�@�Ì˓c�y�̗̉w�Ǝ���/34
��\��@��ˍ��v�c�S�X
�@�@�������{�c�_�Սs�V���E�x��/36
��\��@���������R�_�А_����/37
��\�O�@��B���c�A�S/37
��\�l�@��㍑���h�{��c��/39
��\�܁@�c�A�̂Ȃ�тɔ_�k�_���̗w��/40
��\�Z�@��Ï鉺�����啍�̕��g�E
�@�@���\�퐔�̎�/41 |
��\���@�}�O�����N�n��������̓�/42
��\���@�J��x��/43
��\��@�x�̗�/43
���\�@�n���̗w��/45
���\��@���{���y�L�̎R��/45
���\��@���ꑐ�q�̗w�Ə��̗�/46
���\�O�@������/47
�{��
���@�����N����/49
��@�J��/51
��@�啗��/65
�O�@������/89
�l�@�A��/111
�܁@�A���{�i�Z�a���{�j/129
���@���鎛�`�L�����J��/139
��O�@�ِ��鏴���`��/149
��l�@��v���Ȋ�/161
��܁@�V�ҋ����̗w�W/173
��Z�@���m�����T���̉�/209
�掵�@���ׂ���/213
�攪�@������w�����J��/219
���@�O�B�݊y�S�̓c��
�@�@���i�V���̓c�́j/229
��\�@�Ì˓c�y�̗̉w�Ǝ���/237
��\��@��ˍ��v�c�S�X |
�@�@�������{�c�_�Սs�V���E�x��/279
�s�V��/280
�x��/283
��\��@���������R�_�А_����/289
��\�O�@��B���c�A�S/305
��\�l�@��㍑���h�{��c��/321
��\�܁@�c�A�̂Ȃ�т�
�@�@���_�k�_���̗w��/327
��\�Z�@��Ï鉺�����啍�̕��g�E
�@�@���\�퐔�̎�/343
���g�m��/344
�\�퐔�m��/344
��\���@�}�O�����N�n��������̓�/347
��\���@�J��x��/351
��\��@�x�̗�/361
���\�@�n���̗w��/371
���\��@���{���y�L�̎R��/377
���\��@���ꑐ�q�̗w�Ə��̗�/383
��/385
��/391
���\�O�@������/399
���@��\�l��㍑���h�{��
�@�@����c�̕��/407
�E
�E |
�U���A�u�������v�� 1961�N�Łv���u�����������ی�ψ���v���犧�s�����B�@�@
pid/2527202�@�@�d�v
|
�}��
�@�߁E�K��/p1
�w�蕶�����ꗗ/p29
�����������`������/p37
�������ی�s���̊T�v/p43
�w�蕶�������/p47
�ʏ���/P49
�_�ԏ��/p49
�ɑc���/p51
���c�����/p53 |
�ɔg���/p55
�ɕ~�����/p57
��u����/P59
���i�̕�/p61
����q�a�̐Ԗ،Q/p62
���~���̃n�}�W���`���E�Q��/p63
�E�u���h���̃m�V���Q��/p64
�ψ����/p65
������/p67
�������b�̌��� �V���~�K��/p67 |
�㗢��̒����� ���O/p77
�����̞����ɂ��� �O�Ԑ��K/p93
�����ɂ������Ղ̓y��A�{�b��A����A
�@�@�����̎���敪 ���a�c�^�~/p121
�ԃC���R�̈�� ���{�L�q ���a�c�^�~/p133
�Ì��L�˔��@�� �������G/p145
�c�NJԏ����̈�Օ��z�ɂ��� �V�c�d��/p163
������̗R���y�э\���`��/p167
�E
�E |
�X���A�ߋE�����w��ҁu�ߋE���� = Bulletin of the Folklore Society of Kinki : �ߋE�����w���� (28)[(35)]�v���u�ߋE�����w��v���犧�s�����B�@�@pid/6046009
|
�����Ί_���̔N���s�� / �ې參��/p1�`5
���Ẩ����� / ���{�S�j/p5�`11
�k�͓��S��쒬�̋{������(��) / ���J�d�v/p11�`20 |
�l�`���� / ���v�`/p20~24
���k�n���̐A������ / ��c�l�Y��/p25�`30
��G��/p31~31 |
�o���ċg���N�� / �㓡����/p33�`35
�E
�E |
�P�O���A�q���P�u�v�z (�ʍ� 448) �@��g���X�v�Ɂu����ɂ����閯���ӎ��̌`���Ɣ��W--���̉���j�ɂ����āv�\����B
�P�P���X���A�c�Әa�Y������c��w�C�O�����T�������Ƃ��ăL���}���W�����ɓo�R���A���a���ăi�C���r�̕a�@�ŖS���Ȃ�B�i���N�G�U�P�j
�P�Q���A �w��㊕����x�ҏW�� �ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka (5)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437723
|
�^�얩�蕶�ɂ��� / �����P��/p2�`10
�АΏ� / �����[����/p11�`12
�����Q���^�_���̃V�j�O�Պnj�/����O/p13�`17 |
�O�V�N�l / �����\�G/p18�`23
�����ȗ��̖��ᗥ�ɂ���(4)/��l�G��/p24�`28
�悤�ǂ�Ί��ɂ��� / �O�Ԑ��K/p29�`34 |
�ɔg���Q�I�W�̓��e/p35�`35
�����Z�M/p36�`37
�E |
���A���̔N�A��������w, ������w�ҁu��������w,������w������������������
��1���v���u��������w�v���犧�s�����Bpid/3002615�@�k�戵���Ӂl
|
�P�D�@�J��n�̔_�ƌo�c�\����Ί_���ɂ�������Ԓ����\ �r���^��E�R�����W/p1
�Q�D�@���������̒{�Y�̎��� �ѓc�d�K�E���z���g/p13
�R�D�@�^�ߍ��������ۗ� ���r��E�c�����Y/p30
�S�D�@�^�ߍ����̐��Y�� ���m�Y/p41
�T�D�@��㊓��ߔe�s���߂̗��N���� ���c���Y�E�R����/p46
�U�D�@�Ί_���̗��N���� ���c���Y�E�R����/p53
�V�D�@������p�Y�T�c�}�C�i�������ɂ��āi�p���j �����Z�F/p61
�W�D�@���������ɂ�����l�R�u�����ɂ��āi�p���j �a�J�����E���ǓS�v/p67
�X�D�@���������ɂ����鐸�_���҂̏����̌����ɂ��ā@���������ɂ����鐸�_�a�Ɋւ��钲���i��P���j
��������/p70
10�D�@���������ɂ����鐸�_�a�̒n���F�ɂ��ā@���������ɂ����鐸�_�a�Ɋւ��钲���i��Q���j ���������E�O�c����/p79
11�D�@���������ɂ����鑭�Ԃ̖��M�ɂ��ā@���������ɂ����鐸�_�a�Ɋւ��钲���i��R���j ��������/p81 |
���A���̔N�A���쐴�q���u��������̒��̏��v���u�O�ʎЁv���犧�s����B�@�@�@�@�@pid/9543883
|
�łƗ���
��`���ɋA���/8
����������ɋA���/11
�Ȃ̈ʒu/19
���̍�/27
�Ƃ̂����l/39
���̏�����
�C��/50
�ݝ��S/52
������/60 |
�ԉg�S/63
�ЂƂ̊�/66
�̘b�̏���/71
���ꂩ��/79
�ߐ����Ə����̖�����/91
�ԉł̑r��/101
�Q��̗��j/111
�e�̂���\�~�\/127
�\�ܖ�̎q��/135
�O��̎q��/145
|
���O�̂���/155
���Ƃ�/165
�N���X�}�X���炨������/173
�������Ǝᐅ/183
�ЂȂ܂�/191
���َq/199
�[�߂̐ߋ�����Ȃ�/205
���Ƃ���/212
�E
�E |
|
| 1962 |
37 |
�E |
�U���A�u�w�蕶�����ʐ^�W�v���u�����������ی�ψ���v���犧�s�����B137p �@�����F��㊌����}���فF1003727458
�X���A�M�Z�j�w��ҁu�M�Z [��3��] 14(9)�v���u�M�Z�j�w��v���犧�s�����B�@�@pid/6069636
|
�k���W�l �_�Ƃ̔N���s���ƐH��
�@�@��--�M�B�ɓߌS�ѓ����ѓ��Ƃ̎��� / �����`��/p2�`11
�k���W�l �������S�h������n���ɂ�����
�@�@���Y��V��ɂ��� / ���ʐM�v/p12�`18
�k���W�l �����o��--���̒�N / ���R�M���Y/p19�`23,18�`18
�k���W�l �a���̔O���x�� / �����_/p24�`37
�k���W�l ���Ԏ�̍�@�ɂ�����z�K�M�� / ��t����/p38�`46
�k���W�l �u������ڂ��v�Ɓu���ǂ��v�̕��� / �͌��G/p47�`54
|
�k�Ǔ��l ���c���j�搶�����Âт��� / ���Y/p55�`57
�k�Ǔ��l ���c���j�搶�̊w���lj����� / ���Ԑ�/p57�`59
�k�V���Љ�l��ؖq�V�u�H�R�L�s�v / ���H����/p60�`60
�k�V���Љ�l�u��̊������_���̌����v
�@�@��(��؎�) / �����g�� ;���c�� ;��ؖ��v ;���������N/P61~62
�k�����l �������/P64~64
�k�����l �ҏW��L / �˓c����/p64~64
���G �a���̔O���x�� |
�P�P���A���쐴�q���u���̂͂��炫 : �ߐ����̗��j�v���u�����Ёv���犧�s����B�@�@�@pid/9544266
|
����D����������/7
�R���ƌĂꂽ����/7
�Ȕ����E������/14
���̋@��/19
�����q�̋@��/27
���̒J�̕ϑJ/32
�@�D�S/37
�֓��̋@��܂��/44
�������ƍ��茦/44
�����/48
�ː��� �\���̗��j/51
�ː��� �\���̌���/56
�R���̏����ƌ�/61
�R�z��/61
���쑺/66
����/71
���ꑺ/74
���Q�̖�/78 |
���H�̂ӂ邳��/82
���̑��̂��炵/82
�Y��/89
�A��/91
�{�\/94
�D��/97
�J�l����̘b/99
�v�z��D����������/104
�łƂ��Ă̈ߗ�/104
����̕z/111
���䓇�̌�/121
�����Ȍ�/127
�����̈ߐ���/130
���]�^����/130
���z�Ɩ��z/131
���z�𒅂��l����/133
����/142
���F/145 |
���/147
�h�q�Ɨ��D/149
�Q��/152
������/154
�����̖�/157
����/159
���z�̍Ō�/162
���z�̂���/162
���̒���/169
�Δn�Ŋ���������/174
��D�ؖȂ̂���/178
��Â̖ؖ�/178
�������̕���/187
�ؖȂ̂����/191
�ߗ��̕ϑJ�Ə���/195
���l�̐���/195
���z�Ɩȕz�̌��/196
�}�z/201 |
���z/205
�V�i�E�w��/212
�쐶����/214
���Ƃ킽/216
�ߐ����̓]��/225
�a���Ɨm��/227
���s/230
�ꖇ�̒���/231
�̖K�L/234
���k�ւ̗�/234
�����\����/236
�����\����/240
�����\����`��\�O��/241
������\�l��/259
������\�ܓ�/259
���Ƃ���/269
�ʐ^�� �F����o�j �A�����ق�
�E |
�P�Q���A���͉̂�ҁu���͉̂��� ��4��2��(�ʊ�7��)�v���u���͉̂�(�ߔe���Z�����N���u��)�v���犧�s�����B
�@�@�@�P�Up�@���ʍ� �o�C���_�[�t�@�C������ �@�Y�t�F���h��������(���Ǒ�v)�@�����F���ꌧ���}���ف@1002250791
���A���̔N�A�{�c�������u�쓇�̖K�L : ����̐M���Y�\�v���u���P�����X�v���犧�s����B�@�@pid/9580890�@�@�d�v
|
�͂��߂�
�쓇�̖K�L/1
���d�R����/3
��㊂ց\��Ս�/3
���d�R�ց\�Ί_�̓`��/6
�g�Ɗԓ���/19
�약�ցi��j/28
�Ί_���̕��x�Ɩ��w��/30
���ۂ̕䗘��/32
�{�ǂ̐Ԃ܂����܂�/56
�V��̕䗘��/58
�약�ցi��j/65
�^�ߍ�����/72
������/101
�|�x����/121
���\��/137
����/142
�Ί_�ɂ�/150
�{�Ó�/154 |
�쌴�̖_�x�E�܂��Ƃ��/154
�V���̊��x�E��������x/157
�{���̂�������x/158
���E�Ƃ��/159
��������/160
�떓�̓`��/166
���ӂ����E�̂�����/169
�����̓`��/170
�{�Â̗x/171
��㊖{��/174
�����Y�\�ӏ܉�/197
�v������/203
�ɍ]����/207
����̃G�C�T�A/216
�^�V�E���x�c�E�×z/219
�P����/228
���������E��L��/233
��㊂��Y�\/241
�i��j ���ۂ̖��� |
�i��j �V��̊��x
�i�O�j �Ί_�̉J��x
�i�l�j �Ί_�̕z�N��
�i�܁j �약�̂܂�Ȃ�
�i�Z�j �^�ߍ����̎i
�i���j �^�ߍ����̂Ȃ��Ȃ��
�i���j �^�ߍ����̖_�x
�i��j ��������
�i�\�j �V�铇�̊��x
�i�\��j �Ì��̑K����
�i�\��j �|�x���̒b��H����
�i�\�O�j �|�x���̂���
�i�\�l�j �{�Ó��쌴�̂܂��Ƃ��
�i�\�܁j �V���́u�D�̐e�v
�i�\�Z�j �{���̂�������x
�i�\���j �ɍ]���̏j���̋F?
�i�\���j ���x�c�̃G�C�T�A
�i�\��j �×z�̓쓇�x
�i��\�j �{�앑�x |
�쓇�̐_��炬
���L
���쓇�̖K�L/269
�Ăщ�㊂�/271
�g�Ɗԓ�/273
�Ί_���i��j/301
���ԓ�/306
���\��/317
�Ί_���i��j/328
�V��E���l�E�|�x/345
�Ί_���i�O�j/357
�{�Ó�/363
��㊖{��/371
���^
���ԑg/387
��a�F�W/406
���Ƃ���/415
����/419
�}�Ŗژ^ |
���A���̔N�A�u�������v�� 1962�N�Łv���u�����������ی�ψ���v���犧�s�����B�@pid/2526635
|
�}��
�@�߁E�K��/p1
�w�蕶�����ꗗ/p29
�����������`������/p37
�w�蕶������� |
���A�m���/p47
������/P47
�m�O���/p49
�ψ����/p53
������ |
�����|�\���J�ɂ��� �V�铿�S/p55
�n�r���L�˔��@�� ���a�c�^�~ �O�Ԑ��K �������G/p63
����ɉ�����Β��̏C�����ɂ��� �����NjI/p75
�����_���p���� �`�����i���w�i�j�_���Y/p79
�����Ê��������� ��쐴/p1 |
���A���̔N�A�r�c��O�Y, �{��������ҁu���w���j�U�� [��4] (��B�E�����)�v���u�͏o���[�V�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9542023
�@���c�ḮE�����Ȍ�E�i�䔒�k�r�l�E���R�܁E�����d���Y�E�{���������E���������Y�E�������i�E�c�ӏ��Y�E�v�ۂ��E�ɔg��N �i���M���j
|
������
���c��/11
������/15
�����q��S/17
�j���ڏo�x/19
�����ǂ�/22
�k��B�Y�B��/25
�����̏h��x/29
�����̒��R�S/32
���ꌧ
�~��/36
�x�̐V���Y����/39
�ݐ��/42
���茧
�Ԃ�Ԃ��/44
���l�D/47
���l�x/51
����Ȃ܂�/53
�c�A�S/57
������/60
�V�n��/63
�̂�̂���/66
�I�[�����f�[/68 |
�~�߂�S/71
�~�\�ܖ�j���S/75
�J�̍~����/78
�z�C��/81
�F�{��
�������/82
�c����/85
�L���L���L��/86
�|���|�R�j��/89
���_��/91
��ւِ�/94
�Ȃ�Ȃ�Ȃ���/97
�ܖ̎q��S/100
�啪��
���c��/102
�R�c�R�c��/104
�ߍ�x/107
�F�ڂ̉S����/110
�L�����/113
�{�茧
�B����/115
���v��/117
�����؉S/122 |
�_�y����S/122
��Ηx/127
�P���ۗx/131
�c����S/134
�U�x/136
�ו��x/138
�F�P�x/143
��������
�������I�n����/145
�������悳������/147
�������n������/150
�������l��/151
�Z���q/152
�錜�n/153
����/155
�_�x/158
�䉏��/160
���ؐ�/161
���v���}�c�o���_/164
�i�����哇�j
���Ԑ�/170
���ݒ��l��/172
�r�ǐ�/174
|
���邾���/176
�쒃�V/179
�r����/180
�Y�x��/182
����Ƃݐ�/185
�����x�̉S/188
���
��������/197
�l�璹��/198
�J���O��/199
�Ԕn��/201
�����������^/202
���Ԑ�/206
������/208
������/209
��������/210
�ԕ�/213
���N
���]��/217
�����R��/218
�A������/220
�E
�E |
���A���̔N�A�c���Ԓm�����u�����瑐�V���v���u�i�ߔe�j�c���ԗE�v���犧�s����B�@�@�@pid/3449876
|
�ژ^
�����̊T�v/1
���U/1
���������̗R��/2
�����Ɉ��ވ�b/2
������/3
�\�Z����/4
���n���̗R������/5
����o�̔n/6
����/6
�ފݍ�/6
���M/7
�O���O��/7
������/8
�A�u�V�o���[/8
�Z�����ܓ�/9
গ��D�̗R��/9
�Ԕт̗R��/10
�j�҂̗R��/11
���[��/12
᱗��~��̘b/13
�O᱗��~��/14
�V�o�T�V/15
�����\�ܓ�/15
�d�z�i�e���j/16
����w��/16
�J�}�}�[�C/17
����/17
�~��/17
�S��/17
���_��/18
�����u��̗R��/19
�Ί����̗R��/19
������/19
�R�~�ߊC�~��/20
���N�T���V/20
��̗R��/20 |
��/21
��������/22
�����̏��q���������@����
�@�@�����@�g�D�i�Ր���v�j/24
�i�̐l�`�j
���������/26
���l�x�m�R�̎�/27
���l����͉�/27
��u���/30
�Ԍ��q�i�������Ƃ����Ӂj/32
�����g���Ǝ�����/34
�哪��ߔe�̒���/34
���R��/35
�����V�v�}�o�V�e�_��/36
������e/36
���ǘ`�{��/37
�n�Õ~�y�[�N�[/37
�L��H��/39
���ҐΗ�/39
���l�̖���/40
������/41
�ɖ�g�̃��[���e��/42
������̎�/43
���l�_�J�̎�/44
���~���F��̎�/45
�q�u���͂̎�/46
���q�u�������ɂĂ̎�/47
�S���̎�/48
���~����/49
�^�p��e/50
��l�L��/51
���Ǐ�\�[�W���[/52
���l����/52
�Ôg�×��P/54
���́@�a�́@�a���̖��l/54
�����y�a���Ɗ���/55
�\����/57 |
��Ƃ̖��l/58
���v����㣐O��Î������l/59
�v�ē����̔䉮/59
�Z�p��s������/59
�Ӗ��e���A�T���a�߂�
�@�@��������ꂵ��/60
�����e���������ԃJ���a��/60
�Y�Y���R��/61
�V������/62
��V��e��/63
�썑����/63
���������e��/65
���s���̎�/66
�����E�n��/66
�����̓��n�̎�/67
�i�P�j�@�ؓc�厞/67
�i�Q�j�@�ؓc�厞/68
����ꉥ�J��/68
�L���唪�����/69
�i���t�f�B�[/71
��������/71
����ᏼ/72
��������/73
�`�����_���[/73
�X��V�q/74
�䒃�������ܘY/74
������N�B��/75
���l��P�̑��/76
�썲��/78
���{�Ў���ς�蔲��/82
�^�ʋ`���Ɩ��H�V��/83
�q�������߂錾�t/83
�n�c���̉ȋ���鄂̎���
�@�@�������ɓ���/84
�������y/85
�쑺���̈�b/87
�g�x�̍��/87 |
�������g�x�̋N��/88
�V���̘b/89
�̏��m�O�̎�/89
��Ǝ���/90
���u����/90
������@��/91
���R�c���R/92
����É؎R/93
�C�{��/95
�ȐS�`�S�_�/95
�ƕ����̓`��/96
���w�̏��ƊC�M�{�G�̊z/96
���ڑK�����̎�/97
��㊗{�̎n/97
���^�̋N��/97
����ɉ�����ނ̐���/98
�ꗢ�˂̐��x/98
����/98
গ��D�́i�ߔe�v�Ĕ��j/99
�T���W���E�[�j�[�̗R��/101
��q��/102
�ی��i����͏��j/103
�V�C�\���̓���/145
�����i����͏��j/145
�l���̐��ٖ̈�/152
���ٖ̈�/153
���M�W�i����́j��/153
���M��萳�M/165
�l���L�O�j��/170
�蕗���L�i���������j/172
���/172
�����y�����̎��ԕ\/173
���������n�Ðl�`�L/174
�����瑐�V��
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��2�v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@pid/1658750
|
���G�@���җ���
����
���t��y�̂����Ƃ�
�V�n��
�R�c�k�����搶�̏���
�}��
�\��
��L
�ڎ�
�{���̊T�v/7
���ҁ@���y�Ɩ�����
���@�Ɍ��ꂽ�������ƌ���i�S�ŌːВ��ׁj/8
���{���@�̕��z�Ɨ����i�V����^�̗��t�j/10
���V���̐��́i�����Ɍ�������̊_�j/16
�������@�̗����ƕ��z�i���E���@�̍��ێs��j/19
���������̌𗬁i���匠�҂̋t�̖ʑ��j/23
�A�C�k�Ɨ����̑��ʂ���C�i���N�c�J���Ɠۂݐ��j/25
�k��ď����̖����y
�@�@���i�啽�m�݂͓��m�ɁA�吼�m�݂͐��m�Ɏ���j/27
�C���J�Ɠ��m����
�@�@���i�P�`�������͓��{�l�ɁA�O�����j�[���͗����l�Ɏ���j/60
�C���J�͓��̗�����
�@�@���i�C���J���㉤�}���R�J�p�c�N�́A�o�z�����`�{�����j/63
�A���[���`���̖������y���x�i�G���I�^�s�A�̍D�Ӂj/83
�y���[�̖������y���x�i�N�X�R�̓C���J�̖{���j/104
����Ė������y�T�_�i�l��A���z�A�y��j/111
���@�ʼn������E����
�@�@���i�啽�m�Ŕ��˂��āA���͓�āA���͗����ō����j/116
�掵�ۖ������y��c�Ŋw�����\�i���s�ɉ̔茚���j/120
���{�����y�����i���G�������݁j/130
�{�����C�A�̖������y���x�i���m�F���Z���j�i�lj��j/132
���ҁ@���@�Z�p�T�_
���́@�����i�㌴�������A���c�s�����A�R���]�ʐ��j/137
���߁@�^��ɔ���������/138
���߁@�^�������̒x�ꂽ����/138
��O�߁@���t��y�̎���/141
���́@�ܓx���@�̍\���\��/142
���߁@���@�̔������B/142
���߁@���@�̔����ꏊ�ƈڐ��z��/143
��O�߁@���E�O��n�����@��r/145
��l�߁@�ܓx���@���̂������R�i����Ƃ̑���j/145
��ܐ߁@�W�x���@�ƂT�x���@�Ƃ̑Ώ�/147
��Z�߁@�e���̑��ΊW�ƒ����@�̒�/148
�掵�߁@�����̏��i/148
�攪�߁@���@�Ɗy��/149
���߁@�O����@�̌`��/149
���Z�߁@�z�A�̊ϔO�����i�z�A�͐��@���ł͂Ȃ����ʖ��j/150
����߁@���@�Ɛ��Ƃ̌`�ԊW/151
����߁@�ڒ�/152
���́@�ܓx���@�̍\���@/152
|
���߁@�ڌ��@/152
���߁@�ڑ��@�i���ڊO�ړ��ځj��?���@/153
��O�߁@�i�s�@/157
��l�߁@����/159
��l�́@�w��/160
���߁@�ꌳ�_�i���E�S���̏W�����������@�����ő̓��j/160
���߁@���@�̋t�]�_
�@�@�@���i�M�y�A���Ɨ��y�d�A���@�͋t�]�Ɉ�v���j/165
��O�߁@�h���_�i��Ȃ���\���̐��@�ω��j/169
��O�ҁ@���@�e�_
�����@���@��ɂ�閯������/171
���́@�������@�̈�x�i��p�����A���҈ĕS����j/171
���́@�C���������@/175
���߁@�����̐��@�i���ƒ��̌����ɖv���������j/175
���߁@���m�M���V�����̐��@
�@�@���i��{���@�͂S�x�A���@�Ɖ��K�̈�v�j/179
��O�߁@�m�y�Ɠ��m�y�Ƃ̌�����r/182
��O�́@�����������@/183
���߁@�Â̐��@�i�Â����璆���j/183
���߁@���N�̐��@�i���{�ւ̐��@���p�n�j/183
��O�߁@���{�̐��@/185
(A) ���v�ƌ���/185
�i�a�j�@�ꌳ�I�\���i���w�ł͐��@�Ɛ��̌`�ԕω��AⵁA
�@�@���O�h�ł͌q���ƒ����̍�p�ω��A�O���̍�A�@�A
�@�@�����y�����l�̓�������A���S�̉�U�j/187
(C) ⵎO�h�̒��h/198
�i�c�j�@ⵒ����̊y���i���q�̑g�D�I���ށA
�@�@�������q�����܌�̐V���q�쐻�@�A�ܓx�ڒ��t�@�A
�@�@����ƋЂ̎g���A�������Ȃ��Ȃ����R�j/200
�i�d�j�@���K�A�]���A�a���i�����͂T���ł��t�@�ɂ͂P�O������j
�@�@���ڒ��A�]���A�]���A����/221
(F) ��y�A�����A�w�Ȃ̐��@/231
�i�f�j�@�M�y�̔ᔻ�i�d�A���@���Ȃ��j/233
��l�́@�����������@/233
���߁@�T��/233
(A) �啽�m�̎l������/233
(B) �Ñ��̓���i�o/233
���߁@��x�x�߁A��m�i�X�����h�����ƃy���c�O���j
�@�@����m�F�A�������A�r���}�A�A�C�k�A�k��ē��̐��@/235
��O�߁@�����̐��@/242
�i�`�j�@�T�_�i���E�S�����������Ĉꌳ���A�Ɠ��̉d�A���@�j/242
(B) ���@�Ɛ��ʂ̎��/243
�i�b�j�@�q���ƒ����̎�ށi�W�x�̔��͂T�x���@�_�̗��t�A
�@�@���O����ⵂ̒��q�A�꒲�q�̒A�]���A
�@�@���G���O�����f�C�b�V���A���������@�̑ΏƁj/245
�i�c�j�@���K�A�H�H�l�y���i�����w�����p�j/250
�i�d�j�@�i�s�A�����A�I�~�A���S�x�A�J�m���A�Έʎ��A�a��/251
(F) �ނ���/253
��́@���_/253
���E���@�݂̍���A�����ւ̕��� |
|
| 1963 |
38 |
�E |
�U���A�|�\�w��ҁu�|�\ 5(6)(52)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276597
|
�����̂��Ƃ�-�����ɂ����颎���Ƣ�ʣ/p5�`5
�܌��搶�k��-8- / �˔N�� ;�܌��M�v/p6~10
�v�ۓc�����Y�搶�����̂�(���k��) / ����M���Y/p11�`22
�v�ۓc�����Y�搶 / �O��O�Y/p23�`25
�̕���N�\���� / �͒|�ɏr/p34�`34
�A�W�A�̕��x--�����̊� / �匴�A��/p26�`29
�c����c��-�ؑ]�H�̗���R���_�y / ��������/p30�`31
����D����\�\���S�������� / �Y�R���Y/p38�`39
�������T-52- / ��v/p43~48
|
���̗��̃`�����X--���낲�̂ݎ��T-12- / ������/p49�`53
�|�\�W�]/p58~59
�ނ�����x--����̖����s�� / �V�铿�S/p35�`37
�l���̌������|�\�\���ˎs����l-1- / ���w�@��w���b������/p61�`65
�W�H�̐l�`�ŋ�(�ʐ^�ƕ�) / �F����o�j/p32�`33
�i���j
�`���|�p�̉�l���������� / �g�؈�ᩎO/p71�`71
�i���j
�E |
�U���A�������{�������ی�ψ���ҁu����̕������v���u�������{�������ی�ψ���v���犧�s�����B
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1010038014
|
�͂����� �{�� �h�P�^[��]
�������Ƃ͉����A���̎�ނ���ѕی�
����̕������̓��F
�L�`������
������ |
���p�H�|�i
����
���`������
���y
�g�x |
�����|�\
���p
�L�O��
�j��
���� |
�V�R�L�O��
����������
�L��
�p�����
�w�蕶�����ꗗ |
�R���A���{�L�q���u����_�p = OKIDAI RONSO 3(2) p.9-34�����w�v�Ɂu�ɕ������̐�j��ցv�\����B
|
�u�ʏ��ԁv�̈�߂ɁA�u���݂̂ɂ����炸�A���Â̂��킴�ɂ��A�������Ȃ��ɂ́A���ɂ��ւ��܂́A�݂�т��邱�Ƃ́A�̂���邽���Б����v�Ɠc�ɂɓ`�����錾��╗�K�ɁA���m�ȌÑ�v�f��F�߁A����Ɂu���Ƃɂ��Ȃ��ɂ́A�ӂ邭�������낱�Ƃ��ق��A���ׂĂ��T�邽�����̎������A���X�̂悤���A�C�Â�R������̗��X�܂ŁA���܂˂��q�˕����߂āA���ɂ����邵�����܂ق����킴�Ȃ�B�v�ƁA�C�l�R�Ԃ̑��X��K�˕����āA�L�^���Ă����ׂ����Əq�ׂĂ��邪�A����̂����̊w�p�����́A����̌Â��p���c�������w�̕�ɂƉ]���Ă���ɕ�������8���Ԃɂ킽���č̖K�A���̎��̒����L�^�ɂ���āA��X�̖����Ŗ��ƂȂ�ׂ������͐������������A�����ł͎��̏����ɂ��ċL�q���邱�Ƃɂ���B(1)
�_�АM�� (2) �L�N�F�� (3) �����Ԃ��̎��q(�V�[�T�[) (4) ��ᓇ�̉J��F��
(5) �������̓`���ɂ�����썰��(�}�u�C���V) |
�W���A���v�`������w�j�w�E�n���w��ҁu�j�� = Shisen : historical & geographical studies in Kansai University�@ (�ʍ� 27�E28) �v�Ɂu�Z�g�̍֓��ƛޏ��v�\����B
�P�Q���A���{�����w��� �u���{�����w��� (31)�v���u���{�����w��v���犧�s�����B�@�@pid/2206598
|
�d�R�V���搶�̕Ď����ꂷ //p1�`1
�C�����Ɩ���-��- / �ː����/2�`12
�M�B���쎁�ƛޏj����-��-�b��O�Y杂̊Ǘ��҂��߂�����/���c�W/13�`31
�����䗅�{�̋{���ɂ��� / ���v�`/32�`37
��a���R���̎q�����ςɂ��� / ���G��/37�`41
�����Ñ��ɂ�������K��--
�@�@����n�̃g�E��ɂ��Ă̎�̍l�@ / �����O�Y/42�`45
�r�_�_�y�̑��� / �O�Y�G�G/45�`49 |
�J��Ɨ��� / ���J�d�v/49�`52
�؍������w�̌��� / �C����/53�`55
���] �����w�ɂ�����@���j�����̉ۑ�--�x��Y���m��
�@�@���u�@���E�K���̐����K���v�ɂ��� / ���䓿���Y/p55�`58
�w�E�L�� //p58~62
�G���_���v�� //p62~64
�V������ //p64~65
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��3 (�����̕��x�ƌ�g���x) �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B
pid/1658751
|
���G
�P�@�g�^�p/3
�Q�@��O�x�̎]��/4
�R�@�莚/5
�S�@����/7
���@�{�c�������@����/9
�ڎ�/12
�ʐ^�Ɖ��/113
I �ߑ�(�G)���x/113
II�@�ÓT���x/133
III�@�̖��D/150
IV�@�������x/151 |
V�@���g�x/163
VI�@�̌�/168
VII�@���d�R���x/171
VIII�@�n�앑�x/178
IX�@��g���x/193
���v/205
���x�̋N��/205
�������x�̊T��/206
I�@�|�p�I�{�\/206
II�@�����Ƒg�D/208
III�@���㕪�ޖ@/210
�����/211 |
�����@�������x/211
I�@��@/211
II�@�n��/215
III�@���@/217
IV�@���/219
�����@�ÓT���x/226
I�@���̑O�Ԃ�/226
II�@���/228
III�@�g�x�Ƒ��ŋ�/229
IV�@����/235
V�@�Z�p�̌���/238
��O���@�n�앑�x/243 |
I�@����ʂƎ��/243
II�@���Ǝŋ����猀�c��/245
III�@���㕑�x/258
����/260
��I�@�ÓT���x�̌^�Ɋւ���
�@�@���쓾�v���͎��̘b/263
II�@�쓾�v���͎��Ƃ̘b����/264
���җ���/266
�����ژ^/266
���t/267
II�W�@���]�@�]�����s��Y��/267
II�W�@���]�@���R�[��/268 |
|
| 1964 |
39 |
�E |
�R���P���A�{���c�s�i�݂�Ȃ� �܂��������S���Ȃ�B�i�V�P�j
�R���A�����T�W���u�ŋ���w�������� 13 p.49-51 �ŋ���w�������v�Ɂu�ܒ���l�̌����v�\����B�@�iIRDB�j
�X���A���֏�v,��������,���a�c�^�~���u���Y��w�Z������. �l���Ȋw�с@9�v�Ɂu�����g�Ɗԓ����c���L���̔��@�����v�\����B�@�@�ŏd�v
|
�T�g�Ɗԓ��̈ʒu�A�n�`�y�ђ����̖ړI
�U���c����Ղ̔����ƑS��Ղ̔��@�����̌o��
�V���c���L����Օ��
�W�L�ˏo�y�̈╨�ɂ��Ă̍l�@ |
�X���c���n��ɉ�����\�ʍ̏W����
�Y�g�Ɗԓ���n��̈��
�Z�g�Ɗԓ��o�y�Ɠ`������Ί�
�[�g�Ɗԓ���j�����̌n�� |
�\�@�g�Ɗԓ������̒�������
�]�@����̖������̍l�@
�]�T����
�E |
|
�]�@����̖������̍l�@
�]�T�����i�S���j�j
|
�P�O���A�u�����{���� 29(2)�@���W�F(��P 2 �����)(�� 1, 2 ���������v�|)�v�����s�����BJ-STAGE
|
���[���V���n�E�e�X�g�̐l�ފw�I�K�p�ɂ��ā@�����숤�@ p.141
�c��c�@��t�����@ p.141-144�@
�_�k�V��ƒn����F�Ƃ̊W�@����i�F p.144-145�@�@
���{�ɉ�����V�特�y�̌����@���c���q�@p.145-146
�ߍx�_���̈��ω��@�s�쌒��Y�@ p.146-147
���{�ɂ�����e���̏����@�勋�ߒB�@ p.147�@
�p����(������t����)�̖{�M�ɂ����镪�z�@������v p.148
�Љ�I�����ƘA�ѐ� : ���n�E�����̂����@�g�c ���� p.148-149
���_�ƎЉ�\���@��c���@ p.149-150
�M�\�҂ƌ��ҁ@�E �����@ p.150-151 |
���n�ɂ����鋙�Ƃ̓W�J : ���쒬�C�m���̏ꍇ�@���씎�@p.151-152
�Ε��C���S�ց@�j�{�Á@1 p.152-153
���q�@���������� p.153�@
�ؔ��̋Z�@�@�����������@ p.153-154�@
�ւ̑�������㊕������̓y��@�]��P���@ p.154-155
���{��ƍ�����@���R ���Y�@ p.155-156
���N�̓����@�E �����@�@ p.156-157
�Ñ㒆���l�̖��Ɋւ���v�ҏ����@�r�c�s��j�@ p.157-158
�A�t���J�̖�Ł@�ΐ쌳���@ p.159-160�@
�E
|
�P�O���A���a�c�^�~,���{�L�q���u���{�l�Êw����������\�v�| ���a39�N�x
�@���{�l�Êw����v�Ɂu�ߔe�s�R������ꓴ�i�����j���@�v�\����B
�P�P���A���{�̗w�w��ҁu���{�̗w���� 2(0)�v���u���{�̗w�w��v���犧�s�����B
|
�u�����̘a�]�ɂ��� ���� ���v p.7-11
���{�̗̉w �u�c ���` p p.1-5
�̎��ɂ����鉹�����̌��p ��� �b�� p.6-10
�c�A�����n�̗w�����̈��--�������`���̗w�Ȃǂ�
�@�@���߂����� �^�� ���O p.p.12-18
�������W�q�S�Ό������́u�c�A�₵�v�̉��y�I����
�@�@��:���|�n�́u�c�A�₵�v�̉��y�I���i�ւ̍l�@�𒆐S�Ƃ���
�@�@�� ���c ���q p.19-26
|
��ڗ��Ɨ��s�̗w--�ߏ������ڗ����S�� ���� ����Y p. p.41-45
�����Ɖ̗w ��Y �F�M p.46-50
�������W�q�S�Ό������́u�c�A�₵�v��
�@�@�����y�I���� ���c ���q p. p.19-26
�q�Ǔ��r�����ؐM�j�搶�𓉂� �u�c ���` p.59-59
�q�|���r�c�̎G�{�A�x�o���A�R��x���ǂ��A�x�̊�Î�T�A
�@�@����B���R�x�́@��� ���] ���� p.60-79
�q�����r |
�P�Q���A�u����j�w (18)�v���u����j�w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/2238645
|
���K�L���_�Ђ̗��� / �哇�����Y/p1
���ΏW�ɂ݂��鉺�썑�̕��� / �u�c�x��/p7
���c�݂͊𒆐S�Ƃ���n�ǐ���㗬�̑��^/��˗Ǔ�/p12
�V��}�o�� / �����쓿�v/p18
�F�s�{���l / �{�c��/p23
�����p���h�̏��� / ���v�×F�j/p27
�Έ��F�̐m�� / �{�����s/p30
�����l�Ƒܒ���l / ������/p36
�J�����G�L / ���J����/p42
�߉ϐ여���㊕��y�� / ��ؓ�O�j/p44 |
���y�j�Ɋւ�����w������� / �N�����v/p47
�֏�-���̗��j�Ǝ���(�哇�����Y��) / ���䏺/p51
�n�������y�j(�n������) / �ΐ쌒/p51
�����s���]�Õ�(���Õv��) / �����q�j/p52
�Ñ�q�ƈ��(��쐴��)/p56
�����/p6
���얯��/p6
�Ȗ،������w�����W�] / �������Y/p53
�����ɂ�����Õ��������T�� / ���c�_�~/p54
�o������Ղ̔��@/p11 |
�P�Q���A�L���鑺�j�Ҏ[�ψ���ҁu�L���鑺�j�v�����s�����B
���A���̔N�A��䓾�� ���ďC�u���{�ӂ����T�� 6 (��B�E�����)�v���u���X�v���犧�s�����B�@pid/1658598
|
��B�n��
�i�ȗ��j
��㊒n��
����/199
��x�E�m��/202
|
�n�u����������߂��}���O�[�X/204
�T�b�͂��E�咆�͂��E�����E��/209
�Ђ߂��̓�/217
����ɂ�����V�̊�˂⍂�V��/220
�Ԃ����ƃT���S�ʂ̐Ί_�̓�/222 |
�O����/225
������������������A���/226
�Ί_���̉J����/228
�E
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��4 �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����Bpid/1658752
|
�Ƃт�/1
���G�ʐ^/3
�c�ӏ��Y�搶�Ɋ��ӂ̂��Ƃ@����/5
������Ɋւ���t�V�̏d�v���@�����P��/7
�T���������@���R����/7
���E�B��̋M�d�ȑ��݁@�c�ӏ��Y/8
���×��������@�ɔg���Q/10
�����@����/11
���Ⴂ�̐����@�]�����s��Y/14
�}��/15
�ڎ�/16
�{���̊T�v/22
���_�@�{�_/23
�P�D�@���{�̂�����/25
�Q�D�@�̂�̂�����/44
��A�@���[���̂�����/49
��A�@�ʏ�Ԑ؎������̂�����/55
�O�A�@�������̂�����/56
�l�A�@�c�NJԓ����Ԗ����̂�����/72
�R�D�@�ԚL�̂�����i�������V�j/83
�S�D�@�V�e�c�i�c�A�j�́j/85
��A�@�i�Y�Y�����j/86 |
��A�@�i�ʏ�~���g�E���j / 86��2
�O�A�@�i�Y�Y���j/87
�T�A�@�䒃�тƗ���O��
�@�@���i���c�f�ՑD�̑����̋ȁj/88
�U�A�@�N���[�i�i�Ñ��揁j/92
�̃N���[�i/102
��A�@���̃N���[�i/102
��A�@�����V�[�i�̍��D�j/111
�O�A�@�t�V�O���[�i/122
�l�A�@�x���/134
�܁D�@�G�߁@��������/138
�ߔe�̃V�^�[���[�O���[�i/139
�c�NJԓ����Ԗ��̃N���[�i/140
�V�D�@������N�i�������_���j�ƌ�V����/146
�W�D�@�P���/160
�X�D�@�쓇�x�@�Z�\�x�i�ߔe�����݁j/174
�P�O�D�@���闎���j�̖،�����/180
��A�@��
��A�@�ߔe
�O�A�@����
�P�P�D�����O��/198
�P�Q�@�����Y�i���{�n�V�|�j/244
|
�P�R�D�@���Y�n�i�V���n�救�j/262
�P�S�D�@�H���y�i������O�y�j/274
�P�T�D�@����y�ƌc��g�i�����̉�y�j/294
�P�U�D�@���_�y/308
�P�V�D�@�ʼn�ꉂƑ啽��/312
�P�W�D�@গ��D/324
�P�X�D�@���ӕ�/334
�Q�O�D�@���q���@���{��/340
�Q�P�D�@�j�I/342
�Q�Q�D�@�Ǐ��@�g�x�̒j�E�q���E
�@�@�����E�Ԃ̕��̂����/354
���^
�i��j�@�M�O�ƓV��/359
�i��j�@�o�ŏj����L�^/262
�i�O�j�@���m���^���ƎR�����j/374
�i�l�j�@�Ñ㗮���̓��{�n���x/374
(��) ��II(���v��)
�@�@����III(�c�Ӑ搶)�W�̏��]�Љ�/376
���t/380
�����|�\�S�W�o�Ŗژ^/380
�E
�E |
���A���̔N�A�u�n�����\���N�L�O�� : 1963 �������w�Z (������������)�v���u�������w�Z�v���犧�s�����B�@�@pid/3447047
|
�����̂��ƂE�ҏW�ψ����@�K�]��h/1
�n�����\���N���}���āE�Z���@�������^��/4
�����E�암�A���拳�璷�@����G�g/6
���j�̂��ƂE���������w�Z���@�V�_�����Y/8
�j���E��㊋��E����@���ǒ��c/10
��Z�n�����\���N���j���āE�������/12
�j���E���������@�㌴�T��Y/14
�����E������@���ܗǓ�/16
�n�����\���N�L�O����
�@�@��������W�Ɋւ����ӏ�/19
�n�����\���N�L�O�s����
�@�@�����ƁE�����㌴�K�E/23
�w�Z�T�v/30
�I���̋���������k��/49
�ݍZ���i���A���A���Z�j�̍앶
����ǂ������E��N�@�������/61
�邷��E��N�@��܂��Ƃ�/62
�Ă�Z���������܂���E��N�@��c�Ƃ��q/62
���̂������������ǂ������E��N�@�吼��/63
�����\�ܖ�E�O�N�@�Ƃ���ЂƂ�/64
�^����E�O�N�@���a��/64
�������E�l�N�@�R��[�q/65
�ǒJ�E�ܔN�@���F�q/66
���E�ܔN�@�R�闘�b�q/67
�^����E�Z�N�@�F���x�q/68
���w�Z�E����@�V�_���b�q/69
���w�Z�ł̏T�Ԃ̎v���o�E����@�㌴����/69
���̏o�g�Z�����E����@�ʏ�h�q/70
���w�Z�𑲋Ƃ��āE����@���X�G/72
���w�Z�̍��̎v���o�E����@������/73
���₾���J�~��E����@�㌴���q/75
���w�Z�̍��̑z���o�E����@���䐴�G/76
�ł����E�����莞�l�@�ӓy���N�q/78
���E�� |
��̞Վ��ɂ������āE����r/80
�l��[�������l�E���b�q/81
�V�ċ��t�͌��E����v�ێq/83
���z�i���N�̏o�����Ɓj�E�����K��/85
���Ɛ��̉��
�ߋ��̎v���o�E�^�������t/87
�v���o�E��c����/91
�V�W�̝_�ؔ��E���m�����h/97
��z�^�E���חY/100
���ꂩ��Z�������킴��E��������/102
�j�������w�Z�E�㌴���t/104
��Z�̎v���o�E�ɍ]����/105
��Z�ɊāE�{�����/106
��Z�n�����\���N�L�O����
�@�@���āE�^�h�c��/108
�v���o�E�V�_��/110
��Z�̔��W���j���E�ʏ�p��/112
��Z�̔��\���N���j���E���鐾�h/112
��Z�ɊāE��[�M��/113
���̎���̎v���o�E�㌴����/115
��锻/116
�ł����̍Z��E��[����/118
�㌴���q/119
�v���o�E�㌴�t�W/121
����O�q/122
���k�ւ̌���E����h�q/124
���̐����فE�{���Ǐ�/125
���̏��w�Z�̍��E�g���^�P/126
���n���E������/128
�e���g�����̍��E��ԃV�Q�q/128
���炨���Ēk�`�i��e�j�E�̐d/129
����E��[����/131
����G�L/132
���z�E�{��D���Y/133 |
���E���̒Ǒz�^
�v���o�̐��X�E�������N/136
�������w�Z�̊F���܂ցE�Ö��c�@�h/139
���̍��E�{�c��/142
���z�E���v�{�k�P/144
�������w�Z�̂Ȃ������v���o�E
�@�@����c���G/147
�v���o�̉ƒ�w�K�E�㗢���Y/150
�z���z������̎v���o�E�����K��/151
�����w�Z����E���/153
�v���o�G�k�E���n�K�P/155
��z�E�ɕ~�쑠/158
�v���o�͐[�������Z�E���Ԓm�G/160
�v���o�E�Ɖ����q/161
���\���N���j���E�]�F���m/164
�v���o�E�R�������q/165
�v���o�E�����i�F/168
�S�̂ӂ邳�ƁE��p�x�q/169
���\���N�̗��j���ڂ݂āE�쑺����/170
�������w�Z�n�����\���N���T��
�@�@��������ɂ�����āE���g�i��/172
�����̉��v�E���ܗǓ�/175
�����̗��j�E�`�����_���Y/182
�����̃n�[���[�l�E���ܗǓ�/190
�����̕������E��×Ǔ�/194
�������ՁE�㌴����Y/197
�Y��E�ʏ鎟�Y/202
�����̍s���Ƃ��̔w�i�E����M/208
�̑�Ȃ��o�ҋʏ鏁�搶�E�㌴�M�Y/216
�ׂ₩�ȏ�i�̋ʏ�ꎁ�j�E�ɕ~�쑠/218
���̑��Ղ�q�˂āE�ʏ镐��/219
�n�����\���N�L�O���ƊҖF��/223
�ҏW��L/269
�E |
���A���̔N�A�������{�����Nj��猤���ە��u�����j�� ��10�W ������2�v���u�������{�����ǁv���犧�s�����B�@�@pid/1704650
|
�� �����s��/1p
(��)���ꎐ�m��c�^(�������W���l��-�l�Z�N
�@�@��������j�����O�W���Ę^)/1p
(��)�I�풼��̕������̕ϑJ(������j�����O�W���Ę^)/2p
(�O)���ꕶ������������̕�������(���Ę^)/3p
(�l)�������̖ڕW/4p
(��)�Љ��w���v��(���ꕶ��������l�Z�N)/4p
(�Z)�W��y�яW���ɉ����錾�_�w���Ɋւ��錏(���l�Z�N)/8p
(��)�s�����������Ɨv��(���ꕶ��������l���N)/8p
(��)�V����G������ꥎʐ^�ق̔F�ɂ���(���l���N)/13p
�� ���ĕ������/14p
(��)������ق̗��j�ƖړI(USCAR���A�p��)/14p
(��)������ِ}�����̏�(�����N�\�������̗�������)/19p
(�O)�ߔe���ĕ������(���܌ܔN�ꌎ�`�\�̓��v)/20p
(�l)�ΐ엮�ĕ������(���ܘZ�N���s���ُЉ��)/22p
(��)���d�R���ĕ������(���ܔ��N��Ί_�s���\���N�L�O������)/25p
�O ������/25p
(��)���������ًK��(�{������l�N)/25p
(��)����������(�{���l�N)/27p
(�O)�䉮������ً��{��������(�v�ē�����l�N)/30p
(�l)���c�����ً��{�������ɂ���(�X�������l�N)/31p
(��)��������(�^�ߍ�����l�N)/32p
(�Z)�F�������ً��{����(�ǒJ����܌ܔN)/36p
�l ������/37p
(��)�����ى��v ���܌ܔN�ȑO��O������������ى��v�j�/37p
(��)�����i��/37p
(�O)�Q�ώҐ��� ���܌ܔN�ȑO��O������������ى��v�j�/67p
(�l)�����ِ����Ɋւ��錏 ���l���N/69p
(��)���������̐\������o�ɂ��� ���܁Z�N/70p
(�Z)�����ٌ����z�����\�� ���܁Z�N/70p
(��)���ꔎ���ٕ�����ӏ����ɕ������Ɗ���W�v�j ���܁Z�N/71p
(��)���ꔎ���ِݗ���ӏ��ɏA���ĉ� ���܁Z�N/71p
(��)���ꋽ�y�����ٕ����v�j�ɏA���� ���܁Z�N/71p
(�\)�����ٌ��z�ɂ��Ē� ���܈�N/72p
(�\��)�������N�W�v��ɂ��Ē� ���ܓ�N/72p
(�\��)�����ٖ��̕ύX�̌��\�� ���܌ܔN/72p
(�\�O)�y�����S�N�ՋL�O�٥�����ٗ�������/73p
[(�\�l)]�s�����L ���܌܈ȑO��܍�����������ى��v�j�/73p
�� ������/79p
(��)�j�֕ۑ���X����W��ӏ� ���l���N/79p
|
(��)�d�v�Ȃ�Ñ㌚�����ɔ��p�H�|�i�̒����y�т��̔F�� ���l���N��/79p
(�O)�j�֕ۑ��ɂ��� ���l���N����/79p
(�l)����j�֕ۑ���X�� ���l��N��Z��/80p
(��)�������Ζ�C������W��ӏ� ���܈�N�ꌎ/80p
(�Z)�������ی�@�̉�� ���܈�N�ꌎ/81p
(��)�䂤�ǂ�p�c���̐Ί� ���l�N���/83p
(��)�������̊����m�F ���l�N���/84p
(��)�x�[���ʂ�������E�h������܌ܔN�ꌎ�l��/84p
(�\)�������ی��Ɋւ�����������o���˗��ɂ��� ���܌ܔN�ꌎ/85p
(�\��)�������ی�@��|�O��̍s���ւ̋��͂ɂ��� ���܌ܔN�ꌎ/85p
(�\��)�����������ی��ւ̔��W�I���� ���܌ܔN�\��/86p
(�\�O)�������ی�s�� ���܌ܔN�\��/87p
(�\�l)�w��ꗗ ���܌ܔN���/89p
�Z �ό�/90p
(��)�n���C�ό��q�ւ̂��m�点�ΐ�s���������ی����� ���܁Z�N�O��/90p
(��)�n���C�ό��c���}��/91p
(�O)����ό�����ݗ���ӏ� [�V] ���l�N/92p
(�l)����ό�����芼 �H�n���������� ���l�N��/93p
(��)�ό�����X����(���܌ܔN��ꌎ����)��ό����ꍆ ���܌ܔN��ꌎ/95p
(�Z)�ό��Ң�n�����������N�L�O������܌ܔN�\��/95p
�� �����W���ƂɊւ��鏔����/103p
(��)�������L��(�S�̖\��)�̎�����o����肢�ɂ��Ă̐����v��/103p
(��)�썑�����Ï��`���O�S�܁Z�N��j���ɋL�O���ƂɊւ��錈�c(���@�@���l�N)/104p
(�O)�Y�ƐU���̑剶�l�̋{��S�v�搶�̈̋ƌ��ь����ɂ���(���܌ܔN)/105p
(�l)�n�����������N�L�O���s�ɂ���(���܌ܔN)/106p
(��)�V�Ԑ^��`���s�ɂ���(���܌ܔN)/107p
(�Z)�C�O����O�\�N���v���тɓ��R�v�O�`���s�ɍۂ���(���܌ܔN)/108p
(��)�u�쉮�L�O�}���ق̓��e/108p
(���^)�y�������q�S�N�L�O�Ɋւ��鎑��/109p
(��)��ė��e�P����ݒ�̕z��(���ܓ�N)/109p
(��)�y�������q�S�N�L�O�s���ɂ���(���O�N)/109p
(�O)�y�����S�N�ՋL�^(���O�N�Z�����s�������W�����\����)/109p
�� �X�|�[�c/138p
(��)��y�ыK��/138p
(��)�̈�s��/147p
(�O)�{�y�W����/158p
(�l)����̈狦����x���Z�� ���܁Z�N����ܓ�N
�@�@������O�N����l�N����܌ܔN/167p
(��)���̑��W����/174p
�E |
���A���̔N�A�u����̓��瓇�c�b : �e�������̂̒lj�����v���u���c�b�����Ռ�����v���犧�s�����Bpid/2983093
|
��Z����
�펀�����s������/p1
�Ō�̉�㊌��m���@����D�v/p3
����̐_�@�Y�菃/p35
�l�ԗ�]�@�ɓ������Y/p43
�lj��̋L/p55
�ِF�̊���/p57
���c����̑z���o�@�쑺�E�O/p58
���c�����z�Ӂ@�k�h��/p62
���c����̎v���o�@�O�֗ǗY/p66
���c�b���̎v���Ł@���c��/p69
���c�����Âԁ@�]��V��/p78
���c�b���𓉂ށ@��썲��/p81
���c������Â�Ł@�������r/p86
��t����̓��c����@�R�c�v��/p88
�u�C�s���v�@�p���Ɏs/p91
���炢�l���c����@�Ō�̉�㊌��m�����v���@���X�ؗY��/p93
���z���������Ɉ��/p99
���a�����錻�݂ɉ��Ă����@���@�X�藹�O/p101
���c�N�Ǝ��@���@�Ð�Օv/p103
���c�b�N���Âтā@�O��@�����ǎO/p105
�lj��@�O��@���ꍑ��/p106
�������Ł@�܉�@��쐴��/p108
�܉�@�z�R�Ώr/p110
�܉�@�R���B/p111
���c�N�Ǝ��@�Z��@����d�g/p114
���c�b�N�̉�z�@�Z��@��v�ۑ��O�Y/p116
���c�b�N���Âтā@����@�]��/p119
�������ÂԈ����Y�@����@�L�n��ܘY/p121
����@������Y/p124
���F���c�b�N�̉��z�@����@�A�c�ɕ�/p127
���c�叫�̎v���o�@����@����F�F/p132
�Ǒz�@����@�����O�Y/p136
�썑�̋S���c�b�@����@���͓����j/p138
���m���x�@�����̓��c�b�@����@�������j/p141
�ؗF���c�b�N���Âԁ@����@�O���ܘY/p145
����@�L�|�C��/p150
�u�D�����c�v���͖S����� ����@�O�Ŋm�O/p153
|
�v���o�@���@�Ό����Y/p157
�̑�Ȃ�싅�ē��b���@���@���c��/p160
����ʉe�@���@�����L/p165
�O���싅���Ɖb����@���@���q���Y/p167
���c�b��y�̎v���o�@���@����`�Y/p171
���c��y�ɂ��ā@�\��@�F�쏯��/p174
����̓��@���c����̎v���o�@�\��@���䌳�F/p177
���c����̉����o�@�\��@�c�����/p180
�Ō�̉�㊌��m���@�\���@�|����/p183
������̖ʉe�@�\���@�v�R�G�Y/p186
���c��y���Âԁ@�\����@�r�c�F��/p188
�j�ē��c�b�N�@���E���@��㏯�O/p191
���c�b�N���Âтā@���E���@�⑺�ДV��/p193
���w������̓��c�m���@���E���@����Y/p199
���z�������a�̐l��z���@���E���@�M�c��/p201
���c�N�̉����o�@���E���@�сi�����j�P/p203
���c�b���̎v���o�@���E���@���c�`�^��/p205
�݂肵���̏�C���̎��@���E���@�����o�g/p208
���c�b����������@���E���@���J�G�Y/p211
�t�E�X�|�[�c�Ƌ���/p215
�u�f�v�̈ꎚ�@���c�p��/p217
���_�D�F����ɖ��@�����F�V/p220
���F�Ǔ��@�������Y/p224
�b����̎v���o�@�ÊC���V/p232
A����̉����o�@�����v��/p235
�ǂ��F�@�[���c�b����[�@�۔���/p239
�b����̒Ǔ��@�R����/p241
����̓��@�o���폇/p242
A����̏��@�ҏ��O/p246
���c�N�͖{���������@�È���/p249
���c���̉����o�@������O/p251
����Ɩ{�y�Ƃ̂�����/p253
�m������������@�������Y/p255
�������̏��@�������i/p257
���c�t���ā@�x����`/p262
����/p265
���^/p301
���Ƃ��� |
���A���̔N�A��B��w���d�R�Q���w�p�������ҁu���d�R�Q���w�p������ ��2�W�v���u��B��w�v���犧�s�����B
�@�@ (��B��w�C�O�w�p�����ψ���w�p�� ; ��2��)�@�@pid/3048549
|
�܂�����
��ꕔ
I.��B��w����d�R�S���w�p������/p1
�����̎�|/p1
���̐���/p1
�����̍\��/p2
�����ۑ�/p3
���̍s���L�^/p3
i)�o���܂�/p3
ii)�n���E�A�����ԁE�����ǂ̍s���L�^/p5
iii)��w�ǂ̍s���L�^/p11
��ʑ���/p13
�H�Ƒ���/p17
���������ȋL�^/p25
II.���d�R�Q��,���ɐ��\���y�є��ԓ��́���/p31
1.���d�R�Q���̊T��/p31
�Q�D���\���̒n�`�C�C�ۋy�юY��/p32
�R�D���ԓ��̒n�`����юY��/p34
���
�P�D���d�R�Q�����\���̔��d�R�w�Q�ΒY�̉ԕ�����
�@�@���������E���{�k���L�l�v/p35
�Q�D���d�R�Q�����\���ɂ����锪�d�R�w�Q����̏d�z��
�@�@��������V��E���{�{�k���L�l�v/p47
�R�D���d�R�Q�����\���ɂ�����ΎR��� ���{�k���L�l�v/p57
�S�D�������d�R�Q�����\���l���̓��ꐫ�i�\��j ���c�Ə�/p75
�T�D��B��w���d�R�Q���w�p�������̏W��
�@�@�����d�R�Q���Y�̃S�L�u���� ����ސ���Y/p93
|
�U�D��B��w���d�R�Q���w�p�������̏W��
�@�@�����d�R�Q���Y��x�� ����ސ���Y/p95
�V�D��Q�d�R�Q���������̍̏W������������
�@�@���i�i�K�J�����V�Ȃ���уT�V�K���Ȃ������j�i�p���j �{�{����/p99
�W�D��B��w����d�R�Q���w�p�������ɂ���č̏W���ꂽ
�@�@���i�K�J�����V����уT�V�K�����V�ɂ��āi�p���j �����P�W/p111
�X�D���d�R�Q���������̍̏W������� �{�{����E�{�����v/p117
10�D���d�R�Q���̃L�W���~�ނɂ��āi�p���j �{�����v/p121
11�D���d�R�Q�����\���̃N�T�J�Q���E�Ȃɂ��� �K�R�o/p133
12�D��B��w����d�R�Q���w�p�������ɂ���č̏W���ꂽ
�@�@�����\���̐����b���ށi�p���j �������F�E�{�����v/p135
13�D���d�R�Q���̃e���g�E���ށi����j �_�J���V/p145
14�D���d�R�Q���̃n���V�ɂ��āi�p���j �،��V��/p149
15�D��B��w���d�R�Q���w�p�������ɂ���č̏W���ꂽ
�@�@�����d�R�Q���̒��ށi�p���j ������/p157
16�D���d�R�Q���̉�ނɂ��āi�p���j ���G��/p165
17�D���d�R�Q���̃I�h���o�G�Ȃɂ��� �O�}�L��/p173
18�D���d�R�Q���w�p�������̍̏W�ɂ��A�V�u�g�R�o�`�Ȃ̖ژ^ �y����\/p179
19�D���d�R�Q�����\���̍g���т̕��U�\���̉�� ���J�M��/p181
20�D�^�ߍ�����a��R���̓����ɂ��� �i�䏹��/p247
21�D���d�R�Q�����\���Y�u���̂����v�̓��W���ɂ��� ��g�P�F/p251
22�D���d�R�Q���^�ߍ����E���\���E���ԓ��ɂ�����t�B�����A����
�@�@�����c���E�{������/p257
23�D���d�R�Q�����\���E���ԓ��ɂ����钰�NJ�徒��ނ̒���
�@�@���{�������E���c��/p267
���Ƃ���
�E |
|
| 1965 |
40 |
�@�E |
�Q���A�ߋE�����w��ҁu�ߋE���� = Bulletin of the Folklore Society of Kinki : �ߋE�����w���� (36)(41)�v���u�ߋE�����w��v���犧�s�����Bpid/6046016
|
�ޗnj��L�˒���̘̐b / ���{�r�g/p1361�`1368
�{���ƍ֓�(�ዷ�q���V���̓����V��) / ���v�`/p1368�`1381
�n�_��ƎГ��� / �ѓc�`��/p1381�`1383
���g���n�S��F���̐��� / ������O�Y/p1383�`1384
�p�₳�ꂽ�u�����߂�̂��ׂ����v / �ې參��/p1384�`1385
�u�O���o�H�ⓚ�v�鏴 / �O�c���ܘY/p1385�`1387
|
��B�L�ˎs�̋{��(8) / ��z���H/p1387�`1397
���̈���̕��K�ɂ��� / �c���v�v/p1397�`1411
���ꌧ���������̑��ۗx / ����/p1411�`1421
�o���ċg���Ǝ� / �̋{���ȎO/p1421�`1427
���_�M�̈�`�� / �r�c�a��/p1428�`1428
�ޗnj��䏊�s����/p1428~1428 |
�R���A�V�铿�S���|�\�w��ҁu�|�\ 7(3)(73) p22�`25�@�|�\���s���v�Ɂu����Ì����̖����|�\�v�\����B�@pid/2276618
�T���A�|�\�w��ҁu�|�\ 7(5)(75)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2276620
|
�����̂��Ƃ�`���̕���ۑ��Ɉꌾ //p5�`5
�o�ΑΒk(���k��)-��- / �܌��M�v/p6�`9�`
�c����c���\����̔\ / ��������/p20�`21
���ȍ\���Ɋւ����l�@(2)-�����̍��m�҂ɂ���/ �����v/p13�`16�`
���Ղ��ڂ���-�n�̏C�Ƃ̂���܂�-17-/����ӎO�Y ;�x�R����/p30~33~
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-70- / ���������Y/p37�`42�`
�J�̂䂤����--���낲�̂ݎ��T-35- / ������/p43�`47�`
����l����݂���^������� / ���v/10�`12
���������×w��Ȃ̌�����L / �R�����j/p22�`25�`
|
����w������Ȍ�O�\�N�\���{�̗w�w��n���܂�/�u�c���`/p26�`27
�|�\�W�] //p54~55
�w���`�x���o���� / �`���|�p�̉�/p17�`19
���J�슨���q--�����l�ʐ�-26- / ���c�m/p34�`36�`
�E�Y�x�N���֍s��-1- / �F����o�j/p28�`29�`
�\�E�����\�\���L���̊�� //p53~53
�Z���̖����|�\�Ƃ��̎��� / �R�H����/p62�`63
�ǂ���������˂�����(12)-���y��̘̐b/�쑺����/p61�`61�`
�� |
�W���A�u���{���� (21)�v���u���{����������v���犧�s�����B�@�@pid/2380005
|
�����@�G�q�h�̔��W�ƒ��q�� / ���}���^/1�`13
�c���ۈ��̎�--�Q�͓�����Ƃ̓��v�Ɋ֘A����/���ѐ���/14�`31
�����M�ƃ~���N-��-���ӐM�̖����w�I�l�@/�{�c�o/32�`37 |
��R�����N(�|��) / �^�ۋ�/41�`62
�ܒ���l���̌Îʌo��a�]��� / �ߓ��씎/38�`40
��V���Љ�⏔�ˑf������@�R��l�̌���I����/���쏃�F/63�`64 |
�P�P���A�u�^������ ���ꉹ�y�����@�����|�\(���w)�v���u�R�����r�A�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�@�傫���A�e�ʓ� �^���f�B�X�N 16�� : �A�i���O (LP) , 33 1/3rpm ;
30cm
�@�@�@�@�ʍ�������t��(260p), ���n�^��, ��20��|�p�ՎQ��
�@�@�@�@�X�_��Y(���, �ďC) ; �O�G���v�Y(�ҏW, ���)
|
| �m�� |
. |
. |
| 1 |
SIDE-A
<�y����> |
�g�x-���G��(���܌��S, �������, �^�ߔe����, �e������(�Z���t) ; ���Ԑ���,
��c���v(�S, �O����) ; ��l����(��)) |
SIDE-B
<�y����> |
�̌�-������(�e������, �{��\��, �ɔg���q��(�Z���t) ; ��c���v, �R���㎡(�S,
�O����) ; ��l����(��))(1)����-�ɍ��a���̖�O�̏�E�A�`�J���l�̏�(2)�ܖ�-�⌾��A�̂̏�(3)��l-��O�̏� |
| 2 |
SIDE-A
<�ÓT�O�������y��> |
(1)����{��-�X����-��c��(���Ԑ���(�S, �O����) ; �T�J�E�g(��))(2)����{��-�X����-����c�ߏ�(���Ԑ���(�S, �O����) ; �T�J�E�g(��))(3)����{��-�X����-����c�߉�(���Ԑ���(�S, �O����) ; �T�J�E�g(��))(4)����{��-�X����-�g��c��(���Ԑ���(�S, �O����) ; �T�J�E�g(��)) |
SIDE-B
<�ÓT�O�������y��> |
(1)����{��-���x�c��-�\������(�{���t�s(�S, �O����) ; ���a�c�X�~(��))(2)����{��-���x�c��-����(���x��)(�{���t�s,
��鏕�g(�S, �O����) ; ���a�c�X�~(��))(�C)���Ԑ�(��)���Ԑ�(�n)����Ȃ��� |
| 3 |
SIDE-A
<�ÓT�O�������y��> |
(1)����{��-���x�c��-�q����(�{���t�s(�S, �O����) ; ���a�c�X�~(��))(2)����{��-�쑺��-�����Ȑ�(�ɍ��쐢�[(�S,
�O����))(3)����{��-�쑺��-��(�ɍ��쐢�[(�S, �O����)) |
SIDE-B
<�ÓT�O�������y��> |
(1)����{��-�쑺��-������ŕ���(��c���v(�S, �O����) ; �^�V���}�q(��))(2)����{��-�쑺��-���[��(��c���v(�S,
�O����) ; �^�V���}�q(��))(3)����{��-�쑺��-���ɕ�����(��c���v(�S, �O����)
; �^�V���}�q(��))(4)����{��-�쑺��-����͂O��(��c���v(�S, �O����)
; �^�V���}�q(��))(5)����{��-�쑺��-���Ă���(��c���v(�S, �O����) ; �^�V���}�q(��)) |
| 4 |
SIDE-A
<�ÓT�O�������y��> |
(1)����{��-�쑺��-�Ő�(��c���v(�S, �O����) ; �^�V���}�q(��))(2)����{��-�����W-������(��R��v,
���x�c�|�v, ��ԓ����Y(�S, �O����))(3)����{��-�����W-�l�G����(��ԓ����Y,
���x�c�|�v(�S, �O����))(4)����{��-�����W-������(��R��v(�S, �O����))(5)����{��-�����W-������(���x�c�|�v(�S,
�O����)). |
SIDE-B
<�ÓT�O�������y��> |
(1)���d�R-�Ԕn�߁E������(��l���}, �ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J)
; ���g���}(����))(2)���d�R-���̉Ԑ߁E�匴�z�n��(��l���}, �ʑ㐨���`(�S,
�O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(3)���d�R-����l�߁E�D�z��(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����)) |
| 5 |
SIDE-A
<�ÓT�O�������y��> |
(1)���d�R-�h�̒���(��l���}, �ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ;
���g���}(����))(2)���d�R-�₭����ܐ�(��l���}, �ʑ㐨���`(�S, �O����)
; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(3)���d�R-�z���炵�߁E�ĂȂ��߁E�܂��̂Ɛ�(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(4)���d�R-�Ì��̉Y��(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(5))���d�R-�Ƃ�ܐ�(��l���}(�S,
�O����) ; ���ǍK(�S)) |
SIDE-B
<�ÓT�O�������y��> |
(1)���d�R-�����߁E���₢������(��l���}, �ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J)
; ���g���}(����))(2)���d�R-���k�[�x�[�}(��l���}(�S, �O����) ; ���ǍK(�S))(3)���d�R-����߁E�v��R�z�n��(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(4)���d�R-��������(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����))(5)���d�R-���ߐ�(��l���},
�ʑ㐨���`(�S, �O����) ; ��l���g(���J) ; ���g���}(����)). |
| 6 |
SIDE-A
<����Q�������|�\��> |
(1)���J���y-�I����-�m���̋F��̃I����[�C�_��](�{����X����-�R��g��)(2)���J���y-�E���W���~�̉S[�C�_��](�{����X����-���܃}�c,
�R��g��, �{��A�L)(3)���J���y-��|[�C�_��](�{����X����-���܃}�c, �R��g��,
�{��A�L)(4)���J���y-���ґ��ʂ̃I����[����](�{�����A��������-�h�ԃT��,
��Ã��V, �ɗ�L�~)(5)���J���y-�V�k�O-�����x(�{����{������u��-��u���E�V,
���g�Ã^�}, �Ɖ��J����)(6)���J���y-�V�̂ڂ萯(�{����{������u��-��u���E�V,
���g�Ã^�}, �Ɖ��J����)(7)���J���y-�����(�{����{������u��-��u���E�V,
���g�Ã^�}, �Ɖ��J����)(8)���J���y-���ł��炵(�{����{������u��-��u���E�V,
���g�Ã^�}, �Ɖ��J����)(9)���J���y-�N�G�[�i-�V�e�c�N�G�[�i(�{���ʏ鑺������-��ԕ����Y,
��鍶��)(10)���J���y-���N�F�[�i(�{���ߔe�s����-���g��q, ����i�G,
����c��)(11)���J���y-�N�G�[�i-���肶��N�G�[�i�[(�{���ߔe�s����-���g��q,
����i�G, ����c��)(12)���J���y-�J�-�J��S(�Ì���-������)(13)�s�����y-�n�[���[-�n�[���[�S�E�ӂ�����[�Ɂ[����(�{���ߔe�s��-���{����,
���{����, �O�Ԑ�����)(14)�s�����y-�،���-����������(�{�����쒬��-��Î��O,
�R���[�T��, ��ÐÎq��)
|
SIDE-B
<����Q�������|�\��> |
���x���y(1)���x-�H���y[��y](�{�����A�m���N��-�^�V�x�O, ��䐭��, ��㐴�F, ���O�Y)(2)���x-���҂̑��(�{�����A�m��-����`��, �Î�[�G��, �V�铿�S)(3)���x-������(�{�����~����o��-�{�錹���Y, ���c��v, �Ð�����)(4)�P����-�P����(�{����X������@��-�O�c�}�c, ����J�}�h, ���ljh�q, ���ǃJ�}�h)(5)�P����-�P����(�Ì���-�Ê쉮�J�}, �{���, ������)(6)�����x-�X���X����(�{�����������x�X-��u���m�u, �쌴�E�^, �쌴�E�V��)(7)�_�x-��̓�(�{���ߔe�s����-�ʈ�T�g, �V�_���B, �ʈ�h��)(8)���q��-���q��(�{���ߔe�s��-���Ǖ~���M, �ɍ�����Y, �^�V���)(9)�G�C�T�[-�G�C�T�[�O��(�{�����~����o��-�{�錹���Y) |
| 7 |
SIDE-A
<����Q�������|�\��> |
���x���y(1)�G�C�T�[-�����G�C�T�[(�{����X������@��-����J�}�h, �R��}�c, ���ǃG�C�q��)(2)�ʼnԌ�-�ʼnԌ�(�{�����鑺�ɏW-�V�_���r, �V�_���E, �V�_����)(3)���x-��x(�Ì���-�����P�g, ��銗��)(4)���x-�ЂƂ�(�Ì���-�����P�g, ��銗��)(5)�����Y-������(�{���������A��-�����Y�ۑ���)(6)�����Y-��m�s(�{���������A��-�����Y�ۑ���)(7)�����Y-�n�����[(�{���������A��-�����Y�ۑ���)(8)�����Y-�n������(�{���������A��-�����Y�ۑ���) |
SIDE-B
<����Q�������|�\��> |
(1)�J��S-�Ă҂��S(�{����X������@��-����J�}�h, ���ǃG�C�q, �O�c�E�V��)(2)�J��S-�����S(�ɍ]��-�R�镶�j,
�^�ߏ钉�g, ���E�V��, ���]�g�V)(3)���S-���[�Ղ���(�ɍ]��-�^�ߏ钉��,
�R�镶�j)(4)�G��-���A�m�݂�[����(�{�����A�m��-�V�铿�S, ��ԍK�})(5)�G��-��ԓ���(�{���v�u�����-���R���M)(6)�G��-�܂����(�ɍ]��-�R�镶�j,
���]�g�V, �^�ߏ钉�g, ���E�V��)(7)�G��-���ĂȐ�(�ɍ]��-�^�ߏ钉��, �^�ߏ钉�g)(8)�G��-�C�̃`���{�[��(�ɍ]��-�^�ߏ钉��,
�R�镶�j)(9)�G��-�ؖȉԐ�(�v�ē�-�����L��, ���Ԑm��, �R��K, �v�i�ˎq)(10)�G��-���n�͂O��(�v�ē�-�����L��,
���Ԑm��)(11)�G��-�v�Ĉ��Ð�(�v�ē�-�����L��, ���Ԑm��, �R��K, �v���ˎq) |
| 8 |
SIDE-A
<����Q�������|�\��> |
(1)�їV��-�����肩�����[��E�J���O�E���Ȃ�[�V��E��������ߏ��E���K�R�E���D�ǁ[��(�{���ߔe�s-�{���t�s��������)(2)�їV��-�z����(�{���R�U�s�R��-���܊��P)(3)���㉫��̎O�������y-���(��P��, �Ôg�ÐM�s, �����Ĉ�)(4)���㉫��̎O�������y-�l�G�̉S(��Ït�q, �ʉh���, ���l��h, �Î芡�я�)
|
SIDE-B
<����Q�������|�\��> |
(1)���㉫��̎O�������y-�Ƃ��(��l����, ��l�݂�, ��l���h)(2)���㉫��̎O�������y-�����������^(��Ït�q,
�ʉh���, ���l��h, �Î芡�я�)(3)���S-�q��S[2��](�{���R���n��-�V��R�I,
�V��ݍ])(4)���S-�q��S[3��](�{����X������@��-����J�}�h, �O�c�Z�c,
���ǃG�C�q)(5)���S-�q��S(�ɍ]��-�^�ߏ钉��)(6)���S-�q��S�Ƃ��S(15��)(�n���삠����(�w��)
; �n������q, �����^���q, �����N�q��, �鐼���w�Z������)(7)���S-���S(6��)(�{�����A�m��-�V��R�I,
�V��ݍ])(8)���S-���S(5��)(�{����X������@��-����J�}�h, �R��}�c,
���ǃG�C�q��) |
| 9 |
SIDE-A
<�{�ÌQ�������|�\��> |
(1)���J���y-�݂�[������-�݂�[�����̃A���O(�r�ԓ�-�F������, �O������)(2)���J���y-�����̃A���O-�����̃A���O(�r�ԓ�-���A�L��)(3)���J���y-�����̃A���O-�����̃A���O(�{�Ó�����-�Ì��@�Y)(4)���J���y-�����̃A���O-�����̃A���O(���NJԓ�-���R�p�q)(5)���J���y-���F��̃A���O-���h�̃A���O(�r�ԓ�-���A���q)(6)���J���y-���F��̃A���O-���Ԃ̎�(�{�Ó�����-�Ì��@�Y,
�V���q)(7)�s�����y-�n�[���[�S-�����}�u�i�����̃A���O(�{�Ó�����-���Ԍ���,
��g�`�Y, ���\�P�h)(8)���x���y-�N�C�`���[-�Ƃ����ɌZ(�{�Ó�����-���Ԍ���,
���쌺�K, ���\�P�h��)(9)���x���y-�N�C�`���[-���NJԂ�[(���NJԓ�-�O�Y���E,
���R�p�q, �L���L�N) |
SIDE-B
<�{�ÌQ�������|�\��> |
(1)�j�S-�Ɓ[���ɃA���O(�{�Ó�����-�Ì��@�Y)(2)�j�S-���ɂ��܂���(�{�Ó�����-���Ԍ���)(3)�j�S-���Ԃ̃u�i�K�}(�{�Ó�����-�V��~�G)(4)�j�S-�ƌ��ẲS(���NJԓ�-�O�Y���E,
���Ït��, ���R�p�q��)(5)�G��-�{���̎o����(�{�Ó�����-�`��������, �V���q)(6)�G��-�r�Ԃ̎�(�{�Ó�����-���鏇�_)(7)�G��-�������̃}����(�{�Ó�����-���\�P�h)(8)�G��-�Y���v�̃A���O(�{�Ó�����-�g������)(9)�G��-�떓�̃C�T�~�K(�{�Ó�����-��g�`�Y)(10)�G��-�ɗǕ��Ƃ�����(�{�Ó�����-�Ì��@�Y)(11)�G��-�l���̎�(�{�Ó�����-���@���h��) |
| 10 |
SIDE-A
<�{�ÌQ�������|�\��> |
�G��(1)�����Ԃ̃J�i�K�}(�{�Ó�����-���鏇�_, �V���q)(2)�������̃}�`�K�}�̃A���O(�{�Ó�����-���쌺�K,
���\�P�h)(3)�Η�̓��̃A���O(�{�Ó�����-����M��)(4)�v�D�z�[�߂̃A���O(�{�Ó�����-����}�c)(5)��D�e�̍ȕۓߗ��̃A���O(�{�Ó�����-�Ì����q,
�Ì��@�Y)(6)��v��N��(�{�Ó�����-�I�����K)(7)�V���̏��i�̃A���O(�{�Ó�����-�V��~�G)(8)���ԃE�X�~�K�K�}(�{�Ó�����-�I�����K)(9)�Ă̂���(�{�Ó�����-�g������)(10)�Ì��̎�̃A���O(�{�Ó�����-�`��������)(11)���o�ł̃A���O(�r�ԓ�-���A���q)(12)���Ԃ܂��炢(�r�ԓ�-��ߔe�T�J�G)(13)���Ǖl�̃n�C�}(�ɗǕ���-���v���}�c�q) |
SIDE-B
<�{�ÌQ�������|�\��> |
(1)�G��-�ɗǕ��Ƃ�����(�ɗǕ���-���a�c�J�j)(2)�G��-�Η�̐Ԃ���(�ɗǕ���-���a�c�J�j)(3)�G��-�}�c�K�}�A���O(�ɗǕ���-���v���}�c�q)(4)�G��-���Ȃ��Ⴊ�܃A���O(�ɗǕ���-���v���}�c�q)(5)�G��-���NJԂ��悩���(���NJԓ�-�O�Y���E)(6)�J��S-�@�D��̃A���O(�r�ԓ�-���A����,
���A���q)(7)�D�S-�r�̑��L���e(�r�ԓ�-���v�{���, ���A�L��)(8)�D�S-�ɗǕ���̂��ɐe�̃A���O(�r�ԓ�-���v�{���)(9)���S-�q��S(�{�Ó�-�Ì����])(10)���S-�q��S(���NJԓ�-���R�p�q,
�L���L�N)(11)���S-�q��S(���NJԓ�-���R�p�q)(12)���S-�Ђ�̉S(�r�ԓ�-���v�{�m�q)(13)���S-�܂���̉S(�r�ԓ�-�O�����q) |
| 11 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
���J���y(1)�������-���������^(����-����p�q, �|�z����, �O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(2)�������-���������^(����-����p�q,
�|�z����, �O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(3)�L�N��-�L�N�肢�S(�Ί_������-�약�T,
�약��, ���C �T, ���C���V)(4)�L�N��-�ɂ������̉S(�Ί_������-�약�T, �약��,
���C �T, ���C���V)(5)�L�N��-�v����(�Ί_������-�약�T, �약��, ���C �T,
���C���V)(6)�L�N��-�T�[���C(�Ί_������-�약�T, �V�{��, �V�{�P�N��)(7)�L�N��-���[��ʂƂ�����(�Ί_������-�약�T,
�V�{��, �V�{�P�N��)(8)�L�N��-������(�Ί_������-�약�T, �V�{��, �V�{�P�N��)(9)�L�N��-�^�ߔe��(�Ί_������-�약�T,
�V�{��, �V�{�P�N��)(10)�L�N��-���ې�(�Ί_������-�약�T, �V�{��, �V�{�P�N��)(11)�L�N��-��J��(�Ί_������-�약�T,
�V�{��, �V�{�P�N��)(12)�L�N��-�݂낭��(�Ί_������-�약�T, �V�{��, �V�{�P�N��)(13)�L�N��-���[�����[��(�Ί_������-�약�T,
�V�{��, �V�{�P�N��)(14)�L�N��-�����(�|�x��-�K�{�L��, �T��ە�, ��R��Y��)(15)�L�N��-�g���`���[(�|�x��-��R��Y,
�F������, ����������) |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
���J���y(1)�L�N��-���S(�|�x��-�K�{�L��, �����{�c��, �F��������)(2)�L�N��-�݂낭��(�|�x��-�K�{�L��,
�����{�c��, �F��������)(3)�L�N��-���Ǔc��(���\���c�[-���R���v)(4)�L�N��-�݂낭��(���\���c�[-���R���v)(5)�L�N��-���s�̉S(���l��-�吓�G�Y,
�O�����Y, �������}��)(6)�L�N��-�Ɠ��̉S(���l��-�吓�G�Y, �O�����Y, �������}��)(7)�L�N��-�x�̉S(���l��-�吓�G�Y,
�O�����Y, �������}��)(8)�L�N��-�}�x(����-����p�q, �|�z����, �O�M�ʃE�c�P,
���ꃄ�}�g)(9)�L�N��-���x(����-����p�q, �|�z����, �O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(10)�L�N��-�҂�[�Ȃ���(����-����p�q,
�|�z����)(11)�L�N��-�y���T(����-����p�q, �|�z����)(12)�L�N��-���炩���[(����-����p�q,
�|�z����). |
| 12 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
���J���y(1)�L�N��-���x(����-����p�q, �|�z����, �O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(2)�L�N��-���ĂԂǂ�(����p�q,
�|�z����)(3)�L�N��-�A�J�}�^�[�o���̉S(�V�铇-���c�F��, �{�ꍲ����, �F��������)(4)�L�N��-�_�l�����̉S(�V�铇-���c�F��,
�{�ꍲ����, �F��������)(5)�L�N��-���x(�V�铇-�{�ꍲ����, �F������, ���l�Ñ�)(6)�L�N��-�A�J�}�^�[����̉S(�V�铇-�{�ꍲ����,
�F������, ���l�Ñ�)(7)�L�N��-����W���o(���ԓ�-�Y��p�s, �c��_)(8)�L�N��-���g���W���o(���ԓ�-�Y��p�s,
�c��_)(9)�L�N��-�앗���W���o(���ԓ�-�Y��p�s, �c��_)(10)�L�N��-�p�M�̉S(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�K)(11)�L�N��-���M�̉S(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�K)(12)�~��-����ɕ�(���l��-�I������,
�������}, �吓�G�Y)(13)�~��-�ւ����ǂ���(���l��-�������}, �I������, �吓�G�Y,
�O�����Y). |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)�����-�_�h�_�[�̉S(���l��-�o���q, ��ꃈ�l, �Ί_�q���R��)(2)�ߍ�-��a����O�W���o(�Ί_���약-���܊���, ���O�Y, ���ܐ���)(3)�ߍ�-��ω��W���o(�Ί_���약-���܊���, ���O�Y, ���ܐ���)(4)�ߍ�-�҂�[��(���\���c�[-���R���v, �ߍ��O)(5)�ߍ�-�����̌ւ炵��(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v)(6)�ߍ�-�ڂł�(���\���c�[-�ߍ���)(7)�ߍ�-�����ӂ�(���\���c�[-�ߍ���)(8)�ߍ�-��������(�V�铇-���ۉp��, ���ڌF��, �{�ꍲ���ˑ�)(9)�ߍ�-��(�V�铇-���ۉp��, ���ڌF��, �{�ꍲ���ˑ�)(10)�ߍ�-�^�Ӊ���(�V�铇-���ۉp��, ���ڌF��, �{�ꍲ���ˑ�)(11)�ߍ�-�E�u�k�s�[�_(�V�铇-���ۉp��, ���ڌF��, �{�ꍲ���ˑ�)(12)��q�ǂ��-��q�ǂ�A���E(�Ί_���{��-��c�v�g, ��v�鍲)(13)��q�ǂ��-���S(�|�x��-�����{�c��, �F������, ��R��Y��)(14)��q�ǂ��-���x(�|�x��-�����{�c��, �F������, ��R��Y��)(15)��q�ǂ��-���Ɛ���(�|�x��-�����{�c��, �F������, ��R��Y��) |
| 13 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)���J���y-��q�ǂ��-����̉S(�|�x��-�����{�c��, �F������, ��R��Y��)(2)���J���y-��q�ǂ��-�������S(�|�x��-�����{�c��,
�F������, ��R��Y��)(3)���J���y-�i����-���D�W���o(�^�ߍ������-�O�I���i�n,
�O�I���}�i�r, ������m)(4)���J���y-�J�-�J��̃A���E(�Ί_������-�약�T,
�약��)(5)���J���y-�J�-�J��̃A���O(�^�ߍ����c�[-���l���Y)(6)���J���y-���F��-�c������(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�K)(7)���J���y-���F��-�g�O���ԃW���o(�^�ߍ����c�[-���l���Y)(8)���J���y-���F��-����D�W���o(�^�ߍ����c�[-���l���Y,
�c���ƎO)(9)���J���y-���F��-����O��(�^�ߍ����c�[-�ѓc���b)(10)���J���y-���Ă�-�����ف[����(�Ί_���약-���ܐ���)(11)���x���y-���q��(�Ί_���Ί_�s�o���L�u)(12)���Ƌ���-���Ԃ�(�^�ߍ������-�^�ߔV���c)(13)���Ƌ���-�������(�^�ߍ����c�[-��x���Ό�)(14))���Ƌ���-�҂�(���ԓ�-�Y��G��) |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)���Ƌ���-��q������(�|�x��-�K�{�L��, �����{�c��, ��R��Y��)(2)���Ƌ���-�Ƒ���̃����O�g(�Ί_������-���C�T, ���{��v, �V�{�P�N)(3)�j�S-�Ƒ���̊��x(�Ί_������-������v, �V�{���l, ?�C�T��)(4)�j�S-�Ƃ����т̃W���o(���̈�)(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v)(5)�j�S-�Ƃ����т̃W���o(���̓�)(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v)(6)�j�S-�߂ł�����(�Ί_���{��-�c���F�×�, �c���t�q, ��c����, �������)(7)�j�S-�{�Nj���(�Ί_���{��-�c���F�×�, �c���t�q, ��c������)(8)�j�S-�������~(�|�x��-�K�{�L��, �����{�c��, �F��������)(9)�j�S-�c�A�S(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v)(10)�j�S-����A���E(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v) |
| 14 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)�j�S-�Č���̃A���E(���\���c�[-�ߍ���, �ߍ��O, ���R���v)(2)�j�S-������(���\���c�[-���R���v)(3)�j�S-���l��(���l��-�O�����Y, ��ꃈ�l, �吓�P�O)(4)�j�S-��J��(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�K)(5)�j�S-�g�Ɗԓ���(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�K)(6)�j�S-���Ԓ���(���ԓ�-�Y��p�s, �Y��p��)(7)�j�S-�{�nj���(�Ί_���{��-�c���F�Í�, ��c����)(8)�j�S-��������(����-��l���}, ��l�����`, ��l���g��)(9)�j�S-�g�ƊԌ���(�g�Ɗԓ�-�Đ��P�s) |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)�j�S-�ɕ��c����(���ԓ�-�c��_, �Y��p��)(2)�j�S-�^�ߍ�����(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q)(3)�G��-�������(�Ί_������-������v, �V�{��, ���C���V, ������)(4)�G��-�ڂ��ہ[��(�Ί_������-������v, �V�{��, ���C���V, ������)(5)�G��-�e����(�Ί_������-�약��, �V�{��, ������, ���C���V)(6)�G��-������(�Ί_������-�약��, �V�{��, ������, ���C���V)(7)�G��-���c��(�Ί_������-������v, �V�{��)(8)�G��-��˂Ɓ[���(�Ί_������-������v,
������)(9)�G��-�v����(�Ί_������-������v, �V�{��, ������, ���C���V)(10)�G��-���т炨�[����(�Ί_������-������v, �V�{��, ������, ���C���V)(11)�G��-�匴�z�n��(�Ί_���약-���܊���, ���O�Y)(12)�G��-�܂�������(�|�x��-�K�{�L��, �����{�c��, �F������) |
| 15 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
�G��(1)�c�[�x��(���\���c�[-�ߍ��O)(2)�ۊԖ~�R��(���\���c�[-�ߍ���)(3)�a�l��(���\���c�[-�ߍ��O)(4)�����]�V�P�}(���\���c�[-�ߍ���)(5)�^�R��(���\���c�[-�ߍ���)(6)�y���K���Ƃ�(����-����p�q,
�|�z����, �O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(7)�}���K�j�X�b�c�A(����-����p�q, �|�z����,
�O�M�ʃE�c�P, ���ꃄ�}�g)(8)�V�铇�̑O�̊C�̉S(�V�铇-�{�ꍲ����, ��C�ǎq,
��C���})(9)�z����(�V�铇-���ڌF��, �{�ꍲ����, �������V�q��)(10)�����ɂ���(�V�铇-�{�ꍲ����,
��C�ǎq, ��C���}��)(11)���Ԍ��W���o(���ԓ�-�Y��p�� |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)�G��-�D�}�̉S(�^�ߍ������-������m)(2)�G��-�Ȃ��Ȃ��(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q,
���{�Ƃ�)(3)�G��-���݂�(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q, ���{�Ƃ�)(4)�G��-�^�ߍ��̔L��(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q)(5)�G��-�h�i���Ƃ��(�^�ߍ����c�[-�c���ƎO)(6)�G��-�h�i������(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q,
���{�Ƃ�)(7)�G��-�ǂȂ���(�^�ߍ����c�[-���{�Ƃ�)(8)�J��S-�E�D�W���o(�Ί_���{��-��c�v�g,
��������G, ��c������)(9)�J��S-���^���E�}(�Ί_���{��-��������q,
�Y�Δ���q, ��������G, ��c�v�g)(10)�J��S-�Ɓ[��(�Ί_���{��-��c�v�g,
��������q, �Y�݂�, ��������G) |
| 16 |
SIDE-A
<���d�R�Q�������|�\��> |
�J��S(1)�D�̐e(�Ί_���{��-�O���`�p, �c�����×�, �c���t�q��)(2)�܂ւ�����^(�Ί_���Ί_-��l���},
�ʑ㐨���`, �V�郀�c��)(3)�x��삤����(�Ί_���Ί_-�c�����×�, �c���t�q,
��c����, �������)(4)�R�������^(�Ί_���Ί_-��l���}, �ʑ㐨���`, �V�郀�c��)(5)�����������^(�Ί_���Ί_-��l���},
�ʑ㐨���`, �V�郀�c��)(6)�R�C�i�[�����^(�Ί_���Ί_-��l���}, �ʑ㐨���`,
�V�郀�c��)(7)�쎵��(�Ί_���Ί_-��l���}, �ʑ㐨���`, �V�郀�c��)(8)�L�����^(�Ί_���Ί_-��l���},
�ʑ㐨���`, �V�郀�c��)(9)�����^(�Ί_���Ί_-��l���}, �ʑ㐨���`,
�V�郀�c��)(10)�Ì��̉Y�u�i���[�}(�Ί_���Ί_-��l���}, �ʑ㐨���`, �V�郀�c��) |
SIDE-B
<���d�R�Q�������|�\��> |
(1)�J��S-���т̂���(�|�x��-��R��Y, �������~, �����H�T��)(2)�J��S-�݂�ʉS(�^�ߍ����c�[-���l���Y)(3)�J��S-�͂������f���o(�^�ߍ����c�[-�{�|�G�O)(4)�J��S-�܂�����f���o(�^�ߍ����c�[-���l���Y, �{�|�G�O)(5)���S-�`���[�K��(�Ί_������-?�C���V, �V�{��, ������, ������v)(6)���S-���̎q��S(�Ί_���Ί_-��l���})(7)���S-��̎q��S(�Ί_���Ί_-�ʑ㐨���`)(8)���S-�����낤��(���l��-�������},
�o���q, ������)(9)���S-�q��S(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q)(10)���S-�q��S(�^�ߍ������-����Ƃ�)(11)���S-���S(�Ί_������-?�C���V,
�V�{��, ������)(12)���S-���S(5��)(�^�ߍ����c�[-�x�����X�q) |
|
�P�Q���A�y�������u�Ñ�̗w�ƋV��̌����v���u��g���X�v���犧�s����B�@�@pid/1361826
|
�܂�����
�}��
���́@�{���̖ړI�ƕ��@/1
���́@�����̋N��/11
���߁@�����̋N���Ɋւ��鏔��/11
���߁@�����Ɖ̊_�Ƃ̊W/14
��O�߁@�����E�̊_�̋N���Ƃ��Ă̏t�R����/22
�P�@�Ԍ��ƉԌ���/23
�Q�@�R�s���ƎR��/29
�R�@��x�Q��Ƃ��̉�/40
�S�@�����ƍ�����/45
�T�@�쓇�ɂ����鍑���Ɖ̊_/56
��l�߁@�Ñ�̎R�V��/59
�P�@���t�W�u�|�扥�v�̉̕���Ɓu��V�v�̉�/59
�Q�@�Ċ����b�E�������b�ƋV��Ƃ̊W/65
�R�@�����n�c�_�b�̖����I�w�i/70
�S�@�Ċ���ƒ|�扥/78
�T�@�����ɂ����鍑���Ɖ̊_/81
���́@�����s���ƎR�l�̋V��/97
���߁@�t�R����Ɛ����s��/97
���߁@�����̗��K�_�\�����E�}����߂����ā\/103
��O�߁@��d�E���E�іȂ�/108
��l�߁@�R�l�̋V��/112
�P�@�R�l�̐d�Ə�/112
�Q�@���t����_�ɂ���/116
�R�@����ꌾ��_�Ɩ����p/132
�S�@����Ղ��̑��ɂ�����R�l/140
�T�@�u�a���v�̗R���Ɩ��`/147
��O�́@�̕��̃^�}�t���I�Ӌ`/161
���߁@�^�}�t���̎���/162
�P�@�u�^�}�t���v�Ƃ�������/162
�Q�@�~�A���E���甦�ɂ���/173
�R�@�_���̊ϔO�Ɓu�A���v�̌�`/177
���߁@�����ՂƂ��̋N�����b/190
�P�@�����Ղ̐��i/190
�Q�@�����N�̎�p�ƓV��˂̐_�b/193
�R�@�������̎�p���`�������̐_�b/201
�S�@��p����@���ց\�V��˂̐_�b���߂����ā\/206
��O�߁@�_�y�Ɛ_�y��/214
�P�@���_�ɂ���/214
�Q�@�u�_�V�сv�Ɓu�_�y�v/216
�R�@��������_�y�ƌÐ_�y�Ƃ̊W�@���l����@�̈Ӗ�/221
�S�@�Ð_�y�̂̍\���Ɛ��i
�@�@���@�\�_�y���̏�Ƃ��̐����̖��ɂ悹�ā\/241
�T�@��������_�y�̍\���Ɛ��i/252
��l�́@�����̈Ӌ`/265 |
���߁@�Ԍ��E�����̃^�}�t���I�Ӌ`/265
�P�@�u����v���Ƃ̎�p�I�Ӌ`/266
�Q�@�����I�i���Ƃ��ẲԁA���A�_�A���Ȃ�/280
���߁@�V�c�����̐����I�Ӌ`/295
�P�@�L�I�E���t�ɂ�����V�c�ƍc�c�_�̍���/295
�Q�@���y�L�n�����b�̐��i/299
�R�@�V�c�����̈Ӌ`/302
��O�߁@�����ƒn���c�_�̍���/310
��́@�����̂Ƃ��̓W�J/319
���߁@�����̂̐��i�A���z�A�f��/319
���߁@�u�v���́v�ɂ���/325
��O�߁@�V�c�̍�����/335
�P�@���_�E�m���V�c�̍����̂ƍ����I�]������/335
�Q�@�����V�c�́u�]���́v/342
��l�߁@���]�߉̂̌n��/346
�P�@�R�]�߉̂Ƌ{�]�߉�/346
�Q�@���]�߉̂Ɩ��t�u�G�́v/348
�R�@���������́u�]���́v/353
�S�@�u�����v�Ƃ�������/356
��ܐ߁@�����I�]���̂Ƃ��̓W�J/365
�P�@�����I�]����/365
�Q�@�����I�]���̖̂��t�ɂ�����W�J/369
��Z�́@�̊_�̈Ӌ`�Ƃ��̗��j/379
���߁@�̊_�̈Ӌ`/379
�P�@�̊_�̊T�O�Ƃ��̎���
�@�@���@�\�^�_���ƒ������Ӗ����̉̊_���߂����ā\/379
�Q�@�u�E�^�K�L�v�̌�`/389
�R�@�̊_�̗\�j�I�Ӌ`/391
�S�@�u�̊|���v�̈Ӌ`�\�����E�����E����ɂ��ā\/394
���߁@�̊_�̗��j/403
�P�@�̊_�̋N���ƕω�/403
�Q�@�R�ォ�琅�ӁE�s��/411
�R�@�̊_�Ɠ��E����/413
�掵�́@�̊_�̉̂Ƃ��̓W�J/425
���߁@�̊_�̉̂̎��E���i�E���z�@�Ƃ��̎��/425
���߁@�̊_�̉�/434
�P�@�j���̗U����/434
�Q�@�����̂Ƃ͂˂���/442
�R�@�V�l�̉�/456
�S�@�V�l�ɑ��靈�����̂Ȃ�/470
�T�@���̋��P��/480
�U�@���̑��̉�/484
��O�߁@�̊_�̉̂Ɩ��t�u�����v�̉�/491
�P�@�u�����v�̈Ӗ�/491
�Q�@�̊_�̉̂Ɩ��t�u�����v�̉�/495
���� |
���A���̔N�A�����Y���u�������j��b�v���u������Ёv���犧�s����B
���A���̔N�A�˓c���u���ꕶ���̌��� : �蕶�ɐ�����`���v���u�ŋ���}���v���犧�s����B�@�@pid/3026357
|
����
����
���́@������
(��) ���������̑�{/p1
A�@�����قɂ����̑�{/p3
B�@�e�n��ɂ����̑�{/p10
(��) �������Ȃ���̑�{/p44
A�@�����[���ɏ���/p45
B�@�j�����~�����U/p63
�i�O�j�@�����[�{�u�������蕶�L�v/p68
�i�l�j�@�c�������i���߁j�O�\��t/p117
A ��Z���I�̎��ߏ�(���ȏ���)/p118
B �ꎵ���I�̎��ߏ�
�@�@��(���ȂƊ����̍���)/p129
C �ꔪ���I�̎��ߏ�(��������)/p134
���́@�����ҁ\�����̉���\
(��) ��������蕶�̉��/p154
A�@�����ُ��U/p154 |
B�@�e�n��ɂ����/p159
(��) �������Ȃ���̉��/p173
A�@�����[���ɏ��U/p173
B�@�j�����~�����U/p187
�i�O�j�@�����[�{�u�������蕶�L�v/p192
A�@�蕶�L�̕ҏW�ɂ���/p192
B�@�蕶�L�̖ژ^/p193
C �����҂ɏo�Ă���蕶�L���
�@�@��(��{�ɂȂ�����)/p195
D�@�����[�{�ƈɔg�{�Ƃ̍Z��/p211
(�l) �c���������/p216
��O�́@�蕶�Ɍ����鉫�ꕶ��
(��) ����/p225
(��) �@��/p226
(�O) ����/p233
(�l) ����/p242
(��) �w�p/p256
(�Z) ����/p264 |
(��) �y�،��z/p276
(��) ����/p292
����/p311
�t�@����蕶��Ǐ��
�@�@�����ӎ���/p313
��l�́@�蕶�Ɍ����鉫�ꏑ���j
(��) �Ñ�{�y�Ƃ̌��/p319
(��) ��ܐ��I�̏���/p321
(�O) ��Z���I�̏���/p326
(�l) �ꎵ���I�̏���/p337
(��) �ꔪ���I�̏���/p340
(�Z) ��㐢�I�̏���/p344
(��) ��Z���I�̏���/p346
�k�t�L�l�@�ܒ���l/p352
��{�̂��肩��/p354
���������j�N�\/p356
��㊒n�}/p362
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��5 �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@pid/1658753
|
���G
��
�c�ӏ��Y�搶
���\���ӈ�搶
���҂̂��Ƃ�
���t���s��/P115
���L��
�Ȗ� |
�����P�@��i�@�ꗎ����/17
�V�Q�@��i�@�n����/20
�V�R�@�O�i�@�]�ː���/23
�V�S�@�l�i�@���q����/26
�V�T�@�ܒi�@�����琛��/29
�V�U�@�Z�i�@����/32
�V�V�@���i�@����/40
�S���W�@�D����/49 |
�V�X�@�Δn��/50
�V�P�O�@������/51
���^
�ҋȂP�P�@�l���@������/96
�V�P�Q�@�ቹ�@���ҏo����/100
�V�P�R�@���Ȃ�[��/102
�V�P�S�@�ȁ[����Ɂ[/103
�V�P�T�@���Ԑ�/104 |
��ȂP�U�@���܂Â����/106
�V�P�V�@�Ђ�݂����Ԃ�/109
�V�P�W�@�N�ē�
�@�@���i���̉����̉Z���ˁj/111
�V�P�X�@��㊃����f�B�[/112
�V�Q�O�@�A�����J��/114
�E
�E
|
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��6 �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@�@
pid/1658755
|
���G
�����@�c�ӏ��Y�搶
����
�T��
����t���@�\�����Ƃ̔�r�\
�}��
�y���L��
�ڎ� |
�Ȗ�
�{��
�H�H�l�y��
���t�E�S�W�o�ŏ���
�ܐ��y��
�p��ڎ�
�lj����^
�i��j�@�X�����̉̎�/119 |
(��) NHK��ÃR�����r�A���R�[�h�����I�O�ʐ^/126
�i�O�j�@���Ɖ��y�Ɨ����ÓT�y�̗��[/127
�i�l�j�@�َ�X������ے肷/133
�i�܁j�@���c�p���X���e������̓`�����/153
�i�Z�j�@�X�����̐����ƈْ[�@���ǐ��g/155
(��) ��L(VI�W�o�ł𗹂��� �o�łƕی� �N���)/157
�E
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��6 �ʍ����^�v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@�@pid/1658754
|
�X�����H�H�l
�ژ^
��c�� |
����c�߁@���o�g�o�A��
��
�a�����i�� |
������
�g��c�߁@���o�g�o����
�Ő� |
���A���̔N�A��ё��ǂ��u�����̋N���v���u�p�쏑�X�v���犧�s����B�@ (�p��V��)�@pid/9544941�@�@�S�O�O�~
|
���� ���Ɛl��/7
���̋N��/7
�����ƎЉ�/8
���� ��j����̑���/12
�����̂͂���/12
���A��₩����/14
�_�k�ƂƂ���/16
��O�� �����w�I�����̕���/20
�����Ɩ����w/20
�����̕�������/21
�n�挤���̐i�W/24
�����Ɨ��s/25
�������s���ᔻ/27
��l�� �����̏��`��/31
���҂ɑ����̑ԓx/31
���҂ւ̋���Ƒ��h/32
���̕���/35
���̔j��\����/39
���ق̓�/40
�Α�/42
�R���関�S�l/47
�T�e�B�ƃC���h�_�b/48
�}��/50
��㑒�Ǝ��㑒/53
���҂̉�/56
���A��/56 |
����/59
����/65
�Ђ�����Ԃ��̌���/67
����/69
���߂Ȃ�����/71
���u/73
�揬��/75
���̂̕��ʂƖ����ړ��̕���/79
���ʂ̕s��v/82
�M��/84
���̕ۑ��Ɠ��W�����q/86
�~�C���ƉΑ��̌���/89
�����H�l��/93
����/94
�����Ƒ��E��/97
�썰�̕\�ۂƕ���/102
��� ���{�̑���/105
���|���̖�/105
�Α��Ƃ̌��т���/107
���N�̎��㑒/108
�k�A�W�A�̎��㑒/110
���{�̎��㑒/113
���҂̎R/113
�R�㑼�E/115
���Ɛ��Ƃ��Ă̎R/118
�R�����E�ƏĔ��k�앶��/121 |
�����Ɨ��搧/122
��㊂̐�/127
��㊂̕���/131
�ƕ����͂ǂ��炪��s��/133
���n�̉���/136
�����Ɨ��搧/140
���N�̕���/146
�����Ñ�̑���/148
����A�W�A�̕����Ɩ����ړ�/150
�e�B���[/152
���҂̏M�Ɨ썰/154
�e�B���[�̒i�K/157
�e���|���E�e�����̖���/159
�M���Ƒ��z�M��/162
���̍��ƊC�㑼�E/166
�C�㑼�E�ϔO�̕��z/170
�V���D/170
�h���\�������Ɓu�V���D�v/173
���~�˂̕lj�ƕ����ړ�/175
�V���D�ƕ���/178
�V���D�̂ɂȂ���͂��ꂩ/181
��Z�� �G�s���[�O ���F���̔҉�
���Ƃ���
�Q�l����
�E
�E |
|
| 1966 |
41 |
�E |
�P���A���{�N�فu�Љ��v�ҏW���u�Љ�� 21(1)�v���u���{�N�فv���犧�s�����B�@
pid/7961227
|
���W�E����N�̕����I���{/7�`40
������ ����I�l�Ԃ̌`�� / �X�˒C�j/p7�`7
�N�Ɠ`������--������Y�̌p����...... / �����v/p8�`12
���N�W�c�����ւ̎��_ / �O�ؖ�/p28�`31
�A���P�[�g �M�c�̂ł́A�ǂ̂悤�ȕ���������ϋɓI�ɐi�߂������A�܂��i�߂Ă��邩
/ ���{�N�c���c�� ;���{�o�ϐN���c��
�@�@��;�S���ΘJ���N�c�̋��c�� ;�F���N���u�� ;���{YMCA���� ;���{BBS�A��/p13~15
���j���w�ԁu�y�̉�v--���x�����Q���̒��Ő��܂��� / �؈��/p16�`18
���g�l�`��ڗ���`������--����������k�����w�Z���|�N���u / ����_��/p19�`21
�������w�ԐN�c--�ޗnj����s�S���������̎��� / ������/p22�`24
����ɂ����閯���|�\--������������鋽�y�ւ̈���,�������_ / �V�铿�S/p25�`27
���N�̉��l�ςɊւ��錤��--�������猤����1964.10 / ���c���j/p32�`35
���N�̉��l�ӎ�����--International Journal of Adult and Youth Education��16����2�� / ���_�q/p36~40
�Љ��̕������߂�����--�n���Љ��s���ƈ�ʍs�����j�Ƃ̊W�ɂ��� / �c�㌳��/p48�`52
���ꂩ��̐N�c�� / �֓����~/p53�`57
�� |
�P���A���a�c�^�~�F�����u����n����Օ��z�}[�n�}����]���u���a�c�^�~] ���犧�s�����B
�@�@�@�傫���A�e�ʓ� 1�� ; 86�~51cm�@�@�k�� 1�F174000 �ĔŁ@�@�����F���ꌧ���}����
�Q���A�ʓߔe�p�q���u�ۈ�̗F 14(2) p41�`41�@�S���Љ�����c��v�Ɂu�J���[�E�Z�N�V���� �ۈ畗�y�L(��34��)�@����̊��v����e����B pid/7971671
�R���A���P�オ����w�j�w�E�n���w��ҁu�j�� = Shisen : historical & geographical studies in Kansai University (�ʍ� 31) p.32�`42�v�Ɂu�����Ə��v�\����B
�S���A�u���z 4(4)(34) �v���u���}�� �v���犧�s�����B�@pid/1792571
|
����ɂ��͍��` / �O�؏~/4
�X����24���� //8
�V���[��E�B���h�̒��̐l�� //17
���㐶���ҥ�`�� //22
���`�̋x�� //26
�J�W�m�ƐΏ�̊X�}�J�I //30
���`�̖��͂����/�������u ;�֓����c ;�R���q�� ;���ԏ䕽/37
���{�����鏎���̕lj� / �L���� ;�����ӎs�N ;�s���q�j/50
���G�t��G���̐��U / �����ӎs�Y/73
�G���̂ӂ邳�� / ���g���� ;�{���ʐ^��/65
��ࣖ�ڂȑ�O�|�p�̈�Y / �L����/70
����̕��� �m�[�g���_���̂��ނ��j / G.���W���[ ;�ҝ�/77
�킽���̃m�[�g����_����h��p�� / �����B�l�Y/75
����̗� ���̑����ƕ�Ύs�� / ���� ;�i�c����/120
���F�g�i���o��5���O�̉���ČR / �������F/84
camera eye'66 �k�̃|�[�g���[�g / �_�J�_/110
���ꂩ��̃��|�[�g ��n�Ƃ������̍앨 / �X���/108
|
�L���ێq�� ����}�} / ���������� ;
�@�@���H�R���E ;�������Y ;�n��̂ڂ�/104
�z�[�� �M�������[�s�J�\�q���鏗�r //45
�q���鏗�r��� / �X�F�Y/44
�ւÂ��� / ����P�Y ;�����P�Y ;�ÎR�� ;����P�Y/91
���܂�(4)���Z����L���Z�ނɂ� / �{�e�h/149
���N�M�̂͂Ȃ� / ��q�w�� ;�����M���Y ;���؍��g/136
�X�R�b�` ���̖��Ƃӂ邳�� / ���؋`�_/144
���{�̖� ����̘a�َq //142
���炾�̔閧(12)�ɂ� / ����猕v ;�y�����v/129
���i�j���[�t�F�[�X �j�̂������̂��̑� //157
�v���Ⴂ / �䕚���� ;���ɔV��/134
㣋l�͐M�p�ł��邩 / ���v/99
����\�ɖ������� / �ϐ����v ;�쑺���� ;�{�c���� ;���c����/125
������ƋC�ɂȂ邱�� / �ё� ;���v ;���R���q ;�{�n���i ;
�@�@������l�Y ;��Ȃ������� ;�R���� ;����F�q/42
����܂����(3)���[�X����������p�� / �����_/158 |
�T���A�R���ӈꂪ���{�����w��ҁu���{�����w��� (�ʍ� 45) p.22�`33�v�Ɂu�u�e���S�̐_�v�ɂ��āv�\����B
�U���A�q���P�u���� 18(9) (�ʍ� 206) p.22�`25�@������茤�����o�ŕ��v�Ɂu�x�g�i���̏�Ɖ���̏--�A�W�A�̓����v�\����B
�U���A���c���q���u�������y��w�A�����I�v = Kunitachi College of Music journal 1 p.29-58�v�Ɂu�L���E���������Ɍ�������u�c�A�₵�v�̉��y�̊O�ς̌����k�̕����l�v�\����B�@�@�@�iIRDB�j
�W���A�u�܂� = Festival (11) �v���u�܂蓯�D�� �v���犧�s�����B�@pid/7930487
|
�c�̓D�𗎂Ƃ���--�O���������̑���
�@�@�� �q���Ǝʐ^�r / �쑽�c��/p4�`28
�J��ƔO���x / ���J�d�v/p29�`31
�e�n����� �X�� / �����Õv/p32�`33,84�`32,84
�e�n����� ��茧 / �X������/p34�`37
�e�n����� ������ / �R�����Y/p37�`40
�e�n����� �V���� / �ߓ�����/p41�`42
�e�n����� �R���� / ��X�`��/p43�`45
�e�n����� ���쌧 / ���c�`��/p46�`52
�e�n����� ���� / �{����/p53�`55
�e�n����� ���䌧 / �i�]�G�Y/p56�`59
�e�n����� ���쌧 / �쑽�c��/p60�`62
�e�n����� ���s�{ / �c���L�`/p63�`63 |
�e�n����� ���R�� / �����Ďi/p64�`66
�e�n����� �R���� / �������v/p67�`69
�e�n����� ���ꌧ / �s�꒼���Y/p70�`72
�e�n����� ���茧 / ���]��/p73�`74,84�`73,84
�e�n����� �{�茧 / �����/p75�`75
�e�n����� �������� / ����d�N/p76�`78
����̔O���x--�`�����_���[(�����Y) / ���Ԉ�Y/p78�`81
�T�C�����{�E�Y / ���J����/p82�`82
���ɓ`���y�ɂ��� / �R�c��F/p83�`84
�O�͒n���O���x�̌n�� �� �O�͒n���O���x�ꗗ�\ / �ɓ��Njg/p85�`110
�a���̔O���x �q���Ǝʐ^�r / �č荂�z/p112�`113
�O���|�\�̌n�� / �ܗ��d/p114�`122
�E |
�W���A�u�W�] (92) �v���u�}�����[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/1795851
|
�l�Ԃ̂��Ȃ����E / ���q����/9
���p�̊w����̂�т�� / �����M��/10
�������̖� / ���Y����/11
���W�Љ�Ƒa�U�Љ� / �{�n�`�O�Y/12
�_�Əb�̂͂��� / �^�ǐm/15
���a�̗ϗ��Ƙ_�� / ���c��/17
���{�����_�ւ̔ᔻ�I�l�@--
�@�@����ؑ�٥�a�ғN�Y�̏ꍇ / �~����/48
�l�Ԃ̖��������(���k��) / �Γc�p��Y/120
�O���l�ɂ��� / ���c�~/92
�_���̂����� / �ēc���D/116
�܌���\�����̋L / ����d��/136
���S�ۏ�̌����͉��� / �ݓc���V��/75
|
�펞������--�ꋳ��҂̈₵�����̋L�^ / �X����Y/164
�������̈�т����\�}--�O�����O����{�̏������ / ���a���Y/113
���㋳��̒��S���͉���--�����W���[�i����
�@�@������̍��̋��t����� / ��ܘZ/148
����I�s / �����q�Y/152
�풆��ו����L����� / ����M�v/141
�J�C�o�����z���̈�� / �[�c�v��/182
��M�҂ƌ�飂ɂ悹�� / �ɓ��p�Y/294
�t���[�x�[���ɂ�����K���ӎ� / �T���g��J.P.;�c�_��Y/96
���Ɏ��ܔ��\ / �䕚���� ;�ΐ�~ ;�P��g�� ;
�@�@�����؏��O ;�͏�O���Y ;�������v/186
���ւ̗� / �g����/266
�E |
�X���A�O�Ԑ��K�� ; ��{����ʐ^�u���{�̍H�|�@�ʊ��@�����v���u�W��V�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/2475636
|
���F���G/p1
�}��1/p21
�y�̑��^/P61 |
�}��2/p93
�؍H�̔閧/p109
�}��3/p125 |
�����̎�/p181
�}��4/p213
�H�|�̎�X/P229 |
���A���̔N�A���c�劰���u��x�{�ŋ��{���� 14(2) p.751-754�v�Ɂu�ܕS���藪�S���L�ɂ���:�ܒ���l���ޔ@�ҐM�v�\����B�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A�}�y�銰���u�����|���̌����v���u�L�����o�Łv���犧�s����B�@pid/1348052�@�@�@�P�O�O�O�~
|
�͂������i�R�ݓ����j
�}��
�������w�̗��O�ƕ���/1
�T�ƒ�������/23
�����|�\�Ƃ��ɕ��ƌ����߂���ā\���_�j�Ɩ����w�̕��@�\/35
���������L�Ɍ��ꂽ�鈤�|�A���ԁA�o���ԁ\�ӎu�̖v���\/58
���j�Ɠ`���\�]�䕨�ꐬ���l�\/95
���邩��l/110
�z�K�{�n�E�b��O�Y�\�����@��_���W�ɂ��ā\/126
�����Ɩ{�n���w��/163
�]�����w�Ƌ��c�̕���/198
�������w�Ƃ��Ă̕S���@�k/217
�����������|�Ɣ��i�@�t�̕���/230
���������Ɛ̘b/247
�R�̏@���ƎR�̕��|�\���a�R�{�n�ƌF��{�n�\/253
�_�a���Ɛ��Օ��w/263
�_���W�ƋߌÏ����\�{�n�������̋�̓I���@�\/277
�u���̗��j�I�l�@/324
���o�鏴�ɂ���/342 |
�ٖ{�E�ʏW�ɂ���/348
�F���E�◠��/360
���m�̏���/363
���D�f�`/375
�w�ȂɌ��ꂽ�鉅��v�z/387
���Ǝ��q/400
�Ñ���{�̐M�ƕ���/406
�ӂ����E�날���猩����b�R/413
�����ƕ���/422
��y���Ɛ����E�|�\/436
�|�\�Ɛ����l��/449
�ܒ���l���`/465
��������/471
�u�����_���L�v�J��/479
�}�y�銰���N��/518
�}�y�銰���q�ژ^/520
����/523
��L/547
�E |
���A���̔N�A�u���쌧�w�蕶���������� ��2�W�v���u���쌧����ψ���v���犧�s�����B�@pid/2526144
|
�܂�����
���쌧��
���R�����_�Ћ����Аz�K�ЎГa/p7
����_�Ж{�a/p9
�ؑ������͎m����/P10
�ؑ����ω�����/p12
���쌧���`������
�a���̔O���x��/p17 |
��Ղ�/p19
�╔�̓~�Ղ�/p21
�J�{�̌�_��/p23
���쌧�j��
�O�͓c��ˌÕ�/p27
���]���e���ˌÕ�/p30
�R�Y�^�Y���/P32
��ˎR���/p34 |
�r�m���������/p36
�ɓߌ���(�ѓ��w��)��/p39
���쌧�V�R�L�O��
�C�K�̕P����/p45
���^�̃N��/p46
�̃g�`/p47
�{�e�̃n���M��/P48
�O���̃T����/p49 |
���s�c�̃q�C���M/p50
����̃��~/p51
�剖�̃C�k��/p52
������̃X�M/p53
�V��̃C�`�C/p54
�L���̃J�c��/p55
�^���̃N��/p56
�_�˂̃C�`���E/p57 |
���A���̔N�A�{���v���u�_�b�̓��E�v���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B
�@�@pid/3449907
|
�_�b�ƍՂ�̓�/1
���̂������܂�/9
��˂��@��ʓ�/19
���n���Y���x/27
�C���u�[�̈ꐶ/35
�������ԉł�����/43
|
���n�̂��Ȃ���/51
�Y��̐���/57
����/63
�j���̐���/71
�I�i�����o��������/77
���l�m���Ə�����/87
|
�_�X�̏W��/93
�C�U�C�z�E/99
�j�����̂��Ղ�/123
�����ւ̋���/131
�������Ƃ͂��������/139
���Ƃ���/145 |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��11�㊪ �v���u�����|�\�S�W���s��v���畜������B �@pid/1658759
�@�@�@�Ԓ�y���쑺���H�H�l(����)
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��11�����v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����Bpid/1658758
|
��c��
�a�����i��
��
�V���h����
����
������ |
�̒���
�a�����i��
����
�\������
���R�}��
�����u�� |
�̃J�f�N��
���
�V���
�j�}�d����
���ɕ�����
�ʐ��� |
���]��
�ɖ�g��
������
�q����
�E
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��11�@�����v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@�@pid/1658757
|
������
�q����
�U�R��
������
���V���C�i�t��
���ڐ�
�g���ڐ�
������
���_��
�S����
���V�Y��
���c����
�ɓ�����
������
�O�V�M��
�V�q����
�⌴���� |
�g���V�Y��
������
������
�g���m���v��
���H�v��
�g���H�v��
�X�L��
�r���^�E��
�o�ߐ�
�v�ăn���^�O��
���N����
������
�{��Y��
�n�����N���C�j����
�F�n����
����
������ |
�ɏW����c��
�ɏW�V�ؐ�
�V���E���K�i�C��
�V�z���A��
����
������
�V�z���C��
�ݍJ�t�X��
�E�t���V������
�T�C���\�{��
�Ɍv����
ꝍb��
�z����
��Ԑ�
�V�����_�t��
�\���J����
�����R�m�V�� |
������
���K�V���
���g��
�e�������E��
���A��
�W�c�T�E��
�C������
�A�J�P�i��
���M��
�ΔV������
���Ԑ�
�z�N��
�����M��
�i�J���^��
�E
�E
�E |
|
| 1967 |
42 |
�E |
�U���A���c���q���u�����{���� 32(1) p.63-64�v�Ɂu���}�����c�A���q�̉��y�I���i�ɂ��� : ���{�����w���4��E��5�����v�|
(���{)�v�\����B�@J-STAGE
�V���A�ɂ��Ȃߌ�����ҁu�V���̌��� ��R�S�v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@�@�@pid/2979831
|
���� �O�}�{���m/p1
�另�Ղɂ������̂��戵���ɂ��� ��o���F/p7
�֗]�̋{�\���܂Ƃ��̂Ə��_�\�r�c��O�Y/p25
�V��T���L�ƐV�� �֎�/p43
�ĂƐM�� ���r���V/p65
����̂܂� �{�c����/p79
�쓇�̋��H ���쐴�q/p93 |
�u�������R���L�v�ɂ����ꂽ�_�k�V��̏��� ���c�v�q/p109
�_�_�`���̕��͂ƍ玮�̏� �O�Y�O�Y/p135
�^�C�̍���_�Ƃ��̋V��\�^�C�̍��� ���[�E�|���v���߂���ϔO�\�����P�Y/p157
�N�C���̈��V�� ��c�c��/p171
�����_���̍����N���_�b�i��j �R�c����/p191
�Ă̓��l�i��e����ю����j ���c���j/p207
�E |
�P�P���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (14)�v���u �j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����Bpid/6051447
|
�����̌��t�r �l�Êw�𖣗͂�����̂� / �֖�Y/p1�`1
���������� / �X�L/p2~3
�s�A�ڍu���t ���{�̋��Ί�(����)
�@�@���啪����ˋ��Ί펞���Ղ̒���/�ڑ�/p4�`5
�������Ñ�̓S�̗A�� / ���a�c�^�~/p8�`10
�����팤�����(����1)�����̃��X��h�ˊ�/���q�_��/p15�`19
�s���E�l�Â̗��t �C�M���X�̌Ñ��ՖK��L/����p�Y/p11�`14
�s��ՏЉ�t ��ʌ������R�s�Ԑ������/����˗Lj�/p21�`23
�s��ՏЉ�t ����(�]��)�̗q�� / �Z�Ԍb��/p25�`29
���F�{���R���s�t�锭���̓y�� / �G�Ǝu ;��������/p7~7 |
���É����֓c���Õ��Q�̕ۑ� / ����|��/p24�`24
�����{�l�Êw���� ���a42�N�x������w�ŊJ��/�ҏW��/p20�`20
���b��E�搶�̐����𓉂� / �]��P��/p6�`7
�s�V�����]�t �����w��w����U�w
�@�@������� �w�[�x��Ձx / ��˘a�`/p30�`30
�s�����ژ^�t/p31~32
�s�l�Ãj���[�X�t/p33~38
�O���t ���킪�����̋��Ί펞��̐���o�y�����啪����ˈ��
�O���t ����ʌ������R�s�Ԑ������
�E |
�P�Q���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (15)�v���u�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051448
|
�q�����̌��t�r �������������n���ȒÌy�̂Â� / ���䐴�F/p1�`1
������̐�j���� / ���a�c�^�~/p2�`6
�s����u���t �ꕶ�y��--��B��(6) / �]��P��/p7�`10
�s���E�l�Â̗��t �J���{�W�A�̍l�Êw���� / �ߐX��/p17�`19
�s��ՏЉ�t ���k�C�������s�I���l���g��Ղ̒���/
�@�@�� ����� ;�k�\���j/p14~16
�s��ՏЉ�t �����k�����K�������L�� / �k�P��/p20�`21
�s�O�������t �J�i�_���@���s�L / �ь���/p11�`13
���~�_�� / �]��P��/p19~19 |
�s�V�����]�t �O�㎟�j,�w�菲��ҁw���j���㉺�x
�@�@��(���{�̍l�ÊwVII) / �������P/p22~22
�s�V�����]�t �v�ۏ퐰���w�ŋ��l�Êw�����x / ����G/p23�`23
�s�����ژ^�t/p24~25
�s�l�Ãj���[�X�t/p26~30
�s���ڎ��t--�n����~1967�N12����/p31~34
�O���t ���k�C�������s�I���l���g���
�O���t ���J���{�W�A�̍l�Êw����
�E |
�Z���̔N�A��c���G���u����̖��O�ӎ��v���u�O�����V�Ёv���犧�s����B�@�@pid/2977084
|
�܂�����
���́@�V���̐����Ɩ��O�ӎ�
�P�@�V���ȑO�̃R�~���j�P�[�V����/p1
2 �V�������̒x��/p10
3 ����̎Љ�\��/p18
4 �@���K��̎G��/p31
5 ���_�A�@���̒e��/p54
6 ���O�����̕n��/p67
7 �ʐM�A�^�A�A��ʂ̔��B/p85
���́@�w�����V��x�̑n��
1 �x�z�K���̋@�֎�/p92
2 �N�h�̝���/p92
�R�@����l�̐����x�z���D��/p98
4 �����Ɗ����̑Ë�/p103
5 �{�Ô_���̍����/p109
6 �������/p116
��O�́@�Ӊԏ��Ɩ����^��
1 �Ӊԏ��̐�������/p127 |
2 �ޗnj��m���Ƃ̍R��/p130
3 �����y���̌���/p138
�S�@�w���ꎞ�_�x�Ɓw�����V��x�̝h�R/p140
5 �Q�����^���̍���/p147
��l�́@�w����V���x�̓o��
1 �O���҂̋@�֎�/p162
2 �n�����Y�҂ւ̌���/p163
3 �����̈ړ]���/p169
4 ���Z�@�ւ̔��B/p177
5 �_�Ƃ̔敾�ƈږ�/p192
6 �Ⴂ���x�ƐŐ��x/p200
��́@�w���ꖈ���V���x�̔���
1 ���O�̋@�֎�/p214
2 �ߔe�Ύ�/p224
�R�@�ŏ��̌��c�I�ƐV���Ԃ̑Η�/p230
4 ���O�ӎ��̍��g/p246
��Z�́@���ʈӎ��̌`��
1 ���{���l�̉����/p264
|
2 ����̒p���u�җV�f�v/p279
3 �l�ފَ���/p289
4 ��m���ݒu���/p296
5 ���a�@���̍X�R/p303
6 �͏㔣�̐�Ў���/p316
7 �L�Øa�Y�̕M��/p319
8 ����l�̗�/p326
�掵�́@��������̐��s
1 ����l�̔ߊϘ_/p331
2 �c��������̋���/p341
3 ������F���̔r��/p369
4 �_���̕��y�ƒ���/p387
�攪�́@�����ӎ��̍��g
�P�@�{�ÁE���d�R�����̍����/p408
2 �����{�s�Ɩ����̊g��/p418
3 �V���Ԃ̓����̍ĔR/p446
4 �����Q���̎���/p463
�E |
���A���̔N�A����j�N���u���v���A�� : �C��A���v�X ���̕��y�Ɩ����̎R�X�ւ̂����Ȃ��v���u�_�䏑�X�v���犧�s����Bpid/3006434
|
����搶�Ƃ����l�@�H�g��/p9
���v���ɂ���/p19
���[�̒�/p23
�K�W���}���̋���
�T�g�E�L�r��
�ċG�̗���M
�@�|�_�ЁE�@�|��
���؏�E���v���ςݏo�����
�t�c�C��
���[�����J�̕����A�����J��/p32
���V���������o�R
���̂��ƁA�����J/p46
�����J����_�Ƃ��Ĕ����R�[�X/p52
�O�㐙
�E�B���\����
�剤��
���q�x�A�����R�[�X
���v�����́E�W�ށE�^�ފe���ƌ���
�������A���A�����R�[�X |
�剤���\�{�V�Y�x�\�ԔV�]�͈���A
�@�@�����r�ނ��R�[�X/p72
�����J�\�Βˁ\�ԔV�]�́\�{�V�Y�x/p80
�{�V�Y�x����i�c�x�A�i�c�����ւ̓�/p98
�ԔV�]�͂�艺�R�O�R�[�X/p104
�ԔV�]�́`�I��
�ԔV�]�́`����
�ԔV�]�́`���V��
�����J�\���Ԃ̃R�[�X/p110
�{�V�Y�̒��Ƃ��̎���/p115
�����c��`
�{�V�Y�̒�
�u�ˎq
�\�l�L�����n�̉��v��
�{�V�Y�̒�����{�V�Y�x�o�R/p127
�������ɂ�����o�R/p138
�R�P�̂͂Ȃ�/p142
�����ꂽ�ό��n�\�썑�̕���/p145
�I�� |
�C�K���̎Y��
���̑�
���Ԃ̃K�W���}���̖�
����
����
���V�ԂƖ{�x�x/p157
�{�x�x���ʕǓo���L�^
�����A�ꖩ/p170
����̗��A�i�c�Ƃ��̕t��/p174
�i�c�̂��ꂱ��
�i�c����
�o�R�A�ό��A�����̑g�ݕ�/p190
���v���ό��ŒZ����
��ʓo�R�R�[�X
����A�^�b�N
�ό��R�[�X
���Ƃ���/p203
���v���Ƃ킽���@��c����/p206
�E |
���A���̔N�A���v���u�ɓ߂̌|�\�v���u�ɓߎj�w��v���犧�s����B�@ 1967 (�ɓߕ��� ; ��4)�@pid/9581799
|
�� �_���|�\
�� ��Ղ�/1
�� �╔�̓~�Ղ�/3
�O ���g�̂��L�l/5
�l �[���̋_���Ղ�/7
�� �����Ղ�/9
�� �\�A�\����
�� �\�Ɣ\����/13
�� �ϐ����ؑ���/14
�O �ѓc�˂̔\/15
�l �ԉJ�Ɛ^�|�ق�/16
�� ��蒷������/17
�Z �����ɔ\�Ȋw�l�X/18
�� �����Ȍ�̊ϐ���/21
�� ���̏���/21
�� �ߐ��̊ϐ���/23
��Z �ߑ�̗w�ȊE/24
�O �x��
�� �V��̖~�x��/27
�� �O���x��/30
�O �a���̔O���x��/31
�l ��ؗx��/33
�� �Â��ѓc�̗x��/35
�Z �������ǂ�/36
�� �t�c��/40
�� �J��x��/41
�� ���ܕ��q�x��/43
��Z �G���̉S/44
��� �ѓc�̍Ղ�Ɨx��/45
��� �x����/47
��O ���x���여 �Ԗ���/49
�l �l�`�A�ŋ��A�n����
�� ��ڗ��Ƌ`���v/53
�� �l�`�ŋ�/54 |
�O ���c�l�`/55
�l ���c�l�`/56
�� ����c�l�`/58
�Z ���^�l�`/60
�� �ޘa�ێR�l�`/61
�� ���s�ɑ���א��҂̐���/62
�� �]�ˎ���̉�/64
��Z ���D��H�ɗ���/66
��� �s��c�\�Y����/68
��� ���D���㏼���V��/69
��O �ѓc�݂Ɋ�䔼�l�Y����/70
��l ��A�ƒn����/71
�� �����Ȍ�̌|�d
�� �����Ȍ�̋��y�|�\�E/163
�� �������c/165
�O �s�m�Ƒs�m�ŋ�/166
�l ���D�����M�Z/172
�� ���J��O�̐���
�@�@�@���i�����̐痼���җ���j/173
�Z �R����Y/176
�� �吳�N��̌|�\�E/179
�� ����{���q�̗���/185
�� �ؓ��ꡖ剺�̋��y�l/187
��Z �k���ƐԉH�F�q/190
��� ���Q���ƗѓV��/191
��� ���g�Ǒ��Y��/193
��O �ɓߌ|�p������/194
��l �ѓc���c��/194
��� �g�J�Q������/195
��Z �ѓc����������/196
�ꎵ ���ɓߐN�����R���N�[��/197
�ꔪ ���Z��������/198
��� �щƐ��y�̂���/199
�Z ���q�� |
�� ���q��/201
�� ��V��̎��q/205
�O �R�����̎��q/206
�l �哇�R�̎��q/208
�� �������꒚�ڂ̎��q/209
�Z ����̎��q/210
�� �������̎��q/211
�� ��a���̎��q/212
�� �����̎��q/213
��Z �����̎��q/218
�� ���ȁA��
�� ���S/221
�� �������N�̋n����l/222
�O ��ڗ��Ƌ`���v/225
�l ���˂Ƌn����l/228
�� �O����/230
�Z ��/236
�� �J/236
�� ���ہA�Â�/237
�� �ڔ�/239
��Z ����/240
��� �Y�����A�ߑ�����/240
��� �y��X/242
�� ���w�A���w
�� �������Ȑ�/245
�� �������Q��̉S/246
�O �ѓc�����n���S/248
�l �����߂̗��s/250
�i�ѓc���Â����r��A���É��r��j
�� �ڏ��Ƃ�������/252
�Z �ѓc�n�ǂ��S/254
�� �`�ނ��S/256
�� ���S/258
�� ���҉S/258
|
��Z ������S/259
��� �j�V�S/260
��� �h�_�����/260
��O ����x��/261
��l �e�n�̖��w/262
��� ���s��/269
�� ����̕ϑJ
�� �ѓc�̉���/277
�� �̕��ꕑ��/278
�O �ѐ����ƖP����/281
�l ��Ս�/281
�� ���L���i���L���j/282
�Z �ᏼ���i�k���A�叼���j/284
�� ����/286
�� �̕����/287
�� �ʔ���y���i�����j/288
��Z �ѓc�p�m���}�فj/289
��� �V�y�فA��������/289
��� �d�C�فA�鍑��/290
��O �ѓc�����i�ѓc��فj/290
��l ��Ռ���/291
��� ����/292
��Z �ѓc��������/292
��Z �����̌���
�� �V�x������哇����/293
�� �s�c�̌���/294
�O ���̌���/295
�l �����̌���/296
�� �������/296
�Z ��������/296
�� �l�C���i����k���j
�@�@���i�{���j/297
�� �J�����i�V��j�i�{���j/297
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��10 (�Ԓ�y���X�����H�H�l(����))�v���u�����|�\�S�W���s��v���畜������B�@pid/1658756
|
�X�����H�H�l
�ژ^
��c�� |
����c��
���o
�g�o�A�� |
��
�a�����\��
������ |
�g��c�߁@���o�g�o����
�Ő�
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��12�㊪�v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@�@pid/1658761
|
��Ɂ@�}�@�ƏE����
�J�M���f����/1
���[��/2
����n���^�O��/3
�ӕ~��/4
�v�m����/4
���~��/5
���������/6 |
������/7
���Ԑ�/9
��������/10
�匓�v��/11
�Ɍv����/12
����/12
�ԕ���/13
��}�d����/14 |
����c��/16
������/17
������/18
������/19
���m�t��/20
���ɕ�����/21
��c��/23
�a�����i��/26
|
��/28
������/29
����/32
������/34
瓜��/36
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��12�����v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@pid/1658760
|
���Ɂ@�}�@����K�v�m�߁X�y�i�m���m���i���i���m�y�O�E����
�뗎����/1
�n����/2
�]�ː���/3
���q����/4
�����琛��/5 |
�Z�i����/7
���i����/11
�D����/15
���n��/15
������/16
�ݍu�Ґ�/19
�I�z���V������/20
|
�T�C���X����/21
�ɏW
����c��/21
������/22
��N�n�f�T��/23
����c��/25
�g��c��/26
|
���Ԑ�/27
���P��/28
�q����/28
�U�R��/29
���ڐ�/30
�_�璹��/31
�E |
|
| 1968 |
43 |
�E |
�Q���A�R���ӈ� �����{�����w��ҁu���{�����w��� (�ʍ� 55) p.37�`46�v�Ɂu��E���̃��^�ɂ��� (��19��k���{�����w��l�N��\�v�|)�v�\����B�@
�Q���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (17)�v���u�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6051450
|
�������̌��t�� �l�Êw�̕��݂Ɩ����������ی��/�]��P��/p1�`1
�����m�ɂ����� ���W�I�J�[�{���E�f�C�e�B���O--�V���g���[
�@�@�����m�̘_���Љ� / ���R��/p4�`6
��B���k���ɂ݂��� �T�C�h�E�u���C�h�ɂ���/�����v/p14�`16
����̕������ی�s�� / ���a�c�^�~/p2�`3
���p���y�@�� / ���R�O�Y��/p11�`13
�y��̐��@ / �����j/p22~24
�ᐢ�E�l�Â̗��� �؍��̕�������K�˂� / ����^��/p18�`21
��O�������� �l�p�[���ʐM(III) / ��l�G��/p17~17
|
��O�������� �A�����J�̍l�Êw���� / �ь���/p25�`26
���ՏЉ�� �ޗnj������s�����{�� / �ɒB�@��/p7�`10
��V�����]�� �]��g�v���w�R�n�������Ɓx / �u�����i/p27�`27
��V�����]�� ���i��Y���w�l�Êw�̑��x / ��l�G��/p27�`28
�ᕶ���ژ^�� / �ҏW��/p29~30
��l�Ãj���[�X��/p31~34
�O���t �ޗnj������s�����{�� / �ɒB�@��
�O���t �؍��̕�������K�˂� / ����^��
�E |
�R���A��Ԕɂ��u������w����w���I�v (11)�@p151�v�Ɂu�Z�̗������w�ɂ�鍇���ȁv�\����Bpid/2213479
�S���A ��ɏ�ꗲ���u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 69(4) p52�`64�@���w�@��w�v�Ɂu�ߐ����������̐��i--���Î��̗����x�z�ɂ��āv�����\����Bpid/3365378
�S���A���{�N�ٌ��v���ƕ��ҁu�����|�\ (32)�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4418365
|
������ �����|�\�̌����ɐ[�x�� / ���c����/p9�`9
�ᐏ�M�� �� / �P�c�r�ܘY/p10~11
�ᐏ�M�� �ËȐV�Ȃ����Ė��� / ���{����/p11�`12
�ᐏ�M�� �ԁE���E�l�� / �͍��ǐ�/p13~13
���s�{�O��n���̂����₵ / ���~�q/p14�`21
�O�d�����̂��x�� / �q�c���M/p22�`28
�����̉J����x��-��₱�x��̖��̂��c���̗w/�R�H����/p29�`36 |
���E�̖������x(4)�؍������|�\�̗� / �S�i����/p37�`44
���x��] �f���Ȏ��݁u���̉�v�ꌎ��� / ���p�䐳��/p45�`45
���x��] ���������O���|�\���� / �R�H����/p46�`46
���x��] ��ߎq���x������ / �{��������/p46�`47
���x��] ��������u�����̌��v���� / ���ɔn�t��/p47�`47
��
�E |
�S���A�u�e�A�g�� (297) �v���u�J���~�[���Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/7900513
|
���k�� �V���̕���ɂ����� "�p"�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂� /
�@�@�� ����p���Y ;���� ;������ ;�吼�M�s/p8~18
���ȁE�ᖡ�E��--����̘b�| / �]����/p20�`27
�����̌�--����̏ꍇ / ��쐽��/p28�`34
�b���|�ɂ���--�̕���̏ꍇ / ������/p35�`41
�������] �o�D�̖��͂Ƃ������� / �˕����/p42�`49
����ɐ�����(26)�X�˕q / �F�����X��/p4�`7
�㉉���]/50�`83
���] ��g�������̌ǓƂɂ���--���w���E
�@�@���N�K�����E����/ ����g���Y/p50�`52
���] �`�F�z�t���Ɖ��o--�o�D���E�O�l�o��/ �����Y/p69�`73
���] ������܂肵���]�_��--�N���E
�@�@����{���n�ɂ��Ă̈��/ �����C/p73�`75
|
���] �����ꂳ��ɑ���--2���̐V�� / ������/p75�`81
���] ���ܐꕑ��ւ̎p��--2���̊� / �����O�Y/p81�`83
���] ���A���e�B�̖��--2���̌��� / ������/p85�`87
�v�ۉh�搶�Ƃڂ�--�v��\���N�� / �H�l��j/p90�`90
���̂����ɍ������V���̖��̂�������(5)�� / �ВJ�嗤/p101�`106
�؉p���L����(III)���E�����V�[�Y�����ς� / ���ۏ\�O�j/p107~112
�����̌����ς� / �S�i����/p89�`89
�Y�� ���͊C�����z���Ă��܂��� / ���c���v/p113�`163
�݂炠�ځ[�� //p92~93
�e�A�g���E�j���[�X //p91~91
�����̐V�� //p94~99
�����j���[�X //p100~100
�� |
�T���A����^�C���X�ЁA�{���v���u�j�Ֆ��|�̗� : ���W�v�ē��̊��v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@
�@�@56p(�}��)�@�@�����F���ꌧ���}���ُ����F1001645231
|
���|�̗��̎v���o �c�{���q
�v�ē��G�� �ʓߔe���g
���Ă��̃~�\�K�������� �{��Đ� |
�����̃t�@���^�W�@ Y�ET�q
�v�ē��̒� ���얡����
�u�v�ē��v ��� ���� |
���ꕶ���j�T�_ ���g������
�ҏW��L
�E |
�U���A�������{�������ٕҁu�������{�������يٕ� �n�����v���u�������{�v���犧�s�����B
�@�@�@ �������{�������� ��Ït�����Ƀ}�C�N�������{�@�����F���ꌧ���}���فF1003009485
�V���A�q�쐴���u���d�R�̖��a��Ôg�v���u�q�쐴�i����o�Łj�v���犧�s����B�@�d�v�@�����F�L�������}�����@�@�P�O�O�O�~
�V���A���{�N�ٌ��v���ƕ��ҁu�����|�\ (33)�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4418366
|
������ / �{�c����/p13~13
�ᐏ�M�� �_���|�ƊϏO / ���p�䐳�c/p14�`15
�ᐏ�M�� �������� / ���R�×Y/p15~16
�ᐏ�M�� ���n�����̖~�x / �{�����q/p16�`17
���m���̈��������̔O���x--���̌`���ɂ���/�ɓ��Njg/p18�`26
�Ԗ������q�𓉂� / �{�c����/p27�`27
���ЏЉ�/p28~29
�ɗ\�̉J������x / �R�H����/p30�`34
�Øa��x��ɂ��� / ���{��g/p35�`39
���E�̖������x(5)
�@�@���t�B�������h�̖����������w�J�������x / �P�c�r�ܘY/p40�`44
���x��] �O�ԙՎO�� / �����G�Y/p49�`49
���x��] �K��ւ̈ӗ|�u���̉�v�O����� / ���p�䐳��/p49�`50 |
���x��] �u���ȁv�� / �R�H����/p50�`51
���x��] �u����`���|�\�̗[�v / �c���p�@/p51�`51
�O�͂̍��x�� / ��{�Ǝq/p52~59
���V���̃L���[�_���ɂ��� / ����w�v/p60�`64
���Q�̉Ă̕���--�S�ʂ̏o��|�\ / �X���j/p65�`71
�����|�\�F�̉�j���[�X/p72�`72
�����|�\(���a37�N5���`41�N10����20���`��29��)
�@�@�����ލ��� / �{���^�j/p73�`76
�S���~�x�ꗗ/p77~79
�\���E���G�E�ʐ^���/p80~81
������k/p82~82
�����Z�M/p83~83
�E |
�X���A���K�F�͂��u���ꕧ���j�v���u�썑���v���犧�s����B�@�@pid/12285126
�X���A�]�w��Y���|�\�w��ҁu�|�\ 10(9)(115)�@p61�`61�@�|�\���s���v�Ɂu�c�ӏ��Y�����m���p����ꉹ�y�I�s��v���Љ��B�@pid/2276310
�X���A�V�铿�S���u�u���A�m���v�̔q���E���� : ���y�̕���������v���u�V�铿�S�v���犧�s����B
�P�O���A�u���E (275)�v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�@�@pid/3366831
|
�k�O���r�A�l���ꥐ���O�N�̗��j //p1�`16
���W ����͎咣���� /
�ǎ҂� //p18~19
����Ǝ�(�u��) / ���� �D�v/p20~35
���_ ����̎{�����Ԋ҂Ɗ�n���--
�@�@���{�y�Ɖ���Ƃ̘A�т�����i�߂邽�߂�/�Ԑ��@;�����Y ;
�@�@����Ê��Y;�쉮���^�h;����b�L;�O�ԕĎq;��c���G/p36~76
I ����̌��_�ƑΕĎp��(1) //p37~43
II ����̌��_�ƑΕĎp��(2) //p43~46
III ����̐��}�Ɛ��� //p46~49
IV �c�����A�^���̓W�J //p49~56
V ���A�^���̎v�z //p56~60
VI ��n���ƕw�l //p60~76
��6 ��n���ƕw�l / �O�ԕĎq/60�`63
���_/63�`76
����o�ς̌��� / ����b��/p77�`785
����l�����̈ꑤ��--�z�ߐR���������̉ߒ�/����G�O/p86�`95
����̖{�y���A�Ɋւ���ӌ� / ���� ��/p96�`127
<�C���^�����[> ����Ȍ��ɕ���/���ǒ��c ;��������/p128~138
�����������ɕ���/135�`138
�������̔���--�R����n�Ɖ���̐��N�̈ӌ�/���� �N/p139�`150
���| ������Z���N���� //p151�` |
I ����E���E��܂̎��� / ���ؑF/p151~155
II "�V���o�[�E�_�K�["���̓W�J / �����`��/p156~518
III �ߔe�`�̃R�o���g60 / �g�c�k�O/p158~162
IV ��̉��k-"�C������"�Ɗ�`�^ / �Ό��a�v/p163~164
V ���ꋳ��E�ƕ������ / �{�鐭��/p165~168
�L�[�E�X�g�[���͐��낾����--�S����R�J�g�̓���
�@�@��(���W�E����͎咣����) / �n���� ����/p169�`176
<�}��>��n�̂Ȃ��̉���/
�@�@�������� ;���A�N�� ;�R�䏻�q/p177~189,�}2p
���ꌻ�n���_�����̎�Ȍ���/190
�ċɓ��헪���̉��� / ������/191�`200
���A�^���Ƃ��̎��� / �V�� ����/p201�`209
�����ƒp�J�Ƃ̒J�Ԃ�--
�@�@��������̈�̑���/���n���M/p210�`212
1968�N�̉���--�u���ցv�ւ̗��j�̂Ȃ���
�@�@��(���|���^�[�W��)-1-/�g�� ����Y/p213�`220
����̓� / ���� �ɓs�q/p221~228
�]������ăA�W�A����Ɠ��{ / �F�s�{���n/p229�`241
���{�ƃA�����J�̑Θb--�u����ƕϊv�Ɋւ��鍑�ۉ�c�v�̊��z/
�@�@�� �ߌ� �r��/p242�`253
��
�E |
�P�P���A������G���u�_�Ƒ� : ����̑����v���u������w���ꕶ���������v���犧�s����B�@pid/3449990�@�T�O�O�~�d�v
|
�͂�����/1
�_�Ƃ�/7
�Z�W(shiji)�������������/7
���S���̐_/9
�_�X�̋���/10
�����̐_�ƊO���̐_/12
��Ԃ̐_/14
����/14
�u�������v/15
��Ԃ̐_�͌��̂Ȃ���c��_/19
���Ƃƕ��Ƃ̔z�u/24
�m���Ƃ̈ʒu/27
���Ƃ͐_�Ƌ���/29
���ƌQ�����ƌQ�̏�ʂƂȂ��Ă��鑺��/33
���̉Ɖ��z�u�������m���K��/35
�������ƍ����v�z�̐����ƉƉ��z�u/35
�_�s�݂̉��摺/37
��ԂƑ���/39
��Ԃ̐��Ƒ���/39
���̌��/44
�i��j�@����{���Ƃ��̗����̑��̌��/44
�i��j�@�擇�����̑��̌��/47
�i�O�j�@���������̑��̌��/52
|
�i�l�j�@�u���̌�ԁv/56
�_�̋���/58
���_/58
�_�Ɛ���/61
���l��/66
�����Ǎ�/67
�쓇�̈╗/70
�Ñ�l�͎��l��|��Ă��Ȃ�/72
�_�̏Z��/76
�_�̋���/78
�O�X�N/79
���/84
�ړ������{���/86
�u�ʂ�����ԁv/88
�u��ʂ����v/94
�u�e���v/95
�u�j�C���X�N�v/98
�C�̐M�ƎR�̐M��/104
�M�̒n�搫/104
�I�{�c�E�J�O��/107
�̐��E/109
�̐_/115
�ǂ��O���_/115 |
�����I�ɂ͉ƌn�Ɩ��W/117
�e������D���Q/119
�呰�ΐ_�͍ŋ߂̔���/121
�����̏ꍇ�̉ΐ_�Ƃ̊W/123
���l�Ɖΐ_/126
�E�ΐ_/129
���̐_/133
���J�ꏊ/137
�u�a(��)�v/138
��ԂƓa�Ƃ͕\���̊W�ɂ���/139
�u�_�A�V�A�Q�v/145
��������/155
�i���~/155
�g�l��/157
�~���[/160
�g�l���R�V/163
�����̐_�Ƒ���/165
�}�L����/167
�}�L�̒�`/167
�n�J�E�p�J/174
�����}�L����/178
�_�͉����ցI/181
�Q�l����/185 |
�P�P���P�P���`�P�Q���A�����Ȋw�����قɉ����āu��T��ЊQ�Ȋw�����V���|�W�E���v���J����A���a�W�N�ɔ����������d�R��Ôg�̂��Ƃ����\�����B�@�@���\�ҁA�_���̕\��ɂ��Ă͖��m�F�Œ������@�Q�O�Q�R�E�R�E�W�@�ۍ�@ �Ί_�s���}���فF��������Ă��Ȃ�
���A���̔N�A��ԕ����ҁu�S�Ɨ����v���u���G�S�H�v���犧�s�����B�@�@pid/3445458
|
���E�����H�ƘA����@��u���@��
�����̂��ƂE���G�S�H������ЎВ��@�����G�M
�͂��߂�
�����Ñ�̓S�̗A���E�������{�������ی�ψ���厖�@���a�c�^�~�i���ʊ�e�j/6
�b��̓`���ƌ��
�S���̎n�c�ƔV��e/23
�{�Â̒b��̓`��/25
���d�R�̒b��̓`��/39
��������̒b��̐��x
�b���s/47
�b��E/47
�i����A��������̊C�O�f�ՂƓS
�Q�Y��������ƓS�̗A��/55
�@�x�̖f��/60
���b�u�̖f��/63
�N�Ƃ̌�ʂƗ����̕���/64
���^���̕����̓P�p�ƊO��/67
�����̖f�Օi���Ɍ���ꂽ����/70
��ؓS����{�ɉ^�����D/73
�䕨��/75
�_�̂ɂ�����ꂽ�S�A�b��A����
�v�ē��̂�����/79
�{�Âɓ`���b��_�́u�ɂ���v/83
������ɂ݂���O�R��������̕���/95
�|�x���́u�����J�U�O�v/102
�����Ɋւ���`���ƋL�^
����������/113 |
������/116
�����ۂƋ����g��/122
���b�u�ƌ�/124
�L���鑺�ɓ`��铁�̓`��/129
�k�J�ؐ�/131
���d�R�A�i�����b��H/132
�S���q�̂̌i��/135
�`���哇�㊯�̓�/135
�S�K
�����ېV�O��̓S�K�ƕ�����/139
�S�Ɣ_��
�Ί���S��֔_��̉��v/147
��������̓S�ނ̊Ǘ��Ɣ_��/149
���d�R�̔_��̓`���Ɖ��v/151
���d�R�l��^���̌��v����/152
���ƂƓS
���Ƃ̑n�n�ƓS���i/157
������̖A�Ηւ�S�ւ�/158
�����@�̉���/161
����@�̉��ǔ�����/162
���w�ɂ�����ꂽ���H
�ɔg�̋��H/167
�ҕ�����/175
�S�Ɋւ���͂Ȃ�
���Ԓb�艮��ՖK��L/181
�ސj�Ɋւ���`��/184
���Â̕���y�Y���p��/190
�S��\�킷����/190 |
�����l�ƓS�C/192
�����̐_/193
�b��Y/194�����ɂ�镨�X�����ƓS/197
�S���̊�/199
�S�Ɋւ��问���̘ی�/200
�Δ�̓S������/201
�ÓS��U�ƕē�U�ƌ���/203
�����g�b���{�ꐻ�S�������w/205
�����̞����y�т���
����O����/211
�����̞���/212
�F��̏�/214
���g�̊J��/216
���N��/217
�����̂���/232
�嗢��̉_��/233
�ߑ�̓S�H��
��������̍H�Ə��/237
�����ȓS�H�Ǝ�/240
�t�^
����E����̓S�H�Ƃ̊T��
�X�N���b�v�@�u�[��/258
�S�H�Ǝ҂̊���/259
�ƎҖ���i���Z���N���݁j/270
���Ƃ���/279
�S�̗��j�N�\/283
�E
�E |
���A���̔N�A���m���y�w��ҁu��m�E��p�E���ꉹ�y�I�s�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s�����B
�@�@(���m���y�I�� ; 5)�@pid/2517095
|
���s�̎� �c�ӏ��Y
�� �c�ӏ��Y/p3
��� ����/p10
��m(���O�l�N���a��N)/p15
��/p16
��A �������s�̓��@/p19 |
��A �������s�̏����H��/p27
�O�A �������s�̓���/p30
�l�A �p���I��/p33
�܁A �g���b�N��/p46
�Z�A �|�i�y��/p96
���A �N�T�C��/p129 |
���A �����[�g��/p143
�k�⒍�l�킪�Ñ�̖_�x�ɂ���/p169
��p�ƙ͖�(�����N�吳�\��N)/p173
���(�����N�吳�\��N)/p253
�{�I���̕ҏW�ɓ�����/p321
�ҏW��L/p323 |
���A���̔N�A�`�����i���w�i�j�_���Y���u����o�ώj : �Ñ�̎Љ�ƌo�ς̎d�g�v���u���ꕗ�y�L�Ёv���犧�s����B
�@�@���L ����o�ώj�N�\:p.198-206
���A���̔N�A�_�c���P���u���ꋽ�y���j�ǖ{�v���u���������}���v���犧�s����B�@pid/3449885
|
���_
��A�@�n���j�̕ҏW/1
��A�@������j�̎���敪/2
���ҁ@�Ñ�@�V���q�@�w�V
�����@��a���֓�������/9
���́@�V���q�ƍՐ���v/9
���́@�ޗǒ��ȑO�ɉ�����
�@�@���쓇�l�̓���/11
������a���Ƃ̌�ʐ��ގ���/13
��O�́@�{�y��ʂ̐��ށA
�@�@�������g�Ɖ���/13
��l�͖{�y����̌����ƌ��ג�/15
��́@�����̎c�}�Ɖ���/17
��Z�́@����Ɨ���/19
�掵�́@�V��������̕���/21
���ҁ@�����@�w�V�@�@�x
�攪�́@�w�V/25
���́@�`�{�Ɖp�c/27
��\�́@�p�c�̎��������`���/29
��\��͋ʏ�̈����ƎO�R����/32
��\��́@��C�����Ɠ��Î�/34
��O�ҁ@�ߐ��@�@�x�@���J
��\�O�́@�@�x/39
��\�l�́@�@�x�̐���/42
��\�́@���Ƃ̌�ʂ��J��/45
��\�Z�͒��N�Ƃ̌�ʁA��m�f��/48
��\���́@�{�Ô��d�R�]��/52
��\���́@���J�̗����A
�@�@�����v�ЂƏ��b�u/54 |
��\��́@�k�R�ł�/57
���\�͓�R�̖ŖS�ƎO�R����/60
���\��́@�������Ɛ_��/63
���\��́@���v�ƕ����̗���/68
���\�O�́@�썲�ۂƈ����a��/71
���\�l�́@�����S�E����/76
���\�́@����×��̍��J�Ə@��/80
���\�Z�́@���~/83
���\���͏��^�̒����W���ƊK�����x/89
���\���́@���d�R�ԖI�̗�/93
���\��́@�哇�̖�/97
��O�\�́@�`���Ɖ���/100
��O�\��́@�����g�Ɗ��D/103
��O�\��́@�i�v�g/106
��O�\�O�́@�������{�Ɖ���/109
��O�\�l�́@���Î����������/112
��O�\�́@�ߐ��̕����E���x/116
��l�ҁ@�ߑ�@���J�@����
��O�\�Z�́@����c���̖�/131
��O�\���́@�Ï��y�����@�̓`��/142
��O�\���́@���L�E�����E����/147
��O�\��́@�����̐��ނƃL���X�g��/150
��l�\�́@�����Ƃ̊W/156
��l�\��͓��얋�{�y�юF���Ƃ̊W/163
��l�\��́@����E���v/166
��l�\�O�́@�H�n���G���ی�/168
��l�\�l�́@���ꕶ���̋ɐ��Ə��h/170
��l�\�͋�u���e������ƎY�Ɛ���/175
��l�\�Z�́@����̏C�j/186 |
��l�\���͏��s�E���d�R�̑�Ôg/190
��l�\���͏����̍D�w�Ɗw�Z�̐ݗ�/195
��l�\��́@�����E���k�R�E�l�E����E
�@�@�@�����ׂƂ��̎���/205
��\�́@�x�b�e���n�C���V����`��/210
��\��́@�y�����̗��q
�@�@�����{�J���̍����n/219
��\��́@���[���b�p�����Ƃ̌��A
�@�@���q�u���͎���/227
��\�O�́@�ߑ�̕����E���x/241
��ܕҁ@����@�����Ȍ�
��\�l�́@�����ېV/303
��\�͔˖��̑�p����Ƒ�p����/305
��\�Z�͏���Ɖ���̔p�˒u��/312
��\���́@�����s���@�ւ̕ϑJ/381
��\���́@�����̔��B�A����c��
�@�@���E����c��/386
��\��́@����̕��y���B/390
��Z�\�́@�Y�Ƃ̔��B/406
��Z�\��́@��ʁE�^�A�E�ʐM/434
��Z�\��́@�������x�ƌR���@��/444
��Z�\�O�́@�i�@�E�x�@�E�Љ�ƁE
�@�@���q���E�̈�/449
��Z�\�l�́@�@���̔��B�Ɛ^�@���/460
��Z�\�͑d�Ő��x�̉����ƌo�ς̔��B/466
��Z�\�Z�́@�C�O�ږ��̐�쓖�R�v�O��
�@�@�������̊C�O���W/517
��Z�\���́@���ꌧ���̂��߂�/538
�E |
�Z���̔N�A�u���� : �����ꂽ�����̉ۑ� �V���|�W�E�� �v���u�O�ȓ��v���犧�s�����B�@
(�O�ȓ��V��)�@pid/2977048
|
I�@���ċ��������Ɖ�㊕Ԋ҉^��
��@���ċ����������ǂ����邩/p2
��Ƃ��Đ����I�E�o�ϓI���ʂɂ���
��Ƃ��ČR���I���ʂɂ���
��@�ԊҘ_�E�Ԋ҉^�����߂�����/p15
(��) ��/p15
��@�ԊҘ_�ƕԊ҉^���ɂ��ā@�V�萷��
��@�ԊҘ_�ƕԊ҉^���ɂ��ā@�q���P��
(��) ���_/p40
|
II�@�����ɂƂ��āu��㊁v�Ƃ͉���
��@��㊂̋���ƕ����ɂ���/p80
(��) ��/p80
�w��E����E�����̗̈�ł̉�㊖��@�X�c�r�j
(��) ���_/p90
��@��㊂̌o�ςɂ���/p107
(��) ��/p107
��㊂̌o�ς��ǂ��݂邩�@������
(��) ���_/p116 |
�O�@��㊂Ɩ{�y�\�F����[�߁A��̂�����
(��) ��/p133
��㊂Ɩ{�y�����Ԃ��́\�l�ԉ����
�@�@�������ӎ��@�؉�����
(��) ���_/p141
����/p175
�Q�l����/p209
�E
�E |
���A���̔N�A���֏�v���m�ËH�L�O�ψ���ҁu���{�����Ɠ�������v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9545696
|
I ���{�l�̑̎��ƌn�� = I ���{�l�̐g�̓I�K���Ƃ��̋N��
II ��j�Ñ㕶���̏��� = II ���A�W�A�ɂ������j�l�Êw�̑I�����ꂽ����
III ��w�����̏����ƒS���� = III ����̕��������Ƃ��̎w�� |
IV �`�������̔�r���� = IV ���������̔�r����
V ����A�W�A�̖����ƕ��� =
�@�@��V Peoples and Cultures of Southeast Asia |
|
| 1969 |
44 |
�E |
�Q���A�O�D�������{�n�k�w��ҁu�n�k = Zisin : journal of the Seismological Society of Japan 21(4) p.314�`316�v�Ɂu1771�N4��24���̑�Ôg�ɂ��āv�\����B�@ J-STAGE�@�d�v
�Q���A���{�����w��ҁu���{�����w��� (59)�v���u���{�����w��v���犧�s�����Bpid/2206559
|
�̘b�̌���--���̖��_�ɂ���-��- / �쑺����/1�`11
�؏����b�l--������Ȃ���̐������߂����� / ���c��/12�`18
�A�����J���O���ɂ�����������|�����̍ŋ߂̌X�� / ���c���}�q/19�`26
�̘b�̕��i�ɏo��Ƒ��b / ���[���t�@�j�[��w�[�M��/26�`28
����M�Ɛ̘b / ����/28�`32
����ڂ���f�z / ���Ԑ�/32�`34
����ƋV��--���i�Ǖ����𒆐S�Ƃ��� / ���v�`/36�`45
�ޗǂ̓��R���ɂ�����R�̐_�M�̎�X���ƒn�搫 / ���E���Y/46�`52
�l�����������m��������(����)�ƈ���(��J)�̗��搧
|
�@�@��/ �ɓ��G/53�`54
���R������̐��^ / ����ƍO/55�`63
�Γc�p��Y�N�̂��� / �員���F/p64�`65
�����Љ�/p65~65
�w�E�L��/p66~70
�V������,�G���_���v��/70�`73
�V������/p70~71
�G���_���v��/p71~73
�E |
�R���A�u������w����w���I�v (12)�@�@������w����w�� ������w����w��
1969-03�@pid/2213481
|
�����ÓT���x�̃G�l���M�[��ӂɂ��� / ���Ǖ�/199
���x��i���`�--�R�V�������W��� / ������q/237 |
�����̉��y�̌���--���y�_�ɂ��� / ��Í�/251
�q�����r |
�@�@�@�@��{�@�R�V�������W �����炬���Ɂ@�@�@�����s���n��ΐ_�䒬��500 �R�V�����A�����[�A��33�A1��
�S���A���K�F�͂��u����̖��M�ƕ����v���u�g�V��썑���v���犧�s����B �@�@�����F���ꌧ���}����
�S���A�i�䏹�����u���{�l�Êw���������\�v�| ���a44�N�x p.9-10 ���{�l�Êw����v�Ɂu�퐶����̊��L���L�ւɂ��� I�@�c�؊L�ւ̏ꍇ�v�\����B�@
�T���A���v�`, ���P�オ�u���{�����̌����v���u�n���Ёv���犧�s����B�@ (�n���w�p�o��)�@pid/12171988
�@�@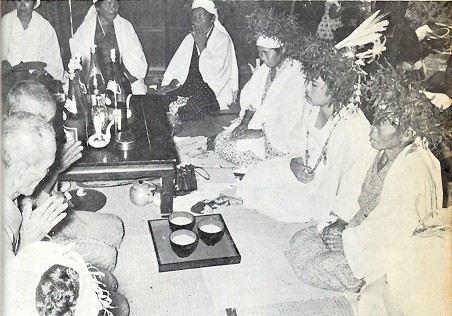
�@�@�����哇��F�@�V��ԁi�A���z�o�i�j�̍Ղ��@ |
�i�ʐ^�����@�����P�j
�@���쏔���ł́A�ޏ����m���Ƃ����B�J�Y���̂͂��܂��A���ɂ��������̉H�A�����A�m�ԕz�̔��߁A�ω��̂Ȃ����q�ł������_�̃I�����A�_�ɂł͂Ȃ��A���̃m���Ɍ������Č����ɍ������鑺�̌ØV�A�����哇��F�ł̐V��Ԃ̍Ղ�́A���̂܂܂ŌÑ�̎p�������Â��Ă��邩�̂悤�ȍ��o�ɂ��������܂���B
|
|
���́@�l
�@�����V��
�@����
�@�����̐E��
�@���Ǝ���
�@����
�@�_�k�V��
�@�֓��ƛޏ�
���́@���� |
�@���ƊK����
�@�[�����
�@�\���
�@������
�@�p�ƗV�s
�@����
�@���E
��O�́@�Đ�
�@�����Ə� |
�@��c��
�@����
�@�����o��
�@�m�Ɛ_�{
��l�́@�����̋V��
�@���J�\���̌o�ϓI�w�i
�@�����䗅�{�̋{��
�@�{���ƍ֓�
�@���q���l���V�� |
�@�{���̊K�w�ƋV��
��́@�c��
�@�����V��̏���
�@�����Ɛl�`
�@�ɉ�̐_��
�@�{���V��̍\��
�@��K�G��
����
�E |
�T���A�������ҁu���������� (5)�v���u ���傤�����v���犧�s�����B�@pid/2802867
|
�V���쌠�@��-����ɒ�o //p2�`4
���{�|�p�@��Ҍ��܂� //p4�`5
���a43�N�x�|�p�I������ //p5�`5
���������ߑ���p�ِV�ٗ��� //p6�`6
�n���|�p�����s���̏������܂Ƃ܂� //p7�`8
���a44�N�x�@���@�l�������C�� //p8�`8
������(���p�H�|�i)�̊Ǘ����� //p8�`9
�J���ɔ��������������ً}�����̍ŋ߂̌X�� //p10�`10
�������ی�@���z�L�O��-�������f��̂ǂ�- //p10�`10
|
�������⏕����t���܂� //p11�`11
���ꕶ�����̕����ɑ���Z�p���� //p11�`12
�d�v���`�������ێ��ҔF�菑��t�� //p12�`12
�`���H�|�t�̓W���� //p12~13
��������̒��� //p13~14
���������فE���p�ق���� //p14�`14
�n������� //p15~15
�����������E�l���ٓ��E��c�\�� //p16�`16
�q�ʐ^�r�V�������������ߑ���p�ّS�i / |
�T���X���`�P�P�����A�u�����D�����̂� �ʏ钩�O�����|�\�� : �g�x�㉉250�N�L�O�v�����������B
�T���A����^�C���X�������ƋǏo�ŕ��ҁu�����D�����̂� �ʏ钩�O�����|�\��
: �g�x�㉉250�N�L�O �q�����v���O�����r�v���u����^�C���X�������ƋǏo�ŕ��v���犧�s�����B�@�����F���ꌧ���}���فF1006635641
�T���A����|�\����ҁu�����ʏ钩�O�F�g�x�㉉��S�\�N�L�O���v���u ����^�C���X�v���犧�s�����E
�@�@�@289p �} �@�����F���ꌧ���}���فF1002079901
|
���S���� ���� ��Y
���S������� ���� �M
�썲�ۓG�� ���� ���
�썲�ۓG��(�ꖼ �G��)��� �^�ߔe ����
�����q �^�ߔe ����
�����q��� �약 ���\
������ �{�� �k��
������(�ꖼ �l���l)��� �� ���Y
�F�s�V�� ���� ���
�F�s�̊���� �^�ߔe ���� |
���O�́w�ܑg�x�ɂ���
�䊥�D�x��̐_�� ���x��Ƃ����ǂ����
���x�̉̎����
�g�x�ܔԂ̉��y �̎�
�ʏ钩�O�̑g�x�n�씭�\250�N�Ղɍۂ��� ���̓`���Ɠ`���̗��j
�ÓT���x�̒m��ꂴ�鑤�� �����ɔ��d�R�̋Ȃ���ꂽ�����m��
�ʏ钩�O�̔N���ƕ]�`�@ p.247-260
�������x�`�����j �䊥�D�x�ȍ~
�����̉��y�j
�E |
�U���A�V�铿�S���u����̖��w�̎��Ɖ���v���u�V�铿�S�^�O�c�������(�����)�v���犧�s����B�@236p
�V���A���m���y�w��ҁu�n���O�\���N�L�O�F���{�E���m���y�_�l�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s����B
pid/12432825
|
���m���y�Ɛ��m���y�̑Η��ɂ��Ă̋^�`(�c�ӏ��Y)
��y�ȐV�l(�ь��O)
�u�����v�]��(���o�v�Y)
�匴�����R�����ɉ�݂���o�ߓI�ω��ɂ���(�V�铹��)
�����̉��g���Ɋւ����l�@(��c�@��)
�V���ɂ���(��������)
�u�̌n�}�v�̒���(�q�c��O)
�Y�ꏥ�̝�(��v�Ԋ��Y)
�u�����́v���y�ɂ�������Ɣ��t(���ӌ�)
��ڗ��]���L�����̉����j�I�Ӌ`(���R��)
�]�˂ɂ�����L��߂̒�~�ƍČ��̑O��(���c����)
���S<����>�̌`������(�c���`���q��)
�J�u�L�̉������y�ɂ���(�F�߈�`)
�ߑ㕧�����y�̓W�](�|���~�L)
�����̌ÓT���y�ƕ��Ɖ��y�̌��т�(�R�����j)
�����䓇���w�l(�n�ӏ]�`)
�c���̈�♂��߂����l�@(�R�����q) |
�������y�̌𗬂ւ̈ꎋ�_(����m��)
�����^�C�g�� �ڔ��̉����ɂ���(���X�`�Y)
�������y�w�ƌ���w�̕��@�_��̕��s���ɂ���(���{��)
�������y�̔�r���w(�쑺�ǗY)
�x�ߓN�w�ɂ�����̗w�Ɖ��y(����ʘY)
���펁�ɂ�镽�Ɣ��i�u�R�H�v�̉��������ɂ��Ă�
�@�@���^�₨��ђ������_(�������Y)
���E�q�_�̊y��(����)
�M�����[�N���w�̉��g�D�ɂ���(�J�{��V)
���䓇�̂��ׂ�������(���L��o�u)
�������w�ɂ�����O�����ɂ���(��������)
�\������p���ĉ��g�D���r���͂�����@(�`�،�Y)
�������@�ɂ��Ĉ�l�@(�吼�F�M)
�u�c�A�₵�v�̓c�A�̗w�̎��^�ƋȌ^�̊W�ɂ���(���c���q)
ⵑg�̂̐����`�Ԃɂ���(�O�J�z�q)
���厛������(�q��p�O)
��y�ɂ�����u���q�v�ɂ���(���{��v�q) |
�V���A��鏹���ҁu������P�搶�����L�O���v���u����P�搶���ь�����v���犧�s�����B
�@�@325p�@�����F���ꌧ���}�����F1005905839
|
����P�搶�N�� �V�� �S�v�^�� |
���ꎩ�R�E�̊w��I�J��ҁu����P�v �V�� �S�v�^�� |
�V���A��鏹���ҁu������P�搶�����L�O���v���u����P�搶���ь�����v���犧�s�����B�@�@CiNii
Books �@�@325p
|
���� ����搶�̗����ƋƐ�
���� ����搶�_���I�W |
��O�� �L�O���W
��l�� ����P�����茚���n�� |
�V���A����P�搶���ь�����ҁu������搶�̗����ƋƐсv���u����P�搶���ь�����v���犧�s�����B�@
�@�@�@43p�@1007386400�@�@�w����P�搶�����L�O���x����
|
����P�搶�N�� �V�� �S�v�^��
���ꎩ�R�E�̊w��I�J��ҁu����P�v �V�� �S�v�^��
����P�搶�Ɖ���̍��� �� ����^�� |
����搶�̂��Ƃǂ� ���� �����^��
����P�搶 ���� �r��^��
�E |
�@�@�@�@�@���@�R���͓���{�i����j�Ǝv���邪����\��̐������K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�Q�P�@�ۍ�
�V���A���{�N�ٌ��v���ƕ��ҁu�����|�\ (37) �v���u�����|�\���s�ψ��� �v���犧�s�����B�@pid/4418370
|
������ / �{��h��/p13~13
�쓇�̌|�\ / �c�ӏ��Y/p19~24
���d�R�����̃A���K�}�x / �{�nj���/p25�`32
���d�R�̑��E�_(1) / �O�����Y/p33�`39
���V���̍s���� / ����w�v/p40�`46
��̓��̌|�\�ɍl���� / �������Y/p47�`51
�g�J���̖~�x / ���c�v�q/p52~53
���W�m�[�g / �c���p�@/p54~56 |
�����M�� �j���a���̎��q�� ��㊂̐l ��̓��̎ŋ� /
�@�@����闧�T ;�������q ;�c����ѕv/P14~18
��q���̗x / �쑽�c��/p57~60
�̕����u���l�E���v��{ / �{��������/p61�`72
������k/p73~73
�V�����ЏЉ�/p74~75
�����Z�M/p76~76
���G�ʐ^���/p77~77 |
�W���A�����Ɩ����uOKINAWA����OKINAWA : �ʐ^�W�@����Ɋ�n������̂ł͂Ȃ���n�̒��ɉ��ꂪ����v���u�ʌ��v���犧�s����B
pid/9768938
�X���A�u���R�Ȋw�Ɣ����� 36(9/10)�v���u�����Ȋw�����فv���犧�s�����B�@
pid/2376661
|
���_���m�L / ���R����/�\���ʐ^�`
���ނ̋N���Ɛi��-1- / �F�c�i�Y/219�`229
�L�N�ȐA���̊��тƉԊ��ɂ���
�@�@���L�N�ȐA���̕��ތ`���̈�l�@/���R����/230�`242
���ɉf�鑜�ɂ��� / �����K�T/243�`247,���\����
�Ȋw�����ق݂̍�� �W���𒆐S�Ƃ��� / ���]��/248�`265 |
�k�}���Љ�l����P�\�\����P�搶�����L�O�� / ��䎟�O�Y/265�`265
�S�������كj���[�X //266�`266
�{�كj���[�X //266�`267
���ĉȊw����f��������� //267�`267
�{�ٍs���L�^ //267�`
�E |
�P�O���A���{�N�ٌ��v���ƕ��ҁu�����|�\ (38)�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4418371
|
������ / �㓡���v/p13~13
��\���̖����|�\ / �{�c����/p14�`15
�̏W�]�k / ���p�䐳�c/p16~17
��\���S�������|�\���|�\��� �щz���̉��N / �����G�Y/p18�`24
��\���S�������|�\���|�\��� ��t�̖��w / ����h/p24�`28
��\���S�������|�\���|�\��� ���R�̖~�x / �c���p�@/p28�`33
��\���S�������|�\���|�\��� �匳�_�y / �|�{�R��Y/p33�`36
�����\����܂ł̖����|�\���o�����ځE����/p82�`83
�щz���̖������_�ՂƉ��N�� / �X������/p37�`41
�[�����w���y�L / �����v/p42�`45
���R�̎������ƃq�[���C�x�����L / �S�i����/p46�`48 |
���R�̖~�x�̉��y / �����/p49�`54
�匳�_�y�ɂ��� / �Βˑ��r/p55�`57
�S�Ɠ���--�������x�G�� / �Έ�݂ǂ�/p58�`63
���d�R�̑��E�_(2) / �O�����Y/p64�`70
����n���̐����S / �K�R���s/p71�`75
�ɉꕽ�c�̋_���܂� / ���X�M��/p76�`76
��������̖����|�\���� / ���p�䐳��/p77�`77
�F�̉�j���[�X/p78~78
�V�����ЏЉ� / O/p79~79
������k/p80~80
�����Z�M/p81~81 |
�P�P���A���쐴�q���u����̍����v���u�����p�Ёv���犧�s����B
�@�@�@(�������|�o�� ; 47)�@�@236p �@�����F��㊌����}���فF1009591320�@�@pid/12168444�@�d�v
|
�܂����� 1
��@����̐��N�����獥���܂� 7
���N�� 8
������ 29
�����̎��含 39
���������̉ߒ� 50
��Ғ��� 76 |
�e���̖��� 84
�����V�� 94
��@���������̍����̑ԗl 103
�O�@����E�����̏��� 135
�I�i���_ 136
���q�Ƃ��Ă̏��� 157
�� 166 |
�����x�i 170
�����Վi 175
�ނ��� 191
�l�@����̑��O�� 199
�܁@�쓇�̋��H 217
�E
�E |
|
�Q�l�F����̍��� ( �������|�o��47 1979.5��)�@�����F��㊌����}�����F1002248423�@�@�@�\�t�F�V���ؔ� ���쐴�q���Ǔ��@�@
�@���@���{�ɁA�V���̐ؔ������邱�ƂɁ@�����������B�搶�͂P�X�W�S�N�ɂȂ��Ȃ��Ă���B�@�@�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�P�@�ۍ� |
�P�Q���A���]�F�`���ҁu ���ꖯ�w�����ȏW 1�v���u �z�b�^�K�N�t�v���犧�s�����B�@�@59p
|
�Ă����ʉ� / ��㊂��ׂ��� ; ���]�F�`���̕��E�ҋ�
���� / ��㊂��ׂ��� ; �������V���̕��E�ҋ�
���[����[�n��(���܂���) / ��㊂��ׂ��� ;
�@�@�����]�F�`���̕� ; �������V���ҋ�
������ / ��㊂��ׂ��� ; ���]�F�`���̕� ; �������V���ҋ�
���[�݁[�ǁ[�� / ��㊂��ׂ��� ; ���]�F�`���̕� ; �������V���ҋ�
�ߔe(�Ȃ�)�n���̎q��S / ��㊂��ׂ��� ;
�@�@�����]�F�`���̕� ; �������V���ҋ�
��(��)�ʔ�(����) ����/ ��㊂��ׂ��� ; ���]�F�`���̕� ; �������V���ҋ�
�R��(����)����(��)�������ǁ[ / ��㊂��ׂ��� ; ��Ԕɍ̕��E�ҋ�
��̎q��S / ��㊂��ׂ��� ; ��Ԕɍ̕��E�ҋ�
���[�x(����Ȃ���) / ��㊖{�����w ; ��Ԕɍ̕��E�ҋ� |
������(���Ȃނ��Ԃ�) / �ɍ]�����w ; ��Ԕɍ̕��E�ҋ�
�J���O(����߁[) / ��㊖{�����w ;
�@�@�����э��̕� ; �����Y�ҋ�
������(�����ǂ�)�����^ / ���d�R�Q�����w ;
�@�@�����э��̕� ; �����Y�ҋ�
�{�Ó���3�̉�. 1 �떓(����܂�)�̐e�_(���₪��)
�@�@���̃j�[�� : �_�� / �{�Ó����w ; ���g�ۗY���
2 �q��S���₮ : �����^��(���������Ƃ���Ȃ�) /
�@�@���{�Ó����w ; ���g�ۗY���
3 ���ɂ����̂��₮ : �d���� / �{�Ó����w ; ���g�ۗY���
����ǂ��̉� / ����h���쎌 ; �{�ǒ����� ; ��Ԕɕҋ�
���ォ��䂵 / ��㊖{�����w ; �Ɏu�䒩���̕��E�ҋ� |
���A���̔N�A�M�y�ƕ��x�Еҁu���{���x��n [��3] (���ꕑ�x)�v���u�M�y�ƕ��x�Џo�ŕ��v���犧�s�����B
�@�@�@pid/2526138
|
���G�ʐ^
���x�u��c�߁v(�J���[)
�g�x
�u�G���v
�u�����q�v
�u�璹�߁v
�V�l�x�u�������v
��O�x�u���Ă��߁v
��˗x�u�O�̕l�v
���x�u�ɖ�g�߁v
�G�x
�u���Ȃ悤�v
�u�J���O�v
�u�ԕ��v
�̌�
�u�n�R��v
�u���R�̉��O�v
�v�����̃C�U�C�z�[
��㊖{������
�c�`�E���W���~�� |
��㊖{������ẨP����
��㊖{����u���̃V�k�O
��㊖{�����x�x�̃G�C�T�[
�{�Ó��{���̃N�C�`���[
�Ί_���V��̊��x��
�Ί_�������̖L�N��
�Ί_���약�̎��q��
�� �|�\�̗��j�ƌn��
�� �T�� �c�ӏ��Y/p25
�� �����Ɣ��W �{�c����/p64
�O �����ƌ|�\ �O�����Y/p94
�l �䊥�D�x�� ����^����/p126
�� ���y�̗��_(���q�Ɛ��@) �R�����j/p143
�� ����o�D�̋L�^
�|�k�A�g�x�̌^ �n��~���/p193
�O ���h�ƌ���
�� ���n�ɂ����� ����^����/p265
�� �{�y�ɂ����� �Ζ쒩�G/p267
�l ������
�� �g�x��{ ����^����/p277 |
�썲�ۓG��
�`�b����
���S����
���ΓG��
�����q
����
�F�s�̊�
�Ԕ��̉�
������
�萅�̉�
�� ������W ����^����/p421
�O ���x ����^����/p426
�l ���y �R�����j/p467
�� �����|�\ �V�铿�C/p494
��
�� �|�\�j�N�\ ����^����/p555
�� �g�x������ ����^����/p599
�O �����|�\���z�}�ƌ|�n�} �V�铿�C/p603
��㊕��x�Ɖ��y�ƁE�{�y��㊌|�\�c�̖���
�E |
���A���̔N�A�O�����Y�ҁu����̌|�\�v���u�M�y�ƕ��x�o�ŕ��v���犧�s�����B�@�@
|
�|�\�̗��j�ƌn�� �T��(�c�ӏ��Y)
�����Ɣ��W(�{�c����)
�����ƌ|�\(�O�����Y)
�䊥�D�x��(����^����)
���y�̗��_-���q�Ɛ��@(�R�����j)
����o�D�̋L�^ �|�k�A�g�x�̌^(�n��~���) |
���h�ƌ��� ���n�ɂ�����(����^����)
�{�y�ɂ�����(�Ζ쒩�G)
������ �g�x��{(����^����)
������W(����^����)
���x(����^����)
���y(�R�����j) |
�����|�\(�V�铿�C)
�� �|�\�j�N�\(����^����)
�g�x������(����^����)
�����|�\���z�}�ƌ|�n�}(�V�铿�C)
�E
�E |
���A���̔N�A�u���쌧���ɓߌS���쒬�a���������v���u�Ռ��w���Z����w�����������v���犧�s�����B�@pid/9536035
|
���ɂ�����/1
�����ɂ�������/2
�ڎ�/3
�n�}
���쌧�S�}/5
���쒬�a���S�}/6
���� �Ƒ����\��
���v/7
�T��/7
���\��/9
����/10
|
�Ƒ����x/15
���� ����
�_��/19
�{�\/23
�ы�/25
�{�Y/27
��O�� �ߐH�Z
�ߕ�/29
�H��/32
�Z��/37
��l�� ��������
|
�Y��/43
����/47
����/52
��� �M��
���@/59
�_��/59
�����F��/63
�֊��E�\���E��p/64
�u/67
��Z�� �N���s��
�N���s��/69
|
�掵�� ���b�E�|�\
�`��/79
�|�\/82
���w/83
�攪�� �O���x��
�N��/93
���e/93
��������/101
��������/104
�������̂�������/105
�E |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W ��13 �v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B
�@pid/1674737
|
�{��
�ڎ�
���@���҂̂��ƂE�R�����j
���E��������
���E�K�n�T��� |
�y�T
�H�H�l�㊪�Ȗ�
�{���̖ڎ�
���y�����H�H�l�̊e�ȕ�/12
��L�@���ܐ��q�����̑S�W�@�\�m�V�[�g������
|
��L�@�R���w�Z�̗��̐��������������āE���c����
��L�@�f���炵�������Ƙ^���ɑz���E���]�F�`��
���t�@���҂̗����@�o�Ŗژ^
�ܐ��y���e��/7
�v���t�F�[�X�ƃR���e���c |
���A���̔N�A�R�����j���u�����|�\�S�W�@��14�v���u�����|�\�S�W���s��v���犧�s����B�@�@pid/1674738
�@�@�@ ����ⵊy�� : ���y�����H�H�l�ƌܐ�����. �㊪(�[�߁j
�@�@�@���L �t�^: ����ⵊy���㊪ (�[��) �^���e�[�v1���[��
�@�@�ۑ�^�����|�\�S�W�V�E�W�E�X���ɂ��Ă̏��݂��s���ł��������Ɓ@�@�܂��A�P�T�`�Q�Q���ɂ��Ă����݂��s���ł��������Ƃ��A�����ɒԂ��Ă����܂��B
�@�@�@�@�@�@�����āA��ςȘJ��ł��������ƂɊ��ӁA�܂��䐄�@�\�������܂��B�@�Q�O�Q�R�E�S�E�W�@�ۍ�
���A���̔N�A�V������,��闧�T�������V��Еҁu����̕S�N ��1���v���u�����o�ŎЁv���犧�s����B�@pid/9768965
�@�@�@���L�@�w�����V��x��1967�N1��1������1968�N9��21���܂�1�N9�����ɂ킽���ĘA�ڂ��ꂽ����
���A���̔N�A�����T�����u����Ɠ��{�l: �̎��ԂƋ��P�v���u�I���I���o�ŎЁv���犧�s����B�@�@�V�V�O�~
�@(�I���I���u�b�N�X)�@pid/9768973
|
�n���I�ߌ�
�ɓ��̗v��/7
���{�̂Ȃ��̕����n��/16
���������̒J��/20
������u��㊐l�v
�ِl�툵��/25
��������/31
��㊂̂�����/35
��㊂Ɠ��{�l
����̎�����/41
�����|�͌�/44
���ݗ�����/49
��㊂̐���
��a�Ԃ�̉ʂ�/53
���ʐ���̈��/59
���c�b�m�����c��������
����̂��肩���ւ̔���/65 |
���{�l�̖�����/69
�������̊�/73
�S�̎p��
�g���݂Ɛ^�̎�����/79
���ւ̋��D/82
�K���S/85
���Ђ����v���C�h��/89
�~���s���̔g��
���v�D��ƎЉ�I�s�ύt/93
�u���\�~���v�����I���z/98
�̐��Ŕj�ƎQ���ւ̗~�]/102
�l���̐���
��㊂̐�������/109
�Q�y���玿�̌����/114
��㊂̎��R���y
���̋N����/119
�䕗����ƐΊ_/121 |
�o�i�i�Ɓu�\�e�c�n���v/125
��㊂̖���
�A�݂��A���N�j��/131
��L�ƍg�^/137
�u�n�[���[�v�Ɓu�y�[�����v/143
�j�����q/146
�̂Ɨx��
�����^�Ǝ֔��/149
�u�A���S�v/153
���S�A�q���̗V��/163
��㊂̏��Ǝ�
�u�ٓ��J���v/169
�u���ݎ��v/172
�u��V�сv�Ɓu�������v/176
�Ⴂ�����͌��/180
���Ƃ���/183
����Ɠ��{�l : ���̎��ԂƋ��P (�I���I���u�b�N�X) |
���A���̔N�A�O�����Y�ҁu����̌|�\�v���u�M�y�ƕ��x�o�ŕ��v���犧�s�����B�@pid/12431908
|
�|�\�̗��j�ƌn�� �T��(�c�ӏ��Y)
�����Ɣ��W(�{�c����)
�����ƌ|�\(�O�����Y)
�䊥�D�x��(����^����)
���y�̗��_�[���q�Ɛ��@(�R�����j)
����o�D�̋L�^ �|�k�A�g�x�̌^(�n��~���) |
���h�ƌ��� ���n�ɂ�����(����^����)
�{�y�ɂ�����(�Ζ쒩�G)
������ �g�x��{(����^����)
������W(����^����)
���x(����^����)
���y(�R�����j) |
�����|�\(�V�铿�C)
�� �|�\�j�N�\(����^����)
�g�x������(����^����)
�����|�\���z�}�ƌ|�n�}(�V�铿�C)
�E
�E |
���A���̔N�A�u�F��̓��X�v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@�@�@�@pid/9768931
|
��q��/5
�y�J���[�z����C��
�F����
����̊≮
�S�C�`���I����
��q���ƕ�n
�F���Z���^�[
���̐��V�\�`
�y�O���r�A�z���V�\�`
�\�e�c
�K�W���}��
���q���M
��q��
�F���
�ۖ؏M
���P�b�g�ŏグ
�T�g�E�L�r�ƃn�T�~
�n�ѓ��t�R�`
���v��/29
�y�J���[�z�V���N�i�Q�Ɖi�c�x
�i�c�x�̖��X |
�K�W���}���Ƒ剤��
���v���̖���
���b�`�����x
�y�O���r�A�z�{�V�Y
�i�c�x�R��
���v��������
����
�g���I�L�̑�
���V��
���V�Y
�o�i�i��
�ꖩ�̈�{�ނ�
���i�Ǖ�����
�g�J����/61
�y�J���[�z����
�O���o�C�q���K�I
�z�K�V����
�g�r�E�I��
�����l�X
�y�O���r�A�z�m��̓�
��Ԕ��̃T���S�ʌ� |
�T���S��̂ƃA�R�E
�n�u�ƃG���u�E�i�M
�\���ۂƓ���
�����Q��/85
�y�J���[�z��a���̍��q
���V���̃J���Ԃ��W��
���i�Ǖ����̏�����
�c�F��
����ƓD�Ő��߂�����
�@�@���哇��
�y�O���r�A�z�����s
�A���}����
�Y�V����
��E��
���V���̓���
������
�^�_��
���X�̖���/117
�y�J���[�z��[�Ƃ��[�x��
��q���̑�x��
�ʗx�� |
����
�����̏M��������
�y�O���r�A�z���q�Ɩ���
���̃��~�ł�
�\�̋{�l�ƃg�r�E�I����
�Γ��܂�
���~�̕�Q��
�x��̋G��
�K���[�M�ƛޏ��M��
�j���ƃ��^
�{��
��� ���̔N���s�� ����d�N/143
�F�쏔���̖����|�\ ����q��/146
���ԐM�� �R���ӈ�/150
�G�b�Z�[�@
�F�쏔���̎��R�ƕ��� ���V�a�r/155
�Q�l����/184
�K�C�h/185
�E
�E
�E |
|
| 1970 |
45 |
�E |
�P���A�u�������� : ����̗��j 1 ����̂͂��܂� ��60���v���u��������Ёv���犧�s�����B
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004265508
|
����̂͂��܂�
����l�̑c��
�_�Ƃ̂͂���
�{�ÁE���d�R�̕���
�嗤�Ƒ�a�Ƃ̌��
���Ɨ����̂�і�
������_�b
���n����̂��肩���
�`���E����ɂ������ג�
�Ȃ�q�Ƃ̐����ʂ�
�ؕ������ג�
�w�V�����̒a��
�w�V�����ق��
�ꂿ��Ȃ����ǁA�� |
�@���ڂ���͌��C-�Η䎙�����̎q��������
�@���߂������E�܂�������
�l������������� -�c��`���̔�@��
�@�@����a���Ȃ����Â���30�N
�J�����E�h�L������
25�N�̓{��A�R�U�ɔR��
�����Ă��܂邩
�O���[�v����
�l�Êw�E
�a�ٌ�����
�암�_�ѓ�����
�ߔe���[���Y�F�̉�
��k�H�Ɠ�����
����b��� |
���NJԂ̖L�N�܂�
����{���^�N�V�[�^�������\
�����A���炾�����ɕ��� -�R�U�ɂ͂���q�b�s�[��
�M�������ł��܂����Ƃ� -���ƌx����
�@�@���h���C�o�[���N�ɂ�����S��
���ɂ͗삪�݂����! -�D�P�������ɂł��Ȃ�
�@�@����s�K�[���̈�������Â����Г���
�������x�E������ŕ��� �ʏ� ���`�^
�@�@��[�x��] �약 ���\�^[���]
�܂��Ȃ̓��L ���� ���ȁ^[��]
�l���p�g���[��
�ҏW��
�t �������x�̎�قǂ��q1�r������ŕ��E�ʏ� ���`
�E |
�R���A�u������w����w���I�v (13)�v���u������w����w���v���犧�s�����B�@�@pid/2213482
|
�p�[�X�L���w�̌���-3-���ߓ��e�ƈӖ��ƏK�� / �Đ��T��/1
��C���e���Q���`����̎Љ�w�I�_���\���̎��� / �F��B/17
���B�����̂��߂̃}���R�t����f���̖�� / ����`�i/25
��ϓI�����Ə�I�֗^�x�ɂ���-1- / ����`�i/33
�c���̉ۑ�����ɂ���ڂ����f���̉e�� / �O�����q/45
�q��@�����n��ɂ����鎙���̐��i�����ɂ���-
�@�@��-Y-G�e�X�g�EP-F�X�^�f�B�ɂ��l�@ / ���쒩�M/51
���w���̐H���ɑ���n�D�x�ɂ��� / �V�_���q ;����`�i/63
����ɂ����闝�ȋ���̎���͓I����--
�@�@����Ƃ��ċ��t�̔N�ߥ�w���Ƃ̊֘A�ɂ����遨
|
�@�@���Ȋw�I�v�l����̎��Ԃɂ��� / �g�c�ꐰ ;���l���d/71
���w���̑̈�w�K�ɑ���ԓx�̌`���v�� / ��鏺�q ;����`�i/97
�_���X�̕\���Z�\�̓����ɂ��� / ������q/105
TSPI�ɂ��{�w�^�������̐��i���� / ������v��/139
�Z�̕���--���Z�_���I��ɂ��� / �r�c��D/145
�����̉��y�ɂ����郊�Y���̓����ɂ��� / �Ɏu�䒩��/p157
�������w�ɂ��6�̂��� / ��Ԕ�/167
�A�����J�̐E�Ƌ���ɂ��ā\�\�H�Ƌ���𒆐S�Ƃ��� / ��l�G�h/p189
SCR�C���o�[�^�������u�̌��� / �㌴����/p207
�L�Ӗ��x����(����) / ���]���V/223 |
�R���A�`�����i���w�i�j�_���Y���u��㊔_���j�v���u��㊕����o�ŎЁv���犧�s����B
�R���A�u�W�] (135)�v���u�}�����[�v���犧�s�����B�@�@pid/1795894
|
�F��������F / �g�s�~�V��/9
�G�R�m�~�b�N��t�F���[����A�j�}�� / ���a���Y/10
���̑� / ���c��/11
���̔ᔻ�����ʂ��� / �a�F/13
�������ƉƂƏ�����Ƃ̏ꍇ / �n��/14
�ЂƂ�ЂƂ肩��--���݂̏̂Ȃ��� / ���c��/16
����Ɛl��--��@�̂Ȃ��ɂ���
�@�@�����o�ɗ�����(�Βk) / �X�L�� ;�؉�����/41
�A�����J�1960�N��--�Љ�I��̂ւ�
�@�@���i�s�������̏\�N / �����m�v/27
�C�k���] �̂Ǝ���̈ӎ� / X�EY�EZ/58
��w��ϗ������--��̈ӌ��Ƃ��� / �ێR��/64
�l�����o����-��-(�����̎���-3-) / ���c�O/98
����'70��Љ�̋��Ǝ�(���k��)/�i�Z�� ;���{�� ;�]�����v/73
�p�����z���s--�㌎�̃p���́�
|
�@����,�������ȑ؍݂̈�ۂ��� / �����Ɉ�/104
�t�����c��t�@�m��-1-�v���ƂƂ��Ă̐��U /
�@�@���K�C�X�}���s�[�^�[ ;�Έ�ےj/91
�W������s�A�[�\�� �����É��̋R�m / �ԓc���P/114
���쏺�� ���炭�� / �����G�r/116
���c��C��� ���c�i�t����(��ꊪ) / ���앶�O/118
�S�_�[�� �S�_�[���S�G�b�Z�C�W / �������j/120
�������� ���{����܂� / ����F��/122
�b�ԓ��x�����Y-17- / ����D�v/124
���R�z�̊w�|-3- / �����^��Y/137
����擇�̈ꎍ�l / �������/158
�~�� //230
��D�k�n //102
��F ��܉ɏ�܍�Ƃ̐V�� / �`�k��/160
���ܖ� �����݂́q��r(��O��) / �P��g��/209 |
�T���A��ԔɊďC�A���������ҁu �݂�Ȃʼn̂��� : ����̂Ƃ������̉́v���u�T�������v���犧�s�����B�@
�@�@�@31p�@�@�����F��㊌����}���فF1001670155 �@
�U���A���R�d�ҁu�����_���L : �٘@��(�ܒ�)�W�v���u�p�쏑�X�v����čs�����B�@�@�@pid/12271228
�@�@���R�d���a11�N���̕���. �ꕔ��������@���L ���e:�����_���L,��������,�_���W����,��k��n�W
�@�@�����W�ܒ���l�`�L����,�ܒ���l���q�ژ^�����
�U���A�������ďC�u���������� (�ʍ� 81) �v���u���@�K�v���犧�s�����B
|
����̗��j�ƕ��� �R�� �i�g p.3�`8
���ꕜ�A�̂��߂̏����̐���
�@�@���������ی�s����̖��_ �ΐ��Y �@p.9�`12
����̕������ی�s���̌��� �������� p.12�`15
����̔��p�H�| ��鐸�� 0 p.16�`18
����̌����� �ې��v p.19�`21
����̎j�� ����M�Y p.22�`25
|
����̖��������� �m�O�E p.26�`28
����̖����E�V�R�L�O�� ���a�c �~ p.29�`31
����̖��`������ �V�铿�S p.32�`34
����̗� �����厡�Y p.35�`41
�������{��������(���p�فE�����ق߂���-49-) �O�Ԑ��K p.42�`43
�����_���L �ߓ��씎 p.44�`48
����̕������k�ꗗ�\�l p.49�`50 |
�U���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.1�v���u����l�Êw��v����n�������B�@�@�����F���ꌧ���}����
|
�}�� (�Y�Y�L�� ����{�Ք��@)
�n���̂����A ���{ �A�ʁ^��
�j�� ���� ��Y�^��
�l�Êw�̎��� ���a�c �^�~�^��
�O�V�N���߂����� ���� �����^�� p4�`8
�Y�Y�L�˒����T�� �V�c �d���^��
���ꌧ���o�y�̑K�݂ɂ��� ���� ���G�^�� |
����{�Ք��@�����ɎQ������ �m�O �E�^��
�������
����l�Êw��K��
��������
����
�������
�E |
�V���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (3)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����B�@pid/7931783
|
���V�������w�p�����ɂ���--1969�N�x���������� / ���V�a�r/p1�`10
���V���̐�j�w�I���� / ���،��a��/p11�`34
���V�����̌o�ϔ��W--������߂���J������ / �����ǐ�/p35�`55
���V�����ɂ�����l�������ɂ��� / �R�c���k/p56�`71
���V�����ɂ�����l���ړ� / �쑺�O�Y/p72�`100
���V���ɂ�������_�k�V�特�y�ɂ��� / ���c���q/p101�`119
�������w�̔����`��--�Ȗڂ̌n����T�����@ / ����w�v/p120�`135
���V���̖��w�ɂ��� / ���N/p136�`145
��Ԃ̖��� / ���c�m�q/p146~158
���V�����ԐM�����o�� / ���c���@/p55�`69
���V���̔N���s��--���V��𒆐S�Ƃ��� ����q��/p39�`54p
�@�܂����� / ����q��/p39�`39
�@(1)�A���V�` / ����q��/p39�`40
�@(2)�V�o�T�V / ����q��/p40�`42 |
�@(3)�^�l�c�P / ����q��/p42�`43
�@(4)������ (�C)�L�W�A�\�r / ����q��/p43�`44
�@(4)������ (��)���A�\�r / ����q��/p44�`45
�@(4)������ (�n)�A���_�l / ����q��/p45�`46
�@(5)�V�L���} / ����q��/p46�`48
�@(6)�^���C / ����q��/p48�`49
�@(7)�n�}�E�� / ����q��/p49�`50
�@(8)�A�L���` / ����q��/p50�`51
�@(9)�����\�ܖ� / ����q��/p51�`52
�@(10)�~�Y�K�~�Ղ� / ����q��/p52�`53
�@���Ƃ��� / ����q��/p53�`54
���V���̋ߐ� / ���V�a�r/p1~38
�������K��/p159~160
����(�����^)�E���Ƃ���/p161~162 |
�X���A�Y���[�삪�u���d�R�����^�W : ����×w�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s����B�@�R�R�O�O�~�@pid/12434617
|
��ʂ̉́@���v�@1
���y�ƃ����^�@��ɏ�i�c�@2
�����^�W���s�ɂ������ā@�{�ǒ����@6
�u�����^�W�v�ɂ悹�ā@�ɔg��N�@8
�����@�Y���[��@10
�����^�W���o�̉��߂ɂ��ā@�Y���[��@13
�����^�̂����������ɂ��ā@�Y���[��@13
�̕��ɂ������ā@��R�����@14
�}��@18
1�A�@�Y�M(����ӂ�)�@�����^�@20
2�A�@������ʁ@���[���[�܈��(����)�@�����^�@21
3�A�@�Ì��Y��(����́[��)�@�ԂȂ�[�܁@�����^�@22
4�A�@��肭�ʂ��[�@�����^�i�Ƃ������j�@22
5�A�@�F��(����)�ʉ�(��[)�@�����^�@24
6�A�@���Â��܂ց[�@�����^�i�Ƃ������j�@24
7�A�@��ؓ�(�͂����ǂ�)�@�����^�@28
8�A�@���내�ā[�@�����^�@30
9�A�@�ߍ��^��(�Ȃ��܂�[)�@�����^�@32
10�A�@�r��(����ӂǂ���)�@�����^�@34
11�A�@�h(����)�ʒ�(�Ƃ��邢)�@�����^�@37
12�A�@��(���イ���)�@�����^�@38
13�A�@������[�@�����^�i�Ƃ������j�@38
14�A�@�^�쉳(�܂ց[���)�@�����^�@40
15�A�@����(��������)�@�����^�@40 |
16�A�@�����ȁ@�����^�@42
17�A�@�W(�ނ�)����(�Ԃ�)�@�����^�@43
18�A�@�L(�܂�)�@�����^�@44
19�A�@�c�c��(�����ނ�)�ʁ@����[�܁@�����^�@45
20�A�@��������[�܁@�����^�@46
21�A�@�命��(���ӂ��ˁ[)�@�����^�@47
22�A�@���C(���)�@�����^�@48
23�A�@���NJ�(�����)�@�����^�@50
24�A�@�Ƃ���@�����^�@52
25�A�@�앗(�͂�����)�ʁ@�������@�����^�@54
26�A�@��R(�������)�@�����^�@56
27�A�@�R��(��܂�[)�@�����^�@58
28�A�@�Ԓ�(�����)�ʁ@�ڍ�(�݂���)�[�܁@�����^�@60
29�A�@�x����(�ӂ����ʁ[)�@����(�������ȁ[)�܁@�����^�@62
30�A�@�x���(�ӂ����ʁ[)�ʁ@����(�������ȁ[)�܁@�����^�i�Ƃ������j�@
31�A�@�Ԍ�(������[)�@�����^�@64
32�A�@�Ì�(����)�ʁ@�ā[�����@�����^�@65
33�A�@�钆(��Ȃ�)��[�@�����^�@66
34�A�@��(����)�낤���@�����^�@67
35�A�@���(���)����(��[)�@�����^�@68
36�A�@������(�����ǂ���[)�@�����^�@70
37�A�@�V��(����ނ�)�@�����^�@72
38�A�@������(�܂��ˁ[)�@�����^�@74
�E |
�X���A�u�܂� = Festival (16)�v���u�܂蓯�D��v���犧�s�����B�@pid/7930492
|
�����̃n�[���[/�����Y/p81~89
����́u�~�x��v/�X�ۉh���Y/p90�`102 |
�v�����̃A�~�h�V�� / ���Ԉ�Y/p103�`111
�v�����̃C�U�C�z�[ / �c���`�L/p112�`131 |
�v�ē��́u��q��v�s�� / �����P�G/p132�`140
�v�ē����������́u���Ձv/ �]�F��/p141�`162
|
�P�Q���A���v�` ������w�j�w�E�n���w��ҁu�j�� = Shisen : historical & geographical studies in Kansai University (�ʍ� 41) p.1�`31�v�Ɂu�ɐ��_�{�̐����v�\����B
���A���̔N�A�u���ʏd�v�������V�����C���H�����v���u�����������ی�ψ���v���犧�s�����B
���A���̔N�A���c���q���u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (�ʍ� 30�`33) p.23�`39�v�Ɂu���V���̓c�A�̂̎��^�ƋȌ^�Ɋւ���l�@�v�\����B�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���v����w��A���ҁu�l�މȊw : ��w��A���N��@ (�ʍ� 23) p.167�`184�v�Ɂu ���ꉹ�y�̉��K�v�\����B
���A���̔N�A��v�� ���Y���u���{�̗w���� 9(0) p.57-58�v�Ɂu�q���]�r���m���y�w��ҁw���{�E���m���y�_�l�x�v���Љ��B
���A���̔N�A�u���{�̓`�����y�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s�����B�@�@�����F�����Ɛ���w �}�����@�d�v�@�@
|
���e:�`�����y�T��(��v�Ԋ��Y)
���{��Ǝ{��(���c��t�F)
�����|�p�Ƃ��Ă̓��{���y(�S�i����)
�����h�̐����Ɠ��ꐫ(���R���V��)
��y�̗��j�ƕϑJ(���c�Njv)
�����̉��v�ƊT��(�Љ��`��)
�\�̑听�ɂ����鐢����(���{�) |
��ڗ��̌���Ɖ��t(�q�c��O)
�Z�|�`���̏ォ�璷�S�̗��j�����ǂ�(���c����)
���i��ⵂ̉��y(���쌒��)
�ڔ��E���E�J�E�@�|(�C�����@�c)
���^�Ɋς閯�w�̕ϑJ(��쌚��)
�u����M�y�v�̍����I�Ӌ`(���L��o�u)
���{���y�̊ӏ܂ɂ���(�g��p�j)
|
�ӏ܋��މ��(����)
���w�̕��̂�����ƕ��@(���R��)
���w�ҋȂ̕��@(���яG�Y)
�����w�̉̏��ɂ���(���c���q)
���{���y�j�N�\(����)
���{�̊y��(�ēc�k�o)
���R�[�h�͉���I�Ԃ�(��l���O) |
���A���̔N�A�J�쌒�� �ҁu����̎v�z�v���u�؎��Ёv���犧�s�����B�@�@ (�p���킪����
; ��6��)�@�@pid/9769289
|
��
�u���v�̎v�z�Ƙ_���\����ɂ�����v�z�̎����ɂ��ā\ �V�얾/3
����ɂ�����V�c���v�z �얞�M��/73
�������̔��z�\����̋����̈ӎ��ɂ��ā\ ���{�b��/131
�����I���p����̓��{���A �Đ{����/193
���O�ɂ�����ُW�c�Ƃ̐ڐG�̎v�z�� |
�@�@���\����E���{�E���N�̏o�����\ �X��a�]/225
2
�C�̐_�ƈ��̃A�j�}�\�����̂�����������˂ā\ ��R�ٌܘY/257
�C�ƎR�Ƃ̌����\�쓇�����_�\ ����d�N/307
����\����̎v�z�̐����I���p�\�J�쌒��/339
�E |
|
| 1971 |
46 |
�E |
�P���A���a�c�^�~���u�k���̐A�� = The Journal of Geobotany 19(1�E2) p.31-39�@�k���̐A���̉�v�Ɂu�����A�������^ (��)�v�\����B�@
�P���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 8(2/3)(33/34)�@�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@�@�@�@�@pid/4437749
|
���������̓���--��ڂƓW�] / �R���ӈ�/p1�`11
���������̌ꌹ�ɂ��� / ���v��/p12�`20
�����̔N���s�� / �c���p��/p21�`34
�����̎q�������O�g / �b���`��/p35�`51
�����̌Õ��� / �R�c����/p52~68
�������w�T�� / �v�ۂ���/p69�`78
�����E����ɂ����郈���i�n�n���V���̗̉w / ����w�v/p79�`94 |
��E���̖��� / �O����/p95~107
���V���̖��ԓ`��--�`���E�̘b�o�� / ����]/p108�`121
���i�Ǖ����̐_�b / ��c����/p122�`131
�^�_���̖��w�Ɛ��� / �h��v��/p132�`147
�w�E�j���[�X/p121~121
���������/p147~147
�E |
�Q���A���K�F�͂��u����̕��K�Ɩ��M�v���u�썑���v���犧�s����Bpid/9769491
|
�܂�����
���� ����/1
�̂̎̌�����
�������ʂ̌������K
�v�����̌������K
����̔_���e�n�̌������K
�������E�������܂���
�����̘b
�����̘b
�V�n�܍s��
�\���Ə\��x
���߂̏�
�����Ɋւ�����M
���� �K�P/41
�K�P�Ƌ֊�
�����̈�w
���E���ʂ̖��M
�J�j�ƃn�}�O��
��O�� �o�Y/58
���̂�����
�v�����̂��Y
�̂̂��Y
�e���̂��Y���K
�̐_
�ʉ̘b
���Y�Ɋւ�����M
�ٓł̘b
��c�т̘b
��l�� ����Ɩ�N/91
�{�y�̉���̏j
����̉���̏j
��N�̘b
����e�n�̖�N�炢
���E�̖�N
���߂̖�N
���̃^�u�[
|
��� �a�C�ƌ��o/104
���˂��̏�
�Α���̂���
�a���悯�̂܂��Ȃ�
���C�a�Ɩ��M
��ጂ̘b
���o�̘b
��Z�� �O��/116
�O�m�点�̂��낢��
���ƍ�
������݂̘b
���킳�������
�O���Ɋւ�����M�W
�掵�� ���N/139
���w��
�I���Ɩ싅
�R�b�N������
������
���N����
�攪�� ������Ƃ�����/150
�ԗ��
�N�̍��Q��
�V�c�̂�����
�����ʐ_
�O���ł̂�����̘b
������
���Ȃ肳��
���˂̘b
�s�K�̎莆
���� �܂��Ȃ��Ǝ���/172
����̂܂��Ȃ�
�ߕ�
�܂��Ȃ��̂��낢��
�܂��Ȃ����t
�Ί����Ɠ��c�_
�����̘b |
��\�� �d���Ɨ썰/190
�����̈�O��
����̉��k
�s��̓c��
�������̂̂��낢��
����̗d��
���{�̗H��
���m�̗H��
�����̗H��
����̗H��
��\��� ����/223
�����̕��@
�k���̘b
�����Ɋւ�����M
��\��� ��/258
��̌`
����̕�
�K�n���咆��
����e�n�̕搧
��Ɋւ�����M
��\�O�� �@��/273
�@���̈Ӌ`
���_����
�{��S�܂�
����̖@��
�n���̈ꓔ
�ʔv�̘b
�����̘b
�@���̎��
���K�̘b
��\�l�� �֊�/300
�����t
����̋֊�
��܂��b
�z���K�P
�M�\�̖� |
��\�� �����ƕ��p/313
����̘b
�Z�j�̘b
����j�g�ƌ�
���p�̋g��
��\�Z�� ����Ɠ��̖��M/333
����n��
���n�}�G��
�Z��d�Ȃ�
���q��������
��͏��N�ɑ���
���̊����Ɛl�Ԃ̐���
��\���� �̂̏@���s��/343
���^���̍Ր�
����̂��ԐM��
�̐_�̐M��
���~�_
�咆�̍�
������̘b
��\���� �̂̔N���s��/358
�ꌎ
��
�O��
�l��
�܌�
�Z��
����
����
�㌎
�\��
�\�ꌎ
�\��
���Ƃ���
�E
�E
�E |
�R���A������q���u������w����w���I�v (14)�@p59-70 ������w����w���v�Ɂu�W�c�ɂ��\�� �v�\����B�@�@�@�@�@pid/2213483
�R���A�Y�菃���u���̃G�������h�̊C : ���d�R�Q��������n���L�v���u��������Ёv���犧�s����B 900�~
�@�@ �@205p �@�����F���������}���فF00103331407
�R���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.2�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@
�@�@�@45p�@�����F���ꌧ���}���فF 1003064019
|
�}�� (�g�㓴���o�y�l��)
�쐼�����ɂ�����Ñ��쎑�� �O�� �i�^��
�����j�n���w���� �F�� �p��Y�^��
�g�㓴���o�y�l���Q�ɂ��� ���Е� �X�^��
�쓇�l�Êw�W��v����(1970�N�x��)
������Ւ����� �m�O �E ���{ �A�ʁ^�� |
�|�x�����؈�Ս̏W���� �ʏ� �����^��
�Ñ�E��������j�����ɂ��� ���� �i�^��
�쓇��j�y��̕ҔN���߂�����-�Ăѐ������G����- ���� �����^�� p.40-41
�쓇�l�Êw�W��v����(��)
�l�Êw�Ɨ��j �� �����^��
���ʉ���E�V������� |
�S���P�V���A�Ί_�����łR�Ԗڂɑ傫���ʏ́u�K�[�����W�v�܂��́u�K�[�i�v�̉����X�R�b�v�Ńg���l�����@��ђʂ������ƂŒÔg�ɂ��ʉ]�ł��邱�Ƃ��ؖ������B
|
| �H����S�������l�X�F�O���P��A����F�A���l�V�F�A�O���P�� |
|
�S���A�u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� 12(2)(50/51)�v���u�����������w��v���犧�s�����B�@pid/6024802
|
�ŐA�Ղ̂��� / ���c�
�\�y��n�������F�����l--�d���y�ƈ����P�l / �u�ꍄ/p1�`3
�V�l�̘b--���������̌���(�O) / ���c�/p4�`7
���������ɂ��� / ����d�N/p7�`12
�k��q�̓���K��--�������𒆐S�Ƃ��� / �X�c����/p12�`13
���̐_�G�r�X���܂ɂ��� / �k�R�Ք�/p13�`15
����n���ɉ�����c�̐_ / ���R�D��/p15�`18
���ؖ�s�r��̉��ǂ�u--���������̎肪����Ƃ���/�q���Y/p18�`19
���z�C�� / �R������/p20~23
���������ǂ̃G�����]�ɂ��� / �l�c�����q/p23�`24
�u�z�u�̍����x�� / �s��蒷��/p24�`27 |
�����㗬�ɂ�����M�\���{�� / �я��j/p27�`40
���܂̗������� / �k�R�Ք�/p40�`43
�ɐ��u�Ƃ��̍s��--��ӌS��Y���{���ƕ���/�l�c�����q/p43�`48
��q���̖��� / ����q��/p48~59
�����w�̒�����������@�ɂ���--(�k�b���)/p60�`63
��������������̕���/p64~66
���������/p66~68
�������������w���/p68~71
�������������w��/p72~72
���ҏW��L/p71~72
�E |
�T���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 8(4)(35)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437750
|
�w���z�x�ɂ��� / ���K�����Y/p1�`17
�i�̌ꌹ / �O�Ԏ�P/p18~30
���ꕶ�w�j�ɂ�����u�g�x�v���͂̈Ӌ` / ��Î�/p31�`40
�u����v�_--���������_�m�[�g(1) / ���{�b��/p42�`57
�u�����̚L�v�_ / ��������/p58~70 |
�^�_�ꕶ�@�̓��� / �R�c��/p71�`85
���i�Ǖ����̓`�� / �@�����g/p86�`89
���] �n���^�����u�����Z�킽���v��ǂ� / ����O/p90�`94
�w�E�j���[�X/p41~41
���s�j���[�X/p70~70 |
�T���A��،����u�ߌ��쌀 24(5) p.50�`53���쏑�[�v�Ɂu����̕����� (�����ƕ���(���W))�v�\����B
�U���A�J�쌒�� �ҁu���������́v���u�؎��Ёv���犧�s�����B�@ (�p���킪����
; ��4��)�@�@pid/9769644
|
��
�Ñw�̑� ������G/3
�Ñ㕔���}�L������_�k�����ւ̔��B ����~/71
�Q
����Ñ�̐����\��E�����E�_�k�\ ���܌���/91
�O
�����̗�Ђ��߂���o�� �A������/185
������N�ƌ�V���� |
����̖����ƐM�� ���܌���/293
������N�ƌ�V���� �R�����j/329
�⑫�\������G���ɂ��V�_���ꉥ�̕��������𒆐S�Ɂ\ �ҏW��/342
�l
����̍����N�����b �n������/357
�쐼�����̓V�l���[� �Ό��V��/381
�V�~�菗�l ���v��/401
��� �J�쌒��/427 |
�V���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (4)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����Bpid/7931784
|
�����哇�}���������w�p�����ɂ���--
�@�@���t1970�N�x���������� / ���V�a�r/p1�`7
�哇�S�}�����̐�j�w�I���� / ���،��a��/p8�`23
�������̗����_���ɂ�����w�l�̔_�Ɗ� / ����N��/p24�`38
�����{���k���̌o�ϔ��W--
�@�@����`�����ő�̊J���헪 / �����ǐ�/p39�`54
�����哇�}�������m�̔����x�̉��y--
�@�@�����^�ƋȌ^�̊W�𒆐S�Ƃ��� / ���c���q/p55�`64
�������w�̍̏W�Ǝ�����--�}���n�撲���̐��ʂƔ��Ȃ��ӂ܂���
�@�͂��߂� / ����w�v/p65�`65
�@�kI�l�Ȗ� / ����w�v/p66�`67
�@�kII�l�S�̏�ƖړI / ����w�v/p68�`70
�@�kIII�l��������`�� / ����w�v/p70~71
�@�kIv�l���Ɖ́E�̎��̌X���y�ю��^ / ����w�v/p71�`74
�@�kv�l�����`���y�уn���V�� / ����w�v/p74�`76
|
������ / ����w�v/p76�`76
�����哇�}�����̖��� / ���c���@/p77�`98
�}�����̖��� / ���c�m�q/p99~118
�̐����搶�𓉂� / ���V�a�r/p119�`124
�f�����������t�B�[���h���[�N �����搶��
�@�@���v���o / ���c���q/p125�`127
����E���Ƃ���/p128~128
�����哇�̔Ε�E�ϐΕ� / ����d�N/p1�`21
�����g�L�o���ɂ���--���������������W��
��A�͂����� / ���V�a�r/p22�`23
��A���v�C�����̃g�L�o�� / ���V�a�r/p23�`27
�O�A�}�����̋g�������T�ɂ��� / ���V�a�r/p27�`43
�l�A�������G�����Η�ɂ��� / ���V�a�r/p43�`50
�܁A��E���̃g�L�o���ƕ̋g������ / ���V�a�r/p50�`51
�Z�A�ނ��� / ���V�a�r/p51�`51 |
�V���A�u �e�A�g�� (339)�v���u�J���~�[���Ёv���犧�s�����Bpid/7900555
|
����Ɖ���(���W)/8�`64
���W ����Ɖ��� ���ɂƂ��ĉ���Ƃ͉��� / �؉�����/p8�`12
���W ����Ɖ��� ����Ɖ��� / ��闧�T/p13�`20
���W ����Ɖ��� ����̌|�\ / �{�c����/p21�`29
���W ����Ɖ��� ����̌ÓT�|�\���ꂱ�� / ���P�Y/p30�`35
���W ����Ɖ��� �V���c�u�n���v�̏\�N�� / �m�O���^/p36�`41
���W ����Ɖ��� �����ɂ����鉫��u�� / �쑺��/p42�`51
�E |
����Ǝ�/52�`64
���z ����Ǝ� ���͐�--����ŋ� / �Ôg���ۍD/p52�`55
���z ����Ǝ� ������Ƃ�����̊� / �Ζ쒩�G/p55�`57
���z ����Ǝ� ��l�̖��҂Ɖ��� / ���𐳖�/p57�`60
���z ����Ǝ� �����͍��� / ������Y/p60�`62
���z ����Ǝ� ���̂Ȃ��̉��� / �g������Y/p62�`64
����ɐ�����(65)�z�H���� / �F�����X��/p5�`7
�� |
�W���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (59)�v���u�j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6051492
|
�q�����̌��t�r �l�Êw�ƃ^�C�|���W�[/p1�`1
�����J���q�ِՂ̒��� / �c���N�Y ;�Ώ��D�Y/p2~8
�����������u�S�όÕ��̌����v(2)���B�n���𒆐S�Ƃ���/���J��/p9�`14
�������Ñ�̓S�̗A��(����2) / ���a�c�^�~/p15�`16
�����茧���Y�s���ӂ̐�y�핶�� / ��������/p17�`20
���V���Љ� �G���u���E�l�Êw�v / ��������/p21~22
���{�茧���������فq�����وē��r / �c����/p24�`25 |
���`�c��̂������s2���y�� / �]��P��/p16�`16
���Y�a�s�̏W�̍����A�n���y�� / �~�Ï� ;���X���s/p23~23
�����ђB�Y���́u�ꕶ����v�ɂ悹�� / ��c�h�V/p20�`20
�s�V�����]�t �w�C�̍l�Êw�x / �]��P��/p26�`26
�s�����ژ^�t/p27~30
�s�l�Ãj���[�X�t/p31~35
�O���t �����J���q�ِ� |
�W���A�ʏ�`�O������^�C���X�������ƋǕҁu�ɕ����E�ɐ����̗� : �Â����������X��K�˂� ��9��j�ցE���|�̗��v���u����^�C���X�o�ŕ��v���犧�s����B �@pid/9769531
|
�ɐ������i�߁[���[�j
�I�v�Ȃ铇�X/15
�_�X�̛�/19
�ɐ������/23
���n�т̕�����/27
�ɕ��������̐�j����/29
�C�M�^���Ɨ��M�^��/32
���~���`��/34
���~���݂ق���/41
�ɐ����ʌ�a/43
|
�ɐ������̋���/46
���D�������/51
�ɐ���������������/55
���[�E�̎m��N/57
���c�̍j����/59
���ɓ`���e���N��/62
�C���`�����[�Ղ�/64
�ɐ������̌É�/66
�ɕ������i�������[�j
���S�̂��ۗ{�Z���^�[/73 |
�ĉ��i�ӂ܂�[�j/75
�c���̔O������/78
�受�`���̖�����/80
���̕�����u�Փ���v/83
��ꏮ���ƈɕ�����/85
�c���̏�A�i�ʂ������j/88
�ɕ������̌É�/91
�ɕ����E�ɐ����ւ̗��s����/96
�u�j�Ֆ��|�̗��v�ɂ���/100
�E |
�W���A�u����̗��j (3) : �����a���̗��E�C�O�f�Ձv���u��������Ёv���犧�s�����B�@
�@�@�@ (���������62��)�@38p�@�����F��㊌����}���فF1001600020
�@�@�@�t�F�������x�̎�قǂ�(3)���d������(��{ ���� ���T)
|
���������60���`62���ɋL�ڂ��ꂽ�u�������x�̎�قǂ��q1�`3�r�v���̓��e�ꗗ�\�@
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
���e |
| 1 |
���������60�� |
1970-01 |
������ŕ��@�i��{�@�ʏ� ���`�j |
| 2 |
���������61�� |
�@- |
�@- |
| 3 |
���������62�� |
1971-08 |
�������x�̎�قǂ�(3)���d�����ˁ@(��{ ���� ���T) |
| 4 |
�@- |
�@- |
���ȉ����e�s���Ȃ��ߒ����v�@�Q�O�Q�R�E�X�E�Q�U�@�ۍ� |
|
�W���A�Y�菃���u����̋ʍ� : ����Q���ʍӐ�̐^���v���u���{���؎� �v���犧�s����B�@
(���ؐV��)�@�P�U�T�O�~
�@�@�@�@�����F��㊌����}���فF1001665296�@�@�@pid/12398026
|
�c�NJԗ̏W�c����
�ߌ��̌c�NJԗƐԏ����
�Ί_����Ǝ���
���ޓ��̑��� |
���̓��E�g�ƊԒ��ԕ�������������
�R�l�̔Ɣ���
�����ł̏Z���ߌ�
���c�E�ȉ����� |
�j�ꂽ�l���\�� �E�]�̓�����
���Ƃ���
�E
�E |
�X���A�O�Ԏ�P���u���w�E�|�\�ҁv���u���}�Ёv���犧�s����B (���ꕶ���_�p)
|
����: ������̕��| / ��Ït�� [��]
�������w�̋N���ƕϑJ / ���钩�i [��]
���ꕶ�w�̓W�] / �O�Ԏ�P [��]
����̕��w / �i�ψ��� [��]
������E���킢�ɂ�: �N���C�j�����߂����� / �ɔg���Q [��]
�v�ē�������ɏA���� / ���獑�j [��]
�����댤���̕����ƍďo�� / �����P�� [��]
�a�D�����̍l / ����d�N [��]
����: ���̊T�� / ��Ït�� [��]
�����ꂨ��ї��̂ɂ��� / �����l�Y [��]
���̂̓��� / �X������ [��]
���̂��߂����� / �Ö��c�@�h [��]
�g�x�E�����E�l�`�ŋ�: �g�x��ȑO / �܌��M�v [��] |
�g�x�T�� / ��Ït�� [��]
����́u�����v / ��Ït�� [��]
����̐l�`�ŋ� / �R�����j [��]
�����E�{�ÁE���d�R�̗̉w: �̗w�̔��B�Ɠ��� / ������ [��]
�{�Âɉ�����j�̂̔��B�ɂ��� / ����~ [��]
���d�R���w�̎j�I�l�@ / ��ɏ�i�c [��]
�|�\: ����̌|�\ / �{�c���� [��]
���V���̖����|�\ / ����w�v [��]
���ŋ��̎v���o�ƒ��҂̑�� / ���܌��� [��]
�����̕��x / �r�c��O�Y [��]
���y�ƕ��x / ��Ït�� [��
���: �O�Ԏ�P
�E |
�X���A�u�������_ 86(12)(1013) �v���u�������_�V�Ёv���犧�s�����B�@pid/3365829
|
���㒤����12�l(�J���L�v) / �����S��
���̏���(�֓��Α�) /
<�ʐ^>�o�H�R�[ / ���R����
�s�ݏؖ�(�{�J�j�q) / �����Ɩ�
�����̌��t //p37~37
�������� //p38~45
71�N�㔼�̐������� //p38~39
�l�x�ڂ̃N����������@ //p40�`41
�����o�ς̐��v�Ǝ��� //p42~42
���p��O���̂��炭�� //p44~45
�l�������_ / �͖쌪�O ;�|���`�� ;�����B�Y ;����/p46~53
<�}���K> �������v //p47,49,51,53~47,49,51,53
���a�̂��߂̋���--���ۘa���Ɛ푈�̌��̌p��/�{�c���Y/p54�`83
���f���܂�����{�k�Β�������l / ���R ����Y ;�X�R���Y/p84~95
<�{���J�b�g> / �F�����u�q
�O���Ȃ͂���ł����̂� / ��X ��/p96�`106
�������퉻�Ƒ�p��� / �c�K���`/p107�`117
�u�j�N�\���K���v�ƃA�����J�̘_�� / �i��z�V�� ;���]��/p118~131
�w���ߌ��x / ���쌒�j/p132~133
�w�����߁x / �a��F��/p134~135
�w����������x / ����������/p136�`137
���W ����͎咣���� //p138~305
�Ȃ��u��������v�� / �v�� ���F/p138�`147
����������y�n���p�v��(���W�E����͎咣����)/�R��V�D/p148�`157
��n�o�ς��ǂ��ς��邩(���W�E����͎咣����)/�R�����W/p158�`164
���Q�͉����(���W�E����͎咣����) / ���x�c ���[/p166�`177
���A������Ƃ�ᔻ����k������w�̍����ڍs�����Ƃ��āl
�@�@��(���W�E����͎咣����) / �{�� ����/p178�`186
�{�y�v�V�ւ̒��� / ���n �E��/p187�`195
�y���O�q�̍Đ���₤--
�@�@���{�y�n�Ɖ��ꓬ���̍s��/�얞�M��/p196�`205
���A���Ȃ���Ȃ���--���_�����ɂ݂鉫�ꌧ����
�@�@���Ԋҋ���]��/ �O�� ���l�Y/p206�`215
�������{ / ���� �V�o��/p216�`228 |
�����̎��p(��������) / ������b
������w�j�q�� / �я���
�����Ƃ��Ă�<���{(���}�g)> / �V�� ��/p241�`257
�f�́E����I�j�q���Y�� / �q�` �ĎO/p258�`266
����ɂƂ��Ă̒���(���W�E����͎咣����)/�� ����/p267�`273
����̌��ꂩ��--
�@�@�����ꂪ��l���ł͂Ȃ�����/���R �ǖ�/p274�`280
"���{�R"�̉���i��(���W�E
�@�@������͎咣����)/�吼 �ƗY/p281�`289
�{�y���{�x�z���̔��d�R(���W�E
�@�@������͎咣����)/���� ��/p290�`295
�ڂ������ɑc���͂Ȃ� / �Ί_ ���ݎq/p296�`305
�W���[�i���X�g�c���̍����-1- / �c �p�v/p306�`313
�Γc���ɒ��킷�� / ���c �K�O/p314�`319
�|�\�]���L / �吼�M�s/p320~323
���[���b�p�͒n���ł���(�h�C�c�ʐM) / ���{ ���q/p324�`337
�\��̎��R / ���c�b���Y/p338~341
��������q���V�} / �ɓ� �s/p342�`355
�u���A���G�e�v(���ˋL) / �g�c ����/p356�`363
�@�R�@�ɂ� / �����/p364~365
�t����� / �������H/p365~367
�剺�� //p365~365
�c���Y //p367~367
�N���X�g�t�F���X�ӂ����� / �����r�Y/p367�`368
�w�d���x�̗��Ə\���q / ���J��/p368�`370
�{��̂肨 //p369~369
<�\���̌��t> / �֖쏀��Y/p371~371
�R�͎c���� / ���R�g��/p370~371
������--�ܑ�Q�Y�`(���b)--�Ⴋ�p�Y���̑��@��
�@�@�������ɂ��Đb���̐l�S�����ݤ�V����
�@�@�������ɂ�����/������/p372�`393
�@�@--�A��(����) / �O�H���Y/p394�`409
<�������_�������\> / ����P�F/p410�`413
�M�҂ƕҏW���ւ̎莆 //p414~ |
�P�O���A��،��� , �V�Ԕ�C�u�G�u�L�ǂ�ƃL�W���i�[ : ����̘̐b�v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@pid/12467729
|
���F�̚�
�q���ɂȂ����ԉ�
���Y�ƎO�Y�Ɣn�D�_�Ƌ��D�_
�����̕@�k�� |
���̐�����
�V�ɓ͂����|
�V���̂ނ���
�S��H���� |
��㊐l�̂͂��܂�
�n�̗�
�̊�
�S |
|
�P�P���A�u���{�l�Êw����������\�v�| ���a46�N�x�v���u���{�l�Êw����v���犧�s�����B�@�@
|
�쓇�l�Êw�̏���� ����,���� p.2-5
�e�n�ɉ�����퐶����搧�̓W�J �k��B�̊T�v ���c,�x�m�Y p.5-8
�R�A�ɉ�����퐶����搧�̓W�J �ߓ�,�� p.9-11 |
�ߋE�n���ɉ�����W�J �c��,���� p.11-16
�k���n���ɉ�����W�J �g��,�N�� p.17-20
�֓��n���̕��`���a�� �����,�Lj� p.20-25 |
�P�P���A�u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� 12(4)(53) �v���u�����������w��v���犧�s�����B�@�@pid/6024804
|
1�����ɂ����� / ���c�/p1~1
2����n���ɂ����鎁�_ / ���R�D��/p2�`5
3�J�����Ɍ��������s / �X�c����/p5�`7
4����쉺���ɂ�����u���v�̋��@�ɂ��� / �R������/p7�`9
5�[����n��̍��� / �k�R�Ք�/p10�`12
6�̘b�̕ω��ɂ��� / ���萳��/p12�`16
7�V�ÁE����̑D��l / ��������/p16�`19 |
8�g�������̈�� / ���l����/p19�`26
9�쓇���ΒʐM�@ / ����q��/p26�`27
�������������w��̕���(9���`10��)/p28�`28
���������/p28~31
���ҏW��L/p31~32
�����Љ�/P32~32
�E |
�P�P���A�J�쌒��ҁu�N���_���v���u�؎��Ёv���犧�s�����B�@�@ (�p���킪����
/ �J�쌒���, ��3��)
|
�g�Ɗԁ\�g�ƊԒʐM4�\ ���֏�v/3
���������Ƃ��̌���\�������̉����ᔻ�\ �{�Ǔ��s/5
��A���\�������ʖ��/5
��A�w�@���x�́u�����v�͑�p�ɈႢ�Ȃ�/7
�O�A���������͖����ォ��/12
�l�A�����j�ȑO�̓쓇/14
�܁A���֎��̉����͌��ꕨ���_��/18
�Z�A�g�ƊԂ̖��`�ɂ���/20
���A���������̖{��/22
���A���������̋���/25
���d�R�Q���̌Ñ㕶���\�{�ǔ��m�̔ᔻ�ɓ����\ ���֏�v/31
��A����/31
��A�@���́u�����v���ɂ���/32
�O�A�����̓S����/34
�l�A���{�l�̃C���h�l�V�A�v�f�Ɨ����l�̃A�C�k�v�f�ɂ���/38
�܁A������̖��ɂ���/41
�Z�A�^�o�R���̖��`�ɂ���/53
���A�g�ƊԂ̖��̂ɂ���/58
���A�����̒n���ɂ���/61
��A���d�R�̐�j����/68
��Z�A���d�R�̐�j�����̌����Ƃ��̉e��/77
���A���d�R�n���l�̑̎��ɂ���/88
���A�����ɂ����镶���̓�Q/94
��O�A��������̕K�v���ɂ���/102
��l�A����/105
�����̌���Ɩ����̋N�� �����l�Y/111
�����̌���Ɩ����̋N���\���������̘_�l�ɓ�����\ ���֏�v/122
���������̘_�l�ɓ�����\�Ǖ�ƒ����\ ���֏�v/125 |
�����̌���Ɩ����̋N���i�]�_�j �����l�Y/127
���{��̗��������ɂ��� �����l�Y/137
��A�u�����v�Ɓu���n��v/139
��A���C�Ή��̖@��/141
�O�A�����̓���/145
�l�A����N��w/155
�܁A�Õ��y�Ɖ��V��/157
�쓇��j����̋Z�p�ƕ��� ��������/165
��y�펞��/168
�y��̓o��/172
�Ί�E����E�L��/191
�ƒ{/207
�쓇�̏M/212
���^�̐��Y/214
�����ƍՎ�/216
�쓇�̖��������\���ɓ��{�c��̌`����
�@�@���������߂�����ɂ悹�ā\ ��������/223
��A�͂��߂�/225
��A�쓇��j���㌤���̐i�W/227
�O�A�`���ƌ���/230
�l�A�����ɂ���/233
�܁A��B�퐶�l�̓�Q�͂�������/235
�Z�A�n���̖��\���{��n���_�Ɋw�т�/240
���A�����ɂ�������{��̌`���̎������߂�����/244
���A���Ƃ���/248
���A��㊍l�Êw������� �F��p��Y/251
��� �J�쌒��/287
�E |
�P�P���A�V�铿�S�ҁu�����(�A�K���E�}�[�C)�̔q�����Ձv���u���y�̕���������v���犧�s�����B
���A���̔N�A�u�ߔe���̂̏œ_ : ���ʎ��^ �ʐ^�ɂ݂�ߔe�̖ʉe�v���u���ꕶ���o�Łv���犧�s�����B�@pid/9769478/
|
���M�ҏЉ�/2
�͂��߂�/2
�����ʎ��^
�ʐ^�Ɍ���ߔe�̖ʉe/8
�ߔe�̌Ñォ����܂Ł@�u�Ǔ����p/40
�����w�V���ʂ��@�x�������ƒʂ���O�܂�
�O���i�����W���ȑO�j
����i�����W���Ȍ�j
��O���F���̕��f�ƂȂ��Ă��p�˒u���̑O�܂�
��l���p�˒u������ČR�ɐ�̂����O�܂�
�Ós�ƌÐ}�@���a�c�^�~/100
��Ձ@�V�铿�S/112
|
�킪�lj��̓ߔe�@�D�z�`��/138
�ߔe�l���C���@�R���i�g/155
��������̓ߔe�@���c����/166
�����̋L
�^�a�u�̉��v/228
���\�̉��v�@���Ԉ�Y/238
�哹�E����̎v���o�@���c���@/248
��O�̋���/251
�ߔe�̌o�ρE���Z�@��F���`�Y, �^�Ӕ�/268
�E�ߔe�̕����@�{������/292
�E�ߔe�̍H�|�@�O�Ԑ��K/344
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʎ��^ : �����l�s��L(�V��3�N���̕����j�@�R�ł݂̂��@�������K�v�i���m�F�j�@�Q�O�Q�R�E�T�E�R�P�@�ۍ�
���A���̔N�A�員���F, ����O�� �u������ 1,2�v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@
(��㊕����_�p, ��2-3��)
�@�@ 2�̕Ҏ�: �n������, ����O
|
1����: �C�_�{�l / ���c���j [��]
�������K: ���������k / ��Ït�� [��]
�����̐H�����ɏA���� / ���c�{�� [��]
���������ɉ����閯�Ƃ̍\���y���K / �{�Ǔ��s [��]
����̍����V�� / ���쐴�q [��]
�쓇�Ñ�̑��� / �ɔg���Q [��]
�����哇�ɂ����鑒��y�ѐ� / ���c�{�� [��]
����̐K�� / ���Ð^�鏟 [��]
�e���ƃ~���[ / ������G [��]
�N���s��: �쓇�̈��s���ɂ��� / �ɔg���Q [��]
���������N���s�� / ������ [��]
�Ñ㉫��̐��� / �{��^�� [��]
����ɐ������̔N�����J / �A������ [��]
���[���̔N���s�� / ���c�v�q [��]
���\�̐ߍՂƃA���K�}�x / ��Ð��� [��]
গ��D�ɂ��� / �n������ [��]
�|�x���̎�q�ǂ� / �������v [��]
���l���̃j���[�_ / �{�nj��� [��]
����̂�炴�� / �{������ [��]
�쓇�̓��n(�j��)�ɏA�� / ������v [��]
�_�ƍ��J: �������_���L / �܌��M�v [��]
�R���̌�x / �{��^�� [��]
�O�V�N(��)�̐��i / �������� [��]
�����哇�̍�Ɣ\�C�̐��� / ������ [��]
���Ȃ�_ / �ɔg���Q [��]
����擇�̃I�i���_ / �n������ [��]
�̐_�l / �ɔg���Q [��]
���i�Ǖ����̊��_ / ����H [��]
���z���q�Ɖ̐_ / �����P�� [��]
�쐼�����ɂ�����_�ϔO�E���E�ς̈�l�@/���[�[�t�E�N���C�i�[ [��]
�����̍��J�Ɛ��E�ς��߂����� / ��Ð� [��]
���Ԑ��b: �V�~��V�l / ���v�� [��]
��E���̘b / ��q�s�Y [��]
�^�ߍ��`�� / �r�ԉh�O [��] |
2����: �쓇�����̖ړr / ���c���j [��]
���������̏o�� / �܌��M�v [��]
���{�����w�Ɖ��ꌤ�� / �員���F [��]
���ꌤ���ɂ����閯���w�Ɩ����w / �n������ [��]
����: �W�� / �����P�� [��]
����̑����g�D / ��Ït�� [��]
�����̗��n�Ǝ�� / ������G [��]
�����_���̗^(�g)���x / �`�����_���Y [��]
���ꎅ���w�l�̌o�ϐ��� / ������� [��]
���J�g�D: ����̑��X / �h�� [��]
���ꖯ���̌��� / ���c���� [��]
�Ñ㗮�������ɉ�����ޏ��g�D / ���z���O�Y [��]
���ꍑ������n�̊C�_�� / �{�{���F [��]
���ꍑ���̃V�k�O�� / �{�{���F [��]
�����哇�̑����\���ƍ��J�g�D / ���[�[�t�E�N���C�i�[ [��]
�����̐_�� / �ɓ����� [��]
�_�肢�ɂ��������� / ���c�v�q [��]
���NJԓ��G�L / �_�ԗǍ� [��]
�擇�̌�Ԃ��߂����� / �A������ [��]
�����{�Ï����̍��J�\�������̖��_ / ������ [��]
�g�Ɗԓ����̑��̎��q�g�D / �n������ [��]
�g�Ɗԓ��̐_�s���ɂ��� / �R���l���E�X�E�A�E�G�n���g [��]
�咆�E�e���E�Ƒ�: �×����́u�Ђ����x�v�ɂ��� / �ɔg���Q [��]
�����̓����c�\�� / �n�Ӗ������Y [��]
�̖咆�ƍ��J / ��Ït�� [��]
���E�����������ɂ�����\���_ / �������� [��]
����E�n���쓇�̖咆�ɂ��Ă̗\���I�� / �R�H���F [��]
������Ԗ����̖咆�g�D / �������T�Y [��]
�咆�̐��� / �n���^�� [��]
�n�}�Ɩ咆 / �n���^�� [��]
�쐼�����̐e���W�c�̌� / ����O [��]
�E�ߔe�����ɂ�����e���W�̌�ɂ��� / ���钩�i [��]
�l�ςɊւ���{�Õ��� / �������k [��]
�E |
���A���̔N�A�u���ꕶ���_�p ��3���v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@pid/9769590
|
�}��
�n������E����O ���/1
����
���c���j �쓇�����̖ړr/58
�܌��M�v ���������̏o��/63
�員���F ���{�����w�Ɖ�㊌���/101
�n������ ��㊌����ɂ����閯���w�Ɩ����w/114
����
�����P�� �W��/122
��Ït�� ��㊂̑����g�D/137
������G �����̗��n�Ǝ��/147
�`�����_���Y �����_���̗^�i�g�j���x/157
������� ��㊎����w�l�̌o�ϐ���/169
���J�g�D
�h�� ��㊂̑��X/196
���c���� ��㊖����̌���/207
���z���O�Y �Ñ㗮�������ɉ�����ޏ��g�D/213
�{�{���F ��㊍�������n�̊C�_��/233
�{�{���F ��㊍����̃V�k�O��/240
���[�[�t�E�N���C�i�[ �����哇�̑����\���ƍ��J�g�D/249 |
�ɓ����� �����̐_��/263
���c�v�q �_�肢�ɂ���������/276
�_�ԗǍ� ���NJԓ��G�L/285
�A�����E �擇�̌�Ԃ��߂�����/307
������ �����{�Ï����̍��J�\�������̖��_/322
�n������ �g�Ɗԓ����̑��̎��q�g�D/345
�R���l���E�X�E�A�E�G�n���g �g�Ɗԓ��̐_�s���ɂ���/360
�咆�E�e���E�Ƒ�
�ɔg���Q �×����́u�Ђ����x�v�ɂ���/376
�n�Ӗ������Y �����̓����c�\��/379
��Ït�� �̖咆�ƍ��J/390
�������� ���E�����������ɂ�����\���_/397
�R�H���F ��㊁E�n���쓇�̖咆�ɂ��Ă̗\���I��/407
�������T�Y ��㊍��Ԗ����̖咆�g�D/425
�n���^�� �咆�̐���/457
�n���^�� �n�}�Ɩ咆/461
����O �쐼�����̐e���W�c�̌�/473
���钩�i �E�ߔe�����ɂ�����e���W�̌�ɂ���/495
�������k �l�ςɊւ���{�Õ���/505
�����ژ^/519 |
���A���̔N�A�u���ꕶ���_�p ��4���v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/9769591
|
�}��
�O�Ԏ�P ���/1
����
��Ït�� ������̕��|/42
���钩�i �������w�̋N���ƕϑJ/54
�O�Ԏ�P ��㊕��w�̓W�]/111
�i�ψ��� ��㊂̕��w/171
������E���삢�ɂ�
�ɔg���Q �N���C�j�����߂�����/198
���獑�j �v�ē�������ɏA����/213
�����P�� �����댤���̕����ƍďo��/247 |
����d�N �a�D�����̍l/278
����
��Ït�� ���̊T��/294
�����l�Y �����ꂨ��ї��̂ɂ���/311
�X������ ���̂̓���/328
�Ö��c�@�h ���̂��߂�����/336
�g�x�E�����E�l�`�ŋ�
�܌��M�v �g�x��ȑO/350
��Ït�� �g�x�T��/364
��Ït�� ��㊂́u�����v/368
�R�����j ��㊂̐l�`�ŋ�/372 |
�����E�{�ÁE���d�R�̗̉w
������ �̗w�̔��B�Ɠ���/398
����~ �{�Âɉ�����j�̂̔��B�ɂ���/413
��ɏ�i�c ���d�R���w�̎j�I�l�@/438
�|�\
�{�c���� ��㊂̌|�\/448
����w�v ���V���̖����|�\/478
���܌��� ���ŋ��̎v���o�ƒ��҂̑��/504
�r�c��O�Y �����̕��x/512
��Ït�� ���y�ƕ��x/527
�����ژ^/532 |
���A���̔N�A�����Y���u�������j��b : �������j�̗��ʂ��𖾂���v���u���ꕶ���o�Łv���犧�s����Bpid/9769507
|
��A���щ���j
�����Ȃ킩�痮����
��A���~�����ȏ��ꗗ�\
�O ���~���ƘV���炭�̗�
�l ����Љ��ވʌ��̓�
�� ���^���̈��~�ٕ� |
�Z�A�}���Ƃ����c������
���A�V���̐��̂̒T��
���A����̏����͉��̋����̂�
��A�D�F���̐��U
�\�A��������̒��Љ�_�l
�\��A�p�˒u�����O�̒җV�f |
�\��A�C���̕����j
�\�O�A���������j
�\�l�A�p�C���̗��j
�\�܁A�A���Ɨ��j
�\�Z�A���������̘b
�\���A���Ȍ䊥�D�s�� |
�\���A�������̒a��/270
�\��A���~�̖���/278
���Ƃ���/283
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�u��y�@�S�� ��17�� (��9�S �`�L�n��[2])�v���u��y�@�J�@���S�N�L�O�c�]�����ǁv���畡�������B
�@�@�@pid/12271829�@�@��y�@�@�T���s���40�N���̕���
|
���J�����l�`(���o)
�@�R��l��`(����)
�{���c�t�`�L�G��(�^��)
�����l�����L,
�@�R��l�`
,�@�R��l�`�L
,�@�R��l�`�G��(�Ԉ�)
�@�R��l�`,������l�`(����)
�R����l�`(����) |
���_��l�s�ƋL,
��y�{�����m�`(�S��)
�V����`(����)
�������t���`
,������l�`,��@�썑��(�ǐM)
���O�m�`(�M�g)
�̔O��l�s��L(����)
�e����l�G���`(�)
�����ӏ�l�s��(����) |
�`�d�R�J�c�ۗ���l�`(��_)
�I���q�������J�c�M�_��l�`(����)
�ܒ���l�`
��ޏ�l���`
,���ؘa���s��L(�ϑR)
�ϐ�l�s�ƋL(�ϑR)
�����@�J��Ȕ���l�s��L(�f�M)
���(�c���~��)
�E |
���A���̔N�A���z���O�Y���u���ꏎ�������j�v���u�Y�R�t�o�Łv���犧�s����B
(���������j�I�� ; 2)�@pid/9769646
|
�܂�����
��1�� ���K�Ɩ����̕ϑJ/1
�� �Ԑؔԏ��Ɩ�l/3
��l�ւ̓�
�M�Z�m��
���y�n���ƕ�s�l
��l�̗̍p�ƔC��
�E��Ɠ��e
���^�Ɩ��n
�� �n�����x�ƍv�d/17
�y�n�ɑ���ϔO�Ɗ��K
�y�n���x�ƍv�d�̗��j
�n����̔N���Ɣz��
��̓y�n���v��
�F���˂̎x�z�ƌc�����n
�H�n���G�̓y�n����
�n���n
�I�G�J�n
�d���n
�y�n���v�̉e��
�y�n�ƐŐ�
������N�F���˂̍Č��n
�O �Ԑؑ����@�Ɖȗ�/38
�������̌Y�@ |
���@�����������ꂽ����
���@�̓��e
���@�̋N��
�����@�ƉȑK
���ʂ̉ȑK
�����̔n���Ɨ����̐g��K
�����^�̖��M�ƉȑK
���݂̉ȑK
��[�ĂƖ��[�҂̏���
�ȍ�
�l �呰�ƍ��J/51
�咆�P�ʂ̑���
���ΐM�Ɓu�_�q�݁v
�咆��
���[�߂Ɛ�
�����̂��镗��
�����Ɨ�܂�
�����̐_�u�䍖�v
�_�A�V���M�̏���
�m���̌���
�u�̐_�̓a�v
�咆�ȊO�̗^�g�D
��2�� ����ԐE�{���ԐE���[�ԐE
�@�@���ɍ]���撲��/67
|
�����j�t�Ԑؗ����g�ⓚ��
�d�Ŗ��[�m��/69
�n���m��/77
�l�m��/89
����m��/94
�n���������j��n�������^�m��/99
�����E�����E����ݎm��/102
��[�������n���L���������p�X����/106
��������m��/110
�����m��/114
�����m��/117
�Ց����m��/119
�͍��m��/123
�t�̓m��/128
��m��/129
�����r��
�l�g����/153
�V�Y/160
����/166
�����L�V�R�уj�փX���͔|���̃m��/167
�e���_���Αďܔ����앨�����m��/173
���H�����m�C�U�ː݃m��/176
��������m��/176
�C�ݑD�����Ɠ�������m��/178 |
���A���̔N�A�u�~�o�����啜���H�����v���u�����������ی�ψ���v���犧�s�����B |
| 1972 |
47 |
�E |
�Q���U���`�R���P�Q�����A�u�������{�������فv�ɉ����āu50�N�O�̉��� - �ʐ^�ł݂鎸��ꂽ�������v�W���J�����B
�R���A���a�c�^�~���u����̂����߁v���u���ꕶ���o�ŎЁv�v���犧�s����B�@�@�@pid/12715552
�R���A������w�j�w��ҁu����j�w = Ryudai review of history (3) ������w�j�w��v�����s�����B�@�@pid/7945224
|
�Ί_��������A�^�h�������̑����ړ��Ə���Ԃ̗R��/�{�Lj��F/p1�`13
�A�����J�w�l�w�̎Љ�ƕ����̎j�I�l�@--
�@�@��Ann Landers�u�g�㑊�k�v���Q�l�� / �F��p��Y/p14~39
|
�q�����m�[�g�r ���d�R�ɂ�������ږ��j�ւ̒�/�Ί_�v�Y/p40�`48
�q�����m�[�g�r �R���D / ���Ð^�X��/p49�`59
�q�u���r ���d�R�̖��a��Ôg�ɂ��� / �q�쐴/p60�`74 |
�R���A�ʏ钩�O�� . �ɗǔg���g�� ; �{��\����� ; �X�ۉh���Y����u�g�x�F�s�̊�
. �̌����R�̉��O : ���� �v���㉉�����B�@�@�@(�������ꗮ���|�\�����㉉��{, ���a47�N3��24��-26��)
�R���A�u������w����w���I�v (15)�v���u������w����w���v���犧�s�����B �@pid/2213484
|
�p-�X�̌��ۊw / �Đ��T��/p1
���c�N�w�ɂ����颋t�Ή����
�@�@���L�F���P�S-���N�w�ɂ����颋t��/���ǐM��/p17
���ꌧ���w�Z����̕ϑJ-2-�吳���𒆐S�Ƃ���
�@�@����V����^����̓��� / ���g������/p27
�A�����J����������v�̕ϑJ-1-�n�C��X�N-���̋N��/�ʏ�k�v/p43
G.C.�z-�}���Y�ɂ����颎Љ����̊T�O--
�@�@���Љ�̌n�_�ւ̃A�v��-�`�𒆐S�Ƃ���/�F��B/p61
���{�̐_�b�`���ɂ��Ă̕����I����/ ��`�i/p75
�@�K�������������w���̑ԓx/���鑏/p83
���Ì��ʂɊ֘A����l�i�v���B/ ���鑏/p89
���A�����̗��w��-���v�Ɠ��w/���鑏/p95
|
���w���̋Z�p��ƒ�Ȋw�K�ɑ���ԓx /
�@�@�� �V�_���q;�n�����q;����`�i/p101
����̔N���s�� / �����M/p109
�^���w�K�ɂ�����X�s-�h�Ɛ��m���̑��ΓI����/������v��/p131
�_���ɂ�����Z�̔�r�I���� / �r�c��D/p137
�����̉��y�̌���--���K�_�ɂ���-2- / ��Í�/p143
���y���y�̋���ւ̓���--�w�K�w���Ď���2�_/ �Í�/p151
�������y�����ɂ���--���闧����̖���N/�Ɏu�䒩��/p165
�d�C����̌���-3-���^���M�@�̐��� / ��l�G�h/p171
�r�C�ǒ��ω����r�C���ɂ���ڂ��e���ɂ��� / ���g�h��/p179
�A�z�ꉫ��-2-�����ɂ���(����) / ���]���V/p183
������w����w���I�v(��11�`��15�W)�_������/p209 |
�R���A�u���������w���w���I�v (�ʍ� 86) �v���u���������w���w���v���犧�s�����B�@pid/1756216
|
�쓇�l�Êw�̏���� / ���������@p1�`27
�ܐ����̌���-2- / �Óc�G�v/1,�\4�� |
����̖@���ƕ���--�ŗƥ���ץ���ԐM�W�̋K�� / �������
��`�����s�Ꝅ��Ɋւ����̋L�q�j�� / �����L��Y |
�S���A�������{�������ٕҁu�������{�������يٕ� No.5 �v���v�������{�������فv���犧�s�����B
�@�@�@�����F���ꌧ�������فF1005775059�@�@64p
|
�������������L�˒����T�� �V�c�d��
�r�Ă̔��ɂ��� �{��Đ� |
����̊L�� ��]�F ��
�E |
�S���A�l�Êw�W���[�i���ҏW�ψ���ҁu�����l�Êw�W���[�i�� (67)�v���u �j���[�E�T�C�G���X�Ёv���犧�s�����B�@pid/6051500
|
�፡���̌��t��w�C���o�[�h���̗r�ъ�����/p1�`1
��������̕��ފw�I�l�@ / ���a�c�^�~/p2�`8
�����s�����p���Սl / �~�{��/p9�`12
�k�C���[�쒬�̃C���N�e(�������)
�@�@�� / �F�c��m ;�����W�� ;�z�c����Y/p13~15
���������ᕽ���V�����̒n�����y��/�㑺�r�Y ;����`��/p17~21
�؍��̈�Ո╨���w���s�ē��L(3) / �]��P��/p23�`25 |
���k��u�؍��l�Êw�E�̋ߋ��v�Ɋ� / ��������/p16�`16
������s�����̒n�������� / �O�����������c/p22�`22
��l�Ô����ف������وē��� / �{��p��/p26�`27
��V�����]��w�����l�Êw�����x / ��_�W��/p28�`28
�ᕶ���ژ^��/p29~30
��l�Ãj���[�X��/p31~35
�O���t �p�����y����o�y�����C���N�e
�O���t �����E�O���n�������� |
�S���A��ÍN�Y [�B�e] �u����E����v���u�����ʐ^���w�@�o�ŋǁv���犧�s�����B�@�@pid/12429343
�S���A�u���w 40(4) ���W�F����̕��w�E�����v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�d�v
|
����w�̍����I�ۑ�@�i�ψ���,�O�Ԏ�P,��]���O�Y p.1�`32
�ߑ�̉���ɂ����镶�w�����@���{�b�� p.33�`45
����̐�L���w�@���� ���� p.46�`58
��������Ɠ��{��--�����ɂ�
�@�@�������傪��������Ă��邩�@�������� p.59�`64
�쓇�̗w�̌n��-��-�@�O�Ԏ�P p.65�`79
���̏��� �@�r�{���� p.82�`94
���̂̐���--���Ă悱��,������肩��@�Ö��c �@�h p.95�`105
�\�����I�ɂ����鉫�ꕶ�w�̓����ƓW�J�@��� �� p.106�`117
�쓇�����_ �@����a�r p.118�`126
�����̗w�̌`���@����w�v p.127�`135 |
���d�R�̗w�ɂ�����g�D�o���[�}�߂̔��� �����H�^�s p.136�`145
����̕��x�@����^���� p.146�`152
���ꉹ�y�̉��l �@�@�c�ӏ��Y p.152�`155
�����j�����߂����ā@���R�d,�O�Ԏ�P p.156�`162
�O�Ԏ�P���u���肸��̓�--
�@�@�����ꕶ�w�Ǝv�z�̒ꗬ �i�ψ��� p.163�`171
���ꌤ���ɂ�������j�F��--�u��Ït���S�W�v�ɂӂ�ā@
�@�@���䉮���ƕv p.172�`180
�����@�K�����j p.200�`201
�ߑ� �@�����q�v p.202�`203
�E |
�T���P�P���`�T���R�P���A�u�i�����j�T���g���[���p�فv�ɉ����āu���A�L�O���ʓW�F50�N�O�̉��� - �ʐ^�ł݂鎸��ꂽ�������v�W���J�����B
�T���P�T���A����i���������y�ё哌�����j�̎{�������A�����J���O��������{���ɕԊ҂����B
�����A�{���Ì쎌,��Ԕɍ�ȁA���ꌧ�ҁu���ꌧ���̉́v�����肳���B
�@�@�@�@1�� �@�@�����F��㊌����}���فF1004674626
�T���A�u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� 13(2)(55)�v���u�����������w��v���犧�s�����B�@pid/6024806
|
1���������̕ۑ� / ���c��/p1~1
2�L�̘b / �����O�Y/p5~7
3�F���̉��ʎt / ���R����/p7~13
4����ƑD�ԓ� / ���|�G�Y/p13~16
5�F�쏔���k���ɂ�����Ĕ��_�� / �����a�O/p16�`22
6������ / �k�R�Ք�/p22~24
7���k�c / �k�R�Ք�/p24~25 |
8�����|�\�̓`�d�ƕϗe--�k�F���ۗx���ʂ��� / ����q��/p25�`31
9�����_�y�ɂ��� / ����s��Y/p32�`36
10�ɍ��n���̘m�H / ���萳��/p37�`37
�����������w��������/p38�`41
�����������w��̕���--(1���`4��)/p42�`42
�ҏW��L/p43~44
�E |
�T���A�w���Y�x�ҏW�ψ���ҁu���Y (233)�v���u���{���Y����v���犧�s�����B�@�@�@pid/7932009
|
��㊂̓��Z / �l�c���i/p6~9
���������ƒ����̊W / �O�Ԑ��K/p10�`14
����̐��D���� / �����g�E�q��/p15�`18
���|�قɂ� / ��쉀�G/p24~26
�O���t�u��㊂̍H�|�i�v / ���{���|�ّ�/p25�`38
���{�̖����Öʁ���̕��Ɠ����ʁ�/�����F��/p39�`43
����̒��̒���(�\�l) / �ߓ����k/p44�`47
�e�n���|����ݒn/p55~55 |
�W���� ����H�|�i�W(���{���|�ٓ��ʒ�)/p20�`23
�W���� �����W�E�H�|��/p48~49
�W���� ������{���|�W/p50~51
�W���� ���E�̖��|�W/p52~53
�W���� �����h�l�Y�荗���a����i�W/p54�`54
�ҏW��L/p58~58
�ڎ���@���֔����y�r�@����E�≮�q/p5�`5
�E |
�T���A�O�Ԏ�P���{���Еҁu�����{ : ���߂Ƌ��ނ̌��� 17(6)[(231)]�@p163�`165�@�{����] �Ɂu��㊂Ɩ��t�̉̊_�v�\����B�@�@pid/8099276
�U���A��،����V���{�o�ŎЕҁu�����]�_ (�ʍ� 130) p.56�`67�@�V���{�o�ŎЁv�Ɂu����̕���|�p--�g�x�Ɖ���|�\(���W�E����ƍ����̕����I�ۑ�)�v�\����B
|
����̌���ƕ����̌����@�@��������,�V���b��,�O�Ԏ�P p.2�`30
�s���̋Ɛсu���[�J�������v�@����̌���ƕ����̌����@�q�c�� p.10�`12
������߂��鋳��̖��@���쑾�Y p.31�`42 |
����j�ɂ����鉫���̈Ӌ`�@���X�ؗ��� p.43�`55
����̕���|�p--�g�x�Ɖ���|�\�@�@��،� p.56�`67
����ɂ݂��R�̉́@�@���{�M�v p.68�`85 |
�U���A�u�������_ 87(6)(1023)�v���u�������_�V�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/3365839
|
����ʼn��12�l(�͚q)
���̏���(�x�]�O�Y)
<�ʐ^>���郈�[���b�p / �e��N�j
�s�ݏؖ�(������G) / �����Ɩ�
�����̌��t/p37~37
��������/p38~45
��s"�y�n����"�̂��炭��/p38�`39
�\�A�O���̑A�W�A��U��/p40�`41
�L�҃N���u�͂���ł悢�̂�/p42�`43
����钩�N�Ñ㌤���̎p��/p44�`45
�l�������_ /�O�ؕ��v;�啽���F;���c��;���c�ؐi/p46~53
5��15���E����̌o�� / �v��//���F/p54�`63
���Ƌ@���Ɓu���R�ȏ�ʁv / ����//�K��/p64�`78
���n�ҏW ���W ����̎v�z�ƕ���/p80�`239
���{���ƂƂȂ����������Ȃ��� /
�@�@�� ���{�b�� ;�V�얾 ;�얞�M��/p80~89
���O�_--�A�W�A�I�����u���̖͍� / �얞�M��/p90�`106
�����������牫�ꏈ���� / �䕔���j/p107�`119
�����㐭���̍\�} / ���@��//�E/p120�`127
�Ӌ��_--����̓��Ȃ鍷�� / �V��//����/p128�`137
�u�̎v�z�v�Ƃ͉��� / �㌴//���j/p138�`146
�×����̏@���Ɛ��� / �^�ߍ�//��/p147�`161
|
�����p���̘_�� / �r�{//����/p162�`173
����E�����E���E / �V��//�i/p174~181
������̉��ꕶ���_ / ���//���v/p182�`189
�k���l������ / ���c���M/p190~191
��㉫��̕��w / ���{//�b��/p192�`209
�����ƖL���̌��v�z / ���A�ɗY/p210�`220
����̉���--�ى��Ɠ����̑��� / �����F��/p221�`230
����̌|�\--���O�|�\�̍Č��� / ���ꂢ/������/p231�`239
���ۑS�̍��ۋ��͉͂\�� / ����//�ߕv/p240�`251
�Ôn�̂��Ă��݂ƃ^�C���� / ��//��/p252�`260
�����̎��p(�l�p�[��) / �c�����\
���n / ���ѐV��
�Ē���k�������̊�@ / ��X��/p273�`286
�j�N�\�����ɂ�����l���̌��� / ����ѓ�Y/p287�`297
�I���v���}��̃��b�Z�����m / �a�c�t��/p298�`311
������퐶���ᔻ / ��//��/p312�`335
���Ɛ�[�N�� / �M��//����/p338~343
��[�N���Ƌ��Ɉ�̎���͋����� /
�@�@���T�C�f���X�e�b�J�[//E.G. ;����//�O�Y/p344~347
�x������Ƃ������� / ����D�v/p348�`349
��
�E |
�V���A���a�c�^�~���A�������G���ҏW�ψ���ҁu�A�������G�� = The journal of Japanese botany 47(7) p.203-203�@�c�����v�Ɂu�g�E���^�̉����i(�G�^)�v�\����B
�V���A�O�D���E�q�쐴�����{�n�k�w��ҁu�n�k = Zisin : journal of the Seismological Society of Japan 25(1) p.33�`43�v�Ɂu1771�N4��24���̑�Ôg�ɂ���-2-�v�\����B�@J-STAGE�@�@�d�v
�V���A�q�쐴���u�V���d�R���j�v���u�q�쐴�i����o�Łj�v���犧�s����B�@
�@pid/9769257�@�@�����G�����s�������}���ف@���ꌧ���}����
|
���d�R�Q���n�}
�����E���d�R�̗��j�T��/1
�}��/8
�ڎ�/9
����/21
���� ����/23
��A�Q���̈ʒu�Ɠ��וʏ���/23
��A�Q���̒n�j/26
�O�A���d�R�̓��̖�/27
�l�A���d�R�̐l��/34
���� ��/48
��A��̂̏K��/48
��A�H�l�������j/51
�O�A���d�R�𒆐S�Ƃ�����k�������j/54
�l�A�쓇�l�̓���/74
��O�� ����/75
��A��a��i������j�̈��/75
��A�{�ÁE���d�R�̒��R����/78
�O�A�m���ƕ���/79
�l�A���N�Y�����̔��d�R�����L/84
�܁A�Q�Y��������/94
�Z�A�I���P�ԖI��������/111
���A���NJԁE�^�ߍ��������/123
��l�� �ߐ�/132
��A�����̑n��/132
��A���ю��ƌ�����/143
�O�A�L���X�g���̓`���Ɩ@��/147
�l�A���X�̑n��/151
�܁A�l����/169
�Z�A�������{�̔��d�R�J��j/189 |
���A�ΔԂނ�/196
���A�{�Nj��̉ˋ�/197
��A�Ì��̐����������C��/198
��Z�A�����̓`��/198
���A�ƕ��̕ҏC/206
���A�K���̉��P/207
��O�A�o�˂ƕx��ω���/209
��l�A�{�ÁA���d�R�Ɉ�t�h��/209
��܁A���D�̋Z�p/210
��Z�A���d�R�̖��a��Ôg/211
�ꎵ�A��ψًL/225
�ꔪ�A���d�R���̋Q�[�E�u�/231
���A���N�䕗/231
��� �ߑ�/234
��A�p�˒u���Ɠ����̔��d�R�̎Љ�/234
��A�p�ˌ�̍s�����@�ւ̐V�݁A���p/240
�O�A����̐���/244
�l�A�{�ÁE���d�R�������/250
�܁A�����Ƃ̖u��/252
�Z�A���ЁE��s�̐i�o/254
���A�y�n��������/256
���A���d�R�x���̉��v�i��O�j/262
��A�������p����/266
��Z�A�p�ˌ�̔��d�R�J��/276
���A���d�R�̒n�������������ɊJ���j/281
���A���d�R���Y�Ƃ̋��S/292
��O�A�R�����̗��s/311
��l�A��s�@�̔�/313
��܁A���d�R�S�����v�z����/314
��Z�A�n���������x�̐���/314 |
�ꎵ�A�i���������{�R����/323
�ꔪ�A��p�ւ̑a�J/326
���A��^�e�̏��u/329
��Z�A�I��Ɛl�I�E���I��Q�̏�/331
���A�����m�푈���̓���/334
���A���d�R�̃}�����A�i��O�j/346
��Z�� ����/353
��A���d�R�������{�̔���/353
��A���d�R�x���̉��v�i���j/355
�O�A���d�R�̃}�����A�i���j/358
�l�A���[�f�[����/365
�܁A�n���������x�̐��ځi���j/365
�Z�A����̐��ځi���j/376
���A�Ί_����Ǝ���/388
���A���d�R�̓���/390
��A���d�R�̊J��j�i���j/404
��Z ���d�R�̃p�C���Y��/414
���A�Ί_�s�㐅������/424
���A�Ί_�`�p���ݎ���/432
��O�A�d�C����/439
��l�A�V����L���ʖ�������/444
��܁A�Ί_�s�E��l���̍���/447
��Z�A���d�R�̐��}/450
�ꎵ�A��t��/459
�ꔪ�A�����E���Ղ̗��j/466
���A����̎{�����ԊҖ��/474
���d�R���j�N�\/485
����/504
�Q�l����/518
���Ƃ���/520 |
�V���A���c�M�v�ҁu����5����10���� : ���{���A���}��������̐l�X68�l�̓��L�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B
�@�@pid/9769193�@�@�d�v
|
�͂��߂�
��ꕔ �s���ƍ����Ɠ{��
���{�͂ق�Ƃ��ɑc���Ȃ̂� ����ԏ\���a�@�E�Ō�w �X�c���q�q/11
���t�E�����Ɠ��� ��w �O�ԕĎq/18
���X���������a�ŖL���ȓ��� �N���u�o�c �㌴����q/27
�����I����I� ��� ����F/31
���}�g���ɑ���x���S �O�����o�c �����F�}/44
�������Ȃ�����Ɨ����Ȃ�� ���e�t �V��m�q/48
���͓��{�l���D���Ă͂��Ȃ� �z�e���E�t�����g ��F���q�q/51
�S�[�C���O�E�}�C�E�E�F�C �R�s�C�E�T�[�r�X �쑺��/53
���̊ۂ̔����ŕ��A�L�O ���w�̎� ���NJ_�c�q/56
�����̊k�̒�����o�悤 �S�ݓX�E�؎蔄�� �����m�q/57
�܂�Ő푈�O�̊�@�� �^�a�u���Z���@ ��u���N�q/60
�N���オ�푈�̉̂ɕ����� ������ ��È�Y/63
��� �����̍��ɋA�����Ӗ�
���ċ����̉���Ǘ���� ����^�C���X�E�L�� ���g�i�[/71
�\�t�g�������� ���ꌧ�����ꎑ���ҏW�����E��� ��闧�T/80
���傰���������߂ĕl�㗤 ����e���r�Ґ��� �{�ǖM�v/95
���������}�����Ȃ�ސw�v���H �{�Õ������� �K�n����/100
�V���b�N�̐ςݏd�� �R�U�s�����E�����U���� �^�ߔe���O/107
�����Ȃ�����Ă�����j ������ ���h�q/110
�j�����̂��R�c������̂� �^�N�V�[�^�]�� ���a�c���P/113
�K����E������E�f�� ���ꍑ�ۑ�w�E�w�� �ԏ�ʑ�/117
���{�ň�p�[�Z���g�̉����� �J���ȕw�l���N�� �ɔg�\�q/120
��O�� �h������~�ւ̇��l�グ���ւ臁
���̂���҂����������c�� �R�U�g���E���w ������]/127
����ƃ��}�g���`���[�̊Ԃ� ��� ���ؗ��O/129
�C�m���\��n�̂��钬�� �{������ ��������/138
���A�ŏ��Ȃ��Ȃ�_�n ����s�E�_�� ��Ð���/140
��c�Ɖ��ڂɒǂ��� �ߔe�s�� ���ǗǏ�/143
���J�̓�������Ă��� ���w�Z���@ �ʏ钩�q/145
|
���l������������ ���w�Z���@ ���c���q/150
��l�����߂Ȃ�q�ǂ������ł� ���w�Z�Z�N ��Ñ��q/151
�搶��w���������Ȃ��� ���w�Z�Z�N ���ЂƂ�/153
�����l�ԂȂ̂ɂǂ����āH ���w�Z�Z�N �������/154
����̐��C�A������܂ł� ���w�Z�Z�N �{���/155
�N�̂��߂ɕ��A����̂� ���Z�� �X������/156
�����Ό��̊��������͂��߂� �x�@�� ������j/157
�����m�������Ȃ� �N���u�E�z�X�e�X �I���X�[�W�[/162
�\�ܓ��ɍ���w�ւ����炤 �S�ݓX�X�� ���ǂ₷��/163
���n�̐l�͂���������Ȃ� �o�[�E�z�X�e�X �n���R���q/166
�c�����A�̓��ɍ~��J ���E �q�`�a�q/168
�h���̕������ɂ͐e���߂� �i���X�E�E�F�C�g���X ���ܖ��q/169
�����싅�c���}�I ������ �ԗ䏇�q/172
�݂Ȃ����m���L��W�Ƃ��� ���ꌧ�m�������L��W ���NjT�V��/173
�������{��Ȃ��牫�ꌧ�m���� ���ꌧ�m�� ���ǒ��c/179
��l�� ���ꏈ���̌���
�����b�ɂȂ�܂��u�~�v���� �N���u�E�z�X�e�X ���������q/187
������������肫�ꂢ�ȋC�� ���W�I����� ���[��/189
��H�ɗ���O�^�� ����^�C���X�E�L�� �ʏ�^�K/193
���������s�҇��ӂ��� ����c�[���X�g ���c���L/201
���Ƃ͂Ȃ��ɔ�ꂽ���X ����ԏ\���a�@�� ��Î�/203
�����͐H�����̂Ȃ̂� ���d�R�����V�� ������/206
���͂Ƃ��Ă̕ꍑ������ ���ꌧ���d�R�x�� ���R�P��/214
�Ă�Ă������ƁA�Ƃ܂ǂ��� �R�U�d�d���� �I���n��/223
�L�l�O�\�Z���̕��A �J�����}�� �g���U/224
�m�b�g�E�M���e�B �ٌ�m �}�[�N�E�A���X�^�[�_��/232
���ԋL�O�� �ČR���m RB�E�z�r�b�g/236
��Ȃ����{ �����V��В� �r�{��G��/240
�����\���N�̗��j/250
���Ƃ���/254
�E |
�W���A�O�Ԏ�P, �V���K���ҁu�{�Ó��̐_�́v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@pid/12502770
�@�@349p �@�@�����F��㊌����}���فF1004043624
|
�܂����� �O�� ��P�^��
�떓�̗̉w(�j�[�� �@�s���[�V �@�t�T �@���x �@�A�[�O �@�N�C�`���[ �@�g�[�K�j)
�r�ԓ��̗̉w
(�_�� �@���A�[�O �@�M�����A�[�O �@�N�C�`���[ �@�^�E�K�j�A�[�O �@������ �@�����̕��� ��)
���(�{�Ó��̗̉w)
���Ƃ��� �O�� ��P�^�� �E |
�W���A�}�����[�ҁu���ꐶ�� (�ʍ� 251)�@����̂��Ƃƕ���(���W�j�v���u�}�����[�v���犧�s�����B
|
�����E����̕��| (����̂��Ƃƕ���(���W)) p.38�`67,74�`91
�������w�Ɍ���u�Ñ�v �v�� ���� p.38�`45
�u������v�ɂ��� �ʏ� ���� p.46�`55
����̗��� ���� ���� p.56�`61 |
�g�x�G�� ��� �� p.62�`67
�{�Ó��̗̉w �� ���~ p.74�`81,55
���d�R�̗w--���̂Ƃ��̉���@ �{�� ���F p.82�`91
�E |
�W���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (5)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����B�@�@pid/7931785�@�@�d�v
|
���i�Ǖ��������w�p�����ɂ���--
�@�@���t1971�N�x���������� / ���V�a�r/p1�`8
���i�Ǖ����̐A�� / ���ƍD/p9�`75
���i�Ǖ����̍��� / �v�ۖM��/p76�`93
���i�Ǖ����̏W���ϗe�̒n���w�I���� / ��،�/p94�`108
���i�Ǖ��̌o�� / �����ǐ�/p109�`121
�m�\�Ƒn����--�n�捷�𒆐S�Ƃ���(����1) / �Ð�`�a/p122�`138
�a�����̎Љ�̈�ɂ��� / �R���F��/p139�`145
|
���i�Ǖ����̂��ׂ���--
�@�@�����K�̖��𒆐S�Ƃ��� / ���c���q ;�X�L�x/p146~167
���i�Ǖ����̖��� / ���c�m�q/p168�`192
����{�̕����ɂ���--�쓇�����ҔN���_ / ���V�a�r/p1�`14
�ɒn�m�ψ��ƌI���M�[--���ƕ����̏Љ� / �O�ؖ�/p15�`28
���i�Ǖ����ɂ�����n���_�b�Ɠ������V / �R���ӈ�/p29�`48
���i�Ǖ����̖����s�� / ����q��/p50�`67
�E |
�W���A���{�N�ٌ��v���ƕ� �ҁu�����|�\ (49)�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/4418381
|
���y���q���ݍΊy / �{�c����/p10�`14
�������Ԃ������u�������v�l / �R�H����/p15�`24
��㊂̖����ƌ|�\ / ���c�^��/p25�`34
�_�ˎs�{����Ԃ̉��� / �������Y/p35�`41
�}�������|�\����(��) / �{��������/p42�`43
���䓇�n���̍Վ��F?�`��(��) / ���R���D/p44�`50
��������F���̉J��x�� / �w�l�i/p51�`51 |
���q�c�y�̐_�̔�r�l(��) / �{���^�j/p52�`56
�����n���_�y�����̖K�L / �R�H����/p57�`65
�����|�\�w��E�F�̉�j���[�X/p24�`24
���ЏЉ� / �֓��^��/p66~68
�����Z�M/p70~70
������k/p71~71
�ҏW��L/p72~72 |
�X���A�����Y�p�{��ҁu�����Y�p = Ars buddhica (�ʍ� 88)�@����̕����Ɣ��p���W���v���u�����V���o�Łv���犧�s�����B�@�@pid/7925689
|
��㊂̗��j / �V���~�K��/p3~16
��㊕����j / ��Ït��/p17~26
��㊂̏@�� / �����Y/p27~38
������\�� / �O�Ԏ�P/p39~56
��㊂̞����Ƌ��Ε� / �O�Ԑ��K/p57�`65
�������� / ���c��/p66~76
��㊂̓��|�j / �R���i�g/p77~85
�����g�^ / ���q�F���Y/p86~97
��㊂̕��x�Ɗy�� / ����^����/p98�`107
�����̌��z / �c�ӑ�/p108~125
��㊕��������������̕������� / �ې��v/p126�`133
�k���G����l �u���ǕM�u�G�}�v / �^�ۋ�/p134�`135
��㊂̏d�v������ //p135~138 |
�ߊ��̔��p�� //p138~141
���ҏW��L �����\�� //p142~142
�t�^ ��㊌��n�} //p143~143
�\�� ���F�� �}�~���ԊG�q(��㊌������p�ّ�)
���G ���F�� ���F�n�g�^���}�������O�������i�e�ԕ��ؖȏ�ߗ��n�E
�@�@�����F�n�g�^���}�������O�e�Ԕ��A���啶�ؖȒn��ߗ��n(���q�F���Y��)�C
�@�@�����O�����Z�p�H��(�T���g���[���p�ّ�)
���G �P�F�� �u�G�}�v�u���ǕM(��q�������c��)�C�o��������~�C
�����b�䔓�G�C(�ȏ�T���g���[���p�ّ�)�C
���F�n�g�^�_���P������z�ߋy�ѓ��}��(���Ƌ���)�C
������������y�ѐ�ୁC���䉮����ԐΖ�C�V�����E�ٍ��V���C
���~�o���������C�ʗˁC���{�Ǔa��
�E |
|
���ҏW��L�i�S���j�^����̖{�y���A���L�O���āA�u����̕����Ɣ��p�v�ɂ��ĔF����V���ɂ��邱�Ƃ́A�����_�ɂ��������ꍑ���̋��ʂ�������ł���A�~���ł����낤�B���̂��сA����̕�������g�������Ď�藧�ĂĂ���ꂽ�n���̏���w�ɁA�{�y�̉��ꌤ���҂������āA���n�̑�\�I������Y��H�|�Z�p�A�����|�\���L���Љ�邱�Ƃ��Ƃ�S������ł�܂Ȃ��B�^���̉���͍������ɂƂ��Č���ɐ₷��h�_�����߁A�����̌������╶����Y�������ɂ��������B���n��K���l�͍�����̂悤�ɐ푈�̔ߎS�����v���m�炳���B�������Ȃ���A�W�҂̔M�ӂƓw�͂̂��������āA�����̉�͗͋����炿�A�ŋ߂͉ߋ��̕�����Y�ɑ��镜�����Ƃ��}���ɐi�߂��Ă���B�܂��A�����K���l�X�́A����݂Ȃ��`������Ă����H�|�Z�p�▯�����x�ɐ[���������o����̂ł���B�^��������ꂪ�����ʂŏ����̉���ɖ]�ނ��̂́A���P�����z�̂��Ɠ썑���L�̍��ɂ̋�Ƃ����������X��ʂ̊C��w�i�ɂ��Ĕ������l�Ԑ��ɂ͂����܂�Ă���������L�̕����Ɣ��p���A���A�ɔ����e��̊J�����Ƃɂ���ĕώ����r�p���邱�ƂȂ��A���̔��������R�Ƃ��ǂ��˂ɂ����܂����A�����₩�ɕی�琬����čs�����ƁA���̂��ƈȊO�ɂ͂Ȃ��̂ł���B�i�_�c���j |
�X���A�������悢����,��������G�A���a�c�^�~�F����u����̖閾���v���u���y�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@ (���{���@����S�W ; 13)�@�@203p(�}��) �@�@�����F���䌧���}���فF1020026868�@�@�@�@ �����F��㊌����}���فF1002235750
|
�݂Ȃ����
���̔����ۂ̌�
�����ڂɗ�������ނ����̐l
������������! |
�ꖜ����N�O�̍�������
��������������
�Ȃ����Ђ߂�������
�_���܂��V���炨��Ă�����
|
����Ɏc���ꂽ�L��
�ߌ��̓�\���x��
�L�ւ̂��ǂ�����̓�
����̐�j���� ���a�c �^�~�� |
�X���A�����Ɩ����u�A�T�q�J���� = Photograpy journal Asahicamera 57(10)(477) p121�`142�@�����V���Ёv�Ɂu�I�L�i���E��Ă̂Ƃ��v�\����Bpid/7969671
�X���A�ɔg��N���u���ꕗ�����W�v���u�O�h�Ёv���犧�s����B�@�@�@�@�P�P�O�O�~
�@�@�@158p �@�@�����F���ꌧ���}���فF1006831273
�P�O���A�q���P�u�G�R�m�~�X�g 50(46) p.56�`61�@�����V���o�Łv�Ɂu����̌Ñ�ƌ���--���X�̗��j������v�\����B
�P�P���A�q���P�u���� 24(12) p.56�`61�v�Ɂu�n����߂ƌR�p�n�_����(���ꂩ��̕�-4-)�v�\����B
|
�q���P���� 24(9)�`12)�ɔ��\�����u���ꂩ��̕�1�`4�v���̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
24(9) p.50�`56 |
1972-08 |
�v�ē��́u�R�̕����v(���ꂩ��̕�) |
. |
| 2 |
24(10) p.43�`48 |
1972-09 |
�����̂ӂ��������Ƃ������� (���ꂩ��̕�-2-) |
. |
| 3 |
24(11) p.40�`46 |
1972-10 |
�ɍ]����K�˂�(���ꂩ��̕�-3-) |
. |
| 4 |
24(12) p.56�`61 |
1972-11 |
�y�n����߂ƌR�p�n�_����(���ꂩ��̕�-4-) |
. |
|
�P�Q���A�M�����Ǖ����u�����Ƒܒ���l : ���������Ƃ��̍s�Ձv���u���@�ю��v���犧�s����B�@�@��3��
�P�Q���A�q���P���j�Ȋw���c��ҁu���j�]�_ = Historical journal (�ʍ� 271) p.126�`137���j�Ȋw���c��v�Ɂu����̗��j�̗�--���{�Ñ�j�̌��_�Ƃ��Ẳ���Ñ�j�v�\����B
���A���̔N�A�u���ꕶ���_�p ��1���v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9769588
|
�}��
�V���b�� ��� / 1
����
���钩�i ��㊌����j / 50
���鐳�� ������s�u��㊗��j�v�����̌���Ɩ��_ / 81
�c�`���� ��㊒n��j�����ɂ����鎞��敪 / 106
��j�i�l��
�������� �j�O����̉�� / 126
�������G �l�Êw�̏����Ƃ��̌��� / 131
��i�����j
�c���r�Y ��㊂̌Ñ㕶���Ɖ�㊕����̍l���� / 150
�ɔg���Q �����a���l / 175
���K�����Y �w���g�^�x��ʂ��Č����\�Z���I���t�̉�� / 188
�{���h�P �����×��ɓy�n���ʖ@ / 201
�ߐ�
�^�������� ��㊂̏C�j�Ɓw���z�x�̕Ҏ[�ɂ��� / 212 |
�����[���� �w���R���Ӂx�ɂ��� / 222
�����P�� ���Ði���̗��j�I�Ӌ`�ƕ]�� / 234
�R�{�O�� �ߐ���㊎j�̏���� / 266
�n���^�� �������l / 295
�c�`���� �ߐ������̉�㊔_���ɂ��Ă̈�l�@ / 324
��Ït�� ��㊂ɂ����閾�������́u���ւ�v / 355
�{������ �u�{�ÎZ�@�v�ɏA���� / 361
�ߑ�
�ɔg���Q ���������͈��̓z������ / 376
�����O�Y �����ˏ������̍l�@ / 380
���R�Ύ� �������N�̗������ / 411
��㐴 ���������Ƃ��̌� / 421
�����y�m�j �u���������v�_ / 441
���鐳�� ��p�����i�ꔪ����`���l�N�j�ɂ��Ă̈�l�@ / 454
���鐳�� �u���������v�Ɩ�������̖�� / 478
�����ژ^ / 513 |
���A���̔N�A�u���ꌧ�j ��22�� (�e�_�� 10 ���� 1)�v���u�������{�v���犧�s�����B�@pid/3017289
|
�����̂��Ƃ� �s����ȁ@���ǒ��c
���́@�����@�����Y
�� �C��̓��\������/P3
��@�����ʖ�����/p8
�O�@���{�����̌Ñ��ۑ��n��/p11
�l�@�����̖����̉e���Ƃ��̎�e/p21
�܁@��㊂̕��y�E���j�Ɩ���/p28
���́@���Ɛ����@������G
���߁@���̕���/p52
���߁@�����S����/p55
��O�߁@���̗��n�ƕ��z/p61
��l�߁@���Ǝ��R�I�ЊQ/p66
��ܐ߁@���̍\��/p75
��Z�߁@�ƂƖ咆/p95
�掵�߁@���̌`��/p104
�攪�߁@���摺��/p108 |
���߁@���Ɛ�/p111
��\�߁@���̓���/p116
��\��߁@���݉������s/p120
��O�́@�߁E�H�E�Z�@���~�ߎ��@���g�^�O
���߁@��/p127
��O�߁@�H��/p178
��O�� �Z(�Z�����z)/p240
��l�́@���Ɓ@���_���Y
���߁@�_�ы�/p301
���߁@����/p381
��O�߁@�����̏���/p413
��́@�ꐶ�̋V��@�����Y�@���Ð^�鏟
���߁@�Y��/p471
���߁@��N�E�N�j/p503
��O�߁@����/p518
��l�߁@����/p567 |
��ܐ߁@�搧/p654
��Z�́@���ԐM�@�`��������
���߁@�_�ϔO/p703
���߁@�썰�ϔO�̍l�@/p731
��O�߁@���J�ƍ��J�W�c/p753
��l�߁@���J�ҒB/p799
��ܐ߁@�d���A�ߕ��A�֊�/p820
�掵�́@���ԗÖ@�@���a�c�^�~
���߁@��p�I�Ö@/p845
���߁@���ԗÖ@/p867
�攪�́@�����@���_���Y
���߁@�����̖���/p905
���߁@�n��/p909
���ꌧ�j ��22�� (�e�_�� 10 ���� 1)
�E
�E |
���A���̔N�A�c�S������u�c�A�����̌����v���u�O��䏑�X�v���犧�s����B�@�@pid/12501365
|
�_�l��
�c�A�����̗w�̐���(�ዽ�ДV�i)
�c�A�����̕��|(�^�珹�O)
�c�A�����̃I���R�ƃI���V(���V�㑁�c)
�c�A�����̎����_(�c������)
�c�A�����̖���(�����O��v) |
�c�A�����̓`�����Ƒg�D(�n�ӏ���)
�c�A�����̉��y(���c�����q)
���|�Ό��n�̓c�A�{�Ɠc�A����(�F�v����)
�c�A�����Ɣ���E�����n�c�A�̂Ƃ̊W-
�@�@�����͂̌^�Ԃ̖ʂ���(�|�{�G�v)
�c�A�����Z���{��(�R���m��Y) |
�c�A����������(�R���m��Y)
�����n���̓c�A��-�L������
�@�@�����S��(���)(�L���������|������)
�c�A�̌����p����(�c�S������)
�c�A���������������ژ^(�n�ӏ���)
�E |
���A���̔N�A��_���O�Y���u�������b : ���̊����鉫��̕��y�L�v���u���ꕶ���o�Łv���犧�s����B�@pid/9769278
|
���E����
��������ɂ��ā\���d�̒��H��y�X�Ɓ\/1
�썑�̕����\���M�т̎��R�E�\/6
���G���̉ƕ��\�̐X�E�g���Ɓ\/15
�����͗��{�\�C��E�{�a�E���P�\/18
����̂��Ƃ\�ߋ��̓��{��\/21
�A���s�\���̏��̗[��\/36
����l�̑c��\��a�����̗��\/42
�����x�̎O�p�W�\�����̗��j�\/51
����̏K���\���Ɠ����_�E�ق�_�\/77
�ߔe�̍`�s�\������̓s�s�\/90
�̋��s�\���S���̐Ձ\/96
�K�����x�̖��c�\�i���ƕێ�\/106
��������f���ց\�f���̊쌀�ߌ��\/112
�ߋ�ƈ������\����̔N���s���\/122
�썑�̎�����\��y�̂��܂��܁\/127
�������ƍ������\���ʂ̐e�q�\/136
�썑�̃s���O�����\�H����𗷂��痷�ց\/140
����̌Ð_���\�������q�̐_�E�\/150 |
�n���̉ʂ܂Ł\�C���j���̈ӋC�\/158
�v�w�ʎY���\�����l�̉ƒ�\/163
�v�����̕��K�\�̂����Ɍ���\/170
�썑��̂قƂ�\�Ï��̗R���\/176
�э��ւƃ}���O�[�X�\�����ɐ����E���ۂɎ��s�\/180
�{�Ó��̒f�Ё\�`���Ɨ��j�\/192
��n�̗��\�n�̂悤�ȋ{�Ôn�\/200
�Ӊ��̋L�O��\�h�C�c�c��̔����\/206
���l�S�E���̏r���\�Ǔ��ɓƂ�₵���\/210
���d�R�̐Ί_�`�\�̓��E�����̕l�\/214
�������̐��ҁ\���쎢���\/219
�q���M�̗с\�����̐X�с\/224
�|�x���K��̋L�\�Ɖ��̌Ǔ��E�͔͂̑��\/229
���R�̎c�s�\���d�R�̉ߋ��\/236
�Ǔ��̕����\�^�ߍ����̋L�W�����\/246
�G�͌���\����ܗE�m�\/261
�����A����\��`�ۂ̊ۑ����\/268
����N�N������/274
�����ۋL/284 |
|
| 1973 |
48 |
�E |
�P���A�|�\�w��ҁu�|�\ 15(1)(167)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276362
|
�����̂��Ƃ��������ꇁ�ɂ̂��ޣ //p7�`7
��狋�N���l-28-���c�ꑼ�l��e��g�����ࣂ��߂�����-6- / ������Y/8�`14
�܌��M�v�̎蒟-4- / ����O�F/15�`21
狋�Z�̂̕��y--���-1- / �����_/22�`31
�̕��ꉹ�y�W��-72- / �n���h���q��/32�`35
�A�[���X���[���̉ԍՂ�(�I�����_)<�ʐ^�ƕ�> / �F����o�j/p36�`37
�|�\�W�] //p38~39
�O�����Y������{�����|�\�T�_� / �R���o�M�v/p40�`40
�k�쒉�F����c�͍Z��������W� / ���}�����q/p41�`42
���������Y�Ң�\�Ƌ����̐��E��\5�l�̐l�ԍ���ɂ��� / �R�H����/p42�`43
�q�c������c���j� / �����y��Y/p44�`45
�ߑ㕶�w�]�_��n9������_� / ���c�m/p45�`46
�����Z�g������{���w���T� / ����K��Y/p46�`47 |
�����N�\(11��16���`12��31��) / �|�\ �w��/48�`55
���x�N�\(���a47�N������) / �@���q/62�`65
���a�l�\���N�x�|�p�Ց�ܥ���D�G�ܥ
�@�@���I�l�R���o�� //p66�`74
���������Ɏ�ނ�������\��� / ��،�/p56�`56
���x��|�p�Ղ̐��ʣ / �m�����Õv/p57�`57
�f�梃`���b�v�����f��̑�q�b�g� / ���Njv�l�Y/p58�`58
�\���������������ϋq�m-���� //p59�`59
�m���72�N�����������i�Q� / �����/p60�`60
������(2�E3) //p75~77
�̔\���� //p61~61
�V�����ē� //p81~81
�E |
�Q���A���|�t�H�ҁu�T�����t 15(5)(711)�v���u���|�t�H�v���犧�s�����B�@pid/3375473
|
�Z��Q��--�i�Z���"�K��Βk"--�Q�X�g / ����r��/66�`70
����̋ꂵ���� "�їV��"�̊y������ //66�`
�q�����r |
�R���A�������C���u��㊐؎�̂ӂ邳�Ɓv���u���q�o�ʼn�v���犧�s�����B
|
�����؎�͌��Â��� / ���R���� [���M]
���E�Ɖ�㊂��Ȃ��������؎� / ��R���` [���M]
�؎�f�U�C���ɂ��Ă̎v���o / �ɍ���V [���M]
�E�`�i�[���`���̕��g"�V��" / ���R�ǖ� [���M]
���̂ʂ����� ��㊂̓���E���� / �D�z�`�� [���M]
�Ӊԏ������ׂ荞�܂��� : �̐l�V���[�Y�̐l���I��� / ��闧�T [���M]
�V���Ȃ鉫㊕����̖��i�� / ���g������ [���M]
�C���N�ŕ`�����ŏ��̗����؎� / ��ÏG���Y [���M]
���s����Ȃ�����"�؎�" / ��䏸 [���M]
��㊂̐��j����� / �^�h��E [���M]
�����������Ȃ��Ȑ؎肽�� / �������� [���M] |
��㊂̎��R�ɐ�����V�R�L�O������ / ���ǓS�v [���M]
�T���S�ʂ̊C�ɗ�������M�ы� / ��u���@�O [���M]
�o�ꂵ�����˂��������Ԃ��� / �������� [���M]
�Ԃ̂��问���؎�ɂ悹�� / �V�萷�q [���M]
�F�N�₩�ȉ�㊂̖����s�� / �N�㌳�Y [���M]
�Õ������Ƃ��̓`���Ȃ� / �X�ۉh���Y [���M]
��㊂̋��Ɩ{���T�[�� / ���䏫�^ [���M]
��㊂̈̐l ��ƋX�p���� / ���q�K�� [���M]
�؎�̂Ȃ��̉�㊕��x�Ƒg�x (���݂��ǂ���) / ���Ԉ�Y [���M]
��㊐��j�Ɛ܁X�̐؎� / �ɐ����� [���M]
�E |
�R���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.3�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�d�v
�@�@�@31p�@�����F���ꌧ���}���فF1003064001
|
�}�� (����̕搧 �O�V�N�o�y������)
����ɂ�����^�ϐ��l�ވ�Ղ̒��� �n�� ���o
������Տo�y�̖ؒY�E�L�̃J�[�{������ꗗ�\ �����Ȃ�o�ŕҏW��
�n���w�I�Ɍ�������̓����Ƃ��̑͐ϕ� �y ����
�ِl�̌�������l�Êw Richard J.Pearson |
����̕搧 ���Ð^ �X��
�āu�O�X�N�v�l ���� ��G
�ߔe�s�䂤�ȑ�(1972�N12��14��)
�@�@���ɂ�����W��ƒǍl ���� ����
�O�V�N(��)�o�y�������ɂ��� �F�� �p��Y ���� ���G |
�U���A�O�ʎЕҁu�Ô��p (41) �v���u�O�ʎЁv���犧�s�����B�@pid/6063336
|
���W�L�� �����g�^�� / ���q�F���Y/p17�`26
���W�L�� ����̐S�ƍg�^ / �O�Ԑ��K/p27�`32
���W�L�� �g�^�T�_ / �ҍ���㑾�Y/p45�`56
���W�L�� �����̍g�^ / �x�R�O��/p57�`59
�g�^����H���k�ʐ^�\���l/58�`59
�V�J�S���p�ق̕����G/60�`72
���W�L�� �V�J�S���p�ق̕����G �o�b�L���K���E
�@�@���R���N�V�����̗��j / �h�i���h�E�W�F���L���Y/p60�`63
���W�L�� ���������G�ʼn�ɂ��� / �⍲�^/p64�`72
���i�ӏ� �y���V�A�E�F�≻�؎q�K���X�̓��`��/�O�㎟�j/p79�`80
���i�ӏ� �ԉԉʕ��։Ԕ� / ���J���y��/p81�`82
���i�ӏ� �`���]�ˌ[�M�]�㐴�V�} / ����O/p87�`88
���i�ӏ� �r���M�w�ېϐ��} / ��ؐi/p89�`90
���i�ӏ� �`�⍲���ȕM�̐�}���� / ���@�d/p93�`94
�V�����Љ� ���[�̈����������� / �㌴����/p103�`105
�V�����Љ� 腙֓��ޙ֒����ɂ��� / �^��r��/p106�`108
�V�����Љ� �]����M�V���Q��} / �]���M��/p115�`117
�V�����Љ� �t���_�ЎЌi�}�ɂ���/�u���[�X�E�_�[�����O/p121�`128
�V�����Љ� ���ؐl�����a���o�y
�@�@�������W(����) //p130�`133
������k �������p�W �͂ɂ���ʓW / �_�R�o ;�]��a�F/p134~135
������k �_�쎛����W �@�،o�̔��p / �O�R�i ;�{���j/p136~136
���p�ُЉ� ��t�����㑍�����ق�
�@�@������ˈ╨�ۑ��� / �i��M��/p138�`139
�{�̏Љ� �����̔� �n�ӎn����lj� / �ҏW�� ;���d�J/p140~141
�ҏW�]�L //p142~142
�\�� �g�^ ����͗l ���}�����E�e���啶 //p12�`12
�Íg�^(���W)/9�`59
���W �g�^ ��͗l �|�~�ߕ� //p9�`9 |
���W �g�O�^ ���͗l �g�t�~�� //p10�`10
���W �g�O�^ ���͗l �C���ԊL�� //p10�`10
���W �g�O�^ ��͗l ��c��O�e�� //p11�`11
���W �g�^ ����͗l ���}�����E���O�E�e���i��/p12�`12
���W �g�^ ����͗l ���}�����E�e���啶 //p12�`12
���W �g�^ ��͗l ���O�P�P�� //p13�`13
���W �g�O�^ ���͗l �~�ԕ� //p14�`14
���W �g�^ �ז͗l �g�t�~�ԕ� //p14�`14
���W ���^ ��͗l ���O������ //p15�`15
���W �g�^ �ז͗l �~�� //p16~16
���W �g�^ ���͗l �g�t�� //p16~16
���W �g�^�^�� ��͗l���n�^ //p33�`37
���W �g�^�^�� ��͗l���n�^ //p38�`41
���W �g�^�^�� ���͗l���n�^ //p42�`43
���W �g�^�^�� �O����͗l���n�^ //p44�`44
�V�J�S���p�فE�����n���G ���v�̓���(����)/p65�`65
�V�J�S���p�فE�����n���G ���v�̓���(�S�})/p66�`67
�V�J�S���p�فE�����n���G ���Ԍ����[ //p66�`67
�V�J�S���p�فE�����n���G ����ނ� //p68�`68
�V�J�S���p�فE�����n���G �ۂ̉����� //p68�`68
���i�ӏ� �y���V�A�E�F�≻�؎q�K���X�̓��`��/p75�`76
���i�ӏ� �ԉԉʕ��։Ԕ� //p77�`78
���i�ӏ� �`���]�ˌ[�M �]�㐴�V�} //p83�`84
���i�ӏ� �r���M �w�ېϐ��} //p85�`86
���i�ӏ� �`�⍲���ȕM �̐�}���� //p91�`92
�V�����Љ� ������������ //p99�`100
�V�����Љ� �t�֓��ޙ֒��� //p101�`102
�V�����Љ� �]����M �V���Q��} //p111�`114
�V�����Љ� �t���_�ЎЌi�} //p119�`120 |
�V���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (14) ���W ���ؐ� �v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@�@pid/6067668
|
���W ���ؐ� ���ؐ� / �R���/p8�`10
���W ���ؐ� ���ؐ����D�i�̓W�]--���ؐ��̂ӂ邳��/�x�R�O��/p11�`13
���W ���ؐ� ���p�n���̎������E���� / �I�R����Y/p14�`16
���W ���ؐ� �암������ / ���d�~��/p17�`18
���W ���ؐ� �g���ɂ��� / ��؍F�j/p19�`21
���W ���ؐ� �[�B���V / �ҏW��/p22�`24
���W ���ؐ� ������ / ���c���/p24�`30
���W ���ؐ� ����̐A�������ɂ��� / �O�Ԑ��K/p31�`34
���W ���ؐ� ���g�̗� / �㓡����/p34�`36
���W ���ؐ� �������Q�ƐA�������ɂ��� / ���x�F/p37�`39
|
���W ���ؐ� ����ŋ��߂钅�� / ���c�q�q/p40�`41
���W ���ؐ� ���g / �g����Y/p42�`44
���W ���ؐ� �Q�㑳����Ă� / �@�L�͎O/p45�`48
���W ���ؐ� �O�g�z��z�� / �㑺�Z�Y/p49�`50
���W ���ؐ� ���̍���--
�@�@���X�P�b�`�E�C���^�r���[/���Y���� ;�ҏW��/p51~53
���W ���ؐ� ���F�̍H��/p10~10
���W ���ؐ� ��/p21~21
���W ���ؐ� ���������ɂ���/p48�`48
���W ���ؐ� �b�̃o�X�P�b�g/p53�`54 |
�V���A�̔�Ït���̑����E�����m�[�g��e��5,900���]�Ɠ����E���ȗނȂǂ��A�v�l�̔�Éh�q�����ꌧ���}���قɊ���B�@�`�u��Ït�����Ɂv�n�܂�`
�W���A�V�铿�S���u��u���̃V�j�[�O : �Ñ�`���̍Ղ�v���u�O�c�������(�����)�v���犧�s����B�@46p, �}��7��
�W���A���ђ��Y, ���K��j���u�\�o : ���_�ƊC�̑��v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s����B�@�@pid/12168715
|
��
�@��@�����ł̓_�i
�@��@���_�`��
�@�O�@�\�o�͂₳����
�T�@�C�ɐ����閯�E���̗��j
�@��@�Ñ�[�[���ƏM
�@��@�Γ��R�M�Ɣ\�o����
�@�O�@�ߐ������̐��� |
�U�@�V�l�ƈ鋙�̑�
�@��@���������̗��j�I���i
�@��@��Ӄ����̗��j
�@�O�@�����ɂ�����Ƃ̓]��
�V�@���_�Ƌ����̍Ղ�
�@��@�L���V���E�̂���
�@��@�^�Ă̔\�o��
�@�O�@���_�Ƌ����̍Ղ� |
�@�l�@�����ƃ������u
�@�܁@�����̋֊��ƐS�ӓ`��
�W�@�ς��䂭�\�o����
�@��@�C�ɖ߂��čs�����
�@��@�\�o���[�[���ނ�������
�@�O�@���\�o���[�[��҂����̎c�郀��
�@�X�@��V�����̐����j
���Ƃ��� |
�W���A�u�n�� 18(8) �v���u�Í����@�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7893384
|
�n���̂��Ƃ� / ������`/p7~8
�k���ʊ�e�l ���ɒʂ��ʋΎ� / �y�[�^�[�E���C�X�o�[�K�[/p9�`16
�_�ƒn��̕ω�(���W)/p17~65
�_�ƒn��̕ω� ����_�Ƃ̒n��\�� / �֓����g/p17�`24
�_�ƒn��̕ω� �s�s���ɔ����_����
�@�@���n��\���ω��Ƃ��̒����@ / �ؐL�D/p25�`32
�_�ƒn��̕ω� �����{�̎R���̕ω� / ���n����/p33�`53
�_�ƒn��̕ω� �k�C���_�Ƃ̒n�搫�ƑQ�ڑ� / ���c��/p54�`66
�J�i�_�̏������Y / ����q/p66�`72
���R��h�̔j�� �k���E�̒n�����{�̒n���l / �Đ��ǖ�/p74�`75
�܂�������Ă��Ȃ����E(�Z) / ����/p76�`84
���Ă̂����I�s / ����C��/p85�`90
�Ί_�s �k���{�̒��Ƒ��l / ���c�T��/p91�`98
���d�R�Q���̖��a��Ôg / �q�쐴/p99�`109
|
�o����n �k�ǐ}�Ɣ��ǁl / �����P/p110�`111
����̒� ��Îᏼ �k�n��Y�Ƃ̒��l / �ؑ��v���q/p112�`119
�n�������S�̐��藧��(��) / ��ԎO�Y ;����E��/p120~124
�n���w�K�̖��͂�T�� �k���ރR���T���^���g�l / ���q����/p125�`131
���Ȃ��̎��ƌv���f�f���� / �n��M/p131
�n���̂����� //p132~134
���� //p139~146
�g�s�b�N�X�������� //p147~152
�b�̃A�E���E�J���g / �ےJ�r�q/p73�`73
�����̕\�� �Â��Ɏc��ߍx�̔��� / ����h��/p152�`152
�o�҂��̑� (���\�l�E���炵) / ���h����
���G ����_�ƂƓs�s��--��������k�����w���� / ����h��
���G �o����n / �����P
�E |
�@�@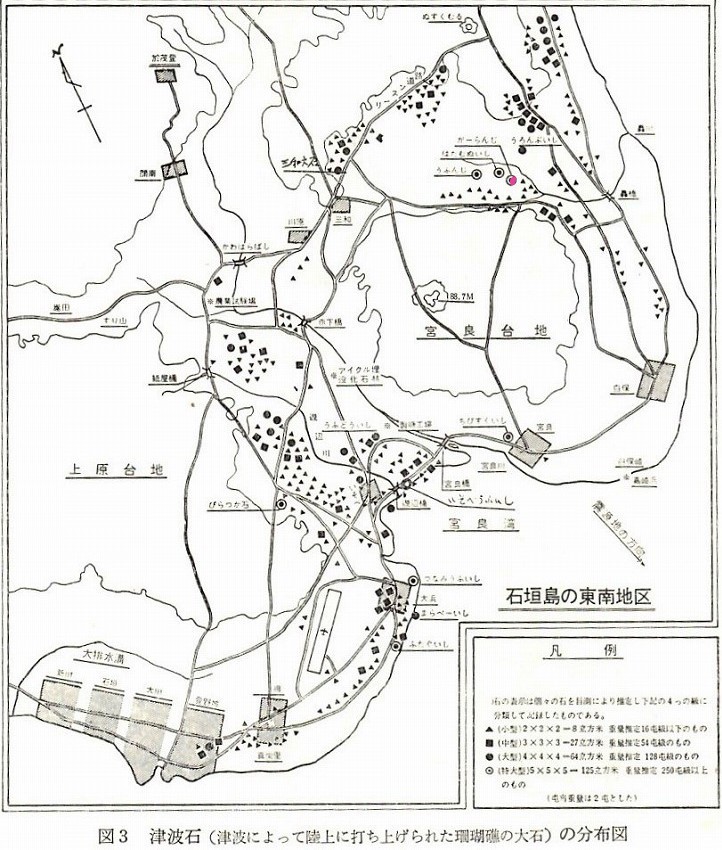
�@�@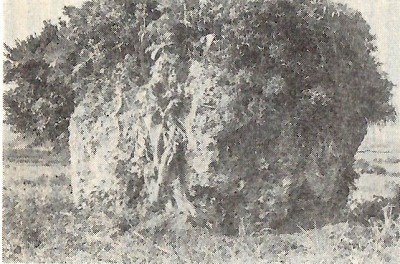
�W���A�u�Ǔ����p,���a�c�^�~,�V�铿�S,�D�z�`��,�R���i�g,���c����,���Ԉ�Y,���c���@,��F���`�Y,�^�Ӕ�,�{������,�O�Ԑ��K���u�ߔe���̂̏œ_ : ���ʎ��^ �ʐ^�ɂ݂�ߔe�̖ʉe�v���u���ꕶ���o�Łv���犧�s����B�@��3�Ł@����: ���a46�N��
�@�@�@�@���ʎ��^�F�������l�s��L�i�V�ۂR�N���̕����j�@��R��
�@�@�@�@�@���@�������l�s��L�i�V�ۂR�N���̕����j�͑�R�ł݂̂������v�@�Q�O�Q�R�E�T�E�R�P�@�ۍ�
�X���A�V�铿�S���u���j�ǖ{ 18(10)�@p138�`145�@�V�l�������Ёv�Ɂu���W���|�[�g ����ƒm��ꂴ��� ���ꐏ��̍��A�m�� �嗤�̉�����v�킹�鉫㊍ő�̏�s���A�m��̑S�e�v�\����B�@pid/7975183
�X���A��鏺�q,������q���u���{�̈�w��� (24) p.281�i�菑���j�v�Ɂu���x�̊ӏ܁E�]���Ɋւ��錤���v�\����B
�P�O���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (6)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����B�@pid/7931786
|
��E�������w�p�����ɂ��� / ���V�a�r/p1�`10
�ސ{�b��W��(�����哇�E���V���E��E��) / ���،��a��/p11�`24
��E���̕���� / ����d�N ;���V�a�r ;���c����/p25~54
��E���̐A�� / ���ƍD ;������Y/p55~114
��E����E���ԘA�̔����x�̉��y / ���c���q ;�X�L�x/p115~127
��E��ꒆ�w�Z���k�̗̑͂ɂ��� / �R���F��/p129�`146
��E���̖����s������--
�@�@���V�`�I�����E�t�����~�E���̑� / ���c���@/p147�`161
|
��E���̖��� / ���c�m�q/p163~188
�ʎR�{�_�� / ���m��/p187~201
��E���̐����`�� / ����d�N/p1�`15
��E���̓����������b�Ɠ������] / �R���ӈ�/p17�`30
��E���Ɠ��Ôː� / �O�ؖ�/p31�`50
�c�搒�q�̏���--���i�Ǖ��������E���� / �c�����u/p51�`57
�E
�E |
�P�P���A��������, ���X�؍����ҁu�쓇�̌Ñ㕶���v���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@pid/9769186
|
�V��������w�̂��߂� ��ؕ���/7
����̗��j/9
�쓇�Ñ㕶���̌n�� ��������/17
�����j���ڂ݂�/19
�^�ϐ��̓쓇/20
�쓇�̐�j�y��/23
��Ɖƒ{���̖��/29
��ՂƗ��n�n�`�E�N��/32
�{�b��E�{�b���y��̓o��/37
�����߂�����/38
�]��E��p�Ƃ̊W/41
�K�����߂�����/45
�쓇���͔_�k�����̗��� ���X�؍���/51
�͂��߂�/53
�w�C��̓��x���߂�����/54
�쓇���Ӎk�����̉���/56
��̓��X�Ƃ��̔_�k����/58 |
�o�^�����̓`���I�_�k����/61
�^���C���ƌ@�_/64
�����C���ƃ^���C��/66
�^���C���ƃA���̏Ĕ�/69
���d�R�Ɏc��A���ƃC���̕���/73
����{���̓`���I����Z�p/75
�쓇�n���͔_�k�����̓��F�Ƃ��̌n��/78
���`�ƃC���ƏƗt���ѕ�����/81
�u�V�E�C��̓��v���l����/85
���������̐������߂����� ���R���Y/89
�u�C���v�̕����^/91
���{��̒��̓쓇��I�v�f/95
�����̑Ή��W�̉���/101
��p���Z���̌���Ƃ̊W/104
���E���ꕪ���̎���/111
�j���C�J�i�C�ƃg�R���̎v�z �J�쌒��/119
����ɍs�����E/121
|
�~���Ȃ���̐��E��/126
�ߋ����Ɨ��������˂�Ƃ���/133
�����̐��E�̕ώ�/139
�u�̓��v�����߂�/143
�V���|�W�E���u�쓇�̌Ñ㕶���v/149
���{��͍�������/151
����N��w�̖��/155
�]��A��p�Ƃ̂Ȃ���/157
�����_�b�̌n��/167
�@���O���@��/175
�����̗l���ƃj���C�J�i�C�M��/184
�D�����猩���쓇����/193
�C�㖯�̈ړ��̌_�@/196
���^�y��̖{�y�n��/200
���Ƃ����ɂ����� ��ؕ���/206
�E
�E |
�P�P���A�V�铿�S���u �u���A�m��� (�Ȃ�����ʂԂ�)�v�q���E���Ձv���u���y�̕���������v���犧�s����B�@��3��
�P�Q���A���a�c�^�~�����N���W���ꂽ�l�Î��������ꌧ�������قɊ������B
�P�Q���A������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v ���(17)�v���u������w����w���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2259151
|
���\���Y�G�L�m�C�h����/�쌴�q�G/p25~26
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-1-2-�Ӗ������@�ɂ��/������q/p27�`50
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-2-2-�Ӗ������@�ɂ��/������q/p51�`72
�����E�L���E�o�V���E�̑@�ۂ̋��L�x�Ɣ��\���ɂ���/
�@�@�� �㓡�l�j ;���숻�q/p145~149
����ߐ������喼��m���̗畞�ɂ��� / ����^���q/p155�`163 |
���x�̊ӏܥ�]����--
�@�@����������ꕑ�x�̊ӏ܌� / ������q/p201�`224
������̕��x����-1-(1945�`1972) / ������q�@�d�v
�@�@���i���������̋��͎ҁF�������ݎq�^�ʏ�m�q�j/p225�`256
�q�����r
�E
|
���A���̔N�A�͑����Y���u��������̒T�� : ���ŏ����ꂽ���ꖯ���j ���v���u���ꕶ���o�ŎЁv���犧�s����B�@pid/9770579
|
����/1
���� ���������̒T��/1
�� �T���̖ړI/3
�� �T�������H��/5
�O �z���̗����ƌ����̗���/9
�l �ߔe�E�̑���/14
�� �����̏����l��`�o��/17
�Z �u���������̌l��`�I�Ƒ��v/19
�� �Ƒ���`�̎���/27
�� ���⓰�̓`��/33
�� �����̓��ƐK/35
��Z �����̌��t/38
��� ���̍ד��i��j/40
��� ���̍ד��i���j/43
��O �u���̋��Y�����v/48
��l ���̋����X/50
��� �R�r�̈���/54
��Z �u�n����l�v/57
�ꎵ �A���[�o�ԗ�/60
�ꔪ �����̓����\�v����/64
�i��j�A�}�~���[�J���U�i�V�[��/65
�i��j�C�W���C�z�[�Ձ\�����呀����/66
�i�O�j����/69
�i�l�j�u���D�����v/72
�i�܁j�u�Ǔc�����@�v/74
�i�Z�j�v�������E�G���u�V/76
��� �����̕�/78
��Z ��̍\��/81
��� �̊��K/87
��� �搧�̕ϑJ/90
��O �̐_/93
��l ������/97
��� �u�ҁv�Љ�w/99
|
��Z �ߔe���{�Â�/102
�� �{�Ó����̑�a��/104
�� �{�Â̓��A��E�u������v/109
��� �l�ސł̎j��/114
�O�Z ��_���̐_��/117
�O�� �r�ԓ��̌������x/123
�O�� �F���̌Õ�/127
�O�O �ނ���/129
���� ���d�R�����̒T��/131
�� �͂�����/133
�� ���\���̈��/134
�O �c�[�̔q��/137
�l �����̂��Y�Ɩ�����/139
�� ���d�R�̐��҂��Â�/142
�Z �g�ƊԌ��C�̍r�g/144
�� �Ց����̔g�Ɗ�/147
�� �g�ƊԂ̔q��/149
�� �_�������ޔg�ƊԂ̉���/152
��Z �_�������̋�S/154
��� �Î��L�̐���/156
��� �g�ƊԂ̔[��/161
��O ���d�R�̉p���E�|�x��/162
��l �^�ߍ��ւ̗�/165
��� �^�ߍ������̗R��/167
��Z ����P���̃O���{�[/169
�ꎵ ��a��w��/173
�ꔪ �l����Ƌv���NJ�/177
��� �^�ߍ��̒���������/179
��Z ���d�R�̘m�Z/184
��� �^�ߍ��̐e���ď̖@/188
��� �^�ߍ��́u�q���{�ʌď̖@�v/191
��O ���l�����珬�l����/199
��l ���l�̐ԃ}�^�E���}�^/202 |
��� ���l�̖��M�ⓚ/207
��Z �ނ���/211
��O�� �{�Õ����̒T��/213
�� �͂�����/215
�� �{�Â̓�����̐_�b/216
�O �{�Ấu�O�֎R�v�`��/219
�l �{�Ì�ƌÌ�/222
�� �{�ÂƓ�ؖf��/228
�Z �Ô��H��̗�/230
�� ���n�̋�t/233
�� �{�Ẫ��^���/235
�� ���ԓ��̓n�M/238
��Z ���Ԑ�̃��[�}���X/239
��� �����̔z���E���NJԓ�/243
��� ���[�̕S���ᕨ��/245
��O ���[�̑�̕�/252
��l ���[�̋���/256
��� ���NJԂ̖L�N��/261
��Z ���NJԂ̖L�N�Ղ̎Љ�I�Ӌ`/270
�ꎵ ���NJԓ����ɗǕ�����/274
�ꔪ �ɗǕ����́u�q���{�ʌď̖@�v/277
��� ���Ǖl�̃����`/280
��Z �r�Ԃ̕�����Z��/283
��� �r�Ԃ��/286
��� �J���ʑ�_���̐_��/288
��O �哇�_�̋֍����x/291
��l �e�_�̓���/293
��� ���K�̃p�[���g�_/294
��Z �떓�̖L�N��/297
�� �J��̎Љ�I�Ӌ`/299
�� �ނ��с\�u�݂₱�v���u�݂₱�v��/303
�E
�E |
���A���̔N�A���g���������u�ČR�Ɣ_�� : ���ꌧ�ɍ]���v���u��g���X�v���犧�s����B (��g�V��)�@pid/9769174
|
I �ɍ]���E�^�ӂƂ킽��/1
1 �ɍ]���E�^�ӂ̗��j
2 �킽���̐��������Ɛ^��
II �^�ӂ̔_���ƒ�K��/19
1 �y�n���̔��[
2 �ČR�Ƃ̉�k
3 ��K��
III ���肭��j��/55
1 �����сi�K�j�ƌ��Ƃ͌��ʘb��
2 �ǂ߂Ă����R����
3 �_���������ꂽ����
IV �P���Ă����ČR/85
|
1 ���܌ܔN�O���\���
2 �������{�ɍ��荞��
3 �������₢���ڂ�O�l���l��
4 �����̃i�}�̋L�^
V ��H�s�i/125
1 ��H��������̂͒N��
2 ���ԓP��
3 �������j�N�̑ߕ߁E����
4 ����̂�������
VI �ČR�Ɣ_���̍��C�����/143
1 �R��k�ɂ������Ă̐S�\��
2 �Â��ߕ߁E����
|
3 �������y�ɂȂ����y�n�_�ۂ̔_��
4 ��N�̔���
5 �R�̐V���Ȍ���
VII �K������]�@/175
1 �ɍ]���y�n������
2 �ɍ]���̊w�K����
3 �x�g�i���푈�ƈɍ]��
4 �ɍ]������~�T�C����ǂ��o��
5 �c������̌���
���Ƃ���/217
���g������Ǝ��i�q���P��j/223
�E |
���A���̔N�A�q���P�u����̗��j������v���u�����Ёv���犧�s����B�@pid/9769187
|
�qI ����сr
�v�ē��́u�R�̕����v/3
���̌���ɗ�����
���a���̂��̂̓���
��\��l���s�E
������������
�����ɂ�������a����
�u�c�R�v�̐��i
���R�́u���n�ȁv
�����������ɂ������Ă��釁�̂�
�u�E�l�����͗���ȁv�̊Ŕ�
��㊂̂ӂ��������Ƃ�������/12
�살�炵�̔���
K����̈�l����
�s�E�͘Z����\������
������ˑR�u�c�R�v��
�Đ{�����̍��F
������Ƌ@�֏e
�J�}�h���ے��������
���̂̎��̂��݂�����
�������肷��Ƈ���n�ό���
�ɍ]����K�˂�/22
�A�c�`�N���T�[�r�e
��n�̒���
�ɍ]���Ɖ��䏯�ꂳ��
�ČR������邢
���������g����
��[��n��/30
���C���ȕ��͋C
�����ƎO����
KC135�����@
�ۖ����k������
���������̏����̕ω�
�R�p�n�_�ۂ̂�������/47
�u���A�v����̉ߓn��
�h�q���̂�����
�ɍ]���̃`���V
���������̃e���|
�ό����{�ɂ��{�ÁE
�@�@�����d�R�̓y�n�����/58
�s�[�J�W�i�̕��j
�Éi�ܔN�Ș҂̊��� |
�s�K�ɂ����ޓy�n�����
�s��̃A���}�[/69
��������Ă�懁
�s��̍��k��
�X�q���c��������
�n���͖X�q�̂��߂�
��؏�̏���l
�������N�ɂ����Ȃ�����
�����Ɛe�̒��a
�C�J�̖n���������
��㊖{���k���삯����L/77
�o���ɓ�����
�G�b�\�̇������̐㇁
�����˂Ȃ��
�Ɛl�̑��ǂ��ǂ���
�C�����H
�������̕�̃A�p�[�g
�A�����J�ɂ��܂��ꂽ�T�^
�C�����H�ɂ������ꂽ����
���z�̍��v�삳��
���v�삳��̘b
��Ԃ̎ˌ���
�u�ŃK�X���v�̔��[
�N�C�c�N�E�����[�X�̌���
�T�u���b�N��n
��㊌����s�i
�Q�����P���̕ĕ�
������C
�������C
�����琼��
�X�N�̊��C
�A�����J�̂���
VOA�̃A���e�i
�u���g���Ӂv
�C����o���̕l
�ӌ˖���
��\���x���̓�̐��i
���̗��ĕ�
���̊C��
�ɕ��x�̇��Ð�ꇁ
�Q�����P���̎R
�H�n
|
�Ђ�Ղ�E�����܂�
�����̐l�E���[�i�x
�J���O
��\���N�̏k�}
���Ð�ꇁ���}�z�e��
�qII ���j�сr
���܂ɐ����鉫㊌Ñ�̍�/115
�\�\���d�R�̐ԃ}�^�Ə��A�̑�j���\�\
1 ���d�R�̐ԃ}�^�E���}�^
2 ���A�̑�j��
3 �|�x���̍K�{����
4 ���ԂƂ͂Ȃɂ�
���{�Ñ�j�̌��_�Ƃ��Ẳ�㊌Ñ�j/134
1 �^�_���́u�}�L���v
2 ��ՂƎj����
3 �{�ÁE�떓�̑�i
4 ��㊖{���̗��j������Ȃ����������E�擇
5 �Ր���v�̌Ñ㉫�
6 ���Ԃ�Njy�����Ñ�V�c��
7 ��㊂̌Ñ㖯���`
�v�ē����j����/163
1 �i�����̗��j�Ƌv�ē�
2 �u�}�L���v����i��
3 �v�ē��́u�i����v�Ɓu������v����
4 �u�Ñ�v�ē����Ɓv
5 ��㊎j�̔w�i����݂��v�ē�
6 �u�Ñ�v�ē����Ɓv�̕���Ƌv�Ă̌N�앗
�m�O�����ƉY�Y�����/203
1 �Ñ㉫㊒a���̒n�E�m�O����
2 �Y�Y�̈�Ղ������
�Ñォ�畕�����܂ł̓��{��������l����/219
�\�\���N�l�̕Y���L�ɂ悹�ā\�\
1 �O�l�̒��N�l�ƂƂ���
2 �^�ߍ��̃g���O�c�E�N�u������
3 �\�ܐ��I���̗^�ߍ���
4 ���\�������Ƌ{�Õ�����
5 ��̕��z�ɂ���
6 ���̎���̗��j�I�w�i
7 �Ñ�����Ő����̓ߔe
8 ��㊁E��B�E���N�̐��I�̗�
9 �퐶���畕������܂œ�N�ŕ������l����
�E
|
���A���̔N�A�u����̕��y�L : ����͐����Ă���v���u�����{����}���v���犧�s�����B�@�@pid/9769300
|
���j����݂�����/7
����̗��j�i�Ɨ����Ƃ��Ẳ���j �V���~�K��/8
�l�Êw����݂����� �������G/12
�O���l�̉����ۋL �약���\/14
�@������݂�����/17
����̏@���i���̓y���I�Ȃ��̂ƊO���I�Ȃ��́j ��Ð��v/18
����̕����i��y�@�̗R���j ���K�����Y/20
����̐M�� �`��������/22
���R����݂�����/24
����̊C �����M��/25
����̐A�� ��Ԓ���/30
����̓��� ���ǓS�v/34
��������݂�����/37
�������ՂƔN���s�� �Î��d��/38
����̖��b �����Y/44
����̗V�| ���c����/46
����̐��x �{������/48
����̂��Ƃ킴 ����Ԍ���/50
�H�w����݂�����/52
����̌��z ���g�^�O/53
��̗��j ���Ð^�X��/56
�|�p����݂�����/58
����̖����|�\ ���g������/59
����̉��y ���K����/64
����̋�� ���䏫�^/66
����̉��� �O�Ԓ��M/68
�Y�Ƃ���݂�����/71
���F�L���ȍH�|�i �O�Ԑ��K/72
�����Ȃ�̂����� �Ð��Îq/76
�����̖f�� ��ԕq��/78
�J���ƌo�� ���_���Y/80
����̖��� ��]�F��/84
����̕��y/86
����ꂽ���̂ւ̋��D �×z���j/86
�{����/90
�{�Ó��q���ǎs�E���n���E��Ӓ��E��쑺�r/93
��_���q���ǎs�r/99
���[���q���NJԑ��r/102
���ԓ��q���n���r/105
�r�ԓ��q���ǎs�r/108
�ɗǕ����q�ɗǕ����r/112
���n���q�ɗǕ����r/116
���NJԓ��q���NJԑ��r/118
���d�R����/123
�Ί_���q�Ί_�s�r/126
�^�ߍ����q�^�ߍ����r/131
��t�q�Ί_�s�r/135 |
�V�铇�q�|�x���r/138
���l���q�|�x���r/142
�����q�|�x���r/145
����_���q�|�x���r/148
���ԓ��q�|�x���r/150
�g�Ɗԓ��q�|�x���r/152
���\���q�|�x���r/156
�|�x���q�|�x���r/161
�ɕ����E�ɐ�������/165
�ɕ������q�ɕ������r/166
��ᓇ�q�ɕ������r/170
��u�쓇�q�ɐ������r/172
�ɐ������q�ɐ������r/174
�哌����/178
��哌���q��哌���r/180
�k�哌���q�k�哌���r/183
�v�ē��Ƃ��̎��ӂ̓��X/186
�v�ē��q�������E��u�쑺�r/187
�n���쓇�q�n���쑺�r/192
�������q�������r/195
�������q�������r/196
�c�NJԗ�/199
�n�Õ~���q�n�Õ~���r/200
���Ó��q���Ԗ����r/204
�c���ԓ��q���Ԗ����r/206
���Ԗ����q���Ԗ����r/208
�^���̓��X�Ƌv����/210
�����q���A���r/212
���������q�^�ߏ鑺�r/214
�l����q���A���r/217
�Ɍv���q�^�ߏ鑺�r/220
�{�铇�q�^�ߏ鑺�r/222
�M�n���q�^�ߏ鑺�r/224
�v�����q�m�O���r/225
�ɍ]���Ɩ{���̓��X/229
�ɍ]���q�ɍ]���r/230
�ÉF�����q���A�m���r/234
����q�{�����r/236
���[���q�{�����r/238
����n���q����s�r/240
����{��/243
�m�O��/248
�����s/250
������/256
�R�U�s/258
��u��s/261
��u����/264
|
��X����/266
�ΐ�s/268
��[��/270
�^�ߏ鑺/272
�X��p�s/274
�{����/276
����/278
������/280
������/282
�X�����/284
��������/286
�L���鑺/287
���[��/288
������/290
�k�J��/292
�앗����/293
����s/294
�ʏ鑺/298
�Y�Y�s/300
�k���鑺/302
�嗢��/304
���A�m��/307
���~��/310
�^�ߌ���/312
���A��/314
�ǒJ��/316
���鑺/318
�ߔe�s/321
�n�}
���V��/2
�쐼����/3
������/88,89
�{����/90
���d�R����/124,125
�ɕ����E�ɐ�������/165
�哌����/178
�v�ē��Ƃ��̎��ӂ̓��X/186
�c�NJԗ�/199
�^���̓��X�Ƌv����/210
�ɍ]���Ɩ{���̓��X/229
����{��/242,244,245,246,247
�ߔe�s/328
�܂�����/6
���Ƃ���/334
�Q�l����/335
���t/336
�E |
���A���̔N�A�u���ꌧ�j ��23�� (�e�_�� 11 ���� 2) �v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@pid/2994248
|
�����̂��Ƃ� ���ꌧ����ψ���@���璷�@�ÉÎR���g
���́@�N���s���@��Ð��v
���߁@�N���s���Ɩ���/p3
���߁@����܂ł̉���̔N���s������/p5
��O�߁@�e�_/p6
��l�߁@����̔N���s�������̉ۑ�/p67
���́@�|�\��y�@�약���\�@���n�B��
���߁@�_���|�\/p93
���߁@�����|�\/p161
��O�� ��y/P250
��O�́@�̘b�Ɩ��b�@�V���~�K��
����/P279
���߁@����̘̐b/p299
|
���߁@����̓`��/p367
���с\����̘̐b�E�`��
�@�@���i���b�j�̌��W�ƕۑ�/p393
��l�́@�̗w�@�X�ۉh���Y
���߁@����/p397
���߁@�J����/p399
��O�߁@�j�Ղ̉�/p418
��l�߁@�N���s���̉�/p433
��ܐ߁@�ʉߋV��/p487
��Z�߁@���̑�/p491
��́@���Y�E���ׂ����E�ߋ�@�O���v
���߁@�T��/p497
���߁@���Y/p499 |
��O�߁@���ׂ���/p514
��l�߁@�ߋ�/p591
��Z�́@���@����^����
���߁@���_/p607
���߁@���̓��e/p621
�掵�́@����@��]�F��
���߁@�T��/p679
���߁@�ߐH�Z�Ɋւ������/p691
��O�߁@���ƁE���Y�Ɋւ������/p730
��l�߁@�^���E�ʐM�Ɋւ������/p772
��ܐ߁@���ՂɊւ������/p785
��Z�߁@�M�E�V��Ɋւ������/p786 |
���A���̔N�A�{�c�������u���{�̖����|�\ 5 (�����E�G�[)�v���u�؎��Ёv���犧�s����B�@�@�@pid/9546208
|
��㊂��Y�\
��㊁\�Y�\�̕��y/3
��㊂��Y�\/13
���d�R�̐M���Y�\/49
��A �o�ߚ����̗x��/82
��A ���\���̍Չ�/85
�O�A ���ԓ��̉��/94
�l�A �����̗x��/98
�܁A �|�x���̉�/99
�Z�A �g�Ɗԓ��̉�/102
���A �Ί_���̌��/111
���A �Ί_���약�̉�/120
���A�{�Ó����ߍ����₮
�{�y���Y�\�Ƃ�萗�/129
�g�x�Ɣ\��/146
�g�x�E�[�x�̌^/148
I �g�x�̌^/148
II �[�x�̌^/209
�Ή������x�B��/215
�����̌��Ƃ��̎��/223
��㊏����̌�揂ƕ��x����/226
I �{�Ó��̉�/238 |
II �|�x���̉�/251
III �ɍ]���̉�/262
IV ��㊖{���̉�/267
�|�x���̋���/273
��㊏����̉�/291
��㊖{���̉�/294
���d�R�̉�/302
�{�Ó��̉�/320
�����ꑩ/323
�������/333
�������C���Ղ̕��x�v���O����/339
��㊕��x�̕���/341
�ɓ��̓����Y�\
��A �O����Y�\/402
��A ���U�����Y�\/451
�O�A �V�����Y�\/465
�l�A �_�����Y�\/498
�܁A �����̐_�ى�/516
�Z�A ���䓇���Y�\/519
���A �������Y�\/567
���A ���̐_�F/572
��A �哇���Y�\/584
|
�_�ٕ��
��A ��K�Ԟ��/601
��A �K�X�_���/629
�O�A �叞�_�ً���/659
�l�A �ۊ���������/762
�܁A 誊�v���̐_��/765
�Z�A ��B�̐_��/782
���A �另��I�I���r�́i���O�j/827
�������
��A �b��Џ�R������/921
��A �y�J�x/922
��趎[
�R�Ԃƍ՚��q��/935
�]�˖،�
�]�˖،�/997
�،��̎�/1002
���^ �Y�p�Ղ̖����Y�\
I �\��N�j/1067
II �Y�p�Ղ̖����Y�\/1074
���H�̉��
�E
�E |
���A���̔N�A�u�_�W���{�����̋N�� 5�v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@645p �@ pid/12239782�@
|
���{�l��_ ���(�r�c���Y)
��O�̓��{�l��_�̗���
�@�����{�Ί펞��l��_�Ɋւ���O��̊w��(���쌪��)
���{�ɂ�����Ñ�l��̍���(E.S.���[�X)
�R���{�b�N���k�C���ɏZ�݂��Ȃ�ׂ�(�؈䐳�ܘY)
���{�Ί펞��̏Z��(������ǐ�)
�É_�Ί펞��l�̓A�C�k�l�Ȃ��(���쌪��,�{�{���l)
���{�����̐���(���J�����l)
�������푰�Ƃ̗މ�
�@�����{�l�̋N���Ƃ��̐l��w�I�v�f(E.V.�x���c)
���{�l�̓������w���A�g������т��̒n����(������)
�����ɂ�������{�l(�����L)
���{�l�̑c���������(�Ô����)
���{�l�w��̓��v(�{�c���`)
���{�l�̎w��Ɋւ��錤��(���r�h����)
���L��[�e�C]��(���������Y) ���{�l�ƃA�C�k(���l�)
�A�C�k�̐l�핪�ޏ�̈ʒu�̖��(���ʍ썶�q��)
���̌Ñ�l���Ɋ�Â����{�l��_
�@����j���ォ�猻��Ɏ���
�@�����{�l�̏��i���I�ω�(��؏�)
�퐶����̓��{�l(���֏�v) |
���Ύs���ߐ����؍ŐV���O���͐Ϗo�y
�@���l�ލ���(�p�^)�̌��n���ɏA����(���J�����l)
����z�R�Ŕ������ꂽ�^�ϐ��l�ނ̏�r��(��؏�)
�����ژ^:p.291-299
����w ���(���W)
���_ ����n���̖��(�V���o)
���{��̈ʒu(��������)
���N��Ƃ̏����̔�r�_ ���{��ƒ��N��̔�r����(W.G.�A�X�g��)
���ؗ����ꓯ�n�_(���O�Y)
�������Ƃ̊W �I�[�X�g���A�W�A��Ɋւ��鏔���(���{�M�L)
���{��E����=�ə��ꓯ�n�_(��)(C.K.�p�[�J�[)
�k������Ƃ̊W �A���^�C����Ɠ��{��̔�r(G.J.�����X�e�b�g)
�Î��L�ɉ����郂�̉����̗p�@�ɂ���(�L��G��)
����j �n����(��)(���c�ꋞ��)
���̔��W
�@�����{��Ɨ�����E���N��E�A���^�C��Ƃ̐e���W(�����l�Y)
���{��ƒ��N��Ƃ̌�b�̔�r�ɂ��Ă̏���(���W)
�u���v�Ɓu�́v�̈��(�l�c��)
���ȂĂ�E�Ă邵�̍l(���R���Y)
�����̌���Ƃ��̓���(���)
�����ژ^:p.629-642 |
���A���̔N�A�������l�X�R����ҁu��B�����_�W 1�v���u���}�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/9573407
|
���s�ɂ�������
�͂�����
I ��j����̋�B�Ƒ嗤�E
�@�@��������� ��������/13
�͂��߂�/15
���� ��B���߂��鎩�R��/17
���� �Z�p�̓W�J/21
���� �^�ϐ��̐Ί�Z�p/21
���� �^�ϐ��ɂ����铌���̕Ӌ��n��/23
��O�� ��B�ɂ�����y��̓o���
�@�@���^���̓W�J/30
��O�� ��B�n��Ɗؔ����Ƃ̌���/43
���� ���O���L�˂̋ߔN�ɂ�����
�@�@�����@���ʂ��߂�����/43
���� �ؔ������펞��̋ߔN�̔���/49
��l�� ������߂���z��/56
���� ��j�E���
�@�@�����N�����E�����̈��/56
���� ㊕�������\�ӊ��ɂ�����
�@�@�����������̌���/62
��� �����ƎЉ�/66
���� ���@�Ɍ�����ϗe/66
���� �Ӌ��n���ɂ�����l��/71
��Z�� �쓇�̊��ƕ���/74
���� �썑���߂��鎩�R/74
���� ��㊖{���𒆐S�Ƃ���
�@�@����j��ՕҔN�̎���/75
��O�� �Z�p�̌���/77
��l�� �L�̌���/87
��ܐ� �g�J���C���ɂ������n/88
��Z�� �]��E��p�Ƃ̌���/89
���Ƃ���/97
II �Õ������̐����Ƒ嗤 ���{�떾/99
���� ���`���a��Ƌ�B/101
���� �����Õ��̖��/101
���� ���`���a��̕��z/105
��O�� ���`���a��̐��i/108
��l�� ��B�̕��`���a��/112
��ܐ� �����Ɛ����Ƃ̑���/117
���� �O����~���̔���/120
���� �����ɂ�����Õ��̐���/120
���� �O����~���̌��`/128 |
��O�� �O����~���̔���/130
��O�� �M�`�Ί��̖��/136
���� �M�`�Ί��̕��z/136
���� �M�`�Ί��̔���/141
��l�� �����Õ��̐���/147
���� ������B�̎O�̕�����/147
���� �����Õ��̕��z/152
��O�� �ֈ�̗��Ƃ��̔w�i/158
��l�� �V���̌Õ��Q/163
��ܐ� �S�Ɖ�/168
��Z�� �����Õ��̉e��/172
III �l�ފw���猩��
�@�@���Ñ��B�l ���֏�v/179
�� �����y�ё��`�����ɂ��l�@/181
�� �`�����猩�������B�l/185
�O �����B�l��
�@�@���l��_�Ɋւ���w��/191
�l �����B�l��
�@�@���n�����Ɋւ��鑍��/198
�� �Ñ��B�l�̌`��/200
�Z ���͂܂��c���Ă���/207
IV ��B�ɂ�����
�@�@���Ñ㍋���Ƒ嗤 ����M�Y/213
���� �����̕��@�Ɗ�b/215
���� ��a�����Ƌ�B�̌Ñ㍋��/225
���� �����̔��e/225
���� �u���v�E�u�Δn�v�̍���/227
��O�� �u�}���v�̍����i��j/230
��l�� �u�}���v�̍����i��j/233
��ܐ� �u�}���v�̍����i�O�j/249
��Z�� �u�L�v�̍���/251
�掵�� �u�}���v�Ɓu�L�v�̓���/257
�攪�� �u��v�̍���/259
���� �u���l�v�n��̍���/263
��\�� �������Ə�����/268
��O�� �O�A�l���I�̋�B/273
���� �u�`�l�`�v�̐����g�D/273
���� �הn�䍑�_�Ƃ̐ړ_/279
��l�� �C�l���ƋR�n�����_/282
V ��ɕ{�Ƒ嗤 �|�����O/291
���� ��ɕ{�̐���/293
���� ��ɕ{�ȑO/293 |
���� �}���s�{�̐���/297
���� ��ɕ{�̍\��/302
���� ��ɕ{�̓s���Ɗ���/302
���� ��ɕ{�����̍\���i��j/308
��O�� ��ɕ{�����̍\���i��j/313
��O�� ��ɕ{�̔ɉh/318
���� �s�s�I�i��/318
���� ��ɕ{�̋@�\�I�����i��j/322
��O�� ��ɕ{�̋@�\�I�����i��j/330
��l�� ��ɕ{�@�\�̒o�ɂƕϖe/338
VI �쓇�ɂ����镶���̌�
�@�@�@�����{�떾/345
����/347
���� �쓇�ɂ�����
�@�@���������W�i�K��/349
���� �}�L������o�[����/349
���� ���Ɛ����̓`��/352
��O�� ���̖��_/355
���� �Ñ�ɂ����鏔�����̌�/357
���� ���{�̋L�^�ɂ݂���쓇/357
���� �{�b��̏o��/360
��O�� �����Ɠ쓇/362
��l�� �����I���̉��/365
��O�� ���E��ؓ���̏o�y/369
���� ���̕��z/369
���� ���A��̔��@/373
��O�� �����哇�̐�/376
��l�� ���Ɠ�C�Ƃ̌���/382
���� ���Ɨ���/382
���� ��C�Ƃ̌���/385
��O�� ���{�E���N�Ƃ̌���/387
��l�� ���Ɛ����̊�b/389
��� �쓇�ɏo�������_��/390
���� ���{�Ñ�̃~�R/390
���� �����̐_��/391
��O�� ��㊂̐_��/394
��l�� �擇�̐_��/397
��ܐ� �����E
�@�@���擇�ɂ����鉫㊂̉e��/401
��Z�� �_���̋N��/405
����/410
�E |
|
| 1974 |
49 |
�E |
�Q���A�|�\�w��ҁu�|�\ 16(2)(180)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276375
|
�����̂��Ƃ�����|�\�ƍ�������ƣ //p7�`7
狋�Z�̂̕��y--���-13��2- / �����_/10�`15
�_���|�\�Ƃ��Ă̑�ڗ� / ���䐴��/16�`22
�n���� �̕���Y�ȉ��-155- / ���������Y/23�`28
�̕��ꉹ�y�W��-85- / �n���h���q��/29�`33 |
�o�����̍���(2)�C���h�l�V�A<�ʐ^�ƕ�> / �F����o�j/p34�`35
�|�\�W�] / ����p��/p50~51
�����u�����|�p�v / �i�c�t�g/p36~37
��
�E |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 10(2)(41)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@�d�v
|
�쓇�É̗w�̉̌`�̌n��(��) / ����d�N/p1�`26
��������ɂ�����u�������v�̌n��/�n�v�n����/p27�`36
�������u���Ӂv�ɂ��� / �O�Ԏ�P/p37�`41
������̓����I�~�`�̍\���ɂ���/�R�c��/p42�`59
������㊉������j / ��Î�/p60�`74
|
�����P���搶�̎Љ�v�z / ���C�Ɉ�Y/p75�`81
������㊔蕶�L(��) / �茴�P�V/p82�`99
�Ꮡ�]�� ���ԁE�F���Ғ��w��㊑��NJԓ��̑g�x�x/�Ɗ얼�ɕv/p100�`106
�w��j���[�X/p41~41
���s�j���[�X/p59~59 |
�R���A�u�܂� = Festival (25)�v���u�܂蓯�D�� �v���犧�s�����B�@pid/7930501
|
�V�����������S�� ���c�܂� / ���R���O�Y/p5�`14
�É������q�S�����_�Ђ�
�@�@���\��i���y�̕����ɂ��� / �����͍]/p15�`33
�Ί_�̖~�s�� / �茴�P�V/p34~41
�~�q�P�ƕ�ɂ��� / �O�Ԑ��K/p42�`46
|
���A�m�́u�H���y�v�ɂ��� / ���@���K�s/p47�`55
�L���̓y���_�Ղ� / �c���`�L/p56�`72
����Ȃ�ł��_�� / ��ؐ���/p73�`80
�ɜQ�����_���̐_�_�ƍ��J / �Βˑ��r/p81�`97
�ʐ^ �L���̓y���_�Ղ� / �O���K�� |
�T���A�Î��d�삪�u����̐_�X�ƍ� : �N���s���v���u�V���}���v���犧�s����B�@�@
�U���A��������ЕҏW ; �F�������ʐ^�u�J���[����̂܂�v���u��������Ёv���犧�s�����B�@
�@�@�@�@(��������Ђ̃J���[�V���[�Y, No.6)�@�@�@���:��Ð��v, ���Ԉ�Y, ��]�F��, �X�ۉh���Y
�U���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 1�v���u�@����w���ꕶ���������v����n�������B�@pid/9769602
|
�I�v�u���ꕶ�������v�����̎�
���������`���̎v�z�\�����v�z�j�̈�ꑂƂ��ā\ �����N/1
���R�����h�́u���������_�v�\�m�����e�_�E�A���_�E�����_�̒����\ �䉮���ƕv/79
����{�w���R�����x�ɂ��� �Î�[�@��/98
��g�ҕ��O�̌n���ƕ��M �n���^��/115
�˔i�g�D���r�����j�Ƃ͉����\���̒����ǐՕi�\��j�\ ���a�c�^�~/135
�A���V�c�E�V�o�T�V���_ ����d�N/164 |
�u�咆�v�������߂��鏔���\
�@�@������O���̘_�l�𒆐S�Ɂ\ ��Ð��v/185
����|�\�j�T���i���_�j ���P�Y/204
��������̈�� �n�v�n����/245
����Ɩ��c���j �������n/276
�����ɂ������ā@�@���]�F�i p.296-296
�E |
�U���A�u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� (62)�v���u�����������w��v���犧�s�����B�@�@pid/6024811
|
�ʎғa / �{���e��/p1~4
�o���̎q���g / ������N/p4~6
�A�� (2)�H��̖��� / �q���N/p7~9
�o���̎Y�� / ������N/p9~12
�͏�_�ЁE�������E�j���� / ���c��/p12�`15
���i�Ǖ����̃��^�M�� / ���_��/p16�`20
�I�I�E���l�o�� / ���c��/p21~23
|
�{�ÌQ����_���̒ʉߋV��ɂ��� / �R�c���q/p23�`25
���W�ɂ̏��N�P���ɂ��� / ���c��/p15�`26
�卪�蒬�[�����̘Z���� / ���c��/p27�`27
����� / ���l����/p28~30
��(����) / ���l����/p30~32
���~�̎��ȂǕ�[ / ���l����/p32�`34
�ꌎ���L �ҏW��L / (����)/p35�`36 |
�U���A���o�ŎЕҁu�� (180)�v���u���o�ŎЁv���犧�s�����B�@�@1974-06�@�@pid/3367791
|
�����I�[�v���������ԍ◣�{�X���Ōf��
�@�@���V���[�Y��ƣ�}�o��/�R�I�M
���̐l/�]��扗��/�֓��N��
�������v���J�[�h�X���䂭 / �����e���Y
�����e�B�O�̢�e�����|�p�Ƃ���� / �I���I���P����
�����Č�-�a�J��̊� / ����M
|
�킪�̌� ����������������� / �P��g��/p71�`73
�킪�̌� ������ / �ؓ��ߑ��Y/p73�`75
�f�X�NMEMO(3��16��~4��15��) / �V��//���j/p76~85
�����ʂœ��{�l���l���� / �i�n//�ɑ��Y ;����//�q�Y/p86~115
��
�E |
�V���A���{���y���x��c�ҁu���y�̐��E = The world of music : ���y�Ƃ�����|�p�E�Љ�̂��߂̋G���� 13(7)(134)�v���u���{���y���x��c�v���犧�s�����B�@�@pid/4437892�@�@�d�v
|
��咣�⎩��̈ӎu�𖾂炩�ɂ���Ƃ�������/p2�`3
���{�̉̃[�~�i�[���L�^ ��܂Ƃ��Ƃ������ / �؉���/p4�`11
�����|�\�Ɛ����V���[�Y(9) �t�B�[���h�E���[�N�̊�b�m��--
�@�@�����c���q���ɂ��� / ���R�T��Y/p12�`16
�����|�\�Ɛ����V���[�Y(9) �߉��~�x�͂��Â��� / �O�ːM�l/p15�`15
�A�� �����{�̉��y��i�N�\ ����M�y��IV--
�@�@��1972�N2���`1973�N12�� / ���{���y���x��c ;�r�c��q/p17~20
�� ���t�B���C�����͈��ׂ��H �c���G���e�m�[�����T�C�^��
�@�@���������O�o���g�����T�C�^�� / �ēc�m/p21�`23
���C �n�����̃��T�C�^�� / �r�c��q/p28�`30
���C ���t�B���E���㉹�y�̗[��/p30�`30 |
���C ���y��x��\��\(7��)/p28�`28
������ ��������X�Ђ炩��/p26�`27
������ �V�^�c�ψ��̕���/p26�`27
���] �P�X�g�i�[�C�x���t�C�k��Ŏq ���O�d�q�|
�@�@�����{���w�ɂ�� / ���{�����]/p31�`33
���] �~���[�W�J���u���j�̓_����I�v / �֍���q/p34�`34
���y���x��\��\/p35~37
�ǎ҂̂Ђ��/p24~25
�o�b�N�i���o�[�Љ� (�I�[�P�X�g���E������)/p22�`22
(�����[�~)/p32~32
�Z�M/p35~371 |
�V���A���䓿���Y���u����̃V���}�j�Y���v���u�O�����v���犧�s����B�@�Q���i���ŁF���a�S�W�N�V���j�@�@�d�v
|
�܂�����
�}��
������Ӑ}
�����@����̃V���[�}���@
���с@���ƛޑ�
�@���́@���̋V��Ɩ��ԛޏ� p25
�@���́@���搧�ƛޑ� p60
���с@����V���}�j�Y���̌��_
�@���́@�X�W�t�@�̖�� p115
|
�@���́@����ދV�̓W�J p118
�@���́@�X�W�t�@�ޑ��̏��`�� p138
�@��O�́@�썰�ς̍\�� p183
��O�с@����{���̛ޑ�
�@���́@���^�̈˗��� p199
�@���́@���^�̐��މߒ� p213
�@��O�́@�n���W�̎��C p239
�@��l�́@�ޏ��̐_�肢 p256
�@��́@�}�u�C�O�~�i���Ă߁j p275 |
��l�с@�@�ޑ��̏@���I�W�J
�@���́@���̒�N p323
�@���́@�ޏ��̓��ނƑ{�_ p328
�@���́@���V���_�̐��i p346
�@��O�́@���Бg�D�Ƃ��̐��� p363
���Ƃ��� p417
����ޑ���b���� p432
�E
�E |
�X���A������q,���镐���u���{�̈�w��� (25) p.121�i�菑���j�v�Ɂu���x�̔F�m�\���ɂ��� : ���x�R�~���j�P�[�V�����E���f�����_ �v�\����B
�P�O���A�J�쌒�ꂪ�u�����y�̑��e�v���u��a���[�v���犧�s����B�@�@
|
�@�T�@
���c���j�́u�����v�@�i1972-10�@�u�s�G���^�v��Z���A�啝���e�j�@
�u���앨��v�̐��E���@�i1972-11 �w���앨��x�i��a���[���j����j
�f�́E���c���j�@�i1973-02�@�u���c���j�����v�{
�@�@��1973-9 �u�������_�o�c���v�H�G���ʍ��j�@
���c���j�̐��E�@�i1962-8-20�t�@�u���{�Ǐ��V���v�j�@
���c�w�̍Č����̈Ӗ��@�i1973-1-22�t�@�u�K���Ǐ��l�v�j�@
���c�w�̕��Ր��@�i1973-93-26�t�[���u�����V���v�j�@
�����̐��_�Ƃ͉����@�i1973�u�H���u���{�y���{�l�v�j�@
�@�@���m���c���j�E�܌��M�v�E�a��h�O�E���@�x�ɂ��ān�@
�u����ꂽ���l�v�̂܂Ȃ����@�i1972�l�w����F��S�W�x�攪���A����j
�܌��M�v�Ɠ쓇�@�i1973-6�u���㎍�蒟�Վ������v�啝���e�j�@
�@�U�@
�����q�Y�ɂ�����쓇�@�i1973-10�u�����w�\���ߋ��ނ̌����v�j�@ |
�����̗��l�E���X�V���@�i1971-9�w�����̌Q��8�x�����j�@
㹓�̕ێ��`�@�i1974�u�H���u���{�y���{�l�v�j�@
���{�l���Ǝ˂���َ������@
�@�@���i1972-6�w�ߑ㖯�O�̋L�^5�@�A�C�k�x����j�@
�������Ĕ�ԁ@�i1972-11-20�t�u���{�Ǐ��V���v�j�@
�@�V�@
�҂��Ƃ̂ł���l�@�i1972-1�w�ђB�v����W�x��Z���A�����m�[�g6�j
���˂Ȃ��ߌ��I���w�ҁ@�i1973-3-5�t�[���u�����V���v�j�@
�@�@���m�[�Y�ɂ��ān�@
�j�Ə��E���ƒj�@�i1972-1�u�����S�ȁv�j�@
�����I�s�@�i1972-10�u�ʍ����㎍�蒟�v���V�O�j�@
���Q�̍c�q�����@�i1971-11�u���j�ǖ{�v�j�@�m���ǐe���ɂ��ān�@
���Ƃ����@
���o�ꗗ�@ |
�P�O���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (5)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@pid/4419215
|
�_�� ������W���J���^�c�����{�l�̌̋��Ƃ̉��M/�����/p1�`27
�_�� �@�����z���Ƃ��Ắu�_�A�V���M�v�Ɋւ��錤��/��������/p28�`38
�_�� ����V���[�}�j�Y���̓��� / ��]�F�q�v/p39�`59 |
���]�ƏЉ�/�a�c�v�� ;���씎 ;�͖�~��Y ;���`��/p60~71
�쓇�W�����ژ^ / ����W�`/p72�`75
��L��/p76~78 |
�P�O���A�R���ӈꂪ���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 96) p.49�`63�v�Ɂu�����̓����������b�ɂ���-1- (�������|���W��)�v�\����B�@
�P�O���A �w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 11(1)(42)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B
�@�@pid/4437756�@�d�v
|
�u���R���Ӂv���`�E�����J蓐_�b�̎j���ᔻ�I���� / �O�钼�q/p1�`37
�쓇�É̗w�̉̌`�̌n�� (��) / ����d�N/p38�`47
�������̌����Ƌ��� / ���|����/p58�`74
�і���d�Ɠ��--���ꌧ�y�n�����@�𒆐S�ɂ���/�e�R����/p75�`92
�u�ӂ߁v����u�Q��v��--�R�V�����̏������� / ��������/p93�`93
|
�Ꮡ�]�� �w�ɔg���Q�S�W�x�ɂ悹�� �ɔg���Q�_�̉ۑ�--
�@�@���w�ɔg���Q�S�W�x���E�ɂ悹�� / ���Ǒq�g/p108�`114
�w��j���[�X/p107~107
���s�j���[�X/p114~
�E |
�P�O���A�������ҏW�u���`�������L�^ �|�\�� 3 (�����|�\ �����E�����{)�v���u���@�K�o�Łv���犧�s�����Bpid/10259293/
|
���L �t (�t�C�������R�[�h1��)
�����ɂ��� �{�c����/14
�k�C��
����̎��q��/20
���f�̋�x��/22
�X��
����O�����S�x��/24
�����ȂԂ�r�n/26
��l��̓암�Օ�/28
���ق̓암��x��/32
�Ìy���q�x��/36
�����̗x��/38
�����̌{��/42
��茧
���̎��q�x��/44
�ԑ�Z����/48
�s��X�̌����t���������x��/50
���̋S����/52
���×��߉H�ߎ��x��/54
�㑾�c�̂��x��t�͂₵��/56
�ߐ�O������/60
�����̐��q����/62
�c�씨�̎��x��E����/64
�i��̑�O������/68
��q�̋S����/70
�����̐��q����/74
����̎��x��/76
�{�錧
���R�c�₷�Ƃ�/80
�F�쓰�\��_�̎��x��/82
�H�c��
���R���q/84
��B���䋟���X�y/86
�ˑ���/88
���n�����̖~�x��/90
���Վu�Ύ�L��x��/92
|
�R�`��
����̎��q�x��/94
�������x���O��/98
������
���킫�����O���x��/100
����̑�q���q��/104
���r�̎��q��/106
���͓V���O��/108
�{���̉Ԋ}�O���x��/110
���n�̗x��/114
���c�̉�Ö~�x��/118
���܂̎O�C���q��/120
�Î��R�̎���y/122
��錧
�Փ����q/128
�^�Ƃ݂̂��ܗx��/130
�Ȗ،�
�֔����q��/134
��L��/138
��������q��/140
��n�̂����玂�q��/142
�Q�n��
������/144
��q��/146
�J���J���x��/148
�؍艹��/150
�ʑ��̉��M����/152
�������q��/154
��ʌ�
�������̖���x��/158
��z�̂����玂�q��/162
���ԋv���̎��q��/164
�������/166
���n���̎��q��/168
�F��̂����玂�q��/176
�������x��/178 |
��t��
���ΐ_�Ђ̉ԗx��/182
�k�V�K�J�̎��q��/186
���傱��/188
�F��݂̂낭�x��/190
���ēc�̎��q��/192
���������x��/194
���ԒÂ̂�����x��/196
�����q��/198
�����s
��X�̐��~��/200
���䓇�̊~���x��/202
�P���̕�/206
�_�ސ쌧
����������x��/210
�Y��̌x��/212
��������/214
�e���̈����x��/218
�`���b�L���R/220
���{��̎����x��/222
�g�l�̎����x��/224
�V����
���q��/226
���̏����q��/230
�p���q���q/232
���n�̉Ԋ}�x��/234
���n�̏t��/236
��̍�x��/238
�V��M���̋S����/240
�x�R��
��O�V�x��/242
�܂��R�̗x��ƉS/246
�ȎR�̐V��Ñ�_/250
�����̉z�������x��/254
�ē��x��/256
�E |
�ΐ쌧
��K�̂����x��/258
�����ߗx��/260
����̂��x��/262
���䌧
�r�͓����ۗx��/264
�_�l���q/266
�H���]�x��/268
�R����
�����̏t��/270
������̔O���x��/272
�����̎��q��/274
���쌧
�Օ��̗x��O��/276
���x��/280
�₫�����x��/282
�a���̔O���x��/284
��
���̖_�̎�/286
���q�x��/288
����d�����{�|/290
�S��̖~�x��/292
�J���x��/296
�g��̋n�U��x��/298
�D�Â̖~�x��/300
�����_�Ђ̐_���|�\/302
����
�M�C���{�_�Ђ̎����x��/304
���c�̎����x��/306
�����̎����x��/308
�q�[���C������/310
����̖~�x��/314
���m��
���n�̖�O���Ɩ~�x��/318
��C�̕���/322
�c���̔O���x��Ɩ~�x��/324 |
�P�P���A�|�\�w��ҁu�|�\ 16(11)(189) �v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276384�@�d�v
|
�����̂��Ƃ���׃��[�h�������̕���/p9�`9
狋�Z�̂̕��y--���-22- / �����_/12�`18
�a���̔O������(���Ɉ��쒬) / �����_/19�`24
�̕��ꉹ�y�W��-94- / �n���h���q��/31�`35
�}���]�̕��X������ / �����䐴��/36�`38�@�@
�b�����ƂΥ��b-6-�����̖��� / ��������/25�`30
�A���n��E�B�[�N�q�ʐ^�ƕ��r�A�����J�̍Ղ�(9) / �F����o�j/p50�`51
�|�\�W�] / ����p��/p52~53
�V���Љ�Ɣ�] ���a�j����K��j ���c�A�W�I��{�c�o��
�@�@������������n���h�u�b�N� / �q�c��/p39�`39
���c�璘��~�x�肭�ǂ�� / ��쌚��/p40�`40
����K�Y����z�n������ / ����G��/p41�`41
��������|�\�������Ң���|������ / ���c�m/p42�`42 |
�����N�\(10��1���`10��30��) / �|�\ �w��/65�`72
���x�N�\(���a49�N������) / �@���q/60�`64
���a49�N�x�|�p�ՎQ����i����^����/p54�`58
���R�[�h�]������ / ���c��t�F/p59�`59
�V���ēࢌÊG��݂̂����\�\���Ɠ`���/p46�`46
������`���I�\���̃G�l���M�[� / ��،�/p43�`43
���x����x�̑N�x� / �m�����Õv/p44�`44
���y��ē��G�Y�̎�� / �{��c��/p45�`46
�\����L�c������ׂ��炸�/p47�`47
�m����W�[����Ƣ�R���V�F���W����� / �����/p48�`48
�\�̔\����/p49~49
������(1�E2)/p73~74
�V�����ē�/p75~75 |
�P�P���A�V���{����}���ҁu���Ƃ̂� : �����E�����E�l�ÁE�l�� ��1���v���u�V���{����}���v����n�������B�@
�@�@�����F��㊌����}���فF1005653744
|
[�����m�[�g]
�͂Ԃ��̐A���w ���a�c�^�~ p83-88
[�ʐM] |
����ʐM
�q�ɕ������r �O�� �i p134-136
�E |
���A���̔N�A�͑����Y���u��������̒T�� : ���ŏ����ꂽ���ꖯ���j ���v���u���ꕶ���o�ŎЁv���犧�s����B
�@�@pid/9770580
|
���� �c�NJԂ̓��X/1
�� �܂��ї�����/3
�� �u�ό��c�v�Ɓu���̂낯���v/8
�O �����j�݂Ɠ����_��/11
�l �c�NJԌQ���̓W�]/13
�� ��Í��Ԗ�����/15
�Z �u���Ԗ��̌Î��L�v�̐���/18
�� �c�NJԂ̔n/28
�� ����̉Y/32
�� �Y���̂��߂Ȃ�/34
��Z ���Â̂��Ԃɉ�����_�l�I���c/37
��� �u����v�̐_��/42
��� �u����v�̔鎖�̖\�I/46
��O �c���Ԃ̒������̍s��/51
��l �u����v�̃I�����̍̏W/55
��� �n�Õ~�̛ޏ��̑g�D/60
��Z �V�l�Ə��q������̌c�NJ�/63
�ꎵ ���S���ƃf�C�S�̉�/67
�ꔪ �c�NJԓ�̃N���M/72
��� �߂����ĉ����O��/76
��Z �����ƕW����̖��/80
��� �ނ���/87
���� �����E�n����I�s/89
�� ���������/91
�� �����̐_��/94
�O �����̑c��ՁE�O�[�V�[��/96
�l �����l�̈ʔv�̈��/98 |
�� �����̂�����/102
�Z �W�������锪�\�O�Ή�/107
�� �Ɩ{�ʌď̖@�Ƃ��Ă̈����̉���/111
�� �����l�ɍ���/115
�� �������n�����/120
��Z �n����l�̌ւ�/122
��� �n�u���ꂳ��/124
��� ���n�����̍\��/131
��O �n����́u�����Q�[�V�v�Ɓu�l����v/134
��l �̖��/137
��� �����ɉ�����u�C�G�X�E�m�[�v�̖��/142
��Z �ނ���/153
��O�� �ɕ����̓��X/157
�� �͂�����/159
�� �����ɉ����閄���̍���/163
�O �ɐ����̑�����/167
�l �j�l���̔q��/171
�� �����̒呀�тƂ��Ắu���[�`���v�̕R/175
�Z ��u�쓇���o�Ė�ᓇ��/183
�� �����E�������M�̖�ӂ�������/187
�� �������̓`��/191
�� �ɕ����̓`���̒n�����Â˂�/197
��Z �ɕ����́u�V�≮�v/200
��� �ނ���/205
��l�� �����̓��X/207
�� �܂�����/209
�� ���̕s����/210
�O �Ɍv���̌܌��E�}�b�`�[/216 |
�l �u�̐_�v�Ƃ肩��/220
�� �䂪���ŏ��̔��N���`������/225
�Z �����͂Ȃ/228
�� �\�܂̏j/231
�� ���������̌ØV/233
�� �����̐N�h/237
��Z ���̒��炵����/240
��� �V�k�O��/245
��� ���l�̋��l���̕��z/248
��O �L���X�g���ɉ��@����
�@�@���ʏ�́u�m���v/253
��� �����̓��X/259
�� ����n���w�Z�́u���y�ǖ{�v/262
�� ᚉ@�E���y����ᚂɊւ�����M/269
�O �ÉF�����̔q��/274
�l �ÉF�����̐_��/278
�� ���̔q���̐_�Љ��̖��/282
�Z �A�I���G�i�̌���/286
�� �ɍ]���̎q���{�ʌď̖@/288
�� �����Ȃ��ʔv/295
�� �ɍ]���G�i���^�j/297
��Z ���߂�����I����/299
��Z�� �I�s�ɂ�����/301
�� �܂�����/303
�� �v�ē��I�s�ɂ�����/304
�O �{�ËI�s�ɂ�����/309
�l ���d�R�I�s�ɂ�����/317
�� ���_�ɂ�����/322 |
���A���̔N�A�u�����̖���:�������Ɩ��������ً}���� ���ꌧ�������������v���u���ꌧ����ψ�����ہv���犧�s�����Bpid/9769051�@�@��������:
���a48�N7��19��-8��31��
|
���� �ÉÎR���g
���������ً}�����̒����T�v
1.�߁E�H�E�Z ���~�ߎ�/5
2.�����ɂ����鋙�� ��]�F�� �O���v/17
3.��ʁE�^�A�E�ʐM�E���ՁE�o�҂� �茴�P�V/41
4.�Љ�� ��Ð��v/63 |
5.�����m�� ����P/69
6.�����|�\�E��y�E�V�Y�� �X�ۉh���Y/72
7.�l�̈ꐶ
�����̎Y��Ɛ��N�j�� �����Y/78
�����̍������� �����Y/81
�����̑��� ���Ð^�X��/90 |
8.�N���s�� �N�㌳�Y/98
9.�����`�� ���Ԉ�Y/106
10.���� ��]�F��/111
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�N�㌳�Y, �R���ӈ� �����u����E�����̖��ԐM�v���u�������[�v���犧�s�����B�@pid/12168852
���A���̔N�A�����Y���u�������j��b : �������j�̗��ʂ��𖾂��� ���v���u���ꕶ���o�ŎЁv���犧�s����B�@
�@�@pid/9770114
|
�� �s��Ə�/1
�� �ߐ�����l���j�̓�/17
�O �Y�Y�̗��j�̒T��/45
�l ���������̍�������/71
�� �F����z�ƎF����/87
�Z ��������̊Ԉ����K/91
�� ����̎��R�ƕ���/95
�� �������I�ȗގ���/106
�� �ʏ钩�O�̐l�y�ь|�p/115
�\ ���d�R�Ì��n���ɂ�����
�@�@�����Ƃ��̐M�s��/121
�\�� ����̏@��/137
�\�� ��ԂƐ_�X/156
�\�O �g�D�V�r�[�j���̖���/167
�\�l ��Ֆ��ь��͖͋[����/184
�\�� ����̔N���s��/214
�\�Z ����̖����|�\/221
�\�� �v�����̃C�U�C�{�[��/234
�\�� �����ƒ呀/259
�\�� �����̖K�k�i�����j/266
��\ �n�[���[�����s���̌n��/276
��\�� �����̃n�[���[/286
��\�� �V�k�O�ɂ��Ă̊o������/294 |
��\�O �^�i�o�^�Ղ̓�d�\��/313
��\�l �_�b�̖����w�I����/338
��\�� �ʔ����̕���W/353
�����̎g��/353
�_�l�̖�����b/355
�ŏ��ɍs����҂�/357
���悯�����Đ_��/359
���{����A�������̘b(1)/360
���{����A�������̘b(2)/362
�L���}�����̌Y��/364
�ܒ���l�����^/366
���ʂ̑�Ȃ�_/368
�@�ƌ䊥�D/370
�@�x���ƃn�u/372
���̊C���x�ߊC/374
�_�̍ȁi���j/376
�_�T�T�M/378
�d���k�`/380
�L�W���i�[�̉����b/382
�����̓����/384
�����̓u��/386
���⓰�R��/388
���A�̎���/390 |
�T�ɏ�����ꂽ�c��g/392
��ɏ�����ꂽ�i�v�g/394
����ގ��`��/396
�I�e���c�敨��/397
���̉œ���/399
�ׂ̐Q���Y�E�����/401
�S��������̒E�o/403
�ÉF�����_�b/405
���ɉ������V�v�w/406
����ŁE�Y���`��/408
���̌������`��/410
���n���̌p�q�`��/412
�Ԕт�������N���s��/413
����̉H�ߓ`��/415
�Ղ̋N�����b/417
�j�����̋N��/419
�J�W�}���[�̏j��/421
�Õ��Ȍ����̘b/423
�g�D�V�r�[�ƒ����j��/424
���~�̈ɐ����E�o/426
���X���̓쓇�T��/428
�E
�E |
���A���̔N�A���a�c�^�~���u����̎j�ՁE�������v���u���y�L�Ёv���犧�s����B�@pid/9769465
|
������
���~�o��������/4
�V����/6
���䉮����ԐΖ�/8
���������Ζ�y�ѐ��/9
�ʗ˕�ː��/10
�����ƏZ��/12
�������Ԑؑ������/13
��]�F�ƏZ��/14
���{�Ǔa��/16
�������_�a/17
������/18
�V�@�{/20
���\��/21
�ɐ����ʌ�a/22
�����m�Ƃ̕�/23
������/24
�q�W�싴�y�ю�t���H/24
�m���^�ǖL���e�̕�/26
���i�̕�/26
�������/28
�ɑc�̍����/28
�ى��r�Ă̂ڂ�q�����/30
�����̋v���/31
�j��
���A�m���/32
���얡���/34
���c�����/35
���A���/36
�m�O���/37
������/38
���/40
�������/41
�~�o����/42
��u����/43
���g�{��/44
�֏���/46
�كK��/47
���K�y�т��̎���/48
�F���l���/48
�썑���ǂ̕�/50
���~�����a�n���~���݂ق���/50
�h�C�c�c�锎���L�O��/51
�����H�n���L/51
���@���L���e�̕�/52
��䉮�R���/54
�쌴�x�̗��/55 |
�ɐ������/56
���~�悤�ǂ�/56
�����̑��/58
���A�m�������n��/59
�������/60
�약�L��/61
�ʏ���/62
�_�ԏ��/63
�ɑc���/64
�ɔg�L��/65
�����L��/65
�v�ē��匴�L��/66
���c���L��/66
�R������ꓴ��/67
����n�^�V���T�o���L��/67
�썑�L�ˌQ/68
����L��/68
�������L��/69
�Đ{�L��/69
��R�L��/70
������/70
���ԊL��/71
�����L��/71
�Y�Y�L��/72
�l��L��/72
�ɔg���/73
�ɕ~�����/74
��u����/75
���钬�Ώ���/76
�ɍ]�����̉���/77
�É�m�ėq��/78
�F�]����/79
�E�e�B�_��/80
����
���̑�/81
������/82
�Ί_�ƒ뉀/83
�ɍ]���̏�R/84
�X��p�s�̐X�̐�/85
�V�R�L�O��
���g�̃^�i�K�[�O���C�̐A���Q��/86
�^�ߔe�x�V�R�ی���/87
�c�`���̐A���Q��/88
�c�����p�̃q���M��/89
���u��Ԃ̐A���Q��/90
����/91
����̑�A�J�M/92 |
�������̃V�}�`�X�W�m�������n/92
�Č��̃��G���}���V�Q��/94
���v�ۂ̃��G���}�V�^��/94
�r��̃J���q�U�N�������n/96
�{�ǐ�̃q���M��/97
�����V�R�ی���/98
�D�Y�̃j�b�p���V�Q��/100
���Ԑ�V�R�ی���/101
�E�u���h���̃��G���}���V�Q��/102
���܂������̂�/104
����̂Ђ�Ղ��܂�/105
���A�m�����e���̂��Ă���/106
���܂⓴����/107
�c���̃N�o�R/108
�O������/109
�ɐ�����Ղ̊⏼�̌Q��/110
�D���̃��G���}�n�}�S�E/111
�v�Ă̌}�̏�/112
�F���̑�\�e�c/114
�{����Ԃ̃����E�L���E�`�V���m�L/114
���g�̃T�L�V�}�X�I�E�m�L/116
���~���x�c��̃n�}�W���`���E�Q��/117
�������������̏���/118
�����ѐΊD��A���Q��/119
�������^�ӂ̃`�����t�N�M/120
�ÒÉF�x�A���a�x�A���d�x�V�R�ی���/121
���l�o����Ԃ̈��M�ъC�ݗ�/122
�{���O�̌�Ԃ̃n�X�m�n�M����/123
�m�O�`�Q��/124
�����E�L���E�L���o�g/125
�P�i�K�l�Y�~/126
�g�Q�l�Y�~/127
�C���I���e���}�l�R/128
�W���S��/129
�J���������V/130
�����Ђ�/131
���̐_���C���ɐB�n/132
�P���}�W�J�y�т��̐����n/132
�ӂ������傤/134
���̂͂��傤/134
�哌�I�I�R�E����/135
�Z�}���n�R�K��/135
�����E�L���E���}�K��/136
����̗L�`�������ɂ���/137
���E���w�蕶�����ꗗ/139
�E
�E |
|
| 1975 |
50 |
�E |
�P���A�{���Еҁu�����{ : ���߂Ƌ��ނ̌��� 20(1)(273)�@���{�̐_�X(���W)�v���u�{���Ёv���犧�s�����B�@pid/8099317
|
���{�̐_�X(���W)/6�`155
�Βk �_�X�̍�--�_�ϔO�ɂ�����W�� �_�ϔO�Ɖ�����
�@�@���Η��ƒ��a�\�[�Ԃ̖�� ���L�ƃV�e�\�\�Ɛ_�X �́E����E
�@�@���ٌ`�� / �R�����j ;�n�ӎ��/p6~28
�_�X�̌��Ɖe--���{�_���j�̎��� / ���c�C/p29�`37
�u������_�v�Ɓu�����Ȃ��_�v / �����p�v/p38�`44
���{�_�b�̔w�i / ��c����/p45�`52
���Z�A�_�ւ̕ϐg / �S�i����/p53�`59
��r�_�b�w�I���/60�`78
��r�_�b�w�I��� �ă��[���V�A�I�ϓ_����-
�@�@���ڂ��琶�ꂽ���z/��ё���/p60�`65
��r�_�b�w�I��� ���N�_�b����̏Ǝ�-
�@�@���_�d���ƓV�̌䒌�𒆐S�ɂ���/������/p66�`70
��r�_�b�w�I��� �쓇�̐_�̍\��/�R���ӈ�/p71�`74
��r�_�b�w�I��� ����A�W�A���� �s�[�ƌ��/�ؕ�/p75�`78
���{�̐_�̋@�\/80�`116
���{�̐_�̋@�\ �Ñ�l�̍��ɂ��� / �J�쌒��/p80�`86
���{�̐_�̋@�\ �J��グ�J����Ă̍\�� / �{�c�o/p87�`94
���{�̐_�̋@�\ ���w�ɂ�����_�̈ʑ�-
�@�@���{���钷�𒆐S�� / �������Y/p96�`104
���{�̐_�̋@�\ ���c���j�̐_ / ���J�s�l/p105�`110
���{�̐_�̋@�\ �M�헬��杈Ȍ�-
|
�@�@���܌��w�̓W�J/���]����/p111�`116
��w�Љ�̐_/118�`131
��w�Љ�̐_ �j���|�̐_�X / ����/p118�`121
��w�Љ�̐_ �ޗ��̐_-
�@�@���Y�B�̂�܂̐_���߂�����/�X��a�]/p122�`126
��w�Љ�̐_ �}�^�M�̐_ / �ː�K�v/p127�`131
�_�̕��i��/132�`139
�_�̕��i�� ���̂ɂ��_�̕���-�I���X�g�̏ꍇ/���\�Y/p132�`134
�_�̕��i�� ���ΑK�ƕ��i / �Ύq����/p134�`137
�_�̕��i�� �Đ��Y�����_�X-
�@�@��㊕��Ɩ퐶�̂��킢��/�c���_/p137�`139
�_���̌n��/140�`155
�_���̌n�� �k��V�_���N / ����D�N/p140�`141
�_���̌n�� �����P / �哇�L�u/p142�`143
�_���̌n�� �_���W / ���c�a�v/p144�`145
�_���̌n�� �����_���L / �c����v/p146�`147
�_���̌n�� ����̎� / �͑��m�q/p148�`149
�_���̌n�� �l�۔閧�� / ���h���}/p150�`151
�_���̌n�� �c�������� / ����O�q/p152�`153
�_���̌n�� �D�C���L / �v�c����/p154�`155
��
�E |
�P���A�R���ӈꂪ���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 97) p.p55�`72�v�Ɂu�����̓����������b�ɂ���-2-�v�\����B
�P���A�P�c�r�ܘY���m�җ�L�O�_���W�ҏW�ψ���ҁu���{���w�̓`���Ɨ��j�v���u�����Ёv���犧�s�����B
�@�@pid/12450872
|
�`���Ƒn��-�Ñ㕶�|�̐���(��v�Ԋ��Y)
�W�C���̕���(���䖞)
�u�ꔒ���Y�̌Q-��̌��`�̐���(�n������)
���Ȃ�����z-�Ǝ��Ɨ��l(���蒨�i)
�������Ӌg���C(�������H)
�̌o�W���̈Ӗ�-����Ȍ�ƗV�y�V���_(�R����)
�̕���ɂ�����u�a�̂̍��v(���c���i)
�P�����̕lj�Ƙa��(�����P��)
���������ɂ��ā[�@�����ɂ�����
�@�@����M���̐l�̐��U(���@�Y)
�㒹�H�@�{�����̓��ِ�(��؉h�q)
�u�����v(���[�W)�A���̏��{�̐����ɂ��Ă̌���(�v�ۓc�~)
�w��Ɣ��㏴�x�_�_�̂Ɋւ����l�@(�㓡�d�Y)
�����@�E����v�W�̔��[(����F���C)
�V���a�̏W�{���Z������(�l������)
�u���̎R�v�����l-�钷�a�̂̋��\��(��v�ې�)
�̖��u�Z�ʐ�v��(�����ǗY) �Ԃ̓s(�����Z��)
���_�̖{����������
�@�@���[�����q�̗̉w�ɂ���(�F�v����)
���Ȃɂ������l���v�z�̎�e(������)
�����^�C�g�� ���̂̎l�G(�O����s�q)
�����̕�����(���䐴��)
���Ŗ@��l(���Ώ��v)
�Ջ�W�o��-��l�O�Ԃ��߂�����(�^�珹�O)
�u��c�V�́v(�ɐ��_�{���ɑ�)
�̎��͒���1-�u��������[�E�����́[�E���̕Ắ[�E
�@�@������藈��⒯���n�v�̎l�̎��͂ɂ���(�|�{�G�v)
�������N���ʁw�֒�_�Гc�A�́x�͋U�삩(�i��`��)
�����̍��l(���T�q) |
���{�̐_��(��������)
���Q���ɉ����郆�^�̛މ̂ɂ��ā[�������y�I�l�@(���c���q)
�쓇��a�̍l(�O�����Y)
�����˓`���ɂ�����ߌ����̓W�J(�扪����)
���ٕ���̍\��-����������̈ʒu�Â�(�����M��)
���ꂴ��y�����L��l�̎��(���J�p)
�єV�̏o��(�����q�v)
�Z���䑧���Ɣ��؎���(�O�ύ_��)
�[�畨��Ƌ�顕���Ƃ̐ړ_-
�@�@���u�_�b�I�v�҂̕���I�_���v�̖��(���іΔ�)
���������`�ɂ��Ă̍l�@(�M�u����)
�F���E�╨��ɂ����铐�l�ە���b�ɂ���(�t����)
�u�C������v�̓��s��-���i�@�t�̎���(���X�؍I��)
�w�`�o�����蕨��x�Ƌ`�o�L ����7(����w)
�������q�w�������x�̔w�e(�哇���F)
��ڗ������ߒ��ɂ�������b�I�v�f-
�@�@���u���@�L���v�̌n�����߂�����(�����t�~�q)
�w�P����͂Ȃ��x���l(�]�{�T)
�w�}�K�B��`�x(�@���\��)
�m�Ԉ��ɂ��Ă̈�l�@-�m�Ԉ��͒��c���O��(�������H)
���ؓc�ƕ��ƃL���X�g��-�`�L�̂��߂�(�ҋ��O�Y)
���C����̕��͌���(�b��m�b�q)
�킪���ɂ�����u�`��杁v�̕��ނɂ���(�c������)
���ߑ���(���Y) �_�E[�n��]�E[�R�E]�E�؝�-���̏��̎���(�V�C��)
���h�C�c�u���p�m���M�[�v�̓����ƍ��w(�q����)
�z��ݕ{���L�����u�Í����̏��v(�|���Ɖ��)(���c�G��)
��Α������̉�(��쌚��)
�P�c�r�ܘY���m����N��(��[��)
�E
|
�Q���A���ꌧ����ψ��� �ҁu���ꌧ�j ��6�� (�e�_�� 5 ���� 2)�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@pid/3026363
|
�����̂��Ƃ@
�@�@����㊌�����ψ���璷�@�r���b��
��l���@�|�p
���́@���y�@��Ԕ�
���߁@����/p5
���߁@�×w/p12
��O�߁@�O���y�̉萶��/p49
��l�߁@�|�p�̋Ȃ̒a���ƓW�J/p58
��ܐ߁@�ߑ�ւ̋��n��/p86
���́@�����|�\�E���x�@����^�@����
���߁@�����|�\/p95
���߁@���x/p141
��O�́@�����@�r�{�����@�X�ۉh���Y
���߁@�����ȑO�̉���/p171
���߁@�������Ɖ����̔����\
�@�@�����юŋ��O��/p190
��O�߁@�������Ɖ����̓W�J/p194
��l�߁@�吳�A���a���c�̋��S/p233
��ܐ߁@�������l���̐���/p241
��Z�߁@�m���l�̎Q��/p261
�掵�߁@�펞���̌��c/p263
�攪�߁@�����Ɩ��O�\���тɂ�����/p265
��l�́@���w�@�r�{�����@���{�b��
���߁@�����ȑO�̕��w/p275
���߁@�ߑ㉫�ꕶ�w�̏����/p292
��O�߁@�]�����̕��w�̏���/p301
��l�߁@���w�����̓W�]/p315
��ܐ߁@���тɂ�����/p363
��́@���p�@�ʓߔe���g
�͂��߂�/p371
���߁@��������̔��p/p373
���߁@��������̔��p��/p380
��O�߁@�吳����̔��p��/p397
��l�߁@���a����̔��p��/p408
�ނ���/p415
��Z�́@�H�|�@�O�Ԑ��K
���߁@�H�|�̊T��/p421
���߁@����/p426
��O�߁@����/p446
��l�߁@�g�^/p463 |
��ܐ߁@�D��/p475
��Z�߁@���̑�/p500
�掵�́@���z�@���g�^�O
���߁@����/p517
���߁@�Ñ㌚�z/p518
��O�߁@�i���㌚�z/p518
��l�߁@�������㌚�z/p520
��ܐ߁@����w�茚����/p617
��Z�߁@�p�˒u���Ȍ�̌��z/p638
�掵�߁@���z�p��/p643
���t�^�P��
���ꌤ���̏����Ƃ��̔w�i�@�V����P
�}��
��@���ꌤ���̏���/p671
��@�������y�̂Ȃ��̉��ꌤ��/p707
�O�@�[�֊��ɂ����鋽�y����/p921
�l�@���y����̕��y�Ƌ��y����/p992
�܁@���������̊T�v/p1057
���t�^�Q��
���ꕶ���j�N�\/p1071
�����̂��ƃo�@
�@�@����㊌�����ψ���璷�@�r���b��
��l���@�|�p
���́@���y�@��Ԕ�
���߁@����/p5
���߁@�×w/p12
��O�߁@�O���y�̉萶��/p49
��l�߁@�|�p�̋Ȃ̒a���ƓW�J/p58
��ܐ߁@�ߑ�ւ̋��n��/p86
���́@�����|�\�E���x�@����^�@����
���߁@�����|�\/p95
���߁@���x/p141
��O�́@�����@�r�{�����@�X�ۉh���Y
���߁@�����ȑO�̉���/p171
���߁@�������Ɖ����̔����\
�@�@�����юŋ��O��/p190
��O�߁@�������Ɖ����̓W�J/p194
��l�߁@�吳�A���a���c�̋��S/p233
��ܐ߁@�������l���̐���/p241
��Z�߁@�m���l�̎Q��/p261 |
�掵�߁@�펞���̌��c/p263
�攪�߁@�����Ɩ��O�\���тɂ�����/p265
��l�́@���w�@�r�{�����@���{�b��
���߁@�����ȑO�̕��w/p275
���߁@�ߑ㉫�ꕶ�w�̏����/p292
��O�߁@�]�����̕��w�̏���/p301
��l�߁@���w�����̓W�]/p315
��ܐ߁@���тɂ�����/p363
��́@���p�@�ʓߔe���g
�͂��߂�/p371
���߁@��������̔��p/p373
���߁@��������̔��p��/p380
��O�߁@�吳����̔��p��/p397
��l�߁@���a����̔��p��/p408
�ނ���/p415
��Z�́@�H�|�@�O�Ԑ��K
���߁@�H�|�̊T��/p421
���߁@����/p426
��O�߁@����/p446
��l�߁@�g�^/p463
��ܐ߁@�D��/p475
��Z�߁@���̑�/p500
�掵�́@���z�@���g�^�O
���߁@����/p517
���߁@�Ñ㌚�z/p518
��O�߁@�i���㌚�z/p518
��l�߁@�������㌚�z/p520
��ܐ߁@����w�茚����/p617
��Z�߁@�p�˒u���Ȍ�̌��z/p638
�掵�߁@���z�p��/p643
���t�^�P��
���ꌤ���̏����Ƃ��̔w�i�@�V����P
�}��
��@���ꌤ���̏���/p671
��@�������y�̂Ȃ��̉��ꌤ��/p707
�O�@�[�֊��ɂ����鋽�y����/p921
�l�@���y����̕��y�Ƌ��y����/p992
�܁@���������̊T�v/p1057
���t�^�Q��
���ꕶ���j�N�\/p1071 |
�Q���A�V���{����}���ҁu���Ƃ̂� : �����E�����E�l�ÁE�l�� ��2���v���u�V���{����}���v���犧�s�����B
�@�@�����F��㊌����}���فF1005899230
|
�C��̓� -�C���E�G�ߕ��E�������߂�����- �������� p21-33
�g�J���C�� ���،��a�� p34-39
�ٍl�u�쓇�̓��v �ēc���F p53-57
�{�Ó����߂���C��̓� ���{�b�� p64-68 |
�X�r�ƃX�r�P���Ղ̂��� �O���i p86
�q�A�ځr�쓇�̓ƖؑD 1 ��q���̊ۖ؏M ���W�� p87-89
����ʐM�q�g�Ɗԓ��r �V��S�g p92-94
�E |
�R���A���ꌧ�������ٕ� �u���ꌧ�������ًI�v (1) �v���u���ꌧ�������فv����n�������B�@�@pid/3467944
|
�u�����I�v�v�̑n���ɂ������� / �O�Ԑ��K
�̐Ί��� / ��]�F�� ;�{��Đ�/p1~18
���@�x�̉��ꕶ���_ / �n���얾/p19�`28
�����Љ� �m�O��N���N���L�ˍ̏W�� |
�@�@���L���i�ɂ��� / �V�c�d�� ;����N/p29~35
�O�V�N����J�n���̎�̖��ɂ��ā\�\
�@�@���v�ē����W���[�K�}��Ղ̒������� / �����i/p36�`54
���ꌧ�Y�̎�ȉ��� / ����N/p55�`70 |
�R���A������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v ���(18)�v���u������w����w���v���犧�s�����B�@�@�@�@pid/2259152
|
���x�F�m�̈Ӗ��_�I����-1- / ������q ;���X��/p27~39
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-3-�������x�̔F�m�\�� / ������q/p41�`60
���T�Ɋւ���S�������w�I���� / ������/p153�`160
�S�g�̓���Ɋւ���S���w�I���� / ������/p161�`172
|
�H�i�����Ɋւ��錤��--����Y�H�i��
�@�@����ʐ������͒l�ɂ��� / �O�Ԃ䂫 ;�j���q/p195~200
�q�����r
�E |
�S���A�R���ӈꂪ���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 98) p.p68�`78�v�Ɂu�����̓����������b�ɂ���-3-�i���j�v�\����B
|
�R���ӈꂪ�u���{�����w (�ʍ� 96�`98) �ɔ��\�����u�����̓����������b�ɂ���-1�`3-�v�ɂ��Ă̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 96) p.49�`63 |
1974-10 |
(�������|���W��)�@�����̓����������b�ɂ���-1- |
| 2 |
(�ʍ� 97) p.p55�`72 |
1975-01 |
�����̓����������b�ɂ���-2- |
| 3 |
(�ʍ� 98) p.p68�`78 |
1975-04 |
�����̓����������b�ɂ���-3-�i���j |
|
�S���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (6) �v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@pid/4419216
|
�_�� ������j�ɑ���^��--�w�V�����̐�����
�@�@���������̑哇�����Ɋւ��� / �{��h��/p1�`9
�_�� �g�x���{�̍l�@ / ���Ԉ�Y/p10�`25
�_�� �\�Z���I�ɂ�����J���{�W�A��薎����F�g�i���̐ڐG�ɂ���--
�@�@���J���{�W�A�N��L�𒆐S�Ƃ��� / �v���R���q/p26�`39 |
�_�� ����̐e�������F���̕��@�_�̌���(����2) / �n�ӋӗY/p40�`55
���]�ƏЉ� / �X�ۉh���Y ;��]�B�q�v ;��ӋԈ�/p56~63
�쓇�W�����ژ^ / ����W�`/p64�`69
��L��/p70~74
�E |
�S���A���a�c�^�~���u�k���̐A�� = The Journal of Geobotany 22(4) p.54-57�@�k���̐A���̉�v�Ɂu�����A�������^ (��)�v�\����B
|
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
���e |
| 1 |
. |
. |
. |
| 2 |
. |
. |
. |
| 3 |
. |
. |
. |
| 4 |
. |
. |
. |
| 5 |
. |
. |
. |
| 6 |
. |
. |
. |
| 7 |
�k���̐A�� 19(1�E2) -15 p.31-39 |
1971-01 |
�����A�������^ (��) |
| 8 |
�k���̐A�� 22(4) -15 p.54-57 |
1975-04 |
�����A�������^ (��) |
| 9 |
. |
. |
. |
| 10 |
. |
. |
. |
|
�@�@�@���@�����A�������^ (��`�Z)�܂��㍆�ȍ~�ɂ��Ė��m�F�@�Q�O�Q�R�E�U�E�P�W�@�ۍ�
�T���A���a�c�^�~���,���Ǒ�v�B�e�u����̎R��̉ԁv���u���y�L�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@144p �@�J���[�ʐ^�@�@161��
�U���A�������ҏW�u���`�������L�^ �|�\�� 4 (�����|�\ �����E�����{)�v���u���@�K�o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@���i���ꌧ���܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�j
|
�O�d��
�~����㹌ۗx��/14
�����̂������x��/19
�}���̂��x��/21
�R���̐_���x��/23
���ꌧ
�����̑��ۗx��/26
�����_�Ђ̏��x��/29
�k���̑��ۗx��/3
���͓��̑��ۗx��E�z�U��/34
���_�_�Ђ̑��ۗx��/38
���s�{
�o�_��_�{�̉ԗx��/40
���{�̂₷�炢��/43
�≮���ǂ�/46
�]�K�̑����U��/48
�{�����ڗx��/50
�͖ʒn�x��/52
���k�̍����q/54
�c�R�̉ԗx��/56
���{
����x��/59
�Z�g�x��/61
��_�J�̂����ǂ�/63
���Ɍ�
�H�ÕS�Ηx��/65
�����̕�����x��E���x��/67
��˂̕����_�x��/70
��v�ۗx��/73
�吙�̂����x��/75
�v�J�̂����x��/79
�V�@�t�x��/82
�����̂����x��/85
�ᐙ�̂����x��/87
�ޗnj�
�\�Ð�̖~�x��/89 |
�a�̎R��
�~�x��/91
���挧
�����̎P�x��/93
�z�H�̉J��x��/95
�����Ƃ肳���x��/99
�͂˂��x��/102
�Q�l�x��/104
���R��
�����̓��q�x��E�����x��/106
��{�x��/108
���Ηx��/110
�K����/114
�{���x��/116
�L����
�V���̓��x��/118
�̎R���ǂ�/120
�{�n�̉Ԋ}�x��/124
�݂����肨�ǂ�/126
�R����
�ԍ�_�Ђ̊y�x��E���x��/128
�N����x��/131
����̔O���x��/133
����̉Ԋ}�x��/136
������
�\�䎁�_�Ђ̐_�x��/139
���c�J�̐_��x��/142
�R�쒬�_����x��/146
�R�͓��|��x��/149
�R��̏ނ��ǂ�/151
���쌧
�����̈��q�x��/153
��{�O���x��/156
�k��O���x��/158
�슛�O���x��/160
�E
|
���Q��
���̖~�x��/163
�����x��/166
�E�c�喾�_��x��/168
�������̑D�x��/174
�p����̖~�x��/176
���m��
���_�Ђ̐_�x��/178
�얔�̉Ԏ�x��/182
�V�b�g���g�x��/185
�R�k�_�x��/189
������
�����y/191
�c���̏�y/193
�t������/196
�����y/198
���y/201
��������x��/203
�͂�║�E����/205
���ꌧ
�ꐺ����/208
�F�y��̍r�x��/210
�����̖ʕ���/214
�����̍r�x��/217
���x��/221
�쌴����/224
�s��̓V�Օ�����/227
�{���̕���/231
����̏�����/235
�e��̑�O��/237
���茧
�L��~�g�x��/239
��F�����ۗx��/243
�I�[�����f�[/245
������������/247
���~�x��/249
|
�F�{��
�]�Ô��̖~�x��/255
���̑��̕Z�\��/257
�܉Ƒ��v�A�q�x��/259
���ėx��/261
�Ȃ�Ȃ�Ȃ���/263
�l�g�̉P���ۗx��/265
�{�Y�̖_�x��/268
�@�����s/271
�啪��
�ˊy/273
�g�O�y/277
�瑩�y/279
�ҊԊy/282
�{��y/285
�{�茧
�����x��/288
�܃����̍r�x��/291
�������̉P���ۗx��/294
�ו��x��/297
�����̖_�x��/299
�֑��ۗx��/301
��������
�����哇�̔����x��/304
��Y���̑��ۗx��/307
�\�ܖ�\�����C/309
��R�c�̑��ۗx��/312
���R���̔����x��/314
��x��/317
���R�̋����m�x��/319
���Z�x��/321
�R�c�y/323
�E
�E
�E
�E |
�V���Q�O���`���N�P���P�W�����A�u���ꍑ�ۊC�m������v���J�����B
�@�@�i����ԊҁA���ꌧ�̓��{�{�y���A�L�O���ƂƂ��ĉ��ꌧ�����S�{������183���Ԃɘj���čs��ꂽ�B
�V���A����Y�ҁu����������̕��y�v���u���������v���犧�s�����B�@�@pid/9770081
|
����̂����ڂ́^����Y/6
����������̕��y/9
���j�Ǝj��/25
�C�m�����̗��j�^��闧�T/26
�`���H�|�ƕ����^�O�Ԑ��K/41
�g�^/49 |
�R/55
����/61
����/67
����̌���/73
����̌o�ρ^�R�����W/73
����ƊC�m�J���^��ǕF/90 |
����Ȃ�����̖����^����Y/94
�킪����^���{���Y/99
�킢�̂���/105
�߂������̂��Ɓ^�]�숻�q/106
���Ƃ���/110
�E |
�V���A��Î����u���w 43(7) p.p775�`789�v�Ɂu������̓lj�@�ɂ���--������ǖ@�̖��_�v�\����B�@�@
�V���A�V���{����}���ҁu���Ƃ̂� : �����E�����E�l�ÁE�l�� ��3���v���u�V���{����}���v���犧�s�����B
�@�@�����F��㊌����}���فF1005653751
|
�{�Ó��̃E���K����(�}��) p8
�V���}�j�Y���̏���� -���ɃV���[�}�j�b�N�E�g�����X�𒆐S�Ƃ���-
�@�@������ �����Y�^�� p21-33 |
�o���̛ސl �������� p39-41
�쓇�̓Ɩ؏M 2 �����哇�̃X�B�u�l ���W�� p100-102
�����m�[�g �}�^�_�̋G�߁@-�A���̃V�k�O���_- ���n�B�� p156-163 |
�W���Q�S���A����s�^������(���㋣�Z��)�ɉ����ĉ���s�S���G�C�T�[�R���N�[�����J�Â����B
�W���A����s�ҁu����s�S���G�C�T�[�R���N�[���J�×v�j ��2��v���u����s�v���犧�s�����B
�@�@�@�@�p���t���b�g�o�C���_�[ �����F���a50�N8��24������ �ꏊ�F����s�^������(���㋣�Z��)�@�@�����F���ꌧ���}����
�W���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu ����{���� (8)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����Bpid/7931788
|
���˓��������w�p�����ɂ��� / ���V�a�r/p1�`16
�n���I�ɂ݂��������˓��n��̉ߑa / ��،�/p17�`29
�������˓��̖��w / ���c���q/p31�`46
���˓����̎Љ�̈�̎��� / �R���F��/p47�`62
���˓����̖��� / ���c�m�q/p63�`78
�������˓����̗���̓�����--
�@�@����ɚM���E���E��E�����ނɂ��� / �X�c���`/p79�`86
���˓����̒��� / �v�ۖM��/p87�`111
�������˓�������x--�g���{���Ƃ��̕����ɂ���/�����a��/p113�`125
|
����E�������K���E���Ƃ���/p126�`129
�����Q���X���̎�̓I�Ȋ����ɂ��Ẵm�[�g-
�@���u���V���㊯�L�W���v�L���̏Љ�𒆐S�� / �O�ؖ�/p1�`13
�^�H���E�����́u�m���v�Ɓu���^�v / �R���ӈ�/p15�`28
���˓����̊����Ǝj / �o����O/p29�`42
�^�H���̐l���V�� / ���x�d��/p43�`49
�k�����Љ�l �����ɂ�����N�c�����̋L�^--
�@�@������N�c��c�^�̏Љ� / ���c���@/p51�`72
�E
|
�W���A�ʏ�G�q�� ; �X�ۉh���Y�ҁu�����|�\���� �ʏ鐷�d �ʏ鐷�`�� : �ʏ�G�q�P����I�L�O���v���u�ʏ�G�q�i����o�Łj�v���犧�s�����B
�W���A���镐,����[�q���u���{�̈�w��� 26(0) p.191�i�菑���j�v�Ɂu���x�̔F�m�\���ɂ��� : �[�n�앑�x�ɂ�����p�t�H�[�}���X�̔F�m�[�v�\����B�@
�@�@�܂��A����[�q���u����p.194�v�Ɂu����̗x��̕\�������Ɋւ��錤�� : �ÓT���x��ɂ��� :�̈�S���w�Ɋւ��錤���v�\����B
�X���A�����Ɩ����u���z�̉��M : �[����E�C�Ƌ�Ɠ��Ɛl�тƁ@�����ē���A�W�A�ց[�v���u�����V���Ёv���犧�s����B
�X���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.4�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
|
�}�� ���{�o�y�̌��l���Ԏ���ɂ���
����Ƃ��ɏ��A��̏o�y�i�𒆐S�Ƃ��� � �ǖ��^��
�����j���j����̎�H�ޗ��ɂ��� ���a�c �^�~�^��
�쓇�̐Ί��ڐ� ����� �O�� �@�x �O�� �i�^��
�ăO�V�N�l �F�� �p��Y�^�� |
�ΐ�s�ɔg�㌴��Ւ����T�� ���^ �k��^��
���d�R�Ί_���̐V�Ί펞�㖳�y���� ��l �i�j�^��
�ÉF�����̐�j��Ւ����T�� ���� ���I�^��
����l�Êw�ɂ��Ă̓�A�O�̊��z ���� �k�~�^��
�E |
�X���A�������ҁu �����w : ���߂Ɗӏ� 40(10)[(515)]�Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V<���W>�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059632
|
�Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V<���W>/p6�`189
�̗w�̐��a--���̔�V�� / �P�c�r�ܘY/p6�`12
�Ñ�̗w�̐��E/p14~37
�����E�̊_�E���� / �㉺�\��/p14~19
�`���E�����E�W�c--�Ñ�̗w�o�� / �R��]/p20�`25
�{��V��Ɖ̗w--�����V��̂��߂�����/�q�ѐ���/p26�`31
�̊_�̖����w�I�l�@ / �n�ӏ���/p32�`37
�Ñ�̗w�̕��@/p40~72
�����ƚg�@ / ���{�B�Y/p40~45
���^�Ɨl�� / �u�c���`/p46~51
���z�ƕ\��--�A�a�X�L�^�J�q�R�l�_�b�u�ȁv
�@�@���̗w�𒆐S�Ƃ���o�� / �{�c�`��/p52�`59
�F�ʂɂ��� / �Ɍ���/p60~66
�_�b�I�z����--�V�c��呒�̎l��𒆐S��/���h���}/p67�`72
�Ñ�̗w�̓���/p74~115
�����ƌ��� / �H�����/p74~79
�̎�V / �˒J����/p80~87
���Ɗ� / �������H/p88~94
�G���X�Ɣ��R / �n�ꂠ���q/p95�`100
�Z���̗�--�ߐe��������݂� / �O�J�h��/p101�`109
�R���₷���� / �X�G�l/p110~115
�Ñ�̗w�Ǝ�/p118~125
�Ñ�̗w�̘A�z�� / �����؍K�j/p118�`119
|
�쓇�×w�̖��� / �����a/p120�`121
��̊��z--���Ƃ̉��� / �O�o�u�v/p122�`123
���o�̉��ɂ݂��Ă��� / �g������/p124�`125
�`���̖��/P126~157
�Ñ�`���Ɖ̗w / �R�萳�V/p126�`131
���}�g�����̃��}���Ɖ̗w / ���c�^�K/p132�`138
�����̏����Ɖ̗w / �g�i�o/p139�`145
�O�֎��̌Ó`���Ɖ̗w / ����K�O/p146�`151
�Ђ������̒���--���}�g�^�P���`���Ɖ̗w / �R���q�b�q/p152�`157
�����j�E�ۑ�Ǝ��_/p158~182
�|�\�j�̎��_���� / ���]����/p158�`163
����̌×w�ƌÑ�̗w���� / �r�{����/p164�`169
�Ñ�̗w���������ē� / �g���/p170�`182
�Ñ�̗w�ɂ���(�ǎ҂̃y-�W) / ���O�m/p184�`189
��-21-�u�V�畨��v�̐��� / �}���L�v/p190�`205
���㕶�w�f�f-44-���݂���̓��� / ���{�O/p206�`209
���W �Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V �w�E���](43)
�@�@���ÓT�̌y�� / �Ɏ��/p210�`211
���W �Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V ���̑��Ƙ_��(49)
�@�@���i��ו����� / �{��B�Y/p212�`213
���W �Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V
�@�@�����] �^�珹�O���u�c�A�����̗w�S�l���v / ��쌚��/p214�`215
���W �Ñ�̗w�E���̖��Ɣ�V �ǎ҂̃y�[�W���e��W�ɂ���/p87�`87 |
�P�O���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 2�v���u�@����w�o�ŋǂ��犧�s�����B�@�@pid/9769603
|
����{���k���n��ɂ�����u���v�E�u�e�ށv�E�u���v
�@�@���\�䕔�c�͕����̏Љ�Ƃ��̍l�@�\ ����O/1
�u�ԃ}�^�E���}�^�v���J�̍\�� ����V��/54
�ߐ������̗����� ����]/69 |
���̂̌����Ƃ��̐��� ��Î�/97
����̐l�`�ŋ��\�`�����_���[�|�\�ƔO���́\ �r�{����/143
����ɂ�������̕��w���� ���{�b��/191
�����ꂩ��݂��w�Î��L�x�́u�Ӂv�u�x�v���̉��� �R�c��/231 |
�P�P���A�V���{����}���ҁu���Ƃ̂� : �����E�����E�l�ÁE�l�� ��4���v���u�V���{����}���v���犧�s�����B
�@�@�����F��㊌����}���فF1005653769
|
���Γ��̔_�k�ƔN���V�� ���c�@�� p52-59
�����U���@ �K �q�����@ �����Ł^�� p92-95 |
�b���Ɣ��y�@ ���� ���@ p143-146
�쓇�̓Ɩ؏M 3 �g�J���̃X�B�u�l ���W���@ p147-148 |
�P�P���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 40(12)[(517)]�@���b�̐��E<���W>�v���u
���傤�����v���犧�s�����B�@pid/6059634
|
���b�̐��E<���W>/p6~172
�������b�ς̑��� / �h��/p6�`16
�̘b�����̉ۑ� / �哇���F/p17�`23
���b�E���̎n��/p25~51
���b�E���̎n�� ���b�̐��a�E�`�� / �P�c�r�ܘY/p26�`34
���b�E���̎n�� �_�b�E���b / �R���ӈ�/p35�`43
���b�E���̎n�� �̘b�E�`���E���Ԙb / ��c�_��/p44�`51
���b�E���̓���/p53~78
���b�E���̓��� ���b�̐l�����^���]���̔Ɏ��Y�ق���
�@�@��/�쑺����/p54�`61
���b�E���̓��� �Η��̘_�� / �O���K�v/p62�`69
���b�E���̓��� �{�i�̘b�ƏΘb�����̗l���̖�聄
�@�@��/�������X/p70�`78
���b�E���̎v�z/p79~103
���b�E���̎v�z ���b�ɂ����錻�����S�v�z�̔��f/�␣��/p80�`86
���b�E���̎v�z ���b�ɂ����镧���I���ʎv�z�̍�
�@�@�����u�m���ג��ҁv���߂����ā� / ���c�W/p87�`96
���b�E���̎v�z ���b�ɂ����銩�P�����̊� / ������/p97�`103
���b�E���̈ʑ�/p105~132
���b�E���̈ʑ� ����ɂ��������|�̕ϗe/����r�v/p106�`116
���b�E���̈ʑ� �n��ɂ��b�^�̗ގ��Ƒ���/�r�ؔ��V/p117�`124
|
���b�E���̈ʑ� ���{�̖��b�ƊO���̖��b/�іL���j/p125�`132
���b�E���̗l�X�Ȍ`/p133~161
���b���̗l�X�Ȍ` ��� / �ΐ쏃��Y/p134�`140
���b���̗l�X�Ȍ` �v�x� / ����/p141�`147
���b���̗l�X�Ȍ` �Ⴊ����杁������Đ��̘̐b��
�@�@��/ ���c��/p148�`154
���b���̗l�X�Ȍ` ��� ���u�����R�W�v�𒆐S�Ɂ�
�@�@�� / ���Ό���/p155�`161
���b�Ǝ�/p162~172
���b�Ǝ� ���b�ƌ��� / �X�{�N�Y/p162�`166
���b�Ǝ� �Y�p�̖��b �����n�̊O�C�{�ɂā�
�@�@��/�����j/p167�`172
�ǎ҂̃y�[�W ���b�ɂ��� /
�@�@�� �X�K�� ;�R�c�͐� ;�m�當�G ;�c������q/p173~177
��(23)�c��̖��A�V�N�̃G���X / �}���L�v/p178�`190
���㕶�w�f�f(46)�����̏��� / ���{�O/p192�`195
�w�E���](45)�����Ɗ��e�� / ���M�j/p196�`197
���̑��Ƙ_��(51)�킪���_�̂���
�@�@���u�����Д\�_�l�v / ���c����/p198�`199
���] �������Y���u�֓��g�Ƃ��̎��Ӂv/�{�я��v/p200�`201
�ǎ҂̃y�[�W���e��W�ɂ��� //p78�`78 |
�P�P���A�u��y = Monthly jodo 41(11)�v���u�@�R��l�r��v���犧�s�����B�@�@pid/6075734
|
�q�ݍ��ӂ��Ƃ����A�\��O / ��c�P��
���C���Ǝ��ƕ����� / ����^��/p2�`5
����J���̑c�ܒ���l--�ܒ����̍Č����c���j���� / �����L/p6�`9
����̃��������l����(9)�u�����v �łƌƂ̖�� / ���M��/p10�`13
����̃��������l����(9)�u�����v �łƌƂ̖�� / �ē����r/p13�`16
����̃��������l����(9)�u�����v �P���̑��� / ���c�r��/p16�`18
|
���@��ɂ������� �@�R��l�̐l��
�@�@������(11)���������ւ̑ԓx / ��c����/p19�`25
�n���C�ɐ�����(��)--���n�l�Љ�j / �V�ۋ`��/p26�`29
���̎l�G(8)�~�����t�⎺���� / �ыѓ�/p30�`32
�ߌo�̏W �u���X�@�̈߁v�ɏA����(5) / �Δ��r��/p33�`37
�O���Ђ���O���u(19)�@�R��l���߂���l�X / ������g/p38�`48 |
�P�P���A�R��h���u�A�������G�� 50(11) p.328-328�v�Ɂu���a�c�^�~����Ǒ�v�F����̎R��̉ԁv���Љ��B
�P�P���A��Ԕɂ����{���特�y����ҁu���特�y 19(11) �@p37�`39���y�V�F�ЂɁu���y�m�[�g���㊣�v�\����Bpid/2375608
�P�Q���A�V�_�P�Ă��u�V�ҕ��y�L ��� (�钃����蕶)�v���u �x�����G�v�v���犧�s����B�@pid/9769619
�@�@�V�ҕ��y�L(�����)(1972�N���s)�̑��ҁ@�@307p �}35���@�@�����F��㊌����}���فF1001656618
|
������W�̗��j/1
�������K�̖ؐ��̋|��/7
�K�ʃ}�[�^�[/7
������刢��̓���/9
������W��I�z����/13
�����苴�̖��i/17
������厚���ʔ蕶/19
�T�V�J�w�V�����m�蕶/20
�w�Ǝw�A��/22
����̗����㗤/24
���b�싍�̊�/30
�����Ȃ��̐�/32
���{���̓�����/34
�������̓�����/35
����̗����㗤�ɂ���/38
����̌��i/40
��̎�����/43
���R�{�W/44
�Y�p���V�k�V�蕶/44
�Y�p����̂Ђ̂���/47
�Y�p�卶�E�V���������ɏA��/49
�����납�猩���Y�p��/52
�j�ꂽ�蕶�Ɛl��/54
����V�N��嗓����/58
�N�֗����V�L/58
���Ɩ����ɂ���/62
��̎��_���̂Ђ��/65
���̂Ђ�ԐΖ�ɏA����/68
��邱��ɂ�/70
��̎��ɏA����/73
�Ζ�ɏA����/74
�����͐Ό����Ό�/77
�ߓ����ƌ��/78
���̋Z�p�ɏA����/79
�ߓ����̗��p/80
�i���̓����\��/82
�I�����Ɍ���z�ҏ�/83 |
�ߓ����̖� ����/86
�咆��ƐɏA����/87
���q�A�����A�����̐�/88
�I�������猩���ʗ˔�/90
����L���/92
�NjL�ʗ˔�/98
���a�ɏA����/100
�ʗˁu�����[�搶�̐��v/101
���a�̋`�Ȃ��/102
���q�̌��̖��i/103
���a�̓����\��/104
�����̎��ɏA��/105
�����̐��ɂ��鎺/106
���ʗ˂Ɖ���/108
���h���̉��C�H��/109
������̕����/111
����ࢂɂ���/113
�ɔe�i�R�ҋL/115
�A�V�[�X/115
�����葺�̔������/119
�V�Ԑ^��ƃT���S��/123
�V�Ԑ^��̌���/125
����������o�H/127
�c��}�e�_��V����/128
限싴/133
限�Ɣ�Ӑ�/135
�Ô艽�|/137
�썲�ۂ̌Ô�/138
��O�썶�ە��/140
�������̌��/141
�Γc��蕶/144
�����̕߂����Ǝ���/146
�����̎���͎��s/147
���V��̔�ɏA����/149
���V��蕶/150
�A�����Y�Y�e���̒˔�/152
�A�����̗R��/153 |
��������/155
���[��/157
����n���^�O��/158
�R�e�C��/160
�ӕ~��/162
����c��/163
������/165
���~��/167
���������/168
���ɂ��/170
�Ӗ���/171
�匓�v��/172
�`����/173
��������/174
�o����/176
������/177
������/179
���Ԑ�/181
�c�i�M��/182
�{�U�R��/183
��{��/185
�S�G����/186
�{������/188
�`��������/189
��c����/190
�{��v��/192
�{�ԕ���/193
���̗t��/194
�ɍ]��/195
�����m����/196
�{�c����/198
�ԕ���/199
�g��c��/200
���}�x/201
�Ԃ����͂ł���/203
�^���n�̂͂����傤��/204
�x���͂ł���/205 |
��������/206
�\������/208
�h�d�M�k���یo/210
�߈�/213
�ߓ�/214
�ߎO/215
�ߎl/217
�������Ȑ�/218
�U�R��/219
��̐߂ɏA����/222
�̐߂Ǝ��x/224
����x���Ԑ�/225
���c��x��c��/227
���x/228
�������u�m�ԕz��
�@�@���R���v�ɏA��/230
�m�ԕz�̗R��/231
������L/262
������̐���/263
�ݍΗ�L/264
�ݍΗ�L�̊�������/266
�������W/268
��쏼���蕶/270
�𖾗N�c�V��/271
���_��e�ɏA����/273
�l�͎Ԃƚ�쓹�H/274
���q����/277
���_�R�Ɖ��_���/278
���V�R�Ɠn����/280
�䕨�隬�ɏA����/282
��炴���肮�����̔�/283
������o�����/292
������k/296
�O�R����R��/299
�R�Ɩ�����/301
���Ƃ���/305
�E |
���A���̔N�A����|�\�j������ҁu����|�\�j�������� ��1���`��9���v���u�����Y�\�j������v���犧�s�����B
�@�@1975.7�`1976.3�@�@1���@�@�����F���ꌧ���}���فF1002260741
|
��1�� 1975.7 2p
������̔����ɂ������� �Ɖ� ���P
����|�\�j������
�������
�|�\�j�W�}���ē�(1)
��2�� 1975.8 2p
�����ǂ��ɏA����(�v�|) �Ɖ� ���P
�|�\�j�����s���ꗗ(8�����{?10��)
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(2)
�g�x������ �ߏ� �ʐ^�̓W���� ����(1)
��3�� 1975.9 2p
�ϋq����݂�����ŋ� �Î�� �d��
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(3)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(2)
��4�� 1975.10 2p |
����̌��c�̕ϑJ�ɂ��� �X�� �h���Y
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(4)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(3)
��5�� 1975.11 2p
���NJԓ��̔����x��ɂ��� ���� ��Y
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(5)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(4)
��6�� 1975.12 2p
�����g�݂̂������|�\ ��� ��i
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(6)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(5)
�V�t���ʍ� 1976.1 6p
������ɏA���� �Ɖ� ���P
�V�t����|�\�ӏ܉�
����|�\�j������ |
�������
��7�� 1976.1 2p
���ی|�\�Ƌ����� ���� �P�ܘY
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(7)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(6)
��8�� 1976.2 2p
����̗x��̕\�������ɂ��� ���� ���q
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(8)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(7)
��9�� 1976.3 2p
�g�x�̊K�����ɂ��� ���� ���
�|�\�j�W�}�� �_���ē�(9)
�u�g�x������W�v�o�i�ژ^ ����(8)
�E
�E |
���A���̔N�A�u���ꎑ���W�� : ���R�E���j�E�����E���y�v���uGreen life�v���犧�s�����B�@pid/9769378
|
1.����̎��R/13
����̒n�� �쌴���G/19
����̋C�� ��ԗ��v/23
����̒n�� ���ܐL�O/29
����̐A�� �����Z�F/34
����̓��� ���ǓS�v/42
�쒹 �^�ߏ�`�t/48
�� ����M�Y/51
�ߊC�� �������l/53
�n�u�̐��Ԃƙ��� �g�c���[/61
2.����̗��j/67
����j�\���̃A�E�g���C���\ �V���b��/77
���n����̉��� �������G/82
����̗��j�T�� ���G�Y/86
����̗��j�T�� ������s/107
����̋���ϑJ�j ���g������/120
����̋���ϑJ�j �ʏ�k�v/133
����̌R����n�j ���g�i�[/144
����̕��A�^���j ���×^�u/169
����̈ږ��ϑJ�j �ʏ���ܘY/185
3.����̕���/197
���ꕶ���̌��_ ��闧�T/207
����̌ŗL�M�� �^�ߍ���/212
����̕� ���Ð^�X��/217
����̍Ղ� ���Ð^�X��/225
����̌�揂ƃI���� �r�{����/238
����30�I�E���������̓��� �㌴��v/250
����̖����|�\ ���]�F�`��/256
����̌ÓT���x ���]�F�`��/262
����̐��D �����쏇�s/266
����̎��| �O�c�F��/274
�������� �V�����q/278
�����A�� �^�ߗ�O��/288
����̓��� �{��Đ�/294
����̖��� ��]�F��/297
����̌��z �R���③/303
����̌Õ��p �{��Đ�/323 |
4.����53�s�����Љ�
�@�@�����M�ҁ����c����E���ꌎ��E
�@�@�����Ð^�X�� ���A�ɒj�E�����i���Y�E
�@�@��������s�E���]�O�F �{��h���E
�@�@�����m�P�E���l�ǏC�E��ɏ�ꗲ
�@�@���_�ԗǍ��E�R��P�O�E�V�c�F�v�E
�@�@����[����E���䒼�q/327
�ߔe�s/329
���K�n��/385
�����s/387
���~��/401
�L���鑺/411
��������/421
��u����/429
�ʏ鑺/439
�m�O��/447
�^�ߌ���/457
�嗢��/465
�앗����/473
�����n��/483
�Y�Y�s/485
�X��p�s/497
����s/507
��u��s/523
�ΐ�s/531
�^�ߏ鑺/539
���A��/547
�ǒJ��/557
���鑺/565
��[��/575
�k�J��/583
�k���鑺/589
������/597
�����n��/617
���[��/619
�X�����/627
������/633 |
����s/641
�{����/661
���A�m��/671
�ɍ]��/681
����/691
��X����/697
������/705
�v�ē�/719
������/721
��u�쑺/735
�c�NJԗƎ��ӂ̓��X/753
�n�Õ~��/755
���Ԗ���/765
�n���쑺/773
������/781
�ɐ������E�ɕ�����/791
�ɐ�����/793
�ɕ�����/809
�哌����/825
��哌��/827
�k�哌��/839
�{�ÌQ��/845
���ǎs/847
��Ӓ�/867
���n��/875
��쑺/881
�ɗǕ���/887
���NJԑ�/893
���d�R�Q��/913
�Ί_�s/915
�|�x��/929
�^�ߍ���/949
�t�^/963
������j����/965
����ό�����/984
�Q�l����/993
����/995 |
���A���̔N�A�����O�ᒘ�u�����̌����v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@268p
�@ pid/9769436 �@�@�P�O�O�O�~
|
�� �g�c����/1
����/3
���� �����̖��̍l/15
���� �����̊J蓒k/22
��O�� �����̉��v���тɎj�_/30
�� ���� �w�V�����萼�Ў���Ɏ���/30
�� �j�_�̈�/31
�O ���� �@�x�����菮������Ɏ���/35
�l �j�_�̓�/37
�� ��O�� ���~�����菮����Ɏ���/39
�Z �j�_�̎O/43
�� �j�_�̎l/45
�� �j�_�̌�/47
�� �j�_�̘Z/54
��l�� �����̒n��/59
�� �����̈ʒu�y�ы��/59
�� �����̒n�`�y�ђn��/60
�O ����{���̒n�`�y�ђn��/61
�l �C��/63
�� �A��/65
�Z ����/66
��� �����̐l��/69
�� ���x���v/69
�� �Y�ƁA���/70
�O ����A����/71
�l �@���A�ƍ�/74
�� �����A�K��/76 |
�C �Ɖ��i��a�A�a���A�_�Ɓj/76
�� ���H���i��H���A���H���A�n�D���j/78
�n �����i�̂̊K�������A�w���̕����j/80
�j �����i�V���A���n�j/83
�z ����i�����A����̍\���j/84
�w �V�Z�i�֔���A���n�A�p�́A����A�ŋ��A
�@�@���O���V�Aগ��D�A�j�g�A�쓇�x�j/86
�g �N���s���i�c�q�̏j�Ձj/89
�` �Gઁi�m�Z�A�ی`���A�C�_�ՁA�������v�A
�@�@���c�q�Ñ��A�ʉ݁A�������j/93
��Z�� �����̖�������/97
�� �ߔe�`�̐l��/97
�� ���Y�̖��c/101
�O ��̗[��/107
�l �c�ɂ̗��H/116
�� �����̔��e/133
�掵�� �����̌��ꕶ��/136
�� �_��/139
�C ������i�������̂�����A
�@�@�����݂��̂�����j/139
�� ���ނ�/141
�n ������y�т������ׁi�݂��₾�����
�@�@��������A���퉺�̂������ׁj/143
�j ���삢�ɂ�i������삢�ɂ�j/146
�� ����/149
�C �Z��/150
�� ����/156 |
�n ����/156
�j ����/158
�O ���w/160
�C �P���ۂӂ�/160
�� ����������/160
�n �q���/161
�j ���/162
�z ���s�́i�����A���ǒ҂̒����j/163
�l �Y��/167
�C �����i�V��g�j/167
�� �g�x�i�萅�̉��ꖼ�g���R�A
�@�@���`�b����ꖼ���g�̔䉮�j/172
�� �a���y�јa��/200
�C �n�ƋL/201
�� �ۂ̉�/208
�n �a��/218
�Z �蕶�����y�ю�/220
�C �悤�Ƃ�̂Ђ̂���/221
�� �������V�������_�L/222
�n �ƕ���/222
�j �������i/223
�v���o�̋L �������q/225
���E�����O��̂��� �R�c���X�q/229
�N�� �O�荎�v/235
�w�����̌����x��
�@�@���w�j�I�ʒu �������/241
�E |
���A���̔N�A�����l�Y, ���@�����P, �O�Ԏ�P�ҏW�u�ɔg���Q�S�W ��7���v���u���}�Ёv���犧�s�����Bpid/9769610
|
�����l��_/1
�����j�̐���/5
���^ �i���_���ς��问����
�@�@���p�˒u���k�����l/14
�����̌܈̐l/15
����/17
�}��/19
���p����/21
�O�̐l�Ƒ��w�i/25
���� �����̏�Îj
�@�@���i���{�y�юx�߂Ƃ̊W�j/25
���� ��������ɉ�����
�@�@�������l�̊����k�����l/29
��O�� �����̓�ؖf�Ձk�����l/30
��l�� �F���Ɨ����Ƃ̊W�k�����l/30
��� �x�߂Ɨ����Ƃ̊W�k�����l/30
��Z�� �����̋ꋫ�ƌ��ی�/31
�掵�� ���̒��a���/32
�攪�� ���������ƋX�p���ہk�����l/36
���� ���_/37
���ꏗ���j/39
�×����ɉ����鏗�q�̈ʒn/41
|
���ނ̗��j�k�����l/59
�������L/63
����/67
���G���/69
�Ǔ���̗����\��/71
��/74�`��Z/83
�����j��ɉ����镐�͂Ɩ��p�Ƃ̍l�@
�@�@���\�썲�ۂɏA���Ă̋^����o�����ā\/85
��/91�`��/168
���c�F�_�̈Ӌ`������܂�
�@�@���\������u�T�_���̌����v���/169
�쓇�̗̉w�Ɍ��͂ꂽ�ג��̗�����/188
�×����̗̉w�ɏA����/198
�Վ����x�\�����肭�킢�ɂ�/227
�����Ñ�̗����\�����͂�̗V�с\/242
��/243�`��/248
�x�߂̓����Ɨ����̑ԓx
�@�@���\�����`�̎O�ϑJ/253
�ɂ��ā\�\���N�O�̓�҂ɓ���/264
���ꌧ���̃��h���\
�\�s�s�Ɣ_���Ƃ̌��Ɋւ����l�@/267
�w�n�����L�x���Љ/288 |
���˖�������/306
�w�����ǎ��ȏW�x�ɂ���
�@�@���\��Ð��͌N��/314
������̕�C���v/325
������̐����ɂ���/342
���^ ���w����̎v�o�\���̈�т�
�@�@�����t�����搶�ɕ���/357
����扽���ցk�����l/379
���������j�l/385
���l���q/387
����Ə̂���V��/390
�w�������R���L�x���/409
��/411�`�\/447
�w���������L�x���/449
��/451�`��/490
���j�_�l/497
��R���̒��N�S���\�w�������^�x
�@�@�����ڂ̎j���ɂ�ď������ꂽ
�@�@����R�̗��j/499
��� �O�Ԏ�P�E��Î�/519
�E
�E |
���A���̔N�A�^�������u���т瓇�������`���X�̂����`�v���u�R�����r�A�v���犧�s�����B�@
�@�@�^���f�B�X�N 1�� : �A�i���O (LP) , 33 �@�@����r��(�S, �O����)�@�@�@��������}���ُ���ID:000008613654 |
| 1976 |
51 |
�E |
�P���A�u����|�\�j�����@�n�����v���u����|�\�j������v���犧�s�����B�i�m�F���j�@�d�v�@ ��660�@�@�V���ɂ��i�����v�j
�Q���A��闧�T, ����F, ��،����u����̓`���v���u�p�쏑�X�v���犧�s����B�@ (���{�̓`�� ; 2)�@pid/12468009
|
����̓`���U�� �� ��F
����`���\��I ��� �� |
����ɂ�����`���̈Ӗ� ��� ���T
���w�̏W�蒟�q����r �|�� �� |
�t����`���n�}
�E |
�R���A��w��A���ҁu�l�މȊw : ��w��A���N��@(�ʍ� 28)�@���W�i�쓇--�����̑��������Ɍ����āj�v�����s�����B
|
���W�@�쓇-�����̑��������Ɍ����ā@ p.p1�`128,1�`69,����p3�`4,�\1��
�͂����� �@�D�c ���Y p.����p3�`4
�쓇���Ƃ�܂��C--���̊C��n�`�ƊC�� �@�����l p.p1�`11
�W�c��`�w�I�Ɍ����쐼�����@���{�b�s p.p13�`25
���������ɂ������b�����̈Ӗ� �@���������v p.p27�`37
���������̒n�� �@�k���r�v p.p39�`49
�����̐e���g�D�@�������T�Y p.p51�`58
�����Ɖ���E�_���̎Љ�I�����̑���ɂ���
|
�@�@��-�ߐ����ɂ�����y�n���x�Ɣ_���w�̕����𒆐S��-
�@�@���^�ߍ��� p.p59�`74
�쓇�̑����ɂ�����L���X�g���̎�e�ƓK��
�@�@��--���꒲�����牂���Ɍ����� �@���L p.p75�`91
�������w�̉��y�I���i��ʂ��Ă݂�
�@�@�����Ӓn��Ƃ̊֘A���@���c���q p.p93�`113
��E���̌��� �@�ɑ��i p.p115�`128
���������ژ^�@ p.p1�`69 |
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu���d�R�Ί_���������{��Ԉ�Ք��@�����v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@(���ꌧ������������, ��3�W)
|
���^���̂��ь�����ψ���ł́A�͂��߂Ĕ_�Ɗ�Ր������Ƃɔ��������������̔��@�������������܂����B�^���ꌧ�̔_�Ɗ�Վ��Ƃ́A�ׂ̎��������̒B������T�O���ɑ��āA��P�O���Ƃ����ᗦ�ł���A���̎�̎��Ƃ̒x��́A���̂܂܉���̑�ꎟ�Y�Ƃ̑啝�Ȓx����Ӗ����Ă���Ǝv���܂��B���������āA���a�S�V�N�A�{���������{�ɕԊ҂����ƁA�_�яȂȂ�тɉ��ꌧ�_�ѐ��Y���́A����_�Ƃ̋ߑ㉻���߂����A���N���\���~�𓊓����ĉ��ꌧ�̔_�Ɗ�Ր������Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B����͉��ꌧ�ɂƂ��Ă܂��ƂɈӋ`���邱�Ƃł���܂��B�^�������_�Ɗ�Վ��Ƃ́A�_���A���{�݂ƂƂ��ɍL��̓y�n�����ǂ��܂��̂ŁA���̒n��ɑ��݂��閄���������A�V�R�L�O���A�������������̓y�n�ɔ����������́A�����Δj��邱�Ƃ�����܂��B����̐Ί_�s�����c���c�̉c���n�ё����y�n���ǎ��Ƃɂ����镽�����{��Ԉ�Ղ����̗�O�ł͂Ȃ��A�����ۂ̖����S������������Ղ̃p�g���[���������Ƃ��ɂ́A���łɂ��̔������j�ꂽ��ł����B�^�����̑c��̎c�����M�d�ȕ�����Y�́A���R�̕�����푈�A�e��̊J���Ȃǂɂ��j��ɂ���ĔN�X�������Ă���A��x�j�ꂽ�y�n�ɔ����������͓�x�ƌ��ɖ߂邱�Ƃ͂���܂���B�������镶�����̉��l�͂��悢�摝�債�Ă���܂��B����ɐ���L��������́A��l�̎c����������Y�����̐���ֈ����p���`��������܂��̂ŁA������ψ���́A�c���������̕������{��Ԉ�Ղ̔��@���������邱�Ƃɂ������܂����B�^���̔��@�����ɂ�����A����������W�O���̕⏕���܂����B�܂����@�����A���쐬�ɂ������ẮA�n���Ί_�s�W�҂̌䋦�͂܂����B�������Ȃ�тɒn���̐ϋɓI�Ȍ䋦�͂ɑ��A���ӂ̈ӂ�\���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@���a�T�P�N�R���^���ꌧ����ψ����^���璷�@�r���b�� |
�R���A������w�j�w��ҁu�����j�w = Journal of Rissho Historical Society (40)�v���u������w�j�w��v���犧�s�����B�@pid/7937878
|
�i�m�����Ɋւ����O�̖�� / �����\��/p1�`19
��E��l�Ɗω��M�� / �y���F��/p21�`32
�]�˖��{�ɂ��Ă̈�l�@ / ���X�x�v/p33�`46
�X�������J�̕����� / ��l�G��/p47�`51
�������]�^�� �ޗǎ���̈�㎁ / �������l/p52�`54
�������]�^�� �����̐_�� / ��]�F�q�v/p54�`55�@�d�v |
�S���召�l / ���x�m�v/p56~60
��z�̑����j���ژ^--���哈���E
�@�@���ђ|���E�q��ƕ��� / ������w�Õ���������/p61�`89
���V���Љ ���c�r�t��[�ŐV���j�N�\] / ��J�p��/p20�`20
�b��/p90~104
�E |
�R���A��]�F�q�v���u������w���w���_�p (�ʍ� 55) p.p23�`51�v�Ɂu����ɂ�����̐_�M�̎j�I�l�@--���ɉ̐_�̏o�����߂����āv�\����B
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (2) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467945
|
�� / �O�Ԑ��K
�v�ē��̒n���\�\���ɗ����ΊD��Ɗ��V���C���r�V�ΊD��ɂ��� / ����N/p1�`17
�����s�쉮�������L�ˏo�y�̑]���E���n�y��ɂ��� / �V�c�d��/p18�`28
�썑��2��Ք����̑]���E���n�y��ɂ��� / �V�c�d��/p29�`33
���鎟�Y�N�� / �{��Đ�/p34~38
���̂т��̕��� / �n���얾/p39�`58
�����Љ� �r�����l�Y�̕��w�v�ē�����x / ��]�F��/p1�`18 |
�R���P�R���`�S���P�P�����A���ʓW�u���a�c�^�~�������l�Î����W�v���u���ꌧ�������فv�ŊJ�����
�R���A�u���� (114)�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@ 1976-03�@pid/3465003
|
�X���m�Z�E��4���E �X���m�Z���f��B�e�W�c / ���\��
1954�N3��1��=�r�L�j�������� / �I����q/p1�`1
�A���_���V�A�ƃJ�^���j�A / �ѓc�C/p2�`8
���肪�����l���� / �����O�F/p9�`14
�ǎ҂̃y�[�W //p15�`22
�����q����̎�L��ǂ�� / �����v/p15�`16
�u�؍����w���X�p�C�����v�Ɠ��{�̗ǐS / ��J����/p16�`18
���{�Ƃ����̋U�P�ƋU�� / ���c�h��/p18�`19
���ɖ{�u�[�����l���� / ����O/p19�`20
���Ƃ̈Ӗ�������� / ������q/p20�`22 |
���ꂩ��̕ւ� (4) / ���낳��悤��/p23�`28
�ǎ҂̊F����� //p29�`29
�Ō�̐R��=�~�P�����W�F�� / ���Ñ��Y/p30�`31
������� / �֓���X�q/p32�`33
���������̍����̎���
�@�@���������R���_��쓬���ψ���/���p�q/p34�`39
�� �w�C�쏬�L�x�O�� (��) �R���ӈ� / �������/p40�`45
�i���̔_�w / ����ӂ�/p46�`51
�v������ / ���J�\�Y/p52�`56
3���V���ē� //p1�`4 |
|
�� ����������u���� (89�`114) �ɔ��\�����u�w�C�쏬�L�x�O�� (1�`16)�v���̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
���� (98) p7�`12 |
1974-11 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (1) �c����� |
pid/3464970 |
| 2 |
���� (99) p14�`19 |
1974-12 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (2) ���X�V�� |
pid/3464972 |
| 3 |
���� (100) p40�`45 |
1975-01 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (3) �����O�� |
pid/3464974 |
| 4 |
���� (101) p38�`43 |
1975-02 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (4) ���쎢 |
pid/3464976 |
| 5 |
���� (102) p34�`39 |
1975-03 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (5) �ɔg���Q |
pid/3464979 |
| 6 |
���� (104) p32�`37 |
1975-05 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (6) ���c���j |
pid/346498 |
| 7 |
���� (105) p22�`27 |
1975-06 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (7) �܌��M�v |
pid/3464985 |
| 8 |
���� (106) p20�`25 |
1975-07 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (8) ��Ït�� |
pid/3464987 |
| 9 |
���� (107) p9�`14 |
1975-08 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (9) ����^���p |
pid/3464989 |
| 10 |
���� (108) p18�`23 |
1975-09 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (10) ���钩�i |
pid/3464991 |
| 11 |
���� (109) p14�`19 |
1975-10 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (11) �͑����Y |
pid/3464993 |
| 12 |
���� (110) p18�`23 |
1975-11 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (12) �n������
����ł̉����O�� �O�荎�v p50�`51 |
pid/3464995 |
| 13 |
���� (111 p18�`23 |
1975-12 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (13) �n������(��) |
pid/3464997 |
| 14 |
���� (112) p36�`41 |
1976-01 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (14) �������� |
pid/3464999 |
| 15 |
���� (113) p34�`39 |
1976-02 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (15) ��ɏ�i�c |
pid/3465001 |
| 16 |
���� (114) p40�`45 |
1976-03 |
�w�C�쏬�L�x�O�� (��) �R���ӈ� |
pid/3465003 |
|
�S���A�M�y�Еҁu�G���M�y (7)�v���u�M�y�Ёv���犧�s�����B�@ �@�@pid/2202336
|
�\�̉���O�ԙ�
�����|�\�̎O�ԙ�
�N�O�ԙ�
���O�ԙ�
���̎/���g���O��
���=���y�ƌ|�\�̗�
�V�t�̌|�\ / �O�����Y/p22
�̂��x�艹�y���閯 / �������q/p28
�ÓT�|�\�\�\�����̗����L���� / �g��p�j/p36
���W �O�ԙՁ\�\���̐S�Ƃ�����/p41
����̌ꌹ���� / �r�c�\�O�Y/p41
�\�̉� / ���{�T��/p44
���S�̎O�ԙՂ����ǂ� / ���c����/p50
���q�ɂ݂�O�ԙ� ���S�̖� / �c���`���q��/p56
�n�̥ⵋȂɂ݂�O�ԙ� �O�e���ɕ������n�̌��� / ��ыI�q/p60
|
�L���ڗ��ɂ݂�O�ԙ� �O�̏j�V�� / �Y�R���Y/p64
�`���v�ɂ݂�O�ԙ� �ٍʂ���y�������� / ���ӌ�/p68
�����|�\�ɂ݂�O�ԙ� �_�Ɛl�̑������� / �{�c����/p71
�l�ԍ���V���[�Y�q�Βk�r�x�R����/���Η���/p117
�k���ʍ��k��l�|�p�Ղ����\�\�O�\�͍Ղ莖�̋Ȃ�p/p98
��O�\��|�p�ՎQ�������҂̐�/p108
���{���y�̗��j�����ǂ� ������(3) / ���{�/p78
���̗t(�O�����g�̒���) / ���{�@��{�̗w������/p126
�c�ӏ��Y�v���o�Ȃ� / �c�ӏ��Y/p93
�M�y�p�ꎫ�T / ��������/p111
�ڔ��̂����߁\�\��U��O�N��R�����N / �k��⹎R/p86
���i�y�̕����̂��߂� ����Ȃ��̐� / �W���[�W��M�b�V��/p13
�����\��/p139
�ҏW�G�L/p140
�E |
�T���A�q���P���j�Ȋw���c��ҁu ���j�]�_ = Historical journal (�ʍ� 313) p.p58�`62�v���u �u����w�v�̈Ӗ�--�ɔg���Q���a�S�N�Ɋāv�\����B
�T���A�u���� (116) �v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/3465007
|
���̎����ƘA�т��߂����� �����̃A�N�Z�X�����߂�� / ���c�Ŏq
1952�N5��1��=���̃��[�f�[ / �c����/p1�`1
�q�������v�z�r�����߂� (1) / �喴�c��/p2�`6
�}�b�N�X�E�x�A�[�̃G���Q���X�K��L / �����Б��Y/p7�`11
���ƐL�q / ����ӂ�/p12�`21
�f�b�T��=�~�n�C���E�V���~�A�L�� / �����Y/p22�`23
���ꂩ��̂���� (6) / ���낳��悤��/p24�`29
�z�n������ƃv�����p�W�̎v���o / ����O/p30�`31
�}���N�X��`���{��`���Ƙ_�̐V�W�J (II) /
�@�@���J�s�^���X�e�C�g ; �����T/p32�`35 |
�o���Z���i�ƃX�y�C������ / �ѓc�C/p36�`43
�ǎ҂̃y�[�W //p44�`50
����̖{�ɎO��ނ̒艿 / ���c��/p44�`45
�L���̒��Ŋ撣��Ȃ��Ă� / ���y�c�\�q/p45�`46
��V���͉�������Ă��? / ���c����/p46�`47
����F�l�̎� / ���c����/p47�`48
�u���q��v���� / �������s/p48�`50
�v������ / ���J�\�Y/p51�`55
�ҏW��L / M�EM/p56�`56
5���V���ē� //p1�`4 |
|
���낳��悤�����u���� (111�`116)�v�ɔ��\�����u���ꂩ��̂���� (1�`6)�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
���� (111) p13�`17 |
1975-12 |
���ꂩ��̂���� (1) |
pid/3464997 |
| 2 |
���� (112)�@p30�`35 |
1976-01 |
���ꂩ��̂���� (2) |
pid/3464999 |
| 3 |
���� (113) p10�`17 |
1976-02 |
���ꂩ��̂���� (3) |
pid/3465001 |
| 4 |
���� (114)�@p23�`28 |
1976-03 |
���ꂩ��̕ւ� (4) |
pid/3465003 |
| 5 |
���� (115)�@p10�`15 |
1976-04 |
���ꂩ��̂���� (5) |
pid/3465005 |
| 6 |
���� (116)�@p24�`29 |
1976-05 |
���ꂩ��̂���� (6) |
pid/3465007 |
|
�V���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 3�v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@
pid/9769614
|
�u�]�ˏ��j���v���̌|�\�j�� �{��h��/1
�I�����̍\�� �ʏ鐭��/61�`124 IRDB
�����̖��Ԑ��b�̐��E �R���ӈ�/125
�����̏����� ��������/173 |
���z�̖ƒ��\�\�u������v�Ɓw�^���x�\�\ �����N/209
���c���j�Ɓu�C��̓��v ��������/229
�������u���肸��v�Ɓu��āv �O�Ԏ�P/244
�E |
�V���A����|�\�j������ҁu�����Y�\�j���� �n�����v���u����|�\�j������v����n�������B�@�@�d�v�@�P���ɂ��i�����v�j
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001617164�@�@ 155p�@ �}��6��
|
������l ���̉��߂Ɗӏ� �Ɖ� ���P�^��
�ՁEⶂɂ��Ă̍l�@ ���H�� �m�u�^��
����ŋ��̐�������������܂� �Î�� �d��^��
���ԓ��̖L�N�� ��� �w�^��
���͑��삠�ꂱ��-���~�߂̗R�� ��n ���k�^�� |
����{�������̓�̓��x ���� �r�O�^��
�Ӗ������@�ɂ�鍂�Z���̑g�x�u���S�����v�� ���� ���q�^��
��w���́u���x�v�C���[�W�ɂ��� ���g �^�I�q�^��
�����̉E�q���Ƃ̘b������ ���� ���T�^��
�E |
�V���A���Ԉ�Y���u����̍Ղ�ƌ|�\ : ���{�����ƌ|�\�̌��_�v���u�Y�R�t�o�Łv���犧�s����B�@(���{�̖����w�V���[�Y
; 2)�@�@�@pid/12431971 234p
|
�}��2��
�͂��߂�
�Ղ�ƌ|�\ |
�����|�\�Ƌ�����
�{��|�\�̐��E
����ŋ��̐��E |
�q�t�r
�����g�x�菔�{�ꗗ
������ |
|
�W���A���g�^�I�q,������q���u���{�̈�w��� (27) p.163�v�Ɂu���x�C���[�W�̈��q���͓I�����v�\����B
�@�@�@���{�̈�w���27���� �J�Òn: ���k��w �J�Ó�: 1976/08/20�` 1976/08/22�@
�X���A��ޒ������u�o�Ńj���[�X = Japanese publications news and reviews : �o�ő����� (1052)�@p14�`14�@�o�Ńj���[�X�Ёv�Ɂu���c���G���u����̖��O�ӎ��v�v���Љ��B�@�@pid/3435381�@�@
�X���A�����Ɩ����u����ǂ�̉� : ������L�v���u�O�ȓ��v���犧�s����B�@�@�Q�R�W��
�P�P���A�j�Վ�Ջv�c���\���@�����ψ���ҁu�v�c���\���@�������v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@���g�^�O,���a�c�^�~,����o�g
�P�Q���A�u�����������v�ҏW�ψ���� �u���������� (66/67) �v���u�����������w��v���犧�s�����B�@pid/6024814
|
��̌ÓT / ���c�/p1~2
�_�b�̍��܂ꂽ�n���Q / �{�c�e��/p3�`15
�����̃��[�V�W���[ / �����O�Y/p15�`17
���s�������̍M�\ / �����`��/p18�`20
�n���j�ɂ�������j�Ɩ���--
�@�@�����B�̗��j���Ƃ��� / ���R����/p21�`29
���ۗx�R���L�Ɖ��{�ꑾ�ۗx�� / �����`��/p29�`32
|
���B�E�F�쏔���E���������̘̐b�̏W�ƌ����ɂ��� / ����q��/p32�`39
�\���ʐ^����/p20~21
�V������E�Z���\�L�ύX/p40~40
�V���Љ�/p41~42
���Љ�/p42~43
�ҏW��L / ����/p43~43
�E |
�P�Q���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 13(1)(46)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437760
|
�V������w�h�̂��� / ���ܑS�K/p1�`9
��Սl(��) / �q�˞@�q/p10~22
�����̗w�u�i�K���́v�ɂ��� / �c����H/p23�`41
�������u���v�̗p��ƕ��@�I���i / �O�Ԏ�P/p42�`53
�Ñ㓌����Ɨ�����Ƃ̔�r��@ / �R�c��/p54�`83 |
��㊓� �X��p�s�ԓ������A�N�Z���g / ���a�c�^��Y/p84�`106
���X�V���������쓇�W�����ɂ���(1) / ����]/p107�`113
���{���q�w�����������C�̌�����ǂ�Łx / �����H�^�s/p114�`119
�w��j���[�X/p120~120
���s�j���[�X/p41~41 |
�P�Q���A������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v ���(20)�v���u������w����w���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2259154
|
�����Y�I�X�g���R�[�h�� �V�e�����W�f�A / �쌴�q�p/p1~6
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-4-�������x�̔F�m�\��-2- / ������q/p7�`28
���x�F�m�̈Ӗ��_�I����-2-�������x�̏��� / ������q ;���X��/p29~39
���ꌧ�ɂ�����ߐ����̎��Ԓ���-1- / �n�����q ;���숻�q/p81~86
�����w���ɂ����鉫��Y�H�i�Ɋւ��錤��--���ɂ��� / �V�_���q/p87�`98
�N�̉��y�n�D�Ɋւ���S���w�I����--���y�C���C�W�̔�r�����I�l�@ / �ъ��j/p99�`115
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-2-�ÓT���x����ԣ�ɂ��� / ������q/p117�`162
����̗x��-2-�ÓT���x����ԣ--���x���̑̌n�����߂����� / ������q/p163�`209
�q�����r |
|
������q ;���X�����u������w����w���I�v ���(18�`20)�v�ɔ��\�����u���x�F�m�̈Ӗ��_�I�����i1�`2�j�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(18)�@p27�`39 |
1975-03 |
���x�F�m�̈Ӗ��_�I����-1- |
| 2 |
�i20�j p29�`39 |
1976-12 |
���x�F�m�̈Ӗ��_�I����-2-�������x�̏��� |
|
���A���̔N�A�약���\���u����̎j�ւƕ��� : �ӂ闢�̐S�v���u���z�����[�v���犧�s����B�@�@�@pid/9769529
|
�̊�
1 �Ə�/1
2 �����a�i�Ȃ����������ǂ�j/5
3 �咆��i���ӂ����т�j/7
4 ����i��j/9
5 ���䉮����ԁi���ʂЂ�����j/12
6 �銽���/14
7 ��̗���/16
8 �ٍ˓V���i�тŁ[�Ă���j/18
9 �~�o��/20
10 �ʗˁi���܂��ǂ�j�ʗ˔�/22
11 �R��ʗˁi��܂������܂��ǂ�j/25
12 �R����i��܂����ӂ����Ⴀ�j/27
13 �������i������[�j/29
14 �̂����ɐ�/31
15 �J���ԁi���ア���܂����ʂ������j
16 �䒃����a�i������₤�ǂ�j/35
17 ���钬�i���ア���Ȃ��������傤�j/37
18 �ɍ]��a�̕���/39
19 ���g�Вd�i������������j/41
20 �܂���/43
21 �ق��x�i�т�̂������j/45
22 �q�W�싴/47
�ߔe�̊�
23 �g�V��i�Ȃ�݂�j/49
24 �썑��/52
25 �����������R/54
26 ������i�ɂ��傤�j/56
27 ��̖��i��[���ʂ����j/58
28 �T�����[�W�ƃo�N�`�����[/60
29 �����v�R�i�������ɂ��R�j/62
30 �V�܁i�Ă���ҁj/64
31 ����َ̉q�ƓV�܂̑O�\��/66
32 �E�q�_�\�[���_�i��������ԁ[�j/68
33 �䕨��i���ނʂ������j/70
34 �ߔe�E�����R�i�����̂�܁j/72
35 �����i������j/74 |
36 �����̑O�i���ʂ߁[�j/76
37 �ߔe�`/78
38 �V�v�{�Ɛ�����/80
39 ������/82
40 ���������{/84
41 ����c����/86
42 �ӂȂ�i�D���j/88
43 ����i�Ȃ����傤�j/90
44 �N�c�n����/92
45 �N�c�̕�n/94
46 �ى�/96
47 �������i�����Ȍ�a�j/98
48 ���Ǎ��X��i��炴�ނ��������j/100
49 �O�d��i�݁[�������j/103
���K�̊�
50 �����̔��⓰/105
51 ��R����/108
52 �Î�u��i���ł������j/110
53 �a��X�i��Ƃ��Ȃނ��j/112
54 �쉮���̋�u�����/114
55 �ʏ鑺�̎�������/116
56 �m�O����/118
57 �֏��ԁi���[�ӂ키�����j/120
58 �v�����ƃC�U�C�E�z�[/122
59 ���i��i�{���g�E��j/126
�����̊�
60 ���낭��₭�����̕�/129
61 �Y�Y�䂤�ǂ�/131
62 �������i�Ȃ����������傤���j/134
63 ���A����/136
64 �X�̐�/138
65 ����썑���ǂ̕�/141
66 ���얡����/143
67 �ɔg����ƊL��/145
�����̊�
68 ���[�x�ƃi�x�[/147
69 ���쐹�l�ƂЂ�Ղ�K�W�}��/149 |
70 �^�V�`/152
71 ���A�m����i�Ȃ����傤���j/154
72 ���A�m�̒����n��i�Ȃ����܂����j/157
73 �ÉF�����ƃV���T/159
74 �c�`��ԂƊC�l�Ձi����݁j/161
75 �`�{���̋ʗ�/163
�����̓��X
76 �ɍ]���Ɩ����|�\/165
77 �ɕ����̎�����i���Ђ�ʎ�����j/167
78 �ɐ�����i�����Ȃ������j/169
79 ���܂�[�Ɩ������i�݂��j/171
80 �v�ē� �䉮��̑��z��/174
81 �v�ē� �^�ӂ̔�����/176
82 �v�ē��̓V�@�{/178
83 �v�ē��̑����ƍ��ΐX���
�@�@���i���邵�ނ��������Ԃ��j/180
84 �F���̑�h�S�Ƌv�Ă̌}�̏�/182
85 �{�Â̟����_��/184
86 �{�Â̂Ԃ���/186
87 ���n���Ɛ얞��a/188
88 ���@���L���e�̕�/190
89 �E�C�k�b�d����Ƒ�a��ˁi��܂Ƃ����j/192
90 �h�C�c�c�锎���L�O��/194
91 �{�Ẫu�E�p�J���C�X�i�l���Őj/197
92 �{���E�C�s�A���/199
93 ���d�R������/202
94 �؎x�O�}���ҋ{�Ǔ��̕�/204
95 �I���P�ԕ�̔�\��l/206
96 �^�ӈ��i�܂��[�j/208
97 �|�x��/210
98 ��������/212
99 �^�ߍ���/214
100 �^�ߍ��T���j�̑�/216
101 �v���ǃo���[/219
102 ���Ԑߔ��˒n/221
�t ���E���w�蕶�����ꗗ�y�э��E
�@�@�����w�蕶���������ꗗ/223 |
���A���̔N�A�쓇�j�w��ҁu�쓇 : ���̗��j�ƕ����v���u�������s��v���犧�s�����B�@�@pid/9769810
|
�͂������i�E�����j
�ߐ������ɂ�������{�̊C�O�f�� �����/3
�A�����J��͖f�ՑD ���o�[�g�E
�@�@���o�E�����̔��d�R�Y������ ���a�F/25
�� �͂�����/25
�� �\�㐢�I�����̒�����͖f��/26
�O ���d�R�Y���j����肨��ь����_��/28
�l ���o�[�g�E�o�E�����̔��d�R�Y��/30
���~���l �y���^��/37
�͂�����
�� ���ہi���~�j�ƌ䕨��䍽����/38
�� ���s�ߔe/39
�� ���v�f�ՂƋv�đ�/42
�� �����ɂ�����s�@�����̑��o/46
�� ���Q�̖��f/46
�� ��̕s�@�ߕ��D��/52
�O ����戫����/58
�O ��C�����ɂ����问�D����̍s��/66
�ނ���
�V�䔒�̗������� �{�蓹��/75
�� ���������̐��҂Ƃ��Ă̔���/75
�� ���̗����F���̒��Z/81
�O ���e�{�w�쓇�u�x�ɂ���/85
�]�_
���̏��_�Ɠ��E���̑Ή� �{�c�r�F/95
�� ���ɕ{�̉��ǐe��/95
�� ���j�̗lj��㌾�̓E�\�ł���/100
�O �����̒��v/102
�������̎O�R����ɂ��Ă̐V�l�@ �a�c�v��/105
�u���q�A���E�v����݂�
�@�@�����d�R�n���̈��V�� �Ί_��/137
�܂�����
�� �×w�u�A���E�v�ɂ���/138
�� ���ۑ��́u���q�A���E�v/139
�O �d��V��/151
�� ���̓`���Ǝ�q��j�̎���/151
�� ���Ɛ����̊W/152
�O ��̔d��Ɛ��i�P��/154
��㊌|�\���ς�����j�̈�� �약���\/161
��㊂̌|�\�ƔO���x �X�ۉh���Y/177
�� �~�x��̖ړI/177
�� �~�s��/178
�O �G�C�T�[�ƃA���K�}�̌`��/179 |
�l �G�C�T�[�ƃA���K�}�̉̎�/180
�� �����Y�ƔO���x��ɂ���/181
�@�y�E�q�W���C�E�g�`�W�V���E�C �E����/189
�� �͂�����/189
�� ���`�E��p�n��/190
�O ��㊌��n���t�ϏB��/203
�l �ނ���/214
�ϏB���́u�T�h���v �����M�s/219
�� �ϏB���̉Ƒ��E�e���̊T��/219
�� �T�h���ɂ���/222
�O �ϏB���ɃT�h���̊�{�\��/227
���������Љ���̖ړr �������/233
�w�������R���L�x�ɂ݂�n�捷 ��Ð��v/247
�� ���̏���/247
�� ���Ԃ̐_���̒n�捷/249
�� ��㊂̌��/252
�� �{�Â̌�Ԃɂ���/256
�O ���d�R�̌��/259
�O �ނ���/261
���Ɩ咆 �{��h��/263
�� �܂�����/263
�� �����𒆐S�Ƃ������̐���/265
�O ���̑g�D/267
�l ���̋@�\�E���x��/270
�� ��@�̈ʒu/270
�� �ʔv���E����/272
�O ���e���̖@���I�@�\/274
�� �c�Ɉ��E�咆�̐���/277
�Z ����/280
��㊂̍Ղ�ɂ݂���n���I���E ��������/283
�����哇�w�l�̓��n�i�n�Y�B�L�j �R������/291
��㊌������S�����́u�������ꂽ�ΔŕЁv�ɂ��� �V�c�d��/303
�� �͂��߂�/303
�� �����j/307
�O �����Љ�/309
�� ����1/309
�� ����2/311
�O ����3/314
�l ����4/315
�� ����5/320
�Z ����6�E7/322
�� ����8/324
�l �ނ���/326 |
���A���̔N�A�����q�Y�ҁu�����̕��� : �����I�����v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@pid/9769364
|
��
���Ƒn�n�E�c���N�Ԑ��ւ̋^�� ���蕽/2
�F�˂̑哇�Ɖ��i�Ǖ��ɑ��铜�Ɛ���̍��� �b���N/43
�����O�㋇�R�̎F���˂��~�����哇�̍��� ���юO�Y/50
�w�}�����ƕ��̉���x�\���y�j���������̈�[�Ƃ��ā\ �c���E�O/54
���D�̗����n���Ɠ��̓� ��������/93
�����c���ꇁ�`���^ �������h/97
��
�����m�������̏Љ� �R�c����/104
���v�C�����m���M�o���\�����n������
�@�@���m�����x�𒆐S�Ɂ\ J.KREINER/115
��F�����ɂ����閯�ԐM�̕��K�Ə@�� �T�䏟�M/126
�c�_�Ձw�Ђ��Ⴊ�܁x�ɂ��� �ёh��j/163
���V���ɂ�����u���_�v�M�ɂ��� �i�g�B/170
���^�̃N�` �T�䏟�M/174
�_�ʂ̂肩�������� ���p�g/180
�O
�����s�����̌�@�ɂ��� ���t���v/184
���i�Ǖ��������̌��W���ɂ��ā\�E�L���i�m���j��
�@�@���E�`���i�a���j�Ƃ̑��ᔭ���ɂ��Ă̈�l�@�\ �i�g�B/199
�쓇�̒n���������� ����H/207
�쓇�̒n���\���E�염�y�K���̘A�ց\ ����H/218
�������߂̒n���ɂ��� ���a�l/226
�C����b �c���p��/228
���b���тɎR�@�ɂ��� �c���p��/238
�����S�̌ꌹ ���v��/248
�l�̌�Ɛe����\�����s�������ɂ������b�\ �b���`��/252
���������ƐԐF�ɂ��� ���c�{��/275
�����̐ԂƐA�y�ѐF���ɂ��� ���c�{��/279 |
���������ɂ�����u�H���v�̌ď̂ɂ��� �i�g�B/289
�l
��E�����K�E�`���E�s�����L���� ��L/298
�䂪���̕����K���i���V���V�钬���v�j �y��P��/323
���E��y�ђ���̍�@�ɂ��� ���ԏ[/334
�����̐H�����ɂ��� ���c�{��/339
���V���̃��`�����s���\�ʓ�ł̕����\ ���x�d��/347
�����哇�̃N���M ����q��/359
��̈�ċV�� ������Y/369
���i�Ǖ����́u�Q�N���Ձv�ɂ��� �i�g�B/371
���i�Ǖ����ɂ�����Սs���ɂ��� �R���E�`/375
�u�Z���v�Ɓu�V�}�����v�ɂ���
�@�@���\ ���v�C�����H�������̑�������\ �i�g�B/380
��
�����Ȑ߂̌��� ����w�v/390
���V���u�L���[�_���߁v�l ����w�v/400
���V���̌��� �{�c�F/408
�u�V���v�ɂ��� ���a�l/413
�����̎q��S�ƌ��� �c���p��/416
�����̉����̎q����ƏW �b���`��/430
���i�Ǖ����ی��W �ʍ]���� ��������/479
�ZI
�����哇�̋A���A���ɂ��� �q�`�X/504
�����Q���̓����T�����j �X�c���`/519
��
�哇�S�o�σj�փX���ӌ� ������/524
�u���V���D���v�ɂ��� �����u�N/535
�u�����̕����v�� �����q�Y/550
�w�������y�������x���ڎ�/556 |
���A���̔N�A���{�M�v���u�O�������{ : ����ł��Ђ���y���߂� �q�ǂ������̎O�������t�ƂƂ��Ɂv���u����ݏo�Łv���犧�s����B
|
������
���ɂ����ā@�ݕӐ��Y�@���v
�͂��߂Ɂ@5
��1���@�O�����ɂ��ā@13
��1���@���{�̎O�����Ɠ����@14
��1���@���y��Ƃ́@14
��1���@�O�����̗��j�@15
��1���@���Ǔ_�Ɠ����@16
��1���@1�@�������ĉ�����Ђ낰��
��1���@2�@��(�ǂ�)�̔���l�R,�C�k�ɂ���
��1���@3�@��(��)����i(�т�)��
�@�@�����̂悤�ȑ傫�Ȃ��̂ɂ���
��1���@4�@�T�����̍l��
��1���@�O�����ƎO�������y�̎�ށ@18
��1���@�O�����Ɖ��K�@19
��1���@�O��������ɂ��ā@20
��1���@�O�����̖��́@20
��1���@���̂���, �y��̐��������܂����@21
��1���@1�@����(�˂�)�Ɍ�������
��1���@2�@���܂��Ɍ�������
��1���@3�@����(���傤����)������O��
��1���@4�@�y��̐������Ǘ�
��1���@�y��̂��܂����@22
��1���@��(��)�̎�����,�ł����@23 |
��1���@������(���߂�����)�̃p�^�[���@24
��2���@��b���K�@27
��2���@����(���傤����)�@���(�ɂ�)����@28
��2���@�܂��₵�@29
��2���@���K��(1)
��2���@I�̃|�W�V����(�ʒu)�@30
��2���@���K��(2)
��2���@���K��(3)
��2���@���K��(4)
��2���@���K��(5)
��2���@IV�̃|�W�V����(�ʒu)�@33
��2���@���K��(6)
��2���@V�̃|�W�V����(�ʒu)�@34
��2���@���K��(7)�@�u�����������v
��2���@VI�̃|�W�V����(�ʒu)�@36
��2���@���K��(8)
��2���@VII�̃|�W�V����(�ʒu)�@37
��2���@���O����(��������݂���)�ɂ���
��2���@�X�N�C�Əd��(���イ����)�@38
��2���@���K��(9)
��2���@�X���@39
��2���@���K��(10)�@�u������v�q��d�t�r
��2���@II��III�̃|�W�V����(�ʒu)�@41
��2���@���K��(11)�@�u�������v�q��d�t�r |
��3���@���{�̂����W�@45
��3���@���K��(12)�@�u�����肱�Ԃ��v�@�x�R��
��3���@������(�������傭����)�@47
��3���@���K��(13)�@�u���c�Ԃ��v�@������
��3���@���K��(14)�@�u�務���������݁v�@�{�錧
��3���@���K��(15)�@�u�悳�����Ԃ��v�@���m��
��3���@�{���q(�ق傤��)�@54
��3���@�n�W�L�@54
��3���@IX�̃|�W�V����(�ʒu)�@55
��3���@�O�A��(������)�@55
��3���@���K��(16)�@�u�Ԃ����x��v�@�R�`��
��3���@����̉��K�@III+�̃|�W�V�����@58
��3���@���K��(17)�@�u�A�J�i�v�@���ꌧ��
��3���@���K��(18)�@�u�ăB���ʉԁv���ꌧ���
��3���@���K��(19)�@�u����(�߁[����)�v���ꌧ���
��3���@���K��(20)�@�u������(�����ǃD��[)�����^�v���ꌧ���d�R
�t�^�@����̃T���o�@66
�t�^�@���炵���y�Ŋy��@66
�t�^�@�T���o�̂�����@68
�t�^�@�T���o�̑ł����@70
�t�^�@����1 ����2
�����Ɂ@75
�E
�E |
���A���̔N�A���d�R����������ҁu���d�R�����_�W ��[��1��],��2��,��3���v���u���d�R����������v���犧�s�����B
|
3: �w�Ôg�ɂ��Ôg���������̐���Ɋւ��錤���x�ɑ��鏊�� / �q�쐴��
���d�R�̃K�����[(��������)���z�̋L�^ / �Ί_����
���b�̌n�� : �p�C�p�e���[���b�̐��E / �Ί_�ɒ�
���d�R�����̖Ԉ��� / �Ί_���F��
����̌Ñw�����ƒ��� : ���K�_�V����߂����� / ��Ð��v��
������� : ���d�R�����̉Ƒ��V��̗w(1) / �{�Lj��F��
��l�̃t���X�g����Ղɂ��� / ���_�i�j��
|
���d�R���w�����j�m�[�g : ���|���l���u�Z�u���v�̒a���Ɣ��d�R�ߑ㕶�w�̏o��
/ ����N�Y��
�`����t(�Ő�)�̓������@(�ɂƂ����ق�) : �����嗤�ɂ����鑫�Ղ�K�˂�
/ �l���c�O��
���Ǒ��̗��j / �������꒘
�j�����d�R���������ᒠ / ���d�R����������|��
�u���d�R����������v�ٕ� / ��u�Ò�
���d�R������������� / ���_�i�j��
�q�쐴���̐l�ƋƐ� : �w��Nj��ɓ��W : �����[���Տ܂̎�܂��������� / �Ί_�ɒ� |
�@�@�@�� [��1��],��2��,��3���@��������Ă���_�����������ɂ��Ă͌������K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�R�E�Q�@�ۍ�@
���A���̔N�A�u�N�G�C�T�[�Ղ�[�p���t���b�g] ��12��v���u���ꌧ�N�c���c��v���犧�s�����B
�@�@�@��� ���ꌧ�N�c���c��
���A���̔N�A�r�c��O�Y [��]�ҁu���{��������n ��10�� (�������� 1) �v���u�p�쏑�X�v���犧�s�����B
|
��B�n�� ���ꌧ ���������k(��Ït��)
�ē������f��(���q����)
�ɕ����̘b(���������Y)
���������@�������̎v���o(������)
�쐼�����̓`��(�Ζ�H�l)
�f[�J]�h��������(�g���`�Y)
���������\�����̖���(�~������)
��������V�Y�̖K�L(���������Y)
��������ƕ�����������(������������������)
���茧 �ŗt�I�s(�M�͍ؔs)
�啪�� �L�㍑�����n���̖��ԓ`��(���R���Y)
�g�E�q�唶(���c����)
�F�{�� ��㍑���h�S���M��(���؎O��)
���h�J�̔_�Ɠy��(���{�F�L)
���茧 ��O�]�̓��L(���c����) �O�����Əo���̒���(���c����)
�������b(�ڗNjT�v)
���ꌧ ��O��㋽�̘b(�{���l��)
������ �}�O�哇�̖���(����O��)
�����E�l���n�� ���m�� �y���̘b(�������`)
�����S�n���̑���(�������r) |
���Q�� ��������̖����L(���c��)
���쌧 �]��N�����l(�O�؏t�I)
�����̖K�L(�����m��)
������ �c�J�R���̖���(���J�d�v)
�u���R�v�[��������(�R�c���v)
�R���� ���h���j��������(���鎟�Y)
�������L(���쐴�q)
����Z���������L(���c����)
�@�@���� ���|���֓�������(���鎟�Y)
���|�E�L���̋�������(�L�������w���D��)
���R�� �������c�S�̓��X(�����m��)
���O�̘̐b(�������F)
������ �Ό��̔N���s��(��㉄����)
�o�_�̐m�E�q�唶(�����͑�)
�B�����̑���K��(��c�F�N)
���挧 �����암�̓`��(�ߓ��씎)
�N���s���ƐH��(�R����v)
���(�員���F)
�Q�l��������(��ؒʑ�,���c����Y��):p.496-543
�E |
���A���̔N�A���ꂠ���ь������,�A�����: ���a�c�^�~�u�����Ȃ�q���̂�����
�A���ҁv���u�Ђ邬�Ёv���犧�s�����B�@ pid/12439058
���A���̔N�A�r�c��O�Y���ҁu���{��������n ��1�� (����)�v���u�p�쏑�X�v���犧�s�����B�@�@�d�v
|
�^�ߍ����}��(�{�R�j��)
���d�R�����w��(��ɏ�i[�W����])
�V�}�̘b(����^���p)
�쓇���b(����^���p) |
����̐l�`�ŋ�(�{�Ǔ��s)
�R���̓y��(���܌���)
�����哇������(�Ζ�H�F)
���(�員���F) |
�Q�l��������,
���җ���
�E
�E |
���A���̔N�A�����m [��]�u�����̐����j�v���u�����m�v���犧�s�����B�@�@�i��W�j
�@pid/9770147�@�d�v�@�W�O�O�O�~
�@�@���L �u�����̐����j���G�W���L�O���a�ޏE��N�ތ��E����v�Ƃ���@�@�@�@�����F���������������}����
|
�n�C�r�X�J�X/1
�����̔_�@��/2
���^��/3
���r�i����j�≮��/4
�~�q�P/5
�~���K���i�≮�āj/6
��q����i�≮�āj/7
�J���J���ƃ`���N�i�����Â��j/8
�l����/9
���䗅�_�Ёi���˓������Ì��j/10
�������Y���ג��Ɛ��˓�/11
���ݎŋ��i�V�o�C�j
�@�@���i���˓��������������݁j/12
���ݎŋ�/13
�Ē����i����1�j/14
�Ē����i����2�j/15
�������i�}�[�V���^�L�j/16
�A�����|�g�i�b���j/17
����������i����1�j/18
����������i����2�j/19
����/20
�i���̎��Ƃ�i����1�j/21
�i���̎��Ƃ�i����2�j/22
�ԃ����K�̃J�}/23
�i���݂�/24
�i������i�\�e�c�̎�����j/25
�b��/26
�\�e�c��i����1�j/27
�\�e�c��i����2�j/28
�������i����1�j/29
�������i����2�j/30
�����}���J�C/31
�W�����E�i�C�����j�E�q�j���C/32
��̐��Ƃ�/33
��փ}�O/34 |
���Ԃ��� �����ӂ��i�E�u�V�j�i����1�j/35
���Ԃ���i�E�u�V�j�i����2�j/36
���ؐ�/37
�ԗ֔~��i�e�[�`�ؐ�j/38
�哇�ہi�h�����j�i����1�j/39
�哇�ہi�h�����j�i����2�j/40
�h�����i�e�[�`���I�m�ō��ށj/41
�Y��/42
�ؒY�����̔w�ŎR���낵�����Ă�����/43
�R�r�L/44
�͂�/45
���i�Ǖ�/46
�������i����1�j/47
�������i����2�j/48
���ނ�̋A�蓹/49
������/50
������/51
���莅�i�̈�j/52
�}�`�ԂƂ݂͂��/53
���/54
���K�̗t�ł̐���/55
�M�Ō��i���j�ɍs��/56
���݂���i���邷�j/57
�c����/58
��ǎd��/59
���Ȃ���/60
���k/61
�R��Ɏq����A���/62
�J���n/63
�R�r����/64
�p���v�ނ̘b/65
�K�W���}��/66
��M/67
�ӂ��D�i��D�j/68
�������M�i�����M�j�i����1�j/69 |
�������M�i����2�j/70
����D/71
�t�D/72
�J�W���}���ƑD/73
�}�[�����D�i����1�j/74
�}�[�����D�i����2�j/75
�}�[�����D�i����3�j/76
�܉E�q�啗�C/77
�h�����ʂ̕��C/78
�q���̗V��/79
�J���l�̋�ʁi�q���̗V�сj/80
�|�n/81
�R�}�V��/82
����n/83
���ю��i�T�N�E�^�i�K�j/84
�Ƃˉ�/85
�C�ӂ̃A�_��/86
�T�^�ԁi���j/87
�T�^�ԁi�n�j/88
���V�Ǖ��i�p�F���j/89
���V���i�ނ��됣�j/90
���V���i������R�j/91
�Z�p��̃}���O���[�u�����n/92
��E���i�S�m��j�i����1�j/93
��E���i�S�m��j�i����2�j/94
����/95
�I�풼��i����1�j/96
�I�풼��i����2�j/97
��������/98
����{�V���L��/99
�ǔ��V���L��/100
��C���X�V���L��/101
NHKTV/102
�E
�E |
���A���̔N�A���a�c�^�~���u�A���Ǝ��R ��10��12���@p18-22�v�Ɂu����̊O���A������v�\����B
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002256020
���A���̔N�A���䏟�V�i�ҁu�_�Ɠm�v���u�_�Ɠm���s��v���犧�s�����B�@�@pid/12266358
|
�_�ޔ��̓m(�؋I��)
�_�ЗтƎ��R�ی�(�n��)
���N�̐X(��������)
����(�ѓc����)
�R�E�m�E��(�r�Ӗ�)
�_�̂��킷�m(�ΐ_�b�q�Y)
�J�~�ƃ���(�Γc���)
�O���Ǖ�(�ɓ����Y)
�R�Ɖ_�ƈ(��c�c��)
�_�ƍ�(��R�t��)
�_�{�̌�[�R�ƌ�_�̂���(�F�m��F)
�_�X�̖{��(�~����)
������R(���c�C��)
�_�X�̂ӂ邳��(�i�R�t��)
�����j�ɂ�����R��(���؍O�Y)
�㕐�����̎R�Ɛ��ƐX(���s�r�Y)
�m�Ǝ�(��Y�o)
�_���Ȃ�̓���(�N���C�i�[�E���[�[�t)
�u�_�V�сv�̐S(�S�i����)
�T�J�L�̗��j(�ߓ��씎)
���E�̐_��(���䏟�V�i) |
���{�̎R�{�Ɗ؍��̓��R(���䓿���Y)
���N�J�{(���������Y)
���E�X�сE�_��(���J��)
��F�R�Ɖz���̋{(���{����)
�_�l�̍�(�����)
�o�̐X(���搳�j)
�_�Ђ̓m�Ɛ_�E�_��(��쐭���Y)
�R�̐_�̖�(��t����)
�_�ƎЂƓ��{�l(�ː����)
�X�̖��{�̍Č��Ƃ��Ă�
�@�@������Ԃ̍\��(�˓c�`�Y)
�_���Ɠ��{�̐S(���c�p�G)
���{�l�̎��R�ςƎO�֎R�M��(���R�a�h)
�u�Ёv�Ɓu�m�v�̕����ɂ���(���{�ꖯ)
�u�_�Ɠm�v�ɂ���(�F��h)
�_���܂苋����(�����r�v)
��[�n��(���|���_)
�努��(���c�q��)
�l�̎��R�̐M��(������V)
�K���A�̐X(�W���[�N�E�v�Y�[�� �J�����Y��)
��{�R�ƎR���E�ؖ{��(�Ð�^��) |
�_�͍s���䂯�E�����͗��܂�(�x�c�g�Y)
�_�ւ̌h�i�A�m�ւ̊���(�{�c����)
�_�̓m(�{�c����)
����̐X����(�����Č�)
�X�̐��z(���{�M�L)
�����Ñ�̎ЂƗёp(���{�떾)
�m�ւ̈��ƈؕ|���c(��q�Y)
���̐_�X(�O�Y�Y��Y)
����̐X�Ɛ_�З�(���O)
����̐_�Ɠm(�{��h��)
���R�Ɛ_��(�O�֔֍�)
�╔�̓~��(���R��d)
�{���g�b�N���ɂ����鐹���ƏW��(��������)
�_�؎v�z�ƉA�z���E�����̌���(���R�C��)
����Ԃ̌���(���i����)
�_�{�̐X(�����)
�_�{�{��тƎ�(�R�����q)
�G���U�x�X�����ƃg�C���r�[���m(���h)
�ꏼ�R(�ᏼ����)
�����̐_(�a�̐X���Y)
�킪����̐X(�����Y) |
|
| 1977 |
52 |
�E |
�P���A���y�v�拦��� �u�l�ƍ��y 2(5)(12) �v���u���y�v�拦��v���犧�s�����B�@�@pid/2832349
|
���������R / ���㕺�q/p8~9
�ꉹ�����Ǝq������ / �p�c���M ;���v/p10~19
�V���y�̑n���� / �����K�V��/p20�`24
�ڗ��Љ��s�s�����̂� / ��������/p25�`32
�s�s�H�w�I�ɂ݂���s�_ / ���F/p33�`36
�����Ǘ��@�\�W�ς̌��� / ������/p37�`41
�s�s�̉��K�� / �쓇�C�F/p42~49
��s�ړ]�ɂ��� / �R���Ǖ�/p50�`54
��s�̃C���[�W / �V�䑥�v ;�L��Y/p55~63
�]�˂ɂ������s�s��� / �{����q�Y/p100�`104
�V��s�u���W���A�̌��� / �i�c���v/p105�`109
�C�M���X�̓s�s�c���}���� / �F�V�Z/p64�`69
|
��������ۣ�s���ƐV�n�ˈ / �g�䋧��/p90�`91
��s�����l���� //p79~88
�����_�I���U�_ / �{��O/p94~95
��ƂƂ��ɐ����� / �_���l/p96�`97
�Â��܂��ɐ��s�̐V�����܂��Â��� / �������Z/p98�`99
�_�Ƃ̎������߂����헤���c�̔_������ / �������V/p110�`113
���m���\�\�y�n�J���s�ׂ̋K���ɂ��� / �t���䕶�l/p114�`117
�a�̎R���\�\���y�̏����W�] / ���Y���h/p117�`119
���ꌧ�\�\�R�p��n�̐��p��� / �R�鐳�h/p120�`123
���[���b�p���P�����ُ��� / �ҏW��/p75�`78
�~����j�s�E���ˎs //p71~73
�c�������̒��Â���E�{�茧���� / �ҏW��/p92�`93 |
�Q���A�u����R���� (2132)�v���u����R�o�ŎЁv���犧�s�����B�@pid/7894648
|
��@��s�͌��_�ɑJ���� / ���c�`�C/p2�`3
����ǒ��lj��̌�e�������� / ���c�ϗz/p4�`5
�����C���u�Ñ�C���h�B���_�v�̈�ǂ������߂� / �{��E��/p5�`5
�A�t�K�j�X�^���̗� / ���K�F��/p6�`7
�䉓���ɐ�s���� �S�@�c�I�Ȗ����w�l��̌�����z�� / �R�藳��/p8�`9
����@��9�����ω� �L�O���Ƃ���ɓ��c 1�����{���ŊJ��/p10�`11
�c�R�̊��C�s� �X�_���ܓx�̒��Ŏ��{/p11�`11
���喧�������������� ����`�Ƒ�m���J�� ��12���w�����c��/p12�`12 |
�^���e�h����{�R�� �\���{�R���q����
�@�@������Ȃǐ\����/p13�`13
�����^���@�X�� ����3��15���J�×\��/p13�`13
��o���h�@�c���I ����28�����[���{/p13�`13
���썂�O������@��
�@�@��������J�m�������ɑ���/p14�`14
�ޗǕ���@�R���15���X�_���̋ʐ�Ő��s/p14�`14
�E |
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (3) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467946
|
�� / �O�Ԑ��K
�����ɂ����鎭���ΎY�o�n�ɂ��� / ����N ;�쌴���G/p1~11
���n,�Ñ�̉���(1) / �V�c�d��/p13�`33
��n�������������T�v�\�\�䕨��̍l�Êw�I�m�� / �V�c�d��/p34�`40
�����̐ԊG / �{��Đ�/p41~53
���^(�C�G�[�K�^)�̋Z�@�\��ԉh�쎁����̕������������Ƃɂ���/�n���얾/p54�`63 |
���ꌧ��������30���N�L�O�u�� //p64�`77
���ꓮ������݂�����̎��R / �r����Y/p64�`71
�����j�ƒn���w,�l�Êw�Ƃ̐ړ_ / �F��p��Y/p72�`77
�쓇�Ƒ����m�̃V���R�L���� / ���R��/p78�`98
�v�ē��̕搧�Ɋւ��鎑����� / ��]�F��/p1�`13
�E |
�R���A�ߋE�����w��ҁu�ߋE���� = Bulletin of the Folklore Society of Kinki : �ߋE�����w���� (71)�v���u�ߋE�����w��v���犧�s�����Bpid/6046048
|
�J��l �J��l(1) / ���J�d�v/p2974�`2977
�Ί_���약�ɂ����閯�ԐM�ɂ��� / �c���^��/p2978�`2988
�I�Ɏ��Q���̋����K��(1) / ��ؐ��`/p2989�`2997
|
�I�k�ɂ����鐅�̐M�`�� / �{�{���T/p2998�`2999
�G�z�l / �����v���q/p3000~3005
���ۗx��S / ���v�`/p3005~3005 |
�R���A�ɓ������ق����u���{�_�b�Ɨ����v���u�L�����o�Łv���犧�s����B (�u�����{�̐_�b / �w�u�����{�̐_�b�x�ҏW����, 10)
|
���{�_�b�Ɨ����_�b / �ɓ�������
�����J蓐_�b�̕��z�Ɣ�r / �������璘
�w�����낳�����x���߂����� / �R���ӈ꒘
�{�Ó��̐_�w : �떓�����𒆐S�� / �V���K���� |
�����̖����ƌ������| / ���������
�����̏@���V��Ɠ��{�_�b / ����������
�A�C�k�E���[�J�����߂����� / �V�J�s��
�E |
�V���A���g�Î}��������ҁu���g�Î}�������� ��1�\��v���u���g�Î}��������v���犧�s�����B
�@�@�@28p �@�@�����F��㊌����}���فF1009057801
�@�@�@�����F���a52�N7��8���E9�� �ꏊ�F�����V��z�[��
|
���������� ���g �Î}�^[��] 1
���\����]�ւ� ���� �F���^[��] 2
�g�b�v�̐V�l�t�� �r�{�� �G�Ӂ^[��] 3 |
����ɐ����ʂ��� ����^�@�����^[��] 4
�j�� �{�� �t�s�^[��] 5
���\����j�� ��X�� �����Y�^[��] 6 |
�j�� �ʏ� �ߎq�^[��] 7
�E
�E |
�V���A����|�\�j������ �ҁu����|�\�j���� ��2���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001691508 �@125p
|
��N�̌�V����Ƀ����V�[�͑啨 �R�� ���j
�����ÓT���y�Ɋւ����l�@ �g�� ���S |
�������y�w����݂�����ÓT���y ��� �x�q
�����E�吳����̌��]�̕��� �Î�� �d�� |
�P�O���A���g�^�I�q,������q���u���{�̈�w��� 28(0) 1977 p.181�v�Ɂu�����C���[�W�̈��q���͓I����(2) : ���E���E��w���̕����C���[�W�v�\����B�@�i�菑���j
�@�@���{�̈�w���28���� �J�Òn: �R����w �J�Ó�: 1977/10/12�` 1977/10/14
�@�@�܂��A������q���u����p.182�v�Ɂu����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��(2)
: �j�x��ɂ��āv�\����B
|
������q���u���{�̈�w���(26�`28)�v�ɔ��\�����u����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��(1�`
2) �v�ɂ��Ĕ��\���ꂽ����ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
���{�̈�w��� (26) p.194 |
1975-08 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤�� : �ÓT���x��ɂ��� :.�̈�S���w�Ɋւ��錤�� |
| 2 |
���{�̈�w��� (28) p.182 |
1977-10 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��(2) : �j�x��ɂ��� |
|
�X���A�R���ӈꂪ�u�����̃V���[�}�j�Y�����u�O�����v���犧�s����B (���{�����w�����p��)�@�@pid/12292547
�P�O���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 42(12)[(546)]�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059663
|
���{�_�b�ɂ�����O�݂Ɠ���
�@�@�������{�_�b�_�ɂ�����n���ƓW�J�� / �v�c����/p6�`15
�_�b�Ɖ��� //p17~69
�_�b�Ɖ��� ���_�b�ւ̍\�z
�@�@��i���_�̘b�Ƃ��Ă̐_�b��/�Ë��M�F/p18�`30
�_�b�Ɖ��� �_�X�̒����������Ɛ_�b�� / �O�Y�C�V/p31�`41
�_�b�Ɖ��� �����E���J�E���͂Ɛ_�b
�@�@�����L�I�_�b�ւ̓��W��/�H����/p42�`50
�_�b�Ɖ��� ���O�Ɛ_���n���_�b--�z�K�� / ��������/p51�`59
�_�b�Ɖ��� �n���_�b���e�r�쁄/���C�Y/p60�`69
�_�b�ƍ��J //p71~108
�_�b�ƍ��J �A�C�k�����̐_�b�ƋV��ɂ���/�����v�a/p72�`78
�_�b�ƍ��J �_�b�Ƌ����̂̍Đ�
�@�@������㊂̍��J�Ɛ_�b��/��������/p79�`86
�_�b�ƍ��J �Õ����J�Ɛ_�b / ���Α���Y/p87�`95
�_�b�ƍ��J ���ւƐ_�b / ���c����/p96�`104
�_�b�ƍ��J �^�}�t���V��Ɛ_�b / ���䐳�O/p105�`108
�_�b�ƌ�� //p109~141
�_�b�ƌ�� ���{�_�b�̌��̕��@ / �������X/p110�`119
�_�b�ƌ�� �_�b�̘_���Ɛ̘b�E�`���̘_��/���c�W/p120�`128
�_�b�ƌ�� �_�b�Ɛ��b���w / ����K�O/p129�`134
�_�b�ƌ�� ���N����邱��
|
�@�@�����_�b�Ǝ��Љ��N��/���J�쐭�t/p135�`141
�_�b�Ɖ̗w //p143~183
�_�b�Ɖ̗w �{�Â̐_�b�Ɛ_��/�{�i��/p144�`150
�_�b�Ɖ̗w �n���Ƃ��Ă̎���
�@�@���������̐_�b�Ɛ_�́�/�R���ӈ�/p151�`158
�_�b�Ɖ̗w �T�P�w�ɂ݂�l�Ԃ�
�@�@���J���C�Ƃ̌𗬁��A�C�k�̐_�b�Ɛ_�́�/�V�J�s/p159�`167
�_�b�Ɖ̗w �_�b�̂��������{�_�b�Ɖ̗w��/�����a/p168�`174
�_�b�Ɖ̗w �l���̒��̂Ɛ_�b / ���R�N�F/p175�`183
����ɂƂ��Đ_�b�Ƃ͉��� //p184�`187
����ɂƂ��Đ_�b�Ƃ͉��� ���_���� / �����i/p184�`185
����ɂƂ��Đ_�b�Ƃ͉��� �_�b�E
�@�@�����̓�I�Í��̒��̎��� / �n�ꂠ���q/p186�`187
�ǎ҂̃y�[�W ���{�_�b�ɂ��� /
�@�@���\���L ;���䏟 ;������F ;�쓇���O/p188~192
�]�_�̌n��(92)��G�g(2) / �g�c����/p193�`204
�w�E���](68)�����w���������ق̊J�� / �s�Ò原/p206�`207
���̑��Ƙ_��(74)
�@�@���u���t�l�̑n�쐶���ɂ��āv/�����@�F/p208�`209
���] ��������閽��ɔ���\�́����J���
�@�@���u���w�̋��\�Ǝ����v�� / ��L�p�v/p210�`211
�ǎ҂̃y�[�W���e��W�ɂ��� //p59�`59 |
�P�O���A���a�c�^�~���u�A�����ށE�n�� 28(4) p.99-101�v�Ɂu���搶�̂��Ƃǂ��v����e����B�@�@
�P�P���A�I�R�g�O�Y���u�g�^���߁v���u���D�Ɛ����Ёv���犧�s����B�@�@ (�Z�@�p��)�@�@pid/12866580�@
�P�P���A�Ɖ��я��Ғ��u���ꕑ�x�n�w�S�W : ������ŕ����瓂�D�h�[�C�܂Łv���u���ꋽ�y�|�\���D��v���犧�s�����B
�@�@�@�@151p�@�@�����F��㊌����}���فF1006983983
�P�Q���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.5�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
|
�T���S�ƊL�A�쓇�����o�� �O�� �i�^��
�ɍ]���̐�j���� ���� �k�~�^��
�����哇�Ɏq�Έ�Ղɂ��� �L�R �~��^�� |
�����l�Êw�����ژ^ (1975.1�`1977.11) �F�� �p��Y�^��
������� �����ǁ^��
�E |
�P�Q���A�ʏ��}�q�ҁu�����̉� ��1��@�ʏ闬 �ʏ��}�q��������i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ��}�q��������v���犧�s�����B�@�@���a52�N12��4��(��) �Y�Y�s����ّ�z�[���@16p�@�����F��㊌����}���فF1004148555
���A���̔N�A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 4�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����Bpid/9770061
|
���������_���ɂ�����ƍ��J�̌n�̌`���\�䕔�c�͕����̏Љ�Ɩ����j�I�l�@�i��j�\
����O/1
�����������̔z�����L ���K�����Y/59
�n�������됬���̎��Ӂ\�n��������ƕ����̏o�����\ ��Î�/105�@�iIRDB�j
���V���ɂ�����q�ǂ��̗V�� ���x�d��/141
���i�Ǖ����̕S������ ��c����/197
�����ߒ��ɂ����鍑�ƂƎ��Ӓn��\�������`���ߒ��̐����I�Ӌ`�\ �䕔���j/239
������j�_���� �V�萷��/285
�v�ċ�u��Ԑ،��`���ɂ��� �e�R����/311 |
���A���̔N�A��ɏ�i�c���u���d�R������ �����v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B�@�@pid/9770098�@�@�d�v
|
�̕���
���d�R�̉��y�ƕ��x/5
�������d�R�̉��y�ƕ��x/23
���d�R�̖��w�Ɨx��/29
���w/29
���x/32
���d�R�|�\�ƋΉ���/36
�͂��߂�/36
���d�R�|�\�̏���/37
���d�R�ɂ����镑�x�̐���/45
���d�R���x�ƋΉ���/50
�Ή����̓�\���i����j/56
���d�R�ɉ����镑�x�̒a��/68
���d�R�����w/74
�g�D�o���[�}�̏W���/131
�u�h�����^�v�Ɓu�h�ʒ����v�ɂ���/138
�u�����������^�v�l�\�㑺�Z�Y���m�ɓ�����\/161
�V�����������^/163
�����������^/166
����Ɛ��x������
�@�@�����W�X�^���X��w������/172
�������̃N���}�̓`���ɂ���/175
���}�[�y�[�ƃ`���_���߁\�j������
�@�@���Ɖ��������ږ��̈��b�\/177
�ς��ӂ� �ӂ� ��ǂ��\�������u��/183
�����I�s�Ɣ��d�R�̌|�p/227
�R���L�� |
�c���c�c��R���L��
�@�@�����o�ɂ���/265
�c���c�c��R���L/265
���/277
�刢��_�E�̗R��/284
�ω����̑n��/291
��a��̗R��/296
�蕶�L�W/303
�^�ӈ�˔�/303
�����A�����̔�/303
�{�ǐ�ˋ���/304
�Ԕn�̉̔�/306
�V�{�����/307
���a��Ôg����ҍ�����/308
�O�����̔蕶/308
��}���̔蕶/310
�^�ߓc���̔蕶/311
�c����J�w�蕶/312
�Β�n���i�[���̔蕶/313
�I���P�ԖI�V��/314
�Ί_�i������/315
�{����������/316
�g�Ɗԍ��N����/317
���쎢�̔�/318
�G��
�p���R�́u�T�}�������v��
�@�@�����d�R�����T��/321
|
�܂�����/321
�T�}�������A�Ί_���֓��d/322
���������̑���/323
���ю��E�������̌|�p/328
������̌ꌹ/335
�u�Ԃ悤��v�̌ꌹ�ɂ���/338
�����ڏZ�������j/344
��l�i�ږ��j�j/344
���d�R�z�ƊE�̉��l
�@�@����l���߂Ɛ��\���ΒY�̉��v/349
���\�剮�q�E�g�Ɗԍ��N��/354
���d�R�j��̐؎x�O���\���Ԃ��
�@�@���Ȃ������d�R�̏}���ҁ\/358
�w�C�쏬�L�x��ǂ�/363
���c���Ɠ쓇/367
���c���̗���/367
���c���Ɠ쓇�k�b��/368
���d�R�ɂ�����l���̘b/370
���������̊G�t/377
�����̊G�t/377
���d�R�̊G��Ƃ��̐l�X/380
��F�����M�Ƌ{�Lj���/385
���d�R���̑������l/391
���^�E�N��/395
����
���Ƃ���
�E |
|
| 1978 |
53 |
�E |
�P���A�{���v��,�Έ�`���ʐ^�u�������̏����� : �u�_�b�̓��E�v���v �v���u�v���W�F�N�g�E�I�[�K���o�ŋǁv���犧�s�����B
|
�}��8�� �܂����� �����Ă����_�b�u�C�U�C�z�E�v
���k��u�C�U�C�z�E�����āv �j����̂̍Վ� ���̂������܂� ���Ƃ��� |
��������̂��Ƃ� �O�� ���Y�^��
�E |
�R���A�^�������u�w�Z�ɂ����鉫��̗x��v���u�R�����r�A�^����̗x�苳�ތ�����v���犧�s�����B
�@�@�@�t�^�F������q(�ďC), �t�u�w�Z�ɂ����鉫��̗x��v������q�Ғ�(284p)
�@�@ 284p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001503836 �@�@�^���f�B�X�N 1�� : �A�i���O
(LP) , 33
|
| SIDE-A |
(1)������ŕ�(2)�l�|�x��(3)�l�璹(4)�щԗx��(5)���Ԑ�(6)�J���O�� |
| SIDE-B |
(1)�H�̗x��(2)���������(3)�Ă��̉�(4)�Ԃʕ���(5)�}�~�h�[�}�[(6)�����ʃN�C�`���[(7)���D�h�[�C�[ |
|
|
�͂����� ���� ���q
�����Ɋ� �O�� �����Y
�����ɂ������� ���� ���T
�w�Z�ɂ�����_���X����
�����̗x��̊w�K����
�x��̑I���ɂ���
�w�K�w���̓W�J
�����K�ҁ�
�x��̂��߂̃E�H�|�~���O�E�A�b�v |
�x��̎�ȓ���
���x������
������ŕ�
�l�c�|�x��
�l�璹
�щԗx��i�ƕ��j
�щԗx��i�W�c�̗x��j
���Ԑ�
�J���� |
�H�̗x��
�����������^
�Ă����ʉ�
�Ԃʕ���
�}�~�h�[�}�[
�����ʃN�C�`���[
���D�h�[�C�E�J�`���[�V�[
�x��̕���
����̗x��ɂ��� |
����̗x��̊T�v
����̗x��̋敪���Ǝ��
�������x�̎��
����̔N���s���E�Ղ�Ɗ֘A�����|�\
�u������ŕ��v�̗x��}
�j�x��̓���
���x��̓���
�E
�E |
�R���A������w�@���w���ҁu���A�W�A�������ɂ����鉫��̎Љ�E�����ɂ��Ă̑����I�����v���u������w�@���w���v���犧�s����B�@�@
(���茤���I�v ; ���a52�N�x��1�W)�@�@pid/9773332
|
�����̌���̏�� �㑺�K�Y/1
�u���c���j�v�����̑O��Ƃ��Ẵm�[�g ���{�b��/7
�����ȗ��̐��i �\����������e�̈�`�ԁ\ ������/17
���������v�̐��̍\���Ɠ���
�@�@���\���������̏ꍇ��ʂ��Ă݂��\�i�T�v�j���鐳��/31
����̐��������Ɋւ��錤���i�T�v�j ��Ê��Y/33
��㉫��̒n�Ж�� ����b�L/35
��㉫��̔_�ƕ��� �R�����W�E����v/45
�����Ɖ���풼��̌��������i�T�v�j �K�n����/63
�ٍ��D�K���L�ɂ�鉫��̎Љ�ƕ��� �F��p��Y/67
�u�c��v�ϔO�̍l�@ |
�@�� �\���ꒆ���̃����𒆐S�ɂ��ā\ �`��������/85
���ꕶ���̓Ǝ����ɂ��āi�T�v�j ��c���G/93
�����̏d�w�ƌ|�p �\���̎j�I�l�@���\ ����Ԍ���/95
�����҂Ƃ��ẴA�����J�l�̑Ή���i�l�j�ςɂ���
�@�@���\���̉p���V���E�G���A���̑��̎�������\�i�T�v�j �{��x��Y/107
���Z���̐����s���ɂ݂�Main-island�ւ̎w���ɂ���
�@�@�� �\�ɐ������̏ꍇ�\ ���R��/109
���̐��Ԋ�� �\�����̕��� �ڍ�Θa/117
���̃G�R�V�X�e�� ���ܐL�O/131
�����̐��̐��� �\����W�����̎��W�v��Ǝ��{�\ �䕔���j/143
�E |
�R���A���c���q���u�c�A�₵�����v���u�Y�R�t�v���犧�s����B�@�d�v
|
�����@1
�����@�c�A�₵�Ƃ͉����@12
��1���@���_�@15
��1���@��1�́@�c�A�₵�̌n���ƒn��I���ށ@16
��1���@��2�́@�c�A�₵�̗��j�@25
��1���@��3�́@�c�A�₵�̖����@30
��1���@��3�́@��1�߁@�c�̐_�M�@30
��1���@��3�́@��2�߁@�c�A�₵�n��̈��V��@33
��1���@��3�́@��2�߁@(��)�@�d��V��@33
��1���@��3�́@��2�߁@(��)�@�c�A�V��@36
��1���@��3�́@��2�߁@(�O)�@���̐����ߒ��ɂ�����V��@38
��1���@��3�́@��2�߁@(�l)�@���n�V��@39
��1���@��3�́@��2�߁@(��)�@�����̗\�j�V��@39
��1���@��3�́@��3�߁@�c�A�₵�̌^�ԁ@42
��1���@��3�́@��3�߁@(��)�@�d���c�@42
��1���@��3�́@��3�߁@(��)�@��c�A�@43
��1���@��3�́@��4�߁@�c�A�₵�Ɠc�y�n���|�\�Ƃ̊W�@48
��1���@��3�́@��4�߁@(��)�@�c�A�₵�Ɠc�A�_���@49
��1���@��3�́@��4�߁@(��)�@�c�A�₵�Ɠc�y��@52
��1���@��3�́@��4�߁@(�O)�@�c�A�₵�Ɠc?�@53
��1���@��4�́@�c�A�₵�̕��w�@55
��1���@��4�́@��1�߁@�c�A�̖{�@55
��1���@��4�́@��2�߁@�w�c�A�����x�@58
��1���@��4�́@��2�߁@(��)�@�͂��߂Ɂ@58
��1���@��4�́@��2�߁@(��)�@�w�c�A�����x�̐��������@58
��1���@��4�́@��2�߁@(�O)�@�w�c�A�����x�̍\���@59
��1���@��4�́@��2�߁@(�l)�@�w�c�A�����x�̕��|���@61
��1���@��5�́@�c�A�₵�̉��y�@74
��1���@��5�́@��1�߁@�c�A�₵�̗w�̉��y�I���ށ@74
��1���@��5�́@��2�߁@�c�A�₵�̗w�̎��^�ƋȌ^�@77
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@���|�n�W���^�c�A�̗w�Q�@77
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@��肤���̗w�Q�@82
��1���@��5�́@��2�߁@(�O)�@�т키���̗w�Q�@88
��1���@��5�́@��2�߁@(�l)�@����n�W���^�c�A�̗w�Q�@92
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@���}�����̗w�Q�@96
��1���@��5�́@��2�߁@(�Z)�@���Z�E�߉�S�n�̗w�Q�@98
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@�I���V�^�̗w�Q�@105
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@�e�́E�q�̌^,�K�b�^�̗w�Q�@113
��1���@��5�́@��2�߁@(��)�@����n�N�Y�V�n���̗̉w�Q�@114
��1���@��5�́@��2�߁@(�\)�@�J�c�}�n���̗̉w�Q�@118
��1���@��5�́@��2�߁@(�\��)�@�N�h�L�n���̗̉w�Q�@118
��1���@��5�́@��2�߁@(�\��)�@���ۂ�ʓc�A�̗w�@122
��1���@��5�́@��3�߁@�y��@124
��1���@��5�́@��3�߁@(��)�@��ށ@124
��1���@��5�́@��3�߁@(��)�@�`�ԁ@125
��1���@��5�́@��3�߁@(�O)�@�@�\�@127
��1���@��5�́@��3�߁@(�l)�@�Ґ��@128
��1���@��5�́@��3�߁@(��)�@�t�@�@129
��1���@��5�́@��3�߁@(�Z)�@�t�@�̏K���@132
��1���@��5�́@��3�߁@(��)�@���[�_�[�̎w���̕��@�@133
��1���@��5�́@��4�߁@�c�A�₵�̊�y�ȁ@135
��1���@��5�́@��4�߁@(��)�@���s�̉��y�@135
��1���@��5�́@��4�߁@(��)�@�Ȃ傤�@140
��1���@��5�́@��4�߁@(�O)�@���꒲�q�@140
��1���@��5�́@��4�߁@(�l)�@�c�_���낵�̉��y�@140
��1���@��5�́@��5�߁@���K�@141
��1���@��5�́@��5�߁@(��)�@�O��̃f�g���R���h�@141
��1���@��5�́@��5�߁@(��)�@�f�g���R���h�̐Ϗd��=���K�̍\���@142
��1���@��5�́@��5�߁@(�O)�@���K�̍����@144
��1���@��5�́@��5�߁@(�l)�@�c�A�₵�̗w��
�@�@�����K��̓���(���_)145
��1���@��5�́@��6�߁@�����^�@147
��1���@��5�́@��6�߁@(��)�@�����̃O���t�C�q�@147
��1���@��5�́@��6�߁@(��)�@�j���E���艹�E���ԉ��̐ݒ�@147
��1���@��5�́@��6�߁@(�O)�@��{�p�^�[���̐ݒ�@148
��1���@��5�́@��6�߁@(�l)�@�����\���̐����@�̐ݒ�@149
��1���@��5�́@��6�߁@(��)�@���_�@149
��1���@��5�́@��7�߁@���Y���ƃe���|�@156
��1���@��5�́@��7�߁@(��)�@�c�A�̗w�̃��Y���@156
��1���@��5�́@��7�߁@(��)�@�c�A�̗w�̃e���|�@160
��1���@��5�́@��7�߁@(�O)�@�Ŋy��̃��Y���p�^�[���@161
��2���@�e�_�@167
��2���@��1�́@���|�n�̓c�A�₵�@168
��2���@��1�́@��1�߁@�w�c�A�����x�̉��y�@168
��2���@��1�́@��1�߁@(��)�@�w�c�A�����x�̕��w���@168
��2���@��1�́@��1�߁@(��)�@�c�A�₵�Ɓw�c�A�����x�@172
��2���@��1�́@��1�߁@(�O)�@�w�c�A�����x�̉��y�I�����@174
��2���@��1�́@��1�߁@(�l)�@�w�c�A�����x��
�@�@�������ɂ�鉹�y�I�l�@176
��2���@��1�́@��1�߁@(��)�@�w�c�A�����x�̗̉w��
�@�@�@���u�c�A�₵�̗w�Q�v�̒��̈ʒu(���_)�@179
��2���@��1�́@��2�߁@�������W�q�S�Ό�������
�@�@�@���c�A�₵(���y�𒆐S��)�@186
��2���@��1�́@��2�߁@(��)�@�d���c�ɂ�����c�A�₵�̉��y�@188
��2���@��1�́@��2�߁@(��)�@�{���ɂ�����c�A�₵�̉��y�@196
��2���@��1�́@��2�߁@(�O)�@���_�@202
��2���@��2�́@����n�̓c�A�₵(�n��Љ�Ƌ��{�c�A)�@203
��2���@��2�́@(��)�@�͂��߂Ɂ@203
��2���@��2�́@(��)�@�L�����̒n��Љ�@205
��2���@��2�́@(�O)�@�L�����̋��{�c�A�@209
��2���@��2�́@(�l)�@���_�@225
��2���@��3�́@���}�����̓c�A�₵(���F�Ɖ��l)�@227
��2���@��3�́@(��)�@�͂��߂Ɂ@227
��2���@��3�́@(��)�@���}�����ɂ��ā@227
��2���@��3�́@(�O)�@���}���ߏd����Ɠc�̂̍\���Ƃ��̉��l�@228
��2���@��3�́@(�l)�@���}�����c�A�₵�̎Љ�I�w�i�@231
��2���@��3�́@(��)�@���}�����c�A�₵�̉��o��̓��F�@234
��2���@��3�́@(�Z)�@���}�����c�A�₵�̉��y��̓��F�@235
��2���@��3�́@(��)�@�c�ۂ̏���@245
��2���@��3�́@(��)�@�d���c�̓c�́@249 |
��2���@��3�́@(��)�@���_�@249
��2���@��4�́@���Z�E�߉�S�n�̓c�A�₵(���y�𒆐S��)�@251
��2���@��4�́@(��)�@�͂��߂Ɂ@251
��2���@��4�́@(��)�@���s�̉��y�@252
��2���@��4�́@(�O)�@�c��́@252
��2���@��4�́@(�l)�@�c�A�́@255
��2���@��4�́@(��)�@�c�_���낵�̗�́@262
��2���@��4�́@(�Z)�@���_�@264
��2���@��5�́@���c�S�n�̓c�A�₵
�@�@��(7�E7�E4���̗w�̉��y�I�W�J)�@266
��2���@��5�́@(��)�@���c�S�ɂ�����唏�q��
�@�@�@��7�E7�E4���̗w�̉��y�I�W�@266
��2���@��5�́@(��)�@���c�S���{��������
�@�@�@��7�E7�E4���̗w�̉��y�I�W�J�@270
��2���@��5�́@(�O)�@���c�S���{�������̂��̑��̓c�A�̗w�@275
��2���@��5�́@(�l)�@���_�@280
��3���@���{���ӂ̓c�A�́@281
��3���@��1�́@���V���̓c�A���@282
��3���@��1�́@(��)�@�͂��߂Ɂ@282
��3���@��1�́@(��)�@���V���̈��V��@282
��3���@��1�́@(�O)�@���V���̈��V��̉��y�@287
��3���@��1�́@(�l)�@���V���̓c�A�̌|�ԁ@294
��3���@��1�́@(��)�@���V���̓c�A�̂̉��y�I���i�@296
��3���@��1�́@(�Z)�@���_�@319
��3���@��2�́@�����̓c�A�́@322
��3���@��2�́@(��)�@�����̒n��Љ�@322
��3���@��2�́@(��)�@�����̓c�A�̌|�ԁ@324
��3���@��2�́@(�O)�@�����w�I�ɂ݂����N�E
�@�@�����{�̓c�A�K���̔�r324
��3���@��2�́@(�l)�@�����̓c�A�̂̕��w���@328
��3���@��2�́@(��)�@�����̓c�A�̂̉��y�I���i�@331
��3���@��2�́@(�Z)�@���_�@337
��4���@���_�@341
���Ƃ����@�����O��v�@347
����(��������,�̗w����)�@353
�y���ڎ�
����1�@���|�n�W���^�c�A�̗w��r�����@79
����2�@��肤����r�����@84
����3�@�т키����r�����@89
����4�@����n�W���^�c�A�̗w��r�����@94
����5�@���}�����A���q�@95
����6�@���}�����_���낵�̉��y�@99
����7�@���}�����c��́@100
����8�@���Z�E�߉�S�n�c�A�̗w��r�����@103
����9�@�̂��o���̉�(�c�_���낵�̉�)�@106
����10�@�唏�q�E�T�L���߁E���́E���c�߁E
�@�@�����|�n�I���V��r����109
����11�@�i�K�V�@111
����12�@�e�́E�q�̌^�̗̉w�@113
����13�@�K�b�^�̗̉w�@114
����14�@�I���n���̗̉w��r�����@116
����15�@����N�Y�V�n���̗̉w�@117
����16�@�I���J�c�}�n���̗̉w��r�����@117
����17�@�J�c�}�E���̉́@119
����18�@����n����S�@120
����19�@�c�_���낵�̗�́@121
����20�@���ۂ�ʓc�A�̗w
�@�@��(���̃l���́E�����́E��~�́E�c���)��r�����@123
����21�@���s�̉��y(���|�n)�@136
����22�@�Ȃ傤�̉��y(���|�n)�@138
����23�@���꒲�q(���}����)�@139
����24�@�w�c�A�����x�̉��y�̕���(���|�n�W���^)�@181
����25�@�w�c�A�����x�̉��y�̕���(���|�n��肤��)�@185
����26�@�w�c�A�����x�̉��y�̕���(���|�n�I���V�^)�@186
����27�@�c���(�d���c)�@189
����28�@�\�����т�(�����傤��)�@194
����29�@�����-(�����傤��)�@195
����30�@���s�̉��y(�{���E�Ƃ炯��)�@197
����31�@�c���(�{���E��肤��)�@199
����32�@�c�A�́@221
����33�@����S�@223
����34�@���s�̉��y(�����q)�@236
����35�@���s�̉��y(���s)�@237
����36�@���s�̉��y(�{�߂���)�@238
����37�@�c�_���낵�̉��y�@240
����38�@�c��́@244
����39�@�A���q�@246
����40�@�c��́@254
����41�@�c���(���)�@254
����42�@�c�A�́@258
����43�@��F(���)�@260
����44�@���s�̉��y�@260
����45�@���i���q�@263
����46�@�c�_���낵�̗�́@265
����47�@�͓��߁@271
����48�@���J�P(�y�t��)�@273
����49�@�i���W���C�߁@273
����50�@�R�����q�@276
����51�@����n�W���^�c�A�́E���|�n��肤����r�����@277
����52�@�h���h���ߔ�r�����@289
����53�@�����x��(�������Ђ�����)�@292
����54�@�����x��(�܂�������)�@293
����55�@��̐�̓c�A�́@298
����56�@�ԓ��̓c�A�́@302
����57�@��X�̓c�A�́@306
����58�@��Ԃ̓c�A�́@311
����59�@���V���̓c�A�̏����̉̔�r�����@314
����60�@���V���̓c�A�̒j���̉̔�r�����@316
����61�@(���@�c�A��)�@339�@
����62�@(���@�����c�A��)�@340 |
�R���A�M�y�Еҁu�G���M�y (14) �v���u�M�y�Ёv���犧�s����B�@�@�@�@pid/2202343
|
�\ ����/p5
�̕��� ���i��/p8
��z�K����/p12
���q�@�y��̕����ɂ��nj�/p9
���w���̕��Ɖ��t�ɂ�银����ޗ˕p/p10
�J���[��� �E�q�_�̉�y�Ǝq���̕��y / ���c�Njv/p14
���W ���i��/p22
����i����̂��낢�� / �i�R����/p22
�\����Ɖ̕��ꢊ��i��� / ���ѐ�/p31
����i����ٌ̕c�������� / ���R���V��/p39
���W ���a�\��N�x �|�p��/p62
�|�p�ՎQ���ِ̈F��ǂ��� / ������Y/p62
�|�p�Ղ̖M�y�ɂ��� / ��Q���S�N/p67
�|�p�Ղ��ĉ�?/ �J���/p72
�䂸��t�ɂ͂Ȃ�Ȃ� / �R�c����q/p74
���W �M�y�E�ɖ��o���V�������c�̂̐����낢�Ɩ����/p102
�M�y4�l�̉� / �k��⹎R/p102
���S������ / �������\�Y/p104
�n��M�y�̉� / �������\�Y/p107
|
���{���y�W�c / �����f�q/p109
�����щ� / �H�ꊲ�q/p112
�ӂ��̉� / ���䐟�q/p113
�D�y���y�W�c���Q�� / ��ˉĐ�/p114
���a�\��N�x �M�y�E�����Z / �|�����h/p45
���a�\��N�x ��������̖M�y���t��� / �h������/p16
�M�y�M�d�����̕����u�[�� / ���쌒��/p96
��������̉̕��ꌤ�C�ƕ��y���C / �����S�\/p90
����ł̓��{�̗w�w��m���y�w������
�@�@���q���{�̗w�w��r / �P�c�r�ܘY/p50
���d�R�����|�\�ɐڂ��āq���m���y�w��r / �Љ��`��/p54
�K��L ���h���y�@(ⵋȊw�Z)�K��L / ���������������/p118
���y / ���R�×Y/p123
�ڔ� �����čs��(���̎l) / ���R����/p58
�c�ӏ��Y�v���o�Ȃ� / �c�ӏ��Y/p77
���{���y�̗��j�����ǂ� / �g��p�j/p83
���̗t(�O�����g�̒���) / ���{�@��{�̗w������/p128
���̑I�{�ƃ��R�[�h / ������Y ;�������q ;����/p136
�M�y�p�ꎫ�T ��ڥ�Ȏ��(3) / ��������/p145 |
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (4)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@�@�@pid/3467947
|
�� / �O�Ԑ��K
���d�R����,�g�Ɗԓ��̒n�`�ƒn���\�\���S�ʂ̌`���ߒ�����ђn�k�ϓ��ɂ��Ă̗\�@ / �͖��r�j ;����N/p1~16
�����}���K���m�W���[���\�\���̌`��E�z���w�I�E�n�����w�I���� / �쌴���l ;����N/p17~30
�����̌��{�G�\�\�����问�����t�ɂ��� / �{��Đ�/p31�`43
�ɕ������̖K�L�\�\���K�����̖����������� / ��]�F��/p44�`62
�g�^�̌^���ƌ^����\�\��ԉh��m�[�g�����Ƃɂ��� / �n���얾/p63�`73
��R�Ɋւ��镶���ژ^�\�\�����s�������ی�ψ���ɂ���R��Ւ����������� / �V�c�d��/p75�` |
�R���A�u�ɍ]����u���L�ˁv���u�ɍ]������ψ��� (���ꌧ) �v���犧�s�����B�@ (�ɍ]��������������
; ��4�W)
�@�@�@�F��,�p��Y,���{,�L�q,����,���G,����,�G�q,�ēc,�P��,����,��,����,�`��,�o�ߔe,����,�Ɠc,�~��,���{,�땶�@,����,����,����,�k�~
|
�ɍ]����u���L�˒����T�� / �F��h��Y, ���{�L�q
����o�y�̖퐶���y�� / �F��h��Y |
��u���L�˂̂͂Ȃ� / �F��h��Y
�ɍ]���̈�Օ��z / �����k�~ |
�R���A�u���ꌧ�ɍ]���S�w�Y���̒����@��2���T��v���u�ɍ]������ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�i�ɍ]����������������5�W�j�@���J��,�P�a,����,�W��,��R,����,�쓇,�R��,����Y,�쌴���G,�슡�ƍG,����c��,�R���q
|
�����ɂ悹��
1 �͂��߂�
2 ���Ս��̂��鎭�p�ɂ��� |
3 �������Y����l���p
4 �S�w�Y���̏b�ވ�[�Q�W
5 �S�w�Y���o�y�̐l���ɂ��� |
6 ������
�E
�E |
�R���A�u�ɍ]���̃p�W�`�����v���u�ɍ]������ψ���v���犧�s����ꂤ�B
�P�U��(�ɍ]��������������, ��6�W)�@�d�v
|
�ɍ]���̃p�W�`������ / ���Ð^���v[��] |
�n(�n�W�`)�̈�l�@ / ��]�B�q�v[��] |
�R���A���ꌧ����ψ���ҁu���ꌧ�Ў��E��ԗђ����� 1�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@ 120p�@�@�i���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y�@�@��15�W�j�@�����F���ꌧ���}���فF1001567450
|
���������̎�Ȍ�菊�̐A��1 �V��a��
�X���������菊�т̐A�� �@�V�[�`�n
�������̌�菊�т̐A�� �@�V�[�`�n |
���A�m���̌�菊�т̐A�� �@�{��N��
���������̎Ў��E��ԗт̐A�� ���z����
�����S����v��Ԃ̐A�������� �@�V��S�v |
�R���A�u�ɍ]���쐼�n��̈�Օ��z�v���u�ɍ]������ψ��� (���ꌧ) �v���犧�s�����B
�@�@�@ (�ɍ]�������������� ; ��7�W)�@�@���Ð^,���v,����,�k�~
�S���A���{�̗w�w��ҁu���{�̗w���� (�ʍ� 17)���u���{�̗w�w��v���犧�s�����B�@�@J-STAGE
|
�ڎ��i17���j ���{�̗w�w�� p.0-0
�����䔄�`���Ɖ̗w�̍\�� �{���O p.p1�`9
�a�����o--���o�鏴�Ɩ{�n��瑎v�z ���×Y p.p10�`15
���o�鏴�ޏ��� �n�� ���q p.p16�`21
�u����͌������v�̗̉w�� ���{�\�O�Y p.p22�`26
���É���֒Îj�l--���ڊݑ����߂�����
�@�@�����c���g p.p27�`32 J
��R�q���̓��w ���T�q p.p33�`38
�����̛މ́u�i�K���́v--�u�������߂Ȃ��ˁv��
�@�@�����S�ɂ��� ���c ���q p.p39�`45 |
J.-B.Lully�̒��̃C�^���A�ƃt�����X--����<�{��o���[>���̃C�^���A���
�@�@�����V�ƃt�����X��̃��V���߂����� ���� ��q p.p46�`53
�q���̂̐����Ɖ��K�\���̌���--
�@�@�����̗ތ^���̎��� ���c��,����G�� p.p54�`63
����K��Y���u���w�̏��v ���H �C�Y p.p64�`67
�u���{���w��ϋ�B��(�k��)�v ���c���q p.p67�`69
�ዽ�ДV�i�E�^�珹�O���u���ׂ����v �V�Ԑi�� p.p69�`71
�q���]�r�����t�~�q�ҁw�y����ڗ����{�W�x�S�O�� �P�c�r�ܘY p.71-72
�p���ڎ��i17���j p.999-999
�E |
�S���A�㌴���P ,��闧�T,���n�N�v���u�쓇�̕��y�Ɨ��j�v���u�R��o�ŎЁv���犧�s����B
�@�@�@(���y�Ɨ��j ; 12)�@pid/9770178
|
�� ���ɐ�����/3
������/4
�C�ɐ��ޗ��j/7
�䕗�Ɲ��/9
������/13
�_�X�ƍՂ�/16
�����Ƃ₳�����̕���/19
1 �C��̓�/23
�����m��ʉ��������/24
�C���E�A������/26
�Ɨt���т̉A/29
�쓇���l�̐��E/31
�O�̕�����/34
�嗤�ւ̓�/37
�J���ꂽ�C��̓�/40
�S����/43
2 �쓇���S����l�X/47
�g���쓇�H/48
�s���̕���/50
�r�������/53
�쓇�̕���/56
���l�̓�/59
�����h����/61
3 �_�X�̓�/67
�}�L���Ɛ_/68 |
�ܖڐߓ�/70
�I�i���_�ƃV���[�}��/75
�T�b��̂��镗�i/78
4 �e��/83
�h��铌�A�W�A���E/84
�O�R������/88
�i�ƃO�V�N/91
��������̖�/96
��ւ̔e��/100
�ߔe��/103
�����̒×�/107
�S�Y�Y/110
5 ���E��a�̂͂��܂�/115
�H���y�̍s��/116
�B���ꂽ�t���h�V/120
�G�ꂽ����/123
�������/127
�u���X�̍��v�Ȃ�ǂ�/131
���̉��F���R��/135
6 �������/139
�쎀/140
�~���N���E��̊肢/143
�����鍻����/147
��z����/150
��̑i��/154 |
7 �C�m�������̖���/159
�C���͂��鏗/160
���D�Ɠ���/164
�O���̋���/167
�n�����O�̉�/170
�䊥�D�x/173
�їV�тƑ��ŋ�/176
���j�̏d�ׂ�/179
8 �����m�̏\���H/183
�����̊O/184
�E�����_�[�Ƃ̏o�/186
�u�������v/189
���{����/193
�L���X�g�[��/198
9 �쓇����/203
�c���́u�����v/204
�����̏I��/208
�擇������/211
���ܓ�N�l����\����/216
10 ���炪�����X�̐S/221
�����萢������/222
�����̍��q�@�ܘY�㋞��/226
�肨�Ƃ��ꂽ�l�����w/231
�q�풆�w�Z�X�g���C�L����/235
�쓇�̕����I�i����`/238 |
11 �������߂閯�O/247
�u�p�˂̎m���v����/248
�悻�����Ȃ����|�\/251
�җV�f/254
�̌��̖���Ə���/256
12 �C�m�̉c��/261
�q�V�̂߂���/262
��̂���D/264
�������v/268
�D����̐_��/271
13 �����͂ǂ���/277
���n�̏�����/278
�l�ފ�/282
�u���܂�ւ问���l�v/284
�����͈��M��/287
��シ��m���l/291
�����_��/294
14 ����ǂ��ւ䂭/301
�ɔg���Q�̐�M����/302
�c���Ɨ����/304
�A�����J�����烄�}�g����/309
�����Ɠ��{��Ɖp���/312
���y�Ɨ��j�̖�����/315
���Ƃ���/321
�E |
�T���A�|�\�w��ҁu�|�\ 20(5)(231)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276426
|
�����̂��Ƃ�J���I�P���s� / �O�����Y/p7�`7
�Y�_�ɂ���-1-�V�Y�_�॓�Y�_�॑��� / �h�p�N/p8�`20
����������R�ƒ����̣-35- / �O�����Y/p21�`28
���-�܌��M�v�̐��E(17) / �R�������Y ;�F����o�j/p38~39
���̕��ꉹ�y�W��--�����-40- / �n���h���q��/p29�`37
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-188- / ���������Y/p40�`43
�F���g������c���j�(���{����������n1) / �������H/p44�`45
�R��ɓ��꒘����{�Y�\�̋N��� / �q�ѐ���/p45�`46
���c���q����c�A�₵����� / �������q/p46�`47
�����N�\(4��1���`4��30��) / ���c�m/p53�`61
���x�N�\(���a53�N�㔼��) / �@���q/p62�`65 |
����������Q���� / ��،�/p49�`49
���x��n������̑�{���� / �m�����Õv/p50�`50
�f�梓��{�f��ɎႢ�˔\��!� / ���Njv�l�Y/p51�`51
�m���u��������P���l�v / �����/p52~52
�\�������Ɩ��Ƀo�b�N�����|�/p66�`66
�\�̗\�]��ϐ��͇����s�k�����낦�/p67�`67
���a�\�O�N�x�t�̏��M��͎�/p68�`68
������(I.�EII.)/p69~73
�V���Љ� �Ð�v����\�̐��E��������̐��E�/p48�`48
�V���ē�/p48~48
�E |
�U���A���֏�v���u�����������v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s����B�@�@pid/9770245
|
��
�쓇�̌Ñ�/2
�����ʐM/8
���d�R�̖���/20
�K�[�T�ƌ���/25
�썑�L�˔����̊J���ʕ�ɂ���/27
�^�_�����߂�����/33
����g�Ɗԓ����@�̐Ί�/36
���Ɨ����Ɩ{/39
|
�o�W���E�z�[���w�嗮�����q�C�T���L�x/43
���u�̘��F�Ǝ�q��/47
�w�^���I�N�x�Ɍ����问���W�L��/50
����̋��F/55
�앗�����۔��m������/58
�J�[�̎v���o/61
2
���d�R�Q���̌Ñ㕶���\
�@�@���{�ǔ��m�̔ᔻ�ɓ���/66
|
�����̌���Ɩ����̋N���\
�@�@�����������̘_�l�ɓ�����/152
���d�R�{�w��a�̏W�x/156
�O
�����̗�/184
�^�_�̗�/269
��� �����N/282
���Ƃ���/291
���o���\�o����/293 |
�U���A�V���{����}���ҁu���Ƃ̂� ��10���v���u�V���{����}���v���犧�s�����B�@�����F��㊌����}���فF1003003413
|
�𖾐i�ލ����̊L�̓��̐��E ���G�J���[
�L�̓��̍l�Êw �i�� ���� ��������
����̒T�� ����̖���
�����̊L�̓��̐��E ���䒷�� ��q���̕��� ���֏�v
�����S�z�E���ꌹ�l �i�䏹��
�쓇�̖������� �N�㌳�Y
��̐_���J�铇 ������G
���ꏔ���ɂ�����C�ӂ̔q�� ��]�F�� |
�}�W�J���݂��鉫��l�Êw ���{�A��
�擇�̌Ñ㕶���Ɠ쓇�I�v�f �V�c�d��
�𖾂����ލ����Ñ㕶�� �O���i
�쓇��j�����Ǎl ��������
�쓇�̕搧 ���Ð^�X��
�×����̕��� ����^���q
����̗��o�V�� �n���얾
��㕶�w�ɂ݂��l �������X |
�U���A�얞�M�ꂪ�u����E������̖₢ : �����ւ̊��]�v���u�ח��Ёv���犧�s����B�@
�@pid/9770234
|
�~�N������т���̔��z/7
�w���܂�ւ问���l�x�����̈Ӗ�/7
�����o�Ő���ƍ��ƌ���/11
���ʉ����ꂽ�s���̋K��/16
�~�N������̑ٓ��̈�/22
����c�����A�̈Ӗ�/27
����Ɠ��{����/27
�[�������̂Ƃ��Ẳ���/32
��}�����O�̕��A����Ƃ���/38
�������ւ̊��]/44
���O�_�\�A�W�A�I�����u���̖͍�/50
���v�z�̖��_/51
�s�����t�Ɓs�����t/58
���������燀�A�W�A����/64
�A�W�A�I���O�����̎v�z/69
����Ɠ��{�̒f�w�\�������̂ƓV�c��/78
���l�ŖS�̎S��/78
�������̂̍ՋV�̈Ӗ�/84
�ՋV�̎i�Վ҂Ɛ�������/88
���O�̎����ɂ���R/94 |
�����ւ̎u��/97
����ɂ�����V�c���v�z/101
��債�����Ǝ�`/101
���������̈Ӗ�/105
�c��������̂Ȃ���/117
�������ƓV�c�M��/129
�{�y�u���̐V���ȋU�ӎ�/155
���v�z�ƓV�c��/168
�푈�ӔC�_�̕s�O��/168
�����v�z�ɂ����ĕێ�Ƃ͉���/180
�Ȃ��V�c���v�z�����ɂȂ邩/183
�{�Ø_�E�������̂̐��ƕ�
�@�@���\�����u���̖͍�/187
���ʂ̖��ɂ���/187
�{�y�Ɨ���/187
����{���Ƌ{��/192
�����̕���/201
�{�Ó������̑c�^/201
�����\���̓`��/207
�{�Ðl�̔��z�̓���/209 |
�����̘_�\�\���ւ̖͍�/212
1 �Ȃ������̂���ɂ��邩/215
�v�z�Ƌ������̊W/223
����̋��������ǂ��Ƃ炦�邩/229
�����̓��̕����I�Η��W/233
�_�X�̏���ƕ���/235
2 �{�\�Ƃ��Ă̎Љ/243
�n���_�b�̍�א�/247
�����̂̔��ˌ`��/250
�������z�̓]��/254
���l�ςւ̗ꑮ����̉��/259
3 �̎��R���Ƌ����̂̋K����/263
�u�v���v�̎w�W�ƊϔO�̋�a��/268
�s�s�G�S�C�Y���Ƒ���������/272
���鋤���̗̂L�@�I�\��/278
���̎��R�����������H�ƎЉ�/282
�ނ���/287
���Ƃ���/289
�E
�E |
�V���A����|�\�j������ �ҁu����|�\�j���� ��3���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B�@
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001691490�@105p
|
����̌|�\ �{�c ����
�]�ˏ�莞�̊y��Ƃ��̍\�� �{�� �h��
���a�O�\�N�O��̉���ŋ� �Î�� �d�� |
�����ÓT���x�őg�x�u������v�ɂ��� �Ɖ� ���P
���NJԓ��Ό��Ə����{�u�萅�̉��v-�����Љ�- ���� ��Y
�E |
�V���A�V�Ԕ�C�u�^��E��u�����G�C�T�[ : ����̖~���ǂ�v���u���ǂ��̂Ƃ��i�Q�U�W���j�@�����ُ��X�v�ɔ��\�����B
�V���A������G���u�Ñw�̑� : ���ꖯ�������_�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B�@
�@ (�^�C���X�I�� ; 4)�@pid/9770537
|
���� �i������G�j
�Ñw�̑�
��A�͂�����/11
��A���̗��n/15
�O�A�Ñ�̃}�L����/21
�l�A���̐_�Ɛ���/27
�܁A�a�Ɛ_�A�T�M/51
�Z�A�}�L����/61
���A�������̉Ɖ��z�u/72
���A���҂̍s��/82
����̏W���Ɠy�n���x
��A�͂�����/85
��A�����S�����̕��ʓI�`��/86
�O�A���~�тƕ����/93
�l�A�u���ԁv�Ɓu�O�X�N�v/98
�܁A�k��n�ƕ�n/101
�Z�A�n�����W��/111
���A�ړ������ƕ����n��/132
���A�ނ���/136
����̑����\�u�}�L�v�Ɓu���v�̔����ƌ`��
��A�܂�����/139
��A�}�L���̂̑������z/140
�O�A����ɂ�����}�L�̎���/142
�l�A�u�}�L�v�ď̂̔���/146
�܁A�ߋ��ɂ�����}�L�̕��z�Ɩ��x/151 |
�Z�A��������ɔ��������}�L/153
���A�u���v�̐���/156
���A�u���v�̌`���ƃ}�L�Ƃ̊W/157
��A����/160
�_���ɂ�鉫�ꑺ���̋���
��A�܂�����/163
��A�����ړ��̊T�v/164
�O�A�ړ������̔���/167
�l�A�_���W����̑����ړ����莖��/174
�܁A���Ƃ���/185
�쓇�̊C�_��
��A�͂��߂�/191
��A�j���C�E�J�i�C�ƊC�_/192
�O�A���K�_�̌o�H/194
�l�A���R���Ɛ_/198
�܁A�C�_��/199
�Z�A������/201
���ԁE�O�X�N�E�㐶
�u���ԁv�̖{��/203
�u�O�V�N�v�l/210
�āu�O�V�N�v�l/219
�u�����v�l/233
�u�e���v�Ɓu�~���[�v/239
���z���́w�����@���j�̌����x��ǂ��/246
�n���w���猩������̗��j |
��A�͂��߂�/261
��A�����̊��/262
�O�A�f�ՂƉ����`��/265
�l�A���ƈӎ�/269
�܁A���Îx�z�Ɖ���Љ�/272
�Z�A����̉���Љ�/273
�����ɂ�����}�����A�a
��A����/275
��A����y�ы{�ÌQ���ɂ�����}�����A/276
�O�A���d�R�Q���ɂ�����}�����A/283
�l�A�}�����A�Ɠy�n�̐���/292
�܁A�}�����A�ƋC��/298
�Z�A����/302
�������v�̌`���Ɣ��W
��A����/305
��A�������v�̋N��/305
�O�A�������ƕ��߂̒n�`/309
�l�A�Ɠ��̋��@/313
�܁A������/316
�Z�A�o�ږ�/319
���A�����o�҂Ǝq��/322
���A���O�o�҂ƒ�����Əo��/325
��A�C�O�o�҈ږ�/328
�\�A����/331
�E |
�V���A���ʏ闬�ʐ��ҁu�ʏ闬�ʐ��x��̉�[�����p���t���b�g]�v���u�ʏ闬�ʐ��v���犧�s�����B
|
���������� �ʏ� �G�q 1
�ÓT�|�\�̐S������� �^���� �R�N 2
�����ɓ��X�̐��i ��� ��q 3
���y���t
��������
��c�� |
��������
�{��v
�{�щ�
������
�V��
�� |
�ɖ�g��
����
�g�x�u���S�����v
���x��̗D�z �r�{�@���� 20
�u���S�����v�̎�� �r�{�@���� 22
�E |
|
��㊌����}���ق���������u�ʏ闬�ʐ��x��̉�v�̌����p���t���b�g�̓���ꗗ�\�@�@���
�ʏ闬�ʐ��
| �� |
�������� |
�����ꏊ |
���e |
��㊌����}���� |
| �E |
1978�N7�� |
�E |
�� |
�ʏ闬�ʐ���
31p�@1009071224 |
| 3 |
1979�N12��5�� |
�����V��z�[�� |
�E |
1�� 1006771057 |
| 5 |
1982�N7��10�� |
�����V��z�[�� |
�E |
12p 1004239420 |
| 7 |
1986�N7��30�� |
�����V��z�[�� |
�E |
38p�@1004238869 |
| 8 |
1988�N12��4�� |
�����V��z�[�� |
�E |
42p 1004691950 |
| 13 |
1994�N10��1�� |
�������y���� |
�j�����x�Ƃɂ��ÓT���x��Ƒn��
�V��������ւ̊�� ��闧�T p13 |
�n�v�n�� �ҏW
15p 1004686026�@ |
| 15 |
1998�N12��5�� |
�p���b�g�s������ |
�E |
�ʏ鐷�`���������
22p 1004685713 |
| 18 |
2004�N5��29�� |
�������ꉫ�� |
�������ꂨ���Ȃ�J��L�O���� |
1���@1004681340 |
| 19 |
2005�N12��10�� |
�������y���� |
�j�����x�Ƃɂ�鋣�� |
�ʏ闬�ʐ����� �ҏW
1���@1004680938 |
| �E |
�E |
�E |
�E |
�E |
| �E |
�E |
�E |
�E |
�E |
|
�W���A�|�\�w����u�|�\ 20(8)(234)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276429
|
�����̂��Ƃ�܌��M�v���m�ƌ|�\� / �q�c��/p7�`7
�Y�_�ɂ���--�V�Y�_�॓�Y�_�॑���-2- / �h�p�N/p9�`22
����������R�ƒ����̣-38- / �O�����Y/p23�`30
�؍��̍Ղ�̐_�� / �{�c����/p3�`33
�܌��M�v�̐��E(20) / �����_ ;�F����o�j/p34~35
���̕��ꉹ�y�W��--�����-43- / �n���h���q��/p36�`41
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-191- / ���������Y/p42�`44
��t������������w�̂����� / �q�c��/p45�`46
��씪�Y����ΐ_�M�£ / �����K�Y/p46�`47
��蕐�v������������v�l� / �эW��/p47�`48
A����r�I��O�c�[��[���X�
�@�@���x�W���[��-����o���G�̐���� / �R�씎��/p48�`49
�������l��c�R�͍ƒ�����{�f���ƑS�j�
�@�@��(�㥉�) / ���Njv�l�Y/p49�`50 |
�����N�\(7��1���`7��31��) / ���c�m/p65�`76
���x�N�\(���a53�N�㔼��) / �@���q/p59�`64
������T���V���C������ / ��،�/p51�`51
���x��|�p�ՎQ���ւ̎��o� / �m�����Õv/p52�`52
�f�梃X�|�b�g�����т钷�҃h�L�������^���[� / ���Njv�l�Y/p53�`53
�m����O���S�����B�`�̌��㐫� / �����/p54�`54
���y��܂���ʂ�܂������Ƃł���ߣ / �{��c��/p55�`56
�\�������[�y�ӏܔ\���̌�/p57�`57
�\�̗\�]����R�Ȕ���~�́w���[�x�/p58�`58
������(I.�EII.�EIII.)/p77~81
��܌��搶��\�ܔN�գ�ɂ��Ă̂����点�
�@�@�����{�̗w�w��H�G�������\�v��(����)/p64�`64
��O�\����{�����w��N��ē�(����)/p76�`76
�V���ē�/p50~50 |
�X���A ���k�V�n�����s��w�l�ފw������ҁu�G���l�ފw 9(3) p.p27�`101�v�Ɂu���\���̈��:���R�E�q�g�E�C�l--�`���I���ƂƂ��̕ϗe���߂����āv�\����B
�X���A�u���E (�ʍ� 394) �v�Ɂu����-�n���C�ږ��m�[�g�v�����W�����B9 p.p206�`239
|
�n���C�ږ����j�@�R�����C p.p206�`213
�z��(�n���C)�̂����� ��ÐÊ� p.p214�`219
���ꌧ�l�̎v�z�I�s�� �@�N�쐴�h p.p220�`228 |
���J�̒��ɐ����� �L���Nj� p.p229�`233
�n���C�ʼn�����l���� �n�ӗ�O p.p234�`239
�E |
�P�P���A�u���j�ǖ{ 23[(14)][(293)] �v���uKADOKAWA,,�V�l�������Ёv���犧�s�����B�@�@pid/7975262
|
��C�E�Ő��̓Ƒn�� / ��R�t��/p46�`56
�a�Պw����݂��Ő��E��C / ���/p74�`79
�R�x�M�ƏC���� / �{��E��/p80�`86
���Ɠ��̈ӏ� / �ߓ��L/p88~93
�����I�̓������ƕ��� / �����a�Y/p94�`99
�嗤�n�q�H�ƌ����g�D / �Έ䌪��/p102�`109
�Ő��Ƌ�C�̈�n / �O�}�a�q/p116�`117
���ʓC�k �ʐ^�ƂƉ�ƂƔ��p�j�Ƃ������������G��̖���
�@�@�� ��䶗� ���̉F���ςƃG���X /
�@�@���Ό��ה� ;�O�c��� ;�^��r��/p58~73
��t�`���̔w�i / ��ʕ{��/p110�`115
���E�ߐ��ɂ������b�R / ���R�C��/p118�`123
���E�ߐ��ɂ����鍂��R / �M�c��/p124�`129
�����̐����⚬ / �g���`�L/p100�`101
���������ƌ��㕶�w / �X��B��/p130�`135
��r�l������ �Ő��E��C�̂��ׂ� ���������̌��_��T��
�@�@���o�� ���� ���� �֘A�l�� ���Ȃɂ݂闼�҂̊W
�@�@�� �֘A�j�� ���Ւn�} �ΏƔN�\ �ߔ������m
�@�@���Q�l���� / �֓����r ;�������� ;�������B ;
�@�@���ؓ�Ꟊ� ;���c����/p137~163
���ʓǕ� ��p�̃~�C�� / �[�����/p204�`207
���ʓǕ� �����ƏC�s / �ˎR���Y/p208�`211
���ʓǕ� ��䶗��̖͎ʂ��I���ā��t�O���r�A�� /
�@�@�� ���ώq ;�{��^/p212~213
�O���r�A �J���[���G �`�^���@���E�֒���(������)
|
�O���r�A �����W�O���r�A����b�R�ƍ���R
�O���r�A �J���[���`������ ���Ύ��z�E�����܂��q(�{�錧)
�O���r�A ���j�N���u�K�� �L�������O�������w�Z�j�w��
�O���r�A ���j�����ق߂��� �{�ꌋ��ې��D������ �菏��
�O���r�A �J�����E�g�s�b�N ��p�̃~�C��
�O���r�A ���� ���@�̗� �\������
�O���r�A �ӏ܁E�\���낢�� ���� �������� / �ēc���j
�����Ђ� ���̔����\�ܓ� / �c���p�O/p37�`39
�����Ђ� ���̍����锭�� / �I������/p39�`41
�����Ђ� �֖���q��Ɓw�̂��ۂ���L�x / ��������/p41�`42
�����Ђ� �ёO�̉�S / �|�{����/p43�`44
�����Ђ� �� / �����V��/p44~45
���J�n1350�N�L�O ���n���̐�/�Ԗ�G�r/p234�`239
���J�n1350�N�L�O �V�ۉ��v�Ǝŋ�������/�g�؈�ᩎO/p240�`245
���J�n1350�N�L�O �]�ˎs��l����`/���X���g/p246�`251
���J�n1350�N�L�O �����l��̒��ɑ��Â��j��
�@�@�� / �쑽����V/p252�`260
���J�n1350�N�L�O �J���[�Òn�} ���ꗗ�}
���J�n1350�N�L�O �j�ՋI�s ���� ��
���J�n1350�N�L�O �Ǝ� / �R�{���p/p262�`263
���J�n1350�N�L�O �Ǝ� / �Ɠc����/p264�`265
���J�n1350�N�L�O �Ǝ� / �{�ܐ�b�q/p266�`267
��
���j�N���u�K�� �L�������O�������w�Z�j�w�� / �����k�s/p269�`269
�� |
�P�Q���A������q��������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��� (�ʍ� 22) p.p21�`53�@ ������w����w���v�Ɂu���x�̊ӏ܌�E�]����-3-���x�\�����̂��߂�--���{���x�̊ӏ܌�o���G�̊ӏ܌�v�\����B
|
������q���u������w����w���I�v. ��� (�ʍ� 16�`22)�v�ɔ��\�����u���x�̊ӏ܌�E�]����v�ɂ��Ă̘_������ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(16) p.199-227 |
1972-12 |
���x�̊ӏ܌�E�]����ꗗ : ���x�\�����̂��߂Ɂ@ |
| 2 |
(17) p.201-224 |
1973-12 |
���x�̊ӏ܁E�]���� : �����E���ꕑ�x�̊ӏ܌�@ |
| 3 |
(�ʍ� 22) p.p21�`53 |
1978-12 |
���x�̊ӏ܌�E�]����-3-���x�\�����̂��߂�--���{���x�̊ӏ܌�o���G�̊ӏ܌�@ |
|
�P�Q���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (1)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@pid/7955130
|
�n���̂������� / �N�㌳�Y/p1�`2
�_���W�c�̍\�} / �Ôg���u/p3�`10
����E�����ɂ�����|�̖���ɂ��� / ��]�F��/p11�`24
����̌�x�Ɠ`�� / �N�㌳�Y/p25�`32
�w���z�O����V���B�x���ڂ̐��b�̍l�@ / �c���q�a/p33�`43
����̗d���ω� / �茴�P�V/p44�`51
�Ì����̓��x��Ƃ��̎��ӂ̖��_ / �X�ۉh���Y/p52�`56 |
�����̍� / ���n�B��/p57~63
���d�R�̘̐b / ���ǖL��/p64~72
�����̗V�тƂ��S / �O���v/p73�`76
��e�E��@�Õ������������� / �ꐔ��h/p77�`84
����W�����ژ^(���a52�N�x) / ��u������ ;�{����/p85~87
���ꖯ��������/p88~88
�E |
�P�Q���A�M�y�Еҁu�G���M�y (17)�v���u�M�y�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/2202346
|
���W ������/p5
���̎�\�킽���̏E������ / �g��p�j/p12
�Ƃ킽�� / �g��p�j/p13
�����̌|�\���́\�t���ĂԌ|�\ / �O�����Y/p14
�ΒU���̂ɂ��� / �|�����h/p21
���������ƖM�y / �x�c�G/p28
���S���O���[�v���J�i�_������ / ��Q���S�N/p94
���m���y�̃A���g���疯�����y�� / ���c���q/p51
�{�铹�Y�L�O�ف\���݂̈Ӑ}�Ƃ��̓��e / �R������/p55
�����Ɍ��ꂽ�ڔ� / �������T/p125
���������|�\�ӏ܁\�V�������{�|�\�̊ӏ܌`�� / ���R�ω�/p135
�M�y�R���N�[��/p34
�V���R���N�[�� / ������Y/p34
�{���ⵋȃR���N�[�� / �c�ӏG�Y/p36
�S���ӊw����ӐN�M�y�R���N�[�� / �ЎR�F�O/p38
���i�y�R���N�[�� / ���c��t�F/p40
�k�C���S���O�ȃR���N�[�� / �g��p�j/p41
���������� ���Ȃ̃��[�c/p62
|
�O�������y�̢���������̣ / ���쌒��/p62
�������̋Y�� / �����ݗ��Y/p70
����S������Ƒ�a�|�\ / ���P�Y/p78
������q����������̗x�� / �˕����/p81
������q��Ƣ��������̔�r���� / ����/p85
NHK�̖M�y���� / ���q�v/p103
�e���r�̖M�y�ԑg/p33
�s���k��t�M�y�����̉ߋ�����ݥ����/p106
�E�q�_�ՓT�Ƌg�т̉�y
�@�@��(����17)�c�ӏ��Y�v���o�Ȃ� / �c�ӏ��Y/p46
(ⵋ�)�Đ앶�q�t(����)�m�Ï�߂��� / �ЎR�F�O/p142
�M�y�p�ꎫ�T ��ڥ�Ȏ��(6) / ��������/p162
���̑I�{�ƃ��R�[�h / ������Y/p152
���̑I�{�ƃ��R�[�h / ����/p154
���̑I�{�ƃ��R�[�h / �������q/p157
�ҏW���f����/p141
�����\���E�ҏW�G�L/p168
�E |
�P�Q���A�m���芰�����J�j�w��� �u���J�j�d = The journal of history of Ryukoku University (�ʍ� 76) p.p57�`76�v�Ɂu����ɂ����鉤���̏@���I���i�v�\����B
�P�Q���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.6�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@
�@�@�@54p �@�����F���ꌧ���}���فF1003063870
|
�����l�Êw�̎��ӉȊw(�p��)-��e- �F�� �p��Y
�F��p��Y�搶�̐����𓉂�
���ꏔ���ɂ�����V�Ί펞��̕ҔN(����) |
����l�Êw������\�v�| ���{ �A��
�����s����O����Տo�y�̎��쉺�w���y��ɂ��� �ݖ{ �`�F �R�c ��
�}���A�i������ՒT�K�L-�O�A���E�e�B�j�A���E�T�C�p��- ���� �k�~ |
�P�Q���A��X�`�����u�����w�������I�v (�ʍ� 3) p.165-206�@�����w�����w�������v�Ɂu��X����-1-����̏W�L�v�\����B
�P�Q���A�ɂЂȂߌ�����ҁu�V���̌��� 2 (��ƍՋV)�v���u�w���Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/12141715
|
�另�Ղɂ�������
�@�@�����戵���ɂ��� ��o���F��.
�֗]�̋{ �r�c��O�Y��.
�V��T���L�ƐV�� �֎���.
�ĂƐM�� ���r���V��. |
����̂܂� �{�c������.
�쓇�̋��H ���쐴�q��.
�u�������R���L�v�ɂ����ꂽ
�@�@���_�k�V��̏��� ���c�v�q��.
�_�_�`���̕��͂ƍ玮�̏� �O�Y�O�Y��. |
�^�C�̍���_�Ƃ��̋V�� �����P�Y��.
�^�C���̈��V�� ��c�c����.
�����_���̍����N���_�b �R�c������.
�Ă̓��l ���c���j��
�E |
���A���̔N�A�O�Ԏ�P�@���{�p�v���u���{����������n 12�v���u�u�k�Ёv���犧�s����B�@�@�@pid/12286064
|
�ɔg���Q : �����댤�� / �O�Ԏ�P
���c�ꋞ�� : ���[�J������ / ���{�p�v |
�ɔg���Q�N���E���c�ꋞ���N���E�Q�l�����ژ^: p461-491
�E |
|
| 1979 |
54 |
�E |
�P���A�����Ɩ����u���镗-���� : ���{�̔��v���u�W�p�Ёv���犧�s����B�@�@ (������{�ʐ^��S�W ; 8)�@ 133p
|
�J���[
1�@�v�ē��@�䉮��
2�@�n�Õ~���@���g�A
3�@�{���@�v��
4�@�{�Ó��@���Ǎ`
5�@���l���@��
6�@���\���@��
7�@����@��
8�@����@�ߔe
9�@���Ԗ����@����
10�@���Ԗ����@����
11�@���\���@����
12�@�v�ē��@����
13�@�ɗǕ����@���Ǖl
14�@�Ί_���@����
15�@�v�ē��@����
16�@�v�ē��@���n
17�@���l���@����
18�@���l���@����
19�@�v�����@�v��
20�@�v�����@�v�� |
21�@����@����
22�@����@���c
23�@�������@�l
24�@�{���@���K
25�@�{���@�O�l
26�@�n�Õ~���@���g�A
27�@����@�ߔe
28�@�{���@����
29�@�������@��
30�@�v�����@�v��
31�@���\���@�Y����x��
32�@���\���@�匴
33�@����@�m�O
34�@����@�Ӗ��n
35�@�{���@�v��
36�@���l���@����
37�@�{�Ó��@�떓
38�@�^�ߍ����@�c�[
39�@�{���@����
40�@���l���@��
41�@�������@�l |
42�@���NJԓ��@����
43�@���Ԗ����@���^
44�@�ɗǕ����@���Ǖl
45�@�Ί_���@�{��
46�@�Ί_���@�{��
47�@����@����
48�@����@��n
49�@����@���c
50�@����@���c
51�@�{���@��Y
52�@�{�Ó��@�쌴
53�@�Ί_���@����
54�@�Ί_���@����
55�@�{�铇�@�㌴
56�@�{���@����
57�@����@���c
58�@�Ί_���@�Ί_
59�@�r�ԓ��@�r��
60�@�{���@����
61�@�^�ߍ����@�v����
62�@���NJԓ��@���� |
63�@���l���@����
64�@���NJԓ��@�O��
65�@�{���@����������
66�@����@����
67�@�{���@����
68�@�v�ē��@��]�F
69�@����@�ӌ˖�
70�@�v�����@�O�l
�{��
�s�v�c�Ȗ��邳 ���� �Ɩ� 6
�����Ɩ��Ɖ���̌� �K�� �b�q�Y 82
�����ʂ̐��E�� �J�� ���� 92
����̑��� �����@��G 100
�ʐ^�̎v�z�ƌ| �x�� ���b�q 108
��i��� ���� �Ɩ� 112
����@�n�} 120
�����Ɩ��@�N�� 131
���{�ʐ^�j�Q���@���@
�@�@�������̍L���ʐ^�Ƃ��� �d�X �O�� 122
�E
�E |
�P���A���{�N�ٌ��v���ƕ��ҁu�����|�\ (59)�@�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4418391
|
��28��S�������|�\�����W��/p1�`8,10�`45,78�`80
���N�̖����|�\ / �{�c����/p10�`11
��28��S�������|�\���|�\���/p12�`25
����_�Ђ̐_���x / �����G�Y/p12�`17
���Ă̎����_ / ����h/p17~19
���ÉY�̑��ۗx / �����G�Y/p19�`19
�⋾�_�y / �|�{�R��Y/p19~24
������̎��q�x / ����h/p24�`25 |
�R���̐_���x / �q�c���M/p26~33
���Ă̎����_ / ���c�O�P/p34~37
�̕����̕��y�v�f--�⋾�_�y / �{�c����/p38�`41
���싽�̐����q�x / �X������/p42�`45
����̖K�L / �I�،b�q/p46~64
�u���b�N�ʖ����|�\�����L / ����h/p65�`72
��
�E |
�Q���A�r�{�������u�G���ǂ�߂� 20 p.10-21�@�����[�v�Ɂu����̗V�s�| �`�����_���[�ƃj���u�`���[�v�\����B�@�@
�Q���A���c�W�ҁu����n���̖��ԕ��| : ���������@1�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B�@�@pid/12502714�@
�@�@�@1598p�@�����F���ꌧ���}���فF1006930299
|
�� ���c �W
�̘b ���c �W
�`�� ���� ����
�̗w ��� ��
��-���d�R�n���̏ꍇ- �␣��
����̌䍖�Ɠ`�� �N�㌳�Y
�ɗǕ����䉮�䍖�N�����b�̖�� �R���ӈ�
�{�Âɂ����间�{���b�̈ʑ� �ێR ����
����n���ɂ�����S������b
�@�@��-�|�x���̓`���Ɖ�������`����- ���є��a
�u�M���ȁv�̈ꌹ��-�쓇�̃V�B�[�~�[�̘b�Ƃ��������-
�@�@�� ���Z���d��
����n���̏Θb-�{�Ó��𒆐S��- �c�����Y |
�u��̂Ȃ��e�v�� ���Q �v�q
�Ì����̏���-�u��[��s�߁v�l- �r�{����
���d�R�����̗̉w �떓 �b��
���̊o��-�����ߐ��̗w�j�̈�[�Ƃ���- �^�珹�O
�{�Î떓�̃j�[��-�܁Z�N�O�̃m�[�g- �r�{ ����
�{�ÁE��Ӓ�-���ꌧ�{�ÌS��Ӓ�- ���c�W�^�� ���n���K��
�{�ÁE��쑺-���ꌧ�{�ÌS��쑺- �␣���^�� ���n�R������
���d�R�E�|�x��-���ꌧ���d�R�S�|�x���|�x- ���c�W �떓�b���
���d�R�E���l��-���ꌧ���d�R�S�|�x�����l-
�@�@�����c�W�� �㐷���G�� ����������
���d�R�E����-���ꌧ���d�R�S�|�x������- ���������� �_�R�N����
�u���z�v�ɂ�����n�����b ���Ï���
���Ƃ���-�����̌o��- ���c�W |
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (5) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467948
|
�� / �O�Ԑ��K
�����ɎY����}���K���m�W���[���̉��w�g�� / �쌴���l ;����N/p1~16
�����G���i������ / �{���/p17�`38
�g�^�̌^�u������d�グ�܂Ł\�\��ԉh��m�[�g�����Ƃɂ���(����2) / �n���얾/p39�`52
�ɕ������̖K�L(����2) / ��]�F��/p53�`63
�����Љ� �w���������L�x���\�\�R���v�l�Y�������ʖ{ / ���Ð����Y/p1�`22 |
�R���A���ꌧ����ψ���ҁu���ꌧ�Ў��E��x�ђ����� 2�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@�@(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��18�W)�@�@210p �@�@�����F���ꌧ���}���فF1001567468
|
�{�����̌�菊�̐A�� �{��N��
�^�ߏ鑺�E���A���̌�菊�̐A�� �{��N��
�ΐ�s�̎�Ȍ�菊�̐A�� ���ܞD
�Î�[���̎�Ȍ�菊�̐A�� ���ܞD
�ǒJ���̎�Ȍ�菊�̐A�� ���ܞD
�k�J���E�X��p�s�̎Ў��E��菊�т̐A�� �V��a��
�k���鑺�̎�Ȕq���̐A�� �V�[�`�n |
���鑺�̎�Ȍ�菊�� �V�[�`�n
�������̎�Ȍ�菊�� �V�[�`�n
�L���鑺���̌�Ԃ̐A�� �{�钩��
�ߔe�s���̎�ȎЎ��E��Ԃ̐A�� �{�钩��
�앗�����̎�Ȍ�菊�̐A�� �V���`��
�����S�E���K�S����v��Ԃ̐A�������� �V��S�v
�E |
�S���A��������u���{�̗w���� 18(0) p.55-57�v�Ɂu�q���]�r���c���q���w�c�A�₵�����x:���̖������w�I�l�@�v���Љ��B�@�@�@�@�@J-STAGE
�S���A�{�闬�{��\�P�����������ҁu�������\�� �{��\�P�����������i�������q�j�v���u�{��\�P�����������v���犧�s�����B
�@�@�@���� 1979�N4��15��(��)�ߌ�2���E6���� �ꏊ �����V��z�[�� �@�@32p�@�@�����F��㊌����}���فF1004239693
�U���A������q,���X�����u�̈�w���� = Japan journal of physical education, health and sport sciences 24(1) p.p13�`24�@���{�̈�w��v�Ɂu���x�F�m�̈��q���͓I����-3-�����ɂ��āv�\����B�@�@
|
������q,���X�����u�̈�w���� 21(2)�`24(1)�v�ɔ��\�����u���x�F�m�̈��q���͓I�����i1�`
3�j���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
21(2) p.p77�`86 |
1976-06 |
���x�F�m�̈��q���͓I�����@�@ |
| 2 |
22(2) p.p101�`117 |
1977-07 |
���x�F�m�̈��q���͓I����-2-���x���ޘ_�̎��݁@ |
| 3 |
24(1) p.p13�`24 |
1979-06 |
���x�F�m�̈��q���͓I����-3-�����ɂ��ā@�@ |
|
�V���A��ÍN�Y,�J�쌒�ꂪ�u�_�X�̓� : ����v�����̂܂�v���u���}�Ёv���犧�s����B�@pid/12169617
�V���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 44(8)(569)�v���u ���傤�����v���犧�s�����B�@�@�@pid/6059686
|
�×w�̌n�� / p19�`44
�×w�̌n�� �_�̂Ə����� / ����d�N / p21�`28
�×w�̌n�� �R��̂̐��� / �r�{���� / p29�`36
�×w�̌n�� ���y����݂�����×w / ����] / p37�`44
�쐼�����̌É̗w<���W> / p6�`156,204�`208
�w�L�x�w�I�x�̗w�Ɓw������x�̗w �������`�� / �g�{���� / p6�`18
���X�̉� / p45�`124
���X�̉� ���� �T�J(�t)�̂Ƃ̏o� / ���R���G / p46�`52
���X�̉� ���� �Ǝ����������ƃi�K�� / �R���ӈ� / p53�`59
���X�̉� ���� ���́E�����x��̂ɂ����釀�̊|�������߂�����/����w�v/p60�`66
���X�̉� ���� �E���C�Ƃ��̎��� / �Î芡��ߎq / p67�`73
���X�̉� ���� ������Ɨ��� / �������X / p74�`79
���X�̉� ���� �C�U�C�z�[�̐_�� / �N�㌳�Y / p80�`85
���X�̉� �{�� �떓�̐_�̂ɂ��� / �֍����i / p86�`93
���X�̉� �{�� �Վ��̗w�^�[�r�̔w�i / �{�i�� / p94�`99
���X�̉� �{�� �N�C�`���[����g�[�K�j�w / �{�i��� / p100�`106
���X�̉� ���d�R �Վ��w�̍\�� / �Ί_���F / p107�`114
���X�̉� ���d�R ���d�R�̉r�u�����O�h�D�v�̍\��
�@�@�������^�����O�h�D�̍\��/�{�����F/p115�`118
���X�̉� ���d�R �����^�|�������� / �茴�P�V / p119�`124
�g�{�����̌���<���W> / p157�`202
�����W �g�{�����̌��� ���ڐ�����S�̐���
�@�@�� �w�]�ʂ̂��߂̏\�сx�Ȍ�/�����a�q/p158�`166
|
�����W �g�{�����̌��� ��N�̂䂭�� �g�{�����w��㎍�j�_�x �q������/p167�`176
�����W �g�{�����̌��� �\���j�_�Ƃ��Ắw�����̗w�_�x/��ؓ��o�j/p177�`184
�����W �g�{�����̌��� �쓇�_�̈ӑz / ���� / p185�`193
�����W �g�{�����̌��� �\�����߂���A�\���̂ނ�����/���R�h��/p194�`202
�ǎ҂̃y�[�W / �勴��v ; ���Lj� ; ����됟 ; �a�c�M�q / p204�`208
�w�E���] ���{���w�̘A���� / �����i / p210�`211
���̑��Ƙ_���w��������_�x / ���v / p212�`213
���] ��i�_�E��Ƙ_�E���w�j�_���O�c�����w�����t�̐��E�x��/�R�c�L��/p214�`215
�ǎ҂̃y�[�W���e��W�ɂ��� / p202�`202
�쐼�����̌×w�ē� ���w�ƕ��y �������������ꁄ���{�Á������d�R�� /
�@�@�@������w�v ; ����߈� ; �Î芡��ߎq ; ���ꂢ�E������ ; �{�i�� ;
�@�@�@���ɗǔg���j ; �{�Lj��F ; ����N�Y / p126�`141
<����>�×w�ē� / ����w�v / p126�`127
<����>���w�ƕ��y / ����߈� / p128�`129
<����>�×w�ē� / �Î芡��ߎq / p130�`131
<����>���w�ƕ��y / ���ꂢ������ / p132�`133
<�{��>�×w�ē� / �{�i�� / p134�`135
<�{��>���w�ƕ��y / �ɗǔg���j / p136�`137
<���d�R>�×w�ē� / �{�Lj��F / p138�`139
<���d�R>���w�ƕ��y / ����N�Y / p140�`141
�쐼�����̌×w����݂��Ñ�̗w / p143�`156
�쐼�����̌×w����݂��Ñ�̗w �A���� �����ȑO/�Ë��M�F/p144�`150
�쐼�����̌×w����݂��Ñ�̗w �Ñ�̗w�̏I�n/�����a / p151�`156 |
�V���A���䖞�ҁu�_�̓��̍Ղ�C�U�C�z�[�i����v�����j�v���u�Y�R�t�o�Łv���犧�s�����B
�@�@ (���{�̖����w�V���[�Y ; 4)�@pid/12286057
�V���A���a�c�^�~���u�A���n���E���ތ���(�k���̐A��) en : The journal of phytogeography and taxonomy (The Journal of Geobotany) 27(1) p. 36�`37�v�Ɂu�Ί_���Y�i�X���̈�V��v�\����B
�X���A�ÓT�Ɩ����w�̉�ҏW�u���ꌧ�v���������v���u�ÓT�Ɩ����w�̉�v���犧�s�����B�@
(�ÓT�Ɩ����w�p�� ; 3)
�X���A����т��`���Z�p�ۑ���ҁu�g�^ : �`���Z�p�ۑ����i�W�v���u���D�Ɛ����Ёv���犧�s�����B�@
�P�O���A���j��,������q���u���{�̈�w��� (30) p.199�v�Ɂu���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��(5) : �ӏ܍\���̔��B���v�\����B�@�܂��A������q���u�����@p.175�v�Ɂu�������x�̗v�f�]��ɂ��F�m�̌n�v�\����B�@J-STAGE
|
���j��,������q���u���{�̈�w���(24�`30)�v�ɔ��\�����u���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��(1�`5)�v�ɂ��Ă̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_�����^���� |
| 1 |
(24) p.282 |
1973-09 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤�� : �Ӗ������@�ɂ�� : 9. ����E�]���Ɋւ��錤���^����
���q�@�@ |
| 2 |
(25) p.257 |
1974-09 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤�� : �������x�̔F�m�\�� : 6. �̈�S���w�Ɋւ��錤���^����
���q�@ |
| 3 |
(27) p161 |
1976-08 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��(3) : ���x��i�̗ތ^���^���� ���q,��� �X���@
|
| 4 |
(28) p.180 |
1977-10 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��(4) : �ӏ܍\���̒j����r�^��� �X��,���� ���q�@�@ |
| 5 |
(30) p.199 |
1979-10 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��(5) : �ӏ܍\���̔��B���^��� �j��,���� ���q�@�@ |
|
�P�O���A�u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 8(1)�v���u���ꍑ�ۑ�w���w���v���犧�s�����B�@
|
���������Ƌ�B�������Ƃ̔�r(I)�@�@�쌴�O�` p.��1-16
�}�g�ⓚ�̍l:�Ӌ`�Ɣw�i�@�@���R�� p.1-18
���������߂���ԕP�B�̑����ƛސ��@�@�O�ύ_�� p.19-28 |
��������̓���(1)�t���t�E�Í��E�ɐ��E�F�Õہ@
�@�@���_�Ԃ�ݎq,���@���F�q,���c������,�O�ύ_�� �@p29-66
�L�N�Ղƌ×w�@�@�ʉh���� p.67-86 |
�P�O���A�|�\�w��ҁu�|�\ 21(10)(248)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276443
|
������ �V�h���̎��ƐV / �������H/p7�`7
���l�ו��̌|�\� / �H�둾�Y/p9�`13
�������������̕�(�����܂�)����ϒ����� / �u�c���`/p14�`15
�|�\�j�����m-�g-3-�c�y�Ɋւ����,�O�̖�� / �㓡�i/p16�`24
����������R�ƒ����̣-52- / �O�����Y/p25�`36
�܌��M�v�̐��E(34) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41
���̕��ꉹ�y�W��--�����-57- / �n���h���q��/p33�`36
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-205- / ���������Y/p37�`39
�r�c��O�Y����W(�S�\��) / �������H/p42�`45
���{�����j�w��Ң���{�����j���T� / ���J��/p46�`46
�S�i�����ďC��щËg���ʐ^��O��̕��� / �{�c����/p47�`47
��������ꎑ���W������ژ^(��)/p68�`69 |
�����N�\( 9��1���`9��30��) / ���c�m/p55�`63
���x�N�\(���a54�N������) / �@���q/p64�`67
��������ꏗ�D�ЂƂ�ŋ�� / ��،�/p49�`49
���x��V���o�[��p���[� / �m�����Õv/p50�`50
�f�梓��{�f��E�V��������!� / ���Njv�l�Y/p52�`52
�m���uM�E�A�����ƃW�W�E�J�V�����A�j���v / �����/p51~51
�\�������铢�]�����������/p53�`53
�\�̗\�]���������̍���ң/p54�`54
���a�\�l�N�x�|�p�ՎQ���\�������ꗗ/p70�`74
������(II.�EIII.)/p75~80
�V���Љ�/p48~48
�V���ē�/p81~81 |
�P�P���A�X�ۉh���Y���u�������x���� : �x��̌��ǂ���E�����ǂ���v���u�앗�����i���ꌧ�j�F�ߔe�o�ŎЁv���犧�s����B
�P�Q���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (12)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����B�@�@
pid/7931792
|
���a53�N�x�̌������̊���/p1�`20
�Ί_���̃p�C���A�b�v���Y�� / ��،�/p21�`31
�Ί_�����ۂ̈��̉��y--�c����̂ɑ���l�@�𒆐S�� / ���c���q/p33�`49
��F���l���ς������̐l���V�� / ���c���@/p51�`64
���ꌧ�Ί_�s�ɂ�����c���́u��{�I�K���̎����W���N��v�ɂ��Ă̒������� / ���q��O�s ;�����p��/p65~85
���\���̐A���T�� / ���ƍD/p87�`104
�o���S��c���́u�_�Ƃ̈ӎ������v�ɂ��� / �R�c���k/p105�`113
��c���_�Ƃ̌���ƌ��ʂ��Ɋւ���_���ӎ� / �R�c�W/p115�`135
��c���ɂ����錒�N�E�X�|�[�c�ςɂ��Ă̒��� / �R���F��/p137�`148
��c���ɂ����镶�����ւ̊S�Ɋւ��钲���� / �O�ؖ�/p149�`159
�����ɂ����閯�ԃe���r�̕��f�J�n�̉e���ɂ���--���㒲�����v�����W / �Ð�`�a/p161�`182
�|�x���̇��×w���A���[�C�����^�C�W���o--�u�Ί_�|�x�����^�A��̉�v�̊��������𒆐S��
/ ���{�M�v/p1�`40 |
�P�Q���A������q,�ԏ�m�q��������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��� (�ʍ� 23) p.p61�`86�@������w����w���v�Ɂu���x����̕\�����Y���Ɋւ��錤��--�������x�ƃC���h���x��EMG�p�^�[���ɂ����v�\����B�@�@
���A���̔N�A�쓇�j�w��ҁu�쓇 : ���̗��j�ƕ��� 2 �v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@pid/9773232
|
���������Ɖ��� �E����/1
��l���̃v�[���B�i�L�N�Ձj �Ί_���F/39
��A�͂��߂�/39
��A��ԁkon�l/41
�O�A�N���s��/48
�l�A�I���v�[���B/52
�܁A�����v�[���B/56
�Z�A������/69
�����ÓT���x�E�őg�x�u������v�ɂ��� �Ɖ����P/77
�r�f�B���Ɩ��ԐM�� �ې參��/99
��A�_�k�V��ƃr�f�B��/100
��A�w�C�쏬�L�x�́u�͂���v/104
�O�A���~�_�ƃr�f�B��/109
�l�A�r�f�B���̈Ӗ�/111
����ƝU�� �R�{�B�Y/113
�s��t�Ɓs����t�\�^�_���̐_�q�݁\ �������t/133
��A��/133
��A�T��/134
�O�A��/135
�i��j������/135
�i��j������/138
�i�O�j��̃����o�[�V�b�v/139
�l�A����/147 |
�܁A����/151
����̐e���ςɂ�����u���v�̊T�O �c���^���q/159
�퐶����̓쓇�Ƌ�B�\�L���i�Ƒ������߂��鏔���\ �O���i/171
��W�w����āx�ɂ��� �{�c�r�F/185
��A��W�w����āx/185
�i��j�w����āx�Ƃ̏o�/185
�i��j�����̓��e�Ƃ��̐���/189
��A���b�u�������@�ɂ���/192
�i��j����/193
�i��j���R���̎R�쉤�ɑ���D��/194
�i�O�j�O�R�̓���/197
���g�̖��É��ʍs�Ƒݖ{���u��y�v ���R�w/199
��A�͂��߂�/199
��A�ݖ{���u��y�v�Ɨ�����/202
�i��j��y�E���ˈ��E�̌���/202
�i��j��y�̗��������{/205
�i�O�j�����掏/209
�i�l�j���̑��̍e�{�i���z�����}��j/213
�O�A��蕶�ɂ́u��y�v�{�ɂ���/214
�l�A�u�����掏�v���̑��Ɍ���V�ێO�N�̗��g����/216
�܁A������/226
�t�^ �|���j��/233
�t�^ �}�Ŏj��/251 |
���A���̔N�A�Έ䗲�r���u�吳��w��y�w��������w�@�����I�v 5 p.47-49�v�Ɂu�ܒ���l�̐��������v�\����B |
| 1980 |
55 |
�E |
�P���A�ËH�L�O���a�c�^�~�I�W���s��ҁu���a�c�^�~�I�W : �ËH�L�O �l�ÁE�����E���j�E�H�|�сv���u�ËH�L�O���a�c�^�~�I�W���s��v���犧�s�����B�@�@367p �@�����F��㊌����}���فF1002063137�@�@�@�@�@�S�O�O�O�~
|
�}��(�ё�)
���� ���{ �A��
�l�Õ�[�����̋N��
����̐�j����
�����̊L�˕��z�ƕҔN�̊T�O
�����̊L�˕��z�ƕҔN�̊T�O���(1�`2)
�J���ʕ�ɂ���
��̌��A�ƎJ�s
�@�@�� �����ɉ������Ղ̓y��
�{�b��E����E���̎���敪
��������̕��ފw�I�l�@
�����Ñ�̓S�̗A��(����1?2)
����̐�j���j����̎�H�ޗ��ɂ���
�间���ɂ���
����l�Êw�E�̏����
�l�Êw�̎���
�l�Â̗� �L�ːl�̈��]
������[�×����̍Ջ� |
�͂Ԃ��̐A���w
����̈��V��
�t�B���v���E�C�V�K���g�[�E
�@�@���V�[�T�[ �T���j���K�[�T
����̕�]
���j�E�����
[�Ós�ƌÐ}
���R�̕�ɐ�t����
�����̕��p
�K�[�i�[�X�ƃi�n�L�n�M
�����̌ꌴ�l]
�H�|��
[����̎���f�ނƎ����̖��
����̎����A���Ƒ@�ېA��
�˔�(�g�E�r����)�Ƃ͉���
��ɏꕶ�ɂ́u�ي����ᒠ�v]
���M���̑�
[�l�Êw�Ǝ� |
��Ք��@�ɜ߂����
�w���ւ̓��@
�镜���Ɏv��
�E�U�l�L�˂ƕӌ�
�u�Ί펞��̉���v��ǂ�
����̕������ی�s��
�����[�搶�̎v���o
��ɏꂳ��Ǝ�
��[�V�����┪�d�R���j�v
���� ���̌����v����
�A�����Ԋw�҂̌���
�@�@���u���{�̂ӂ邳��-�����v]
���a�c�^�~�搶���N��
���a�c�^�~�搶����ژ^
���a�c�^�~�搶����� �@���{ �A��
�ҏW���Ƃ���
�^�����E���N�l�E�ҏW�l�����ꗗ
�E |
�P���A�u�|�p�V�� 31(1)[(361)�v���u�V���Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6048612
|
�A�[�g�E�j���[�Y �I�[�N�V���� �p���Ŕ���ɏo���ꂽ�����G //p78�`79
���M ���̍Ύ��L���V�A�ځ� �ꌎ�E�� / �r�g�����Y/p88�`89
���M ���͑��z�H �\�j�A�ƃ��x�[�� / �c����/p90�`91
���M �������z�ɐ��_�{ / �X�e�B�[���E���A/p91�`92
���M ��������O�c���� / �{�c����/p92�`92,97�`98
���M �̂̂Ȃ��̕��i / �\���K��/p98�`99
���[�J���E�K�C�h(25)���� ���I�t�Z�b�g�� �|�x����q��� �m�ԕz
�@�@���g�^ �֏��Ԃɂ� �|�x���̖��� �c�ɐ������� //p166�`180
�A�[�g�E�j���[�Y �����W�� �V���E���{���p�j / �g����i/p5�`38
�A�[�g�E�j���[�Y ���́@��M�ƏC�w�@--
�@�@���V�n�n���̎������Ă���/��ؑ��/p6�`8
�A�[�g�E�j���[�Y ���́@�P�����̒��̋�--���{�̋�̐�ΐ�//p9�`11
�A�[�g�E�j���[�Y ��O�́@�_�̂����--���E�B��̐��_�\��//p12�`13
�A�[�g�E�j���[�Y ��l�́@���Ɩ�--�����Ƃ��Ă̓V�E�ƒn��//p14�`16
�A�[�g�E�j���[�Y ��́@�\���--���_�̐[���Ƃ͉��� //p17�`19
�A�[�g�E�j���[�Y ��Z�́@
�@�@���ߒq��}�͂ǂ����猩����--���_�̎��R�ƍč\�� //p20�`21 |
�A�[�g�E�j���[�Y �掵�́@���b���ƛ����G--�s���ʼn����ȉ��ߖ@//p22�`23
�A�[�g�E�j���[�Y �攪�� �����ɂ�����t����
�@�@��--I ��Ԃ��t���������� II ��Ԃ̊J���� //p24~27
�A�[�g�E�j���[�Y ���́@�L�d��������--���s�̕\���͎ΐ��ʼn\��//p28�`29
�A�[�g�E�j���[�Y ��\�́@�u�ԂɎ��Ԃ�������
�@�@��--�G��͎��Ԍ|�p�ł��� //p30�`31
�A�[�g�E�j���[�Y ��\��́@�F���������F--�F�ɑ���₢����//p32�`33
�A�[�g�E�j���[�Y ��\��́@�]���̔� //p34�`35
�A�[�g�E�j���[�Y ��\�O�́@�A�e�@�͊G����������
�@�@��--�����G����̑����Z //p36�`38
�A�[�g�E�j���[�Y �b�� �s�J�\�ő�̃R���N�^�[
�@�@���s�J�\--�t�����X�Ɉ②���ꂽ�����\��i / �c������/p39�`42
�A�[�g�E�j���[�Y �b�� �����G���������
�@�@��--���߂Ắu��������W�v���@�� / ���Z��/p43�`53
�A�[�g�E�j���[�Y �f�U�C�� �J�����_�[��I�� / ���V ;�����ɓs�q
�@�@��;���Ԋ� ;���c�ɗY ;�a�c�� ;�r�c�����v ;�����r�q/P62~63
�A�� ���{�̂�����(13)��` / ���F���q/p112�`115
�q�����r |
�Q���A�|�\�w��ҁu�|�\ 22(2)(252)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@��id/2276447
|
������������ƃL���O�R���O� / ��ѐ��Y/p7�`7
��]�䕨��̌���-2��-�K�ᕑ�ȂƗw�� / �ˍ�i/p8�`17
�|�\�j�����m-�g-6-���h�_�y�l��-��- / �㓡�i/p18�`22
����������R�ƒ����̣-55- / �O�����Y/p23�`30
�N�ƕ��� / �܌��M�v/p44~49
�܌��M�v�̐��E(38) / ��X�`�� ;�F����o�j/p42~43
���̕��ꉹ�y�W��--�����-61- / �n���h���q��/p31�`37
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-208- / ���������Y/p38�`41
���c�W�Ң����n���̖��ԕ��Y� / �哇���F/p51�`52
�������\�������Ԃ܂磂Ƃ��̕ʍ� / ��ѐ��Y/p52�`53 |
�r�c�\�O�Y����O�c�炿� / ����p��/p53�`54
�����N�\(1��1���`1��31��) / ���c�m/p62�`72
���x�N�\(���a54�N������) / �@���q/p73�`77
�����u�ĉ��̍D�@�v / ��،�/p55~55
���x������̂Ɨx�� / �m�����Õv/p56�`56
�f�梖��͂�����{�f���!� / ���Njv�l�Y/p58�`59
�m�����11�x��]�Ƌ���ܣ / �����/p57�`57
�\�������s���\�ƉH�߃o���V�L�/p60�`60
�\�̗\�]��Z�Y���Y�֎������/p61�`61
������(I.�EII.)/p78~80 |
�Q���A�Y�R����,���R�f��,��Ó��P ���u���{���z�w�����. ��B�x��. 2, �v��n (25) p.277-280�v�Ɂu���J�Ɖ��ɂ��Ă̎��_ : �_�A�V�A�Q�̏ꍇ(���z�j�E���z�ӏ�) �v�\����B
�Q���A���v���G�~�y���u�{�ǒ����ȏW�v���u�v���W�F�N�g�E�I�[�K���o�ŋǁv���犧�s�����B
|
���Ԑ� / �{�ǒ���쎌
�Q���̊C / ��l�M���쎌
�Ԃ��̉� / ��l�M���쎌
�썑�̉� / �k���d�h�쎌
�[�₯ / ��l�M���쎌
����M / ��l�M���쎌
����ǂ��̉� / ����h���쎌
�S���ǑP�� / �k���d�h�쎌
�ӂ闢 / ����h���쎌
����� / �F�v�{�����쎌
������(�����݂��Ԃ�) / ���{���쎌
���_ / �{�Ǔ��s�쎌
�h�̒� / �[�ƍ쎌
�I�����_���~ / ���R�����쎌
|
�w�H(���܂₶) / �[�ƍ쎌
����� / �{�Ǎ��v�쎌
�t���J / �[�ƍ쎌
�Ï� / �ɔg��N�쎌
�[�� / �V���~�K�ɍ쎌
�D�H / �{���Ì쎌
�A��M / �{�Ǎ��v�쎌
�R�C�i�E�����^ / �[�ƍ쎌
�L�����^ : �����O������ /
�@�@�� �{�ǒ���쎌�E�ҋ�
�L�����^ : �����l������ /
�@�@���{�ǒ���쎌�E�ҋ� ; ���F���Ǖҋ�
�Ȃl / �{�Ǎ��v�쎌 ; �{�ǒ���ҋ�
��� / �[�ƍ쎌 ; �{�ǒ���ҋ�
|
����×��g / �������w ; �{�ǒ���ҋ�
�����،��� / �V���~�K�ɍ쎌 ; �{�ǒ���ҋ�
��J / ��l���C�쎌
��̐� / �{�ǒ���쎌
�R�̎q��� / �{�Ǎ��i�쎌
���D(�Ƃ�����) / �[�ƍ쎌 ; �{�ǒ���ҋ�
������ / �{�Ǎ��v�쎌
���̏o�� / �{�Ǎ��v�쎌
�K�̎� / �{���Ì쎌
�r��̉� [: �v�ē����w�u���Â�颐��v���] /
�@�@�� �{���Ì쎌 ; �{�ǒ���ҋ�
���d�R���� / ���Òn�p���쎌
�E
�E |
�Q���A�{���v���u����E�킪�S�̂����� : �{�ǒ���̐��E�Ƃ��̔w�i �i�ʍ��j�v���u�v���W�F�N�g�E�I�[�K���o�ŋǁv���犧�s�����B�@�@ 380p �@�@�����F��㊌����}���فF1002078945
|
�}��(14��)
�܂�����
���U�Ƃ��̎��� |
�{�lj��y�ƎЉ�I�w�i
���ɂ�����u�{�ǒ���̐��E�v
�{�lj��y ���̎v���o |
���Ƃ���
�{�ǒ���N��
�����|�\���y���N�\ |
�Q�l�����Ǝ���
�E
�E |
�R���A���K�����Y���u�w�����w�I�v��1���@�����w�n��20���N�L�O���x�@��1�`15�@�����w���{���v�Ɂu�썑���̑n���Ɠ��G��l�v�\����B
�R���A�������Z����w�}���ψ���ҁu�������Z����w�����I�v (25)�v���u�������Z����w�v���犧�s�����B�@pid/1769714
|
���w�ɂ����Ă̔����̎v�z�Ƃ��̎��Ӂ\�\�w�k�R���x�ɂ����� / ����q�v/1
�����L���[���̖��ɂ��� / ��X�k�`/15
��ꎟ���E���ƃh�C�c�m���l�Q��(�O) / ���g�F�B/29
�|�� �}�[�N��|�X�^�[;��}���N�X�Ĕ����Ƒa�O�T�O� / �i�䖱/41
D.H.�������X�̒Z�ҏ���(1) / �ɓ����i/7
�z���[�X��}���̋����v�z�ɂ��ā\�\�ߑ�����琬�����ɂ�����x�z�I�������F��(����1) / ��V�G��/21
�����m�[�g ���ʃ[�����_�ł�CP�̔j�� / �e�쏇�q/33
������ ����{���k���̎������\�\��X���� �`�g�Â̎����C�F���T�[(1) / ���эK�j/41
�������w�̎��ɂ��ϑt�� / �����Y���Y/77
����̎q���̂������u�s�A�m���ȏWVI.�v / ���{�M�v/99
�S�R�nj��搶�𓉂ށ\�\�Ɛіژ^��N�� / �|�V������/1 |
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���������ّ��������� 1 (������(�����ɂ���))�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����Bpid/9773363
|
�������� �O�Ԑ��K
���������j �������Y/1
�������̍l�Êw���� �m�O�E/9 |
�������̃g�D�[�W ��]�F��/21
�������̓����� �{��Đ�/29
�������̒n�`�ƒn�� ����N/39 |
���ʊ�e
�������̗���Ғœ��� ���R����/51
�E |
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (6)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467949
|
�� / �O�Ԑ��K
�����ΊD�₩�甭�����ꂽ�A�T�q�K�j���ɂ��� / ����N ;����c�Ώ[/p1~8
�v�ē����n�������W�̌L��ɂ��� / ��]�F��/p9�`14
���A��o�y�̌����t�Ђɂ���(�����Љ�) / �m�O�E/p15�`19
���Ē������� / �{��Đ�/p21�`31
�v�ē���v���Ə����̍g�^���ɂ��� / �n���얾/p1�`11 |
�R���A���ꌧ����ψ���ҁu���ꌧ�Ў��E��ԗђ�����3�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@
�@�@�@����{�����암�y�ю��ӗ����̒����B432���@(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y20)
�R���A�����w�������I�v (�ʍ� 4) �v���u�����w�����w�������v���犧�s�����B
|
�I�i���_�������߂����ڂƓW�] �n������@ p.p1�`98
�}���W�����̏}�� �c������ p.p99�`114
�V�@���^���̗ݐѓI���B�ߒ�--
�@�@�����a��\�N��̗�����-1- �X������ p.p115�`154 |
�C��Y�������̍��ʂ̍\��-1- ������� p.p155�`183
�������L���o���k�V�ۏ\��N ����-�]�ˊԁl ���R�q���Y �|�� p.p185�`238
��X����-2-����j���̏W ��X�`�� p.p239�`286
�E |
�R���A��w��A�����������ψ���ҁu�����ɂ����鎩�R�E�Љ�E�����Ɋւ��鑍�������v���u��w��A�����������ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/9773914
|
��1�� ���R���Ɛl��
��1�� �n���I����
�� �g�J������щ��������̒n���w�I���� �֓��B/2
1.���������ɂ����錻���T���S�ʂ̔��n�`�\���Ɩ������� �x�M�s/3
2.���������̐��ɂ��� �V�䐳/5
��2�� �g�̓I����
�� �l�ފw�I�ɂ݂������Z�� �����u��/7
1.�����哇�Z������� ����V���E���c���j�E����J���E�����݂��q/7
2.��`�I���^�`�����݂������哇�Z���̈ʒu�Â� ���{�b�s/8
3.�����ɂ�������N�̑̑g�D�ƍ�Ɨe�ʂ̊֘A �������F/9
��2�� ���������̒n�搫
��1�� ���������ɂ�����n�搫
1.���������̊C�Ɛl�� �k���r�v/12
2.���������̔_�k�Z�p�`�� �a�c���F/13
3.�u�����x��v�̒n�搫 ���c���q/14
4.�����E�O�����S�̐����`�� ��������/15
5.�����哇�̃V�}�E�^�ɂ�����n��l���ƌl�l�� �R���C/16
6.���̓R�V���E�V�����\��b�̌n�̓����\ ���������v/17
7.�����哇�̓�k�Η��\������̑��\ �ēc��/18
8.�u�����v�͂ǂ���\�\�哇�̗����Ƃ��܈��\�\ �^�c�M��/20
9.�u���v�Ɓu�j�v�\�\�哇�̃A�N�Z���g���z�\�\ ��؊��h/22
10.�����ɂ����镧���̎�e�`�� ���䐳�Y/24
11.�c����J�ƌn���� �{������/25
12.�g�J�������ɂ����鋙�����ƐH���� ��˖����Y�E�����K�Y/26
��2�� �����Ɖ���
1.�����̓y�n���x �^�ߍ���/29
2.���������̓��y���� �|�c�U/31
3.���������̔N���s�� ��]�F��/33
4.���������̜߈ˌ��� ���c�v�q/34
5.�����哇�E���˓����̃��^�ɂ��� ���X�؍G��/35
6.�����̃��^�ɂ��Ă̒����E���� �R���ӈ�/37
7.�����n���̒����I�M�ƏK�� �E����/37
8.���ʂ̌ď� ���{���q/39
9.�����̈ꎚ�� ��錒/40
|
10.��E���̓������p�\�咩�˕����ɂ��ā\ ���{��/40
11.���˓��̉��C�\���Ì������ɂ��ā\ �^�V����/41
12.���V�������̓����\�����E�`�e�����p�ɂ��ā\ ���Ԓ��m/42
��3�� �����Ɩ{�y
1.���{�̉��y�������ɂ����鉂�����y�̈ʒu �������q/44
2.�����|�\�̌n�� �ݕӐ��Y/45
3.���������̉��ʍs�� ���R����/46
4.�_�Ў��ɂ݂鉂���̒n�搫 ���c��/48
5.������������уg�J���ɂ�����`���I�����`�� �֓��B/49
6.��Ԃɂ݂鉂���哇�̒n�搫 �����p��/50
7.�u�S�z�E���v�L�̐����m�F�Ɛ��� �i�䏹��/52
8.�����s�ɂ�����c������̎��� �˓c��/52
9.���N�̉��l�ӎ� �g�쌦�q�E���c��j/55
10.���Z���̓s�s������ �l�����r/56
11.������uU�^�[�����ہv�̕��� �l�����r�E�ɑ��i/56
��3�� �����Љ�̕ϓ�
��1�� �n��Љ�
1.�����Q���̐U���J�� ���F��/60
2.�����_���̍\���ƕϓ� �������Y�E�˒J�C�E�@�����F�E�L���Ɗ�/61
3.���������̎Љ�I�E�ے��I�����̍č\���\�\���ƕω��\ ��������/64
4.�g�J���̑����Љ�̕ω� �����E���zᩔV/64
5.��E�����20�N�̎Љ�ω� �������j�E���a�j/69
6.�哇�ې��Y�̕ϓ��Ɩ��_ �k�엲�g�E�ēc���V�E������/72
��2�� �����ƐM��
1.��E�����`�ɂ�����H�����̕ω��ƌl�� ��˖����Y�E����_/74
2.�����̎����E���k�̔얞���X�� ���g�q�v�E��˖����Y�E�����F�K/75
3.�玙�����E�玙�ԓx��20�N�̐��� �ɑ��i�E����C�v/76
4.�����e���r�̉e�� �����`��/77
5.���v�C�����������ɂ����鐶���ƐM�� ���L/78
6.�����哇�̓V���� ���q�O��/79
7.�����ɂ�����V�@�� ��㏇�F/80
���������o�ߊT�v/84
�������\�̋L�^/91
�E |
�S���A�u�G�������w 4(2)(12)�@�v���u���������w������ �痢�������c�v���犧�s�����B�@pid/7953644�@
|
�\�� �W���X�~����E�ޏ��� / ������/p2�`2
�l�Ԃ̐��E �C�^���A�����ƃT�T�j�V�L / �Ґ×Y/p3�`5
�V�q���̂Ƃ��鑺 / �㓡�W/p6�`19
�p���O�A�C�̃��[�X�҂� �O�A���j�[���̃j�����h�D�e�B / ����C��/p20�`25
�Y�C���o�W���E / ��c�C/p26~37
���{�̂��܂��E�k��10����1 ���������w�����ق̖��Ɩ͌^/ ��Y�o/p38�`51
���b�Z�� �����b�R�E�R�n�Ǝs�̍ՓT / �Ԓn�o�v/p52�`61
���L�V�R�암 �C���f�B�I�̎��ËV�� / �g�c����/p62�`71 |
���w�ł͂��� ���{�̂͂����� / ���c�S�Y/p72�`77
�J���o�̃N������c / ��c��/p78�`91
�J�������̉��y / ���c���q/p92�`97
�n���̌��n���C���n�ږ��̗��j / ���q�O��/p98�`105
�|�[���E�A�q�̐��E / �]����v ;�F����I/p106~111
�_��E�M�B�E�l��̗�
�@�@�������̏��������������˂� /�����F�Y/p112�`122
�E |
�S���A����x�����u���{�̗w�����i19�j p.48-59�@���{�̗w�w��v���u�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@:�i1�j�v�\����B�@J-STAGE
|
����x�����u���{�̗w�����i19�`21�j�ɔ��\�����u�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@:�i1�`3�j�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�@�_�����@�@���x�R�n���𒆐S�Ƃ����u�~�x��S�v�̌��� |
| 1 |
(�ʍ�19) p.48�`59�@ |
1980-04 |
�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@-1- |
| 2 |
(�ʍ� 20) .p44�`54 |
1981-05 |
�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@-2- |
| 3 |
(�ʍ� 21) .p35�`51 |
1982-05 |
�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@-3- |
|
�T���A�V���Ҏ[�ψ���ҁu�l�Ԃƕ��� : ���{�u���W 8�v���u�O����v���犧�s�����B�@(�O���V��)
|
�L�ւƖ퐶�l �i�䏹���q
�n�k�ƌ��z ���x����q |
�̂Ɩ��� ���c���q�q
�Ñ㒩�N��Ɠ��{�� ���v�Y�q |
�Ζ��헪�ƃG�l���M�[�̖��� �����c�O�q
�E |
�T���A�{�Ǔ��s�� ; ���Ԉ�Y�ҁ^�������w�����сu����̐l�`�ŋ��E�|�\�E���w�_�l�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@ (�{�Ǔ��s�S�W ; �P�Q)�@ pid/12502725
�U���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 7 �v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B
�@�@(�@����w���ꕶ���������I�v ; 7)�@�@�@pid/9773378
|
�쓇�́u�����v�s�� ������G/1
�M��Ȃ����̂̓쓇�I�`�ہ\��`���ɂ݂�쓇�̎v�z�\ ��Î�/28
�w�����S�T�x�Ɖ����̌��s�̗w ����w�v/54
�{�Ó��̐_�̂Ƃ��̗�����߂����� �������q/91
�떓�̐_�X�\�_�[�r�E�s���[�V�����ƂɁ\ �V���K��/113 |
�����L�^�E���w���_�\�����敪�ɂ��ā\ ��������/140
�����ɂ�����l�g�����E�����`�F�̌��� ��R�ٌܘY/159
�w��a���ړ��L��O��x�ɂ��� ���n�B��/179
�������� ���z������/198
�E |
�U���A�M�y�Еҁu�G���M�y (23)�v���u�M�y�Ёv���犧�s�����B�@pid/2202352
|
���炵 //p5
�؍����y���C���s //p8
����������̣�̉𖾂Ɗӏ܂̗[�� //p12
ⵋȂ̓`��������̊��ƌ����ɂ��� / �|�{�R��Y/p13
ⵋȂւ̏�M�ƈ���Ɏx����ꂽ�� / ���P�Y/p15
�؍��Ɏ̉�y��--
�@�@���؍����y���C���s�c�ɂ���/�c�ӏG�Y/p18
�؍��E�q�_��y�ƍ��y���� / �^�D��/p20
�؍��̕��_��y�ɐڂ��� / ���q���O�Y/p26
�؍��̏� / �R�{�G�q/p26~27
���ʂƊ� / �����/p27
��̎O���R���L����� / ���芲�j/p29
�ߔN���@���ꂽ�퐶������̊y�� / ���O�C/p37
�l��|�{�Ñ�v�|�b-1-���J�c�R�L��O�̐إ
�@�@���w��-1- / �v�ۓc�q�q ;�i�R���� ;�|�{�Ñ�v/p45
���M���j���� �g��p�j�搶�̎v���o�b���� / ��Q���S�N/p57
�ܒ|���̒|���u�̒�������Ă܂��E��(�|�ǖⓚ) / �R�쒼�t/p67
"�l��(������)(�Ӑl�̒�����)"�ɂ��� / �n�Ӎ_��/p71
�~�x��~�S--���̗��j�Ɠ��� / �R�H����/p74
���炵(���Ȃ̃��[�c�[7-)<���W>/p78�`99
����Ȃ̢���炵� / ���b�q/p78 |
ⵋȥ�n�̢̂���炵� / ���쌒��/p81
���S�Ə�֒Â̢���炵� / ��v�Ԋ��Y/p86
����炵��̉̕��ꕑ�x / �˕����/p89
���̢���炵��Ɖ̕���̍r�� / ���ѐ�/p93
�u�z���炵�v�̘b / ���r�O/p96
ⵂƎq�ǂ����� / �������P/p100
�ق������䂤�������� //p104
�c�ӏ��Y�v���o�Ȃ�-23-�������_���������� / �c�ӏ��Y/p109
�֓���k�Ђ̑̌��k--�M�y���Ƃɒ���/���\���ӈ�;�ЎR�F�O/p114
���̑I�{�ƃ��R-�h / �������q ;���� ;������Y/p123
����̌|�\�̌��� / ���Ԉ�Y/p132
�C�O�ŖM�y�����t����l�ւ̏���/p135�`140
�M�y�̊C�O���t�ɍۂ��� / �k��⹎R/p135
�C�O�ŖM�y�����t����l�� / �f�r�b�g �q��-�Y/p137
������������,�C�O�ɒʂ��铹 / �O�ؖ�/p138
���a�\�ܔN�x�M�y���w������� �����|�p��w�E
�@�@����㉹�y��w�ENHK�E���h���y�@ //p141
�M�y�p�ꎫ�T--�E�\������ / ��������/p157
�M�y���܃N�C�Y //p162
�ҏW�G�L //p164~
�E |
�W���A�{�Ǔ��s���A�X�ۉh���Y�ҏW�u�{�Ǔ��s�S�W 11���d�R�×w�E�̗w�_�l�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�@�����F�V�������}����
�W���A�R�����j�ҁu�����j�j�ꉉ�t��v��[�R�����j�i����o�Łj]���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�����v���O���� �莚�F���܌��T �����F1980�N8��30�� �ꏊ�F����^�C���X�z�[��
�@�@�@�����|�\�S�W��7���o�� ������ �X���������Ƌ����^�L�O ���ÁF�R�����j
�������[ �t�F�����p���t���b�g
�W���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 2(8)(11)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@�@pid/7952612
|
�؍����y�̗� / ���c���q/p2�`3
�؍��̓`�����y / ���c��/p4~10
���J���[�� �W��Ȓ��ׂ�t�ł� ��y��E���y��E���y��/p17�`20
�؍��̃A���s�j�X�g / ���J��P�j/p46�`50
���₫���̌𗬎j(4)���@�x�Ɨ���/���q�ʏd/p30�`33
�V�A�� �����j�I�ɂ��̔錍���������Ă݂� �؍��l�̃��b�ƃ}�b(1)/�p�e�i/p11�`16
���S�����ł͐��Ƃ͂����Ȃ� ���Βk�� / �C�ٍ� ;������/p22~27
�v�z�̂ӂ邳�� �����C�s���𐳂������m ���ƍ��t�E�m�c�̎v�z/�����i/p36�`39
�l�ÁA���p�A�����w�����ɍv�� �c����w�Z���������� / �p����/p34�`35
|
�����̊ӏ� �r�̌Ñ㑢�`/�I�F�M/p28�`29
�ÓT������� �w�j���M�k�x/���r�F/p21�`21
���b�T�̕�/p40~41
�Ύ��L �싅�Ƃ��Ȃ��̔���/p41�`41
�]���̖{/p42~43
�}�X�R�~�_��/p44~45
�؍������̌�����T��(��)/������/p51�`54
�؍������E�̓���/p55~56
�؍������@�����/p57~57 |
�X���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 2(9)(12) �v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@pid/7952613
|
�����̉˂��� / �\�����/p2~3
�V���[�}�j�Y���Ɗ؍��̎v�z / �����A/p4�`8
���̖��̃V���[�}�j�Y��(��)--�؍��Ɠ��{/���䓿���Y/p9�`14
�����lj�̂Ȃ��̃V���[�}�j�Y�� / �I���/p15�`16
<�J���[> �ނ̍Ղ�/p17~23
��@�Ƃ̐��ڂɂ݂� ���ǂ̉ƒ� / �ɓ����l/p27�`31
���₫���̌𗬎j(5)���������Ɩ��@�x/���q�ʏd/p32�`35
�؍��l�̃��b�ƃ}�b(2)���͐��Ȃ�Օ�
�@�@���݂͈�̃V���p���� / �p�e�i/p47�`50
�v�z�̂ӂ邳�� �z���w���_��̌n������
�@�@�����J�E�A�ēl�̎v�z / ����i/p38�`41 |
��j���ォ�猻��Ɏ��鑍�������ق��߂�����
�@�@���\�E����w������--�����i�� / ���/p24�`25
�����̊ӏ� �ÐV���Ύ��Ɉ��u����Ă��� �O�ԗ�O����/�A�݁k�N���l/p36�`37
�ÓT������� �w�����V�́x / ������/p26�`26
���b �Ղ̂��ꂽ��/p42~43
�Ύ��L �H�[�̌��E�㌎/p43~43
�]���̖{/p44~45
�}�X�R�~�_��/p46~46
�؍������E����/p51~52
�؍������@�����/p53~53
�E
|
�X���A������ �ďC�u�����������@ (�ʍ� 204) �v���u���@�K�v���犧�s�����B
|
���ׂ̓`��-�ނ̌n���𒆐S�Ɂ@ ���䓿���Y p.p4�`5
�쓇�̐_���̐��E-����b�� �@�R���ӈ� p.p26�`30
���[�J���ւ̂����Ȃ� �������} p.p31�`35
�����̗��� �@�֎R�a�v p.p11�`17
|
�����̒��ɐ�������蕨-����ڗ����ڏ��S �����G�Y p.p42�`47
�\�E�����E�K���<���> �H�c�� p.p18�`25
�l�`��ڗ� �˕���� p.p36�`41
���̌����`�� �@�P�c�r�ܘY p.p6�`10
|
�P�O���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 2(10)(13)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@pid/7952614
|
�e�����߂����ٍ��ւ̗� / ������C�u/p2�`3
�؍��̗��j���V���[�Y(1)�؍��̎j���Ҏ[���̗��j��
�@�@���ۑ���/�����/p4�`7
���̖��̃V���[�}�j�Y��(��)�؍��Ɠ��{/���䓿���Y/p39�`44
<�J���[> �؍��̉�/p17~20
�؍��̑�����(��1��)�؍������̂Ȃ��Ɉ�т��ė���Ă���̂�
�@�@���؍��ŗL�̐_��v�z�ł���/�A�݁k�N���l/p21�`28
�؍��̑������l(1)���`���p�ɂ݂铮����/ �щi��/p46�`47
�l�G�̖����߂���(1)�p�������W��������X/p16�`16
�Βk �؍��l�̕��̌����A�l���� / ���Z�� ;�c����/p10~15
�����ٔ��p�ق����(13)�\�E����w�Z������
�@�@���l���p��/���/p48�`49
�ÓT�������(12)�w����j�x / �͏�m/p45�`45
�؍��̖��b(13�b)�ς̉�������/p54�`55 |
�����ߗ�̌Î��������˂�(1)�\�E���̈���\���厛�� / ���g��/p8�`9
���₫���̌𗬎j(6)(�ŏI��)�L���`���P
�@�@������؍��̏ے� / ���q�ʏd/p30�`34
�؍��l�̃��b�ƃ}�b(3)���ߒu����͉Ă̐_��
�@�@���L���`���߂͓~�̐_�� / �p�e�i/p35�`38
�v�z�̂ӂ邳�� �؍��ŏ��̃J�g���b�N�_�� ���匚�̎v�z/���^��/p50�`53
�]���̖{ �w�Ñ㒩�N�����Ɠ��{�����x
�@�@���w���N�̍Ղ�ƛޑ��x/�c������ ;���g��/p56~57
�}�X�R�~�_�� ����I�ȋ�����v�ق�/p58�`59
�؍������E�̓��� 9���̃K�C�h/p60�`61
�؍������@����� ��5���؍���u��/p63�`63
�{������1���N�L�O ���ܘ_����W�����I �؍����j�̗����ҁ�
�@�@�� �ǎ҃A���P�[�g���S����1981�N�J�����_�[�v���[���g��/p62�`62
�E |
�P�O���A�쓇�j�w��ҁu�쓇 : ���̗��j�ƕ��� 3�v���u ��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/9773442
|
���d�R�Ñ㕶�����߂��鏔��� ��������/1
��㊂Ɖ���/35
�쓇�����j�̌����\�Ƃ��ɋ{�ÁA
�@�@�����d�R�����̌����߂����ā\ �q�쐴/65
��A�͂��߂�/65
��A�{�ÁA���d�R�̒��R����/68
�O�A�^�ߔe�����L���e�������Օ���ɂ���/70
�l�A�w�c���c�c��R���L�x�̋L�q/71
�܁A�������v�����̗^�ߍ��Ƒ�|�c�[���V���̗^�ߍ�����/73
�Z�A�^�ߍ����̒��R�����Ƒ��NJԁA�^�ߍ��������/77
���A�{�ÌR�̗^�ߍ��i�U����/80
���A���R�̌`���I�x�z����Ǝ����I�x�z����/83
��A�I���P�ԖI���������̐^���T��/86
�\�A����������̔��d�R�Љ�̕ϖe/90
�\��A�ނ���/94
�ߐ����������Y���̒����l�ƒ��N�l�̌쑗 ���a�F/101
��A�͂�����/101
��A���������ւ̕Y���ƌ쑗/105
�O�A���Ƃ���/115
�t�H���J�[�h�ƃ��E�e�����f���\��㊂̐؎x�O�����\ �����q�Y/123
��A�O��/123
��A�鋳�t�Ƃ��̗���/123
�O�A��l�̋L�^/125
�l�A�t�H���J�[�h�̓�N/127
�܁A���E�e�����f���̗���/141
�Z�A�鋳�t�ؗ��̈Ӌ`�\���_/144
�����̃��^�̐��ނ��߂�����\
�@�@����㊁E�擇�����̎���Q�Ƃ̗\���I�l�@�\ �R���ӈ�/151
��A�͂��߂�/151 |
��A�����̃��^�̐��ދV��̎���/153
�O�A��㊁E�擇�����̃��^���ގ���Q/162
�l�A�����̃��^�̐��ނƉ�㊁E�擇�����̃��^�̐��ނ̑Δ�/172
�����E���B�́u���_�v�ɂ��� �㓡�d��/189
���d�R�n���́u���V��v�\���̈�A
�@�@���d��V��ɂ��ā\ �Ί_��/203
��A�܂�����/203
��A�u���q����[�v�ɂ���/204
�O�A���d�R�̈��@/213
�l�A���d�R�̈��V��̍\��/214
�܁A���d�R�n���̔d��V��/216
�Z�A���Ƃ���/230
�{�Ó��̒b��E�ɂ��Ă̗\���I�� �������u/233
��A�͂��߂�/233
��A�{�Ó��̒b��E�̌n��/236
�O�A�E�l�Ƃ��Ă̓���/239
�l�A���j�I�ω��ƎЉ�E�o�ϓI�w�i/246
�܁A������/249
���d�R�����ɂ�����u�_���v�̌n���\�� �}������/253
��A�͂��߂�/253
��A�u�_���v�̍��J�I���/254
�O�A�u�_���v�̌n���\��/257
�l�A���_/268
�����̛މ́\�\�������y�w�I�l�@�\ ���c���q/275
��A�͂��߂�/275
��A�����́u���^�v�ɂ���/275
�O�A�����̛މ�/280
�l�A���_/314
���d�R�Ɍ�������g�x�ʖ{�̓��� ���Ԉ�Y/321 |
�P�O���A�v���^�b�N �ҁu�����x��̉���ÓT���x�@�i�����v���O�����j�v���u�v���^�b�N�v���犧�s�����B�Q�O�O�O�~
�@�@ �����F1980�N10��17�� �ꏊ�F���������z�[��(�����V�h)
�@�@�@12p�@�@�����F��㊌����}���فF1002275889
|
��� ��� �P�Y
�������x�T�� �X�� �h���Y |
���O�t���́u���x��v�Ɋ��҂��� ���� ��Y
���O�t���F�ʏ�ߎq�E���g�Î}�E�ʏ��}�q�@�d�v |
11���A�؍������@�ďC�u�����؍�����2(11)(14)�v�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@pid/7952615
|
�S���鏭�N����̑z���o / �]��P�\/p2�`3
��c�B�c�������@�������|�[�g(2)��c�������o�y
�@�@�����ꊢ��? ���c��93�N�����V���ő�̎�����
�@�@���S�e�����X�ɖ�������� / ��R�T/p11�`16
���J���[�� ������o�߂��c�����̊��Ɓk�Z���l/p17�`20
�؍��̑�����(��2��)���@�E���@�E�O�̉� / �A�݁k�N���l/p21�`25
�؍��̑������l(2)�������l�̗���Ƃ��̎�� / �щi��/p38�`39
�����ٔ��p�ق����(14)�����w�Z������ / �����p/p45�`47
���̖��̃V���[�}�j�Y��--����ދV�̔�r/���䓿���Y/p4�`9
�l�G�̖����߂��� �\�ꌎ �]�ؓ�--���j�̓�/p10�`10
�ÓT�������(13)�w��_���x / ������/p44�`44 |
�؍��̖��b �x�҂ƂȂ����Ǖw / �c���a/p26�`27
�؍��l�̃��b�ƃ}�b(4)���̏C���ƍՕ��̈Ӗ� / �p�e�i/p33�`36
�����ߗ�̌Î��������˂�(2)�،��� / ���g��/p28�`32
�v�z�̂ӂ邳�� �����]�����̑啶�� ���p�̎v�z / ����i/p40�`43
�]���̖{ ����\���E�˓c��S�q��w�؍����ԓ`���Ɩ��b�̌����x
�@�@�������^���E�c���a��w�؍��Θb�W�x/p48�`49
�}�X�R�~�_�� �A�J�f�~�Y���̑哹�ق�/p50�`51
�؍������E�̓��� �����̃K�C�h/p55�`56
�؍������@����� �}�����ē�/p57�`57
�{������1���N�L�O ���ܘ_����W�����I �؍����j�̗����ҁ�/p37�`37
�E |
�P�P���A�������Z����w�}���ψ���ҁu�������Z����w�����I�v (26) �v���u�����Z����w�v���犧�s�����Bpid/1769715
|
�N��L�����Y�ɉ�����q���\�r�̐���(��)���D�y����l(���w���̌`��������)(�U) / �I�c�L��/1
��ꎟ���E���ƃh�C�c�m���l�Q��(�l) / ���g�F�B/21
�������w��r�ǎ�ߣ�ɂ��� / ��������/1
��e�̗{��ԓx�̍\������(1)�є��m�̐��ʉ����_�ɂ��p�^�[������ / �e����/21
��e�̗c�t�����ɑ���{��ӎ�(����2) / �֓���Y/31
�z���[�X��}���̋���v�z�ɂ��ā\�\�ߑ�����琬�����ɂ�����x�z�I�������F��(����2) / ��V�G��/45
D.H.�������X�̒Z�ҏ���(2) / �ɓ����i/55
�����m�[�g �ߐ��b�{�鉺���̓`�n�� / �y�c�Lj�/65
�|�� J.T.�t�F�C:1950�N�㖖����̐��w����ɂ�������v�\�\���O�Ǝ���:�A�����J���O���̏ꍇ / ���{�ǒ�/75
����{���k���̎�����(2)�������^�߂Ɖ��Ԃ̎����� / ���эK�j/89
�|�V�����Ȏ��ƒ����\�\��p���Ώƒ����n���l�����T������Ɋ� / ���c�G�v/111
����̎q�ǂ��̂������u�s�A�m���ȏWVII.�v / ���{�M�v/119
�O�̔_��Ɖ� / �����Y���Y/139 |
�P�Q���A��ÍN�Y�ʐ^,�J�쌒�ꕶ�u������ �������̍Ձv���u�����V���Ёv���犧�s�����B�@�@�@
�P�Q���A�g�����d���u����ڂ��� 11(4) p.78-79�v�Ɂu�L�ތ����̏W�җ�` (44) : ����P �v�\����B
�P�Q���A�{�Ǔ��s�������H�^�s�ҏW�u�{�Ǔ��s�S�W 8 �@���d�R��b. �b�сv���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B
�P�Q���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 45(12)[(586)]�@�_���E�̌��̐��E<���W>�@p6�`146�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059703
|
���k�� ���_��聄�Ɓ��̌�聄--�V�l���[杂̎��� �͂��߂Ɂ^
�w��V���|�W�E�����e�̕Ɗ��z�^
�쓇�̖��Ԑ��b�����̖��_ �m���ƃ��^ ���^�͎n���I�Ȏp��`���Ă���^
�j�M�O�`�_�ՂƐ_�� ���^�̎E�m���̎� �Ƙb�^�����V���S�^
�̌��t�Ɠ���̌��t �����邱�ƂƉ̂����� ���^�̕ϗe ���^�̐��ގ� �}���K�^���^
���^�̎̌p�� �m�ԃi�K�� �m�ԕz�̐���ߒ������������Ƃ̈Ӗ��^
�N�T�i�K�� �쓇�̘̐b �O�������b�^�b���ƌ��E�����o�i�V�^
�^���̘b�Ƃ����łȂ��b�^�쓇�̘̐b�̒�N������́^����̌����̉ۑ� /
�Ë��M�F ;�R���ӈ� ;�֍����i ;�����a/p6~43
<�_���><�̌��>�̋�̓I����/p44�`61
���_��聄�E���̌�聄�̋�̓I���� �֖�����杂̕��� / ����r�v/p44�`51
���_��聄�E���̌�聄�̋�̓I���� �V�l���[�ɂ���-
�@�@�������̓`���𒆐S�� / �R������/p52�`61
<�_���>�E<�̌��>�̊�{�I���/p64�`79
���_��聄�E���̌�聄�̊�{�I��� �b�����Ƃƌ�邱�� / �g�c���F/p64�`69
���_��聄�E���̌�聄�̊�{�I��� ��邱�ƂƏ������� / �R�{�g���E/p70�`73
���_��聄�E���̌�聄�̊�{�I��� �����Ƃ����� / �����a/p74�`79
<�_���>�E<�̌��>�̌ʓI���/p82�`126
�_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���_��聄���̗l�� / �O�Y�C�V/p82�`87 |
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���̌�聄���̗l�� / ���c��/p88�`92
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���_��聄����E���� / �Ë��M�F/p93�`97
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���̌�聄����E���� / ����/p98�`102
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���_��聄�`�d�ƒn�搫 / ����K�O/p103�`107
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���̌�聄�`�d�ƒn�搫 / ���c�W/p108�`116
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���_��聄�`����������� / �����a�F/p117�`121
���_��聄�E���̌�聄�̌ʓI��� ���̌�聄�`����������� / �␣��/p122�`126
<�_���><�̌��>�̐V��������/p128�`146
���_��聄�E���̌�聄�ւ̐V�������� �����_�b / ���c�a�v/p128�`133
���_��聄�E���̌�聄�ւ̐V�������� �A�C�k / �����v�a/p135�`139
���_��聄�E���̌�聄�ւ̐V�������� ���� / �Ɍ|�O�q/p141�`146
���|�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p<���W>/p147�`182
�����W ���|�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p �\�����̌��� / �����i/p148�`154
�����W ���G�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p ���������̌���/�r�c�A�i/p155�`161
�����W ���G�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p �K�ᕑ�Ȍ����̌���/�����K��/p162�`168
�����W ���G�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p ���o�|�E�ӑm�|�����̌���/���c��/p169�`175
�����W ���G�E�g�̌|�����̌���--�����̎��p ��̕��w�E�|�\/�֍����i/p176�`182
��
�E |
�P�Q���A�u�}�����y�̂��炵�ƕ��� �㊪ ����{���E�����сv���u�V���}���o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@�Q�l�F�E���� ����E�����с@1981�N���s
�P�Q���A������w����w���}���I�v�ψ���� �u������w����w���I�v ��i24�j�v���u������w����w���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2259158
|
�����ɂ�����Z�p�̌���-1-���Z(����Z) / ���鏼�h ;���c�ؒ��l/p1~9
�L�`���̍z���g���ɂ��� / ���c�`�� ;�쌴���G/p51~55
����̃T���S�ʈ�ɂ�����L�`���̕��z / �z����� ;�쌴���G/p57~63
�����x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-5-���x�v�f�]��ɂ�问�����x�̔F�m�̌n / ������q/p65�`75
���x����̕\�����Y���Ɋւ��錤��-2-�������x����{���x��C���h���x�̋ؕ��d�y�ьċz�p�^-���ɂ��� / �ԏ�m�q ;������q/p77~101
�����̈ߕ��ƃA�W�A�̈ߕ��Ƃ̊W�ɂ���-2-(����������̈ߏ��Ɨ����̉��ւƂ̔�r) / �n�����q/p189�`196
�����E�L���E�o�V���E�@�ۂ̐��\�Ɋւ����b�I����-1- / �������q/p203�`207
�q�����r |
|
���� ���q�Ƒ�� ���q�� �u������w����w���I�v. ��� (�ʍ� 16�` 24)�ɔ��\�������u���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-1�`5�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 16) p.p57�`79 |
1972-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-1-�@ ���� ���q,��� ���q |
| 2 |
(�ʍ� 16) p.p41�`56 |
1972-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-2-�@ ���� ���q,��� ���q |
| 3 |
(�ʍ� 17) p.p27�`50 |
1973-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-1-2-�Ӗ������@�ɂ��@���� ���q |
| 4 |
(�ʍ� 17) p.p51�`72 |
1973-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-2-2-�Ӗ������@�ɂ��@���� ���q |
| 5 |
(�ʍ� 18) p.p41�`60 |
1975-03 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-3-�F�������x�̔F�m�\���@���� ���q |
| 6 |
(�ʍ� 20) p.p7�`28 |
1976-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤�� 4 �F �������x�̔F�m�\�� 2�@ ���� ���q
|
| 7 |
(�ʍ� 24) p.p65�`75 |
1980-12 |
���x�̊ӏ܍\���Ɋւ��錤��-5-�@�F���x�v�f�]��ɂ�问�����x�̔F�m�̌n�@
���� ���q |
|
���A���̔N�A�u�A�������Y �v������^�A�������Y�ۑ���v���犧�s�����B�@
58p�@�����F ���ꌧ���}���ف@ ���ꌧ���}���فF1007883984
|
�����Y���ς� �R�� ���j
�A�����̗R���L ���^ �M
�O������ �R�� ���j�^�쎌
�A�������Y�̗R�� ���^ �M |
�A�������Y�̗w �n�Õ~ ���Y�^�S �R�� ���j�^��
�A�������Y�̉̎�
�����Y�̎��̔�r ���^ �M
�u�A�������Y�v���`�����������Ɏw�肳�� |
�A�������Y�̉��v
�A�������Y�ۑ���
�A�������Y�ۑ���������ꗗ
�E |
���A���̔N�A�Έ䗲�r���u�吳��w��y�w��������w�@�����I�v 6 p.32-34�v�Ɂu�ܒ���l�`���������v�\����B
���A���̔N�A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 7�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����Bpid/9773378
|
�쓇�́u�����v�s�� ������G/1
�M��Ȃ����̂̓쓇�I�`�ہ\��`���ɂ݂�쓇�̎v�z�\ ��Î�/28
�w�����S�T�x�Ɖ����̌��s�̗w ����w�v/54
�{�Ó��̐_�̂Ƃ��̗�����߂����� �������q/91
�떓�̐_�X�\�_�[�r�E�s���[�V�����ƂɁ\ �V���K��/113 |
�����L�^�E���w���_�\�����敪�ɂ��ā\ ��������/140
�����ɂ�����l�g�����E�����`�F�̌��� ��R�ٌܘY/159
�w��a���ړ��L��O��x�ɂ��� ���n�B��/179
�������� ���z������/198
�E |
���A���̔N�A�^�������u�쑺���ÓT���y���d�R�ÓT���w�v���u�`�^�����v���犧�s�����B
�@�@�@�^���f�B�X�N 1�� : �A�i���O (LP) , 33�@�@�F��p��(�S, �O����)
|
| SIDE-A |
(1)���ʂȐ�(2)�܂�́[�ܐ�(3)�㌴�ʓ���(4)�ł�(5)�������[��(6)�Ì��̉Y�� |
| SIDE-B |
(1)������ŕ���(2)���Ԑ�(3)���q����(4)������(5)������(6)�q���� |
|
|
| 1981 |
56 |
�E |
�P���A����O�v���u�A�������G�� 56(1) p.24-24�v�Ɂu�r���������C���a�c�^�~�ďC�F����A����O���p�}�� �S6���v���Љ��B
�P���A�{�Ǔ��s�������H�^�s�ҏW�u�{�Ǔ��s�S�W 8 ���d�R��b. ���сv���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@
�P���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 3(1)(16)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@�@
|
�؍��T�����̗��j�I�W�J / �؊�l/p12�`15
�����ߗ�̌Î��������˂� ���L��(2) / ���g��/p36�`39
�����ٔ��p�ق����(16)���ϊّ唎���ق̌��� / �{����/p50�`51
�؍��̑������l(4)�Õ��lj�̓������l / �щi��/p34�`35
�Βk �����킽��؍��̂��� / �r���q ;���c���q/P4~11
���Ɏv�z��H�� / �����r/p45~48
�؍��̗��j��(4)�w����j�x�Ҏ[�̌o�� / �����/p42�`44
�l�G�̖����߂��� �ꌎ ���B--�S�ς̋����s���ւ�X/p49�`49
�؍��̖��b ����킵���U�f / �c���a/p40�`41 |
�ÓT�������(15)�w�����V�b�x / ��J�X��/p16�`16
�؍��l�̃��b�ƃ}�b(6)�_���ȎR�ƕ����Ƃ��Ă̐_�h��/�p�e�i/p29�`33
�]���̖{ ���c�ΗY���w���N�����̎��Ɨ��j�x
�@�@���ÎR����Y���w�g���ŗ�x/p52�`53
�}�X�R�~�_�� �����́u���v���}���� ���_���������@�̍���/p54�`55
�ǎ҂̂Ђ�� ���O���t�@�E�g���T��/p56�`56
�؍������E�̓��� �����̃K�C�h/p57�`58
�؍������@����� �����u����ق�/p59�`59
�{���n��1���N�L�O ���ܘ_�����偃���I �؍����j�̗����ҁ�/p11�`11 |
�P���A�R���ӈꂪ�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 46(1) p.p155�`162�@���傤�����v�Ɂu�N���s���Ɛ_��(��)��--�쓇���������̐ܖڂ𒆐S�� ("��N���ʂ�"�N���s���̖���<���W>)�v�\����B
�@�@���@�����̕��@�ɂ���Ę_���̕\�肪������̂Œ��ӂ��K�v�A������v���B�@�@�Q�O�Q�R�E�T�E�W�@�ۍ�
|
��������}���كI�����C���i�G���L�������j
�N���s���Ɛ_��(��)��--�쓇���������̐ܖڂ𒆐S�� ("��N���ʂ�"�N���s���̖���<���W>)
��������}���كf�W�^���R���N�V�����@pid/6059704
"��N���ʂ�"�N���s���̖��� �����W �N���s���Ɛ_��(��)��--�쓇���������̐ܖڂ𒆐S�� / �R���ӈ�/p155�`162 |
|
�P���A�_�{�i���L�ҁu���_ (122)�v���u �_�{�i���v���犧�s�����B�@�@pid/7930665
|
�\�� �O�{�̒�
�V�����N�̏��߂� / �J��/p1�`1
���ւ̔��� / �c���@�r/p2~3
�O�}�{���m�e�����ܗ��a���䌋���Ɍ�Q�q/p4�`4
�^�ЂƋ����Ƃӂ���--�_�{��J���`���̈�݂̂��� / �������Y/p5�`12
�ɐ��Q�{���s / �V���C�O/p13~14
�ɐ��Ƃ������̌R�� / �Ð�M�s/p15�`18
�_�{�Ǝ� / �ЎR���F/p19~22
�_�{�_�ƊقƓc���F�j / ��쌛��/p23�`28
���Q�{�̎v���o���߂�����--�Ɨt���ѕ����̂��� / �R�c���j/p29�`32
�k�C�����O�̈ɐ��M�� / ��ֈ䕐�G/p33�`34
�v�����Ǝ��q���_���� / �{�c����/p35�`38
�_�{�Ǝ��Ɣo�� / �c����/p39~43 |
���K��◁E�s��q�v�Ȃ̔��� / �������Y/p44�`44
�O���́u�ɐ��c��_�{�ƍ��Z���v��ǂ�� / �揼�G��/p45�`48
��㊂���Q�{���� / �x���L�N/p48�`48
�_�{�ό�����I�씭�\/p49~50
�b�� �_�{�̍ՓT/p51~53
�b�� ����/p53~62
�b�� "�݂�����"�̑��������ł��܂���/p63�`63
�b�� �ǎ҃J�[�h���������܂�/p64�`64
�b�� ���N�́u���Ǝ��v/p14~14
�b�� ���܂ꂩ���������/p28�`28
�b�� �畐�Քo����/p48~48
�b�� �_�{���C���w����W/p65�`65
�E |
�Q���A������������m�_���u�䂪���C��ړ������̎Љ�l�ފw�I���� : ���̗��n�蒅�E�����ݗ��ߒ��v�\����B
�Q���A�u�]������ : �ʐ^�W ��5�� (���ꌧ�l�����i�ʐ^�W)�v���u�{�M���Ёv���犧�s�����B (���p��)�@pid/9773698
|
���i��
�F�P���i���j
���X����c����]��/1
��㊗i�n���j/2-3
�ɍ]��/4
�k�g��/4
�g�V��S�i/5
�ߔe�`/5
�ߔe�s�S�i�i��j/6
�ߔe�s�S�i�i��j/7
�s�X�R�`���O/6
�s���������O/7
�s�X���O��/8
�s�X������O��/8
�E�q�_�O�i/9
�E�q�_����/9
�ߔe�s�����I�V��/10
�ߔe�s�����~�s��/10
�ߔe�s�����s��i��j/11
�ߔe�s�����s��i��j/11
�����R�����S�i/12
�k���������䕨���]��/12
������/13
�g�V���d���v�[��/13
���`�̎R���D/14
���M/14
�R���D/15
���ޒ��S�i�i��j/16
���ޒ��S�i�i��j/16
�o�ߌ����S�i/17
�V����/17
���ʋ�/18
��Ӌ�/18
��������/19
��������/19
���X��/20
�c���/20
�鐳�a/21
���Ɛ���/21
�����V��/22
���K/22
����������/23
��������/23
���S�����a/24
���S������/24
���S���R��/25
���S���œa�̕��`/25
���䉮�����/26
������/26
�ʗˁi�ˌ�a�j/27
�V����/27
��㊐_��/28
�Вd/28
���g�{�i��j/29
���g�{�i��j/29
���������{/30
�����{/30
�����{����/31
�����{�̋S��/31
���V�Ԟ܌�/32
�ߓ������܌���/32
�J�����P�_��/33
�������A���܌���/33
�g�V��욠��/34
�욠���R��/34
�x�b�e���n�C���L�O��/34
�g�V��_�Н`�a/35
�g�V��_�АΒi/35
���ނ̔��⓰/36
�{�����_��/36
���d�R�c�[���/37
�Ո�c��L�O��/37
�j�L�O��/37
�E�q�_���a/38
����p��������/38
��㊒����V����/39
�����V���БS��/39
�p���j�q�t�͛{�Z/40
�p����ꒆ�{�Z/40
�p����{�Z/40
�p����O���{�Z/41
�p���H�ƛ{�Z/41
�p����O�������{�Z/41
�ߔe�s�����Z����
�@�@���R������/42
�o�ߌ��C�݂ɉ�����
�@�@���ꍂ�����̐��j/42
�ꍂ�����̍�����
�@�@���u���F�j�X�̏��l�v
�@�@���@��̏�/42
�s�����q
�@�@���H�Y�{�Z����/43
�ꍂ�����̃X�|�[�c����/43
�{���̓�����K/43
�ߔe�s�������{�Z/44
���ޏ��{�Z/44
�n�v�n���{�Z/45
�ɍ]�����{�Z/45
�v�ē����Â�颐��C��/46
�K���T�[�X/46
�v�ē��V�ԍ`/47
���P����/47
���P������ԍ��]��/48
�����i��j/48
�����i��j/49
���̔䉮�̑��z��/49
�쐶�̑h�c/50
�}���O���[�u�i�Ђ邬�j/50
���V�ԊX���̏�����/51
���d�m�̒|��/51
�p�p���i��j/52
�p�p���i��j/52
�o�i�i/53
���S��/54
���엖/54
���㗖/55
���U/55
�r�/56
�ւ�/56
�n�u/57
�������ˉt�̎�/57
�X��i��j/58
�X��i��j/58 |
�v�ē��Y�C��/58
�Վ��̟������W�߂�
�@�@���J�������ޓc�q��/59
�V���P/59
�����R�����O�̐����M/59
����/60
�����̑��/61
�ߔe���������n/61
�q�`/62
������/62
�썲�ۂ̕�/62
��Ӑ�/63
����/63
���쒬�S�i/64
���쒬�̕���/64
�������{�Z���
�@�@���ÒÉF�Ԃ�]��/65
�d���`/65
���d�m��ՋL�O��/66
����㗤�L�O��/66
�^�V�`/67
���d�m���/67
�n�v�n�`/68
�n�v�n�`�z�`�H��/68
�ɍ]�����i/69
�挴�蓕�i/69
�ߔe���d�ǂ̍���/70
�Ί_�����i��j/71
�Ί_�����i��j/71
�Ί_�`/72
�����`/72
���Ǎ`/73
���\�`/73
�Ì��̖k��/74
�{�ǐ�/74
�r�i�C�T�[���i���j/75
�C�]�c�c�T�[�i�͋����j/75
�o�ߚ�/75
����p�K/76
�p���c����/76
��X��������/77
��㊌Y����/77
����p���a�@/78
�p���u����������/78
�Ǝ�鄏�/79
�����_��/79
���Ƌ�s�ߔe�x�X/80
��㊏d���@�ᢓd��/80
�����_�Ƒq��/81
�_�Ƒq�ɓ��̔엿���H��/81
����/82
��䱎�/82
�p��������/83
��㊐������Ћ{�ÍH��/83
��㊐������ЉÎ�[�H��/84
��㊐������Ѝ���H��/84
��㊐������А����H��/85
�����q�ɓ��̍����M/85
�s�O��/86
�A���H����̕Đ��/86
�������U�P/87
�A��������/87
���퐻��/88
�����̗���/88
���퐻��/89
�ى����P����/89
����̏��i�\�j/90
����̏��i���j/90
���������Ԃ̑喋�o�՚�/91
�g�^��㉂����݂͂�/91
�@�D��/92
�X�q�҂�/92
��������/93
�ĝ���/93
�����s���̊C�ؕ߂�/94
���ߐ����H��/94
�b���d�c�i��j/95
�b���d�c�i��j/95
�P��g���o�`���̌@��/96
�g���o�`���̌@�̌��i/96
�v�ē����c�`�̃K�}/97
�v�����̕�/97
���E�h���i��j/98
���E�h���i��j/98
�욠�`���̕�/99
�V������̕�/99
�j����/100
ꝍb��/100
�ߔe�s���̕�/101
�ߔe�ߍx�̕�n/101
�V��/102
�җV�s�i��j/103
�җV�s�i��j/103
�ߔe�̗V���i�l�t�j/104
���W�i��O���j/105
���W�i�V��x�j/105
�V���̕��i�ݍΌ����j/105
���ޔn�s��/106
���W�̔��ޔn/107
���ޔn�s��i��j/107
���ޔn�s��i��j/107
�l�c�|��/108
�J�i�[���[��/109
���x�@����/110
���x�@�_�璹/110
���x�@�ݍΈ�i/110
���x�@�ݍΓ�i/110
���x��/111
�����O�����L�O����/112
�ɘm���K/112
���菸�i��/112
���剮��ɉ�����
�@�@��������K/113
�c���{���蕔��/113
���������/113
�_�p/114
�_�p�g��/114
�j�g�s��i��j/115
�j�g�s��i��j/115
�ߔe�̍j�g/116
�o�ߌ��̍j�g/116
���n/117
骋�/117 |
গ��D����/118
�o�D������̚�/118
�l����
�����̉��q�i���j
�������̏�/120
���牤�̏�/120
����/120
�ȋʂƋ���/120
�����ƉG�іX/120
�X�s���ۂƂ��̘a��/121
�������Ƃ��̊���/121
�{���ږ�y�M�O�_�c��
�ɍ]�����@��쎟��/122
���X���@�ԏ�i�n/122
������O���@�|������/122
��R�k���@����I��/122
�{���ږ�y�_�s��
�ɔg���Q�@��錓�`/123
���c���~�@���_�M��/123
�n�������@���@������/123
�{���ږ�y�R�l
���ߌ��a�@���o�ߌ�����/124
����ꝏ��@�n������/125
�e�����ȁ@���n���C/125
�l����
�����i�B�E���c���X�ǁE
�@�@�������x���U/126
�ɍ]���r�E�ɍ]����/126
�ΐ�P���E�ɒ���/126
�r�{���P�E�ɓ������i/126
�Ɍ��x���E�㗢�Ҏ��E
�@�@��������V��/127
�㌴���j�E��X������/127
�������m�E�����c/127
��錓���E��鐷��/127
�����ǍF�E�����ǕہE
�@�@�������ǚ�/128
�勴���V���E���Ԓ���/128
�e���N�i�E���͒���/128
��쉮�@�M�E��ӏG�T/128
���A���p�E�Î芡�M���E
�@�@���약����/129
���鐳�P�E�����M/129
���镟�U�E�_�c���P/129
���ߒ���E�쉮������/129
�쉮���ۏ��E�����ǐm�E
�@�@���v�����g/130
���g���r�E�K������/130
�쓾�v���́E���������v/130
�Ôg�U���āE���͒��B/130
���_�G��E�茴�c���E
�@�@����R�p�M/131
���v�c���́E�u�쉮�F�M/131
�ēc�������E�ēc�ĎO/131
���܌������E���܌�����/131
���܌����E���n���߁E
�@�@�����n���M/132
�����E�V�钩��/132
���A�K�����E�P���ǒ�/132
�^�쌳�ƁE�^�얾�B/132
���������E�������r�E
�@�@�����ǐM��/133
���×nj����E���×nj��G/133
�|��ċg�E�������X/133
�������q�E�|������/133
�c�菹���E�c�蒩���E
�@�@���c�㐴�Y/134
���c�쓱�E���Ït��/134
�ʏ镐���E�m�O���P/134
�m�O�ϒ�E�Ì��F�i/134
�Җ쐽��E�Ôg�Ï[�v�E
�@�@���n������/135
�c�Ԝ��āE�c�Ԏk��/135
�c�R���E沐쒉�i/135
�����������E��������/135
�������́E�������O���E
�@�@�����@������/136
���n�I�W�E���n����/136
�����p��E���䛒��/136
���g�nj��E���g���q/136
����ԏ@��E���쒩�h�E
�@�@�������P����/137
�_���N�Y�E�����[����/137
��Ðe�g�E��×Ǔ�/137
��Ït���E���Η�/137
�䉮������E���~���p�E
�@�@�����c�g��/138
������㏼�E�x���z�`��/138
�O�ԗNjV�E�{�鐴/138
�{��K���E�{��m�E/138
�{��V���E�{�����ہE
�@�@���{���Ǖ�/139
�{���c��E����������/139
�{������E��������/139
�X�c�Жr�E�O��司/139
���g�N�a�E�����m���a�E
�@�@�����c���E�ʖ�/140
�����t���E���V��/140
�R���S���E�R��Ēj/140
�R�鍂���E�R�鋻�P/140
�R�����j�E�R���[�����E
�@�@���R������/141
�R���N�E�g�c����/141
�o�ߗ䌫ꝁE
�@�@���`�����q����/141
椒J�R���`�E�N��W�l/141
�㌴�i���E�L�V���Y�E
�@�@�����F����/142
���ܑS�B�E���i���G/142
�����P���E�ԏ�i��/142
���쒩�G�E�o���O��/142
��铛���
�ߔe�s���c��/143
�p���a�@�E���ꓯ/143
��㊓������Ƒg������/144
�M�p���̍w���g��
�@�@�����������/144
���������A��
�@�@�����g��ᢘ���/145
�������z�����/145
�������d�R���F��/146
�������d�R���x
�@�@�����F������/146 |
�����ɍ]�����F��/147
�����ɍ]�����u��/147
�ߌ���㊘���/148
�ߌ�����p�l���u��
�@�@���p�͑��/148
����p���Y����
�@�@��������������/149
����p���Y����
�@�@����㈴������/149
��㏬�R���l��/150
������p�l���ɉ�����
�@�@������卲�u��/150
���勅������/151
�ݍ㖼�����F��/151
�ݍ�v�ē����F��/152
�ݍ㉫��p�l���u��
�@�@���p�͑��/152
�O�I�v�ē����l������/153
�ݕz���p�l�ꚠ�V����/153
�����n���������Ə���/154
��㏤�D�ߔe�x�X��
�@�@���v�����x�X��/154
�ߔe���������n�Ǝs���c��/155
�v�ē��V�ԊC�݂�
�@�@����ݍH������/155
����p���c��/156
�S�p���X�ǒ�/157
���⓰�Ǝ��ޒ��L�u/158
��������p�l��/159
�����l��/160
�x�m���z�a�ѐ��H��
�@�@������p�l���H/161
���_�ߌ�����p�l���u��/162
���욠�֎��/163
萐�����p�l�����/164
�_�ˉ���p�l��/165
��㓌�����N��/166
�˔��h�����ؒÍH��
�@�@���p�l���u��/167
���ɓ���������/168
�a�̎R����p�l���u������/169
�o���R�F�m�v��/170
���^����
���������V��i���j
����p�n���i�����j
�ڍv�D�o�`�V��/1
�Y�Y���ᢌ@�̌Ê�/2
�i�v�D/3
���łւ̎g�҂�熗�/4
�����남������/5
�ߔe�Òn��/6
�ߔe�s�n��/7
���ی��̕�/8
��̕M��/9
�䋳��/10
�u���ǂ���`/11
�ʏ钩���̘a��/12
�ŏ��̚���/13
��㊌��o�D/19-25
���^
��㊗��j/1
�����l�͓��{�����ł���/1
�����l�̊C�O�Y��/5
�Q�Y�����Ǝl�����̋��S/7
�����W�܂Ɨ�������/9
�F���̗�������/10
�E�˒u�p�Ƃ��̌�/13
���萌W�����ژ^/14
����p�l�����ژ^/16
��㊖��
��������/18
���[��/18
���ɕ�����/18
����n���^�O��/18
������/18
�ӕ~��/18
������/18
��������/19
����c��/19
�ԕ���/19
������/19
�������/19
�l�G����/20
�ݍΌ���/20
�ݍ��ӂ�/21
���ق���/21
�x�N�n�f�T��/21
���Ԑ�/21
�약��/21
�J���O��/22
���̉Ԑ�/22
���P��/23
�q����/23
�U�R��/23
������/23
�q���/23
���ڐ�/24
���ǐ�/24
�_�璹��/24
�V�����K�i�C��/24
���_��/24
�{�ÃA���O/25
��Ԑ�/26
�������/26
��c��/26
�a�����i��/26
��/26
���ݐ�/26
����/27
�ɖ�g��/27
���Ԑ�/27
�V�L�_�~�߁E�h�k���߁E
�@�@����̓�/27
�g�x�@�萅�̉�/18-27
����椕�
���̔䉮�̕I�|�ɏA����/28
��S�N�O�̉�㊂̔�s��/28
�A���ʂɂȂ�܂�/29
�A���̐���/29
���̉��ҖA��/29
�ҏS��L/30
�E
�E |
�R���A�������Z����w�}���ψ���ҁu�������Z����w�����I�v (27) �v���u�����Z����w�v���犧�s�����B�@pid/1769716
|
�閽�Əُ��� / ���ѕq�j/1
���z���̕ۍb�@�ɂ��� / �O�c�i/21
��ꎟ���E���ƃh�C�c�m���l�Q���\�\�s���I�G�[�g�X�̕���(��) / ���g�F�B/31
��e�̗c�t�����ɑ���{��ӎ��\�\1��3�c���̐_�o���K�Ȃ̗L���̔���(����3) / �ē���Y/1
�s��������̊ϓ_����̗c�t������2�T��3�Q�ւ̕��ށ\�\�є��m�̐��ʉ����_�ɂ�� / �e����/9
�_�C�i�~�J����CP�̎����I�j�� / �e�쏇�q/31
�����m�[�g�w�l�d�V�ԁx�Ɍ����鍕���]�ȉ��E�����̈�l�@ / ���c�G�v/39
�������s�̗c�t���ɂ����颉��y���Y����ɂ��Ă̒����� / �~�����q/55
����{���k���̎������\�\���������Ԃ̎�����(3) / ���эK�j/87
�s�A�m�̂��߂̃��v�\�f�B�[ / �����Y���Y/101
����̎q���̂������u�s�A�m���ȏWVIII.�v / ���{�M�v/119 |
�R���A �Y�R����,����P,���R�f�u���{���z�w�����. �����E��B�x��.
2, �v��n (5) p.373-376�v�Ɂu���J�Ɖ��ɂ��Ă̎��_(II) : �Ă艮�̏ꍇ(���j�E�ӏ�)�v�\����B
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (7) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B pid/3467950
|
�� / �O�Ԑ��K
��㊌Q���̗�����ޑ�(I) / ���R����/p1~8
�w�䓖���䍂������[���ϋL�x�L�ڎ����N�\ / �c���C ;�������� ;�n���얾 ;���Ð����Y/p9~14
�����Љ� �������t�����M�̂��ƂȂ� / �{��Đ�/p15�`21
�v�ē���]�F�e�_��́u�ƋL�v / ��]�F��/p1�`37 |
�R���A�u���ꌧ�Ў��E��x�ђ����� 4�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@
�@�@�@ (���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��21�W) �@�@�@�@316p�@�����F��㊌����}���فF1001567484
|
| �m�� |
���ꌧ�Ў��E��ԗђ����� |
���s�N�� |
�����n |
���� |
| 1 |
���ꌧ�Ў��E��ԗђ����� 1�@
(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��15�W)
120p �����F��㊌����}���فF1001567450�F |
1978-03 |
���������̎�Ȍ�菊�̐A��1 |
�V�� �a�� |
| �X���������菊�т̐A�� |
�V�[ �`�n |
| �������̌�菊�т̐A�� |
�V�[ �`�n |
| ���A�m���̌�菊�т̐A�� |
�{�� �N�� |
| ���������̎Ў��E��ԗт̐A�� |
���z ���� |
| �����S����v��Ԃ̐A�������� |
�V�� �S�v |
| 2 |
���ꌧ�Ў��E��x�ђ����� 2�@�@
(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��18�W)
210p�@�����F��㊌����}���فF1001567468 |
1979-03 |
�{�����̌�菊�̐A�� |
�{�� �N�� |
| �^�ߏ鑺�E���A���̌�菊�̐A�� |
�{�� �N�� |
| �ΐ�s�̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���� �D |
| �Î�[���̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���� �D |
| �ǒJ���̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���� �D |
| �k�J���E�X��p�s�̎Ў��E��菊�т̐A�� |
�V�� �a�� |
| �k���鑺�̎�Ȕq���̐A�� |
�V�[ �`�n |
| ���鑺�̎�Ȍ�菊�� |
�V�[ �`�n |
| �������̎�Ȍ�菊�� |
�V�[ �`�n |
| �L���鑺���̌�Ԃ̐A�� |
�{�� ���� |
| �ߔe�s���̎�ȎЎ��E��Ԃ̐A�� |
�{�� ���� |
| �앗�����̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�� �`�� |
| �����S�E���K�S����v��Ԃ̐A�������� |
�V�� �S�v |
| 3 |
���ꌧ�Ў��E��x�ђ����� 3�@
(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��20�W)
432p�@�����F��㊌����}���فF1001567476 |
1980-03 |
�ɕ������̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�� �`�� ���� �D |
| �ɐ������̎�Ȍ�菊�� |
���� �D �V�� �`�� |
| ���[���̎�Ȕq���̐A�� |
���v�{ �� |
| ��u��s�̎�Ȍ�菊�� |
���� �D |
| ����s�̎�Ȍ�菊�� |
���� �D |
| �Y�Y�s�̎�Ȕq���̐A�� |
�{�� ���� |
| �����������̌�菊�̐A�� |
�쉮���h�q ���z���� |
| �m�O�����̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���z ���� |
| �ʏ鑺�̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�� �`�� |
| ��u�����̌�菊�̐A�� |
�쉮�� �h�q |
| �v�ē��������̌�ԗ� |
�V�[ �`�n |
| �v�ē���u�쑺�̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���z ���� |
| �n�Õ~���̎�Ȕq���̐A�� |
���v�{ �� |
| ���Ԗ����̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���z ���� |
| �������̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�� �a�� |
| �k�哌���̎Ў��̐A�� |
���v�{ �� |
| ��哌���̎Ў��̐A�� |
�{�� ���� |
| ��X�����̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�� �a�� |
| ���ꐼ��������v��Ԃ̐A�������� |
�V�� �S�v |
| 4 |
���ꌧ�Ў��E��x�ђ����� 4
(���ꌧ�V�R�L�O�������V���[�Y ; ��21�W)
316p�@�����F��㊌����}���فF1001567484 |
1981-03
|
�ɍ]���̎�Ȍ�菊�̐A�� |
���� �D ���z���� �{��N�� |
| ����s�̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
�{�� �N�� ���� �E |
| ���~���̎�Ȍ�ԋy�єq���̐A�� |
�V�[ �`�n |
| ���ǎs�̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
��� �M ���z ���� |
| ��Ӓ��̎�Ȍ�ԐA�� |
��� �M ���z ���� |
| ��쑺�̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
���� �D ���M ���z���� |
| ���n���̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
���z���� ���� �D ��� �M |
| �ɗǕ����̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
���z ���� ���� �D |
| ���NJԑ��̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
���� �D ���z���� ��� �M |
| �Ί_�s�̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
�V�� �a�� |
| �|�x���|�x���̎�Ȍ�菊�т̐A�� |
�V�� �`�� |
| �|�x�������̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
�V�[ �`�n |
| �|�x�����l���̎�Ȍ�菊�̐A�� |
�V�[ �`�n |
| �|�x�����\���̎�Ȍ�Ԃ̐A�� |
�{�� �N�� |
| �|�x���g�Ɗԓ��̌�ԗ� |
�V�[ �`�n |
| �^�ߍ����̌�� |
�{�� ���� |
| �擇�Q���̎�v��Ԃ̐A�������� |
�V�� �S�v |
|
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (3)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@pid/7955132
|
����{�������ꑺ���ɂ������̕ω��Ƃ��̘_��/�Ί_�݂��q/p1�`10
�w�������R���L�x�L�ڍ��J�̐��i�Â���
�@�@���ւ���\���I�l�@ / �Ôg���u/p11�`19
���ꏔ���ɂ�����_�̂̐����l�� / �����/p21�`30
����̕��� / �n�����q ;�A�����q/P31~36
�����Ă��Ղ�ɂ��� / �X�ۉh���Y/p37�`42
�u�v���ꂱ�� / ��]�F��/p43~48 |
�l�ƌ|�p ��ÍN�Y�̎d�� / �N�㌳�Y/p49�`50
���d�R�n���ɂ�����N���s�� / ���ǖL��/p51�`61
���d�R�Ί_�s�약�̎Y��ƍ���/���Ð^�X��/p63�`74
�v�����̌������| / �茴�P�V/p75�`83
�v�������������u��ʁE�^�A�E�ʐM�E���Ձv/����G��/p85�`86
����W�����ژ^(���a54�N) / �{����/p87�`93
�E |
�R���A�R���ӈꂪ�u�����w�������I�v (�ʍ� 5)�@ p.p101�`149�@�����w�����w�������v�Ɂu�����̃��^�̐��ނ̖��--��,�O�̎����ʂ��āv�\����B
�R���A�u���i�Ǖ����������v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
�@�@�@ (�n�挤���V���[�Y ; no.2)�@�@pid/9774016
|
���� �ʖ��F�Y/1
����Ɖ��i�Ǖ����Ƃ̗��j�I�W �{��h��/3
���i�Ǖ����\���̒n���I���i�\ ���O����/11
���i�Ǖ��̐�j�╨ ���{�A��/21
���i�Ǖ����̐����p �ʖ��F�Y/49
���i�Ǖ����̌o�ςƔ_�Ɓ\�v�ē��Ƃ̔�r�\ ���ԑגj/53
���i�Ǖ��̑哇�ې��Y �O�֗��v/65
���i�Ǖ����̋��� �쌴�S��/73
|
�����̐��� �Ό�����/77
���i�Ǖ����̔N���s�� ���R��/79
���i�Ǖ����̕��� �����r�O �쌴�O�`/87
�I�C�`�������g�D�C�W �g���E�v/107
���i�Ǖ����̉��~�тƊC�ݐA�� �{��M��/119
����y�щ����n���̍��q���z �R���③/133
�����c���� ���n�N�v/147
�E |
�R���A�u�n�挤���V���[�YNo.3�u�g�Ɗԓ��������v�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����Bpid/9774167
|
�����@���{�A�q ��1982-03�@p1-
�g�Ɗԓ� : ���̒n���I�T���@���O���� �@p3-8
�g�Ɗԓ���simana : <����>�@�쌴�O�` p 9-18
�g�Ɗԓ��̖L�N��(�v�[����)��
�@�@���F�N��(�A�~�a�����[)�@���R�� p19-38
�g�Ɗԓ��̔_�Ƃƃ��C�̈Ӌ`�@���ԑגj p39-58
|
�g�Ɗԓ��̋��Ɓ@�@�쌴, �S�� p59-66
�g�Ɗԓ��E�Ί_���E���\���̋����X�Ƒ����\���@���m������,���O���� p67-76
�g�Ɗԓ��̒n��I�����Ɛ푈�̌��@�Ό����� p77-88
�����a�J�ƃ}�����A�@�@���n�N�v p89-94
1910�N��`1930�N��ɂ�����g�Ɗԓ��̐����@���n�N�v p95-104
�g�Ɗԓ��̐A���T�ςƓ������@�@�{��M�� p105-123 |
�R���A���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���ҁu���킴 �n�����v���u�i�Y�Y�j���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���v���犧�s�����B
�@�@71p �@�@�����F��㊌����}���فF1001528171�@�d�v
|
���� ���g �^�O�^��
���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���ݗ���ӏ�
�
|
���ƌo��
���ł����{�E�Õ������̏C�� / ���Ԍb��
����������̏C�� / �O�c�F��
|
�ނ̐ڒ��ɂ��� / �R���③
�����̋��Ε��Ƒ�{ / ���g�^�O
�������̏C���ƕۑS / ��]�F�q�v
|
�@�@�@�@�@�@���@�R���ȍ~���炪���m�F�Ȃ̂Ŋm�F���K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�U�E�Q�@�ۍ�
�R���A����|�\�j������ҁu����|�\�j���� ��5���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004249593
|
�I�������y���O�������y��(���O) ���g�� ����
����̉̌��Ɩ��w �Î�� �d��
�`���|�\�̕ۑ��ɂ��� �c�c �� |
�������̃}�[�X���[�ƃE�t�W���[�^�[ ���� �P�ܘY
�����Љ�
�Ί_�s���Ə����{�u�ɑc�̎q�g�v ���� ��Y |
�S���A �n�v�n�����u�n��J�� (�ʍ� 199) p.p64�`70�@���{�n��J���Z���^�[�v�Ɂu���d�R�����̎��R�� (����V�}������<���W>
; �n��Љ�̒m���\�������̂��߂̒m���Љ�w--�������������𗬂̌��_�Ƃ���)�v�\����B
�T���A �w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 17(2)(55)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437769�@�d�v
|
������A�� / ���a�c�^�~/p1~12
�h���K�E�g���`�l--�쓇�N���s���̍\�� / ����d�N/p13�`28
�������l / ���ʐ��C/p29~39
�����{�Õ����̓����I�~�`�̐��� / ���Ð^�O��/p40�`58
��㔽�����Q�\���a���Q��(������u�\�e�c�n���v��)�ɂ�����
�@�@����㊌��̔_�Ɛ��Y�̍\���I����--�_���I�������Y�̕��͂�
�@�@�����S�Ƃ��� / �약���Y/p59�`87 |
����d�N�u�쓇�É̗w�̉̌`�̌n���v��
�@�@���ւ����̋^�� / �g�Ɗԉi�g/p88�`95
�n���C�̗���2 / �O�Ԏ�P/p96~105
�������c�搶������ / ��l�G��/p106�`111
����u��㊕�������܁v�ɂ���/p112�`113
�w�E�j���[�X/p12~12
�V���Љ�/p28~28 |
�T���A���{�̗w�w��ҁu���{�̗w���� (�ʍ� 20)�v���u���{�̗w�w��v���犧�s�����B�@J-STAGE
|
���{�����ɂ�����̗w�̋@�\�@�@��Y�F�M p.p1�`5
��ڗ��̂��̗w�I���i�@�@���R�� p.p6�`10
�Ǖ��߂̌����ɂ��ā@�@��쌚�� p.p11�`15
���́u��v���Ȋ��v�̐����Ɣ�鏕���@�O���v�] p.p16�`20
�����x�̂ɂ������̖��_�@�^�珹�O p.p21�`26
��a���̂��Ɓ@�@�q�c���M p.p27�`34
�V�����ɂ�����u�������v�̌����@����G��,�������l p.p35�`43 |
�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@-2-�@����x�� p.p44�`54
�G���u���w���l�v�ɂ��ā@�㑺���� p.p55�`59
�q���k��r"���{�̗w�w��̂����"�@��쌚�� �� p.p60�`74
��쌚��,�Έ䏇�O,�P�c�r�ܘY,���c���q,��v�Ԋ��Y,�g��p�j,
�@�@���V�Ԑi��,�{���L�F,���H�C�Y,���c���i,���V�u
�@�@��,�O�����Y, �����ǂ��O���@�@ p.60-74
�E�@�@ |
�V���S���A������炪�S���Ȃ�B�@�i���N�F95�j
�V���A�u�� 55(7)(652)�v���u�V����,���{��ʌ��Ёv���犧�s�����Bpid/7887901�@�@�d�v
|
4�F�n�} ����{���K�C�h�}�b�v
�@�@�����ꌧ����ʃ}�b�v/�������}������/p89�`92
2�F���ʃK�C�h 26�̗��� �R���v���[�g�E�K�C�h/p93�`108
���d�R�� �Ί_�� �|�x�� ���� ���ԓ� �g�Ɗԓ�
�@�@���V�铇 ���l�� ���\�� �^�ߍ���/p93�`100
�{�×� �{�Ó� �r�ԓ� �ɗǕ��� ���n��
�@�@�����NJԓ� ���ԓ�/p101�`103
�c�NJԗ� �n�Õ~�� ���Ԗ��� ���Ó� �c���ԓ�/p104�`105
�{�����ӂ̓��X �ɍ]�� �v���� �v�ē�
�@�@���ɕ����� �ɐ����� ��� ���[��/p106�`108
�J���[�O���t �����o���������E�{���k�����C�� / �����Y��/p9�`16
�J���[�O���t �C�ƎX��ʂ�... / �O☐���/p18�`22
�J���[�O���t ���Ȃ铇�E�v���̍Ղ� / ��ÍN�Y/p25�`30
�J���[�O���t �ߔe���X�U�� / �������W/p35�`40
�J���[�O���t ���d�����̓��E�r�ԓ� / �X�c�ėY/p41�`47
�J���[�O���t �Č� / ���Ǖq�F ;���Ð����Y/p145~148 |
�{�����W�L�� ����ݑܗ��s / ���c�M�q/p60�`65
�{�����W�L�� �^�ߍ��� / �����a��/p66�`73
�{�����W�L�� ��������K�˂� �ɕ������A�ɐ����� / ����/p74�`79
�{�����W�L�� �u�͂��ނ�Ԃ��v�̋x�� / �˓��m�q/p116�`119
�{�����W�L�� ���R�U�̔M���釁�͍�... / �ɍ���q/p120�`125
�{�����W�L�� ���{�l�̃��[�c�Ɖ��� / ��闧�T/p126�`129
����m�[�g�E���̃G���T�C�N���y�f�B�A �����|�\���� / �R����/p130�`131
����m�[�g�E���̃G���T�C�N���y�f�B�A ���̔m�Ԏ��ċ� / ���c��/p132�`133
����m�[�g�E���̃G���T�C�N���y�f�B�A �C�ƃT���S�� / ���c�ƗY/p134�`135
����m�[�g�E���̃G���T�C�N���y�f�B�A �����A���� / ��������/p136�`137
����m�[�g�E���̃G���T�C�N���y�f�B�A ����l���l / �V���b��/p138�`139
�ߔe�^�E���K�C�h/p109~112
�^�C�v�ʁE����c�A�[�K�C�h/p112�`113
������A�E���E�J���g �Ă̍Ղ�E�����E���E�����ŋ��E���w�E
�@�@�������K���X�E�C���I���e���}�l�R/p114�`115
�� |
�V���A����B�肪�u���R�w�� 29 p.86-87�@���s���R�Z����w�v�Ɂu�ܒ���l�̔��L��������o������l�̋��w�v�\����B
�W���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 46(8)[(594)]�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@pid/6059711
|
���b�̊��E���� �������b�Ə����ꂽ���b
�@�@��-�w��V���`�x�𒆐S��/�R���ӈ�/p94�`99
���b�̊��E���� ���b�ƕ��� / �����a/p100�`106
���b�̊��E���� ���b�ƌ�蕨
�@�@��--�@�̐��o���߂�����/���c�W/p107�`115
���b�Ɠ`��/p117~149 |
���b�Ɠ`�� �ߐ����O�@���̐��b / �{�c�o/p118�`124
���b�Ɠ`�� �O��̉��N / �H�t���q/p125�`131
���b�Ɠ`�� ���O�͂̐��b�Ɠ`��--�_�y�Օ��̐��E / ���䐳�O/p132�`138
���b�Ɠ`�� �Δn�ӑm�̃T�������Ƃ�--�s�҂̐��A
�@�@���T�����̐� / ���R����/p139�`149
�� |
�W���A�����V��Еҁu�����[���ՑS�W 9�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/9773719
|
��w�_�l/1
������k�\�����ꖼ���`�i����e�j�\/3
�b���[���Ր搶�̉����w�u��/82
���䓿���\�����ɂ�����S�g�����O�Ȏ�p�̑n�n�ҁ\/96
鰎m�N�̊O�Ȏ�p/103
�㐶���K���L�O��/107
�㐶���K�����\���N�Ɋ�/109
����{���Ƃ��̒���/111
�]�`/135
�ɍ]�N������/137
�ɍ]�N�̎��ǂ�/140
�ɍ]�����N���Â�/143
�r�{�N�̌����ƎO������ӂ̕Ғ�/145
�O�������{�ƒr�{�N�\����y�@�̐��������X�s���\/147
�ɔg���Q�N�Ɓu������v/150
�u������v�̕��ɔg�N�̌����ԓx��
�@�@���]���āu������v�V�l���N�Ɉꌾ��/153
�{���钷�ɔ䂷�ɔg���̌���/155
�ɔg�N�̑z�o/157
�ɔg�N�̈⍜���̎R�Ɍ}�ւ�/160
��������/163
���߂���/165
�����ǐm�y�@������/169
���������}�������鐴��/171
�u�쉮�F�M�N������/174
���܌����N��������/177
���{�̍�����s���\���ܑS���N�Ƃ��̋Ɛс\/181
���䖾�B�N/186
�̒��{�����N/188
�������̑z�o/193
��Ð��͌N������/195
�O�Ԍ���/198
���g�N�a�N��ߔe�s���ɐ��E��/201 |
���A���g�N�a�N/203
�g��h�̏��Ɖi�g�̚�/206
�R���i�g�N�Ɣ�����/208
���]/211
������N�j�̕����ɂ������/213
�������m�̇�����V�w�k�̎�L����ǂ�/215
�����n���������Љ/221
�w�����x��ǂ�/225
���㔘��/227
����/245
���i�x�����`���w�������@����x�j/247
����(Bull,E.R.�w�y������O�̕����w���� �����ߓ`�x)/250
�C���K���`���E(Bull,E.R.�w�y������O�̕����w���� �����ߓ`�x)/253
��i�O�؉h�w������ʎj�l�x�j/258
���i�y���琴�w�������y�l�x�j/260
���玁�H�H�l���i�ɍ��쐢���E���獑�j�w���y�����H�H�l�x�j/267
���i�O�؉h�w�R�c�����x�j/269
���i���H���Y�w��s�ƕ����x�j/272
���i�^�h�c���N�w�����ŋ�����x�j/275
���i�r�{��P�w�����O������Ӂx�j/279
���ɂ����āi�w���ܑS������W�x�j/281
���Â݂̔����Ɋi��B��w�}���ٌ㉇��w���Â݁x�j/287
���a�����L���i����Ɠ`�j�ɑ肷/289
���i�����Џ��w���y�����X�����H�H�l �S�x�j/292
���i�R�����j�w�����̉��y�|�\�j�x�j/300
���M/303
�z�o���l�E���E��/305
�̎R�_�`/502
�킪�ڂŌ�������/528
������������/539
���̖ڂŌ�������/546
���/1
����/15 |
�X���A���a�c�^�~���u����ƒ�͔|�Ɩ���v���u�V���}���o�Łv���犧�s����B�@�@ 1447p
�P�O���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 18(1)(56)�v���u��㊕�������@�@pid/4437770
|
��e
�̏�̉� / ��Éh�q
�́@��Ït���搶����
I �̔�Ït���搶���ʎ�/p5~13
�Ǔ��̎� / �����l�Y/p5~7
��Ït�����Ƃ̕ʂ� / ����D�v/p7�`8
���킩��̌��t / ����F�q/p8�`9
���ʂ�̂��Ƃ� / ���{�O�v/p10�`11
���� / �V���b��/p11~13
���Ԗ���/p14~14
���d/p15~26
���ʎ�������/p26~26
II �Ǔ��̕��\�\��ꕔ/p27~33
�t���搶�𓉂� / ��������/p27�`27
��㊋ߑ�̋�����Ït�� / �L���nj�/p28�`30
��Ït�����Ɖ�㊌��� / �����N/p30�`31
��㊂̋�����������Ït�����𓉂� / �O�Ԏ�P/p31�`33
III �Ǔ��̕��\�\���/p34~67
���_�Ƃ��Ă̑��� / �V�얾/p34�`36
�t���֑ɗ� / �ΐ쐳��/p36~40
�t���搶�̂��� / ���{�b��/p40�`43
�ӔN�̔�Ït���搶 / ����O/p43�`44
���ʂ�̂��Ƃ� / �K�n�V��/p45�`47
��Ït���搶����̂��莆 / ��l�G��/p47�`50
�t���搶�̎v���o / ���@�����P/p50�`54
��z�̔�Ït���搶--"���̎���"��
�@�@���W���݂ƂƂ��� / �䉮���ƕv/p54�`57
��㊗��j������̂��ƂȂ� / �R�䏻�q/p58�`61
���������Z���^�[�̂��� / �g�c�k��/p61�`62
��Ït���搶�ƃn���C / �N�쐴�h/p62�`67
IV �Ǔ��̕��\�\��O��/p68~104 |
�t���搶�Ǝ� / ��������/p68~69
�t���搶�Ǝ� / �V��S�v/p70~71
�t���搶�Ǝ� / �V�萷�q/p71~74
��㊎j�̗ǂ������ / �r�{��G��/p74�`75
���W�I���������ʂ� / �Ζ�a��Y/p75�`77
�t���搶�Ǝ� / ���Z���/p77~78
�t���搶�Ǝ� / ��闧�T/p78~79
��Ït������̂��� / �員���F/p80�`81
�����b / ��[�@��/p81~83
�۔�̐e��--�t������Ǝ� / ���g�^�N/p83�`85
�t���搶�Ǝ� / ���ʐ��q/p85~87
�t���搶�̂��� / �Ôg�q����/p87�`88
�t���搶�Ǝ� / �茴�v/p88~90
�t���搶�Ǝ� / ���K�����Y/p90�`91
�t���搶�Ǝ� / ���ܑS�K/p91~93
�t���搶�킪���Ɍ��� / ��ԓ��h/p93�`95
��Ït���搶�Ǝ� / ���a�c�^�~/p95�`97
�t����������̂��� / �����r��/p97�`98
�t���搶�Ǝ� / �������b/p99~100
�w��㊂̗��j�x�̏��� / �����Y/p101�`102
�t���搶�Ǝ� / �������d/p103~104
V �}�X�R�~�ɎÂԔ�Ït���搶/p105~115
�ɂ��� / �C�Z�a�j/p105~106
�u�ЂƁv���@��Ït���@�Ԋҋ�����^�⎋���鉫㊗��j�w��/p106�`107
��������㊂̐S/p107~108
�u�V���l��v��/p108~109
�u�A�V���M�v��"�]�E�N�t���V........."��/p109�`109
�t--�j���[�X����/p110~115
������������ / ��Éh�q/p116�`123
��Ït���I ���̏W/p124~148
���Ƃ���/p148~150 |
�P�O���A�R���ӈꂪ���{���w����ҁu���{���w 30(10) p.p20�`30�v�Ɂu�쓇�̗w����݂��镗�y�L (���y�L--翂���̔��z<���W>)�v�\����B
�P�O���A���ꕶ������ҁu����̖��������v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9774070�@�@�S�O�O�~
|
����̓y���v�z�ƕ��� �q�`�ĎO/2
�����ʂƖ{�B��/6
��ꕔ ���R�Ɨ��j
����̎��R��
�@�@����j�Ñ㕶�� ���{�L�q/10
�`�쌴�l/12
�ŗL�̓y�핶����/13
�Òn��/14
�C�m�����Q/15
�X���/16
�����̒n�`�ƍ\����/17
����̒n��/18
��� ����̐M�E�Α�����
����̐M�� �����\�G/20
�E���K���Ղ�/22
�j���C�J�i�C�M��/24
�E���W���~/25
���[�N�C�i����j/26
�L�N��/27
����o�[���[/28
�J�[�i���j/29
�y��N/30
�r�W����/31
����/32
�Ί���/33
����/34
�g�[�g�[���[/34
�~���g���O�X�N/35
�A�[�`�i�Α���j/36
���ю�/37
�X��̌��/38
�Ƃ̖�����/39
���~�_/40
�V�[�T�[/41
�����̎��_������/42
���c�̂��ʂ�/43 |
�������炵/43
�C�U�C�z�[/44
��O�� �C�O�𗬁E�����̐ێ�
����Վ���̉��� ���Ǒq�g/46
�����̊C�O�f�v�}/48
�i�v�D/49
�|���g�K���n�}/50
���ߏ�/51
���B/52
���j��/53
�����/53
�ߔe�`�}/54
������/55
�蕶�i���܌��j/56
��K��/57
�T�b��/58
�T�g�E�L�r/59
�C��/59
��l�� �����Ɛ��Y
����̎��R ���{�b��/62
�� ��]�F��/63
�t�N�^�[/63
�m�ԕz/63
�h�^�e�B�[/64
�v�t�}/64
�~�m/64
�Q�^/65
�T�o/65
�H ��]�F��/66
�J�}���^/66
�z����̖��p/67
�i�r�Q�[/67
�q���E�^���̃q�V���N/68
���`�E�u�T�[/68
�ΉP/68
������/69 |
�A���_�K�[�~/69
�V/69
�ٓ��d/70
�ٓ���/70
���[�V��/70
�E�~�t�]�E/71
���i�o�[�L�[/71
�w���J�S�i�K���V�i�[�j/71
�Z ��]�F��/72
�z�[�`/72
�P�[/72
�j�N�u�N/73
�~��/73
�`�[�i��ׁj/73
��/73
�����v/73
�N�o�I�[�W/74
�T�M�W���[�L�[/74
���q/74
�_�� ���{�b��/75
�N��/76
�N��/76
�X�L/76
�I�[�_�[/77
�w��/77
�T�[�^�[���[/77
���� ���{�b��/78
��/78
�T�o�j/79
���K�l/79
���[�g�C/79
�ǂ�������/80
�l����/81
�����Z/81
�̎���/81
���`/82 |
�}�X�E�\���o��/82
��/82
�l���� ���{�b��/83
��ܕ� �|�\
�����̌|�\���� �r�{���_/86
�x��ߏ�/88
�g�^/89
�x��̏�����/90
��O�x�i���Ă��߁j/92
�V�l�x�i�������j/93
���x�i���������j/94
��˗x�i�ア�����j/95
�����q/96
�G��/97
������/98
���S����/99
�H�H�l/100
�F�s�̊�/101
�쓇�̗w�听/102
�������/102
�j��/103
�n�[���[/104
����/105
�O����/106
�]�ˏ��/106
�A���K�}/108
�N�B�`���[/109
�����x��/110
��Z�� �����E�̗w
���� ��������/112
�����낳����/112
�������W/114
�̗w ��������/115
����̔N���s���ꗗ/117
���Ƃ���/124
�E |
�P�O���A�쑺���ꂪ�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 82(10) p.p62�`65�v�Ɂu��ÍN�Y�ʐ^�J�쌒�ꕶ�u������ �������̍Ձv�v���Љ��B
�P�P���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (17/18)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4419227
|
����<���W>/p1~251
���W ���� �����哇�̍k�n���x�Ɣ_���̗��ɕ���--���Ƃɍ����ꔄ���̒ב��ƉƐl�̔����ɂ��� / �����Y/p1�`33
���W ���� �m���ƃ��^--�����̉�ڂƓW�](1) / �R���ӈ�/p34�`51
���W ���� �����̃��^�Ƃ��̎���--�V���}�j�Y���Ɖ��y / ���c���q/p52�`67
���W ���� �������̐����ϓ��Ə@�� / ���V�L/p68�`94
���W ���� �������w�ɂ����鎌�^�E�Ȍ^�E�����^�̕ϑJ--���̒��̐������l���邽�߂� / ����w�v/p95�`109
���W ���� �o�n�Љ�̐e���̌n--�^�_���ɂ�����e���ĕҐ��̍\�� / �������t/p110�`143
���W ���� �����哇�̐�j��� / ���R����/p144�`155
���k�� ���������̌���ƓW�] / �������� ;�R���ӈ� ;���q��ꗲ ;���c�� ;�E���� ;��ӋԈ� ;�������t ;���R�{/p156~187
�_�� L�E�h�D�[�_�[���C���̉������� / J�E�O���C�i�[/p188~198
�_�� �{�Ó��ɂ�����V������e�Ɗ�w�@�� / �������u/p199�`221
�_�� �V�}�Љ�ɂ����鋤�H���s�ɏA���Ă̈�l�@--�����̎O���ƈ�d��r����|����� / �[��G�v/p222�`251
���]�ƏЉ� / ���R�{ ;���Ð^�O�� ;���N�m/P252~259
���ꌧ����ψ���ҁu���ߏ����Õ����������v(���ꌧ��������������\���W)
�@�@��,���ꌧ����ψ���ҁu���d�R�����𒆐S�Ƃ����Õ����������v(���ꕶ������������O�\�W)
/ ���R�w/p252�`255
�O�Ԏ�P���u���{��̐��E9�E����̌��t�v / ���Ð^�O��/p256�`258
�쓇�W�����ژ^ / ��R���F/p260�`264
���/p264~265
�u�쓇�j�w�v���ڎ�(1��~16��)/p266~268 |
�P�P���A�{�c�������|�\�w��ҁu�|�\ 23(11)(273) p7�`7�@�|�\���s���v�Ɂu����������d�R��{�Â̌������|��v����B �@pid/2276468
�P�Q���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.7�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�@68p �����F���ꌧ���}���فF1003063888 �@�@�ŏd�v�@
|
����E���ԑ��L�ˍ̏W�̐Ί� ���� ���� �Ð� ���� �O�� �i�^��
������쓇�o�y�̊L������ɂ��� �㌴ ���^��
�L���e�포�l �؉� ���q�^�� |
�ҔN���Ă̈ꕔ�C���ɂ��� ���{ �A�ʁ^��
���ꌧ�ɂ����閄���������̊�@ �{�� ���M�^��
�E |
�P�Q���A������q,�ԏ�m�q���u������w����w���I�v ��� (25) p49-91 �@������w����w���v�Ɂu�A�W�A�̖������x�Ɋւ����r���x�w�I���� : ���x����̕\�����Y��
(3) : �������x�E���{���x�E�C���h���x�̋ؕ��d�y�ьċz�p�^�[���ɂ��āv�\����B
�@�@�����ȉȊw������⏕���������ʕ�
|
���^�^�A�W�A�̖������x�Ɋւ����r���x�w�I���� : ���x����̕\�����Y�� (3) : �������x�E���{���x�E�C���h���x�̋ؕ��d�y�ьċz�p�^�[���ɂ���
(1)1.�u���ޓ���v�̋ؓd�}�́A�������x,���{���x���ɁA�����̋ؕ��d�����̋،Q�`��]�E�m�X�E�̊��N���E�O���E�L�w�`�̕��d�ɔ�ׂĎア�B����ɑ��A�C���h���x�ł́A�ނ���A�����̕������̌Q�ɔ�ׂĕ��d�����������Ă���B�܂��A�ċz�ɂ��ẮA�O�҂Ƃ��A��r�I�A�ċC�E�z�C���K���I�Ɍ�����ċz�Ȑ��������Ă���B(2)2.�u���������I�ȓ���v�ł́A�������x����́A�m�X�A��]�A�̊��N���̋������d�ɉ����A�O�����g�����u�˂��蓮��v���A�Ɠ��ȕ\����@�̂ЂƂƂ��ė��p����Ă��邱�Ƃ����@�����B(3)3.�u��������v�̋ؕ��d�́A�������x�ł́A�������������o�`�勹�E�m�X�E�O���E�L�w�`�Ɏ������d���݂���B����A���{���x�ł́A��Ƃ��āA�m�X�������A���̋،Q�͎ア���d�������Ă���B�܂��A�������x�Ɠ��{���x�ɋ��ʂȌċz�Ȑ��Ƃ��āA�������O�ɌċC�Ȑ��������A���̌�A���₩�ȉ��~����`���B�����餢�����߂�v��Ԃ�ۂ��Čċz���s�Ȃ��Ă���_����������B(4)�C���h���x����ɂ�����3.�u��������v�̋ؕ��d�́A���،Q�`�勹�E�m�X�E�����E�̊��N���E�O���`�Ɏ����I���d���݂��A��r�I�A�����ɋ��������Ă���B����A�ċz�Ȑ��́AJump up �ł͋z�C�Ȑ��A Jump down �ł͌ċC�Ȑ���`���Ă���B(5)4.�u��]����v�ɂ�����A�������x����{���x�ł́A�����̕��d�͋ɂ߂Ďキ�A�ނ���A�̊��N���Ɏ������d���݂���B�܂��A�C���h���x�ɂ����ẮA�t�ɁA�����ɔ�r�I�������d���݂���B�ċz�Ȑ��́A�������x�A���{���x����r�I�A�ċz�E�z�C�����Ԋu�Ń��Y�~�J���Ɍ�����̂ɑ��A�C���h���x�ł́A�܂��n�߂ɋz�C�Ȑ��������B���̂��Ƃ́A�O�҂����s�n�̂܂�蓮��ł���A��҂���]�n�̂܂�蓮��ł��邱�Ƃ���A���쎞�ɂ�����A���҂̌ċz�p�^�[���ɑ��ق������Ă�����̂ƍl������B�I�v�_�� |
|
������q�Ɖԏ�m�q���u������w����w���I�v���(23�`25)���\�����u���x����̕\�����Y���Ɋւ��錤���i1�`3�j�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
���e |
| 1 |
������w����w���I�v���
(23) p.p61�`86 |
1979-12 |
���x����̕\�����Y���Ɋւ��錤��--�������x�ƃC���h���x��EMG�p�^�[���ɂ��ā@
|
| 2 |
������w����w���I�v���
�i24�jp77�`101 |
1980-12 |
���x����̕\�����Y���Ɋւ��錤��-2-�������x����{���x��C���h���x�̋ؕ��d�y�ьċz�p�^-���ɂ���
|
| 3 |
������w����w���I�v���
(25)p.49�`91 |
1981-12�@ |
�A�W�A�̖������x�Ɋւ����r���x�w�I���� : ���x����̕\�����Y�� (3) : �������x�E���{���x�E�C���h���x�̋ؕ��d�y�ьċz�p�^�[���ɂ��� |
|
���A���̔N�A�u�}�����y�̂��炵�ƕ��� �����v���u�V���}���o�Łv���犧�s�����Bpid/9773683�@�㉺���g�@�T�O�O�O�~
|
�����
�L�ˎ���̉��� �m�O�E/10
����̗��j �c���^�V/28
���p ��鐸��/80
�Ђ��� ��ԗ�i/98
����̈�� ���Ԉ�Y/114
����̎� ��]�F�q�v/140
��Â��� �ҏW��/152
|
������
�����Ɖ��� �R���ӈ�/178
�����̓����� ���R�E�A�E���R����/180
�J���i���j �b���`���E
�@�@���ёh��j�E�d�]�ǕF/190
�J���i�C�j �R���p��/202
��ʁE�^�� �d�]�ǕF/212
���� ���R���q��E�ёh��j/218 |
�H�� �v���Ђ��/240
�Z���E���~�͂� �o�R�C/254
�M�� �R���ӈ�/260
�܂� �R���ӈ�E�ёh��j�E����w�v�E�b���`��/282
�l�̈ꐶ �ёh��v�E�o�R�C/300
�|�\�Ƃ����� ����w�v�E�ёh��j�E�b���`��/312
�}�ňꗗ
�E |
���A���̔N�A�u�C : ���R�ǖ{�v���u�͏o���[�V�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9671010
|
�J�����ӏ� �X�|�[�c�̊C
���C�Ł\���L�V�R�p���ʐM
�@�@���A�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C�^���c�k����/14
��㊂̃i�|���I�� ������/22
���v�C���� �����q�Y/32
�n������������!?�\�u�C�v �|����/38
�u�C�ց\�`���҂����v
�}�[���C�h�ւ̃��u���^�[ �x�]����/46
�}�[�����A�������� �X�e�t�@���E�c���@�C�N �֓퐶��/50
�C�̖`���҂��� �O��T��Y/61
�Ǖ��̃C���X�g�C�m�T���j �����Ǖ�/83
�Ȋw�̊�(1)�^�ю�Ƃ��Ă̍��� �O�D��/98
�u���݂����ʖ��m�v
���j���� �w�ۍ��k�� �G�[�Q�C�̑啬�� ���������^
�@�@����؏G�v�^�|���ρ^���{���g�^�쑺���/104
���̑嗤�S���h���i ���܂��X�V������m�� �ސ{�I�K/125
�C�̑��M�Ǝ��R���� ���Y���T/130 |
�C��̌Ñ㒤�� ���]�c�Y/144
�Ȋw�̊�(2)�C���̌��Ɖ� ����ʕ�/150
������̐��ҁu�т��Ƃ肠�ہv�ɂ݂�D���� �q�J���V�M/154
�Ȋw�̊�(3)�D�͖k�シ���C���Ɏア �{���x��/169
�u�C�ւ�Ȃ铹�v
�O�C�Ɠ��{�l �Ζђ���/176
���{�̋��� �{�{���/181
�C�̍K�Ə��̍K�� ���쐴�q/187
�Βk�Y�����̎v�z �R�c�@�r�^����G��/190
�Ȋw�̊�(4)�C�̔g ����ʕ�/204
�u�C����̓`���v
�A�t���J���̂Ȃ������q�C �k�m�v/210
�����m�������̂��̂ɂ�����@ �J����/218
���̉Ă��̊C ������/220
�C�̒��ɂ����ЂƂ̉F�������� �˓��m�q/221
�Ȋw�̊�(5)�A�N�A�����O���� �H�����j/224
���C�E�L�b�X���̑D�� �X�ɋv�\/235 |
|
| 1982 |
57 |
�@�@�@�@�E |
�P���A����s����ψ���ҁu����s�ÓT�|�\�ӏ܉� ���x��̂��ׂ� ���a56�N�x�v���u����s����ψ���v���犧�s�����B�@�@�@�@�@11p �@�����F��㊌����}���فF1004245997�@�i�����p���t���b�g�j
�@�@�@���a57�N1��16��(�y)�ߌ�6��30�� ����s����ّ�z�[�� ��ÁE����s����ψ���
�P���A���������ۑ�w�����n�摍���������ҁu����{���� (14)�v���u���������ۑ�w�����n�摍���������v���犧�s�����Bpid/7931794
|
1980�N�x�̓���{���������������� / �O�ؖ�/p1�`28
��E���̕\�� / ��،�/p29~41
�ߑa�n�тɂ�����"���m�J���`���A"�̌`���ƘJ���̑��ݍ\��
�@�@��--��E���o�ς̓W�J�ߒ��ɑ����� / ��������/p43�`73
�o���s�u�_�Ƃ̈ӎ������v�ɂ��� / �R�c���k/p75�`88
�o���s�_�Ƃ̌���ƌ��ʂ��Ɋւ���_���ӎ� / �R�c�W/p89�`103
�o���s�_�Ƃ̎q�ǂ��E����ɂ��Ă�
�@�@���ӎ��Ɋւ��钲����/��V�G��/p105�`112
|
�o������ɂ�����~�J���͔|�̓W�J
�@�@��--�o���s�E��c���̏ꍇ/�y�c�Lj�/p113�`126
�{�����̃E�V�f�[�N--�����A��X���A
�@�@�����v�u���Ƃ̔�r�𒆐S�Ƃ��� / ���ь��]/p127�`166
��㊁E�ǒJ���̂��ׂ��� / ���{�M�v/p45�`77
��E���̍�Ƃ����C�g�D / ���{�M�v/p33�`44
�������l�`��ڗ��̉��y�ɂ��� / ��������/p25�`31
�u�����G�X�q�܁v������ɖ|�� / ��X�k�`/p1�`23 |
�Q���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (19)�v���u�쓇�j�w�� �v���犧�s�����B�@pid/4419228
|
������������ǂ�--�L�E��x�E��Ȃ� / ���{���q/p1�`7
�����̖����Ɋւ�����������̏� / �R���ӈ�/p8�`19
��p�T�f�b�N���̋`�Z��Ǝq�ǂ��̔F�m / �R�H���F/p20�`44
�哇�ɕY�������������--��W����Ăɋ��� / �{�c�r�F/p45�`50
���������u�_�c�M�̌����v / �a�c�v��/p51�`56
�E�������u���������Ɠ쓇�v(�쓇�����p����ꊪ) / ���c��/p56�`60
���{���q���u�}�������ꎫ�T�v / ���Ǒq�g/p60�`63 |
�k�ĉ���l�j�ҏW�ψ���ҏW
�@�@���u�k�ĉ���l�j�v/��ӋԈ�/p63�`66
���]�ƏЉ� / ���R�{ ;����P/p67~69
�쓇�W�����ژ^(��55.3�`��57.5) / ��R���F/p70�`76
���/p76~77
�u�쓇�j�w�v���ڎ�(14��~17�E18��)/p79
�E |
�Q���A�u�g�Ɗԓ������� �v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
(�n�挤���V���[�Y ; no.3)�@pid/9774167
|
���� ���{�A��/1
�g�Ɗԓ��\���̒n���I�T�� ���O����/3
�g�ƊԂ�simana:�q�����r �쌴�O�`/9
�g�Ɗԓ��̖L�N�ՂƋF�N�� ���R��/19
�g�Ɗԓ��̔_�Ƃƃ��C�̈Ӌ` ���ԑגj/39
�g�Ɗԓ��̋��� �쌴�S��/59 |
�g�Ɗԓ��E�Ί_���E���\���̋����X�Ƒ����\�� ���m������ ���O����/67
�g�Ɗԓ��̒n��I�����Ɛ푈�̌� �Ό�����/77
�����a�J�ƃ}�����A ���n�N�v/89
1910�N��`1930�N��ɂ�����g�Ɗԓ��̐��� ���n�N�v/95
�g�Ɗԓ��̐A���T�ςƓ����� �{��M��/105
�E |
�R���A���ꎩ�R������ҁu���ꌧ���R���ۑS�n��w����n�w�p������ : �m�ԃO�X�N�E�֏��ԂƂ��̎��Ӓn��v���u���ꌧ�v���犧�s�����B�@�@130p�@�@�����F�}���o�^�ԍ��F1002238275
|
�� �V�� �S�v�^
����s�m�ԏ�Վ��ӂ̒n�� ��� ��N�^
�m�ԃO�X�N�̐A�� �V�� �S�v�^
�m�ԃO�X�N�̐A��
�@�@���V�� �`�� �V�c �@�� ��n �b�q�^ |
�m�ԏ�Ղ̓���
�@�@�����Ӗ� ���h �V�� �`�� �^�u�� ��q�^
�m�ԏ� ���� �����Y�^
�m�O���֏��Ԏ��ӂ̒n�� ��� ��N�^
�֏��ԋy�т��̎��ӂ̐A�� �V�� �S�v�^ |
�֏��ԂƂ��̎��ӂ̐A��
�@�@���V�[ �`�n ��n �b�q �V�c �@���^
�֏��Ԏ��ӂ̓��� �m�O ���r�^
�֏��Ԃ̍��J�Ɠ`�� �N�� ���Y�^
�E |
�R���A�������ҁu�����w:���߂Ɗӏ܁@47(3)�@���Љ��N�̐��E�@-���Љ��N60��<���W>-�v�����s�����B�@�d�v�@pid/6059718
|
���Љ��N�̐��E�@�ܗ��d�@ p.p6�`12
���Љ��N�̐��E�@p.p14�`33
�@�����_�b�Ƃ��Ă̎��Љ��N--�w�_���W�x�u�O���喾�_���v�𒆐S�ɂ��ā@�Ë��M�F�@p.p14�`19
�@�V�����ƌ��--���o�u����Ƃ��ہv�l�@��蕐�v�@ p.p20�`24
�@����肷��G�����Ǝ��Љ��N--���̊G��`�ԂƁu���������N�v�̂��� ���c�a�v�@p.p26�`33
�����Љ�Ǝ��Љ��N�@ p.p35�`63
�@�����Љ�ƎЎ����N--���@�ւ̔��Ȃ����߂ā@����D�N�@p.p36�`41
�@�_�̉��N�ƐE�Ƃ̗R��--�Y���ҕ����_���l�@�^��r�a�@p.p42�`46
�@�ω��M�Ǝ��Љ��N--�����̒n�Ɍ��钆�������̗���@���ْ��O�@p.p47�`53
�@�n���M�Ǝ��Љ��N--�������������M�̖�� �@�ΐ쏃��Y�@p.p54�`58
�@�C���Ǝ��Љ��N--�ܗ��C���́u�������R�v�𒆐S�Ƃ��ā@�{�Ə� p.p59�`63
���Љ��N60�� (���Љ��N�̐��E--���Љ��N60��<���W>)�@p.p65�`187
���Јē� p.p66
�A�C�k�̐_�b--�Ó���K�Ƃɂ܂���_�X�̗R���@�����v�a�ҁ@p.p67�`69
��؎R�@���c �� ���@�@ p.p70�`187 |
|
��؎R / ���c��/p70�`71
���R / ���c��/p72�`73
�H���R / �������q/p74�`75
���R / �������q/p76�`77
���a�R / �������q/p78�`79
��r�R / �������/p80�`81
�F�s�{�喾�_/���J�쐭�t/p82�`83
�ԏ�R / �ێR�m��/p84�`85
�����_�� / ���c��/p86�`87
�O��R / �Γc���v/p88�`89
�����_�{ / �����Z��/p90�`91
����_�{ / �����Z��/p92�`93
�� / �㑺���F/p94�`95
�����V�_ / �|���G�Y/p96�`97
�����_�� / ����w/p98�`99
�x�m�R / ����w/p100�`101
�O�����_ / ������/p102�`103
�����R / ������/p104�`105
�z�K�_�� / ����T��/p106�`107
�ˉB�R / ������/p108�`109
���R / �����K��/p110�`111
|
���R / ���ш���/p112�`113
���O�͂̎���/���䐳�O/p114�`115
�M�c�_�{ / �X���l/p116�`117
�ɐ��R / �_�쓡���v/p118�`119
�|���� / �X���l/p120�`121
�t����� / �ۍ�B�Y/p122�`123
�g��R / �ܗ��d/p124�`125
�M�M�R / �}�䏹��/p126�`127
������ / ���R����/p128�`129
������ / �_�쓡���v/p130�`131
���J�� / �O�J�M��/p132�`133
�O�֑�� / �X���j/p134�`135
�F��R / �ܗ��d/p136�`137
������ / ���R����/p138�`139
���͎� / �����T��/p140�`141
��Ύ� / �O�Y�C�V/p142�`143
�_�������V��/���c��b/p144�`145
�k��V�_ / �n�ӊ�/p146�`147
�M�D�_�� / �_�쓡���v/p148�`149
������ / ���c��b/p150�`151
�Ɣn�� / �_�쓡���v/p152�`153 |
�p���� / �O�J�M��/p154�`155
�l�V���� / �����͗Y/p156�`157
�Z�g��� / �O�Y�C�V/p158�`159
���{�ΐ_�� / �g�c�C��/p160�`161
���ˑ�R / �O�Y�G�G/p162�`163
�����_�� / �����T��/p164�`165
���h���� / ���䐳�O/p166�`167
���R / �c���P��/p168�`169
�� / �X���j/p170~171
�w�U�R / �g����`��/p172�`173
�p�F�R / ��_�M�/p174�`175
������ / �R���ۖ�/p176�`177
�ŗt�R / ���䐳�O/p178�`179
�����̎��� / �R���ӈ�/p180�`181
���� / �Î芡��ߎq/p182�`183
�{���������/�g�n�R����/p184�`185
���d�R�����ю�/�Ί_���F/p186�`187
�������N�ɂ���/�}�䏹��/p188�`189
�c�_�܂�Ǝ�/���n�R����/p190�`191
�E
�E |
�R���A��ÍN�Y, �N�㌳�Y���u����̐��Ȃ铇�X�v���u�o�ŎЁv���犧�s����B
(���{�̐���, ��7��)
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (8)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467951
|
�� / ��铿���Y
��㊓���O�I���K�w�Y�o�̃z�z�W���U������
�@�@���A�I�U�����̎� / ���P�\ ;����N/p1~7
���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(I) / ���a�c�^�~ ;�m�O�E/p9~36
�u�������v��ǂ� / �n���^��/p37�`40
|
���āE����G��j�N�\ / �{��Đ�/p41�`54
����������ޕ����ژ^ (�b��) / ���R����/p55�`88
�����Љ� �u�䏑�@�䕨���v(��㊌��������ّ�)�u��������v
�@�@��(��)�u�䏑�@���앗��a�䏰���v(��) / �n���얾/p1�`40
�E
|
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu ��㊕��� = The Okinawa bunka 18(3)(58)�v���u��㊕�������v���犧�s�����Bpid/4437772
|
�w�����ٕ����x�o�� / �n������/p1�`11
���[���̃��C�A�J�f�[�Y / ���ʐ��C/p12�`29
�u�\�e�c�n���v�̒f�� / �약���Y/p30�`47
�����{�Õ����̓����̐ڑ��` / ���Ð^�O��/p48�`64
�n���C�̗���(4) / �O�Ԏ�P/p65~74 |
�w�}�������ꎫ�T�x��ǂ��--�Ί_�����Ɋւ��� / �{��M�E/p75�`79
�V���Љ�/p64~64,74~74
���s�j���[�X/p79~79
���]/p80~83
�E |
�R���A�u�쓇���� 4�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B �iIRDB�j
|
�{�_���W�̂Ƃ�܂Ƃ߂ɂ������� :
�@�@�@����̓�����̎��̃��b�Z�[�W �ʖ��F�Y 4-9
�A���ƍ��� �@����ވ�Y p.5-10
�������{�̊O��p�A�� �@�{��h�� p.11-24
|
�A���Y�Ƃ̌���ƓW�] �@�O�֗��v p.35-58
�A���̏������ �@��Ì� p.59-74
���Q�ɂ��� �@�������Y p.75-88
����̎��ƕ��w : ��_�ƍՂ�@ ���R�� p.89-104 |
�S���A�����h�l�Y�A�L���nj����u ����̎��v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B
�T���A�_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (2)�v���u�_�ˏ��q��w�j�w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/4424468
|
�_�� �Ő��̓��R�O��̕���� / �M���萳�F/p1�`24
�_�� �����g�̌o�c���O / �ҐߗY/p25�`38
�_�� ���{�Ñ�s��̌��^--�k�M���E�l�������čl/�H�R���o�Y/p39�`84
�����m�[�g �����E�F���̐^�@�M�҂Ə�[���� / �m���芰/p85�`96
�w�E���� ���h�C�c�j�w�E�Ɓq�A�i�[���r�w�h / �������K/p97�`110 |
�u���Ɍ��o�g�̗��j�w�ҁv(���̈�)�ґP�V��/�ؑ����v/p111�`116
�V���Љ� �����a�Y���w���v�����j�_�l�x��
�@�@�����s���c�� / ���x�{�G/p117�`119
�j�w�Ȃ����/p120~121
�j�w�����/p121~122 |
�U���A�V�閖�F�����u���E (�ʍ� 439) p.p239�`248�v�Ɂu�����̃G�C�T�[(������N���k��) (���ꕜ�A��Z�N)�v�\����B
�U���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 9 (�@����w���ꕶ���������I�v
; 9)�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�@�iIRDB�j�@pid/9774202
|
����̊�����\�^�ߌ����q�𒆐S�Ɂ\ ��]�F��/1
���×̍��̕��\���n���Ɨ����̐� �n���^��/37
���A�i�����a���̖��_�̂��߂� �약���\/49
�|�x���̒b��`�� �㐨����/64
���d�R�̗w�̉̌`�̏��� �g�Ɗԉi�g/104 |
���d�R�̉ƕ��o�� �V��q�j/228
�쓇�ɂ����镨��I�̗w�̌����\�{�Ï����𒆐S�Ɂ\ ���a�c�����q/283
�k�����Љ�l
�h�C�c����D���̎�L ���n�]/375
�E |
�V���A���K�F�͕ҁu��� �V����N���s���v���u�썑���v���犧�s�����B �@�@�@�����F���ꌧ���}����
�V���A����|�\�j������ �ҁu����|�\�j���� ��6���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004237465�@�@164p
|
���̂Ə��w�@ ���̊ԓ����𒆐S�� �Ɖ� ���P
�ÓT���x��̉̋Ȃ̈ٓ����l���� ���� ��Y
���ꉉ���̒��̏����� �S�������̂Ȃ�����̗��� �Î�� �d�� |
�X�����ɂ��� �R�����j���u�����Ԓ�y���X�����v�̌��� �g�� ���S
�������@�̐��� �O���Ǝ��� ���g�� ����
�ĂђX���@�ɂ��� �c�c �� |
�V���A�n�v�n�����u�n��J�� (�ʍ� 214)�@ p.p18�`30�A p.p31�`37�@���{�n��J���Z���^�[�v�Ɂu����̓��ׂ̓����A���א��Ԍn�̓����Ɨ�������
(����V�}�������̌��_<���W>)�v�\����B
�V���A�u�ߑ㌚�z36(7)�v���u�ߑ㌚�z�Ёv���犧�s�����B�@�@�@pid/6046490
|
���z�E�̑g�D / ����Y/p13�`14
��2�k���z�܁A���a56�N�x�k�C�����z�܁A
�@�@����7��g�c�\���܁A�f�U�C���M�������[/p15�`15
���M�̌��i��-3-�����ꂽ�ꏈ / �k�X���/p16�`17
<���E�̍\��>--�ǂ̕ϖe-1-(��Ԙ_�m-�g-7-) / �ۍ�z��Y/p18�`19
���W1981�N���Ɛ���E�����|�p��w/p3�`17
������ �Â��ȕ��� / �ЎR�a�r/p18�`18
�Q���̌���-1- / ��c��/p19�`26 |
�V���[�Y���n�߂�ɂ�������/p20�`21
��/�֏��x-��-/p22�`26
���ѓ@ / �╣���c�������z�v������/p27�`38
LUCKNOW �k�C���h�̓s�s��K�˂� / �����E�m/p39�`52
���W�E���쌚�z�v������ ������w�A�ܓ��s�����ɁA
�@�@���{���s���S�g��Q�ҕ����Z���^�[�A�����w���A�D�c�w���ق�/p53�`74
�Z��̐��܂��v�͈�˒[���z����̒E�p���K�v / �������M/p75�`75
�}�e���A���R�[�i�[/p80�`81 |
�W���A�O�荎�v���u�k�̗��l�\����ɖ�����ꂽ���t�����O��̐��U�v���u�䒃�̐����[�v���犧�s����B
�@�@�@ (�������V���[�Y�q1�r)�@197p pid/12262812�@�@�P�O�O�O�~
|
�����O��^1865�|1939�@����-���a����O���̉��ꌤ���ҁB�c�����N10��6�����܂�B����32�N���ꒆ�w�̔����w���t�ƂȂ�,����̗��j�E�����Ȃǂ̒������ʂ��u�����l�ފw�G���@�����O��@�v�ɔ��\�B34�N����w�p���������������,���N���茧�̒��w�ɓ]�B���a14�N4��6�������B75�B����(�ނ�)�O�O(�X��)�o�g�B����Ɂu�����̌����v�B |
�W���A�V�铿�S���u����̏�Ձv���u�V�铿�S�^�Ɛ����Ёi�����j�v���犧�s����B�@pid/9774401
|
�����E���a�c�^�~/1
����/2
���_/9
��A�z��̔��B/10
��A��̎��/17
�O�A�n�`��́u�\���`���v/19
�l�A�\����́u�z��`���v/23
�O�R�̏��/27
���A�m���/31
���v�ƈʒu�y�іʐ�/31
�z��`��/33
�\���`��/34
��Փ��̋���/36
�k�R�̋��S/46
�k�R��ɂ܂��`��/63
���/73
��R��Ձi�����Ձj/86
�Y�Y���/95
�k���n��/101
���Ӗ����/102
�Ôg���/106
������/108
�e��ƉH�n���/111
������/118
�v�u���/119
�Ŗ����/122
������/127
|
�R�c���/131
�ɐ������/136
�V����/140
�����n��/143
���얡���/146
���Ǐ��/151
�k�J���/154
�ɑc���/159
�ɔg���/164
��u���Ձi�����j/167
���c�����/172
���i���/178
�]�F���/180
�쉮�����/185
���A���/191
�z�����/198
�m�ԏ��/201
�����/206
������/211
�I�����/216
�K�n���/219
�Ê앐�c���/223
����Ձi���������j/225
����Ձi�{�铇�j/226
�Ɍv���/228
�암�n��/231
���\���/233 |
�L������/240
�ۉh�Ώ��/245
���Ǐ�Ձi�암�j/247
������/249
�������/254
�嗢���/258
�����/265
�m�O���/272
���~���/278
�ʏ���/286
�������/293
�_�ԏ��/297
�~���g�����/299
��u�����/302
���c�����/305
�����/313
�V����/316
���d�����/319
�^�h�����/324
���g���/326
��u���Ձi�����s�j/334
�㗢���/339
�Đ{���/344
�^�Ǐ��/348
�n������/353
�v�ē�/355
�ɕ~�����/357 |
��u����/370
�F�]����/377
�o���ߔe���/384
�N�j���/389
�E�j�V���/392
�������/397
�^�ߗ���/403
�{���n��/407
��̂Ï��/408
�ۗ����/412
������ՂƔ��/414
��Y���u���/420
��ԏ��/424
��ԉÏ��/430
�썲�^���/434
�v����/438
��䉮���/443
���d�R�Q��/447
�X�N�R���/450
�x��K�o�l���/455
�약���/461
�t���X�g���/465
�|�x���̏��/472
�����̏��/483
�^�ߍ����̏��/489
�s�����ʏ�Ոꗗ�\/494
�Q�l����/512 |
�W���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 47(9)[(607)]�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059724
|
�����ʂ̂��Ƃƕ��|<���W>/p6�`200
���k�� �쓇�������߂����� / ���{���q ;�{�Lj��F ;��Î� ;
�@�@�����Ð^�O�� ;�c����H ;���{��/p6~28
���_ ����{��/p29~72
���_ ����{�� �������������̏��� / ����v�_/p29�`36
���_ ����{�� ���������̐����Ǝ���w
�@�@�����{��̌��������ǂ� / ���{���q/p37�`47
���_ ����{�� �����ʂ̒n�������̂��߂� / ���Ï���/p48�`55
���_ ����{�� ������ �j�̂Ƃ������� / ��Î�/p56�`62
���_ ����{�� �R�V�����_ / �|������/p63�`72
���������̂��Ƃƕ��|/p74�`119
���������̂��Ƃƕ��| ��E���̕��� / �P����/p74�`86
���������̂��Ƃƕ��| �^�_������ / ������/p87�`96
���������̂��Ƃƕ��| �����̖��b�̍̏W / �{�c�F/p97�`106
���������̂��Ƃƕ��|
�@�@�����Ƃ킴�ƎE�̘b�E�E�^/�c����H/p107�`119
����{���̂��Ƃƕ��|/p121�`138
��㊖{���̂��Ƃƕ��| ���������
�@�@�����N�ꎑ��/���a�c�^��Y/p121�`130
��㊖{���̂��Ƃƕ��| ����̖��b���� |
�@�@���ߔe�����𒆐S�Ƃ��� / �Ɍ|�O�q/p131�`138
�{�ÁE���d�R�̂��Ƃƕ��|/p140�`163
�{�ÁE���d�R�̂��Ƃƕ��| �{�Õ�����
�@�@���ӂ邳�Ƃ����炵�� / ���Ð^�O��/p140�`152
�{�ÁE���d�R�̂��Ƃƕ��| ���d�R�̗w�u��킠�悤�v��
�@�@���`�� / �{�Lj��F/p153�`163
����ɐ�����쓇�����̖���/p164�`195
����ɐ�����쓇�����̖���
�@�@��B�EH�E�`�F���o�������/�R���h�S/p164~170
����ɐ�����쓇�����̖��� �{���c��_(��)/�����H�^�s/p171�`177
����ɐ�����쓇�����̖������������̎�i�\���̖��_
�@�@�� ��q�s�Y�w��E�������W�x�̉��l / ���{��/p178�`185
����ɐ�����쓇�����̖���
�@�@�����v���w�����ɐ�������{�Ñ㕶���x / �n粋ӗY/p186�`195
�t�B�[���h�E���[�N�̌��L �����w����
�@�@������������g�D����/�A������ ;����N�F/p196~200
�A�� ��[�N������(27) / ���c���F/p201�`203
�A�� �R�{�L�O�]�`�E�V����(22)����(���̏\��) / �i�쌫/p204�`209
���̑��Ƙ_�� / �]���F��/p210~211
�E |
�W���A�u�ߑ㌚�z36(8)�v���u�ߑ㌚�z�Ёv���犧�s�����B�@�@�@
|
��2��ȃG�l���M�[�Z��R���N�[��'83�A
�@���������z�ܕ�W�v�j�A��14���EDAS�w���f�U�C���܂ق�/p7�`7
1982�N���z�Ƌ����(��23��BCS��)/p8�`8
��8���s���z�m�����������/p9�`9
���M�̌��i��-4-���葋�̐l�`���� / �k�X���/p10�`11
<���E�̍\��>--�ǂ̕ϖe-2-(��Ԙ_�m-�g-8-) / �ۍ�z��Y/p12�`13
�����E�吳�E���a�}���ژ^(1) / ������/p14�`15
�V���}���w���܂��̖��Áx�w���㌚�z�Ɓx�ق�/p16�`16
���W 1981�N�x���Ɛ���E���s��w/p3�`12 |
��i����E���݂��ӂ肩������ / �O���_�j/p13�`14
�Q���̌���-2-��/�֏��x-��- / ��c��/p15�`22
�V���փv�����X�z�e�� / ����E�X���z������/p23�`34
���k���n�ی���ÃZ���^�[��t��a�@ / ����d�����z������/p35�`40
�^�E���n�E�X�ԍ� / ��V�v������/p41�`44
�������z�������E��i�W �V�k��B�M�p���ɖ{�X�A��䐻���B�H��A
�@�@���ٗp���i�`���h�ɁA�]���l���n�C���������ق�/p45�`68
�ȃG�l���M-�ƃv-���{�v�� / ���E�Ǝ{�������������/p69�`76
�}�e���A���R�[�i�[/p80�`81 |
�P�O���A��Ð��v���u���ꖯ���w�̕��@ : ���Ԃ̍Ղ�Ƒ����\���v���u�V��Ёv���犧�s����B�@�@pid/9774203
|
��
�퐢�_�Ƒ��E��/6
����̔N���s��/27
�� �N���s���Ɩ���/27
�� ����܂ł̉���̔N���s������/30
�O �e�_/32
�l ����̔N���s�������̉ۑ�/97
���Ԃ̍Ղ�/104
�� �A�J�}�^�E�N���}�^�̍Ղ�/104
�� �E���W���~�Ղ�/111
�O �V�k�O�Ղ�/121
2
���ꖯ���w�̉ۑ�ƈɔg���Q/132 |
�� ����ɂ����閯�������̌���/132
�� �ɔg���Q�̉��ꖯ������/136
�O �u���Ȃ�_�v�̊w�j�I�ʒu�Â�/142
�l �u�����v���߂�����/146
�� �N�^���M�ɂ���/157
�Z �ނ��тɂ�����/160
��Ït���\���̌����ƕ��@/163
�� ���̗���/163
�� ���̊w��̔w�i�ƕ��@/164
�O �Ɛт̈ʒu�Â�
�@�@���\�u���������k�v�Ȃǁ\/169
�l �ӔN�A����ւ̖�/177
�E |
�O
����̑����\���Ɛ��E��/184
�ŋ߂̉��������ˌ�/201
�l
�Љ�l�ފw���猩��
�@�@�����Ƃ̈Ӗ��\�q��r�Ɓq���r/212
�� �Љ�l�ފw�ɂ����錾��/212
�� ���NJԓ��ɂ�����q��r�E�q���r�̊T�O/215
���NJԓ��̍��J�g�D�f�`/221
�� �����̊T��/221
�� �܂���߂���l�X/223
�O �_�K�J��������l�X/243
���Ƃ���/244 |
�P�O���A�������q���u���{���y�̌Ñw�v���u�t�H�Ёv���犧�s����B�@�@�@pid/12432846
�P�O���A����v�ē������ψ���ҁu����v�ē� : �u����v�ē��̌���E�����E�Љ�̑����I�����v���v���u�O�����v���犧�s�����Bpid/9774205�@
|
�v�ē��̗��j �����P�G/1
�v�ē��̎��R �R����/69
��j����̋v�ē� ���{�A��/89
�v�ē���u�쑺�k���C�݂̐�j��� �v��~��/105
�v�ē��̃O�V�N�ɂ��� ��������/127
�v�ē��̐����N�� �������Ƙ_�̈ꌟ���Ƃ��� �����N/147
�ߐ��v�ē��̓y�n���L�ƒn�� �R�{�O��/159
�v�ē��̋ߐ����� ����]/191
�v�ē��̋K�͒��E�������ɂ��� �~�ؓN�l/207
�펞���̋v�ē��Љ�ɂ��Ă̈�l�@
�@�@���ČR�L�^�𒆐S�ɂ��� ��c���G/225
�v�ē������Љ�̊�� ���c���c�`�Ԃ�
�@�@���W���ړ��̊W�ɂ��� ����O/239
�V�Ԃ̏W���ɂ��� �{��K�g/291
�v�ē��̔N���s�� ��]�F��/309
�v�ē��������䉮��ɂ�����Ƒ��Ɛe�� ��Ð��v/345
�����̍��J�̍\���Ƌ@�\ �Ƃ��ɍՒn�E�ՋV�Ɛ_���̌p��
�@�@�����䓿���Y �������t ���쏇�h �c���q�a/357
�v�ē��̕����� �{������/389
�v�ē��̊G��E������ �{��Đ�/393 |
�v�ē���v���Ə����̍g�^���ɂ��� �n���얾/413
�v�ē�������̉��߁w�����낳�����x�����u���߂̓�܂��肨�����o���v��
�@�@���{���Ɖ��� �O�Ԏ�P ���\�G �����K�� �����G�� �g�Ɗԉi�g/423
�v�ē�������ɂ��āw�����낳�����x��\��Ƒ����̔�r ��Î�/679
�v�ē������̉��� ���������𒆐S�� �����h��/697
�v�ē������̓����E�`�e���̍\���ɂ��� ����v�_/717
�v�ē����������̌`�e�� ���Ð^�O��/729
�n�s�E���s�l�i�����̊��p �v�ē���u�쑺���������𒆐S�� ���Ԓ��m/741
�v�ē������̏��� �쌴�O�`/747
�E�~���`���̐�����b �C�m�W�̌�b ���{���q/769
��㊋v�ē��ɂ����鍑�ꋳ�� ���{���q/779
�����ژ^�i���a�ܘZ�N����݁j �����K��E���K����/789
�܍��n�}/801
�}��E�ԍ�����
�S�}1 �v�ē���ԁE�q���n�}
�S�}2 �v�ē����Ւn�}
�S�}3 �v�ē��Ó��n�}
�v�ē������Љ�̊�� �}2 ���c�n���̌`��
�p���v�|
�E |
�P�O���A����d�N���u�������������̌����v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s����B�@pid/9774231
|
�������������̌����^�ڎ�
�܂�����
I �����̐_�Ղ�
�����_�Ղ�̍\���ƃe���R�_/2
�� �w�j�ɂ݂�i���R�E�e���R/2
�� �����_�Ղ�̎���/6
�O �����_�Ղ�̍\��/17
1 �~�ܖڂƉĐܖ�/18
2 �V��ԂƐ����Ղ�/20
3 �E���P�ƃI�[�z��/22
���v�C�����̐_�Ղ�/28
�� ���J�g�D�̊T�v/28
1 �_�R/29
2 ��Ɛ_��/30
3 �A�V���Q�ƃg�l��/31
4 �_�l��/34
5 �Ղ�̊T�v/36
�� �E���P�ƃI�[�z��/40
1 ���̎���/40
2 �E���P�A�I�[�z���̍l�@/45
�O �A���z�o�i/51
1 ���̎���/51
2 �A���z�o�i�̍l�@/54
�l �~�j���N�`/59
1 ���̎���/59
2 �~�j���N�`�̍l�@/62
�� �E�t�����ƃt���E����/66
1 ���̎���/66
2 �E�t�����A�t���E�����̍l�@/69
�Z �s����̍Ղ�/74
1 ���̎���/74
2 �L�g�E�Ȃǂ̍l�@/76
�����̃I�i���_�̍Ղ�/80
�����̐_�R/92
�� �������}�i�X�R�j/93
�� �I�{�c���}/101
�O �J�~���}�E�I�K�~���}/109
�l �e�����}�E�S���Q�����}/115
�� ����/117
II �쓇�̉Đ���
�쓇�̓~�쐳��/122
�� �Z���N�������Ɛ����ܖ�/122
�� �����ߐ����ƒ��q���/128
�O ��̓~��Ɠ쓇����/134
�����̃J�l�T���\�\�M�\�M�E
�@�@���R�̐_�E�c��/141
�� �J�l�T���̒n�}/141
�� �R���牺��_/143
|
�O ����Ղ��/151
�h���K�E�g���`�l�\
�@�@���쓇�N���s���̍\��/158
�� �����哇�̐߂̍\��/158
�� �h���K�E�g���`�̎���/162
1 �����哇�̎���/162
2 ��E���̎���/164
3 ���V���̎���/165
4 ���i�Ǖ����̎���/165
5 �^�_���̎���/166
�O �h���K�E�g���`�̐��i/167
�Đ����Ƒ���̖���/180
�� �Đ����̉���/180
�� �����h�b�i���Z���A���j/182
�O �l�u�C�n�i�V�i�������Z���j/186
�l �u�b�A�K�C�i���������j/192
III �쓇�̈��V��
�����̈��V��/198
�� �c�Ŏn�ߋV��/198
1 �~�j���N�`�i�����j/198
�� �d��V��/210
2 �j���[�_���h�C�i���q���j/210
3 �z���l�I���V�i�{��q�����j/216
�O �c�A�V��/226
4 �\�[��/226
�l ����V��/234
5 ���V�A�V�r�i���V�сj/234
�Z �A�W���l�i�A�W���m�w�j/243
�� ����V��/248
7 �V�L���}�A�C�j�N���A�E�`�L�w/248
8 �A���z�o�i�i�V��ԁj/259
�Z ���n�V��/265
9 �A���K�V�L�A�A�L���`/265
�I���/274
���E���V��\�̂������l/283
�� �Y��V��Ɛ̂�����/283
�� �_�k�V��Ɛ̂�����/286
�O �ߋV��E�ޏ��V��ɂ݂鏬��/290
�l ���E���V��/294
IV �V�k�O�E�E���W���~
�^�_���̃V�k�O�ƃE���W���~/304
�� �^�_�V�k�O���w�L/304
�� �^�_�V�k�O�̓�ތ^/310
�O �^�_���V�k�O�Ɖ�����c�V�k�O/319
�l �E���W���~�ƃV�k�O/326
�V�k�O�E�E���W���~���_�\
�@�@���A�}�~�E�V�l���Õ����̂���/332
�� �V�k�O�ɏo������_/332 |
�� �A�}�~�L���E�V�l���L���̌ꍪ/335
�O �V�k�O�ƃE���W���~�̐��i/340
��c�̒������J��s���\
�@�@���c��V��̔����ɂ���/347
V �쓇�̖h�ЋV��
���V���̕l����/360
�� �l����̊T�v/360
�� �l����̓��e/361
1 �����q�m�G�̓�/361
2 �����q�m�g�̓�/363
3 ��O���c�`�m�G�̓�/367
�O �����x/370
�l �l�@/372
�쓇�l����̏��`��/378
�� �l����̏���/378
�� �O���ߋ�ƃ}�l�A�X�r/382
1 �O���ߋ�̓`��/382
2 �}�l�A�X�r�̓`��/383
3 �O���ߋ�ƃ}�l�A�X�r/384
�O �A�u�V�o���ƒ��A�X�r/387
1 �A�u�V�o���̓`��/387
2 ���A�X�r�̓`��/389
3 �A�u�V�o���ƒ��A�X�r/392
�l �b�q�A�X�r�ƃ~�j�A�X�r/394
1 �b�q�A�X�r�̓`��/394
2 �~�j�A�X�r�̓`��/395
3 �b�q�A�X�r�ƃ~�j�A�X�r/396
�� �l������߂�����/398
1 �s���Ɠ`���̌ŗL��/398
2 �A�j�~�Y���̐��E/398
3 �l����̏d�w��/400
�R�g�Ƃ��̎���/403
�� �R�g�̓��/403
�� ���B�̃g�L/409
1 �a�C�E�ЂȂǕs����̃g�L/409
2 ���X�Ȃǒ���̃g�L/410
3 �_�k�̃g�L/411
�O �����̃L�g�E�ƃJ�l�T��/416
�l ����̃V�}�N�T���V�ƋS��/420
�� �R�g�����Ət�S�g/425
�Z �h�ЋV��̎���/431
���\�\�c�N�����m�E����E���]/441
�� ���̃c�N�����m/441
�� ���̐���/446
�O ���Ƌ��]/451
�����i�����j
�ʐ^�ڎ��i���a43�N�`56�N���ҎB�e�j
�������������̌��� |
�P�O���A���q�F���Y���u���ꕶ���̈�� �ʐ^�v���u��g���X�v���犧�s����B�@
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004295802 �@402,13p
|
�����̔w�i
�E�ߔe���̈��
�����G��̌n�� |
�����̍H�|
�{���̎ʐ^�̊� �O�� ���K�^��
�ʐ^�ꗗ |
�P�O���A���q�F���Y���u���ꕶ���̈�� �m�{���ҁn �v���u��g���X�v���犧�s����B�@�@
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004295786 285p
|
����
���ꕶ�������̔w�i
[���R�̏���,�l�Ԃ̏���(�����ƕ���)
�����̉���]
����e�n�̈��ƈ�ՂƐ_��
(��
����̐_��
�Y�Y��
��k��
��O��
�ߔe�`����
����
���E�V�v����
��a�E���{�Ƃ��̈��)
|
�����G��̌n��
(���{��l�`�y�ъL����s���G�t�n��
��㍑���y�я��b�ё���)
�����̍H�|(���H�|
���F�H�|
�D�H�|
���H�|
���H�|�E���H�|�y�G�H�|)
����
(�{�����^�������W�̈ʒu���}
�������������n���}
����̍��w�蕶�������̈ꗗ)
���Ƃ���
�u���ꕶ���̈��v�Ɗ��q�m�[�g �O�� ��P�^�� |
�P�P���A�@�w��㊕����x�ҏW�� �ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 19(1)(59)�@�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437773
|
���{�I�������@�̌����ƒn���E���C���@ / �����/p1�`13
���d�R���w�́u�����v�ɂ��� / ���w/p14�`29
�w�Í����̏W�x�Ɓw�Í��a�̏W�x�̔�r����--
�@�@���l�G�̉̂𒆐S�� / �Ɖ��Ȃ��q/p30�`47
���^����㊌ꉹ�C�l / ���a�c�^��Y/p48�`69 |
�n���C�̗���(5) / �O�Ԏ�P/p70~79
�w�}�������ꎫ�T�x�̕��@ / ���{���q/p80�`82
�V���Љ�/p83~84
�w�E�j���[�X/p13~13
���]/p84~85 |
�P�P���A���R�Ă��u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 11(1/2) p.113-120�v�Ɂu�������[�J�r�̔�V : �C�[�`���[�n���[�`���[�̐_�́v�\����B�@�@ �iIRDB�j
���A���̔N�A�u���{�����w��I�v (�ʍ� 20)�@���ƕ��x<���W>�v���u���{�����w��v���犧�s�����B
|
�~���[�W�J���ɂ�����u�x��v�̉����I�@�\�ɂ��� ���� �u�Y p.p1�`12
���ƕ��x�@�L���ʓT p.p13�`23
�A�W�A�̉̕����l �{������ p.p24�`36 |
���x����݂��^���c���E�m���l ������ p.p37�`46
���{�|�\�j�ɉ����鉫��̌|�\ �{�c���� p.p47�`57
�E |
�Z���̔N�A�Y�R���ꂪ�u�쐼�����ɂ������Ԃ̌��z�I�`�ԂƋ�ԂɊւ��錤���v���u����E�ƌP���Z����w�Z�v���甭�\����B�@�@�����ȉȊw������⏕���������ʕ�
���A���̔N�A���v���u���d�R�̖��w�v���uSeven Seas�v���犧�s����B (���v�̈�Y : �������y�̑b, 16)
|
�Ƃ���[�� : �Ί_
���q����[ : �Ί_/�o���
�r�ʂԂ������ : �Ί_/�{��
�D�ʂ�[��� : �Ί_/�{��
���ې� : �Ί_/����
���NJԂ���Ƃ� : �Ί_/�약
|
���[�����[��[���[��[ : �Ί_/�약
�������~ : �|�x/�g����
�������� : �|�x/�g����
�Ì��̉Y�� : ���\/�Ì�
�ł� : ���\/�㌴
������[ : ����
|
�������Ԃ���[ : ����
�܂݂ނ�ʂ��������� : �g�Ɗ�
����� : �^�ߍ�
�ǂȂ��� : �^�ߍ�
���ł���� : �^�ߍ�
�ԂƂނĂ� : �^�ߍ� |
�@�@�@�@�@�@�@�@���@���s�N�ɂ��Č������K�v�Ǝv���B�@�^�������ł͂Q�O�O�Q�ł����邪�@�@�Q�O�Q�R�D�R�D�P�R�@�ۍ�
���A���̔N�A����x�����u���{�̗w���� 21(0) p.35-51�v�Ɂu�u�~�x��S�v�̐����Ɋւ����l�@:�i�O�j�v�\����B�@J-STAGE
���A���̔N�A�u���ꕜ�A�\���N��̉ۑ�v���u�n�h�o�Łv���犧�s�����B�@�@pid/9774396
|
��㊕��A�O�� �ҏW�ږ� �܈�쐳/40
���{�{�y�̐l�B�ɂƂ��ĉ�㊂Ƃ�...�i�A���P�[�g�j/2
�g�b�v�ƃy�P ���/5
��㊂̒n���E�A��/9
�L�̘b���ꂱ��/11
��㊂�̑�햡/12
�n�u�̘b/16
��㊂̓`���H�|�s��������t/17
��㊂����A���Ă���̕���/20
�O�҉�k ��㊂��l����/24
��㊔_�Ǝ�ރ��|�[�g ��㊃p�C���Y�Ƃ̎���/30
���������� �Ђ߂��ɂ܂�邱�ڂ�b/36
��㊕��A���}�������s5�E15�h�L�������g�t/50
�ČR��n�̖��/54
��㊂̔N���s���E�Ղ�/58
�|�x���̃~���T�[�D��Ɛ���/60
���W ��㊁E�{�ÁE���d�R�����Ď��ӂ̑S�� �O���ށI
���̓��̘̎b�A���A�d�C�A
�@�@���n�u�Ȃǂ��̓���K��鎞�ɐ�ΕK�v�ȏ��etc...
��㊁E�D�̍q�H�y�є�s�@�̍q��H���}/66
��㊖{��/68
����/69 |
�n�Õ~��/70
�c���ԓ�/71
���Ԗ���/72
����/73
�v����/74
�Ɍv��/75
�l���/75
�ÉF����/76
��������/77
����n��/77
���/78
���[��/79
�ɍ]��/80
��ᓇ/82
�ɐ�����/83
�ɕ�����/84
�v�ē�/85
������/86
�n���쓇/87
������/88
��哌��/89
�k�哌��/91 |
�{�Ó�/92
�ɗǕ��� ���n��/94
��_��/95
�r�ԓ�/96
���NJԓ�/97
���[��/97
���ԓ�/98
�Ί_��/99
�|�x��/101
���\��/103
���ԓ�/105
�V�铇/106
�R�z��/107
������/107
����/108
���l��/109
�^�ߍ���/110
�g�Ɗԓ�/111
��㊕��A�\���N���}�����l�X�̐�
���ꌧ�m���E�ߔe�s���E�Ί_�s���E
�@�@���|�x�������̑�/112
�ҏW��L/128 |
���A���̔N�A��Î����u�����̐��E�v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s����B�@pid/12502734�@�@�P�T�O�O�~
���A���̔N�A�쓇�j�w��ҁu�쓇 : ���̗��j�ƕ��� 4�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@pid/9774264
|
�������������̓���ʂɕz�ڍ������y��ɂ���
�@�@���\�\�ʍ̎掑���𒆐S�Ɂ\ ���R�E�A/1
��A�͂��߂�/1
��A�z��A�y��o�y�n/2
�O�A�܂Ƃ�/8
���������Ɍ���쓇��w�����̓��F ����q��/15
��A�͂��߂�/15
��A�L/16
�O�A�I���Q�[�Ə��`�n/18
�l�A�Ќ����Ɗۖ�/20
�܁A�e�B���Ɣw������q/23
�Z�A�@��_�ƃw��/25
���A�����R��/27
���A�C�[�U�C��ಁE���k/29
��A�܂Ƃ߁\�\�����������Ƌ��E�\�\/31
���d�R�̖��a��Ôg�Ɛl���̐��� �q�쐴/35
��A�͂��߂Ɂ\���a��Ôg�̊T�v/35
��A�Ôg�O�̔��d�R�̐l��/36
�O�A�Ôg��ł������Q���l���̌��ތ��ۂƂ��̗v��/39
�l�A�l���̉Ƃ��̗v��/48
�܁A�ނ���/49
�����n�����}�_�M��
�@�@�@���\���̈ʒu�Â��𒆐S�Ƃ��ā\ �E����/57
�V�u���Ȃ�_�l�v ������G/83
��A����/83
��A��Ȃ钲���n/84
�O�A����/85
�l�A�ނ���/95
�m���_�̕ϐg ���x�d��/97
��A���Г��̕��y�L�^/97
��A�m���_�Ɋւ���L�^/99
�O�A�m���_�̕ϐg/101
�l�A�m���_�Ƃ�/107
�܁A�m���Տꂩ��_�Ђ�/111
���d�R�I���g�R�̐_�ɂ��� �Ί_���F/117
��A�͂��߂�/117
��A�w���z�x�A�w�����낳�����x�A�w�������R���L�x
�@�@�����ɂ݂�I���g�R�̐_/119
|
�O�A���d�R�×w�ɂ݂�I���g�R�̐_/129
�l�A�ނ���/138
�ŋ߂̃V���[�}�j�Y���w�����猩�������̃��^��
�@�@�����V���[�}���I���i���ɂ��� ���X�؍G��/143
��A���̏���/143
��A��T�O�Ƃ��Ă̇��V���[�}����/146
�O�A�����̃��^�̃V���[�}���I���i/152
�l�A��̂܂Ƃ�/159
�C�̋֊��Ƃ��̔w�i�\�����哇���˓����𒆐S�Ɂ\ �o�R�C/163
��A�͂�����/163
��A�C�̋֊�/164
�O�A�D��M��/172
�l�A�D�H��/176
�܁A�l��/180
�����哇�̉Ƒ��ƈʔv���J�\�Z�p���s�̎��Ⴉ��\ ���ؓc�N�V/185
��A�͂��߂�/185
��A�Ƒ��\��/186
�O�A�����ƌp��/188
�l�A�ʔv���J/194
�܁A��̍l�@/199
���������̂Ƌ�����̋@�\ �c������/205
��A�͂��߂�/205
��A�����������̊T��/207
�O�A�����p�^�[���Ƌ�����/209
�l�A�A���p�^�[���Ɛ���������/218
�܁A�ނ���/222
�_�̎q�琌^�����������b�̏d�w�� ���c�W/227
�� �쓇�����^���b�̕���/227
��A�_�̎q�琌^�����������b�`���̏���/230
��A�{�y�ɂ�����_�̎q�琌^������������Q/240
�O�A�{�y�ɂ�������������^�̐��b�Q/249
�l�A�_�̎q�琌^�����������b�ɂ�����{�y�Ɖ���/256
�܁A����/266
���������̉^��ߘb �{�c�F/273
��A�͂��߂�/273
��A�u�^��ߘb�v�̓��e�Ɛ��i/274
�O�A������/288
�E |
|
| 1983 |
58 |
�E |
�P���A�����V�����ҁu����w�̌Q���v���u�{�M���Ёv���犧�s�����B�@�@pid/9774454
|
���R�^�������� �؍�b�q�Y/2
����̓y�� ����M/6
�������̌��p ���O�q/10
�����ΊD��Ɛ��� ������/14
���{�]���E�C���X�̐��� �F�Ǐ@�P/18
�����̊J�� �R���C/22
�������̗L�����p ���R���P/26
�L�E���ɂ��n���� ���ƍG/30
�T���S�ƃI�j�q�g�f �R����/34
�q�q�g�r�̑c�`�����߂� ���[����/38
���v�g�X�s���ǂ�ǂ� �����\��/42
�L�ւ̕��z�Ɛ��� �r����Y/46
�E���~�o�G ���R�d�Y/50
���M�ƔD�P�̃v���Z�X �n�Õ~�V��/54
���Ζ��̂Ȃ�؇��T���S ��c�k��/58
�q���������܂��� �ݖ{���j/62
�A���̗D�Ǎy�� �ʏ镐/66
�����ł̗����O�Ւǂ� �͖��v/70
���Y�N�ƃE�~�u�h�E ���^��/74
���A�����̎핪�� ���Ӗ����h/78
�M�сE���M�т̉ʎ� ��Ïƕv/82
�S�Ɖ��Q ��u�K��/87
�H�i�̐��� �O�Ԃ䂫/91
����̉� �{���Y/95
���z�M�G�l���M�[�̗��p ���c�F�u/99
����_�Ƃ̉ۑ� ���ԑגj/103
�L�r��Ƌ@�B�� ��T��/107
�n���ƒn�ՍЊQ �㌴����/111
�����̒n�` �ڍ�Θa/115
����̗ы� �������Y/120
�n�u�R�őf�̊J�� �R��뉄/125
�T�g�E�L�r�̈琬 �i�x���I/130
�����̗����G�r ����c�Ώ[/135
���n�荩���� ������/140 |
�䕗�̔����A���B�A���� �Γ��p/145
�����T�� ����N/150
����̒n���� �Ð씎��/155
�}���O�[�X�̐��� �{��M��/160
�C�w�r�ɒ��� ������/165
�L�r�ƕa�Q�� �R������/170
�����̊C�� �����^��/175
�L�N�U�g�A�I�w�r�Ȃ� ��v�����B/179
�v�ē��̐A�� ���g��Y/184
�đΊO���� �{������/188
����̐��_�q������ ���X�ؗY�i/192
����j�̒������� ���Ǐ鐷��/196
����̌o�ϊJ�� �O�֗��v/200
����l�̍��i �����/204
�����哇������� �V�萷��/208
�w��Ƃ��Ắu�����v ���c��Y/212
�n���`�̓W�J �ʖ��F�Y/216
�S�̂�����p�}�b�g���J�� �Îӌi�t/220
�ږ������j �c���F�N/224
�����Ǝ���w�i ���J���ǎq/228
����̊K�w�\�� �g���E�v/232
�o�ϊJ���Ɠ�����Љ� �^�h����/236
�������Ǝ��R�� ��ؐM/240
���̉������j �i��P��/244
��ÁA��ォ�畜�A�܂� ��쉮�Lj�/248
���ꏔ���̎���ҔN ���{�A�q/252
��Q���ۈ� �g�앐�F/256
�����̕��� �㑺�K�Y/260
���̂̔�����T�� �������X/264
�q�ǂ��ƌ���\�� ���]���V/268
���F��ɂ݂錧���� �Ό�����/272
����̗��ʖ�� �V��r�Y/276
��t�̖@�I�n�� �Ίԉh/281
�����̎�Ì`�� �茴����/286 |
�ԊҌR�p�n�̍s�� �������`/290
����̗������ ���ǗL��/294
����̊ό� �ΐ쐭�G/298
�ږ������̈ӎ��\�� �ΐ�F�I/302
�č��̑Ή��ꋳ�琭�� �ʏ�k�v/307
����̃r�W�����M�� ���~�ߎ�/312
���t�͊w�Z�ɂ݂�
�@�@���c�������� ���g������/317
�����̕\������ ������q/321
����̖咆 ��Ð��v/326
����̋ߑ㕶�w ���{�b��/331
����̓��� �{��Đ�/336
����̋���j ��쐽/341
���l�鋳�t�݂̂����� �X�c�Аi/346
����̑����E�搧 ���Ð^�X��/351
����̌��z�����j ���g�^�O/355
����̖��b ��������/360
���R�����h�̗����_ �䉮���ƕv/365
���ꐅ�Y�j�Ǝ������v ��c�s��v/370
����̌|�\�u�g�x�v ���Ԉ�Y/375
�������� ���/379
�v�ē����� �����P�G/384
�T�C�R�h���} ���b���q/389
��p���Q�����Ƌߑ㉫�� ���g����/394
���y�j���� �ɔg���Y/399
���܂��� ���@���K�s/404
�����ƕ� �c���^�V/408
�����̓��S ����w�v/413
���^�ƐM�� �F��/418
�����̐j�� �s��d��/423
�l�ނ̐����� ����V�n/427
���{�ߑ�j�Ɖ��� �䕔���j/432
���y���_�Ƒn�� ������/437
�E |
�Q���A�n���������u���������ƌ�̐_�l (�q�k�J���K�i�V�[)�v���u���ۗ����w�@�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@���L�@�@����̔N���s��: p258-259
�R���S���A�����V��z�[���ɉ��āu��4��@�쓇�����s���u�� �~���N���ʕ�ƒ��҂̑��v�ɂ��Ă̊Ϗ܉�J�Â����B
�@�@�@�@��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� �����V��� ���ꌧ
�R���A���R�Ă����ꍑ�ۑ�w�쓇�������������u�쓇�����s���u�� ��4��@�ӏ܉�v���O�����@�~���N���ʕ�(�䂪��)�ƒ��҂̑��(���ӂ���)�v�����s�����B�@�@�@���҂̑��ƊJ蓐_�b / ���R��
�R���A���ꌧ���H�ό������������ەҁu���ꕶ���̌������l���� : ���A10���N�L�O�s�����ꌤ�����ۃV���|�W�E�����v���u���ꌧ�v���犧�s�����B�@
�R���A����s����ψ���� �u�R�����j�� ���{�����뒲�����v���u���ꌧ����s����ψ���v���犧�s�����B�@
(����s������������ ; ��5�W)�@�v��F�R�����j�́u���{������v�܋ȘZ���u�@�̎��^�����@pid/12502763�@�iIRDB�j
�R���A���ꌧ�X���������ψ���ҏW�u�X����̋����Y�v���u���ꌧ�X���������ψ���v���犧�s�����B
�@ (�X������T������ ; 8)
�R���A�u�ɗǕ����������v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
(�n�挤���V���[�Y ; no.4)�@�@pid/9774940
|
���� �������Y/1
�ɗǕ����\���̒n���I�T�� ���O����/3
���Ǖl���Ƃ̔_�� ���ԑגj/11
�ɗǕ����̉Ƒ� �ʏ闲�Y/27
�ɗǕ����ɂ�����q�̂����Ɋւ��钲������ �������Y/59
�J���X�\�ɗǕ����̔N���s���\ ���R��/79
|
�ɗǕ����̓����ƐA�� �{��M��/113
�ɗǕ����\�ςڂ����铇�̐����\ �{��C�j/121
�ɗǕ����̓��� �쌴�O�`/139
�ɗǕ����Z���̓��퐶���s������݂�
�@�@�����������Ԃ���ѓ��O�Ƃ̌��т� ���O����/151
�����T�v�\�܂Ƃ߂ɂ����ā\ �ʏ闲�Y/163 |
�R���A�u�쓇���� 5�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
|
����ԊҌ��j�@�Ίԉh p.1-26
����̕��A�^���ɂ��Ă̈ꎋ�_�@�����X�� p.27-38
���A�Ɖ��ꌧ�̍������@���E p.39-64
���A�Ə������ʁ@�@��G p.65-102
���A�Ə��N��s�@�O��F�V p.103-128 |
����U���J�����Z���ɂ�10�N�@�@�v�ꐭ�F p.129-147
���A�Ɗ� : ���A���ʑ[�u�𒆐S�Ƃ��ā@�V�_���O p.147-164
�����X�Ƒ���������(2)�@�@���m�������@�ʏ闲�Y�@���O���� p.165-232
�|��x�b�e���n�C�����u������Ɠ��{��̕��@�̗v�j�v(4)�@
�@�@���얼�����@�ɔg�a���@�X�f�v�@�����r�O p 231-243 |
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (9)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467952
|
�� / ��铿���Y
���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(II) / ���a�c�^�~ ;�m�O�E/p1~22
�����̎��ނƃL�����މ��̕����\�\
�@�@�������̌ÐҒœ�����(����VIII) / ���J��P�a ;����N ;�쌴���G/p23~30
�����ٕ����u��100��L�O�u���\�\�����ق̗��j�W���ɂ��� / �؈䐴��/p31�`46
�����Љ� ���ߏ����Õ����������(��) / ��]�F�q�v/p1�`13 |
�R���A���ꌧ�������C���Z�p�ҋ����� �u�킴 ��2���v���u���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���v���犧�s�����B�@�d�v
�@�@�@�P�O�T���@�@�����F��㊌����}���فF1004698120�@
|
����
���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���ݗ���ӏ�
���ꌧ�������C���Z�p�ҋ���X��
���ƌo�� |
�≮�̏�ėq[�o��q] �R���③
�q�Ɠ���� �{��Đ�
���d�R�q�Ǝj�W�j��(������)
����̃T���V��[�O����]�l ���g�^�O |
�R���A���ꌧ����j���ҏW���ҁu����j���ҏW���I�v (8) �v���u���ꌧ����j���ҏW���v���犧�s�����B�@pid/2221440
|
��O����ɂ����閳�Y�^���k�� �����l / ���m������/p1
�R�k�Ď���߂�����_ / ���Ǒq�g/p39,�}2��
�����ɂ�����펀�Ґ��ɂ��� / ��鏫��/p55
����i�S�撷��c�֒�o������ɂ��� / �����/p72 |
�{���h�P����(�����Љ�) / ��鏫��/p134
��㔪��N������j�W��v�_���ژ^ / ���͔��Îq/p148
����j���ҏW������/p200
�E |
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (4)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@pid/7955133
|
�N�㌳�Y�搶�ފ��L�O���ɂ悹�� / ��]�F��/p1�`1
��Վ�q��̔p��ߒ� / �x�c�g�Y/p3�`11
���ԛގ҂ƈ˗��� / �Ί_�݂��q/p12�`31
�V�@����e�ɂ�����ߔe�Ɩk���_���̔�r / �H���v�v/p32�`40
���Ɩ����w / �N�㌳�Y/p41~42
�N��搶�̋C�� / �ې參��/p43�`43
���ӗN�㌳�Y�搶 / �n�Õ~��/p43�`44
�����k�����J�͈�ɂ����遃�ʍ��J�� / �Ôg���u/p45�`54 |
�����E���V�������̎Y�� / ���Ð^�X��/p55�`61
�n���쓇�̎O�\�O�N���� / ��]�F��/p62�`68
�����ɂ��� / �n�����q/p69~85
���Ẩ��~�ƏZ���̏K�� / �����Εv/p86�`92
�ނ���H�̘b�Ɖ������q / �茴�P�V/p93�`97
���d�R�n���ɂ�����J�����s�Ɛ��ʌv�Z / ���ǖL��/p98�`105
�N�㌳�Y�搶�̗����ƒ���ژ^/p106�`107
���j���Љ �����e�_��䉼������L(1) / ���n�B��/p1�`14 |
�R���A���^�k�ꂪ�u���ꌧ�������������@��T�R�W�@�������@�O�X�N���z�����i�T�j�@�[����{���y�ю��ӗ����[�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s����B�@�@�iIRDB�j�@�@�d�v
|
�����i�S���j�^���ꌧ���ɂ́A�O�X�N�ƌĂ���Ղ����������݂��Ă��܂��B�O�X�N�ɂ��Ă͉���̗��j�𗝉������ł���߂ďd�v�ł���A����l�����̈₵���M�d�ȕ�����Y�̈���Ƃ����Ă��܂��B�Ƃ��낪�ŋ߂ɂ����鏔�J����
�Ƃ̐i�s���ɂ��֘A���āA�����̃O�X�N�̕ۋނ��傫�Ȗ��ƂȂ��Ă��Ă���܂��B���Ƃ��A�O�X�N�̑������ΊD��u�ˏ�ɗ��n���邱�Ƃ��獜�ޗp�̗̍̐J���ڂɂ�������A���邢�͒��]�̂�����r�I�����ꏊ�Ɉʒu���邱�Ƃ����ɂ���Ĕj�ꂽ��A���̖��̂������܂��܂��[���ɂȂ��Ă��Ă�
�܂��B �^�����̌���܂��A������ψ���ł́A�������̕⏕���Č����i����͋{�ÁE���d�R���̐擇�n���������
�j�ɏ��݂���O�X�N�̕��z���������{ ���Ă��܂������A���̕������s���Ĉ�Ղ̕ی�Ɏ����邱�Ƃɂ��܂����B���z�����͓����A���a52�N�x����p��
4���N���ƂƂ��Ď��g�݁A���a55 �N�x�ɏI�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A���̊ԁA���������������ً}�������̋}���ɂ���Ē������̎�s��������
2���N�Ԏ��Ƃ𒆒f���錋�ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B�^���̂悤�ɓ����̌v��Ƃ͈���āA�������̒��ł̒����ƂȂ�܂������A�]�����������`���Ȃǂł܂������m�邱�Ƃ̏o���Ȃ������V���ȃO�X�N�̔� ����O�X�N�ɔ����Ί_��\�̔����A���邢�͂܂��A��Ղ̕ۑ��̏�ŕK�v�Ȕ͈͂̊m�F�F���ł���ȂǑ傫�Ȑ��ʂ������邱�Ƃ��o���܂����B �^�Ō�ɁA���̊��s�ɂ����蒲����S�����ꂽ�e���������͂��߁A�����ɋ��͂��ꂽ�W�e�ʂɑ��܂��āA�[�����ӂ̈ӂ�\���܂��B
�^�{�����L�������̕��X�ɗ��p����A�O�X�N�̕ۑ��A���p�A�����ɖ𗧂Ă�K���ł��B�^ �� �a 58�N 3 �� ���ꌧ����ψ��� ���璷 �V�_�Y�v |
|
| �n�� |
�m�� |
�s������ |
�O�X�N�i��j�� |
�k
��
�n
��
�� |
1 |
�ɕ����� |
�c����ՁA���w�[�O�X�N |
| 2 |
�ɐ����� |
�ɐ�����ՁA�A�}�O�X�N |
| 3 |
�ɍ]�� |
�ɍ]��� |
| 4 |
������ |
�A�}���O�X�N�A���ԃO�X�N |
| 5 |
��閡�� |
���Ӗ��O�X�N�A��@�ÃO�X�N�A�Ôg�O�X�N�A�O�X�N |
| 6 |
���A�m�� |
���O�X�N�A���A�m��ՁA�V�C�i�O�X�N�A�n�i�O�X�N�A�^�[���O�X�N �A�����O�X�N�A�ÉF���O�X�N |
| 7 |
�{���� |
����O�X�N�A�����O�X�N�A�{����u��X�O�X�N�A�R��`�a�O�X�N�A�w�N�X�N�M�A�����O�X�N�A�x���O�X�N |
| 8 |
����s |
����O�X�N�A�A�}�O�X�N�A�E�`�O�X�N�A��O�X�N�A��O�X�N�A�^�쉮�O�X�N�A�e�O�X�N�A�e��O�X�N�A�f�[�O�X�N�A�O�c�O�X�N�A����O�X�N�A�㗢�O�X�N�A�×z�O�X�N |
| 9 |
������. |
���߃O�X�N |
| 10 |
������ |
�����O�X�N |
| 11 |
���[�� |
���[�O�X�N�A�C�`�O�X�N�A�R�c�O�X�N�A�K�a���O�X�N�A�A���i�[�O�X�N |
��
��
�n
��
�� |
1 |
�ǒJ�� |
�J�i�O�X�N�A�����g�O�X�N�A�g�E���}�O�X�N�A�F���O�X�N�A�}�e�[�W�O�X�N�A���얡��ՁA�^�J���}�O�X�N�A�C�b�g�J�O�X�N�A���N�~�[�O�X�N
�A �g�}�C�O�X�N�A�E�t�O�X�N�A ���[�_�O�X�N |
| 2 |
��[�� |
�Î�[�O�X�N�A���ǃO�X�N�A�����O�X�N |
| 3 |
�ΐ�s |
�ɔg��h |
| 4 |
��u��s |
�V�^�O�X�N�A���c����ՁA���Ӓi�O�X�N �A��u��O�X�N�A�]�F�O�X�N�A�쉮���O�X�N�A�N�[�O�X�N |
| 5 |
�^�ߏ鑺 |
�Ɍv�O�X�N�A���O�X�N�A���������O�X�N�A���������O�X�N�A�i�`�W���O�X�N |
| 6 |
���A�� |
��������O�X�N �A�t�j�O�X�N �A���A��ՁA �l�O�X�N�A��ÃO�X�N�A�N�|�E�O�X�N�A�V��O�X�N |
| 7 |
����s. |
�m�ԃO�X�N�A�z���O�X�N�A���@���O�X�N�A�C���W���O�X�N�A�A�}�O�X�N |
| 8 |
�k�J�� |
�k�J�O�X�N�A�C�`�O�X�N |
| 9 |
�X��p�s |
��F���O�X�N �A��@�ÃO�X�N�A�����X�O�X�N�A�Ð��O�X�N |
| 10 |
�k���鑺 |
�q�j�O�X�N�A���J���O�X�N �A���O�X�N�A�}�[ �V���O�X�N |
| 11 |
���鑺 |
�����ՁA ��O�X�N �A�V�_ �O�X�N |
| 12 |
������ |
�C�V�O�X�N�A �I���O�X�N �A�K�n�O�X�N�A�Ê앐���O�X�N �A��ӈ�� |
| 13 |
�Y�Y�s. |
�Y�Y��ՁA�ɑc��ՁA�e�x�ŃO�X�N�A���ԃO�X�N�A�k�^�N�V�l�O�X�N�A�W���O�X�N�A�R�E�O�X |
��
��
�n
��
�� |
1 |
�ߔe�s |
��ՁA�N���_�O�X�N�A�Γc�O�X�N�A�O�d�O�X�N�A���Ǎ��X�O�X�N�A�䕨�O�X�N�A�V�v�O�X�N�A��u�O�X�N�A
���\�O�X�N�A�����O�X�N�A�V�܃O�X�N�A�T�L�n���O�X�N |
| 2 |
�L���鑺 |
�L����O�X�N�A�����O�X�N�A����O�X�N�A���ǃO�X�N�A�ۉh�O�X�N�A�Ό��O�X�N�A�n�����O�X�N�A���_�}�O�X�N |
| 3 |
�앗���� |
�E�`�~�O�X�N�A���ԃO�X�N |
| 4 |
�������� |
���d���O�X�N�A������O�X�N�A�e�~�O���O�X�N�A�W���O�X�N |
| 5 |
�嗢�� |
���O�X�N�A�嗢��ՁA�~�[�O�X�N�A���� |
| 6 |
���~�� |
���~�O�X�N�A����v�O�X�N |
| 7 |
�m�O�� |
�m���O�X�N�A���i�O�i�[�����_�[��ՁA�����^�O�X�N�A�����O�X�N�A�ÊԃO�X�N�A
�E�t�O�X�N�A �u�쉮�O�X�N�A �m�O��ՁA �e�~�B�O�X |
| 8 |
�ʏ鑺 |
�_�ԏ�ՁA�~�� �g����ՁA���h�^�O�X�N �A�ʏ��ՁA ������ՁA���O�X�N�A�D�z�O�X�N�A���O�X�N |
| 9 |
��u���� |
��u����O�X�N�A���X���O�X�N�A��u���O�X�N �A�~ �h���O�X�N�A�V��O�X�N |
| 10 |
�����s |
���x�O�X�N�A���g���O�X�N�A�ꐔ�O�X�N�A�����O�X�N�A���X�O�X�N �A��R��ՁA�^���O�X�N
�A����O�X�N�A���ԃO�X�N�A����O�X�N�A�Ɖ��O�X�N �A���g�O�X�N�A�^�h���O�X�N�A�t�F���T�O�X�N�A�ɕ~�O�X�N
�A�`�`���}�O�X�N �A���ԃO�X�N �A�쉮���ÃO�X �N�A��u���ՁA�J�^�n���O�X�N�A���Ӗ��O�X�N�A�R��O�X
�N�A�㗢�O�X�N�A ���c�O�X�N �A���F�O�X�N�A�g���O�X�N�A�Ό��O�X�N�A�Đ{�O�X�N�A�K�[���O�X�N�A�I�h�T�g�O�X�N
�A�����m�O�X�N�A�^�ǃO�X�N�A�F�]��O�X�N�A�V�_�O�X�N�A�^�h���O�X�N�A
�v�����O�X�N�A���ԃO�X�N�A�`���O�X�N�A�����O�X�N |
| 11 |
���Ԗ��� |
���[�O�X�N�A�V���O�X�N�A�O�X�N�R |
| 12 |
�n���쑺 |
�X���W���O�X�N�A�A�}�O�X�N�A����� |
| 13 |
��u�쑺 |
��u���ՁA�ɕ~����ՁA�}�J�C�O�X�N�A�N�B���O���O�X�N |
| 14 |
������ |
���]���ՁA�o���ߔe��ՁA�v���O�X�N�A�E�j�V�O�X�N�A������ՁA�^�ߗ�O�X�N�A�V�{�O�X�N
�A�~ ���`���v�i�[�O�X�N�A���O�X�N |
| 15 |
�I���� |
���d��O�X�N |
|
�S���A���������i�悵�䂫�j���u�����w�̎��p�v���u�����[�v���犧�s����B�@�@�@pid/9774413�@�@�d�v
|
�͂�����/1
��ꕔ �����w�̎��p
�����w�̎��_�ƕ��@/3
�� �ɔg���Q�Ɨ����w/3
�� �����w�ƕ����w�̎��_/6
�O �����w�̒n���I�̈�/10
�l ���������̌`��/13
�� �����w�Ɣ�r����/17
�Z ���ȔF���̊w��/21
�k�t�l�����w�̌ÓT�ɏA��/24
���T�Ђɂ��ǂ问������/29
�� �Ύv�̔���/29
�� �t��E���H�̎���/32
�O ���l�Ɠ쓇�l�Ƃ̌���/36
�l ���܂ݐl�̋L��/40
�k�t�l���x�����̓�������/43
�L�I�̐��E�Ɣ��l����������/49
�� �����̗���/49
�� �Y�w���ł��Ԃ�K��/54
�O ���l�ƈ�����l�̖��/59
��� �_�X�Ɛ��n
��Ԃƃj���C�J�i�C/67
�� �����_���̐��n/67
�� �j���C�J�i�C�̌��z/70
�����̛ޏ��̋V��/75
�� �����_���L�̑���/75
�� �N�X��j���̐V����/79
�O �R��_��/83 |
��ԂƎR�x�M��/88
�͂��߂Ɂ\�\���v���̌�x�M��/88
�� ���������̃I�^�P/90
�� �^�ߍ����̉F�Ǖ��x�M��/94
�O �R�x���߂���@���V��/97
�l �I�^�P�̕ϑJ/101
�ނ��с\�\�I�^�P�M�̗̈�/105
����̐��n�\�\�O�X�N�ƃe����/113
�͂��߂�/113
�� �O�X�N�̏��`��/114
�� ���n�Ƃ��ẴO�X�N/118
�O �g�㌠���̃O�X�N�ƃe��/123
�l ���A�ƕ����M��/128
��O�� ���������̔F��
���i���_�̖��/141
�� ���̗͂̔���/141
�� �D���Ɣ����ƃ��i����/146
�O ���V��ƃ��i���_/150
�l ���i����_�ƃ��P����_/154
�� �����܂�����/157
�Z ���i���_�̌�`/163
���i���_�ƍȂ̗�/169
�O ���i�����Ȃ�/169
�� �����̐_�̗�/171
�O ��̌Z��̌��ЂƂ��̗�/173
�l �����̐_�Ђ̏���/176
�� ���I�W�[���̏�/179
�����̊J蓐_�b�̕���`��/184 |
�� �J蓐_�b�̊�`��/184
�� ����Q���i�ÓT�j/186
�O ����Q���i�`���j/190
�l ���i�Ǖ���/192
�� ��E���E�哇/195
�Z �^�_��/199
�� �{�ÌQ��/200
�� ���d�R�Q��/203
�� ���ӂ̓�O�̖��/206
�̘b����问���O�j/213
�� �G�Ɩ��/213
�� �F���q/219
�O �@��~�e/225
�l ���ۓ�/231
������Ɨ���/244
�� ���̎��^�̔���/244
�� �I�������痮�̂�/247
�O �t�V�E�^�̒ꗬ/250
���������̔�r���w�I�W�]/254
�� �_�c�`���ƕ��V�Ԍ���/254
�� �O������O������/258
�H�K���Ɩ����w�I�F��/262
�� ���ю��̍�@/262
�� �̐��_����/264
��L/267
�E
�E |
�T���A��ё��� [�ق�]�ҁu����̌Ñ㕶�� : �V���|�W�E���v���u���w�فv���犧�s�����B�@�@pid/9774459
|
�V���|�W�E���Q���҂̏Љ�/5
��_ �u�S�����̓쉺�v���߂����� �J�쌒��/7
�ג��n���`�������ǂ�/8
���鍑�̐����Ƒ�ꏮ���̒a��/9
�����̍�������Ə����̒��v�f��/11
�`���Ɏc��x�z�҂ƓS/14
�k�����炫���n���_�A�}�~�L��/17
�g�����Ԃɂ݂郄�}�g�̉e/19
���X�ɓ`���b��_�̓`��/22
����ꂵ���S�̗�/23
��_ ���ꕶ�������̉ۑ�Ǝp���ɂ���
�@�@���\�����������ǂ��݂邩�\ �����\�G/27
�����`���ɖ�����������������/28
�j���C�J�i�C�M�̐����v�z/30
�쓇�Ɏc��{�y�̌Ñ��/34
�������Ȃ����{�Ɨ����̕���/36
�B���ꂽ�{�y�Ƃ̌���/39
���Ɨ��������������ւ̋^��/42
���{�Ɠ��Âւ̗畨�i��/45
���{�̑����Ƃ��Ă̋L�^/48
�Ί��ɋL���ꂽ���Ɖ��̏̍�/49
�u������v�ɂ݂�{�y�Ɨ����̈�̊�/53
�����������܂˂��������{���ꇁ/56
���_ ����Ñ㕶�����߂����ā\���ꂩ��̕����A
�@�@������ւ̕����\ �q�i��r���Ǒq�g/59
�O���N�O�̎R�����l�̕���/62
���ꋌ�Ί펞��̈ʒu�Â�/66
�܌`���y��ƋǕ������Ε�/69
��B�������ɓ���ꕶ�O���̉���/74
�ŗL�̓y�킪�h�����ꕶ���/78
�퐶�����̐Z���x�͖��m��/80
�O�X�N����͈�I����/82
������i��ł�����������/84
�����j����n��j��/86
�œ_�͊e�n��Ԃ̔�r����/89
��Ɏc���ꂽ�`�l�̋L��/91
�s�V�s���̖�������߂�/93
�p�ɂ������]��n���Ƃ̌���/95
�o�N�\�������Ƃ̊֘A��/99
�S�퓱���ɂ���ޗ��j�̃v���Z�X/102
����̐Ί�l�\�V�l�A���̏ꍇ/105
�O�X�N�͓S�펞��̏ے���/107
�����뎞��̉B�ꂽ���/109
�S�����̎���ɂ��n�捷/111
���Ȃǂ�Ȃ��Ί�̈З�/113
�ӊO�ɑ��������D�̔��B/117
�A���ɗ����Ă����S��/118
�x�[���ɕ�܂ꂽ�y��̌n��/121
|
�u���v�͉����̔ے�ɂȂ��邩/125
�Õ����㕶���̗�����j����/129
�u��̌��t�v�Ɓu���̌��t�v/132
��̂������������{/134
�u���̎�v�͒n��̓���/137
�������̕����I�����I�e���g���[/139
�u�×�������v�͍����`���̎���/142
�T���K�ɂ݂鏗�_�g�D�̃��f��/144
�������{�̃_�C�i�~�Y��/148
�����[���k�C���Ƃ̔�r/152
���E�֒ʂ��Ă����C�̓�/154
��� ����Ñ㕶���̔w�i/159
����̃O�X�N���� �������G/160
�u�O�X�N�v�̕��z�Ɨ��n����/160
���ʂ�����l�Êw�I����/162
�╨�ɂ����ꂽ�O�X�N����̓���/167
������̗A���������炵���Љ�̕ω�/172
�ҔN�A���ޕʂɂ݂鐫�i�̕ϑJ/174
�Ȃ��������𖾕���/179
�u������v�Ƃ͂Ȃɂ� �r�{����/184
�x�z�҂̎v�z�f/184
�J��Ԃ��̑����Ɠ��Ȏ��^/187
���J�A�V��̂Ƃ��Ĕ��W/189
�V����ւ̊�@���Ɏx����ꂽ�ҏW����/192
�����̏������ɂȂ肦�Ȃ������_��/195
������ɂ��ā\�\���{��̂Ȃ��ł̈ʒu�Â��\ ���{���q/199
�Ǝ��̗��j����ޗ�����/199
�����Ƃɕ����������G�ȕ���/201
�d�v�Ȍn���ƌꌹ�̉�/204
���C�@���Ɏc�錴���{��̓���/207
�����̑Δn�Ə@���\�����̗����̂��߂� �r��דT/211
�O���ƍ��h�̍őO���ɕ����ԓ�/211
�`���̋��_�ƂȂ����Δn/213
�y�̐E���߂���{�@�Ə����Ƃ̑���/216
�Δn���\��Y�̎x�z�֏��o��/218
�ʌ�f�Ղ̓���������/221
�C�㊈���ւ̈ˑ������߂�/224
�O�Y�̗��ŋ��߂�ꂽ���N�f��/226
���������Ƃ̊W�������璩�N�o��/228
�ߐ��ւ̓W�]�\�����̏����Ƃ̔�r/231
�����Ɠ���A�W�A�̏����� ���c��/233
�A���^�������Ƃ̖��ڂȊW/233
���Ղ̃C�j�V�A�`�u���Ƃ����؋�/235
�f�Ղ̗��v�ō��ƌ��͂��m��/238
�V���x�Ƀ^�C�����̍���/240
�����Ւn�}/72
����W���j�N�\/244
�p��E�ŗL�����/255 |
�T���A�u�{�闬 �{��\�P���������� ��O�� ���x���\��v�����s�����B�@
�@�@�@�Ƃ��F���a58�N5��14��(�y)�E15��(��) �Ƃ���F���������������� �@�����V��z�[���@�@53p�@�@�����F��㊌����}���فF1004250419
�U���A�������v���u�ޏ��ƕ����j : �F���u��̎g���ƓW�J�v���u�g��O���فv���犧�s����B�@
�@�@�@�@(������w�l���Ȋw�������p��)�@pid/12266378
�U���A���v�`���u���m�_�� �Ñ㖯���M�̌����v�\����B�@
�V���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.8�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
|
�u���ꌧ�ǒJ���n��m������Տo�y�̑]���n�y���
�@�@�����̉��w�o�y�̓y����߂����� -���{�{�y�̓ꕶ�y�핶����
�@�@���؍��̋����n�y�핶���Ƃ̌𗬖��v �]�� �P�\�^��
����ɂ�����S�֘A��ՂƓS�펑���ɂ��� �O�X�N��Ղ�
�@�@�������𒆐S�Ƃ��� ��� �d�^�� |
����o�y�̜\���y��ˌ� (1) �ݖ{ �`�F�^��
�����E��E���r�ؔ_����Տo�y�̃C�g�}�L�{��������
�@�@���퐶���y�푼 �㌴ �Á^��
���v���y��(1) ���R �����^��
�V���W����(�l�ÊW)�ꗗ �F�� �G�q�^�� |
�V���P�O���A�Ί_�s�V�l�����Z���^�[�z�[���ɉ����āu��8��|�\�j����������\���v���J�����B
�V���A����|�\�j������ҁu��8��|�\�j����������\��� : ���J�u��
�������\�v�|�y���Y�\�ӏ܃v���O�����v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@42p�@�����F���ꌧ���}���فF1004262521
�W���R���A���q�F���Y���S���Ȃ�B�i���N�F�W�S�j
�W���Q�O���A���v���S���Ȃ�B�@�i���N�F�T�U�j
�X���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 20(1)(61)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437775�@
|
������n���_�b�ɂ����鏕���u�ȁv�̉���
�@�@��=Interpretation of the Particle / �O�Ԏ�P/p1~5
�w�����낳�����x�̌W�茋�тɂ���=�ԋ{���i/p6~25
�I������b�l--<��>�ɂ���=�I������b :
�@�@���T�O�̍l�@ / ���R�a�s/p26~37
�u�d���I�����v--���{���w������u�d���I�����v�𒆐S��
�@�@��=�����K��/p38~55�̎ʖ{�Ɏ����ꂽ�_���v���P�[�V�����𒆐S��
�w�����낳�����x�ɂ�����l�i������
|
�@�@���č\�A�p�`�ɂ���=�ԋ{���i/p56~65
�u������v���l=�g�Ɗԉi�g/p66~74
�w���ꕶ���x�� ���ڎ�(1961~1983)=�S���e/p77~93
�I�����\�V��1����1�̃I����=�I������1����30�̃I����
�@�@��/���r���E�g���v�\��/p<>~<>
�V���Љ�=�V�����ЏЉ�/p55~55,93~93
���s�j���[�X=���s�j���[�X/p65~65
���]=���] / ���Ԓ��m/p75~76 |
�X���A�|�\�w��� �u�|�\ 25(9)(295)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276490
|
����������y�j�����Ɩ����w� / �쑺����/p7�`7
���c�����Ǝs��c�\�Y / ����ӈ�/p8�`16
�n���ʉ̕���Y�ȉ��-251- / ���������Y/p17�`19
�܌��M�v�̐��E(81)-���o�Β��̉� / ����O�F ;�F����o�j/p20~22
���y�ς̃R�y���j�N�X�I�]��\
�@�@���������q����{���y�̌Ñw� / ���䓿���Y/p23�`24
�s��뒘����x�̃R�X�����W�[� / �����/p25�`25
�˕���쒘�u�̕���v/p26~26
�����N�\( 8��1���` 8��31��) / ���c�m/p27�`36
���x�N�\(���a58�N6�������7��) / �@���q/p37�`41 |
�����u��O�����v / ��،�/p42~42
�m�����l�㕑�x�t�F�X�e�B�o���\
�@�@���n�����x�Ƃ̊���� / �����/p43�`43
���x��쎌�̒��쌠�N�Q� / �m�����Õv/p44�`45
�f�梌|�p�ՂƓ��{�f�� / ���Njv�l�Y/p45�`46
�\���������]�ł������܌������ / �ӎO�Y/p47�`47
�\�̗\�]��_���ƃr���X��d�\����ף/p48�`48
���a�\���N�x�|�p�ՎQ������/p49�`53
������/p54~56
�]��/p56~57�@�V���ē�/p58~58 |
�X���A���c ���q�����{�̗w�w��ҁu���{�̗w���� (�ʍ� 22) p.p65�`68�v�Ɂu�u���{���y�̌Ñw�v�������q�v���Љ��BJ-STAGE
�P�O���A����v�ē������ψ���ҁu����v�ē� : �u����v�ē��̌���E�����E�Љ�̑����I�����v��
�����сv���u�O�����v���犧�s�����Bpid/9774574
|
��ꕔ �v�ē��Õ����i��j
�i��j�{����
�� �v�Ē������L / 3
�� �N�앗�R����ʊK������ / 62
�O �v�ċ�u��Ԑ؋��L / 85
��� / 96
�i��j������ / 99
��� �v�ē��Õ����i��j
�}�� / 210
�� �v�Ē����Ԑ،������q贐��\�O�N�r / 211
�� �v�Ē����Ԑ،������q�����\��N�r / 235
�O �v�Ē����Ԑ؏��������� / 282
�l �v�ċ�u��Ԑؗᒠ / 298
�� �Ȑl������ / 310
�Z �@�� / 314
�� ���Z���ƕ� / 322
�� ���j���ƕ� / 365
�� �������ƕ� / 372
�\ ���c�R���L / 389
�\�� �a�B���ƕ��n�� ���� / 403
�\�� �v�ċ�u��Ԑ؏��n���쓾�� / 410
�\�O �v�ċ�u��Ԑ� �Î芡�� ��]�F���� �� |
�@�@�� ��[������ / 416
�\�l �v�ċ�u��Ԑ� ��]�F���E�R�����E���n���E�Î芡�� ��u�쑺�E
�@�@�����ڑ��E���������E��c���E���鑺 �c����[�� / 419
�\�� �v�ċ�u��Ԑ� ��]�F���E�R�����E���n���E�Î芡�� ��u�쑺�E
�@�@�����ڑ��E���������E��c���E���鑺 ������[�� / 428
��� / 432
��O�� �v�ē��̖������
��w�������R���L�x���ڋv�ē���Ԃ̌��� / 441
�� �v�ē��e�W��������Ւn�} / 465
�O �v�ē��e�W��������Վʐ^�W / 483
�l �v�ē������n�_�ꗗ�\ / 505
�� �v�ē������n�}�E�����ꗗ�E�������� / 510
�����ژ^��� / 516
�܍��n�} / 517
�}��E�ԍ�����
�S�}1 �v�ē���ԁE�q���n�}
�S�}2 �v�ē����Ւn�}
�S�}3 �v�ē��Ó��n�}
�v�ē������n�}
���Ƃ����\�v�ē��������I���ā\ �O�Ԏ�P / 521
�t�^�E�@����w�Z�N�Ԃ̋v�ē����� �O�Ԏ�P / 523
�E |
�P�O���A���c���q���u�������w�Ƃ��̎��Ӂv���u�Y�R�t�o�Łv���犧�s����B
�P�P���A���{�������u蔗� : ����w�l�Êw���������b�� 8 p.6-7�@����w�l�Êw���������v�Ɂu�p�v�A�E�j���[�M�j�A�쐼�݂̃J�k�[�v�\����B �iIRDB�j
�P�P���U���A�ߔe�s����ّ�z�[���ɉ����āu��Ԕɂ����Ȃ�������� ���T�C�^���v���J�����B
�P�P���A��Ԕɂ����Ȃ�����������s�ψ���ҁu��Ԕɂ����Ȃ���������v���u��Ԕɂ����Ȃ�����������s�ψ���v���犧�s�����B�@�@28p �@�����F��㊌����}���فF1005223407 �@
�P�Q���A�u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 12(2)�v���u���ꍑ�ۑ�w���w���v���犧�s�����B
|
����̗��K�_�`�� : ����{�����������̐_�b�ƋV�� �������� p.1-12
���������Ƌ�B�������Ƃ̔�r(V) �@�쌴�O�` p.A1-A14
�u�������v�����̍l(��) : �҂_�� ���R�� p.13-28 |
�u�����낳�����v�̏����u����v�ɂ��� �����r�O p.29-38
��㕶�w�̕\���E�ے��ƚg :
�@�@���u�[��̎����v(�Ŗ��َO)���߂����� �Y�c�`�a p.39-49 |
�P�Q���A�����Ǐ͒��ҁu�䊥�D��b�v���u��ĎЁv���犧�s�����B�@318p�@�@�����F��㊌����}���فF1001512340
�@�@�@����Ǐ͂̌��^������:�Ôg���ۍD, ��Ԕ�, �ď�b
���A���̔N�A�n�Õ~��͂��u����̓`�����x(�ÓT���x��͐l���̗̉x)�v���u��|���v���犧�s����B�@
�@�@�@211p �@�����F���ꌧ���}���فF1001617610
|
���x�̑n�삳�ꂽ�N��ƈӐ} 1
�����^�V�Ƃ̉ƕ��v�} 10
�ʏ钩�O�̎��x�W�听�̈Ӑ} 15
���̉̎��ƕ��x�̎� 20
�̂̉���ƚ��q�� 25
���Ɨx��̓��e�Ɣ͈� 28
���Ɨx�� 30
�^�Ǝ� 40 |
���s�ƃK�}�N�Ɠ��g�ɂ��� 47
�ڕt�ɂ��� 53
��O���ɂ��� 58
��{���x�Ƃ��Ắu������ŕ��v�ɂ��� 68
�ߖ�(�Ȗ�)������ŕ��߂ƃJ���W���蕗 81
�����e�_����G���t�Ƃ����q�O�Z�� 85
�ÓT���x�̉�� 87
����@��Ԗځ@�{�щ� 90 |
��Ԗځ@�V�� 96
�O�Ԗځ@�������� 107
�l�Ԗځ@�� 124
�ܔԖځ@��c 153
�Z�Ԗځ@�ɖ�g�� 161
���Ԗځ@���� 187
�v���o(�ʐ^�W) 204
���Ƃ��� |
���A���̔N�A�{�Ǔ��s�� ; ���Ԉ�Y�� ; �Ί_���F�� �u���d�R��������@���{�����p���@�������w�I�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@
(�{�Ǔ��s�S�W ; �P�W)
���A���̔N�A�R�� �C���u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (�ʍ� 49) p.p146�`148�v�Ɂu�u�������w�Ƃ��̎��Ӂv���c���q���v���Љ��B |
| 1984 |
59 |
�E |
�P���A������q��������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��� (�ʍ� 27) p.p213�`245�@������w����w���v�Ɂu����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-4-�ÓT�E���x��u�ɖ�g�߁v�ɂ��āv�\����B
|
������q���u������w����w���I�v. ��� (�ʍ�19�` 27)�ɔ��\�����u����̗x��̕\�������i1�`4�j�v��
�@�@�@�u����̗x��i1�`4�j -���x���̑̌n�����߂�����-�v�Ɋւ���_���̓���\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 19) p.p51�`67
(�ʍ� 19) p.p69�`85 |
1976-03 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-1-�ÓT���x�u������ŕ��v�ɂ���
����̗x��-1-�ÓT���x�u������ŕ��v--���x���̑̌n�����߂����� |
| 2 |
(�ʍ� 20) p.p117�`162
(�ʍ� 20) p.p163�`209 |
1976-12 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-2-�ÓT���x�u���ԁv�ɂ��ā@
����̗x��-2-�ÓT���x�u���ԁv--���x���̑̌n�����߂����ā@
|
| 3 |
(�ʍ� 21) p.p33�`96
(�ʍ� 21) p.p97�`157
|
1977-12 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-3-�ÓT���x�u�����ǖ��v�ɂ��ā@
����̗x��-3-�ÓT���x�u�����ǖ��v--���x���̑̌n�����߂����ā@
|
| 4 |
(�ʍ�26) p.73-124 |
1983-01 |
����̗x��-4- �ÓT���x�E���x��u�ɖ�g�߁v : ���x���̑̌n�����߂����ā@
|
| 5 |
(�ʍ� 27) p.p213�`245 |
1984-01 |
����̗x��̕\�������Ɋւ��錤��-4-�ÓT�E���x��u�ɖ�g�߁v�ɂ��� |
|
�Q���Q�O���A���쐴�q���Ȃ��Ȃ�B�i���N�F88�j
�Q���A�����V��Еҁ^����|�\�A���ҁu���O�� : �ʏ钩�O���a300�N�L�v���u�����V��Ёv���犧�s�����B
�@�@�@77p �@�@�����F���ꌧ�������فF1004838585
|
�u���O�Ձv�J�Âɓ����� �ɓ��� ����
�u���O�Ձv�ɓ����� �{�� �\��
�u�ʏ钩�O�ƌ���v ��� ���T |
���O�́u�ܔԁv�ƒ��O�� �r�{ ����
�u�p���Ƒn���̌��Ȃ����̔N�v ���� ��Y
�����v���O���� |
�ʏ钩�O�g�x�u�ܔԁv�r�{
�ʏ钩�O�̔N�����^
�E |
�Q���A���{���������j�w��ҁu���������j = Design of life (2)�@�v���u���{���������j�w��v���犧�s�����Bpid/7957687
|
���G A�E�J���[ ���m�N�� ����݂̐������ƌ��p ����݁E�U�E���[���h �n������
����E���z�� / ���c�F�N/p5�`
���G B�E���m�N�� �Ί_���약�̌���� ���ߍ� ���\���d�[�̐ߍ� / ���v�`/p61�`64
���k�� ������o�ƔN���s��--���G�ȗv�f������錻����{�l�̐����̒��̗�����o���߂����� / ���c�F�N ;�k���r�v ;�F��o/p13~21
��݂��� ���z�ƌ��ɂ�������̐��藧�� �l�ނɗ�������炵���v��\���I�����̒m�b
/ ���c�F�N/p24�`33
��݂��� �_���ɉe����^������Ǝ��R�� ��̐�����Ă����_�k�V��Ɣ_���Љ� / �c�����/p34�`44
��݂��� �N���s���̍\���_ �N���s���̗R���ƍ\�����̎����ɏƂ炵�ĉ� / �k���r�v/p46�`53
��݂��� �召��𒆐S�Ƃ������{�l�̗�̎����� ���j�̗���̏�ɗ����E�Ɋ�������{�̃J�����_�[
/ ����ꐬ/p54�`60
��݂��� �����ɂ��������̑卬�� �����J��--�s�s�ߑ㉻�ւ̔����V���̍��� / �F��o/p66�`71
��݂��� ���{�l�Ɨ�̋g���� ����ɂ��̂������E���łȂǂ̃��[�c��T��� / ��J���j/p74�`84
�w��_�� �Ƃƕc�� �T�ؔ��݉ƍċ�����ʂ��� / ��˓c���j/p85�`91
�w��_�� �擇�̐��n�ƍՋV / ���v�`/p92�`104
�R���� etc �I���� ����̏�ɗ��u�����L�O�̓��v / ����ꐬ/p22~22
�R���� etc ���[�f�[ "���E�����Ԃ̗�"�̈Ӗ� / �F��o/p23~23
�R���� etc ���[ ���}���ɖ��������`���ƍ��Ղ�̐M�s���� / �{�{�U���Y/p45~45
�R���� etc �\�ܖ� �_���ɂƂ��Ă͑厖�Ȏ��n�V�� / �ѓ��g��/p65~65
�R���� etc �N���X�}�X ���z�����̓��u�~���̍Ղ�v / �X�I�Έ�/p72~72
�R���� etc ��Ɖ��� �@������`�������w�ɂ��ƂÂ����� / �����a�v/p73~73
���] / ����ꐬ ;�����` ;���z���O�Y/p105~106
�w��̓���/P107~107
���{���������j�w�� �������ꗗ/p107�`107
�����ǂ����/p108~108 |
�Q���A�F�쏬�l�Y������l�`���Z���^�[ �ҁu����l�`���Z���^�[�I�v�@�R�@����l�`���Z���^�[�v���u����̐l�`�ŋ��u�����Y�v�i�`�����_���[�j�̌����v�\����B�@�@102p �@�@�����F��㊌����}���فF1001692118
|
����̎��������Y 1
�`�����_���[�Ƃ������̂ƗR��� 4
�n���`���ɂ��� 13
�A���j�����̃t�g�E�L�}�[�V�[ 20
�����Y�̌|�̎��� 33
�G�|�c�I�Ȑ��i�ɂ��� 33 |
�㉉�̋G�Ə��]�̗v�� 37
�㉉�̐l���Ґ� 40
���̕��� 42
�l�`���� 43
�l�` 52
���� 60
|
�����Ƃ��̓��e 62
�����Ƃ��̓��e 62
�����ɔ����̎� 63
���_ 100
���Ƃ��� 101
�E |
�R���A�얞�M�� �ҁu�V���ꕶ�w ��59���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001674058
|
�q�Όہr�u�j����v�̍K�� �v�z�̕s�݁E�s�݂̎v�z �F�� ��l
����w�̂䂭�� �֍� ���i
�s�t�̕��� �X�c �Аi
�q���k��r�a�߂�ɐ荞�� �ʖ��F�Y
�@�@�����A�ɗY �n�v�R�� ���� ���^�k �얞 �M��^�i��
�i�݂䂭�c�Љ� ���ꂢ ������
�݉��ČR-���̌��� ���� ���_
�J���Ɠ��Љ�̍r�p ���� ���v
���ꂩ��̕�-���k�w���l�j �K�� �ǏG
�����s���̕n�� ���� ����
�J���s���Ǝ��R�j�� �� ����
���A���́u�����퍑�j�v�� �ʖ� �ꕺ
���w�̌��� ���{ �b��
���y�̌��� ���� ��
�G���W�[�g�����]�h �_�J ���P
����̍H�|�Y�Ƃɂ�������_�Ə����̓W�] ��� ����
�S�͎ዷ�� �V�� �i
�q�����r �i�ތ��܂�ʐ����S��(����)
���ꂵ���������(�o��)
�g�ԐM���h�̌�����(�s��)
�u�`���v�̈Ӗ�(����)
|
����o�ώ����_�ւ̋^�� �^�v�c ��
�q�C�O�W���[�i���r �������(�A�����J) �{�� �x��Y
���x��(�t�����X) �剺 �ˎ}
���������ƈ�ʎs���ɗ₽������(�\�A) �T�b �m��
���z�̊X�E�ߔe(5) �q�` �ĎO
�q���]�r �u���ւ�藠�ʎj�v
�u�吢�ш��M�v �u�������w�Ƃ��̎��Ӂv
�u�^�ߍ����̘̐b�v
�u���ꎖ�n�߁E�����j���T�v
�ʐ^�W�u����̖쒹�v
�u�쓇�k�s�v
���ꌎ���W�u��āv
�u���k���v �u�����Ìꎫ�T�v
�u���w�̓��v�̐�����
�u�䊥�D��b�v ���{���F���W�u���Ɋāv
�u����̕����v
�u�T�� ����̘J���o�ρv
�u�����ے}�O�哇�Y���v
�u�����̉ԁv �F���o�v�̏W�u�������ǂ�v
�q���|���^�[�W���r���܂蓇����Ă� �� ����
����W�V���}���ژ^ |
�R���A��]�F�q�v���u�����w�������I�v (�ʍ� 8) p.33-88�@�����w�����w�������v�Ɂu�u�l�{���Ɨ�v�Ɖ��ꖯ��--����E�r��ɂ��āv�\����B�@
�@
�R���A��t�������u�x��j�{ 61 p.111-120�x��j�w��v�Ɂu �������v���w�ޏ��ƕ����j-�F���u��̎g���ƓW�J-�x��ǂށv���Љ��B
�iIRDB�j
�R���A���v�`�����{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 152) p.p52�`55�v�� �u�ޏ��ƕ����j--�F���u��̎g���ƓW�J�v�������v�� �v�\����B
�R���A�����o�ŕҁu���j�蒟 12(3)(125)�@ ���W�E���������̕����`�����v���u�����o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@pid/2246785�@���j�蒟�@��12��3���@���W�E�������̕����`���@�u�b�N�G���h�@�R�����b�{�s���g��1,000
|
�J��`���ƒn��_�]�� / ���䐳�O/p4�`10
�ŗt�_�y�̏����\�h�襋����V���������/�n�ӐL�v/p11�`21
�Վ��Ɛ_�a / �r�،v�q/p22~32
���ŗt�̉P���ۗx�� / �n�ӗǐ�/p34�`35
�����ӑm���i�̖K�L / ���R����/p36�`45
���ˑ��̌|�\�\�ӑm�ƃS�[�`��/����o��/���䐳�O/p46�`49
���y�����ُЉ� �ŗt�����j����������/�b��^�@/p33�`33
�������z ���j�Ǝ� / ���{�S�j/p3�` |
�����ېV���̏��]�ˎ�J�X�����ɂ���(��) / ���T�s/p50�`52
�ǎғ��e ���鑐�͂̌����\�\���c�������` / ����ꏺ/p53�`55
�q�ǂ��Ɛ̘b�\�����̃X�g�[���[�e���[����(1)
�@�@���̘b�ƌ���/�����y�q/p56�`57
���ɕ{�����}(�ŏI��)(20)�������Ղ߂��� / ���q���F/p58�`59
�Εt������,�����ߗގn���̎�(15)�Õ������j�U�� / �������/p60�`64
�n���j�o�Ŗژ^/�n���j�G�������ژ^/p65�`81
�E |
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (10)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@�@�@pid/3467953
|
���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(III) / ���a�c�^�~ ;�m�O�E/p1~24
����Q���̗�����ޑ�(III) / ���R����/p25~36 |
�R�����j�����u��q�̖쑺�H�H�l�v�ɂ��� / �X�ۉh���Y/p37�`44
�����Љ� ���ߏ����Õ����������(��) / ��]�F�q�v/p1�`24 |
�R���A�u�ɕ����E�ɐ��������� �v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@
�@ (�n�挤���V���[�Y ; no.5)pid/97754591
|
���� �{��C�j/1
�ɕ����E�ɐ����\���̒n���I�T�v�\ ���O����/3
�ɕ������ɂ����錋 ��ËP�K/15
�ɕ����E�ɐ����ɂ����鋤�����X�Ƒ��������� ���O����/25
�ɕ����E�ɐ����̉Ƒ��\�V�l�𒆐S�Ɂ\ �ʏ闲�Y/31
�E���U�~�ƃV�k�O�\�ɕ������c���̔N���s���\ ���R��/67
�V���|�W�E���u�ɕ������̒n��Â�����l����v�i�� ���O����/99 |
�������� �r�c���i/99
���
�n��Â���̉ۑ� �{��C�j/101
�_�ƐU���ƒn��Â��� ���ԑגj/109
�ɕ������ɂ�����n��Â���̎��ԂƖ��_ �����^��/115
���_/121
�E |
�R���A�Y�R���ꂪ�u���{���z�w�����. �����E��B�x��. 3, �v��n (6)
p.349-352�v�Ɂu�u������N��V����v�̌��z�I�f�` : ����̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤�� ����6(���z�j�E���z�ӏ�)
�v�\����B
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu��� : ��ԐM�K�����z���� 1 �F����{���y�ю��ӗ����v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@
(���ꌧ������������ ; ��59�W)�@�@�@106p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001687589
|
�� �}�� �T���u����̌�ԁv �茴 �P�V�^��
�����n��
������ ���� �r�O 7
���� ���� �r�O 19
�{���� �c�� ���� 23
�X����� ���� �r�O 29
������ ���� �r�O 37 |
�����n��
�ǒJ�� ���Ð^�@�X�� 41
����s �{�� ���� ���� �r�O 49
���K�n��
�m�O�� �g�l �E 57
�^�ߌ��� �茴 �P�V 67
�앗���� �g�l �E 73 |
����
�ɍ]��(�ɍ]��) ��� �w 85
�ɐ�����(�ɐ�����) ��� �w 91
�{�铇(�^�ߏ鑺) �茴 �P�V 97
�Ɍv��(�^�ߏ鑺) �茴 �P�V 101
�Ì���(���A��) ���Ð^�@�X�� 105
�E |
�R���A���u�\��, �X�e�B�[�u ���u���ۓ��{���w�����W���c�^ (7) p.73-87�@�����w���������فv�Ɂu�������\(2)�@�푈�Ǝ��@�\�^�Ӗ쏻�q����R�V�����܂Ł\�v�\����B
�S���A�����Ɩ����u�����ؖ� : �����Ɩ��̐��̏ؖ��v���u�����V���Ёv���犧�s����B�@ (���a�ʐ^�E�S�d��) 157p;
�T���A�u���� (212) �v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@pid/3465324
|
�ʐ^=�t,�݂��̂� / ��c����Y/p1�`1
���W ���쐴�q�搶=�Ǔ� //p2~31
�u���`�v��� / ���쐴�q/p2~6
���쐴�q����ƕ�n�E����/�n������/p8�`11
���쐴�q����̂��� / �����Y/p12�`13
�{���̂̋���҂��� |
���{���̂̌�����/��ؓ�Y/p14�`15
���̐��쐴�q����/���c�v�q/p16�`17
�B��f���t�A��,���쐴�q�搶/�s���N�q/p18�`19
����̓I�E���쐴�q�搶/���Ђ�q/p20�`21
�u�C���L�v�ƕ�̎���̏�����/�V�앐/p22�`23
�ʔ��������� / �{����/p24~25 |
���쐴�q�����
�@�@�����P/�؈�m��/p26�`27
�v������ / ���J�\�Y/p28~31
5���V���ē� //p1~4
�E
�E |
�U���R�O���`�V���Q�Q�����A�u���ꌧ�������فv�ɉ����āu�����|�\�̐��I :
�ʏ钩�O���a300�N�L�O�v�W���J�����B
�@�@�@�@��ÁF�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ� ���ꌧ����ψ��� ���ꌧ��������
�U���A�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ�W���ψ���ҁu�����|�\�̐��I : �ʏ钩�O���a300�N�L�O�v���u�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ�v���犧�s�����B�@�@�@114p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002096384
�U���A���{���q, ��Î����u���ꕗ�����v���u��C�ُ��X�v���犧�s����B�@�@pid/9774804
|
���y�Ƃ��Ƃ� ���{���q
���y/3
�^�앗����߂���/4
�����̕��y/6
�������̑傫���̌��t/12
���������{�A�傫������/14
�E���W��������/17
���y���琶�܂��G��/20
���R/29
���z�ƃj���C�M��/30
���/38
�䕗/40
�C�̃`���{�[���[/44
�C�ƒÔg/46
�X�ƎR/56
��Ɛ�/60
�n�[�x�[���i���j�Ƃ��̌ꌹ/63
���̃N�K�ƃg�D�k�J/68
�n�u/70
�e�B���V���O�k�n�i�i�P��ԁj/76
�n�C�r�X�J�X�ƒ��/79
����/83 |
�D�Ƌ��Ɓ\���C�ƊO�C/84
�j�k�t�@�u�V�i�k�ɐ��j���߂�����/100
�E�F�[�N�i�D�j�̌ꌹ/103
�c���Ɣ_�Ɓ\���Ƃ�����/108
����̈��/119
�}�̕���/127
�H�����\���A���A�A�R�r�A��/134
�S�[���[�ƃi�[�x�[���[/151
�D���[�V�i���j�̌ꌹ/155
���[�A�V�r�[�i�їV�сj/157
�n�[���[�iগ��D�j/163
���^�̎Љ�/166
�L�W���i�[�i�d���j/171
�O�[�T���i��j�̌ꌹ/174
�l��/177
��������/178
�߂[��[�̌ꌹ/180
�l�̌Ăт���/182
�����r�i�[�i�����j/185
���R�̑叫�����o�[�T�W�[/188
���ǂ��҂͑�������/191
�e�[�t�@�i��k�j�̌ꌹ/194 |
�E�`�i�[������_/196
�E���[�i�c��j�Ƃ��O�͓���/199
�E�X���[�i�c���j�ƃn�[���[�i�c��j/201
�T�g�D�i���j�ƃ��]�i�����j/203
�i�K�j�ƃ��j�i�w�Ƌ��j/207
�����ƌ|�\ ��Î�
���҂̂䂭���\���E�̃C���[�W/213
���Ԃ̐��_�Ö@��\���^�̈�@�\/216
�}�u�C���߁\������/219
���̗\���\�K���̉��ƃJ���X�̖���/221
�C�_�Ձi�E���W���~�j/223
�n�u�ƃ}���O�[�X/225
�V�[�T�[�i�����q�j/228
�ߔe�s��/229
�����̉���\�V�h��/231
����ƒ���/234
���j��\�ԓy�̗��o�ƎX��ʂ̎�/237
���Љ�Ɛ��\�J��Ƒ䕗/239
�̌��w�����Áx�\����Ń��~�I�ƃW�����G�b�g/244
�l����\���ӂ̘J���Ɨ��̎n��/247
����ŋ�/249
�䊥�D�x��\����̋{��|�\/250���Ƃ���/253 |
�U���A�u���w 52(6) p.p1�`228�@����̕��w�E�|�\<���W> �v���u��g���X�v���犧�s�����B�@ �P�O�O�O�~
|
�쓇�̗w���߂����� �O�� ��P,�R�� ���j,��] ���O�Y p.p1�`32
�쓇�̗w�ɂ݂�u���v�L���̐����� �O�� ��P p.p33�`47
�쓇�̗w�̉̌`�@�ʏ� ���� p.p48�`59
���d�R�̗w�̌`��--"��"�Ɖ̏��@�𒆐S�� �g�Ɗ� �i�g p.p60�`73
"�̊|��"�������̒��̓쓇 �y�� �� p.p76�`89
������̏C���w--���g�ƈÚg���l����Hugh Clarke p.p90�`100
�E�o�Ɖ�A--����̏��a�������w�̈�� ���{ �b�� p.p101�`109
�A�W�A�̒��ɂ݂鉫��̌|�\�@�{�c���� p.p110�`118
���{�̒��̉���̌|�\--
�@�@�����x�̋Z�@�𒆐S�� �O�� ���Y p.p120�`131
�\�Ɖ���̌ÓT���x�@ ���P�Y p.p132�`142
�A�W�A�̒��ɂ݂鉫��̉��y ���c���q p.p143�`152 |
���{�̒��̉��ꉹ�y �������q p.p153�`162
����ɂ����钆�����y�̎�e�ɂ���
�@�@��Robin Thompson ��,���] �F�i �� p.p163�`176
���q�F���Y�u���ꕶ���̈��v�nj� ���� �N p.p177�`182
�_�̐��a���߂���ՋV ���� �����Y p.p183�`186
�p�e�B���[�}�̐_�� �Z�J ��F p.p187�`191
����̐_�X�Ƃ̏o� Josef Kreiner p.p192�`194
���q�F���Y�搶�̗����|�p�����̂��ƂȂ� �{�� �Đ� p.p195�`198
�������� �ɍ��� �V p.p199�`205
�����R���������� ��� �� p.p206�`217
����̌���̂₫���� ���� �M�v p.p218�`223
�����Ɠ��̏ĕ��l�� ��� ���� p.p224�`228 |
�U���A�n������, ���c���ҁu�쓇�̈�앶�� : �^�ߍ����𒆐S�Ɂv���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@�@pid/9774816
|
�͂�����
I �쓇�̔_�k�ƈ��
�u�쓇�v�̔_�Ɗ�� ���J�D��/2
�쓇�̓`���I���_�k�Z�p ���X�؍���/29
���d�R�̈�̌n���\�H���Ăƍݗ��� �n������/67
II �쓇�̈��Љ�ƕ���
�ΊO�W����݂������Ñ�j�\
�@�@���쓇���j�̗����̂��߂� ���c��/94
�쓇�̈��V��\����E���d�R�E�^�ߍ� �Ί_���F/126
�쓇���N���`���̌n�� ��ё���/160
|
�����E�Ƃ��Ă̍\���ƒ��� ���J�I�v/191
�^�ߍ��Љ�̓쓇�I���i�\���̐��Ԃƍ\���ւ̎��_ �ѓ���/213
III �^�ߍ����̈��
�^�ߍ����̐��c���n�ƈ��Z�p�\�H���ē����ȑO��
�@�@���`���I���̑̌n�𒆐S�� �c���k�i/232
�^�ߍ����ɂ����鐅�c�̕��ނƍݗ��̈��_�� ���R���v/263
�^�ߍ��_���̐����\���\���Ƃ̑Δ䂩�� ����V�n/295
�^�ߍ����W�����ژ^ ����V�n/324
��������
�E |
�U���A���a�c�^�~���u�Ȋw���� 44(6)(519)�@p100�`101 �����V���Ёv�Ɂu�����(6)�f�C�S�R�����Ԃ͉���̐S�v�\����Bpid/233529
|
���a�c�^�~���u�Ȋw���� 44(1�`6)�v�ɔ��\�����u�����(1�` 6)�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
44(1)(514) p100�`101 |
1984-01 |
�����(1)�\�e�c��̏�Ō��������R�ɑς��� |
pid/2335286 |
| 2 |
44(2)(515) p100�`101 |
1984-02 |
�C�Y�ѐ��ӂɍL����M�т̕ʓV�n �����(2) |
pid/2335287 |
| 3 |
44(3)(516) p100�`101 |
1984-03 |
�����(3)����L �Ñ�̒���f�Ղ��x�����ʉ� |
pid/2335288 |
| 4 |
44(4)(517) p100�`101 |
1984-04 |
���Ԗ� �����̖����~�����A��(4)����� |
pid/2335289 |
| 5 |
44(5)(518) p100�`101 |
1984-05 |
�����(5)��ؗt �H�������ʂ����J�[�V�� |
pid/2335290 |
| 6 |
44(6)(519) p100�`101 |
1984-06 |
�����(6)�f�C�S�R�����Ԃ͉���̐S |
pid/2335291 |
|
�U���A�얞�M�� �ҁu�V���ꕶ�w ��60���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�@
|
����E��p���j�̏���(�ʐ^)
�q�Όہr���q�G�b�Z�C ��p�Ǝ��r
�@�@��������p�Ŋw���� ���ǒ��c
��p�̓`�������ی�^���̎v���o �약���\
���̌̋� ���� �ϐ��
��p�Ǝ��̂����₩�Ȃ������ �K�����
��p�ς̊Â��� �N�㌳�Y
�X�p�C�e�^�őߕ߂���� �n������
�u�����v�Ɓu�W���c�v �ɍ]����
��p�ł̎��������^�� �약���� |
����l�����ɍ݂� ���鏇��
�u����a�v �n���� ��
�q���W�r�M���፷��-���ꂩ���p��
�@�@���������Ƃ̊w��I�𗬂ɖ]�� �E����
�ߐ��ɂ������p�Ɨ��� ���K�����Y
��p�A���n�x�z�Ɖ���(�l) ���g����
�u��p�̑O�r�v�ɂ������Ă������ ��ѐ���
��p���������Ɨ��@��� �t�R���N
���ꋳ��Ƒ�p���� �c����q
���k������ ���ʌ[�q
|
��p�̖�������� ��]�F��
���������镶�w �㗢����
����-��p�𗬂̑O�� �c���^�V
���� ���ؖ����̌���
���z�̊X�E�ߔe(6) �q�`�ĎO
�q�C�O�W���[�i���r���q���]�r
�u��ꂽ�I�L�i���v�ɉ����� ��쐽��
�����퍑�j(�n�̊�) �×z ���j �R��ꕽ
����W�V���}���E�G���_���ژ^
�E |
�V���V���A�Ɖ����P���ߔe�s����ψ���3�K�z�[���ŊJ�Â��ꂽ����|�\�j�������\���Łu�\�����߂ɂ��āv�\����B
�@�@�@12p�@�����F���ꌧ���}���فF1004574610�@�p���t���b�g�o�C���_�[�F����
|
��A���_ 1
��A�ʑ㐨�@�_���ւ̔��_ 5 |
�O�A�����[���Ր��ւ̔��_ 8
�l�A���_ 11 |
�V���A�����N�N���u�앗�̐����� : ����ǒJ���W�c�����v���u���S�Ёv���犧�s����B
�@�@(�m���t�B�N�V�����E�u�b�N�X)�@�@�d�v�@�W�O�O�~
�V���A�u����v�z 12(8)�v���u�y�Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6055440
|
���{���l���� �Z���`�����^���Y���̕|���� / �ё�/p8�`12
���{���l���� �ᖳ�ׂ̒��S��Ɓ�S�̐��� / ��ё���/p13�`17
���{���l���� �ꕶ�̓� / ������N/p18�`21
���{���l���� �`�l�����̍ĕ]�� / �X�_��/p22�`25
���{���l���� �n�ƌ��Ɠ�--���{�l�_�̂��߂� / �n������/p26�`29
���{�̎��R ���{�̐��� / ����O�O/p197�`207
���{�̎��R �V���ƒ�Z�̐l�ގj / ���c���K/p216�`223
���{�̎��R �Ɨt���т��߂����� / ���B�V/p208�`215
���{�̎��R �X�̕���--���Ԏj�I���{�_ / ���c�쌛/p224�`235
���{�l�̃��[�c �k���n���{�l�Ɠ���n���{�l / �ɓ�����/p66�`75
���{�l�̃��[�c �c��͊��l��
�@�@��-���{�l�N���_�̕��� / �����u��/p59�`65
����ƕ����̌n�� ���{�̕��l�̌��� / ���V�a�r/p256�`265
����ƕ����̌n�� ���{��̌n�������ǂ� / ���{���q/p266�`277
�������܂ꂽ�����ƕ��� ���̃��[�c / ���z���O�Y/p76�`85
�쓇�̃t�H�[�N���A--���E�ς̍\���^�j���C�J�i�C�^�u���{�v�̎v�z�^
�@�@���㐶�ƊC��^�Ȃ������_���ςȂ̂��^�u���v�̈Ӗ��^
�@�@���퐢����̐����́^�E�u�X�i�l / �J�쌒�� ;�R���ӈ�
�@�@��;�r�ؔ��V ;�g���b���q/p326~358
���{�̉������߂� �j�b�|���̉� / �ēc��Y/p236�`247
���{�̉������߂� �G�X�L���[�E�A�C�k�E
�@�@�����{--�k���������̉��ƕ����̌n�� / �J�{��V/p248�`455
����ꂽ�y������ �ڈ̐����ƕ��� / �V�쒼�g/p296�`305
����ꂽ�y������ �y�w偓`���Ƃ��̎��� / ����S/p306�`317
�t�H�[�N���A�̓_�Ɛ� �u�N���`���v�l |
�@�@���q�ǂ��ɈӖ����^������Ƃ� / �{�c�a�q/p186�`196
�t�H�[�N���A�̓_�Ɛ� ���{�u�����v�l �q���̖����w / �{�c�o/p278�`285
�t�H�[�N���A�̓_�Ɛ� ���|���f�̌��{
�@�@�����c���j�Ƌ{���̂����� / �R�ܓN�Y/p286�`295
���{�l�̎v�z�̍���ɂ������ ���{�Ñ�̃��^�t�B�W�b�N
�@�@���A�C�k�Ɖ���̕������肪����ɂ��� / �~����/p30�`51
���{�l�̎v�z�̍���ɂ������
�@�@�� �w�Î��L�x�_�b�ɂ����钆��\�� / �g�c�֕F/p86�`103
���{�l�̎v�z�̍���ɂ������ �Ñ���{�l�̐��E�� / ����m�[/p152�`161
���{�l�̎v�z�̍���ɂ������ �u���̍��v�ƊC�m�@�� / �ܘҏd/p104�`111
���{�l�̎v�z�̍���ɂ������
�@�@�������̎��R�ςƏC�s�_ ���߂���f�� / ����חY/p162�`169
�v�z�Ɗ����̍����� �u���̂�����v�`����w / ���Nj�/p170�`185
�v�z�Ɗ����̍����� ���{�l�̔��ӎ�
�@�@���u����Ȃ̍��~�v����̎��_ / �͍����Y/p52�`58
���������{�I���Ȃ̂� �t���܂ً̈�--
�@�@�������{���C���[�W�̕��� / �r�c��V/p318�`325
���������{�I���Ȃ̂� ���{�̃G�f�B�v�X / M�E�p���Q ;�O�Y�M�F/p112~119
�ٕ����Ƃ��Ă̓��{ �������̎v�l ���{�l�̍s���l��--��r�v�z�̗��ꂩ��^��_���Ƒ��_���^
�@�@���Ȃ����{�ł͉�������Ȃ̂��^����̐l�ފw�^�։�v�z�^���j�I�����Ɨ����^
�@�@���c�쐒�q�^���{�̖@���^�i�`�������I�[�_�[�̎v�z�^�ٌ�m�̂���Ȃ����^���{�l�͌Y���������^
�@�@���ڂɂ͖ڂ��^�_��Ƃ��Ă̌����^�_�̂��鍑���Ȃ����^�����ɂ��ۏ�ƎЉ�ۏ�^�h���̌����^
�@�@���]���Ɖ�S�^��ؐ��O�Ǝ��{��`�̐��_�^���ˊw�Ɣp�����߁^�����ɂ݂����u����{�j�v /
�@�@�� ������ ;�R�{����/p120~151
�E |
�V���A���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 154) �@�����҂��߂��閯��--���R�N��V���|�W�E���Ɍ�����<���W>�@p.p1�`90�v���u���{�����w��v���犧�s�����B
|
�����~�^�e�@�員�䂫 p.p1�`6
�����Ԃ�K���@�ѓ��g�� p.p6�`14
�ւ����߂��鎀��--�搧�ƍ��J��� �@���c�v�� p.p15�`23
��[�ɑ���S���̍l�@ �@������ p.p23�`27
���җ��ΏۂƂ����ʉߋV��--���c�J�R���̏ꍇ �ߓ����� p.p27�`40
���̃^�u�[���߂����l�@--���搳�j�̐��𒆐S�Ɂ@�я~ p.p41�`45
���n�̑����K��-���̂̈����Ƌ������̂��Ɓ@�O�Y �G�G p.p46�`52 |
���R�̎��҂��߂��閯���@�O�Y�G�G p.p52�`57
���O�n���̎��҂��߂��閯�� �O���v p.p57�`63
���҂��߂��閯��-�쓇�̎��_���� �R���ӈ� p.p63�`68
�����V��Ƃ��̍\���v�f�ɂ��ā@�V�J���I p.p69�`73
�\�o�n���̊ω����-�n��I���̔�����
�@�@���O�\�O�������̎��� �@�R�J�T�� p.p74�`90
�E |
�W���A�����V��Еҁu �G�C�T�[���� : �����O�|�\�v���u�����V��Ёv���犧�s�����B
�@�@�@�P�V�X�Ł@�@�����F���ꌧ���}���فF1004579494 �@�@�X�P�O�~
|
�O�Ԃꑾ��(�܂�����)
���Ȃ��G�C�T�[�Ȃ̂� �X�� �h���Y�^��
�}��10�� |
�G�C�T�[�Ł[�т�(�m����)
�G�C�T�[�E�G�b�Z�C
�݂�Ȃŗx�낤�T�[�G�C�T�[(���Z��) |
�킵���G�C�T�[(������)
�E
�E |
�X���A�얞�M�� �ҁu�V���ꕶ�w ��61���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�����F���ꌧ���}���فF1001674074�@�@
|
�{�Â̕��y�ƕ��� ���@�� ����
��j�w�͂�����ꂽ�� ���K�����Y
�{�Îj�_���̌��i�K ���� ���F
�{�Õ��w(�̗w)�̌����Ɖۑ� �V���K��
�l�Êw�ɂ݂�{�� ���n�a�G
�쓇�Ƒ��E ���� �a��
���̒�̃t�@�C���_�[ �����a
�P��ƁJ�C�̗��� �ݖ{�}�`�q
���V���Ƌ{�� ��� ��
��w�a�@��ǐ����ł̋{�� �R�� �p��
�{�Ðl�̋C�� ���� ����
���₮�̝R�� ���� ���g
���C�h�[�E���C�h�^���̂߂������� ���l�K�v |
�{�Â̐�㐭�� ���� �D��
���g�����}���镶�w���y �{�� �k��
���̕��������ƌ��� ���� �K�v
�{�Â̔N���s��(��) �{�i ��
�{�Â̖��w ���� ���K
�{�Â̊ό��ɂ��Ẵ��|�[�g �V�� �N�j
�{�Â̂��Ƃ� ���Ð^ �O��
�{�Â�������(�Z�́E�o��E��)
�ʓߔe���g�搶���Â� ���� ��Y
���M��搶���Â� ��� ��G
�o�ϐ�������ɐ��j���Ƃ炦�� -
�@�@���u��㉫��o�ώj�v��ǂ�� �V�� ����
�q�C�O�W���[�i���r |
�q�����Ȃ������E���ꂱ��(20)�r
�@�@�� �E�t�h�D�����[�C �V�� �i
���z�̊X�E�ߔe(7) �q�` �ĎO
�q��10��u�V���ꕶ�w�܁v�\�I���\�r
�q�����r
�q���]�r
�����퍑�j(���̊�) -
�@�@�����������n��30���N�L�O����
�@�@���×z ���j�^���� �R�� �ꕽ�^�r�{
����W�V���}��
�G���_���ژ^
�E
�E |
�X���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� �H�G���v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@�@pid/6067713
|
�������̘_��/�P�c�r�ܘY/p4�`6
���{�̗d��
�@�@���s�k�������m�K�~�����̖���/���O��/p7�`14
�d���̕������z�Ƃ��̉���
�@�@�����c���̍Č��� / �^�c�M��/p15�`19
�d���ꃂ�E�E���b�R�ɂ���/�J�쌒��/p20�`20
�؍��̗d�� ���邢�g�P�r�̐��i/������/p21�`25
���ǂ������̂��킢���� / �֓�����/p26�`29
���d�R�̗d�� / �q�쐴/p30~31
�����哇�̗d�� / �b���`��/p32�`33
|
�F�{�̉��k / ��������/p34~35
�Δn�̗d�� / �i���v�b/p36~37
�]��E���g�E�ɗ\�̗d��/���c��/p38�`39
�y���̉��� / �g���i��/p40~41
�����̗d�� / ���Ώ��b/p42~43
�R�z�H�̗d�� / ����і�/p44~45
�ɐ��̗d�� / �x�c�g�Y/p46~47
�F��̗d�� / ������z/p48~49
�ዷ�̗d�� / ���������Y/p50~51
�k���̐��d�`��/���ђ��Y/p52�`53
|
�x���̎R������ / ��{����/p54�`55
�M�B�̗d�� / �q�Β��F/p56~57
�֓��̗d�� / �ѓ��g��/p58~59
�z��̗d�� / ���v�ԓՈ�/p60~61
�o�H�̗d�� / �ː����/p62~63
�����̗d�� / �e�r�h��/p64~65
�Ìy�̗d�� / �X�R�ב��Y/p66~67
�A�C�k�̗d�� / �����/p68~69
�f��u�j�b�|�����E���~���v�]
�@�@��/������v/p70�`70 |
�X���A�ߔe�o�ŎЕҏW���ҁu���� : ���Ȃ�ꂽ�������ƕ��� �ʐ^�W�v���u�ߔe�o�ŎЁv���犧�s�����B
�@�@�@��������}���ُ���ID�F000001747927�@�@�S�O�O�O�~
|
���s�ɂ������ā@1
����������@9
��������
��@29
1�@�����
2�@�鐳�a
3�@�鐳�a����(�k)
4�@�鐳�a
5�@�鐳�a����
6�@�鐳�a
7�@�鐳�a�Ɠ�a
8�@���a�Ɣԏ�
9�@���a
10�@���a�V��
11�@��k�a
12�@�銽���
13�@�n���^���R
14�@�銽���
15�@�銽���Ύ��q
16�@�銽���㕔�E
17�@�銽���
18�@�间��
19�@�间��
20�@�鐐���
21�@�鐐���(��)
22�@��i����(��)
23�@��R����
24�@���_��̊K�i
25�@��p����
26�@��L����
27�@��䒆���
28�@�����
29�@����G�z
30�@���R��ƈ���ʂ�
31�@�����
32�@�����K�a
33�@�����K�a���̕���
34�@�������猩����K�a
35�@���
36�@��v�c�傩��E�t��֒ʂ��铹
37�@���ǂ̕���
38�@��E�t��֒ʂ��铹
39�@��E�t��
40�@�锒���Ɠ��A�U�i�֏���Βi
41�@�锒���Ɛ��a
42�@�锒���
43�@�铌�A�U�i�֏���Βi
�~�o���@55
44�@�~�o���R��ƕ�����
45�@�~�o�����a
46�@�~�o������
47�@�~�o������
48�@�~�o���E�e��
49�@�~�o�����e��
50�@�~�o������
51�@�~�o��������
52�@�~�o������������
53�@�~�o���R������̏\�Z������
54�@�~�o���R��(����)
55�@�~�o�����a�Ə��O
56�@�~�o�����a����
57�@�~�o�����q�A�{��d
58�@�~�o�������a����
59�@�~�o�������a����
60�@�~�o�����a�{��d
61�@�~�o�����a�V��
62�@�~�o�����a�O�w�~��
63�@�~�o�����q�A
64�@�~�o�������a
65�@�~�o�������a�V��
66�@�~�o�����a�ƌ�Ɠ����Ȃ��Ώ�
67�@�~�o�������a�G��
68�@�~�o�������a����
69�@�~�o�����O
�������@71
70�@��������
71�@���������_
72�@����������
73�@����������
74�@�������O������
75�@���������_����
76�@���������_����
77�@���������_����
78�@���������_����
79�@���������_�{��d
80�@��������(����)
�_�� ���t �_���@78
81�@���d�R�������{�a
82�@���g�{���i
83�@���g�{����
84�@���g�{�{�a���C��
85�@���g�{�C��
86�@�g�V��{
87�@�g�V��{
88�@���V�ԋ{�q�a
89�@���V�ԋ{�{�a
90�@�V�v�{�{�a
91�@���{�{�a ���������{ ���{�q�a
92�@���������{
93�@���������{��
94�@�ՊC��
95�@�����{
96�@�_����
97�@���V�Ԑ_�{��
98�@�������⓰
99�@�{�Êω���
100�@���d�R����������
101�@���d�R�������q�a
102�@���d�R ���ю�
103�@���ю��m����
104�@���d�R�ω���
105�@�ߔe�E�q�_����
106�@�ߔe�E�q�_����
107�@�ߔe�E�q�_�听�a
108�@�ߔe�E�q�_����
109�@�ߔe�E�q�_���ϓ���
110�@�ߔe�E�q�_���ϓ�
111�@�ٍ��V��
��a�E�뉀�@94
112�@�䒃����a(����)
113�@�䒃����a(����)
114�@�䒃����a�뉀�̐Ύ��q
115�@�����a�\��
116�@�����a�\�����
117�@�����a
118�@�����a
119�@�����a
120�@�����a��
121�@�D����(�쉑)
122�@������
123�@������
124�@������ ��a�̉J�[(���܂͂�)
��ԁ@103
125�@���䉮�����
126�@�ك���
127�@�ك��ԉ��]
128�@�^���W(�܂���)��Ԕq�a
129�@�^���W��� �� |
130�@�{����� ��
131�@���\���c���̌��
��ˁ@107
132�@�Y�Y�悤�ǂ����
133�@�Y�Y�悤�ǂ�����ƑO��
134�@�Y�Y�悤�ǂ�掺
135�@�ʗ� ����ƕ_��
136�@�ʗ� ����
137�@�ʗ� ����
138�@�ʗ� �擰�̉���
�����@111
139�@�^�ʋ�
140�@��苴
141�@��苴
142�@��������
143�@��������
144�@�ΉΖ(�����т�[��)
145�@���h��
146�@���K�Ɛ�����
147�@������������
148�@��Ӌ�
149�@��Ӌ�
150�@�q�`��
151�@��(�ނ�����)
152�@�ǒJ �h��
153�@�V���� ������
��Ձ@120
154�@������
155�@������
156�@������
157�@���A�m���
158�@���A�m����̔q��
159�@���A�m����̔q��
160�@��R���
161�@�Y�Y���
162�@�L�������̐Α��i��
163�@�L�������̔q��
164�@���A���
165�@���Ǎ��X��
166�@���Ǎ��X�����
167�@���Ǎ��X�� �O�d��
��@128
168�@�Ҍ��̕�n�Q
169�@�썲�ۂ̕�
170�@�썑���ǂ̕�
171�@�V�Ԑ^��̕�
172�@���ی�(�H�n���G)�̕�
173�@�j����
174�@�T�b��
175�@�����̖咆��
176�@�� ��
177�@�� �Ί_��
���Ɓ@132
178�@�������Ƃ̐���ƐΊ_
179�@�������Ƃ̐Ί_
180�@���Ƃւ̓���
181�@���Ƃւ̓���
182�@�{�Ǔa���\��
183�@�{�Ǔa������
184�@�m���̉� �m�O���v����
185�@�Ί_���̖���
186�@�ߔe�s�x�O�̖���
187�@�ߔe�s�x�O�̖���
188�@�ߔe�s�x�O�̖���
189�@���Ƃ̑䏊
190�@���ݑq
191�@���Ƃ̒|��
192�@�t�[��
���@139
193�@���1
194�@���2
195�@���3
196�@���4
197�@���5
198�@���6
199�@���7
200�@���8
201�@���9
�����E�Љ��
�@143
202�@�≺
203�@�≺
204�@�O��
205�@�k��(�ɂ�����)
206�@�ك��Ԃ��猩����̋u
207�@���K�r
208�@���K�r
209�@���K�r�̟����H��
210�@�咆�̐Ί_
211�@�咆���(���ӂ� ���ӂ�)
212�@�Ί_
213�@�Ώ���
214�@�~�o�����a�ƎQ�w�̐l�X
215�@���剺
216�@���剺
217�@�Ώ������s���V�k
218�@������
219�@�����a����̍c���q
220�@���ꌧ���t�͊w�Z
221�@���ꌧ����ꒆ�w�Z
222�@���ꌧ�����q�H�|�w�Z
223�@�s�c�o�X
224�@���V�̎��̋ʗˑO�̉��̍Ւd
225�@���T�V�̎��̋ʗˑO�̉��̍Ւd
226�@���T��̑���
227�@�A���H�� ������
228�@�A���̐�`�|�X�^�[
229�@�A���H�� �����~�̚�
230�@�m�Ԃ̌s�������w�l
231�@�@�D�@
232�@�@��D��V��
�ߔe�@161
233�@�ߔe�`�̎R���D
234�@�ߔe�`���� ���Ǎ��X��
235�@�ߔe�`����
236�@�ߔe�`
237�@�ߔe�`
238�@�����R�������猩���ߔe
239�@�ߔe�` �k������
240�@�ߔe�`�� �n�n�̓��D�x
241�@���� �_��
242�@�����O
243�@����(���Ă���)�̐����D
244�@�ߔe�얾����
245�@�����̉��c
246�@�����R����
247�@�p�˂̃T�����[
248�@�ߔe�����s��ʂ�
249�@�ߔe����
250�@�ߔe�s�X
251�@�ߔe�s�X
252�@�R�`���K�ォ�猩�������ʂ�
253�@�����s��ʂ�
254�@�V�ܒ��ʂ�
255�@���k�N�[���[
256�@�V�ܒ��ʂ菤�X�X
257�@�g�V��{�Q��
258�@�g�V��{�ʂ���� |
259�@�҂̑O��
260�@�҂̒���
261�@�҂̌㓹
262�@�җV�f�̔��ނ̕���
263�@�剮�̂ڂ�q
264�@����^�ԕw�l
265�@�~�q�K���ɍʐF���鏗��
266�@�F�����
267�@��s��
268�@�ߔe�s�x�O�̃t�F�[���`�K�}
269�@�ߔe�̎q�s��
270�@�ߔe�̓j�E��
271�@�ߔe�����̔����s��
272�@�ߔe�̂������[�s(�}�`)����
273�@�ߔe�̎s
274�@�ߔe�����s��
275�@�ߔe�̋��s��
276�@�ߔe�̎s��
277�@�ߔe ��z��
278�@�ߔe���Y���
279�@����
280�@�吳����
281�@�^�y���吳����
282�@�鍑��
283�@�J�t�F�[�V��
284�@�������𑖂�s�d
285�@�y�֓S���ߔe��ԏ�
286�@�y�֓S���̋@�֎�
287�@�捇�n��
288�@���ꌧ��
289�@���K�S����
290�@�ߔe�n���ٔ���
291�@�ߔe�n���ٔ����������i
292�@�ߔe�s�����T�C������
293�@�����a
294�@���ꑪ��
295�@�b�C���w�Z
296�@���ꌧ���������w�Z
297�@���ꌧ����w�Z
298�@��������̓V�ܗc�t����
299�@�ߔe���Ɗw�Z
300�@�ߔe�E�q�_�听�a�O�ߚ�
301�@��T��
���K�@201
302�@�����̋��`
303�@�����̊X��
304�@������˂̏�������
305�@�ɂ��키�����̎s��
306�@�����w
307�@�o�����鎅���̃T�o�j
308�@�����̊C��
309�@�������
310�@�����̒n�o�[���[
311�@�^�ߌ��w�\��
312�@�^�ߌ��S�i
313�@�^�ߌ��w
314�@�R���D�̔������ї�����^�ߌ��`
315�@���~���w�Z�̉^����
316�@�^�ߌ��̑�j��
317�@����w�̏o�����m�����蕗�i
318�@�������w
319�@������
320�@������������
321�@������
322�@�c�NJԗv����z�R
�����@214
323�@���V�ԊX��
324�@�ߔe�E����ԃo�X�J��
325�@��@����
326�@�Î�[�A���ǎl�{��
327�@�����_�ъw�Z�Z��
328�@�q�`���i
329�@�썑��
330�@��Ӑ�͌�
331�@�����_�ъw�Z����
332�@�ǒJ�R����
333�@�A���̏捇�o�X
334�@�ؒY�o�X��ꍆ
335�@�A���C�����H�Ɛ���
336�@���ꌧ�c�S���Î�[�w
337�@��������������Ղ̃R�o�e�C�V����
338�@�ǒJ�R���̔_��
339�@�������ɂ������ԏ�
�����@224
340�@���[�n��̏�����
341�@���[���R�c�C��
342�@����邩�猩������̒�
343�@�����ʂ�
344�@�捇�����ԑ�ꍆ
345�@����p�̕��i
346�@��z�����Ԃ�A�^�t�H�[�h
347�@����p�̃C���J�߂蕗�i
348�@�{���n�v�n�`
349�@���A�m�������n��̋��n���i
350�@���������w�Z�Z��ł̐폟�F���
351�@��X��������
352�@��@�Â̌S���H��
353�@����̃g���o�[�`����o�����i
354�@�ɍ]���̏�R�Ɩ���
�{�Á@233
355�@���ǟ����`
356�@�����`�̋q�D���`���i
357�@���ǒ��̊X��
358�@�{���X��
359�@�����s��
360�@�{���H���i�X
361�@���ǐ�����ʂ�
362�@����(���C�K�[)
363�@�A�}��
364�@���ǒ�������ʂ�
365�@�v���ܗE�m
366�@�v���ܗE�m�Ɗ��^��
367�@�{�Ó��_�Јړ]���c��d���
368�@���i
���d�R�@241
369�@�Ί_�`�V��
370�@�Ί_���̋��s��
371�@�Ί_���̋��s��
372�@���̓d�M�ʂ�
373�@�Ί_�̎G�ݓX
374�@��ǂ��w�l
375�@�Ί_������
376�@�Ί_�̓��������i
377�@���a�����̔_�k���i
378�@����̕l���i
379�@���i
380�@�약�̌�ؖ{�^��{�B��
381�@�ޗǍ����̏v�H
382�@�͂��߂ĕ��t�@��������
383�@���ߍH��
384�@�Ղ����������V�k����
385�@���̕��i
386�@���\�Y�B�V��
387�@���\�Y�B
388�@��t�����̕���
389�@��t�����̕���
�E
�E |
�P�O���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO9.�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
59p
|
����ɂ������B�n�퐶�O���y��-
�@�@���^�h���L�ˈ╨�̌���- ���c �x�m�Y
���v���y��(2) ���R ���� |
��Տo�y�p���̑̒������@-�i�����E�u�_�C�𒆐S�Ƃ���- �ɔg ����q
�V���l�Êw�W�����ꗗ(2) �F�� �G�q
�E |
�P�O���A�u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 13(1) �v���u���ꍑ�ۑ�w���w���v���犧�s�����B
|
�����̐����s�� : �j�����̗̉w�𒆐S�� ���R�� p.1-14
�����w�I���̂̌���(4)(��):�u���Ȃ�_�M�v�𒆐S�Ƃ��� ���Ï@�� p.15-30 |
23�̗H��b�ƘZ���䑧���������̑��� �O�ύ_�� p.31-44
���Ɏ��w�V�ߏ������x�_ : �ߑ㏬���̕��� ���c�`�a p.45-64 |
�P�O���A�����x�m�q�i�c���`�m��w�̈� �������j���u���{�̈�w��� (35)
p.89�v�Ɂu���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ���(����1)(1.�̈�j,��ʌ���)�v�\����B
|
����̌|�\�́A���� �A�����ē������̉e���������A���A���{�{�y�̕��y�A�\
��O�̕�����Y�̕���̉e���������Ȃ���Ɠ��̉Ԃ��炩���Ă���B�������������Ɏ�荡���ɓ`���ė������Ƃ́A���X�̌Ǔ���A�����I�h���̗��j������������̐l�X���A��������̒��ł����ɓ`��������ʂ��Ă��������a������Ă�����������������̂ł���B�q�����r |
�P�O���A�Y�R���ꂪ�u���z�G��. ���z�N�� �i1984�j p.111- �v�Ɂu������N��V����v�̌��z�I�f�`(����̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤���E����6)�v�\����B
|
�Y�R���ꑼ�����\�����u����̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤�� ���̂P�`6�v ���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
���� |
| 1 |
. |
. |
�s���i���m�F�j |
. |
| 2 |
�w�p�u���[�T�W. �v��n 55(0) p.1979-1980 |
1980-09 |
���J�{�ݏ�̗̈�I����:
�@�@������̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤��-����2 |
�Y�R����,���R�f��,����P |
| 3 |
�w�p�u���[�T�W. �v��n 55(0) p1981-1982 |
1980-09 |
���J�{�Q�̏ے��I�\������:
�@�@������̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤��-����3 |
�Y�R����,���R�f��,����P |
| 4 |
���{���z�w����� .- (5) p.369-372 |
1981-03 |
�uKumu^+ dza:(�Ă艮)�v�ɂ��Ă̕�:
�@�@������̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤�� ����4(���j�E�ӏ�) |
�Y�R����,����P,���R�f�� |
| 5 |
���{���z�w����� - (6) p.349-352. |
1984-03 |
�u������N��V����v�̌��z�I�f�`:
�@�@�� ����̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤�� ����6(���z�j�E���z�ӏ�) |
�Y�R����. |
| 6 |
���z�G��. ���z�N�� (1984)
p.111- |
1984-10 |
�u������N��V����v�̌��z�I�f�`
�@�@��(����̍��J�Ɖ��Ɋւ��錤���E����6)
|
�Y�R���� |
|
�P�P���V���U���R�O���A�ߔe�s����ّ�z�[���ɉ����āu�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O�\�y����
�ϐ��� �\�E������ : ���� �Չ� �d�� �D�ٌc�v�����������B
�P�P���A�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ�ҁu�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O�\�y���� �ϐ��� �\�E������ : ���� �Չ� �d�� �D�ٌc�v���u�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ�v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1006973349
�P�P���Q�V���`�Q�X���A�u���ꕨ�Y�Z���^�[��L�v�ɘV���āA�u�ʏ钩�O����
�`���|�\���p�W�v���J�����B
�P�P���A����^�C���X�Е� ;�����V��Еҁu�ʏ钩�O���� �`���|�\���p�W�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@45p �@�����F���ꌧ���}���فF1006779795
�P�P���A�쓇�n��j������ҁu�q�쐴�搶�ËH�L�O�_�W�v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@�@
|
�q�쐴�搶�ËH�L�O�_���W
���d�R�̑�Ôg�̈ʒu�Â�/�O�D��
�ꎵ����N���a��Ôg�ЊQ�̎Љ�I���Ɋ֘A�����l�@/�_������
�q�쐴�搶�Ɣ��d�R��Ôg/�F�������v
�Ί_��������/�w�R�`�v
���d�R�ɂ����錴�n�Ñ㕶���̏����/��l�i�j
�Î��L�ƒ��R���� : �w�Î��L�x�㊪�Ɓw���R���Ӂx
�@�@����1���Ƃ̐_�X�̐��i�̈�l�@/�{�Lj��F
�u�c���c�c��R���L�v�čl/�{�n�h�q |
�p���j�o�� : ���R���Ղ������˂�/��R��
�쓇�l���ł̕��ۖ@�ɂ���/��ɏ�ꗲ
�吳����ɂ�����u���d�R�ʑ��}���فv�_�`/�V����P
�{���c��ƌ��ꌤ�� : ����̋O�ՂƂ��̔w�i/�O�،�
���d�R�̌È�˂̕��ނƎ����/�ʒÔ���
�u�^�ӈ�ˁv�Ɋւ����l�@ : ���ۑ��̒�����/�Ί_��
�������̔d��V��/�Ί_���F
�|�x���́u���x��́v�ɂ���/�떓�b��
�E |
�P�P���A���|�p��w�|�p�������^�c�ψ���ҁu�|�p : ���|�p��w�I�v (7)
�v�����s�����Bpid/7953733�@�d�v
|
�A���f�X�����̊L���� / �g����Y/p4�`14
���A�t���J�E�k���i�C�W�F���A �n�E�T���̗����z�u�A�f���E
�@�@���N���X�v�̐���Z�@�ɂ���/��֘a��/p15�`27
��̋L���|���A�W�A�̗\�j�s�� / ���P��/p28�`39
���ʑ̂Ƌ�Ԑ����ʑ� / �{���x�i/p40�`50
�u���B�W���A���R�~���j�P�[�V�����v�ɂ����� |
�@�@������̈ӎ�/�g�c�K��/p51�`62
���E�ƁE�ƁE�ЁE�сE���E�ƁE�ȁE���E�� / ��Q�n/p63�`66
�����h�[���ɂ�����p�t�H�[�}���X /
�@�@���L�����q ;���V�G�� ;�ߓ��� ;�u���N/p67~77
������p�����W(7) �_�����V���^�b�g�|�p�Ƒ� / �M��/p78~84
�E |
�P�P���A��ɏ�ꗲ�ҁu�쓇�n��j���� ��1�S�v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@pid/9774922
|
�����ɍۂ��� ��ɏ�ꗲ
��I��
���d�R�̑�Ôg�̈ʒu�Â� �O�D��/1
�ꎵ����N���a��Ôg�ЊQ��
�@�@���Љ�I���Ɋ֘A�����l�@ �_������/21
�q�쐴�搶�Ɣ��d�R��Ôg �F�������v/31
�Ί_�������� �w�R�`�v/37
��II��
���d�R�ɂ����錴�n�Ñ㕶���̏���� ��l�i�j/39
�Î��L�ƒ��R���Ӂ\�w�Î��L�x�㊪�Ɓw���R���Ӂx
�@�@����ꊪ�Ƃ̐_�X�̐��i�̈�l�@�\ �{�Lj��F/69
�u�c���c�c��R���L�v�čl �{�n�h�q/85
|
�p���j�o���\���R���̎���\ ��R��/107
�쓇�l���ł̕��ۖ@�ɂ��� ��ɏ�ꗲ/127
�吳����ɂ�����u���d�R�ʑ��}���فv�_�` �V����P/167
�{���c��ƌ��ꌤ���\����̋O�ՂƂ��̔w�i�\ �O�،�/197
��III��
���d�R�̌È�˂̕��ނƎ���� �ʒÔ���/239
�u�^�ӈ�ˁv�Ɋւ����l�@�\���ۑ��̒����\ �Ί_��/271
�������̔d��V�� �Ί_���F/297
�|�x���́u���x��́v�ɂ��� �떓�b��/325
�q�쐴 �N�� �q�쐴/345
���Ƃ��� ��ɏ�ꗲ
�E |
�P�P���A�u�l�Êw�G�� = Journal of the Archaeological Society of Nippon 50(2)�v���u���{�l�Êw��v���犧�s�����Bpid/3548620
|
�k�C����C�S�����A���g�t�R��Ք��x������ / ���{//��/p1�`20
���P����s�m�̐Ί핶��--��s�m�^���ւ̒��� / ���X�h�� ;�������Y/p21~38
���쌧�������������Ւ����T��(��1���`��3��) / ����T�� ;�Έ䑥�F/p39~48
�����哇�y�l���[�����A��Ւ����T�� / �i�䏹�� ;�O���i/p49~64
�����Љ�/p65~71
�ؗ��`�y��(���G���)�\�\��ʌ������R�s����o�y / ����˗Lj�/p65�`66
�k�C���o�y�̓���^�ΐ� / �F�c��//�m ;�͖�{�� ;�����v�a/p67~71
�����}��/p72~77
�p���v�� / ���{�� ;���X�h�� ;�����B�v ;����V�� ;�Έ�T�F ;�i�䐳�� ;�O���i/p1~5 |
�P�P���A���H���m�u���u�����Y�\�j���������98���v�Ɂu�V�����̌�ⵂɂ��āv�\����B
�@�@�@�p���t���b�g�o�C���_�[����@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1006980203�@�@ 1��
�P�Q���A���c���q���u���w 52(12) p.p23�`35�v�Ɂu�Ɨt���ѕ������ɂ�����̊_�Ɖ̊|���v�\����B�@�@
�P�Q���A�ÓT�Ɩ����w�̉�ҁu���ꌧ�v�����̖����v���u�ÓT�Ɩ����w�̉�v���犧�s�����B�@
�@�@�@�@ (�ÓT�Ɩ����w�p�� ; 8)�@pid/9775180/1/1
|
���G�ʐ^�i�\�l�t�j
�l���\���̖����_�� ���䖞/11
�� ���j�I�`��
�� �i�[�a�L�[
�� �C�U�C�z�[�Ɛ_��
�O ���̖���
�l���V���b/22
�����i���Y�j/23
�Y��i�e�n�`�T�j/31
�N�j���ƔN��K��i�������j/41
�����i��Αוv�j/50
�����\�ߐH�Z�̏��� ����x�`/58
�͂��߂�
�� ��
�� �H
�O �Z
���� |
�_�k�\����̓`���ƕ��� ��{����/75
�� �t�N�M���Ǝq��S
�� �����Y���`���̎���
�O ����X���Ƃ��̐H�@
�l ����Ɨ֍�
�� ���O��
�����\�E�~���`���̓� �c���E/102
�� �T��
�� ���Ɨ�Ƌ���
�O ���@
�l ���������ƕ��z
�� �����ƍՋV
�Z �����ƕ���
�Љ�\�V�}�̑g�D�ƃ\�[���C�K�i�V ���؍G�q/118
�� �����̑g�D
�� �E�~���`���̊���
�O �\�[���C�K�i�V�Ɠ����� |
�l �\�[���C�K�i�V�̈Ӌ`
���J�\�Ղ�Ɍ��铇�̔��W ���R��/128
�͂��߂�
�� ���̌��\��蕨�\
�� �C����\���̗́\
�O �C�ց\�Z�̗́\
�l �����̘_���\�������ہ\
����
�|�\�\�E�X�f�[�N�𒆐S�� ���Ԉ�Y/144
�� �E�X�f�[�N�i�O���C�j
�� �i�I�g�~�V���E
�M�\�썰�Ɛ_�� �����Z��/159
�� �~�s��
�� ���Ɨ썰
�O �_�ϔO
�y�����z�_�̏�/176
���Ƃ���/183 |
�P�Q���A�u�V���ꕶ�w ��62���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001674082
|
�q���k��r �g�x�̌��݂�₤ �^��u �N�� ���� ����
�@�@�@������ ��Y �֍� ���i �ʖ� �ꕺ�^�k �얞 �M��^�i��
�q�C���^�r���[�r�{�������ɕ����r����-���{�b���u���O �g�x�����̉ۑ�v
�ʏ钩�O�N�� �r�{ ����
�ʏ钩�O�W�_���E�}���ژ^ ���� ��Y
����̖��� ���� ���o�Y
�Ă��̂͂� �����g �h��
�g���v�N�g�D �i�R ���}
�����̎��W�E���Ɩ� ���� ����
�Ύ��̂��肩 ���� ��
�����̉���(��) Kaminski Marek�^�� ���� ���q�^�� �R�� ���ȁ^���
���앶�O�_ �㌴ ���j
����̂��߂� ���� ����Y
�ے��s�ׂɂ�����n���I�z�� �Đ{ ���� |
�G�߂͂���̏���T �䕔 ���j
�N���v���[�g�Ɨ��� �X�c �Аi
�`���Ƒn���̂͂��܂� ���� �G�p
�q�����Ȃ������E���ꂱ�� (21)�r �����ăB�ǃD �イ�Ƃ��� �V�� �i
���z�̊X�E�ߔe(8) �q�` �ĎO
�q��10��u�V���ꕶ�w�܁v���\�r
�ÊԗǐS�� �g�c �X�G�q
����鍳 �R���[ �M�q
�q�I�]�r ���� �q�Y ��� ���T �q�` �ĎO
�q�����r
�q�C�O�W���[�i���r
�q���]�r
����W�V���}���ژ^
�E |
���A���̔N�A�Γc���ꂪ�u����̐S�����߂āv���u�Ђ邬�Ёv���犧�s����B�@
(�����Ȃ핶�� ; 15)�@�@pid/9775093
|
����Ƃ̏o�/9
�]�̃V���b�N/11
�Ă����̉�/13
�ʂĂ̓��̋D�ԃ|�b�|/16
�^�Ă̓ߔe���C/19
���}�g���`���ٔ�����/21
�ł����̎��Ɍ}�����/23
�ɕ~�������U�̔ߌ�/25
����̖@��/28
�u���ۖ@��v/30
�E�`�i���`���̖ڂƐS/33
�E�`�i�[�w�̃A�v���[�`/35
���y�ƐS�ւ̗�/37
�֏��Ԃ̕��䍁/38
����̍L���Ǝ���/42
�Ԋ��̉ƂƃR���N���[���[/46
�E�`�i�[�s�r�̂͂��܂�/48
�R���H�𑖂�/51
���̃W���M���O/53 |
�V���C�̕���/55
�i�[�t�@�̃}�`�O���[/57
�ӌ˖�����l�w�`/64
�H�ׂ����̃A�C�X/68
�y�D�ԏ�Ă��܁[������/71
�V�b�^���K���K��/73
���}�u�Ȃ́v/81
�o�X��҂�/85
�D���̊C�O���s/89
���[�J���q��/92
��Ă̍��̍Ύ��L/97
�䕗�Ɠ�����/99
���������̉���/102
�u�~�v���߂�/106
�n�u�͂ǂ���/112
����̔o��/115
�����Ă��͂��܂�/117
���Z���̂т�^����/119
�ꖇ�̎ʐ^����/122 |
�x��̍�/125
���d�R�̔��Ԑ�/127
�܂�ƐM��/130
����ŋ��ɂӂ��/135
�g�̐����~�܂�/137
�g�x��ƃE�`�i�[�O�`/138
�q���M���[�A�q���M���[/141
��ĕ���́u��̔����v/144
����l���ɐ�����/147
�������Ȃ�ʂ����C�i�O/151
�{���x�ɂ̂���/153
�X�`���A�f�X�̂ЂƂ�/156
�����̂�����/159
���Ă��ȏ�������/161
������Ɠ��̉S/165
�t���[�e�B���O/167
�r�[�`�̃T�N���j��/171
�������̖��l�|/173
���̓��̒�����/177 |
�A�����J�����Ղ�[/183
�������̂��肻��/185
�y������̐ڑҗ���/188
�X�e�[�L��ʐM��/193
�Î�[��n�̌�����/197
���߂��蓌����k/203
���̐��͂�����/205
���̂��ł���T��/210
�������̂�����/214
�u�n�C�n�e���}�v�����߂�/217
��������Ƃɂ���/221
�n�u���m�Ƃ̏o�/223
���Ȃ����̈��/224
�Z�O���A�W�T�V�̖�/227
�Ԃł����Ƃ̕ʂ�/230
���Ƃ���/233
�E
�E
�E |
���A���̔N�A�{�������ҁu�|�x���×w�� : �Ñ㕶���̌�����K�˂āv���u�|�x���×w������v���犧�s�����B�Q�O�O�O�~
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002097739
|
�� �약 ���\�^��
�܂�����
�|�x���{��̉�
�|�x���̍��� |
�|�x���ɓ`�����ꂽ�×w
�|�x���̂��x��
�q���^�r
�|�x���×w����������� |
�|�x���×w������̂����
�|�x���W���̉��~���p�̐��ڂƌ���
����
���{ |
����
�����N����r�\
���Ƃ���
�E |
���A���̔N�A���c���q���u���̒��ɕ��� : ���q���`�v���u�i���É��j���c�����{���v���犧�s����B�@
���A���̔N�A�@����w�S���N�L�O�v�ē������ψ���ҁu����v�ē��̑����I�����v���u�O�����v���犧�s�����Bpid/9774913
|
�v�ē��ɂ�����ŋ߂̋C��ϓ��ƃT�g�E�L�r�̎��ʂɂ��� �c���m/1
�v�ē��̕��Ɣ_�ƋC�ۍЊQ�ɂ��� ���J���/17
�v�ē��Љ�j�̈�f�ʂƓ`���Y�Ƃ̖���
�@�@���������́u�v�ē��ۘ_�v���Ƃ肠���� ���]�F�i/31
�v�ē��ۂƉ����哇�� ���{�암��
�@�@�@���`���I�Ȑ��D �G���F�����E�V���~�b�g/53
�v�ē��̊C�O�o�ږ��̎Љ�o�ϓI���� ������Y/57
�v�ē����K�����̑c��s�� ����/91
�ږ���������݂����� ���V��/135
�����ɂ����镗�]��Q���̗\�㒲�� ��R��/199
���ꌧ�o�ς̍\���I�����Ƌv�ē� �������j/219
�v�ē��ɂ�����Y�ƌo�ς̊T�� �����ΗY/229
|
�v�ē��ɂ�����Y�Ƃ̔��W �i��i/267
�v�ē��ɂ�����_�Ə]���҂̎��Ԃ�
�@�@���_�ƐN�l���̓��� ���c�K��/285
�v�ē��Ì���߂̑f�` �O�Ԏ�P/303
�쓇�̉J��̋V��I���E �J��̗w��ǂ̑O�� ��Î�/325
�����ٍ��D�̋v�ē����q �������j/335
�ߐ����̋v�ē��Ɠ��D ����]/345
�ߐ�����̋v�ē��̓y�n���L �R�{�O��/361
�v�ċ�u��Ԑؐ��������s�|���t ���K����/375
�v�ē��ɂ����镗����
�@�@�����Ƃ̌��z�\�@ �R�c���� �Ð�C��/411
�v�ē����Ƃ̋�ԍ\���ɂ��� ���҉p��/445 |
|
| 1985 |
60 |
�E |
�P���A���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 157�E158)�@�����҂��߂��閯��<�V���|�W�E��> (���R�N��k���{�����w��l���W��) p.p12�`56�v���u���{�����w��v���犧�s�����B
|
�U��Ă̈Ӗ� �@��� �� p.p13�`24
���}�g�E������r�̎������� �@����q�� p.p24�`28
���搧�ɂ��� �@�V�J ���I p.p28�`39 |
�V�J���I���̕ɑ���ӌ��@�c���v�v p.p39�`44
�����s���̍\��--�~�^�}�̔т𒆐S�Ɂ@���X�؏� p.p46�`56
�E |
�@�@�@�@�@�ā@�{�_�́u���҂��߂��閯��<�V���|�W�E��>�v�̑��҂ɑ�������B�ʔԂ��Ȃ��@���_�͂P�X�W�S�N�V���@�@�Q�O�Q�R�E�T�E�V�@�ۍ�
�Q���A�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ���� ���u�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ�j���[�X
No.11�v���u�ʏ钩�O���a�O�S�N�L�O���Ɖ���ǁv���犧�s����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004238331
�Q���A�@����w���ꕶ���������v���������ψ���ҁu����v���������� :
�u����v�����̌���E�����̑����I�����v���v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�@�@pid/9775284
|
�v���������Љ�̊�Ձ\�u�n���g�v�̑g�����́\ ����O/1
���ԍՎi�̏@���I�@�\�\�ՋV�גS�҂̃V���[�}�����\ ���䓿���Y/23
�y�n���x�̌���Ɖ��v �R�{�O��/41
�v�����R���L�Ƌv���ƌn���L ����]/49
�����ېV���̋v�����O�j �������j/61
�v�����̍��J ���{/67
�v�����y�ю��Ӑ���̐_�́\�v�����W�I������
�@�@�@�����߂𒆐S�Ɂ\ �O�Ԏ�P �g�Ɗԉi�g/85
���l�ɂ݂�×����̎v�z�\���֑o�P�_���̐����𒆐S�Ɂ\ ��Î�/153
|
�v���������̐��i�Ƃ��̌`��
�@�@���\���C�E�`�ԁE��b����\ ���{���q/173
�v���������̕��@�Ƃ��̓��� ���Ԓ��m/193
�v�����ƃG���u�E�~�w�r�i�G���u�E�i�M�j �V�_���E/215
�v�����̌����ƓW�] ��������/223
�v�����̒n�� �㌴�F�O/229
�v�����̌�ԁE�q���E���E������Ւn�}
�@�@���g�Ɗԉi�g �㌴�F�O/235
�v�������������ژ^ �㌴�F�O/239 |
�Q���A���w�ٕ��u�n���̐��E (53)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@�@pid/1737928
|
�V�����d���_�̂��߂� / �����a�F/6
�d�������̔w�i�q�V���|�W�E���r / �������H ;�~���� ;�͍���Y ;
�@�@�������a�F ;��c�[��/26
�ꕶ�����̓���� / ���X�؍���/48
���{����-��̊�w�q�V���|�W�E���r / �~���� ;�͍���Y ;
�@�@����c�[�� ;���X�؍��� ;������/72 |
���\�_(5)�h�X�g�G�t�X�L�[�̎��]�ɂ���(��) / ��c�[��/98
�T������q�g��(��U��)(3)���s�������̎Љ� / �͍���Y/158
�̐_�����ȉ~���� / �~����/178
�����A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌�������
�@�@��(8)�q�O�}��c��_�ɂ��R���b /
�@�@�� B��s�E�X�c�L ;�k�C���E�^������D�y�x���A�C�k�����/124 |
�Q���A������q,���X����������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��� (�ʍ� 28)�@ p.p67�`88�@������w����w���v�Ɂu����A�W�A�������x�̈�ۋ��-1-�v�\����B
�R���A�g�x�A�u���S�����v�䂩��̒n�A���g�������Ɂu�ʏ钩�O���a300�N�L�O��v�����������B
�R���A�u�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ�j���[�X 12���v���u�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ���ǁv���犧�s�����B
�R���A�u�^�C�g�� �ʏ钩�O���a300�N�L�O 1984�F�����v 1�����u�ݐ� �Ђ��Ԃ�v�Ƃ��ꉫ�ꌧ���}���قɏ��������B
�@�@�d�v�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002263794
|
1.�����|�\�̑c �ʏ钩�O���a300�N�L�O �ߔe �ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ� 1984.3
�@20p,
2.�ʏ钩�O���a300�N�L�O �S���������j���� �Ɖ��ƐV�� �Ƃ��F���a59�N3��18�� �ߌ�6��30�� �Ƃ���F�J��������ّ�z�[��,
3.���a300�N�L�O �x�������ʏ钩�O�����Ռ��� �ߔe ����^�C���X�Е������Ƌ� 1984.2 �����F���a59�N2��16��(��) �ꏊ�F����^�C���X�z�[�� ��ÁF����^�C���X�� �������� �㉇�F���ꌧ����ψ��� ���^�F����|�\����,
4.���a300�N�L�O �x�������ʏ钩�O�����Ռ��� �ߔe ����^�C���X�Е������Ƌ� 1984.5 �����F���a59�N5��12��(�y) �ꏊ�F����^�C���X�z�[�� ��ÁF����^�C���X�� �������� �㉇�F���ꌧ����ψ��� ���^�F����|�\����,
5.���a300�N�L�O �x�������ʏ钩�O�����Ռ��� �ߔe ����^�C���X�Е������Ƌ�
1984.6 �����F���a59�N6��16��(�y)�`17��(��) �ꏊ�F�^�C���X�z�[�� ��ÁF����^�C���X��
�������� �㉇�F���ꌧ����ψ��� ���^�F����|�\����,
6.�ʏ钩�O���a300�N�L�O �����|�\�̐��I �ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ�W���ψ���� �ߔe �ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ� 1984.6 114p ����F���a59�N6��30��?7��22�� ���F���ꌧ�������� ����t�����ژ^,
7.�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ�j���[�X ��1���`��12��(1984.1�`1985.3) �ߔe
�ʏ钩�O���a300�N�L�O���Ɖ���� |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 21(2)(64)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437778
|
�ۗLj�Ք��@��Z�N�� / ���q�G���J/p1�`18
�w��㊌����v���x�ɂ����錓�Ɣ_�ƊT�O�ɂ���/���䐴�j/p22�`33
�I�����̑�@ / ���]�q/p36�`44
�k�����m�[�g�l �I������ǂւ̊K��--�啔�ɂ�����
�@�@���L�ڂ̏ȗ��ɂ��� / �g�Ɗԉi�g/p46�`62 |
�u���@�����P�搶�w�m�@�܁E
�@�@��������܂��j����v��/�ҏW��/p64�`75
���] / ������w�@��/p34~35
�V���Љ� / ���]�q ;���]�q ;�g�Ɗԉi�g ;�㌴���O
�@�@�@�@��/p20~21,33~33,45~45,63~63 |
�R���A���v�`���u�����M�̓`���v���u�l�����@�v���犧�s����B�@228p�@pid/12166696
|
���ɂ�����
���́@�����̍\��
�@�擇�̐��n�ƍ��J�^�����̍\���^���K�_�̑f��
���́@�_�k�̍��J
�@���y�L�Ɩ����w�^����̋V��^��c�A�ƍՋ� |
��O�́@�i�Ղ̓`��
�@�q�i�����̓`���^�����^�{���̌����I�`��
���Ƃ���
���o�ꗗ
�E |
�R���A���ǎs����ψ���ҁu���K�̃p�[���g�D������ : ���I�`�����������L�^�쐬�v���u���ǎs����ψ���v���犧�s����B�@�@77p,�}�ŋ� �@�@�����F��㊌����}���فF2000235123
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (11)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@�@pid/3467954
|
���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(IV) / ���a�c�^�~ ;�m�O�E/p1~14
�R�����j�����u��q�̖쑺�H�H�l�v�ɂ���(��) / �X�۞Ď��Y/p15�`28
�p�[�\�i���R���s���[�^�[�ɂ�锎���َ�����
�@�@�������̎���/���R����/p29�`34 |
�G��O��\�\�u���ǁE������E���� / �Ôg�Ñ�/p35�`38
���V�������� / ��]�F��/p39~47
�Δ�T�ρ\�\�����̐Δ�̑���ʂ���(��)/��]�F�q�v/�E1�`16
�E |
�R���A�؍������@ �ďC�u�����؍����� 7(3)(65) �v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@
�@�@pid/7952666�@�d�v
|
���ԃ����F���̊w�p�� / �N�䓿���Y/p2�`3
�؍��f��̎j�I�W�] �J���[�O���r�A �؍��̉f��/�����M�v/p15�`24
�O������̕�������(1)�����lj�Ƃ��̕��� / ���{���N/p4�`9
�Ñ�̖����Ɍ���`�E�؊W--�������I�N���品�E
�@�@�������x���E���c�������l���摜�� / �n�ӌ��q/p25�`31
�؍��̐����̍Ύ�����(��) / ���ԍ�/p10�`14
������E�����₫���̃m�[�g(1) / ���c�G�q/p36�`40
�M�Z�̒n�Ɍ���ؗ�����(�I) / ����גj/p46�`47
�؍��j�ՒT�K 鋏B / ���݊�/p32�`35 |
�V���̋��Ε�(13)�U�B��O�����E���K�N���ق�/�c���r��/p41�`45
�؍��̖��b(49)�F�q�ɂȂ������� / �c���a/p48�`49
�]���̖{ �w���N�̊G�E���{�̊G�x
�@�@���w�ϏB���Ñ㕶���̓�x / �R�����O ;�v����/p50~51
�}�X�R�~�_�� 21���I�Ɍ��������Ǘ�
�@�@�������m�̕�����/�؍����� ;���N����/p52~53
�ǎ҂̂Ђ�� ���O���t�@�E�g���T��/p54�`54
�؍������E�̓���/p55~56
�؍������@�����/p57~58 |
�R���A�u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 13(2) �v���u���ꍑ�ۑ�w���w���v���犧�s�����B
|
�e�B���N�O�`�l : �ɕ����̖L�N�� ���R�� p.1-32 |
�����w�I���̂̌���(4)(��) : �u���Ȃ�_�M�v�𒆐S�Ƃ��� ���Ï@�� p.33-42 |
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu���Ε��v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@ (���ꌧ������������, ��69�W . ���j����������; 5)�@�@266p�@�u������v
|
| �m�� |
��{�� |
�Ő� |
���ݒn |
�����N�E�傫���� |
| 1 |
���A�m���i���Ė� [��{] |
p13�@ |
���A�m�������� |
�����N�F1749(���h37) |
| 2 |
�O�{������I(��) [��{] [��ԗ�i��]�@�@ |
p14-15 |
����s������@ |
�����N�F1750(���h38) |
| 3 |
�O�{������I(�\) [��{] [��ԗ�i��]�@ |
p14-15 |
����s������ |
�����N�F1750(���h38) |
| 4 |
�����H�n���L[��{]) |
p15-16�@ |
. |
1744(����9)
2�� ; 153.6�~68.3cm(���ł� 156�~73cm)�A
�@�@152.2�~68.6cm(���ł� 157�~73cm)�@ |
| 5 |
���얡�e����i���Ė�[��{] �@ |
p19 |
. |
1843(����23)�@
1�� ; 101.8�~31.6cm(���ł� 105�~36cm) |
| 6 |
�������o���{�� [��{] |
p27�@ |
�k���鑺������ |
�����N�F1807�N(���k�R�E�l4)
2�� ; 13.7�~68.3cm(���� 138.9�~69.7cm)
�@�@�@138.9�~68.3(���� 139.8�~69.6cm) |
| 7 |
�v�a�z�� [��{]�@ |
p27-28 |
���������Î芡 |
�����N�F1738�N(���h26)
�̑�N�F1984�N7��10���i�܂ɋL�ڗL�j |
| 8 |
�扤�����L [��{]�@ |
p28-29�@�@ |
���������Î芡 |
1738�N(���h26)
�̑�N�F1984�N11��15��(�܂ɋL�ڗL) |
| 9 |
���@�@�،o�S���� [��{] �@ |
p34-35 |
�ߔe�s�ԓc |
�����N�F1776(���s25)�@
�̑�N�F1985�N1��5��(�܂ɋL�ڗL) |
| 10 |
���������O�H��Ԕ蕶 [��{]�@ |
p36-37�@ |
�ߔe�s�������@ |
�����N�F1814�N(���k�R�E�l11)
2�� ; 99.5�~54.9cm(���� 101�~56.5cm)�A
100�~54.5cm(���� 101.6�~55.8cm) |
| 11 |
���V��� [��{]�@�@ |
p37-38 |
�ߔe�s�����钬 |
�����N�F1863�N(����16) |
| 12 |
�喼���蕶 [��{]�@ |
p72 |
�앗�������喼 |
�����N�F1769(���s18) |
| 13 |
���ʐ� [��{] �@�@ |
p74 |
��u�쑺����u�� |
1�� ; 68.6�~53.4cm(���� 69.8�~54.8cm) |
| 14 |
�ω����o�˔�[��{]�@ |
p77-78 |
. |
1736 (����1)�@
2�� ; 102.8�~34.3cm(���ł� 105�~39cm)�A
�@�@104.2�~34.1cm(���ł� 109�~39cm) |
| 15 |
��{��[��{]�@ |
p78 |
. |
1864�i����3�j�@
1�� ; 73.4�~49.5cm(���ł� 78�~49cm) |
| 16 |
�^�ߔe�O�R�̔�[��{]�@�@ |
p80 |
. |
1771(����36) |
| 17 |
���e�����V�����D�� [��{]�@ |
p81 |
�Ί_�s���Ί_ |
. |
| 18 |
�O������[��{]�@�@ |
p81-82�@ |
���\���O���� |
1715(�N�54)�@�@���\���̎O�����ˋ��L�O�� |
| 19 |
�I�����ݍ��E�R�Ί���[��{] |
p81 |
. |
�r���C���@�^�C�U���@�C�V�K���g�E�@ |
| 20 |
��}���� [��{]�@ |
p83 |
�|�x������ |
�����N�F1715(���h3)- |
| 21 |
�^�ߓc����[��{]�@�@ |
p85 |
. |
1718(�N�57) |
| 22 |
�I�����_���� [��{]�@�@ |
p93 |
����s���^�V�� |
�����N�F1846�N(����12) |
| 23 |
�����{��e�_���� [��{] |
p96�@ |
�^�ߏ鑺���c�� |
�����N�F1764�N(���s13)�@�̑�N�F1984�N10��9�� |
| 24 |
���X�̏�̕�� [��{]�@ |
p96-97�@ |
��u��s���ԓ��@ |
�����N�F1704�N(����36) |
| 25 |
���X�̉��̕�� [��{])�@ |
p97-98�@ |
��u��s���ԓ� |
�����N�F1704�N(����36) |
| 26 |
�]�F�i��� [��{]�@�@ |
p98 |
��u��s���{�� |
�̑�N�F1984�N1��27��(�܂ɋL�ڗL) |
| 27 |
��� [��{]�@ |
p101 |
�X��p�s���u�^�u |
�����N�F1740�N(���h28) |
| 28 |
���R�ƕ掏 [��{] �@ |
p102-103 |
�����������ߔe |
�����N�F1792�N(���s41)
�̑��F1984�N12��16�� |
| 29 |
�Ɗ얼�ƕ��[��{]�@�@ |
p103 |
. |
1749(����14)�@
1�� ; 93�~34.4cm(���ł� 97�~39cm) |
| 30 |
���ƕ掏 [��{] |
p103 |
�����������ߔe |
1�� ; 45.9�~34.2cm(���� 47.5�~35.7cm) |
| 31 |
�e�B��a����� [��{]�@ |
p104-105�@ |
�ߔe�s�ԓc�� |
�����N�F1620�N(���J32) |
| 32 |
��쏼����� [��{]�@�@ |
p107-108 |
. |
�����N�F1679�N(����11) |
| 33 |
���\�ƕ�� [��{]�@ |
��112-113�@ |
�ߔe�s�ɑ��� |
�����N�F1846�N(����12) |
| 34 |
�썑���V�q�����Ί��� [��{]�@ |
p117�@ |
. |
1688(�N�27) |
| 35 |
�������� [��{] �@�@ |
p119-120 |
�����s���^�h�� |
�����N�F1855�N(����8) |
| 36 |
�������c�ƕ�� [��{] |
p120�@ |
���~������o�� |
�����N�F1698�N(����30) |
| 37 |
���i�������U�掏�� [��{] |
p121-122 |
�嗢�������@ |
�����N�F1892�N(����25)�@
4�� ; 84�~69cm(���� 88.5�~73.2cm)
�@�@33.2�~26.2cm(���� 35.9�~29cm)
�@�@25.6�~33.1cm(���� 28.6�~36.1cm)�A
�@�@34�~52.1cm(���� 37�~56.4cm) |
| 38 |
���͗��V�q�e�_����[��{] |
p123�@ |
. |
1872(����11) |
| 39 |
�V�[�N�ԐΊ��� [��{] �@�@ |
p124�@ |
�Ί_�s������ |
�����N�F1625�N(���L5) |
| 40 |
�����N�Ȑ~�q�P��[��{]�@ |
p124-0125�@ |
. |
1695(�N�34) |
| 41 |
�����ω�������[��{]�@�@ |
p124-0125 |
. |
. |
| 42 |
�O���٘a���~�q�P�� [��{]�@�@ |
p127-128 |
�Ί_�s������ |
1766�N(���s15) |
| 43 |
���R���a����� [��{]�@�@�@ |
p129 |
. |
753(����18)
1�� ; 81.5�~34.0cm(���ł� 86�~39�p) |
| 44 |
�v��ƕ��[��{]�@�@�@ |
p124-0125 |
. |
. |
| 45 |
���l���[��{] |
p129�@ |
�|�x�������l�̕揊 |
1777(����42)�@
�|�x�������l�̕揊�ɗ���@ |
| 46 |
�L�R�������m�V�� [��{]�@�@�@ |
p131-132 |
. |
1707�N(����39) |
| 47 |
�ɍ]�ƕ��[��{] �@�@ |
p132-133 |
�ߔe�s�Η� |
1777(���s26) |
| 48 |
������(�k���鑺������) [��{]�@ |
p141�@ |
�k���鑺������ |
. |
| 49 |
������(�k���鑺���M�c) [��{] )�@ |
p142 |
�k���鑺���M�c |
. |
| 50 |
���J���ːΊ�����[��{]�@ |
p143 |
. |
. |
| 51 |
������(�L���鑺) [��{]�@ |
p146�@ |
. |
. |
| 52 |
�����Ί���(�L���鑺) [��{] |
p146-147 |
�L���鑺 |
. |
| 53 |
������(������ �N���k��) [��{] �@�@ |
p147 |
���������l�@ |
�����N�F1692�N(����24) |
| 54 |
������[��{]�@�@�@ |
p147-148�@ |
. |
1692(�N�31)
�����������̔q��(���)�̞����� |
| 55 |
���R��՞����� [��{]�@ |
p148�@ |
���NJԑ����� |
1701(�N�40)- |
| 56 |
���R��Ռܗ��{�� [��{]�@�@ |
p148 |
���NJԑ����� |
1701(�N�40) |
| 57 |
�y���L���e���[��{] |
p149 |
. |
1701(�N�40)�@
1�@�� ; 87.2�~34.5cm(���ł� 92�~39cm) |
| 58 |
������(���ю�) [��{]�@ |
p149-150�@ |
�Ί_�s ���ю� |
. |
| 59 |
�O���Ɗ��ؕ�[��{]�@ |
p155-168 |
. |
������@1846(����26) |
| 60 |
���V�����ɍ^���� [��{]�@)�@ |
p184-185 |
. |
�����N�F1456�N(���v3) |
| 61 |
������T���^���� [��{]�@�@ |
p186-187 |
. |
1456(�i��7) |
| 62 |
���쉞�������� [��{] [��]�F�q�v��]�@ |
p190-191 |
. |
1457(�i��8)�@
3�� ; 25.8�~32cm(���ł� 31�~37cm)
�@�@�`28.9�~34.5cm(���ł� 34�~39cm) |
| 63 |
���~�o���a�O���� [��{]�@�@ |
p196-197 |
. |
�����N�F1495�N(���^19) |
| 64 |
���~�o���a������ [��{] |
p198-199�@ |
. |
�����N�F1495�N(���^19)�@�̑�N�F1984�N2��18��
4�� ; 23.8�~34.8cm(���� 25�~35.7cm)�A
�@�@23.8�~34.6cm(���� 24.9�~35.7cm)�A
�@�@23.6�~34.5cm(���� 25.2�~35.7cm)�A
�@�@25.4�~34.2cm(���� 25.4�~35.1cm)
|
| 65 |
���~�o���O���� [��{]�@�@ |
p200-203�@ |
. |
�����N�F1697�N(����29)�@�@
�̑�N�F1984�N12��17��?(�܂ɋL�ڗL) |
| 66 |
�������^���� [��{]�@�@ |
p204-205�@ |
. |
1457(�i��8)�@
��{5���̓�2���͓������e ������ |
| 67 |
����Ίz(���J�쌹)[��{] |
225,249p |
�S�� |
�����N�F1800(����6)
1�� ; 53.8�~161.6cm(���ł�56.5�~165.9cm)�@�@ |
| 68 |
. |
. |
. |
. |
| 69 |
. |
. |
. |
. |
���@���L �w���Ε��x(���ꌧ���璡�����ە� ���ꌧ����ψ��� 1985)��������Ŗ��ɂ܂Ƃ߂����d������Ƃ���⏊�݂̖��L���ȂƂ��낪����A�S�̓I�ɂ܂Ƃ߂���Ȃ������B�������A�쐬�̒��łm��67�̕s���ƂȂ��Ă��܂������̂�A����̉ۑ�Ƃ��Ăm��13�́u���ʐv�́A�L���Ƃ����S���F�肷�邽�߂̂��̂��A�͂Ă܂��A�������A�Z�g�A�ΐM�Ɍq������������L�������B�@�@�Q�O�Q�R�E�U�E�T�@�ۍ�
|
�R���A�u��� : ��ԐM�K�����z���� 2 :�{�Ï����y�є��d�R�����v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@ (���ꌧ������������, ��70�W)�@�@239p �@�@�����F��㊌����}���فF1001560059
|
�������}�ၞ�q�{�Ï����r���NJԑ�
�q���d�R�����r���d�R�����̌�ԐM�K�����z�����m�[�g
�Ί_�s (�o���A�Ί_�A�V��A�����A��}�A�����A
��l�A�{�ǁA���ہA�嗢�A�약�A�Ί_�k��) |
�|�x�� (�|�x�A���l�A�����A�V��A���\�����A
���\�����A���ԁA�g�Ɗ�)���^�ߍ���
���d�R��ԐM�K���W�����ژ^�� �g�Ɗ� �i�g�^��
�E |
�S���A���c ���q�����{�̗w�w��ҁu���{�̗w���� (�ʍ� 23) p.p24�`31�v�Ɂu�Ɨt���ѕ������ɂ�����̊_�v�\����BJ-STAGE
|
(��j�@�Ɨt���ѕ�����
�i��j�̊_�̊T�O�K�� |
�i�O�j�����̉̊_
�i�l�j�l�p�[���̉̊_ |
�i�܁j���k�^�C���������̉̊_
�i�Z�j���{�̉̊_ |
�i���j�ނ���
�E |
�S���A�R�{�O���搶�җ�L�O�_�W���s�ψ���ҁu�����̗��j�ƕ��� : �R�{�O�����m�җ�L�O�_�W�v���u�{�M����
�v���犧�s�����Bpid/9775375
|
����̎� ���Ð����Y
�������f�Ղ̎F���Ɨ��� �n������/1
���ϋL�̐��E �c���C/25
�d���n�Ɋւ����l�@ ��������/55
���������O��̒ʉݖ��\���ւ�l�\ ������s/67
��O����㊌��̗A�ڏo���\���\�\�Đ��Y�c���̑O��Ɂ\ �약���Y/109
�ߐ������ɂ�����C�^�j�̈ꑤ�� ���Ǒq�g/125
�����`�����̗����ݔԕ�s �^�h���[��/141
�ߐ��n�����Ɋւ����l�@�\�����Ԑ��Ƃ��ā\ �c���^�V/157
�������̋N�����ɂ��� �~�ؓN�l/179
�ٍ��D�戵���K��Ɋւ����l�@ ���K����/197
�E���^�Ƃ��̎��� ����]/211
��㊂̃O�X�N�����ɂ��� ���Ð����Y �m�O�E/229
�����뉼�����̌��� ���{���q/267
���l�ɂ݂�×����̎v�z�\���֑o�P�_���̐����𒆐S�Ɂ\ ��Î�/291
�w�������R���L�x���O�E�l�w���n�E�����x�ɂ���
�@�@���\���Ɂw���؎��n�x�w��a���n�x�̈��p�Ɋ֘A���� �����K��/315
��㊕����j�̈�f�ʁ\�ߐ������ɂ����� |
�@�@�������Ȃ̎�e�������ā\ �n���얾/349
�ߐ������̏o�ŕ����\�����Ŗ{�𒆐S�Ɂ\ �x���s�p/409
���������G�} ��]�F��/419
��㊂̓��e�ҁ\�����E�吳���G�����e�҈ꗗ�\ ��������/479
�v�[�z���x�̋v�ē��ۂ̏����W�J�\���̐�O�E�풆�����o��
�@�@�����w�A�����J���x�̏I�����܂Ł\ ���]�F�i/507
�펞��㊂̖h�q���Ɋւ����l�@
�@�@���\��b�����̏Љ�Ɩ{���암�ɂ��ā\ �ʖؐ^�N/537
�w�j���Љ�x
����ߒ��ɂ�����V�����
�@�@���\�����������̐V���ؔ��m�[�g�𒆐S�Ɂ\ �䕔���j/564
�������ɂ��� �c���C/587
�v�ē��ɂ�����n�� ��������/623
�w���z�x
��㊂̋�ƊC�ƋF�� �R�{�O��/657
�R�{�O�����������E�_���ژ^�A�N�� �쐬�E���K����/660
���Ƃ��� ����]
�E |
�T���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 50(6)[(647)]�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059764
|
�A���o�� �A�W�A�̕��Q�|/p5�`8
�ÓT�|�\--�߂���߂����E<���W>/p10~158,�}p5~8
���̐l�ɕ��� ���Q�|�Ǝ� / ���� ;�щ�F/p10~28
�ÓT�|�\�̖��� / �O�����Y/p29�`38
�|�\�̍\��/p39~49
�|�\�̍\�� �Ў��̌|�\ / ���]����/p39�`43
�|�\�̍\�� �f�ƌ|�\ / �z�K�t�Y/p44�`49
�|�\�̏���/p50~100
�|�\�̏��� �̊_ / �n�ӏ���/p50�`54
�|�\�̏��� ���l / �n����q/p55�`58
�|�\�̏��� �a�] / ���Ώ��v/p59�`62
�|�\�̏��� ���� / �R���G��/p63�`67
�|�\�̏��� �K�ᕑ / ����w/p68�`71
�|�\�̏��� ���o�� / �R�{�g���E/p72�`75
�|�\�̏��� ��ڗ��Ɖ̕��� / ������/p76�`79
�|�\�̏��� ��Ȍ|�\����ƍu�k / �֎R�a�v/p80�`84
�|�\�̏��� �G���� / �щ�F/p85�`88
�|�\�̏��� �̂������炭�� / �R�{�c��/p89�`92
�|�\�̏��� �ڏ��S / �����M�v/p93�`96
�|�\�̏��� �c�A�� / ���×Y/p97�`100
�n���̌|�\/P102~121
�n���̌|�\ �����́u����\�v / �n�ӗǐ�/p102�`104 |
�n���̌|�\ �[���́u�S���}�v / �����v/p105�`107
�n���̌|�\ �͓��́u�����x�́v/�^�珹�O/p108�`111
�n���̌|�\ �|���́u�����������v/�F�v����/p112�`115
�n���̌|�\ �I�����Ɨ���/��Î�/p116�`118
�n���̌|�\ �����́u���́v / ����w�v/p119�`121
�_�Ԍ����|�\/p122~139
�_�Ԍ����|�\ �w�����ߏ��x�ɂ݂�|�\ / ���l�ʗ�/p122�`127
�_�Ԍ����|�\ �u�������O�}�v�ɂ݂�|�\ / ���V�O/p128�`133
�_�Ԍ����|�\ �u�G�n�v�ɂ݂�|�\ / ���G��/p134�`139
�|�\�}���� / ��]���͉� ��/p140�`150
�|�\�}���� ��]���[�w���S�q�L�x / ��]���͉�/p140�`141
�|�\�}���� �������t�w�V���y�L�x / �g���_�l/p142�`143
�|�\�}���� �֓������w���ȗގ[�x / ��v�Ԋ��Y/p144�`146
�|�\�}���� ������w���p�ԓ`�x / ���ь���/p147�`148
�|�\�}���� �呠�Ֆ��w����ב��x / ���{����/p149�`150
�����̎���� �ÓT�|�\��v�������ژ^ / �����p�I/p151�`158
�����w���r�[ �{ / �z����/p160�`161
�G���|�T�� �u�����v�Ɣ����́u���ȁv / �g��q�Y/p162�`163
�V���Љ� �R�����I���w�Ñ���{�ꕶ�@�̐����̌����x/���c����/p175�`175
�A�� ��[�N�����ȏW(57) / ���c���F/p164�`166
�A�� ���{��w ���{��ƃ^�~����̊W(29) / ���W/p174�`167
�E |
�T���A����m���ҁu���{���y�ƌ|�\�̌����v���u���{�����o�ŋ���v���犧�s�����B�@ (���{�����̌��������߂�, 3)
|
���{���y�����̌������l���� : ����N�ɂ����� / ����m��
���{���������N���_�̖��_ / ��ё���
���{�̉��y: ���{�̖������y / �����
���{�̌Ñw�̎���̉��y / �������q
���{�̌|�\: �Ղ�ƌ|�\ / �O�����Y
���{�|�\�̓`�d�ƕϗe / �R�H����
�Ɨt���ёт̉��y�ƌ|�\: �Ɨt���ётɂ�����`�x�b�g�E
�@�@���r���}�ꑰ�̐����Ɖ��y : �k���^�C�̃A�J���𒆐S�Ƃ���/���c���q
������א��E�̉��y: �~�N���l�V�A�E |
�@�@���T�^�������́u�����v�̏ے��� / �ΐX�G�O
�������̉��y�ɂ��� / �C�z��
�k���A�W�A�̉��y / �J�{��V
���N�����̉��y�ƌ|�\: �؍����y�̌��� / ���ݞ�
�؍��ލՂ̖����|�\�I���i�ɏA���� :
�@�@���ʐ_�n�N�b�̍\���ƕ����̈�I���� / ����\
�����̉��y: �������������̉��y�ƌ|�\ / ���B��
�����̉��y�Ɗy�� / �O�J�z�q
�E |
�U���A�q�쐴��������w�j�w��ҁu����j�w = Ryudai review of history (�ʍ� 14) p.p1�`20�@������w�j�w��v�Ɂu���E���d�R���x�X�������R��--���d�R�Q���̌�x�Ɋւ��钲���������ԕE�Ί_���v�\����B
�V���A�^���x�q���u����j���S�v���u�}�����[�v���犧�s����B�@�@pid/9775253
|
���͓n/4
�锼�̐�/52
�~�Z/58
�R�����̖�/62
��������/68
�N�C�[���E�G���U�x�X/72
��/79
���Ԗ����ɂ�/86 |
��l��/92
����/97
������/102
�j���S/112
�n�`�E�N�V�[/119
����/127
�����̐�/133
�z�[�z�P�L��/140 |
�j��/146
�ܖڔ�/157
������/164
�/177
�L�̃X�[�v/183
�����A���v/189
��������ɂ�/200
�D�_/204 |
����/209
�ꊦ��/219
�ؖ���/225
�J�`���[�V�[/228
���[�j���O�R�[��/233
���Ƃ���/237
�E
�E |
�X���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (10)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@pid/6067717
|
���q�Ƌ��� / �����r�Y/p4~7
��߉ނƏ��߉ނ̐_�b���E / �R�ܓN�Y/p8�`10
�C�k�E���l�Ə��l / ��ё��� ;�J�쌒�� ;���c�C/p11~28
�`�����ꂽ���l�Ə��l�̃C�}�[�W�� / �S�i����/p29�`32
��r�_�b�E�X�N�i�r�R�̓��ِ� / �g�c�֕F/p33�`36
���l�E���l�`���̐S���w / �D�c����/p37�`41
�A�C�k���b�̒��̋��l�Ə��l / �������}/p42�`43
���k�n���̋��l�Ə��l / ��F�`��/p44�`45
�֓��n���̋��l�`�� / �ѓ��g��/p46�`47
���B�̃_�C�_���{�b�`�ƎO�ږV / ��{����/p48�`49 |
�M�B�̑�l�E�f�[�����{�[�̑��� / ���Ԉ�/p50�`51
���l�`���Ɖ������Ꝅ / ���ђ��Y/p52�`53
�ߋE�n���̋��l����l / ���J�d�v/p54�`55
�R�A�n���̋��l�Ə��l / ���Ώ��b/p58�`59
�����n���̋��l�Ə��l / ����і�/p60�`61
�l���n���̋��l�Ə��l / ���c��/p62�`63
�R�����Ɩk��B�̋��l�Ə��l / �ɓ���/p64�`65
�F���̋��l�Ə��l / �R���ӈ�/p66�`67
���d�R�����l / �q�쐴/p68~69
�Q�l�����E����/p70~70 |
�P�O���A�����o�ŕҁu���j�蒟 13(10)(144) ] �v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@�@pid/2246587
|
����̏@���I���E�\�\���̊�w�ɂ������ / ��Î�/p4�`9
�����̎v�z�\�\�������E�ς̎��Ԙ_�I�l�@ / ��ؐ���/p10�`16
�g�D�n�V���l�\�\����̉Ƃ̐_�ɂ��Ă̈ꎎ�_ / �ԗ䐭�M/p17�`23
�w�������R���L�x�Ƒ������J / �Ôg���u/p24�`29
�����̗�-������N / �������X/p31�`37
�m���ƃ��^�\�\���j�I�W�J�ƎЉ�I���� / �c���^�V/p38�`43
����̕����� / �V��q�j/p44~51 |
�t�E��v�Q�l�����ژ^/p52~57
�������z ���j�Ǝ� / �j��a�Y/p3�`
�_��v�z(15)���y�L���Ђ炭 / �뉹�\�V/p58�`59
���Ɣ�����(10)�]�˥�����̓s�s��ǂ� /
�@�@���w���G�M��ɓ���j/p60�`65
�n���j�o�Ŗژ^ / �ҏW����/p66�`69
�n���j�G�������ژ^ / ���V���v/p70�`81 |
�P�O���A���Ï@�����u�����w�I���̂̌���(5) : �u���P�́v�𒆐S�Ƃ��āv���u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v.
�����w�� 14(1) p.26-41�@���ꍑ�ۑ�w���w���v�ɔ��\����B
|
���Ï@�����u���ꍑ�ۑ�w���w���I�v. �����w�� 3�i1�j�` 14(1)�v�ɔ��\�����u�����w�I���̂̌���(1�`5)���̓���ꗗ�\�@�@ �iIRDB�j
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
, |
| 1 |
3(1) p.33-46 |
1974-10 |
�����w�I���̂̌���(1):����A�썇���A�엣��𒆐S�ɂ��� |
, |
| 2 |
3(2) p.11-25 |
1975-03 |
�����w�I���̂̌���(2):����E���ӐM�ɂ��� |
, |
| 3 |
4(1) p.1-14 |
1975-10 |
�����w�I���̂̌���(3):�`���𒆐S�Ƃ��� |
, |
| 4 |
13(1) p.15-30 |
1984-10 |
�����w�I���̂̌���(4)(��) : �u���Ȃ�_�M�v�𒆐S�Ƃ��� |
, |
| 5 |
13(2) p.33-42 |
1985-03 |
�����w�I���̂̌���(4)(��) : �u���Ȃ�_�M�v�𒆐S�Ƃ��� |
, |
| 6 |
14(1) p.26-41 |
1985-10 |
�����w�I���̂̌���(5) : �u���P�́v�𒆐S�Ƃ��� |
, |
|
�P�P���A�u���V�������� 3�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
�@�@ (�n�挤���V���[�Y ; no.8)�@pid/9775927
|
���O���� ���V���A�T�Â̒��S�n�`���Ɠs�s��/1
���i���� ����і�ߑ㉻�@�Ɠ��V����X�̋��L��/19
�Ό����� ���V���ݏZ����o�g�҂̐����j/47
���n�N�v ���a��O���ɂ�����V�钬�̋��ƂƎ����n�����\
�@�@�������E���y��ݏZ�̎����n�����̐����j�𒆐S���\/55
�E���� �����V���̊��_�M��/67
|
�X�ۉh���Y ���V���̖����|�\�\���ɖ~�x��ɂ��ā\/79
�R���ӈ� ���V���ɐ��n�ɂ�������b�Q
�@�@���\���b�Ƃ��̐����̃_�C�i�~�Y���\/93
��]�F�� ���V���ɂ�����\�e�c���p�ɂ���/135
���~�ߎ� ��ʓ�̑��搧/151
�����r�O ���V���ɐ咬�����̌�b�\���ԕ\/173 |
�P�P���A���a�c�^�~, ��c���q���u����̖S�� : �N�ɂł��ł���̗��p�@
: �₳�����������ƈ��ݕ��v���u�V���}���o�Łv���犧�s����B
�P�Q���A�����x�m�q���c���`�m��w�̈猤�����ҁu�̈猤�����I�v = Bulletin of the Institute of Physical Education, Keio University 25(1) p.p19�`29�c���`�m��w�̈猤�����v�Ɂu���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ���-3-�Ղ�ƌ|�\�v�\����B
|
�����x�m�q���̈猤�����I�v 23(1)�`25(1)�ɔ��\�����u���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ��ā@1�`3�v�܂ł̓���ꗗ�\
| �m�� |
���\�G������ |
���s�N�� |
�_�����Ɠ��e |
| 1 |
23(1) p.p35�`45 |
1983-12 |
���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ���-1-
1�͂��߁@2���x�̔����@3�u������v�@4�g�x�̐����@5�ʏ钩�O�Ƒg�x��@6�ނ��� |
| 2 |
24(1) p.p29�`40 |
1984-12 |
���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ���-2-
1�͂��߁@2�]�ˏオ��@3�u������v����O�������y�ց@4���̂̐����Ɠ����@5�ނ��� |
| 3 |
25(1) p.p19�`29 |
1985-12 |
���ꕑ�x�̗��j�I�w�i�ɂ���-3-�@�Ղ�ƌ|�\
1�͂��߁@2�Ñ�̐_�̊ϔO�@3���X�̍Ղ�@4�Ղ�ƌ|�\�@5�ނ��� |
|
�P�Q���A�~���w�@��w�n�敶�������� �ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v
= Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (1) �v���u�~���w�@��w�n�敶���������v����n�������B�@�@
�@�@�@�@��������}���كI�����C���@�w�p�@�փ��|�W�g���f�[�^�x�[�X�iIRDB�j�F404 Not Found
|
�u�I�v�v�����Ɋā@�@�����א� p.1-1
���{���{�_�Ђ̐�����s�����߂�����@�������� p.3-16
�g�c���A�̐��E�ρ@�@�ߓ��~�q p.17-32
���|�\����(1)(����26�N-����32�N)�@�@�������s p.33-48
���֎s�W�䓇�̗V�Y�̂Ə������Ƃ@�@����M�q p.49-64
�L�Y���A�c��Տo�y�̋��Ё@�������v �~ p.1-7
�q�H�ו����y�L�r �������Ɓ@�@�R�c�����Y p.7-8 |
�L���P�ʍl�@�@�؉����q p.9-18
���ւɂ�����ؔ����̕��� :
�@�@���O���[�����[�����X�X�̒n���w�I�l�@�@�L�c�� p.19-26
�����a60�N�x���� �V���|�W�E���E�n�敶�����l����@ p.27-55
���������̕����Ɩ��� : �����哇�E���i�Ǖ����E
�@�@���^�_���̉����L�q�𒆐S�Ɂ@���c�{�� p.57-80
�W�䓇�̉́E��̎q�Ղ̉́@�@���R�� p.81-86 |
���A���̔N�A�u�쓇 : ���̗��j�ƕ��� 5 �쓇�j�w�� �� ��ꏑ�[ 1985/pid/9639749/1/1
|
�O�ߑ�A�W�A�̊C���� �a�c�v��/1
�y���[�͑��̏��җ����\���̍Č��o�߁\ �K����� ����[/21
�ÉF����A��Ղɂ����鋙�������ɂ��� �c������q/35
�� �ÉF����A��Ղ̈ʒu�Ɛ��i/35
�� �������������̂��߂̕��@/36
�O �i�����E�u�_�C�𒆐S�Ƃ������������̕���/46
�l ����/51
����ɂ����鍩�z�H�ތ^�̓��F�Ɨ��j�I�Ӌ`�t�� ��Ό\��/69
�� ���_�\����̍��z�H�̓��F/69
�� ���z�H�̗ތ^/70
�O K-T�_�C���O�����̍쐻/71
�l ���z�H�ތ^���z/73
�� ���z�H�j�N�\/75
�Z �����Ȍ㒆�����z�f��/77
�� ����ɂ����鍩�z�H�ތ^�ɋy�ڂ����u���z���v�̉e��/78
�� �܂Ƃ�/80
�}���[�V�A�E�V���K�|�[���ɂ��������B�l��
�@�@�������_�M�ɂ��� �J���[�j/91
���V���̒n���l ���x�d��/115
�͂��߂�/115
�� ���n�ƒn��/116
�� �L�^�n���̒a��/117
�O ���̒n��/120
�l �n���l�̎菇/121
�� ����n���l/128
�I���/150
���㗮�����́u�v�đ��l�v�̐��͂ɂ��ā\
�@�@���w����āx�ɂ��\ �������q/153
�� �͂��߂�/153 |
�� �v�đ��l�̑����y�ъ��E�ʐl��/155
�O ���v�E�f�Ղɂ�����v�đ��l�̖���/159
�l �����ʐ��c��v�E���j�E�ʎ���/164
�� �v�đ��l�̐���/167
�Z �u�O�\�Z���̒��Ӂv�ɂ���/168
�� ������/174
�擇�ɂ�����l���Ő��x�n�݂Ɋւ��錤�� �q�쐴/179
�� �͂��߂�/179
�� �����̍������R/181
�O �Ȃ����擇�̒n��Ɍ��肵�ē��ʐŐ����{�s���ꂽ��/183
�l ��z�l���Ő��x�ւ̈ڍs/185
�� �F���˂̋��m���x�Ɩ劄���x�i��j/186
�Z �F���˂̋��m���x�Ɩ劄���x�i��j/189
�� ���m�E�劄���x�ƍݔԁE�l���Ő��x�̑ΏƔ�r/191
�� �u�t���J�h�D�v�Ƃ����Ì�ɂ���/195
�� �l���Ő��x�̑n�݂Ƃ��̎Љ�I�e��/199
��Z �l���ł��߂���ŋ߂̏����ɂ���/201
��� �ނ���/204
���Ŋ��̓쓇���g���l �s��d��/213
�� �쓇���g�̔p�~/213
�� �쓇���g�̕��l/214
�O �쓇���g�̑��`��/230
�ߐ��������̒����g�߁\���̍v���Ɨ����l��n�\ ���a�F/239
�� �͂�����/239
�� �v���Ɋւ���j�����/240
�O ���B�|�k���Ԃ̍v��/249
�l �k�����Ƙp�̗����l��n/263
�� ���Ƃ���/272
�쓇�j�����Ƃ��̊w�ې� ��������/279 |
���A���̔N�A���k�V�n���u�_�k�̋Z�p 8 p.1-27�@�_�k�̋Z�p������v�Ɂu <�_��>���\���̃^���C�� --���̓`���I�͔|�@�Ɨ��p�@--�v�\����B�@�@�iIRDB�j
���A���̔N�A���ǎs����ψ���ҁu���I�`�����������L�^�쐬���K�̃p�[���g�E�������v���u���ǎs����ψ���v���犧�s�����B�@�@�����F���s�{���}���� ���ꌧ���}����
���A���̔N�A���ꌧ�N�c���c��[�ق�]�ҁu�N�ӂ邳�ƃG�C�T�[�Ղ� : ���N�n�抈�����y�|�\���\��
��21��v���u���ꌧ�N�c���c��[�ق�]�v���犧�s�����B
���A���̔N�A�떓�b�ꂪ�u���{�̗w���� 23(0) p.101-102�v�Ɂu�q���]�r���c���q���w�������w�Ƃ��̎��Ӂx�v���Љ��B�@J-STAGE
���A���̔N�A�V��S�v���u�V��S�v�m�[�g 8 �v���L�q����B�@1�� �����F��㊌����}���فF1002233615
|
��㊌����}���ق���������u�V��S�v�m�[�g �P�`8�v���̕\�蓙�̓���ꗗ�\�@
| �m�� |
�m�[�g�� |
�L�q�N |
���e |
�����R�[�h |
| 1 |
�V��S�v�m�[�g �P |
1974 |
�\���Ɂu���z�m�[�g�v�@����P�E�c�����N���쐬�p�m�[�g |
1002233540 |
| 2 |
�V��S�v�m�[�g 2 |
- |
����P�E�c�����N���쐬�p�m�[�g |
1002233557 |
| 3 |
�V��S�v�m�[�g 3 |
- |
�̎���4���Y�t �\�t�F�V���ؔ� �ɔg��N ���S�L�� |
1002233565 |
| 4 |
�V��S�v�m�[ �g4 |
- |
- |
1002233573 |
| 5 |
�V��S�v�m�[�g 5 |
1980 |
���e�F�������W�p���� |
1002233581 |
| 6 |
�V��S�v�m�[�g 6 |
- |
���e�F�������W�p���� |
1002233599 |
| 7 |
�V��S�v�m�[�g 7 |
1984 |
�\���Ɂu�V��T�������� |
1002233607 |
| 8 |
�V��S�v�m�[�g 8 |
1985 |
�\���Ɂu�����N�W�����v |
1002233615 |
|
|
| 1986 |
61 |
�E |
�P���P�W���A�u����s����ّ�z�[���v�ɉ����āu����s�ÓT�|�\�ӏ܉� �ÓT���x��ƎG�x��̗[��
��8��v���J�����B
�P���A����s����ψ���ق��ҁu����s�ÓT�|�\�ӏ܉� �ÓT���x��ƎG�x��̗[��
��8���i�����p���t���b�g�j�v���u����s����ψ���v���犧�s�����B�@14p �@�����F��㊌����}���فF1005965015�@
�Q���A�u���̐��E (2)�v���u���肽���̉�v���犧�s�����B�@pid/4427330
|
�����̂��Ƃ�/p1~1
���W1 �u���^ �����̃��^�̐��b�Ɖ� / ���c���q/p4�`12
�@���W1 �������m�[�g �����Ɛ̘b / ���Y�M�q/p13�`15
���W2 "�S��`�������"'85�H�̘A���u��
�@�ǂ݂������ƌ��̈Ⴂ / �ȓc����/p16�`18
�@�J��Ԃ��̈Ӗ� / �ߓ��K�q/p19�`21
�@�V���������"���̃��J�V" / �����d�v/p22�`24
�@�Â��ɂ��݂���邱�� / �O�Y���q/p25�`27
�@�䂪�Ƃ̌��(1) / ��{�I�q/p28�`31
�@�䂪�Ƃ̌��(2) / �؉����m�q/p32�`34
�@ '85�H�̍u���ɎQ������ / ������q ;���삠���q ;�@ |
�@����؍O�q ;�����v���q ;���R�b���q/p35~35
���ꂩ��̃��|�[�g �}���قŌ�邱�ƁA
�@�@�������Č������b�Ƃ̏o���� / �x�c��/p38�`43
�킽�������̌����l����(���̈�)
�@�@����邱�Ƃ�ʂ��Ďq�ǂ��������ƈ�Ă��� / �N����I/p48�`53
�k��ŕ������̘b �n�R�_�ƕ��̐_/p44�`46
�G�b�Z�C ���₷�ݑO�̂�������� / �ΌE����/p36�`36
�G�b�Z�C ���Ɓu�䂫����ȁv / �����ݍ]�q/p47�`47
���ǂ��̌���C���^�r���[ �����ƌ��ꏊ���ق�����/�ȓc��傤����/p37�`37
������� ���ɂ̂���������B/p54�`54
�ʐM�̃y�[�W ���肽���̉�ɂ��āE���m�点/p55�`55 |
�Q���A�������ďC �u���������� (�ʍ� 269) �v���u���@�K�v���犧�s�����B�@�@�d�v
|
�������ɂ݂鉫��̂����� �@��闧�T p.p4�`6
���ꌧ�̍H�|�Z�p �n���� �� p.p7�`11
�{�Ẫp�[���g�E �@���w p.p12�`16
����̌ÓT�|�\ �@�X�ۉh���Y p.p17�`20
�|�x���̐����ƏW���ۑ� ���� �q���q,�O���M�B p.p21�`28
|
�������̏C�� �@�؍O�� p.p29�`32
�����������Ƃ��̕������� �@�� ���v p.p33�`37
�鐳�a�Ղ̒��� �@���^�k��,�㌴�� p.p38�`40
�����̎��ߏ� ���� �q�g p.p41�`44
�V�w��̕����� �������������ی암 p.p45�`53 |
�R���P�V���A�R�����j�i��܂��� �����Ђ�j���S���Ȃ�B�i�X�U�j
�R���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ���̌Ñw���l���� : �@����w��7�ۃV���|�W�E���v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@�@pid/9775443�@�@�P�O�O�O�~�@�@�d�v
|
�q�͂������r �����G/1
�q�J��A�r �����N/3
�q�j���r ��������/6
�q�L�O�u���r�������Ƃ��Ẳ��� ��]���O�Y/9
��I�� ����ɂ�����_�ϔO�Ɛ��E��
�q��1�r�����𒆐S�Ƃ����쓇�̐_�ϔO�Ɛ��E�� J�E�N���C�i�[/38
�q��2�r�g�Ɗԓ��ɂ�����_�ϔO��
�@�@�����E�ς̈�l�@ C�E�A�E�F�n���g/52
�q��3�r�w�����낳�����x�Ȃǂɂ݂鉫��̐_�ϔO��
�@�@�����E�� �O�Ԏ�P/64
�q���_�r����ɂ�����_�ϔO�Ɛ��E��/81
��II�� ���ꌤ���̌���Ɖۑ�
�q���A�r ����O/136 |
�q��1 �l�Ár����ɂ������j���� ���{�A�q/138
�q��2 ���j�r���ÐN����̋v�ē��̓y�n���x �R�{�O��/155
�q��3 �����r���ꖯ�������̌��_ ���䓿���Y/166
�q��4 �Љ�l�ށr���ꕶ���̎Љ�\���I��� ��������/179
�q��5 ����r����w����݂��������� ����v�_/192
�q��6 �������y�r���K���_����݂����ꉹ�y�̌Ñw ���v/204
�q��7 �|�\�r�R�l���蕶�����Ɖ���̌|�\ �O�����Y/220
�q��8 ���z�r���{�ɂ�����쓇�n�Z���̋�ԍ\�� �R�c����/241
�q���_�r���ꌤ���̌���Ɖۑ�/260
�q���Ƃ����r �O�Ԏ�P/301
�q�v���O�����̑S�e�r/303
�q�Q���҂̃v���t�B�[���r/307
�q�p�����W�����r/����1 |
�R���A�����Y�p�w��ҁu�����Y�p = Ethno-arts (2)�v���u�����Y�p�w��v���犧�s�����B�@�@��id/7959287
|
���N�����̌|�p �����̛���/p8�`20
���������G�l / �g�c�G�u/p21�`31
���N�����̓��� / �ɓ��葾�Y/p32�`41
���펞�㗆���ɂ݂鐿���Z�@�̍����� / �͓c��/p42�`52
���N�̉��y / �u���N�j/p53�`59
�_�X�̜߈˂Ɖ��Y�E���� / �J�O/p60�`71
�킪���Ɗ؍��́u�|�\�v�ɂ݂�`���`�Ԃ̍��� / �X�i���v/p72�`81
�����|�p�̏��w �����|�p�ƕ��y / ����\/p82�`83�@�@
�i�����遃�@�ۂ̌|�p�� / ������m�q/p84�`97
�l�����̓o�� / ���쏟/p98�`109
�J���f�B���X�L�[�̖����w�����ɂ��� / �ɓ���Y/p110�`119
�y���h�ƍ�O�̏ё��� / ��ԍ�/p120�`130
�k���^�C���������̐����Ɖ��y / ���c���q/p131�`145 |
���̂Ȃ��̐��x / �R�c�z��/p146�`163
�������b�Ɩ����Љ� / ��X���i/p164�`170
�V���|�W�E���u�����|�p�Ƃ͂Ȃɂ��v���߂����� / �J���W/p171�`173
�����|�p�̘_�� / ���m/p174�`175
�����|�p�w�̓Ǝ������l���� / �N��N�j/p176�`177
�����|�p�w�Ƃ͉��� / �O�쓹�Y/p178�`181
�W����] �g���R�����W�Ɋ� / �呺���q/p182�`185
�W����] �e�L�X�^�C���E�I�u�E�I�[���h�E
�@�@���W���p���W��/����ܘY ;�Ђ낢�̂Ԃ�/p186~188
�W����] �R�x�M�̈��W�] / ����쐰/p189�`192
���] / ���їm/p193~194
�b��/p195~198
�E |
�R���A�u���V�������� 4�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@
�@�@(�n�挤���V���[�Y ; no.9)�@�@pid/9775928/1/1
|
���~�ߎ� ��/1
���R�� �����̓V�l���[杁\�`���ƐM�\/3
�g���E�v �����K�w�\���̎j�I�W�J�\�n��E����W�𒆐S�Ɂ\/25 |
���c�h�� ���V���̊C�ݐA��/47
�쌴�O�` �{��M�� ���V���̓���������b/91
���n�N�v ���V����������/177 |
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (6)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@pid/7955135
|
�g�D�n�V�����߂��鏔��� / �ԗ䐭�M/p1�`9
�ʔv�p�����߂���֊��Ɖ��--�ߔe�s���\�̎��ᕪ�͂��� / �㌴�G���q/p10�`20
�ʔv���J�Ƌ֊�--����{�������ɂ����鎖�ጤ�� / �����r��/p21�`33
�v�ē��Ɉ��A�V�A�Q�R���l--�����������̓`���I���� / �F�]�삿���q/p34�`42
�}�u���[�E�[�ɂ��Ă̈�l�@ / �×z���q/p43�`48
�ɕ������̎�q��Ə��s��--��쉮�����̏ꍇ / �n�v�n����/p49�`51 |
�؍��̍j����--�S���k���}���W�������̏ꍇ
�@�@�� / �X�ۉh���Y/p52�`58
�ϏB���̖��� / ��]�F��/p59~67
�������m�[�g�� �{�Ó��刢��̌p�� / �ʖ؏��F/p1�`7
���j���Љ �䉼������L(3) / ���n�B��/p8�`18
�E |
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (12)�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/3467955
|
���ꌧ�������ُ����́u�H�H�l�v�ɂ���(�O) / �X�ۉh���Y/p1�`6
���d�R�̎��ɂ��� / ���쐳�q/p7�`12
�D�֘q���֖�̗��� / �Ôg�Ñ�/p13�`18
�����ɂ��� / ��]�F�q�v/p19�`24 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(V) / �m�O�E/p25~42
���������ق̐D��(I) / �^�ߗ��q/p43~60
�v�ē��W�j�� / ��]�F��/�E1�`8
�E |
|
���a�c�^�~�^�m�O�E�����ꌧ�������ًI�v(8�`12)�ɔ��\�����u���a�c�^�~�������W�̍l�Î���(�T�`V)�v���̓���ꗗ�\�@
| �m�� |
�����ًI�v���Ő� |
���s�N�� |
�_���� |
pid |
| 1 |
8 p.9-36 |
1982-03 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î����i1�j |
pid/3467951 |
| 2 |
9 p.1-22 |
1983-03 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î����i2�j |
pid/3467952 |
| 3 |
10 p.1-24 |
1984-03 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î����i3�j�@ |
pid/3467953 |
| 4 |
11 p.1-14 |
1985-03 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î����i4�j |
pid/3467954 |
| 5 |
12 p.25-42 |
1986-03 |
���a�c�^�~�������W�̍l�Î����i5�j |
pid/3467955 |
|
�R���A��쑺����ψ���ҁu���I�`�����������L�^�쐬 �{�Ẫp�[���g�D
: �u�쌴�̃p�[���g�D�v�������v���u��쑺����ψ���v���犧�s�����B�@ (��쑺������������ ; ��4�W)�@56p�@�@�����F��㊌����}���فF1006993875
|
�����ɂ悹�� ���� ����
�ጾ ���� ��F
�{�Ó��A�쌴�̈ʒu�} ���n�R ����
�{�Ẫp�[���g�D(�쌴�̃p�[���g�D�s���ʐ^) �V�� ����
��1�� �쌴�̊T�� �E�E�E ���쐴��A������F ��� �w
��2�� �쌴�̑���-��ԑ��Ƒ��z�M��- �E�E�E ���n�R���� ���ǐV��
��3�� �쌴�̎j�� �E�E�E �V������ |
��4�� �쌴�̔N���s�� �E�E�E ���w
��5�� �쌴�̃p�[���g�D�̓`�� �E�E�E ���n�R����
��6�� �p�[���g�D�̏o������u�T�e�B�p���E�v�ɂ��� �E�E�E ���ǐV��
�쌴�W���}
�쌴�g�����}
�T�e�B�p���E���H
�E |
�R���A�u���V�������� 4 �v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@
�@�@(�n�挤���V���[�Y ; no.9)�@pid/9775928
|
���~�ߎ� ��/1
�����̓V�l���[杁\�`���ƐM�\ �@���R��/p3
�����K�w�\���̎j�I�W�J�\�n��E����W�𒆐S�Ɂ\�@�@�g���E�v/p25 |
���V���̊C�ݐA���@�@���c�h��/p47
���V���̓���������b�@�@�쌴�O�`�E�{��M���@ /p91
���V�����������@���n�N�v /p177 |
�R���A�����s���}���ٕҏW�u�O��t�����ɖژ^�v���u�����s���}���فv���犧�s�����B�@�@592p�@�@�P�O�O�O�~
�T���A�V��S�v�ҁu���������� ��1���`3���v���u�o�ŎЁF������v���畜�������B�@38,52,43p�@�����F���ꌧ���}����
|
��1�� ����O�\�N������ �c����蒘 38p
��2�� �����A���̌��� ���a�c�^�~,��������� 52p |
��3�� �z�������L ���R�v�O�� ���ǐ��g�� 43p
�E |
�U���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO10.�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}����
80p
|
�ꖩ���y��̕ҔN�I�ʒu�ɂ��� �㑺 �r�Y
��u�쎮�y�� ���{ �A�� ���� �k�~
�쓇����(13�`15)
(13) �^�J���K�C�E�A���r�ƃ��R�E�K�C
(14) �X�r(�V�r)�O�̌Â�
(15) ���͂�Ⴂ- �O�� �i |
����n���̐���Z�@�l�@
(1) �Y�Y��Տo�y�̊��𒆐S�Ƃ���- ���n ���L
�u���d�R���y��ɂ��Ă̈ꎎ��-�^�ߗǁA�����A
���}�o���[��Տo�y�y��̕��͂��Ƃ�����-�v ���c �F��
�V���l�ÊW�����ꗗ(3) �F�� �G�q
�E |
�U���A���Ǒq�g��,��ˏ��v�ʐ^�u�������牫��ցv���u�|�v���Ёv���犧�s�����B (����̎��R�ƕ����V���[�Y ; �P�O)
|
�u����̎��R�ƕ����V���[�Y�@ 1�`10�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�m�� |
���s�N�� |
���� |
�ʐ^ |
�^�C�g���� |
| 1 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y 1 |
1986-06 |
������F |
��ˏ��v |
����̂��������C |
| 2 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y 2 |
1986-06 |
�╍�M�I |
�╍�M�I |
��̓��̍������� |
| 3 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y 3 |
1986-06 |
��ؗǖF�� |
��ؗǖF�� |
�ӂ����ȓ��������̂��ޓ� |
| 4 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@4 |
1986-06 |
�V�[�`�n |
��ˏ��v |
��̓��̐A�� |
| 5 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@5 |
1986-06 |
��c�s��v |
��ˏ��v |
����̋��ƂƂ��炵 |
| 6 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@6 |
1986-06 |
�^�h���� |
��ˏ��v |
����̎Y�ƂƂ��炵 |
| 7 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@7 |
1986-06 |
���w |
���w |
����̂����������ǂ�Ɖ́@ |
| 8 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@8 |
1986-06 |
���w�� |
��ˏ��v |
����̔N���s�� |
| 9 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@9 |
1986-06 |
��]�F�ϕ� |
��ˏ��v |
����̂��炵�ƕ��� |
| �P0 |
����̎��R�ƕ����V���[�Y�@10 |
1986-06 |
���Ǒq�g |
��ˏ��v |
�������牫��� |
|
�U���A�u�܂� = Festival (46)�v���u�܂蓯�D��v���犧�s�����Bpid/7930519
|
�C�_�ƌb��{�M�� / �V��P��/p7�`40
�{�ÈɗǕ��̃q�_�J�� / ��ÍN�Y/p41�`51
�I�B�c�ӂ̃G�r�X�Ղ� / �_�ݍG��/p52�`61
���̕l�U��� / ���c��/p62~74 |
�\�o���̃g���o�^�Ղ�--�\�o�����̊C��n��� / ���q�w/p75�`93
�F�쥑�ӘH�̊C�̂܂� / �����ϋg ;�����_��Y/p94~100
�C�̐_�ɂ�����--�����͂�̔�V / �x�c�g�Y/p101�`118
�`�̐��l�ƊC�_�̃��[�c--�Δn�̊C�_�`����� / �i���v�b/p119�`144 |
�V���A�k���v�搶�Ǔ��_���W�l�ҏW�ψ�����u�����̉� : ���v�搶�Ǔ��_���W�v���u���y�V�F�Ёv���犧�s�����Bpid/12432731
|
I: �������y�w�ƓT����w / �쑺�ǗY
�ӂ��̎^�� (�C���k�X) : �L���V�^�����y�ƃX�y�C������ / �F��B�v
II: ���{�̖��w�Ɩ������y: ���l���̌���� : ���̌|�\�Ɗw�K�\�� / �����x���q
���d�R���w�����^, �A���[�̔��� : ���Y������̎��� / �����
���ꌧ�̉P���� / ���ь��]
����{�����G�C�T�[�̉��K / ���эK�j
�a�̎R���̓c�A�� / ��ыI�q
�⍑�̓��x��ɂ��� / �Ћˌ�
�����|�\�̈ꌤ�� : ���������_�Ƃ��� / �g�����
���s�{�̖��w / �����, �����x���q, �����͎q
���{�̗��j�I���y: �������l / �������Îq
���{�Ñ�̃V���}�j�Y���ƃc�d�~ / �������q
�ڔ��ÓT�{�Ȃ̓`���l�@ : ���p�[�g���[�̌`���ƕϗe / ����P�q
���{�̉��y����Ɗw�K: ���{�̉��y����ɂ����閯�����y / ����
�[�~�i�[���u���{�`�����y�̗��_�I���K�v�Ɋւ�����@�_�I���|�[�g / ���{�ꋤ�q
�`���v�߂̊w�K�@ : ���{�`�����y�ɂ�����̌��I�w�K�@�̈Ӌ`�ƍ���̉ۑ� /
�Ύ�،��q
���{�̗̉w��: ���̂̃��Y�� / ���c�^�I
���̉̏��@�̓�, �O�̑��ʂɂ��� : �����O���t��p���ĐX�i���
�@�@���x���J���g���@�Ƃ��r���� / �������� |
III: ���A�W�A: Sori �̐��E : �؍��ɂ����鉹�̕����̍\�� / �N��N�j
���B�����y�T�_ / ���R����
����A�W�A: �k���^�C�E���I���̉��y / ���c���q
�^�C�ÓT�|�\�̓`���̌��� : �o���R�N�̕���|�p���w�Z���Ƃ��� / �N��♎q
�^�C���ÓT�̋Ȃɂ�����̎��̐����Ɖ̂̐����Ƃ̊W / �퐣�z�q
�o�����e���K�i�����ɂ�����Љ�\���Ɖ��y���� / �R�{�G�q
�����m: �t�B�W�[�̖������y / �O�J�z�q
1860�N��̃x���E���y���_�Ԍ��� : �ٕ����l�E�y���Ƃɂ��L�q��
�@�@�����Ƃɂ������j�I�l�@�̎���, ����т��̖��_ / �R���C
�C���h�E�`�x�b�g: �o���^�E�i�[�e�B�����̃A���[���b�v�̔�r�l�@ / ��J�I���q
�`�x�b�g�������� : �j���}�h�ɂ�����c�F�E�`���̉��y�I�\�� / ���B�q
��C���h�ÓT���y�ʼn��t����郉�[�K�̌���ɂ��� / �I��T�q
���A�W�A: �V���A������: ���`���̉��g�D / ���q�G�q
�g���R���w�̃��Y��: Uzun Hava (������) �l���ɂ��� / ���Ă͂��
�`���j�W�A�`�����y�Ɋւ����l�@ : ���@�̌n�̓��� / ����M�j
���V�A�E���[���b�p: ���y�̋q�̉��Ǝ��R�x�z : ��r���w�I�ɂ݂�
�@�@�����m�ߑ㉹�y�̓��ꐫ�ɂ��� / ��������q
�O���W�A�̑����I�Ȗ��w�ɂ��� / �X�c��
�E |
�V���A����q�����u���}�g�����Ɨ������� : ��̓��X�̐����s���ɉf�������{�����̌Ñw�n�}�v���uPHP�������v���犧�s����B (21���I�}���� ; 77)�@pid/12174146
|
�܂�����
�T�i�}�n�Q�̓�
�P�i�}�n�Q�Ƃ͉���
�Q���}�g�̐����E�����̐���
�R�J�~�Ɛl�Ԃ̌����@
�S�Ȃŗ��K�_�͏o������̂�
�U�����j����삷��M��
�P���Ɖ��ςƌ��z�V�� |
�Q���}�g�̑D��E�����̃E�i���K�~
�R�_�c�i�܂��j�M�Ƌ��]
�S�j�����ڂ������D�ʂ�
�V�ǂ̐_�͂ǂ����痈����
�P�ǂ̐_�ƉA�z��
�Q�����̑��Ƒ��l�̑��̐��E��
�R�C�I�R�[�ƎR�̐_
�S���}�g�������ے����鋛
|
�W���}�g�̖��Ɨ����̖�
�P�����Ȃ�_�̗e��
�Q�J�}�g�����Ɩ��̎��
�R��̓��X�̊ی���
�S������T��l�Ԃ̗��j�Ɛ���
���Ƃ���
�E
�E |
�W���A �w���Y�x�ҏW�ψ���ҁu���Y (404)�v���u���{���Y����v���犧�s�����B�@pid/7932180
|
���ꓩ�Y�̊T�� / �O�Ԑ��K/p2�`12
����ĕ�/P13~12
�O���t ����̓���(�Ԑ��A���������)/p25�`
�Òn�}�ӏ�(1)���B��Òn���V�} / �R���a��/p16�`19
��M2 / ����/p20~24
���閯�Y�^���҂̗������E�s����(2)
�@�@���Z�\�N�̉�ڂƓW�] / �O���g�V��/p41�`47 |
�� ���q���y�����N��23(��) �Q�l�����E
�@�@�������A�����A�����I���� / �����j�q/p48�`53
�S�����������_��A�ύX�̂��m�点/p14�`14
�u�����̖��Y�v�W�ɍ��ی𗬊���A���{������艇��/p14�`14
�Ċ��w�Z(���{)�̌�ē�/p15~15
�e�n���Y�وē�/p54~55
�ҏS��L/P64~64 |
�W���A���w�ٕ��u�n���̐��E (59)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@pid/1737934]
|
���{�̐X�т��l���� / �l���j�p/6
�X�̕����s�V���|�W�E���t / �~���� ; �͍���Y ; �k������ ; ��c�[�� ; �l���j�p/32
����̐_�Ƒ� / ������G/58
�_�X�̂ӂ邳�Ɓs�V���|�W�E���t / ��R�t�� ; �~���� ; ��c�[�� ; ���Ð^�X�� ; ������G ; �����v�a/82
���\�_(10)�h�X�g�G�t�X�L�[�̐��E(9)�w�����N�x�ɂ���(��) / ��c�[��/106
�T������q�g��(��U��)(9)�P�Y�Q�̎Љ�\���Ǝq�E�� / �͍���Y/124
�Βk ���{�w�̕��@�\�\�A�C�k�Ɖ���̎��_���� / J��N���C�i�[ ; �~����/160 |
�X���A����̏K��������Ғ��u�咆�q������̎���� : �����n�̗��j�Ɠ`���v���u��������Ёv���犧�s�����B
�@�@�@150p �@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001560000
|
���S�҂̃K�C�h�u�b�N�Ƃ���
������̎�Ȕq�� |
���A�m���̎�Ȕq��
�_�b�E���`����q�� |
�������ЂƏ\������
�q���Ɩ咆 |
|
�X���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (28)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4419235�@
|
�W�����o�y�����h�D�A�������� / ���c�_�O/p1�`21
���\���̃��}�m�C����--���̓`���I�͔|�@�Ɨ��p�@/���k�V�n/p22�`43
�u����S���l������n�C���L�v(�j���Љ�) / �Έ䐳�q/p44�`75
�����W�ɂ����问���̔n / ���c��/p76�`93 |
�@����w���ꕶ���������̊��s���ɂ���/�������j/p94�`97
�u��S�W�v��l�G���Ғ� / ��ɏ�ꗲ/p98�`101
�쓇�W�����ژ^ / �����֔V/p102�`102
���/p103~103 |
�P�O���A�g�Ɗԉi�g���u���w 54(10) p.p86�`97�v�� �u�����낳�����v�̜ߗ�\��--�T�V�u�E���c�L�𒆐S�Ƃ����\���I�l�@�v�\����B
�P�P���A�|�\�w��ҁu�|�\ 28(11)(333)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B
|
��������V���}�j�Y���ƃq���}�j�Y��� / �c���`�A/p7�`7
�c���_-��- / �V��P��/p8~14
���ꉹ�y�̒��ɔR�Ă�����������--
�@�@����ȉƋ����v�q����̐��U / ���c���q/p15�`17
�܌��M�v�̐��E(119)-�����ݒZ�̉�(��)
�@�@�� / ��ؑ��� ;�F����o�j/p18~19
����y�̉��y �S3������{�|�\�Z�~�i- / �͒|�o�u�v/p20�`22
����⍲�v�n���W-���̍���l��� / ���Α��/p22�`23
�����\�����㋳�痧�@�o��� / ���ے�/p23�`24
�֎R�a�v������ꖼ�l�`� / ���їE/p24�`25
��:�����V���E�}�g�D�[��&�^���O�u�C���h�� |
�@�����{�̖��ԓ`���v/�^�珹�O/p26~26
�����N�\(10��1��~31��) / ���c�m/p27~38
���x�N�\(���a61�N6�������7��) / �@���q/p39�`44
�������݂����ꌀ���ԣ / ��،�/p45�`46
���x���������̇��n�쎎���� / �m�����Õv/p46�`46
�m����q�������o���G�c����ꣁ`
�@�@���n��30�N�L�O����� / �����/p47�`47
�f��������f��̗����� / ���Njv�l�Y/p48�`48
�\�����������b����� / ���ѐ�/p49�`49
���a�Z�\��N�x�����M�͎�͎ҥ�������J��/p50�`51
������/p52~56�@ �]��/p56~57�@�V���ē�/p58~58 |
|
| 1987 |
62 |
�E |
�P���A����������u�Y�C���̐l�ފw�v���u�O�����v���犧�s����B�@
�@�@p364, 12p �@�����F��㊌����}���فF1002342580
|
���_
��P�́@�����j(�ƑD,����)
��Q�́@��˒��̊T��
��R�́@��˒����˕����̎Љ�\��
��S�́@�����w�l�̌o�ϐ����@�Ƃ��Ƀ��^�N�T�[�i�����j�ɂ��� |
��T�́@���������̐����ߒ��@���̂P
��U�́@���������̐����ߒ��@���̂Q
��V�́@�q�C���S���̐M��
��W�́@�C��Y�����̗��n�蒅�ߒ�
���_ |
��_�@���ɏオ�铌��A�W�A�̕Y�C��
��� ��{���v ���X�؍G�� �{�c�o
���Ƃ��� ��� ���q
���ҁE���� �ژ^
���� |
�@�@�����������1986�N 1�� 4���A 57�Ɖ]���Ⴓ�ł��S���Ȃ�ɂȂ�܂����B
�P���A�{��\�P�ҁu�{�闬 �{��\�P�Ɖ��� : ���t�ɗx��u�g�x�ƎG�x�̐S�v ��2��i�������q�j�v���u�{��\�P�v���犧�s�����B
�@�@�@�@�Ƃ��F1987�N1��16��(��)�E1987�N1��21(��) �Ƃ���F�^�ߌ����Љ���Z���^�[�E�����V��z�[��
�@�@�@�@�㉇�F�����V��ЁE����e���r�ENHK��������ǁE����|�\�A���E�`���g�x�ۑ����@�@�P�� �@�����F��㊌����}���فF1004338263
�Q���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 13 �v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�@�iIRDB�j
|
�ܒ���l�Ɨ����̌F��M�^�����@�N�@p.1-23
�����~���^���Ɠ��{�E�����^���� ��s p.25-106
�펞����̖h���ɂ��āF��������O��R��
�@�@���h����𒆐S�Ɂ^�ʖ� �^�N p.107-142
�g�x��u�����q�v�����̊�b
�O�����w��e�ƃ��[�J���E�J���[ : ���ꖾ����
�@�@�����d�ɂ��������^���� ���� p.195-239 |
���d�R���w�̊y���^����� p.241-289
�����ÓT���y�ɂ������剺��\���F���̒���
�@�@���������l���邽�߂�(����2)�^���� �w�v�@p.291-332
�����Õ����ɂ�����C�މ��Ή����̕\�L�ɂ���
�����E�����ɂ�����n�拤���̂Ƃ��Ắu��v�̌`���Ƌ@�\
�w��Y�k�x��ǂށF�쓇�̗��j�Ɩ������l���邽�߂Ɂ^�R�� �ӈ� p.433-535
���B�̌ÐՂ��猩���Ñ�̒����W�^��U��,�^�h��, �[��[��] p.537-563 |
�R���A���ꌧ�������ٕ��u���ꌧ�������ًI�v (13) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@�@pid/3467956
|
�ߔe�s���\���鑭�́k��̖сl�̐A�� / ���z���� ;�V��a��/p1~16
�O���ӏ܉�ɂ��� / �X�۞Ď��Y/p17�`30
�����Љ� ���������ق̐D��(II)�䏰 / ���u�Îq ;�^�ߗ��q/p31~48 |
�����M�w���ߐ}�x�E�w�Ԓ��}�x / �Ôg�Ñ�/p49�`52
�䉼������L / ��]�F�q�v/p1�`14
�E |
�R���A�~���w�@��w�n�敶���������ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v = Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (2)�v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@pid/4424698�@
�@�@�@�w�p�@�փ��|�W�g���f�[�^�x�[�X�iIRDB�j404 Not Found�@�@�d�v�@�@�i���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă͍���@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�Q�T�@�ۍ�j
|
���R���߂���h���̖���--�C�ƎR�Ƌ�Ԃ� �����a61�N�x����/p1�`33
�쓇�l�ÁE�����T�K�L(��) / ��������/p34�`50
�����ւ̓� / �ѓS��/p51~55
���ߍx�̎Ў��j���ɂ݂�_���K���Ƒ��̕����̎��� / ���{��/p56�`62
�J���҂̒������A�����Ėk��B--�J���҉����������v�� / ���i�N/p63�`65
���|�\����(��) / �������s/p66�`77
�I�z�[�c�N�C���ݎ��V / �蕔�ǕF/p78�`90
�Ί_���{�ǂ̃A�J�}�^�E�N���}�^ / ����/p91�`100
�u���̐V�������v�K��L / �����r�q/p101�`105 |
�n��̃X�|�[�c���D�҂ɂ݂�X�|�[�c��/���x�r�Y/p1�`11
���ւɂ�����ؔ����̕��� / �L�c��/p12�`23
���֎s�s�s�v��Ɋւ��鎖��]���I�l�@/
�@�@���F�얫 ;�ΊۋI��/p24~29
�O�ؕʗW�Љ�̑h�h�M�� / ���m�� ;���R��/p30~51
���d�R���c���L�ˏo�y�Ί� / �؉����q/p52�`66
���H�ׂ��̕��y�L���܂ނ� / �R�c�����Y/p67�`68
���V�ѕ��y�L�����܂��炯�� / ���{���Y/p69�`71
�E |
�R���A�u���������ّ��������� 4 (�Ɍv��(����������))�v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@pid/9639747
|
�������� ���@��
�Ɍv���̒n�`�ƒn�� ����N/1
�Ɍv�����j ��]�F�q�v/9 |
�Ɍv���̈�� �m�O�E/21
�Ɍv���̏Z���̎��� ��]�F��/29
�Ɍv���̓����̕��� ���R����/35 |
�Ɍv���̐��D �^�ߗ��q/45
�E
�E |
�R���A����s����ψ�����ە��u�A���̋����Y�v���u����s����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@(����s������������ ; ��10�W�j�@�@54p�@�@�����F��㊌����}���فF1002096269
|
�����̂��Ƃ� ��� ���i�^��
�������ɂ悹�� ���n ����^��
�T�� |
�A���̋����Y
�����Y�̕��z
�ۑ���̉�E�g�D�y�щ��v |
���Ƃ���
�E
�E |
�R���A���ǎs�j�҂���ψ���ҁu���ǎs�j ��7�� (������ 5 �����E�̗w)�v���u���ǎs����ψ���v���犧�s�����B�@pid/9776117
|
�ʐ^
�����̂��Ƃ� ���ǎs�� ���n�Ĉ�
�}��
������
���� �T�� �e���@��
��A�{�Â̈ʒu�y�ю���/2
��A�{�Â̋C��/4
�O�A�{�Â̒n���Ɠy��/9
�l�A�����̊T��/12
���� �Љ�� ���n�N�v
���� �����̍\���E�@�\/26
��A�떓/26
��A��Y/33
�O�A���R/44
�l�A�{��/52
�܁A�v�L/54
���� ���W�c/62
��A�w�l��/62
��A�V�l��/69
�O�A�N��i�r�ԁj/76
��O�� ���ݕ}��/77
��A���ю��n�ǂɂ��āi��Y�j/77
��A�Ƃ̐V�z���߂��鑡�^���s�A
�@�@�����̑��i�����j/83
��l�� �g���E�ٗp�W/90
��A�q��/90
��A���/93
��ܐ� ����/93
��O�� ���� ���n�R���g
���� �_��/98
��A�k�n�̎�ނƗ��p�@/98
��A�_�앨/99
�O�A�엿/113
�l�A�_��/115
�܁A�_�k�V��E�֊�/117
�Z�A��_���̔_�Ɓi��O�j/118
���� ����/120
��A�D/120
��A���@�̎�ނƕϑJ/124
�O�A���Y���H/143
��O�� �{�Y/148
��l�� ����/156
��ܐ� ��z���Y/166
��Z�� ���E/173
��l�� �ߐH�Z ���ǐV��
���� ��/184 |
��A����߁i�d���߁j/184
��A����/190
�O�A�m�ԕz/200
�l�A�Q��E���Ԃ���́i���g��j/206
�܁A���^/210
���� �H/212
��A��H�ƕ��H/212
��A�s������/231
�O�A�����E���H�H�i/239
�l�A�R���E������/244
��O�� �Z/246
��A���~/246
��A�Ɖ�/251
�O�A���z�V��/263
�l�A����/266
��� �M�� ���{�b��
���� �q��/272
��A�r��/272
��A�떓/274
�O�A���K/279
�l�A�v��/281
���� �_��g�D/285
��A�r��/285
��A�떓/288
�O�A���K/290
�l�A�v��/292
��O�� ��ȍ��J/294
��A�r�Ԃ̃��[�N�C/294
��A�떓�̑c�_��/302
�O�A���K�̑c�_��/313
�l�A���K�̃p�[���g�D�E�v�i�n/318
�܁A���K�̃V�c��/320
��l�� ��ʐM��/321
��A���̐_�M��/321
��A�ƁE���~�̐M��/328
�O�A�}�E�_�M��/332
�l�A�ƒ�̈˗��F��/336
��ܐ� �V���[�}��/338
��Z�� �l���V�� �{���蓿
���� �Y��/364
��A�K�P/364
��A�o�Y/365
�O�A����/366
�l�A����/367
���� ����/372
��O�� ����/377 |
��A���̗\���k(1)�����ɂ��\��
�@�@��(2)���ɂ��\��
�@�@��(3)���ۂɂ��\���l/377
��A�ՏI/377
�O�A�ʖ�/379
�l�A�o��/380
�܁A���{�E�@��/383
�Z�A�����Ɋւ���֊��E���M/384
�掵�� �N���s�� ���Ԍ��K
���� ���Ǔ����̔N���s��/388
���� ���ǐ����̔N���s��/390
��O�� ���ǖk���̔N���s��/394
��l�� ����̔N���s��/396
��ܐ� �v���̔N���s��/399
��Z�� �����̔N���s��/405
�掵�� �{���̔N���s��/408
�攪�� �����̔N���s��/413
���� ��Y�̔N���s��/418
��\�� ���K�̔N���s��/423
��\��� �떓�̔N���s��/428
��\��� �r�Ԃ̔N���s��/431
�攪�� ����`�� ���Ԍ��K
���� �`���Ɛ̘b/438
���� ���Ƃ킴/446
��O�� �Ȃ�/460
��l�� ���퐶���p��/461
���� �����m��
���� ���� �{���蓿/466
���� �m��E�܂��Ȃ� ���{�b��/470
��O�� ���� �{���蓿/476
��l�� �֊��E���M ���{�b��/482
�̗w��
�� �t�T
�� �^�[�r
�O �s���[�V
�l �j�[��
�� ���A�[�O
�Z �N�C�`���[
�}�[�C���j
�� �g�[�K�j�[
�� ����
�V�щ�
�q���
�� ���̑��̃A�[�O
�E
�E |
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (7)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@�@pid/7955136
|
���咆���Ɓ��`���`���[�f�[��--�嗢���ڎ�^�ɂ�����
�@�@���咆���̈�f�� / �����r��/p1�`15
�쓇�����Z�p�����̎���--�b��̏C�Ɖߒ����߂����āv
�@�@��/�����N��/p16�`24
�v�����̔N���s���Ɛ_���̕��� / �×z���q/p25�`34
�v���������� / ��]�F��/p35~43 |
��p�̐l�`������ / �X�۞Ď��Y/p44�`46
1986�N�x ���_���\��\�v�|/p47�`53
�O�����̑傠�ނ����̐_���ƏA�C�V�� / �n���얾/p1�`8
�v�ē��E��u��ԐɊւ��閯������-
�@�@���u�v�ċ�u��Ԑ؋K�͒��v�𒆐S�� / �ʏ鏇�F/p9�`21
���j���Љ �u��������j�փX������ �S�v���� / �F�]�삿���q/p22�`31 |
�S���A�֓����ҁu���{�l�Êw�_�W 9 (�k�������Ɠ쓇����)�v���u�g��O���فv���犧�s�����B
�@pid/12205547�@
|
�w�j�I�W�] �k�C���Ί펞��T�v �͖�L����
�쓇�Ñ�̑��V �ɔg���Q��
�k�������ւ̗��� �k�C����j�����Ƒ嗤���� ��ꗘ�v��
�k�C���̗��j����ɂ�����l�Êw ��㔣��
�ꕶ�����ƎC������ �k�C���̑��ꕶ���� �X�c�m����
�C������-�k�C���̐�A�C�k���� ���{����
�C�������ƃI�z�[�c�N�����̊W�ɂ��� ��䐰�j��
�I�z�[�c�N�����̐��ƋZ�p ���{�L�O��
�A�C�k�̕��� �A�C�k�����̐���-�����A���j�A�l�Ï��w�̍����_ �n�Ӑm��
�A�C�k�l�Êw �F�c��m��
�A�C�k�����ɂ�����Ñ���{�I�v�f�`�d�̎����Ɋւ��遨 |
�@�@���ꎄ��-�C���������̈Ӌ`�Ɋ֘A���� �Ε���O�j��
�쓇�����ւ̏Ǝ� �쓇�l�Êw�̏���� ����������.
�퐶����ɂ������C�Y�L�g�p�̘r�� �O���i��
�O�X�N�_ ����̃O�X�N�Ɛ��� ������G��.
�ăO�V�N�l �F��p��Y��
�����̏� ���R������
���l�̖�� �F�P�E���l�l ���a����
�Ñ��ӕ����̍l�Êw�I�l�@ ���v�d����
���l�ːΑ����̐��������ɂ��� �㑺�r�Y��
���. ��v�Q�l����:p441�`451
�E |
�U���A��Ð��v���u�����D�ʂƒj�n���� : ����̖����Љ�\�� �V�}���猩�����{�����_
�v���u�M���Ёv���犧�s����B
�@�@�@ (�V�o�V������ ; 4)�@�@�@pid/9776037
|
�܂�����/1
I ����Љ�̖����I����
1 ����Љ�Ɓu�₳�����v�̍\��/13
2 ���������Љ�̍\���ƕϗe/39
3 �������߂�����/56
4 ����̑����ɂ������p�E�@���I���E
�@�@���\����{���암�̎���𒆐S��/68
5 ���ԛގ҂ƎЉ�\���\���d�R�̎��Ⴉ��/93
6 ���閯���Љ�/108
7 ����̊�������/122
II ���ꌤ���̋O��
1 �Ǎ��Ȃ�G�g�����W�F�\�����O��_/139
2 �����̉��ꖯ���w�ƍ���^���p/157
|
3 �O���l�ɂ�鉫�ꑺ�������\�Љ�l�ފw�̎��_����/167
III �Ǐ��m�[�g�\���ꖯ���Љ�����̉��
�w�_�Ƒ��\����̑����x�q������G�E���r/197
�w����̌Ñ㕔���}�L���̌����x�q����~�E���r/201
�w����̎Љ�g�D�Ɛ��E�ρx�q�n粋ӗY�E���r/207
�w�咆���y�L�x�q���a�c�^���E���r/217
�w���V��̌����\�������c�_�̍Č����x�q�ɓ������E���r/226
�w�n�����꒘��W�x/229
�w�|�x�����\���b�E�����сx�q�㐨�����E���r/232
�w�����ʂ̐��E�x�q�J�쌒��E���r/235
�w�퐢�_�\���{�l�̍��̂䂭���x�q�J�쌒��E���r/238
�w����̏@���ƎЉ�\���x�qW�EP�E���[�u���E���r/241
���Ƃ����ɂ�����/245 |
�U���A���g�Î}�Ɖ��� [��] ; �ʏ�V��Y�ҏW�u�ʏ闬�Đ߉� ���g�Î}�Ɖ���
: �Z���Z�����Z���@�i�����p���t���b�g�j�v���u���g�Î}�Ɖ���v���犧�s�����B�@�@�@�@68p�@�@�����F��㊌����}���فF1004673362
�@�@�@�����F���a62�N6��6�� �ꏊ�F�����V��z�[�� �@�@�@
�V���A�ʏ��}�q�ҁu���ނ����� �ʏ闬�Đ߉� �ʏ��}�q : �n�앑�x�W�E�̌����l��v���u�ʏ��}�q��������v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�@60p�@�@�����F��㊌����}���فF1004250468 �@�@�P�O�O�O�~
�@�@�@�����F���a62�N7��12�� �ꏊ�F�Y�Y�s����ّ�z�[��
�V���A���юs�����u�M�Z���� (1208) p71�`81�M�Z�����v�Ɂu���� �������搶�̐��U�v�\����B�@ pid/6070773
�V���A����|�\�j������ҁu����|�\�j���� ��7���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1006983934 �@�������e�Ȃ��̂��ߊm�F�v�@�Q�O�Q�R�E�V�E�Q�T�@�ۍ�
�W���A�u�{�̑� 10(7)(61) �v���u���w�فv���犧�s�����B pid/3475135�@�@�d�v
|
���W=�����Ȃ� //p2~39
�Βk �����Ȃ�̍���E�����E���� / ��闧�T ;���Ǒq�g/p2~13
�G�߂̂��� (49) ����̊��� / �����؍K�j/p14�`15
�A�ڐ��z �V�ɑ���莆 (34) �����L�̋� / �X��/p16�`17
���A���q / ���ؗ��O/p18~19
����̐� / �V�Ԕ�C�u/p20~21
�u������v�ɂ݂鉫��̕��y�Ƃ����� / ��Î�/p22�`25
���j�X�|�b�g ����ɓV�c������N / ��]�u�T�v/p26�`29
�����\�W�c�����ƏZ���s�E�\ �w���a�ւ̏،��x��� //p30�`31
�t�H�g�E�h�L�������g ����{�y���A15���N / ����N�v/p32�`39
�Ȋw�Ƃ��̂� (17) ���͂ǂ��� / �����j�q/p40�`43
�`���R�����̂������Ȃ��F����(18)
�@�@�������e�N���X�g����/���荶�i�q/p44�`47
���b�Ύ��L (7) �s��� / �ӌ������/p48�`51
��[�Ȋw�V���[�Y (28) �����t��ɂƂ� / ����F�Y/p52�`55
|
�t�H�g�V���[�Y ���a�j�n�} (7) �{�����������s�� / ���J��h/p56�`59
�����Ȃ�ƒ��悭�Ȃ�{15 / �M�؏ۋg/p60�`63
���҂ƌ�� �V�����u�n�`������v / �������j ;�V�����l/p64~67
���̕ҏW�����{ �w�܂��Ɣ閧�@�x�w�₾����!�x�� / ��/p68~69
���ʘA�� ���l�������� (��\��) ���� / ���˓��⒮/p70�`83
����ɂ��͔o�� (28) ���Q�o / ���c�ǎq/p84�`85
�؍��E�V�����ČÂ��� (7) ��n����n���L(�l) / ���w��/p86�`89
�����͂āE�ӂ邳�ƁE�߂܂�ׂ� (7) �k ����������/��㖾�q/p90�`93
������̃A���O�� (18) / �얞�h/p94�`95
�ǎ҂̑� / �i���j/p96~97
�ǎ҃t�H�[���� / ��/p100~102
�\����� //�\2
�ҏW��L�E���t / ��/p104~104
���w�ُo�ňē� //p105~
�E |
�W���A����O���u�ߐ�����̖����j�v���u�O�����v���犧�s����B�@�@ (���{�����w�����p��)�@�@pid/9776065
|
�� �đq��Y/1
����/3
��ꕔ �}�L�E�q�L�E�E���N�̖����j
���_ ��̎Љ��ԁE�L��_�I���@�Ƃ��̎�@/15
���� �{�y�ɂ͂ǂ̂悤�ȕ����̌Ă����邩/23
���� �̌Č����̏��E��b�̕��ޑ�j/23
�� ������b����F�Ƃ��鐼���{/26
�� �����{�̌����W�}�̌�/28
�O �}�L�̓������߂�����/30
�l ���E���ɘi��C�g�R/38
�� �I���R�̖{���ƕ��Ր�/41
���� �������ʂ̐e���W�c�̌Ăƕ��z�\��/54
�͂��߂�/54
�� �����Ə̌Č�b�̕��ޑ�j/55
�� �E���N�n�̒n�摊/57
�O �E�F�[�J�n�̗���/60
�l �E�g�D�W���n�ƃ`���[�f�[�n/61
�� �n���[�W�n�ƌꌹ���̖���/65
�Z �n���n�̓�/70
�� �S���I�ȃq�L�n�̕��z/73
�� �咆�n�ƈ��n�̊W/80
��O�� ���z�\������݂������j�I�ҔN/81
�� �{�y�Ɨ������ʂ̕��z�\������/81
�� �������ʐe���̌Ă̕��z�\���ƕҔN/84
�]�_/86
���_�i��j�j�������̃}�M�ƃI���O�ɂ���/89
���_�i��j���T�C�̃I�h �X���Ìy�n���e���̌Ă̈�f��/97
��� �ߐ�����Љ�̖����j
���� ����̖咆�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�
�� ���ꌤ���̋N�_�Ƃ��Ă̖咆/107
�� �咆�����̏�/109
�O �咆�ɂ݂鐧�x������я��ϔO�i���̈�j/113
�l �咆�ɂ݂鐧�x������я��ϔO�i���̓�j/120
���� �j������݂��咆�̗��j/130
�� ���@�Ɖƕ�����݂��m���咆�̌��p��/130
�� ���Ԏj������݂��ʗp��̕ϑJ/147 |
���ʂ̋A��/153
��O�� �k�����c�_�����Ԃ�q�L�̖����j/156
�� �w���Ђ�����ڒ��x�̌���/156
�� �Y��̕�o�p��/173
�O �u�Z��d���v�Ɓu���q�����v�w�܂����L�x�̕���/188
�l �_���̈ʔv/196
���_�i�O�j ���] �n���^�����w�����Z�킽���x��ǂ�/202
���_�i�l�j����ɂ������̕�^�Ƃ��̔N��/207
��O�� �ߐ����ꕶ���̖����j
���� �w�������R���L�x����݂��ߐ�����̖���/223
�� �w�e�����J�x�̐}���I�\���Ƃ��̕���/224
�� ��q�ˏ�ŏN�W���ꂽ�w�e�����J�x/225
�O ���K�E�����̊e�����J�ɂ݂��̋�/228
�l �k�������ɂ�������J�̌n�̒n��I���F/236
�� ���ꏔ�����Ԃɂ݂���J�̌n�̒n�摊/241
�Z �擇�n��̍��J�̌n/242
���ʂ̋A��/244
���� �ߐ������ɂ����閯�����J�̌n�̐V�W�J/247
�� �m�K�w�ɂ�����ƍ��J�̋K�͂ƂȂ����w�l�{���Ɨ�x/247
�� �ߐ��m���ƍ��J�̊����E�w�Ó����K�͒��x/259
���ʂ̋A��/267
��O�� �ߐ������̖k�����c�_���ɂ݂�ƍ��J�̑ԗe/268
�͂��߂�/268
�� �j�������̌o��/269
�� ���l�ȉƓ����J�̑Ώ�/271
�O ��������ƍ��J�̌n�̕���/277
��l�� �w�ƕ��ՓT�x����鐴���Վ�e��?��/290
�͂��߂�/290
�� �w�ƕ��ՓT�x�̓��e/293
�� �����Ցn�n�̓��@�Ƃ��̌���/294
�E�v/297
���_�i�܁j�w��Ɖƌ��x���邢�́w�l�{���Ɨ�x�̂���/298
���_�i�Z�j�w�l�{���Ɨ�x���̌�/311
�� �O�Ԏ�P/317
����N��/322
�E |
�W���A�Y�R���ꂪ�u�w�p�u���[�T�W. F, �s�s�v��, ���z�o�ρE�Z����, ���z���j�E�ӏ�
�i1987�j p.899-900�v�Ɂu�֏��Ԃ̍��J�p�����ɂ��� : �u������N��V����v�̌��z�I�f�`-����2-�v�\����B�@�@
�X���A �n�v�n�������u���H���� (476)�@p34�`35�@���{���H���Ƌ���v�Ɂu����̐��n����v�\����B�@�@pid/3309822
�P�O���A�_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (5)�v���u�_�ˏ��q��w�j�w��v���犧�s�����B�@pid/4424471
|
�Ǔ��� / �s�g�Ə� ;�H�R���o�Y/p1~5�@�@�@�^�ؑ����v�搶������j�w�W����ژ^/p6�`13
�_�� ����̑��z�M�Ɖ���--�j���C�J�i�C�Ɩ��O�̑��z�M�𒆐S�� / �m���芰/p14�`35�@�iIRDB�j�i�@�փ��|�W�g
�_�� ���O�ă����w���ɖk�֓��D�[���x�̃c�z�ƃX���n�` / �ԕ��юq/p36�`55
�_�� �����������[���b�p�ɂ�����ؖȐD���H���y�ɂ���--�k�C�^���A�ؖȐD���H�Ƃ̔��W�̊֘A���� / �������K/p56�`82
�_�� �u�Б��v�ꑰ���{�}�v�ɂ��� / �k����/p83�`105
�����m�[�g �풆�E�����v���̖f�Տ��� / �ҐߗY/p106�`127
���] �M���萳�F���w���ƕ����ϗe�ߒ��̌����x / �{��m��Y/p128�`134
�j�w�Ȃ����/p135~138�@�@�^�j�w�����/p139~139 |
�P�O���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 24(1)(69)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437783
|
�c�����O�Y�̐��U / �R���d��/p1�`16
����̐�����\�j���C�J�i�C�E�����̕���H / �ؑ�����/p17�`41
������čl--���Ɯ߈� / ���c����/p42�`52
����̑c�_�A�}�~�N�_�̌n�� / �O�Ԏ�P/p53�`72
�k�����Љ�l �n���C��w��ߕ��ɑ�
�@�@�� ���w�{�Ó��̉́x��b�E�����W / �V���K��/p73�`115 |
�w���ꕶ���x���̐V�����o�� / �����H�^�s/p119�`119
���] / ������Y/p116~118
�V���Љ� / �g�Ɗԉi�g/p118~118
���s�j���[�X/p16~16
�E
�E |
�@�@�@�@�@���w�{�Ó��̉́x�ɂ��Ă�1925�N�̍��ɋL���B�@�@�Q�O�Q�R�E�X�E�Q�Q�@�ۍ�
�P�P���A�؍������@�ďC�u�����؍����� 9(11)(97)�v���u��掺�A�[�g�v�����j���O�v���犧�s�����B�@pid/7952698
|
���{�̒��̒��N����(4) / ���B��/p2�`8
�̑�Ȃ铌�m�̎v�z�ƁE���ތk(�l) / ���T�q/p9�`13
���W �����̖���(1) / �ɒO��/p14~16,21~22
���J���[�O���r�A�� �����̖���/p17�`20
�S�ς̗ɐ��o�c�ɂ��� / ���l��/p23�`27
�؍���������̌����E�� / �p�r��/p28�`29
���l�ʐM ��؍����̌�����(11)���{��̖��� / �H�J�L/p30�`31
����̛��� / �A���c/p32~36
�؍��̂��Ƃ킴�Ɍ���A���� ������ / �ᏼ��/p38�`41
�؍��̏d�v���`������(10)�؏��R�܂� / �ҏW��/p42�`43 |
���J���N�������l(7)�G�g�̒��N�o�� / �J�L��/p37�`37
�؍��̖��b(81)��͐��̊�� / �c���a/p44�`45
�ǎ҂̂Ђ�� ���O���t�@�E�g���T��/p50�`50
�؍������E�̓���/p51~52
�؍������@�����/p53~53
�]���̖{ ���䓿���Y����W(7)���A�W�A�̖����@��/p46�`46
�]���̖{ �؍��̌Î��E�Ó� / ���݊�/p47�`47
�}�X�R�~�_�� ���E���쌠����̔��� / ��������/p48�`48
�}�X�R�~�_�� �L�`�̔ӏ��A�����̋G�� / �؍�����/p49�`49
�E |
�P�P���A�J�쌒�� �ҁu���{�̐_�X:�_�ЂƐ��n ��13���@�쐼����:�g�J���E���������E���ꏔ���E�{�×E���d�R�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@pid/12267665
|
�g�J����
�g�J���̐��n�Ɛ_�X�@����q���@9
1�@�T�ρ@9
2�@���R�̐��n�@14
3�@�l�ׂ̐��n�@19
4�@�_�ЂƏ��K�@31
5�@�V�����W���@60
6�@���ƕ����@62
7�@���с@67
��������
���������ɂ�����_�X�̎����@�R���ӈ�@75
���������̐��n�Ɠ`���@�R���ӈ�@77
���������̐_�R�@����d�N�@86
1�@�������}�@86
2�@�I�K�~���}�ƃI�f�[�@92
3�@�I�{�c���}�@97
�C�r�ƃA���g�@����d�N�@104
���������̃m���ƍ��J�g�D�@�R���ӈ�@108
���������̐_�ЂƓ`���@�R���ӈ�@111
1�@��E���Ɖ����哇�̕��Ɠ`���Ɛ_�Ё@111
2�@�����ȍ~�ɂ�����_�Ђ̌����@118
3�@���i�Ǖ����̐��V��`���Ɛ_�Ё@119
4�@�^�_���̈i�j�b�`�F�`���Ɛ_�Ё@125
���ꏔ��
��\�������]����_�X�@�������X�@133
1�@���n�Ƃ��Ă̎�@133
2�@���{�̐_���@144
3�@�����Ɛ_���@151
4�@���ʂƏ@���V��@156
5�@�����V��̖{�`�@160
������N��a�\�����_�����x�z����_���@�������X�@168
1�@������N��a�̐_��@168
2�@������N�̌n���@176
3�@������N�̌��Ђ̐����@182
4�@�����̕�����N�̋V��@187
5�@������N�̌�V����@197
�O�����̑傠�ނ����\
�@�@���̏鉺���̌`���ƍ��J�g�D�@�������X�@211
1�@�O�����̎O�a���@211
2�@�O�����̑傠�ނ����̍��J�@215
3�@�̑傠�ނ����ƍ��_�@220
4�@�O�����̌�ԁ@223
5�@�O�����̍��J�g�D�@230
�^�ӁE�ߔe�l���E�v�đ��E���̑傠�ށ\
�ߔe�̍`���̌`���ƍ��J�g�D�@�������X�@237
1�@�^�ӂ̑傠�ށ@237
2�@���̑傠�ށ@243
3�@�v�đ��̑傠�ށ@245
4�@�ߔe�̑傠�ށ@247
5�@�ߔe�l���̑��̑g�D�Ɣq���@250
6�@���̑傠�ށ@253
�����\�������x���鐹�n�̏��q�@�������X�@260
�_�q�݁\��a�R�\�^�ߌ��e��\�n�V��ԁ\���\
�@�@����Ă����\�֏��ԁ\�m�O��Ձ\�m�O���\
�@�@�����n���d�J�T�\�l���ԁ\�E�����~���g�D����\
�@�@���ʏ��Ձ\�ʏ�j���a��
�����\�O�X�N�̐��n�̌`���@�������X�@284
�M�n���ƕl��Ó��\�n���_�b�Ɩ��O�̐_���_�w�@�������X�@294 |
�ӌˌ�ԁ\��R�̃A�t���M�@�������X�@302
�����n���̌�ԁ\�ӌ˂̌䐅�\���v�^�Ƃ̌��Ё\
�@�@���A�t���M�\��R�M�̌Ñ�
���A�m���\�k���̉��҂̐��n���q�@�������X�@317
���A�m��\���A�m���ӂ����a�\���A�m�j���a���\�N�o����ԁ\
�@�@���v�g�D�L�̃C�b�s���\�S�i��
�ɐ������\���J�g�D�̂Ȃ��̈��V��@�������X�@334
���~���̐��ւƐ_�E�\�_��g�D�\��Ԃ̍��J�\���V��Ɣ���V��
�v�����̐_���\�^�}�K�G�[�ƃE�v�e�B�V�W�@��ÍN�Y�@376
�}�u�C�ƃV�W�\�O�̃V�W�\�E�v�e�B�V�W�ƃE�^�L�\�E�v�e�B�V�W�̌p��
�C�U�C�z�[�@��ÍN�Y�@393
��藧�\�C�U�C�z�\����ځ\����ځ\�O���ځ\�l����
�ɍ]���@��]�F�ρ@417
�c�NJԏ����@��]�F�ρ@421
�v�ē��@��]�F�ρ@425
�O�X�N�ƌ�ԁ@���Ð����Y�@432
�u������v�Ɍ��鏉���̃O�X�N�\
�@�������̃O�X�N�Ɋւ��鏔���\�h�����甭�������O�X�N�\�O�X�N�ƌ��
�_�Ђƕ_�\����{���𒆐S�Ƃ��ā@���~�ߎ��@449
1�@��a����̊����_�@450
1�@�g��{�\���{�\���������{�\�����{�\���g�{�\�V�v�{�\���V���{�\
�@�@�������{�\�Z�g�_�Ё\�����_�Ё\�V���{�\�ΐ_�E�Z�[�k�_�E�r�_�\
�@�@����ΐM�ƌ��т��������ЂȂǁ\�ߑ�ɑn�����ꂽ�_��
2�@�����嗤����̊����_�@468
2�@�V���_�\�V�ܕ_�\�����a�E�֒�_�\�E�q�_�\�y��N
3�@�����Ɖp�Y�@473
3�@���Ԍ�a�\����_�Ё\�����_�Ё\�n���̉p�Y���܂�_��
�{����
�{���@�{�i���@481
1�@�떓�̔q�����g�D�@481
2�@�떓�̃E���K�����J�@487
3�@���K�̉��ʐ_���J�p�[���g�D�v�i�J�@493
�r�ԓ��@�{�i���@500
��_���@���Ԍ��K�@503
�N���s���\�c�_�Ղ�
�ɗǕ����@���b�ǁ@511
���ԓ��@�A�����@519
�q���\�_���\�ՋV�Ɛ_�X
���NJԓ��@��Ð��v�@524
��ԁ\�_�Ё\���̑��̐���E�Տ�
���d�R����
�Ί_���@�Ί_���F�@539
�q���\�N�����J
�|�x���@�Ί_���F�@554
�q���\�N�����J
���l���@�Ί_���F�@564
�q���\�N�����J
���\���@�Ί_���F�@573
�q���\�N�����J
�V�铇�@�A�����@581
��n�\���n�\�ՋV�Ɛ_�X
�^�ߍ����@�A�����@589
�^�ߍ����̐_�X�\�q���\�_�X�ƋV��
�g�Ɗԓ��@�{�Ǎ��O�@599
���̖����I���E�\�`�����猩���W���`���\��Ԃƍ��J�̍\��
���M�ҁE�ҎҏЉ�@609
���n�E�_�������@1
�E
|
�P�P���A�X����k����u�����_���L : �S��v���u���m�}���o�Łv���犧�s�����B
�P�P���A�����F�ҁu�������ċ��̋O�� : -�m�Ԏ��ւ̃��}�������߂�-�v���u���y���],�������v���犧�s�����B
�@�@�@�@�@�ҏW�F���y���],�ԕ��a�Y ��]�F�q�v
�P�Q���A���a�c�^�~���u�A���n���E���ތ��� = The journal of phytogeography and taxonomy 35(2) p.83-84�@���{�A�����ފw��v�Ɂu����{���N�}�^�P�������̐V�G��ɂ��āv�\����B
���A���̔N�A�g�Ɗԉi�g�u�쓇���J�̗w�̊�b�I�����v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s����B�@
�@�@�@���L �����ȉȊw������⏕���������ʕ� |
| 1988 |
63 |
�E |
�Q���A�Ö�^���j�� ; ���a�c�^�~�ďC�u���u�w���̐A���}�� : -���ꏭ�N�@-�v��
�u�Ö��^ ���j�v���犧�s�����B154p
�Q���A�u�ߌ��쌀 41(2)(448) �v���u���쏑�[�v���犧�s�����B�@�@�@pid/7923405
|
���ꉉ��<���W>/p8~55
���E����̉���--����Ɩ{�y(��܂�) / ��،�/pp8~18
�������ƐV���Ƃ̂͂��܂�--���̐�㉉���̌�/��闧�T/pp19�`23
����̌ÓT�|�\--���̗��j�ƌ��� / ���P�Y/pp24~32
�����X(�����ɂނ�)�����날��L--
�@�@������V�o�C�V-�̉�z / �^��u�N��/pp33�`39
�����W�c�u�n���v��80�N�� / �K��ǏG/pp40~43
���W ���ꉉ�� �؉�����Ɓw����x / �]�����v/p44�`45
�u�l�ފفv�Ȍ� / ���˂�����/pp46~48
�F��d�g��������L ����� / ���F�Ƃ���/pp49~55
�������G�b�Z�C �u�g�X�L�i�A�v�ɂ��� / ��ꐳ/p6�`7
���Z�ɂ���-2-�ߋ��Ɋw�� / ���[�����X�E�I�����B�G ;�q����/pp65~71 |
���A�ڃG�b�Z�C �������d��b(5) �n���S�N���}�����̕����/�ޒJ��l/p60�`61
���A�ڃG�b�Z�C �G��(4) / ����G��/p82�`85
���G�b�Z�C �x���ւ̓Ƃ茾--�u���Ɓv���I���� / �����܂�q/p62�`64
���V�A�̃T-�J�X�E���l�b�T���X--�����t���U�����R�ƃ��V�A�E�A���@���M�����h-3��- / �哇���Y/pp72�`81
�͍삪���������...(�����M) / �֓����G/pp86~89
���킪���^ �u�g�X�L�i�A�v / �O�Y�`��/p90�`91
Une heure avec--�R��w / ���c�� ;�R��w/pp92~94
1���̂���/p56~59
�������] / �������ӕ� ;�{�ݑ�/pp96~113
���Y�� ���̃����^ / �Ӗ����c��/p114�`118,127�`157 |
�Q���A������q���u���x�ɂ�������ւ̎��_�v���u��B��w�o�ʼn�v���犧�s����B�@�@�Q�T�O�O�~
�@�@�@350p �}��[10]p �@�@�����F��㊌����}���فF1001512225
�@�@�@�@�w������w����w���I�p�x�y�сw�̈�w�����x�ɔ��\�����_�����e���܂Ƃ߂�����
�@�@�@�@�����F���� 1 �����ÓT���x��u���ԁv�̍\���Ɨx��̑S�̑� ���� 2 ���x�̊ӏ܌� ���� 3 ���x�ʐ^�ꗗ
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 1�v���u���ꌧ���|�p��w�����������v����n�������B
|
�ÓT�������x���̎��݁@���� �ݗ��Y�@ p.(1)-(57)
�����̂��Ƃ@�� �x�F�@ p.1
���d�R�̌�ԐM�K���o���@�g�Ɗ� �i�g�@1 p.3-25 |
���d�R�̌�ԐM�K���W�����ژ^�@�g�Ɗ� �i�g�@ p.27-80
�����|�\�����֗�(���̈�)�@�@���� �ݗ��Y�@ p.81-139
�E |
�R���A�M�P���Ǖ����u�ܒ���l : ���������Ƃ��̍s�� : �J�R�ܒ���l�O�S�\�N�䉓���L�O�v���u���@�ю��v��������Ċ�����B
�@�@�\�����Ɂu���@�ю��Łv�Ƃ���
�R���A���ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (13)�@�V��S�v���W ���ꌧ����ψ���v�����s�����B�@�@pid/7960802
|
�V��S�v���W�k�� ����ژ^�E�����l/p1�`72,�ё�����1��
���̔����ƌ��� / �V��S�v/p2�`26
�V��S�v���Ɖ���̐A���w / �V�[�`�n/p27�`36
�L�ތ����҂Ƃ��Ă̓V��S�v�� / ���Z�ϓ�/p37�`42
�V��S�v���Ɩ����� / �����/p43�`52
<�V��S�v���W> �V��S�v���Ɩ����� ����1�V��S�v�̒���ژ^/p53�`60
<�V��S�v���W> �V��S�v���Ɩ����� ����2�V��S�v�̕��������{/p60�`61
<�V��S�v���W> �V��S�v���Ɩ����� ����3�V��S�v�̌���/p61�`64
<�V��S�v���W> �V��S�v���Ɩ����� ����4�V��S�v�̗���/p64�`70 |
<�V��S�v���W> �V��S�v���Ɩ�����
�@�@������5�V��(����)�Ɉ��ޓ��A��/p71�`72
�V�̎v�z--���ی�������� / ��������/p73�`95
����ŏ��̈ږ��Ɋւ���V���L�� / �c�`���a/p96�`101
�u����V�����v�W�j�� / �n���얾/p102�`113
������j�W��v�_���ژ^(1987�N) / �Ί_����/p114�`168
�j���ҏW������(��㔪���N)/p169�`171
�������{�������p�������/p172�`173
�E |
�R���A�~���w�@��w�n�敶�������� �ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v
= Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (3) �v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@pid/4424699�@�@�d�v
|
�n�敶�������Ƃ� / ��������/p1�`2
���m�l��Ղ̖퐶����O������--��ꎟ������ / �������� ;�ɓ��ƗY ;�؉����q/p3~46�@�@404 Not Found
���܂�u�y��P�l�l�v�̎w�W�� / ���c��/p47�`54
�����Y�C���̎��� / �ɓ���/p55�`66
����������^�R / ����h��/p67�`70
�R���g�[(�ʗ���) / �V��S�g/p71�`72
���s�Ŋm�F���ꂽ�u�̏K���I���ƕό^�u�� / �����쐬��/p73�`81
�y�^�R�̖��̗R���́H / �v���O/p82�`84
�֖�C������̕����� / ����M�q/p85�`95
���ΏW / �n�ӌ��i�ق�/p96~131
���ւɂ�����ؔ����̕���(����3) / �L�c��/p132�`143
�U�B��J����ǒ��� �ՋT�����ǒ���(��) / ����i ;������ ;���R�R��/p144~170
���U�w�K����̎Љ�� / ���y�r�Y/p171�`181
���H�ׂ��̕��y�L�� �]��� / �R�c�����Y/p182�`184
�n�敶��������62�N�x������/p185�`186 |
�S���Q�W���`�T���Q�X�����A���s���������قɉ����āu���ʒ�@�ܒ���l�ƒh���@�ю��v�W���J�����B
�S���A���s���������ٕ� �u�W����ژ^�F���ʒ�@�ܒ���l�ƒh���@�ю��v���u���s���������فv���犧�s�����B
�T���A�������ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 53(5)[(683)]�v���u���傤�����v���犧�s�����B�@�@pid/6059800
|
�̌|�\--���{�l�̂�����<���W>/p5�`176
�A���o�����̌|�\ / ���p�䐳��/p5�`16
�����|�\�ƌ|�\�j / ���p�䐳��/p18�`23
�؍��̃N�b(��)�Ɨx��i���j���{�̌|�\�Ƃ̐ړ_ / �A�N�_/p24�`32
�k�C���E���k/p34~58
�k�C���E���k ���[�J��(�k�C��) / �������}/p34�`37
�k�C���E���k �щz���̉��N(���) / �_�c���q/p46�`48
�k�C���E���k ������Օ�(�X) / �ΐ쏃��Y/p38�`40
�k�C���E���k ���r���_�y(���) / �剮����/p49�`51
�k�C���E���k �H�c����(�H�c) / ꎓ����/p41�`45
�k�C���E���k ����\(�R�`) / ���e�N�v/p52�`54
�k�C���E���k �k�C���E���k�̖����|�\ / ���j�l/p55�`58
�֓��E����/p59~94
�֓��E���� �S���}(��t) / �����v/p59�`61
�֓��E���� ���C�̓c�y�\(����) / �����K��/p75�`77
�֓��E���� �Ԑl�`(����) / �{���o�j/p62�`64
�֓��E���� ���B��O��(�É�) / ��{�v/p78�`80
�֓��E���� ���n�̐l�`�ŋ�(�V��) / ���B�ޏ���/p65�`68
�֓��E���� �V�Îi��(�R��) / ��؍F�i/p81�`83
�֓��E���� ���q��(�V��) / ���}�����q/p69�`71
�֓��E���� �ԍ�(���m) / ���쓧/p84�`87
�֓��E���� ��O�V�x(�x�R) / ���c�v�v/p72�`74
�֓��E���� �S��x��(��) / ���c��/p88�`90
�֓��E���� �֓��E�����̖����|�\ / ��Y�T��/p91�`94
�ߋE/p95~121
�ߋE �]�B����(����) / �֎R�a�v/p95�`97
�ߋE �d�B�̕���(����) / �������Y/p108�`110
�ߋE �ɐ���_�y(�O�d) / �㓇�q��/p98�`101
�ߋE ��ڗ�(�ޗ�) / ���䐴��/p111�`113 |
�ߋE �p����O������(���s) / �牮�B/p102�`104
�ߋE �������̗����{(�ޗ�) / �����טY/p114�`117
�ߋE �͓�����(���) / ���q���i/p105�`107
�ߋE �ߋE�̖����|�\ / ���j�l/p118�`121
�����E�l��/p122~141
�����E�l�� ���Ηx��(���R) / �����R��/p122�`124
�����E�l�� ���т���(����) / �F�쏬�l�Y/p131�`133
�����E�l�� �p���̉ԓc�A(�L��) / ���c���q/p125�`127
�����E�l�� �ɗ\����(���Q) / �㓇�q��/p134�`137
�����E�l�� �Øa��̍땑(����) / �R�H����/p128�`130
�����E�l�� �����E�l���̖����|�\ / ��Y�T��/p138�`141
��B�E����/p142~161
��B�E���� �K�ᕑ(����) / �������q/p142�`145
��B�E���� ��q��Ղ�(����) / �A������/p152�`154
��B�E���� ���u����(����) / �đq����/p146�`148
��B�E���� �����ÓT���x�Ɨ���(����) / �O�Ԏ�P/p155�`157
��B�E���� �����_�y(�{��) / �n�ӗǐ�/p149�`151
��B�E���� ��B�̖����|�\ / ���j�l/p158�`161
�����̂��߂̎�� ���a51�N�ȍ~
�@�@�������|�\�W�P�s���ژ^ / ���B�ޏ��� ;�n�_��/p162~171
�����̂��߂̎�� �����|�\�� / ���B�ޏ���/p172�`176
�G���\�T�����u���y�v--�_�˂���̐�
�@�@���n��N�ƁE�R�{�䍲�g�� / �g��q�Y/p179�`180
�T�Ɠ����w�V���L�җ�B�x���� / �J��i��/p181�`182
�A�� ���{��w ���{��ƃ^�~����̊W(65) / ���W/p183�`190
�C�O����̕ւ聁�\�E�������--
�@�@���؍��̓������������(7) / �{�c��/p177�`177
���x�������̓��ƃZ���^�[�X���O�W��
�@�@�@��"�����炨�Ƃ�" / ���J���/p178�`178 |
�U���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (21)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@�@pid/6067728
|
�Ċ_�_�� / ���Ώ��b/p4~13
�����Ղ�[�_�X������u���v�Ɓu���] / �O�����Y/p14�`23
�ɎG�{��c�A�� / ���䖞/p24~31
�R�x�M�Ƒ���[�n���}�Ă���߂�����] / ��ؐ���/p32�`42
�Ñ���J�̎��Ԏ� / �����G�O�Y/p43�`47
�C�U�C�z�[ / ��ÍN�Y/p48~57
|
�{�Ó��̑c��Ղ� / ���{�b��/p58�`63
[�V�A��] �@�g�̗�����(1)�������� / ��������/p64�`67
[�V�A��] �n�����̕ۑS���߂������A���|�[�g
�@�@���w���狤�L�̖����x / �،��[�g/p68�`71
�F�o�ẪL���R�Ղ� / �������Y/p72�`75
�f��Љ�u�R�̕��v / �s��`�v/p76�`76
|
�U���A�u SD : Space design : �X�y�[�X�f�U�C�� (285)�v���u�����o�ʼn�v���犧�s�����B�@pid/2309737
|
����`�����v��--�����̃N���X���[�h<���W> //p5�`84
����`�����v��//5�`5
���㌚�z�n�}//28�`29
���y�̂Ȃ��̌��㌚�z/�Êٍ���/32�`48
���ꌚ�z�E�ɂ����钇���v�Y�̖���/����~��/49�`49
����̐Α�������-���̑��l�Ȍ`��/�����x��/50�`51
����̐Α�������/������/52�`53
�ق������-���얡�������/��،���/54�`55
���ꌚ�z�N�\[1945�`1987]//56�`59
�썑�I�ȕ��U�^���]�[�g-[���B�� �I�N�}���]�[�g]��
�@�@��[�͂��ނ�Ԃ�]/60�`63
�E�`�i���`���[��C���^�r���[/�ؕ��^�b�m/64�`73
���ꔭ�A�W�A�q�H�h�L�������g--
�@�@��<��>�ōs������p/��|���q/p74�`77
���썑:����/�܌��b/78~83
��n�̃I�L�i��/�܌��b/84�`84
�t�H�g��h�L�������g//6�`31
�V�[�T�[//6�`7
����//8�`9
��//10�`11
��//12�`13
�Ŕ�//14�`15 |
�s��//16�`17
�H//18�`19
�ړ�//20�`20
�A��//21�`21
�F//22�`23
�l//24�`25
���㌚�z//26�`27
�T��//30�`31
�ߑ���{�̓Ɨ��Z��ɂ������ԍ\��(3)
�@�@���ΐS������������L����\��/�����G��/89�`92
�Ñネ-�}�̗���(��-���b�p����̗�-2-)/�����K/p96�`99
�Ñネ�[�} �T�[�J�X�����p������/�r���I/94�`95
��݂���s�s���-2-�f�B�x���b�p-�s�s���--
�@�@���J���̃��j�b�g��/�c������/p101�`104
�j���[�X//106�`107
���m�点//108�`108
�������Y�̢����������W �y�钾��/���э��O/110�`113
�m���Љ�//115�`115
���]//117�`119
�V���Љ�//123�`124
�C�O���z��� 8806/DUCTSPACE/p127~132
�E |
�W���A�Ӗ����c���i�W���i���g �P�C�t�N�j���u�A���}�[�B�̃J�`���[�V�[ : �Ӗ����c���Y�ȏW�v���u�V���{�o�ŎЁv���犧�s����B�@
�@�@�@266p�@�@�@�@�����F��㊌����}���فF 1001699568
|
������(�����܂���) |
���̃����^ |
�A���}�[�B�̃J�`���[�V�[ |
�W���A�̈�{�ݏo�ŕҁE���{�̈�{����ďC�u�����̈�{�� : �X�|�[�c�{��&�}�l�W�����g���
17(9)(211) �v���u�̈�{�ݏo�Łv���犧�s�����B�@pid/7948293
|
��
�j ���싪�������J�͎�� //118�`118
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� //49�`65
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� �{�݂̐����ɓw�͂��Đ��U����̑̌n�Â��� / ���W������/50�`51
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� ��C�w�����̈琬�}�� �w�Z�̎{�݊J���͐i�� / �v�꒷�N/52�`53
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� �����E�{�݈���������{�y���݂�...��������
/ �X�۞Ď��Y/54�`57
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� �i�g���E���ێ揭�Ȃ� ���ނ̗������H�v���� / ��ؐM/58�`59
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� �g���[�j���O�@��78�� ���p�҂Ɗy�����Y�N�� / �R��@��/60�`61
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� �����A�����Ĕj����3�_���������`�F�b�N / �a�c����/62�`63
�ڕ� ��49��S���̈�{�������c���--�n��̓��������w�͂� ���^�����Łu�ӌ��v��[�߂�... / �S�̉�c/64�`65
�� |
�W���A������q�Ғ��u����̗x�� : ���މ��̕��@�����߂āv���u����R���j�[(���)�v���犧�s�����B�@
�@�@�@�@60p �@�@�����F��㊌����}���فF1001534468
�X���A�Y�R���ꂪ�u���{���z�w�����. ��B�x��. 2, �v��n (26) p.477-480�v�Ɂu��Ԃ̌`�ԓI����(����1) : ���d�R�Q���E�|�x��(���z�j�E���z�ӏ�)�v�\����B
|
�Y�R���ꂪ���\�����u��Ԃ̌`�ԓI����(����1�`5)�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
���{���z�w����� - (26) p477-480 |
1982-03 |
��Ԃ̌`�ԓI����(����1) : ���d�R�Q���E�|�x��(���z�j�E���z�ӏ�)�@ |
| 2 |
�w�p�u���[�T�W. �v��n 57(0) p.2301-2302 |
1982-08 |
��Ԃ̌`�ԓI����(����2) : ���d�R�Q���g�Ɗԓ� : ���z���j�E���z�ӏ��@ |
| 3 |
. |
. |
�s���i���m�F�j |
| 4 |
�w�p�u���[�T�W. F, �i1985�j p.829-830 |
1985-09 |
�u�C�r�v�̋�ԑc�^�ɂ��� : ��Ԃ̌`�ԓI����(����4)�@�@ |
| 5 |
�w�p�u���[�T�W. F, �i1988�j p.967-968 |
1988-09 |
����̔z�u�\���Ɋւ����ጴ�� : ��Ԃ̌`�ԓI����(����5)�@ |
|
�X���A���쌒�� [�ق�] ���M�A�������� [�ق�] �ҁu�`���ƋL�^�v���u��g���X�v���犧�s�����B
�@�@�@ (��g�u�����{�̉��y�E�A�W�A�̉��y / �������� [�ق�] ��, ��4��)
|
���y�̓`���ƋL�^ / ���쌒��, �R���C [���M]
��y�Õ��Ƃ��̉�ǂɂ����鏔��� : ��Ƃ��Ĕ��i���ɂ��� /
�@�@�� �X�e�B�[�����EG�E�l���\�� [���M]
���Ƃƒn���y�Ƃɂ����鉹�y�`�� / �鐅�G [���M]
�����̊y���ƋL���@�̕ϑJ / �V��O�� [���M]
��Ӑl�Љ�ɂ����镽�Ȃ̋���Ɗy���̌��� / �E�c���q [���M]
�O�������y�̓`���Ɨ��h : �L��n��ڗ��̏ꍇ / �|�����h [���M]
ⶎO�������y�̊y���o�łƋL���̌n / �v�ۓc�q�q [���M]
�������y�̋L���̌n / ���R���� [���M] |
�|���l�V�A���y�̓`���ƃn�i�V�̓`�� / �R�{�^�� [���M]
�^�C���������ɂ����鉹�y�`�� :
�@�@���X�R�[�E�J�������̎���𒆐S�Ƃ��� / ���c���q [���M]
�C���h���y���x���̓`���ɂ����鉻�� :
�@�@����C���h�E�P�[�����̌ÓT���x�����Ƃ��� / ��ݗR�I [���M]
���A�W�A���y�ɂ�������`�Ə��` / ����M�j [���M]
�u���́v�Ƃ����p��Ɋւ��鏔��� :
�@�@�� �Ƃ��ɗ��j�I�p��@�̊ϓ_���� / ��t���V�� [���M]
�����̋L���w / �R�����j [���M] |
�P�O���A������q�Ғ��u���x���� : ���x���ނ̎w���W�J ����2�v���u������q�^����o�Łv���犧�s����B
�@�@�@�@�����F������w �����}���ف@�����@����2�@ 375�^KI�^22003402798,�@�@98p
|
������q���u���x���� : ���x���ނ̎w���W�J ����2�v�Ɋ֘A����Ǝv����_���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
�w�Z�̈� 35(2)�@p124�`128 |
1982-02 |
����ƌ��������Ȃ� ���x����̗��_�Ǝ��H�@������q�@pid/6027270 |
| 2 |
�w�Z�̈� 38(3)�@p66�`67 |
1985-03 |
�w�Z�̈玞�] ���x����ɂ�����`���Ƒn�� ������q�@pid/6027314 |
| 3 |
����o�Ł@�@98p |
1988-10 |
���x���� : ���x���ނ̎w���W�J ����2 �@������q |
|
�P�Q���A�V�����i�|�āE�� ; ��@�Ö�h����u������(�g�D�}�C �A�[�J�[) :
�����Ȃ�ߗ����̂����� �v���u�ߔe�o�ŎЁv���犧�s�������B (�܂��쌀��, 1)�@ ���: �X�ۉh���Y
�P�Q���A�q�쐴�ҁu�H�����J��:���a��Ôg����҈ԗ�V�������L�O���v���u�k�Ί_�l���a��Ôg����҈ԗ�V����^��v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�������N�L�O���@�@�@�@�d�v |
| 1989 |
64 |
�E |
�P���A���̔����ٕҁu�S���� (72)�v���u���̔����فi�����s�k��̔R�������j�v���犧�s�����B�@pid/3333092
|
���G������g�^���� / ������q
���̓��x�[�p�[����[�h / ���c���V/p1�`3
�u����u����̎��v/p4~6
�������̂���� / ��]�F�q�v/p6�`11
�����F�̋Ɛт̈Ӌ`--����Ȃ��l�͎��������̂� / ������/p11�`17
�k���G�����l/p17~17
�����̎��W����J�� / �w�|��/p21�`25
�k�ǎ҂̍L��l�����a����m���Ă��܂���--
�@�@�������̓u��W������ / �_�Ԑ�b�q/p26�`27
�{�M�N���t�g���H�ꎖ�n��--�g����������Ԓ�������
�@�@���Βk�𒆐S�� / �А؏�/p28�`41 |
��\��� ���ە������ۑ��Ȋw��c�J�� / ���c���F/p42�`45
���쥒��R��������K�˂�--�荗���a����
�@�@���V�����o�c�헪 / ���їǐ�/p46�`61
�a��������G�K���L / �T�䌒�O/p62�`67
�V�����ЏЉ�/p69~69
���̔����ُo�ňē�/p70~71
�ɗ������/p72~74
�ُ���/p75~84
��S��������ڎ�(�ǘ^)/p����1�`����6
���Ƃ���/p�\��3~�\��3
�E |
�Q���A�r�������� ; ���a�c�^�~�ďC�u����A����O���p�}�� ��10��(��������)�v���u�V���}���o�Łv���犧�s�����B
|
����A����O���p�}�� 1�@�͔|�A���Ɖʎ��@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o��
1979-12�@ 1984-00
����A����O���p�}�� 2�@�͔|�A���@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o��
1979-12�@ 1984-00
����A����O���p�}�� 3�@�A���A���@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o��
1979-12�@ 1984-00
����A����O���p�}�� 4�@�C�ӂ̐A���ƃV�_�A���@�@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o�� 1979-12�@
����A����O���p�}�� 5�@��n�̐A���@�@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o��
1979-12�@ 1984-00
����A����O���p�}�� 6�@�R�n�̐A���@�r�� ����/��,���a�c �^�~/�ďC �V���}���o��
1979-12�@ 1984-00
����A����O���p�}�� ��7�� (�V�_�A���`�܂߉�)�@�@�r������ �� ; ���a�c�^�~
�ďC �V���}���o�� 1989�E�Q
����A����O���p�}�� ��8��(��ȁ`���˂̂܂���)�@�@�r������ �� ; ���a�c�^�~
�ďC �V���}���o�� 1989�E�Q
����A����O���p�}�� ��9��(�����ˉȁ`����)�@�@�@�r������ �� ; ���a�c�^�~
�ďC �V���}���o�� 1989
����A����O���p�}�� ��10��(��������)�@�@�@�r������ �� ; ���a�c�^�~ �ďC �V���}���o�� 1989�E�Q |
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (9)�v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B�@�@pid/7955138
|
�C���h�l�V�A���W�����B�X�J�u�~�̓S���_��B���j / �����N��/p1�`17
�^�_���ɂ����鎀�̖���--�����߂��鏔��� / �ߓ����s/p18�`38
�Ί������l / ���֏�v/p39~40
�{�Ï�Ӓ��F�������ɂ�����C�̖��� / �F�s����/p41�`48 |
�����哇�����W���̎Y��K�� / �c����H/p49�`58
1988�N�x���_���\��\�v�|/
�@�@�@�����]�F�m�q ;�����G�O ;��×Ǎs ;�L�c�B�v/p59~64
�E |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 2�v�����s�����B
|
���d�R�̕��y�E���j�E���� �@�g�Ɗ� �i�g p.1-31
��11�I�����̏d���W�m�[�g �g�Ɗ� �i�g p.32-53 |
�ÓT�����������̎��� ���� �ݗ��Y 1 p.57a-1a
�E |
�R���A�u�쓇���� 11�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�@�@ �iIRDB�j
|
���˓������}�_�M�� : ���ꌧ���Ɣ�ׂ� �E���� p.1-8
�|�x���c�[�E�Ì������̏������� �@�쌴�O�` p.9-44
�������̃��K���ܖ� : �R��杁E�V��E�_�� �@���R�� p.45-108 |
�NꤔN�Ԗ��ƎR���a���쎁�b�a�Y���L�L�ڒn���l ���P�� p.109-118
���ʉ��E�p�[���@ �㌴�y��j p.119-126
�E |
�R���A���ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (14)�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@pid/7960803
|
���ꌧ�����S���H�n���ɂ�����n�����̔p�~�Əo�ږ�--
�@�@����������������Ƃ��� / �ΐ�F�I/p1�`34
�O�X�N�Ɛ��^ / ��������/p35~70,�}����1p
���鎟�Y���Ɠ��L / �����/p71�`107
������1���j���Ċق̗����W�������
�@�@���V�j���ɂ��� / ���Ð����Y/p108�`120 |
���D����3�� / ��]�F�q�v/p121~136
������j�W��v�_���ژ^(1988�N) / �Ί_����/p137�`185
��\�l��S�����j�����ۑ����p�@�֘A�����c��
�@�@��(�S�j����)�S�����̊J��/p186�`187
�j���ҏW������(��㔪���N)/p188�`190
�������{�������p�E������/p191�`192 |
�R���A���эK�j���u���s�����w�I�v. A, �l���E�Љ� 74 p.79-96�v�� �u���R�[�_�[����̂߂������� : �����{����w�ł̎w���̖��_����̍l�@�v�\����B�@
�iIRDB�j
�@�@�܂��A�����͎q���u����p.155-166�v�Ɂu�����x��̉��y�w�I���� : �i���ꌧ�j�y�R���̑��ۗx��I(�x��̍\��)�v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�X���������ψ�����u�X����̋����Y�E�������v���u�X���������ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@(�X������T������ / �X���������ψ����, 8)
�R���A�Y�Y�s����ψ���ҁu�ʏ钩�O�̕撲�����v���u���ꌧ�Y�Y�s����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@ (�Y�Y�s������������)�@�@56p �@�@�����F���ꌧ���}���فF; 1001530169
|
��������
�}��4��
�ጾ
�͂��߂�
�ʒu�Ɗ� ���n ���L
�����̌���[�����ʏ钩�O(�ӓy����)�̕�̍\���ɂ��� ���g�^�O
�ʏ钩�O��(�ӓy���ƕ�)�̐l�X �c�� �^�V |
�ʏ钩�O��(�ӓy���ƕ�)�̐~�q�P ��]�F ��
�ʏ钩�O�̌|�\ ���w
�ʏ钩�O �r�{����
�撆���ɂ��� ���n ���L
�ߐ������m�����ƒ��O ���Ǒq�g
�l�Êw���猩���ʏ钩�O�̕�ɂ��� �r�c�h�j
�E |
�R���A�~���w�@��w�n�敶���������ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v = Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (4) �v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@pid/4424700
|
���p���̖K�� �����̖̍K / �������� ;���y�r�Y/p1~11
���p���̖K�� �l�Êw����݂��p�� / ���Ό� ;�؉����q/p12~23
���p���̖K�� �����̘̍^ / �{�c��/p23�`32
���p���̖K�� �����̒��� / ����M�q ;�Z�c��q/p32~50
���p���̖K�� �p���̂��ƂΊo������ / ����M�q/p51�`67
�狣�Z�E�T�K�m�[�g(1) / ���y�r�Y/p68�`78
�M�\���E�M�\�M�Ƃ��̎��� / ���K���v/p79�`83
�����m�l�o�y�L�ւȂ�:�n�敶�������������L���i�����Љ� / �؉����q/p84�`93�@�@404 Not Found�@�@�d�v
�����ׂ��̕��y�L�����ł� / �R�c�����Y/p94�`96
���`���|�̃^�p���� / ���c�{��/p97�`98
����l����� �ؔ����Ɠ��{�̖������� / �Ôg���u ;�˓c��S�q ;��������/p99~113
���ւɂ�����ؔ����̕���(����4) / �L�c��/p114�`129
�U�B��J����ǒ���(����ǒ���)(��) / ����i ;������ ;���R�R��/p130~147
���{�I���i�̎v�z / �r�ؐ���/p148�`165
�n�敶��������63�N�x������/p166�`166 |
�R���A�����ّ�w���b���w������, ���~������ψ���ҁu���ꥍ��~���̘̐b�v���u�����ّ�w���b���w������v���犧�s�����B�@
(���~�������� ; 4)
|
�ʐ^
���@���璷�@�{���
�ڎ�
�n�}
<���>
��A�@���̊T���@���{�F�O�@21
��A�@�̘b�̖K�L�^�@�����h�q�@27
�O�A�@�`���̌n���E�@��@���{�F�O�@29
�l�A�@�`����������@���c�W�@42
<�{��>
�}��
�_�b
1�@�A�}�~�L���̓����@57
2�@�A�}�~�L���̎q���@58
3�@�N�o�̗t���̐_�X�@58
4�@�l�̎n�܂�(1)�@59
5�@�l�̎n�܂�(2)�@60
6�@�v�����̎n�܂�(1)�@60
7�@�v�����̎n�܂�(2)�@61
8�@�܍��̎n�܂�@62
9�@��̎n�܂�(1)�@62
10�@��̎n�܂�(2)�@64
11�@��̎n�܂�(3)�@64
12�@���̎n�܂�@65
13�@�A�}�~�L���ƒ��҂̃E�t�X�[�@65
14�@�ÉF�����̐H�ו��̎n�܂�@66
15�@�A�}�~�L���̐��Ⴂ�@67
16�@�A�}���`���[�̑��Ձ@68
�`��
17�@���̃C�U�K�[�����@71
18�@�Ɍv���̌���˗R���@71
19�@���J�̃E�u�K�[�̘b�@72
20�@��ӂ̃V�[�T�[��(1)�@73
21�@��ӂ̃V�[�T�[��(2)�@74
22�@�t�b�`���[�ΗR���@75
23�@���V�Ԍ����R��(1)�@76
24�@���V�Ԍ����R��(2)�@77
25�@��Ԑ̘b�@79
26�@�v�U�@80
27�@�S�l�c�n�O���e���@82
28�@�S�l��������@83
29�@���V���E�~�`���̘b�@84
30�@�^�ʋ��̐l���@85
31�@�����̉Z��(1)�@87
32�@�����̉Z��(2)�@88
33�@�����̉Z��(3)�@90
34�@��̉ԁ@91
35�@����v�̓y��N�@92
36�@���⓰�R��(1)�@93
37�@���⓰�R��(2)�@96
38�@����H�ׂ�n�܂�@97
39�@��H�ׂ�n�܂�(1)�@98
40�@��H�ׂ�n�܂�(2)�@99
41�@�ӂ�ǂ��̗R���@100
42�@�j�[�r�`�R���@100
43�@���~�̗R��(1)�@101
44�@���~�̗R��(2)�@103
�{�i�̘b
45�@�A�J�}�^�ۓ���(1)�@105
46�@�A�J�}�^�ۓ���(2)�@107
47�@�A�J�}�^�ۓ���(3)�@107
48�@�V�l���[(1)�@108
49�@�V�l���[(2)�@109
50�@�L���[(1)�@110
51�@�L���[(2)�@111
52�@�p�q�̔�����(1)�@113
53�@�p�q�̔�����(2)�@114
54�@�p�q�̔�����(3)�@115
55�@�p�q�̓�\�����@115
56�@�p�q��@116
57�@�p�q�̋@�D��@117
58�@�p�q�̓œ���ٓ��@118
59�@�p�q�̈��������@118
60�@��̋q(1)�@120 |
61�@��̋q(2)�@121
62�@�S�ݗR��(1)�@123
63�@�S�ݗR��(2)�@125
64�@�S�ݗR��(3)�@127
65�@�S�ݗR��(4)�@128
66�@�S�ݗR��(5)�@129
67�@�W�̎R<�D��>(1)�@130
68�@�W�̎R<�D��>(2)�@131
69�@�W�̎R<�r���m���>�@132
70�@�����咆�̋a�ʂ��@133
71�@�Ҋ����̗R���@134
72�@�Y�����Y�@135
73�@�L�Ɗ��W�@136
74�@���@137
75�@�Z��̒�����@139
76�@�n�����̉A���@140
77�@��u���e���̒m�b(1)�@142
78�@��u���e���̒m�b(2)�@143
79�@��u���e���Ɩ���e��(1)�@144
80�@��u���e���Ɩ���e��(2)�@145
81�@���[�C�e��<�F���̓��>(1)�@146
82�@���[�C�e��<�F���̓��>(2)�@148
83�@���[�C�e��<�F���̓��>(3)�@150
84�@���[�C�e��<�F���̓��>(4)�@152
85�@���[�C�e��<�F���̓��>(5)�@156
86�@���[�C�e��<��>�@157
87�@���[�C�e��<�Ŏ��>�@158
88�@�n�Õ~�y�[�N<�Ŏ��>�@159
89�@���[�C�e��<���ʂƑ���>�@159
90�@���[�C�e��<�����͈��>�@160
91�@���[�C�e��<�|����>�@161
92�@�n�Õ~�y�[�N�̓ڒm<�U�^�сE
�@�@���X�ʌ��̋z�����E���Y����>�@162
93�@�n�Õ~�y�[�N�̕U�^�с@164
94�@�n�Õ~�y�[�N�̖��X�^�с@164
95�@�n�Õ~�y�[�N�̌�ł��@165
96�@�n�Õ~�y�[�N<���̂Ƃ�����>166
97�@�n�Õ~�y�[�N<���l���g��>�@167
98�@�n�Õ~�y�[�N<���Ə��m>�@167
99�@�n�Õ~�y�[�N�̋��הn�@168
100�@�n�Õ~�y�[�N<�\�O�錎>�@168
101�@���A�o�}�[<�\�O�錎>(1)�@169
102�@���A�o�}�[<�\�O�錎>(2)�@170
103�@���N�Ƒ�H�@172
104�@��������(1)�@174
105�@��������(2)�@176
106�@��������(3)�@177
�j�
107�@�`�[�O�[���@179
108�@��V�m���̋A��(1)�@180
109�@��V�m���̋A��(2)�@182
110�@��V�m���̋A��(3)�@183
111�@���b�u���̏o��(1)�@184
112�@���b�u���̏o��(2)�@186
113�@���b�u���̏o��(3)�@188
114�@���b�u���̏o��(4)�@191
115�@���b�u���̒m�b<����?��>(1)�@194
116�@���b�u���̒m�b<����?��>(2)�@195
117�@���b�u���̒m�b<�Ԃ̎n�܂�>�@196
118�@���ǂ̈����a���̒m�b<�Ԃ̎n�܂�>196
119�@���~���i�̗͔��(1)�@197
120�@���~���i�̗͔��(2)�@198
121�@���~���i�̗͔��(3)�@199
122�@���m�̗͔�ׁ@200
123�@�֏��Ԃ̘b�@201
124�@�m�O��i�ƌp��@202
125�@�����a���ƌ썲�ہ@203
126�@�ؓc�厞�̐痢��(1)�@204
127�@�ؓc�厞�̐痢��(2)�@206
128�@�E�u�V�J�}�V�O�`�̐痢��@207
129�@�`���E���^�}�M���[��
�@�@���A�����P�{�[�W���[(1)208
130�@�`���E���^�}�M���[��
�@�@���A�����P�{�[�W���[(2)210 |
131�@�`���E���^�}�M���[��
�@�@���A�����P�{�[�W���[(3)212
132�@�k�J���q�ƍ�������(1)�@213
133�@�k�J���q�ƍ�������(2)�@214
�����E�����b
134�@�N�X�N�F�[�R���@215
135�@�Ŏ��R���@217
136�@�����Ԃ�����<�i�[�`���~�[�R��>(1)218
137�@�����Ԃ�����<�i�[�`���~�[�R��>(2)219
138�@�����Ԃ�����<�i�[�`���~�[�R��>(3)220
139�@�����L�̏h�@221
140�@�L�W���i�[�ƗF�B(1)�@221
141�@�L�W���i�[�ƗF�B(2)�@224
�Θb
142�@��V�̂����ߕ߂�@225
143�@�R���ƒc�T(1)�@226
144�@�R���ƒc�T(2)�@227
145�@�t�Ȃ��̘b�@227
���b�����
146�@���F�s(1)�@229
147�@���F�s(2)�@230
148�@���F�s(3)�@231
149�@���F�s(4)�@232
150�@�R�[�i�[���O���@233
151�@�J�^�s�F�@234
152�@�\��x�R��(1)�@235
153�@�\��x�R��(2)�@237
154�@�\��x�R��(3)�@238
155�@���̋r(1)�@238
156�@���̋r(2)�@239
157�@���̐K�̐Ԃ��킯�@240
158�@�����̎n�܂�@241
159�@�������@242
���Ԙb
160�@�L�W���i�[�̋�����(1)�@243
161�@�L�W���i�[�̋�����(2)�@244
162�@�L�W���i�[�Ɛ����@245
163�@�L�W���i�[�@245
164�@���[�J�r�[�ƃ��^�@246
165�@��O�̘b(1)�@247
166�@��O�̘b(2)�@248
167�@��O�̘b(3)�@248
168�@�^�}�K�C�̘b�@249
169�@�ւɌ�����ꂽ���@249
170�@�����̉����L�@251
171�@�W�[�t�@�̖����@252
172�@���j���M��@252
173�@�L����̉����̉ԁ@253
174�@����ŕ��Ɓ@254
175�@��A���̓��l�@255
176�@��ԃi�[�J�Ɠ��l(1)�@257
177�@��ԃi�[�J�Ɠ��l(2)�@258
<�Ζ�>
178�@�S�l�c�n�O���e���@259
179�@�����̉Z��@262
180�@�l����̗R���@265
181�@�Z��̒�����(1)�@266
182�@�Z��̒�����(2)�@267
183�@���[�C�e��<���ʂƑ���>�@270
184�@��V�m���̋A���@272
185�@���b�u���̏o��(1)�@274
186�@���b�u���̏o��(2)�@277
187�@���b�u���̏o��(3)�@286
188�@���~���i�̗͔��(1)�@288
189�@���~���i�̗͔��(2)�@290
190�@�ؓc�厞�̐痢��@292
191�@�R���ƒc�T�@295
192�@���F�s�@296
193�@�R�[�i�[���R���@297
�b�^�Ώƕ\�@299
����ꗗ�@313
�̖K�Җ���E�|���Җ���@317
���Ƃ����@�����ّ�w�����@���c�W�@318
�E |
�S���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (33)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/4419240
|
�F���˂̓������@�ƒ��� / ���c���Y/p1�`19
�����̕����m���Ɛ��E��--��n�����Ɋւ���c�_���߂����� / �n�ӋӗY/p20�`43
���\���ƌ��c���� / ���c�Z/p44�`62
�쓇�̃T���S�ʂƐl--�ŋ߂̌����̈�f�` / �n�v�n��/p63�`79
�u�E�����搶���꒲��20�N�L�O�_���W--����̏@���Ɩ����v�E�����搶���꒲��20�N�L�O�_���W���s�ψ����
/ ����N�F/p80�`85
�u�ߐ��C�Y���o�ώj�̌����v�r���p�� / �؍�O��/p86�`89
���/p90~93 |
�S���A�|�\�w����u�|�\ 31(4)(362)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276651
|
�܌��M�v�ƌ|�\<���W>/p10~41
���z �܌��搶�ƎG����|�\� / �˔N��/p10�`11
�����|�\�ƌ|�\���� / �O�����Y/p12�`20
�|�\�j�̎v�z / �ɓ��D�p/p21~27
���J�ƌ|�\ / �������/p28~34
�|�\�ɂ�������� / �Óc���K/p35�`41
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(1)�܌��M�v�̉���̖K/������ ;�F����o�j/p6~
�� �|�\�����ƍ̏W / ������/p9�`9
��`�������̍Ĕ�������g���V / �������H/p42�`44
��{�ג� ���z�W�w�嗘���̗���ɉ����āx / �����G�Y/p45�`45 |
�����N�\(3��1��~31��) / ���c�m/p46~56
���x�N�\(2��15���`����) / �@���q/p57�`64
���� ���A���Y�����čl / �n�ӕ�/p65�`65
�M�y �V������ԂƓ`�����y / ���P�Y/p66�`67
�m�� ���{�̗m���̏����� / ����C��/p67�`67
�\����� �ϐ����D�ʂ̌��� / ���{����/p68�`68
�f�� ���Ԍ|�p�̐��ʁ\�\���������G���
�@�@������[�h���B�q� / �n����/p69�`69
������/p70~71
�V���ē�/p72~72 |
�T���A�|�\�w����u�|�\ 31(5)(363�j�v���u�|�\���s���v���犧�s�����Bpid/2276652
|
�����E����̐M�ƍ��J-1-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�͂��߂� / ������/p10�`10
������낳������ɂ݂�×����̐��E��--������������̐M��/�O�Ԏ�P/p11�`23
���������̐M�Ɛ_�b--�H�ߓ`���𒆐S�Ƃ��� / ��ё���/p24�`37
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(2)����V�Ԃ̕���/������ ; �F����o�j/p6�`
<��>�ӂ邳�Ƒn���Ɩ�� / �����G�Y/p9�`9
���] �s�꒼���Y���w�����{���������l���x / �R�H����/p38�`38
�����N�\(4��1���`30��) / ���c�m/p39�`49 |
���x�N�\(3��1���`����) / �@���q/p50�`58
������ߑ㣂̍� / �n�ӕ�/p59�`59
�m�y �N���V�b�N���y�E�̎l�� / ���c�R�V/p60�`60
�M�� ���x�̖��͂�������� / �˕����/p61�`61
�\����� �����v�n�́w���c��x�̖��_/���{����/p62�`62
�e���r �ԑg�ɂ��o���G�e�B�[ / ��{�m/p63�`63
�V���ē�/p64�`64
�E |
�T���A�茴�P�V���u�n���h�u�b�N����̔N���s���v���u����o�Łv���犧�s����B�@�@
�U���A�|�\�w��ҁu�|�\ 31(6)(364) �v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276653
|
�����E����̐M�ƍ��J-2-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�쓇�̑��������Ɛ_ / �J�쌒��/p10�`21
���J�ƌ|�\ / �O�����Y/p22~37
�u�܂�v�ꗗ�\--�X�ۉh���Y���쐬�w���ꕶ���j���T�x
�@�@��(�������o�Ŋ�)����/p34�`37
�܌��M�v�̐��E(��܁Z)�����(3)
�@�@����������̂��Ƥ���̑��/������ ;�F����o�j/P6~
�q���r���w�ً}�����Ɏv�� / ����K��Y/p9�`9
�X�c�E�j�Y�ʐ^�W�w�؍��̉��ʁx / �F����o�j/p38�`38
����ꕗ����؏@��Ѣ�܍��ڂ́w��ڗ���i�v���x� / ���c�m/p39�`39 |
�����N�\(5��1��~31��) / ���c�m/p40~49
���x�N�\(4��1���`21��) / �@���q/p50�`57
������������̉����գ / �n�ӕ�/p58�`58
�M�y ���{���y�W�c�̓�\�ܔN / ���P�Y/p59�`59
�m�� ���x�R���N�[���̌��� / ����C��/p60�`60
�\����� �n���C��w�̍��ۉ�c�w�\�������
�@�@������I���E�x/���{����/p61�`61
�f�� �Y�Ɖf���̌��� / �n����/p62�`62
������/p63~63
�V���ē�/p64~64 |
�U���A����a�Y, �������q�ҁu�V���[�Y�����ƕ��� 4 �ނƏ��_ �v���u���}�Ёv���犧�s�����B
|
�_�ɒǂ��鏗���� : ����̏����i�Վ҂̏A�C�ߒ��̌���/�������
�u�ʈ˃q���v�čl : �w���̗́x�ᔻ / �`�]���q
�u�ʏ��v�̐����ƌ��E : �w�����a�����z�L�x����
�@�@���w�e�a���L�x�܂�/�c���M�q
���ƌ��� / �������q |
���l���Ɛ��Q / �����טY
����R�[�������̔����Ƌ@�\ : ���ɐ痢��O��
�@�@���ޏ��I���i�ɂ��� / ���쐼����
�u�����ƕ����v���߂���o������ :
�@�@���u�ނƏ��_�v���߂�����/����a�Y |
�U���A�{��\�P���u�{�闬 �{��\�P�Ɖ��� : �ÓT�E�G�x�E�n�앑�x ��4��i�������q�j�v���u�{��\�P�v���犧�s�����B�@
�@�@�����F�������N6��4��(��) �@�ꏊ�F�����V��z�[���@�@ 56p�@�����F��㊌����}���فF1004863872
�V���A�ˈ䏹�����u����G�{�v���u�����Ёv���犧�s����B�@�@�S�O�O�~
�V���A�u�|�\ 31(7)(365) �|�\�w�� �� �|�\���s�� 1989-07pid/2276654/1/1
|
���������̐M�ƍ��J-3-�A�l�̗�--�N�����������̗��
�@�@��(���i�L�O���J�u��) / ���c�v�q/p10�`21
�܌��M�v�̐��E(��܈�)�����(4)������̂т���� / ������ ;�F����o�j/p6~
�q���r�|�p�͐l�̎�d�� / ���c�m/p9�`9 |
���P�Y���w���ꕑ�x�̗��j�x / �O�����Y/p22�`23
�� |
|
�����i�L�O���J�u��(1�`3)���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_�����e |
pid |
| 1 |
�|�\ 31(5)(363) p10�`37 |
1989-05 |
�������E����̐M�ƍ��J-1- |
pid/2276652 |
| 2 |
�|�\ 31(6)(364)p10�`37 |
1989-06 |
�������E����̐M�ƍ��J-2- |
pid/2276653 |
| 3 |
�|�\ 31(7)(365)/p10�`21 |
1989-07 |
���������̐M�ƍ��J-3-�A�l�̗�--�N�����������̗��/���c�v�q |
pid/2276654 |
�@�@���@���@�m���P�E�Q�ɔ��\�Җ����L������Ă��Ȃ��̂Ŋm�F���K�v�@�@�Q�O�Q�R�D�P�P�D�P�T�@�ۍ� |
�W���A ���c ���q���u�w����̗̉w�Ɖ��y Ethnomusicological considerations�x�v���u��ꏑ�[
�v���犧�s����B�@
�@�@�����F��㊌����}���فF1001618006
|
����
�A�W�A�̒��ɂ݂鉫��̉��y
����̏����̗w�Ɖ��y
�{�Ï����̛ޑ��ƛމ�
�����̃��^�̐��b�Ɖ�
�����E���˓��̖��w
�u�����x��v�̒n�搫 �[�u�ł�����v���߂����ā[ |
Shima-Uta of Amami Sunnary�FSongs
and Ballads in Oikina
A list of Musics Examples
����ꗗ
���o�ꗗ
����
�E |
�W���A�J�쌒��ҁu�ޏ��̐��E�v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@ (���{�������������W�� / �J�쌒���, ��6��)
|
�ڈ̗w�Е��Ɍ�����ޏ� / ���c�ꋞ��
�C���[�̘b / �v�ێ���F
�ޏ��ƛމ� / ���c�ꋞ��
�����A�C�k�̃V���[�}�j�Y�� / �s���X�c�L
�C�^�R�E�����݂�E�{�T�} / ������
�������̓`�� / ����쏁���Y
���邷��ޏ����� / ����쏁���Y
���ޏ��̓`�� / �ΐ쏃��Y
�Ìy�̃S�~�\ / �]�c���q
�X�ƏH�c�̃S�~�\ / �]�c���q
�X���̌��ޏ��T�K / �����I�q
���R�̃C�^�R / ���k�w�@��w�����w������
���R�C�^�R�̕����낵�̎��� / ���k�w�@��w�����w������
���̛ޏ� / ��������q
�_�Â��̎� / �]�c���q
���ޏ��̕������� / ������q
���������̃~�R / ��������
�{�錧�k�n���̃~�R / ��������
���ޏ� / �����I�q
�I�J�~�T�}�̍l�@ / �֓����i
�I�J�~�T�}�̃J�~�c�P / ���k�w�@��w�����w������
�x�@���揑�Ɍ������ޏ��̒q / �����S��
���p�S�ɂ�����~�R�̑g�D�Ƌ@�\ / �n�ӈ�q
�_�Â����Ƃ����炳�� / �����P�O
�_���l�̘b / ����~��
|
�I�V�����l�̘b / �ˍ�i
�O�t���_�{ / ����~��
�ɓ��P���̛ޏ� / ����K��
�P���ޏ��̍Օ� / ����K��
�I�B�c�ӂ̛ޏ��̘b / �G��原�Y
�B��̋F���t / �����̈�
���B�̃V���[�}�j�Y�� / ����q��
��q���́u���m��v�ɂ��� / �����`�D
���v���̛ޑ� / ����q��
�g�J���E���Γ��̃l�[�V�Ɋւ���o�� / ���c�@��
�l�[�V<�ޏ�>�o���� / ��_���F
���������\�����̒j�ޏ� / ���c�@��
�g�J���l�[�V�̃C�j�V�G�[�V�����Ƌ@�\ / ����q��
���^�ɂ��� / ���؍G�v
�����̃��^�̐��ނ̖�� / �R���ӈ�
�����ꑺ���̕a�C�� / ������
�^�_���̃��^�ƈ˗��҂ɂ��Ă̗\���I�l�@ / ��R���F
���^������ / �Ö{�O
���^�������� / ���c�M�q
�u���^�v�ƒn��Љ�̐l�ԊW / �勴�p��
�V���[�}�j�Y���̍l�@ / �`��������
��p�Ɨ썰�� / �K�n�N
���ǎs����E���ÎR��ԓ��J�����N / ���{�b��
���ԛގ҂ƎЉ�\�� / ��Ð��v
�E |
�X���A���эK�j���u���s�����w�I�v. A, �l���E�Љ� 75 p.117-133�v�Ɂu����@�ɂ����鋳���{���̂��߂̃��R�[�_�[�̎w�� : ���s�����w�u���y���ތ����v�ł̎��H�Ɩ�� �v�\����B�@�@�iIRDB�j
�X���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (26)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@pid/6067733
|
�V��̃A�J�}�^�E�N���}�^ / �A������/p4�`6
�A�J�}�^�����L--[�V���n�������] / �q�쐴/p7�`7
�����_�̌Ì^ / �J�쌒��/p8~9
���ʉ����̏K��--[���d�R�������ɂ���A�J�}�^�E
�@�@���N���}�^�_] / �{�Ǎ��O/p10�`21
�����̑����_ / ��ÍN�Y/p22�`35
|
���B�̑��ؐ_ / ���R����/p36�`43
���S�̊�[�ِl�E���ƃ}���r�g�̑���] / ���c�v��/p44�`51
�j���[�M�j�A�̑����_ / �L�c�R�M�v/p52�`59
[�A��] �@�g�̗�����(6)�����ȍՎ��� / ��������/p60�`63
��������z���� / �{�c����/p64�`73
�E |
�P�O���A�|�\�w��ҁu�|�\ 31(10)(368)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2276657
|
�l���j�E�|�\�����̏��a-1-<���W>/p10�`36
�͂��߂� / �O�����Y/p10~10
���c���j�ƌ|�\ / �q�c��/p11~13
�܌��M�v / ������/p14~16
�����Z�g�̕��x���� / �J�O/p17�`19
����F���Y / �O�����Y/p20~21
�k�씎�� / �ۍ�B�Y/p22~23
���p�䐳�c / �������H/p24~26
�ɔg���Q / �X�۞Ď��Y/p27~28
���c����--���w�ϗe�ȑO�������� / ����K��Y/p29�`31
�{�������� / �{���o�j/p32~33
�r�c��O�Y / �������/p34~36
�܌��M�v�̐��E(��l)�����(7)���c�ƈ��g/������ ;�F����o�j/P6~ |
<��>�`�������\�t�g���o�Ō����� / ���p�䐳��/p9�`9
<���]>��ؓ��q���w���O�ͥ�ԍՂ�
�@�@���_�y<�_�̎���l�̐�>�x / ��쐽/p37�`38
�q�Љ�r�㓡�i�Ң�V�s�|�\� / �n�ӗǐ�/p38�`39
�����蒟(8��) / ���c�m/p40~43
���x�蒟(7��) / �@���q/p44~47
����������h���Ɠ����̊ϋq� / �n�ӕ�/p48�`48
�M�y��{�q���̏����`���v� / ���P�Y/p49�`49
�m����킩��Ȃ����x�ɂ��ģ / ����C��/p50�`50
�\�������w�����x���I�]���ւ̔��ȁx / ���{����/p51�`51
�f�梋���f��̑��� / �n����/p52�`52
������/p53~55
�V���ē�/p56~56
|
�P�P���A��g���X�ҏW���ҁu���w 57(11)�@�V�쓇�̗w�_<���W>�v���u��g���X�v���犧�s�����B
�d�v
|
�V�쓇�̗w�_<���W>�@ p.p1�`272
�V�쓇�̗w�_<�V���|�W�E��> �@�O�Ԏ�P �� p.p1�`43
�쓇�Ɍ����A���_�̑f�� �@�O�Ԏ�P p.p44�`57
�쓇�̐_�̂Ɗ؍��̛މ�--���̌�q
�@�@��(�Ђ݂̂�)�^�̛ޑc�_�b���߂����Đ��J�c�� p.p58�`75
�g�x��̂���ӂƉ��y�Ɍ��錀���@���P�Y p.p76�`97
�쓇�ɓ`���@�D��̉́@ ���эF�q p.p100�`108
�����Ɖ���̏\������ �@��l���O p.p109�`126
�Ñ�̗w�̌`��-�Ñ�̗w�Ɠ쓇�̗w�Ƃ̔�r���_ �|���d�Y p.p127�`146
�����̃����O�g�D�̎�����-�u�����v�Ƃ����s�ׂ� |
�@���u���~�S�g�v �c����H p.p147�`162
����v�����̃e�B���� ��� �w p.p163�`175
�{�Â̐_���Ɗ肢�� �@�V���K�� 1 p.p176�`192
���d�R�̃����O�g�D�@ �����H�^�s 1 p.p193�`209
���̂ɂ�����<�I>�̃��`�[�t�@�ʏ鐭�� p.p212�`227
�u�����낳�����v�̋L�ږ@--�L�ڂ̏ȗ��ƃI������
�@�@���{���������߂����� �g�Ɗԉi�g p.p228�`245
�쓇�̗w�Q�̒��̃I����--�u�쓇�̗w�听(1)
�@�@������я�v�ɂĂ炵�� �l�c�q p.p246�`259
���d�R���w�̉��y�`���Ǝ��` ����� p.p260�`272 |
�P�Q���A���ꕶ������n��40���N�L�O�� �w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 25(2)(72)�v���u��㊕�������v���犧�s�����Bpid/4437787�@�@�d�v
|
�͂��߂� / �O�Ԏ�P
�_���� �����w�_�l�� ����Ì�T�K--�u��Ӂv�u���Ӂv�u�v�Ӂv / �O�Ԏ�P/p11�`21
�_���� �����w�_�l�� �̗w�Ɍ�����l�ɂ���--���z�E���E���E���E��x / ���a�c�����q/p22�`50
�_���� �����w�_�l�� ��Ƃ̐߂�����Q--������Z�̂̐��� / ����d�N/p51�`70
�_���� �����w�_�l�� ���̃��`�[�t--�������遄�𒆐S�� / �_��^��/p71�`126
�_���� �����w�_�l�� �E�V�f�[�N�̉̂Ɖ����̊֘A�� / ����w�v/p127�`154
�_���� �����w�_�l�� ���̂ɂ����鎩�R�̃��`�[�t--�u����炳(���炳)�v���� / �ʏ鐭��/p155�`180
�_���� �����w�_�l�� �{�Ó������̔N���s���T��--�̗w�Ƃ̊֘A���߂����� / �㌴�F�O/p181�`218
�_���� �����w�_�l�� �k�����Љ�l �{�Ó��떓�̐_�̕��(2)�u�䕗���߁v�̃j�K���ƃs���[�V / �V���K��/p219�`254
�_���� �����w�_�l�� �|�x���̎�q���Ղ̗̉w--���J�Ɖ̗w�̑��ւɂ��Ă̗\���I�l�@ / �g�Ɗԉi�g/p255�`319
�_���� �����w�_�l�� ���d�R�����̋���(3) / �{�Lj��F/p320�`360
�_���� �����w�_�l�� �u�����v�̑��u--�u���ԏ����v�m�[�g / ��������/p361�`372
�_���� ������_�l�� ���d�R�����́u�킽�������v�u�킪�Ɓv�̓�̕\�� / �{��M�E/p375�`383
�_���� ������_�l�� �A�}�~���E�V�l�����l / ���Ԓ��m/p384�`420
�_���� ������_�l�� �{�Õ������C�_�̖��_ / �����H�^�s/p421�`439
�_���� ������_�l�� �����Ɠ��{��ƒ��N��̑Ώ�--�`�ԁE�����̎O�A�l�̖�� / ���a�c����Y/p440�`466
�_���� ������_�l�� �w�����낳�����x�̉�����--��ɂ����鏕���̗L���𒆐S�� / �����r�O/p467�`492
�_���� ������_�l�� �I�����̏����` / ����܂������Ђ�/p493�`537
�_���� �����j�_�l�� �{�Â̖��q�ɂ��� / ���K�����Y/p541�`557
�_���� �����j�_�l�� �ߐ����d�R�̖�l�Ɗ��_ / �V��q�j/p558�`580
�_���� �����j�_�l�� �w�k�J�Ԑ،K�]���Ɠ����x�j�}�����̊�b��� / �����i/p581�`598
�_���� �����j�_�l�� �V���K�|�[���̎����l--���h�ێ����𒆐S�� / �������ӂ���/p599�`618
�_���� �����j�_�l�� �j���Ƃ��Ắu�䓖���䍂������[���ϋL�v�ɂ��� / ��l�G��/p619�`640
�_���� �������E�|�\�E�����_�l�� ���ꖯ���j�� / ����O/p643�`659
�_���� �������E�|�\�E�����_�l�� ���D�̎��� / ���P�Y/p660�`678
�_���� �������E�|�\�E�����_�l�� �����Y�̌|�\--�u�X����̋����Y�v�𒆐S�� / ���{/p679�`707
�_���� �������E�|�\�E�����_�l�� �v�ē��{�\�̉��l���˒|�j / �{��K�g/p708�`722
�_���� �������E�|�\�E�����_�l�� �哇�̓� / ���J�c��/p723�`739
��z�^ �ɔg���Q�搶�ƒ��i�̎v���o���ꂱ�� / ����F�q/p743�`751
��z�^ �v���o�����ƂȂ� / �����N/p752�`761
��z�^ �\�N��̑z�� / �������K/p762�`768
��z�^ �c���p���搶�̎v���o / �R������/p769�`774
��z�^ ���̎v���o--�����������l���� / �㐨�����q/p775�`780
��z�^ ���E�����Y�̂��� / ���K����/p781�`785
���� �w���ꕶ���x������ ���\���Z�� (���a�O�Z�N�l���\�Z�O�N�O��) / ��ؘa��/p856�`786
���Ƃ��� / �g�Ɗԉi�g/p857~858
���M�҈ꗗ/p859~861 |
�P�Q���A��ÍN�Y���u�_�X�̌Ñw�@�P�F�����j�����N�j : �v�����̔N���s��
�i1�j�v���u�j���C�Ёv���犧�s����B
�@�@�@�@145p �@�@�����F��㊌����}���فF1002062881
|
�ӎ��̉萶��
�t�o���N
���� |
���E���̏���V��
���E���̎��n�V��
�E�v�}�[�~�L |
�s�[�}�b�e�B
�n�e�B�O���e�B
����_���̎� |
�P�Q���A�u�|�\ 31(12)(370) �|�\�w�� �� �|�\���s�� 1989-12/pid/2276659/1/1
|
����<���W>/p10~38
��p�ʂƉ��o--��i����̏ꍇ / ���ѕێ�/p10�`18
���ʉ����s�������̂䂭�� / �F����o�j/p19�`29
�\�ʂƖ����|�\��--�ԍբ��S��Ɨw�Ȣ�ԑm��̊W���� / �㓡�i/p30�`38
�܌��M�v�̐��E(��ܘZ)�����(9)�Ί_���ł̖̍K / ������/p6�`
<��>�����҈琬�̏�� / �O�����Y/p9�`9
<���]><���D�ێR��v�̖���>����K�Y��
�@�@���w�o�D��ێR��v�̐��E�x / ��،�/p39�`40
�����蒟(10��) / ���c�m/p41~44 |
���x�蒟(9��) / �@���q/p45~48
������Ȃ�̂��߂ɤ�N�̂��߂ɣ / �n�ӕ�/p49�`49
�M�y��Đ�q�q�̃��[�r�����y��ܣ / ���P�Y/p50�`50
�m������j�I�Ȍ������̃X�X��� / ����C��/p51�`51
�\������������ȑO�̌Í�Ƃͣ / ���{����/p52�`52
�f�梉f��u���̂����� / �n����/p53�`53
�Έ䏇�O������Âԉ� / �����G�Y/p54�`54
�ē�/p55~56
�E |
���A���̔N�A�O�،����u���d�R�����̐l�X : ����l���p���v���u�j���C�Ёv���犧�s����B�@�@
|
�V�����̐�o�ҁE���쎢
���d�R�����̕��E��ɏ�i�c
���������w�̑n�n�ҁE�{���c�s |
�s�ł̋��y���y�E�{�ǒ���
��M�̈������l�E�ɔg��N
�����|�\�����̊J��E�{�nj��� |
�����̐����j��Ԃ�E�{�镶
���̖��O���l�E�Γ��p��
���d�R�����̌p���Ɣ��W�E�q�쐴 |
���A���̔N�A�L���鑺�q�ǂ���琬�A�����c��ҁu�Ă�!�L����̐��N : �������N�x
�L���鑺�̂ӂ邳�Ƒn������ �W�v���u�L���鑺����ψ���v���犧�s�����B
|
��1�� �L���鑺���N���ی�(��p�K��) ��1�� �S����q�ǂ��G�C�T�[�܂�
�t�^ ��9�� �L���鑺�q�A���O���C(�o�����E�{�茧�k�����K��)
|
���A���̔N�A����S���܂���s�ψ���ҁu����S���G�C�T�[�܂� ��34��v���u����S���܂���s�ψ���v���犧�s�����B
���A���̔N�A������q���u���{���q�̈�A���I�v 1989(89) p.92-92�v�Ɂu�������x�̕��Ɨx�̋Z�@�v�\����B�@�@
���A���̔N�A�����ݗ��Y,������q���u���x�{ 1989(12Appendix) p.2-6�v�Ɂu�^�x�̍\���ƋZ�@�ip2�j�@�������x�̌n���ip3�`6�j�v�\����B�@ |
| 1990 |
�����Q�N |
�E |
�P���A���������u���������� (1)(256) �v���u���傤�����v���犧�s�����B�@pid/2803112
|
���W�\�\���x //p4~18
���k��\�\���ǂ邱�ƁE���邱�Ɓ\�\���x��܂ނ��� / �Ԗ�����C ;���c� ;�����B�} ;�u�c�[�q ;���؏�/P4~11
���ʂȂ镑�x�̓��� / �˕����/p12�`13
���x�E�̌������l���� / ���`�ߎq/p14�`15
���x�̍��ی𗬁\�\���ĕ���|�p�𗬎��Ƃ��� / ���c�ꕽ/p16�`16
���炽�߂ď��v�搶�̈̑傳�������� / �R��˓�/p17�`17
���x�������쌻�ꂩ�� / �ÒJ���O/p17�`18
�s���{���̃y�[�W�\�䂪���̕����s��(33)���a�Ŗ��邢���͂��鉫�ꌧ�̎����߂����� ���ꌧ / ���璡������/p19�`21
�s���{���̃y�[�W�\���F���锎���فE���p�ُЉ�(14)�[���̎��R������������
��t�������������� / �X���o/p22�`23
�s���{���̃y�[�W�\����2�N�x��������������ē�(1) //p24�`24
���{,���ە����𗬍s���v������� //p25�`25
�����������\�������N�x�����U����c�ɂ��� //p26�`29
��
��������j���[�X //p31~31
|
�Q���A�c�䓙�Εҁu�G�����|���@�� ��39���@���W ��������@�v���u�i�ߔe�j�����s���v���犧�s�����B
�@�@�@�@�����F��������}���ف@137p
|
�S���� �������
���̐��������Ƃ��̐��U ������
�����搶�Ƃ��̒�q���� ���a�c�^�~
�R���̎��R���������搶 ��Ïƕv
�V�ߖ��D�̐l�������搶 �{���� |
����Ȃ����R�����������t�̎v���o ���l�^��
���R�E�̑�剀���^�����[ �Ɖ��Ƙa
�����搶�̎v���o �V���F�a
�����j�^�����[�������搶 ���Z�c�q
�F���̐m�ҁu��牥�v���Â� ���]�� |
�w�E�Ŗ����������搶�̂��� �����^�}
�킪���h����t������^ ��������
�������N��
�E
�E |
�R���A�ߋE��w�����w�������ҏW�u�������� 2 <���W>�C�m�[�̖����v���u�ߋE��w�����w�������v���犧�s�����B
|
<�ʐ^>�C�m�[�̋��v�@��ÍN�Y�@ p.235-242
�C�m�[�̒n�`�ƒn�� �@���ܐL�O,�n�v�n���@ p.243-263
�u�C�m�[�v�̖��� �@������G�@ p.265-292
�X�N����уX�N�K���X�ɂ��� �@�{��K�g�@ p.293-305 |
�C�m�[�̊�(���C����)�E����҂̂��ƂȂǁ@�V�_���E�@ p.307-333
�Ί_���C�m�[�̐��������L �@��c�Òj�@p.335-350
�q���M�ƃO�[�U�@��{����@ p.351-364
�C�_��̗R�� : �X�N�̗���� �@�J�� ����@ p.365-378 |
�R���A�_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (7) �v���u�_�ˏ��q��w�j�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4424473
|
�_�� �t�����X���V�������ܐ��̈�Y�ژ^�ɂ݂�ߕ�����/�������K/p1�`29
�j���Љ� �O�Z��y���̑g�D�E���� / �R�{�l�Y/p30�`50
�j���Љ� ���{�莛�������W�j�� / �m���芰/p51�`69
�j�w�Ȃ����/p69~70
��\��j�w��C���s--���l�E���q�E�������ʂ�K�˂�/�����f�q/p71�`75 |
���m�j�[�~�������C���s�ɂ���/���m�j������/p76�`88
�C�m�_����� ���a63�N�x/p89~89
���Ƙ_����� ���a63�N�x/p89~91
�G���E�}��/p91~93
�E |
�R���A���ꌧ�����U����������يǗ����j���ҏW���ҁu����Č��� (1) �v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@�@6, 139p �@�@�����F��㊌����}���فF1002084240�@�@�@pid/2212079
|
�n���ɓ����� �Î�� �Ɉ�
����Ăɂ��� ���t�c �~�^ 1
�i���� �։��w����āx�j �� �N�^�� 121
�������㒆���E�����W�̋M�d�Ȍ�����-�u����āv- �� ���^�� ���� �W���^�� 13
�w�����낻�����x�̊C�O������(1) ��� ���^ 19
�i�����v�|��̗w���q�⒆�I�C�O�������i1�j �� �N�^�� 133
�q�j���Љ�r
���������j���Ċق̗����W������̐V�j���ɂ���
�@�@������ �����Y[�ق�]�^ �R�c�`���^ �� �N�^ 37 |
�i�����v�| �֘����������j���ĊٓI�����j�� �� �N�^�� 135
�~�ΐ����̓����ɂ��� ���� �����^ 55
�i�����v�| �֘��~�ΐ����I���i�j �� �N�^�� 139
�q�����r
�w����āx�̌����}���وڊǎ��̐V���L��(���a���N) 69
�w����Ėژ^�x 77
�w����Ėژ^�x�ɂ��� �x�� ��p�^ 77
����ĊW�����ژ^ �x�� ��p�^ 101
�t�^�i�W�K���E�ҏW�ψ�����j 115 |
�R���A�g�Ɗԉi�g���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 3 p.1-90�v�Ɂu�I�������������<���������>(����)�v�\����B
�R���A���эK�j���u���s�����w�I�v. A, �l���E�Љ� 76 p.155-176�v�Ɂu���ꌧ�������ӕ~�̎������v�\����B�@ �iIRDB�j
�R���A���ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (15)�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@pid/7960804
|
���\�����������̓W�J / �㌴���P/p1�`42
�g�x�u�萅�̉��v�̌����ʖ{�̍l�@--���Ɏg�p���y�𒆐S��/���Ԉ�Y/p43�`97
���Q�̗ϗ��Ƙ_��--�g�x�u�썲�ۓG���v�𒆐S�Ƃ����l�@/��������/p98�`114
���z���H�Ƃ̐ԓ_�E���_�E�_�ɂ��� / �����/p115�`121 |
�y�n�����������ƊW���� / ��]�F�q�v/p122�`139
������j�W��v�_���ژ^(1989�N /�Ί_����/p140�`201
��㔪��N�j���ҏW������/p202�`203
�������{�������p��/p204~204 |
�T���Q�R���A�ߔe�s����قɉ����āu�\�Ƒg�x��r�ӏ܉� : �ϐ����E�\�]���Î�/�g�x�ݍΓG��
��2��v���J�����B
���A���̔N�A���Ԉ�Y�ҁu�\�Ƒg�x��r�ӏ܉� : �ϐ����E�\�]���Î�/�g�x�ݍΓG��
��2��v���u�u�\�Ƒg�x�v��r�ӏ㉉���s�ψ���v���犧�s�����B�@ ��ÁF�u�\�Ƒg�x�v��r�ӏ㉉���s�ψ��� �����R慉� ����|�\�j������@�@�����p���t���b�g
�T���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (11) �v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B�@pid/7959561
|
�����x��̎n��--������a���̎��Ⴉ�� / ��Αוv/p1�`20
�u��q���v�̌`��--���̏��͂Ƃ���,�n��̏@��������
�@�@���|�\�ւ̐g�̓��@ / �X�K���v/p21�`43
�ߑ�̔_���ɂ�����l�`��ڗ�--���s�{���́@ |
�@������𒆐S�Ƃ��� / �r�c�~/p44�`72
�����哇�}�����F�h�̔����x�� / ���c��/p73�`88
�u�ɐ��_�y�̍l�v�{�c���� / ��c��/p89�`94
�E |
�U���A�q�쐴���u���d�R�̂��� : �ԁX���E�R���E���J�E���j�v���u���`�܂���v���犧�s����B
�@�@�@682p�@�}��17���@�����F���ꌧ���}���فF1005889603�v
|
���ɂ����� �Ί_ �Ɂ^��
�܂����� ���ʂ��邨�Ԃ̊�@
�}��
��w�M�T�� �B�쏔���̊�w�M�T��
���d�R���ԁX�����ɓ��R��
���Ԃ̑����E���ށE�g�D ���Ԃ̑����ƕ��ށ����Ԃ̍��J�ƊǗ��̑g�D
�W���L�̉�� �u���d�R�����L�v�A�u���d�R���R���L�v�̐���
�u���d�R���刢��R���L�v
���Ԃ̍��J ���Ԃ̍��J�o��鑺�̗�
��p�������̍ՋV�K�� ��p�ڏZ�҂̖L�N��
�_�ЁE�����E��� �_�ЁE�����̓�Q ���ԂƐ_��
��i�����Ƃ��� ��앶�� ���ԂƔ_�k�V��̓�Q
�_�ϔO�̖�� �_�ϔO�̖�� �_�ɂ��l�ԎЉ���̕ێ�
�_�X�̝| �m���E�c�J�T �_�J�E�_�j�E�_��
���^�Ɛ_�����茻�� �푈�Ɛ_�̑��� ���R��M����S
���Ԃ��߂��鏔��� ���d�R�̂��Ԃ��߂��鏔��� |
���d�R�̎��@(����)�E�����E������
���Ƃ���
�ʐ^ (�ӎ�)
���� �Q�l����
�q�]�H�r
���Ԃ̌f�z
�Ì��̃T���_���J
�C�[���B�J���U(�����)
���Ԃ̕���
�u���[�v�ɂ���
�B(�Ђ�)�̕����̓s�[
�u����v�l
�����Ȃ�̏@��
�{�Â̂��ԉ��N
�ԃ}�^�[�_���̓`��
���ԍr�炵 |
�U���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (29)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@�@pid/6067736
|
�̊_�Ƃ��̂Ђ낪�� / �������q/p4�`9
�A�W�A�̉̊_[�Ɨt���ётɉ�����] / ����m��/p10�`15
�����E����̉̊_�I���E / ����w�v/p16�`23
�������������n��̉̊_[�̊|���̗R�������߂�] / ����h/p24�`31
�^�C���̏��������̉̊_ / ���c���q/p32�`35
�X�ɂ����܂���|�J
�@�@��[�p�v�A�j���[�M�j�A�̒j�����̃��b�Z�[�W] / �R���C/p36�`41 |
�؍��̖L��F��̎�p�I�s���Ɠc�A�� / �э݊C/p42�`48
�p���g�D��[�}���[�����̋L����] / �c���j/p49�`53
[�A��]���E�����s�s�̎s����(6)�L�� / ������F/p54�`65
�Q�l�}��/p65~65
�}���Љ�/p66~66
�E
�E |
�U���A�|�\�w����u�|�\ 32(6)(376)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276665/1/1�@�@�d�v�@�@�V�O�O�~�@
|
������<���W>/p9~38
������裂̌Ñ㎏--�|�\�����̋N�_ / �ɓ��D�p/p10�`16
�_�y�ɂ������Ă鉉�o / ���䐳�O/p17�`24
����ɂ������Ă�̋V��ƌ|�\ / ���w/p25�`31
�H�R������Ɠc�V�т� / ���q�v/p32�`38
��t����{��գ(��Z��)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ;�F����o�j/p6~7
<��>��Ă裏ȗ����� / �O�����Y/p9�`9
<���]>�����ۗY���w�Öʂ̔��x / �㓡�i/p39�`39
�����蒟(4��) / ���c�m/p40~43
���x�蒟(2�����{�`3�����{) / �@���q/p44�`47 |
������g�E�q�匀�c�̕���� / ������/p48�`48
�M�y�u�C�B�̏d�݁v / �˓c��/p49~49
�M������ܤ�ߖڂɑz��� / ���`�ߎq/p50�`50
�\����������̐���� / ������Y/p51�`51
�����|�\����w��j�Ə�� / �����G�Y/p52�`52
�f�梓V�˥���V���̕���� / �c�R�͍�/p53�`53
�|�\�w���� / ���ʐM/p54�`54
�|�\�w��K��/p55~55
�V���ē�/p56~56
�E |
�X���A���эK�j���u���s�����w�I�v. A, �l���E�Љ� 77 p.45-59���s�����w�v�Ɂu�w�Z���y�֖������y������ɂ������Ă̈ꎋ�_�v�\����B�@
�iIRDB�j
�X���A�w��㊕����x�ҏW���� �u��㊕��� = The Okinawa bunka 26(1)(73)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437788
|
�w�����낳�����x�̏����u���v�Ɓu�́v(��) / ���Ԓ��m/p1�`16
�I�����̖����̊i / �R�邠���/p17�`30
�I�����̓����̌`�Ԙ_ / ����^���P ;�^�쉮����/p31~44
���_"�R�̃t�V���C"���߂����� / �㌴�F�O/p45�`73
��������̒����I�F�� / ���e��/p78�`104 |
�y�ꌹ�U��z"�����"��"�M����" / �{��M�E/p74�`75
��11��u���ꕶ������܁v���\/p105�`107
�V���Љ�E���s�j���[�X / �g�Ɗԉi�g/p16�`16,75�`75,124�`124
�������/p108~124
�E |
�X���A�r�{�������u����̗V�s�| :�� �`�����_���[�ƃj���u�`���[�v���u�Ђ邬�Ёv���犧�s����B
�@ �@�@���`�����_���[(�����Y)�@�@�j���u�`���[(�O����)
�P�O���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 91(10)(1003)�v���u���w�@��w�v���犧�s�����B�@�@pid/3365642�@
|
�ߚ��V��̈�� / �V�C//��/p1~17
�u���{��ًL�v����u�O��G�v��--�̓`���o�H�̈�l�@/
�@�@�����эG��/p18�`29
�k�k�b���l ���Ĕ�Ȃ���� / ��슮�O�Y/p30�`31 |
�u�ɐ����ꑝ�I���v�̌���-���Ɨ��u�Ò��v�Ƃ�
�@�@���֘A�𒆐S�Ƃ���/��N�v/p32�`46
�u����̗̉w�Ɖ��y�v���c���q / ���Ԉ�Y/p47�`52
�u���e���A�����J�̐V�����`��-<��̕���>�̂��߂Ɂv������/�쑺����/p53�`56 |
�P�O���A��ÍN�Y���u�_�X�̌Ñw�@�S�@���K����S : �p�[���g�D���{�Ó����v���u�i�ߔe�j�j���C��
�v���犧�s����B
�P�P���A�␣��,�R���ӈ�Ғ��u����������T�� : ���|�E�����E���j����̃A�v���[�`�v���u�C���Ёv���犧�s�����B (�쓇�p��, 56)
|
�����̕��Ɠ`�� : �V���|�W�E�� / �|�퐭��, �␣��, ���ѕq�j
����^���ۓ��̌Ñw : �쓇�̓`������� / ���c�W
�ߌ��̎��� : �������b�Q�̈�l�@ / �R���ӈ�
����������ōl���� : ���ꂩ�牽�������邩 / �r�{����
�����ɂ�����ߑ�m���l�̖��w�� / ����w�v
�����O�g�D�̐��b�� / �떓�b�� |
�����̖��� : ����Ɣ�r���� / ����d�N
�u�����̏㍑���L�v�ɂ��� / �R������
�����́u���ƕ����v�j���ɂ��� / �|�퐭��
�����̏C���E�N�`�Ȃǂ̎��� / ���x�d��
��E���̖��Ԑ��b / ���Q�v�q
�E |
�P�P���A�u�����Љ��v�ҏW�ψ���ҁu�����Љ�� 34(11)(412)�v���u�{��Ёv���犧�s�����B�@�@pid/6052825
|
������� �������ފw�K�� / �㓡�a��/p5�`5
������--�w�ԗ͂����<���W>/p6�`48
90�N��̒n�攎���ّ� / �����V/pp6~13
�Z���̋��߂锎���ّ� / �n�ӕێq/pp14~21
���s��̎��R�����ɂ���--
�@�@�����s���N�Ȋw�ق̎��H / ��{����/pp22�`32
���p�ك�-�N�V���b�v�̉\�� / �������T/pp33~40
"���a������"�̌���Ɖۑ� / ������/pp41~48
�������̕��i / �Õz�v�W�i/p50�`51
���a����Ǝ��� / ���c�G�Y/pp52~57
�h�L�������g�Љ����H�j<����>-2-"�ނ�"�̍��Z�ʐM����-- |
�@�@���㑾�����w�Z�ʐM���狳�畔�̊J��҂��� / �呺�b/pp64�`76
�ǎ҂̃y�[�W--�ǎ҃��r�[ //p62�`63
�{--�j���[���[�N�ߑO0�� ���p�ق͖���Ȃ� / �V�c�G��/p58�`59
�R�~���j�e�B���̌����ق̕ϗe(��) / ������w�����ٌ�����/p77�`89
�V���[�Y���H�Z�p--�N�̂��܂��_(3) / �{�c�a�F/p92�`95
�f��--�~�~�̉ċx�� / �R�c�a�v/p60�`61
�X�|�[�c�̑� / �J�������Y/p49�`49
�k�W��l--���k�̎Љ����l���錤���W�� //p90�`91
�����R�[�i�[ //p96~97
�БS������� �ҏW�R�[�i�[���� //p98�`100
�E |
�P�P���A�|�\�w��ҁu�|�\ 32(11)(381)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2276670
|
�另�Ղƌ|�\<���W>/p10~33
�{��̗w�����̋@�� / ������/p10�`16
�������̈Ӌ`--�V�當���w�̗��ꂩ�� / �q�ѐ���/p17�`25
�另�Ղ̍\���V�_ / �g��T�q/p26�`33
��O�c�̖��t���s(��)�(167)�܌��M�v�̐��E / ������� ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\--��茧 / �剮����/p34�`47
<��>�Ă�̍Ղ�̍Đ��Ǝ� / �O�����Y/p9�`9
<���]>�q�쐴���w���d�R�̂��ԁx / ���F�M/p48�`48
�����蒟( 9��) / ���c�m/p49~52 |
���x�蒟(8�����{�`9�����{) / �@���q/p53�`56
������匀�ꉉ���̕ϗe� / ������/p57�`57
�m�y�u��NHK�w���W�I�[��ցx�������v / �{���r�v/p58~58
�m����]�����ɂ��閯�����x� / ���c�ꕽ/p59�`59
�\���������ߌ����̉�z� / ������Y/p60�`60
�����|�\����w��]������E�Ǖ��գ / �����G�Y/p61�`61
�e���r����㌀�̃p�^�[���E�o�̎��ݣ / �u��M�v/p62�`62
������/p63~63
�V���ē�/p64~64 |
�P�Q���Q�P���A���a�c�^�~���i���킾 �����j�S���Ȃ�B�@�i���N83�j
�P�Q���A�{�闬�{��\�P�����������ҁu�{�闬 �{��\�P���������� �l�l�̉� : �ÓT�E�G�x��ւ̂����Ȃ��i�����p���t���b�g�j�v���u�{�闬�{��\�P�����������v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@ �Ƃ��F����2�N12��7��(��) �@�Ƃ���F�����V��z�[�� �@�@1���@�@�����F��㊌����}���فF1004692057
�P�Q���A�J�쌒��ҁu���̖������v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@ (���{�������������W�� / �J�쌒���, ��5��)
|
�C���̂Ȃ��� / ���C���g
�Y�����̔����� / �Έ䒉
�Y���̖��� / �J�쌒��, ���R��悢
����̊C���E�C��E�C�݂̒n�� / �쓇�n�������Z���^�[��
����̃T���S�ʊC��̒n�� / ���ܐL�O
�m�O���̊C�ݒn�� / �V�_���E
���d�����̒n��
�n���쑺�̗��ƊC�̒n�� / ��쏼�g |
���H�̖��̂ƒn���ɂ��� / �{��K�g
�^���C��̒n�� / ���c�NJ��t
�r�ԓ��ɂ�����C�ݕ��̏��n���Ɗ����� / ���O����
�� / �����O�N
�����哇�̊C�ݒn�� / �q��N�Y
�쓇�̃T���S�ʂƐl / �n�v�n��
�쓇�̊C���E�C�݁E�C��̒n��(���) / ���ܐL�O
�E |
���A���̔N�A����S���G�C�T�[�܂���s�ψ���ҁu����S���G�C�T�[�܂�
��35��v���u����S���G�C�T�[�܂���s�ψ���v���犧�s�����B |
| 1991 |
3 |
�E |
�P���A�u�����������v�ҏW�ψ�����u���������� (99)�v���u�����������w��v���犧�s�����B
�@pid/6024843�@�@�@�d�v
|
�o�b�`���}(�\�����) / �_�c�N�K/p1�`1
���ۗx��̕ϑJ / ����d�N/p2�`10
�w�u�������܂��ˁv�͉̂��̂��x���߂����� / ��������/p10�`15
�\�ܖ�s�� / ��{��/p15~19
�͂Ȃ��̘b(�l) / ���c�r�u/p19~20
�ۃ}�c�a�̓`��(�l) / �{�c�F/p20�`27
�ӑm�c�e--�u�ߐ����������v�ɂ݂� / ���c�/p28�`28 |
���e���猩���c�̐_�� ���c�_�̗ގ��_�Ƒ���_ / ��щh��/p29�`30
�u�j�̖v�ɂ��� / ���c�/p31~34
�����V�� 6������ / ���蕽/p34�`38
�u�_�S�Ղ�v�l / ���c�/p39~39
�w��̊���/P40~
�ҏW��L/p41~
�E |
�P���A�A�����Εҁu�_�X�̍��J�v���u�M���Ёv���犧�s�����B�@ (�����C�̖����ƕ���, 2)
|
�_�X�̍��J / �A������
�؍��̑��Ղ� / ���g��
����̌�ԐM�� / ��{���v
����k�V���E�l�Ղ̋V���� / �ÉƐM��, ���{�_��
�����̐_�Ղ� / ����d�N
�C�U�C�z�[ / ��ÍN�Y
�{�Î떓�̃E�K�������J / �{�i��
��p�̑��ƍՂ� : �k���q�Ƒ��̏ꍇ / �A������
�N���s���̔�r���� : �����̔N���s���̒��N�A
�@�@�����{�ւ̉e���ɂ��� / �˓c��S�q
����̑����Ɛ_���� : �V�k�O�E�E���W���~�̍��J�\�� / ��Ð��v
�암�����ɂ�����ے��I�_ / �������� |
����̍j�� / ���~�ߎ�
�V�����J�̔�r���� : �����E��p�𒆐S�Ƃ����ʍc���
�@�@���a���Ղ��߂����� / �n粋ӗY
���[�_�� / �˓c��S�q
���^�̕ϊv���Ɋւ����̊o�� :
�@�@�� �V���[�}��-���J�_�Ƃ̊֘A�ɂ����� / ���X�؍G��
���� / ����N�F
�؍��ɂ�����_�ϔO�Ɛ��E�� / ����
���d�R�Q���ɂ����鎞�ԔF���̏��� / ��ؐ���
�����̕����m���Ɛ��E�� :
�@�@����n�����Ɋւ���c�_���߂�����/ �n粋ӗY
�E |
�R���A���{�̈�w��u�̈�̉Ȋw = Journal of health,physical education and recreation 41(3) ���x���Ȋw����<���W>�v���u�Ǘя��@�v���犧�s�����B�@ pid/6085869�@�@�@�d�v
|
���x���Ȋw����<���W>/p172~211
���W ���x���Ȋw���� �͂��߂̂��Ƃ� ���x�ƉȊw��
�@�@���ړ_�����Ƃ߂� / �X���͂��/p172�`173
���R�̂�����,���x�̂����� / �X���͂��/pp174~178
�����̗x��--��r�s���w�I���_���� / ��ߎq/pp179~183
���W ���x���Ȋw���� �g���[�j���O�Ƃ��Ẵ_���X--
�@�@���G�A���r�b�N�_���X / ���j��/p184�`190
���x�̊ӏ܍\��--�������x�𒆐S�� / ������q/pp191~197
�_���T-�̉���E��Q / �R�ۓN�v/pp198~203
�_���T-�ƌ��o���� / ���X�؏��� ;�@�c�� ;�ڍ�o/pp204~207
�Z���s-�Ƃ��Ă̕��x / �H�R�� ;�����肳/pp208~211
�X�|-�c�l�ފw�A���\���W--12-
�@�@���g�̋Z�@�ƃX�|-�c / �쑺���/pp215�`218 |
�^�������w�g�s�b�N�X-17-�\�ʓd�ɖ@�ɂ�蓱�o�����
�@�@���P��^���P�ʂ̊����d�ʂ̔g�`��� / �X�{��/pp219�`223
�z���̃g��-�j���O���� / ���{���P/pp225~228
�A�t���J�ɂ�����C�M���X�̐A���n�o�c�ƃX�|-�c����--
�@�@���ߑ�X�|-�c�`���̈�f�� / �Γc���K/pp233�`236
�����q���̓���(1990)-1-(�ی��w������)
�@�@��/ �̈� �� �Ȋw �ҏW��/pp238�`242
������|�[�g / �F�����O/p244�`245
������|�[�g �^�����䌤����|�[�g / �}��B��/p246�`247
���] �G�N�T�T�C�Y�A�t�B�b�g�l�X�A���N / ���j��/p243~243
���m�点 ���ē� //p236~236
���Ƃ��� / J.Y./p248~248
�E |
�R���A��Î������ꌧ�����U����������يǗ����j���ҏW�� �u����Č��� (2) p59�`71�@���ꌧ����ψ���v�Ɂu�w�����낻�����x�̊C�O������(�� ) �v�\����B�@pid/2212080
�R���A�@����w���ꕶ���������ҁu���������ȁE�������j�̌��� <���ԕ�>�v�������B
�@�@����2�N�x�����ȉȊw������⏕���ɂ�錤�����ʕ�
|
���ۊw�p�����̂߂������� : ��㊕����������̒����E
�@�@�������Ȓ����ɂ���/��Î�
�������j�̎��p / �����N
�����E�����̖����@����r : �����Ȃ̌��n�����܂���/ �N�䓿���Y
�u���D������<���E��>�W�j�v�����Ɍ����� :
�@�@���R�́u�`�d�Ən���v���̃p�[�X�y�N�e�B�� / ���]�F�i
����C�݂̕����i��(�\��) / ����O
���B�����ق̖����ɂ��� / �~�ؓN�l |
�����_���̋�ԍ\���𖾂ɂނ��� / ������
�嗤�Ɨ̕����𗬎j�l�@ / ���{���q
�����g���q�Ɋւ���C�E���H�̌��� / ����]
�������̓������ƕ��B�E�͖�E��p :
�@�@�������ɑウ�� / �������j
���������E�W���̔�r�������ԕ� / ���҉p��
�������쉈�C�̉��y���������{������
�@�����y�����ɑ���e�� : �Ȓ��̍l�𒆐S�� / ���s�� |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 26(2)(74)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437789
|
����ɂ�����n��j�Â���̓��� / �������i/p1�`11
���d�R�����̕���I�̗w--�����O�g�D��
�@�@�������^�̊ւ��𒆐S�� / �떓�b��/p12�`31
���̖̂����̊i / ��ÍO��/p32�`73
�w�����낳�����x�̏����u���v�Ɓu�́v(��) / ���Ԓ��m/p74�`99 |
�k�����Љ�l �w�n��x�Ɖ���̓��e�҂���
�@�@��--����ߑ㕶�w�������@(3) / ��������/p100�`108
�V���Љ�E���s�j���[�X / ��������肱/p11�`11,109�`110
�w��j���[�X/p73~7
�E |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 4 �v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
�����哇�}������O�c�̔����x��́@ �v���c�W p.1-87
���ꌧ���|�p��w�����������b�� p.89-94 |
�I����������ꗗ�k���ʁl �g�Ɗԉi�g p.1a-101a
�E |
�R���A���эK�j�����s�����w�ҁu���s�����w�I�v. A, �l���E�Љ� �@ (�ʍ�
78) p.p127�`156�v�Ɂu���ꌧ�������F�Â̎�����--���G�C�T�[�̉��y�̊�{�I���i�ɂ��āv�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A����m���ӔC�ҏW ; [���c���q�ق����M�u���ԐM�ҁv���u�������Ёv���犧�s�����B
�@�@�@(�������y�p�� / ����m���ďC ; �N��N�j [�ق�] ��, 5 . �V��Ɖ��y ; 2)
|
�Ђ�����ȋF��̉� / ����m��
�A�W�A�̈��V��u�c�A�₵�v/���c���q
�J���[�V�����̏t�Ղ�E�W���V�Ƃ��̉��y/�����ߎq
�t�@�O�A�[ : �t����ԃz�[���[�Ղ�̉̐�/���ؗS�q
���m���k�݊y�S�u�ԍՁv�̉��y/�������O
|
�V��Ƃ��Ă̕��A�u���v��n��o����/�J�O
�ޑ��V��Ɖ��y/������
�A�T�b�N���̃K���E�A���V�� : �o���̃T���M�������߂���l�@/ ���D�q
�u���J���_�v�̋V��Ɖ��y : �����A�t���J�̃C�j�V�G�[�V�����V��̌���/�˓c����
���l�p�[���E�����u�[���̋V��ƃ����h�D�� : �V�T���V��ƃg���V���V��/�n��Y�i
|
�R���A���ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (16)�@�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@pid/7960805
|
�v�n�����Ɩ����剮�q�̓��� / ���Ǒq�g/p1�`16
�����������ᒠ / ��]�F�q�v/p17�`32
�ږ��Ɋւ���V���L��--����36�E37�N / �c�`���a/p33�`61
��R�Ə����ɂ�����ƕ��W�����ɂ��� / �����/p62�`69 |
�g�x�u�������^�Ìˁv�ɂ��� / ���Ԉ�Y/p70�`76
������j�W��v�_���ژ^(1990�N) / �Ί_����/p77�`137
�j���ҏW������(����Z�N)/p138�`139
�������{�������p��/p140~140 |
�R���A�ߋE��w�����w�������� �u�������� 3�v���u�ߋE��w�����w�������v���犧�s�����B
�@�@�@290p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004667653
|
<���G�ʐ^>�L���C�̕��i �� ���Òj p.1-8
�Ñ�C�l���̍��� : �X���E�c�c�E�A���E�A�I���߂����� �J�� ���� p.9-32
����K���čl ���X�� �N�� p.33-61
�ɓ������̃J�c�I���Ɖ��z : ���̗��j�Ɩ��� ���� ���� p.63-79
�w��̓��{�j�x���ēǂ��� : �w�另�Ղ̐����x��L �J�� ���� p.81-90
�L���C�̊����� (�o�w) (<���W>�L���C) �_�� �P�� p.93-131
�F�{���F�y�������ӂ̃X�L : ���n�I���@�E����̎c�� (<���W>�L���C)
�x�~ �K�O�Y p.133-139
������̓`�� : �L���C=�C���̎��Ԃƌo�ύ\������̈ʒu�Â��@ (<���W>�L���C)
�ӓ��� ���i p.141-160
�L���C�̋��������ɂ��� : �L���C�C�_�R�ى��ꋙ (<���W>�L���C) ����
���O�Y p.161-186
�L���C������ : �q�{ �K���̔������� (<���W>�L���C) ��{ ���� �fp.187-246
<���]�ƏЉ�>�s�s�����w�͐������邩 : ���ђ��Y���w�s�s�����w�x �q�Β��F���w�s�s�����_�����x
<���W> �X�I �Έ� p.249-253
<���]�ƏЉ�>��ё��ǒ��w���Ɛ� �C�ƎR-���{�̕����̈�x <���W>
�b�� ���V p.253-256
<���]�ƏЉ�>�|�c �U���w�Z�핪�̖����x <���W> ���R �a�F p.256-259
<���]�ƏЉ�>�|�c �U���w�c����J�Ǝ��쌋���x <���W> ���q �q�v
p.259-262
<���]�ƏЉ�>�{�� �����w�@�������w�x <���W> ��� ���� p.262-266
<���]�ƏЉ�>�X�I�Έ꒘�w�͌����̖����n���_�x <���W> �c�� �o
p.266-269
<���������>�w���d�R�̂��ԁx �q�� �� p.271-274
<���������>�w�C���Ɗ�-���y�̊����x ���Y �L�q p.275-278
<���������>�w���������w�m�[�g�x �� �B�� p.278-281
<�����ւ̎莆>�J�쌒�꒘�w�另�Ղ̐����x�ɂӂ�� ����N�Y p.283-286 |
�S���A����ƈ�w�̉�ҁu����ƈ�w 39(4)(454)�v���u�c��`�m��w�o�ʼn�v���犧�s�����B�@�@pid/6043642
|
�Ȃ���,��Ðl�ފw��<���W>/p302�`376
[������]����l���� / �r�c���D/p302�`303
���A�Ȃ���Ðl�ފw�Ȃ̂� / �g���b���q/p304�`310
�a�C�̐g�̂ɂ����鎩�� / �l�{��/p311�`316
��Â��x����Ƒ� / �쓈���R��/p317�`324
�f�l�Ö@�ƌ����Ȃ��� / ����G�v/p325�`332
�V���[�}�j�Y���ƈ��--
�@�@������́u���^�v�̏ꍇ/�勴�p�� ;���ۉp�E/p333~339
�̗͂̍l���� / �Έ䏟/p340~345
�I�����_�̏o�Y���� / �����x�q/p346�`352
�؍��̃V���[�}�j�Y���Ǝ��ËV�� / �����͏�/p353�`359 |
�@���ƈ�Â̐ړ_--���Ǝ��� / ���䐳�Y/p360�`366
�V��Ǝ����ς̕ω� / �ߓ����s/p367�`376
(���e) �����e�̐��h�C�c�K��L / �O�ؐÎq/p377�`382
���ꋳ��̃y�[�W
�@�@�@��(�����ȓ��ꋳ��ہE�������ꋳ�瑍��������)/ ����W/p386�`391
��Q�ґ�̐��i�ɂ��� / �����G��/p386�`389
�v���l�����-184-���H�������c����I���� / ����W/p389�`391
�J�����g�E�g�s�b�N�X / �����m/p383�`383
���] / ��^/p384~385
����ƈ�w�W�����m�[�g //p392�`393
�ҏW��L / �ێR�F��/p394~394 |
�T���A��Î����u�×����̎v�z�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B�@ (�^�C���X�I�� ; �U�E5)
�U���A�����Z�F���u�A���n���E���ތ��� = The journal of phytogeography and taxonomy39 p12-�@���{�A�����ފw��v�Ɂu���a�c���~���𓉂ށv����B
�V���A���c���q���u���m�_���@�������w�Ƃ��̎��Ӂv�\����B�@�@�@
|
�͂������\�����ɉ̂����߂ā\ / p1
���� �������w�Ƃ��̎���(I) / p13
1.���������̗��j�T�� / p13
2.���������Ɍ������閯�w�̕��� / p15
3.�������w�̉��y�I���i��ʂ��Ă݂����Ӓn��Ƃ̊֘A�� / p16
��1�� �����̐_�� / p27
1.�͂��߂Ɂ\�m���̐_�́\ / p27
2.�����̛މ́\�������y�w�I�l�@�\ / p37
��2�� �����̃C�g�D / p67
1.�͂��߂Ɂ\�����̃C�g�D�\ / p67
2.���V�G�̓c�A�̂̉��y�I���i�ɂ��� / p81
3.���V���̓c�A�̂̎��^�ƋȌ^�Ɋւ���l�@ / p108
��3�� �����̂��ׂ��� / p119
1.�͂��߂Ɂ\�����̃����O�g�D�Ƃ��ׂ����\ / p119
2.���i�Ǖ����̂��ׂ����\���K�̖��𒆐S�Ƃ��ā\ / p129
��4�� �����̔����x��� / p149
1.�͂��߂Ɂ\�_�ՂƔ����x��́\ / p149
2.�����哇�}�������m�̔����x��̉��y�\
�@�@�����^�ƋȌ^�̊W�𒆐S�Ƃ��ā\ / p153
3.������x�裂̒n�搫 / p164
��5�� �����̓��� / p187
1.�͂��߂Ɂ\�̂����ѥ�̎ҥ�̊|����̊_�\ / p187
2.�����̓��́\�������y�w�I�l�@�\ / p194
��6�� �������w�Ƃ��̎���(II) / p237
1.�V���[�}�j�Y���Ɖ��y�\�����̃��^�Ƃ��̎��Ӂ\ / p237
2.�Ί_�����ۂ̈��̉��y�\
�@�@���c����̂ɑ���l�@�𒆐S�Ɂ\ / p253
3.DIE VOLKSLIEDER AUF DEN AMAMI-INSELN / p275
�� / p289
�����o�ꗗ / p291
����ꗗ / p293
A List of Music Examples / p297
���� / p299
�ڎ� / p5
���G /
���� / p1
���� �A�W�A�̒��ɂ݂鉫��̉��y / p3
I �͂��߂� / p3 |
II ���ꉹ�y�̌���ƕ��� / p3
III �A�W�A�̒��ɂ݂鉫��̉��y / p6
�W �ނ��� / p18
���� ����̏����̗w�Ɖ��y�\���J�̗w�𒆐S�Ƃ��ā\ / p21
I ����Ɖ��y / p21
II ����̗̉w�Ƃ��̌n�� / p24
III ����̍��J�̗w / p25
�W �ނ��� / p79
��O�� �{�Ï����̛ޑ��ƛމ� / p93
I �͂��߂� / p93
II �{�Ó��̃J���J�J�����ƛޑ� / p95
III �{�Ó��̛މ́\��E�N�C�l��\ / p104
IV �r�ԓ��̃A�[�O�V���̜ߗ�̉� / p117
V �ނ��� / p129
��l�� �����̃��^�̐��b�Ɖ� / p137
I �����̐��b�Ɖ̗w / p137
II �����̃��^�ƃV���[�}�j�Y�� / p139
III ���^�̛މ̂Ɛ��b / p140
IV �ނ��� / p180
��� ��������˓��̖��w�\
�@�@���@���̗w�̖��𒆐S�Ƃ��ā\ / p183
I �͂��߂� / p183
II �m���̏@���̗w�\�I�����\ / p184
III ���^�̏@���̗w�\�މ́\ / p188
IV �����x�� / p193
V ���́\�O�����́\ / p197
VI ���ׂ�����q�炤�� / p199
VII ���̑��̖��w / p201
VIII �ނ��� / p203
��Z�� ������x�裂̒n�搫�\��ł����棂��߂����ā\ / p211
I �͂��߂� / p211
II �����x��̕��z�Ƣ�ł����壂̕��z / p213
III ��ł����壂̉̎��ɂ��� / p220
IV �����x��̉��y�Ƣ�ł����棂̉��y / p227
V �����x��̕��x�Ƣ�ł����壂̕��x / p239
VI �����x��ɂ�����O���̗w�̎�e / p242
VII �ނ��� / p250
�i�p�����j |
�V���A�|�\�w����u�|�\ 33(7)(389)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276678
|
�_�y��<���W> / p10�`30
<��>�ᔻ�Ɠ��� / �㓡�i / p9�`9
�_�F�l / �{�c���� / p10�`16
��B�̐_�y��--��㍑�̐_�y�̢������𒆐S�Ƃ���/�n�ӐL�v / p17�`23
�_�y�̂̉𖾂Ɛ_�y�̉𖾂� / ��c�� / p24�`30
��O�c�̖��t���s�w��܉�x���̓�(�ꎵ��)
�@�@���܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y ; �F����o�j / p6�`7
���{�̖����|�\-9-���ꌧ / �������� / p31�`44
�r�{�������w����̗V�s�|�\�\�`�����_���[��
�@�@���j���u�`���[�x / �ɓ��D�p / p45�`45
�{�c�������w���{�̓`���|�\�x / �����Ύq / p46�`46
�l�`����j������ҁw�l�`��ڗ�����j�x / �a�c�C / p47�`47 |
���c�������w�\�Ƌߑ㕶�w�x / �������H / p48�`48
�����蒟(5��) / ���c�m / p49�`52
���x�蒟(3�����{�`4����) / �@���q / p53�`56
������w�I�O���x�Ɖ��V���̍˘r� / ��{�Y�O / p57�`57
�m�y��I�y�������̓��ꗿ�� / �O�H���� / p58�`58
�m����R���N�[���������ς�� / �R�씎�� / p59�`59
�\�������~�ᖜ�O�Y�̎�� / ���N�� / p60�`60
�����|�\����䖯�w���ǂ��l���� / �������q / p61�`61
�e���r�CNN��GNN� / ����ˎO / p62�`62
������ / p63�`63
�V���ē� / p64�`64
�E |
�W���A���w�ٕҁu�n���̐��E (79)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@�@pid/1737956
|
�_�ƕ��̏o��\�\�s��̖��� / ��㐳/6
���{�̏@�����`�s�V���|�W�E���t / �������� ;��㐳 ;�~���� ;�͍����Y ;�Ì��G�L ;�R�ܓN�Y/28
�}���O���[�u�т̐��Ԍn�ƕۑS / ����a�F/48
���R�͑��l���D�ށs�V���|�W�E���t / ������� ;�~���� ;����a�F ;�͍���Y ;���c���� ;�R�ܓN�Y/68
��͓S����e�w���(3)�C���h�̃G���X�Ɛ_��(����1) / �R�ܓN�Y/120
�X�тƓ��{�l(11)�h�C�c�ъw�Ƃ̑��� / �k������/142
���c���j�̔���(12)����/�Y���̐��_�j����m�ƖіV�� / �ԍ⌛�Y/164
�V�ߥ���{�̕���(7)�Ƃ͂������� / �x�����b�q ;�͍����Y/88 |
�X���A�{�c�������u����̍Ղƌ|�\�v���u��ꏑ�[�v���犧�s����B�@ (�쓇�����p��
; 13)�@
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007200734 �@�Q�Q�O�O�~
|
��
�M�̏���
(����̐M��.���d�R�̐M��
�@�@��.�����̐M��)
����̍Ղƌ|�\
(����|�\�̕���
�C�U�C�z�[
�^�ߍ����̃J���u�i�K
�L�N��
�~��
�����}���J�C |
�����̔����x
�\�ܖ��
���NJԓ��̔������
�����
�ߍ�
���j
����̍s���ƌ|�\
(�c�A�ܖ�
�O���V�сE�l�~��
����
�_�[�g�E�_�M�E���[�^�J�r |
��V��
�N�C�`���[�x
�J��x)
�Ì|�\
(���x
�j���ƍj�̎�
���̗̂x
�N�G�[�i
�P���
�V�����J�l�R
�}�X�g�����E�،� |
�����Y
�w�ȁE�����E���q)
�O���̌|�\
(���,গ��D,���q��,�_�x,�ʼnԌ�)
�{���̌|�\
���d�R�̕��̓��F
�t��
����̌|�\-�����̌���Ɖۑ�
���� |
�X���A������w���J�u���ψ���ҁu������w�������J�u���@12: �������x�̐��E�@�`������Ƃ������` �v���u������w���J�u���ψ���v���犧�s�����B�@�@207p�@�@�@�@�����F��㊌����}���فF1002941134
|
�������x�̍L���� �O�� ���Y
�������x�̗��j ��� �P�Y
�ÓT���x�E�j�x�� ���� ���q
�ÓT���x�E���x�� ���� ���q
�g�x�ƌÓT���x �{�� �\�P |
�G�x��Ƒn�앑�x ���� ���q
���^�ƒ��t ���� ���q
�x��̈ߏ� �j�� ���q
�n�S�� ���Γs �~��
���{���x �Ԗ� �����K |
�C���h�l�V�A�̗x��̓��F ���� ���q
�^�C�̗x��̓��F ���� ���q
�������x���̍l�Ă����߂� ���� ���q
�E
�E |
�P�O���A���{��������ҁu���{���w��� ���ꉂ�� ���ꏔ���сv���u���{�����o�ŋ���v���犧�s�����B
719p
|
��
�}��
�f�ڋȈꗗ
�쐼�����̎��R�E���j�E����
1 ���R�ƕ��y�@1
�i1�j �n��
�i2�j �C��
�i3�j ���E�A��
2 ���j�@2
�i1�j ��j����
�i2�j �O�X�N���ォ�琭���I�x�z�҂̏o���܂�
�i3�j �����̐����Ɖ^�c
3 �����@3
�i1�j ���̂̕����̒��ɂ݂�쓇�����̕�����
�i2�j �����o�ς̒����琶�݂����ꂽ�S�̕���
4 ���{��̒��̉����@4
�i1�j �����͈̔͂Ƌ敪
�i2�j �����̕���
�i3�j �����̓���
�쐼�����̉��y�����T��
1 ���y�I�����@7
�i1�j �̂̒S����
�i2�j �̂̃W�������ƌ��n�ď�
�i3�j �����`��
�i4�j ���y�̏��v�f
�i5�j �y��
�i6�j �x��
�i7�j �|�\
�i8�j �`���̂����
2 ���ނƔz��@12
���ꏔ���̕��y�E���j�E����
1 ���y�@15
�i1�j ���y
�i2�j �C��
2 ���j�@16
�i1�j ��j����ƃO�X�N����
�i2�j �����̒a���Ɖ�������
3 ����̕����@18
�i1�j ���|
�i2�j �|�\
�i3�j ���p�E�H�|
4 �ŗL�M�ƍՂ�@20
�i1�j �ŗL�M�ƍՂ�
�i2�j �Ղ�
���ꏔ���̉��y�T��
1 �Ȏ�̕��ނƔz��ёI�Ȃɂ��ā@23
2 �ߑ�̖��w�j�[�`�d�ƕϗe�[�@24
3 ���w�̉��y�I���F�@26
�i1�j �y�킩�猩�����w
�i2�j ���y
����̗w�̓��e�E�\���E���`
1 �V��̗w�̓��e�E�\���@28
2 �V��̗w�̎��`�@29
�i1�j ��
�i2�j ������
3 �����̗w�̓��e�@31
4 �����̗w�̍\���E���`�@32
�q��`���r
�i1�j �Ӗ����e�̗ގ����C���@�I�ȈӖ��̓��ꐫ
�i2�j �Ӗ����e�̑ΏƐ��C���@�I�ȈӖ��̓��ꐫ
�i3�j �Ӗ����e�̗ގ����C���@�I�ȈӖ��̑Η���
�q��`���r
�y���E�̎��E���
I �q�ǂ��Ƃ̊ւ��
���ׂ����@37
�q��́@96
II �V��E�s���E�j��
�_���Ɋւ��́@115
�E���C�E�N�F�[�i�@115
�C�U�C�z�[�ɂ��ā@156
�A�}�E�F�[�_�@189
�e�B���N�O�`�@192
���̑��̐_���̉́@201
�����̍s���́@207
�����̍s���́@207
�P���ہ@207
�G�C�T�[�E�������@343
�|�\�ɔ����́@432
�����Y�@432
�ƍs���́@439
���O�F�[�i�@439
�j���́@447
�Ƒ���́@456
�O���@458
III �d���E���
��Ɖ́@469
�|�\��������Ɖ́@475
IV �����E�V��
�����́E�V�щ́@481
�~���[�N�j�[�@481
�����@498
�Ԉ����́@511
�J�`���[�V�[�@527
�G�x��́@547
���̑��̍����́E�V�щ́@572
�V���w�E���s�́@624
�V���w�@624
V �ÓT
�ÓT���y�@653
��@683
�Q�l�����@694
GENERAL VIEW ON THE NANSEI ISLANDS�@696
����
�Ȗ������@701
�n��ʉ����ҍ����@705
���������@709
���Ƃ����@715
�ҏW��L�@719
�f�ڋȈꗗ
I �q�ǂ��Ƃ̊ւ��
���ׂ����@37
1 ���̗����_ �k���l���������c�@39
2 �������[�̎q�� �k���l���������c�@40
3 �J�̎q�B�~��� �k���l���������c�@40
4 �N���Q��Ɓ[���[ �k���l���������c�@41
5 ���܂ɐQ��Ɓ[���[ �k���l����s�v�u�@42
6 �����[ �k���l���������c�@43
7 ����Ȃ���[ �k���l���������c�@43
8 ����Ȃ� �k���l���Ԗ������Ԗ��@44
9 �����Ƃ��[ �k���l���Ԗ������Ԗ��@45
10 �V�̉����� �k���l���������c�@46
11 �Ă��[���[�݁[��[ �k���l���������@46
12 �������� �k���l�������^�߁@47
13 ��܂����܂܂ł� �k���l�������^�߁@49
14 �����͐����ǁ[ �k���l���������ԁ@51
15 �������[����܁[�߁[����[ �k���l���������ԁ@52
16 ����̉��� �k���l���������ԁ@53
17 ���쉮�̂��܂��[ �k���l���������ԁ@54
18 ��� �k���l���������ԁ@55
19 �₠�� �k���l���������ԁ@56
20 ��[�܁[������ �k���l���������ԁ@57
21 �������[�� �ɂ��[�� �k���l�{�����l���@58
22 �ЂƂӂ��Ƃ��炶��[ �k���l�{�����ɖ�g�@58
23 �{�{�ʁ[��ʁ[�� �k���l�{�����ɖ�g�@59
24 ���肠�� �k���l����s�v�u�@60
25 ���[�������� �k���l����s�v�u�@62
26 ����ۂ���� �k���l����s�v�u�@64
27 ��������[�߁[ �k���l�ߔe�s�@65
28 �ȁ[����ȁ[���� �k���l�ߔe�s�@66
29 ����܂��Ă��[��[ �k���l�ߔe�s�@66
30 �ԓc�a�� �k���l�ߔe�s���@67
31 �����ȁ[�Ƃ̏Ă��Ɓ[��ǁ[ �k���l�ߔe�s��V��69
32 �����ȁ[��[�����ȁ[ �k���l�ߔe�s���@69
33 ���������������� �k���l�ߔe�s��V���@71
34 ���������������� �k���l�������l�@72
35 ������[���[�Ђ�[ �k���l�ߔe�s���@73
36 ���̎R���Ă� �k���l�ߔe�s�ِ�@73
37 ���\�L���� �k���l�ߔe�s�ِ�@74
38 �|�̒��̂��������낮��[�� �k���l���������c75
39 ����[����[�B�M�́� �k���l���������@76
40 �O�Y����[ �k���l�ߔe�s���@76
41 ���� �k���l�ߔe�s���@77
42 ���� �k���l���������ԁ@77
43 ���� �k���l�{�����ɖ�g�@78
44 ���� ����� �k���l�ߔe�s���@79
45 ����Ȃ�Ȃ� �k���l�ߔe�s��V���@79
46 ����Ȃ� �k���l�ߔe�s���@80
47 �V�̂Ɓ[�Ɓ[�߁[����[ �k���l�ߔe�s��V���@81
48 �Ԃ̕��܂�[ �k���l�ߔe�s���@81
49 ��a������ �k���l�ߔe�s���@82
50 ����[�����������ǁ[ �k���l�ߔe�s���@83
51 �^�ߌ��n�Ԃ���[ �k���l�ߔe�s���@84
52 ��[���[���т�� �k���l�ߔe�s�ِ�@84
53 ��[�������[������ �k���l�ߔe�s��V���@85
54 ���[�������[ �k���l��������������@86
55 �Ɓ[�Ɓ[�߁[����[������ �k���l��������������87
56 ���В��l �k���l�����s�嗢�@87
57 �������[�l���H��H�� �k�ɐ��l�ɐ����������@89
58 ����Ƃ���L�Ԃ�� �k�ɐ��l�ɐ����������@89
59 �����[�������� �k�ɐ��l�ɐ����������@91
60 ��ɗ�������� �k�ɐ��l�ɐ����������@91
61 �Ɖ����� �k�ɐ��l�ɐ����������@92
62 ����邽�� �k�ɐ��l�ɐ����������@93
63 ���܂��� �k�v�āl�������^�Ӂ@94
64 �������т炩�� �k�v�āl�������^�Ӂ@94
�q��́@96
65 �������[��� �k���l�{���������@97
66 ����ǂ��� �k���l�{�����l���@97
67 �������[����܁[�܁[������ �k���l�ߔe�s���@99
68 ��������[ �k���l�ߔe�s���@99
69 �����卪�� �k���l�������l�@101
70 �Ɓ[�Ɓ[�߁[���� �k���l�ߔe�s��V���@101
71 �Ɓ[�Ɓ[�߁[��[ �k���l���Ԗ������Á@102
72 �Ɓ[�Ɓ[�߁[��[ �k�v�āl�������^�Ӂ@103
73 ����V�� �k���l�ߌ��s���@105
74 �ł��܁[ �k���l�����s���g�@106 |
75 ����[�� �k���l�����s���g�@107
76 �������[�q�Ƃ�����[�q�� �k�ɐ��l�ɐ����������@107
77 ���[�̑O �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@108
78 ������[�O�̐�h�� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@110
II �V��E�s���E�j��
�_���Ɋւ���
���E���C�E�N�F�[�i�@115
79 �����ނ�[ �k���l�������^�߁@117
80 �C�_�̃N�F�[�i(1) �k���l��������n�@118
81 �C�_�̃N�F�[�i(2) �k���l��������n�@120
82 ��V�т̃E���C �k���l��X�����Ӗ���@121
83 ����̃E���C �k���l��X�����Ӗ���@123
84 ����䑗��� �k���l��X�����Ӗ���@124
85 �č� �k���l��X������@�Á@125
86 �Ƒ���̃E���C�� �k���l��X������X���@128
87 �܂ւ�Ȃ��� �k���l�������ǁ@130
88 �V�ѐ� �k���l�������ǁ@132
89 ��_���M ��j���M �k���l�������ǁ@135
90 ���������E���C �k���l�������ǁ@136
91 �C�E���C(1) �k���l����s�Ӗ�Á@137
92 �C�E���C(2) �k���l����s�Ӗ�Á@138
93 �R���E���C �k���l����s�Ӗ�Á@140
94 �M�E���C �k���l����s�Ӗ�Á@141
95 ���납���̃E���C �k���l����s�Ӗ�Á@142
96 �����O�F���i(1) �k���l���A���������@143
97 �����O�F���i(2) �k���l���A���������@146
98 �����O�F���i(3) �k���l���A���������@146
99 �E�}�`�[�̃O�F���i �k���l���A���������@148
100 �O���̓��� �k���l���A���������@150
101 �����̃E���C�� �k���l���A���������@151
102 �J��̃N�F�[�i �k�Ál���A���Ì��@152
103 �x���̃N�F�[�i(1) �k�Ál���A���Ì��@153
104 �x���̃N�F�[�i(2) �k�Ál���A���Ì��@154
105 �ނƂ��e�B���� �k�v���l�m�O���v���@155
106 �[�_�V�т̃e�B���� �k�v���l�m�O���v���@157
107 �ێ��̃e�B���� �k�v���l�m�O���v���@160
108 �����̃e�B����(1) �k�v���l�m�O���v���@160
109 �����̃e�B����(2) �k�v���l�m�O���v���@162
110 �����̖� �k�v���l�m�O���v���@164
111 �ā[��[���[�݁[ �k�v���l�m�O���v���@165
112 �M���̃E���C �k�v���l�m�O���v���@166
113 ���Q���i �k�ɕ��l�ɕ������c���@168
114 �`�����W���}�[ �k�ɕ��l�ɕ������c���@170
115 ���邿���[ �k�ɐ��l�ɐ����������q�@171
116 �k���邿��[��[�̂��炵�l �k�ɐ��l�ɐ����������q172
117 �k���邿���[�̓Y���́l�� �k�ɐ��l�ɐ����������q173
118 ���ˁ[���Ⴍ�E���C �k���l���������@174
119 ���[�Ƃ��܁[ �k���l���������@175
120 ���ю��܂����� �k���l���������@176
121 �����E���C(1) �k���l���������@177
122 �����E���C(2)�� �k���l���������@178
123 �����̃I���� �k�n�l�n�Õ~���n�Õ~�@180
124 �x�o��̃E���C �k���l���Ԗ������Ԗ��@182
125 �܌��E�}�`�[�̃E���C �k���l���Ԗ������Ԗ��@183
126 �E�[�w�[�C�̃E���C �k���l���Ԗ������Ԗ��@184
127 �N���q�݂̃R�C�i �k���l���Ԗ������Ԗ��@184
128 ��E���C �k�v�āl��u�쑺�����@186
129 �}���E���C �k�v�āl��u�쑺�����@187
130 ���т�R���i �k�v�āl��u�쑺�����@188
���A�}�E�F�[�_�@189
131 �A�}�E�F�[�_ �k���l�Y�Y�s�@190
132 �A�}�E�F�[�_ �k���l�ʏ鑺�������@190
���e�B���N�O�`�@192
133 �e�B���N�[�~ �k�ɕ��l�ɕ�������쉮�@193
134 �e�B���N�O�`�� �k�ɕ��l�ɕ������c���@196
135 �e�B���N�O�` �k�ɐ��l�ɐ����������@198
�����̑��̐_���̉́@201
136 ���O�� �k�v���l�m�O���v���@201
137 ���[������[ �k�v���l�m�O���v���@202
138 �O���O���̉́� �k���l���Ԗ������Ԗ��@203
139 ���[��[�̉� �k���l���Ԗ������Á@205
�����̍s����
�����̍s����
���P���ہ@207
140 �O�N�܂�̃V�k�O �k���l���������g�@209
141 �U�R�� �k���l���������g�@210
142 ���m���v�� �k���l���������g�@212
143 �n�[���[���� �k���l���������g�@213
144 ���g�� �k���l���������g�@214
145 ���H �k���l���������c�@215
146 韐� �k���l���������c�@217
147 �C�̂��������� �k���l���������c�@219
148 �n���o�R�[�� �k���l���������c�@220
149 �������� �k���l���������c�@221
150 ������ �k���l�������^�F�@223
151 �v���� �k���l�������^�F�@224
152 �n���[�� �k���l�������^�F�@225
153 �����炯�[ �k���l�������^�F�@227
154 ���ˁ[�� �k���l���������@228
155 ��c�� �k���l���������@230
156 ��[�˂̉J���� �k���l���������@232
157 ���� �k���l���������@233
158 ����� �k���l���������@234
159 �V���Ȃ� �k���l�������ӌˁ@236
160 �F�n���� �k���l�������ӌˁ@237
161 �ɂ��̑�ԂĂ� �k���l�������ӌˁ@239
162 �ӕ~�� �k���l�������ӌˁ@240
163 ���`�N�V�� �k���l�������^�߁@241
164 韍��� �k���l�������^�߁@242
165 �f�B���S�[�� �k���l�������^�߁@243
166 �Ӗ��� �k���l�������^�߁@245
167 ���Ô� �k���l�������^�߁@247
168 ���c�ΕӒ� �k���l���������ԁ@249
169 ���̍��� �k���l���������ԁ@250
170 �k�J�^�� �k���l���������ԁ@252
171 �Փ��R �k���l���������ԁ@253
172 �n���R�� �k���l���������ԁ@255
173 �Ђ������� �k���l��X�����c�×��@256
174 �r�̏� �k���l��X������@�Á@257
175 ���� �k���l��X������@�Á@258
176 �����x�� �k���l�{������u���@259
177 �^�ӂ̑傠���� �k���l�{������u���@261
178 ���]���������� �k���l�{���������@262
179 ���ᒗ �k���l�{�����l���E�n�v�n�@264
180 �{������ �k���l�{�����l���E�n�v�n�@267
181 �V�̌Q �k���l�{�����ɖ�g�@269
182 �}�^�Ӗ��n �k���l�{�����Ӗ��n�@270
183 ���ڐ� �k���l�{��������@272
184 ���ڐ߁� �k���l���������@273
185 ���ᒗ �k���l����s���a�@274
186 �����肩�� �k���l����s�×z�@276
187 �������� �k���l����s�×z�@278
188 �n�����Ⴍ �k���l����s��ԁ@279
189 �i�[���[�w �k���l����s�����@280
190 ����l �k���l����s��Y�@282
191 �������[ �k���l����s��Y�@283
192 �Ԕn �k���l���[�����Ð^�@285
193 �䌎�̐��炳 �k���l���[�����Ð^�@286
194 �ł��[�� �k���l���[���J���@288
195 ��N��� �k���l���[���x���@289
196 ���傳��� �k���l���[�������@290
197 �哇 �k���l�ΐ�s�ΐ�@291
198 ��l�̐璹�� �k���l��u��s�c��@292
199 �͂܁[ �k���l��u��s��u��@293
200 ���r����[ �k���l�^�ߏ鑺���c���@294
201 ����ł��[���[ �k���l�^�ߏ鑺���c���@296
202 �������� �k���l�^�ߏ鑺�`�Ӂ@297
203 ���l�� �k���l�^�ߏ鑺�������@298
204 ����́[��[ �k�{��l�^�ߏ鑺�㌴�@300
205 ���c�ɒn �k�{��l�^�ߏ鑺�{��@301
206 �i�Ǖ����� �k�Ɍv�l�^�ߏ鑺�Ɍv�@302
207 �n�[���[���[�� �k���l���A���앗���@304
208 ���m���v�� �k���l���A���������@305
209 ����� �k���l���A�����~���@306
210 �~�o�� �k���l���A�����~���@308
211 �ԓc�� �k�l�l���A���l�@310
212 �L���Ȃ�� �k�l�l���A����Á@311
213 �i�Ǖ���[ �k�Ál���A���Ì��@312
214 ���������� �k���l����s�r���@314
215 �Η�� �k���l����s�m�ԁ@315
216 �V����Ȃ� �k���l����s�z���@317
217 ���� �k���l����s�Ӊ��E���@���@319
218 ��{�� �k���l����s��n�@320
219 �Ɓ[�P���� �k���l����s�R���@321
220 �ł�ȁ[�ف[�� �k�v���l�m�O���v���@323
221 �Ȃ��Ƃ��ݎ� �k�v���l�m�O���v���@325
222 �������� �k���l�ʏ鑺�����@326
223 ���̏K�킵 �k���l�ʏ鑺�����@327
224 �ߔe�� �k���l��u���������@329
225 �������� �k���l��u���������@331
226 ���[�� �k���l��u���������@332
227 �A�Z�������[���[ �k���l���������x���@334
228 �V�^���� �k���l��������������@335
229 ������� �k���l�����s����@336
230 �n�C���[�� �k���l�����s�Đ{�@337
231 ��c���� �k�ɕ��l�ɕ������c���@339
232 ������Ă��� �k�ɕ��l�ɕ�������쉮�@340
233 ���� �k�ɕ��l�ɕ�������쉮�@341
���G�C�T�[�E�������@343
�����H
234 ���m�x�� �k���l���A�����~���@346
235 �������� �k���l���A�����ԁ@350
���O��
236 ���� �k���l�^�ߏ鑺���c���@350
237 �����O�� �k���l�������^�߁@353
238 ���� �k���l�������^�߁@355
����t��
239 �T�t�G�� �k���l������c�@356
240 ���܂ʂ���܁[�� �k���l�����s���g�@358
241 ���܂��痈��ł��[�E
�@�@����������[���� �k���l�����s���g�@359
����������
242 �s�[�������[���[ �k���l�������^�߁@360
243 �����Ӗ��n�� �k���l��X���������@361
�����
244 �Ɍv�� �k���l�������F�Á@363 |
245 �ł�����[ �k���l�������F�Á@364
246 �����Z �k���l�������F�Á@366
247 ����肮��[�g �k���l�������ӕ~�@368
248 �J���O �k���l�������ӕ~�@369
249 ���g�̂͂Ȃׁ[ �k���l�������^�߁@371
250 ������߁[�����Ƃ��O�� �k���l��X�����Ӗ���@372
251 �n���R�[���}�R�[ �k���l�������^�߁@373
252 �����ǁ[ �k���l�������ӓy���@374
253 ���T�R�C�� �k���l�������ӓy���@375
254 ��g���� �k���l�������ӓy���@377
255 ���d�R���[ �k���l�������ӓy���@378
256 �Д��� �k���l���������ԁ@379
257 �����т���[ �k���l���������ԁ@379
258 �ɏW�̂��܂�����[ �k���l���������ԁ@381
259 �ёg����݂Ă��� �k���l��X������@�Á@382
260 �l�Ȃ��[ �k���l���������ԁ@382
261 ��N���� �k���l��X�����c���@384
262 �������܂ǂ�����[ �k���l��X�����c�×��@385
263 ���� �k���l��X�����Ӗ���@386
264 ������݂��� �k���l��X������@�Á@387
265 �����遦 �k���l��X�����`�g�@388
266 �l���̓� �k���l��X������@�Á@389
267 ���v�߂�ρ[�� �k���l��X�����匓�v�@390
268 ����g���� �k���l��X������@�Á@391
269 �{��l �k���l��X�����`�g�@392
270 �Ԃ̕��܂�[ �k���l��X�����`�g�@393
271 �V�̌Q�� �k���l��X�����匓�v�@395
272 ����V�� �k���l��X�������H���@396
273 �����e���� �k���l��X������X���@397
274 ��喘�� �k���l��X�������H���@397
275 ��E��Z�Ԑ� �k���l��X���������@398
276 �e�����[ �k���l�����{��@400
277 �^�߂̍��Ђ灦 �k���l�������ӕ~�@401
278 �`���`�G�[ �k���l�{���������@402
279 ���e�B�J�� �k���l�{���������@404
280 ��v������[ �k���l�{���������@405
281 �C���T�[�W�i�[ �k���l�{���������@407
282 �璹��� �k���l�{���������@408
283 ���t �k���l�{���������@409
284 ���O�� �k���l�{���������@411
285 ���₮ �k���l����s���x�c�@412
286 �Ɏɓ��O �k���l����s���x�c�@414
287 �ЂĂ̎聦 �k���l��X������X���@416
288 ���A�m�̏� �k���l����s���x�c�@416
289 �X�[���� �k���l�����������@418
290 �X�[����� �k���l��X�������H���@419
291 �Ƃ��[���� �k���l����s���c�@420
292 �������� �k���l�������ӕ~�@422
293 �C�₩��[ �k���l����s���c�@423
294 �v�� �k���l�Î�[���猴�@425
295 �z�� �k���l�Î�[���猴�@427
296 ������т���[ �k���l�Î�[���猴�@428
297 �ɏW�̂��܂�����[ �k���l�Î�[���猴�@430
�|�\�ɔ�����
�������Y�@432
298 ��m�s �k���l����s�A���@433
299 ���h�� �k���l����s�A���@435
�ƍs����
�����O�F�[�i�@439
300 ����(1) �k���l�ߔe�s�@439
301 ����(2) �k���l�ߔe�s�@441
302 �×�g�̑D�� �k���l�����s���g�@443
303 ����߉� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@444
304 �~�o�� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@446
305 �N�F�[�j���� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@447
���j���́@447
306 �Ɓ[�����j���́� �k���l�����s�嗢�@448
307 �����O�F�[�i �k���l�������l�@448
308 �×�̉� �k�n�l�n�Õ~�����g�A�@449
309 �����̃N�F�[�i �k���l���Ԗ������Á@452
310 �k�o���j���̉́l�� �k���l���Ԗ������Ԗ��@454
311 �c�NJԃO�F�[�i �k���l���Ԗ������Á@454
���Ƒ���́@456
312 �Ƒ���̃R�C�i �k���l��u��s��u��@456
313 �Ƒ���̃R�C�i �k���l���鑺�Ɏɓ��@457
���O���@458
314 ���җ��� �k���l�����s���g�@460
315 �e�̈⌾�� �k�ɕ��l�ɕ������c���@461
316 �e�̌䕈�て �k���l���������@463
317 ������ �k���l�������l�@463
318 �p�e�O�� �k�n�l�n�Õ~���n�Õ~�@465
III �d���E���
��Ɖ́@469
319 �c�悦�[ �k���l���������c�@469
320 �������Ɂ[��[�� �k���l��������������@471
321 �k�n���̉́l�� �k���l���������x���@472
322 �k���Ԃ��˂鎞�̉́l�� �k�ɕ��l�ɕ������c���@472
323 �ނ���������[ �k�ɐ��l�ɐ��������c�@473
324 �ނ�������߁� �k��l�ɕ��������@475
�|�\��������Ɖ�
325 �����J�� �k���l���������ԁ@475
IV �����E�V��
�����́E�V�щ�
���~���[�N�j�[�@481
326 �~���[�N�j�[ �k���l���A�m�������@482
327 �{���~���[�N�j�[ �k���l�{�����ɖ�g�@486
328 �k�c�����̃~���[�N�j�[�l �k���l����s�v�u�@489
329 �~���[�N�j�[(1) �k�ɐ��l�ɐ��������c�@490
330 �~���[�N�j�[(2)�� �k�ɐ��l�ɐ��������c�@491
331 �~���[�N�j�[�� �k�ɐ��l�ɐ����������q�@492
332 ���j���[�N�j�[�E������ �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@494
�������@498
333 ������ �k���ꏔ���l�@498
334 ��������� �k���ꏔ���l�@500
335 �\�Ԍ����� �k���ꏔ���l�@501
336 �ҕ������� �k���ꏔ���l�@502
337 �l�G���� �k���ꏔ���l�@505
338 ������ �k���ꏔ���l�@507
339 ������ �k���ꏔ���l�@509
���j�����́@511
340 �k�j�����́l �k���l�^�ߌ����^�ߌ��@512
341 �k�j�����́l �k���l�����s���g�@518
342 �k�j�����́l�� �k���l�����s�Ɖ��@519
343 �k�j�����́i���[���[�̂͂₵�j�l�� �k���l�����s�嗢�@520
344 �k�j�����́i���[���[�́j�l�� �k���l�����s�嗢�@520
345 ������� �k���l�����s�^�h���@521
346 �k����ȁ[���[���[�̉́l �k�ɐ��l�ɐ��������c�@523
347 �k����ȁ[���[���[�̉́l�� �k�ɐ��l�ɐ����������q�@526
���J�`���[�V�[�@527
348 ��������߁[����[ �k���ꏔ���l�@528
349 ���K�R �k���ꏔ���l�@531
350 ���D�ǁ[�� �k���ꏔ���l�@535
351 ���Î�v �k���ꏔ���l�@538
352 ���� �k���ꏔ���l�@541
���G�x��́@547
353 �J�i�[���[�V�� �k���ꏔ���l�@548
354 ���H �k���ꏔ���l�@554
355 �J���O �k���ꏔ���l�@558
356 ������ �k���ꏔ���l�@561
357 �ԕ� �k���ꏔ���l�@563
358 �l�璹 �k���ꏔ���l�@565
359 �ނ��[ �k���ꏔ���l�@567
360 �߂�U �k���ꏔ���l�@569
�����̑��̍����́E�V�щ́@572
361 �ɍ��w�C���[ �k���ꏔ���l�@572
362 ��� �k���ꏔ���l�@575
363 �j�� �k���ꏔ���l�@577
364 �C�̂���ځ[��[ �k���ꏔ���l�@579
365 �����W���g�[���[ �k���ꏔ���l�@582
366 ���� �k���ꏔ���l�@584
367 ������ �k���ꏔ���l�@587
368 �ނ���������[����[ �k���ꏔ���l�@590
369 �ڏo�x���� �k���ꏔ���l�@592
370 ����ˁ[�߁� �k���l�{�����ɖ�g�@595
371 �삽��� �k���l�ǒJ�����l�@595
372 �Ă����̉� �k���l�ߔe�s���@597
373 ����[���[�̉� �k���l�������ӓy���@598
374 ���������[ �k���l�m�O���m���@600
375 ���������[ �k�ɐ��l�ɐ��������c�@602
376 �����������Ԃ� �k�v���l�m�O���v���@603
377 ��c���߁� �k�ɐ��l�ɐ��������c�@604
378 ������ �k�ɐ��l�ɐ����������q�@604
379 �l�� �k�ɍ]�l�ɍ]���약�@605
380 �܂���� �k�ɍ]�l�ɍ]���약�@607
381 �g�c �k�ɍ]�l�ɍ]���약�@609
382 ���O���� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]�O�@611
383 ��̑O �k�ɍ]�l�ɍ]�����]�O�@613
384 �{�Ð� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]�O�@615
385 �ؕ� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@618
386 ��������(1) �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@620
387 ��������(2)�� �k�ɍ]�l�ɍ]�����]��@621
388 ��V�щ� �k���l�������l�@622
�V���w�E���s��
���V���w�@624
389 ���̉J�P �k���ꏔ���l�@624
390 ������ �k���ꏔ���l�@627
391 ������ �k���ꏔ���l�@629
392 ���l�� �k���ꏔ���l�@631
393 �֎q�� �k���ꏔ���l�@633
394 �����b�� �k���ꏔ���l�@635
395 ��m���S �k���ꏔ���l�@636
396 ������� �k���ꏔ���l�@639
397 �q���~�J�` �k���ꏔ���l�@641
398 �X�q���܁[ �k���ꏔ���l�@644
399 ���Ð� �k���ꏔ���l�@646
400 ���c������ł��[���[ �k���������l�@648
V �ÓT
���ÓT���y�@653
401 ������ŕ��� �k���ꏔ���l�@654
402 �\������ �k���ꏔ���l�@658
403 �������ւ��߁� �k���l�ߔe�s�@664
404 ���ݐ� �k���ꏔ���l�@665
405 ������ �k���ꏔ���l�@670
406 �ɖ�g�� �k���ꏔ���l�@674
407 �O�̕l�� �k���ꏔ���l�@679
�E
|
�P�O���A�}�����������l������w����w���ҁu���l������w�l���I�v. ����, �N�w�E�Љ�Ȋw (�ʍ� 37) �@ p.p37�`54�@���l������w����w���v�Ɂu���j�̓�,���̗��j--����ɕ������̔q���E�`���E�c��ς��߂���o���v�\����B�@
�P�P���A���w�ٕ��u�n���̐��E (80)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@pid/1737957�@�@�@�d�v
|
���t�̖����w �����Ɠ��{�����ԕ����A���� / �����i/6
�}���Ɨ����̐M��V���|�W�E���� / �F������ ;�~���� ;�͍����Y ;�����i ;�Ë��M�F ;�R�ܓN�Y/22
�g��P�����Ȋw���� �n�C�e�N�l�Êw���n / �V��N�� ;�ɓ��ĕF ;�|�R���� ;���{���� ;���c�x ;�X����N ;�X�i���F ;�n�ӌ�/39
�n�C�e�N�l�Êw�̉\����V���|�W�E���� / �V��N�� ;�ɓ��ĕF ;�|�R���� ;���{���� ;���c�x ;�X����N ;�X�i���F ;�n�ӌ�/66
�����A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌�������(28)�V�E�_���\�͂��D��Ă���Ƃ����l�Ԃ̗R���b(��)
/ B��s�E�X�c�L/102
��͓S����e�w���(4)�C���h�̃G���X�Ɛ_��(����2) / �R�ܓN�Y/112
�X�тƓ��{�l(12)�X�M�ւ̈��� / �k������/140
���c���j�̔���(13)����/�Y���̐��_�j��Z���̑��v / �ԍ⌛�Y/161
�V�ߥ���{�̕���(8)���I���� / �~���� ;�͍����Y/80 |
�P�P���A������q,�j�䋱�q��������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��ꕔ�E��� (�ʍ� 39)p.p287�`303�@������w����w���v�Ɂu��������--�������x�̑���-3-�j���^�Ƃ��炶�����v�\����B
|
������q,�j�䋱�q���u������w����w���I�v. ��ꕔ�E��� (�ʍ� 38�`39�v�ɔ��\�����u���������v�Ɋւ�����e�̈ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 38) p.p181�`229 |
1991-03 |
��������--���x�Ƒ���-1-�ÓT���x��̑��� |
| 2 |
(�ʍ� 39) p.p245�`286 |
1991-11 |
��������--�������x�̑���-2-�����^�Ƃ��炶���� |
| 3 |
(�ʍ� 39) p.p287�`303 |
1991-11 |
��������--�������x�̑���-3-�j���^�Ƃ��炶���� |
|
�P�Q���A�������ďC�u���������� (�ʍ� 339)�v���u���@�K�v���犧�s�����B
|
�V�w��̕����� �������������ی암 p.p4�`11
�������������فk����l���A20���N�L�O���ʓW-�C��̓�-����̗��j�ƕ��� ���
�m��,���X�� ���a,���Y �G��Y �� p.p12�`23,�}����2p
�ΎR�D�Ŗ����ꂽ���l�̈��--�w�h�s��������� ���R �o p.p24�`33
�����ɂ����镶�����̕ی�Ɠ������� �� ����,���� ����Y �� p.p34�`39
����2�N�x�`���H�|�Z�p�L�^�f��V���[�Y�[18-�u�v�����R�v�̐���--��� ������
��� ���v p.p40�`48 |
�P�Q���A���n�R�������u���� : �{�Ó��̉���杁v���u������o�Łv���犧�s����B
�@�@�@�@�ʐ^���W�u���K�̃p-���g�D�v
���A���̔N�A�k���F�Y���u�����{���� 56(3) p.329-332�v�Ɂu���������, �w�Y�C���̐l�ފw�x, �O������, 1987, 364��, 6800�~�v���Љ��B
���A���̔N�A�L���鑺�q�ǂ���琬�A�����c���ÁE�L���鑺����ψ����Áu�S����q�ǂ��G�C�T�[�܂�
��3��v���u�L���鑺����ψ���v���犧�s�����B�@�@
���A���̔N�A�u��y�@�S�� ��P�V���@��c�ʓ`�v���u��y�@�@�T���s��v����čs�����B
�@�@�@���L ��y�@�@�T���s��@�����S�O�|�吳�R�N���̕���
|
���J�����l�`�P���i���o�j
�@�R��l��`�R���i�����j
�{���c�t�`�L�G���S���i�m�^���n��j
�����l�����L�P���C�@�R��l�`�Q���C�@�R��l�`�L�X���C
�@�@���@�R��l�`�G���X���i�Ԉ��j
�@�R��l�`�P�O���C������l�`�P���i�����j
�R����l�`�P���i�����j
���_��l�s�ƋL�P��
���`����
��y�{�����m�`�W���i�S���j
�V����`�i�m�`���j�T���i����j
�������t���`�P���C������l�`�Q���C��@�썑�тP���i�ǐM�j |
���O�m�`�P���i�M�g�j
�̔O��l�s��L�Q���i�����j
�e����l�G���`�Q���i��j
�����ӏ�l�s��P���i�m�~���E�n���j
�`�d�R�J�c�ۗ���l�`�P���i��_�j
�I���q�������J�c�M�_��l�`�P���i�����j
�ܒ���l�`�P���C��ޏ�l���`�P���C���ؘa���s��L�P���i�ϑR�j
�ϐ�l�s�ƋL�P���i�ϑR�j
�����@�J��Ȕ���l�s��L�P���i�f�M�j
����i�c���~���j
��X�S�@�`�L�n��. �k�Q�l
�E |
���A���̔N�A�Ð��p���u�n�w�G��100�i4�j�v�Ɂu�����ʂƉ���g���t���B�j�@�[���ɉ���g���t�̌`���N��ɂ��ā[�v�\����B |
| 1992 |
4 |
�E |
�P���V���`�Q���P�U�����A�u�������������ٓ��m�ٓ��ʓW�����v�ɉ����āu�C��̓�
: ����̗��j�ƕ��� ���A20���N�L�O���ʓW�v���J�����B
�P���A�������������ٕҁu�C��̓� : ����̗��j�ƕ��� ���A20���N�L�O���ʓW�i�}�^�j�v���u�ǔ��V���Ёv���犧�s�����B
�@���: ��������������, �ǔ��V����
�@�@�@�@�p���t�L, List of exhibits �����@�@�@�@�@�@�@�����n�}: p148�@�@�@�@�@�@�@�@�@����j�N�\:
p149-153
�P���A�h�����h�Ҏ[�u�������������p�� ��1�S ��6�� (�`�L�� ��)�v���u�������y��v����Ċ������B�吳14�N�ł̕���
|
�{���`���@�嗪��c�` �喻��
�ܒ���l�` |
���b�R�J�R�����t���N ���C��
�����哿�N��. |
���a���N�� �q�H��
�E |
�P���A��Î�����g���X�ҁu���w 3(1) p.p147�`160�v�Ɂu����ɂ�����ג��`��--�Ɨ��_���܂̐[�w�ɂ�����́v�\����B
�P���A�ԍ⌛�Y�Ғ����u�Y������፷���v���u�V�j�Ёv���犧�s����B�@ (�p���j�w���@�� / �ԍ⌛�Y��,
��5��)
|
�\�ƒ����̋��C�E������ : �Y�����鐸�_ / �א���꒘
�тƒ呀 : �����鏗�����̒��� / ���X�֎q��
�V�s���w�_ : ������ّ��̏����� / ���҂Ƃ��풘
�ޏ��Ɨ�R : �J�~�T�}�����̊�؎R�M�� / �r��ǐ��� |
�u�T���J�v�Ƃ�ꂽ�l�X : �ړ��������m�[�g / �����C��
�_�Ɛ���̑Η��Ƃ����p���_�C�� : �܌��M�v�́u�Y���v�̏I��� / �������Y��
����̃j���u�`���[�E�`�����_���[ : �V�s���Ɖ����̊W�Ƃ��̕ϑJ/�c��R���Y��
�ܖ̎q��S�l : �B���ꂽ����杂��@�� / �ԍ⌛�Y���u |
�P���A�|�\�w��� �u�|�\ 34(1)(395) �v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@�@pid/2276684
|
��<���W>/p10~29
�q���r���̎����̊m���� / �������H/p9�`9
��x������ꂱ�� / ���ʐM ;�쑺����/p10~14
�̕���̉� / �@���q�F/p15~19
�����̉� / ������/p20~24
���̌|�\--���̌n�� / �R�H����/p25�`29
��C�R���̉̔�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E /
�@�@�������� ;�F����o�j/p6~7
���{�̖����|�\-15-�� / �ɓ��v�V/p30�`43
�㑍�p�Y���w�����ڗ��̐��E�x / �D�c�h��/p44�`44
�J�쌒�꒘�w�쓇���w�����_�x / �g�c�C��/p45�`45
|
�^��r�a���w���{�V�s�@���_�x / ���{�T�V/p46�`46
�s�쉎�V���ҏW�w�N�ӂ�������'90�x / ���F�M/p47�`47
�����蒟(11��) / ���c�m/p48~52
���x�蒟(9�����`10�����{) / �@���q/p53�`57
������r�{�����x���̔g�� / ��{�Y�O/p58�`58
�m�y��Êy�̕����Ƥ����s�����̊m��� / �O�H����/p59�`59
�m����w����......�x��ӓ|����̒E�p� / �R�씎��/p60�`60
�\�������F�}��v�v�̕��[�ߣ / ���N��/p61�`61
�����|�\����w�����̃��[���h��~���[�W�b�N����������̣/�������q/p62�`62
�e���r�u�ߖڂ�NHK��̓h���}�v / ����ˎO/p63~63
�V���ē�/p64~64 |
�Q���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g:<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
1�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v����n�������B�@�@37p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002959185 �@�@�@�@
|
�͂��߂� ���� ���V
���j�����Ɠ쓇-��N�x�����˂�- �啽 ��
�M�ё����m���ו��ɂ�����Љ�i���Ɛl�� |
����-�������������̐l�ފw�I�����ɂނ���- �㓡 ��
������w���d�R�|�\������́w���������x �R�� ����
�z�z�����A�\�A�}�A�����E������̋L�^ |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 5 �v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
���l���̌�Ԃ̐_�� �g�Ɗԉi�g p.1-23
���I�X���D�\�������� ���x�B p.25-42
�����哇�������H���̔����x�� �v���c�W,�������q p.43-149 |
NO IN DER GESTALT DES KUMIODORI
�@�@��Hennemann Horst Siegfried �@ p.151-168
���ꌧ���|�p��w�����������b�� p.169-175 |
�R���A�X�ۊ�v�������ȕҁu�������� = The monthly journal of Monbusho (�ʍ� 1383) p.p51�`53�v�Ɂu �킪�܂��̋���E����-24-���ꌧ�L����(�Ƃ݂�����)��--�S����q�ǂ��G�C�T�[�܂�v�\����B
�R���A�~���w�@��w�n�敶���������ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v = Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (7) �v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@�@�@pid/4424703
|
���掵����� �k�Y�̊C�ƑD/�ēc�b�i;�������K;���y�r�Y/p1~18
�w���֎s�k��B�s����n�}�x��� / ����M�q/p19�`38
���֎s�ώ@�@�ܗ֓��A���i�R�c�Ȃ�тɏ��쎩�R�Δ�A
�@�@���F�����c�⍏�撲���� / �؉����q/p39�`62
�f���̗��j�N�w / �r�ؐ���/p63�`76
�R�������猩���k�C�M�̏��� / ���J���l/p77�`90
�ЎR�P�ǂƁA���̎���(���̈�) / �{�c��/p91�`104 |
���Ό��R���̌F��̓`�����߂�����/��������/p105�`111
�啪���C�ݕ��ɂ�����u�̕��z/������/p113�`117
�R�l�̌��`�u�䂤�ǂ��v�l / ���јa���q/p119�`122
���H�ׂ��̕��y�L���A�S / �R�c�����Y/p123�`125
�狣�Z�T�K�m�[�g(4) / ���y�r�Y/p127�`141
�W�����E���g�\���E�t�H�X�^�[�Ɖ��֏��/�ߓ��~�q/p143�`154
�E |
�S���A�|�\�w�� �ҁu�|�\ 34(4)(398)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276687
|
���炭��ƌ|�\<���W>/p10~29
<��>���ߊw���̌|�\�ӎ� / ���p�䐳��/p9�`9
�l�`�ŋ��̂��炭�� / �F�쏬�l�Y/p10�`14
�R�Ԃ��炭��l�`�̐��E / �S���G��/p15�`19
���~���炭��l�` / �R��\��/p20�`24
�R�Ԃ��炭��l�` / �R��\��/p25�`29
��Ì����̍��Ɛ̣(�ꔪ�l)
�@�@���܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
���{�̖����|�\�q���ꌧ�r / ���{/p30�`43
�q�ѐ����ďC�w�s���{���� �玖�T
�@�@���q���m���r�x / ���p�䐳��/p44�`44
�����G�Y�ق��ďC�w�s���{����
�@�@�� ��s���q���ꌧ�r�x / ���p�䐳��/p45�`45 |
�B���v�������w�̕���哹��t�x / �D�c�h��/p46�`46
�����蒟(2��) / ���c�m/p47~50
���x�蒟(11�����{�`12����{) / �@���q/p51�`55
������V�i��������Ƃ̎��ٌ�� / ��{�Y�O/p56�`56
�M�y�u������v / �ږ�P��/p57~57
�M������ƍ˂��ɣ / �����|�V��/p58�`58
�\�������w���x�㉉���̓���ɂ��ģ / ���N��/p59�`59
�����|�\����w��S���e�s���{���ʂ̖����|�\����� / ����h/p60�`60
�f�梉f��w�O�Ȏ��x�̐�~���s� / �i�c�Y�g/p61�`61
������ //p62~63
�V���ē� //p64~64
�E
�E |
�S���A�����G�Y, ��ÍN�Y�ҁu��s�� : �s���{���� ���ꌧ�v���u�����Ёv���犧�s�����B�@�@
�T���P���A ���c ���q���S���Ȃ�B�i���N�@�V�Q�j
�T���A��ÍN�Y���u���܂�E���� : �A�����J��������{���� ��ÍN�Y�ʐ^�W�v���u�j���C�Ёv���犧�s��B�@�@
�T���A���w�ٕҁu�n���̐��E (82) �v���u���w�فv���犧�s�����B�@pid/1737959
|
�_�ɂȂ��D�c�M�� / �H�c�T�B/6
�M���̖�]�ƍ��܁s�V���|�W�E���t /
�@�@���H�c�T�B ; ���J�� ; ��R�t�� ; �~���� ; �R�ܓN�Y/32
�Ƒ����q�g�� / �͍���Y/54
�T������q�g�ւ̎Љ�w�s�V���|�W�E���t / ���[���� ;
�@�@���͍���Y ; ��c�[�� ; �c����Y ; �X�B/76 |
�������A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌�������(29
�@�@��)�\�͂̂���l�K���_�̒������Ƃ����R���b /
�@�@�� B��s�E�X�c�L ; �k�C���E�^������D�y�x���A�C�k�����/108
��͓S����e�w���(6)��\�͂ƒf�H / �R�ܓN�Y/120
�X�тƓ��{�l(14)���{�̃u�i�� / �k������/140
���c���j�̔���(15)����/�Y���̐��_�j��뗎�����蕔 / �ԍ⌛�Y/157 |
�T���A�u���j�ǖ{ 37(9)[(569)]�@�v���u�V�l�������Ёv���犧�s�����B�@�@ 1992-05/pid/7975509/1/1
|
[���W �J���[] ���l���E ����R�E����R�̈يE
���l����m��A�v���[�` �����w �����ӎ��ƕs��ς̍��� / �{�c�o/p38�`45
���l����m��A�v���[�` ���� �~�ςƂ��Ă̏��l���� / ����a�Y/p46�`53
���l����m��A�v���[�` �C���� ���������������� / ���R�C��/p54�`61
���l����m��A�v���[�` �_�� �������J�̓`���Ƌ֊� / �n�����|/p62�`69
���l����m��A�v���[�` �����l�ފw �����u�Ă鐢�E�̖��� / �a�c����/p70�`77
���l����m��A�v���[�` �Љ�w �ƂƉƕ������̐��� / �������c/p78�`85
���l���̎��� ����R ���֊������̖{�� / ���쐼����/p86�`93
���l���̎��� �}�^�M �R�̏��_�ւ̋��� / ��Y����/p94�`99
���l���̎��� ���� ���̗�͂Œe�ޑD / �T�R�c��/p100�`105
���l���̎��� �_�� �c�߂�ꂽ�����̖��� / ���c����/p106�`110
���l���̎��� �y�U �`�����r������告�o / �������/p112�`117
������ �����M���珗�l����� / 眓��o�T/p118�`125
�W���Γ`������鏗�l���E / �������/p126�`133
�����ʂ̍��J���E �����D�ʂ̈ʑ� / ��ÍN�Y/p134�`141
�i���R�̈Ќ����q��������R / �������l/p142�`149
�������ʂ��l���� �u�������v�̓��{�j �E�Ƃɂ݂鏗������ / �v�ď���/p150�`157
|
�������ʂ��l���� ���u���l���v�����j / ���c�~/p160�`168
���ʊ�e "�ؓ�"�Ñ�n���̍l�@ / ���z�L/p170�`177
��D�]�I�A�ڒ� ������ǂ�(5)���o���s��
�@�@�����c����w�M���L�x��� / ���ѐ瑐 ;�瑐�q/p188~197
��D�]�I�A�ڒ� ���������V���X�N���b�v�ɂ݂�
�@�@�������ېV�Ƃ��Ă��� ��b(5)���v�O�N�����\�����̐��� / �����k�O/p210�`215
��D�]�I�A�ڒ� �V���L����ǂނ��߂� ���j�j���[�X�w�W / ��R��/p216�`221
��D�]�I�A�ڒ� �������m�� �c����K�˂ĎO�痢(41)�O�d�� / �O�H���/p230�`234
�V�A�� �_�X�̈يE ���n�̃R�X�����W�[(2)�ˉB�R���い / �������q/p178�`187
�J���[���O���r�A ����̗�(64)�L��{���� / �֓����H
�J���[���O���r�A �_�X�̈يE(2)�ˉB�R���い / �������q
�J���[���O���r�A �V�ҏ����_�Е��y�L ��Εʗ��_��(���s�s�k��)
�J���[���O���r�A ����@�̗� ���蔪���{�̌Ó��� / ���{���s
�J���[���O���r�A �ӏ܁E�\���낢�� ������ ��c(����) / �ēc���j
�J���[���O���r�A �j�ւ�K�˂� �R���ɍ��܂ꂽ���R���p�̐�(�Ȗ،�������)
�j�ւ�K�˂� �Ȗ،������� �R���ɍ��܂ꂽ���R���p�̐� / �ҏW��/p198�`209
�� |
�T���A�ߓ����s�����{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (�ʍ� 190) p.p71�`87�@���{�����w��v�Ɂu�����}���镶���̕ϗe--���Љ�̒������͂���v�\����B
�T���A�|�\�w����u�|�\ 34(5)(399)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276688
|
��H�ɗ��u���w�v<���W>/p10~30
�q���r���w���ӕ� / ����K��Y/p9�`9
���w�̌p�����W�̂��߂Ɏ������� / �������q/p10�`15
�̏��Z�@����݂����w�Ƃ������̂̋^�� / �ēc�k�o/p16�`20
�{�R�̖��w�Ɨ��s���w�� / �ێR�E/p21�`25
���w��O�����̕ۑ� / ����K��Y/p26�`30
��^�ӂ̈È�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
���{�̖����|�\-19-�{�錧 / ��t�Y�s/p31�`44
�{�c�������w����̍Ղƌ|�\�x / �O�����Y/p45�`45
���䖞�ҁw�v�����̍Ղ�Ɠ`���x / �k����v/p46�`46 |
�����蒟(3��) / ���c�m/p47~50
���x�蒟(12����{�`1�����{) / �@���q/p51�`55
���������Ɍ���c�@��U�e�̔ߌ�� / ��{�Y�O/p56�`56
�m�y����Ԃ���V���������勳�� / �O�H����/p57�`57
�m������x���s�̉萁��� / �R�씎��/p58�`58
�\�������|�p�I���Ɋϐ���V�� / ���N��/p59�`59
�����|�\����w��V�����Љ�ł̖������y��|�\� / �������q/p60�`60
�e���r��{�i�h���}�̕���?� / ����ˎO/p61�`61
�\�Ƒg�x��r�ӏ܉��/p62�`63
�V���ē�/p64~64 |
�U���A�u��̉��������v���u���{��������v���犧�s�����B�@
|
1993�NNHK��̓h���}�̗��j�E�����K�C�h
�����Ȃ�G�� / �w�b
���������̎l�Z�Z�N / ���Ǒq�g
���A�W�A�̕����Ɏ����ꂽ�u�����v / �c�����v
�����ƃA�W�A�̊C�O�� : �Y�Y����݂����j�� / �^�h���[��
����������ځE�F��������� / ������
�ג��`���Ɖ��� / ��Î�
�����̏\�l�E�\�ܐ��I / ���Ǒq�g
�`���E��q�C����Ɨ��� / ���c��
���A�W�A�������̒��̗��� / �c���D�q
�u���̕����v�A�u��̕����v / ���{��
��j����̓쓇 / �r�c�Ďj
�y���[���q�O��̗����� / �L���R�a�s
|
���̉��� / ��闧�T
���A�W�A�̒��̗��� / �w�b, ���Ǒq�g
�^�ߍ��̌Ñ� / �����a��
�L�N�Ղ̒��Ɩ� / ����
����̗�X / ��������
����Ƀ{�[�_�[���X�́u�Ձv���N���� / ��[���n
���� / �J�쌒��
�S���̂��x��|�p�̍��E���� / �������q
�w�����낳�����x�̐��E / �O�Ԏ�P
�_�̂��܂��� / ���c����
�ϑw���錚�z���� / �����L
����̐F�ƍg�^ / �o�ߗ��q
����̒n�� / ������G |
�U���A�J�쌒�ꑼ���u�����ʂ̐��E�v���u���w�فv���犧�s����B�@ (�C�Ɨ��� / �Ԗ�P�F [�ق�] ��, ��6��)
|
�u�×����v�ȑO�̐��E : �쓇�̕��y�Ɛ������� / �J�쌒��
�����ʂ̒n���w : �����̐����Ɠ��F / ����N
�����ʂ̍l�Êw : �����Ɖ��ꏔ���𒆐S�� / ���،��a��
�O�X�N�̗��j�ƍl�Êw / ���Ð����Y
�A�W�E�m���E�� : ����̍\���Ƙ_�� / �n���얾
���������̗��j : ���E����̐����ƓW�J / �㌴���P
�������R�����ƊC��f�� / ���c��
�����ʂ̐M�� / ������G
�����̃V�}�Ɛ_�� : �m���ƃ��^�𒆐S�� / �R���ӈ� |
�v�����Ɛ_�� : ��V����ƃC�U�C�z�[�𒆐S�� / �N�㌳�Y
�_�̂Ɠ��S / �֍����i
�ɕ��������̔_�k�V��Ƌ����K�� / ��]�F��
����̗����� : ���������̗��j�Ɛ��� / ��c�s��v
�{�Â̗��j�ƐM�� / ���@������
���d�R�E������̓��X : �I���P�A�J�n�`�̗��𒆐S�� / �Ί_���F
���d�R�X�N����̒b���ՂƓ`�� / ���_�i�j
���\���̈��Ɣ��� : �쓇�_�k�����̌��������߂� / ����V�n
�E |
�V���A�������q�����y�V�F�Еҁu���y�|�p 50(7)�@��149�`149�@���y�V�F�Ёv�Ɂu���c���q���𓉂ށv���� �@pid/2293731
�V���A����|�\�j������ �ҁu����|�\�j���� ��8���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�����F���ꌧ���}���فF1001691383 93p
|
�V���Ɍ��閾���̉��ꉉ�� ��� ���Y
ⶂ̑����I�Ȓm��(�y���) ���H�� �m�u
����ƒ����́w�ʼnԌہx�V�l(���s��) |
�̌��u�萅�̉��v�ɂ���-�ǒJ�������l�̎���- ���l �^�E
�q�j���Љ�r�g�x�u�g�֒����v�ɂ��� ���� ��Y
�E |
�W���A���w�ٕҁu�n���̐��E (83) �v���u���w�فv���犧�s�����B�@pid/1737960
|
�ƍN�̐헪�\�\���إ�փP���̍��� / �}�J�a���/6
���쉤���̖��Ǝ��s�V���|�W�E���t / �ԍ⌛�Y ; ���J�� ;
�@�@���}�J�a��� ; �O�J�� ; �R�ܓN�Y/34
�X��m�낤��X���y������ / �k������ ; ������ ; �����K�q ;
�@�@�����X���b ; ���c�^���q ; �͍���Y/67
�����Ƃ��Ă̐X�с\�\���{�Ɖ��Ă̐X�т��ς� / �k������/69
�X�Ƌ��ɐ����� / ������/85
�X�̊y���� / �����K�q/92
�쐶�����ƗV�� / ���X���b/97 |
�̕��������� / ���c�^���q/101
���R�Ƃ̌�M�s�V���|�W�E���t / �����K�q ; ���X���b ;
�@�@���͍���Y ; ������ ; ���c�^���q/106
��͓S����e�w���(7)��\�̖͂\�� / �R�ܓN�Y ; �r�c�ꌛ/142
�X�тƓ��{�l(15)�����{�Ɛ����{ / �k������/160
���c���j�̔���(16)����/�Y���̐��_�j�
�@�@���I�V���V�� / �ԍ⌛�Y/182
�V�ߥ���{�̕���(10)�F���E�╨�� / �����a�� ; �͍����Y/114
�E |
�W���A�|�\�w��ҁu�|�\ 34(8)(402)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276691
|
�q���r�����̍s�� / ���ʐM/p9~9
�\�y�j�̂Ȃ��̏�����<���W>/p10�`27
�\�y�j�̏�����--����ӂƂ̕��� / ���{����/p10�`13
���ϐ������Ƃ̒q����--���̎��ւ�2,3 / �V�앶�Y/p14�`20
�����̖z(��)������--�Ñ��I�O�q�̂��� / ���ʐM ;�Ñ��玟�Y/P21~27
��v�����̃C�U�C�z�[�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���{�̖����|�\-22-���쌧 / �g�����/p31�`44
����^�C���X�Еҁw�����Ȃ�̍Ղ�x / ������/p45�`45
���c�P�Y���w�V ���ǂ댩��x�w�ʐ^�W �{����\�� ���̕��x�Ɓx / ���ʐM/p46�`46
�����蒟(6��) / ���c�m/p47~60
|
���x�蒟(4����{�`5����{) / �@���q/p51�`54
������s�����z�ό���̐���� / ��{�Y�O/p55�`55
�M�y�u�̂ƍ��v / �ږ�P��/p56~56
�M����������Ďv�����ƣ / �����|�V��/p57�`57
�\�������\�y�������̎����\�w�����x� / ���N��/p58�`58
�����|�\����w������w�p�𗬂Ɩ����|�\� / ����h/p59�`59
�f�梃w�A�[�ɑ���<���{>�ɂ��ģ / �i�c�Y�g/p60�`60
��3��CIOFF�A�W�A�����|�\�� / �x�b���q/p28~30
������/p62~63
�V���ē�/p64~64 |
�W���A�a���̔O���x��ۑ���� �u�a���̔O���x��F��M�B�̔鋫�v���u�a���̔O���x��ۑ���v���犧�s�����B
�@�@�@�����F��������}���ف@���ꌧ���}����
�W���A�_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (9) �v���u�_�ˏ��q��w�j�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4424475
|
�_�� ���^�̗��j�I�����ɂ��Ă̍l�@ / �m���芰/p1�`18
�_�� �Õ��ɂ�����j����l���� / �ԕ��юq/p19�`41
�����m�[�g �W�H�̐Q���Õ��ƒj����̕� / ���䗘��/p42�`55
�����m�[�g �����E��C���j�I�s��� / ���A�f�Y/p56�`69
�j���Љ� ���s�V�������ɂ��� / �R�{�l�Y/p70�`129
|
�j���Љ� �_�ˎs��t����Տo�y�̔����l���� / �������/p130�`134
�j�w�Ȃ����/p136~137
���C���s�̋L�^--�M�B����E���{���ʂ�K�˂� / �������/p137�`140
�G���E�}��/p141~142
����3�N�x�C�m�_����ځE���Ƙ_�����/p143�`145 |
�X���A�|�\�w����u�|�\ 34(9)(403)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276692
|
<��>�ė��u���̎���v / ���c�m/p9~9
�̕���j�̂Ȃ���"��"����<���W>/p10�`30
�������t�Ƃ����]�˂̏��D / �@���q�F/p10�`16
�㏗���̎c��--�����҂Ə��D�̊� / �_�R��/p17�`23
�������Ԃ��̏�--���������Ȃ������������� / ���}�����q/p24�`30
��v�����̃C�U�C�z�[(2)�(�ꔪ��)
�@�@���܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\-23-�a�̎R�� / �~���P�s/p31�`44
�y���b��Y���w���\�o�D�`�x / ���c�m/p45�`45
���}�����q���w�s�s�ƌ���x / �J�O/p46�`46 |
�����蒟(7��) / ���c�m/p47~50
���x�蒟(5����{�`6����{) / �@���q/p51�`55
������Вc�@�l����{���c���c��̔���� / ��{�Y�O/p56�`56
�m�y����y�R���N�[���̃C���F���g��� / �O�H����/p57�`57
�m����ڂɗ]�鎆�̖��ʂÂ���� / �R�씎��/p58�`58
�\�����������펩�M�{�w��@�t�x�̏㉉� / ���N��/p59�`59
�����|�\����w��w���܂�@�x�����������̂ţ / �������q/p60�`60
�e���r��[��̍���?� / ����ˎO/p61�`61
������/p62~63
�V���ē�/p64~64 |
�P�O���A���g�������u�������� : ���ꔽ��̐S�v ���u��g���X�v���犧�s����B�@
(��g�V��, �V�Ԕ� 249)�@pid/12730008
|
���`���������� : �����Ɓu������݁v�����̑̌�����
���A��̉���A�����Ĉɍ]��
�u���핽�a�����فv��n��
�푈�̏؋����i������� |
���̕s�����������ٔ�
�S�̕��Ɛ^���̓���
���g������̐��U���������d�� / �q���P��
�E |
�P�O���A��ÍN�Y���u�_�X�̌Ñw : ���s����_�i(�J�[�u)���� �}�`��[�^�ߍ���] 12�v���u�j���C�Ёv���犧�s����B�@
|
��ÍN�Y���u�j���C�Ёv���犧�s�����V���[�Y�u�_�X�̌Ñw1�`12]���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�_���� |
���s�N |
���e |
| 1 |
�����j�����N�j : �v�����̔N���s���i1�j |
1989-12 |
���ӎ��̉萶�� �t�o���N �@�@���� �@�@���E���̏���V�� �@�@���E���̎��n�V��
�E�v�}�[�~�L �@�@�s�[�}�b�e�B �@�@�n�e�B�O���e�B �@�@����_���̎� |
| 2 |
�����j�����N�j : �v�����̔N���s���i2�j |
1990-04 |
. |
| 3 |
�V�s����c��_ : �E���K���k�{���l�@ |
1991-08 |
. |
| 4 |
���K����S : �p�[���g�D�k�{���l |
1990-10 |
. |
| 5 |
��w���_�ɂȂ鍏 : �C�U�C�z�[�k�v�����l |
1990-05 |
. |
| 6 |
���K����}���̐_ : �}�����K�i�V�[�k�Ί_���l�@ |
1992-05 |
�ߍ�(�V�c)�s������ꗗ�\: p104�E�약�̌��(�I��)�E���(�J�[)�E�q��: p105
�약�̌��(�I��)�Ɛ_�E�҈ꗗ�\: p106�E�약�̔N���s���ꗗ�\(1991�N�x): p107 |
| 7 |
���K����M���[�̐_ : �V�}�m�[�V�k�n���쓇�l�@ |
1991-01 |
. |
| 8 |
�يE�̐_���K���̗��K : ���K���E���~ [������]�@ |
1991-12 |
. |
| 9 |
���𑆂��� : �V�` [���\��]�@ |
1991-08 |
. |
| 10 |
�C�̐_�ւ̊肢 ���{�j�K�C[�{�Ó�]
|
1992-12 |
. |
| 11 |
�C�̐_�ւ̊肢 : ���{�j�K�C�u�{�Ó��v |
1993-03 |
. |
| 12 |
���s����_�i(�J�[�u)���� �}�`��[�^�ߍ���] |
1992-10 |
�N�u���}�`���E�E���}�`���E���f�B�}�`���E���}�i�J�}�`���E���_���}�`��
�^�ߍ����̃E�K���E��Օ��z�}�E�}�`���s������ꗗ�\
�E�K���Ɛ_�E�҈ꗗ�\�E�i��̂̔N���s���ꗗ�\
|
|
�P�O���A �ߓ����s���u���{���O�q���G�� = Japanese journal of public health 39(10) p.p799�`808�@���{���O�q���w��v�Ɂu�I�����P�A�Ɠ`���I�@���V��̊ւ��-�����ɂ����钲�������v�\����B
�P�O���A�u�|�\ 34(10)(404) �|�\�w�� �� �|�\���s�� 1992-10 /pid/2276693
|
<��>������̏������c / ���؉���/p9�`9
��O�|�\�Ə�������<���W>/p10�`29
���a10�N��̏����� / �X�G�j/p10�`14
�����̌��Ɖe / �q�c��O/p15~19
�������낵�������u�k / ���ѕS���l/p20�`24
�����`���v��100�N / �r�c�O��/p25�`29
��v�����̃C�U�C�z�[(3)�(���Z)
�@�@���܌��M�v�̐��E/�O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���{�̖����|�\-24-������ / ���c�O�P/p30�`43
���������w�����̕���o�D�_�x / �@���q/p44�`44
�{�c�x�����w�ዷ���y�̌����x / �㓡�i/p45�`45
���{�������w�����|�\�l�̎v�z�x / ������Y/p46�`46 |
���{��������ҁw���{���w���(���ꥉ���)�{�Ï����ҁx / �O�����Y/p47�`47
�����蒟(8��) / ���c�m/p48~51
���x�蒟(6�����{�`7����{) / �@���q/p52�`56
������o�u���o�ϕs���Ɖ���� / ��{�Y�O/p57�`57
�M�y������y��Ƃ��̉��y� / �ږ�P��/p58�`58
�M����|�p�Ղ̗v�|��K���Ɏv��� / �����|�V��/p59�`59
�\�������q���ɂ��ģ / ���N��/p60�`60
�����|�\����w������|�\�̓`���ۑ��̖�� / ����h/p61�`61
�f�梃A�j���f��w�g�̓x�̑�q�b�g� / �i�c�Y�g/p62�`62
������/p63~63
�V���ē�/p64~64
�E |
�P�P���A�����������b��ҁu�S���}���وē� ���v���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B
|
��
�k�{�茧�l
���s�s���j���������ف@517
�����R�~���j�e�B�Z���^�[
���j���������ف@518
���璬���j���������ف@518
�����s�s����ٓ����L�O�ف@519
�q���L�O�ف@519
�s����j�����ف@520
�{�葍�������ف@521
�k���������l
���ǒ����j���������ف@523
���v���s�����y�����ف@524 |
���������ف@524
�o�����s���j���������ف@525
�����������j�����Z���^�[
�t���ف@526
�}�������j���������ف@528
�P�k�����j���������ف@528
���ÏW���ف@529
����s���j�����ف@530
���l�������j���������ف@531
�����_�Еف@531
�V�Ò����j���������ف@532
���q�������y�ف@533
�k���ꌧ�l |
�Ί_�s�����d�R�����ف@534
�Y�Y�s���}���ف@535
���ꌧ���}���ف@536
���ꌧ�������ف@537
���ꌧ�����a�F�O�����ف@538
����s�����y�����ف@539
�X��p�s�����y�����ف@540
���씎���ف@540
�ߔe�s�����U���ہ@541
�ǒJ�������j���������ف@542
���d�R�����ف@543
��イ������Z�����ف@543
�E |
�P�P���A���w�ٕҁu�n���̐��E (84)�v���u���w�فv���犧�s�����B�@pid/1737961
|
�}���_���̉F���� / ���앐��/6
���ƍĐ��̃V���{���Y���s�V���|�W�E���t / ��c�Տ� ; �~���� ;
�@�@���͍����Y ; ���앐�� ; �{��G�� ; �R�ܓN�Y/26
���W/�����Ɗ� �����Ɗ��̎d�g�� / ���ԗ�/51
�����Ǝv�l�̃p���_�C�� / ��������/65
�l�������Ɗ�� / �O�V/81
��`�q�͎q���ւ̑�ȑ��蕨 / �я��F/86
�܂��n����m�낤 / ����F�T/90
�����������n������� / �X������/94
�Ȋw�̑O���z�u�̓]���Ɗ��Љ��` / ���X�ؗ�/98 |
�V���|�W�E�� / �R�ܓN�Y ; ���X�ؗ� ; �X������ ; ����F�T ;
�@�@�� �я��F ; �O�V/106
�������A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌�������
�@�@��(30���)�߂��_�������̃e������l�Ԃ��~�����Ƃ����R���b/
�@�@�� B��s�E�X�c�L/136
��͓S����e�w���(8)��\�̖͂\��(����2) / �R�ܓN�Y/146
�X�тƓ��{�l(16)�ፑ�̐X�����і� / �k������/162
���c���j�̔���(17)����/�Y���̐��_�j��I�V���V��(��)/�ԍ⌛�Y/181
�V�ߥ���{�̕���(11)�Î��L / �c�Ӑ��q ; �͍����Y/112
�E |
|
�������A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌�������(1�`29)���̓���\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N |
���e�i���ҁFB��s�E�X�c�L ;�k�C���E�^������D�y�x���A�C�k�����j |
pid |
| 1 |
�n���̐��E (46)p99 |
1983-05 |
(1)�^�C�g�������s�� |
pid/1737921 |
| 2 |
�n���̐��E (47)p112 |
1983-08 |
(2) �^�C�g�������s�� |
pid/1737922 |
| 3 |
�n���̐��E (48)p116 |
1983-11 |
(3)�����܂�ȏ����������R���b |
pid/1737923 |
| 4 |
�n���̐��E (49)/p134 |
1984-02 |
(4)�C�^���̏o���ɂ܂��R���b |
pid/1737924 |
| 5 |
�n���̐��E (50)p118 |
1984-05 |
(5)�E�C���^�Ƃ̐킢�ɔs�����R���b������ |
pid/1737925 |
| 6 |
�n���̐��E (51)p98 |
1984-08 |
(6)�E�C���^�Ƃ̐킢�ɔs�����R���b |
pid/1737926 |
| 7 |
�n���̐��E (52)p134 |
1984-11 |
(7)�_�Ղ�ɂ��Ă̗R���b��ܘb |
pid/1737927 |
| 8 |
�n���̐��E (53)p124�@ |
1985-02 |
(8)�q�O�}��c��_�ɂ��R���b |
pid/1737928 |
| 9 |
�n���̐��E (54)p148 |
1985-05 |
(9)�̉����ɑ�������ƈꐶ�s�^�ɏI���Ƃ����R���b |
pid/1737929 |
| 10 |
�n���̐��E (55)p144 |
1985-08 |
(10)�̉�����ގ��������@�̗R���b |
pid/1737930 |
| 11 |
�n���̐��E (56)p84 |
1985-11 |
(11)�q�O�}���ł���悤�ɂȂ����R���b |
pid/1737931 |
| 12 |
�n���̐��E (57)p104 |
1986-02 |
(12)�����̗�����ގ�����R���b |
pid/1737932 |
| 13 |
�n���̐��E (58)p140 |
1986-05 |
(13)�����p�̏��N���q�O�}�̏��_���~�������R���b |
pid/1737933 |
| 14 |
�n���̐��E (61)p104�@ |
1987-02 |
(14)�Ȃ̍���D�����L�^�L�c�l�_��ގ�����R���b |
pid/1737936 |
| 15 |
�n���̐��E (62)p116 |
1987-05 |
(15)�l�Ȃ̍����L�^�L�c�l�_���������q�O�}�_�̗R���b
|
pid/1737937 |
| 16 |
�n���̐��E (63)p98 |
1987-08 |
(16)�L�[�����l���ɉh���邱�Ƃ̗R���b |
pid/1737938 |
| 17 |
�n���̐��E (64)p96�@ |
1987-11 |
(17)�Q�[�̐_���Ղ�悤�ɂȂ����R���b���s����t |
pid/1737939 |
| 18 |
�n���̐��E (65)p120 |
1988-02 |
(18)�I�^�X�b�̎��Q�[�̐_(���ނ�������_)���Ղ�悤�ɂȂ����R���b |
pid/1737940 |
| 19 |
�n���̐��E (66)p120 |
1988-05 |
(19)�Z��̍�������l�Ȃ��~�����L�^�L�c�l����_�̗R���b |
pid/1737941 |
| 20 |
�n���̐��E (67) p98 |
1988-08 |
(20)�Z��̍�������l�Ȃ��~�����L�^�L�c�l����_�̗R���b(��) |
pid/1737942 |
| 21 |
�n���̐��E (70)p116�@ |
1989-05 |
(21)�����p�̏��N�������̉�����ގ�����R���b(��) |
pid/1737945 |
| 22 |
�n���̐��E (71)p62�@ |
1989-08 |
(22)�����p�̏��N�������̉�����ގ�����R���b(��) |
pid/1737946 |
| 23 |
�n���̐��E (72)p132 |
1989-11 |
(23)�����p�̏��N�������̉�����ގ�����R���b(��) |
pid/1737947 |
| 24 |
�n���̐��E (74)p112 |
1990-05 |
(24)�q�O�}�ɗ^��������ꂽ�j�̗R���b |
pid/1737950 |
| 25 |
�n���̐��E (75)p138 |
1990-08 |
(25)�g���̈Ⴄ�_�Ɛl����������Εs�^�ɂȂ�R���b |
pid/1737951 |
| 26 |
�n���̐��E (77)p138 |
1991-02 |
(26)�a��Ȏ҂ł��L�\�Ȝ߂��_�ɂ���ĊJ�^����R���b |
pid/1737954 |
| 27 |
�n���̐��E (78)p104 |
1991-05 |
(27)�V�E�_���\�͂��D��Ă���Ƃ����l�Ԃ̗R���b(��) |
pid/1737955 |
| 28 |
�n���̐��E (80) p102 |
1991-11 |
(28)�V�E�_���\�͂��D��Ă���Ƃ����l�Ԃ̗R���b(��) |
pid/1737957 |
| 29 |
�n���̐��E (82)p108 |
1992-05 |
(29)�\�͂̂���l�K���_�̒������Ƃ����R���b |
pid/1737959 |
| 30 |
�n���̐��E (83) |
1992-08 |
�L�ڂȂ� |
pid/1737960 |
| 31 |
�n���̐��E (84)p136 |
1992-11 |
��(30���)�߂��_�������̃e������l�Ԃ��~�����Ƃ����R���b |
pid/1737961 |
|
�P�P���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (40)�ʍ��t�^�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B �@�@pid/4419248
|
�����l�N�x(���\���) �쓇�j�w����/p1�`1
�u�_�����������v�Ƃ������� �����V���[�}�j�Y����
�@�@�������錾���̏����ɂ��� / �X�땶/p2�`2
���d�R�̔�Ղɂ��� / �Ί_���F/p3�`4
�{���l�I�̎��R�ƕ��� / ��䗲/p4�`5
�����×��ƃ��[�嗤 / �ؑ�����/p5�`6
�C�O�f�Ւ�����̔����Ɠ쐴���s�H��� / ��c��/p6�`7
|
����̎���� �����E�؍��Ƃ̍Ј��_�I��r���� / �������q/p7�`8
���^�̗��j�I�������߂��鏔��� / �m���芰/p8�`9
�����Q�����v�C����������
�@�@�����q�l�ފw�I��r���� / �����Q��/p10�`10
�j���ɂ݂问���ٍ̕˓V�M�� / �^��uꢎq/p10�`11
����k���ɂ����问���g�� / ���a�F/p11�`12
|
�P�P���A�R�c��q�q ; ���k�M�q, ���k�V�n�ҁu���\���ɐ����� : ���������̎��R�������v���u�Ђ邬�Ёv���犧�s�����B�@�@ (�����Ȃ핶��, 63)
�P�P���A�u�������z (102)�v���u���{�������z�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4418469
|
���G ��ɕ���z�O���H�S�R���̑� / �����厡�Y/p1�`1
������ ���ׂ̌��z�̐��ɍĂщ����]�̖������Â� / �����d�v/p3�`5
�R���_���E�������\ �V������쑺���J�̖��Ƃ̋�ԍ\����
�@�@�����Z���Ɋւ��錤��(����1)�W���̌����ƍĐ� /
�@�@�� ��C�� ;�R�c���� ;�{������ ;���G�k�����l/p6~24
���u�� ���Ƃ̂��镗�i / �n���吴/p25�`31
�������\ �a�C�̑卑�ƏZ�� / ������N/p32�`38
�������\ ���l�������̋���--
�@�@�������I�Ȃ���̂��ɍ����Ɣ�r���Ȃ��� / ��D�B�Y/p39�`47 |
������\ ����E�n���쓇�̖��ƂƏW���̋�ԍ\���Ɋւ��錤��-
�@�@��-��n�ɂ����肱�� / �i������/p48�`55
�������z���t���̂��� / �s���P�m/p57�`66
��19����w�� �z�O�̖���--���䌧�ۉ����A���R�s�A���s�A
�@�@���r�c���A�����s�A�I�]�s / ����F�m/p67�`77
��
�R���� �w����^�C���X�x�H�̌��w��L��/p121�`121
�E
�E |
�P�P���A�|�\�w����u�|�\ 34(11)(405)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276694
|
<��>����A�W�A�̉� / �������H/p9�`9
����A�W�A�̖����|�\<���W>/p10�`29
���F�g�i���̖����y��Ɖ��t�@ / �F����o�j/p10�`13
�����W�����̑�O������N�g�v��� / ���ԏ��q/p14�`17
�|�ƌ|�\--�o�����̌|�\�ƋV���� / �{������/p18�`21
�T�����N(���}��-�V�A)�̌|�\ / �m�c���k/p22�`25
�k�^�C��A�J���̃u�����R�� / �����/p26�`29
��v�����̃C�U�C�z�[(4)�(����)
�@�@���܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\-25-���s�{ / �A�؍s��/p30�`43
���c�m���w�����N�\�x / �˔N��/p44�`44
�䑐���v���w�߉���k�̌����x / ����됅/p45�`45 |
�����L�s���w�R�����v�`���̌����x / �������/p46�`46
�����蒟(9��) / ���c�m/p47~50
���x�蒟(7����{�`8����) / �@���q/p51�`55
�������͂��̈�l�ŋ�� / ��{�Y�O/p56�`56
�m�y����y�z�[���̃`���C��� / �O�H����/p57�`57
�m����w����݊���l�`�x�������ς�� / �R�씎��/p58�`58
�\�������X�c���t�̎��ƐX�c��� / ���N��/p59�`59
�����|�\����w����w�E�͌��_���A�֣ / �������q/p60�`60
�e���r����f�G���łȂ��b� / ����ˎO/p61�`61
<�Ǔ�>�M�y�w�� ���쌒���N�̂��� / ���c��t�F/p62�`63
�V���ē�/p64~64
�E |
�P�Q���A�|�\�w��ҁu�|�\ 34(12)(406)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@pid/2276695
|
<��>�ޏ��̌��_�b / �������/p9�`9
�쓇�̐_�b�E�_�w<���W>/p10~32
�����̃m���ƃ��^�̎��d�ɂ���--�I�����ƃ}���K�^���̑Δ�/�R���ӈ�/p10�`17
���z�̐_�Ɣ��n�̗��--�v�����̃e�B-��-�K-�~�̐_�� /��������/p18�`25
�떓�̃t�T--���̋N�� / �Ë��M�F/p26�`32
��Ί_���̃A���K�}�(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\-26-�V���� / �ߓ�����/p33�`46
���{�@��{���w���{����������n�x
�@�@�����ꊪ ���@�_����Z�� �|�\�`��� / ������/p47�`47
�D�ؗT���w���c���j�O�`-�����܂̎v�z�x��c�����w���c���j-��ŗL�M�£�̐��E�x��
|
�@�����c�A�W�I���w���c���j�̖����w�x / �������H/p48�`49
�����蒟(10��) / ���c�m/p50~53
���x�蒟(9�����{�`���{) / �@���q/p54�`57
����������ő匀��̃��j���[�A��� / ��{�Y�O/p58�`58
�M�y��싅�l�̌���̐S����� / �ږ�P�O/p59�`59
�M���������������i�Â���̎p��� / �����|�V��/p60�`60
�\�������X�[�p�[���i�\� / ���N��/p61�`61
�����|�\����w������|�\�̍�� / ����h/p62�`62
�f�梑�܉����ۉf��գ / �i�c�Y�g/p63�`63
�V���ē�/p64~64 |
�P�Q���A�u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (12)�v���u���{�������y�w��v���犧�s�����Bpid/4427625
|
�������F�����Ɩ��w / �����G�Y/p1�`1
���{���w�̒n�搫�����Ɍ����Ă̎��_(����2)--���{���w�̓��{�C���Ɛ��˓��C�� / �������q/p2�`12
�z�O�̓c�V�ѐ_���̉��y--���R�̐����_���Ƒ�X�̖r���_�� / ���]��q/p13�`23
�n��̋���Ɩ��w���� / ���іL/p24�`29
����̉P���ۉ̂ɂ����隒���� / ���ь��]/p30�`35 |
���A���̔N�A�u�G���n���̐��E�v�m���D�S�U�`�W�S�ɘA�����ꂽ�u�����A�C�k�̌���Ɩ��b�ɂ��Ă̌��������F�a�D�s�E�X�c�L�^��,�k�C���E�^������D�y�x���A�C�k�����^��v�������Ƃ��Ėk�C�����}���قɏ��������B
�@�������ɂ��Ă͌������K�v�@�Q�O�Q�R�E�R�E�Q�X�@�ۍ�
���A���̔N�A�^�珹�O���u���{�̗w���� 32(0) p.172-173�v�Ɂu�q�Ǔ��r�̓��c���q�����E���쌒�������v����B�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���K��i�j�j�����m�_���u���������̓`����̂Ɋւ���l�@�v�\����B�@�@pid/3072501
|
�ڎ�/p1
���_ ���������̎��p
��1�� �����w�ɂ����鋙������/p1
��1�� �`����̂Ƃ��Ă̋����̓���/p1
��2�� �����w�ɂ����鋙���Љ�̔c��/p3
��3�� ���c�����ɂ݂�`����̔c���̕ώ�/p6
��2�� �`����̂Ƃ��Ă̋����Ƌ����Љ�/p11
��1�� �`����̂̈Ӌ`/p11
��2�� ���������Ƌ����̐S��/p12
��3�� �����Ƌ����Ƒ�/p16
��4�� �����j�����̈Ӌ`/p18
��1�� �`����̂Ƃ��Ă̋����Љ�
�@�@���\�\�o�����������Љ�̎��ԕ��́\
��1�� 聃��������Љ�̓����ƍ\������ƌ^�����Љ�\
�@�@����_�]���^����/p26
��1�� �[�����̊T��/p26
��2�� ���ƌ`�Ԃ̕ϑJ/p32
��3�� �K�w�\���Ƒ����\��/p40
��2�� �H�����������Љ�̓����ƍ\���
�@�@�����ƌ^�����Љ�\�務�]�_�^����/p58
��1�� �H�������̊T��/p58
��2�� ���ƌ`�Ԃ̕ϑJ/p69
��3�� �Љ�I���s�ƊK�w�\��/p74
��3�� ��샀�������Љ�̓����ƍ\��������^�����Љ�/p85
��1�� ��샀���ɂ����鋙�Ƃ̊T��/p85
��2�� ���ƌ`�Ԃ̕ϑJ/p94
��3�� �����\���ƉƑ����s/p103
��4�� �_���o���C�u�ƃ\�o�u/p122
��4�� ���郀�������Љ�̓����ƍ\����o�Ҍ^�����Љ�/p127
��1�� ���郀���̊T��/p127
��2�� ���ƌ`�Ԃ̕ϑJ/p146
��3�� �����\���Ɩ������s/p156
��5�� ���������Ƌ����Љ�\�������Љ�̓����ƍ\��/p188
��1�� ���������̈�ʓI���i/p188
��2�� �����̊T�O�Ɨތ^/p195
��3�� �������Љ���߂��鏔���/p202 |
��2�� �`����̂Ƃ��Ă̋����̐S�ӂƍs��
��1�� �����颋����C����ɂ���/p219
��1�� �C�ɐ�����l�т�/p219
��2�� �C�̋��E�Ƌ����̑���/p219
��3�� �����̑��M�I���E/p225
��4�� �����̗ތ^�Ƌ�������/p228
��2�� ���Y�V����݂��_��������̎��ԔF��
�@�@���\���݂��߂��閯���𒆐S�Ƃ���/p232
��1�� ���{�ɂ����閯�������̑��Ή�/p232
��2�� ���V��̏���/p232
��3�� ���\�o�̃A�G�m�R�g�s��/p235
��4�� ���V��ɂ�������̌p���Ɠc�̐_�̋���/p239
��5�߁u���݁v�̏���/p242
��6�� �����Љ�Ɛ_�̓���/p248
��3�� �����j��ʂ��Ă݂��������\�k�C���V���S�V����/p253
��1�� �����̊��ʂ��Ă݂��V�����Ǝj/p253
��2�� �V�������̐����j/p253
��3�� �V�����Ƃ̑���/p263
��4�� �V���j�V�������̘J���Ɛ���/p278
�I�_ �����Љ���ɂ����鍡��̉ۑ�
��1�� ����Љ�Ɩ����ϗe/p289
��1�� �����ϗe�̏��v��/p289
��2�� �ߑa���Ɠs�s��/p290
��3�� �����̕ϖe����łƕ������ی�/p293
��4�� �����ϗe�̖����w/p294
��2�� �����Љ�̕ώ��Ɩ����w/p296
��1�� �����Љ�̕ώ��\���鋙���̓_�i����/p296
��2�� ���㋙���Љ�ɑ��閯���w�̊�/p299
��3�� �C�m�l�ފw�̑��ՂƋ�������/p303
��1�� �C�m�l�ފw�̑���/p303
��2�� �����Љ�ɂ����鏗���̒n��/p305
��4�� �`���I�����̗ތ^���ɂނ���/p310
��1�� ���̏���/p310
��2�� �����ތ^���̎w�W/p311
�Q�l�����ژ^ / (1)
�E |
|
| 1993 |
5 |
�E |
�P���A�V�铿�S�ҁu���x���������j�N�\�v���u�V�铿�S�^���}�����[�{�X(����)�v���犧�s�����B��5�Ł@���ŁF1993.1
�P���A�|�\�w����u�|�\ 35(1)(407)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276696
|
<��>�Y�\�w��\���N / �{�c����/p9�`9
�|�\�w--�܌��M�v�̕��@<���W>/p10�`32
�܌��搶�Ɖ̕��� / �˔N��/p10�`11
�����w�ƌ|�\�w--���c���j�Ɛ܌��M�v��"�|�\�_" / �q�c��/p12�`18
�܌��w�̍\��--�|�\�`���_�̍��i / �O�����Y/p19�`25
�܌��M�v�̌|�\�̏W / ������/p26�`32
�܌��M�v�̐��E���O
�@�@����Ί_���약�̃}�����K�i�V� / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\-27-���m�� / ���،[�v/p33�`46
�{�茧�j���s��w�{�茧�j�x / �������H/p47�`47
|
���](���W �\�E����) / ���ʐM/p48~49
�����蒟(11��) / ���c�m/p50~53
���x�蒟(9�����{�`10����{) / �@���q/p54�`57
���������Ă̊O���l���o�ƣ / ��{�Y�O/p58�`58
�m�y��h�C�c��œ��{�̋Ȃ��̂�� / �O�H����/p59�`59
�m�������4�N�͊O���������b�V��� / �R�씎��/p60�`60
�\�������呠���R�{�Ƃ̏[��� / ���N��/p61�`61
�����|�\����w��`�������U���̕�������� / �������q/p62�`62
�e���r��w�s�f�x�̃e���r� / ����ˎO/p63�`63
�V���ē�/p64~64 |
�Q���A�|�\�w��ҁu35(2)(408)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004264576
|
<��>�܌��M�v�Ɛ_���� / �ۍ�B�Y/p9�`9
�܌��|�\�j��ǂݒ���<���W>/p10�`30
�|�\�̏���--������ꂴ��q��čl / ���{�T�V/p10�`16
�����|�\�_ / �Έ䐳��/p17�`23
�����|�\�����ɂ�����ϋq�_-3�̉\�� / ��쐽/p24�`30
����\���c�[�̐߃A���K�}(1)�(194)�܌��M�v�̐��E /
�@�@�� �O�����Y ; �F����o�j/p6�`7
���{�̖����|�\-28-���Q�� / �X���N/p31�`44
�c�Ԉ�Y�ďC�w�����|�\���T�x / �O�����Y/p45�`45
Book Review(���W �̕���) / ������/p46�`47
|
�����蒟(12��) / ���c�m/p48�`51
���x�蒟(10�����{�`���{) / �@���q/p52�`55
������������ꗿ���ƃ`�P�b�g�����̔�� / ��{�Y�O/p56�`56
�M�y�����w�������q���t��x� / �ږ�P��/p57�`57
�M����ÓT��i���܂̈Ӌ`� / �����|�V��/p58�`58
�\���������N�lj凜ԊO�ң / ���N��/p59�`59
�����|�\����w��b��ƂȂ肻���Ȍ����e�[�}� / ����h/p60�`60
�f�梕s���ɋ����Ƃ�����f�� / �i�c�Y�g/p61�`61
�w���/p62�`63
�V���ē�/p64�`64 |
�Q���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g : <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 2�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002811485�@�@1993/2
|
����{���k���̍j���� ��������
������J�Âɂ������� �������V
���������ƍ��� �t�F���E�E�����E���� -�ߐ� |
���{�Ɨ���- �e�r�E�v
�ߐ������̗� ���_-�吴������ƑI��
�ʏ�- ���c�I��u |
�Q���A�u�L���鑺�j�v���u�L���鑺 (���ꌧ)�v����Ĕł����B�@���ŁF�L���鑺�j�Ҏ[�ψ���ҁ@ 1964�E12
|
���j�����@���� ��鐷��
�j���@�s����� ��c����
�j���@���@�@�c�� ����H�v
�j���@����� �����_
�����@�Ҏ[�l ���鐷��
�ʒ�
���́@���R�̏�
���́@���߁@�ʒu�ƒn���@��
���́@���߁@�ʒu�E�n�`
���́@���߁@�u�ˑтƕ���
���́@���߁@�͐�k�n�Ɠy�n�\��
���́@���߁@�y��̎��
���́@���߁@�{���y���y��
���́@���߁@�y�땪�͕\
���́@���߁@�����������y�n�̎O���@
���́@���߁@�n�w����.
���́@���߁@�����̋C��@�ꎵ
���́@���߁@�C�ۊT��
���́@���߁@�C�ے����\
���́@���߁@��ȑ䕗�̊T��
���́@���߁@�{���䕗�ЊQ�T��
���́@���߁@�����ɂ�����C�ۂ̖����Ɨ\��
���́@���߁@�����ɂ���
���́@�L���鑺�̔���
���́@���߁@�L���鑺�̐�j����@�O�O
���́@���߁@�L�˂ƈ��
���́@���߁@�L���鑺�̊J�J
���́@���߁@�����ɂ������ԁ@�O��
���́@���߁@�����̎x�z���Ƃ��Ă̌��
���́@���߁@�����̌��
���́@���߁@����̌��
���́@���߁@�R���L���̌��(�L����Ԑ�)
���́@���߁@�����̌��
���́@��O�߁@�e�����J�̏@�l�Z
���́@��O�߁@�L���鑺
���́@��O�߁@��ߔe��
���́@��O�߁@���Òn��
���́@��O�߁@�ɗǔg��
���́@��O�߁@�u�Γc��
���́@��O�߁@������
���́@��O�߁@�n�Õ~��
���́@��O�߁@�ۉh�Α�
���́@��O�߁@������
���́@��O�߁@���Ǒ�
���́@��O�߁@���䑺
���́@��O�߁@�X�ۑ�
���́@��O�߁@������
���́@��O�߁@�`�g��
���́@��O�߁@������
���́@��O�߁@���Ǒ�
���́@��O�߁@���w����
���́@��O�߁@�Ð���
���́@��O�߁@�^�ʋ���
���́@��O�߁@�Օ�
���́@��O�߁@���Ղ̏�
���́@��l�߁@�����I�匠�Ɛ_�E�̕ϑJ�@�܌�
���́@��l�߁@�����ƍ��_
���́@��l�߁@�i�Əj��
���́@��l�߁@�_�E�g�D�̊���
���́@��l�߁@�a�ɂ���
���́@��l�߁@�����̐_��
���́@��l�߁@�n���̐_��
���́@��ܐ߁@�ꌹ�ɂ��ā@�Z��
���́@��ܐ߁@���K�̌ꌹ
���́@��ܐ߁@�L����̌ꌹ
���́@��Z�߁@�����̕ϑJ�@�Z��
��O�́@�s��
��O�́@���߁@�L����Ԑؔԏ��ȑO�@����
��O�́@���߁@��������
��O�́@���߁@�i����
��O�́@���߁@���^���̎���
��O�́@���߁@�L����Ԑؔԏ�����@����
��O�́@���߁@�i�|
��O�́@���߁@�n����
��O�́@���߁@�剮�q
��O�́@���߁@��|
��O�́@���߁@���|
��O�́@���߁@�앗�|
��O�́@���߁@�啶�q
��O�́@���߁@���t���q
��O�́@���߁@���k�쓖
��O�́@���߁@���R������\
��O�́@���߁@������
��O�́@���߁@�v�n��
��O�́@���߁@�|
��O�́@���߁@��
��O�́@���߁@�k�쓖
��O�́@���߁@�R��
��O�́@���߁@���m��
��O�́@���߁@����
��O�́@��O�߁@�����̊K�����x�ƒn���@����
��O�́@��O�߁@�K�����x�̂���܂�
��O�́@��O�߁@�n���ɂ���
��O�́@��l�߁@�p�˒u����@����
��O�́@��l�߁@�l���ɋ敪
��O�́@��l�߁@�����g���̑g�D�ƋƐ�
��O�́@��l�߁@���n����Ԑؒ������ꗗ
��O�́@��l�߁@�Ԑ؎J�����E�ҋ�
��O�́@��l�߁@���s���ꗗ
��O�́@��ܐ߁@�L����ԐE�����@�@��Z�O
��O�́@��ܐ߁@�_���Ɋւ���Ԑؓ��@
��O�́@��ܐ߁@�����@
��O�́@��ܐ߁@�������@
��O�͑�Z�߁@�����̍�t�����ƍv���ɂ��ā@���l
��O�́@�掵�߁@���̕��݁@���Z
��O�́@�掵�߁@�����O��̊T��
��O�́@�掵�߁@�����a�J�ɂ���
��O�́@�掵�߁@���{�a�J�ɂ���
��O�́@�掵�߁@���̕���
��O�́@�掵�߁@�R�p�y�n����
��O�́@�掵�߁@����������
��O�́@�掵�߁@���L��
��O�́@�掵�߁@�L���鑺�\������
��O�́@�攪�߁@�������@��l��
��O�́@���߁@���c��@�ꎵ��
��l�́@�����̏����x
��l�́@���߁@�y�n�̐��x�@���O
��l�́@���߁@���ˎ���̓y�n���x
��l�́@���߁@�S���n
��l�́@���߁@�n���n
��l�́@���߁@�I�G�J�n
��l�́@���߁@�m���N���C�n
��l�́@���߁@�d�����n
��l�́@���߁@�d���m�s�n���n
��l�́@���߁@���~�n
��l�́@���߁@����n
��l�́@���߁@�����n
��l�́@���߁@�n������y�n�̎��
��l�́@���߁@�p�˒u����̓y�n���x
��l�́@���߁@�y�n���L���F��(���)
��l�́@���߁@�y�n�Ē���
��l�́@���߁@�_���A�E���Ǝ��Ɓ@��Z�Z
��l�́@���߁@�����_���@�ւ̐ݒu
��l�́@���߁@�_�����ƒn���̔_��
��l�́@���߁@�_���ɂ����鏧�㎖��
��l�́@���߁@���R�����ɂ���
��l�́@���߁@�_����
��l�́@��O�߁@�Ő��̉��v�@���Z
��l�́@��O�߁@��������
��l�́@��O�߁@�i����
��l�́@��O�߁@���^������
��l�́@��O�߁@�Ő��̊m��
��l�́@��O�߁@���̕ϑJ
��l�́@��O�߁@�n�d�̕�����
��l�́@��O�߁@�ŖڂƐŕi
��l�́@��O�߁@�v�d�Ɨ^���x
��l�́@��O�߁@�F���ւ̍v�[���̗R��
��l�́@��O�߁@�L����Ԑؔ[�Ŋz
��l�́@��O�߁@�v��K�Ə��i��㒠
��l�́@��l�߁@�����̉ݕ����x�@����
��l�́@��l�߁@�×����̉ݕ�
��l�́@��l�߁@���ւ藮���ʕ�
��l�́@��l�߁@���̐��x
��l�́@��ܐ߁@�ːА��x�@���Z
��l�́@��ܐ߁@���{�̖����ȍ~�ɂ�����ː�
��l�́@��ܐ߁@�ːЕҐ��]�� |
��l�́@��ܐ߁@���̌ːЎ���
��l�́@��ܐ߁@�V���@�̎{�s
��l�́@��ܐ߁@�Z���o�^���x�̊T�v
�́@�o�ϐU����{�v�揑�v���
��́@���߁@���j�@��O��
��́@���߁@�ڕW�̍���@��O��
��́@��O�߁@�ڕW�B���̂��߂̕���@��l
��́@��l�߁@���ƌv��@���
��́@��ܐ߁@�����v��@�Z
��Z�́@����
��Z�́@���߁@�M�Z�m�Ï��ƌ�a��� �䋳���@�O
��Z�́@���߁@�L���鏬�w�Z�̑n���@�Z
��Z�́@��O�߁@��㗮������̂���܂��@�Z
��Z�́@��O�߁@�Z�A�O�A�O�A�l���x�̎��{
��Z�́@��O�߁@�n������s��
��Z�́@��O�߁@�����ƍ���
��Z�́@��O�߁@�w�Z�Z�Ɍ��z�o��
��Z�́@��O�߁@�w�Z���H
��Z�́@��l�߁@�L���鑺����@�ց@�l
��Z�́@��l�߁@����ψ���
��Z�́@��l�߁@���Z(�ݔN)
��Z�́@��ܐ߁@�������w�Z�@���Z
��Z�́@��Z�߁@���䏬�w�Z�@���l
��Z�́@�掵�߁@��c���w�Z�@��㔪
��Z�́@�攪�߁@�L���钆�w�Z�@�O�Z�Z
��Z�́@���߁@��K����@�O�Z��
��Z�́@���Z�߁@�Љ��@�O�Z��
��Z�́@����߁@����p��x�@�O�ꔪ
��Z�́@����߁@�암�_�э����w�Z�@�O���
�掵�́@�l��
�掵�͑��߁@�����e�_��̍F�s�ƌ������̋N���@�O���
�掵�́@���߁@�X�ې����@�O��O
�掵�́@��O�߁@��鐷���@�O��l
�掵�́@��l�߁@�������@�O��l
�掵�́@��ܐ߁@���NjT���@�O���
�掵�́@��Z�߁@�L�쒉�i�@�O��Z
�掵�́@�掵�߁@�㌴�m���Y�@�O��Z
�掵�́@�攪�߁@��鐷���@�O��
�掵�́@���߁@�X�ې���@�O��
�掵�́@���Z�߁@�����T���Y�@�O��
�掵�́@����߁@�����_�@�O���
�攪�́@����`��
�攪�́@���߁@��n�����ہ@�O�O��
�攪�́@���߁@�������@�O�O��
�攪�́@��O�߁@�^�ʋ��̓����q�@�O�O�O
�攪�́@��l�߁@�n���Əj���@�O�O�O
�攪�́@��ܐ߁@�����@�O�O�l
�攪�́@��Z�߁@�L�W�����ƗF�B�ɂȂ����l�@�O�O�l
�攪�́@�掵�߁@�����߁@�O�O��
�攪�́@�攪�߁@�\�l�����Y�Ɠ���@�O�O��
�攪�́@���߁@�e�[���V�J�}�O�`�@�O�O��
�攪�́@���Z�߁@�ԗ�V�{���̑P�s�@�O�l��
���́@����
���́@���߁@�e�����撷�ꗗ�@�O�l�O
���́@���߁@���ʑ��c����c���ꗗ�@�O����
���́@��O�߁@���L����@�O����
���́@��l�߁@���X�ہ@�O��Z
���́@��ܐ߁@����ߔe�@�l�Z�Z
���́@��Z�߁@�����Òn�@�l�Z�l
���́@�掵�߁@���c���@�l�Z�Z
���́@�攪�߁@�������@�l�Z��
���́@���߁@���^���@�l���
���́@���Z�߁@���ɗǔg�@�l��O
���́@����߁@�������@�l���
���́@����߁@���n�����@�l�ꎵ
���́@���O�߁@����c�@�l���
���́@���l�߁@���n�Õ~�@�l���
���́@���ܐ߁@�������@�l��l
���́@���Z�߁@���ۉh�@�l��
���́@��ꎵ�߁@������@�l�O��
���́@��ꔪ�߁@�����ǁ@�l�O��
���́@����߁@�������@�l�O��
���́@���Z�߁@���`�g�@�l�l��
���́@����߁@�����ǁ@�l�O
���́@����߁@�������@�l��
���́@���O�߁@���Ð��@�l�Z�Z
���́@���l�߁@���^�ʋ��@�l�Z�l
���́@���ܐ߁@���������@�l�Z��
��\�́@����
��\�́@���߁@�������ց@�l���O
��\�́@���߁@�L������
��\�́@���߁@�������
��\�́@���߁@������
��\�́@���߁@�ۉh�Ώ��
��\�́@���߁@���Ǐ��
��\�́@���߁@�^�ʋ�
��\�́@���߁@�ΉΖ
��\�́@���߁@�쐔�̉Y
��\�́@���߁@�Ð��o���^
��\�́@���߁@�C�R��{�҈ԗ�V��
��\�́@���߁@�̗w�@�l��Z
��\�́@��O�߁@���w�@�܈�O
��\�́@��l�߁@�q���̗V�с@�܈�Z
��\�͑�ܐߗ����×��̓ǐ��ƌ���y�L�W�����@�ܓ��
��\�́@��ܐ߁@���̌Ă���
��\�́@��ܐ߁@����Z�y�L�W����
��\�́@��ܐ߁@�L����̃X�[�`���[�}�[
��\�́@��Z�߁@�ی��@�ܓ�Z
��\��́@���̕����K��
��\��́@���߁@�c�搒�q�@�O�l
��\��́@���߁@�c�搒�q
��\��́@���߁@���Ɖ������߂ɂ���
��\��́@���߁@���M�@�O��
��\��́@���߁@�j�Ր_��Ɋւ��鑭�M
��\��́@���߁@����̍s�����ۂɊւ��鑭�M
��\��́@���߁@�g�����f
��\��́@���߁@�����f
��\��́@��O�߁@�咆�@�l�l
��\��́@��O�߁@�咆�̐_
��\��́@��O�߁@�_�l
��\��́@��O�߁@�咆�̋������J
��\��́@��O�߁@�咆�̑g�D�Ƃ��낢��̐��x
��\��́@��l�߁@���̕����K���@�l��
��\��́@��l�߁@�a��
��\��́@��l�߁@����
��\��́@��l�߁@����
��\��́@��l�߁@����̍�
��\��́@��l�߁@��
��\��́@��l�߁@���n
��\��́@��l�߁@�Ƒ���
��\��́@��l�߁@�您����
��\��́@��ܐ߁@�ߐH�Z�@�ܘZ�l
��\��́@��ܐ߁@�Z��
��\��́@��ܐ߁@����
��\��́@��ܐ߁@���H��
��\��́@��ܐ߁@�����َq
��\��́@��ܐ߁@��������
��\��́@��Z�߁@�_����y�@�܋��
��\��́@��Z�߁@�j��
��\��́@��Z�߁@���x
��\��́@��Z�߁@�_�x
��\��́@��Z�߁@গ��D
��\��́@��Z�߁@�O���V��
��\��́@��Z�߁@���ŋ�
��\��́@��Z�߁@���n
��\��́@��Z�߁@���y
��\��́@��Z�߁@���
��\��́@��Z�߁@�p��
��\��́@�N���s��
��\��́@���߁@�s���̂���܂��@�Z�Z�O
��\��́@���߁@�܂�����
��\��́@���߁@�N���s���ꗗ
��\��́@���߁@��ʍs��
��\��́@���߁@����s��
��\��́@���߁@�ꌎ�@�Z�Z��
��\��́@���߁@���U
��\��́@���߁@�O���̏���
��\��́@���߁@�ΐ���
��\��́@���߁@�����̏j
��\��́@���߁@���N�j
��\��́@���߁@�\�Z��
��\��́@���߁@�\����
��\��́@���߁@��\������
��\��́@��O�߁@�@�Z���
��\��́@��O�߁@���
��\��́@��O�߁@�ފݍ�
|
��\��́@��l�߁@�O���@�Z���
��\��́@��l�߁@�O��
��\��́@��l�߁@������
��\��́@��ܐ߁@�l���@�Z��l
��\��́@��ܐ߁@�l��
��\��́@��ܐ߁@���e��(�����������)
��\��́@��Z�߁@�܌��@�Z���
��\��́@��Z�߁@�l���̓�
��\��́@��Z�߁@�܌��ܓ�
��\��́@��Z�߁@�܌����
��\��́@��Z�߁@গ��D
��\��́@�掵�߁@�Z���@�Z�ꔪ
��\��́@�掵�߁@�Z�����
��\��́@�掵�߁@�J�V�`�[
��\��́@�掵�߁@�j��
��\��́@�攪�߁@�����@�Z���
��\��́@�攪�߁@�^�i�o�^
��\��́@�攪�߁@�~��
��\��́@�攪�߁@�G�C�T�[
��\��́@�攪�߁@�}�}�E���j���u�`(�p�e�O��)
��\��́@�攪�߁@�`�����W�����i�K��(���҂̗���)
��\��́@���߁@�����@�Z��
��\��́@���߁@���[�J�r�[
��\��́@���߁@�č���
��\��́@���߁@�Ď��̏j
��\��́@���߁@�\�ܖ�
��\��́@���߁@�t�`���M
��\��́@���߁@��ݍ�
��\��́@���߁@�_�q��
��\��́@���߁@������̗�n
��\��́@���߁@�q��
��\��́@���Z�߁@�㌎�@�Z�O�O
��\��́@���Z�߁@���ԏj(�J�W�}���[)
��\��́@���Z�߁@�㌎���
��\��́@���Z�߁@�Ď�q(�}�[�_�j)
��\��́@���Z�߁@����q��
��\��́@��\��߁@�\���@�Z�O�l
��\��́@��\��߁@�Ώ��̌��
��\��́@��\��߁@��q���
��\��́@��\��߁@�\�ꌎ�@�Z�O��
��\��́@��\��߁@�ӂ�����
��\��́@��\��߁@�~��
��\��́@��\��߁@���N�T���V
��\��́@��\�O�߁@�\�@�Z�O�Z
��\��́@��\�O�߁@�S��
��\��́@��\�O�߁@�}��
��\��́@��\�O�߁@�N�̖�
��\��́@��\�l�߁@�j�Փ��@�Z�O��
��\��́@��\�l�߁@�����̏j�Փ�
��\��́@��\�l�߁@���{�̏j���ƋL�O��
��\�O�́@�Y��
��\�O�́@���߁@�_�� �{�Y ���Y �H�Ɓ@�Z�l�O
��\�O�́@���߁@��̓`��
��\�O�́@���߁@�Ă̐��Y��
��\�O�́@���߁@�����ɂ���
��\�O�́@���߁@�썑�����ƋV�Ԑ^��
��\�O�́@���߁@�������v����
��\�O�͑��ߓ����͔|�̉��P�Ƌ���}�o�V�e�_��
��\�O�́@���߁@�����i��̕ϑJ
��\�O�́@���߁@���̓�������i��
��\�O�́@���߁@�����̋N��
��\�O�́@���߁@�����͔̍|
��\�O�́@���߁@�i���r����
��\�O�́@���߁@�Y����
��\�O�́@���߁@��������@�̕ϑJ
��\�O�́@���߁@�����f�Վ��R������
��\�O�́@���߁@�{�Y
��\�O�́@���߁@���a��N���̒{�Y
��\�O�́@���߁@��O�ɂ�����L���鑺�̒{�Y
��\�O�́@���߁@���̒{�Y
��\�O�́@���߁@���̖L���鑺�̒{�Y
��\�O�́@���߁@�ڏo�`�؉��|
��\�O�́@���߁@���̑`�؉��|
��\�O�́@���߁@�_�ƎG��
��\�O�́@���߁@�_��ƍ앨�i��
��\�O�́@���߁@�_������
��\�O�́@���߁@�������i���
��\�O�́@���߁@������
��\�O�́@���߁@�a���͔|
��\�O�́@���߁@���Y��
��\�O�́@���߁@�H��
��\�O�͑��ߖL���鑺�_�Ƌ����g���̉��v�@���l�Z
��\�O�́@���߁@�����ӔC�L���鑺�w���M�p�g��
��\�O�́@���߁@�ۏؐӔC�L���鑺�M�p
�@�@���̔��w�����p�g��
��\�O�́@���߁@�����ϑ����ݒu
��\�O�́@���߁@�L���鑺�_�Ɖ�
��\�O�́@���߁@���_�Ƒg���ݒu
��\�O�́@���߁@���g�����ꗗ
��\�O�́@���߁@�L���鑺�_������
��\�O�́@���߁@�L���鑺�_���햱��E��
��\�O�́@���߁@�L���鑺�_�Ƌ����g��
�@�@����v���萄�ڏ�
��\�O�́@��O�߁@�������Ƌ����g���@���܁Z
��\�O�́@��O�߁@���|�_����
��\�O�́@��O�߁@�R���`�؎戵�v��
��\�l�́@���ݒʐM
��\�l�́@���߁@��ʂ̕ϑJ�@���܋�
��\�l�́@���߁@��O
��\�l�́@���߁@���
��\�l�́@���߁@��݊���Ɩ����Ď���
��\�l�́@���߁@�����H�ɂ���
��\�l�́@���߁@�����y�n���ǎ���
��\�l�́@���߁@�����ɂ���
��\�l�́@���߁@�암�㐅��
��\�l�́@���߁@���{��
��\�l�́@���߁@����
��\�l�́@���߁@������
��\�l�́@���߁@�L���鑺��ʐ}
��\�l�́@���߁@���Đe�P�ƌ��݁@���Z��
��\�l�́@��O�߁@�d�C�ʐM�@������
��\�l�́@��O�߁@�d�b
��\�l�́@��O�߁@�d�C
��\�l�́@��O�߁@�e�q���W�I
��\�l�́@��l�߁@���z�@�����l
��\�́@�Љ�
��\�́@���߁@��ÂƖ�a�@������
��\�́@���߁@��̂����
��\�͑��߁@��A�Z�Z�Z�N���̗����̕a�C��
��\�́@���߁@������p�A��
��\�́@���߁@��p����
��\�́@���߁@���
��\�́@���߁@�Y�k
��\�́@���߁@�I���p
��\�́@���߁@�����̕ی��@�����
��\�́@���߁@������
��\�́@���߁@���l�a
��\�́@���߁@�q�������v��
��\�́@���߁@�ی����ƌ��Ŋ���
��\�́@���߁@�V�l����
��\�́@���߁@����̉�̕��z
��\�́@���߁@�����J�ƈ�t
��\�́@���߁@�Y�k��
��\�́@��O�߁@�Љ�����Ɓ@���Z��
��\�́@��l�߁@���쎖�Ɓ@�����
��\�́@��ܐ߁@�ږ��ڏZ���Ɓ@�����
��\�́@��ܐ߁@�L���鑺���Z�ˌ�����
��\�Z�́@����
��\�Z�́@���߁@�ԏ��h���@����O
��\�Z�͑��߁@�L���鑺�X�ǂ̉��v�@����O
��\�Z�́@���߁@�L����X��
��\�Z�́@���߁@�ǒ��X��
��\�Z�́@���߁@���̖L����X��
��\�Z�́@��O�߁@�������ݏ��@����Z
���^
���������ꗗ�@���O�Z
����j�N�\�@���O��
���ꌧ��㒷���@���l
���s����ȁ@���Z��
����(�����_���p��)�@���Z��
�n���}�@������
�咆�����\�@������
�䂪�Ƃ̌n�}�@��Z��
�Q�l�����@��Z�l
�E
�E |
�R���A�|�\�w��ҁu�|�\ 35(3)(409)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����Bpid/2276698
|
<��>�܌��M�v�v��l�\�N / �F����o�j/p9�`9
���{�|�\�̏����<���W>/p10~30
�A�\�r�ƒ���--�`�{�l���C�̎��� / ���䖞/p10�`16
�����|�\�Ɋւ���1�̌��� / �㓡�i/p17�`23
���Ð�Ƃ̒f�� / �����N��/p24�`30
�܌��M�v�̐��E(����)����\���c�[�̐߃A���K�}(2)� /
�@�@�� �O�����Y ;�F����o�j/P6~
���{�̖����|�\-29-���쌧 / �q�Β��F/p31�`44
<���]>�����N�璘�w���Ҙ_�� �]���x / �����b��/p45�`45
�Ǔ� �˔N�� / �n�ӕ� ;���c�m/P46~49
|
�˔N��̎��� / �n�ӕ�/p48~49
�����蒟(1��) / ���c�m/p50~53
���x�蒟(10�����{�`11�����{) / �@���q/p54�`57
������匀��w�����x�����̏���� / ��{�Y�O/p58�`58
�m�y��I�y���̏㉉�ƃ��p�[�g���[�̊m��� / �O�H����/p59�`59
�m����`���C�R�t�X�L�[�̖v���Z�Z�N� / �R�씎��/p60�`60
�\���������������L���ɐV�@�ƣ / ���N��/p61�`61
�����|�\����w����w�̐�������`���� / �������q/p62�`62
�e���r��c�_�S�o�̎l�\�N�� / ����ˎO/p63�`63
�V���ē�/p64~64 |
�R���A�R�{�G�q�����������������������|�\���ҁu�|�\�̉Ȋw = Gein no kagaku 21 : �|�\�_�lXIV p.149-182�@�����������������v�Ɂu����ǒJ���̃G�C�T�[�̓`���g�D�\�����|�\�̓`���g�D�ƎЉ�E�o�ύ\���Ƃ̑��K��W�\�v�\����B�@�@�iIRDB�j�@�d�v
|
�u���N�v�̒�`�ƊT�O�ɂ���
�H�c�⒘�C�����|�\�Ɍ��鉄�N�̏���
���̂Q�|��ږ��Ƃ��Ẳ��N����
�����Ύq���C�щz���̏j��
���q�b�q���C���N�̉��y�i��j�|�����̏ꍇ |
�����������C���Ѝs���ɔ����u���y�v�̎�e�ƕϗe�ɂ��ā|�l�V�������y�̓`�d�����߂�����
�������s���C�S�̚��q�̌Ñԁ|�q���c�r�Ńn�^���C���\��
���K���Âݒ��C����ǒJ���̃G�C�T�[�̓`���g�D�|
�@�@�������|�\�̓`���g�D�ƎЉ�E�o�ςƂ̑��K���W
�R�{�G�q���@�|�\�_�l. �P�S |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 6�v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
���l���̌���� �g�Ɗԉi�g p.1-21
�u��p�z㉌`�V���{�v��
�@�@���u��G�}�v�ɂ������R�̕��ނƔ�r ���x�B p.23-34 |
���Ԗ������Â̔N���s�� :
�@�@�� �n�}�E��(�l����)�𒆐S�� �v���c�W,�������q 1 p.35-102
���ꌧ���|�p��w�����������b�� p.103-110 |
�R���A���쐭�����u����̕� : �ɔg���Q�Ƃ��̎���v���u��g���X�v���犧�s����B
|
��P�́@���ւ���Ƃ߂�
��Q�́@�V�m���l�̒a���ƋA��
��R�́@�w�×����x |
��S�́@���_�v���̕z����
��T�́@�]��Ɨ���
��U�́@�u�Ǔ���v�Ɓu�쓇�v�ӎ� |
��V�́@�u���v�Ȃ郄�}�g
��W�́@�S�т̂��Ƃ�
�E |
�R���A�R�����j���u�R�����j����W�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B
|
��1�� �����̉��y�|�\�j. ��� �r�{����,���]�F�`����
��2�� ���������×w��Ȃ̌���.
�������y�̎��n�I���� ��� �r�{����,���]�F�`��
��3�� �_���W ���y�E�y���� �����̉��y�ɏA����
�����̉��y
�������y�̔����̎p
�������y�j��
���{�O�����̗R����ǂ݂�
���ԉv�F��Z�ɒ悷
�^�ߗ䌘�T�Z�ɓ���
���̍��x�̕W��.
�������y�̎��Ԃ̑��x
�M�y�Ɨ������y�Ƃ̊y���I�W
���w�Z���̋����G��
|
���������×w��Ȃ̌�����L
�ӂ邳�Ƃ̉��y
�̗w�E�|�\�� �O�\��(����)�̎��`�ɂ���
�s�X��Ɨ���(������)�̉̌^�I�q����
�\�����߂ɂ���
�����̗̉w�ɂ���
�����ɉ�������S�̖��H�ƔO���y�і��̌���
����̐l�`�ŋ�
������N�ƌ�V����
��N�̌�V����Ƀ����V�[�͑啨
�����̖~�x
�w�������x�j�x����
�����̐��_�Ɛ��_�y. ��� ��Éx�q��
�N���E����ژ^:p493�`509 |
�R���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (40)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@
pid/6067747
|
�C�k �쓇���w�̔����Ɠ`��--���w�ƃV���[�}�j�Y��
�@����Ƃ̏o� / �J�쌒�� ;�Ë��M�F ;�����K�� ;��ÍN�Y/P4~9
�@������߂��镶�w�ƃC�f�I���M�[ / �J�쌒�� ;�Ë��M�F ;
�@�@�������K�� ;��ÍN�Y/p9~12
�@�l���łƉ��� / �J�쌒�� ;�Ë��M�F ;�����K�� ;��ÍN�Y/p12~15
�@�����̒n�搫�Ƌ��ʐ� / �J�쌒�� ;�Ë��M�F ;�����K�� ;��ÍN�Y/p15~19
�@�w�쓇���w�����_�x�Ɛ܌��M�v / �J�쌒�� ;
�@�@���Ë��M�F ;�����K�� ;��ÍN�Y/p20~23
�@�����Ƌ{�ẪV���[�}��/�J�쌒��;�Ë��M�F;�����K��;��ÍN�Y/p26~33
�@���^�̑n���́E�`���̔���/�J�쌒��;�Ë��M�F;�����K��;��ÍN�Y/p42~45
�@�떓�̃t�T�A�Ñ�E����/�J�쌒��;�Ë��M�F;�����K��;��ÍN�Y/p50~55
�@��� �����ǂ̐��Y�����\�� / �����K��/p20�`20 |
�@��� �m���̕\���ƃ��^�̕\�� / �����K��/p24�`24
�@��� �u�����_���L�v�̒��̏@����/�����K��/p31�`31
�@��� ���������Ƌ{�Ô��d�R / �����K��/p34�`34
�@��� ���^���|�̐��� / �����K��/p46�`46
�@������I��/p43~43
�@������II��/p51~51
�A��(2)���؋� �����^��(���̓�)���͗l/�������V/p56�`57
�V�A�� ���t�͐����Ă���(1)�����݂̎���/�ΐ쒉�b/p58�`61
�V�A�� ���������y�m�̃C�T�[���s
�@�@��(1)�A�W�A���| / �~�Øa��/p62�`67
�E |
�R���A��ÍN�Y���u�_�X�̌Ñw : �L�N�������� �q���Z�}���J�C[�����哇]
11�v���u�j���C�Ёv���犧�s����B
�@�@�@ 111p�@�@�����F��㊌����}���فF1002062782
�S���A�r��דT[�ق�]�ҁu�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�j 6 (�����ƋZ�p)�@�v���u������w�o�ʼn�v���犧�s�����B
|
�A�W�A�̒��̓��{���� �i���c��
�Z�p�̓`�d�Ɠ��{ ���X�؋�풘
���N�̎��w�Ɛ��w ��������
�u����܁v�̔�r�j �����F�N�� |
�����킩�猩����r�Z�p�j�_ ��ǖ���
��E�V�����߂��鏔�� �R��������
�A�W�A�ɂ�����e�ƖC �t���O��
�����ƊO�� ����͉ |
���̓��Ǝm��v �F�q���v��
��������̔�r�j ���{�K�v��
�֎q�ƍ� ����a�q��. �H���Ƌ��� ���c�M�j��
�A�W�A�̒��̓��{�̉��y ���c���q�� |
�S���A�r��דT, �Έ䐳�q, ����͉�ҁu�����ƋZ�p�v���u������w�o�ʼn�v���犧�s�����B
(�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�j / �r��דT, �Έ䐳�q, ����͉��, 6)
|
�A�W�A�̂Ȃ��̓��{���� : �u���{�����_�v�ᔻ�̈ꎋ�p/�i���c��
�Z�p�̓`�d�Ɠ��{ / ���X�؋��
���N�̎��w�Ɛ��w / ������
�u����܁v�̔�r�j / �����F�N
�����킩�猩����r�Z�p�j�_ / ��ǖ�
��E�V�����߂��鏔�� / �R������
�A�W�A�ɂ�����e�ƖC / �t���O |
�����ƊO�� / ����͉�
���̓��Ǝm��v / �F�q���v
��������̔�r�j / ���{�K�v
�֎q�ƍ� : ������̕����𒆍��E���N�E���{�Ɍ��� / ����a�q
�H���Ƌ��� / ���c�M�j
�A�W�A�̂Ȃ��̓��{�̉��y : �O�����y�̎�e�ƒ蒅 / ���c���q
�E |
�S���A �^�������u�S�鉫��̉̂����`�{�쉹�y�E����{���ҁv���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B
�^���f�B�X�N 2�� �F�i71��48�b/71��14�b�j
|
| [1] |
(1)������ŕ���(2)��(3)����c��(�����o��)(4)��(�グ�o��)(5)�\������(6)�q����(7)������(8)�V�e�c�N�F�[�i(9)���N�F�[�i(10)���肶��N�F�[�i(11)�����x(12)�V�̌Q��(13)���ᒗ(14)�r���炵(15)��@�ẪE�V�f�[�N(16)�Ì����̃E�V�f�[�N(17)���q��(18)�J��S(19)�����G�C�T�[(20)�H���y(21)���҂̑��(22)��̓� |
| [2] |
(1)�������[��`�J���O�`���߃��[�`���K�V��߁`��������߁[���`���K�R�`���D�ǁ[��(2)�n�[���[�S�`�ӂ�����[�Ɂ[����(3)�ʼnԌ�(4)������(5)��m�s(6)�n��(7)���h��(8)����������(9)�Ă҂��S(10)�����S(11)���[�Ղ���(12)���A�m�݂�[����(13)�l�璹��(14)��ԓ���(15)�܂����(16)�v�Ĉ��Ð�(17)���ĂȐ�(18)�C�̃`���{�[��(19)���n�͂O��(20)�q��S(�悢�悢�悢�`�킪��������)(21)��(�Ɓ[�Ɓ[�߁`�z�C�z�C�z�C�`�ꂿ��݂[(22)��(�݂�Ȃ̂߂́[�̂��炭�݂�)(23)���S(�܂��܂��ʂ�ʂ�`�[���`�タ�ʂԂ�`���Ԃ��݁`�����܁[��`�Ȃ�炵���[���Ⴊ)(24)��(���̏�ˁ[�`�������ᐳ���ǂ��[�`�ɍ]�͂�����[���`�ߔe�ʂ܁[�`�����`�ЂȂ�Ȃ�Ȃ�) |
|
�T���A�u���ϕ��� (28)�v���u�|�[������������ �v���犧�s�����B�@pid/1845843
|
�Βk:����̑��g�������l���� / �O�Ԏ�P ;����q��/2�`15
�ɖ�g�߂̏��� / �D�z�`��/16�`17
�G�Ɍ��问�����l / ����F/18�`19
���ꥌ��ƍg�^�̐F / �o�ߗ��q/20�`21
������̕���������� / �R����/22�`23
����Ɉ���������Ɛ� / �ݖ{�}�`�q/24�`28
�������x�̒S����Ƃ��� / �^�������q/29�`32
�������x�̔� / �r�{����/33�`40
�I�����Ɍ�����ӎ��Ƒ��� / �g�Ɗԉi�g/41�`52
����̉��ʐ_�Ƒ����_ / ���{/53�`66 |
�쓇�̓��n�K���\�\���Ƃ��Ă̐j�� / ���Ð^�鏟/67�`79
���F�l�c�B�A����̎莆(��) / �咬�u�Îq/80�`87
���ς̑��_��W���� //113�`113
�G��Ɍ��鉻��(8) / �����T�q
���w���T��(1) / ������/88�`89
�쌀�ɂ݂鉻��(4) / �����w/90�`97
�Ñ�C���h�l�̂悻����(26) / ���R�r���Y/98�`113
���Ϥ���̃R�~���j�P�[�V����(2) / ��V��v/114�`128
���p��U�w����(4) / �����j/129�`142
�E |
�T���A�|�\�w��ҁu�|�\ 35(5)(411) �v���u�|�\���s���v���犧�s�����B
�@�@�@pid/2276700�@�����F���ꌧ���}���فF1001646908
|
<��>�����̕� / ���ʐM/p9~9
�|�\�w��E����|�\�j����������<���W>/p10�`30
�g�x��{�̢��\(�݂Ȃ݂�����)���k�\(����������)����l���� / ���Ԉ�Y/p10�`16
�������{�ɂ����钆���n�̉��y�Ƣ����y��̉��� / ��Éx�q/p17�`23
�܌��M�v�̉���|�\����--
�@�@����O�̉���̋��y�����Ƃ̊ւ��𒆐S�� / ���F�M/p24�`30
���Ƃ����낳�����(��㎵)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/P6~
<���]>�_�_��V���Z�T�C�U�[�_�y� / �����G�Y/p31�`31
�q����̏������r(����)���w�a�m�^ / ����K��Y/p32�`33
���](���W����) / ���ʐM/p34~35
�O�V���~�V�����w�͂Ȃ����ҋƁx���|���b����|�\���b��� |
�@�@���w�Í���������Ǝ��T�x / �r�c�O��/p36�`36
�����蒟(3��) / ���c�m/p37~40
���x�蒟(12����{�`1����) / �@���q/p41�`44
�������̓������ / ���ʏˎq/p45�`45
�M�y���Ԃւ̐g�̂̑Ή�� / ����p�r/p46�`46
������y���̊��p� / �������v/p47�`47
���{�̖����|�\-31-�啪�� / �����j/p48�`61
�w��ē�/p62~62
������/p63~63
�V���ē�/p64~64
�E |
�U���A�{�Ǎ��O�ҁu���{�������l���� : �k�Ɠ삩��̎��_�v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@
|
�l�Êw����݂��k�C���Ɠ쓇 / ���{��
�l�Êw����݂�����Ɩk�C�� / �m�O�E
�u���ꕶ�����v���߂����� / �哇���s [
�k�Ɠ�̎��R���� / ��{�^�s
���ƁE���E�E���� / �|�X�i
�u���v�̕�̂Ɖ���j / �q���P��
����Ɣ��� / ��Ό\��
"�k"��"��"�̖����ېV / �c����
����E�k�C���Ƒ�p�A���n / ���g����
�ߑ���{�Ɠ����A���n / �K���^�l
���O�Z�N�㋳���g���^�� / ���쐳 |
�������c�_����n��ŗL���� / ���Ô��
����Ɩk�C���ɂ����錻�㕶���̑n�� / ���c�D�M
����̉Ƒ������ւ̐ڋ� / �����Y
�Ǝ��̗��j�ƕ����̕��� / �V�萷�� [
�u��̊C�v�̊��ۑS�Ɛ��Y�� / ��c�s��v
������{�̔_�Ɩ��Ɓu��k��g�v / ���c������
�u���Ӂv�̌|�\ / �J�{��V
�������y / ���X���p
�ĂƓ� / ���c�M�j
�k�Ɠ�̔�r�H���� / ����{���q
�H�����̌p�� / ���c�����q |
�U���A�u�}������ (16) �v���u�}�����w����w�Z����w�� (������)�v���犧�s�����B�@�@pid/4425357
|
��A�u�����ǂ��֍s���v�_(1)�R�V���тƉ��� / ��������/p1�`17
��A�w�݂��ꔯ�x�ɂ݂鏻�q�̐^�� / ����]/p18�`30
�O�A�u�꒼�ƕ��w�ɂ�����u�������v�ɂ��� / ���c�K�b/p31�`44 |
�l�A�u�������v���l--
�@�@�����\�R�̗��͂Ȃ��N�������̂� / �剺���R�M/p45�`61
�܁A�u�����s�����̓��ԁv--�A���P�[�g�𒆐S�� / �x�g����/p62�`75 |
�V���A��Î��ҁu���Ɩ{�w�����낳�����x�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�@�@�@(���ꌤ������, 14)
�V���A�F���g�������o�ϑ�w�l�����R�Ȋw������ҁu�����o�ϑ�w�l�����R�Ȋw�_�W (�ʍ� 94) p.p162�`150�@�����o�ϑ�w�l�����R�Ȋw������v�Ɂu��x�M�Ƒc�搒�q-���d�R�Q���E�Ί_���̏ꍇ�v�\����B
�V���A�u �|�\ 35(7)(413) �|�\�w�� �� �|�\���s�� 1993-07/pid/2276702/1/1
|
<��>�����̌|�\�ɂ��Ă̏�� / ����h/p9�`9
����̖��ԓ`��<���W>/p10~30
��������ꉉ���̕���j / ��쓹�Y/p10�`16
���ŋ��̕��� / �i�R����/P17~23
����̖��ԓ`�� / �O�����Y/p24�`30
��֏��ԣ(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
<���]>�_�_�����������˂Ȃ�Ȃ���� / �R�H����/p31�`31
���w�a�m�^ ��l��q���É��R�O�̐��́r / ����K��Y/p32�`33
���]�q���W�E�����r / �X�N��/p34~35 |
�͒|�o�u�v���w�و���x / ���{����/p36�`36
�����蒟(5��) / ���c�m/p37~40
���x�蒟(3�����{�`4�����{) / �@���q/p41�`44
���������̕���ւ̋^�� / ���ʏˎq/p45�`45
�M����f�x��̈ӎ�� / ����p�r/p46�`46
���w����{���w�����ق̐ݗ��� / �������v/p47�`47
���{�̖����|�\-33-�X�� / �O�菃��/p48�`61
�V���ē�/p64~64
�E |
�W���A�A�����G�{�̉;�{�NjM�q�G�u�G�C�T�[�v���u���ꎞ���o�Łv���犧�s�����B (�ӂ邳�ƊG�{�V���[�Y, II. 3)
�W���A���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (�ʍ� 58) p.p91�`93�v�Ɂu�̓��c���q���𓉂ށv���f�ڂ����B
�@�@�܂��A�������Îq���u����p.p92�`93�v�Ɂu�̓��c���q���̔N���ƋƐ� (�̓��c���q���𓉂�)�v����B
�W���A���{��������ҁu���{���w��� ���ꉂ�� ���������ҁv���u���{��������v���犧�s�����B
|
��
�}��
�f�ڋȈꗗ
�����ꉹ�ߕ��ޕ\
�^�������̏o���ꗗ�\
�쐼�����̎��R�E���j�E����
1 ���R�ƕ��y�@1
�i1�j �n��
�i2�j �C��
�i3�j ���E�A��
2 ���j�@2
�i1�j ��j����
�i2�j �O�X�N���ォ�琭���I�x�z�҂̏o���܂�
�i3�j �����̐����Ɖ^�c
3 �����@3
�i1�j ���̂̕����̒��ɂ݂�쓇�����̕�����
�i2�j �����o�ς̒����琶�݂����ꂽ�S�̕���
4 ���{��̒��̉����@4
�i1�j �����͈̔͂Ƌ敪
�i2�j �����̕���
�i3�j �����̓���
�쐼�����̉��y�����T��
1 ���y�I�����@7
�i1�j �̂̒S����
�i2�j �̂̃W�������ƌ��n�ď�
�i3�j �����`��
�i4�j ���y�̏��v�f
�i5�j �y��
�i6�j �x��
�i7�j �|�\
�i8�j �`���̂����
2 ���ނƔz��@12
���������̕��y�E���j�E����
1 ���y�@15
2 ���j�@16
�i1�j ���n������
�i2�j �i����
�i3�j ������������
�i4�j �ߐ�
�i5�j �߁E����
3 �l�X�̂��炵�@18
�i1�j ����
�i2�j �ߐH�Z
4 �M�ƍՂ�@19
�i1�j �m���i�j���j�ƃ��^�i�ގҁj
�i2�j ���X�̖��Ԃ̍Ղ�
���������̉��y�T��
1 ���ނƔz��C�I�Ȃɂ��ā@22
2 �������w�̉��y�I���F�@23
�i1�j �W�������Ԃ̐����̌�
�i2�j �y��
�i3�j �����`��
�i4�j �̎��Ɛ���
�i5�j ���Y���E�e���|
�i6�j ���E���K
���������̗̉w �N�`�C�����x��̒��S��
1 �_�w�Q�@27
�i1�j �N�`�̈З�
�i2�j �T�J�E�^�̎���
2 �����x��@28
�i1�j �A���Z�c�i�V�߁j
�i2�j �V�o�T�V�i����j
�i3�j �V��̂Ƃ��Ă̔����x���
�i4�j �����x��̂̉̏��@
�y���E�̎��E���
I �q�ǂ��Ƃ̊ւ��
���ׂ����@35
�q��́@107
II �V��E�s���E�j��
�_���Ɋւ��́@121
�V���`���K�}�ƕ����}���J�C�@124
���������̃m�����J�ɂ��ā@130
�����̍s���́@166
�����̍s���́@166
�����x��́@166
���V���̔����x��ƕl����s���@282
���̑��̋����̍s���́@307
�H���̖ݖႢ�i�ނ��ނ�j�@316
�|�\�ɔ����́@333
���ݎŋ��ɂ��ā@336
����L�N�Ղɂ��ā@340
�^�_�\�ܖ�x��ɂ��ā@358
�ƍs���́@383
III �d���E���
��Ɖ́@421
���V���̏W�c�̊|�������́@448
IV �����E�V��
�����́E�V�щ́@469
�V���w�E���s�́@723
�V���w�@723
��@728
�Q�l�����@734
GENERAL VIEW ON THE NANSEI ISLANDS�@738
����
�Ȗ������@743
�n��ʉ����ҍ����@748
�e���̎��^�n��n�}�@733
���������@751
���Ƃ����@758
�ҏW��L�@763
�f�ڋȈꗗ
I �q�ǂ��Ƃ̊ւ��
���ׂ���
��������
1 ���v�[�v�[ �k��l�����s�������@36
2 ���X��� ����� �k��l�Z�p�� �s�@36
3 ��� ������� �܂�� �k��l�Z�p�� �s�@37
4 ��� �k���l���V�������v�u�@37
5 ���������� ���������� �k��l�����s�������@39
6 ������Ȃɂ� ������Ȃɂ�
�@�@�� �k��l�����s�������@39
7 �݂���܃� �k��l�����s�������@40
8 �J����ߎu �k��l�����s�������@41
9 �V�̉Ƃ̔R���� �k��l�����s�������@42
10 ���� ���� �k��l�}�����F�h�@42
11 �Ԃ炴�[���[ �k��l�����s�������@43
12 �m�����l��C����H�� �k��l�����s�������@43
13 �m�����̒c���D �k��l�����s�������@44
14 ��E�l�̐ԉH�K�b�^ �k��l�����s�������@45
15 �����l�̖ڂ͂� �k��l�����s�������@46
���܂����
16 ����[��� ����[��� �k��l�}�������m�@46
17 �������炪����� ��ޒ����� �k��l�}�����F�h�@47
18 ���Ԃ� ���Ԃ� �k��l�}�����F�h�@48
19 ���܃^���^�� �k��l�������ˌ��@50
20 ��� ��� �k��l�������ˌ��@50
21 �������痈��M�� �k��l�����s�����@51
22 ����ǂ� ����ǂ� �k��l�����s�����@52
23 �����`���`�� �k��l�����s�������@53
24 ���[���� �s�����
�@�@����������� �k��l�Z�p�������@55
25 ��ɒk���k�� �k��l�����s�������@55
26 �ӂ����オ�� �k��l�����s�������@57
27 �ߎq�g�~�������� �k��l�Z�p�������@61
28 ������ �k��l�Z�p�������@62
29 ��������ׂ� �k��l���˓�����@63
30 ��ԏ��� �k��l�F�������p�@63
31 ������ ������ �k��l�F�������p�@64
32 �����ԖV���� �k��l�F�������p�@66
33 ���̂͂� �k��l�F�������p�@67
34 ��� �k��l�F�������p�@70
35 �V���痎���� �k��l�F�������p�@72
36 �Ă����݂Ⴛ�[�� �k��l�F�������p�@73
37 �ł� �ł� �k��l�F�������p�@74
38 �Ƃ�Ɨׂ� �k��l�F�������p�@74
39 �ǂ�Ԃ艺�� �k��l�F�������p�@75
40 �����݂₫�� �k��l�F�������p�@76
41 �͂ډ��߂܂���� �k��l�F�������p�@77
42 ���Ƃ����큦 �k��l�F�������p�@78
43 ���� ���� �k��l��E���r�@79
44 �P�X����� �k��l��E���ԘA�@80
45 ����Ȃ�M���� �k���l���V�������v�u�@81
46 ����Ƃ����� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@82
47 �͂��͂��܂����� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@83
48 ���{ ���{ �k���i�l�m�����㕽��@84
49 䕎R �k�^�l�^�_�����ԁ@84
50 ���z���� �k�^�l�^�_�����ԁ@85
51 �ꂿ���� �k�^�l�^�_�����ԁ@86
�����炾�V�т̉�
52 ��� ���� �k��l�}�����p�@87
53 ���ԓ���ԓ��E��^��^ �k��l�}�����F�h�@87
54 ��^��^ �k��l�F���������@88
55 �Ή�� �k��l�����s�������@89
56 ��l��l �T�̎q �k��l�����s�������@90
57 �^��Y ��Y �k��l�����s�������@90
58 ��̉� �k���i�l�a�����a���@91
59 �������� ���� �k��l�����s�������@91
60 �� �� �ݍ� �k��l�����s�������@93
61 �Ă���݂� �Ă���݂� �k��l�F���������@94
62 �����ނ��ȁ[�ނ� �k���l�ɐ咬��O�@95
63 �����Ղ����� �k���l�V�钬�����ؖ��@96
64 �ӂ����キ��Ƃ� �ӂ�܂��� �k��l�}�����p�@96
65 ������������ �k��l�����s�������@97
66 ���������[�� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@98
67 ���K�b�^���� �k��l�}�����p�@98
������ʂ̉�
68 ������[ �k��l��E���r�@99
69 �ꂫ��� �k��l��E���ԘA�@100 |
70 ���ꂷ���� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@100
���S�������̉�
71 �ؖȂ���炶��� �k��l�F���������@101
72 �e�̎q���� �k���l�ɐ咬��O�@102
�����̑�
73 ��̔_�w�Z �k��l���˓�����@103
74 �荇���ፇ���� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@104
75 ������ �k���l���V�������v�u�@105
76 ����q�悤���� �k���l���V�������v�u�@105
�q���
77 �����Ȃ��� �k��l�}�����F�h�@107
78 �����ȃ� �k��l�}�����F�h�@108
79 ���C�������ȃ��V �k��l�����������@109
80 �����ȋ����ȃ� �k���l���V�����ԓ��@110
81 �˂�˂삵�� �k���l���V�����ԓ��@111
82 �C������ �q���� �k���l���V�����T�Á@111
83 �q��� �k���i�l�a�����a���@112
84 �q��́� �k���i�l�m�����m���@114
85 �q��́i�����j �k�^�l�^�_�����ԁ@115
86 �q��́i�����j�� �k�^�l�^�_�����ˁ@116
87 �q��́i���[���[�T�[�j(1) �k�^�l�^�_�����ԁ@117
88 �q��́i���[���[�T�[�j(2) �k�^�l�^�_�����ԁ@118
II �V��E�s���E�j��
�_���Ɋւ���
89 �m�����}���J�C�̉́n �k��l�������H���@121
90 �����ʗx�� �k��l�������H���@123
91 �m�V���`���K�}�̉́n �k��l�������H���@125
92 �~��I���� �k��l�����s��F�@127
93 ���_�̃I���� �k��l�����s��F�@129
94 �������܂��� �k��l�����s�Y��@131
95 �m�������܂��ˁn �k��l�����s�������@141
96 �m�Ɠ����S�n�i���^�̋F��j �k��l�����s�������@145
97 �m���������V�Ð_�n �k��l���˓����Ðm���@152
98 ����̃I���� �k���l���˓������ā@154
99 ����̃I���� �k���l���˓����ԕx�@155
100 �}���̃I���� �k���l���˓����ԕx�@157
101 �A���z�o�i�̈��̃I���� �k���l���˓����U�@159
102 �A���z�o�i�̈��̃^�n�x�F �k���l���˓����U�@160
103 �����l �k���l���˓������v�@161
104 �[���l�� �k���l���˓������v�@162
105 �͂��������܂��� �k���l���V�������a���@163
106 �m�H�Ð��́n �k���l���V�����T���@164
�����̍s����
�����̍s����
�������x���
107 �\���T���}���G �k��l�}�������m�@170
108 �˂낶�� �k��l�}�������m�@171
109 ���\���m�g�C�g�C�� �k��l�}�������m�@173
110 ���m��̂��ԁ� �k��l�}�������m�@174
111 �j���� �k��l�}�������m�@174
112 �Ԗؖ��ω��� �k��l�}�����p�@177
113 �Y���ǂ��� �k��l�}�����p�@178
114 ��E�Ă̔� �k��l�}�����p�@180
115 �i�����i�[�������l�E
�@�@���͂Ȑ��E�G�������R���j �k��l�}������}���@181
116 ���ڂ��� �k��l�}������}���@187
117 ��̎����� �k��l�}������}���@188
118 �l���ŏ��i�[���ԕ���ԁE
�@�@������ɂႾ��j �k��l�}������}���@189
119 ���̕��_ �k��l�}�����F�h�@193
120 �F�h�x�� �k��l�}�����F�h�@196
121 ���g���p�� �k��l�}�����F�h�@198
122 ���܂�������� �k��l�������H���@199
123 �Ȃ�卂�� �k��l�������H���@201
124 ������ �k��l�������ˌ��@203
125 �����̍� �k��l�������ˌ��@204
126 �l�璹 �k��l�������ˌ��@205
127 �����͂��� �k��l�����s�����@207
128 �Ē��̉Ԏ� �k��l�����s�����@208
129 �������x�� �k��l�����s�����@209
130 ��E�p�� �k��l�����s�������@210
131 ����˂��� �k��l�����s�������@212
132 �ɂ��̎��v �k��l�����s�������@213
133 ������Ƃ��i�[�V�̂Ђ��j �k��l�Z�p������@214
134 �C�̍����� �k��l�Z�p������@216
135 �⌳ �k��l�Z�p������@217
136 ���ڂ��� �k��l�Z�p�������ԁ@218
137 �ɂ������ᏼ�l �k��l�Z�p�������ԁ@221
138 �߂�� �k��l�Z�p�������ԁ@223
139 ���̎R�x �k��l�Z�p�������ԁ@225
140 ���Ȃ� �k��l��a�������@227
141 ���� �k��l��a�������@228
142 ���t�i�[�m���t�ł���́n(1)(2)�j �k��l��a�������@230
143 �G��� �k��l�F�������p�@234
144 ����܂��� �k��l�F�������p�@235
145 ������ �k��l�F�������p�@237
146 ��艺�� �k��l�F�������p�@239
147 �͂Ȑ� �k��l�F�������p�@240
148 ������_���_�� �k��l�F���������@241
149 �T���p �k��l�F���������@243
150 ����� �k��l�F���������@244
151 ���v������ �k��l�F���������@246
152 �����Ⴒ �k��l�F���������@248
153 �V�̂���܂��て �k��l�F���������@250
154 ���[�n�� �k��l�F���������@251
155 �����{�[�{�[�`�F �k��l�F�����F���@253
156 �����Ⴐ���Ⴐ�� �k��l�F�����F���@255
157 �h���h���� �k��l�F�����F���@256
158 ���ƂĂ� �k��l�F�������A�@257
159 ���߂��V �k��l�F�������A�@259
160 �ʂ�܂����� �k��l���˓�����@260
161 �Ƃ�� �k��l���˓�����@261
162 ������� �k��l���˓����Ðm���@262
163 �l���� �k��l���˓����Ðm���@264
164 ���Ă��� �k��l���˓����ÓS�@265
165 ����D �k��l���˓����ÓS�@267
166 �j�ꃀ�b�R�E �k��l���˓����ÓS�@269
167 �������ł��[ �k���l���˓������݁@271
168 ���ݒ��l �k���l���˓������݁@272
169 �z�[�G���G�[ �k���l���˓������݁@274
170 �G�n�C�� �k��l��E�����`�@274
171 �Ђ䂦�[ �k��l��E�����`�@276
172 �}�[�^�[�e�B�[�o �k��l��E�������@277
173 �ԋ����� �k��l��E������Á@279
174 �������l �k��l��E������Á@280
175 �\�����C���C�i�[���ݒ��l�j �k���l���V�����ԓ��@281
176 ����Ђ����܁� �k���l���V������V��@286
177 �����݂��Ⴊ�� �k���l���V������V��@287
178 �������玵�� �k���l���V������V��@288
179 �ڎ�@ �k���l���V������V��@291
180 �ł��炱 �k���l���V������V��@293
181 �Ƃ���� �k���l���V������V��@295
182 ���̂���x�� �k���l���V������V��@296
183 �R�̓Êx �k���l���V������V��@297
184 ��̑��~�� �k���l���V�����T�Á@298
185 ������ �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@300
186 ���x �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@301
187 �䂪�Ȃт� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@303
188 ���z�ؖ� �k���l�ɐ咬���c�z�@304
189 ��U�� �k���l�ɐ咬���c�z�@305
190 �Ė� �k���l�V�钬����@306
�����̑��̋����̍s����
191 ����˂��� �k��l�}�����p�@307
192 �ւ炵�� �k��l�}������}���@308
193 �����}���J�C �k��l�}�����ߓc�@310
194 ���ڂ���i�킨�낵�̓��́j �k��l�������H���@312
195 �M�\���ڂ��� �k��l�����s�����@315
196 ������ �k���l���V������X�@316
197 �݂��ڂ� �k���l���V������X�@318
198 �C�b�T���T�� �k���l�ɐ咬���c�z�@320
199 ���� �k���l�ɐ咬���c�z�@321
200 �L���[�_�� �k���l���V�������v�u�@322
201 �܂V�� �k���l�V�钬���v�@325
202 �l������ �k���l���V�����T���@328
203 �`�F���`�F���� �m���i�l�a������X�m���@330
204 ��K���� �k���i�l�a������X�m���@331
�|�\�ɔ�����
205 �ɐ����� �k��l���˓����h���@333
206 �X�c���N�e���i���ݎŋ��j �k���l���˓������݁@334
207 �����͐߁i���ݎŋ��j �k���l���˓������݁@335
208 ���D�߁i���ݎŋ��j �k���l���˓������݁@336
209 ���傤�߁i���ݎŋ��j �k���l���˓������݁@337
210 �ւ炵��i���ݎŋ��j �k���l���˓������݁@339
211 �z�[�G���G�[�i����L�N�Ձj �k��l���˓�������@340
212 �l�z����i����L�N�Ձj �k��l���˓�������@342
213 ���߁i����L�N�Ձj �k��l���˓�������@343
214 �Ƒł��x�� �k���i�l�a���������@344
215 �z�x�� �k���i�l�a���������@347
216 ���[�� �k���i�l�a�����i��@350
217 �`���J���x�� �k���i�l�m�����v�u���@352
218 �X���� �k���i�l�m�����c�F�@356
219 �������Վ��i�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_����@358
220 �Z�\�߁i�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_����@361
221 �m���́n�i�^�_�\�ܖ�x��j(1) �k�^�l�^�_����@365
222 �m���́n�i�^�_�\�ܖ�x��j(2) �k�^�l�^�_����@366
223 �D�x��i�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_����@368
224 ��x�䂤�āi�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_�����ˁ@371
225 ���̒�i�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_�����ˁ@375
226 �����̌ւ炵��i�^�_�\�ܖ�x��j��
�@�@���k�^�l�^�_�����ˁ@377
227 �N�l�i�^�_�\�ܖ�x��j�� �k�^�l�^�_�����ˁ@377
228 �⌳�i�^�_�\�ܖ�x��j �k�^�l�^�_�����ˁ@378
229 �����ܗ������i�^�_�\�ܖ�x��j�� �k�^�l�^�_�����ˁ@381
230 �仉Ԃ̉ԁi�^�_�\�ܖ�x��j�� �k�^�l�^�_�����ˁ@381
231 ������i�^�_�\�ܖ�x��j�� �k�^�l�^�_�����ˁ@382
�ƍs����
���j���E���ʂɔ�����
232 ���ق�߁i�����j���j �k��l�����s��F�@384 |
233 ���ق�߁i�V�z�j���j�� �k��l�����s��F�@388
234 ����� �k��l�������H���@389
235 �E���`�����V�����j���w�F �k��l�F�����F���@390
236 ������ �k���l���V������V��@391
237 ������ �k���l�V�钬��ԁ@395
238 �܂��� �k���l���V������V��@398
239 �܂��� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@400
240 ��O�� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@401
241 ��O���i�O�\�O�N���j�� �k���l�V�钬�����ؖ��@406
242 �ۗV�� �k���l���V������V��@406
243 �ƌ��ėx�� �k���l�ɐ咬���c�z�@408
�����ҋV��ɔ�����
244 ����i�E���C�j �k���l���V������V��@410
245 ����ނ� �k���l���V������ԁ@410
246 �₪�ܐ� �k���l���V������X�@411
247 �����傮���� �k���l���V������ԁ@413
248 �O���i�O�\�O����j �k���i�l�a���������@414
249 �O���i�O�\�O����j�� �k���i�l�m���������o�@416
III �d���E���
��Ɖ�
250 �M�����C�g�D �k��l�}�����p�@423
251 �x�肳��C�g�D �k��l�}�����p�@423
252 �r�n�ł��C�g�D �k��l�}�����F�h�@424
253 �M�����C�g�D �k��l�}�����F�h�@425
254 �m�y�ł߃C�g�D�n �k��l�������H���@426
255 �m�y�^�уC�g�D�n �k��l�������H���@427
256 �c�̑����C�g�D �k��l�F�������p�@428
257 �c�̑����C�g�D �k��l�F���������@429
258 ���̎O����i�y�̂ăC�g�D�j �k��l���˓�����@431
259 ���܂ځ[�i�ؔ���C�g�D�j �k��l���˓�����@432
260 �܂��肱 �k���l���˓������݁@432
261 �o�����C�g�D �k��l��E���r�@433
262 �D�����C�g�D �k��l��E���r�@434
263 ���|���C�g�D �k��l��E���r�@435
264 �������A���C�g�D �k��l��E���r�@436
265 ���ł��C�g�D(1) �k��l��E���r�@437
266 ���ł��C�g�D(2) �k��l��E���r�@438
267 �������C�g�D�i�n�j �k��l��E���r�@440
268 �������C�g�D�i��a�n�j(1) �k��l��E���r�@442
269 �������C�g�D�i��a�n�j(2) �k��l��E���r�@443
270 �c�A�� �k���l���V�����ԓ��@445
271 �c�A�� �k���l���V������V��@449
272 �c�A�́� �k���l�V�钬����@453
273 �r�n�ł��C�g�D �k���l���V�����ԓ��@454
274 �M���낵�C�g�D �k���l���V������ԁ@455
275 �m�������̉́n �k���l���V������V��@457
276 �ƌ��ăC�g�D�i�T�m�������R�j �k���l���V�����T�Á@458
277 �������� �k���l�V�钬��ԁ@459
278 �I�l�R�[ �k���l�V�钬���y��@460
279 ���[�n�����[�i�R�o���̃C�g�D�j �k���l�V�钬����@463
280 �P������ �k�^�l�^�_�����ԁ@463
IV �����E�V��
�����́E�V�щ�
281 ���Ԑ� �k��l�}�������m�@474
282 ���Ԑ� �k��l���˓����Îu�@476
283 �V�� �k��l�}�������m�@479
284 ����ɂႾ��� �k��l�}�������m�@480
285 �ł�Ȃ��� �k��l�}�������m�@483
286 ���[�J�i�� �k��l�}�������m�@484
287 �V�u���� �k��l�}�����p�@486
288 ����ː� �k��l�}�����p�@489
289 ���̎R�x�� �k��l�}�����p�@491
290 ���ԕ���Ԑ� �k��l�}�����{��@493
291 ���܂̕��_�� �k��l�}�����{��@496
292 �����̂͂���ߐ� �k��l�}�����茴�@499
293 �����ܖ����� �k��l�}�����茴�@502
294 ���ǐ߁� �k��l�}�������m�@504
295 �L�N�߁� �k���l���˓��������@505
296 �Z�� �k��l�}�����F�h�@506
297 ������ǐ� �k��l�}�����茴�@507
298 �r�ǎ�߁� �k��l�}�����Ԗؖ��E���@510
299 �܂��� �k��l�}�������@511
300 ���C�X���� �k��l�}�������@513
301 ����ߐ� �k��l�������H���@516
302 �������� �k��l���������؉���@518
303 �������� �k��l�������Ԕ��@521
304 ���z�̗��Ă܂���� �k��l�����������@524
305 �r�ǎ�� �k��l�����s�L�ǁ@526
306 �Ԑ��ߐ� �k��l�����s���h�@529
307 ���傤�������� �k��l�����s�������E�F�������p�@532
308 ������ˎo�� �k��l��a������v�@535
309 �������ߐ� �k��l��a�������@538
310 ���ʂ�� �k��l�F�������p�E�����@540
311 ����Ƃݐ� �k��l�F�������p�@542
312 ��{�� �k��l�F�������p�@545
313 ���ƌː� �k��l�F�������p�@547
314 �Ó��Ȃ��ߐ� �k��l�F���������@549
315 �������� �k��l�F���������@552
316 �А\����� �k��l�F���������@554
317 �R�Ɨ^�H���� �k��l���˓����Îu�@556
318 ���_�� �k��l�F�������݁@559
319 ���J��� �k��l���˓����Ԗ�q�E��a������v�@561
320 �������l�� �k��l���˓����Ðm���@564
321 �Ȃ���卂���� �k��l���˓����h���E�Ԗ�q�@567
322 �J���ݐ� �k��l���˓������Ì��@569
323 ���ꗧ�_�� �k���l���˓��������@571
324 ����� �k���l���˓��������@574
325 �s�����ɂ���ߐ� �k���l���˓��������@578
326 ����ڂ��ݐ߁� �k���l���˓����ԕx�E�����@581
327 ���ݒ��l�� �k���l���˓��������@582
328 �ѕĎ��� �k���l���˓��������E�Ԗ�q�@585
329 �n���� �k���l���˓��������@588
330 �s���傤��� �k���l���˓����ԕx�E�����@591
331 ���V���� �k���l���˓����ԕx�@593
332 �₿��V�� �k���l���˓����U�@596
333 �����Ԑ� �k��l��E���u�ˉ��@600
334 �₿��V�� �k��l��E���u�ˉ��@601
335 �n���� �k��l��E���u�ˉ��@603
336 �T�Ò��Ԑ� �k���l���V�����T�Á@604
337 ��V���Ԑ� �k���l���V������V��@607
338 ���R�����Ԑ߁� �k���l�ɐ咬�n���@609
339 ���߁i��オ��߁j �k���l���V�����ԓ��@610
340 ��V�̂��щ��ߎu�i��オ��߁j
�@�@�� �k���l���V�����R�@612
341 ������� �k���l���V�����ԓ��@615
342 �\�Ԍ��� �k���l���V�����ԓ��@617
343 �L�N������ �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@621
344 ��ؐ� �k���l���V������ԁ@623
345 ��ƃm�[�G �k���l���V������ԁ@624
346 �Ȃ邪������ �k���l���V������V��@626
347 ���C�V������ �k���l���V������V��@627
348 ���_�߁i�G���g���j �k���l���V������V��@629
349 �������匴�����傤���� �k���l���V�����T�Á@632
350 ���ނ�̖����� �k���l���V�����T�Á@634
351 �O���̌� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@636
352 �悽������� �k���l�ɐ咬�ڎ�v�@639
353 ��� �k���l�V�钬��ԁ@642
354 ������i�[�W���� �k���i�l�a���������@644
355 �T�[�T�����T�����T �k���i�l�a���������@645
356 �V�[���[�t�[ �k���i�l�a���������@647
357 �X�[���X�[���C �k���i�l�a���������@648
358 �i���_�C�� �k���i�l�a���������@650
359 ���̑œ��� �k���i�l�a���������@652
360 ���b�J�� �k���i�l�a���������@654
361 �A���`�����[�� �k���i�l�a�����a���@657
362 �C�̂����� �k���i�l�a�����a���@658
363 ���_�� �k���i�l�a�����a���@660
364 ���� �k���i�l�a�����a���@662
365 �G���g�� �k���i�l�a���������@664
366 �X�����C�߁i�߁j �k���i�l�a���������@665
367 ���c�z��� �k���i�l�a���������@666
368 �E�V�E�V�� �k���i�l�a���������@668
369 ���ɂ���䂵��ہ� �k���i�l�m�����V��@670
370 �����̌ւ炵�ၦ �k���i�l�a���������@671
371 �W���g�E�� �k���i�l�a���������@671
372 �����K�X�[���C �k���i�l�a���������@673
373 �������� �k���i�l�a�����i��@674
374 ���җ��ꁦ �k���i�l�a�����i��@677
375 �������� �k���i�l�a���������@678
376 �삽�ʕ� �k���i�l�m�����㕽��@679
377 �]�c�F�n�� �k���i�l�m�����]���@681
378 ��������� �k���i�l�m�����m���@683
379 �r���߁� �k���i�l�a���������@685
380 �����Ⴍ�� �k���i�l�m�����m���@685
381 ����� �k���i�l�m�����m���@687
382 ����������� �k���i�l�m�����m���@688
383 �m�����݉́n�� �k���i�l�m�����c�F�@689
384 �̒r���� �k�^�l�^�_���ߊԁ@689
385 �g���r���� �k�^�l�^�_�����ԁ@692
386 �V�ђr���� �k�^�l�^�_�����ˁ@695
387 �������W�� �k�^�l�^�_�����ˁ@698
388 �����������W�� �k�^�l�^�_�����ԁ@701
389 �ڃw�����[ �k�^�l�^�_���ߊԁ@703
390 �������ł��� �k�^�l�^�_�����ԁ@705
391 ������ �k�^�l�^�_���ߊԁ@706
392 �����߁� �k�^�l�^�_�����ԁ@708
393 �V�k�}���_�C �k�^�l�^�_�����ԁ@709
394 ���ゲ�����I�� �k�^�l�^�_�����ԁ@711
395 ����������� �k�^�l�^�_�����ԁ@713
396 �V�̌Q�ꐯ�� �k�^�l�^�_�����ˁ@715
397 ����c �k�^�l�^�_�����ˁ@716
398 �{�Ð� �k�^�l�^�_�����ԁ@719
�V���w�E���s��
���V���w
399 �i�Ǖ��S���̉� �k���i�l�m�����]���@723
400 �^�_���S �k�^�l�^�_�����ԁ@724
�E
�E |
�W���A�|�\�w����u�|�\ 35(8) (�l�`�|�\�ƕY��<���W>)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����Bpid/2276703
|
���{�|�\�j�Ƌ��l�M��--����̍l�@�𒆐S�� �@�ɓ��D�p p.p10�`16
���� �����Y�̐l�`�Y �@�F�쏬�l�Y p.p17�`23
�؍��̐l�`���R�N�g�D�t���m����--�j���}�͕Y���ƈ��������z���ā@�p���
p.p24�`30 |
�W���A�|�\�w����u�|�\ 35(8)(414)�v���u�|�\���s���v���犧�s�����B�@�@pid/2276703/1/1
|
<��>���a�̕��w��|�\�ƌ˔N�� / ����O�F/p9�`9
�l�`�|�\�ƕY��<���W>/p10~30
���{�|�\�j�Ƌ��l�M��--����̍l�@�𒆐S�� / �ɓ��D�p/p10�`16
���� �����Y�̐l�`�Y / �F�쏬�l�Y/p17�`23
�؍��̐l�`���R�N�g�D�t���m����
�@�@��--�j���}�͕Y���ƈ��������z���� / �p���/p24�`30
������Y�(����1)(��Z�Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���w�a�m�^(��܉�)��w�Ђł��߁x�Ɓw�G�q�߁x� / ����K��Y/p32�`33
<���]>�_�_�����̍s��� / �������H/p34�`34 |
<���]>�{���L�F���w���{�����̗w�̌����x / �q�Β��F/p35�`35
�����蒟(6��) / ���c�m/p36~39
���x�蒟(4�����{�`5�����{) / �@���q/p40�`43
������������ꂼ�� / ���ʏˎq/p44�`44
�M�y���Ă饈�£ / �r�c�O��/p45�`45
�����|�\������̗��߂͍D���ł���������ł���� / �{����/p46�`46
���{�̖����|�\-34-�k�C�� / ���{�p�v/p47�`58
�w���/p59~59
�V���ē�/p60~60 |
�X���A�u�`���ƕ��� (17)�v���u�|�[���`�������U�����c �v���犧�s�����B�@pid/4422713
|
���z �X�� ��������� / �k���N�Y/p2�`3
�ӂ��[��� �u��ԉh��ɂ݂�g�^�̐��E�v / ��]�F�q�v/p4�`11
�����W�E1�� �u���G�E�c���P���̂킴�Ɩ��́v / ������/p12�`20
�����W�E2�� �u��12��`�������|�[���܁v/p21�`28
�`�����x����l�X �d�v���`�������u�{�Ï�z�v/��ꊲ�v/p29�`38
�N�����N�E�A�b�v �u�ɂ傤�v���������� / ���씪�F�Y/p39�`41
|
�N�����N�E�A�b�v �u�Ð���Əo��܂Łv/�]�c�M/p42�`44
�N�����N�E�A�b�v �u���Q�鍰�v / ����m��/p45�`47
�ӂ邳�Ƃ̂܂� �ٌ`�̉��ʗ��K�_
�@�@���u�{�Ẫp�[���g�D�v / ���@������/p48�`49
�ӂ邳�Ƃ̂킴 �u���l�`�v / ��������/p50�`51
�̋���K�˂� �{�Ï�z�̌̋���K�˂�/p60�`60 |
�X���A���{�i�V���i���g���X�g�ҁu���R�ƕ��� (42)�v���u���{�i�V���i���g���X�g�v���犧�s�����B�@
|
���A�W�A�̍j�� / ����P�v/p4�`11
�؍��̍j�� / ���m��/p12~19
�@�r�s�E���Α��E��R[�؍�] / ���G�j/p20�`26
�I�̍j��[�؍�] / �쑺�L��/p27~29
���ƍj�� / ����d�N/p30~39
����̍j�� / �c�Ԉ�Y/p40~47
���d�R�����̍j�� / �Ί_���F/p48�`55 |
���{�̍j�����s�� / �V�앐/p56�`61
[�A��] �����݂̎���(3)�����݂Ɗό� / �ΐ쒉�b/p62�`65
[�A��] �A�W�A���|(3)�o�����̉��Ƌ�C / �~�Øa��/p66�`70
�Q�l�����E�}��/p70~70
���c�@�l���{�i�V���i���g���X�g����̃��b�Z�[�W
�@�@��[�����j�Ƃ��Ă̐H����] / �\���E/p71�`71
�E |
�P�O���A��ÍN�Y���u�_�X�̌����v���� �㊪�v���u��ꏑ�[�v���犧�s����B
�P�O���A��ÍN�Y,��|���q���u��̎�l�����̏ё�-6-��ÍN�Y�v���u�|�p�V��
44(10) p.p122�`133�v�ɔ��\����B�@�@
�P�P���R��(��)2���E(��)6��30���A�p���b�g�s������ɉ����āu����ⶋȂ̒��� : ����ⶋȋ��z�� ���H���m�u���� �n��25���N�L�O���� ����ⶋȋ��z��H���m�u�����v���J�����B
�@�@�@�@�㉇�F�ߔe�s�E����ⶋȋ��z��E�����V��ЁE����|�\�A���ENHK��������ǁE����|�\�j������E�X�����ۑ���E
�@�@�@�@�@�쑺�����y����ߔe�x���E�쑺���`�����y����
�P�P���A�ʏ��}�q��������ҁu�ӂꂠ���Ă��� ���̕� : �ʏ闬 �ʏ��}�q���������\���N�L�O�����i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ��}�q��������v���犧�s�����B�@�@42p�@�@�����F��㊌����}���فF1005228380
�@�@�@�@�Ƃ��F1993�N11��28��(��)��2���E��6��30�� �Ƃ���F�Y�Y�s����ّ�z�[��
�P�P���A��ÍN�Y���u�_�X�̌����v���� �����v���u��ꏑ�[�v���犧�s����B
�@�@�@�@�@ �v�������J�p����:����:p[465]-474
�P�P���A�u�� 67(12)(801)�@�v���u���{��ʌ��� �V���Ёv���犧�s�����B�@�@pid/7888061
|
��
��B�E���� �~�̓ꕶ�� / �R���喾/p108�`110
��B�E���� �������S���˔���ꍂ�F / �܌��b/p111�`111
��B�E���� �L��{���E���q�]�s��� / ���}�O�`�Q��/p112�`114
��B�E���� �۔��� / �g�{���Y/p115�`116
��B�E���� �T���S��A / �ɓ����q/p117~119 |
��B�E���� �Ԋ��̏W���E�l / ��ÍN�Y/p120�`121
��B�E���� �x����������铇�̂��� / ��������/p121�`123
��B�E���� �T�L�V�}�X�I�E�m�L / �o���n/p124�`124
��B�E���� �^�ߍ����E�� / �{������/p125�`127
��i���--(�S�_�B�e�f�[�^�A�n�}�t)/p129�`161
�E |
�P�P���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 94(11)(1040)�v���u���w�@��w�v���犧�s�����B�@pid/3365679�@
|
�܌��w�̌���<���W>/p1~212
�E�B���w�����E�����g�Ɛ܌��M�v / �����[��/p1�`15
�u�g�Ŋہv�̏o�� / ��������/p16~32
�܌��M�v�̕���v�f�_ / ���t��/p33�`46
��狋�̉~�₷�鎞 / ����//���H/p47�`59
�ɐ��_�{�Ɩ��t�W / ���䖞/p60�`73
"�]��̉J"�čl--�J�ƉZ�Ɣn�� / �㌴�P�j/p74�`88
�܌��w�́u���₷����v / ���}�����q/p89�`100
�܌��M�v�̉���|�\�j����--
�@�@���u�g�x��ȑO�v�𒆐S�� / ���Ԉ�Y/p101�`115 |
�u���͓��̎����x�v�Ǝ�O�̕���x-
�@�@��-�����̕����������߂�����/���p�䐳��/p116�`129
���m�ƃ��m�̔���--�����ЂƂ�́u�U�V�L�����V�v / �쑺����/p130�`142
�}�`�E���E�s�s / �q���F/p143~154
�J�����_�X--�G�_�ւ̋��a�E���{�ƍՂ�̐��� / �c�����/p155�`167
�܌��M�v�̍Ύ��_ / �q�ѐ���/p168�`180
�܌��w�̍Č���--�}���r�g�_�Ə퐢�_���߂����� / ���O��/p181�`201
�܌��M�v�E��ՒT�K�̂��Ƃ���--�܂�тƂ̗� / �O�����Y/p202�`212
�E
�E |
�P�P���A������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v ��ꕔ�E���
(43)�v���u������w����w���v���犧�s�����B pid/2310968
|
����̂��߂̕��͕\������̒T�� / ����C��/p1�`55
���哌��(���N�����)�̑�4�I�n�k�ϓ��Ɋւ����l�@ / �͖��r�j ;��o��/p57~69
��R�k����ƍ\�z����--�s���e���f���̒�� / ����m��/p71�`89
�R���x���V�����Y�Ƙ_���� / �^�h����/p91�`101
���ꖯ�w--�{�ÃA-�O�̌���--���y�̉��y���މ��̊ϓ_���� / �Ɏu�䒩��/p103�`124
3�̉��y����@�̗��O�k�p���l / Yoko Shayesteh/p125~132
�w���v�^�����ɂƂ��Ȃ��ʒm�\���P�̎��ԂƉۑ�--�ϓ_�ʊw�K�]���𒆐S�� / �����K�j/p133�`151
�������Ɛ����W��-�i���Y��--������-3-�k�����l / ������s/p153�`190
����̓`���|�\�ɂ�����w�K�ߒ��̌���-1-�������x�̊w�K���e�ƕ��@ / ������q/p191�`228
�����|�\�̊�{�I�Z�@�Ǝw���̎���-1-���x�Ɖ̥�O�� / �쐣�T�m ;������q/p229~271
���w�Z�ɂ����钵�є��^���̎��H�I����--�n�����t�Ə��C���t�̔�r / �ʏ鏺�q/p273�`284
���Z���ɂ�鉫��̗x��̎��H�I����-1-��щԗx�裂̎w���̍H�v / �ʏ鏺�q ;���R�����q/p285~308
��
����ɂ����鏗�q���Z���̐H�����Ɋւ��錤�� / �{��ߎq ;���˗��b/p441~448
����Ɋւ���������ނ̍H�v--���w�Z�ƒ됶���̈�ł̎��H / �������q ;��Ìb���q ;���c�T�q/p449~454
���ꌧ���w�Z�ɂ�����R���s��-�^�̎��Ƃւ̊��p�� / �V�c�ۏG ;���Ԑ��_/p455~461
���ꌧ�̒��w�Z�ɂ������猤�C�̏ɂ��� / �V�c�ۏG ;���Ԑ��_/p463~469
�������̉��ꌧ�ɂ�����X�|-�c�j�N�\ / �^�h���/p471�`479 |
�P�Q���P�P���A�ܗ��d�i������j���S���Ȃ�B�i���N�W�T�j
�P�Q���A�������ҁu���������� (12)(303)�v���u ���傤�����v���犧�s�����B�@pid/2803159
|
���W �Õ����E���j�����̍Ĕ��� //p4�`15
���ɕ⏕���ƒ����Õ����������j����������\�N���ӂ肩������/
�@�@�����p�H�|��/p4�`8
����ꓬ�̂��̏\�N / �{�{���Y/p9�`12
���ꌧ�ɂ�����Õ��������A���j���������̓�\�N / ������/p12�`15
�s���{���̃y�[�W //p16~21
�����m�ł���?����ȕ�����(6)����{�ՁA�t����{����Ղ̐_���|�\ /p16�`18 |
��x�͍s�����������فE���p��(8)
�@�@���ΐ쌧�\�o���K���X���p�� //p19�`21
�@�l�Љ�-�����ɑ������\�e�n���w�فE
�@�@���L�O�ق̊j�Ƃ���(��)���{�ߑ㕶�w�� //p22�`23
ACA(������)�j���[�X //p28~44
��
�ҏW��L //p48~48 |
�P�Q���A�u���ꕶ������ 20 �v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�i IRDB�j
|
�V�k�O�E�E���W���~�_ : �����k�����̕����@����d�N p.1-32�@
�����̃}���r�g���J���߂��鏔��� : ���V�i�C�����̈�̎��_����@�g������
p.33-72�@�@
���ꔪ�d�R�̍��J�̗w�@�g�Ɗԉi�g p.73-111�@
�_�k�V��Ɖ̗w : �Ñ�̗w�Ɠ쓇�̗w�Ƃ̔�r���_(3)�@�|���d�Y p.113-143�@
����O���Ƃ��̉��y�̗��j��T��@�@��, �s�� p.145-189�@
�u���������v�ߒ������Ɋւ���ꎎ�_ : ��v�ۓ��������𒆐S�Ƃ��āu�o���v���Ɂ@�씨�b
p.191-229�@�@
�F���������̌K��[���Ɣm�Ԏ�[���@��c���� p.231-263
�w�X�o���x�Ɖ���̉̐l���� : ����ߑ㕶�w�������@4�@�������� p.265-308
�A�����J�A�J�i�_�ɂ����鉫�ꌤ���̗��j�Ɖۑ� ���n�� p.309-335
���ɂ̋�(���쐭����, �w����̕� : �ɔg���Q�Ƃ��̎���x, ��g���X, ����O�N)�@�䕔���j
1 p.337-343�@ |
���A���̔N�A ���{����,�C�V���C���u���{�̈�w��� 44B(0) p.869�v�Ɂu����ɂ�����G�C�T�[�̗x���Ɨx��̏�̑��݊W�ɂ��āv�\����B |
| 1994 |
6 |
�E |
�P���A�{����v���u<�E�`�i�[>���ʂĂʖ� : �{���h�P�Ƃ��̎���v���u�{�[�_�[�C���N�v���犧�s����B
�@�@�@�@240p �@�����F���ꌧ���}���فF1001049707
�Q���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 3�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@43p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002959201�@
|
�ߐ������̗���߂����� ���_���̓� -������ƎF����- ���c�I��u
�يE�֓��錮�Ƃ��Ă̒ނ�j �㓡�� |
���B�̕搧-�u���l�v�̎Љ�- �啽��
��p���~���̒����L�^ �������� |
�R���A�~���w�@��w�n�敶���������ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v = Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (9) �v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@�@pid/4424705
|
�q������r �R����--���̐l�ƕ��w �R���ƒ������� / �����א�/p1�`6
�q������r �R����--���̐l�ƕ��w �R���Η]�� / �a�c��/p7�`8
�q�t�B�[���h���[�N�@���r ����L--�{�i�I�����̂��߂̊o�����Ƃ��� /
��������/p9�`12
�q�t�B�[���h���[�N�@���r ������^�@�t�B�[���h���[�N���I���� / �����r�q/p13�`27
�q�t�B�[���h���[�N�@���r ���m�Y�������E�����̏M�������� / ���y�r�Y/p28�`36
�q�t�B�[���h���[�N�@���r ���茧���S���m�Y���{���̉ƌď̂Ɨאl�ď� / ����M�q/p37�`48
�q�t�B�[���h���[�N�@���r ���鎮�y��ɂ݂���h�啶�����̗l�� / �͑��g�s/p49�`61
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �y�䃖�l�L�ւ̌�����--��ꎟ�`�������̈╨�𒆐S�� / �؉����q/p62�`74
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �R�̏��_�u���Ƃ̂�����v�ƒŗt�u���낵�̉S�v / ���јa���q/p75�`83
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �؍������̔��M�n�Ƃ��Ẳ���--�؍��̉̋ȁu�J�S�o�v����̍l�@ / �L�c��/p84�`89
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �q�H�ׂ��̕��y�L�r���₭�ƌܖ� / �R�c�����Y/p90�`93
�q�t�B�[���h���[�N ���r �s������݂��|�P�b�g�p�[�N�̕]���ƌv����� / �F�얫 ;�ؑ����n/p94~106
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �T�䏺�z�E���R�z�̕����ɉ�����ĉ�--�o��̏ꏊ�_(�O��) / �r�ؐ���/p107�`116
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �ЎR�P�ǂƁA���̎���(���̓�) / �{�c��/p117�`125
�q�t�B�[���h���[�N�@���r �u��L(��) / ���c����/p126�`141
�q�t�B�[���h���[�N ���r �q�|���r�{�������j���������ّ��w�v�c�A�ˉ̍e�x(��) / �{�c�� ;�v�ۓc�[��/p142~176
|
|
�R���A������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v ��ꕔ�E���
�i44�j�v���u������w����w���v���犧�s�����Bpid/2310969
|
����{���ߊC�̗��I��Ɍ�����T���S�����̕��ː��Y�f�N�� / ���c�L�� ;�쌴���l/p185~193
�������x��-7-���x�襈ɖ�g�ߕ� / ������q/p195�`235
�������|�\�̊�{�I�Z�@�Ǝw���̎���-2-���x������ƍH�H�l�̓ǂݕ���̂��� /
�쐣�T�m ;������q/p237~263
���U�X�|-�c�Ƃ��Ẳ�����-1-���l���̓��� / �O�ԓN�O ;������q/p265~280
���Z�ɂ����鉫��̗x��̎��H�I����-2-��G�C�T-��̋��މ���ڎw���� / �ʏ鏺�q ;���R�����q/p281~298
�����a���̉��~�z�u����ъԎ��̍l�@ / ��؉�v/p313�`320
�q�����r |
|
��������q,�쐣�T�m���u������w����w���I�v. ��ꕔ�E��� (�ʍ� 43�`44)
�ɔ��\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����|�\�̊�{�I�Z�@�Ǝw���̎��ہi1�`2�j�v�ɂ��Ă̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 43) p.p229�`271 |
1993-11 |
�����|�\�̊�{�I�Z�@�Ǝw���̎���-1-���x�Ɖ́E�O�� |
| 2 |
(�ʍ� 44) p.p237�`263 |
1994-03 |
�����|�\�̊�{�I�Z�@�Ǝw���̎���-2-���x������ƍH�H�l�̓ǂݕ��E�̂����@ |
|
�R���A�u���ꌧ�����������������W�@���ꌧ�̖����|�\�@�\���ꌧ�����|�\�ً}�������\�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
|
����
�O���r�A
�����n�}
�ڎ�
�ጾ
���́@�����̊T�v�@1
���́@���ꌧ�̖����|�\�̊T���@7
��O�́@�ڍג����@13
��O�́@1�A�@���̏����q���@13
��O�́@2�A�@���y�c�̃G�C�T�[�@14
��O�́@3�A�@����s�m�Ԃ̏\�ܖ�|�\�@18
��O�́@4�A�@��y�[�`���@30
��O�́@5�A�@�����O�i�ǒJ����p�j�@37
��O�́@6�A�@�x���A�V�r�g�D�C�P�[�ɂ��ā@40
��O�́@7�A�@�Ì����̏��N�����i�n�`�E�N�V�[�j�@42
��O�́@8�A�@�k���鑺�M�c�̃t�G�[�k�V�}�@44
��O�́@9�A�@�������I���̖��ӕ����@53
��O�́@10�A�@�ԓc�́u�݂邭��}�v�@58
��O�́@11�A�@�������߁@60
��O�́@12�A�@��������߁@62
��O�́@13�A�@�Ì��̃X�f�B�`���[�A���V�[�i�L�N�Ձj�@64
��O�́@14�A�@��u���������̒��҃k���@67 |
��O�́@15�A�@��哌���̔��䑾���@71
��O�́@16�A�@��哌���̑��o�r��@81
��O�́@17�A�@��哌���̐_�ЍՂƍՑ��ہ@87
��O�́@18�A�@��哌���ɂ����锪��n�̉̕��@94
��O�́@19�A�@���ǎs���K�́u�Y�[�R�[���[�C�v�@97
��O�́@20�A�@���ǎs��Y�́u�Y�K���[�C�v�@99
��O�́@21�A�@�{�Ó����쑺�̃i�[�p�C���J�ɂ��ā@101
��O�́@22�A�@���d�R�Ί_�s�약�̃V�B�V�B�p�[�V�B�i���q���j�@105
��O�́@23�A�@�Ί_�̃��C�s�g�D�`�J�C�V�@111
��O�́@24�A�@���l���̉Ɖ��������ƕ����̖��t���@111
��O�́@25�A�@���\���c�[�̉Ɖ��������@112
��O�́@26�A�@�^�ߍ����̉Ɖ��������ƕ����̖��t���@114
��O�́@27�A�@���\���Ì��̌���Ղ̌|�\�u�T�g�v�@114
��l�́@���F�����@121
��l�́@����k���n��@121
��l�́@���ꒆ���n��@124
��l�́@����암�n��@142
��l�́@�{�Ï����@159
��l�́@���d�R�����@164
��́@�����|�\�ꗗ�\�@171
��Z�́@�����|�\�W�����@195
�E |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 7 �v�����s�����B
|
���\���Ì��̌���ՂƋ����@�g�Ɗԉi�gp.1-37
���́E�g�x��ɂ����铮���̊��p�\ ���� �q p.39-82, 83a-89
���i�Ǖ����a������X�m���̗V�їx�� �v���c �W p.107-123 |
���������g�̉P���� : �̂̓`�d�Ɋւ����l�@ ���� ���] p.125-175
���ꌧ���|�p��w�����������b��@ p.177-185
���I�X �V�F�����A�����̐D�������@�� �x�B�@ p.91-106
|
�R���A���ꌧ�����U����������يǗ����j���ҏW���ҁu����Č��� (5) �v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
pid/22120821
|
�w����āx�������̈Ē�ɂ���/�r�J�]�q/p1�`18
�k�j���Љ�)�w�����i�v�^�x�ɂ���/��Î�/p19�`40 |
�k�j���Љ�l�Ë`�����ɂ̗����W�����j���ɂ���/�O�Ԃ݂ǂ�/p41�`49
�E |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 29(1/2)(79/80)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437794
|
[�u��] ���ꌤ����B�̎v���o / ��l�G��/p1�`11
��������_���ɂ�������@�x�̎v�z / ���Ô��/p12�`52
�ߐ������̒����n���y�u���y�v�Ɋւ����l�@ / ���c���q/p53�`91
�^�ߍ����̖��Ԏ��Î�--�_�u�Ǝw���E
�@�@�������Î҂ɂ��� / �a�c���q/p92�`127
�另�Ղƌ�V���� / ���c����/p128�`146 |
��������\�����邱�Ƃ� / �l�c�q/p147�`165
�w�����낳�����x�̐ڎ��u�I���C�v / �V���B��/p166�`198
�w�z�g�g�M�X�x�Ɖ���̔o���҂���
�@�@��--����ߑ㕶�w�������@(6) / ��������/p199�`211
[�����Љ�] ����@���j�����̌���-
�@�@��-����F�Z�Y�����Â� / ���ܑS��/p212�` |
�R���A���~�ߎ������m�_���u����̑c����J�Ɋւ��錤���v�\����B�@pid/3103127
|
���� ���_/p1
���́\�{���̉ۑ�\/p2
���� ���E��/p7
���� �j���C�E�J�i�C/p7
�� ���c���j�̎R�����E�ς�
�@�@���܌��M�v�̢�C�ޣ�̑��E/p7
�� �ɔg���Q�̢�j���C��J�i�C��l/p8
�O ���c���j�́u�C�_�{�l�v/p12
�l �I�{�c�E�J�O���_��/p15
���� ��Ԃ̍Ր_/p16
�� ���_�̍Ր_/p16
�� ��Ԃ̍Ր_/p17
�O ��ԂƃO�X�N/p18
��O�� �Z�a/p19
�� �Z�a�̜߈�/p19
�� �Z�a�̃��F�N�g��/p21
�O �}�i�I�ϔO/p23
�l �_���̎�/p24
���� �썰��/p28
���� �⍜���d/p28
�� �쓇�̓�d��/p28
�� ���搧���߂���_��/p29
�O �V��/p30
���� �l��_���J�镗�K/p32
�� �u�l�͎��˂ΐ_�ƂȂ�v/p32
�� �c�_���J��W�c/p33
��O�� ���/p35
�� �����/p35
�� ����/p36
�O ���/p37
���� �{�_/p39
���� ���삩��c���/p40
���� ���������䶔��ƔN��/p40
�� �Սϑm�̊֗^/p40
�� �ܒi�K�̕���/P41
�O �����V�n/p42
�l �q/p43
�� �N��/p44
�Z �l���/p46
|
�� �N���̂܂�/p47
���� �����Ղ̎�e
�@�@���\�ɐ����̎���\/p49
�� �ɐ����ʗ˂̐�����/p50
�� ��n�_/p51
��O�� �ߥ����̑����ƔN��/p52
�� �_�r�Əč�/p52
�� �ߑ�X��p�̏K��/p56
��l�� �ߥ����̈����J/p77
�� �_�I�ł܂�c�_�\�ߔe�@/p77
�� �c�_�ƍ��J�����_���\�ߔe�A/p79
��ܐ� �ƕ���/p84
�� ���R�ƕ���/p84
�� �w���ǔV�e�ޒ����L�x/p92
���� �ʔv���J�̎�e�ƕ��y/p100
���� ��������̕��/p100
�� ��ꏮ���̉��_/p100
�� ����̉��_/p101
�O ���_�ȊO�̕��/p104
�l �����E���k�W���l��/p105
���� �ʔv���J�̕��y/p107
�� ���ꏔ��/p107
�� �{����/P108
�O ���d�R����/p109
��O�� �ʔv�E���O/p109
�� �u�ʔv�v�̐���/p109
�� �ʔv�̗ތ^/P110
�O �ʂ��ʔv/p112
�l ���O/p112
��l�� �ʔv���̎���/p114
�� ����/p114
�� �v�Čn�̋���/p116
�O �ѐ��r���/p117
�l �ѐ��L�����/p118
�� ����������/p118
�Z �����c����/p119
�� �����c���/p119
�� �ɐ����̋���/p120
�� �X����̋���/p129 |
�\ �Y�Y�̋���/p131
�\�� �嗢�̋���/p132
�\�� �v�ē���u�쑺�̋���/p132
�\�O �n�Õ~�̋���/p133
�\�l �����̋���/p134
�\�� �{�Â̋���/p135
�\�Z ���d�R�̋���/p135
��O�� �j���Ɍ���ʔv�̏��p/p141
���� �j���̏��p/p141
�� ���p�̌���/p141
�� �r�s�E�P�q�E�ߖ[/p141
�O �ߌp/p143
�l �{�ʔv�Ƙe�ʔv/p145
���� �����̏��p/p145
�� �u�����ʔv�v�̏��p/p145
�� �����́u�ʔv���p�v/p148
�O �ʔv�̗��A��/p149
��l�� ��̌`�Ԃƍ\��/p150
���� �Ƒ���Ɩ咆��/p151
�� �ߔe�̕�n/p152
�� ���A�m������R�̌Õ�/p158
�O ���A�m���������̖咆��/p170
�l ����/p187
�� �v�����̕�n/p192
���� �T�b��/p218
�� �T�b��̐���/p218
�� ��ى�A��/p232
��� �掏/p251
���� ����̕掏/p251
�� �掏�̎��/p251
�� �~�q���̋L�ڌ`������e/p263
�O ����/p265
���� �t�E�����̕��/p268
�� ���˓����̕��/p268
�� �ɐ咬��ʓꑺ����n�̕��/p278
��O�� �I��/p284
�� ����/p285
�� �W�]/p291
�Q�l����/p293 |
�T���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (19)�v���u�����|�\�w��v���犧�s����B�@�@pid/7959569
|
�������畑�x����-�V���������̌䌉�Ղ��
�@�@����������Ƃ�������/�J�O/p1�`21
�u�����|�\�̌o�ϊw�v�Ɍ�����--��t���^�|�\
�@�@��(���q���E�Օ��E�G�C�T-)�Ƃ��̌o�� / �R�{�G�q/p22�`48 |
�˂��E�˂�܂���"�F����" / �����G�O�Y/p49�`71
�ɐ���F�\�̉��� / �㓡�i/p72�`80
�u���܂�@�v�Ɏv�� / �|���K�v/p81�`88
����4�N�\�{�ɂ݂�_�y�̔\�̈Ӑ}�ƍ\��/��c��/p89�`109 |
�T���A���j�Ȋw���c��ҁu���j�]�_ = Historical journal (529) �v���u���j�Ȋw���c��v���犧�s�����B�@ pid/7940738
|
����̏����j<���W>/p1~64
���W�ɂ�������/p1~1
�ɔg���Q�u���ꏗ���j�v�̌���I�Ӌ`/����T�q/pp2~14
�u�����낳�����v�ɂ݂�_���Q��/�Î芡��ߎq/pp15~23
����ɂ�����_���̕ϗe�Ɩ��O�K���̕ω�/��쐽/pp24�`37
�����ɂ����鋙�Ƃ̕ϑJ�ƍȂ����̘J��/�����v�q/pp38�`46
��n�Ə��� / �_�R�K�q/pp47~58
���������_�o����--���Ǒq�g���̋ߋƂɂ悹��/�|�����_/pp59�`64
���k�쌹���ɂ݂�V�c�ƂƗL�����@/�v�ۋM�q/pp65~81
��Օۑ��^�����l����-9-�@��
�@�@���c���������Ƃ̕ۑ����߂�����/�c���G��/pp82�`85 |
�u�A�����J�w�l�鋳�t--�����̔w�i�Ƃ��̉e���v
�@�@�����w�R���C/����i�q/pp86�`90,103
�u���������v�������� / �c����Y/pp91~95
�L�^�Ə،�--���c�z��Җ�u�����W
�@�@���������{���Y�}�ƃR�~���e�����v�ɂ悹��/�Γ�����/pp96�`99
�u�����W�E�������{���Y�}�ƃR�~���e����
�@�@���v���c�z��Җ�/���ۋ`��/pp100�`103
��a�a������̐l�Ɗw�� / ��i�B/p104�`105
����E���W��\�e�n�̋L�^(1)��/p106~109
�L�^�E�ҏW��L/p110~111 |
�U���A�@�����������u�ꕶ���� 77 p.32-45�@��B��w���ꍑ���w��v�Ɂu���ꂩ�瓌���� : �R�V�����ď㋞�l�i��j�v�\����B
�U���A���j�Ȋw���c��ҁu���j�]�_ = Historical journal (530) �v���u���j�Ȋw���c��v���犧�s�����B�@�@pid/7940739
|
���j�w�ƃ}�X���f�B�A--�j���ƃt�B�N�V�����̂�����<���W>/p1�`84
���j�w�Ɨ��j����/p1~28
���j�w�Ɨ��j�����̂����� / �i��H�q ;���c�O�q ;�����Ďq/pp1~20
���j�ƕ��w�̂͂���-�k�����O�u�j�R�̐��v��ǂ�/�����a�F/pp21�`28
���j�w�Ǝ��㌀/p29~59
���ˉ���Ƃ������b�L���E / �n���/pp29~37
����u�`--�]�ˎ���̍ٔ����x�Ƒ剪�z�O/�R�{����/pp38�`44
��{���n�̐l�������߂����� / ���Α�/pp45~52,66
���j�����҂̋Ɛт̕������p�ƒ��쌠�@/�z�c�m��/pp53�`59
���j�}���K/p60~79
�w�K�}���K���{�̗��j��ǂ� / �ː�_/pp60~66
�}���K�ƂƓ��{�j�����҂̐ړ_--�@�� |
�@�@���ҏW���͂̑̌����� / �ؔ��q�j/pp67�`74
�u�܂� �M�B�̗��j�v��ҏW���� / �؍F��/pp75~79
���j�ƕ��w�Ɛl�Ԑ���--��w���̗��j�ӎ��E����/���c�K�j/pp80�`84
���̂����߂�1���̖{ / �F�쑏/pp85~92
����̏����j--�y�n�����ƃg-�g-��-���s�̐���/�V���Q�q/pp93�`104
�Љ��`���l����-1-�Љ��`�Ɩ����`/�l�ѐ��v/pp105�`113
��Օۑ��^�����l����-10-���R�R��w�Z�Ւn���甭�����ꂽ
�@�@���l���̏ċp�������Ȃ��^����!/ �ەl��/pp114~117
�V���|�W�E���u�����j�w�ƈ��Ǐ闝�_�v
�@�@���Q���L(�Ȋw�^���ʐM) / �_�J�q/pp118�`122,126
�u���c�j�w���l����v����I����(�Ȋw�^���ʐM)/��/pp123�`126
�L�^�E�ҏW��L/p127~128 |
�U���A�������q, ����m���ҁu���{�̉��̕����v���u��ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@�R�R�O�O�~
|
�̗�̓��E���{ �������q��
���{�`�����y�Ɖ��̂�炬 �勴�͒�
�u���̕����v�@����u���̕��i�v�̎v�z ���z�����q��
.���߂��]�˂̃X�g���[�g �������
���̂Ɠ��{���� �R�ܓN�Y��
.��O�u���W���̓��n���R�[�h�Y�� �א������
.�����O�̗w�ɂ݂���{�l�̌� �����܂�q��.
�ɐ����_�y�n���q���̕��ȍ\���Ɲ����̂ɂ��� ���]��q��
�����x��̂̍\���ƒn���q �����͎q��
�l���\���E������̂��炵�Ɖ��y���� ��䐳�_��
�{�茧�̐_�y�l ���؈����q��
���B�̕��m�x�̗w ����������
���̂ɂ݂鏖���̏���̂̉萶�� ����w�v�� |
�������w�����̃��Y���\�� �v���c�W��
���ꕑ���ɂ�����K�}�N�Z�@�_ �O�����Y��
���ꉹ�y�ɂ����鉹�����ƃ��Y���̌`�� �������
����̉P���ۋȂ̐����\�� ���ь��]��
�p�t�H�[�}���X�̊ϓ_����Ƃ炦�������|�\�̋��ސ� �����x���q��
���{�̌��Ղ̌��� ����珏��
��t���ŎR�n���o�y�e�Տ��ւ̓��ِ� �{��܂�ݒ�
�V���}���ّ��w��ⵕ��x�̋L���@�Ɠ��y�̃��Y�� �������q��
�����`����� ��{�����q��
�\�ǂƈ�ߐ� ���K���Âݒ�
�R�c���Z�̍�i�ɂ�����ⵓ�ʂ̍��t�ɂ��� ������q��.
�����O���̓��{���y�j���� �ˌ��N�q��
.�������q���N���E����ژ^:p611�`625 |
�U���g�c�퍶�q�傪�A�u�������v���u�g�c�퍶�q��v���犧�s����B�@�@(���X�X�c�ޕ����{
; ��4,5�W)
|
[��1����] ���\�̐�玆 ���R�͕M 23p
[��2����] �m�Ԏ��ɖ������� �����F[��] �@��]�F�q�v�����C�g 12p
[��3����] �����F����̂��� ���؎O�Y�M10p
[��4����] �����F����Ƃ̎v���o ���c���v[��] ������(�J�b�`����)�̎v���o
�����M��Y[��]�@�@10p
�t:�m�Ԏ�(2��) �����݂[�D(1��) �������W�N�\ ��]�F�q�v�쐬(1��)�@�@���{�����V���}���ف@
�@�@����: ���������X ���� 150������Ł@�@�����F�a�̎R�����}���� |
�W���A�u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (�ʍ� 59)�v���u���m���y�w��v���犧�s�����B
�@�@J-STAGE
|
�A���E�L���f�B�[�̉��y�_�@�V��T�q p.p1�`22
����˂��ڏ����ڏ��S�@Gerald Groemer p.p23�`42
��\���I���������L���X�g�����y��e�ɂ����鉹�����̌����@�������q�@p.43-58,L3
2��ډ��]�I�F�l�@�@�@�R�� �� p.p59�`70
���s�̖��여�O�����ɂ��ā@�Óc���q p.p71�`85
�k�������� (��Z�����Ɖ��y����)�@�@�J�{��V p.p86�`91
��p��Z�� (��Z�����Ɖ��y����)�@�@�P�쐉�� p.p91�`96
���ꕶ�������y�����̍őO���@���� �� p.p96�`101
���_ (�C�O�ɂ�������{���y����)�@�@�ѐA���� p.p102�`107
���� (�C�O�ɂ�������{���y����)�@�@�� ���� p.p108�`112
�p�ꌗ (�C�O�ɂ�������{���y����)�@�@���c�A���\�� p.p112�`115
�u����̗̉w�Ɖ��y�v���c���q�@�v���c�W p.p116�`118
�u�\�̚��q���v���m���y�w���(���m���y�I�� 4)�@�O�Y�T�qp.p118�`120
���ۋg�F���w�������y�w�v�@�ɓ��M�G�@p.121-122
�ѐA���꒘�w���E���y�ւ̏���-�������y�w����x�@�ɓ��M�G p.124-125
�n���K�O�Y���w���|���S�W�̌���-�ߐ��M�y�j��������-�x�@������@ p.125-127
����m���E����M�j�E�R���C�E�N��N�j�E�˓c����ҁw�������y�T�_�x�@�@���q
�G�q�@ p.127-128
�ˌ��N�q���w�\�㐢�I�̓��{�ɂ����鐼�m���y�̎�e�x�@�@�㓡 ���q p.128-130
�u���Ɣ��i--���Ɖ��y�v���Ɣ��i������ҁ@�@���c ���� p.p131�`133
�u���ւ̊y��--�y��j����݂��l�Î����v�{��܂�݁@�@�S�i ���� p.p133�`135
�u���{���w���--����E����(�S4)�v���{���������,�u�������{���w���(�S9)�v���{��������ҁ@����
���� p.p136�`138
�u���B�̗w�̌����v���������@���� �K�j p.p138�`141
�u�F�����i�̐^��--���K�g�搶�̔�^�Ɖ��v���Ð��Ғ��@���� �`�� p.p141�`143
�u�����������z���_�v�A�؍s��,������ҁ@�@�g�� ���� p.p144�`147
�ݕӐ��Y�E�r�c��O�Y�E�S�i�����ďC,���쌒���ҏW�E�\���u��n���{�̓`�����y�v(�����o�����]--��������)�@��c�Ďq �� p.p148�`150
�u�V�����E�h�D�E�����h�������y���C�u�����[�v(�����o�����]--��������)�@�@�X���j
p.p150�`154
�Ԗ�P�F�E����a�Y�E����E�����K�Y�E�{�c�o�E�R�H�����ҁu���Ɖf���ƕ����ɂ���n���{���j�ƌ|�\�v
�@�@��(�����o�����]--�f������)�@���]��q p.p154�`157 |
�W���A�u�a���̔O���x��v���u���쌧���쒬�a���O���ۑ���v���犧�s�����B�@�@�����F��������}����
�X���A�u���R�ƕ��� (46)�@�@���{�i�V���i���g���X�g �� ���{�i�V���i���g���X�g
1994-09/pid/6067753/1/1
|
�C�k ���X�V���̒T���Ɣ���/�J�쌒��;����];�Ί_���F/p4~23
���X�V��[���̐��U�Ǝ���] / ����]/p24�`31
�����ƍ��X�V�� / �R���ӈ�/p37�`41
�{�Ó��̍��X�V�� / ���@������/p42�`45
���X�V���Ɛ瓇�T�� / ���X�ؗ��a/p46�`53
���X�V�����N��/p32~36 |
[�A��]�V�Ɉ�ԋ߂��ɏZ�ގR�̐l�X(4)
�@�@�@���J�G�̑�/��������;���{�h��/p54~68
[�A��]�����݂̎���(7)�����A�S�A/ �ΐ쒉�b/p69�`73
�W����ē��E����/p74~74
���c�@�l���{�i�V���i���g���X�g����̃��b�Z�[�W
�@�@��[�u�i�V���i���g���X�g�^���v�̕����I���p]/���x���O/p75�`75 |
�P�P���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (�ʍ� 20)�@10���N�L�O���v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B�@pid/7959570
|
�k�����|�\�w��ݗ��l10���N�L�O��/p1~165,����p1~16
�����|�\�����̌��݂Ɖߋ�<���W>/p1�`27
�����|�\�������n�߂��猻�݂܂� / �{�c����/p1�`7
�����|�\�w��10�N�̂���� / �O�����Y/p8�`11
�s���Ɩ����|�\ / �����G�Y/p12�`15
���J�W���̌��߂ƓW�] / ���p�䐳��/p16�`20
�����|�\�����̏����� / �R�H����/p21�`27
�ςƖ����|�\--����,�����x��E���q���E
�@�@����t���|�𒆐S�ɂ���/��X�b�q/p28�`40
�������x�̓`���̏�ɂ�����n��ɂ���--
�@�����ꌧ���A�����~���̃G�C�T-������Ƃ���/���{����/p41�`64
��A���v�X�|�\���z�����_--����E���{�여��̐_�y��
�@�@�����S�Ƃ���/�v�ۓc�T��/p65�`82 |
�����ɂ�����O���|�\�̓W�J--
�@�@�����i�Ǖ�����33�N���𒆐S��/���䐳�q/p83�`117
�|�\�̂���--�����ɂ́u�|�\�v��`���́u�܂�v��
�@�@�����̍s���Ɍ���/�c���`�L/p118�`125
�A�W�A�̎��_����--�����|�\�����̈����<�k�����|�\�l
�@�@���w��ݗ�10���N�L�O�V���|�W�E��>/p126�`165
���N�̔N���N�n�̌|�\ / �쑺�L��/p126�`130
���n�`�x�b�g���̋S���� / ���R��/p131�`139
���K�_�̒��قƌ|�\--�����̎��Ⴉ��̍l�@ / ����h/p140�`148
�C���h�E�X�������J�̍��J�ƌ|�\ / ��ؐ���/p149�`153
�R�����g�E�f�B�X�J�b�V���� / �Q�i����/p154�`165
�����|�\���������ژ^--����5�N / �n�ӐL�v/p1�`16
�E |
�P�P���A�m���芰���u����@���j�̌����v���u�Վ��Ёv���犧�s����B�@�@ (�_�ˏ��q��w���������������p�� ; ��10��)
�P�P���A���Ƃ킴������^�ҏW�u���Ƃ킴���������W�� ��P�W���v���u���Ёv���犧�s�����B
|
�V�C�\�l�Ì��ی�
���d�R�̘ی��i�肰��j
�쑍�̘ۑ� |
�_�Ƙی��l
��e�F�����W
�������̘ی� |
�d�B���n���̌�
�y���ی��W
�n���̂��Ƃ킴 |
�P�P���R�O���A�ߔe�s����ّ�z-���ɉ����āu�����̕� ���ܗ��ƌ���Ð��q�|��Z�\���N�L�O����
�v���J�����B
�@�@�@���ÁF�����V��� �㉇�FNHK��������� ����e���r �������� ���W�I���� ����|�\�A��
����`�����x�ۑ����� �ߔe�s�������� ����|�\�j
�P�P���A���ܗ��ƌ���Ð��q�Z�\���N�L�O�������s�ψ���ҁu�����̕� ���ܗ��ƌ���Ð��q�|��Z�\���N�L�O����
�v�����s�����B
���A���̔N�A�v���c�W���u���m���y���� (59) p.116-118�v�Ɂu���c���q���w��㊂̗̉w�Ɖ��y�x�v���Љ��B�@
J-STAGE
���A���̔N�A���{ ����,�C�V���C���u���{�̈�w��� 45(0) p.673�v�Ɂu����̖������x�u�G�C�T�[�v�̍\������ : ���A�����~���̃G�C�T�[������Ƃ���(12.�X�|�[�c�l�ފw,��ʌ������\)�v�\����B�@�@�@J-STAGE�@ |
| 1995 |
7 |
�E |
�P���A�u�v�z�̉Ȋw�v�ҏW�ψ���ҁu�v�z�̉Ȋw ��8�� (24)(520)�v���u�v�z�̉Ȋw�Ёv���犧�s�����B
�@�@ pid/2314998�@�@�d�v
|
�`���Ƃ��ẴG�R���W---�����m�f���B�b�h�E�X�Y�L�ƖK�˂�
�@�@�������ЂƂ̃j�b�|��<���W> /
�@�@���f���B�b�h�X�Y�L.�ҐM�� �ʖ�E�\��/p4~82
���̂͂��߂� / �f���B�b�h��X�Y�L/4�`5
�V�}�F��--��������z�� / ��ÍN�Y/p6�`12
�����̊w�Z--
�@�@�������Ȃ��̂ɂȂ��Ă݂�.���ɂ��ɂ�/���R�q�q/p13�`21
�A�C�k�͂����ɂ��� / �L��k��/p24�`30
�ݓ��Ƃ����� / ������/p31~37
�ۂ͐S���̌ۓ� / ��q���V��/p38�`43
�D���͉��₩�Ȏd�� / �Ί_���q/p44�`51
�������ڂ��Ă���[�₯���������� / �����^�P�� ;�����F�q/P52~57
�F�襂�����m��Ȃ����̂Ƃ̑Θb / ��[���g/p58�`62
��ꂽ�������R�����߂Ă��� / ����R��/p64�`68
���̐l�����������͂��߂�Ƃ����Ō�̂Ƃ��Ȃ�/�x�z�R���q/p70�`76
�����I���� / �ҐM��/p77~82 |
�ӎu�̔������ɂ���--
�@�@���X����q�ɂ��Ă̊o������/��c�m�F/p105�`120
����̎���(23) / �y���Ƃ��q/86�`
�M���E��j���E(6) / �a��~�q/88�`
�����ɂ���킯 �������t�����킯 / �������/90�`91
�e���r�������Ȃ��� �f�W�^�����̃A�i���O����/�R�{����/92�`93
�p�b�p���� �S�萬�A / ���c��b�q/94�`95
���y�Ȃ�Ɋy �ېV�h�̏��S�n / �������/96�`97
���ɂƂ̂��������� ���[���b�g�Ƃ����� / �g�q�\��/98�`99
�Ƒ���Ƒ���̕��i / ��������/100�`101
�Z���t��|�[�g���[�g �������̐��E / ��������/84�`84
�Z���t��|�[�g���[�g ���邢�G / �k��X�q/104�`104
�����s��O�Y�ܣ��W�̂��m�点 //85�`
�����\�� //57�`57
�T�[�N���ƍÂ� //103�`102�@�@
�ҏW��L / �ҐM�� ;�����T�m ;�����[�q/126�`126 |
�Q���A�����K�ꂪ�u���ꕶ������ = ���ꕶ������ 21 p.385-394�@����w���ꕶ���������v�Ɂu�w���Ɩ{ �����낳�����x(��Î��ҁu���ꌤ�������v14��)���s�Ɋāv���Љ��B�@�@�iIRDB�j
�R���A�g�Ɗԉi�g���u���m�_���@�쓇���J�̗w�̌����v�\����B�@pid/3082462�@�ŏd�v
|
�܂�����
��ꕔ �쓇�̍��J�Ɖ̗w
���� �쓇���d�R�̍��J�_����-���J�̗w�_�̂��߂�-
���� ���d�R�̌�ԐM�K��/p1
���� �I��(���)�̍��J�g�D/p31
���� �쓇�̍��J�Ɖ̗w�̌���
����/p57
���� �^�ߍ����̃}�`���̍��J�Ɖ̗w/p64
���� �|�x���̃^�j�h�D���̍��J�Ɖ̗w/p118
��O�� �|�x�����\���c�[�̃V�`�̍��J�Ɖ̗w/p259
��l�� ���\���Ì��̃v�[���B�̍��J�Ɖ̗w/p324
��ܐ� ���l���̃����|�[���B�̍��J�Ɖ̗w/p389
��Z�� �{�×��ԓ��̃��[�}�X��C�v�i�J�̍��J�Ɖ̗w/p419
�掵�� �ɐ����������q��
�@�@���C���`�����[����[�j�Q�[�̍��J�Ɖ̗w/p468
�攪�� ����̌Ñ㕶�w����-��_�̣�����̌��ꂩ��-/p497
��O�� ���d�R�̗w�̌`��
���� ���d�R�̗w�̌`��-"��"�Ɖ̏��@�𒆐S��-/p503
���� ���J�Ɖ̗w�̑��ւɂ��Ă̗\���I�l�@
�@�@��-�|�x���̎�q���ՂƉ̗w-/p527
��O�� ���ꔪ�d�R�̍��J�̗w/p592
��l�� �����O�g�D�o��-���d�R�����O�g�D�̌`��-/p624 |
��� �쓇���d�R�̍��J�ƌ|�\
���� ���d�R�̕��y�ƍ��J�ƌ|�\/p645
���� ���d�R�̌���Ղ̌|�\
���� ���\���Ì��̌���ՂƋ���/p671
���� ���l���̌����/p720
���� ���d�R�̖~�s���̌|�\
���� ���d�R�̃A���K�}�ⓚ�o��-����̕𒆐S��-/p743
��O�� �w�����낳�����x�ƃI�����̌���
���� �w�����낳�����x�̋L�ږ@
���� �I������ǂւ̊K��-�啔�ɂ�����L�ڂ̏ȗ��ɂ���-/p803
���� �I�����̑啔�Ɣ��������߂�����-�I�����̔����𒆐S��-/p835
��3�߁w�����낳�����x�̋L�ږ@-�L�ڂ̏ȗ���
�@�@���I�����̖{���������߂�����-/p869
���� �I�����ƍ��J�I���E
���� �w�����낳�����x�̜ߗ�\��-�T�V�u�
�@�@�����c�L�𒆐S�Ƃ����\���I�l�@-/p901
���� ����ԃP�I�m�E�`���߂�����/p922
��O�� �I�����ɂ݂���ӎ��Ƒ���/p945
��l�� �u������v���l/p968
��O�� �v�����W�I�������߂�����
���� �v�����Ɖ��{���J-�v�����W�I�����̉��߂𒆐S��-/p983
�E |
�R���A�g���������u���m�_���@���������̑����I�\���Ɋւ��镶���n���w�I�����v�\����B�@pid/3116070
|
��./p1
1.�����̖ړI�Ǝ��_/p1
2.�����̕��@/p2
3.�u�}���r�g�v�Ƃ����T�O/p4
I.�}���r�g���J���߂��錤���j/p6
1.���{���������̌`��/p6
2.�}���r�g���J�ƕ��������_/p17
II.�v�����̃}���r�g���J/p30
1.�v�����̊T��/p30
2.�v�������J�̊T��-�O�̍��J����/p34
3.�v�����̃}���r�g���J/p53
III.�����̃}���r�g���J-�v�������痮���w-/p63
1.���ʉ����̃}���r�g���J:����{=�}���r�g���J��̎��_����/p63 |
2.�C�_�߈˂̃}���r�g���J:��j���C=�}���r�g���J��̎��_����/p98
3.�n�c�_�߈˂̃}���r�g���J:����=�}���r�g���J��̎��_����/p117
4.�ӂ��̍��J�����ƃV���}�j�Y���I�v�f/p156
���_/p160
1.���������̑��l���̗��j�I�`���ߒ�/p160
2.�v�����̍��J���E�̑����I�\��/p170
�s��_1�t����ՂƎ��n�Ղ̔�r����/p175
�s��_2�t��j�̍Ղ裂Ƣ���̍Ղ裂̍��J�����_�I�m��/p185
�s��_3�t���g�[�e���I�ϔO�Ǝփg�[�e���I�ϔO-
�@�@�����V�i�C�����̈�̎��_����-/p192
��/p1
�Q�l����/p1
�E |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 30(1)(81)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@pid/4437795
|
���A�m�ɂ�����n��j���� / �����O�N/p1�`14
���P���c��ʂ��Č�����㉫��ŋ� / ����/p15�`67
�X�����Ɩ쑺�� / �c�c��/p68~85 |
���d�R�Ί_�����̕��@--1�D���� �㖼�� / �{��M�E/p110�`90
�w��j���[�X/p67~67
�V���Љ� / �V���܂��/p86~86 |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 8�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�d���I�����̎����@�g�Ɗԉi�g p.1-56
�}�����F�h�̔����x�� : �T�ςƉ̎��̋ǖʂ��� �@���c��,�v���c�W p.75-180 |
�q�����r
�E |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 4�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002959227 �@�@1995�E�R
|
����̋������� ���������@p1
�ߐ��쓇�̋Q�[ �e�r�E�v p7
�ߐ������ɂ������ ���_���̎O -�R���Ɠ����v- ���c�I��u p17 |
���������E������� �啽 �� p26
Okinawa's Encounter with�@
�@�@��Christianity Richard*Klecan �@p1�i38�j |
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu�����蓙�֘A�q���������� 1�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@ �@ (���ꌧ������������ ; ��118�W)�@52p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002946893
|
����
�ጾ 1
�n�} 3
��1�́@������̊T�v 4
��2�́@�m�O���̔q�� 7
�֏��� 8
�m�O�� 12
�m�O��� 14
�m����� 16
|
���z��� 18
��3�́@�ʏ鑺�̔q�� 21
�ʏ�� 22
�ʏ�m���a�� 24
�~���g�D���O�X�N 26
��������� 30
�E���� 32
���u�T�c��� 36
�l���� 38
|
���n���a�J�T 40
��4�́@���~�E�^�ߌ��E�̔q�� 43
��� 44
�n�V��� 46
�^�ߌ��e�� 48
��a�R 49
���䉮����� 50
�كP�x 51
��5�́@�����Љ� |
�R���A������q��������w����w���}���I�v�ψ���ҁu������w����w���I�v.
��ꕔ�E��� (�ʍ� 46) p.p225�`248�@������w����w���v�Ɂu�������x��-10-���x��E�l�|�v�\����B�@�@
|
������q���u������w����w���I�v. ��ꕔ�E��� (�ʍ� 37�`46) ���ɔ��\�����u�������x��-1�`10�v���̓��e����\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
(�ʍ� 37) p.p161�`185 |
1990-12 |
�������x��-1-����ƋL���@�@ |
| 2 |
(�ʍ� 37) p.p187�`210 |
1990-12 |
�������x��-2-���������@�@ |
| 3 |
(�ʍ� 41) p.p147�`190 |
1992-11 |
�������x��-3-�ÓT���x--������ŕ� ���x��E�V�l�V���x�蕈�@ |
| 4 |
(�ʍ� 41) p.p191�`235 |
1992-11 |
�������x��-4-�j�x��E���������@�@ |
| 5 |
(�ʍ� 42) p.p225�`259 |
1993-03 |
�������x��-5-���x��E�����������@�@ |
| 6 |
(�ʍ� 42) p.p261�`292 |
1993-03 |
�������x��-6-���x��E�V��@�@ |
| 7 |
(�ʍ� 44) p.p195�`235 |
1994-03 |
�������x��-7-���x��E�ɖ�g�ߕ��@�@ |
| 8 |
(�ʍ� 45) p.p165�`214 |
1994-10 |
�������x��-8-���x��E���ԕ��@ |
| 9 |
(�ʍ� 45) p.p215�`290 |
1994-10 |
�������x��-9-�j�x��E�����ǖ��Ε��@�@ |
| 10 |
(�ʍ� 46) p.p225�`248 |
1995-03 |
�������x��-10-���x��E�l�|�@�@ |
|
�U���A������q�����{�S�g��w�� �ҁu�S�g��w = Japanese journal of psychosomatic medicine 35(5) p.p375�`380�@���{�S�g��w��v�Ɂu�}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ����ʂɂ���--�������x�J�`���[�V�[�̌��ʂɊւ���S�g��w�I�����v�\����B�@�@
�U���A�u���{���� : ���ۓ��{���������Z���^�[�I�v 12�v�� �u���ۓ��{���������Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@�iIRDB�j�i�@�փ��|�W�g���j
|
�����_�Ђ̓o�� : �y�Ђ̌n�� �@����N�F p.11-32
���{�Áu�`��v�w�Y���q�`�x�̌��� : ���������ɂ�����_�b���珬���ւ̋O�Ղɂ��Ă̌���(���̈�)
�@���Ё� p.33-72
<�t�H�[����>���{�^�g�D���߂��鏔���i����2�j : ���R�������̔ᔻ�ɉ�����
�}�J�a��� p.73-88
<�����W�]>�ߑ�Ƒ��_�̋Ȃ���p(1) �@�����b���q p.89-100
<����������>�����������̕搧�Ƒc��� �@����q�� p.101-119
<����������>�Տ�̐Ԃ��V�W�Ɣ����V�� : ����v�����̔N�����J�Տ�Ɍ��问���������J�Տ�ܐ݂̉e
�@�ɜn�� p.121-157
<����������>���{�^�V�X�e���Ƃ��̕��͓I���_ �@�g�c�a�j p.159-180
<����������>�Ƒ����ރX�L�[���Ə@����� �@���ؐ��N p.181-208 |
�U���A;�x�V�T���u���特�y 50(6)[(582)]�@p36�`37�@���{���特�y���� ���y�V�F�Ёv�Ɂu�ʍ��t�^ �V��ɂ�鉹�y��̍����ȏW ����ǂ��̉� 2������ /����h�� ;�{�ǒ���v�\����B�@pid/6035754
�V���A����|�\�j������ҁu�킪�t����� : �����|�\�̐�B�v���u�ߔe�o�ŎЁv���犧�s�����B�@
�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002792628�@�@(�ߔe�o�ŕ��� ; 3)�@284p
|
����Ǐ��t����� �R�c ��q
�V�_���t����� ��� ���q
�^�����R�N�t����� �^���� ����
�ʏ鐷�`�t����� ���c �s��
���܌��T�t����� �r�� ���q
�e�����Ǝt����� �e�� �v��
���l�v�M�t����� ��n ����
�����@��Y�t����� �ʏ� �@�g
���A���d�t����� �ʉh ���� |
�K�n�T���t����� ���� ���Y
���䐷�|�t����� ���� ��v
��p���L�t����� ���H�� �m�u
���Ԑ����t����� �ʏ� ����
��F�����m�t����� ��� ��r
�{���t�s�t����� �ݖ{ �g�Y
�^�����R�N�̌| ��� ��i
�^�����R�N�́u�ᕥ�v ���� ��Y
�^�����R�N��u�ɍ]���n���h�D�O���[�v�l �Î�� �d��
|
�ʏ鐷�`�̐l�ƍ�i �Î�� �d��
�ʏ鐷�`�搶�̎w���@ �ʏ� �ߎq
�ʏ鐷�`�̑g�x������ ���� ��Y
���܌��T�E���̐l�ƌ|�̐S �{�� ��v
���܌��T�搶�Ƃ̏o� ���� ���S
�n�w���Ƃ߂��҂Ƃ��� ���� ���Y
�n�w�Ƃ��Ă̈��x�c�|�v ���� ����
���x�c�|�v�搶�Ɋw�� �쐣 �T�m
���x�c�|�v�̋Ɛ� ���� ��Y |
�U���A������������B��w���ꍑ���w��ҁu�ꕶ���� (�ʍ� 79) p.22�`36�v�Ɂu���}�g�Ɖ���̂͂��܂�--�R�V�����Ɖ���(2)�v�\����B
�V���A�A�h�E�X�^�b�t�ҏW�u�ʏ闬�����݉� ���g�Ύ}�̉� �ÓT���x��i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ闬�����݉�g�Ύ}��������v���犧�s�����B�@21p�@�����F��㊌����}���فF1004688329
�@�@�@�@�����E�ꏊ�F����7�N7��7���E���ꌧ�����y����(�������),
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����7�N9��23���`24���E����\�y���C��(��������)
�W���A�c�葏�ҁu���S�y�� 1995���č� : ����E�����t��-�N�ɂ�����Ɋy��@ Vol.5�@���W�F�Ă̕������u�G�C�T�[�v�v���u�i�ߔe�j�p��-�n�E�X�v���犧�s�����B
�W���A����e���r����������Е��u��݂������O�̉��� : �ʐ^�W�v���u����o�Łv���犧�s�����B�@�d�v�@�P�U�O�O�~
|
�����с@5
�������̖��Ɓ@6�E7
�����s��(�ߔe)�@8
�����s��@9
�����s��E���݂̖q�u���ݎs��@10
�����s��E���݂̓����s��t�߁@11
�����s��(����)�@12
�����s��@13
���d�R�����s��@14
�O���n��(�{��)�@15
�O���n�ԁ@16
���ꐻ���{�ÍH��@17
�������i�@18
�������i�@19
�������i�@20
�������i�@21
�������i�@22
�^�_���̎q�������@23
�v�����̎q�������@24�E25
�{�Ò��w�̉^����@26
�{�Í������w�Z�̉^����@27
������(���Ǎ`)�@28
�R�r�Ɠ@29
���c�@30
���������@31
���ߍH��(�r��)�@32
�v�����̑��O���C�@33
�������(�㉺)�@34
�������(�㉺)�@35
���������I���ā@36
���������I���ā@37
���݂ۗ̕ǐ�@38
�ۗǐ�(��Ӓ�)�@39
�ۗǐ�@40
���(����)�@41
�g��Ձ@42
�g���(��E��)�@43
���݂̔g���(�_�K��)�@44
���݂̔g���(�_�K��)�@45
���̎��n���i(�g�Ɗ�)�@46�E47
���ł����i�@48
�_��@49
�k�앗�i(�g�Ɗ�)�@50
���݂̍k�앗�i�@51
���q(�^�_)�@52
�K�̗t�E��(�|�x)�@53
��ƕ��i(�^�_)�E�T�o�j�@54
�\�e�c�̎��E���n���i(�^�_)�@55
������(�v��)�@56
������(��u��)�@57
�T�o�j�����ς��̋�(�^�_)�@58
�n���̗l�q�@59
���X�@60
�A�_���t�̂�@61
�K���@63
�}�[�����D�@64�E65
���q(�^�_)�@66�E67
������(�g��{)�@68
�g��Ձ@69
���݂̔g���-�_�K��-�@70
���݂̔g���-�䗷����-
�@�@��(�p���b�g�v�Βn�O)�@71
�g���(�����_��)�@72
�g���-�_�K��-�@73
����^���@74
�w�l�Ǝq��(����)�@75
�s�ꕗ�i(��u��)�@76�E77
�v�����@78
�ۗǐ�(��E��)�@79
�E���K�[�@80
�R���̏����@81
�����̖��l�̔�(�{��)�@82
�i�}�R�̓�����(����)�@83
�������i�@84
�����E�[�c�����E�ΊD�q(�{��)�@85
�v���̐_�A�V���M�E
�@�@�����݂̋v���̐_�A�V���M�@86
���[�E�C(�{��)�@87
���[�E�C�@88
�䊠��̗l�q�@89
�q�������@90
�~�o�������@91
�q��(�{��)�@92
�q��(�{��)�@93
�q��(�{��)�@94
�������(�{��)�E���݂̟������95
������ԁ@96
���݂̟�����ԁ@97
�҂̓����@98
�҂̓����̗l�q�@99
�ʏ鐷�d(�ߔe�q�포�w�Z)�@100
�ʏ鐷�d(������ŕ�)�@101 |
�ʏ鐷�d(�g����哹�s����)�@102
����������x��c��^�J�q�@103
�ނ���x��c��^�J�q�@104
��O�����߁@105
�|�x���u��̌f���@106
��u�������}�@107
��u�����y�땪�z�}�@108
�|�x���@109
�z��(���V�ԋ{)�E���݂̗z��(���V�ԋ{)�@110
���݂̗z�@111
���ʐE���݂̕��ʐ��@112
������@113
�T�o�j�̕ۊǏꏊ(�{��)�@114
�����V��@115
�����V��@116
��Q��̗l�q�@117
���@���L���e�̕�(�{��)�@118
���݂̒��@���L���e�̕�@119
�T�b��̈��@120
�T�b��(����)�@121
�Y�̕�n(�^�ߍ�)�@122
���݂̕�n�@123
��n(�^�_)�@124
�������i(�{��)�@125
�{�Î떓�W���ɂ�����
�@�@��������(�g�D�����[)�@126�E127
�떓�W�������Ζ�(�g�D�����[)�@128
���݂̎떓�W�������̖�(�g�D�����[)�@129
�떓�W�������Ζ�(�g�D�����[)�@130�E131
�E���[�t�[���@132
���Ɏc�钆����(���w��d�v������/
�@�@���k���鑺)�̃E���[�t�[���@133
�搅���i�@134
���^���N(����)�@135
���i�с@137
����_�ЂƌĂ�Ă����鐳�a138�E139
���݂̎鐳�a�@140�E141
���j��(�鐳�a)�@142
���݂̎鐳�a���j���@143
�銽���(���a13�N11��)�@144
���݂̎銽���@145
�鐐���(���a13�N11��)�@146
���݂̐����E���݂̗���@147
�鐳�a���@148
�鐳�a2�K�ɂ������y��@149
�鐳�a2�K�ɂ��������|�@150
����(���a13�N11��)�@151
�~�o�����a(���a13�N11��)�@152�E153
���݂̉~�o��(����)�@154
�~�o�����a�{��d��߉ގO�����ƕ���@155
�������ɂ�(���a13�N)�E
�@�@���������ɂ�(���a16�N)�@156
�������ꂽ�������@157
�������ꂽ�������@158�E159
�瓿��̑Ί݂̒z�R����S���r�Ɛ��A
�@�@����a������@160
�������̐Ώ�@161
��t����(�k����)�@162
�k�����@163
�k�����@164
�k�����@165
���ޓ��̍�Ə����E���ޓ��@166
�Z�O���A�W�T�V�̎Y���@167
���ޓ��E���ޓ����i�@168
������(�v�)�@169
�F�쏔���̓��X�@170
�L�`�̊C�@173
���V���@174
�F�쏔���̓��X�@175
�����с@176
���݂̖����с@177
�ɕ����������ᓇ���݂�@178
�{�Nj�(�Ί_)�@179
��_���@180
���ꐻ���{�ÍH��E���݂̋{�Ð����@181
�^����(�{�������w�Z)�@182�E183
�}�[�����D(�{��)�@184
�T�o�j�ƃ}�[�����D�@185
����(�������E��)�@186
���݂̉��̒����@187
�߂铹(����)�@188
�߂铹�@189
���݂̖߂铹�@190
���݂̖߂铹�@191
��R(�ɍ]��)�@192
�̂ǂ��Ȕ_�����i�E�_�Ɓ@193
�≮�@194
�≮�@195
�ΐ��(�`��)�@196
�ΐ��(�`��)�@197
���V�ԋ{�@198
���݂̕��V�ԋ{�@199 |
���V�ԋ{�����@200
���݂̓��������E���������@201
�떓�E���c(�^�ߍ�)�@202
����������E���݂̓���������@203
�ۗǐ�t�߁E���݂ۗ̕ǐ�@204
�}�����̕�@205
����������@206
���݂̐���������@207
�������i�@208
�{�Á@209
�ۗǐ�E���݂ۗ̕ǐ�@210
���(�{��)�@211
���ԓ��̊C�݁@212
���݂̗��ԓ����猩���{�Ó��E
�����ԑ勴�@213
��ۋ�(��X����)�@214�E215
���ʐ�(�떓)�@216
���݂̕��ʐ@217
�r�ԓ�����@218
���݂̒r�ԓ�����@219
���q�̗l�q(������)�@220�E221
�t�l�E�M�E�D�@222
���Ǎ`�Ǝs�X�@223
���Ǎ`�@224
�I�����A(����)�@225
��Ƃ�����w�l�@226
�����ہ@227
�ߔe�`�@228
�����蕗�i�@229
�ߔe�`�@230�E231
�D�����猩���ߔe�`�E
�@�@�����݂̓ߔe�`(�O�d����)�@232
���݂̓ߔe��`�t�߁E���݂̓ߔe��`233
���Ɓ@234
��p�̎s�������فE��p�s�X�n�@235
���q���i�@236
���ƃV���T�M�@237
���q���i�@238�E239
�A��i�@240�E241
��с@243
�V�[�T�[�@244
�C���̂Ђȁ@245
�|�x�q�포�w�Z6�N���̎���
�@�@��(���w�Z�̍Z��)�@246�E247
�R�c���N�@248
�q�������@249
�n���̓�(?)�̌��i�@250�E251
�^�_���̏��������@252
���p�̏���(�{��)�@253
�I�[�g�O�ւ̎q������(�^�_)�@254�E255
��Ƃ������l�X�@256
�E�o�̗t�̂�̈�s�@257
��t�߁@258
�����[�@259
�{���q�q����@260
�x��̃|�[�Y���Ƃ�{���q�q����
�@�@��(�������ɂ�)261
�{���q�q����(��)�@262
�p���炢�̕\��̋{���q�q����(������)263
�f�ʉ�̗l�q�@264
�x��q�@265
�_�y���@266
���݂̐_�y���@267
�g��Ղ̍s��@268
�g��Սs��̂��t������@269
���_���K�[���@270
�_�яȃ����z�Β����c�ы`�O�c���@271
�L�O�B�e(�^�_)�@272
�H�����i�@273
�o���O�̋L�O�B�e�@274
�L�O�B�e�@275
�������E�����o�b�N�Ɂ@276
�ߌ�̂ЂƂƂ��@277
��˖�V���������@278
���@���̑�ˏ������Əo�y�������i�Ё@279
��Ƃ��鏗�������@280
�\�e�c�̎����n�@281
���m����ɂ��鏗���@282
�[���@283
�������с@285
�ƍ��_�БO�u�ƍ��ʂ�v�@286�E287
�ѓc�o�X�@288
�R���D�@289
�m�����@290
�w�h�����u���ނ�����v�@291
�u�F���x�m�v(�J���x)�@292
�����_�Ё@293
����̃J�c�I�@294
����`�@295
������(1)�@�쐼���������c��s�s��
������(2)�@�����c��s�̍s���n�}
������(3)�@���я��v���t�B�[�� |
�X���A�u�n�� 40(9)(475)�v���u�Í����@�v���犧�s�����B�@�@pid/7893655
|
���d�R ���̎Љ���l����<���W>/p1�`3,29�`66
�@�@�������̕\�� ���āC���̊e�W���ň�Ăɍs����ՁB�ŋ߂�6���́u����ԗ�̓��v(�w�Z���x�Z�ɂȂ�)�ɍ��킹�āC
�@�@���Z�����o�ōs����B�������̑g�ɕ�����āC�M�̋����Ŋy���ށB/ ���J���
�����̌��G ���W ���d�R / ���k�V�n ;���F�� ;���J���/P1~3
�����̌��G �V���[�Y���ӂ̂��܁E�ނ��� / ������/p4�`5
�����̌��G �V���[�Y���̋L���@�A�C�X�����h / ��ؗ��u/p6�`7
�����̌��G �V���[�Y���̋L���@���V�x���A�k�Ɍ� / ���錉/p8�`8
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� ���d�R�̋ߌ���ƌ��� / �Γ�����/p32�`37
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� �Ί_���̈ږ��Ɩ����W�c-��p�n�ږ��̉ʂ���������
/ ���F��/p38�`42
���W ���d�R ���̎Љ���l���� ���͒N�̂���-"���}�l�R�̓�"����̖₢����/���k�V�n/p43�`48
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� �����ƌ���-�u�喧�f�Ձv������ӂ�Ԃ���/�Ό�����/p49�`54
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� ���d�R�̊C�͍�-�V�������炵�Ɗ��ۑS/���J���/p55�`61
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� �Ӌ����̏d�w-��������肩�������/������/p62�`66
���W ���d�R�@���̎Љ���l���� �����E�����@�փK�C�h //p30�`31
�� |
�P�P���A�����i [�ق�]�ҁu�l�ނ̑n���ց[�~���҂Ƃ̌�_���� : �~���ҌËH�L�O�_���W�v���u�������_�Ёv���犧�s�����B�@
|
����̐L�яk�� �v�쏺��
�ʂ̎v�l �Ó��N����
�~���ω����߂����� �������p��
���t�W�ɂ����鎩�R�Ɛl�� �ɓ��r���Y��
�����̌���I�Ӌ` �͍����Y��
�w���҂̏��x�Ɓw�g�Ŋہx �R�ܓN�Y��
�u�ЂƂ̂��̂��v�l ���H���P��
����ꂽ�l�ʑ����t�y�� �n�Ӑ��� |
���܂Ɣn�̌�� �����i��
�ؑ]�`�� ��_�O���꒘
�~���҂ƕ��w�n�� �������v��
���{���p�ɗ����A�j�~�Y�� �҈җY��
�����G�t��̏�O ���앷����
�k��/�k�����
�@�@����r�����w�ւ̗U�� �ԍ⌛�Y��
�u���{�炵���v�̑��ݘ_�I��b �l���b�r��
|
�u�Đ����鍰�v ��ÍN�Y��
�ߑ�Y�ƂƁu�����v �ѓc�o�v��
���{�����̃L�[���[�h�Ƃ��Ă�
�@�@���A�C�k �����a�Y��
�X�ƕ����̗� ���c�쌛��
���A���̓N�w�A���N�w �����m�O�Y��
�����_�Ƃ����p���_�C�� ����F�T��
�E |
�P�Q���A���{�N�ٌ��v���ƕ��� �u�����|�\ (76)�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4418408
|
���������� / �|���o/p2~3
����������45��S�������|�\���v���O����/p4�`5
���N�̖����|�\ / �O�����Y/p6�`7
�a���̔O���x�� / �O�����Y/p8�`16
�Ԃ̉��� / �R�H����/p18~22
�������̑D�x�� / ���p�䐳��/p24�`26
���R�����_�y / �g�����/p28~44
�ۑ���̊����A���P�[�g��������/p45�`52
�e�n�̖����|�\ ��37��u���b�N�� |
�@�@�������|�\���̕� / �ē��T�k ;�{�c�ɍK/p54~65
�{�c�����搶�̕������J�҂��j�� / �����G�Y/p66�`68
�N�����Ɩ����|�\ �`���|�\�p������
�@�@���w�����m�����x�̎��g�� / �����a��/p69�`72
�N�����Ɩ����|�\ ��43��S���N���
�@�@�����y�|�\�̍u�] / �����G�Y/p74�`75
�N�����Ɩ����|�\ ��44��S���N���
�@�@�����y�|�\�o���c�̈ꗗ/p76�`76
�S�������|�\�ۑ��U���s�����A���j���[�X/p77�`78 |
���A���̔N�A�������������ی암�`�������ەҁu�g�x������`���|�\�̕���l���y�ѓ���̒��������v���u�������������ی암�`�������ہv���犧�s�����B�@�@�������Ɖ���J����������7�N�x���{�����u����U���J���v�搄�i�����v�ɂ��Ă̕�
|
�g�x�̕���l�� / ���w, �ʏ�`��
�g�x�̏㉉��Ԃ��l���� / �{��M��
�����̕���l�� / ���w, �X�ۉh���Y, �ʏ�`��
�����̎��� : �{�Ï����y�є��d�R���� / ���w, ���ꐳ��
���ꏔ���̋��� / �X�ۉh���Y
�g�x�́u���t�v�Ɋւ��钍�߂Ǝ�̍l�@ / �r�{���� |
�g�x���̕ۑ��E�`���̂�����ɂ��� :
�@�@������g�x�̓`���A�ۑ��̌���Ɖۑ� / ���܌��j
�g�x�̃e�L�X�g�E���W�[ / ��闧�T
�g�x�`���̒S�����₤ / �O�G���Y
��������|�\������(����)�ݒu�̎� / ���p�䐳��
�E |
���A���̔N�A�V�Ԕ�C�u�����u�����G�C�T�[ : ����̖~���ǂ� �����Łv���u�����ُ��X�v����Ċ������B
�@�@ ���łP�X�V�W�E�V |
| 1996 |
8 |
�E |
�P���Q�O���A�����V��z�[���ɉ����āu�u�V���|�W�E��<�����ÓT���y�̏����ɂ���>�v���O����
: ���ɉ����𒆐S�Ɂv���J�����B
�@�@��ÁF�����Y�\�j������,�V���|�W�E�����s�ψ��� ���ÁF�����V���
�P���A�V���|�W�E�����s�ψ���ҁu�V���|�W�E��<�����ÓT���y�̏����ɂ���>�v���O����
: ���ɉ����𒆐S�� �����Y�\�j������v���u�����Y�\�j������v���犧�s�����B
�Q���A�u���ꕶ������ 22 (���@�����P�搶�Ǔ����W��)�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B�@�B �iIRDB�j
|
�܂����� : ���@�����P�搶�̂��� ��Î� p.iii-vii
���@���搶�̈�ʁu�������l�v �F���g p.1-3
���@�����P����̂��� �������� p.4-11
���@�����P�搶�Ɨ^�ߗ� ������} p.12-13
�����̈Ӗ��E���݂̏� �����ɓs�q 1 p.14-19
�O���̏o���� �Ζ��瓹�q p.20-21
�Ǔ��� ��ڍL�� p.22-24
������w�ƒ��@���搶 �N�㌳�Y p.25-31
���@�����P�搶�̂������𓉂� �{������ p.32-33
�����q�̔߂��݂�w������ �g���G�q p.34-35
���@���搶���Â�� �{���� p.36-38
���@�����P�搶 �匩�ˎq p.39-47
���@�����P�搶�̑z���o �����H�^�s p.48-55
�w�����낳�����x�́u�Ȃ�v�Ɓu���v �֍����i p.56-61
���@���搶�̂��� ����@�� p.62-65
��ؔ���n���ږ�E���@�����P �V�萷�� p.66-71
�w����E�̓k : ���悤�Ȃ�搶 �얞�M�� p.72-87
�Y�����Ƃ̓�O�� ���{�b�� p.88-94
�v���o �쌴���q p.95-99
���P�搶�Ƌg��Ɣ� �R�錫�F 1 p.100-103 |
���@�����P�搶�����̂� �����r�O p.104-114
�Ǔ��E���@�����P �������� p.115-117
���@�����P�搶�Ɩ�������Y�搶�̏o� ����T���q p.118-130
�����ʂ́u���ڂv ������G p.131-134
�g�Ɗԕ����̉��C���� �����H�^�s p.137-181
���{�c��̃��s�� ���Ð^�O�� p.183-235
�u�����v�o�� �����r�q p.237-264
����̎�Ҍ��t �쌴�O�` p.265-282
�w�����낳�����x�ɂ݂���n��敪�ɂ��� :
�@�@���n���I�����𒆐S�� �Î芡��ߎq p.283-322
�d���I�����̍l�@ : �u�d���v�̎��ԂƁu�d���v�T�O�̒� �g�Ɗԉi�g p.323-357
�I�����̔��̌� �����K�� p.359-394
���̂ɂ�����<��>�̌`�� �ʏ鐭�� p.395-443
�V�u�Ƃ͂���v�l ����O p.445-496
<�r�Ԗ���>�l : �{�Ó��ו����̌��ƕ����I���̋��� �}������ p.497-565
��m���̌��w�Z������j�Ƌ���̎��� :
�@�@�����O�Z�N�㏉���𒆐S�� ����T���q p.567-618
�u�ӉԖ����v�_�ɂ��Ă̈�l�@ : ���ɉ����
�@�@���u���{���A�v�Ɋւ��� �嗢�m�q p.619-698
�E |
�Q���A�ԍ����v�� ; �ˌ����G�u�K�W���}���̖����w�Z�v���uPHP�������v���犧�s�����B�@ (PHP�n��V���[�Y, )
|
�������͑����m�푈�̎��A�w�Z����P�ŏĂ��Ă��܂��A�Z��̑傫�ȃK�W���}���������c��܂����B�������A����̂Ђƌ��O�̎����A�A�����J�R��̉��ɂ�������炸�A���̖����ŐV�����w�Z���X�^�[�g������B�����ɂ́A���a���肢�A�т��ʂ������̐l�����̐S�w�ʂ��ǂ���x�i�������A���������̂Ȃ���j���������̂ł��B���w�����ȏ� |
�R���A���ь��]���u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (�ʍ� 19) p.50�`64�v�Ɂu����̉P���ۂƃG�C�T---���n�������߂����āv�\����B�@pid/4427629
|
�k���{�������y�w��l��9����(1995)/1�`49
�u���v�| �A�W�A���y�̃_�C�i�~�Y��--�A�W�A�E�|�b�v���߂����� / ����m��/p1�`4
2.�A�W�A�̉��y�����Ɠ��{�������y�w�� / ����m��/p5�`6
3�D�V���|�W�E���u���{�Ƃ��̎��ӂ̖������y�����v / �������q ;�v���c�W ;�b�n���b
;�N��N�j/p7~25
4�D�������\�v�| //p26�`49
����̉P���ۂƃG�C�T---���n�������߂����� / ���ь��]/p50�`64
�����l���^�c�̂̉��y�I����--�����c�ɂ�����̊|���̎��ۂ�ʂ��� / �㐼���q/p65�`75
�����|�\�̕ϗe�Ƌ��މ�--���������킫�ɓ`�������u�����O���x��v�ɂ�鋳�މ��}�j���A��
/ �~�����q/p76�`89
�_�� 4.�p���v�| //p90~92
������(1995) //p93~93 |
�R���A�u�쓇���� 18�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�iIRDB�j
|
�����ʂ���ё�p�o�y�̊J���ʕ�--����7�`12���I����̈�Ղ𒆐S�� ���{�L�q,�v���O
p.1�`11
���ꓜ�Ƃ̊�@�Ƃ��̓W�] ���ԑגj p.13-30
�֎q���ƋT�k�� ����,���j ��,���F�� �� p.31�`61
�����s�̐̉� 3 �G�C�T�[�� �j���� ���{�M�v p.63�`96
�k��NGO�t�H�[�����Ɖ���̏��q�J��--����,�Q��,���� ��ËP�K p.97�`107
Peace Tourism as a Path to Sustainable Development and the Full
�@�@��Utilization of Okinawa��s Human Resources ��ËP�K,Karen Lupardus
p.109�`124
Planting the Seeds of Peace in the Foreign Language Classroom Karen Lupardus p.125�`132
��v�ҍ�����u���a�̑b�v�̋@�\�Ɩ��� �Ό�����,�V�_���q p.133�`148
�����Љ� ����34�N���i��� ���ԑגj p.1�`40 |
�R���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (22) �v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B
|
���C�R�n���C���̍Ղ�ƌ|�\ / �_�c���q/p1�`17
�W������|�\--���씪���{��𒆐S�Ƃ��� / �v�ۓc�T��/p18�`34
�����Љ�{��q�b�F�L�u�L�O��ː_�y �R���_�y�u�v--
�@�@�����������_�Г����O�\�O�Ԑ_�y�ƖL�O��ː_�y�ɂ��Ă�
�@�@����̐��� / �Ζ؉h/p35�`37 |
�����Љ� �{��q�b�F�L�u�L�O��ː_�y�@�R���_�y�u�v //p38�`58
�쓇�����|�\�����̉��v--���ʍu��(����7�N�x������) /
�@�@�� �X�ۉh���Y/p59�`62
�Ζ؉h���w�܂�`���_�x / �v�ۓc�T��/p63�`65
�E |
�R���A�Y�\�w��ҏW�ψ���ҁu�Y�\ (2)(419) �v���u�Y�\�w��v���犧�s�����B �@pid/4428629
|
<94�N�������>�������\/4�`41
�؍��̒ǙT�i�c�C�i�j�k�i�l / �c����/p4~11
�؍��]�˂̒[�ߍ� / �ɓ��D�p/p12�`20
�b��암�n���̎��q�� / �������c/p21�`30
�u�V�����l�v�����m-�g / �H���Ƌ`��/p32�`41
<94�N�������>�u�� �{�q���ɂ�����|�̓`��/�r�c�O��/p42�`51
<94�N�������>�|�\�Z�~�i- �֍O�q���ɕ���--
�@�@��"���"�̐��ݏo���F���̓h���} / �֍O�q ;������/p52~63
<95�N�������>�|�\�Z�~�i�[�u���J��Ԃƌ|�\��ԁv/64�`95
�����|�\�̍��J��Ԃƌ|�\��� / �F����o�j/p64�`68
���J��ԂƉ̕��� / �D�c�E��/p69�`75
���{���x�̐�����Ԃƌ|�p��� / ����p�r/p76�`85
�u���v�̑g���ƍ��J�� / ���R��/p87�`92
<���J��Ԃƌ|�\���>���߂����� / �H�c��/p93�`95
�܌��M�v�̐��E(204)�t����S�E�Ȃ܂͂�/��ϐ��� ;�F����o�j/p96~102 |
�q�r ���䂩�����r���{����--
�@�@���č��~�h���x����w�ɂ� / �����r�q/p103�`103
�����q�j�w�當���j�̌����x / ����}��/p104�`105
�n�ӏ��`�w�����Ղ̌����x / �ۍ�B�Y/p106�`107
���}���w��p�̓����Ɩ��ԐM�x / �����W��/p108�`109
���Y���P�w�܌��M�v�_�x / ���c���q/p110�`110
�����G�Y�E�F����o�j�ďC�w���{�̓`���|�\�x/������/p111�`111
�k���k�̏C���n�_�y�́u��v / ��Αוv/p112�`114
�u�܌��M�v�Ɖ���w�Ɓv�̂܂Ƃ߂Ɍ�����/���F�M/p115�`117
�z���S�̌��� / �Ύ�،��q/p118�`120
����̎d��--(�����Z�N�\�ꌎ�`�������N�㌎)/p121�`130
�L�^�\���--('94�E12~'95�E11)/p131~133
�w���� �������N�x �|�\�w�����/p134�`134
�w���� �������N�x �|�\�w�������/p135�`135
���G �u�t����S�E�Ȃ܂͂��v / �F����o�j ;��ϐ��� |
�R���A�u���c���L�ˁE�唑�l�L�ˁ@�@�[��1�E2�E3�����@������v ���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@
�@�@�@�i���ꌧ��������������74�W�j�@�d�v
|
���^�{�������͔��d�R�S�|�x���g�Ɗԓ����݂́A���c���L�ˋy�ё唑�l�L�˔��@�����̐��ʂ��L�^�������̂ł���܂��B�^���Ĕg�Ɗԓ��ɂ����ẮA�������N�_�Ɗ�Ր������Ƃ���K�͂Ɍv�悠�邢�͎��{����Ă��Ă���܂��B�{��Ղ̈ʒu���鉺�c���n��ɂ��Ă��ޏꐮ�����Ƃ��v�悳�ꂽ���߁A�����������͈̔͂Ƃ��̐��i�𖾂炩�ɂ��A�K�ȕۑ���}�邽�߂̋��c���s���K�v������������ł���܂��B�^�����œ�����ψ���ł͕������̕⏕�āA���a58�N�x��� 3���ɂ킽��A���Y��Ղ͈̔͊m�F�̂��߂̔��@�������Ƃ����{���Ă܂���܂����B�{�N�x�͍ŏI�N�x�ɂ����邽�߁A����܂ł̒������ʂ��ЂƂɂ܂Ƃ߂ĕ���^�тƂȂ������̂ł���܂��B�^���c���L�˂́A���ł͏��߂Ă̔��@�������J�n���ꂽ��Ղł��邱�Ƃ�A���̕������e������n��Ƃ̕����I�֘A����������ȂǁA���d�R��j����̏d�v�ȕW����ՂƂ��čL�����ڂ���Ă����Ƃ����Ă���܂��B�^����̔��@�����ɂ����Ă��A��j����̏d�v�Ȉ�\��╨���o�y���A���d�R��j����̐����ƎЉ�̗l���Ȃ�тɕ����I�n����T�������ŁA�ɂ߂ċM�d�Ȑ��ʂ�����ꂽ�悤�ł���܂��B���̐��ʂ���ɁA�����̋M�d�Ȗ������������_�Ɗ�Ր����̌v�����ɂ������Ă��\���ɔz������A���̓K�ȕۑ����}����悤���c������i�߂����ƍl���Ă���܂��B�^�܂��A�{���������̏��J���v��̍���ɂ������Ă̕ۑ����c��b���Ƃ��ė��p�����ƂƂ��ɁA�������ɂ��Ă̕��y�Ȃ�тɕ��������N�v�z�̍��g�A����ɂ͗��j�w�K�̋��ނ���ъw�p�����ȂǑ����ʂɊ��p����邱�Ƃ����҂��鎟��ł���܂��B
�@�@�@�@���a61�N 3��31���^���ꌧ����ψ����^���璷 �đ��K�� |
�R���A <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g : <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
5�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@23p�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003077730 1996�E�R
|
���S������ǂ�-����g�x�� �m�[�g1- ���� ���V p1-14
�t�����X�ɂ����鉫��̏@���̏Љ� ��� �� p15-18 |
�u�������v�̗��s �e�r �E�v p19-22
�E |
�R���A�~���w�@��w�n�敶���������ҁu�n�敶������ : �n�敶���������I�v = Study of regional culture : journal of the Institute of Regional Culture (11) �q�������ꋳ���Ď��L�O�r�v���u�~���w�@��w�n�敶���������v���犧�s�����B�@�@pid/4424707
|
�ܓ����l��̒n�Ղ� / �������F/p1�`8
�����Z�N �Ԕ��R��ŕ�[���ꂽ�_�y / ���O�i��/p9�`13
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r ��������Ɋw�Ԃ��� / �蕔�ǕF/p14�`22
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r �����搶�Ƒ�p / �ߓ��~�q/p23�`28
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r �R��������z�R/�n�ӈ�Y/p29�`38
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r ���Ȍ��肵���肳���ꏊ/�r�ؐ���/p39�`48
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r �����̑I��/���ȂׁE�Ђł̂�/p49�`56
�q�������ꋳ���Ď��L�O�r ����s�働��Y�̕ߌ~/�ɓ���/p36�`60
�q�H�ׂ��̕��y�L�r�J�c�I�̃^�^�L / �R�c�����Y/p61�`64
�狣�Z�T�K�m�[�g(7)�F��s�E��ؓ��Ղ� / ���y�r�Y/p65�`82
�ЎR�P�ǂƁA���̎���(���̎O) / �{�c��/p83�`91
�{�Ϗt���̐��Ɨ� / �b�����V/p1�`13
���������ƃV�R�j���A�Ñ㎇����/
�@�@�����c�W;���q�r�q;���J�u�m;�c��۔�/p14~22 |
�I���G���g�̃t�B���h�m�[�g���� / ����h��/p23�`34
���֎s�F�쒬�E�▼�Õ��ɂ��� / ��쏺�j/p35�`48
���d�R�������y�핶�������̂��߂̃A�u���[�` / �g�c����/p49�`57
�K���]�ȓ�n��̌Ñ㕶�� / ���i�R ;���Ό�/p58~76
�k�Y�̋����M�� / �������K/p77�`89
���s�����̕��� / ����M�q/p90�`98
�ܓ��E����R�������̖�����b(2) / �L�����F/p99�`110
�r�f�I�w��������搶��
�@�@���Ƃ��Ă����̘b�x�̂ł���܂�/���k�V�n/p111�`117
�q��11����r ���傱�Ƃ��ꂱ��--
�@�@������̃\���ƂE�z���Ƃ� / ����M�q/�@p118�`126
�q��11����r �����E���ւɂ���/ ���c����/p127�`133
�q��11����r �R�����̕����A�N�Z���g/�Y�c�����Y/p134�`140
�E |
�W���A���{����,���c�a�炪�u���{�̈�w��� (47) p.646�v�Ɂu����{���ɂ�����G�C�T�[�̗������x������� : �������x�̕ω����m�肷��`���v�\����B�@�@�@J-STAGE
�W���A���w���u����V���w�̌n�� �v���u�Ђ邬�Ёv���犧�s����B�@�������Ȃ핶��78��
�X���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (23) �v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B�@�@pid/7959573
|
������{�Z�g�x�Ɩ���(�O��)--<������>�|�\�̈�Ƃ��� / ��ؓ��q/p1�`28
�ߑ�̉��܂킵�̗��j�I�ϑJ�ƌ���I�W�J--���h���܂킵������� / �����q/p29�`49
�V���|�W�E�� �Ղ肩��|�\��--�쓌�̓��X�ɒT��(����7�N�x������) / �O�����Y
;�g�Ɗԉi�g ;�㌴�F�O ;���w ;�v���c�W/p50~87
�Љ� �w�������j �����|�\�ҁx / �鏊�b�q/p88�`88 |
�X���A�_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (13)�v���u�_�ˏ��q��w�j�w��v���犧�s�����B�@pid/4424479
|
�_�� �ߐ������ɂ�����m���̊���=�L�� �ߐ������ɂ�����m���̊��� / �m������/p1~21
�_�� ��ꎟ�j���t���̓S������=�L�� ��ꎟ�j���t���̓S������ / �����F��/p22~50
�����m�[�g ��̏����t�����{�b��=�����m�[�g �����ȃC���[�W�̑�������̃y�A/�ԕ��юq/p51~76
�j���Љ� ���O���O�ΐ���������=���O��������������/p77~
�l�Ɗw�� �����̉��(2)=��l�̗��j�ƂƂ��Ă̎��` �������(2) / �R�{�l�Y/p124~143
�j�w�Ȃ����=���m�点 / �����F��/p144~146�@�^�j�w��C���s�L/p146~150�@�^�G���E�}��/p150~155�^
����7�N�x�C�m�_����� ���Ƙ_�����/p156�`160 |
�X���A�������X���u�ʍ����j�ǖ{68�@���T�V���[�Y29�@��21��38���@���{�u��n�E����v���� �v�Ɂu����̐_�q�݂̏���E�v�����v�\����B
�P�P���A���{�N�ٌ��v���ƕ� �ҁu�����|�\ (77)�@�v���u�����|�\���s�ψ���v���犧�s�����B�@pid/4418409
|
����������46��S�������|�\���v���O����/p2�`3
���N�̖����|�\ / �O�����Y/p4�`5
���؎R�Ԋy--�{�C���Ԋy�Ɣ��؎R�Ԋy/���R��/p6�`18
��q�̑�O�� / �A�؍s��/p20~27
���q�̉⎂�q / �����b��/p28~36
�^���i�\�x�j�̃G�C�T- / ���w/p38~44
�ۑ���̊����A���P�[�g�������� //p45�`52 |
�e�n�̖����|�\ ��38��u���b�N�ʖ����|�\���̕�
�@�@�@�� / �{�c�ɍK ;����h ;�ē��T�k/p53~65
�N�����Ɩ����|�\/66�`70
���y�|�\�ւ̎��g�� / �쑺��/p66�`67
��44��S���N���y�|�\�̍u�] / �����G�Y/p68�`69
�N�����Ɩ����|�\ ��45��S���N���y�|�\�o���c�̈ꗗ/p70�`70
�S�������|�\�ۑ��U���s�����A���j���[�X //p71�`72 |
�P�P���A�哇�ŗY [�ق�]�ҁu��B�E����̖��� ���������ҁv���u�O�ꏑ�[�v���犧�s�����B�@�@ (���{�����������W��)
|
��������������(���a40�N��)
����여��̖��� 1�`2(���a49�`50�N��) |
�i�g�여��R�[�n�т̖���(���a51�N��)
���̖��� 1�`2(���a52�`53�N��) |
�P�P���A�R��G�Y���u��` : �����̉Ȋw 50(11) p.65�`68,�}����1p�@�G�k�E�e�B�[�E�G�X�v�Ɂu����̐������̕s�v�c�Ȑ���(8)�K�W���}��--��C�d���`���ƐA�������w�v�\����B�@�@
�P�P���A������q���u�����q�� = Japanese journal of health and human ecology 62(6) p.319�`327�@���{�����q���w��v�Ɂu�}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ�����--�������x�u�J�`���[�V�[�v�̌��ʂɊւ��錤���v�\����B
�P�Q���A�R�ܓN�Y�ҁu���{�����̐[�w�Ɖ���v���u���ۓ��{���������Z���^�[�v���犧�s�����B�@
�@�@ (�������p�� = Nichibunken Japanese studies series, 12 . ���ۓ��{���������Z���^�[���������j
|
�_��<�Ȃ肫��><�ނ�>�̑f��(������) / ���Ԓ��m
�嗤�����ɂ����镗���ϔO�Ɩ����ɂ��� / �n粋ӗY
���{�̉̐_�M�� : ���ɓ쐼�����𒆐S�Ƃ��� / ����q��
�ؗd���̍l�@ : ����̏o�� / �c����H
�×������̉����ɂ����鋋�c�̈ړ� : |
�@�@���{�q�Ε������������̃X�P�b�` / ���Ǒq�g
�A�C�k�̉̐_�ɂ��� / �R�c�F�q
���ꏔ���ɂ�����_�k�̋N�� : ����{���𒆐S�� / ���{�L�y
�v�����ɉ�����u�Ɓv�u���g�D�v�ɂ��� / ��ÍN�Y
�E |
�P�Q���A �^�������u����(�ʂ�)�R���邤���`����2001�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�^���f�B�X�N 6�� : ���^����: 63��06�b/61��30�b/61��37�b/64��22�b/65��04�b/69��25�b�@�i�Ȗڂ�2008�N�łɋL���j
���A���̔N�A���ꌧ���H�J�����ό������Ǖ����U���ەҏS;�X�ۉh���Y����E�ďC;
�U�N,�ɍ���d�|��u�������D = Ryukyuan dance �v���u���ꌧ���H�J�����ό������Ǖ����U���ہv���犧�s�����B
���A���̔N�A�u����S���G�C�T�[�܂� ��41��v���u����S���܂���s�ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@����S���܂���s�ψ��� ���
|
| 1997 |
9 |
�E |
�Q���A�R�����ꂪ�u����̖������Ƃ܂��Ȃ�:�t�[�t�_(���D)�̌����v���u��ꏑ�[�v���犧�s����B�@
�@�@(�쓇�����p�� ; 18) �@�@�����F���ꌧ���}���فF1003151626
|
�� �����������j�Ɩ{���̍\��
���� ����̃t�[�t�_(���D)
�͂��߂�
�� ����́u�����k�L�����v
�� ����̃t�[�t�_�̎���
�O ����̎����̏���
�l �����j���Ɍ��鉫��̎���
�� �t�[�t�_�̌����Ǝ�e�̔w�i
�Z �t�[�t�_�̎n���ƌ_�@
������ |
���� ���d�R�����ُ����̂܂��Ȃ�����
�͂��߂�
�� ���Џ����̂܂��Ȃ�
�� �u�܂��Ȃ����v
������
��O�� ����^���p���W�̂܂��Ȃ�����
�͂��߂�
�� ��
�� ����
�O �u���撠�v�Ɓu���o���v |
������
��l�� ��炵�̒��̂܂��Ȃ�
�� �c���̖鋃���Ƃ܂��Ȃ�
�� ������݂̎����u�N�X�N�F�[�v
�O �n�k�����̎����u�L���E�c�J�v
�l ��̌��J
���Ƃ���
����
�E
�E |
�Q���A�؉����q�����m�_���u�쓇�L�����̌��� : �L�̓��̍l�Êw�v�\����B�@pid/3123152
|
���\�쓇�l�Êw�̌����j�Ɩ{���̖ړI/p1
��1�� �퐶�����ƊL�̓�
��1�� ��C�Y�L�ւ̌n��/p13
1 �͂��߂Ɂ\�����j�Ɩ��̏���/p13
2 �쓇�̊L��/p16
3 ��B�퐶�����̊L��/p29
4 �퐶�����ɂ������C�Y�L�ւ̌n���\
�@�@���܂Ƃ߂ɂ�����/p42
��2�� ��C�Y�L�ւ̐����ƓW�J/p49
1 �͂��߂Ɂ\�n��敪/p49
2 ��C�Y�L�ւ̒n��ʓ���/p50
3 II�ފL�ւ̐����ƓW�J/p63
4 �܂Ƃ�/p74
��3�� ��C�Y�L�֒����K���̍\��/p79
1 �͂��߂�/p79
2 �܂�^�L�ւ̒����K��/P79
3 �����܂��^�L�ւ̎v�z/p93
4 �܂Ƃ�/p100
��4�� �L�ւ��瓺����/p105
1 �͂��߂�/p105
2 �L�ꓺ���������j�\���_�̐���/p105
3 �L�n��������/p108
4 ����^�L�ւƗL�ꓺ��/p121
5 �L�n�����̐����ƓW�J/p129
6 ������/p134
��5�� ��C�Y�L���Սl/p137
1 �͂��߂�/p137
2 ��B�퐶�l�̊L����Ɨ��ʃV�X�e��/p139
3 �L�c�l�̊L����/p154
4 �쐼�����̊L����/p157
5 ������/p175
��6�� �L�̓��̐l�X/p185
1 �L�̓�/p185
2 �y��P�l�L�ւ̌����́\
�@�@����1���`��5�������̈╨�𒆐S��/p190
3 �Ƃǂ��Ă����g���\
�@�@���k�Y�̖퐶����ɂ悹��/p203
|
4 �C������(���[��)�����̃S�z�E���L��/p208
�t �퐶����L�֏o�y�ꗗ/p221
�t �����ꗗ/p232
��2�� ���ƌ`���ƊL�̓�
��1�� �L�`�̒a���\�������̌n��/p241
1 �L�`�Ό����̌���Ɖۑ�/p241
2 �L�`�̂������̌n��/p244
3 �L�`�Βa���̔w�i/p261
��2�� �Õ�����̊L����L�̓��\
�@�@��3�`8���I�̓쓇����/p273
1 �͂��߂�/p273
2 �퐶����I�����̊L����L�̓�/p275
3 �Õ�����O���̊L����L�̓�/p294
4 �Õ����㒆���̊L����L�̓�/p304
5 �Õ��������̊L����L�̓�/p327
6 ����\�Õ�����̓쓇���Ղ̈Ӗ�/p336
�t �C���K�C�������n��\
�@�@���R�n�����̒��̓�C�Y�L/p351
��3�� ����@���L�����l�\
�@�@����C�����i�̈ꌟ��/p365
1 �͂��߂�/p365
2 �����ۊǂ̏���/p366
3 ��?�𒆐S�ɂ݂����������i�̉��v/p371
4 �����Ƣ�����L�����̈Ӗ�/p378
5 ���{�ɂ����鏉���̏�?/p380
6 �܂Ƃ�/p383
��3�� �쓌�̊L����
��1�� �쓇���E�ƊL�˂̊L/p389
1 �͂��߂�/p389
2 �쓇���E�̒n��/p389
3 �T���S�ʐ��E�ƊL/p394
4 �쓇�̊L�ˊT��/p399
�t �L�ˌ������j/p419
��2�� �쓇�̌Ñ�L����/p427
1 �͂��߂�/p427
2 �L���i����/p428
3 �L���i�T��/p430
|
4 �쓇�̊L�����̓��F/p439
�t �쓇�̊L���i�\�������ꎁ�
�@�@���������F�������̏Љ�/p444
��3�� �L�Ƒ����K���\
�@�@�����ꌧ�^�u������Ԍ�
�@�@������Ղ̕���/p449
1 �͂��߂�/p449
2 �o�y�L���i/p450
3 �L�Ƒ����K��/p463
4 �����Ɂ\����̉ۑ�Ƃ���/p477
��4�� 焎ׂ̊L�\���Ⴑ�����l/p479
1 �͂��߂�/p479
2 �l�Î����ɂ݂邵�Ⴑ����/p480
3 ���Ⴑ�����̎���/p496
4 ����/p508
��5�� �L���e�포�l/p515
1 �͂��߂�/p515
2 �L���e��̐ݒ�/P515
3 �L���e��̏���/p516
4 ���R�E�K�C���q�V���N��e��/p523
5 �q�V���N��e��̗p�r/p526
6 �܂Ƃ�/p527
��6�� �삩��݂��L�̓��\
�@�@����̌��Ղ̂����炵������/p533
1 ��̊L�̓�/p533
2 �L�̓��̑��܂�/p533
3 �L�̓��̐l�X/p534
4 �L���Ղ̐��n�ƊL�̓��̉���/p536
5 �����ЂƂ̊L�̓�/p537
6 �L�̓��̂����炵������/p538
��7�� �L�c��ՂƊL��/p541
1 �����������q���L�c���/p541
2 �L��/p550
3 �L�����l�̌n���\
�@�@���쓇�̎�������/p560
���Ƃ���/p575
�E |
�R���A���d,�L���R��,����ς����ꌧ���璡�����ەҁu�N�c�×q�� : �����Ɍx�@�����݂ɌW�锭�@����
�V�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s����B�@�@�@�@ (���ꌧ��������������129�W)�@�@�d�v
�R���A��u��s�j�҂���ψ���ҁu��u��s�j ��3��(���b��) �� (�`��)�v���u��u��s����ψ���v���犧�s�����B
|
���G
�����̂��Ƃ@�{���i�@17
�s�j��O���u���b�ҁv��̊��s�ɂ������ā@�����ۍs�@19
�����Ɋā@���{�i���@21
�}��@23
�ڎ��@27
�{���ڎ��@28
�{���@1
��u��s�T���@�����ۍs�C��]�F�q�v�@829
����@���������@895
�����T�v�@�^�ߌ����a�q�@961
�������b�����@�떓�ɋv�@1030
�Q�l����
�ҏW��L
�s�j�҂���ψ���E�҂�����
�{���ڎ�
��u��̓`��
1�@��́E��u��́[�~���C�@��u�������@3
2�@���NJԒn����@�V�_���h�@7
3�@���NJԒn����Ə��A�o�[�}�@�������g�@9
4�@���NJԒn����̉��������@�V��p�^�@11
5�@�i��ƃA�J�o���^���@���c�����Y�@12
6�@��́E���ǃu�T�[�@������ĐM�@14
7�@��́E���Ǐ��u�T�[�̒|����@���c�������@19
8�@��́E���Ǐ��u�T�[�Ɠ앗���O�ԁ@�ɋ��J�}�h�@22
9�@��́E���Ǐ��u�T�[�̒��j�̘b�@�V��p�^�@24
10�@��u��q�W���W���[�@�`�c���@26
11�@��u��q�W���W���[�Ɠ앗���O�ԁ@���������@29
12�@��u��q�W���W���[�@���c�������@32
13�@��u��q�W���W���[�@�m�O�����@34
14�@��u��A�r���[�@�m���E���@35
���̂ق��̘b�@36
�c��̓`��
1�@�c��E��u��̎n�܂�@��v�R�O�Y�@41
2�@�E�t�S�[���[���C�Ɠc��`�@�V�_�`�u�@43
3�@�c��ƃE���[�O���[�@�������h�@46
4�@�i�J�t�i�[�Ɣ����̖��̗R���@�������k�E�@47
5�@�c��̌�菊�Ɣ��ց@�ʊ�}�c�G�@48
6�@�c��E�u�K�[�Ɠc��u�V�@�V�_�`�u�@50
7�@�c��̃E�X�f�[�N�̎n�܂�@�V�_�`�u�@54
8�@�c��̃e�B���x�[�@���c�����Y�@56
9�@�c��̍��l�R���@���c���ā@57
10�@�c��j���̗��ƃi�N�K�[�@�ʊ�}�c�G�@59
11�@�c��̋ʊ�v�߂Ɖ�����@�ʊ�T���@60
12�@�X���e���̓c��B���@�V�_�`�u�@62
13�@�X���e���̓c��B���@���c�������@65
14�@�c���H�@�h��쐷�D�@67
15�@�c���H�Ǝ�@���c�i���@75
16�@�c���H�̑��q�Ɖ~�o���̏C���@��鐷���@78
17�@��́E�c�ꃓ�W���T�[���@���c���ĎO�@79
18�@�r�[�G�[�L�@���c�������@82
19�@�E�t�S�[���[���C�̃L�W���i�[�@���c�����h�@84
���̂ق��̘b�@87
�Ԗ�̓`��
1�@�Ԗ쉮��̎n�܂�@���ÎO���@91
2�@�Ԗ�̎������@�v�����P�@92
3�@��́E���Ԗ��R�˂ƃE�t�A�u�V�[�@�v�����P�@94
4�@�u�a���ҕ�̃J�l�[���@���ÎO���@96
���̂ق��̘b�@98
�F���̓`��
1�@�F���̃r�W�����@�h��쐷�D�@101
2�@�A���t�`��x�@�h�����@102
3�@�A���t�`��x�@�i�R�V�Y�@104
4�@�������}�K�C�̑�V�@���Ԗ��ǐ��@106
5�@��c�̎���Ɖh��쐩�@�h��쐷�D�@108
���̂ق��̘b�@109
�V��̓`��
1�@�A�[�}���`���[�ƓV��̎n�܂�@���c���S���Y�@113
2�@���b�u���̉����ƓV��@���ljh�@114
3�@�V�葾�Y���ƃ`�`�O�V�N�@���c�i���@116
4�@�V�葾�Y���̋|��̑Ό��@���c�����h�@118
5�@�V�葾�Y���̍ȂƋ������ԁ@���c�i���@120
6�@�V�葾�Y���ƓؐH���̎n�܂�@�V�_�`�u�@122
7�@�V�蒷�҂ƍ����@���R�����@124
8�@�A�J�q�W�G�[�L�@���c�����h�@125
9�@�V�蔑�œ�j������ؐl�Ɠ쓇�x�@�_�c�K���@127
10�@�V�蔑�œ�j������ؐl�Ɠ쓇�x�@���c�i���@130
11�@�F���ƓV��̎��q���@���Ǎ_�@132
12�@�V��̊w�҂ƃu�V�@���c�i���@134
13�@�쉻�X�̐_�@�_�c�K���@136
14�@�`�`�O�V�N�̃J�[�ƃu�V�@�����Á@137
15�@�V��̏j���a���@�����Á@138
16�@�r�[���̗R���@�r�[�t�q�@139
17�@�V��N�F�[�W���[�@�������p�@140
18�@�������̋�����@���������@141
19�@�E�}�C�[�̓}�W�����@�^�Óc�E�g�@142
20�@�V��n��̈�O�@���Ԗ��@���@144
21�@�V��n��̗H��@���l���q�@147
22�@�V��́[�~�[�J�[�̃}�W�����@�����Á@149
���̂ق��̘b�@150
���z�̓`��
1�@���z�̎����̎n�܂�@���Ԗ��@���@155
2�@���z�̒��̎n�܂�Ǝ������@���v�쒷���@157
3�@��ɑ������܂ꂽ���v��^�����@���Ԗ��@���@159
4�@�^�J�r�����~�肽���Ɣn�@���Ԗ��@���@162
5�@�S��ɏP��ꂽ�V�k�@���Ԗ��@���@164
6�@���ޕ�̉̐��@���R�����@168
���̂ق��̘b�@169
�h���̓`��
1�@�K�}�Ɖh���̕Ԃ��r�@�^�Óc�F���@173
2�@�h���̓�[�k�t�@��x�@�������J���@176
3�@�h�����Ɣ��l�@�������J���@178
4�@�����E�h���J�}���^�[�̉B�ꓴ�A�@���R�����@179
5�@�h��䉜���Ƒ^�쉳�M�@�ΐ쐷�F�@180
6�@�h��䉜���Ƒ^��^�}�`�[�@�ԏ�E�V�@183
7�@�����[���Ɖ̐_�̔��@����m���@185
���̂ق��̘b�@188
���̓`�� |
1�@���̎n�܂�@����P���@191
2�@���E�u�K�[�̑�V�@�ΐ�G�q�@192
3�@�����K�[�ƈ��c���K�[�@�����ۍs�@193
4�@��́E���J�T���^�[�Z��@�����ۍs�@194
5�@�`�`�O�V�N�̃}�W�����@���J���@198
���̂ق��̘b�@200
���c���̓`��
1�@���c���̔��ď�@�����ۍs�@203
2�@���c���̔��ď�@�ÎӐ��q�@205
3�@���c���K�[�ƒ����K�[�@���썃���@207
4�@���c���̃E�X�f�[�N�Ƒl�@���@���t�q�@209
5�@��������@�m�O�c�@210
6�@�n�悢����@����A���@213
7�@��́E���c���e�B�[���@�㌴�~�l�@214
8�@���c���̋h���ҁ@�����Ԏ��ǁ@215
���̂ق��̘b�@216
�����̓`��
1�@���q�R�̖��̗R���@�����ۍs�@219
2�@�����̖��̗R���@�����ۍs�@220
3�@����̎n�܂�@�Îӈ����@221
4�@�������t�@�����[�̗��@��]�F�J�}�h�@223
5�@�����̍K��������@�����ۍs�@224
6�@�T�̓���H�ׂȂ��킯�@�����ۍs�@225
���̂ق��̘b�@228
���ǐ�̓`��
1�@���ǐ�̎n�܂�@���c�������@231
2�@�e�[���W���[�̓��A�ƕ��ǐ�̖��@����a�}�@232
3�@�t�F�[���[��ގ���������������@����X�q�@233
4�@���ǐ_�c��̉̎O���@����O�h�@237
���̂ق��̘b�@238
�쒇�̓`��
1�@�쒇�̎n�܂�@�������Y�@241
2�@�쉮���}�[�u�̋|��@�{��J�}�h�@243
3�@�쉮���}�[�u�̉�����@�u�c�^�����@245
4�@�쒇�̐Ί����@�Ɍ|��@245
5�@�쉮���}�[�v�̈�O�@�V��b���@247
���̂ق��̘b�@249
�㕽�ǐ�̓`��
1�@�鋃���@�V��b���@253
2�@�㕽�ǐ�̃C���K�[�@���钿���@255
���̂ق��̘b�@256
�L���̓`��
1�@�L���̎n�܂�Ɩ��̗R���@�����R���@259
2�@��v�R�咆�̐�c�@��v�R���h�@260
3�@��v�R�咆�̐�c�@��v�R�^���@261
4�@�L���̃q���V���[�̔q���@���������@263
5�@��́E���얡���^�����[�@�Ɖ����M�@265
6�@��́E�����R���@�����O�Y�@268
���̂ق��̘b�@269
��]�F�̓`��
1�@��]�F�̎��̎n�܂�@���������@273
2�@�t�V�N�u�@�u�c�^�����@274
3�@������q�W�[�_�c�@�������@275
4�@��]�F�̃V�`�����G�[�L�@���������@277
5�@��́E�V��^�����[�@���������@278
6�@���l�E�ɓc���Ӌ|�@����E�g�@279
7�@��]�F�o���^�̎��҂̐���@��]�F���M�@281
8�@�J�}�h�D�C�̈�O�@��]�F���h�@283
9�@���o�L�����@�����[�J�c�@284
10�@��́E�h���u�T�[�@�����i�w�@286
���̂ق��̘b�@287
�����̓`��
1�@�����̖��̗R���@�����ۏ��@291
��c�̓`��
1�@��c�̈��̗R���@�ʉh���Y�@295
2�@�����u�V�E�v���@�u�c�^�����@297
3�@�}�W�����ɏP��ꂽ�N�@��u�������@298
4�@�q�V�`�[�^�����[�Ɗ�������@���@���t�@303
��c�̓`��
1�@�]�F���Ɛ�c�̎n�܂�@�×z�@���@307
2�@�×z���@�×z�@���@308
3�@��c�̖h�g��@�×z���Y�@309
4�@��]�F�K�`�@�×z�@���@310
5�@���y����@�×z�@���@311
6�@�n�̓���H�ׂȂ��×z�Ɓ@���䃄�X�@313
���̂ق��̘b�@314
���Ӓi�̓`��
1�@���Ӓi�O�V�N�����ƃJ���W���[�K�}�@�_�J�i���@317
2�@���Ӓi�O�V�N�̃g�D���O���@�K��U�H�@320
3�@���Ӓi���@�ʏ鏼���@321
4�@���Ӓi���@�_�J�i���@322
5�@���Ӓi�̍��_�咆�@���Ë����@324
6�@�~�[�o�J�O�[�t�͉����X�@���Ë����@325
7�@�q�Y�݃N���C�@���Ë����@327
8�@���Ӓi�̎O��c�@���ܐ��K�@328
9�@���Ӓi�r�W�����ƗF��Ɓ@�K��U�H�@330
10�@�C�W�����}�V�K�[�̗R���@���J�q�f�@332
11�@���Ӓi�N�~�������@���܊��@334
12�@���Ӓi�N�~�������@�ÎӐU�T�@336
13�@���Ӓi�N�~�������@���܃J���@338
14�@���ŋ��̖���E���܊쏕�@���Ï@�L�@339
15�@��́E���Ӓi�`�W���C�[�@���Ë����@341
16�@�W���[�~�[�`���[��̗H��@���J���V�@345
17�@���Ӓi�E�e�[�̃}�W�����@���Ï@�L�@346
18�@�����ȃ}�W�����@����c���@349
���̂ق��̘b�@351
�Č��̓`��
1�@�Č��̎n�܂�@�a�F�c���`�@355
2�@�Č��̕��Ɓ@�Îӈ����@357
���̂ق��̘b�@358
�]�F�̓`��
1�@�]�F�j���ƍ]�F�̎�q��@�V��^���@361
2�@�]�F�n����̌��n�@�쉮���ӂ����@367
3�@�]�F�̈ړ��@�_�c�D�q�@368
4�@�]�F�̈ړ��@�쉮���ӂ����@369
5�@�]�F�̎��q���@�{��c���@370
6�@�]�F�O�X�N�̃A�J�}�^�[�@�×z���Y�@372
7�@�A�u�V�o���[�ƃA�J�}�^�[�@�X�ۂ����@374 |
8�@�]�F�̃u���O���[�@�����ۍs�@376
9�@�]�F�O�X�N�̈�˂̐���@���g����@377
���̂ق��̘b�@378
�{���̓`��
1�@�{���̑����ā@���鐷���@381
2�@�{���̒����咆�R���@���܃~�l�@382
3�@�{���̕��@���]�F�����@383
4�@�{���̕��@���]�F���Ɂ@385
5�@�{���̋������@���g����@386
6�@�N�[���r�L�̖��̗R���@������r�@387
7�@�{���ƓV���̐��Q�@���܉p���@388
�ԓ��̓`��
1�@���l����̐ԓ����[�O���[�@�{��J�}�h�@391
2�@�`���~�[���C�̃^�}�K�C���@�u�쉮�}�J�g�@393
3�@�A�q���[�}�W�����Ɠ}�W�����@�������i�@395
���̂ق��̘b�@396
���]�F�̓`��
1�@���]�F�̒Ôg�Ɛl���@�����Ԉ�@399
2�@���]�F�H�[�L�ƌ��̓G�[�L�@���ܖL���@400
3�@���]�F�H�[�L�@�Ɖ����Y�@404
4�@��́E���剮�����K�T�ƍ��]�F�́��̎n�܂�@���ܖL��407
5�@���]�F�~�[�����@�䉮���h���@409
6�@��́E���]�F�E�[�����[���@���܉�M�@410
7�@��́E���]�F�E�[�����[���@���X�^�h�@412
8�@���c���J�}�h�D�[�̗��@���c�����Y�@414
9�@���]�F�̑�H���n�Õ~�@���ܗя��@415
���̂ق��̘b�@416
�O���̓`��
1�@�g�D�[���K�}�@���錫���@419
2�@�g�D�[���K�}�̗��@����R�Y�@422
3�@�r�W�����̐���@���錫���@424
4�@�O���̉���̎n�܂�@���ܗя��@426
5�@�a����ꂽ����̑c��@����R���@428
���̂ق��̘b�@430
�u�ѐ�̓`��
1�@�u�ѐ�K�[�̗R���@�{��J�}�h�@433
2�@�u�X�_�X�̗R���@�茴���q�@435
���̂ق��̘b�@436
�L��`��
1�@�A�[�}���`���[�@�����ԕS�ˁ@439
2�@�A�[�}���`���[�@���M�@442
3�@�Z��n�c�@�^�V�X�G�@444
4�@�T�[�J�̏��V�@����m���@448
5�@����̎n�܂�@���{�́@452
6�@����̎n�܂�@���c�����Y�@454
7�@���V�Ԍ����@���샀�_���@456
8�@���V�Ԍ����@���{�J�}�^�@467
9�@���⓰�R���@���@���E�g�@471
10�@�̐_�@������@477
11�@���ǃ����`�@����Î}�@482
12�@�v�U��@�������_���@486
13�@�p��������@�ɗǔg�����@489
14�@���x���@�������ǁ@493
15�@�^�ʋ��̐l���@�m�O�c�@497
16�@�o�˗R���@��]�F�����@504
17�@���̎n�܂�@�ɍ��E�V�@507
18�@�j�[�r�`�R���@�쉮���~�q�@510
19�@�J�W�}��i�R���@�ʉh���Y�@513
20�@�J�W�}���[�R���@�ʉh���Y�@521
21�@�n�W�`�R���@�ڎ�^�E�g�@525
22�@������t�@�ʊ�}�c�G�@529
23�@�ؐH���̎n�܂�@�������k�E�@532
24�@���ނ̎n�܂�@�^�V�X�G�@534
25�@�T�����їR���@�ڎ�^�E�g�@538
26�@�e��R���@�ΐ�_�@545
27�@�ʔv�̎n�܂�@��Ì��ʁ@548
28�@�l�����R���@�`�c���@550
29�@�n�u�悯�����@�����}�J�g�@552
30�@�䊥�D�x�Ƒg�x�@�ÎӐU�T�@555
31�@���ג��@���{�́@559
32�@���ג��@������@561
33�@���b�u�@�X����O�Y�@565
34�@�`�[�O�[���@���샀�_���@586
35�@�V����q�卪��������b�r�@�ÎӐU�T�@592
36�@�V����@�������L�@595
37�@�k�J���q�ƍ�������@��鐟�q�@602
38�@�`���[�t�O���e���@�{�镁���@��
39�@�����a���ƌ썲�ہ@�c�ꐷ�M�@612
40�@�Ӗ��e���@�������L��@624
41�@�쑺�e���@�������ǁ@633
42�@�O�Ўq�@�ÎӐU�T�@641
43�@����`���Ƌ�u�A�E���@���钿���@645
44�@����e���Ƌ�u���e���@���c�i���@654
45�@����e���@�ÎӐU�T�@657
46�@�F��e���ƕ��~�����q�@�h��쐷�D�@663
47�@���~�����q�@���钿���@671
48�@���e���@���i�M�@676
49�@��Ԓ��@���c��Y�@678
50�@��Ԓ��@���ܐ��h�@684
51�@��Ԓ��@����J���@687
52�@��Ԓ��ƖV����@�������ǁ@690
53�@�D�z���[�K�[�G�[�L�@�ɋ����q�@693
54�@�x���J���W�F�[�N�@�����퐷�@695
55�@�t�W�`�J���W�F�[�N�@��[�g�~�@698
56�@�����[���Ɖ����@���c�����h�@701
57�@�g���`���[�@���c�}�c�@704
58�@�g���`���[�@�V�芗�ˁ@711
59�@�g���`���[�@���ߎq�@715
60�@���[�i�x�@�ڎ�^�E�g�@731
61�@�K��ƂƓ��D�h�[�C�@�K��U�H�@735
62�@���D�̑D����������c�Ɠ�j�D���~�������b�@����Î}740
63�@�썑�e�_��@�×z���Y�@742
64�@�[���̐���̂�����݁@���钿���@746
65�@�R�c�j���a���̉����L�@���܉�M�@748
66�@�t�����H��@�������L�@753
67�@�L�W���i�[�̋��߂�@�ʊ�}�c�G�@760
68�@�L�W���i�[�@�ÎӐU�T�@764
���̂ق��̘b�@771 |
�R���A����m��,���V�O�V,�匎���V,����e�q,�쑽���V,���эK�j,���E�v,�������悪�u���s�����w������H�����N�� 13 p.121-135�@���s�����w����w������������H�����w���Z���^�[ �v�Ɂu�w���̉��y�w�K���ƍs������
: ���E�֘A���y�Ȗڂ̉��P�Ɍ����āv�\����B�@�iIRDB�j
�R���A���ь��],���эK�j���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
9 p.71-150�v�Ɂu���A�m�G�C�T�[�̉��y : ��R�E�����E�����̎�������ʂ��āv�\����B�@
�R���A�u���ꌧ���|�p��w�I�v 5�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�����Ջ� : �����̎�X���@�@�������Îq,���H���m�u�@ p.1-18
�������x�ɂ�����g�̋Z�@ : �u�K�}�N����v�Ɋւ��錤���@�@���g���]�}�@ p.19-32
�E���ꂵ��烂̖��ւ̈����� : �����t�t���[�g�̂��߂́@�@���{�M�v�@ p.33-42
���t�@�_�Ɖ��t�̂��߂̃\���t�F�[�W�� : �u�����\���t�F�[�W���̒v�@�@�����ׁ@�@
p.43-84
�u���ꌧ �̂��ׂ����v : ��������(�܂��͏�������)�ƃs�A�m�̂��߂́@�@���X�ؐ^���q�@
p.85-124
���g�~�b�N���_�ɂ�����y�ȕ��͂Ɛg�̕\�� : �������y�Ƃ̐ړ_�ɐG��Ȃ���@�@��R�L�q�@�@1 p.125-146
�}�����ߊw���猩�����G : ���m�̏ё���ƌ��G�@�@�������F�@ p.147-172
�n��m�[�g�@�@�����݁@ p.173-174 |
�R���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (24)�v���u�����|�\�w��v���犧�s�����Bpid/7959574
|
������{�̏Z�g�x�Ɩ���(���)<������>�|�\�̈�Ƃ��� / ��ؓ��q/p1�`26
�����G�C�T-�V���J�ɂ�����G�C�T-�́u�o���v--�u���Z�̖������v�ւ̎��݂Ƃ���
/ ���э���/p27�`50
�����̎{�݂Ɋւ��錟��--�����E����E���q���E�y���ɂ��� / �����m�V/p51�`68
���ꌧ���A���������̗̉w--���̋L�^�ƕۑ����߂����� / ��Éx�q/p69�`74
����h���w�̊_�Ɣ��y�̖�����--�����ɌÑ�̉̕���K�˂āx / �z�K�t�Y/p75�`78
�Љ� ��������������ҁw�퍷�ʕ����̖����`���u���v�\�ØV����̕������x / ���]��q/p79�`80
�����|�\���������ژ^--����6�`7�N / �n�ӐL�v/p1�`18 |
�R���A��Î�,�N�䓿���Y,�������j,���]�F�i,�~�ؓN�l,���N�Ɩ@����w���ꕶ�����������u���ꕶ������
23 p.229-276�v�Ɂu���k�� �w���������ȁE�������j�̌����x�����Ɋāv�\����B�@�iIRDB�j
�R���A���c�p��,�y����,�r����Y���u��` : �����̉Ȋw 51(3) p.65�`69�@�G�k�E�e�B�[�E�G�X�v�Ɂu����̐������̕s�v�c�Ȑ���(12 ��)����̐�����:���̓��F�E����Ə��� �v�\����B
|
�u�����̉Ȋw 50(4) �`51(3�v)�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�u����̐������̕s�v�c�Ȑ����i�P�`�P�Q�j�v�ɂ��Ă̌f�ژ_���ꗗ�\�@
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���\�� |
| 1 |
50(4) p.92�`95 |
1996-04 |
(1)�C���I���e���}�l�R--���M�ѐX�т̃l�R |
�ɑ��q,�y�쏺�v |
| 2 |
50(5) p.65�`68 |
1996-05 |
(2)�n�u--���낵���Ŏւ͐g�߂� |
�������F |
| 3 |
50(6) p.61�`64 |
1996-06 |
(3)�T���S�[1-���������Ƃ��ẴT���S |
�������Y |
| 4 |
50(7) p.87�`90, |
1996-07 |
(4)�T���S�[2-�C�V�T���S�ނ̐����j |
�����F |
| 5 |
50(8) p.65�`68 |
1996-08 |
(5)�}���O���[�u--�C���ɓK�������M�т̐A������ |
�n��ɍK |
| 6 |
50(9) p.63�`66 |
1996-09 |
(6)�E�~�K��--�{���ɃJ���͖��N�����邩 |
����N�s |
| 7 |
50(10) p.97�`100 |
1996-10 |
(7)�T���S�K�j--�T���S�K�j�̋S�ގ� |
�y���� |
| 8 |
50(11) p.65�`68 |
1996-11 |
(8)�K�W���}��--��C�d���`���ƐA�������w |
�R��G�Y |
| 9 |
50(12) p.59�`62 |
1996-12 |
(9)�V�I�}�l�L--�傫�ȃn�T�~��U�肩�����_���X�̃v�� |
����� |
| 10 |
51(1) p.93�`96 |
1997-01 |
(10)�J���V�����^�A�u�����V--�V�G���璇�Ԃ����A�u�����V |
�V�_���Y |
| 11 |
51(2) p.68�`71 |
1997-02 |
(11)�V���I�r�A�Q�n--���l�����܂��Ă킪�g�����`���E |
�㐙���i |
| 12 |
51(3) p.65�`69 |
1997-03 |
(12 ��)����̐�����:���̓��F�E����Ə���
|
���c�p��,�y����,�r����Y |
|
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu���ꌧ�̍Ղ�E�s�� : ���ꌧ�Ղ�E�s���������v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@�@�@(���ꌧ������������
; ��127��)
|
����
�O���r�A
�����n�}
���ꌧ�̍Ղ�E�s���@�ʒ����̒n�}
���ꌧ�̍Ղ�E�s���@��b�����n��
�ڎ�
�ጾ
���́@�����̊T�v
���́@�i�S���j�Ղ�s�������̎��{�v�́@1
���́@�Ղ�s�������E�����v��̗��ӓ_�@2
���́@�������ڑI���̎�|�ƍ��ڕʎ�v���⎖���@3
���́@���ꌧ�Ղ�E�s�������v���@8
���́@���ꌧ�Ղ�E�s���������ڂ̍\���@11
���́@�������ځi�����[�j�@12
���́@���ꌧ�Ղ�E�s����b�����n��@13
���́@�ʒ�����
���́@�ۉh�̏\�ܖ�i�L�N�Ձj�ƃ}�`�_�@15
���́@������������E�����̃K���S�[�����@22
���́@�|�x���̏\�ܖ�@30
���́@����n���̃A�u�V�o���@37
���́@�����̐����V��\�V�����K�`�c�i�q�L�i�����j�����j�@41
���́@����s�v�u�́u�h�[�h�[�n�v�@48
���́@���������X���̓�\�������@50 |
���́@���H�n�̃E���M���~�@55
���́@���l���̔O���x���@59
���́@�{���̃V�k�O�@67
���́@��u���̃V�j�[�O�@76
���́@�����̃V�j�O�@84
���́@����̃E�t���~�V�k�O�C�@93
���́@�ΉÔg�i���ΉÔg���j�̃V�k�O�C�@99
���́@�l��Ó��̃V�k�O�@103
���́@�약�̃}�����K�i�V�@117
���́@�^�ߌ����Ǖ~�̂ȂЂ��@133
���́@�^�ߌ����匩���̍j�����@137
���́@����s�����́u���Ă��v�s���ɂ��ā@141
���́@�{���̃��i�t�J���J�@145
���́@�V���̎i����Ԃ̃V�c�}�X�@157
���́@���NJԓ��̃X�c�E�v�i�J�@166
���́@���ԓ��̔N���s���E���[�}�X�v�i�J�@174
���́@�|�x���Ì��̃v�[���B�@177
���́@����W���̃j�K�c�O���C�k�t�c�ɂ��ā@183
���́@�A�~�h�D�V�@�v�����|�@186
���́@�ǒJ�����얡�̖咆�_�䐴���Ձ@190
���́@���������Ԃ̃g�[�`�[�N�i�y��N�j�Ղ�@193
��O�́@��b���������ꗗ
�E |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
6�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003236708�@�@
|
�����ꂽ�J(���O�ܔԂ�ʒꂷ�����)
����g�x�� �m�[�g2 ���� ���V �{�w����
�Ñ㍑�ƂƓ쓇 �啽 �� �{�w���� |
�ߐ������ɂ������̐��x ��b�I�l�@ ���c �I��u �{�w����
���J�V���|�W�E���u�쓇�̐_�ϔO�Ɛ��E�ρv(���^���������̘^)
�@�@���O�Ԏ�P ���_���� ���c�����v�^�k �������V�^�i�� |
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu�����蓙�֘A�q���������� 2�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@ (���ꌧ������������ ; ��128��)�@�@67p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002752408
�R���A �����r��,���NJԗ��G�q���u���ꌧ�������ًI�v 23 p.111-139�v�Ɂu���ꌧ�������ّ��n���Ɋւ���m�[�g�v�\����B
�R���A�Y�\�w��ҏW�ψ���ҁu�Y�\(3)(420) �v���u�Y�\�w��v���犧�s�����B �@
|
�F����o�j�炪�u�|�\19(1)(215)�v����u�Y�\(3)(420)�v���ɔ��\�����u�܌��M�v�̐��E��(�Q�O�V�j�v���̓���ꗗ�\�@
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_�����ƒ��� |
pid |
| 1 |
�|�\19(1)(215)
|
1977-01 |
�܌��M�v�̐��E(I.) / �����_ ;�F����o�j/p38~39
|
pid/22764101�@ |
| 2 |
�|�\19(2)(216) |
1977-02 |
�܌��M�v�̐��E(2) / �����_ ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276411 |
| 3 |
�|�\19(3)(217) |
1977-03 |
�܌��M�v�̐��E(3) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276412 |
| 4 |
�|�\19(4)(218) |
1977-04 |
�܌��M�v�̐��E(4) / �����_ ;�F����o�j/p40~41
|
pid/2276413 |
| 5 |
�|�\19(5)(219) |
1977-05 |
�܌��M�v�̐��E(5) / �����_ ;�F����o�j/p40~41
�����G�O�Y��_������[�t�H�[�N���A�̊�T� / �F����o�j/p45�`46 |
pid/2276414 |
| 6 |
�|�\19(6)(220) |
1977-06 |
�܌��M�v�̐��E(6) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276415�@ |
| 7 |
�|�\19(7)(221) |
1977-07 |
�܌��M�v�̐��E(7) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276416�@ |
| 8 |
�|�\19(8)(222) |
1977-08 |
�܌��M�v�̐��E(8) / �����_ ;�F����o�j/p36~37
|
pid/2276417 |
| 9 |
�|�\19(9)(223) |
1977-09 |
�܌��M�v�̐��E(9) / �����_ ;�F����o�j/p48~49 |
pid/2276418 |
| 10 |
�|�\19(10)(224) |
1977-10 |
�܌��M�v�̐��E(10) / �����_ ;�F����o�j/p40~ |
pid/2276419 |
| 11 |
�|�\19(11)(225) |
1977-11 |
�܌��M�v�̐��E(11) / ����O�F ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276420�@ |
| 12 |
�|�\19(12)(226) |
1977-12 |
�܌��M�v�̐��E(12) / ����O�F ;�F����o�j/p36~37 |
pid/2276421 |
| 13 |
�|�\20(1)(227) |
1978-01 |
���-�܌��M�v�̐��E(13) / �R�������Y ;�F����o�j/p34~35
|
pid/2276422 |
| 14 |
�|�\20(2)(228) |
1978-02 |
���-�܌��M�v�̐��E(14) / �ڗNjT�v ;�F����o�j/p38~39
�C�z��ďC��^������p���Z����(������)�̐y� / �������q/p43�`44 |
pid/2276423 |
| 15 |
�|�\20(3)(229) |
1978-03 |
���-�܌��M�v�̐��E(15) / �R�������Y ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276424 |
| 16 |
�|�\20(4)(230) |
1978-04 |
���-�܌��M�v�̐��E(16) / �R�������Y ;�F����o�j/p44~45 |
pid/2276425 |
| 17 |
�|�\20(5)(231) |
1978-05 |
���-�܌��M�v�̐��E(17) / �R�������Y ;�F����o�j/p38~39
���c���q����c�A�₵����� / �������q/p46�`47 |
pid/2276426 |
| 18 |
�|�\20(6)(232) |
1978-06 |
pid/2276427�@���-�܌��M�v�̐��E(18) / �R�������Y ;�F����o�j/p36~37 |
pid/2276427 |
| 19 |
�|�\20(6)(232) |
1978-06 |
�|�\ 20(7)(233) 1978-07�@�@�܌��M�v�̐��E(19) / �F����o�j/p36�`37 |
pid/2276428 |
| 20 |
�|�\20(8)(234) |
1978-08 |
�����̂��Ƃ�܌��M�v���m�ƌ|�\� / �q�c��/p7�`7
�؍��̍Ղ�̐_�� / �{�c����/p3�`33
�܌��M�v�̐��E(20) / �����_ ;�F����o�j/p34~35
��܌��搶��\�ܔN�գ�ɂ��Ă̂����点����{�̗w�w��H�G�������\�v��(����)/p64�`64 |
pid/2276429 |
| 21 |
�|�\20(9)(235) |
1978-09 |
�܌��M�v�̐��E(21) / �����R�� ;�F����o�j/P32~33
���������V���̓���������� / ��،�/p46�`46
|
pid/2276430 |
| 22 |
�|�\20(10)(236) |
1978-10 |
�܌��M�v�̐��E(22) / �����R�� ;�F����o�j/p40~41
�̐܌��M�v�搶��\�ܔN�� / ���J�쐭�t/p74�`74 |
pid/2276431 |
| 23 |
�|�\20(11)(237) |
1978-11 |
�����̂��Ƃ�ԍՉ�ق̏v�H�Ǝw�W� / �F����o�j/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(23) / �����R�� ;�F����o�j/p34~35 |
pid/2276432 |
| 24 |
�|�\20(12)(238) |
1978-12 |
�܌��M�v�̐��E(24) / �����R�� ;�F����o�j/p32~33 |
pid/2276433 |
| 25 |
�|�\21(1)(239) |
1979-01 |
�܌��M�v�̐��E(25) / �������H ;�F����o�j/p40~41
�O�Ԏ�P�E�V���K�����u�쓇��揑听III.�E�{�Õсv / ���P�Y/p42~43 |
pid/2276434 |
| 26 |
�|�\21(2)(240) |
1979-02 |
�܌��M�v�̐��E(26) / �������H ;�F����o�j/p48~49
�C�U�C�z---���ꌧ��v���� / ���w/p21�`30 |
pid/2276435 |
| 27 |
�|�\21(3)(241) |
1979-03 |
�܌��M�v�̐��E(27) / �������H ;�F����o�j/p34~35 |
pid/2276436 |
| 28 |
�|�\21(4)(242) |
1979-04 |
�܌��M�v�̐��E(28) / �������H ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276437�@ |
| 29 |
�|�\21(5)(243) |
1979-05 |
�܌��M�v�̐��E(29) / �������H ;�F����o�j/p38~39
����˓�����(������)���h��(�����哇����˓���)������� / �O�����Y/p44�`45 |
pid/2276438 |
| 30 |
�|�\21(6)(244) |
1979-06 |
�܌��M�v�̐��E(30) / �������H ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276439 |
| 31 |
�|�\21(7)(245) |
1979-07 |
�܌��M�v�̐��E(31) / ��X�`�� ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276440 |
| 32 |
�|�\21(8)(246) |
1979-08 |
�܌��M�v�̐��E(32) / ��X�`�� ;�F����o�j/p34~35
�c���p�������쓇�̗w�听V�����ѣ����w�v�w�������w���x / ���P�Y/p40�`41
|
pid/2276441 |
| 33 |
�|�\21(9)(247) |
1979-09 |
�܌��M�v�̐��E(33) / ��X�`�� ;�F����o�j/p26~27
���䐴����������|�\�Ɖ�揂̌���� / �{�c����/p45�`45 |
pid/2276442 |
| 34 |
�|�\21(10)(248) |
1979-10 |
�܌��M�v�̐��E(34) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41
��������ꏗ�D�ЂƂ�ŋ�� / ��،�/p49�`49 |
pid/2276443 |
| 35 |
�|�\21(11)(249) |
1979-11 |
�܌��M�v�̐��E(35) / ��X�`�� ;�F����o�j/p26~27 |
pid/2276444 |
| 36 |
�|�\21(12)(250) |
1979-12 |
�܌��M�v�̐��E(36) / ��X�`�� ;�F����o�j/p32~33
�����|�\�u�䊥�D�ƎG�x�v/p74~74 |
pid/2276445 |
| 37 |
�|�\ 22(1)(251) |
1980-01 |
�܌��M�v�̐��E(37) / ��X�`�� ;�F����o�j/p44~45 |
pid/2276446 |
| 38 |
�|�\ 22(2)(252) |
1980-02 |
�܌��M�v�̐��E(38) / ��X�`�� ;�F����o�j/p42~43
���c�W�Ң����n���̖��ԕ��Y� / �哇���F/p51�`52 |
pid/2276447 |
| 39 |
�|�\22(3)(253) |
1980-03 |
�܌��M�v�̐��E(39) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276448 |
| 40 |
�|�\ 22(4)(254) |
1980-04 |
�܌��M�v�̐��E(40) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276449 |
| 41 |
�|�\ 22(5)(255) |
1980-05 |
�܌��M�v�̐��E(41) / ��X�`�� ;�F����o�j/p35~37 |
pid/2276450 |
| 42 |
�|�\ 22(6)(256) |
1980-06 |
�܌��M�v�̐��E(42) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~40 |
pid/2276451 |
| 43 |
�|�\ 22(7)(257) |
1980-06 |
�܌��M�v�̐��E(43) / ��X�`�� ;�F����o�j/p32~33 |
pid/2276452 |
| 44 |
�|�\22(8)(258) |
1980-08 |
�܌��M�v�̐��E(44) / ��X�`�� ;�F����o�j/p24~25
���Ԉ�Y�Ң�{�Ǔ��s�S�W���\�� / ���P�Y/p42�`44 |
pid/2276453 |
| 45 |
�|�\22(9)(259) |
1980-09 |
�܌��M�v�̐��E(45) / ��X�`�� ; �F����o�j/p32�`33
|
pid/2276454 |
| 46 |
�|�\22(10)(260) |
1980-10 |
�܌��M�v�̐��E(46) / ��X�`�� ; �F����o�j/p19�`21
|
pid/2276455 |
| 47 |
�|�\22(11)(261) |
1980-11 |
�܌��M�v�̐��E(47) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276456 |
| 48 |
�|�\22(12)(262 |
1980-12 |
�܌��M�v�̐��E(48) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p26�`27 |
)pid/2276457 |
| 49 |
�|�\23(1)(263) |
1981-01 |
�܌��M�v�̐��E(49) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276458 |
| 50 |
�|�\23(2)(264) |
1981-02 |
�܌��M�v�̐��E(50) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276459 |
| 51 |
�|�\23(3)(265) |
1981-03 |
�܌��M�v�̐��E(51) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276460 |
| 52 |
�|�\23(4)(266) |
1981-04 |
�܌��M�v�̐��E(52) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p36�`37 |
pid/2276461 |
| 53 |
�|�\23(5)(267) |
1981-05 |
�c�V�т̒��� / �V��P��/p20�`27
�܌��M�v�̐��E(53) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276462 |
| 54 |
�|�\23(6)(268) |
1981-06 |
�܌��M�v�̐��E(54) / �����_ ; �F����o�j/p20�`21
|
pid/2276463 |
| 55 |
�|�\23(7)(269) |
1981-07 |
�܌��M�v�̐��E(55) / ���䕐�u ; �F����o�j/p22�`24 |
pid/2276464 |
| 56 |
�|�\23(8)(270) |
1981-08 |
��������I�L�i������� / ������Y/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(56) / ���䕐�u ; �F����o�j/p24�`25
���x��w�������x�̕ό^���̣ / �m�����Õv/p50�`50 |
pid/2276465 |
| 57 |
�|�\23(9)(271) |
1981-09 |
�܌��M�v�̐��E(57) / ���䕐�u ; �F����o�j/p20�`22 |
pid/2276466 |
| 58 |
�|�\23(10)(272) |
1981-10 |
�܌��M�v�̐��E(58) / ���䕐�u ; �F����o�j/p14�`16
|
pid/2276467 |
| 59 |
�|�\23(11)(273) |
1981-11 |
����������d�R��{�Â̌������|� / �{�c����/p7�`7
�䒌�̘b-1- / �܌��M�v/p8�`11
�Ǔ�����c����<���W> / �R���m��/p17�`31
���c������������̂� / �g��p�j ; �s�� ; �������q/p18�`25
���c�����搶�]�` / �R���m��/p26�`28
���N��������Ȓ��� / �R���m��/p28�`30
�V���e���ɂ悹��ꂽ�Ǔ��k / �r�c��O�Y/p30�`31
�܌��M�v�̐��E(59) / ���䕐�u ; �F����o�j/p12�`13 |
pid/2276468 |
| 60 |
�|�\23(12)(274) |
1981-12 |
�䒌�̘b-2- / �܌��M�v/p9�`16
�܌��M�v�̐��E(60) / �|���� ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276469 |
| 61 |
�|�\24(1)(275) |
1982-01 |
�܌��M�v�̐��E(61) / �|���� ; �F����o�j/p24�`26 |
pid/2276470 |
| 62 |
�|�\24(2)(276) |
1982-02 |
�܌��M�v�̐��E(62) / �|���� ; �F����o�j/p26�`28 |
pid/2276471 |
| 63 |
�|�\24(3)(277) |
1982-03 |
�O�@���b�̊G���� / �n�ӏ���/p8�`19
�܌��M�v�̐��E(63) / �|���� ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276472 |
| 64 |
�|�\24(4)(278) |
1982-04 |
�܌��M�v�̐��E(64) / �|���� ; �F����o�j/p34�`36 |
pid/2276473 |
| 65 |
�|�\24(5)(279) |
1982-05 |
�܌��M�v�̐��E(65) / �|���� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276474 |
| 66 |
�|�\24(6)(280) |
1982-06 |
�܌��M�v�̐��E(66) / �|���� ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276475 |
| 67 |
�|�\24(7)(281) |
1982-07 |
�܌��M�v�̐��E(67) / ���䕐�u ; �F����o�j/p30�`31
�|�{�G�v���w�c�A�̂̊�b�I����-��R�ߌn�c�A�̂��厲�Ƃ��āx / �V�Ԑi��/p27�`28
�\�̗\�]�����g�x��̋S��тƐd�\�/p53�`53 |
pid/2276476 |
| 68 |
�|�\24(8)(282) |
1982-08 |
�܌��M�v�̐��E(68) / ���䕐�u ; �F����o�j/p26�`28 |
pid/2276477 |
| 69 |
�|�\24(9)(283) |
1982-09 |
�܌��M�v�̐��E(69) / �|���� ; �F����o�j/p30�`32 |
pid/2276478 |
| 70 |
�|�\24(10)(284) |
1982-10 |
�܌��M�v�̐��E(70) / �|���� ; �F����o�j/p26�`28
|
pid/2276479 |
| 71 |
�|�\24(11)(285) |
1982-11 |
�܌��M�v�̐��E(71) / �|���� ; �F����o�j/p18�`21
|
pid/2276480 |
| 72 |
�|�\24(12)(286�j |
1982-12 |
�܌��M�v�̐��E(72) / ���䕐�u ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276481 |
| 73 |
�|�\25(1)(287) |
1983-01 |
�܌��M�v�̐��E(73) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p20�`21
|
pid/2276482 |
| 74 |
�|�\25(2)(288) |
1983-02 |
��������܌��M�v���m�O�\�N�Ղɂ������ģ / �q�c��/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(74) / �|���� ; �F����o�j/p18�`20 |
pid/2276483 |
| 75 |
�|�\25(3)(289) |
1983-03 |
�܌��M�v�̐��E(75) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276484 |
| 76 |
�|�\25(4)(290) |
1983-04 |
�ŗt�_�y�̓��F / �{�c����/p8�`14
�k���ł̎v���o / �r�c�Ă��q/p15�`23
�܌��M�v�̐��E(76) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276485 |
| 77 |
�|�\25(5)(291) |
1983-05 |
�܌��M�v�̐��E�\�\�ԍՂƐ܌��M�v(77) / �㓡�i ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276486 |
| 78 |
�|�\25(6)(292) |
1983-06 |
�ԍՂƐ܌��M�v(78)�܌��M�v�̐��E / �㓡�i ; �F����o�j/p26�`
��������I������Ǝ�P� / ��،�/p53�`53 |
pid/2276487 |
| 79 |
�|�\25(7)(293) |
1983-07 |
�܌��M�v�̐��E(79) / ����ɗY ; �F����o�j/p26�`28
�܌��M�v�搶�O�Z�N��/p28�`28 |
pid/2276488 |
| 80 |
�|�\25(8)(294) |
1983-08 |
��������܌��M�v�搶�ƌ|�\� / �Έ䏇�O/p7�`7
��V������l--�͓��ߌ��s�Ȃɂ�� / �g���q/p8�`12
�܌��M�v�̐��E(80) / ����ɗY ; �F����o�j/p16�`17 |
pid/2276489 |
| 81 |
�|�\25(9)(295) |
1983-09 |
�܌��M�v�̐��E(81)-���o�Β��̉� / ����O�F ; �F����o�j/p20�`22
���y�ς̃R�y���j�N�X�I�]��\�\�������q����{���y�̌Ñw� / ���䓿���Y/p23�`24 |
pid/2276490 |
| 82 |
�|�\25(10)(296) |
1983-10 |
�܌��M�v�̐��E(82)�\���o�Β��̉�(��) / ����O�F ; �F����o�j/p12�`14
|
pid/2276491 |
| 83 |
�|�\25(11)(297) |
1983-11 |
�܌��M�v�̐��E(83)-���o�Β��̉�(�O) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`26 |
pid/2276492 |
| 84 |
�|�\25(12)(298) |
1983-12 |
�܌��M�v�̐��E�\�\���o�Β��E�G(84) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`30
���c�܂�q����������w�Ƃ��̎��ӣ / �{�c����/p35�`36
|
pid/2276493 |
| 85 |
�|�\26(1)(299) |
1984-01 |
���������тɈ��閯��� / �{�c����/p7�`7
�A�W�A��������-1-���`�̋��Y--���e�ԂƏt�H�Y���w�Z / �{������/p8�`16
���w�@�̒�(85)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p22�`24
���c��t�F����P���L�����̏Z�l� / ���ے�/p25�`25
|
pid/2276494 |
| 86 |
�|�\26(2)(300 |
1984-02 |
����������y�����̉�z�ƍ���̊��ң / �q�c��/p7�`7
���a�Z�̎j���l--�܌��M�v���ϒ���k�����H��ؖ��C / ��ϐ���/p8�`18
�܌��M�v�̐��E�\�\���w�@����(86) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276495 |
| 87 |
�|�\26(3)(301) |
1984-03 |
��������S���s���������̂Ɩ����|�\� / �F����o�j/p7�`7
���c���j�Ɛ܌��M�v--���y������̂��Ƃǂ��Ȃ� / �q�c��/p8�`20
�܌��M�v�̐��E(87)-�������̖� / ����O�F ; �F����o�j/p21�`22
|
pid/2276496 |
| 88 |
�|�\26(4)(302) |
1984-04 |
��������������y����I�[�v��� / ���ӌ�/p7�`7
�܌��M�v�̍���u���s--�t ���{��ߑ�ߏ��W��̂��Ƃǂ� / �s�꒼���Y/p8�`10
�܌��M�v�̐��E�\�\�ӔN�̕M��(88) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276497 |
| 89 |
�|�\26(5)(303) |
1984-05 |
�m��������c�̐����炭�� / �{�c����/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(89)-�Ñ㌤����(��) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29
|
pid/2276498 |
| 90 |
�|�\26(6)(304) |
1984-06 |
����������ʂ̃R���N�V�����Ɣ����َ���� / �㓡�i/p7�`7
���G�����̋�--�ߏ��̎ϗ��ᔻ / ��R��/p8�`12
�܌��M�v�̐��E(90)-�Ñ㌤����(��) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276499 |
| 91 |
�|�\26(7)(305) |
1984-07 |
����������w�̃A�W�A����� / �O�����Y/p7�`7
�O��@�Ɛ܌��搶 / �c�Ӑ��j/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(91)-�������̕\�D / ����O�F ;�F����o�j/p28~29
|
pid/2276500 |
| 92 |
�|�\26(8)(306) |
1984-08 |
������������\�y���\�y(�O��)���C�J�u� / ���ѐ�/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(92)-�����{�w���҂̏��x / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
�{�c������������s�����|�\��� / �㓡�i/p28�`29 |
pid/2276501 |
| 93 |
�|�\26(9)(307) |
1984-09 |
��������`���|�\�̎q�ǂ��q� / �F����o�j/p7�`7
�ߏ����o�̎��_-1-����E���n��� / ��������Y/p8�`12
������e�A�g������-6-�����̉ƌ����̏���ׂ₩�� / �ق�����/p13�`18
�܌��M�v�̐��E(93)-������p�B��(1) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276502 |
| 94 |
�|�\26(10)(308) |
1984-10 |
��������̎��ƌ|�\�ƕ��w�̂͂��ܣ / ���іΎ�/p7�`7
�������x�̊T���Ɠ��F / ������ ; ������/p8�`13
������e�A�g������-7-����Q�L��Ƃ����l���h���}�� / �ق�����/p14�`19
������p�B��(��)(94)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
������l�`���q�����Y�̉S�r� / ��،�/p49�`50
|
pid/2276503 |
| 95 |
�|�\26(11)(309) |
1984-11 |
�܌��M�v�̐��E(95)-������p�B��(�O) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276504 |
| 96 |
�|�\26(12)(310) |
1984-12 |
��������|�p�Ղ̉��v�ƒn��̎��ԣ / �����ߌ�/p7�`7
��]����S����̎l�̈Ӌ` / ��R��/p8�`18
�܌��M�v�̐��E(96)-������p�B��(�l) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276505 |
| 97 |
�|�\27(1)(311) |
1985-01 |
������������|�\�w�̔��� / �{�c����/p7�`7
��z �r�c��O�Y / �����p���Y/p8�`17
�܌��M�v�̐��E-���z(97) / ����O�F ; �F����o�j/p28�` |
pid/2276506 |
| 98 |
�|�\27(2)(312) |
1985-02 |
��������|�\�����26�N / �Έ䏇�O/p7�`7
�����y�čl-��- / �R�H����/p8�`19
�܌��M�v�̐��E(98)-���z���瑝�㎛ / ����O�F ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276507 |
| 99 |
�|�\27(3)(313) |
1985-03 |
��������O���n��-�����|�\�̌𗬂Ɛ[���̂��߂ɣ / �������H/p7�`7
�����y�čl-��- / �R�H����/p8�`18
�܌��M�v�̐��E(99)-�����{�@�Z�n��ڍ��s����S�q��_ / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29
�g��T�q����ՂƓ��{�̍��J� / ���c�\��/p30�`31
|
pid/2276508 |
| 100 |
�|�\27(4)(314) |
1985-04 |
���������O�̐V�l�ƐV����������� / ��v�ۖ[�j/p7�`7
�܌��M�v��R�Ă裂ւ̉��^--���̔s�풼��̐^�������߂� / ���J�쐭�t/p8�`13
�܌��M�v�̐��E�\�\�[��(100) / ����O�F ; �F����o�j/p14�`15
�{�c������������s�����|�\������� / �㓡�i/p21�`22
�����N��Z����O�l�g�O�f�����(�V�����{�ÓT�W��) / �A����/p22�`24
��܌����m�L�O�Ñ㌤�����I�v(��4�S)� / ��m�֒��l/p25�`27 |
pid/2276509 |
| 101 |
�|�\27(5)(315) |
1985-05 |
��������o���G�̍��ی𗬣 / �����/p7�`7
��c�A�Վ��l-��- / �R�H����/p8�`16
�܌��M�v��p�̐��E--�\�Ǝŋ� / ��ϐ���/p17�`19
�Ƒ����ɎE���ꂽ�j--�����q���l / ��R��/p20�`23
�܌��M�v�̐��E(101)-�Ð��~ / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276510 |
| 102 |
�|�\27(6)(316) |
1985-06 |
����������������ƌ��肽��� / �쑺����/p7�`7
��c�A�Վ��l-��- / �R�H����/p8�`15
�܌��M�v�̐��E�\�\�L�����R���̉ԍՂ�(102) / �O�����Y ; �F����o�j/p16�`17
|
pid/2276511 |
| 103 |
�|�\27(7)(317) |
1985-07 |
�܌��M�v�̐��E(103)-�L�����R���̉ԍՂ� / �O�����Y ;�F����o�j/p26~27 |
pid/2276512 |
| 104 |
�|�\27(8)(318) |
1985-08 |
������������������\�N� / �����G�Y/p7�`7
�[�˂̏j���`��--�̘b���̉Σ���߂����� / �쑺�h�q/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(104)-�ԍ�(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276513 |
| 105 |
�|�\27(9)(319) |
1985-09 |
����������O�ҍ��\�\���܂钆���̌|�\� / �������H/p7�`7
�܌��M�v�̉���̖K / �ۍ�B�Y/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(105)-�ԍ�(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19
�������z�̔o�D��
|
pid/2276514 |
| 106 |
�|�\27(10)(320) |
1985-10 |
������������̖����|�\�����@�ւ� / �R�H����/p7�`7
�����ÓT���nj� / �ɓ���/p8�`14
�܌��M�v�̐��E�\�\�ԍՂƂ��̉�(106) / ����O�F ; �F����o�j/p15�`17
|
pid/2276515 |
| 107 |
�|�\27(11)(321) |
1985-11 |
��������N�֣ / �㓡�i/p7�`7
��Γc�̖g�Ɛ܌��M�v--���萳�G���̑z���o / �B��h��/p8�`11
��R��ɂ������̉����y--�`������̕����I����-��- / ����/p12�`21
�܌��M�v�̐��E�\�\�S�̋���(107) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276516 |
| 108 |
�|�\27(12)(322) |
1985-12 |
��������A�W�A�����|�\�ե�S���N���̋��y�|�\� / �{�c����/p7�`7
��R��ɂ������̉����y--�`������̕����I����-��- / ����/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(108)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276517 |
| 109 |
�|�\28(1)(323) |
1986-01 |
�܌��M�v�̐��E(109)-���(��) / �ˍ�N�� ;�F����o�j/p22~23
|
pid/2276518 |
| 110 |
�|�\28(2)(324) |
1986-02 |
�܌��M�v�̐��E(110)-��܂薽���R�� / �O�����Y ;�F����o�j/p20~21 |
pid/2276519 |
| 111 |
�|�\28(3)(325) |
1986-03 |
��Ղ�̐풆���(111)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p22~23 |
pid/2276520 |
| 112 |
�|�\28(4)(326) |
1986-04 |
�吳��N�̗��ƐV��(112)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ;�F����o�j/p16~17 |
pid/2276521 |
| 113 |
�|�\28(5)(327) |
1986-05 |
��ƕ���-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �牮�B/p8�`13
�Ղ�̖�̊��\(113)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p14�`15
�������z�̔o�D�ƕ���-12-�V�É����Ƣ���͓�� / �ق�����/p16�`20 |
pid/2276522 |
| 114 |
�| �\ 28(6)(328) |
1986-06 |
�܌��M�v�̐��E(114)-���|���]��䎖���(��) / ��ؑ��� ;�F����o�j/p16~17
|
pid/2276523 |
| 115 |
|
1986-07 |
��������������̎w�� / �㓡�i/p7�`7
�����|�\�̒��̓c�y(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �㓡�i/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(115)-���|���]��䎖���(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276524 |
| 116 |
|
1986-08 |
�l�`�Ɛl�`�|-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �S�i����/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(116)-�V���Ђ̒Z��(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p22�`23
�g�����̋��_�\�\�L�O�ق̑����z�v�� / ��،[��/p24�`24
�g��T�q����A�z�܍s�Ɠ������J� / �n粋ӗY/p25�`26
|
pid/2276525 |
| 117 |
�|�\28(9)(331) |
1986-09 |
�l�`�Ɛl�`�|-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �S�i����/p8�`15
�܌��M�v�̐��E(117)-�V���Ђ̒Z��(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p16�`17
|
pid/2276526 |
| 118 |
�|�\28(10)(332) |
1986-10 |
�c���_-��- / �V��P��/p8�`14
�܌��M�v�̐��E(118)-�����ݒZ�̉�(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19
�������̔\�ƌ|�_��������� / �R����/p20�`22
�n�ӕے����������� / ���c�m/p22�`23 |
pid/2276527 |
| 119 |
�|�\28(11)(333) |
1986-11 |
��������V���}�j�Y���ƃq���}�j�Y��� / �c���`�A/p7�`7
�c���_-��- / �V��P��/p8�`14
���ꉹ�y�̒��ɔR�Ă�����������--��ȉƋ����v�q����̐��U / ���c���q/p15�`17
�܌��M�v�̐��E(119)-�����ݒZ�̉�(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276528 |
| 120 |
�|�\28(12)(334) |
1986-12 |
���������щz�����N�̢����� / �{�c����/p8�`14
�܌��M�v�̐��E(120)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p22�`23
�A�W�A�ɂ����鉼�ʂ̌|�\ ���ی����W�� / �R�{�G�q/p24�`25
|
pid/2276529 |
| 121 |
�|�\29(1)(335) |
1987-01 |
�܌��M�v�̐��E(121)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276530 |
| 122 |
�|�\29(2)(336) |
1987-02 |
�܌��M�v�̐��E(122)-�t����{����Ղ̑�h���� / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276531 |
| 123 |
�|�\29(3)(337) |
1987-03 |
�t����{�����-���{�ՂƂ��n�莮(123)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276532 |
| 124 |
�|�\29(4)(338) |
1987-04 |
�t����{�ŕ���ł̌|�\(124)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29/
|
pid/2276533 |
| 125 |
�|�\29(5)(339) |
1987-05 |
��t�Ɓw���앨��x(125)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p26�`27
�������--�l�`��ڗ��̎�ē�����Y / �X�W�Z/p28�`30
��������ꕜ�A15���N�L�O����� / ��،�/p50�`50
|
pid/2276534 |
| 126 |
�|�\29(6)(340) |
1987-06 |
����ƎR���v�j����(126)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p24�`2
|
��id/2276535 |
| 127 |
�|�\29(7)(341) |
1987-07 |
����쥍��P���٣(127)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ;�F����o�j/p24~25
��|�\�̒J<�ɓߒJ>(�S4)��O�����Y / ��ؐ��F/p26�`28
��ϐ�������܌��M�v���p�̐��E� / �q�c��/p29�`29
|
pid/2276536 |
| 128 |
�|�\29(8)(342) |
1987-08 |
����������������w�Z��ݗ���]�ޣ / ���c�m/p7�`7
��V�ߕ���쏉�ԣ�����ȑO--��_���O�ߍ��O����߂����� / �~��j�q/p8�`19
��㉉���̗V����-9-������������O�ɏo���m�� / �ق�����/p13�`19
�܌��搶�̔�(128)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276537 |
| 129 |
�|�\29(9)(343) |
1987-09 |
����������̌��肩��s�s�̃X�g�[���[�e���[�֣ / �쑺����/p7�`7
�s�i��o�E�V���̌W�ƃA�e�l���� / �c���`�L/p8�`15
��㉉���̗V����-10-�����c����I����n���L / �ق�����/p16�`21
�܌��搶�ƎR���_�y��Ԋy(129)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276538 |
| 130 |
�|�\29(10)(344) |
1987-10 |
��������̕���w�̔����Ɏv�� / �x�㌪/p7�`7
�Q�w��䶗��̓ǐ}�Ɍ����� / ��@�ʖ�/p8�`16
��㉉���̗V����-11-�܂ŋA���̏��D����1�l�� / �ق�����/p17�`23
����\(130)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276539 |
| 131 |
�|�\ 29(11)(345) |
1987-11 |
��������܌����m���a�S�N���������ģ / �q�c��/p7�`7
��-���b�p�̖����|�\�� / �c���`�L/p8�`13
��㉉���̗V����-12-�ܗ����̃i�C�g��J�u�L / �ق�����/p14�`19
����\�����̎�(311)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p20�`21
���Ԑ��b�̌���--���{�Ɛ��E(�h�ᔎ�m�Ď��L�O�_���W) / ����O/p22�`26 |
pid/2276540 |
| 132 |
�|�\ 29(12)(346) |
1987-12 |
����\���{�̎�(132)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p28�`29
��������Ң�܌��M�v�S�W��m�[�g�ҒǕ��ꊪ� / ���їE/p30�`30
�܌����m�L�O�Ñ㌤�����Ң�܌��M�v�蒟� / ���F�M/p32�`32 |
pid/2276541 |
| 133 |
�|�\ 30(1)(347) |
1988-01 |
�|�x���̎��� / �{�c����/p8�`13
�܌��M�v�̐��E(133)��ɂイ��� / �q�c�� ; �F����o�j/p20�`21
�ߓ��씎����������M����� / ��㑸��/p25�`26 |
pid/2276542 |
| 134 |
�|�\ 30(2)(348) |
1988-02 |
��t����S�(134)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p26�`27
������ċ���������!��\�\�܌��M�v�搶�̎v���o / �J���z�q/p28�`29 |
pid/2276543 |
| 135 |
�|�\ 30(3)(349) |
1988-03 |
������炳�ܣ(135)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p18�`19
��R�x�܂�̐��E�����v�Y / �L����/p20�`22 |
pid/2276544 |
| 136 |
�|�\ 30(4)(350) |
1988-04 |
��������n�����������Ƃ̗\�Z� / ���c�m/p7�`7
�܌��M�v�̉\��-��-�܌��M�v�̑n����--���c���j�Ɠ���F��Ƃ̑Δ�ɂ�����(���a100�N�L�O�u����) / �ߌ��a�q/p8�`17
����R�ƃC�^�R�(136)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276545 |
| 137 |
�|�\ 30(5)(351) |
1988-05 |
�܌��M�v�̉\��-��-�܌��M�v�ɂ����閯���Ɨ��j(���a100�N�L�O�u����) / �R�ܓN�Y/p8�`20
�������(�����l�`)�(137)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276640 |
| 138 |
�|�\ 30(6)(352) |
1988-06 |
�F�������{������̘��S�Y�čl / �R�H����/p8�`14
���l��ܘY�(138)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p22�` |
pid/2276641 |
| 139 |
�|�\ 30(7)(353) |
1988-07 |
�[����<���i>--�������Q�w��䶗����e�N�X�g�ɂ��� / ���R��/p8�`24
������£(139)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p32�` |
pid/2276642 |
| 140 |
�|�\ 30(8)(354) |
1988-08 |
��������������������|�\�����Ɏv��� / �㓡�i/p7�`7
���{���w�Z��������̐܌��M�v / �����R��/p8�`11
���Đ��\�Y���̗֊s--�ߐ��� / �|��×Y/p12�`20
����Ƃ̓�̉̔�(140)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276643 |
| 141 |
�|�\ 30(9)(355) |
1988-09 |
����������ԃV���}�j�Y���̓`��� / �哇���F/p7�`7
�t���̔��������� / �{�c����/p8�`14
�����㉉���̗V����-4-�M�d�ȍ��Y�̉Ԗ��\�� / �ق�����/p15�`21
����_�Ђ̉̔���Ɍ�c�A�գ(141)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p22�`23
��܌��M�v���T��������� / ���؍�/p24�`26
�����G�O�Y���w�ڂł݂閯���_�x(�S�O��) / �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276644 |
| 142 |
�|�\ 30(10)(356) |
1988-10 |
��������`���ƍĐ�� / �c���`�L/p7�`7
�������������y�Ƒ��̙T���Y / �㓡�i/p8�`18
�����㉉���̗V����-5-�̕���E�S�̂̔��ȋ��߂� / �ق�����/p19�`25
��Ƃ̐V�����̎莆�(142)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276645 |
| 143 |
�|�\ 30(11)(357) |
1988-11 |
�������NG���\�\�e���r�͂���ł����̂�� / ���؉���/p7�`7
�C�ƎR�̑��ŋ�--����n�ŋ��̖���-��- / �i�R����/p8�`18
�����㉉���̗V����-6-�Č��̖��V���̃��b�J / �ق�����/p19�`25
��ƂƉ��{�Ƃƣ(143)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276646 |
| 144 |
�|�\30(12)(358) |
1988-12 |
��������Έ䂳����Âԣ / �˔N��/p7�`7
�C�ƎR�̑��ŋ�--����n�ŋ��̖���-��- / �i�R����/p8�`20
�����㉉���̗V����-7��-�j���̃x�e��������ˉ��o / �ق�����/p21�`27
���O�ւ�狋�̔�Ƃ��̎��ӣ(144)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29
���҂���颐茋���--�̕���w��̑n���� / �ы���/p30�`32
|
pid/2276647 |
| 145 |
�|�\31(1)(359) |
1989-01 |
�ݗt�W�G������ݗt�W���(145)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ;�F����o�j/p28~29 |
pid/2276648 |
| 146 |
�|�\31(2)(360) |
1989-02 |
��������|�\�̐V�������� / �P�c�r�ܘY/p7�`7
�b��암�n���ɂ����鎂�q���l-��- / �������c/p8�`16
����Đ��\�Y��̕ϑJ-��-���\�Y�̑��^ / �|��×Y/p17�`25
����{�̒뉀�գ(146)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
�㓡����Y�ďC����c���j������Ғ��w���c���j�`�x / ���J�쐭�t/p28�`29
�w�܌����m�L�O�Ñ㌤�����I�v ��S�x / ������/p29�`30
�鎭���T���w�_�������|�\�̌����x / �q�c����/p30�`31 |
pid/2276649 |
| 146 |
�|�\31(3)(361) |
1989-03 |
��������w�|�\�x�̍ďo���Ɋ��ң / �q�c��/p7�`7
���̏C���w(���g���b�N)--�@��_�y�̚��q�ɂ�����ے��\�� / ����T/p8�`17
�b��암�n���ɂ����鎂�q���l-��- / �������c/p18�`27
�����̌��̉̂Ƃ��̒n���l(147)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276650 |
| 148 |
�|�\31(4)(362) |
1989-04 |
�܌��M�v�ƌ|�\<���W>/p10~41
���z �܌��搶�ƎG����|�\� / �˔N��/p10�`11
�����|�\�ƌ|�\���� / �O�����Y/p12�`20
�|�\�j�̎v�z / �ɓ��D�p/p21~27
���J�ƌ|�\ / �������/p28~34
�|�\�ɂ�������� / �Óc���K/p35�`41
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(1)�܌��M�v�̉���̖K / ������ ;�F����o�j/p6~
�� �|�\�����ƍ̏W / ������/p9�`9
��`�������̍Ĕ�������g���V / �������H/p42�`44 |
pid/2276651 |
| 149 |
�|�\31(4)(363) |
1989-05 |
�����E����̐M�ƍ��J-1-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�͂��߂� / ������/p10�`10
������낳������ɂ݂�×����̐��E��--������������̐M�� / �O�Ԏ�P/p11�`23
���������̐M�Ɛ_�b--�H�ߓ`���𒆐S�Ƃ��� / ��ё���/p24�`37
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(2)����V�Ԃ̕��� / ������ ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276652 |
| 150 |
�|�\31(6)(364) |
1989-06 |
�����E����̐M�ƍ��J-2-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�쓇�̑��������Ɛ_ / �J�쌒��/p10�`21
���J�ƌ|�\ / �O�����Y/P22~37
�u�܂�v�ꗗ�\--�X�ۉh���Y���쐬�w���ꕶ���j���T�x(�������o�Ŋ�)����/p34�`37
�܌��M�v�̐��E(��܁Z)�����(3)��������̂��Ƥ���̑�� / ������ ;�F����o�j/p6~ |
pid/2276653 |
| 151 |
�|�\31(7)(365) |
1989-07 |
���������̐M�ƍ��J-3-�A�l�̗�--�N�����������̗��
�@�@��(���i�L�O���J�u��) / ���c�v�q/p10�`21
�܌��M�v�̐��E(��܈�)�����(4)������̂т���� / ������ ;�F����o�j/p6~
���P�Y���w���ꕑ�x�̗��j�x / �O�����Y/p22�`23 |
pid/2276654 |
| 152 |
�|�\31(8)(366) |
1989-08 |
���z �~�̗x / �{�c����/p10�`11
᱗��~��Ƙb�| / �֎R�a�v/p12�`18
�~�s���ƌ|�\--���s�𒆐S�� / �R�H����/p19�`25
����� �ӓy���̃A�V���Q(��ܓ�)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276655 |
| 153 |
�|�\31(9)(367) |
1989-09 |
�܌��M�v�̐��E(��O)�����(6)�ق����Ƃ���قǒ������l / ������ ; �F����o�j |
pid/2276656 |
| 154 |
�|�\31(10)(368) |
1989-10 |
���c���j�ƌ|�\ / �q�c��/p11~13
�܌��M�v / ������/P14~16
�����Z�g�̕��x���� / �J�O/p17�`19
����F���Y / �O�����Y/P20~21
�k�씎�� / �ۍ�B�Y/p22~23
���p�䐳�c / �������H/p24~26
�ɔg���Q / �X�۞Ď��Y/p27~28
�܌��M�v�̐��E(��l)�����(7)���c�ƈ��g / ������ ;�F����o�j/p6~
<���]>��ؓ��q���w���O�ͥ�ԍՂƐ_�y<�_�̎���l�̐�>�x / ��쐽/p37�`38
�q�Љ�r�㓡�i�Ң�V�s�|�\� / �n�ӗǐ�/p38�`39 |
pid/2276657 |
| 155 |
�|�\31(11)(369) |
1989-11 |
�܌��M�v�̐��E(��܌�) / �����/p8�` |
pid/2276658 |
| 156 |
�|�\ 31(12)(370) |
1989-12 |
���ʉ����s�������̂䂭�� / �F����o�j/p19�`29
�\�ʂƖ����|�\��--�ԍբ��S��Ɨw�Ȣ�ԑm��̊W���� / �㓡�i/p30�`38
�܌��M�v�̐��E(��ܘZ)�����(9)�Ί_���ł̖̍K / ������/p6�` |
pid/2276659 |
| 157 |
�|�\32(1)(371) |
1990-01 |
�O�ԙ�<���W>/p10�`41
�_���Ɠs�s��L���̕ϊ��q��O�ԙգ�|�\�j�̋ߐ��I�W�J�r / �����K�Y/p10�`11
�O�ԙՂ̖ⓚ�̕ϑJ / ���c�K�q/p12�`18
�̕���̢�O�ԙգ / ������Y/p19�`25
�M�y�̎O�ԙ� / �Ύ�،��q/p26�`33
�O�ԙ]�� / ���p�䐳��/p34�`41
�܌��M�v�̐��E(���)/�����(10)�A���K�}������ / ������ ; �F�f���o�j/p6�`
|
pid/2276660 |
| 158 |
�|�\32(2)(372) |
1990-02 |
�܌��M�v�̐��E(��ܔ�)/�����(11)�{�ǂ̃i�r���h�D / ������ ; �F�f���o�j/p6�`7 |
pid/2276661 |
| 159 |
�|�\32(3)(373) |
1990-03 |
�C����ƌ|�\--��������𒆐S�Ƃ��� / ��ؐ���/p17�`23
�̕���Ƣ����̌|�\ / ���c���i/p24�`30
�܌��M�v�̐��E(��܋�)�����(12)�����̖K�蒟��Ƣ����̖K�L� / ������ ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276662 |
| 160 |
�|�\32(4)(374) |
1990-04 |
��O�c���ݗt���s�(160)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276663 |
| 161 |
�|�\32(5)(375�j |
1990-05 |
�܌��M�v�̐��E(��Z��)(���̓�)�ݗt���s / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276664 |
| 162 |
�|�\32(6)(376) |
1990-06 |
������<���W>/p9~38
������裂̌Ñ㎏--�|�\�����̋N�_ / �ɓ��D�p/p10�`16
�_�y�ɂ������Ă鉉�o / ���䐳�O/p17�`24
����ɂ������Ă�̋V��ƌ|�\ / ���w/p25�`31
�H�R������Ɠc�V�т� / ���q�v/p32�`38
��t����{��գ(��Z��)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ;�F����o�j/p6~7
<��>��Ă裏ȗ����� / �O�����Y/p9�`9 |
pid/2276665 |
| 163 |
�|�\32(7)(377) |
1990-07 |
���ƌ|�\ //p10�`10
���E��"�ՋV = �|�\"�Ƃ��Ă̐_�y / ��c��/p11�`19
���K�_--���ԥ��Ԃ̋����o������_ / �����G�O�Y/p20�`28
�ޗǍ�|�\�� / �㓡�i/p29�`36
��ԍՂ�(��Z�O)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276661 |
| 164 |
�|�\32(8)(378) |
1990-08 |
����̌|�\<���W>/p10�`37
�g�x��̓W�J--�����Ȍ� / ���P�Y/p10�`17
�X�����8���V�� / �c���p�@/p18�`23
�������x�̓���--�ÓT���x��ƎG�x��𒆐S�� / ���A�ɒj/p24�`30
����̑��x�� / ���Ԉ�Y/p31�`37
��V�� ��Ղ�(��Z�l)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`
<�Љ�>�c���`�m��w�����w������ҁw�쓇�����Ɛ܌��w�x������q���w����̗̉w�Ɖ��y�x�Ɖ����P���w����̌ÓT�|�\�x / ���ʐM/p38�`39
|
pid/2276667 |
| 165 |
�|�\32(9)(379) |
1990-09 |
�O���ƌ|�\<���W>/p10�`38
�O�����{�ƌ��� / �剮����/p10�`17
���B�̖~�O��--���̓`�����ԂƗ��j�I�ϑJ / �g��S�q/p18�`24
��a�̘Z�֔O�� / ���J�M/p25�`32
��O�R�㋽�̑�O�� / ���⏟�j/p33�`38
��V��~�x��ƐV��̑��������(165)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`
<��>�_�y�a����M�y�̋����� / �����G�Y/p9�`9
�͒|�o�u�v�ďC������G�Y�ҏW��щËg�ʐ^�w�̕���r���x / �{�c����/p39�`39
�R�H�������w���̍��\�\�|�\�������̒����x / �������H/p40�`40
|
pid/2276668 |
| 166 |
�|�\32(10)(380) |
1990-10 |
��܌��搶�ƐH�ו����(��Z�Z)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ;�F����o�j/p6~7
<��>�܌��M�v���ꂩ��̂͂��� / ������/p9�`9
|
pid/2276669 |
| 167 |
�|�\32(11)(381) |
1990-11 |
�另�Ղƌ|�\<���W>/p10~33
�{��̗w�����̋@�� / ������/p10�`16
�������̈Ӌ`--�V�當���w�̗��ꂩ�� / �q�ѐ���/p17�`25
�另�Ղ̍\���V�_ / �g��T�q/p26�`33
��O�c�̖��t���s(��)�(167)�܌��M�v�̐��E / ������� ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\--��茧 / �剮����/p34�`47
<��>�Ă�̍Ղ�̍Đ��Ǝ� / �O�����Y/p9�`9
<���]>�q�쐴���w���d�R�̂��ԁx / ���F�M/p48�`48 |
pid/2276670 |
| 168 |
�|�\32(12)(382) |
1990-12 |
�̖�̗��K�_ / ��ؐ��F/p10�`17
�z�N��}�t�̌|�\ / ���c�nj�/p18�`24
�܌��M�v�̐��E(��Z��)����t���s(��)� / ������� ; �F����o�j/p6�`7
|
pid/2276671 |
| 169 |
�|�\33(1)(383) |
1991-01 |
�Ìy�ɂ������t�|�̐����Ƃ��̋ߑ㉻ / ���a�Y/p10�`16
�t����Ԍ������� / �_�c���q/p17�`23
���w��̗w�Ɍ����t�j���| / ����K��Y/p24�`30
����t���s(��)�(��Z��)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�`
<��>�|�\����݂��另�Ձ\�\�^�킵���I�� / ���p�䐳��/p9�`9
|
pid/2276672 |
| 170 |
�|�\33(2)(384) |
1991-02 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ�Z)���O�t���s(��)� / ������� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276673 |
| 171 |
�|�\33(3)(385) |
1991-03 |
���O�t���s(��)�(171)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�`7
�Ï銰�����w�܌��M�v�̒����_�x / �Óc���K/p46�`46 |
pid/2276674 |
| 172 |
�|�\33(4)(386) |
1991-04 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ��)���O�t���s(�O)� / ������� ; �F����o�j/p6�`
|
pid/2276675 |
| 173 |
�|�\33(5)(387) |
1991-05 |
���l�t���s�(�ꎵ�O)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276676 |
| 174 |
�|�\33(6)(388) |
1991-06 |
��O�c�̖��t���s(��܉�)���̈�(�ꎵ�l)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y ;�F����o�j/p6~7 |
pid/2276677 |
| 175 |
�|�\33(7)(389) |
1991-07 |
��O�c�̖��t���s�w��܉�x���̓�(�ꎵ��)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y ; �F����o�j/p6�`7
�r�{�������w����̗V�s�|�\�\�`�����_���[�ƃj���u�`���[�x / �ɓ��D�p/p45�`45
|
pid/2276678 |
| 176 |
�|�\33(8)(390) |
1991-08 |
�_�y��<���W>/p10�`30
���B�̐_�y�� / ���R����/p17�`23
��O�c�̖��t���s�w��܉�x���̎O�(�ꎵ�Z)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y/p6�`7
��{���꒘�w�F��R�C�����l�x / ��ؐ���/p46�`46 |
pid/2276679 |
| 177 |
�|�\33(9)(391) |
1991-09 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ��)��O�c�̖��t���s(��Z��)(���̈�)� / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`
�X�R�d�Y���w�܌��M�v����҂̏���̐��E�x / �������H/p46�`40
�����������w�܌��M�v�̊w��`���x / ������/p47�`47 |
pid/2276680 |
| 178 |
�|�\33(10)(392) |
1991-10 |
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̓�(�ꎵ��)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`7
����̌|�\�ߏ�--�g�x�ɂ݂�ߏւȂǂɂ��� / ��ԗ�i/p24�`30 |
pid/2276681 |
| 179 |
�|�\33(11)(393) |
1991-11 |
�\�Ƒg�x<���W>/p10�`29
<��>����ɂ����� / ���R�h��/p9�`9
���������Ƣ���S����� / �{�c����/p10�`14
�g�x�G�� / ��闧�T/p15�`19
������q��Ƣ�H�ߣ�̒�� / ������/p20�`24
�g�x�̐��E--���������Ƣ���ΓG����̑�햡 / ���Ԉ�Y/p25�`29
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̎O�(179)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`7
�ؕꎛ�ҁw�~��˥�ؕꎛ�̕���x/p44�`44 |
pid/2276682 |
| 180 |
�|�\ 33(12)(394) |
1991-12 |
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̎l�(�ꔪ�Z)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ;�F����o�j/p6~ |
pid/2276683 |
| 181 |
�|�\34(1)(395) |
1992-01 |
��C�R���̉̔�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
�����|�\����w�����̃��[���h��~���[�W�b�N����������̣ / �������q/p62�`62
|
pid/2276684 |
| 182 |
�|�\34(2)(396) |
1992-02 |
��؏������̐գ(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
�\�������|�p�Տ܂ɔ~�ᐷ�`� / ���N��/p59�`59
|
pid/2276685 |
| 183 |
�|�\34(3)(397) |
1992-03 |
���ЎQ�w��䶗��ƊG�������ւ̎���--�G�����̊T�O,�����Ď��Љ��N�G���玛�ЎQ�w��䶗��� / �щ�F/p19�`27
�Ў��Q�w��䶗��̌|�\�� / ���c�a�v/p28�`34
��v�����̖̍K�(�ꔪ�O)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
�����|�\����w������|�\���ό��̍ޗ��ɂ����!!�v / �������q/p62~62 |
pid/2276686 |
| 184 |
�|�\34(4)(398) |
1992-04 |
��Ì����̍��Ɛ̣(�ꔪ�l)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
���{�̖����|�\�q���ꌧ�r / ���{/p30�`43 |
pid/2276687 |
| 185 |
�|�\ 34(5)(399) |
1992-05 |
���w�̌p�����W�̂��߂Ɏ������� / �������q/p10�`15
��^�ӂ̈È�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
�{�c�������w����̍Ղƌ|�\�x / �O�����Y/p45�`45
���䖞�ҁw�v�����̍Ղ�Ɠ`���x / �k����v/p46�`46
�����|�\����w��V�����Љ�ł̖������y��|�\� / �������q/p60�`60 |
pid/2276688 |
| 186 |
|
1992-06 |
����������̏o���(�ꔪ�Z)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`
�����|�\����w�����̍Ղ�̕ϗe� / ����h/p61�`61 |
pid/2276689 |
| 187 |
�|�\ 34(7)(401) |
1992-07 |
���n�̎R�͑O���̋�ɣ(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276690 |
| 188 |
�|�\34(8)(402) |
1992-08 |
��v�����̃C�U�C�z�[�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
����^�C���X�Еҁw�����Ȃ�̍Ղ�x / ������ |
pid/2276691 |
| 189 |
�|�\34(9)(403) |
1992-09 |
��v�����̃C�U�C�z�[(2)�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w��w���܂�@�x�����������̂ţ / �������q/p60�`60 |
pid/2276692 |
| 190 |
�|�\34(10)(404) |
1992-10 |
��v�����̃C�U�C�z�[(3)�(���Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���{��������ҁw���{���w���(���ꥉ���)�{�Ï����ҁx / �O�����Y/p47�`47
���֏�v������������� / ���P�Y/p49�`50 |
pid/2276693 |
| 191 |
�|�\34(11)(405) |
1992-11 |
�|�ƌ|�\--�o�����̌|�\�ƋV���� / �{������/p18�`21
��v�����̃C�U�C�z�[(4)�(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w����w�E�͌��_���A�֣ / �������q/p60�`60
|
pid/2276694
|
| 192 |
�|�\34(12)(406) |
1992-12 |
<��>�ޏ��̌��_�b / �������/p9�`9
�쓇�̐_�b�E�_�w<���W>/p10~32
�����̃m���ƃ��^�̎��d�ɂ���--�I�����ƃ}���K�^���̑Δ� / �R���ӈ�/p10�`17
���z�̐_�Ɣ��n�̗��--�v�����̃e�B-��-�K-�~�̐_�� / ��������/p18�`25
�떓�̃t�T--���̋N�� / �Ë��M�F/p26�`32
��Ί_���̃A���K�}�(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276695
|
| 193 |
�|�\35(1)(407) |
1993-01 |
<��>�Y�\�w��\���N / �{�c����/p9�`9
�|�\�w--�܌��M�v�̕��@<���W>/p10�`32
�܌��搶�Ɖ̕��� / �˔N��/p10�`11
�����w�ƌ|�\�w--���c���j�Ɛ܌��M�v��"�|�\�_" / �q�c��/p12�`18
�܌��w�̍\��--�|�\�`���_�̍��i / �O�����Y/p19�`25
�܌��M�v�̌|�\�̏W / ������/p26�`32
�܌��M�v�̐��E���O��Ί_���약�̃}�����K�i�V� / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w��`�������U���̕�������� / �������q/p62�`62
|
pid/2276696 |
| 194 |
�|�\35(2)(408) |
1993-02 |
<��>�܌��M�v�Ɛ_���� / �ۍ�B�Y/p9�`9
�܌��|�\�j��ǂݒ���<���W>/p10�`30
�����|�\�����ɂ�����ϋq�_-3�̉\�� / ��쐽/p24�`30
����\���c�[�̐߃A���K�}(1)�(194)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
�c�Ԉ�Y�ďC�w�����|�\���T�x / �O�����Y/p45�`45 |
pid/2276697 |
| 195 |
�|�\35(3)(409) |
1993-03 |
�܌��M�v�̐��E(����)����\���c�[�̐߃A���K�}(2)� / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w����w�̐�������`���� / �������q/p62�`62 |
pid/2276698 |
| 196 |
�|�\35(4)(410) |
1993-04 |
������<���W>/p10~30
�叕�\�̔ԑg��<����������>--
�@�@�����Q�����}���ّ���x��叕�\�ԑg����߂����� / �V�앶�Y/p10�`14
�Ԋy�̒��̈�������P--�������e�L�X�g�l / �ѐm/p15�`20
��p���V���E�l�ӣ�Ɛl�`�̏����� / �����F��/p21�`25
��|�҂Ǝ��--�ٍ��Ő��܂ꂽ�������� / �O����/p26�`30
������գ(���Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276699 |
| 197 |
�|�\35(5)(411) |
1993-05 |
<��>�����̕� / ���ʐM/p9~9
�|�\�w��E����|�\�j����������<���W>/p10�`30
�g�x��{�̢��\(�݂Ȃ݂�����)���k�\(����������)����l���� / ���Ԉ�Y/p10�`16
�������{�ɂ����钆���n�̉��y�Ƣ����y��̉��� / ��Éx�q/p17�`23
�܌��M�v�̉���|�\����--��O�̉���̋��y�����Ƃ̊ւ��𒆐S�� / ���F�M/p24�`30
���Ƃ����낳�����(��㎵)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���](���W����) / ���ʐM/p34~35
�������̓������ / ���ʏˎq/p45�`45 |
pid/2276700 |
| 198 |
�|�\35(6)(412) |
1993-06 |
����䉮����ԣ(��㔪)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276701 |
| 199 |
�|�\35(7)(413) |
1993-07 |
��������ꉉ���̕���j / ��쓹�Y/p10�`16
���ŋ��̕��� / �i�R����/P17~23
��֏��ԣ(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276702 |
| 200 |
�|�\35(8)(414) |
1993-08 |
<��>���a�̕��w��|�\�ƌ˔N�� / ����O�F/p9�`9
�l�`�|�\�ƕY��<���W>/p10~30
���{�|�\�j�Ƌ��l�M��--����̍l�@�𒆐S�� / �ɓ��D�p/p10�`16
���� �����Y�̐l�`�Y / �F�쏬�l�Y/p17�`23
�؍��̐l�`���R�N�g�D�t���m����--�j���}�͕Y���ƈ��������z���� / �p���/p24�`30
������Y�(����1)(��Z�Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276703 |
| 201 |
�|�\ 35(9)(415)
�|�\ 35(10)(416)
�|�\ 35(11)(417)
|
1993-09
1993-10
1993-11
|
�܌��M�v�v��40�N�L�O--�܌��|�\�w�̑S�e<���W> / ���T�j/p10�`29
�܌��M�v�̐��E��(��Z��)������Y�(����2) / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
��>�܌��M�v�l�\�N�� / �q�c��/p4�`5
�����{��̒j�|��(��Z��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p8~9
���G �����{��̒j�| / �F����o�j/p2�`2
�����{��̏��x(203)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���G �����{��̏��x / �F����o�j/p2�`2
���̂��ύX
�|�\ 35(11)(417)�@�@�@�|�\�w��� �@���s�^�|�\���s��
�Y�\ (1)(418) �Y�\�w��ҏW�ψ���� �@���s�^�Y�\�w�� |
pid/2276704
pid/2276705
pid/2276706
|
| 202 |
�Y�\(1)(418) |
1995-03 |
�܌��M�v�̐��E(202)��狋�̉̔�ɉ / �[���g�V�� ;�F����o�j/p97~99 |
pid/4428628 |
| 203 |
�Y�\(1)(418) |
1995-03 |
�܌��M�v�̐��E(203)�g�� / ���؊�� ;�F����o�j/p100~105 |
pid/4428628 |
| 204 |
�Y�\(2)(419) |
1996-03 |
<94�N�������>�������\/4�`41
�؍��̒ǙT / �c����/p4�`11
�؍��]�˂̒[�ߍ� / �ɓ��D�p/p12�`20
�b��암�n���̎��q�� / �������c/p21�`30
�u�V�����l�v�����m-�g / �H���Ƌ`��/p32�`41
<94�N�������>�u�� �{�q���ɂ�����|�̓`�� / �r�c�O��/p42�`51
<94�N�������>�|�\�Z�~�i- �֍O�q���ɕ���--
�@�@��"���"�̐��ݏo���F���̓h���} / �֍O�q ; ������/p52�`63
<95�N�������>�|�\�Z�~�i�[�u���J��Ԃƌ|�\��ԁv/64�`95
�����|�\�̍��J��Ԃƌ|�\��� / �F����o�j/p64�`68
���J��ԂƉ̕��� / �D�c�E��/p69�`75
���{���x�̐�����Ԃƌ|�p��� / ����p�r/p76�`85
�u���v�̑g���ƍ��J�� / ���R��/p87�`92
<���J��Ԃƌ|�\���>���߂����� / �H�c��/p93�`95
�܌��M�v�̐��E(204)�t����S�E�Ȃ܂͂� / ��ϐ��� ; �F����o�j/p96�`102
�q�r ���䂩�����r���{����--�č��~�h���x����w�ɂ� / �����r�q/p103�`103
�����q�j�w�當���j�̌����x / ����}��/p104�`105
�n�ӏ��`�w�����Ղ̌����x / �ۍ�B�Y/p106�`107
���}���w��p�̓����Ɩ��ԐM�x / �����W��/p108�`109
���Y���P�w�܌��M�v�_�x / ���c���q/p110�`110
�����G�Y�E�F����o�j�ďC�w���{�̓`���|�\�x / ������/p111�`111
�k���k�̏C���n�_�y�́u��v / ��Αוv/p112�`114
�u�܌��M�v�Ɖ���w�Ɓv�̂܂Ƃ߂Ɍ����� / ���F�M/p115�`117
�z���S�̌��� / �Ύ�،��q/p118�`120
|
pid/4428629 |
| 205 |
�Y�\(3)(420) |
1997-03 |
<95�N�������>�u�� ���{�������y�����\�N / �������q/p4�`16
<95�N�������>�������\/17�`51
�|�\�Ǝq�� / �{�c�ޔ��q/p17�`25
�C���ւ̎��� / �F�엲��/p26�`33
���㉬�]�I�F�̎��� / �R���/p34�`41
�V���čl / �ۍ�B�Y/p42�`51
<95�N�������>�|�\�Z�~�i- �x��ƉS�ŒT��]�˂́u���v / �h�� ; �O�����Y ; ���Ԋ����b/p52�`61
�܌��M�v�̐��E��(205��)�܌��M�v�̒����s / �������H ; �F����o�j/p62�`67
���q�̊T�O�Ɋւ���l�@--�����|�\�ɓo�ꂷ�鎂�q����ʂ��� / �����K/p68�`77
����h�w�̊_�Ɣ��y�̖�����--�����ɌÑ�̉̕���K�˂āx / ���R��/p78�`79
�����K�Y�w�]�ˉ̕���̔��ӎ��x / ����됅/p80�`81
����O�F�w�܌��M�v�̋L�x / ������/p82
�V�ҁw�܌��M�v�S�W�x��21�E22��(�|�\�j1�E2) / �������/p83
�R���s��c�_�Џ����א�H�֊֘A�̚��q�`���̏Љ� / �R�{���q/p84�`85
�_�q�V���|�W�E���� / �_�c���q/p86�`87
�ɐ���_�y����̌���Ɩ��_ / �㓇�q��/p88�`89
���ۍl / �v�ۓc�T��/p90�`91
���G �u�܌��M�v�̒����s�v / �F����o�j ; �������H |
pid/4428630 |
���V���[�Y�u��Z��^�Q�O�R)�܌��M�v�̐��E�v���d�����Čf�ڂ���Ă���̂��u�܌��M�v�̐��E(20�V��)�ɂȂ�̂Œ��ӂ��K�v�@�Q�O�Q�T�E�S�E�P�W�@�ۍ� |
�S���A�O�Ԏ�P, �g�Ɗԉi�g�Ғ��u��{�������R���L�v���u�p�쏑�X�v���犧�s�����B
�S���A�����ɓs�q���u����̍��v���u��g���X �v���犧�s����B�@�@ 206p ;
|
�ӂ����сu����̓��v
���A�����̎u |
���̂��Ȃ���
�Ԗ�����߂� |
��������
�E |
�T���A�N�㌳�Y, ���G�q���u����̐��n�v���u�ނ��Ёv���犧�s�����B�@155p �@�����F���ꌧ���}���فF1004470751
|
���Â���̐_�b
�@�q�����̓V�n�n���r |
�@�q�����J�тႭ�̎���ԁr
�@�q������(�A�K���E�}�[�C)�r |
�@�q���A�m���(�i�`�W���k�u�C)�r
�@�q��V����(�E�A���E��)�r |
�T���A�g�Ɗԉi�g���u�{�̗��l = Travelers of the books 3(5) p.38�`41�v�Ɂu�w�������R���L�x�̐��E--�ߐ�����̕����Ə@���I���E�ւ̓����v�\����B�@
�T���A�u�ό��C�x���g�̉^�c���ԁv���u���{�ό�����v���犧�s�����B
|
�ό��C�x���g�̌���Ɖۑ�@1
9�E4�E6�I���}�C�}�C���h �k�C�����H�s�@10
�N�ʌ���I�z�[�c�N100km
�@�@���N���X�J���g���[�X�L�[��� �k�C�����y���ق��@12
�R�ʌR�^�� �k�C�����ǒ��@14
�I�z�[�c�N���X�̂��Ƃ胉���h�ԑ� �k�C���ԑ��s�@16
�m���t�@���^�W�A �k�C�������@18
��������A�C�X�L�����h���t�F�X�e�B�o�� �k�C�����쒬�@20
���쒬���ێʐ^�t�F�X�e�B�o�� �k�C�����쒬�@22
�k�C���o���[���t�F�X�e�B�o�� �k�C����m�y���@24
�����ۂ��܂� �k�C���D�y�s�@26
��E�x┌ΕX���܂� �k�C����Ύs�@28
���a�V�R���ېፇ�� �k�C���s�˒��@30
�I�z�[�c�N���ۖ����� �k�C����N�ʒ��@32
���̌��c�A�[ �X���c�Ɋّ��@33
�Ìy�O�����t�F�X�e�B�o��IWAKI �X����ؒ��@34
�ΐ_�܂� �X���X�c���@36
�̂����܂� ��茧��c���@38
�Ⴀ���莖�� ��茧���c���@40
��蒬���ېΒ��V���|�W�E�� ��茧��蒬�@42
�k��݂��̂��|�\�܂� ��茧�k��s�@44
�ɂ��ۂ�S�b�Y�t�F�X�e�B�o�� ��茧�k��s�@46
���E�t�܂� �{�錧���s�@48
SENDAI���̃y�[�W�F���g �{�錧���s�@50
��O�ؓ��u�����D�グ�v �H�c�����ؑ��@52
�ꕶ�y�[�W�F���g�u�Ղ̌v �H�c���Ջu���@54
�k��40���H�c�������]�[�[�g�J�b�v
�@�@��100�L���`�������W�}���\�� �H�c���鑃���ق��@56
�䂫�Ƃт����� �H�c���H�㒬�@58
�S��������� �R�`���O�쒬�@60
������S���j�n���� �R�`���������@62
�l�ԏ��� �R�`���V���s�@64
���{��̈��ω�t�F�X�e�B�o�� �R�`���R�`�s�@66
��R����S�����������w�`������� �R�`����R�s�@68
���������l�܂� �Ȗ،��������@69
���I���ۖ�O���p�W ��ʌ����I���@71
�x�Y�l�`���t�F�X�e�B�o�� ��t���x�Y���@72
���̉Ղ� ��t����h���@74
�ŎR�͂ɂ�� ��t���ŎR���@76
��ё哹�|�E�B�[�N �_�ސ쌧���l�s�@78
���l�J�`�L�O�݂ȂƍՍ��ۉ����s�� �_�ސ쌧���l�s�@82
�n�x�C��݃A�[�g�y�C���e�B���O �_�ސ쌧���{��s�@83
�����喼�s�� �_�ސ쌧�������@86
�~�܂� �_�ސ쌧���c���s�@88
����ς̉œ���s�� �V�����Ð쒬�@90
�z�㏼�V�R����m �V�������V�R���@92
���o��܂�u���ېፇ����v �V�������o���@94
�A�[�X�E�Z���u���[�V���� �V�������ؒ��@97
���{��X���t�F�X�e�B�o�� ���쌧���{�s�@100
���̍�����j�������� ���쌧��M�Z���E�É������E���@102
�R�̓s�b�{��D���܂� �R�����b�{�s�@105
�͌��n�[�u�t�F�X�e�B�o�� �R�����͌��Β��@107
�哹�|���[���h�J�b�v�C���É� �É����É��s�@109
�ɓ������A�[�g�t�F�X�e�B�o�� �É����ɓ��s�@112
�P�l���� �����]���@113
�����݂ȂƍՂ� �É��������s�@114
���Ȃ��l�`���܂� �É����������@116
�Ƃ�܃X�m�[�s�A�[�h �x�R���x�R�s�@118
������O���y���u�z�����t����杁v �x�R�������s�@120
�������t�܂� �x�R�������s�@122 |
���Ȃݍ��ۖؒ����L�����v �x�R����g���@124
�ƂȂ݃`���[���b�v�t�F�A �x�R���v�g�s�@126
�m�ԍՎR������S���o���� �ΐ쌧�R�����@129
�t�[�h�s�A���� �ΐ쌧����s�@130
��̐쉀�V�� �ΐ쌧����s�@132
�Ⴞ��܃E�B�[�N �ΐ쌧�������@134
�ᒆ�W�����{�����܂�i�܂�����܂�j �ΐ쌧�������@136
���{�ꂩ����܂� ���������@138
������Ƃ����� �����q���@140
�ɉ���NINJA�t�F�X�^ �O�d�����s�@142
�|�p�Ŋy�s�y���iARTINNAGAHAMA�j ���ꌧ���l�s�@144
�A�C�A���}���E�W���p���E�C���т�Α�� ���ꌧ�@146
�v���l�h���S���J�k�[�I�茠��� ���s�{�v���l���@148
�V���������Ă�M���� ���s�{�{�Îs�@150
�䓰�p���[�h ���{���s�@151
�L�n�咃�� ���Ɍ��_�ˎs�@153
�C�m�u�^�_�[�r�[ �a�̎R�������ݒ��@154
���쒬�����y�Ձu�ӂ邳�ƃ~���[�W�J���v ���挧���쒬�@156
��։����̌n������ �������哌���@158
���{�Ό��_�y��� �������l�c�s�@160
���{�̎q��S�t�F�X�^in�䌴 ���R���䌴�s�@162
�Ђ낵�܃t�����[�t�F�X�e�B�o�� �L�����L���s�@163
�G�̂܂������l�G�W �L���������s�@165
�Ƃ�܂ӂꂠ���t�F�X�e�B�o��
�@�@���i�S���{�Ԉ������[�X�j �L�����L�����@167
�����~�̂܂�[�h���[���C���~�l�[�V�����C��
�@�@�� �^�J�}�c�[���쌧�����s�@169
�l������҂�̕����ŋ� ���쌧�Օ����@172
���N���G�[�V�����Ɛl�`���̃J�[�j�o�� ���쌧������@174
�l������̂����܂� ���Q����V�]�s�@176
���q�����y ���Q�����q���@178
��{��������s�L�O��� ���Q�������l�s�@180
�[���v���b�g�z�[���R���T�[�g ���Q���o�C���@182
�S���u���܂ڂ��̊G�v�W���� ���Q����쒬�@184
�䑑�p���Ċ����� ���Q���䑑���@186
������傢�S���Ă܂� �������k��B�s�@187
�A�W�A�}���X �����������s�@189
�}��g��̏����Ȕ��p�ق߂��� �������g�䒬�@191
�}��g��̂��Ђȗl�߂��� �������g�䒬�@193
�Ó��f��� ���ꌧ�x�m���@195
����C���^�[�i�V���i���o���[���t�F�X�^ ���ꌧ����s�@196
�����K�^�����s�b�N ���ꌧ�����s�@198
�g�샖���̉ԃ}�[�` ���ꌧ�_�钬�E�O�c�쒬�@200
�c�A�S�A�W�A�t�F�X�e�B�o�� ���ꌧ���L�c���@202
���胉���^���t�F�X�e�B�o�� ���茧����s�@204
�A�^�b�N�E�U�E���{�[�i�錾�^�C�����[�X�j �F�{���������@205
�����E�P�����}���`�b�N�C�����f����
�@�@���|�C�J�_���[�X �啪���������@206
�~�X�e���A�X���C�u�C������ �啪���������@208
�L�㐅���x�i��N������ �啪���ߌ����@210
�������ؔ����{�[�g�n�C�L���O �啪���������@212
�_�b�̗��t�F�X�e�B�o�� �{�茧����䒬�@213
�s�䖦�܂� �{�茧���Ԏs�@215
���ؖ�l���n��� �����������ؖ�s�@217
����l���̍ՓT �������������c�s�@218
�~�V�}�J�b�v ���������O�����@220
����S���G�C�T�[�܂� ���ꌧ����s�@222
�嗮���E�܂艤�� ���ꌧ�ߔe�s�@224
�S���{�g���C�A�X�����{�Ó���� ���ꌧ�{�Ó��@227
�E |
�T���A�u�����������v�ҏW�ψ�����u���������� (111) �v���u���������w��v���犧�s�����B�@pid/6024855
|
�����_�{�̍r�_��(�\�����) / �o����O/p1�`1
�����Ί����̎����Ƃ��̉�� / ���c��/p2�`26
�����㗬�̓��Y / ���萳��/p27�`34
���萳���搶�̎v���o / ���c�/p34�`34
�u�݂��E������v-���̃J�[�\�h�@/�q���Y/p35�`36
�u������E��������v--
�@�@������n���̑����ɂ���/�㓡�ǗY/p37�`37
���筐_�З��L�n�����^ / ���y���L��/p38�`39
�����Ɩ������z(3)�i�}�R�r���� / ����O�Y/p40�`51 |
�u�����\�Б喾�_�Ղ̐_�y�́v�ɂ��� / ���c�/p51�`52
���W �H���_������ �H���_�������ɂ��� / ���蕽/p53�`53
���W �H���_������ �����E�H���_������(�]���S�L�����F��_��)/p54�`83
���W �H���_������ �����`���a�̖H���_�������ɂ��� / ���蕽/p84�`84
���W �H���_������ ���� �L�����H���E
�@�@���F��_�А_������(�����`���a)/p85�`112
����8�N�x��v���Z�Ɗč���/p113�`113
�w���/p114~114
�ҏW��L/p115~115 |
�U���A���{�@���w��ҁu�@������ = Journal of religious studies 71(1) ���W ����̏@�� p.1�`231�v���u���{�@���w��v���犧�s�����B
|
���d�R�ɂ�����ߑ㉻�Ɩ����@���̕ϗe ���䓿���Y p.1�`30
�_�̂ɂ�����_�b�I�n�� �@���ǒ� p.31�`54
����ɂ�����c����J�̐��� �@�ԗ䐭�M p.55�`78
����Љ�ɂ�����c�搒�q��
�@�@�@�����ȃA�C�f���e�B�e�B�̍\�z ���B�`�O p.79�`103
|
���ꕶ�����ɂ�����c����J�̒n�搫�ɂ��� �c������ p.105�`125
�V�铇�̍ՋV���� �@�A������ p.127�`153
����̕�����e�ƃV���[�}���I�E�\�� �@��݂��q p.155�`181
����ɂ݂�V���[�}���I�E�\�҂̑m�����@���J�����N p.183�`206
���㉫��ɂ�����L���X�g������^���̓W�J�@�r��ǐ� p.207�`231 |
�V���A���g�Ύ}�ҁu���g�Ύ}�̉� : ���ꌧ���|�p��w�t�y�����t���i�����p���t���b�g�j�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�@�@ �����F����9�N7��26��(�y) �ꏊ�F���ꌧ���|�p��w�t�y���@�@�@�@12p �@�����F��㊌����}���فF1004686000
�W���A���{���炪�u�����N�� 1997 p.59-62 �ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������v�Ɂu�������x�ƒn��A�C�f���e�B�e�B�[ : ����̖������x�G�C�T�[�̎���v�\����B�@�@�@�@�@�iIRDB�j
�X���A�ʏ�ߎq�ҁu�x �ʏ�ߎq���T�C�^�� : �ÓT���x��Ƒn�앑�x ��15��v���u�ʏ�ߎq�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�����p���t���b�g�@�@1���@ �����F��㊌����}���فF1004681191�@�@�@�@�����F����9�N9��3��(��)�E4��(�y)
�J��F���ꌧ�����y����
�P�O���A�u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (20/21)�v���u���{�������y�w��v���犧�s�����B�@�@pid/4427630/1/1
|
��10����u�������y�̌p���Ɣ��W�v(1996) �����s���������فE���������Z���^�[/1�`114
�u���v�|/1�`13
1.�u���v�| (1)�����̉̂̐��E / ����w�v/p1�`6
1.�u���v�| (2)�A�W�A���猩�������̉��y / ����m��/p7�`13
2.�V���|�W�E�� �������y�̌p���Ɣ��W / ���c���/p14�`32
���E���h�e�[�u��/33�`65
3.���E���h�e�[�u�� (1)�J�T���̂ƃq�M���� / �㐼���q ;���ь��]/p33~48
3.���E���h�e�[�u�� (2)���w�̊w�K���@ / ���c���/p49�`65
4�D�������\�v�| //p66�`76
�_�� 1.�����Ȃ��y--�����|�\�Ɍ����鉹�y�w�K�̑��� / �ɖ�`��/p77�`91
�_�� 2.�����̉����o�������������y�̎w�� / �������q/p92�`103
�_�� 3.����{���ɂ�������̂̕ώ��ߒ� / �������q/p104�`114
������(1996) //p115~115 |
�P�O���A�������ҁu���������� (10)(349)�v���u���傤�����v���犧�s�����Bpid/2803205
|
���W�\�\���������Â��܂��Â��� //p4�`19
�����C���^�r���[�\�\�n��ɍ����������������ɂ��� �n�Ӕ����q���� / �n�Ӕ����q/p4�`5
�����Z���^-�Â���Ǝs���Q�� / ���� �T�V/p6�`7
�_�y�̐S���ɂ����h�{��--�u�y�t�ꗬ�Ôn�y�_�y�v�̕����Ɨ��� / ���� �Ύq/p8�`9
��錧��J��/�A-�J�X�\�z�p�C���b�g���� / ���� ����/p10�`11
�Ȗ،��v�q��/���E�Ɍ����Ă̕����̔��M / ���x ��/p12�`13
���������_��/�����ȑ��̑傫�Ȗ� / ���R �y�M/p14�`15
���ꌧ���L�c��/���,�A�W�A,�₫���̂��L-��-�h--�c�A�S�t�F�X�^����,
�@�@���k�z�m�I�l�Ɖ��̃V���t�H�j-���Ƃ� / �� ��/p16�`17 |
���ꌧ����s/�����O�邠���݂��̂܂��Â��莖�� / �n��m ����/p18�`19
�A�� //p20~28
���z�\�\���v���[�̑��� / �щp�N/p20�`21
���{�̓`�����ƋZ�����l�X(13)�ΏB�����Z�p�҉� / �v�ۓc�ۈ�/p22�`24
�C�O�����C�O�̕�������\�\�t�����X��(6) //p25�`25
���Z�i�Љ�(7)(��)�������p���c / ��앐/p26�`27
���t�̏����\�\�V���ƂV���[�Y���(7) //p28�`28
ACA(������)�j���[�X //p29~39
�� |
�P�P���A�X�۞Ď��Y���u�G�C�T�[ : ����̖~�x��v���u�ߔe�o�ŎЁv���犧�s����B
�P�Q���A�n�v�n�����u�n��J�� (�ʍ� 399) p.34�`37�@���{�n��J���Z���^�[�v�Ɂu�����߂���(3)�T���S�ʂ̓��X�̊ό�--����E���Ԗ����v�\����B
���A���̔N�A���{����,���c�a�炪�u���{�̈�w��� 48(0) p.631�v�Ɂu�u�V�}�̗x��v����u����̗x��v�� : ���̉���ɂ�����G�C�T�[�̕ω��v�\����B�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���䐳�q���u���m�_�� �����̊|���̃f�B�A���[�O : �����сE�E���T�E���v�\����B
pid/3131665�@�{���\
|
���G
�}��A�p�ꓙ/P8
����/p3
���t�B�[���h���[�N�̌o��/p6
����������V���̓`���̗w�̌���\
�@�@�����Z�N�����̃t�B�[���h�m�[�g���/p9
���t�B�[���h�����̕��@�ƃ^�C���X�p���̐ݒ�/p15
I ������
1 �W�c�̊|�������̂̐��E�\���n����/p27
�꤃G���X�ƌ����`���\���V���́q��(��)���x��r���߂�����/p27
���X�́s�܂�t�\����}�������꣕���/p37
�O���s��̒��̉̊|���\<�Ėڗx��>�I����X�e�[�W/p39
2 �����̏����Ɨl�����\<�Ėڗx��>�ɂ݂�L�@�I�ȑ�����/p43
��A�͂��߂�/p43
��A��V���<�Ėڗx��>/p45
�O�A�ڎ�v��<�����x��>/p56
�l�A������/p61
3 �s�c�A�́t�ɂ�����O�n���\�̗̂��ʂƗl��/p63
��A�T���Ɩ��̏���/p63
��ڎ�v�̢�V�}�ߣ�Ƣ���ߣ/p68
�O��n�������(1)�\��r���ɂ݂�O�n��/p71
�l��n�������(2)�\�\���I����/p74
�܁A������/p85
4 ���v�u�́s�L���[�_���t�\���̗R���Ɖ̎�/p93
��A�͂��߂�/p93
��A���v�u�ɂ����錻��/p94
�O�A���v�u�ւ̓`��/p98
�l���قƂȂ����|�\�s�ۂ����сt�Ƃ̊W/p99
�Y�t�����\���v�u�s�L���[�_���t�̎��W/p103
5 �L���[�_���ƃ}���J�C�\�����s�ׂ��畑���/p113
��A�͂��߂�/p113
��V���\����g����/p114
�O��哇�Ƃ̐ړ_�\��X�������R/p127
�l��哇�̃}���J�C�\���䉻�ւ̓��̂�/p131
�ܤ�����s�ׂ��畑��w�\���V���Ƒ哇�̑Δ�/p142
II �E���T
1����킳(�S�V�b�v)�̣�̎��Ӂ\�̂����т̎��Ⴉ��/p147
��A�͂��߂�/p147
��p�[�t�H�[�}���X�̏�=�̂�����/p148
�O�A����/p150
�l�A�l�@/p156
2 �ِl�Ɖ́\����킳�̣���߂���l�X/p161
��A�͂��߂�/p161
��A��O�̌ØV�͌��/p162
�O��s���傤�����t�s�悽�������t�s���邾��ǁt�̘A����/p168 |
3 �����́��������V�X�e�����\����킳�̣�̊T�O���ƓW�J/p173
��A�͂��߂�/p173
���킳�̍\����̏����/p174
�O�A�����哇�ł̓W�J/p184
�l������Ɂ\�����ʂ̗̉w�j�ւ̎��p/p188
III ��
1 ���Ɖ̊|���̖������\�V�}��ԂƉ�/p195
��A�͂��߂�/p195
��̂Ɛ����̕���\�V�}(�W��)/p196
�O������̋��\�}�u��(��)�����鎞/p203
�l��g�D�M(�d�a�l���Ԃ߂�̊|��)/p207
�ܤ�����o�`(����)�Ƃ̉̊|��/p216
�Z�A�T�J��(�p�̉�)/p219
�����������Α��w�\�����̌��ς��Ӗ��������/p222
2 ���V���̑��́\�����̥����̂̌���/p227
��A�͂��߂�/p227
��A���̂̎���/p228
�O�A�l�@/p243
3 �V�}�E�^�����̈�ߒ��\�s�₪�ܐ߁t�Ɓs����߁t�̊�/p251
�ꤓ��V���̑��̌Q�̈ʒu�Â�/p251
��s�₪�ܐ߁t�\�̊|���ւ̓]���_/p255
�O�A�s����߁t�\���̑��`��/p265
�l��s�₪�ܐ߁t����s����߁t�w
�@�@���\�l�̉̂����ʓI�Ȣ�����щ̣��/p272
�ܤ�����ʂ̢�r�̣݉�Ƃ����W������/p278
4 ���i�Ǖ����́s�O��(�~���u�`)�t�\�V��Ɖ�/p285
�꤉̂���R���e�L�X�g(����)�\�O�\�O�N��/p285
��V��̉ߒ��\�����o�ƌl�z�̎O�\�O�N������/p287
�O��̂�ꂽ�e�L�X�g(�̎�)/p297
�l�����̔O���̂Ƃ̊֘A�\���͖ʂ���/p304
5 �`�����_���[�̉e�\�����ʂ̔O���̂Ɖ���/p313
��A�͂��߂�/p313
��A�����ʂ̔O���̊T��/p314
�O����i�Ǖ����́s�O���t�̌n���\���y�I���ʂ���/p319
�l������ɂ�����O���|�\�̓W�J/p322
�ܤ�����Ɂ\�`�����_���[�̉e/p331
�I��/p339
l �Ζʕ����̃��^�t�@�[�Ƃ��Ắu�̊|���v/p339
2 �Z���^�̗w�̐����Ɨl��/p340
3 �����ʂ̍L��Ȃɂ���/p343
���p�E�Q�l�����ꗗ/p346
���o�ꗗ/p354
���Ƃ���/p357
����/p1
�E |
���A���̔N�A�����ς����m�_�� �u���������ɂ�����W���̋�ԍ\�������Ɋւ���n���w�I�����v�\����B�@pid/3140846
|
��1�� �͂��߂Ɂ\���̏���/p001
��2�� ���������̃~�N���R�X���X�Ƃ��Ă̏W�����/p005
��1�� �p��̌���/p005
��2�� ���������̃~�N���R�X���X�Ƃ��Ă̏W�����/p007
(1)���������̏W��/p007
(2)������G�̏W���_/p008
(3)��������̏W����Ԙ_/p011
��3�� �y�n���x�̕ϑJ�ƏW���̋�ԍ\��/p016
��1�߂͂��߂�/p016
��2�� �n���쓇�n����W���̊T�v/p017
��3�� �n�����ƒn���g/p021
��4�� �n���g�̉��/P026
��5�� �n���g�̑g������/p040
(1)�����c�̔��k�n�����\�k�n�z���䗦�Ɗւ���ā\/p040
(2)�n����/p041
(3)������/p045
��6�� �W���ړ��ƏW���̋�ԍ\��/p046
(1)���W��(�}�L��)�Ƃ��̈ړ�/p046 |
(2)�n���g�̑g��/p047
(3)���n����W���̌`��/p050
��4�� ���n��q���ƏW���̋�ԍ\��/p057
��1�� �͂��߂�/p057
��2�� ���NJԓ����NJԏW���̊T�v/p057
��3�� �W����Ԃ̍\���v�f/p060
(1)�����(�|�[�O)/p060
(2)���n�Ɣq��:���Ќܛԣ�ƃT�g�D�K��/p066
(3)�s���g�D�̕ϑJ�ƍs���n��敪/p076
(4)�������J�Ƃ��̉��/p083
��4�� �W����Ԃ̍\�������ƕ��ʊ�/p089
(1)�ے��I�_�Ɋւ���/p089
(2)���ʊ�/p091
(3)�W����Ԃ̍\������/p093
��5�� ���������̏W����ԁ\���_/p099
�Q�l����/p106
��_I ���������̔����s���ɂ��ā\���̕��z�ƕϑJ�\/p110
��_II �ŋ߂̕��������ɂ���/p134 |
���A���̔N�H�A�n�����B�e�E�ҏW�u�`�����_���[ : �|�\�̌n�� 1,2 �v ���u�i���ꌧ�����S�k�J���j�n����� �v���犧�s�����B�@�@�r�f�I�J�Z�b�g 2���@�@���j�@���s�N���m�F�v�@�@�Q�O�Q�R�E�T�E�T�@�ۍ�
�@�@�@�@1�@��1��s�|�\�� ����7�N9��24�� ����s����ّ�z�[���@
�@�@�@�@2�@��2��s�|�\�� ����8�N10��27�� ����s����ّ�z�[�� �@
|
| 1998 |
10 |
�E |
�P���A�n�v�n�����u�n��J�� (�ʍ� 400) p.52�`54�@���{�n��J���Z���^�[�v�Ɂu�����߂���(4)�k���O���W�}�̗Βn�ۑS--�g�Ɗԓ��𗷂��āv�\����B
�P���A�����j�������ّ�w�l���w��ҁu�����ٕ��{ = The journal of cultural sciences (�ʍ� 552) p.1005�`1020�@�@�����ّ�w�l���w��v�Ɂu����E�L���鑺�́u�����ߗR���v�v�\����B�@�@
�R���A�u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (22/23)�v���u���{�������y�w��v���犧�s�����B�@�@�@pid/4427631
|
�_�� 1.���s�J�̎�ނƉ��� / �������v/p1�`8
�_�� 2.���ׂ����ɂ�����s�m�艹�̉����I���� / ���N�q/p9�`17
������ 1.�B�����߂̗R�� / �ߓ���/p18�`23
��11����u�������y�����̌�--���˂���_�Ƃ��āv(1997)/24�`68
�@ 1.�u���v�| (1)�n�C���߂̓`�d�ƕϗe / �������q/p24�`27
�@ 1.�u���v�| (2)�؍������猩���ؓ����������̌�--�����̕����l�ފw / ���g��/p28�`30
�@ 2.�V���|�W�E�� �������y�����̌�--���˂���_�Ƃ��� / ���ь��]/p31�`39
�@ 3.���E���h�e�[�u�� (1)��B�ɂ����閯�����y�̌� / �㐼���q ;���ь��]/p40~49
�@ 3.���E���h�e�[�u�� (2)���y����ɂ����閯�����y�̈ʒu�t�� / ���c���/p50�`58
�@ 4.�������\�v�| / �����x���q/p59�`68
������(1997) //p69~69 |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 10 �v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
�Ì����̂��炵 ��꒩�v p.1-35
�Ì��̏W���Ɣ��d�R�̑��D ����܂��q p.37-46
�Ì��̃v�[���B�̍��J�Ɖ̗w �g�Ɗԉi�g p.47-111
�Ì��̌���ՂƋ��� �g�Ɗԉi�g p.113-165
�Ì��̌���� ���{ p.167-180 |
�Ì��̓`�������|�\ �X�c���� p.181-260
�Ì��̉��� ��꒩�v p.261-263
�Ì������̊�b��b �����H�^�s 1 p.265-320
�u���\���Ì��̓`�������̒��������v��
�@�@���I����ɂ������� �g�Ɗԉi�g p.321-324 |
�R���A���ꍑ�ۑ�w���J�u���ψ���ҏW�u�쓇�����ւ̗U���v���u���ꍑ�ۑ�w���J�u���ψ���v���犧�s�����B
�@�@ (���ꍑ�ۑ�w���J�u��, 7)
|
�쓇�����ւ̗U�� : �쓇�����Ƃ͉����E
�@�@���͍����猩������ƃA�W�A / �g���E�v [��]
�쓇����Љ�_�ւ̗U��: ���㉫��̋��F��Љ�/�Ό�����[��]
�쓇�l�Êw�ւ̗U��: ����̃��[�c / �c���k�� [��]
�쓇�ߐ��j�ւ̗U�� : ���{�̒��ٍ̈� / ���n�N�v [��]
�쓇�����@���ւ̗U��: �쓇�̑c����J / ���~�ߎ� [��]
�쓇�����l�ފw�ւ̗U��: �������痈�������v�z/ �F�� [��]
�����Љ�ɂ�����u�������v������l�@ / ���N�� [��] |
���������ւ̗U�� : ���������̒n�搫 / �����H�^�s��
�����E�Љ�����w�ւ̗U�� : ����̎�Ҍ��t�l/�쌴�O�` [��]
���ꖯ�b�ւ̗U�� : �L�W���i�[�ƃJ�b�p / �������� [��]
�������w�ւ̗U�� : �w�����낻�����x�̖��� / �Î芡��ߎq [��]
���ꖯ�����y�ւ̗U��:�_�̂���I�L�i�����E�|�b�v�X�܂�/��Éx�q[��]
�쓇�����|�\�ւ̗U��:�Ղ�⑺�V�тɏo������x��_�E
�@�@�����K�_ / �X�۞Ď��Y [��]
�E |
�R���A�O�Ԑ��K,�����r�͂��u���ꌧ�������ًI�v �f�ڊ� (24)�v�Ɂu���ꌧ�������ّ��n���ɂ����镶�������W�Ƃ��̔w�i�v�\����B�@�d�v
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
7�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1002756292�@
|
�쓇�̊�w�����ƒÌ����̖���(��)
�@�@��-���K�_�ƃJ�[�̗R��杂𒆐S��- �R�c����
�쓇�̕��������ƍ^�����b �㓡��
�����q��ǂ�(�V�����S������ӎ�)-����g�x��m�[�g3- �������V |
�ߐ������̗� ���_���̎l-��ʂ̎����ƕ�- ���c�I��u
���] �R�����꒘�w����̖������Ƃ܂��Ȃ�
�@�@��-�t�[�t�_(���D)�̌���-�x �啽��
�E |
�R���A������q���u������w����w���I�v�@��ꕔ�E��� (52) p.121-128�@������w����w���v�Ɂu������ɂ�����}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ�����
: �������x�u�J�`���[�V�[�v�̌��ʂɊւ��錤���v�\����B
|
������q���u�������x�u�J�`���[�V�[�v�̌��ʂɊւ��錤���v�֘A�ɂ��Ă̘_���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
�S�g��w 35(5) p.p375�`380 |
1995-06 |
�}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ����ʂɂ���--
�������x�J�`���[�V�[�̌��ʂɊւ���S�g��w�I���� |
| 2 |
�����q�� 62(6) p.319�`327 |
1996-11 |
�}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ�����--
�������x�u�J�`���[�V�[�v�̌��ʂɊւ��錤�� |
| 3 |
������w����w���I�v��ꕔ�E��� �@(52) p.121-128 |
1998-03 |
������ɂ�����}�e���|���y�ɔ������R�����I���x�̋C���ɋy�ڂ����� :
�������x�u�J�`���[�V�[�v�̌��ʂɊւ��錤�� |
|
�S���A�n�������ďC,�_�k���������U����ҁu�_�k�̐��E�A���̋Z�p�ƕ��� 5 (�����ʂ̔_�k����)�v���u�喾���v���犧�s�����B
|
�����̂��Ƃ�
���F�����ʂ̔_�k�����@��ё��ǁ@�P
�T�[�P�@���������ɂ�����ߐ��[
�@���������̃C�l�͔|�̕ϗe�ߒ��@���іC�v���N��@�P�O�[�S�Q
�T�[�P�@�P�@��G�̕ω��@�P�P
�T�[�P�@�Q�@��G�̕ω��̔w�i�@�P�X
�T�[�P�@�R�@�i��̌��@�Q�T
�T�[�P�@�S�@�ނ��тɂ����ā@�R�T
�T�[�Q�@�쐼�����̓������߂����ā@�|��b���q�@�S�R�[�T�T
�T�[�Q�@�P�@����̓����i��������j�@�S�R
�T�[�Q�@�Q�@���������̓����i��������j�@�S�W
�T�[�Q�@�R�@�������@�ɂ�����쐼�����^�@�T�O
�T�[�Q�@�S�@�u�쐼�����^�v�̓����̐����ƕ��z�@�T�Q
�T�[�Q�@�T�@�����Ɂ@�T�R
�T�[�R�@���{�̔��̎�d���V��@��������@�T�U�[�W�Q
�T�[�R�@�P�@���{�̔�����q�Ƌv�����@�T�V
�T�[�R�@�Q�@�v�����̔�����q�@�T�X
�T�[�R�@�R�@�v�����̔���V��̌Ñw�@�U�Q
�T�[�R�@�S�@���ɗ��̖�l�Ɣ�����q�@�U�T
�T�[�R�@�T�@������q�̓��̕Ď�q�@�U�W |
�T�[�R�@�U�@���{�́q�Гc�E�e�\�r�@�V�P
�T�[�R�@�V�@�_�k�̐V�N�V��@�V�T
�T�[�S�@���\���̃T�g�C���� �@
�@�@�����̓`���I�͔|�@�Ɨ��p�@�@���k�V�n�@�W�R�[�P�O�V
�T�[�S�@�P�@���\���̊T���ƌ����̕��@�@�W�S
�T�[�S�@�Q�@��E�i��̓���ƍ͔|�@�̊ώ@�@�W�U
�T�[�S�@�R�@���\���E�����E���p�@�̕����Ƃ�@�W�X
�T�[�S�@�S�@�ώ@�ƕ����Ƃ���߂����̖��_�ɂ��ā@�X�W
�T�[�S�@�T�@�c���ꂽ���_�ƍ���̓W�]�@�P�O�Q
�T�[�T�@���\���̐��c���� �@
�@�@�����c�̐��ݗ͂Ɋւ���ꌤ���@�����m�@�P�O�W�[�P�S�X
�T�[�T�@�P�@���\���E�c�[�̊T�ρ@�P�O�X
�T�[�T�@�Q�@���c�̂���� �@�����̏�Ƃ��Ă̐��c���@�P�P�T
�T�[�T�@�R�@���c�����̂�����@�P�Q�T
�T�[�T�@�S�@���\���ɂ����鐅�c�����̓����@�P�S�O
�T�[�T�@�T�@�����Ɂ@�P�S�T
�T�[�U�@��p�A�~���̐��c���@���R���v�@�P�T�O�[�P�V�O
�T�[�U�@�P�@�A�~���̐��c���̊T���@�P�T�R
�T�[�U�@�Q�@�A�~���ɂ݂��p�ݗ��̐��c���@�P�T�V
�T�[�U�@�R�@�܂Ƃ߁@�P�U�V |
�U���A�q�B�Y�ďC �u�Ԃ��̂����� : ���O�ƂƂ��ɕ��ܒ���l�v���u(���s)������o�Łv���犧�s�����B
�@�@�t:�ܒ��݂����s���C���X�g�}�b�v(1��)�@�@�t������:�^���f�B�X�N(1�� 8cm)�@�@�@�@120�Ł@�Q�O�O�O�~
|
��P�́@�q�B�Y�~��[���g�X�y�V�����C���^�r���[
��Q�́@�ܒ���l�ւ̎v��
�@�@�ܒ���l�`�i�M�����Ǖ��j
�@�@�ܒ���l�Ƃ̏o��i�q�B�Y�j |
�@�ܒ���l�ɂ�������āi��[���g�j
�@�ܒ���l�ƌ|�\�i�O�c�����j�j
��R�́@�ܒ��݂����s��
�E |
�V���A�����J����q,�Y�R���ꂪ�u�w�p�u���[�T�W. E-2, ���z�v��II, �Z���E�Z��n, �_���v��, ����i1998�jp.379-380�v�Ɂu�|�x���̏W���`���ߒ� : ���̈ړ��ƌ�Ԃ̎��q���z�v�\����B
�V���A��g���X�ҁu���w 9(3)�@���W �������w�̒����Ƌߐ�;�����̎����w���v���u��g���X�v���犧�s�����B�@�d�v
|
�����̎����w p.112�`127
�Ԗؕ��� �����K�� p.112�`114
�Ί_�s�����d�R������ �����ߎq p.115�`117
���ƕ����ɂ��� �c���^�V p.118�`120 |
�ɔg���Q���� ��ӑ��Y p.120�`122
�n���C��w�̃z�[���[���� �Î芡��ߎq p.123�`125
���q�F���Y���W�߂�����W�������� �g�Ɗԉi�g p.125�`127
�E |
�X���A����ƍO�����{����w��ҁu����� = The study for mingu (118) p83�`87�@���{����w��v�Ɂu�w���{����T�x��ǂ��--����̖���̓��F�v�\����B�@pid/7955958
�P�O���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (52)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@pid/4419259�@�@�d�v
|
�u�쓇�j�w�v���ژ^--�t ���E���ጤ����ꗗ/1�`114
�u�쓇�j�w�v���ژ^�̊��s�ɂ��� / ��ɏ�ꗲ/p1�`2
�u�쓇�j�w�v���ژ^(�n�����`��\�ꍆ) / �����/p3�`35
�u�쓇�\���̗��j�ƕ����\�v���ژ^(�����`��܍�)/p36�`40
�쓇�j�w����(����`���\�Z��)--�������\�E
�@�@�����J�u�����ꗗ/p41�`65 |
�쓇�j�w��ጤ����(����`��S���\���)�ꗗ/p66�`88
�쓇�j�w��/p89~90
���̌ږ�E�]�c��/p91~92
�쓇�j�w���ژ^�l������/p93�`114
�E
�E |
�P�O���A�X�۞Ď��Y�F�ďC�u�G�C�T�[�v���u���ꌧ ���ꌧ���������������ۋǕ����U���ہv���犧�s�����B�@
�@�@�@���̔N�AEISA(�p���)�@���{���M ; ���c�ėY�ҏW�@��攭�s: ���ꌧ���������������ۋǕ����U����
�@�@�@���@���{��Ł^�p��ł������Ɋ��s���ꂽ���ɂ��Ă͖��m�F�@�@�Q�O�P�R�E�R�E�R�@�ۍ�
���A���̔N�A���K�炪�u�������Љ�ɂ����鋙���Љ�̖����ω��Ə����̖����v���u�哌������w�v���犧�s����B�@
���A���̔N�A����m�q���u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (�ʍ� 18) p.77�`92�v�Ɂu���̃G�C�T�[�Ղ�Ɋւ����l�@--������܂�̉�ɂ���������v�\����B
���A���̔N�A���{���炪�u���{�̈�w��� 49(0) p.677�v�Ɂu���̉���ɂ�����G�C�T�[�̓W�J : �u�݂�/�݂���v�������x�̕��y(�X�|�[�c�l�ފw)�@�v�\����B�@�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A����s��敔���a�����U���ەҏW�u�G�C�T�[360�x : ���j�ƌ��݁v���u����S���G�C�T�[�܂���s�ψ���v���犧�s�����B |
| 1999 |
11 |
�E |
�P���A�u�Ă����ʂӂ� : ���z�̎q : ����E���S�@for kids�@�v���u���y�Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@68p
|
�m�ԕz�i���傤�Ӂj�@�쎌�E�g�����@��ȁE���v���P�E�@2
�ԁ@�쎌�E��[���g�@��ȁE��[���g�@5
���Ƃ����є��@�쎌�E�������F�@��ȁE�������F�@8
�^���|�|�@�쎌�E�떓�ɋv�E���X���q�@��ȁE�吼�i�@14
����ǂ��̉ԁ@�쎌�E����h���@��ȁE�{�ǒ���@16
���B���B�@�쎌�E��c�p���@��ȁE�m����j�@18
�Ă����ʂӂ��@�쎌�E�{�邿���@��ȁE�������@21
�Ă����ʉԁ@�{���̂��ׂ����@24
����@�ߔe�̂��ׂ����@26
����ʂ����イ�����@�쎌�E����C�u�@��ȁE�O�c�M��@28
�������i�����Ƃ�j��@���d�R�̖��w�@30 |
�ԓc�a���i����������ǂ��j�@�n���̂��ׂ���33
�O���߁i�݂ނ�Ԃ��j�@�{���̂��ׂ����@36
���ނ�����@�쎌�E���l�T�E���c���@��ȁE���l�T�@38
���D�i�Ƃ�����j�h�[�C�[�Ă��[�@�{���̖��w�@41
�O���[�h�A�b�v�o�[�W����
�m�ԕz�i���傤�Ӂj�@�쎌�E�g�����@��ȁE���v���P�E�@44
�ԁ@�쎌�E��[���g�@��ȁE��[���g�@48
���Ƃ����є��@�쎌�E�������F�@��ȁE�������F�@52
�Ă����ʉԁ@�{���̂��ׂ����@59
�ԓc�a���i����������ǂ��j�@�n���̂��ׂ����@62
����ǂ��̉ԁ@�쎌�E����h���@��ȁE�{�ǒ���@66 |
�P���A�v���c�W���u����w�����. MUS,[���y���Ȋw]30 �v�Ɂu���ꉹ�y�����̌��� : �������y�E�|�s�����[���y�𒆐S�Ɂv�\����B�@
�R���A�u���w��j�Ս֏���: �������ƕ� ���@�����E�����ҁ@(�m�O��������������
; ��8�W)�v���u�m�O������ψ���v���犧�s�����B�@134p
|
��T�� �֏��Ԃ̊T�v
1 ��Ղ̈ʒu�Ɗ�
2 �j�Վw��̌o��
�U ���@�����̐���
1 �����̊T�v
2 ��\ |
3 �w��
4 �o�y�╨
5 �O�ɗ��̈ꊇ�╨
�V �֘A���w�����̐���
1 �֏��Ԃ̐A��
2 �֏��Ԃ̍��J |
3 �֏��ԎO�ɗ��̐���
�W �����̂܂Ƃ�
[�ق�]
�E
�E
�E |
�R���A <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 8�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003499348
|
���d�R��l����꜖̍��ɂ��� �R�� ����^�� ������w����
�ߐ������ɂ����铂�D�̑��}�̐��@�[�v�ē��̎���𒆐S�Ɂ[ �[�V �H�l�^��
���ꌧ�����U����j���ҏW��
���J�V���|�W�E�� �쓇�̌|�\�ƐM�E�V�}(�W��)�̃R�X�����W�[ -�������V���A���a���W���̎���-
���R ���G�^
�@�@����u�� ���c �����v�^�p�l���X�g �R�` �F�v�^�J��A ���� ���V�^�R�����e�[�^
�㓡 ���^�i��
�ߐ������̗� ���_���̌� -�I���ʏ����{
�Ƌv�đ��- ���c �I��u�^�� �{�w���� |
�R���A�u�쓇���� (�ʍ� 21)�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
|
��p�䓌�����|���Ս̏W�̋��n�^�Ε����@�@���{�L�q,�v���O p.1�`10
�����s�̐̉� 6 ���ׂ��� ���@���{�M�v p.11�`44
�Ó��{�̋��Ƃ��Ă̗���-���c���j�Ɖ��ꌤ���̘g�g�݁@���Ô� �� p.45�`173 |
�v�����̓��K�~���[�N�j�̉̌��@�@���R�� p.1�`5�@ p.�E1-5
�v�����̍��J�g�D�̕ϗe : ���̌�@���R�� p.�E6-7
�E |
�R���A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu�n�挤���V���[�Y No.26�@�{�ÁA���ǎs������4�@�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�@76p �@�@�����F���ꌧ���}���فF1002864963
|
���ǎs�̌o�ςƔ_�Ƃ̓��v���z ���� �גj
���ǎs�̍������z �n�� ���� |
�{�Ó������̌����قɂ�����̗w�F�u���~���[�k���V�L�_�~�̋V���� �㌴ �F�O
�E |
�R���A�u�n�挤���V���[�YNo.27�u���d�R�A�|�x��������(1)�v�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�iIRDB�j
|
�|�x���E���l���E�����̒n���I�T�ρ@�@���� �� p1-8
���d�R�|�x�����l�����̏���(1)�@�@�쌴�O�` p9-24 |
�|�x�O��(�|�x�E���l�E����)�̌o�ςƔ_�Ɓ@���ԑגjp 25-38
���l���̎�q���Ղ̋V��Ɖ̗w�@�@�g�Ɗԉi�g �@p39-86 |
�R���A�u�B������ (7)�v���u�A�W�A�B���������v���犧�s�����B�@�@pid/4427499
|
�u�X�����L�v�Ɓu���Q�L�v / �P�c�r�ܘY/p1�`6
�Δn�̍r�_ / ���c�[��/p7~30
�u�S�̋S�v�l / ���ш�b/p31~57
����ƕ������߂�����(1) / �q�c����/p59�`75 |
�|���w�_���c�@��`�L�x(4) / ��[��/p77�`85
�����̎j�Փ_�`--���㔪�N�ăC�X���G���E�p���X�`�i���s�L(1) / ��[��/p87�`99
���Љ �S���|�x����������� �w���ꌧ�|�x����
�@�@����q��Ց�{�W�|�\�̌����i�x / ��[��/p101�`105 |
�R���A�X�c�^�炪���m�_���u����ɂ�����i�Վ҂ƍ��J�g�D�̖����w�I�����v�\����B�@pid/3154139
|
�_���v�|/p1
�ڎ�/p1
����/p1
1 �_���̖ړI�ƕ��@/p1
2 ����Љ�̓���/p7
3 ����e�n��̏@���I���E�̓����ƌ����j/p14
4 �@���I�E�\�Ҍ����̖��_�`�i�Վ҂ƛގ�/p44
��I�� �u�v�����̎i�Վ҂ƍ��J�g�D�v/p56
��1�� �����n�̊��ƎЉ�/p56
1 �v���������j/p56
2 �n���I�T�v/P60
3 ���Ƃƒn����/p67
4 ���j�I�w�i�ƌ܍��N�����b�`
�@�@���������{�Ƃ̊W/p72
5 �ƂƖ咆�`���n�ӎ��Ɩ咆�̗�����/p77
��2�� ���J�g�D�̏���/p83
1 �m���ƃN�j�K�~/p83
2 ���g�D�K�~�ƃE�������O���[/p88
3 �������J�W�c�ƃC�U�C�z�[/p94
4 ���J�g�D�̒��̒j���Ɛ_��/p105
��3�� �_���Ƃ��̋@�\/P110
1 �l���J�ɂ�����E�������O���[��
�@�@�����^�̖���/p110
2 �ƍ��J�ɂ�����咆�ƃE�������O���[�̊W/p122
3 �咆���J�Ɛ�c��/p133 |
4 �������J�ɂ�����_����
�@�@���ʒu�ƍ��J�̉���/p140
��4�� �_���̌p���Ɛ��E��/p153
1 �n�c�_�b�Ɛ_���Ɩ咆/p153
2 �_���̌p���Ɛ���/p160
3 �_���̐��i�E���މߒ�/p174
4 �_���̐�����/p182
5 ���E�ς̋��L�Ɗ����`
�@�@���_���̒m���̝h�R��/p192
��5�� �v��/p197
1 ���e�v��/p197
2 �v�����̐_���ƍ��J�g�D�̓���/p201
��II�� �u�|�x���̎i�Վ҂�
�@�@�����J�g�D�v/p204
��1�� �����n�̊��ƎЉ�/p204
1 �|�x�������j/p204
2 �n���I�T�v/P207
3 ���j�I�T�v/p213
4 ���ƂƊό����̗���/p215
��2�� ��ԋA���W�c�ƍ��J/p220
1 ��ԂƐ_�b/p220
2 ��ԂƋA���W�c/p226
3 ��ԋA���W�c�Ƒ������J/p230
4 ��q���Ղƌ|�\/p235
��3�� �_���̌p���Ƌ@�\/p247 |
1 �_���ƌ��/p247
2 �_���̌p��/p253
3 �_���̐��i�E���މߒ�/p262
4 �l���J�Ɛ_���̛ގҐ�/p270
5 �������J�Ɛ_���̖���/p277
��4�� �v��/p287
1 ���e�v��/p287
2 �|�x���̐_����
�@�@�����J�g�D�̓���/p291
�I��/p295
1 ��r����/p295
2 ���_�`�i�Վ҂ƛގ҂̖��/p301
3 ����̉ۑ�ƓW�]/p311
������/p317
I-(1)�v�����̉����Ɩ咆/p317
I-(2)�v�����̔N�����J/p321
I-(3)�v������
�@�@���܍��N�����b�̔�r/p323
I-(4)�v�����̎ʐ^/p328
II-(1)�|�x���̔N�����J/p331
II-(2)�|�x���̎�q���Ղ̌|�\/p333
II-(3)�|�x���̎ʐ^/p335
��/p337
�����ژ^/p358
���Ƃ���/p374 |
�S���A�����ɒj�ďC,�����Y, �����F��, �n�ڏ���ҁu�}�����킫�̗��j�v���u���y�o�ŎЁv���犧�s�����B (�������̗��j�V���[�Y)
|
�}�����킫�̗��j
�ڎ�
�J���[���G�@1
�����@<�����ɒj>�@17
���Ί�E�ꕶ����
�X�͊��̃L�����v�����@�唨���K�n�_�E�֎R��Ձ@26
�ŌÂ̏Z���ՂƍL��𗬁@�R�ԕ��̒|�V����Ղ�
�@�@���C�ݕ��̗��厛��Ձ@28
�C�݂ɉԍ炭�L�˕����@���L�̐��Y�Ǝ����̊L�ˌQ�@30
�����Z�p�����������������@
�@�@���C�������ߊl���߂������唨�E���e�̊L�ˁ@32
�u�˒n�̓ꕶ�l�̐����@��Z�Ə���̈��J��Ձ@34
�R�����@���킫�̎��p��������@36
�퐶�E�Õ�����
���c�_�k�̎n�܂�@�ԏ��n��Ձ@38
�����{�ő�̖퐶��Ձ@���E����Ձ@40
�퐶����̂ނ�Ɛ����@���厛���Ձ@42
�O����~���̏o���@�E�������ƋʎR�Õ��@44
���F�ɋP�������i�@�K���̒��؍������Õ��Ɖ����@46
�Õ���������ւ̃i�]�@�_�J���Z�ꍆ�Õ��̏��Q�@48
�Õ�����̍������@�@�ܕ�A��ՁE����B��Ղ�
�@�@���������҈�ՁE�[�����҈�Ձ@50
�掺���ʂ鑕�������@�Ԕ��̒��c�����Ɛ����̊ڎR�����@52
�R�����@�W�c��@54
�ޗǁE��������
�؊Ȃ͌��@�r�c�ڏ𗢈�Ձ@56
�֏�S�ƂƌS���@���݈�ՁE�Ĉ�p���Ձ@58
�������œ�[�̌S�Ɓ@�e���S�Ɣ��̌S��Ձ@60
�Ñ�_���̐����@��m����Ձ@62
���߉��̓y�n���x�@�r�c�ڏ𗢂̒n���@64
�Ñ�֏�̍����@�֏�b�Ɖ��쎮���Ё@66
�o�˂ɍ��߂�ꂽ�肢�@��m���o�˂��@��@68
���@�v�z�̐���@��������ɓ��Ƌ���@70
�R�����@�z��Ñ㊯����ǂ��@�ܗ��u�˒n�̌Ó��Ƌe��?�@72
���q�E��k���E�����E�퍑����
���B�����ƍD�����̐����@�і씪���{�̑��c�Ɣі�ƕ����@74
���q���{�Ɗ�鎁�@��鎁�ꑰ�̐����@76
��Ɛl�Ƒ��X�@���������E���{�����@78
�^�������̔ɉh�@�T�ӂƔ�@80
���q���������h����@��u�P���̏o�łƑ����@82
��莁�̓����@���J���\��ʊω������̑ٓ����@84
�і씪���{�̍H�|�i�@��㓁�E�튊���E�����@86
��y�@���z�h�̕z���@�@�����ƗǎR��l�@88
��k�������N����@�ɉꎁ�ƍ������̓����@90
�������{�Ɗ�鎁�@�C���܌S�Ꝅ�@92
����ɂȂ���^���@�̔��W�@��闲���Ɩ��̍Č��@94
��y�@���z�h�̔��W�@��̎��Ǒ��l�Ɩ��@96
�R�x�M�̔ɉh�@�F��O�R�ƉH���R�@98
���Ƃ̖{��Ə鉺���@���y�قƔі약��@100
���a�F��_�Ђ̍�@�t���c�y�ƕ����@102
��鎁�̗̍��o�c�@�̒n�̊g����͂����鎁�@104
���l�����̓����@�㉓���𒆐S�Ƃ��ā@106
��鎁�ƈɒB���@�v�ەP����@108
�T�@�̔��W�@�T�����Ɨ��厛�@110
�퍑�����ƕ����@���c�㌓�ځE�ᑺ�@112
�G�g�̉��H�d�u�@�L�b�G�g����@114
�^���@�Ə�y�@�̏@�_�@�ܒ���l�̕z�������@116
�R�����@�і씪���{�̍�@���L�n�ƌ��a�@118
�]�ˎ���
���Ƃ̒����Ɠ��쐭���@�F��L�Ƃ̔і약����@120
�֏镽���z���@���������̎x�z�@122
�����Ƃ̓����Ɨ̓��̊J���@���������ƒ����@124
�V�������Â���@�V�c�J���Ǝ��Ё@126
�����Ƃ̍s�����s�ҁ@�����q�ƍ����m���q�@128
���@�̖{�����x�@��y�@���z�h�h�тƐ�̎��@130
��˂̐��ځ@�����E�q�E�{���Ɓ@132
�����J�˂̗��j�@�����Ƃ̌����œ�Z�Z�N�@134
�y���Ƃ̂��ƒf��@�E�c�˂̖ŖS�Ɩ��̌E�c�w���@136 |
���˂���Ă�ⵋȉƁ@�ߐ�ⵋȂ̑c�E�������Z�@138
�]�˔o�~�̗����@�����I���@140
�֏鎵�l�̔ɉh�@���D�ƕߌ~�@142
���鉺�̔��W�@���鉺�G�}�Ɍ��铖���̒��@144
�㉓�잸�����@�a�ꂽ�z�i���q�d�Y���@146
�_���̔敾�@�����̕S���Ꝅ�@148
���̏����l�̑㊯�����@���R�O�L�E�����d���Y�̎��с@150
���̂̑��݁@�I�q�˂Ɗ}�Ԕˁ@152
�����̉��v�𐄐i�@�{�����Ԃ̐��U�@154
�ߎS���ɂ߂������@�V���E�V�ۂ̋Q�ށ@156
����Ă���ЊQ�@�Ôg�E�䕗�E�^���E�`���a�@158
�������������@�R�_�E���_�E���ꑈ���@160
���O�̋~�ρ@�w�m�Ɠc�ɑm�̊���@162
�_�����v�ɐs�������l�X�@���Y�v���E�n�Ӎō��q��E
�@�@���v�ۖؒ�E�q��E�č��o�O�Y�@164
�l�X�����s���@�l�X���G���Ɍ���֏�@166
�o�~�l�b�g���[�N�̃L�[�}���@�����̔o�m�������@168
�֏�̗��j�ƕ������L�^����@��c�O�P�Ƃ��̎��Ӂ@170
�ꐶ�Ɉ�x�̐_�w�Ł@���a�����ƍu���ԁ@172
�w��̕��y�@�֏�O�˂̔ˍZ�Ɗw�ҁ@174
�ΒY�̔����ƍ̌@�@�Њ��Ɖ��[�쎟�Y�@176
�����O���̗����ҁ@�V�������Δn��@178
�R�����@�o�~�̃p�g�����@���Ձ@180
�����E�吳����
�֏�̕�C�푈�@���H�z��˓����Ɣ֏�O�ˁ@182
���{�ŏ��̒��w�Z�@���˂̋��琭��@184
�������{���}���������̂Â���@
�@�@�������E�֑O���E�������Ƒ�E����@186
�V�����v�z�ƒn���̓����@���R�����^���Ƌ����Ё@188
�n�����{���璆�����{�Ƃ̌o�c�ց@�֏�Y�{�Ђ̐ݗ��@190
�ߑ�Y�Ƃ̑c�@�R�蓡���Y�Ɣ��䉓���@192
��������̕����l�@���R�R�E�V�c�����E��{��?���@194
�R����A���@���L�і�����߂��^���@196
�o�ς̐i�W�Ƌ�s�̊J�݁@�ߑ�Y�Ƃ̔��W�𑣂������Z�����@198
��������}�����n�������@�������N�̒������@200
���{�d���֏���E�։z�����̊J�ʁ@�ߑ�Y�Ƃ̔��W�𑣐i�@202
�ߑ㋙�Ƃ̔��M��n�@�����������Y������@204
�ߑ�̔��p�Ƃ����@�`���̓��{��Ɨm��̊J�ԁ@206
�C�̈��S������Ĉ�Z�Z�N�@�����铔��@208
���Ŗ��\�L�̑�@�����O��N�A�ɉ؊X���Ď��@210
�ߑ�H�Ƃ̔��W�@�Z�����g�ƁA���������Ɓ@212
���{����߂������R���j���N���Y�@�_�R���̊����앨�@214
��������̕��y�@�����֏钆�w�Z�ƍ������w�Z�@216
����ƐΒY�@���{����̐����@218
�֗��ɂȂ��������@�d�b�E�d���E��蕨�̕��y�@220
�Y�z�J���҂̉��P�𑣂��@�֒Y���c�ƎR��g�@�@222
���Y�Ƃ̋ߑ�̓��@���߂̉��ǂƊ��g�@224
�_���Ɠ`���|�\�@���˂̓z�s��Ƃ�܂ƕ��@226
�ߑ㎍�̎�������@�R���钹�ƒ��Ԃ����@228
�吳����̕��������@�J�t�F�[�E�o�[�E���X�g�����@230
�����l���`�̌��݁@���F���̊���@232
���ƉƁE�����ʁ@�n��U���ɐs�����@234
���E�ɉH�����@���E����̐��U�@236
�̋�����𗣂�Ċ���@���{�c�h�O�Y�Ƌ��c�����@238
�k�C���J�w�̓����Ƃ����@���떞���̎��Ɓ@240
�R�����@�ߑア�킫�̐����E�o�ϊE���ʂ�@���䉓���@242
���a����
�ΒY�Ƌ��ʼnh����@���키���̏��X�X�@244
�푈�ւ̓�����ށ@�펞���̐����Ɛ�Ё@246
�N���̋���z�͂���@�̎�E�������̐��U�@248
��̉����{�̏k�}�@�������Ɛ���s���@250
�������甭�W�ց@�V�Y�Ɠs�s�w��ƐV�s�a���@252
������ʎ���̖������@��֎����ԓ��Ɣ։z�����ԓ��J�ʁ@254
���w�̐U���ƕ��y�@�u���킫�s������S���L�O���w�فv�̊J�ف@256
�w�}���@���킫�̗��j�x�N�\�@259
���Ƃ����@<�����F��>�@265
��ȎQ�l�����@266
�ʐ^�E��������т����b�ɂȂ������X�@268 |
�V���A�����Y�\�j������ҁu����|�\�j����������\��� : ���J�u���E�������\�v�|�y�уV���|�W�E���E�v���O����
��24��v���u����|�\�j������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1009748169�@�@�T�X��
|
�������E�u�t�Љ� ��� ��i�^[�q]
<���ʌ���>����ŋ��Ƌߑ㉫�� ��� ���Y�^[�q]
<�������\>
���̂̉��߂Ə��x�� ��� �i�~�^[�q]
�����i���ɏ��x��j�ɂ����锏��̑ԗl�ɂ��� ���� ��a�^[�q]
�ǒJ�������l�̑g�x�u�{���啠�v�ɂ��� ���l �^�E�^[�q]
|
�����̌��u��t���v�̍\���ɂ��� �^�ߔe ���q�^[�q]
�g�x�u�萅�̉��v�̉��y���ɂ��� ��� ���v�^[�q]
<���ʍu��>���P���c�Ɖ���ŋ� �� �D�q�^[�q]
<�V���|�W�E��>����ŋ��̌���E�ۑ�E�W�] ���� ���j�^
�@�@��[�p�l���X�g] �ɗǔg ��q�^[�p�l���X�g] ��� ���Y�^[
�@�@���p�l���X�g] �^�ߔe ���q�^[�p�l���X�g] �c�� ��Y�^[�i��] |
�@�@�@���@�������̋L�q�Ȃ������̂Ō����v�@�Q�O�Q�R�E�V�E�Q�T�@�ۍ�
�V���A�R�� ���ꂪ�u�Ñ���{�Ɠ쓇�̌𗬁v���u�g��O���فv���犧�s����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1001474095
|
���� �Ñ�쓇�ւ̖{���̍\��
7���I�̓쓇
���ߍ��ƂƓ쓇 |
�����g�Ɠ쓇�H
�쓇�̍v�i�E���Օ�
�Ñ�쓇�Љ�̊K�w�� |
�Y���������L�ɂ���
�����ƓW�]
���o�ꗗ |
���Ƃ���
����
�E |
�W���A�^�������u��㊂̌ÓT���y�`�����̕��v���u�L���O���R�[�h�v���犧�s�����B
�@�@�@���^�N��: 1997.11, �@���^����: 69��09�b�@ �^���f�B�X�N 1�� : CD
|
(1)�q�V�l�x�r�`������ŕ���(2)�q��O�x�r�`��O���Ă���(3)�q���x�r�`�l�|(4)���`��������(5)���`�V��(6)���`�ɖ�g��(7)���`����
���]�쐰,�ʏ鐳��(��,�O��)�{���G��(�)�Ð����M(�J)���g�^��(�Ӌ|)�����(����) |
�W���A�@�w�������ɂ��x�ҏW�� �ҁu�������ɂ� 10(9)(114)�v���u��C�ُ��X�v���犧�s�����B�@�@pid/4426028
|
����ň����̖������l���Ă݂� / �i���T��/p2�`5
�]��̖���--�V���E
�@�@���Z�������ɂ��ƂÂ�������(2) / ��ё���/p94�`99
���W ���ꕶ���ǖ{ ���A�W�A�̂Ȃ��̉��ꁄ
�@�@��������34�̃L�[���[�h //p15�`83
����̂͂��܂� / ����܂������Ђ� ;���t�� ;
�@�@���n��I�j ;�����i/p16~23
�����̂��Ƃ� //p16~17
�`��l //p18~19
�L�̓� //p20~21
�O�X�N //p22~23
���������̕��� / ���Ǒq�g ;�^�h���[�� ;
�@�@���L���R�a�s/p24~41
�� //p24~25
�����g //p26~27
����(�Ƃ�����) //p28~29
�i�v�D //p30~31
�v�đ�(���߂ނ�) //p32~33
�F���N�U //p34~35
���� //p36~37
�y���[���q //p38~39
�������� //p40~41
�_�X�ƐM�� / �ԗ䐭�M ;�勴�p�� ;�s�z���q/p42~55
�A�}�~�N�E�V�l���N //p42~43
�j���C�J�i�C //p44~45
���(�E�^�L) //p46~47
�~���N //p48~49
�V�� //p50~51
�m���E�c�J�T //p52~53
���^ //p54~55
�����ƏK�� / �O�Y���Y ;�n粋ӗY ;��Ð��v/p56~71
���� //p56~57
�T�b��(���߂�����) //p58~59
�Ί���(��������Ƃ�) //p60~61 |
���q(�V�[�T�[) //p62~63
����(�q���v��) //p64~65
� //p66~67
�T���W���\�[ //p68~69
�咆(�����`���E) //p70~71
���|�ƌ|�\ / �㗢���� ;�r�{����/p72~83
������Ɨ��� //p72~73
�����E���� //p74~75
�́E�O��(�����E�T���V��) //p76~77
���D�|�\ //p78~79
�G�C�T�[ //p80~81
����ŋ� //p82~83
�������ق��̂�����-5-�ς̉�(��) / ��g���q/p6�`9
�`���C�i�ȂЂƂт�--�ߑ���{�̒����-5-�b�x�� / �����L/p10�`13
�A�� �����̂��Ƃ킴(29)��O���X / ��얾����/p14�`14
�A�� �`�������W�I �N���X�����p�Y��(53) / ���������q/p84�`84
�A�� �ɂقœǂފ���(11)�c�Ƃ̏t�] / �ؑ��N��/p85�`85
�N�a�V�H�Y�s-8-���� / �떀����Y/p86�`89
�����̔��w �Z�����l�̌Q��-11-
�@�@�������Ȃĕ����ɕ�������̂݁E�]�� / ���ƗT�q/p90�`93
�A�� ���]�����s(5)���N�s�s�E���� / ���V�v��/p100�`101
�L�^�C���V-29-���̏��A���邢�͖{�̉^�� / ���}��/p102�`105
�����̌o�T��ǂ�-5-
�@�@���w���搶����ȗ��x�쒩�V�t���̉��v/�R�c����/p106�`111
�A�W�A�̕�-65-�؍� �������p�ɂ݂�؍��̕������֓x / ������/p112�`115
�A�W�ANOW ���P���[�h����ς����Ē��W //p116~117
���F���� ���] �R�c�������w�Z�������V�X�̌����x / ���t��/p118�`119
���F���� �����w�őO��(36)[�����N���̍l�Êw] / �����G�T/p122�`123
���F���� �V���Љ� //p120~121
���F���� ���C�u�����[ //p124~125
���F���� �C���t�H���[�V���� //p126�`129
��C�ق̈�� �C��ꗲ���w�n�}�Ɍ�����{�x / �C��ꗲ/p130�`130
��C�ق̈�� ���쌪�w����50�N�̋����Ǝ����x/���쌪��/p131�`131
���G ���]�����s(5)���N�s�s�E���� / ���V�v�� |
�W���A�u����ʐM ����� : �����m��A�W�A��m�� �@��2����8��(�ʊ�17��)�@���W�F���G�C�T�[�v���u�i�ߔe�j�O�Y�N���G�C�e�B�u �v���犧�s�����B
�X���A���v�`���u蔗� : ����w�����ٜb�� 39 p.2-3�v�Ɂu�V�g�M�ƕ��H�����v�\����B�@�iIRDB�j
�P�O���A�w��㊕����x�ҏW���� �u��㊕��� = The Okinawa bunka 35(1)(90)�v���u��㊕�������v���犧�s�����B�@�@pid/4437804
|
���E�Ɍ��Ԃ̗��j--�Ɍ��ԑ��ƏM�z���𒆐S�� / ��������/p1�`51
�c�����O�Y�̉��ꌤ��--���ꎑ���ɂ��� / ꎓ���q/p53�`75
�����̋������l����--�m���̌l���Ɛ�剻�Ƃ������_���� / ��[�q/p77�`96
����v�ē��^�ӕ����̉��C���� / ������/p146�`113
�{�Ñ�_�������̘a��n�����ɂ������� / �v��}���q/p166�`147
|
���s�j���[�X/p52~52
�V���Љ�/p96~96,109~110
��20��u���ꕶ������܁v���\/p97�`108
�E
�E |
10���A�ʏ闬�����݉�g�Ύ}��������ҁu�Ύ}�E��}�q�̉� ��4���i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ闬�����݉�g�Ύ}��������v���犧�s�����B�@20p �@�����F��㊌����}���فF1004685754
�@�@�@�@�@�����F����11�N10��25��(��) �ꏊ�Fabc��كz�[��
�@�@�@�@ ���F1�E2������܂ł̃^�C�g���w�ʏ闬�Đ߉� �Î}�E��}�q�̉�x
�P�O���A���c�W, �r�ؔ��V�ҁu���M�E�ӑm�̓`�����E ��1�W�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B�@
|
���M�`����
���M�Ɖ��E���y�@�w�Ìy�n���̃C�^�R�A�S�~�\�A�����x/���X���p/5�[28
�C�^�R�Օ��u��؎R���L�v�̐���/���c�W/29�[89
�ޏ������I�V���T�}�R��杁w���E�{��̃I�J�~�T���̓`���x/�쓇�G��/90�[105
�K���@���҂����w�������Ɛ����_���܂����߂āx/���C����/106�[135
�䉾���q�u�Ԓ������v�̛ޏ�/�^������q/136�[152
�q�|���r�Δn�̐_�y�Օ��u�S������o�v�i���́j�i�������ꎁ�����j/�q�c����/153�[180
�����ɂ�����_�l�̍��w�V��E�̗w�E�R��杁x/���R��/181�[210
�_���E�ގ҂Ɛ_�b�w����{�Ï�������x/�^����/211�[227
�쓇���w�����̖��w�u�n�i�V�v����u�E�^�v�ւ̕������x/�R���ӈ�/228�[248
�{���u�����N�b�v�Ɓu�S�����b�v/���^��/249�[287
�ӑm�`����
�ӑm�̎n��/�r�ؔ��V/291�[307
�g��{�̖ӑm�`���w�{�茧���P�n�S���ˑ��x/�R���ۖ�/308�[327
��O�ӑm�ƏΘb/�{�n���F/328�[341
�ӑm�̊����\�L�́u�ߕ��v�ɂ���/�����h�g/342�[366
�������̔����i����/���c�@��/367�[384
�R�����n�_�ӑm���������w�����R�Ɩӑm�x/�ɓ��F�}/385�[376
���h�ɗ��̏��쎛�ӑm�j���ɂ���/���J���l/397�[422
�ӑm�����̈Ӌ`�Ɖ\���w���o��Q�҂̗��ꂩ��x/�L���_��Y/423�[437
���Ƃ���//438
|
|
�P�Q���A�떓�b�ꂪ�u���m�_�� �쓇�̗w�̌����v���u���؏��[�v���犧�s����B�@�@pid/3176449
|
���� �����j�Ɩ{���̗���
��A�쓇�̗w�������t��/p3
��A�쓇�̗w�����̋���/p5
�O��쓇�̗w�̌`�Ԃ̌���/p13
�l��쓇�̗w�����̓W�J�Ɣ����_/p19
�܁A�{���̗���ƍ\��/p24
���� �j���C�J�i�C�̓`��
���� ����_�ƃj���C�J�i�C/p35
1 �쓇�ɂ����鎀��̐��E/p35
2 �㐶�ƃj���C�J�i�C/p40
3 �c���̎���ƃA�J�}�^�_/p46
���� ���K����c��/p51
I �O���҂ƃj���C�J�i�C/p51
2 ���~�ɗ��K����A���K�}/p59
3 �_�k���J�ɗ��K����A���K�}/p69
��O�� ���K�_�Ɛ_���̉�/p76
1 �j���C�J�i�C����̗��K�_/p76
2 ���_���̉�/p83
��l�� �j���C�J�i�C�Ƃ��̐��̉���/p85
1 ������ƃj���C�J�i�C/p85
2 �q���̒a���ƃj���C�J�i�C/p90
���� ��Ԃƍ��J�`��
���� ��Ԃ̐_�Ɣ_�k���J/p100
1 �쓇�ɂ������Ԃ̐_/p100
2 �|�x���̌�ԂƔ_�k���J/p107
3 �|�x���̐_�X�ƌ�Ԃ̗R��/p112
���� �|�x���̎�q���/p120
1 �쓇�̎�q���/p120 |
2 ��q��Ղ̍s������/p125
3 ��q��Ղ̌|�\/p131
��O�� �R���`���ƎƉ̗w/p142
1 ��q��Ղ̎R���`��/p142
2 ��q��Ղ̎�/p151
3 ���q�A���[/p155
4 �ƈ��q�A���[�̖`����/p160
5 ���[�N�C�̊�����/p164
��l�� ��q��Ղ̐_���|�\/p172
1 �z���W���[(��)/p172
2 ���Ӑ_/p181
3 �V�h�D�����j/p188
��O�� �쓇�̎Ǝ�
���� �쓇�̎�/p201
1 �Ǝ�/p201
2 �̃N�`/p207
3 �̃^�u�F/p212
4 �����̃����O�g�D�Ɠ����t/p215
5 �����̃T�J��/p221
���� �Ǝ̗l��/p226
1 �j�M�O�`/p226
2 �n�u�O�`/p232
3 �앨�̎Ǝ�/p237
4 �Ό�̎��͂Ǝ���/p241
��O�� �쓇�̎�/p250
1 �ɐ����������q�̏Ƃ�q��/p250
2 �|�x���̊肢��/p255
3 �~�Z�Z���ƃI�^�J�x/p262
|
4 �}�����K�i�V�̐_����
�@�@���z���W���[�̌���/p267
5 �}�����K�i�V���������_��/p273
��l�� �쓇�̕���̗w
���� �����̗w�̏���/p289
1 ���Y�����Ə��s����/p289
2 �_���̏���/p303
���� ����̗w�̏���/p317
1 �a�D�̏����ƕ���̗w/p317
2 ���s�Ƌ����̕���̗w/p330
3 �_���̕���̗w/p337
4 �}�u�i���̕���̗w/p343
5 �s�ς̕���̗w/p352
��O�� ����̗w�̗l��/p360
1 ����̗w�̐l��/p360
2 �q�@���Ȃ�̂��r �̋^�⎫/p367
3 ���d�R�̃����O�g�D�̗l��/p376
�I�� �쓇�̗w�̔���
��A���J�̗w�̔���/p395
��A�Z���`�̗w�̔���/p410
�O�A�u�r���|�̔���/p427
��/p439
���Ƃ���/p475
���o�ꗗ/p481
���^ ��������CD�̎���/p483
����/p1
�E
�E |
�P�Q���A�g�Ɗԉi�g���u�쓇���J�̗w�̌����v���u���q�����[�v���犧�s����B�@�@
(�ʗ����p�� ; 4)
�P�Q���A�ԍ⌛�Y�����w�ٕҁu�n���̐��E (112) �v�Ɂu���c���j�̔����i42�j�@�f��(����4)�ꍑ�����w���z���āv�\����B
|
�ԍ⌛�Y���u�n���̐��E (68�`112) �v���ɔ��\�����u���c���j�̔����i1�`42�j�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N |
�_���� |
pid |
| 1 |
(68)p151�` |
1988-11 |
���c���j�̔����i1�j ����/����̈ť����ɂ� |
pid/1737943 |
| 2 |
(69)p159�` |
1989-02 |
���c���j�̔����i2�j ����/�R�̐��_�j��ŗt��� |
pid/1737944 |
| 3 |
(70)p 153�` |
1989-05 |
���c���j�̔����i3�j ���� �R�̐��_�j����ƕY�� |
pid/1737945 |
| 4 |
(71)p p159�` |
1989-08 |
���c���j�̔����i4�j ���� �R�̐��_�j��V�R�̗� |
pid/1737946 |
| 5 |
(72)p 167�` |
1989-11 |
���c���j�̔����i5�j ���� �R�̐��_�j��R�l���̌� |
pid/1737947 |
| 6 |
(73) p167�` |
1990-02 |
���c���j�̔����i6�j ���� �R�̐��_�j��R�l�̒a�� |
pid/1737948 |
| 7 |
(74) p167�` |
1990-05 |
���c���j�̔����i7�j ���� �R�̐��_�j���̕��i |
pid/1737950 |
| 8 |
(75)p 174�` |
1990-08 |
���c���j�̔����i8�j ���� �R�̐��_�j����n�l�Ə햯 |
pid/1737951 |
| 9 |
(76) p143�` |
1990-11 |
���c���j�̔����i9�j ���� �Y���̐��_�j��A���̛��M |
pid/1737952 |
| 10 |
(77) p166�` |
1991-02 |
���c���j�̔����i10�j ����/�Y���̐��_�j��Y���l�� |
pid/1737954 |
| 11 |
(78) p158�` |
1991-05 |
���c���j�̔����i11�j ����/�Y���̐��_�j��_�̎q��
|
pid/1737955 |
| 12 |
(79) p164�` |
1991-08 |
���c���j�̔����i12�j ����/�Y���̐��_�j����m�ƖіV�� |
pid/1737956 |
| 13 |
(80) p161�` |
1991-11 |
���c���j�̔����i13�j ����/�Y���̐��_�j��Z���̑��v |
pid/1737957 |
| 14 |
(81) p165�` |
1992-02 |
���c���j�̔����i14�j ����/�Y���̐��_�j��c�q����� |
pid/1737958 |
| 15 |
(82)p 157�` |
1992-05 |
���c���j�̔����i15�j ����/�Y���̐��_�j��뗎�����蕔 |
pid/1737959 |
| 16 |
(83) p182�` |
1992-08 |
���c���j�̔����i16�j ����/�Y���̐��_�j��I�V���V�� |
pid/1737960 |
| 17 |
(84)p181�` |
1992-11 |
���c���j�̔����i17�j ����/�Y���̐��_�j��I�V���V��(��) |
pid/1737961 |
| 18 |
(85) p177�` |
1993-02 |
���c���j�̔����i18�j ����/�Y���̐��_�j����]�^���̗� |
pid/1737962 |
| 19 |
(86) p165�` |
1993-05 |
���c���j�̔����i19�j ����/�Y���̐��_�j��Y���ƒ�Z |
pid/1737963 |
| 20 |
(87) p164�` |
1993-08 |
���c���j�̔����i20�j ����/�Y���̐��_�j��Y���ƒ�Z(��) |
pid/1737964 |
| 21 |
(89) p159�` |
1994-02 |
���c���j�̔����i21�j ��O��/�C�̐��_�j��R������ |
pid/1737966 |
| 22 |
(90) p168�` |
1994-05 |
���c���j�̔����i22�j ��O��/�C�̐��_�j����E�̓��� |
pid/1737967 |
| 23 |
(91) p172�` |
1994-08 |
���c���j�̔����i23�j ��O��/�C�̐��_�j����E�̓���(��) |
pid/1737968 |
| 24 |
(92)p 182�` |
1994-11 |
���c���j�̔����i24�j ��O��/�C�̐��_�j��A���ƈږ� |
pid/1737969 |
| 25 |
(93)p181�`202 |
1995-02 |
���c���j�̔����i25�j ��O��/�C�̐��_�j��A���ƈږ�(��) |
pid/1737970 |
| 26 |
(94)p154�` |
1995-05 |
���c���j�̔����i26�j ��O��/�C�̐��_�j��w�����x�̎��� |
pid/1737971 |
| 27 |
(95)p195�` |
1995-08 |
���c���j�̔����i27�j ��O��/�C�̐��_�j��k�ّ̈� |
pid/1737972 |
| 28 |
(96) p167�` |
1995-11 |
���c���j�̔����i28�j ��O��/�C�̐��_�j��k�ّ̈�(��) |
pid/1737973 |
| 29 |
(97) p166�` |
1996-02 |
���c���j�̔����i29�j ��O��/�C�̐��_�j��ꍑ�����w |
pid/1737974 |
| 30 |
(98) p180�` |
1996-02 |
���c���j�̔����i30�j ��O��/�C�̐��_�j��ꍑ�����w(��) |
pid/1737975 |
| 31 |
(99) p168�` |
1996-08 |
���c���j�̔����i31�j ��3��/�C�̐��_�j����N�_��(��) |
pid/1737976 |
| 32 |
(100) p182�` |
1996-11 |
���c���j�̔����i32�j ��3��/�C�̐��_�j����N�_��(��) |
pid/1737977 |
| 33 |
(101) p166�` |
1997-02 |
���c���j�̔����i33�j ��3��/�C�̐��_�j����N�_��(��) |
pid/1737978 |
| 34 |
(102) p188�` |
1997-05 |
���c���j�̔����i34�j ��O��/�C�̐��_�j��ԂƃC�i�E(��) |
pid/1737979 |
| 35 |
(103) p160�` |
1997-08 |
���c���j�̔����i35�j ��3��/�C�̐��_�j��ԂƃC�i�E(��) |
pid/1737980 |
| 36 |
(104) p154�` |
1997-11 |
���c���j�̔����i36�j ��O��/�C�̐��_�j��C��̓�(��) |
pid/1737977 |
| 37 |
(105) p148�` |
1998-02 |
���c���j�̔����i37�j ��O��/�C�̐��_�j��C��̓�(��) |
pid/1737982 |
| 38 |
(106) p184�` |
1998-05 |
���c���j�̔����i38�j ��O��/�C�̐��_�j��⌾ |
pid/1737983 |
| 39 |
(109) p187�` |
1999-02 |
���c���j�̔����i39�j �f��(1)�Ĕ��̂��镗�i |
pid/1737986 |
| 40 |
(110) p164�` |
1999-05 |
���c���j�̔����i40�j �f��(2)�����̃t�H�[�N���A |
pid/1737987 |
| 41 |
(111) p182�` |
1999-08 |
���c���j�̔����i41�j �f��(����3)�������������ړ� |
pid/1737988 |
| 42 |
(112) p97�` |
1999-12 |
���c���j�̔����i42�j�@�f��(����4)�ꍑ�����w���z���� |
pid/1737989 |
|
�P�Q���A�吼�ƗY���u �u�������m���s�E�̒n�v���K�˂� : �s���āE���āE�m���߂ā@�u�b�N���b�g�O���v���u�吼�ƗY�v���犧�s����B�@�@�@�@�@ (��ƌ��V���[�Y 2)�@�@�@���a�K�C�h�����@�@�@39,5p�@�@�@�����F��㊌����}���فF1001486768
|
�u�́E�������m���s�E�̒n�v���K�˂�
�s�c���ƂȂ�F�y���� |
�U��̃X�p�C �W�F�m�T�C�h�E�l�҂����̋��\
���^ |
�u������V���[�Y�U�v�ւ̍l�@
�u��ؔ�Ɋւ���v���� |
���A���̔N�A����~�q���u�N�y���� (�ʍ� 16) p.5�`26�v�Ɂu���ɑ��Â�����|�\�u�G�C�T�[�v--�吳��u�����܂�̉�v�ɂ݂閯������̗��E�v�\����B
���A���̔N�A�X�۞Ď��Y���u�O���̂͂Ȃ��v���u�Ђ邬�Ёv���犧�s����B (�����Ȃ핶��
; 88) |
| 2000 |
12 |
|
�Q���A���c���q���u�{�Ó��떓�̐_�� : ���̌p���Ƒn���v���u�v���t�o�Łv���犧�s����B�@
�@�@283p �@�@�����F��㊌����}���فF1002874566
|
�_���܂�l����
�_�̂��Ȃ炤
�_�̖� |
�_�̍��~
�_�̎v��
���炢�ł��� |
�_�̂̂�����
�_�̂̓`���ƕϗe
�E |
�R���A�u�B������ (8)�v���u�A�W�A�B���������v���犧�s�����B�@�@�@pid/4427500
|
���Đl�̋ߐ��E�ߑ���{�� / �{�蓹��/p1�`42
��S�Ɩҋ�--����Ɖp�� / �P�c�r�ܘY/p43�`44
���]�^��--����G���ƈɐ��R / ����i��/p45�`65
�Δn�ɂ�����Ԃ̐_ / ���c�[��/p67�`87
��O�̉���� / �{�n���F/p89~113
�u����͂��v�l / ���ш�b/p115~160 |
�쓇�̗w�ƋL�I�̗w�̑Ό�Ɣ�g / �떓�b��/p161�`174
��D�� / �����X�q/p175~200
�Z�@���y�����钎 ���q�J�����H���^ / ���c��/p201�`221
���|���w�_���c�@��`�L�x(��) / ��[��/p223�`222
�q�Љ�r �O�ύ_�㒘 �w��������Ɖ����ًL�x / ���ш�b/p233�`240
�E |
|
���Q�l
�|�� ��쌺�����w�_���c�@��`�L�x �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������
(�ʍ� 4) 1996 p.75�`95
�|�� ��쌺�����w�_���c�@��`�L�x(��) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (�ʍ� 5) 1997 p.61�`82
�|���w�_���c�@��`�L�x(3) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (�ʍ� 6) 1998-03 p.83�`97
�|���w�_���c�@��`�L�x(4) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (�ʍ� 7) 1999 p.77�`85
�|���w�_���c�@��`�L�x(5) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (8)
2000 p.223�`232
�|���w�_���c�@��`�L�x(6) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (9)�@2001-3
�@�@�����F���ꌧ���}���ف@���e���m�F
�|�� ��쌺�����w�_���c�@��`�L�x(7) �� �[�� �A�W�A�B�������� �f�ڎ� �B������ (10) 2002 p.235�`242 |
�R���A���R���������ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (�ʍ� 25) p.179�`188�@���ꌧ����ψ���v�Ɂu�����̃I�J���h�J���ނɊւ��閯���I�`���ɂ���(���_)�v�\����B
�R���A�u�n�挤���V���[�Y�@No.28 �@���d�R�A�|�x��������(2)�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�iIRDB�j
|
���d�R�|�x�����l�����̏���(2)�@�@�쌴�O�` p1-16
�|�x���̂��܂ǐ_�M��:���\���𒆐S�Ƃ��ā@�E���� p17-37
�|�x���̎Љ�g�D : ���J����݂��d�w�I�E
�@�@�������I�ȁu�����v�@�ʏ�B p39-74 |
�|�x���ɂ�����ό��̌��́@�����L 75-88
���d�R�Ί_���́u�݂��Ⴎ�p�[�V�B�v�@���{�M�v�@ p86-136
���l���̌×w : �_���ʃJ���U���A�A���[�A�����O�g�D�A�W���}�A�Ƃ�[�����A
�@�@�������^�A�_�[�g�D�[�_�A���ׂ����@���{�M�v p137-174 |
�R���A�Y�R���ꂪ�u���m�_���@���ꔪ�d�R�����̑����M�ɂ�����`���I���J�{�݂̋�ԍ\���Ɋւ��錤��
: ���Ȃ��Ԃ̌`�Ԋw�����v�\����B
�R���A ���c�O�},�����z�q���u�L�����w�@��w�����Ȋw���I�v = Journal of the Faculty for Human Life Science, Hiroshima Jogakuin University / �L�����w�@��w�����Ȋw���I�v�ҏW�ψ��� �� (�ʍ� 7) p.77�`92�v�Ɂu����̔N���s���ƍs���H�Ɋւ��錤��(��2��)�v�\����B
�R���A���ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (26) �v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@�d�v
|
���o��Q�҂ƃ~���[�W�A���A�N�Z�X--����̎��݂��Ƃ����ā@�O�c�^�V p.1�`20
���W���̔ɐB�@�@�^�ߏ�`�t p.21�`26
���ꌧ���ɂ����Ė�O�ώ@�⏝�a���̕ی�y�є����َ����W�{���ɂ��
�@�@���m�F���ꂽ�����[�����ނ̋L�^�ɂ���--�u���ꌧ�Y���ޖژ^�v���
�@�@����������,�r���T�j,���铹�j �� p.27�`46
���g�����̐A���ƃI�I�R�E�����̉a�A���ɂ��ā@�{�钩��,�������� p.47�`84
���畁�y�̎��H:�����w�Z�̎��g�݂�ʂ��ā@�@�ɔg�x�q p.85�`112
���ꌧ�̕������ی�j--
�@�@�����a�������痮�����{����̊����𒆐S�Ɂ@�@������ p.113�`155 |
�����قɂ�����O���Â���-�@�̌��w�K����
�@�@���u�O���Â���v�̎��H���@�@����P�� p.157�`171
�n���C�݂̎O���ɂ��ā@������ p.173�`182
�����ٕ����u���l(2)���Z�������وӎ������A���P�[�g���
�@�@�����NJ� ���G�q,��v�� �q�q p.183�`192
�q�j���Љ�r�g�_�ƕ����u�ۊW���ށv���
�@�@���ۊW������� �o�ߗ��q,�R�c�t�q p.219�`193
�E
�E |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 9�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@50p�@ �����F���ꌧ���}���فF1002872396�@�@�@
|
�V���|�W�E���u�쓇�̗��j�ƕ����v�J�Âɂ������� �啽��
���d�R�̉̂Ɨx�� �R������
�g�x��u�G���v�m�[�g -�B���ꂽ�A�}�I�G��- �������V |
���] �R�����꒘�w�Ñ���{�Ɠ쓇�̌𗬁x �啽��
����̗��j�F���Ɨ��j����ɂ��� �V���b��
�E |
�R���A�u�Ñ㕶�� = Cultura antiqua 52(3) (�ʍ� 494)�@(���S �쓇�l�Êw�����̌���Ɖۑ�)�v���u�Ñ�w����v���犧�s�����B
|
���S �쓇�l�Êw�����̌���Ɖۑ� p.129�`194,�}����2p
���ꋌ�Ί펞�㌤���̌��� ���� �k�~ p.131�`136
����V�Ί펞�㌤���̌��� �ݖ{ �`�F p.137�`141
�l�Êw����݂��O�X�N����l ���^ �k�� p.142�`148
�擇�l�Êw�����j ���� ���� p.149�`152
�����l�Êw�����̌��� ���R ���� p.153�`157 |
�y�킩��݂������̌𗬎j ���n ���L p.158�`161
�{�b�킩��݂������̌𗬎j �r�c �Ďj p.162�`166
�Ê�����݂������̌𗬎j �㌴ �� p.167�`171
���p���i����݂������E����n��̌𗬎j ���{ �M p.172�`177
�L���i����݂������E����n��̌𗬎j ���� �t�� p.178�`184
�K�݂���݂������̌𗬎j �؉� ���q ��p.185�`193 |
�R���A���x�w��ҁu���x�w = Choreologia (�ʍ� ����3)�@���W�F���x�w��n��20���N�L�O �V���|�W�E���u�����̎���ɂƂ��ĕ��x�Ƃ͉����v
���x�ւ̐ڋ� ���ۂƂ��̌����@�v���u���x�w��v���犧�s�����B�@�@�d�v
|
���x�w��n��20���N�L�O �V���|�W�E���u�����̎���ɂƂ��ĕ��x�Ƃ͉����v
�@
�@�����x�ւ̐ڋ� ���ۂƂ��̌����@�@���x�w�� p.7�`163
��1�� ���x�̌��� �@���x�w��@ p.7�`112
���̂͂��炫(��9��E���ʍu��) �@�ߓ� �l�Y p.7�`9
�����E���E�r�̕\��(��32��E�V���|�W�E��) ���� ���q p.16�`19
�C���h���x�ɂ������Ɗ�̕\��(��42��E�V���|�W�E��) ��J �I���q p.20�`22
�����̕��x�\��(��42��E�V���|�W�E��)�@�ᏼ ���� p.25�`28
�u�A�W�A���x�ɂ݂��̕\���p�v�ƃA�W�A���x�̎���(��45��E��u��) �{�� ���� 3 p.29�`31
�i���I�ɂ݂������Ɛl�Ԃ̓���(��7��E���ʍu��) ���� �u�� p.33�`37
���̃C���[�W�ƕ��x�\��(��7��E�V���|�W�E��) �t�����N �z�b�t,��H ��,�ڑ� �� p.38�`42
���x�Z�@�ɂ�����j���̕\���E�����̕\��(��21��E�V���|�W�E��) ��� ���Y,���� ���F,�ᏼ ���� �� p.43�`45
�s�����w�Ƃ��Ă̕��x(��6��E���ʍu��) �ߓ� �p�j p.49�`53
�l�`�ƕ��x(��22��E�V���|�W�E��) �S�i ����,���� ����,���� �@�� �� p.54�`62
Dance movement�̈Ӗ��̂Ƃ炦��(��31��E�V���|�W�E��) �� �ߎq p.72�`74
�������x�̌n��(��26��E�u��) ���� ���q p.86�`89�@
�~���[�W�J���E�R���f�B�̃h���}�c���M�[(��28��E�u��) ���� �u�Y p.90�`99
���x�Ə�����(��35��E���k��) �S�i ����,�ᏼ ����,���c �ꕽ p.102�`104
���x�ɂ�����u����v�̈Ӌ`(��41��E�V���|�W�E��) �S�i ���� p.107�`109
���x�̕����̓���(��41��E�V���|�W�E��) ���� �ݗ��Y p.110�`112
��2�� ���x�w�����@ �@���x�w��@�@ p.115�`163
�_�y�ƕ��x--���{�`�����x�����̑f�ނƕ��@���߂�����(��36��E�u��) �@�g�� ���� p.115�`116
�����J�[���Z���^�[�E�_���X�R���N�V����(��8��E��) �s�� �� p.117�`120
�g�̕\���̍l�����Ǝ���(��10��E���ʍu��)�@��� ���u p.121�`124
���l�͐�V�I�Ƀ_���X�����܂��Ƃ������Ƃ��߂�����(��14��E�u��) ���� �� 3 p.125�`130
�e�[�}�Ɛg�̂̌���(��34��E�V���|�W�E��) ���� �S�� 3 p.133�`135
�^���ƃC���[�W�Ɋւ����������(��34��E�V���|�W�E��)�@���{ ���h p.136�`145
���x����ɂ�����m��������(��36��E�V���|�W�E��) ��� �G�� p.146�`149
���x�w�̐V�������@��T��(��36��E�V���|�W�E��) �O�R �I�v�q p.150�`152
���x�w�Ɋ��҂������--��r�����j�Ɍg���҂̗��ꂩ��(��36��E�V���|�W�E��) �n�� �m�� p.153�`155 |
�R���A�g�Ɗԉi�q�����m�_���u���ꕑ�x�ɂ�����Z�@�u�R�l����v�̓�������v�\����B�@
pid/3191137
|
��1�� �ړI/p1
��1�� ���ꕑ�x�ɂ�����Z�@��R�l����/p1
1.���̏���-���ꕑ�x�̊�{���좃��l����/p1
2.���ꕑ�x�̎�v�W�������ɂ����颃R�l����/p9
3.�㎈����Ɋւ����s����/p20
��2�� �{�����̖ړI/p32
1.��i�S�̂ɂ����颃R�l���裂̈ʒu�Â�/p33
2 �u�R�l����v�̗ތ^/p33
3.�u�R�l����v�ƑS�g����/p33
4.��R�l���裂Ƒ��̏㎈�Z�@/p33
��2�� ���@/p34
1.�����Ώۂ���ъ���/p34
2.���͕��@/p41
��3�� ���ʂ���эl�@/p50
��1�� ��i�S�̂ɂ����颃R�l���裂̈ʒu�Â�/p51
1.�u�R�l����v�̏��p��/p51
2.�u�R�l����v�̏o���l��/p54
3.��R�l���裂̏��p���Ɣ��t���y�Ƃ̊֘A��/p61
4.�܂Ƃ�-��i�S�̂ɂ����颃R�l���裂̈ʒu�Â�-/p61
��2�� �u�R�l����v�̗ތ^/p64
1.�㎈����̗ތ^/p64
2.��R�l���裂̢�j�^��Ƒ��l��/p86 |
3.�܂Ƃ�-�u�R�l����v�̗ތ^-/p91
��3�� ��R�l���裂ƑS�g����/p95
1.�̊�����щ�������̓���/p95
2.�����̓��삨��іڐ��̓���/p107
3.�܂Ƃ�-��R�l���裂ƑS�g����-/p113
��4�� ��R�l���裂Ƒ��̏㎈�Z�@/p114
1.�{�앑�x�̃t���A�p�^�[��/p114
2.��R�l���裂̢�j�^��Ə㎈�Z�@/p118
3.�܂Ƃ�-��R�l���裂Ƒ��̏㎈�Z�@-/p127
��4�� ���_/p129
1.�ړI�E�ΏہE���@/p129
2.���ʂ���эl�@/p133
3.����/p138
4.�W�]/p139
�ӎ�/p145
���p����/p146
�v�|/p154
�p���v�|/p155
�ʐ^���X�g/p7
�\���X�g/p8
�}���X�g/p9
�E |
�S���A�u�����ւ�JCCA (207) �v���u���݃R���T���^���c����v���犧�s�����B
�@pid/2372979
|
�y���b�Z�[�W�z21���I�̊C�ݍs�� / �쓈�N�G/4~4
�C�݂��߂��铮�� / �|�������Y/5�`5
�y�����ւ�JCCA�z���݃R���T���^���g�̂��ꂩ�� / �Έ�|�v/6~6
�y���W�z�ӂ邳�ƥ�Ȃ���������� �C�� //7�`33
�Ȃ����Ƃ̋��� ������ԂƂ��Ă̕l�� / ���K��j/8�`11
�C�K���Ƌ�������C�� / ���c��/12�`15
�M���Q�̌i�ςƂ��̉��ɔ�߂�ꂽ���j / �a�v�c���v/16�`18
�����̓D�͖��̓D--�����̏�p�Ƃ�����
�@�@���Z�ސ������̒B / �n粐���/19�`21
�Ȃ����̍Đ� ���ꂩ��̂Ȃ����Â��� / ���ш�N/22�`25
�荻�C�݂̕ۑS / �쑺���v.�E�{�T��/26�`29
�����ƍ��y���܂��� / �����m��/30�`33
�V�����C�݂ɂ�����T���h�o�C�p�X���� / �g�c�a�Y/34�`37
�F���C�݂ɂ�����T���h���T�C�N���H�@ / �c�q�m��/38�`41 |
�i�ςɔz���������R�C�݂̈ێ��Ƒn�� / �������j/42�`45
���v����(�͌���������������) / ��������/46�`49
�y�y�؈�Y�̍��z�̕��ɔ����h���X��Z���������_��/�˖{�q�s/50�`51
�y�M�������[�zJCCA�M�������[ / �e�n����q/52~52
�y�C�k�V���[�Y�z21���I�̔����Ђ炭 �l�Ɛ�
�@�@�����R�Ƃ������Z�p / �����T ;����P�Y ;�g���L��/53�`61
�C�O��� �R�[�J�T�X�����ɂ�����C���t�������̉ۑ�/�ؑ��r�v/62�`65
���őO�� ���ےP�ʌn(SI)�ڍs�ɂ���--
�@�@�����H���Z�p��ɂ�����SI�ڍs / ����/66~69
�y�y�������[�z�y�������[ //70~71
�ψ���� �k�Вc�@�l ���݃R���T���^���c����l
�@�@��ITS���ψ���̊��� / ���쏲�j/72�`75
����11�N�x���ܘ_����ʓ��ܘ_���W/82�`91
�w���Ώۘ_�� �D�G�� �����I���݈�Ǘ��Ɍ�����/����c�m�u/84�`87 |
�S���A�R���ӈꂪ�uFront 12(7) (�ʍ� 139) p.32�`33�@���o�[�t�����g�����Z���^�[�v�Ɂu�V�}�̃R�X�����W�[ (���W �剂��--�앗�̉F����)�v�\����B
�T���P�R���A��ÍN�Y���S���Ȃ�B�i���N�U�P�j
�T���A�Î芡�я����^�������u�W���[�`���A�E�g���b�N�X�E�I�u �Î芡�я��v���u�r�N�^�[�G���^�e�C�������g�v���犧�s����B
�@�@�@�^���f�B�X�N 1�� : CD ; �i76��59�b�j
|
(1)������(����������Ԃ�)(2)�Ȃ��ѐ�(3)�C�̃`���{���߁`��������(�Ƃ܂������͂��Ԃ�)(4)�Q���̔~(5)�q���X�[���ޏ�(����肮��[)(6)�F�s����(�����������ǂ���)(7)�z����[(��������[)(8)�ʂ�ʂ���������(9)�_�C�T�i�W���[(10)��������[(11)�僓�Ȑ�(�����Ƃ����Ԃ�)(12)�e��̍�(13)�������[��(����[)(14)�Ђ߂��̉S(15)�g�D�o���[�}(16)��N��ؐ�(���ʂԂԂ�)(17)���݂̉S(18)���ʉ�(�����ʂ͂�)(19)�i�Ǖ��璹(����Ԃ������[)(20)�ꗎ��(�������Ƃ���)�`������ŕ�(�ӂ�) |
�U���A�^�������uKiNG Twin BEST�`���ꖯ�w�̂��ׂāv���u�L���O���R�[�h�v���犧�s�����B�@�@�@
�@�@�@�^���f�B�X�N 2�� (56��36�b/57��00�b)
|
| [1] |
(1)�����������^(���d�R)(������)(2)���K�R(�{��)(�m����j)(3)�J���O�`�Ɍv���߁`�J���O��(�{��)(�m����j)(4)�Ƃ��`��(���d�R)(��l����,��l�݂�)(5)�������(�{��)(�m����j,�{���N�q)(6)������(�{��)(��ÍN�t,�����i)(7)���ʔ�����(���d�R)(��l�݂�)(8)���NJԂ����(�{��)(�l��t�q)(9)�m�ԕz(�{��)(������)(10)�C�ʃ`���{�[��(�{��)(�m����j)(11)���߃��[��(�{��)(�Ɗ얼����)(12)�Ă��ʉ�(�{��)(�{���N�q,�{���ޔ��q,�ÎӔ����q,�䉮���K�T)(13)���Ԑ�(���d�R)(������)(14)�Z����(���d�R)(��꒩�v,����������)(15)�����S���̉�(�{��)(������)(16)�j����(�{��)(������) |
| [2] |
(1)��(�{��)(������)(2)���̓�(�{��)(������)(3)���l��(���d�R)(��꒩�v,����������)(4)�ɗǕ��Ɓ[����(�{��)(���K�}�c)(5)���D�h�[�C(�{��)(�m����j)(6)�q����(�{��)(���ܐ��Y)(7)�Î�v(�{��)(�m����j)(8)��ԓ��`���ʖ�߁`(�{��)(�Ɗ얼����)(9)�ԓc�a��(�{��)(�䉮���K�T,�{���N�q,�ÎӔ����q,�{���ޔ��q)(10)�Ԕn��(���d�R)(�ʎ�����,�V�銰�O,��l���N,���R�P��)(11)�{�ÂƁ`����(�{��)(�F������)(12)�L�N�̉�(�{��)(����b�g,�V������,�H�n�T��,�x�l�v�j,�v�L���g,���]�F���,���͏G�j,�m�Ԍ���,������E,����K��,���n���Y,���v�{��)(13)������ŕ���(�{��)(���ܐ��Y,�ݖ{�g�Y,��ԓ����Y,�V�_�ݑP)(14)��[��s(�{��)(�Ɗ얼����)(15)�R�C�i�[�����^(���d�R)
(��l�݂�,�ʎ�����,��l���N,�䉮���F�q)(16)���̎q���(���d�R)(�������̂�q) |
|
�V���A�^�������u����̉��y�`�����̎��v���u�L���O���R�[�h�v���犧�s�����B
�@�@�@ �^���f�B�X�N 1�� : �i 67��26�b�j
|
�q�ÓT�r(1)������ŕ���(���]��t)(2)�q����(���ܐ��Y)�q�g�x�r(3)�u�����q�v���q����ⵋȁr(4)���� ��i�`�O�i(�{��G�q)(5)�J���O(�m����j)(6)�Ă����ʉ�(�{���N�q)(7)�i�[�N�j�[(�m����j)�q�J�`���[�V�[�r(8)��������߁[��(��[���i)(9)���D�h�[�C(��[���i)�q�{�Ár(10)�L�N�̉�(�{��)(����b�g)(11)���NJԂ����(���NJ�)(�l��t�q)�q���d�R�̖��w�r(12)�Ƃ���[��(�Ί_)(��꒩�v)(13)��������(�|�x/�����������^�̌���)(��������)(14)�Ì��̉Y��(���\)(��꒩�v)(15)���ς�����[(����)(�^��������)(16)�������Ԃ���[(���l)(�吓�G�Y)(17)�܂݂ނ�ʂ���������(�g�Ɗ�)(�{����Y)(18)�����(�X���J�j)(�^�ߍ�)(��Ԍ[��) |
�V���A���c�g�F���u�����ʐM 89 p.58-66�v�Ɂu�G�C�T�[ : ���ɍ��Â�������|�\�v�\����B
�V���A�G������, ���ь��], ��g�������u���y�̃��e���V�[�v���u�I�u���E�p�u���P�[�V�����v���犧�s����B�@
�@�@2005�E�R(��3��)�@�P�P�O�O�~
�V���A�u���{��w 19(8)(225)�v���u�������@�v���犧�s�����B�@�@pid/7956965
|
���W ����̂��Ƃƕ���/6�`92
����̂��ƂƂ��̗��j���l���� / �O�Ԏ�P/p6�`16
��̉��u���̂ʂ�����Ɗ낤��--����������ʂ��� / ���Ԓ��m/p17�`26
�e����b�̏��� / �쌴�O�`/p27�`35
�l�̌�b�̐��E����݂������{�Ï������� / �v��}���q/p36�`50
���d�R�����ƕ��� / �����H�^�s/p51�`60
���������̑Ύґҋ����z�̕\�� / ������/p61�`69
�w�����낳�����x�ɂ݂�×��̂̑z�O / �g�Ɗԉi�g/p70�`82
���ꌧ�ߔe�s�̈��A���Ƃ� / �V�_����q/p83�`92
�A�� �Ԃ����{�� �|��@�B / �������F/p4�`5 |
�A�� ���Ƃ̎U����(27)�O�K���� / ���j�Y/p50�`50
���[�~���̌���w(34)
�@�@���p�\�R�������郆�[�~���\���O(15) / �ɓ����/p94�`101
���ꌤ���ƌ���f�[�^�̋��L ��12��
�@�@���d�q���R�[�p�X�̃^�O�̕K�v��(��) / ����j�j/p102�`104
���{��͌��|�[�g(9)
�@�@���Љ�l�̓ǂݎ��\�͂�(1) / ��{�M��/p106�`110
�V���E���� //p112~113
��� //p114~117
�����\�� //p120~120 |
�V���A���c�W, �R������, ������o�u�ҁu���d�R�E�Ί_���̓`���E�̘b 1�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B
�@�@�@�i�����̓`����������� ; 1�j�@�@ 185p �����F���ꌧ���}���فF1004470777
�W���A��E�����Ҏ[�ψ���ҁu��E�����v���u��E���v���犧�s�����B
|
�����Ɋā@�쑺�Ǔ�
�ҏW�ɂ������ā@�p�F��Y
���́@���R�ƒn��
���߁@��E���̌`���E���́@1
��@���̌`���@1
��@���̖��́@4
���߁@�ʒu�Ɩʐρ@5
��O�߁@�n�`�ƒn���@7
��@�n�`�ƏW���@7
��@�n���@8
1�@���K�w�@9
2�@�����ΊD��@9
3�@�u�ˉ��w�@9
4�@���N�T���S�ΊD��@9
5�@���u�@9
�O�@�ߓ�������ѓ��A�@9
1�@��J���ߓ����@9
2�@�i�i�e�[�K�}�@10
3�@�K�����@10
�l�@�C��n�`�@11
1�@��E���n�k�@11
2�@�n�k�Ôg�@11
3�@��E���n�k�@12
��l�߁@�C��@13
��@�C���ƍ~���ʁ@14
��@�������{�@14
�O�@�䕗�@15
��ܐ߁@�l���@17
��@�l���̐��ڂƓ��ԁ@17
��@�j���ʔN��ʐl���@18
�O�@�W���ʐl���Ɛ��ѐ��@19
��Z�߁@���A���@21
��@�����@21
1�@�ƒ{�@21
2�@�쐶�����@21
3�@�쒹�ށ@22
4�@���ށ@22
5�@����ށ@23
��@�A���@23
1�@�A���̊T�v�@23
2�@�_�앨�@24
3�@�ʎ��ށ@24
4�@���R�ی�w��A���@25
�掵�߁@�i�ρA���R�ی�@25
��@�i�ρ@25
��@��������n��@25
1�@������ʒn��@25
2�@��O����ʒn��@26
3�@���ʒn��i�C��j�@27
�O�@���R�ی��@27
1�@�i���ی��@27
2�@��Օی��@27
3�@�A���ی��@27
4�@�C���ی��@28
���́@�l�Êw���猩����E��
���߁@��E���̍l�Êw�I�����@31
��@�`���l�ފw�ɂ��DNA�̌����@31
1�@�ꕶ�l�@31
2�@�퐶�l�@31
��@�l�Êw�I�����@32
�O�@��Ձ@33
1�@�O��@�x�ɂ�钲���@33
2�@���a�c�^�~�ɂ��@33
3�@���a�O�\��N��w��A��
�@�@�������哇���������@34
4�@��R��Ք��@�����@36
5�@�n���^��Ք��@�����@38
6�@����B��Ք��@�����@47
7�@�I������Ց��O���
�@�@�����@�����i����Òn��j�@48
8�@�O����Ց��O��Ք��@�����@52
9�@�����Ց��O��Ք��@�����@53
10�@��m���Ձ@61
11�@��E���̐�j����@62
�t�\�@��E����Ւn���\�@64
�t�}�@��E����Ր}�@66
��O�́@�Ñ�
���߁@�쓇�Ɠ��{�{�y�@71
��@�쓇�̎���敪�@71
1�@�쓇�̕������@71
2�@���a�c�^�~�̕ҔN�Ɖ���L�ˎ���@72
3�@���{�L�q���̎b��ҔN�@72
��@��E���̈�ՁE�L�ˁ@73
�O�@���Z�n�̕ϑJ�@74
�l�@�╨���猩�������I�ȍ~�̌𗬁@75
���߁@�����Ɍ����Ñ�̓쓇�l�@76
��@���{�̐��j�ɓo��@76
��@�����l�̖{�y�P���@84
�O�@�����l�̑�ɕ{�Y���@87
��O�߁@�����Ɖ����A����@87
��@�����̎j���ɋL���ꂽ�����A����@87
��l�߁@���������ȍ~�̓쓇���Ձ@89
��@��ɕ{�o�y�̖؊ȂƐԖ@89
��@�w�V���y�L�x�̔��Y�^�l�@90
��ܐ߁@���������̊�E���@92
��@�ג��`���@92
1�@�ג��̐��������@92
2�@�ג���E���֕Y���@92
��@�m�r���̋S�E���z���@93
1�@�����J�̖d�c�I���Ɖ��������@93
2�@�`�r����̔��@�@93
�O�@�������̋M�C���Ǔ��@96
1�@�����̌����@96
2�@�V�쉓�i�̕@96
�l�@���Ɨ��l�̗����@97
1�@��������s�̊�E���Y���@98
2�@���Ƃ̎�͑哇�ց@99
��Z�߁@�A�}�����[�i�������j�@100
��@�V�}�i���j���Ă̗v���@100
��@�����E���l�E���_�@101
�O�@�_�R�E�_��E�~���E�_�̓��@101
1�@�n���^��ՂƐ_�R
�@�@���u�����R�v�i�}���k�[���}�j�@101
2�@�㍻�i�E�B�T�O�j��Ղ�
�@�@�����[�l���J�[�̐_�R�@101
3�@�A�M�A���X�c�A�O�c�A��x�A
�@�@�����ш�ՂƐ_�R�u�E�`���X�N�v�@102
�掵�߁@�A�W���[�i�i���j�@102
��@�i�����̒i�K�@103
��@��E���̈i�@103
�O�@�i�i�q���[�j�̊���@104
1�@�{�y���Ղ̗����ҁ@104
2�@�i�̐����I��r�@104
�l�@�����̕�炵�@105
1�@�H�@105
2�@�����@107
3�@�Z���@108
��l�́@�i�n���i���[�j
�@�@���i����������������j�̉����Ɗ�E��
���߁@��E���̕����N��ɂ��Ă̍l�@111
��@���Z�Z�i���~��D���i�O�j�N���ւ̋^��111
��@����������ꏮ�������̊�E������113
1�@��ꏮ�������̖k��
�@�@���i�����n��j�ւ̐��͊g�吭��@113
2�@���A���͂̊�E���ւ̐i�o�@115
3�@�u�썲�ہE�����a���̗��v�Ƃ��̌�̏��A��119
4�@���}�g�i�{�y�j���̍����@124
5�@�������̊�E�������@126
6�@��E���̕����@130
���߁@�����O���
�@�@�����������ɂ����鐭���̓����@131
��@��ꏮ�������̖ŖS�@131
��@��������̒a���ƒ����W���̊m��133
��O�߁@���������ɂ�鉂���E��E���̓���135
��@���������̓����@135
��@��E���̓����@137
1�@���̍s�����@137
2�@�Ԑ�V�}�����邨�����l�i�n����l�j138
3�@����v�W���́u�Đ{���V�q�v�`���@141
4�@�m���@147
��l�߁@���O�̕�炵�@160
��́@�ː�����i1�j���}�g���[�i��a���j
�@�@�������N�U����F���˒�������
���߁@�����N�U�Ɖ����@169
��@�F���˂̐����@169
��@�����N�U�@170
�O�@��������̕����@176
���߁@�����̕��j�Ƌ@�\�̐����@178
��@�S�E���u�ڏ��X�@178
��@�㊯�Ƌl���@182
�O�@�s�����@187
��O�߁@���ۂ܂ł̉��v�@188
��@���n�E���@188
��@�L�n����̊��_�@190
��l�߁@�����̐i�W�@194
��@�n�}��o�Ɠ���@194
��@���^�E�m���ւ̋K���@198
��ܐ߁@�l���ƍЊQ�@200
��@�ː��Ɛl���@200
��@�Q�[�E�u�a�E�ЊQ�@203
1�@�Q�[�@203
2�@�u�a�@204
3�@���R�ЊQ�@205
��Z�́@�ː�����i2�j�����ꔄ���̋���
���߁@���Ƃ̊J�n�ƍ�����[�@209
��@���Ƃ̐��Y�Ɣ������@209
��@��ꎟ�莮�������̎{��@210
���߁@�y�������ƓV�ۂ̍������v�@213
��@��ꎟ�y�������@213
��@��莮�������@215
�O�@��y�������ƓV�ۂ̍������v�@219
1�@�O�������y�䔃���Əo�Y���@219
2�@�����o�n���t�̕��@�@221
3�@�������p�̕i���̉��i�ƒ����@221
4�@�˂̐ꔄ�����ł̗����@225
5�@�T���̋֎~�@226
6�@��픲�ׂ̋K���@229
�l�@���ׂƌ����@230
1�@�������ׁ@230
2�@��E���̑傪����Ȕ��ׁ@231
3�@�����߂̋K��@233
��O�߁@�Ɛl�i�k�U�[�j�̔����@237
��l�߁@�����@�̉��ǁ@240
��@�������Y�@240
��@�S�֎Ԃ̓����@242
�O�@�u���V����ԁv�̊�E�������@242
��ܐ߁@�����̐��ǁ@244
��@��������Éi�̐����@244
1�@���w�}����@244
2�@�������}�����@245
3�@�Éi���}�����@247
��@�����Ɖ����l���@250
1�@���w�}����@�ꎵ�܁Z�i�����O�j�N�@250
2�@�������}�����@�ꔪ�Z���i�����܁j�N�@255
3�@�x�ˁE���y���˂̎��V�������@
�@�@���ꔪ��l�i�������j�N�@258
4�@�Éi���}�����@�ꔪ�܁Z�i�Éi�O�j�@266
5�@���c�V���@�ꔪ�Z��i���v��j�N�@268
��Z�߁@��E�n�̗��p�ƕېH�_�Ё@274
�掵�́@�ː�����i3�j
���߁@�˒����n�Ɓu�������V���v�@279
���߁@�����̐��Ɗ�E���@280
��@�����ւ̌������i�v���j�@280
��@�˂Ɠ��V���Ɨ����̓`�B�@�\�@285
�O�@�w����āx�̐��E�Ɗ�E���@286
��O�߁@�C���ʂƒʎ�`�@287
��l�߁@�m�Ԃƈ�����Ձ@297
��@�m�Ԏ��̗p�r�@297
��@�m�Ԏ��̌��Ձ@298
�O�@�˂ɂ�问���ւ̔��p�@300
��ܐ߁@�����M�Ɗ�E�G�@301
��Z�߁@��E���ƕāA�Q�[�A�Y���@304
��@�ĂƊ�E���Ɖ��v���A�����@304
��@��E���̋Q�[�Ɨ����@306
�O�@�Y���A�Y���̑Ή��Ɣq�ؕā@307
1�@��E���̓�����D�̕Y���@307
2�@�ٍ��D�A�����D�̕Y���@310
3�@�哇�����̊�E�����Ղƃ��\���Y���@313
�掵�߁@���l�i�����l�j�Ɗ�E���@313
��@���l�ւ̋K���Ɛ����@313
��@�]�ˁA�˓��A���V�����̗��l�@315
�O�@�������{����̗��l�@321
�攪�߁@�Y�����D�Ɠ��ʎ��@323
��@�Y�����D�Ƃ��̔w�i�@323
1�@���V���Y�����D�@324
2�@���v��𗮋��ց@324
��@���ʎ��@327
1�@�Y�����D�̈����@327
2�@���ʎ��̐E���@328
3�@�E�K�ƊǏ������E�@329
�O�@�����ƕ����@330
�l�@���ʎ��旧�Ă̐\�n���Ɠ��V���@330
1�@���ʎ����u�����܂Ł@330
2�@���ʎ��旧�Ă̐\�n���Ǝ��������@331
3�@���V���̓��ʎ��@332
4�@�㍑�̐����@334
�܁@��E���̓��ʎ��@334
1�@���ʎ��̐��E���]�{���@334
2�@�����Ƃ̓��ʎ��@336
3�@���̌S�Ɓ@338
4�@�l��i�F�v�j�Ƃ̓��ʎ��@339
5�@�@�āE���x�@340
6�@�������E���́@342
�Z�@���ʎ��Ɣ˂̐���@348
�攪�́@�O�ߑ�̕����Ɛ���
���߁@�����̕ϑJ�@353
��@���������ɂ������E���̕����@353
��@�ː�����̕����@353
�O�@���l�̕����I�e���@354
���߁@���w�@354
��@���R�ܘY���q�i���E�o���E���j�@354
��@�[�쉥�̈ɘC�g�́@355
1�@�ɘC�g�̂̍Ĕ����@355
2�@�[�쉥�̐l�ƂȂ�@355
3�@�ɘC�g�́@357
�O�@�m�ԉ��̋��@363
��O�߁@�|�\�@364
��@�쓇�̗w�̔��B�Ɠ����@364
1�@�����̂̔����@364
2�@�I�������痮�́A���̂ց@364
3�@�������w�̎�ށ@365
4�@��E���̔����x��@367
��l�߁@�@���@368
��@�m���@368
1�@�n�}�E�ʔv�Ɍ���m���@368
2�@�m���̍Ք�ߖ�Ɋւ���
�@�@���u�����]�n�v�i�����j�@370
��@���^�@371
�O�@��E���̃z�E�V���i�@�ҁj�@371
�l�@�����@372
�܁@�_�Ё@372
1�@��E���̐_�Д��˂̓`���@372
2�@�_�Јꗗ�@373
�Z�@���̑��̐M�@376
1�@���܂ǐ_�M�@376
2�@�Ί����i�C�V�K���h�E�j�@376
��ܐ߁@���퐶���̐H�A�߁A�Z�@377
��@�H�@377
1�@�H�ށ@377
��@�߁i�����j�@377
1�@���i���@377
2�@�瑕�@377
3�@�����@378
4�@���n�@378
�O�@�Z���@379
1�@�Ɖ��̍\���@379
2�@�Ɖ��̔z�u�@379
3�@���~�̈͂��@379
��Z�߁@�l���V��@380 |
��@�����@380
1�@�����̎葱���E�����@380
2�@���[�@380
3�@�K���@380
4�@�ł̈����ڂ�@381
5�@�O���߂�i�~�`�����h�B�j�@381
6�@�����@382
��@�Y��@382
1�@�o�Y�@382
2�@�E�߁i���ȁj�̏����@382
3�@�V���s��@382
�O�@�����@382
1�@�V�����̈������@382
2�@�ł������i�E�b�^�`�[�j�@383
3�@�q��i�J�����A�j�@383
4�@�q���̏j���E�ߋ�@383
�l�@�����@383
1�@��E���i���������j�̑����@�[�����̕ϑJ�[383
2�@�l�̎��Ƒ���i�\�[���[�j�@384
���́@�����E�吳�̊�E��
���߁@�s���̕ϑJ�Ɛ����@389
��@�ߑ�̍s���ϑJ�@389
��@�����̐����@390
���߁@�����̐��Y�@394
��@�����̓��Ɓ@394
1�@���Ɖ��P���Ƃ̕ϑJ�@394
2�@���㎖�Ɓ@396
��@��E���̓��Ɓ@399
1�@�T�g�E�L�r�͔̍|�@399
2�@�����@401
��O�߁@�������R�����^���i���萢�^���j�@409
��@�v�����߂��鐭�{�ƌ��̑Η��@409
��@���Б̐��Ǝ���̎d�g�݁@410
�O�@�����̉^���ƌ��ʁ@412
1�@�哇�����̗v���@412
2�@�\�����̐V�_��Ə�����ՊT�Z�@413
3�@�㌧��c�@414
4�@�`���`����x�����Ɠ����̍Ō�̉^���@415
��l�߁@�O���@�^���@420
��@�ۓc�엢�ȍ~�̎���@420
��@�V�[�x�����ƈ����F���Y�@421
�O�@���������l�Ɠ����̉^���@422
1�@���Ə��l�̓����@422
2�@�쓇���Y���Ђ̐ݗ��@424
3�@�쓇���Y���Ђƈ����g�@426
4�@�����̕������̎d�g�݁@427
�l�@�O���@�^���̒Ƒg�D�@429
1�@���ߑ�O�\�㍆�P�p�^���@429
2�@�O���@�^���̒@430
3�@�����̍ٔ��Ɠ����̏��i�@432
��ܐ߁@�u��E�����k�ڏO�v�����@434
��@�L�u�����Ɗ�E���@434
��@�u��E�����k�ڏO�v�����̌o�߁@435
�O�@�ٔ��̌��ʂƋU�؍߁@440
1�@�\�R�ƌ̏ᔻ���̌��n���@440
2�@�U�؍߁@444
�l�@�O���@�^���̍ٔ������̍s���@446
1�@�ٔ��̌��ʁ@446
2�@���������l�̍s���@448
��Z�߁@�C�^�Ƃ̔��B�@450
��@�q�H�J��ƕl�㌪���@450
1�@�l�㌪���̗����@450
2�@�哇���Ɗ�����Аݗ��@450
3�@�����̌��т���������Г���@451
4�@������̉����̊C�^�@452
5�@�^���@453
6�@�}�[�����D�@453
�哇���Ɗ�����ЊW�����@453
�掵�߁@�o���ҁ@456
�攪�߁@�l�X�̐����i�ߐH�Z�j�@461
��@�߁@462
��@�H�@463
�O�@�Z�@467
��\�́@���a�O���̎Љ�
���߁@���a�O���@?���a��\�N�܂�?�@477
��@���a�V�c�̉����哇�s�K�@477
��@���a��V��@478
1�@�����V��@479
2�@�֎���@479
�O�@���a�O���̐��ǁ@480
1�@���B���ρ@480
2�@�����푈�@480
�l�@�펞�̐��̋����@481
1�@���Ƒ������@�@481
2�@�吭���^��@482
3�@�펞���̕��������@483
�܁@�펞�̐����̊�E���@483
1�@��E���x�h�c�@483
2�@�����s���@484
3�@�ϖR�����@484
�Z�@�����m�푈�@485
1�@�C�R��E����s��@485
2�@�R��Ƃ̓����@486
3�@�����a�J�@486
4�@��E��������@487
5�@��P�@489
6�@���߁@490
7�@�A�C�X�o�[�O���@491
8�@�I��@493
���߁@�����ƕ����̓_�`�@493
��@�߁E�H�E�Z�@493
��@����@494
��\��́@�s���������i�A�����J���j�̉����Ɗ�E��
���߁@��E��錾�@499
���߁@�s���������̉����@503
��@�R���{�̐ݒu�@503
��@�s���@�\�̉��p����ёI�����@505
1�@�哇�x���̔p�~�ƗՎ��k���쐼���������̔����@505
2�@�����c��̑n�݁@505
3�@�Q���m���E�Q���c��c����
�@�@�����I�Ɖ����Q�����{�̔����@506
4�@�����������{�̐ݗ��Ɨ��@�@�c���̑I���@506
5�@�����������{�����n�����̐ݒu�@507
�O�@�i�@�@�ւ̋@�\���v�Ɨ�����s�̐ݗ��@508
1�@�i�@�@�ւ̋@�\���v�@508
2�@������s�̐ݗ��@509
��O�߁@�s���������̊�E���@510
��@���E�����@510
1�@�������̖���O���@510
2�@�������E������i�����c��j�c���I���@512
3�@�������̍����@517
��@�Y�Ǝ���@525
1�@�_�Ɓ@525
2�@���Ɓ@529
�O�@�����_�`�@534
1�@�p�R�̒��̃E�Y���o���[���[
�@�@���i�@�������j�ł̐����@534
2�@������ɂ������l�X�@536
3�@���X�i�e�W���j�Ŏ��x�c��g�D�@542
4�@�������������q�@544
��l�߁@���A�^���@548
��@���A�^���̓W�J�@548
1�@���A���c��̌����Ƒ�ꎟ�����^���@548
2�@����S�������N���ƒf�H�F��@550
3�@���q���A��c�̔h���@551
4�@�Γ��u�a���̒���@552
5�@��������̉^���@553
��@���A�����@556
1�@�_���X�����@556
2�@�ߊ�B���@557
��\��́@�c�����A�ȍ~�̊�E��
���߁@�����̊T���@561
��@��E���Ƒ������̍����@561
��@�����̌����Ɛ��ځ@564
1�@�����̎��ԁ@564
2�@�������́@571
�����@��E���̍Γ��E�Ώo�@576
�O�@���U���Ƃ̎��тƐ��ځ@587
1�@���ʑ[�u�@�̐��ځ@587
2�@���U���Ƃ̎��с@591
3�@��Z�N�x���Ǝ��с@595
4�@�n���_�����Ɓ@599
5�@�_�Ɗ�Ր������Ɓ@601
6�@���U���Ƃ̍���̕������@
�@�@�������I���W�ւ̔��z�̓]���@607
���߁@�Y�Ɓ@609
��@�_�Ƃ̌���Ɛ��ځ@609
1�@�Y�Ƃ̊T���@609
2�@�_�ƌo�c�̓����@614
3�@��앨�@?���Ƃ����с@623
4�@�_�Ƌ����g���@628
��@���Y�Ɓ@630
1�@���D���Ɓ@630
2�@�{�B�Ɓ@640
3�@���_�ƍ���̉ۑ�@642
4�@�ނ��с@645
�O�@���H�Ɓ@646
1�@���Ɓ@646
2�@�H�Ɓ@654
�l�@�ыƁ@662
1�@���N�}�I�E�̑��с@662
2�@��E���̑��ьv��@662
3�@��E���X�ёg���@663
�܁@�哇�ہ@665
1�@���Y�@665
2�@��_�@�哇�ۓ��Ƒg�������^���i���a��[�\��N�j�@679
��O�߁@��ÁE�ی��q���@682
��l�߁@�����@685
��ܐ߁@�^�A�E�ʐM�@687
��@�^�A�@687
1�@�C���ʁ@687
2�@�����ʁ@691
3�@�q��@693
��@�ʐM�@696
1�@�X�ց@696
2�@�d�M�@696
3�@�d�b�@697
4�@�g�ѓd�b�@698
��Z�߁@�y�E���z�@698
��@�`�p�@698
1�@�p�`���܍`�@698
2�@�������`�@700
��@���H�@709
�O�@���z�@713
�掵�߁@�x�@�E���h�@718
��@�x�@�@718
1�@�����x�@����E�����h�o���̉��v�@719
2�@���ݏ��̉��v�@720
��@���h�@725
�攪�߁@�d�C���Ɓ@728
��\�O�́@����̉��v
���߁@�����l�̉e���@735
��@�����l�̋L�^�@735
��@�����l�Ƌ���ւ̂������@736
���߁@�w��E�����x�@736
��@�����������w��E�����x�@736
��@���ҁE���������@738
��O�߁@�t�����̋���@739
��@�t�����̎���@739
��@�w��E�����x�ɂ݂�t�����̋���@739
�O�@��E���̎t�����@742
��l�߁@���Z�@744
��@�w���̔Еz�@744
��@�������̋��Z�ƕϑ����w�Z�@745
�O�@�����哇�̋��Z�@746
�l�@��E���̋��Z�ݗ��@747
��ܐ߁@���w�Z�@747
��@�������w�Z�̐ݗ��@747
��@����߂Ɗw�Z���x�@748
�O�@�����̗{���@749
�l�@���q����Ə��w�Z���̑��݁@752
��Z�߁@�ȈՉȏ��w�Z�@754
��@���w�Z�߂̌��z�Ƌ`�����琧�x�̎�|�̊m���@754
��@��E���̊ȈՉȏ��w�Z�@755
�O�@�ȈՉȏ��w�Z�O��̋���@756
�掵�߁@�q�포�w�Z�E�������w�Z�@757
��@���w�Z�߂̉����Ƌ`������N���̊m���@757
��@��E���̐q�포�w�Z�@757
�O�@�����̍������w�Z����@760
�l�@�������w�Z�̊J�݁A�q�퍂�����w�Z�ւ̉��́@761
�܁@���苳�ȏ����x�ɂ��ā@764
�Z�@�����哇�S�����Ƌ������莎���@769
���@����̕����@771
���@���Ɛ��̉�z�@772
�攪�߁@�����w�Z�@776
��@�����w�Z�߂ƍ����w�Z�̋���@776
��@��E���̍����w�Z�@776
���߁@�ΘJ�N�̋���@779
��@���ƕ�K�w�Z�@779
��@�N�P�����@781
�O�@�N�w�Z�@781
�l�@���ƍ����w�Z�@784
��\�߁@�Z�E�O�E�O�E�l���̎��{�@785
��@�������Ԓ��̋���@785
��@���A�ォ�畽���ւ̋���@800
�Z�́E�w�Z�S�i�@831
��\��߁@�A�w�O�̕ۈ�@844
��@��E���̗c�t���@844
��@��E���̕ۈ珊�@849
��\��߁@�Љ��@854
��@�Љ��@854
��@�����ق̊����@872
�O�@��E���}���ف@877
��E���̋��版�v�N�\�@882
��\�l�́@�ߌ���̏@��
���߁@�����@891
��@��y�^�@�@891
��@���@�@�@892
���߁@�L���X�g���@892
��@�����n���ւ̃L���X�g���`���@892
��@��E���J�g���b�N����@894
�O�@���{�z�[���l�X���c��E�L���X�g����@895
�l�@���{�L���X�g���c��E����@896
�܁@��E�C�G�X�V��싳��@897
��O�߁@�V�����@898
��@�����x����h�@899
��@����勳���F������h�@900
��l�߁@��{�@900
��ܐ߁@�n���w��@902
��Z�߁@���E���a���c�i�a���j�@903
��\�́@��E���̔N���s��
���߁@�s���̊T�v�@907
���߁@�_�ƂƋG�߁@908
��O�߁@�N���s���ꗗ�@910
��l�߁@���ʂ̍s���@911
��\�Z�́@�������E�j�ՁE�����E�L�O��
���߁@�������@927
��@���w��L�`�������@927
1�@�H�|�i�E���̑��@927
2�@�����@939
3�@�l�����@941
��@���w��L�`�����������@941
�O�@���w��V�R�L�O���@952
�l�@�������Ɏw�肳��Ă��Ȃ��M�d�������@954
�܁@���`�������@959
���߁@�j�Ձ@960
��O�߁@��������ыL�O��@970
��@�����@970
��@������@975
�O�@�L�O��@981
1�@�S���N�L�O��@981
2�@��t�S�F�̔�@983
3�@������@986
4�@���L�O��@993
5�@���V�{�@1008
��������
����O���E���c��c��
�N�\
�E |
�X���A���c���q���_�ސ��w���{�햯�����������ҁu����}���X���[ 33(6) (�ʍ� 390)
p.7570�`7576�v�Ɂu ����E���d�R�̌܍��v�\����B
�P�P���A�Ί_�ɕҏW�u�{���c�s�L�O�_�W�v���u�{���c�s���a�S�N�L�O���Ɗ�����v���犧�s�����B�@�@
|
���� / ������
���d�R�������瓌�k�����܂� :
�@�@�����{��̕����`���ߒ��ɂ��� / �㑺�K�Y
���d�R�Q���̓����N���Ɋւ��錤�� / �q�쐴
���쎢���� : �u ���d�R���w�W�v�𒆐S�� / �V����P
���̏��j : ��쑺�̊T�� / ��R��
�{���c�s�������w�u���m�[�g / �X�ۉh���Y
���d�R�약�̐e���ƍՒc�̍\�� / ��Ð��v
�Ί_���E���ۑ��̎��n�V�� / �Ί_��
���d�R�Ɍ��݂���g�x�ʖ{ : ���ɈɎɓ��p���������̉��l/�c�Ԉ�Y
���d�R�̐e����b / �����H�^�s
���d�R�����̖��b / �{�Lj��F
|
���d�R�̏o�ŕ����Ɋւ����l�@ : ����ʁA����ʁA
�@�@�����וʕ��͂𒆐S�� / �O�،�
�V��̃r���[�X�N(���ǒ�)��ՂƂ��̎��� / ���_�i�j
���ю��n�������̏@�|���߂���l�@ / �l���c�O
���d�R�̗w�ɗw��ꂽ�u���v / �R������
���ԓ��̉J��� / ���{
�Ί_���E���v�ۑ��̏��j : �Ɨ����Ƃ��Ă�
�@�@�����v�ۑ������̍��܂� / ��������
�Ί_���̒n�� / ���Ï���
�����\���_�̎��� : ��̃Z���e���X�𒆐S�� / �����|�Y
���d�R�����̋��ɂ��� / �E�G�C���E���[�����X
�ҏW��L / �Ί_�� |
�P�P���A�u���N��� 47(11)�v���u���N��茤����v���犧�s�����B�@�@pid/2745392
|
�ƒ�œ`���镶���̊�b / �ѓ��`/p2�`3
�����ɑΉ�������N����̂���� / �X�c�E��/p4�`9
����Љ�Ŏq�ǂ��̗V�тƂǂ���������/���씎�v/p10�`15
�Ղ�ƔN���s��--���X�̕�炵�͂��ׂ�
�@�@���Ƒ�����݁E������� / ���C����/p16�`21
���{�̐H���� / ���v/p22~28
�q���̕���u���i���v���㉉--
�@�@��������������2�N�ڂ�����/�k�쏟�F/p34�`39
��y�̓`���Ɛ��N���� / �D�c//����/p40�`45 |
�G�C�T�[�Ǝ�҂��� / ���w/p46�`51
�u�q�ǂ��Ǐ��N�v�ƕ����Ȃ̎�g/������ ���U�w�K�� �w�K����/p29�`33
�C�M���X�u1999�N���N�i�@�y�ьY���؋��@�v�̐���--�����N�ؐl�E
�@�@����������邨����̂���ؐl���ɑ���
�@�@���Y���葱��̕ی� / ���R��/p52�`55
�����12�N�x���N���S�琬�����t�H�[�������
�@�@���J�Âɂ���/���������N���{��/p56�`56
���N���W��v�L���Љ� //p57�`57
�E |
�P�P���A���O�j������ҁu���O�j���� (60)�v���u���O�j������v���犧�s�����B
�@ pid/7932412
|
�����d�@�̓W�J--�����O���d�@�ɂ�����S������𒆐S�� / ���c���l/p1�`20
�������ɂ�����C�l����n�̋��E���--��\�㗢�n��̕l�Œn������� / ���j�F/p21�`37
�j���Љ� ��㉫��ɂ����鐭�������̏o��--��Ït�����Ɏ����w����̌���x�̈Ӌ`�Ǝ˒�
/ ��糏G��/p39�`54
���] �R�A���t�v�ҁw���̂��ɑ����̐��E--�w�ԁE�����E���ׂ�x�㊪ / �����a�F/p55�`59
���] ����݂ǂ蒘�w�ى��Ɠ����̊�--�퍷�ʕ����F���̋O�Ձx / ����/p61�`71
�y�V���Љ�z �v�����Q���ɓW�L�^�W�ҏW�ψ���ҁw��̊��̌��_�E�o�łƕ����x
/ ����T�q/p38�`38
�y�W����Z�]�z ���c�s�����R���������فu��3��푈�W �R���ւ̂܂Ȃ����v / ��糏G��/p60�`60 |
�P�Q���A�u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (56)�v���u�쓇�j�w��v���犧�s�����B�@�@/4419263
|
�×��������ƕ���-���v�E�����E���^��
�@�@����������𒆐S��/�m���芰/p1�`26
�j�����̉F�� / ������/p27~46
��p�R���v�z�̈�l�@--��p�Ɨ��h�̍R���v�z/�ɓ����F/p47�`58 |
���]�ƏЉ� �w�����E�����̂��ׂāx-��ɏ�ꗲ��/���씎/p59�`60
�쓇�W�����ژ^ / ���씎/p61�`73
���/p74~74
�E |
���A���̔N�A�v���c�W�����ی𗬊���ҁu���ی� 23(1) (�ʍ� 89) p.31�`35�v�� �u����G�L�]�`�V�Y���̌��� (���W �|�X�g�ό��Љ�ւ̖͍� ; �ό��̉ߋ��E���݁E����--�|�X�g�R���j�A���Љ�Ɗό�)�v�\����B
���A���̔N�A���{���炪�u���{�̈�w��� 51(0) p.518�v�Ɂu����̖������x�u�G�C�T�[�v�̌|�ԕ��z�v�\����B�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���эK�j���u���m���y���� 2000�@(65) p.75-78�v�Ɂu��������w���}�g���`���̂��߂̉��ꉹ�y����x�v���Љ��B J-STAGE
���A���̔N�A�X�ۉh���Y�����{�����j�w����u�����j�w = Historical review on manners and customs : ���{�����j�w� (13) p.54�`60�v�Ɂu����̌|�\�ߑ� (������W�� 2000�N�H)�@�v�\����B�@�@ |
| 2001 |
13 |
�E |
�Q���A���эK�j���u�Ђ�� : ���s�̋��� (125) p.63-65�v�Ɂu���̓��͂��������� : �����A��������B�v�\����B
�Q���A���ꌧ���璡������ �ҁ@�u���E��Y���������̃O�X�N�y�ъ֘A��Y�Q�F�ʗˁE���䉮����ԐΖ�E���A�m��ՁE���얡��ՁE���A��ՁE�����ՁE��ՁE�������E�֏��ԁv���u�u���������̃O�X�N�y�ъ֘A��Y�Q�v���E��Y�o�^�L�O���Ǝ��s�ψ���v���犧�s�����B
�@199p ; 31cm
�R���A�g�Ɗԉi�g���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 13
p.105-170�v�Ɂu�u����������v��ǂ� �g�Ɗԉi�g�v�\����B
�@�@�@202p �@�@�@�@�����F��㊌����}���فF1003838321
|
�Ì������̊�b��b �����H �^�s�^��
�u����������v��ǂ� �g�Ɗ� �i�g�^�� |
���I�X�̍��@�ƍ��@�E�בы@ �� �x�B�^��
���ꌧ���|�p��w�����������b�� |
�R���A�g�Ɗԉi�g���u���{���w 50(3) �@ p.75-7�v�Ɂu���c���q��, �w�{�Ó��떓�̐_��-���̌p���Ƒn��-�x, ��Z�Z�Z�N��Z��,
�v���t�o�Ŋ�, �O��, �Z�Z�Z�Z�~�v���Љ��B�@�@J-STAGE
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (9)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
��(����)�����I���w�Ɋւ����̉��ߊw�I���ɂ��ā@�@Henckmann Wolfhart,���R�h��
�� p.1�`11
�W����w�Z�U���k�Ɠ��{�x�ɂ��Ă̊o���@�@���t�j�@ p.13-29
Le Nez--A propos d'un conte japonais�@���� �}���E�|�[�� p.31�`42
�����E���C�̑��ʂ��猩�����ÁE���J�̏��́@�@���� ���Îq p.43�`60
18���I�U���c�u���N��ȉƂ̃V���t�H�j�[�ɂ����郁�k�G�b�g�y�� �l�@�O���킩��
p.61�`73
�����X�g���b�`���O--�X�g���b�`���O�������ꂽ�������x�̊�{����@���g�Ύ} p.75�`92,102
�����X�g���b�`���O�ƃ~�[�N�[�`���[�@�@���{�M�v p.93�`102
<�n��m�[�g>�@�h�֓N��@ p.103-104 |
�R���A�����k�~�����ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (26) p.205�`220�@���ꌧ����ψ���v�Ɂu���a�c�^�~�̉���l�Êw�����J�n���̐V������-��v�����B�V���R���N�V�������v�\����B
�R���A���v�`���u����w�����ًI�v 7 p.1-20�v�Ɂu���d�i���傤�낤�j�̛ޏ��v�\����B�@�@ �iIRDB�j�@�d�v
�R���A�u�쓇���� (23) �v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s����B�@
�iIRDB�j
|
�������� ��p�_�Ƃ̓�����WTO�����ւ̑Ή� �@���ԑגj,�n�ӂ䂫�� p.1�`14
���`�����W���}�̃e�L�X�g ���R�� p.1�`9
������̕��w�ƕ��y �Î芠,�ߎq p.15-26
�����j�ɂ����閯�O�̖���(3) ���n�N�v p.11�`26
�w�p�������x�ɂ����铯�m�̊��p�̌^ �����r�O p.27-44
GIS�\�t�g�𗘗p������ԕ��z�̕���--��v�Җ����� �n�ӍN�u p.45�`58 |
��22��쓇�����s���u���L�^ p.59�`92
�A�����J���̘J���͎���ƈږ� �V���i�r p.59�`68
����ږ��W�J�̔w�i�Ƒ��Րΐ�F�I p.69�`79
��u��s�ɂ݂�ږ��̂��낢��) �ɔg���q p.81�`92
�O�ΌQ���̍l�Ò��� ���{�A��,�v���O,�A�Ɣ� p.93�`111
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�Ő��ɂ��ẮA�Ċm�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E5�E15�@�ۍ�
�R���A�u�n�挤���V���[�YNo.29 ���d�R�A�|�x��������(3) �v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
�iIRDB�j
|
�����̐����j��গ��D���� : �V��E�̗w�E���@���R�� ��p1-42
���\���E�V�铇�E���ԓ� : ���̒n���I�T�ρ@��l�� p1-8
���\���ɂ�����_�ƌo�c�̌��� : 1995�N�_�ƏW���J�[�h�𗘗p����
�@�@������� p9-20 |
���\���̂��܂ǐ_�M�@�E���� �@p21-35
�M���A�c�[�A�����̌×w : �g�ߍ�(�V�`�B)"�̂�����
�@�@�����S�� ���{�M�v ��p37-85
���d�R�|�x�����������̏��� �쌴�O�`�� p87-111 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�Ő��ɂ��ẮA�Ċm�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�S�E�Q�S�@�ۍ�
�R���A���A�ɗY���u�������x�̐��E : ���̊ӏܖ@�v���u�䂢�o�Łv���犧�s����B�@329p �@�����F��㊌����}���فF1003563424
�R���A�X�ۉh���Y�������w�@�o�w���ҁu�����w�@�o�w���I�v (1) p.81�`85�v���u�u���NJԂ̖L�N�Ձv�̍��w��̌��ʁv�\����B
�R���A���ꌧ���A�m�����j�����Z���^�[�ҁu�V�铿�S���� : �����L�^�m�[�g�v���u���ꌧ���A�m������ψ��� : ���A�m�����j�����Z���^�[�v���犧�s����B�@ (�Ȃ����� : ���A�m�̎��R�Ɨ��j�ƕ���, vol. 10)
�R���A���ꌧ�������ٕ� �u���ꌧ�������ًI�v ��27���v���u���ꌧ�������فv���犧�s�����B�@
139p�@
�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003633326�@
|
���ꌧ�����̂܂��Â�����Ɣ����� �O�c�^�V
����n���̒n�`�ƒn�� �_�J����
<�j���Љ�>�u���������̐��F�����V-�o���ԐD-�v �^�ߗ� ��q�@ �K��V
������암�̎s�X�n�ŔɐB�����c�~��
�@�@�������E�L���E�T���V���E�N�C��2��ɂ��� �������� |
��哌���Y���ޖژ^ �o���@ ��������
�w�E���}(�����)�V��x�Ɍ�����̕������ی�ٓ����ɂ�����
�@�@���W�L���ɂ��� ������ p.77�`112
���ʓW�u���n�ږ�1���I�W�v����v���O�����̎��{�ɂ��� ����P
���ꌧ���̔����قɂ����闈�َҒ��� ���ؗS ��v�� �q |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 10�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@ 51p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003627344�@�@
|
�V���|�W�E��
�u����E�|�x���̓`��-�_�b�E�`���E�|�\-�v �@�떓 �b��^��� �וv
�� ����|�x���̎�q��Ղ̓`��
�R�����g�^���^����
|
�����l���B�����S���l�Y���ꌏ �e�r�E�v
�ߐ������̗� ���_�Z
�@�@���擇�����̎���(�Ƃ��ނ�) ���c�I��u
����Љ��O�}�̓}���ɂ��� ���ђ��� |
�S���A�u���k�w. [��1��] 4 �����W �̏Ĕ������v���u���k�|�p�H�ȑ�w���k���������Z���^�[�v���犧�s�����B�@
|
�����W �̏Ĕ����� �� p.215�`310
�C���^�r���[ �̏Ĕ�����--�}�j���A���Ȃ����s��
�@�@����{����,�ԍ⌛�Y p.216�`236
���R�[�̏Ĕ� �@�k��g p.237�`247
���k�̏Ĕ�--�A���L�^�Ĕ����ǂ��ǂނ��@������ p.248�`261
���u���L�̖���--�����E�l���n���̏Ĕ��@ ���Ώ��b p.262�`268 |
�y���֎R(�l��)�̏Ĕ� �@ �c�ӎ��j p.269�`277
��B�R�n�̏Ĕ��k��-
�@�@���{�茧���P�n�S�ŗt���𒆐S�Ƃ��� �@�i���� p.278�`289
������̏Ĕ�-���B�Ɠ���A�W�A�̒|�̏Ĕ� ���a�� p.290�`301
���\���̏Ĕ�--�����n�͂������ �@���k�V�n p.302�`310
�E |
�T���P�T���`�T���Q�O�����u�ߔe�s���M�������[�v�ɉ����āu�u��ÍN�Y��ړW�g���ƕ��Ɛ_�X�̐��E"�v�W���J�����E
�T���A�u�{��\�P�̉� : �_�ɍ��Ă�v���u�{�闬�P�̉� �v���犧�s�����B
�@�@�@��� �{�闬�P�̉� �@�@�����F����13�N5��3��,�ꏊ�F�������y����@�@�@1���@�����F1003638754
�T���A��ÍN�Y��ړW�g���ƕ��Ɛ_�X�̐��E"�ҏW�ψ���ҁu��ÍN�Y��ړW�g���ƕ��Ɛ_�X�̐��E"�v���u��ÍN�Y��ړW�g���ƕ��Ɛ_�X�̐��E"���s�ψ���v���犧�s�����B
�T���A��C�����V���Еҁu���ꂼ��̉����_�E50 : ����21���I�ւ̏��t�v���u����V�Ёv���犧�s�����B
|
1: ��̂Ƃ��Ẳ��� / �R���ӈ�
2: ��������鉂�� / �֍����i
3: �ω��̒ꗬ������� / �|�퐭��
4: �y���ɍ����� / �O����
5: �����b�q / �o���q
6: �V�}�E�^��Ƃ��� / ��������
7: �n��E�]�_�E�����A��㉂���̕��w/�ԍO�u
8: �u���z�v������̊m���� / �勴���R��
9: ���ق������� / �����L��
10: �����c���A����ς��邩 / �������
11: �s���s / �c�m��i�q
12: �|�\�`���ƃA�C�f���e�B�e�B�[/���䐳�q
13: �����o�ς̐i�ނׂ��� / �F������
14: ������S������ / ���|���q
�@15: �o���Y�ꂽ�h�� / ��؎��Y
16: �����������͂Ɩ�����n���/�����Δ�
17: �����ւ̗��� / ���Ǖ�
|
18: ���ꂩ��̉������l���� / ��O�O
19: �w���A�^���x�̌����͂Ɋw��/
�@�@�� ���o�[�g�ED�E�G���h���b�a
20: �V�^�̈�Y / ��������
21: ���p�����Ƃ���n�܂����/�����_�q
22: ���א��Ԍn�̈���Ƃ��� / ������j
23: �����ꂽ�F���̗��j���� / �����˗�
24: ���邩�牂�������� / �Y���x�q
25: �����Ƃ����^�C���}�V�� / �����N�O
26: �m��ꂴ�鉂�������̗��j / �����C
27: �É����̓T�^�J���B���L / �����Ύ�
28: ���ݑ����鉂���l�Êw / ���R����
29: �����ƐU�� / �c�����q
30: ���Ƃ��Ă̕��i / �ʕ{����
31: ���ꂩ�牂���̌|�\���݂�/�v���c�W
32: �쓇�̕��w / �Y�c�`�a
33: ��Z�Z�Z�N�����̂���� / �O�c�F�V
|
34: �����̋����̌��ꂩ��/�֍����Ђ�
35: �{���̓��{�l / �X�{����Y
36: �l�Ɛl�Ƃ̌�:�̂Ɨx��̏�/�����䂩��
37: �����̍����P�� / ������
38: ���S�A�����W�̌���ɂ�/�ɒn�m���q
39: ���͉����̎q / ������
40: �����̐S�Ɠ`�� / �c����H
41: ���̕� : �w�R�𐒔q�x / �ʕ{�`�A
42: ���ʔ��ʂ̌��E�� / ���{��
43: ����������[ / ���a��
44: �����Ƃ̏o���� / �V���j
45:�u�Ă��Ă��v�̐�ɂ������/�_�J�T�i
46: �����ɕ�炷 / ��a�q
47: ���A�^���̌��p���y��
�@�@�����U�̂���� / �����x��
48: ���������A���̋L�q���߂�����/�������Y
49: ����21���I�̉\�� / ������Y |
�V���A�٘@�Бܒ���,���c�Z�Y�u�����_���L : ���E�ܒ���l���M�e�{�e��v���u�Վ����сv���犧�s�����B
�@�@�w�����_���L�E�ܒ���l�G���`�x(�S���)�@�t: ������܂�ʐMNo.25�@�����F���������}���ف@���s���}����
�W���A�g�Ɗԉi�g��}�u�v�ē��̌䍖�E�q���E���Տ��ݒn�}�v���u���ꌧ���}���فv���犧�s�����B
�@�@�@�@��18��@����w���ꕶ�����������J�����u�v�ē��X���C�h�̉�v�@ �i�p���t���b�g�o�C���_�[����j�@�����F���ꌧ���}����
�X���A���A25���N�L�O��3��u���ꌤ�����ۃV���|�W�E���v���s�ψ���, ���ꕶ������ҁu���E�ɂȂ����ꌤ��
: ���A25���N�L�O��3��u���ꌤ�����ۃV���|�W�E���v : ������E�V�h�j�[���v���u���A25���N�L�O��3��u���ꌤ�����ۃV���|�W�E���v���s�ψ���v���犧�s�����B
|
������ ���E�ɂȂ����ꌤ�� / �O�Ԏ�P �ق��q
�����̕��Ր� / �����i ��
�C�O�ɎU�킵�����������H�|�̕]���ɂ���/�O�c�F�� ��
�|�\�ɂ݂鉫��Ƃ��̎��� / ���P�Y ��
������E�J���B���L�E���ΐ��Γ炩��݂�
�@�@��12���I���̉��� / �������I ��
7�`13���I�̊L���ՂƓ쓇 / �؉����q ��
������݂�����̐l / �y�쒼�� ��
�O�X�N(��)�̌ꌹ / �ԋ{���i ��
7���I���12���I�܂ł̑�p / �A�Ɣ� ���v���O ��
�鎞��O��Ɋw�ۓI�A�v���[�` / ���{�A�� ��
�p���̗����i�o�ɂ�铌�����ے��������̖��C
�@�@��(1832�`1854) / ���[�Y ��
�����̊C�O���݂��]�����̒����� / �^�h���[�� ��
�u�O���v�Ɨ��������Љ� / �㌴���P ��
�����Ɠ��{��ƒ��N�� / ���a�c����Y ��
������������̉��ꊲ�ɂ��� / �����r�O ��
����{�������ɂ�����ꉹ�̌n�ɂ��� / �{�ǐM�� ��
����̎�Ҍ��t�l / �쌴�O�` ��
�ߑ㉫�ꕶ�w�ƕ��� / ��闧�T ��
����̏����̐V�����W�J / ���{�b�� ��
�u��m���w�v�̒��̉���l�� / �������� ��
����̎�҂̌���ƈӎ� / ��p�� ��
�I�����̕\���ƍ\�� / �g�Ɗԉi�g ��
���Ƃ��Ă̕�A��Ƃ��Ă̓� / ���[�X�E���[�g�� ��
�g�x��̓Ǝ��� / �������V ��
�u���w�v���ȉ�̂܂Ƃ� / �����i ��
�����l�ފw�̉��ꌤ���͒�������A��? / �}������ ��
���d�R�ɂ����鑺���i�ς̕ϗe / �����N�� ��
����ɂ�����c����J�̐��� / �ԗ䐭�M ��
���A�W�A�̕����_ / �n粋ӗY ��
�����̎��ӕ����Ƃ��Ẳ���E�؍��E
�@�@���x�g�i�������̗ގ����ƈَ��� / ���N�� ��
�݊O����֘A�����������ɂ��� / ������ ��
�C�O�ɓn�����������H�Y�i / ����`�� ��
�����̒����Ɣ��G / �r��_�a ��
�×����g�^�͗l�̐��E / �Љ��~ ��
������ċz����H�| / �V�_�g�I ��
�u���p�H�|�w�v���ȉ�̂܂Ƃ� / �O�c�F�� ��
�g�x�����̉ۑ� / �r�{���� ��
�����̌���y�ƒ������y / ���s�� ��
����A�W�A�̉��y�Ɖ��ꉹ�y / ����� ��
�������x�̗l���� / ��J�I���q ��
����̌|�\�Ɠ���A�W�A�̌|�\�ɂ���/�X�ۉh���Y ��
�u�|�\�w�v(�掵���ȉ�)�̊T�v / ���P�Y ��
����ɂ����铇�o�ς̗��_�ƍ\�z / �����r�� ��
����ɉ�����21���I���a�H�w / ���i���h�EA�E���[�X �� |
���ꔭ���E�ցA�L�p������(EM)��
�@�@�����ړI���p�̑̌����� / ��Ïƕv ��
�����Y��l�I�����Ғœ����̓n�� / ����N ��
���M�т̓�����̐A�� / ���c���k ��
�T���S�ʊC��Ɖ���̊C�� / �������� ��
�ϏB�Ɖ���̓����v�����N�g����r / ���L�� ��
����{���̗��� / �����E ��
�j���ɓo�ꂷ��Ŏփn�u / ���ʐ��C ��
���ꌧ�ό����Ƃ̐U���ۑ� / ���J�B�j ��
����U����Ɗ�ƕ��� / �{���i ��
�n�抈�����̉ۑ�Ɗw�ۓI���� / ���N�� ��
�V�h�j�[��� ����A���̕��ՂȂ���� / �����i ��
���E�j���猩������ / ���[�[�t�E�N���C�i�[ ��
21���I���������ꕶ�� / ��闧�T ��
���ꏔ���ɂ�����鎞��O��̗l�� / ���{�A�� ��
�C��̓�:�čl / ���{�L�y ��
�������쐭���̓��A�W�A�O���Ɨ����� / �㌴���P ��
�x�C�W���E�z�[���̃i�|���I����L / �R���d�� ��
�u�l�Êw�v���ȉ�̂܂Ƃ� / ���{�A�� ��
�Ί_(�l��)�����̓������p��
�@�@���ꉹ�f���̕s���S�w�� / �E�F�C���E���[�����X ��
����������"��"�̕\�� / ������ ��
�����́u�����v�̐��� / ���a�c����Y ��
�ς��䂭����̌��t / ��p�� ��
���������A�N�Z���g�����̉ۑ� / ���P�� ��
��b�̈Ӗ��I�����Ƒ̌n / ���V�m�� ��
���㉫�ꕶ�w�̏����� / �g�����Y ��
�I�����̎��R / �������V ��
��㉫��̎������w�E�G�{ / �V�؊���q ��
�|�\�̖����ω��Ɨl���Ɋւ����l�@ / �������q ��
��ڗ��̑g�x�ւ̉e���ɂ��� / ���P�Y ��
�w����m�[�g�x�Ɍ����]���w / �N���A�����g�N�q ��
�w���o�鏴�x�̗̉w / ���эO�q ��
�y�n�̎��� / ���V�]�L�� ��
�������w�ɂ݂郄�|�l�V�A�_�̔����ƓW�J / ����O ��
���Ȃ�}�u�C / ���[�X�E���[�g�� ��
���w�E�|�\�w(��O���ȉ�)�̊T�v / ���P�Y ��
�_���a�� / �㌴�F�O ��
�ɓ��A�W�A�̊�w�ɂ���J�~�ϔO / ���J�c�� ��
����ƃA�C�k���E�ɋ��ʂ���n�� / �ЎR���� ��
����̓c�A���V��Ɩ{�y�̓c�A���V��Ƃ̔�r����/�|���d�Y��
���嗤�I�[�X�g�����A�̓��א��Ɠ������� / �����r�� ��
�V��������̃A���f���e�B�e�B�[�Ƃ��Ă̒�������/�H��^�j ��
�K���ɘa�Ɖ���̌o�ϔ��W / �x�쐷�� ��
�Љ�Ȋw�̂Ȃ��́u���ꌤ���v / �x�쐷�� ��
�����̃w�r�ނɂ��� / ���ʐ��C ��
�����m�������̒��̉���Ɠ��{ / �O�Ԏ�P �ق��q |
�X���A���ܐL�O,�n�v�n����������w�l���Љ�w���ҁu�l�ԉȊw : ������w�l���Љ�w���l�ԎЉ�w�ȋI�v = Human sciences : bulletin of Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of the Ryukyus, Department of Sociology and Human Sciences (8) p.151�`192�@������w�l���Љ�w���v�Ɂu�T���S���ɂ�����T�g�E�L�r�_�Ƃ̕ω�--�ޏꐮ����̔g�Ɗԓ��̎���v�\����B
�P�O���A�u���k�w �u�����D�T�@�i���W �C�Ɠ��̖����j�j�v���u�i�R�`�j���k�|�p�H�ȑ�w���k���������Z���^�[�v���犧�s�����B �W�W�O�~
|
�k�̓��C���E�Ƃ��Ă̒Ìy�C���@�ԓc��v�@p.45�`55
���Ɠ��{�C���E ���� �F�F�@ p.56�`67
�k���̊ۖ؏M�̖���--���V�x���A�E�A���[����E�T�n�����E�k�C����H��ۖ؏M�̗���@�ԉH���t�@ p.68�`79
���������_�@���c�Õv p.80�`92
�ɓ������̍l�Êw--�����{�̂Ȃ��̈ɓ������@���������@ p.93�`111
�C���^�r���[ �����̊C�m���E--<�n��>�Ƃ������@�A<���E�j>�̎���--����͉�
,�ԍ⌛�Y p.112�`127
�C���^�r���[ �������_�̉\��--�G���z������{�C����--�s�쌒�v ,�ԍ⌛�Y�@ p.128�`140
�T�`�o�A�̐�c�Ղ�--�����̏������@��_���F p.141�`173
�g�J���C��j�̎��_--�C���ʂƈٍ��D���q���߂����ā@�^�h���[���@ p.174�`185
�w�C��̓��x�čl--���B�E���������ƃ��I�X�E�^�C�̃A�J���̈��E��p���V��̔�r���� �@���a���@p.186�`200
����̑D�E�q�C�E���J--���b�Ɖ̗w����@�g�Ɗԉi�g p.201�`224
���A�W�A�̊C�l���E�@�H���q�\ p.225�`237
�ۖ؏M�̐��E--�Ǝ��ӃA�W�A�@�o�����qp.238�`252
|
�P�O���A��ԓ����Y�ق����t�A�^�������u�����ÓT���y�W�� Ryukyuan classical music�v���u�r�N�^�[�`�������U�����c�v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�^���f�B�X�N 2�� : CD�@�@���t:��ԓ����Y,�����P��,�V�_�m�P,����h�ܘY(�S,�O��)
��Ԉ��q(�)
|
| DISC1�s�����ÓT���y�W��1�t |
��O���r(1)������ŕ���(2)���[��(3)���ɕ�����(4)����͂O��(5)�����߁q���|�~�r(6)�g��c��(7)������(8)�ԓc�ԕ���(9)������(10)������(11)��J��(12)�����߁q�^���n�̂͂����₤�r(13)�{�c����(14)�^���n�̂͂����₤��(15)�g���H�v�߁q���r(16)����(17)�V���(18)������� |
| DISC2�s�����ÓT���y�W��2�t |
�q�Ə���(�{���q)�r(1)�{�ԕ���(2)�{���q������(3)�ԓc���߁q�̐߁r(4)��c��(5)��܂Â��(6)����c�߁q��̐߁r(7)������(8)�����߁q�Ə���(��g��)�r(9)�U�R��(10)������(11)�q���� |
|
�P�O���A�{���c�v�����L�O���ҏW�ψ���ҁu�����L�O���{���c�v�搶�v���u�{���c�v�����L�O���Ɗ�����v���犧�s�����B�@289p
�@�����F���ꌧ���}���فF1008622738�@�@�d�v
�P�Q���A�F�V��炪�u�f�ڎ� ����Ȋw���� 19 p.57-67�@�����s����w����w�������v�� �u���������Ȍ�A�������ɂ����鉫��Љ�\��
: �ɔg���Q�𒆐S�Ƃ����u�V�m���l�v�W�c�̒a���̍l�@�̂��߂Ɂv�\����B �iIRDB�j
���A���̔N�A�{�і��v�����{�@�������w��ҁu�@���������� = Studies of religious folklore (11) p.1�`24�v�Ɂu���K�_���J�̐��E��--�{�Ó��E���K�̃p�[���g�D�̎��Ⴉ��v�\����B�@�@
���A���̔N�A�g�Ɗԉi�g���u�L���X�g�����������������N�� = Christianity and culture annual : �����Ə@�� (35) p.3�`31�v�Ɂu�n���O���N�L�O �u���� ����̐_�X�̌`��--���b�̐_�ƍ��J�E�|�\�̐_�v�\����B�@�@�@�@�@�@
���A���̔N�A����~�q���u�N�y���� 18 p.5�`22�v�Ɂu�E�`�i�[���`��(����l)�ɂȂ邽�߂̃G�C�T�[--���E���ۘ��ɂ݂�|�\�ƃA�C�f���e�B�e�B�̊ւ��v�\����B
���A���̔N�A�����q�����{�������Y�{��ҁu�������Y���� = Studies in folk-narrative (24) p.152-155�v�Ɂu���] �g�Ɗԉi�g���w�쓇���J�̗w�̌����x�v�\����B
���A���̔N�A���R�Ă��u�쓇���� (23) p.1�`9�@���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v�Ɂu�`�����W���}�̃e�L�X�g�v�\����B�@�@�iIRDB�j�@�@ |
| 2002 |
14 |
�E |
�P���A�O�Ԏ�P���u����w�ւ̓��v���u��g���X�v���犧�s����B(��g���㕶��, �w�p ; 75)
�Q���A�O�Ԏ�P, �g�Ɗԉi�g�Ғ��u��{�����낳�����v���u�p�쏑�X�v���犧�s�����B
�R���A�X���j�ҁu�����V��̐��E�v���u�������o�Łv���犧�s�����B�@�@�@
|
���J�V�� �䉼������݂��ޗǖ~�n�̍��J / �X���j ��
��R�ƎԊy / ������ ��
���o�Ɛ_�� / �s�r�� ��
��������郈���}�V / ���c��[ ��
���^�ƌĂꂽ�i�Վ� / �ɓ��M�� ��
��V�̓`�� / ��؏H�F ��
����_�a�Ƃ��Ẵi���Y�V�Ɋւ����l�@ / ���c�藝 ��
�ʉߋV��ƔN���s�� �݂̂䂭�� / �ߓ����� ��
�E�߂��v� / ����T�V ��
|
�u�Ñ�I�v�����V��̑n�o / �s��G�V ��
��̏��L�`�ԂƐ�c���J�̏� / �������� ��
���Z�̒����� / �����P�T ��
�a��n��ɂ�����J��V�� / �������� ��
�@���ƎЉ� ����o���l�̏@������ / �Ì��D�q ��
���h�Ƃ����ƈꎛ�� / �X�{��F ��
�q�l(�}���r�g)���b�̍\���Ƒ��������� / ���X�؍N�l ��
�ܒ���l�Ɓw�����_���L�x�ɂ݂�\�O���M�� / ������r ��
�����̏@���Ə������� / ���v�` �� |
�R���A�m�O������ψ���ҏW�u�֏��� �������ƕ�(�H���E������)�v���u�m�O������ψ���v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (�m�O�������������� ; ��9�W)�@�@�@176p�@�@�@�����F��㊌����}���فF1004336358
|
��T�� �֏��Ԃ̊T�v
��1�� �T��
��2�� ���v
��3�� �j�Վw��̌o��
��U�� �֏��Ԃ̒���
��1�� ��������
��2�� ���@����
��3�� ���C�T��
��4�� �{�[�����O����
��V�� �������Ƃ̊T�v
��1�� ���Ƃ̌o��
��2�� ���ƌo��
��3�� ���Ƒ̐�
��W�� �������Ƃ̕��j�ƍH��
��1�� �H��
��2�� �A��
��3�� �����E�U���T�C��
��X�� ���p�ƍ���̉ۑ�
��1�� ���p��
��2�� ����̉ۑ�
��Y�� �����ɂ��Ă̈�l�@
��1�� ����Ƃ��Ă̋�Ԑ����̕���
��2�� ���J��Ղ̐����ɂ���
��3�� ���̍֏�_��
��4�� �ό������Ƃ��Ă̍֏���
��5�� �u���������̃O�X�N�y��
�@�@���֘A��Y�Q�v�̐��E��Y�o�^
��Z�� �Q�l����
�@ �֏��ԊW�N�\
�A ������N�p���}
�B �d�v�������w��ƕ��͌��ʂɂ���
�C �Q�l����
�}�}�ڎ�
�T-1-1 �֏��Ԃ̈ʒu
�T-2-1 ��Ԃ̐��� |
�T-2-2�w�������R���L�x�ɋL�ڂ�
�@�@�@���e�ԐE���̌�Ԑ�
�T-3-1 �֏��Ԃ̎w��͈�
�U-1-1 �M���ޒ����̓������[�g
�U-1-2 �g���b�v�̐ݒu�ꏊ
�U-1-3 �M���ނ̊m�F�n�_
�U-1-4 ���ނ̒����o�H
�U-1-5 �����ނ���ނ̒����p��
�@�@���݂����Z���T�X���[�g��
�@�@�����̋�抄(A-D)
�U-1-6 �����͈͂ƒ������[�g
�U-1-7 ���Y�L�ޒ����̓����͈�
�U-1-8 �֏��Ԃ̗��L(1)
�U-1-9 �֏��Ԃ̗��L(2)
�U-1-10 �I�I���h�J���ނ̓������[�g
�U-1-11 �g���b�v�̐ݒu�ꏊ
�U-2-1 �E���[�J�[�ւ̓�
�U-2-2 ������d�����f�ʐ}
�U-2-3 ��ɗ���\���ʐ}
�U-2-4 ��ɗ��n���\�I�o��(1)
�U-2-5 ��ɗ��n���\�I�o��(2)
�U-2-6 ������\
�U-2-7 �O�ɗ��̔r����\
�U-2-8 �O�ɗ�(�C�r�k���[)�̑w��
�U-2-9 �O�ɗ��n��̑w��(�퐶��)
�U-2-10 �E���[�J�[�n��̒�����
�U-2-11 ��(�J�[)���ʐ}
�U-3-1 �T�����@�}
�U-3-2 �T�������}
�U-3-3 �ُ�_�ʒu�}
�U-4-1 �{�[�����O�����ʒu���ʐ}
�U-4-2 �{�[�����O���u�̑S�̐}
�U-4-3 ����암�̒n���}
�U-4-4 ����y�w�f�ʐ}
�W-1-1 �֏��ԋy�ю��Ӑ�����{�\�z�} |
�W-1-2 �֏��Ԑ�����{�v��}
�W-1-3 �V�L���_������
�@�@���A�}�_�����̕����͎��}
�W-2-1 �֏��Ԃ̐A���z���͎��}
�W-2-2 �֏��Ԃɂ�������̐A���ߒ�
�W-2-3 �֏��Ԍ���}�y�ѕ��ʐ}
�W-3-1 �����Ŕz�u�}
�W-3-2 �����E��ɗ�������
�W-3-3 �E�O�p�������
�W-3-4 �E���[�J�[�ق�������
�W-3-5 �T�C���ݒu�ڍא}
�X-1-1 �V������
�X-1-2 �֏��ԃ��[�t���b�g
�X-1-3 �m�O���������K�C�h�u�b�N
�X-1-4 ���������쏭�N��̊���(1)
�X-1-5 ���������쏭�N��̊���(2)
�X-1-6 �u�L��v����
�X-2-1 ���w�Z�̗��j�V��
�Y-1-1 �����̒n��
�Y-1-2 �Ώ����̗�
�\�ڎ�
�U-1-1 ���ރZ���T�X����(1)
�U-1-2 ���ރZ���T�X����(2)
�U-1-3 ���ރZ���T�X����(3)
�U-1-4 ���ރZ���T�X����(4)
�U-1-5 �����ނ���ނɊւ���V��E�C���Ȃ�
�U-1-6 �֏��Ԃɐ������闼���ށA
�@�@����ނ̂����A�����≫�ꌧ��
�@�@�����b�h���X�g�Ɍf�ڂ���Ă����Ƃ��̃����N
�U-1-7 �֏��Ԏ��ӂŊm�F���ꂽ������
�U-1-8 �֏��Ԏ��ӂŊm�F���ꂽ�`���E��
�U-1-9 �֏��Ԏ��ӂŊm�F���ꂽ�N����
�U-1-10 �m�F�퐔�ɂ���
�U-4-1 ������암�̒n���w���\
�E |
�R���A�c�����q�����ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ� : ���ꌧ���|�p��w���y�w������ (3) p.39�`51�v�Ɂu����ό��ɂ�����G�C�T�[�̊T��--�G�C�T�[�c�^�앗(�܂ӂ�����)�𒆐S�Ɂv�\����B�@�@
�R���A�g�Ɗԉi�g���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 14
p.1-125�v�Ɂu���d�R�̗w�ɂ݂�n���v�\����B
�R���A�X�ۉh���Y���u�����w�@�o�w���I�v (2) p.49�`53�����w�@�o�w���v���u������(���[���[��)����(1) �v�\����B
�R���u�n�挤���V���[�YNo.30 ���d�R�A�|�x��������(4)�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�iIRDB�j
|
�܍��L���̐_�J�� : �����̋������́g��"�ɂ���
�@�@�����c���q p1-25
���\���̂��܂ǐ_�M��(��) �E���� p 27-37
���d�R�|�x���V������̏����@�쌴�O�` p39-74 |
���\���ɂ�����Љ�����H: �����ψ��̎��H�𒆐S�Ɂ@��c���q p 75-86
�������� : �V�铇����앗���ւ̈ڏZ:1941�N�̈ڏZ�̌��𒆐S�Ɂ@���n�N�v
p 87-98
��㏉���{�Â̔��d�R�J���ƈڏZ:�V���Ɍ���:1946.6�`1950.5�@���@������ p
99-121
�E |
�R���A���ꌧ���|�p��w���u���ꌧ���|�p��w�I�v (10)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�����ÓT���y���y�c���̓`�����@�ɂ������l�@--��g�u�U�R�߁v�Ɏ�l�}�Ɖ����������� ���� �L�� p.19�`29
����Ђ�ƃG�f�C�b�g�E�s�A�t�B������̈̑��2���U Nakamura Marie-Paule
p.31-56
�{�y���A�ȍ~�̉���ɂ�����m�y�̎�e--���J���t��̑��ʂ��� �O�� �킩�� p.57�`75
�̋� ������A�E���C���z�k�y���y�щ��l ���{ �M�v p.77�`93
�������x�ɂ�����������x�̌���--����S���̑n�앑�x��i��� ���g �Ύ} p.95�`117
�n��m�[�g ��i �J���オ�� �j�� ���q p.121�`123 |
�R���A���ꌧ�����U���ەҏW�u�����Ɩ��ʐ^�ژ^ : ���ꌧ��������p��(����)�@����14�N�x�v���u���ꌧ�����U���ہv���犧�s�����B�@�@�@���t�̃^�C�g��: ����14�N�x�����Ɩ��ʐ^��i�ژ^
�R���A�����������ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (28) p.13�`54�@���ꌧ�������فv�Ɂu�����p������y�����قɂ��āv�\����B�@
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 11�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1003770110�@ 2002�E�R
|
�L���X�g������������ ���J�u���� �u����̏����̒n�ʂƖ����v ��Ð��v
�g�O�`�t�@�C�����O�V�c�e�����j�^�����O�J�n�Ɋ�
�@�@���n���P���@(����}�C�N���Z���^�[) |
�n���P������̂���-���������A
�@�@������A�������E- ���� ����
�ҏW��L |
�R���A�^�������u����䂵����`�������x�ȁv���u�L���O���R�[�h�v���犧�s�����B�@
�@�@�@�@�^���f�B�X�N 1�� �F���^����: 78��58�b
|
(1)������ŕ�(��������ł��ӂ�)(2)�l�璹(3)���߃��[(4)��ԓ�:��ԓ��߁`���ʖ�(�����ʂ�)��(5)��[��s(���ʂԂ��傤)(6)�щ�(�ʂ���):���x�߁`��Ԑ�(7)���P�x��:�Ԋ}�߁`��������(8)���Ԑ�(9)�g��c(���������Ă�):�g��c�߁`�ɏW����c(������͂������Ă�)��(10)�ɏ���:����c�߁`�ɏ���(11)������(�ʂԂ����ǂ���)(12)�������(���������ǂ���)(13)�O�V�l(�߁[�ʂ͂�):�O�V�l�߁`�⌴����(������炭�ǂ���)�`�^�ߌ�(��Ȃ�)��(14)�J���O(����߁[):�J���O�߁`�Ɍv��(�����͂Ȃ�)��(15)�H�̗x��(16)�l�c�|(�x���͂ł�)(17)���D(�Ƃ�����)�h�[�C |
�R���A�O�،����u�{�ǒ��� : �u���ꉹ�y�v�̐��v���u�j���C�Ёv���犧�s����B
�@�@�@333p�@�@�@�@�����F��㊌����}���فF1003750237
|
�P�@�{�ǒ���̐��U
�@�@�@�@�i�u���ꉹ�y�v�̃p�C�I�j�A�G���y�Ƃ̌��G�����ɔR����G�̋����d�R����ɁG�吳���̉��ꌧ�t�͊w�Z�Ł@�ق��j
�Q�@�{�ǒ���y�I�s
�@�@�@�@�i������f�B�[�̗����X�G����̂ӂ邳�Ɓ@
�@�@�@�@�����d�R�i�Ί_�E�^�ߍ��j�G���������̎c�f-�E�ߔe�G���d�̒��H�͂邩-�v�ē��G����邳��-��u���j
�{�ǒ����Ȗژ^: p320-323�^�{�ǒ���N��: p324-328�^�Q�l/�֘A����: p330-332 |
�S���A�u���k�w �u�����D�U�@(�y���W�z<��>�̐��_�j)�@�v�� �u�i�R�`�j���k�|�p�H�ȑ�w���k���������Z���^�[�v���犧�s�����B
|
���k �u�C��̓��v�Ɠ쓇����--���c���j�̎v�z�̍Č����@�J�쌒��,�����a,�ԍ⌛�Y�@ p.65�`83
��̓ꕶ���E--�����ЂƂ̓ꕶ�����@�V���W��@ p.84�`109
�g�J���A���̊C�m�����@���i�a��@ p.110�`119
�L�J�C�K�V�}�̌Ñ�E����--<��>�̋��E�̈�ւ̂܂Ȃ��� �@�i�R�C��@
p.120�`131
�m��ꂴ�鉂�������j�@�����C�@ p.132�`147
���i�Ǖ����̖����M�@��c �����@ p.148�`157
�N���_���̓� �@�����i p.158�`166
����̌��--���̐��n�ς��߂����� �㌴�F�O�@ p.167�`175
�������{�Ə��������@�@�������q�@ p.176�`187
�{�Ó��E�떓�̗̉w�ƋV�� �ʏ���@ p.188�`199
�C���^�r���[ ����̍l�Êw�̌���--�L�ˎ���E�E���}����E�O�X�N����@���{�A�q,�c��R���Y,�㌴�F�O���@
p.202�`220
��̌��t�u�A�t(��)�v�̎������E��--����Ƌ��ʂ���A�C�k��n������ǂ݉����@�ЎR���� p.221�`231
����̓c�A���Ɓu�c�A���́v--�A�}�E�F�[�_�̎��Ӗ� (�y���W�z<��>�̐��_�j)�@�@�|��
�d�Y�@�@ p.232�`241
<�o��> �A�C�k���w�Ɨ������w--���c�ꋞ���ƈɔg���Q�Ɋւ��@�g�Ɗ�
�i�g�@ p.242�`253
�ߑ㉫��̎����Ə]��--�ɔg���Q�̓z�����_�𒆐S�Ɂ@�^�h�� �[���@ p.254�`267
�ɔg���Q�ɂ�����u����w�v�̌`��--�������c�_�Ɣ�r����w�̉e���@���Ô�
���@ p.268�`284
����d�N�̖����w--���̒���I�p���̂��߂Ɂ@��� �a���@ p.285�`295
���|�l�V�A�͂ǂ��֍s����--�d��A�x����A�����ĉz������EXO �@���� ���@
p.296�`305 |
�S���A�u�܌��M�v�S�W ����@�S�v���u�������_�V�Ёv���犧�s�����B
|
�܌��M�v���u�܌��M�v�S�W ����i1�`40�j�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
���s�N�� |
������e�i 1995.2-2002.4�j |
| 1 |
1995-02 |
��狋�Ƃ����M��/�x�����b�q �܌��M�v�̕��w�����_�Ƃ̏o�/�Ë��M�F �܌��M�v�̕��s
/ �P�@�ҏW������ |
| 2 |
. |
�nj��A�������͌����Ȋw�̔���/��ؒ���@�u�܂�тƂȂ�S�v�̂���/�쑺����@�܌��M�v�̕��s
/ �Q�@�ҏW������ |
| 3 |
. |
���k��Q�[���߂�����/�J�쌒��@�u�܂�тƁv���邢�́u�O���v����̔��z/�����a�F�@�܌��M�v�̕��s/
�R�@�ҏW������ |
| 4 |
. |
�w���҂̏��x���z/�쑺��Y�@���I����/ �X�R�d�Y�@������/�L�˖Ύ��@�ҏW������ |
| 5 |
. |
�܌��M�v�ƕ��y�L�Ǝ�/�u�c�x��@�q���낲�̂݁r�̘_/��ؓ��o�j�@�܌��M�v�̕��s/
�S�@�ҏW������ |
| 6 |
. |
�w��D�k�n�x�Ɓw���撟�x/�����i�@�܌��̔�r�����w/������@�܌��M�v�̕��s/
�T�@�ҏW������ |
| 7 |
. |
�w���t�W�u�`�x�̂���/�X���j�@�w���t�W�x�ɋL���ꂽ�]��/�R�{���g�@�܌��M�v�̕��s/ �U�@�ҏW������ |
| 8 |
. |
�`�{�l���C���V���l���čl/����x�`�@�e�L�X�g�Ƃ��Ắw���̑`�x����/�ߓ��M�`�@�܌��M�v�̕��s/�V�@�ҏW������ |
| 9 |
. |
�B��݂�/�ےJ�ˈ�@�ҏW������ |
| 10 |
. |
�u��q��v�̗�/�n�ꂠ���q�@�w����x���^��/�����Z��@�܌��M�v�̎����ƏW����/�������@�ҏW������ |
| 11 |
. |
���t�тƂ̎��T�� / �����Z��@�ǓƂƂ����炢/����Ɏq�@�Ɍ��̒�����/�������@�ҏW������ |
| 12 |
. |
�[�ł̌lje/�a�c�@�O��d�����܌��M�v�̑n���J�߂��Ӗ�/���������@�w��̕��@�Ƃ��Ă̗�/�������@�ҏW������ |
| 13 |
. |
�w���҂̏��x�Ɓu�g�Ŋہv��/��g��@�O��d�����܌��M�v�̑n���J�߂��Ӗ�/���������@���c�̊w�ւ̎Q��/�������@�ҏW������ |
| 14 |
. |
�O��d�����܌��M�v�̑n���J�߂��Ӗ�/���������@�O�M���R�Ԓn�т̗�/�������@�ҏW������ |
| 15 |
. |
�܌��M�v�̉z��/�O�c����q�@�܌�����ƕ� / �֓��Α��@�܌��M�v�̗��̎�� / �������@�ҏW������ |
| 16 |
. |
�܌����m�Ɖ�������/�����^��Y�@���{�̗썰�M��/�����ی���@�@����Ɏc������Ñ㐶��/�������@�ҏW������ |
| 17 |
. |
���e�̐l/�������@�܌��M�v�̓��@/��k��@�����M�ւ̒��� / �������@�@�ҏW������ |
| 18 |
. |
�܌��w�̊w�K / �j���F�V�@�܌��M�v�Ɖ���ŋ� / �O�����Y�@�m�F���ꂽ���K�_�̋�ې�
/ �������@�@�ҏW������ |
| 19 |
. |
���@���Ƃ��Ă̐_����/����V��@�܂�тƘ_�\�z�ւ̒��� / �������@�ҏW������ |
| 20 |
. |
�猩�����s�Ƌ����̖�����/���p�䐳��@�܌��搶�̏f�ꂳ��/�������v�@�ҏW������ |
| 21 |
. |
�܌��M�v�Ƒ啧���Y��/���c���F�@�܌��M�v�̏����ςƃZ�N�V���A���e�B/�������q�@�ҏW������@
�܌��M�v�S�W�S�R�V���ʊ��S��������\�ꊪ |
| 22 |
. |
�V���w�ւ̊���/��c�ā@�@�܌��M�v�̂܂Ȃ���/���쒼�V�@�ҏW������@���l�� |
| 23 |
. |
�܌��M�v�Ɖ���/�O�Ԏ�P�@�@�u���̉ԁv��/�����a�@�@�ҏW������ |
| 24 |
. |
�u�V�Í��O��v�̖���/�쑺�W���@�@�܌��M�v�Ɖ���/�O�Ԏ�P�@�@���̐��ƗF�l/�����a�@�@�ҏW������
|
| 25 |
. |
�ǂ�Ŗʔ����w�����A���W�x /�O��K�Y ���́w�Ñ�����W�x /�{�m���� �Z�̂��玍��/�����a
�@�ҏW������
|
| 26 |
. |
����̖쐫�Ƃ��Ă̏���/ ����V��@�@���̌`���Ɛ�/ ��@�@�ҏW������
|
| 27 |
. |
��㗬�́w���̌X��x/�䍡���q�@�j�_�u���������̏o���v�Ə������u������̊��v/�O�Ԏ�P�@���̌`���Ɛ�/���@�ҏW������ |
| 28 |
. |
�_�����̖��/���c�`�Y�@�����Ԃ�̃A�W�A/ ��@�ҏW������
|
| 29 |
. |
�퐢�̂�����/���{����@�����Ԃ�̃A�W�A/ ���@�ҏW������@�@�t�^�G �Βk
�̐l�����č����w��/�ےJ�ˈ�C����O�F
|
| 30 |
. |
���a�\�N�̐܌��M�v�̑�O�ꗷ�s/���F�M�@�@�g�����̂��h��z��/�����a�@�ҏW������ |
| 31 |
. |
��(�J�w)�̂���/�����L���@�g�����̂��h�̊o��/�����a�@�ҏW������
|
| 32 |
. |
���I�푈�́q��㐢��r/���v�ۑK�@�w�����A���W�x�Ƃ͉���/�����a�@�ҏW������
|
| 33 |
. |
������z���s/���������@�̂Ɗw��/�����؍K�j�@�ҏW������
|
| 34 |
. |
�g�쐶�̎v�l�h�̐l/ ��c�����@���w�@��̐E������/�����t�q�@�܌��M�v�Ɖ��[����
/ �P�@�ҏW������
|
| 35 |
. |
�w���҂̏��x�̖�/�Γ��O�@�@�܌��M�v�Ɖ���̉��l/�O�Ԏ�P�@�@�ҏW������ |
| 36 |
. |
�Ō�̋����q/���s��@�܌��M�v�Ɖ��[����/ �Q�@�ҏW������
|
| 37 |
. |
�܌��M�v�ƍ��w/���c����@�[���̔���/�c���T�@狋�Z�̎���/ �P�@�ҏW������
|
| 38 |
. |
�Ñ㒆���ƌÑ���{�̏퐢���E�يE��/��g���q�@�܌��M�v�ƃI�[�����E�R���|�W�V����/�����T�ȁ@狋�Z�̎���/2�@�ҏW������
|
| 39 |
. |
�\�o�E�v���āE�o�_/�����j�@��狋�́u���@�ᑠ�v/��ϐ����@��狋�̘A��/����O�F�@�ҏW������
|
| 40 |
2002-04 |
�M�v�搶�Ɏ���g�����/�c�Ӑ��q�@���c�搶�͖����̐l/����O�F�@�ҏW������ |
|
�U���A�����������u����̔M�����v���u���|�Ёv���犧�s����B
|
�O����
�Ђ߂�蕽�a�F�O������ - �����̕����ɂ� -
�r��C��
���ꌧ���a�F�O������
���a�̑b�`�����̓� |
�����̓�
�A�u�`���K�}�i�����̍��j
���������p��
�Î�[�u���ۂ̌�����u�v����
�V���N�K�} |
�ɍ]�� - �k�`�h�E�^�J���i��������j�̉�
�ɍ]�� - �F���̓�
��܂� - �Ӊԉx�q����̘b���� -
�ꖜ�l�̃G�C�T�[�Ղ�
�㏑�� |
�U���A���Ƃ킴������,����P,�D�Ð�,�����D�q���u��������A����ی��W�ق��v���u�N���X�o�Łv���犧�s�i�����j�����B�@ (���Ƃ킴�����p�� / ���Ƃ킴�������, ��9��)
|
�u��������v�@�@���{: �]�ˊ�, �n���C��w��敶�ɏ���
�u��������Í��W�v�@�@���{: �]�ˊ��ٖ{, ���ꌧ���}���ُ���
�u�����ی��v�@���{: �w�����l�ފw�G���x, ����30(1897)-33(1900)����
�u����������W�v�@���{: ����33(1900), �w�����V��x�f�� |
�u���z�ی��W�v�@���{: ����39(1906).5, �w�����V��x�f��
�u�ی��Ƌ��P�v�@���{: ����39(1906).6, �w�����V��x�f��
�u����ی��W�v�@���{: ����42(1909), �w���ꖈ���V���x�f��
���: �����D�q |
�U���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� ��21���v���u����l�Êw��] ���犧�s�����B�@72p�@�������F���ꌧ���}���فF1004282149
|
15���I��̃^�C�E�m�C��q�n�l���قɂ��� �������E
�@�@����u���̓��v(1459�N��Αw�ꊇ)���S�Ƃ��� ���n���L
����̈�Ղ���o�y���铝���o�ω��̎��� �R�{����
�O�X�N����W�������̓���(��) �c���R�k
�� ���܈���
�����Ղ̍��u���n�ɂ��� �V���M�V
���g�Ɗԓ����c���L�ˍ̏W�̐Ί펑�� �㌴�� �@������,�����@p.37-48�@ |
����E�v�ē��E�����L�ˍ̏W���� ���t��
��4�� ���ꌤ�����ۃV���|�W�E�� ���[���b�p��� �{��ޏ�
���]
���q�_���w���q�_������ژ^�W�x
�������Y���w�O�X�N�T�K�K�C�h�x
�w�쓇�l�Áx�o�b�N�i���o�[�̏Љ�
�E |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���g�Ɗԓ����c���L�ˍ̏W�̐Ί펑���@��L�̘_���͒��Җ��̊m�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�U�E�P�U�@�ۍ�
�V���U���`�Q�W�����A�Y�Y�s���p�قɉ����āu�����Ɩ��ʐ^�W : ����}���_��
�v���J�����B
�@�@�@��� ; �Y�Y�s���p�� ���� ; �Y�Y�s����ψ��� ���� ���ꌧ
7���A���v�`������w�j�w�E�n���w��ҁu�j�� = Shisen : historical & geographical studies in Kansai University (96) p.1�`17�v�Ɂu�u�� �_�{�я��Ɛ��т̐��b�v�\����B
�W���Q�T���A�u����s����ّ�z�[���v�ɉ����āu�k���O�Y 45���N�L�O���� :
���A30���N�L�O ����ŋ������v���J�����B
�W���A�k���O�Y�ҁu�k���O�Y 45���N�L�O���� : ���A30���N�L�O ����ŋ�����
�v���u�k���O�Y45���N�L�O�������s�ψ���v���犧�s�����B�@ 2002 (����s�|�\�� ; ��8��) �����p���t���b�g �@�@28p �@�����F��㊌����}���فF1005229370
�W���A���R�S�m �Ғ��u�S��������~���[�W�b�N�v���u�h���~�y���o�ŎЁv���犧�s�����B�@�@ (�s�A�m�E�\���E���C�u�����[)�@�@121p
|
�S��������~���[�W�b�N
1.�@��(�Ȃ�)���������@BEGIN�@12�E106
2.�@���Ƃ����є��@�������Ȃ��݁^�X�R�ǎq�@15�E106
3.�@���_�c�~�̖@�����Ƃ��@18�E107
4.�@Best Friend�@Kiroro�@21�E107
5.�@�V�����G�̃S�[���[�}���@�K���b�W�Z�[���@24�E108
6.�@���ł��N�����@��X�E���@27�E108
7.�@NEVER END�@�����ޔ��b�@30�E109
8.�@���S�@THE B00M�@34�E109
9.�@�����ԁ@Kiroro�@37�E110
10.�@�ԁ@��[���g�@40�E110
11.�@�߂ł����߂ł����@���o���h�@43�E111
12.�@�������C�@��X�E���@46�E111
13.�@�o�C�o�C����@�l�[�l�[�Y�@50�E112
14.�@�����̉ԁ@�l�[�l�[�Y�@53�E112
15.�@�E���J�W�i�ʉe�j�@�l�[�l�[�Y�@56�E113
16.�@������@TINGARA�@59�E113
17.�@��Ԕ�s�@TINGARA�@62�E114
|
18.�@���肪�Ƃ��@���o���h�@65�E114
19.�@����@BEGIN�@68�E115
2O.�@����i�����ȁ[�j�@�N�얾�@72�E115
21.�@���C���C�i���ꁬ���@�[�W�����j�@�㌴���F�^�m����j�@75�E116
22.�@���̃u���[�X�@�O���݁^�a�c�O�ƃ}�q�i�E�X�^�[�Y�@78�E116
23.�@���l�i���܂�j�ʕ�@BEGIN�C�V�ǍK�l�C�哇�ۍ��C
�@�@���Đ��݁C�l�[�l�[�Y�C���[���[�@82�E117
24.�@�����܂܂Ɂ@��[���g�@84�E117
25.�@����ǂ��̉ԁ@����h���^�{�ǒ����@87�E118
26.�@�m�ԕz�@�g�����^���v���P�E�@90�E118
27.�@�Ă����ʉԁ@���ꖯ�w�@93�E119
28.�@�J���O�i����߁[�j�@���ꖯ�w�@96�E119
���ꖯ�w���h���[
29.�@�����������^�@���ꖯ�w�@100�E120
30.�@������i�ɂ��傤�j�߁@���ꖯ�w�@101�E120
31.�@���Ԑ߁@���ꖯ�w�@102�E121
32.�@�g�D�o���}�i�J�k�V���}�߁j�@���ꖯ�w�@103�E121
�E |
�P�P���A�m���芰���u�_����j�w = Shinjodaishigaku : the journal of history 19 p.43-65�v�Ɂu�����~�o���ƈ������̑n���ɂ��āv�\����B�@�@�@�iIRDB�j
�P�Q���A���c�������u�����Ȃ�_�X�̓`�� : ����̐��n�v���u�����[�v���犧�s����B
�@�@�@�@231p�@�@�����F��㊌����}���فF1003878392
�P�Q���A�ʏ闬�����݉�g�Ύ}��������ҁu�������x-�V�ɕ���- : �ʏ闬�����݉�
���g�Ύ}��������@�Ƌ����^���x�����i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ闬�����݉�g�Ύ}��������v���犧�s�����B�@�@�@�k6p�l�@�����F��㊌����}���فF1004692016
�@�@�@ �����F2002�N12��26�� �@�ꏊ�F�p���b�g�s������
���A���̔N�A�u�f�������@����v�����̃C�U�C�z�[�v���u�����V�l�}�V�Ёv���犧�s�����B�@ DVD�F2�� (112��)
|
| DISC1�q��ꕔ�r |
�E�K���_�e�B/�Տꏀ��/�E�v�e�B�V�W/���N�l�[�K�~�A�V�r/�n�V�������A�V�r/�^���}�~�L/�郊�L�B |
| DISC2�q��r |
�j�[���[�n�[���[/�A�T���}�[�C/�O�b�L�}�[�C/�V�f�B�K�t�[/�t�o���N |
|
���A���̔N�A���ь��],���эK�j�����y��������ҁu���y������ (�ʍ� 19)
p.11�`32�v�Ɂu����s�̎�x��G�C�T�[--�{�����E���A�m���Ƃ̔�r��ʂ��āv�\����B
���A���̔N�A�Óc���q�A �����͎q, ��ؗR��q, ���эK�j, ���ь��]���u����O�����ɂ�鋞�s���r�n�̂̐ߕt
: �M�D�E���炵�E����̏t�v���u���s�c����v���犧�s����B
���A���̔N�A�T����, ����ό����Ƌ����g�����u�����ނ���̂����� : �����������x���������c�v���u�i���[���j���K�R�������v���犧�s����B
���A���̔N�A����~�q���u��剹�y�w�� (1) p.21�`31�v�Ɂu�������т������|�\--����E�猴(�����)�G�C�T�[�v�\����B�@�@
���A���̔N�A�����������u���{�E���N�����암�E��p�̋����Ƒ��M�ɂ��āv���u�������F��������v���犧�s�����B�@����
|
�u��������w��w�G���v33-45���Ɍf�ڂ��ꂽ�u���{�̋����Ƒ��M�ɂ��āv1-7���A
�u���N�����암�ɂ����鋌���Ƒ��M�ɂ��āv�A�u�������̋���,���M�y�ѐ��b�vA-D�̔������������{�������� |
|
| 2003 |
15 |
�E |
�P���A���c�W�ďC,�k���c�W�l�ËH�L�O�_�W���s�ψ���ҁu�`�������̓W�] : ���{�̖����E�ÓT�E�|�\�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B�@
|
�����`�� �t�̗R�����̐��� / �i���� ��
����E�c����߂��邢���Ȃ�����F�� / �����P�� ��
�����u�ތρv�̉��o�ƈ�אM�� / ��X���q ��
���̉����ɍ������Ă� / �����o�j ��
�����`�� �C�U�C�z�[�̎�t���V�т̃e�B����/���R�� ��
�����V�}�E�^�Ɣߌ��`�� / ����i�K ��
�u���̓��v�̌��ג� / ������Y ��
���ԑ�e�Ǝ@�x�� / ���c�M�V ��
���̐_�̐��b�`�� / ���эK�v ��
�ዷ�̐��s�`�� / ���{�F�O ��
�n���M�Ɛ��b�E�`�� / �ԕ��p�Y ��
�p�q杂ɐ��ނ��� / ���n�S���q ��
�u�G�p���[�v�̗��D�̏� / �O�Y�r�� ��
�N�V���~�̑��M�Ɛ̘b / ����O ��
���̐_�b�̐��� / �^���� ��
�ÓT�`�� ���d�����_�̐��i / �ێR���� ��
�u�����I�v�̗w�̔F��ƓW�J / �{���O ��
�X�^�\�[�}���{��杂Ɓw�O��G�x / �����j ��
�Í��W�ɂ݂�Ñ�́u������v / �_�c�m ��
�w��������x�鍳��O����杂̔w�i / ��{���q ��
�ٔ\�̈��m�B / �����^�� ��
��s�����̋�������y�� / �����K�� ��
�^�������w���o�ˊw���x���߂��鉝���`�̌n��/���䍲����
�^���{�w�]�䕨��x�ɂ�����
�@�@���V�c���o�咖�ގ��̍\�z/��{���N�G �� |
�w�]�䕨��x�Ɓw�x�m�쉝���x / ������o�u ��
����̍�Ҋ� / ���є��a ��
�w�ٖ{�`�o�L�x�̍\�z / �R�{�~ ��
���S����S�@������i�O�^�O���Ή掲���߂�����/���{�� ��
�`�����|�Ɛ}�� / ���c�a�v ��
�w���������Y�x�����_ / �^������q ��
�䉾���q�w�핺�q�l�x�̏���� / ���Q�v�q ��
�؍��ϏB���́u�����{���v�l / ���^�� ��
���t�l�̐��� / �c������ ��
���~�̎� / ��M�F ��
�ԁw�R���̏��x�_ / ���Z���d�� ��
�v�z�E���� �O�֗��_���ɂ�����_����
�@�@�������ƌc�~�`/����������
�w[�A�C]�X��x�̑嚢�` / �����쌳�� ��
�������u�F��R���Z�������z�L�v�̌��\�Ɛ�������/��荄�u��
�����Љ�w���R���N�x / ���؏ˎq ��
���`�u���̌Ñ㑜�Ɛ����̌Ñ㑜 / �R���v�v ��
�|�\�`�� �s���Y�t�̐����Ɠ�k������ / �V�앶�Y ��
�\�s�^���䌴�t����̓��@�Ɣw�i / ���ь��� ��
���ȁu���d�v�ɂ��Ă̍l�@ / ����ޓs�q ��
�w�r���A��[�^�}�c�o�L]�x���l / ���c���g ��
�����́u�C���S��v�ɂ��� / �{�c�x�� ��
���M�ӑm�Ɛg���I���� / ���C���� ��
�ߑ�̕��Q / �����z�q ��
���������|�\�̔��� / �떓�b�� �� |
�R���A���c�W, �R���ӈ� �ҁu���M�E�ӑm�̓`�����E ��2�W�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B
|
���g�R�������̍��J�w���g�R���Ղ𒆐S�Ɂx/���c���i/5
���g�Ђ̛ޏ��E�L��q�E�؎�/�����^�l/24
�_�������ȑO�̐_�q�E���w�Ɛ_�y�E�F���̎��ԁw�R���R�̖��w�ЂƔ�O�̗S����ׂ𒆐S�ɂ��āx/��X�b�q/54
�ޏ��̓���w�����N�ƋV��p��x/�쓇�G��/73
�����̃��^�Ɓu�V���[�W�v�̖��w�\�@�Ƃ��āx/�R���ӈ�/89
�u��ƏC���v��������/�i����/115
�c��T�t�M�̓W�J�Ɣ��C�R�s��/��؏��p/130
�Δn�̍Օ��̐��E����w�u�l������q�F���v�Ɓu�l���̂����v�i�������ꎁ���j�y�ё��c�Օ����߂����āx/�����M�v/162
�����Ȃ����u�V�Y���̍Օ��v�ƕa�l�F���̐��E/�֓��p��/180
�w������{�n�x�w���B��{��{�n�x�̌������i��j/���c�W/205
�ѕ���́w�S�G��}�x�Ƌ��@���{�w�F��ϐS�\�E�֒����x/��؏@��/233
���̖ӑm�E�ޏ��ɂ��āw�א��҂ɂ������̎戵�����߂����āw�x?/���`�M�v/257
�n�_�ӑm�ƍr�_�M��/�������F/273
�ӑm���@�̌n���w�{�茧���s�s����W���̒n�������N�x/�����h�g/292
���������̊�b�I�l�@�w�w�����E�v�^�x�ɂ��āx/��؍F�f/332
���Ƃ���//361 |
�R���A�c�����q�����ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ� :
���ꌧ���|�p��w���y�w������ (4) p.93�`104�v�Ɂu�G�C�T�[�̓`���Ɋւ����l�@--����s���c(����)�N��̃G�C�T�[�̃t�B�[���h���[�N��ʂ��āv�\����B
�R���A�L���s�j�҂���ψ���ҁu�V�C�L���s�j ��7�� �����v�����s�����B
|
��1�́@����s�s�̒��̖���-
�@�@���L���̐����������l����-�@1
��1�́@1�@�{���̂˂炢�@2
��1�́@2�@���������̓����@3
��1�́@3�@�{���쐬�̂��߂̖��������@4
��1�́@4�@�L���s���3�̖����w�@5
��1�́@4�@�ނ�Ƃ��Ă̖L��
��1�́@4�@����Ƃ��Ă̖L��
��1�́@4�@�V�����}�`�Ƃ��Ă̖L��
��1�́@4�@����̖L���̕���
��1�́@5�@�����w�ɂ�����u�����v�T�O�̍Ē�`�@11
��1�́@6�@�s�s�́u�����v�ց@12
��1�́@7�@��s�s�ߍx�̓s�s�E�L���̖������@13
��2�́@�ނ�Ƃ��Ă̖L���@15
��2�́@��1�߁@�ނ�̈ڂ�ς��@16
��2�́@��1�߁@1�@�ނ�@16
��2�́@��1�߁@1�@�ނ�̎���
��2�́@��1�߁@1�@�����c��ނ�
��2�́@��1�߁@2�@�ߐ��̂ނ�@19
��2�́@��1�߁@2�@�ނ�̐��藧��
��2�́@��1�߁@2�@�ނ�̐���
��2�́@��1�߁@2�@�ނ�̓���
��2�́@��1�߁@2�@����l
��2�́@��1�߁@3�@�ނ�̐����@26
��2�́@��1�߁@3�@�ނ�Ƃނ�
��2�́@��1�߁@3�@���ɂ�
��2�́@��1�߁@3�@�ނ�̊K�w
��2�́@��1�߁@4�@�ߑ�̂ނ�@32
��2�́@��1�߁@4�@�ނ�Ƒ�
��2�́@��1�߁@4�@���܂��܂ȉ���
��2�́@��1�߁@4�@�n��Ə���
��2�́@��1�߁@4�@��V�c�̏�
��2�́@��1�߁@4�@���쑈�c
��2�́@��1�߁@4�@�_�n���v�Ɛ痢�j���[�^�E��
��2�́@��2�߁@�ނ�̎d�g�݁@46
��2�́@��2�߁@1�@�ނ�̑g�D�Ɖ^�c�@46
��2�́@��2�߁@1�@�ނ����
��2�́@��2�߁@1�@�ނ�̂�����
��2�́@��2�߁@1�@�撷�Ƒ���
��2�́@��2�߁@1�@�J�C�`����
��2�́@��2�߁@1�@��荇��
��2�́@��2�߁@1�@�J�P�}�C�E�~���f���E�������
��2�́@��2�߁@1�@�f�c�u�V(�o�ׂ�)
��2�́@��2�߁@1�@�ނ�x��
��2�́@��2�߁@1�@�ݏ�
��2�́@��2�߁@2�@�ނ�Ōق��@58
��2�́@��2�߁@2�@�����h�R(������)
��2�́@��2�߁@2�@�A���L(����)
��2�́@��2�߁@2�@����
��2�́@��2�߁@3�@���������ց@61
��2�́@��2�߁@3�@������
��2�́@��2�߁@3�@������
��2�́@��2�߁@4�@�J�C�`�ƍs���@63
��2�́@��2�߁@4�@�J�C�`(�_��)
��2�́@��2�߁@4�@�ɐ��u
��2�́@��2�߁@4�@�N��
��2�́@��2�߁@4�@��u
��2�́@��2�߁@5�@�ނ�̂��܂��܂ȑg�D�@69
��2�́@��2�߁@5�@��ґg
��2�́@��2�߁@5�@�N��E�N�c��
��2�́@��2�߁@5�@�Ղ�ƐN�c
��2�́@��2�߁@5�@���h�c
��2�́@��2�߁@5�@�V�l��
��2�́@��2�߁@5�@���ƒh��
��2�́@��2�߁@5�@����u�ƈ�u
��2�́@��3�߁@�l�Ɛl�̂Ȃ���@82
��2�́@��3�߁@1�@���g�@82
��2�́@��3�߁@1�@����
��2�́@��3�߁@1�@�n��w�̒ʍ�
��2�́@��3�߁@1�@��ʂ̒ʍ�
��2�́@��3�߁@1�@�ʍ���
��2�́@��3�߁@1�@�J�h�~�Z
��2�́@��3�߁@1�@�{�q���g
��2�́@��3�߁@2�@�e���W�@91
��2�́@��3�߁@2�@�I�����ƃC���L��
��2�́@��3�߁@2�@�V�����C
��2�́@��3�߁@2�@�{�E���ƂƃV�����C
��2�́@��3�߁@3�@����l�ƃf�C��(�o����)�@97
��2�́@��3�߁@3�@�N�G���
��2�́@��3�߁@3�@�f�C��
��2�́@��4�߁@�ނ�̕�炵�@100
��2�́@��4�߁@�H��
��2�́@��4�߁@�ߕ�
��2�́@��4�߁@�Z�܂�
��2�́@��4�߁@������
��2�́@��5�߁@�ނ�̐���?�_�Ɓ@111
��2�́@��5�߁@1�@�_�Ƃ̂���܂��@111
��2�́@��5�߁@1�@�L���s��̔_��
��2�́@��5�߁@1�@���
��2�́@��5�߁@1�@���Ɖʎ�
��2�́@��5�߁@1�@���Y���̕ω�
��2�́@��5�߁@2�@��э�@116
��2�́@��5�߁@2�@�c�A���܂�
��2�́@��5�߁@2�@�c�A��
��2�́@��5�߁@2�@���̊Ǘ�
��2�́@��5�߁@2�@���n
��2�́@��5�߁@2�@����
��2�́@��5�߁@2�@�_�ƂƋ�
��2�́@��5�߁@3�@�^�P�m�R�@124
��2�́@��5�߁@3�@�^�P�m�R�͔|
��2�́@��5�߁@3�@�^�P�m�R�s
��2�́@��5�߁@4�@���|�앨�̕ϑJ�@126
��2�́@��5�߁@4�@�~�J���͔|
��2�́@��5�߁@4�@�Ԗ͔̍|
��2�́@��5�߁@4�@�Ԗ̏o��
��2�́@��5�߁@4�@�T�c�}�C���Â���
��2�́@��5�߁@4�@�Ԗ̍ċ�
��2�́@��5�߁@4�@���Ԃ͔̍|
��2�́@��5�߁@4�@�ċe
��2�́@��5�߁@4�@�C�`�S�͔|
��2�́@��5�߁@4�@�ԓ��͔̍|
��2�́@��5�߁@4�@�ԓ��̏o��
��2�́@��5�߁@5�@�R�̗��p�@134
��2�́@��5�߁@5�@�R�̒��̂ނ�
��2�́@��5�߁@5�@���L�R�̕ϑJ
��2�́@��5�߁@5�@�R�̕���
��2�́@��5�߁@5�@�A�}�I�`
��2�́@��5�߁@5�@���̔���
��2�́@��5�߁@5�@�ĂƐd
��2�́@��5�߁@5�@����
��2�́@��5�߁@5�@�R��
��2�́@��5�߁@6�@�������猩���_�Ƃ̕�炵�@139
��2�́@��5�߁@6�@�_�Ƃ̏���
��2�́@��5�߁@6�@�씨�̉ԙ��͔|
��2�́@��5�߁@6�@�_�Ƃ̗{���ƂȂ�
��2�́@��5�߁@6�@�ƋƂ̎�`������
��2�́@��5�߁@6�@�o�c�҂�
��2�́@��5�߁@6�@�_�Ƃł̐���
��2�́@��5�߁@7�@��ƒr�@147
��2�́@��5�߁@7�@�L���̗p���H�Ɣr���H
��2�́@��5�߁@7�@�痢��
��2�́@��5�߁@7�@������
��2�́@��5�߁@7�@��̍a���炢�ƍ^��
��2�́@��5�߁@7�@���ߒr
��2�́@��5�߁@7�@�C�P�K�J��
��2�́@��5�߁@7�@�r�̂��܂��܂ȗ��p
��2�́@��5�߁@7�@���ߗ��Ă�ꂽ���ߒr
��2�́@��5�߁@7�@�Z��J��
��2�́@��6�߁@�l�̈ꐶ�@158
��2�́@��6�߁@1�@�͂��߂Ɂ@158
��2�́@��6�߁@2�@�o�Y�@158
��2�́@��6�߁@2�@�o�Y�̏���
��2�́@��6�߁@2�@�o�Y
��2�́@��6�߁@2�@�吳����ȑO�̏o�Y�̗l�q
��2�́@��6�߁@2�@��Y�̏���
��2�́@��6�߁@2�@�g���A�Q�o�A�T�����珕�Y�w��
��2�́@��6�߁@2�@���C�J�_�`(�Z������)
��2�́@��6�߁@2�@�o�Y�Ɓu�P�K���v
��2�́@��6�߁@2�@���~�A�P(���ݖ���)
��2�͑�6��2�@�R�h���m�i�J�}�C��(�q�ǂ��̒��ԓ���)
��2�́@��6�߁@2�@�I�^��
��2�́@��6�߁@2�@�N�C�]��(�H������)
��2�́@��6�߁@2�@�n�c�V���E�K�c(������)�E
�@�@���n�c�[�b�N(���ߋ�)
��2�́@��6�߁@2�@�^�C���E�q���I�g�V
�@�@��(�R���Ƃ�)�E�W���E�T���}�C��(�\�O�Q��)
��2�́@��6�߁@2�@�J���I��(���e)
��2�́@��6�߁@3�@�ɐ��Q��@165
��2�́@��6�߁@3�@���J�i�J(�ᒆ)
��2�́@��6�߁@3�@�ɐ��Q��̏o��
��2�́@��6�߁@3�@�����z�E���C(������)�E
�@�@���E�`�z�E���C(�ƕ���)
��2�́@��6�߁@3�@�T�J���J�C(��}��)
��2�́@��6�߁@4�@�����@168
��2�́@��6�߁@4�@�������̑����T��
��2�́@��6�߁@4�@�^���C��(�M����)
��2�́@��6�߁@4�@������
��2�́@��6�߁@4�@���[�Ǝ��̓����
��2�͑�6�߁@4�@�吳����ȑO�̌��[�Ƌ����̏���
��2�́@��6�߁@4�@�q�����N�o��(��I�ڔz��)
��2�́@��6�߁@4�@�j�I�N��(�ב���)�Ƌ����̏���
��2�́@��6�߁@4�@�������̔��`�Ɖԉňߑ�
��2�́@��6�߁@4�@�n�C���R�~(���荞��)
��2�́@��6�߁@4�@��I��
��2�́@��6�߁@4�@�w���~�}�C(����������)
��2�́@��6�߁@4�@�I�`��(����)�E�j�J�U��(����)
��2�́@��6�߁@4�@�q����(��I��)
��2�́@��6�߁@4�@�T���j�`�K�G��(�O���A��)
��2�́@��6�߁@4�@�g�I�J�K�G��(�\���A��)�ȍ~
��2�́@��6�߁@4�@�i�R�E�h�m���C(���l�̗�)
��2�́@��6�߁@4�@�吳����ȑO�̍���
��2�́@��6�߁@5�@��N�ƔN�j���@179
��2�́@��6�߁@5�@��悯
��2�́@��6�߁@5�@�g�V�C���C(�N�j��)
��2�́@��6�߁@6�@�����@180
��2�́@��6�߁@6�@�����̏���
��2�́@��6�߁@6�@�o��
��2�́@��6�߁@6�@��ӑ���
��2�́@��6�߁@6�@�Α�
��2�́@��6�߁@6�@�����̕ʂ̌`��
��2�́@��6�߁@6�@���̂ق��̒n��̑��V�̗l�q
��2�́@��6�߁@6�@�@��
��2�́@��6�߁@6�@�吳����ȑO�̑���
��2�́@��7�߁@��N�̍s���@189
��2�́@��7�߁@1�@�͂��߂Ɂ@189
��2�́@��7�߁@2�@1���̍s���@190
��2�́@��7�߁@2�@�V���E�K�c(����)
��2�́@��7�߁@2�@���J�~�Y(�ᐅ)
��2�́@��7�߁@2�@���w��
��2�́@��7�߁@2�@�G�ρE���ߗ���
��2�́@��7�߁@2�@�}���E���i�C(���肢)
��2�́@��7�߁@2�@���q��
��2�́@��7�߁@2�@�g�V�_�}(�N��)
��2�́@��7�߁@2�@�X�L�n�W��(���n��)
��2�́@��7�߁@2�@�m�}����(����)
��2�́@��7�߁@2�@�V�S�g�n�W��(�d���n��)�E
�@�@�����}�m�J�~(�R�̐_)
��2�́@��7�߁@2�@�J�K�~�I���V(�����낵)�E
�@�@���t�N�A�J�V(��������)
��2�́@��7�߁@2�@�J���m�C��(���̓���)
��2�́@��7�߁@2�@�i�i�N�T(����)
��2�́@��7�߁@2�@�G�r�X�}�C��(�b��{�Q��)
��2�́@��7�߁@2�@�C�Z�R�E(�ɐ��u)
��2�́@��7�߁@2�@�W���E�T���j�`�R�E(�\�O���u)
��2�́@��7�߁@2�@�g���h
��2�́@��7�߁@2�@��O�̃g���h
��2�́@��7�߁@2�@���l���R�E(��Q��u)
��2�́@��7�߁@2�@�R�V���E�K�c(������)
��2�́@��7�߁@2�@�J���E���i�C(���肢)
��2�́@��7�߁@2�@�l���V��(�N��)�E���u�C��(�M����)
��2�́@��7�߁@2�@�z�l�V���E�K�c(������)�E
�@�@���n�c�J�V���E�K�c(��\������)
��2�́@��7�߁@2�@���Q��
��2�́@��7�߁@2�@�J�����`(����)
��2�́@��7�߁@3�@2���̍s���@199
��2�́@��7�߁@3�@�q�g�G�V���E�K�c(�������)
��2�́@��7�߁@3�@�Z�c�u��(�ߕ�)
��2�́@��7�߁@3�@�I�o�P(������)
��2�́@��7�߁@3�@�L�c�l�m�Z���j��(�ς̎{�s)�E
�@�@���J���Z���M���E(���{�s)
��2�́@��7�߁@3�@�n�c�E�}(����)
��2�́@��7�߁@3�@�E�V�}�C��(���Q��)
��2�́@��7�߁@3�@�L�Q���Z�c(�I����)
��2�́@��7�߁@3�@�V���J�l�n���G(�߉ޟ��ω�)
��2�́@��7�߁@4�@3���̍s���@201
��2�́@��7�߁@4�@�����m�Z�b�N(���̐ߋ�)�E
�@�@���q�i�}�c��(���Ղ�)
��2�́@��7�߁@4�@�S�N���E(�����{)
��2�́@��7�߁@4�@�i�J���}�}�C��(���R�Q��)
��2�́@��7�߁@4�@�q�K���m�`���E�j�`(�ފ݂̒���)
��2�́@��7�߁@4�@�~���E�z�E�R�E(���@�u)
��2�́@��7�߁@5�@4���̍s���@204
��2�́@��7�߁@5�@���}���L(�R�s��)�E
�@�@���I�x���g�E�r���L(���ٓ��J��)
��2�́@��7�߁@5�@�e���h�E�o�i(�V����)
��2�́@��7�߁@5�@�n�i�}�c��(�ԍՂ�)
��2�͑�7��5�J�C�`���E����(
�@�@���_�����E�J�����E�_�����)
��2�́@��7�߁@6�@5���̍s���@206
��2�́@��7�߁@6�@�`���c�~(���E��)
��2�́@��7�߁@6�@�^���S�m�Z�b�N(�[�߂̐ߋ�)
��2�́@��7�߁@6�@�A�L���X�~(�H�x��)
��2�́@��7�߁@7�@6���̍s���@208
��2�́@��7�߁@7�@�n�K�^��(���ł�)
��2�́@��7�߁@7�@�~�]�T���G(�a����)
��2�́@��7�߁@7�@�~�`�u�V��(������)
��2�́@��7�߁@7�@�A�������R�r(�J�x��)
��2�́@��7�߁@7�@�T�i�u���E�m�V���W�}�C
�@�@��(�c��d����)
��2�́@��7�߁@7�@�i�S�V�m�n���C(�ĉz���P)
��2�́@��7�߁@8�@7���̍s���@209
��2�́@��7�߁@8�@�n�Q(���Đ�)
��2�́@��7�߁@8�@�^�i�o�^(���[)
��2�́@��7�߁@8�@�Q���悯�E���V�I�N��(������)
��2�́@��7�߁@8�@�čՂ�E���}�m�J�~(�R�̐_)�E
�@�@���^�m���V�R�E(����q�u)
��2�́@��7�߁@8�@�h���E�{�V(�y�p����)
��2�́@��7�߁@9�@8���̍s���@211
��2�́@��7�߁@9�@��|��
��2�́@��7�߁@9�@�i�k�J�{��(�����~)�E
�@�@���C�h�K�G(��ˑւ�)
��2�́@��7�߁@9�@�݂�
��2�́@��7�߁@9�@�~�E�\���W������
��2�́@��7�߁@9�@12��?�~�̏���
��2�́@��7�߁@9�@13��?�\���W��������}����
��2�́@��7�߁@9�@14��?�\���W������ւ̂�������
��2�́@��7�߁@9�@15��?�\���W������𑗂�
��2�́@��7�߁@9�@���u�C��(������)
��2�́@��7�߁@9�@�Z�K�L�G(�{��S��)�E
�@�@�����N�T�C�l���u�c(�Z�֔O��)
��2�́@��7�߁@9�@�W�]�E�{��(�n���~)�E
�@�@���j�W���E���b�J�{��(��\�l���~)
��2�́@��7�߁@9�@�A�^�S�}�c��(�����Ղ�)
��2�́@��7�߁@9�@�{���I�h��(�~�x��)
��2�́@��7�߁@9�@���l�t�L(��������)
��2�́@��7�߁@10�@9���̍s���@219
��2�́@��7�߁@10�@�n�b�T�N(����)
��2�́@��7�߁@10�@�c�L�~(����)�E�_���S�c�L(
�@�@���c�q�˂�)
��2�́@��7�߁@10�@�I�I�~�l�}�C��(����w��)
��2�́@��7�߁@11�@10���̍s���@221
��2�́@��7�߁@11�@�N���Z�b�N(�I�ߋ�)
��2�́@��7�߁@11�@�^����E�{���o
��2�́@��7�߁@11�@�A�L�}�c��(�H�Ղ�)�E
�@�@���E�W�K�~�}�c��(���_�Ղ�)
��2�́@��7�߁@11�@�}�����C�Q�c(������)
��2�́@��7�߁@12�@11���̍s���@221
��2�́@��7�߁@12�@���O�Ղ� |
��2�́@��7�߁@12�@���N�T�N(�y��)�E�J�}�I�T��(���[��)
��2�́@��7�߁@12�@�C�m�R(��q)
��2�́@��7�߁@12�@�j�C�i���T�C(�V����)
��2�́@��7�߁@13�@12���̍s���@223
��2�́@��7�߁@13�@�I�g���m�c�C�^�`
��2�́@��7�߁@13�@�V�o�J��(�Ċ���)
��2�́@��7�߁@13�@�R�g�n�W��(���n��)�E�X�X�n�L(���|)
��2�́@��7�߁@13�@�V���i���d�N��(���A����)
��2�́@��7�߁@13�@�~��
��2�́@��7�߁@13�@�J�h�}�c(�叼)
��2�́@��7�߁@13�@�Z�C�����o���C(��������)
��2�́@��7�߁@13�@���Q��E��|��
��2�́@��7�߁@13�@�݂�
��2�́@��7�߁@13�@���`�o�i(�݉�)
��2�́@��7�߁@13�@���������̏����E
�@�@���c�S�����\�o(�A����)
��2�́@��7�߁@13�@�g�V�g�N�T��(�Γ�����)
��2�́@��7�߁@13�@�i���L�[��(���ؐӂ�)
��2�́@��7�߁@13�@�I�I�c�S����(��A)
��2�́@��7�߁@13�@����̏�
��2�́@��8�߁@�L���Ɠ`���@228
��2�́@��8�߁@1�@�l������@228
��2�́@��8�߁@1�@�l�ƍ�����
��2�́@��8�߁@1�@�S�E�O��(����)
��2�́@��8�߁@1�@�g���h��
��2�́@��8�߁@1�@���ю�
��2�́@��8�߁@1�@�n�X��
��2�́@��8�߁@1�@�g���~�Y(��萅)
��2�́@��8�߁@1�@�o��
��2�́@��8�߁@1�@���ю���
��2�́@��8�߁@1�@�V����̒�h
��2�́@��8�߁@1�@�`���W������
��2�́@��8�߁@1�@�V����
��2�́@��8�߁@1�@�K��
��2�́@��8�߁@1�@����
��2�́@��8�߁@1�@���˂̒n��
��2�́@��8�߁@1�@�~�C(��)����
��2�́@��8�߁@1�@�����ƂƓ싽
��2�́@��8�߁@1�@�t���_��
��2�́@��8�߁@1�@�����@�̌�쉮
��2�́@��8�߁@1�@���ʂ̎�p�̓���
��2�́@��8�߁@1�@�싽�t���_�Ђ̍Ղ�
��2�́@��8�߁@1�@�Ɠ`�̊ۖ�u���d�~�v
��2�́@��8�߁@1�@�_�`���E�ƃI���h���R�̖�
��2�́@��8�߁@1�@�q�K�b�T���~�`(������)�E
�@�@���q�K�b�T���~�](������a)
��2�́@��8�߁@1�@�K�̕�
��2�́@��8�߁@1�@�I�I�C�W(���H)
��2�́@��8�߁@1�@�c�̖���
��2�́@��8�߁@1�@�ۉȉƂ̉��~
��2�́@��8�߁@1�@�ۉȒe����5�l�U
��2�́@��8�߁@1�@�V�c�S�Ꝅ�ƕۉȉ��~�̘S��
��2�́@��8�߁@1�@�T�r
��2�́@��8�߁@1�@�r�̐X�̌�
��2�́@��8�߁@1�@������
��2�́@��8�߁@1�@�n���ƂƉƂ̊Ԃ̃R�\�o�C
��2�́@��8�߁@1�@�J���Z���M���E(���{�s)
��2�́@2�@�R���߂���`���E�����߂���`���E
�@�@�@���ςƒK���߂���`���E���ԐM�@250
��2�́@2�@(1)�@�R���߂���`���@250
��2�́@2�@(1)�@�O�W��
��2�́@2�@(1)�@�Ҍ��R
��2�́@2�@(1)�@�ʍ�R
��2�́@2�@(1)�@�ғ�R
��2�́@2�@(1)�@���R�̒J
��2�́@2�@(1)�@�Č��̓V�_�R�ƃS�E�O��(����)
��2�́@2�@(1)�@�Č��̃I�I�o�J(���)
��2�́@2�@(1)�@�n��
��2�́@2�@(1)�@���c�R�̃^�J�j���E�h�E(������)
��2�́@2�@(1)�@���c�R�̓�
��2�́@2�@(1)�@�ێR
��2�́@2�@(1)�@�A�R�E(���ÁE����)��
��2�́@2�@(2)�@�����߂���`���@255
��2�́@2�@(2)�@�t���_�Ж�t���
��2�́@2�@(2)�@�����R�k�J�̈��
��2�́@2�@(2)�@���c�̐��ƍO�@��t
��2�́@2�@(2)�@����(�͂��肢)
��2�́@2�@(2)�@�}�_�Ђ̒r�ƃ��V���S�x��
��2�́@2�@(2)�@�M�r
��2�́@2�@(2)�@���P�r
��2�́@2�@(2)�@�z�E�L�J�r
��2�́@2�@(2)�@�g���X�r
��2�́@2�@(2)�@�Z�\�r
��2�́@2�@(2)�@����r
��2�́@2�@(2)�@�K�^��
��2�́@2�@(2)�@�r�̃q�k�L(��)
��2�́@2�@(2)�@�痢�̃K�}�h
��2�́@2�@(2)�@���n��̃t�`(��)�̎�
��2�́@2�@(3)�@���Əo�����@259
��2�́@2�@(3)�@�J�
��2�́@2�@(3)�@�J��̓͂��o
��2�́@2�@(3)�@����16�N�̝ۂ�
��2�́@2�@(3)�@����16�N�̝ۂƉJ�
��2�́@2�@(3)�@�����R�Ə��H�̐�����
��2�́@2�@(3)�@�ԍ]�ƌۃ���̊�
��2�́@2�@(3)�@�痢��̍^��
��2�́@2�@(3)�@�R�r�}���z�[������
��2�́@2�@(4)�@�ςƒK���߂���`���@267
��2�́@2�@(4)�@�ς̐e�q
��2�́@2�@(4)�@�J�`���}�̌�
��2�́@2�@(4)�@�ς̂��傤����s��
��2�́@2�@(4)�@�̋�
��2�́@2�@(4)�@����(�܂���)�R�̌�
��2�́@2�@(4)�@�ςɂ��܂��ꂽ�q�ǂ�
��2�́@2�@(4)�@�K�ɉ������ꂽ����������
��2�́@2�@(4)�@�ςɉ�������čs���l�тƂ̘b
��2�́@2�@(4)�@�ς�K�ɉ�������Ȃ���@
��2�́@2�@(4)�@�ς̋��{�E�ς̃Z���j���E��u
��2�́@2�@(5)�@���n��������߂���`���@269
��2�́@2�@(5)�@���c�̂��T�n��
��2�́@2�@(5)�@�����R�̎�Ȃ��n��
��2�́@2�@(5)�@����E�{�쌴���̒n��
��2�́@2�@(5)�@���
��2�́@2�@(5)�@�˂̐��ےn��
��2�́@2�@(5)�@���c�̎q���n��
��2�́@2�@(5)�@���֒r�̖k���n��
��2�́@2�@(5)�@���c�̖��͒n��
��2�́@2�@(6)�@�_�����肷��l�тƁ@274
��2�́@2�@(6)�@�s������
��2�́@2�@(6)�@�ێR���
��2�́@��9�߁@�q�ǂ��̕�炵�ƗV�с@276
��2�́@��9�߁@�����q�ǂ�����
��2�́@��9�߁@�q�ǂ������̗V�я�
��2�́@��9�߁@�K�L�叫�Ǝq�ǂ��W�c
��2�́@��9�߁@�o�C�V��
��2�́@��9�߁@�x�b�^���E�j�b�L�E�r�[��
��2�́@��9�߁@�w�n�V��
��2�́@��9�߁@�ւ܂킵
��2�́@��9�߁@�l���ċS
��2�́@��9�߁@���̂��܂��܂ȗV��
��2�́@��9�߁@���肨������
��2�́@��9�߁@�N���s���Ǝq�ǂ�����
��2�́@��9�߁@�I�X�Ǝ��ŋ�
��2�́@��9�߁@�ʉَq��
��2�́@��9�߁@�����ԂƎ��]��
��2�́@��10�߁@�Ղ�Ƃ��̎d�g�݁@296
��2�́@��10�߁@1�@�L���̍Ղ�@296
��2�́@��10�߁@2�@���c�_�Ў��q�_���Ձ@299
��2�́@��10�߁@2�@���c�_�Ђ̉��v
��2�́@��10�߁@2�@���q���u�I�e���T���v
��2�́@��10�߁@2�@���c�_�Ў��q�_���Ղ̊T�v
��2�́@��10�߁@2�@���˒n��̍��J�g�D
��2�́@��10�߁@2�@���c�n��̍��J�g�D
��2�́@��10�߁@2�@������
��2�́@��10�߁@2�@���c�n��̒n�揄��
��2�́@��10�߁@2�@��O�̒n�揄��
��2�́@��10�߁@2�@���{�Ղ̑叼��
��2�́@��10�߁@2�@�Ղ�̗��蕨
��2�́@��10�߁@2�@�{����Ƌ������s
��2�́@��10�߁@2�@���q�ǂ��_��
��2�́@��10�߁@2�@���q�_���Ղ̕ω�
��2�́@��10�߁@2�@�V���ȍՂ�̒S����
��2�́@��10�߁@3�@����_�Ў��q�_���Ձ@325
��2�́@��10�߁@3�@����_�Ђ̉��v
��2�́@��10�߁@3�@����_�Ў��q�_���Ղ̊T�v
��2�́@��10�߁@3�@�Z����
��2�́@��10�߁@3�@���{��
��2�́@��10�߁@3�@���c�_�Ў��q�_���ՂƂ̊W
��2�́@��10�߁@3�@�V���ȍՂ�̒S����
��2�́@��10�߁@4�@�������З�Ձ@334
��2�́@��10�߁@4�@�������Ђ̉��v
��2�́@��10�߁@4�@���{�n��̍��J�g�D
��2�́@��10�߁@4�@�������З��
��2�́@��10�߁@4�@�Ղ�̒��́u���{�v
��2�́@��10�߁@5�@�t���_�З��Ձ@342
��2�́@��10�߁@5�@�t���_�Ђ̉��v
��2�́@��10�߁@5�@�t���_�Ђ̍��J�g�D
��2�́@��10�߁@5�@�t���_�З���
��2�́@��10�߁@5�@�V���ȍՂ�̑n�o
��2�́@��10�߁@6�@�Ղ�̌��݁@346
��3�́@����Ƃ��Ă̖L���@347
��3�́@��1�߁@�����̐��藧���@348
��3�́@��1�߁@�����̐����ƒ���̔ɉh
��3�́@��1�߁@�����E�ĉ�����
��3�́@��1�߁@�����ېV�ƖL�����̒a��
��3�́@��1�߁@��ʋ@�ւ̔��B�ƏZ��J��
��3�́@��1�߁@�����Z��̊J��
��3�́@��1�߁@�L�����̒a���ƌ��ݎs��̊J��
��3�́@��1�߁@�Y�Ɠ��H�̊J�ʂƖL���s�̒a��
��3�́@��1�߁@���̕ϖe
��3�́@��1�߁@�V�������Ǝ{�݂̏o��
��3�́@��1�߁@���X�X�̐���
��3�́@��2�߁@���Ƃ̕�炵�@367
��3�͑�2��1�@�吳�����珺�a10�N��܂ł̏��X�X�@368
��3�́@��2�߁@1�@���܂��܂ȏ���
��3�́@��2�߁@1�@����̏��E�ƁE����Ƃ��Ă̋@�\
��3�́@��2�߁@1�@���C���X�g���[�g�ł̏���
��3�́@��2�߁@1�@���l�h�̗l�q
��3�́@��2�߁@1�@���X�X�̕��i?���Ƃ̓X��
��3�́@��2�߁@1�@�v���o�Ɏc�閡�E�ɂ����E��
��3�́@��2�߁@1�@���
��3�́@��2�߁@1�@��y�����ŋ�����
��3�́@��2�߁@2�@�����̊��C?�Ղ�Ɛ��������@378
��3�́@��2�߁@2�@�H�Ղ�
��3�́@��2�߁@2�@��������
��3�́@��2�߁@2�@�N�c�Ə��h�c
��3�́@��2�߁@3�@�������ӂ̗l�q�@380
��3�́@��2�߁@4�@�V�܂̕�炵?�ǖ{��?�@382
��3�́@��2�߁@4�@���ƂƂ��Ă̗ǖ{��
��3�́@��2�߁@4�@�~�n�ƓX��
��3�́@��2�߁@4�@�X�̊Ԃ̗l�q
��3�́@��2�߁@4�@�ǖ{�̐M��
��3�́@��2�߁@4�@�X���̔�
��3�́@��2�߁@4�@������Ɛ��̒��B
��3�́@��2�߁@5�@�ݖ��������̕�炵�@388
��3�́@��2�߁@5�@���Ƃ̂�������
��3�́@��2�߁@5�@�V�сE��`���E��
��3�́@��2�߁@5�@�ƋƂ��p���܂ł̕�
��3�́@��2�߁@5�@�X�̗l�q
��3�́@��2�߁@5�@�N���N�n�̂��킽������
��3�́@��2�߁@5�@�ݖ�����̋G��
��3�́@��2�߁@5�@�����E����̎d����
��3�́@��2�߁@5�@�ݖ�����̕��@
��3�́@��2�߁@5�@�V��������
��3�́@��2�߁@5�@���Ɣ͈͂Ɠ��Ӑ�
��3�́@��2�߁@5�@�̔��E�z�B�W��
��3�́@��2�߁@5�@���C�o���Ƃ̋���
��3�́@��2�߁@5�@����̕ω��Əݖ�����
��3�́@��3�߁@�E�l�����̕�炵�@404
��3�́@��3�߁@1�@���܂��܂ȐE�l�@404
��3�́@��3�߁@1�@�E�l�̈ڏZ
��3�́@��3�߁@1�@�ڏZ�̌o��
��3�́@��3�߁@1�@����̐E�l
��3�́@��3�߁@2�@�E�l�ɂȂ�܂Ł@408
��3�́@��3�߁@2�@��H�̌��K��
��3�́@��3�߁@2�@����̌��K��
��3�́@��3�߁@2�@�̌��K��
��3�́@��3�߁@2�@�|���̌��K��
��3�́@��3�߁@2�@�Ή��̌��K��
��3�́@��3�߁@2�@�m�R�M���b��̌��K��
��3�́@��3�߁@3�@�d���ƕ�炵�Ԃ�@412
��3�́@��3�߁@3�@��H�̎d���ƕ�炵
��3�́@��3�߁@3�@�E�l�̍�
��3�́@��3�߁@3�@����̎d���ƕ�炵
��3�́@��3�߁@3�@�̎d��
��3�́@��3�߁@3�@�|���̎d��
��3�́@��3�߁@3�@�Ή��̎d��
��3�́@��3�߁@3�@�ڗ��ĉ�
��3�́@��3�߁@3�@����䂭�E�l
��3�́@��3�߁@3�@���̖ʉe
��3�́@��4�߁@���X�X�̏�i�@426
��3�́@��4�߁@1�@�\���X���E�ɒO�X��
�@�@��(�s�����ʂ�)�����̓X�@427
��3�́@��4�߁@�]�ˎ��ォ�瑱�����ǂ@�@�y���
��3�́@��4�߁@�����n�Ƃ̗������@����
��3�́@��4�߁@�L�����̃Z���t�T�[�r�X�̓X�@���O�ߗ�
��3�́@��4�߁@���ق��牻�ϕi�E�G�ݓX��
��3�́@��4�߁@�X�������̔��S���@��y���X
��3�́@��4�߁@�吳�n�Ƃ̘a�َq�X�@�@�v�h���َq�X
��3�́@��4�߁@�R�E��(����)����ӂƂ�X�ց@����ӂƂ�X
��3�́@��4�߁@���X�X�̕��C���@����
��3�́@��4�߁@�����h�W���E���i�@��T��
��3�́@��4�߁@�����̉f���
��3�́@��4�߁@2�@�ʊ_�Ղ̓X�@444
��3�́@��4�߁@2�@���������炨�D�ݏĂ����ց@��܂Ƃ�
��3�́@��4�߁@2�@3�㑱���r�����@�~�c��
��3�́@��4�߁@2�@�Ö{������i���X�ց@�h����
��3�́@��4�߁@2�@�s�����̃X�|�[�c�p�i�X�@US�X�|�[�c
��3�́@��4�߁@2�@�����ōŏ��̗m�H���@�͂�d
��3�́@��4�߁@3�@���X�X�̏����@451
��3�́@��4�߁@3�@����X�̏���
��3�́@��4�߁@3�@�s���Y�X�̏���
��3�́@��4�߁@3�@���ǂ̏���
��3�́@��5�߁@�܂��Â��芈���̎n�܂�@456
��3�́@��5�߁@�܂��Â��芈���̑O�j
��3�́@��5�߁@�u�y�j��v�A
�@�@���u�����܂��݂�ȂŘb������v�̌���
��3�́@��5�߁@�u��x�J�[�j�o���v�̊J��
��3�́@��5�߁@���̌�̓W�J
��4�́@�V�����}�`��ԂƐ����@465
��4�́@��1�߁@�V�����}�`�ւ̈ڂ�ς��@466
��4�́@��1�߁@�����n��̐��藧��
��4�́@��1�߁@��O�̏����n��̕��i
��4�́@��1�߁@�����n��̕ϖe
��4�́@��1�߁@�J���I�ȕ��͋C�̐V�����}�`
��4�́@��2�߁@�u�n�̃����v�Ɓu�V�Z���v�@471
��4�́@��2�߁@�u�n�̃����v�Ɓu���\�̃����v
��4�́@��2�߁@�y�n��������
��4�́@��2�߁@�s�s�̒��̂ނ�
��4�́@��2�߁@�u�n�̃����v�Ɓu�V�Z���v
��4�́@��2�߁@�������
��4�́@��2�߁@�ȋߏ��t������
��4�́@��2�߁@���̏Z�܂��ƏI�̏Z�܂�
��4�́@��3�߁@�V�����}�`�̂ɂ��킢�@483
��4�́@��3�߁@1�@���X�X
��4�́@��3�߁@1�@�����w�O�̕��i
��4�́@��3�߁@1�@���X�X�̐��藧��
��4�́@��3�߁@1�@�L���s��
��4�́@��3�߁@1�@���鏤�X��̕�炵
��4�́@��3�߁@1�@�����{�ʏ��X�X
��4�́@��3�߁@2�@�����ƌ�y�@489
��4�́@��3�߁@�邪�Ȃ���
��4�́@��3�߁@�u�ԓd�ԁv
��4�́@��3�߁@�X������
��4�́@��3�߁@�f���
��4�́@��3�߁@�{�E�����O��
��4�́@��3�߁@�r�����[�h��
��4�́@��3�߁@�p�`���R |
��4�́@��3�߁@3�@���C���@494
��4�́@��3�߁@3�@���C���̕�炵
��4�́@��3�߁@3�@�e���̏�Ƃ��Ă̕��C��
��4�́@��3�߁@3�@�ܐF��
��4�́@��3�߁@4�@�����@498
��4�́@��3�߁@4�@�����̕ϗe
��4�́@��3�߁@4�@�������猩�������̃}�`
��4�́@��3�߁@4�@����
��4�́@��3�߁@4�@�����̌���
��4�́@��3�߁@5�@�����̌��Ɖe�@501
��4�́@��4�߁@�u���J�ɏZ�ށ@502
��4�́@��4�߁@1�@�u���J(�����Z��)�@502
��4�́@��4�߁@1�@�ۏ؋�
��4�́@��4�߁@1�@�ƒ�
��4�͑�4��1�@�s���Y����Ǝ҂��猩���u�Z�܂��T���v
��4�́@��4�߁@2�@�u�u���J�v�ł̕�炵(1)�@
�@�@�����a45�N�̒�������@508
��4�́@��4�߁@3�@�u�u���J�v�ł̕�炵(2)�@
�@�@������Ƒ��̐����j����@512
��4�́@��4�߁@3�@�V�������̎n�܂�
��4�́@��4�߁@3�@�����Ƃ̓���
��4�́@��4�߁@3�@�ߏ��Ƃ̕t������
��4�́@��4�߁@3�@�����Ȃ�����y�����䂪��
��4�́@��5�߁@�O���l�̏Z�ޖL���@518
��4�́@��5�߁@1�@�L���ɏZ�ފO���l�̌���@518
��4�́@��5�߁@1�@�O���l�o�^�̌���
��4�́@��5�߁@1�@�L���s�̍��ۉ�����̐���
��4�́@��5�߁@1�@�s���ɂ�鍑�ی𗬊���
��4�́@��5�߁@2�@�L���ɏZ�ފO���l�̐��@524
��4�́@��5�߁@2�@(1)�@���퐶����̉ۑ�@524
��4�́@��5�߁@2�@���t�̖��
��4�́@��5�߁@2�@�Z�܂�
��4�́@��5�߁@2�@����Ɗw�Z
��4�́@��5�߁@2�@(2)�@�L���̈�ہ@529
��4�͑�5��2�@���܂��܂ȏo��̂���}�`�L��
��4�́@��5�߁@2�@�ߏ��t���������ȃ}�`
��4�́@��5�߁@2�@�e���݂̃}�`����
��4�́@��5�߁@2�@(3)�@�g�߂ȍ��ی𗬁@534
��4�́@��5�߁@2�@���܂��܂ȏo��ƌ�
��4�́@��5�߁@2�@���܂��܂ȕ����𗬂Ɛl�I��
��4�́@��5�߁@2�@�O���l�����o���V��������
��4�͑�6�߁@��_�E�W�H��k�Ђƕς��䂭�}�`�@539
��4�́@��6�߁@�k�Ђ̏�
��4�́@��6�߁@�k�Ќ�̏Z���
��4�́@��6�߁@�k�Ђ���̕����ƏZ���̓]�o
��4�́@��6�߁@���C�̏����ƍĊJ���ւ̊���
��4�́@��6�߁@�ς��䂭����
��5�́@��炵�̓���@547
��5�́@��1�߁@�L���̖���[���Y�p��𒆐S�Ɂ[�@548
��5�́@��1�߁@�������Ƃ��Ă̖���
��5�́@��1�߁@���y�w�K���ނƂ��Ă̖���
��5�́@��1�߁@�����̊T�v
��5�́@��1�߁@�_��̗���
��5�́@��1�߁@�u�ےÍ��e�S�_��}�v��
�@�@���`���ꂽ�L���s��̔_��
��5�́@��2�߁@����Ɩ���@560
��5�́@��2�߁@1�@�L���̔���@560
��5�́@��2�߁@2�@����Ɩ���@561
��5�́@��2�߁@2�@�L���̔���
��5�́@��2�߁@2�@������
��5�́@��2�߁@2�@���܂�
��5�́@��2�߁@2�@���̊Ǘ����
�@�@��(�y�E�����E�{��E������)
��5�́@��2�߁@2�@������ƒE��
��5�́@��2�߁@3�@�Ǎ�Ɛ����@569
��5�́@��2�߁@3�@�L���̖Ǎ�
��5�́@��2�߁@3�@�Ǎ�Ɩ���
��5�́@��2�߁@4�@�|�т�⡁@571
��5�́@��2�߁@4�@�痢�u�˂�⡍͔|
��5�́@��2�߁@4�@�|���̊�
��5�́@��2�߁@4�@�^�l�_�P�̑I��
��5�́@��2�߁@4�@����
��5�́@��2�߁@4�@�{��
��5�́@��2�߁@4�@�y����
��5�́@��2�߁@4�@���n
��5�́@��2�߁@4�@�g���K�ƒb�艮
��5�́@��2�߁@4�@�o�ׂƉ��H
��5�́@��3�߁@���c�k��@577
��5�́@��3�߁@1�@���R���ƈ��@577
��5�́@��3�߁@2�@�~�̏����@577
��5�́@��3�߁@3�@�c����Ƒ���@578
��5�́@��3�߁@3�@�r�N����
��5�́@��3�߁@3�@�Ȃ���
��5�́@��3�߁@3�@�ォ��
��5�́@��3�߁@3�@���̖����Ɛ�p�̓���
��5�́@��3�߁@4�@��c�@582
��5�́@��3�߁@4�@����Z��
��5�́@��3�߁@4�@��܂��@582
��5�́@��3�߁@5�@�c�A��
��5�́@��3�߁@5�@�c�̉^��
��5�́@��3�߁@5�@�c�A��
��5�́@��3�߁@6�@�Ǘ��@584
��5�́@��3�߁@6�@��T�E�r�����
��5�́@��3�߁@6�@����
��5�́@��3�߁@6�@�{��
��5�́@��3�߁@6�@�h��
��5�́@��3�߁@7�@���n�@588
��5�́@��3�߁@7�@���
��5�́@��3�߁@7�@��ˊ���
��5�́@��3�߁@7�@�E��
��5�́@��3�߁@7�@����
��5�́@��3�߁@7�@����
��5�́@��3�߁@8�@�m�̗��p�@592
��5�́@��4�߁@����ɐe���ށ@�[�L���s����
�@�@������W���E�����{�݁[�@594
��5�́@��4�߁@1�@���w�Z�@595
��5�́@��4�߁@1�@�s���k�����w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���������w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s������J�����w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s�����ˏ��w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s�����c���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s�������쏬�w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���V�c���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���琬���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���L�����w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���L�������w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s�������R���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���씨���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s�����c���w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���L�쏬�w�Z
��5�́@��4�߁@1�@�s���u�r���w�Z
��5�́@��4�߁@2�@���w�Z�@612
��5�́@��4�߁@2�@�s����w�Z
��5�́@��4�߁@3�@�����ف@618
��5�́@��4�߁@3�@���{���ƏW��������
��5�́@��4�߁@4�@���̑��̎{�݁@619
��5�́@��4�߁@4�@�F��c�����
��5�́@��4�߁@4�@�s�����猤����
��5�́@��4�߁@4�@�s����ψ���Љ��ۋ��y������
��5�́@��4�߁@4�@�F���~������B�v��
��6�́@��炵�̒��̂��Ƃ@637
��6�́@��1�߁@�L���̂��Ƃ@638
��6�́@��1�߁@1�@����܂��@638
��6�́@��1�߁@2�@���{���̒n�捷�@639
��6�́@��1�߁@2�@(1)�@�������@639
��6�́@��1�߁@2�@(2)�@���{����n�}�@640
��6�́@��1�߁@2�@�앗
��6�́@��1�߁@2�@���Ƃ�J
��6�́@��1�߁@2�@���̂��炢(������)
��6�́@��1�߁@2�@���̂��炢���������܂��Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@�g�C��
��6�́@��1�߁@2�@�s���Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@���Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@���Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@���Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@�����(��i�����̌ܒi������)
��6�́@��1�߁@2�@�ҋ��̕⏕�����n���̎g�p
��6�́@��1�߁@2�@�~���Ă���(�p����)
��6�́@��1�߁@2�@�~���Ă���(���ʑ�)
��6�́@��1�߁@2�@(3)�@���s�@
�@�@�����ԕ����O���b�g�O���������@657
��6�́@��1�߁@2�@�s���Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@�s�����Ƃ��ł��Ȃ�
��6�́@��1�߁@2�@�ҋ��̕⏕�����n��
��6�́@��1�߁@2�@�ҋ��̕⏕��������
��6�́@��2�߁@�����I�������猩���L���̂��Ƃ@662
��6�́@��2�߁@1�@���C�̌n�@662
��6�́@��2�߁@1�@(1)�@�ꉹ�̓����@662
��6�́@��2�߁@1�@�u�C�v�̉�
��6�́@��2�߁@1�@�u�E�v�̉�
��6�́@��2�߁@1�@�ꉹ�̌��
��6�́@��2�߁@1�@�A�ꉹ�̓���
��6�́@��2�߁@1�@�ꉹ�̖�����
��6�͑�2��1�@(2)�@���ꉹ�̓��F�mkw�Agw�n�̎c���@664
��6�́@��2�߁@1�@(3)�@�q���̓����@665
��6�́@��2�߁@1�@�T�s���ƃn�s���̌����
��6�́@��2�߁@1�@�U�s���E�_�s���E���s���̍���
��6�́@��2�߁@1�@�ꒆ�́mm�n�Ɓmb�n�Ƃ̌��
��6�́@��2�߁@1�@�mju�n�́mi�n�ւ̕ω�
��6�́@��2�߁@1�@�mse�Aze�n�́mfe�A3e�n�ւ̕ω�
��6�́@��2�߁@1�@(4)�@�����E�����E�����@666
��6�́@��2�߁@1�@���ߖ����̒�����
��6�́@��2�߁@1�@�I��̒����̒Z����
��6�́@��2�߁@1�@����(��)�̔�������
��6�́@��2�߁@1�@����(�b)
��6�́@��2�߁@1�@������
��6�́@��2�߁@2�@�A�N�Z���g�@667
��6�́@��2�߁@2�@1���ߖ���
��6�́@��2�߁@2�@2���ߖ���
��6�́@��2�߁@2�@2���ߌ`�e��
��6�́@��2�߁@2�@2���ߓ���
��6�́@��2�߁@2�@3���ߖ����E�`�e���E����
��6�́@��2�߁@2�@�������~
��6�́@��2�߁@2�@���N���ƒ�N��
��6�́@��2�߁@2�@�A�N�Z���g�̐V��������
��6�́@��3�߁@���@�E�\���@�̓������猩��
�@�@���L���̂��Ƃ@670
��6�́@��3�߁@1�@�����@670
��6�́@��3�߁@1�@���R�`
��6�́@��3�߁@1�@�A�p�`
��6�́@��3�߁@1�@���`
��6�́@��3�߁@1�@�I�~�E�A�̌`
��6�́@��3�߁@1�@����`
��6�́@��3�߁@1�@���ߌ`
��6�́@��3�߁@1�@�ӎu�E���ʌ`
��6�́@��3�߁@2�@�`�e���@672
��6�́@��3�߁@2�@�A�p�`
��6�́@��3�߁@2�@�I�~�E�A�̌`
��6�́@��3�߁@2�@����`
��6�́@��3�߁@2�@���ʌ`
��6�́@��3�߁@3�@�`�e�����@673
��6�́@��3�߁@4�@�����\���@674
��6�́@��3�߁@4�@�g��\��
��6�́@��3�߁@4�@�\�\��
��6�́@��3�߁@4�@�ҋ��\��
��6�́@��3�߁@4�@�A�X�y�N�g�\��
��6�́@��3�߁@4�@����\��
��6�́@��3�߁@5�@�����@678
��6�́@��3�߁@6�@��N�w�̂��Ƃ̓��ԁ@679
��6�́@��3�߁@6�@(1)�@�����ɂ��ā@679
��6�́@��3�߁@6�@(2)�@�����̑Ώێҁ@379
��6�́@��3�߁@6�@(3)�@���ʂƍl�@�@681
��6�́@��3�߁@6�@��҂��g�����Ƃ̌X��
��6�́@��3�߁@6�@�j����
��6�́@��3�߁@6�@�����̂��Ƃ�
��6�́@��3�߁@6�@���e�̏o�g�n
��6�́@��3�߁@6�@���Z�n(�n��)�ɂ��Ⴂ
��7�́@�L���Ύ��L�@689
��7�́@��1�߁@����̍Ύ��@690
��7�́@��2�߁@�V�t�̖L���@691
��7�́@��2�߁@���w��
��7�́@��2�߁@���h�o���ߎ�
��7�́@��2�߁@�����t���n�ߎ�
��7�́@��2�߁@�t�̎����W
��7�́@��2�߁@�\�����т�
��7�́@��2�߁@��
��7�́@��2�߁@���l��
��7�́@��2�߁@�Ƃ�ǍՂ�
��7�́@��2�߁@�ߕ�
��7�́@��3�߁@�t�̖L���@699
��7�́@��3�߁@�����Βn�̔~��
��7�́@��3�߁@���c�_�Џt�Ղ�
��7�́@��3�߁@�c�o�L�@�����Βn�s�s�Ή��A����
��7�́@��3�߁@���Ǝ��Ɠ��w��
��7�́@��3�߁@���ފ�
��7�́@��3�߁@�N�̉Ƃ��Ԃ��E�����O�t�F�X�e�B�o��
��7�́@��3�߁@�c�c�W�@�@�{�R����
��7�́@��3�߁@���L���i�M�ƍ��@�V���쉈��
��7�́@��3�߁@�O�c�r�̍�����
��7�́@��3�߁@�s���̍��̖����ƍ��܂�
��7�́@��3�߁@����������\���X��
��7�́@��3�߁@�ԍՂ�
��7�́@��3�߁@�s�������Q�܂�
��7�́@��3�߁@�^�P�m�R�@��@����J�����w�Z
��7�́@��3�߁@���@����
��7�́@��3�߁@�o��?��m�ؒr����
��7�́@��3�߁@�T�c�L�W
��7�́@��3�߁@�n�i�V���E�u�@�痢�j���[�^�E���E���J�r
��7�́@��3�߁@�����Βn�̃X�C����
��7�́@��3�߁@�A�W�T�C�@���{���ƏW��������
��7�́@��4�߁@�Ă̖L���@709
��7�́@��4�߁@�u�̗[�ׁ@�V�L����
��7�́@��4�߁@�i�c�n�M�@���̎�
��7�́@��4�߁@�����Βn�̃n�X
��7�́@��4�߁@���[�܂�
��7�́@��4�߁@���Z�싅�������A���p�[�N�ƖL�����[�Y����
��7�́@��4�߁@���a���Ԃ̍Â�
��7�́@��4�߁@�L���܂�
��7�́@��4�߁@�L���܂�ƖL������
��7�́@��4�߁@�Z��s�s����s�Ɠ`�����x�G�C�T�[
��7�́@��4�߁@�T���}�e�I�s�Ƃ̏��N�e�P�싅��
��7�́@��4�߁@���~
��7�́@��4�߁@���~�̃y�b�g�쉀
��7�́@��4�߁@�ēV�_�ՂƑ��̎��F��
��7�́@��4�߁@8���̐d�\
��7�́@��5�߁@�H�̖L���@723
��7�́@��5�߁@�h�V�̍Â�
��7�́@��5�߁@�H�̉ԁ@�R�X���X�Ɣ�
��7�́@��5�߁@���c�_�Ђ̑叼��
��7�́@��5�߁@�H�Ղ�
��7�́@��5�߁@�H�o���Ɓu�s�̉ԁw�o���x���ԓW�v
��7�́@��5�߁@���w�������ɒ���
��7�́@��5�߁@�Ƃ�Ȃ����ۃl�b�g���[�N�܂�
��7�́@��5�߁@�s���p�W
��7�́@��5�߁@�e�ԓW
��7�́@��5�߁@�W���Y�t�F�X�^
��7�́@��5�߁@���N�Â���ӂꂠ���E�I�[�N
��7�́@��5�߁@�_�ƍ�
��7�́@��5�߁@�����ق܂�
��7�́@��6�߁@�~�̖L���@733
��7�́@��6�߁@�N���{�����e�B�A
��7�́@��6�߁@�n�蒹�̔�
��7�́@��6�߁@�c�t�����̖݂�
��7�́@��6�߁@�}�������E�W�@�����Βn�s�s�Ή��A����
��7�́@��6�߁@�N���X�}�X��
�@�@�������Ɍ��������܂��܂ȍu�K��
��7�́@��6�߁@�W�����{�G�n
��7�́@��6�߁@�N���X�}�X
��7�́@��6�߁@�N�������݂����ɂ�����
�L���Ύ��L�J�����_�[�@740
�Q�l�����@745
�}�E�\�E�ʐ^�ڎ��@755
�����@765
�ҏW���I���ā@798
���͎ҁE�b�҈ꗗ�@800�@�@
�҂���ψ��E���M�҈ꗗ
�E
�E |
�R���A���ꌧ�^����E����u[�c�u�c]�G�C�T�[�F�|�\�v�v���u ���ꌧ�v���犧�s�����B�@�����F��������}����
�@�@ (����14�N�x����f�W�^���A�[�J�C�u���������@16�@�P���i�S�S���S�W�b�j
�R���A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu�Ί_�������� 1�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B(�n�挤���V���[�Y
;No.31�j
|
�Ί_��-���̒n���I�T�� / ��l�� ��
�Ί_���̒n�` / �͖��r�j ��
�Ԏ�̌×w / ���{�M�v ��
�Ί_���약���ƒ|�x���́u���@�苶���v / �떓�b�� ��
|
�Ί_�s�_�Ƃ̌���Ɖۑ� / ���ԑגj ��
�Ί_���ɂ�����N�����ւ̕�����蒲��. 1 / �Ќ��b�� ��
�ߑ���A�Ί_���l�ӂ̏��Ƌ�ԂɊւ����̍l�@ / ���O���� ��
�c�����u���ꌧ���擇�ӌ����v / ���ԑגj �� |
�R���A�f�������u�G�C�T�[�F����̓`���s���G�C�T�[: �̃h���h���Ⴂ�����������v���u���ꌧ���H�J�������Y�ƐU���ہv���犧�s�����B�@�@�V���[�Y���FWonder����
�R���A��ԋI���q���u���ꍑ�ۑ�w�ꕶ�Ƌ���̌��� (4) p.92�`98�@���ꋳ�猤�����v�Ɂu�R�c�r����i�̌���--�u�����̋����v�_�@�v�\����B
�R���A����s�����y�����ٕҏW�u�����A���ژ^�v���u����s����ψ���v���犧�s�����B
�i����s������������ ��30�W�j 97p
|
1 �����Ɏ���o�܋y�ьo��
2 �����A���ژ^(����)
3 �����A���̌��� |
4 ���a�c�^�~�搶�Ɖ���s
5 ��z
���a8�N�ɔ������ꂽ���a�c���~���́u�����A���ژ^�v�����^�@ |
�@�@�@�@�@�@�@���@���ꌧ���}���فF1007956731�ł͏o�ŔN��:2000.3�Ƃ��������u����s������������ 30�v�̏o�ŔN�Ɣ�r���ĂQ�O�O�R�N�Ƃ��܂����@�Q�O�Q�R�E�U�E�P�W�@�ۍ�
�R���A�@�����������ꌧ�������ٕҁu���ꌧ�������ًI�v (29) p.55�`86���ꌧ�������فv�Ɂu�吳����ɂ����鉫�ꌧ�̕������w��֘A�̍s�������ɂ��āv�\����B
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 12�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@40p�@�����F���ꌧ���}���فF1003886015�@�@ 2003�E�R
|
�u�{�y���A�̈Ӗ��[���A�O�\�N�ڂ̉���v �{�������u�q]
�u�חF�`���Ɖ���v ��Î�[�q]
�ߐ������̗� ���_���̎� �I���ʏ��̍Ō�[�čl ���c�I��u |
����̎q�ǂ��̋K�������߂�����
�@�@���[�c�t���ƕۈ牀�̔�r �Óc�`���j
�ҏW��L |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g:<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 13�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@25p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004018782�@�@�@�@ 2003�E�R
|
�� ���̉F���[�������w�̒n���[ �������V
�j �u�{���h�P�����v�ɂ��� ���ђ��� |
�O �{���h�P�Ɋւ���o�� ���ђ���
�E |
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v11�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B2003
|
�G�~�[���E�x���i�[���̌����Z�U���k(1) ��� �t�j p.1-19
���J�����`�w���x�w�H�̓��x�̐���ߒ��Ɋւ���l�@--31���̃G�X�L�[�X�����Ƃ� ���� ���q p.21�`34
�Ñ�D���̍Č�����юd�l�`��̌��� ���� �S�� p.35�`46
���|�ƁE�͈䊰���Y���֖�m�[�g�̒�������(����) �쌴 �N�F p.47�`51
��(����)--�����y��ƍמ��O�����̂��߂̕ϑt�� 2002�N4�� ��˝`�q��ȁk�� �y���l ��� �`�q p.53�`67
����̂��ׂ����g��--���������̂��߂́k�� �y���l ���{ �M�v �� p.69�`107
���̂Ɣ���Ђ� Nakamura Marie-Paule,Kamijo Mitsuko p.109-124
�������{����ɂ�����m�y��e--����l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̑n�o�ƈٕ�����e�̂͂��܂�
�O�� �킩�� p.125�`146
�n��m�[�g �������̏�(���S����) ���g �Ύ} p.149�`151,�}����7�`8�@ �d�v
�q�����r |
�S���A����~�q�����ǂ�����ԕҁu���A�W�A�Ɠ��{�̉��y�v���u�|�v���Ёv���犧�s����B�@
�@�@ (���ۗ����ɖ𗧂��E�̖������y ; 1)�@47p ; 29cm + CD1�� (12cm)
|
���{�Ƃ��Ȃ���̐[��,�����E�����S���E�؍��̉��y��,���́E�G�C�T�[�𒆐S�Ƃ��鉫��̉��y,���{�̖M�y�E��y�Ȃǂ��Љ�B (���{�����}���o�ŋ���) |
�S���A��Í��Ғ��u����ł��e����ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� : ��������ÓT�܂Łv���uRuon�Ёv���犧�s�����B
|
1�@�u�O���i����j�̊e���i�v�@4
2�@�u���i����j�̌��ѕ��A�O���̍\�����v�@5
3�@�u�O�����Ɨm�y���Ƃ̊W�v�@6
4�@�u�O���̊����i���Ԃǂ�����j�Ɨm�y���Ƃ̊W�v�@6
5�@�u�����ɂ��āv�@7
6�@�u�H�H�l�ɂ��āv������ŕ��߁@8
7�@�u�����i���݁j�ɂ��āv�@10
8�@�u�����̎d���v�@12
9�@�u�e���̊����ɂ��āv�@12
10�@�u�����̖ڈ�̕t�����Ǝw�g���v�@13
�{���q�i�ق傤���j�@14
11�@�J�����̗��K�@
�@�@���k�ނ���łЂ炢�ā@���傤���傤�@�Ă����ʉԁl�@14
12�@�l���w�̗��K�@�Ă����ʉԁ@16
13�@���w�̗��K�@�ނ���łЂ炢�ā@18
14�@���w�̗��K�@20
15�@�u�����ƑS���E�����̊W�v�@20
16�@��̃V�i�ځj�̗��K�@�Ă����ʉԁ@20
17�@��O���̃t�@�i���j�̗��K�@22
18�@���\�L����i���邭�Ƃ��݂������j�i���j�@23
19�@���e���̗��K�@24
19�@���\�L����i���j�@24
20�@�u�|���i�������Ƃ��j�A�����i�ʂ����Ƃ��j�̗��K�v�@26
21�@�Ⴊ���i�ނ�j�i���j�@26
22�@�u�ʼn��i�������Ƃ��j�̗��K�v�@28
23�@�ԓc�a���i�������@����@�ǂ��j�i���j�@28
�u�H�H�l�i���[�j����̗��K�v�@30
24�@��肱�̂��߁i��肭�ʂ��[�Ԃ��j�i�Áj�@30
25�@�����߁i���邵�܂Ԃ��j�i�Áj�@32
26�@�N���N�߁i���邭�Ԃ��j�i�Áj�@34
27�@�����߁i���Ȃނ��Ԃ��j�i�Áj�@35
28�@��Ԑ߁i�Ȃ��Ԃ��j�i�Áj�@36
29�@�ڏo�����߁i�߂ł����Ԃ��j(��)�@38
30�@�j�߁i���킢�Ԃ��j(��)�@40
31�@�u�|�W�V�����ɂ��āv�@42
32�@�u���ׂ�e���ƃ|�W�V�����ړ��v�@42
33�@�u���������@�}�����i���������邵�j�v�@44
34�@�뗎�����i�������Ƃ������������j�i�Áj�@44
35�@�H�̗x���i�����̂��ǂ�j�i�������j�i�݂����@���ǂ����j�i�Áj�@46
36�@�u�O���̓`���A���h�A�^�A�ߖ��v�@48
37�@�u���̂̌`�ԁv�@48
�{���q�̒��Ⴂ�@49
38�@�u�����ߌ^�̎ڂ̊����v�@49
39�@�u��2�|�W�V�����v�@50 |
40�@�R�r�̗D���i�ׁ[�ׁ[�ʂ܂������j�i���j�@50
41�@�g��c�߁i���������Ă�Ԃ��j�i�Áj�@52
42�@���₤�Ȃ��߁i����ˁ[�Ԃ��j�i�Áj�@55
43�@���x�߁i�����ǂ���Ԃ��j�i�Áj�@56
�{���q�̒Z���@�@58
44�@�u�����@�ƒZ���@�ɂ��āv�@58
45�@�u�{���q�̒Z���@�̗��K�v�@58
46�@���g�߁i���͂Ԃ��j�i�Áj�@59
47�@�������i�����ǂ���j���(��)�@60
48�@�Ԃ̕��ԁi�͂Ȃʂ����܂�[�j�i���j�@62
49�@�q��߁i����ނ��Ԃ��j�i�Áj�@63
50�@�Ȃ��܂��₮(��)�@64
51�@�h�̒��߁i����Ƃ����Ԃ��j(��)�@66
��g���q�i�Ɂ[�������傤���j�@68
52�@�u��g���q�̗��K�v�@68
53�@�����J��i��������j�i���j�@68
54�@�⌴�����i�����͂炭�ǂ����j�i�Áj�@70
55�@�^�ߌ��߁i��Ȃ�Ԃ��j�i�Áj�@72
56�@�l�璹�߁i�͂܂��ǂ���Ԃ��j�i�Áj�@74
57�@���m�߁i�ނ��Ԃ��j�i�Áj�@76
��g���q�̒Z���@�@78
58�@�u��g���q�̒Z���@�̗��K�v�@78
59�@���̔������i���ʂ�������j�i���j�@78
60�@�Ƃ���[��(��)�@80
61�@�u��g���q�̕ʂ̒Z���@�̗��K�v�@82
62�@�O�̕l�߁i�߁[�ʂ͂܂Ԃ��j�i�Áj�@82
���g���q�i�����ɂ������傤���j�@84
63�@�u���g���q�̗��K�v�@84
64�@�܂���߁i���g���q�j(��)�@84
65�@�u��g���q�ƈ��g���q�v
�@�@���u���g���q�ƎO�g���q�i�������傤���j�v�@86
66�@�܂���߁i�O�����q�j(��)�@86
67�@���l�߁i����͂܂Ԃ��j(��)�@88
68�@�J���O�߁i����߁[�Ԃ��j(��)�@90
��g���q�i�����������傤���j�@92
69�@�u��g���q�̗��K�v�@92
70�@�����߁i�ׂ͂邮��[�Ԃ��j�i�Áj�@92
71�@�����߁i�����肴�Ƃ��Ԃ��j�i�Áj�@94
72�@������ŕ��߁i������ł��Ӂ[�Ԃ��j�i�Áj�@96
73�@���[�߁i����ȂԂ��j�i�Áj�@98
���Ƃ����@100
�@�@���u�v�̍��ڂ͐������͗��K�A���̍��ڂ͊y�ȍ��͗��K�B
�@�@�Ȗڂ̌�́i���j�́u���ׂ����v�A�i�Áj�́u�ÓT���y�v(��)�́u���w�v�������B
�@�@�ÓT���y�A���w�ɂ��Ă�48�y�[�W�Q�ƁB |
�T���A�X�F�I���u�����]�̃R�[���X�E�A���o�� : �����O������/�s�A�m���t : ���ꉹ�y���W�`����̖��w����|�b�v�X�܂Łv���u�P�C�E�G���E�s�[�v���犧�s����B�@�@�@79p
|
�Ă����ʉԁ@���ꖯ�w�@6
���a�̗��́@�l�[�l�[�Y�@9
���Ƃ����є��@�X�R�ǎq�@14
�܂��������@�Đ��݁@18
���_�i���т��݁j�`�V�̎q��S�`
�@�@���i�݂�Ȃ̂����o�[�W�����j�@�R�{���q�@24
�ԁ@�`���ׂĂ̐l�̐S�ɉԂ��`�@��[���g���`�����v���[�Y�@28
������ׁ@�Đ��݁@33 |
���S�@THE BOOM�@38
�m�ԕz ���ꖯ�w�@44
����~�E�A���[���@�f�B�A�}���e�X�@50
���ʔ��i�����j����@�Đ��݁@56
���l�i���܂�j�ʕ�@BEGIN�@62
����ǂ��̉ԁ@����h���^�{�ǒ���@68
���ꖯ�w���h���[�@���ꖯ�w�@72
�i������i�ɂ��傤�j�߁@�`�J���O�i����߁[�j�`�����������^�j |
�T���A����m��G�u����ǂ��̉� : ���ꂤ���̊G�{ : �{�ǒ�����f�B�[�@�v���u�j���C�Ёv���犧�s�����B�@�@55p
|
�R�̎q��S�@�쎌�@�{�Ǎ��i�@4
�Ԃ��̉ԁ@�쎌�@��l�M���@6
�����@�쎌�@�{�Ǎ��v�@8
�K�̎��@�쎌�@�{���Ì@9
�t���J�@�쎌�@�[�Ɓ@10
�Ȃl�@�쎌�@�{�Ǎ��v�@12
����ǂ��̉ԁ@�쎌�@����h���@14
�ӂ闢�@�쎌�@����h���@16
�I�����_���~�@�쎌�@���R�����@18
�A��M�@�쎌�@�{�Ǎ��v�@20
�Ï�@�쎌�@�ɔg��N�@22
�썑�̉ԁ@�쎌�@�k���d�h�@24 |
���̏o���@�쎌�@�{�Ǎ��v�@26
����M�@�쎌�@��l�M���@28
�[�₯�@�쎌�@��l�M���@30
�����߁@�쎌�@���{���@32
���݂�@�쎌�@�V�_�e�q�@33
���Ԑ߁@�쎌�@�{�ǒ���@34
�Q���̊C�@�쎌�@��l�M���@36
��鏬��@�쎌�@��l�M���@37
�H�H�l(�O����)�@�ڎ�
����ǂ��̉ԁ@40
�K�̎��@41
�Ȃl�@42 |
�����������^�@44
�I�����_���~�@45
�A��M�@46
������g�@48
���D�@50
�����߁@52
����y�̖��́@��R�L�q�@53
�{�ǒ���N���@55
�y���ďC�@��R�L�q
�H�H�l�ҋȁ@�������j
�E
�E |
�U���A�{�ǒ��� [���],��R�L�q�ҁE�Z���u�{�ǒ����ȑS�W : ���a120�N�L�O�v���u�����V��Ёv���犧�s�����B�@
|
��ցE���̋����@�C�V��q�@1
��ʂ̃����f�B�[���㐢�Ɂ@�O�،��@2
�}��@7
�y�̋ȁE���w�z
�J�@�P�s�{���W���@10
�`�m��̉́@�{�ǒ���@11
���ʂ̉́@�{�ǒ���@12
�t�𑗂�́@�{�ǒ���@13
�q����̉́@�{�ǒ���@14
���݂�@�V�_�e�q�@15
�������́@�{�ǒ���@16
��鏬��@��l�M���@17
���Ԑ߁@�{�ǒ���@19
�Ԃ��̉ԁ@��l�M���@22
�Q���̊C�@��l�M���@24
�[�₯�@��l�M���@30
�Ö�̒��ׁ@���R���^�@31
����M�@��l�M���@33
�썑�̉ԁ@�k���d�h�@34
����ǂ��̉ԁ@����h���@36
���_�@�{�Ǔ��s�@38
�P�ց@����i�D�@40
��̋����@�����v�@41
���@�얞�B�����@42
��艥���@�k���d�h�@43
�q�����@�k���d�h�@44
�ӂ闢�@����h���@46
�J�ꂽ�����@�O��O�O�@48
������@�F�v�{�����@49
�ł����@�k���d�h�@52
��F�̏��܁@�����v�@53
�ǎ��@���䒼�H�@54
�S���ǑP�́@�k���d�h�@55
�h�̒��@�[�Ɓ@56
�w�H�@�[�Ɓ@59
�t���J�@�[�Ɓ@62
�I�����_���~�@���R�����@64
�D�H�@�{���Ì@66
�[���@�V���~�K�Ɂ@68 |
�Ï�@�ɔg��N�@71
�A��M�@�{�Ǎ��v�@74
�����߁@���{���@76
�����@�{�Ǎ��v�@77
�R�C�i�����^�@�[�Ɓ@78
�L��̊U�@�{�Ǎ��i�@81
�L�����^�@�{�ǒ���@82
��́@�[�Ɓ@84
������g�@�������w�@88
�����،��́@�V���~�K�Ɂ@90
�Ȃl�@�{�Ǎ��v�@94
��J�@��l���C�@96
�������@�{�Ǎ��v�@97
�R�̎q��S�@�{�Ǎ��i�@98
���D�@�[�Ɓ@100
��̐��@�{�ǒ���@102
�K�̎��@�{���Ì@104
���̏o���@�{�Ǎ��v�@105
��čՁ@�[�Ɓ@108
���d�R�����@���Òn�p���@109
���͖A���@�{�Ǎ��v�@112
���쏬�S�@���ܑS�K�@114
�����������^�@�������@116
�r��̉́@�{���Ì@118
���q�̉́@�{�ǒ���@120
���̌����@�{�ǒ���@121
�ԂƖI�@��F���p���@122
�������@��F���p���@123
�����Y�@��F���p���@124
�钎�@���w�G�����@125
�y�����V�ׁ@���݊���@126
���R�閜�˃}�[�`�@�s���@127
���ł̌��@�s���@128
�ւ��܂̒I�@����h���@129
�t�[���@�s���@130
������@�s���@131
����@�s���@132
���l�̂��Ɂ@�s���@134
�E |
�y�Z�́z
�������w�Z�@���~����@136
�������w�Z�@���~����@137
���쏬�w�Z�@���Ì�����@138
�����w�Z�@�������M�@139
�^�����w�Z�@�V���~�K�Ɂ@140
�v�Βn���w�Z�@���ߌ��N�@141
�^�a�u���w�Z�@�㌴�W�@142
�m�O���w�Z�@�������G�@143
�v�������w�Z�@�O�ԗNjV�@144
���䏬�w�Z�@�R��Ēj�@145
�^�Ǐ��w�Z�@��Ïr���@146
��u�����w�Z�@�s���@147
�v�ē����w�Z�@�{���Ì@148
���ۏ��w�Z�@�k���d�h�@149
���\�����w�Z�@�Γc�ߖP�@150
��l�q�퍂�����w�Z�@�k���d�h�@151
��l�q�퍂�����w�Z�i�s�i�ȁj�@�k���d�h�@152
���ꌧ����w�Z�@����ȐE���@153
��u��q�퍂�����w�Z�@�Ôg���ۏ��@154
���ꌧ�����q�H�|�w�Z�@���A���p�@155
�����q�퍂�����w�Z�@�c�[�ꑺ�@156
�Ί_�q�퍂�����w�Z�@�L�c�M���@157
���ꌧ����O���w�Z�@�V���~�K�Ɂ@158
���ꌧ�t�͊w�Z�������w�Z�@���d�Ҏ��@159
���ꌧ��������w�Z�@�R�鐳���@160
�y�c�̉́E�j�́z
�ߔe�s�s���́@���������@162
��u�쏬�w�Z�\���N�L�O��j�́@�Ôg���ۏ��@163
�Ί_���́@�ɔg��N�@164
���d�R�_�w�Z�J�Z�L�O���̉́@�{�Ǎ��v�@166
��݂����钷����f�B�[������ɂ����ā��@167
�V���@��i�\�@172
�{�ǒ���N���@175
�{�ǒ����i�\�@179
�����@183
�Ҏҗ���
�E
�E |
�U���A�u���� : �Ղ�E�����E���Q�|�F����t�ďH�~�v���u Sony Music House�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�^���f�B�X�N 4�� 1975�N��i�@�@
|
�����̂��₮ / ���g����
�u�k�E����̂��낿 / ���i�s
�n���� / �����J��, �㌴�^�P, �ݖ{���t
�蕨:�O�`���ہ`�O���E�ꗎ���`���t�E
�@�@���ꗎ���A�n��]�E�A�ɏW����c/
�@�@���`�ӈ��q, ���ؐ��j, ��H�N�O,
�@�@���Î芡�я�, �Ɖ��я�, �m����j
�Ђ[���ޏ� / �Î芡�я�
�䕨��s / �Î芡�я�, �������q
������ŕ� / �����J��
�ŋ�:�o�₵ / �m����j
�ӂꑾ�� / ���ؐ��j
��� / �Î芡�я�
��X�������Y���̘b
�ŋ��E�u�̈�{�� / �����J��
��l�ŋ��E���A�V�y�[ / ��Ñ��g
���@�i�[�N�j:�R����ԓ�/�Î芡�я�,�������q
��������[ / �Î芡�я�, �������q
�悤���߃��[ / �������q
�Ղ�:�P����-��X������@�Âɂ�
�@�@���`����-���c���ɂā`�������E�\��
���d�R�s / �������q, �Î芡�я�, �v��m�q
�g�D�o���} / �Î芡�я�
�L�N�̂��₮ / ���g���� |
�R�������^ / �R�[�j�[����
�V�����J�l�� / ���@������
���̃}�s���[�} / ��H�N�O
���:�l�璹�̃����O�g�D�`�蕶/
�@�@����H�N�O, �R�[�j�[����
���^�̊蕶�`�}�[�j���l�[�������/
�@�@�����×ǒ���, �Ɖ��я�,
�����Y:�A���̋����Y�`�������̋����Y/
�@�@���������N��̊F����
�Ղ�:�^�R�j����-���~���ɂ�
���A�m�̃G�C�T�[
���c���̃G�C�T�[
���~���̃G�C�T�[
�N���_���h�E�� / ������
�哇�炿 / ������
�V���K�|�[���� / �Ôg�P��
�ʂ�̉� / �m�����, �Î芡�я�
�푈���̌�� / ����r��
���������̋� / �m����j
����̗��� / �Î芡�я�
���Ð� / �Î芡�я�
�{����� / ���g����
���b�p�� / �Î芡�я�, �������q
����t�̌���E������ / ���i�s |
���w�V���[�E�A�V�e�r�`�̉̂Ȃ�
�@�@��-�N���u�u�Ȃl�v�ɂ� / �O���N
�`���b�L������ / ������
������ / �Î芡�я�
�c�c�J���i�[ / ����r��
������ / �Î芡�я�
���������� / �������q
�їV�с[�̘b�Ȃ� / �R�镶�j
�O�C�`���{�[���[ / �^�ߏ钉��
���s / �R�镶�j, �^�ߏ钉��
�{���̉Y / �R�镶�j, �^�ߏ钉��
�H���y-���A�m�ɂ�
������ / ���v������, ���v�����q
�ԕ� / �����J��
�Ғ����S / �����J��
�C�̃`���{�[�� / �����J��
�x���i�[�N�j�`�n���^��/�o�쐽�m,�m����j
�ҕ����� / �o�쐽�m, �m����j, �����J��
���D�h�[�C / �o�쐽�m, �m����j, �����J��
�G�s���[�O:���璹 / �Î芡�я�, �m�����
����t�ďH�~
�Βk:�ό����݂Ȃ����:�������|/
�@�@������, �Ɖ��я�, �|���J
���I,II / �|���J |
�V���A���R�Ă��u���m�_�� ����̍��J�`���̌��� : �V��E�_�́E���v�\����B
�V���A���э��オ�u�A�W�A�V�w (53) p.52�`60�v�Ɂu��s���ɂ�����G�C�T�[�̑n��--�u�䂤�Ȃ̉�v������ (���W ���ꕶ���̑n��)�@�v�\����B
�V���A���v���u���v����I�W �P�v ���u�w���v���犧�s�����B�@�@
|
���y�̏�
�Ŋy��̕����j
�q��S�̎Љ�w
���ׂ����Ɩ�����
�l�͂Ȃ��̂��������� |
�A�W�A�̉��y�E���[���b�p�̉��y
�A�W�A���y�̖���
�A�W�A�̒��̉��ꉹ�y
�V���N���[�h�̖������y��T��
�������y�Ǝ]���� |
���E�̏@�����y
�������y����w�Ԃ���
�����Ă�����{�̓`�����y
���{�̉��y�����̂䂭��
�l�͂Ȃ��̂��������� : ���v�t�B�[���h���[�N |
|
�V���A���R�S�m �Ғ��u����/�̃��}���E�s�A�m�E�R���N�V�����v���u�h���~�y���o�ŎЁv���犧�s�����B
(�s�A�m�E�\���E���C�u�����[) �@125p
|
1.�@���Ƃ͕� �X�R�ǎq�@12 110
2�@�܁i�Ȃ��j�������� BEGIN�@16 110
3.�@���Ƃ����є� �������Ȃ��݁^�X�R�ǎq�@19 111
4.�@�Ђ���E�������� �����Ƃ��@22 111
5.�@��̖�Ɛ�̒� �����Ƃ��@26 112
6.�@�ЂƂԂ̗� Kiroro�@31 112
7.�@�R���i����j�� BEGIN�@34 113
8.�@ALIVE SPEED�@38 113
9.�@�V�����G�̃S�[���[�}���� �K���b�W�Z�[���@42 114
10.�@���S THE BOOM�@45 114
11.�@�� ��[���g�@48 115
12.�@�߂ł����߂ł��� ���o���h�@51 115
13.�@�o�C�o�C���� �l�[�l�[�Y�@54 116
14.�@�����̉� �l�[�l�[�Y�@57 116
15.�@�E���J�W�i�ʉe�j �l�[�l�[�Y�@60 117
16.�@������ TINGARA�@63 117
17.�@��Ԕ�s TINGARA�@66 118 |
18.�@���肪�Ƃ� ���o���h�@69 118
19.�@���� BEGIN�@72 119
20.�@����i�����ȁ[�j �N�얾�@76 119
21.�@���C���C�i���ꃍ���@�[�W�����j �㌴���F�^�m����j�@79 120
22.�@���̃u���[�X �O���݁^�a�c�O�ƃ}�q�i�E�X�^�[�Y�@82 120
23.�@���l�i���܂�j�ʕ� BEGIN �V�ǍK�l�@
�@�@�@���哇�ۍ��@�Đ��݁@�l�[�l�[�Y�@���[���[�@86 121
24.�@�����܂܂� ��[���g�@88 121
25.�@����ǂ��̉� ����h���^�{�ǒ����@91 122
26.�@�m�ԕz �g�����^���v���P�E�@94 122
27.�@�Ă����ʉ� ���ꖯ�w�@97 123
28.�@�J���O�i����߁[�j ���ꖯ�w�@100 123
���ꖯ�w���h���[
29.�@�������i�����ǂ�j�����^ ���ꖯ�w�@104 124
30.�@������i�ɂ��傤�j�� ���ꖯ�w�@105 124
31.�@���ԁi�͂Ƃ܁j�� ���ꖯ�w�@106 125
32.�@�g�D�o���}�i�J�k�V���}�߁j ���ꖯ�w�@107 125 |
�X���A�������ꂪ�u�����̓s�s�Ƒ����v���u����w�o�ŕ��v���犧�s����B�@ (萐���{�����{�p�����������p��, 23)
|
��P���@�����ɂ�����W���ƒn���ρi�u�Òn�}�v��
�@�@���鉺���̕����G�鉺���̓s�s�v��Ƃ��̊�{���O�G
�@�@�����h�v�đ��̌i�ςƂ��̍\���G
�@�@������̊i�q��W���Ɋւ���\�@�I�l�@�@�ق��j |
��Q���@���d�R�Òn�}�ɂ��W���̕���
�@�@���i���d�R�̏W�������̈Ӌ`�Ƃ��̕��@�G�Ί_���̏W���G
�@�@���|�x���E�����E�V�铇�E���l���̏W���G���ԓ��E���\���̏W���@�ق��j
�E |
�X���A����ǂ������� ���E�Ԃ�u�p�[���g�D�v���u�V���Ɂv���犧�s�����B�@�@
�X���A���ܐ��q�ďC�u�ڂŌ��閼��E�����S��100�N�v���u���y�o�ŎЁv���犧�s�����B�@�@
|
�����E�吳����
��A�@�����E�吳�̕�炵�Ɛ��Ɓ\���ꂩ��̎���́@12
��A�@�V�쐻�ޏ��@12
��A�@�����S�����@13
��A�@�_�A�V���M�@13
��A�@�a���̒j���@13
��A�@�J���v�[�@13
��A�@�o�[�L��w���������@14
��A�@�����n��@14
��A�@�^�V�̕�@15
��A�@�����̃T�[�^�[���[�@15
��A�@�����s����x�X�@16
��A�@���ꋤ����s����x�X�@16
��A�@�^�h�鏤�X�@16
��A�@��ӏ��X�@17
��A�@�V���q�포�w�Z�@17
��A�@�{���q�포�w�Z�̎����@17
��A�@�{���q�퍂�����w�Z���ƋL�O�@17
��A�@�Ì|�q�포�w�Z�@18
��A�@�Ì|�q�퍂�����w�Z�����Ȉ�E��N���@18
��A�@��@�Ðq�포�w�Z�@18
��A�@��X���q�퍂�����w�Z�@18
��A�@�Â��̂̕��i�_�`�\�����m��肪����@19
��A�@�����ʂ�@19
��A�@����p�@20
��A�@�n�v�n�`�@20
��A�@�^�V�`�@21
��A�@���̑�@21
��A�@���A�m��Ձ@22
��A�@���ג����㗤���V��̔��@22
��A�@����̋T�b��@23
��A�@�H�n�̐��c���i�@23
��A�@�w�S�Ƃ���̔��@24
��A�@���m�Ԃ͔̍|�@24
��A�@���⋴�̊����L�O�@25
��A�@��@�Â̍`�̒�h��ݍH���@25
��A�@����̌k�J�@25
��A�@�吳����̃q���v���K�W���}���@26
��A�@���͐�̋��@26
��A�@���͂̎������@26
���a��O
��A�@���a�̖��J���\�ږ��E�o�҂��ց@28
��A�@�O�_���J�̐_�`�s��@28
��A�@�H�n���������̊ȈՐ����^���N�@29
��A�@�E�b�J�K�[(���)�̕����@29
��A�@�����c�t���@30
��A�@�K��掖�����@30
��A�@���[�M�p�̔��w�����p�Y�Ƒg���@30
��A�@�K��̃A�T�M�i�[�@31
��A�@�p���g�D�[�J���x����@31
��A�@���[�x���]�@31
��A�@�����`�@32
��A�@�n���Z���a�̎��ݎ��e���@32
��A�@���a��O�̋���\�w�Z����̕��y�@33
��A�@�����q�퍂�����w�Z�_��@33
��A�@�����q�퍂�����w�Z�̏����k�@34
��A�@����q�퍂�����w�Z�q��Ȃ̑��ƋL�O34
��A�@���w�Z�̒���@34
��A�@����n�q�퍂�����w�Z�@35
��A�@�����̏o���L�O�@35
��A�@��{���N�����u�K�L�O�@35
��A�@�ɍ]�q�퍂�����w�Z�@36
��A�@�ɍ]�����w�Z�@36
��A�@�����q�퍂�����w�Z���ƋL�O�@37
��A�@�X����q�퍂�����w�Z�Z�Ɂ@37
��A�@�Ôg�����w�Z���k�@37
��A�@���ꌧ����O�������w�Z�@38
��A�@�닅���̗D���L�O�@38
��A�@���ꌧ����O���w�Z�@38
�O�A�@�e������\�w�l�����̐Ӗ��@39
�O�A�@�r���O⥐D��@39
�O�A�@��Ԃ��炨�{�ց@40
�O�A�@�o���L�O�@40
�O�A�@�펞���̉f��ف@40
�O�A�@�q���v���K�W���}���@41
�O�A�@�A�u�V�o���[�@41
�O�A�@�ɍ]���̈�Ƒ��@41
�O�A�@�ɍ]�X�ǁ@42
�O�A�@�����ł̐d���Y��d�@42
�O�A�@�{�����x�h�c���q�~��ǁ@43
�O�A�@�n�v�n�_�Ɋ��������@43
�O�A�@�������|�k������@44
�O�A�@�����|�����@44
�O�A�@�Ă������閯�Ɓ@45
�O�A�@���̎q�ǂ��@45
�O�A�@�ɕ����̖��Ԑl�ߗ��@46
�O�A�@�ɍ]���̈�Ƒ��@46
�O�A�@���~����Z���@47
�O�A�@�A�����J�R���b�l���ꂽ�k�m���@47
�O�A�@���ߕl���̃A�����J�R���Ԓn�@47
�O�A�@�p�ЂƉ���������@48
�O�A�@���a�@�ƂȂ����O���}���ف@48
�O�A�@���ɐݒu����Ă����^���N�@48
���a���
��A�@�œy����̏o���\�Ƃɂ����A������@50
��A�@����m���I�@50
��A�@�{�������ꗎ���j���@51
��A�@�����x�@���@51
��A�@��@�Ì����ٗ����@51
��A�@��Î�Ȃ̈ɍ]���K��@52
��A�@�A�[�j�[�p�C���̈ԗ��@52
��A�@�L�����E�F�C�����ٖ������}���i53
��A�@���Đe�P�@53
��A�@�����̊�n�����w�@53
��A�@��[�N�������@54
��A�@���N�����j�@54
��A�@���]�O�����قŁ@54
��A�@�J�[�����[�̐V�z�@54
��A�@�ٔF�k�n�@55
��A�@���d�R�J��ږ��@55
��A�@�����e�������_�`�@56
��A�@�����̊X���݁@56
��A�@�����ɏW�߂�ꂽ�e�n�̐l�тƁ@57
��A�@�ɍ]���ߗ����e���ł̒������i57 |
��A�@��������鏗���@58
��A�@�l�ӂŐ���@58
��A�@�A�����J���̊Ď��̂��ƍ�ƂɌ������Z���@59
��A�@���ߎ��e�����̕a�@�ƈ�t�A�Ō�w59
��A�@���e���I���O�̌|�\��@59
��A�@���e���ł̍Ղ�@60
��A�@�ƘH�ɒ����Z���@60
��A�@���Õߗ����e���@60
��A�@���Î��e�����ł̍�Əo���O�̓_��60
��A�@�ϖe����ӂ邳�ƌ����i�\�v���o�ƂȂ����X���݁@61
��A�@�ɕ������ɂ����鐸�ĕ��i�@61
��A�@�Ŗk�[�̃o�X��@62
��A�@�q�҂��̘V�l�@62
��A�@�{���̃I�o�A�����@62
��A�@����̃��C���X���[�g�@63
��A�@���㌴�̗t�^�o�R���������@63
��A�@�����D�̌����@63
��A�@���߂̐����@64
��A�@��r��l�тƁ@64
��A�@����̐����H��@64
��A�@�����J�[�ʼn^�ԁ@64
��A�@�����̍̎�@65
��A�@�T�o�j�̎��������鋙�t�@65
��A�@�c���k���@66
��A�@���̈��@66
��A�@�T�g�E�L�r�̗A���@66
��A�@�E���@67
��A�@�y�Ԃ̑䏊�@67
��A�@�E�b�J�K�[(���)�Ő��������l�т�68
��A�@�q�ǂ������̗V�с@68
��A�@�A�����J�R�̃g���b�N�ɏ�荞�ޏ��w��69
��A�@�p�C���̎��n�@69
��A�@�n�v�n�`�Ł@70
��A�@�������̖��Ɓ@70
��A�@����n�X�ǁ@71
��A�@���߃o�v�e�X�g����@71
��A�@����掖�����@71
��A�@�䕔�c�͂ł̋L�O�B�e�@72
��A�@�ӓy���n�拳�玖�����@72
��A�@���������ف@73
��A�@�q���v���K�W���}���@73
��A�@���앗�i(1)�@74
��A�@�ɍ]���w�Z����R��]�ށ@74
��A�@���[���i�@74
��A�@���앗�i(2)�@75
��A�@���䕗�i�@75
��A�@�������i�@75
��A�@�X���^�̉ƕ��݁@76
��A�@�n�v�n�E�J���̕��i�@76
��A�@���i�@76
��A�@�����S�i�@77
��A�@����{���Ƌ{������ԁ@77
�O�A�@���̋���\����̍Đ��Ɣ��W�@78
�O�A�@�V�m�����w�Z�̋��H�@78
�O�A�@��c�����w�Z�@79
�O�A�@��{���w�Z�Ɨ��L�O���T�@79
�O�A�@�V�m�����w�Z�̋��H���i�@79
�O�A�@�{�������w�Z�@79
�O�A�@�ɓ������E���w�Z�̍Z�Ɂ@80
�O�A�@�Ӊԏ��w�Z�̉^����@80
�O�A�@�ӓy�������w�Z�@80
�O�A�@���H���i�@81
�O�A�@���@81
�O�A�@���[���E���w�Z�@81
�O�A�@�R�c���E���w�Z�@82
�O�A�@�쐣�������E���w�Z�@82
�O�A�@�{�����w�Z�̊w�|��L�O�@82
�O�A�@�������w�Z�̉^����@82
�O�A�@�������w�Z�@83
�O�A�@�����w�Z���C�����Ďg�p�����ɍ]���w�Z�@83
�O�A�@���������w�Z���Ɛ��@83
�O�A�@�{�������w�Z�̊J�Z�@84
�O�A�@�k���H�ƍ����w�Z�̒n���Ձ@84
�O�A�@�X��������w�Z�Z�Ɂ@84
�O�A�@�ӓy�������w�Z�R���Z�b�g�ł̍u����@84
�l�A�@��������`���̍Ղ�\�Â����̂��ӂ����с@85
�l�A�@�����̃E���K�~�Ńn�[���[���}���鏗�������@85
�l�A�@����̃n�[���[�@86
�l�A�@�n�[���[�@86
�l�A�@�������̃n�[���[�@86
�l�A�@���ǘp�ł̃n�[���[�@87
�l�A�@��j�����@88
�l�A�@�X����̑�j�����@88
�l�A�@�v�u�̍Ղ�@88
�l�A�@���̓��W���l�[�@89
�l�A�@���[�̃G�C�T�[�@89
�l�A�@�V�m���̃G�C�T�[�@89
�l�A�@���g�̃E�V�f�[�N�@90
�l�A�@���a�̃E�V�f�[�N�@92
�l�A�@���NJ_�̃G�C�T�[�@92
�l�A�@�������̖L�N�x��@93
�l�A�@�����@93
�l�A�@�_�p�@94
�l�A�@����̖L�N�Ղ�@94
�l�A�@�����̊C�_�Ձ@94
�l�A�@���v�c�̖L�N�Ղ�@95
�l�A�@�����̖L�N�x��@95
�l�A�@�������с@96
�l�A�@�䕔�c�͂̎��q���@96
�l�A�@�ɖ�g�̃��N�W���@97
�l�A�@���̃V�k�O�@97
�l�A�@�䕔�c�͂̃A�T�M�@98
�l�A�@�����A�T�M�̖����s���@98
�l�A�@�E�����̃E���K�~
�l�A�@�����̃n�[���[�@99
�l�A�@���Ẫt���K���T�ց@99
�l�A�@���ẪA�T�M�@99
�l�A�@�E���K�~�̓����@99
�܁A�@�n��̔��W�\����̕����@100
�܁A�@����\���H���s���I�����s�b�N�������[�@100
�܁A�@�I�����s�b�N�������[�@101
�܁A�@�c���q���v�ȗ����@101
�܁A�@�C�M���̂Ɍ����ā@101
�܁A�@�I�����s�b�N�I��̖͔͉��Z�@102
|
�܁A�@�����h�쑍����b�̉���K���@102
�܁A�@�A�����J�R��n�ł̐Ό��T���Y�@103
�܁A�@�����K�ꂽ��u���p���I���@103
�܁A�@�������̑Ζʁ@103
�܁A�@���쒬���l�Z���N�L�O�p���[�h�@104
�܁A�@����s���{�s�@104
�܁A�@�N�����̃_���X�p�[�e�B�[�@105
�܁A�@������Ղ�@105
�܁A�@�������E���w�Z�ł̓��[�@106
�܁A�@���I���p���[�h�@106
�܁A�@�ŐV���|���v�����ԓ����@107
�܁A�@����c�t���@107
�܁A�@���쎩�R���A������
�@�@��(�l�I�p�[�N�I�L�i��)�̊J���@107
�܁A�@����勴�̊J�ʁ@108
�܁A�@����o�C�p�X�J�ʁ@108
�܁A�@����n�勴�J�ʁ@108
�܁A�@����p�̖����H���@109
�܁A�@�^���̔�Q�@109
�܁A�@��O�{�Ñ䕗�̔�Q�@110
�܁A�@���ݏċp�F���ݖ��@110
�܁A�@�A�����J�R�Ƃ̖��C�@110
�܁A�@��X���̃p�C�����@111
�܁A�@�����̕����@111
�܁A�@�E�s�g�D���
�܁A�@�s�g�D��(1)�@112
�܁A�@�s�g�D��(2)�@112
�܁A�@�s�g�D��(3)�@113
�܁A�@�s�g�D��(4)�@113
�܁A�@�ߊl���ꂽ�U�g�E�N�W���@113
�܁A�@�n�v�n�`�ł̕ߌ~�@113
�܁A�@�����ꍑ�ۊC�m������@114
�܁A�@�C�㖢���s�s �A�N�A�|���X�@114
�܁A�@���ꍑ�ۊC�m������J���@114
�܁A�@�����ف@115
�܁A�@�܁Z���l�߂̓���ҁ@115
�܁A�@�C�m�����@115
�܁A�@���̑� �̂�̂�o�X�@116
�܁A�@�������m�̐����@116
�܁A�@�G�L�X�|�E�����h�@117
�܁A�@����C�m���N�c�@117
�܁A�@����V���[�@117
�Z�A�@�A�����J�������a���ց\
�@�@�������錴���i�̌`���@118
�Z�A�@�הn�Ԃł̉^���@118
�Z�A�@����s���ݎs��@119
�Z�A�@�{���̃}�`�O���[�@119
�Z�A�@�V�����[�i�[�r�[�@119
�Z�A�@�f��ْʂ�@120
�Z�A�@��������铹�H�@120
�Z�A�@�q���v���J�W���}�����Ӂ@121
�Z�A�@�s�X�n���i�@121
�Z�A�@��m���̃E�J�~�}�[�`�@121
�Z�A�@����̔_�n���i�@122
�Z�A�@����̏����@122
�Z�A�@�����p�[�V�@123
�Z�A�@���̉��~�с@123
�Z�A�@�V�m�����i�@124
�Z�A�@�X������C���X�g���[�g�@124
�Z�A�@��鏤�X�@124
�Z�A�@�J���W���̓�[����k����]�ށ@125
�Z�A�@�^�b�`���[(��R)���Ӂ@125
�Z�A�@�������@126
�Z�A�@���������g���i�@126
�Z�A�@���엮�ĕ�����ف@127
�Z�A�@����n�拳�玖�����@127
�Z�A�@�X����A���拳��ψ���
�@�@���������Ձ@127
�Z�A�@���̗X�ǁ@128
�Z�A�@���[�X�ǁ@128
�Z�A�@�I���I���r�[���H��@128
�Z�A�@�R�c����@129
�Z�A�@�J���e�b�N�X�@129
�Z�A�@�ɍ]�o�X�Ɖ^�]��@130
�Z�A�@���[���r�[�`�@130
�Z�A�@���n��̐����ŗV�ԁ@130
�Z�A�@�n�ɂ��^���@131
�Z�A�@�c���̎��n�@131
�Z�A�@��؍��@132
�Z�A�@���E�݁@133
�Z�A�@�É�m�̋@�D�@133
�Z�A�@�m�Ԃ̒������@133
�Z�A�@���̃��W�I�̑��@134
�Z�A�@�������ޏ����@134
�Z�A�@�L�O�ƂȂ������l���@134
�Z�A�@�ɍ]�`�@135
�Z�A�@�O�ŗV�Ԏq�ǂ������@135
�Z�A�@��t�X�|�[�c���N�c�@136
�Z�A�@�����ω����@136
�Z�A�@���(�E�K��)�@137
�Z�A�@�����̍��@137
�Z�A�@�E�����X
�Z�A�@�����������X�@138
�Z�A�@���NJ_�����̔��X�@138
�Z�A�@�����������X�@138
���A�@�������J���\����̎��R���c���邩�@139
���A�@�������C�����ف@139
���A�@�������̂ڂ�Ղ�@140
���A�@�X������Z�싅���b�q���o��@140
���A�@��B�E����T�~�b�g�@141
���A�@���[�������ف@142
���A�@�I���I���r�[���@142
���A�@���̉w�������݁@142
���A�@�����Ɓ@143
���A�@���n�_���@143
���A�@�ɍ]���^�[�~�i���@143
���A�@�ÉF���勴�@144
���A�@�����̃}���O���[�u�с@144
���A�@�c�����p�̃q���M�с@144
�J���[���G�@1
���s�ɂ������ā@<���ܐ��q>�@5
���Ƃ����@145
�ʐ^�E�����҂���т����b�ɂȂ������X�@146
��ȎQ�l�����@146
|
�P�O���A����P, ���\����ďC�u�ڂŌ��铇�K�E�{�ÁE���d�R��100�N�v���u���y�o�ŎЁv���犧�s�����B
|
�����E�吳����
��A�ߑ㍑�Ƃ̏o�� ���ꌧ�̒a���@14
��A�������w/�@14
��A�Ί_�����Ə������쎢��/�@15
��A���d�R�x��/�@15
��A�c���q�̏o�}��/�@15
��A�y�֓S���^�ߌ��w/�@16
��A�V������蕨/�@16
��A���\�Y�B�ƍB�v����/�@17
��A�Ί_���̃g���b�R/�@17
��A���哌��(�T����)�̗Ӎz�̌@����/�@17
��A�����m�Ԑ̍`�p�J��H��/�@18
��A�약�p�̌�ؖ{�^��{�B��/�@18
��A�J�c�I�H��̏]�ƈ�����/�@18
��A���d�R���ߐ�����/�@19
��A�{�����X/�@19
��A������̂����ڂ�
��A�������q�포�w�Z�Ǝ���/�@20
��A��������w�Z/�@21
��A��u���Ԑؔԏ��Ղɂ�������u���q�포�w�Z/21
��A�哌���q�퍂�����w�Z/�@21
��A�����̐��� ���d�R�̊J���ƌ����@22
��A�J��V���̎Q����/�@22
��A�^�ߌ��S�i/�@23
��A�����`/�@23
��A�����̏W�������䂩���]����/�@23
��A�X�̒ʂ�/�@24
��A���d�R�E�x��ω����{�a/�@24
��A�{�Â̊ω���/�@24
��A�약�̖q��/�@25
��A����^�ߌ��֔�����X��/�@25
��A���\���̒��ǐ�̑D����/�@26
��A���Â̊C��/�@26
��A�Ƒ��̎ʐ^/�@27
��A���Ƃ̉Ƒ�/�@27
��A�c�����������/�@27
��A�����̎s��/�@28
��A�T�[�^�[���[/�@28
��A������/�@28
��A�؉P�Ƌn�ŕĂ𝑂��_�Ƃ̏���/�@29
��A�v�ē��ۂ�D�鏗��/�@29
��A���N�Y��������l�т�/�@29
��A�약�̎��q��/�@30
��A�����n�[���[/�@30
���a��O
��A�@���a�̖��J�� �\�e�c�n������c��������ց@32
��A�@��O�̃^�N�V�[�^�]��/�@32
��A�@�������w/�@33
��A�@�h�C�c�c�锎���L�O�茚���Z�Z���N�L�O���T/�@33
��A�@�g�Ɗԓ��̗Ӎz��������s/�@33
��A�@�^�ߌ��w/�@33
��A�@��ӑ�������z�L�O/�@34
��A�@�^�ߓc���̗����L�O/�@34
��A�@�R���N���[�g��/�@34
��A�@�����ق̑O�ɗ��V���̐N�c/�@35
��A�@���㋣�Z�����I����/�@35
��A�@�E�s�ȁu�Ð��̖_�v�̎g���肽��/�@35
��A�@�~���N�s��/�@35
��A�@�����W���̐ߍ�(�V�c�B)/�@36
��A�@���ɖ���ڂ��ĕ�������/�@36
��A�@�֏��Ԃ̉��ʼnׂ��ڂ��ĉ^�ԏ�������/�@36
��A�@�����W���鐻����
��A�@��O�̕��n����������/�@37
��A�@���Òn����������/�@37
��A�@��O�̃T�g�E�L�r�̔��o���/�@38
��A�@�����M�ϑ���/�@38
��A�@?��ˎ���̕��i
��A�@���⓰�߂��́u�����̈��(�V���[���J�[)�v/�@39
��A�@�ۗǐ�/�@39
��A�@�ÉÎR�̋������/�@40
��A���~���̋������/�@40
��A�������̐�O���i �f���o���ꂽ�����̐����@41
��A�^�Ǐ��/�@41
��A�L�����ՊO��/�@42
��A��R��Ղ�K�ꂽ�R�萳�����m�Ɠ��܌���Y����/42
��A�a��X(���_�L�i�[)/�@43
��A���ɗ��R�蔎�m/�@43
��A���⓰/�@43
��A�^�ʋ�/�@44
��A�V���ʂ�/�@44
��A��ؖ{�^���Ў�����/�@44
��A�Ί_����ʂ菤�X�X/�@45
��A�����̃V�V�}�`/�@45
��A�I�X�ŋ�(�C��)�鏗��/�@45
��A�C�݂ɌW�����ꂽ�T�o�j/�@46
��A�^�ߌ����ƍ`/�@46
��A�약�̌�ؖ{�^��/�@47
��A�Ί_�`/�@47
��A�Ί_�`�t�߂̃T�o�j/�@47
�O�A���a��O�̋��� �n��ɖ���������O�̊w�Z����@48
�O�A�܁Z���N�j��^����/�@48
�O�A���NJԐq�퍂�����w�Z/�@49
�O�A�V��q�포�w�Z�̈�N������Z�N���܂ł̎����Ƌ���/49
�O�A�앗���q�퍂�����w�Z/�@49
�O�A�ʏ�q�퍂�����w�Z/�@50
�O�A�^�ߍ��q�퍂�����w�Z�̑��ƋL�O/�@50
�O�A�v���o�̔_��/�@50
�O�A�������q�퍂�����w�Z�Ǝ���/�@51
�O�A����q�퍂�����w�Z/�@51
�O�A���~�q�포�w�Z�����Ȃ̑��Ǝ�/�@51
�O�A�m�O�q�퍂�����w�Z�̑��ƋL�O/�@52
�O�A��l�q�퍂�����w�Z�����̏C�w���s/�@52
�O�A���Ǒ���w�Z/�@53
�O�A���Ǒ��q�퍂�����w�Z/�@53
�l�A�e������ �~�V�K���}�Z�����c�}�f�n�@54
�l�A�������ł̓��c���̌����蕗�i/�@54
�l�A�I����Z�Z�Z�N��j���j�G��W����/�@55
�l�A���\�N�w�Z�D�����Z�̐��k�Ƌ���/�@55
�l�A�^�h���N��y��/�@55
�l�A�����c/�@56
�l�A�h�ΌP��/�@56
�l�A������ƒn�ŕޏꐮ���ɏW�܂����ꐔ�̏��q�N�c��/56
�l�A�_�Ɋ��ۈ珊/�@57
�l�A���嗢�̑����������L�O/�@57
�l�A�������@58
�l�A�A�����J�R�̕����ɘA����ĕ����l�т�/�@58
�l�A�A�����J�R�̏㗤���ɋ�������c���ԓ��Z��/�@59 |
�l�A���̎蓖�Ă��鏭��/�@59
�l�A�A�����J�R�̏㗤�ɑ��R�Ƃ��鈢�Ó��̏Z��/59
�l�A���Õ��Ɏ��e���ꂽ�Z��/�@59
�l�A��Ԃ���q�ɊC�݉����ɔ���Z��/�@60
�l�A�푈�Ŕj�ꂽ�^�ߌ��w/�@60
�l�A�^�ߌ��S�i/�@60
���a���
��A�s�킩��̕��� ����_���̋O�Ձ@62
��A�������i/�@62
��A�����g����/�@63
��A���������̓d�b/�@63
��A�������X��/�@63
��A���������������h�o��/�@64
��A�m�O�n�������a�@/�@64
��A�{���/�@65
��A�S����Ќǎ��@/�@65
��A��l������̌���/�@66
��A�ʏ鑺����/�@66
��A�������O�ł̋L�O�B�e/�@66
��A�R���Z�b�g�̖��꒡�ɑO�ɂ�/�@67
��A��V����̎������[�^�[�v�[��/�@67
��A�������[�^�[�v�[���̏]�ƈ�/�@68
��A�R�c�^�A/�@68
��A�I�[�g�O��/�@68
��A���ې��o�X�̊J��/�@69
��A�o�X�̐ςݍ��ݕ��i/�@69
��A���a�Y�ƃo�X/�@69
��A������d���̏]�ƈ�/�@69
��A�����̊�������Ԏq�ǂ�����/�@70
��A���Ôg�Ì����قł̃��W�I�̑����i/�@70
��A�Ôg�Â̓y��N(�g�[�e�C�N��)�K����/�@71
��A���~�̓�����/�@71
��A�n�V����/�@72
��A���[�X�䕗�̔�Q�����^���W��/�@72
��A�~�������x��/�@72
��A�N�������g�������̒E��/�@73
��A�c�A��/�@73
��A�p�C���A�b�v���͔̍|/�@74
��A�V�[�g�[��/�@74
��A���c�A�_���o�Y�Ƃ̏]�ƈ�/�@74
��A�������`�̌~��̏�����S�i/�@75
��A�n�V�̌~��̍H��/�@75
��A���Òn�Ɉړ]�������̖L����H��/�@76
��A�{�B�L�̎d����/�@76
��A���Ǎ`�̘I�X���i/�@77
��A�Ί_�s�̋���ʂ�/�@77
��A�R�c���X/�@77
��A�ϖe����ӂ邳�Ƃ̌����i �ό��ƊJ���@78
��A���Ǎ`/�@78
��A����Z�N�ڍ��̏W�����i/�@79
��A�Ɖ��̃J�[/�@79
��A�o�q���̏㗬�Ő��������l�т�/�@79
��A�Ί_�`�̎V��/�@80
��A���ߗ��ĈȑO�̋��`��n��/�@80
��A�������[�^���[/�@81
��A�I�풼��̋K�i�Z��/�@81
��A�������ԋK�i�Z��/�@81
��A���~�̐V���n��/�@82
��A����\���H/�@82
��A�T���o�V�l�҂��R���]��/�@82
��A�������O���H�t��/�@83
��A�o��鏬�w�Z�O/�@83
��A�����W��/�@83
��A�o�t�c�t��/�@84
��A�^�h���N��/�@84
��A���S���N���u/�@84
�O�A��㋳��̏o�� �w�Z����̈ڂ�ς��@85
�O�A���d�R�����w�Z�̑싅�N���u/�@85
�O�A�I�풼��̍��~���w�Z/�@86
�O�A�^�ߌ����w�Z/�@86
�O�A�ʏ鏬�w�Z/�@86
�O�A���������w�Z/�@87
�O�A���^���w�Z/�@87
�O�A���䏬�w�Z�ƂƂ�ݏ��w�Z�̍����^����/�@87
�O�A���l���E���w�Z�̉^����/�@88
�O�A�|�x���w�Z�̏��a��l�N�x���ƋL�O/�@88
�O�A�앗�����w�Z���珬�w�Z�E�����]��/�@89
�O�A��_���w�Z/�@89
�O�A�ߌ������w�Z/�@89
�O�A���i�g�l�ł̊C����/�@90
�O�A�和�ɍZ���̊|�����������̏�n���w�Z/�@90
�O�A�����l�Z�����^����/�@90
�O�A�S�������w�Z/�@91
�O�A�C�w���s���i/�@91
�O�A�����E���R���Z�Ǝ������w�̐e�P���j���/�@91
�O�A��l�����w�Z/�@92
�O�A���ے��w�Z���Ɛ�/�@92
�O�A���\���w�Z�̑n���L�O/�@93
�O�A�������w�Z��l�����ƋL�O/�@93
�O�A�ʏ钆�w�Z/�@94
�O�A�{�Í����w�Z���㕔/�@94
�O�A�암�_�э��Z/�@94
�l�A�n��̔��W �n��Y�Ƃ̕ϑJ�`���K�E�{�ÁE���d�R�@95
�l�A�c�����A��s�i������ʂ�/�@95
�l�A�����I�����s�b�N�̐������[/�@96
�l�A����/�@96
�l�A���a�̉̉Ύ��A�x�����[�o����/�@96
�l�A������/�@97
�l�A�����L�O�S�N��/�@97
�l�A���NJԑ�����/�@97
�l�A�L����X��/�@98
�l�A�V�Ί_�s�a��/�@98
�l�A�����s���{�s��Z���N�L�O���T/�@98
�l�A�{�×��ĕ�����ِE��/�@99
�l�A�����ٖ������}���T�ł̉��Z/�@99
�l�A�����o���q�ǂ������₷���m/�@99
�l�A�s���e����/�@100
�l�A���E�O�Z��ʕ��@�ύX/�@100
�l�A���n����`�ւ̒���֏A�q/�@101
�l�A���c�o�X�ƃo�X�^�[�~�i��/�@101
�l�A�݂Ȃƃ^�N�V�[/�@101
�l�A���̐^�ʋ�/�@102
�l�A���Ǎ`�ł̉��낵/�@102
�l�A���ݒ���OHK����̓S��/�@103
�l�A��H���⥁E���\��҂�/�@103
�l�A��ꎟ�C���I���e���}�l�R����/�@103
�l�A���{�Ãg���C�A�X����
|
�l�A����g���C�A�X�������/�@104
�l�A����g���C�A�X�������(1)/�@104
�l�A����g���C�A�X�������(2)/�@105
�l�A����g���C�A�X�������(3)/�@105
�l�A���푈�̒܍�
�l�A�����m�̕a�@���Ղɂ�/�@106
�l�A���x�̎i�ߕ�����/�@106
�l�A���{���̕��/�@106
�܁A��������`���̍Ղ� �ӂ邳�Ƃ̕��������@107
�܁A������j�����̓��Y�l�[/�@107
�܁A�������̊C�_��/�@108
�܁A�����n�[���[/�@108
�܁A�Ôg�Â̍j����/�@108
�܁A������̍j����/�@109
�܁A�V���̍j�����E�j�̏��/�@109
�܁A�x�x�����̎��E�Y�j�̓o��/�@110
�܁A��c�̍j�ł����/�@110
�܁A�`���̈ɗǔg��j����/�@110
�܁A�E���K��(�c�_)���J/�@111
�܁A�c�[�̐߃A���K�}/�@111
�܁A�����E�t�f�[�N �F�_���O/�@111
�܁A�m�O��Ղł̃E�}�`�[/�@112
�܁A�ۉh�̑�L�N��/�@112
�܁A�l���̒��ł��낮��҂���/�@113
�܁A�{���̃N�C�`���[/�@113
�܁A�y��N(�g�[�e�C�N��)�Ղ�/�@113
�܁A�^�h���L�N��/�@114
�܁A������j�����̓��Y�l�[�ł̗x��/�@114
�܁A������Z���N�L�O�j��/�@115
�܁A������j�����̓��Y�l�[�ł̃N���W�����T�o�N�C/�@115
�܁A�x���̏\�ܖ�/�@115
�܁A�匴�̌����/�@116
�܁A���NJԓ��̔����x��/�@116
�܁A��Ղ̐_�`/�@116
�܁A�Ôg�Â̗x�莂�q���Č�/�@117
�܁A�V���̎��q����/�@117
�܁A�����̎��q����/�@117
�܁A���q��/�@118
�܁A�쉮���̏\�ܖ�A�V�r�[/�@118
�܁A��q���(�^�j�h�D��)/�@118
�܁A�p�[���g�D�v�i�n/�@119
�܁A�����̍�������/�@119
�܁A���L����̊���/�@120
�܁A���NJԓ��̃X�c�E�v�i�J/�@120
�Z�A����������炵�U�� �ϖe���鐶���Ƌ{�Ó��䕗�@121
�Z�A�p�C�i�K�}�r�[�`/�@121
�Z�A�^���W���̐N�c������/�@122
�Z�A���~���w�Z�ł̒����^����/�@122
�Z�A�����I���̓��I���/�@122
�Z�A������̐��|���/�@123
�Z�A�ԉōs��/�@123
�Z�A���t�K�[/�@124
�Z�A�n�V�`�ŋ��𐅗g������l�т�/�@124
�Z�A�r�ԓ��̈��/�@124
�Z�A��Y�p/�@125
�Z�A�����̎s��/�@125
�Z�A���������܂�/�@126
�Z�A�T�g�E�L�r�̎��n��Ƃ̍���/�@126
�Z�A�ΐ�/�@126
�Z�A����������l�т�/�@127
�Z�A�t�J�q��/�@127
�Z�A���ߍH��œ����l�т�/�@128
�Z�A�����X��/�@128
�Z�A���o���^����L����O�X�N��]��/�@128
�Z�A���������q�ǂ���������
�Z�A�Ԃ����R���N�[��/�@129
�Z�A�S���Œނ������q�ǂ�����/�@129
�Z�A�T�V�o�������N/�@129
�Z�A�ۗǐ�Ő��V�т���q�ǂ�����/�@130
�Z�A����������ău���b�N���Ɋ��Y���q�ǂ�����/�@130
�Z�A�`��/�@130
�Z�A�n�V�c�t���̃R���Z�b�g�Z��/�@131
�Z�A�y�c���c�t�������L�O/�@131
�Z�A�����̌����ۈ牀������c�ƖL����c�n���Ɋ���/131
�Z�A���D�Ɛl�тƂ̕�炵
�Z�A����M�𑆂��l/�@132
�Z�A�Ί_�`�o�q���i/�@132
�Z�A�ɗǕ����畽�ǂւ̒���D/�@132
�Z�A�擇�q�H�D��/�@132
�Z�A���ԓ��T�o�j��S���q�ǂ�����/�@133
�Z�A�T�o�j���}����/�@133
�Z�A���Ó��Ƃ̊Ԃ���������n���D/�@133
���A�������J�� �n��̔��W�Ǝ��R���@134
���A�r�ԑ勴�J��/�@134
���A���ԑ勴�n�菉��/�@135
���A�T�U���Q�[�g�u���b�W/�@135
���A�t�F���[�u�����Ƃ��v�̉חg�����i/�@135
���A�����V��/�@136
���A�n�Õ~�`/�@136
���A���ꌧ��������/�@136
���A�����s����/�@137
���A�앗�������Z���^�[���J��/�@137
���A�嗢�O���[���^�E��/�@137
���A����ςɃ��[��/�@137
���A�A�E�g���b�g���[��/�@138
���A�����̃h�C�c������/�@138
���A���ΐ����E���n�Z���^�[/�@138
���A�O�X�N���[�h����/�@139
���A�ʂ�r/�@139
���A���������/�@140
���A�ނ��̔�/�@140
���A���{�Ő��[�̔�/�@141
���A�}�̏�/�@141
���A����炳��W�]��/�@141
���A�嗢���/�@142
���A�l����/�@142
���A�n���엢���/�@143
���A����/�@143
���A��k�e�P����p�͑��/�@143
���A�n�[�x�X�^�[�ɂ��T�g�E�L�r�̊������/144
���A�k�H�[/�@144
�J���[���G/�@1
�ʐ^�Ƃ������̋L�^<����P>/�@5
���Ƃ���/�@145
�ʐ^�E�����҂���т����b�ɂȂ������X/146
��ȎQ�l����/�@146
�E |
�P�O���A�٘@�Бܒ��� ; ���c�Z�Y��u�ܒ���l�G���` (���y��)�v���u�Վ����сv����Ċ������B�@���ŁF�Q�O�O�P�N
�P�P���A���F�M���u���É��s����w�l���Љ�w�������I�v 15 p.19�`42���É��s����w�l���Љ�w���v�Ɂu���ꌧ�������̍��J�V��Ɋւ���l�@(��)���K���ܖڂ𒆐S�Ɂv�\����B
�P�P���A�떓�b��, �ێR�����ҁu���\���E�����E�g�Ɗԓ��̓`���E�̘b�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B
�@�@ (�����̓`����������� ; 2) �@�@�@247p �@�����F���ꌧ���}���فF1003970009
�P�P���A���p������y�@�o�ŕҁu�ܒ���l�v���u�i���s�j��y�@�v���犧�s�����B�@�@ (�Ă炱��u�b�N�X ; 18)
���A���̔N�A����オ�u���y�����̑n�� : cmc : ���y�����Ɛ��U�w�K�̑������E������
28 p.54-57�v�Ɂu�����|�\�̉��E���y(8)�G�C�T�[ �����鎄�����̎v�����̂��āv�\����B
���A���̔N�A�uInter communication = �C���^�[�R�~���j�P�[�V���� 12(4) (�ʍ�
46)�@���W ����--<�鍑>���牓������āv���uNTT�o�Łv���犧�s�����B
|
�J���[ OKINAWA BAROQUE ���� ��Y p.6�`16
�Βk ����--�����Ǝ��摜�̑��� ���F�p��+�������@
�@�@�����F�p��,������ p.17�`49
����ւ̎���/���ꂩ��̎����@ p.52�`83
����̗H��--���]�T�i�ƐR�^���̉f�悩�� �k���H���u p.86�`91
�R�`���ۃh�L�������^���[�f���2003
�@�@��������W--�����d�e��`/���E�̃����_�[�����h�@p.92�`95
�ʐ^��<����>--�L�^�ƕ\���̂͂��܂� �@��|���q p.96�`101 |
����|�b�v�Ɓu���܂����v--�Z�����鋫�E �v���c�W p.102�`107
�u����v�����܂��ꏊ--
�@�@���r��i��C���^�����[ �r��i��,�����i p.108�`112
�u����l�v�����^���A�[�g�v�Ɓu������v--
�@�@��������j�̏I���̌��� �X��Y p.114�`118
�g�̂̉��̊�?--<����>�ƃw�e���g�s�A�̎v�l �㑺���j p.120�`128
�܍� ����}�b�v--��b�f�[�^/���j�E��n�E�ό� p.�}4p
�E |
���A���̔N�A���y��������ҁu���y������ (�ʍ� 20)�v�����s�����B
|
�̎��E�y������ ���ꌧ���A�m���^�ߗ�̎�x��G�C�T�[�^���� ���] p.129�`136
�̎��E�y������ ���ꌧ���A�m���z�n�̎�x��G�C�T�[�^���� �K�j p.137�`144 |
���A���̔N�A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������I�v�F�쓇���� ��25���v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
|
�������ɂ�����y�n���p�̕ω� ���� �� p.1�`19
�����C�l�̉�--�u�����s�̐̉�1�`7�v�̕�� �@���{�M�v p.21�`32
���ꌧ���ɂ�����ŋ߂̊Ȓ��ނ̓n���L�^�ɂ��� ��������,����h��,���T�M �� p.33�`46
�n�Ў����𗘗p�������j��Ԃ̕������(2)�}�����A�L�a�n�̒n���I���i ��l��
p.47�`72 |
���A���̔N�A���{�M�v���u�쓇���� (25) p.21�`32�@���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v �Ɂu�����C�l�̉�--�u�����s�̐̉�1�`7�v�̕��v�\����B
|
���{�M�v���u�쓇���� (14�`25) �ɔ��\�����u�����s�̐̉�1�`7.���]���̓���ꗗ�\�@�@�iIRDB�j
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
| 1 |
�쓇���� 14 p.17-84 |
1992-03 |
�����s�̐̉� I : �_�̃n�[���[�̃E�V�f�[�N�́@�@ |
. |
| 2 |
�쓇���� 15 p.51-94 |
1992-03 |
�����s�̐̉� II : �j�g�́@ |
. |
| 3 |
�쓇���� 18 p.63-96 |
1996-03 |
�����s�̐̉� 3 : �G�C�T�[�̏j���� |
. |
| 4 |
�쓇���� 19 p.63-84 |
1997-03 |
�����s�̐̉�4 : ������ |
. |
| 5 |
�쓇���� 20 p.39-86 |
1998-03 |
�����s�̐̉�V : ���ׂ��� ��@ |
. |
| 6 |
�쓇���� 21p.11-44 |
1999-03 |
�����s�̐̉�VI : ���ׂ������@�@ |
. |
| 7 |
�쓇���� 22 p.39-74�@ |
2000-03 |
�����s�̐̉�VII : ���ׂ������@�@ |
. |
| 8 |
�쓇���� 25 p.21�`32 |
2003- |
�����C�l�̉�--�u�����s�̐̉�1�`7�v�̕��@�@ |
. |
|
���A���̔N�A�啪������ψ���[�ق�]�ҁu��B�n���̋ߐ��Ў����z 2(�啪�E�{��E�������E����)�v���u���m���сv���犧�s�����B (�ߐ��Ў����z�������W�� ; ��20��)�@�V���[�Y���� ����[�W��]��, �T��L�Y,
��a�q ���@�@�d�v
|
�啪���̋ߐ��Ў����z / �啪�����璡�Ǘ��������� ��
�{�茧�̋ߐ��Ў����z / �{�茧���璡������ ��
���������̋ߐ��Ў����z / ������������ψ������ ��
���������̋ߐ��Ў����z(������) / �����������璡������ ��
���ꌧ�̐M�Ɋւ��錚���� / ���ꌧ���璡������, ������w�H�w�����z�H�w�� ��
�i�啪�E�{��E���������͏ȗ��j |
|
���ꌧ�̐M�Ɋւ��錚�����ߐ��Ў����z�ً}
�@�@���������ڎ�
I�@�������Ƃ̊T�v�@8
I�@1.�@���Ǝ�́@8
I�@2.�@���Ɗ��ԁ@8
I�@3.�@�����̖ړI�@8
I�@4.�@�����͈́@8
I�@5.�@�����̕��@�@8
I�@6.�@�������@8
I�@7.�@���͎ҁ@9
I�@8.�@���������@9
II�@���ꌧ�̋ߐ��Ў����z����ѐM�Ɋւ���
�@�@���������̔w�i�@12
II�@1.�@�n���A���y�@12
II�@2.�@���j�@12
II�@3.�@�ߐ��Ў����z����ѐM�Ɋւ��錚�����̎�ށ@13
II�@4.�@�������̌`���Ɗe���̖��́@14
III�@���ꌧ�̋ߐ��Ў����z����ѐM�Ɋւ���
�@�@���������̊T�v�@16
III�@1.�@�����������ꗗ�@16
III�@2.�@�ʉ�����������ݒn�}�@24
III�@3.�@�ߐ��Ў����z����ѐM�Ɋւ���
�@�@���������̌ʉ���@27
���E���w�蕶�����������ꗗ�@151
�Q�l�����@152
�ʉ���Ώی�����
�ԍ� ���� ��
001�@���K�̐_���������@27
002�@�ɐ����ʌ�a�@28
003�@�����Ƃ̕�@30
004�@�ɐ����̐_�A�V���Q�@31
005�@�����q�̐_�A�V���Q�@31
006�@�����̐_�A�V���Q�@32
007�@���c�̐_�A�V���Q�@32
008�@�`�{���̕�@33
009�@�Ӗ���̐_�A�T�M�@34
010�@�i��@35
011�@�V���W���@36
012�@�L���̃E�t�V���W���@36
013�@�r���@37
014�@��R�̐_�A�T�M�@38
015�@�S�i��@39
016�@����̓y��N�@40
017�@��u���̐_�n�T�[�M�@42
018�@�v�u�ω����@43
019�@�썲���{�@44
020�@���Ԍ������@45
021�@���߃k��ԁ@46
022�@���c�剮�̕�@47
023�@�y�c�k��ԁ@47
024�@�����ω����@48
025�@�É́@50
026�@�ΐ���̍����@51
027�@�Î芡�́@51
028�@�k���a���̉̐_�@52
029�@���]�F�̓a�@53 |
030�@�c��K�[�@53
031�@������@54
032�@�����@55
033�@�l��̎��@55
034�@�얼�̓y��N�@56
035�@����ˁ@57
036�@���g���̔q���@58
037�@����ˁ@58
038�@�g���̐_�����@59
039�@�g���̔q���@59
040�@���R�l�o�����̔q���@60
041�@��V�b�O�̔q���@60
042�@�n���̃e���@61
043�@�����a�@62
044�@�����̉̐_�@63
045�@�M�c�̃R�[���[�@63
046�@��ɏ��꜉��@64
047�@��ɏ���̕�@64
048�@�E�i�U�����@65
049�@��̌�ԁ@65
050�@�n���̓a�@66
051�@��ɏ�̉̐_�@66
052�@�썲�ۂ̕�@67
053�@�Ôe��꜉��@68
054�@�����̎��@68
055�@��F���̃J�[�@69
056�@�X�̐�@70
057�@��@�Ãq�[�W���[��@71
058�@���\��@72
059�@��Ӗ��̓y��N�@73
060�@�Î芡�̓a�@73
061�@�I���̓y��N�@74
062�@�E�t���~�E�^�L�@75
063�@�ɑc�̍����@75
064�@�Y�Y�悤�ǂ�@76
065�@�Y�Y��a�̕�@77
066�@���~�o������@78
067�@���i�}���@79
068�@���g�{�@80
069�@�ǒJ�R��a�̕�@81
070�@�X��p��a�̕�@82
071�@��u�e���̕�@83
072�@�ɍ]��a�Ƃ̕�@84
073�@���J��ԁ@85
074�@������ԁ@86
075�@�����m�Ƃ̕�@87
076�@���~�悤�ǂ�@88
077�@�쉮���v�a�@89
078�@�V���̓y��N�@89
079�@���i�̕�@90
080�@������ԁ@91
081�@�H�h�X��ԁ@92
082�@�J�j�}����ԁ@93
083�@�M�����C��ԁ@94
084�@�`�`���K�[�@94
085�@�������q�[�W���[�@95 |
086�@�앗���i�̕�@96
087�@���g�����及�V�a�@97
088�@�����K�[�@98
089�@�K�n���咆�̕�@99
090�@���`������@100
091�@�O��@101
092�@�����Ƃ̕�@102
093�@�l��Ƃ̕�@103
094�@�V�@�{�@104
095�@���K�̐Ε�@106
096�@�m���^�ǖL���e�̕�@107
097�@�l���̎�̕�@108
098�@���c�K��@109
099�@��a��@110
100�@���@���L���e�̕�@111
101�@�A�g���}��@112
102�@�n���̃E���J�[�@113
103�@�E�B�s���[���g�D�̍Տ�@114
104�@�j�X�j����ˁ@115
105�@����ߐ�@116
106�@�O����@116
107�@�ɂ��@117
108�@�^����ԁ@118
109�@�O��@119
110�@�i�K�C����ԁ@120
111�@�A�i��@121
112�@�X�T�r�~���[�J�@121
113�@�^���ԁ@122
114�@�y���L���e�̕�@124
115�@����ԁ@125
116�@���V�q��@126
117�@�����ԁ@127
118�@�y��ω����@128
119�@�A�[����ԁ@130
120�@�V���ԁ@131
121�@�����ԁ@132
122�@�{���䒹�@133
123�@���c���̕�@134
124�@�����B�u�V�I���@135
125�@�R���ԁ@136
126�@�C�T���`�����[�@137
127�@�}�J�i�C�l�̕�@138
128�@�k�_�R��@139
129�@��]�n�_��@140
130�@���v�ɁE���R��ԁ@141
131�@�Õۍ���ԁ@142
132�@�i�J���h�D�[�����@143
133�@�V�{��ԁ@144
134�@�Q�[�g�z�[����@146
135�@�ۑ����Ƃ̕�@147
136�@�����Ƃ̕�@147
137�@�k�b�N���ԁ@148
138�@�E���m���ԁ@149
139�@�g�D�O�����ԁ@150
140�@�E�j�E�u�X�̕�@150
�E |
|
| 2004 |
16 |
�E |
�P���A�u�������ꂨ���Ȃ�v���J�ꂳ���B
�P���Q�R���`�Q�T�����A�u�������ꂨ���Ȃ�v�ɉ����āu�g�x �䊥�D�x��z�肵�������G���v�����������B
�P���A�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�ҁu�g�x �䊥�D�x��z�肵�������G���v���u
�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s�����B
�@�@�@32p�@�@�@�����F��㊌����}���فF1005887250
�@�@�@����16�N1��23��(��)6�����J��, 1��24��(�y)6�����J��, 1��25��(��)6�����J���@�ꏊ:
�������ꂨ���Ȃ�匀��
�P���A������ �ďC�u���������� (484)�@�@���W ����--�������ꂨ���Ȃ�J��L�O�v���u���@�K�v���犧�s�����B
|
���W ����--�������ꂨ���Ȃ�J��L�O p.1�`59
���G��� �������ꂨ���Ȃ�ɂ��� p.4,1�`3
�J��܂ł̌o�܂Ǝ{�݂̊T�v �������ꂨ���Ȃ�̐ݗ��ɂ���--�̂Ɨx��̓��A
�@�@���|�\�̕��"����"�̓`���|�\�̋��_�Ƃ��ā@�������`��������
p.7�`11
�������ꂨ���Ȃ�J��L�O�����̔ԑg�\�� �������ꂨ���Ȃ�^�c���c p.12�`15
����̕������T�K �鉺�̕������U�� �r�{ ���� p.16�`19
����̕������T�K �|�\�E�H�|�Z�p�E������������ �������`�������� p.20�`29
����̕������T�K ���p�H�|�i ���������p�w�|�� p.30�`35
����̕������T�K �L�O�� �������L�O���� p.36�`45
����̕������T�K ������ p.46�`52
����̕������T�K ����̍��w�蕶���������X�g�@�������������� p.53�`58 |
�P���A�c���k�ꂪ�������ۑ��S�����c��ҁu�����ւ̕����� (51) p.36�`38�v�Ɂu����� ����̃O�X�N���E��Y�o�^�ƕۑ��v�� (�k�������ۑ��S�����c��l��34��ޗǑ����W�� ���{�̐��E��Y�Ɠޗ�)�@�v�\����B
�P���A�X�۞Ď��Y���u�������ꉫ��̉ʂ��������v���u���{�����w��z���������ψ���v���犧�s����B�@ (���z����������� ; AA-2004-09)
�P���A�ߓ����s���u�{�ّ�w�@�w���ҁu�u�{�ٖ@�w = Shigakukan law review (5) p.213�`241�@�u�{�ّ�w�@�w���v�Ɂu�^�_���ɂ�����K���̌���v�\����B
�P���A�쑺�L��Ғ��u���A�W�A�̏��_�M�Ə��������v���u�c���`�m��w�o�ʼn�v���犧�s�����B
(�c��`�m��w���A�W�A�������p��)
|
����-���A�W�A�̊�w�����̊�����߂�
�@�@�@�����V�i�C���ӂ̏��_�M�Ə��������j�̎��_ / �쑺�L�� ��
�����E����E���N�̊C�ӂ���̊፷��
�@�@�@�� �@���Y�Ȃ̏������Ɩ����Y�Ȃ̏������̔�r / �c���ꐬ ��
�����Ȃɂ����鏗���̐����Ə��_�M�̗��j / ���Ŗ] ��
���_���Ƃ̋V��ƌ|�\�`�� / �t���� ��
���_�M�̌���I�ϗe / ��ؐ��� �� |
�{�Ó��̍��J�̗w����݂����_ / �㌴�F�O ��
�{�Ó��E�떓�Ɍ���ߑ�ƌÑw / ���_�K�q ��
�×����̏����Վi�̊��� / ������� ��
�ϏB���̊C�������̂̐��Ǝd�� / �ؗщ� ��
�S���쓹�̏��_�Ƃ܂� / ����[���E] ��
�؍��̒����ɂ����鏗�� / ���_�� ��
�E |
�Q���P�O���`�Q���Q�X���A���ꌧ�������قɉ����āu��O�E���̕������ی� : �����v�Y�̊������Ƃ����āv�W���J�����B
�Q���A�u�����搧�����W�� ��1���v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@(��5��)�@���Ł@
1979.12 pid/12168639�@�d�v
|
���@ / �y��쎡, �����Ďi ��
���_ / �y��쎡, �����Ďi ��
���@�̎�� / ��V���͎� ��
�����̖��Ɋ� / �ēc�� ��
�ۏB�O�����̌��� / ��ʕ{�� ��
�Α��E���� ���{�ɉ�����Α��n���̖�� / ��c�F�N ��
�䍑�ɉ�����Α��̖��Ԏ�e�ɂ��� / �x��Y ��
���������搧�ɂ��� / ��c�O�Y ��
��˕�̂��� / �員�䂫 ��
���� �����Ɋւ����� / �y��쎡 ��
���̈���̕��K / �c���v�v ��
�쓇�Ñ�̑��� / �ɔg���Q ��
���V���̊≮�� / ���x�d�� ��
���l�� / ������G ��
�����E�� �����哇�̐ƕ��� / ���c�{�� ��
�����ɉ�����̕��K / ���钩�i ��
����̐V�� / ���Ð^�X�� �� |
�{�Ó��{���̈ڑ��E�E�搧 / ���䓿���Y ��
�l�����������m��������(����)�ƈ���(��J)�̗��搧 / �ɓ��G ��
���������搧 / �ŏ�F�h ��
���ꑒ�@ �ؒn�t�̑��@ / ���c���j ��
���̕��Ɋւ���֊� / �j��a�Y ��
�s�w�̎r���َ����������� / ����F�� ��
���ٕ����������� / �R�����Y ��
"�a�l"�����V���ň͂�"��"�ɂ���b / ������ ��
�q�� / �c���v�v ��
���ߕ�ȑO / �����Ďi ��
���a�R�n�̑��g��(�~�C��)�Ƃ��̔w�i / �x��Y ��
�e�n�̑��@���� �n�J�݂̐� / �V�J���I ��
�X����Ӓn�n���̑��� / ���s���O ��
�_�ސ쌧�Ëv��S�n���̑��� / ��؏d�� ��
���䓇�̑����E�搧 / �c���ۏ��F ��
���V���̑��� / ���R���G ��
�E |
�Q���A�{�ǒ��� [��],�O�،�, ��R�L�q�Ғ��u�{�ǒ����W : ���ꋳ�特�y�_�v���u�j���C�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@264p�@�@�����F��㊌����}���فF1003997093
|
��P���@�{�ǒ���M�_���i���ꉹ�y�̉��v�y�щƒ뉹�y�̕��y��G���珥�̂̌����G���w�N�����̕��ʌ�ɂ��@�ق��j
��Q���@�{�ǒ���̋���ρE���y�ρi�{�ǒ���̉��y�ςƍ�ȏW���s�̌o�܁G�{�ǒ���̉��y����ƍ�Ȋ����j
��R���@�������ɂ݂�{�ǒ���E�l�Ɖ��y�i����͒���������Ƃŋ~���Ă���i�R�c�k⩁j�@���y�̋ߑ�I�V�ˁi��_���O�Y�j
�@�@�@�@�@���u�Ï�v�̂��Ɓi�ɔg��N�j�@�ق��j |
�R���A�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�ҁu�g�x�̐́E���E���� : �������ꂨ���Ȃ�J��L�O�����@��W�T�v���u
�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s�����B �@
�@�@����16�N3��19��(��)�ߌ�6�����J��, 20��(�y)�ߌ�6�����J��, 21��(��)�ߌ�6�����J���F�������ꂨ���Ȃ�匀��
|
�u�������ꂨ���Ȃ�J��L�O�����v�ƕ���̂�����1�`8�T���̓���ꗗ�\�@�@
| �T�� |
�����N���� |
����F�����ړ��e |
�@�ʁ^�����R�[�h |
| 1 |
����16�N1��23��(��)6�����J��, 1��24��(�y)6�����J��, 1��25��(��)6�����J�� |
�g�x �䊥�D�x��z�肵�������G�� |
32p�@1005887250 |
| 2 |
����16�N1��30��(��)6�����J��, 1��31��(�y)2���E6�����J��, 2��1��(��)2���J�� |
����`�����x�E�n�앑�x�@ |
32p�@1005887243 |
| 3 |
�Q���@2004�N5��29��(�y)�i�����v�j�@ |
���ꖯ�w�Ɖ���ŋ��@ |
40p�@1004055149 |
| 4 |
�Q�� |
�����|�\�V�}(����)�̓��킢 |
48p�@1005887227 |
| 5 |
�Q�� |
����̓`���|�\�ɉe����^�����{�y�̌|�\�u�\�y�����v
|
28p�@1005943236 |
| 6 |
����16�N3��6��(�y)2���E6�����J��, 7��(��)2���E6�����J�� |
�A�W�A�E�����m�n��̌|�\ : �A�W�A�E�{�y�̎O���ނƉ���̎O�� |
36p�@1005889074 |
| 7 |
����16�N3��12��(��)�ߌ�6�����J��, 13��(�y)�ߌ�6�����J��, 14��(��)�ߌ�6�����J�� |
�O�����y�̓`���Ƒn�� |
36p�@1005887219 |
| 8 |
����16�N3��19��(��)�ߌ�6�����J��, 20��(�y)�ߌ�6�����J��, 21��(��)�ߌ�6�����J�� |
�g�x�̐́E���E���� |
CiNii |
| - |
����16�N5��29��(�y) |
�ʏ闬�ʐ��x��̉� : ��18�� �ʏ闬�ʐ�� |
1�� 1004681340 |
| - |
����16�N�x12��5��(��) |
�ʏ�G�q�̉� : �ʏ闬�ʐ�� |
1�� 1004688923 |
|
�@�@�@�@�����ړ��e�ɂ��Ă͍���̌����ۑ�Ƃ��Ď��g�ޗ\��ł��B�@�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�Q�X�@�ۍ�
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu����̍j�����K���������v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B�@
�@�@ (���ꌧ������������, ��143�W) �@ 318p
|
����̍j�����s���̕��z
��1�� �����̊T�v
��2�� ����̍j�����s���̊T��/��]�F��
��3�� �d�_������
I �����n�� / ���F��
II �����n�� / �茴�P�V
III �ߔe�s�� / ���]�F�֎q
IV ���K�n�� / �ԗ䐭�M
V �{�Òn�� / ���@������
VI ���d�R�n�� / �����r�� |
��4�� ��b������
1.�ɐ����������q / ���~����
2.���������� / ������,����y�q
��5�� �j�����W����
����̍j�����s���̕��z
��1�� �����̊T�v
��2�� ����̍j�����s���̊T��/��]�F��
��3�� �d�_������
I �����n�� / ���F��
II �����n�� / �茴�P�VI |
II �ߔe�s�� / ���]�F�֎q
IV ���K�n�� / �ԗ䐭�M
V �{�Òn�� / ���@������
VI ���d�R�n�� / �����r��
��4�� ��b������
1.�ɐ����������q / ���~����
2.���������� / ������,����y�q
��5�� �j�����W����
�E
�E |
�R���A�{���,��ؗǖF��,�c����,��������,���a�l,�����v�X,���^�k��,����,��,�O�c�^�V,�o�ߗ��q,�ʏ�P�N���u���l������������2004�@Survey reports on natural history, history and culture of Kohamajima Island�v���u���ꌧ�������فv���犧�s����B�@146p
|
���l���̒n�`�n�� / �{���
���l���Ŋm�F���ꂽ�w偌`�ށA�O�r�ނ���є{�r�ނɂ��� / ��ؗǖF��,�c����
���l���ɂ����闼����ނ̌���ɂ��� / �c����
���l���ɂ����钹�ނ̋L�^�ɂ��� / ��������
���ꌧ���l���̘H��ɂ�����S�C�T�M�̑҂������^�̐H�s�� / ���a�l,�c����
���l���ɂ�����C���h�N�W���N�̌���ɂ��� / �c����
���l���ɂ����郄�G���}�I�I�R�E����
�@�@��Petropus dasymallus yayeyamae�̉a�A���ɂ��� / �������� |
���l���̈�� / �����v�X
���l���̃N�X(�O�X�N) / �c���k��
���l�����痬�o�����ËL�^�Ɓu���ꕶ���W�v�ɂ��� / ������
���l�����w�Z�ɂ��� / �O�c�^�V
���l���̐��D�T�� / �^�ߗ��q
�T�g�E�L�r�͔̍|�Ɠ��̕�炵 / �ʏ�P�N
�E
�E |
�R���A���]�F�i������\���@����w���ꕶ���������ҁu�����ɂ�����Љ�I�A�����I�l�b�g���[�N�̌`���ƕϗe�Ɋւ��鑍���I�����v���u���]�F�i�^�����(���)�v���犧�s����B�@�����Ȋw�ȉȊw������⏕���������ʕ�
|
�u�A�W�A�̒��̓��{�w�v�\�z�̐헪�I���_�Ƃ��Ă̗����w
����̋L���ƈӎ�
����o�ς̐V����
�F���ˁE�����E�����ɂ�����ߐ������̐V�c�J��
�u�����j���v�̎j���w�I����
���������̐��i�ƒ��N����
�w�����낳�����x�̔��n�Ƙh
�vጂ̌n�� |
�엮���������C�̌n�̕ω��X��
���������Ɗ؍���ɂ����鉹�C�̑Ώ�
�R�x�����ƊC�m���ז����̃l�b�g���[�N�\�z�ƌp��
�����E����A�W�A�̍��q�ƕ�����Ɋւ��閯����
���{�A���n����ɂ�������{�l�̑�p�l�C���[�W
���{�́u��i�v�Ƌ��琭��̕ϗe
�A�W�A�R�������̌`���Ɨ����E�����R�̕����I����
�E |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw:���ꌧ���|�p��w�����������I�v 16�@�^�ߍ����̓`����������������,�����H�^�s�����ފ��L�O���v�����s�����B�@
|
�����H�^�s�����ފ��L�O���̊��s�ɂ������ā@�g�Ɗ� �i�g�@ p.1-3
�^�ߍ������ɂ��ā@�����H �^�s,���� ���@ p.17-74
�ߐ��^�ߍ��̎x�z�ƍv�[�@���� ���ہ@ p.75-101
�^�ߍ����E���̎R�����Ӗ��@�약 ���Y�@1 p.103-126
�^�ߍ��̐��n�ƍ��J(1)�@�^�ߔe �m��,�g�Ɗ� �i�g�@ p.127-170
�^�ߍ����̌|�\�o���@�ѓc �וF�@ p.175-227 |
�g�x�u���ΓG���v�̌h��\���@���� �q�@ p.229-240
�Ί_�����̋[���[�Ԍ�(1)�@�O�� ���ގq�@ p.241-257
���d�R���l�����̉��C�@���� �� p.259-287
��_���̉��C�ɂ��ā@Sakumoto Shige�@ p.289-303
�u���q�F���Y�m�[�g�v���ڕ��������ɂ��ā@ꎓ� ��q p.305-352
���d�R�����̋����������@�ѓc �וF�@ p.353-432 |
�R���A�ʏ鐭��������\�F�ʏ鐭�����u�������ꏔ���ɂ�����V��̗w�̎��W�E�����ƃf�[�^�x�[�X���v���s���B
�@�@ (�Ȋw������⏕��(��Ռ���(B)(2))�������ʕ�, ����12�N�x�`����15�N�x)
|
���ꏔ���̋V��̗w�̊T�� / �ʏ鐭��
�����s��F�̃m�����J�Ɋւ����l�@ /�v���c�W
�v������<�C�N�k�q�[> / �ԗ䐭�M
�����E���W�����f���E�����e�[�v�ژ^ |
�̗w�̓`���n�_�ʃf�[�^�x�[�X
���W�̗w�̃f�[�^�x�[�X
��������̗w�֘A�����ژ^�f�[�^�x�[�X
�E |
�R���A���R��,���X���p�����w�������I�v�ҏW�ψ���� �u�I�v = The bulletin of Hirosaki Gakuin University (40)�@ p.1�`11�O�O�w�@��w���w���v�Ɂu����̖��ԐM�� : �ɗǕ����̃J���X�v�\����B
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v12�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
�@�@�@ 184p �@�@�����F��㊌����}���فF1004025860
|
���`�f�ނƂ��Ă̎���ɂ���--���ꎽ������ ���g�[�� p.37�`50
�����ÓT���x�ɂ݂��O�x��̑n�쌤��--���{�I�������Ƃ���ꂽ��O�x��w�Փ��R�x
���g�Ύ} p.51�`63
�ɕn���� ����--�R�V���т̎��ɂ��̋ȏW ���{�M�v p.117�`144
�w�����̗����x�l : ��̎҂̎�����������e �O�� �킩�� p.145-152
�q�����r |
�R���A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu�Ί_�������� 2�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@
�@�@�@ (�n�挤���V���[�Y ; no.32)
|
�Ί_���E�s�풼��̐����ɂ��� / �����X��
��͂�l���ł͂Ȃ����� / ���ԑגj
��z�Z�E���Z�E�m�Z(�u���d�R��������ǁv�̂���) / ���ԑגj
�V�{�ƕ����u���d�R���l���ŕ��ۑ䒠�v(����) / ���ԑגj |
19���I���d�R�̐l���̔N��ʍ\�� / ���ԑגj
�Ί_���ɂ�����`���H�|�]���҂ւ̕�����蒲��. 1 / �Ж{�b��
�V�{�ƕ����w���b�x�̖|������ђ��� / �����r�O, ���{�q
�E |
�S���A�u�����w�v���s�ψ���ҁu�����w : ���̒n���Ɣޕ��@�R���ӈꎁ�̑�w�ސE�L�O���v���u����V�Ёv���犧�s�����B
|
��ꕔ���k�����̖���(����)��T���� : �����w���̒n���Ɣޕ�
������w�̒n�� : �����������E : �����E�_�̍s�� :
�@�@�� �m���E�ِl�E�ٍ��V / ������Y��
�m������������ : �����E��a����I / ���c�e���q��
�����̏���V��̍\�� : �����s��F�̎��Ⴉ�� / �v���Ђ�ݒ�
�u慉̓|��v�Ɓu�T�J�E�^�v�̊֘A / ���R���G��
�u�������܂���v�Ɋւ����l / ���ʉi����
�̂ނ��� / ���v���]��
��E���E�����́u�\�[�����K�u�[�v���l / �������Y��
�w�Z�̕|���n�i�V : �����s���������w�Z / ��a�q��
�F��̕��i / �z�Ԑ���
����ւ̈ʑ� : �����̈ꎚ�����Ƌ��y�i�ɂ��� :
�@�@�����̗��j�I�w�i / �|�퐭�Ȓ�
�����Q���̖����ɂ��� / ���c�G�� |
�Ñ�̓쓇�o�c�Ɖ����̒n���\�L�l / �ёh��j��
�n���Ɍ���u�v�̎v�z / �����`����
�쐼�����̓����� / ��c������
�����O�X�N�����O�� / ���R������
��E������̔��M / ������
�F���˂̎R�сE�y�n����Ɖ��������̕�炵 / �`�x�O��
���ɕ{���サ���Ԗ؍l / ��c�L�t��
�����ւ̉�H : �u�������l�T���X�v�̌ď̂��߂����� / �ԍO�u��
��\�ꐢ�I�ɂ����铇�����ւ̎��_ / ��c���F��
���A�\���N���I�������� / �v���w��
�����������ō݂葱���邽�߂� / ��������
�v���Ƒz���̊Ԃ� : ���̒��̉��� / ���Ԓ��G��
�����E���̈�_���� / ���V�K�q��
��������̎R���ӈꂳ�� / ����߈꒘ |
�S���A�ѐD�����^�������u�H�̌��v���u�|�j�[�L���j�I���v���犧�s����B�@�@�^���f�B�X�N 1�� : CD �@���^: 2004�N4��
|
(1)�H�̌�(������Y)(2)�r��̌�(������Y)(3)�H���̉�(�R�c�k�)(4)���t��(���яG�Y)(5)���炽���̉�(�R�c�k�)(6)���Ƃ����є�(�������F)(7)����ǂ��̉�(�{�ǒ���)(8)�h�B���(�����Lj�)(9)�����̉����̉�(�����Lj�)(10)���̃^���S(�����Lj�)(11)�ЂƂ����̖�(�������F)
|
�T���A�������V���u�ʏ钩�O�̐��E : �����g�x�v���u���؏��[�v���犧�s����B�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004742340
|
�͂��߂�
��� ���O�ܔԂ̒a���Ə㉉
���� �g�x�̒a���\�\�w���z�x�Ɓu�ƕ��v
���� ���O�ܔԂ̏㉉
�P ���D���� �Q �g�x�̏㉉ �R ���O�̉��o
��� ��ƂƂ��Ă̒��O��
���� ���O�̐l�Ԋ�
�P ���O�ܔԂ̕]�� �Q ���R�Ɨ~
�R ���̏K���Ɛ��̒�� �S �u��v�̏d��
���� �Љ�̋��R�ƒ��O�\�\�n�肮�ꂵ��
�P ���J�̊Q �Q �n�肮�ꂵ�� �R ���O�̌��E
��O�� ���O�̏@����
�P �Ɓu���̑剮�q�v �Q ��ƒ��O
��l�� ��c��̎�i���O�̔ӔN�j
|
�P �~�q�P�̖��� �Q ���������čč�
�R ���̏o�� �S �͎��ւ̌X��
�O�� ���O�ܔԂ̑S�e
���� ���D�Ƃ̂������
�P �g�x�̏j�V�� �Q ���{�̊֗^
�R �u�����q�v�Ɓu�R���L�v
���� �ʒꂷ��_���ƈӎ��\
�@�@�������ꂽ�Ƒ�
�P �ƕ��� �Q ��q���J �R ���e�̕s��
��O�� �ܔԂ̃e�[�}�Ɛl����
�l�� �g�x�̓Ǝ���
���� �G���Ƒg�x
�P ���܌��̗��� �Q �u�Y�v�Ƒg�x
���� �ď̗̂h��
|
�P �������x�� �Q �����ƌĂ��g�x
��O�� �g�x�̓Ǝ���
�P �������̌|�\ �Q ���{�Ɨ��� �R �����Ɨ���
�� �g�x��ǂ�
���� �u�G���v�\�B���ꂽ�A�}�I�w��
�P �̎��Ƃ̂������ �Q �A�}�I�w�̏d��
�R ����Ƃ�܂�� �S ���ǂ̂��܂��
���� �u���S�����v
�P �X�g�[���[�̓W�J �Q �����ɐ�����
������
�t ���O�ܔԑ�{�i������{���j
�ʏ钩�O���N���@p.338-346
����
�E |
�T���A�u�������z (125)�v���u���{�������z�w��v���犧�s�����B�@�@pid/11198656
|
���G �؍��̖���/���G��
������ ���q�l�i�Ԃ肭��j/�R��O/1�`
���{�������z�w�� �����d�v�搶 �Ǔ�//3�`16
������𓉂�/�R��O/3�`
2003�N�A�����搶�́A�Y����Ȃ��Ïk�����v���o/�Ð� �C��/4�`7
�����d�v�搶�̂������𓉂�/�H�R ���q/7�`9
���z�{�ɑz�����c��/�{�� ���O/9�`11
�݂肵���̍����搶/�{���q/11�`
�u�t��v���̍����搶�v/�����K�F/12�`
�v���o������/�y�m�c���q/13�`
�����d�v�搶�𓉂�Ł\�����q�Ƃ���30�N/���_���T/14�`
���ۃV���|�W�E���u���ĂƓ��A�W�A�ɂ݂�`�����z�̊��p�v
�@�@���������̂��钬���݂����邽�߂ɓ`�����z�̊��p�͔@���ɂ���ׂ���/�Ð�
�C��/17�`33
�R���_�� �c粖۔V�i�̌n���Ɗ���--�ԏ������𒆐S��/�{�� �M�v/34�`46
�R���_�� �͐여��Ɍ`�����ꂽ�ߐ��̏W���ɂ������ԍ\���Ɋւ��錤��--
�@�@���k���̉��쌴�͍`�W���ɂ���/���� ���Y ;�ѕ� �N�� ;�i�� �N�Y/47�`56
�k���{�������z�w��l���\�����_���E��//57�`85
���Ƃɂ��������p��̌���--�R�W�L���̍l�@�𒆐S��/���� �؏� ;�Ð� �C�� ;�p �^�J/57�`66
����E���p�̐�㕜���Z��ƌ��z�ƒ����v�Y/�i�� ���� ;���� �p��/67�`75
�H�k���̏@�K�ɂ���--�������]�Ȃ̎R���W���ƏZ��Q�Ɋւ���j�I�����i����4�j/���� ��F/76�`85
����15�N�x�H�̌��w��� ����i�������j�ƒ}��i�������j�̖��Ƃ�K�ˁA���ދv����ɔ��܂�/���c ���� ;�镔 �~�q/86�`101
��39��k���{�������z�w��l������\��-2 �܉ӎR�̉��������Z�p--�w�i�ƌ���(2)�܉ӎR�̍��������̍\���I����/���� �o�[�o��/102�`109
��41��k���{�������z�w��l������\�� �t�����X�E���}�l�X�N��L��Ԃ���C�^���A�E���}�l�X�N��L��Ԃւ̋O��/�|�� �T��/110�`118
VIEW����(26) ���쌧�J�c��/�{�菟�O/120~
�V���Љ� (1)�w���̂Ɛl�Ԃ̕����j117���܂ǁx���q����/�i������/33�`
(2)�w�l�Êw�ҐΖ씎�M�̃A�W�A�������z���Ă���L�x�Ζ씎�M��/�{�菟�O/109�`
(3)�w�����̓s�s�Ƒ����x�������꒘/�i������/119�`
(4)�w���R�̐����V��x�ߓ�������/�ÎR����/126�`
(5)�w�����̎Љ�l�ފw�\�����Ƃ��̎��Ӕ�r�x�n�ӋӗY��/���u���\�q/127�`
�k�������z�W�l�����Љ� �P�s�{�E���A�_���A�w��\//122�`123
��� ����16�N�x��31����A������A��S����c�A�����/������/124�`
�� |
�U���A�O���킩�Ȃ����{���y�w��ҁu���y�w = Journal of the Musicological Society of Japan 49(3) p.202�`204�v�Ɂu�Đ�̉��̗������{����ɂ����镶����e--���y�����𒆐S�Ƃ��āk�� ���^�����l (���{���y�w���54��S������ ; �������\�v�|)�v�\����B�@
�V���A�u�����Y�\�j����������\��� : ���ʍu���E�������\�v�|�y�ёΒk�E�v���O����
��29��v���J�����B
�@�@�@�@�����F���ꌧ�������فF1004030670 �@�@71p
|
����|�\�j����������\��� : ���J�u���E�������\�v�|�y�уV���|�W�E���E�v���O�����ꗗ�\
| �m�� |
�J�Ó� |
�J�Ïꏊ |
�v���O�����̓��e |
| 1 |
1976�N7��3�`4�� |
�ߔe�s���������كz�[�� |
��1�� �@����|�\�j������ |
| 2 |
1977�N7��30�`31�� |
�ߔe�s���������كz�[�� |
. |
| 3 |
1978�N7��29�`30�� |
�ߔe�s���������كz�[�� |
. |
| 4 |
1979�N7��7�`8�� |
�ߔe�s���������كz�[�� |
. |
| 5 |
1980�N7��5�`6�� |
�ߔe�s�����������كz�[�� |
��5�� ����|�\�j������ |
| 6 |
1981�N7��4�`5�� |
�ߔe�s�����������كz�[�� |
. |
| 7 |
1982�N7��3�`4�� |
�䂤�ȑ��܊K�z�[�� |
��7�� ����|�\�j������ |
| 8 |
. |
. |
. |
| 9 |
1984�N7��7�`8�� |
�ߔe�s����ψ���O�K�z�[�� |
. |
| 10 |
. |
. |
|
| 11 |
1986�N7��5�`6�� |
�䂤�ȑ�5�K�z�[�� |
��11�� ����|�\�j������ |
| 12 |
1987�N7��4�� |
.. |
�����ݗ��Y�ҁu�|�\�̌p���ƑJ�](�R�s�[)�v�@11p
����|�\�j������ �����F���ꌧ���}���فF1004246482 |
| 13 |
1988�N�V��2�`3�� |
�䂤�ȑ��܊K�z�[�� |
. |
| 14 |
1989�N�V��8�`9�� |
�䂤�ȑ���K�z�[�� |
. |
| 15 |
. |
. |
��15�� |
| 16 |
1991�N7��6�`7�� |
�䂤�ȑ�5�K�z�[�� |
. |
| 17 |
1992�N12��12�`13�� |
�䂤�ȑ�5�K�z�[���@ |
�|�\�w�� ����|�\�j���������� ����4�N�x
�����F���ꌧ���}���فF1007091364 �@15p
|
| 18 |
1993.7 |
. |
�����F���ꌧ���}���فF1002944054�@�@48p
|
| 19 |
1994.7 |
. |
�����F���ꌧ���}���فF1002791653 �� |
| 20 |
. |
. |
. |
| 21 |
1996�N7��2���E3��
���a�N���F���a63�N |
�䂤�ȑ��܊K�z�[�� |
�����F���ꌧ���}���فF1004262588 55p�@�@�@ |
| 22 |
1997 �E�V |
�E |
�����F���ꌧ���}���فF1008279182 56p |
| 23 |
1998�E7��7���E8��
���a�N������2�N |
�䂤�ȑ��܊K�z�[�� |
�����F���ꌧ���}���فF1006983900�@ 56p |
| 24 |
1999.7 |
. |
�����F���ꌧ���}���فF1009748169 59p
|
�������E�u�t�Љ� ��� ��i�^[�q]
<���ʌ���>����ŋ��Ƌߑ㉫�� ��� ���Y�^[�q]
<�������\>
���̂̉��߂Ə��x�� ��� �i�~�^[�q]
�����i���ɏ��x��j�ɂ����锏��̑ԗl�ɂ��� ���� ��a�^[�q]
�ǒJ�������l�̑g�x�u�{���啠�v�ɂ��� ���l �^�E�^[�q]
�����̌��u��t���v�̍\���ɂ��� �^�ߔe ���q�^[�q]
�g�x�u�萅�̉��v�̉��y���ɂ��� ��� ���v�^[�q]
<���ʍu��>���P���c�Ɖ���ŋ� �� �D�q�^[�q]
<�V���|�W�E��>����ŋ��̌���E�ۑ�E�W�] ���� ���j�^
�@�@��[�p�l���X�g] �ɗǔg ��q�^[�p�l���X�g] ��� ���Y�^[�p�l���X�g]
�@�@���^�ߔe ���q�^[�p�l���X�g] �c�� ��Y�^[�i��] |
|
| 25 |
2000 |
�E |
. |
| 26 |
2001 |
�E |
. |
| 27 |
2002�N7��6�`7�� |
������K�z�[�� |
�����P�S�N |
| 28 |
2003.7��4�`5��
�����N�F����10�N |
�䂤�ȑ��܊K�z�[�� |
��28�� |
| 29 |
2004.7 |
�E |
��29���@�@�����G���ꌧ���}���فF1004030670 |
| 30 |
2005 |
�E |
�R�O��ȍ~�s�� |
| 31 |
2006 |
|
|
| 32 |
2007 |
|
|
| 33 |
2008 |
|
|
| 34 |
2009 |
|
|
| 35 |
2010 |
|
|
| 36 |
2011 |
|
|
| 37 |
2012 |
|
|
| 38 |
2013 |
|
|
| 39 |
2014 |
|
|
| 40 |
2015 |
|
|
| 41 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�X�͒��x�m�F�ł��܂������R�O��ȍ~�͕s���Ȃ��ߊm�F�͕K�v�@�Q�O�Q�R�E�V�E�Q�V�@�ۍ� |
�V���A�O�� �����u�{�ǒ���̐��E ( �₢�ܕ��� 7 ) �v���u��R�Ɂv���犧�s����B300p
1004059356
|
�ߑ㉫�ꉹ�y�̕�-�{�ǒ���̐l�Ɖ��y- 7p
����y�Ƃ��̎��� 69p |
������f�B�[���x�������l���� 141p
�E |
�W���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 31 �Ǔ��_��,�����N�搶�Ǔ��L�O���W���v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B
|
�͂��߂�
�����N�̏W
�����N�搶���M�_�l
���������`���̎v�z�@�|�����v�z�j�̈�ꑂƂ��ā|
�v�ē��̐����N���@�|�������Ƙ_�̈ꌟ���Ƃ��ā|
�k�u�����Ȃ����Ƃ̑O�r�v��� �ѓc�O�l
�����Ȃ����Ƃ̑O�r
�s���k��t�@���ꌤ���̉ۑ�@���[�[�t�E�N���C�i�[�A�Z�J��F
�����N�A�O�Ԏ�P
�����N�搶����ژ^
�����N�搶�̗���
�Ǔ����@�|�����N�搶���Â�Ł|
�����@�V�萷��
�����@�����F�}
�����N�搶�Ɩ@����w���ꕶ���������@�@�����G |
�����搶�̂��Ɓ@�@�R�{�O��
�����N�搶�̌��O�� ��@�@��m�i
�����N�搶�̎v���o�@�@�������j
���l�E�����N�搶�̋����@�@����]
�����N�搶�̓�̏��@�@���҉p��
����{�̊g��ƖL�`�̊w��\�z�@�@�䕔���j
�u��ԗL��v�|�����N�搶�̎v���o�|�@�@�~�ؓN�v
�����̘A���|�Ǔ��E�����N�|�@�@��������
�̒����N���Ɖ���@�@�������T
�Ǔ��@�����N�搶�@�@�����K��
�}���^�G��E�����Ƃ����Ă݂������N�搶�@�@�i������
�w�F���_�b�ƌN�匠�͂̋N���x�̓�������
�@�@���|�����N�搶�̎u���ǂ������p���ł������| �@�דc���Îq
�u���c���j�̈�u�v�Ɖ��ꕶ���������@�@�g������
�����N�搶�̎v���o �@�@���]�F�i |
�Ǔ��_��
�u�A�W�A�̒��̓��{�w�v�\�z�̐헪�I���_�Ƃ��Ă̗����w : ���̂��߂ɕK�v�Ȃ������̎��p�@ �ѓc�O p.301-314
����̋L���ƈӎ��䕔 ���j p.315-331
�F���ˁE�����E�����ɂ�����ߐ������̐V�c�J�� : �������̌`�� �@�~�ؓN�l
p.333-365
�����E����A�W�A�̍��q�ƕ�����Ɋւ��閯���� �@����] p.367-416
��p�E��m�Q���E�䗥�o : �u�哌���푈�v���̒��앨���߂����ā@ ��������
0 p.417-448
�A�W�A�R�������̌`���Ɨ����E�����R�̕����I����:�u�R�̋N���E�`�d�E��e�E�n���v�_�I�����̂��߂̏��́@
���]�F�i p.449-490
�w�����낳�����x�̊w : �A���A�m�A�����ċʏ� �@�g������,������
p.491-522
�����N�搶�̐A���n�@�����ɂ��ā@�{���^�� p.523-542
�Ԗؕ��ɑ��w���b�ⓚ��x�Z�@ �ؒ×S�q p.543-657
���W�Ƃ̑Θb �n���A�����A���{��̂��܂��l���� : ��̂�q�� ���W�w�߂肩���炸�x��ǂށ@
��� �� p.659-707 |
�W���A�u�A�W�A�V�w (66) ���W ���S�̖��́v�����s�����B
|
�O���E�O���E�O���� �R�{ �G�q p.6�`17
�O���Ɛl�X���J�@��� �{�@p.18�`27
����|�b�v�̂������� �v���c �W p.30�`40
�u�I�L�i���̏����v�Ƃ����A�C�h������--�����ޔ��b�ƔăA�W�A�I�g�́@�{�l �G�F�@p.41�`48
���̈�� �l�璹(�������[)�@�哇 �ۍ��@ p.50�`52
�G�C�T�[--����̉Ă̕������@���� ���],���� �K�j p.53�`69
�C��n�鉫��̉̂Ɨx�� ���� ���q�@p.70�`81
�V�}�S���瓇�S�ց@�z�n �r�� p.82�`89
���Ȃ��Ǝ������ԉ�--�����哇�암�ÓS�W���ɂ�����t�B�[���h���[�N���� �@���Y �M���q�@ p.90�`108
�ٕ�������݂������̓��S�@�R�{ �G�q�@p.109�`115
���̈�� �ނ�����ߐ� �@RIKKI p.116�`118
�����Ȃ�E���܂݂̂��ׂ��� �@�ԉH �R�K�q8�@ p.120�`140 |
�X���A�{�ǒ���a�S��\�N�L�O���Ɗ�����ҏW�u �ӂ邳�Ƃ̕� : �{�ǒ���a�S��\�N�L�O���v���u�{�ǒ���a�S��\�N�L�O���Ɗ�����v���犧�s�����B
�@�@ �t (�ʍ� 28P ; 19cm) : �i���̒�����f�B�[�{�ǒ�����̏W
|
�����ɂ悹�� / ��R��
���E�{�ǒ�������(���k��) / �{�lj��q/��
�{�ǒ���̎v���o(�L�O�����[�G�b�Z�C)
����̖��ȒT�K / �哇�C
�Ï�/�Ȃl/�Ԃ��̉�/����M/�Q���̊C/
�@�@���[�₯/����ǂ��̉�/�ӂ闢/�V�����������^
����y�̔��W�Ɍ�����:�u�{�ǒ���L�O�فv�̒�� / �O�،� |
�{�lj��q����̎莆 / �{�lj��q
��6���u����u�{�ǒ���Ƃ��̎���v / �O�،�
�{�ǒ���W������� / �O�،�
��7���u���� / �{�Ǒ��ߎq
�{�ǒ���N��
�{�ǒ����i�ꗗ
�E |
�X���A�V�Ԕ�C�u ���E�G�u�G�C�T�[�K�[�G�[ : �����Ȃ�̂��ق�v���u�i�����j���b�N�v���犧�s�����B
�@�@�@�p�ꕹ�L�@�p��: ��݁EHayashi Yates�@�@1�� �@�@�����F��㊌����}���فF1004078158
|
�v��E���^ �����7��13���A����̓���(�����肳��)���ł͂���c���܂��}���A15���ɂ����肷��܂Łu�G�C�T�[ �G�C�T�[ �X�� �T�[�T�v�Ɨx��B�~�x��̊G�{�B (���{�}���ً���) |
�X���A�X�۞Ď��Y���u�g�x����v���u����^�C���X�Ёv���犧�s����B�@�@261p �@�����F��㊌����}���فF1004079982
|
�g�x�u�ܔԁv�̑�{�E����� �ʏ� ���O�^�� �ʏ� ���O�^�� �ʏ� ���O�^�� �ʏ� ���O�^�� �ʏ� ���O�^��
�g�x����u�O�ԁv�̑�{�E����� 0 ���~�� ���q�^�� ���{�� �e�_��^�� �c���e�_�㒩���^��
�g�x�̗��j�Ɨl��
�g�x�̊T�v |
�P�O���A�g�Ɗԉi�q���u��r���x���� = Japanese journal for comparative studies of dance : ��r���x�w��w�p�@�֎� 10(1) (�ʍ�) p.40�`49�@��r���x�w��v�Ɂu���ꌧ���鑺�Ôe�̎��q���ɂ݂鎓�Y�̓���v�\����B
�P�P���A���O���u�����{�@�������j�w��ҁu���{�@�������j���� = The Journal of Japanese religious and cultural history 8(2) (�ʍ� 16) p.89�`98�v�Ɂu�j���Љ� �h���@�ю����� �ܒ���l���M�{�w�V���������L�[���x�v���f�ڂ���B
�P�P���A������F�̉�ҁu�ܒ���l�t�H�[���� : ����400�N�E���̗��j�I�Ӌ`���l����v���u������F�̉�v���犧�s�����B
�P�P���Q�V���A����s�z�e���ɉ����āu�ܒ���l�t�H�[���� : ����400�N�E���̗��j�I�Ӌ`���l����v�̃t�H�[�������J�����B
�@�@�@��ÁF������F�̉� ���ÁF(��)�C�m������L�O�����Ǘ����c �p���t���b�g�o�C���_�[����(31cm)
�@�@�@�@6p �@�����F��㊌����}���فF1003664750
|
�J�Âɍۂ��� ���� �q�g
�ܒ���l�Ɨ����[�w�����_���L�x�Ɓw���������x�̐��E ���� �a�� |
�ܒ���l�Ɨ������� �m�� �芰
�ܒ���l�Ɓw���������x �r�{ ���� |
�P�Q���A�ʏ闬�ʐ��ҁu�ʏ�G�q�̉� : �������ꂨ���Ȃ�J��L�O�����i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ闬�ʐ��v���犧�s�����B�@�@1��
1004688923
�@�@�@�@�@�@�@�@�����F����16�N�x12��5��(��) ���F�������ꂨ���Ȃ�(�匀��) ��ÁF�ʏ闬�ʐ��
���A���̔N�A���c�����q���u���y����w 34(2)�@p.13-15�v�Ɂu�u���]�v�O�،��^��R�L�q�ҁw�{�ǒ����W�x�v���Љ��B
���A���̔N�A���lj��q���u�R�~���j�e�B = Community (7) p.13�`18�v�Ɂu���ꌧ�O�ł̃G�C�T�[���� (���W ���m�w���w�R�~���j�e�B����w�� ����15�N�x
���Ƙ_��(�I��))�v�\����B
���A���̔N�A��c���q�������ψ���ҁu��㉹�y��w�����I�v = Bulletin of Osaka College of Music (43) p.23�`40�v�Ɂu���Ő��������G�C�T�[�̏�--����G�C�T�[���ۘ��𒆐S����Ɂv�\����B
���A���̔N�A�i�f�������j�^��y�@ ����E�� �u�G�C�T�[�s�v�c�E�H�[�N�@2004
�G�C�T�[�ɔ�߂�ꂽ����v���u��y�@�v���犧�s�����B�@�@�ܒ���l����400�N�L�O�@�r�f�I�f�B�X�N 1�� (60��) : DVD�@
���A���̔N�A���ь��]���u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (70) p.131�`134�v�Ɂu���] ��������w���ꉹ�y�̍\��--�̎��̃��Y���Ɗy���̗��_�x�v���Љ��B�@�@ |
| 2005 |
17 |
�E |
�P���P�P���A�������ꂪ�Ȃ��Ȃ�B�@(���N�F�X�U��)
�P���A�@�{�u�� = Review of law and political sciences 102(2) (�ʍ� 733) p.1�`236,�}����1���@�@����w�@�{�u�ы����v�Ɂu�����N�搶�����E����ژ^�v���҂܂��B
�P���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (23) ���ꖯ���w��2005-01 p.33�`44
|
��]�F�ς���ޔC�L�O�� p.1�`141
�u�� �u���ꖯ���w��v�ւ̕���--���ꖯ���w��O�����E
�@�@�����ꌧ���|�p��w�ɂĎ��^(2003�N�O���\�ܓ�) �@ p.1�`14
�k������̕搧�Ƃ��̕ϑJ--�P���搧�Ɩؑ��ƌ^�� �������t p.17�`32
�v�����̃^���g�D�j���̌`�� ���R�� p.33�`44
�ړ��ƃW�F���_�[ ���� p.45�`55 |
�A���҂����̓`���n�o �}������ �@p.57�`65
�v�ē��̎O�ɗ�--�V�ԁE�Î芡�̍��J�̗w�ɂ݂�����
�@�@����̎O�ɗ��̋L�� �ɜn�� p.67�`95
�����̎n�c�Ɩ咆�̎n�c--�v�����̖咆��
�@�@�����ۂ̈ꑤ�� �ԗ䐭�M p.97�`116
�E |
�R���A�J�O�ҁu����ɂ�����G�C�T�[�|�\�̓��Ԃ̑����I�����v���u���ꌧ���|�p��w���y�w���J�������v���犧�s�����B (�Ȋw������⏕����Ռ���(C)(2)�������ʕ�, ����9�N�x�]����11�N�x)
�R���A������F�̉�ҁu�u�ܒ���l�t�H�[�����v���{�� : �����l�Z�Z�N�E���̗��j�I�Ӌ`���l����v���u������F�̉�v���犧�s�����B�@�@�@�@�����F���ꌧ���}����
�R���A�`���g�x�ۑ���O�\���N�L�O���ό��ψ���ҁu�`���g�x�ۑ���O�\���N�L�O���v���u�`���g�x�ۑ���v���犧�s�����B
|
���� �`���g�x�ۑ���O�\���N�L�O���Ƃ̂܂Ƃ�
�n��g�x�������� / ��闧�T
�g�x�u�萅�̉��v / ���{
�u���ΓG���v�̑�햡 / �c�Ԉ�Y
�g�x�u�Ԕ��̉��v�̍�҂ƍ�i / �r�{����
�u�G���v���Ȃ����O�͍ŏ��ɏ㉉������ / �X�۞Ď��Y
���ʊ�e �g�x�w��̌o�� / �X�۞Ď��Y
|
���� �`���g�x�ۑ���O�\�N�̕���
��O�� �`���g�x�ۑ���g�x�u���̋L�^
�u�g�x�v���ʊӏ܉�͂��߂̂��� / ���{
���������㉉�̂������� / ���{
��l�� �`���җ{�����Ƃ̋L�^
��� �O�\���N�ێ��ҍ��k��Ɖ���G��
��Z�� ������ |
�R���A�����^�m�q���u���{�@�Z����w�I�v 22 p.109-143�v�Ɂu���ꌧ�|�x���̕�[���x�Ɋւ����l�@
: �ÓT���x�u������ŕ��v�ɂ����问�����x�Ƃ̔�r�v�\����B�@�@�@�@�d�v�@
|
�͂��߂��i�S���j�^�u������ŕ��v�͉��ꏔ���ŏj��̎��̍��J ���Ƃ��ėx ����j�V���x�� �A�l�X�ɍł��h�� ����e ���܂�Ă���ÓT���x �ł���B �u������ŕ��v�u���[�߁v�u����͂߁v�u�����߁v�u���ɕ����߁v�̌܋Ȃ� �A���� ������ ���o�̌�O�ʼn��t�����̂ŁA�u��O���v�Ƃ�����ꂽ �B���̕��x�ɂ͐���̂��ׂĂ̊�{�� �� �荞�܂�Ă���A�������� �������݁A���ʂ̂Ȃ���U ��A���̑בR�� �����\���ɂ͊Ȍ��ʼn��̐[��������ǂ�A����҂����R�ɗI�R�Ƃ��������� �C���ɂ�������̂����� �B�{���͉� �E�[�̘V�l�x ��Ƃ��ėx ���Ă������A���݂͎�҂������ŗx������A��v �w�����ǂ��x��Ȃǂ��낢��ȉ��o�������� �B�l���ő�̊�тJ�̉Ԃł͂Ȃ��A�Q�̂��܂��ɊJ�����Ƃ��镗��ɂ��Ƃ��A���I�������邱�ƂŎ��R�݂̂��݂� ����������\�� ���Ă���B�^���̏d�v���`�����������̎w����Ă��鉫�ꌧ�|�x���̎�q��Ղ͓쓇�e�n������
�d��ՋV�̑�\�I�Ȃ��̂ŁA�N�A��̋� �A�\�����̍b�\�̓�����b�߂̓��Ɏ���\����Ԃɂ킽���Ď���s�Ȃ���B�_�ɋF�肵�A�܍��L���̊��ӂ�����邽�߂̕��x�́A��̌|�\�⋶��
�A�g�x ��� �ǂ̌|�\�ƂƂ��ɁA�M�Ђ̓��Ɛh�K�̓��̐_�O�ŕ�[ �����B���̕�[���x�ɂ́A��O�x��A��˗x
��A���x ��A�ł��g�x ��Ȃǂ�����A�ÓT���x�ƕ��ނ��ꂽ�x�肪�嗬���߂Ă��邪
�A�u������ŕ��v�͐����Ȃ��ÓT���x���ڂ̈�ł��� �B�^�����Ŗ{�����ł͕x���̎�q��Ղɕ�[ �����ÓT���x�u������ŕ��v�ɒ��ڂ��A���I�^��������
���Ă̑��ʂ���Ƃ炦�A�i�̝����E�����E���e �ȂǕ��x�v�f�ɂ��Č������A�����ڂ̖{���ɂ����问�����x�Ɣ�r
���Ȃ��炻�̕\�������� �炩�ɂ������ƍl�����B |
�R���A�؉����q���u�n�敶������ 20 p.1-21�@�~���w�@��w�n�敶���������v�Ɂu�Ñ㋿�剈�݂Ɠ��A�W�A : �y�䃖�l���(�R�������֎s�L�k��)�ɂ݂镶���̑��ʐ��v�\����B
�R���A <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g : <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
14�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004212708
|
�l�Ԃ̒a���Ǝ�-�r�ԓ�����̔��M- �������V
���J������ �������������ƒ��N����(1) �g������ |
�������������ƒ��N����(2)-�w�����낳�����x�ɂ݂�
�@�@���n��I�l�b�g���[�N�̈Ӗ��������- ������ |
�R���A���ꌧ���|�p��w���u���ꌧ���|�p��w�I�v (13)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�{�ǒ���̉̋ȗl���ɂ݂�X�^���_�[�h��--���̂⓶�w�Ƃ̂�������ʂ��� �O�� �킩�� p.67�`90
�x�[�g�[���F���̏��ŕ��Ɖ����--<�f�B�A�x�b���ϑt��> Op.120�̏ꍇ ��� ���q p.91�`109
�������ׂ������؋� ��2�W��1�k�� �y���l ���{ �M�v ���ꌧ���|�p��w p.137�`158
�f�I�_�E�h�E�Z�����b�N�ɂ�����u�n���`�v�Ɓu�G�O�]�e�B�X���v�̌��� ����
�͎q p.159�`170
�����g�^�ɋL�q���ꂽ�����|�\--�u���q�x�v�����̎��� �\���E�앑�ɂ��� ���g
�Ύ} p.171�`193
�q�����r |
�T���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� NO.24�v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���ف@�@100p
|
��������搶�̎��𓉂� ����,���G p.1-2
�O���i�搶�̂������𓉂� �V�c,�d�� p.3-4
�쓇�̓ꕶ�Ε� ���m�],�a�� p.5-18
�O�X�N����ɂ�����搧�̏W�� ����,�N�� p.19-34
�q�g�ɂ�铇�X�ւ̐A��:�����n���w�I�Ȋϓ_��� �E�B���A���E�G�t�E
�@���L�[�K������уW�����h�E�G���E�_�C�A�����h�@
�@��William,F.Keegan,Jared,M.Diamond,�F�J,��,����,�K��
�@��,�ē�,����,����,��Z,���J��,���b,�l�J,�ی�,�R�c,�a�j,���{,�L�y p.35-81 |
���\���E�Ԏ��Քp��Q�̒��� ���d�R�S�|�x�����Ԏ摺��
�@�@�����ƕ搧�ɂ��� ���,�i�v p.83-91
�|�x�����\���ߑ��ՂɎc��� ����,����,����,���i p.93-96
���{�L�q�E�m�O�E�ҁw�l�Î�����ρx12�L�ˌ������
�@�@�� �{��,�O�� p.97-97
���{�L�y���w���̐�j�w�x �V��,�M�V p.98-98
���{�L�y���w���̐�j�w�x ����,�גj p.99-99
�E |
�R���A�u�Ί_�������� 3�v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B
(�n�挤���V���[�Y ; no.33)
|
���d�R�ɂ�����܍��̌�� / ���c���q ��
�Ί_���ɂ�����w�Z�}���ي��� / �R���^�� ��
���גn��ɂ�����ԙ��ސ��Y�n�̒n����� / ����� �� |
��p���]�f�Ղ�ʂ��Č���u�ߑ�v���A�W�A / ���g�� ��
�g�x�䎌�̃f�[�^�x�[�X���̎��� / �����r�O ��
�E |
�T���A�n�Õ~��NjL�O���ҏW�ψ���u���ꉉ���E�̋��F���n�Õ~��ǂ̐��E�v���u�n�Õ~�����Y�̘��v���犧�s����B�@�@
|
��ǂ̃A���o��
���E��ǂ̈̋�:�܂������ɂ����� / �n�Õ~���
���� ���:�l�ƌ|
�E�܌��M�v�̉�(���)
�E���E����̌|�\�ׂ̈� / �܌��M�v
�E�����ł̉���|�\�ۑ��� / �r�{��P
�E�ÓT�����㉉�� / �^�h�c���N
�E���z�� / �^�h�c���N
�E�n�Õ~��� / ��闧�T
�E�n�Õ~��� / �r�{����
�E����|�\�̖��� / ���P�Y
�E�ʏ鐷�d�ƐV�_���܂Ɠn�Õ~��� / ���P�Y
�E�n�Õ~��Ǐ� : �����E�吳�E���a���D�` / ����^����
�E�n�Õ~��� : ���߂Č��c�ɋK��������"�V�c" / �Î��d��
�E�n�Õ~��� / �Î��d��
|
�E�n�Õ~��� / ���P�Y
�E���x�̌��u�O����(�A�J�}�^�[)�v�ɂ��� / �c�Ԉ�Y
�E�n�Õ~��ǂ̌|�� : ���́u�p���ƌ����v�Ɋ��� / �{���v
�E�n�Õ~��ǂ̋L�O�������I���� : �n�Õ~�����Y�̘����㐢�� / ������q
�E�n�Õ~��ǂƉ���ŋ� / ������
�E�����̗x��̖� / ���ꗲ�O�Y
�E����|�\�ۑ���� / �R���[��
���� ��ǂ̌|��
��O�� ��ǂ́u�����`�v�u�|�k�v
��l�� ��ǂ̗����ÓT���x����m�[�g
��� �V���Ɍ���n�Õ~���
��Z�� ��ǂ̌|�\�����L�^
�掵�� �N�� / ������
���Ƃ��� / �c�Ԉ�Y
�E |
�T���A�^�������u����\���O�X �������ʕ��v���u����EMI�v���犧�s�����B
�@�@�@�^���f�B�X�N 1�� : CD
|
(1)�V���(�����J��)(2)����(��u�����q)(3)��������[(�R�����L)(4)�Ўv��(�������q)(5)���̉�(�V�_���S��)(6)���z��(�{���ޔ��q)(7)�ׁ[�ׁ[�ʑ�������(TINGARA)(8)�J���x(�{�ǖq�q)(9)�V�уV�����K�l�[(���Ⴉ��)(10)���ʔ�����(�t�W�R)(11)���s�ʉ�(��������)(12)���[�Ɓ[�Ƃ�(�{�鏬�S��)(13)�i�[�N�j�[(��@�Â��q)(14)����ǂ��̉�(���c��)(15)���オ��Ɨ��܂��(���NJ_�c�q)(16)�\��̏t(�����b)(17)�������ʕ�(Orange Clover)(18)�V�˂��鋴(�ÎӔ����q)
|
|
�U���X���A�u�����|�p�����ʐ^�i�Q�P�P�X���j�q���q�F���Y�B�e�r�v���u�d�v�������v�Ɏw�肳���B
�@�@�@�ۊǎ{�݂̖��́F���ꌧ���|�p��w
|
������F�{���͊��q�F���Y�i�ꔪ�㔪�`��㔪�O�B���F�ƁA���ꕶ�������ƁB�̂��̐l�ԍ���j���A��O�ɉ��ꌧ�ōs�����u�����|�p�����v�Ɋւ��ʐ^�Ƃ��̊֘A�����ł���B
�@���q�́u�����|�p�����v�́A��ꎟ���吳�\�O�N�i����l�j�܌����瓯�\�l�N�܌��܂ŁA��͑吳�\�ܔN���珺�a��N�܂łƑO������{���ꂽ�B�{���Ɏ�Ƃ��Ċւ��̂͂��̂�����ꎟ�����|�p�����̐��ʂł���B��ꎟ�����|�p�����͈ɓ������i�ꔪ�Z���`���l�B���z�j�ƁA������w���_�����B�����M�͎�͎ҁj�Ƃ̋��������Ƃ����`�����Ƃ�A���c�@�l�[�����̕⏕�����Ď��{���Ă���B�^��ꎟ�̗����|�p�����ɂ����Ċ��q�́A����݉Ɓi�����a�j�A���j�݉Ɓi���R��a�j�Ȃǂɂ��问�����Ƃ䂩��̕��������͂��߉~�o���A��������Ί_���̓��ю��Ȃǂ̎��@���A�܂���ߔe�̖��Ƃ���������H�|�i��G���i�Ȃǂ�ΏۂɐϋɓI�Ɏʐ^�B�e�������������s���Ă���B�^�B�e�����K���X���͎l�ؔ�����уL���r�l�����p�����Ă���A���ĕt���܂����T�C�Y�̈�掆��p���A�����咆���̊e�T�C�Y�̑䎆�ɓ\����Ă���B���ɍ����Z�p����g�����B�e���s���Ă���A���ꎩ�̏\�������|�p���Ǝ������Ƃ���������i�Ɏd�オ���Ă���B�^��ʑ̂ɂ́A�����G��j���l�����Ŗ����ł��Ȃ���㍑���̏ё���i���G�j���͂��߉~�o���̕lj�A�܂�������u�y����z���ǂȂǂƂ����������̊G�t�����̍�i������ɓ`����B��̎����ƂȂ��Ă���B���q�͂����̎��������ƂɁA�������������ł͕K�{�̏��ƂȂ��Ă���w���ꕶ���̈��x�i���a�\���N�j�ɑ��p����ȂǐϋɓI�ɏЉ�Ă���B���Ɏ���ʂ������q�̎ʐ^�͎�̏��a�̕����ɑ傫����^���Ă���B�^�Ȃ��A���M���ׂ��́A���q�̒����̑Ώە��������̑��łقƂ�ǂ��D���ɋA���Ă��邱�ƂŁA�����������̋L�^�Ƃ��Ă���߂ċM�d�ł���B�^���y������z�Ƃ������q�́u�����L�^�v�͎B�e�Ώۂ̕������Ɋւ���ڍׂȏ����܂݁A���A�����j��d�v�Ȏj���ނ����ʂ�����A���������̘̍^�ȂǑ����I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A���ꎩ�g�����̌����f�ނ����B�^��q�̂悤�Ɏ���ꂽ�������������㐢�ɉi���`����Ӗ��ł��A�������̕����I�Ȍ��������݂��ł����q�̎����Ȃ��ɂ͕s�\�ł���A���̏d�v���͂͂��肪�������̂�����B�^�Ȃ��{�����́A���q����т��̈⑰������A�O�x�ɂ킽���ĉ��ꌧ���|�p��w�Ɋ��ꂽ���̂ł���B�i���w�蕶�������f�[�^�x�[�X�^���������]�ʁj |
�U���A���c �d���u���j�� 13(25) (�ʍ� 575) p.22�`25�v�Ɂu�ɕ��̌�������(35)�@60�N�ڂ��}�����ǒJ���̃`�r�`���K�}(�����1)�u�W�c�����v�̔ߌ�����
���҂̍����p�������v�\����B�@
�U���A�u��㊂̂��� ���ꏔ���� 1�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B
�@�@ (����V���[�Y ; 1) �^���f�B�X�N 1�� (74��) : CD
|
(1)��(���ԍF�Y)(2)�m�ԕz(���[K�R���r)(3)�\��̏t(��H�N�O,��@�Â��q)(4)�����G�C�T�[(�m����j,��������,�O��猫)(5)���C���C(�䉮���K�T)(6)���W���g���[(��@�Â��q)(7)�n�C�T�C��������(�O��猫,�p�C����)(8)�̂��Ȃ���(�`�ӈ��q)(9)�䂤�Ȃ̉�(���^�B�q)(10)���Ȃ���ǁ[(�O��猫)(11)���̏�(�c�ꐷ�M)(12)�q���~�J�`��(�g�c�N�q,�{���ޔ��q)(13)�o�C�o�C����(���c���g)(14)���̎���(�Y��N�q,���w��g)(15)����炿(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(16)����܁[�`���ʈ�Ԓ���(�Y��N�q)(17)�e�[�Q�[(���܌b���q,�{���b���q)(18)��b(�c�ꐷ�M,�`�ӈ��q)(19)���肪�Ƃ�(���܌b���q)�^�ďC:�O�����Y |
�U���A�u��㊂̂��� ���ꏔ���� 2�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B
�@�@�@ (����V���[�Y ; 2)�@�^���f�B�X�N 1�� (73��) : CD
|
(1)�ȁ[���Ɂ[�E�R����ԓ�(�Î芡�я�)(2)�C�ʂ���ځ[��[(�O��猫)(3)�V�т���ˁ[(�`�ӏ��q)(4)�܂����(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(5)�Ă����ʉ�(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(6)�������(�Î芡�я�,�������q)(7)�����b(�t�m��,��㏟��)(8)�ږ�����(�m����j)(9)���H��(��@�Â��q)(10)���Ð�(�m����j)(11)�P�S���̉�(�c�ꐷ�M)(12)���Ԃ�(�`�ӈ��q)(13)�Бz��(�������q)(14)������(����r��)(15)����(�Î芡�я�)(16)��������߁[��(�m����j,��������,�O��猫)(17)�Î�v(�m����j,��������)(18)���D�ǁ[��(�m����j,��������,�O��猫)�^�ďC:�O�����Y |
�U���A���������������L�O���ۊďC�u�j�Փ������̂Ăт� : �ۑ��Ɗ��p�̂��߂�
4(�����)�v���u�����Ёv���犧�s�����B
|
����҂̊��p�ɓ������ā@1
��1�́@��K�͎j�Փ��̕ۑ��Ɗ��p�@2
��2�́@�������Ƃ̍l�����Ƃ��̌����@84
��3�́@�������Ƃ̐i�ߕ��Ƒ̐��Â���@146
��4�́@�����̎�@�ƋZ�p�@204
��5�́@���p�̎�g�݁@262
�t��1�@�C�O�ɂ�������j�I�E�����I��Y�̐����@335
�t��2�@�������Ƃɂ���������o����̒��ړ_�@347
��1�́@��K�͎j�Փ��̕ۑ��Ɗ��p
��1�́@�ɂ��₩�ȏW����ڎw���� �O���ێR��Ձ@4
��1�́@�����v��Ɋ�Â��Ñ���̍Đ� �����Օ����Ձ@10
��1�́@���������ɂ������Ջ�ԕ\���̐^���� �H�c��Ձ@16
��1�́@�Õ������ƌ𗬂̏�Â��� ��ʌÕ��Q�@22
��1�́@��݂�����퍑�鉺�� ���J���q����Ձ^���J���q���뉀�@28
��1�́@���������̑̌��u�{���j���}���L��v�{�Ձ@34
��1�́@2�̎j�ՁE2�̑̐� �ߍ]�����Օ��y�R��ՁE
�@�@���]��Ձ^���y��Ձ@40
��1�́@�������i�ޓޗǂ̓s ����{�Ձ@46
��1�́@����Ƌ�������Ñ�̕��i ��ɕ{�Ձ^����Ձ@52
��1�́@���a�ւ̃��j�������g�ƂȂ鐮�� ���쉮��Օ��w�Ձ@60
��1�́@��݂�����퐶����̍��̌�Ə��i�s�j�g�샖����Ձ@66
��1�́@�Õ��Q������j��ǂ݂Ƃ��K�͐��� ���s���Õ��Q�@72
��1�́@�����̎p�ɂ�݂����������������̕{�� ����@78
��2�́@�������Ƃ̍l�����Ƃ��̌���
��2�́@���H������]�ގC���̑� �k�l��Ձ@86
��2�́@������s�̎�a�� ����Ձ@90
��2�́@�Ñ����Ǒ̌��ł��銯�ɂ̕��� �u�g��Ձ@94
��2�́@�_��̕��Ɖ��ȉԂ̑�����̊� �����������R�A���Q���@100
��2�́@�䂪���ŌÂ��}�厮�^�͂̕��� �����ʑD�x�@104
��2�́@���j�݂̂���܂��Â���Ƒ喼�뉀 �{�_�فi������~�j�뉀�@108
��2�́@���S�������s�����Õ� �X���R�ˌÕ��@112
��2�́@�w���Ղ̌������������������� ���R�w���Ձ@116
��2�́@�Õ������ƏZ���Q�� �i�K���R�Õ��@120
��2�́@���@�����̂܂܂��P���Ɛl�������w�\ ���G��Ձ@124
��2�́@���Â͂���j�Ǝ��R�̔������Â��� �����R��Ձ^
�@�@���Δn�ˎ�@�ƕ揊�^���Ώ�Ձ@128
��2�́@�C���ɒz���ꂽ�O����~���̕��� �T�ˌÕ��@134
��2�́@�ꕶ�̐X�ɗn�����ސ�����ڎw���� ��쌴��Ձ@138
��2�́@�F��̋�ԁu��x�v�̕��� �֏��x�@142
��3�́@�������Ƃ̐i�ߕ��Ƒ̐��Â���
��3�́@�X�ѓ��ɕ������ꂽ�k���̑� ��C��Ձ@148
��3�́@���̏��ƒn��Z�� ���c��Ձ@152
��3�́@2�̑�r�Ƒ�K�͑��Ռ��̊����� ���R��Ձ@156
��3�́@���̕ϑJ�ɂ�蔠���Ɏc���ꂽ������Y
�@�@���������Ε��Q�^�������X���^�����Ձ@160
��3�́@���R���ɓW�J�������m�c�̈�ՌQ ���R����و�Ձ@166
��3�́@�n��Z���Q���ɂ��Õ��̐��� �g�q�R�Õ��^��R�Õ��@170
��3�́@�V�r�n�j���H������̕ۑ��E�����E���J
�@�@������ˌÕ����V�r�������Ձ@176
��3�́@�j�Ղ����p�����s�����ւ���Â��� �ԕ��Ձ^
�@�@�����ԕ��뉀 �{�ے뉀 ��V�ے뉀�@182 |
��3�́@�]�ˎ���̕��͋C��̊��ł����s���� ���]��@186
��3�́@�������ƂƂ��Ă̏�s���� �������R��Ձ@190
��3�́@�n��I���F�������Ñ㎛�@�̕��� �]�����Ձ@196
��3�́@�Ɛ��ʂɒ��a����������̕ۑ����� �@���r�����Q�@200
��4�́@�����̎�@�ƋZ�p
��4�́@�A����̗h�~�Ɠ��A���̕������� ��{���A�@206
��4�́@�G�ؗт����������z�Έ�\�ƏZ���̕��� ���R��Ձ@210
��4�́@��y�뉀��r�̕���
�@�@���щz���Օ�����АՁ^�щz���뉀�@214
��4�́@�y�����Z���̓ꕶ�ނ�̕��� �䏊���Ձ@218
��4�́@�ꕶ�l�̐��E�ς��̊��ł�������� �哒���@222
��4�́@�O����~���ɂ����錩�ǂ��떞�ڂ̐��� �ۓn�c�Õ��Q�@226
��4�́@�C�i��@�ɂ�钆���R��̕��� �R����Ձ@230
��4�́@�Õ�����̑�a��\�@���̎p�œW�� ��V�z��Ձ@234
��4�́@�{���̓ޗǎ���뉀�������鐮��
�@�@�����鋞�����O���V�{�Ւ뉀�@238
��4�́@�C���Ȃ����ޗǎ���̐ΐϕ��� �����@242
��4�́@�Ñオ�̊��ł���l�r��̕���
�@�@�� ���ˍ��{�� ������ �@�؎������ �s������Ձ@246
��4�́@�R��̓����������ʘH���� �x�c��Ձ@250
��4�́@����Q�����ɂ�����y�\���̕��@ ���c����Q�@254
��4�́@�ߐ���s�̍��Ί_�̏C���ƒ��� �ۋT��Ձ@258
��5�́@���p�̎�g��
��5�́@�����ېV�A�k�ɐ������h�l�����̈�Y ���V���ːw���Ձ@264
��5�́@�ꕶ�̑�������������j�Ղ�ڎw���� �k�����L�ˁ@268
��5�́@�ߐ����D�≮�̍Đ��Ɗ��p �������@274
��5�́@�Ɉ͂܂ꂽ�L�˂̑����I�Ȋ��p��ڎw���� �㍂�ÊL�ˁ@278
��5�́@�n��Ŏ���Ă�ꕶ�W�� ���ÒJ���Ձ@282
��5�́@�Ñ�ƌ��オ�������镑��� �㑍�����Ձ@286
��5�́@�����i�����������Õ����� �J�̋{�Õ��Q�@290
��5�́@�����Ă���M�̓��Ƃ���Ȃ銈�p �x�m�R�g�c���o�R���@294
��5�́@�嗈�c���n���̃��}�����߂� �Č��p���Ձ@298
��5�́@�s�S�Ɏc���ꂽ�{�a��Ղ̊��p ��g�{�Օ��@�~���Ձ@302
��5�́@�j�ՂƎЉ��{�݂̘A�g �O�b�˔p���Ձ@308
��5�́@�퐶����̖��������ƈ�Ղ̌������� �y�䃖�l��Ձ@312
��5�́@�u���ӂ̃����v�ł̊��Â��� ���ː�Y��Ձ@316
��5�́@���m���q�Ղɂ�����q�����̌� ��O�g����������q�Ձ@320
��5�́@���g��́u�퐶�̃����v���� �������W����Ձ@324
��5�́@�邪����ɂȂ��� ���얡��Ձ@330
�t��1�@�C�O�ɂ�������j�I�E�����I��Y�̐���
�t��1�@�C�O�ɂ�������j�I�E�����I��Y�̐����@336
�t��2�@�������Ƃɂ���������o����̒��ړ_
�t��2�@�����̃C���[�W�@348
�t��2�@�����ɂ����锭�@�����@350
�t��2�@���ʂƐ}�ʍ쐬�@352
�t��2�@�����E�����ψ���̐ݒu�@354
�t��2�@���j�I�뉀�̕ۑ��Ɛ����@356
�t��2�@���j�I�������̏C���@358
�t��2�@�Z���Q���̕K�v���@362
�t��2�@�R���T���^���g�̖����@364
�t��2�@������̕ی��@366 |
�V���A���F�M���u���É��s����w�l���Љ�w�������I�v (19) p.37�`78�@���É��s����w�l���Љ�w���v�Ɂu���a��O���̖{�y�ɂ����鉫��|�\�̎�e
�v�\����B�@�@�@�d�v
|
�͂��߂�
���a��O���̖{�y�ɂ����鉫��|�\�֘A�N�\
��P�́@�����K�ꂽ���}�g�D���`���E���ς�����|�\
��Q�́@�{�y�ɂ����鉫��|�\�����̃��}�g�D���`���E�ɂ��]��
������ |
�V���A�v�����䂪���{�ߐ����w��ҁu�ߐ����Y 82(0) �@ p.49-62�v�Ɂu�w���|�����x�̕��@�v�\����B
�X���A��Í��Ғ��u�ܐ����H�H�l (���[): �O���ƏK�� �ÓT�� v.1�v���uRuon�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@�@97p ; CD1���@�@�����F��㊌����}���فF1004445373
|
�����Ɣ��q�ɂ��ā@4
�����ɂ��ā@4
�H�H�l�̉������ɂ��ā@5
�w�g���A�����A�����L���@6
�h�J���ɂ��ā@6
�����̉����ɂ��ā@7
�����L���ɂ��ā@7
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@8
�����}�ƌܐ����̊W�@8
�L�@�ɂ��ā@10
�Ŕ����ɂ��ā@10
�w�ԍ��ɂ��ā@10
�|�W�V�����ɂ��ā@11
1�@������ŕ��߁i������ł��Ӂ[�Ԃ��j�@12
2�@���[�߁i����ȂԂ��j�@16
3�@����͂O�߁i�Ȃ����������͂߁[�Ԃ��j�@18
4�@���Ă��߁i���Ă��Ԃ��j�@22
5�@����c�߁i�͂������Ă�Ԃ��j�@26
6�@�ӕ~�߁i���Ⴖ���Ԃ��j�@28
7�@��������߁i���炵�͂����[�Ԃ��j�@30
8�@粖��߁i�тʂ��Ԃ��j�@32
9�@�����߁i����Ԃ��j�@34
10�@���~�߁i�ӂ������Ԃ��j�@36
11�@���ɂ�߁i���ɂ�Ԃ��j�@38
12�@�匓�v�߁i���ӂ��ɂ��Ԃ��j�@42
13�@�`���߁i��ȂƂ��͂�Ԃ��j�@44
14�@�������߁i�Ȃ���Ԃ��j�@46 |
15�@�o���߁i���ł����ȂԂ��j�@49
16�@�����߁i�����[�Ԃ��j�@52
17�@�����߁i������Ԃ��j�@54
18�@���Ԑ߁i�Ȃ��܂Ԃ��j�@56
19�@�Ȃ��߁i���Ȃ��Ԃ��j�@59
20�@�䉏�߁i������Ԃ��j�@62
21�@�{�U�R�߁i�ނƂ������܂Ԃ��j�@64
22�@������߁i������Ԃ��j�@66
23�@��{�߁i�����ނƂ��Ԃ��j�@70
24�@�{�Î�v�߁i�ނƂ����ł����Ԃ��j�@72
25�@�{�����߁i�ނƂ��ԂȂ��Ԃ��j�@74
26�@�g��c�߁i���������Ă�Ԃ��j�@76
27�@�ԕ��߁i�͂ȂӁ[�Ԃ��j�@79
�Q�l�@83
�O�V�l�߁i�߁[�ʂ͂܂Ԃ��j�A�⌴�����i�����͂炭�ǂ����j
�@�@���^�ߌ��߁i��Ȃ�Ԃ��j�A���D�i�Ɓ[����j�ǁ[���ɂ��ā@84
28�@�O�V�l�߂̒����@�@86
29�@�O�V�l�߂̒Z���@�@87
30�@�⌴�����̒����@�@88
31�@�⌴�����̒Z���@�@90
32�@�^�ߌ��߂̒����@�@92
33�@�^�ߌ��߂̒Z���@�@93
34�@���D�ǁ[���̒����@�@94
35�@���D�ǁ[���̒Z���@�@95
�����ÓT���y�ƔN�\�@96
���Ƃ����@97
�E |
�P�O���A���{���炪�u�ꋴ��w�X�|�[�c���� 24 p.21-28�@�ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������v�Ɂu �V�}�̐g�̂��牫��̐g�̂� : �G�C�T�[��x��g�̗̂��j�v�\����B
�P�O���A�ʏ��}�q���u�d�q���ʐM�w��Z�p������. HIP, �q���[�}�����
105(358) p.19-22�v�Ɂu�������x�ɂ������̎d��(�u��v�y�уq���[�}��������)�v�\����B
|
�v��E���^�@�������x�Ƃ͉���(����)�őn�삳�ꂽ���x�ŁA��ʂ���ƍ��J���x�A�{�앑�x�A�G�x��(�������ǂ�)�y�і������x�A�n�앑�x�ɕ������܂��B���x���ӏ܂���ۂɏd�v�ȍ��ڂ́A�g�̓���≹�y�A�ߑ��ȂǑS�̂Ƃ��ăo�����X�悭���藧���Ă��邩�ǂ����ł��B�X�̗v�f(�e���ʂ̓�����ߑ�)�̑g�ݍ��킹���d�v�ɂȂ邽�߁A�X�̗v�f���ǂ̂悤�ȉe����^����̂���͂��Ă������Ƃ��厖�Ȃ��Ƃł��B�{�e�ł͎�w�̓����ɒ��ڂ��A�����̂Ȃ��Ɏ�������Ă��鉫��̏����̐����ɂ����鏊�삩��o�Ă�����{�ɂȂ�Ǝv�����w�����3���(������A�q�ݎ�A���˂��)�����܂����B���x�̒��ł̂����̎�w�̓������A�ǂ̂悤�Ȉ�ۂ�^����̂��ɂ��ĉ�����܂��B |
�P�P���W���t�Łu���������a���c�r�v�������T�[�����w�莼�n�ɓo�^�����B
�P�P���A�R�c�����������w�Љ�C�m�x�[�V�����w��ҁu�����w�Љ�C�m�x�[�V�������� �@ 1(1) p.101�`109�@�����w�Љ�C�m�x�[�V�����w��v�Ɂu���] �������V���w�����g�x �ʏ钩�O�̐��E�x�v���Љ��B
�P�P���A�A��������������u�A�������Y : �w�Ɖ̎��Ɨx�� �v���u�i����j�A������������v���犧�s�����B
�P�Q���A�{���N�F�����傤������ �u�I / 22(12) p.3�`5�v�Ɂu�Y�ꂽ���Ȃ��j�b�|���̕��i(45)�����̓��̓`���̉Ƃ͌˖�����
���ꌧ�^�n���쓇�v�\����B���傤����
�P�Q���A�k�����j�Ҏ[�ψ���ҁu�k�����j ���ҁv���u (�{�茧)�k��������ψ���v���犧�s�����B�@
|
�k�����j�ڎ�
����
��
(��)�@���́A��������
(��)�@����
(�O)�@�������́A��������
(�l)�@�k�������}
(��)�@�k��������t�ߗ��}
(�Z)�@�k�������i�A�k������㑺���A��㏕���A���������A��㋳�璷�A
�@�@�����c���A��㕛�c��
���ҁ@����
���ҁ@���́@���R���@3
���ҁ@���́@���߁@���y�@3
���ҁ@���́@���߁@�����Q�@3
���ҁ@���́@���߁@�y�n�y�ѐl���@4
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�n���y�ђn�������@4
���ҁ@���́@���߁@(��)�@1.�@���c�̓��z�R�@6
���ҁ@���́@���߁@(��)�@2.�@�l���y�ьː��@7
���ҁ@���́@���߁@(��)�@3.�@�ߑa��@8
���ҁ@���́@���v�@12
���ҁ@���́@���߁@�]�ˎ���@12
���ҁ@���́@���߁@(��)�@���Ñ�k�����̉��v�Ƒ���l�@12
���ҁ@�k�����s���j
���ҁ@���́@�c���@�ց@21
���ҁ@���́@���߁@�k�������c��@21
���ҁ@���́@���߁@���c��c���@22
���ҁ@���́@���߁@���̑��̋c�����тɎ���@�֓��@27
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�č��ψ���@27
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�č��ψ���ψ��@27
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�_�ƈψ���@29
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�_�ƈψ���ψ��@30
���ҁ@���́@���߁@(�O)�@�����ψ���@41
���ҁ@���́@���߁@(�O)�@�����ψ���ψ��@41
���ҁ@���́@���߁@(�l)�@�Œ莑�Y�]���R���ψ���@43
���ҁ@���́@���߁@(�l)�@�Œ莑�Y�]���R���ψ��@44
���ҁ@���́@�k�����s�@�ց@46
���ҁ@���́@���߁@���v�@46
���ҁ@���́@���߁@(��)�@����̉��v�@46
���ҁ@���́@���߁@(��)�@���ꎖ���@�\�@47
���ҁ@���́@���߁@���̑��@49
���ҁ@���́@���߁@(��)�@���y�����@49
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�n�В����\�@50
���ҁ@���́@���߁@(��)�@����ψ���@51
���ҁ@���́@���߁@(��)�@1.�@����ψ���ψ��@51
���ҁ@���́@���߁@(��)�@2.�@���h���厖�y�юЉ��w�����@53
���ҁ@���́@���߁@(��)�@3.�@���O����w������(���ی𗬈�)�@54
���ҁ@���́@���߁@(��)�@4.�@�c�t���@54
���ҁ@���́@���߁@(��)�@�c�t���̉��v�@55
���ҁ@���́@���߁@(�O)�@�k�������Z���@64
���ҁ@���́@���߁@(�O)�@���Z���̉^�c�Ɖ��U�@64
���ҁ@���́@���߁@(�l)�@�Z���o�^�@65
���ҁ@��O�́@�k�����̍����@68
���ҁ@��O�́@���߁@���̗\�Z�E���Z�@68
���ҁ@��O�́@���߁@(��)�@��ʉ�v�Γ��Ώo���Z���@68
���ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�������N�ی����Ɠ��ʉ�v�Γ��Ώo�\�Z�E���Z���@78
���ҁ@��O�́@���߁@(�O)�@�V�l�ی����Ɠ��ʉ�v�Γ��Ώo�\�Z�E���Z���@78
���ҁ@��O�́@���߁@(�l)�@�ȈՐ������Ɠ��ʉ�v�Γ��Ώo�\�Z�E���Z���@79
���ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�_�ƏW���r�����Ɠ��ʉ�v�Γ��Ώo�\�Z�E���Z���@79
���ҁ@��O�́@���߁@(�Z)�@���ی����Ɠ��ʉ�v�Γ��Ώo�\�Z�E���Z���@80
���ҁ@��O�́@���߁@���L���Y�@81
���ҁ@��O�́@��O�߁@���̑d�ł̕��ے����@83
���ҁ@��O�́@��O�߁@(��)�@���ł̏@83
���ҁ@��O�́@��O�߁@(��)�@1.�@�����Ł@84
���ҁ@��O�́@��O�߁@(��)�@2.�@�Œ莑�Y�Ł@84
���ҁ@��O�́@��O�߁@(��)�@3.�@�������N�ی��Ł@85
���ҁ@��O�́@��O�߁@(��)�@�������ېłɂ��ā@85
���ҁ@��l�́@�����U���̂��߂̏�����w���܂��� �Ղ�� "��������"�x�@86
���ҁ@��l�́@���߁@��O���k�������������U���v��@86
���ҁ@��l�́@���߁@�v�����̊�{�I�����@88
���ҁ@��l�́@���߁@���́@�v�����̈Ӌ`�@88
���ҁ@��l�́@���߁@���߁@�v�����̈Ӌ`�@88
���ҁ@��l�́@���߁@���߁@�v��̐��i�@88
���ҁ@��l�́@���߁@��O�߁@�v����ԂƋ��@89
���ҁ@��l�́@���߁@���́@�k���̊T���@90
���ҁ@��l�́@���߁@���߁@���R�I�����@90
���ҁ@��l�́@���߁@���߁@�Љ�I�����@92
���ҁ@��l�́@���߁@��O�߁@�o�ϓI�����@94
���ҁ@��l�́@���߁@�Y�Ƃ̏@97
���ҁ@��l�́@���߁@�Ί�̔������l�Ԑ��̏����@105
���ҁ@��l�́@���߁@��l�߁@�ڕW�B���̎�@�@106
���ҁ@��l�́@���߁@��O�́@��{�\�z�@110
���ҁ@��l�́@���߁@��l�߁@�ڕW�B���̎�@�@110
���ҁ@��l�́@���߁@�k�����̏������@111
���ҁ@��l�́@���߁@��l�́@��{�v��@118
���ҁ@��l�́@���߁@���R�Ƌ��������֗��ȋ��Z���@118
���ҁ@��l�́@���߁@�݂ǂ�������L���Ȑ����̑n���@123
���ҁ@��l�́@���߁@�Ί�̔������l�Ԑ��̏����@126
���ҁ@��́@�I���@131
���ҁ@��́@���߁@���[���@131
���ҁ@��́@���߁@�I���Ǘ��ψ���@131
���ҁ@��́@���߁@�I���Ǘ��ψ���ψ��@132
���ҁ@��Z�́@�k��������̖��B�J��ږ��@137
���ҁ@��Z�́@���߁@�J��c�@137
��O�ҁ@�{���_�Ƃ̉��v
��O�ҁ@���́@�_�Ɓ@145
��O�ҁ@���́@���߁@�_�ƐU���n�搮���v��@153
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@�_�U�v��@153
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@�ޏꐮ���@165
��O�ҁ@���́@���߁@�_�Ɖ��Ǖ��y���Ɓ@167
��O�ҁ@���́@���߁@�_�Ɖ��Ǐ����@�̐���ƕ��y���Ƃ̔����@167
��O�ҁ@���́@���߁@���y�w�������̕ϑJ�@167
��O�ҁ@���́@�{�Y�̏@172
��O�ҁ@���́@���߁@�ƒ{����@172
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@�{�@172
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@�a���@172
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@�a�����i�@173
��O�ҁ@��O�́@�ыƁ@174
��O�ҁ@��O�́@���߁@�k�����̐X�эs���@174
��O�ҁ@��O�́@���߁@(��)�@���X�ѐ����v��@174
��O�ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�ۈ��т̐����v��@177
��O�ҁ@��O�́@���߁@(�O)�@��Ɣǂ̊����Ƒ��̏����[�u�@178
��O�ҁ@��O�́@���߁@�ыƍ\�����P���Ɓ@180
��O�ҁ@��O�́@���߁@�\�����P���ƔN�x�ʎ��Ɣ�@181
��O�ҁ@��l�́@�ő��@182
��O�ҁ@��l�́@���߁@�ő��@182
��O�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�ő��͔|�@182
��O�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�ő����Y�ʂ̐��ځ@184
��O�ҁ@��l�́@���߁@�ؒY(�����Y�̋� �k����)�@185
��O�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�ؒY�̐��Y�Ɖ��i�@185
��O�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�S���Y�T�~�b�g��Z�Z��@186
��O�ҁ@��l�́@��O�߁@����і쐮�����Ɓ@189
��O�ҁ@��l�́@��O�߁@����і�@189
��l�ҁ@��ʋy�ђʐM |
��l�ҁ@���́@��ʁ@195
��l�ҁ@���́@���߁@���H�@195
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�����@195
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�����@196
��l�ҁ@���́@���߁@(�O)�@�����@196
��l�ҁ@���́@���߁@�ѓ��@199
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�L���ѓ�(�Z��X��)�@199
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�ѓ��@199
��l�ҁ@���́@��O�߁@�_���@202
��l�ҁ@���́@��O�߁@(��)�@�_���@202
��l�ҁ@���́@��O�߁@(��)�@�_�Ɠ��H�@203
��l�ҁ@���́@��l�߁@�����Ԏ���@204
��l�ҁ@���́@��l�߁@�Ԏ�ʕۗL�䐔�@204
��l�ҁ@���́@�ʐM�@205
��l�ҁ@���́@���߁@�X�ց@205
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�X�ǂ̉��v�@205
��l�ҁ@���́@���߁@�d�C�E�ʐM�@207
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�d�C�������Ɓ@207
��l�ҁ@���́@���߁@(��)�@�ʐM�@�ւ̉��v�@208
��l�ҁ@���́@���߁@(�O)�@���炫��т����̐ݒu�Ɖ^�p�@209
��ܕҁ@����
��ܕҁ@���́@�w�Z����@215
��ܕҁ@���́@���߁@�w�Z����̉��v�@215
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@�k�����w�Z�@215
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@���؏��w�Z�@221
��ܕҁ@���́@���߁@(�O)�@�k�����w�Z�@226
��ܕҁ@���́@���߁@�w�Z�ی��@237
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@�k�����w�Z�@237
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@���؏��w�Z�@239
��ܕҁ@���́@���߁@(�O)�@�k�����w�Z�@242
��ܕҁ@���́@��O�߁@���̑��̋���@�ց@243
��ܕҁ@���́@��O�߁@(��)�@PTA�̊����@243
��ܕҁ@���́@��O�߁@(��)�@�x�������c��@254
��ܕҁ@���́@�Љ��@261
��ܕҁ@���́@���߁@�Љ��@261
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@�k�����Љ��w�����̓����@261
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@���h���厖�E�O����w������@264
��ܕҁ@���́@���߁@(�O)�@�e��w��(�n����w�E�����w���E����Ҋw��)�@267
��ܕҁ@���́@���߁@�e��c�́@268
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@���������ق̕ϑJ�Ɗ����@268
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@�k�����w�l�A�����c��̔����ƌo�߁@280
��ܕҁ@���́@���߁@(�O)�@�k�����N�c�̊����@283
��ܕҁ@��O�́@�Љ�̈�@290
��ܕҁ@��O�́@���߁@�Љ�̈�@290
��ܕҁ@��O�́@���߁@(��)�@�k�����ɂ�����Љ�̈犈���̌����@290
��ܕҁ@��O�́@���߁@(��)�@�̈狦��@294
��ܕҁ@��O�́@���߁@(�O)�@�����̈���@299
��Z�ҁ@�@��
��Z�ҁ@���́@�_�Ё@309
��Z�ҁ@���́@���߁@�_�Ѝ�@309
��Z�ҁ@���́@���߁@(��)�@�O�_�Ѝ���̓���@309
��Z�ҁ@���́@���߁@(��)�@�F�[�Ԉ�ב喾�_�@309
��Z�ҁ@���́@���߁@(�O)�@�k�����̐_�y�ƉY���̕��@312
��Z�ҁ@���́@���߁@(�l)�@�����P���ۂ̕����@313
��Z�ҁ@���́@���߁@(��)�@�����̗��x��@315
��Z�ҁ@���́@���߁@(�Z)�@�����(�G�C�T�[)�@316
��Z�ҁ@���́@���߁@(��)�@�R�̐_�̍��J�Ɠ`���@319
��Z�ҁ@���́@���߁@���t�@321
��Z�ҁ@���́@���߁@�F�[�Ԓn���R���@321
�掵�ҁ@�`������
�掵�ҁ@�Γ��̘T��C��@327
�掵�ҁ@�_�p�̒B�l�@328
�掵�ҁ@�ΎԂ̂͂Ȃ��@329
�掵�ҁ@�����˂Ə�������@331
�掵�ҁ@�Ă�ւ�(�Ƃ̎q)�@332
�掵�ҁ@��(���키��)�@333
�掵�ҁ@�����Ət�������@334
�掵�ҁ@�ӑm����ƒn�_�o�@335
�攪�ҁ@����
�攪�ҁ@�k���̕����@341
���ҁ@�l��
���ҁ@(��)�@�l���@39
���ҁ@(��)�@�Ђ��̂Ƃb�@435
��\�ҁ@�Љ������
��\�ҁ@���́@�Љ���@449
��\�ҁ@���́@���߁@�����@449
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@�����ی�@�@449
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@���������@450
��\�ҁ@���́@���߁@(�O)�@��q�����@452
��\�ҁ@���́@���߁@(�l)�@�V�l�����@453
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@�����N���@456
��\�ҁ@���́@���߁@(�Z)�@�Љ�����c��@460
��\�ҁ@���́@��Á@462
��\�ҁ@���́@���߁@��t�y�ѕی��t�@462
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@��t�y�ѕی��t�@462
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@�������N�ی����Ɓ@466
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@1.�@�������N�ی����x�̕ϊv�@466
��\�ҁ@���́@���߁@(��)�@2.�@��Ë��t��@466
��\�ҁ@��O�́@�ȈՐ������Ɓ@472
��\�ҁ@��O�́@���߁@�ȈՐ����@472
��\�ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�����ȈՐ����@472
��\�ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�F�[�ԊȈՐ����@473
��\�ҁ@��O�́@���߁@(�O)�@���؊ȈՐ����@475
��\�ҁ@��O�́@���߁@(�l)�@�H���ȈՐ����@477
��\�ҁ@��O�́@���߁@(��)�@�����؊ȈՐ����@479
��\�ҁ@��O�́@���߁@(�Z)�@����ȈՐ���(����E�⌳)�@481
��\�ҁ@��l�́@�⑰��@483
��\�ҁ@��l�́@���߁@�⑰��@483
��\�ҁ@��l�́@���߁@�⑰��Ɖp����@483
��\�ҁ@��l�́@���߁@���̑��@484
��\�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�k�������c�Z��̊T�v�@484
��\�ҁ@��l�́@���߁@(��)�@�S�z���Ƒ��k���@486
��\�ҁ@��l�́@���߁@(�O)�@�V���N�㌩���x�@486
��\��ҁ@�e��@��
��\��ҁ@���́@�����g���@491
��\��ҁ@���́@(��)�@�_�Ƌ����g���̍L�捇��(�����_���̔���)�@491
��\��ҁ@���́@(��)�@�X�ёg���k���x���@494
��\��ҁ@���́@�k�������h�c�@496
��\��ҁ@���́@���߁@�{�����h�c�̉��v�A�@�\�A�����@496
��\��ҁ@���́@���߁@(��)�@���h�c�̉��v�@496
��\��ҁ@���́@���߁@(��)�@�k�����̎�ȍЊQ�@500
��\��ҁ@��O�́@�x�@�����ݏ��@503
��\��ҁ@��O�́@���߁@�x�@�����ݏ��@503
��\��ҁ@��l�́@�k�������H��@505
��\��ҁ@��l�́@���߁@���H��̉��v�@505
��\��ҁ@��l�́@���߁@(��)�@���H��̎��Ɓ@505
��\��ҁ@��l�́@���߁@(��)�@���H�������@510
��\��ҁ@��l�́@���߁@(��)�@���H��E���@510
��\��ҁ@�ό�
��\��ҁ@���́@�ό��s���v��@513
��\��ҁ@���́@(��)�@�ό��v��@513
��\��ҁ@���́@(��)�@�ό�����@514
�k�����j�N�\�@518 |
�P�Q���A���ꍑ�ۑ�w���J�u���ψ���� �u����|�\�̉\���v���u���ꍑ�ۑ�w���J�u���ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@(���ꍑ�ۑ�w���J�u��, 14)�@�@�@����E���: 2004�N6��19��-11��13��
���ꍑ�ۑ�w7����201����
|
��������Ɖ���|�\�̉\��/���{
�������x�Ƌʏ鐷�` / �ʏ�ߎq
����̖��b�ƌ|�\ / ��������
�����|�\�̉\�� / �떓�b��
|
����ŋ��Ɖ������ / ���ؐ��j
���̂����A�̂� / ���ܐ��Y
���J�|�\�̒n���I��� :
�@�@���{���������̌i�ϕω�/��l�� |
�{�y�|�\�Ɨ����|�\ : �o�� / ���Ȑ���
�������x�Ə���{��\�� / �{��\��
�n��g�x�̉\�� : ��闧�T�́u�V�ܔԁv/��엲�V
�g�x�A���܂ނ��� / ���܌��� |
���A���̔N�A���ь��]���u��������w����y���y�̍\�� -�̎��̃��Y���Ɗy���̗��_-�x�v�𓌗m���y����
2005(70) p.131-134�v�ɏЉ��B�@J-STAGE
���A���̔N�A���{���炪�ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������ҁu�ꋴ��w�X�|�[�c����
24 p.21�`28�v�Ɂu�V�}�̐g�̂��牫��̐g�̂�--�G�C�T�[��x��g�̗̂��j (�X�|�[�c�̃O���[�o���[�[�V�����ƃ��[�J���[�[�V�����Ę_)�v�\����B
���A���̔N�A �u�G�C�T�[�@�t�V�M�E�H�[�N�F�G�C�T�[�ɔ�߂�ꂽ����v���u��y�@�v���犧�s�����B
�@�@�@�@�ܒ���l����400�N�L�O�@�U�O���@�����o�@�����F�H�c�����}�����@���@�쐬�N�ɂ��ĂQ�O�O�S�N�ł�����m�F���K�v�@�Q�O�P�R�N�Q���Q�V���@�@�ۍ�
���A���̔N�A�v���c�W������|�p�ЕҏW���ҁu21���I�̉��y���� 6 p.82�`91�v�Ɂu����̉��y����݂�a�� ([�e�[�}] �a��--���F���ʂ����) �v�\����B
���A���̔N�A�v���c�W���u���x�{ 2005(28) p.38-38�v�Ɂu����|�b�v�̌��݁v�\����B�@�i -STAGE |
| 2006 |
18 |
�E |
�P���A�u��v�`����W ��P�� �v���u�������o�Łv���犧�s�����B
|
�я��̌���
�l
����
�q�i�����̓`�� |
������P�̎���
������ƍ։�
�E�C�̖m���Ə����i��
����̏���ƌÑ㍋�� |
�ɐ��_�{�̐���
���C��_�{�ƈɐ��_�b
�t���Ɠs�V�R�̓�
���\���Ղ̐��� |
�_����̐����Ɠ`�d
�O���j�ƍ����̕l�~��
�Вn�Ɛ��n
�����@���̊ |
�Q���A����`������CD����ψ���u���{������ƃE���C : ����̌É̗w�v���uFontec�v���犧�s����B
�@�@�^���f�B�X�N�@1�� (51��)
|
�R�����j���̏��̉��{������
�@�������ւ��ӂ�
�@���������Ԃ�
�@������ӂ�
�@�������߂Â炵�₩�ӂ�
�@������Ƃӂ�
����s�m�Ԃ̃E���C
�@�E���C�V���J�̃E���C(���ۂ���)
�@�E���C�V���J�̃E���C(���ۂȂ�)
�@�_�l�ɂ�鋌14���̃E���C
�@�_�l�ɂ�鋌15���̃E���C |
���A���������̃E�}�`�[�O�F���i: �J����_����
��X�����Ӗ���̃E���K�~�̃E���C
�@��V�тʃE���C
�@���ʃE���C
�@����ʃE���C
�@�E�h�D����ʃE���C
�@�Ȃ��著���ʃE���C
�@�R�̐_�����ʃE���C
�E
�E
�E
|
��� : CD�u����̌É̗w�`
�@�@�����{������ƃE���C�v�ɂ���/��Éx�q
�R�����j�搶�̓`�������{������/�g�Ɗԉi�g
���{������Ƃ���������m����/���m������
�u���{������v5��6�߂̎��͂ɂ���/�r�{����
�u���{������v5��6�߂̉��y�I�l�@/��Éx�q
����s�m�Ԃ̃E���C�Ɖ��{�I����/�����
�R�����j�N��
�E
�E
�E |
�Q���A���R�Ă����m�_���u����̍��J�`���̌��� : �V��E�_�́E���v���u���؏��[�@�c�F�� (����)�v���犧�s����B�d�v
|
���́@1
���́@��@�ړI�@3
���́@��@�e�_�@9
���́@�C�U�C�z�[�Ɩ��t��[�v����]�@13
���́@��@�͂��߂Ɂ@15
���́@��@�v�����ւ̗U���@17
���́@��@1�@�ꖇ���銗�����@17
���́@��@2�@���͐_�l�A�j�͊C�l�@21
���́@��@3�@�O�ԑ��Ƌv�����@22
���́@��@4�@���_�E���_�Ǝn�c�`���@24
���́@��@5�@��ʐ_���g�D�@28
���́@��@6�@�j���N��K�@31
���́@��@7�@���{�̐_�̓��@33
���́@��@8�@�C�U�C�z�[�Ɩ��t���@37
���́@�O�@�C�U�C�z�[�̎���@39
���́@�O�@1�@�C�U�C�z�[�̎���̈ꗗ�@39
���́@�O�@2�@��藧�ā@42
���́@�O�@3�@����ځ@44
���́@�O�@4�@����ځ@48
���́@�O�@5�@�O����(�ԑ}���V��)�@50
���́@�O�@6�@�l���ځ@56
���́@�O�@7�@��茋�с@60
���́@�O�@8�@�C�U�C�z�[�̖{�`�@61
���́@�l�@�C�U�C�z�[�̐_�̂̕��ށ@62
���́@�l�@1�@�_�̂̕��ށ@62
���́@�l�@2�@�e�L�X�g�@64
���́@�܁@��ނ̐_�́@66
���́@�܁@1�@�[(��)�_�V�т̃e�B����(2)�@66
���́@�܁@2�@������V�т̃e�B�����@76
���́@�܁@3�@��_�V�т̃e�B�����@82
���́@�܁@4�@��t���V�т̃e�B�����@87
���́@�܁@5�@�����̃e�B����(1)(�O�ԓa)�@97
���́@�܁@6�@�����̃e�B����(2)(�v���a)�@111
���́@�܁@7�@��ނ̐_�̂̓����@120
���́@�Z�@��ނ̐_�́@121
���́@�Z�@1�@���ێ��̃e�B�����@121
���́@�Z�@2�@�j���C�J�i�C�y�q�̃e�B�����@129
���́@�Z�@3�@�j�̃e�B�����@132
���́@�Z�@4�@��ʉƒ���̃e�B�����@142
���́@�Z�@5�@��ނ̐_�̂̓����@147
���́@���@��ނƓ�ނ̕��������_�́@148
���́@���@1�@�C�U�C�z�[�̌��e�B�����Ɨ[
�@�@��(��)�_�V�т̃e�B����(1)�@148
���͎�2�@�u�C�U�C�z�[�̌��e�B�����v�̖��`�@159
���́@���@�C�U�C�z�[�̗R��杁@161
���́@���@1�@�{�߂̂˂炢�@161
���́@���@2�@�u�Ζ咆�̌��@161
���́@���@3�@�u�Ζ咆�̌��̌`���@164
���́@���@4�@�v���n���̌��@167
���́@���@5�@�����n�ȗR��杁@169
���́@��@���t���@170
���́@��@1�@�{�߂̂˂炢�@170
���́@��@2�@�j�̍Ղ�@170
���́@��@3�@���t���̎���̈ꗗ�@172
���́@��@4�@�_�����@173
���́@��@5�@���t���@174
���́@��@6�@���t���̃e�B�����@176
���́@��@7�@�_���グ�@190
���́@��@8�@�_���̃e�B�����@190
���́@��@9�@��a��ł̖��t���@201
���́@��@10�@���t���̍��J���E�@201
���́@��@11�@���z�_�@203
���͋�12�@���{�̑D�q�̒j���N��K�@203
���́@��@13�@�C�U�C�z�[�Ƃ̏Ɖ��@206
���́@��Z�@�J���W���i�V�[�@�t�@���҂̑D�@208
���́@��Z�@1�@�{�߂̂˂炢�@208
���́@��Z�@2�@���K�_����������Ղ�@208
���́@��Z�@3�@�����@209
���́@��Z�@4�@�A�J�J���W���i�V�[�@209
���́@��Z�@5�@�����[�o�[�@211
���͈�Z�@6�@�G���u���̑務�F��Ƒ務���Ӂ@214
���͈�Z�@7�@���҂̑D�@215
���͈�Z�@8�@���̘_���Ɖ��{�̐_�̓��̘_���@218
���́@���@�t�o���N�@220
���́@���@1�@�{�߂̂˂炢�@220
���́@���@2�@���s�̃t�o���N�̗v�f�@221
���́@���@3�@���s�̃t�o���N�̎���̈ꗗ�@222
���͈��@4�@���s�̃t�o���N�̈���ڂ̎���@225
���́@���@5�@�t�o���N�̃e�B�����@228
���́@���@6�@�|�����̌�֎�(��)�@235
���́@���@7�@�|�����̌�֎��̃e�B�����@236
���́@���@8�@�ޖ��@241
���́@���@9�@���{�̐_�̓���
�@�@����ʐ_���g�D�̍ĕҁ@242
���́@���@10�@����ڂ̌ߌ�̎���@243
���́@���@11�@����ڂ̏����@244
���́@���@12�@����ڂ̑D�����V��@244
���́@���@13�@�X�N�̑務�F��@249
���́@���@14�@�܂Ƃ߁@250
���́@���@�C�U�C�z�[�̌`���@�t�@�^���g�D�j����
�@�@���E���T�N�w�̏��C�@251
���́@���@1�@�{�߂̂˂炢�@251
���́@���@2�@�u���Ẵt�o���N�v����
�@�@���C�U�C�z�[�ƌ��s�̃t�o���N�w�@253
���́@���@3�@�u�͂��߂̃t�o���N�v����
�@�@���u���Ẵt�o���N�v�ց@267
���͈��@4�@�^���g�D�j���ƃE���T�N�w�̏��C�@276
���́@���@5�@�܂Ƃ߁@288
���́@��O�@���t���̌`���@289
���́@��O�@1�@�{�߂̂˂炢�@289
���́@��O�@2�@�u�͂��߂̖��t���v����
�@�@���u���Ă̖��t���v�ց@289
���́@��O�@3�@���s�̖��t���̌`���@291
���́@��l�@���с@292
���́@�����̍����N���`���ƍ����V��[�v����]�@297
���́@��@�͂��߂Ɂ@299
���́@��@�����N���`���̃��`�[�t�ꗗ�@301
���́@�O�@�v�����̍����N���`���@304
���́@�O�@1�@�v�����̍����N���`���̍[�T�@304
���́@�O�@2�@�����L�g���̌��@306
���́@�O�@3�@�����V�Y�����̌��@308
���́@�O�@4�@����i�֓����̌��@311
���́@�O�@5�@�w�������R���L�x(2)�̌��@313
���́@�O�@6�@�w�������R���L�x(4)�̌��@317
���́@�O�@7�@�w���������L�x(2)�̌��@318 |
���́@�O�@8�@�w���������L�x(3)�̌��@320
���͎O9�@�w��V���`�x�Ɓw�v�����R���L�x�̌��@321
���́@�l�@���{�̍����N���`���@328
���́@�l�@1�@���{�̍����N���`���̍[�T�@328
���́@�l�@2�@�w���������R���Ӂx�̌��@329
���́@�l�@3�@�w���R�����x�̌��@333
���́@�܁@�v�����Ɖ��{�̗���@335
���͌�1�@�l�̗���Ɛ_�̗���@335
���͌�2�@�����̎함�Ǝ������ꏊ�ƍ��ƓI���J�@338
���́@�܁@3�@�A���̎함�ƌ�x�̂͂��܂��
�@�@�������V��̍Ջ�̂͂��܂�@340
���́@�܁@4�@�v�����Ɖ��{�̍����V��̂͂��܂�@342
���́@�Z�@���с@346
��O�́@�J���W���i�V�[[�v����]�@349
��O�́@��@�͂��߂Ɂ@351
��O�́@��@�j���C�J�i�C�̐_���Ղ�_�l�@354
��O�́@�O�@�l���̃J���W���i�V�[�@358
��O�́@�O�@1�@�l���̃J���W���i�V�[�̎���̈ꗗ�@358
��O�́@�O�@2�@�����(�ʂ�O)�@360
��O�́@�O�@3�@�����(�J�V�e�B�[)�@361
��O�́@�O�@4�@�O����(�A�J�J���W���i�V�[)�@364
��O�́@�O�@5�@�j�����q�ƃg�D���e�B���[�@391
��O�́@�O�@6�@�ʂ�O�@392
��O�́@�O�@7�@�l����(�����[�o�[)�@392
��O�́@�l�@�㌎�̃J���W���i�V�[�@405
��O�͎l1�@�㌎�̃J���W���i�V�[�̎���̈ꗗ�@405
��O�́@�l�@2�@�����(�T�[�����N���a���L)�@406
��O�́@�l�@3�@�����(�J�V�e�B�[)�@408
��O�́@�l�@4�@�O����(�A�J�J���W���i�V�[)�@410
��O�́@�l�@5�@�l����(�����[�o�[)�@415
��O�́@�܁@�����ē`���@416
��O�́@�܁@1�@�V��Ɛ_�̂ƌ��̕⊮�W�@416
��O�́@�܁@2�@�����ē`���ƍՂ�@420
��O�́@�܁@3�@�����Ă̐��E�ρ@423
��O�́@�Z�@���с@425
��l�́@���[�J��[�v����]�@427
��l�́@��@�͂��߂Ɂ@429
��l�́@��@�����̏j���@433
��l�́@�O�@���U�߂̌c�с@442
��l�́@�l�@���с@445
��́@�����̐_�l�̍�[�v�����E��ᓇ]�@447
��́@��@�͂��߂Ɂ@449
��́@��@�v�����̐����@451
��́@��@1�@�����̎���̈ꗗ�@451
��́@��@2�@�����ƍ̖�@454
��́@��@3�@���U�@455
��́@��@4�@���N�����@464
��́@��@5�@�O���ߋ�(�j)�@464
��́@��@6�@�q���ɉh�@466
��́@��@7�@�C�ނ̐��������炷�j���@468
��́@��@8�@���̖L��������炷�����@468
��́@��@9�@�_�l�̍��Ɏn�܂�ɉh�@469
��́@�O�@��ᓇ�̔��������@471
��́@�O�@1�@���������@471
��́@�O�@2�@����Ɛ_�l�g�D�@472
��́@�O�@3�@���s�̎���@474
��́@�O�@4�@���Ă̎���@476
��́@�O�@5�@�q���ɉh�@483
��́@�O�@6�@�C�ނ̐��������炷�j���@486
��́@�O�@7�@��̖L��@492
��́@�O�@8�@�_�l�̍��Ɏn�܂�ɉh�@493
��́@�l�@���с@494
��Z�́@�V�k�O�̃`�����W���}(�g���U�})[�ɕ�����]�@497
��Z�́@��@�͂��߂Ɂ@499
��Z�́@��@�`�����W���}(�g���U�})�̃e�L�X�g�@502
��Z�́@��@1�@�{�߂̂˂炢�@502
��Z�́@��@2�@�c���̃e�L�X�g�@503
��Z�́@��@3�@��쉮�̃e�L�X�g�@506
��Z�́@��@4�@���e�L�X�g�̔�r�@512
��Z�́@�O�@�c���̃V�k�O�̎���@515
��Z�́@�O�@1�@�c���̃V�k�O�̎���̈ꗗ�@515
��Z�́@�O�@2�@�����@517
��Z�́@�O�@3�@�g�[�K��(�P��)�@517
��Z�́@�O�@4�@�j���̏j���@519
��Z�́@�O�@5�@�V�k�O��ł̊����́@520
��Z�́@�O�@6�@�A�T�M�ł̊����́@525
��Z�́@�O�@7�@���N�F�[�i�@528
��Z�́@�O�@8�@�`�����W���}�@528
��Z�́@�O�@9�@�E�V�f�[�N�@529
��Z�́@�O�@10�@���s�̃V�k�O�@530
��Z�́@�O�@11�@�j�Ə��̌𗬁@530
��Z�́@�l�@�j�q�̗��z�I�Ȑ����@532
��Z�́@�l�@1�@�a�����琬�l�ց@532
��Z�́@�l�@2�@�����a�����@532
��Z�́@�l�@3�@������j��l���@537
��Z�́@�܁@��쉮�̃V�k�O�̎���@�t�@
�@�@�����K�̃V�k�O�@540
��Z�͌�1�@��쉮�̃V�k�O�̎���̈ꗗ�@540
��Z�́@�܁@2�@�I�[�i�U���[(�P��)�@542
��Z�́@�܁@3�@�j���Ə����̏j���@543
��Z�́@�܁@4�@�����́@544
��Z�́@�܁@5�@�|�n�Ɠ��D�h�[�C�@545
��Z�́@�܁@6�@�g���U�}�@546
��Z�́@�܁@7�@�E�V�f�[�N�@547
��Z�́@�܁@8�@�^���g�m�[�V(�������)�@547
��Z�́@�܁@9�@�j�q�̗��z�I�Ȑ����@547
��Z�́@�܁@10�@�j�Ə��̐��E�̘a���@548
��Z�́@�܁@11�@���K�̃V�k�O�@549
��Z�́@�Z�@�j���̓I�����@550
��Z�́@�Z�@1�@�V�k�O�ƃE���W���~�@550
��Z�́@�Z�@2�@�j���̉����V��@552
��Z�́@�Z�@3�@����_�@553
��Z�́@�Z�@4�@�c���Ɖ�쉮�̈���_�@555
��Z�́@���@���̌��z�@557
��Z�́@���@1�@�R���̃V�k�O�@557
��Z�͎�2�@�`�����W���}(�g���U�})�Ƃ̋��ʓ_�@564
��Z�́@���@3�@�܍��L���Ǝq���ɉh�@565
��Z�́@���@�ΏƓI�ȗR��杁@566
��Z�́@���@1�@���ލ��@566
��Z�́@���@2�@���܂Ȃ����@567
��Z�́@���@3�@�_�̘_���@569
��Z�́@��@���с@571
�掵�́@���K���ܖ�[������]�@575
�掵�́@��@�͂��߂Ɂ@577
�掵�́@��@���n�E�Ր_�E�_�l�g�D�@580 |
�掵�́@��@1�@���n�ƍՐ_�@580
�掵�́@��@2�@�_�l�g�D���̑��@581
�掵�́@�O�@�R��杁@583
�掵�́@�O�@1�@�o�T�@583
�掵�́@�O�@2�@����@583
�掵�́@�O�@3�@����@585
�掵�́@�O�@4�@�O���@586
�掵�́@�O�@5�@�l���@587
�掵�́@�O�@6�@���s�̍Ղ�Ƃ��Ă̍Ղ�@588
�掵�́@�O�@7�@�����̊֗^�@590
�掵�́@�O�@8�@����K�@590
�掵�́@�O�@9�@�j���O���C�@592
�掵�́@�O�@10�@���_�Ɨ��K�_�@594
�掵�́@�O�@11�@�R���`�@595
�掵�́@�l�@�V��@596
�掵�́@�l�@1�@���K���ܖڂ̎���̈ꗗ�@596
�掵�́@�l�@2�@�����(�R�̐_)�@598
�掵�́@�l�@3�@�����(���K������)�@601
�掵�́@�l�@4�@�O����(�{�Ղ�)�@604
�掵�́@�l�@5�@�ߎN���@614
�掵�́@�l�@6�@���Ă̎���@614
�掵�́@�܁@���s�̐_�́@616
�掵�́@�܁@1�@�_�͈̂̔͂Ə�@616
�掵�́@�܁@2�@�䐒�сE�肢���@617
�掵�́@�܁@3�@�E���k�L�O�g�D�@621
�掵�́@�܁@4�@�E�l�[�W���N�E���C�@630
�掵�́@�܁@5�@�L�[�g�}�[�@635
�掵�́@�܁@6�@���q�a�����Ƒ�a���@639
�掵�́@�܁@7�@�x�߂�E���C�@645
�掵�́@�܁@8�@�C�X�M�X�M�@649
�掵�́@�܁@9�@���K�t�V�}�}�}�j�@652
�掵�́@�܁@10�@�j�V�k�q�[�^�@654
�掵�́@�܁@11�@�x�߂��̃E���k�L�O�g�D�@664
�掵�́@�Z�@��s����_�́@667
�掵�́@�Z�@1�@�w���������×w��Ȃ̌����x��
�@�@���w�������R���L�x�̐_�́@667
�掵�́@�Z�@2�@�`�[�O�E���C�@668
�掵�́@�Z�@3�@�ց[���}�[�@670
�掵�͘Z4�@���[�W�E���C<�E�[�w�[�C�w�[�C>�@671
�掵�́@�Z�@5�@�L�[�g�}�[<�I�[�q���[�q>�@679
�掵�́@�Z�@6�@�I�i�C�W���N�I����
�@�@��(�E�l�[�W���N�E���C)�@687
�掵�́@�Z�@7�@����V���@693
�掵�́@�Z�@8�@���I�����@695
�掵�́@�Z�@9�@�j�V�k�q�[�^�̑O�g�@697
�掵�́@�Z�@10�@�R�l����S�@699
�掵�́@�Z�@11�@�A�ȂƑ����_�́@705
�掵�́@���@���с@707
�攪�́@���K���ܖڂ̗R��杂ƋV��[������]�@711
�攪�́@��@�͂��߂Ɂ@713
�攪�́@��@�R��杁@714
�攪�́@��@1�@���_�̒����Ɖ����@714
�攪�́@��@2�@���K���̐_�̑f���@722
�攪�́@�O�@�V��@727
�攪�́@�O�@1�@�V��̎���@727
�攪�́@�O�@2�@���̎��n�Ձ@730
�攪�́@�O�@3�@�Đ����@734
�攪�́@�l�@�V��ƗR��杂̑Ή��@736
�攪�́@�܁@�����̂̈ێ��@738
�攪�́@�Z�@���с@741
���́@�J���X[�ɗǕ���]�@743
���́@��@�͂��߂Ɂ@745
���́@��@�Ղ���x����W�c�@747
���́@��@1�@�����_���Ƒ��̏����@747
���͓�2�@�j���_���ƒj���N��K��W�c�@749
���́@�O�@��ꌎ�̃J���X�@752
���͎O1�@��ꌎ�̃J���X�̎���̈ꗗ�@752
���́@�O�@2�@�����@755
���́@�O�@3�@����ځ@755
���́@�O�@4�@����ځ@777
���́@�O�@5�@�O����(�i�n�k�g�D�J)�@782
���́@�O�@6�@�l���ځ@799
���́@�O�@7�@�ܓ���(�}���T��)�@799
���́@�l�@��̃J���X�@802
���́@�܁@�R��杂̌`���@804
���́@�܁@1�@�搣��x�̊֗^�@804
���́@�܁@2�@�����_���p������
�@�@���j���N��K�̃����N�@812
���́@�܁@3�@�������̌��@816
���́@�Z�@���с@819
���Z�́@�����j��গ��D����[����]�@823
���Z�́@��@�͂��߂Ɂ@825
���Z�́@��@�C�ނւ̓���@830
���Z�́@��@1�@���R�̗R��杁@830
���Z�͓�2�@���̑��̌�x�̗R��杁@834
���Z�͓�3�@�ӂ��Ɩ��Ӗʂ̗R��杁@837
���Z�́@��@4�@�C�̒j�Ɠ��̏��@839
���Z�͓�5�@�������a�[�Ɛ��(���g��)�@843
���Z�́@�O�@�����@844
���Z�́@�O�@1�@�����s���̎���̈ꗗ�@844
���Z�́@�O�@2�@�����@845
���Z�́@�O�@3�@��x�q�݁@846
���Z�́@�O�@4�@�j�����@847
���Z�́@�O�@5�@���������^�@847
���Z�́@�O�@6�@�j���������^(��E��)�@854
���Z�́@�O�@7�@�j���������^(�O�E�l)�@858
���Z�́@�O�@8�@�j���������^(��)�@860
���Z�́@�O�@9�@�e�ˏ���@865
���Z�́@�O�@10�@�j�����̈Ӌ`�@865
���Z�́@�O�@11�@���̑��̐����s���@866
���Z�́@�l�@�L�N�Ձ@867
���Z�͎l1�@�L�N�Ղ̎���̈ꗗ�@867
���Z�́@�l�@2�@�����@869
���Z�́@�l�@3�@��x�v�[���@870
���Z�́@�l�@4�@���v�[���@876
���Z�́@�l�@5�@���ԓ��̖L�N�Ձ@883
���Z�͎l6�@গ��D�_���̗R��杁@888
���Z�́@�l�@7�@�v�[���j�̍s���@893
���Z�͎l8�@�v�[���j���琳���j�ց@894
���Z�́@�܁@���с@895
�I�́@901
���Ƃ����@911
���o�ꗗ�@913
�����@(1)
�E |
�R���A�k�J���j�ҏW�ψ���ҁu�k�J���j ����(�ږ��E�o�҂���)�v���u�k�J������ψ���v���犧�s�����B
|
�����̂��Ƃ@�k�J������ψ���璷�@���c�����G
�����ɂ������ā@�k�J���j�ҏW�ψ����@�r�{����
�����ɂ悹�ā@�k�J�����@�썑���t
�}��
�{����ǂނɂ������ā@�ږ��E�o�҂��Ґ�啔��@���c�@��
�{�_
���́@��O�̖k�J���ƈږ��E�o�҂��@1
���́@���߁@���v�ɂ݂��O�����ꌧ�̈ږ��E�o�҂��@3
���́@���߁@����E���O�̉��ꌧ�̈ږ��̗��j�@3
���́@���߁@����E���O�̉��ꌧ�̐A���̗��j�@8
���́@���߁@���v�ɂ݂��O���k�J���̈ږ��E�o�҂��@11
���́@���߁@�N���ʓn�q�n�ʊC�O�ږ����@11
���́@���߁@�N���ʎ��ʊC�O�ږ����@18
���́@���߁@�n�q�n�ʎ��ʊC�O�ږ����@20
���́@���߁@�n�q�n�ʊC�O�ݗ��Ґ�����ё����z�@26
���́@���߁@�n�q�n�ʐB���n�ݏZ�Ґ��@29
���́@���߁@�s�����ʓ��{���ʌ��O�ݏZ�Ґ��@30
���́@���߁@���R����(1)�@�ږ��n�̊����\�L�@32
���́@��O�߁@�ږ��E�o�҂����o�̐����E�Љ�I�w�i�@34
���́@��O�߁@�吳�E���a���̉���ƈږ��E�o�҂��@34
���́@��O�߁@�ɗ産�̉ʂ����������@37
���́@��O�̖k�J�����̈ږ��E�o�҂���@45
���́@���߁@���O�@47
���́@���߁@�t�B���s���@47
���́@���߁@�n���C�@60
���́@���߁@�y���[�@70
���́@���߁@�u���W���@79
���́@���߁@�j���[�J���h�j�A���@87
���́@���߁@�V���K�|�[���@92
���́@���߁@�J�i�_�@95
���́@���߁@���R����(2)�@�����Ɏc��ږ��E
�@�@���o�҂��̋L���@100
���́@���߁@�A�����J���O���{�y�@102
���́@���߁@�A���[���`���@107
���́@���߁@���̑��̍��ƒn��@111
���́@���߁@���A���n�@115
���́@���߁@��m�Q���@115
���́@���߁@���B�@135
���́@���߁@��p�@146
���́@���߁@���R����(3)�@�q�ǂ��ɂƂ��Ă̈ږ��E
�@�@���o�҂��@�[����ɋA�����ā[�@149
���́@���߁@���N�@150
���́@���߁@�C�쓇�E�O�}���@151
���́@��O�߁@�����@153
���́@��O�߁@���{�{�y�ւ̏o�҂��@153
���́@��O�߁@�哌�����@156
��O�́@�푈�E�����g���@159
��O�́@���߁@�ږ��E�o�҂��Ƒ����m�푈�@161
��O�́@���߁@�푈�ƒ���Ă̈ږ������@161
��O�́@���߁@�t�B���s���E�쑾���m�̐��@162
��O�́@���߁@�s�풼�O�̓�m�Q���ƘV�c�w���q�@163
��O�́@���߁@���̋��������g���@166
��O�́@���߁@���{�̔s��ƈ����g���̊T�v�@166
��O�́@���߁@��m�Q������̈����g���@168
��O�́@���߁@���R����(4)�@���g�҂̊�ɉf��������@171
��O�́@���߁@�t�B���s������̈����g���@172
��O�́@���߁@��p����̈����g���@172
��O�́@���߁@���{�{�y����̈����g���@174
��O�́@���߁@�����E���N�E�V�x���A����̈����g���@175
��O�́@���߁@�O�n���g�҂̈ړ��Ɩ{�y��Z�@176
��O�͑��߁��R����(5)�@��Љ���~���^����
�@�@���k�J���̕���178
��l�͐��̖k�J���ƈږ��E�o�҂��@181
��l�͑��ߓ��v�ɂ݂�������ꌧ�̈ږ��E�o�҂�183
��l�͑��ߔN���ʊC�O�ږ����@183
��l�́@���߁@�n�q���ʊC�O�ږ����@184
��l�́@���߁@���v�ɂ݂�����k�J���̈ږ��E�o�҂�186
��l�́@���߁@�N���ʊC�O�ږ����@186
��l�́@���߁@�n�q���ʊC�O�ږ����@186
��l�́@��O�߁@�ږ��E�o�҂����o�̐����E�Љ�I�w�i�@191
��́@���̖k�J�����̈ږ��E�o�҂���@197
��́@���߁@���O�@199
��́@���߁@�{���r�A�@199
��́@���߁@�u���W���@209
��́@���߁@�A���[���`���@224
��́@���߁@�y���[�@229
��́@���߁@�J�i�_�@232
��́@���߁@�A�����J���O���@236
��́@���߁@�����E���̑��@241
��́@���߁@���d�R�J��ږ��@241
��́@���߁@���R����(6)�@���Γo�ɓ`�����
�@�@�������O��(�㐨��)�G�C�T�[�@256
��́@���߁@�{�y�A�E�@258
��́@���߁@�O���D��g���@271
��Z�͈ږ��E�o�҂����߂��錻�݂Ɩ���
�@�@���[���ی𗬂̉˂����Ƃ��ā[279
��Z�́@���߁@�C�O�̖k�J���l��g�D�@281
��Z�́@���߁@�y���[�k�J���l��@281
��Z�́@���߁@�݈��k�J���l��@285
��Z�́@���߁@�u���W���k�J���l��@287
��Z�́@���߁@�n���C�k�J�E�Î�[���l��@290
��Z�́@���߁@���E�̃`���^���`���ƂƂ��Ɂ@295
��Z�́@���߁@�u���E�̃E�`�i�[���`�����v�Ɩk�J���@295
��Z�́@���߁@�C�O�ڏZ�Ҏq�팤�C��������Ɓ@298
��Z�́@���߁@��Ĉږ��E�O���̓��{�o�҂��@302
�̌��L�^
���́@�ږ���ŕ�炷�`���^���`���@305
�@���߁@�y���[�@307
�@���߁@����l���c���ăy���[�ց@��l�J���@307
�@���߁@��O�Z�N�ԁA�{�{�Ƃ��c�ށ@��ÃE�V�@310
�@���߁@�_�����o�ă��X�g�����e���o�c�@���^�P�@312
�@���߁@�N���ē]��ł܂��N���ā@�ɗ琳�T�@314
�@���߁@�����̑���Б��Ɉ͂܂�ā@��ÃJ���@316
�@���߁@�q�ǂ������ɂ͏\���ȋ�����@��ԃc���@320
�@���߁@�푈������ăy���[�ֈږ��@��Ԑ����@328
�@���߁@�푈���ɉ^�]�Ƌ������グ����@���~�P�g331
�@���߁@�{�茧����y���[�ֈږ��@��ԏ��q�@333
�@���߁@���}�s���Ń��X�g�����e���o�c�@��×ѐ��@334
�@���߁@�o�����c���ĕ�ƈږ��@���g���Y�@337
�@���߁@���̎q�ǂ������͌b�܂�Ă���@����L�q�@340
�@���߁@��ԉ��l������̂́A�����g�����Ɓ@�ÉÎR�n�C��343
�@���߁@�A���[���`���@348
�@���߁@�y���[�A�{���r�A���o�ăA���[���`���ց@�Ɖ��v�M348
�@���߁@���A�蒆�̒j���ƌ����@�쐣�}�c�@352
�@���߁@�ԉňږ��Ƃ��ăA���[���`���ց@�茴�Ƃ�@354
�@���߁@���ƈꏏ�ɐ���X���o�c�@�V�_�P�Ɓ@357
�@���߁@���e�̓y���[�A���̓A���[���`���@�V�_�Ύq360
�@���߁@�ʐ^�����ŃA���[���`���Ɉږ��@�ԏ�i�w361
�@���߁@�o�̏Љ�Ŏʐ^�����@�n�Õ~�����@363
�@���߁@�c���̌ĂъŃA���[���`���ց@��䐷�X365
�@���߁@�u���W���o�R�ŃA���[���`�������@�q�u�@��367
�@���߁@�Z�̌ĂъŃA���[���`���ց@��䐷�s�@370
�@���߁@����Y�ƊJ���N�����o�Ĉږ��@���A�ޕv�@372
�@���ߏo�҂����ɊO���l�ł��邱�Ƃ��ӎ������@�ԏ�~�Q��376
�@���߁@�}���K�������L�߂����@��F�������ʁ@378
�@��O�߁@�u���W���@380
�@��O�ߓ�m����A���ău���W���ց@�Ɖ��J���C�Ɖ����P380
�@��O�߁@�푈���ɃT���g�X��ǂ���@�R���E�g�@384
�@��O�߁@���\�܂Ńt�F�C���ɏo��@�Đ{�c���@387
�@��O�߁@�S���H�v�����Ă����v�@�c��e�C�@388
�@��O�߁@�O�Z�N�Ԃ�̌̋��͊O���̂悤�@�c��T���@390
�@��O�߁@�^��V�ɔC���ău���W���Ɉږ��@�Ôe����@392
�@��O�߁@�q�ǂ��������݂�ȒB�҂ōK���@��ԃJ�}�h�@395
�@��O�߁@����̍s���͖Y��Ȃ��@���܃J�}�g�@397
�@��O�߁@���W��ĕv�w�Ńu���W���ց@���g�V�@403
�@��O�߁@�C���H�A�Ƌ�E�l�Ƃ��ē����@��䐷�K�@405 |
���́@��O�߁@���A�҂̑������}�����A�ɂ�����@���͒����@407
���́@��O�߁@�Ƒ����O��ɕ�����Ĉږ��@���g�g�~�@410
���́@��O�߁@�Ƒ����l�Ńu���W���ց@�茴���g�C�茴�g���q�@411
���́@��O�߁@���{�ւ̏o�҂����o���@���͒����C���̓��V�q�@413
���́@��O�߁@�Ƒ��ŃN�X�g�D�[�����o�c�@�V�_���C�V�_�����@415
���́@��O�߁@��m���܂�̃u���W���ږ��@�m�O���E�q�@418
���́@��O�߁@�R�[�q�[������s�X�n�ց@���v�쐭���C���v�쏉�q419
���́@��O�߁@������ɃT���p�E���œƗ��@���͒����@422
���́@��O�߁@�o�i�i�͔|�ƃN�X�g�D�[���@�������r�v�@424
���́@��O�߁@�����̓y�n����ăE�����͔|�@��䐷���@426
���́@��O�߁@�k�J���o�g�̕v�ƌ����@���������q�@428
���́@��O�߁@�J�W�}���[���}������@�����o�q�@430
���́@��O�߁@�T���g�A���h���s�ŃV���[�J���@�ʓߔe����@431
���́@��O�߁@�Z�Ɠ�l�Ńu���W���Ɉږ��@���g���q�@434
���́@��O�߁@�{�������ƂƉ^���Ƃ��c�ށ@��鐷���@435
���́@��l�߁@�{���r�A�@438
���́@��l�߁@�������{��ꎟ�v��ږ��Ƃ��ă{���r�A�ց@
�@�@���ÉÎR���Y438
���́@��l�߁@���ڏZ�n������ڏZ�n�ց@�{�������@446
���́@��l�߁@�����������J���@�K�n�L�C�K�n�x�q�@449
���́@��l�߁@�Ȃ̎��Ƃƈꏏ�Ƀ{���r�A�ց@��F�������@455
���́@��ܐ߁@�n���C�@459
���͑�ܐ߃}�E�C���Ő��܂�k�J�ň�@�^�h�c���q�@459
���͑�ܐ߃n���C�̃`���^���`���͓����ҁ@�m�O���V�I�@�E�B���A��460
���͑�ܐ߃z�m�����s�����ǂɋΖ��@��������Y�C�����F�q461
���͑�ܐ߈ꐢ�ږ��̑c����̋�J���Â�Ł@�����q�J���r��464
���́@��Z�߁@�A�����J���O���{�y�@465
���́@��Z�߁@�n���E�b�h�Ŏ��Ƃ������@���g�h�C���g�C�@465
���́@��Z�߁@�n���C�ƃ��T���[���X�ŕ�炷�@��ԂƂݎq�@468
���́@��Z�߁@��ɂ̓t�[�`�o�[�ƃT���j���@�g�V�R�@�A���s�@469
���͑�Z�߁@�J���t�H���j�A�B�A
�@�@���R�����h�B�ŕ�炷�@�Ďq�N���[�\��471
���́@�掵�߁@�J�i�_�@474
���́@�掵�߁@�q��e�r�Ƒ��̗��j?�W���[�W�E���V�q�T�E
�@�@���q�K�ƃ��V�R�E�q�K?�@���[���C���@�}�N�j�[���@474
���́@�����ŕ�炷�`���^���`���@477
���́@���߁@���d�R�J��ږ��@479
���́@���߁@���Γo�̐挭���ɍŔN���ŎQ���@��F�������@479
���́@���߁@���Γo�x�̂ӂ��ƂŐ�����@��F���g���@485
���́@���߁@�Ƒ����l�ʼn��Γo�ɓ��A�@��Ìi�Ɂ@488
���́@���߁@���{�{�y�@492
���͑��߁@�Z�F�����̐��ՍH�Ƃ��ĐÉ��s�ɒ蒅�@
�@�@���^�ߔe���g492
���͑��߁@�_�o�I��������g���č�ʂɓ��A�@���g�g�d496
���͑��߁@���̃E�`�i�[���`���Ƃ��Đ�����@�Ɖ����`500
���͑��߁@��ʂɗc�t�����J�݂������@�Η�T�q509
���͑��߁@�����s����Ō��݉�Ђ��o�c�@��钩�v513
���͑��߁@�������̖{�y�A�E�̌��@������q�q�C�x�����q517
��O�́@�ږ��E�o�҂�����A���Ă����`���^���`���@527
��O�́@���߁@�t�B���s���@529
��O�́@���߁@�_�o�I�ł̖��͔|�@�茴�E�g�C�茴�����@529
��O�́@���߁@�z���Ɛ����������_�o�I�@�ɗ�O�@533
��O�́@���߁@�{�y�o�g�҂Ɛe�����t�������@���c�T�_�@538
��O�́@���߁@�t�B���s���ɂ͕|���čs���Ȃ��@�茴���g�@545
��O�́@���߁@�펞���̃_�o�I�����т�@�������Ɂ@548
��O�́@���߁@�_�o�I�ʼn߂��������N����@���܉�v�@553
��O�́@���߁@�_�o�I�ɂ͗ǂ��v���o���Ȃ��@�^�쉮���F�@562
��O�́@���߁@�푈���n�܂�Ɛ�������ρ@�Đ{���q�@566
��O�́@���߁@�����~���������X�@�X�ۈ��h�@573
��O�́@���߁@�y�����������ԏ��w�Z�@�茴���N�@576
��O�́@���߁@��m�Q���@580
��O�́@���߁@�Ƒ������킢���Ċݕǂɗ��@��l�c���@580
��O�́@���߁@�T�C�p�����ł̕�炵��U��Ԃ��ā@
�@�@�����ǃ}�T�C�ڎ�^����q�@584
��O�́@���߁@�������������ăT�C�p�����ց@��ÃX�~�q�@589
��O�́@���߁@�������邽�߂ɃT�C�p�����ց@��F���n���@593
��O�́@���߁@�A�M�[�K�����ł̕�炵�@�Ɖ����p�C�Ɖ����V�@594
��O�́@���߁@�T�C�p�����͑��̌̋��@���ǒ���@598
��O�́@���߁@��̓��Ő����Ƃɏ]���@�Ôe����@603
��O�́@���߁@�T�C�p�������_��ł̕�炵�@�ԏ�n���@605
��O�́@���߁@�u�h�����v�Ɠ��{���ɋ������@��l���@609
��O�́@���߁@�t������߂��������^���@�֎R���@612
��O�͑��߁@��O�̂��Ƃ͖Y���悤�ɓw�͂��Ă����@�×z�c���g616
��O�́@���߁@�K���p���ŗX�Lj��Ƃ��ē����@���c���a�@621
��O�́@���߁@�T�C�p�����ő̌����������n���@�ɔg�����@626
��O�́@���߁@�T�C�p�����Őj���É@���J���Ă������@
�@�@�����������C�������V�Q�@635
��O�́@���߁@�s��Ȑ��������ā@���{�鐴�@642
��O�́@���߁@���{�͕����Ă��Ȃ��ƐM���Ă����@��Îv�h�@649
��O�́@���߁@�a�J��ł̖��̎��@��F���g���@655
��O�́@���߁@�������ăp���I�ց@�ԏ���@659
��O�́@���߁@����ɂ͒N�����Ȃ��Ǝv���Ă����@���n���q�@662
��O�́@���߁@�A���K�E�����ł̏��N����@���ǐ����Y�@665
��O�́@���߁@�J��ږ��Ƃ��ăN�T�C���ց@�ݖ{�{�h�@671
��O�́@���߁@��肩��Ƒ��̂����m�ց@���g�^�h�@674
��O�́@���߁@�|�i�y���ł̕�炵�@�n�c����^�C�n�c���g���@677
��O�́@���߁@�|�i�y���ł��܂��܂Ȏd�����o���@�茴�����@682
��O�́@��O�߁@���B�@685
�@��O�߁@�������Ƃ��Ė��֊J����N�`�E�R�ɎQ���@�n�c���ꋝ685
�@��O�߁@�搶�̊��߂Ŗ��֊J����N�`�E�R�ɉ���@�ɗ瑷��689
�@��O�߁@�{�y�œ��������Ƒ嗤�ɓn��@�����Îq�@698
�@��O�߁@���B�d�d���O�]�����ǂœ����@��l���i�@704
�@��l�߁@�{�y�o�҂��@710
�@��l�߁@���s�s�d�ǂ̓]�Q��@�ݖ{�D���C�ݖ{��q�@710
�@��l�߁@�_�ˁE���ł̏o�҂��@���n�F�g�C���n�V�Q�~�@712
�@��l�߁@�_�ˁE���É��ł̏o�҂��@�茴���q�C�茴�c���@713
�@��l�߁@�e�̔���U����ē��n�ց@�Ɖ��q�q�@716
�@��l�߁@���Ƙa�̎R�̉�Ђœ����@��F�����M�@717
�@��l�߁@��������̐l�������ƂɏW�܂�@�ԏ�c���q�@720
�@��ܐ߁@�O���D��g���@725
�@��ܐ߁@�O�Z�N�Ԃ��O���D�ʼn߂����@���{���F�@725
�@��ܐ߁@�M�����[�}���Ƃ��ĊO���D�ɏ��@�茴���a�@732
�������͎ҁE���͋@�ց@737
�����ҁE�@�ց^�|�͎ҁ^�ҏW��L�@739
�k�J���j�@�����@�ږ��E�o�҂��ҁ@���^�ږ��E�o�҂��֘A�n�}
���^�n�}
�}1�@�����m(�`���^���`���̈ږ��E�o�҂���Ɛl��)
�}2�@�k�đ嗤���C��
�}3�@���X�u���b�W����(�J�i�_)
�}4�@�n���C����
�}5�@�I�A�t���z�m�����s���S��(�n���C)
�}6�@��đ嗤
�}7�@���}�E�J���I�s�X�n(�y���[)
�}8�@�T���p�E���s�X�n(�u���W��)
�}9�@�u�G�m�X�A�C���X�s�X�n(�A���[���`��)
�}10�@�T���^�N���X���ӂ̈ڏZ�n(�{���r�A)
�}11�@�T���p�E���B�̎�v�S���ƈږ���v���Z�n(�u���W��)
�}12�@�_�o�I(�t�B���s��)
�}13�@�t�B���s���S�y
�}14�@��m�Q��
�}15�@�}���A�i����
�}16�@���^��
�}17�@�T�C�p����
�}18�@�e�j�A����
�}19�@�p���I����
�}20�@�p���I�{��(�o�x���_�I�u��)
�}21�@�R���[����
�}22�@�g���b�N����
�}23�@�|�i�y��
�}24�@���B
�}25�@���N
�}26�@��p
�}27�@���{�{�y
�}28�@��ʌ�����s����(���g�W)
�}29�@����{������(���g�W)
�}30�@���d�R�J��ږ����A�n�E |
�Q���A��Í��Ғ��u�ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� �ÓT�� �@Vol. 2�v���uRuon�Ёv���犧�s�����B�@
�@�@�@94p ; 30cm + CD1��
|
�H�H�l�ƌܐ����H�H�l�̔�r�@4
�H�H�l�ɂ��ā@6
�H�H�l�̓ǂݕ��@6
�O���̊����Ɨm�y���Ƃ̊W�@7
�����Ɣ��q�ɂ��ā@8
�����ɂ��ā@8
�H�H�l�̉������ɂ��ā@9
�w�g���A�����A�����L���@10
�h�J���ɂ��ā@10
�����̉����ɂ��ā@11
�����L���ɂ��ā@11
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@12
�e���q�ƌܐ����Ƃ̊W�@12
�L�@�ɂ��ā@�Ŕ����ɂ��ā@14
�w�ԍ��ɂ��ā@14
�|�W�V�����̈ړ��ɂ��ā@15
�㊪���
1�@�{�c���߁i�ނƂ����[�ȂԂ��j�@16
2�@�V���߁i������ɂʂ݂��Ԃ��j�@18 |
3�@��V�t�߁i����ނʂӂ�Ԃ��j�@20
4�@�Ԃ����͂ł��߁i���������ӂ�ł��[���Ԃ��j�@22
5�@�ɍ]�߁i���[�Ԃ��j�@25
6�@�^���n�V�͂����₤�߁i�܂ӂ����ʂӂ��[���傤�Ԃ��j�@28
7�@�{�ԕ��߁i�ނƂ��͂ȂӁ[�Ԃ��j�@32
8�@�x���͂ł��߁i�����ǂ������ӂ�ł��[���Ԃ��j�@37
9�@��c���߁i���ӂ��[�ȂԂ��j�@42
10�@�������߁i�Ԃ��j�@44
�������
11�@��c�߁i�����Ă�Ԃ��j�@46
12�@�����Ȑ߁i�����ȁ[�Ԃ��j�@54
13�@�߁i�����Ԃ��j�@60
14�@����ǂ�߁i����ǂ���Ԃ��j�@66
15�@�ԓc���߁i�������Ӂ[�Ԃ��j�@72
16�@�����߁i�����Ԃ��j�@76
17�@�Ő߁i���������Ԃ��j�@86
�����ÓT���y�ƔN�\�@93
���Ƃ����@94
�E |
�R���A�u�O�w��ꕶ 32�v���u�O�O�w�@��w���ꍑ���w��v���犧�s�����B
|
��c�H�����`�����ω�(�ւ�) �X�c��Y p.1�`5
�����̂Ƃ��Ắu�v�Ђ���v�� �����K�O p.6�`13
���k�l�i--���c���j�̑I�т��� ���؍� p.14�`27 |
����̍��J�`���̌����̕��@�ƌ����j ���R�� p.28�`32
�V�Í�����̉̐l�B(1) �ێR���� p.66�`60
�E |
�R���A���R���������ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (31) p.1�`18�@���ꌧ����ψ���v�Ɂu����̌Õ����ƃI�J���h�J���ނƂ̊֘A�ɂ���(�\��)�v�\����B
�R���A�����r�h, �|���͕ҁu�C�̗́v���u�p��w�|�o�Łv���犧�s�����B�@(���{�C�w�̐V���I ; 6)
�@�@����;�x�R�����ہE���{�C�����, ���{�C�w���i�@�\���
|
2005�N�x���{�C�w�V���|�W�E�� ��X�s�[�`/�A���N�T���_�[�E�g�D�J�[�����q
�p�l���f�B�X�J�b�V���� / ����i �ق��q
���ꂩ�猩�����{�C / ���䓿���Y, �g�Ɗԉi�g, ���c��� �q
���{�C�Ƃ͂ǂ̂悤�ȊC�� ���{�C�̐����n���w�ƒn�������w/�����B��
���{�̓~�G�̋C��Ɠ��{�C / �ؑ����� ��
�C�m�����Ɠ��{�C / �����r�h ��
�[�C���猩�����{�C / �c��ȎO ��
�g���s�J�����{�C�̍ŐV���Ύ��� / �V��a�F ��
�\���̊C �C�m�[�w���Œz�����S�ŖL���ȎЉ� / �������� ��
������̔R�������ޓ��{�C / �|���� ��
�C�m���x�����d�𗘗p�������{�C�̍Đ��� / �㌴�t�j ��
|
���{�C�̋��Ɛ����Ǝ����̐��Y / ���u ��
�G�߂̗��l�u�X�����C�J�v�Ɠ��{�C / ����� ��
�ߐ����{�C�̑哮���A���{�C�X���̌`���ƓW�J/�[��r�O��
�������x����C / �r�c�@�Y ��
�~�Ƌ���������{�C / �����N�v ��
���z�ɑz�� / ���P�M ��
�����E�z�̊C ���ꂩ��̌x�� / ���c��� ��
�q�����̐����j�ɂ݂�X���C�̘A�� / �c���� ��
�X�ѐ���C�I���l / ���R�d�� ��
凋C�O�̂��̐�� / �Óc���� ��
���{�C�w�̒� / �x�R�����ہE���{�C����� �� |
�R���A���ꌧ���璡�����ەҁu�{�ẪN�C�`���[�������v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@(���ꌧ������������, ��145�W)
|
��1�� �����̊T�v
��2�� �{�Ẩ̗w�g�N�C�`���[�m�K�C���E
��3�� ������
1.�����ǎs�̃N�C�`���[
�@�떓�̏\�ܖ�̃N�C�`���[ / �V���K��
�@�r�ԓ��~���[�N�d�c�̃N�C�`���[ / ���{
�@�����̔N���s���ɂ݂���N�C�`���[ / �㌴�F�O
�@�v��(�v�L����)�̃N�C�`���[ / ���@������
2.����Ӓ��̃N�C�`���[
�@����̃N�C�`���[ / �{���v�j
�@�F���̃N�C�`���[ / �{���v�j
�@�����Y�̃N�C�`���[ / �{���v�j
�@�����̃N�C�`���[ / �{�i��
�@�V��̃N�C�`���[ / �{�i�� |
3.����쑺�̃N�C�`���[
�@����쑺�{���̃N�C�`���[ / �V���K���E�㌴�F�O
�@�쌴�̃N�C�`���[ / ���n�R����
�@�V���̃N�C�`���[ / ���n�R����
4.�����n���̃N�C�`���[
�@�^�ߔe�̃N�C�`���[ / ���n�R����
5.���ɗǕ����̃N�C�`���[
�@���Ǖl�̃N�C�`���[ / �V���K��
�@�ɗǕ��E���n�̃N�C�`���[ / �茴�P�V
�@�ɗǕ������a�c�̉J�����N�C�`���[ / �㌴�F�O
6.���NJԑ��̃N�C�`���[
�@���NJԓ�(����E����)�̃N�C�`���[ / ���@������
��4�� �N�C�`���[�t�F�X�e�B�o�� / �v���c�W
��5�� �{�ẪN�C�`���[�W���� |
�R���A�u���{�E�����E����ɂ����閯�ԕ����𗬂̌����v���u�b���w�����������v���犧�s�����B
�@�@�@(�b���w�����������p�� ; 85)
|
�͂��߂Ɂ@����O�@3
���䓿���Ɩ����p�@�ғc���O�C�V�_�q�Y�C�ғc�o���q�@9
�����ɂ݂�_�c�M�Ɠ`���`�v�ē��V�@�{�R���Ƃ̊֘A���`����O�@39
�`�����_���[�n�̗w���߂���\���I�l�@�@�v���c�W�@57 |
�C�O���݂������Ɨ���
�@�@���@�`�A�w���푈��̏���߂����ā`�@�^�h���[���@71
���������Ɍ��镟�������@�Ӌ���@87
�E |
�R���A����|�\�j������ҁu����|�\�j���� ��9���v���u����|�\�j������v���犧�s�����B
�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004683965�@108p
|
������ �c�� ��Y
�����ÓT���y�̌n��-���y�c���Ɩ쑺�� �V�� �j
����ⶋȂ̃��[�c�Ɠ`���E�`�� ���� ��v
�����g�x�A���{�\�A�����Y�Ȃ̔�r �� �x��
��O�̑g�x�㉉�L�^�Ɠc����i ��� ���Y |
�����ҁu�썲�ێo��G���v�u�͎o�ȕ�e���v ������
��㉫��{���n��ɂ����鉫��ŋ��̊����ɂ���-���P���c�𒆐S�� ����
�u�����̔��w�v-����|�\���_ �^�ߔe���q
����\�ۂ̌���-�u�������ꂨ���Ȃ�v���J�ꂵ��2004�N �^�ߔe�q
�E |
�R���A ���F�M���u�܌��M�v�Ɖ���w�� : �܌��M�v������ŏo������l�X�v���u���F�M(����)�v���犧�s����B
�@�@�@�@���ʁF�܌����m�L�O�Ñ㌤�����I�v��9�S�@p72�`97 �@(���{�@��w�܌����m�L�O�Ñ㌤����)���
�p���t���b�g�o�C���_�[����
�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004520472
�R���A���F�M���u�l�ԕ����������N�� (1) p.40�`45�@���É��s����w�l�ԕ����������v�Ɂu�E�^�L�E�E�O�����E�O�����X--����̐M�����ɂ݂�u�����v
(���W �@���Ƌ��� ; �@���̌���I����)�v�\����B
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: <��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� 15�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004481683 �@�@
|
�u����u�搧����݂问������-����E
�@�@���Ƒ��悩�痮�������̎����ɂ��܂�v�̊J�Âɂ��� �啽 ��
�� �����̋ߐ����T��-�l�Êw�ƌ`���l�ފw����̃A�v���[�` ��� ����
�O �j���C�J�i�C�̉��{-�Y�Y�悤�ǂꂩ��݂��p�c�����Ƒ��z�q�v�z ���� �i |
Le Royaume de Ryukyu et la relation
�@�@��internationale en Asie-l'e poque de grand
�@�@��commerce de Ryukyu-
�@Naoki Imabayashi |
�R���A�؉����q���u�n�敶������ 21 p.1-8�@�~���w�@��w�n�敶���������v�Ɂu�������ꂪ�̂��������́v�\����B�@
�@�@�@�@404 Not Found�@�@�d�v
�R���A�u�q��21����r ����������̐��E�v���u�n�敶������ 21 p.1-2�@�~���w�@��w�n�敶���������v�Ɍf�ڂ����B
�@�@�@�@404 Not Found�@�d�v
�@�@�@�@��L�Q�_���i�������ꂪ�̂��������́E��������̐��E�j�ɂ��ẮA���ɓ��e�̊m�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�X�E�Q�Q�@�ۍ�@�d�v
�@�@�@�@����������F1908�N4��28�� - 2005�N1��11���@(���N�@96��)
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v14�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
���M�ѐA���@�ۂ̖a�ѕ��@�Ƃ��̏��i�W�J ���� �S�� p.1�`13
���|�ƁE�͈䊰���Y���֖�m�[�g�̒�������(��3��) �쌴 �N�F p.15�`40
�V�K�d�q�Đ��F����(1) �ۓc �� p.41�`46
�������̖��؋� ��2�W��2�k�� �y���l ���{ �M�v p.47�`66
�{�ǒ���̎t�͒N��?--�ߑ㉫��ɂ����鉹�y�����̌n���Ƃ��̔w�i �O�� �킩�� p.67�`95
�n�앑�x�u�������̏��v�̌���--�ʏ钩�O5�ԑg�x�u���S�����v��� ���g �Ύ} p.111�`124
�����p�ɂ�����̎e�E�̂����--�X���ł̊����𒆐S�� ���� ���q p.125�`136
�u���S�����v�ƕ������q--�ᏼ�Ɓu�O���v �g�� ���Y p.189�`205
�q�����r |
�T���A�O���킩�Ȃ����{���y�w��ҁu���y�w = Journal of the Musicological Society of Japan 51(3) p.201�`203�v�Ɂu�������\D "�r�O�Ɠ���"�ɂ݂�{�ǒ���̉̋ȗl������--���a�����̌R���̐����Ƌ��y����̂͂��܂Łk��
���^�����l (���{���y�w���56��S������ ; �������\�v�|)�v�\����B
�U���A�{�ǒ���f�搻�쐄�i�ψ���ҁu�f��u����ǂ��̉ԁv���b�Z�[�W�W : �{�ǒ���a120���N ���60���N�L�O��i : �ɂ��ۂ�搶�̉̂͂��܂ł��v���u�{�ǒ���f�搻�쐄�i�ψ���v���犧�s�����B�@�@�@89p�@�����F��㊌����}���فF1008909952
�U���A�u�Ñ㕶�� = Cultura antiqua 58(1) (�ʍ� 564) �v���u�Ñ�w����v���犧�s�����B�@�d�v�@
�@�@�@�����F�L�������}���فF01300631528
|
���\�ۂƊ��q���������W�@�@���� �q�L p.1�`15
�ڐG�ɂ�镶���ϗe�̌^���w�I���f���̍쐬�@�|�� �r�� p.16�`41
�퍑鰍��ɂ�����u���v���̐���--
�@�@��鰍�����̌����𒆐S�Ƃ��ā@���c �� p.42�`55
�ÓT���A�e�i�C�ɂ����鏈�Y�ƍߐl�̈�̏���
�@�@��--�o���g�����ւ̍ߐl�����ɂ��ā@�V�� �M�O p.56�`70
�w���{���I�x�ɂ�����w�n�c�x�Ǝ��@�@�|�{ �W p.71�`85
|
�Ñ�W���ɂ����镶���̓`�d�ƓW�J--
�@�@����錧���Ύs������Տo�y���������̌����@�� ���b p.86�`102
�Ñ�k���H�̗��ߓI���J�@�@�V�� ���� p.103�`116
��R���Ɩ퐶����������--�j�O�w�Ɓw�L�x�w�I�x�_�b�@���c �� p.117�`128
�퐶������--���{���ɂ�����j�O�����@��R ��,���c �� �� p.129�`139
�w�j �������ꂪ�̂��������́@�@�؉� ���q p.140�`145�@�d�v
���] ��،��Y���w�l�Êw�͂ǂ�Ȋw�₩�x�@�k�� �F�� p.146�`148 |
�V���A�|���i�a, ���R�� �ҋȁu���Ȃ���ǁ[/����̉� : �M�^�[�Ƒt�v���u �I���L���E�p�u���V���v���犧�s�����B�@85p
|
�ԓc�a��(����������ǂ���)���ꖯ�w�@4
�m�ԕz�g�����^�쎌�E���v���P�E�^��ȁ@7
������(�����ǂ�)�����^�|�x�����w�@10
������(�����݂��Ԃ�)���{���^�쎌�E�{�ǒ���^��ȁ@12
�ނ�{�Ó����w�@14
���ォ��䂵���ꖯ�w�@16
����(���Ȃ�)���Ör���^�쎌�E�Ɖ��ь��^��ȁ@19
�Ԃʕ���(�����܂�)���ꖯ�w�@22
�������[����܁[�܁[���������ꖯ�w�@24
�\��̏t�{�|�T���^��쎌�E���ꖯ�w�@26
����(�����)�T�o�N�C���ꖯ�w�@28
���ꖯ�w�@30
����ǂ��̉ԋ{�ǒ���^����@32
|
�Ă����̉ԉ��ꖯ�w�@34
���V�̐��V��a���^�쎌�E��n�����^��ȁ@36
ꡂ����ꔎ�^�쎌�E��ȁ@40
���_(���т���)�`�V�̎q��S�`�ÎӔ����q�^�쎌�E������Ɓ^��ȁ@44
���S�{��a�j�^�쎌�E��ȁ@54
�_�l�̕�łł������{��a�j�^�쎌�E��ȁ@58
�ԁ`���ׂĂ̐l�̐S�ɉԂ��`��[���g�^�쎌�E��ȁ@62
�������[���ؑ����B�^�쎌�E�~���M�}�����^��ȁ@66
��(�Ȃ�)���������X�R�ǎq�^�쎌�EBEGIN�^��ȁ@69
�Ў�ɎO��(����)���{�u�Ό��E�A���x���g��ԁ^�쎌�E�A���x���g��ԁ^��ȁ@74
�C�����C����l�哇�ۍ��^�쎌�E��Éh���^��ȁ@78
���l(���܂�)�ʕ�BEGIN�^�쎌�E��ȁ@82
�E |
�V���A�吳����q�ǂ��G�C�T�[�c�ҁu�G�C�T�[�̘b : ���ǂ������ցv���u�i���j�吳����q�ǂ��G�C�T�[�c
�v���犧�s�����B�@�@�@�����F���s���}����
�V���A��Í� �Ғ��u�ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� �ÓT�� Vol 3�v���uRuon�Ёv���犧�s�����B�@ 2006�E�V
�@�@�@108p ; 30cm + CD1�� �@�@�����F��㊌����}���فF1004580914
|
�H�H�l�ƌܐ����H�H�l�̔�r�@4
�H�H�l�ɂ��ā@6
�H�H�l�̓ǂݕ��@6
�O���̊����Ɨm�y���Ƃ̊W�@7
�����Ɣ��q�ɂ��ā@8
�����ɂ��ā@8
�H�H�l�̉������ɂ��ā@9
�w�g���A�����A�����L���@10
�h�J���ɂ��ā@10
�����̉����ɂ��ā@11
�����L���ɂ��ā@11
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@12
�e���q�ƌܐ����Ƃ̊W�@12
�L�@�ɂ��ā@�Ŕ����ɂ��ā@14
�w�ԍ��ɂ��ā@14 |
�|�W�V�����̈ړ��ɂ��ā@15
�������
1�@�̒��߁i���͂т�Ԃ��j�@16
2�@�������Ȑ߁i�Ȃ������ȂԂ��j�@27
3�@�i�Ǖ��߁i����ԂԂ��j�@39
4�@���߁i�Ȃ��Ԃ��j�@42
5�@�̉Î�v�߁i�����ł����Ԃ��j�@60
6�@�\�����߁i���イ�����͂��Ԃ��j�@62
7�@���א߁i�ӂ��������܂Ԃ��j�@72
8�@�����߁i�����Ԃ��j�@76
9�@�V��߁i���܂��[�Ԃ��j�@78
10�@�ɏW����c�߁i������͂������Ă�Ԃ��j�@89
11�@���߁i��Ȃ��Ԃ��j�@92
�����ÓT���y�ƔN�\�@107
���Ƃ����@108 |
�V���A�{������.���ߔe�S�l.���_�G��.�{�ǐM�ڕҒ��u����ʕ�炵�Ƃ��̘b�v���u����ꕁ�y���c��v���犧�s�����B�@
|
�̘b : ���Ƃ���
�L�W���i�[
���܂�N
�K�[�i�[�X
���ʗz�ԁ[��
�\��x�Ƃ��L
���[�C�[�e��
�A�J�i�[
�ǂ�ǂ�
������ʈ�O��
���т��
����l�ʌ䌳�c
�����ʐ��E��Y : ���
������
���얡���
���A�m���
���A���
�ʗ� |
���䉮�����
������
�֏���
��炵(����) : �l����[
�������[
�j��
গ��D�����ʗR��
�їV�тƂ�����
�a����
�̂ʏ��N�ʈ��
�̂ʏ����ʈ��
�H��
�Ɖ�
����
����
���w�Ƃ��a�w�Ƃ��w��
�i��
��� |
�������ʌ�j�V
��\�l��
��b : ����̈��A��
�a���E������
���Օ�
��������
�f�Õ�
����
�z�e������
�����ʉ̂��肭�� : �����Ƃ����y��
�X���e���Ƃ��m�O�э�
�m�O�э��Ƃ����y
���̂ʕ��
���y�Ƌ��P
��̂Ƃ������
���̂ʏo��
�̐l���
�E |
�X���A��Í��Ғ��u�ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� �ÓT�� Vol 4�v���u Ruon�Ёv���犧�s�����B�@ 2006�E�X
�@�@�@�@99p �@ CD1�� �@�����F��㊌����}���فF1004580948
|
�H�H�l�ƌܐ����H�H�l�̔�r�@4
�H�H�l�ɂ��ā@6
�H�H�l�̓ǂݕ��@6
�O���̊����Ɨm�y���Ƃ̊W�@7
�����Ɣ��q�ɂ��ā@8
�����ɂ��ā@8
�H�H�l�̉������ɂ��ā@9
�w�g���A�����A�����L���@10
�h�J���ɂ��ā@10
�����̉����ɂ��ā@11
�����L���ɂ��ā@11
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@12
�e���q�ƌܐ����Ƃ̊W�@12
�L�@�ɂ��ā@�Ŕ����ɂ��ā@14
�w�ԍ��ɂ��ā@14
�|�W�V�����̈ړ��ɂ��ā@15
�������
1�@��܂Â�߁i���ɂ܂���Ԃ��j�@16
2�@�����߁i������[�Ԃ��j�@21
3�@�ʐ��߁i�����݂Â��Ԃ��j�@24
4�@���ɕ����߁i�Ȃ����Ђ�[�Ԃ��j�@30 |
5�@�{�ɕ����߁i�ނƂ����Ђ�[�Ԃ��j�@36
6�@�䉮��߁i�Ђ₶�傤�Ԃ��j�@42
7�@���]�߁i������[�Ԃ��j�@44
8�@�ɖ�g�߁i�ʂӂ�Ԃ��j�@49
9�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j�@54
10�@�q���߁i���������[�Ԃ��j�@59
11�@�����߁i���܂Ӂ[�Ԃ��j�@62
12�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j�@71
�������
13�@�����߁i�ӂ����Ԃ��j�@74
14�@�q���߁i����ނ���[�Ԃ��j�@76
15�@�U�R�߁i�����܂Ԃ��j�@78
16�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j�@81
17�@���V���C�i�E�߁i�䂵�Ⴂ�́[�Ԃ��j�@86
18�@�q���߁i���������[�Ԃ��j�@88
19�@���ڐ߁i�������Ⴍ�Ԃ��j�@92
20�@�g���ڐ߁i�����������Ⴍ�Ԃ��j�@94
21�@�S���߁i�ЂႭ�ȂԂ��j�@96
�����ÓT���y�ƔN�\�@98
���Ƃ����@99
�E |
�P�O���A��Í��Ғ��u�ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� �ÓT�� v.5�v���uRuon�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@135p�@ CD1�� �@�����F��㊌����}���فF�L�ڂȂ��@�H
|
�H�H�l�ƌܐ����H�H�l�̔�r�@4
�H�H�l�ɂ��ā@6
�H�H�l�̓ǂݕ��@6
�O���̊����Ɨm�y���Ƃ̊W�@7
�����Ɣ��q�ɂ��ā@8
�����ɂ��ā@8
�H�H�l�̉������ɂ��ā@9
�w�g���A�����A�����L���@10
�h�J���ɂ��ā@10
�����̉����ɂ��ā@11
�����L���ɂ��ā@11
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@12
�e���q�ƌܐ����Ƃ̊W�@12
�L�@�ɂ��ā@�Ŕ����ɂ��ā@14
�w�ԍ��ɂ��ā@14
�|�W�V�����̈ړ��ɂ��ā@15
�������
1�@�����߁i����Ƃ���[�Ԃ��j�@16
2�@�Ì��V�Y�߁i����́[��Ԃ��j�@19
3�@���c���߁i�₳�ȂԂ��j�@22
4�@�T�A�T�A�߁i���[���[�Ԃ��j�@24
5�@�O�V�l�߁i�߁[�ʂ͂܂Ԃ��j�Z���@�@26
6�@�O�V�l�߁i�߁[�ʂ͂܂Ԃ��j�����@�@27
7�@�⌴�����i�����͂炭�ǂ����j�@28
8�@�^�ߌ��߁i��Ȃ�Ԃ��j�@30
9�@���_�߁i�������ނԂ��j�@32
10�@�����߁i�������܂Ԃ��j�@34
11�@�ɓ����߁i�����݂Ԃ��j�@36
12�@�V�q���߁i�������т���ނ���Ԃ��j�@38
13�@���������i������[���ǂ����j�@39
14�@���]�߁i������[�Ԃ��j�@40
15�@���]�߁i������[�Ԃ��j�@44
16�@�l�璹�߁i�͂܂��ǂ���Ԃ��j�@46
17�@�^�m���]�߁i���ʂނ��Ԃ��j�@48
18�@�V���E���K�i�C�߁i����ˁ[�Ԃ��j�@50
19�@�V���E���K�i�C�߁i����ˁ[�Ԃ��j�g�o�@52
20�@�n�C�����G�߁i�͂��䂦�[�Ԃ��j�@54
21�@��J�߁i�䂠�݂Ԃ��j�@55
22�@�����߁i�Ȃ��ǂ��܂��Ԃ��j�@57
23�@�^�E�K�l�߁i�Ɓ[���ɂԂ��j�@58 |
24�@�����߁i�����肴�Ƃ��Ԃ��j�@60
25�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j���o�@62
26�@�q���߁i���������[�Ԃ��j���o�@66
27�@�����߁i�ׂ͂邭��[�Ԃ��j�@69
28�@�����W�����߁i�ނ��Ԃ��j�@70
29�@�r���^�E�߁i������Ɓ[�Ԃ��j�@72
30�@�v�ăn���^�O�߁i���݂͂߁[�Ԃ��j�@74
31�@��Y�߁i���ӂ�Ԃ��j�@77
32�@�œ��߁i�����܁[�݂Ԃ��j�@78
33�@�F�n���߁i�����ǂ��܂��Ԃ��j�@80
34�@�n�����O���B�j���߁i�͂�肮���[�ɂ�Ԃ��j�@82
35�@�����߁i����ׂ͂�Ԃ��j�@84
36�@�Ì��߁i������Ԃ��j�@86
37�@���g�߁i���ӂ�Ԃ��j�@89
38�@�o�ߐ߁i��ȂԂ��j�@90
39�@�Y�Y�߁i�����Ԃ��j�@92
40�@�V�z���C�߁i����[�炢�Ԃ��j�@94
41�@�ɏW�V�ؐ߁i������ʂ��Ԃ��j�@96
42�@���A�߁i�������Ԃ��j�@98
43�@�z�N�߁i�ʂʂ��炵�Ԃ��j�@100
44�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j�@102
45�@��Y�z�n�߁i���ӂ炭�����Ԃ��j�@104
46�@���{�߁i�܂��ނƂ��Ԃ��j�@107
47�@�W�c�\�E�߁i�������[�Ԃ��j�@110
48�@�ΔV�����߁i�����ʂ݂�[�ԂԂ��j�@112
49�@���V�Ԑ߁i����ʂȂԂ��j�@114
50�@�V���E���K�i�C�߁i����ˁ[�Ԃ��j�@117
51�@�{��Y�߁i�ނƂ����ӂ�Ԃ��j�@118
52�@�V�z���A�߁i����[��[�Ԃ��j�@120
53�@�v�Ĉ��Ð߁i���݂��[���Ԃ��j�@121
�������
54�@���N���߁i��ȂƂ������Ԃ��j�@122
55�@�_�Ԑ߁i�����ʂ͂ȂԂ��j�@124
56�@���I�v�߁i�����ɂ��Ԃ��j�@126
57�@�g���I�v�߁i���������ɂ��Ԃ��j�@128
58�@���m���v�߁i����ɂ₭�Ԃ��j�@130
59�@�g���m���v�߁i��������ɂ₭�Ԃ��j�@132
�����ÓT���y�ƔN�\�@134
���Ƃ����@135
�E |
�P�O���A�O���킩�Ȃ��u�����w�l���w���I�v = Journal of Humanities and Social Sciences 8 p.85-89�@�����w�l���w���v�Ɂu���m���y�̗��j�ψ琬�Ɗӏ܋���Ƃ̐ړ_�v�\����B�@�@�@�iIRDB�j
�P�O���A�����V��Еҁu�{��\�P�l�ԍ���F��L�O�j����� ���|�@�i�����p���t���b�g�j�v���u�����V��Ёv���犧�s�����B
�@�@�@�@�����F����18�N10��10��(��) ���F����R���x���V�����Z���^�[���
�@�@�@�@��ÁF�����V��ЁE����R���x���V�����Z���^�[ ���ÁF���ꌧ�E���ꌧ����ψ���E�`���g�x�ۑ���E����|�\�A��
�P�O���A�{��\�P���u�l�ԍ���v�F��L�O�j�����s�ψ���ҁu�{��\�P�u�l�ԍ���v�F��L�O�j���i�j���p���t���b�g�j�v���u�{��\�P���u�l�ԍ���v�F��L�O�j�����s�ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@�����F����18�N10��17��(��) ���F���ꂩ��䂵�A�[�o�����]�[�g�i�n(6�K�j���C�J�i�C�̊�)
�@�@�@�@1���@�@�����F��㊌����}���فF1004680755
�P�P���A�␣��, ������Y, ���Q�v�q�ҁu��E���̓`���E�̘b�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B
�@�@�@�i�����̓`����������� �R�j�@ 170p �@�����F���ꌧ���}���فF1004449425
|
�}��
��E���̗��j�ƕ�炵�@1
��E���̕��i�@3
��E���̃V�}�W�}�@5
�V�}�W�}�̕�炵�@8
��E���̗��j�@11
��E���̓`���E�̘b�@17
�`���֘A�n�n�}�@18
1�@�y���琶�܂ꂽ�l�ԁ@19
2�@��E���̓����ā@23
2�@(��)�@23
2�@(��)�@23
3�@��v�Ëv�i�Ă��Â��j�̃V�}���ā@27
3�@(��)�@27
3�@(��)�@29
4�@��v�i�������j�̃V�}���ā@33
4�@(��)�@33
4�@(��)�@34
5�@����i�Ȃ��݂ˁj�̃V�}���ā@40
6�@���˂̐_�@43
6�@(��)�@43
6�@(��)�@44
7�@����@48
8�@�V�l���[�@51
8�@(��)�@���[�̗R���@51
8�@(��)�@�V���̕��@52 |
9�@���o�����̗R���@56
10�@���Ɠ`���@59
10�@(��)�@��ҁi����܂��j�̐�@59
10�@(��)�@���ƐX�i�ւ�������j�@59
10�@(�O)�@�}�i���܂ǁj�̗R���@60
10�@(�l)�@����i�ȂȂ��傤�j�̋S���@61
11�@�Y���̖V��@65
11�@(��)�@�V���R�E�V�@65
11�@(��)�@�O�c���i�܂��������j�@66
12�@�r���̖S��@69
13�@�O�@��t�̈ꎚ��Όo�@72
14�@�Ó݁i���ǂ�j�̒����̐�@74
15�@�̓`���@77
15�@(��)�@���l�̑�Ə�@77
15�@(��)�@�v�w�@77
15�@(�O)�@�鋃���@78
16�@���[�i���킶�傤�͂ȁj�@82
17�@�r�؉��ƎR�c���̗͔�ׁ@84
18�@�������l�@87
19�@�S���i���ɂ��܁j�@90
20�@�܂r�i���߁j�̗R���@92
21�@���ۓ��@95
21�@(��)�@�}�b�^�t�@�ۓ��@95
21�@(��)�@�����̗R���@96
22�@�p�q�b�@101
22�@(��)�@�p�q�̍��i�Ƃǂ낫�j�@101 |
22�@(��)�@�p�q�̖��U�@102
22�@(�O)�@�p�q�̔������@105
23�@�ԏn�c�i�͂Ȃ��݂��j�@109
24�@�Ҋ��̗R���@112
25�@�l���E�o�@114
26�@���̐�����̎g�ҁ@117
27�@�����̖S��@121
28�@�S��Ɛl�Ԃ̋Ɣ�ׁ@125
28�@(��)�@�S��Ƒ��o�@125
28�@(��)�@�S��Ɖ̊|���@126
29�@�S��ɗ��܂ꂽ�b�@129
29�@(��)�@�S��̎؋��Ñ��@129
29�@(��)�@�S��̑��蕨�@130
30�@�͓��݁i�J�c�p���[�`�B�j�̗R���@132
31�@�}�X�J�i�ƃ��`���J�i�@134
31�@(��)�@�q�K���̃}�X�J�i�@134
31�@(��)�@�g�n���E���`���J�i�@136
32�@���ۓ��i�Ζ�j�@141
33�@�V�l���[�i��j�@144
34�@�p�q�i�܂�܁j�����i�Ζ�j�@151
35�@�����ҁi�Ζ�j�@158
36�@�^��ߘb�i�Ζ�j�@163
���Ƃ����@169
�}��@�Бq�P�j
�E
�E
|
�P�P���A��c�������m�_���u�G�C�T�[�ɂ݂�I�L�i���������̃A�C�f���e�B�e�B : �n���C����n�ږ��ɂ�����u�Ȃ���v�̑n�o�v���@���s��w�v���\����B�@�iIRDB�j
�P�P���A��Í��Ғ��u�ܐ����H�H�l(���[): : �O���ƏK�� �ÓT�� v.6�v���uRuon�Ёv���犧�s�����B
�@�@�@�@�@140p�@CD1�� �@ �����F���ꌧ���}���فF1004574925
|
�H�H�l�ƌܐ����H�H�l�̔�r�@4
�H�H�l�ɂ��ā@6
�H�H�l�̓ǂݕ��@6
�O���̊����Ɨm�y���Ƃ̊W�@7
�����Ɣ��q�ɂ��ā@8
�����ɂ��ā@8
�H�H�l�̉������ɂ��ā@9
�w�g���A�����A�����L���@10
�h�J���ɂ��ā@10
�����̉����ɂ��ā@11
�����L���ɂ��ā@11
�O���̑t�@�L���ɂ��ā@12
�e���q�ƌܐ����Ƃ̊W�@12
�L�@�ɂ��ā@�Ŕ����ɂ��ā@14
�w�ԍ��ɂ��ā@14
�|�W�V�����̈ړ��ɂ��ā@15
�����𐳊m�ɉ������悤�@137
�������
1�@�i�J���^�߁i�Ȃ��炽�Ԃ��j�@16
2�@���h�߁i�䂴�����Ԃ��j�@18
3�@�]���߁i�����Ԃ��j�@20
4�@�����߁i�����͂Ȃ�Ԃ��j�@22
5�@�V���E���K�i�C�߁i����ˁ[�Ԃ��j�@24
6�@���x�߁i�����ǂ���Ԃ��j�@26
7�@�ؖȉԐ߁i�ނ݂�ȂԂ��j�@27
8�@�������i�͂����ǂ����j�@29
9�@�����i�������j�i���ǂ����ʂԂ����ǂ����j�@30
10�@�g�����i�������ǂ����j�@33
11�@�߁i���j�i�l�G�j�����i���ǂ����j�@34
12�@�������i�݂��킭�ǂ����j�@36
13�@�E�t���V�����߁i���ӂ��Ԃ��j�@39
14�@�T�C���\���߁i����Ԃ��j�@42
15�@�Ɍv���߁i�����͂Ȃ�Ԃ��j�@44
16�@���˃J�E�X�߁i�܂����[�����Ԃ��j�@46
17�@�{��N�n�f�T�߁i�݂�[������������[�ł��[���Ԃ��j�@49
18�@�����߁i�Ȃ����Ƃ��Ԃ��j�@53
19�@��Ԑ߁i�Ȃ��Ԃ��j�@56
20�@�V�����_�E�߁i�����ǁ[�Ԃ��j�@58
21�@�����R�m�V�߁i��肭�ʂ��Ԃ��j�@60 |
22�@�̓c���߁i�����[�ȂԂ��j�@62
23�@�\���J���߁i���肩��Ԃ��j�@65
24�@�����߁i���邵�܂Ԃ��j�@66
25�@�T�b�߁i���݂��[�Ԃ��j�@68
26�@����c�߁i����[�����Ă�Ԃ��j�@70
27�@�^�V�O���c�߁i��[���߁[�Ԃ��j�@72
28�@�J���L���C�߁i���Ⴂ�Ԃ��j�@76
29�@�약�߁i���т�Ԃ��j�@78
30�@�������߁i�Ȃ�����Ԃ��j�@79
31�@�Ђ悭�߁i�Ԃ��j�@82
32�@��R�߁i������܂Ԃ��j�@84
33�@�T�b�N�߁i�������Ԃ��j�@85
34�@�\���o���߁i�����[�Ԃ��j�@86
35�@�q��߁i���ނ��Ԃ��j�@88
36�@�ԓc�ԕ��߁i�������͂ȂӁ[�Ԃ��j�@89
37�@���l�߁i���܂Ԃ��j�@92
38�@���c���N�n�f�T�߁i�₫�Ȃ���[�ł��[���Ԃ��j�@94
39�@�V�V���E���K�i�C�߁i�������т���ˁ[�Ԃ��j�@96
40�@�V���ݐ߁i�������т���ǂ���Ԃ��j�@98
41�@���K�V��߁i���܂��肠�܂��[�Ԃ��j�@100
42�@���Ԑ߁i�͂Ƃ��܂Ԃ��j�@104
43�@�T�C���E�߁i������[�Ԃ��j�@106
44�@�ߋT�߁i���邩�݂Ԃ��j�@108
45�@�I�����J���߁i���݂₩��[�Ԃ��j�@110
46�@�O���c�߁i�߁[�Ԃ��j�@112
47�@�����߁i�Ȃ��Ӂ[�Ԃ��j���o�@114
48�@�q���߁i���������[�Ԃ��j�{���q�@118
49�@���Ӑ߁i�݂邭�Ԃ��j�@121
50�@�N���N�߁i���邭�Ԃ��j�@122
51�@�q���߁i���������[�Ԃ��j��g���q�@124
52�@�x�^�E�K�l�߁i�����ǂ����Ɓ[���ɂԂ��j�@126
53�@�����߁i���Ȃނ��Ԃ��j�@129
54�@�������i��������ǂ����j�Z���@�@130
55�@�������i��������ǂ����j�����@�@131
56�@�����e�N�߁i���Ă����Ԃ��j�Z���@�@134
57�@�����e�N�߁i���Ă����Ԃ��j�����@�@135
58�@�m���t���߁i�̂�ӂ�Ԃ��j�����@�@138
59�@�m���t���߁i�̂�ӂ�Ԃ��j�Z���@�@139
���Ƃ����@140 |
�P�Q���A�ʏ鐷�`�L�O���ҏW�ψ���ҁu�O�\�O�N���L�O�@�ʏ鐷�` : �]�`�v���u�ʏ闬�ʐ��v���犧�s�����B
|
�nj��E�ʏ鐷�` / �D�z�`��
�ʏ鐷�`�Ƃ��̉ƌn / ��ԗ�i
�ʏ鐷�`�搶���c��������`���|�\ / �X�۞Ď��Y
���`�Ɠ������z�����l�X / �c�Ԉ�N
�Ԃ͍g �l�͂����� / ����u�N��
���`�搶�ɔ|��ꂽ���̐l�� / �V�ې��P
�x��̐_�l / �Ɗ�[����
�t�E���`�搶�̎v���o / �r���V�Y
|
�S��㇗��E���`�Ɛ����������� / ��R���q
�i�ɓ����Ċi���o��Ƃ������� / ��闧�T
�ԁE�ʏ�ɉh������ / �O�����Y
�ʏ鐷�`�̑n��ɂ��� / �K��ǏG
�ʏ鐷�`�ƕ��̕� / ����Ԍ���
�ߌËߐ��|�\�ҝ��� / �r�{����
�ʏ鐷�`�̌|���ƌ|�� / ���{
�E |
�P�Q���A���c�W, �R���ӈ�ҁu���M�E�ӑm�̓`�����E ��3�W�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B�@�@
2006�E�P�Q
|
����E�{�ÁE�u���ÎR��x�v���߂�����@�R���ӈ�@5
�v�����̃C�U�C�z�[�̊�w�[���{�̐_�̓��̈�ʐ_���̒a���[�@���R��29
�{�n����u�����E�x�m�R�̖{�n�v�Ɗ؍��́u�����{���v�@���^��42
�ޏ��Ɩ����u�@�쓇�G��@68
�O���ƏC���[��t���D���s�̓V���O���̎��Ⴉ��[�@��ؐ���86
�M�B�ѓc�ڏ��̑��Ձ@��؏��p136 |
�w������{�n�x�w���B��{��{�n�x�̌�����(��)�@���c�W173
�w�Y�ē����l��{�n�x�@���E�|���@�������j�@204
�����́w�Î��ځx�@���Ɩ|���@��؍F�f�@246
���ǔ˂̖Ӗڂ̌n���w�萬�������x����̎����@�����h�g280
���Ƃ���368
�E |
���A���̔N�A�������V���u�L���X�g�����������������N�� = Christianity and culture annual : �����Ə@�� (40) p.3�`8 �@�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v�Ɂu�{��w�@�n����O�Z���N�L�O����
������w���d�R�|�\����������Ɋāv�\����B
���A���̔N�A�{�����W���u���k�w. [��2��] (9) p.124�`135���k�|�p�H�ȑ�w���k���������Z���^�[�v�Ɂu����ɂ�����ƒ{�̋��]--�q�V�}�N�T���V�V��r���߂�����
(���W �ƒ{�ƃy�b�g)�v�\����B
���A���̔N�A��c���q�������ψ���ҁu��㉹�y��w�����I�v = Bulletin of Osaka College of Music (45) p.13�`32�v�Ɂu�w�[�V(���q)�̗�--����G�C�T�[���ۘ��̏ꍇ�v�\����B
���A���̔N�A���ь��],���эK�j�����y��������ҁu���y������ (�ʍ� 23) p.29�`46�v�Ɂu�̎��E�y������ ���ꌧ���A�m�����~�̎�x��G�C�T�[�v�\����B
���A���̔N�A���J��ρ@�n�v�n���@�㓡�q�Ɓ@��،h�q���u���{�n���w��\�v�|�W 2006s(0) p.28-28�v�Ɂu���������ɂ�����吳���Ə��a�E�������̓y�n���p�ω��v�\����B�@�@J-STAGE |
| 2007 |
19 |
�E |
�Q���A��������, ��������ҏW�u����t�B�[���h�E���T�[�` 1,2�v���u�H�c��w���當���w���v���犧�s�����B
�@�@(���{�E�A�W�A�����������K��, 2006�N�x-2007�N�x)
|
1: ���ꕶ���̓`���Ƒn��
�u�́[�܂イ�v���猩���鉫�� / ���R�R��
�ߔe��j�҂��߂���l�X�̈ӎ��ƒm�� / ������
����̌��[�ƌ�����I�� / ���{�G
����̓`���y��O���Ɋւ���l�X�̈ӎ� / �H�����P
�ǒJ���ɂ�����ǒJ�R�ԐD�̕ϑJ / �a�J���
�����K���X�̏��� / �c����
�u�����Ȃ�V���c�v����u����䂵�E�F�A�v�܂� :
�@�@������̊ό��Y�Ƃ܂��� / �H�R�a��
����̐��������Ɠs�s����
�h���s��̖����� / �����L��
�������X�̌��� / �z�܂�
�ߔe�̊� / �哹�v��
�f�C�S�z�e������ : �z�e������݂���n�̊X�R�U/�����܂䂫
����̓s�s�`�� : A�A�C�X�̌�肩�� / �{�c��
����̃^�N�V�[���� / �r�䐳��
���㉫��̏Z��� / �˓��ˎq
��ƒ납�猩�鉫��̐������� / ��������
����̂��ƂƎЉ�
�����̖��O�̕ϑJ���猩��{�y�Ɖ���̈ӎ���/��������
�ߔe�����̎w�����u�O���[�v�̈Ӗ��E�p�@ / �֓����
�W�����s�̎��ԂƐl�X�̈ӎ� : �����D�ɒ��ڂ���/���c����q
�f��w�i�r�B�̗��x�Ɍ��鉫�ꌾ�ꎖ��/�˓��ˎq
�̎����猩�鉫�ꉹ�y�̕ϗe / �H�����P
����t�B�[���h�E���T�[�`�@ |
�n�} / ��������
����̌�ʋ@�� / �r�䐳��
����̔N���s�� / ���{�G, ��������
����̐H / ��������
���ꖯ���p��W / �˓��ˎq, ��������
�u������܂�t�@�~���[�v(�w�����V��x�A�ڃ}���K) / �����R�R����
����ʐ^�W / ���{�G, ��������, ��������
2:1.����̎Љ�E�M�E�`��
�N��猩�鉫��Љ� / �������
�͍����猩�鉫��Љ� / ������
���^�Ǝ� / ���X�؉��q
�l��Ó��ɂ�����_�b�̐��E / �����I
�}�_�����ƃ}�J���� : �`���̍��� / �˓c�L��T
�L�W���i�[�`���Ɍ���`���̏� / �ۍ�^��
�ʐ^�Ō��鎅�� / �R�{�C��
2.����́u�`���v�ƌ���
���㉫��̕Ĕ_�Ǝ��� / ���G��
�`���������V�����[�i�[�r / �����R��
�E�`�i�[�ٓ� / ���엢��
�ČR��̂ƃR�U�̔��W :
�@�@�������̕�炵�Ԃ肩�猩���R�U�̊X / ���c������
�u�`���v������̐��E / �R�c�]��
���W�I����u�����j���[�X�v���猩�鉫����� / �ēc�^��
�u�����v���猩�鍆�߂��Ƃ̍L���� :
�@�@�����ƊJ�n�E�I���𒆐S�Ƃ���/ �����B�� |
�Q���A�d�{ ���ꂪ�哌������w���{���w��ҁu���{���w���� (46) p.55�`66�v�Ɂu�w���|�����x�_�v�\����B �iIRDB�j
�R���A�H���q�\�ҁu���Ɛ��E��Y : �i�ρE���E��炵���߂����āv���u���w�فv���犧�s�����B�@�@
|
���E��Y�̊�@�Ɩ��� / �H���q�\ ��
���Ǝ��R��Y ���j�I���R�Ƃ��Ă̒m���̊C / �F�m�`�a ��
���_�R�n�̐l�Ɛ� / �q�c�� ��
�A���̕�ɁE���v�� / ���{�M�a ��
���ƕ�����Y ���싽�E
�@�@���܉ӎR�̍�������W���i�ς̐����ƕ�炵 / ���R���� ��
���������ǂ���ΐ_�Ђ̐_ / �����W�j ��
�F��̕��� / �ڍ�Θa ��
|
����߂��鐅 / �g�Ɗԉi�g ��
���ƃA�W�A�̐��E��Y ���E�n�̐����Ɛ�
�@�@��-�_��ȁu�O�]�����v�n�� / �������� ��
�R���f�B���G���ɂ�����I�c�i�ς̊�@ / �吼�G�V ��
�ϏB���̒n�����J�� / �S���G ��
�_���]�Ï�̏�������i�V���Љ� / ����V ��
����A�W�A�Ñ㕶���ɂ݂鐅 / �V�c�h�� ��
�E |
�R���A�O�Ԏ�P���u��z80�N : ����w�ւ̓��v���u����^�C���X�v���犧�s����B�@�@
�@�@�@�@����^�C���X�� (2006�N1��-12��, 176��) �ɘA�ڂ�������
�R���A�O���x��ۑ���ҁu�a���̔O���x��v���u�O���x��ۑ���v���犧�s�������B�@�@�����F��������}����
�R���A�R��@��������w�������ҁu����w : ����w�������I�v 10(1) (�ʍ� 10) p.91�`104�v�Ɂu�ܒ���l�ƃG�C�T�[�v�\����B
�R���A�R�{�������u���ƊE = The journal of retailing 60(3) (�ʍ� 739) p.90�`94�v�Ɂu�����E����ɂ���Ă����G�C�T�[�̑䕗--����k�����a�V�����X�X�E���J���q���̒��� (���W ����p���[�Ŋ���������!)�v�\����B
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� ���u���ꌤ���m�[�g: �s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@�� �i16�j�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B
|
���d�R�|�\�̖���--������w���d�R�|�\������l�\�N�̕��݂���@�R������@
p.1�`7
�ߐ������ɂ������--���_(8)��w�I���ƒn����n�@�@���c�I��u�@ p.8�`25
���@�����P�Ɨ�����w�������������N���u--��㗮�������������t���@���ђ����@
p.44�`31
���҂Ƃ̋��ɂ̂킩��--��������̚L������(�����́r ���䐳�q p.30�`26 |
�R���A���R���������ꌧ�����U����j���ҏW�� �ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (32) p.1�`20�@���ꌧ����ψ���v�Ɂu�����̃I�J���h�J���ނɊւ��閯���I�`���ɂ���(���_2)�v�\����B
�R���A�v�����䂪�u���� 34 p.58-69�v�Ɂu�ɓ��哈�̈ג� : �w���|�����x�_ �v�\����B
�R���A����l�Êw��ҁu�쓇�l�� ��26���@���a�c�^�~�搶���a�S�N�L�O���W���v���u����l�Êw��v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���ف@1004582357�@�@�d�v
|
���a�c�^�~�搶�̐l�ƋƐ� �m�O �E
���a�c�^�~�搶�Ƃ̏o��E�v���o ���� ���G
�� ���a�c�^�~�搶 ���a�S�N�Ɋ�-�搶�Ƃ̏o�- �V�c�d��
���a�c�^�~�搶���N�����a�c�^�~�搶����ژ^
�u���a�c�ҔN�v�����̔w�i�ƌ���敪�̍ĕ]�� �����k�~
�J�_�������Ƃ��̒����j-�ɍ]������n�܂���
�@�@������̋��Ί핶������- ���c �Õv
�ɔg���y��̕ҔN�I�ʒu�t���ɂ��� �m�O �E
�쐼�����o�y�̃q�X�C���i �V�� �M�V
����L�ˎ������o�y�̓S��ɂ��� ��� �d
�L�ˎ���ɂ�����_�k��茤���j �ɓ� �\
�ِ��W���Y�L�ނ���݂���j����̉��ꏔ���ɂ�����
�@�@�����ٔ_�k�̉\�� ���Z�ϓ�
������A�͍��ɂ��Ă̈�l�@-���ꌧ���ɂ�����
�@�@���c���֘A��Ղ̏W���Ɍ�����- ��� �� ��c�\��
���ꏔ���ɂ�����O�X�N���㌚���Ղ̕ϑJ�ɂ��� �{��O�� |
14�E15���I�ɂ�����W���ƃO�X�N�̏���-����{������ю��ӗ�����
�@�@���u�h�䐫��L����W����Ձv�𒆐S�ɂ���- �R�{ ����
���A�m�^�C�v�����q ���� ���I
�����E�����E��ɂ�����T�тƊC��-15���I�㔼�ɂ�����
�@�@�������C�����m�T�уl�b�g���[�N- �X������
����ɂ����钃�̓��̕��y�Ƃ��̉e��-14���I�`17���I����
�@�@���l�Î�������̌���- �V�_ ��
������g���E�{�B�Y���킩�猩��15�`16���I�̗����� ���� �N��
����o�y�̔��O�āE��� �r�c �Ďj
�����o�y�̗L�E�Տi�A�����͓��ɂ��� �㌴��
�N�c�×q�̍ĕ]��-�N�c�×q�Ղ̌��ۊ�- �Έ䗴��
�擇�����ɂ������j����̐Ε��ƊL�� ���t ��
�{�Ó��A���t��Ղ̃V���R�K�C���L���Ɨ���-�L�����[��\��
�@�@���l�@�𒆐S��- �]�� ���K
���ΐ�q���o�y�̎{�֓���ɂ��� ��������
�E |
�R���A�u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 19 �v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
���r���[�ɂȂ����������x-��O�̖{�y�ɂ����问�����x�㉉�̈�`��- ���� �܂�q
p.1-32
�u���|�����v�̗����C���[�W-���E�����E�X�p�C- �g�� ���Y p.33-42
�����|�\�ɂ����鏔�T�O�̌`���ߒ�-���d�R�|�\�́u��O�y���x�Ɩ��w�̉�v�ւ̏o�����߂�����-
�v���c �W 1 p.43-71
�����������V���̒��Ԑ߂ɂ�����u�n�搫�v�Ɓu�l���v�̍l�@ �}�b�g �M���� 1 p.73-94
�쎌�ƁE��ȉƂƂ��Ă̒m����j-2- -�l�[�l�[�Y��i�s�e�[�Q�[�t�s�E���J�W�t�̕��͂�ʂ���- ���� ���� 1 p.95-125
�ߑ㉫��̌|�p����1 -���g����(����~)�Ɗ��q�F���Y- ���� ���q p.127-141 |
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (15)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�����Ƒ͋ыZ�@�̗������� : �鎽�P�����O�����������~�ƍ����R�����͋ё�������(�����}���E�|�p�����ُ����i�Љ�)�@�@���� ���q p.VI
�G�~�[���E�x���i�[���̌����Z�U���k(3)�@��� �t�j p.1�`12
���|�ƁE�͈䊰���Y���֖�m�[�g�̒�������(��4��)�@�@�쌴�N�F p.13�`30
�������{�������قɂ����鏺�a42�N(1967)���{�Ô��p�W�ɂ���--���̕����I�����I�܈Ӂ@�@�쉮������ p.31�`42
���f�ތ���--��B���J��ƍݗ������Z�p�@�@�@�u���� p.43�`60[�� �p�ꕶ�v�|]
���㉫��̍E�q�_���߂��鑽�p�I�Ȏ���--�Вc�@�l�v�Đ�����̊����𒆐S�Ɂ@�@���ԋM�m p.61�`75
�������y�w�Ǝ��ؓI���y�w�@�@���� �� p.77�`83
��p�E�X�����ɂ����镶������Ɖ̎e�E�����@�@���䗺�q p.85�`96
�c�ӏ��Y�ƌ��퐴��--���̑������闼�҂̉��y�����p���ɂ��ā@�@�Η�t�q
p.97�`107
����������ܐ�����--�ߑ������̓Ǖ��w���̎��ԁ@�@�O���킩�� p.109�`126
�N�w�I����|�p�g�̘_(1)�f�B�h���E������E�E�B�g�Q���V���^�C�����߂����ā@�����N�T
p.127�`135
�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^--����������̈Ӌ`�@�@��闹�q p.137�`153
�����(�킪���ւ̎q�炤��)[�y��]�@�@���{ �M�v p.155�`174
�w���o�c�ɐ������Љ�I�X�L���̌���(5)�A�T�[�V�����E�g���[�j���O�����TT���Ƃ�ʂ��ā@�V��
��,�Ð� ���q,�㌴ �i �� p.175�`191
17���I�@���v�z�ɂ����闝���̈ʒu�Â��ɂ���--�~���g���Ƃ��̎��Ӂ@��� �M�� p.193�`208[�� �p�ꕶ�v�|]
�n���w�I�Ȍ|�p�w�ɂ����镶�������̌���--�u�z�u�v�E�u�ʑ��v�̊W�T�O���l����@�@���� �v�p p.209�`228
�n��m�[�g �V�K�d�q�Đ��F����(2)�@�ۓc �� p.229�`232 |
�R���A���F�M���u�l�ԕ����������N�� (2) p.38�`40�@���É��s����w�l�ԕ����������v�Ɂu���肪�����Ȃ�����--����̏ꍇ (���W
�g�����X�i�V���i���Y�� ; �O���l�Z���Ƃ̋���)�v�\����B
�R���A���k�V�n�i�����䂤���j�Ғ��u���\���̔_�k���� : �C��̓��̔����v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s�����B�@�d�v
�@�@�@�@���t�Ɂu�R��������w�w�p�����o�ŏ����v�Ƃ���
|
��P���@���̐��E�[�l�Ǝ��R�Ɛ_�X��
���R�E�q�g�E�C�l�[�`���I���ƂƂ��̕ϗe�G
�쓇�̔_�k�����Ɓu�C��̓��v
�u�����v�̗͂Ɓu�v�̗́[��̈�����߂�����
�Ԏ�ނ̔_�Ƃ̓`���ƔN���s���i�R�c���j���E���j
��R���ł̕�炵�i�약�i�����j
��Q���@����[�삩��̓��A�k����̓�
�T�g�C���ނ̓`���I�͔|�@�Ɨ��p�@
�T�g�C���̗������i���k�M�q���j
���}�m�C���ނ̓`���I�͔|�@�Ɨ��p�@ |
���тƂ̌��Ĕ��G
�Ĕ��Z�p�̐��Ԉʒu�Â�
���̍앨�ꗗ
��R���@����������[���X�̌𗬂��߂�����
�^�ߍ��_���̐���
�������ƒႢ���̌�
���Ŕ_��U�z���n�܂����[���R���p�̗��j
���_�̎Y�����n�܂���
�����o��
�E �@�@�@�@�@�@�@�uBOOK�f�[�^�x�[�X�v��� �@�@ |
�R���A���˓��������j�ҕҎ[�ψ���ҁu���˓����� ���j�ҁv�����s�����B�@
|
���ҁ@���R�E�n��
�@���́@���˓����̎��R�@3
�@���́@���߁@�n�`�Ɗ��@3
�@���́@���߁@��@���˓����̈ʒu�Ɩʐρ@3
�@���́@���߁@��@�����哇�̒n�`�@3
�@���́@���߁@�O�@�X�тƍk��n�@4
�@���́@���߁@�l�@���v�C�����@4
�@���́@���߁@�܁@�����@5
�@���́@���߁@�Z�@�^�H���@5
�@���́@���߁@���@�����哇�̐����@5
�@���́@���߁@���@�����哇�̐������̓����@7
�@���́@���߁@���R�ی�@7
�@���́@���߁@��@�V���Ȗ��_�@7
�@���́@���߁@��@�ی�ւ̎��g�݁@8
�@���́@���˓����̐A���E�����@11
�@���́@���߁@�A���@11
�@���́@���߁@�����@22
�@���́@���߁@��@���̍������̓����@22
�@���́@���߁@��@�H�������@23
�@���́@��O�߁@�Ғœ����@28
�@���́@��O�߁@��@�M���ށ@30
�@���́@��O�߁@��@���ށ@32
�@���́@��O�߁@�O�@��ށ@33
�@���́@��O�߁@�l�@�����ށ@35
�@���́@��O�߁@�܁@���������ށ@37
���ҁ@��j�E�l��
�@���́@�����̍l�Êw�@41
�@���́@���߁@���������̈ʒu�Ɗ��@41
�@���́@���߁@��@���������̕������@41
�@���́@���߁@��@���≻�ɂ�鍻�u�̌`���ƊC�݁@42
�@���́@���߁@���������̍l�Êw�@50
�@���́@���߁@��@�������珺�a�����̒����@50
�@���́@���߁@��@���̒����@50
�@���́@���������ɂ�����y��ҔN�@52
�@���́@���߁@����܂ōs���Ă����y��ҔN�@52
�@���́@���߁@��@���a�c���~�̕ҔN�@52
�@���́@���߁@��@���{�A�q�̕ҔN�@52
�@���́@���߁@�O�@���������̓y��ҔN�@53
�@���́@���߁@�l�@�Ó���Ղ̐��ʁ@54
�@���́@���߁@�e����̉��������@55
�@���́@���߁@��@���Ί펞��̉\���@55
�@���́@���߁@��@�ꕶ����@56
�@���́@���߁@��@1�@�܌`���y��̔����@56
�@���́@���߁@��@2�@�]���n�y��@57
�@���́@���߁@��@3�@�]���n�y��̎����I���@58
�@���́@���߁@��@4�@�������R�c��Տo�y�̑]���n�y��@59
�@���́@���߁@��@5�@���������Ǝ��̓y��@61
�@���́@���߁@��@6�@�F�h���w�Z�\����Ձ@61
�@���́@���߁@��@7�@��E�������O���E���h��Ձ@63
�@���́@���߁@��@8�@���i�Ǖ��̈�Ձ@65
�@���́@���߁@��@9�@�ꕶ�������A�ӊ��������̉��������@66
�@���́@���߁@�O�@�퐶���㑊�����@67
�@���́@���߁@�O�@1�@��Ղ̕��z�@67
�@���́@���߁@�O�@2�@�o�y�╨�@68
�@���́@���߁@�l�@�Õ�������s���̉��������̓y��@70
�@���́@���߁@�l�@1�@�X�Z���c���y��@70
�@���́@���߁@�l�@2�@�ˑѓ\�t�A�ʏy��@72
�@���́@���߁@�l�@3�@�������y��@72
�@���́@���߁@�l�@4�@�����@73
�@���́@���߁@�܁@�Õ����ォ�璆���@74
�@���́@���߁@�܁@1�@�����ɓo�ꂷ�鎞��w�i�@74
�@���́@���߁@�܁@2�@�O�X�N�����O��@75
�@���́@���߁@�܁@3�@�����哇�̃O�X�N��������@76
�@��O�́@���˓����̐�j����@80
��O�́@���߁@���˓����̈ʒu�Ɗ��@80
�@��O�́@���߁@���˓����ɂ������Ղ̗��n�ɂ��ā@81
�@��O�́@���߁@��@�e����̈�Ղ̗��n�@81
�@��O�́@���߁@��@�W�����̈�Ղ̗��n�@85
�@��O�́@���߁@�O�@���`�i�̃J���B���L�o�y�n�_�ɂ��ā@89
�@��O�́@���߁@�l�@���˓����̈�Ղ̗��n�X���@90
�@��O�́@��O�߁@�Ó���Ձ@92
�@��O�́@��O�߁@��@�Ó���Ղ̈ʒu�Ɗ��@93
�@��O�́@��O�߁@��@�����̌o�܁@93
�@��O�́@��O�߁@�O�@��\�ƈ╨�@94
�@��O�́@��l�߁@�Ó���Ղ̑w�ʁ@96
�@��l�́@�܂Ƃ߁@100
�@��l�́@���߁@��ȕ����̉��@100
�@��l�́@���߁@��@��������ق��ҁu�����哇�̐�j����v�@100
�@��l�́@���߁@��@1�@�F�h�L�ˁ@100
�@��l�́@���߁@��@2�@���V���ʓ��2�L�˒����@102
�@��l�́@���߁@��@3�@���V���ʓ��4�L�˒����@104
�@��l�́@���߁@��@�u���������哇�S���V���ʓ�L�˂ɏA���āv�@105
�@��l�́@���߁@�O�@������Y�u������j�w�Ɋւ���o���v�@105
�@��l�́@���߁@�l�@�w�Ó���Ձx�@106
�@��l�́@���߁@��j�E�l�Â̌���Ɖۑ�@107
�@��E����
�@���́@�Ñ�@111
�@���́@���߁@�����I�̉����\���ߍ��ƂƂ̊ւ��@111
�@���́@���߁@��@�Z���N�u�C�����v�o��@111
�@���́@���߁@��@�u�Ύv�v�o��@111
�@���́@���߁@�O�@�u�t��v�o��@113
�@���́@���߁@�l�@�����I�O���̓��{�ƒ����@113
�@���́@���߁@�܁@�u�f��紁v�o��@115
�@���́@���߁@�Z�@�쐼�����̖��̕ω��@115
�@���́@���߁@���@�Z���N�ɉ������o�ꂵ���w�i�@116
�@���́@���߁@���@�쓇�H�ւ̊S�@117
�@���́@���߁@�����I���`�����I�̉����\�쐼�����Ɠ쓇�H�@118
�@���́@���߁@��@����̓쐼�����F���@118
�@���́@���߁@��@��a����֒��v�J�n�@119
�@���́@���߁@�O�@�Z����N�쐼�����W�����V���@119
�@���́@���߁@�l�@���̌�̓쐼�����̕������@119
�@���́@���߁@�܁@�Z����`���N�ɘ\���������ҁ@120
�@���́@���߁@�Z�@���v�����Ł@121
�@���́@��O�߁@�����I���`�㐢�I�̉����\��ɕ{�Ƃ̊W�@121
�@���́@��O�߁@��@��ɕ{�̖؊ȁ@121
�@���́@��O�߁@��@�v�̕�C�����@122
�@���́@��O�߁@�O�@��q���̔p�~�@123
�@���́@��l�߁@��Z���I���`��ꐢ�I�̉����\�����l�̓o��@125
�@���́@��l�߁@��@�������l�̎F�����̏P���@125
�@���́@��l�߁@��@��̗����@125
�@���́@��l�߁@�O�@��㎵�N�̉����l�̓����@126
�@���́@��l�߁@�l�@��ɕ{���l�̓����@127
�@���́@��l�߁@�܁@��㎵�N�����͍v�[���珤����ւ̓]���@128
�@���́@��l�߁@�Z�@�u��v�̎F���P���@129
�@���́@��l�߁@���@��ꐢ�I�̏������̔w�i�@129
�@���́@��ܐ߁@��I�̉����\�����O�̏��l�@130
�@���́@��ܐ߁@��@���l�ܔN�̕Y���u��؏��l�v�̌����@130
�@���́@��ܐ߁@��@�L�揤�l�u���Y�^�l�v�Ɖ����@131
�@���́@�܂Ƃ߁@132
�@���́@�����@134
�@���́@���߁@�����̑O���@��@135
�@���́@���߁@��@��@135
�@���́@���߁@��@�M�C���@136
�@���́@���߁@�O�@���w��i�ɂ݂��@137
�@���́@���߁@�l�@�M��@138
�@���́@���߁@�܁@��O���I�@139
�@���́@���߁@�����̑O���@��\��l���I�����i���q����j�@139
�@���́@���߁@��@�j���ɂ��ā@139
�@���́@���߁@��@���}�����@140
�@���́@���߁@�O�@���}���@141
�@���́@���߁@�l�@�������@141
�@���́@���߁@�܁@���}���Ə���@142
�@���́@���߁@�Z�@����̓쐼�����֘A�̏��E�@146
�@���́@���߁@���@���ܓ��Ɖ������@147
�@���́@���߁@���@�������A�����A�����A��֓��@148
�@���́@���߁@��@�n���E�A�S�i�E���@148
�@���́@���߁@��Z�@�����̐��}���̖{�@�Ɠ@149
�@���́@���߁@���@�������֘A�j���@150
�@���́@��O�߁@�يE�Ƃ��Ẳ����\�����̑O�E�����̒n�}�j���\�@152
�@���́@��O�߁@��@�����̊G�n�}�@152
�@���́@��O�߁@��@�쐼������`�����G�n�}�@153
�@���́@��O�߁@��@1�@�̖��������́u���{�}�v�i���ɖ{���{�}�j�@153
�@���́@��O�߁@��@2�@���������́u���ە��F����{�������}�v�@156
�@���́@��O�߁@��@3�@���{�������́u���{�}�v�@157
�@���́@��O�߁@��@4�@���c���������́u����{���n�k�V�}�v�@159
�@���́@��O�߁@�O�@�G�n�}�Ɍ����钆���̉����@161
�@���́@��l�߁@�����̒����@163
�@���́@��l�߁@��@�O�R�Ɨ����̓���ȑO�̉��@163
�@���́@��l�߁@��@�����̓��ꉤ���@163
�@���́@��l�߁@�O�@��l���N�̍��얡�z��ւ̓����@164
�@���́@��l�߁@�l�@��l�܁Z�N�����ɑ����Ă��������@165
�@���́@��l�߁@�܁@�����哇�Ɨ������̐킢�@166
�@���́@��l�߁@�Z�@���������ƈi�@166
�@���́@��l�߁@���@�O�X�N�Ɠ`���@167
�@���́@��l�߁@���@���������̃O�X�N�@168
�@���́@��l�߁@��@�哇�q�Ɗ}���@169
�@���́@��l�߁@��Z�@��ܐ��I���̗������ƒn���s���@169
�@���́@��l�߁@���@��l��O�N�̉������߂���Η��R���@170
�@���́@��l�߁@���@���N�ɓ`�������j���@171
�@���́@��ܐ߁@�����̌���@173
�@���́@��ܐ߁@��@�������{�Ǝj���Ƃ��Ă̌���@173
�@���́@��ܐ߁@��@����̔��ߕ����Ƃ��Ă̓����@175
�@���́@��ܐ߁@�O�@���˓�����̌���@176
�@���́@��ܐ߁@�l�@�n���s�����x�Ɩ�E�Ҕ��ߑ̐��@177
�@���́@��ܐ߁@�܁@�Ԑ̖�E�\�剮�q�E�Ɩ�E�҂̈ٓ��@177
�@���́@��ܐ߁@�Z�@���˓��̊Ԑ@178
�@���́@��ܐ߁@���@�����̐��@179
�@���́@��ܐ߁@���@�{�q�ƌÎu���ӂ̌����@180
�@���́@��ܐ߁@��@��O���N�̉����哇�ɉ��{�R�����㗤�@182
�@���́@��ܐ߁@��Z�@���Ԑ̈�Z�N�ɋy�����@183
�@���́@��ܐ߁@���@��l�l�N�ȍ~�̎�Ί_�������@184
�@���́@��ܐ߁@���@�����N�������A�����哇���ēx�����@185
�@���́@��ܐ߁@��O�@��܋�O�`��l�N���{������@185
�@���́@��ܐ߁@��l�@���˓��̊Ԑ̌���@186
�@���́@��ܐ߁@��l�@1�@���˓����Ԑ@186
�@���́@��ܐ߁@��l�@2�@���˓����Ԑ@187
�@���́@�܂Ƃ߁@190
��l�ҁ@�ߐ�
��l�ҁ@���́@�����@195
��l�ҁ@���́@���߁@�F���˂̗����N�U�@195
��l�ҁ@���́@���߁@��@�F���˂̐N�U�@195
��l�ҁ@���́@���߁@��@1�@�����ɑ���]�˖��{�̗v���@195
��l�ҁ@���́@���߁@��@2�@�����N�U�ɂ�����o�߂Ɣ˓����̖��@195
��l�ҁ@���́@���߁@��@�L�^�Ɍ���哇�e�n�̐퓬�@197
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@�퓬�����R�k���@199
��l�ҁ@���́@���߁@�F���˂̑哇�x�z�\���@200
��l�ҁ@���́@���߁@��@������������̉������ׂ̕����@200
��l�ҁ@���́@���߁@��@�哇���������u�哇�u�ڏ��X�v�@204
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@�哇�㊯���̋@�\�@208
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@�Ԑؖ����̋@�\�@213
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@1�@���˓��̔ː�����̍s���敪�@215
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@2�@���˓��̗^�l�@216
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@3�@���˓��̉��ځ@219
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@���ی��n�@221
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@1�@���ی��n�Ɛ��˓��̐��@221
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@2�@�哇�{���̌��n�T���@222
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@3�@�����Ɍ������錟�n���@224
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@4�@�����̌��n���@225
��l�ҁ@���́@���߁@�Z�@���˓��̉z�i�@227
��l�ҁ@���́@���߁@���@�n�}���o�߁@232
��l�ҁ@���́@���߁@���@�㍑���x�Ɨ^�l�i�^�l�̏㍑�ƌ�c���j�@234
��l�ҁ@���́@���߁@���@1�@�㍑�^�l�@234
��l�ҁ@���́@���߁@���@2�@�㍑�̗��R�@236
��l�ҁ@���́@���߁@���@3�@�㍑�܂ł̏����@239
��l�ҁ@���́@���߁@���@4�@�D���̓����@241
��l�ҁ@���́@���߁@���@5�@���㕨�E�i�㕨�@243
��l�ҁ@���́@�o�ρ@246
��l�ҁ@���́@���߁@�����Ɖ����@246
��l�ҁ@���́@���߁@��@�����`���̌c���E���\���@246
��l�ҁ@���́@���߁@��@1�@�J�`�_�Ђ̗R���@246
��l�ҁ@���́@���߁@��@2�@�c����ܔN�����`�����@247
��l�ҁ@���́@���߁@��@3�@�c���N�Ԃɑ���^����@247
��l�ҁ@���́@���߁@��@4�@���\���̓o��@248
��l�ҁ@���́@���߁@��@���������ɂ��ā@251
��l�ҁ@���́@���߁@��@1�@�Â������@�@251
��l�ҁ@���́@���߁@��@2�@�u�哇���l�v�ɂ݂鐻���@�E���̑��@252
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@�����������ƓV�ۍ������v�@254
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@1�@�莮�������ȑO�@254
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@2�@��ꎟ�莮�������@254
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@3�@��ꎟ�y�������@254
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@4�@��莮�������@256
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@5�@��y�������@259
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@���Ƃ����э͔|�ɂ��ā@264
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@1�@�o�n�����@�@264
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@2�@�������Y�ւ̎w���@266
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@���������@268
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@1�@�哇�ɂ����锒�������@268
��l�ҁ@���́@���߁@�܁@2�@�c���N�Ԃɂ����锒�������@270
��l�ҁ@���́@���߁@���˓��̍��_�@274
��l�ҁ@���́@���߁@��@���˓��̍��_�ɂ��ā@274
��l�ҁ@���́@���߁@��@1�@���˓��̍��_�@274
��l�ҁ@���́@���߁@��@2�@���_�щƁ@275
��l�ҁ@���́@���߁@��@�ʼnƂɂ��ā@275
��l�ҁ@���́@���߁@��@1�@�R������ʼnƁ@275
��l�ҁ@���́@���߁@��@2�@�Ŏ��Y�i�D���j�̍�������@276
��l�ҁ@���́@���߁@��@3�@�ʼnƂ̍��Y�@277
��l�ҁ@���́@���߁@�O�@������[�Ƒ�X���m�i�@278
��l�ҁ@���́@���߁@�l�@���m�i�̈ꎚ�����@282
��l�ҁ@���́@��O�߁@���˓��̌�ʂƌ��Ձ@285
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@�D�̃l�b�g���[�N�@285
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@1�@�������Ɖ����̑D�@285
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@2�@���˓��̖��@287
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@�ʎ�`�ɂ��C���ʁ@305
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@1�@�ʎ�`�@305
��l�ҁ@���́@��O�߁@��@2�@�o����@306
��l�ҁ@���́@��O�߁@�O�@�D�̐ωׂƌ��ՂƕY���@307
��l�ҁ@���́@��O�߁@�l�@�m�Ԏ��̌��Ձ@309
��l�ҁ@��O�́@�Љ�@314
��l�ҁ@��O�́@���߁@�@���D���Ɛl���@314
��l�ҁ@��O�́@���߁@�Q�[�A�ЊQ�A���a�ɂ��ā@317
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@��Âɂ��ā@323
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@��@�㓹�m�Á@323
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@��@���E�a���E��ҁ@325
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@�O�@���Ǝӗ�@326
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@�l�@�A�t���@327
��l�ҁ@��O�́@��O�߁@�܁@���ԗÖ@��@328
��l�ҁ@��O�́@��l�߁@�����̐��ƃV�}�̎Љ�@330
��l�ҁ@��O�́@��l�߁@��@�u�����V���v�̉��������@330
��l�ҁ@��O�́@��l�߁@��@���Ԑؐ�������Z�l�̕Y���E�Y���@330
��l�ҁ@��O�́@��l�߁@�O�@�u���������v�ւ̐V���ȋ��\�@331
��l�ҁ@��l�́@�����E����E�����@334
��l�ҁ@��l�́@���߁@���j�Ɠ`���@334
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@��[�ɂ܂��u�\�x�߁v�`���@334
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@��Q�[�~�����p���@���ϏO�@337
��l�ҁ@��l�́@���߁@�ː����̋���@339
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@���l�Ƌ���@339
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@1�@���ɗ����ꂽ�m���l�@339
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@2�@�哇�Ŏg��ꂽ���ȏ��@341
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@3�@���̒m���l�̑����@342
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@���˓��ɗ������l�@343
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@1�@������@343
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@2�@���c?���@345
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@3�@�d���㈁@345
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@4�@�g�䎵�Y�E�q��@346
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@5�@���������@346
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@6�@�����V���q��@347
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@7�@�X�m���@347
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@8�@�͖�F���q��@347
��ܕҁ@�ߌ���
��ܕҁ@���́@���˓����̐����@351
��ܕҁ@���́@���߁@�����ېV�Ə����x�@351
��ܕҁ@���́@���߁@��@�s���@�\�̕ϑJ�@351
��ܕҁ@���́@���߁@��@1�@���������̍s���ϑJ�@351
��ܕҁ@���́@���߁@��@2�@�s����ƐE���̕ϑJ�@352
��ܕҁ@���́@���߁@��@3�@�呠�Ȃɂ��哇���\�z�̐���Ӑ}�@352
��ܕҁ@���́@���߁@��@4�@���v�x���ݒu�̔w�i�ƓƗ��o�ρ@355
��ܕҁ@���́@���߁@��@�����x�̉��v�@357
��ܕҁ@���́@���߁@��@1�@�����x�̉��v�@357
��ܕҁ@���́@���߁@��@2�@�`���`����x�����ɂ�鋌�����v�@358
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@�Ɛl����@363
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@1�@�Ɛl����̋K��@363
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@2�@�G�f������̓����@366
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@3�@�{�����Ɋւ���ٔ��Ƌ��@369
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@4�@�N�G�E���N�G�Ɛl�̉���@371
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@�������R�����^���@374
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@1�@�哇���Аݗ��ɑ��錧�Ɛ��{�̑Ή��@374
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@2�@���萢�����^���̓W�J�@375
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@3�@�^���ɂ��_��̕ύX�@379
��ܕҁ@���́@���߁@�܁@�哇���ЈȌ�̉^���@382
��ܕҁ@���́@���߁@�܁@1�@�哇���i�V�[���O���C�ȑO�@382
��ܕҁ@���́@���߁@�܁@2�@�V�[���O���i�Ɨ��ʉ��v�@386
��ܕҁ@���́@���߁@�܁@3�@�O���@�^���@387
��ܕҁ@���́@���߁@�Z�@�m�����Зv���@389 |
��ܕҁ@���́@���߁@�Z�@1�@���\�m���ғ��̌o�܁@389
��ܕҁ@���́@���߁@�Z�@2�@�u�����v�g���Ƃ��ꂽ�w�i�@392
��ܕҁ@���́@���߁@�s���̈ڂ�ς��@393
��ܕҁ@���́@���߁@��@���ג������̎{�s�@393
��ܕҁ@���́@���߁@��@1�@���������v�C�����ƂȂ�@395
��ܕҁ@���́@���߁@��@2�@���ʒ������̎{�s�@398
��ܕҁ@���́@���߁@��@3�@�Ðm�����̒a���@398
��ܕҁ@���́@���߁@��@4�@�哇�������тɎx���ړ]���@400
��ܕҁ@���́@���߁@��@���˓����̐l���@403
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@���������A���˓����̒a���@407
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@1�@���A�E�����ւ̑�������@407
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@2�@���{���A�ƒ��������@410
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@3�@�����̋��͂Ȑ��i�ҁ@�哇�x���̑O�c�����@411
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@4�@�����ϋɔh�̉��v�C�����̓@412
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@5�@�T�d�������Ðm�����Ɛ������@413
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@6�@�����ց@415
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@7�@���˓����̒a���@416
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@8�@��㒬�����E�����E�������@420
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@���������E�c�̂̉��v�@423
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@1�@�x�@�@423
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@2�@�X�ǁ@429
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@3�@���Z�@�ց@434
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@4�@�g���E�c�Ə��@435
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@5�@�������@437
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@6�@���̑��̊������@439
��ܕҁ@���́@��O�߁@�c��̐��ځ@445
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@�����c��̕ϑJ�@445
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@1�@�c��x�̑n�ݎ���@445
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@2�@���ג������̎{�s�@446
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@3�@�펞���̋c����@446
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@4�@�ČR�����ɂ�����c��@446
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@5�@�u�n�������@�v���������i�c��W�j�@447
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@6�@�c�����A��̎s�����c��@448
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@7�@���˓��������Ƌc����@448
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@8�@�������������c��c����̑g�D�Ǝ��Ɓ@452
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@9�@�哇�S�s�����c��c����̑g�D�@452
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@10�@�哇�{���암�c��A����@452
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@���I�o�c���@452
��ܕҁ@���́@��l�߁@���˓��Ɛ푈�@453
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@���˓��ɂ�����R���@453
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@�������珺�a�O���ɂ����Ă̐푈�@454
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@1�@�����푈�@454
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@2�@���I�푈�@458
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@3�@��ꎟ���E���@458
��ܕҁ@���́@��l�߁@��@4�@����E���@459
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@�펞���̐����@460
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@1�@������Ɨבg�@460
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@2�@�吭���։�@461
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@3�@�z�������̐����@461
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@4�@��P�Ƃ��̔�Q�@462
��ܕҁ@���́@��l�߁@�l�@�I��Ɛ�Е����@463
��ܕҁ@���́@��l�߁@�l�@1�@���������@463
��ܕҁ@���́@��l�߁@�l�@2�@�����S�h�����̕����@463
��ܕҁ@���́@��l�߁@�l�@3�@��Е����̏@463
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@�풆���̎�ȏo�����Ƃ��ڂ�b�@464
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@1�@�����v���O�Y�ł̋�P�Ɣߌ��@464
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@2�@�����R����e��ɂ̎��ԁ@465
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@3�@�D�����s�@�̎c�[�������p��Ɂ@465
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@4�@�풆�n�u�������҂��o�Ȃ������b�@465
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@5�@�h�S�Œ��ŏǏ���N�����������@466
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@6�@�R�n�̗g���Ƌ@���D�̑ҋ@�@466
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@7�@�펞���̗����X�p�C���̐^���@466
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@8�@�J���Ă̕��o�Ƃ��̔����@466
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@9�@�g���L�������Ō��˂������@�@467
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@10�@�ʋl�̋�Ŏ�֒e�̎葢��@467
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@11�@��l�l�k�m���ʍU�������O�؏\�Y�̂��Ɓ@467
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@12�@�R�s�Ðm���̊X�̏@468
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@13�@���\�ہi�Z�Z�g���j�͓G���ɋ����B��̗A���D�ł������@468
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@14�@��@�ꔯ�̏W�c�����Ƃ��@468
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@15�@�O�R���ؖ�����R���ɍŌ�̌}���w�n��z���@468
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@16�@�C�ɓ������ꂽ�e��@469
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@17�@�C�R�q����Ðm����n�i�������U�@�@469
��ܕҁ@���́@��l�߁@�܁@18�@���U�����Ɠ��̖��@470
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�č��Ǘ����̔��N�ԁ@472
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@��E��錾�ƍs�������@472
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@�č����R�R���Ɉڊǁ@475
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@1�@�E�c���̑����I�@475
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@2�@�R���{���R�Ɉڍs�@475
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@3�@�H�Ɠ�̎���@475
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@4�@�u�Վ��k���쐼���������v�̔����@475
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@5�@�ČR���ʑ��{����{��ɐݒu�@476
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@6�@������s�n�݁@�Ðm���Ɏx�X�@476
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@�s���@�\�̉��ҁ@476
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@1�@�@�������ψ���̔����@476
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@2�@�E�c��c���@�Ăѓ���I���I�@476
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@3�@�ʉ�B��R�[��{���ĂɁ@477
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@4�@�����Q�����{�̔����@477
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@5�@�������@�@�c��I���@477
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�O�@6�@�����n�����̔����@478
��ܕҁ@���́@���˓����̎Y�ƁE�o�ς̓����@479
��ܕҁ@���́@���߁@�������̎Y�Ɠ����@479
��ܕҁ@���́@���߁@��@�����O�Z�N��܂ł̐��Y�̓����@479
��ܕҁ@���́@���߁@��@�������̌o�ς̓����@483
��ܕҁ@���́@���߁@�吳�`���a�O���̎Y�ƁE�o�ς̓����@485
��ܕҁ@���́@���߁@��@�吳�����`���a�����̌o�ϕs���@485
��ܕҁ@���́@���߁@��@1�@�Ɨ��o�ρi���f�����j�\�哇�\�Z�@485
��ܕҁ@���́@���߁@��@2�@�Z���̐����E�o�҂��@486
��ܕҁ@���́@���߁@��@�_�ыƁ@489
��ܕҁ@���́@���߁@��@1�@�_�ыƂ̎��ԁ@489
��ܕҁ@���́@���߁@��@2�@�����哇�ɂ����鏬�엿����@493
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@���Y�Ɓ@494
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@1�@�Ǎ��ԋ��Ƃ̗R���@494
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@2�@���ƌ��̓��D�@496
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@3�@�Ðm���ݏZ����o�g�҂̋��Ɛ����@496
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@4�@�����Ɓ@499
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@5�@�ߌ~���Ɓ@504
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@6�@�}�x�^��{�B�@507
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@���Ɓ@512
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@1�@�����̔����t�����߂��鏤�ЁE���l�̐i�o�@512
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@2�@�吳���ɂ����鏤�Ƃ̌���@513
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@3�@���a���ɂ�����Y�ƂƐ��Y���̗A�o�@516
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@4�@�����̓X�@517
��ܕҁ@���́@���߁@�l�@5�@�Y�Ƒg���@518
��ܕҁ@���́@��O�߁@�ČR�����̌o�ρ@520
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@�ČR�̌o�ϐ���Ɣ_�ƌo�ρ@520
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@1�@�o�ϐ���@520
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@2�@�_�ƌo�ρ@521
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@�����ƎЉ�o�ρ@525
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@1�@�����@525
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@2�@�Љ�o�ρ@526
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@�Z���̐����_�`�@527
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@1�@���Ðm�����̂悤���@527
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@2�@���������̂悤���@528
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@3�@���������̂悤���@528
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@4�@�����v���̂悤���@528
��ܕҁ@���́@��l�߁@���A��̌o�ϓ����@529
�@���́@��l�߁@��@�����Q���������ʑ[�u�@�ƕ����E�U���E�U���J���v��@529
�@���́@��l�߁@��@1�@�����Q���������ʑ[�u�@�ƕ����v��@529
�@���́@��l�߁@��@2�@�����Q���������ʑ[�u�@�ƐU���v��@530
�@���́@��l�߁@��@3�@�����Q�������J�����ʑ[�u�@�ƐU���J���v��@530
�@���́@��l�߁@��@4�@�i����j�����Q���U���J�����ʑ[�u�@�Ɓi����j�U���J���v��@531
�@���́@��l�߁@��@5�@���Ɣ�z�y�юY�Ǝ��{�E�Љ�{�����@533
�@���́@��l�߁@��@������ܔN�x�{���̉��U���Ɓ@535
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@���˓����̎Y�Ɓ@537
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@1�@���Y�Ɓ@537
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@2�@�H��U�v�y�т��ѐ|�H��@541
��ܕҁ@���́@��l�߁@�O�@3�@�_�ыƁ@545
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@�Ðm�����X�X�̕ϑJ�@554
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@����E���O�̌Ðm���̃}�`�Ə��X�X�@554
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@1�@�Ðm���̏��X�X�`���Ɋւ��w�i�@554
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@2�@�吳����̌Ðm���̃}�`�@556
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@3�@���a��Z�N��̌Ðm���̃}�`�@561
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@����E����A�Ðm���ɂ�����}�`�̕����Ə��X�X�@564
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@1�@���̕����Ə��X�X�@564
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@2�@�Ðm����ƃ}�`�̕����@565
��ܕҁ@���́@��ܐ߁@��@3�@���X�X�̔��W�Ɛ��ށ@566
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��ʁE�ʐM�E�d�́@568
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@�C���ʁ@568
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@1�@�C���ʂƑD���@568
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@2�@���˓�����̊C���ʁ@569
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@3�@�Ðm���\����q�H����D�@584
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@4�@�����E�{�y�q�H����D�@584
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@5�@�`�p�@592
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@6�@����@593
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@�����ʁ@597
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@1�@���݂̓��H�ԁ@597
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@2�@���݂̃o�X�H���@597
��ܕҁ@���́@��Z�߁@��@3�@���H�̐����@598
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�O�@�ʐM�W�@603
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�O�@1�@��O�̒ʐM���Ɓ@603
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�O�@2�@���̒ʐM���Ɓ@604
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�l�@�d�́@608
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�l�@1�@�吳����`��O�E�풆�@608
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�l�@2�@���E�������ԁ`���{���A�̍��@608
��ܕҁ@���́@��Z�߁@�l�@3�@���˓����a����@610
��ܕҁ@��O�́@���˓����̎Љ�@615
��ܕҁ@��O�́@���߁@�t�����̎Љ�̓����@615
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@�Љ�^���̖G��@615
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@�V�c�s�K�Ə��a��V��@618
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@1�@���a�V�c�̉����哇�s�K�@618
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@2�@���a��V��@619
��ܕҁ@��O�́@���߁@�c�����A�^���@620
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@���A�^���̂�����@620
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@1�@�u��E��錾�v�@620
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@2�@�������̂��炵�E�w�Z�̂悤���@621
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@3�@����ւ̏o�҂��@621
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@���A�^���̌o�߁@622
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@1�@���{���A���c��̌����@622
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@2�@���A�����^���@622
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@3�@���{�{�y�ł̕��A�^���@623
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@4�@����S�������N���@624
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@5�@�f�H�F��@624
��ܕҁ@��O�́@���߁@��@6�@���{���A���i�Ðm���������@626
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@�_���X�����ƕ��A�̎����@627
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@1�@�_���X�����@627
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@2�@�A���V���Ղ��Ă̑��Z��S�����@628
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@3�@���{�����c�Ðm���Ŋe�{�݂����@�@629
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@4�@�����ŕ��A���i���@629
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@5�@���{���A���Ɏ����@629
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@6�@�d���m���傢�Ɍ��@631
��ܕҁ@��O�́@���߁@�O�@7�@���ꂩ�甼���I�`���p���A������z�����߂Ɂ`�@632
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@���˓����̍ЊQ�@633
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@��@�Ё@633
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@��@1�@�Ðm����@633
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@��@�����Q�@636
�@��O�́@��O�߁@��@1�@�䕗�O���i���ܘZ�N�l����ܓ��j�@636
�@��O�́@��O�߁@��@2�@���A�˕��ɂ������v��l�l����i���Z�l�N�����l���j�@636
�@��O�́@��O�߁@��@3�@�䕗�㍆�i��㎵�Z�N������O���j�@636
�@��O�́@��O�߁@��@4�@�F��p�ʼnݕ��D���v�i��㎵�ܔN�Z���j�@637
�@��O�́@��O�߁@��@5�@�䕗�ꎵ���i��㎵�Z�N�㌎����j�@638
�@��O�́@��O�߁@��@6�@�����암�ɏW�����J�i��㎵���N���������j�@638
�@��O�́@��O�߁@��@7�@�䕗��Z���i��㎵��N�㌎�����j�@639
�@��O�́@��O�߁@��@8�@���J�A�哇�암���P���i��㔪�O�N�܌������j�@639
�@��O�́@��O�߁@��@9�@�䕗��㍆�A���u�y�Η���S���i����Z�N�㌎�ꎵ���`�����j�@640
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@��@10�@�䕗�����i����O�N��������j�@641
��ܕҁ@��O�́@��O�߁@��@11�@��������őS�ʒʍs�~�߁i����l�N�Z�������j�@641
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�Љ���@642
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@��@���˓����̌����@642
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@��@�����W�̋@�ցE�g�D�@642
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@��@1�@�哇�x�����˓������������ہi�����˓������o�����j�@642
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@��@2�@���˓�������@�ی������ہ@643
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@��@3�@�Љ���@�l�@���˓����Љ�����c��@643
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�O�@�Љ���W�{�݁@644
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�l�@��ȎЉ���{�݂̊T�v�@645
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�l�@1�@���V�l�����{�ݓ��ʗ{��V�l�z�[���u�����̉��v�@645
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�l�@2�@�{��V�l�z�[���u���V���v�@645
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�l�@3�@���V�l�����{�ݓ��ʗ{��V�l�z�[���u���v�C�����v�@646
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�l�@4�@�m�I��Q�ҍX���{�݁u�Ȃ̂͂ȉ��v�@646
��ܕҁ@��O�́@��l�߁@�܁@�����W�c�́@646
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@�ی��q���@647
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@��@��������̕ی��q���@647
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@��@���A�����E�o�H�����@648
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@�O�@�������E�㐅���@649
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@�l�@��Ñ̐��@649
��ܕҁ@��O�́@��ܐ߁@�܁@�ی��q���֘A�{�݂̂���݁@650
��ܕҁ@��l�́@���˓����̋��當���@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@�w�Z����@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@�w�Z���x�̐����@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@1�@�w���@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@2�@���Z�@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@3�@���w�Z�@652
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@4�@�����`�K���@654
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@5�@���Ɗw�Z�@654
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@6�@�哇�S�����@654
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@�R�����̋���@656
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@1�@���w�Z�@656
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@2�@�N�w�Z�@657
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@3�@�����w�Z�@657
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@�R�����̖��勳��@659
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@1�@���w�Z�ƒ��w�Z�@659
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@2�@�Ðm�������ƍ����w�Z�@659
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@3�@�V���琧�x�ɂ�鏬�w�Z�A���w�Z�@659
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@4�@�Ðm�������w�Z�@660
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@5�@�������萧�x�@661
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@6�@����ψ���̕Ґ��@662
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@7�@PTA�̒a���@662
��ܕҁ@��l�́@���߁@�l�@�w�Z�̓��p���@664
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@�w�Z�̉��v�@673
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@1�@�c�t���@673
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@2�@���w�Z�E���w�Z�@675
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@3�@�����w�Z�@695
��ܕҁ@��l�́@���߁@�Љ��@696
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@��㉂���̎Љ��̕��݁@697
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@1�@�I��`�Վ��k���쐼���������̐ݗ��܂Ł@697
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@2�@�Վ��k���쐼���������`�����Q�����{�ݗ��܂Ł@697
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@3�@�����Q�����{���畜�A�܂Ł@697
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@4�@���A��̐l���E���x�Ȃǁ@698
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@�R�����ɂ�����Љ��@699
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@1�@�����ق̊J�݁@699
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@2�@���˓��n��ɂ���������يJ�݂̏@701
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@3�@�����̌����ي����@702
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@4�@�Ðm�������l����ψ���@704
��ܕҁ@��l�́@���߁@��@5�@�Βk�L�^����@705
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@���˓���������̎Љ��@711
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@1�@�w�l�^����̊J�Á@711
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@2�@���������ٕ��ِ��x�̓����@712
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@3�@���h���Љ��厖�̉ʂ����������@712
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@4�@����������̐ݗ��@712
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@5�@�������̕ی��@713
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@6�@�����̕Ҏ[�@713
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@7�@�����t���y�U�̐ݒu�@714
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@8�@�����Љ�猤����@714
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@9�@���˓������U�w�K���i���@715
��ܕҁ@��l�́@���߁@�O�@10�@���̎Љ��W���N�\�@715
��ܕҁ@��l�́@���߁@�l�@���������ق̌��݂Ƃ��̕��݁@717
��ܕҁ@��l�́@���߁@�l�@1�@���������ق̊J�݁@717
��ܕҁ@��l�́@���߁@�l�@2�@�u�����ق܂�v�̊J�Á@717
��ܕҁ@��l�́@���߁@�l�@3�@���������ق̕��݁@718
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@���˓������}���فE���y�ف@719
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@1�@�}���فE���y�ٌ��݂̌o�߁@719
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@2�@�}���ق̃I�[�v���@720
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@3�@�������w�R�[�i�[�̏[���@721
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@4�@���y�ق̊J�ف@721
��ܕҁ@��l�́@���߁@�܁@5�@�ړ��}���ق̊J�݁@722
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�������E�����E���Ձ@722
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@��@���w�蕶�����@723
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@��@1�@���݃V�o���i���w��d�v���`�����������j�@723
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@��@���w�蕶�����@727
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@��@1�@����̖L�N�x��i���w�薳�`�����������j�@727
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@��@2�@�m�����J��ꎮ�i���w��L�`�����������j�@729
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@���w�蕶�����@730
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@1�@�������@730
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@2�@�G��@731
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@3�@�����@731
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@4�@�H�|�i�@732
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@5�@�Õ����@732
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@6�@�l�Î����@733
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@7�@�L�`�����������@734
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@8�@���`�����������@735
��ܕҁ@��l�́@��O�߁@�O�@9�@�L�O���@736
��Z�ҁ@�l��
��
�N�\�@767 |
�R���A������ďC,���l�i, �ÉF���m��, ���c�ꗘ, ��m�s�ҁu���ꖯ�w�E�������H�H�l�i���[�j�W ��1���v���u�L�����p�X�v���犧�s�����B
|
�����̖{�̎g����
�������̕��@
�y�[�W
�������@(1)
�ߋT�߁@(3)
�j�߁@(4)
�j�߁i���e���j�@(5)
�߂ł����߁@(6)
�ڏo�x�߁@(7)
�������߁@(8)
�����������^
�@�@���i�V�����������^�j(9)
���g�߁@(10)
��y�������S�@(11)
�łݐ߁@(12)
�L�N�����@(13)
�J�`���[�`�ǂ�ǂ�(14) |
��v�@(16)
�A�b�`�����[���@(17)
���K�R�@(18)
�����@(20)
���D�h�[�C�@(23)
������̉S�i�V�[���v�[�j(24)
�q���~�J�`�߁@(25)
���͑傫�����w�̎�@(26)
������߂Ȃ��Ł@(28)
�����߁@(29)
����ǂ��̉ԁ@(30)
���Ȃ���ǁ[�@(31)
�S���t�߁@(32)
�l�G�̉S�@(34)
�̈����߁@(35)
����C�̉́@(36)
�݂��ъщԁ@(37) |
�Ă����ʉԁ@(38)
�̉���@(39)
���V�с@(40)
�V�ђ�@(42)
���ʕ�Ł[�т�@(44)
���ӂ̕l�@(45)
����b�@(46)
�����璹�@(47)
�����߁@(48)
�Z�포�߁@(49)
�L�߁@(50)
�V�уV�����K�l�[�@(51)
�~�̍���@(52)
���݂Ȃ��߁@(53)
����i�����ȁ[�j�@(54)
��ԗF���@(55)
�o�C�o�C����@(56) |
����܁[�`���ʈ�Ԓ���(57)
���邳���〈���~����(58)
���ā[�ނ�@(59)
�Ԍ��q�@(60)
����@(61)
������я��߁@(62)
�̂̐S�@(63)
���̃V�����J�l�[(64)
��������[�@(65)
�{���i�[�N�j�[�@(66)
�ǒJ�R�i�[�N�j�[
�@�@���J�C�T���[�@(67)
�{���@(69)
�x���i�[�N�j�[�@(70)
�E
�E
�E |
�S���A������ďC,���l�i, �ÉF���m��, ���c�ꗘ, ��m�s���u���ꖯ�w�E�������H�H�l�W ��2���v���u�L�����p�X�v���犧�s�����B
|
�����̖{�̎g����
�������̕��@
�y�[�W
�Ԕn�߁@(1)
�h�ʒ��@(2)
�g�D�o���[�}�@(3)
�^�ߍ��ʂ܂�[��(4)
���ʔ�����@(5)
�f���T�[�߁@(6)
�܂�ܖ~�R�@(8)
������[���@(9)
�^�ߍ��V�����J�l�[(10)
�����߁@(11)
���l�߁@(12)
�����Ȃ�@(13)
�܂݂Ɓ[�܁@(14)
�R��ʂ��Ԃ���[��(15) |
�Z���߁@(16)
���X������@(17)
���s�ʉԁ@(18)
�����Ԃ��@(19)
���g�Ԃ��@(21)
�s�����Ԃ����ꂢ�Ԃ����(22)
�n�C�ӂ�����ݐ߁@(23)
���m��߁@(24)
�\�����߁@(25)
��l�����@(26)
���f����ȁ@(27)
�p�����@(28)
��t�����@(29)
�`�����@�I�[�@�`�����@(30)
����@(32)
�S�[���[�߁@(33)
���̎���@(34) |
�ŋ�����@(35)
���܁[��@(36)
�n�C�^�C�J�}�h�@(38)
���W���g�[���[�@(39)
��m���S�@(40)
���_�߁@(41)
���O�l�Ԃ��Ⴉ��(43)
�����@(44)
�k�J�^���@(45)
�����W���g�[���[(46)
�����p����@(47)
���܁@(48)
���H�V�����J�l�[(49)
�����ȁ[�@(50)
�t��t�߁@(51)
�{�P�Ȃ����S�@(52)
���Ђ��@(53) |
��m�A��@(54)
�ƃK�i�V�@(55)
�������@(56)
�V�ђ����@(57)
�z���V�����K�l�[�@(58)
�h���߁@(59)
�k�J���@(60)
���[���[�����[�̂���(61)
�A������@(62)
���܂ڂ�������܂��悤��(64)
�C�ʃ`���{�[���[�@(65)
�I�W�[�����̃I���I���r�[��(66)
�{�[�i�X�y�[�W
��̓��̃G�C�T�[�Ղ�(69)
��F�@(71)
�`�������|�����@(72)
�E |
�S���A���Ð�ˎq�������̐����y������ҁu�����̐����y�_�W (9) p.31�`45�v�Ɂu����ȊO�̒n��ɂ�����G�C�T�[�c�̂ɂ��āv�\����B�@�@�@�iIRDB�j
�T���Q�Q���`�U���P�O�����A���ꌧ�������������Z���^�[�E�G�g�����X�z�[���ɉ����āA�u���a�c�^�~�搶���a�S�N�L�O�p�l���W�v���J�����B
�T���A���ꌧ�������������Z���^�[�ҏW�u�����P�X�N�x���ꌧ�������������Z���^�[���W�u���a�c�^�~�搶���a�S�N�L�O�p�l���W�v�v���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s�����B
�T���A�O���킩�Ȃ� �w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 41(2) (�ʍ� 102) p.130�`93�v�Ɂu�ߑ㉫��ɂ�����ܐ����̎�e--�{�ǒ���̖��w�̕��𒆐S�Ɂv�\����B
�U���R���A���ꌧ�������������Z���^�[���C���ɉ����āu���\�Z���u���@���a�c�^�~�搶���a�S�N�L�O�V���|�W�E���v���J�����B
|
�e�[�}�F�u����l�Êw�̌���Ɖۑ�v
���
���a�c�ҔN�̕]���^�����k�~
�L�ˎ������̌����^�{��O��
�O�X�N�̌����^�c���k��
�擇�̍l�Êw�^�������I
���_ |
�W���A�O�����Y, �哇�ŗY, �g�c���q�i������������ψ���, ���ꌧ����ψ���j�ҁu��B�n���̖����|�\
6�@���{�̖����|�\�������W�� ; 24�v���u�C�H���@�v���犧�s�����B
|
���������̖����|�\�i��́`��Z�́j�@
�i���������̖����|�\�@�i��́`��Z�́j�@������E�O�N�x�j
�i���ꌧ�̖����|�\�\���ꌧ�����|�\�ً}�������\�����Z�N�O���j
���ꌧ�̖����|�\�@299
���{�̖����|�\�������W���@���@�O�����Y�@551
�������́u�����|�\�ً}�����v�ɂ��ā@�g�c���q�@557
������E�O�N�x�@���������̖����|�\
�@�@�@���@�\�����|�\�ً}�������\�@�i��́`��Z�́j�@
��́@�����@829
��́@�i�_���j
��́@�u�z�u���c�̉Y�R�{�_�Ђ̓c�q�Ղ�Ɛ_���@����d�Y�@830
��́@�m�����L�ʕP�_�Ђ̐_���@�V�i���m�@833
��́@��Ӓ��ёq�_�Ђ̓c�̐_���@�V�i���m�@843
��́@�i�_�y�n�j
��́@���V�\�s�Óc�̎��q���@����w�v�@850
��́@�m���������o�̎��q���@����q���@855
��́@�i�c�V�сj
��́@�����������_�{�̂��c�A�Ձ@���c�@꤁@861
��́@�V�钬�O��̓c�A�S�@����w�v�@867
��́@�i���c�A�Ձj
��́@���l���������_�{�̂��c�A�Ձ@����q���@871
��́@�i�_�x�j
��́@�g�c���{��Ԕ��_�Ђ̖_�x��@���c�@꤁@886
��́@�����������x�̘Z�ږ_�x��@���c�@꤁@895
��́@�ɏW�@���і���̖_�x��Ƌ����m�x��@����w�v�@899
��́@���g���z�K�̍��x��@����w�v�@904
��́@��Ӓ��{���H�̖_�x��@����w�v�@909
��́@���g���S�ې_�Ђ̋����m�x�@����q���@914
��́@�S�R���啽�̎��q���@����q���@920
��́@�i���ۗx�j
��́@�{�V�钬�R��[�̏H�Õ��@����q���@928
��́@�������R�c�̎R�c�y�i�S�l���j�@����d�N�@937
��́@�S�R���Ԕ��̑��ۗx��@����d�N�@942
��́@����������x��@����d�N�@946
��́@���V�\�s�[��߂�x��@����d�N�@951
��́@���q���s�i���V���̑�x�i����x�j�@����q���@955
��́@���q���s�i���̎R���x��@�^�痲�F�@962
��́@����s�����U���ۗx��@����d�N�@966
|
��́@�ɏW�@�����d��o�����ۗx��@����d�N�@971
��́@�����������̎�q���x��@�^�痲�F�@975
��́@�������������ۗx��y�@����d�N�@978
��́@�i���_�x�j
��́@�����s���q���̏ޗx��@����d�N�@983
��́@�i�~�x�j
��́@�V�Ò��v�u�̖~�x��i���ۗx��j�@����d�N�@987�k
��́@�����s�쓌�����������x��@����d�N�@992
��́@���V������V��̉Ėڗx��@����w�v�@996
��́@�O�����������̖~�x�@���c�@꤁@1002
��́@���v���̈��[�̔@�|�x�i�`�R���x�j�@���c꤁@1010
��́@�i�����x�j
��́@��E����ÓS�̔����x��@����w�v�@1017
��́@�i�vx�j
��́@�S�R����˂��vx��@����q���@1022
��́@��Y����̂��vx��@����d�N�@1033
��́@�i�m�x�j
��́@��e�����V���̕��m�x�@���c�@꤁@1036
��́@�i���l�x�j
��́@���l����K�����l�x��@����d�N�@1043
��́@�R�쒬���i�̗����l�P�x�@����q���@1047
��́@�i�z�x�j
��́@�a�����������b�R�x�A���@����q���@1057
��́@��e���q��̓z�x�@���c�@꤁@1066
��́@�i���̗x�j
��́@�V�Ò���m�V�̏\�ܖ�s���@����d�N�@1072
��́@���q���s�i�㗢�̃`�N�e���@����q���@1076
��́@�i�j���|�j
��́@�}�����ߓc�̃}���J�C�@����w�v�@1082
��́@���V�������v�u�̃L���[�_���@����w�v�@1087
��́@�i���~�|�j
��́@���q�����R�̎\���@�^�痲�F�@1091
��́@���q�����R�̍��~���@����q���@1093
��Z�́@�������������|�\�W�����ꗗ�@1099
��Z�́@��
��Z�́@(1)�@������r�f�I���^�ꗗ�@1104
��Z�́@(2)�@����{�����������r�f�I�e�[�v�ꗗ�@1106
�E |
�W���A��g����, ���ь��], ������ҁu�\���̕����Ƌ���v���u�I�u���E�p�u���P�[�V�����v���犧�s�����B
|
�\���̍s�ׂƕ����̒n�� / ��g���� ��
�g�߂ȑ��݂Ƃ��Ă̕\�������Ɓu�킴�v�̓`�� / ���ь��] ��
���x�����ƕ\�� / ������ ��
���Z�����Ȃ̎��ƌ��� / �X���� ��
�F�m�ƕ\���̔��B / ���ѓT�q �� |
�g�߂ȕ\���̕��@ / �K�n�v�J�ޔ� ��
�G�搧��ƃR���{���[�V�����̎��� / ���c���� ��
������{�̈��ȉƂ��猩���`���Ƒn���̖�� / �����D�O ��
���{�搧��ɂ�����R���s���[�^�̊��p / �E�c�� ��
����s�A�m��i�Ɍ���t�@�̊g��Ǝ�킴�̊J�� / ��J���a �� |
�W���A�uGreen port report (120) p.10�`11�@���c���ۋ�`�L�v�Ɂu�T�K�`���Ղ�&�C�x���g(��2��)����`�N�c���p���`���s���u�G�C�T�[�v�v���f�ڂ����B
�@
�W���A�{��G��ҁu�R�U�c�� : �t�H�[�g�E�R���N�V�����v���u�O�U�P�R�[�v���畜�������B�@�@
���ŁF�I���W�i����� 1984
|
���ł̏o�Ŏ�: �I���W�i�����
�C�̔ޕ��̎ʐ^�ƂƁA��̔ޕ���
�@�@�玍�l��(�����ł̏��ɂ�����)�@02
���@06
�z��������@09
�����������@12
�v���U�n�E�X�@14
�J���e�b�N�X�@16
�R����(1)�@17
�R����(1)�@���̎c������ǂ݂������v���P�E17
�R����(1)�@�����̉S����{�c�g��17
�R����(1)�@�u���̓��v���灝�Έ䓹�N17
�R����(1)�@�R�U�̂��Ɓ@���W�����E�|�b�^�[18
�R����(1)�@����n�M�C�}���V�������{�錫�G18
�R����(1)�@�R�U�J�@�����R�S���Y�@18
�R����(1)�@�܂��R�U�ց@���ɓ��a�O�@19
�R����(1)�@�ɉ؊X�Ǝq���̗V�яꁝ���͖�19
�R����(1)�@�R�U��!�@���|���W�@19
�R����(1)�@���ƃR�U�@�������a���@20
�R����(1)�@�R�U����n�܂������g�V����20
�R����(1)�@�R�U���ł������R�`
�@�@������3�̖����ړ��`�����͏�21
�R����(1)�@���E��Ԑ��P�̋O�Ձ���Ԑ���21
A�T�C���o�[�@22
�Q�[�g�ʂ�@25
�Ӊ��\���H�@30
��㉮���v�X�Ƃ���ȕS�ݓX�@32
���[�Y�H���@36
�G�C�T�[����@38
������ʂ�@40 |
���c�c��ʂ�@42
�J�}�n���̍�@46
�R����(2)�@48
�R����(2)�@�R�U�@���a�c�����@48
�R����(2)�@���ƃR�U�Ɖ��ꖯ�w�Ɓ��ʕ��r��48
�R����(2)�@�R�U�c���@��Marie�@48
�R����(2)�@MY SWEET HOME KOZA �`
�@�@���R�U�ʂ��̌�����`�����{�z�[�e��49
�R����(2)�@�G�C���A���E�C���E�R�U
�@�@�� �`�e�[�Q�[��炵�A�R�U��炵�A
�@�@��20���I�Ō��10�N�`���S�g�E�䂤����49
�R����(2)�@�R�U�̖�@�����c�����Y�@49
�R����(2)�@�J�^�J�i�̊X�@���x�{���@50
�R����(2)�@�R�U�̌��@�����n�̂ԂЂŁ@50
�R����(2)�t�@�[�X�g�C���v���b�V�������g�c�t��51
�R����(2)�@�t�̊X�E�R�U����@�Â��q51
�Z���^�[�ʂ�@52
�j���[���[�N���X�g�����@55
���H��i�@57
�N���u�E�I�L�`���[�r�B�[�@60
�L���s�g���ف@61
�Z���^�[�ʂ�(��B)�@62
�L���s�g���قƏ�f���̉f��Ŕ@64
�R�U�s�����N�L�O�p���[�h�@65
����(1950�N��)�̃Z���^�[�ʂ������@66
�R�U�����a�@�@67
�R�U���H�M�p�����g���@68
��1��~�X�R�U�R���e�X�g�̓���69
�R�U�\���H�@70
�����u�V���v�@71
|
�I�t���~�b�c�@72
�{���l�b�g�E�o�X�@73
�R�U���Z�ʂ�@74
�R�U�����w�Z�@75
�������[�@76
���d���@78
���������@87
�R���Z�b�g�@88
�I�풼��̊w�Z�@89
�R�U���w�Z�@90
�q�������@92
���z���X�@94
�����@96
�䂩�荆�@97
�R�U�̉f��ف@98
�猩���R�U�s�@100
�R����(3)�@102
�R����(3)�@�R�U�Ƃ����X�N���[��
�@�@�����R��@�i�@102
�R����(3)�@�t���b�V���[���K�]��102
�R����(3)�@�Ȃ����܁[����[�̍�
�@�@�������R�w�@102
�R����(3)�@�������������R�U
�@�@�����ɓ�����@103
�R����(3)�@KOZA���r�Z�J�c103
���Ƃ����@104
�����ŕҏW��L�@106
��ދy�юʐ^�ҁE�Q�l����107
�E
�E |
�W���A���{�q�ǂ��̖{������ҁu�q�ǂ��̖{�I : �������]��36(8) (�ʍ� 466)
���W ���� ���j��`����v���u���{�q�ǂ��̖{������v���犧�s�����B
|
���W ���� ���j��`���� �@ p.18�`33
�L���̕��f�߂�ɂ́@�������� p.18�`22
�~�N���̖ڂƃ}�N���̖�-�������ǂ��Ƃ炦�邩 ���J�쒪 p.23�`26 |
�u�Ԉ��w�v�����ǂ��`���Ă�����-�u�������̐푈��
�@�@�����a�����فv�̊�����ʂ��ā@ ����ڔ��q p.26�`29
�u�Ԉ��w�v�����Ⴂ����ɓ`���邽�߂Ɂ@���� �̂肱 p.30�`33 |
�W���A�����������u��C��w�Љ�Ȋw���������� 530 p.103-103�v�Ɂu�Ќ�������Ԓ����ɎQ�����āv�\����B
�X���A���ꌧ�������������Z���^�[�ҁu���a�c�^�~�搶���a�S�N�L�O��Q�e�@���a�c�^�~�搶�̌����ƐтƔ���������Ձv���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@
�P�O���A�u���y�c�����߉�n�����\���N�L�O�� �[�R�H�J���u[�����ÓT���y]���y�c��������
���y�c��������n�����\���N�L�O���Ǝ��s�ψ��i��j�v���犧�s�����B
�@�@�@�@CD���^���e�F��c�߁A�a�����i�߁A�߁A���Ԑ߁A�Ő߁A�����߁A�̒��߁A�ꎵ���߁A�����߁A����c��
�@�@�@�@306p�@�@�@�����F��㊌����}���فF1008227546
|
�̓��v�@ �Ɏ��×z�e�_�㐳��
���y�c���̗R�� �Ì� ����
�Ì����ƈ��y�c�����߉� �{�� �t�s
���������� �ݖ{�g�Y�@ �ʏ鐳�� �������O�� �����Y�u �ɔg�m��
�@�@����ÒC ��闧 �O�����Y �������q ���p�䐳 �c�Ԉ�Y
�ʐ^�Ɍ�����y�c���̂����
���k��
�V���|�W�E��
�����ǐm����� �c�� ��Y
���y�c�����̎���ƎЉ�w�i �r�{ ����
��������(�ꔪ�l��`�����)����� ���c �i�N
�Ì����ۂ��߂��问�����y������ �V�� �j
���y���̕K�v���Ɗ��p�@�ɂ��� ���� ��
�E |
���� �^����CD�ɂ��� ���y�c����B�̉����� ��p ���V
�@�����ǐm�搶�̋��� �{�� �_�i
�@���y�c�����߉�̕��� ���N(�吳�\�ܔN���a���N)�`
�@�@����Z�Z���N(�����\��N)
�@���w��d�v���`�����������ÓT���y�ێ���(�l�ԍ���)
�@���w��d�v���`�������u�g�x�v(�����w��)�ێ���
�@���w�薳�`�������u����`�����x�v(�O��)�ێ���
�@���ꌧ���`����������`�����y�u���y�c���v�ێ���
�@�����}
�@�ӏ܉�ꗗ
�@�t�́E���t�Ƌ���t�ꗗ
�@�|�\�R���N�[�����
�@����A�O���A�{�s�ψ��A�n�w���C���A���Ȃ��̉�A�H�H�l����
���Ƃ��� |
�P�O���U���A�m�O�E���u���ꌧ�������������Z���^�[�v�ɉ����āu�����u�� ;
��28��@���a�c�^�~�搶�����̈�Ղɂ��āv���u������B
�P�O���A���ꌧ�������������Z���^�[ �ҏW�u���a�c�^�~�搶�����̈�Ղɂ��āv���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@
(�����u�� ; ��28��)
�P�O���Q�P���`���N�Q���Q�S�����A���ꌧ���a�F�O�����قɉ����āu����̐푈���
: ��8����ʊ��W�u�����Ɛ푈��Ձv�}�^ : �퐢�̐^����`���邽�߂Ɂv���J�����B
�P�P���Q�S���A���ꌧ�j�������Q��Z���^�[�u�Ă����v�ɉ����āu�ÓT�E�V��g�x�̏�����-�g�x�Ƃ͉���-���ʑΒk
: ���{������ 2007�N�x �H�̌����W�� : �u����(�|�\)�̒��̏����\�ہv�v���J�����B
�P�P���A����|�\�j�������� ��闧�T �q ; �^�ߔe���q �q ; ���{������ҁu�u
�ÓT�E�V��g�x�̏�����-�g�x�Ƃ͉���-���ʑΒk : ���{������ 2007�N�x �H�̌����W��
: �u����(�|�\)�̒��̏����\�ہv�v���u���{������v���犧�s�����B
�P�P���A�g�Ɗԉi�g�ҁu�����̗��j�ƕ��� : �w�����낳�����x�̐��E�v���u�p��w�|�o�Łv���犧�s�����B
(�p��I�� ; 412)
|
�����낳�����x�ւ̗U�� / �g�Ɗԉi�g ��
�w�����낳�����x���牽��ǂ݂Ƃ邩 / �g�Ɗԉi�g ��
�l�Êw����w�����낳�����x��ǂ� / �����i ��
����Վ���ƃI���������ăq�L / ���Ǒq�g ��
�������ɂ�����C�^�ƍq�C���_�M�� / �L���R�a�s ��
|
�w�����낳�����x�̐_�o���̕\�� / �g�Ɗԉi�g ��
�v�����̍��J�Ɖ̗w / �ԗ䐭�M ��
�I������v�� / �����r�O ��
�w�����낳�����x�̔�g�\�� / �g�Ɗԉi�g ��
�I�����ӏ� / �g�Ɗԉi�g �� |
�P�Q���A������ �ҁu�����w : ���߂Ɗӏ� 72(12)�@���W=�܌��M�v�Ɩ��c���j
; �A�W�A�̒��̐܌��Ɩ��c�v���u�������v���犧�s�����B
|
�A�W�A�̒��̐܌��Ɩ��c�@(p.34�`59
�A�W�A�̒��̐܌��E���c--�쓇���ۂƓ��{�������̂��Ɓ@�C������ p.34�`41 |
���c���j�Ƒ�p�����w �@総i�� p.42�`49
�������w�����ɂ݂���c���j�Ɛ܌��M�v �g�Ɗԉi�g p.50�`59 |
�P�Q���A�ؒJ�^�I�q���u�O���R�I�v�Ɖ̕���v���u�˗я��[�v���犧�s����B�@
|
���́G�풆���̉̕���
�P�u�n���ρv
�Q�u���g�ԁv |
�R�u�F��v
�S�u���u�I������L�v
�T�u�ނ��߂��̂ݑю�r�v |
�U�u���|�����v
�I�́G�u���|�����v�Ȍ�
�C���^�r���[ / �i�R���b�C���J�슨���q |
���o�ꗗ
���Ƃ���
�E |
�P�Q���A���ꌧ���a�F�O�����ٕҁu����̐푈��� : ��8����ʊ��W�u�����Ɛ푈��Ձv�}�^
: �퐢�̐^����`���邽�߂Ɂv���u���ꎞ���o�Łv���犧�s�����B
�@�@����E���: ����19�N10��21��-����20�N2��24�� ���ꌧ���a�F�O������
|
1.�@���{�R�̔z���Ɖ����@3
2.�@�푈��Ղɂ݂鉫���@�k�g�l�E�l�@6
3.�@�����̐푈��Ձ@10
3.�@�ČR�㗤�̒n(�ǒJ���E�k�J��)�@12
3.�@�ǒJ���E�k�J���̓��U���铽���Q�@13
3.�@�`�r�`���K�}(�ǒJ��)�@14
3.�@�V���N�K�}(�ǒJ��)�@15
3.�@�k�`�V�k�W�K�}(����s)�@16
3.�@�����̕���a�ƒ�����(����s)�@17
3.�@�Ð���������̐푈���(�X��p�s)�@18
3.�@�Y�Y��ՁE�O�c���n�̐푈���(�Y�Y�s)�@22
3.�@�������̐푈��Ձ@24
3.�@���얡�̉��̍�(�ǒJ��)/���V�苴(����s)/
�@�@���V��E�N�{�E�O�X�N���ӂ̐w�n���Q(����s�Ì���)/
�@�@���h��(��[��)�@26
3.�@�V���K�[���[�t(�ߔe�s)�@27
3.�@��������ӂ̐푈���(�ߔe�s)�@28
3.�@������(�ߔe�s)/�ߔe���E�^�a�u������̍�(�ߔe�s)/
�@�@�����ƂԂ��R��(�ߔe�s)/�����w�Z���Z��(�ߔe�s)�@32
4.�@�암�̐푈��Ձ@33
4.�@�앗�����R�a�@��(�앗����)�@34
4.�@�C�R�i�ߕ���(�L����s)�@36
4.�@�i�Q�[����(�앗����)/��24�t�c��2���a�@��(�L����s)/
�@�@���嗢��Ղ̖C����(���s)/�֏��Ԃ͖̊C��(���s)�@37 |
4.�@�����A�u�`���K�}(���s)�@38
4.�@��24�t�c��1���a�@��(���d����)�@40
4.�@�k�k�}�`�K�}(���d����)�@41
4.�@���������̍�(�����s)�@42
4.�@�Ɍ���O�O�ȍ�(�����s)�@43
4.�@���̍�(�����s)�@44
4.�@���a�F�O�������ӂ̐푈���(�����s)�@46
4.�@�O�얯�Ԗh�Q(���s)/�N���V���W���E�̍�(���d����)/
�@�@���R�ږѐ푈��ՌQ(�����s)/�}���[�K�}(�����s)�@52
5.�@�k���̐푈��Ձ@53
5.�@���y���̐푈���/�^�V�`�̋������铽���@54
5.�@�ɍ]���̐푈��Ձ@56
5.�@�E�X����ČR���a�@�W�c�����n��(�X�����)/
�@�@����X���̏Z�����Q(��X����)/�{���Ď�����(�{����)/
�@�@���厼�т̌�^�e��썈(����s)�@58
6.�@�����̐푈��Ձ@59
6.�@���Ԗ����̐푈��Ձ@60
6.�@�n�Õ~���̐푈��Ձ@61
6.�@�v�ē����̐푈���/��k�哌���̐푈��Ձ@62
6.�@�{�Ó��s�̐푈��Ձ@63
6.�@�|�x���̐푈��Ձ@64
6.�@�Ί_�s�̐푈��Ձ@65
7.�@�푈��Ղ̕ۑ��E���p�@66
8.�@�W�������ژ^�E�Q�l�����@70 |
���A���̔N�A�����a�q,�H�c�������u���{�n���w��\�v�|�W 2007s(0) p.62-62�v�Ɂu��E���ɂ����鉮�~�͂��Ƃ��Ă̐Ί_�̕��z�Ɨl��:���`�W���Ə���ÏW�����Ƃ��āv�\����B�@�@�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A�u�� : ���j�E���E���� : �w�|������ : �G�� : history, environment, civilization : a quarterly journal on learning and
the arts for global readership 30�@���W �������A�u�����̎����v��--�u���A�v�Ƃ͉��������̂� ; �u�����̎����v�̎v�z�Ǝ��H�v�����s�����B
|
�u�����̎����v�̎v�z�Ǝ��H
�@�@�� (���W �������A�u�����̎����v��--
�@�@���u���A�v�Ƃ͉��������̂�) p.160�`261
�����̎����ƌ��@ �@�얞�M�� �@ p.162�`169
�����̖��@ ����,���M���� p.170�`173
�����E�������A���n���� ���� �� �@ p.174�`177
���̂܂����A�����̉\���@�@�R�䏻�q p.180�`183
���A�Ƃ͉���--�V�}�Â���̍����
�@�@�������邱��/��Ó��q p.184�`187
�u��(����)��v�ɂ�鐢���� �@�C���� �L p.188�`191 |
�������w�̌ŗL���Ǝ�̐� �@�@�g�Ɗԉi�g p.192�`198
�����E����j�ɂ�����u�������v/ ������s p.200�`205
�Q�̂Ȃ��n��--�����Z�̗���������/ ��c�� �� p.206�`209
�A���ӎ��̍s��--���A�E�Ɨ��E����/ �Ί_���F p.210�`212
���\�����ق肨����--���\�Ǝ��̐��j /�Ί_���� p.220�`229
��������l�X--�r�ԕc�E�㌴���M�E�D�����́E
�@�@�����g�����E�Ί_���q/ ������ p.230�`237
�^�ߍ����̍����𗬂Ǝ���/�c������ �@p.240�`247
����̖L�������ǂ��v�邩--
�@�@�����"�L����"���l���邽�߂̊�b���/���쏁 p.249�`261 |
���A���̔N�A�g�Ɗԉi�g�ҏW�u��Ԃ̃E�V�f�[�N : ���̍Ղ�:�E�V�f�[�N�̍ċ���ڎw���āv���u����s����ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�r�f�I�f�B�X�N1�� (46��)�@���L �i���[�V����: �K�n�D�q�@ �B�e�E�ҏW:
�X�^�W�I�E�G�[�X�@
�@�@�@�ʃ^�C�g�� ���ꌧ����s��ԁi�e�B�[�}�j�̃E�V�f�[�N
���A���̔N�A�A�O���킩�Ȃ����ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (15)
�@p.109�`126�v�Ɂu����������ܐ�����--�ߑ������̓Ǖ��w���̎��ԁv�\����B
���A���̔N�A���y��������� �u���y������(�ʍ� 24)�v�����s�����B
|
�r�N�g���A--���e�b�g�̐��E �~�� ���q p.1�`14
�c���̖M�y�ӏ܋��ނƂ��Ă̏������̉\��--����u���x�ρv�𒆐S�� �r��
�b�q,�щ� ���� p.15�`36
�̎��E�y������ ���ꌧ�{�������G�̎�x��G�C�T�[ ���� ���],���� �K�j p.37�`64
��p�̊w�Z���y����--���ȓ����̎��_���� �� �E p.65�`80
�m�I��Q�{��w�Z�ɂ�������{���x�̕\���E�ӏw��--�̎��Ɓq�U��r�̊W�ɒ��ڂ������ƂÂ���
���J �͎q,�� ���q p.81�`96
�����̈��Ǎ��ۂ�p��������--���Z�̌��Ɗӏ܂�ʂ��� �� �q p.97�`113
�w���y�������x20�`23�f�ژ_����ڈꗗ[2003�N�`2006�N] p.117�`1182 |
���A���̔N�A�� �x�Ԃ��u���m���y�����@ (72) p.83-95�v�Ɂu�����ɂ����钆���Y�Ȃ̎�e�v�\����B�@J-STAGE
���A���̔N�A�Η�t�q�����ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (15) p.97�`107�v�Ɂu�c�ӏ��Y�ƌ��퐴��--���̑������闼�҂̉��y�����p���ɂ��āv�\����B |
| 2008 |
20 |
�E |
�Q���A���ь��],���эK�j�����s���q��w���B����w���I�v�ҏW�ψ���ҁu���s���q��w���B����w���I�v = Bulletin of the Faculty of Human Development and Education (4) p.83�`102�v�Ɂu���ꌧ�{�������̃G�C�T�[�v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�O���킩�Ȃ����ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ� : ���ꌧ���|�p��w���y�w������ (9) p.87�`99�v�Ɂu����������̉��y��v���O�����ɂ�����u���w�v�T�O�̌`���v�\����B
�R���A���p�����u����G�C�T�[�a���Ȃ� : �ܒ��Ƃ����V���܂̐��U�v���u���m�o�Łv���犧�s����B�@�@�P�P�O�O�~
�R���A���ь��]�E���эK�j���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
20 p.43-63�v�Ɂu���A�m���̎�x��G�C�T�[ -�{�������̑��n��Ƃ̔�r��ʂ���-�v�\����B
�R���A�_�ˏ��q��w�ÓT�|�\�����Z���^�[ �ҁu�_�ˏ��q��w�ÓT�|�\�����Z���^�[�I�v
�P�v���u�_�ˏ��q��w�ÓT�|�\�����Z���^�[�v����n�������B�iIRDB�j
|
�G�C�T�[�`���ɂ��Ă̗��j�w�I�l�@ �m�� �芰 p.3�`19
�����E����̐_�Ղ�ɂ݂�|�\ �v���c �W p.21�`26
�O���̎���--�O���E���i�E�O���� ��� ���u p.27�`36
�w�����낳�����x�Ɍ��鏗�_���J--�u���݂Ă���̂������ق����Ɓv�_���𒆐S��
�r�{ ���� p.37�`47
������J�̔�]���E���z�� ���� �O p.49�`55
������J��\�N�̎���--������J�����f�[�^�x�[�X�ɂ݂鉫����J�̗l�� ����
����q p.57�`69
�p�l���f�B�X�J�b�V���� ������z���ĉ�����J�̎������� �r�{ ����,��X ���i,�v�ۓc �W �� p.71�`94
�w�Ȃ���R�O�Z��ʁx���E����(�Љ�Ɩ|��) ��� �O�V p.95�`112 |
�R���A��Y�p�Y�����j����ҋ��c��ҁu���j�n������ ����(727) p.92�`95�v�Ɂu���Z�����x��u�G�C�T�[�v�̖���--�����Ղł̃X�e�[�W���\����n��̊����� (���ꂩ�猩������{--�����E���ȏ��E��n�E����--�Ȃ���ߋ��ƌ��� ; ����̕����E���R)�@�v�\����B�@
�R���A�쑺���������ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu�j���ҏW���I�v = Bulletin of the Historiographical Institute (33) p.111�`122�v�Ɂu�h���@�ю����� �ܒ���l�����W���������v�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�g�Ɗԉi�g���A�W�A���������w��ҁu�A�W�A������������ = Asian folk culture studies (�ʍ� 7) p.175�`187�v�Ɂu���̗w�̉����� (�V���|�W�E�� �A�W�A�̉̂̉�����)�v�\����B�@�@�@�@�@
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: �s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@��(17)
�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004675698
|
�Ñ�E�����̃L�J�C�K�V�}�Ɗ�E�� �i�R�C�� p.1�`24
�����i���w�����̉����ƃO�X�N�x �啽�� p.25�`32
�u���������v�j�ɂ�����u�����v--�u���������v�j
�@�@�������Ɋւ����b�I�l�@�@���c���j�@ p.33�`48
�Y�Y�悤�ǂ�̉Α���-����Ɨ���(����)�@�������V p.49�`64 |
���G--�������A�����A
�@������Ƃ�-�������F�w�y���Ȃ���G�x�ɂ悹�ā@��㌤��Y�@p.65�`72
���@�����P���a�S�N���}���ā@���� ���� p.88�`79
��ւ̂܂Ȃ���--���w�ƃg�|�X(�I���G���^���Y���̒E�C�f�I���M�[)
�@�@������:�v�l�̘A���@��� �� p.78�`74 |
�R���A����,�k�~ ���u�I�v���ꖄ������ 5 p.147-158�@���ꌧ�������������Z���^�[�v�Ɂu���a�c�^�~���u�������z�v�u�������z ���̓�v�v���Љ��B
�iIRDB�j
�R���A�m���芰���_�ˏ��q��w�ÓT�|�\�����Z���^�[�ҁu�_�ˏ��q��w�ÓT�|�\�����Z���^�[�I�v
(1) p.3�`19�v�Ɂu �G�C�T�[�`���ɂ��Ă̗��j�w�I�l�@�v�\����B
�R���A�{�����W���u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (26) p.33�`53�@���ꖯ���w��v�Ɂu�j���ɂ݂�u�V�}�N�T���V�V��v-�����������W�j���A�w�������R���L�x����v�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�A�W�A���������w��ҁu�A�W�A������������ 7 �v���u�A�W�A���������w��v���犧�s�����B
|
��p���Z���ɂ������� �R�c �m�j p.1-101 J-STAGE
����ɂ�����s�V�}�N�T���V�V��t�̖��̂Ɋւ����l�@--�V�}�N�T���[�ƃJ���J�[�Ƃ������t�̈Ӗ��ɂ���
�{�����W p.103�`119
�����Γ�ȖP�����c���̊_������ �H���� p.121-144 J-STAGE
�V���|�W�E�� �A�W�A�̉̂̉����� p.145�`201
�V���|�W�E���ɂ��� �������u p.145-147 J-STAGE
�A�W�A�̒��̘a�� ������ p.149�`160
�����ÓT���̉�����--�����Ɛl�א� �����N p.161�`173�@J-STAGE
�쓇�̗w�̉����� �g�Ɗԉi�g p.175�`187 J-STAGE
�̊|���̂ɂ���������ւ̎w����--�������쏭�������̗w�̉������@ �����k���Y
p.189�`201J-STAGE |
�R���A�J�O�ҁu����ɂ�����g�̂̋ߑ㉻ : �䊥�D�x��̎�e���߂����āv���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B�@ (�Ȋw������⏕��(��Ռ���(B))�������ʕ�, ����17�N�x�]����19�N�x)
|
�_�l�E�����|�\�ɂ�����u�ÓT�v�T�O�̌`�� :
�@�@�� ���a11�N�̗����ÓT�|�\�����߂����� / �v���c�W [��]
|
����44�N�́u�d�C�x��v / �V�䖜���� [��]
�����E�����|�\�W�V���L������(���a21�N�`���a47�N) / �J�O�� |
�R���A�����ɕF�ҁu�ړ�����l�тƁA�ϗe���镶�� : �O���[�o���[�[�V�����ƃA�C�f���e�B�e�B�v���u�䒃�̐����[�v���犧�s�����B
|
1.�@�ϗe�G�[�W�F���g�ɂ�镶���̑n�o�@�\�n���C����n
�@�@���R�~���j�e�B�ɂ����鎖�ጤ���@�����ɕF�@3
1.�@I�@���̏��݂Ɩ{�e�̖ړI�@3
1.�@II�@��v�T�O�̐����@6
1.�@III�@�I�L�i�����E�t�F�X�e�B�o���̑n�n�̌o�܁@�\�`���̑n�o�C
�@�@���I�L�i�����̑��сC�{�����e�B�A�@7
1.�@IV�@����H�̃��C�W���[�f�r���[�@>�\�`���I�ƒ뗿�����狽�y�����ց@13
1.�@V�@���y��������G�X�j�b�N�E�t�[�h�ց@>�\�ϗe�G�[�W�F���g�̂͂��炫�@17
1.�@VI�@�ˋ��I�ϗe�G�[�W�F���g�̂͂��炫�@�\����̓W�]�@21
2.�@�I�L�i�����E�n���C�A���E�X�^�C���@�\�n���C�ɂ����鉫��n�ږ���
�@�@����Z���n�����̌����@��c���@25
2.�@I�@�}���`�E�G�X�j�b�N�Љ�n���C�ւ̎����@25
2.�@II�@�N���X�E�G�X�j�b�N������n���C�@>�\�^���X�ɂ݂�G�X�j�V�e�B�̌����@27
2.�@III�@�ږ���őn�o���ꂽ�I�L�i�����E�A�C�f���e�B�e�B�@29
2.�@IV�@�I�L�i���������ɂ��N���X�E�G�X�j�b�N�̏p�@32
2.�@V�@�����Ɂ\�������ȃn���C�̂������Ȗ��́@41
3.�@�n���C�̃I�L�i�������̑n���@�\�����c�̏o�ł�
�@�@���N�b�N�u�b�N�ɂ݂镶���ϗe�@���������]�@49
3.�@I�@�{�e�̖ړI�@49
3.�@II�@�n���C�̃I�L�i�������̑n���@53
3.�@III�@���_�@67
4.�@�n���C�̃A�����W�A���@�\���z�����Ɓ����[�J��������
�@�@���q���A�C�f���e�B�e�B�@��������@73
4.�@I�@�z���҂Ƃ��ẴA�����W�A���@73
4.�@II�@�A�����W�A���̃P�[�X�E�X�^�f�B�[�@74
4.�@III�@�l�@�@86
5.�@�n���C�ɂ����钆���n�R�~���j�e�B�̕����ϗe�@�\�G�X�j�b�N�E
|
�@�@���t�F�X�e�B�o���𒆐S�Ɂ@���썎�F�@7
5.�@I�@�����̖ړI�@97
5.�@II�@�����n�̕����ϗe�ƃG�X�j�b�N�E�A�C�f���e�B�e�B�@98
5.�@III�@�����n�̃G�X�j�b�N�E�t�F�X�e�B�o���ƕ����ϗe�@102
6.�@�V����̓��n�u���W���|�\�l�A���W�F�E�C�V�@�\���̃L�����A�헪�ƃG�X�j�b�N�E
�@�@���A�C�f���e�B�e�B�@115
6.�@I�@�{�e�̖ړI�@�\�u���W���̓��n�|�\�l����������Ӌ`�@115
6.�@II�@����Љ�@119
6.�@III�@��r���́@�\���n�|�\�l�̊፷���Ǝ咣�@133
6.�@IV�@�{�����̌��E�ƍ���̉ۑ�@137
7.�@�O���[�o���[�[�V�����ƃ��[�J���e�B�\�����E
�@�@�������́u����v�̎���@���c���q�@141
7.�@I�@�O���[�o���[�[�V�����ƃ��[�J���e�B�@141
7.�@II�@�����Ɠs�s��Ԃ̋@�\�����̉ߒ��@143
7.�@III�@��������U������g���̐ݗ��\���n���^�Љ�W���{
�@�@��(bridging social capital)�@150
7.�@IV�@��������́u�i���v�\���[�J���ȕ����I�����@153
7.�@V�@�ނ��с@160
8.�@�s�s�j�Ղ�S���l�X�\�ړ��E��Z�E�����́u�n���v�@�K�]�F���@163
8.�@I�@���̏��݁@163
8.�@II�@�s�s�ڏZ�҂̎Љ�I�ʒu�Â��ƃA�V�o�Ղ̐����i1970�`80�N��j�@164
8.�@III�@�}�C�m���e�B�W�c�̑��𗬂Ƃ��Ẵ`�������P�Ղ�
�@�@���G�C�T�[�c�̂̑����Ƒ��l���i1990�N��j�@167
8.�@IV�@�u����̃G�C�T�[�v�𖼏�邱�ƁC
�@�@���u����v�ɍ��t�����Ɓ\����`�����v���[�t�F�X�^�i2000�N��j�@171
8.�@V�@�l�@�@179
���M���Љ�@189 |
�R���A�ߓ����s, �����a�F�Ғ��u���̋V�@ : �ݑ�Ɍ��鑒�̗�߁E�����ρv���u�~�l�����@���[�v���犧�s�����B�@�@
|
���s�ɂ������ā@�����ό����̈Ӌ`/�����a�F���ɑウ��
�@�@���@�ݑ�̖��ɂ��� / �ߓ� ���s
��h���@����猩�鎀����
1�@�^�_���ɂ�����ƂƎ����� / �� �����Y
2�@�^�_���̕�n��ʂ��Č��鎀����/�ߓ����s
3�@�����V�炩�猩�銿���̎����ρ@���̏ꏊ�Ɨ썰�ρE
�@�@���c��ς̍l�@�𒆐S�� / �� ����
4�@�V���[�}�j�Y���Ǝ����� / �������q
5�@�S�g�s�����̑Ώ��s���Ɍ��鎀���ρ@
�@�@���H�c���k���ɂ�����ގ҂ƒn��Z���̏���/���ۉp�E
6�@���������Ɍ��鎀���� / ���� �O�q
��h�h���@�����V��̕ϑJ
1�@�^�_���̑��@ / �� �����Y
2�@����ɂ����鎀�̌��݁@�Α��̕��y�E
�@�@�����V�Ђ̗��p�E�m���ւ̈˗� / �������q
3�@���������̑��@ / �� ���� |
4�@���{�̑��@�Ɖ���E�^�_�̎�����/�ߓ����s
5�@�ߒ��Ƃ��Ă̑��V�Ƃ��̌������@��Ԃ̈ړ��̌�����ʂ���/�R�c�T��
6�@���@�̕����Ȋw / ���V���v
��h�h�h���@������{�̎�����
1�@�^�_���̎���S / �ߓ����s
2�@�ݑ�̌����E�a�@�� / �� �C��
3�@�l������̏����� / ����G��
4�@�S���w���猩�鎀���ρ@���̕ω��Ƌ@�\ / ���ۉp�E
5�@�����̂������@�u���{�l�̎����ρv�Ɛ����ϗ�/��щ�V
6�@�u�ݑ�v�Ɓu�O�݉��v�@�l�Ɖ� / ��������
7�@��t�|���ҊW�ɂ����鎀���ς̌ʐ��@
�@�@���Ƒ��̑��݂ɂ��ā@���Ҏ҂ɂ��m�㎑���ĕҁ�/�m�㍂��
8�@���Ǝ�����l����ی� / �� �C��9�@���@�̐V���Ȃ鎎��/���V���v
��IV���@�^�_�̏�i���₤����
�@�@���^�_���N�_�Ƃ��鎀���ό����̉ۑ�/�ߓ����s
���������l������ |
|
���L ���������� ; 82�^"�{���́A���ۓ��{���������Z���^�[�́A����ɂ�鋤�������u���{�ɂ�����w���̏ꏊ�x�Ǝ����ς̕ϑJ�Ɋւ��鑍���I�����v(2005�N4���`2006�N3��)�̕��Ƃ��ĕ҂܂ꂽ����"�Ƃ��� |
�R���A���ꌧ�������فE���p�ٕҁu���ꌧ�������فE���p�ٔ����ًI�v (1)�v���u���ꌧ�������فE���p�� �v���犧�s�����B�@
|
�C�m�V�V���̍��i�����ɂ��� �m�O�K�q �fp.1�`3
�������э��A�m����R�C�݂ɂ�����I�J���h�J���ނ̐��Ԓ��� �c���� p.5�`19
�X�Ζʂɂ�����L�Z�L���C�̉^���ω� ���c�S��,���a�l 2008 p.21�`26
��j����ɂ����鍘�x�n���j�̗��ʂƉ�� �R��^�� p.27�`34
�w�і�絓a��������R���������x�ɂ���(��) �茴��� p.35�`44
�ߑ㗮���̏ё��� ����M�K p.45�`58
�����قÂ���--���ꌧ�������ِV�ُ�ݓW���̏ꍇ ������ p.59�`79
�̌��L�b�g�����--���ꌧ���|�p��w�̊w���B�Ƃ̋��畁�y�v���O�����̎���
�o�ߗ� ��q �@ p.81�`98 |
�R���A�V���ꂪ�������ꂨ���Ȃ풲���{���ەҁu����ŋ��哹� �㊪�v���u�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s����B
�@�@ (�������ꂨ���Ȃ�|�\�����W ; ��1�W)�@229p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004702088
|
����ŋ��哹� �V����
�V���ꎁ�̗��� ���{ |
����|�p�̎���E���N�� �R�����l
�����̌��̗��j �r�{���� |
����ŋ��֘A���N�\ ���{
�E |
�R���A�r�c�Ďj�ҁu�Ñ㒆���̋��E�̈� : �L�J�C�K�V�}�̐��E�v���u���u���@�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@308p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1008414813
|
�͂��߂� �r�c �Ďj
1 ���E�̈�̗��j�w
��E����v��ՌQ�ƌÑ�쓇�Љ� ��� ����
�Ñ�̉����E���ꏔ���ƍ��ێЉ� �c�� �j��
���{�Ñ㍑�ƂƓ쓇�A���� �R�� ����
�������{�ƌ×����̂͂��� ���� �͉�
�������猩���L�J�C�K�V�} �i�R �C��
2 ���@���ꂽ���E�̈�
��E����v��ՌQ ���c ���q ��� ��i |
��ɕ{�Ɠ쓇�Љ� ���� �P���Y
��v��ՌQ�̒����� ���� �^��
���ΐ��Γ�̗��ʂƗ����� ��� �N�V
��E���̌Ñ�E������� �r�� �k��
�Ñ���s���ɂ����鉂�������̍ݒn�y��ҔN ���� �C
���V���쉺����̌Ñ�E������� �{�� �M�_
���Ƃ��� �r�c �Ďj
���M�҈ꗗ
�E |
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v 16�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
������佂Ɖ���--���ꗷ�s���̓��L�ƍ�i��ʂ��� ���� ���q p.11�`30
�����g�^�ɋL�q���ꂽ�����|�\--�u���H���v�����̎��� �\���E�앑�ɂ��� ���g
�Ύ} p.133�`147
�N�w�I����|�p�g�̘_(2)�f�B�h���E������E�E�B�g�Q���V���^�C�����߂�����
���� �N�T p.149�`155
���ꉹ�y�̋ߑ㉻�Ɖ��R���� �O�� �킩�� p.157�`178
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(4)��i����1(�����E�吳��) ��R �L�q
p.187�`206
�q�����r |
�S���A������w�ҁu���炩����̊w�Ǝv�z : ������w�̒m�ւ̗U���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@
�@�@�@�@447p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004694145
|
����̗��j���w��
�J���B���L���� �r�c �h�j
���L�I(����)�l�̎��� ���� �q�g
�ߐ������j���̌����� -�����E�����E����- �L���R �a�s
�Ȃ��A�����J�͉��ꓝ�����s�����̂� �䕔 ����
����_�Ƃ̐��藧���Ɨ��j -�_�k������������- ���n �@�r
�U �ϗe���鉫��̎Љ�Ɩ���
�L�W���i�[�̖����w �ԗ� ���M
�V�[�T�[�̂�����i ���� ��Y
����̃A�����W�A�� ��� ����
����A�C�f���e�B�e�B�̓ǂݕ�
�@�@�� -�����̋A���ӎ��̒�������- �� ��
���ꌧ�ɂ����鑽�d�����ƕn�� �ԏ� ���}�q
�V ���t�Ɛl��
�����ꌤ���̖��� -���l���������Ă���邱��- �떓 �ɋv
�u�����ȁ[�����v�Ƃ͉����@�`��������` �{�� �M��
�R���s���[�^�Ɖ���̂��Ƃ� -�n������ƍ��ې�������
�@�@���������������߂�����- ���� �x�v
���ꕶ�w�Ύ��L ���� �����^��
�Ăё�n�ɍ��������߂� -�A�����J�̐�Z���̕��w- ��[��]
�W ����̊ό��ƎY��
�Y�����Y�Ɨ��{��֍s���� ���� ��F
�j���[�c�[���Y���Ɖ���̎��R �� |
�@�@��-�V���Ȑl�Ǝ��R�̂������Ɋ��҂���- �Ԉ� ����
���ƕ��̃}�[�P�e�B���O -����ό��̃C���[�W�ƃ��b�Z�[�W- �ɔg���q�q
�����Ɗό��J�� �~�� �N�v
�X ����̎��R
���M�т̐X�ɃC���I���e���}�l�R��ǂ� ���V ��q ���� ��
�T���S -�l���䂫���Ă�܂Ȃ����̖��͂Ƃ�- �鑺 ���q
�d�g�ŊC�𑪂� ���� �q�j �v�� �K��
�C��d�b���ɂ��C���ϑ� ���� �S�� �� �[��
���̐��I�ɂ����鉫��̐����� ���� ��l
�Y ����̎��R�ЊQ�ƌ��z
�l���P�������Ă��ꂽ���d�R��Ôg ���{ ��
�䕗�������̍ŋ߂̑䕗���� �^�� ����
�n����ЊQ�̌y���Ɍ����� �X�� ����
�����̒������l���� �R�c �`�q
��㉫��̃R���N���[�g�Z�� ���q ���V
�Z �]�ƌ��N
���ɍ��܂ꂽ����l�̗��j �y�� ����
�ߐ��v�ē��̐l�X�̌��N�ƕ�炵 �Γc ��
���ǂ��̐����K���a -���^�{���b�N�V���h���[���̊C�ɉj��
�@�@������̂��ǂ�����- ���c �F�j
����̐����K���a�ƒ����̊�@ �뉺 �C�� �剮 �S��
����ƍR�_����p ���m�� �m�q
����̃E�C���X�ƍۂ��瑾�Ẫq�g�̗����m�� �X ���� |
�T���A�c�R�P������E�ʎ������Ғ��E�{��M�E�ďC�u���I���d�R�ÓT���w�W 1�v���u������
(���ꌧ)�ې�����v���犧�s�����B�@�@�b�c�Q��
|
�����u��V�N�q���փc�v
�@�@�����҂ɉ�����ꂽ����/�X�c����/4
�����o���ϖ�/���d�m��Y/6
�����w���I���d�R�ÓT���w�W�x
�@�@�������Ɋ�/��Éx�q/8
����-CD�̐��삨��щ̎��W�̕ҏW�ɂ���-//10
���d�R�ÓT���w�͔��d�R��
�@�@���Љ�I�Y���ł���-�V���A�ڂɂ�������-//12
���d�R�ÓT���w�̐����E���W�̊T�v//14
�y�}��z//16
���d�R�ÓT���w�̉��ߕ\//18
�Ԕn��(�{���q)//20
�h�ʒ���(�{���q)//32
�ߋT��(�{���q)//46
���Ԑ�(�{���q)//52
����l��(�{���q)//64
�㌴�ʓ���(�{���q)//72
�ɏ���(�{���q)//76
�Ƃ��܂���(�{���q)//84
���Ǔc��(�{���q)//90
���ʉԐ�(�{���q)//96
�g�Ì��ʉY��(��g��)//104
������(��g��)//110 |
�璹��(��g��)//116
��J��(��g��)//120
��Y�z�H��(��g��)//126
���l��(��g��)//132
���Ӑ�(��g��)//138
��[���[��(��g��)//144
�z���(�{���q)//148
������(�{���q)//156
�����O��(�{���q)//166
�܂�́[�ܐ�(�{���q)//176
���炭����(�{���q)//182
�ʛ�����(�{���q)//186
�Ì��ʉY��(��g��)//192
��������(��g��)//204
���ʂʂׁ[�ܐ�(��g��)//214
����ː�(��g��)//224
��R��(��g��)//236
���ʐ^���Ԑ�(��g��)//242
�Ƃ���[�ܐ�I(��g��)//248
�Ƃ���[�ܐ�II(��g��)//250
���ڂ�b
(1) �������ɂ���//30
(2) �c�ӏ��Y��<�Ԕn��>�]//30 |
(3) ���㉹�̂����炢//42
(4) �N�o(����)�̌ď̂ɂ���//62
(5) �u���d�R��v���̕\���ɂ���//63
(6) �u�����v���Ȃ��u�E���v�Ƃ�����//102
(7) �u�t�^�C���v�̌ꌹ�ɂ���//153
(8) ���T�ނ̎g�p�ɂ���//154
(9) �Ì����̗��K�_��q��//202
(10) �E�h�D�M���[�u�h�D�͓K��//220
(11) �`���̗w�̉���ɂ���//233
(12) ����ː߂̉̎��ɂ���//235
(13) �̎��̊w�K�ɓ�������//256
��ȗp�����//71
��ȕ��@�p�����(1)//109
��ȕ��@�p�����(2)//131
��ȕ��@�p�����(3)//143
��ȕ��@�p�����(4)//147
��ȕ��@�p�����(5)//191
��ȕ��@�p�����(6)//213
��ȕ��@�p�����(7)//247
���Ƃ���//258
����//271
�E
�E |
�U���A���g�Ύ}�ďC;�ʏ��}�ďC�u�ʏ闬�Ă��E�����݉��J�ݎO�\���N�L�O����
�\�H�̓������@�i�����p���t���b�g�j�v���u�ʏ闬�Ă��E�����݉�35���N�L�O�������s�ψ���v���犧�s�����B�@�@ 63p �@�����F��㊌����}���فF1005182744
�@�@�@ �����E�ꏊ�F����20�N6��22�� �@�Y�Y�s�Ă����z�[��
�U���A�^�������u�����R���邤������2001 1 ���ꏔ���� 1�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B
�@�@�^���f�B�X�N 1�� (64��) : CD
|
(1)�ȁ[���Ɂ[�E�R����ԓ�(�Î芡�я�,�Î芡�ю��j(2)�ɍ��ւ���[�߁E�ł[��(�O��猫,�`�ӏ��q)(3)���ʉ�(�`�ӏ��q)(4)�C�ʂ���ځ[��[(�O��猫)(5)�V�т���ˁ[(�`�ӏ��q)(6)�܂����(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(7)�v�Ĉ��Ð�(���c�O��)(8)�ȁ[���ѐ�(�`�ӏ��q)(9)���₮��(�m����j,��������,�O��猫)(10)�E����(�v�u��Y,�䉮���K�T)(11)���݂Ȃ���(�c�ꐷ�M)(12)������(����r��)(13)�����G�C�T�[(�m����j,��������,�O��猫)(14)����(�Î芡�я�,�Î芡�ю�)(15)��������߁[��(�m����j,��������,�O��猫)(16)�Î�v(�m����j,�������� |
�U���A�^�������u�����R���邤������2001 2 ���ꏔ���� 2 �v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� (62��)
|
(1)���D�ǁ[��(�m����j,��������,�O��猫)(2)�Ă����ʉ�(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(3)���H(�m����j,�������q)(4)�ԕ�(�Ɗ얼����)(5)���߂�[(�����J��,�o�쐽�m)(6)�l�璹��(�Ɗ얼����)(7)�ނ��(�Ɗ얼����)(8)��ԓ�(�m����j)(9)�������(�Î芡�я�,�������q)(10)�����b(�t�m��,��㏟��)(11)���l��(�v�u���,�{���b�q)(12)������(�O��猫,����b�q) |
�U���A�^�������u�^������ �����R���邤������2001 3 ���ꏔ���� 3 �v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� (62��) : CD�@�@
|
(1)���Ԑ�(�Ɗ얼����)(2)�щ�(�Ɗ얼����)(3)��������(�Î芡�я�,����b�q)(4)�u�̈�{��(�����J��)(5)�ږ����S(�o�쐽�m,���NJ_�c�q)(6)������(�Ό��b���q)(7)�ږ�����(�m����j)(8)��m���S(�����J��)(9)���H��(��@�Â��q)(10)�R�l�߁E�F�{��(�Î芡�я�,�������q)(11)���̉�(�`�ӈ��q)(12)����炿(�R��܂��&���C���C�V�X�^�[�Y)(13)���b�p��(���c�O��,�`�ӈ��q)(14)�\��̏t(��H�N�O,��@�Â��q)(15)���Ð�(�m����j)(16)�O�єL�E�ׂ�g�̉́EPW����Ȏ�(�Ɖ��я�)
|
�U���A�^�������u�����R���邤������2001 4 ���ꏔ���� 4�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� (65���j
|
(1)���������̋�(���c���̂�)(2)����̗���(�Î芡�я�,�Î芡�ю�)(3)��b(�c�ꐷ�M,�`�ӈ��q)(4)���̐�����(�o�쐽�m)(5)���Ԃ�(�`�ӈ��q)(6)�z�Â�(�T�J���m)(7)���т�(�Ό��b���q)(8)�Бz��(�������q)(9)�P�S���̉�(�c�ꐷ�M)(10)�v�w�D(�����J��)(11)�m�ԕz(���[K�R���r)(12)�䂤�Ȃ̉�(���^�B�q)(13)�q���~�J�`��(�g�c�N�q,�{���ޔ��q)(14)�o�C�o�C����(���c���g)(15)���̒��N�c(�C�����L)(16)�n�C�T�C��������(�O��猫,�p�C����)
|
�U���A�^�������u�����R���邤������2001 5 ���ꏔ���� 5�E�{�Ï����� 1 �v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� (66��) : CD
|
�q���ꏔ����5�r(1)����ʂ����イ��(�g�c�N�q,�{���ޔ��q,�䉮���K�T,�c���]���q)(2)�Z�포��(���c���g)(3)�̂��Ȃ���(�`�ӈ��q)(4)���W���g���[(��@�Â��q)(5)���̎���(�Y��N�q�Ɩ��w���g)(6)���Ȃ���ǁ[(�O��猫)(7)���̏�(�c�ꐷ�M)(8)����܁[�`���ʈ�Ԓ���(�Y��N�q)(9)�`�o�����[(�Ɗ얼����)(10)���肪�Ƃ�(���܌b���q)(11)���C���C(�䉮���K�T)(12)�e�[�Q�[(���܌b���q,�{���ޔ��q)(13)��(���ԍF�Y)(14)����S�V��(��������,���c�O��)�q�{�Ï�����1�r(15)�Ȃ�R���₮(���g����)(16)�L�N�̉�(���g����)(17)���Ԃʎ�(���g����) |
�U���A�^�������u�����R���邤������2001 6 �{�Ï����� 2�E���d�R������ �v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� (70��) : CD
|
�q�{�Ï�����2�r(1)������(���g����)(2)�Ɓ[����(���g����)(3)��c��(���g����)(4)�ɗǕ��Ɓ[����(���g����)(5)�떓�ʂ����݂�(���g����)(6)�����ʃN�C�`���[(���g����)�q���d�R�����ҁr(7)���������(����������,���؏G�g,�������̂�q,�͏���ގq)(8)�����Ȃ��(����������,���؏G�g,�������̂�q,�͏���ގq)(9)�Ԓ��ʖڍ��I���(����������,���؏G�g,�������̂�q,�͏���ގq)(10)���ʔ�����(�������̂�q,�͏���ގq)(11)�h�ʒ���(����������,���؏G�g)(12)�ł�(����������)(13)�Ì��ʉY��(����������,���؏G�g)(14)����ː�(����������)(15)�Ƃ���[��(����������,�������̂�q)(16)�R��ʂ��Ԃ���[�ܐ�(����������,���؏G�g)(17)�Z����(����������,���؏G�g)
|
�U���A�m���芰���u���������j�̌����v���u�Վ����сv���犧�s����B�@�@(�����ʑp��,
17)
�U���A�ԋ{���i���@����w���ꕶ���������ďC�u����Ì�̐[�w : �������̒T���v���u�X�b�Ёv���犧�s����B
(�p���E�����m��)�@�@�@ 189p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004704407
|
�O�X�N�v�u�j���C�E�J�i�C�v�ȂǁA������ے����錾�t�͂ǂ����炫���̂��B����ŌẨ̗w�W�u�����낳�����v�̌�����A�o����ł����a�Ì�Ɣ�r���Ȃ���A���̌ꌹ��T��A���L�̕��@�̌n�������������B |
|
1 ����Ì�̌ꌹ
�O�X�N�̌ꌹ
�e�_�̌ꌹ
�I�����̌ꌹ
�i�̌ꌹ
�~�����E�J�i���̌ꌹ
�A�}�~���E�V�l�����̌ꌹ
�I�{�c�E�J�O���̌ꌹ
1 ����Ì�̌ꌹ |
�O�X�N�̌ꌹ
�e�_�̌ꌹ
�I�����̌ꌹ
�i�̌ꌹ
�~�����E�J�i���̌ꌹ
�A�}�~���E�V�l�����̌ꌹ
�I�{�c�E�J�O���̌ꌹ
2 �I������̕��@�ƕ\�L
�W�茋�т̎�ނƗp�@ |
�����K�̕\�L
�����e�̕\�L�ƌ��
�ސ��\�L���߂�����
3 ���� �ꌹ�E���@�E�\�L
�a���E�̌ꌹ
�E���Y���̌ꌹ
���̖����A�E��
�����n�̕\�L�E����
�E |
�U���A���l��c�ҁu���l��c 46(6) (�ʍ� 549) ���W ����́A���܁v���u���l��c�v���犧�s�����B�@2008-06
|
���W ����́A���܁@p.4�`65
����E�����Ƃ��Ƃ� �@�@���{ �M�v p.42�`48
�푈�ƎR�V���� ���� ���� p.49�`55
���Ɖ���@�R�V�� �� ���l��c�@ p.56�`58
���ȏ�����Řc�߂�ꂽ�����̐^�� �@�ΎR �v�j p.59�`63
��O�Z����Ɏ��� ���J���l���W�w��R�x�@ p.66�`81 |
��܍�i�� (��O�Z����Ɏ��� ���J���l���W�w��R�x)�@p.67�`73
����W�w��R�x��ǂ� (��O�Z����Ɏ���
�@�@�����J���l���W�w��R�x)�@�F�h �ꐬ p.78�`81
���W�] �\������Ƃ͂����Ȃ�s�ׂȂ̂��@�k�� �^ �� p.118�`121
�����] �Úg�̎������������@���c ���V p.122�`125
�E |
�V���A�O☗��K���u��B���ۑ�w���{���� = Studies of liberal arts 15(1) (�ʍ� 41) p.212�`177�v�Ɂu�ɔg���Q�u����㊐l�̑c��ɏA�āv �v�\����B �@�ɔg���Q�������V��A�P�X�O�U�N�P�Q���T�����瓯���X�����ɔ��\�����_�����e�̍l�@�@�iIRDB�j�@
�V���A�������V���{��w�@���q��w���{���w��ҁu���{���w�m�[�g (43) (�ʍ�
65) p.84�`97�@�{��w�@���q��w���{���w��v�Ɂu�����̍���(�o��)--�Ñ���{�̑��ƕ��w
�v�\����B
�W���A�������q,�O���,�����^�R�����u���{������w��@�N��_���W (24) p.40-41�v�Ɂu�f�W�^���E�A�[�J�C�u��p�����n��Ԏ����̋��މ� : ����̃G�C�T�[,�����x��̃I�[�����q�X�g���[����(�f�W�^���E�A�[�J�C�u�̐V�����W�J�ƍ���̉ۑ�(1),�V��������̔g)�v�\����B
|
���^�^�`�������̃f�W�^���E�A�[�J�C�u���͑������n�掑���̏����ł��������A�����1�̓��F�ł���e�n��Ԃ̊֘A(�����N)�����邱�Ƃɂ��V�������l�Ȋw�K�����Ƃ��Ă̊��p���\�ɂȂ�B�����̎���Ƃ��āA���ꌧ�̃G�C�T�[�A���������킫�s�̂����O���x��A�ܒ���l�Ȃǂ̎����̊֘A���\�ɂ�����A�P�Ȃ鎑���̎��W�ł͂Ȃ��A�f�W�^���E�A�[�J�C�u�Ƃ��Đl������j�I�Ȕw�i�A����ɃI�[�����q�X�g���[���̗��p��p�������ō\�������B��������w�Z����A�����w�K�Ȃǂœ`�������̊w�K�f�ނƂ��āA����ɐV�����w�K�ۑ�����o���鎑���Ƃ��Ă̒\�Ƃ����B |
�W���A�{�ǒ���, ��R�O�Y�Ғ��u���x�ȏW:���d�R�ÓT���w�v���u����o�Ł^�{�ǒ����F��R�O�Y�v�����B�@
�@�@�@�w�����L�����@���d�R�ÓT���w�@���x�ȏW�ڎ��@���\�Z����(����͕��x�ȗp�̉̎�)�@�@�����F��㊌����}���فF1007225368
|
�h�ʒ��߂̗x
�h�̒��߁@��Z
�������̗x
�����炭���߁@���
���^�h�߁@��l
�㌴�ʓ��̗x
�㌴�ʓ��߁@��Z
�ł߁@��
�Ԕn�߂̗x
�Ԕn�߁@���
����[��߁@�O��
���ʂςȂ̗x(���̈�)
���ʂςȐ߁@�O�O
�O�ʓn�߁@�O��
���ʂςȂ̗x(���̓�)
���ʂςȐ߁@�O�O
��Y�z�H�߁@�O�Z
���炭���̗x
���炭���߁@�O��
�������ܐ߁@�l��
�܂�́[�܂̗x
�܂�́[�ܐ߁@�l�O
���e�Ȃ�ΐ߁@�l�l
�܂�́[�ܐ߁@�l�O
���݂邭�߁@�l��
�z�N�̗x(���̈�)
�z�N��(�Ί_)�@�l��
�z�N��(���)�@�l��
���O�ʓn�߁@�l��
�z�N�̗x(���̓�)
���o�ߔe�߁@�܈�
���z�N��(���)�@�ܓ�
�����ΐ߁@�l
�z�N�̗x(���̎O)
���z�N�߁@�ܘZ
����p�z�߁@�ܔ�
�z�N�̗x(���̎l)
���z�N��(���)�@�܋�
�����m���v�߁@�Z��
����l�̗x
����l�߁@�Z�O
�M�z�߁@�Z��
���Ǔc�߂̗x
���Ǔc�߁@�Z��
�ʛ����߁@�Z��
�c�[���߁@���Z
���Ǔc�߁@�Z��
�����߁@����
���C�z�N�̗x
���z�N��(���)�@���O
���z�N��(�Ί_)�@���l
�����ΐ߁@����
���z�N�̗x
���z�N��(���)�@����
�����炵�@����
���l�߂̗x
���l�߁@����
�����ݐ߂̗x
�����ݐ߁@����
�{�Nj��߁@���Z
�����ݐ߁@����
�ɏ���(����)�@����
�����߂̗x
�����߁@����
���ΐ߁@��Z
�܂ց[����߂̗x
�܂ց[����߁@��O
�Ɓ[�����@���
�X�|�̗x(���̈�)
�������Ɓ[��߁@�㎵
���ʛ����߁@�㔪 |
���g���I�v�߁@��Z��
�X�|�̗x(���̓�)
�������Ɓ[��߁@��Z�O
����l�߁@��Z�l
�����ΐ߁@��Z�Z
�ߋT�߂̗x(���̈�)
�ߋT�߁@��Z��
���ΐ߁@���Z
�ߋT�߂̗x(���̓�)
�ߋT�߁@���O
�ڏo�x�߁@���l
�ʛ����߂̗x
�ʛ����߁@���Z
�c�[���߁@��ꎵ
�����߂̗x
�����߁@����
���������[�߁@����
�g�Ì��ʉY�̗x
�Ԃ܂��[�߂̗x
�Ԃ܂��[�߁@���O
�g�Ì��ʉY�߁@���l
�Ì��ʉY�߂̗x
�Ì��ʉY�߁@���
�^�ߔe�߂̗x
�^�ߔe�߁@��O��
���Ӑ߁@��O��
�^�ߔe�߁@��O��
���ې߁@��O�O
�������߂̗x
��������(��g)�@��O��
��������(����)�@��O�Z
��������(�{��)�@��O��
���Ԑ߂̗x
���Ԑ߁@��O��
�璹�߂̗x
�璹�߁@��l��
��J�߁@��l��
�Ԃ܂��[�߁@��l�l
���₩��߂̗x
���₩��߁@��l��
���ł߁@��l��
������K���ۂ̗x
���Ì��ʉY�߁@��܁Z
�����ΐ߁@��܈�
�z��߂̗x
�z��߁@��O
�O�ʓn�߁@��܌�
�������Ԃ�̗x
�������Ԃ�߁@���
���ӂ����߁@��ܔ�
���܂ց[����߁@��܋�
���ʕ�߂̗x
���ʕ�߁@��Z��
�����炵�@��Z��
���ʕ�߁@��Z��
�����ʂςȐ߁@��Z�O
���ʕ�߁@��Z��
��J�߁@��Z�l
��Y�z�H�߂̗x
��Y�z�H�߁@��Z��
�����߂̗x
�����߁@��Z��
���Ƃ���[�܁@�ꎵ��
�����߁@��Z��
����[��߁@�ꎵ��
��J�߂̗x
�璹�߂̗x
�璹�߁@�ꎵ�O
��J�߁@�ꎵ�l
�K���ۂ̗x
�약�߁@�ꎵ�� |
�ߋT�߁@�ꎵ��
���ΐ߁@�ꎵ��
�ɏ��߂̗x
�ɏ��߁@�ꔪ��
�Ƃ��܂��߁@�ꔪ�O
�����ʂςȐ߂̗x
�����ʂςȐ߁@�ꔪ��
�����ΐ߁@�ꔪ�Z
�Ӓ��̕��̗x
������c�߁@�ꔪ��
���Ӓ��̕��@����
�����炵�@����
�Ȃ��Ȃ�߂̗x
�Ȃ��Ȃ�߁@���l
�^���W�߂̗x
�^���W�߁@���Z
�����Ӑ߁@��㎵
����[�߁@��㎵
�݂ȂƁ[�܂̗x
��R��(�{��)�@��Z�Z
�݂ȂƁ[��(����)�@��Z�Z
�匴������̗x
���^�h���߁@��Z�O
�����ΐ߁@��Z�l
�ڏo�x�߂̗x
�ڏo�x�߁@��Z��
�ɏ���(����)�@��Z��
�|�������̗x
���|�������߁@���Z
���ߐ߂̗x
���ߐ߁@����
�v���߂̗x
�v���߁@����
�C��߁@���l
�v���߁@����
�܂₮��[�߁@����
�����߂̗x
������(����)�@���
�Ӓ��̉S(����)�@���
������(����)�@���
���ې�(����)�@��O�Z
������(����)�@���
��ǎR��(����)�@��O��
�������߂̗x
�������߁@��O�O
�e�܂���߂̗x(���̈�)
�e�܂���߁@��O�Z
�R����ΐ�(����)�@��O��
�e�܂���߂̗x(���̓�)
�e�܂���߁@��O��
�{�Nj��߁@��l�Z
�O�ʓn�߂̗x
�O�ʓn�߁@��l��
���Ӑ߁@��l��
�����߂̗x
�����߁@��l�l
�̐V�̕��̗x
�Ԕn�߁@��܁Z
�����߁@��l�l
�R��ʂ��Ԃ���[�܂̗x
�܂ɂ����߁@��l
�R��߁@��l
�R��߁@��l
�����߁@��܌�
�܂�܂Ԃ�߂̗x
�܂�܂Ԃ�߁@��ܔ�
�a�l��(����)�@��܋�
�^�h���߂̗x
�^�h���߁@��Z��
�����ΐ߁@��Z��
�Ɓ[���ɂ����[�̗x |
�Ɓ[���ɂ����[�߁@��Z�l
����������(����)�@��Z��
���ɂ�[�ܐ߂̗x
���ɂ�[�ܐ߁@��Z��
���������[�߁@��Z��
�܂ɂ����߂̗x
�܂ɂ�����(����)�@��
���ΐ߂̗x
���ΐ߁@�O
���ʕ�����̗x
�����ʕ�����@��
��������ŕ��߁@��
�Ί_�����̗x
���Ί_�����@��
��������ŕ��߁@��
���d�R�������̗x
�����d�R�������@�Z
��������ŕ��߁@��
���d�R��������̗x
�����d�R�������@�O
��������ŕ��߁@�l
���Ԍ����̗x(�͂₵����)
�����Ԍ����@��
���Ԍ����̗x
�����Ԍ����@���l
��������ŕ��߁@���l
���\�����̗x(�͂₵����)
�����\�����@��㎵
�|�x�����̗x
���|�x�����@�O�Z��
���������̗x
�����������@�O�Z��
�x���ʋ��ȁ[�܂̗x
�x���ʋ��ȁ[�܁@�O���
�Ɓ[�����@�O�ꎵ
�F�s�����̗x
���F�s�����@�O��Z
���ʂʂׁ[�܂̗x
���ʂʂׁ[�ܐ߁@�O���
���������߁@�O���
���ʂʂׁ[�ܐ߁@�O���
���ł�(��g)�@�O��O
�ĉԐ߂̗x
���ĉԐ߁@�O��Z
�����炵��(����)�@�O��Z
�q�߂̗x
�q�߁@�O��
�Ɓ[�����@�O���
���ʂ܂Ղ���[�ܐ߂̗x
���ʂ܂Ղ���[�ܐ߁@�O�O�Z
���Ƃ���[�܁@�O�O��
�Ӓ��̕��̗x
���ɏW����c��(����)�@�O�O�O
�Ӓ��̉S�@�O�O��
�n��Ì��ʉY�̗x
�Ì��ʉY�߁@�O�O��
���Ƃ���[�܁@�O�l�Z
����߂̗x
�����(����)�@�O�l��
�v��R�z�H�߁@�O�l�O
�����邭�[���̗x
�������邭�[��(����)�@�O�l��
�����߂̗x
��������(����)�@�O�l�Z
����ː߁@�O�l��
��R�߁@�O�l��
���ʂ܂Ղ���[�ܐ߁@�O�܁Z
�Ƃ���[�܁@�O�ܓ�
�E
�E
�E |
�W���A�����P��, ���c�ꗘ�Ҏ[�u�̎��W����̂��� : �������w���瓇�����|�b�v�X�܂Łv���u�L�����p�X�v���犧�s�����B�@
�X���A���ܐ��Y�Ď��j��L�O�������s�ψ���ҁu�����̐^�� : �����ÓT���y�ێ��ғ��ܐ��Y�Ď��j��L�O����:�Ɖ���@�i�����p���t���b�g�j�v���u���ܐ��Y�Ď��j��L�O�������s�ψ���v���犧�s�����B�@
31p �@�@�����F��㊌����}���فF1005182660
�@�@�@�����F2008�N9��28�� �ꏊ�F����s����ّ�z�[��
�X���A���j����ҋ��c��ҁu���j�n������ (727)������;�v���u���j����ҋ��c��v���犧�s�����B�@pid/11198454
|
���ꂩ�猩������{--�����E���ȏ��E��n�E
�@�@������--�Ȃ���ߋ��ƌ���//1�`136
�����Ƌ��ȏ����//10�`53
�����c�Ȃ��������ꌧ���̉^���m�� ��E��㌧������
�@�@�������鍂�Z���̔����n/�R�� ���j/10�`19
�u�W�c�����v���ȏ�������̌o��/��{ ��/20�`27
��]�E��g�����ٔ��̑��_/���q �O/28�`31
�u�W�c�����v�͂Ȃ��N�����̂�/�� ���j/32�`39
�̌��҂������d�������J����/�Ӊ� ����/40�`46�A1�`
������w�ԍ��Z������--�u�W�c�����v�R���폜���ȏ������
�@�@�����ނ�/��]�F �R��/47�`53
��n���������铇 ����//54�`91
���ē����ĕ҂Ɖ���̌���/��v�� �N�T/54�`59�A2�`
�A�����J�̑Β����R���헪�Ɖ���/��� �/60�`65
�u�����m�̗v�v--�A�����J��̉��̉���/��� �`�O/66�`69
����̕��A���u���{�v�ɖ₢�����Ă��邱��/�ەl ��/74�`91
�ČR��n�g�p���́A�N���A
�@�@�������略���Ă���̂�/���� �גj/82�`85
��n�Ԋ҂łǂ��������ꂪ�����̂�
�@�@��--�ǒJ���̎��g�݂Ɖۑ�/�k��c ��/88�`91�A3�`
�R����//70�`
������A�����J�Ɂu�����������v�V�c�Ɠ��{���{/���q�O/70�`
�_���̌ւ���������ɍ]���̓y�n����/�V���/72�` |
�ʐ^�Ɍ���x�g�i���푈�Ɖ���/�⍪����/78�`
������Ė���/�I�����q/80�`
����n��/�n�剀��/86�`
����̕����E���R//92�`111�A4�`
���Z�����x��u�G�C�T�[�v�̖���--�����Ղł̃X�e�[�W���\����
�@�@���n��̊�����/��Y �p�Y/92�`95
�S�������܂������鉫��̉S/���� �ލ�/96�`99
���̂���a���\�H�ƕ���/������/100�`
�ό��Y�Ƃ̌��Ɖe/�ēc ��/106�`111
�R����//102�`
�o���G�e�B�u��n�����v���猩���邱��/�R�c��q/102�`
�f���Ŋw�ԉ���/�Ҍ��i/104�`
����Ɩ{�y���ނ���//112�`136
����Ɓu�{�y�v��"���x��"�̔w��ɂ������/���� �L��/112�`117
�ČR��n�̂���܂��ň������/�m�Ԗ���/118�`
���ꂩ�痈�Ďv������/�_�Ԑ^��/120�`
���H�L�^�^���w�Z6�N �����ʼn�����`����/���� �喞/122�`125
���H�L�^�^���w�Z ����킩�牽���w�Ԃ�
�@�@��--�����W�c���̎��Ƃ���/���� ���Îq/126�`130�A1�`
���k�� ����ƂȂ��鎄����--����̎��ɂ݂�Ȃ��������
�@�@���o��������炱��/�R�� �v�ܘY ;�ēc �� ;���� �_��/131�`136
�j�Ղ����(125) ���ꗤ�R�a�@�앗�����Q20��
�@�@�� �i���ꌧ�앗�����j/�É꓿�q/5�` |
�X���A�J�쌒��[�ҁu�q����r�_�W�� : �p���킪���� ��3�� (�N���_��)�v���u���{�}���Z���^�[�v���犧�s�����B�@
�@�@���L �u�N���_���v (�؎���1971�N��) �̕���
|
�g�Ɗ� / ���֏�v ��
���������Ƃ��̌��� / �{�Ǔ��s ��
���d�R�Q���̌Ñ㕶�� / ���֏�v ��
�����̌���Ɩ����̋N�� / �����l�Y �� |
�����̌���Ɩ����̋N�� / ���֏�v ��
���������̘_�l�ɓ����� / ���֏�v ��
�����̌���Ɩ����̋N�� / �����l�Y ��
���{��̗��������ɂ��� / �����l�Y �� |
�쓇��j����̋Z�p�ƕ��� / �������� ��
�쓇�̖������� / �������� ��
���A��㊍l�Êw������� / �F��p��Y ��
��� / �J�쌒�� �� |
�P�O���Q�S���t�A�ǔ��V���Ɂu���{�̒m�́^��T���@�@���ōl����u�R�v�v�̒��ŁA�u�{�Ó��̐l�X���_�X�ƌ𗬂���E�^�L�B�K�W���}���̖X�ɕ���ꂽ�X�̒��ɂ������v�ƁA�f�ڎʐ^�̐������t����������B
�P�O���A�f�������u�Րl�G�C�T�[ ���ꌧ�E�{�y���A35���N�L�O��i 1�`�R�v���u�V��v���犧�s�����B
�@�V���[�Y���F (�����̕�)�@�i�r�f�I (�f�B�X�N)�j
|
| �m�� |
���^�n |
| 1 |
(1)�I�[�v�j���O(2)����s�o��N��(3)����s�ÊԗǐN��(4)����s�Z�g�N��(5)����s���{�N��(6)�X��p�s��@�ÐN��
(7)����s�������N��(8)�J�`���[�V�[(9)�G���f�B���O |
| 2 |
(1)����s���~���N��(��) (2)�Î�[���猴�G�C�T�[�ۑ��� (3)�����s�嗢�N�� |
| 3 |
(1)�I�[�v�j���O(2)�k�J���h���N��(3)����s�z���N��(4)����s�Ԗ�N��(5)����s���c�N��(6)�J�`���[�V�[(7)�G���f�B���O |
|
�P�P���A�{���N�F�����傤�����ҁu�I 25(11)�@ p.3�`5�v�Ɂu�����{��T����(20)�����̓��Ő������v��--���ꌧ�n���쓇�v�\����B
�P�P���A���ǎ����ҏW�ψ���ҁu���ǂ̎����v���u�ߔe�s���Ǖ�F��v���犧�s�����B�@�@�@
|
�����̂��Ƃ@�ߔe�s���Ǖ�F���@�ԕ��x���@i
�����ɂ������ā@���ǎ����ҏW�ψ����@��u���h�@ii
�u���ǂ̎����v�����Ɋā@�ߔe�s���@�����Y�u�@iii
�j���@�ߔe�s���ǎ�����@��u�L���@iv
��1�ҁ@���ǂ̎��R�@13
��1�ҁ@��1�́@�C��E�n�`�E�n���@14
��1�ҁ@��1�́@��1�߁@�C��@14
��1�ҁ@��1�́@��2�߁@�ʒu�E�n�`�@17
��1�ҁ@��1�́@��3�߁@�n���E�y��@20
��1�ҁ@��2�́@�A���̕��z�@22
��2�ҁ@���ǂ̗��j�@25
��2�ҁ@�͂��߂Ɂ@26
��2�ҁ@��1�́@���{����̍��ǁ@27
��2�ҁ@��1�́@��1�߁@�L����Ԑ؎���̍��ǁ@27
��2�ҁ@��1�́@��2�߁@���\�Ԑ؎���̍��ǁ@31
��2�ҁ@��1�́@��3�߁@���{����̍��ǂ̍��J�@35
��2�ҁ@��2�́@��������`���a��O���̍��ǁ@38
��2�ҁ@��2�́@��1�߁@��������`���a��O���̉���@38
��2�ҁ@��2�́@��2�߁@�n�����x�̕ϑJ�Ə��\�E���ǁ@46
��2�ҁ@��2�́@��3�߁@��������`���a��O���̏��\�@49
��2�ҁ@��2�́@��4�߁@��������`���a��O���̍��ǁ@62
��2�ҁ@��3�́@�����m�푈���̍��ǁ@70
��2�ҁ@��3�́@��1�߁@���ǂւ̗F�R(���{��)�̒����@70
��2�ҁ@��3�́@��2�߁@�����̑a�J�̌��@71
��2�ҁ@��3�́@��3�߁@�����̊w���a�J�̌��@73
��2�ҁ@��3�́@��4�߁@�����̐푈�̌��@79
��2�ҁ@��4�́@��㕜�����̍��ǁ@104
��2�ҁ@��4�́@��1�߁@�����y�n���x�E�����Z��x�@104
��2�ҁ@��4�́@��2�߁@�R��Ǝ���@108
��2�ҁ@��4�́@��3�߁@���̌�y�@112
��2�ҁ@��4�́@��4�߁@���ǂ̍ЊQ�@114
��2�ҁ@��4�́@��5�߁@���ʉ݂̕ϑJ�@116
��2�ҁ@��5�́@�C�O�ږ��@123
��2�ҁ@�͂��߂Ɂ@123
��2�ҁ@��1�߁@���ꌧ�ɂ�����C�O�ږ��̓����@124
��2�ҁ@��2�߁@���ǂ���̊C�O�ږ��Ɣ��d�R�J��ږ��@127
��2�ҁ@��6�́@���ǂ̋���Ƃ��̊��@130
��2�ҁ@��6�́@��1�߁@���������ȍ~�̊w�Z����@130
��2�ҁ@��6�́@��2�߁@�q�������r��O�̏��q����@139
��2�ҁ@��6�́@��3�߁@��㋳��̏o���E���\�̋���@153
��2�ҁ@��6�́@��4�߁@���琧�x�̕ϑJ�@156
��3�ҁ@���ǂ̐����ƕ����@161
��3�ҁ@��1�́@���ǃ����̐����@162
��3�ҁ@��1�́@��1�߁@�����̓����@162
��3�ҁ@��1�́@��2�߁@�����̔_�ƂƐ����@163
��3�ҁ@��1�́@��3�߁@�������̏��E�@166
��3�ҁ@��1�́@��4�߁@�������@�@166
��3�ҁ@��1�́@��5�߁@�����̐����@168
��3�ҁ@��2�́@���J�s���Ɛ��n�@171
��3�ҁ@��2�́@��1�߁@���ǂ̌�ԂƓa�@171
��3�ҁ@��2�́@��2�߁@���J�s���̎i�Վҁ@172
��3�ҁ@��2�́@��3�߁@���ǂ̚����E����ԉƁ@172
��3�ҁ@��2�́@��4�߁@���k�O�Ɓ@174
��3�ҁ@��2�́@��5�߁@���ǂ̐���E�����K�[�@174
��3�ҁ@��2�́@��6�߁@�E�����O���[�k�E�B�[�@175
��3�ҁ@��3�́@���ǂ̍Ղ�ƔN���s���@177
��3�ҁ@��3�́@��1�߁@���ǂ̔N���s���@177
��3�ҁ@��3�́@��2�߁@���ǂ̍j�����@178
��3�ҁ@��3�́@��3�߁@�O���s���@180
��3�ҁ@��4�́@�l���V��@182
��3�ҁ@��4�́@��1�߁@�D�P�E�o�Y�@182
��3�ҁ@��4�́@��2�߁@�����@182
��3�ҁ@��4�́@��3�߁@�����@183
��3�ҁ@��4�́@��4�߁@�^���J�[���[�G�[�@184
��3�ҁ@��4�́@��5�߁@�Ǝ���`���@184
��3�ҁ@��4�́@��6�߁@�W���[�T�����[�G�[�@184
��3�ҁ@��4�́@��7�߁@�n�W�`(�j��)�@186
��3�ҁ@��4�́@��8�߁@�z��҂̑I���E�����@188
��3�ҁ@��4�́@��9�߁@�J�W�}���[�@188
��3�ҁ@��4�́@��10�߁@�l�Ԃ̎��@�����̏����Ƒ��V�@190
��3�ҁ@��4�́@��11�߁@�@192
��3�ҁ@��5�́@���ǂ̖����|�\�Ƒ��V�с@193
��3�ҁ@��5�́@��1�߁@�N�V���b�L�[�@193
��3�ҁ@��5�́@��2�߁@���V�с@194
��3�ҁ@��5�́@��3�߁@�їV���@196
��3�ҁ@��5�́@��4�߁@���\�Ԑ،����@196 |
��3�ҁ@��6�́@���ǂ̉����@199
��3�ҁ@��7�́@���ǂɉł��ł��ā@201
��3�ҁ@��7�́@��1�߁@���ǂɉł��ł���܂Ł@201
��3�ҁ@��7�́@��2�߁@���ǂ̐������@203
��3�ҁ@��8�́@���ǂ̈߁E�H�E�Z�@205
��3�ҁ@��8�́@��1�߁@�߁@205
��3�ҁ@��8�́@��2�߁@�H�@208
��3�ҁ@��8�́@��3�߁@�Z�@214
��3�ҁ@��9�́@���ǎs��S���̍��̍��ǁ@218
��3�ҁ@��10�́@���ǂ̕����@221
��3�ҁ@��11�́@���ǂ̖��b�@226
��3�ҁ@��11�́@��1�߁@�q����������ȁ@��u�h���@226
��3�ҁ@��11�́@��2�߁@�����ɉ������@��u���q�@228
��3�ҁ@��11�́@��3�߁@�������̃E�^�L�̘b�@��u�����Y�@231
��3�ҁ@��11�́@��4�߁@����ԍ��͂Ɛԗ�W�b�`���N�@��u�Ï��@232
��3�ҁ@��11�́@��5�߁@
�@�@���ԗ�W�b�`���N�ƃe�B�[�W���N����ˁ@��u�Ï��@235
��3�ҁ@��11�́@��6�߁@�p�q�ƓJ�@��u�g�~�@236
��4�ҁ@���ǂ̖咆�@239
��4�ҁ@��1�́@�e�咆�̗R���ƍ��J�@240
��4�ҁ@�͂��߂Ɂ@240
��4�ҁ@��1�߁@�V�_�咆�@241
��4�ҁ@��2�߁@�����a���咆�@242
��4�ҁ@��3�߁@��咆�@244
��4�ҁ@��4�߁@����咆�@245
��4�ҁ@��5�߁@�������咆�@247
��4�ҁ@��6�߁@���쏬�E������咆�@248
��4�ҁ@��7�߁@�O�˖咆�@249
��4�ҁ@��8�߁@���䏬�咆�@250
��4�ҁ@��9�߁@�ԗ����@251
��4�ҁ@��10�߁@�O�㌴�咆�@252
��4�ҁ@��11�߁@����咆�@253
��4�ҁ@��12�߁@�b��u�咆�@254
��4�ҁ@��2�́@���ǂ̚����u����ԉƁv�Ɓu����咆�v�̗R���@258
��5�ҁ@������(1)�@265
��5�ҁ@��1�́@������蒲���̋L�^�@266
��5�ҁ@�͂��߂Ɂ@266
��5�ҁ@��1�߁@��1�����@267
��5�ҁ@��2�߁@��2�����@289
��5�ҁ@��2�́@���ǂ̐l���@326
��6�ҁ@���ǂ̌���Ɖۑ�@341
��6�ҁ@��1�́@���Ǖ�F��̌���Ɖۑ�@342
��6�ҁ@��2�́@���ǎ�����̌���Ɖۑ�@343
��6�ҁ@��3�́@���ǒ�����̌���Ɖۑ�@344
��6�ҁ@��4�́@���Ǖw�l��̌���Ɖۑ�@345
��6�ҁ@��5�́@���NJ����ۑ���̌���Ɖۑ�@346
��6�ҁ@��6�́@�G�^�@349
��6�ҁ@��6�́@��1�߁@���Ǖ�F��ɂ��
�@�@��������ԉƉ��~�Վ擾�̌o�߁@349
��6�ҁ@��6�́@��2�߁@���ǂ̌R�p�n�@���̎擾�Ɗ��p�@350
��6�ҁ@��6�́@��3�߁@�����Ɋ��҂���@��u���`�C�ɖ�O����q353
��7�ҁ@�ʐ^�Ō��鍂�ǁ@355
��7�ҁ@I�@�ČR�㗤���O�̍��ǁ@356
��7�ҁ@II�@��㕜�����̍��ǁ@358
��7�ҁ@III�@���Ǖ�F��W�@369
��7�ҁ@IV�@�ǎ�����W�@377
��7�ҁ@V�@���ǒ�����W�@391
��7�ҁ@VI�@���Ǖw�l��W�@394
��7�ҁ@VII�@���ǐN��W�@398
��7�ҁ@VIII�@���ǂ̑�j�����E�����W�@408
��7�ҁ@IX�@�����ҏW�W�@420
��8�ҁ@������(2)�@433
��8�ҁ@��1�́@�u���\�����T�v(���a11�N)�v(��)�@434
��8�ҁ@��2�́@�u�����\��������
�@�@���ߔe�s���ւ̎������p��(1954�N)�v(��)�@444
��8�ҁ@��3�́@�n�}�����@449
��8�ҁ@��4�́@���ǂ̗��j�N�\�@451
��8�ҁ@��5�́@�u���a�̑b�v��������@���Ǐo�g��v�Җ���@462
��8�ҁ@��6�́@���NJW�c�̂̉�E���Z�E����ꗗ�@470
��8�ҁ@��6�́@��1�߁@��@470
��8�ҁ@��6�́@��2�߁@���Z�@481
��8�ҁ@��6�́@��3�߁@����ꗗ�@489
��8�ҁ@��7�́@���Ǖ�F��������@496
��8�ҁ@��8�́@�ҏW�ψ����@507
�ӎ��@512
�ҏW��L�@513
|
�P�Q���A�{��\�P���u������ = Island power : ���̕����� 3(2) (�ʍ� 6) p.62�`77�@�N�C�`���[�p���_�C�X�F�̉�v�Ɂu�g�x�ւ̓�--�d�v���`�������ێ���(�g�x����)�l�ԍ���
�{��\�P�v�\����B�@�@ (��̓��̋{��y�� �g�x)
�P�Q���A�ʏ钩�O��,�@�c���p�@�ďC�@�{��\�P�w���u�g�x���S���� ����̓`���|�\
: �������y��w�������y���������J�u�����v���u���{�E�G�X�g�~���X�^�[�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�^���f�B�X�N 1�� (58��) �^��: 2000�N11��8�� �@�@�ꏊ�F�������y��wJ�كX�^�W�I
|
(1)�V�l�x������ŕ�(2)��O�x���Ă���(3)��˗x������(4)��˗x�O�̕l(5)�g�x���S����
���t:����L��,�ԏ�p��,�Y��F�Y(�̎O��) ���ǎ��](�) �Ð����M(�J) �V�_�r��(�Ӌ|)
���ߗ�O(����)
�@�@�� �V�_��,���]�T�g,�Î芡�ш�,�ΐ쒼��,�Ð����F,���ÏC(VO) |
|
���A���̔N�A����s�����y�����ٕҏW�u����s�̃G�C�T�[ : �`���̌p���҂����v���u����s�����y�����فv���犧�s�����B�@
(����s�����y������ ���W ; ��36��)
���A���̔N�A����S���G�C�T�[�܂���s�ψ��ҁu����s�G�C�T�[�C�x���g���S�K�C�h
: �G�C�T�[�̂܂�����s�v���u����S���G�C�T�[�܂���s�ψ���v���犧�s�����B
���A���̔N�A���،��m���u���{�����l�ފw������\�v�|�W 2008(0) p.75-75�v�Ɂu����`���|�\�u�G�C�T�[�v���猩����u�Ĕ����ҁv�ƃG�X�j�V�e�B�̒n�搫�v�\����B�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (16)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
������佂Ɖ���--���ꗷ�s���̓��L�ƍ�i��ʂ��ā@���� ���q p.11�`30 |
���ꉹ�y�̋ߑ㉻�Ɖ��R���� �@�O�� �킩�� �@p.157�`178 |
���A���̔N�A�����K�ꂪ���m�_���u�w�����낳�����x�𒆐S�Ƃ��问�����w�̌����v�\����B
���A���̔N�A���y��������ҁu���y������ (�ʍ� 25) �v�����s�����B
|
�����q���f�~�b�g�́u�O�q���v�Ɋւ����l�@--�s�����Ɂc
�@�@�����Ƃł����� In einer Nacht... Traume und Erlebnisse�top.15���Ƃ��ā@�ɓ����� p.1�`14
�������͂��������t�j�����̎���--���[�c�@���g��Ȍ����ȑ�40�ԑ��y�͖`���̉��t���͂�ʂ��ā@�쒆���q,�r��b�q
p.15�`34
�̎��E�y������ ���ꌧ���A�m�����u�̎�x��G�C�T�[�@�@���ь��] p.35�`57
�̎��E�y������ ���ꌧ�������ӓy���̃G�C�T�[�@�@���эK�j p.59�`86
���t�̃��Y���w�K�Ƃ��Ẵ��H�C�X�E�v���_�N�V����--�u���Ղ�v�̑n��w�K���Ɂ@�@���E
p.87�`96
���ׂ�����p������Q���ۈ���H--�u�ւ̑��`�v�ł̗V�тɊւ���l�@�@�@�a�c�K�q
p.97�`108 |
���A���̔N�A�g�Ɗ� �i�g���u�A�W�A������������ 7(0) p.175-187�v�Ɂu�쓇�̗w�̉������v�\����B�@J-STAGE
���A���̔N�A�R���ӈꂪ���V�̂Ȃ��������ҁu�ǂ��Ɛ̘b = Children and folktales : �q�ǂ��Ɛ̘b��������l�����̋G���� (37) p.16�`22�v�Ɂu���ɂƂ��Ă̘̐b--�̘b�������҂����̕��� �̋������哇�̓`���ɖ�����āv�\����B
���A���̔N�A ���ђ������u�������Љ�ɂ�����@���ƕ��� : �������� (12) p.67�`76�@�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v�Ɂu��������������� �Ɖ��q�q
(�x�i�q�Îq�搶�ސE�L�O�� ; ���J�V���|�W�E�� �u�������Љ�̏�������--���̐�������ǂ݉����v��)�v�\����B |
| 2009 |
21 |
�E |
1���A���g�Ύ}�̉�ҁu �����w�э������� : ���ꌧ���|�p��w�ފ��L�O�����@�i�����p���t���b�g�j�v���u���g�Ύ}�̉�v���犧�s�����B �@�@�@�����F����21�N1��11�� �ꏊ�F�������ꂨ���Ȃ�@�@19p �@�����F��㊌����}���فF1005890973
�P���A�g���������u���{�S���_�b�E�`���̗��v���u�א��o�Łv���犧�s����B�@
|
��
��㕔�@����̓`��
��㕔�@�������牫��ց@��Z��
��㕔�@��ԂƓV���E���V�`���@��Z���
��㕔�@�`���n��K�˂�
��㕔�@������ԁ@�{�Ó��s���ǎ������@��Z���
��㕔�@�K�Ԍ�ԁ@�{�Ó��s���ǎ������@��Z�O��
��㕔�@�ڗ��^(��)��ԁ@�{�Ó��s���n���얞�@��Z�O��
��㕔�@����ꂽ�`���n�@��Z�O��
��㕔�@��X��@�X��p�s�^�u��@��Z�O��
��㕔�@�G�X�q��@��������Ӂ@��Z�O��
��㕔�@��h��@�앗�����{���@��Z�O��
��㕔�@�v�꓄�@�^�ߌ����^�ߌ��@��Z�O�O
��㕔�@�Ί_���̌�ԁ@��Z�O�O
��㕔�@�����ԁ@�Ί_�s�o���@��Z�O�O
��㕔�@�{����ԁ@�Ί_�s�Ί_�@��Z�O�O
��㕔�@�_�̓��@��Z�O�Z
��㕔�@�`���n��K�˂�
��㕔�@�v�����@���s�m�O���v���@��Z�O�Z
��㕔�@�A�}�~�L���̕�@����s(�l��Ó�)�@��Z�l��
��㕔�@�����@���s�ʏ鎚�S���@��Z�l��
��㕔�@���V�ԋ{�@�X��p�s���V�ԁ@��Z�l�O
��㕔�@�썑�_�ЂƉ��{�@�ߔe�s�����R���@��Z�l��
��㕔�@���E��Y�̏�Ƌ��Ձ@��Z�l�Z
��㕔�@�`���n��K�˂�
��㕔�@���A�m��Ձ@���A�m���@��Z�l�� |
��㕔�@�����Ձ@���鑺���@��Z�l��
��㕔�@���A��Ձ@����s���A�앗���@��Z�ܓ�
��㕔�@���얡��Ձ@�ǒJ�����얡�@��Z�ܘZ
��㕔�@�m�ԏ�Ձ@����s�m�ԁ@��Z�ܔ�
��㕔�@�֏��ԁ@���s�m�O���v�茘�@��Z�܋�
��㕔�@���䉮����ԐΖ�@�ߔe�s�@��Z�Z�Z
��㕔�@�ʗˁ@�ߔe�s���钬�@��Z�Z��
��㕔�@�������@�ߔe�s�^�n�@��Z�Z��
��㕔�@�^�ߍ����@�C���ՂƓV�ɕ@�@�^�ߍ����@��Z�Z��
��㕔�@�C���Ձ@��Z�Z��
��㕔�@�V�֕@�@��Z�Z��
��㕔�@����̖��������@��Z�Z��
��㕔�@�`���n��K�˂�
��㕔�@�������ꔎ���فE���p�ف@�ߔe�s�����뒬�@��Z�Z��
��㕔�@����ᏼ�̕�@�k���鑺���J���@��Z�Z��
��㕔�@�����Ɓ@�k���鑺���@��Z�Z��
��㕔�@�Ԍ��q�{�@�ǒJ���^�Ӂ@��Z����
��㕔�@���B���@�ߔe�s�v�ā@��Z���l
��㕔�@�V�[�T�[�@��Z���Z
��㕔�@�`���n��K�˂�
��㕔�@�x���̐Β��厂�q�@���d�����x���@��Z����
��㕔�@�≮���@�ߔe�s�≮���@��Z����
��㕔�@����V�[�T�[�̈ڂ�ς��@��Z���Z
��㕔�@��b�A���b�Ƃ��ẴV�[�T�[�@��Z����
��㕔�@�Ί��c�@��Z���Z
�� |
�P���A�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�ҁu�J����N�L�O �������ꂨ���Ȃ�J��L�O�����ʐ^�W�v
���u�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s�����B�@�@�@ 15p�@�@�����F��㊌����}���فF1004779573�@[2009.1��]
�Q���A���ь��],���эK�j�����s���q��w���B����w���I�v�ҏW�ψ���ҁu���s���q��w���B����w���I�v = Bulletin of the Faculty of Human Development and Education (5) p.99�`112�v�Ɂu���ꌧ���A�m���Ӗ��̎�x��G�C�T�[�v�\����B�@�@�iIRDB�j
�Q���A���{�|�p�����U��������꒲���{�������E�ҏW,�����K�Y�ďC�u���{�̓`���|�\�u�����x�E�����v���u�W���Ёv���犧�s�����B
|
���{�|�\�̌����E��y / �������q ��
���Ђ̍ՋV�ƌ|�\ / �����P�� ��
������|�\�҂��� / �^��r�a ��
�\�E�����̐����̔w�i / �����S�� ��
�\�̕���Ɖ��o�E���Z / �R����q ��
���� / �Έ�ώq ��
�K�ᕑ�E�ȕ� / �����K�� �� |
�̕���̐����Ɣ��W. 1 / �a�c�C ��
�̕���̐����Ɣ��W. 2 / ���Ηz�q ��
�̕���̕\�� / �n�ӕ� ��
�l�`�ŋ��̗��� / �R�c�a�l ��
�l�`��ڗ�(���y)�̔��W / �㓡�Õv ��
���x���Ɨx / ��؉p�� ��
����̌ÓT���x / �X�۞Ď��Y �� |
��O�|�\�̗��� / ���������Y ��
�\ / �n粎�� ��
�̕��� / �_�R�� ��
���y / �X���^�| ��
���x / �È�ˏG�v ��
�E
�E |
�R���A���،��m�����m������w�����������������ҁu�����̕������� = Journal of cultural symbiosis research (2) p.180�`190�v�Ɂu���m���ɂ����郍�[�J���ȉ���G�X�j�V�e�B--�n�搫�ɍ�p���鉫��|�\�u�G�C�T�[�v�v�\����B
�R���A���эK�j�A���ь��]���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
21 p.61-84�v�Ɂu���G�C�T�[�̉��y(����1)�v�\����B�@�@�@���@�u���G�C�T�[�̉��y(����1)�v�Łi����2�j�i����3�j�Ɖ]���悤�ȑ��҂��s���Ȃ̂Œ����m�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�R�E�U�@�ۍ�
�R���A�O���킩�Ȃ��u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 21
p.99-111�v�Ɂu�R�����j�ɂ���O���̉��y�����v�\����B
���ꌧ���|�p��w �f�ڎ� ���ꌧ���|�p��w�I�v / ���ꌧ���|�p��w �� (17)
2009�E�R
|
Le paysage aixois ou Bellevue vu et peint par Paul Cezanne �@��� �t�j
p.1�`11
�w���o�c�ɐ������Љ�I�X�L���̌���(7)P-F�X�^�f�B��p���Ă̌���[�� �����w�K�w����]�@�@�V��
��,���v�{ ����,���� �L�q p.13�`31
�w���S�����x�̎ᏼ�̖�--�Y�j(�R�P�b�g)�Ƃ��Ă̎ᏼ�@�@�g�� ���Y p.33�`46
����̒n�敶���`�����߂��鏬�w�Z�ƒn��̘A�g�ɂ��ā@�@�F�V ��� p.47�`62
�@����`�ƒn��Љ�̖����w�I�싻�_--�����p�ƈɌv���Ƃ̊C��g���l���\�z���l����@�@����
�v�p p.63�`83
����N�v�̍�ƓI�p��(1)��������--�e���r�r�{�ƂƂ��Ă̋���N�v�@�@��� �M��
p.85�`99
�����ɂ����镧���M�Ɋւ����l�@--�����ɂ����镧���M�̎�e�ɂ��ā@�@������
�M p.101�`120
�u�]�ˏ��̌|�\�v��藮�����x��i����--�����l���y�䊪���A�����l���y����V�}����ɕ������݁@�@���g
�Î} p.121�`140
�J�g�u�y���v�̈핶���߂��鏔���@�@���� ���q p.141�`153
�R�����j�ɂ���O���̉��y�n��--���̌��y�ѐV���w�W�������𒆐S�Ɂ@�@�O��
�킩�� p.155�`174
�ׁ[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^��i31�̓��̏��ŕ����߂����ā@�@��� ���q
p.175�`192
�A�����J���y����V�X�e��(1)���t���m�ے��@�@��� �p�� p.193�`201
�_�ƕ��l�ɂ��Ă̈�l�@�@�@���q ���� p.205�`209 |
|
���g�Ύ}���u���ꌧ���|�p��w�I�v�i5�`17�j�v�ɔ��\�����_���̓���ꗗ�\
| ���m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
�i5�j p.19-32 |
1997-03 |
�������x�ɂ�����g�̋Z�@ : �u�K�}�N����v�Ɋւ��錤���@�@���g ���]�} |
| 2 |
(9) p.75�`92,102 |
2001-03 |
�����X�g���b�`���O--�X�g���b�`���O�������ꂽ�������x�̊�{���� ���g�Ύ} |
| 3 |
(10) p.95�`117 |
2002-03 |
�������x�ɂ�����������x�̌���--����S���̑n�앑�x��i��� ���g �Ύ} |
| 4 |
(11) p.149�`151
�}����7�`8�@�d�v |
2003-03 |
�n��m�[�g �������̏�(���S����) �@���g�Ύ} |
| 5 |
(12) p.51�`63 |
2004-03 |
�����ÓT���x�ɂ݂��O�x��̑n�쌤��--���{�I�������Ƃ���ꂽ��O�x��w�Փ��R�x
���g�Ύ}
|
| 6 |
(13) p.171�`193 |
2005-03 |
�����g�^�ɋL�q���ꂽ�����|�\--�u���q�x�v�����̎��� �\���E�앑�ɂ��� ���g �Ύ} |
| 7 |
(14) p.111�`124 |
2006-03 |
�n�앑�x�u�������̏��v�̌���--�ʏ钩�O5�ԑg�x�u���S�����v��� ���g �Ύ} |
| 8 |
(16) p.133�`147 |
2008-03 |
�����g�^�ɋL�q���ꂽ�����|�\--�u���H���v�����̎��� �\���E�앑�ɂ��� ���g
�Ύ} |
| 9 |
(17) p.121�`140 |
2009-03 |
�u�]�ˏ��̌|�\�v��藮�����x��i����--�����l���y�䊪���A�����l���y����V�}����ɕ������� ���g �Î} |
|
�P�@���R���A���g�Ύ}�ҁu���x�n�쌤���_���W : ���ꌧ���|�p��w�I�v�v���u���g�Ύ}�v�����s����B
�@�@�@183p �@�@�����F��㊌����}���فF1005883473�@
�@�@�@���u�u�]�ˏ��̌|�\�v��藮�����x��i����--�����l���y�䊪���A�����l���y����V�}����ɕ������݁v�̔������m�F���K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�P�O�@�ۍ�
�@�@�@�@�܂��A�u���x�n�쌤���_���W�v�͉�No1�`9�̘_����Z�߂�ꂽ���̂��m�F���K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�P�P�@�ۍ�
�R���A�O���킩�Ȃ����ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ�
: ���ꌧ���|�p��w���y�w������ (10) p.65�`80�v�Ɂu�ߑ㉫��ɂ����鉹�y����ς̕ϑJ--�G���w��������x�w���ꋳ��x�̕��͂�ʂ��āv�\����B�@�@�@�@
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 42(2) (�ʍ� 104) ���@�����P�搶���a�S�N�L�O�V���|�W�E�����W���v�����s�����B
|
���@�����P�搶���a�S�N�L�O�V���|�W�E�����W�� p.1�`158
�������l �@���@�����P�@ p.1�`53
�����ɂ��Đ^����m��A�����l�ɓ`���邩--la verite
�@���q�^���r�����܈�̃L�[���[�h�Ƃ��ā@�㑺�K�Y p.56�`60
�u�Ђ߂��v�͂ǂ̂悤�ɕ\�ۂ���Ă�����--
�@���n�����́u�Ђ߂��v�\�ۂ𒆐S�Ɂ@������ p.61�`70
�쓇�_������݂��I���������̈ꑤ�� �@�Ɖ� �� p.71�`100
���ܒ��@�����P���ǂ��l���邩�@
�@�@�������H �^�s,�g�Ɗԉi�g,�떓�ɋv �� p.101�`111
|
�䂪�t�E���@�����P�搶��z�� �@�����H�^�s�@ p.101�`104
���@�����P�搶�ƃI�������� �@�g�Ɗ� �i�g p.104�`107
���������̊�b�z��--���z���������ōs���@�떓 �ɋv p.107�`109
�u�Ђ߂��v�̎�L�҂���--��l��l�̋L�^�㐢�Ɂ@���c�W�q p.109�`111
���@�����P�搶 ���N�� p.112�`119
���d�R���ە����̃��Y��=�A�N�Z���g�I�\��
�@�@���������������N���u p.158�`130
���@�����P�Ɨ������������N���u��
�@�@���A�N�Z���g������ ����܂� �����Ђ� p.129�`120 |
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g�F�s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@��(18)�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004846315
|
��������������U��Ԃ�--���܁Z�N��`���Z�N���
�@�@�����S�� �씨 �b p.1�`24
�������������j�̃i���e�B�� ���c ���j p.25�`40
�ČR����������ɂ�����t�B���s���l�ւ̂܂Ȃ���--
|
�@�@�������N�Ԃ̐V���L�������Ƃ� ���� �M p.41�`59
�{�錧�ېX���̋������X�u�Ȃ�ł���v�̌���Ɖ\���ɂ���
�@�@��--����{���k���̋������X�Ɣ�r���Ȃ��� �y�� �� p.77�`60
�����ւ̏o���_--��ւ̂܂Ȃ��� ��� �� p.82�`78 |
�R���A������w�ҁu�Z�����鋫�E�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@�@�@
�@�@�@�@�@(���炩����̊w�Ǝv�z ; 2)�@�@331p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1004789242
|
����́u�@�v�̌��� ���� �S�� 12
���E�ɂȂ��鉫��̎����Ɩ��� ���� �� 22
����ߑ�j���l���� �ɍ� ���� 34
�ړ����鉫��̐l�X �@ ���c �@�� 44
�A�W�A�ɂ����鍑�ە����Ɠߔe��`�@ �m�O �� 54
����̑�����Љ���l���� �@ �Ό� ���p 64
�����������A�����Ȃ������̊C���� �@ ���� �C�� 74
���A�W�A�����������Ɨ��� �㗢 ���� 84
�z�����鉫��̑�O���y ���� �� 102
�{��z���� �@ ���� ���q 112
�E���g���}���������ς� �@ �R�� �G�Y 126
���M�щ���̓~�̊����Ɠ������� �@ ���c �p�� 140
GPS�Ō��������ʂ̃v���[�g�^�� ���� �q 158 |
����̋�C �V�_�Y�� 170
�Ȋw�̗͎͂�҂ɖ��Ɗ�]��^���� �@ ���� �h�O 182
�n��̑f�ނ����H���� �@ ���{ �� 200
��̓��̃C���^�[�l�b�g �ʏ�@�j�N ���c�@�q�a 210
�j���g�����낢�� ���c �� 224
����̓��p�� �ʏ� ���M 238
����̃��M ���� ���� 248
�����悤�̗��j�ƃT�C�G���X ���c ���� 260
��`�q������q�g�ƕa�C���݂� ���x ���� 272
�h��Ɗ��̑��݊W�ɂ݂鋤���̖� ���� �ǖ� 284
��̎�ᇕ��ː���w ����@�a�F �˔� �F�� 296
���炩�����ۓ��וی� �O�� �o���q �u���C���E�I���f���u���N 308
�E |
�V���A�V���j���u��剹�y�w�� (7) p.35�`48�v�Ɂu�R�����j�̗������y�����Ɓu�U�j�v�v�\����B
�V���A�u�A�W�A�V�w (124)�@���W ���A�W�A�̎��҂̍s���Ƒ��V�v���u�א��o�Łv���犧�s�����B
|
���A�W�A�̎��҂̍s���Ƒ��V �z�K�t�Y p.6�`12
���҂͎R�ɐ��ނ�?--�u���{�l�v�̗썰�ρE�čl �����O�v p.13�`19
�J�~�E���҂̕s�݂ƑO����~�� ��v�ۓO�� p.20�`28
�ƂƐ�c--���{�l�̐�c�ς̕ϗe�@�����r�q p.29�`37
���{�����̑����@���c�� p.38�`45
�I�{�ւ̑r�_�ɂ݂��鎀�҂̊ϔO �������� p.46�`52
���ւ̎v���Ƒ��ՋƎ� �R�c�T�� p.54�`62
��������Α���--����ɂ����鑒�V�̕ϑJ ���F�� p.64�`73
�؍��ɂ����āu�������v���҂𑗂邱��--
�@�@�����Z�N��̋L�^�ƋL����� �^��S�q p.74�`83 |
�؍��V���[�}���̎���� �˓c��S�q p.84�`95
�؍��L���X�g���̎��ҋV�� �����蓹 p.96�`104
����؍��̑��V���� �R�c���q p.105�`113
�u�l�C�Ɓv�Ɓu���y���v--������ׂ��n�́A
�@�@���������������Ȃ̂� ��v p.114�`122
�����Ñ�̍��̂��肩 ��`�O p.124�`132
�����̎����ϖI���M�v p.134�`143
�����̖��ԐM�ɂ����閻�E�� ��K���P�O p.144�`150
�����ɂ����鑒�V�Ǝ��҂̍s�� �ێR�G p.151�`157
���㒆���̑��V--�u�q�V�فv�𒆐S�� �c���a�F p.158�`167 |
�W���A�n粋ӗY���u������������ (10) p.303�`307�v�Ɂu�u�G�C�T�[�v�Ƃ͉��ł�������--�����Ă݂����n粑��ҁw���ꖯ�����T�x(�g��O����)�v�\����B
�W���X���i���j�A�������ꂨ���Ȃ�匀���ɉ����āA�u�����Ȃ�l�`�ŋ� �V�`�����_���[ : �l�`���c�����܂ �n��35���N�L�O�����v���J�����B�܂��A���̓��A�u�l�`���c�����܂���u�����Ȃ�l�`�ŋ� �V�`�����_���[ : �l�`���c�����܂ �n��35���N�L�O�����v�̃v���O�������z�z�����B�@
�@�@ �l�`���c�����܂�n��35���N�L�O�����v���O�����@ �����F2009�N8��9��(��)14�F30�J��
���F�������ꂨ���Ȃ�匀��
�W���A���{�q�ǂ�������ҁu�q�ǂ��̂����킹 : ��Ƌ��t�����ԎG�� (�ʍ� 702) ���W ����E�L���A�����ĕ��a�v���u�����ُ��X�v���犧�s�����B�@�@
|
���W ����E�L���A�����ĕ��a�@�@ p.7�`29
���퐶����ʂ��ĕ��a���l����-����u�앗�����q�ǂ�
�@�@�����a�w�K�𗬎��Ɓv�̎��݁@���ǎ��q p.8�`11
�L������싞�E�A�E�V���r�b�c��-���V���ɔ픚�҂�
�@�@���v���y���� �������q p.12�`17 |
�c���_�̎q�̐���--�w�����̎q�x�͎��̐l���̌��_ �@���c�痲 p.18�`20
���Z���̐����Ă�! ���a�w�K��ʂ��Ċw����--
�@�@���������Z�����a�[�~�i�[���̌o������@ p.21�`24
�V�����푈�������w��͍�����--
�@�@���u���͂Ȃ��̃s�[�X�E�H�[�N�v���߂����ā@���� �̂肱 p.25�`29 |
�X���A�쑺�L�ꂪ�u���V�i�C���J�|�\�j�_�����v���u�����Ёv���犧�s����B
|
���́@13
��@�͂��߂Ɂ@13
��@�����@17
���́@���k�T�T�C�l�̌n���ƌ|�\�@33�@���k���{�́l�ՁF�ϊ��s�\���T�T�C���H
���́@�E�v�@34
���́@�k�T�T�C�l�Ƃ́@35
���́@���J�|�\�j����݂��k���E�l�@38
���́@��@���_�u�_�k���ӍՂƂ��Ă̌n���v�ɂ��ā@39
���́@��@���_�u���M�̍��J�|�\�̌n���v�ɂ��ā@43
���́@�O�@��O�_�u�����A�Η��̌|�\�̌n���v�ɂ��ā@45
���́@�l�@��l�_�u�k���E�l�A������c�A
�@�@�����Ԃ̎ЍՂȂǂ̌n���v�ɂ��ā@49
���́@�l�@1�@�k�T�T�C�l�A�c�̌n���@49
���́@�l�@2�@�ЍՂ̌n���@52
���́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@58
���́@I�@�쓇�̃V�c�ƖL�N�Ձ@58
���́@I�@���ݓ`��1�@�����̃A���Z�c�@58
���́@I�@���ݓ`��2�@���������c�̃V�k�O�@60
���́@I�@���ݓ`��3�@���ꌧ�����p�n�您���
�@�@����n�E���Ԃ̃E���W���~�@63
���́@I�@���ݓ`��4�@�ÉF�����̃E���W���~�A�L�N�Ձ@63
���́@I�@���ݓ`��5�@���\���̃V�`�B�@65
���́@I�@���ݓ`��6�@�^�ߍ��̖L�N�Ձ@67
���́@I�@���ݓ`��7�@�g�Ɗԓ��̃��V���[�}�@69
���́@I�@���ݓ`��8�@���NJԓ��̖L�N�Ձ@71
���́@I�@���ݓ`��9�@�{�Ó��s���ǐ����̃��[�N�C�@73
���́@II�@�����̌��i�@75
���́@II�@���ݓ`��10�@�؍��S�����̓��R�N�b�@75
���́@II�@���ݓ`��11�@�ϏB���̐����\�V�ߍ@77
���́@III�@�ދV�ɔ��������с@79
���́@III�@���ݓ`��12�@�������N�b�̂����с\
�@�@����N�b�A�g���m���A��N�b�@79
���́@�S��炢(�T�V)�̌n���ƌ|�\�@87
���́@�E�v�@88
���́@��T�@89
���́@���Ԃ̙T�̌n���@90
���́@��@���_�u?�ɗR������T�̒T���v�ɂ��ā@92
���́@��@���_�u���Ԃ̙T�̌`���ɕ����̉e����
�@�@���l�����邱�Ɓv�ɂ��ā@93
���́@�O�@��O�_�u�w����̙T�x�̒T���v�ɂ��ā@96
���́@�O�@I�@�u�k�T�T�C�l�ɗR������Ƃ݂���
�@�@�������_�̂����сv�ɂ��ā@97
���́@�O�@II�@�u���J�Ǎ��ւ̜��Ƃ��̋��{�v�ɂ��ā@98
���́@�O�@III�@�u�Đ��ւ̋����v�ɂ��ā@101
���́@�O�@III�@���S�Y�ɂ��Ă̍ĔF���@108
���́@�O�@III�@���͂̂܂Ƃ߁@114
���́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@115
���́@I�@�T�Y�@115
���́@I�@���ݓ`��13�@�M�B�ȓ��]�y�Ƒ��̙T�Y�@115
���́@I�@���ݓ`��14�@�쓇�̗��K�ҁ@117
���́@II�@�������J�̂Ȃ��̙T�̂����с@119
���́@II�@���ݓ`��15�@���N�암���R�Ղ̔_�y���Ƌ�T�@119
���́@II�@���ݓ`��16�@���q�ގ��̃^���{�Ǝ��q�\
�@�@�����N�암�̉��ʋY���@121
���́@II�@���ݓ`��17�@���V�i�C�n��̎��q���@122
���́@III�@�Վ��̙T�̂����с@125
���́@III�@���ݓ`��18�@�����Ȃ̖k�l�Y�\�q�̐����F��@125
��O�́@�ނ̋V��̌n���ƌ|�\�@133
��O�́@�E�v�@134
��O�́@��@�މ̂Ƃ��Ă̋�́@135
��O�́@��@��̂Ɠ��V�i�C���ӂ̛ޑ��@144
��O�́@��@I�@���_�u�ނ̍��J�Ƃ��̏�ɂ�����
�@�@�����Y�̖��v�ɂ��ā@145
��O�́@��@I�@1�@��̂������̌����Ƃ��邱�Ƃɂ��ā@146
��O�́@��@I�@2�@���N�ޑ��̓W�J�ƌ|�\�ҁ@148
��O�́@��@II�@���_�u��̂ɂ݂���w�D�x
�@�@�����Ȃ킿���M(���D)�̖��v�ɂ��ā@153
��O�́@��@III�@��O�_�u��̒��̍Ō�̉�
�@�@���w�獰�x�ɂ�����Ԃ̈Ӗ��v�ɂ��ā@155
��O�́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@158
��O�́@I�@�Y���ɂ݂��钆���̛ޏ��̖��c�@158
��O�́@I�@���ݓ`��19�@�����Ȏ��J�����[���̘��S�Y�@158
��O�́@II�@���V�i�C�ɂȂ���؍��̛ޑ��V��@160
��O�́@II�@���ݓ`��20�@�؍������̎��җ싟�{�@160
��O�́@II�@���ݓ`��21�@�ϏB���̗����}���@162
��O�́@III�@��p�̓��m�A�@�t�̋V��@164
��O�́@III�@���ݓ`��22�@ቐ_����̏����Ƒ���@164
��l�́@���_���q�̌n���ƌ|�\�@169
��l�́@�E�v�@170
��l�́@��@���_�u�ω��ȑO�\�n�c���_�����ƌ|�\�v�ɂ��ā@173
��l�́@��@���_�u�����ꂨ��т��̎��ӂ�
�@�@�����_�����ƌ|�\�v�ɂ��ā@175
��l�́@�O�@��O�_�u���l�ω��ƌ|�\�v�ɂ��ā@177
��l�́@�O�@I�@�����̋Y���ɓo�ꂷ��ω��@178
��l�́@�O�@II�@�����j(����)��̊ω��@179
��l�́@�O�@III�@��蕨�̂Ȃ��̊ω��@180
��l�́@�O�@IV�@���ԍ��J�|�\�̂Ȃ��̊ω��@182
��l�́@�l�@��l�_�u�ω��Ȍ�̏��_�����ƌ|�\�v�ɂ��ā@184
��l�́@�l�@I�@�_�c�Ɗω��ȑO�̊C�̏��_�Ƃ̂Ȃ���\
�@�@���_�c�̋Y�����Ȃ����ƂƂ̊W�@185 |
��l�́@�l�@I�@1�@�_�c�̏o���@185
��l�́@�l�@I�@2�@�Â��C�_�M�T���A���̂ӂ��̌n���@186
��l�́@�l�@I�@3�@�����C�_�M�ɕt�����ꂽ�ω��ƛ_�c�@188
��l�́@�l�@II�@�ޑ��Ɠ����\�Ր��v�l��
�@�@����l���Ƃ����v�l�Y�̑��݁@189
��l�́@�l�@II�@1�@�ޏ����珗�_�ւ̋O�Ձ@190
��l�́@�l�@II�@2�@���Ɛ����̏��_�@190
��l�́@�l�@II�@3�@�T�_�Ƃ��Ă̖����ƕv�l�Y�@191
��l�́@�l�@III�@�p������̎哱������J�\�����̌|�\�@193
��l�́@�l�@III�@1�@�����̌|�\�Ƃ��ā@193
��l�́@�l�@III�@2�@�p��������J�̓����@194
��l�́@�l�@III�@3�@�p��������J�̂܂Ƃ߁@197
��l�́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@198
��l�́@I�@���_�Ƃ��Ă̊ω��@198
��l�́@I�@���ݓ`��23�@�ω���F�̒a�����@198
��l�́@I�@���ݓ`��24�@�����ȓ���s��������
�@�@���ژA�Y�\�ω��Ɨ����@199
��l�́@II�@�Ր��v�l�ɂ��ߊց@202
��l�́@II�@���ݓ`��25�@�����Ȏ��J�����[���̑��Ɣk�}��202
��l�́@III�@�p������ɂ����J�\�����̌|�\�@204
��l�́@III�@���ݓ`��26�@�p������̐擱����`�m�M�Z�i��204
��l�́@IV�@�����̋Y���̂Ȃ��̏��E�m�����\������̖���206
��l�́@IV�@���ݓ`��27�@��Y�ɂ����鏗�������@206
��́@�ԁA�ւƍ��J�|�\�@213
��́@�E�v�@214
��́@��@�Ԃ̍��J�ƌ|�\�@216
��́@��@I�@�Éz�n���������n��̉Ԃ̍��J�\
�@�@���k�Q���V���E�l�n���@216
��́@��@II�@�Éz�����̒n�ɂ�����Ԃ̍��J�@217
��́@��@III�@�ϏB���̉Ԃ̍��J�@219
��́@��@IV�@���{�̉Ԃ̍��J�@221
��́@��@IV�@1�@�ԍՂ̉Ԉ�Ăɂ��ā@222
��́@��@IV�@2�@���ԍՂɂ��ā@223
��́@��@IV�@3�@�ԂƎR�̏������ā@224
��́@��@�ւ̍��J�ƌ|�\�@227
��́@��@I�@�֍��J�̖��Á\���V�i�C���Ӓn��ł́A
�@�@���ւ̍��J�͖��Âɗ�������邱�Ɓ@228
��́@��@II�@�l���g�̐_�\���A���M���J�ȑO�̐_�@230
��́@��@III�@�ւ�c��Ƃ���l�тƂ̍��J�@232
��́@��@IV�@�C�_�̍��J�ϑJ�j�\
�@�@���ւ̍��J�Ɨ��̍��J�̕����@234
��́@��@IV�@1�@�C�_���痴���ց\�ւƗ��̕����@236
��́@��@IV�@2�@�����Ɖ����̌��т��@238
��́@��@IV�@3�@�͂��߂̊C�_�̕����\�ω��ƛ_�c�A�Ր��v�l239
��́@��@IV�@4�@�͂��߂̐��E�C�̐_�̖��c�\�ؗ��A
�@�@������A�D�\�i���A�t�i�_�}�Ȃǁ@240
��́@�O�@�u��@�ւ̍��J�ƌ|�\�v����̓W�]�@246
��́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@248
��́@I�@�Ԃ��߂�����J�@248
��́@I�@���ݓ`��28�@�c���̒��ԁA
�@�@���_�c�_�̍̉Ԏ}�A�ϏB���̐����̉ԁ@248
��́@I�@���ݓ`��29�@���Ր��v�l�_�̍[�ԁk�\�E�l�@250
��́@II�@�ւ��߂�����J�@252
��́@II�@���ݓ`��30�@�ϏB���̓e�R���|���v��)�@252
��́@II�@���ݓ`��31�@�Ր��v�l�_�̋V��Ɩ@��@253
��Z�́@�����A�����ƍ��J�|�\�@261
��Z�́@�E�v�@262
��Z�́@�{�͐ݒ�̓����Ƙ_�_�@263
��Z�́@�l�̘_�_�@266
��Z�́@��@���@�̋Y��ƗD�l�@267
��Z�́@��@I�@���@�̋Y��ƗD�l�@267
��Z�́@��@II�@�����ƕ\���̂������@272
��Z�́@��@���@�ƒ����̂������@273
��Z�́@�O�@��Y�̂Ȃ��̏����Ƃ��̋~�ς̗ތ^�@277
��Z�́@�O�@I�@������Y�̌n���̏����@277
��Z�́@�O�@II�@�키�����\�Л�p�Y���̑��@284
��Z�́@�O�@II�@1�@�n���@284
��Z�́@�O�@II�@2�@�����̓�Y����@286
��Z�́@�O�@III�@�u��Y�̂Ȃ��̏����Ƌ~�ς̗ތ^�v�̂܂Ƃ�288
��Z�́@�l�@�����Ƙ��S�Y�@289
��Z�́@�܁@��Z�͂̂܂Ƃ߁\
�@�@���z���铌�V�i�C�n��̍��J�|�\�@294
��Z�́@�s���J�|�\�̌��ݓ`���t�@296
��Z�́@I�@���_�̋Y��@296
��Z�́@I�@���ݓ`��32�@�������̕_�ƕ���@296
��Z�́@I�@���ݓ`��33�@�O����O���̛_�c�_�ƕ���@298
��Z�́@II�@�ژA�Y�̓`���@300
��Z�́@II�@���ݓ`��34�@�����̗썰���{�ƖژA�Y(�O�a���x)300
��Z�́@II�@���ݓ`��35�@�O�ꋳ�ɂ�钆���̒��x�u�]���v�@302
��Z�́@III�@���S�Y�@303
��Z�́@III�@���ݓ`��36�@���N�����̃R�N�g�D�t��
�@�@�������тƕ��������@303
��Z�́@III�@���ݓ`��37�@���]�Ȓ�C�̕z�܋Y�\
�@�@���������O���̏j�����@305
���Ƃ����@313
�Q�l����(�\����)�@317
�W�n�}�@331
���J�|�\�j�W���N�\�@338
�ʐ^�}�ňꗗ�@343
�����@364 |
�X���A�嗢�����ҏW�ψ���ҁu�嗢�����v���u�����s���嗢�����فv���犧�s�����B
|
���G�@2
�����̂��Ƃ@�����ْ��@�㌴�a�Y�@33
�����������j���@�ږ�@�ʏ鐭���@34
�ҏW�ɂ������ā@�ҏW�ψ����@�㌴�X���@36
���́@�嗢�̈ʒu�ƊT�ρ@63
���́@��A�@�嗢�̈ʒu�@65
���́@��A�@�嗢�̒n���@65
���́@�O�A�@�嗢�̒n���@67
���́@�l�A�@�嗢�̏����@67
���́@��R�E����E�嗢�̗��j�@79
���́@�͂��߂Ɂ@81
���́@���߁@��j����̑嗢�@81
���́@���߁@��A�@�嗢�̈ʒu�Ɛ������@81
���́@���߁@��A�@�L�ˎ���̑嗢�@82
���́@���߁@�O�A�@�O�X�N����̑嗢�@83
���́@���߁@�l�A�@�嗢�̈�Ձ@83
���́@���߁@�l�A�@�i��j�@�����s�w��j�Ձ@��R��Ձi���j�@83
���́@���߁@�l�A�@�i��j�@���X�O�X�N�@85
���́@���߁@�l�A�@�i�O�j�@�嗢�ɓc�c������Ձ@86
���́@���߁@�l�A�@�i�l�j�@�嗢�Ó���Ձ@86
���́@���߁@�l�A�@�i�܁j�@�嗢�O����Ձ@86
���́@���߁@�l�A�@�i�Z�j�@�a��X��Ձ@87
���́@���߁@�×������̓�R�̗��j�@88
���͑��߈�A�@�w�����낳�����x�ɉr�܂ꂽ�嗢�ƉÎ�u��Ɓu�����̐��̂ʂ��v�@88
���́@���߁@��A�@�i��j�@�嗢�ƉÎ�u��@89
���́@���߁@��A�@�i��j�@�u�����̐��̂ʂ��v�@90
���́@���߁@��A�@�O�R�C���ƎO�R����@91
���́@���߁@��A�@�i��j�@�O�R�C���Ɠ�R���@92
���́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@��R�����@92
���́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�R�쉤���@�x�ƎR�쉤�f���p�����@92
���́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�R�쉤�����c�@93
���́@���߁@��A�@�i��j�@��R�̖ŖS�ƎO�R����@95
���́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���D���@95
���́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�w�������R���L�x�Ɍ���u�Î�u��v�@96
���́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@��{�w���R�����x�Ɍ���u�R�쉤���D����ł��v96
���́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�w�����ƕ���@�x�Ɍ����R�ŖS�@97
���́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�����c���@�A�����̓�����Â��@98
�O�A�@���^�����̋��Ε��ɋL���ꂽ��R�{�Ƃ��܂���̌R���@99
�O�A�i��j�u������L�v�i���~���L�W�i�n�m�蕶�j�ɋL���ꂽ�u�k�R�{�E��R�{�E���R�{�v99
�O�A�i��j�@���܂���̋��ƌR���@99
�O�A�i��j�@1.�@�u�^�얩�蕶�i�Ζ�̐��̂Ђ̂���j�v�ɍ��܂ꂽ
�@�@���u�����܂���v�Ɓu���܂������傳�Ɓv�@99
�O�A�i��j�@2.�@�u��炳���肭�����̔�v�ɋL���ꂽ
�@�@���u�������܂���v�Ɓu����߁v�A�u���܂������傳�Ɓv�@100
���́@��O�߁@�ߐ������̓��K�嗢�i����j�Ԑ@102
���́@��O�߁@��A�@�ߐ������̏@102
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@���Î��̗�������@102
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@�c�����n�ƐŁ@102
���́@��O�߁@��A�@�u���G�}�v�֘A�������Ɍ���ߐ��̊ԐƑ��@105
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@�u�������G�}�v���Ɍ��铇�K�嗢�Ԑ@105
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@�]�˖��{�̍��G�}�������Ɓ@105
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@�u�����܂���v���瓇�K�O�Ԑ�
�@�@���i���K�嗢�E���K����E���K�^����j�@105
���͑�O�ߓ�A�i��j3.�@�w�G�}�������x�Ɓw�������������x�Ɍ��铇�K�嗢�Ԑ�106
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@�\�����I�㔼�̊Ԑ̋��E�������Ɩ��̕ύX�@107
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@�H�n���G�̂���̊ԐE���̓��p���@107
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@���K�廗��Ԑ��獂��Ԑւ̉����@107
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@3.�@�w�������R���L�x��w���������L�x�̕Ҏ[�@108
���́@��O�߁@��A�@�i��j�@4.�@�w�G�}�������x�w�������R���L�x�w���������L�x�Ɍ���
�@�@�@�������̓��p���@108
���́@��O�߁@�O�A�@��[�̐��ƐŁ@110
���́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@��[�̐��̕ϑJ�@110
���́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@���㊯���@110
���́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�l�㊯���@110
���́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@3.�@��[��s�@111
���́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@�����w�����������x�Ɍ��鍂�@111
���́@��O�߁@�l�A�@�����̑��x�z�ƍ���Ԑ@112
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@�u�Ԑؐj�}�v�̍쐬�@112
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@1.�@�����̑��x�z�@112
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@2.�@�u�^�NJԐؐj�}�v�@112
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@3.�@�u����Ԑؐj�}�v�Ɓu����Ԑؐj�}�v�@114
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@�w�������y�G�}�x�Ɓw�������V�}�x�@114
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@1.�@�w�������y�G�}�i�Ԑ؏W���}�j�x�Ɍ��鍂��Ԑ@114
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@2.�@�w�������V�}�x�@115
���́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@3.�@�w�F���˒����}�x�@115
���́@��O�߁@�܁A�@���K�����C����h���̐����@115
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@�u���K�����C���v�Ɓu�ꗢ�R�v�@115
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@1.�@�w���ێO�����N�G�}���V�ʁx�Ɍ���u���K�����C���v�@116
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@2.�@�u�ꗢ�R�v�@116
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@�h���̐����@116
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@1.�@�h���@116
���́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@2.�@��y�ё��ԐƂ̋����@117
���́@��O�߁@�Z�A�@�g�����̊m���Ɣ_���x�z�@117
���́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@�ߐ������̎Љ�Ǝm�_�����@117
���́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@�@���D���Ɓu�l�������v�̍쐬�@118
���́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@1.�@�F���ˎx�z���ɂ�����@���D���@118
���́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@2.�@�u�l�������v�@118
���́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@3.�@�@���D�@120
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�O�j�@�ƕ��̕ҏW�@120
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�O�j�@1.�@�n�}���̐ݒu�@120
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�O�j�@2.�@�ƕ��̕Ҏ[�@121
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@�n���@122
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@1.�@�n���@122
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@2.�@����Ԑ̗����n���̉Ɩ��@122
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@3.�@�i�n���i��a�j�@123
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@4.�@���n���i�a���j�@128
���́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@5.�@�e�n���@129
���́@��O�߁@���A�@�_���x�z�̎��ԂƔ敾����_���@129
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@�Ԑؔԏ��Ƒ����@129
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@1.�@�Ԑؔԏ��̐ݒu�@129
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@2.�@�ԏ����Ó�����Ñ��u��㌴�Ɉڂ��@129
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@�n����l�@130
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@1.�@�w�������R���L�x�Ɍ��鍂��Ԑ̒n����l�@130
���́@��O�߁@���A�@�i��j�@2.�@�u�{�����e�Ԑ؊e���v�n���ȉ������v�Ɍ���
�@�@�@������Ԑؖ�l�@131
���́@��l�߁@�ߑ�̍���Ԑ@132
�@��A�@�����ˋy�єp�˒u����̍���Ԑ@132
�@��A�@�i��j�@�����˂̐ݒu�@132
�@��A�@�i��j�@1.�@�]�˖��{�̏I���Ɩ������{�̔����@132
�@��A�@�i��j�@2.�@�����˂̐ݒu�@132
�@��A�@�i��j�@3.�@�����˂ւ��ːЖ@���{�s�@132
�@��A�@�i��j�@���ꌧ�̐ݒu�@134
�@��A�@�i��j�@1.�@�p�˂̒��@���Ɣp�˒u���̒B���@134
�@��A�@�i��j�@2.�@�p�˒u���̈�ʖ��O�ւ̍��@�Ɖ��ꌧ���̐ݒu�@135
�@��A�@�i��j�@3.�@��l�̌p���C�p�@136
�@��A�@�i��j�@4.�@�S���ɗ����p�˒u���̕z���@136
�@��A�@�i��j�@5.�@���Ԑؖ�l�̒�R�Ɖ��m���E���ғ��̉�E�@136
�@��A�@�i�O�j�@�Ί��̔h���Ɩ����̐ݒu�@137
�@��A�@�i�O�j�@1.�@�Ί��ƐV���ȑ����ݔ˂̐ݒu�@137
�@��A�@�i�O�j�@2.�@�Ί��̔p�~�Ɩ����̊J�݁@139
�@��A�@�i�O�j�@3.�@���K�����l�Ί��@140
�@��A�@�i�O�j�@4.�@�^�ǔԏ��l�Ί��c������@140
�@��A�@�i�l�j�@���ꌧ�ݒu����̍���Ԑ@141
�@��A�@�i�l�j�@1.�@�ːВ����ƍ���Ԑ̐l���̐��ځ@141
�@��A�@�i�l�j�@2.�@�����L�^�Ɍ����鍂��Ԑؔԏ��̗l�q�@141
�@��A�@�i�l�j�@3.�@�w���ꌧ�{���}�x�Ɍ��閾���\���N�ꌎ���݂̐l���@142
�@��A�@�i�l�j�@4.�@���䏬�w�Z�̐ݒu�Ƃ��̕ϑJ�@142
�@��A�@�u���ꌧ�m�S�Ґ��j�փX�����v�y�сu���ꌧ�搧�v�̎{�s�ƍ���Ԑ@143
�@��A�@�i��j�@�u���ꌧ�m�S�Ґ��j�փX�����v�̎{�s�@143
�@��A�@�i��j�@�u���ꌧ�搧�v�̎{�s�@144
�@�O�A�@�Ԑؗ����K���̂���̍���Ԑ@145
�@�O�A�@�i��j�@�Ԑؗ����K���y�ъԐؓ��K���ƍ���Ԑ@145
�@�O�A�@�i��j�@1.�@�Ԑؗ����K���ƍ���Ԑ@145
�@�O�A�@�i��j�@2.�@�Ԑؓ��K���ƍ���Ԑ@146
�@�O�A�@�i��j�@�y�n�������Ɓ@148
�@�O�A�@�i��j�@1.�@���Ƃ̖ړI�Ɣw�i�@148
�@�O�A�@�i��j�@2.�@���Ƃ̌o�߁@149
�@�O�A�@�i��j�@3.�@���Ƃ̈Ӌ`�@150
�@�O�A�@�i�O�j�@�������̎��{�@150
�@�O�A�@�i�O�j�@1.�@���{�̒������@150
�@�O�A�@�i�O�j�@2.�@�������̉���ւ̓K�p�@151
�@�O�A�@�i�O�j�@3.�@����Ԑƒ������@151
�@�O�A�@�i�l�j�@�����O�\�Z�N�̐l���Ɠy�n���p�ƕ��Y�@152
�@�O�A�@�i�l�j�@1.�@�ː��E�l���@152
�@�O�A�@�i�l�j�@2.�@�y�n���p�@153
�@�O�A�@�i�l�j�@3.�@���Y�@154
�@�O�A�@�i�܁j�@��������Ŗ@�̎{�s�Ɖ����̐���@155
�@�O�A�@�i�Z�j�@���I�푈�ƍ���Ԑ@156
�@�O�A�@�i�Z�j�@1.�@�w�i�@156
�@�O�A�@�i�Z�j�@2.�@�o�߁@156
�@�O�A�@�i�Z�j�@3.�@���I�푈�Ɖ���@157
�@�l�A�@���䑺�̐ݒu�ƍs���@158
�@�l�A�@�i��j�@�s�����i�ԐE���j�̖��̕ύX�@158
�@�l�A�@�i��j�@1.�@���ꌧ�̊ԐE���̖��̕ύX�@158
�@�l�A�@�i��j�@2.�@�����l�\�N���ߑ�l�\�܍������ꌧ�Ɏ{�s�@159
�@�l�A�@�i��j�@�u���ꌧ�y���ג������v�ƍ���@159
�@�l�A�@�i��j�@1.�@�u���ꌧ�y���ג������v�ƍ��䑺�@159
�@�l�A�@�i��j�@2.�@����̈ʒu�@160
�@�l�A�@�i�O�j�@�����I���@160
�@�l�A�@�i�O�j�@1.�@�M���@�@161
�@�l�A�@�i�O�j�@2.�@�O�c�@�@161
�@�܁A�@��ʁE�^�A�E�ʐM�@162
�@�܁A�@�i��j�@�����Ɠ��H���W�@162
�@�܁A�@�i��j�@1.�@�w�����\�O�N���ꌧ���v���x�Ɍ��铹�H�@162
�@�܁A�@�i��j�@2.�@���ꌧ�Ǔ������\�̕ϑJ�@163
�@�܁A�@�i��j�@3.�@�����̎O���w�쓇�I���O�сx�Ɍ���e�ԏ������@164
�@�܁A�@�i��j�@4.�@������\��N�́u���ꌧ�Ǔ������v�Ɍ��闢���@164
�@�܁A�@�i��j�@5.�@�吳�O�N�́u���ꌧ�Ǔ������\�v�Ɍ��闢���@164
�@�܁A�@�i��j�@6.�@���H���W�̈ʒu�@165
�@�܁A�@�i��j�@���K�S�̊X�������Ɛ^�NJX���@166
�@�܁A�@�i��j�@1.�@���K�S�̊X�������@166
�@�܁A�@�i��j�@2.�@�^�NJX���̐����@166
�@�܁A�@�i�O�j�@�X���̌����F��@167
�@�܁A�@�i�O�j�@1.�@�Đ{�ߔe���@168
�@�܁A�@�i�O�j�@2.�@�����^�ߌ����@168
���́@�嗢�̍s���@169
���́@�͂��߂Ɂ@171
���́@���߁@�掖�����i�W��j�̕ϑJ�@171
���́@���߁@��A�@�������[�i�����j�@171
���́@���߁@��A�@�掖�������݂Ɍ����Ă̎��g�݁@172
���́@���߁@�O�A�@�V�����ٌ��݂Ɍ����Ă̐V���Ȏ��g�݁@173
���́@���߁@�嗢�ȈՐ����̐ݒu�Ɛ����n�����@193
���́@���߁@��A�@�嗢�ȈՐ����̐ݒu�@193
���́@���߁@��A�@�i��j�@�ȈՐ����̐ݒu�@193
���́@���߁@��A�@�i��j�@�ȈՐ����������Ƌ������@195
���́@���߁@��A�@�i�O�j�@�励�ƉÎ�u����C�H���@196
���́@���߁@��A�@�i�l�j�@�ȈՐ����̐����W�Ɛ��������@197
���́@���߁@��A�@�i�܁j�@��߃^���N�y�іŋۑ��u���̐ݒu�@198
���́@���߁@��A�@�i�Z�j�@�������ƕ�������@198
���́@���߁@��A�@�i���j�@���䏬�E���w�Z�A���H�Z���^�[�ւ̋����@199
���́@���߁@��A�@�����n�����@199
���́@���߁@��A�@�i��j�@���̔��[�@199
���́@���߁@��A�@�i��j�@�Î�u�쐅���n�����ɂ��ā@199
���́@��O�߁@�嗢�̗��撷�@203
���́@��l�߁@�嗢�o�g���s�����c��c���@208
���́@��ܐ߁@�嗢�o�g���s�������@210
���́@��Z�߁@�嗢�o�g��㎅���s�_�ƈψ��@211
��O�́@�嗢�̍s���g�D�@213
��O�́@���߁@�g�D�y�і����@215
��O�́@���߁@��A�@�g�D�@215
��O�́@���߁@��A�@�s���@�\�@215
��O�́@���߁@�O�A�@���������i������\��N�O�����݁j�@215
��O�́@���߁@�l�A�@�����ٖ��������i������\��N�O�����݁j�@216
��O�́@���߁@�܁A�@�\�Z�i������\��N�x�j�@217
��O�́@���߁@�嗢��s���̋K��W�@218
��l�́@�嗢�̎Y�Ɓ@223
��l�́@���߁@�嗢�̔_�Ɓ@225
��l�́@���߁@��A�@�嗢�_�Ƃ̊T���@225
��l�́@���߁@��A�@�i��j�@�嗢�_�Ƃ̊T���@225
��l�́@���߁@��A�@�i��j�@�嗢�̏����ʐϋy�я����}�@226
��l�́@���߁@��A�@�V�����`����u�����E�吳����v�̑嗢�̔_�Ǝ���@228
��l�́@���߁@�O�A�@�u�y�n���L���v�̕t�^�@248
��l�́@���߁@�l�A�@�䕗�E�����̎��R�ЊQ�@249
��l�́@���߁@�܁A�@�_�Ƌy�є_�ƎҐ����̈ڂ�ς��@250
��l�́@���߁@�܁A�@�i��j�@�嗢�̐�ƁE���ƕʔ_�Ɛ��@250
��l�́@���߁@�܁A�@�i��j�@�嗢�̌o�c�k�n�K�͕ʔ_�Ɛ��@251
��l�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@�嗢�̔N��ʔ_�Ɛl���@251
��l�́@���߁@�Z�A�@�_�Ɛ��Y�̈ڂ�ς��@252
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@�_�앨�@252
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@1.�@���Ƃ����сi����j�@252
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@2.�@�Ï��@257
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@3.�@����@260
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@4.�@��@262
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@5.�@�哤�@264
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@6.�@���瓤�@265
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@7.�@�����@266
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@8.�@�ʎ��@267
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@���H�_�Y���@271
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@1.�@�������@271
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@2.�@�{�\�@273
��l�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@3.�@�t�����@275
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@�{�Y�@276
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@1.�@���p���@277
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@2.�@���p���@278
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@3.�@�n�@279
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@4.�@�i���[�j�@280
��l�́@���߁@�Z�A�@�i�O�j�@5.�@�R�r�i�q�[�W���[�j�@283
��l�́@���߁@���A�@�g���N�^�[�̓����@284
��l�́@���߁@���A�@�y�n���ǎ��Ɓ@286
��l�́@���߁@���A�@�i��j�@�y�n���ǎ��Ƃ̊T���@286
��l�́@���߁@���A�@�i��j�@�y�n���ǎ��Ƃ̒n��ʊT�v�@287
��l�́@���߁@���A�@�i��j�@1.�@�嗢�y�n���Nj�@287
��l�́@���߁@���A�@�i��j�@2.�@�嗢�k�y�n���Nj�@287
��l�́@���߁@���A�@�i��j�@3.�@�嗢��y�n���Nj�@289
��l�́@���߁@���A�@�i�O�j�@���n�������Ƃ̊T�v�@290
��l�́@���߁@���A�@�i�O�j�@1.�@�R�쌴�������H���ݎ��Ɓ@290
��l�́@���߁@���A�@�i�O�j�@2.�@�嗢��y�n���Nj�@290
��l�́@���߁@���A�@�i�O�j�@3.�@�嗢�y�n���Nj�@290
��l�́@���߁@��A�@���䑺�_�Ƌ����g���̉��v�@291
��l�́@���߁@�嗢�̏��H�Ɓ@293
��l�́@���߁@��A�@�嗢�̏��Ɓ@293
��l�́@���߁@��A�@�嗢�̓y�،��Ɓ@295
��́@����@297
��́@���߁@�w�Z����@299
��́@���߁@��A�@��O�̊w�Z����@299
��́@���߁@��A�@�i��j�@�u���O�̕�������@299
��́@���߁@��A�@�i��j�@���m���l������@300
��́@���߁@��A�@�i�O�j�@�ԏ�����@300
��́@���߁@��A�@�I�풼��̋���@300
��́@���߁@�O�A�@����q�포�w�Z�@302
��́@���߁@�l�A�@������ƍ����w�Z�@303
��́@���߁@�܁A�@�`�������N���{�s�i�Z�E�O�E�O�V�w���̊m���j�@303
��́@���߁@�Z�A�@�嗢�o�g���Ɛ����ꗗ�@304
��́@���߁@�Z�A�@�i��j�@���䏬�w�Z�@304
��́@���߁@�Z�A�@�i��j�@���䒆�w�Z�@305
��́@���߁@���A�@���䋳�F��i�嗢�o�g�Җ��j�@306
��́@���߁@���A�@�㌴���g�����蕶�@307
��́@���߁@�Љ��@308
��́@���߁@��A�@�嗢�����ف@308
��́@���߁@��A�@�i��j�@�����T���@308
��́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�N�ԍs���@308
��́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�嗢�n�`�Y���[�i�����O���j�@309
��́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�g�D�V�r�[�i���N�j�j�@309
��́@���߁@��A�@�i��j�@�������N�j�@309
��́@���߁@��A�@�i��j�@�L�O�ʐ^�i��1��`��46��j�@312
��́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�嗢�斯��^����@335
��́@���߁@��A�@�i��j�@������\��N�x�����ٔN�Ԏ��ƌv��@339
��́@���߁@��A�@�i�O�j�@������\��N�x�����َ��x�\�Z���@341
��́@���߁@��A�@�i�l�j�@�����s���嗢�����يّ��@342
��́@���߁@��A�@�i�܁j�@�������ْ��@345
��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@��e�@���B���i���V�^�����j�E�����̑��i�E�t�K�[�j
�@�@�@�@���i�Î�u��j�@�O�嗢�������@�㌴�K���@347
��́@���߁@��A�@�嗢������@349
��́@���߁@��A�@�i��j�@�����T���@349
��́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�T���@349
��́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�Љ��d�����@349
��́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@���{�u���@349
��́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@���N���i�@350
��́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�ݐЋy�ѕ������@351
��́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@�s�V�A���с@352
��́@���߁@��A�@�i��j�@7.�@�������ҁ@353
��́@���߁@��A�@�i��j�@8.�@���������ҁ@355
��́@���߁@��A�@�i��j�@9.�@�N�x�ʕ\����y�ъ��ӏ�ҁ@356
��́@���߁@��A�@�i��j�@������\��N�x���ƌv��@357
��́@���߁@��A�@�i�O�j�@������\��N�x���x�\�Z���@358
��́@���߁@��A�@�i�l�j�@���嗢�������@359
��́@���߁@��A�@�i�܁j�@���������@361
��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@��e�@������̂���ς��ɂ��ĎR����q�@363
��́@���߁@�O�A�@�嗢�w�l��@365
��́@���߁@�O�A�@�i��j�@�����T���@365
��́@���߁@�O�A�@�i��j�@�����\���N�x���ƌo�߁@367
��́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@�嗢�w�l���@368
��́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@�w�l�����@369
��́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@1.�@�嗢�w�l�����@369
��́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@2.�@��㍂�䑺�w�l�����嗢�o�g�Җ���@370
��́@���߁@�l�A�@�嗢�N��@372
��́@���߁@�l�A�@�i��j�@��O�̊����T���@372
��́@���߁@�l�A�@�i��j�@���̊����T���@376
��́@���߁@�l�A�@�i��j�@1.�@�I�풼��̊����@376
��́@���߁@�l�A�@�i��j�@2.�@���A��̊����@377
��́@���߁@�l�A�@�i�O�j�@������\��N�x�s���@388
��́@���߁@�l�A�@�i�l�j�@������\��N�x�\�Z�ā@389
��́@���߁@�l�A�@�i�܁j�@�嗢�N���㐳����@390
��́@���߁@�܁A�@�n��f�C�T�[�r�X���Ɓ@�R��a�q�@393
��́@���߁@�܁A�@�i��j�@�����\���N�x�嗢�n��f�C�T�[�r�X���ƌv��\�@395
��́@���߁@�܁A�@�i��j�@���͈��̋Ɩ��Ƌ��͈�����@396
��́@���߁@�܁A�@�i��j�@1.�@�Ɩ����e�@396
��́@���߁@�܁A�@�i��j�@2.�@���͈�����@396
��́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@���{�@398
��Z�́@�e���@401
��Z�́@���߁@�e���@403
��Z�́@���߁@��A�@�e�����������Ƃ@403
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�e���Ƃ̊W���������Ƃ@403
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�����@404
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�z��҂ƈ����@407
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�e�����܂Ƃ߂Ă������Ƃ@408
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@��̐e���W�@408
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@��̐e���W�ɂ�����́@408
��Z�́@���߁@��A�@�e���@409
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�e�ʁ@409
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�E�F�[�J�@409
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�e���ɂ��Ă̂��Ƃ@410
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�咆�@410
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�嗢�̖咆�̂��Ɓ@410
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�咆�̐����@412
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�嗢�̖咆�@413
��Z�́@���߁@��A�@�i�O�j�@�ߔN�ڏZ���Ă����l�X�@424
��Z�́@���߁@�O�A�@�Ƒ��@424
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�Ƒ��@424
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�͂��߂Ɂ@424
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�����̑f�`�@424
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�Ƒ��\���@425
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@���ƂƉ����@428
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@1.�@���Ɓ@428
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�����@428
��Z�́@���߁@�O�A�@�i��j�@3.�@�嗢�W���̑����@432
��Z�́@���߁@�p���@434
��Z�́@���߁@��A�@�p���Ƒ����@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�p���@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���[�i�Ɓj�̌p���@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@��w���̌p���@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�����@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���Y�@434
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�����l�@435
��Z�́@���߁@��A�@�O�����X�̍��J�ƌp���@435
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�O�����X�̍��J�@435
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�O�����X�@435
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�O�����X�̍��J�@436
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@�O�����X�̌p���@436
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�O�����X�̌p���@436
��Z�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�O�����X�p���̋֊��@437
�掵�́@�l�̈ꐶ�@439
�掵�́@���߁@�D�P�E�o�Y�E�玙�@441
�掵�́@���߁@��A�@�D�P�@441
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�D�P�F��@441
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�D�P�@441
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�D�w�@441
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@���@441
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�D�P���̐H���@442
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�D�P���̋֊��@442
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@���с@442
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@�o�Y�̏����@442
�掵�́@���߁@��A�@�o�Y�@442
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�Y���@443
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�J�b�e�B�E�Y�k�E���Y�w�@443
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���@444
�掵�́@���߁@��A�@�i�l�j�@�ւ��̏��ƃC���[�̏����@444
�掵�́@���߁@�O�A�@�o�Y��@444
�掵�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�Y���ƎY���@444
�掵�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�J�[�E���[�@445
�掵�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@�i�[�W�L�@445
�掵�́@���߁@�l�A�@�Y���傭���@446
�掵�́@���߁@�l�A�@�i��j�@���[�g�D�M�@446
�掵�́@���߁@�l�A�@�i��j�@�W���E���ƃ}���T�����[�G�[�@446
�掵�́@���߁@�l�A�@�i�O�j�@�Y�w�@447
�掵�́@���߁@�l�A�@�i�l�j�@�n�`�A�b�L�[�@447
�掵�́@���߁@�܁A�@�玙�@447
�掵�́@���߁@�܁A�@�i��j�@�����Ɨ����H�@447
�掵�́@���߁@�܁A�@�i��j�@���V�l�[�E���@448
�掵�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@���k���[�@448
�掵�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@�^���J�[���[�G�[�@448
�掵�́@���߁@�܁A�@�i�܁j�@�q���@449
�掵�́@���߁@�܁A�@�i�Z�j�@�����c�t���Ɣ_�Ɋ��������@450
�掵�́@���߁@�Z�A�@���l�ւ̉ߒ��@450
�掵�́@���߁@���A�@���̑��@451
�掵�́@���߁@���A�@�i��j�@�������@451
�掵�́@���߁@���A�@�i��j�@���Y�E�c���̎��S�@451
�掵�́@���߁@�����@451
�掵�́@���߁@�͂��߂Ɂ@451
�掵�́@���߁@��A�@�����@452
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�g�D�W�N�[�C�i�Ō�j�@452
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�T�L���C�i�j�@452
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@�j�[�r�L�i����j�@453
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@1.�@���N�C���i������j�@453
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@2.�@���~���P�[�i�Ō}���j�@453
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@3.�@�œ���E�������@454
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@4.�@����̌����@454
�掵�́@���߁@��A�@�����Ɋւ��鎖���@457
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�ԉňߑ��E�œ��蓹��@457
�掵�́@���߁@��A�@�i��j�@�m���ƕ����Ƃ̌����@457
�掵�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���}�f�B�}�i�n��ԁj�@457
�掵�́@���߁@��A�@�i�l�j�@���[�A�V�r�[�i�їV�сj�@458
�掵�́@���߁@��A�@�i�܁j�@���ی����@458
�掵�́@��O�߁@�����@459
�掵�́@��O�߁@��A�@���̗\���@459
�掵�́@��O�߁@��A�@�ՏI����o���܂Ł@460
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@�ՏI�@460
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@�ՏI�@460
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@���҂���߂�@460
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@3.�@�������𒅂�������@460
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@4.�@���҂��ԍ��Ɉ��u����@461
�掵�́@��O�߁@��A�@�i��j�@�ʖ�@461
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@�����̏����@461
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@1.�@�ǂ̖����@461
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@2.�@����@462
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@�j���u�`���[�@462
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@�č��ƍ��T�@463
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@1.�@�č��@463
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@2.�@���T�@464
�掵�́@��O�߁@��A�@�i�Z�j�@�[���Əo���@464
�掵�́@��O�߁@�O�A�@��ӑ�����q�i�����j���P�i��j���@464
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@��ӑ���@464
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@����@464
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�V�}�~�V�[�@465
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@3.�@�咆��ɑ���@465
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@�q���P���@465
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�A���[�U���[�@465
�掵�́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@���[�U���[�@466
�掵�́@��O�߁@�l�A�@���㋟�{�@466
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@�����̗����@466
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@�i���J�@466
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@1.�@�����@466
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@2.�@���[�W�P�[�@467
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i�O�j�@�~�[�T�@467
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i�l�j�@�N�����{�@467
�掵�́@��O�߁@�l�A�@�i�܁j�@�V��@468
�掵�́@��O�߁@�܁A�@꜁i�K���j�@468
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@���ꑒ�@�@469
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@�~�Ɏ��S�����ꍇ�@469
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@�i��j�@�D�w�����S�����ꍇ�@469
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@�i�O�j�@���E�E�M���̏ꍇ�@469
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@�i�l�j�@�C�Ŏ��S���Ĉ�̂��Ȃ��ꍇ�@470
�掵�́@��O�߁@�Z�A�@�i�܁j�@�c�������S�����ꍇ�@470
�掵�́@��O�߁@���A�@�펞���E�I�풼��̑����@470
�掵�́@��l�߁@�搧�@471
�掵�́@��l�߁@��A�@��̌ď̂Ǝ�ށ@471
�掵�́@��l�߁@��A�@��̈ʒu�@471
�掵�́@��l�߁@�O�A�@��̌`�Ԃƍ\���@473
�掵�́@��l�߁@�O�A�@�i��j�@��̌`�ԁ@473
�掵�́@��l�߁@�O�A�@�i��j�@�咆��̍\���@474
�掵�́@��l�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�����̍\���@474
�掵�́@��l�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@��̕~�n���ɂ�����́@474
�掵�́@��l�߁@�O�A�@�i��j�@3.�@�C�V�[�[�N�@475
�掵�́@��l�߁@�l�A�@��̔N���Ղƕ�Q��@475
�掵�́@��l�߁@�l�A�@�i��j�@��̔N���Ձ@475
�掵�́@��l�߁@�l�A�@�i��j�@��Q��@476
�掵�́@��l�߁@�܁A�@�嗢�̕�@477
�@�܁A�@�i��j�@�咆�̕�@477
�@�܁A�@�i��j�@1.�@�������i�A�T�g�o���j�咆�̕�@477
�@�܁A�@�i��j�@2.�@�h�����i�C�[�g�D�N�o���j�咆�̕�@478
�@�܁A�@�i��j�@3.�@�z�����i�E�B�[�N�o���j�咆�̕�@478
�@�܁A�@�i��j�@4.�@��n���i�E�B�[�`�o���j�咆�̕�@479
�@�܁A�@�i��j�@5.�@�㌴���ɗ����i�E�B�[�o�T�O�C�o���j�咆�̕�@480
�@�܁A�@�i��j�@6.�@�ビ�啠�i�E�B���W���[�o���j�咆�̕�@480
�@�܁A�@�i��j�@7.�@�㑺�����i�E�B���_�J���o���j�咆�̕�@482
�@�܁A�@�i��j�@8.�@���n���i�E�h�D�o���j�咆�̕�@482
�@�܁A�@�i��j�@9.�@��[���i�J�[�o�^�o���j�咆�̕�@483
�@�܁A�@�i��j�@10.�@�_�����i�J�~���g�D�o���j�咆�̕�@484
�@�܁A�@�i��j�@11.�@���Ε��i�X���o���j�咆�̕�@484
�@�܁A�@�i��j�@12.�@���ԕ��i�i�J�}�o���j�咆�̕�@486
�@�܁A�@�i��j�@13.�@�������i�i�~�U�g�o���j�咆�̕�@486
�@�܁A�@�i��j�@14.�@�R�镠�i���}�O�X�N�o���j�咆�̕�@487
�@�܁A�@�i��j�@15.�@������i�E�B�[�U�o���j�咆�̕�@488
�@�܁A�@�i��j�@16.�@�������i�j�V���U�o���j�咆�̕�@488
�@�܁A�@�i��j�@�n�̕�@489
�@�܁A�@�i��j�@1.�@��ԉƂ̕�@489
�@�܁A�@�i��j�@2.�@�����Ƃ̕�@489
�@�܁A�@�i��j�@3.�@�l���Ƃ̕�@489
�@�܁A�@�i��j�@4.�@�����Ƃ̕�@489
�@�܁A�@�i��j�@5.�@�^�V�Ƃ̕�@490
�@�܁A�@�i��j�@6.�@���g�Ƃ̕�@490
�@�܁A�@�i��j�@7.�@�y�c�Ƃ̕�@490
�@�܁A�@�i�O�j�@����i�����r�o�J�j�@490
�@�܁A�@�i�l�j�@�i��ƃm����@490
�@�܁A�@�i�l�j�@1.�@�i��@490
�@�܁A�@�i�l�j�@2.�@�m����@491
�@�܁A�@�i�܁j�@���̑��̕�@492
�@�܁A�@�i�܁j�@1.�@�g�[�k���[�̕�@492
�@�܁A�@�i�܁j�@2.�@�z���K���̕�@492
�@�܁A�@�i�܁j�@3.�@�W�����u���@492
�攪�́@�����@493
�攪�́@���߁@�߁E�H�E�Z�@495 |
�攪�́@���߁@��A�@�߁@495
�攪�́@���߁@��A�@�͂��߂Ɂ@495
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�����A�����Ȃǁ@495
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���i���@496
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�d�����@496
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@���ꒅ�@496
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�����@497
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�q�ǂ��̈ߕ��@497
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@�Q�Ԓ���Q��@497
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@7.�@���g��A�����A�����A���A�����@498
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�V��ƕ��@498
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�c���̈߁@498
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�q�ǂ��̋V�畞�@498
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�����̕��@498
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���D���@499
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@1.�@�D���@499
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�����@499
�攪�́@���߁@��A�@�H�@499
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�H���@499
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�H���̖��̂Ɖ@499
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@��H�̎�ށ@500
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�J�e�B�����i�������j�@501
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�N�X�C�����i���{�H�j�@503
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�������@504
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@���h���@505
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�n�D�i�@506
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���@506
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@���@506
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�����@506
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@�ۑ��H�@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@1.�@�X�[�`�J�[�i�ؓ��̉��Ђ��j�@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�Ђ����@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@3.�@�J���X�O���[�i���h�j�@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�l�j�@�����p�i�ƈ��H��@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�l�j�@1.�@��@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�l�j�@2.�@���̑��̐����p�i�@507
�攪�́@���߁@��A�@�i�l�j�@3.�@���܂ǂƔR���@508
�攪�́@���߁@��A�@�i�܁j�@�������@508
�攪�́@���߁@�O�A�@�Z�@509
�攪�́@���߁@�O�A�@�͂��߂Ɂ@509
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�T�ρ@509
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�W���Ɖ��~�@509
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�Z�܂��̕ϑJ�@509
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@���~�\���@510
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�ꉮ�@510
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�q�U�C�K���[�i���\���j�@511
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@3.�@���{�݂̔z�u�@511
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@4.�@���~�͂��@512
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@���z�@513
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@1.�@�A�i���i�����j�@513
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@2.�@�k�`�W���[�i�і؉��j�@513
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@3.�@���̏Z��@514
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@4.�@���z�ށ@515
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@5.�@���[�t�L�@515
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@6.�@������@516
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@�Z�܂��ƏK���@517
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@1.�@�Ԏ��@517
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@2.�@�Z�܂��ɂ������K���@517
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@3.�@���Ɓ@518
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@4.�@���z�V��@519
�攪�́@���߁@�����@520
�攪�́@���߁@��A�@��ʁE�^�A�@520
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�嗢�W���̓��H�@520
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�嗢�W���̑����@520
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@���[���E�X�g���[�g�Ǝ�v���H�@521
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�����J���@521
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@��ʖԂƌ�ʋ@�ց@522
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@�ԎЉ�̕��̈�Y�@523
�攪�́@���߁@��A�@�q���E��Á@525
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@�q���@525
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@��Á@525
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�����E�吳�E���a�̈�Á@525
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�������܂�̍��䑺�o�g�̈�t�@526
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@��O�̑嗢�̎Y�k�@526
�攪�́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@���̈�Á@526
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���Y�w�E�Ō�w�@527
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@1.�@���Y�w�̎�L�@�ʏ�@���@527
�攪�́@���߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�Ō�w�̌o���@�R��@�L�@528
�攪�́@���߁@�O�A�@�Љ���@529
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�����ψ��E�����ψ��@529
�攪�́@���߁@�O�A�@�i��j�@�����ی�@530
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@�V�l�����@531
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@1.�@�V�N�l���̏@531
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@2.�@�嗢�̍���ҁi����\�Έȏ�j�@532
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�O�j�@3.�@�J�W�}���[���}�������X�@534
�攪�́@���߁@�O�A�@�i�l�j�@�Љ���W�\���@538
�攪�́@���߁@�l�A�@�������K�@538
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@�U���E���`�@538
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@1.�@�_���p�`���[�i�f�����j�@538
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@2.�@�����̔��`�@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@���ρ@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@1.�@���ρ@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@2.�@�����@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i��j�@3.�@�T�o�L�i�̋��j�@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i�O�j�@���C�@539
�攪�́@���߁@�l�A�@�i�l�j�@�n�W�`�i�j�ˁj�@540
�攪�́@���߁@�܁A�@�����̏����@542
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@���R�@542
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@1.�@�E�t�K�[�i�Î�u��j�Ɛ������@542
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@2.�@��Ԑ������@545
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@3.�@��ނ�ɐ��ސ������@546
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@4.�@�Ƃ̐������@547
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@5.�@�e�b�|�E�����A���̑��@549
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@6.�@�铹�E����@550
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@������Ձ@550
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@1.�@�W�B�[�i�y�n�j�@551
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@2.�@���[�i�Ɖ��j�A���̑��@551
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@3.�@�㐅���@552
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@4.�@�d�C�@553
�攪�́@���߁@�܁A�@�i��j�@5.�@�R���@553
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@�o�ϐ����@554
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@1.�@�ƌv�@554
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@2.�@�s���@554
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@3.�@�ČR�{�����̒ʉ݁@555
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�O�j�@4.�@�͍��i�������j�@555
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@�����̒f�ʁ@556
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@1.�@���ݕ}���@556
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@2.�@��x�c�@557
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@3.�@�n�D�@558
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@4.�@���H�X�@559
�攪�́@���߁@�܁A�@�i�l�j�@5.�@�@���@560
�攪�́@���߁@�Z�A�@�������P�@562
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@�V�����^���@562
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@1.�@�V�����^���̒@562
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@2.�@����Z��w�l��̎��g�݁@563
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@3.�@�V�����^���w���ҍu�K��@563
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@4.�@������������ْ��ւ̌����@564
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@�������P�@564
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@1.�@�������P���@564
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@2.�@�������P�O���[�v�@565
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@3.�@���j�V�̕ϑJ�@567
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@4.�@������̌��莖���E�v�]�����@568
�攪�́@���߁@�Z�A�@�i��j�@5.�@�l�ݔ��̏@569
�攪�́@���߁@���A�@�e�r��@570
�攪�́@���߁@���A�@�i��j�@�嗢�̐e�r�͍��@570
�攪�́@���߁@���A�@�i��j�@�����ݏZ�嗢���F��@571
���́@�����E�|�\�E�����@573
���́@���߁@�����E���Ƃ@575
���́@���߁@��A�@�����@575
���́@���߁@��A�@�i��j�@���ԗÖ@�@575
���́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@��p�A���@575
���́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@��p�����@575
���́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�u�[�u�[�E���[�`���[�@575
���́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@��p�Ö@�@576
���́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�E�O�����i���j�@576
���́@���߁@��A�@�i��j�@���M�@576
���́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@���k�V���V�i���m�点�j�@577
���́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�܂��Ȃ��Ɛ肢�@577
���́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�}�u���[�O�~�i������j�E�V��@578
���́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@�^�u�[�i�֊��j�@578
���́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�j�[�r�L�i�����j�E�o�Y�@579
���́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@���E�����@579
���́@���߁@��A�@�i��j�@7.�@���̑��@579
���́@���߁@��A�@�i�O�j�@���Ƃ킴�@580
���́@���߁@��A�@�嗢�����@581
���́@���߁@��A�@�i��j�@�嗢�̕����@581
���́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�g�̖̂��̂Ƃ��̋@�\�@581
���́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�ߐH�Z�i�����j�@581
���́@���߁@��A�@�i��j�@3.�@�l�ԁE�Љ�W�@582
���́@���߁@��A�@�i��j�@4.�@���R�E���R���ہ@582
���́@���߁@��A�@�i��j�@5.�@�����E�A���@582
���́@���߁@��A�@�i��j�@6.�@��ԁE���ԁ@582
�@��A�@�i��j�@7.�@�㖼�����@583
�@��A�@�i��j�@�����̉�����̉��@�ʏ鐭���@583
�@��A�@�i��j�@1.�@P������F���ցAF������H���ց@583
�@��A�@�i��j�@2.�@�`������L���ց@583
�@��A�@�i��j�@3.�@�T�����iS�j����n�����iH�j�ց@583
�@��A�@�i�O�j�@��p��@584
�@�O�A�@���̂��Ƃ@584
���́@���߁@�|�\�E�����@586
�@��A�@�|�\�@586
�@��A�@�i��j�@���q�����@586
�@��A�@�i��j�@��O�̃����A�V�r�@586
�@��A�@�i��j�@1.�@�����A�V�r�̉��ځ@587
�@��A�@�i��j�@2.�@�W�[�E�e�[�i�n�w�j�i���������j�@587
�@��A�@�i��j�@3.�@�x���@587
�@��A�@�i��j�@4.�@���ڂƖ��@587
�@��A�@�i��j�@5.�@�����A�V�r�Ɋւ����X�̎����@588
�@��A�@�i��j�@6.�@��̉��ڂɂ��ā@589
�@��A�@�i�O�j�@���̌|�\�@590
�@��A�@�i�O�j�@1.�@���̌|�\�̕����@590
�@��A�@�i�O�j�@2.�@���̑��ŋ��@590
�@��A�@�i�O�j�@3.�@���̑��̌|�\�����@593
�@��A�@�i�O�j�@4.�@�G�C�T�[�@593
�@��A�@��y�@595
�@��A�@�i��j�@��l�̌�y�@595
�@��A�@�i��j�@1.�@�s���̂Ȃ��̌�y�@595
�@��A�@�i��j�@2.�@���[�A�V�r�[�i�їV�сj�@595
�@��A�@�i��j�@3.�@�ŋ��E�f��@596
�@��A�@�i��j�@4.�@�p�́i�������j�E�k�r�E���㋣�Z�@596
�@��A�@�i��j�@5.�@����̌�y�@597
�@��A�@�i��j�@�q�ǂ��̌�y�@597
�@�O�A�@���������@599
�@�O�A�@�i��j�@�嗢���Ɂ@599
�@�O�A�@�i��j�@���́@599
�@�O�A�@�i��j�@1.�@�Z�́@599
�@�O�A�@�i��j�@2.�@���́@600
�@�O�A�@�i��j�@3.�@�o��@601
�@�O�A�@�i��j�@4.�@����@601
�@�O�A�@�i��j�@5.�@���@601
�@�O�A�i�O�j�@�u���ł����i���ӂ��[�j�v�i�́E�O���E���x�j�̒a���@603
�@�O�A�i�O�j�@1.�@�u���ł����v�̑n��ɓ����������X�@603
�@�O�A�i�O�j�@2.�@���{�M�v����ł̎�����i����O�k�����܁l�N�\�j�@603
�@�O�A�i�O�j�@3.�@�嗢�����قł̕��x���\��i����ܔN�k�������l�O���j�@603
�@�O�A�i�O�j�@4.�@�́E�O���E���x�̓������u���ł����i���ӂ��[�j�v�̉̎��@603
�@�O�A�@�i�l�j�@���y�@604
�@�O�A�@�i�l�j�@1.�@�T���V���i�O���j�@604
�@�O�A�@�i�l�j�@2.�@ⵋȁ@605
�@�O�A�@�i�܁j�@���p�@605
�@�O�A�@�i�Z�j�@���x�@606
�@�O�A�@�i���j�@�����@606
�@�O�A�@�i���j�@�X�|�[�c�@606
��\�́@���J�@609
��\�́@�͂��߂Ɂ@611
��\�́@���߁@�`���@613
��\�́@���߁@��A�@��R�̗R���@613
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@���R�@613
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@����R�@613
��\�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���R�@614
��\�́@���߁@��A�@���ג��`���@615
��\�́@���߁@�O�A�@�嗢�̋��Ɓ@616
��\�́@���߁@�q���E���q�@618
��\�́@���߁@��A�@�q���@618
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@��R�鎃�̔q���@618
�@��A�@�i��j�@1.�@�}�ʁu��R������j���P�����J�O�̕�A��A�x�m���ʒu�v�@618
�@��A�@�i��j�@2.�@���}�ʂ���ǂݎ��邱�Ɓ@620
�@��A�@�i��j�@�w�������R���L�x�ɋL���ꂽ�q���@623
�@��A�@�i�O�j�@�W�����̔q���@626
��\�́@���߁@��A�@���q�@640
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@�z�����咆�̏��q�@640
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@�z�����咆�̓��������q�@640
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@�z�����咆�̍��A�m�q�݁@643
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@��n���咆�̏��q�@643
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@1.�@��n���咆�̃A�K���E�}�[�C�@643
��\�́@���߁@��A�@�i��j�@2.�@��n���咆�̍��A�m�}�[�C�@644
��\�́@���߁@��A�@�i�O�j�@���Ε��咆�̏��q�i�q���K���}�[�C�j�@644
��\�́@���߁@��A�@�i�l�j�@�_�����咆�̏��q�i���A�m�E�K�~�j�@644
��\�́@��O�߁@���J�@645
��\�́@��O�߁@��A�@���J�@645
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@���J�Ɋւ��鎖���@645
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@�_���@645
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@�J�~���`���@646
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@3.�@�Ր���v�@646
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@�_���@647
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@�R��m���Ɛ����m���@647
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@�R��m�����@648
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@3.�@�����m�����@651
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@�E�B�[�f�[�X�@654
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@1.�@�m���a���@654
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�ビ��@656
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@3.�@�����@659
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@4.�@�������@662
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@5.�@�_���@664
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@6.�@�z���@666
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@7.�@���@669
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@�咆�@672
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@���W���Ƃ̂Ȃ���@673
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@1.�@���嗢���o���Ƃ���咆�@673
��\�͑�O�߈�A�@�i�܁j�@2.�@�R��m���a���_���ւ̎Q�q�咆�Ƃ��̉@675
��\�͑�O�߈�A�@�i�܁j�@3.�@�������_���i�h���j�ւ̎Q�q�咆�Ƃ��̉@676
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@4.�@�Q�q�̒n�敪�z�@676
��\�́@��O�߁@��A�@���̍��J�@678
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@�嗢�̍��J�@678
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@�R��m�����s����ȍ��J�@678
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@1.�@���J�[�E�K�~�i���J�[�q�݁A���ꌎ����j�@678
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@2.�@�_�q�N���i���ꌎ�O���j�@681
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@3.�@�E�}�`�[�i���\�ܓ��j�@681
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@4.�@�O���E�n�`�i���O�������̓m������߂�j�@681
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@5.�@�_��i�J�~�E�j�V�[�~�[
�@�@�@���i���O�������̐߂ɍs���B���œ����߂�j�@681
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@6.�@�n�[���[�̃E�O�����@681
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@7.�@�܌��E�}�`�[�i���܌��\�ܓ��j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@8.�@�Z���E�n�`�i���Z���j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@9.�@�Z���E�}�`�[�i���Z���\�ܓ��j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@10.�@�`�i�E�O�����i�������\�l���j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i��j�@11.�@�㌎�E�n�`�i���㌎�j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@�����m�����s����ȍ��J�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@1.�@���J�[�E�K�~�i���J�[�q�݁A���ꌎ����j�@689
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�_�N���i���ꌎ����j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@3.�@�E�}�`�[�i���\�ܓ��j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@4.�@�O���E�n�`�i���O���Z���j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@5.�@�_��V�[�~�[�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@6.�@�܌��E�}�`�[�i���܌��\�ܓ��j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@7.�@�Z���E�n�`�i���Z���j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@8.�@�Z���E�}�`�[�i���Z���\�ܓ��j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@9.�@�㌎�E�n�`�i���㌎�ܓ��j�@690
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@10.�@�������E�O�����i���\��\���j�@691
��\�́@��O�߁@��A�@�i�O�j�@11.�@�����m�����̍��J�Ɋւ��鎑���@691
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@���嗢���s����ȍ��J�@692
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@1.�@���i���[�E�O�����i���ꌎ�E�O���E�����j�@692
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@2.�@�j�����i���Z����\�ܓ��A�����\�l���j�@692
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@3.�@�R�[���}�i꜁j�̃E�O�����i�������\���j�@693
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@4.�@�V�[�V���o�M�[�i���q�ՁA�������\�ܓ��j�@695
��\�͑�O�ߓ�A�i�l�j�@5.�@�~�[�k�r�[���E�O�����i���\�ꌎ��ꖤ�̓��j�@696
��\�́@��O�߁@��A�@�i�l�j�@6.�@�V���[�V�k�E�O�����i���\�j�@697
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@�E�}�`�[�@697
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@1.�@�E�}�`�[�ɂ��ā@697
�@��A�@�i�܁j�@2.�@�w�������R���L�x�Ɍ��鉮�Ñ��i�嗢�j�̃E�}�`�[�@698
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@3.�@�R��m�����̃A�T�J���i�ߑO�̃E�K�~�j�@699
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@4.�@�����m�����̃A�T���w�[�i�ߑO�̃E�K�~�j�@700
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@5.�@���Ε��̌ߑO�̃E�K�~�@702
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@6.�@���E�J���i��R�ł̌ߌ�̃E�K�~�j�@702
��\�́@��O�߁@��A�@�i�܁j�@7.�@�E�}�`�[�Ɋւ��邻�̑��̎����@703
��\��́@�N���s���@709
��\��́@�͂��߂Ɂ@711
��\��́@�ꌎ�@712
��\��́@�@715
��\��́@�O���@715
��\��́@�l���@716
��\��́@�܌��@716
��\��́@�Z���@717
��\��́@�����@736
��\��́@�����@738
��\��́@�㌎�@740
��\��́@�\�ꌎ�@741
��\��́@�\�@741
��\��́@�����Ƒ嗢�@743
��\��́@���߁@�����̂���܂��@745
��\��́@���߁@��A�@�����y�ь����̓����@745
��\��́@���߁@��A�@����h�q�̐��@746
��\��́@���߁@�O�A�@�a�J�Ə\�E�\��P�@746
��\��́@���߁@�l�A�@�푈�̔ߎS���@747
��\��́@���߁@�����Ƒ嗢�@747
��\��́@���߁@��A�@�푈�O�̍��䑺�̊T���@747
��\��́@���߁@��A�@�i��j�@����@747
��\��́@���߁@��A�@�i��j�@�_�Ɖ�@748
��\��́@���߁@��A�@�i�O�j�@�w�Z�@748
��\��́@���߁@��A�@�i�O�j�@1.�@���䍑���w�Z�@748
��\��́@���߁@��A�@�i�O�j�@2.�@�N�w�Z�@748
��\��́@���߁@��A�@�i�l�j�@���I�{�݁@749
��\��́@���߁@��A�@�i�l�j�@1.�@�X�ǁ@749
��\��́@���߁@��A�@�i�l�j�@2.�@���ݏ��@749
��\��́@���߁@��A�@�i�l�j�@3.�@�a�@�@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@�c�́@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@1.�@�吭���^��@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@2.�@���^�s�N�c�@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@3.�@�x�h�c�@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@4.�@���R�l��@749
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@5.�@���h�w�l��@749
��\��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@�a�J�@749
��\��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@1.�@�w���a�J�@749
��\��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@2.�@�R���a�J�@749
��\��́@���߁@��A�@�嗢�̐�Џ@750
��\��́@���߁@��A�@�i��j�@�����O��@750
��\��́@���߁@��A�@�i��j�@�a�J�@751
��\��́@���߁@��A�@�i�O�j�@�����@751
��\��́@���߁@��A�@�i�l�j�@���O���ݎ҂Ɛ푈�@752
��\��́@���߁@��A�@�i�܁j�@���̍Č��@753
��\��́@���߁@��A�@�i�Z�j�@��v�@753
��\��́@��O�߁@�嗢�̈�ʏZ���̐푈�̌��@754
��\��́@��O�߁@��A�@�h�q���Ƌ`�E���@754
��\��́@��O�߁@��A�@���q�N�c�@754
��\��́@��O�߁@�O�A�@�R���a�J�@754
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@�Ôg�ւ̑a�J�@754
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@��ꎟ�a�J�ҁ@755
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@��a�J�ҁ@755
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@���ꏊ�ł̐����@756
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@1.�@�����@756
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@2.�@�����ƐH�Ɓ@757
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i��j�@3.�@�f�}�ɖ��킳���@757
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i�O�j�@���Ԑl���e���ł̐����@757
��\��́@��O�߁@�O�A�@�i�l�j�@�̋��i�嗢�j�A��@758
��\��́@��O�߁@�l�A�@�{�y�a�J�@758
��\��́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@�T�v�@758
��\��́@��O�߁@�l�A�@�i��j�@���䑺�@758
��\��́@��O�߁@�l�A�@�i�O�j�@�{�茧�s�_�i�́j���a�J�҂̏،��@759
��\��́@��O�߁@�܁A�@���Ԑl���e���@760
��\��͑�O�ߌ܁A�i��j�@�嗢�o�g���̈ړ��O���[�v�Ƃ��̃��[�g�@760
��\��͑�O�ߌ܁A�@�i��j�@1.�@���쒬�×z�E�v�u���ֈړ������O���[�v�@760
��\��́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@2.�@�������ֈړ������O���[�v�@760
��\��́@��O�߁@�܁A�@�i��j�@�×z�ł̐����@761
��\��́@��l�߁@���̐푈�̌��i�������y�э��k��j�@762
��\��́@��l�߁@��A�@���B��s�@����������Ё@�㌴�T��@762
��\��́@��l�߁@��A�@�s�_���a�J�̎v���o�@���������@765
��\��́@��l�߁@�O�A�@�a�J�̎v���o�@���ǔ���@766
��\��́@��l�߁@�l�A�@�s�_���ł̑a�J�����@�㌴�X���@770
��\��́@��l�߁@�܁A�@�s�_���ւ̑a�J���ڂ݂ā@�R������@773
��\��́@��l�߁@�Z�A�@�s�_���ł̑a�J�̌��L�@��雉�a�@776
��\��́@��l�߁@���A�@�{�茧�s�_���ɑa�J���ā@���ܗY��@779
��\��́@��l�߁@���A�@�o���s�s�\���N�Ɋā@�R������@782
��\��́@��l�߁@��A�@���̐푈�̌��@���䒩��@785
��\��́@��l�߁@�\�A�@���̐푈�̌��@�㌴�M�g�@786
��\��́@��l�߁@�\��A�@�̌��k�i������蒲���j�@�ʏ鐭�M�@788
��\��́@��l�߁@�\��A�@���N�̊�ɉf�����푈�@�R�鐳�h�@789
��\��́@��l�߁@�\�O�A�@�̌��k�@�㌴���g�@792
��\��́@��l�߁@�\�l�A�@�̌��k�@���������@793
��\��́@��l�߁@�\�܁A�@�̌��k�@�㌴�ɗY�@793
��\��́@��l�߁@�\�Z�A�@�����̒����珗�̎q���@�㌴�a�v�@794
�@�\���A�@�u�킳���v�����Ȃ��l�X��Y���ȁ@�㌴�����@796
��\��́@��l�߁@�\���A�@�R���i�����o���j�a�J�@�R�鐴�r�@798
��\��́@��l�߁@�\��A�@�����o���ł̔��Ǝ��e�������@�㌴���Y�@810
��\��́@��l�߁@�ʐ^�\�����@812
��\��́@��ܐ߁@���̐����i���y�̕����j�@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@���䑺�̕����̊T���@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@����E�������獑�g�ց@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@�s���Ə��@�ց@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@1.�@���䑺����@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@2.�@�z�����@814
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@3.�@�q���ۂƍ���f�Ï��@815
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@4.�@���䏄�������h�o���@815
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@5.�@���䏉���w�Z�@815
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@6.�@�L���̒a���@816
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i�O�j�@�e���@816
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i�l�j�@�����ւ̈ړ��@818
��\��́@��ܐ߁@��A�@�嗢������n�ł������i�������j
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@��Ԏc�[�ꏊ�Ƒ䐔�@818
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i��j�@�ČR��^���e�����ɂ�錊�@818
��\��́@��ܐ߁@��A�@�i�O�j�@��^�����{�݂̏Ď��@819
��\��́@��ܐ߁@�O�A�@�⍜���W�y�ђe��Еt��
��\��́@��ܐ߁@�O�A�@�i��j�@�⍜���W�@819
��\��́@��ܐ߁@�O�A�@�i��j�@�a���V���@820
��\��́@��ܐ߁@�O�A�@�i�O�j�@�e��Еt���@820
��\��́@��ܐ߁@�l�A�@�푈�]�b�@821
��\��́@��ܐ߁@�l�A�@�i��j�@�����Ƃ̃g���u���@821
��\��́@��ܐ߁@�l�A�@�i��j�@�����\�ܓ��̏I����@821
��\��́@��ܐ߁@�l�A�@�i�O�j�@�I�������J���Ԝf�r�i�ق������j�@821
��\��́@��ܐ߁@�܁A�@���i�K�}�j�̎ʐ^�@821
��\��́@��Z�߁@�푈�Ə����i�̌��k�j�@825
��\��́@��Z�߁@��A�@���̐푈�̌��@�R��n���@825
��\��́@��Z�߁@��A�@�e�j�A���Ɖ���Ő푈��̌��@�㌴�~�c�@828
��\��́@��Z�߁@�O�A�@�펞���̕ی��w�̕��݁@�ʏ镶�@831
��\��́@��Z�߁@�l�A�@�t�B���s���̎R����f�r�i���܂�j���@�R��[�}�@837
��\��́@��Z�߁@�܁A�@�����o���ł̑a�J�̌��@�㌴�t�q�@839
��\��́@��Z�߁@�Z�A�@���̐푈�̌��@�R��M�q�@839
��\��́@��Z�߁@���A�@���̐푈�̌��@�������q�@842
��\��́@��Z�߁@���A�@���̐푈�̌��@�������@843
��\��́@��Z�߁@��A�@���̐푈�̌��@�����i�c�q�@843
��\��́@�掵�߁@�펞���ƏI�풼��̎莆�@846
��\��́@�掵�߁@��A�@����̕�����a�J�n�ւ̎莆�@���܍K��@846
��\��́@�掵�߁@��A�@�����҂���̎莆�@�ʏ鐳��@851
��\��́@�掵�߁@��A�@�����������̊���@852
��\�O�́@�嗢�̊C�O�ږ��@855
��\�O�́@�͂��߂Ɂ@857
��\�O�́@���߁@�ږ��Ɋւ��鎑���@860
��\�O�́@���߁@��A�@���ꂩ��̈ڏZ�Ґ��i�n�q�n�ʁE�N���ʁj�@860
��\�O�́@���߁@��A�@�嗢�o�g�C�O�ڏZ�Җ���@861
��\�O�́@���߁@��A�@�i��j�@��O�@861
��\�O�́@���߁@��A�@�i��j�@���@882
��\�O�́@���߁@���̈ږ��̌��@885
��\�O�́@���߁@��A�@�T�C�p�����̌��L�@����^�P�@885
��\�O�́@���߁@��A�@���B�ւ̑a�J�@�R��a�q�@887
��\�O�́@���߁@�O�A�@�{���r�A�ږ��̌��L�@�ʏ�P�r�@890
��\�l�́@�l���ҁ@895
��\�l�́@��A�@�����@897
��\�l�́@��A�@����@909
��\�l�́@�O�A�@�_���@917
��\�l�́@�l�A�@�_�ƈψ��@920
��\�l�́@�܁A�@�����@922
��\�l�́@�Z�A�@���ƌ������@924
��\�l�́@���A�@�n���������@926
��\�l�́@���A�@��Á@930
��\�l�́@��A�@�o�ρ@934
��\�l�́@�\�A�@�����@936
��\�l�́@�\��A�@���M�@939
��\�l�́@�\��A�@�Љ�@940
��\�l�́@�\�O�A�@�X�|�[�c�@945
��\�l�́@�\�l�A�@��Ɓ@948
��\�́@�����ҁ@951
��\�́@��A�@�����كz�[���ɂ����ꗗ�\�@953
��\�́@��A�@�i��j�@���ӏ�@953
��\�́@��A�@�i��j�@�\����@955
��\�́@��A�@�i�O�j�@�X�|�[�c�\���@961
��\�́@��A�@������V���Ɍ���嗢�@973
��\�́@��A�@�i��j�@���܌��̗��K�@973
��\�́@��A�@�i��j�@��R�隬�@975
��\�́@��A�@�i�O�j�@��R�_�БJ�����@976
��\�́@��A�@�i�l�j�@���c���j�̗��K�@977
��\�́@�O�A�@�u�嗢�撷���L���v���@978
��\�́@�l�A�@�嗢�̗̉w�@980
��\�́@�l�A�@�i��j�@���ׂ����@980
��\�́@�l�A�@�i��j�@�q�炤���@982
��\�́@�l�A�@�i�O�j�@�܂�������@984
��\�́@�l�A�@�i�l�j�@�����j���́@987
��\�́@�l�A�@�i�܁j�@�ƕ��i��[�Ӂj���j���@987
��\�́@�l�A�@�i�Z�j�@��V�i���[�����j�щ́@987
��\�́@�l�A�@�i���j�@�j�g�i���ȂЁj�����i���[�j���[�̃O���[�@988
��\�́@�l�A�@�i���j�@���ł��[���i���ӂ��[�j�@993
��\�́@�܁A�@���k��u�嗢�����v�@997
��\�́@�܁A�@�i��j�@997
��\�́@�܁A�@�i��j�@1006
��\�́@�Z�A�@���сE�l�����v�\�@1015
��\�́@���A�@���嗢�Z���}�@1016
��\�́@���A�@�����ȍ~�̐���E�N���Ώƕ\�@1027
��\�́@��A�@���嗢�N�\�@1042
*�R����
��R��ǂ̒Q���@85
��R��Ղ̔q���Ɋ�i���ꂽ��u�쉤�q�̐��F�@125
��R���J�����Ċw�Z�~�n�ɂ����������@143
�����ݒu�ɂ��ā@193
���嗢���Ƃ̓�R�����̈ʔv�Ƒ������@222
��R�{�[�W�ƃe�B�����{�[�W�@463
�J�~�~�`�@463
�`�J�u���@471
*�V���L��
�X�L���V�b�v�Ō𗬂��N��肽���Ɖ���35�l�@399
�ꐢ�I����R��J�i����i�����s�j�@536
����ɃJ�W�}���[�ʏ�ʎq����A�㌴�T�炳��@537
���a�肤�S�ς�炸17�N�Ԃ̌𗬐[�߂�@845
���p�E�Q�l�����@1043
�嗢�����ҏW�ψ���g�D�}�@1045
�ҏW��L�@�����ǒ��@�㌴�P�Y�@1046
�E |
�P�O���A�u�I�L�i���O���t (571) p.10�`17�v�Ɂu����S���G�C�T�[�܂�v���f�ڂ����B
�P�P���A�c�R�P������E�ʎ�����, �{��M�E�Ғ��ďC�u���I���d�R�ÓT���w�W
2�v���u�c�R�P���v���犧�s�����B
�@�b�c�Q��
|
���� ���d�R�ÓT���w�̖{�i�I��
�@�@�����ߌ����@�����H�^�s�@4
���� ���d�R�ÓT���w�u�K��v�̏��@�g�Ɗԉi�g�@6
����-�w���W�x�̐���E�ҏW�ɂ�������-�@8
�y�}��z�@10
���d�R�ÓT���w�̉��ߕ\�@12
���d�R�ÓT���w�̓��ꉹ�߂���юg�p��@14
�ڏo�x��(�{���q)�@16
�����ݐ�(�{���q)�@26
����[���(�{���q)�@32
�C���(�{���q)�@42
�^�h����(�{���q)�@50
����[����(�{���q)�@56
�c�[�x��(�{���q)�@66
�ł�(�{���q)�@72
������[����(�{���q)�@84
��g��(�{���q)�@96
���ې�(�{���q)�@102
�g�ƊԂʓ���(�{���q)�@108
�����܂��[��(�{���q)�@118
�^�ߔe��(�{���q)�@124
��{�R����(�{���q)�@128
�o�H�E�ᑾ�z(�{���q)�@128 |
���H�E�_����(�{���q)�@130
�މH�E���Ӑ��ʕ�(�{���q)�@132
���ʕ��(�O����)�@140
�܂�ܖ~�R��(��g��)�@148
���[�˂ܐ�(��g��)�@156
������(�{���q)�@166
���������[��(�{���q)�@174
�M�z��(�{���q)�@180
���₫��(�{���q)�@188
�^�Ӑ�(�{���q)�@196
�������(�{���q)�@204
�v��R�z�H��(�{���q)�@216
�₮����[�ܐ�(�{���q)�@226
�z�N��(�Ί_����)(�{���q)�@238
�z�N��(��쑺��)(�{���q)�@244
�����ց[��(�{���q)�@250
�������ܐ�(�{���q)�@258
�܂�������(�{���q)�@266
���ΐ�(�{���q)�@276
�O�ʊC��(�{���q)�@288
�Ȃ��Ȃ��(�{���q)�@296
��������(��g��)�@304
���ʔ�����[��(��g��)�@312 |
���ڂ�b
(1)�@�E�O�J�k�~���ɂ��ā@23
(2)�@�R���N�[���]�b�@49
(3)�@�ÓT���w�̍쎌�E��Ȏ҂�?�@71
(4)�@<�`��>�ւ̖��̕ύX�ɂ��ā@95
(5)�@���㉹�̂����炢�@101
(6)�@���l���̗��K�_��q�ށ@122
(7)�@�Ì�u�J�E�v�Ƃ̏o�����@155
(8)�@�����̋������y���ށ@165
(9)�@��w�̌��Ɣᔻ�I�p����!�@172
(10)�@�C�f�B�`�D�[�ƃX���`�D�[�@194
(11)�@�g�D�o���[�}�̌ꌹ�ɂ��ā@215
(12)�@�u�`���v�ɂ��ā@248
��ȗp������@187
��ȕ��@�p�����(1)�@237
��ȕ��@�p�����(2)�@265
��ȕ��@�p�����(3)�@275
��ȕ��@�p�����(4)�@287
��ȕ��@�p�����(5)�@311
���Ƃ����@322
�����@337
�E
�E |
�P�Q���A�g�Ɗԉi�g���w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 43(2) (�ʍ� 106) p.55�`71�v�Ɂu�I�����̏��҃A�J�C���R�̑��e�v�\����B
�P�Q���A���쒼�V�ҁE����u���{�����I�W ��14���v���u�N���X�o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@�@��㊏��Џ��a16�N���Ƌ��y�����Џ��a3�E5�N���̕������{
|
�����S�b ���܌���Y �� |
���d�R�×w �{�Ǔ��s ��� �{�ǒ��� �̕� |
���A���̔N�A�u���{�n���w��\�v�|�W 2009f(0) �v���u���{�n���w��v���犧�s�����B�@
|
�u���{�n���w��\�v�|�W 2009f(0)�v�ɔ��\���ꂽ����֘A�̘_���ꗗ�\
| No |
������ |
�_���� |
���\�Җ� |
| 1 |
p.16-16 |
���M�ыC��̓s�s�q�[�g�A�C�����h�̓��ԁ`�ߔe�s�̏ꍇ |
�匴 �ێu |
| 2 |
p.20-20 |
����n��ďo�g�҂̓��{�ɂ�����ړ��o���Ɋւ��錤��
�@�@��:���l�s�ߌ���ݏZ�҂�����Ɂ@ |
���� ���덁 |
| 3 |
p.23-23 |
�{�Ó�����̎悵���r�[�`���b�N�����̊r���N��ƌ�����V���̊C�����ϓ� �@ |
���� �v�m�v |
| 4 |
p.28-28 |
���N�T���S�ʂ������}�j���C�a�E�t�B���s���C�a�� ����n�k�������� |
�� �_�V,�����X �m�G���i,�y���X �W�F�t���[ |
| 5 |
p.29-29�@ |
���d�R�����E�����ɂ�����C�H�R�̔g�Q������̕��z����݂�
�@�@���T���S�ʂ̒Ôg�̔g���������� �@ �@ |
���� �N��, ���q ���� |
| 6 |
p.30-30 |
�{�Ó��f�w�тɂ����銈�f�w���� |
�z�� �q�Y,���� ��u,�S�J ���p,�s�� ���m,��� �F��,�O�� �p��,�ΎR �B��,���q ���W,�J�� �O,�͖� �r�j,���� ��v,�k�c �ޏ��q,���� �M�u |
| 7 |
p.38-38 |
�Ί_���̗��������̕ϓ������Ɋւ����l�@�@�@ |
�ĎR ������,���� �_��,�ѐ� ���q,���� �~�q�@ |
| 8 |
p.79-79 |
��R�̏�Ƃ��Ă̎��R:�|����s�Ӗ�Â̊C���n���ݔ��Ή^�����߂����ā|�@ |
���� �O��@ |
| 9 |
p.96-96 |
�Ί_�s�E���l�ӑ��ɂ�����u����сv�̌���^�R�� �M�p,�Y�R ����,�F�J �����@
|
���^:�̔w�i�ƖړI�^�Ί_�����͂��߂Ƃ��鉫�ꌧ���d�R�n���ł́C�W���S�̂̎��͂���̎����邢�͐X�ň͂��u�z�[�O�v�C������u����сv�̑��݂��m���Ă����D�����u����сv�́C�����ɂ��炳��₷�����n���ɂ����ďW���ƉƉ��Ƃ�������������Ƃ���C�܂����̑��ݎ��̂��W���̈���������̂Ƃ��āC�e�n�̑��G�}�ɂ����m�ɕ`����Ă����D�����āC���������e�n�́u����сv�ɂ��ẮC���̖����ƋN���ɂ��Ă̋c�_���������Ă����D��҂ɂ��ẮC�w�k�؎R�����L�x�Ȃǂ̕��͂�ʂ��āC���̋N�����C18���I�ɒ����E�����Œm�����w�сC�����e�n�̏�s���݂�W���ړ��Ɋւ�����Ƃ������̎w���ɂ��A����ꂽ�u����v�Ȃǂɋ��߂���Ƃ���Ă����D�@���������݁C�����́u����сv�́C���NJԓ��̂悤�Ɍ��̓V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ������ĕۑ���Ԃ̗ǂ����̂��������C���̑啔�����C�s�X�n�̊g��Ȃǂɔ����ď��ł�����D�����Ŗ{�ł́C�Ί_�s���̋��l�ӑ��ɑ��݂����u����сv�̌��݂̏��Љ��ƂƂ��ɁC�ČR�ʐ^�C�u�y�n�������Ɓv�ȍ~�������ꂽ�n�А}�Ȃǒn�Ў��������ƂɌ��������C�ߑ�ȍ~�́u����сv���ł̃v���Z�X���Љ��B
�@���l�ӑ��ɂ�����u����сv�̌���^���l�ӑ��́C���݂̐Ί_�s�̎s�X�n�ɑ�������D�쑤�ɊC��Ղ݁C�����ɒ������т����͈̔͂����͂ނ悤�ɁC���āu����сv���A�����Ă����D�������C���łɋߐ����G�}�̎��_�ŁC�W���̓����[�C�Ƃ��ɐ����ɂ����āC�u����сv�͕s���m�ȏ�ԂƂȂ��Ă����l�q���`����Ă���D�����āC����E���ɂ��������o�āC�c����Ă����������̂���C�؍ނƂ��ďW���̕����Ɋ��p���ꂽ�Ƃ����D�@���́u����сv�̂����C�W���̔w��C�k�����͂��Ă��������ɂ��ẮC�ČR�ʐ^�̎��_�ł͐X���c����Ă������C���̕~�n�̈ꕔ�����݂ł͍L���́u�Y�Ɠ��H�v�Ƃ��Ċ��p����Ă���D�����āC�����H�ɕ~�n���������c��̍ג����Ւn�͌��݁C�����ق⋳��Z���^�[�Ƃ����������{�ݗp�n�ƂȂ��Ă���D����́C���Ắu����сv�̕~�n���ˑR�Ƃ��ċ��L�n�ł��邽�߂ł���D�@����ŁC�W���̓����[�́u����сv�́C���̐Ղ͖��m�ł͂Ȃ��D�Ƃ��ɐ����́C���ݕ�n�ƂȂ��Ă���n�M����ђ�w�Z��������Ԓn�M���C���Ắu����сv�̕~�n�ɊY������Ǝv���邪�C���̎��͂ƍۂ������i�ς̈Ⴂ��������Ƃ͂����Ȃ������D�����ɂ��ẮC���݁u�ۈ��ʂ�v�ƌĂ�Ă��铹�H���u����сv�̕~�n�̈ꕔ�Ǝv���邪�C���̎c��̐Ւn�ƂȂ�C���H�����ɍג����L�т�y�n�́C�l��̒�⒓�ԏ�ƂȂ��Ă���C�ꌩ����Ɓu����сv�̐ՂɌ����Ȃ��D�������C����炩�Ắu����сv�̐Ւn�Ǝv����y�n�ɂ��ẮC�P�v�I�Ȍ������͂قڌ��Ă��Ă��Ȃ������D�n�А}��ł����������u����сv�̂������ӏ��͓Ɨ������n�M�ƂȂ��Ă���C�אڒn�M�̋��Z�҂ł����Ă����̒n�M�����ꂽ��C���������Ă��肷�邱�Ƃ͓���悤�ł���D�@�������āC���H������{�ݗp�n�ƂȂ��đ啔�������ł����u����сv�ł��邪�C���łɎc����Ă��镔��������D���ꂪ�C���ďW�������͂�ł����u����сv�́u�l���v�Ƃ�����ӏ��ł���D�u����сv���C�ɒB����ӏ��́C������u�E�^�L�i��ԁj�v�Ƃ��āC���݂ł��Z���̐M�̑ΏۂƂ��Ắu�q���v��u�J�[�i��ˁj�v��������L���ȐX���c����Ă���D�����āC���̑Ίp�ƂȂ�C�Ƃ��ɖk���[�̒n�M���C�ČR�ʐ^�̎��_�ł��̎��͂́u����сv�Ɣ�ׂčL�����́C�܂Ƃ܂����X���c����Ă����D���������͌��݂��C��������ѓ쑤�����H�ƂȂ钆�ŁC���̕��̒n�M�ƁC�ꕔ���c����Ă���B
�@�u����сv���ł̃v���Z�X�^�ȏ㌩�Ă����悤�Ɂu����сv�ɂ��ẮC���̕~�n���u�y�n�������Ɓv�ɂ����ēƗ������n�M�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�̂��C�����ēy�n���L�W������m�Ɂu���L�n�v�ƂȂ��Ă��������C��̏��ł̓x�����Ɋւ���Ă���\�����w�E�ł����D���Ȃ킿�C�u���Ɓv�̎��_�ł��łɂ��̑��݂��s����ł������\���̂��鐼�[�́u����сv�́C�܂Ƃ܂����n�M�ƂȂ炸�C���݂ł͂��̐Ղ����߂邱�Ǝ��̂�����ƂȂ��Ă���D����ŁC�W���k���́u����сv�́C���Ƃ��ƕ����L���C���m�Ɂu���L�n�v�n�M�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���Ƃ������āC���݂ł����H�p�n������{�ݗp�n�Ƃ��Ă��̕~�n�͈̔͂�e�ՂɊm�F���邱�Ƃ��ł����ԂƂȂ��Ă���D�����āC���ł��u����сv�̎l���ƂȂ镔���ɂ��ẮC���݂ł����m�ɐX���c����Ă����D���̂悤�ɍ���̌�������́C�W�������͂ށu����сv�̒��ł��C�ۑ��D��x�̍����ӏ��ƁC�e�ՂɎ���ꂽ�ӏ��Ƃ����邱�Ƃ������ꂽ�B |
|
| 10 |
p.99-99 |
���{�̒n���ɂ�����ό��̍��ۉ�:�[�����������Ɂ[�@�@�@�@ |
�k �c �W�i�@�@ |
| 11 |
p.109-109 |
���ꌧ�̍��o�����̗v��:���ꌧ�암�n��̒��������ƂɁ@�@
|
�R�� ���a,�]�� �Y��,���� ���Y,���r �i�N,�� �j�� |
| 12 |
p112-112 |
���v���ɂ�����k������n�Ɣ_�n�̊Ǘ� |
�Y�J �� |
| 13 |
p.116-116 |
�Ί_���̉͐여������Ɖ͐쐅���������Ɋւ���n���w�I���� |
�ĎR ������,���� �_��,�ѐ� ���q,���� �~�q�@ |
| 14 |
p.119-119 |
����ɂ�����X�ї��p�̕ϑJ�̉𖾂Ɍ����� |
���� ���i |
| 15 |
p.122-122 |
���ߔe�̓s�s�v��Ɓu�ꏊ�̐����v:�q�Ғ��r�̍ċ����߂����� |
���� ���m |
| 16 |
p.128-128 |
�쐼�����������l���D��ۑS�n��iBPA�j�ɂ�����T���S�ʐ�C��ł�
�@�@�����R�n���I���j�b�g�iPGU)�̉��p�@�@�@ |
���� �B�Y,�ēc ��,�R�� ����,���� �Ύ� �f |
| 17 |
p.154-154 |
���������ߔe�̒n�`�i�ϕ����̂��߂�GIS�f�[�^�\�z�@�@ |
�͊p ���T |
| 18 |
p.155-155 |
���ꌧ�{�Ó��̊C�݂ɕ��z���鋐����̓����Ɛ��Y�v���Z�X |
���� �O,�}�� ��,���� �^�V |
| 19 |
p.156-156 |
�{�Ó��ɂ�������j�n�k�ƈ�ՂŊm�F���ꂽ�Ôg�͐ϕ��@�@ |
�͖� �r�j,���J�� ��,���� �a��,�v�L ��k,�z�� �q�Y,���� ��u,�S�J ���p,�s�� ���m,���
�F���@ |
| 20 |
p.157-157 |
�{�Ó����ݕ��̒n�`�w�I�����Ƌ{�Ó��f�w�т̊������̌��� |
���� ��u,�s�� ���m,��� �F��,�z�� �q�Y,�S�J ���p,�͖� �r�j,���� �L��,�ēc ���@ |
| 21 |
p.158-158 |
�{�Ó��f�w�тɊւ��C�您��ї���̒n�`�n���w�I���� |
�s�� ���m,��� �F��,�S�J ���p,�z�� �q�Y,���� ��u,�X �ǎ�,�͖� �r�j�@ �@ |
| 22 |
p.159-159 |
�{�Ó����Ӊ��݈�ɂ�����C��}���`�`�����l�����g�T�����ʁ@�@ |
�z�� �q�Y,�S�J ���p,�s�� ���m,���� ��u,��� �F��,���� ��v�@ |
| 23 |
p.160-160 |
�����ɂ�����Ôg�ЊQ:�V���|�W�E���̎�|���� |
�͖� �r�j |
| 24 |
p.161-161 |
�{�ÁE���d�R�����ɂ�������j�Ôg�̏P���ƒÔg�ЊQ:
�@�@���Ƃ���1771�N���a�Ôg�C1667�N�n�k�Ôg�C�����1500�N���̒Ôg |
�͖� �r�j |
| 25 |
p.162-162 |
�Ί_�����ۉ×ǛԎ��ӂ̈�ՂŊm�F���ꂽ�n�k�ƒÔg�̍���
�@�@��:�V�Ί_��`�\��n����Ք��@�����̐��ʊT�v |
�R�{ �����@�@�@�@ |
| 26 |
p.163-163 |
���l�V�~�����[�V�����ɂ�鉫�ꌧ���݈�̒Ôg�Z���\���@�@�@ |
���� �z��,�|�� �m,�쉮�� �V,�� �@�� |
| 27 |
p.164-164 |
�펞���̕ČR�B�e�ʐ^�����炩�ɂ�������C�n�k�Ôg��Q�Ɣ��n�`�̊W�@�@ |
�F�� ��,���W �M��,������ ����,��� �N�O�@�@ |
| 28 |
p.165-165 |
���n�����Ɛ��l�v�Z�Ɋ�Â��Ôg�̈ړ���͂Ɩh�Ђւ̉��p �^�㓡 �a�v�@
|
���^:�Ôg�ɂ�苐�I���^���Ƃ����C������u�Ôg�v�ړ����ۂ́C���{�ł͌Â�����m���Ă���D���ł��C1771�N�ɉ��ꌧ�̐Ί_����{�Ó����ӂ��P�������a�Ôg�ɔ������̂��L���ł���i�Ⴆ�C�q��C1968�G�͖��E���c�C1994�j�D�Ƃ��낪�C�Ôg����ɒÔg���ڍׂɊώ@�E�L�ڂ���������͐��E�I�ɂ��ɂ߂ď��Ȃ��C���̎��Ԃ͕s���ł���D���̂��߁C�Ôg�̔F������܂��Ă��Ȃ������łȂ��C���z��T�C�Y�Ȃǂ̏��C�h�Џ�L�v�ȒÔg�̐����ʁi�g��������Ȃǁj�Ɋւ���������̂��Ȃǂ͑S���킩���Ă��Ȃ��D�^2004�N�C���h�m��Ôg�ɔ����C�^�C�E�p�J�������ł́C�����[�g����̃T���S���I����ʂɏʌ���ɑł��グ��ꂽ�D�Ôg�O��̉q���ʐ^�̔�r�⌻�n�Z���̏،�����C�����͒Ôg�őł��オ�������Ƃ����Ăł���D���̏�C�Ôg����ɔg����Z����Ɋւ��钲�������{����Ă��邽�߁C�Ôg�Έړ����ۂƒÔg�̐����ʂ��֘A�t���ċc�_���ł���C���E�ŏ��߂Ă̎���ł���D �{���\�ł́C�p�J�������̒Ôg�̌��n�����Ɛ��l��͌��ʂ����ƂƂ��ɁC�Ôg����Ôg�Ɋւ���ǂ̂悤�ȏ�����o����̂���C���a�Ôg�ɔ������I�Q�Ƃ̗ގ����ɂ��ċc�_����D�^�p�J�������̋��I�Q�́C��600 m�̕��̏ʌ���ɎU�����Ă���D�ő咼�a�͖�4
m�ŁC�d�ʂɊ��Z����Ɩ�23�g���ł���iGoto et al., 2007�j�D���̐��͐���䂤�ɒ����C�召���܂��܂ȃT�C�Y�̋��I�����݂�����Ԃō������ȉ��ɑ͐ς��Ă���C�ő�T�C�Y�̋��I���C�ݐ��t�߂ɑ͐ς��Ă���D�����āC����ɂ͈���ł��オ���Ă��Ȃ��Ƃ�������������D�����̌����́C�C�݂ɕ��s�ȕ�������z���Ă���C���������Ƃ��āC��]�܂��͒���`�Ԃɂ���Ĉړ��������̂ƍl������iGoto
et al., 2007�j�D�܂��C���I�ɕt�����Ă���T���S��[����C���I�͌��X�ʉ��������[10
m�Ȑ�̏ʎΖʏ�ɕ��z���Ă����ƍl������D�^�p�J��������ΏۂƂ����Ôg�k��v�Z�̌��ʁC�^�C�ł͒Ôg�ɂ�钪�ʕϓ��͒��ʒቺ����n�܂邱�Ƃ�C���g�����g���P�O�ɂ͒��ʂ��ő�6
m���ቺ���C�ʌ������o���邱�Ƃ��킩�����iGoto et al., 2007�j�D�ʎΖʏ�ł̒Ôg�����͍ő�15
m/s�ɒB���C�ő�T�C�Y�̋��I���ړ�������̂ɕK�v�ȗ������͂邩�ɏ����Ă����Ɛ��肳���D�܂��C�Ôg�Έړ����f���iImamura
et al., 2008�j��p���ċ��I�̈ړ���͂��s�������ʁC�S�Ă̋��I���������ȉ��Œ�~����̂́C�r�[�`���ӂ̎Ζʁi��3
m�̍��፷�j�ɒi�g���Փ˂����ۂɔ��˔g���������C�k�㗬�Ƃ͋t�����̗��������������˔g�����ɓ`�d����̂ɔ����C�ʌ���̒Ôg�������}�����邱�Ƃ������ƍl������D�^�f�ʈꎟ���Ôg�Έړ����f����p���C�Ôg�̏����U���E���������܂��܂ɕς��C�p�J�������̋��I�Q�̈ړ���͂��s�����D���̌��ʁC2004�N�C���h�m��Ôg�Ɠ��K�͂̔g���E�����̔g����˂����ꍇ�ɂ̂݁C�S�Ă̋��I���������ȉ��ɒ�~���C���ő�T�C�Y�̋��I���C�ݐ��t�߂ɓ��B����Ƃ����C���n�̋��I���z��ǍD�ɍČ��ł��邱�Ƃ��킩�����iGoto et al., 2009�j�D���̎�@��p����C�Ôg�̏ڍׂ��s���Ȓn��ɂ����Ă��C���I�̌��݈ʒu�Ə����ʒu����ђn�`������ł���C���I���z������Ôg�g���E�����̏������C������x����ł���ƍl������D�^�Ί_�����C�݂ɕ��z���鋐�I�Q�̕��z�ׂ����ʁC�啔���̋��I���������ȉ��ɒ�~���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����D���C�݂ł́C�r�[�`�̔w��ɍ��u�����B���Ă���C�p�J�������̃P�[�X�Ɠ��l�ɁC���u�ɒÔg���Փ˂����ۂɔ������锽�˔g�ɂ���ĒÔg�������}�����C���I���������ȉ��ɒ�~�������̂Ɛ��������D���̏ꍇ�CIV�͂ŏq�ׂ����@���K�p�\�ł���C�Ί_�����P�������a�Ôg�̋Ǐ��g���E�����̑g�ݍ��킹�𐄒�ł�����̂Ɗ��҂����D |
|
| 29 |
p.166-166 |
2004�N�C���h�m��Ôg�ƃ}���O���[�u�ш�̔j��Ɋւ����ʓI�ȕ]����@�@�@�@
|
�{�� �L�F,���� �p��,�n�� �ɍK |
| 30 |
p.169-169 |
����̎��R�ی�ƃW�I�p�[�N�@�@ |
���� �B�Y�@ |
| 31 |
p.170-170 |
�W�I�c�[���Y���őn��Â���̖����@�@�@ |
�͖{ ��n |
| 32 |
p.171-171 |
�W�I�p�[�N�̉\���@�@�@ |
���� ���K |
| 33 |
p.173-173�@ |
�W�I�c�[���Y���ɂ����鎩�R�n������̖����@�@ |
���� ���K�@ |
| 34 |
p.174-174�@ |
����암�̐ΊD��n��ɂ�����K�C�h�c�A�[�̎��H�@�@�@�@ |
���� �I�@ |
| 35 |
p.175-175�@ |
�l�ފw�E�l�Êw����݂�����̃W�I�c�[���Y���̉\���@�@ |
���c �S��,�R�� �^���@ |
| 36 |
p.176-176 |
����ɂ�����W�I�c�[���Y�����i�̉\���^�哇 ���q
|
�v��E���^:�^�Q�D���n�ł��邱�Ƃ���������̃W�I�E�T�C�g�^�W�I�c�[���Y���̑ΏۂƂȂ�ꏊ�ɂ́A��R�⓴��������ꍇ�������B�����͐̂���l�̕�炵�Ƃ������������Ă����B�Ⴆ�A�����̓����t�߂��̏�Ƃ�����A�����̓������͂��ĕ�Ƃ��ė��p���Ă������Ƃ�����W���[���B���ɁA�c��⎩�R�𐒔q���A�R���A�C�A�A�ɐ_���h��Ƃ����Ă��鉫��ł́A�_���~�Ղ����ꏊ��_���J�����ꏊ������i�E�^�L�j�A���n�ƌĂсA�l�X���F�������Ă���ꏊ�ł��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�܂��A�����ɂ����Ă��A�����𗬂�鐅���M�d�Ȉ������ɂ��Ȃ�A�����̐l�X�̖������h�Ƃ��Ă̖������S���Ă����B���݁A���ꌧ���ɂ͐���𐔂���قǂ̌�Ԃ����݂���Ƃ����A�T���o���Ă��Ȃ����n�����������݂���Ƃ������Ă���B�^�W�I�E�T�C�g�̔��@�₻�̎�舵���ɂ����ẮA�_���ȋ�Ԃ��Ɏ���Ă�����l�����Ɍh�ӂ��͓̂��R�̂��ƁA�K�ȉ���҂̑��݁A��������ꏊ�̋��A�펯�I�ȍ�@������̓O��ȂǁA���p�̃K�C�h���C���������K�{�ł���B�ɂ���Ă͐l���������邱�Ƃ̋K���◧�����点�Ȃ��`�ŕی삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꏊ�����邱�Ƃ𗝉����A�Ώےn�Ƃ��ď��O����Ƃ������f���ό������Ƃ��ė��p����ۂɂ͋��߂���B |
|
| 37 |
p.177-177 |
����ɂ����鎩�R�ی슈���̌���@ |
�ڑ� �M�N�@ |
| 38 |
p.178-178 |
�����̃G�R�c�[���Y��:��Z�����G�R�c�[���Y���̎��_����@ |
���� �L�܁@ |
| 39 |
p.180-180�@ |
�`�����@�Ί����̕ۑ��Ɗ��p�@ |
�c�a ���F |
| 40 |
p.183-183 |
����ɂ����������V�C���Ɛl�Ƃ̊ւ��:�����m��ɂ�����
�@�@���u���Ȃ鋛�v�u�G���v�u�������v�Ƃ��Ă̗��p���r�@ |
���� �C�@ |
| 41 |
p.185-185 |
�����E���ꗣ���ɂ�����l���ω��ƍ���@�@ |
�{�� �v��,���� ���@ |
| 42 |
p.186-186 |
42�{�Ó��ɂ����鏬�K�͏h���{�݂̋}���Ƒ��l���@ |
���d �Y�v�@ |
| 43 |
p.187-187 |
43�����哇�F���������o�g�҂�U�^�[���ړ��̓����Ɣ����v���@�@ |
�A �����@ |
| 44 |
p.188-188 |
���ꌧ�|�x�����ԓ��ɂ�����w�Z�̖����ƏZ���ӎ��@ |
�x�{ ��́@ |
| 45 |
p.199-199�@ |
�����ς��ΊC���ς��:�J���s�ׂɔ����T���S�ʐ�C��̕ω� |
���J�� �ρ@�@ |
| 46 |
p.200-200 |
�u�����сv��Ƃ��ẴT���S�� |
���� �B�Y�@ |
| 47 |
p.201-201 |
�G�}�E�C�}����݂��T���S�ʁ@�@ |
�ڍ� �Θa�@ |
| 48 |
p.202-202 |
�����̌��T���S�ʂ̊C�@ |
�n�v�n ���@�@ |
| 49 |
p.203-203 |
�T���S�ʂƁu���ނ�(��蕨�j�v�̎v�z�^�x �M�s�@�@
|
�v��E���^�^���ނ�v�Ƃ����l�����́A���{�̊e�n�A�Ƃ�킯�����E����n���ɂ����āu�l�ԂƎ��R�̊W���v���l����ꍇ�̍�����Ȃ����̂Ɖ��҂͍l���Ă���B���̍l�����T���S�ʒn��ŋ�̓I�Ɏ��������̂����}�ł���B���\�ł͂������̎���������Đ����������B�Ⴆ�A�^�_���̒n���u�S�����l�v�́u��肪�l�v�ł���A�Y����N���D�Ɏg���闬�Ɋւ���^�u�[�A�����ƊC������̎O�c�����т����v�����̍��J�Ȃǂ����グ��B�����̎��Ⴉ�猩���Ă���̂́A���R�ɑ���l�ԑ�����̏����A�u���ނ�v�̒j���I���i�������яオ��B���̍l�����̉�����ɂ́A�l�ԁA�����ăT���S�ʂ��̂��̂��A���R�̏ے��I���E�ł���j���C�J�i�C����́u���ނ�v�ł��낤�Ƃ����l�������w�E����B�����@�x�@�M�s(1992)�@�y�̃C���[�W�E�̃C���[�W�F�����E����ɂ݂鎩�R�ƂЂƂƂ̌𗬁B�T���S�ʒn�挤���O���[�v�ҁw�M���S�̓��F�T���S�ʂ̕��y���x�Í����@�App.31-47. |
|
| 50 |
p.206-206 |
�Ί_�����여��ɂ����錜�����y��ƒ��f�E�����̗��o�ʐ��� |
�ѐ� ���q,���� �~�q,�W�F���\���E�C�����_,���c�O |
|
|
���A���̔N�A�uAJJ = �A�W�A�E���{�����Z���^�[�I�v (�ʍ�5) (�V���|�W�E��
�A�W�A�̏Ĕ����牽���݂��邩) �v���u���m�ڑ�w�A�W�A�E���{�����Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@�iIRDB�j
|
�u�V���|�W�E���v�A�W�A�̏Ĕ����牽���݂��邩
�@�@�����c�M�j�@,�P�c���`,�@���a���@�{�����W�@,�R�c�m�j |
���{�̏Ĕ����� �P�c���` p.151�`158
���I�X�̏Ĕ����� ���a�� p.158�`167 |
����̏Ĕ� �{�����W p.167�`171
��p�̏Ĕ� �R�c�m�j p.171�`174 |
���A���̔N�A���� �K�j�����y��������ҁu���y������ (�ʍ� 26) p.21�`51�v�Ɂu�̎��E�y������
���ꌧ��X������X���E�匓�v�̃G�C�T�[�v�\����B�@ |
| 2010 |
22 |
�E |
�P���A�������ҁu�����w ���߂Ɗӏ� ��75��1�� ���W ��@����Ƃ��ẴA�C�k��Ɨ�����v���u���傤�����v���犧�s�����B
|
��@����Ƃ��ẴA�C�k��Ɨ�����(�O��)���̓��{���
�@�@���`���E���W�ւ̂������ �㑺 �K�Y p.6�`26
�A�C�k�� p.27�`100
�����l�Y�搶�̒�q�Ƃ��ĕ��ݎn�߂����X �c�����U�q p.27�`34
�R�c�G�O�ƃA�C�k��n������ ���英�q p.35�`38
�w����̃A�C�k�ꎫ�T�x�ɂ��� �������� p.39�`43
�A�C�k�ꎑ���̕ۑ��Ɗ��p ���c���� p.44�`48
�A�C�k��̕��@�I���F �����m�� p.49�`55
�A�C�k��̒n�捷--�k�C�������𒆐S�� ����T p.56�`60
����A�C�k��ƌ������|�̃A�C�k�� �ؑ։p�Y p.61�`65
�A�C�k�ꌤ���̐V�����i�K �䓛���M p.66�`72
����ɂ�����T�n�����A�C�k��
�@�@�@��(�����A�C�k��)�̌��� ��ˏ��F p.73�`77
�A�C�k�̖k�̗אl����--�E�B���^�ƃj�u�t�@�Ëȕq�Y1 p.78�`83
�A�C�k�����w�̓W�] �����@ �v�a p.84�`88
�A�C�k��Ə헤�̒n�� ��@ �� p.89�`94
�A�C�k��E�A�C�k�������w�ɂ��Ă�
�@�@����v�����ژ^ �Ό� �� p.95�`100
������ p.101�`199
OCLS�Ɨ����̌���n���w ����v�@ �_ p.101�`107
�w�����낳�����x�̌���̏��� ���� �@�r�O p.108�`112
�ߔe�����E�����A������� p.113�`117 |
�����̕��@--�����j�ƕ��@�I�ȓ��� �Ôg�Õq�q p.118�`122
�ߔe���������f�[�^�x�[�X ���Ԍb�q p.123�`127
���̂ɂ��� �O��~�q p.128�`131
���D�^��u�N���Ɨ�����w�ł�
�@�@������ŋ��r�{���̍�� ������ގq p.132�`137
�����j���[�X�Ɖ����u��--�V�}�N�g�D�o�ɂ��
�@�@���\�����߂��� �����q p.138�`143
�����䂭�����ƌ�������--���@�����P�搶��
�@�@�����A�m�����̌��� ���܍K�q p.144�`147
���̈ɍ]�����������j �����r�q p.148�`154
����������������--�E�`����̌����𒆐S��
�@�@�� �܂��� �Ђ낽�� p.155�`163
�łт䂭���̌��t--���V������(����)�̍s�� �������� p.164�`167
���c�{������̌���������--�����哇��a�l�����̕E
�@�@���L�q��ʂ��� �{�R���ێq p.168�`172
���d�R���������j�̓�l�E�{���c���
�@�@���{��M�j(�Ƃ��̕�) �����H�^�s p.173�`177
���a�̑�Ôg�Ɣg�ƊԁE���ە��� �Ί_�� p.178�`181
���d�R�̂��ׂ��� �o��郋���q 1 p.182�`188
���d�R�×w--���d�R�×w�u����v�̓��� �{�� �F p.189�`192
�����ꏔ�����̎���--�����ƂɈقȂ���� ���]�F���q p.193�`199
�E |
�P���A�~�c�ߎq�����{�v�z����������ҁu���{�v�z�������� = The journal o Japanese thought and culture 3(1) (�ʍ� 5)�@ p.85�`93�@���ە����H�[�v�Ɂu�I�s�� �X�Ƌ�Ԃ̐��n--���(������)--����E�v�����𒆐S�Ɂv�\����B
�Q���A���Ύ���, �n�v�n���ҁu�C�ƎR�̌b�݁v���u�{�[�_�[�C���N�v���犧�s�����B�@
(���������E���̐����� ; 4. ����̂��炵 ; 2)�@�@�@110p�@�@�@�����F��㊌����}���فF1005426083
|
��1�́@�{���������E�T���S�ʂ̊C�Ƌ��Ƌ� 7
��2�́@����s�O�X�N���}�E���}�͐��������� 37
��3�́@�ߔe�s�����E�s��̎v���o 59 |
��4�́@���������ԁE�^�ߔe�x�Ɏ����ꂪ�������� 73
��5�́@���������c�E�E������̎R���� 95
�E
|
�Q���A���ꌧ�����U����j���ҏW���ҁu���ꌧ�j �e�_�� ��3��(�×���)�v���u���ꌧ����ψ���v���犧�s�����B
���i�F �i
|
�����̂��Ƃ�
�}��
���_�@�u�×����v�T�O�̍Č����@3
���_�@�R����(1)�@�����Ɖ���̊T�O�̐����@20
���_�@�R����(2)�@�������{�̓�Ɩk�@22
��ꕔ�@���������ւ̓�
��ꕔ�@���́@�����̊�w�����@27
��ꕔ�@���́@�R����(3)�@���`�����i�@46
��ꕔ�@���́@�R����(4)�@�����̃C�l�̓��@48
��ꕔ�@���́@�o�y�l�������×����̐l�Ɛ����@50
��ꕔ�@��O�́@�T���S�ʂƉ��������Ձ@66
��ꕔ�@��O�́@�R����(5)�@�����̃T���S�ʁ@86
��ꕔ�@��O�́@�R����(6)�@�^�u������Ԍ����E
�@�@������Ղ̕��ƏW���@88
��ꕔ�@��l�́@���`�\�I�̗����@90
��ꕔ�@��l�́@�R����(7)�@�w�@���x�̗����ƊJ���ʕ�@110
��ꕔ�@��́@�O�X�N�����̌`���Ɠ��A�W�A�@112
��ꕔ�@��́@�R����(8)�O�X�N�����J�n�N����߂��鏔���@132
��ꕔ�@��Z�́@���̃O�X�N�Ɖ��ˁ@134
��ꕔ�@��Z�́@�R����(9)�@���������̏�s��Ձ@154
��ꕔ�@��Z�́@�R����(10)�@�{�Ẩp�Y�`���ƍl�Êw�@156
��@���������̓W�J
��@���́@�����̐����ƒ��v�J�n���̏����@161
��@���́@��������̐����@179
��@��O�́@���^���̒����W���@201
��@��l�́@���R�����Ɖ����@217
��@��́@���R�����Ƌ{�ÁE���d�R�@240
��@��Z�́@�����̊C����Ɨ����@260
|
��@�掵�́@���R�����ƎF���@279
��@�攪�́@���J�����̓o��@301
��@���́@�ܒ��݂̂��×����@321
��O���@�×����̎Љ�ƍ��J
��O���@���́@�×����̑��ƕ�炵
��O���@���́@���߁@�Z�E�߁E�H�@343
��O���@���́@���߁@�×����̖~�s�����߂����ā@353
��O���@���́@���s�̐����@363
��O���@��O�́@�`���ߔe�̓W�J�@387
��O���@��l�́@�O���l�̋L�^�Ɍ���×����@409
��O���@��́@��\����݂�×����̎�@427
��O���@��Z�́@���{�̍��J�ƐM�@451
��O���@�掵�́@�����̓`���ƓW�J�@471
��l���@�×����̒f��
��l���@���́@�v�đ��̐����@495
��l���@���́@�蕶�ƃI��������݂�×����̉��{�ՋV�@511
��l���@��O�́@�����̑K�Ɨ��������@527
��l���@��l�́@�×����̑��搧�@545
��l���@��́@�擇�̐�j�����@559
��l���@��Z�́@�擇�̏W���@575
��l���@�掵�́@�������{�̗����ρ@591
��l���@�攪�́@�N���_���Ƃ͂Ȃɂ��@611
�ҏW�o�߁@628
���M�҈ꗗ�@630
���͋@�ւ���ы��͎҈ꗗ�@631
�}�ŏo�T�ꗗ�@18
�N�\�@11
�����@1 |
�Q���A�����������u���ꕶ�w�̏��� : ��㕶�w�E�������E�Y�ȁE���́E�Z�́v���u�{�[�_�[�C���N�v���犧�s����B (�p���E�����m��)
�@�@�@�@256p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1005419955�@�@
|
���ꕶ�w�̏���/������
�O�����ɑウ��-���ꕶ�w�̓�n��
�T ��㕶�w�̏o��
��㉫�ꕶ�w�̏o��
�h�Պ��̎������w-��㉫��ɂ����鎙�������^���̓W�J
�U �������̏o���E�J��
�����������̓W�J-���ƈ�̉���߁E���㎍
�������̐��E
|
�V �Y�Ȃ̊v�V�ƓW�J
�����v�V�ւ̑ٓ�-�u���ԉS�v���߂�����
�����̉��-�u�閾�n���v���߂�����
�ʔv�ƈ⍜-��́u�o����i�v���߂�����
�W �C�O�̗��́E���̒Z��
�����m�r�̂̒n��-�Z�̂̒��̐푈
�wHawaii Pacific Press�x���Ɍf�ڂ��ꂽ�y���[�̗���
���Ƃ��� |
�R���A������w�ҁu�m�̒×�(���̂����傤)�v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B (���炩����̊w�Ǝv�z / ������w��, 3)
|
�\����͍����� �C�̃V���N���[�h�Ɛi�v�D / �ԗ�� ��
���������ɂ����銿���b�ɂ��� / �蔎�u ��
�n���C��w�ɂ����鉫���ƕ����R�[�X / ���c���q ��
���l������p��Ɖp�ꋳ�� / �ēc���I ��
�C�̕��w / �R��V ��
�u���ꉹ�y�̕��v�{�ǒ���̐��U�Ɖ��y / �� ��
�A�W�A�̐D���E����̕z / �Љ��~ ��
���o�̉��������_ / �Ôg���u ��
���m�֒��ޗ� �w�ё������l���� / �w�˔��j ��
���m�Ȃ�C�Ɠ�����̒��� / ��锣 ��
�݂�ȂŎ�낤����u�����h / ���~�O�j ��
�����̌o�c�̌������������ɂ��Ď������邩/�ڌ��_�� ��
21���I�Ƃ�������ɂ����鉫��o�ς̖��͂Ɖ\��/���E�� ��
�J���@�̂Ȃ��Ȃ��? / ��쏹�_ ��
���M�т���̖₢ �T���S��H���r��
�@�@�����I�j�q�g�f�͐�ł�����ׂ���? / �l�萷�N ��
�M�сE���M�т̊C������̖�����T�� / ���r�M�v �� |
�C�ɔ���V���Ȋ���� / �I�����q ��
����ӂ�Ȃ������A���M�т̓��Ƃ�������̖ƐX/�V���F�a ��
����ō����Љ�̐i���ɔ��� / �Ҙa�� ��
���M�ђn��ł̐H�Ƃ̈��S��
�@�@�����ۑS�̂��߂̔_�� / ���n���h�E�A���U�h�E�z�T�C�� ��
�~�N���l�V�A�n��̓��X�̒n�` / �O��W ��
�J���n�� ���Ɗm���_ / �R���� ��
�r�[�J�[�̒��̉F�� / �ē����q ��
�f�W�^���Z�p����? / �a�c�m�v ��
�F�����"�ӎv����"���x������ / �{�锹�v ��
�S���w�Ɣ]�Ȋw���琶�U���B���݂� / �x�i��� ��
�������߂��鐢�E �����Ȑ��E�̕���/�g�[�}�E�N���E�f�B�A ��
���₩�ȃQ�m���̂͂Ȃ� / �v�� ��
�ł��邱�Ƃ���n�߂� / ���镟�� ��
���������`��������̎��� / ����M�v ��
�A�W�A�E�����m�n��̓��וی�/�R�����E�E�B���A���E�r���Y ��
�S�₳�������I�X��Ï]���҂Ƃ̋��� / �_�ԃV�Q �� |
�R���A�^�ߍ����j�Ҏ[�ψ�����Ǖҁu���������������E�ǂ��Ȃ��̐������鐢�E�́A���Ǝ��̈ʑ�(�g�|���W�[)�@�v���u�^�ߍ����v���犧�s�����B (�^�ߍ������j ; ��2��(������))
|
�����ɂ������ā@�^�ߍ������@�O�Ԏ�g�@1
�v�����[�O�@6
�u�����ނ�сv�łȂ��鐶�Ǝ��A���Ɛ��̘A���@�ď霨�@8
���́@�^�ߍ����@�Ñw�̑��̂������܂��@11
���́@���ۍ��G�}�ɕ`���ꂽ�^�ߍ����@12
���́@���N�Y�����̗^�ߍ������^�i���@���^��Z�܊��j�@14
���́@�C�悩�猩��l�b�g���[�N�̉\���@25
���́@�擇�̋��S�́\��Ăƍޖւ̗~�]�@�J�쌒��@26
���́@�u����p�C�v�������̎��_���猩��
�@�@���^�ߍ��̓��ۊW�j�@���m�d�@34
���́@���y���[�Y�͑��̑��ʂ����^�ߍ����@52
��O�́@�N���s���@55
��O�́@(1)�@�X���K�e�B�i�����j�̊肢�@58
��O�́@(2)�@���ʃj�K�C�@60
��O�́@(3)�@�`�`�ʃj�K�C�@60
��O�́@(4)�@�^�i���h�D���@60
��O�́@(5)�@���k���@64
��O�́@(6)�@�E�`�j���A�C�@67
��O�́@(7)�@�C�X�J�o�C�@69
��O�́@(8)�@�h�D�K�ʃq�@72
��O�́@(9)�@�A�~�E���@73
��O�́@(10)�@�E�K���t�g�D�e�B�@74
��O�́@(11)�@�A���K�_�g�^�K�r�@75
��O�́@(12)�@�A���~�f�B�@75
��O�́@(13)�@�_�e�B�O�N�C�@76
��O�́@(14)�@�V�e�B�@79
��O�́@(15)�@�J���u�i�K�@81
��O�́@(15)�@�^�ߍ����ɂ�����r�f�B���Ɋւ���
�@�@���c�A�V��@�ې參���@90
��O��(15)�@���d�R�|�\�Ɩ��ӐM�u�|�\�͐V�����_�ƂƂ��Ɂv
�@�@���u�Ղ̎w��������^�l�v�@�떓�b���@108 |
��l�́@���n�ƍ��J�@115
��l�́@�\�^�ߍ����̐��n�ƍ��J�@�^�ߔe�m��C�g�Ɗԉi�g�@118
��́@�}�`���̏����@145
��́@�}�`���̊�{�p��@147
��́@�iA�j�@�^�ߍ����́w�_�̌��x�@�����h�u�@154
��́@�iB�j�@�^�ߍ��̃}�`���Ɛ_����J�@�A��O�q�@186
��́@�iC�j�@�^�ߍ����̃}�`���i�J���u�i�K�j�̐_�́@
�@�@���g�Ɗԉi�g�C�X�c�����@212
��́@�^�ߍ������̑��E�`�����߂����ā@�ɓ��Njg�@256
��́@�^�ߍ����̓V�C���Ƃ킴�ɂ��ā@���؏��@278
��́@�u���̎v�z�v�@�\���[�g�s�A��������\�@��R���@286
��Z�́@�l�̈ꐶ�@309
��Z�́@�����̕����\�ߐ������߂����ā@�r�ԕc�@310
��Z�́@�����@�ʏ鐳�_�@318
��Z�́@�o�Y�@�y���N�q�@346
��Z�́@���̎q�ǂ������Ƃ��̐��E�@�r�ԕc�@356
��Z�́@�^�ߍ��̐H�@�y���N�q�@412
��Z�́@�H�����@���ʌh�q�@426
��Z�́@�Z���E���<��>�E��@�{�ǕۑS�@434
��Z�́@�o�ߚ��̏������@���c���j�@498
��Z�́@�����̓`�d�ƐM�@�V��q�j�@508
�掵�́@���ҋV��@549
�掵�́@������o���A�Y���n��������ӑ���̑���@550
�掵�́@��������O�O�N���܂Ł@�ď霨�@552
�掵�́@���ɚL�i�ȁj���@�\�^�ߍ����̑����́@���䐳�q�@626
�k�����l�@646
�k�Q�l�E���p�����l�@678
��������т����͂������������X�@681
�i�^�ߍ����j�Ҏ[�ψ���A�����ψ��ق��j
�ҏW��L�@682
�E |
�R���A����s�����y�����ٕҁu����s�̓`���������˂� �{�i�̘b�ҁv���u����s����ψ���v���犧�s�����B
�@�@ (����s������������ ; ��38�W)
|
���������@3
�}��@4
�ڎ��@6
��@�ٗލ����
��@[1]�@�����E�ٗޖ��@9
��@[1]�@(1)�@�֖�����(����)�@9
��@[1]�@(2)�@��W(����)�@18
��@[1]�@(3)�@�l����@19
��@[1]�@(4)�@���������A�J�}�^�[�@30
��@[1]�@(5)�@�֖�����@30
��@[1]�@(6)�@��������@32
��@[2]�@�����E�ٗޏ��[�@34
��@[2]�@(1)�@�V�l���[�@34
��@[2]�@(2)�@�l�璹���[�@50
��@[2]�@(3)�@�L���[�@52
��@[2]�@(4)�@�؍����[�@54
��@[2]�@(5)�@�߂ƌ��̈�Ďq�@58
��@����
��@(1)�@��薹�E�Ł@59
�O�@�a��
�O�@(1)�@�q��ėH��@67
�O�@(2)�@�������@79
�l�@�^���ƒv�x
�l�@(1)�@�Y�Ă����ҁ@81
�l�@(2)�@�Y�_�ⓚ�@83
�l�@(3)�@�q���̎���(�Ď��R��)�@84
�l�@(4)�@�e�̐��͐_�̐��@90
�l�@(5)�@��N�ց@92
�l�@(6)�@�������ƕn�R�ҁ@97
�l�@(7)�@�������Ɛ_�l�@98
�l�@(8)�@���̐ԐK�R���@98
�l�@(9)�@�������̂���܂��@99
�l�@(10)�@���ǃ����`(�����ɂ�)�@101
�l�@(11)�@���̏�ɂ͋|����������Ȃ��@108
�l�@(12)�@�v�w�̉��@109
�l�@(13)�@�̐_�@111
�l�@(14)�@�����͉����@112
�܁@�^���
�܁@(1)�@���̐_�̉^�@113
�܁@(2)�@���̐_�̎����@113
�܁@(3)�@�\�ܖ�R���@114
�܁@(4)�@��q�̎����@115
�Z�@�����
�Z�@(1)�@���ƔL�Ǝw�ց@117
�Z�@(2)�@�������P�@120
�Z�@(3)�@�������@125
�Z�@(4)�@�����L�@127
�Z�@(5)�@�����̉ԁ@128
���@�Z���
���@[1]�@�������@129
���@[1]�@(1)�@�ł̓��@129
���@[1]�@(2)�@�F�s�Ȏq���@145
���@[2]�@���ǃ����`�@146
���@[2]�@(1)�@�E�i�M�@146
���@[2]�@(2)�@�C�m�V�V�@168
���@[2]�@(3)�@�Z��̒�����@169
���@��̋q
���@(1)�@�����ҁ@170
���@(2)�@��̋q�@187
��@�p�q�b
��@(1)�@�p�q�̔����@196
��@(2)�@�p�q�̒����݁@207
��@(3)�@�p�q�̐����݁@207
��@(4)�@�p�q�̔�����ٓ��@208
��@(5)�@�p�q�̐����݁E�ٓ��@213
��@(6)�@�p�q�̒����ѕ��@213
��@(7)�@�p�q�ƃj�K�i�@214
��@(8)�@�p�q�ƒ|�̎q�@217
��@(9)�@�p�q�ƃJ���_�@218
��@(10)�@�p�q�̋@�D��@219
��@(11)�@�p�q�̈�ˌ@��@220
��@(12)�@�p�q�̉��������@222
��@(13)�@�p�q�̈�ˌ@��E���������@223
��@(14)�@�p�q�Ə\�ܖ�̖݁@224
��@(15)�@�p�q�ƉΎ��@224
��@(16)�@�p�q�̒ʂ�r�@225
��@(17)�@�o�����߁@227
��@(18)�@�łƌƂ̘b�@227
��@(19)�@�p�q�Ɠ�\�����@228
��@(20)�@�p�q�̃V�[�̎����E�����@230
��@(21)�@�p�q�̓�\�����E�@�D��E
�@�@���G�ƕٓ��E�����݁@230
��@(22)�@�p�q�̉́@232
��@(23)�@�p�q�̕��͂�@233
��@(24)�@��Ȃ����@233
��Z�@������
��Z�@(1)�@���@234
���@����
���@(1)�@�S�ݗR���@235
���@(2)�@�N�X�P�[�R���@258
���@(3)�@�L������Ȃ��킯�@269
���@(4)�@�}�X�̊p�@269
���@�����ȓ���
���@(1)�@�L�ƃJ�}�u�^�@270
���@(2)�@���ƃJ�}�u�^�@271
���@(3)�@�؉��������@272
��O�@�I�q�
��O�@[1]�@�e�̎R�@273
��O�@[2]�@�����̉Z��@284
��l�@�͍���
��l�@(1)�@�̂��[���@291
��܁@���̑�
��܁@(1)�@�����Ԃ������@292
��܁@(2)�@���ׁ@293
��܁@(3)�@������ԁ@295
��܁@(4)�@���l�ƃE�i�C�_�@298
��܁@(5)�@���y�҂̓c�A���@299
��܁@(6)�@�k���邩�@300
��܁@(7)�@�T�M�r�T�[�͂����Ȃ���@301
��܁@(8)�@�����ɂȂ������l�@302
��܁@(9)�@�L�W���i�[�@303
�{���f�ژb�ꗗ
��@�ٗލ����
��@[1]�@�����E�ٗޖ�
��@[1]�@(1)�@�֖�����(����)
��@[1]�@(1)�@(1)�@�֖�����@�^�ߗ䏼�h(�r��)�@9
��@[1]�@(1)�@(2)�@�֖�����@�K���}�c(�r��)�@10
��@[1]�@(1)�@(3)�@�֖�����@�����L��(�r��)�@11
��@[1]�@(1)�@(4)�@�l����R��<�֖�����>�@
�@�@�@���h���g��(�m��)�@11
��@[1]�@(1)�@(5)�@�A�J�}�^�[�@���܃g��(���{)�@13
��@[1]�@(1)�@(6)�@�֖�����@���ԃV��(��O)�@13
��@[1]�@(1)�@(7)�@�֖�����@���X�n��(���c�c)�@14
��@[1]�@(1)�@(8)�@�֖�����<�X�q>�@
�@�@�@����]�F�}�J�g(�䉮��)�@15
��@[1]�@(1)�@(9)�@�֖�����@�{��^�P(�^�V)�@16
��@[1]�@(1)�@(10)�@�֖�����<�ԂĂʂ���>�@
�@�@�����ǃJ�}(�o��)�@17
��@[1]�@(2)�@��W(����)
��@[1]�@(2)�@(1)�@�֖�����@���܃E�V(�r��)�@18
��@[1]�@(3)�@�l����
��@[1]�@(3)�@(1)�@�֖�����@���@���J��(�o��)�@19
��@[1]�@(3)�@(2)�@�֖�����@���c�V�Q(�o��)�@20
��@[1]�@(3)�@(3)�@�֖�����@�����Y(�m��)�@22
��@[1]�@(3)�@(4)�@�֖�����@�ʏ�J��(����)�@22
��@[1]�@(3)�@(5)�@�֖�����@�Č��q�f(�Ɖ�)�@23
��@[1]�@(3)�@(6)�@�֖�����@���܋`��(�Î�)�@23
��@[1]�@(3)�@(7)�@�֖�����<�Ăʂ���>�@
�@�@������n��(������)�@27
��@[1]�@(3)�@(8)�@�֖�����@���v���K(�A��)�@27
��@[1]�@(3)�@(9)�@�֖�����@��ÃJ�c(���̒�)�@28
��[1](3)(10)�@�֖�����@�쉮���p��(�v�ۓc)28
��@[1]�@(4)�@���������A�J�}�^�[
��@[1]�@(4)�@(1)�@�֖�����@�K�]����(���̒�)�@30
��@[1]�@(5)�@�֖�����
��@[1](5)(1)�֖�����@�ӓy���i�x(�r��)�@30
��@[1](5)(2)�֖�����<�֏��[>�n�����l(����)31
��@[1]�@(6)�@��������
��@[1]�@(6)�@(1)�@��������@���g�L��(���̒�)�@32
��@[1]�@(6)�@(2)�@��������@�g�����V(�R��)�@33
��@[2]�@�����E�ٗޏ��[
��@[2]�@(1)�@�V�l���[
��[2](1)(1)�V�l���[<�����q>�^�ߗ䏼�h(�r��)34
��@[2�j(1)(2)�@�V�l���[<����̎n�܂�>�@
�@�@���K���}�c(�r��)�@37
��@[2]�@(1)�@(3)�@�V�l���[�@����i��(���{)�@38
��[2](1)(4)�@�V�l���[�@���h�^�Z�c(���̒�)�@41
��@[2]�@(1)�@(5)�@�V�l���[�@����i�x(���{)�@41
��@[2]�@(1)�@(6)�@�V�l���[�@�i�R�E�V(�嗢)�@42
��@[2]�@(1)�@(7)�@�V�l���[�@���v�{�g��(�A��)�@43
��[2](1)(8)�@�V�l���[<�@�x��>�����h�g(�r��)43
��@[2]�@(1)�@(9)�@�V�l���[<�V����~��َq>�@
�@�@����������(��)�@45
��[2](1)(10)�V�l���[<��>�g�c(����)�^�P(�m��)45
��[2](1)(11)�@�V�l���[�̉́@���܃g��(���{)�@48
��[2](1)(12)�@�V�l���[<�����q����>�@
�@�@���v�c�ɕv(����)�@48
��@[2]�@(2)�@�l�璹���[
��@[2](2)(1)�@�l�璹���[�@���v���E�V(�Êԗ�)50
��@[2](2)(2)�@�l�璹���[�@�_���}�J�g(���c�c)50
��@[2]�@(2)�@(3)�@�l�璹���[�@�㍪�E�T(�{��)51
��@[2]�@(3)�@�L���[
��@[2]�@(3)�@(1)�@�L�����@�㍪�E�T(�{��)�@52
��@[2]�@(4)�@�؍����[
��@[2]�@(4)�@(1)�@�؍����[�@������(����)�@54
��@[2]�@(4)�@(2)�@�����T�o�N�C<�؍����[>�@
�@�@����Ð^��(��O)�@54
��@[2]�@(4)�@(3)�@�؍����[�@���X�n��(���c�c)55
��@[2]�@(4)�@(4)�@�؍����[�@���鏉�q(�Z���^�[)56
��@[2]�@(4)�@(5)�@�����T�o�N�C<�؍����[>�@
�@�@����������T(���c)�@57
��@[2]�@(5)�@�߂ƌ��̈�Ďq
��@[2](5)(1)�߂ƌ��̈�Ďq�@���v���E�V(�Êԗ�)58
��@����
��@(1)�@��薹�E��
��@(1)(1)��薹<�V�[�O�_�L>�@���ܐ���(�m��)59
��@(1)�@(2)�@�V�[�O�_�L�@���v���K(�A��)�@62
��@(1)�@(3)�@���Ł@���v���K(�A��)�@62
��@(1)�@(4)�@�j�[�u�C�����Y�@�K�]����(���̒�)�@63
��@(1)�@(5)�@�A�J�o�i�[�@���鏉�q(�Z���^�[)�@64
�O�@�a��
�O�@(1)�@�q��ėH��
�O�@(1�j(1)�q��ėH��<�Ŏ��R��>���܃E�V(�r��)67
�O�@(1)�@(2)�@�q��ėH��@�ӓy���i�x(�r��)�@68
�O�@(1)�@(3)�@�q��ėH��@���c�V�Q(�o��)�@69 |
�O�@(1)�@(4)�@�q��ėH��@���c�J�}�h(�o��)�@70
�O�@(1)�@(5)�@�q��ėH��@��[�J�}(�o��)�@71
�O�@(1)(6)�q��ėH��<�Ŏ��R��>�@�h���g��(�m��)72
�O�@(1)�@(7)�@�q��ėH��@������(�Z�g)�@74
�O�@(1)�@(8)�@�q��ėH��@�䉮���P�q(���c�c)�@74
�O�@(1)�@(9)�@�i�[�`���~�[�R��<�q��ėH��>�@
�@�@����[���D(��)�@75
�O�@(1)�@(10)�@�q��ėH��@�m�O�P��(�Î�)�@75
�O�@(1)�@(11)�@�q��ėH��<����>�@�K�]�K�q(�A��)�@75
�O�@(1)�@(12)�@�q��ėH��<�Ŏ��R��>�@�ɍ��c��(�A��)�@76
�O�@(1)�@(13)�@�q��ėH��@���鏉�q(�Z���^�[)�@77
�O�@(1)�@(14)�@�q��ėH��@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@77
�O�@(1)�@(15)�@�q��ėH��@��F���g�V(���c)�@77
�O�@(1)�@(16)�@�q��ėH��@�{�鎟�Y(���c)�@78
�O�@(2)�@�������
�O�@(2)�@(1)�@�������<��o��>�@���@�����Y(�o��)�@79
�O�@(2)�@(2)�@�������<��o��>�@���@���t�~(�o��)�@80
�l�@�^���ƒv�x
�l�@(1)�@�Y������
�l�@(1)�@(1)�@�Y�Ă����ҁ@�_���}�J�g(���c�c)�@81
�l�@(2)�@�Y�_�ⓚ
�l�@(2)�@(1)�@�Y�_�ⓚ�@���v���E�V(�Êԗ�)�@83
�l�@(3)�@�q���̎���(�Ď��R��)
�l�@(3)�@(1)�@�Ď��R��<�q���̎���>�@��[����(�o��)�@84
�l�@(3)�@(2)�@�q���̎���<�Ď��R��>�@���鏉�q(�Z���^�[)�@87
�l�@(3)�@(3)�@�q���̎����@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@89
�l�@(4)�@�e�̐��͐_�̐�
�l�@(4)�@(1)�@�e�̐��͐_�̐��@���X�n��(���c�c)�@90
�l�@(4)�@(2)�@�e�̐��͐_�̐��@�F�ǖF�q(���̒�)�@91
�l�@(4)�@(3)�@�e�̐��͐_�̐��@�R������(�쓍��)�@91
�l�@(5)�@��N��
�l�@(5)�@(1)�@��N�ց@���ǃL��(�F�h���J�}�h)(�z��)�@92
�l�@(5)�@(2)�@��N�ց@���ԃV��(��O)�@92
�l�@(5)�@(3)�@��N�ց@���n�R�S�Z�C(��O)�@93
�l�@(5)�@(4)�@��N�ց@���v���E�V(�Êԗ�)�@93
�l�@(5)�@(5)�@��N�ց@���n�R�Ď}(����)�@94
�l�@(5)�@(6)�@��N�ց@���X�J��(���c�c)�@95
�l�@(5)�@(7)�@��N�ց@���܃T�_(����)�@96
�l�@(5)�@(8)�@��N�ց@�����}�c(�v�ۓc)�@96
�l�@(6)�@�������ƕn�R��
�l�@(6)�@(1)�@�������ƕn�R�ҁ@���v���E�V(�Êԗ�)�@97
�l�@(7)�@�������Ɛ_�l
�l�@(7)�@(1)�@�������Ɛ_�l�@���ԃV��(��O)�@98
�l�@(8)�@���̐ԐK�R��
�l�@(8)�@(1)�@���̐ԐK�R���@�����V�Y(����)�@98
�l�@(9)�@�������̂���܂�
�l�@(9)�@(1)�@�������̂���܂��@�Ì��@�M(���c�c)�@99
�l�@(9)�@(2)�@�������̂���܂��@���X�n��(���c�c)�@100
�l�@(10)�@���ǃ����`(�����ɂ�)
�l�@(10)�@(1)�@���ǘR�r<�p�q�̂����ɂ�>�@
�@�@�@�����鏉�q(�Z���^�[)�@101
�l�@(10)�@(2)�@�F�s���ƃk�u�V�̋ʁ@���v���E�V(�Êԗ�)103
�l�@(10)�@(3)�@���ǘR�r�̑�V�@���ܐV�h(�r��)�@103
�l�@(10)�@(4)�@���ǃ����`�@�����}�X�C(�r��)�@104
�l(10)�@(5)�@���ǃ����`<�����ɂ�>�@�㍪�E�T(�{��)105
�l(10)�@(6)�@���ǃ����`�̐����ɂ��@�{��^�P(�^�V)�@106
�l�@(10)(7)���ǃ����`<�����ɂ�>�@��Ò�M(���̒�)107
�l(10)(8)���ǃ����`<�F�s�̊�>�@�ɍ����O(�R��)107
�l�@(10)�@(9)�@���ǃ����`�@�h���g��(�m��)�@108
�l�@(11)�@���̏�ɂ͋|����������Ȃ�
�l(11)(1)���̏�ɂ͋|����������Ȃ��@��������(�r��)108
�l�@(12)�@�v�w�̉�
�l�@(12)�@(1)�@�v�w�̉�<������>�@���c�k��(�o��)�@109
�l�@(13)�@�̐_��
�l�@(13)�@(1)�@�̐_�@���v���K(�A��)�@111
�l�@(14)�@�����͉���
�l�@(14)�@(1)�@�����͉����@�����}�c(�v�ۓc)�@112
�܁@�^���
�܁@(1)�@���̐_�̉^
�܁@(1)�@(1)�@���̐_�̉^�@���n�R�S�Z�C(��O)�@113
�܁@(2)�@���̐_�̎���
�܁@(2)�@(1)�@���̐_�̎����@���v���E�V(�Êԗ�)�@113
�܁@(2)�@(2)�@���̐_�̎����@���v���K(�A��)�@113
�܁@(3)�@�\�ܖ�R��
��(3)(1)�\�ܖ�R���@���ǃL��(�F�h���J�}�h)(�z��)114
�܁@(4)�@��q�̎���
�܁@(4)�@(1)�@��q�̎����@�K�]����(���̒�)�@115
�Z�@�����
�Z�@(1)�@���ƔL�Ǝw��
�Z�@(1)�@(1)�@���ƔL�Ǝw�ց@�����Y(�m��)�@117
�Z�@(2)�@�������P
�Z�@(2)�@(1)�@�������P�@���@�����Y(�o��)�@120
�Z�@(2)�@(2)�@�������P�@���v�c���(����)�@121
�Z�@(2)�@(3)�@�������P�@�㍪�E�T(�{��)�@123
�Z�@(3)�@������
�Z�@(3)�@(1)�@�������@�㍪�E�T(�{��)�@125
�Z�@(4)�@�����L
�Z�@(4)�@(1)�@�����L�@�㍪�E�T(�{��)�@127
�Z�@(5)�@�����̉�
�Z�@(5)�@(1)�@�����̉ԁ@����i�x(���{)�@128
���@�Z���
���@[1]�@�������
���@[1]�@(1)�@�ł̓�
���@[1]�@(1)�@(1)�@��������<�ł̓��E�����G�C�T�[>�@
�@�@�@�����v���E�V(�Êԗ�)�@129
���@[1]�@(1)�@(2)�@�������<�ł̓�>���܋`��(�Î�)�@130
���@[1]�@(1)�@(3)�@�������<�ł̓�>��F������(���c)�@132
���@[1]�@(1)�@(4)�@�������<�ł̓�>�@�v�ꐭ�O(���c)�@133
���@[1]�@(1)�@(5)�@�������<�ł̓�>�@�Ɖ��c��(�Ɖ�)�@135
���@[1](1)(6)�������<�ł̓�>��]�F�}�J�g(�䉮��)�@136
���@[1](1)(7)�������<�ł̓�>�쉮���p��(�v�ۓc)�@137
���@[1]�@(1)�@(8)�@�������@�㌴�E�V(�Z�g)�@138
���@[1]�@(1)�@(9)�@�������<�ł̓�>�@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@139
���@[1]�@(1)�@(10)�@�������@���]�F����(�Z���^�[)�@140
���@[1]�@(1)�@(11)�@�������<�O�j�̊́E
�@�@���G�C�T�[�̎n�܂�>�@���鏉�q(�Z���^�[)�@141
���@[1]�@(1)�@(12)�@���̐���<��������>�@���M(�r��)�@142
���@[1]�@(1)�@(13)�@�������<�ł̓�>�@����i��(���{)�@143
���@[1]�@(1)�@(14)�@��������@���]�F��(���{)�@143
���@[1]�@(1)�@(15)�@�������<�ł̓�>���n�R�S�Z�C(��O)144
���@[1]�@(1)�@(16)�@�����剤<�ł̓�>�@��[���D(��)�@144
��[1](1)(17)�@�������<�ł̓�>�@�{��n�i(�^�V)�@144
��[1](1)(18)�@�������<�ł̓�>�@�K�]����(���̒�)�@145
���@[1]�@(2)�@�F�s�Ȏq��
���@[1]�@(2)�@(1)�@�F�s�Ȏq���@���v���E�V(�Êԗ�)�@145
���@[2]�@���ǃ����`
���@[2]�@(1)�@�E�i�M
���@[2]�@(1)�@(1)�@�Z��̒�����@�_���}�J�g(���c�c)�@146
���@[2]�@(1)�@(2)�@�Z��̒�����@���^��(�A��)�@147
���@[2]�@(1)�@(3)�@���ǃ����`<�Z��̒�����>�@
�@�@�@�������}�c(�v�ۓc)�@148
���@[2]�@(1)�@(4)�@�Z��̒�����@�����h�g(�r��)�@149
���@[2](1)(5)�Z��̒�����<���ǃ����`>�@���܃E�g(�r��)150
���@[2]�@(1)�@(6)�@�Z��̒�����@���c�k��(�o��)�@151
���@[2](1)(7)�Z��̒�����<���ǃ����`>�@��[�J�}(�o��)152
���@[2]�@(1)�@(8)�@���ǃ����`<�Z��̒�����>�@
�@�@���쉮���p��(�v�ۓc)�@153
���@[2](1)(9)�Z��̒�����<���ǃ����`>��[���D(��)�@154
���@[2]�@(1)�@(10)�@�Z��̒�����<��>�@�ɍ����O(�R��)�@154
���@[2]�@(1)�@(11)�@���������`��<�����ɂ��E�Z��̒�����>�@
�@�@�@�����ܐV�h(�r��)�@155
���@[2]�@(1)�@(12)�@�Z��̒�����@���X�J��(���c�c)�@157
���@[2]�@(1)�@(13)�@�Z��̒�����@�㍪�E�T(�{��)�@159
���@[2]�@(1)�@(14)�@�Z��̒�����@�L�c��i(�R��)�@160
���@[2]�@(1)�@(15)�@�Z��̒�����@�m�O�^��(�Ӊ�)�@161
���@[2]�@(1)�@(16)�@�Z��̒�����@�m�ԃc��(�Êԗ�)�@161
���@[2]�@(1)�@(17)�@�Z��̒�����@�g�c(����)�^�P(�m��)�@162
���@[2]�@(1)�@(18)�@�Z��̒�����<���ǃ����`>�@
�@�@�@���K�]�J�}�h(������)�@163
���@[2]�@(1)�@(19)�@�Z��̒�����@�i�R�E�V(�嗢)�@164
���@[2]�@(1)�@(20)�@�Z��̒�����<��>�@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@164
���@[2]�@(1)�@(21)�@���ǃ����`�@��Ò�M(���̒�)�@165
���@[2]�@(1)�@(22)�@�Z��̒�����@�{��^�P(�^�V)�@166
���@[2](1)(23)�Z��̒�����<�E�i�M>�@���ܐ���(�m��)167
���@[2]�@(2)�@�C�m�V�V
���@[2]�@(2)�@(1)�@�Z��̒�����@���Ð^���V(����)�@168
��[2](2)(2)�@�Z��̒�����<��>�@���鏉�q(�Z���^�[)�@168
���@[2]�@(3)�@�Z��̒�����
���@[2]�@(3)�@(1)�@�Z��̒�����@���@�����Y(�o��)�@169
���@��̋q
���@(1)�@������
���@(1)�@(1)�@�����ҁ@�K���}�c(�r��)�@170
���@(1)(2)��̋q<���̐ԐK�R��>�h���g��(�m��)172
���@(1)�@(3)�@�����ҁ@�m�ԃc��(�Êԗ�)�@175
���@(1)�@(4)�@������<���E��>�@�_���}�J�g(���c�c)�@175
���@(1)�@(5)�@�����ҁ@�g���E�V(�Ɖ�)�@178
���@(1)�@(6)�@������<���̐ԐK�R��>�@���܃L��(����)�@182
���@(1)�@(7)�@�����ҁ@���鏉�q(�Z���^�[)�@183
���@(1)�@(8)�@�����ҁ@�����}�c(�v�ۓc)�@184
���@(1)�@(9)�@�����ҁ@�v����b(�Z���^�[)�@185
���@(1)�@(10)�@������<�`�u���̎�>�@���܃T�_(����)�@186
���@(2)�@��̋q
���@(2)�@(1)�@��̋q�@���c�V�Q(�o��)�@187
���@(2)�@(2)�@��̋q<�ᐅ�R��>�@�K�]�M�q(�A��)�@189
���@(2)�@(3)�@��̋q<�ᐅ�R��>�@���^��(�A��)�@191
���@(2)�@(4)�@��̋q�@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@191
���@(2)�@(5)�@��̋q<������>�@���Í](�r��)�@193
���@(2)�@(6)�@��̋q�@���R�S�h(�A��)�@193
���@(2)�@(7)�@��̋q�@�K�]����(���̒�)�@194
���@(2)�@(8)�@�����ҁ@�c�^�A�L(�Ӊ�)�@194
��@�p�q�b
��@(1)�@�p�q�̔���
��@(1)�@(1)�@�p�q�̔����@���@���J��(�o��)�@196
��@(1)�@(2)�@�p�q�̔����@�g�c(����)�^�P(�m��)�@196
��@(1)�@(3)�@�p�q�̔����@�h���g��(�m��)�@198
��@(1)�@(4)�@�p�q�̔����@���c�E�g(���{)�@198
��@(1)�@(5)�@�p�q�̔����@�������}�c(����)�@199
��@(1)�@(6)�@�p�q�̔����@���X�n��(���c�c)�@199
��@(1)�@(7)�@�p�q�̔����@�_���}�J�g(���c�c)�@200
��@(1)�@(8)�@�p�q�̔����@���v���J�}�h(���c�c)�@200
��@(1)�@(9)�@�p�q�̔����@�㍪�E�T(�{��)�@201
��@(1)�@(10)�@�p�q�̔����@�Ɖ��c��(�Ɖ�)�@201
��@(1)�@(11)�@�p�q�̔����@�K�]�J�}�h(������)�@202
��@(1)�@(12)�@�p�q�̔����@�쉮�����(�A��)�@202
��@(1)�@(13)�@�p�q�Ɣ����@�{��^�P(�^�V)�@203
��@(1)�@(14)�@�p�q�̔����@��������T(���c)�@203
��@(1)�@(15)�@�p�q�̔����@���c�q(�R��)�@204
��@(1)�@(16)�@�p�q�Ɣ����@���c�k��(�o��)�@204
��@(1)�@(17)�@�p�q�̔����@�V��L��(����)�@205
��@(1)�@(18)�@�p�q�̔����@�m���^�P(�z��)�@205
��@(1)�@(19)�@�p�q�̔����@���v���E�V(�Êԗ�)�@205
��@(1)�@(20)�@�p�q�̔����@�����E�g(�Z�g)�@205
��@(1)�@(21)�@�p�q�̔����@��[���D(��)�@205
��@(1)�@(22)�@�p�q�̔����@�������}�c(�Î�)�@206
��@(1)�@(23)�@�p�q�Ɣ����@�K�]�M�q(�A��)�@206 |
��@(1)�@(24)�@�p�q�̔����@���鏉�q(�Z���^�[)�@206
��@(1)�@(25)�@�p�q�̔����@�F�ǖF�q(���̒�)�@207
��@(1)�@(26)�@�p�q�̔����@���{�ǎq(������)�@207
��@(2)�@�p�q�̒�����
��@(2)�@(1)�@�p�q�̒����݁@���@���t�~(�o��)�@207
��@(3)�@�p�q�̐�����
��@(3)�@(1)�@�p�q�̐����݁@�V�����V�q(�z��)�@207
��@(3)�@(2)�@�p�q�̐����݁@�m�ԃc��(�Êԗ�)�@208
��@(4)�@�p�q�̔�����ٓ�
��@(4)�@(1)�@�p�q�Ɠœ���ٓ��@���X�J��(���c�c)208
��@(4)�@(2)�@�p�q�Ɠœ���ٓ��@�㍪�E�T(�{��)209
��@(4)(3)�p�q�Ɠœ���ٓ��쉮���p��(�v�ۓc)210
��@(4)�@(4)�@�p�q�Ɠœ���ٓ��@���@���L��(�^�V)�@211
��@(4)�@(5)�@�p�q�Ɠœ���ٓ��@���v�c���(����)�@211
��@(4)�@(6)�@�p�q�Ɠœ���ٓ��@�K�]�M�q(�A��)212
��@(4)(7)�p�q�Ɠœ���ٓ��@���v���E�V(�Êԗ�)212
��@(4)(8)�p�q�b<���ƕٓ�>�@�m�ԃc��(�Êԗ�)212
��@(5)�@�p�q�̐����݁E�ٓ�
��@(5)�@(1)�@�p�q�b�@����n��(������)�@213
��@(6)�@�p�q�̒����ѕ�
��@(6)�@(1)�@�p�q�b�@�h���g��(�m��)�@213
��@(7)�@�p�q�ƃj�K�i
��@(7)�@(1)�@�p�q�ƃj�K�i�@�㍪�E�T(�{��)�@214
��@(7)�@(2)�@�p�q�b�@�g�c(����)�^�P(�m��)�@215
��@(7)�@(3)�@�p�q�ƃj�K�i�@���]�F��(���{)�@217
��@(8)�@�p�q�ƒ|�̎q
��@(8)�@(1)�@�p�q�ƒ|�̎q�@���@���J��(�o��)�@217
��@(8)�@(2)�@�F�s���q�̘b<�p�q�ƒ|�̎q>�@
�@�@�����X�n��(���c�c)�@217
��@(9)�@�p�q�ƃJ���_
��@(9)�@(1)�@�p�q�b<�J���_>�@�h���g��(�m��)�@218
��@(10)�@�p�q�̋@�D��
��(10)(1)�p�q�̋@�D��@���n�R�S�Z�C(��O)�@19
��@(10)�@(2)�@�p�q�̋@�D��@�v��i��(�Z�g)�@219
��@(10)�@(3)�@�p�q�̋@�D��@�l��Ãi��(�Z�g)�@219
��(10)(4)�p�q�̋@�D��@���c�c��(�쓍��)�@219
��@(11)�@�p�q�̈�ˌ@��
��(11)(1)�p�q�̈�ˌ@��@���X�J��(���c�c)220
��(11)(2)�p�q�̈�ˌ@��@���X�n��(���c�c)221
��(12)�p�q�̉�������
��(12)(1)�p�q�̉��������@�_���}�J�g(���c�c)222
��@(13)�@�p�q�̈�ˌ@��E��������
��@(13)�@(1)�@�p�q�b�@�_���}�J�g(���c�c)�@223
��@(14)�@�p�q�Ə\�ܖ�̖�
��@(14)(1)�@�p�q�Ə\�ܖ�̖݁@��������(�Î�)224
��@(15)�@�p�q�ƉΎ�
��@(15)�@(1)�@�p�q�ƉΎ��@��������(�Î�)�@224
��@(16)�@�p�q�̒ʂ�r
��@(16)�@(1)�@�p�q�̒ʂ�r�@�㍪�E�T(�{��)�@225
��@(16)�@(2)�@�p�q�̒ʂ�r�@����i�x(���{)�@226
��(16)(3)�ʂ�r�̌p�q�䏔�����}�c(����)227
��@(17)�@�o������
��@(17)�@(1)�@�p�q�b�@��Ãt�W�G(�R��)�@227
��@(18)�@�łƌƂ̘b
��@(18)�@(1)�@�łƌƂ̘b<�E�h���ƃ~�~�Y>�@
�@�@�����{�ǎq(������)�@227
��@(19)�@�p�q�Ɠ�\����
��(19)(1)�p�q�̔����Ɠ�\�������܃E�g(�r��)228
��(19)(2)�p�q�Ɠ�\�����@���@���J��(�o��)228
��@(19)�@(3)�@�p�q�̔����E��\�����@
�@�@���i�R�E�V(�嗢)�@229
��@(19)�@(4)�@�p�q�Ɠ�\�����@�쉮�����(�A��)�@229
��@(19)�@(5)�@�p�q�̓�\�����@�K�]����(���̒�)�@230
��@(19)�@(6)�@�p�q�̓�\�����@�g�����V(�R��)�@230
��@(20)�@�p�q�̃V�[�̎����E����
��@(20)�@(1)�@�p�q�b<�V�[�̎����E����>�@
�@�@�@�������}�c(�v�ۓc)�@230
��@(21)�@�p�q�̓�\�����E�@�D��E�G�ƕٓ��E������
��@(21)�@(1)�@�p�q�b<��\�����E�@�D��E
�@�@���G�ƕٓ��E�����݁E����>�@�㌴�E�V(�Z�g)�@230
��@(22)�@�p�q�̉�
��@(22)�@(1)�@�p�q�b�@���܃g��(���{)�@232
��@(22)�@(2)�@�p�q�����߁@�����g�V�q(�Z�g)�@233
��@(23)�@�p�q�̕��͂��
��@(23)(1)�p�q�̕��͂�@���n�R�S�Z�C(��O)233
��@(24)�@��Ȃ���
��@(24)�@(1)�@��Ȃ����@���v���E�V(�Êԗ�)�@233
��Z�@������
��Z�@(1)�@����
��Z�@(1)�@(1)�@���@���X���V(�z��)�@234
���@����
���@(1)�@�S�ݗR��
���@(1)�@(1)�@�S�ݗR��<��>�@�h���g��(�m��)�@235
���@(1)�@(2)�@�S�ݗR���@���܋`��(�Î�)�@238
���@(1)�@(3)�@�S�ݗR���@�c���g�N(��)�@239
���@(1)�@(4)�@�S�ݗR��<�S>�@���c�t�~(�o��)�@239
���@(1)�@(5)�@�S�ݗR��<�y>�@�K�]�M�q(�A��)�@240
���@(1)�@(6)�@�S�ݗR���@�㌴�c��(������)�@240
���@(1)�@(7)�@�S�ݗR���@���ܔ��q�q(�^�V)�@240
���@(1)�@(8)�@�S�ݗR���@�K�]�K�q(�A��)�@241
���@(1)�@(9)�@�S�ݗR��<��>�@����i��(���{)�@241
���@(1)(10)�S�ݗR��<��>�g�c(����)�^�P(�m��)�@243
���@(1)�@(11)�@�S�ݗR��<��>�@���}�c(����)�@245
���@(1)(12)�S�ݗR��<��>�������q(�Z���^�[)�@246
���@(1)�@(13)�@�S�ݗR��<�S>�@���ǃn�i(����)�@246
���@(1)(14)�S�ݗR��<�K���X>���c���D�q(��O)247
���@(1)�@(15)�@�S�ݗR���@�K���}�c(�r��)�@249
���@(1)�@(16)�@�S�ݗR���@�㍪�E�T(�{��)�@250
���@(1)�@(17)�@�S�ݗR���@�m�O�h�q(����)�@250
���@(1)�@(18)�@�S�ݗR���@���Í](�r��)�@251
���@(1)�@(19)�@�S�ݗR���@��������T(���c)�@252
���@(1)�@(20)�@�S�ݗR���@���X���V�G(�嗢)�@253
���@(1)(21)�S�ݗR��<�z�[�n�C>���@�����q(�z��)253
���@(1)�@(22)�@�S�ݗR���@�g�����G(�Ɖ�)�@255
���@(1)(23)�S�ݗR��<�S�E��>�m�ԃc��(�Êԗ�)257
���@(1)�@(24)�@�S�ƃA�[�T�@�L�c��i(�R��)�@258
���@(2)�@�N�X�P�[�R��
���@(2)�@(1)�@�N�X�P�[�R���@�㍪�E�T(�{��)�@258
���@(2)�@(2)�@�N�X�P�[�R���@�Ɖ��B���q(���c)�@260
���@(2)�@(3)�@�N�X�P�[�R���@�쉮���p��(�v�ۓc)�@262
���@(2)�@(4)�@�N�X�P�[�R���@�g�����V(�R��)�@263
���@(2)�@(5)�@�N�X�P�[�R���@���@���J��(�o��)�@264
���@(2)�@(6)�@�N�X�P�[�R���@�����Y(�m��)�@265
���@(2)�@(7)�@�N�X�P�[�R���@�����}�X�C(�r��)�@266
���@(2)(8)�N�X�P�[�R��<�H��ⓚ>�V��L��(����)266
���@(2)�@(9)�@�N�X�P�[�R���@���@�����Y(�o��)�@268
���@(2)�@(10)�@�N�X�P�[�R���@�c��T�_(����)�@268
���@(3)�@�L������Ȃ��킯
���@(3)(1)�L������Ȃ��킯�@���߃c��(�Êԗ�)269
���@(4)�@�}�X�̊p
���@(4)�@(1)�@�}�X�̊p�@�F�ǖF�q(���̒�)�@269
���@�����ȓ���
���@(1)�@�L�ƃJ�}�u�^
���@(1)�@(1)�@�L�ƃJ�}�u�^�@���X�n��(���c�c)�@270
���@(2)�@���ƃJ�}�u�^
���@(2)�@(1)�@���ƃJ�}�u�^�@���܋`��(�Î�)�@271
���@(3)�@�؉�������
���@(3)�@(1)�@�؉��������@�ɍ����O(�R��)�@272
��O�@�I�q�
��O�@[1]�@�e�̎R
��O�@[1](1)�W�̎R<�V�o�܂�E���>���v���K(�A��)273
��O�@[1]�@(2)�@�W�̎R<���>�@���X�n��(���c�c)�@275
��O�@[1]�@(3)�@�W�̎R�@���X�J��(���c�c)�@276
��O�@[1]�@(4)�@�e�̎R<���>�@���܃E�g(�r��)�@277
��O�@[1]�@(5)�@�W�̎R�@�ӓy���L��(����)�@278
��O�@[1]�@(6)�@�W�̎R�@�l��Ãi��(�Z�g)�@279
��O�@[1]�@(7)�@�W�̎R<�D��>�@�㍪�E�T(�{��)�@279
��O�@[1]�@(8)�@�e�̂Ă������@���c�V�Q(�o��)�@280
��O�@[1]�@(9)�@�W�̎R<���b�R>�@�{�鎟�Y(���c)�@281
��O�@[1]�@(10)�@�W�̎R<���>�@�ʏ�J��(����)�@281
��O�@[1]�@(11)�@�e�̎R<���>�@�R�鐴�P(���̒�)�@283
��O�@[1]�@(12)�@�W�̎R<�A�u�V�o���[�R��>�@
�@�@�@�����v�c���(����)�@283
��O�@[1]�@(13)�@�e�̎R<�}�܂�>�@��������(�m��)�@284
��O�@[2]�@�����̉Z��
��O�@[2]�@(1)�@�����̉Z��@��������(�Î�)�@284
��O�@[2]�@(2)�@�����̉Z��@�㍪�E�T(�{��)�@287
��O�@[2]�@(3)�@�����̉Z��@�ɍ��c��(�A��)�@288
��O�@[2]�@(4)�@�����̉Z��@���c�k��(�o��)�@288
��O�@[2]�@(5)�@�����̉Z��@��[���D(��)�@290
��l�@�͍���
��l�@(1)�@�̂��[��
��l�@(1)�@(1)�@�̂��������@���ܐ���(�m��)�@291
��܁@���̑�
��܁@(1)�@�����Ԃ�����
��܁@(1)�@(1)�@�����Ԃ������@�����J�}(����)�@292
��܁@(1)�@(2)�@�����Ԃ������@�{��c��(�Z���^�[)�@292
��܁@(2)�@����
��܁@(2)�@(1)�@����<�q�͕�>�@�v��J��(���c)�@293
��܁@(2)�@(2)�@�q�͕�@���n�R�S�Z�C(��O)�@293
��܁@(2)�@(3)�@�q�͕�@�������V�Y(���c�c)�@294
��܁@(2)�@(4)�@���ׁ@��������(�r��)�@294
��܁@(2)�@(5)�@�������ƕn�R�̕��ׁ@
�@�@�@���K�]����(���̒�)�@294
��܁@(3)�@�������
��܁@(3)�@(1)�@������ԁ@���v���K(�A��)�@295
��܁@(3)�@(2)�@������ԁ@�����J��(���c)�@296
��܁@(3)�@(3)�@������ԁ@�n�c�����(�A��)�@296
��܁@(3)�@(4)�@������ԁ@���v���E�V(�Êԗ�)�@297
���(3)(5)�O�l���̉�����ԁ@���v�c���(����)297
��܁@(3)�@(6)�@������ԁ@���n�R�S�Z�C(��O)�@298
��܁@(3)�@(7)�@������ԁ@���鏉�q(�Z���^�[)�@298
��܁@(4)�@���l�ƃE�i�C�_
���(4�j(1)�D���ƃE�i�C�_�@�V��J�}�h(���̒�)298
��܁@(4)�@(2)�@�D���ƃE�i�C�_�@���v���K(�A��)�@299
���(4)(3)�E�i�C�_�ƑD���@���h�^�Z�c(���̒�)299
��܁@(5)�@���y�҂̓c�A��
��܁@(5)�@(1)�@���y�҂̓c�A���@�����Y(�m��)�@299
��܁@(6)�@�k���邩
���(6)(1)�k���邩<���͉×�>����n��(������)300
��܁@(7)�@�T�M�r�T�[�͂����Ȃ���
���(7)(1)�T�M�r�T�[�͂����Ȃ���@�㍪�E�T(�{��)301
��܁@(8)�@�����ɂȂ������l
��܁@(8)�@(1)�@�����ɂȂ������l�@���v���K(�A��)�@302
��܁@(9)�@�L�W���i�[
��܁@(9)�@(1)�@�L�W���i�[<���E�����E�ǂ�����>
�@�@����]�F�}�J�g(�䉮��)�@303
���(9)(2)�L�W���i�[<�����>�@����i�x(���{)�@304
��܁@(9)�@(3)�@�L�W���i�[<�����E��>
�@�@�@���@�g�c(����)�^�P(�m��)�@305
���(9)(4)�@�L�W���i�[�ƛ��@�㍪�E�T(�{��)�@306
���(9)(5)�@�L�W���i�[<��>�@���ǃE�V(���c�c)�@306
���(9)(6)�@�L�W���i�[�̋����@�c�R��(����)�@306
�E
�E |
�R���A����h,���ь��],�����x���q �����u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (35) p.47�`58�v�Ɂu�����g�����̑����������̖K���āv�\����B
�R���A�g�Ɗԉi�g���u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 22�@ p.171-184�v�Ɂu�u�������w�Ɍ��鉫��l�̐S�� -�������w�̌ŗL�����߂�����-�v�\����B
�R���A�����K�ꂪ�u�w�����낳�����x�Ɨ������w�v���u�}�ԏ��@�v���犧�s����B
�@�@�@�@�w�ʐ����_���u�w�����낳�����x�𒆐S�Ƃ��问�����w�̌����v (2008�N, ������w)
��ҏW��������
�R���Q�O���i�y�j�A�u�×w�Ɖ��ꉹ�y�̋ߑ㉻ : �R�����j�a��120���N�L�O�R���T�[�g�v���u�Y�Y�s�Ă����z�[���v�ŊJ�����B
�@�@�@�@������ ��� ; ���ꍑ�ۃA�W�A���y�Վ��s�ψ��� �@���ÁF�Y�Y�s����ψ���@ (������̌×w�R���T�[�g ; 2)
�@�@�@�@�p���t���b�g�o�C���_�[ �������u�n�敶���|�p�U���v�����v �@�@�����F���ꌧ���}����
�R���A���ꍑ�ۃA�W�A���y�Վ��s�ψ���ҁuIslands power�@�`�������q�����X�̌×w�`�v���u�Y�Y�s����ψ���v���犧�s�����B�@�@ (������̌×w�R���T�[�g ; 1)�@�@���L �p���t���b�g�o�C���_�[ �������u�n�敶���|�p�U���v�����v �@���́F���ꌧ�����U����
�@�@�@�@�ʃ^�C�g�� ���ꍑ�ۃA�W�A���y��musix2010�@�@�@�@�����F���ꌧ���}����
�@�@�@�@���@(����̌×w�R���T�[�g ;1/ 2) �ɂ��Ă̓��e�͍Ċm�F���K�v���@�Q�O�Q�R�E�R�E�Q�R�@�ۍ�
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@�� �ҁu���ꌤ���m�[�g�F�s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@��(19)�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�����F���ꌧ���}���فF1005057219
|
���] �䉮���ƕv���w��㉫��̐��_�Ǝv�z�x
�@�@��(���Ώ��X�A��Z�Z��N�A����) ���ђ��� p.1�`6
���] �ߓ�����Y�w�ߑ㉫��ɂ����鋳��ƍ��������x
�@�@��(�k�C����w�o�ʼn�A��Z�Z�Z�N)�@���c���j p.7�`14
����^�C���X�u�����v��ޔǕҁw���ꂪ |
�@�@�������łȂ��Ȃ���x��ǂ�� �y���� p.15�`18
���q�����̏ꍇ--��ւ̂܂Ȃ���(3) �@��엺 p.24�`20
���Î��x�z���̗����j���̓]��--���ƁE�Љ�E���O �L���R�a�s p.37�`25
���Ɨ����l--�ߐ���B�̎R���Ɨ����̂����� ����O�� p.48�`38
���J������u���������v�ɂ��ā@�䕔���j p.74�`49
|
�S���A�@���J�C���u���� (535) p.30�`33�@�����Ёv�Ɂu��ÍN�Y�̎B�������́v�\����B�@
�T���A�J���v, ��ؖ��q�ҁu���������̒T�� : �q�Β��F�搶�ËH�L�O�_���W�v���u��c���@�v���犧�s�����B�@
|
���҂Ɗϋq ��������W�E�Ƃ߂�g�� / ����I�a ��
�u�悳�����v���߂����Ҙ_�̌��� / ���c���� ��
�����o�̊ϋq�_ / �T��D�b ��
�Ղ�ƐM�̍\�� �ؑ]��ԍu�Ɛ��Ղ� / �q������ ��
�n�_�M�̌`���ƓW�J / ���薃�� ��
�~�Ɍ}����� / �J���v ��
����v�����̍��J�Ɛ_���̋敪 / �X�c�^�� ��
��폤�ɂ����铯�Ɛ_�M�Ƃ��̍��J�W�c/�������� ��
�����n�}�̉\�� �����n�}�Č������_/�q���q ��
�����n�}���e���V�[ / �����m �� |
�\����̃����f�b�|�E�̏������t / �O���q ��
���̐��� �u��̓����v�l / �H�쏻�q ��
��c�Ɍ��������̗��j / �����c ��
�܌��M�v�u���������ӏ��v�Ƒ�㌾�t / ��쐽 ��
�����w�̕��@ �q�Γs�s�����w�̌p���ƓW�J / �a��t�� ��
�c���牡�� / ��ؖ��q ��
�����̔��� ���g�҂̖����w / �������� ��
�؍��ɂ����镃�e�̖��ɑ��邵���̕ω� / �q�Δ��s ��
����������؎��ɂ��֎x�z�̓��� / �R��䌒�� ��
�E |
�U���A�{��\�P�o���u�{��\�P�q�l�ԍ���r�������x�W�v���u�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�v���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�r�f�I�f�B�X�N 3�� (182��) : DVD�@�@���^: 2009�N12�� �������ꂨ���Ȃ포����
(����)
�@�@�@�ďC�E���:���{ ����:RBC�r�W���� ���t:���]��t(VO,�O��) ��ԍG�q(�O��)
�{��G�q(�) �{��p�v(�J) �약�ꓹ(�Ӌ|) �����(����)
|
| DISC1 |
�s�V�l�x�E��O�x�E��Ηx�ҁt�q�V�l�x�r(1)������ŕ�(������ł��Ӂ[)�q��O�x�r(2)��O������(�킩���キ�Ă��Ԃ�)�q��Ηx�r(3)������(�ʂԂ����ǂ���)(4)�������(���������ǂ���)(5)�O�̕l(�߁[�ʂ͂�)(6)��(���[)(7)�����ǖ���(�����Ł[��܂�) |
| DISC2 |
�s���x�ҁt�q���x�r(1)��c(�����Ă�)(2)��������(��������)(3)�V��(���܂��[)(4)�{�M��(�ނƂ��ނ���)(5)��(��Ȃ�)(6)�ɖ�g��(�ʂӂ��Ԃ�)(7)����(����ǂ���) |
| DISC3 |
�s�G�x��(�������ǂ�ւ�)�t�q�G�x(�������ǂ�)�r(1)�l�璹(�͂܂��ǂ���)(2)�ނ��(3)���߂�[(���Ȃ�[)(4)�H�̗x��(5)��Ԃ�(�Ă��[�܂Ƃ�)(6)��[��s(����ʂԂ���[)(7)���Ԑ�(�͂Ƃ��܂Ԃ�)(8)�ԕ�(�͂ȂӁ[) |
|
�V���A�F�����y�L�̋u���j���������� (�啪����),���ꌧ����ψ���u�s���{���ʓ��{�̍Ղ�E�s���������W��
12�v���u�C�H���@�v���犧�s�����B
�@�@�@�������: �A�؍s��, �e�r����
�@�@�@�@���L �啪�����F�����y�L�̋u���j���������ٕ���7�N���Ɖ��ꌧ����ψ����9�N���̕������{
�V���A�������u�]�� 41(7) (�ʍ� 494) p.4�`7�v�Ɂu�G�߂�������N���s�� �썑����̖~�ƃG�C�T�[�v�\����B
�W���A�������q,�V�_�p�i,�����H���q,�O���,�V���z�q,�Ҍ��q,��؍��q�q���u���{������w��@�N��_���W
(26) p.390-393�v�Ɂu�d�q���ȏ��̋��ނƂ��ăG�C�T�[�E�ܒ���l�̊֘A�n�掑���̍\�� : ����E���킫�s�E���s�̑f�ނɂ���((���ʌ���A)�f�W�^��(�d�q)���ȏ��̕������ƍ���̉ۑ�(1),����̌��_�Ɍ��Ă�@�[�����̒��̖{�������o���[)�v�\����B
�P�O���A�{��w�@���q��w�����L���X�g�������������ҁu���ꌤ�� : ��䂩�甭�M���鉫��w�v���u�{��w�@���q��w�����L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1005458912�@
|
�O�X�N�����o�� �����i���́u�O�X�N����v�_�𒆐S�� �啽 ��
���B�l�̗����Y���Ƒ��� �����Z�N���NJԓ��Y���ꌏ �e�r �E�v
�吴�������̂Ȃ��́u�����v ���c �I��u
����̋ߑ�͂ǂ̂悤�ɕ`����Ă����̂��낤��
�@�@�����������j�����𒆐S�� ���c ���j
��㉫��̐����Ɛ��} ���� ����
����ɖ߂�Ȃ������t�B���s���l���� �@�ČR��������
|
�@�@������ɂ����鉫�䍑�ی����Ƒ��ւ̂܂Ȃ��� ���� �M
���z(�e�_)�̉F�� �I�����̑����А��ƓƎ��� ���� ���V
���ꌧ�ɂ����闬�ʃV�X�e���̍ĕҐ��ƃ����o���n��ւ̉e��
�@�@�@���R�[�v�����Ȃ�̋����w���ɒ��ڂ��� �y�� ��
����̃N�������̓~�z�� �c�� ��T
����̌��(�E�^�L)�̃C���[�W�ɂ��Ă�
�@�@�����ؓI�Ȍ��� ���Y ���a�^�L�V �O�L |
�P�P���Q���`���N�P���T�����A���ꌧ�������قɉ����Ĕ��p�ي��W�u�ꂽ���̐_
��ÍN�Y�W�v���J�����B
�P�P���A���ꌧ�������فE���p�ٕ� ; �����p�q�ďC�u�ꂽ���̐_ ��ÍN�Y�W ���̂Ȃ��� : -�ʐ^�W������܂���-�v���u���ꌧ�������فE���p�فv���犧�s�����B�@�@�p���t���b�g�o�C���_�[
�P�P���Q���`�V�����A�Ί_�s���}���قɉ����āu�q�쐴���a�P�O�O�N�L�O�E���d�R����������ݗ�40���N�L�O�F�q�쐴���쁕�R���N�V�����v�W���J�����B
11���A�m���芰���_�ˏ��q��w�j�w��ҁu�_����j�w (27) p.55�`85�v�Ɂu��y�^�@�����`�d�̗��j�I�O��--�F����k�̓����𒆐S�Ɂv�\����B
�P�Q���A�����q ���u���{�̗w���� 50(0) p.13-29�v�Ɂu���̓���čl:������̍��J��ԂƉ̗w�v�\����B�@ �@�@�@J-STAGE
�P�Q���A�g�Ɗԉi�g��������w���ۉ��ꌤ�����ҁuInternational journal of Okinawan studies 1(2) (�ʍ� 2) p.122-128�v�Ɂu���] �����K��(SHIMAMURA Koichi)���w�w�����낳�����x�Ɨ������w�x�v���Љ��B�@�@�@
���A���̔N�A���y��������ҁu���y������ (�ʍ� 27)�v�����s�����B
|
���ꌧ����s����n��̃G�C�T�[�Ɩ{��������G�C�T�[�Ƃ̊W ���� ���] p.1�`16
�̂��l�̐��̕s���Ɋւ����l�@--�̂��w�ԑ�w����A�}�`���A�����c����ΏۂƂ������⎆������ʂ���
�� ���q p.17�`34
���B��Q�����Ώێ҂̎�̓I�Q����z�肵�����y�̔������Ɋւ����l�@--
�@�@�����ʎx���w�Z(�m�I��Q����)���w�����y�ȋ��ȏ����͂�ʂ��� �� ���I�q
p.35�`56
�]���܂Ђ�B���̃L�[�{�[�h���t�ւ̎��g�݂ƍl�@ �a�c �K�q p.57�`70
�Ǖ��w���ɋ��߂��鎋�_--�c�������U�w���̎����̌��� �g�c ���q p.71�`84
�̎��E�y������ ���ꌧ��X�����Ӗ���̃G�C�T�[ ���� �K�j p.85�`116
�g�уf�W�^���I�[�f�B�I�v���[���[�ň��o�������y�ɂ���--���y�̔w�i�ƒ��쌠�ɂ��čl���� �ߓ� ���q p.117�`13 |
���A���̔N�A�c�����a,�X�R���q,����{���q,�����L���q���u���{�����Ȋw��������\�v�|�W
22(0) 2010 p.200-200�v�Ɂu����̑c����J:�|�����ՁE�~�̋����𒆐S�Ɂ|�v�\����B�@�@�@
���A���̔N�A��쐳�͂������Y�p�w��ҁu�����Y�p = Ethno-arts 26 p.192�`199�v�Ɂu���������̏��]�s�ɂ����鐼�m�|�p���y�̕��y�ɂ���--���t��E�V���E���R����
(�����Y�p�w�̏���)�v�\����B�@�@�@
���A���̔N�A���،��m���u���m������w��w�@���ە��������Ș_�W= Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies Aichi Prefectural University�@ 11 p.175-199�v�Ɂu����E���d�R�����ɂ����鉫��|�\"�G�C�T�["�̒n�搫--�e�W���ɂ�����|�\�̋@�\�𒆐S�Ɂv�\����B�@�iIRDB�j
���A���̔N�A�u�O��t������ �Q�V�O���v���u�����s�����}���فv���犧�s�����B
�@�@�����s�����}���ف@���y���ʎ������@�@���s�N�^�ҏW�N���s���Ȃ��ߊm�F�����K�v�B�@�Q�O�Q�R�E�X�E�P�O�@�ۍ�
|
�Q�R�W�W�m���y�|�\�n���茧���ދn�S���蒬���~�x�@
�Q�R�W�X�m���y�|�\�n�F�{���R���s�@�����s�@
�Q�R�X�O�m���y�|�\�n�l�g�P���ۗx�@
�Q�R�X�Q�m���y�|�\�n�F�{���l�g�s�P���ۗx�@
�Q�R�X�T�m���y�|�\�n�{�茧���юs�ז���֑��ۗx�@
�Q�R�X�U�m���y�|�\�n�ו��x�@�_�x�@�����m�x�@�����q��S
�Q�R�X�V�m���y�|�\�n�������呾�ۗx�@
�Q�S�O�W�����q�@
�Q�S�O�X�����̒M�_�`�@
�Q�S�P�X�r�_���i�@
|
�Q�S�Q�P���y�l�`�ŋ��@
�Q�S�Q�Q���o���̑��@
�Q�S�Q�U������ː_�Ѝ����_�y�i���_�y�a�j���a�l�\�O�N�㌎���@
�Q�S�Q�V�����@��ӑm���i
�Q�S�R�P����ܘY�@���h�R���_�����̎R�ԁi���a�Z�N�㌎�����|�p�獆�j�@
�Q�S�R�Q�R���_���땑�]�R���s����_�Ё]�@
�Q�S�R�R�R���_�������]�R���s����_�Ё]
�Q�S�R�S�������x�@
�Q�S�U�Q�P�n�ΘŁ@
�Q�S�U�R�P�n�Θ� |
|
| 2011 |
23 |
�E |
�Q���A���䐳�q���������ꖯ�ԕ��|�w��ψ���ҁu�������ꖯ�ԕ��|�w = The science of Amami-Okinawa folk literature (10) p.116-107�v�Ɂu����G�C�T�[���`���Ɖ̎�(������2)�v�\����B
�@�@�@(������1)�ɂ��Ă͓��e���m�F�Ȃ̂Œ������K�v�@�Q�O�Q�R�E�R�E�P�@�ۍ�@
�Q���A�O�V�����g�Ɗԉi�g, ������S, �����ƒj�Ғ��u�|�x�������T�v���u��R�Ɂv���犧�s����B
�R���A�v���c�W���@����w���ꕶ���������ďC�u����̖����|�\�_ : �_�Ղ�A�P���ۂ���G�C�T�[�܂��v���u�{�[�_�[�C���N�i�ߔe�j�v���犧�s����B�@�@�V���[�Y�F�p���E�����m���@�@�@�@368p �@�����F���ꌧ���}���فF1005603806
�R���A�v�ۓc �G�����u�Ћ���� (64) p.4-6�v�Ɂu�G�C�T�[�ƂƂ��ɕ��� : ����̐N���� (���W �n�敶���̐U���ƎЉ��)�v�\����B
�R���A ����m��,���эK�j,���i�� �����u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (36) p.66�`89�v�Ɂu�V���|�W�E�� �������y�ɂ�����y��̕��z (��24��[���{�������y�w��]���u���{�̖������y�ɂ�����y��̕��z�v--2010
����) �v�\����B
|
��24��[���{�������y�w��]���u���{�̖������y�ɂ�����y��̕��z�v--2010 ���� p.58�`99
��u�� ���{�̖������y�ɂ�����y��̕��z ���� ���q p.58�`65
�V���|�W�E�� �������y�ɂ�����y��̕��z ���� �m��,���� �K�j,���i �� �� p.66�`89
�������\�v�| ���w���n���Ƃɂ�������ׂ����̈���[�� ���^����] ���쎛 �ߎq p.91�`93
�������\�v�| �������͂̕��@�_(3)�ŗt�̖��w�ɂ݂���߂܂킵�̋��L���ɂ���[��
���^����] �㐼���q p.97�`99
�쐼����(������)�̖������y�ɂ�����y��̕��z ���эK�j p.67�`69
��B�n���̖������y�ɂ�����y��̕��z ���i�� p.69�`71
�����n���̖������y�ɂ�����y��̕��z �Ћˌ� p.72�`74
�ߋE�k��(���s�A����A�ޗǁA���ɁA���)�̖������y�ɂ�����y��̕��z �����͎qp.74�`76
���C�E�ߋE�암�n���̖������y�ɂ�����y��̕��z ���� ���� p.76�`78
���̖������y�ɂ�����y��̕��z �v���F p.78�`80
�֓��n���E�k���n���̖������y�ɂ�����y��̕��z ���]��q p.80�`82
���k(���{�C��)�̖������y�ɂ�����y��̕��z�@�@�j ���� p.83�`85
���{�̖������y�ɂ�����y��̕��z�E�V���|�W�E���E���^�����̕� �@ p.87�`89 |
�R���A�勴��������r����������ҁu��r�������� (25) p.164�`191�v�Ɂu�O���x��̌��݂Ƃ��̖����p��--���쌧���ɓߌS���쒬�a���n��̎���
(���W �c����J�ƕ�������(2))�v�\����B�iIRDB�j
�R���A�ѓc����݂��u����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v 23
p.30-56�v�Ɂu�Ί_�s�V��ɓ`�������O���́u�����O�Łv�ɂ��āv�\����B�@
�R���A<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g�F�s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@��
(20)�@���W�G (�쓇�ɂ����閯���Ə@����Z���N�V���|�W�E�� ����A�����A���--����̉ߋ��E���݁E����)�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1005592835
|
���] Mitsugu Matsuda, The government of the Kingdom of Ryukyu, [���c�v]�w���������j��Z�Z��-�ꔪ����N�x�@���c���j p.1�`7
�쓇�ɂ����閯���Ə@����Z���N�V���|�W�E�� ����A�����A���--����̉ߋ��E���݁E�����@ p.8�`69
�������� �{��--�v���o����� �@���Y ���q p.8�`17
���J�u�� �����̐Ԃ����{�Ɣ�������--�����E����j�̃p���_�C�����������@�����i
p.18�`37
���J�u�� �w�����낳�����x�p�Y��`���� �@������ p.38�`59
���J�u�� ���������Ɗ؍������@�g���P�j p.60�`69
����̋L�������p��--�ΐ�W�F�b�g�@�ė����́@���ђ��� p.94�`90
����{���k���ɂ����闬�ʃV�X�e���ێ��Ɋւ��錤���@�y���� p.89�`72
|
�R���A���{�M�a ��,�c������, ���k�V�n�ӔC�ҏW�u���ƊC�ƐX�̊��j�v���u���ꑍ���o�Łv���犧�s�����B
�@�@(�V���[�Y���{�̎O���ܐ�N-�l�Ǝ��R�̊��j ; ��4��)
|
���ƊC�ƐX�̊��j / �c������, ���k�V�n
�k�C���̐l��-���R�W�j �C�m�����̗��p�ƌÊ�/�E��[��
�l�ށA�I�b�g�Z�C�ɏo� / �����N
�A�C�k�̎��R�ςƎ������p�̗ϗ� / �������q
�����F���̕ω�-���l���玝���\�ȗ��p��
�@�@���k�̐��Y�����E�X�ю����̗��p�Ƃ��̔F��/�c������
�k�C���̊J��ƐX�є��� / �O�Y�הV
�k�C���ŋ��𑝂₷�O�̕��@ / �[�T��
�X�P�g�E�_�����ɐ����鋙�t�����̒m�b�ƍH�v/�����
�����E����̐l��-���R�W�j ���l������̗̂��l�E��łւ̓� |
�@���l�Êw����݂������̃��R�E�K�C����/�؉����q
�W���S���̗��l�Ɛ�ł̗��j / ���R����
�����E�o�ς����R�ɗ^�������� �ߑ㓝�v���Ɍ��鉂���A
�@�@������̐l�Ǝ��R�̂������ / ���Ύ���
�����\�ȗ��p�̖͍� �T���S�ʂ̊��F���Ǝ������p/�n�v�n��
���\���̃C�m�V�V�ɂ݂闤�Y�쐶�����̎����I���p/傌��ꕽ
�l�ԂƎ��R�̂������ɂ��čl����
�@�@���ׂ荇�����X�̌𗬂̋L�� / ���k�V�n
�u�����ȗ��p�v�Ɗ��K�o�i���X / ���k�V�n, �c������
�E |
�R���A���R�m�����u�哌�A�W�A�w�_�W (11) p.122-130�@�哌������w��w�@�A�W�A�n�挤���ȁv�Ɂu�`���|�\�G�C�T�[�̕ϗe : �`������n���
(������� �A�W�A�n�挤�����猩�����{�ɂ����镶���ϗe)�v�\����B
�R���A�������ꂨ���Ȃ풲���{���ەҏW�u�G���v���u�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s�����B�@(�������ꂨ���Ȃ�㉉�����W,
23 . �������)
|
�u�G���v����E���炷���E�݂ǂ��� / ���w
����Ɖ��o�����u�썲�ۓG���v(�G��) / �����Ǐ�
�����a���Ɛl���l / �R�c�L��
���a11�N�u�����ÓT�|�\���v�X�P�b�` / �ЎR�t��
�g�x�Ɣ\�y�Ƃ̍l�@(�E�^) / ����������
|
�g�x�Ƒ�a�|�\(�E�^) / �����q�Y
�u�G���v�ɂ��� : �ߑ��E�^�E��s�|�\�Ƃ̔�r(�E�^) / ���NJ_�G��
�g�x�̌^(�G��) / �n�Õ~���
�g�x�E�썲�ۓG���̌^ / �n������
�u�G���v(�w���̌䊥�D�{�x�Ɓw�Ђ̌䊥�D�{�x) / ���w
|
�R���A���A�m�����j�����Z���^- �ҁu�Ȃ����� : �R���̃����E�V�}�u���y�ђ����L�^
Vol.18�v���u���A�m������ψ���F���A�m�����j�����Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@260p�@�@�����F��㊌����}���فF1007896978
|
��1��R���̃����E�V�}�u��-
�@�@����X�������Ӗ�-
1. ���Ӗ�(�E�C)�O�X�N�Ƒ��X
2. ���Ӗ�(�E�C)�O�X�N�Ƒ��X(�����n��)
(1) �����Ԑ̍���(�N���W����)��
�@�@���������Ӗ�(�C���W���~)
(2) ���Ӗ�(�E�C)�O�X�N�ƏW���Ƒ�(����)
(3) ��X���Ԑ�
(4) ���Ӗ�(�E�C)�O�X�N�Ɗւ��o����(���j)
3. ��X�������Ӗ��̃E���K�~
��2��R���̃����E�V�}�u��-
�@�@�����H�n�Ԑ̎O��-
1. �H�n�n��(�Ԑ�)�̎O�̃����E�V�}
2. �H�n�i�䏉��
3. ���������c�䓙���Ɛe�쑺
4. �H�n�̎O�̃���(�U�c���E�c�䓙�E�e��)
(1) �U�c������
1 �U�c���̌����ف`�U�c���̃E�^�L
2 �U�c���E�^�L�̃C�x
3 �U�c���̐_�A�T�M�Ɲ|�k�_
4 �E�^�L�̌����`�H�n����
�@�@���c�䓙�����̃f�[�O�X�N��]��
5 �U�c���̏W���ƃE�y�[�t�K�[
6 �j�K�~�K�[�ƃj�K�~���[
(2) �c�䓙����
1 �c�䓙�����̐����_�a��
2 �ɐ���(�C�V�h�D)�_�a�ƃr�W����
3 �����V���K�[�Ɠc�䓙�̐_�A�T�M
4 �A�v�n�~�k�~���[�Ɠ�̓���
(3) �e�샀��
1 �E�F�K�[�K�[
2 �H�n(�e��)�ԏ���
3 �H�n(�e��)�O�X�N�Ɛe��̐_�A�T�M
(4) �H�n�̎O�̃����E�V�}�̂܂Ƃ�
��3��R���̃����E�V�}�u��-����s��
�@�@������R����(���]�E��E�匓�v)-
1. ���쑺�ƎO�̑�(���]�E��E�匓�v)
2. ����O�X�N(�E�^�L)�𒆐S�Ƃ������J
3. �����(�i���O�X�N)�ƎO�̃���
(1) �ٓ��ł̃��N�`���[
1 ����O�X�N���猩�����i
2 ���K�J����t�X�~���[���K
3 �a����
4 �K�i�`�E�`�K�~���[
5 �K�i�r���̐_��
(2) ����O�X�N�̐_�A�T�M�Ƃ��̑�
1 �E���咆�̃C�x
2 �O�X�N���ɂ����`�x�ւ̌�p
(3) ��Ճ����̐Ղ����ǂ�
1 �t�o�k�q�`��(�N�o�̉�)
2 ����_��
3 �m����
4 ���_���[
(4) �������E�������`�������������邩��
��4��R���̃����E�V�}�u��-
�@�@��������(�����E����)-
�͂��߂�
1. �����Ԑ؋�����
1 �����Ԑ̃m���NJ���
�@�@��(�w�������R���L�x1713�N)
2 �����Ԑ؊e���m���N���C����(����17�N��)
3 �����m���̈�i
2. �����������E����
1 ���쓴�A�╨�U�z�n����
2 ���_��
3 �g�D���X�Y�̌��
4 �����m���h�D���`
5 �����m���h�D���`�����Ǝ���
6 ���̓r���ʼn�����������
7 �_�A�T�M�ՂƋ����O�X�N�̐Ζ�Ղ̐�
8 ��k�ь����Ƌ����߂̔�
9 �E�K�~�ƃi�[�J���C
10 �L���^�K�[����̔q��
11 �L���^�K�[(�c���c��)
12 �L���^�K�[����̌��
13 �s�v�c�ȐԊ��̂�����
14 ���[�V�k���C�`�k���h�D���`�K�[
15 �Ō�̂��y���݁`
16 �����E�����̂܂Ƃ�
��5��R���̃����E�V�}�u��-���[���R�c-
�Ԑ��瑺��
1 �R�c�����̐_�c(?)��
2 ���[�K�[�ƒ�(������)��
3 �썲�ۂ̕��c�̕�
4 �R�c�����̐_�A�T�M��
5 �N���K�[
6 �R�c�E�^�L�̃C�x
7 �R�c��������̂܂Ƃ�
��6��R���̃����E�V�}�u��-�������ӌ�-
�������X���^�E�ӌ�
1 �X���^�W���ƃI�����_��
2 ���ł��o���^
3 �߂铹(���c�R�����搶��)
4 �`�{���̕�
5 �q�`������� |
6 ����������艺���������肵�ĕ�������
7 �q�`������Ԃ̃C�x
8 �ӌ˂̂������
9 �������ƍ��A�m�A�I�����G
10 ������ƂЂƑ�
11 �ӌ˂̍��_���ƃk���h�D���`
12 �ӌ˂̐_�A�T�M
13 �ӌ˂̊C�_�ՂƃV�j�O
14 ���ӌˋ掖�����Ƌ������X
15 �X���^��a�ƋX���^������
�����L�^(2008�N1��)
���A�m���^�V
�ÉF�����̈�
�ɕ��������ɐ�����
�ɕ������̓c���m���a��
�ɕ������̖��
�ɐ����m���a��
�F���R�̗����N�U
����̐��E��Y
�����哇�Ɛ��˓������v�C����
���V�� ����͂܌��̈�
�k�R�Ɗւ����Ε�
�n���ƕ�(���\��)
���W��
�����̒n�}
���A�m�Ԑ؍Ō�̒n����
�����L�^(2008�N2��)
�V�铿���ƐV�铿�K�̕����j��
������4�N���̔��\��
�e����̐l��
�ɍ]���̃��G�J�l
�ɍ]���̕����̃m��
�ɍ]���̐ܖ�
�ɍ]���̈�
�I�[���[�E�h�D���̓�̈ʔv(�K�[�i)
���A�m�i�Z����c�̈ʔv��
�@�@�����������b(�I�[���[)
���A�m���w��̕�����
���ǐV���W�̎���
������̉ƕ�
�k�R�̗��j�ƕ���
�m�O�Ԑ̔ԏ�
���w��̕�����
���A�m�O�X�N�̎l��̐Γ���
��シ���̓y�n���ʂɊւ���u���Y�^�v
�w�V�Q�����ƕ��x(��@)�������
���ǐV����
��X���Ԑ̑n�݂Ɨ��y�n����
��X���ԐƗ��y�n����
��X���i��(��a)
��X���a��
�V�铿�S���m�[�g(�u��Y��v���)
�����L�^(2008�N3��)
�����Ԑƍ����i�ƍ����e��
�����ԐƗ��y�n����
�����e��(�e���n����?�����a��)
��������n�̐��F�ƐΓ���
�������ӌ˂̐Γ��ĂƐ̍��F
���������̐Γ��ĂƐ̍��F
�R���̊Ԑƒn����
�{���ԐƗ��y�n����
�{���Ԑ̘e�n��
���[��a�ƂƑy�n����
���[�Ԑƈi�n����
���n�R�y�n����(��)
���[�ԐƘe�n��
�ߐ��̉�
�H�n�ƒn����l
�H�n�ԐƗ��y�n����
�u�ߔN�H�n�i�l�䏉�n�����L�v
��a�Ɠa���ւ̕���l(��Ԑؖ�l��)
���������̃E�K�~(�_��)�ɂ���Γ���
�����E�V�}�u��
�́u�كK�x�v
�كJ��
���̂���Γ��Ă���F
������(����)�̌��-�X���`�i���-
�g���ƕ�(�ɍ����)
���v�C����(�����E����)
���u��Ԃ̌Õ�
�ʏ�O�X�N�̐Γ���
�w���q�F���Y�����W�x(�m�[�g��1)
�������̌������̐Γ���
���K�̃����E�V�}
���ʏ鑺�̃����E�V�}(�����s)
���m�O��(���s)
1 �u�쉮
2 �R��
3 ��u��
4 �m�O
�X��p���q���ˊ�i���Ė�
�ӓy���́u���_�V�{�v���K
�����L�^(2008�N4��)
�����O�X�N�̐Γ���(���s)
���R����(����)�L����� |
1 �����O�X�N�̐Γ���
2 �����O�X�N�̐Γ���
3 �����O�X�N�̐Γ���
4 �����O�X�N�̐Γ���
5 ����
�����q�̍��F
�����q�̌�ԂƃX���`�i���
�Γ��Ă⍁�F�̖��̒���
����100�N�̕���
�ɔg�O�X�N(������s)
�F�B�E�]�ˏ��(��)�y���q�ƕ���l
���A�m
����100�N�̕���
����41�N���珺�a20�N�܂ł̏o����
�y�[�t���[
�@�@��(������)�̈ʔv(���A�m���Ӗ�)
�l���(������s)
�l��Ó��̃���(������s)
�H�n�Ԑ؈�䑺��
�@�@���^�Ɗ쉮��{�̍��F��
���a27�N�`30�N��ɂ����ẴX���C�h
����100�N�̕���
��X�����c�`�Ƒ�X���̃E�^�L�̍��F
��X������X���̌�Ԃ��K�ƍ��F
�����E�V�}�u��
���a�̕��Ԍ���(����s���a)
���䂫
�E�^�L�ƃC�x
�����L�^(2008�N5��)
�_�ˁE���ɁE���
�ߐ��̗����̓���
�_�˂̊X
�]�ˏ��(�]�˗�)(�F����)
�]�ˏ��(�]�˗�)
���
�����E�V�}�u��
��a���~�ƃI�[���[�E�h�D�����~
���K�n��
�H�n�i�l�䏉�n�����L
�n���n�֏���(���L5�N9��16���F1855)
�@�@��(�e�n���̖���)
�n���n�֏���(���L8�N12��27���F1858)
�@�@��(�e�n��)
�n������D�@������
�@�@��(�y�n������)
�v�u�e����v�u�e�_��Ȃǂ̎F�B�䂫
���w���̗��j�w�K
�y���q�Ƃ��Ă̍]�ˎQ�{
�w���R�����x���F�B��]�ˏ�̐e���E
�@�@���i�E���q�Ȃ�
�^�_���Ɩk�R
���A�m�̓`���E���b
������`���|�\
���鑺�V�_�̏W���ƌ��(�O�X�N)
���L����(�Y�m��)
���i�Ǖ����̒m�����Ƙa����
������3�N
���j�̊w�K
���A�m�O�X�N�Ɗւ��`��
���A�m�O�X�N���ӂ̉摜
���{���獡�A�m�Ԑւ̏h��
��Җ�(�E�}�`���[)
�摜�̐���
�w���z�x(���h��4�N�̏��F1716�N)
�w���z�x(���h��19�N�̏��F1734�N)
�[�̏W��
�����L�^(2008�N6��)
����Ƌv�u�ω���
���A�m�ɓ`���`���E���b
���A�m�O�X�N�Ǝ��ӂ̏W��
�H�n(�e��)�O�X�N�ƏW��
���A�m���������b
����O�X�N�ƏW��
���Ӗ��O�X�N(�E�C�O�X�N)
�����Ԑ̍���(�N���W����)��
�@�@���������Ӗ�(�C���W���~)
���Ӗ��O�X�N�ƏW���Ƒ�(����)
���A�m���̋ʏ�
��������n
���A�m���������b�a��
�@�@��(�I�[���[�h�D��)���K
�����E�V�}�u��(���A�m���ʏ�)
�{�����ɖ�g�`�����t��
�吳13�N�ɊJ�ʂ������A�m�O�X�N�ւ̓�
�ӓy�����Z�̐��k�փ��N�`���[
�^�V�ɒu���ꂽ�C�R�̕����̕���
���A�m�O�X�N�̃n���^��
���A�m�Ɛe���̏W��
�W���ړ��Ƌ���
�k�R�̗��j
�k�R�Ď������������(���Ď玞��)
�O�X�N����(�E�^�L)
���a30�N���̗l�q
�ҏW��L
�E |
�T���A�c�R�P������E�{��M�E�Ғ��ďC�u���I���d�R�ÓT���w�W 3�v���u�ߔe�F��������v���犧�s�����B�b�c�Q��
|
���� ���d�R���y�̐_���̓`�����A
�@�@���n���I�p���Ɍ����ā@���{�M�v�@4
���� �V���Ȕ��d�R
�@�@���ÓT���w�̃e�L�X�g�a���@���{�@6
����-�w��O�W�x�̐���E�ҏW�ɂ�������-�@8
�y�}��z�@10
���d�R�w�̉��ߕ\�@12
���d�R�ÓT���w�̓��ꉹ�߂���юg�p��@14
�܂����ɂ�[�ܐ�(�{���q)�@16
������(�{���q)�@22
�e��肣��(�{���q)�@30
��ǎR��(�{���q)�@34
�^���W��(�{���q)�@44
�����ʒ[��(�{���q)�@50
�c���Ԑ�(�{���q)�@64
�R����ΐ�(�{���q)�@70
�{�Nj���(�{���q)�@78
��߂�[��(�{���q)�@84
���ߐ�(�{���q)�@96
�������~��(�{���q)�@102
���ӂ�����(��g��)�@108
�܂݂Ɓ[�ܐ�(��g��)�@114 |
�Ɓ[���ɂ�������(��g��)�@124
��������[��(��g��)�@134
�Z����(��g��)�@144
��R��(�{���q)�@150
�V����(�{���q)�@162
�܂ɂ�������(�{���q)�@174
�ڂ��ہ[��(�{���q)�@182
�^�R��(�{���q)�@186
�����Ⴍ��(�{���q)�@198
��c��(�{���q)�@202
�a�l��(�{���q)�@214
������[�ܐ�(�{���q)�@224
�T�v����(�{���q)�@232
�약��(�{���q)�@242
�R���(�{���q)�@256
������(�{���q)�@262
�܂₮��[��(�{���q)�@274
�v����(�{���q)�@284
���z����(��g��)�@290
���ڂ�b
(1)�@�f�C�S�ɂ܂�錿�ɂ��ā@21
(2)�@�J���x�̌���ɂ��ā@28 |
(3)�@�w���I���d�R�ÓT���w�W
�@�@��(��)�E(��)�x��ǂ�Ł@42
(4)�@<�����ʒ[��>�̉̈ӂɂ��ā@59
(5)�@<�����ʒ[��>�̃J�^�t�[�ɂ��ā@61
(6)�@�������ӂ̋���ނɂ��ā@95
(7)�@�^�ߔe�ݔԂ̍ݔC���Ԃɂ��ā@101
(8)�@�E���J�C�W�E���g�D�J�C�W�̌ꌹ�@112
(8)�@���㉹�̂����炢�@122
(10)�@�g�[���̌ꌹ�ɂ��ā@143
(11)�@�E�}�V���[���E�`�D�i�V���[���@171
(12)�@�d�����ɂ��ā@180
��ȗp�����(1)�@77
��ȗp�����(2)�@197
��ȗp�����(3)�@201
��ȕ��@�p�����(1)�@241
��ȕ��@�p�����(2)�@255
��ȕ��@�p�����(3)�@299
���Ƃ���-�����{�n�k�E�Ôg�ЊQ��
�@�@���������"��������"�Ɏv��-�@302
�����@317
�E
�E |
�U���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 45(1) (�ʍ� 109) �v�����s�����B
|
��y�^�@�����`�d�̎����ƎF����k�@�m���芰 p.1�`21
�ߔe�s�����̎O���V��--�E�X�f�[�N�̂̕��w�I�����̈�Ƃ��Ă̈�l�@�@����
�O�� p.22�`64
�u�I���G���g�v�́u�I���G���g�v��:���v���ƃO���[�o�����̎���ɂ����鉫��j����ށ@Rosa Caroli p.66�`93
���ߑ㉫��ɂ�����ܐ����̎�e--�R�����j�̌ܐ�������ΏۂƂ��ā@�O�� �킩��
p.128�`94 |
�V���R�O���i�y�j�A�����w2-301�����ɉ����āu �� 1 �� �ΊD��n��V���|�W�E���i�j�@�ΊD��n���m��ŏ��̈���v�Ƒ肵���V���|�W�E�����J�����B�� 80 �l���Q����
|
��|���� �O�� �W�i�I�[�K�i�C�U�[�C������j
��u�� �㌴ �y��j�i�����j�F�u�ΊD��n��̎��R�Ɛl�v
���u���P ���� �q�i���ꍑ�ۑ�j�F�u�ΊD��n��̓y������v�^�R�����e�[�^�[�F�A��
�F�i������j
���u�� 2 �c�� �L�i������j�F�u�ΊD��n��̃W�I�c�A�[�̎��H�v�^�R�����e�[�^�[�F����
���K�i������j
���u�� 3 ��ߔe �O�i�Y�Y���j�F�u�ΊD��n��̐��E��Y�v�^�R�����e�[�^�[�F��]�F
�O�i���ꍑ�ۑ�j
���p�l���f�B�X�J�b�V���� �p�l���X�g�F�O��W�i�i��j�E���� �q�E�c�� �L�E��ߔe�O
��l �����i���ꍑ�ۑ�j�F�����i��@ |
�V���A�|�䉏��������猤�����ҁu������� 41(7) (�ʍ� 524) p.111�`117�v�Ɂu�����̃g�|�X(112)�u�q�ǂ���v���Ȃ��������Ȃ�--�吳����q�ǂ��G�C�T�[�c�v�\����B�@�@
�V���A�O���킩�Ȃ��u������w����w�����y�Ș_�W (3) p.167-190�@������w����w�����y�ȁv�Ɂu�R�����j�̃��R�[�h���w�@-�m�y�̑�O���ƃi�V���i���e�B�\�ۂ̊ϓ_����-�v�\����B�@�@�iIRDB�j
�V���A����䂤�q���^�������u��v���uKing Records�v���犧�s����B�@�@�@�@�^���f�B�X�N
1�� : CD
|
(1)�{�Nj���-����ǂ��̉�(2)�^���Ԃȃf�C�S�̍炭���a(3)�_�C�i�~�b�N����(4)�ӂ邳�Ƃ���̐�(5)�p�C�k�J�W(6)�z���l�A���(���ނ��тƁA�͂͂�)(7)������(8)�ӂ邳�Ƃ���̐�(�C���X�g�D�������^��)
|
|
�W���A���쒼�V,���u�_�ސ��w�@���ۏ햯���������@�\ �N�� 2 p.113-122�_�ސ��w�v���u��B���S�Y�i�����炢���j�Ɖ���؋�Y�i�����������j�Ɓv�\����B
|
�v�|�F���ۏ햯���������@�\�̃v���W�F�N�g�u�A�W�A���J�|�\�̔�r�����v�ł́A2010�N9���ɒ��������Ȑ�B�s�ɂ����āA���̒n���ɓ`������Ă�����S�Y�A���b�Y�A�����Y�A�쉹�Ȃǂ̎��n�����ƌ��n����������{�����B�{�e�́A�����̂����̒����������瑀��l�`���ł������؋�Y�̂����A�ꕔ�������ł����_�F�ł́u�U���S�v���N�_�ɁA���J�|�\�����ɂ̓A�W�A�I���_�ɂ���r���K�v�ł��邱�ƂƁA���̔�r�̋�̗�Ƃ��ĉ���ɂ�����؋�Y�A�܌��̖؋�E�؋�Y�_�����グ�Ę_���邱�Ƃō���̌����ۑ��������̂ł���B�@�ꕔ�������ł�������؋�Y�́A��B�s�̓��ԕ_�ōs���Ă���u�U���S�v�ł���A����́u������v�l�`�ɂ��u�������v�̐��_����n�܂�؋�Y�ł���B���̑�����͍��b�Y����ł��J����ȂNjY���_�Ƃ��Ĉʒu�Â�����B�������������̌��n�����̐��ʂɂ��āA�]���̍䏮�q�A�t�����A�n���A�쑺�L��A��ؐ�����̌�������ʒu�Â���ƂƂ��ɁA���̒n���̖��Ԙ��S�Y�ɂ́A�@�����Ɩ��������t�����邱�Ƃ��m�F�����B���̏�ŁA��r�����̈�̉\���Ƃ��ĉ��ꌧ�ɑ��݂����j���u�`���[�i�O���ҁj�E�`�����_���[�i�����Y�j�����グ�A���̌����j�ɐG��Ȃ��炱�ꂪ���@�����Ɩ��������T�ς����B��B�؋�Y�Ɣ�r������̂́A�O���ҁE�����Y���؋�������ĔO������������A��t���Ȃǂ��s�����肷��@�����Ɩ������ł��邱�Ƃ�����B�O���ҁE�����Y�ɂ��Ă͑����ɐ܌��M�v�����ڂ��Ă���A�܌����������߂Ă���u�p�e�̔O���v�͖~�̌���O���ƂȂ��Ă�����̂ŁA����͓��A�W�A�ɍL�����݂���ژA�`���Ƃ̊֘A���\���ł��邱�Ƃ��w�E�����B����ɂ��������؋�Y�̉��҂̐������A�܌��́u�����v�u�ق��ЂтƁv�_���������A���̗��_�����g�g�݂𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA����̔�r������̉ۑ�ɂ��Đ܌����_�����Ƃɒ����B |
�X���A�O�Ԏ�P, �g�Ɗԉi�g�Ғ��u��{�������R���L�v���u�p��w�|�o�Łv����i�āj���s�����B ���ŁF1997/4�@
�X���A�������꒘,����V�n�ҁu���{���������� : �Ñw�Ƃ��̎��ӂ�T��v���u�����i�s��{�����فv���犧�s�����B�d�v
�X���A�������ق��ҁu�����Ɩ��Ɖ��� : ���z�ւ̃��u���^�[= Tomatsu, Shomei + Okinawa photographs : love letter to the sun�v���u��a�v���X�v���犧�s�����B
|
���e�Љ�F �����{�̎ʐ^�j�ɐ��X�̏d�v�ȑ��Ղ��c���A�u�ʐ^�̋��l�v�ƕ]����铌���Ɩ��̉���Ɋւ���d�v�Ȏʐ^�V���[�Y����A2011�N�B�e�̍ŐV��܂�240�_�����^�B2011�N9��23���`11��20���ɉ��ꌧ�������فE���p�قŊJ�Â��ꂽ�W����̃J�^���O�B |
|
����������
���b�Z�[�W
���u���^�[�ƒ������ �\ �����Ɩ��́q�����/���ꂩ��r
�C���^�[�t�F�C�X�� �\ �����Ɩ��̍�i���E
����̏��a �\ �����Ɩ��m�[�g
�u�������C���[�W�v�Ǝʐ^�̋��x
�}��
�T�� �s����{�̌����i�q�`���[�C���K���ƃ`���R���[�g�r1959-67
�U�� ��̃V���[�Y�Ō�̒n�u����v�qOKINAWA�r1969
�V�� �u���т������v�z������B�v�q���z�̂���҂r1969-73
�W�� �J���[�ւ̓]���q�쓇�r�q���镗�r1973-79 |
�X�� �ʐ^�̓C���[�W�ŒԂ郉�u���^�[�q�����`�����v���r
���ꂩ��40�N
�u�B�葱���邱�Ɓv
�C�����̂���ʐ^�Ɠ����Ɩ������
��������v��
�������p�j����j
����
�N��
����Ɋւ����v����
��i���X�g
�E |
�P�O���A�u��56�� ����S���G�C�T�[�܂�v���u�I�L�i���O���t (595) p.46�`48�v�Ɍf�ڂ����B
�P�O���A�w�p�������s��ҏW�u�����w�N���ʘ_���W �����w��ʕ���21(2009)�N�v
���u�����o�Łv���犧�s�����B
|
�u���E�𖢒m������v���w / �� �k��
�����j�̉\�� / ���� ���j
�a�̂ɂ����镶�̍\�� / �� ���N
��Íc�q�ƍ��ƕ� / ���� ����
�̘b�̍����ɂ������ / ���c ��
�̘b�`���ɂ�����<����-������>�_�̌n��/�L��S��
�̘b�ɂ�����يE�� / �גJ ���}
����{�����������̑̌��̃A�N�Z���g�^�Ƃ��̌n��/���X���q
������̔�r����w�I�l�@/ �������a
�g�Ɗԕ����Ɨ^�ߍ�������
�@�@���`�e�����������ڐG����݂�/ ����܂������Ђ�
���v�ē���u�쑺��]�F�����̏���/ �쌴�O�`
���ꌧ���A�m���Ӗ������̃A�X�y�N�g�E
�@�@���u�e���X�E���[�h / ���� �K�q�@����܂� �����Ђ�
���k�n���̃A�C�k��n���̍Ċm�F/ ��������
�k�C�����Ԑ��b�̌��� / ���� �q�v�^��
���c���j�Ɠǎ҂̃l�b�g���[�N�Ґ� / ��� �h��
�{�{���u�y�������v�Ȃǂɂ݂���
�@�@���F�D�݂̕��i�ƍ��Í�/�O�ύ_��
<����>��<����>�ɕ�܂���邩 / �k�� �O���^��
���C�E���R�n���ɂ�����ӎu�E���ʕ\���̌��ƕ���/�F�����
���u�l / ���� �v�q
����̗��� / ���� �^��
����(�������)��b�l / �g�� ��
�������̑��l�� / �V�� �݂ǂ�
�ԓ������u�ˁv�Ɓu�ł��ˁv/�ɓ����p�q |
�V���������̐V���Еʌ�b��r/���|�G�Y
�V�����\�����g��ꂾ���Ƃ� / �R�� ����
�c���f���\���̑ҋ��� / ���c ����
���b�s���ɂ�����u�Łv�̖��� / ���o �c��
�������S�т�Ƃ� / �F�J ���q
���R�[����̕��������Ɛ̘b�Ɍ���������̌�@/�V�c�N�v
���茧���암�{�y�����̓����e�`�ɂ�����`�ԉ��C����/�L�����F
���ꋳ��ƕ��w / ���� �j�q
�w���ꋳ�玏�x�̏����ƋL�ړ��e�T�v/�L���T
���w�Z�ɂ�����u�������Ɓv�̊w�K�w��/���� ������@�|���
�����w�Z�ÓT������ɂ�����w���̍H�v�ɂ���/ �i�g���s
���ꋳ�ށu���͂̊ցv����w�����̂ق����x�� / ��v�� ���q
��U�Ȉ�N�u���{�̌��t�ƕ��w�v�w���X�搶�h�Ԗ��x�̎���/���L��
�u�`���I�Ȍ��ꕶ���ƍ���̓����v�ɂ��Ă̎w���@����/���ː���
�u�`���I�Ȍ��ꕶ���ƍ���̓����v�ɂ��Ă̎w���@����/ �� ����
����̎��Ƃɂ������g�\���̎w���ɂ��� / ���c �r��
�����o�ł̓��{�ꋳ�ȏ��̋��ޕ��� / �勴 �֕v
���{��Ƃ�܂Ƃ��Ƃ� / �ᓈ ����
<����>��<����>�ɕ�܂���邩 / �k�� �O��
���{�ÓT��p�u�Ӓ��̕��v�ɂ��� / �͍� ��
�ɔg���Q�u����l�̑c��ɏA�āv / �O� ���K�^��
�v�����̎��n�Ղƍ����N���`�� / ���R ��
���k�V���r�[�������ɂ�������ꉹ�f�̎����̎���/�勴����
�������y�{�w��߂��͂��x�ɓo�ꂷ��l���̌��t����/�R�{�~
���ꊴ�o���o��̎w�� / ���c����q
�E |
�P�P���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 45(2) (�ʍ� 110) �j�����s�����B
|
�×����Љ�̓����Ɖ���̍`�p�@�\�@�@�㗢���j p.1-30
�w����`�����u�x�̌��� : ���{�̌n���W�ɂ��ā@ḛI�� p.31-70
�{�Ó��E�����́u���̌䏉�v���J�V��Ɖ̗w�ɂ��ā@�㌴�F�O p.71-90
�y���Ɍ���O���֘A�����̊W�Ƃ��̍\���@�ѓc����� p.128-91 |
�P�P���P���`�P�Q���P�P�����A��B���������قɉ����āu�����Ƒܒ���l�W : �G�C�T�[�̋N�������ǂ� : ���s�E�h���@�ю��J�n400�N�L�O�v�W���J�����B
�P�P���A��B����������, ���ꌧ�������فE���p�ٕҁu�����Ƒܒ���l�W = Ryky and priest Taich : �G�C�T�[�̋N�������ǂ� : �g�s�b�N�W���i�}�^�j�v���u��B���������فv���犧�s�����B
�P�P���A�M�P���땶, �ΐ�o�u�Y���u�h���@�ю��ܒ���l : �����Ƌ��s�̉˂����v���u�W���Ёv���犧�s����B
�P�P���A���s�j�ҏW�ψ���ҁu���s�j : ������ (�ʎj)�@�v���u���s����ψ���v���犧�s�����B�@�@
|
���������@���s���@�Îӌi�t�@3
�����̂��Ƃ@���s���璷�@���䒩�E�@4
���s�j�����Łi�ʎj�j���d�グ��
�@�@���@���s�j�ҏW�ψ���@�{���v�@5
�}��@6
���́@���s�̎��R�@13
���́@��@�C�ہ@�C���T�L�N�T�[�~�Ɩ��@14
���́@��@�C�m�@�C�m�[�ƍ��{�@15
���́@�O�@�n�`�@16
���́@�O�@(��)�@��n�Ƌu�ˁ@16
���́@�O�@(��)�@���n�ƗN���@17
���́@�O�@(�O)�@�����\���͈ł̒����t�@18
���́@�l�@�n���@19
���́@�l�@(��)�@�y�n�̂���@19
���́@�s�R����1�t�@����̒n�w�@�N�`���@21
���́s�R����1�t(��)�ΎR�ƍ��R�̏��\�V���ÊD��w�@21
���́s�R����2�t����̒n�w�@�j�[�r�@22
���́s�R����2�t(�O)�@�̂ނ����̃T���S�ʁ\�����ΊD��w�@23
���́@�s�R����2�t�@�l)�@�n���ׂ�Ƌ�����@24
���́@�s�R����2�t�@(��)�@�n�w�̂Ђ��݁\�t�B�b�V���[�@26
���́@�s�R����3�t�@���K�̋���M�����ڋ��@27
���́s�R����3�t(�Z)�y���琶�܂�ł������⋅�\�}���K����27
���́@�܁@�n���ƐA���@28
���́@�܁@(��)�@�R���R�ƍ֏��ԁ@28
���́@�܁@(��)�@�n�}�W���`���E�Ƒ��ށ@30
���́@�s�R����4�t�@�u�v���͐_�̓��v�����R��������@31
���́@���j�̂͂��܂�@33
���́@��@���j�̕���Ƃ��Ă̓��s�@34
���́@��@��j����̉���@36
���́@��@(��)�@���ΐl���@36
���́@��@(��)�@����̍ł��Â��y�핶���@38
���́@��@(�O)�@��j����̓��s�@44
���́@��@(�O)�@1�@���s�ŌÂ̓y�핶���@44
���́@��@(�O)�@2�@�O�琔�S�N�O����̓��@46
���͓�(�O)�@3��琔�S�N�`�琔�S�N�O����̓��47
���́@��@(�O)�@4�@���N�`�琔�S�N�O����̓��48
���́@��@�s�R����1�t�@�ΊD�⓴���ɉ��ΐl����ǂ��@51
���́@��@�s�R����2�t�@�y��̌^���ƍl�Êw�@51
���́@��@�s�R����3�t�@�����ȓ��ɉ؊J�����L�˕����@52
���́@��@�s�R����4�t�@��j����̕�@53
��O�́@�×�������̓��s�@55
��O�́@��@�×����̐����ƓW�J�@56
��O�́@��@(��)�@�×����Ƃ́@56
��O�́@��@(��)�@�×����͈̔͂Ɠ����@56
��O�́@��@(�O)�@�×����̐����̗���@57
��O�́@��@(�l)�@�I�����ƌ×����̓��s�@59
��O�́@��@�O�X�N����̓��s�@62
��O�́@��@(��)�@�O�X�N����̉���\���̊T�ςƓ����\�@62
��O�́@��@(��)�@1�@�O�X�N����̑O�j�@62
��O�́@��@(��)�@2�@�O�X�N����@63
��O�́@��@(��)�@3�@�O�X�N�̗��n�@64
��O�́@��@(��)�@4�@�O�X�N���甭�������╨�@64
��O�́@��@(��)�@�O�X�N�������̂���݁@65
��O�́@��@(��)�@1�@���s�̃O�X�N�@65
��O�́@��@(��)�@2�@�O�X�N�̒����@67
��O�́@��@(��)�@3�@�O�X�N��ǂ݉����@71
��O�́@��@�s�R����1�t�@���E��Y�̂͂Ȃ��@73
��O�́@��@�s�R����2�t�@�꒣��@74
��O�́@��@�s�R����3�t�@�O�X�N�A��A�`���V�@74
��O�́@�O�@�O�R����Ɠ��s�@75
��O�́@�O�@(��)�@�O�R�Ƃ́\���̗R���ɂ��ā\�@75
��O�́@�O�@(��)�@�j���Ɍ��ꂽ�O�R�����@76
��O�́@�O�@(�O)�@�O�R�����@76
��O�́@�O�@(�O)�@1�@����ւ̗���@76
��O�́@�O�@(�O)�@2�@���Y�嗢����U�߂�@77
��O�́@�O�@(�O)�@3�@���R�����J���U�߂�@79
��O�́@�O�@(�O)�@4�@�k�R���@79
��O�́@�O�@(�O)�@5�@��R���łԁ@80
��O�́@�O�@(�O)�@6�@���b�u��@���ɗ������邩�@82
��O�́@�l�@���������̐����Ɠ��s�@83
��O�́@�l�@(��)�@���������Ƃ́@83
��O�͎l(��)���������Ə��~���\�^�̈Ӗ��ł̉����̊m���\84
��O�́@�l�@(��)�@1�@���~�̌o���@84
��O�́@�l�@(��)�@2�@�썲�ہE�����a���̗�������@84
��O�́@�l�@(��)�@3�@���~���̐����@85
��O�́@�l�@(�O)�@���^���̐����\�×����̉�������\�@86
��O�́@�l�@(�O)�@1�@�����W���̊m���@87
��O�́@�l�@(�O)�@2�@���^���̏@������@88
��O�́@�l�@(�O)�@3�@�O�𐭍�@89
��O�́@�l�@�s�R����4�t�@�����̋����@89
��O�́@�l�@�s�R����4�t�@4�@�×�������̓��s�@92
��O�́@�܁@�I�����ɂ݂���s�@92
��O�͌�(��)�͂��߂Ɂ\�I�����ɓ��s�������˂�̂͂Ȃ���92
��O�́@�܁@(��)�@1�@�n��̗��j�ƃI�����@92
��O�́@�܁@(��)�@2�@�I�����Ɓw�����낳�����x�@93
��O�͌�(��)�R���s�̃I���������^����w�����낳�����x�̊��X95
��O�́@�܁@(��)�@���s�̃I�����ɗw��ꂽ�y�n�Ɛ_�Ɛl�@95
��O�́@�܁@(��)�@1�@���~�n��̃I�����@95
��O�́@�܁@(��)�@1�@(1)�@�I�����Ɍ����鍲�~�̒n���@95
��O�͌�(��)1(2)�@���~�̃I�����ɗw��ꂽ�_�E�_���E�l�@97
��O�͌�(��)2�m�O�n��̃I�����@99
��O�͌�(��)2(1)�@�I�����Ɍ�����m�O�̒n��99
��O�͌�(��)2(2)�@�m�O�̃I�����ɗw��ꂽ�_�E�_���E�l102
��O�́@�܁@(��)�@3�@�ʏ�n��̃I�����@103
��O�́@�܁@(��)�@3�@(1)�@�I�����Ɍ�����ʏ�̒n���@103
��O�́@�܁@(��)�@3�@(2)�@�ʏ�Ɍ�������n��
�@�@�@���s���̌�Ԃ���A���̑��̒n���@105
��O�͌�(��)3(3)�@�ʏ�̃I�����ɗw��ꂽ�_�E�_���E�l105
��O�́@�܁@(��)�@4�@�嗢�n��̃I�����@109
��O�́@�܁@(��)�@4�@(1)�@�I�����Ɍ�����嗢�̒n��109
��O�͌�(��)4(2)�@�嗢�̃I�����ɗw��ꂽ�_�E�_���E�l110
��O�́@�܁@(�O)�@���s�̃I�����ɗw��ꂽ���{���J�@111
��O�́@�܁@(�O)�@1�@���{�̌����ՋV�Ɠ��s�̃I�����@111
��O�͌�(�O)2�@�{�_�b�̐��n�Ƃ��Ă̓��s�ƃI�����@113
��l�́@�ߐ��̓��s�@117
��l�́@��@�F�����Î��̗����N���@118
��l�́@��@(��)�@�F���̐N���@118
��l�́s�R����1�t�����̌R���͎F���R�Ƃǂ̂悤�ɐ������119
��l�́@�s�R����1�t�@(��)�@�F���̗����x�z�@119
��l�́@�s�R����1�t�@(��)�@<�j��1>�@�|�i�\���j�@120
��l�́@�s�R����1�t�@(�O)�@�u�]�˗��v�Ɨ����̒n�ʁ@121
��l�́@�s�R����2�t�@���{�Ƃ̊W���ǂ̂悤�ɉB�������@121
��l�́@�s�R����2�t�@(�l)�@�F���˂Ɖ��{�̍����@122
��l�́s�R����2�t(��)�F���x�z���ɂ����钆���ւ̐i�v�̈Ӌ`123
��l�́@�s�R����2�t�@(�Z)�@���E�������̗����@124
��l�́@��@�ߐ������̎d�g�@126
��l�́@��@(��)�@�H�n���G�̐������v�@126
��l�͓�(��)<�j��2>�w�H�n�d�u�x�ɂ݂�Â����K�̉��v127
��l�́@��@(��)�@�ߐ������̐����g�D�@128
��l�́@��@(�O)�@�g�����x�̊m���@129
��l�́@��@(�l)�@�ƕ��̍쐬�Ɩ����@130
��l�́@��@(��)�@�@�T�̐����@131
��l�́@��@(��)�@<�j��3>�@�ʏ�Ԑ؊e�����@�@132
��l�́@��@(�Z)�@��̐���@133
��l�́@��@(�Z)�@<�j��4>�@�w�䋳���x�ɂ݂�_���x�z�@134
��l�́@�O�@�ߐ����̓��s�@135
��l�́@�O�@(��)�@�n�����x�̎d�g�@135
��l�́@�O�@(��)�@���K���Ɠ��l�Ԑ@136
��l�́@�O�@(��)�@1�@���㊯���i�×����`�ߐ������j�@136
��l�́@�O�@(��)�@2�@�l�㊯���i��Z�Z�Z�`�ꎵ�N�j�@136
��l�́@�O�@(�O)�@������@137
��l�́@�O�@(�l)�@�n���ƊԐ̊W�@142
��l�́@�O�@(��)�@�_���Љ�̎d�g�@143
��l�́@�O�@(��)�@1�@�S���̕��S�i�d�Łj�@144
��l�́@�O�@(��)�@2�@�Ԑؔԏ���l�̐E�����e�@144
��l�́@�O�@(��)�@3�@�������n�ɂ݂�k��n�̑����@145
��l�́@�O�@(��)�@4�@���{����̓��s�@146
��l�́@�O�@(��)�@4�@(1)�@���~�Ԑ@146
��l�́@�O�@(��)�@4�@(2)�@�m�O�Ԑ@147
��l�͎O(��)�s�R����3�t�@�v��������i�D���j�̊���@149
��l�́@�O�@(��)�@�s�R����3�t�@(3)�@�ʏ�Ԑ@149
��l�́@�O�@(��)�@�s�R����3�t�@(4)�@�嗢�Ԑ@150
��l�́@�O�@(�Z)�@������N�̌�V����@151
��l�́@�s�R����4�t�@�֏��ԁ@152 |
��l�́@�s�R����5�t�@�ʏ钩�O�@153
��l�́@�s�R����5�t(��)�n�����_���̕�炵154
��l�́s�R����5�t(��)�~�r�H���Ƃ��Ẵ\�e�c154
��l�́s�R����6�t�ʏ�̉u�a���Âɍv��������t156
��l�́@<�j��5>�@���{�ւ̐V�Q�m���E���@157
��l�́@<�j��5>�@(��)�@���K���́u���j�̓��v�@157
��l��<�j��5>(��Z)�w���z�x�ɂ݂铌�l�Ԑ̐l��159
��l�́@�s�R����7�t�@�������ω����@163
��l�́@�l�@�V��������̏��ȁ@163
��l�́@�l�@(��)�@���đD�̗��q�@163
��l�́@�l�@(��)�@<�j��6>�@�ꔪ�l�l�N��
�@�@���O���D���q�Ɋւ���u�����v�@164
��l�́@�l�@(��)�@1�@�Y�������l�ւ̑Ή��@165
��l�́@�l�@(��)�@2�@���D�ւ̎F���E���{�̑Ή��@166
��l�́@�l�@(��)�@3�@�y���[�̗��q�Ɠ��{�̊J���@167
��l�͎l(��)<�j��7>�z�[���卲��
�@�@�@������y���[�̔ᔻ168
��l�́@�l�@�s�R����8�t�@�q�u�����@168
��l�́@�l�@�s�R����8�t�@4�@�y���[�͑��Ɠ��l�Ԑ@169
��l�͎l�s�R����8�t<�j��8>
�@�@�@���u���D������t�ߔe��ĔV���L�v170
��l�́@�l�@�s�R����9�t�@��ɏ꒩���@170
��́@�ߑ�̓��s�@173
��́@��@�O�́E����̕ϊv�ː�����
�@�@�@�������ւ�"���ւ��"�@174
��́@��@�V���u���ꌧ�v�ƂȂ�@177
��́@��@(��)�@�u���A�l�̈قȂ�Љ�@177
��́@��@(��)�@�p�˒u���O��̍s���@178
��́@��@(�O)�@�y�n�����Ɖ���̍\���@181
��́@��@(�l)�@�������Ɣ[�ł̋����@184
��́@��@(��)�@�_������̌��R�����@185
��́@��@(�Z)�@�Y�ƁA�����ǐU��킸�@189
��́@�O�@��O�̌�ʎ���@192
��́@�O�@(��)�@�Ȍ�ʏ@192
��́@�O�@(��)�@��ʂ̑�v���u�y�֓S���v�@195
��́@�l�@���ꌧ���Ɛ푈�@197
��́@�l�@(��)�@�����푈�Ɓu������v�^���@197
��́@�l�@(��)�@�n�V�`�Ƀ^���O���@199
��́@�l�@(�O)�@�������x�ւ̒�R�@200
��́@�l�@(�l)�@�R���̐��̋����Ƒg�D�@202
��́@�l�@(��)�@�����푈���瑾���m�푈�ց@204
��́@�܁@���s�̋���@207
��́@�܁@(��)�@�ߑ�̋��玖��@207
��́@�܁@(��)�@1�@�p�˒u���ȑO�̋���@207
��́@�܁@(��)�@2�@�p�˒u���Ȍ�̋���@208
��́@�܁@(��)�@3�@�ߑ�̎Љ��@209
��́@�܁@(��)�@�w�Z����ƎЉ��@210
��́@�܁@(��)�@1�@���s�̊w�Z����@210
��́@�܁@(��)�@2�@���s�̎Љ��@213
��́@�Z�@����̖��|�^���Ɩ��O�@213
��́@�Z�@(��)�@���ꖯ�|�ւ̖ڊo�߁@217
��́@�Z�@(��)�@����h�邪�����u�����_���v219
��́@�Z�@(�O)�@���ꖯ�Y������ւ̑ٓ�220
��͘Z(�l)���c�A�܌��������݂�����̖���221
��́@���@���s�̖��������@224
��́@���@�O�́E���s�̖����M�ƍՎ��@224
��́@���@(��)�@������Ɩ咆�@224
��́@���@(��)�@�v���̍Վ��u�C�U�C�z�[�v�@225
��́@���@(�O)�@�Ì��̃~�[�~�����[�@228
��́@���@(�l)�@�������̐e�c���@229
��́@���@(��)�@��o���̌Î��G�C�T�[�@231
��́@���@(�Z)�@�����n��̎��q���@233
��́@���@(��)�@�����j�g�̓��F�@234
��́@���@���s�̈ږ��@238
��́@���@�\�͂��߂Ɂ\�@238
��́@���@(��)�@���嗢���̈ږ��@239
��́@���@(��)�@1�@���嗢���ɂ����鎚�ʁA
�@�@�@�����E�n��ʈږ��@239
��́@���@(��)�@2�@���嗢������̐��ږ��@240
��́@���@(��)�@���ʏ鑺�̈ږ��@241
��́@���@(��)�@1�@���ʏ鑺�ɂ����鎚�ʁA
�@�@�@�����E�n��ʈږ��@241
��́@���@(��)�@2�@���ʏ鑺����̐��ږ��@243
��́@���@(�O)�@�����~���̈ږ��@243
��́@���@(�O)�@1�@�����~���ɂ����鎚�ʁA
�@�@�����E�n��ʈږ���@243
��́@���@(�O)�@2�@�����~���̎��ʈږ��@245
��́@���@(�O)�@3�@���������̐��ږ��@246
��́@���@(�l)�@���m�O���̈ږ��@246
��́@���@(�l)�@1�@���m�O���̐�O�ږ��@246
��͔�(�l)2���m�O���̎��ʁA���E�n��ʈږ��@46
��́@���@(�l)�@3�@���m�O���̐��ږ��@247
��́@���@(��)�@���s�̈ږ��`�ԁ@248
��́@���@(��)�@1�@�n���C�ږ��@248
��́@���@(��)�@2�@�A�����J���O���ږ��@249
��́@���@(��)�@3�@�y���[�ږ��@250
��́@���@(��)�@4�@�u���W���ږ��@250
��́@���@(��)�@5�@�A���[���`���ږ��@252
��́@���@(��)�@6�@�t�B���s���ږ��@252
��́@���@(��)�@7�@�j���[�J���h�j�A�ږ��@253
��́@���@(��)�@8�@�{���r�A�ږ��@253
��́@���@(��)�@9�@��m�ږ��@254
��Z�́@���̓��s�@259
��Z�́@��@���e������͂��܂������@260
��Z�́@��@(��)�@�����̎�Ȋe��̏@261
��Z�́@��@(��)�@1�@�v�茘��@261
��Z�́@��@(��)�@2�@�R����@262
��Z�́@��@(��)�@3�@�u�쉮��@263
��Z�́@��@(��)�@4�@��u����@265
��Z�́@��@�s�R����1�t�@�m�O�����ʼn萶����
�@�@�@���c�����A�ւ̓��@266
��Z�͈�(��)�e�����e���ɂ��������o�����w�Z267
��Z�́@��@(��)�@1�@�v�茘�����w�Z�@267
��Z�́@��@(��)�@2�@�m�O�����w�Z�@268
��Z�́@��@(��)�@3�@��u�������w�Z�@268
��Z�́@��@(��)�@4�@�R�������w�Z�@269
��Z�͈�(��)5�u�쉮�����w�Z�E���c���Z270
��Z�́@��@(��)�@6�@�S�������w�Z�@270
��Z�́@��@(��)�@7�@�ʏ鏉���w�Z�@271
��Z�́@��@(��)�@8�@�D�z�����w�Z�@271
��Z�́@��@(��)�@9�@�嗢�����w�Z�@272
��Z�́@��@(��)�@10�@��鏉���w�Z�@272
��Z�́@��@(��)�@11�@�m�O�����w�Z�@273
��Z�́@��@(�O)�@�w�����v�Ɛ��̋���s���@273
��Z�́@�s�R����2�t�@���ƃK�����苳�ȏ��@274
��Z�́@��@���ꎐ�m��̐ݒu�ƒm�O�s�̒a���@275
��Z�́@��@(��)�@���ꎐ�m��@275
��Z�́@��@(��)�@�m�O�s�̒a���@276
��Z�́@��@(�O)�@�k�����n�悩��̋A���@277
��Z�́@�O�@���s�̐�㕜���@278
��Z�́@�O�@(��)�@���l�����̏I�풼��̏@278
��Z�́@�O�@(��)�@1�@�����~���@278
��Z�́@�O�@(��)�@2�@���m�O���@279
��Z�́@�O�@(��)�@3�@���ʏ鑺�@279
��Z�́@�O�@(��)�@4�@���嗢���@280
��Z�́@�O�@(��)�@��㕜�����̓��s�@282
��Z�́@�O�@(��)1�閧��n�iCSG�j�m�O�L�����v�̐ݒu282
��Z�́@�O�@�s�R����3�t�Đe�P�ψ���̐ݗ��@282
��Z�͎O�s�R����3�t2���s�ɂ�����
�@�@�@���R���{�Ɖ��ꖯ���{283
��Z�͎O�s�R����3�t3���s�ʼn萶����
�@�@�@����㖯���`�̐���284
��Z�́@�l�@�u�啽�m�̗v�v�ƂȂ�������@284
��Z�́@�l�@(��)�@������ݓ����@284
��Z�́@�l�@(��)�@�ČR�x�z���̉���̎������@286
��Z�́@�l�@(�O)�@�ČR�x�z���̊�n��Q�@287
��Z�́@�s�R����4�t�@�ČR�̍��������̎��ԁ@289
��Z�́@�܁@�c�����A�^���@289
��Z�͌�(��)���a���@�̂��Ƃւ́u�c�����A�^���v289
��Z�́@�s�R����5�t�@�x�g�i���푈�Ɖ���@290
��Z�́@�s�R����5�t�@(��)�@���A�O��̉���̏@291
��Z�́@�s�R����6�t�@�R�U���Ď����@291
��Z�́s�R����6�t(�O)���`���A�O��
�@�@�@���l�I�E�����I��291 |
��Z�́s�R����6�t(�O)1�����
�@�@�@�����{�{�y�̕����I��292
��Z�́@�s�R����6�t(�O)1(1)����̕����I������292
��Z�́@�s�R����6�t�@(�O)�@1�@(2)�@��Ƃ����@293
��Z�́s�R����6�t(�O)1(3)�@�W���[�i���X�g��
�@�@�@���𗬂Ɓu���������̑�����v�@294
��Z�́s�R����6�t(�O)2���s��
�@�@�@���߂���𗬂ƌ|�p����298
��Z�́s�R����6�t(�O)2(1)�@���p�Ƃ����̉���@298
��Z�́s�R����6�t(�O)2(2)�@���{���Y�Ƌv�����@298
��Z�́s�R����6�t(�O)2(3)�@���ᩖ��
�@�@�@�����������ւ̖ڊo�߁@300
��Z�́@�s�R����6�t�@(�O)�@3�@����o�g���l�E
�@�@�@���R�V�����ƕ��A���@301
��Z�́@�Z�@���A��̓��s�@304
��Z�́@�Z�@(��)�@�u����N�Ԋҁv���܂�@304
��Z�́@�Z�@(��)�@1�@��㏉�̍����Q���@304
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@�h�����@304
��Z�́@�Z�@(��)�@3�@���ꍑ��@305
��Z�́@�Z�@(��)�@�s���E�s���̐��ւ��@305
��Z�́@�Z�@(��)�@1�@����U���J���v��@306
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@���q���z���@306
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@(1)�@���s�̎��q���@306
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@(2)�@���s�̊�n�Ԋҁ@307
��Z�́@�Z�@(��)�@3�@���A�㏉�̒m���I���@307
��Z�́@�Z�@(��)�@4�@���ۊC�m������@307
��Z�́@�Z�@(�O)�@���}�g���i�ށ@308
��Z�́@�Z�@(�O)�@1�@��ʕ��@�̕ύX�@308
��Z�́@�Z�@(�O)�@2�@�ێ猧���a���@308
��Z�́@�Z�@(�O)�@3�@�����Ƌ��ȏ�����@309
��Z�́@�Z�@�s�R����7�t�@�O���������Ɂ@309
��Z�́@�Z�@(�l)�@���A��Z�N�@310
��Z�́@�Z�@(�l)�@1�@���̊ہE�N����@310
��Z�́@�Z�@(�l)�@2�@�C�M���́@310
��Z�́@�Z�@(��)�@���a���畽���Ɂ@311
��Z�́@�Z�@(�Z)�@���E�̃E�`�i�[���`�����@312
��Z�́@�Z�@(��)�@�����̓{�蕬�o�@312
��Z�́@�Z�@(��)�@1�@10�E21�������@312
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@��n�Ō������[�@313
��Z�́@�Z�@(��)�@3�@���a�̑b�v�����@313
��Z�́@�Z�@(��)�@4�@���ȏ���肪�ĔR�@313
��Z�́@�Z�@(��)�@���l�����̎�ȏo�����@314
��Z�́@�Z�@(��)�@1�@<��㎵��`����N>�@314
��Z�́@�Z�@(��)�@2�@<��㔪�Z�`����N>�@315
��Z�́@�Z�@(��)�@3�@<����Z�`���N>�@315
��Z�́@�Z�@(��)�@4�@<��Z�Z�Z�`�Z�ܔN>�@316
��Z�́@���@���s�̒a���@317
��Z�́@���@(��)�@�l�����������@317
��Z�́@���@(��)�@1�@�����̌o�߁@318
��Z�́@���@(��)�@2�@�u�V�s���v��v318
��Z�͎�(��)2�@(1)�@�l�����u����Ɖۑ�v319
��Z�͎�(��)�s�R����8�t�@���́u�����s�v320
��Z�͎�(��)�s�R����8�t�@(2)�@�n��ʂ̐���321
��Z�́@���@(��)�@�V�����s�@322
��Z�́@���@(��)�@�y���s�s�����́z�@322
��Z�́@���@(��)�@1�@�Y�Ɓ@322
��Z�́@���@(��)�@1�@(1)�@�ό��̐U���@322
��Z�͎�(��)�s�R����9�t�֏��Ԃ���Ȃ��I323
��Z�́@���@(��)�@�s�R����9�t�@(2)�_�Ƃ̐U��324
��Z�́@���@(��)�@�s�R����9�t�@(1)�Y�n�̎w��325
��Z�́@���@(��)�@�s�R����9�t�@(2)�_�Ɛl��325
��Z�͎��@(��)�@�s�R����9�t�@(3)�{�Y�Ƃ̐U��326
��Z�͎��@(��)�@�s�R����9�t�@(4)���Y�Ƃ̐U��326
��Z�͎��@(��)�@2�@�����E���N�@327
��Z�́@���@(��)�@2�@(1)�@���������@327
��Z�́@���@(��)�@2�@(2)�@����ҕ����@327
��Z�́@���@(��)�@2�@(3)�@��Q�ҕ����@328
��Z�́@���@(��)�@2�@(4)�@�Љ�����c��@328
��Z�́@���@(��)�@2�@(5)�@���N�Â���@328
��Z�͎�(��)�s�R����10�t�@�u���^�{�v�ގ��@329
��Z�͎�(��)�s�R����10�t(6)
�@�@�@���V���o�[�l�ރZ���^�[�ݗ�329
��Z�͎�(��)�@�s�R����10�t(7)
�@�@�@���s���ۈ珊�c��329
��Z�́@���@(��)�@3�@�����@330
��Z�́@���@(��)�@3�@(1)�@�������@330
��Z�́@���@(��)�@3�@(2)�@���E��Y�@331
��Z�́@���@(��)�@3�@(3)�@�l�ԍ���@331
��Z�́@���@(��)�@3�@(4)�@�s�j�ҏW���Ɓ@332
��Z�́@���@(��)�@3�@(5)�@�`���|�\�E�s���@332
��Z�́@���@(��)�@3�@(6)�@�V���K�[�z�[���@333
��Z�́@���@(��)�@4�@����̐U���@334
��Z�́@���@(��)�@4�@(1)�@�C�O�Z�����w���x�@334
��Z�́@���@(��)�@4�@(2)�@�u�ٓ��̓��v���{�@335
��Z�́@���@(��)�@5�@��ʁE�ʐM�@335
��Z�́@���@(��)�@5�@(1)�@���s�̓��H�@335
��Z�́@���@(��)�@5�@(2)�@�n�C�r�X�J�X�l�b�g�@335
��Z�͎�(��)5(3)�@�����E�����C���^�[�l�b�g336
��Z�́@���@(��)�@6�@���s�̎�ȃC�x���g336
��Z�͎�(��)6(1)�@���ӂ��ƃk���[�`�[����336
��Z�͎�(��)6(2)���b�u�n�[�t�}���\���@337
��Z�͎�(��)6(3)���ۃW���C�A�X�����@337
��Z�͎�(��)6(4)�o��Q�҃}���\��������338
��Z�́@���@(��)�@6�@(5)�@�`�������W�f�[�@338
��Z�͎�(��)7���s�c��@339
��Z�͎�(��)7�s�c��̎�Ȉӌ����E�錾��339
��Z�́@���@(��)�@8�@���̑��@340
��Z�͎�(��)8(1)�@���s���u�i�ύs���c�́v340
��Z�͎�(��)8(2)�@����䒬���o���s�s��340
��Z�́@���@(��)�@8�@(3)�@���㋣�Z���@341
��Z�́@���@(��)�@8�@(4)�@���s�̕s���e��341
��Z�́@���@(��)�@8�@(5)�@�I���@342
��Z�́@���@(��)�@�y�s�������z
��Z�́@���@(��)�@�y���c��c���z
��Z�́@���@(��)�@�y����c���z
��Z�́@���@(��)�@�y���m���z
���ʎ��M�@���l�����㔪�N���ڂ݂�@345
��@�L���ȁu�����v�̐��藧���u���~�Ԑv����
�@�@�@�@���u���~���v�ւ̕ϑJ�@346
��@(��)�@�y�Ôg�Ã����z���키���̍`���@346
��@(��)�@�y���J�����z���I�ȋZ�̒|�H���@347
��@(�O)�@�y�V�������z���j�̑��Ղ��c���@347
��@(�l)�@�y���v�����z���n�̗��̔������@348
��@(��)�@�y���~�����z���̒��S���j�ςށ@348
��@(�Z)�@�y��o�������z���������̌Â���349
��@(��)�@�y�Ɍ������z���Z�ȃV���N�i�X�̘[349
��@(��)�@�y����v�����z�{�\�����̐�i�n350
��@(��)�@�y�O�ԃ����z���R�����̌����ǂ���350
��(��Z)�y���ɕۃ����z�C�ӂ�O�ɉ���闢350
��@(�\��)�@�y�y�c�胀���z�}�[�X��
�@�@�@���m��ꂽ�����܂ǁ@351
��@(�\��)�@���ƒn��Ƃ��Ắy�V�J�z�@351
��@(�\�O)�@���~����̌i���n�y������z�@351
��@���m�O���̍��̂Ƒ����㔪�N�̉�ځ@352
��@(��)�@�Ĕ��i���Ȃ�j�E
�@�@�@���u�m�O�v�ƈ�씭�˓`���@352
��@(��)�@�v�����Q�w�ƍ֏��Ԃ̌�V����352
��@(�O)�@���H�̕ϑJ�@354
��@(�l)�@�w�Z�̎n�܂�ƏI��O��̋��玖��355
��@(��)�@�Ԑؔԏ��Ƒ����㔪�N�@356
�O�@���ʏ鑺���㔪�N���ڂ݂�@358
�O�@(��)�@���ʏ鑺�̑O�j�ƊԐ̋N���@358
�O�@(��)�@�����������㑺���@359
�O(�O)���ʏ鑺���̒��ŋL����
�@�@�@���c���ۓI�Șb��@359
�O�@(�l)�@�ʏ鑺�o�g�A��O�̐����Ɓ@362
�l�@�嗢���̏W�����Ǝ����@364
�l�@(��)�@�n�����x�Ɣ_���̂��炵�@364
�l�@(��)�@�W���̓����@366
�l�@(�O)�@���c��ٕ��@367
�����@370
���͋@�ւ���ы��͎ҁ@381
�ҏW�ψ��E���ψ��E�����ǖ���@382
�ҏW��L�@383 |
���A���̔N�A���c�M�j, �Ɠc����,�����m��Y�ďC�u�Ĕ�(�₫�͂�)�̊��w : ���Ĕ��Ƃ́v���u�v���t�o�Łv���犧�s�����B (�n�������C�u�����[ ; 17)
���A���̔N�A���c�������u���a���q��w�����j���� (14) p.24�`36�v�Ɂu�u�ܒ��`�v�̓`�{�ɂ���(����1)��뎛���w�ܒ���l�G���`�x���߂����āv�\����B�@�@
���A���̔N�A���c�������u���a���q��w��w�@�����@�\�����ȋI�v 20 2011 p.168�`160�v�Ɂu��뎛���w�ܒ���l�G���`�x�̎����ƊG�ɂ��āv�\����B
���A���̔N�A�������� ����C��w�Љ�Ȋw�������ҁu�Љ�Ȋw�N�� = The Annual bulletin of social science (45) p.37�`46�v�Ɂu�P�[�X�X�^�f�B:��p�̃u�����h�u�G�C�T�[�v�v�\����B |
| 2012 |
24 |
�E |
�P���Q�T���`�P���P�X���A���ꌧ�������فE���p�قɉ����āu�����Ƒܒ���l�W
: �G�C�T�[�̋N�������ǂ� : ���s�E�h���@�ю��J�n400�N�L�O�v�W���J�����B
�P���A��������, �c���ъďC�E�x�R���ۑ�w���A�W�A�𗬌�����ҁu���A�W�A�n��̗��j�����ƌ���Љ� : �x�R���ۑ�w�E�ɔJ�t�͑�w�����_���W�v���u�j���[�v���犧�s�����B
|
���A�W�A�̌𗬂Ɗ� ���{�C�w���x�[�X�ɂ���
�@���n��ۑ�ւ̐V���ȓW�J / �k��F��
���A�W�A�n��ɂ����鐅���ۑS�̂��߂̊����犈��/ �����[�q
���ۋ�������ɂ������w�̖��� / �˓c�t�v
���A�W�A�̌𗬂Ɨ��j�E���� �݊C���������
�@�@���Ñ���{�̑Ο݊C���� / ������
����̋ߐ��W���`���Ɋւ��u����v�тɂ���/�Y�R����, �F�J����
�_�����Ñ㐒���瑭�I�N�� / �c����
�}��]����I����j�^���� / ���Z�Q
��Ӑ��O�����ᒆ�I���E�^���� / ���M��
�`�������Ηɓ��I���� / �m�^�`
�ɓ�������[�V�Ί펞��l�ސ����ώ@ / ������
����"��������"�l�ۖ����Α��l�� / ���Z�Q, ���G�k
����"�@��"�̌đ��֖��l�@ / ���ʌN
�_�O�������W�I��K�i / ����[�C�c]
�ɑ��݊C�����I�O��� / �c��
|
���A�W�A�̌𗬂Ɗό� ���{�ɂ����鍑�ۊό���
�@�@���W�J�ƒn��̉ۑ� / �������K
���A�W�A�ɂ�����ό��v���Ɨ��̖L�����̌��� / ���V�`�e
���ۊό��ɂ�����ٕ��������ƌ𗬂ɂ��Ă̍l�@ / ����q
���E��Y�E�܉ӎR�n��̊ό��̌���Ɖۑ� / �����x�v
���E�C�����V���W�Α�A�I�[�� / �ӏt�R, �ѐ�
�؊ӓ��{�o�ϔ��W��A���V / ��
�����ɔJ���E������Y�ی엘�p���� / ���r�E
����Ԉʎ��p�I�ɔJ���C��s���V�����͕]�� /
�@�@�� ���P, ���G, ��F��, ����
���A�W�A�̌𗬂ƎY�ƁE�o��
�@�@���n�掑���̊��p�ƌ𗬁E�A�g / ��������
�������n��Ƃ̌o�c�����`���Ɠ��k�n��̎Y�ƐU�� / ������
�o�ϊ�@��̓��A�W�A�o�ς̉ۑ�ƓW�] / �吼�ꐬ
��p�ւ̓��n�h����Ɛi�o����̌��� / �֓��q�q
�k���n���ɂ���������f�Ղ̕ω��Ə������� / Bogdan Pavliy |
�Q���A����T���E�������i ���u���ꌧ������U�� : ���������A�邩���ԁA�G�C�T�[�A�A���܂œ썑�E�I�L�i���̖��͂��悭�킩�錈���!�v���u
KADOKAWA�v���犧�s�����B�@ (�V�l������ ; ��-7-1)
�Q���A�����N�炪�u���^�v�e�B�q�A�J : ���É���w��w�@���w�����ȋ��猤�����i���N�� 6 p.177-180�v�Ɂu�����|�\�ɂ�����`���Ə@���ϔO�̍Đ��Y�Ɋւ��钲�������v���W�F�N�g
: ���ꌧ�́u�G�C�T�[�v�̎��Ⴉ��v�\����B�@�iIRDB�j
�Q���A����K�ꂪ�u���A�W�A���������� = Journal of East Asian�@ 5�@p371-388�v�Ɂu�����ɂ�����W���`���ߒ��̈�l�@ : �ÉF�����̐��n�ƍ��J������Ƃ��āv�\����B
�Q���A�u����n���w����@�� 55 ���v�Ɂu�� 1 �� �ΊD��n��V���|�W�E���i�j�ΊD��n���m��ŏ��̈���v�Ƒ肵���V���|�W�E���̓��e�����B
�Q���Q�P���`�R���P�P�����A���ꌧ�������������Z���^�[�ɉ����āu���ꌧ�L�`������(�l�Î���)�w��L�O �É�n���L�ˁE���c���L�ˏo�y�i�W�v���J�����B
�Q���A���ꌧ�������������Z���^�[�ҁu���ꌧ�L�`������(�l�Î���)�w��L�O �É�n���L�ˁE���c���L�ˏo�y�i�W�v���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s�����B
�o�c�e
|
�����������^�����琔��N�O�̐�j����A���ꏔ���Ɛ擇�����ɂ́A���ꂼ�ꃋ�[�c�̈قȂ镶���������݂��Ă��܂����B���̂��сA�����̕��������ے������Ղƌ�����u�É�n���L�ˁv�y�сu���c���L�ˁv����̏o�y�i���A���ꌧ�̗L�`�������i�l�Î����j�Ƃ��Ă͂��߂Ďw�肳��邱�ƂɂȂ�܂����B������L�O���ē��Z���^�[�ł́A�w�肳�ꂽ��Ȉ╨�𒆐S�Ƃ�����W���J�Â��邱�Ƃɂ������܂����B�^���̓��A����s�ΐ�ɏ��݂���É�n���L�˂́A���ꎩ���ԓ����݂ɔ����L�^�ۑ������Ƃ��āA1983�i���a
58�j�E1984�i���a 59�j�N�ɔ��@�������s���A�S��̒G���Z���Ղ�F�Ղ̂ق��A�����̔p����ł���L�˂��m�F����܂����B�܂��A����ɔ��������̓y���Ί�A�L�E�����i���o�y���Ă��܂��B��Ղ͒�����̊J���ɂ��ꕔ���c���݂̂ƂȂ�܂������A���̐��ʂ͉���ɂ�����ꕶ���㒆�`����̕����𖾂炩�ɂ��A�����̂��炵�����ɓ`���Ă��܂��B�^���ɁA���c���L�˂͔��d�R�����̒|�x���g�Ɗԓ��ɏ��݂����ՂŁA1984�i���a59�j�E1985�i���a 60�j�N�ɓy�n���njv��ɔ����͈͊m�F�������s���܂����B���̌��ʁA������F�ՁA�a���\�����o�����ƂƂ��ɁA���c�����y���Ί�A�L�E�����i�ȂǁA�擇�������L�̈╨�������o�y���Ă��܂��B���̔N��́A���ː��Y�f�N�㑪��ɂ��A������� 3,800 �N�O�Ƃ����l�������Ă��܂��B���̗���Ղ̒����ɂ��A����̐�j���㌤���͔���I�ɐi�����A���̌�������̌������ʂݏo���Ă��܂��B�@�܂��A����̓W���ł́A�قȂ镶���̏���r�ł���悤�A����Ղ̈╨���@�y��A�A�Ί�E�ΐ��i�A�B���E�L���i�̂R�̃e�[�}�ɕ����A��ʂ��ƂɓW�����邱�Ƃ����݂܂����B�^�@���̋@��ɁA�{���̐�j�����ɂ��Ă�藝����[�߂Ă��������ƂƂ��ɁA���̖��͂≿�l���ĔF�����Ă���������K���ł��B�^���� 24 �N 2 �� 21�� �@���ꌧ�������������Z���^�[�@�����@���d |
�R���A�����M�v���u���s�Y�Ƒ�w�_�W. �l���Ȋw�n�� 45 p.1-34 �v�Ɂu�^���������Ɖ���j�w�̌`���v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�g�Ɗԉi�g���������ꖯ�ԕ��|�w��ψ���ҁu�������ꖯ�ԕ��|�w = The science of Amami-Okinawa folk literature (11) p.90-97�v�Ɂu�×����̃`�a�E�� (�V���|�W�E�� �V���[�}�j�Y���Ɛ_�� ; �e�p�l���X�g����N)�v�\����B
�R���A���ь��],���эK�j���u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (37) p.56-58�v�Ɂu�������\�v�| ����{���{���̉P���� : ���̓����ƌ��݂̓`�� (��25����u�̋�(�ӂ邳��)��������l�X�v(2011����)�v�\����B
|
���c���F��ƃV�k�O�́u�E�V���f�[�N�v�@�@���� �����@ p.25-28
����|�x���F��Ǝ�q�Ղ́u�X���d�������v�@�떓 �b��@p.28-31
��Ђ��������ւ̎v��Ɩ����|�\�̕����@���c �O�P�@p.31-35
���_ (��25����j�@�@�떓 �b��,���� ��,���� ���� �� p.37-39
����̖����|�\�̕��ށ@�v���c �W p.40-47
�������\�v�| ����\�̓`������ɂ����鉉�Z�Ɋւ��錾���ɂ��Ă̍l�@�@�ēc �^�� p.50-52
�������\�v�| �u�[�^���̗w�c�@���� : �|�������Ɛ肢�̏����@�ɖ� �`���@p.54-56
�������\�v�| ����{���{���̉P���� : ���̓����ƌ��݂̓`�� ���� ���],���� �K�j�@ p.56-58 |
�R���A��ؖ����ҁu���{�Ñ�̒n��Љ�Ǝ����v���u�g��O���فv���犧�s�����B�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007509399
|
���{�Ñ�̒n��Љ� �g�����߂���\���I�l�@/���Ï��I
�Ñ�ɂ�����n��Љ�Ǝ�H�Ɛ��Y/���Ώ[
�u���ɉ���w�u����g�䔄�v�̎��� / �֘a�F
�����ߒ��W�g���Ə������ߐ�/�r��G�K
�Ñ�Љ�Ɣn / �����
�n��Љ�ɂ�����]�E�S�����̑O�� / ����쎡
�Ñ��썑�̍�����ʘH�Ɋւ����l�@ / �쌴�G�v
�Ñ���{�̎��� �J�}�h���猟�o���ꂽ�{�b��̚�ɂ���/���c�T�� |
�Ñ�k�C���ɂ����鑾���m���E�����𗬂̎��� / �����h�I
�H�c��Ə鐧 / �F�J���j
���H�ɂ�����Ñ���̏I���Ɓu�فv�̌`�� / ����m�u
�������ȑO / �r�c�Ďj
�V���\�ܔN�̔��l�̒��v���߂����� / �i�R�C��
�������㒆���̓�ؐl�P���������߂����� / �R������
�L�J�C�K�V�}�C��Ɠ��v�f�� / �����C
�E |
�R���A�ѓc����݂����ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ� : ���ꌧ���|�p��w���y�w������ (13) p.53-68�v�Ɂu�O���̂̓`���Ɖ��߂ɂ���:�|�x�����@�@�� �㐨�����q���̌�肩��v�\����B
�R���A���{�ҁu�����E����̌|�\ : ���̌p���Ɛ��E�֑����v���u�ʗ��Ёv���犧�s�����B�@(������w �l�̈ړ���21���I�̃O���[�o���Љ� ; 6)
|
��P���@�V���|�W�E���[�C�O�ɂ�����u����̌|�\�v�̌���ƓW�]
�@�@�i�u�l�̈ړ��ƌ|�p�v�V���|�W�E�������[�x�ԑg�E�剉�҂̏Љ�G�u�l�̈ړ��ƌ|�p�v�V���|�W�E���E�f�B�X�J�b�V����
��Q���@���O�E�C�O�ɂ�����u����̌|�\�v�Ɣ��M�n�E����
�@�@�@�T���t�����V�X�R�ɂ����问�����x�̌���E�ۑ�E�W�]�G�A�����J�ɂ����鉫��|�\�̌���Ɖۑ�G
�@�@�@���O�ɂ����鉫��|�\�����̌���E�ۑ�E�W�]�[��������u�����|�\�����v���ɁG
�@�@�@���n��ɂ����鉫��̌|�\�O���v������Ƒ������ۃ��R�[�h�G�C���^�����[�F�C�O�ɂ�����g����̌|�\�h�̌���ƓW�]
��R���@����̌|�\�ɂ݂�l�̈ړ�
�@�@�ߐ������l���ٍ��Ŋς��|�\�G�g�x�ɂ݂铹�s�|�G����̑D�E�q�C�E���J�[���b�Ɖ̗w����G�ږ��E�o�҂��Ɖ���̌|�\�j |
�R���A�@<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@���ҁu���ꌤ���m�[�g: �s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@��
(21) �v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@�����F���ꌧ���}���فF1005987779
|
���J�u���� �Ñ���{�ƒ��N�A�����ė��� : ����(�Α��A�U��)�̓W�J ���� ���V p.1-12
���������̌������� : ����O�ǁu���ꌧ���@�������v�̏��q���� ���c ���j
p.13-31
�����l�Y�̗��� : �w�����l�Y ���꒲�����L�x��ǂ� ���� ���� p.46-32
�������A������q���w������������x ���� ���� p.50-47 |
|
�{��w�@���q��w�L���X�g�����������������s����<��������>�쓇�ɂ����閯���Ə@��
�ҁu���ꌤ���m�[�g :
�@�@�@�@�@ �s���������t�쓇�ɂ����閯���Ə@�� (1�`18) �v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
���� |
���s�N�� |
�_���� |
�����R�[�h |
| 1 |
(1)
3 7p |
1992-02 |
�͂��߂� ���� ���V�^�� �{�w����
���j�����Ɠ쓇-��N�x�����˂�- �啽 ���^�� �{�w������
�M�ё����m���ו��ɂ�����Љ�i���Ɛl��
����-�������������̐l�ފw�I�����ɂނ���- �㓡 ���^�� �{�w������
������w���d�R�|�\������́w���������x �R�� ����^��
�z�z�����A�\�A�}�A�����E������̋L�^ |
1002959185 |
| 2 |
32p |
1993-02 |
����{���k���̍j���� ���� �����^�� �{�w������
������J�Âɂ������� ���� ���V�^�� �{�w����
���������ƍ��� �t�F���E�E�����E���� -�ߐ� ���{�Ɨ���- �e�r �E�v�^�� �{�w����
�ߐ������̗� ���_-�吴������ƑI���ʏ�- ���c �I��u�^�� �{�w���� |
1002811485 |
| 3 |
43p |
1994-02 |
�ߐ������̗���߂����� ���_���̓� -������ƎF����- ���c �I��u�^�� �{�w����
�يE�֓��錮�Ƃ��Ă̒ނ�j �㓡 ���^�� �{�w������
���B�̕搧-�u���l�v�̎Љ�- �啽 ���^�� �{�w������
��p���~���̒����L�^ ���� �����^�� �{�w������ |
1002959201 |
| 4 |
38p |
1995-03 |
����̋������� ���� �����^�� 1
�ߐ��쓇�̋Q�[ �e�r �E�v�^�� 7
�ߐ������ɂ������ ���_���̎O -�R���Ɠ����v- ���c �I��u�^�� 17
���������E������� �啽 ���^�� 26
Okinawa's Encounter with�@Christianity Richard*Klecan�^�� 1�i38�j
|
1002959227 |
| 5 |
23p |
1996-03 |
���S������ǂ�-����g�x�� �m�[�g1- ���� ���V�^�� p1-14
�t�����X�ɂ����鉫��̏@���̏Љ� ��� ���^�� p15-18
�u�������v�̗��s �e�r �E�v�^�� p19-22 |
1003077730 |
| 6 |
39p |
1997-03 |
�����ꂽ�J(�����O�ܔԂ�ʒꂷ�����) ����g�x�� �m�[�g2 ���� ���V�^�� �{�w����
�Ñ㍑�ƂƓ쓇 �啽 ���^�� �{�w����
�ߐ������ɂ������̐��x ��b�I�l�@ ���c �I��u�^�� �{�w����
���J�V���|�W�E���u�쓇�̐_�ϔO�Ɛ��E�ρv(���^���������̘^)
�@�@���O�� ��P ���_ ���� ���c �����v�^�k ���� ���V�^�i��
�@���ʏ钩�O�i���܂��������傤����j���n�삵���g�x�͒��O�̌ܔԂƂ��A�u���S�����i���イ���˂���j�v
�@�@�@�u�����q�i�߂��邵���j�v�u�F�s�V���i���������̂܂��j�v�u�������i����Ȃ��̂��邢�j�v�u�G���i�ɂǂ��Ă������j�v
|
1003236708 |
| 7 |
45p |
1998-03 |
�쓇�̊�w�����ƒÌ����̖���(��)
�@�@��-���K�_�ƃJ�[�̗R��杂𒆐S��- �R�c ���� �����w����
�쓇�̕��������ƍ^�����b �㓡 �� �{�w����
�����q��ǂ�(�V�����S������ӎ�)-����g�x��m�[�g3- �������V �{�w����
�ߐ������̗� ���_���̎l-��ʂ̎����ƕ�- ���c �I��u �{�w����
���] �R�����꒘�w����̖������Ƃ܂��Ȃ�-�t�[�t�_(���D)�̌���-�x �啽��
�{�w����
|
1002756292 |
| 8 |
44p |
1999-03 |
���d�R��l����꜖̍�(����ނ��[�j�ɂ��� �R�� ����^�� ������w����
�ߐ������ɂ����铂�D�̑��}�̐��@�`�v�ē��̎���𒆐S�Ɂ`
�@�@���[�V �H�l�^�� ���ꌧ�����U����j���ҏW��
���J�V���|�W�E�� �쓇�̌|�\�ƐM�E�V�}(�W��)�̃R�X�����W�[
�@�@�� -�������V���A���a���W���̎���- ���R ���G�^��u�� ���c �����v�^
�@�@���p�l���X�g �R�` �F�v�^�J��A ���� ���V�^�R�����e�[�^ �㓡 ���^�i��
�ߐ������̗� ���_���̌� -�I���ʏ����{�Ƌv�đ��- ���c �I��u�^�� �{�w����
|
1003499348 |
| 9 |
50p |
2000-03 |
�V���|�W�E���u�쓇�̗��j�ƕ����v�J�Âɂ������� �啽 ���^�� �{�w����
���d�R�̉̂Ɨx�� �R�� ����^�� ������w����
�g�x��u�G���v�m�[�g -�B���ꂽ�A�}�I�G��- ���� ���V�^�� �{�w����
���] �R�����꒘�w�Ñ���{�Ɠ쓇�̌𗬁x �啽 ���^�� �{�w����
����̗��j�F���Ɨ��j����ɂ��� �V�� �b���^�� �{�w��w�@�C�m��N
|
1002872396 |
| 10 |
51p |
2001-03 |
�V���|�W�E�� �^�u����E�|�x���̓`��-�_�b�E�`���E�|�\-�v �떓 �b�� ���
�וv�^����
�� ����|�x���̎�q��Ղ̓`�� �@�^�R�����g�^���^����
�����l���B�����S���l�Y���ꌏ �e�r �E�v�^��
�ߐ������̗� ���_�Z �擇�����̎���(�Ƃ��ނ�) ���c �I��u�^��
����Љ��O�}�̓}���ɂ��� ���� �����^�� |
1003627344 |
| 11 |
45p |
2002-03 |
�L���X�g������������ ���J�u���� �u����̏����̒n�ʂƖ����v ��� ���v
�g�O�`�t�@�C�����O�V�c�e�����j�^�����O�J�n�Ɋ� �n�� �P��(����}�C�N���Z���^�[)
�n���P������̂���-���������A����A�����Đ��E- ���� ����
�ҏW��L |
1003770110 |
| 12 |
40p |
2003-03 |
�u�{�y���A�̈Ӗ��[���A�O�\�N�ڂ̉���v �{�������u�q]
�u�חF�`���Ɖ���v ��Î�[�q]
�ߐ������̗� ���_���̎� �I���ʏ��̍Ō�[�čl ���c�I��u
����̎q�ǂ��̋K�������߂����ā[�c�t���ƕۈ牀�̔�r �Óc�`���j
�ҏW��L�@�@�@ |
1003886015 |
| 13 |
25p |
��2003-03
2004-03 |
�� ���̉F���[�������w�̒n���[ ���� ���V�^[��]
�j �u�{���h�P�����v�ɂ��� ���� �����^[��]
�O �{���h�P�Ɋւ���o�� ���� �����^[��]�@
�@�@��2003-03�@2004-03�@�@�m�F���K�v�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�Q�V�@�ۍ� |
1004018782 |
| 14 |
38p |
2005-03 |
�l�Ԃ̒a���Ǝ�-�r�ԓ�����̔��M- ���� ���V
���J������ �������������ƒ��N����(1) �g�� ����
�������������ƒ��N����(2)
�@�@��-�w�����낳�����x�ɂ݂�n��I�l�b�g���[�N�̈Ӗ��������- �� ����
|
1004212708 |
| 15 |
29p |
2006-03 |
�u����u�搧����݂问������
�@�@��-����E�Ƒ��悩�痮�������̎����ɂ��܂�v�̊J�Âɂ��� �啽��
�� �����̋ߐ����T��-�l�Êw�ƌ`���l�ފw����̃A�v���[�` ��� ����
�O �j���C�J�i�C�̉��{-�Y�Y�悤�ǂꂩ��݂��p�c�����Ƒ��z�q�v�z ���� �i
Le Royaume de Ryukyu et la relation internationale en Asie-l'e poque
�@�@��de grand commerce de Ryukyu- Naoki Imabayashi
|
1004481683 |
| 16 |
. |
2007-03 |
���d�R�|�\�̖���
�@�@��--������w���d�R�|�\������l�\�N�̕��݂��� �R�� ���� p.1�`7
�ߐ������ɂ������--���_(8)��w�I���ƒn����n ���c �I��u p.8�`25
���@�����P�Ɨ�����w�������������N���u
�@�@��--��㗮�������������t�� ���� ���� p.44�`31
���҂Ƃ̋��ɂ̂킩��--��������̚L������(�����́r ���� ���q p.30�`26
|
. |
| 17 |
. |
2008-03 |
�Ñ�E�����̃L�J�C�K�V�}�Ɗ�E���@�@�i�R �C�� p.1�`24
�����i���w�����̉����ƃO�X�N�x�@�@�啽 �� p.25�`32
�u���������v�j�ɂ�����u�����v
�@�@��--�u���������v�j�����Ɋւ����b�I�l�@�@���c ���j p.33�`48
�Y�Y�悤�ǂ�̉Α���--����Ɨ���(����) ���� ���V p.49�`64
���G--�������A�Đ����A����Ƃ�
�@�@��--�������F�w�y���Ȃ���G�x�ɂ悹�ā@�@��� ����Y p.65�`72
���@�����P���a�S�N���}���ā@�@���� ���� p.88�`79
��ւ̂܂Ȃ���--���w�ƃg�|�X
�@�@��(�I���G���^���Y���̒E�C�f�I���M�[) ����:�v�l�̘A���@�@��� �� p.78�`74 |
. |
| 18 |
. |
2009-03 |
��������������U��Ԃ�--���܁Z�N��`���Z�N��𒆐S�Ɂ@�@�씨 �b p.1�`24
�������������j�̃i���e�B���@�@���c ���j p.25�`40
�ČR����������ɂ�����t�B���s���l�ւ̂܂Ȃ���
�@�@��--�����N�Ԃ̐V���L�������ƂɁ@����M p.41�`59
�{�錧�ېX���̋������X�u�Ȃ�ł���v�̌���Ɖ\���ɂ���
�@�@��--����{���k���̋������X�Ɣ�r���Ȃ���@�@�y�� �� 2009-03 p.77�`60
�����ւ̏o���_--��ւ̂܂Ȃ����@�@��� �� p.82�`78
|
. |
| 19 |
. |
2010-03 |
���] �䉮���ƕv���w��㉫��̐��_�Ǝv�z�x
�@�@���t(���Ώ��X�A2009�N�A278��)�@���� ���� p.1�`6
���] �ߓ�����Y�w�ߑ㉫��ɂ����鋳��ƍ��������x
�@�@��(�k�C����w�o�ʼn�A2006�N)�@���c���j p.7�`14
����^�C���X�u�����v��ޔǕҁw���ꂪ�����łȂ��Ȃ���x��ǂ�Ł@�y�� ��
p.15�`18
���q�����̏ꍇ--��ւ̂܂Ȃ���(3)�@��� �� p.24�`20
���Î��x�z���̗����j���̓]��--���ƁE�Љ�E���O�@�@�L���R�a�s p.37�`25
���Ɨ����l--�ߐ���B�̎R���Ɨ����̂������@���� �O�� p.48�`38
���J������u���������v�ɂ��ā@�䕔 ���j p.74�`49 |
.. |
| 20 |
. |
2011-03 |
���] ���c�v���w���������j1609�` 1872�N�x�@�@���c���j p.1�`7
�쓇�ɂ����閯���Ə@����Z���N�V���|�W�E�� ����A�����A���
�@�@��--����̉ߋ��E���݁E�����@p.8�`69
�������� �{��--�v���o�����@�@���Y ���q p.8�`17
���J�u�� �����̐Ԃ����{�Ɣ�������
�@�@��--�����E����j�̃p���_�C�����������@���� �i p.18�`37
���J�u�� �w�����낳�����x�p�Y��`�����@�� ���� p.38�`59
���J�u�� ���������Ɗ؍������@�g�� �P�j p.60�`69
����̋L�������p��--�ΐ�W�F�b�g�@�ė����́@�@���� ���� p.94�`90
����{���k���ɂ����闬�ʃV�X�e���ێ��Ɋւ��錤���@�@�@�y�� �� p.89�`72 |
. |
| 21 |
. |
2012-03 |
���J�u���� �Ñ���{�ƒ��N�A�����ė��� : ����(�Α��A�U��)�̓W�J ���� ���V p.1-12
���������̌������� : ����O�ǁu���ꌧ���@�������v�̏��q���� ���c ���j
p.13-31
�����l�Y�̗��� : �w�����l�Y ���꒲�����L�x��ǂ� ���� ���� p.46-32
�������A������q���w������������x ���� ���� p.50-47 |
. |
|
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu�f�ڎ� ���ꌧ���|�p��w�I�v(20)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
�ʓߔe���g�w�� �����x�ɂ��� : �����ƊG��̂͂��܂� ���я��q p.1-12,�}����3p
<��> �ʓߔe���g �w�� �����x �^���y�ѕ�������@ �_�����a p.13-15
����̓`���F�Ɋւ��钲������ : ����̐F�Ƃ́A���̎Y�Ɖ���ڎw���� �k���`�T,���쒩�a,��闺�q�A�X�� �G�� p.17-34
���x��u���ԁv�̐��� : ���̂̎��_���� �J �O p.35-43
���R�����̐��U : ���{�̖��w�����Ƃ߂� �O�� �킩�� p.45-67
���ꌧ�̒��w�Z�E���Z�ɂ�����u�{�ǒ���y�v�̎��H�ƕ�����
�@�@��(4)���w�Z�E���Z���y�S�����@�ւ̃A���P�[�g�����Ɋ�Â��� ��R�L�q
p.69-87
�i���h�ɂ����郊�X�g�̌������]�� ��R�T�q p.89-104
���^�_�ϗ��w�Ƃ��̔w�i�I���E�� : ������̗ϗ��w�I�T���̂��߂� ��� �M��
p.105-121
���������^���@�m�� ���c�_�C���M���� ������M p.123-139 |
�R���A�@����w���ꕶ���������ҁu���ꕶ������ 38�v���u�@����w���ꕶ���������v���犧�s�����B
�@�@�@580p �@�@�����F��㊌����}���فF1006621187
|
���������̌n�}�Ċ��_�Ɓw�����j�k�x�̔w�i : ���������j�c���̊�b�I��� / �|�퐭��
�n�}���Ȃ� : ����W���̎m���n�咆�ɂ��n�}�쐬�̎��� / �����W
�V��̕ω��Ə����_�� : �Ί_���약�̎��� / �V��^��
����������ܐ��I�����ȍ~�̋E�����I�ȓ����Ɖ���V�� : ���l�g�D�Ɖ���V��̕ϑJ
/ �^��uꢎq
��������N���E��v����
��l�̂������́u�s�`���v�Ɓu�ᔽ�v / �V�얾
�Ɋo����z���l���E�Љ�Ȋw : ���Ô������̐��݂̍�悤 / ���쐭��
���Ô���N�̂��� / �V�萷��
�u�����Ґ��v�̊l����ڎw���� / �䉮���ƕv
����ɗ��� / ����/����
���f�B�J���ȉ����<������> : ���܂���C���e�O���e�B�Ɖ�����j�v���W�F�N�g
/ ��������
�w��ւ̎p�� : ���Ô�����w<�ߑ㉫��>�̒m���l-���ܑS���̋O�Ձx����w�� / ���V����
�u���������v�_�Ɨ��j�ӎ� / �嗢�m�q
�ČR��̊��ɂ�����u�����v/�u�O���l�v�Ƃ�����̕Ґ��ƐA���n���� : �哌�����̌n������
/ �y��q�`
�z���҂����̕��A�^�� : ���܁Z�N��O���ɂ�����ݓ��{����l�w���̑g�D�ƈӎ� / ��糏G��
������w�ɂ�����\���ƌ��{ : ���܁Z�N��w������w�w���V���x�𒆐S�� /
�䕔��
�����v�z�j : ���Ô����ǂ݂Ȃ��� / �V���v |
�R���A�����P�ꂪ�u�������j���������ٌ����� = Bulletin of the National Museum of Japanese History 174 p.119-132�v�Ɂu�����ʂɂ�����D�Ǝ���M�v�\����B �@�@�iIRDB�j
|
�͂��߂Ɂ\�D��ƃI�i���_�\
1 �D��H�ƑD��E�ؗ�̍��J�Ǝ��@ |
2 �E����ɂ����f
3 �D�ƃI�i���_�Ǝ��� |
4 �q�C�Ə��_�A�D�̂Ǝ���@�[�����E�����̖�����r�Ɍ����ā[
�E |
�R���A�����M��,�����G�q�����m��w�X�|�[�c���N�Ȋw�ψ���ҁu�X�|�[�c���N�Ȋw�I�v
(9) p.63-67�v�Ɂu�`���|�\�ɂ�����\���̓��� : ���{���x�u�O�ԙՁv�Ɩ������x�u�G�C�T�[�v�̔�r�v�\����B
�R���A�����v�q���@����w���ꕶ���������ďC �u�C�̎�l���ꋙ�� : �����E�~���`���̗��j�Ɛ������v���u���㏑�فv���犧�s����B �@(�p���E�����m�� )�@�@�@�@�@238p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007222514
|
�����ȏM�ő�m���삯�߂���E�~���`���B�E�s�ȊC�m�����͑�^���@�u�A�M���[�v���J�������B���ꋙ�Ƃ̐��藧���ƁA�������̓Ǝ��Ȍo�ϊ����u�J�~�A�`�l�[�v�u���^�N�T�[�v���A���J�ȃt�B�[���h���[�N�Ŗ��炩�ɂ���B |
|
���� �������ƂƊC�l�̍Ȃ����̌o�ϊ���
���� �Ñw�����W���̌`���Ɓu��(�W���[)�v�W�c�̋@�\
��O�� ���������̂Ƃ��Ă̖�(�W���[)�ƊC�̍��J |
��l�� ���d�R�ɂ����鎅�������̏o���ƈڏZ
��� ���d�R���Ƃ̔��W�Ɓu�ق��q���v�̌`��
�E |
�R���A������w�ҁu���Ղւ̌����́v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@
�@�@�@(���炩����̊w�Ǝv�z ; 4�j�@�@351p�@�����F���ꌧ���}���فF1007218330
|
�����E����Ɓu������v ���� �Ђ�݁^�� 10-21
�g�x�ւ̂����Ȃ� ��� �{�^�� 22-37
�������E���}�g�R�g�o�̗����� ���� �֎q�^�� 38-49
�̌�������w �m�̉c�݂������ō\������y���� ���� �m��^�� 50-63
�Q��q�͂ł�����[�Ȃ���ǁ[ ���V �g���^�� 64-79
�q�g�͂Ȃ��A�����Ă��܂��̂�? �v�� �T�́^�� 82-95
�����Ȃ����ł̎x������݂����Ȃ��� �{�� �^�^�� 96-107
�z��ҊԂ̖\�͂��Ȃ������߂� �c�� ����^�� 108-121
�u�炵���v�̑n�o�ƍٗʐ������i�ϋK���̉ۑ� ���� �q�q�^�� 122-133
�Z��̓d�C�G�l���M�[�ɂ��
�@�@�������̎Љ�����ς�� ��Z �q�M�^�� 134-147
�ό��J�����牫����݂� ���� ���F�^�� 148-161
�ό��Ȋw�����Ȃł̌����̗l�q �Љ� �p�q�^�� 162-173
�ČR�ƍ߂ƍٔ����ٔ� �X�� �����^�� 176-187 |
�g���[�h�I�t�̐헪�_ �o�ߌ� ���^�� 188-197
����̕��ː����ƌ��q�͖h�� �Ð� ��p�^�� 198-209
���R�Ȋw�ƌ|�p�̗Z�� �c�K ���M�^�� 210-225
�ő̂̒��̃X�s�� ���c ����^�� 226-237
�Y�f�ޗ��̖��� ��� �W�^�� 238-247
�g�̉��̍ł����炩�����̂�����
�@�@���n�[�h�Ȍ��� ���� ���^�� 248-259
�l�ԎЉ�̖L�����̌� ���Ԍn�T�[�r�X ���c �z�q�^�� 262-273
�������͊���ς��� �y�� ���^�� 274-285
�q�g�Ɣ������̊ւ�荇�� ������ �P��^�� 286-303
�V���A�� ���c �x�^�� 304-317
�������Ă��鍩�� ���� �K�i�^�� 318-327
�}���O���[�u�̐A�ъ�����ʂ���
�@�@���w���Ă��炢�܂��� �n�� �ɍK�^�� 328-339 |
�S���A�Z�J�m�G�ҏW�u�y�������]�̃R�[���X�E�A���o�� : �����O������, �s�A�m���t�v���u�P�C�E�G���E�s�[�v���犧�s�����B
|
�O���̉� / BEGIN
���Ƃ����є� / �X�R�ǎq
�܂������� / �Đ���
���_�`�V�̎q��S�`(�݂�Ȃ̂����o�[�W����)/�R�{���q
�ԁ`���ׂĂ̐l�̐S�ɉԂ�/��[���g & �`�����v���[�Y
���a�̗��� / �l�[�l�[�Y
���S / THE BOOM
�m�ԕz / �g�����, ���v���P�E
����~�E�A���[�� / �f�B�A�}���e�X |
���ʔ����� / �Đ���
���l�ʕ� / BEGIN
����ǂ��̉� / ����h��, �{�ǒ���
���ꖯ�w���h���[(������߁`�J���O�`
�@�@�������������^) / ���ꖯ�w
�\��̏t / ���ꖯ�w
�C�����C����l / �哇�ۍ�
���V�̐� / �Đ���
�Ă����ʉ� / ���ꖯ�w |
�� / ���F��
�Ղꂺ��� / ��Ȃ��[
�������� / HY
�I�����͂��܂� / ����䂵58
�����ȗ��̂��� / MONGOL800
���Ȃ��� / MONGOL800
�p�[�}����� / BEGIN
�ꗱ�̎�`�����` / ����b����
�E |
�S���A���c���j�ďC,�����w�������ҁu���{�l�̕�炵 : �����}�^�v���u���{�}���Z���^�[�v���犧�s�����B�@
�@�@�@�u���{�������^�v (�����V����, 1955�N��) �̕���
|
��
�}��
���{�̖���
�`���@��
�����{�̖ڕW
�����̑J�̒i�K
���Z�@�l
���Ƃ̌`��
�Z���̓���
�������E���z�V�X
�����@��
�����Ǝd����
��蕨�ƈߗ��̝̑J
�H���@��
�ĂƂ��̐M��
�������̐H��
�H�i�̒���
�_�k�@���
�j�쒆�S�̖ږ{�_��
�_�Ƃƕw���̙���
�ыƂƎ�@��l
�R���̐���
��l�̐���
�ؒn���ƃ^�^���t
���Ɓ@��Z
���Ƃ̕��@
�����̐M��
�����@���
�����̌x��
���̌`�ԂƑg�D
�����@���
�������̋@�\
�Ƃ̑��
�e���E�q��
��ґg�̋@�\
�����@���
�Ƒ��ƙ���
��������
��ʁ@��
���^�̝̑J
�Ў��܂���̗�
�ו��̉^��
�Ќ��@���
�����̊��s
���������Ɠ���
�Y��@�O��
�o�Y�ƋV�X
���Z�Ǝq��
�����@�O�l
���������瑺�O����
�����̌`��
�����@�O�Z
�����̌ݏ��g�D
�����̕����ƕ搧
�N���s���@�O��
��ȑO
���Y�ƔN���s��
�M�@�l�Z
���_�E�Y�y�_�E�N��_
�c�ː��`
�햯���~
�~�Ձ@�l�O
�~�Ղ̈Ӌ`
�Ղ̏ꏊ
�~�Ղƕ���
���̍��J��
�H�T���~
�F��Ƌ��Z�@�l�Z
�����F��
�~���Ƃ��Ă̋��Z
�����Y�p�@�l��
��ƌ�
�̘b�ƙB?
���w
�S�ӌ��ہ@�܁Z
���ʼn���@�l
���Ŗڎ�
���̌i�V
��@�猩�������{���R���@��
��@���m�p�����S�������@��
�O�@�ޗ��p�g��S�V�쑺����@��
�l�@�����p����S�v�������@��
�܁@�{���p���P�n�S��ŗt�����?�@�O
�Z�@���Z���p�N����K�@�O
���@���Z���p��������Ł@�O
���@�{���p���P�n�S��ŗt�������d�@�O
����
���~
��@���z�܉ӂ̖���(�����p���S)�@�l
��Z�@�����̖���(�������p�哇�S)�@�l
���@�~�E�̉�(�����p����S)�@��
���@���~��(�����p����S)�@��
��O�@���~�ǂ�(�R���p�����S)�@��
���Ƃ̓����Ɗ_��
��l�@�{���_�Ƃ̓���(�R���p)�@�Z
��܁@�_�Ƃ̓���(�H�c�p��k�S)�@�Z
��Z�@�z�K�P���̖���(�������p)�@�Z
�ꎵ�@�R���_�Ƃ̉��~�\��(�����p���S)�@�Z
�ꔪ�@�z�K�P���̊_��(�������p)�@��
���@�R���̊_��(�{���p���P�n�S)�@��
��Z�@�Ⴊ����(�H�c�p��H�c�S)�@��
���@�䕗�悯�̐Ί_(�����p�ܓ�)�@��
�ꉮ
���@�{�w�_��(�Q�n�p�k�ÞČS)�@��
��O�@��K�̂���_��(��ސ��p���s)�@��
��l�@���k�̖���(�����s�匴)�@��
��܁@�Ȃ��(�H�c�p��H�c�S)�@��
��Z�@�可���̉�(�����p�W�H��)�@��
�@���ɃL�r��������(�����p�����S)�@��
�@�m���̉�(�����p���n)�@��
���@�R���̕���(�{���p���P�n�S)�@��
����
�O�Z�@�����̃c�m(�����p�����S)�@��Z
�O��@�Ԃ̍炭������(�X�p��k�S)�@��Z
�O��@��a��(�ޗǒn��)�@��Z
�O�O�@�Ή���(�X�p�����j�S)�@��Z
�O�l�@���d���R���̖���(�����p�����S)�@���
�O�܁@�����R���̉���(�{���p���P�n�S)�@���
�O�Z�@�ܖ̖���(�F�{�p�����S)�@���
����
�O���@�o���̉�(�����p���S)�@���
�O���@�\�E�Y����(1)(���m�p�����S)�@���
�O��@�_�[��(�������V��)�@���
�l�Z�@�D�[��(�x�R�p�\�V��S)�@���
�l��@�\�E�Y����(2)(���m�p�����S)�@���
�l��@���j�̉X(1)(�X�p�����j�S)�@��O
�l�O�@���̊�������(����p�����S)�@��O
�l�l�@�ď���(�����p�ܓ�)�@��O
�l�܁@���j�̉X(2)(�X�p�����j�S)�@��O
�l�Z�@���}��(�����p�k���Y�S)�@��O
�����ƍ��q
�l���@�M�����̂���_��(�����p�O���S)�@��l
�l���@�_�Ƃ̕��u(��㊖{��)�@��l
�l��@���q(��㊖{��)�@��l
�܁Z�@���䓇�̍��q(������)�@���
�܈�@���q�̌��܂��(���Z���p��E��)�@���
�ܓ�@���i�Ǖ����̍��q(���Z���p)�@���
�O�@�g�Ɗԓ��̍��q(���)�@���
���C�ƕ֏�
�l�@�������C(�����p�����Y�S)�@��Z
�܌܁@��V���C(�����p�k���Y�S)�@��Z
�ܘZ�@�_�Ƃ̕֏�(�Ή��p���{�S)�@��Z
���@�ԎĂ��������I���W(�����p�O���S)�@��Z
�ܔ��@�働�̏��֏�(���p���S)�@�ꎵ
�܋�@���k�n���̕֏�(����p��ˌS)�@�ꎵ
�Z�Z�@�`���E�M(�X�p��k�S)�@�ꎵ
���g����
�Z��@�V�������P(1)(��㊋{�Ó�)�@�ꔪ
�Z��@��(2)(�������哇)�@�ꔪ
�Z�O�@������(�����p�k���Y�S)�@�ꔪ
�Z�l�@�J�[(��㊋{�Ó�)�@�ꔪ
�Z�܁@�N�o�̒ޕr(��㊔g�Ɗԓ�)�@���
�Z�Z�@���(�������哇)�@���
�Z���@���Óc�G�̐��(����p���~�S)�@���
�Z���@�����̈��(���Z���p)�@���
�Z��@���m���̈��(���Z���p)�@���
���Z�@��(��㊖{��)�@���
�Ƃ�?��
����@�y�ԂƏo��(�Ή��p�Y���S)�@��Z
����@���p�̑单��(�{���p����S)�@��Z
���O�@�y�Ԃɂ��鉀�(�������ےJ��)�@��Z
���l�@��a�̃N�h(�ޗ��p����S)�@��Z
���܁@�y�Ԃɂ���J�}�h(�X�p���ˎs�O)�@��Z
���Z�@���~�\�ŗt�̒ߕx���~�\(�{���p���P�n�S�@���
�����@�ݓ�K(�����p�Öؒ�)�@���
�����@���~�I(�����p���˒�)�@���
����@�z��̃C����(�V���p���c�s)�@���
���z
���Z�@������(�X�p�����j�S)�@���
����@���g(���E)�@���
����@�O�X����(���E)�@���
���O�@�d�グ(���E)�@���
���l�@�V�z�j�̋�����(���E)�@���
���܁@�ƍ_��(���Z���p����)�@��O
���Z�@���@��(�X�p��k�S)�@��O
�����@�n��(�����p����S)�@��O
�����@�����ӂ�(�H�c�p�n��)�@��O
����
�d����
����@�є�̎d����(����p�a��S)�@��l
��Z�@���(����p�Ԋ��s)�@��l
���@�I�E���p(����p���S)�@��l
���@���s�ɘ҂鏗����(�H�c���n��)�@��l
��O�@�c�A�̎d����(�H�c�p��k�S)�@��l
��܁@��ǒ�(�H�c�p��H�c�S)�@���
��܁@���n�̏��̎d����(�V���p���n�S)�@���
��Z�@�܂������^�ԃI�o�R(�H�c�p��k�S)�@���
�C�ƎR�Ƃ̎d����
�㎵�@�R�s��(1)�\���\(�����p�O���S)�@��Z
�㔪�@��(2)�\�E����p�\(���E)�@��Z
���@��(3)�\�j�\(���E)�@��Z
��Z�Z�@�R���s�̎p(1)(�V���p�������S)�@��Z
��Z��@��(2)(���E)�@��Z
��Z��@��(3)(���E)�@��Z
��Z�O�@�R����Ƃ̕���(�x�R�p����g�S)�@��Z
��Z�l�@�~��(�����p�����S)�@��
��Z�܁@�d���̎R�s��(�����p�����S)�@��
��Z���@�����̎d����(���m�p�n��)�@��
��Z���@�R�̓�������ɒ݂������l(���m�p�n��)��
���������Ǝ�@���Ղ�
��Z��@�I�o�R�̔�(�H�c�p��H�c�S)�@��
���Z�@�ɓ��哇�̓��c(�������哇)�@��
����@�ɓ��哇�̃C���{���W���}�L(���E)�@��
����@�A�l�T���J�u��(�����p�O���S)�@���
���O�@�z�I�J�u��(���E)�@���
���l�@���R�n�`�}�L(�����p�떃�S)�@���
���܁@�z�I�J�u��(���E)�@���
���Z�@�K���j���J�u��(���E)�@���
��ꎵ�@�z�I�J�u���̌^(1)(����s)�@���
��ꔪ�@��(2)(���E)�@���
����@��(3)(���E)�@���
��蕨
���Z�@�o�I���ƃt���V�L(�X�p��k�S)�@�O�Z
����@���Ўp�̖�(����p�ԉ��s�ߍ�)�@�O�Z
����@����(�H�c�s�B�y��)�@�O�Z
���O�@�J�K�{�V(�R�`�p���c��S)�@�O�Z
���l�@�Ҋ}(��t�p��S)�@�O��
���܁@�p�`�}(�����p�O���S)�@�O��
���Z�@�r���E�W���}(�{���p�{��S)�@�O��
��@�}���W���}(��t�p�������S)�@�O��
��
��@�K���W�Q��(1)�\�O�\(�H�c�p��k�S)�@�O��
����@��(2)�\�w�\(���E)�@�O��
��O�Z�@�n�Ȃ��Q��(���E)�@�O��
��O��@���Q���������I�o�R(���E)�@�O��
��O��@������\���悯�\(���E)�@�O��
��O�O�@�Q���𒅂��˃o�R(���E)�@�O�O
��O�l�@�^�~�m�ƃ^�P�K�T(�����p�O���S)�@�O�O
��O�܁@�X�Q�K�T�ƃX�b�J(�ΐ��p�\�o�n��)�@�O�O
��O�Z�@�r���E�̃~�m�E�J�T(���Z���p����)�@�O����
��O���@�S�U�|�V(�����p�O���S)�@�O�O
����
��O���@���̗���(�H�c�p�p�ْ�)�@�O�l
��O��@�S���x�Ɛ�K�V��(�H�c�p��k�S)�@�O�l
��l�Z�@�c�}�S���܂ƌL�X�y(�H�c�p�����S)�@�O�l
��l��@�n�o�L�Ƙm�B(�H�c�p����S�E����)�@�O�l
��l��@�����O�c�Ɖ_���̎q��(�����p�����S)�@�O��
��l�O�@�X�x(�X�p��k�S)�@�O��
��l�l�@�փJ���W�L(�����p���S)�@�O��
��l�܁@���U(�H�c�p��k�S)�@�O��
������
��l�Z�@������(1)(�V���p�슗���S)�@�O�Z
��l���@��(2)(�����p�X���S)�@�O�Z
��l���@�N��(�H�c�p��k�S)�@�O�Z
��l��@������(�Ȗ��p���h�S)�@�O�Z
��܁Z�@��ނ�(�Ȗ��p������S)�@�O��
��܈�@������(�����p�����S)�@�O��
��ܓ�@�ނ�(���E)�@�O��
��O�@����ނ�(�X�p�����j�S)�@�O��
��H
��l�@��������(�����s�匴)�@�O��
��܌܁@�m�B����(�H�c�p)�@�O��
��ܘZ�@��������(���E)�@�O��
����@��D��(����p)�@�O��
��ܔ��@������(�V���p�슗���S)�@�O��
��܋�@������(���E)�@�O��
�H�K
��������
��Z�Z�@����������(1)(�X�p�[�Y��)�@�l�Z
��Z��@��(2)(���E)�@�l�Z
��Z��@��(3)(���E)�@�l�Z
��Z�O�@�Z�`�K�`�̕ĕU(�����p������)�@�l��
��Z�O�@�T�T�}�c�_�S(���Z���p�w�h��)�@�l��
��Z��l�@�A�N�}�L(���E)�@�l��
��Z�܁@�Ė�(�X�d�[�Y��)�@�l��
��Z�Z�@������(���E)�@�l��
�H������(1)�\��?.�ݖ��\
��Z���@�ݖ�����(�������O�)�@�l��
��Z��@���X��(1)(�X�p�[�Y��)�@�l��
�ꎵ�Z�@��(2)(���E)�@�l��
�ꎵ��@��(3)(���E)�@�l��
�ꎵ��@�B��(�{���p���P�n�S)�@�l�O
�H������(2)
�ꎵ�O�@���n(1)(���Z���p�哇�S)�@�l�l
�ꎵ�l�@��(2)(�����p����S)�@�l�l
�ꎵ�܁@�n(�������p�Λ���)�@�l�l
�ꎵ�Z�@��(1)(�{���p���P�n�S)�@�l��
�ꎵ���@��(2)(����p��ˌS)�@�l��
�ꎵ���@��(3)(���Z���p��粌S)�@�l��
�ꎵ��@��(4)(���Z���p�K�h�S)�@�l��
�ꔪ�Z�@��(5)(�������ɓ��V��)�@�l��
�ꔪ��@(6)(���E)�@�l��
�ꔪ��@�҉P���(�R���p������S)�@�l��
�H��
�ꔪ�O�@���n���{(�����p��В�)�@�l�Z
�ꔪ�l�@��ǂ̙��c��(�����p����S)�@�l�Z
�ꔪ�܁@�D���̃n���{(���E)�@�l�Z
�ꔪ�Z�@����(��㊖{��)�@�l�Z
�H�i���U(1)
�ꔪ���@���`(�{���p���P�n�S)�@�l��
�ꔪ���@�卪��(�H�c�p��H�c�S)�@�l��
�ꔪ��@�ȁE��(�����p�����S)�@�l��
��ズ��@�J�L�݊�(���{��k�S)�@�l��
�H�i���U��(2)
����@�؊���(���ɌS�Ɠ�)�@�l��
����@���n����(�H�c�p��k�S)�@�l��
���O�@�~�̖�ؒ��U(�X�p���Ìy�S)�@�l��
���l�@�J�\�R����(�����p�ܓ�)�@�l��
���܁@���̒��U(�������p�w�h��)�@�l��
���Z�@�h�c�̛��̒n��(�������p���i�Ǖ���)�l��
�_�k
���
��㎵�@��U(�H�c�p��H�c�S�@�܁Z
��㔪�@���ɂ���\�����\(�X�p�����j�S)�܁Z
����@�������U������(���E)�@�܁Z
��Z�Z�@����(�H�c�p��H�c�S)�@�܁Z
�͔�^��
��Z��@�͔�^��(��z����)�@�܈�
�c��ł��炦�ƍr�c�N��
��Z��@�_�k(�����p�g�c�S)�@�ܓ�
��Z�O�@�c�ォ��(�X�p�����j�S)�@�ܓ�
��Z�l�@�c���邵�𗧂Ă�(���E)�@�ܓ�
��Z�܁@�l�h��(�����p�����S)�@�ܓ�
��Z�Z�@�����̂܂�(1)(�����p�W�H��)�@�O
��Z���@��(2)(�����p)�@�O |
��Z���@�呫(�����p���S)�@�O
��Z��@����(�����p����S)�@�O
���Z�@�o�o�v�L(���E)�@�O
�c�A(1)
����@㊐A��(1)(�����p���n)�@�l
����@��(2)(�������p��q��)�@�l
���O�@�O�i�A��(�����p�O���S)�@�l
���l�@�g�A��(1)(�����p������)�@�l
���܁@�������܂���c�A��(���{)�@�܌�
���Z�@�g�A��(2)(�~�ˎs���ə�)�@�܌�
��ꎵ�@㊐A��(3)(���{�k��?�S)�@�܌�
�c�A(2)�\�c�A�p�\
��ꔪ�@���c�̓c�A(1)(�x�R�p���V��S)�@�ܘZ
����@��(2)(���E)�@�ܘZ
���Z�@��㊂̔���(�H�c�p��k�S)�@�ܘZ
����@�c�A�p(�X�p�����j�S)�@�ܘZ
����@������(�A���p�R�p�S)�@�ܘZ
���Ђ�
���O�@���Ђ�(���{�O���S)�@��
���l�@�������(�����{�R��n��)�@��
���܁@������܂Ɛ������(���{��͓��S)��
����
���Z�@�c�̑��Ƃ�(1)(�~�ˎs�{����)�@�ܔ�
��@��(2)(�����p�����S)�@�ܔ�
��@��(3)(�X�p�����j�S)�@�ܔ�
�ĎR�q
����@�����ǂ�(1)(�ޗ��p��a����)�@�܋�
��O�Z�@��(2)(���E)�@�܋�
��O�Z�@��(3)(�����p)�@�܋�
��O��@���������������I�h�V(��t�p�������S)�܋�
��O�O�@���̒����ǂ�(��t�p��S)�@�܋�
�����
��O�l�@�����̊�����(��t�p�����n��)�@�Z�Z
��O�܁@�j��(�����p�������s)�@�Z�Z
��O�Z�@�n����(��㊋{�Ó�)�@�Z�Z
��O���@�����(1)(�H�c�p��H�c�S)�@�Z��
��O���@��(2)(���E)�@�Z��
��O��@��(3)(���E)�@�Z��
�E��
��l�Z�@�E��(1)(�H�c�p��H�c�S)�@�Z��
��l��@��(2)(�ΐ��p�\�o�n��)�@�Z��
��l��@���X��(�X�p�����j�S)�@�Z��
����(1)
��l�O�@�i�X��(�����p���n)�@�Z�O
��l�l�@�Ĕ�(�Ή��p���q�S)�@�Z�O
��l�܁@���k(��㊔g�Ɗԓ�)�@�Z�O
����(2)
��l�Z�@���ӂ�(�����p�����S)�@�Z�l
��l���@�m�̒E��(�����p�ܓ�)�@�Z�l
��l���@�m����(�������������S)�@�Z�l
��l��@�m�ł�(���{�L�\�S)�@�Z���
��܁Z�@�B�̎y�n(�{���p���P�n�S)�@�Z��
��܈�@�K�̎����(�����p)�@�Z��
��ܓ�@�a������(���R�p�q�~�s�O)�@�Z��
��O�@�H�Ƃ�(�����p)�@�Z��
��l�@��t�̖q�n(���{�O���S)�@�Z��
���n����
��܌܁@���̘g(�����p�k���Y�S)�@�Z�Z
��ܘZ�@������(�V���p�������S)�@�Z�Z
����@�n�Ŕ��֍s�����̖�(1)
�@�@��(���Z���p���i�Ǖ���)�@�Z�Z
��ܔ��@��(2)(�����p���n)�@�Z�Z
��܋�@�I�~�J�S���̑�(���p�K��S)�@�Z�Z
�_��
��Z�Z�@�m�ł��̏ꏊ(�{���p���P�n�S)�@�Z��
��Z��@�L(��㊒r�ԓ�)�@�Z��
��Z��@��(�X�p��k�S)�@�Z��
��Z�O�@���(�V���p�슗���S)�@�Z��
��Z�l�@�_��̂��낢��(���E)�@�Z��
�ыƁE��
�؍ޔ��o(1)
��Z�܁@�}����(���m�n��)�@�Z��
��Z�Z�@�A�т̎����(�����p����)�@�Z��
��Z���@�g�쐙�̐���(�ޗ��p�g��S)�@�Z��
��Z���@���ؓ���(�����p�����S)�@�Z��
��Z��@����(�����p���S)�@�Z��
�Z�@�V�����o��(�ޗ��p�g��S)�@�Z��
��@�ؗ���(�X�p�����j�S)�@�Z��
��@�؍ޔ��o(���Z���p���m��)�@�Z��
�؍ޔ��o(2)
�O�@�V�����o��(�啪�p��������)�@���Z
�l�@���̃h�o(�ޗ��p�g��S)�@���Z
�܁@�d�C��(���E)�@���Z
�Z�@������(���E)�@���Z
���@�`�֔��o(�����p���n)�@���Z
�R�̍̎�
���@�����V�̖�(�X�p�����j�S)�@����
��@�_���m�[(����p��ˌS)�@����
�Z�@�ő�����(�啪�p)�@����
��@�i�p�R(�啪�p���S)�@����
��@�R��(�R�`�p�ŏ�S)�@����
���Y
�O�@�a��R���̒Y�K�}(���{��k�S)�@����
�l�@���Z�R���̒Y�K�}(���p�K��S)�@����
�܁@�J�}�n��(1)(�X�p�����j�S)�@����
�Z�@��(2)(���E)�@����
���@��(3)(���E)�@����
���@��B�R���̒Y�K�}(���n�p����S)�@���O
��@�ؒY�̎R(�����p���n)�@���O
���Z�@�ؒY�̐Ϗo��(�a�̎R�p�����K�S)�@���O
����
����@�N���Q��(�H�c�p��k�S)�@���l
����@�����_(���E)�@���l
���O�@�R���E���i(�{���p�Z���S)�@���l
���l�@����(�Ȗ��p���h�S)�@���l
���܁@�J�X�~�ƃI�g������(���E)�@���l
���Z�@��Ȃ߂�(�H�c�p�p�ْ�)�@���l
��㎵�@���_(�R���p)�@���l
��㔪�@�у{�J�C(1)(�H�c�p��k�S��w��?��)�@����
����@����(2)(���E)�@����
�O�Z�Z�@��(3)(�V���p�������S�ԒJ��)�@����
�O�Z��@�A�I�}�^�M(�X�p�l���j�S)�@����
�O�Z��@�n�T�~�ɂ�������(���E)�@����
����
�M
�O�Z�O�@�M�˗l(�����p����S)�@���Z
�O�Z�l�@���M(�����p)�@���Z
�O�Z�܁@���ނ̙��M(��㊖{��)�@���Z
�O�Z�Z�@�}���L(�E)�ƃ`����(�ΐ��p�\�o��)�@���Z
�O�Z���@�z��̃h�u�l(�V���p�����S)�@���Z
�O�Z���@�T���}�f���}(�I�Z���p�K�h�S)�@����
�O�Z��@�}���L(�V���p�������S�Ԑ���)�@����
�O��Z�@�e���o(�����p����S)�@����
�O���@�M����(�����p�ܓ�)�@����
�O���@�M���낵(�����p�k���Y�S)�@����
�ԋ�(1)
�O��O�@���̈�{��(���{���蒬)�@����
�O��l�@�g(���Z���p����)�@����
�O��܁@�˃��_(�{���p)�@����
�O��Z�@�~�̌Q(�a�̎R�p���n��)�@����
�O�ꎵ�@�n�g����(�{���p�j���S)�@����
�O�ꔪ�@�n�g��(�{���p�����S)�@����
�O���@��̒n�g(�x�R�p���Îs)�@����
�O��Z�@壉G���̖ԏグ(���E)�@����
�ԋ�(2)
�O���@�В��Ԃ̏W��(�����p���n�����`)�@���Z
�O���@���(���{)�@���Z
�O��O�@�ܑ�~(�I�B�F��C��)�@���Z
�O��l�@�g��(��㊎���)�@���Z
�O��܁@�Ԋ���(�����p�ܓ�)�@����
�O��Z�@�C�J�e�\�O���M�Ƌ���(�F�{�p�V���S)�@����
�O�@�ԖԂ�����(�������~�Ó�)�@����
����
�O�@����(1)(�A���p��������)�@����
�O���@��(2)(�����p����S)�@����
�O�O�Z�@��(3)(�o�Z���p�K�h�S)�@����
�O�O��@��(4)(�����p����S)�@����
�O�O��@��㊂̕⋭���(�A���p��������)�@����
�O�O�O�@����(���E)�@����
�O�O�l�@�C���J���̋���(��㊖{������)�@����
�C��
�O�O�܁@�w�q���̊C��(�ΐ��p�P���S)�@���O
�O�O�Z�@�u���̊C��(�O�d�p�u���S)�@���O
�O�O���@��Y�̊C��(�R���p�哇�S)�@���O
�C���̋���
�O�O���@�Ή��p��ΌS��葺�@���l
�O�O��@�啪�p����m萒��@���l
�O�l�Z�@�Ή��p��ΌS��葺�@���l
�O�l��@���@���l
�O�l��@�ƉƑD�̃����C(�A���p���m���s)�@����
�O�l�O�@�ƑD��?��(1)(���E)�@����
�O�l�l�@��(2)�@���l
�ƑD
�O�l�܁@�Ղɟd�Ę҂��ƑD�̌Q(�����P�˒�)�@���Z
�O�l�Z�@�Ȃ������v������˂�(���E)�@���Z
�O�l���@�[�M�̎x�x(���E)�@���Z
�O�l���@�����ɍs����w����(���E)�@���Z
�O�l��@��̎d����(���E)�@���Z
����
�O�܁Z�@�����C�݂̐���(���Z���p�̛��S)�@����
�O�܈�@���ł̂��낢��(1)(���E)�@����
�O�ܓ�@��(2)(���m�p���ԉ)�@����
�O�O�@��(3)(���Z���p�K�h�S)�@����
���l
�O�l�@�̗��グ(���Z���p�n�ѓ�)�@����
�O�܌܁@�T����(���Z���p����)�@����
�O�ܘZ�@���l�����鎅�ނ̏�(��㊖{��)�@����
�O���@��(���Z���p���m��)�@����
���Y���H
�O�ܔ��@�T�������������̎q��(���Z���p����)�@����
���܋�@�i�}�R�����������q��(���Z���p����)�@����
�O�Z�Z�@����(���Z���p�n�ѓ�)�@����
�O�Z��@壒����̂���o��(�x�R�p���Îs)�@����
�O�Z��@���߂���(���Z���p��粌S)�@����
�C���̎�
�O�Z�O�@���J������(�����{�O��C��)�@��Z
�O�Z�l�@���̐�L�W(�R���p����)�@��Z
�O�Z�܁@�e���O�T�̌�����(�Ή��p��ΌS)�@��Z
�O�Z�Z�@�C�ۍ̂�(��������X�C��)�@��Z
�O�Z���@�C�ۂ̊���(�����p���q�s)�@��Z
�O�Z���@�C�ۂ̎�t��(�F�{�p�ʖ��S)�@���
�O�Z��@�C�f�Ƃ�(�������p�n�ѓ�)�@���
�L�E��
�O���Z�@�L�E���ɏo����������(���Z���p�K�h�S)�E�c�@���
�O����@���L�Ƃ�(�H�c�p��H�c�S)�@���
�O����@���Ə��ŊL���@�铇�̐l����(�����p�ܓ�)�@���
�O���O�@�E�j����(�����p���n)�@���
�O���l�@����L�̓ɍ�(�O�d�p�u���S)�@��O
�d�c
�O���܁@�d�c�̓W�](���R�p�Z���s)�@��O
�O���Z�@�_�C�ƃR�c�{�Ȃ�(�{���p�n�g��)�@��O
�O�����@�}�O�����Ђ��l(���E)�@��O
�싙�ƌΐ����Ɓ@�O����
��l�@�O����
��l�@�O���Z
��l�@�O����
��l
�O����@�J�W�J��(���E)�@��l
�O���O�@���X�c�L�[���Ƃ�\�I�a�����k�R���@���
�O���l�@�z�K�̃��b�J(�����p)�@���
�O���܁@���i�̃G��(1)(�����p)�@���
�O���Z�@��(2)(���E)�@���
��H��
��
�O�����@�m���̃z�\����(���{�r�c�s)�@��Z
�O�����@�ĂƂ�(���E)�@��Z
�O����@�S(���E)�@��Z
���V����
�O��Z�@�I���炵(���{�O���S)�@�㎵
�O���@���t���̎�(�����p�z�K�S)�@�㎵
�O���@����(���E)�@�㎵
�O��O�@�^��(���E)�@�㎵
�|�H�E�؍H
�O��l�@�M�܂����(�ޗ��p�g��S)�@�㔪
�O��܁@ⴂׂ�(�Q�n�p�����S)�@�㔪
�O��Z�@������(�H�c�p��k�S)�@�㔪
�O�㎵�@�ؒn���̃��N��(���m�p�k�ݞٌS)�@�㔪
���㔪�@�w�M�̊���(�����{�k�K�c�S)�@�㔪
����
�O���@�����鑺(�a�̎R�p�߉�S)�@���
�l�Z�Z�@������(�a�̎R�p�����S)�@���
�l�Z��@�O������(���m�p�����S)�@���
�l�Z��@��������(�����p�����S)�@���
�ĕ�
�l�Z�O�@���Ċ�����(�����p�k���Y�S)�@��Z�Z
�l�Z�l�@���q�ɏ��Z�����鏗(��㊓ߔe�s)�@��Z�Z
�l�Z�܁@���Ă��}(�����p�k���Y�S)�@��Z�Z
�l�Z�Z�@�ΊD�̏��}(����{�Ó�)�@��Z�Z
�l�Z���@�ߔe�̒ى�(��㊖{��)�@��Z�Z
�l�Z���@�o�_�̓��_��(�����p����S)�@��Z��
�l�Z��@�ΐ؏�(���R�p�k�ؓ�)�@��Z��
�l��Z�@�Ή��̒b��(�����p�k���Y�S)�@��Z��
�l���@�ލ̎��(��㊖{��)�@��Z��
��ʁE����
��
�l���@��(�X�p�����j�S)�@��Z��
�l��O�@���̃��O��(���E)�@��Z��
�l��l�@��(�����p���S)�@��Z��
�w����
�l��܁@���J�S(��t�p��S)�@��Z�O
�l��Z�@�G���{�E(�A���p��������)�@��Z�O
�l�ꎵ�@�I�C�R�\�E�\�Z�i�J�`��
�@�@���j�J���[���\(�����p�����S)�@��Z�O
�l�ꔪ�@�R�_�X�\�Α��\(�H�c�p��k�S)�@��Z�O
����^�����̑�
�l���@�n�V�S(����p�����S)�@��Z�l
�l��Z�@�n�V�S��w������(���E)�@��Z�l
�l���@�R�̘@��(�~�ސ��p��R��)�@��Z�l
�l���@�g�E�W���J���C(�{���p���P�n�S)�@��Z�l
�l��O�@���̍s��(�������p�����哇)�@��Z�l
�l��l�@�^��(�R���p���s�ʍ]�Y)�@��Z�l
�l��܁@����@��(1)(���Z���p���m��)�@��Z��
�l�j�Z�@��(2)(�����p������)�@��Z��
�l�@��(3)(�������ɓ��V��)�@��Z��
�l�@��(4)(�O�d�p�m�{��)�@��Z��
�l���@�_�ʼnׂ�����q��(�A���p�K�蒬�\�n)�@��Z��
�^����
�l�O�Z�@�l�R��(1)(�����p����S)�@��Z�Z
�l�O��@��(2)(�����p�����S)�@��Z�Z
�l�O�j�@����(�H�c�s)�@��Z�Z
�l�O�O�@����(���Z���p?�V�Y)�@��Z�Z
�l�O�l�@�y��(�X�p�����j�S)�@��Z�Z
�l�O�܁@�n��(�R�`�p)�@��Z�Z
�l�O�Z�@��(�����p���S)�@��Z�Z
�l�O���@�N���M(���Z���p���m��)�@��Z��
�l�O���@�؍ސϏo��(���Z���p���m��)�@��Z��
�l�O��@�o��(���Z���p�z�K�P��)�@��Z��
�l�l�Z�@�唪�ԂƉ���(���{��k�S)�@��Z��
�l�l��@���n�̔n(�����p)�@��Z��
�s��
�l�l��@�|�b�J(�����p���S)�@��Z��
�l�l�O�@��̂�(�H�c�p��k�S)�@��Z��
�l�l�l�@�y�p�W���̂�(���E)�@��Z��
�l�l�܁@�t���̂�(���p���R�s)�@��Z��
�l�l�Z�@�����̂�(�V���p)�@��Z��
�l�l���@�Ƌ��̂�(��㊖{��)�@��Z��
�l�l���@���̂�(�����p���S)�@��Z��
�l�l��@�Ă��̂�匴��(�����s)�@��Z��
�l�܁Z�@����̂鎅��(��㊖{��)�@��Z��
�l�܈�@�ɘ����O�̃I�^�^(���Q�p���R�s)�@��Z��
�s�ƓX
�l�܃j�@�ߔe�̎s��(��㊖{��)�@���Z
�l�O�@��Y�̃��E�J��(�����p���)�@���Z
�l�l�@���s(�H�c�p�R���S)�@���Z
�l�܌܁@���ނ̋��̂�(��㊖{��)�@���Z
�l�ܘZ�@���m���̓X(���Z���p)�@����
�l���@�N�̎s(���m�p�����S)�@����
�l�ܔ��@�ߔe�̒�(��㊖{��)�@����
�l�܋�@�����X(1)(��㊋{�Ó�)�@����
�l�Z�Z�@��(2)(���E)�@����
����
�x��
�l�Z��@�̔ԓ���(���p���R�s)�@���j
�l�Z�j�@�̌�(�R���p�����S)�@���j
�l�Z�O�@���̓���(��㊋{�Ó�)�@���j
�l�Z�l�@�p����(�H�c�p��H�c�S)�@���j
�l�Z�܁@���̎��v(���Z���p���v��)�@���j
�����s
�l�Z�Z�@�ᐨ�s(�H�c�p����s)�@���O
�l�Z���@�땔���̕���s(1)(�R���p�L�Y�S)�@���O
�l�Z���@��(2)(���E)�@���O
��ҏh
�l�Z��@�ʍ]�Y�̎�ҏh(�R���p���s)�@���l
�l���Z�@��������낤��҂���(���E)�@���l
�l����@�O�P�̎�ҏh(�����p�~��S)�@���� |
�l����@�������̐Q�h(���Z���p�o���S)�@����
�l���O�@�ܓ��̖��h(�����p)�@����
����
�œ�
�l���l�@�R�����s���œ�����(�X�p�����j�S)�c�@���Z
�l���܁@�łǂ�̓��̓�����(���E)�@���Z
�l���Z�@�ł̃X�l�J�W��(���E)�@���Z
�l�����@�j����(���E)�@���Z
�l�����@�����I�N��(1)(���E)�@���Z
�l����@��(2)(���E)�@���Z
�l���Z�@����n���̍��X(1)(���Z���p)�@��ꎵ
�l����@��(2)(���E)�@��ꎵ
�l����@��(3)(���E)�@��ꎵ
�l���O�@��(4)(���E)�@��ꎵ
�l���l�@��(5)(���E)�@��ꎵ
�ԉ�
�l���܁@�œ��ו�(�R�`�p�ŏ�S)�@��ꔪ
�l���Z�@�ԉŎp(1)(�H�c�p��k�S)�@��ꔪ
�l�����@��(2)(�R�`�p�R�ԕ�)�@��ꔪ
�l�����@��(3)(�R�`�p)�@��ꔪ
�l���܁@��(4)(�����s���P)�@��ꔪ
�Y��
�Y��
�l��Z�@�Y��(�X�p�����j�S)�@����
�l���@�Y��(���m�p���ԉ)�@����
�l���@�q�}�G����(���R�p���c�S)�@����
�l��O�@������(���m�p�k�ݞČS)�@����
�l��l�@�Y����(�����p���~�S)�@����
��Z
�l��܁@�������̂�肩��(���Z���p)�@��j�Z
�l��Z�@�G�d���i1�j(�H�c�p��H�c�S)�@���Z
�l�㎵�@���i2�j(�H�c�p�j�͒n��)�@���Z
�l�㔪�@���i3�j(�����p���Ò�)�@���Z
�l���@���i4�j(�����p����S)�@���Z
�܁Z�Z�@���{�܂���\�O�\�i1�j(�����p�ܓ�)�@����
�܁Z��@���\�w�\�i2�j(���E)�@����
�܁Z��@���J����(�����p����S)�@����
�܁Z�O�@�w�܂���(���E)�@����
�܁Z�l�@�q���(�������ɓ��V��)�@����
�܁Z�܁@���̎q���i1�j(���������z�K����)�@����
�܁Z�Z�@���i2�j(�������p���m��)�@����
�܁Z���@�q��w������(�H�c�p��H�c�S)�@����
�܁Z���@�����(���E)�@����
���Y
�܁Z��@�_�}(�����p����S)�@���O
�܈�Z�@�j�i���o(���E)�@���O
�܈��@�z�\�{(���E)�@���O
�܈��@�����z��(���E)�@���O
�܈�O�@�\�j�N�T�\�\��{�|�\(���E)�@���O
�܈�l�@�C�[�`�R�n�[�`�R(���E)�@���O
���Y�Ɗߋ�
�܈�܁@�V�[�\�[�V��(�������p���m��)�@���l
�܈�Z�@�M�̊ߋ�(�������p�z�K����)�@���l
�܈ꎵ�@�^�R�グ(�������p����)�@���l
�܈ꔪ�@�@�j���A�l�R�E�Ñ��A�l�R(�H�c�p��k�S)�@���l
�܈��@���R�A�l�T��(�H�c�p�p�L��)�@���l
�O��Z�@��M�R(�H�c�p��k�S)�@����
�O���@�|�n(�����p�����S)�@����
�O���@���̐\�̏��V��(�����p�g�c�S)�@����
�O��O�@���ԗV��(�X�p���ÏόS)�@����
�O��l�@���̃��i(���E)�@����
�q���̐���
�O��܁@�_���̎q��(�X�p�����j�S)�@���Z
�O��Z�@�ʛ{�i1�j(���m�p�����S)�@���Z
�O�@���i2�j(�����p���S)�@���Z
�O�@�p�̗t�̂�̏���(�H�c�p��k�S)�@���Z
�O���@���N�|�b�J(�����p���S)�@���Z
����
����
�O�Z�@�O�œ�(�X�p�[�Y��)�@���
�O��@�O�œ��̎x�x(���E)�@���
�O��@�n�L���m����(���E)�@���
�O�O�@�r��(���E)�@���
�O�l�@�ߐe�̏�(���E)�@���
�O�܁@����(���E)�@���
���V�ƔN��
�O�Z�@�J�h�A�J�V(�X�p�[�Y��)�@���
�O���@���@��i1�j(���E)�@���
�O���@���i2�j(���E)�@���
�O��@��O�̋�����(���E)�@���
�l�Z�@�\�O�łƎl�\����̖݂���(���E)�@���
�l��@�\�O�Ŗ݁\��i�\��
�@�@���l�\��ڂ̖݁\���i�\(���E)�@���
�l��@�o����(�����p�k���Y�S)�@����
�l�O�@��(���E)�@����
�l�l�@�z�J�N�h(���E)�@����
�l�܁@�N���i1�j(�X�p�[�Y��)�@����
�l�Z�@���i2�j(���E)�@����
�l���@���i3�j(���E)�@����
�r���ƐV��
�l���@�r���i1�j(�����p�O�L�S)�@��O�Z
�l��@���i2�j(�����p�����S)�@��O�Z
�܌܁Z�@�\�[���\���q(�ΐ��p�\�o��)�@��O�Z
�܌܈�@�ȖX�q(�����p�k���Y�S)�@��O�Z
�܌ܓ�@�V��i1�j(�X�p�����j�S)�@��O�Z
�܌O�@���i2�j(���E)�@��O�Z
�܌l�@���\�K��(�����{�k�K�c�S)�@��O��
�܌܌܁@�r���E�\(�V���p�슗���S)�@��O��
�܌ܘZ�@�V��(�Ή��p���{�S)�@��O��
�܌��@���̉͌�(�����p�O���S)�@��O��
�܌ܔ��@�ΐς�(�X�p�O�ˌS)�@��O��
�ˉ�
�܌܋�@�ˉ��i1�j(�����p�O�L�S)�@��O��
�ܘZ�Z�@���i2�j(���E)�@��O��
�ܘZ��@�O����(�����p�ܓ�)�@��O��
�ܘZ��@�ˉ��i3�j(�����p���˒�)�@��O��
�ܘZ�O�@�_粂̖��ߕ�(�����p�O�o�S�j�@��O��
�ܘZ�l�@�I����(�������p�̔l�S)�@��O��
�_�搧
�ܘZ�܁@���ߕ�(�����p�O�L�S)�@��O�O
�ܘZ�Z�@��n(���Z���p�K�h�S)�@��O�O
�ܘZ���@�T�\�}�C(�����p���~�S)�@��O�O
�ܘZ���@���ߕ�ƕ�(���R�p�Z��)�@��O�O
�ܘZ��@�o�_���̕�i1�j(���Z���p�哇�S)�@��O�O
���Z�@��(2)(���E)�@��O�O
��㊂̑���
����@����(��㊖{��)�@��O�l
����@��i1�j(��㊈ɕ�����)�@��O�l
���O�@��(2)(���E)�@��O�l
���l�@����(��㊋v����)�@��O��
���܁@�����̕�Q��i2�j(��㊖{��)�@��O��
���Z�@���i2�j(���E)�@��O��
�N���s��
�叼�E���ݏ��E��������
�����@���Ƃ̐���(�H�c�p�p�ْ�)�@��O�Z
�����@�i���̏�����(�X�p�ђ��j�S)�@��O�Z
����@�叼�i1�j(���m�p�����S)�@��O�Z
�ܔ��Z�@���i2�j(�����p���x�S)�@��O�Z
�ܔ���@���i1�j(���m�p�k�ݞٌS)�@��O�Z
�ܔ���@�܂��(�������ےJ��)�@��O��
�ܔ��O�@��������(�������ɓ��V���j�@��O��
�ܔ��l�@�K��(�����p�ܓ�)�@��O��
�ܔ��܁@�������̕��܂�(����p�B�ьS)�@��O��
�ܔ��Z�@�������̃i���M(����p����S)�@��O��
�������̍s��
�ܔ����@�L�̂�������(�����p���n�S)�@��O��
�ܔ����@����̔N�Ƃ�(�H�c�p��H�c�S)�@��O��
�ܔ���@�i�}�R�g��(����p����S)�@��O��
�܋�Z�@��c�A(�X�p�����j�S)�@��O��
�܋��@�_�C�i�K�_(�ΐ��p�֓���)�@��O��
�܋��@���U�_(�Ȗ��p���h�S)�@��O��
�܋�O�@���c�~�܂�(�R���p������S)�@��O��
�܋�l�@���܂���(�H�c�p����s)�@��O��
�܋�܁@�z���Q�\�M��(�����p�O���S)�@��O��
�܋�Z�@���ǂ�(�R�`�p)�@��O��
�����̖K���
�܋㎵�@�i�}�n�Q(�H�c�p��H�c�S)�@��l�Z
�܋㔪�@�t��(�V���p���n�S)�@��l�Z
�܋��@�X�l�J(����p���όS)�@��l�Z
�Z�Z�Z�@��?(�����p���)�@��l�Z
�t�E�Ă̍s��
�Z�Z��@�R�g����(�����p�Ώ�S)�@��l��
�Z�Z��@���O�}�l(�����p���n)�@��l��
�Z�Z�O�@�g�R���M�\�o�\�E(�H�c�p��k�S)�@��l��
�Z�Z�l�@������s��(�{���p����䒬)�@��l��
�Z�Z�܁@�܌��ߋ��i1�j(�X�p�����j�S)�@��l��
�Z�Z�Z�@���i2�j(���E)�@��l��
�~�i1�j
�Z�Z���@�m�n(�����p�Ώ�S)�@��l��
�Z�Z���@�K�d�L�l(�H�c�p��粌S)�@��l��
�Z�Z��@���[����(����p���ԌS)�@��l��
�Z��Z�@�\�E���I(�Ή��p���q�S)�@��l��
�Z���@�~�ԂƂ�(�X�p�����j�S)�@��l��
�Z���@�~���āi1�j(�����p�O����)�@��l�O
�Z��O�@���i2�j(�����p�k���܌S)�@��l�O
�Z��l�@�~�I(�X�p�����j�S)�@��l�O
�Z��܁@���˒I(�����p)�@��l�O
�Z��Z�@�~�I�i2�j(�X�p�O�ˌS)�@��l�O
�~�i2�j
�Z�ꎵ�@��ڂƂ�(�����p���_�s)�@��l�l
�Z�ꔪ�@�~�I�̖�������(�����p���_��)�@��l�l
�Z���@�V�ł̐��˒I(�����p�W�H��)�@��l�l
�Z��Z�@�~�̃z�J�C(�X�p�����j�S)�@��l�l
�Z���@?�˒I(�R�`�p)�@��l�l
�Z���@���˗���(����s)�@��l��
�Z��O�@�~���h�E�i1�j�i�����p���)�@��l��
�Z��l�@���i2�j(���E)�@��l��
�Z��܁@�~�x��(�����p���n)�@��l��
�H�E�~�̍s��
�Z��Z�@��̎q���(�����p�W�H��)�@��l�Z
�Z�@��̎q�܂�(���E)�@��l�Z
�Z�@����ߋ��̏��蕨(�����s)�@��l�Z
�Z���@����u(�X�p�����j�S)�@��l�Z
�Z�O�Z�@�݂���(����p����S)�@��l�Z
�����̏���
�Z�O��@�叼�̓���(���s)�@��l��
�Z�O��@�R�o�V����(�����p�W�H��)�@��l��
�Z�O�O�@���A㊂���(�ΐ��p���V�s�O)�@��l��
�Z�O�l�@���A㊉�(�O�d�p�Îs)�@��l��
�Z�O�܁@�N�̎s(�������Ǒ�)�@��l��
�M��
�~�K
�Z�O�Z�@�C�{�b�`��(�������ɓ��哇)�@��l��
�Z�O���@�V���@��(�����p���n)�@��l��
�Z�O���@��{����(�����p���˓�)�@��l��
�Z�O��@�g�s���V��(���E)�@��l��
�Z�l�Z�@�j���E�g�r�~�l(���E)�@��l��
�Z�l��@�z�K�l(�a�̎R�p�����K�S)�@��l��
�Z�l��@���~�~(�X�p�����j�S)�@��l��
�Z�l�O�@�j�חl(�����p���˓�)�@��l��
�Z�l�l�@�c�g�{(�����p�ܓ�)�@��l��
�Z�l�܁@�n�~�l(����p�����S)�@��l��
�Z�l�Z�@�K���\�l(�����p�k���Y�S)�@��l��
�Ղ̏�
�Z�l���@��x(��㊋v����)�@��܁Z
�Z�l���@�~�A�V�@�Q(��㊖{���j�@��܁Z
�Z�l��@�̐_(��㊖{���j�@��܁Z
�Z�܁Z�@���~�r�~(�����p����S)�@��܁Z
�Z�Z��@�_�C�W���R�O�܂�(�����p���_��)�@��܁Z
�Z�Z��@�����܂�(���E)�@��܁Z
�c���~
�Z�O�@�����܂�(�����p�ؑ\�n��)�@��܈�
�Z�l�@�c���~�̓m�i1�j(�Ή��p���q�S)�@��܈�
�Z�܌܁@�c�̐a�i1�j(���Z���p�̛��S)�@��܈�
�Z�ܘZ�@���i2�j(���Z���p�K�h�S)�@��܈�
�Z���@�c�ザ��(��t�p�����S)�@��܈�
�~�K�E���l
�Z�ܔ��@�\���Ղ̑�䕼(�����p���_��)�@��ܓ�
�Z�܋�@��{�~�Ѝ��X�̃J�Q�V(�����p���Ð�s)�@��ܓ�
�Z�Z�Z�@�c��Ղ̓n��(�����p�O���S)�@��ܓ�
�Z�Z��@���l�̕�(�����p���Ð�s)�@��ܓ�
�Z�Z��@�����~�Ѝ��X�̓��l(���E)�@��O
�Z�Z�O�@�Ō��Ղ̓��܂�(�����p�O����)�@��O
�Z�Z�l�@���n���̖ᖡ(�ΐ��p�P���S)�@��O
�Z�Z�܁@�����u(�����p���{�s)�@��O
�Z�Z�Z�@�V�k�O�܂�(��㊖{��)�@��O
���X�ƕW�R
�Z�Z���@�_���̎R��(�����p�����Y�S)�@��l
�Z�Z���@���`��(�b���p������)�@��l
�Z�Z��@���i(���m�p���m�s)�@��l
�Z���Z�@�����R(�����p�P�H�s)�@��l
�Z����@���[���[��(1)(�O�d�����h��)�@��܌�
�Z����@��(2)(���E)�@��܌�
�Z���O�@�������炱��(�R���p���s)�@��܌�
�Z���l�@�ʎ��(�A���p����)�@��܌�
�~���E�I�n�O
�Z���܁@�c���~�ւ̋�����(���Z���p�K�h�S)�@��ܘZ
�Z���Z�@�l�G�d�̖_(�H�c�p��k�S)�@��ܘZ
�Z�����@�䋟��(���E)�@��ܘZ
�Z�����@�~���̑��(�a�̎R�p�߉�S)�@��ܘZ
�Z����@�ݍH���~��(�����p���_��)�@��ܘZ
�Z���Z�@�����Ɍ}�����T�J�V�o(�����p���Ð�s)�@���
�Z����@�����̂��邵(���E)�@���
�Z����@�����̖���ɂ��Ă鏼(�����p���_��)�@���
�Z���O�@���̓��̃I�o�P(�����p�����S)�@���
�Z���l�@�I�E�_�\(�����p����s)�@���
�Z���܁@�I�n�P(�����p�O����)�@���
������a
�Z���Z�@�I�J�~�\�̓���ꎮ(�{���p������)�@��ܔ�
�Z�����@������l(�{���p�����S)�@��ܔ�
�Z�����@�����Ȃ��l(�R�`�p���c��S)�@��ܔ�
�Z����@������l���`��(����p���{�S)�@��ܔ�
�ޏ��@
�Z��Z�@���̛ޏ�(1)(���Z���p�o��)�@��܋�
�Z���@�q���֍s���ޏ��̗�(��㊋{�Ó�)�@��܋�
�Z��j�@�i�̎Q�q(��㊔��d�R��)�@��܋�
�Z��O�@���̛ޏ�(2)(���Z���p�����哇)�@��܋�
�a�悯�ƒ�����
�Z��l�@�������~�D(���R�p�a���S)�@��Z�Z
�Z��܁@���̓����̒��@�(�H�c�p���m����)�@��Z�Z
�Z��Z�@�����݂�(�����p�����S)�@��Z�Z
�Z�㎵�@���ǂ�(�����p�����S)�@��Z�Z
�Z�㔪�@�@�a�����̘m�l�`��(�H�c�p��k�S)�@��Z�Z
�Z���@������(��X�p�����j�S)�@��Z�Z
���Z�Z�@�叕���`(����p�v���S)�@��Z�Z
�J��
���Z��@�J��p(�V���p�O���S)�@��Z��
���Z�j�@�ޏ��𓊂��ĉJ��(�ޗ��p)�@��Z��
���Z�O�@�J��F?(���{���S)�@��Z��
���Z�l�@�m�ō�����~(���{�O���S)�@��Z��
�F��(1)
���Z�܁@�Б��呐��(�R���p�����S)�@��Z��
���Z�Z�@�R�_�}�l�ɏグ���(�����p����܌S)�@��Z��
���Z���@�r�~�l�ɏグ��m��(�����������S)�@��Z��
���Z���@�R���~�ւ̊肩��(�H�c�p��k�S)�@��Z��
���Z��@㉔n(�����p���x�Ò�)�@��Z��
����Z�@�a���F��(�����p���˓�)�@��Z�O
�����@�葫�̋F��(�H�c�p��H�c�S)�@��Z�O
�����@�鋃���̃n�C�d�g(�����p���p�S)�@��Z�O
����O�@�I�V�I�C�l(�����p���n)�@��Z�O
����l�@���̋F��(�a�̎R�p�어�K�S)�@��Z�O
����܁@��c���̌䕼(�H�c�p��k�S)�@��Z�O
�F��i2�j
����Z�@���̕a�̒n�U�l(�����p����S)�@��Z�l
���ꎵ�@��ꏂ��~�l(�Ή��p���ΌS)�@��Z�l
���ꔪ�@������̒n���l(���m�p���ԉ)�@��Z�l
�����@���S�x(1)(�����p����S)�@��Z�l
���Z�@��(2)(���E)�@��Z�l
����@���ׂ̒n�U�l(�����p�O����)�@��Z�l
����@�Зl(�Ή��p���ΌS)�@��Z�l
�܂��Ȃ�(1)
����O�@����悯�̂��D(����������)�@��Z��
����l�@���N�T���G�\�d�N(����p���g�S)�@��Z��
����܁@�B���a�悯�̎�(�H�c�p��k�S)�@��Z��
����Z�@�Ί��c(���Z���p�K�h�S)�@��Z��
�܂��Ȃ�(2)
���@���悯�̎�(�Ȗ��p���h�S)�@��Z�Z
���@���Ƃ��D(�����p��В�)�@��Z�Z
�����@���̐K��(�H�c�p��H�c�S)�@��Z�Z
���O�Z�@����̎���(�ޗ��p)�@��Z�Z
���O��@��`�Ǝq���̖�(�a�̎R�p�V�{�s)�@��Z�Z
���c�_���̑�
���O��@���c�~(1)(�����p���}���S)�@��Z��
���O�O�@��(2)(�~�ސ��p�k�`��)�@�ꎵ��
���O�l�@��(3)(�R���p���R���S)�@��Z��
���O�܁@��(4)(�{���p�ɋ�S)�@��Z��
���O�Z�@��(5)(���E)�@��Z��
���O���@��(6)(�������쑽���S)�@��Z��
���O���@��(7)(�~�ސ��p������S)�@��Z��
���O��@�ǂ��낭�l(���{���S)�@��Z��
���l�Z�@��c�l���K(�������ɓ��哇)�@��Z��
���l��@�W���l(���E)�@��Z��
���l��@�G�r�X�~(�����p�����S)�@��Z��
���l�O�@�K�[�^��(�����p�ܓ�)�@��Z��
���l�l�@�q���ω�(���Z���p�o���S)�@��Z�� |
�S���A����K��E�������ꂪ����w�����w�p�������ҁu����w�����w�p�������I�v
= Bulletin of the Institute of Oriental and Occidental Studies, Kansai
University (45) p.107-129�@����w�����w�p�������v�Ɂu�����̓`���I�W���i�ςƂ��̍\���@-�ÉF����������Ƃ���-�v�\����B�@�@�d�v
|
����тɈ͂܂ꂽ�W���̌i�ϐ}�f�ڗ\��
|
�T���A�u�R���N�V�����푈�ƕ��w : �n��� �Q�O�@�� : �I�L�i���I���ʐ푈�v���u�W�p�Ёv���犧�s�����B�@�@
�@�@�@�@�ҏW�ψ��F��c���Y�C������C�쑺���C�����q�v�C���c���� �ҏW���́F�k�㎟�Y
|
�P �C�� / �����p�g
�l�ފ� / �m�O���^
�Q �����̚L / ��������
�J�N�e���E�p�[�e�B�[ / ��闧�T
�M���l�����~ / ���g�h��
�ÊԗǐS�� / �g�c�X�G�q
���a�ʂ�Ɩ��t����ꂽ�X������� / �ڎ�^�r |
�R �� / �c�{�ՕF
�ӂ����сu����̓��v / �����ɓs�q
�� / �D�J�����Y
���Ȃ�� ���Ȃ錊 / �ˎR�P
���G�����ǂ��֍s�� / �R�V����
�A�J�V�A�� / ���Ǖ�
��� |
��� / �����q�v
���ҏЉ�
���^��i�ɂ���
����
���G��� / �؉����G
�E
�E |
�T���A�R�����ꂪ�u�Ñ�̗����ʂƓ��A�W�A�v���u�g��O���فv���犧�s����B�@
�@�@�@ (���j�������C�u�����[ ; 343)�@192p �@�����F��㊌����}���فF1007217795
|
�����ʂւ̎��� - �v�����[�O
�����I�̗����ʂƓ��A�W�A
���N�Ɨ���
�����ʂ̓��X
���`�㐢�I�́u�쓇�v�ƌ����g�q�H |
�K���g�̔h���Ɠ쓇�l�̗���
�����g�Ɓu�쓇�H�v
���m���猩��������
�����ʂ̌��Օ�
�����ʏo�y�̊J���ʕ� |
��Z�`��O���I�̗����ʂƓ��A�W�A
��Z�`��ꐢ�I�O���̓�ƃL�J�C�W�}
��ꐢ�I�㔼�`��I�̗�����
��O���I�̗����ʂƗ������̓���
�E |
�U���A�u�Ñ㕶�� = Cultura antiqua 64(1) (�ʍ� 588)�@(���S ���k�A�W�A�̕���`�Ί�)�v���u�Ñ�w����v���犧�s�����B�@2012-06
|
����{�k���ɂ����鉑�r : �u���щ��v�Ɓu�쉑�v�Ɋւ����l�@ �{���[�� p.1-21
�ꕶ�����E�ӊ��̈�ՌQ���� : ���E�剈�ݕ��ɂ����鍕�F�����y����̌���
�{�n����Y p.22-41
���m���̕��� : ��Ẩ��Ó����N�_�Ƃ����s�s�v�� ���ƖF p.42-65
���S�w���k�A�W�A�̕���`�Ί�x�Ɋ� ���c �T��,���O ���l p.66-68
���V�A���C�n���̕���`�Ί� : �L�Ґn�� O. �����V�i,���c�T�� �� p.69-81
���N�����̓����͕�Ό��@ �� ���M,���c�T�� �� p.82-91
���{�ɂ������������͕�Ί�̏o���ߒ� ���O���l p.92-104
�����[���b�p�E�X�J���W�i���B�A�ɂ�����t�����g�Z���̔��B�Əd�v�� :
�@�@���v�V�E�������e�E�V��Ȍ`�Ԃ̑n�� C. �t���[�}��,���c�T�� �� p.105-122
�w�j ��p�ɋA��������������搶�̎��� �؉����q p.123-128�@�@�d�v
�Ǔ� ���c�C�搶���Â�� �{�� ���i p.132-134
�}�ʼn�� �������E���O���\�V�Z��(�����Ǒ����O���)�̒��� �@�ې�`�L p.135-137,�}����3p
�}�ʼn�� ���O��N��������� �U�ʓ��������������� ���я��� p.138-140,�}����1p
���] �����l�Ì�����ҁw?�̌��� : ���[���V�A�����̍Պ�E�Y��x�@ ������N
p.141-143 |
�U���A�J�쌒�ꂪ�u�J�쌒��S�W 7 (���� 3)�@�S��C��̓��E���{�Ɨ��� ; ���̎v�z
: ���v���u�y�R�[�C���^�[�i�V���i���v���犧�s����B�@
|
�S��C��̓��E���{�Ɨ���
���z�̓��A�|�����̉F����
�����邢���{�|�����̑��E��
���̎v�z
�쓇�ւ̂܂Ȃ��� |
�Ñ���{�Ɨ���
�v�����̎���
�C�̗��K�_�|�쓇�𒆐S��
�����瓌�ց|�w�Î��L�x�Ɨ���
����̓��{�� |
�،��̈Ӗ��������
���v�f�ՂƓ�������
���A�W�A�̂Ȃ��̉���
�E
�E |
�U���A�u��r���x���� = Japanese journal for comparative studies of dance : ��r���x�w��w�p�@�֎� 18�@���W �`���|�\�̌p���ƌ^�v���u��r���x�w��v���犧�s�����B�@
|
���x�ɂ����鉹�y���Y���ƐU��̊W�ɂ��� : �叞�_�y�̏ꍇ �����R�z�q
p.1-8
�������x�ɂ�����ʏ鐷�d�n����h�̌n�� �g�Ɗԉi�q,���i�~,�ԏ�m�q p.9-18
�������x�ɂ�����Z�@�u�K�}�N����v�̓`�� : �ʏ鐷�d�n����h��Ώۂ� �g�Ɗԉi�q,���i�~,�ԏ�m�q
p.19-27
�����ÓT���x�ɂ����鏗�x��́g�K�}�N����h�̓`�� : �ʏ鐷�d�n���h�̕�����蒲������@�@�ԏ�m�q p.28-38 |
�W���A�������ꂨ���Ȃ풲���{���ەҏW�u�o���G���v���u�������ꂨ���Ȃ�v���犧�s�����B
�@�@
(�������ꂨ���Ȃ�㉉�����W, 27 . �������)
|
�u�o���G���v�Ƃ��̏㉉���ꂽ��Ɋւ����l�@ / ��؍k��[��]
�n���ʼn������Ă���g�x�̖��� / �X�۞Ď��Y[��] |
�u���w�������Ό����v�Ɓu�c���x��v / ���J�\�Z[��]
�g�x�́u���t�v�Ɋւ��钍�߂Ǝ�̍l�@ / �r�{����[��] |
�W���A�O�����Y�ďC�u����g�x�I�W ���ꕜ�A40�N�E�u�g�x�v�d�v���`�������w��40���N�L�O�v���u���{�R�����r�A�v���犧�s�����B�@�@�@�@�@�r�f�I�f�B�X�N 2�� (120��) : DVD�@�@ ���^: 2004�N2��, 10��, 2003�N3��, 2008�N9��, 2001�N2�� �ق�
|
| DISC1 |
(1)���S����(���イ���˂���)(2)�G��(�ɂǂ��Ă�����)(3)�����q(�߂��邵�[)(4)������(����Ȃ��̂��邢) |
| DISC2 |
(1)�F�s�̊�(���������̂܂�)(2)���ΓG��(�܂��Ă�����)(3)�Ԕ��̉�(�͂Ȃ���̂���)(4)�萅�̉�(�Ă݂��̂���) |
�o��:�V�_��/���]�S�g/�Î芡�ш�/���ꐳ��/��Ï�F/���܌��q/�_�J���j/��p�O��/�ΐ쒼��/�{��\�P/���܌���/�F���m��/���ÏC/���c�q�V/�e���v��/�ԗ䐳��/��×ǗY/����������/�얞����
���y:�ƉÖ�����/���]��t/��n����/�V�_���P/���܌��j�@�@����:�`���g�x�ۑ���
�ďC:�O�����Y ���:���{ |
�X���A�u�I�L�i���O���t (606) p.30-35�v�Ɂu���̂���ۓ�(��71��)�G�C�T�[�̂܂�����s�v���f�ڂ����B
�X���A�j�E�����E�G�C�T�[�Վ��s�ψ�����ǕҏW�u�j�E�����E�G�C�T�[�Ղ� : ����{�y���A40�N�E�吳�搧80���N�L�O 38�v���u�j�E�����E�G�C�T�[�Վ��s�ψ�����ǁv���犧�s�����B
�X���A���{�q�ǂ��̖{������ҁu�q�ǂ��̖{�I : �������]�� 41(9) (�ʍ� 527)�@���W
���ꕜ�A40�N : ���ꂩ��̔��M�v�K�u���{�q�ǂ��̖{������v���犧�s�����B
|
�X�~���ƌR�p�@ : �u���ꕜ�A40�N�v���l���� ���� �̂肱 p.18-20
�{�y���A40�N�ڂ̕��a���� �@�R���~�qp.21-25 |
�N�ǂƓ������ŕ��a�M : �G�{�̒��Ɍ����������� ���Nj��q p.25-27
�E |
�P�O���A���c�M�j, �O�钼�q, �{�����W���u�������鐶�� : ����̓������]�v���u�䒃�̐����[�v���犧�s����B
|
�V��Ƌ]�� / ���c�M�j ��
�쓇�ɂ�����V�}�N�T���V�̐��i / �{�����W �� |
�n�}�G�[�O�g�D�Ɖ���̓������] / ���c�M�j ��
���͂Ȃ���������̂� / �O�钼�q �� |
�P�P���A���{���v��p���Z��������ҁu��p���Z������ ��16��(2012)�v���u�����Ёv���犧�s�����B
|
��p���Z��������Ղ��� : �ɔ\�Ë�̏W�c���ނ��߂����� / �}��/����
���������B�e<���t>�̋^�� : �g���Îʐ^�����m�[�g 2 / �F��/����
��p���Z���ɂ�����<�����̎�>���_ / �R�c/�m�j
��p���Z�����Ɣ������Q : �� / ����/����
��p�̐l�ފw�����ɂ�����u�o�g���E�^�b�`�̋V���v : 1926�N4���̐X�N�V������ڐ�q�V���ւ̎莆
/ ���V/���O��/�T�q
�u��p���Z�����̉��y�ƕ����v���ۊw�p�V���|�W�E�� : �V���ɂĊJ�Â̕� /
�R�c/�m�j
�u��p���Z�����̉��y�ƕ����v���ۊw�p�V���|�W�E�� : �u��p���Z�������y�̉��t�v�̕� / ���ь��]�@p.142-144
��X�⏕���Y�Ƒ�p���Z�������z���� : ��5����䌴�Z���������t�H�[������
/ �|��/�b���q
�����i���w��p���Z���Љ�̒n����:�}�C�m���e�B��20���I�x / �t�R/���N
���c�g�Y���w��p���Z���̎Љ�I�������Ɓx / �{��/�^���q
�n糏��j���w�g�̂ɑ����ꂽ�L��:��p���Z���̓y�U�������o�x / �R�c/�m�j
�ɓ����q���w����:�^�C�������̘N���̌����x / �F��/����
�яi�����w����I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�Ɖؐl:���q���j:��p������Ƃ��āx /
�Ί_/��
��쓿�����w��p�����K�ɏ������̋�:���Q�̖��T�I�Ɠ��{�x / �V���c/����
�L�L�E緐����E������ҁw�������⚬���~���@�x / �p��/����Y
���u�O�E�k���O�ҁw���⏕���Y���s�������Z�ƒ�����㉎�e�S�W(��)�E(��)�x
/ ����/��
�V����w�����V���Q�l�ٕҁw��p�������A���������̋L���x / �R�{/�F��
�Ȃ�ƂȂ����S�n�̈����P�� : �J�i�J�i�u��́u�@�v / �y�c/��u |
�P�Q���P�S���A�����Ɩ����S���Ȃ�B�i���N�W�Q�j
�P�Q���A������w�ҁu�A���[�i ��14��(2012)�v���u������w�����w�p�����@�v���犧�s�����B�@�@
|
������ / �n�/�ӗY
�����v�z�Ɠ��A�W�A : �w�ۃV���|�W�E�� / �n�/�ӗY
����̕����t�ɒD��ꂽ���̔�� :
�@�@�������Ŗk�[���R�����ɂ�����`���ƕ������H / �����G�C
�������e�̉ϐ��ɂ��� :
�@�@���q�ƈ͗������߂���i�ϐl�ފw�I�l�@ / �͍�/�m��
����́u����v�тɊւ��錤������ / �Y�R/����
�؍������̌`�ǘ_�I���� : �u�C�v�́u�������v�ɕ\��� / �F�J����
���ꌧ�ɂ�����n�А}�E�y�n�䒠�Ƃ��̊��p / �R���M�p
����Z�N��́u�����u�[���v�̎Љ�w�i���čl���� / ���эG��
�C���h�̎��@�ē��o������(�p���_)�̑��^�}�[�P�e�B���O / �a�J�r��
�X��Ǖ����ꂽ���F���t�̐��� / ����/��
����H�炤���� : �^�C�ɂ����郉�[�t���q�V��ɂ݂�
�@�@���t���R���ۂƃq�g / ����/�G���q
�u�[�^���̋ߑ㉻�ƕ������@ / �e�c/���q
�u�[�^���G�L : �����������u���Ƃv�̐��X / ���c���q
���V�x���A�E�n���e�B-�}���V�����Nj�ɂ�����Ζ��J��
�@�@���ƃg�i�J�C�q�{�� / ��ΘЍ�
�Ă�����Ȃ���n���s��! : �Z�l�K���̎q���̍s���^�[�W�F�{��/���b�q
�푈�V�~�����[�V�����E�{�[�h�E�Q�[���������悤 :
�@�@���A�t���J�Ń`�F�X������O�̔錍 / ���O�m
�R�[�q�[�̗t��n�� : �G�`�I�s�A�쐼���J�t�@�n���E
�@�@���u�R�[�q�[���˂̒n�v�ɂ�����`�F�[���̈��p / �g�c���I��
�W�F�l���[�V�����E�M���b�v�Ɓu���ҁv :
�@�@���A�t���J�̎q�ǂ������ɂނ��� / �����M�v
���o���畨��� : �J�����[���암�t�@���l
�@�@���Љ�ɂ����郓�r���V�炩�� / �_�J�ǖ@
�����̎�������<�y����> : ����̖͍�������Ƃ��� / �g�c����
���� : �����W�c�Ƒ�w�ɂ�����l�ԊW�̔�r / ���ыM�K
�u��������v�Љ�ł̔N�V�������l���� / �������T
���҂ƏZ�܂� : �p���ɂ����鋤�Z�̎��H / ����m�q
�����I�Ȓ����l�ό��q / �c���F�}
�J�c���ő傯�������鏗������ / �n糖�����
�u�a���v�_�Ɍ����Ă̒f�� / �_�Y��
�s�v�c�Ȗ� : �`�����̑��̔閧 / �c��
������̂��ׂċ��Ȃ炸 : �킪�Ƃ̖������`��/������v��Y |
�̘b�ƍĐ��|�p / �֓��݂�
�e�a���l�ȋʓ��P�`���Ɋւ����l�@ / ���R�R�z�q
�Ȃ��c�����̂�? / ��/�[��
�u�V���v��҂� : �z�K��Ќ䒌�ՁE�䒌���� / �ΐ�r��
�u�t�v�ւ̎肪���� : �O�ؘj�Ƌ{�{��� / �r�c����
�u��v�ɂ��čl���� : ����Љ��/
�@�@���H�Ɛ��i�̕����������� / ���ѓߗR��
�����l�̐S�� : ���Ɖ��y�� / ������q
���{���s�ɂ̓J���[�������Q���ׂ� : �H�����l����
�@�@�������`�吳���̊O���l�ɂ����{���s / ����_��
�u�����v�Ɓu�������v�Ɓu�����������v�̂Ȃ��� / ��q�L��
�u����v���Ёv�Ƃ����M�� : �L����H�闷 1 / ���R���N
�[�����̃f�U�C���ϗe�Ƒ��E�� / �������b�q
���F�g�i���푈�ƃe���r�E�h�L�������^���[ / ��ԗD��
�u�W���X�~���v���v�ƃ`���j�W�A�j / ����/���Y
�q�}�����A���̕���_ : �l�p�[���A�J���E�K���_�L / �n�i�k�X�r�g
��Õ���ŃX�s���`���A���e�B�̖���_���邱�ƂɈӖ���
�@�@������̂�? : ��w�T�_����̍l�@ / �����ǕF
�����ƃX�s���`���A���e�B : 3�E11���牽���w�Ԃ̂�/����F�u
NDE(�Վ��̌�)���� : �Ȋw���U�Ȋw��? / �J�[���E�x�b�J�[
����̃X�s���`���A���e�B�T�� / ��吳�K
�u�ܑ�v�v�z�̎����� / ���{��
�k�ЂƓ��k / �ԍ⌛�Y
���Ɠ��� : 3 �b��(����12�{)�̓V���E嶁E�ˎ� / �x����
���c�c�C�b�^�[�A�n粋ӗY����̂Ԃ₫�Ƃ������� / �~����
�S�h�t���[�E���[���n�[�g�A�C�M���X�Љ�l�ފw�� / �����M�O
�ߋ����Ȃ�������ɂ��Ȃ� : �S�h�t���[�E���[���n�[�g��
�@�@���Љ�l�ފw�o������ / �o����
1977.Silver Jubilee / ���O�l
�I��O��̔o�d���� �����E�V���u���̒��Օ\ :
�@�@���n�Ă����������w�u�o��v�̍l���w : ����2/����h�O�Y
�n���ɍ��܂ꂽ�����̋L���E�ЊQ�̋L�� / �����m��
�u���l����������҂����v�o�ł̓^�� / �����q�F
����V���[�}�j�Y���̋ߑ� / ����舢��
�펞���̌o�ϊw�� / �e�Y���q
�����m�Ƃ��Ă̕��� |
���A���̔N�A���ь��]���u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (78) p.146-148�v�Ɂu���ЏЉ� �v���c�W���w����̖����|�\�_ : �_�Ղ�A�P���ۂ���G�C�T�[�܂��x(�p���E�����m�� �@����w���ꕶ���������ďC)�v���Љ��B�@�@�R�R�O�O�~
���A���̔N�A�^�������i�X�S���j�u����̌×w, . ���ꏔ���ҁ@�㊪�@�암�v���u���ꌧ�����U����v�����s�����B
�@�@�ďC: �g�Ɗԉi�g�@�@�E�����: ��Éx�q, �g�Ɗԉi�g�@�@���^: 2008�N6��,
2009�N4��, 2010�N10���E11��, 2011�N9���E10���E11��
|
DISC1�q�ߔe�s�r
(1)����(2)���肶��O�F�[�i(3)���O�F�[�i(4)����O�F�[�i
(5)���O�F�[�i(6)����(7)���ǃO�F�[�i�q�ߔe�s�����r
(8)�Ђ傤����x��q�ߔe�s���r
(9)�n�o�[���[�̉́q�����s�����r
(10)����[���̉́q�����s�^�h���r(11)�^�h���C�₩��[ |
|
DISC2�q�^�ߌ����^�ߌ��r
(1)�O�����̉́q���s���~��o���r(2)�O���G�C�T�[�q���s�ʏ鉜���r
(3)�ߔe��(4)�V���ߎu(5)��������q���s�m�O�v���r
(6)�ƃ��T�f�[(7)���z�_(8)�R�C�i
�E
�E |
���A���̔N�A�^�������i210���j�u����̌×w ���d�R������ ���� (�|�x���E�����E���l���E���ԓ��E�^�ߍ���)�v���u���ꌧ�����U����v�����s�����B
�@�@�ďC: �g�Ɗԉi�g ���L �E�����: �g�Ɗԉi�g, ���{, �R�钼�g�@�@���^: 2007�N2��, 5��, 10��, 2008�N5��, 2009�N4��
|
DISC1�q�|�x���r(1)�ʒ[��(2)���ʂ܂ꂫ��ǂ���
(3)�J�J�ӂ��[�ӂ��[(4)�������ʖ�
(5)�T�[��������܂����E�������ł�(6)�R�r
(7)�債��債�㒱(8)�\�Z���\(9)����ʌ����
(10)���ʈi(11)�w�Z��(12)���ʋr
(13)���[��������h���h��(14)�s�[���[�V�ʃ��b�p�[��
(15)���݂���(16)������A���[(17)�������~
(18)�����������^�q�����r(19)���������A���[(20)���������^
(21)�D���������^(22)��(23)�L�N�W���o(���x���)
�E
�E
�E
�E |
|
DISC2�q�����r(1)�Ƒ���W���o(2)�l��ʐ璹�܃A���[(3)�����u��A���[
(4)�T�V�j�I�A���[(5)�����A���[(6)���c�W���o(7)�i�T�}���W���o
(8)�����W���o(9)�F�t�_�C�q���l���r(10)�R�~�A���[
(11)�Ђ��x�A���[(12)���ނƂ���x�A���[(13)�����W���[
(14)�_�[�g�D�_�[
DISC3�q���l���r(1)���l��(2)�͂҂�(3)�����Y
(4)�݂�܂�O���q���ԓ��r(5)��F��(6)�V�~�ʉ�(7)�Â܂ʂ���
(8)����W���}(9)���g���W���}(10)����܁[��
(11)�������ȁ[(�j�������[��̉�)(1)�q�^�ߍ����r(12)�Ƃ������
(13)��������(14)�q�h�D���^(15)�͂�������(16)�䂪�D�f�B���o
(17)�Ƃ����(1)�@�D��(18)�Ƃ����(2)�ފ�(19)�Ƃ����
(3)�f�B�g�D�o���}(20)�Ƃ����(4)�����g�D�o���}
(21)�v���Ă���(22)����ʉ� |
���A���̔N�A�u �N�C�`���[�p���_�C�X����|�\�R���T�[�g : �{�Ó��̂܂�E�������x�E�G�C�T�[�v���u�i��茧�{�Áj�d���Ƌ����g���v���犧�s�����B�@�@�����F��茧���}����
���A���̔N�A���{�������w�ҋ���ҁu���{�������w 58(1) (�ʍ� 597) ���W
����̑n���́E����ւ̑z���́v���u���{�������w�ҋ���v���犧�s�����B�@�@
|
�Ăʓ� �@�������� p.12-18
����̐����ʂ��� �@�^��a�q p.20-25
���ꎙ�����w�T�� �@�V�؊���q p.26-33 |
����̎q�ǂ������鏔��� : �u�q�ǂ��̓��E����v�ւ̖� ��{ �O�g p.34-39
�K�W���}���̖̉��ō������ɉ : ���̉��ꎙ�����w�m�[�g�@���� �̂肱 p.40-45
���w�̓y�� : ���ꐶ���� �@���Ǖ� p.46-51 |
���A���̔N�A�^�������u����̌×w ���ꏔ���� �㊪ (�암)�v���u���ꌧ�����U����v���犧�s�����B
�@�@�@�@���×w�̎��^��Ƃ�2006�N12������2011�N11�����s���܂����B
|
|
�� |
���^�N |
����̌×w�� |
���s�N |
| ���ꏔ���� |
�� (�암) |
2008�N6��,
2009�N4��,
2010�N10��, 11��,
2011�N9�� �ق� |
DISC1�q�ߔe�s�r(1)����(2)���肶��O�F�[�i(3)���O�F�[�i(4)����O�F�[�i(5)���O�F�[�i(6)����(7)���ǃO�F�[�i�q�ߔe�s�����r(8)�Ђ傤����x��q�ߔe�s���r(9)�n�o�[���[�̉́q�����s�����r(10)����[���̉́q�����s�^�h���r(11)�^�h���C�₩��[
DISC2�q�^�ߌ����^�ߌ��r(1)�O�����̉́q���s���~��o���r(2)�O���G�C�T�[�q���s�ʏ鉜���r(3)�ߔe��(4)�V���ߎu(5)��������q���s�m�O�v���r(6)�ƃ��T�f�[(7)���z�_(8)�R�C�i |
2012 |
| �� (�����E���ӗ���) |
2009�N8��
2010�N12��, 10��,
2011�N4��, 11�� �ق� |
DISC1�q�X��p�s�X��p�r(1)�O����(2)�X��p�����q����s���A���~���r(3)����[(4)���A��(5)����̔ԏ�(6)����[���̉�(7)�Ƃ̉×�̉�(8)�䂪���킻�Ă��q����s�^�ߏ镽�����r(9)����[(10)����͂���(11)�Ă���������(12)�Y�X�̐[����(13)���܂₵��(14)����(15)���߂�[(16)�͂���
DISC2�q���Ԗ������Ԗ��r(1)��Ղ̃E���C(2)�܌���Ղ̃E���C(���_)(3)�܌���Ղ̃E���C(�[�_)(4)�務�̕��肢(�C�̌��)(5)�l����(6)�ԓo��(7)�O���O���q�������r(8)����������������(9)���ˁ[�ރE���C(10)�����Ƃ�(11)���ю��(12)�����E���C(�j�V�k�q�[�^)(13)�Ɗ얼��(14)�V�^����(15)������̌���q�ɍ]���r(16)�������F��̉�(17)������O�̐�h��(18)���[�̑O(19)���낵���q�ɐ����������q�r(20)�e�B���N��(21)�ݝ������q�ɕ������c���r(22)�e���R��(23)�e�̈⌾
|
2012 |
| ��(�k��) |
2008�N11��
2009�N9��, 3��, 8��,
2011�N11�� �ق� |
DISC1�q���[�������r(1)���[��(2)���ʂ߁[(3)�Ђ����g�x(4)�X���S��(5)���傳���q�{������u���r(6)�����x��(7)�V�̌Q��(8)��{��(9)�^�ӂ̑傠����(10)�͂[����(11)�r�Ԃ炵�q���A�m���r(12)���A�m�~���[�N�j�[�q��X���������r(13)�����g�̑��x��
DISC2�q���������ԁr(1)���c�ΕӒ��(2)���̍���(3)�k�J�^��(4)�Փ��R(5)���̖�(6)���̕�(7)�オ�苋���(8)�������(9)���̕�̂߁[����[(10)�_���̉���(11)���(12)�₠�G(13)���܁[������(14)����(15)���ڂނ��ρ[(16)���炽�[�ˁ[(17)���̎q�Ƃ����̎q(18)�ڂ̌������(19)�^(20)�^�q�������^�߁r(21)������(22)�ɏW�̍����E�n���R�[���}�R�[(23)�����߁E�C�y(24)�^�_�߁E���g�̂͂Ȃ�(25)�ӕ~��(26)�c�����x�߁q���������c�r(27)�F�n����(28)�܂͂��(29)�������(30)�C�̂�����(31)�n���o�R�[��(32)�Y�X��(33)�C�̂͂�(34)�����q���������g�r(35)�O�N�܂�̂��ʂ���(36)���[��(37)�U�R��(38)�����ɋ���� |
2012 |
| �{������ |
�� (�r�ԁE�떓�E�����E�v��) |
2007�N7��, 10��,
2008�N7��
2010�N8��, |
DISC1�q�r�ԁr(1)�����B�������ʊ�荇����(2)�����ʌւ炵���(3)��l�N�C�`���[(4)���h���ʃA�[�O(5)�\���l��(6)�ݑ��z(7)�ꑾ�z(8)�i�C�J�j(9)�ቤ(10)���m(11)�J�(12)�r�ԃ}�[�W�B�~�K(13)�^�앗�ׂ��~�K�}�}(14)�M�r�݁q�떓�r(15)���l��ʃt�T(16)�V�ʐԐ��ʃj�[��(17)���^�ʂʃj�[��(18)�^�Ð^�ǂʃj�[��(19)���a�ʃj�[��(20)������ʃj�[��(21)���Ԍ��ʃs���[�V(�j)(22)�u�����ʃs���[�V(23)���䌳�ʃs���[�V(24)�\�ܖ�ʍj�����ʃA�[�O
DISC2�q�����r(1)�����B�������ʊ�荇����(2)�~�����x��(3)���h���ʃA�[�O(4)�����炵�A�[�O(��������)(5)�����炵�A�[�O(6)�\���l��(7)����ʃA�[�O(8)�_���g���N�C�`���[(9)���[�z�C�z�C(10)�}���ʃA�[�O(11)���Ԃ��ʃA�[�O(12)�{�Ð߂ʃA�[�O(13)�e����ʃA�[�O(14)��M(15)�x�M���M(16)�Ƃʌ�O��(17)�Ƃʐ_���g���A�[�O(18)�����ʃA�[�O(19)�\�����Ă��ʃA�[�O(20)�r�ʑ�i�L���e(21)���ԃ}�O���C�ʃA�[�O(22)���Ԃ������~�K�K�}(23)�l���ʎ�(24)�����ʃ}���C(25)�����^��(�q���)(26)�����Ȃ�킪�܁q�v���r(27)���N�C�`���[(28)���g�[�K�j(29)���ʑ�ނʑ� |
2012 |
| �� (��ӁE�V��E�F���E����E�����E�V���E����q���[�r�E�ɗǕ��E���NJ�) |
2007�N10��,
2008�N6��, 7��
2009�N7��
2010�N8���ق� |
DISC1�q��Ӂr(1)�Ȃ��܃A���O(2)�����}�u�i�����ʃA�[�O(3)�J�j�V�B�}�q�V��r(4)�V��N�C�`���[�q�F���r(5)���x��(6)�����Z(7)�F���N�C�`���[(8)�j�����ʃA�[�O�q����r(9)�������s���[�V(10)�ꉄ���ʃA�[�O(11)����ʃA�[�O(12)���x��(13)����N�C�`���[�q�����r(14)�M�s���[�V�ʃA�[�O(15)�e����[(16)�����N�C�`���[(17)�L�N�ʃN�C�`���[(18)�^�ߗ�ʎo���ʃN�C�`���[(19)�����ԁq�V���r(20)����(21)�V����q����(���[)�r(22)���ʃj����(23)���ʃj����(24)�[���ʃj����
DISC2�q�ɗǕ��r(1)�n�C���[�k����(2)�����Âʌ��v(3)�����Ⴊ�܃A�[�O(4)���g�[�K�j(5)�ɗǕ��g�[�K�j�q���NJԁr(6)�����a���j����(�i�K�V�K�[)(7)�����ꂪ(�i�K�V�K�[)(8)���NJԓ���(�i�K�V�K�[)(9)�Î芡�ʃj����(�t�_���[)(10)�����a���j����(�t�_���[)(11)�����ꂪ(�t�_���[)(12)�����ꂪ(�A���[�L)(13)���[�ʃj����(�i�K�V�K�[)(14)�Ƃʕꂪ�j����(15)�����ʃG�[�O(16)���NJԐ�(�E�K���v�g�D�L�ʑ��NJԐ�)(17)�J��ʊ肢(18)�A�_�����ʈi(19)���u�����(20)�����z�^�ߔe(21)��_�ʃG�[�O(22)�e��ʃG�[�O(23)�G�ʕ�(24)����(25)���NJԃV�����J�j |
2012 |
| ���d�R������ |
�� (�Ί_��) |
2006�N12��,
2007�N2�� |
DISC1�q�Ί_�s�V��r(1)��_��(2)�A���p���ʂ݂����[�܃����^(3)�L�����^�q�Ί_���Ί_�r(4)�~�V���O�p�[�V�B(5)���[���[�܈�˃W���o(6)�D�ʐe�����^(7)��������[�܃����^�q�Ί_�s���r(8)�ӂ�ӂˁ[-����䂵(9)�h�����^(10)�R�������^(11)���o�ʂ͂Ȃނ�(12)���c�⍲���
DISC2�q�Ί_�s�o���r(1)���������W���o(2)������[�������^(3)�Ì��̉Y�����^(4)�q�����^�q�Ί_�s�����r(5)�䂪���������^(6)���胆���^�q�Ί_�s��l�r(1)����(2)�Î芡�W���o
DISC3�q�Ί_�s�{�ǁr(1)����[�܃A���[(2)�q�j���A���[(3)�D�ʐe�W���o(4)�����ʂԂ����W���o(5)���股������W���o(6)�Ɓ[��W���o(7)����ӂ˃����^�q�Ί_�s���ہr(8)���A���[(�d��̎�)(9)���S(10)��������-���̓n-����(11)�ڂ��ہ[�߁q�Ί_�s�약�r(12)���˂܂ʂ����ρ[��(13)�����ց[�ʂԂ��[(14)���[�҂����[(15)�͂����肳�[(16)����ρ[��(17)�������肨�[��q���d�R�S��r(18)��Ƃ���[��(19)�Ƃ���[�� |
2008 |
| �� (���\�E�g�ƊԁE�V��) |
2007�N2��, 5��, 8�� |
DISC1�q���\���痧�r(1)�D�ʎ�(2)�D�ʃW���o(3)������ɂ�(4)�Ƃ�����܁q���\���c�[�r(5)�Ė���̃����O�g�D(6)�c�A�W���[(1)(��ԃW���[)(7)�c�A���W���[(2)(��ԃW���[)(8)�c�A�W���[(3)(�O�ԃW���[)�q���\���D���r(9)����ݒ�(10)�ڎ�(11)�D�͂�(12)����ʂӂ��炵���
DISC2�q���\���Ì��r(1)�䂪����c�ʕ�(2)�ƍ��̃����^(3)�Ì��̉Y�ʂԂȂ�[�܃����^(4)�삳�����q�g�Ɗԓ��r(5)���x��̃W���o�O��(�p�M)(6)���x��̃W���o����(������)(7)���x��̃W���o���(��쉺������܂�)(8)�܂₵���܂�т�A���[(9)�҂Ă�����W���o
DISC3�q�V�铇��n�r(1)��������(2)������(3)���Ԃʂ҂�(4)�^�ӂ݂���(5)��邩��[��(6)�ς������[(7)��(8)���Ƃ悢�̂���(9)�����ʂςȐ߁q�V�铇���n�r(10)�吢-�����ʓ�(�v�[���̃U���}�C�̉�)(11)�_�M�̃W���o(12)�ʂ�Ԃ���-�Ɍ |
2011 |
| �� (�|�x���E�����E���l���E���ԓ��E�^�ߍ���) |
2007�N2��, 5��, 10��,
2008�N5��,
2009�N4�� |
DISC1�q�|�x���r(1)�ʒ[��(2)���ʂ܂ꂫ��ǂ���(3)�J�J�ӂ��[�ӂ��[(4)�������ʖ�(5)�T�[��������܂����E�������ł�(6)�R�r(7)�債��債�㒱(8)�\�Z���\(9)����ʌ����(10)���ʈi(11)�w�Z��(12)���ʋr(13)���[��������h���h��(14)�s�[���[�V�ʃ��b�p�[��(15)���݂���(16)������A���[(17)�������~(18)�����������^�q�����r(19)���������A���[(20)���������^(21)�D���������^(22)��(23)�L�N�W���o(���x���)
DISC2�q�����r(1)�Ƒ���W���o(2)�l��ʐ璹�܃A���[(3)�����u��A���[(4)�T�V�j�I�A���[(5)�����A���[(6)���c�W���o(7)�i�T�}���W���o(8)�����W���o(9)�F�t�_�C�q���l���r(10)�R�~�A���[(11)�Ђ��x�A���[(12)���ނƂ���x�A���[(13)�����W���[(14)�_�[�g�D�_�[
DISC3�q���l���r(1)���l��(2)�͂҂�(3)�����Y(4)�݂�܂�O���q���ԓ��r(5)��F��(6)�V�~�ʉ�(7)�Â܂ʂ���(8)����W���}(9)���g���W���}(10)����܁[��(11)�������ȁ[(�j�������[��̉�)(1)�q�^�ߍ����r(12)�Ƃ������(13)��������(14)�q�h�D���^(15)�͂�������(16)�䂪�D�f�B���o(17)�Ƃ����(1)�@�D��(18)�Ƃ����(2)�ފ�(19)�Ƃ����(3)�f�B�g�D�o���}(20)�Ƃ����(4)�����g�D�o���}(21)�v���Ă���(22)����ʉ� |
2012 |
|
|
| 2013 |
25 |
�E |
�P���Q�U�E�Q�V���A���m�ڑ�w�ɉ����āu�V���s�W�E���E�g�A�W�A�̊o���h�Ɠ��{���A�W�A�w�����̂��߂Ɂv���J�����B
�P���A�c�R�P�� ����E,�{��M�E �Ғ��ďC�u���I���d�R�ÓT���w�W 4 �v���u��������v���犧�s�����B�@
|
���� �����炵�������S�̌����@��闧�T�@4
���� �����i���̑b�ƂȂ�����@�����q���q�@6
���� ��߂̉̕���ɐG�ꂽ�d�����@��ÍN�t�@8
����-�w��l�W�x�̐���E�ҏW�ɂ�������-�@10
�O���̂͂��ׂ�<�`��>�Ə̂��@12
�y�}��z�@16
���d�R�ÓT���w�̉��ߕ\�@18
���d�R�ÓT���w�̓��ꉹ�߂���юg�p��@20
��������(�{���q)�@22
���₩���(�{���q)�@34
�O�Ō���(�{���q)�@42
�����Ɓ[���(�{���q)�@52
��������(�{���q)�@60
�R����ΐ�(�{���q)�@78
�܂ɂ�������(�{���q)�@86
�R���(�{���q)�@90
�h�ʒ���(�{���q)�@94
��q���(�{���q)�@100
���͂т��(��g��)�@110
�a�l��(��g��)�@118
�q��(��g��)�@122
�܂ӂ��[�炿����(��g��)�@140
�����[���(�{���q)�@158 |
�܂���(�{���q)�@170
�Ɓ[���(�{���q)�@180
���������(�{���q)�@194
�R����(�{���q)�@198
��R���(�{���q)�@210
�V�����(�{���q)�@216
�܂����ˁ[��(�{���q)�@224
�Ì��ʉY�ʂԂȂ�[�ܐ�(�{���q)�@238
��������[�ܐ�(�{���q)�@256
���NJԂ��(�{���q)�@266
�����Ȃ��(�{���q)�@278
�c�c���ʂ����[�ܐ�(�{���q)�@288
�Ԓ��ʖڍ��ܐ�(�{���q)�@300
�x���ʋ��ȁ[�ܐ�(�{���q)�@308
�Q�������(�{���q)�@320
�J�����ΐ�(�{���q)�@326
���ڂ�b
(1)�@�w���I���d�R�ÓT���w�W�x�̐��E�@31
(2)�@�u�e���v�Ƃ����p��ɂ��ā@58
(3)�@��闧�T�搶�̏��Ȃ��@76
(4)�@���d�R�ÓT���w�ƌ܍��ɂ��ā@81
(5)�@�܍��_���̊J����ӏ��@83
(6)�@���d�R�ÓT���w�̍쎌�E��Ȏ҂�?�@88 |
(7)�@�Ə��Ɛď��ɂ��ā@93
(8)�@���d�R�`���̗w����
�@�@�����̒��̕���!�@97
(9)�@�O���̌^�u�]�˗^�߁v�ɂ��ā@108
(10)�@���㉹�̎��o�I�Ȏg�p�E
�@�@���\�L�ɂ��ā@117
(11)�@�ÓT���w�Ƃ�?�@121
(12)�@�u�`���v�̑n���@136
��ȗp�����(1)�@139
��ȗp�����(2)�@157
�ꌹ�U��(1)�@�u�C���v�@169
�ꌹ�U��(2)�@�u�t�^�C�n�_�v�@208
�ꌹ�U��(3�@)�u�N�C���E�N�C���P�[�v215
�ꌹ�U��(4)�@�u�e�B�E�g�D�v�@220
�ꌹ�U��(5)�@�u�g�D�o���[�}�v�@234
�ꌹ�U��(6)�@�u�g�[���v�@252
�ꌹ�U��(7)�@�u�E���r�E�E���r�v255
�ꌹ�U��(8)�@�u�J�E�v�@319
���Ƃ���-�w���W�x�`�����ҁw��l�W�x
�@�@���̐���E�ҏW���I����-�@334
�����Ɂ`�����ЂƂ���!�@338
�Q�l�����ꗗ�@340
�����@350 |
�Q���A�u���Z�_�A�W�A���r���[ = Waseda Asia review (13�j���W ������l����v���u�߂��� : ����c��w�A�W�A�����@�\�������v���犧�s�����B�@�@�����F���{�������}���ف@�@���ꌧ���}����
|
�����n�d���̎���: ���̓�d��͋�����邩�@ ������ p.24-29
��㐢�E�̒��̉���@ �䕔 ���� p.30-35
�푈�̋L���Ɗ���̖�� :
�@������́u���v�Ɛk�Ќオ��������ꏊ����@�k���B p.36-41 |
���j�̋L�����u�Ƃ��Ắu�j�́v�_���� �@�g�Ɗԉi�g p.42-47
�Ȃ����A�����Ɨ��Ȃ̂� :
�@�@�������Ɠ��{�Ƃ̐V���ȊW�����l����@ ������ p.48-53
���ꂩ��́A�����m���w �@ �{�l�G�F p.54-59 |
�Q���A���ь��],���эK�j�����s���q��w���B����w���I�v�ҏW�ψ���� �u���s���q��w���B����w���I�v
= Bulletin of the Faculty of Human Development and Education�i9�j�v�Ɂu���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(4)�v�\����B
|
���ь��],���эK�j���u���s���q��w���B����w���I�v(6�`9)�v�ɔ��\�����u���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(1�`4)�v�̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���e |
| 1 |
���s���q��w���B����w���I�v (6) p.147�`159 |
2010-02 |
���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(1) |
�y�� |
| 2 |
���s���q��w���B����w���I�v (7) p.39�`48 |
2011-02 |
���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(2)�@ |
. |
| 3 |
���s���q��w���B����w���I�v (8) p.53-62 |
2012-02 |
���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(3) |
. |
| 4 |
���s���q��w���B����w���I�v(9) p.71-80 |
2013-02 |
���ꌧ����s�����̎�x��G�C�T�[(4) |
. |
|
�R���A �ѐm,���앐�b,�R�{�q��,�����L�q,�S����,�{�����W,�������v,�͐�r�q,�R�c�m�j���u21���I�A�W�A�w����
11�v�Ɂu�V���|�W�E���@�g�A�W�A�̊o���h�Ɠ��{���A�W�A�w�����̂��߂Ɂ@p135�` 156�@���m�ڑ�w�Q�P���I�A�W�A�w��v�\����B�iIRDB�E�o�c�e�j
|
�u�Q1���I�A�W�A�w��V���|�W�E���v�@������@
2013�N1��26���i�y�j
���A�@21���I�A�W�A�w�����E�����i���F���m�ڑ�w����
�v���[���e�[�V�����F�����L�q�F���m�ڑ�w�����i�o�c�w�j
��u���u���w�ҁE�x�G���\���m����m���l�ցv
�@�@���@�с@�m�F�V����w�����i�����w�j
�ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����@��T���F�ߑ���{�̕ϖe
�u���m�����Ƃ̏o��ƕ�炵�̕ϗe�\�J�`�ꉡ�l��
�@�@�����Ӓn����ނɁv���앐�b�F���l�J�`�����ٕ��ْ��i���j�w�j
�u�R�̋ߐ��Ƌߑ�v�R�{�q��F�я�w�������w�Z���@�i���j�w�j
�u�o�c�ӎ��̕ω������̔铽������J�ցv�����L�q
�������_�T�@�����i��F���c�M�j�F���m�ڑ�w�����i���j�w�j
�R�����e�[�^�[�E�\���悵�F���m�ڑ�w�����i�����w�j
�E |
2013�N1��27���i���j
�ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����@��U���F�ߑ���{�Ɠ��A�W�A
�v���[���e�[�V�����@�����L�q
�u�k�C���A�C�k�̋ߑ㉻�ƕ����J���v
�@�@���S�����F�k�C�������w�y�����i�����l�ފw�j
�u���������Ɖ���̖����v�{�����W�F
�@�@�����ꍑ�ۑ�w���u�t�i�����w�j
�u�����̋ߑ㉻�v�������v�F���m�ڑ�w�����i�����o�ρj
�u���N�����̓��{��v�͐�r�q�F���m�ڑ�w�y�����i���ꋳ��j
�u��p���Z���Ɠ��{�\�u�����v�̋ߑ㉻�Ƃ��̉e���v
�@�@���R�c�m�j�F���k��w���w���y�����i�����l�ފw�j
�������_�U�@�����i��F���c�M�j
�R�����e�[�^�[�E���c�~�F���m�ڑ�w�y�����i���A�W�A���ې����j�j
���A�@21���I�A�W�A�w���E�O�֏t���F���m�ڑ�w���� |
�R���A���ь��]�����b�E�`���w��ҁu���b�E�`���w�@21 p.1-14�v�Ɂu����̉̂Ɨx�� : �|�\�̕��z�Ɠ`���v�\����B
�R���A���ь��]�A���эK�j���u���s���q��w�@���E�����������@�����I�v 26 p.43-68�v�Ɂu���ꌧ�{�����̎�x��G�C�T�[ : �`���̊T�v�Ɖ��y�I�����v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (31) �Ôg���u�搶�ސE�L�O���v���u���ꖯ���w��v���犧�s�����B
|
�R�p�n�ԊҌ�̓y�n���p�ƕ�炵:������s���т̌���ƌ��� �����W p.1-18
����{���암�ɂ����镽���S�����̕�:���d��������u���̏ꍇ ���䑀 p.19-52
���d�R�����g�Ɗԓ��̌�ԍ��J�W�c �@�����悵�T p.53-78
�p��@����݂������E����́u���J�v���� �c����� p.79-86
�{�Ó��F���̃X�}�t�T���V�� �������l p.87-104
�ϏB���ɂ�����Z�������Ə����̐������ : ���{�A���n����𒆐S�� �I����
p.105-122
�؍��_���ɂ�����Α���e�̔w�i�Ƃ��̉e�� : ��������J���hG�@�����R�ɂ�����[����ݒu�̎���𒆐S��
�_�J�q�� �@p.123-159
�^�_���ɂ�����d���̖������I���� �@ �}�b�U�� ���F���j�J p.161-179
�F���ˊ��_�E�J������ɂ�����m���E���^�Ɖ��كP�������ɂ��ĘH���́u���v
�������Y p.207-214 |
�R���A�����댤��� ; ���R�ǖ�, ��鐷��, �g�Ɗԉi�g�ҁu���������� :
�����댤�����܁Z�Z��L�O�v���u�������[(���f�B�A�E�G�N�X�v���X) �v���犧�s�����B
�R���A������w�ҁu���m�̌���v���u����^�C���X�Ёv���犧�s�����B�@
�@�@ (���炩����̊w�Ǝv�z ; 5)�@351p�@�����F���ꌧ���}���فF1007299926
|
������������̂ڂ�
����Ԃɂ݂问�������̍�
�����̗���
���������Ɗ��Ё\�������ꂩ�猩���w�K��
�J������问�������w�̐V���Ȑ��E�\���C�̍�i�𒆐S��
���{�Ñ��u����v�̔�ߋ��`��
���ӂ��̕����j
�T���S�ʂ̒n���}�\���������C�̋L�^
�t�N�M(����)�̖͕s�v�c�Ȗ�
�Z�܂������\�V���A���̐��ԂƂ��̖h��
��]����ԗւ������b
���̉���^�A���H��̎����ɂނ��ā\����̒m�����W�������z�M�G�l���M�[�z���V�X�e���̉��p��
�ق�Ƃ͂킩���Ă��Ȃ������o���N�C�i�c�\����̎�������芈�����ɂ�
���̗��������̖���
��������n���������l���� |
�C�m����������̊C�ɒT�� ���c �o���Y
����{���ɂ����鐅�����̌���Ƃ��̊J���̉\��
�t�Α̂̒m��ꂴ�鐶��
������ƂƊ��s���̓W�J
�N�ƃA�C�����h�ւ̊C�}�\�N�ƉƋ���͂�����̒m�̌���ł���
���N�����ł̌��������ƃn���O��
�Z�p�������{�̋Z�p����
�@��̈��S���Nj��ƕ��a�ȕ�炵�Ɋւ���
���S�ň��S�ł����炵����ɓ���邽�߂Ɂ\���R�ЊQ�ƌv�Z�Ȋw�Z�p
��̓��A���ꌧ�ɂ����銴���ǂ��痮���l�̃��[�c��T��
�i���N���i�C�T�ƌ��N�����l����
���N�Ɍ������Ȃ�NO
�̓����v�̗��ꂪ�z����������č������������N����
�זE�̏��`�B�̎d�g�݂��猩���Ă��邱�Ɓ\�l�ԎЉ�̏k�}�Ƃ��Ă̍זE�Љ�
�E |
�@�@�@�@�@�@���m�̌���@���҂Ɣ��\����Ă���_�����Ƃ��Ⴄ���ߒ����v�@�i���Җ����폜���j�@�Q�O�Q�R�E�X�E�Q�P�@�ۍ�
�R���A���c�@��, ����G�K, �{���v���ҁu�������鉫��n�ږ� : �u���W���A�n���C�𒆐S�Ɂv���u�ʗ��Ёv���犧�s�����B
�@�@�@ (������w �l�̈ړ���21���I�̃O���[�o���Љ� ; 10)�@�@293p�@�����F���ꌧ���}���فF1007301425
|
��㉫�ꌧ�ɂ�����C�O�ږ��̗��j�Ǝ��� �ΐ� �F�I p11-40
�E�`�i�[���`���̉z���I�l�b�g���[�N�ƕR�� ���� �G�K p41-65
�C�O�ɂ����鉫��A�C�f���e�B�e�B�̒n��Ԕ�r ��� ���� p67-94
���ꌧ�n�o�c�҃l�b�g���[�N�̌`���ƓW�J �{�� �v�� p95-130
���n�R���j�A�̎Љ��ՂƁu�u���W�����ꌧ�l��v ���c �@�� p131-151
�u���W������R���j�A�� �V�ۃ��V�[���x�q p153-175
�T���p�E���s�ɂ����鉫�ꌧ�n�l�̎l�\����̃~�T �l�� ���N p177-190 |
�u���W���̐Ί��� �R�� ���� p191-197
�n���C�̃��^ �l�� ���N p199-213
�n���C�ɑ���ꂽ�ߗ����� ���� ���� p215-252
�t�H�[�����u�C�O���n���L�҂݂̂��ږ��Љ�v �O���M��
�@�@���^�i�� ���� �a�j�^�ق���
�@�@�����c �@���^�t�H�[�����R�[�f�B�l�[�^ p253-286
�E |
�R���A�����S�͒��u���쏉���������̑m�ܒ��ǒ�[�����{]�v�����s�����B�@
�@�@�w�|���x��20�N��4��p44�`72�@1924-09�@���� �@(���s�鍑��w���w���ҁj �@�����F���ꌧ���}����
�R���A�����a�����u���z���� : �������w���琢�E�̉�H�ցv���u�}�ԏ��@�v���犧�s����B
|
���w�����̈Ӌ`
�ÓT�w�̍č\�z���߂�����
�ٕ����𗬂̕��w�j��
�������w���琢�E�̉�H��
������w���{�w�������̂���
�C�F�[����w���E
�@�@�����{�����R���N�V�����ژ^���
���V���g���c��}���ق̘a�Ï�����
�c��}���ًy�уC�F�[����w
�@�@���������͎��W�{���߂�����
�j���[���[�N�ƊG��
�ݕĊG���K�����ڂ�����
�`�F�X�^�[�r�[�e�B�[�E���C�u�����B |
�@�@�������G���E�G�{���ژ^�e
��k�̖��Ԍ���
���P���ӊX��
���䎛�̈��
��k�E�k���ɂ�����a�Ï��y��
�@�@���G�掑���ɂ��Ă̊o������
��������N�I
���͎�����z���āB
�n���R�̂����̕lj�
���A�W�A�E�q�m�r�̗V�w�̂��߂�
�j�̕䍂
���m�����}���فu�R�����Ɂv
������w�ւ̗� |
�Ί_�s�����d�R������
����^�C���X�̋L���u�|�[�����h�ɗ����G���v
�w�ܒ���l�t�H�[�����x���|�[�g
�̑���
�̒����ƌ�������
���ɒ������猩��ߑ�
���f�B�A�ƕ��w�\��
�ٕ����𗬂Ɩ|��̓���
��܂Ƒ�]���搶�̎v���o
�약�ς����약�ЂƂ���
���q�����
�E
�E |
�R���A�u���ꌤ���m�[�g (22) �v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�iIRDB�j
|
���c���j�̗��搧�_:����̑��搧�Ɨ��搧���� ����, ���t p.1-23
�����Q���ҔN�j���W�Ҏ[�̎��� �Ώ� �p�� p.24-36 |
�쓇���V : Field Walker or Flaneur ��엺 p(44-37
�E |
�R���A�~�ؓN�l���u�V�������̗��j�v���u�@����w�o�ŋǁv���犧�s����B�@�@�@
(�p���E�����m��)
�@�@�@9,250p�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1006694036
|
�������̗��j�ƓW�J�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��B�����ē��{�Ƃ̂������Ƃ́B�{�B�Ƃ͈قȂ�Ǝ��̍��ƌ`���ƑΊO�W�������������A��ɒ����Ƃ̊W�ɏd�_��u���Ȃ���_����B |
|
�܂����� iii
���_�@�������̐����E�W�J�E�I�� 1
1�@�쓇�ɂ����鍑�ƌ`�� 11
��@��j���� 11
��@�O�X�N 14
�O�@��^�O�X�N�Ə������� 17
�l�@�O�R���� 23
�܁@�@�x�ɂ��i�v�̊J�n�ƍ����̓�d�\��26
2�@�������ꍑ�Ƃ̐����ƓW�J 31
��@���j�ɂ�鉤���̋L�q 31
��@�v�ЁE�b�u�̐����m���Ɖ��� 35
(�C)�@�O�R���� 35
(��)�@���v�� 38
�O�@�����̓`���ƍ��ƌ`�� 43
�l�@���~�����Ə��^��(�������ꍑ�Ƃ̊���)46
�܁@���y�n���_�b�Ɛ_���g�D 48
�Z�@�悠�����ցE��̂ʂ�(�������ꍑ�Ƃ̍\��)57
���@�ΊO�W�̊����� 68
(�C)�@�i�v�Ɠ��A�W�A���ێЉ�̍\�� 68
(���j�@���b�u����Ă̖�������
�@�@�������`���ւ̏��@�̓`�B 75
(�n)�@�J�g�̗��Ɨ��� 79 |
���@�����̐i�v�E�����Ɠ����W�Ƃ̔�r84
3�@���A�W�A���E�̕ϗe�Ɨ��� 89
��@�����̐��ނƗ��� 89
��@���m�̗��Ɠ����E�����W�̕ω� 93
�O�@�L�b�G�g�̓���Ɨ��� 97
�l�@����ƍN�Ɨ��� 101
�܁@���Î��̗����N�U 104
4�@�ߐ��̗�����(��) 113
��@�����d�u 113
��@���ی��̐���
�@�@��(�������̋ߐ��I���v)116
�O�@�����ݔԕ�s�Ǝ����������� 122
�l�@�����̐ݒ� 125
(�C)�@������ 125
(��)�@�o�Ăƒ��� 126
(�n)�@���������{�����̐����\��139
�܁@�ߐ������f�Ղ̎����Ɠ��{��142
(�C)�@�����̖ŖS�Ɛ����̐��� 142
(��)�@�����f�ՂƓ��{�� 145
�Z�@�ƕ��̐����Ɠ��i�� 149
���@�ߐ��̋v�đ� 153
���@�����g�߂̍]�ˎQ�{ 156 |
��@�������i�ɂ��� 161
5�@�ߐ��̗�����(��) 165
��@��̐���
�@�@��(�ߐ��������̊m��) 165
��@���d�R�Ɩ��a�Ôg 171
�O�@�V���̋Q�[ 174
�l�@�F���˂̓V�ۉ��v�Ɨ����f��177
�܁@�ߐ����̔_���敾 181
�Z�@�A�w���푈�Ɨ��� 184
���@�y���[���q�Ɨ��ďC�D��� 188
���@���Ðĕj�̊J�`�\�z�Ɣ��� 190
6�@�������̏I�� 195
��@�����˂̐ݒu 195
��@��p�o���ƌ݊������̒��� 204
�O�@������叼�c���V�̔h����
�@�@�����ꌧ�̐ݒu 206
�l�@�����x�̑��u 211
�܁@�y�n�����ƒn�����x�̉��v 213
���p�������L 219
���Ƃ��� 235
�������̗��j�N�\ 244
�l���E�������� 250 |
�R���A�V�C�L�c�s�j�҂�����ψ���ҁu�V�C�L�c�s�j 15 �ʕ� ���� 1 (�R�n�̂��炵)�v���u���m���L�c�s�v���犧�s�����B
|
�i���j
�攪�́@�N���s��
�攪�́@���߁@�����̍s��
�攪�́@���߁@��@���������ƔN��@678
�攪�́@���߁@��@����E�V��
�攪�́@���߁@��@������
�攪�́@���߁@��@�ݝ���
�攪�́@���߁@��@����
�攪�́@���߁@��@��������
�攪�́@���߁@��@���T��
�攪�́@���߁@��@�N��
�攪�́@���߁@��@�N�z���Q��
�攪�́@���߁@��@�����@687
�攪�́@���߁@��@����
�攪�́@���߁@��@���Q��
�攪�́@���߁@��@�ᐅ����
�攪�́@���߁@��@���ł�
�攪�́@���߁@��@�G��
�攪�́@���߁@��@�N��
�攪�́@���߁@��@��������
�攪�́@���߁@��@�b����E�单�ւ̂�����
�攪�́@���߁@��@���A��
�攪�́@���߁@��@������
�攪�́@���߁@��@�d���n��
�攪�́@���߁@��@�叼�|��
�攪�́@���߁@��@�ܓ����т�
�攪�́@���߁@��@��������
�攪�́@���߁@��@���J���E���J��
�攪�́@���߁@�O�@�������E��\�������E�������@697
�攪�́@���߁@�O�@�������Ƌ�����
�攪�́@���߁@�O�@���`��
�攪�́@���߁@�O�@�݉ԁE����
�攪�́@���߁@�O�@����̔N��
�攪�́@���߁@�O�@���ؐӂ�
�攪�́@���߁@�O�@�j���E�M
�攪�́@���߁@�O�@�U��
�攪�́@���߁@�O�@�C�O�����`
�攪�́@���߁@�O�@��\�������E��\���G�x�X
�攪�́@���߁@�t�E�Ă̍s��
�攪�́@���߁@��@�t�̍s���@705
�攪�́@���߁@��@�ߕ�
�攪�́@���߁@��@�t�̎R�̍u
�攪�́@���߁@��@����
�攪�́@���߁@��@���ω�
�攪�́@���߁@��@�t�̔ފ�
�攪�́@���߁@��@�O���ߋ�
�攪�́@���߁@��@�O�@����
�攪�́@���߁@��@���L����
�攪�́@���߁@��@�Ă̍s���@718
�攪�́@���߁@��@�ԍՂ�
�攪�́@���߁@��@���Ղ�
�攪�́@���߁@��@�܌��ߋ�
�攪�́@���߁@��@�c�̐_�Ղ�
�攪�́@���߁@��@�_�x��
�攪�́@���߁@��@�V������E�_������
�攪�́@���߁@��@�y�p
�攪�́@���߁@��@������
�攪�́@���߁@��@����_�E�I�J�^����
�攪�́@��O�߁@�~�̍s���@729
�攪�́@��O�߁@���[
�攪�́@��O�߁@�~�s���̎���
�攪�́@��O�߁@��|��
�攪�́@��O�߁@����}���Ɩ~�I���
�攪�́@��O�߁@����Ղ�
�攪�́@��O�߁@���쑗��
�攪�́@��O�߁@�~�{��S
�攪�́@��O�߁@���~���{
�攪�́@��O�߁@��O���E�\�l���O��
�攪�́@��O�߁@�~�x��E��O��
�攪�́@��O�߁@�E���~�E�n���~
�攪�́@��l�߁@�H�E�~�̍s��
�攪�́@��l�߁@��@�H�̍s���@744
�攪�́@��l�߁@��@��\���E��\�O��Ƃ������҂�
�攪�́@��l�߁@��@��S�\���E��S��\��
�攪�́@��l�߁@��@����
�攪�́@��l�߁@��@�H�̔ފ�
�攪�́@��l�߁@��@�H�Ղ�
�攪�́@��l�߁@��@�~�̍s���@749
�攪�́@��l�߁@��@�~�̎R�̍u
�攪�́@��l�߁@��@��̎q
�攪�́@��l�߁@��@�J���A�Q�E�m�A�K��
�攪�́@��l�߁@��@�b����u
�攪�́@��l�߁@��@�H�t�Ղ�
�攪�́@��l�߁@��@�u
�攪�́@��l�߁@��@�~��
���́@�M��
���́@���߁@���@�Ɩ@��
���́@���߁@��@�R�ԕ��̎��@���z�@756
���́@���߁@��@�R�ԕ��̎��@
���́@���߁@��@��y�@���h
���́@���߁@��@��y�^�@���h
���́@���߁@��@�����@���@
���́@���߁@��@�ՍϏ@���h
���́@���߁@��@�h�ߎ��ƒh�Ɓ@759
���́@��ܐ߁@�_�I�E���d
���́@��ܐ߁@�b����E�单
���́@��ܐ߁@���~�_
���́@��ܐ߁@�E�W�K�~
���́@��ܐ߁@�r�_
���́@��ܐ߁@���_
���́@��ܐ߁@�I�C�k�T�}
���́@��ܐ߁@�H�T�̐_��
�b�ҁE���͎҈ꗗ
���������n�ꗗ
�V�C�L�c�s�j�҂���W�Җ���
���M���S
���Ƃ���
�i���j
�ʐ^�ꗗ
���G1�@�͏㐣�̃h���h�Ă� ��쐣(��n��) 2013
���G2�@����̏� ����(�����n��)�E�����@2012
���G3�@���w ����(�����n��)�E�������Ƌ{2012
���G4�@�������� ������O�͔N�_�ւ̂�����
�@�@���(��n��) 2012
���G5�@�j���E�M ��쐣(��n��) 2012
���G6�@���`�o�i �(��n��) 2012
���G7�@�b�艮�̎d���n�� (��)�L�`�̒b���A
�@��(�E��)�_�I�ɕ�[���ꂽ�L�` �����(�����n��)2012
���G8�@�R���̏t �命��(�����n��) 2011
���G9�@���܂� ���n(���n��)�E�q���@ 2012
���G10�@�������̃C���V�̓� ���c(��n��) 2012
���G11�@�n���ω��Ղ� �ď�(��n��) 2012
���G12�@�R�̍u�@��쐣(��n��) 2012
���G13�@�R�̍u�@(�E��)������(���n��)�A
�@�@��(����E��)���(��n��) 2012
���G14�@���Ղ� ����(�����n��) 2012
���G15�@�����t�Ղ� ����(�����n��) 2007
���G16�@�ォ�� �H�z(���R�n��) 2011
���G17�@�R���̉� �命��(�����n��) 2012
���G18�@��̂ڂ� �K�c�a(�����n��) 2011
���G19�@�c�A�� ����(���n��) 2011
���G20�@����_ �H�z(���R�n��) 2012
���G21�@�_���Ղ� �k��F(�����n��) 2012
���G22�@���̗ւ����� �k��F(�����n��) 2012
���G23�@�b��̃A���ނ� ����(�����n��) 2011
���G24�@����̐�V�� ���n(���n��) 2011
���G25�@�c�̑���� ��(�����n��) 2012
���G26�@�R���̏H �命��(�����n��) 2011
���G27�@�~�s�� (��)�}���� ���(��n��)�A
�@�@��(��)�q���N�n�b�^�C
�@�@�� �㒆(���n��)�A(��)�~�I ���c��(��n��) 2012
���G28�@��O�� ���n(�����n��) 2012
���G29�@�~�̓��ė��� ����(�����n��) 2011
���G30�@��\���E��\�O�� �{��(���n��) 2012
���G31�H�Ղ� (�E��)�R�� ���c(��n��)�A(����)����n
�@�@���ؐ�(�����n��)�A(��)�_�̎� ����(���n��) 2011
���G32�@��� ����(�����n��) 2011
���G33�@�R���̓~ �命��(�����n��) 2011
���G34�@��̖�t�� �呠(�����n��) 2012
���G35�@���Q ���(��n��) 2012
���G36�@������� ����(�����n��) 2012
���G37�@�a����� (��)�����ς�A(��)�����ق����A
�@�@��(��)���� ����(�����n��) 2013
���G38�@�R�d�� (��)�� ����(���n��)�A
�@�@��(��)���؍�� �쌴(���R�n��) 2012
���G39�@�C�m�V�V�̔� ����(�����n��) 2013
���G40�@�C���� ����(�����n��) 2013
���G41�@�ݝ��� �����(���n��) 2011
����
���́@1-1�@�O�͎R�n�̎R�X(������
�@�@�����R���p���������]��) 2013
���́@1-2�@����Ɣb��̍�����
�@�@�� �͍���(����n��) 2013
���́@1-3�@�R�����̏W�� ��쐣�̑�K�W�� 2013
���́@1-4�@�����̏W�� ���c 2013
���́@1-5�@�L���̏W�� 2013
���́@1-6�@�l���E���ЊQ�̔�Q�� �L�� 1972
���́@1-7�@����̒��S�X 2013
���́@1-8�@���V�^�E���~�E�E�����} �命�� 2013
���́@1-9�@��e�̍̌@�� ��c 2013
���́@1-10�@����~�� �w�����̎��x���
���́@1-11�@��̒҂ɂ�����������N�̓��W
�@�@��(�u�E�ق��炢�� �����͓��v �Ƃ���) 2013
���́@1-12�@�僖���A(�����n��)�Ɠ�(���Q�s)�Ƃ�
�@�@�����̓� 2013
����
���́@2-1�@��̕��i 2013
���́@2-2�@�����̕��i 2013
���́@2-3�@�A�J�̉��i 2013
���́@2-4�@�����Ζ͔͑��ёg���� �����n�� 2013
���́@2-5�@�T�N���}���K(���n�L)
�@�@�@�����������ُ��� 2012
���́@2-6�@�a���̕��i 2013
���́@2-7�@�x�{�̒� �L�c�s���y������
�@�@���ڒz���Ɠ� 2012
���́@2-8�@���̕��i 2013
���́@2-9�@�ɌF�̕��i 2013
���́@2-10�@�R�̐_ �����R 201
���́@2-11�@�J��]�x�̉��i
�@�@���w�R�Ɛ�l������100�N�x���
���́@2-12�@���̓V���Ղ� 2011
���́@2-13�@���� 2013 |
���́@2-14�@�w���q(���܌^) �������������ُ��� 2012
���́@2-15�@�w���q(�L�܌^) �����y�����ُ��� 2012
���́@2-16�@���O���� ����܂��q����
���́@2-17�@���L(��) �����y�����ُ��� 2012
���́@2-18�@�m�R�M�� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-19�@�Ώ��� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-20�@�Y�Ă��q �w�������x���
���́@2-21�@�Y�Ă��q�̒z�q �w�������x���
���́@2-22�@���Y���Ă����i �w�O�B���� �Y�ĕ���x���
���́@2-23�@�G�u�� �������������ُ��� 2012
���́@2-24�@���Y���o��(�q�o��) �w�������x���
���́@2-25�@�ؒY�q�� �w�O�B���� �Y�ĕ���x���
���́@2-26�@�A�юR�̗l�q (��)����39�N�A(��)����40�N
�@�@�� �w�����Ζ͔͑��ёg���̂���݁x��� 1906�`07
���́@2-27�@�����芙 ���������ُ��� 2012
���́@2-28�@�������� �w�������x���
���́@2-29�@�Ԕ��̗l�q �w�R�Ɛ�l������100�N�x���
���́@2-30�@���̗l�q �w�������x���
���́@2-31�@��(��) ���������ُ��� 2012
���́@2-32�@���̖؏o�� �w�������x���
���́@2-33�@�J�� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-34�@�ː��ɂ��W�� �w�R�Ɛ�l������100�N�x���
���́@2-35�@�C���Ɗۑ��̈䌅(����)
�@�@�� �w�R�Ɛ�l������100�N�x���
���́@2-36�@�ؔn ���������ُ��� 2009
���́@2-37�@�ؔn�ɂ��؏o�� �O���H����
���́@2-38�@�ؔn�� �w�������x���
���́@2-39�@������ �w�������x���
���́@2-40�@�S�X�̒��؏�̗l�q �w�������x���
���́@2-41�@�g���b�N�ɂ����o
�@�@���w�����Ζ͔͑��ёg���̂���݁x���
���́@2-42�@�勘 �������y�ُ��� 2012
���́@2-43�@���^�̑勘 �����y�����ُ��� 2012
���́@2-44�@���Ԑ��ލH�� �쌴 2010
���́@2-45�@���Ԑ��ލH��̗l�q �쌴 2010
���́@2-46�@�ޖ؎s�̗l�q �w�R�Ɛ�l������100�N�x���
���́@2-47�@�b��E�R���썇���n�_�̕��i 2013
���́@2-48�@�����n��̒|�т̉��i 2013
���́@2-49�@�n�`�N ��؏��Ȏ��� 2006
���́@2-50�@�}�_�P 2013
���́@2-51�@���E�\�E ��؏��Ȏ��� 2006
���́@2-52�@�g�r�t���� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-53�@�e���� �������y�ُ��� 2010
���́@2-54�@�Z�� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-55�@�E�Q �����y�����ُ��� 2012
���́@2-56�@�c�Ì��̍k�n �w����̗��x���
���́@2-57�@�i�X�̍k�n ��� 2009
���́@2-58�@�R�ԕ��̒I�c �w���̍��̐l�тƁx���
���́@2-59�@����11�N���̉H�z�n��
�@�@�� �w�Z�L�O�H�z���w�Z���x��� 1999
���́@2-60�@���Ƃ̃��}�~�Y���� ������ 2011
���́@2-61�@�R���N���[�g�ō��ꂽ���݂̈䉁 ���� 2010
���́@2-62�@�ΐς݂̃C�~�` �A�J 2010
���́@2-63�@�k�n������̃��~�] �K�C 2010
���́@2-64�@���r ��r 2011
���́@2-65�@�C�m�V�V�h���̓S�� ���� 2010
���́@2-66�@�ߔN���������������Ă���C�m�V�V
�@�@����؏��Ȏ��� 2012
���́@2-67�@�c�A����Ԃ��Ȃ����c �V�� 2011
���́@2-68�@���m���_�Ƒ��������� � 2013
���́@2-69�@�e�A�[ ��� 2009
���́@2-70�@�g�^�����̃A�[�i�~ �c�Ì� 2010
���́@2-71�@�I�c�̏�ɐ݂���ꂽ�����r �c�� 2013
���́@2-72�@���k �w����1���I�x���
���́@2-73�@���k�p� �O�B�������~���� 2009
���́@2-74�@�{�͔n�� �����y�����ُ��� 2010
���́@2-75a�@���L �������y�ُ��� 2010
���́@2-75b�@���C�L ����y�����ُ��� 2010
���́@2-75c�@�����L(��{��) �����ُ̊��� 2010
���́@2-75d�@�����L(�O�{��) �O�B�������~���� 2009
���́@2-75e�@�����L(�l�{��)
�@�@���������������ُ��� 2009
���́@2-75f�@�����L(�l�{��) �����y�����ُ��� 2010
���́@2-76�@��l�� ����y�����ُ��� 2010
���́@2-77�@�ۉ��ܒ��c�� �w���������x���
���́@2-78�@�V���J�L����ɂ��i���V��� ��� 2010
���́@2-79�@�V���J�L �������y�ُ��� 2010
���́@2-80�@���݂̋@�B�c�A�� ��� 2010
���́@2-81�@�X�W�c�P���� ���������ُ��� 2009
���́@2-82�@�c�M �����ُ̊��� 2010
���́@2-83�@�K���d��(�����}���K) �������y�ُ��� 2010
���́@2-84�@�K���d��(�e�}���K) �O�B�������~���� 2009
���́@2-85�@�����@(�������) ���������ُ��� 2009
���́@2-86�@��� ��� 2012
���́@2-87�@���a40�N��̏H�̎��n���i
�@�@�� �w����20���I�̂���݁x���
���́@2-88�@���H�e�̑��i�n�U ��� 2009
���́@2-89�@�����ݎ��E���@ ���������ُ��� 2009
���́@2-90�@����(��ǂ���) ���������ُ��� 2009
���́@2-91�@�����̎g�p ���a41�N
�@�@�� ����܂��q���� 1966
���́@2-92�@���������i �w�����Ёx���
���́@2-93�@��� ���n 2011
���́@2-94�@���� ���a30�N ��؍N�j���� 1955
���́@2-95�@���̓y����@ �O�B�������~���� 2009
���́@2-96�@�n�l�N������ ����y�����ُ��� 2010
���́@2-97�@�R�Ԓn�̔��� �_�a 2010
���́@2-98�@�~��̑卪���� ���� 2009
���́@2-99�@�ΖʂɐA����ꂽ���̖� �c�Ì� 2010
���́@2-100�@�V�C�^�P�͔| �w���������x���
���́@2-101�@����ꂽ�V�o�N�T ��� 2009
���́@2-102�@�����̔n�s �w����1���I�x���
���́@2-103�@�הn �w�O�B���� �Y�ĕ���x���
���́@2-104�@�n�� �w����1���I�x���
���́@2-105�@�� ���a40�N�� ����������
���́@2-106�@�E�V�O���} �����y�����ُ��� 2010
���́@2-107�@�E�V�}�� �K�C 2010
���́@2-108�@���Ƃ̕~�n�����J���Ă���
�@�@���n���ω� ������ 2011
���́@2-109�@���Ƃ̕~�n���ɂ���{���� ���c 2010
���́@2-110�@���L�̃q�c ����y�����ُ��� 2012
���́@2-111�@�g�E�O���̃q�c �������y�ُ��� 2012
���́@2-112�@���ʃX�P�[�g ����y�����ُ��� 2012
���́@2-113�@�I�̑� ����y�����ُ��� 2012
���́@2-114�@�b�艮�̍�ƕ��i ����� 2012
���́@2-115�@�L�`�̃~�j�`���A ����� 2012
���́@2-116�@�^�ړ��y�̐���
�@�@���吳5�N �R�����Y���� 1916
���́@2-117�@�T�o�y�@��̗l�q �����e�v����
���́@2-118�@���ɂ��T�o�y�̉^��
�@�@���吳12�N �R�����Y���� 1923
���́@2-119�@�g���~������ �����n�� 2012
���́@2-120�@�M���}�� �������������ُ��� 2012
���́@2-121�@�Z�Z�� �����y�����ُ��� 2012
���́@2-122�@�E�i�M�^�^�L �L�c�s���y�����ُ���
���́@2-123�@�`���J���� �w�������錾�x���
���́@2-124�@�������� ���a40�N�� �����e�v����
���́@2-125�@���n���� �w�������錾�x���
��O��
��O�́@3-1�@�W�o�� �����y�����ُ��� 2012
��O�́@3-2�@�����q�L �����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-3�@�V���c ���������ُ��� 2009
��O�́@3-4�@�E���b�p�� �������������ُ��� 2012
��O�́@3-5�@�����y ���������ُ��� 2009
��O�́@3-6�@�S�����胂���y �������������ُ��� 2009
��O�́@3-7�@�O�|�� �����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-8�@������ ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-9�@�n�o�L �����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-10�@�e�R�E �������������ُ��� 2012
��O�́@3-11�@����(��) ��� ���z�t�L�㎁���� 2010
��O�́@3-12�@����ߑ��̕ω� (�� : ���a25�N���A
�@�@���E : ���a30�N) �ɌF �l��
��O�́@3-13�@���� �������y�ُ��� 2012
��O�́@3-14�@���V�ʐ^ ���a34�N �ɌF �l�� 1959
��O�́@3-15�@�w�l��̒c�� ���a38�N �ɌF �l�� 1963
��O�́@3-16�@��g �����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-17�@�Y�� ����y�����ُ��� 2012
��O�́@3-18�@�a���̎��� (���a9�N�x���Ǝʐ^)
�@�@�� �w�a�����w�Z�Z�L�O���x��� 1934
��O�́@3-19�@�m���̎���(���a13�N�x���Ǝʐ^)
�@�@�� �w�a�����w�Z�Z�L�O���x��� 1938
��O�́@3-20�@�q�m�L�K�T ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-21�@�X�Q�K�T �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-22�@�I�I�~�m ���������ُ��� 2009
��O�́@3-23�@�Z�i�J�~�m ���������ُ��� 2009
��O�́@3-24�@���܂̌^ �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-25�@���� �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-26�@�������̑� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-27�@�A�g�}�� �O�B�������~���� 2009
��O�́@3-28�@�q�ǂ��p�̃S���C
�@�@������y�����ُ��� 2010
��O�́@3-29�@�o���J�� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-30�@�p�[�}�� �ɌF �l��
��O�́@3-31�@���� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-32�@�^�Ȑ����� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-33�@���}�g�S�^�c �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-34�@���� �����ُ̊��� 2010
��O�́@3-35�@���� �����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-36�@���� �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-37�@�Ȓ� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-38�@�`��� �����y�����ُ��� 2012
��O�́@3-39�@�ٖD���` ���������ُ��� 2009
��O�́@3-40�@�j�� �������y�ُ��� 2010
��O�́@3-41�@�m���ٖ̍D���` ���������ُ��� 2009
��O�́@3-42�@�~�V�� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-43�@�s�� ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-44�@����ƃ^���C ����y�����ُ��� 2010
��O�́@3-45�@�q�m�V �����ُ̊��� 2010
��O�́@3-46�@�Y�A�C���� ���������ُ��� 2009
��l��
��l�́@4-1�@�����p ���������ُ��� 2009
��l�́@4-2�@�[���o�R �������������ُ��� 2012
��l�́@4-3�@�R���j���N�C�� �w�ߑ�̕�炵�ƐHI�x���
��l�́@4-4�@�G�� 2013
��l�́@4-5�@�J���X�~ 2011
��l�́@4-6�@�ܕ��� ���R�n�� 2010
��l�́@4-7�@�[���}�C�Ɩ��g���̎ϕ�
�@�@���w�ߑ�̕�炵�ƐHI�x���
��l�́@4-8�@�����` ���c 2011
��l�́@4-9�@���~�W�C�`�S �w�ߑ�̕�炵�ƐHII�x���
���
��́@5-1�@����E�݂̏W��(����) 2013 |
��́@5-2�@�D��`���̌� ��쐣 2013
��́@5-3�@�命��̏W�� 2013
��́@5-4�@���̏W�� 2013
��́@5-5�@����̏W�� 2013
��́@5-6�@��ʂ̉� 2009
��́@5-7�@�����̏W�� 2011
��́@5-8�@���{�̏W�� 2013
��́@5-9�@���n�̉� 2013
��́@5-10�@�J�h�T�J �c�Ì� 2013
��́@5-11�@�J�h(���) 2013
��́@5-12�@���~�̐_�X ���� 2011
��́@5-13�@�\�M 2010
��́@5-14�@���R���� �����n�� 2009
��́@5-15�@�l�c���̍\�� 2009
��́@5-16�@�������� 2009
��́@5-17�@�䑠��A�� 2013
��́@5-18�@�c�Ì���O�� 2013
��́@5-19�@���Ă̓c�Ì���O��
��́@5-20�@�ɌF��G��
��́@5-21�@��쐣��N�� 2013
��́@5-22�@�L��������ڐ݂����Ö���
�@�@���L�c�s���y�����ٕ~�n�� 2009
��́@5-23�@�R�Ԓn�̊���������
�@�@���ΐ쐳���� 1974�`76
��́@5-24�@�g�}�O�` ���� 2011
��́@5-25�@�u�c�} ���� 2011
��́@5-26�@�C�} ��쐣 2013
��́@5-27�@���K�i ��� 2009
��́@5-28�@�}�����U�V�L ��� 2009
��́@5-29�@�N���������� ���� 2011
��́@5-30�@����� �c�Ì� 2013
��́@5-31�@��� �ɌF 2009
��́@5-32�@��˂ƈ�ː_ ���� 2009
��́@5-33�@��ː_ ��� 2009
��́@5-34�@�����̐� ��� 2009
��́@5-35�@�^�L���� ���� 2011
��́@5-36�@�^�L�������� �䑠 2013
��́@5-37�@�N�h ��� 2009
��́@5-38�@��^�N�h ��� 2009
��́@5-39�@���m�N�h �A�J 2011
��́@5-40�@�͘F�� �������������ُ��� 2009
��́@5-41�@�S�G�������C �������������ُ��� 2009
��́@5-42�@�w�\���C �����y�����ُ��� 2010
��́@5-43�@���֏� ��� 2009
��́@5-44�@�֏� �c�Ì� 2010
��́@5-45�@���� ��쐣 2013
��́@5-46�@���� �A�J 2011
��́@5-47�@���n���� �_�a 2010
��́@5-48�@�y�� �ɌF 2009
��́@5-49�@�ȓ���ƕ�����̓y�� ��쐣 2013
��́@5-50�@�y�������㕔�̃R�e�G �ɌF 2009
��́@5-51�@�~�\�x�� ��� 2009
��́@5-52�@�u�����L�^�v �吳13�N ��������Ə��� 1924
��́@5-53�@�㓏�� ��� 2009
��́@5-54�@�u�������L�^�v ���a14�N
�@�@����������Ə��� 1939
��́@5-55�@�����ւ� ���n��
��́@5-56�@�n�T�~ ���c�� 2010
��́@5-57�@���������R�e �����ُ̊��� 2010
��Z��
��Z�́@6-1�@�A�J�E���c�؊Ԃ̌S�E�� 2012
��Z�́@6-2�@���������J����O�\�O�ω� ���s��X 2007
��Z�́@6-3�@�u���p�ژ^�v �����c�㒬���� 2009
��Z�́@6-4�@�u���p�ژ^�v �Ώ������� 2009
��Z�́@6-5�@�����̏W��� ��͌� 2012
��Z�́@6-6�@�u���c�^�v �Ώ������� 2009
��Z�́@6-7�@�u��c�^�v �����і쒬���� 2011
��Z�́@6-8�@�L���̏W��� ��ʒ��� 2009
��Z�́@6-9�@�L���̏W��� �����R���m�� 2004
��Z�́@6-10�@�g�̏W��� ���{��K�g 2010
��Z�́@6-11�@������ �� 2010
��Z�́@6-12�@���q ��� 2005
��Z�́@6-13�@�c��N���u���Â݁v
�@�@�������c�㒬���� 2009
��Z�́@6-14�@���h���c�̋l�� ���c 2010
��Z�́@6-15�@���� ������ 2009
��Z�́@6-16�@�̌��E �O�� 2005
��Z�́@6-17�@�u�ːЍT�v �K�������� 2011
�掵��
�掵�́@7-1�@����݈ߑ� ���n�� 2007
�掵�́@7-2�@���� �O�B�������~
�@�@��������ЎO�B�������В� 2000
�掵�́@7-3�@�O�O��x �O�B�������~
�@�@��������ЎO�B�������В� 2000
�掵�́@7-4�@�I�T�J�i�R���j�[ �O�B�������~
�@�@��������ЎO�B�������В� 2000
�掵�́@7-5�@��I�� �O�B�������~
�@�@��������ЎO�B�������В� 2000
�掵�́@7-6�@�C�P�� �O�B�������~
�@�@��������ЎO�B�������В� 2000
�掵�́@7-7�@�q���ω� ��� 2010
�掵�́@7-8�@���� �w�������x���
�掵�́@7-9�@�S���Ղ̐��� �ʕ� 2009
�掵�́@7-10�@�O���ɗp������ �ʕ� 2009
�掵�́@7-11�@����ɕ��|�� �ʕ� 2009
�掵�́@7-12�@�Z�������|�� �ʕ� 2009
�掵�́@7-13�@����̐���(�V�J�o�i)
�@�@�����a50�N�� �w�������x���
�掵��7-14�@����̐���(����) ���a50�N�� �w�������x���
�掵�́@7-15�@���� ���a50�N�� �w�������x���
�掵�́@7-16�@�o�� ���a50�N�� �w�������x���
�掵�́@7-17�@�҂�� ��� 2009
�掵�́@7-18�@���� ���a10�N�� �w�������x���
�掵�́@7-19�@���̒|�͂� ��� 2009
�掵�́@7-20�@���~�� ���c 2010
�掵�́@7-21�@���ߕ� ��� 2009
�掵�́@7-22�@�w��� ��� 2009
�攪��
�攪�́@8-1�@�������̋��� ��쐣 2011
�攪�́@8-2�@�f�� ��� 2009
�攪�́@8-3�@�N�����`�ƃz�V � 2012
�攪�́@8-4�@�叼 ��쐣 2010
�攪�́@8-5�@�n�̐_�ɏ���ꂽ�֒��A�� � 2012
�攪�́@8-6�@���|�~�̏���Ƌ��� ��� 2010
�攪�́@8-7�@����̔N��� �� 2010
�攪�́@8-8�@���Q��̋����� ��� 2010
�攪�́@8-9�@��쐣�̎G�� ��쐣 2011
�攪�́@8-10�@�b��{�E�单�ւ̂����� ��� 2010
�攪�́@8-11�@�������̓���̔N�� ��쐣 2011
�攪�́@8-12�@�j���E�M ��쐣 2011
�攪�́@8-13�@�U�� ��쐣 2011
�攪�́@8-14�@�ߕ��̌ˌ��̖����� ��쐣 2011
�攪�́@8-15�@���l�` ���� 2010
�攪�́@8-16�@���l�` ���� 2011
�攪�́@8-17�@�|���V 2010
�攪�́@8-18�@���l�`�ւ̂����� ���� 2010
�攪�́@8-19�@���l�`�ւ̂����� ���� 2011
�攪�́@8-20�@�K���h�E�` �呠 2010
�攪�́@8-21�@�O�@����̐Α� ���� 2011
�攪�́@8-22�@���L���� �H�z 2012
�攪�́@8-23�@���l�`�ƕ��ԍ��~���� ���� 2010
�攪�́@8-24�@�z�I�m�L�̗t���g�������� �_�a 2010
�攪�́@8-25�@�V���Ղ� �� 2011
�攪�́@8-26�@�V���Ղ�ɒ������ďW�܂�Ƒ� �� 2011
�攪�́@8-27�@������ ���� 2011
�攪�́@8-28�@����_�̐l�`��� �H�z 2011
�攪�́@8-29�@����_ �H�z 2011
�攪�́@8-30�@���E�\�N�̌}������ �c�Ì� 2010
�攪�́@8-31�@�}������ �ܕ� 2011
�攪�́@8-32�@�~�I �c�Ì� 2010
�攪�́@8-33�@16�����ɋ�����H�� �c�Ì� 2010
�攪�́@8-34�@�q���E�i 2010
�攪�́@8-35�@�i�X�ƃL���E���̔n �ܕ� 2011
�攪�́@8-36�@�i�X�ƃL���E���̔n �c�Ì� 2010
�攪�́@8-37�@���쑗�� �c�Ì� 2010
�攪�́@8-38�@�q���N�n�b�^�C ���a55�N
�@�@������ �ɓ����A���� 1980
�攪�́@8-39�@�q���N�n�b�^�C �ܕ� 2011
�攪�́@8-40�@�\�l���O�� �ܕ� 2011
�攪�́@8-41�@�O���x�� ���� 2011
�攪�́@8-42�@��O�� ���n 2012
�攪�́@8-43�@��O�����{�� ���� 2010
�攪�́@8-44�@��\��铃�E��\�O�铃 ���� 2011
�攪�́@8-45�@��\��E��\�O�铃�Q�� �{�� 2012
�攪�́@8-46�@�R�̍u ���a37�N �_�a �ߓc���j���� 1962
�攪�́@8-47�@�R�̐_�ւ̂����� �L�� 2011
�攪�́@8-48�@��̎q�ɋ����郏���c�g �c�Ì� 2010
�攪�́@8-49�@��̎q�̂����� �c�Ì� 2010
����
���́@9-1�@�����@ ���� 2008
���́@9-2�@�h�s�� ����� 2013
���́@9-3�@������ ���� 2013
���́@9-4�@�F���� �K�C 2013
���́@9-5�@���X�_�� ���� 2011
���́@9-6�@�L�h�_�� ��� 2013
���́@9-7�@�������Ƌ{�̌����� ���� 2010
���́@9-8�@�����_�Ђ̗��� � 2009
���́@9-9�@����_�_���̃����l�` �H�z 2009
���́@9-10�@�˂����Ă�ꂽ�����l�` �H�z 2009
���́@9-11�@���������{ ���� 2012
���́@9-12�@�����Ղ� ���� 2007
���́@9-13�@�\��_�� ���� 2012
���́@9-14�@���n�� 1998
���́@9-15�@���n���̌아 ����y�����ُ��� 2010
���́@9-16�@��C�G�n �����y�����ُ��� 2010
���́@9-17�@�H�t����̏�铕 ���� 2013
���́@9-18�@�V���Ղ� ���n 2012
���́@9-19�@��ԎR���������㉜�Ђւ̓o�q 2010
���́@9-20�@�R�����ł̋s 2010
���́@9-21�@�r�c�R�̌�Ԃ��� ���� 2011
���́@9-22�@�����R�Δ�Q �֗� 2011
���́@9-23�@����u�� ��J 2011
���́@9-24�@�����̓��� �ʕ� 2009
���́@9-25�@�M�\���̌{�̊G �A�J 2010
���́@9-26�@���Q�� �����k 2011
���́@9-27�@���\�������~�j��� ��� 2013
���́@9-28�@��t�� ���� 2013
���́@9-29�@�ω��� ���{ 2013
���́@9-30�@�O�\�O�ω� ���{ 2010
���́@9-31�@�_���� �a�� 2012
���́@9-32�@�Ε��Q ���� 2012�@
�i�ȉ����j |
�R���A�V���� ���������ꂨ���Ȃ풲���{���ەҁu����ŋ��哹� �����v���u�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�v���犧�s����B�@�@�@�@�@(�������ꂨ���Ȃ�|�\�����W
; ��1�W)�@�@198p�@�����F���ꌧ���}���فF1007082561
|
����ŋ��哹� �V�� ���
�ŋ��G�� �X�c �L�� |
����ŋ�<�Βk> �v�����g�^�����g�F�q
���f���������<�哹���> |
����ŋ��֘A���N�\ ��� �w
�u�V���� ����ŋ��哹��v(�㊪)�ڎ� |
�R���A���A�m�����j�����Z���^�[ ���u�Ȃ����� : �R���̃����E�V�}�u���y�ђ����L�^ Vol.19�v���u���A�m������ψ���F���A�m�����j�����Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@277p�@�@�����F��㊌����}���فF1007961582
|
��1�� 2008�N7���̒����L�^
1 �������n�̊Ɠ���
2 ���A�m�Ԑ؋���}
3 ���a10�N���̐V���L��
4 ��蕨(�~�W����)
5 ��������h�邪���o����
6 ��ܖ�(�E�v���~)�̎��̃����U��
7 �R���̌��(�E�^�L)�ƏW��
8 ���͂̌��(�E�^�L)(����s)
9 ���͂̌��(�E�^�L)���\������v�f
10 ���j�w�K
11 �����E�V�}�u��
12 �����q�̌��(�E�^�L)���\������v�f
13 �����̌��(�E�^�L)
14 �Ď�(���A�m�i)�ƈ��������b
15 ���������Ԃ̃E�^�L(�O�X�N)
16 �R���̌��(�E�^�L)����
17 ����n���̌��(�E�^�L)����
18 ������(���A�m������)
19 �����̌��(�E�^�L)(���A�m��)
20 ����n���̉䕔�̌��(�E�^�L)
21 �k�R��(1���`7���F���A�m�i)
22 �H�n�̉䕔�c�͂̌��(�E�^�L)
���i�Ǖ����܂ł䂭
24 �u�E�E�E��v�Ƃ��Z�̑�(���i�Ǖ���)
25 ���A�m�O�X�N���ӂ̂��Ă̕��i
26 �Ԑؖ�l�̖�E������
27 ����̐��E��Y-���A�m��Ղ𒆐S��-
28 ���A�m�̕��i
��2�� 2008�N8���̒����L�^
1 �n��j���c��̌��C��
2 ���[�j�Q�[
3 �^�_���䂫
4 �����E�V�}�u��-�{�������-
5 ����̃O�X�N(�E�^�L)
�_�A�T�M�Ɠa
7 �k�R����
8 ���ꕗ���}��
9 ���[�Ԑ̑n��
10 ���[�Ԑ��n��
�E�^�L�E�O�X�N�����鎋�_
12 �{�����ӉԂ̃E�^�L(�E�K��)
13 �R���̌��(�E�^�L)�̐���
14 ���(�E�^�L)�ƃO�X�N���݂鎋�_
15 �{������u���̃E�V�f�[�N
16 ���A�m���N��̃E�v���~(�����r�~�`)
17 �����̃V�}�E�C�~
18 100�N�̎����W
19 �W�����
��3�� 2008�N9���̒����L�^
1 ����O�X�N
2 �Ԑ̗���
3 ���ꋌ���n�����x
4 �����Ɠ암�̌��(�E�^�L)
5 �쉮���Ԑ؊쉮����
6 ����s���̕��O��
8 ���A�O�X�N�����_�ɂ������j����
9 ���A�O�X�N���@�\���Ă������j�̗̈�
10 ���A�O�X�N�ł̍��J�ƃ���
11 ���A�����̑��X
12 �^�_���Ɨ���
13 ���A�m�����̕�Ȃ�
14 ����(����)�n��̃O�X�N
��4�� ���A�m�� ����100�N�̕���
2 ���c���O�X�N(��u��ԐF���݂���s)
3 ���W�̍�Ƃ��{�i��
4 �쉮���O�X�N(��u��ԐF���݂���s)
5 �{�����l��
6 �]�B�O�X�N(��u��ԐF���݂���s)
7 ���W-����100�N�̕���-
8 ���Ӓi�O�X�N(�E�^�L)
�@�@��(��u��ԐF���݂���s)
9 ���������
10 ���u�̉����ƍ����̖L�N��
11 �W����̊J��
12 �����̃R�[�i�[
13 �W�����
14 �̌����Ă������j
15 �����E�V�}�u��(�{�����l��)
16 �k�R�̗��j�����鎋�_
17 ����Ҋw��
18 �ɍ]��
19 �R���̌܂̃O�X�N
20 �R���̐V�������j��
21 �k�C��
22 ��l�����̒m�b
23 �k�C���x���Ə��ݒn
24 �E�^�L�ƃC�x
��5�� 2008�N11���̒����L�^ |
1 ��R �V���|�W�E��
2 �{��^������/�����̊C�_��
3 �ÉF�����̃v�[�`�E�K��
4 ���[���̊Ԑؑ��S�}
5 �����Ԑ���̑�(���[�����Ð^)
6 ���{����̎��ߏ�
7 �H�n�Ԑؐ^�쉮�m���a��
8 �ÉF�����̃^�L�k�E�K��
9 �{�����ӉԂ̔q��
10 �ߓx����ڂɂ��Ă���������-������G-
11 ��������n
12 ���A�m�����@���̘V�l��
13 �y�n�Ɋւ�錾�t
14 �Ԑ؏Z���͎O��
15 ����20�N���̊Ԑؐl���̐���
16 �^�V�ɕ��B�D���Y��
17 �^�_���Ɩk�R
18 �����̌×����̎��ߏ�
��6�� 2008�N12�������L�^
1 �w�����ƕ��x(�v�Čn)
2 ���[��(�\��)���Ð^�ƈ��x�c
3 ���[�����Ð^�̎O�̌��
4 ���[�����x�c
5 �^�_�E���i�Ǖ����E���V���̎O���Ɨ���
6 �k�R�̗��j�ƕ���
7 �^�_���Ɩk�R
8 �^�_��
9 �w���ꌧ�����S�u�x
10 ��X�����c�`
11 ����������
12 ���A�m�O�X�N
13 �w�C�������I�x
14 ���A�m�O�X�N�ɂ܂��`��
15 �H�n�Ԑ̉H�n�̓n�j�K�[�ɗR����
16 ���u�̃E�v�K�[
��7�� ���A�m�����O�̖L�N��
�͂��߂�
�T �L�N��(�ق��˂�)
�E2011�N9��8��(��8��11��)�F�L�N�Ւ���
�E���A�m�� ��(����)�̕���
�E���A�m���Ӗ�(�����)
�E���A�m���������q(���肫�Ⴍ)
�E���A�m�����N��(�킭����)
�E���A�m������^�V(���݂���Ă�)
�E���A�m��������(���܂ǂ܂�)
�@���A�m����������L�N�� 2011�N9��8��
�@�@��(��8��11��)
�E��[�x��
�E�k���h�D���`
�E�I�[����a(���ǂ���)
�E�_�p�E���W���l�[
�E����
�A���A�m�����Ӗ���L�N�� 9��10��
�@�@��(��8��13��)
�E���W���l�[
�E����
�B���A�m�����N���L�N�� 9��11��
�@�@��(��8��14��)
�E����L�ꂩ��
�E�O�k�s���[
�E���q��
�C����s������L�N�� 9��11��
�@�@��(��8��14��)
�D����s���]��L�N�� 2011�N9��12��
�@�@��(8��15��)
�E�{�������ɓ�����L�N�� 2011�N9��12��
�@�@��(��8��15��)
�F����s����������L�N�� 2011�N10��5��
�@�@��(��9��9��)
�G����s������[�� 2011�N10��6��
�@�@��(��9��10��)
�U���A�m�������̖L�N�� 2012�N10��6��(�y)
�H���A�m������R�̖L�N��
�I���A�m�����������̖L�N��
�J���A�m�����^�ߗ�̖L�N�� 2012�N10��7��(��)
�V���q��(�����܂�)
�y�����z
�E����(���܂ǂ܂�)�̎��q
�E���@��(�Ȃ�����)�̎��q
�E��^�V(���݂���Ă�)�̎��q
�E�N��(�킭����)�̎��q
�E�ʏ�(���܂���)�̎��q
�E�����q(���肫�Ⴍ)�̎��q
�y���O�z
�E�{�����E�ɓ���(������)�̎��q
�E����s�E���(���킩��)�̎��q
�E����s�E���](�����肦)�̎��q
�E
�E |
�E�X������E���c(�܂�)�̎��q
�W �V�}�E�C�~(���q��)
��8�� �����̕��y�L
1 �����t(���܂��Ƃ���)
2 �ߐH�Z
3 ����
4 �l�Ԃ̏Z(�Z�܂�)
5 �тƗ���
6 �X�q
7 ����̎l�G
8 �_��
9 ���Ă̖��O
10 ������
11 ���̖��O�Ƃ��̎��
12 ���������̖��O�Ƃ��̎��
13 ��̖��O�Ƃ��̎��
14 �ؗt���̎��
15 ���̖��O�Ƃ��̎��
16 �ʎ�
17 �����̖��O
18 �Ǝ���Ƃ˂��݂̗\��
19 �g�D�W�����[�ƃT���y�[�O�[
20 ���Z���̓���
21 �n��ɏZ�ޒ��̖��O
22 ���Ԓ��̖��O
23 ���K���V�̓`��(��̂��炷)
24 �`���`���C�ƃG���W���̉�
25 �Ђ�̉�
26 ���݂̖��O�Ɩ�
27 ���ݎ��̉�
28 �K�[�^�[�ƃ}�~�T�[�g�D
29 �u�̉̂Ƃ��̊��z
30 �C�̋�
31 �X�u�`�u�E�i�[�ƃA�o�[�V
32 �L���[�p�~�ƃN�T�p��
33 �T�o���̘b
34 �C�̂��Ȃ��̖��O
35 �C�̊L�̖��O
36 �i�[�O���z�E���[�̘b
37 ��Ɛ��̒��̋�
38 ���̒��̖̖��O
39 ���O(�f�C�S)�̖̉�
40 �Z�~�ƃV���_���̉�
41 �V���o�}�̎v���o
42 �V���o�}�̏H�̗[�_
43 ���E�n�V�r�[
44 �i�[�g�E�K�[�k�E�i�[�W�̘b
45 ��������̕���
46 �q��̂̊��z
47 �q���
48 �q�炳��Ƃ�����
49 ���A�m��̊��z
50 �z���Ƌ�z
��9�� ��������(��)
�@�@��(�j�[�i�V�J�[�~�i)
�u�Ɂ[�Ȃ����[�݂ȁv�̗R��
1 �q���̍��̗V��
2 �����̊T��
3 ���ӂ̒n��
4 �����̏㌴�܂�
5 ����(�����E�`)�̒n��
6 �����̈��
7 �����̃t���C
8 �t�@�[�C�E���[
9 ���̈�N�Ԃ̍s���ƍՂ�
10 �e���̌ď�
11 �����̐�����
12 �V��
13 �H��b
14 �O�H�̌Ăѕ�
15 7���G�C�T�[
�܂Ƃ�
��10�� ��������
�@�@��(�j�[�i�V�J�[�~�i)(��)
1 �����ɓ`���K��
�@�@��(�}�u�C�O�~�ƃ}�u�C�V�[)
2 �����̖L�N�x��
3 �}������
4 �����̕����̂���
5 ���U�̋F��̌��t
6 �L�N�����̌��t
��11�� �w��ē��x
1 �q��S
2 ���w
3 �{���S
4 ���w(1)
5 ���w(2)
�ҏW��L
�ҏW��L |
�R���A��J�וF���u����c��w��w�@����w�����ȋI�v : �ʍ� 20(2) p.129-140�@����c��w��w�@����w�����ȁv�Ɂu���[�A�V�r (�їV��) �ƕ������lj^���Ɋւ����l�@�v�\����B
�S���A����q�����u����{�̖��������� 8 (����{�̖����|�\�� �k�F������)�v���u����V�Ёv���犧�s����B
|
�T�v ����쒆�E������̖����|�\
�F������s���̖����|�\ ���ӂ̖����|�\����
�@�@�� (�i�g�여��R�[�n�т̌|�\)
�n��ʌ|�\ ���ܒ��F�� (���F����) �̖����|�\
|
���ܒ��ߓc (���ߓc��) �̖����|�\
���ܒ��{�V�� (���{�V�钬) �̖����|�\
�F������s�V���@���̖����|�\
�F������s���k�� (��㒬�E���钬) �̑��ۗx�� |
�T���A�f�������F����S���G�C�T�[�܂���s�ψ���ďC�u��57��S���G�C�T�[�܂�
����c�����A40���N�L�O ��1�`3���v ���u���{�R�����r�A�v���犧�s�����B�@
|
| �m�� |
���^�n |
| 1 |
����s�䉮�����w�Z(�����Ȃ킵�Ђ₲�傤��������)/����s�Ɖ��N��/�X��p�s������N��/����s�ז��N��(�Ȃ����т��܂������˂�)/����s�������N��/�J�`���[�V�[ |
| 2 |
����s���ی𗬋���/���[�������N��/�������Ղ葾��/����s���N��/����s���~���N��(��)(����܂��ւ����₹���˂��E�Ђ���)/�J�`���[�V�[ |
| 3 |
����s�w�l�A����/�Î�[���猴�G�C�T�[�ۑ���(���łȂ��傤����邦�����[�ق���)/����s�r���N��/���s���N��/����s���c�N��(�����Ȃ킵�������˂�)/�J�`���[�V�[ |
|
�T���A�u����v�z 41(6) (�ʍ� �Ց�) �����W �����Ɩ� : �����{�}���_���v���u�y�Ёv���犧�s�����B
|
�w�����Ɩ��Ɖ��� ���z�ւ̃��u���^�[�x�I �@�V�� �`�a �I p.�}��8p
�Ўv���̃��u���^�[�Ўv���̃��u���^�[�@�^�C�� �W���� p.12-17
�f���o���ꂽ�����Ɩ��@���� �L�O �� p.18-23
�ʐ^����葱���� : �����Ɩ��Ɓu�V�����v�o����߂�
�@�@���X�R�哹,�ɓ��r�� p.24-43
�F�� : �����Ɩ� �哇 �� p.44-54
���̕��A�c�c �@���� �Ɩ�,�g�� ���� ������ p.55-62
�����̊X����@�e�n �q�q p.63-65
�����q���� �@�ΐ� �^�� �y�Ё@ p.66-68
�v�z�ʐ^�ƁE�����Ɩ� �@��� �V �y�Ё@ p.69-75
�u���v�̃����^�[�W�� : �����Ɩ��_ )�@�@�y�� ���� p.78-85
�����Ɩ���킽���̒��� : ���A���Y����
�@�@���u�g�ʐ^�v�̊Ԃ� �@�|�t�� p.86-98
���̏��� : �����Ɩ����߂���C �@���� ���� p.99-111 |
�h�L�������g�̎��w : �����Ɩ��̒�� �@���p ���m p.112-119
����̔畆 : �����Ɩ��w<11��02��>NAGASAKI�x�@�ѓc�V p.120-131
�_�����R�ցA�l�N���t�B���A�̐V�������ց@�F�� �� p.132-140
����}���_���̂��� �@���� ���� p.141-151
���������E���獬�����E�� : �]�����铌���Ɩ� �@�������V p.152-161
�C���[�W�̌Q���ƌ��̎��w :
�@�@�������Ɩ��̉���N���j�N��43 ������ p.162-173
���邱�Ƃɓq���� : �����Ɩ��ƃV�} �c���N�� p.174-185
��������ʐ^�A�����邽�߂̎ʐ^ �@�u�ꗝ�]�q,�V���v p.186-201
<���>�ƃJ���[�ʐ^ : �����Ɩ��Ɠ��X �@���c�� p.202-212
�ʐ^�����݂���ꏊ �@��������Y p.213-229
�����Ɩ���v��i�W�E�W������ �@�F�q p.230-241
�N�� �@ p.242-245
�E |
�V���A�u�L�b�Y�E�G�C�T�[ : �^����_���X�\���O�x�X�gnew : ����DVD&CD�u�b�N�v���u���y�Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@
|
1�@�Ă����ʂӂ� �{�邿�� �쎌 ���� �� ��ȁ@3
2�@���C���C ��c�p�� �쎌 �m����j ��ȁ@8
3�@�O����(�݂ނ�Ԃ�) �{���̂��ׂ����@14
4�@�ԓc�a��(����������ǂ���) �n���̂��ׂ����@18
5�@�G�C�T�[�V(����)�� ��H �N�O �쎌 ��ȁ@24
6�@�q���~�J�`�߁`�J�`�E�L���` �쎌:�s�ڍ��:�R�����j�@31
7�@���D(�Ƃ�����)�ǁ[�� ����{�����w�@37 |
8�@����(�͂�݂�)�̐���(��������[) �{�Ö��w�@42
9�@�ǂ�ǂ�ǂǂ� ���c�_�u �쎌�E��ȁ@47
10�@���Ƒ���(����)�Ƒ�n�� ���c�_�u �쎌�E��ȁ@58
11�@�������E���b�Z�[�� ��{�� �͂��� �쎌�E��ȁ@66
12�@���b�N�������ؐ� �Q�n���E�Ȗ،����w�O�Y�P�v �쎌�@76
13�@�L�b�Y�\�[���� �k�C�����w�O�Y �P�v �쎌�@87
�E |
�V���A�ߍ����j�Ҏ[�ψ�����Ǖҁu�����̏Ռ��g : ���̍����ǂ��Ȃ�̑��Ձv���u�^�ߍ����v���犧�s�����B (�^�ߍ������j ; ��3�� (���j��)�j
|
�����ɂ������ā@�^�ߍ����� �O�Ԏ�g�@1
�_�b �Ă�����ǂ�����@�ď霨(�^�ߍ����j�Ҏ[�ψ�)�@6
���́@���R���Ɠ��̌��݁@13
1�@�ʒu�E�n���@������(�^�ߍ�������ψ���)�@14
2�@�C�ۓ����@���؏�(���^�ߍ�������)�@20
3�@�l���̐��ڂ���݂���j�@�Y��i��(���j������)�@24
���́@�×�������̗^�ߍ��@57
���́@1�@�^�ߍ��̂����ڂ́\���̌Ñ�j�����߂����ā\�@
�@�@���k���F��(���C��w�����E�l�Êw��U)�@58
���́@1�@�R�����E2���N�O�l���̔����@
�@�@���Ћː爟�I(���ꌧ�������فE���p�َ�C�w�|��)�@70
���́@1�@�g�D�O���l��Ձ@�����k�~(�����ꌧ�������������Z���^�[����)�@74
���́@1�@�R�����E���d�R�Ɗ�E�������Ԃ��́@�����i(���ꌧ�������فE���p�يْ�)�@84
���́@2�@�\�ܐ��I�̗^�ߍ�
���́@2�@(1)�@�씿���W���@�����k�~�@90
���́@2�@(2)�@�c�c��W���@�������I(�f�Փ�����������������)�@100
���́@2�@(3)�@�����W���@������(����l�Êw��)�@128
���́@2�@�R�����E�������T�K�C�E�C�\�o�@�ď霨�@142
���́@3�@���̊O����݂���
���́@3�@(1)�@�^�ߍ��Ɛ��\�̌𗬎j�@�Ί_����(���\�ݏZ�E���y�j������)�@146
���́@3�@(2)�@�u�������ƕ��v���ɂ݂�S�Վ����@
�@�@�����@������(�{�Ó��s�j�Ҏ[�ψ���ψ���)�@158
���́@3�@(3)�@�u�S�Ղ̖��̃A���S�v�l�@���n���K(�{�Ó��s�j�Ҏ[�ψ�)�@168
���́@�ߐ��̗^�ߍ��@183
���́@1�@���{�E�����Ɨ^�ߍ����@���Ǒq�g(������w���_�����E�����j)�@184
���́@1�@�R�����E�v���NJ��A�l���c�`�����߂����ā@���Ǒq�g�@196
���́@2�@�l���łƗ^�ߍ����@���\���(�@����w���ꕶ�����������C����)�@200
���́@3�@�ߐ��^�ߍ��̖��O�����j�@���\����@214
���́@4�@�^�ߍ������߂���Y���E�Y���@���\����@254
��O�́@�ٕ��̊�\�^�ߍ������̋H�L�Ȃ铥���҂����\�@269
��O�́@1�@������
��O�́@1�@(1)�@���X�V���@�ď霨�@272
��O�́@1�@(1)�@�쓇�T���@����(�����) �������o�v(�������w�Z���@)�@278 |
��O�́@1�@(2)�@���������@�ď霨�@294
��O�́@2�@�吳�E���a��
��O�́@2�@(1)�@�{�R�j��@�ď霨�@298
��O�́@2�@(2)�@�{������@����N�Y(���d�R������������)�@306
��l�́@��O�E���̗^�ߍ��@327
��l�́@1�@�^�ߍ����\��i�E���Y�E�����\�@
�@�@���약���Y(������w�����E����Љ�o�ώj)�@328
��l�́@1�@�R�����E1�@�^�ߍ��V���@�Y��i��@347
��l�́@2�@�A���n��p�Ɨ^�ߍ��@���c�ǍF(���d�R�����V���L��)�@348
��l�́@3�@�����㌧�m���@�^�ߍ���K���@�ď霨�@378
��l�́@3�@�R�����E2�@�Ȃ���@�Y��i��@382
��l�́@4�@�펞���̗^�ߍ��@��c�Òj(���Ί_�s�����ۉے��A���y�j��)�@384
��l�́@4�@�R�����E3�@�F�Ǖ��w����@�Y��i��@405
��l�́@5�@���^�ߍ����̎Љ��z�������f�Ձ@
�@�@���Ό�����(���ꍑ�ۑ�w���_����)�@406
��l�́@6�@���f�Վ���E�Y��h���،�(�C���^�r���A�[�E�Ό�����)�@440
��l�́@6�@�R�����E4�@�c������̑��n���@�Y��i��@475
��l�́@7�@���f�Վ���E��Y���Y�،�(�C���^�r���A�[�E�ď霨)�@476
��l�́@7�@�R�����E5�@�l�g�m�@�Y��i��@504
��́@���삲�Ƃɂ݂��^�ߍ��@507
��́@1�@�_���̂���݁@���k�V�n(���s��w���w���m�A
�@�@���R��������w���ە����w������)�@508
��́@2�@�D���j�@�o�ߗ��q(���ꌧ�������فE���p�َ�C�w�|��)�@528
��́@3�@�|�\�j�@�c�Ԉ�Y(�����Y�\�j������)�@548
���҈ꗗ(�v���t�B�[��)�@580
�t�^�@�^�ߍ����j�N�\�@586
���_�����@629
�����@630
�Q�l�E���p�����@636
��������т����͂������������X
�@�@���@(�^�ߍ����j�Ҏ[�ψ���A�����ψ��ق�)�@639
�ҏW��L�@640
�E |
�X���A�g�Ɗԉi�g���w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 47(2) (�ʍ� 114) p.86-104�v�Ɂu�u���Ζ���v�l(��)�v�\����B�@
�X���A�ܗ��d�i������j���u���Ƌ��{�v���u�����o�Łv���犧�s�����B�@�V���Ł@�@
|
I�@���@�_�\��ᖍ��ƒ����@1
I�@��@�͂��߂Ɂ@3
I�@��@1�@���ƕ����@3
I�@��@2�@��ᖍ��ƃ��K���@7
I�@��@�Ñ�̟q�@11
I�@��@1�@�V�c�Ƃ̟q(�_���\�i�s)�@11
I�@��@2�@�V�c�Ƃ̟q(�����\�p��)�@15
I�@��@3�@�V�c�Ƃ̟q(���Ձ\�q�B)�@19
I�@��@4�@�V�c�Ƃ̟q(�p���\�c��<�Ė�>)�@22
I�@��@5�@�V�c�Ƃ̟q(�F���\�V�q)�@27
I�@��@6�@�V�c�Ƃ̟q(�V��)�@30
I�@�O�@���R���@�ƒ����@35
I�@�O�@1�@���R���@�Ƃ��Ă̟q�@35
I�@�O�@2�@�q�̑h�����@39
I�@�O�@3�@�^�}�V�Y���ƃ^�}�t���@43
I�@�O�@4�@�����_�y�ƃ^�}�V�Y���@47
I�@�O�@5�@�t�y�̕��ƒ����@52
I�@�O�@6�@�V������C�^�R�E�O�����ց@56
I�@�O�@7�@�v�����̕����@62
I�@�O�@8�@��ԂƏ�@67
I�@�O�@9�@���ĂƉԊɁ@72
I�@�O�@10�@���{�Ɵq�@76
I�@�O�@11�@���ĂƎP�Ɗ}�@80
I�@�l�@�c�̎�ނƍ\���\�q�̎c���`�ԁ@85
I�@�l�@1�@���̎��ҋ��{�ƐR�^�q�@85
I�@�l�@2�@�Ċ_�ƐR����сu�݂���v�@90
I�@�l�@3�@���_�^�q�Ɛ،�(���K��)�@96
I�@�l�@4�@���_�^�q�̕ω��@101
I�@�l�@5�@�����h���^�q�̔����@107
I�@�l�@6�@�T���M�b�`���Ɗ��E�L�E�@110
I�@�l�@7�@�R�{�̘m�z�R���ƃI�n�P�@115
I�@�l�@8�@���p�~���ƕ_�@118
I�@�l�@9�@�쉮�^�q�̎c���`�ԁ@123
I�@�l�@10�@������̗쉮�Ƒr���@126
I�@�l�@11�@�M�����Ɓu���v�@129
I�@�l�@12�@�X���^�q�̑c�^�\�V�n�������@134
I�@�l�@13�@�X���^�q�̎�X���@136
I�@�l�@14�@�Č^�q�ɂ��Ă̏��@139
I�@�l�@15�@�U���R���K�V���Ă̎�p���@143
I�@�l�@16�@�Ăƕ�����p�@147
I�@�l�@17�@���_�^�q�Ǝl�����@150
I�@�l�@18�@���_�ƃw���@154
I�@�l�@19�@�ϐΌ^�q�ƒd�z���@155
I�@�l�@20�@���A�^�q�Ɠ��A�M�@158
II�@����_�\���̏@���I�ϔO�@161
II�@��@�͂��߂Ɂ@163
II�@��@1�@����j�����Ƒ���@163
II�@��@�������ƓV�W�@166
II�@��@1�@����ɂ�����l�{���@166
II�@��@2�@�l�{���Ɩ��l���@170
II�@��@3�@�l�{���ƓV�W�̘�ƑT�@�@174
II�@��@4�@�V�W�Ɣ��W�@178
II�@��@5�@�V�W�̖ōߐ��@181
II�@��@6�@�����Ɵ��@184
II�@��@7�@�����ƃ^�}�V�C�u�N���@185
II�@��@8�@���R�ƓV�W�@190
II�@��@9�@�_�y�̔��W�Ƒ��V�W�@193
II�@��@10�@���R�́u�ܐF�̉_�v�Ɨ��@197
II�@�O�@��Ɗ}�E���@201
II�@�O�@1�@��Ǝ��o�̎R�@201
II�@�O�@2�@���̏�Ɩō߁@205
II�@�O�@3�@���̏�ƃC�L�c�L�|�@208
II�@�O�@4�@��Ə��t���k�@213
II�@�O�@5�@����̊}�Ɩ��@216
II�@�O�@6�@���斯�����Ɍ����}�Ɗ����}�@219
II�@�O�@7�@�}���̎���Ɗ}�n���@223
II�@�O�@8�@�f���j���̖��}�@227
II�@�O�@9�@�̘b�̉B�ꖪ�A�B��}�@229
II�@�O�@10�@�[���Đ��̊}�Ɵ@232
II�@�O�@11�@�x�O���̊}�Ɩ��@237
II�@�O�@12�@�l�\��̖݂Ɗ}�̖݁@241
II�@�O�@13�@�}�̖݂̈Ӗ��ƃG�g���݁@244
II�@�l�@�l�ԂƊ����@248
II�@�l�@1�@�l�ԂƁu�n���v�̎l���@248
II�@�l�@2�@�l�ԂƑ��Ԃ̍����@252
II�@�l�@3�@���Ɛ���@255
II�@�l�@4�@�l�Ԃ́u�n���v�Ɣ��n���@259
II�@�l�@5�@�C�����̒n�掮�Ǝl�ԁ@262
II�@�l�@6�@��n�Ɗ����̎l�ԁ@265
II�@�܁@�o��q�@270
II�@�܁@1�@�o��q�Ɖg����䶗��@270
II�@�܁@2�@�o��q�Ɗ��|�U���@274
II�@�܁@3�@�o��q�̖ōߐ��@278
II�@�܁@4�@���R�̕z���ƌo��q�@280
II�@�܁@5�@�����͂Ɓu�͓n��v�@285
II�@�܁@6�@�Љ��R�Q�l���b�Ǝ��҂̒����@289
II�@�Z�@���@292
II�@�Z�@1�@���ƃt�l�@292
II�@�Z�@2�@�P�����牱���A�����ց@295
II�@�Z�@3�@�r���߂̕��������~�ԁ@300
II�@�Z�@4�@�������ƗV���@302
II�@�Z�@5�@���ƞ@306
II�@�Z�@6�@���̑傫���ƞ����@309
II�@�Z�@7�@�T�@�̊��̘�ƕ����@313
II�@���@�L�@317
II�@���@1�@�T�@������@�ƌL�����@317
II�@���@2�@�Ñ�̌L�ƎĐ܂�̎���@320
II�@���@3�@�L�Ə��Ɗ��@324
II�@���@4�@�L�Ɓu����������v�Ɨ����@326
II�@���@5�@�L�����Ɓu�������v�@330
II�@���@6�@���Ɨ썰�Ə@���Ɓ@334
I�@���@������ⴁ@338
II�@���@1�@�����̓��@338
I�@���@2�@����Ƃ��Ă�ⴁ@342
II�@��@���ɑ܂Ɠ����i���@345
II�@��@1�@���ɑ܂ƎO�ߑ܁@345
II�@��@2�@�܍��܂ƒ����@348 |
II�@��@3�@���ɑ܂ɓ����i�X�@351
II�@��@4�@���ɑ܂Ƃ������E���蔻�@355
II�@��@5�@���蔻�ƌ�@359
II�@��@6�@���ɑ܂̘Z���K�Ɛj�@362
II�@��@7�@�����ƔO�����@366
II�@�\�@�����ƔO���ҁ@370
II�@�\�@1�@�����ƔO���@370
II�@�\�@2�@�����O���ƔO���ҁ@375
II�@�\�@3�@�O���҂Ɠ���@377
II�@�\�@4�@�w�킪���͂����ɗ��x�ƔO���ҁ@382
II�@�\�@5�@���썰�_�Ƒ������p�_�@388
II�@�\�@6�@���������̕����@391
II�@�\�@7�@�썰�ƔO���ҁ@394
II�@�\��@���[���b�p�̑���Ƃ��̌������@399
II�@�\��@1�@�����̖����w�����قƑ��掑���@399
II�@�\��@2�@�p���̖��|���������ق̏\���ˁ@402
II�@�\��@3�@�C���@�ƕ�@405
II�@�\��@4�@���[���b�p�́u���Ƒ��搧�v�̌������@409
II�@�\��@�Z���@416
II�@�\��@1�@����̘Z���@416
II�@�\��@2�@�Z���̕��Ր��@420
II�@�\��@3�@�w�����x�ɕ��ꂽ�Z���@423
II�@�\��@4�@�����̏W�Ɍ�����Z���@426
II�@�\��@5�@�ҐC�䃍�[�\�N�X�C�Ɠ����@431
II�@�\��@6�@�Z���̕��ނƏ�|�̈Ӗ��@435
II�@�\��@7�@���`�ՂƖ@�t�A�z�t�@441
II�@�\��@8�@���`�Տj���Ɖ��̊�_�@444
II�@�\��@9�@�Z���ƘZ�ʐΛ�@448
II�@�\��@10�@�Z���ƘZ�n���@451
II�@�\��@11�@�Z�n���̎���~�ρ@456
II�@�\��@12�@�Z�n���M�̕��y�@459
II�@�\��@13�@�Z���ƕ����̏����@462
II�@�\��@14�@�Z�n���Ɠ��c�_�̘̐b�@467
II�@�\��@15�@���`�Ղ̎���`矂̏������b�@469
II�@�\��@16�@���A���́u�O��������v�@473
II�@�\��@17�@�Z���ƘZ���K�@476
II�@�\��@18�@���c�q�̘Z�ƘZ���@480
II�@�\��@19�@����̎c���Ƃ��̕@483
II�@�\�O�@��蕨�@488
II�@�\�O�@1�@�����n�т̑��̔�蕨�@488
II�@�\�O�@2�@�E���n���̑��̔�蕨�@492
II�@�\�O�@3�@���̑��M�E���M�Ə\�O������@494
II�@�\�O�@4�@�R�z�E�R�A�n���̑��̔�蕨�@498
II�@�\�O�@5�@�l���E��B�E�쐼�����̑��̔�蕨�@501
II�@�\�O�@6�@������_�ւ̔��_�@505
II�@�\�O�@7�@���̔�蕨�̕��ށ@509
II�@�\�O�@8�@�z���̕ƎR���̕@512
II�@�\�O�@9�@�����Ƒ����@515
II�@�\�O�@10�@�V�z�I�Ǝu����@519
II�@�\�O�@11�@�����̖ōߐ��ƍ~�����@521
II�@�\�l�@�l�`�ƒƁ@526
II�@�\�l�@1�@����̐l�`�ƒƁ@526
II�@�\�l�@2�@����̐l�`�ƈ������Á@530
II�@�\�l�@3�@����̒Ƃƒ������́@533
II�@�\�܁@���k�@537
II�@�\�܁@1�@���Ƌ��{�̓��k(�����k)�ƃX�g�D�[�p�@537
II�@�\�܁@2�@���{���p�ƌ��E�@540
II�@�\�܁@3�@�l�\��@���k�ƘZ�p���k�@544
II�@�\�܁@4�@���{�̓��k�Ɠ������k�@549
II�@�\�܁@5�@�Z�p���k�Ɗp���k�@552
II�@�\�܁@6�@�̓��k�Ƒ����k�����@555
II�@�\�܁@7�@�Γ��k�Ɣ�@559
II�@�\�܁@8�@���k�̕ϑJ�Ǝێq���k�@563
II�@�\�܁@9�@��^���k�̏@���I�@�\�@566
II�@�\�Z�@�l��Ɖ���@571
II�@�\�Z�@1�@�l��Ƒ��o�Ƒ����@571
II�@�\�Z�@2�@�Ɍ����鉼��Ǝl��@575
II�@�\�Z�@3�@�q�̎l��Ɖ���@578
II�@�\�Z�@4�@�C�����Ǝl��@581
II�@�\�Z�@5�@�l�咹���Ɛ،��@585
II�@�\�Z�@6�@�R�̎l��Ɵq�̎l��@588
II�@�\�Z�@7�@�C�����̑���Ɠ���@592
II�@�\�Z�@8�@��������Ȍ�̎l��̕����@595
II�@�\�Z�@9�@�_�����̎l��Ɩ������@598
II�@�\���@�ʔv�@602
II�@�\���@1�@����Ƃ��Ă̈ʔv�@602
II�@�\���@2�@�ʔv�̔����ƋM���̈ʁ@607
II�@�\���@3�@�ʔv�̏����Ɖ����@610
II�@�\���@4�@�ʔv�ȑO�̊�w�����@612
II�@�\���@5�@�ʔv�ƃz�g�P��(���k)�@617
II�@�\���@6�@�ʔv�ƐΓ��@620
II�@�\���@�����@624
II�@�\���@1�@���{�l�̖��ԏ@���ƒn���@624
II�@�\���@2�@�����Ǝ����Ƌt�C�@630
II�@�\���@3�@�t�C�̌����Ǝ����@634
II�@�\���@4�@�����̉@���̔閧�@638
II�@�\���@5�@�Đ��M�ƑT��卆�@641
II�@�\���@6�@�u���R�s���v�ɂ��t�C�@645
II�@�\���@7�@�u�z����v�̋t�C�@648
II�@�\���@8�@���R�̕z���ƒʉߋV��@653
II�@�\���@9�@�����Ə����M�@656
II�@�\���@10�@�����Ɍ���t�C�@660
II�@�\���@11�@�t�C�ɂ��Γ��Ε��@662
III�@���V�_1�\�ՏI�V��@669
III�@��@�͂��߂Ɂ@671
III�@��@1�@���搧�����̊J�n�@671
III�@��@2�@���V����̕��ނƁu���̗p�Ӂv�@674
III�@��@�����̗ՏI�V��@678
III�@��@1�@�ՏI�V��ƈ��y���@678
III�@��@2�@���{�����̏�y���ƈ��y���@681
III�@��@3�@�w�Z���v�W�x�̗ՏI�s�V�@685
III�@��@4�@�w�ՏI�s�V���L�x�̏Љ�@689
III�@��@5�@�w�ՏI�s�V���L�x�̓��e�@692
III�@��@6�@���y���̂��߂̍�P�@696
III�@��@7�@�ՏI�̌����ƈ��y���@699
III�@��@8�@���{�����Ƒ��搧�̂������@702
III�@��@9�@�w�F�{�W�x�̗ՏI�s�V�@706 |
III�@�O�@�����̗ՏI�V��@710
III�@�O�@1�@�����̐��Ƌt�������@710
III�@�O�@2�@�����ɂ�����ՏI�V��(��)�@713
III�@�O�@3�@�����ɂ�����ՏI�V��(��)�@718
III�@�O�@4�@�u�t�������v�Ɖg����䶗��@721
III�@�O�@5�@���|�U���Ɛ������q�@724
III�@�O�@6�@�g����䶗��ƏC�����@727
III�@�O�@7�@ⴂƔL�ƉΎԁ@730
III�@�O�@8�@�����̐��ƏV��@734
III�@�O�@9�@���тƖ��c�q�@739
III�@�O�@10�@������V�}�@744
III�@�O�@11�@���тƑP�����w��@748
III�@�O�@12�@���тƁu���Ă��v�@752
III�@�O�@13�@�u���Ă��v�Ə����@754
III�@�O�@14�@�m���V�c�I�́u���Ă��v�@759
III�@�O�@15�@�u���Ă��v�ƉA�z���@761
III�@�O�@16�@�u�X�Ă��v�̑h�����@765
III�@�O�@17�@�h���ƒ����\�^�}�t���ƃ^�}�V�Y���@768
III�@�O�@18�@�����ƚL���@772
III�@�O�@19�@�����Ƒ�߁@775
IV�@���V�_2�\�q�a�V��@781
IV�@��@�ʖ�@783
IV�@��@1�@�u���~�����v�Ɵq�a�@783
IV�@��@2�@�q�ƒʖ�@788
IV�@��@3�@�q�ƗV���@794
IV�@��@4�@�ʖ�ƒ����@798
IV�@��@5�@�����Ƃ��Ă̒ʖ�@802
IV�@��@6�@�ߖ�Ƒ��̑����@808
IV�@��@7�@�����ɂ����鑒�̑����@811
IV�@��@���r�@816
IV�@��@1�@���m�V��Ɠ�l�g���@816
IV�@��@2�@���g���Ɣ��ā@819
IV�@��@3�@���s���̕ĂƎ��҂̗�@824
IV�@��@4�@����ƍ����@829
IV�@��@5�@�u����݁v�Ɗ��@831
IV�@��@6�@�����ƍ���(��)�@835
IV�@��@7�@�������d�R�̃R�[�p�i�@839
IV�@��@8�@�������Ƌ����̑��@843
IV�@��@9�@�e�������ƕz�{�@846
IV�@��@10�@�����ƍ���@849
IV�@��@11�@�u���ւ��������v�Ɓu�O���v�@853
IV�@��@12�@���̖��Ց��@857
IV�@��@13�@�g�L�ƍւƐ��i�@859
IV�@��@14�@�������ƃc�i�M�����@865
IV�@��@15�@���̖ō߂ƍ����@869
IV�@��@16�@�����Ԃ��ƕz�{�@872
IV�@��@17�@�����Ԃ��̑V���ƍu�g�@876
IV�@�O�@�싟�@880
IV�O1�@�싟�Ƃ��Ă̖��тƌF�얭�@�R�@880
IV�@�O�@2�@���т̑P�����w��ٓ����@884
IV�@�O�@3�@���т̑h�����@887
IV�@�O�@4�@��Ƃ��蔻�Ƃ������@890
IV�@�O�@5�@���{�l�̗썰�ϔO�ƕ����@893
IV�@�O�@6�@������Ɩō߁@897
IV�@�O�@7�@�썰�̗V�����ƍr���̍r�\�@900
IV�@�O�@8�@�싟�Ƌ����@903
IV�@�O�@9�@�썰�̈ꌳ�_�Ɠ_�@906
IV�@�O�@10�@�R�[�����V�ƃ��W���`�@910
IV�@�O�@11�@���тƖ�с@914
IV�@�O�@12�@���c�q����̖��@918
IV�@�O�@13�@������݂Ƌ����@925
IV�@�O�@14�@�����Ղ̋S���Ǝ���@930
IV�@�O�@15�@����������q���h�����̌���@935
IV�@�O�@16�@���̔тƖ��с@938
IV�@�O�@17�@�q��Ɗ��@940
IV�@�O�@18�@���E�ւ��Ă�@944
IV�@�O�@19�@���̊��Ă�ƃV�A�Q�@���@948
IV�@�O�@20�@�������p�_�Ɛe�a�@951
IV�@�O�@21�@�썰�ے�_�ƕ����@954
IV�@�O�@22�@���ԕ����Ƒ��搧�@957
IV�@�O�@23�@�펀�҂̗썰�̒����@960
IV�@�O�@24�@�����̓�@963
IV�@�O�@25�@�����Ɛ��c�q�@967
IV�@�O�@26�@�����̋N���Ɣ��ف@970
IV�O27�@�ʕ�����َq�A�c�q�̐����ց@974
IV�O�@28�@��������ؑ��ց@978
IV�@�O�@29�@�o�_���ې_�Ђ̐_�a�Ɛ����@980
IV�O30�@�ߍ]���䔪���_�Ђ̐����Ɛ����@984
IV�@�l�@�����@988
IV�@�l�@1�@�����V��Ɠ���@988
IV�@�l�@2�@�����L�Ɍ����铒��@991
IV�@�l�@3�@����ւ̏@�h�I���߁@996
IV�@�l�@4�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@999
IV�@�l�@5�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@1002
IV�@�l�@6�@�����Ƃ��Ă̓���(�O)�@1005
IV�@�l�@7�@�����Ƃ��Ă̓���(�l)�@1009
IV�@�l�@8�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@1012
IV�@�l�@9�@�����Ƃ��Ă̓���(�Z)�@1016
IV�@�l�@10�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@1022
IV�@�l�@11�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@1026
IV�@�l�@12�@�����Ƃ��Ă̓���(��)�@1031
IV�l13�@�u���҂̓��v�Ɓu�����v���M�X�̖�v�@1032
IV�@�l�@14�@�u���b�P���̗d���@1038
IV�@�l�@15�@���狳��̕�n�Ɨ�q���@1040
IV�@�l�@16�@����Ǝ��q�ƃP�K���_�@1044
IV�@�l�@17�@�q��ƍ߂̊ϔO�@1048
IV�@�l�@18�@�����Ƃ��Ă̓���(�\)�@1052
IV�@�l�@19�@�����Ƃ��Ă̓���(�\��)�@1055
IV�@�l�@20�@�O���҂ƑP�������@1060
IV�@�l�@21�@�O���҂Ɣ鎖�@��@1065
IV�@�l�@22�@�鎖�@��Ɠ���@1069
IV�l23�@�w�킪���͂����ɗ��x�̓���`�ʁ@1073
IV�l24�@���Ղ̊�Ɖ��@1076
IV�l25�@�ċC�Ɣ鎖�@��@1079
IV�l26�@����ɐ��Ɠ�\�O���u�̑P�m���@1083
���Ƃ����@1089
���� |
�P�O���A���c���j ���E�ҏW�u���������问���̑��� : �ŗL�����ɂ݂鉫��̊��ςƋ�Ԍ`���Z�p
: �w�ۃV���|�W�E���v���u�x�R���ۑ�w����Љ�w���v���犧�s�����B
�@�@�@�@����E���: 2012�N10��6�� ���ꌧ�������فE���p�ف@��ÁF�L���H�ƍ������w�Z
�@�@�@77p�@�@�@�����F��㊌����}���فF 1007621111
|
�����̗��j�Ƒ��� / ���Ǒq�g �q
�����̑�����Ԃ̕����Ƌ�ԍ\�� / ���c���j �q
����̑����E�s�s�Ɏc��u����v�т̂���� / �R���M�p �q |
����Ƒ����q�ɂ݂鉫��̏W�������̕ω� / ��؈�] �q
����̎�e�����Ƃ��̐A���\���̓��� / ���ԗE�h �q
�؍��́u���v�Ɖ���́u����v / �F�J���� �q |
�P�P���A�{�����W�����{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (276) p.31-51���{�����w��v�Ɂu���������ɂ����铮���E�h���V��s�V�}�N�T���V�V��t�̖��̂Ɋւ��錤��
: ���F�����ɂ��V���ȓW�J�Ɩ��v�\����B
�P�P���A�v���Еҁu���㎍�蒟 56(11) ���W �R�V���� : ���a110�N�A�v��50�N�v���u�v���Ёv���犧�s�����B
|
���ܓǂށA�R�V�����@ �R�V����,��씎�N,���䖾�� p.10-21
�����ł͎������Ȃ��ł��낤 �@�����a p.28-31
����ᎂ�͂ގ� : ������̐V������ : ���m���[�O �@�g������ p.40-45
������ꖂ鎕����� : �R�V�����E�nj��� p.46-48
���܂悦��R�V�����@�쑺�� p.49-51
���A���Y������ : �R�V���� ��ˎ闝 p.52-55
���̊��e���Ɛh煂� �@�I���� p.56-58
������ꂽ���j�̂����� : ���A�R�V������ǂނ��� �����p�� p.62-66
�S�ƌ��t�̂��肩��: �R�V�����̎��Ɠ쓇�̗w ���_ ���䖾�� p.67-73
��l�̎��l�E�R�V�����ƍ����� �@�ɐ����� p.74-76 |
�w�V�� �R�V�����S�W�x����� :
�@�@�����̖��{�� ��������,�q�ɏC�� p.80-88
�w���Ɉ�x���� : �̑�Ȃ��E �^�ߔe���v p.92-94
���{�̖{���̎��́c: �R�V�������a���Z�N�L�O ���Ǖׁ@p.95-97
������E���ꂱ�� ���d�m��Y p.98-101
�w�V�� �R�V�����S�W ��ꊪ ���сx�ɐG��� �������� p.102-107
������Q�ƌ����Ă݂������� ������ p.108-111
���q�����E�R�V�����E�����i : �u�����Ƃ����v�u���̏�v
�@�@���u���܁A�ڂ��́v��ǂ� �������� 1 p.112-116
�R�V���� �N�� ��������1 p.120-125 |
�P�Q���P�P���i���j�`���N�P���P�Q�����A�{�Ó��s���������قɉ����āu���ʓW��
�����v�q�W : ���{�l�������̌����ȍ�ȉƁv���J�����B
�P�Q���A�{�Ó��s���������ٕҁu�{�Ó��s���������ف^���ʓW�� �����v�q�W
: ���{�l�������̌����ȍ�ȉƁv���u�{�Ó��s���������فv���犧�s�����B
�@��^�� ��ÁF�{�Ó��s����������/���́F����O�u���A�V��x�q���A�Ђ߂�蕽�a�F�O�����فA�{�Ó��s�����̃h�C�c�������A�{�Ó��s���}����
���A���̔N�A���ؗE�l �� ; �g�[���}�� �G�u�G�C�T�[���J�v���u����s�o�ϕ����������ό��ہv���犧�s�����B�@
�����F���ꌧ���}����
���A���̔N�A�������q�������Y�p�w��ҁu�����Y�p = Ethno-arts 29 p.140-147�v�Ɂu���K����_�̍ĉ��� : ���ꌧ�{�Ó��s���K�̉��ʍ��J�u�p�[���g�D�v������Ƃ��� (�����Y�p�w�̏���)�v�\����B�@
���A���̔N�A[Van der Vorst Gwendoline] �����m�_���u����̐��n�̌��� : �ʏ鏔�W���̌�ԂƂ��̍��J�������l�@�v�\����B |
| 2014 |
26 |
�E |
�P���A�O���킩�Ȃ��u�ߑ㉫��̗m�y��e : �`���E�n��E�A�C�f���e�B�e�B�v���u�X�b�Ёv���犧�s����B�@�@
�@�@�@���m�_���u�ߑ㉫��ɂ�����m�y��e�̗��j�I���� : �`���ւ̂܂Ȃ����v(2011�N,
���ꌧ���|�p��w) �����Ƃɑ啝�ɏ�������������
�Q���A���ь��],���эK�j�����s���q��w���B����w���I�v�ҏW�ψ���ҁu���s���q��w���B����w���I�v
= Bulletin of the Faculty of Human Development and Education �i10�j p.57-68�v�Ɂu���ꌧ����s����̎�x��G�C�T�[�v�\����B�@�iIRDB�j
�Q���A�g�Ɗԉi�g���w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 48(1) (�ʍ� 115) p.89-103�v�Ɂu�u���Ζ���v�l(��)�v�\����B
�Q���A�镔���u�����ٕ��w = �����ٕ��w 635�@ p.915-898 �����ّ�w�l���w��v�Ɂu�����v�Y�Ɓu�ԃu���b�N�v / ��㉫��ɂ݂錚�z�ƍH�|�v�\����B
�R���A���ь��],���эK�j�����s���q��w�@���E�����������ҁu�����I�v = Journal of the Institute of Religion and Culture (27) p.35-59�v�Ɂu����{���k���̉P���ہv�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�u���ꌤ���m�[�g( 23)�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B2014-03-2
|
�ČR���������ꂩ��t�B���s���ɓn������������ : ���̃t�B���s���蒅�ɂ��Ă̈�l�@
����M p.1-11 �iIRDB�j
�^�ߌ����w��ւ̍⓹ ���q�F���Y�Ƌߑ㉫��̌Q���x(�}�����[�A��Z��O�N)��ǂ�
���ђ��� p.12-17 IRDB�j
�֖����Ғ��w����n��Y�Ƃ̖����x(�V�]�_�A��Z���N�A�l��)��ǂ�� �y���� p.18-21 �iIRDB�j |
�R���A�u���j�� 22(10) (�ʍ� 1000) p.33�v�Ɂu�G�C�T�[���Ȃ����Ί��E����~���� �u�o����傤�����v�̐S�� : �G�C�T�[�Ί� (�����{��k�Ђ���3�N ���W ���k�V���b�N�h�N�g����)�v���f�ڂ����B
�R���A��؍��F�ҁu�V���}�j�Y���̕�����T��v���u�O�O�w�@��w�n�摍�������������v���犧�s�����B�@
|
��j�����ɃV���}�j�Y����T�� / ��؍��F ��
���ꕶ�����ɃV���}�j�Y����T�� / �������� ��
�l�Êw���݂��ږ�Ă̋S�� / ���c�N�Y ��
�I�z�[�c�N�����ɃV���}�j�Y����T�� / �E��[�� �� |
�C�������ɃV���}�j�Y����T�� / ��ؑ��� ��
����̃��^�ɂ݂�V���}�j�Y�� / �������q ��
�q����؎R���L�r�̐��� / ���R�� ��
�E |
�R���A�����ς��u�n���쓇 : �n�����Ɨ��j�I�W���i�ς̕ۑS�v���u�Í����@�v���犧�s����B�@�@
(�p���E�����m��)
�@�@�@3,164p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007168766
|
���悻30�N�Ԃɂ킽���ĉ���̗����A�n���쓇��K�ˑ��������҂��A���̒n�����x�ɂ��Ă킩��₷�������B�u�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��v�w��ւ̂���݂�A�W���i�ϕۑS�����̌���Ȃǂ��������B |
|
��1�� �n���쓇��
��2�� �n���쓇�̒n�����x |
��3�� ���v�`���I�������Q�ۑ��n��ւ̑I��
��4�� �ς��䂭�n���쓇 |
�T���A�n�Õ~���q�ďC�E�ҋȁE���u�����m���ĎO�����y������ �㊪�v���u�n�Õ~���q�v���犧�s�����B�@
|
�Ȗ��E���̑� ���w �ÓT �֘A�n�@��
����̓��X(�n�})
�͂��߂�
���E�̌��t�@�������w�`�������@�V�菼�G
�̎O���̊y��Ǝq���B
�O���̊e�����̖��́E�w�̈ʒu(��)�Ɖ���1
�O����e���O��(�����Ǝ�����)�@2
�O���̒e�����̊�{(�{���q)�E
�@�@���u�����ƎO�����v(�{���q)�@3
�O�����E�F�E�����̐���(�O�����u�H�H�l�v�̐����E
�@�@���F�̐����E�����ƐF�̐���)�@4
�`���_�~(����)�̎d���E(�`���_�~�\)
�@�@��(�`���[�i�[�̎��)�@5
�w(�����E��)�̈ʒu(���l�H����ܘV���Z�ڎ���)6
�u�����A�e���Ă݂悤!�v(�����ƍH�H�l�E
�@�@���L���L�����E�ނ���łЂ炢��)�@7
��������� (������) ���w �|�x���@8
|
�������� ��g�� ���w �|�x���@10
�̂��Ȃ��� ���w ����@12
����� ���w ����@14
�\��̏t ���w ����s�@18
���t���Q ���w �����s�@20
�ؖȉԐ� ���w �v�ē��@22
���l�� ���w �����s�@25
�ɍ��w�C���[ ���w �v�����@28
���_ (�V�̎q���) ���w �Î�[��31
����ǂ��̉� (��i��) ���w ���d�R35
������ ���w �L���鑺�@37
�䂤�Ȃ̉� ���w �ߔe�s�@40
�~�̍��� ���w ����@42
�h�ʒ��� ���w �^�ߍ����@45
���炿 ���w �����哇�@47
�Ȃ��܂��₮ (���P��) ���w �{�Ó�50
�Ă����ʉ� �{���q��E |
�@�@����g�� ���w ����@53
������ (�J����) ���w ��u�����@56
�����G�C�T�[ (�Ղ��) ���w �����s�@59
�v���}���W���[�� ���w ����@61
���Ð� (�푈��) ���w �������@63
���a�̑b ���w �����s�@69
���Ƃ����є� �|�b�v�X ����s�@72
��b (���R�^��) ���w �����s�@76
��m�l�璹 (���D��) ���w ��m���@79
�j�� (�j�V��) ���w ����@82
�Ԃʃg�[�J�` ���w ����@86
����̉̎O���ɂ��ā@89
����(����)�̗��j�@91
�Q�l�����@92
���҂̃v���t�B�[���@93
�E
�E |
�T���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 48(2) (�ʍ� 116) (�O�Ԏ�P�搶�Ǔ����W�� ; �Ǔ��_��)�v���u���ꕶ������v���犧�s�����B
|
�����w �܌��M�v�搶 ��ځu�����̔N���s����
�@�@������ɔ��әB���y�����v �O�Ԏ�P�搶��e)�@�O�� ��P p.3-16
�Ǔ��̎� �u�O�Ԏ�P�搶���Âԉ�v����)�@�@��c ���G p.20-22
�Ǔ��̎� : �O�Ԏ�P�搶�̐����𓉂�
�@�@�� ( �u�O�Ԏ�P�搶���Âԉ�v����)�@���c�P�� p.23-26
�P�ӂł����� ( �u�O�Ԏ�P�搶���Âԉ�v����)�@�@��� ���T p.26-28
�Ǔ��̎� �u�O�Ԏ�P�搶���Âԉ�v����)�@�@��쉮 �q�q p.28-30
�O�Ԏ�P�搶�𓉂�
�@�@�� ( �u�O�Ԏ�P�搶���Âԉ�v����)�@�V�� �K�� p.30-32
�O�Ԏ�P�搶���Â� �@���� ���C p.38-40
�O�Ԏ�P�搶���Â� : ������w�̐ݒu�ɍv���@�����g �Ċ� p.41-43
���@�����P�ƊO�Ԏ�P�@�@�㑺 �K�Y p.43-45
�O�Ԏ�P�搶�̎v���o �@�N���C�i�[ ���[�[�t p.45-47
�O�Ԏ�P�����𓉂� : �w���ɗ�܂������X �@���@�� ���� p.53-55
�Ⴋ���̊O�Ԑ搶�𒆐S�� �@�@�R�� ���q p.55-57
������w�ݐE�����̊O�Ԏ�P�搶�@�Ôg�� �q�q p.60-62
���t�O�Ԏ�P�搶�̂��� �@�@�����H �^�s p.64-67
�O�Ԏ�P�搶�𓉂ށ@�@���� ���m 5 p.68-70
�O�Ԏ�P�搶���Âԁ@��]�F �� p.70-72
�O�Ԏ�P�搶�̗D�����Ɏx�����ā@�@�䕔 ���j 5 p.73-75
�O�Ԏ�P�搶�Ɨ���u�f�B�A�X�|���v�@�@�䉮�� �ƕv 5 p.76-78
�O�Ԏ�P�搶�̎v���o �@�@�쌴 ���q 5 p.78-80
�u����w�v�v���f���[�T�[ �@�@���� �q�g p.85-87
�O�Ԏ�P�搶�@�㐨�� ���q,�㐨�� �F�� p.88-90
�O�Ԏ�P�搶�𓉂� �@�@�O�� ���q 5 p.90-92
�O�Ԑ搶�̂������ɐڂ��ā@�|�� �d�Y p.96-98
�O�Ԏ�P�搶��Ǔ����� �@�@���\ �G 5 p.98-100 |
�O�Ԑ搶�Ɖ���w�@���R �a�s p.100-102
�O�Ԑ搶�ւ̊��ӂƂ��� �@�@�ԋ{ ���i 5 p.102-104
�O�Ԑ搶�Ɠ�Ă����ǂ� �@�@�l�c �q p.104-106
�O�Ԏ�P�搶�ƚ��{�@��{�ƒ|�x�� �@�@�떓 �b�� p.109-111
�O�Ԑ搶�̎v���o �@�@�c�� �^�V p.111-113
�O�Ԏ�P�搶�ƍ��A�m�@���� �O�N 5 p.113-116
�u����v�u�悫�v�u���݁v���g���錻�ꂩ�� :
�@�@���O�Ԏ�P�搶�����̂ԁ@���k �V�n p.116-118
�T���_�̎v���o�@�@�䕔 ���� p.119-121
���̊O�Ԑ搶�@���c�R �a�q p.121-123
�O�Ԏ�P�搶�̏Ί�@�@�㓡 ��d p.123-125
�O�Ԏ�P�搶�̃e���r�ԑg �@�ʏ� ���F p.125-127
����̋L�� : �O�Ԑ搶�̏��N���� �@�^�h�� �[�� p.128-130
�O�Ԏ�P�Ƃ������@�@�O�� �N��Y 5 p.134-136
�L���b�`�{�[���@�O�� ���j p.136-138
���W : �w�������R���L�x��
�@�@���w���������L�x�̊Ԃɂ������ �@�g�Ɗ� �i�g p.141-168
�~�A���K�}���ʂƓy��_���ʂ̔�r�l�@�@��� �{ p.169-186
�A�̌`�������݂��w�����낳�����x�̃I�i��
�@�@���E�i�̉����̎g������ �@����܂� �����Ђ� p.187-198
�w�{�Ó��̉́x�̐������߂����ā@�㌴ �F�O p.199-222
�u���ӂ�E������D�E�E�́E�݂����v�l :
�@�@�����t����݂������j�@�L���R �a�s 5 p.223-232
���̂̋喖�ɂ��郉�ϓ����Z����
�@�@��i����ɂ��� : ui����𒆐S�� �@���� �q p.233-248
������ �V���f�ڋL������ђǓ������@�@��㊕�������@ p.249-273
�E |
�U���A�����_, �r�c�Ďj���u�Ԃ�肠�邫����E�����̔����فv���u���u���[�o�Łv���犧�s����B
|
�܂������@1
�n�}
�ߔe�s�̔����ف@9
���ꌧ�������ف@11
���ꌧ�����p�ف@11
�ߔe�s���j�����ف@17
�ߔe�s���≮�ĕ������ف@19
�Δn�ۋL�O�ف@20
�䂢���[���W���ف@21
������@24
�ʗˁ@33
�������@33
�s���ف@34
����Z�����[�E�X�^�W�A���ߔe
�@�@���싅������37
���B���@38
������w������(������)�@39
���ꌧ�������������Z���^�[�@41
����{���암�̔����ف@43
�L����s���j���������W�����@45
���C�R�i�ߕ����@45
�앗�������Z���^�[�@48
���ꗤ�R�a�@�앗�����Q��Z�����@50
�����Ȃ탏�[���h�E���������鉺���@52
�����Ȃ탏�[���h�E�����������j������53
�����Ȃ탏�[���h���������E�ʐ@54
�����Ȃ탏�[���h�E�M�уt���[�c���@55
�����Ȃ탏�[���h�E�n�u���������@56
�֏��ԁ@57
���d��������u�����j���������ف@58
���ꌧ���a�F�O�����ف@59
���ꕽ�a�F�O���E���p�ف@61
���璱���@62
�Ђ߂�蕽�a�F�O�����ف@63
����{�������̔����ف@65
�Y�Y�O�X�N�@67
�Y�Y�O�X�N�悤�ǂ�ف@68
�Y�Y�s���p�ف@69
�X��p�s�������ف@70
����^���p�ف@72
����O�X�N�@74
�����ƏZ��@74
����s���y�����ف@75
���ꂱ�ǂ������]�[���E���ꂱ�ǂ��̍�76
�ǒJ�������j���������ف@77
�ǒJ�������p�ف@80
���얡�O�X�N�@81
����s���ΐ���j���������ف@82
���A�O�X�N�@84
����{���k���̔����ف@85
���[�������ف@87
�������@88 |
�X������������ف@89
���씎���ف@90
�����Ȃ�t���[�c�����h�@92
�I���I���r�[���H��@93
����C�����ف@96
�C�m�����ف@99
�C�m���L�O�����M�уh���[���Z���^�[101
�{�����������ف@103
���A�m�����j�����Z���^�[�@104
���A�m�O�X�N�@106
�v�ē��̔����ف@109
�v�ē�������
�@�@��(���v�ē����R�����Z���^�[)111
�v�ē��z�^���̗��E�z�^���ف@113
�}�̏��@117
�M�ы��̉Ɓ@117
�v�ē��ۂ̗����C�}�[���ف@118
�v��H��@120
��]�B�ƏZ��@121
�������Ԑؑ����Ձ@122
��u���Ձ@123
�F�]��Ձ@124
�N�앗�a���@124
�V�@�{�@125
�v�ē��E�~�K����(�E�~�K����)�@126
�{�Ó��̔����ف@129
�{�Ó��s���������ف@131
�h�C�c�c�锎���L�O��@132
�����̃h�C�c�������@133
�����L�O�ف@133
�L���_�[�n�E�X�E�q�ǂ������ف@134
�b�q���p�ف@135
�{�Ó��C��ف@137
�{�Ó��s�M�ѐA�����@138
�{���C�������@139
�{�Ó��s�n���_�������ف@140
�{�Ó����K�\�[���[���،����ݔ��@142
�ቖ�~���[�W�A���@142
�C�R���U���i�[�铽���@143
�v���ܗE�m�̔�@144
���@���L���e�̕�@145
�A�g���}��@145
�m���^�ǖL���e�̕�@146
������ԂƐΊ_�@147
�l���Ő@147
��a��@148
�Ί_���̔����ف@149
�Ί_�s�����d�R�����ف@151
�Ί_�₢�ܑ�(�����d�R������)�@153
�쓈���������ف@154
���ۃT���S�ʌ����E���j�^�����O�Z���^�[155
�Ί_���ߓ����@155 |
�����A���p���@156
�Ί_�s�`���H�|�ف@157
�݂[�H�|�ف@158
�A�������ف@159
���d��H��@160
���d�R���a�F�O�ف@162
���_�M��L�O�ف@162
��u���p���L�O�ف@163
�{�Ǔa���@164
�Ί_���뉀�@165
���ю��@166
�������@166
���l��@167
�t���X�g����Ձ@169
�Ôg���@169
�|�x���E���\���̔����ف@171
�M��@�N�W�ف@173
�앗�����ف@174
�|�x�������ف@175
�|�x���|�ف@176
������ԁ@177
������ԁ@177
�|�x���䂪�ӊف@178
���\�쐶�����ی�Z���^�[�@178
���\�M�їш��Z�p���@180
���ԑ��L�ˁ@181
�^�ߍ����̔����ف@183
�^�ߍ����������ف@184
�^�ߍ����`���H�|�ف@185
�A���~�n�r���ف@186
�����Q���̔����ف@187
�y�����哇�z
�����s�����������ف@189
�����p�[�N�@192
�c���ꑺ�L�O���p�ف@193
�����C�m�W���ف@195
(��)�����������c ����_�|������196
���˓��������y�ف@198
�F�������U�w�K�Z���^�[
�@�@���u���C�̏o��فv198
�y���V���z
�V�钬���C�̊ف@200
���V�������y�����ف@201
�ɐ咬���j���������ف@202
�y���i�Ǖ����z
�a�������j���������ف@204
�y��E���z
��E�����j�����������@205
��E�������������Z���^�[�@206
���Ƃ����@207
�Q�l�����@208
�����ُ��ݒn�@210 |
�U���A����q�����u����{�̖��������� 7 (����{�̖����|�\�� �k�F������) �v���u����V�Ёv���犧�s����B�@
|
�����㗬��̖����|�\ �k�F�����̌|�\����
�N�����I��̖����|�\
�N�����g���̑��ۗx��q�l�P�������ۗx��r |
�ɍ��s�̖����|�\
�o���s�q���o���s�r�̖����|�\
�l�g�s����ё��Ǒ��̖����|�\ |
�����s�̖����|�\
�E
�E |
�X���A���ݘa�����t�u�m�q�}�}���I�q�ǂ��ƈꏏ�ɒ��������e�������O���\���Obest26
�e�q�Ŋy���݂܂��傤!�@�v���u ���X�y�N�g���R�[�h�v���犧�s�����B�@�@�@�^���f�B�X�N 1�� (72��) : CD + 1���@�@���t:���ݘa��(�O��)
|
(1)IT�fS A SMALL WORLD(�����Ȑ��E)(�f�B�Y�j�[�����h�̃A�g���N�V�����u�C�b�c�E�A�E�X���[���E���[���h�v�̃e�[�}�E�\���O)(2)�܂�������(�Đ��݂̑�q�b�g��)(3)���C���C(�Ђ炯!�|���L�b�L���)(4)�Ă����ʉ�(����̂��S�̖���)(5)�����������^(�����ǂ���^)(���ꖯ�w�͂܂����̋Ȃ���)(6)������L�W���i�[(����̂��S)(7)�E�C100%(�A�j���u�E���ܗ����Y�v�̃I�[�v�j���O��)(8)�p����������(�A�j���u�͂Ȃ����ρv�̃G���f�B���O��)(9)BEST
FRIEND(Kiroro�̖��ȁu����炳��v�̎���)(10)���Ȃ���(�����S��800�̖���)(11)�Ί�̂܂��(BEGIN
with�A�z�i�X�^�[�Y�̋ȁACX�uFNS27���ԃe���r!!�݂�ȏΊ�̂Ђ傤���v�̃R�[�i�[�u����܁E�����̍��������Ȃ��v�G���f�B���O�E�e�[�})(12)�m�ԕz(���v���P�E��Ȃ̖���)(13)��-���ׂĂ̐l�̐S�ɉԂ�-(��[���g�̑�q�b�g��)
(14)����ǂ��̉�(�{�ǒ����Ȃ̖���)(15)�J���J���O�����ނ���ނ�(BEGIN�̖���)(16)����̉�(��Ȃ��[�̏��ɂ��u�N�����������v�̃G���f�B���O��)(17)�ԓc�a��(����������ǂ���)(����̂��S)(18)���ؖV��(�݂݂���ڂ���)(����̂��S)(19)�Ԃʕ���(�����܂�[)(����̂��S)(20)���������ʓ�(��������ς��ʂ���)(�V�Ί_��`PR�\���O/�r�M����X(��������X��BEGIN)�̋�)(21)�������[����܁[�܁[�������[(���d�R�̂��S)(22)���ʔ�����(���ʂ�������)(���d�R�n���̖��w)(23)����(����̂��S)(24)������(kiroro�̖���)(25)�����ȗ��̂���(�����S��800�̃q�b�g��)(26)�A��ꏊ(HY�̖���) |
�P�O���A�ԗ�䂩�肪�u���� (577) p.30-33�@�����Ёv�� �u���ꂩ��̕�(56)���b�^�[������ˁ[ ���[����Ȃ����v�\����B
|
�m�O�E�V�A�o�V�G���A��c�� �ցA������F�A�ԗ�䂩��炪�u���� (522�`577)
�v�ɔ��\�����u���ꂩ��̕`56�v���̌��o�����e�̈ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N |
�_���� |
| 1 |
(522) p.30�`33 |
2010-03 |
���ꂩ��̕� �u��n�͖{�y�֕Ԃ����v�@�@�m�O �E�V |
| 2 |
(523) p.30�`33 |
2010-04 |
���ꂩ��̕�(2)�u�t�i���_�v���l����@�@�o�V �G�� |
| 3 |
(524) p.26�`29 |
2010-05 |
���ꂩ��̕�(3)���܂������u�V���K�[���[�t�̓����v�@�@��c�� �� |
| 4 |
(525) p.32�`35 |
2010-06 |
���ꂩ��̕�(4)�{�y�ֈڂ��Ă��������@�@�m�O �E�V |
| 5 |
(526) p.22�`25 |
2010-07 |
���ꂩ��̕�(5)���{�Ɖ���Ƃ��ꗁ@�@�o�V �G�� |
| 6 |
(527) p.12�`15 |
2010-08 |
���ꂩ��̕�(6)�����`����Z�\�ܔN�ڂ̉����@�@��c�� �� |
| 7 |
(528) p.24�`27 |
2010-09 |
���ꂩ��̕�(7)���V�Ԋ�n�̌R�J���@�@�m�O �E�V |
| 8 |
(529) p.20�`23 |
2010-10 |
���ꂩ��̕�(8)����Ɠ��A�W�A�@�@�o�V �G�� |
| 9 |
(530) p.14�`17 |
2010-11 |
���ꂩ��̕�(9)���������Ɠ��{�����̊���--�{�����������Z�Z�N�@��c��
�� |
| 10 |
(531) p.14�`17 |
2010-12 |
���ꂩ��̕�(10)�L�Ɩ{�ƐA���n��`�@�@�m�O �E�V |
| 11 |
(532) p.20�`23 |
2011-01 |
���ꂩ��̕�(11)���ꌧ�m���I�̈Ӗ��@�@�o�V �G�� |
| 12 |
(533) p.14�`17 |
2011-02 |
���ꂩ��̕�(12)�R�V�������ɂƉ��ꌧ���}�����@�@��c�� �� |
| 13 |
(534) p.10�`13 |
2011-03 |
���ꂩ��̕�(13)�������ɉƏo�����@�@�m�O �E�V |
| 14 |
(535) p.10�`13 |
2011-04 |
���ꂩ��̕�(14)���ʂ��Ȃ������@�@�o�V �G�� |
| 15 |
(536) p.10�`13 |
2011-05 |
���ꂩ��̕�(15)�k�Ќ�̌R���ƃ��A�̐����@�@���� ��F |
| 16 |
(537) p.16�`19 |
2011-06 |
���ꂩ��̕�(16)�Ɏ��I����A�x�̉߂������@�@�m�O �E�V |
| 17 |
(538) p.14�`17 |
2011-07 |
���ꂩ��̕�(17)�����̂̉\���@�@�o�V �G�� |
| 18 |
(539) p.20�`23 |
2011-08 |
���ꂩ��̕�(18)�����������ꂽ�e�ƃe�N�X�g�̗U�f�@�@���� ��F |
| 19 |
(540) p.30�`33 |
2011-09 |
���ꂩ��̕�(19)�����̃��[�g�s�A�@�@�o�V �G�� |
| 20 |
(541) p.26�`29 |
2011-10 |
���ꂩ��̕�(20)���V�Ԃ̋�E���V�Ԃ̑�n�͂킽�������̂��@�m�O �E�V |
| 21 |
(542) p.30�`33 |
2011-11 |
���ꂩ��̕�(21)�u�����`�v�Ɓu������v�̃t�H�[�}�b�g�@�@���� ��F |
| 22 |
(543) p.26-29 |
2011-12 |
���ꂩ��̕�(22)���E�̃E�`�i�[���`�����@�@�m�O �E�V |
| 23 |
(544) p.26-29 |
2012-01 |
���ꂩ��̕�(23)�u���A�v�Ƃ��������@�@�o�V �G�� |
| 24 |
(545) p.32-35 |
2012-02 |
���ꂩ��̕�(24)�R�U�\���Ƃ����s����Ȍo�H�̉\���@�@���� ��F |
| 25 |
(546) p.18-21 |
2012-03 |
���ꂩ��̕�(25)�ǂ����ĉ���̐����͊w�Z���x�݂ɂȂ�Ȃ��́@�@�m�O �E�V |
| 26 |
(547) p.18-21 |
2012-04 |
���ꂩ��̕�(26)�C�ݐ��̎v�l�@�@�o�V �G�� |
| 27 |
(548) p.18-21 |
2012-05 |
���ꂩ��̕�(27)�u��ˁv�̒�łȂ���X�^���f�B���O�E�A�[�~�[�@�@����
��F |
| 28 |
(549) p.18-21 |
2012-06 |
���ꂩ��̕�(28)�Ȃ��⍑�~�ʼn���́��Ȃ̂��@�@�m�O �E�V |
| 29 |
(550) p.18-21 |
2012-06 |
���ꂩ��̕�(29)�G���A�̍\�z�́@�@�o�V �G�� |
| 30 |
(551) p.18-21 |
2012-08 |
���ꂩ��̕�(30)�g�̂����ɂ��������[�g�s�A�����ā@�@���� ��F |
| 31 |
(552) p.18-21 |
2012-09 |
���ꂩ��̕�(31)���V�Ԋ�n�̒��ɓ����Ă݂��@�@�m�O �E�V |
| 32 |
(553) p.18-21 |
2012-10 |
���ꂩ��̕�(32)���ꕶ���̐����́@�@�o�V �G�� |
| 33 |
(554) p.18-21 |
2012-11 |
���ꂩ��̕�(33)�E�A���n���Ɓu�Ό����v�@�@���� ��F |
| 34 |
(555) p.12-15 |
2012-12 |
���ꂩ��̕�(34)�I�X�v���C���@�@�m�O �E�V |
| 35 |
(556) p.12-15 |
2013-01 |
���ꂩ��̕�(35)�Ɨ��_�̍s���@�@�o�V �G�� |
| 36 |
(557) p.12-15 |
2013-02 |
���ꂩ��̕�(36)��P�ӣ�ŕܑ����ꂽ���͂ǂ�������?�@�@���� ��F |
| 37 |
(558) p.14-17 |
2013-03 |
���ꂩ��̕�(37)����l�̖��̂��߂̃t�F���X�s���@�@�m�O �E�V |
| 38 |
(559) p.12-15 |
2013-04 |
���ꂩ��̕�(38)�����ʒu�ƃW�j�I���W�[�@�@�ԗ� �䂩�� |
| 39 |
(560) p.12-15 |
2013-05 |
���ꂩ��̕�(39)����Ԃ̒f�w�ƍĐ������@�@���� ��F |
| 40 |
(561) p.12-15 |
2013-06 |
���ꂩ��̕�(40)�M�u�A�b�v �t�e���}!�@�@�m�O �E�V |
| 41 |
(562) p.20-23 |
2013-07 |
���ꂩ��̕�(41)Yuree ���b�^�[����̉������ԁ@�@�ԗ� �䂩�� |
| 42 |
(563�j p.12-15 |
2013-08 |
���ꂩ��̕�(42)���ꂼ��́u�\�z�����M�O�v�@�@���� ��F
|
| 43 |
(564) p.20-23 |
2013-09 |
���ꂩ��̕�(43)�t�F���X�ʓ���(���܁[����[)�₳�₳�₳�₳�@�m�O �E�V |
| 44 |
(565) p.12-15 |
2013-10 |
���ꂩ��̕�(44)�e�[�~�k���[��ڎw���ā@�@�@�ԗ� �䂩�� |
| 45 |
(566) p.16-19 |
2013-11 |
���ꂩ��̕�(45)��Z��Z�N�́q�r�r�ƃ|���J�b�c�B�̂䂭���@�@���� ��F |
| 46 |
(567) p.20-23 |
2013-12 |
���ꂩ��̕�(46)�Γc�Y����ւ̎莆 : �w�V�����t�[�i�[(�m���ӂ�)�̖\�́x���߂����ā@�m�O
�E�V |
| 47 |
(568) p.24-27 |
2014-01 |
���ꂩ��̕�(47)���b�^�[ELT : ����p�ꋳ��čl�@�@�ԗ� �䂩�� |
| 48 |
(569) p.24-27 |
2014-02 |
���ꂩ��̕�(48)�u�o�i�i�E�{�[�g�v���z�ȁ@�@���� ��F |
| 49 |
(570) p.30-33 |
2014-03 |
���ꂩ��̕�(49)�Γc�Y����ւ̂��Ԏ��@�@�m�O �E�V |
| 50 |
(571) p.28-31 |
2014-04 |
���ꂩ��̕�(50)�����Ȑ��ƃA�N�V������ςݏd�˂邱�Ɓ@�@�ԗ� �䂩�� |
| 51 |
(572) p.30-33 |
2014-05 |
���ꂩ��̕�(51)����E�{�ÁE��� : �u�s�a�v�Ƃ��̉\���@�@���� ��F |
| 52 |
(573) p.30-33 |
2014-06 |
���ꂩ��̕�(52)��������̑�s������\�Z�N��ɍl����@�@�m�O �E�V |
| 53 |
(574) p.30-33 |
2014-07 |
���ꂩ��̕�(53)���b�^�[����w�̈Ӌ`�@�@�ԗ� �䂩�� |
| 54 |
(575) p.22-25 |
2014-08 |
���ꂩ��̕�(54)���́q���r�Ɠ�������Ȃ��Z�p�@�@���� ��F |
| 55 |
(576) p.30-33 |
2014-09 |
���ꂩ��̕�(55)�u��n�̑������v�̔��� : ���O�ڐݔ��Θ_���l����@�m�O
�E�V |
| 56 |
(577) p.30-33 |
2014-10 |
���ꂩ��̕�(56)���b�^�[������ˁ[ ���[����Ȃ����@�@�ԗ� �䂩�� |
|
�P�Q���A���؍_�ꂪ�u�ˈ��_�p = Research bulletin, Toin University of Yokohama 31 p.21-27�@�ˈ����l��w�v�Ɂu���ꖯ�w�̐g�̐� : �G�C�T�[�ƃJ�`���[�V�[���ꂼ��́w���D�ǁ[���x
(���W �g�́E�X�|�[�c�̐V���Ȓn��)�v�\����B�@�@�iIRDB�j
�P�Q���A�V���F�a,�Ő��Ȃ�������w�_�w���ҁu������w�_�w���w�p�� (61) p.55-66 �v�Ɂu����E���������c�V�k�O�̍��J�A���S���Y�C(1)�v�\����B�@ �iIRDB�j
���A���̔N�A���J�����S�����Z�����w���������c��ҁu���Z�����w�� (197)
p.55-5�v�Ɂu���Z���Ɗy���ލs���̃A�C�f�A ����!!180���̃G�C�T�[ : �����ՂƏC�w���s���Ȃ��Łv�\����B
���A���̔N�A����u�����[�� ; �g�[���}���G�u�G�C�T�[�̗ցv���u����s�o�ϕ����������ό��ہv���犧�s�����B
���A���̔N�A�u���A�W�A�Љ�猤���v�ҏW�ψ���ҁu���A�W�A�Љ�猤���@(19) ���W�F����̒n��Â���v���u�����E����E���A�W�A�Љ�猤����v���犧�s�����B
|
����Βk(6)����̎Љ���S���Ⴋ�Q�� :
�@�@���Љ��厖�W�c�̍����t�́u�n������C��!�v ���ܐ��q,���ѕ��l ���Ɛi�s,���Ԗ��@�q
�Q���� p.174-196
�N�c�^���Ɗw�Z���� : ��㉫��N�^���j�̏،�(����11) �@���ǐe�� �،�,���ѕ��l
������,�R���H ������ �@p.197-208
�s�s���ɂ�������������ق̖��� : �ߔe�s�ዷ�����ق̎��H�@�{�鏁 p.209-222
��㉫��ɂ�����G�C�T�[�̕ϗe�ƐN��@��J�וF p.223-232 |
���A���̔N�A��J�וF���u�Љ��w���� = Japanese journal of adult and community education 50(1) 2014 p.1-10�@���{�Љ��w��v�Ɂu����̃��[�A�V�r(�їV��)�Ɍ���u�K���Ƃ��Ă̋���v
: ���̋���I�����Ƌ@�\�v�\����B |
| 2015 |
27 |
�E |
�R���A�u�������� (42)�@�Ǔ����W�F�O�Ԏ�P�搶 �R�{�O���搶 ���҉p��搶
��Î��搶�v���u�@����w���ꕶ���������v����҂܂��B
|
(�O�Ԏ�P�搶 �R�{�O���搶 ���҉p��搶 ��Î��搶 �Ǔ��L�O���W�� ; �N���E��v����)�@
�O�Ԏ�P�搶�@ p.1-4
(�O�Ԏ�P�搶 �R�{�O���搶 ���҉p��搶 ��Î��搶 �Ǔ��L�O���W�� ; �Ǔ���)�@
�O�Ԏ�P�搶�Ɖ������Ǝ��@�@�ԋ{���i�@p.13-17
�R�{�O���搶�̂������𓉂ށ@���] �F�i�@p.18-22
���҉p��搶���Â� : ���z�����ĉ���̖��ƂƏW����Ԃ����߂� �i�����ȁ@p.23-32
��Î��搶���Â� �@���� �K��@p.33-36
��Î��搶���Âԁ@�@�����K�� p.33-36�@
(�O�Ԏ�P�搶 �R�{�O���搶 ���҉p��搶 ��Î��搶 �Ǔ��L�O���W��)�@
���̔����I�̗������w�����A�����Ă��ꂩ��̌����@�g�Ɗԉi�g�@ p.39-62
�����낳�����̏����� �@�@�|���d�Y�@ p.63-83
�I�����̚��q�� �@���i���@p.85-122
�w�����낳�����x�ɂ݂�_�b�A�`���A���E�� : �����̍s�K�Ɓu�n���I�����v���߂�����
�@���R�a�s�@ p.123-148
�w�����낳�����x�̏����K�̕\�L�čl �@�ԋ{���i�@ p.149-166
�O�Ԏ�P�A�{�É̗w�̌n���̋O�Ձ@�V���K���@ p.167-185
�{�Ó��떓�́u�j�[���A�[�O�v���߂����ā@���F�O�@ p.187-208
�z�B�q�� : �L�J�C�K�V�}�E�w��������x�E�����@�������@ p.209-231
�������猩���w���|�����x�@���� �K��@�@ p.233-253
�V�������ӎ��̓o�� : �������̂̌��o�������́@�@���� �����@ p.255-274
���J���̏x�{�E�]�ˉ��҂ɂ��� : �w������L�x�̌���(1)�@�~�ؓN�l�@ p.275-313
�t�N�M�ɂ���(�o��) �@�c�� �^�V p.315-325
�����ߐ��̌o�ύ\�� : �R�{�O���搶�̌����ɐG��� �@���ԑגj�@p.327-352
�ݕĎ���̋{���o���Ƃ��̎��ӌQ�� : �Ǎ��̈ږ���Ƃ̏ё��@�@�䉮���ƕv�@
p.353-365
����푈�����̃X�p�C(�h���E�Ԓ�)�_�c�ƌR�@�ی�@�@�@�䕔���j�@ p.367-403
�����Ŏ���ꂽ�W���̍Č��ƕč��̓����@�K�ɂ���̐��� �@�����v�q�@ p.405-433
����ɂ�����L�^���p�̉\���@ꎓ� ��q�@p.435-453
����̔��W�ƓW�] : ����̓`���I�Z�܂����p������G�R�n�E�X��ڎw���ā@�p
�^�J p.455-488
�E�`�i�[�E�C�[�`���[�E�C�J�b�g���[�h : ��ڒf�z �@���]�F�i�@p.489-514
�R�{�O���搶�̉��ꌤ���������˂� �@����]�@ p.515-523 |
�R���A�{�����W���u���ꍑ�ۑ�w�����w�p�����I�v 18(1) p.41-54�v�Ɂu���������ɂ�����u�V�}�N�T���V�V��v�̊����Ɋւ��錤��:����Q�̕��͂Ɛ�s�����Ƃ̔�r���𒆐S�Ɂv�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�{�����W��������w���ۉ��ꌤ�����ҁu���ۗ�������_�W = International review of Ryukyuan and Okinawan studies (4) p.79-91�@������w���ۉ��ꌤ�����v�Ɂu���������ɂ�����s�V�}�N�T���V�V��t�̒�������̌��v�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A���ꌧ���|�p��w�����������ҁu����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
(27)�v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B�@�@�@167p�@�@�����F��㊌����}���فF1007657297
|
�\�����I�����ɂ����问���̊����E��������я��D��̊w�K�ɂ��� �����L��
�����|�p ���� ��
�ؖȖa�ю��Ǝ�a���̔��ʕ��@�ɂ��� �V�c�ێq
���q�m�[�g����݂��u�����|�p�����v �v�L�T�q p.63-95 |
���q�F���Y�Ǝʐ^ �������q
���������w����Θb�x(4) ������ �������q �V�_�P��
�@�@�����g���� �n���쏟�� �R�c���}�q �哹�D�q
���ꌧ���|�p��w�����������b�� |
�R���A���ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (23)�v���u���ꌧ���|�p��w�v���犧�s�����B
|
���m�����ɂ�����ۂ̋��ӂƏے� ���` ��a�q p.1-20
�u��F�����ɉ����閯�ԐM�̕��K�Ə@���v�ɂ����镧���I�E�C�����I�v�f�ɂ���
������ �M p.21-35
���q�F���Y�̗����|�p�����ʐ^�ɂ�����|�p�� ���� �G���� p.37-49
�n����������ޕ������� : ��k�����ǁu�q���̎��ԁv�̕������b�𒆐S�� �O��
�킩�� p.51-67
��w�̏��N�x�p����Ƃɂ����鑽�ǂ̎��� : ���ʂƉۑ� ���� ���q p.69-81
�o���̐����S���O�ɂ݂镨���I���ʂƐ_�����̕ω� : 20���I�������猻�݂܂� ���R ���q p.83-96
����G���U�x�X���s���[���^���_�w�̗����I���q : �E�B���A���E�p�[�L���Y�w�L���X�g�ҏ@���̓y��x�ɂ���
��� �M�� p.97-112
�g�Õ~�� �u���� ���x�� �㊪ ��{���x ������ŕ��v �ԏ� �m�q,���� ���q
p.113-129
���l(���т�) : �n�앑�x�̂��߂� : �w�h�b�R�C�߁x�w�V�H���߁x�w����߁x �R�� ���� p.131-138
�n�앑�x�m�[�g ���� �N�q p.139-152 |
�R���A�u�����[ �� ; �q���l�R�E�W�� �G �u�G�C�T�[�̐S�v���u����s�o�ϕ����������ό��ہv���犧�s�����B�@
�����F���ꌧ���}����
�R���A�����M�v���u���s�Y�Ƒ�w�_�W. �l���Ȋw�n�� 48 p.255-280�v�� �u���钩�i�Ɨ����w�̍\�z�v�\����B �iIRDB�j
�R���A�u���ꌤ���m�[�g24�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B
|
���d�R�����̗��j�ƕ��� : �Ί_���ƒ|�x���𒆐S�� ���ђ���, p.1-16 �iIRDB�j
�ѐ^�i���w�u����V�}�����v����x(���o�ŎЁA��Z��l�N�A�����)��ǂ��
�y���� p.17-20 |
�R���A���������w�����َB�e�E����^���c�g�F�ďC�u����̃G�C�T�[�A���̃G�C�T�[�v���u���������w�����فv���犧�s�����B�@ 2015 (�݂�ς��f��������, ��17�W)�@�@ �r�f�I�f�B�X�N1 �� (161��)
|
�B�e: �l��Ó��̃G�C�T�[: 2001�N8��28��-9��4�� ���ꌧ�Г��S���A���l��Ó�
�B�e: ���̃G�C�T�[: 2000-2002�N ���s�吳��
�����^�C�g�� �l��Ó��̃G�C�T�[ : ����̋��~�@�@�@�@�@�@�@�����^�C�g��
���̃G�C�T�[ : �v (����) ���̌����� |
�R���A���ꌧ�������������Z���^�[ �ҁu���ꌧ�̐푈��� : ����22-26�N�x�푈��Տڍm�F�������v���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s�����B�@�@ (���ꌧ�������������Z���^�[������ ; ��75�W)
�R���A������,�茴���q���u���ꌧ�������فE���p�ٔ����ًI�v 8 p.33-61�@���ꌧ�������فE���p�فv�Ɂu�d�v�������u�����i���鐳�a���j�v��X���B�e�ɂ���Ԓ����ɂ��āv�\����B
�R���A�Y�\�w��ҏW�ψ���ҁu�Y�\ (21)�v���u�Y�\�w��v���犧�s�����B
|
�܌��M�v�̋Y�ȁu���S�������N�v�l (�����|�\���W)�@�@�O�����Y p.5-14
�ʏ钩�O�Ɨ����|�\ (�����|�\���W)�@�@��� �{ p.15-26
�܌��M�v�u���S�������N�v���� (�����|�\���W)�@�@�c���p�@ p.27-32 |
��Ƌ����̕����̃g�|�X : ����ߔe�Ғn��̐��̂���݂�
�@�@�����S��(����1) (�����|�\���W)�@�@��q p.33-50
�u�����q�v�`�����l���� : �n���ɂ݂�|�\�@�@�����_�_ p.51-63 |
�R���A�쑺�L�� �Ғ��u���A�W�A�C�敶���̐����ƓW�J : �q�����n���C�r�Ƃ��Ă̗����v���u
�����Ёv���犧�s�����B
�@ (�c��`�m��w���A�W�A�������p��)
|
���� �u�����n���C�������v�̑��e �O�n��̓��F �O�n���r�Ώ�
�@�@�������ƒ� ��w�����̋��L�Ɋ�Â������A�W�A�����̂�
�_�l�� �k�r���l����S�Y�Ɓk�r���l��l�̎Љ���Ƃ̊W/�t�����@����m�O ��
�k�r���l��n���������猩���������� / ���d�n ������m�O ��
�Y��̗\�h�A�Y���Ɣ��x / �ӑ��P�@�R�c���L ��
������B�n��̎��_�E�@�J������ / �R�c���L, ����z��
���`�̒n�敶�������� / �쑺�L�� �ق�
|
���J��ʂ��Ă݂��{�Ó� / �㌴�F�O
����̌��G�ƒ��N����̕����G��̗ގ��� / ���e�V
�ϏB���̗����M�� / ���Ǐi
�����n���C�ւ�/����̃}���A�M�� / ����z��
�ڑ����郍�[�J���e�B/�g�����X�i�V���i���e�B / �{���ǎq
�����n���C�ɂ����鐅�㋏�� / ���V�w
�_�b�ƋV��̊C�m�� / ��ؐ��� |
�S���A�X�ۉh���Y���u�R�����N���݂�����̉���� : �C�N�T�̋L���v���u�Վ����сv���犧�s����B(������܂�u�b�N�X = Gajumaru books ; 8)
�U���A���o�߂̉�ҁu���o�ߌ��� : �F���h�̐��o�߂𒆐S�Ƃ��� ���j�����ҁv���u���䓰�o�Łv���犧�s�����B�@�@
|
���o�̐��� / �r�ؔ�
�Ԑl�`�Ɛ��o�� / �O�c����
���ȂƐ��o�߂̊W�ɂ��� / �~�c�a�q
���o�߂Ə�ڗ� / �i�R����
���S���ێ悵�����o / ��������
�����n���̐��o��ڗ��̌n�� / ���V����
�Ԑl�`�������o�ߌ�薼�� / �v�Ĉ䗺�]
�����̐��o�߂������ / �˕����
��V�Η� / �쑽���M��
�������ɂ�������o�߂̓��� / �i��[�v
�����̐��o�Ɛl�`�ŋ� / ��їS��
�V�ۏ\��N�P�u�ꓝ�A�� �����Z�`��N�_�y�t�����ꗗ �ΎR���Z��l / �{��F�V
��{�_�Ђ̐_�y�t���� �_���E�|�\�҂����̗��� �����Z�N���o��n���� �V�R���S���Ɛ��o�ߑ��v����
/ �퐳��
�����q�Ԑl�`�̘b / ���c���ʋv
�����q�Ԑl�`�ƏH�R���O�Y / �����g
������̎ʂ��G / �v�ۊ��
�������q�o�����G���� ������\�N�㖼�O����� �����Љ�������o��ڗ��̌n��
�����Y��b / �����B�Y
�l�`�����O���� / �����L
�l�`�����g�c�����Y�n�� �吳�\�O�N���������V�� ���ϓA�ؓ����m�̗�������� ���ƌn�� �ؓ�疗y�̕]�_ / �ؓ�疗y
�R�̐����� / ����h��
���̎Ԑl�`��ڗ� / ���c�F�t
�����ΐ����L �ɓސV�h���q�ۑ��� ���c���莖�� ��l�ڂ̉ƌ��\��F���ᑾ�v
/ �~�c�a�q
���o��ڗ��ۑ���̒a���ɓ������ �w���o�������x���� / �{��F�V
�����q�Ԑl�`�E���o��ڗ��̉� ���o��ڗ��Ǝʂ��G�̉� ���o�߂̉���̍� / �{��F�V
�����s�w�薳�`�������w�莑�� ��܉�S��������T�~�b�g�����q�l�`���t�F�X�e�B�o��
/ �{��F�V |
�U���A���䒼�����u�{��{�@���q��{�����_���W (120) �@ p.59-82�@�{��w�@���q��w�I�v�ҏW�ψ���v�Ɂu�擇�����̒n���E�����E���j �@�`�{�Ï����Ɣ��d�R�����`�v�\����B
�W���A���{�q�ǂ��̖{������ҁu�q�ǂ��̖{�I : �������]�� 44(8) (�ʍ� 562)�@���W
���70�N�A�픚70�N ���̋L�� �����ւ̑I���v���u���{�q�ǂ��̖{������v���犧�s�����B
|
�q�ǂ��̖{����u�L���v�̕`��������l����@�L���P�q p.19-21
���p�����q�픘�̕���r�@������ p.22-24
�푈�̋��������𖢗��ɂǂ��`���邩 �@���� �̂肱 p.25-27
���`����A�q�ǂ������Ɂ@���c��ݎq p.28-30 |
�Ƃ��ɎЉ���w�Ԃ��� ����͂Ƃ��ɎЉ�����邱�� :
�@�@�������̕��a���琢�E�̕��a�ց@���Ԑ��� p.31-33
���70�N��MANGA���₤ : ���Z�������u�b�N�K�C�h�@��]�P�s p.34-37
�E |
�X���A�؉����q���u�Ñ㕶�� = Cultura antiqua 67(2) (�ʍ� 601) p.262-265�@�Ñ�w����v�Ɂu�����E���ꏔ���͊�Ղ̓��X�ł������̂� : �w�����m�̊������j�x�����������j�ǂ̌������ʂɂ悹�āv�\����B
�P�O���Q�S���`�P�P���Q�R�����A�u�ŋ���w�@�������~���[�W�A���v�ɉ����āu�C��n�����F��Ɨx��
: �ܒ���l�ƃG�C�T�[ : �H�����ʓW�v���J�����B
�P�O���A���킫�s�����킫�����}���ٕҁu�ܒ���l�|���킫�E����E���s�| : ����27�N�x�Ǐ��T�Ԏ��� ���킫�����}���ي��W�z�z�����v���u���킫�s�����킫�����}���فv���犧�s�����B
�P�O���A�u�C��n�����F��Ɨx�� : �ܒ���l�ƃG�C�T�[ : ������\���N�x�H�����ʓW�i�}�^�j�v���u�ŋ���w�@�������~���[�W�A���v���犧�s�����B�@���M�F�ΐ�o�u�Y, �M�����땶, �����r�p, ���i�m�C�@�@��i���: �A�����, �`�{����@ �ҏW: �A�����
�P�O���R�P���A������w�@�������~���[�W�A���ɉ����āu�ܒ���l : ���̐l�Ƃ䂩��̔��p�v�ɂ��Ă̍u����J�����B
|
�u�t�F�m��u���n�M���� �땶���i�h���@�ю���27���Z�E�A���q���̉Ɨ������j
�m�u���n�ΐ� �o�u�Y���i�`���������ۑ���������\�j
���� �r�p�i�{�w�����w�������j�E���i �m�C�i�{�w�����w�������A�{�ٌ������͎ҁj
�m�W������n�A�� ��Ɓi�{�يw�|���j |
�P�O���A����ӂ��q���u�����ƌo�� (40) p.52-65�@���������w������v�Ɂu����̐��n�ƍ����͔|�v�\����B
�P�O���A������w�j�w��ҁu����j�w = Ryudai review of history (17) (�{�Ó������W��)�v���u������w�j�w��v���犧�s�����B
|
�~�k�Y�}��Ղ̔��@�����̂����炵���{�ẪO�X�N����̐V�W�J�ƍ���̓W�]
�v�L ��k p.5-13
���������̐擇�Љ�Ɩ��O �㌴ ���P �� p.15-28
���{�������̑�p�Ƌ{�Ïo�g���� : �n�䋳���̋K�͂Ƃ��̔w�i�ɂ��� �{�� ��b p.29-39
���NJԓ��̊C�_ : ����ѕۑS�Ɋւ����l�@ �O�� ��� p.41-51
�n�@����݂�{�Â̐D�� ���� �L�b �� p.53-64
�n��̗��j�����Ɂu�ӂ��v���g�݂ɂ��� : �w�Z����ɂ�������j����Ƃ̐ڑ����l����@�V�� �@�j p.65-68 |
�P�P���A�g���r�Ƃ��u �ЂƂтƂ̐��_�j ��5���v���u��g���X�v���犧�s����B�@�@
|
�����Ɖ���Ԋ� : 1970�N�O�� / �g���r�� ��
��㎵�Z�N�O�� / �g���r�� ��
�O���R�I�v / ��ؖM�j ��
�R�{�`�� / �Ŏ�� ��
���{���Y / ���ؖ�� �� |
���R���� / �O�H���V ��
���@�����P / �������� ��
�}���[ / ��߉f ��
��ÍN�Y�Ɠ����Ɩ� / ������ ��
�c������ / ��c�L�I �� |
��{�P�v / ������ ��
���ˍW�� / ����^�� ��
����n������ / ���c�a�F ��
�ؑ���] / �J���� ��
�E |
�P�Q���A�c�Ԉ�Y �ҏW�ӔC�u�����Y�\�j��������Ԃ� �㊪(��1���`��191��)�v���u�����Y�\�j������v���犧�s�����B�@�d�v�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007910068�@430p
|
������̔����ɂ�������
�����ǂ��ɏA����(�v�|)
�ϋq����݂�����ŋ�
����̌��c�̕ϑJ�ɂ���
���NJԓ��̔����x��ɂ���-���̓����Ƒg�x�̓`�d�𒆐S��-
�����g�݂̂������|�\
������ɏA����
���ی|�\�Ƌ�����
����̗x��̕\�������ɂ���
�g�x�̊K�����ɂ���
�g�x�A���S�����ƉԔ���̉��ɂ���
�ՁEⵂɂ��Ă̍l�@
�^�쉮�̑��x��ɂ���
���R�`�M�^�Ɍ�����|�\�L�^
�g�x�ɂ�����}�������̎j�I�l�@
���E������ł����l �\���ɂ��Ă��߂Ƃ̊W�ɂ��ā\
�N���s���Ɩ����|�\
����g�x�Ɣ��d�R���x�Ƃ̈�l�@
�ÓT���y�̕ۑ��ɂ���(��Ƃ��Đ���H�H�l�̌���)
�j���ƌ|�\ �����s���^�h���𒆐S��
�����E�吳����̌��]�̕��� �\�V���_�]�𒆐S�ɂ��ā\
������Ɍ���ꂽ�u�����v�ɂ���
�������y�w����݂�����ÓT���y
�F�h�����{�g�x�u�ᕥ�v�ɂ���
�����ȁ[���̒n�����ɂ���
���x�u�ɖ�g�߁v�̃h���}�� �\��̊ӏܘ_�Ƃ��ā\
����|�\���ꂱ�� �\�e���r�ԑg�̐����ʂ��ā\
�^�쉮���̍��J�Ƒ��x
�X�����̓���
�u���S�����v�̈����ɂ���
�O���̖{�y�ւ̓`�d ���ɂ��̌`�ɂ���
���a25�\35�N����̉���ŋ�
�]�ˏ��g�߂̌|�\����
���̂̔����ɂ��� ���y�Ƃ̊֘A�𒆐S��
��c�߂̉��y�I�l�@
�g�x�Ɍ�����ʊK �\���̊��E���Ƃ̔�r�\
�����j�����l����
�v�u�̃j���W���[�K�i�V�[
���d�R���x�u�Ή����v�ɂ���
ⶋȁu�Z�i�v�̔�r����
�V�����g�x�u�ɑc�̎q�g�v�̍l�@
�Ì����̓��x��Ƃ��̎��ӂ̖��_
�������y�̓�����T��
�g�x�Ɍ���E�ƂƂ��̏��i
�����ÓT���y�ɂ������{��@
�u�����Áv�Ɓu��t���v�ɂ���
���ґ��̂��낢��
�u���S�����v�̖ⓚ�ɍl���� �\�ʖ{�𒆐S�Ɂ\
�������x�̉̎��̖��_
�u���S�����v�́u�^�v�̈Ⴂ�ɂ���
�g�x�u�F�s�̊��v���l����
�������̃}�[�X���[�ƃI�����ɂ���
�w���|���S�W�x�Ɨ������y
�吳�E���a�̉���ŋ�
�u���S�����v�Ɓu�萅�̉��v�̉��y�̓���
���̂̍\���ɂ���
�X�����ɂ��� �\�R�����j���w�����Ԓ�y���X�����x�̌����\
�`���|�\�̕ۑ��ɂ��� -���ɒX�������l����
�X�������l����
�����ÓT�|�\�ւ̃A�v���[�` �X�����𒆐S��
�g�x�̒��t�E������ɂ���
���x��̐ߖ��E�̎��̈ٓ����l����
�ĂђX�����ɂ���
�������@�̐��� �\�O���Ɠ����\
���d�R���w�́u�����v�ɂ���
���̂Ə��w�@ �\���̊ԓ����𒆐S�Ɂ\
�g�x�u���b���@���L���e�g�v�̓��ِ�
�̗w�ɂ݂��錚�z���l����
����^��7���G�C�T�[
�u���{������v�̉��y�I�l�@
�g�x�ɂ����鎞�ԂƋ��
�����̉���̌�
�����T�o�N�C�̓`�d�A����
�u���S�����v�̐����ɂ���
�^�����R�N�̌|�ɂ���
�^�����R�N���u�ᕥ�v�ɂ���
�^�����R�N��u�ɍ]���n���h�D�[�O���[�v�l
�g�x���˓G�����l����
�g�x�̉��Z���l����
���A�J�}�^���� �ւ̐_�b��p�ɂ���
�u���R�̉��O�v�u���������̕�v
�ÓT���y�H�H�l�̏����Ȃǂɂ��� �\�����łÂ问�y�j�\
�����̏�������l����
�w�������v�������x�Ɍ���g�x�ʖ{
�c�������̉ƕ��ɂ���
�g�x�ݍΓG���̂��ӂ��߂ɂ���
�X��p�s�̖��w
�u�ɕ����c���̃e�B���N�O�`�v�ɂ���
����j�{���҂̗����W�U
�X�����ɂ���
�������u�g�x�v�̓��e���l����
�Ăсw���R�`�M�^�x�̌|�\�ɂ���
�g�x�̉��o�E���y�ɂ���
�E���W���~�E�V�k�O�̉��y�I�l�@
�X���l |
�t�B�[���h���猩���������K�̖k��Ɓu�����v��U�^�[���ɂ�����
�ÓT�����x��ɂ���
�V�����̌�ⶂɂ���
�u�e����܁v�l
�ʏ钩�O�����̓���
�������y�̃��[�c���l����
�L�^�f��u�v�����̃C�U�C�z�[�v������
����ŋ��̏��� �\���Ɖ����S�O�N�ڂ��}���ā\
�ÓT���x�̈ߏւɂ���
�X�����̋ȂɐU��������x�ɂ���
�g�x�̋L�^�f����݂�
�Ղ�Ƌ����� �\�A�J�}�^�E�N���}�^�𒆐S�Ɂ\
�ɕ��������c���̑��x��
���d�R�|�\�̔��� �\��ɏ�i�c���̋Ɛс\
���d�R���x���l���� �\��ɏ�i�c���a100�N�Ɉ���Ł\
��ɏ�i�c���̋Ɛт�T��
�̌��u�����Áv�u��t���v�̓T���ɂ���
���ꕑ�x�E�̋ߋ��Ɠ���
��c���߂��̑����l����
�g�x�ɂ݂閯��
�g�x�u���b���@���L���e�g�v�̓���
���������̗� �\�g�x�Ƃ̌𗬁\
�����̃E�V�f�[�N�̉����\��
���NJԐΌ��Ɩ{�u�萅�̉��v�̐ߖ��ɂ���
�w�H�H�l�x�Ɓw�H�ڕ��x�̔�r����
�����ÓT���y�쑺���m�Ö{�ɂ��� �\�X�����Ƃ̂������\
�n�앑�x�u���v�u���Ԃ����v�ɂ���
�u���c��v�Ɓu�������v�̔�r�l�@
�u�ʼnԌہv�ɂ���
�R�����j�̌ܓx���@�ƈꌳ�_�ɂ���
�w�^�����R�N �l�ƍ�i �㊪ �l���ҁx�o�ł̈Ӌ`
����ŋ��G���W�[ �\���c����͂Ȃ��Ȃ����\
�u�Ή����v���l
����̋����Y(�A���𒆐S��)
�^�_���̏\�ܖ�x��ɂ���
�ǒJ���ɂ�����A�V�r�g�D�C�P�[�ɂ���
�ގ��̂ɂ��Ă̍l�@ �\�����E����̊֘A���l����\
�H�H�l�\���@�Ɋւ����l�@
�u�G���v�u���b�썲�ہv�̕���̎j�����ɂ���
�g�x�ɂ݂�u���v
����ÓT���y�Ȃ̉��K�ɂ���
���y�̉���(���_���Ƃ��Ă�)���l����
�n��u�}���������v�ɂ���
���ƌ|�\������
�p�q�����߂̑g�x����
�g�x�u�萅�̉��v�ɂ���
�ÓT���y�̋ȑz�ɂ��� �\���̗l�����Ǝ��ݐ��\
���NJԃV�����J�j�̉��y�I�o�H�Ɠ`�����̂��̂̌p���ɂ���
���鑺�ɏW�̑ʼnԌۂɂ���
�̐߂Ƃ͂ǂ��������̂� �\������̔@���×w�̌n���������ȁ\
�����o���������ŋ��̖��҂��� �\�l�C����14�l�̑��Ձ\
�����m�n��̉��y�Ɖ���
�g�x�u�G���v�n���̔�r�l�@
�n��ւ̎v��
�ʏ鐷�`�t�̑g�x������ �\���a�S�N�ɂ��Ȃ�Ł\
�ʏ鐷�`�̐l�ƍ�i
�ʏ鐷�`�搶�̎w���@ �\���a�S�N�ɂ��Ȃ�Ł\
�̌��Ƒg�x�̊W
�g�x�u�v�Ǘt���v�ɂ���
�g�x�u�Ԕ��̉��v�Ɓu�g�n�j���Ȑ��ےÎ�Ȍ�v(���̕���)���Ƃ��Ȃ���
�O�����̌^�̓���
�ÓT�����x���x��
�n�앑�x�u���v���������v�ɂ���
�g�x�u�萅�̉��v�̌����ʖ{�̍l�@ �\���Ɏg�p���y�𒆐S�Ɂ\
�w�^�����R�N �l�ƍ�i�x�������s�ɂ���
�u�|�\�j�����v�ߋ���
�n�w�Ƃ��Ă̈��x�c�|�v�搶
���y�c�|�v�搶�Ɋw���
���y�c�|�v�t�̋Ɛ�
���{�I�������@�̌����ƒn���E���C���@ �\�_�̂ɂ����钷�u�V�[�\
����̌���̈ڂ�ς��
�w�v�ē��̉̍H�H�l�x�̔����ɂ���
�w�ܐ����{�Â̂��₮�x�ɂ���
�V�����E�g�x�u�������^�Ìˁv�ɂ���
�ʏ鐷���Ɨ����̌�
����̑���
�ǒJ���ɂ�����g�x�`���ɂ���
�g�x�̈ߏւɂ���
�V���� �g�x�u���̖L���v�ɂ���
�^�����R�N�t�����
���Ԑ����t�����
�e�����Ǝt�����
�K�n�T���t�����
�g�x�u�g�֒����v�ɂ���
����Ǐ��t�����
���l�v�M�t�����
�ʏ鐷�`�t�����
�����@���Y�t�����
���A���d�t�����
���܌��T�t�����
��p���L�t�����
��F�����m�t�����
���䐷�|�t�����
�{���t�s�t�����
�E |
�P�Q���A�c�Ԉ�Y�ҏW�ӔC�u�����Y�\�j��������Ԃ� ����(��192���`��357��)�v���u�����Y�\�j������v���犧�s�����B�@�@�d�v�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007910092�@432p
|
�g�x�u�k�R���v�̓��e�ƓW�J
���̂ɂ݂锽�����@
�I�y���u����v�Ɓu�����̎��v
�ɍ]���̑��x�� �\�g�x�u���b���v�𒆐S�Ɂ\
�w�Ӌ|�H�H�l(�ꊪ)�x�̔����ɂ���
���܌��T�E���̐l�ƌ|�̐S
���܌��T�搶�Ƃ̏o�
���܌��T�搶�̌|������� �\�n�w���Ƃ߂��҂Ƃ��ā\
��O�̉������s�����
�g�x�u��̊��v�ɂ���
�n��u�j���C�J�i�C�v�u�O�̈��̉́E�N�[�`�[���[�C�v�ɂ���
�{��M�s���̍�i�ɂ���
�쑺���S��C�ED�^�����ɂ���
��o���̑g�x�u���g���v
�m�O�A�쑺�A���x�c�̔�r�H�H�l�ɂ���
�����̕����I�|�\�����ƒ����O�����y��r�����̓W�]
�Ԓ�X�����H�H�l�̏��R(��)�ɂ���
�g�x�u�v�w���g�̊��v�ɂ���
�u���J�H�H�l�v�̔����ɂ���
�g�x�u���s�̊��v�ɂ���
�w����̌Ӌ|�x�̔����ɂ���
�X��p�s�̃X���T�[�~�[�ƃX���T�[�~�[��
�g�x�w�X��p�G���x�̑�{�����ɂ���
�u�萅�̉��v�̗R���ɂ��� �\�ɐ�����Ƃ̊W�𒆐S�Ɂ\
�w���ꌧ�j���x�Ɏ��߂��g�x�ʖ{�ɂ���
�u�ӂ邳�Ƃ̌ÓT�v�Ɋw��
����̐_�y�ɂ���
�����ʂ̖��w����w���܂�������x�̔����ɂ���
�g�x�w��F�v�l�x�̓��e�Ɠ���
����q�������
�����Ƃݎq�t�����
���y�c�|�v�t�����
�{��k�������
�g�x�u�T�`�`�G���v�̓��e�Ɖ��l
�I�������t�����
�w���j�����ۋ��{�x�̔����ɂ���
�V�����g�x�w�ێ�G���x�̓��e�ɂ���
�`�����Ă��鋻�ƌ|
�e�����Ɛ搶�̑g�x�̏����ɂ���
�e�����Ƃ̏��`�ɂ��� �\�ł��g�ݗx��A
�@�@���g�x�A�̌��𒆐S�Ɂ\
3�A�����ɂ��� �\����H�H�l�̕\���\
���V���g����w�ɂ����鉫�ꉹ�y�w��
�w�����ÓT���y�̌����x���o�ł���
�̐߁A��̐߂̉��y�\�� �\�u���߁v�𒆐S�Ɂ\
�g�ݗx��u�ᕥ�v�O��̔�r�l�@
�H�H�l���̕ϑJ �\�ɖ�g�߂̏ꍇ�\
�ÓT�|�\�ɂ݂鋳�P�ƌ�
�ÓT���y�̖���
�g�x�u�k�R���v�̏㉉�ɂ���
���x��̉��
�ÓT���x��Ƒn�앑�x�ɂ���
��4��u�N�q�̕���v�������I����
�쑺���̋Ȃ̑��x�ɂ���
�g�x�u���F�v�w���`�v�ɂ���
�����ÓT���x��̗l��(1)
�쑺���H�H�l�̑����ɂ��Ă̍l�@
�ߌ��I���Y���\���m�����Ɖ��ꉉ���̔�r
�@�@���\�u�I�C�f�B�v�X���v�Ɓu���S�����v�𒆐S�Ɂ\
�����g�x�ƒ����Y��
�g�x�u���b���Ԃ̊��v�̏㉉
�u���S�����v�̏h�̏��̃C���[�W
�g�x�u���b���Ԃ̊��v������
���x��̗l��2 �������x�̔�
�V�_�`�u�̑n�앑�x���ɂ��� �\���ɑ��g���ɂ��ā\
�g�x�u�����q�v�Ɣ\�u�H�߁v�̏㉉
�쌀�I���Y���\�u���A�m�j���a���v�𒆐S��
�@�@���\�w�g�x�x�̃p���f�B�[�\
�\�l��ⵍH�H�l�����ւ̈�l
�@�@�� ����ⵂ͓Ɨ��y���ɂȂ肤�邩?
���x��Ɖ̎��̉���
�w�g�x�ʖ{�̌����x���㈲����
�쑺���H�H�l�ɂ���
����|�\���B��S���Ƃ������
�g�x�u���̖L���v�̏㉉
�����ɓ`������\�̗��V
�w�ĕ��\�����ɖ������āx���s�ɂ悹��
����ŋ����n���̗l��
���̗����l��
�g�x�u���̊��v�ɂ���
�̕���Ɨ����|�\
�u�Ă����ʉԁv�Ɓu���@���v
�萅�̉��ƕl����
�g�x�u�萅�̉��v�̋ʒÑ�
�v�u�������{�u�g���R�ˁv�̓���
���~�����q�����ɂ��� |
�ÓT�|�\�̎��� �\�V�_���ܐ��a120�N�Ɋā\
�V�_���ܐ��a�S��\���N�L�O�|�\�����̎��{�ɂ�����
�V�_���܂̌|���E�|�] �\���a�S��\���N�L�O�\
�u����ƕ��~�����q�v�ɏo������
�n�앑�x�u�z���v�ɂ���
�쑺���������l�Ǝ���
���m�����̎�e�Ɖ���ŋ��u����v
�u��l�v�̌��� �\���x�c���u�ɖ�g�߁v�̎�l���߂����ā\
�������x�Ɨ������x�Ƃ̔�r����
�`������̓�̗��� �\�g�x�u�������v�ƌ���u�F���p��ƉȎ��v�\
���x�̌��u�O�����v�ɂ���
�n�Õ~��ǂ̌|�����́u�p���ƌ����v�Ɋ���
�n�Õ~��ǂ̋L�O�������I���ā\�n�Õ~�����Y�̘����㐢��-
����ⵋȂ̌���
������̑��x��́u�茴�̈i�v�ɂ���
�����J���̖�
���y�j�ɂ�������y�c�|�v �\�Âԉ��U��Ԃ��ā\
�l���ɖ𗧂w���Ƃ킴�̉́x�s����
������\�ꌼⵂƉ��t�� �\�t�߂̑剹�y�ՂɎQ�����ā\
����|�\�ɂ����锪�d�R�R���̉�
�g�x�u���c�����G���v�ɂ���
�{���t�s�t�����
�u�V�m���E�h�E�x���W�����b�N�v�Ɖ̌��u�̂����댎��̐l���v
�{���t�s�搶�̎w���@
�n�Õ~���ǂƉ���ŋ�
�c�������̍쌀�@�̓���
���V�̓V�n
�����ÓT���y�E�ւ̒� �\�w�����y���̌����x���瓾�����z�\
�����ÓT���y�̉��t���_�ɂ���
������Ƃɂ���
�X���e���K�n�����̂����� �\���̐l�����Ɛ������܂��l����\
���x��Ȃǂ́w�x��ԑg�x�ɂ���
����|�\�u���W�������ɎQ������
�n���C����e�P�𗬌��� �`����̌×w���`
��������ɏ㉉���ꂽ�u���F�w�l�v
�Õ����Ɍ���|�\�҂���
���x��Ɍ��钩���̑g�ݗx��
�c���������a�O�S�N�L�O���Ƃ��I����
�w�g�x�̐��E�x�s���� �\�u���̌����E�y���ݕ��v�\
�L�O���u�����ÓT���y�̌��_�v������
�w�Z�� �����Y�ȏW�x��� �䊥�D���x�ɂ݂��镜�����x
�@�@���w���q��v�̍\���E�앑�ɂ���
�w�����̖��D �V�_���܂̐��E�x�s����
�w�ÓT���x�̕��x���x�̔��s�ɂ�������
�����ÓT���y�̗��� �\�X�������猻��܂ŌÓT���y�͂ǂ��ς�������\
�傫�ȉ��b�w�쑺���ߞٕ����H�H�l�x
�����Y�ȂƗ����g�x
�g�x�u��̔䉮�v�̓��e�Ɠ���
���a��O���̖{�y�ɂ����鉫��|�\�̎�e
����ŋ��u�^�ʋ��R���I�v�ƐV��g�x�u�^�쓹�v�ɂ���
��c�����Ɓu�������y�̎O��ⶋȑ���(�̎�����t)�v�ɂ���
�@�@�� �\��c���v���a�S�N���}���ā\
��c���v�̑n�얯�w�ɂ���
�x���琴���w�������y�l�x�̉��߂ɂ��� �\�O��̋Ȑߖ@�𒆐S�Ɂ\
�����{�앑�x�ƒ������ԉ̕� �\���܌��́w���R�`���^�x���߂����ā\
�O���̕\���̉\���ɂ���
���y�c���Ɩ쑺���̋�@�̈Ⴂ�ɂ���
�w���ꉉ���E�̋��� �n�Õ~��ǂ̐��E�x�s����
���a20�N��̉���̒u���ꂽ�ʒu�E�������x�̎���
�����ÓT���y�Ɩ��w�����Ԑ�c���v�̐��E �\���a�S�N�ɍl����\
���Z�ɂ�����g�x�ӏ܉�ɂ��� �\�����g�ɂ��200��������I���ā\
�\�����߂Ɛ����Ƃ̊ւ������߂�
���܌��j�搶�����
���i�̂킪�J�^�J�V���̎t �\���܌��j�搶�̎v���o�\
���܌��j�搶�̌��������ƋƐ�
�����g�x�̍쌀�@�ɂ��� �\���{�\�A�����Y�ȂƂ̔�r�\
�w���Ô�H�H�l�x�̍Đ����߂����� �\���w�H�H�l�x�Ƃ̔�r�\
�c�c���搶�����
�������y���������l �c�c���t�̊y�����l����
���ꌧ�|�p�Ղɂ����镑�x�����̎��� �\1972�N�`2005�N�\
�V�_�T�q�������
����ⶋȂ̃��[�c��K�˂� �\�������ƛ��n�߂𒆐S�Ɂ\
�w�R�c��q ���̓� ���̂�����x�s����
�w���y�c���g�x�n�w�H�H�l�����{�x������
�|�\���猩��ҕ��� �\����ŋ��̔w�i�\
���{������Ɨw��
���r�t�����
���ʐ��q�̓��s�ɂ�����|�\����
�`�����_���[�E�j���u�`���[�l(��)
�|�x���̎�q��Ղ̌|�\
���{�d�Y�搶�����
���Ô䒩��H�H�l �܂����ǂ�
�R�����j�t�����
�R�c��q�搶����鉶�t�̕��p�ɖ�������
�{����\���t����� �\���S�x���\
����q�t����� |
�P�Q���A�c�Ԉ�Y �ҏW�ӔC�u�����Y�\�j��������Ԃ� ����(��358���`��436��)�v���u�����Y�\�j������v���犧�s�����B�@�@�d�v�@�@�@�@�@�����F���ꌧ���}���فF1007910126�@�@432p
|
�F���L�O�Y�t�����
��[���q�t�����
���a11�N�̑g�x�l�ԏ㉉�̈Ӌ`
�����g�̂��Ƃ����ނ�
�w�|�p�Ց����x�̗������x�ɂ�������j�I�Ӌ`
�O����ⵂ̗��j�I�W
���ߍl -���߂͐[���Ȃ銽�тł���-
�n�Õ~��͎t�����
���������ƈ��y�c���̓`�� -�R�����j�̘_�������Ƃɍl����-
�����q�Y�̉���|�\���� -���Ɂu�g�x�v�𒆐S��-
���ʐ��q�t�����
�����Ԑ��q�t�����
�䊥�D�x��̕����Ɋւ��錤�� -
�@�@������w�I���͂��玎�݂���{�Ȏp���ƕ��݂ɂ���-
�u�y���[���̐S�v��n���Ǝt�����
�c�ӏ��Y�u���ꕑ�x�̂䂭���v
�u���{������v�`���̌o��
���Ɩ{�w�g�x�W�x�̓��e�Ɠ���
��䐷�~�̖v�N��1715�N
�ʏ�@�g�t�����
�쑺�����y����n��85���N�L�O �ɍ��쐢���E
�@�@�����X���j�����w�ߞٕ����H�H�l�x�������Ƃ̂���܂�
�w�ߞٕ������Ô䒩��H�H�l�x���o�ł���
�@�@��-�w���Ô�H�H�l�x���猩���Ă������-
�^���������t����� -�R�N�|���т��������|�̎p-
���g�����̉���|�\���� �\�g�x�𒆐S�Ɂ\
�R�����j�Ɨ���ⶋ�
���g�V�Q�t�����
������Ɋw�ԗ������x�̖{��
�w���Ô䒩��H�H�l�x���߂�����_
�����O��̑g�x���� �\�w�����̌����x���e�u�萅�̉��v
�������x�ɂ�����g�̋Z�@�u�K�}�N����v�Ɋւ��錤��
��䐷�~�́u�ƕ��v����l����
�w�ߞٕ������Ô䒩��H�H�l�x�����Č��������
�@�@�� -�X�����Ɩ쑺���ɗ����n��-
�����ÓT���x�̏㉉��i�̎���
�@�@�� -�Ɖ���E���|�p�ՁE����䂵�|�\����-
�^�����R�N�ƗR�J�����
�{���c��̉���|�\���� -���ɑg�x�𒆐S��-
�_�����I�q�t�����
���c�s���t�����
�u�����Y�̉́v�̌��� �\�j���|�A��A���l���A���h����/
�@�@���n���ҁA�t��/�O���́A�l�`���炭��\
��ċy�іk�Ăɂ�����O���Ӓ��
�w�������B������ⶋȞٕ��x
|
�^���������̉���|�\���� �\�g�x�𒆐S�Ɂ\
�{�镶�t�����
���A���g�A�{�[�����
�g�x�A�p�����W�ւ̉ۑ� �\�`�����ɐV���o�̉��o���\
�V��g�x�w�C���̉��\���J���Ƒܒ���l�Č��\�x
��o�������Ɓw�Օ��x�̕]��
���R�B�\�Y�́w������ڗ��x�ɂ���
����q�t�����
�L����n�[���[�̌@��N�����Ɋւ����
�����×����p�Ɨ������x �`���˂��E������E�����ݎ�`
���c���~�̗����|�\���� �\�g�x�𒆐S�Ɂ\
�ߑ���ɂ�����̉�̉���ɂ��|�\�`�d�ɂ���
�{�鐳�q�t�����
���H���m�u�搶�����
��O���ܐ߂̌n�� �\��O���ܐ߂Ƃ́A���́u�ܐ߁v�Ȃ̂�?�\
���y�c��������85�N�̕���
�@�@���y�l��1�z���a�����܂ł̗���Ɖ��
���d�R���x�̌���Ɖۑ�
�g�^�̗x�ߏց\�ɐ��������q�`���i��
�@�@���e�����Ƃق��ߌ��㕑�x�Ə����ߏց\
�{�c�����̉���|�\����(1) �\���ɑg�x�����ɂ��ā\
�w�|�p�Ց����x�̐��E
�w����ⶋȂ̌����x�o�łƐV���������ۑ�
�\�Ƒg�x �\�v�z�̈Ⴂ�\
�킪�t�u�^�������q�v����� �\
�@�@���^�������q�t���̗������x�l��70�N�̕��݁\
�{�c�����̉���|�\����(2) �\���ɖ����|�\�𒆐S�Ɂ\
���ڐe������ �\�g�x�������̔N���Ƃ��̐��E�\
�Ԍ��q�Ƃ��̎���
�����|�吶�̉̎O��(�����ÓT���y)�̊y���I�����ɂ���
�g�x�̗l���Ɛ��_���ɂ���
�v�����̃C�U�C�z�[�ɂ��� �\���a53�N�̃r�f�I������\
�O���x��ƃe�[���V�J�}�O�`
��l�G�m�搶�����
�g�x�u�ᕥ�v�̍L���� �\�̌��u�������v�ɂ��ā\
�������x�ɂ�����g�R���N�[���h�̉e��
����ⶋȂ̓`���̍l�@�\��䐷�~���璇���}�o�V�܂�-
�w�|�p�Ց����x�ɏ������ꂽ���x��̌^�̉���
�u�����ÓT���y���n���v�̂��ڂ����Ɓu�����̊��v�ɂ���
��O�x��̐g�̋Z�@ �\���x��������Ƃ��ā\
�ÓT���x��u�ɖ�g�߁v�̉^���\�������ɂ���
�@�@�� �\���d�^��i���͂ɂ��\
�C�O�ɂ����问�����x�̎�e
�J�`���[�V�[�̌^(����)�ɂ���
�E |
���A���̔N�A�_�ސ��w�]�_�ҏW���ψ���ҁu�_�ސ��w�]�_ (82) (���W ����̐�㎵�Z�N : �푈�̋L�����猻�݂܂�)�v�����s�����B
|
���ʃC���^�r���[ ����̐�㎵�Z�N�A
�@�@�������u�푈�v�Ɓu��́v �ڎ�^�r,��c���� p.5-32
���� : �푈�̋L���ƕ��a : �u�R���ɂ�镽�a�v��
�@�@���u��R���ɂ�镽�a�v�� �Ό����� p.33-41
��n���Ɖ������߂��钾�É��̍s�� :
�@�@�����܁Z�N��㔼����̔����I��₢���� ���R�~ p.42-50
�����`�Ɖ����� �g���P�j p.51-58
�������И_�Ɣ��d�R�ւ̎��q���z�� ��c�Òj p.59-66
��㎵�Z�N���ꂩ�� �ӉԒ��� p.67-74 |
"���n�u"�͎��ȂȂ� : ���ʂ���� �V�_�B p.75-84
���O�̗��j���n�铬�� �e��T�q p.85-91
��n��� : ��ނ̌��ꂩ�� �������q p.92-99
����Ɠ��{�����@ ������ p.100-107
�����Ɖ���� : ����̐l�тƂ̐����ƕ��V�Ԋ�n ���F�� p.108-117
���j���Ƃ��Ắu�Ӗ�Áv:�u���������v����l���錻�� ��c���� p.118-127
�펀�҂̐� ���g�h�� p.132-135
��㉫��A��̌|�\�R���N�[�� �v���c�W p.136-139
������(������[)�̗��j�Ɩ��� �e��u�ގq p.140-143 |
���A���̔N�A�_��F�G���u���y�w 61(1) p.39-41�v���u�O���킩�Ȓ�, �w�ߑ㉫��̗m�y��e-�`���E�n��E�A�C�f���e�B�e�B�x, ����:�X�b��,
2014�N1��23��, 383��, \7,500+��, ISBN978-4-86405-058-6�v���Љ��B�i-STAGE
���A���̔N�A�������ނ��u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (81) p.193-196�v�Ɂu�����o�����] ���c�g�F�ďC�w����̃G�C�T�[�A���̃G�C�T�[�x(�݂�ς��f����������ꎵ�W)�v���Љ��B
���A���̔N�A���c�g�F�ďC �u����̃G�C�T�[�A���̃G�C�T�[�v���u���������w�����فv���犧�s�i�f�������j�����B (�݂�ς��f�������� ; ��17�W)�@�@�B�e�E����:���������w������ �ďC:���c�g�F�@ ���^�N: 2000-2002�N
|
�l��Ó��̃G�C�T�[����̋��~�@�@�@���̃G�C�T�[�v���̌����� |
���A���̔N�A�����r�p���m���@��y�@�w�������ҁu��y�@�w���� (42) p.356-359�v�Ɂu���ጤ���� �ܒ���l���������́w�O���N�����x���߂����� (������\���N�x ������v�|)�v�\����B
���A���̔N�A���{��,�c�{�R���q���ʐ��w����w���ҁu�_�p : �ʐ��w����w���I�v
[] 2015 p.115-132�v�Ɂu���a��Ôg������,�q�쐴�̌����X�^�C���Ƃ��̍����I�Ӌ`�v�\����B�@�iIRDB�j
���A���̔N�A�c�����a,�X�R���q,��ߔe��肩���u���{�����Ȋw��������\�v�|�W
27(0) 2015 p.187�v�Ɂu�����ɂ݂鉫��̉ƒ뗿��:�|�������X�g�̍쐬���߂����ā|�v�\����B�@�@ J-STAGE
���A���̔N�A���c�k����������w��w�@�����o�ϊw�����ȕҁu�����w�����_�W = Journal of politics (43) p.139-161������w��w�@�v�Ɂu���ꌧ�ǒJ���ɂ�����ČR��n�ڎ��y�ѕԊ҂ɂ�鑺���Ɣq���̍Đ�
: ���F���Ǝ��n��m������Ƃ��āv�\����B |
| 2016 |
28 |
�E |
1���A N27�ҏW�ψ���ҁuN27 : �u���̊�-����v��]�� 1(6) (�ʍ� 6) (�����O���r�A
1970�N12��20���u�R�U�\���v)�v���u�V���o�Łv���犧�s�����B
|
���g�a�v (�����O���r�A 1970�N12��20���u�R�U�\���v) ���g�v p.2-9
��ÍN�Y (�����O���r�A 1970�N12��20���u�R�U�\���v) ��ÍN�Y p.10-17
��ÖL�� (�����O���r�A 1970�N12��20���u�R�U�\���v) ��ÖL�� p.18-25 |
�Q���A�O☗��K���u��B���ۑ�w���{���� = Studies of liberal arts 22(3) (�ʍ� 62) p.73-97�v�Ɂu�ɔg���Q���w���ꏗ���j�x�́u�T��v : �^���������Ƃ́u�����v�Ƃ��ēǂށv�\����B
�R���A���ꌧ���|�p��w�����������ҁu����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
(28) �g�Ɗԉi�g�����ޔC�L�O���v�����s�����B
|
���d�R�̗w�ɂ����鉹�����ƌ�` : ���ꉹ�Ɋւ��l�@�𒆐S�� �����q�@ p.3-16
�s���Ԑ߁t�̓W�J�Ƃ��̔w�i �@�ѓc �וF�@ p.17-34
�w���R���Ӂx�ɂ����钆���ÓT�̈��p�ɂ��ā@���C���@ p.35-46
������ƕ����ߌ��ɂ��� �@�@ḛI�Ё@ p.47-63
�������{���̋L�^�Ǘ��@ꎓ���q�@ p.65-79
���q�m�[�g����݂��u�����|�p�����v(2) �@�@�v�L�T�q�@p.81-103
���������w����Θb�x(5)��� �V���V���@������,�������q,�V�_�P��,���g����,�n���쏟��,�R�c���}�q,�哹�D�q�@p.105-133
�g�Ɗԉi�g���� �o���E�Ɛшꗗ�@ p.150-184
�ߑ㉫��̌�y : �����E�吳���ɂ������y�̈�[�@��� �k���@ p.212-186
�w�������R���L�x���ڂ̃C�x�ɂ��� : �I�����Ƃ̔�r��ʂ��ā@�Ɖ� ���@ p.213-p.238
�u�������v�Ƃ͉��� : �w�����낳�����x����l�ɂ��� �@���� �L�q�@1
p.239-p.254 |
�R���A�u���ꌤ���m�[�g 25 �v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B
|
���x�u����l�߁v�Ɓu���������v �������V p.1-6 �iIRDB�j
���~���a�Z�Z�Z�N : �w���z�x�ɂ݂鏮�~�̑��� ���ђ��� p.7-12 IRDB�j |
�ڏZ�҉Ƒ��ƕ�Ɋւ����l�@ : ���ꌧ�{�����암�ւ�
�@�@���ڏZ�҂̎��Ⴉ�� ����D�q p.13-22 �iIRDB�j |
�R���A�{�����W���u���m�_���@���������ɂ�����V�}�N�T���V�V��̖����w�I�����v�\����B�@pid/10342151
�R���A���Ï@�F���u���ꎩ���̌o�ϊw�v���u���X���فv���犧�s����B (�p���E�����m��)
�@�@�@�@239p�@�����F���ꌧ���}���فF1007856618
|
����̓��{����̌o�ϓI�����͉\���B����o�ς̌���Ɩ��_�𖾂炩�ɂ��A�ό��E���]�[�g�Y�Ƃ̂������n��o�ϊ������ւ̍v���Ƃ����ϓ_���猟���B����o�ώ����̂��߂̒����I�W�]�E�ڕW�����B |
|
�͂��߂�
��1�� �����o�όv�Z���猩�鉫��o�ς̎���
��2�� �d���w�H�ƒ��S�ɂ����Ă������{�̎Y�ƍ\��
��3�� ����U������͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂� |
��4�� �ό��E���W���[�Y�Ƃƌo�ϐU��
��5�� ����o�ώ����̂��߂̌o�ϊw
��6�� ����o�ώ����̂��߂̕���ƌo�ϊw
�E |
�R���A ������ЂƂ�,�ԏ�m�q���u��r���x���� = Japanese journal for comparative studies of dance : ��r���x�w��w�p�@�֎� 22 p.22-31�@��r���x�w��v�Ɂu���a�����̉f���ɂ݂��问���ÓT���x�u������ŕ��v�v�\����B
�T���A�{�����W�����{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (286) p.67-84�v�Ɂu����̍Ύ��K���ɂ����锪���Ƃ�������̈Ӗ��ƕω� : �\�����̋S��(���[�`�[)������Ɂv�\����B
�T���A�u�n�� 61(5) (�ʍ� 731) (���W ���� : �X�ƊC�Ɛl�Ƃ̂������) �v���u�Í����@�v���犧�s�����B
|
���M�сE���ׂ̎��R�Ɛl�Ƃ̂������ ���� �B�Y p.16-25
�����̐������l���ی��
�@�@�����E���R��Y�o�^ �ԗL�� p.26-33
����̃W���S���Ɛl�Ƃ̂������ �g��G�� p.34-43 |
�T���S�ʂ̊C�ɐ����鋙�t�̎��R�F�� �n�v�n��,���{�ԐD p.44-51,�}����10-11
�Đ�̉��̐Ί_���ɂ�����w�����E�t�H�X�^�[�̒n������ : �t�B�[���h�E
�@�@���A�V�X�^���g�R���ߎq����ɕ��� �R���ߎq,���J��� p.52-59,�}����1-9
�E |
�U���A���F�M���u�l�ԕ������� = Studies in Humanities and Cultures 26 p.36-25�v�Ɂu����w�Ƌ��y���� : ��O�̉���w�E���y����������������Ɗ����v�\����B
�@ �iIRDB�j
�V���A������������C���w�_�W�ҏW�ψ���ҁu��C���w�_�W = Commercial review of Senshu University (103) p.39-48�@��C��w�w��v�Ɂu����̘V�܃u�����h:�َq�́u�ӉԂ����ς�v�ƖA���́u�����v�v�\����B
�V���B�z���L�ꊧ�s�ψ���ҁu�z���L�� : ����ׂ����t�̂��߂̏��q���@���W
�����Ɩ� ���ƕ��̗��l�v���u�z���L�ꊧ�s�ψ���v���犧�s�����B
|
�J�������������f�B�I�Q�l�X : �w�V�� ���z�̉��M�x�̕ҏW���I���� �@�������� p.76-87
�w���z�̉��M�x���߂���ʐ^�f�z�@�ΐ엳�� p.88-91
�S�Ă͓����Ȍ��ɊҌ������ : �w���z�̉��M�x����w�V�� ���z�̉��M�x�� �@�F�q
p.92-102
�����Ɩ��ʐ^�W�w�����̓��x�J�ËL�@�ΐ쒼�� p.103-109
�����Ɩ��~�X�R�哹 �@�V���`�a�@ p.110-119
�����Ɩ��͂Ȃ�������������̂�? �@���q ���� p.120-125
�����Ɩ��Ɖ���C���[�W�̕ϗe : �uOKINAWA ���� OKINAWA�v���߂����� �@����G����
�@p.126-132 |
�X���A�^�ߔe���q�����m�_���u�җV�s�v�Ɍ���ߑ㉫��|�\�j���� : �[�V�s�A�W�����A�|�\�[ �v�\����B�@������w
�P�P���A����Y���A�����ĕ�A�쓇�G��A�������F���u�n����S�w��[�T�W39�v�v�Ɂu�Ôg��O�ōs����ԗ�Ղ̎��Ԓ����Ƃ��̌��ʂɊւ����b�����v�\����B
�P�Q���A���{���炪�u�ꋴ��w�X�|�[�c���� 35 p.53-62�@�ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������v�Ɂu�����̏�ɂ����鑽�l�Ȓn�敶���̑n�o
: ���̉���ɂ�����G�C�T�[�̋����ɒ��ڂ��āv�\����B�@�@�iIRDB�j
�P�Q���A�ȏ��������O�����w��ҁuSouthern review : Studies in foreign language & literature (31) p.27-43�v�Ɂu�A���b�N�X�E�J�s���w�A�t���J�ň�Ԕ������D�x : �ُؖ@�I�W�F�t���[�E�X�p�C�T�[�E�V���\�����v�\����B�@
�P�Q���A�哇���q���u������w�ό��Ȋw 8 p.73-86�@������w�@���w���v�Ɂu��8��ό��Ȋw������ �ό��Ȋw�̓��ꐫ�ƕ��Ր��i3�j �ό��̋���͂̍\�����Ɍ����āv�\����B�@�d�v
���A���̔N�A���{���炪�ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������ҁu�ꋴ��w�X�|�[�c����35
p.53-62�@�ꋴ��w�X�|�[�c�Ȋw�������v�Ɂu�����̏�ɂ����鑽�l�Ȓn�敶���̑n�o :
���̉���ɂ�����G�C�T�[�̋����ɒ��ڂ��� (�u�X�|�[�c�Ƒ��l���v�ւ̃A�v���[�`)�v�\����B
���A���̔N�A���ؗE�l�� ; �X�^�W�I�K�[���G�u�G�C�T�[�̖��v���u����s�v���犧�s�����B
���A���̔N�A����s��; ����s�ό����Y�U������G�C�T�[�ƕҁu����s �G�C�T�[�K�C�h�u�b�N[���[�t���b�g]
�v���u����s�v���犧�s�����B
���A���̔N�A�������q���u���{�����l�ފw������\�v�|�W 2016(0) p.F09�v��
�u�n��Љ�̋V��ɂ݂�ϗ�:���ꌧ�{�Ó��s���K�̉��ʍ��J�u�p�[���g�D�v������Ƃ��āv�\����B�@J-STAGE
|
�v��E���^�F�{�����͓��{�̖����Љ�œ`������Ă����`���I���J���A�n�拤���̂ɂ����铹���I�v�l�Ɨϗ��I�s���̌n���Đ��Y����d�v�ȑ��u�̈�Ƃ��čČ���������̂ł���B�䂪���ł������{��k�ЂŔ�Ђ����`���I���J�̕������j�ƂȂ�A�n��Љ�ɑ��铹���I�s�����č\�z�������B�p�[���g�D�V��ɂ�����Z���̍s���₻�̐������Ƃ����āA�����̂ɂ����铹���I�v�l�E�ϗ��I�s���͂��A���K�����̂̍č\�z�ɂ��čl�@����B |
���A���̔N�A�m�O�ǔV,�Ő��Ȃ��u���{�X�ъw����\�f�[�^�x�[�X 127(0)
p.14�v�Ɂu���ꌧ���NJԓ�������Ƃ����d�Y�ޗ��p���߂���n��Љ�̎��g�݂ƐX�ё����ƊǗ��̓����v�\����B�@
J-STAGE�@�d�v
|
�v��E���^�F�{�Ó��ƐΊ_���̂قڒ����Ɉʒu���鑽�NJԓ��́C�ʐ�19.75km2�̗��N�T���S�ʂ̓��ŁC�قڕ��R�Ȓn�`��悵�Ă���B���݂̐X�т́C�k��2�W���̎��ӕ��Ɠ��̊C�ݐ��ɉ����ėётƂ��Đ������Ă���B��Ђ̉e������r�I���Ȃ��������Ƃ�����C���NJԓ���ΏۂƂ��������́C��ɌÕ�����`���s�����̎Љ�Ȋw�I���_���瑽�������݂��C���R�Ȋw�C���ɐX�щȊw�̕���ɂ����ẮC�E���ԁi2009�j�ɂ��u���NJԓ��ɂ�����W������т̐A���E�\���v�Ɋւ��錤�����������Ă͂قƂ�nj����Ȃ��B�Ƃ���ŁC�X�іʐς⎑���ʂ�����ꂽ����̓��גn��ɂ����āC���NJԓ��ł͐d�Y���Y�̎����I�̐����Â�����݂������Ƃ��m���Ă���B�����Ŗ{�����ł́C��ɐ�ォ��K�X�R���������y����1960�N��㔼�܂ł̊��Ԃ�ΏۂƂ��đ��NJԓ��̐d�Y�т̗��p���Ԃ��C���������ⓝ�v�f�[�^�̕��́C���n�ł̃q�A�����O�ɂ�茟�������B���̌��ʁC�����̐X�я��L�����ԓI�ȊǗ�������Ă��������L�̋��L�n�Ɩ��L�n�ō\������Ă������ƁC�d�Y�ނ͂قƂ�Ǔ����Ŏ������Ă������ƁC���ӂ̓��֊����⌌���҂ւ̎x����ړI�Ƃ��Ĉڏo���Ă������Ɠ������炩�ƂȂ����B |
|
| 2017 |
29 |
�E |
�Q���A�R������ ���u����̂܂��Ȃ�:��炵�̒��̖������A�����A�����̖����j�v���u�{�[�_�[�C���N�v���犧�s����B
|
�͂��߂Ɂ@6
���́@����
���́@(1)�@���c����������݂��������@12
���́@(2)�@�n�k���N�������@14
���́@(3)�@�����鎞�@16
���́@(4)�@�Ύ����N�������@19
���́@����̃����k�L����
���́@(1)�@�Ί��c(��������Ƃ�)�@22
���́@(1)�@�y�R�����z�A�W�A�̐Ί��c�@35
���́@(1)�@�y�R�����z�u���W���̐Ί��c�@38
���́@(2)�@�V�[�T�[�@43
���́@(3)�@�t�[�t�_(���D) ���~�A�֏��A�䏊�Ȃǁ@50
���́@(3)�@�y�R�����z�}�X�@����
�@�@��(���イ���イ�ɂ���傤)�@64
���́@(4)�@�L(�V���R�K�C�E�X�C�W�K�C�Ȃ�)�@82
���́@(5)�@�Q�[��(�T��)�@85
���́@(6)�@�q�W���C�i�[(����)�@88
���́@(7)�@���E�C���@90
��O�́@��炵�Ƃ܂��Ȃ�
��O�́@(1)�@�u�����u��(�V�r�����J)�v-�V�z�Ɖ��̂܂��Ȃ��@93
��O�́@(2)�@�n�u�����@101
��O�́@(3)�@���Q�����@108
��O�́@(4)�@���(�����)�ƉJ��@114
��O�́@(4)�@�y�R�����z��ƉJ�@125 |
��O�́@(5)�@���̂܂��Ȃ��@127
��O�́@(6)�@���{���Ɓu�\������v�@134
��O�́@(6)�@�y�R�����z�u���o��(�Ƃ�������)�v��
�@�@���u����o��(���邩������)�v�@140
��O�́@(7)�@�u���̂��炢�v�@145
��l�́@�a���ƎY��̂܂��Ȃ�
��l�́@(1)�@�D�P�E�o�Y�@151
��l�́@(2)�@�E��(����)�̏����@154
��l�́@(3)�@���t���Ɠ�n�@157
��́@���E���E��̂܂��Ȃ�
��́@(1)�@���Ƒ��@162
��́@(2)�@�E�e�B���W�J�r�@166
��́@(3)�@��̖������@176
��́@(4)�@�u�撆��(�ڂ��イ��)�v�@183
��Z�́@�������߂��镶����
��Z�́@(1)�@�������ꂽ�����̂��ӂ��@192
��Z�́@(2)�@�����́u���D�v�@196
��Z�́@(3)�@�h��������(���݂傤�炢��)�@200
��Z�́@(4)�@�㎚(�Օ����ҊF��ݑO)�@207
�t�� �G�b�Z�C
(1)�@���哇��焎ו�(�ւ�����Ԃ�)�ƒ��(������)�@212
(2)�@���̂Ɍ�����u�D�v�@218
���Ƃ����@226
��ȎQ�l�����@234 |
�R���A�u���ꌤ���m�[�g�@26�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B�@ �iIRDB�j
|
�V��̃R�X�����W�[�F�Ñ���{���w�Ɍ���F���ςƂ̔�r �������V�@ p.1-24
�{�ÁE���d�R�����Ɋւ���o�� ���ђ��� p.25-40 |
���d�R�����ɂ����鉓�����ʍk��
�@�@���ւ��錤������ �y���� p.41-45
|
�R���A�{�����W���u Asia Japan Journal = AJ Journal = AJJ = �A�W�A�E���{�����Z���^�[�I�v 12 p.37-50�@���m�ڑ�w�A�W�A�E���{�����Z���^�[�v�Ɂu���������ɂ�����J��Ɠ���
: ���]�I�v�f���݂��Ȃ����R�ɂ��āv�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�����������u���m��w����w�������� 77�@ p.149-178�v�Ɂu�c�ӏ��Y�̉���E���d�R�������y���n�����i1922�N�j-�u�i���ꌧ���|�p��w�����}���ٓ��j�c�ӕ��Ɂv����b�����Ƃ���- �v�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�����q���u���獑�j�Ɖ���w�̎��� : �����ÓT�̒T���҂����v���u�X�b�Ёv���犧�s����B�@
�@�@�@�@289p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1008340463
|
�P�@���獑�j�̎d���i�l���ƌ����̋O�ՁG�w�����낳�����x�����G�g�̂̊y���|�����ÓT���y�쑺���Ɛ��獑�j�́u���y���v�G
�@�@���펞���̗����_�������G���̎��W�w���U�̂����x�����߂āj
�Q�@�V������w�h�Ƃ��̎��Ӂi���ܑS���Ɣ�Ð��́G�ɔg���Q�ƐV������w�h�G�{��^���ƐV������w�h�G����d�N�̕�����ǖ@�j
�R�@�����ҁi�{��^�����e�|���|�u�w�����낳�����̓ǖ@�@�W�ǖ@�̌����x�ɑ���ڌ��v�G���獑�j�W�N���G���獑�j����ꗗ�j
���獑�j�W�N��: p237-248�@�@���獑�j����ꗗ: p249-253�@�@�Q�l�����ꗗ:
p260-271 |
�S���A�{�����W�� �w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 50(2) (�ʍ� 120) p.19-47�@��㊕�������v�Ɂu���������ɂ�����s�V�}�N�T���V�V��t�̗���Ɋւ��錤��
: ���̔N���s���Ƃ̔�r�Ǝ��݂��Ȃ����x�̈Ӗ��v�\����B
�S���A�u���{�@趎� = The Journal of Kokugakuin University 118(4) (�ʍ� 1320) �i���W ���{�����w�̓W�]��� : �`�����w��U�J�ݓ�\���N�L�O)�v���u���w�@��w�v���犧�s�����B
|
���{�����w�ƚ��{�@��{ : ���j�Ɠ`���Ɋw�і����ւƂȂ� �@�V�J���I �@ p.1-73
�܌��M�v�̖����w : ���c���j����̎��� �@���쒼�V p.74-95
�F�V�h�O�̖����w : ���̕��@�Ɖ\���@�Ί_�� p.96-111
�����{�����w���_�������� : ��㎵�Z�N��O��̔��Ȃ̕����𒆐S�� �����W p.112-123
���x�o�ϐ����Ɩ����w �@�֑�܂�� p.124-140
�K�Ƃɂ��� �@�@��Αוv p.141-152
���҂Ɛ��҂����ԎP�g : �O�d���u���s�剤���g��(�Ȃ���)�̐V�~�s������ �@������C�� p.153-170
�g�|�X�Ƃ��Ẳˋ��`���@�@�ԕ��p�Y p.171-184
�̘b�u�ׂ̐Q���Y�v�Ɩ� �@�����a���q p.185-197
�`���L�[�p�[�\���ƍ՚��q : �����s��c��A�_�ސ쌧���s�𒆐S�Ɂ@���v�� p.198-210
�������|�����͂Ȃ��u�^���I�Ȑ��v�ƌ��������Ȃ��̂��@�ёq�`�V p.211-223 |
�@�@�@�@���Q�l�F���{�����w���_�������� : ��㎵�Z�N��O��̔��Ȃ̕����𒆐S��
�����W
�@�@�@�@��L�_���̖����Ɂu���{�����w���@��T���`�X�W���v���̉���Ɋւ���L�q������܂����B�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�R�O�@�ۍ�
�T���A���j�Ȋw���c��ҁu�m���Ă����������j�̐V�펯�v���u�א��o�Łv���犧�s�����B
|
�C��ϓ��_�̌��� / �c������
�����̗�㉤���̖��O�͂ǂ����܂����� / �����Ζ�
���j�w�҂̉c�� �钷�A�w���ڎO��i�x��T�� / �g�c�x�V
���j����̍��ۉ��ƘA���� / �V���ꐰ
��j����̃l�b�g���[�N�ƕ����� / �R�{�F��
�o�_�̌Ñ�j���ǂ��Ƃ炦�邩 / �X�c��v�j
�Ñ���{�̍��ێЉ�ւ̎Q�� / �x��O
|
�����Y�K���X�e��͂ǂ̂悤�ɂ��ē��{�ɂ����炳�ꂽ�� / �J�ꏮ
�Ƒ嗤�����ԓ쓇�j / �R������ p36-39p
�㐢�I���{�ɂ�����V���l�f�B�A�X�|�� / �A�~��
���́v���Ȃ��Ɩk���Љ� / �����h�I
�����m�̗����x�����h���{�� / �͖�۔�
�q�ȉ����r
�E |
�U���A�������ۑ��S�����c��ҁu�������ۑ�70�N�̗��j : �����ւ̕�����Y�v���u�V��Ёv���犧�s�����B�@�d�v
|
�͂��߂Ɂ@3
I�@�������ۑ��̌���Ɖۑ�@���}���D�F�C���g�͌����@11
II�@�ۑ��^���̗��j�ƓW�]�@61
II�@1�@�������ی�@�̐����ƌ��̗Õ��@��؏d���@62
II�@1�@<�R����>�o�C���-���l�Êw�̏o���_�@���g�͌����@81
II�@1�@<�R����>��h���-�펯�����������A���j��������������Ձ@�������v�@84
II�@2�@��㕜���ƃC�^�X�P�Õ��@�{��k�X�X���l�@87
II�@2�@<�R����>��x�L��-���x�����ɖ|�M���ꂽ��Ձ@���{�P�Y�@109
II�@2�@<�R����>�����؋����-���x�������̈�Ւ������Î������鎖���@�����F���@112
II�@3�@���x�o�ϐ����ƕ���{�Ձ@���c�`�@115
II�@3�@<�R����>�c�\���-�ŏ��̖퐶�؊���@�Ζ씎�M�@135
II�@3�@<�R����>���]���L��-����L�˂����鑺���ۂ��ƕۑ��@���q����Y�C����W��@138
II�@4�@�Z���^���̍��g�ƒr��]����Ձ@�Ε����u�@141
II�@4�@<�R����>�ےÉ��Έ��-�퐶����W���̒����E�ۑ��Ɖ��ٔ��@�X���G�l�@160
II�@4�@<�R����>�����j���[�^�E����ՌQ-�L�^�ۑ��ɓO������ՌQ�@�V�c�G���@163
II�@5�@�������i�ׂƈɏ��Ձ@�Ŗ��T���Y�@167
II�@5�@<�R����>��g�{��-��s�s�ɂ�݂����������{�̕ۑ��Ɗ��p�@�ώR�m�@185
II�@5�@<�R����>�؈��-���{�C���������̒��S�W���Q�@��������@188
II�@6�@������ʖԂ̐����Ɨ��R��Ձ@���{�����@191
II�@6�@<�R����>�ˌ��Õ��Q-�g���l���H�@�ŌÕ��Q���c���@��؏d���@206
II�@6�@<�R����>�O�c��I���-�Õ����㍋�����ق̔����@�����a�u�Y�@209
II�@7�@�V�����s���^���Ɠc�a�R��Ձ@�c���`���@212
II�@7�@<�R����>�g�샖����ՌQ-���c���j�����̖��ƈÁ@�R���`���@237
II�@7�@<�R����>�h��E�_�����-�ۑ��^���Ŏc�����������R���̕��R��@�������T�@240
II�@8�@�����I�i�ςƐ��E��Y�@�ї��a�Y�@243
II�@8�@<�R����>�ۂ̉Y-�i�ςƈ��S�E���S�Ȑ����̗������߂����ā@���{���v�@259
II�@8�@<�R����>������V�䏊���-�ۑ��Ǝ����̗������߂����ā@���ԓc��v�@262
II�@9�@��k�Ќ�̕������~�������ƍЊQ��\�̕ۑ��@�e�n�F�N�@265
II�@9�@<�R����>�_�ˍ`�k�Ѓ������A���p�[�N-��_�E�W�H��k�Ђ̒ܐՁ@�X���G�l�@286
II�@9�@<�R����>���ă������A���p�[�N-�V�������z�n�k�ɂ�����k�Ј�\�@�}�g����@289
II�@10�@��㎵�Z�N�Ɛ푈��Ձ@�e�r���@292
II�@10�@<�R����>�����h�[��-�l�ގj��ŏ��̊j�푈�̏؋��@�\�H�x���@309
II�@10�@<�R����>��-��Ђ����݂����������������̏�@�c���k���@312
III�@�������ۑ��S�����c��̕��݁@315
III�@1�@�������ۑ��S�����c��̌����@�\�H�x���@316
III�@2�@�������ۑ��S�����c��̊����L�^�@�ؑ��p�S�C�v���m�m�C���c�`�C�\�H�x���@325 |
�X���A������w�l���Љ�w���ҁu�l�ԉȊw : ������w�l���Љ�w���l�ԎЉ�w�ȋI�v
= Human sciences : bulletin of Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of the Ryukyus, Department of Sociology and Human Sciences (37) �R�����ꋳ���ސE�L�O���v���u������w�l���Љ�w���v���犧�s�����B
|
�R�����ꋳ���̐l�ƋƐ� �@����O�� p.1-12
�k鰍F�����̏����ȂƗ��z�J�s(7)�@�������̏����Ȋ��ւ̔C���ɏœ_�Ăā@�@�����x�O
p.13-70
10���I����E11���IThorney�C���@���̂̌`���Ɠy�n�i�� �@�{��O 9 p.71-101
����E����ɂ�����A�����J�m���l�̃O�A���F�� : �u�G�X�j�b�N��茤����(IEA)�v�̌��_������f�ނƂ���
�@�r���S p.103-131
����E���O�̃y���[�ɂ�������{�l���Ǝґg���̐ݗ��@�@���c�@�� p.133-153
����{���R���̉~���J���X�g�R���t�߂ɕ��z����s�i�N���\�ʂ̔��n�` : ����ɂ�����mm�I�[�_�[�̔�j��v��)�@�A���F,ꠖ{�� p.155-168
�����o�y�̊��ΐ��Γ�j�Ђɂ��ā@�@�r�c�Ďj p.169-188
�����w�ҁE���c���j : ���k��u�����w�̉ߋ��Ə����v(1948)�𒆐S�Ɂ@���
p.189-260
��p�S�펞�㌤���Ɨ����� �@�㓡��F p.261-280
������������(1)�������C�_�Ղ𒆐S�Ɂ@�_�J�q�� p.281-304
�V���^�C�i�[�ƃt�����N�� : ���ƕs�����߂����ā@���Ήx�� p.305-334
���c�ϗ��w�́u���Չ������v�̍����t��������c�_ : �_�Ɣᔻ�̊T�ρ@�v�����W
p.335-364 |
�X���A�����v�X,���n��,����T�M���u���ꌧ���d�R�S�|�x���g�Ɗԁ@���c���L�ˏo�y�i�W�v���u���ꌧ�������������Z���^�[�v���犧�s����B�@�@�@�@�@�����Q�X�N�x�@���ꌧ�������������Z���^�[�ړ��W
�X���P���`�X���P�O�����A�u�Ί_�s�����d�R�����فv�ɉ����āu���ꌧ���d�R�S�|�x���g�Ɗԁ@���c���L�ˏo�y�i�W�v���J�����B
�X���P�T���`�X���P�V�����A�u�|�x�����g�ƊԌ����فv�ɉ����āu���ꌧ���d�R�S�|�x���g�Ɗԁ@���c���L�ˏo�y�i�W�v���J�����B
�X���P�U���P�X������A����T�M���u�g�ƊԔ_���W���Z���^�[�v�ɉ����ĕ����u���u���c���L�˂̒����ɂ��āv�Ƒ肵���u�����s���B
�X���A���c�W, �R������, ���䍲�����u���d�R�E�Ί_���̓`���E�̘b. 2 (�o���E���E�Ί_�E�V��)�v���u�O��䏑�X�v���犧�s�����B
�@�@�i�����̓`����������� 4 �j�@�@ 170p �@�@�����F���ꌧ���}���فF1008549212
|
�Ί_�l�ӂ̗��j�ƕ�炵
�Ί_���̕��i
�l�ӂ̏W��
�l�ӂ̗��j
�l�ӂ̕�炵�Ɠ`��
�Ί_�l�ӂ̓`���E�̘b
1 ���d�R�̎n�܂�
2 �Ί_�l�ӂ̎n�܂�
3 �^���W��Ԃ̗R��
4 �V���Ԃ̗R��
5 ��̓`��
6 �r�b�`���R�̗R��
7 �`�B���i�[�J�[�̗R��
8 ��_���̍���
9 ���d�R�̎o���_
10 ���ׂ̐_�̉��Ԃ�
11 ���[���T�[(��G)�̉��Ԃ� |
12 ���n�Ղ̗R��
13 ��k���J���^�[�_�̗R��
14 �y���̊G�`���Ɛl��
15 �A�J�}���[�O�����B�̐l��
16 �c�N�O���ɖł��ꂽ��
17 ��͂ƃt�c�N�j�����B
18 �l����̗R��
19 �j�k�t�@���̗R��
20 �p�q�̔�����
21 �J�ɂȂ�����
22 �ΐ���
23 �Z��̒�����
24 ���̕���(��)�n�W�J�~�̗R��
25 ���̕���(��)�Y�䂪���ʗ��R
26 �����̗R��
27 �~�̏����R��
28 �E�`�J�r(�Ŏ�)�̗R�� |
29 �q��ėR��
30 �ؖ�����
31 �\�ܖ�̗R��
32 ���G��
33 ��̒m�b
34 �_���Ǝ��ɐ�
35 ���F�s(��)
36 ���F�s(��)
37 ���F�s(�O)
38 �J�^�s�F
39 �c�N�O���s�F
40 �^�L�k�n�C�Y�̕Е��R��
41 ���̐���
42 �H�킸���[(�Ζ�)(�Ӗ�)
43 �Z��̒�����(�Ζ�)
���Ƃ���
�E |
�X���A�g�Ɗԉi�q�i������w�j���u���{�̈�w����\�e�W 68(0) p.289-289�v�Ɂu�����ÓT���x�ɂ�����u��v�̋Z�@:���A�W�A�̕��x�Ƃ̔�r���߂����āv�\����B�@�@
�P�O���A�u�I�L�i���O���t (667) p.33-37�@�V���o�Łv�Ɂu���̂���ۓ�(��130��)�����i�r�B���[�h : ������35�N�̕��݁v���f�ڂ����B
�P�Q���A�V���F�a,�Ő�����������w�_�w���ҁu������w�_�w���w�p�� (64) p.55-63�v�Ɂu����E�ɕ������c���̃E���W���~���J�̍��J���Ƃ��ẴK�W���}���v�\����B�@�iIRDB�j�@�@�d�v
�P�Q���A�����k�~���u�Ñ㕶�� = Cultura antiqua 69(3) (�ʍ� 610) p.427-432�@�Ñ�w����v�Ɂu�l�Êw�l���L : �]�` �����{�̍l�Êw���x�����n�挤����(15)���a�c���~�Ɨ����l�Êw�ҔN�v�\����B
���A���̔N�A�������j���������ٕҁu�u���������w�v�̒��� : �ٕ���Z�������̍őO���v���u�g��O���فv���犧�s�����B�@�d�v
�@�@-�V���|�W�E���u�������Ȃ���w�Ɣ����� :�w�����z�A�N�Z�X���f���x�̍\�z�ɂނ���
�v
�@�@ (2016�N2��27��:�t�N���V�A�����X�e�[�V����5�K��c��H�@, �������j���������َ��)
�̋L�^�W
|
�{�_�W�̎�| / ���J�厷�M
���������w�̑n���ɂނ��� / �v�����_���M
�u�n��̊w�p�����̕����v�Ƒ��������w : �����{��k�Ђɂ����鎑���ۑS�����̑̌�����
/ �O���F���M
���(1945-1953)�̉���̔����قÂ��� : �������W�͂����ɍs��ꂽ�� / ���������M
���������w�̎˒��Ə���� / �㓡�^���M
���s��w���������A�[�J�C�u�ɂ����錤���������̋��L / �ܓ��q�F, �˓c�����Y���M
�R���s���[�^�[�ɂ�鎞�ԏ��̋L�q�Ɗ��p / �֖�����M
������w�j���Ҏ[���̕Ҏ[�Ƃ��̎��ƂɂƂ��Ȃ��f�[�^�x�[�X / �R�c�������M
�u�Ñ�̕S�ȑS���v�Ƃ��Ắw���쎮�x : �ٕ��삩��́w���쎮�x�����̕���
/ ���q���i���M
�����َ����𑽊p�I�ɓǂ� : ���i�ʐ^������� / �R�G�v���M
�����̎��R�Ȋw���� : �y��t�����Ɩ������� / �a�J���q���M
�����̐F�t : �l���Ȋw�Ǝ��R�Ȋw����݂��]�ˎ���̐E�l�Z / �V���w���M
���������w�̖������l���� : �p�l���f�B�X�J�b�V�������� / ���J�厷�M |
���A���̔N�A�X�c�^��,��c�����u�}�����w����w�l�ԕ����������N�� = Annual report of the Humanities Research Institute, Chikushi Jogakuen
University (28) p.1-14�v�Ɂu �t�F���X��������G�C�T�[ : ��㉫��ɂ����閯���|�\�̕����ƕČR��n�v�\����B
���A���̔N�A��c��,�X�c�^�炪�啪�����|�p�����Z����w�ҁu�啪�����|�p�����Z����w�����I�v
55 p.63-90�v�Ɂu�I�X�v���C�ƃG�C�T�[ : ��㉫��ɂ����閯���|�\�̂Ђ낪��ƕČR��n�v�\����B
���A���̔N�A����s�ό����Y�U������G�C�T�[�ƕҁu����s �G�C�T�[�K�C�h�u�b�N[���[�t���b�g]
�v���u����s�v���犧�s�����B
���A���̔N�A �R�����炪���ꌧ���|�p��w���E�ے��ψ���ҁu���E�ے��N�� 2(2)
2017 p.234-245�@���ꌧ���|�p��w�v�Ɂu�����ÓT���y�u������ŕ��߁v�̕\���@�ƕ��� : �u���t�̎�����H�H�l�v�Ɓu���y���K�p�y���v�̍\�z�v�\����B |
| 2018 |
30 |
�E |
�R���A�^�_�����ҏW�ψ���ҁu�^�_���� : �ǘ^�Łv���u(��������)�^�_������ψ���v���犧�s�����B�@
|
�O���r�A(�^�_���Љ�)
�����̂��Ƃ@�^�_���� �R���@�@(22)
�͂������@�^�_�����ǘ^�ŕҏW�ψ���ψ��� �������O�@(24)
�w�^�_���� �ǘ^�Łx�ҏW���j�@(28)
�}��@(29)
���ҁ@�T��
���ҁ@���́@���R���@3
���ҁ@���́@���߁@�^�_���̎��R���@5
���ҁ@���́@���߁@��@�C����@5
���ҁ@���́@���߁@��@�n�`���@10
���ҁ@���́@���߁@�O�@�n���@10
���ҁ@���́@���߁@�l�@�W�I�p�[�N�\�z�@14
���ҁ@���́@���߁@�܁@���R�ЊQ�@16
���ҁ@���́@���߁@���̐A���@20
���ҁ@���́@���߁@��@�A���T���@20
���ҁ@���́@���߁@��@�ʐA���̏@22
���ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�f�w�R�̐A��
���ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�C�݂̍��n�y�эD�ΊD��A��
���ҁ@���́@���߁@��@(�O)�@���~�E�H�T�y�эk������n�E���n�E���n
���ҁ@���́@���߁@��@(�l)�@�ݗ��A��������������O���A��
���ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�C�݂ɕY������ʎ��E��q
���ҁ@���́@��O�߁@���̓����@30
���ҁ@���́@��O�߁@��@�^�_���̗����ނƗ�������ށE�M���ށ@30
���ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@������
���ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@�������
���ҁ@���́@��O�߁@��@(�O)�@�����M����
���ҁ@���́@��O�߁@��@(�l)�@�����炢�Ȃ��Ȃ�������������
���ҁ@���́@��O�߁@��@�Q�l�����@38
���ҁ@���́@��O�߁@�O�@�^�_���̒��ދy�ђ��ށ@40
���ҁ@���́@��O�߁@�O�@(��)�@�^�_�̒���
���ҁ@���́@��O�߁@�O�@(��)�@�^�_�̒���
���ҁ@���́@��O�߁@�l�@�^�_���̃G�r�E�J�j�y�уA��(�a)�@46
���ҁ@���́@��O�߁@�l�@(��)�@�G�r�E�J�j
���ҁ@���́@��O�߁@�l�@(��)�@�A��(�a)
���ҁ@���́@��O�߁@�܁@�^�_���Ύ��L(���b���Z�Z�O)�@46
���ҁ@���́@��O�߁@�Z�@��ƒ��̑唭���Ə��ł̋L�^�@53
���ҁ@���́@��O�߁@�Z�@(��)�@�L�I�r�G�_�V���N�̑唭��
���ҁ@���́@��O�߁@�Z�@(��)�@�I�I�S�}�_���̏���
���ҁ@���́@��l�߁@�C�̓��A���@56
���ҁ@���́@��l�߁@��@�^�_���̋��ށ@56
���ҁ@���́@��l�߁@��@�T���S�ʂ̌���ƕۑS�@59
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@�͂��߂�
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@�^�_���̃T���S�ʂ̌���
���ҁ@���́@��l�߁@��@(�O)�@�T���S�c���������ɂ��T���S�Đ�����
���ҁ@���́@��l�߁@��@(�l)�@�C�E���E�l�̎O�{���ɂ��ۑS����
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@�u�C�v�ɂ�����ۑS����
���ҁ@���́@��l�߁@��@(�Z)�@�u���v�ɂ�����ۑS����
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@�u�l�v�ɂ�����ۑS����
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@����̉ۑ�
���ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@������
���ҁ@���́@�Љ���@69
���ҁ@���́@���߁@�^�_���̐l���̐��ځ@69
���ҁ@���́@���߁@��@�l���̐��ځ@69
���ҁ@���́@���߁@��@�l�������̔w�i�@70
���ҁ@���j
���ҁ@�͂��߂Ɂ@81
���ҁ@���́@�^�_���̐�j����@82
���ҁ@���́@���߁@�^�_���n���̐_�b�@82
���ҁ@���́@���߁@�l�Êw��̗^�_���@83
���ҁ@���́@���߁@��@��j�ȑO�̗^�_�@83
���ҁ@���́@���߁@��@�^�_���̈�Ո╨�̏@84
���ҁ@���́@���߁@�O�@�q���J�̐Ε��@90
���ҁ@���́@���߁@�l�@�l�X�̕�炵�@93
���ҁ@���́@�Ñ�@95
���ҁ@���́@���߁@�^�_�̌Ñ�@95
���ҁ@��O�́@�����@97
���ҁ@��O�́@���߁@�^�_���̔_�k�ƏW���̌`���@97
���ҁ@��O�́@���߁@�^�_�O�X�N�̐����@101
���ҁ@��O�́@��O�߁@�i�Ɛ_���g�D�@106
���ҁ@��l�́@�^�_�̋ߐ��Љ�@115
���ҁ@��l�́@���߁@�F���̑㊯���x�ւ̈ڍs�@115
���ҁ@��l�́@���߁@��Ƃ̌n�}���猩��ߐ��Љ�@118
��O�ҁ@����
��O�ҁ@���́@���a���E��������@131
��O�ҁ@���́@���߁@�T�ρ@131
��O�ҁ@���́@���߁@��@�^�_���̉��i�Ǖ�������̕����@131
��O�ҁ@���́@���߁@��@���a���@132
��O�ҁ@���́@���߁@�O�@��������@132
��O�ҁ@���́@���߁@�O�@(��)�@�o����
��O�ҁ@���́@���߁@�O�@(��)�@�l������
��O�ҁ@���́@���߁@�O�@(�O)�@���q��
��O�ҁ@���́@���߁@�O�@(�l)�@�Α���Ƒ������̕ϗe
��O�ҁ@���́@���߁@�s���@�\�@134
��O�ҁ@���́@���߁@��@�s���@�\�̉��p�ƐE�����̏@134
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�s���@�\�̉��p��(��������)
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�s���g�D�̉��p��(����ψ���W)
��O�ҁ@���́@���߁@��@(�O)�@�E�����̏�
��O�ҁ@���́@���߁@��@���݂̒����̊T�v�@137
��O�ҁ@���́@��O�߁@�ߔN�ɂ����������(������\���N�x �����v��)�@139
��O�ҁ@���́@��l�߁@�c��W�@146
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@�c��\���@146
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@���̑��̋c��̓����@150
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@���c�Ƃ̈ӌ�������̊J��
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@���i�Ǖ��E�^�_�n��c��c�����̊J��
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@(�O)�@�����Q���c��c�����̊J��
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@(�l)�@���傤�c����̔��s
��O�ҁ@���́@��l�߁@��@(��)�@��㎖���ǒ�
��O�ҁ@���́@��l�߁@�O�@���c��c���@152
��O�ҁ@���́@��ܐ߁@���R�ЊQ�̔����y�ёΉ��@153
��O�ҁ@���́@��ܐ߁@��@�䕗�W�@153
��O�ҁ@���́@��ܐ߁@��@���W�@153
��O�ҁ@���́@��ܐ߁@�O�@�n�k�W�@153
��O�ҁ@���́@��Z�߁@�����{�s�L�O���Ɓ@154
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@�����{�s�O�Z���N�L�O���Ƌy�эs���@154
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(��)�@�L�O����
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(��)�@�L�O���T�y�ёO���
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(�O)�@���ӏ�y�ђ������J�ҕ\��
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(�l)�@�L�O�_���E�앶�̗D�G�ҕ\��
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@�����{�s�l�Z���N�L�O���Ƌy�эs���@156
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(��)�@�L�O����
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(��)�@�L�O�s��
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(�O)�@�L�O���T
��O�ҁ@���́@��Z�߁@��@(�l)�@���ӏ�y�ђ������J�ҕ\��
��O�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@�����{�s�܁Z���N�L�O���Ƌy�эs���@158
��O�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(��)�@�L�O����
��O�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(��)�@�L�O���T
��O�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(�O)�@���ӏ�y�ђ������J�ҕ\��
��O�ҁ@���́@�掵�߁@�ߔN�ɂ�����I���̏�(������\���N�x �����v��)�@161
��O�ҁ@���́@�攪�߁@�x�@�E���h�E�@���ǁE�o��@�ցE���̑��@162
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@�x�@�@162
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@(��)�@���ݒn
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@(��)�@�E�ӂɂ��E����
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@(�O)�@�����E���̂̔�����(������\�Z�N)
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@(�l)�@���a������̗��h�o����
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@(��)�@���̑�
��O�ҁ@���́@�攪�߁@��@���h�c�@163
��O�ҁ@���́@�攪�߁@�O�@�@���ǁ@165
��O�ҁ@���́@�攪�߁@�l�@���i�Ǖ��^�_�n��L�掖���g���^�_�������@166
��O�ҁ@���́@�攪�߁@�܁@�哇�x�����i�Ǖ����������������ۗ^�_���݁@166
��O�ҁ@���́@�攪�߁@�Z�@�哇�x�����i�Ǖ��������_�ƕ��y�ۗ^�_���݁@167
��O�ҁ@���́@�攪�߁@���@�����������ƒ{�ی��q�������V���x���^�_���݁@167
��O�ҁ@���́@�攪�߁@���@�哇�x�����i�Ǖ����������݉ۗ^�_���݁@167
��O�ҁ@���́@���߁@��v�{�݈ꗗ(������\���N�x �����v��)�@168
��O�ҁ@���́@��\�߁@����v�������@169
��O�ҁ@���́@��\�߁@��@����ψ����@169
��O�ҁ@���́@��\�߁@��@�I���Ǘ��ψ����@169
��O�ҁ@���́@��\�߁@�O�@�_�ƈψ���@169
��O�ҁ@���́@��\�߁@�l�@�č��ψ��@170
��O�ҁ@���́@��\�߁@�l�@(��)�@�����ψ�
��O�ҁ@���́@��\�߁@�l�@(��)�@�c��I�o�ψ�
��O�ҁ@���́@��\�߁@�܁@�_�Ƌ����g�����@170
��O�ҁ@���́@��\�߁@�Z�@���Ƌ����g�����@171
��O�ҁ@���́@��\�߁@���@�Љ�����c��@171
��O�ҁ@���́@��\�߁@���@�^�_�X�ǒ��@171
��O�ҁ@���́@��\�߁@��@���˗X�ǒ��@171
��O�ҁ@���́@��\�߁@�\�@�ߊԊȈX�ǒ��@172
��O�ҁ@���́@��\�߁@�\��@�̈狦��@172
��O�ҁ@���́@��\�߁@�\��@���H��@172
��O�ҁ@���́@��\�߁@�\�O�@���������ό�����@172
��O�ҁ@���́@��\�߁@�\�l�@���a�����猻�݂̗��撷�E���������ْ��@172
��O�ҁ@���́@��\��߁@�S���Ŋ���^�_��@173
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@�c��ՎR�@173
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@�喴�c�E�r���@179
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@���S���^�_���@185
��O�ҁ@���́@��\��߁@�h�ꂽ���������@186
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@���{�y�ь��̗v���@186
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@�����\�O�N�@186
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@(��)�@���̗v��
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@(��)�@�^�_�������������ݒu
��O�ҁ@���́@��\��߁@��@(�O)�@�^�_�����������ψ����ݒu
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@�����\�l�N�@187
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@(��)�@���̗v��
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@(��)�@���i�Ǖ��E�^�_�n�捇���������ݒu
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@(�O)�@���̍��������y�шӌ�����
��O�ҁ@���́@��\��߁@�O�@(�l)�@�W�����Ɠ�������E�ӌ�����
��O�ҁ@���́@��\��߁@�l�@�����\�ܔN�@190
��O�ҁ@���́@��\��߁@�l�@(��)�@�C�Ӎ������c���ݒu
��O�ҁ@���́@��\��߁@�l�@(��)�@�@�苦�c��Q���ŗh���
��O�ҁ@���́@��\��߁@�l�@(�O)�@�@�荇�����c���ݒu
��O�ҁ@���́@��\��߁@�l�@(�l)�@�Z�����[���𐧒�
��O�ҁ@���́@��\��߁@�܁@�Z�����[�����{�@194
��O�ҁ@���́@��\��߁@�Z�@�Z�����[�̌��ʁ@195
��O�ҁ@���́@��\��߁@���@���{�̍�������̌��ʁ@195
��O�ҁ@���́@��\�O�߁@�^�_������NPO�@�l�@196
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�ӂ邳�Ɣ[�ŏ@199
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@��@���������T���S�ʊ���̎��Ɠ��e�@199
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@��@�{���̎��[�@199
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�O�@�[�����Ɓ@200
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�l�@�e�n�̔[�ŏ@200
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�܁@�哇�n��̂ӂ邳�Ɣ[�Ŏg���݂��ꗗ�@201
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�Z�@�[�Ŏ҂ւ̕ԗ�i�@202
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�Z�@(��)�@���������̕ԗ�i�x�X�g5
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@�Z�@(��)�@�^�_���̕ԗ�i
��O�ҁ@���́@��\�l�߁@���@����̎�g�ƓW�]�ɂ��ā@203
��O�ҁ@���́@�ی��q���E��ÁE�Љ�����@204
��O�ҁ@���́@���߁@�ی��q���@204
��O�ҁ@���́@���߁@���N����21�@204
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@���N�Ղ�
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@���茒�f��f�������(���ەی��w������)
��O�ҁ@���́@���߁@(��)�@(�O)�@�A���R�[�����̕���E�𗬉�̊J��
��O�ҁ@���́@���߁@��Á@205
��O�ҁ@���́@���߁@��@��ÊW�@�ց@206
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@��Ö@�l���꓿�F�� �^�_���F��a�@
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@��Ö@�l���F��p�i�E���f�Ï�
��O�ҁ@���́@���߁@��@(�O)�@��Ö@�l��������N���j�b�N
��O�ҁ@���́@���߁@��@(�l)�@���ʎ��Ȉ�@
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�^�_���ܖ��
��O�ҁ@���́@���߁@��@�~�}�����@207
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�~�}�����̏�
��O�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�����h�N�^�[�w��
��O�ҁ@���́@��O�߁@�Љ���@209
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@����ҕ����@209
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@���ی����x����
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@�n���P�A�V�X�e���ƐV������������
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@�Ⴊ���ҕ����@212
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@��Q�Ҍv��
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@��l���^�_����Q�ҕ����v��
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(�O)�@�n�掩���x�����c��
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(�l)�@�^�_���w����葊�k����
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@�哇�{��w�Z�̖K�⋳��J�n
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(�Z)�@��Q�ҍ��ʉ����@
��O�ҁ@���́@��O�߁@��@(��)�@���_��Q�҉Ƒ��̉�(�����̉�)�̂����
��O�ҁ@���́@��O�߁@�O�@���������@216
��O�ҁ@���́@��O�߁@�O�@(��)�@�F�肱�ǂ���
��O�ҁ@���́@��O�߁@�O�@(��)�@�^�_���È�Z���^�[�ق̂ڂ�
��O�ҁ@���́@��O�߁@�O�@(�O)�@�q��Ďx������
��O�ҁ@���́@��O�߁@�l�@�Љ�����c��@217
��O�ҁ@���́@��O�߁@�l�@(��)�@�Љ�����c��̐ݗ�
��O�ҁ@���́@��O�߁@�l�@(��)�@���v
��O�ҁ@���́@��O�߁@�l�@(�O)�@������\���N�x(��Z��Z)����
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@���E�����W�̎{�݁E�c�́@220
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(��)�@�^�_���n�敟���Z���^�[
��O�ґ��͑�O�ߌ�(��)�@�Љ���@�l�n������������n���������������Z���^�[
��O�ґ��͑�O�ߌ�(�O)�@�Љ���@�l�n��������������ʎq��Ďx���Z���^�[
��O�ґ��͑�O�ߌ�(�l)�@��Ö@�l������ ���V�l�ی��{�� ���ԉ�
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(��)�@��Ö@�l���꓿�F�� �O���[�v�z�[������
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�Z)�@�Љ���@�l���S�� ���@�\�^���Ə� �G�a��
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(��)�@�Љ���@�l���S�� �P�A�z�[��������
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(��)�@NPO�@�l����ǂ���
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(��)�@�^�_������Ȃ��琬��
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\)�@�Վ���(������܂�)�̉�
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\��)�@�^�_�����ʎx������ی�҉�(�W���K�C���̉�)
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\��)�@����o�Y�q��ĉ���������܂��[��
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\�O)�@�R�w���@
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\�l)�@�|���I���@
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\��)�@�N���[�o�[�����@
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\�Z)�@�a�y���É@
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\��)�@�͂肫�イ�@ ���̘a
��O�ҁ@���́@��O�߁@�܁@(�\��)�@���ʐ����}�b�T�[�W�@
��O�ҁ@��O�́@���{�݂̌��݁@225
��O�ҁ@��O�́@���߁@�Α��ꌚ�݁@225
��O�ҁ@��O�́@���߁@��@�����̕ϑJ�@225
��O�ҁ@��O�́@���߁@��@�Α��ꌚ�݁@225
��O�ҁ@��O�́@���߁@�O�@�����\�l�N�^�_���c���������ʎ���@227
��O�ҁ@��O�́@���߁@�l�@�������������ْ����璬���ւ̗v�]�@228
��O�ҁ@��O�́@���߁@�܁@�ό���������̗v�]�@228
��O�ҁ@��O�́@���߁@�Z�@�Α��ꌚ�ݗ\��n���ӏZ���E�y�n���L�ґ�\�E
�@�@�@���������������ْ��E�鎩�������ْ��A���̗v�]�@229
��O�ҁ@��O�́@���߁@���@�Α���(������)�������ƌo�߂̊T�v�@229
��O�ҁ@��O�́@���߁@���@��n���i�̗l�ς��@231
��O�ҁ@��O�́@���߁@��@�������@232
��O�ҁ@��O�́@���߁@�^�_�`�R�[�X�^�����]�[�g���݁@233
��O�ҁ@��O�́@���߁@��@�T���@233
��O�ҁ@��O�́@���߁@��@���Ƃ̕K�v���E�v�]�@233
��O�ҁ@��O�́@���߁@�O�@�\�Z�E���Ɩʐϓ��E�q��ʐ^�@234
��O�ҁ@��O�́@��O�߁@���������J���{�ݐ���(�C���W����)���Ɓ@237
��O�ҁ@��O�́@��O�߁@��@�������Ƃ̉��v�T�v�@237
��O�ҁ@��O�́@��O�߁@��@�^�_���㐅�������J���{�ݐ������ƌ×�
�@�@�@����C���W�����{�ݍH���@239
��O�ҁ@��O�́@��O�߁@�O�@�^�_�����錾�@239
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@���̑��̎�Ȏ{�݁@241
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@��@�n�敟���Z���^�[�@241
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@��@���T�C�N���Z���^�[�@242
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�O�@�����R�~���j�e�B�[�ف@243
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�l�@���i�Ǖ����h���^�_�������@244
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@�^�_���h�ЃZ���^�[�@245
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�Z�@�^�_���ی��Z���^�[�@246
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@���@���i�Ǖ��x�@���^�_�����h�o���@247
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@���@����O�̓��H�g���@248
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@��@�^�_���͔�Z���^�[�@249
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\�@���ʕ~�������u�Z���^�[�@251
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\��@�y��f�f�Z���^�[�@252
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\��@���������Y�i�x���Z���^�[�@253
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\�O�@�T�U���N���X�Z���^�[�@254
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\�l�@�^�_�\�ܖ�x�ۑ��ف@255
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\�܁@���ʑ̌��ف@256
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\�Z�@�ƒ{��@257
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\���@����v�C�݃R�e�[�W���@258
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\���@�Z��@259
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\���@(��)�@���c�Z��
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\���@(��)�@���c�F�a���c�n
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\���@(�O)�@���ؖ��Z��
��O�ҁ@��O�́@��l�߁@�\��@�Љ�̈�{�݁@260
��l�ҁ@�Y�ƌo��
��l�ҁ@���́@�T�ρ@263
��l�ҁ@���́@���߁@�����̎Y�ƌo�ς̊T���@270
��l�ҁ@���́@���߁@��@�^�_���̊T�ρ@271
��l�ҁ@���́@���߁@��@�^�_���̎Y�Ɓ@272
��l�ҁ@���́@���߁@�Y�ƕʓ��v�\�@274
��l�ҁ@���́@��O�߁@�����̐��ځ@280
��l�ҁ@���́@��O�߁@(��)�@�V�����Q���U���J�����Ƃ̐���
��l�ҁ@���́@��O�߁@(��)�@��O�������Q���U���J�����Ƃ̐���
��l�ҁ@���́@��O�߁@(�O)�@�����Q���U���J�����Ƃ̐���
��l�ҁ@���́@��O�߁@(�l)�@�����Q���U���J�����Ƃ̐���
��l�ҁ@���́@�_�Ɓ@293
��l�ҁ@���́@���߁@�����̔_�Ɓ@293
��l�ҁ@���́@���߁@���Ɓ@300
��l�ҁ@���́@��O�߁@�^�_�J�{�`���@310
��l�ҁ@���́@��l�߁@�ۈ��с@312
��l�ҁ@���́@��l�߁@��@�ۈ��т̊T�v�@312
��l�ҁ@���́@��l�߁@��@���̑��@314
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@�{�Y�@315
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@��@�^�_���̒{�Y�Ƃ̕ω��ƓW�]�@315
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@��@�^�_�����p�����i��J�Â̗��j�@320
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@�O�@�ƒ{���{�@322
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@�O�@(��)�@���p��
��l�ҁ@���́@��ܐ߁@�O�@(��)�@�R�r
��l�ҁ@���́@��Z�߁@�_�Ƌ����g���@323
��l�ҁ@���́@��Z�߁@��@�_�Ƌ����g���̕ϑJ�@323
��l�ҁ@���́@��Z�߁@��@���g�����@324
��l�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@�M�p���ƎO�\�N�̂���݁@325
��l�ҁ@���́@��Z�߁@�l�@�������ς̈ڂ�ς��@328
��l�ҁ@���́@��Z�߁@�܁@�̔����̈ڂ�ς��@329
��l�ҁ@���́@��Z�߁@�Z�@�w�����̈ڂ�ς��@331
��l�ҁ@���́@��Z�߁@���@�^�_���_���̉��v�@333
��l�ҁ@���́@��Z�߁@���@�_���̑��Ձ@334
��l�ґ��͑�Z�ߋ�@���������\�z�E�s������̎w���o�܂�JA�̎�g�o�߁@336
��l�ҁ@���́@�掵�߁@�_�Ƌ��ϑg���@337 |
��l�ҁ@���́@�攪�߁@�_���������̎��с@342
��l�ҁ@��O�́@���Ɓ@343
��l�ҁ@��O�́@���߁@�͂��߂Ɂ@343
��l�ҁ@��O�́@���߁@���Ɛ��Y�̌���@343
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@���Ƃ̏��`�ԁ@343
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@���D�̋K�͍\��
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@���[�t���O�̋������Y��
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(�O)�@��{�ނ苙��
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(�l)�@�\�f�C�J����������
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�p���I����
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@���Ƌ����g���̏@349
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@���Ƌ����g��
��l�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@��㋙�Ƌ����g����
��l�ҁ@��O�́@���߁@�O�@�������Ɓ@351
��l�ҁ@��O�́@���߁@�l�@�N���̗A���p�R���e�i�̓����@353
��l�ҁ@��l�́@�H�Ɓ@354
��l�ҁ@��l�́@���߁@�哇�ہ@354
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@���v�@354
��l�ҁ@��l�́@���߁@��@�哇�ې��Y�����̐��ځ@356
��l�ҁ@��l�́@���߁@�^�_�̏Ē��H��@358
��l�ҁ@��l�́@��O�߁@�d�Ɓ@359
��l�ҁ@��l�́@��l�߁@�V�G�l���M�[�@359
��l�ҁ@��l�́@��l�߁@��@�s���̎�g�݁@359
��l�ҁ@��l�́@��l�߁@��@���Ԃ̎�g�݁@360
��l�ҁ@��́@���Ɓ@363
��l�ҁ@��́@���߁@�^�_�����H��@363
��l�ҁ@��́@���߁@��@���v�@363
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@�Ǝ�ʕ��тɒn��ʉ����
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@���H�ƎҁE���H�����
��l�ҁ@��́@���߁@��@�g�D�@366
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@���
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@�ψ���
��l�ҁ@��́@���߁@��@(�O)�@�N���Ə�����(������\���N�x)
��l�ҁ@��́@���߁@��@(�l)�@������(������\���N�x)
��l�ҁ@��́@���߁@�O�@���ƊT�v(������\���N�x)�@367
��l�ҁ@��́@���߁@�O�@(��)�@�����I�T�v
��l�ҁ@��́@���߁@�O�@(��)�@�ނ炨��������
��l�ҁ@��́@���߁@�O�@(�O)�@�S���W�J�x������
��l�ҁ@��́@���߁@�O�@(�l)�@�n��������z���V���ƌ�������
��l�ҁ@��́@���߁@���Z�@370
��l�ҁ@��́@���߁@��@�����哇�M�p���ɗ^�_�x�X�@370
��l�ҁ@��́@���߁@��@�Ɨ��s���@�l�����Q���U���J������@371
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@���v
��l�ҁ@��́@���߁@��@(��)�@�o�����̊T�v
��l�ҁ@��Z�́@�ό��@373
��l�ҁ@��Z�́@���߁@���������ό��̕ω��ƌ��݂̊ό��@373
��l�ҁ@��Z�́@���߁@���������ό�����@376
��l�ҁ@��Z�́@���߁@��@�ό�����Z�Ώo���Ɣ�̓���@376
��l�ҁ@��Z�́@���߁@��@���ό�����@376
��l�ҁ@��Z�́@���߁@�O�@�ό������E���@376
��l�ҁ@��Z�́@��O�߁@�������p�i�E�������@377
��l�ҁ@��Z�́@��O�߁@��@��㍑��(����)�@377
��l�ҁ@��Z�́@��O�߁@��@���哝��(�ό����)�@377
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�������}���\���@377
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@���{�Ńz�m�����}���\�����@377
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@(��)�@���̒��
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@(��)�@�������}���\���̂˂����ƃ��b�g�[
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@���^�c�@378
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@(��)�@���S��ɖ��S��
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@(��)�@����(�����)�������}���\�����x���Z
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�O�@�������}���\���̉��v�@381
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�l�@���ÁE�㉇�E���͎x���̗ց@387
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�܁@�������@388
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�܁@(��)�@������
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�܁@(��)�@���s�ψ���
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�Z�@�������E���S�����E�T�[�r�X�G���A�ʒu�}�@390
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@�Z�@���@�������}���\���̃��b�Z�[�W�\���O�@391
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@���@���̋L�^�@392
��l�ҁ@��Z�́@��l�߁@��@�������}���\����g�@396
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�����@397
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@��@���������N�ʓ����q���̓����@397
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@��@�ό��֘A�{�ݐ����@399
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�O�@�h���{�݁@400
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�l�@�T�U���N���X�Z���^�[�@401
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�܁@���ʑ̌��ف@402
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@�����Ȍ��ǂ���@403
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(��)�@����C��
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(��)�@�g�D�}�C�̕l
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(�O)�@�E�h�m�X�r�[�`
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(�l)�@�n�W�s�L�p���^
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(��)�@�������w
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(�Z)�@�ԍ�ߓ���
��l�ҁ@��Z�́@��ܐ߁@�Z�@(��)�@�^�_������
��ܕҁ@��ʁE�ʐM
��ܕҁ@���́@��ʁ@409
��ܕҁ@���́@���߁@�����̌�ʁ@409
��ܕҁ@���́@���߁@��@�C��̌�ʁ@409
��ܕҁ@���́@���߁@��@����̌�ʁ@415
��ܕҁ@���́@���߁@��@(��)�@���a�Z�\��N�x�ȍ~�̓��H�����̌���
��ܕҁ@���́@���߁@��@(��)�@�ԗ����ۗ̕L�䐔�y�ѓ�����ʎ���
��ܕҁ@���́@���߁@�O�@��̌�ʁ@424
��ܕҁ@���́@�ʐM�@433
��ܕҁ@���́@���߁@�^�_�X�ǁ@433
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@���v
��ܕҁ@���́@���߁@(��)�@�X�����c���Ɏ���܂ł̌o��
��ܕҁ@���́@���߁@(�O)�@���X�ǒ�
��ܕҁ@���́@���߁@�^�_���d��d�b�ǁ@435
��ܕҁ@���́@��O�߁@����Ղ̐����@435
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@�C���^�[�l�b�g���̐����@435
��ܕҁ@���́@��O�߁@��@�g�ѓd�b�̕��y�@438
��ܕҁ@���́@��O�߁@�O�@�h�Ж����̐����@441
��Z�ҁ@����
��Z�ҁ@���́@����s�����@445
��Z�ҁ@���́@���߁@�^�_���̊w�Z���琧�x�@445
��Z�ҁ@���́@���߁@��@�c�t�����琧�x�@445
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@���ǂ����ɂȂ�܂ł̌o��
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@���݂̂��ǂ����̌o�c
��Z�ҁ@���́@���߁@��@���ʎx�����琧�x�@446
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@���ʎx������̕ϑJ
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@�{���ɂ�������ʎx������
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(�O)�@�^�_�����w�Z�ɂ�������ʎx������
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(�l)�@������\�Z�N�x���ʎx������̎���
��Z�ҁ@���́@���߁@������̋���s���@449
��Z�ҁ@���́@���߁@��@����ψ��E����ψ�����ǂ̐��ځ@449
��Z�ҁ@���́@���߁@��@�w�Z����̎�ȉ��v�@452
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@�Љ��̎�ȉ��v�@454
��Z�ҁ@���́@���߁@�l�@�������k���E�N���X���E�E�����̐��ځ@458
��Z�ҁ@���́@��O�߁@������̋�������@460
��Z�ҁ@���́@������̊w�Z����@462
��Z�ҁ@���́@���߁@�T�v�@462
��Z�ҁ@���́@���߁@��@������̗��w���厖�E�Љ��厖�@463
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@���w���厖�ꗗ
��Z�ҁ@���́@���߁@��@(��)�@���Љ��厖�ꗗ
��Z�ҁ@���́@���߁@��@�w�͏̕ϑJ�@464
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@������\���N�x����s���̏d�_�{��@467
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@(��)�@�L���b�`�t���[�Y
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@(��)�@��{���j
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@(�O)�@�d�_�{��
��Z�ҁ@���́@���߁@�O�@(�l)�@���F���鋳��̊T�v
��Z�ҁ@���́@���߁@���Z���NjL�@469
��Z�ҁ@���́@��O�߁@�e�w�Z�̋����z�u�}�@471
��Z�ҁ@���́@��l�߁@�e���ǂ����̉��v�@476
��Z�ҁ@���́@��l�߁@��@�^�_���ǂ����@476
��Z�ҁ@���́@��l�߁@��@���Ԃ��ǂ����@477
��Z�ҁ@���́@��l�߁@�O�@�ߊԂ��ǂ����@478
��Z�ҁ@���́@��l�߁@�l�@�n���������ǂ����@479
��Z�ҁ@���́@��ܐ߁@������̊e�w�Z���v�T�v�@480
��Z�ҁ@���́@��ܐ߁@��@�^�_���w�Z�@480
��Z�ҁ@���́@��ܐ߁@��@���ԏ��w�Z�@481
��Z�ҁ@���́@��ܐ߁@�O�@�ߊԏ��w�Z�@482
��Z�ҁ@���́@��ܐ߁@�l�@�^�_���w�Z�@483
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�c��������ы���̕��݁@484
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@��@����d���̕��y�@484
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@��@���a�l�\��N�ȍ~�̗c��������ы���@484
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@���a����`�������̈�ы���@485
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(��)�@�w�͌���
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(��)�@���k�w��
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(�O)�@��������
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(�l)�@�ی��E�̈�w��
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�O�@(��)�@�i�H�w��
��Z�ҁ@���́@��Z�߁@�l�@���݂̗c��������ы���@486
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@�����\�N�x�ȍ~�̒�����ы���@486
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@��@���̌o�܁@486
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@��@������\���N�x�̒�����ы���@486
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@��@(��)�@���ݏ��������
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@��@(��)�@�����ڑ������̐i�H�w��
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@��@(�O)�@�A�g�^������ы���������s���⊈��
��Z�ҁ@���́@�掵�߁@�O�@���̐��ʁ@487
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@�n����\���N�ȍ~�̗^�_���Z�̕��݁@487
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@��@�n����\���N�L�O�s�����@487
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@��@�n���O�\���N�L�O�s�����@488
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@�O�@�n���l�\���N�L�O�s�����@488
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@�l�@���a�\��N�x�ȍ~�̎�ȉ��v�@488
��Z�ҁ@���́@�攪�߁@�܁@�i�H�@491
��Z�ҁ@���́@���߁@�w�Z����{�ݐ����@491
��Z�ҁ@��O�́@�Љ��@493
��Z�ҁ@��O�́@���߁@�T�v�@493
��Z�ҁ@��O�́@���߁@�ߔN�̎Љ��̓����@494
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@�d�_�{��(������\���N�x)�@495
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@�n��S�̂Ŏq�ǂ�������Ă���Â���@495
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@(��)�@�n�悮��݂Ŏq�ǂ��̈琬
��Z�ґ�O�͑�O�߈�@(��)�@�ƒ�y�ђn��̋���͂̌���y�щƒ닳��x���̏[��
��Z�ґ�O�͑�O�ߓ�@���U�ɂ킽���Ċw�ׂ���Â���ƃX�|�[�c�E�����̐U���@495
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@(��)�@�Љ��E���U����̐��i
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@(��)�@�Љ�̈�̐��i
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@(�O)�@�|�p�E���������̐��i
��Z�ҁ@��O�́@��O�߁@��@(�l)�@�������̕ۑ��E���p
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�Љ��c�̂̕��݁@496
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@���A���N�c�@496
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(��)�@������
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@���n�揗���c�̘A�����c��@498
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(��)�@���a�������畽�������܂ł̕���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(��)�@������̊�����
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(�O)�@�n���A�̂ƒn���A��
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@��@(�l)�@���w�l��E�n���A����
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�O�@���q�ǂ���琬�A�����c��@502
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�O�@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�O�@(��)�@���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�l�@��PTA�A�����c��@502
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�l�@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�l�@(��)�@���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@���V�l�N���u�A����@503
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@(��)�@�V�l�N���u�̕���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@(��)�@�V�l�N���u�̋ߔN�̉^�c�Ɗ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@(�O)�@���V�A�̌���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�܁@(�l)�@����Ǝ�Ȋ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�Z�@�^�_����������@508
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�Z�@(��)�@�����N�x
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�Z�@(��)�@���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@�Z�@(�O)�@���(��Ȏ��)��
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@���@�^�_���̈狦��@509
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@���@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@���@(��)�@���
��Z�ҁ@��O�́@��l�߁@���@(�O)�@������\���N�x�g�D�}
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@�Љ��{�݂ł̊����@512
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@�����}���ف@512
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@���ْ�
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(�O)�@�}���ً��c��
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(�l)�@���������}���ً�����x����\����
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@������\���N�x���p�Ґ��E�o�^�Ґ�
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@���������ف@515
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@��ȕ���
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@�w��Ǘ��ֈڍs
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(�O)�@������\���N�x�g�D�}
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(�l)�@�����ى^�c�R�c��
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@�����\�Z�N�x�����ً����ꗗ
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(�Z)�@������\�Z�N�x�����ٍu���ꗗ
��Z�ҁ@��O�́@��ܐ߁@��@(��)�@��㒆�������ْ�
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@���̑��̎Љ��@520
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@�������E�V�R�L�O���@520
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(��)�@���w�蕶�����u�^�_�\�ܖ�x�v
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(��)�@������̒��w�蕶����
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(�O)�@���w��̓V�R�L�O��
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@�ł������������@522
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(��)�@���\��
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(��)�@���\���Ǝ����y�ё薼
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(�O)�@�R���
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@��@(�l)�@�R����
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@�������p�i�E�����N�̑D�@523
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@(��)�@���C���Ƃ̖ړI
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@(��)�@���ƊJ�n�N�x
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@(�O)�@���C��y�ь��C����
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@(�l)�@���C�l��
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�O�@(��)�@�ŋ߂̌X��
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�l�@���Ԃ̋���x���c�́@524
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�l�@(��)�@�^�_�ė��
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�l�@(��)�@���l���l�^�_���̉�(������)
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�l�@(�O)�@�������|���Ɋw�ԉ�
��Z�ҁ@��O�́@��Z�߁@�l�@(�l)�@�^�_���y������
��Z�ҁ@��O�́@�掵�߁@�Љ��s���@525
��Z�ҁ@��O�́@�掵�߁@��@������\���N�x�̎Љ�̈�s���ꗗ�@525
��Z�ҁ@��O�́@�掵�߁@��@��@������\���N�x�̕����s���ꗗ�@527
��Z�ҁ@��O�́@�攪�߁@�Љ��{�ݐݔ��̐����@527
�掵�ҁ@�����E����
�掵�ҁ@���́@�V�j���O�Ղ�̋L�^�@531
�掵�ҁ@���́@�͂��߂Ɂ@531
�掵�ҁ@���́@���߁@�V�j���O�_���}����ɂ����� -�����-�@534
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�V�j���O�Ղ�̋֊� �`���E���E���E�E���`�@534
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�V�j���O�_�̒ʂ铹����߂� �`�_�����P���`�@535
�掵�ҁ@���́@���߁@�O�@�_�̈ˑ� �`���E���E�|��E�_���`�@537
�掵�ҁ@���́@���߁@�V�j���O�Ղ�{�Ղ� -�����-�@538
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�j�b�`�F�[�T�A�N���̍Ղ� �`���������̍Ղ�`�@538
�掵�ҁ@���́@���߁@��@��Z��ܔN �s����K�������@540
�掵�ҁ@���́@���߁@�O�@�V�j���O�p���^�ł̐_�� �`�_�}�����y�q���`�@542
�掵�ҁ@���́@���߁@�l�@�j�̎q�ɂ���P�� �`�t�D�[�x�[ �n�[�x�[�`�@543
�掵�ҁ@���́@���߁@�܁@�V�j���O�{�Ղ� �`�E�b�R�E�ɂ����鍇���Ձ`�@545
�掵�ҁ@���́@���߁@�Z�@�E�b�R�E�ɂ�����j���O�{�Ղ�����@547
�掵�ҁ@���́@���߁@���@�V�j���O�_�ɕ�����@548
�掵�ҁ@���́@���߁@���@�|������� �`�L���̓I���˂�`�@549
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�E�[�N�C �`�_����`�@551
�掵�ҁ@���́@��O�߁@���Ƃ̍Ղ� -�O����-�@552
�掵�ҁ@���́@��l�߁@�T�A�N������ -�l����-�@553
�掵�ҁ@���́@�����Ɂ@554
�掵�ҁ@���́@�����K���E�����@558
�掵�ҁ@���́@���߁@�u�j�˂��v���l�̌��` -�썰�̃t�@�b�V����-�@558
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�^�_���̐j�˂��@558
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�f�U�C���̊j�@559
�掵�ҁ@���́@���߁@�O�@���h�J���ƒ��@561
�掵�ҁ@���́@���߁@�l�@�g�[�e���Ɨ썰�@562
�掵�ҁ@���́@���߁@�܁@���h�J���̑O�g�Ƃ��Ă̊L�@564
�掵�ҁ@���́@���߁@�Z�@�����̐��l�V��@565
�掵�ҁ@���́@���߁@���@�@567
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�C���}�`�@567
�掵�ҁ@���́@���߁@��@�g�D�}���V�@567
�掵�ҁ@���́@���߁@�O�@�E�`�y�[�@567
�掵�ҁ@���́@���߁@�l�@�y�[�m�[�@568
�掵�ҁ@���́@���߁@�܁@�`�`�A���@568
�掵�ҁ@���́@��O�߁@�^�_���̕����@569
�掵�ҁ@���́@��O�߁@��@��ƌn�}�ɂ���@���@569
�掵�ҁ@���́@��O�߁@��@�F���̎x�z����ɂ���Č������ꂽ�Ǝv����
�@�@���@���{�y�ьl�I�ȏ@���{�݁@570
�掵�ҁ@���́@��O�߁@�O�@�ٍ��V�@�咠�ɋL�ڂ��ꂽ�^�_���̐l�@570
�掵�ҁ@���́@��O�߁@�l�@��ƕ����̋L�^�@571
�掵�ҁ@���́@��O�߁@�܁@�s�n���P�V���ƕٍ��V�@571
�掵�ҁ@���́@��O�߁@�Z�@�l�@�@571
�掵�ҁ@���́@��O�߁@���@�^�_���̕����@572
�掵�ҁ@���́@��O�߁@���@(��)�@�߉ޔ@����
�掵�ҁ@���́@��O�߁@���@(��)�@�����F��
�掵�ҁ@��O�́@���b�Ɩ��w�@574
�掵�ҁ@��O�́@���߁@���Ԑ��b�@574
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@�S�ɂȂ����Ł@574
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@�A�n�p�[�p�[�A�C�V���V��(�C�V���g�D)�ɏo������b�@577
�掵�ҁ@��O�́@���߁@�O�@�����`���A���[�^�V���k(���[�^�`���k)�����ނ���̊��@578
�掵�ҁ@��O�́@���߁@�l�@�s���[�k�p���^�Ń��[�^�V���k�ɂ����@579
�掵�ҁ@��O�́@���߁@���w�@581
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@�^�_���w�E���́@581
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�C�L���g�[
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�j�]���C�J�i���C
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�O)�@�T�g���[��
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�l)�@�哇���b�p��
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�E�����K�L�����h�D
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�Z)�@�T�g�D�K�[�A�f�B�N
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�C���[ �C���[ �T�[
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@����
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(��)�@�������юR
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�\)�@���܂��炫��� �Ղɂ�
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�\��)�@�Ă����� ���Ղ���
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@(�\��)�@��f�S
�掵�ҁ@��O�́@���߁@��@��ʉ̎��@605
�掵�ҁ@��O�́@���߁@�O�@�^�_���S�̎��@424
�掵�ҁ@��O�́@���߁@�l�@���̑��y���@427
�t�� �N��\�E���M�҈ꗗ�E�ҏW���M���S
�N��\�@636
���M�҈ꗗ�@647
�ҏW���M���S�@650
���Ƃ����@�^�_�����ǘ^�ŕҏW�^�c�ψ��� �|���O�@655
|
�R���A������w�@���w���ҁu�����A�W�A�����_�W : ������w�@���w���I�v : bulletin of the Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus (4) ���{�搶�ސE�L�O���v���u������w�@���w���v���犧�s�����B
|
���{�搶�����E�����Ɛ� (���{�搶�ސE�L�O��) ������w�@���w�� p.1-11
�~�̌|�\ : �G�C�T�[�A�V�`�O���`��(���[�C)�ƃA���K�}�Ƃ̔�r���� (���{�搶�ސE�L�O��) ��� �{ p.13-40
���n�u�v�����Ɖ���� : �Ï�����w�ڋ߁x���߂����� (���{�搶�ސE�L�O��)
���� ���� p.41-54
����V�ƕx������̓��{���ʂ�����R (���{�搶�ސE�L�O��) �� ���@ p.55-77
�z�N�ƖY�p�̂Ȃ��̃A�����J : ��Ԑ��Y�w�y�����̑D�x�_ (���{�搶�ސE�L�O��) �V�� ��v p.79-112
���@�����P�u������āv�̓��e�\���ƁA�⏕���ނɂ����ƍ\���̎��� (���{�搶�ސE�L�O��)
��� ���Y p.113-126
�g�D�o���[�}�ɉ̂�ꂽ�q�ԁr�ɂ��� (���{�搶�ސE�L�O��) �O�� �~�q
p.127-151
�u���Ȃ�_�̓��v�̒j���_�� (���{�搶�ސE�L�O��) �ԗ� ���M p.153-173
�������̊O���Ɠ��{�E�������� (���{�搶�ސE�L�O��) �L���R �a�s p.175-191
�|������ �����{�w�Z�@���`�x (���{�搶�ސE�L�O��) �� ���u p.193-248
����Ă̍Z���ƞ��Ďj�� : �����̋{�����@�������Ďj���Ƃ̍Z���𒆐S�� (���{�搶�ސE�L�O��)
�ԗ� �� p.1-14
���������̕��������̈�[ (���{�搶�ސE�L�O��) ���� �q�g p.15-21
���ꌧ���ɂ����钆����\�L�̌���Ɖۑ� (���{�搶�ސE�L�O��) ���� �Ђ�� p.23-34
�\�\���̕� (���{�搶�ސE�L�O��) ���� �O�� p.35-111
���C�ω��̑̌n�� : ���C�ω��Ɖ��C�̌n�̍ĕ� (���{�搶�ސE�L�O��) ����܂� �����Ђ� p.113-137
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�Q���\���Ŋ��s���ꂽ���ɂ��Ă͊m�F���K�v�@�@�Q�O�Q�R�E�T�E�Q�R�@�ۍ� |
�R���A���s����ψ���u���w��j�Ս֏��ԕۑ����p�v��v���u�ꌧ���s����ψ���v���犧�s����B�@137p�@�@������
|
��1�́@���v�ƖړI
1�@�v�����̉��v
2�@�v�����̖ړI
3�@�v��̑Ώ۔͈�
4�@�v��̌����o��
5�@�v��̈ʒu�Â�
��2�́@�֏��Ԃ̊T�v
1�@���n��
2�@�֏��Ԃ̎j�Վw��̊T�v
3�@���E��Y�o�^�̊T�v
4�@�֏��Ԃ̗��j
5�@�֏��ԋy�т��̎��ӂɈʒu�����\���̊T�v
6�@�ۑ����p�̏�
��3�́@�֏��Ԃ̖{���I���l�ƕۑ����p�̖ڕW�E������
1�@�֏��Ԃ̖{���I���l�ƖڕW�E������
2�@�֏��Ԃ̕ۑ��Ǘ��Ɗ��p�Ɋւ��\���v�f�̐���
3�@�֏��Ԃ̕ۑ��Ǘ��E���p�E�����̊�{���j |
��4�́@�ۑ��Ǘ�
1�@�ۑ��Ǘ��̕�����
2�@�j�Վw��͈͂̕ۑ��Ǘ��̕��@
3�@���ӊ��̕ۑS���@
��5�́@���p
1�@���p�̕�����
2�@���p�̕��@
��6�́@����
1�@�����̕�����
2�@�����ɂ������Ă̊�{�I�ȍl�����Ɛ����̓��e
��7�́@�^�c�E�̐��̐���
1�@�^�c�E�̐��̕��@
��8�́@�o�ߊώ@�y�э���̉ۑ�
1�@�o�ߊώ@
2�@����̉ۑ�
�y���������z�v�茘�W���Z�����[�N�V���b�v�̊T�v
�E |
�R���A��c��,�X�c�^�炪�u�啪�����|�p�����Z����w�����I�v = Bulletin of Oita prefectural College of Arts and Culture 55 p.63-90�v�Ɂu�I�X�v���C�ƃG�C�T�[�F ��㉫��ɂ����閯���|�\�̂Ђ낪��ƕČR��n�v�\����B�@�iIRDB�j
�R���A�ichikuin ko�j���u�l�ԉȊw���� = Waseda Journal of Human Sciences 31(1) p.46-46�@����c��w�l�ԉȊw�w�p�@�v�Ɂu�C�m�_���v�| : �`���|�\�������ό��܂��Â���-���ꌧ�ߔe�s�ɂ�����u�ꖜ�l�̃G�C�T�[�x����v�̎�����-�v�\����B�iIRDB�j
�R���A�u���ꌤ���m�[�g�@27�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B �iIRDB�j
|
����̖��ԕ��|�ɂ݂鐯�E���E�� �R������ p.1-19
���d�R�̕�炵�Ɠ`���F���E���E�� �{��K�q p.20-35
�w����A��������w�� �` ���]���V�x�i�Җ{���O�A����^�C���X��
|
�@�@����Z�ꎵ�N�j ���ђ��� p.36-41 �iIRDB�j
�{�Ǎ�E�{�Ǐ���Y���w���A�W�A�̓���������@�^�ߍ������x
�@���i��R�ɁA��Z�ꎵ�N�A���O�Łj��ǂ�� �y���� p.42-45 |
�R���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 51(2) (�ʍ� 122) �v���u��㊕�������v���犧�s�����B
|
�����̉��ɂ�����č��̌��_�����Ǘ����� : ���Ƌ���Ɋւ���R�@�̕��͂���@�g�{
�G�q p.1-24
�����ÓT���y�ɂ����鐺�E�g�́E�� : ���獑�j�̏��E���ᗝ�_�̈Ӗ���T��@�}�b�g �M���� p.25-43
�h�ЋV��ɂ�����l�X�Ɨ��K�_�ɂ�鏜�Ѝs�ׂ̔�r : ����̃V�}�N�T���V�V��ƃp�[���g�D������Ɂ@�{�����W
p.44-63
�����m���M�̗��� : �w���̑�ρx���^�̂��߂����ā@���� ���� p.64-73
���̂ɂ�����u��v�ɂ���(��)�@���i �E���o�m���@�[ p.74-93
������������ɂ�����֕�����Ƌ�蓹�j�@�r�b�g�}�� �n�C�R p.94-124
��O�\����u���ꕶ������܁v���\�@ p.125-133 |
�R���A���c���q,����������,�Y�o�r�a,��c�G�q,�啽�a�O,���؏��t���u�����h�X�P�[�v����
: ���{�����w�� : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture 81(5) p.571-576�v�Ɂu�����哇�ɂ�����m�����J��Ԃ̌p���Ɋւ��錤�� (����30�N�x���{�����w��S���������\�_���W(36))�v�\����B�@�@J-STAGE
�R���Q�T���A����s��n�꒚��1��1��(�R�U�E�~���[�W�b�N�^�E����)�Ɂu�G�C�T�[��فv���J�ق����B
�S���A�{�����W���u���ꖯ������ = Journal of Okinawan folklore studies (35) p.21-49�@���ꖯ���w��v�Ɂu����{���k���̋��Ă�(�E�V���L)�V��Ɋւ����l�@ : ���]���y�ш��V��Ƃ̊֘A���̌����𒆐S�Ɂv�\����B
�V���V���A�_�ސ��w���l�L�����p�X 23 ���� 206 �����ɉ����Đ_�ސ��w�����������Z���^�[��Âɂ��u�ߑ㉫��ɂ�������J�ĕ҂Ɛ_�Ёv�Ƒ肷��V���|�W�E���������ǂɂ���ĊJ�����B
|
2018 �N�x �����������Z���^�[ �� 1 ����J������
�{�ÁE���d�R�̌�ԂƐ_�Ё\�ߑ㉫��̒n��Љ�ƍ��J�ĕ�
�� �ÁF�_�ސ��w�����������Z���^�[�u�ߑ㉫��ɂ�������J�ĕ҂Ɛ_�Ёv������
�� ���F2018 �N 7 �� 7 �� ( �y�j13�F30 �` 18�F00
�� ���F�_�ސ��w���l�L�����p�X 23 ���� 206 ����
�@�@�@�v���O����
�J��A�F�����i��F�Óc�ǎ��i�����������Z���^�[�q���������j
�J�Î�|�F��c���ցi�����������Z���^�[�������j
�� 1 ���@��
�� �� �P�F�u�{�Â̌�Ԃƒ����ɂ��ā`���̔w�i���l����`�v�@���n�a�G�i�{�Ó��s�j�҂���ψ���ψ����j
�Q�F�u��Ԃ̐_�X�Ɣ��d�R�_�Ќ��݁v�@��c�Òj�i�Ί_�s�������ً��c���j
�R�F�u�i�i���C�v�i�{�Â̍��J�f���j�@��ÖL���i�ʐ^�Ɓj
�� 2 ���@���c
�R�[�f�B�l�[�^�[�F ��c����
�p�l���X�g�F���n�a�G�@��c�Òj�@��ÖL�� |
�V���A��邳��肪�u�I�L�i���O���t (676) p.24-29�@�V���o�Łv�Ɂu���̂���ۓ�(��137��)�ς�E�w�ԁE�x��! �G�C�T�[�����̔��M���_
�G�C�T�[��فv�\����B
�W���A����t��,���q���V���u���{���z�w��v��n�_���W = Journal of architecture and planning : transactions of AIJ 83(750) p.1533-1542�@���{���z�w��v�Ɂu����̃R���N���[�g�Z��y�t�����ɂ����钇���v�Y�̌��z�����v�\����B
�W���A�ԗ䐭�M���u�L�W���i�[�l : �̐����Ƃ̐_�ɂȂ�v���u�Վ����сv���犧�s����B
�@�@ (������܂�u�b�N�X = Gajumaru books ; 13)
�X���X���A��Ԉ��T���S�⎛�i�É������}�s�j�ɉ����āu�Ă̏I��̉��ꃉ�C�u
2018�v���J�Â���B�@�@���Q��ځ@�Q�O�P�X�N�X���S��
�X���A�g�Ɗԉi�g���_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[�ҁu����������
= The study of nonwritten cultural materials (16) p.1-35�v�Ɂu����̃E�^�L : ���̐M�E�Ր_�E�\���ɂ��āv�\����B
�X���A�������s �ʐ^�E���u�j�b�|�������̍Ղ� = Festivals of Outlying Islands in Japan�v���u �O���t�B�b�N�Ёv���犧�s�����B
|
�͂��߂�p6
| �t |
���������_�Џt�Ղ�^�����E���Ɍ�p8
���n�̋��y�|�\�^���n���E�V����p14
���[�n�C���Ղ�^�V�������E�F�{��p20
|
������@�؉�^����E���������p24
��R�L�_�Ђ̌�c�A�Ղƈ�l�p�́^��O���E���Q��p28
���K�i�َ��q�^���K���E�k�C��p32 |
|
| �� |
�����n�[���[�^����{���E���ꌧp38
�nj��Ձ^�����E�L����p44
����Ղ�^�����E�O�d��p48
�Y�ˏ����̉čՂ�^�i�Y�ˏ����i�j���A
�@�@�@����X���A�����A�p���j�E�{�錧�jp52
�Ɠ��V�_�Ձ^�Ɠ��E���Ɍ�p58
���d�������̖L�N�ՂƋ��~�s���^���d�R�����E���ꌧp62
|
�_�Ó��̃J�c�I�ސ_���^�_�Ó��E�����sp72
�P���~�x��^�P���E�啪��p76
�G�C�T�[�^����{���E���ꌧp80
���Γ��̃{�[�^���Γ��E��������p86
�_���^�j���E�R����p90
�����}�b�e�B�^�v�����E���ꌧp96
�`�����R�R�E�I�[�����f�[�^���]���A���㓇�E���茧p100 |
|
| �H |
�����哇�̃A���Z�c�^�����哇�E��������p104
�F���������̃����h���^�������E���������@p110
�݂���Ձ^���m���A�@���哇�E������p114
�^�_�̏\�ܖ�x�^�^�_���E��������p120
�����_�ЏH�Ղ�̑��ۑ�^�������E���쌧p124
|
���݃V�o���^���v�C�����E��������p130
�{�Ó��̃p�[���g�D�^�{�Ó��E���ꌧp134
�|�x���̎�q��Ձ^�|�x���E��������p138
�R�m�_�_���^�W�䓇�E�R����p144
�E |
|
| �~ |
�����_�y�^��E���茧p152
�Q�[�^�[�Ձ^�_���E�O�d��p156
�����̃g�V�h���^�������E��������p170
|
�w�g�}�g�^���]���E���茧p166
�����̔N�j���Ə������^�����E�V����p170
�����̍��`���^�����E���ꌧp174 |
|
�����l�`�o�@p178
�����̌�Ղ胊�X�gp180
���Ƃ���p182
�Q�l����p183 |
�X���A�g�Ɗԉi�g���u���������� = The study of nonwritten cultural materials 16 p.1-35�@�_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[�v�Ɂu����̃E�^�L �|���̐M�E�Ր_�E�\���ɂ��ā|�v �\����B�@�iIRDB�j
�P�O���A�V�_(����) �q�q���u�����ƌo�� (43) p.105-113�@���������w������v�Ɂu���쐴�q�̉��꒲���m�[�g�u���^�v : �����m�[�g�̊T�v�ƒ��������̎Љ�v�\����B
�P�Q���A���ԗE�h�A���Ԍ����A���c�h��A�ɉ����u������w�_�w���w�p��
= The science bulletin of the College of Agriculture, University 65���@ p. 91-146�@������w�_�w���v�Ɂu���NJԓ��̌�ԗтɊւ��钲�������v�\����B
�P�Q���A������w���d�R�|�\�������; �R������ҁu�u���d�|�v�\�N : ������w���d�R�|�\������n���\���N�L�O���v���u������w���d�R�|�\������v���犧�s�����B�@�@488p�@�@�����F���ꌧ���}���فF1008622191
|
1�@�\�N�̕���
(1)�@�N�x�ʊ����L�^
(2)�@���ڕʃv���O����
(3)�@������\��E�����ꗗ |
(4)�@�u���d�|�v���j
2�@���N����
3�@�w���ɂ����銈��
4�@��z |
5�@��ގ���
(1)�@������{
(2)�@�H�H�l
�ҏW��L |
���A���̔N�A��������u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (84) p.93-107�@���m���y�w��v�Ɂu�u�����ÓT���y�ȁq������ŕ��߁r�q�ԕ��߁r�q��܂Â�߁r�̕������ԓI�W�v�\����B
���A���̔N�A��c�����u���{�����l�ފw������\�v�|�W 2018(0) p.9�v�Ɂu�n���C�ږ��Ɖ�����ˋ�����u�����v�Ɓu�Ԃ��v:�����̌l�j�ɂ݂鉫���~�ω^���̕���v�\����B�@�@�@J-STAGE
���A���̔N�A���܍K�i���u�n��n�� : ���Â���A�[�g���������܂��i44�j p.75-79�@�n��n���v�Ɂu�C���X�gSCOPE ����ɐ�����|�\��G�C�T�[��v�\����B |
| 2019 |
31 |
�E |
�Q���A�r���S, �����וF, ���c�z�q, �{���^�ҁu���גn��Ȋw�Ƃ�������v���u
�i�ߔe�j�{�[�_�[�C���N�v���犧�s�����B�@ (������w���גn��Ȋw���������C�u����)�@�d�v�@�@�Q�W�O�O�~
|
���ꂩ�甭�M����u���גn��Ȋw�v / �r���S, ���c�z�q
���גn��̎����Ɍ�������w�̖��� / �{���^, �������O
�����ɂ�����t�N�M���~�т̕ۑS�Ɗ��p / �ɉ�, ��c�ɋv�Y
���גn��̓����I���W�ɂ�����s�s�_���𗬂̈Ӌ`/�����וF, �����d�V
�����E�����̎������ɂ��� / �L���R�a�s
���߂������i�� / �g����z
������̑��l���Ɠ��א� / �떓�ɋv
���ꌧ�擇�����ɂ�����Վi�̎��Ԃƕω� / �{�����W
|
�u�����ȓ��v�̌��̐헪 / ��[��]
���גn��Ȋw�ɂ����镶������ / ���
�����قɂ�����n���C�̗��j�ƎЉ�̕\�� / �R�����q
���ׂ̈��S�ۏ� / �䕔���� ��
�u�A�W�A�E�p�V�t�B�b�N�E�V�A�^�[�v�ƒE�R����`�̕�����n������
�@�@���u�R����`�������Ȃ����ۏ����l�b�g���[�N�v / �X������T
���L�I�q�S�[���X�r�̐��E / �ԗ��
�����m���גn��ɂ�����u�A�сv�̌n�� / �r���S |
�Q���A�{�����W���u���������̓����V�� : �V�}�N�T���V�V��̖����w�I�����v���u�א��o�Łv���犧�s����B
�R���X���A�u�w���d�|�x�\�N�v�o�ŏj�����d�|���U����5��30�����痮���V��Љ���뉀�ɉ��ĊJ�����B�@�d�v
�R���A�������ނ����ꌧ���|�p��w�����������ҁu����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
(31) p.59-75�v�Ɂu��O�̉���ɂ�����u�G�C�T�[�v�Ɓu�~�x��v�̏����v�\����B
�R���A������ �ďC�u���������� (666)�@(���W �u���K�_ : ���ʁE�����̐_�X�v���l�X�R���`������Y�o�^)
�v�����s�����B
|
�u���K�_�v�s���̕ۑ��Ɗ��p ���і� p.4-8
�o�^�ɂ��� �u���K�_ : ���ʁE�����̐_�X�v��
�@�@�����l�X�R���`������Y�o�^�ɂ��ā@��R�O�q p.9-11 |
���c��̂���� ���K�_�s���ۑ��E�U���S�����c��̂���� �ɓ����q p.12-14
�\���������@ p.15-36
�E
|
�R���A�u���ꌤ���m�[�g 28�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B2019-03
|
���\���Ɋւ���o�� ���ђ��� p.1-9 �iIRDB�j |
��������Ҏx���̎�i�Ƃ��Ē��ڂ���鋤�����X �y�����@ p.10-15 �iIRDB�j |
�R���A�����������u���m��w����w�������� 79 p.203-232�v�Ɂu�c�ӏ��Y�ɂ����鉫��E���d�R�������y���n����(1922�N)�̐��ʂƎЉ�I�Ҍ��[JOKA�u���{���y�j�u���v�A�̕��ꕑ�x���w�^�ߍ�����x���߂����ā[�v�\����B�iIRDB�j
�R���A ���R�h�͂��_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[�ҁu�����������Z���^�[news
letter (41) p.2-5�v�Ɂu2018�N�x �����������Z���^�[ ��1����J������
�{�ÁE���d�R�̌�ԂƐ_�� : �ߑ㉫��̒n��Љ�ƍ��J�ĕ� : �v�\����B�iIRDB�j
�R���A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu�����哇�E��E���������v���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v���犧�s�����B�@�@ (�n�挤���V���[�Y, No.45)
|
�O�X�N���㏉���̓y�B�� : ��E����v��ՌQ�̓y�B��Ƃ̔�r�𒆐S�Ƃ��ā@ �{��O�� p 1-14
��O����E���ɂ�����ݒn�G���[�g�w�̐A���ړ����� : ���ƃm�[�g����̍l�@
�@�y�썂 p15-28
��E���ɂ�����_�Ƃ̒n����� �@����� p29-41 |
|
���ꍑ�ۑ�w�쓇���������������s�����u�n�挤���V���[�Y�iNo.1�`45�j�v���̓���ꗗ�\
| �m�� |
���s�N�� |
�^�C�g���� |
�Q�l�i��ɖ����w�I�Ȃ��Ɓj |
| 1 |
1980-03 |
�^�_�E���������� No.1 |
. |
| 2 |
1981-03 |
���i�Ǖ��������� No.2 |
.�g�Ɗԓ��̖L�N��(�v�[����)�ƋF�N��(�A�~�a�����[) ���R�� |
| 3 |
1982-03 |
�g�Ɗԓ������� No.3 |
. |
| 4 |
1983-03 |
�ɗǕ��������� ��4
|
�J���X : �ɗǕ����̔N���s�� ���R �� |
| 5 |
1984-03 |
�ɕ����E�ɐ��������� No.5 |
.�ɕ������ɂ����錋(���C) ��ËP�K
�E���U�~�ƃV�k�O : �ɕ������c���̔N���s�� ���R�� |
| 6 |
1984-03 |
���V��������(1) ��6 |
. |
| 7 |
1985-03 |
���V��������(2) No.7 |
. |
| 8 |
1985-11 |
���V��������(3) No.8 |
. |
| 9 |
1986-03 |
���V��������(4) No.9 |
. |
| 10 |
1987-03 |
���������哇�S���˓���������(1) No.10 |
. |
| 11 |
1988-03 |
���������哇�S���˓���������(2) No.11 |
. |
| 12 |
1989-03 |
���������哇�S���˓���������(3) No.12 |
���˓����̊��_�M�� : ���v�C�����𒆐S�Ƃ��� �E���� |
| 13 |
1989-03 |
���������哇�S���˓���������(4) No.13 |
.���˓����̊��_�M�� : ���v�C�����𒆐S�Ƃ��� (��) �E���� |
| 14 |
1990-03 |
���������哇�S���˓���������(5) No.14 |
.���˓��̑��搧 ���~�ߎ� |
| 15 |
1990- 03 |
�{�ÁA���n��������1 No.15 |
.�{�×��ԓ��̊��_�M�� �E���� |
| 16 |
1991-03 |
�{�ÁA���n��������2 No.16 |
. |
| 17 |
1992-03 |
�{�ÁA���n��������3 No.17 |
�{�ÌS���n���̊��_�M�� �E���� |
| 18 |
1992-03 |
�{�ÁA���n��������4 No.18 |
. |
| 19 |
1993-03 |
���NJԓ�������(1) No.19 |
���NJԑ����[�̘̐b ���{�M�v. |
| 20 |
1994-03 |
���NJԓ�������2 No.20 |
���NJԓ��̂��܂ǐ_�M�� �E���� |
| 21 |
1995-03 |
���NJԓ�������3 No.21 |
���NJԓ��̂��܂ǐ_�M��(��) �E���� p111-122 |
| 22 |
1995-03 |
���NJԓ�������4 No.22 |
. |
| 23 |
1996-03 |
�{�ÁA���ǎs������1 No.23 |
. |
| 24 |
1997 -03 |
�{�ÁA���ǎs������2 No.24 |
�{�ÌS��쑺�̂��܂ǐM�� �E���� |
| 25 |
1998-03 |
�{�ÁA���ǎs������3 No.25 |
.�{�Ó��̂��܂ǐ_�M�� : ��쑺�ƕ��ǎs�𒆐S�� �E����p25-40
�{�Ó��떓�̃E�v�C�r���k�̐_�� �V���K�� p51-86 |
| 26 |
1999-03 |
�{�ÁA���ǎs������4 No.26 |
�{�Ó������̌����قɂ�����̗w :
�@�@���u���~���[�k���V�L�_�~�̋V���� �㌴�F�Op 61-76 |
| 27 |
1999-03 |
���d�R�A�|�x��������(3) No.27 |
���l���̎�q���Ղ̋V��Ɖ̗w �g�Ɗԉi�gp39-86. |
| 28 |
2000-03 |
���d�R�A�|�x��������(2) No.28 |
�|�x���̂��܂ǐ_�M�� : ���\���𒆐S�Ƃ��� �E���� |
| 29 |
2001-03 |
���d�R�A�|�x��������(3) No.29 |
.�����̐����j��গ��D���� : �V��E�̗w�E��� ���R�� |
| 30 |
2002-03 |
���d�R�A�|�x��������(4) No.30 |
�܍��L���̐_�J�� : �����̋������́g��"�ɂ��� ���c���q p1-25
���\���̂��܂ǐ_�M��(��) �E���� p27-37 |
| 31 |
2003-03 |
�Ί_�������� 1 No.31 |
�j��̌×w ����,�v 2 p1-53
�Ί_���약���ƒ|�x���́u���@�苶���v �떓�b�� p55-83 |
| 32 |
2004-03 |
�Ί_�������� 2 No.32 |
. |
| 33 |
2005-03 |
�Ί_�������� 3 No.33 |
���d�R�ɂ�����܍��̌�� ���c���q p1-22. |
| 34 |
2007-03 |
���d�R�A�^�ߍ���������1 No.34 |
�V��(��n��)�̌×w ���{�M�v p51-71 |
| 35 |
2008-03 |
���d�R�A�^�ߍ���������2 No.35 |
�^�ߍ��̂��ׂ����đn���m�[�g ���{�M�v p1-84 |
| 36 |
2009-03 |
�v�ē�������(1) No.36 |
.�v�ē��̌×w1 ���{�M�vp 9-118 |
| 37 |
2010:-03 |
�v�ē�������(2) No.37 |
.�v�ē��̌×w2 ���{�M�v p21-113 |
| 38 |
2011-03 |
�v�ē�������(3) No.38 |
�v�ē��̌×w3 : �E���C�A���ׂ����̍̏W�A
�@�@�@�������č�i�̒lj� ���{�M�v p33-53 |
| 39 |
2012-03 |
��p������ No.39 |
. |
| 40 |
2014-03 |
�؍������� No.40 |
. |
| 41 |
2014-03 |
���������� No.41 2014-03 |
. |
| 42 |
2016-05 |
�哌���������� No.42 |
��k�哌���ɂ����锪��n�Ɖ���n���y�̓`�������
�@�@������̔��W���ɂ��Đ��{�M�v p37-53
|
| 43 |
2016-10 |
����m�Q�������� No.43 |
. |
| 44 |
2018-03 |
�؍������� No.44 |
. |
| 45 |
2019-03 |
�����哇�E��E�������� No.45 |
. |
|
�R���A�˓c���ꂪ�u�G�C�T�[���� : �ړ�����l�A�`�d����|�\�v���u���E�v�z�Ёv���犧�s����B
|
�v��E���^ ����̖~�x��ł������G�C�T�[���A���{�S�y�ɍL�������B�`�d�̌���ʼn����N���Ă���̂��B�G�C�T�[��x��A�̂��A�`�����l�X�̕���B
�u��Ȃ��Ƃ͐����Ă���Ǝ����ł���u�Ԃł���A�����^���Ă����̂��G�C�T�[�Ȃ̂��v�\�\����̖~�x��ł������G�C�T�[���A���܂���{�S�y�ɍL�����Ă���B�|�\�`�d�̌���ʼn����N���Ă���̂��B�G�C�T�[��x��A�̂��A�`�����l�X�̕���B�u�͂��߂Ɂv���\�\���āA�{���͂������Ɍ������̑̍ق��Ƃ��Ă͂��邯��ǂ��A���e���̂��̂́u����v�ƌ����Ă悢���̂��B�������i�W����ɂ�āA�`�d�ߒ������ǂ钲���̌��ʂ��A���̂܂܈��́u����v���`�����Ă��邱�ƂɋC�������B����䂦�A�{���̍ő�̓����́A�������ƕ���Ƃ́A���̈ٗ�̍��̂ɂ���B���̕���͔��d�R��������n�܂邪�A�����������ɗ��܂炸�A����{�����c�f���ē��{�{�y�ɂ܂ŒB����B���̊ԂɁA��㉫��́u���f�Ձv�̋����Ƃ��A�G�C�T�[�̎�x��Ɏg����u�͂����v�i�����j�̗R���Ƃ��A�͂��܂�����̎�҂̖{�y�A�E�̏Ƃ��A�������̏����ȁA���邢�͏ꍇ�ɂ���āA�傫�ȃG�s�\�[�h������߂��Ă���B���̌��ʁA�{���͈�ʂ̃G�C�T�[�t�@���̎�҂����A���Ȃ킿�A�G�C�T�[�������Ă�܂Ȃ��A�G�C�T�[�̖��͂̂Ƃ肱�ƂȂ�����҂����ɂ��A�N�Z�X�\�ȓ��e�ƂȂ��Ă���B�Ƃ��ɃG�C�T�[�����H���Ȃ���A�G�C�T�[���̂��̂ɂ��Ă����ƒm�肽���Ǝv���Ă����҂����ɖ{�������Гǂ�łق����B�{���́A������������������҂�O���ɒu���ď�����Ă��邩�炾�B
|
�R���A����t�삪���m�_���u������Z��ɂ����錚�z�ƒ����v�Y�̊����v�\����B�@������w
�iIRDB�j�@pid/12314060
�R���A������w���ےn��n���w���n�敶���Ȋw�v���O�����ҁu�n�����j�l�ފw�_�W ��8�� �i���c�@�������E�n�v�n���y�����ސE�L�O���j�v���u������w�@���w���v���s�����B�@�@�@122p�@�@�����F��㊌����}���فF1008912782
|
���c�@�������̐l�ƋƐ� �{���v�� 5
�n�v�n�@���y�����̐l�ƋƐ� �A���F 13
2000�N��O���ɂ����鉫�ꌧ�{�Ó�����̋G�ߘJ���ړ� �{���v��21
����암���s�ɕ��z����N���̐��� �A���F ����\�� 41
�H�g��ɂ��������d�ۗތQ���̕��z�Ɛ������ �H�c���� �����N 47
�k鰍F�����̏����ȂƗ��z�J�s �����x�O59
|
�O�X�N���㌚����\�Ɋւ���\�@ �r�c�Ďj 73
���쒆�����C�n��̐V�Ί핶�� �㓡��F83
�������������i2�j �_�J�q��93
������
�h�C�c���DR.J.���x���g�\�����Y�������ɂ�����u�������k�v�Ĕ��� :
�@�@���{���E���{�E�h�C�c �r���C 101-113 |
�R���A��R�L�q�����ꌧ���|�p��w�ҁu���ꌧ���|�p��w�I�v (27) p.29-47�v���u�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(10)��i����(5)��ȔN�s�����v�\����B�@
|
��R �L�q���u���ꌧ���|�p��w�Ɖ���L���X�g���Z����w�v�ɔ��\�����u�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤���i1�`10�j�v���̓��e����\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_���� |
| 1 |
���ꌧ���|�p��w�I�v (7) p.89�`112 |
1999-03 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(1)�u�Z�́v��i�𒆐S�Ɂ@ |
| 2 |
����L���X�g���Z����w�I�v (35) p.27�`42 |
2007-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(2)���@��i�̃p�t�H�[�}���X���@ |
| 3 |
����L���X�g���Z����w�I�v (35) p.43�`57 |
2007-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(3)�ŐV�̔��@��i�𒆐S�Ɂ@ |
| 4 |
���ꌧ���|�p��w�I�v (16) p.187�`206 |
2008-03 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(4)��i����1(�����E�吳��)�@ |
| 5 |
����L���X�g���Z����w�I�v (36) p.39�`58 |
2008-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(5)��i����2(���a�O����)�@�@ |
| 6 |
����L���X�g���Z����w�I�v (37) p.31�`60 |
2009-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(6)��i����3(���a�� 2)�@�@ |
| 7 |
���ꌧ���|�p��w�I�v (18) p.163�`182 |
2010-03 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(7)��i����(4)���a��(3)�@ |
| 8 |
����L���X�g���Z����w�I�v (42) p.11-24 |
2014-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(8)���玏�w���特�y�x����|�����
(�R�����I�q�����ޔC�L�O���W)�@ |
| 9 |
����L���X�g���Z����w�I�v (44) p.17-32 |
2016-02 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(9)�u�Z�́v��i�̌p�������@ |
| 10 |
���ꌧ���|�p��w�I�v (27) p.29-47 |
2019-03 |
�{�ǒ���̉��y���犈���Ɋւ��錤��(10)��i����(5)��ȔN�s���с@ |
|
�T���A�������ďC�u���������� (668)�@���W �g�x300�N�v���u���@�K�v���犧�s�����B
|
�g�x�n�n�O�Z�Z�N�Ɏv�� : �`���Ƒn�����߂����ā@��闧�T p.4-7
�g�x�ɑz�� : ���Ԃ��x�Ƃ̉�(���ɂ�)�ɗ�(����)�߂ā@�O�����Y p.8-12
���ƕ����Ƌߐ����������ɂ݂问����������̑g�x�@��؍k�� p.13-16
�������痮�����{����̑g�x �@���{ p.17-20
�g�x�̍L���� : �e�n�ɓ`���g�x �@���{ p.21-23 |
�g�x�̉��y�ɂ�����l�����@����� p.24-28
�������ꂨ���Ȃ�Ƒg�x �@�Ð����F p.29-31
�d�v���`�������u�g�x�v�̌p���ւ̎�g �@�g�c���q p.32-35
�g�x�̒S���肩�� p.36-42
�E |
�U���A�w��㊕����x�ҏW���ҁu��㊕��� = The Okinawa bunka 52(1) (�ʍ� 123) �v���u��㊕�������v���犧�s�����B
|
���ꌧ�o�g�C�O�ږ��̌o�ϓI���� :
�@�@���C�O�ږ����狽���ւ̑����̎���v�@ �ΐ� �F�I p.1-20
�扤���J�Ɨ������� : �������������̕_������ �@���� �L�� p.21-42
�d�R�̍��J�A�|�\�ɂ݂颐���̕\���@�ѓc �וF p.43-78
�����A�C�Ƌ��ɂ����炵�̋L�� : |
�@�@���A���}�[�ɂ�鋛����̌��ꂩ��@�O�c �q p.79-103
���ԓ��̃J�����[�}�@�@�@�����H ���q p.104-122
���{���A�_�Ɣ����A�_�̍����I�Ӌ` �@���� �� p.123-143
���̂ɂ����颐ᣂɂ���(��)�@ ���i �E���o�m���@�[ p.144-172
�E |
�V���A����X���u�ጎ�Ԃ܂�蕑��(����48)���l�\�y�����ʊ������u��T�E��j�̌|�\�v
�{��\�P�́q������ŕ��r�v���u�Ǖ� : �]�ː�Ƃ̒��� 41(7) p.10-13�@�]�ː�Ƙ@�؈��v�v���犧�s�����B
�W���A���c��v,�����,��A�u,�n�v�n�����u Cancer (28) p.33-36�@���{�b�k�ފw��v�Ɂu�����^�_���ɂ�����n�������k�}�G�r��3��̋L�^�v�\����B
�P�O���A�k��c �����u�˂��Ƃ�[�����s (369) p.88-91�v�Ɂu���ꃌ�|�[�g ����E���X���X(85)�t�F���X���z���ċ����猴�G�C�T�[�v�\����
�G�C�T�[�܂� 45 [�����܂�̉�]�o�Ŏ� [�G�C�T�[�Ղ���s�ψ���]�@2019
|
| �� |
. |
. |
, |
. |
| 25 |
. |
. |
, |
. |
| 26 |
. |
. |
, |
. |
| 27 |
�G�C�T�[�Ղ� 27 |
2001-09 |
. |
. |
| 28 |
. |
. |
. |
. |
| 29 |
. |
. |
. |
. |
| 30 |
�j�E����G�C�T�[�Ղ� : ��30��L�O�G�C�T�[�Ղ�@�����܂�̉�/�ҏW,�����ꕶ��/�ҏW
�����܂�̉� |
2004-09 |
. |
. |
| 31 |
�G�C�T�[�Ղ� 31 �����܂�̉�/�ҏW,�����ꕶ��/�ҏW �����܂�̉� |
2005-09 |
. |
. |
| 32 |
. |
. |
. |
. |
| 33 |
�G�C�T�[�Ղ� 33 �����܂�̉�/�ҏW,�����ꕶ��/�ҏW �����܂�̉� |
2007-09 |
. |
. |
| 34 |
. |
. |
. |
. |
| 35 |
. |
. |
. |
. |
| 36 |
�G�C�T�[�Ղ� 36 �����܂�̉�/�ҏW,�����ꕶ��/�ҏW �����܂�̉� |
2010-09 |
. |
. |
| 37 |
�G�C�T�[�Ղ� ��37�� �����܂�̉�@�ҏW,�����ꕶ�Ɂ@�ҏW �����܂�̉� |
2011 |
. |
. |
| 38 |
. |
. |
. |
. |
| 39 |
. |
. |
. |
. |
| 40 |
. |
. |
. |
. |
| 41 |
. |
. |
. |
. |
| 42 |
�G�C�T�[�Ղ� 42 [�����܂�̉�]�o�Ŏ� [�����ꕶ��]2016 |
2016 |
. |
. |
| 43 |
�G�C�T�[�Ղ� : �S����l���ѕ��� 43 [�����܂�̉�]�o�Ŏ�:�����ꕶ��]
|
2017 |
. |
. |
| 44 |
. |
. |
. |
. |
| 45 |
�G�C�T�[�܂� 45 [�����܂�̉�]�o�Ŏ� [�G�C�T�[�Ղ���s�ψ���]2019 |
2019 |
. |
. |
| 46 |
. |
. |
. |
. |
| 47 |
. |
. |
. |
. |
| 48 |
. |
. |
. |
. |
| 49 |
. |
. |
. |
. |
�@�Q�l�F���̃G�C�T�[�Ղ�Ɋւ����l�@--������܂�̉�ɂ���������@�@����
�m�q ���ꖯ���w��@�@�f�ڎ� ���ꖯ������ (�ʍ� 18) 1998 p.77�`92
|
���A���̔N�A���E,�~���B��,�����x���q,����e�q,���ь��],��ؗR��q,�c�������q,�����i�q,��F�},���c��,�����͎q�����y��������ҁu���y������
(36) p.3-17�v�Ɂu�u���y��������̑��n����U��Ԃ���k��v�̋L�^ (���y��������̑��n����U��Ԃ���ʍ�)�v����荇���B
���A���̔N�A�������������{�|�s�����[���y�w��ҏW�ψ���ҁu�|�s�����[���y����
= Popular music studies 23 p.69-74���{�|�s�����[���y�w��v�Ɂu���] �˓c����w�G�C�T�[���� : �ړ�����l�A�`�d����|�\�x�v���Љ��B
���A���̔N�A����c�݂Ȏq���u���m���y���� = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (85) p.163-167�@���m���y�w��v�Ɂu�Ǔ� �˓c���ꎁ �Ǔ����v����B
���A���̔N�A�哇���q���u���{�X�ъw����\�f�[�^�x�[�X 130(0) p.70�v�Ɂu���E���R��Y���n����̐X�ɂ�����l�Ԋ����̉e�����w�ԁv�\����B
|
���^:�@���E���R��Y�o�^��ڎw���u�����哇�A���V���A����k������ѐ��\���v���A2018�N5�����ێ��R�ی�A���iIUCN�j����o�^�����̊������A���{���{���o�^���E����艺�������Ƃ͋L���ɐV�����B�s�����哱���Ă�������܂ł̎�g�݂ɑ��A�����̒n��Z���͓o�^�Ɍ����ėl�X�ȕs�����@�����������킹�Ă�����ɂ���B����́A�u�o�^�����v���ړI�ɂ���A��������炷�����҂̎��_����̐��E��Y�̈Ӌ`�₻�̉e������̓I�Ɍ���Ȃ����Ƃ�����ƌ�����B�@�M�҂́A�ȑO���n��̎w���҂Ƌ��ɂ���̐X�y�т����ɐ������铮�A���̊��ۑS�Ƃ��̗����p�ɂ����Đ��ݓI�ɒn�悪������ۑ�ɂ��Č������A���̉����Ɍ�������g�݂Ƃ��đ��l�Ȋw�т̏�����E�^�c���Ă���B����́A����̐X�̊Ǘ��̌n����їыƂɏ]�����Ă���l�X�ɑ��闝����[�߁A����̐X�̊��p�݂̍����T�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����w��Â̌��J�u���̐��ʂ����B���E���R��Y���n�̎��R���͂����ɏZ�ސl�X�̐����̏�ł�����A�����ŗыƂɌg���l�X�Ɠs�s���ɏZ�ސl�X�Ƃ̊Ԃő̌��^�̊w�т̌𗬂�ʂ����ĕ�������}��w�K�̏�Ƃ��Ă̋@�\���������킹�Ă���B |
���A���̔N�A�i���r�Y���u���{�n���w��\�v�|�W 2019a(0)�v�Ɂu���i�Ǖ����ɂ݂���搳���Ƃ�������`����鎚�̓����v�\����B�@J-STAGE�@ |
| 2020 |
�ߘa�Q |
�E |
�P���A���c�Òj���u���������� = The study of nonwritten cultural materials 19 p.31-49�@�_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[�@�v�Ɂu�w�������R���L�x�ɋL���ꂽ�u�{����ԁv�̍\���ƕω��v�\����B
�Q���A�u�Z���N�V�����푈�ƕ��w �W�F�I�L�i���I���ʐ푈�v���u�W�p�Ёv���犧�s�����B�Q�O�Q�O
�@�@�@�ҏW�ψ��F��c���Y�C������C�쑺���C�����q�v�C���c����@�@��{: �u�R���N�V�����푈�ƕ��w
20�v(2012�N��)�@ 703p
|
�����ǂ��֍s�� / �R�V������
�C�� / �����p�g��
�l�ފ� / �m�O���^��
�����̚L / ����������
�A�J�V�A�� / ���Ǖג�
|
�J�N�e���E�p�[�e�B�[ / ��闧�T��
�M���l�����~ / ���g�h�쒘
�ÊԗǐS�� / �g�c�X�G�q��
���a�ʂ�Ɩ��t����ꂽ�X������� / �ڎ�^�r��
���
|
�� : �����L���� / �c�{�ՕF��
�ӂ����сu����̓��v / �����ɓs�q��
�� / �D�J�����Y��
���Ȃ�鐹�Ȃ錊 / �ˎR�P��
�E |
�R���A�����������u���m��w����w�������� = Bulletin of the Faculty of Education, Kochi University (80) p.231-254�v�ɁuNHK�^���ɂ�鉫�ꉹ�y���R�[�h:1950-1951�N : �X�����E�R�����j�Ɓu���ꏔ���̌×w�Ɨx�̉�v�v�\����B
�@�@�܂��A�����̑���p.255-292�Ɂu���ꌧ���|�p��w�����}���ٓc�ӕ��ɏ����ESP
���R�[�h�ژ^�\�c�ӏ��Y�����E�ŌẨ��ꉹ�y���R�[�h��T��\�v�����\����B�iIRDB�j
�R���A�W�{������ҁu�W�{���� 98�� �v���u�W�{�������v���犧�s�����B�@�@
|
�w�T�����P�x��q�Ӑ}�̍l�@�@�i�� �����@p.1-15
��v�̐W�R���ƏZ���̐E�\ : �o���̐V�����Ӗ��@��c �����܁@p.17-41
�T�w�W�G���_���ژ^(2015�N)�@p.65-73 |
�w���B���l�s�_�x�̘N�T�t�ɂ��ā@�� �����@p.43-63
�����ւ̗ՍϏ@�̈ڐA�l�@��]�F ���G�@p.23-41
�����T�@���z�j�ɂ�����u�V���a�v�̈ʒu�Â��@���X�� ���×��@p.1-21 |
�R���A�u���ꌤ���m�[�g29�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B2020-03-3
|
�{�Ó��̃p�[���g�D ���ђ��� p.1-8 �iIRDB�j
�u��A�C�֍s�������ɂ́A�C�������B�v�F�u�L�W���i�[�ƗF�B�v�b�̔w�i�Ƃ��̌���I�W�J �I���� p.12-24 �iIRDB�j |
�R���A���ꌧ���|�p��w�����������ҁu����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
(32)�v�����s�����B
|
�u�����������L���v�ɋL���ꂽ�g�x�u�����q�v�Ɋւ���l�@ : �u���Y�̎��v�Ƃ̓��e��r�𒆐S�� �䕔 ��a p.3-20
�g�x�ɂ����鉹�y�̗l���� ���� �� ���ꌧ���|�p��w���������� p.21-32
����P���ې����̃��Y�����͎��_ : �����哇�����x������Ɣ�r���ā@�v���c
�W p.33-49
�ߐ������ɂ����銥�D�n�[���[�̏��� : 1838�N�𒆐S�Ɂ@�����L�� p.51-75
�u�䊥�D������v�̌��� :���@�Ζؐm�j p.77-95
����31�N�x ���ꌧ���|�p��w�������������J�u�� �u�g�x�𑽊p�I�ɍl���� :
��������300�N�v�u���T�v�@�@��؍k�� p.113-115
����31�N�x�����u���T�v�E�u���^ ��11�� �{��\�P�搶�u���Ƒg�x�v�@�@�{��\�P,��؍k��
�� p.115-138
����31�N�x�����u���T�v�E�u���^ ��12�� �u���Ƒg�x�v���]��t�搶�@�@���]��t,��؍k��
p.138-161
���i�Ǖ����ɓ`�������g�x ������(�^�J�e�[��)(�ݍw����)�@�@��{�k�� p.178-166
���i�Ǖ����Ƒg�x : ���̓��Ɨ����̕����`���Ɋւ����l�@�@�@��؍k�� p.198-179 |
�R���A���ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�ҁu���[�T = ���̓҃Ѓ� : ���ꌧ���|�p��w���y�w������
(21) �v���u���ꌧ���|�p��w���y�w�����y������U�v���犧�s�����B
|
���w�����Ɠ`���̂��߂̘^�������A�[�J�C�u�̕��@�@����� p.1-9
����������{�̗��ǂ̐��@�@�������q p.11-23
�V���s�̖؋Ճe�B���r���̐���Z�p�Ƃ��̓`���@�ÎӖ���q p.25-38
�`�����_���[�ƃG�C�T�[�̗��j�čl�̂��߂̏��� : �k�����痮���ւ̐l�ƃ��m�̗�����肪����Ɂ@�������q p.39-52
���d�R���x�s�Ԕn�߁t�̍\�� : �������x�s������ŕ��t�Ƃ̔�r����@�R���Í� p.53-65
�u�G���v�ɂ����问���I�v�f : �]�䕨��Ƃ̔�r����@�@�����I�q p.80-68 |
�R���A�V���F�a���u���M�щ���̖�X�◢�R�v���u�u���M�щ���̖�X�◢�R�v�o�Ŋ��s���b�l��v���犧�s����B
�R���A�����K��ҁu�����D�Y���҂́u�����v���E : �w�哇�M�L�x�|���ƌ����v�v���u�א��o�Łv���犧�s�����B�@
(�p���E�����m��)
|
�哇�M�L �����D�Y���L �ؐ�M�b�q���r
�@�@�������l�b ���\��N�������D�Y���L�^�w�哇�M�L�x
�@�@�����{�ɂ��āq�����r / ���R�{ ��
�y�����Y���̗����D�u�����v�����̐��E / �����K�� �� |
�����l�̓��������k�ɂ��� / �^�h���[�� ��
�ߐ��ɂ����问���l�̓��{�Y�� / ���nj���Y ��
�w�哇�M�L�x���߂��铂��́u�`���v�Ɋւ����l�@ / �Î芡�O ��
�w�哇�M�L�x�ɋL���ꂽ������ / �������a �� |
�T���A��]�F�q�v�ҁu�����F : ���̎������l�� : �ʐ^�����W�v���u�����F�L�O�������U��������s�ψ���v���犧�s�����B
�@�@�@�@���L �����t�^: �u�m�Ԏ��ɍg�^���ߍ�i�W�v
�T���A��{�v���u�f�ڎ� �ŋ��o�ό��� 49 p.45-61�@���V��w�����o�ό������v�Ɂu����̔O���̂ƃ`�����_���[ : �A���K�}�[�Ɠ��G�C�T�[�v�\����B�@�iIRDB�j
�U���P�W���A�������Y�\�j�������^�c�Ԉ�Y���Ȃ��Ȃ�B�@�@�i���N�W�P�j
�V���A�����쎟�Y���V����p�w��ҁu�V���i�s�{�� (29) p.203-2�v�Ɂu�Ǔ���
�Ǔ� ���ь��]�搶�v����B�@�@
�V���A��c�Y�m ���E�B�e�u�E�~�T�g�D�� : �������x�ÓT�����x��ʐ^�W�v���u�i���m�j���[�u���o�Łv���犧�s�����B
�@�@�@�@�B�e���ԁF2017�N12������19�N7���܂ł̖�2�N
�@�@�@�@�x���F������}�A�m�O����A�x�����A�Ɏu�䈲�A�V�ԉ��a�q�A�e�삠��́A����[����
�W���A���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������ҁu�������X�̐V���Ȃ����������߂� : ����ɂ���������E�ۑ�E�W�]�v���u�ҏW�H�[���m���v���犧�s�����B�@�@(�쓇�����������p��
; 4)
|
�������X�����j ���������̌��� / ���P�� ��
�����X�̐ݗ� / �{��h�� ��
���ꑺ���̎Љ�I���� / �^�ߍ��� ��
�����̂̌o�ϑg�D�Ɋւ����l�@ / �ʖ��F�Y, �����Y ��
�����X / ���O���� ��
�������X���猩���Ă��鉫�ꑺ���̌��� / �{��\�F ��
����{���k���̋������X�̗��n�ƌo�c�`�Ԃ̕ω� / ����� ��
|
�������̑n�� / ��n��Y ��
�������X�̉ߋ��E���݂ƓW�]
�@�@����Ƃ̎Љ�I�ӔC�ƎЉ�I��Ƃ̌o�ϓI�ӔC / ���㗹�� ��
�ߑa����n��ɂ����鏬�K�͏����X (�������X) / �����הV ��
�������X�ɂ�����n�敟���̖��� / �����u�w ��
���ҊT�O���邢�͎��ȓ��e�Ƃ��Ẳ���
�@�@�����������̂���ы������X���� / �{��\�F �� |
|
�� 2016�N12��17��(�y)�ߌ�2���`5���A���ꍑ�ۑ�w13����301�����ɉ����āA���^�C�g�����Łu�쓇�����s���u��,
��38��v���J����Ă���܂����̂ŁA���j�I�Ȏ����Ƃ��Ă��f�ڂ������đՂ��܂����B�i�ۍ�j
2016 �N�x���^���� 2016 �N 12 �� 17 ���i�y�j<�ߌ� 2 ���`5 ��>���ꍑ�ۑ�w
13 ���� 301 ���������ɂ��āC���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������s���u���Ƃ̋��ÂŁC�u�������X�̐V���Ȃ����������߂ā\����ɂ���������E�ۑ�E�W�]�\�v�Ƃ����e�[�}�̂��ƁC����n���w��V���|�W�E�����J�Â��ꂽ�B�Q���҂͖�
80 ���ł������B�^����̃V���|�W�E���J�Â̎�|�́C�ߔN�C�S���I�ɔ_�����n��𒆐S�ɐl�������ƍ���Љ�̐i�W�ɂ�āC�W���ɂ�����R�~���j�e�B�[�Љ�̎����I�ێ��Ɋւ���ۑ�C����ɂ͉ߑa�n��̍���҂𒆐S�Ƃ���t�[�h�f�U�[�g���s��������ҁt�����݉����Ă���B���̂悤�Ȓ��ŁC���ꂪ���˒n�Ƃ�����u�����X�v�sCommunity
(village)owned shop ���邢�́iCommunity store�j�t���t�[�h�f�U�[�g�������̂��߂̕���̂ЂƂƂ��āC�܂��d�v�ȃR�~���j�B�[�Z���^�[�̏�Ƃ��Ă��̈Ӌ`���ĕ]������Ă��Ă���B�����Ŗ{�V���|�W�E���ł́C����܂ł̉���𒆐S�Ƃ��鋤���X�̂���݁C����Ɖۑ�C����ɂ͏����ւ̓W�]�ɂ��ĊC�O�̎������ۂ̋����X�o�c�҂ɂ�����u�b��D������Ȃ���͍����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B�^�ŏ��̊�u���ł́C���O������(�쓇�������������ʌ������E�v���đ�w���w�����_����)�́C�u1970
�N�`80 �N��ɂ����鉫��̋������X�i�w�쓇�����x�n�����f�ڂ̋������X�_���𒆐S�Ɂj�v�Ƃ����e�[�}�ōu�b���Ȃ��ꂽ�B���̒��œ��O���́C����̋������X�́C�����Z���������ŏo���C�^�c����X�܂̂��ƂŁC�����X�͓���Ɩ��ł��鐶���K���i��H���i�C�_�Ɨp���ނɎd����̔��ɉ����āC�������Ŏ��n���ꂽ�_�Y���̈ϑ��̔��C����ɂ͏W�������ɂ�����d�v�ȏ������̏�Ƃ��Ă̖������͂����Ă����B�܂����ẮC�����X�ɂ����闘�v�͑������ɂ����鏔�s���̊�t�⑺���Z���̔z���Ȃǂɏ[�Ă�ꂽ�肵���B����
1980 �N��ȍ~�C��^�X��R���r�j�G���X�X�g�A�[�̉���{���i�o�C���[�^���[�[�V�����̔��B�ɂ���āC���ނ̈�r�����ǂ��Ă������ƂȂǂ���������B�^�������X�Ɋւ���e�����ł́C�ŏ��ɋ{��\�F��(�쓇�������������ʌ������E�����w�l���w������)�́C�u����E�����ɂ����鋤�����X�̉ۑ�Ɖ\���v�Ƃ����e�[�}�ŕ��Ȃ��ꂽ�B�^���\�̒��ŁC����≂���̉ߑa�n��ɂ����ċ������X�o�c�𑱂��鎖���ɂ͑傫�ȈӖ������邪�C���̔w��ɂ́u���������̐��_�v��u���C�}�[���v�Ƃ������t�ŕ\���ł�����̂ł͂Ȃ��C�������X�����҂̂��܂��܂Ȋ��������݂��Ă��邱�Ƃ����������B�܂��C����͊e�n��̋������X���Ȃ��ĐV���Ȃ�\���̖͍������킹�Ē�Ă����B�^���ɑ��㗹����(�쓇���������������E���ꍑ�ۑ�w�o�ϊw������)
���u�������X�̃}�l�W�����g�\�p���Ƃ̔�r�Ɍ���o�ϐ��ƎЉ�̗����\�v�Ƃ����_��ŕ��Ȃ��ꂽ�B���̕ł́C�������X��������ۑ�ɂ��āC���ɉp���Ƃ̔�r���瓾����o��������āC�������̂��߂̕�������Ă����B���ɂ͎Љ�I�ۑ�͂��炽�߂ĂȂɂ��Ƃ������_����C�t�[�h�f�U�[�g���̂������₢�����K�v��������B�^�Ō�ɁC�������X����C�̎������玁�ɂ��u�n�抈�����Ɖ������X�̉ۑ�v�Ƃ����e�[�}�ŁC���������X�����g��ł���n�抈�������Ƃ�n�掑���̌@��N�����ȂNj�̓I���H��ɂ��ĕ��Ȃ��ꂽ�B�^�㔼���̑������_�ɂ����ẮC�u���҂̒��N�̋������X�����Ɋւ���ڍׂȕ���C�����̎��₪�o����C�������X�̈Ӌ`�Ə��ۑ�C����ɂ͏����W�]�ɂ��Ă��܂��܂Ȏ��_���瓢�_���ł����V���|�W�E���ł������B
�i���ӁF���� ��j
�@�@�@�@2017�N6��30�����s�^����n���w��u����n���w���� �� 66 ���v����@ |
�X���Q�X���`�P�P���Q�R�����A�u�����s�ʐ^���p�فv�ɉ����āu�����ʂ̎ʐ^�v�W���J�����B
�X���A�ɓ��M�O, �Γc�N�N�� ; �N���X�g�t�@�[�E�X�e�B�����X��u�����ʂ̎ʐ^�v���u�����s���j�������c�����s�ʐ^���p�فv���犧�s�����B�@
(TOP�R���N�V���� = TOP collection, )
�@�@�@�@���: �����s, �����s���j�������c�����s�ʐ^���p�ف@�@���E�\��:
�ɓ��M�O, �Γc�N�N
�@�@�@�@�o�i���: �R�c��, ��ÍN�Y, ���ǍF��, �Ɏu�䗲, ���~����, ��ÖL��, �ΐ�^��
�P�P���A�� �������u�쓇�j�w = Journal of Ryukyuan studies (88) p.57-61�v�Ɂu���] �v���c�W�E�O���킩�ȁk�ҁl�w����|�\�̃_�C�i�~�Y�� : �n���E�\�ہE�z���x�v���Љ��B�@
�P�P���A�啽�a�O,��c�G�q,���c���q,���؏��t���_���v��w��ҁu�_���v��w�
= Journal of rural planning 39 (�ʍ� Special issue) p.222-231�v�Ɂu���d�R�̐약�E�|�x�E�����ɂ������Ԃ̋�ԂƍՎ��̌p���Ɋւ��錤�� (�_�����W��)�v�\����B�i-STAGE
�P�P���A�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���@�֎��ҏW�ψ���ҁu�i�`�������q�X�g���[�~���[�W�A�� = Natural History Museum (1) p.1-18�@�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���v�Ɂu���W ���{�ŏ��߂Ă̍������R�j�����ق̐ݗ��Ɍ����āv���f�ڂ����B
�@�@�@��ʎВc�@�l �������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���
�@�@�@��113-0033 �����s������{�� 7-2-2 �{�� MT �r�� 4 �K
�@�@�@E-mail : okinawa.n.h.museum@gmail.com
���A���̔N�A�{�����W���u���{�����l�ފw������\�v�|�W 2020(0) p.E06�v�Ɂu��p���Z���ɂ�����ՋV�ɗv����铮���̉ϐ��ƕs�ϐ��̌���:�䓌���p�C�������i�r�p���j�����钖�Ɠ�����Ɂv�\����B�@�@J-STAGE
���A���̔N�A�g�Ɗԉi�g�����{�������Y�{��ҁu�������Y���� = Studies in folk-narrative (43) p.1-19�v�Ɂu�����̗w�̕����Ƃ̏o� : �w�����낳�����x�́u��/���v�L�ڂ𒆐S��
(��l�O������J�u��)�v�\����B�@
���A���̔N�A���y��������ҁu���y������ (37)�v�Ɂu���ь��]�O��\�Ǔ����W�v���҂܂��B
|
����(��)���]������ (���ь��]�O��\�Ǔ����W)�@ p.143-146
���ь��]����v�Ɛшꗗ (���ь��]�O��\�Ǔ����W)�@p.147-152
�����҂Ƃ��Ă̏���(��)���] (���ь��]�O��\�Ǔ����W)�@���эK�j�@ p.155-164
��w�����Ƃ��Ă̏��ь��]�搶 (���ь��]�O��\�Ǔ����W)�@�@��g�����@�@p.165-167
���]�搶�Ƃ̎v���o (���ь��]�O��\�Ǔ����W ; �Ǔ��̂��Ƃ�)�@���ѓT�q�@p.176-178 |
|
| 2021 |
3 |
�E |
�P���A��J�וF���u���[�A�V�r����G�C�T�[�� : ����ɂ�����K���Ƃ��Ă̎Љ��v���u�{�[�_�[�C���N�v���犧�s����B
�Q���P�O���`�R���Q�X���A�A�u�u�����v�Y�W�v�`����̌��z�ƕ��������������o�g�̌��z�Ɓ`�v�W�����鑺�썲�ۗ��j�����}���قŊJ�����B�@
���ꌧ�����S���鑺������215
|
�����v�Y�W : ����̌��z�ƕ��������������o�g�̌��z�� : �ߘa2�N�x�썲�ۗ��j�����}���ي��W
:
�@�@�����W�p���t���b�g ���鑺�썲�ۗ��j�����}���� �ҏW ���鑺�썲�ۗ��j�����}����
|
�Q���A�^����, �����k���Y, �g�Ɗԉi�g�ҁu���A�W�A�̉̂ƕ����v���u�א��o�Łv���犧�s�����B�@ (�A�W�A�V�w, 254)
|
���A�W�A�ɂ�����̂ƕ����̏o� / �^����
�����Ӌ������̉̂ƕ����̂������ / �����k���Y
�����̗w�̕����Ƃ̏o�:�w�����낳�����x��
�@�@���L�ږ@�𒆐S��/�g�Ɗԉi�g p.29-49
�̂ɂ����鐺�ƕ����̏o��Ƌ��� / �������u
�Ñ�̖̉̂� : �����@�̕ϖe�ɂ���/�G���}�R�[���E�����h�~�[��
���������E����ɂ�����̂ƕ��� : �����낳���� / �Ɖ��� |
���̂Ɠ엮���̝R��̂̕����L�^ / �g�Ɗԉi�g
�쓇�̗w�̋L�^�Ɠ`���̏���:�|�x���̊��S���߂�����/�떓�b��
�s���̊|�����������ɂ����鐺�ƕ��� / ��ˌb�q
�y�[�Օ��ɂ����鐺�ƕ����̉��� / �����k���Y
�����Ð��c���̉̂ƕ��� / �^����
�{�Â̌×w�Ɛ_�� / �{�i��
�y�[���̍Օ� / �y�[�]�N�m�T�C�u�� |
�R���A���_��l���u�k�C����w ���w���@2020 �N�x ���Ƙ_���@p.1-23�v�Ɂu��������ɂ�����N��G�C�T�[�̕ϗe�Ƃ��̔w�i : �k�J���ӊ���N��𒆐S�Ɂv�\����B�@�@�iIRDB�j
�R���A�u���ꌤ���m�[�g�@30�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B
|
����̘̐b�ƕa ���ђ��� p.1-13 �iIRDB�j
|
����E�����ɂ�����ؗd���̓`���Ƌ��E�� �I���� p.14-24 IRDB�j |
�R���A���K�_�s���ۑ��E�U���S�����c����ǕҏW;�Ί_��ďC�u���K�_�K�C�h�u�b�N:���ʁE�����̐_�X:���ޕҁE�����ҁF���l�X�R���`������Y�v���u�i�j���j���K�_�s���ۑ��E�U���S�����c����ǁv���犧�s�����B�@�P�Q�U��
�@�ߘa2�N�x�����������|�p�U����⏕��(�n�敶�����������p���i����)�@�@�����^���e���m�F�̂��ߌ�����v���@�Q�O�Q�R�E�R�E�R�O�@�ۍ�
|
�����̃g�V�h���i���������܂̂Ƃ��ǂ�j
�j���̃i�}�n�Q�i�����̂Ȃ܂͂��j
�\�o�̃A�}���n�M�i�̂Ƃ̂��܂߂͂��j
�{�Ó��̃p�[���g�D�i�݂₱���܂̂ρ[��Ƃ��j
�V���̃A�}�n�Q�i�䂴�̂��܂͂��j
�Đ�̐����Ԃ��i��˂���݂̂����Ԃ�j
�����̃J�[�h���i�݂��܂̂����ǂ�j
�g�l�̃X�l�J�i�悵�͂܂̂��˂��j
�F���������̃����h���i���܂��������܂��߂�ǂ�j
���Γ��̃{�[�i�����������܂̂ڂ��j
��q���̃g�V�g�C�h���i���˂����܂̂Ƃ��Ƃ��ǂ�j
|
�\��̃i�S���n�M�i�̂���̂Ȃ��߂͂��j
��I�c�̃A�}���n�M�i�������肾�̂��܂߂͂��j
�����E䣍�̃A�b�|�b�V���i�������E���݂����̂����ۂ�����j
���d�R�̃A���K�}�i�₦��܂̂��܁j
��R�̃J�Z�h���i���݂̂�܂̂����ǂ�j
�唒�̃g�r�g�r�i�������炫�̂ƂтƂсj
�n���̃g�C�g�C�i���ӂ��̂Ƃ��Ƃ��j
��c���̃i���~�i�̂��ނ�̂Ȃ��݁j
�삳�܂̃��b�J�u�C�i�݂Ȃ݂��܂̂�����Ԃ��j
��F�E�`���̃��b�g���i�Ă��܁E�����ǂ܂�̂����Ƃ��j
�E |
�R���A�Җ{���傤�������{���y�w��� �u���y�w = Journal of the Musicological Society of Japan 67(2) p.103-105�v�Ɂu���] �v���c�W,�O���킩�ȕҁw����|�\�̃_�C�i�~�Y�� : �n���E�\�ہE�z���x�v���Љ��B
�R���A�����������u���m��w����w�������� = Bulletin of the Faculty of Education, Kochi University (81) p.219-261�v�Ɂu�c�ӏ��Y�ɂ��A�W�A�E����̖������y���� : �^���e�N�m���W�[�̔��B�����_�Ƃ��āv�\����B�@�@�@�@�iIRDB�j
�R���A���O��, �얞�M��, �y�~����@����u����E�{�Ó����K�̔�ՃE���K�� : ���O���t�H�g�E�A�C�v���u�Վ����сv���犧�s�����B�@�@�@�@
(������܂�u�b�N�X = Gajumaru books ; 17)
�T���A���Ȑ^�I���A�[�g�E�h�L�������e�[�V�����w��ҁu�A�[�g�E�h�L�������e�[�V�������� = The bulletin of Japan Art Documentation Society (29) p.3-16�v�Ɂu�ʐ^���f�B�A�����Ƃ���������J�A�[�J�C�u�Y : �ʐ^�ƁE��ÍN�Y����������Ɂv�\����B�@J-STAGE
�U���Q�R���A�u�����V��z�[���v�ɉ����āu�������x �ʏ闬�����݉�F���g�Ύ}�@�|��70���N�L�O�����F�u��N�̋F��v�@���\�H�ɗ�����
�x���ւ�`�v�v���J�Â����B
�U���A�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���@�֎��ҏW�ψ���ҁu�i�`�������q�X�g���[�~���[�W�A��
= Natural History Museum (2)�@(���W ��1��V���|�W�E���y�L�^�z ����ɍ������R�j�����ق�!
; ����̍������R�j�����قւ̖�����낤)�v���u�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���v���犧�s�����B
|
��u�� �������R�j�����قƐ������l�� �@���Y �[�� p.4-15
����̎��R�Ɛ������l�� �@�@���R ���� p.16-22
���E��Y���n�u�����E�����v�̎��R : ���̈�Y���l�ƕی�S�ہ@�@��� �@�� p.23-28
�o�C�I�Y�Ƃ̒m�I��ՂƂ��Ă̔����� : �����m�ۂ����f���̈�Ƃ��ā@�Z �ϑ�
p.29-33
�������R�j�����قƊό��@�@���{ ���q p.34-39
����̐������l���Ǝ��R�j�����ف@�@��l�_�u p.40-44
���{�w�p��c�ƍ������R�j�����ٍ\�z�@�@�ݖ{���Y p.45-50
�p�l���f�B�X�J�b�V���� ����ɍ������R�j�����ق�! : ����瓇�̖L���Ȏ��R�𖢗��ɂȂ�
�@�@
�@�@�����c�r�@�Z �ϑׁ@��l�_�u�@�ݖ{���Y�@����@���@���R�����@�@�їǔ��@���Y �[��@���{���q�@�|�����m�@ p.51-65 |
�W���A�{�����W���u������ = The journal of island studies 22(2) p.153-164�@���{���w��v�Ɂu����k���ɂ�����Վi�̎��Ԃƒn��I���� : �j���_���Ə����_���̊W���v�\����B�@�@�iJ-STAGE�j
�X���A�u�ߘa3�N�x�^�ߌ����h�V�� : �^�ߌ�����̐X���Ȃ��z�[���v���u�^�ߌ������ꕟ���ہv���犧�s�����B
�@�@�@DVD 1�� �@ �i��: �v��p
|
�q�ߘa3�N�x�^�ߌ����h�V��v���O�����r�I�[�v�j���O/�^�ߌ�����̐X���Ȃ��ف[��Љ�VTR/�J��̂��Ƃ�(���X����)/���J��(������ŕ�)(������q/��Ð�H/���g�A���q/�^�M�u�D�q)/��Îґ�\���A(�Ɖ���)/���o�j��(�쉮����F)/�^�ߌ��̕l(�R������/�����)/�O�V�l(���ԋ��q)/���̕�(��Ð�H/�^�؎u�D�q)/�ɏ����Ԑ�(���g�A���q)/���߂�[(������q)/�ӎ�(��������) |
�P�P���A���c �L���uHoppo journal = �k���W���[�i�� 50(11) (�ʍ� 625) p.116-121�@�i�D�y�jRe Studio�v�Ɂu�푈��Y���߂��闷(75)�@83�l�̑������u�W�c�����v�������ꌧ�ǒJ���̃`�r�`���K�}
���������Ȃ����ꌧ���̐S��v�\����B
�P�P���P�R���A�I�����C���ɂ���u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v��Âɂ��u��S�R��쓇�����s���u���v���J�����B
|
���搧����݂�ߐ������Љ� : �c��Ǝq���̑Θb
���@���ꂽ������ �{��O�� p3 - 9
�������猩��ߐ������̎Љ�:�q���Ɏc�������b�Z�[�W ��ؗI p10-17 |
�ߐ������ɂ�����푒�F���̕ω�:�c����ǂ��J�邩 �R�c�_��p18-24
�ߐ��̌n���ƍ����̈ʔv �����W �@p25-29
����߂���ٔ��Ɩ@��:���������̎��Ⴉ�� �n�Ӕ��G�@p30-41 |
|
�Q�l�F�u��������}���كT�[�`�v���猟�������u���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������v��Â̑�1�`�S�R�́u�쓇�����s���u���v�̓��e�ꗗ�\
| �m�� |
�J�Ó� |
�ꏊ |
�u�����e |
�G������ |
| 1 |
1980�N2��2��(�y)
�ߌ�1�� |
����^�C���X�z�[�� |
�㉇�F���ꍑ�ۑ�w�A���ꌧ����ψ���A�ߔe�s����ψ���A���������ANHK��������� |
|
| 2 |
1981�N1��31�� |
�����V��z�[��
|
�\�Ƒg�x�̊ӏ܉�^�\�Ƒg�x : �H�ߖ����q
��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� �����V��� ���ꌧ |
|
| 3 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 4 |
1983�N3��4��(��) |
�����V��z�[�� |
�~���N���ʕ�(�䂪��)�ƒ��҂̑��(���ӂ���) ,���R, ��
��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� �����V��� ���ꌧ |
|
| 5 |
1984�N1��28�� |
|
�퐶�O���ɔ�肳�ꂽ�^�h���L�ˁ^���{�A�q
��ÁF����^�C���X �㉇�F�������������NHK��������� |
(�u�n��ƕ����v��17�E18������ |
| 6 |
���a60�N1��26�� |
�����V��z�[�� |
�쓇�̖���������� : �u���ƖA���]��
�A���Y�Ƃ̉ۑ�ƓW�] / �O�֗��v
�A���ƍ����� / �Ɖ���C�q
��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� �����V��� |
|
| 7 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 8 |
|
|
�[�~�i�[������̔_��-���M�є_�Ƃւ̖͍�- |
|
| 9 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 10 |
1989�N1��28��(�y) |
|
��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������A�����V���
�㉇�FNHK���������,����e���r���� |
|
| 11 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 12 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 13 |
1992�N2��1��(�y)
2���`5�� |
����^�C���X�z�[�� |
�g�[�g�[���[�Ƒc�搒�q : ���A�W�A�ɂ�����ʔv���J�̔�r
��13��쓇�����s���u���F���ꍑ�ۑ�w�n��20���N�L�O�V���|�W�E��
�@����̈ʔv���J ���~ ��
�@�c�搒�q�F����?��Ƒ�p�ɂ�����ʔv���J �� �p��
�@�c�搒�q�ƈʔv�ɂ�����؍��l�̈ӎ�-�c��̏����A�q���̎��i �� �m��
�@���A�W�A�ɂ�����ʔv�̂܂� �|�c �U |
|
| 14 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 15 |
1993�N12��18��(�y)2��-5�� |
�X��p�s�����(���z�[��) |
����^���p�̐��E : ���a�S�N���L�O����
���L ���: ���ꍑ�ۑ�w�쓇����������, �X��p�s����ψ���, ����^�C���X�� |
|
| 16 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 17 |
1996�N1��27(�y) |
|
�쓇�����s���u�� : �w�����낳�����x�Ƃ��̎���
��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������E����^�C���X��
�㉇�FNHK��������ǁE�������� |
|
| 18 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 19 |
1997�N12��4��(��)
�ߌ�5���`8�� |
����^�C���X�z�[��
(����^�C���X��3�K) |
�ɔg���Q�v��50�N�L�O�V���|�W�E��
�u����v�̎���E�V�������ȑ����l���� |
|
| 20 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 21 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 22 |
|
|
�A�����J���̘J���͎���ƈږ� �V���i�r p.59�`68
����ږ��W�J�̔w�i�Ƒ��� �ΐ� �F�I �@p.69�`79
��u��s�ɂ݂�ږ��̂��낢�� �ɔg ���q p.81�`92 |
�쓇���� (23) |
| 23 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 24 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 25 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 26 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 27 |
2005�N11��19��(�y) |
���������������� |
���w����݂�����̐��60�N
�����F ��ÁF���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������E����^�C���X�Б�
�㉇�FNHK��������ǁE�������������ENHK��������ǁv |
|
| 28 |
2006�N11��11��(�y)
�ߌ�1��-5�� |
���ꍑ�ۑ�w7���� |
���A�W�A�������̏��� : �����E�؍��E�����̎��R���Ɗ�w����
���: ���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� |
|
| 29 |
2007�N12��1��(�y)
�ߌ�2���`6�� |
|
�n��Ɣ����ق̊ւ����l���� : ���������فE���p�ق̐V���ȓW�J���߂�����
���: ���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������A����^�C���X�� |
|
| 30 |
2008�N11��29��(�y)
�ߑO10��-�ߌ�5��30�� |
�Y�Y�s�����z�[��(���z�[��) |
�ߑ㉻�Ɠ`���|�\
���A�W�A�������̏���| ; part3
���L ���: ���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� |
|
| 31 |
��2009�N12��19��(�y)
�ߌ�1��-5�� |
���ꍑ�ۑ�w
7����2�K7-201���� |
���A�W�A�̒��̗��� : ���Î��̗����N��400�N���l����
���: ���ꍑ�ۑ�w���������@�\�쓇���������� |
|
| 32 |
2010�N11��13��(�y
)�ߌ�1���`5�� |
���ꌧ�������فE���p�ٍu�� |
"���܂��Ƃ���"�̖��� : �����h�̌���Ƃ��̍Ċ�����
|
|
| 33 |
|
���ꍑ�ۑ�w
7����2�K7-201���� |
���A�W�A�̐��b�Ɠ��A�W�A�l�̊��� 2011 (�쓇�����s���u��, ����33��)
������: 2009�N12��19��(�y)�ߌ�1��-5��
���: ���ꍑ�ۑ�w���������@�\�쓇���������� |
�u���̊J�Ó����͌����v |
| 34 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 35 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 36 |
2014�N11��29��(�y)
�ߌ�2���`5�� |
|
�A������݂��V�}�̌����i : �t�N�M�Ɏ���鑺��
|
|
| 37 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 38 |
2016�N12��17��(�y)
�ߌ�2���`5�� |
|
�������X�̐V���Ȃ����������߂� : ����ɂ���������E�ۑ�E�W�] |
|
| 39 |
2017�N12��9���y
�ߌ�1���`6�� |
|
���A�W�A�̋L���ƋL�^ : �l�X�̎v����ǂ�
2017�N�x����Z�ԍ��ۊw�p�𗬍u���� -- �W�莆 |
|
| 40 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 41 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 42 |
|
|
�L�^�Ȃ� |
|
| 43 |
2021�N11��13�� |
�I�����C���J�� |
���搧����݂�ߐ������Љ� : �c��Ǝq���̑Θb
���@���ꂽ������ �{��O�� p3 - 9
�������猩��ߐ������̎Љ�:�q���Ɏc�������b�Z�[�W ��ؗI p10-17
�ߐ������ɂ�����푒�F���̕ω�:�c����ǂ��J�邩 �R�c�_��p18-24
�ߐ��̌n���ƍ����̈ʔv �����W �@p25-29
����߂���ٔ��Ɩ@��:���������̎��Ⴉ�� �n�Ӕ��G�@p30-41
���: ���ꍑ�ۑ�w�쓇���������� |
�쓇�����s���u���@43 |
| 44 |
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
�@�v�]�F�L�ڕ��@�ɓ��ꐧ�������悤�Ɏv���܂����̂ŁA�������܂��������������肢�������܂��B���������Ȃ��悤�ȋC���v���܂����B�@�Q�O�Q�R�E�P�O�E�R�O�@�t�L�@�ۍ� |
�P�Q���A�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���@�֎��ҏW�ψ���ҁu�i�`�������q�X�g���[�~���[�W�A�� = Natural History Museum (3)(���W ��2��V���|�W�E���y�L�^�z ����ɍ������R�j�����ق�! ; ����ɑ���V���������ّ��ɂ��Č�荇����!)�v���u�������ꎩ�R�j�����ِݗ������ψ���@�֎��ҏW�ψ���v���犧�s�����B�@�@
|
����Ƃ�����ɂ����ė~�����u�������l���̉Ȋw�v�̋��_�Ƃ��Ă̎��R�j������
: ���p�҂̎��_����@���c �p�� p.5-10
�����قɂ�����s���Q���^�f�[�^�x�[�X�̍\�z�Ƃ��̐��� �@���\ �G p.11-18
�n�N�u�c�J����,�l�ޕ����̍�������@�֓� ���� p.19-27
�o�C�I�~���e�B�N�X�̕�ɂƂ��Ă̎��R�j������ �@���� ���k p.28-34
�w�Z����Ǝ��R�j�����ق��A�g�������犈���̉\�� : ����̎��R�������p���������n�l�ވ琬 �@���� �K�i p.35-42
�p�l���f�B�X�J�b�V���� �@���c�r,�@��� ��,�@���c�����@,���r�a�v�@�є��@�Îӗ��@�������L
�@�@��,���c�p���@���\�G�@�֓�����@�������k�@�@�����K�i�@�n�n�x�� p.43-61
�L�^�ʐ^�@p.62-64 |
�P�Q���A�V���F�a,�ɉ���������w�_�w���ҁu������w�_�w���w�p�� (68) p.22-27�v���u�����̌Õ����ɂ݂�����J�A���~�K�C���ƃV�a���N�v�\����B�iIRDB�j
|
�u������w�_�w���w�p��(61�`78)�v�ɔ��\���ꂽ�u���J�A���v�֘A�̘_������ꗓ�\
�iIRDB�j
| �m�� |
�G�������� |
���s�N�� |
�_���� |
���\�Җ� |
| 1 |
(61) p.55-66 |
2014-12 |
����E���������c�V�k�O�̍��J�A���S���Y�C(1) |
�V���F�a �@���� |
| 2 |
(61) p.67-78 |
2014-12 |
����E���������c�V�k�O�̍��J�A���S���Y�C(2) |
�V���F�a�@ ���� |
| 3 |
(61)p.79-86 |
2014-12 |
����E���������V�k�O�̍��J�A���C�k�K�V |
�V���F�a �@���� |
| 4 |
(62) p.77-86 |
2015-12 |
����E�{������u����V�k�O�A���ΐ��t���������J�A�����u�j�b�P�C�̈Ӌ` |
�V���F�a �@���� |
| 5 |
(63) p.77-87 |
2016-12 |
����E����s�A�l��Ó��̃V�k�O�A���̃i�K�p�J�j�N�T |
�V���F�a �@���� |
| 6 |
(64) p.41-54 |
2017-12 |
���M�щ���̗��R�Ƌ������鑺���̕�炵 |
�V���F�a �@���� |
| 7 |
(64)p.55-63 |
2017-12 |
����E�ɕ������c���̃E���W���~���J�̍��J���Ƃ��ẴK�W���}�� |
�V���F�a �@���� |
| 8 |
(65) p.147-158 |
2018-12 |
����E����s4���̍��J�A�� |
�V���F�a,�@���� |
| 9 |
(66) p.51-63 |
2019-12 |
����,�ÉF�����Ɖ����p�̃E���W���~�̍��J�A�� |
�V���F�a�@,�ɉ�,�@�Ő��� |
| 10 |
(67) p.7-13 |
2020-12 |
����E�v�����C�U�C�z�[�̍��J�A�� |
�V���F�a�@,�ɉ��@�������G |
| 11 |
(67) p.14-20 |
2020-12 |
����E�v�����̍��J�A���̘A�ւƗ��j�I�Ӌ` |
�V���F�a�@,�ɉ��@�������G |
| 12 |
(68) p.1-6 |
2021-12 |
�����̌Õ����ɂ݂�����J�A���A�U�J |
�V���F�a�@,�ɉ� |
| 13 |
(68) p.7-11 |
2021-12 |
�����̌Õ����ɂ݂�����J�A���_�V�`�� |
�V���F�a�@,�ɉ� |
| 14 |
(68) p.12-21 |
2021-12 |
�����̌Õ����ɂ݂�����J�A���_�V�`���N�M�ƃA�U�J�K�l |
�V���F�a,�@�ɉ� |
| 15 |
(68) p.22-27 |
2021-12 |
�����̌Õ����ɂ݂�����J�A���~�K�C���ƃV�a���N |
�V���F�a �@�ɉ� |
|
�P�Q���A�k�V���炪N27�ҏW�ψ���ҁu�����Ɩ��w���镗 : ����x(1979�N)��ǂ�
: ����ւ�U�^�[���A���邢�͋t�������J���[�ʐ^ (����A�[�g�V�[��)�v�ɁuN27
: �u���̊�-����v��]�� (9) �@ p.98-102�v�\����B
���A���̔N�A���ꌧ�������فE���p�� �u���ꌧ�������فE���p�ٔ����ًI�v (14)
�v���u���ꌧ�������فE���p�فv���犧�s�����B
|
���ʓW�u��v : �R���i�Ђɂ�����J�ÂƎ��ȕ]�� �F���� �� p.1-8
���NJԓ��ɂ����鍩���ޒ����� �e�� ��,���� ��j,��� ����,��� ��} p.9-15
�ɍ]����u���L�˂���o�y���������l���ɂ���(���) �V�Y ����,�y�� ����,�ʞ�
�� p.17-21
�����j����̐ԐF�痿�֘A���� : �ɍ]����u���L�ˁE�{�Ó��s�Y���Ղ���̕@�ʞ�
��,�v�L ��k,�R�� �^�� p.23-32
�����嗤���ݕ��ɂ�����`���֘A�̏��K�͏�s��� : �����Ȗk���E���Y���𒆐S�Ɂ@�R�{ ���� p.33-62
�f��u�����̕����v�Ɋւ����l�@ : ���֘A�𒆐S�Ƃ��ā@�@�茴 ���q p.63-79
��c���G��90�N��̉��� ���M���e�����@�@�O�� ��� p.81-88
1955�N�����̈ɓ��������������ɂ��ā@�@���X ��Y p.89-96
�ߘa���N�x �����َ����C���� : �g�x�W�����Ɋւ���C���@�@���X ��Y,�c�� �I,�y�� �X�q p.97-103
��������������Y�E�W�ύċ����Ƃɂ�����ׂ��b�����O���̒����@�@�� ������,�F�� ���P,���� �� p.105-116
�앗�����V��̉F�v�c�ƌ�q�̕�Ɋւ��钲���@�@���� �r��,��p �䂩��,���� �悵�T,�ۋv�� �z p.117-132
�������W��������̈�l�@�@�@��p �䂩�� p.133-140
�w�Z�A�g���f����������2020 : �V�^�R���i�E�B���X�����g��h�~��܂��ā@�@���
�v�\ p.141-147 |
���A���̔N�A �Җ{ ���傤�����u���y�w 67(2) p.103-105�v�Ɂu���]�F�v���c�W�C�O���킩�ȕ� �w����|�\�̃_�C�i�~�Y���\�\�n���E�\�ہE�z���x �i�����F�����ЁC2020�N4��15���C376�ŁC\2,800�{�ŁCISBN978-4-909544-07-0�j�v���Љ��B�@ J-STAGE
���A���̔N�A��{�v���}�g�w�@��w�}���ى^�c�ψ���ҁu�}�g�w�@��w�I�v = Bulletin of Tsukuba Gakuin University / 16 p.115-125�v�Ɂu����O���̉̎��ƍ\�� : �A���K�}�[�Ɠ��G�C�T�[�v�\����B�@�@
���A���̔N�A���c�^�m���֓��w�@��w���w���l���w���r�����w����ҁuKGU��r�����_�W
= The KGU journal of comparative cultural studies (12) p.127-151�v�Ɂu���E�ɍL���鉫��n�n���C�ږ��̌��� : �G�C�T�[�ɂ���Đ[������E�`�i�[�l�b�g���[�N
(����������� ��ސE�L�O��)�@�v�\����B
���A���̔N�A�쉮����肩,�X�R���q,���܂�,���×T�q,�c�����a���u���{�����Ȋw��������\�v�|�W 32(0) 2021 p.190�v�Ɂu���ꌧ�̉ƒ뗿���@�s���H�̓���:�@�N���s���̗����𒆐S�Ɂv�\����B�@ J-STAGE |
| 2022 |
4 |
�E |
�Q���A�镔�������ّ�w���ی��ꕶ���������ҁu�����ٌ��ꕶ������ 33(3) (�ʍ� 146) p.1-11�@�����ّ�w���ی��ꕶ���������v�Ɂu�����v�Y�Ɖԃu���b�N : ��㉫��ɂ�����R���N���[�g�u���b�N���̑����I�W�J
(2020�N�x���ی��ꕶ�������������[�u���� ; ���f�B�A�Ƃ��Ă̕��i�ƒn��̋L��)
�v�\����B
�Q���A���{�����w��ҁu���{�����w = Bulletin of the Folklore Society of Japan (309)�@�����W �����w�ɂ����鑽�������� : ���A�W�A�̏\�ܖ�s������l����v���u���{�����w��v���犧�s�����B
|
�A�C�k�����̌��u�N���l�`���v�v�ɂ��� �@���c �S�� p.124-143
�����w�ɂ����鑽��������:���A�W�A�̏\�ܖ�s������l���� �@�i���� p.113-123
�\�ܖ��ʂ��Ă݂�q�g/�g�̉e���Ƃ̊ւ�� :
�@�@������E����Ɛl�Ԃ̐g�̉e����͍����鎋�_�@�ߓ����s p.144-168 |
��p�̒��H�̖����`���@�� ���� p.169-185
�����x���ƂȂ������H�߁@�� �� p.186-200
���N�����̏H�[�����̍l�@�@�p �R�� p.201-216
��������`�����w����(�R�����g) �@�������� p.217-224 |
�R���A���ꌧ���|�p��w�����������ҁu����|�p�̉Ȋw : ���ꌧ���|�p��w�����������I�v
(34) �v���u���ꌧ���|�p��w�����������v���犧�s�����B
|
�쓇�̗w�ɂ�����"�������" ��|�L�q p.1-21
���̐�����j�Ղ̐��� : ���ؗ��O�u�X��ʂ̓��Łv���W�I�h���}���Ɍ��鉫��C���[�W�̕ϗe�@����F��
p.23-38
���{��Museum der Kulturen Basel���� ����D���̔�r�@ �� �x�B p.39-48
������D�i�̃��[���b�p�ւ̈ړ��ɂ��� �V�c�ێq p.49-66
����ɂ����郁�f�B�A�����^����n���̎��H : ����|�\�u���q�Ɛm�l�vin����܂�z�[��������� ���z�F�� p.67-91
���i�Ǖ����̃��b�R�x����߂����� ���c���� p.93-129
�C�O�ł̃��[�N�V���b�v�ɂ�问�����x���K�̎��H�Ɖۑ� �@�Â����� p.131-164
���������Â̌|�\�ߑ��̍Č����삩��l�@����Íg�^�Z�@�@ �n����͂��,���쒩�a,�O�c����,�F�Nj��q,�{�鈤��,�����
p.165-180 |
�R���A�����,�v���c�W���u�������y���� = Research on folk music : journal of the Society for Japanese Folk Music (47) p.1-11�v�Ɂu���n�����^���e�[�v�̌��J���@�Ɋւ���l�@ : ���ꖯ�w�����^���f�[�^�x�[�X����v�\����B
�R���A�㌴�F�O���A�W�A���������w��ҁu�A�W�A������������ = Asian folk culture studies (21) p.197-200�v�Ɂu���] �^�����E�����k���Y�E�g�Ɗԉi�g�ҁw���A�W�A�̉̂ƕ����x�v���Љ��B
�R���A�u���ꌤ���m�[�g 31�v���u�{��w�@���q��w�L���X�g�������������v���犧�s�����B �iIRDB�j
|
�t�N���E�ɖłڂ��ꂽ�� �R������ p.1-8
���鎟�Y�Ɋւ���o�� ���ђ��� p.16-29 |
�ߐ������ɂ�����u�vጉ́v�̐��E�F��_���҂̏K���Ɖ��{�ɂ��퓗 �I����, p.1-15
�E |
�R���A�Ôg��H���u�������j���������ٌ����� = Bulletin of the National Museum of Japanese History 234 p.367-394�@�������j���������فv�Ɂu�Α���̐����Ɋւ�����̉����ƍĒ��
: �ߔe�s���\�n��̎��ጤ������v�\����B
�R���A�O�c�F�a���_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[ �ҁu����������
= The study of nonwritten cultural materials (24) p.19-61�@�_�ސ��w���{�햯���������������������Z���^�[�v�Ɂu�ߑ㉫��_�А_���j�ɂ������ԁE�q���̐_�Љ��̔w�i�v�\����B
�R���A���g�Ύ}���Y�\�w��ҏW�ψ���ҁu�Y�\ (28) p.331-335�@�Y�\�w��v�Ɂu�������x�����w��N�̋F��x�ɍ��߂��z�� (�E�C�Y�R���i�̕��䂩��)�v�\����B
�R���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (72) (�ߘa�O�N�x �����|�\�w����V���|�W�E��
�����|�\���������̑̌��I��@�ƕ���)�v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B
|
���r���_�y�v�����C���h�u�̕������N�V���K�[�i�v�u�ߗ�V��|�\�u�[�^�v�Ɏ���
�X�K ���v p.1-5
���A�W�A�̛ނƙT�̍ՋV : ���J�|�\�̌����Ɋw�� �쑺 �L�� p.6-17
�����̃T�[�J�X�Y�ƂƁu�������v �s�ט_���猩������������ ��B �m�u p.18-39
���Y�c�y�ɂ�����ے��I�Ӗ��ƋF�� �N�� �O�l p.40-68
�V�V�i���V�̂��ƂȂ� ���� ��T p.69-71
���] �����O���w���������l�X ��y�Ƒ����̖����|�\�x �{�c �ɍK p.72-74 |
�S���A�^�������u����A�S�̂��� : �����ȁ[�̂��ނ�����ʂ����v���uKing Records�v���犧�s�����B�@
�@�@ ���v����: 68��3�b CD 1��
|
| (1)���l�ʕ�(���܂�ʂ�����)(BEGIN)(2)�܂�������(�i�_�\�E�\�E)(�Đ���)(3)�C�̐�(�l�[�l�[�Y)(4)��(�V���O���E�o�[�W����)(�Η䑏�q)(5)���_-���}�g�O�`(���т���-��܂Ƃ���)(����䂤�q)(6)���S(�E�`�i�[�O�`�E���@�[�W����)(THE BOOM)(7)�n�C�T�C��������(��[���g�ƃ`�����v���[�Y)(8)�_�C�i�~�b�N����(single remix)(����䂤�q)(9)��ăW���g�[���[(���Ȃ���Ɓ[��[)(�l�[�l�[�Y)(10)���ʔ�����(�����ʂ�������)(��l�݂�)(11)�Ă����ʉ�(�{���N�q,�ÎӔ����q,�{���ޔ��q,�䉮���K�T)(12)���オ��ǂ����܂��(���オ�Ȃ����ǂ����ʂ܂��)(�m����j)(13)���Ƃ����є�(����䂤�q)(14)�����̉�(�l�[�l�[�Y)(15)���D�ǁ[��(�Ƃ�����ǁ[��)(�m����j) |
|
�V���A�u�G�������w 46(3) (�ʍ� 181) (���W ���� : ���ɐ�����L��)�v���u�i���c�j�痢�������c�v���犧�s�����B
|
�t�F���X�̌������̌̋� : ��n���̐��n��y�q����l�тƁ@�R������p.4-15
�D���̓��ɑc���q�˂ā@ ���{���q p.16-23
�ƂƂ��ɐ�����:��㉫��̓ؓ��H�����̍Đ��@��×��� p.24-33
���㉫��̃��^:���^�̋��E����l�тƂւ̂܂Ȃ����@����舢��p.34-41 |
�x��G�C�T�[���疣����G�C�T�[�� �@�v���c�W p.42-51
����≮1938~40�N : ���Y�ƍ�ƂƍH�l�@���䌒 p.52-59
�����g�^ : ���������̔��E����̏ے� �@���ʊG���qp.60-71
�����̉���A�ЂƂ̉���@�ݐ��F p.72-83 |
�W���A�����p�q�����얞�M�� �ҁu���A�܁Z�N�̋L�� : ���ꂩ��̐��v���u�������X�v���犧�s����B
|
���ꂩ����{������₤ / ��c���G ��
����Ɛ푈 / �얞�M�� ��
�l�Êw�̎��_���� / �����i ��
�n�C�`���[�X�K�E�E�`�i�[ / ����� ��
�Ί_���̌��� / �약���Y ��
��㉫��̑��ݏؖ� / �ɍ����� ��
���ی������Ȃ��Ȃ� / �䉮���O ��
���������̓Ǝ��� / ��闧�T �� |
�����̐S / �������� ��
�������w�Ɨ����� / �g�Ɗԉi�g ��
�����̐�Ε��a�ƃW���S�� / �C�����L ��
�������� / �����p�q ��
��A�Č��� / �Ί_���� ��
�����̒�R�̂����� / ���Ǖ� ��
�j���C�J�i�C�̂��ɁA���� / ���[�[����c ��
�q�������r��|�邱�ƁA���L���邱�� / ������ �� |
�W���A�u�I�L�i���O���t (726) p.24-27�v�Ɂu���̂���̃G�C�T�[!! (���W �J���o�b�N �G�C�T�[!! : 7�E10 �G�C�T�[�i�C�g2022/7�E17
Kozarocks!)�v���f�ڂ����B
�@�@�܂��A�u���� p.21-23�v�Ɂu�ł�~���n�o�[!! �������ǁ[�G�C�T�[! (���W
�J���o�b�N �G�C�T�[!! : 7�E10 �G�C�T�[�i�C�g2022/7�E17 Kozarocks!)�@�N���X,�Ђ�
��イ���v���f�ڂ����B
�X���A�X�c�^��, ��c�����u�x��u�n���C�v�E�x��u����v = Dancing Hawai'i and Okinawa : �t���ƃG�C�T�[�ɂ݂�u����ƌq����v���u���Ώ��X�v����
���s����B
|
�u����ƌq����ɂ݂镶���̑n���ƃA�C�f���e�B�e�B���� / �X�c�^�� ��
�t���̕���� / �X�c�^��, ��c�� ��
�c�[���Y����������t�� / ��c�� ��
�v���Y���ƃt�� / ��c�� �� |
�G�C�T�[�̕���� / �X�c�^�� ��
�t�F���X��������G�C�T�[ / �X�c�^��, ��c�� ��
�I�X�v���C�ƃG�C�T�[ / ��c��, �X�c�^�� ��
�n��Ɍq����t���ƃG�C�T�[ / ��c��, �X�c�^�� �� |
�X���A�g�Ɗԉi�g, ��؍k��, �����q, ���{�Z���u�g�x �� �v���u��܂ɏ��[�v���犧�s�����B
(�������w��n / ������w�w�������w��n�x�ҏW���s�ψ���Ҏ[, 14)
|
�g�x / ���{��
�ӌ˔V���
���S���� �����q / �ʏ钩�O��
���G��
�`�b���� / �c�������� |
�V��V��i�G�� ��R�a�r / �Z�������Y�ȏW
�썲�ۓG�� / �ʏ钩�O��
���m�g�ւ̊�
�F�s�V�� / �ʏ钩�O��
���� / �c�������� |
������ / �ʏ钩�O��
�萅�̉� / �Ԕ��̉�
���ΓG�� / �c��������
�E
�E |
�X���A�����|�\�w��ҏW�ψ���ҁu�����|�\���� (73) �v���u�����|�\�w��v���犧�s�����B
|
���̓��Ε��� : ���̌����ƕϗe �O�c�� ���q p.1-23
���B�̓����� ���� ���� p.25-42
�u�h��_���v�ތ^���̎��� : �o�_�E�����_�Ёu�h����̐_���v�̋V�炨��шӋ`�Ɋւ��镪�͂Ɍ����ā@����
�N�� p.43-74
�����䂭���O�̖͂����|�\�̌���� ���� �P�Y p.75-94
�������������̑��ɂ��� �쑺 �L�� p.95-120
���ЏЉ� �쑺�L��E�|�����_�E�ۗ����v�ҁw�\�y�̌����𓌃A�W�A�ɖ₤ : ���c�x�Y�w�]���́x���琢����ȑO�ցx
�Ζ؉h p.121-123 |
�P�O���Q�Q���`�P�P���Q�����A�u���ꌧ���|�p��w�����}���E�|�p������2�K�@��1�W�����v�ɉ����āu����{�y���A50���N�L�O���W�F�u50�N�O�̉���v�W�Ɗ��q�F���Y�ʐ^�̍��v���J�Â����B
�@�@���� �F���ꌧ�������فE���p�فA���ꌧ���|�p��w�|�p���������� �@���� �F�������@���������ہA����������������
|
�k�T�v�l �{�W����ł́A�{�y���A50�N�Ɓu50�N�O�̉���v�W�J��50�N���L�O���āA���q�ʐ^�̎B�e�E�ۊǂ�����J�A���ꌧ���|�p��w�ւ̊A�d�v�������w��ւ̌o�������ǂ�܂��B���킹�Č��݁A�������̕⏕���ƂƂ��Đi�߂��Ă��銙�q�ʐ^�K���X���ۑ��E�C�����ƂƓ����������������Ɖ��ꌧ���|�p��w�̋��������Ƃ��Đi�߂��Ă���K���X���f�W�^�����ɂ��ďЉ�܂��B���������̉h�������ɓ`���銙�q�F���Y�B�e�ʐ^�̐��E�����y���݂��������B |
�P�O���Q�Q���`�P�P���P�R���A�������@�֊قɉ����āu�ܒ���l�ƎR�̎��O����
: �O�����J�n�l�S�N�L�O�v���J�����B
�P�O���A�O�����i�ޗǎs�j�E�������������������ҁu�ܒ���l�ƎR�̎��O����
: �O�����J�n�l�S�N�L�O�v���u�Ȃ當���𗬋@�\�v���犧�s�����B
|
���� �ܒ���l�̈�Y�ƔO���� 400 �N �O��O��
�T���P �O�����Ɠޗǒ��̏�y�@���@
�@�@���������^�i�������������������j
�T���Q �O�����̕��� �A����Ɓi�������������������j
�� 1 �� �ܒ��̔O�����J�n�Ɠޗ�
�� 1 �� �O�����J�n
�� 2 �� �ޗǒ��̔O���M��
�R���� ��܉@�̕����G��j
�� 2 �� �ܒ��̈�Y
�� 1 �� �w�m�ܒ�
�� 2 �� ��y�֑ɗ��̌����Ɨ��z
�� 3 �� ��،o�̏N�W�Ɠ���
�� 3 �� ���ς̊m���ƐM�̑��l��
�� 1 �� �ܒ����p������q����
|
�� 2 �� �O�������x�����h�߂���
�� 3 �� ���������M�̓W�J
�� 4 �� ����Y��ׂ̐M��
�R���� �O�����̂����j
�� 4 �� �u�J���V�c�ˁv�ƔO����
�� 1 �� �O�@�R�Ɓu�R�̎��v
�� 2 �� ���v�̏C�ˁj
�� 5 �� �O�����̖���
��e�P �ܒ���l�́u���v�ɓ������ �M�����땶�i�h���@�ю��Z�E�j
��e�Q �ܒ���l�A�����Ղ���������
�@�@�@�������쏟�i�@���@��{�R��t���厖�E�B���w���������j
��e�R �O���������̖���
�@�@�@���V��A���i�V����w�����V���}���َi���j
�O�����N�\�^��v�Q�l���� �w |
�P�Q���A�c���^�V�ďC�u�ʍ����z:���{�̂����� (303)�@���W�F�����E�����m��}�� : ������A��������ށv���u���}�Ёv���犧�s�����B
|
���j���̐_�́w�����낳�����x �@�g�Ɗԉi�g��@ p.6-12
���������S�ƂȂ�A���������ʐ_�X�Ƒc����J��
�@�@�� ; �����E����̐M��)�@�ԗ䐭�M�@ p.13-21
���Ɋ����_�X : ��ÍN�Y�̖����ʐ^ �@���q�V�@ p.22-31
�l�����ƈ�Ւ����A��������T��Ñ�̉���
�@�@��; �����E����̗��j��m��)�@�R��^���@p.34-43
�傫�ȕϊv���琶�܂ꂽ�u�O�X�N����v:�O�R�̑����Ɖ���{���̓���
�@�@�� ; �����E����̗��j��m��)�@�R�{�����@p.44-53
��ꏮ�������̐��藧���Ɛ���
�@�@��; �����E����̗��j��m��)�@�R�{�����@ p.54-59
�C�̉����̎���A�����̑D �@�c���^�V�@ p.60-63
�����̈���ƒ����W�������i�A�×����̉�����
�@�@�� : ����E�O��;�����E����̗��j��m��)�@�c���^�V p.64-70
�����̋ߐ��ɂ����鏔�� : ����E���
�@�@�� ; �����E����̗��j��m��)�@�c���^�V p.71-77
���{�̍��J�V��@��]�F�����@ p.80-83
������������̔��p�ƍH�| ��]�F�����@ p.84-93
����̋ߑ�Ƃ�? : �����������牫�ꌧ��
|
�@�@��; �����E����̗��j��m��)�@�O�c�E�� p.94-99
�ʐ^�ƔN�\�Ō��鉫��� ; �����E����̗��j��m��)�@p.100-103
�ČR��������̉���Љ�
�@�@��; �����E����̗��j��m��)�@�Ôg�U�_ p.104-109
���A�܁Z�N : ����̐����E�o�ρE�Љ�̕ϑJ
�@�@�� ; �����E����̗��j��m��)�@�O������ p.110-116
�C���^�r���[ �⍜�ƂȂ�����v�҂̐��ɂȂ�Ȃ�����
�@�@��: �⍜���W�{�����e�B�A ��u���������� p.117-121
PLAZA HOUSE since 1954
�@�@�� : �u���ĕ����ʐ^�v���f���o������ �@���c���T p.122-127
�����������ォ�獡�ɓ`��问������
�@�@�� ; �����E����̗���)�@�����x���q p.128-135
�ÓT�����X�Ǝp����A�V���ȋȂ��x��ݏo���� ;
�@�@�� �����E����̉��y�ƌ|�\)�@�v���c�W p.136-143
����̌i�ςݏo�����R���N���[�g���z�@���v�����[�@p.150-160
����Ɖf��̗��@���q�V p.161-165
����w�̌n���@�������� p.166-175
�E |
�P�Q���A���؏��t, ���c���q, ��c�G�q, �啽�a�O �Ғ��u�_�h��ׂ̎��R :
���J��̗̂���n��̌��S�ȕ�炵����T��v���uPHP�G�f�B�^�[�Y�E�O���[�v�v���犧�s�����B
�@�@�@���ҁF���a��, ���c�m�u, �c������, �p��K��, ����������, �䌴��, ���c�m�I
|
��P���@�n�c�I�ȍ��J�̏�̌���Ɖۑ�
�������̐X�̐_ / ��c�G�q
���d�R�̌�Ԃƍ��J / �啽�a�O
|
���d�R�̌�ԂƂ� p43
�����ɂ����� p45
�약�̃p�J�[���Ƃ͉����@p49
���d�R�̐약�E�|�x�E��������芪���� p54
��Ԃ̏Z���Ƃ̊ւ�� p59
���̍s���E���J�̎��� p65
���J�g�D�ƈڏZ�҂Ƃ̊ւ�� p69
�䍖�ƍ��J���x���鏔���x p73
�䍖�ƍ��J�̌p���̂���� p75
���d�R�̌䍖�ׂ͗̎��R�ɂȂ蓾�邩 p77 |
|
�����哇�̃m�����J�ƃJ�~���} / ���c���q
��Q���@�s�s��ɂ�������J�̏�̑�����
��_�n��ɂ�����Ў��̕ϗe / ���؏��t
�����s�S�ɂ����鋷���_�Ђ̐��� / ���c���q
���s�X�H�Ɏc���ꂽ���Ȃ�H�T�� / ���؏��t, ��c�G�q
��R���@����Љ�ɂ�������J�̏�̖���
�j���[�^�E���J����ɂ݂铹�c�_�s���̋��� / ����������
�_�Ћ�Ԃ��j�Ƃ����h�ЃR�~���j�e�B�̌`�� / ���c�m�I
���悪�͂����ސ������l�� / ���c�m�u
�����Ƃ��Ă̍��J�̏�̊��p / ��c�G�q, �啽�a�O
���J�̏�̍���̂���� / �p��K��
�E
�E |
���A���̔N�A�ߓ����s���u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� (161) p.52-69�@�����������w��v�Ɂu���ꑤ���猩�鉂���Q���̓��X�Ɖ��� : �������Ɨ^�_���ɂ�����c�����A�C��p���[�h�̍Č���O�Ɂv�\����B
���A���̔N�A�ߓ����s���u�����������v�ҏW�ψ���ҁu���������� (162) p.94-84�@�����������w��v�Ɂu�������Ɨ^�_���Ŏ��{����2022�N�u4�E28�v : �����̊C��W��̖͗l��S���e�����ǂ��`�����̂��v�\����B�@�@
���A���̔N�A�g���N��,�O�D�b�^�q���u�����{�_�p = Journal of lifology 41 p.30-45 ���{�����w��v�Ɂu�ʐ^�� �����Ɩ������ʂ����u��n�̒��̉���v : ���Ă̋��Ԃŗh�炮���A�O�̌����Ɨ��j�ւ̐ӔC�v�\����B
���A���̔N�A�R�~���j�e�B����w��ҏW�ψ���ҁu�R�~���j�e�B���� (20)�@�i�R�~���j�e�B����w��
��20����(2021�N�x)�V���|�W�E���v���u���M���v���犧�s�����B
|
�V���|�W�E���J�Âɂ������� �@ p.6-9
��u�� ����̒n��Љ�ƌ|�\�@�떓�b�� p.9-29
�p�l���f�B�X�J�b�V���� �|�\�ƃR�~���j�e�B ���� ���Y,�떓 �b��,���z ��V,�v���c �W,�y�� ��,�،� �͔� p.30-71 |
���A���̔N�A���������u�ǒJ�R�ԐD : �o�ߗ��̂킴�v���u�V�l�}����v���琻�삳���B
(�`���H�|�Z�p�L�^�f��V���[�Y ; 28)
���A���̔N�A���{�����u�Љ��w���� = Japanese journal of adult and community education 58 p.137-139�v�Ɂu���] ��J�וF���w���[�A�V�r����G�C�T�[�� : ����ɂ�����K���Ƃ��Ă̎Љ��x�v���Љ��B
�i�{�[�_�[�C���N�A2021�N1���A184�y�[�W�A1,600�~�{�Łj�@��-STAGE |
| 2023 |
5 |
�E |
�T���A�哇���q,�v�����a���u���{�X�ъw����\�f�[�^�x�[�X 134(0) p.110�v�Ɂu���鍑�������ɂ����閧�E���̂̊Ǘ��̐��Ɋւ���Θb�̌���Ɖۑ�v�\����B |
| 2024 |
6 |
�E |
�E |
| 2025 |
7 |
�E |
�E |
| 2026 |
8 |
�E |
�E |
| 2027 |
9 |
�E |
�E |
| 2028 |
10 |
�E |
�E |
| �E |
�E |
�E |
|
�q�Q�l�r
�܌��M�v�̐��E(I�`205.) �̓���ꗗ�\
| �m�� |
�G������ |
���s�N�� |
�_�����ƒ��� |
pid |
| 1 |
�|�\19(1)(215)
|
1977-01 |
�܌��M�v�̐��E(I.) / �����_ ;�F����o�j/p38~39
|
pid/22764101�@ |
| 2 |
�|�\19(2)(216) |
1977-02 |
�܌��M�v�̐��E(2) / �����_ ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276411 |
| 3 |
�|�\19(3)(217) |
1977-03 |
�܌��M�v�̐��E(3) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276412 |
| 4 |
�|�\19(4)(218) |
1977-04 |
�܌��M�v�̐��E(4) / �����_ ;�F����o�j/p40~41
|
pid/2276413 |
| 5 |
�|�\19(5)(219) |
1977-05 |
�܌��M�v�̐��E(5) / �����_ ;�F����o�j/p40~41
�����G�O�Y��_������[�t�H�[�N���A�̊�T� / �F����o�j/p45�`46 |
pid/2276414 |
| 6 |
�|�\19(6)(220) |
1977-06 |
�܌��M�v�̐��E(6) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276415�@ |
| 7 |
�|�\19(7)(221) |
1977-07 |
�܌��M�v�̐��E(7) / �����_ ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276416�@ |
| 8 |
�|�\19(8)(222) |
1977-08 |
�܌��M�v�̐��E(8) / �����_ ;�F����o�j/p36~37
|
pid/2276417 |
| 9 |
�|�\19(9)(223) |
1977-09 |
�܌��M�v�̐��E(9) / �����_ ;�F����o�j/p48~49 |
pid/2276418 |
| 10 |
�|�\19(10)(224) |
1977-10 |
�܌��M�v�̐��E(10) / �����_ ;�F����o�j/p40~ |
pid/2276419 |
| 11 |
�|�\19(11)(225) |
1977-11 |
�܌��M�v�̐��E(11) / ����O�F ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276420�@ |
| 12 |
�|�\19(12)(226) |
1977-12 |
�܌��M�v�̐��E(12) / ����O�F ;�F����o�j/p36~37 |
pid/2276421 |
| 13 |
�|�\20(1)(227) |
1978-01 |
���-�܌��M�v�̐��E(13) / �R�������Y ;�F����o�j/p34~35
|
pid/2276422 |
| 14 |
�|�\20(2)(228) |
1978-02 |
���-�܌��M�v�̐��E(14) / �ڗNjT�v ;�F����o�j/p38~39
�C�z��ďC��^������p���Z����(������)�̐y� / �������q/p43�`44 |
pid/2276423 |
| 15 |
�|�\20(3)(229) |
1978-03 |
���-�܌��M�v�̐��E(15) / �R�������Y ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276424 |
| 16 |
�|�\20(4)(230) |
1978-04 |
���-�܌��M�v�̐��E(16) / �R�������Y ;�F����o�j/p44~45 |
pid/2276425 |
| 17 |
�|�\20(5)(231) |
1978-05 |
���-�܌��M�v�̐��E(17) / �R�������Y ;�F����o�j/p38~39
���c���q����c�A�₵����� / �������q/p46�`47 |
pid/2276426 |
| 18 |
�|�\20(6)(232) |
1978-06 |
pid/2276427�@���-�܌��M�v�̐��E(18) / �R�������Y ;�F����o�j/p36~37 |
pid/2276427 |
| 19 |
�|�\20(6)(232) |
1978-06 |
�|�\ 20(7)(233) 1978-07�@�@�܌��M�v�̐��E(19) / �F����o�j/p36�`37 |
pid/2276428 |
| 20 |
�|�\20(8)(234) |
1978-08 |
�����̂��Ƃ�܌��M�v���m�ƌ|�\� / �q�c��/p7�`7
�؍��̍Ղ�̐_�� / �{�c����/p3�`33
�܌��M�v�̐��E(20) / �����_ ;�F����o�j/p34~35
��܌��搶��\�ܔN�գ�ɂ��Ă̂����点����{�̗w�w��H�G�������\�v��(����)/p64�`64 |
pid/2276429 |
| 21 |
�|�\20(9)(235) |
1978-09 |
�܌��M�v�̐��E(21) / �����R�� ;�F����o�j/P32~33
���������V���̓���������� / ��،�/p46�`46
|
pid/2276430 |
| 22 |
�|�\20(10)(236) |
1978-10 |
�܌��M�v�̐��E(22) / �����R�� ;�F����o�j/p40~41
�̐܌��M�v�搶��\�ܔN�� / ���J�쐭�t/p74�`74 |
pid/2276431 |
| 23 |
�|�\20(11)(237) |
1978-11 |
�����̂��Ƃ�ԍՉ�ق̏v�H�Ǝw�W� / �F����o�j/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(23) / �����R�� ;�F����o�j/p34~35 |
pid/2276432 |
| 24 |
�|�\20(12)(238) |
1978-12 |
�܌��M�v�̐��E(24) / �����R�� ;�F����o�j/p32~33 |
pid/2276433 |
| 25 |
�|�\21(1)(239) |
1979-01 |
�܌��M�v�̐��E(25) / �������H ;�F����o�j/p40~41
�O�Ԏ�P�E�V���K�����u�쓇��揑听III.�E�{�Õсv / ���P�Y/p42~43 |
pid/2276434 |
| 26 |
�|�\21(2)(240) |
1979-02 |
�܌��M�v�̐��E(26) / �������H ;�F����o�j/p48~49
�C�U�C�z---���ꌧ��v���� / ���w/p21�`30 |
pid/2276435 |
| 27 |
�|�\21(3)(241) |
1979-03 |
�܌��M�v�̐��E(27) / �������H ;�F����o�j/p34~35 |
pid/2276436 |
| 28 |
�|�\21(4)(242) |
1979-04 |
�܌��M�v�̐��E(28) / �������H ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276437�@ |
| 29 |
�|�\21(5)(243) |
1979-05 |
�܌��M�v�̐��E(29) / �������H ;�F����o�j/p38~39
����˓�����(������)���h��(�����哇����˓���)������� / �O�����Y/p44�`45 |
pid/2276438 |
| 30 |
�|�\21(6)(244) |
1979-06 |
�܌��M�v�̐��E(30) / �������H ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276439 |
| 31 |
�|�\21(7)(245) |
1979-07 |
�܌��M�v�̐��E(31) / ��X�`�� ;�F����o�j/p38~39 |
pid/2276440 |
| 32 |
�|�\21(8)(246) |
1979-08 |
�܌��M�v�̐��E(32) / ��X�`�� ;�F����o�j/p34~35
�c���p�������쓇�̗w�听V�����ѣ����w�v�w�������w���x / ���P�Y/p40�`41
|
pid/2276441 |
| 33 |
�|�\21(9)(247) |
1979-09 |
�܌��M�v�̐��E(33) / ��X�`�� ;�F����o�j/p26~27
���䐴����������|�\�Ɖ�揂̌���� / �{�c����/p45�`45 |
pid/2276442 |
| 34 |
�|�\21(10)(248) |
1979-10 |
�܌��M�v�̐��E(34) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41
��������ꏗ�D�ЂƂ�ŋ�� / ��،�/p49�`49 |
pid/2276443 |
| 35 |
�|�\21(11)(249) |
1979-11 |
�܌��M�v�̐��E(35) / ��X�`�� ;�F����o�j/p26~27 |
pid/2276444 |
| 36 |
�|�\21(12)(250) |
1979-12 |
�܌��M�v�̐��E(36) / ��X�`�� ;�F����o�j/p32~33
�����|�\�u�䊥�D�ƎG�x�v/p74~74 |
pid/2276445 |
| 37 |
�|�\ 22(1)(251) |
1980-01 |
�܌��M�v�̐��E(37) / ��X�`�� ;�F����o�j/p44~45 |
pid/2276446 |
| 38 |
�|�\ 22(2)(252) |
1980-02 |
�܌��M�v�̐��E(38) / ��X�`�� ;�F����o�j/p42~43
���c�W�Ң����n���̖��ԕ��Y� / �哇���F/p51�`52 |
pid/2276447 |
| 39 |
�|�\22(3)(253) |
1980-03 |
�܌��M�v�̐��E(39) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276448 |
| 40 |
�|�\ 22(4)(254) |
1980-04 |
�܌��M�v�̐��E(40) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~41 |
pid/2276449 |
| 41 |
�|�\ 22(5)(255) |
1980-05 |
�܌��M�v�̐��E(41) / ��X�`�� ;�F����o�j/p35~37 |
pid/2276450 |
| 42 |
�|�\ 22(6)(256) |
1980-06 |
�܌��M�v�̐��E(42) / ��X�`�� ;�F����o�j/p40~40 |
pid/2276451 |
| 43 |
�|�\ 22(7)(257) |
1980-06 |
�܌��M�v�̐��E(43) / ��X�`�� ;�F����o�j/p32~33 |
pid/2276452 |
| 44 |
�|�\22(8)(258) |
1980-08 |
�܌��M�v�̐��E(44) / ��X�`�� ;�F����o�j/p24~25
���Ԉ�Y�Ң�{�Ǔ��s�S�W���\�� / ���P�Y/p42�`44 |
pid/2276453 |
| 45 |
�|�\22(9)(259) |
1980-09 |
�܌��M�v�̐��E(45) / ��X�`�� ; �F����o�j/p32�`33
|
pid/2276454 |
| 46 |
�|�\22(10)(260) |
1980-10 |
�܌��M�v�̐��E(46) / ��X�`�� ; �F����o�j/p19�`21
|
pid/2276455 |
| 47 |
�|�\22(11)(261) |
1980-11 |
�܌��M�v�̐��E(47) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276456 |
| 48 |
�|�\22(12)(262 |
1980-12 |
�܌��M�v�̐��E(48) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p26�`27 |
)pid/2276457 |
| 49 |
�|�\23(1)(263) |
1981-01 |
�܌��M�v�̐��E(49) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276458 |
| 50 |
�|�\23(2)(264) |
1981-02 |
�܌��M�v�̐��E(50) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276459 |
| 51 |
�|�\23(3)(265) |
1981-03 |
�܌��M�v�̐��E(51) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276460 |
| 52 |
�|�\23(4)(266) |
1981-04 |
�܌��M�v�̐��E(52) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p36�`37 |
pid/2276461 |
| 53 |
�|�\23(5)(267) |
1981-05 |
�c�V�т̒��� / �V��P��/p20�`27
�܌��M�v�̐��E(53) / �~�؏t�a ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276462 |
| 54 |
�|�\23(6)(268) |
1981-06 |
�܌��M�v�̐��E(54) / �����_ ; �F����o�j/p20�`21
|
pid/2276463 |
| 55 |
�|�\23(7)(269) |
1981-07 |
�܌��M�v�̐��E(55) / ���䕐�u ; �F����o�j/p22�`24 |
pid/2276464 |
| 56 |
�|�\23(8)(270) |
1981-08 |
��������I�L�i������� / ������Y/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(56) / ���䕐�u ; �F����o�j/p24�`25
���x��w�������x�̕ό^���̣ / �m�����Õv/p50�`50 |
pid/2276465 |
| 57 |
�|�\23(9)(271) |
1981-09 |
�܌��M�v�̐��E(57) / ���䕐�u ; �F����o�j/p20�`22 |
pid/2276466 |
| 58 |
�|�\23(10)(272) |
1981-10 |
�܌��M�v�̐��E(58) / ���䕐�u ; �F����o�j/p14�`16
|
pid/2276467 |
| 59 |
�|�\23(11)(273) |
1981-11 |
����������d�R��{�Â̌������|� / �{�c����/p7�`7
�䒌�̘b-1- / �܌��M�v/p8�`11
�Ǔ�����c����<���W> / �R���m��/p17�`31
���c������������̂� / �g��p�j ; �s�� ; �������q/p18�`25
���c�����搶�]�` / �R���m��/p26�`28
���N��������Ȓ��� / �R���m��/p28�`30
�V���e���ɂ悹��ꂽ�Ǔ��k / �r�c��O�Y/p30�`31
�܌��M�v�̐��E(59) / ���䕐�u ; �F����o�j/p12�`13 |
pid/2276468 |
| 60 |
�|�\23(12)(274) |
1981-12 |
�䒌�̘b-2- / �܌��M�v/p9�`16
�܌��M�v�̐��E(60) / �|���� ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276469 |
| 61 |
�|�\24(1)(275) |
1982-01 |
�܌��M�v�̐��E(61) / �|���� ; �F����o�j/p24�`26 |
pid/2276470 |
| 62 |
�|�\24(2)(276) |
1982-02 |
�܌��M�v�̐��E(62) / �|���� ; �F����o�j/p26�`28 |
pid/2276471 |
| 63 |
�|�\24(3)(277) |
1982-03 |
�O�@���b�̊G���� / �n�ӏ���/p8�`19
�܌��M�v�̐��E(63) / �|���� ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276472 |
| 64 |
�|�\24(4)(278) |
1982-04 |
�܌��M�v�̐��E(64) / �|���� ; �F����o�j/p34�`36 |
pid/2276473 |
| 65 |
�|�\24(5)(279) |
1982-05 |
�܌��M�v�̐��E(65) / �|���� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276474 |
| 66 |
�|�\24(6)(280) |
1982-06 |
�܌��M�v�̐��E(66) / �|���� ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276475 |
| 67 |
�|�\24(7)(281) |
1982-07 |
�܌��M�v�̐��E(67) / ���䕐�u ; �F����o�j/p30�`31
�|�{�G�v���w�c�A�̂̊�b�I����-��R�ߌn�c�A�̂��厲�Ƃ��āx / �V�Ԑi��/p27�`28
�\�̗\�]�����g�x��̋S��тƐd�\�/p53�`53 |
pid/2276476 |
| 68 |
�|�\24(8)(282) |
1982-08 |
�܌��M�v�̐��E(68) / ���䕐�u ; �F����o�j/p26�`28 |
pid/2276477 |
| 69 |
�|�\24(9)(283) |
1982-09 |
�܌��M�v�̐��E(69) / �|���� ; �F����o�j/p30�`32 |
pid/2276478 |
| 70 |
�|�\24(10)(284) |
1982-10 |
�܌��M�v�̐��E(70) / �|���� ; �F����o�j/p26�`28
|
pid/2276479 |
| 71 |
�|�\24(11)(285) |
1982-11 |
�܌��M�v�̐��E(71) / �|���� ; �F����o�j/p18�`21
|
pid/2276480 |
| 72 |
�|�\24(12)(286�j |
1982-12 |
�܌��M�v�̐��E(72) / ���䕐�u ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276481 |
| 73 |
�|�\25(1)(287) |
1983-01 |
�܌��M�v�̐��E(73) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p20�`21
|
pid/2276482 |
| 74 |
�|�\25(2)(288) |
1983-02 |
��������܌��M�v���m�O�\�N�Ղɂ������ģ / �q�c��/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(74) / �|���� ; �F����o�j/p18�`20 |
pid/2276483 |
| 75 |
�|�\25(3)(289) |
1983-03 |
�܌��M�v�̐��E(75) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276484 |
| 76 |
�|�\25(4)(290) |
1983-04 |
�ŗt�_�y�̓��F / �{�c����/p8�`14
�k���ł̎v���o / �r�c�Ă��q/p15�`23
�܌��M�v�̐��E(76) / �R�ɐ^�� ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276485 |
| 77 |
�|�\25(5)(291) |
1983-05 |
�܌��M�v�̐��E�\�\�ԍՂƐ܌��M�v(77) / �㓡�i ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276486 |
| 78 |
�|�\25(6)(292) |
1983-06 |
�ԍՂƐ܌��M�v(78)�܌��M�v�̐��E / �㓡�i ; �F����o�j/p26�`
��������I������Ǝ�P� / ��،�/p53�`53 |
pid/2276487 |
| 79 |
�|�\25(7)(293) |
1983-07 |
�܌��M�v�̐��E(79) / ����ɗY ; �F����o�j/p26�`28
�܌��M�v�搶�O�Z�N��/p28�`28 |
pid/2276488 |
| 80 |
�|�\25(8)(294) |
1983-08 |
��������܌��M�v�搶�ƌ|�\� / �Έ䏇�O/p7�`7
��V������l--�͓��ߌ��s�Ȃɂ�� / �g���q/p8�`12
�܌��M�v�̐��E(80) / ����ɗY ; �F����o�j/p16�`17 |
pid/2276489 |
| 81 |
�|�\25(9)(295) |
1983-09 |
�܌��M�v�̐��E(81)-���o�Β��̉� / ����O�F ; �F����o�j/p20�`22
���y�ς̃R�y���j�N�X�I�]��\�\�������q����{���y�̌Ñw� / ���䓿���Y/p23�`24 |
pid/2276490 |
| 82 |
�|�\25(10)(296) |
1983-10 |
�܌��M�v�̐��E(82)�\���o�Β��̉�(��) / ����O�F ; �F����o�j/p12�`14
|
pid/2276491 |
| 83 |
�|�\25(11)(297) |
1983-11 |
�܌��M�v�̐��E(83)-���o�Β��̉�(�O) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`26 |
pid/2276492 |
| 84 |
�|�\25(12)(298) |
1983-12 |
�܌��M�v�̐��E�\�\���o�Β��E�G(84) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`30
���c�܂�q����������w�Ƃ��̎��ӣ / �{�c����/p35�`36
|
pid/2276493 |
| 85 |
�|�\26(1)(299) |
1984-01 |
���������тɈ��閯��� / �{�c����/p7�`7
�A�W�A��������-1-���`�̋��Y--���e�ԂƏt�H�Y���w�Z / �{������/p8�`16
���w�@�̒�(85)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p22�`24
���c��t�F����P���L�����̏Z�l� / ���ے�/p25�`25
|
pid/2276494 |
| 86 |
�|�\26(2)(300 |
1984-02 |
����������y�����̉�z�ƍ���̊��ң / �q�c��/p7�`7
���a�Z�̎j���l--�܌��M�v���ϒ���k�����H��ؖ��C / ��ϐ���/p8�`18
�܌��M�v�̐��E�\�\���w�@����(86) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276495 |
| 87 |
�|�\26(3)(301) |
1984-03 |
��������S���s���������̂Ɩ����|�\� / �F����o�j/p7�`7
���c���j�Ɛ܌��M�v--���y������̂��Ƃǂ��Ȃ� / �q�c��/p8�`20
�܌��M�v�̐��E(87)-�������̖� / ����O�F ; �F����o�j/p21�`22
|
pid/2276496 |
| 88 |
�|�\26(4)(302) |
1984-04 |
��������������y����I�[�v��� / ���ӌ�/p7�`7
�܌��M�v�̍���u���s--�t ���{��ߑ�ߏ��W��̂��Ƃǂ� / �s�꒼���Y/p8�`10
�܌��M�v�̐��E�\�\�ӔN�̕M��(88) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276497 |
| 89 |
�|�\26(5)(303) |
1984-05 |
�m��������c�̐����炭�� / �{�c����/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(89)-�Ñ㌤����(��) / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29
|
pid/2276498 |
| 90 |
�|�\26(6)(304) |
1984-06 |
����������ʂ̃R���N�V�����Ɣ����َ���� / �㓡�i/p7�`7
���G�����̋�--�ߏ��̎ϗ��ᔻ / ��R��/p8�`12
�܌��M�v�̐��E(90)-�Ñ㌤����(��) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276499 |
| 91 |
�|�\26(7)(305) |
1984-07 |
����������w�̃A�W�A����� / �O�����Y/p7�`7
�O��@�Ɛ܌��搶 / �c�Ӑ��j/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(91)-�������̕\�D / ����O�F ;�F����o�j/p28~29
|
pid/2276500 |
| 92 |
�|�\26(8)(306) |
1984-08 |
������������\�y���\�y(�O��)���C�J�u� / ���ѐ�/p7�`7
�܌��M�v�̐��E(92)-�����{�w���҂̏��x / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
�{�c������������s�����|�\��� / �㓡�i/p28�`29 |
pid/2276501 |
| 93 |
�|�\26(9)(307) |
1984-09 |
��������`���|�\�̎q�ǂ��q� / �F����o�j/p7�`7
�ߏ����o�̎��_-1-����E���n��� / ��������Y/p8�`12
������e�A�g������-6-�����̉ƌ����̏���ׂ₩�� / �ق�����/p13�`18
�܌��M�v�̐��E(93)-������p�B��(1) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23 |
pid/2276502 |
| 94 |
�|�\26(10)(308) |
1984-10 |
��������̎��ƌ|�\�ƕ��w�̂͂��ܣ / ���іΎ�/p7�`7
�������x�̊T���Ɠ��F / ������ ; ������/p8�`13
������e�A�g������-7-����Q�L��Ƃ����l���h���}�� / �ق�����/p14�`19
������p�B��(��)(94)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
������l�`���q�����Y�̉S�r� / ��،�/p49�`50
|
pid/2276503 |
| 95 |
�|�\26(11)(309) |
1984-11 |
�܌��M�v�̐��E(95)-������p�B��(�O) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276504 |
| 96 |
�|�\26(12)(310) |
1984-12 |
��������|�p�Ղ̉��v�ƒn��̎��ԣ / �����ߌ�/p7�`7
��]����S����̎l�̈Ӌ` / ��R��/p8�`18
�܌��M�v�̐��E(96)-������p�B��(�l) / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276505 |
| 97 |
�|�\27(1)(311) |
1985-01 |
������������|�\�w�̔��� / �{�c����/p7�`7
��z �r�c��O�Y / �����p���Y/p8�`17
�܌��M�v�̐��E-���z(97) / ����O�F ; �F����o�j/p28�` |
pid/2276506 |
| 98 |
�|�\27(2)(312) |
1985-02 |
��������|�\�����26�N / �Έ䏇�O/p7�`7
�����y�čl-��- / �R�H����/p8�`19
�܌��M�v�̐��E(98)-���z���瑝�㎛ / ����O�F ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276507 |
| 99 |
�|�\27(3)(313) |
1985-03 |
��������O���n��-�����|�\�̌𗬂Ɛ[���̂��߂ɣ / �������H/p7�`7
�����y�čl-��- / �R�H����/p8�`18
�܌��M�v�̐��E(99)-�����{�@�Z�n��ڍ��s����S�q��_ / ����O�F ; �F����o�j/p28�`29
�g��T�q����ՂƓ��{�̍��J� / ���c�\��/p30�`31
|
pid/2276508 |
| 100 |
�|�\27(4)(314) |
1985-04 |
���������O�̐V�l�ƐV����������� / ��v�ۖ[�j/p7�`7
�܌��M�v��R�Ă裂ւ̉��^--���̔s�풼��̐^�������߂� / ���J�쐭�t/p8�`13
�܌��M�v�̐��E�\�\�[��(100) / ����O�F ; �F����o�j/p14�`15
�{�c������������s�����|�\������� / �㓡�i/p21�`22
�����N��Z����O�l�g�O�f�����(�V�����{�ÓT�W��) / �A����/p22�`24
��܌����m�L�O�Ñ㌤�����I�v(��4�S)� / ��m�֒��l/p25�`27 |
pid/2276509 |
| 101 |
�|�\27(5)(315) |
1985-05 |
��������o���G�̍��ی𗬣 / �����/p7�`7
��c�A�Վ��l-��- / �R�H����/p8�`16
�܌��M�v��p�̐��E--�\�Ǝŋ� / ��ϐ���/p17�`19
�Ƒ����ɎE���ꂽ�j--�����q���l / ��R��/p20�`23
�܌��M�v�̐��E(101)-�Ð��~ / ����O�F ; �F����o�j/p24�`25
|
pid/2276510 |
| 102 |
�|�\27(6)(316) |
1985-06 |
����������������ƌ��肽��� / �쑺����/p7�`7
��c�A�Վ��l-��- / �R�H����/p8�`15
�܌��M�v�̐��E�\�\�L�����R���̉ԍՂ�(102) / �O�����Y ; �F����o�j/p16�`17
|
pid/2276511 |
| 103 |
�|�\27(7)(317) |
1985-07 |
�܌��M�v�̐��E(103)-�L�����R���̉ԍՂ� / �O�����Y ;�F����o�j/p26~27 |
pid/2276512 |
| 104 |
�|�\27(8)(318) |
1985-08 |
������������������\�N� / �����G�Y/p7�`7
�[�˂̏j���`��--�̘b���̉Σ���߂����� / �쑺�h�q/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(104)-�ԍ�(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276513 |
| 105 |
�|�\27(9)(319) |
1985-09 |
����������O�ҍ��\�\���܂钆���̌|�\� / �������H/p7�`7
�܌��M�v�̉���̖K / �ۍ�B�Y/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(105)-�ԍ�(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19
�������z�̔o�D��
|
pid/2276514 |
| 106 |
�|�\27(10)(320) |
1985-10 |
������������̖����|�\�����@�ւ� / �R�H����/p7�`7
�����ÓT���nj� / �ɓ���/p8�`14
�܌��M�v�̐��E�\�\�ԍՂƂ��̉�(106) / ����O�F ; �F����o�j/p15�`17
|
pid/2276515 |
| 107 |
�|�\27(11)(321) |
1985-11 |
��������N�֣ / �㓡�i/p7�`7
��Γc�̖g�Ɛ܌��M�v--���萳�G���̑z���o / �B��h��/p8�`11
��R��ɂ������̉����y--�`������̕����I����-��- / ����/p12�`21
�܌��M�v�̐��E�\�\�S�̋���(107) / ����O�F ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276516 |
| 108 |
�|�\27(12)(322) |
1985-12 |
��������A�W�A�����|�\�ե�S���N���̋��y�|�\� / �{�c����/p7�`7
��R��ɂ������̉����y--�`������̕����I����-��- / ����/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(108)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276517 |
| 109 |
�|�\28(1)(323) |
1986-01 |
�܌��M�v�̐��E(109)-���(��) / �ˍ�N�� ;�F����o�j/p22~23
|
pid/2276518 |
| 110 |
�|�\28(2)(324) |
1986-02 |
�܌��M�v�̐��E(110)-��܂薽���R�� / �O�����Y ;�F����o�j/p20~21 |
pid/2276519 |
| 111 |
�|�\28(3)(325) |
1986-03 |
��Ղ�̐풆���(111)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p22~23 |
pid/2276520 |
| 112 |
�|�\28(4)(326) |
1986-04 |
�吳��N�̗��ƐV��(112)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ;�F����o�j/p16~17 |
pid/2276521 |
| 113 |
�|�\28(5)(327) |
1986-05 |
��ƕ���-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �牮�B/p8�`13
�Ղ�̖�̊��\(113)�܌��M�v�̐��E / ����O�F ; �F����o�j/p14�`15
�������z�̔o�D�ƕ���-12-�V�É����Ƣ���͓�� / �ق�����/p16�`20 |
pid/2276522 |
| 114 |
�| �\ 28(6)(328) |
1986-06 |
�܌��M�v�̐��E(114)-���|���]��䎖���(��) / ��ؑ��� ;�F����o�j/p16~17
|
pid/2276523 |
| 115 |
|
1986-07 |
��������������̎w�� / �㓡�i/p7�`7
�����|�\�̒��̓c�y(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �㓡�i/p8�`17
�܌��M�v�̐��E(115)-���|���]��䎖���(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19 |
pid/2276524 |
| 116 |
|
1986-08 |
�l�`�Ɛl�`�|-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �S�i����/p8�`16
�܌��M�v�̐��E(116)-�V���Ђ̒Z��(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p22�`23
�g�����̋��_�\�\�L�O�ق̑����z�v�� / ��،[��/p24�`24
�g��T�q����A�z�܍s�Ɠ������J� / �n粋ӗY/p25�`26
|
pid/2276525 |
| 117 |
�|�\28(9)(331) |
1986-09 |
�l�`�Ɛl�`�|-��-(�u����������Ƃ��Ă̖����|�\�) / �S�i����/p8�`15
�܌��M�v�̐��E(117)-�V���Ђ̒Z��(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p16�`17
|
pid/2276526 |
| 118 |
�|�\28(10)(332) |
1986-10 |
�c���_-��- / �V��P��/p8�`14
�܌��M�v�̐��E(118)-�����ݒZ�̉�(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19
�������̔\�ƌ|�_��������� / �R����/p20�`22
�n�ӕے����������� / ���c�m/p22�`23 |
pid/2276527 |
| 119 |
�|�\28(11)(333) |
1986-11 |
��������V���}�j�Y���ƃq���}�j�Y��� / �c���`�A/p7�`7
�c���_-��- / �V��P��/p8�`14
���ꉹ�y�̒��ɔR�Ă�����������--��ȉƋ����v�q����̐��U / ���c���q/p15�`17
�܌��M�v�̐��E(119)-�����ݒZ�̉�(��) / ��ؑ��� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276528 |
| 120 |
�|�\28(12)(334) |
1986-12 |
���������щz�����N�̢����� / �{�c����/p8�`14
�܌��M�v�̐��E(120)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p22�`23
�A�W�A�ɂ����鉼�ʂ̌|�\ ���ی����W�� / �R�{�G�q/p24�`25
|
pid/2276529 |
| 121 |
�|�\29(1)(335) |
1987-01 |
�܌��M�v�̐��E(121)-���(��) / �˔N�� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276530 |
| 122 |
�|�\29(2)(336) |
1987-02 |
�܌��M�v�̐��E(122)-�t����{����Ղ̑�h���� / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27 |
pid/2276531 |
| 123 |
�|�\29(3)(337) |
1987-03 |
�t����{�����-���{�ՂƂ��n�莮(123)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276532 |
| 124 |
�|�\29(4)(338) |
1987-04 |
�t����{�ŕ���ł̌|�\(124)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29/
|
pid/2276533 |
| 125 |
�|�\29(5)(339) |
1987-05 |
��t�Ɓw���앨��x(125)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p26�`27
�������--�l�`��ڗ��̎�ē�����Y / �X�W�Z/p28�`30
��������ꕜ�A15���N�L�O����� / ��،�/p50�`50
|
pid/2276534 |
| 126 |
�|�\29(6)(340) |
1987-06 |
����ƎR���v�j����(126)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p24�`2
|
��id/2276535 |
| 127 |
�|�\29(7)(341) |
1987-07 |
����쥍��P���٣(127)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ;�F����o�j/p24~25
��|�\�̒J<�ɓߒJ>(�S4)��O�����Y / ��ؐ��F/p26�`28
��ϐ�������܌��M�v���p�̐��E� / �q�c��/p29�`29
|
pid/2276536 |
| 128 |
�|�\29(8)(342) |
1987-08 |
����������������w�Z��ݗ���]�ޣ / ���c�m/p7�`7
��V�ߕ���쏉�ԣ�����ȑO--��_���O�ߍ��O����߂����� / �~��j�q/p8�`19
��㉉���̗V����-9-������������O�ɏo���m�� / �ق�����/p13�`19
�܌��搶�̔�(128)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p20�`21 |
pid/2276537 |
| 129 |
�|�\29(9)(343) |
1987-09 |
����������̌��肩��s�s�̃X�g�[���[�e���[�֣ / �쑺����/p7�`7
�s�i��o�E�V���̌W�ƃA�e�l���� / �c���`�L/p8�`15
��㉉���̗V����-10-�����c����I����n���L / �ق�����/p16�`21
�܌��搶�ƎR���_�y��Ԋy(129)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p22�`23
|
pid/2276538 |
| 130 |
�|�\29(10)(344) |
1987-10 |
��������̕���w�̔����Ɏv�� / �x�㌪/p7�`7
�Q�w��䶗��̓ǐ}�Ɍ����� / ��@�ʖ�/p8�`16
��㉉���̗V����-11-�܂ŋA���̏��D����1�l�� / �ق�����/p17�`23
����\(130)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p24�`25 |
pid/2276539 |
| 131 |
�|�\ 29(11)(345) |
1987-11 |
��������܌����m���a�S�N���������ģ / �q�c��/p7�`7
��-���b�p�̖����|�\�� / �c���`�L/p8�`13
��㉉���̗V����-12-�ܗ����̃i�C�g��J�u�L / �ق�����/p14�`19
����\�����̎�(311)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p20�`21
���Ԑ��b�̌���--���{�Ɛ��E(�h�ᔎ�m�Ď��L�O�_���W) / ����O/p22�`26 |
pid/2276540 |
| 132 |
�|�\ 29(12)(346) |
1987-12 |
����\���{�̎�(132)�܌��M�v�̐��E / �{�c���� ; �F����o�j/p28�`29
��������Ң�܌��M�v�S�W��m�[�g�ҒǕ��ꊪ� / ���їE/p30�`30
�܌����m�L�O�Ñ㌤�����Ң�܌��M�v�蒟� / ���F�M/p32�`32 |
pid/2276541 |
| 133 |
�|�\ 30(1)(347) |
1988-01 |
�|�x���̎��� / �{�c����/p8�`13
�܌��M�v�̐��E(133)��ɂイ��� / �q�c�� ; �F����o�j/p20�`21
�ߓ��씎����������M����� / ��㑸��/p25�`26 |
pid/2276542 |
| 134 |
�|�\ 30(2)(348) |
1988-02 |
��t����S�(134)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p26�`27
������ċ���������!��\�\�܌��M�v�搶�̎v���o / �J���z�q/p28�`29 |
pid/2276543 |
| 135 |
�|�\ 30(3)(349) |
1988-03 |
������炳�ܣ(135)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p18�`19
��R�x�܂�̐��E�����v�Y / �L����/p20�`22 |
pid/2276544 |
| 136 |
�|�\ 30(4)(350) |
1988-04 |
��������n�����������Ƃ̗\�Z� / ���c�m/p7�`7
�܌��M�v�̉\��-��-�܌��M�v�̑n����--���c���j�Ɠ���F��Ƃ̑Δ�ɂ�����(���a100�N�L�O�u����) / �ߌ��a�q/p8�`17
����R�ƃC�^�R�(136)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p18�`19
|
pid/2276545 |
| 137 |
�|�\ 30(5)(351) |
1988-05 |
�܌��M�v�̉\��-��-�܌��M�v�ɂ����閯���Ɨ��j(���a100�N�L�O�u����) / �R�ܓN�Y/p8�`20
�������(�����l�`)�(137)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276640 |
| 138 |
�|�\ 30(6)(352) |
1988-06 |
�F�������{������̘��S�Y�čl / �R�H����/p8�`14
���l��ܘY�(138)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p22�` |
pid/2276641 |
| 139 |
�|�\ 30(7)(353) |
1988-07 |
�[����<���i>--�������Q�w��䶗����e�N�X�g�ɂ��� / ���R��/p8�`24
������£(139)�܌��M�v�̐��E / �q�c�� ; �F����o�j/p32�` |
pid/2276642 |
| 140 |
�|�\ 30(8)(354) |
1988-08 |
��������������������|�\�����Ɏv��� / �㓡�i/p7�`7
���{���w�Z��������̐܌��M�v / �����R��/p8�`11
���Đ��\�Y���̗֊s--�ߐ��� / �|��×Y/p12�`20
����Ƃ̓�̉̔�(140)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276643 |
| 141 |
�|�\ 30(9)(355) |
1988-09 |
����������ԃV���}�j�Y���̓`��� / �哇���F/p7�`7
�t���̔��������� / �{�c����/p8�`14
�����㉉���̗V����-4-�M�d�ȍ��Y�̉Ԗ��\�� / �ق�����/p15�`21
����_�Ђ̉̔���Ɍ�c�A�գ(141)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p22�`23
��܌��M�v���T��������� / ���؍�/p24�`26
�����G�O�Y���w�ڂł݂閯���_�x(�S�O��) / �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276644 |
| 142 |
�|�\ 30(10)(356) |
1988-10 |
��������`���ƍĐ�� / �c���`�L/p7�`7
�������������y�Ƒ��̙T���Y / �㓡�i/p8�`18
�����㉉���̗V����-5-�̕���E�S�̂̔��ȋ��߂� / �ق�����/p19�`25
��Ƃ̐V�����̎莆�(142)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276645 |
| 143 |
�|�\ 30(11)(357) |
1988-11 |
�������NG���\�\�e���r�͂���ł����̂�� / ���؉���/p7�`7
�C�ƎR�̑��ŋ�--����n�ŋ��̖���-��- / �i�R����/p8�`18
�����㉉���̗V����-6-�Č��̖��V���̃��b�J / �ق�����/p19�`25
��ƂƉ��{�Ƃƣ(143)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
|
pid/2276646 |
| 144 |
�|�\30(12)(358) |
1988-12 |
��������Έ䂳����Âԣ / �˔N��/p7�`7
�C�ƎR�̑��ŋ�--����n�ŋ��̖���-��- / �i�R����/p8�`20
�����㉉���̗V����-7��-�j���̃x�e��������ˉ��o / �ق�����/p21�`27
���O�ւ�狋�̔�Ƃ��̎��ӣ(144)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29
���҂���颐茋���--�̕���w��̑n���� / �ы���/p30�`32
|
pid/2276647 |
| 145 |
�|�\31(1)(359) |
1989-01 |
�ݗt�W�G������ݗt�W���(145)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ;�F����o�j/p28~29 |
pid/2276648 |
| 146 |
�|�\31(2)(360) |
1989-02 |
��������|�\�̐V�������� / �P�c�r�ܘY/p7�`7
�b��암�n���ɂ����鎂�q���l-��- / �������c/p8�`16
����Đ��\�Y��̕ϑJ-��-���\�Y�̑��^ / �|��×Y/p17�`25
����{�̒뉀�գ(146)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p26�`27
�㓡����Y�ďC����c���j������Ғ��w���c���j�`�x / ���J�쐭�t/p28�`29
�w�܌����m�L�O�Ñ㌤�����I�v ��S�x / ������/p29�`30
�鎭���T���w�_�������|�\�̌����x / �q�c����/p30�`31 |
pid/2276649 |
| 146 |
�|�\31(3)(361) |
1989-03 |
��������w�|�\�x�̍ďo���Ɋ��ң / �q�c��/p7�`7
���̏C���w(���g���b�N)--�@��_�y�̚��q�ɂ�����ے��\�� / ����T/p8�`17
�b��암�n���ɂ����鎂�q���l-��- / �������c/p18�`27
�����̌��̉̂Ƃ��̒n���l(147)�܌��M�v�̐��E / ���؊�� ; �F����o�j/p28�`29 |
pid/2276650 |
| 148 |
�|�\31(4)(362) |
1989-04 |
�܌��M�v�ƌ|�\<���W>/p10~41
���z �܌��搶�ƎG����|�\� / �˔N��/p10�`11
�����|�\�ƌ|�\���� / �O�����Y/p12�`20
�|�\�j�̎v�z / �ɓ��D�p/p21~27
���J�ƌ|�\ / �������/p28~34
�|�\�ɂ�������� / �Óc���K/p35�`41
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(1)�܌��M�v�̉���̖K / ������ ;�F����o�j/p6~
�� �|�\�����ƍ̏W / ������/p9�`9
��`�������̍Ĕ�������g���V / �������H/p42�`44 |
pid/2276651 |
| 149 |
�|�\31(4)(363) |
1989-05 |
�����E����̐M�ƍ��J-1-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�͂��߂� / ������/p10�`10
������낳������ɂ݂�×����̐��E��--������������̐M�� / �O�Ԏ�P/p11�`23
���������̐M�Ɛ_�b--�H�ߓ`���𒆐S�Ƃ��� / ��ё���/p24�`37
�܌��M�v�̐��E(��l��)�����(2)����V�Ԃ̕��� / ������ ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276652 |
| 150 |
�|�\31(6)(364) |
1989-06 |
�����E����̐M�ƍ��J-2-(���i�L�O���J�u��)/p10�`37
�쓇�̑��������Ɛ_ / �J�쌒��/p10�`21
���J�ƌ|�\ / �O�����Y/P22~37
�u�܂�v�ꗗ�\--�X�ۉh���Y���쐬�w���ꕶ���j���T�x(�������o�Ŋ�)����/p34�`37
�܌��M�v�̐��E(��܁Z)�����(3)��������̂��Ƥ���̑�� / ������ ;�F����o�j/p6~ |
pid/2276653 |
| 151 |
�|�\31(7)(365) |
1989-07 |
���������̐M�ƍ��J-3-�A�l�̗�--�N�����������̗��
�@�@��(���i�L�O���J�u��) / ���c�v�q/p10�`21
�܌��M�v�̐��E(��܈�)�����(4)������̂т���� / ������ ;�F����o�j/p6~
���P�Y���w���ꕑ�x�̗��j�x / �O�����Y/p22�`23 |
pid/2276654 |
| 152 |
�|�\31(8)(366) |
1989-08 |
���z �~�̗x / �{�c����/p10�`11
᱗��~��Ƙb�| / �֎R�a�v/p12�`18
�~�s���ƌ|�\--���s�𒆐S�� / �R�H����/p19�`25
����� �ӓy���̃A�V���Q(��ܓ�)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276655 |
| 153 |
�|�\31(9)(367) |
1989-09 |
�܌��M�v�̐��E(��O)�����(6)�ق����Ƃ���قǒ������l / ������ ; �F����o�j |
pid/2276656 |
| 154 |
�|�\31(10)(368) |
1989-10 |
���c���j�ƌ|�\ / �q�c��/p11~13
�܌��M�v / ������/P14~16
�����Z�g�̕��x���� / �J�O/p17�`19
����F���Y / �O�����Y/P20~21
�k�씎�� / �ۍ�B�Y/p22~23
���p�䐳�c / �������H/p24~26
�ɔg���Q / �X�۞Ď��Y/p27~28
�܌��M�v�̐��E(��l)�����(7)���c�ƈ��g / ������ ;�F����o�j/p6~
<���]>��ؓ��q���w���O�ͥ�ԍՂƐ_�y<�_�̎���l�̐�>�x / ��쐽/p37�`38
�q�Љ�r�㓡�i�Ң�V�s�|�\� / �n�ӗǐ�/p38�`39 |
pid/2276657 |
| 155 |
�|�\31(11)(369) |
1989-11 |
�܌��M�v�̐��E(��܌�) / �����/p8�` |
pid/2276658 |
| 156 |
�|�\ 31(12)(370) |
1989-12 |
���ʉ����s�������̂䂭�� / �F����o�j/p19�`29
�\�ʂƖ����|�\��--�ԍբ��S��Ɨw�Ȣ�ԑm��̊W���� / �㓡�i/p30�`38
�܌��M�v�̐��E(��ܘZ)�����(9)�Ί_���ł̖̍K / ������/p6�` |
pid/2276659 |
| 157 |
�|�\32(1)(371) |
1990-01 |
�O�ԙ�<���W>/p10�`41
�_���Ɠs�s��L���̕ϊ��q��O�ԙգ�|�\�j�̋ߐ��I�W�J�r / �����K�Y/p10�`11
�O�ԙՂ̖ⓚ�̕ϑJ / ���c�K�q/p12�`18
�̕���̢�O�ԙգ / ������Y/p19�`25
�M�y�̎O�ԙ� / �Ύ�،��q/p26�`33
�O�ԙ]�� / ���p�䐳��/p34�`41
�܌��M�v�̐��E(���)/�����(10)�A���K�}������ / ������ ; �F�f���o�j/p6�`
|
pid/2276660 |
| 158 |
�|�\32(2)(372) |
1990-02 |
�܌��M�v�̐��E(��ܔ�)/�����(11)�{�ǂ̃i�r���h�D / ������ ; �F�f���o�j/p6�`7 |
pid/2276661 |
| 159 |
�|�\32(3)(373) |
1990-03 |
�C����ƌ|�\--��������𒆐S�Ƃ��� / ��ؐ���/p17�`23
�̕���Ƣ����̌|�\ / ���c���i/p24�`30
�܌��M�v�̐��E(��܋�)�����(12)�����̖K�蒟��Ƣ����̖K�L� / ������ ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276662 |
| 160 |
�|�\32(4)(374) |
1990-04 |
��O�c���ݗt���s�(160)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276663 |
| 161 |
�|�\32(5)(375�j |
1990-05 |
�܌��M�v�̐��E(��Z��)(���̓�)�ݗt���s / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276664 |
| 162 |
�|�\32(6)(376) |
1990-06 |
������<���W>/p9~38
������裂̌Ñ㎏--�|�\�����̋N�_ / �ɓ��D�p/p10�`16
�_�y�ɂ������Ă鉉�o / ���䐳�O/p17�`24
����ɂ������Ă�̋V��ƌ|�\ / ���w/p25�`31
�H�R������Ɠc�V�т� / ���q�v/p32�`38
��t����{��գ(��Z��)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ;�F����o�j/p6~7
<��>��Ă裏ȗ����� / �O�����Y/p9�`9 |
pid/2276665 |
| 163 |
�|�\32(7)(377) |
1990-07 |
���ƌ|�\ //p10�`10
���E��"�ՋV = �|�\"�Ƃ��Ă̐_�y / ��c��/p11�`19
���K�_--���ԥ��Ԃ̋����o������_ / �����G�O�Y/p20�`28
�ޗǍ�|�\�� / �㓡�i/p29�`36
��ԍՂ�(��Z�O)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276661 |
| 164 |
�|�\32(8)(378) |
1990-08 |
����̌|�\<���W>/p10�`37
�g�x��̓W�J--�����Ȍ� / ���P�Y/p10�`17
�X�����8���V�� / �c���p�@/p18�`23
�������x�̓���--�ÓT���x��ƎG�x��𒆐S�� / ���A�ɒj/p24�`30
����̑��x�� / ���Ԉ�Y/p31�`37
��V�� ��Ղ�(��Z�l)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`
<�Љ�>�c���`�m��w�����w������ҁw�쓇�����Ɛ܌��w�x������q���w����̗̉w�Ɖ��y�x�Ɖ����P���w����̌ÓT�|�\�x / ���ʐM/p38�`39
|
pid/2276667 |
| 165 |
�|�\32(9)(379) |
1990-09 |
�O���ƌ|�\<���W>/p10�`38
�O�����{�ƌ��� / �剮����/p10�`17
���B�̖~�O��--���̓`�����ԂƗ��j�I�ϑJ / �g��S�q/p18�`24
��a�̘Z�֔O�� / ���J�M/p25�`32
��O�R�㋽�̑�O�� / ���⏟�j/p33�`38
��V��~�x��ƐV��̑��������(165)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ; �F����o�j/p6�`
<��>�_�y�a����M�y�̋����� / �����G�Y/p9�`9
�͒|�o�u�v�ďC������G�Y�ҏW��щËg�ʐ^�w�̕���r���x / �{�c����/p39�`39
�R�H�������w���̍��\�\�|�\�������̒����x / �������H/p40�`40
|
pid/2276668 |
| 166 |
�|�\32(10)(380) |
1990-10 |
��܌��搶�ƐH�ו����(��Z�Z)�܌��M�v�̐��E / �[���g�V�� ;�F����o�j/p6~7
<��>�܌��M�v���ꂩ��̂͂��� / ������/p9�`9
|
pid/2276669 |
| 167 |
�|�\32(11)(381) |
1990-11 |
�另�Ղƌ|�\<���W>/p10~33
�{��̗w�����̋@�� / ������/p10�`16
�������̈Ӌ`--�V�當���w�̗��ꂩ�� / �q�ѐ���/p17�`25
�另�Ղ̍\���V�_ / �g��T�q/p26�`33
��O�c�̖��t���s(��)�(167)�܌��M�v�̐��E / ������� ;�F����o�j/p6~
���{�̖����|�\--��茧 / �剮����/p34�`47
<��>�Ă�̍Ղ�̍Đ��Ǝ� / �O�����Y/p9�`9
<���]>�q�쐴���w���d�R�̂��ԁx / ���F�M/p48�`48 |
pid/2276670 |
| 168 |
�|�\32(12)(382) |
1990-12 |
�̖�̗��K�_ / ��ؐ��F/p10�`17
�z�N��}�t�̌|�\ / ���c�nj�/p18�`24
�܌��M�v�̐��E(��Z��)����t���s(��)� / ������� ; �F����o�j/p6�`7
|
pid/2276671 |
| 169 |
�|�\33(1)(383) |
1991-01 |
�Ìy�ɂ������t�|�̐����Ƃ��̋ߑ㉻ / ���a�Y/p10�`16
�t����Ԍ������� / �_�c���q/p17�`23
���w��̗w�Ɍ����t�j���| / ����K��Y/p24�`30
����t���s(��)�(��Z��)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�`
<��>�|�\����݂��另�Ձ\�\�^�킵���I�� / ���p�䐳��/p9�`9
|
pid/2276672 |
| 170 |
�|�\33(2)(384) |
1991-02 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ�Z)���O�t���s(��)� / ������� ; �F����o�j/p6�`7 |
pid/2276673 |
| 171 |
�|�\33(3)(385) |
1991-03 |
���O�t���s(��)�(171)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�`7
�Ï銰�����w�܌��M�v�̒����_�x / �Óc���K/p46�`46 |
pid/2276674 |
| 172 |
�|�\33(4)(386) |
1991-04 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ��)���O�t���s(�O)� / ������� ; �F����o�j/p6�`
|
pid/2276675 |
| 173 |
�|�\33(5)(387) |
1991-05 |
���l�t���s�(�ꎵ�O)�܌��M�v�̐��E / ������� ; �F����o�j/p6�` |
pid/2276676 |
| 174 |
�|�\33(6)(388) |
1991-06 |
��O�c�̖��t���s(��܉�)���̈�(�ꎵ�l)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y ;�F����o�j/p6~7 |
pid/2276677 |
| 175 |
�|�\33(7)(389) |
1991-07 |
��O�c�̖��t���s�w��܉�x���̓�(�ꎵ��)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y ; �F����o�j/p6�`7
�r�{�������w����̗V�s�|�\�\�`�����_���[�ƃj���u�`���[�x / �ɓ��D�p/p45�`45
|
pid/2276678 |
| 176 |
�|�\33(8)(390) |
1991-08 |
�_�y��<���W>/p10�`30
���B�̐_�y�� / ���R����/p17�`23
��O�c�̖��t���s�w��܉�x���̎O�(�ꎵ�Z)�܌��M�v�̐��E / �H�R�Ëv�Y/p6�`7
��{���꒘�w�F��R�C�����l�x / ��ؐ���/p46�`46 |
pid/2276679 |
| 177 |
�|�\33(9)(391) |
1991-09 |
�܌��M�v�̐��E(�ꎵ��)��O�c�̖��t���s(��Z��)(���̈�)� / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`
�X�R�d�Y���w�܌��M�v����҂̏���̐��E�x / �������H/p46�`40
�����������w�܌��M�v�̊w��`���x / ������/p47�`47 |
pid/2276680 |
| 178 |
�|�\33(10)(392) |
1991-10 |
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̓�(�ꎵ��)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`7
����̌|�\�ߏ�--�g�x�ɂ݂�ߏւȂǂɂ��� / ��ԗ�i/p24�`30 |
pid/2276681 |
| 179 |
�|�\33(11)(393) |
1991-11 |
�\�Ƒg�x<���W>/p10�`29
<��>����ɂ����� / ���R�h��/p9�`9
���������Ƣ���S����� / �{�c����/p10�`14
�g�x�G�� / ��闧�T/p15�`19
������q��Ƣ�H�ߣ�̒�� / ������/p20�`24
�g�x�̐��E--���������Ƣ���ΓG����̑�햡 / ���Ԉ�Y/p25�`29
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̎O�(179)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ; �F����o�j/p6�`7
�ؕꎛ�ҁw�~��˥�ؕꎛ�̕���x/p44�`44 |
pid/2276682 |
| 180 |
�|�\ 33(12)(394) |
1991-12 |
��O�c�̖��t���s�w��Z��x���̎l�(�ꔪ�Z)�܌��M�v�̐��E / �����y��Y ;�F����o�j/p6~ |
pid/2276683 |
| 181 |
�|�\34(1)(395) |
1992-01 |
��C�R���̉̔�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
�����|�\����w�����̃��[���h��~���[�W�b�N����������̣ / �������q/p62�`62
|
pid/2276684 |
| 182 |
�|�\34(2)(396) |
1992-02 |
��؏������̐գ(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
�\�������|�p�Տ܂ɔ~�ᐷ�`� / ���N��/p59�`59
|
pid/2276685 |
| 183 |
�|�\34(3)(397) |
1992-03 |
���ЎQ�w��䶗��ƊG�������ւ̎���--�G�����̊T�O,�����Ď��Љ��N�G���玛�ЎQ�w��䶗��� / �щ�F/p19�`27
�Ў��Q�w��䶗��̌|�\�� / ���c�a�v/p28�`34
��v�����̖̍K�(�ꔪ�O)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
�����|�\����w������|�\���ό��̍ޗ��ɂ����!!�v / �������q/p62~62 |
pid/2276686 |
| 184 |
�|�\34(4)(398) |
1992-04 |
��Ì����̍��Ɛ̣(�ꔪ�l)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`7
���{�̖����|�\�q���ꌧ�r / ���{/p30�`43 |
pid/2276687 |
| 185 |
�|�\ 34(5)(399) |
1992-05 |
���w�̌p�����W�̂��߂Ɏ������� / �������q/p10�`15
��^�ӂ̈È�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~7
�{�c�������w����̍Ղƌ|�\�x / �O�����Y/p45�`45
���䖞�ҁw�v�����̍Ղ�Ɠ`���x / �k����v/p46�`46
�����|�\����w��V�����Љ�ł̖������y��|�\� / �������q/p60�`60 |
pid/2276688 |
| 186 |
|
1992-06 |
����������̏o���(�ꔪ�Z)�܌��M�v�̐��E / ������ ; �F����o�j/p6�`
�����|�\����w�����̍Ղ�̕ϗe� / ����h/p61�`61 |
pid/2276689 |
| 187 |
�|�\ 34(7)(401) |
1992-07 |
���n�̎R�͑O���̋�ɣ(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / ������ ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276690 |
| 188 |
�|�\34(8)(402) |
1992-08 |
��v�����̃C�U�C�z�[�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
����^�C���X�Еҁw�����Ȃ�̍Ղ�x / ������ |
pid/2276691 |
| 189 |
�|�\34(9)(403) |
1992-09 |
��v�����̃C�U�C�z�[(2)�(�ꔪ��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w��w���܂�@�x�����������̂ţ / �������q/p60�`60 |
pid/2276692 |
| 190 |
�|�\34(10)(404) |
1992-10 |
��v�����̃C�U�C�z�[(3)�(���Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���{��������ҁw���{���w���(���ꥉ���)�{�Ï����ҁx / �O�����Y/p47�`47
���֏�v������������� / ���P�Y/p49�`50 |
pid/2276693 |
| 191 |
�|�\34(11)(405) |
1992-11 |
�|�ƌ|�\--�o�����̌|�\�ƋV���� / �{������/p18�`21
��v�����̃C�U�C�z�[(4)�(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w����w�E�͌��_���A�֣ / �������q/p60�`60
|
pid/2276694
|
| 192 |
�|�\34(12)(406) |
1992-12 |
<��>�ޏ��̌��_�b / �������/p9�`9
�쓇�̐_�b�E�_�w<���W>/p10~32
�����̃m���ƃ��^�̎��d�ɂ���--�I�����ƃ}���K�^���̑Δ� / �R���ӈ�/p10�`17
���z�̐_�Ɣ��n�̗��--�v�����̃e�B-��-�K-�~�̐_�� / ��������/p18�`25
�떓�̃t�T--���̋N�� / �Ë��M�F/p26�`32
��Ί_���̃A���K�}�(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276695
|
| 193 |
�|�\35(1)(407) |
1993-01 |
<��>�Y�\�w��\���N / �{�c����/p9�`9
�|�\�w--�܌��M�v�̕��@<���W>/p10�`32
�܌��搶�Ɖ̕��� / �˔N��/p10�`11
�����w�ƌ|�\�w--���c���j�Ɛ܌��M�v��"�|�\�_" / �q�c��/p12�`18
�܌��w�̍\��--�|�\�`���_�̍��i / �O�����Y/p19�`25
�܌��M�v�̌|�\�̏W / ������/p26�`32
�܌��M�v�̐��E���O��Ί_���약�̃}�����K�i�V� / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w��`�������U���̕�������� / �������q/p62�`62
|
pid/2276696 |
| 194 |
�|�\35(2)(408) |
1993-02 |
<��>�܌��M�v�Ɛ_���� / �ۍ�B�Y/p9�`9
�܌��|�\�j��ǂݒ���<���W>/p10�`30
�����|�\�����ɂ�����ϋq�_-3�̉\�� / ��쐽/p24�`30
����\���c�[�̐߃A���K�}(1)�(194)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
�c�Ԉ�Y�ďC�w�����|�\���T�x / �O�����Y/p45�`45 |
pid/2276697 |
| 195 |
�|�\35(3)(409) |
1993-03 |
�܌��M�v�̐��E(����)����\���c�[�̐߃A���K�}(2)� / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
�����|�\����w����w�̐�������`���� / �������q/p62�`62 |
pid/2276698 |
| 196 |
�|�\35(4)(410) |
1993-04 |
������<���W>/p10~30
�叕�\�̔ԑg��<����������>--
�@�@�����Q�����}���ّ���x��叕�\�ԑg����߂����� / �V�앶�Y/p10�`14
�Ԋy�̒��̈�������P--�������e�L�X�g�l / �ѐm/p15�`20
��p���V���E�l�ӣ�Ɛl�`�̏����� / �����F��/p21�`25
��|�҂Ǝ��--�ٍ��Ő��܂ꂽ�������� / �O����/p26�`30
������գ(���Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276699 |
| 197 |
�|�\35(5)(411) |
1993-05 |
<��>�����̕� / ���ʐM/p9~9
�|�\�w��E����|�\�j����������<���W>/p10�`30
�g�x��{�̢��\(�݂Ȃ݂�����)���k�\(����������)����l���� / ���Ԉ�Y/p10�`16
�������{�ɂ����钆���n�̉��y�Ƣ����y��̉��� / ��Éx�q/p17�`23
�܌��M�v�̉���|�\����--��O�̉���̋��y�����Ƃ̊ւ��𒆐S�� / ���F�M/p24�`30
���Ƃ����낳�����(��㎵)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
���](���W����) / ���ʐM/p34~35
�������̓������ / ���ʏˎq/p45�`45 |
pid/2276700 |
| 198 |
�|�\35(6)(412) |
1993-06 |
����䉮����ԣ(��㔪)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~
|
pid/2276701 |
| 199 |
�|�\35(7)(413) |
1993-07 |
��������ꉉ���̕���j / ��쓹�Y/p10�`16
���ŋ��̕��� / �i�R����/P17~23
��֏��ԣ(����)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276702 |
| 200 |
�|�\35(8)(414) |
1993-08 |
<��>���a�̕��w��|�\�ƌ˔N�� / ����O�F/p9�`9
�l�`�|�\�ƕY��<���W>/p10~30
���{�|�\�j�Ƌ��l�M��--����̍l�@�𒆐S�� / �ɓ��D�p/p10�`16
���� �����Y�̐l�`�Y / �F�쏬�l�Y/p17�`23
�؍��̐l�`���R�N�g�D�t���m����--�j���}�͕Y���ƈ��������z���� / �p���/p24�`30
������Y�(����1)(��Z�Z)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
|
pid/2276703 |
��
201 |
�|�\ 35(9)
(415)
�|�\ 35(10�j
(416)
�E
�|�\ 35(11)
(417)
�E
�E
�E |
1993-09
�E
1993-10
�E
�E
1993-11
�E
�E
�E
�E |
�܌��M�v�v��40�N�L�O--�܌��|�\�w�̑S�e<���W> / ���T�j/p10�`29
�܌��M�v�̐��E��(��Z��)������Y�(����2) / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
��>�܌��M�v�l�\�N�� / �q�c��/p4�`5
�����{��̒j�|��(��Z��)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p8~9
���G �����{��̒j�| / �F����o�j/p2�`2
�����{��̏��x(203)�܌��M�v�̐��E / �O�����Y ;�F����o�j/p6~7
���G �����{��̏��x / �F����o�j/p2�`2
���̂��ύX
�|�\ 35(11)(417)�@�@�@�|�\�w��� �@���s�^�|�\���s��
�Y�\ (1)(418) �Y�\�w��ҏW�ψ���� �@���s�^�Y�\�w�� |
pid/2276704
�E
pid/2276705
�E
�E
pid/2276706
�E
�E
�E
�E |
| 202 |
�Y�\(1)(418) |
1995-03 |
�܌��M�v�̐��E(202�@204)��狋�̉̔�ɉ / �[���g�V�� ;�F����o�j/p97~99 |
pid/4428628 |
| 203 |
�Y�\(1)(418) |
1995-03 |
�܌��M�v�̐��E(203�@205)�g�� / ���؊�� ;�F����o�j/p100~105 |
pid/4428628 |
| 204 |
�Y�\(2)(419) |
1996-03 |
<94�N�������>�������\/4�`41
�؍��̒ǙT / �c����/p4�`11
�؍��]�˂̒[�ߍ� / �ɓ��D�p/p12�`20
�b��암�n���̎��q�� / �������c/p21�`30
�u�V�����l�v�����m-�g / �H���Ƌ`��/p32�`41
<94�N�������>�u�� �{�q���ɂ�����|�̓`�� / �r�c�O��/p42�`51
<94�N�������>�|�\�Z�~�i- �֍O�q���ɕ���--
�@�@��"���"�̐��ݏo���F���̓h���} / �֍O�q ; ������/p52�`63
<95�N�������>�|�\�Z�~�i�[�u���J��Ԃƌ|�\��ԁv/64�`95
�����|�\�̍��J��Ԃƌ|�\��� / �F����o�j/p64�`68
���J��ԂƉ̕��� / �D�c�E��/p69�`75
���{���x�̐�����Ԃƌ|�p��� / ����p�r/p76�`85
�u���v�̑g���ƍ��J�� / ���R��/p87�`92
<���J��Ԃƌ|�\���>���߂����� / �H�c��/p93�`95
�܌��M�v�̐��E(204)�@206�t����S�E�Ȃ܂͂� / ��ϐ��� ; �F����o�j/p96�`102
�q�r ���䂩�����r���{����--�č��~�h���x����w�ɂ� / �����r�q/p103�`103
�����q�j�w�當���j�̌����x / ����}��/p104�`105
�n�ӏ��`�w�����Ղ̌����x / �ۍ�B�Y/p106�`107
���}���w��p�̓����Ɩ��ԐM�x / �����W��/p108�`109
���Y���P�w�܌��M�v�_�x / ���c���q/p110�`110
�����G�Y�E�F����o�j�ďC�w���{�̓`���|�\�x / ������/p111�`111
�k���k�̏C���n�_�y�́u��v / ��Αוv/p112�`114
�u�܌��M�v�Ɖ���w�Ɓv�̂܂Ƃ߂Ɍ����� / ���F�M/p115�`117
�z���S�̌��� / �Ύ�،��q/p118�`120
|
pid/4428629 |
| 205 |
�Y�\(3)(420) |
1997-03 |
<95�N�������>�u�� ���{�������y�����\�N / �������q/p4�`16
<95�N�������>�������\/17�`51
�|�\�Ǝq�� / �{�c�ޔ��q/p17�`25
�C���ւ̎��� / �F�엲��/p26�`33
���㉬�]�I�F�̎��� / �R���/p34�`41
�V���čl / �ۍ�B�Y/p42�`51
<95�N�������>�|�\�Z�~�i- �x��ƉS�ŒT��]�˂́u���v / �h�� ; �O�����Y ; ���Ԋ����b/p52�`61
�܌��M�v�̐��E��(205�@207��)�܌��M�v�̒����s / �������H ; �F����o�j/p62�`67
���q�̊T�O�Ɋւ���l�@--�����|�\�ɓo�ꂷ�鎂�q����ʂ��� / �����K/p68�`77
����h�w�̊_�Ɣ��y�̖�����--�����ɌÑ�̉̕���K�˂āx / ���R��/p78�`79
�����K�Y�w�]�ˉ̕���̔��ӎ��x / ����됅/p80�`81
����O�F�w�܌��M�v�̋L�x / ������/p82
�V�ҁw�܌��M�v�S�W�x��21�E22��(�|�\�j1�E2) / �������/p83
�R���s��c�_�Џ����א�H�֊֘A�̚��q�`���̏Љ� / �R�{���q/p84�`85
�_�q�V���|�W�E���� / �_�c���q/p86�`87
�ɐ���_�y����̌���Ɩ��_ / �㓇�q��/p88�`89
���ۍl / �v�ۓc�T��/p90�`91
���G �u�܌��M�v�̒����s�v / �F����o�j ; �������H |
pid/4428630 |
���V���[�Y�u��Z��^�Q�O�R)�܌��M�v�̐��E�v���d�����Čf�ڂ���Ă���̂��u�܌��M�v�̐��E(20�V��)�ƂȂ锤�Ȃ̂Œ��ӂ��K�v�@�Q�O�Q�T�E�S�E�P�W�@�ۍ�
|
|
|
�܂Ƃ�
�@�����������̒��ł́A�؉A�͋C�����̗ǂ����̂ł��B�́A�X���Ɍ��ꗢ�˂ɂ́A�|�̖��A�����Ă���܂����B�|�̖͉Ăɂ͗t�����藷�l�̔�����₵�܂����B�Ԃ��Ȃ������̎��͊Â�������₵�܂��B
�@�����A�K�W���}���������ł��傤�B�T�ɂ͌���i�������j���J���Ă���܂����B�l�X�́A���̎��̉��ɏW�܂�A�̂��x��A�����ċ��������Ƃ��������ł��傤�B�[���������j�̒��ŁA�l�X�͂��ꂩ����������������邱�Ƃ��Ǝv���B�݂�ȃK�W���}���̖̉��ɏW�܂�ł��B
�@�q���l�сr�쐬���̌㔼����A���̌����̃e�[�}�ł�����A�������ی�Ɋւ���L�q�����Ă��܂��܂����B�܂��A��^�����Ă��܂����̂ōH�Y�W�ɂ��Ă��������������܂����B�S�̓I�ɕ�����ɂ������̂ɂȂ��Ă��܂��܂������A���e�͂̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�@���A�䍖���J���Ă���X�Ɋւ��ẮA���ɂƂ��Ă̌����̐[���ł�����V���ȍ���҂����Ƃ������Ă���܂��B�i�ۍ�L�j
�O�j
�w�p�@�փ��|�W�g���f�[�^�x�[�X�iIRDB�j404 Not Found
�ӂ邳�Ɛ؎藮�����x�@�{�щԁi�k�g�D�k�`�o�i�j�@�@���s���@1990.8.1 62�~�@
�^�ߔe�@����i��Ɓj |
|